目次
はじめに
この記事で取り上げる映画
監督:岸善幸, Writer:岸善幸, 出演:有村架純, 出演:森田剛, 出演:磯村勇斗, 出演:若葉竜也, 出演:マキタスポーツ, 出演:石橋静河, 出演:北村有起哉, 出演:宇野祥平, 出演:リリー・フランキー, 出演:木村多江
 ポチップ
ポチップ
この映画をガイドにしながら記事を書いていきます
この記事の3つの要点
- 私は「自分のために行動する人」が好きで、だから、本作で描かれる保護司・阿川佳代の葛藤に考えさせられてしまった
- 「強さ」ではなく「弱さ」でしか救えない状況は存在するし、「犯罪者の更生」にもそのような観点が取り入れられるべきだと思う
- 「保護司っぽくない」と感じさせる阿川佳代の言動が、とても素敵に映った
何にせよ私は、「まず彼女自身が幸せになってほしい」と願わずにはいられなかった
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
記事中の引用は、映画館で取ったメモを参考にしているので、正確なものではありません
映画『前科者』が描く「犯罪者の更生の現実」と、「有村架純演じる保護司の葛藤」に色々と考えさせられた
「自分のために行動する人」が好き
私は、「自分のために行動する人」のことが好きだ。しかし、これには少し説明が必要だろう。
あわせて読みたい
【天才】映画『笑いのカイブツ』のモデル「伝説のハガキ職人ツチヤタカユキ」の狂気に共感させられた
『「伝説のハガキ職人」として知られるツチヤタカユキの自伝的小説を基にした映画『笑いのカイブツ』は、凄まじい狂気に彩られた作品だった。「お笑い」にすべてを捧げ、「お笑い」以外はどうでもいいと考えているツチヤタカユキが、「コミュ力」や「人間関係」で躓かされる”理不尽”な世の中に、色々と考えさせられる
決して、「自分勝手に生きている人」という意味ではない。そうではなく、「『誰かのため』と捉えられがちな行動を『自分のためにしている』と自覚している人」が好きなのである。意味が伝わるだろうか?

これは私の中では、弁護士や医師など「報酬を受け取る職業」の人にも当てはまる話なのだが、ちょっと軸がブレるように思うので、分かりやすいように「ボランティア」を例に挙げよう。ボランティアは普通、「誰かのためにしている」とみなされると思うし、従事している当人もそういう認識で行っていることが多いだろう。しかし私は、とても勝手な意見だと理解しているのだが、正直、「誰かのためにしている」という感覚をあまり信じていない。
もちろん世の中には、医師でありながらアフガニスタンで用水路建設に生涯を費やした中村哲のように、「どう見ても『誰かのため』としか言えないような生き方をしている人」もいる。だからそのすべてを否定したいわけではないのだが、一方で、そういう人は決して多くはないと考えてもいるのだ。これは別に「『誰かのため』という感覚を持つなら100じゃなきゃいけない」みたいな話ではない。誰もが0から100の割合のどの程度かで「誰かのため」という感覚を持っているだろうし、そこにグラデーションがあること自体は全然いい。ただやはり、「誰かのため」と”主張する”のであれば、そのレベルは「100に近いもの」であってほしいと思ってしまうし、そしてそういう人は決して多くはないと私は考えているのである。
あわせて読みたい
【情熱】選挙のおもしろ候補者含め”全員取材”をマイルールにする畠山理仁の異常な日常を描く映画:『NO …
選挙に取り憑かれた男・畠山理仁を追うドキュメンタリー映画『NO 選挙, NO LIFE』は、「平均睡眠時間2時間」の生活を長年続ける”イカれた”ライターの「選挙愛」が滲み出る作品だ。「候補者全員を取材しなければ記事にはしない」という厳しすぎるマイルールと、彼が惹かれる「泡沫候補」たちが実に興味深い
だから、例えば70~80程度の「『誰かのため』という感覚」を持っているような場合に、「これは自分のためにやっているんだ」と自覚している人の方が好ましいと私は思っているのだ。私のこの感覚は伝わるだろうか?
ここには、「『あなたのためにやっている』という”圧”が苦手」という理由もある。
さて本作『前科者』では、出所した元犯罪者の更生に関わる保護司が描かれるのだが、まず1点、もしかしたら広くは知られていないかもしれない情報を提示しておくことにしよう。保護司が行うのは、「定期的に元犯罪者と面談する」というなかなかに大変な仕事だが、なんと無給のボランティアなのである。そして、もし私が元犯罪者で、保護司と関わらなければならなくなった場合に、「『あなたのためにやっている』という”圧”」を保護司から感じてしまったらしんどいなと思う。これは他の状況でも同じである。私は大体において、「『あなたのためにやっている』という”圧”」がすこぶる苦手なのだ。
だから私は、自分はそういう雰囲気を発しないように気を付けているつもりだし、さらに、「自分のためにやっている」という認識の方が優位な人と関わりたいとも考えているのである。
あわせて読みたい
【価値】どうせ世の中つまらない。「レンタルなんもしない人」の本でお金・仕事・人間関係でも考えよう…
「0円で何もしない」をコンセプトに始まった「レンタルなんもしない人」という活動は、それまで見えにくかった様々な価値観を炙り出した見事な社会実験だと思う。『<レンタルなんもしない人>というサービスをはじめます。』で本人が語る、お金・仕事・人間関係の新たな捉え方
「弱さ」が誰かにとっての「救い」になることだってあるはずだ
本作『前科者』の中で、私が一番好きなシーンを紹介しよう。女性2人がコンビニの前で話をしている場面でのやりとりだ。1人は保護司の阿川佳代で、もう1人は、かつて彼女が保護司として担当した元犯罪者のみどりである。そして佳代がみどりに、「更生を手助けするなんて大口叩いてきたけど、私には何もできない」と弱音を吐くシーンがあるのだ。
佳代のそんな吐露を受けて、みどりは自身の子ども時代や刑務所時代の話を始める。彼女は子どもの頃、「親が男漁りに行く時は500円もらえる」という環境で生活していた。しかし、母親が1週間帰ってこないこともしばしばで、そんな時は、「私は世界一不幸な子どもだ」と考えていたそうだ。しかし刑務所に入って、「世の中は自分みたいな人間ばかりなのだ」と気付いたという。それに、罪を犯してから出会った人間は「弁護士」や「検事」のような”真っ当な人間”ばかりで、「世間を代表しています」と言わんばかりの顔で「これからは真面目に生きろ」みたいなことを言ってくる。でも、「あたしたちのような前科者がいるお陰で『世間の代表』みたいな顔が出来るんだろ」って思ってたし、だからあいつらの言葉なんか全然耳に入ってこなかった。
あわせて読みたい
【狂気】アメリカの衝撃の実態。民営刑務所に刑務官として潜入した著者のレポートは国をも動かした:『…
アメリカには「民営刑務所」が存在する。取材のためにその1つに刑務官として潜入した著者が記した『アメリカン・プリズン』は信じがたい描写に溢れた1冊だ。あまりに非人道的な行いがまかり通る狂気の世界と、「民営刑務所」が誕生した歴史的背景を描き出すノンフィクション
そんな話を滔々と続けた後で、みどりは佳代にこんなことを言うのである。
でも、佳代ちゃんと会って考えが変わったんだ。私らみたいな人間以外にも、こんなに弱い人間がいるんだ、って。
さらに続けて、こんな風にも念押ししていた。
あわせて読みたい
【絶望】「人生上手くいかない」と感じる時、彼を思い出してほしい。壮絶な過去を背負って生きる彼を:…
「北九州連続監禁殺人事件」という、マスコミも報道規制するほどの残虐事件。その「主犯の息子」として生きざるを得なかった男の壮絶な人生。「ザ・ノンフィクション」のプロデューサーが『人殺しの息子と呼ばれて』で改めて取り上げた「真摯な男」の生き様と覚悟
前科者に必要なのは保護司なんかじゃない。佳代ちゃんみたいな人だよ。
凄く良かったなと思う。

佳代は保護司としての自身のあり方に悩んでいる。というのも、彼女にはどうしても振りほどけない過去があり、その過去に導かれるようにして保護司になったという経緯があるからだ。もちろん彼女の中には、「前科を持つ者たちの更生に真摯に向き合いたい」という強い想いがある。しかしそれと同時に、彼女はどうも、「自分は自分のために保護司をしている」というある種の”後ろめたさ”みたいなものを感じているように見えるのだ。
あわせて読みたい
【思考】戸田真琴、経験も文章もとんでもない。「人生どうしたらいい?」と悩む時に読みたい救いの1冊:…
「AV女優のエッセイ」と聞くと、なかなか手が伸びにくいかもしれないが、戸田真琴『あなたの孤独は美しい』の、あらゆる先入観を吹っ飛ばすほどの文章力には圧倒されるだろう。凄まじい経験と、普通ではない思考を経てAV女優に至った彼女の「生きる指針」は、多くの人の支えになるはずだ
そして彼女は、そのことに葛藤を抱いている。「罪を犯してしまった人たちに寄り添いたい」という気持ちは決して嘘じゃない。しかし実際には、過去に囚われている自分自身のために保護司を続けているのだ。それが彼女には「中途半端」だと感じられているのだろうし、また、「そのせいで『取り返しのつかない事態』を引き寄せてしまったのではないか」とも考えているのである。
みどりは別に、佳代が抱えているそんな葛藤について具体的に理解しているわけではない。しかし、長い付き合いで感じるものがあったのだろう。「佳代ちゃんのその弱さが良いんだよ」という言葉で彼女の背中を押すのである。そのような感覚はよく理解できるなぁと思う。私も、犯罪者ほどではないにせよ、「社会の割と低い方」を生きてきた自覚がある。そしてだからこそ、「弱さ」によって相手を信頼できたり、自分を託せたりするのだ。「前科者に必要なのは佳代ちゃんみたいな人」というのは本当によく分かる。さらにこの言葉は、彼女を勇気づけるものでもあるが、同時に、現行制度の限界を示してもいると言えるだろう。
犯罪者だって「何かの被害者」である
あわせて読みたい
【矛盾】その”誹謗中傷”は真っ当か?映画『万引き家族』から、日本社会の「善悪の判断基準」を考える
どんな理由があれ、法を犯した者は罰せられるべきだと思っている。しかしそれは、善悪の判断とは関係ない。映画『万引き家族』(是枝裕和監督)から、「国民の気分」によって「善悪」が決まる社会の是非と、「善悪の判断を保留する勇気」を持つ生き方について考える
また、「罪を犯してから出会うのは“真っ当な人間”ばかりだった」というみどりの“不満”も、凄く分かるなぁという感じがした。
私は以前、『プリズン・サークル』というドキュメンタリー映画を見たことがある。これは、島根県に実在する刑務所「島根あさひ社会復帰促進センター」に密着した作品で、「日本初の新たな取り組み」を行う刑務所として注目されているのだ。
あわせて読みたい
【対話】刑務所内を撮影した衝撃の映画。「罰則」ではなく「更生」を目指す環境から罪と罰を学ぶ:映画…
2008年に開設された新たな刑務所「島根あさひ社会復帰促進センター」で行われる「TC」というプログラム。「罰則」ではなく「対話」によって「加害者であることを受け入れる」過程を、刑務所内にカメラを入れて撮影した『プリズン・サークル』で知る。
その「新たな取り組み」は「TC」と呼ばれている。「Therapeutic Community」の略で、「治療共同体」と訳されることが多いようだ。元々は「薬物依存者や精神疾患患者が対話を通じて回復を目指す仕組み」として始まったそうだが、それを刑務所にも応用した形である。「島根あさひ社会復帰促進センター」では、「受刑者同士が様々な形で対話を行うことで更生に寄与すること」が期待されているのだという。
そして、そんな「TC」を映し出す映画の中で、特に印象的に感じられた場面がある。グループセラピーの最中に受刑者の1人が、「自分だって被害者だ」と口にするシーンだ。加害者であることはもちろん理解しているが、自分も「虐待の被害者」だったし、誰かがそのことを認めてくれないと「加害者としての立場」になんか立てない。そんな風に訴える者がいたのである。
「なるほど」という感じだった。確かにその通りかもしれない。そしてこの言葉は、本作『前科者』で描かれる状況にも当てはまると言えるのではないかと思う。
あわせて読みたい
【悲劇】アメリカの暗黒の歴史である奴隷制度の現実を、元奴隷の黒人女性自ら赤裸々に語る衝撃:『ある…
生まれながらに「奴隷」だった黒人女性が、多くの人の協力を得て自由を手にし、後に「奴隷制度」について書いたのが『ある奴隷少女に起こった出来事』。長らく「白人が書いた小説」と思われていたが、事実だと証明され、欧米で大ベストセラーとなった古典作品が示す「奴隷制度の残酷さ」
一応書いておくが、「自分も被害者だった」みたいな主張が通るはずのない犯罪者だってもちろんいるし、それまでの生い立ちなどにまったく関係ない身勝手極まりない犯罪も存在する。だから以下の話は、すべての犯罪者に当てはまるわけではない。ただ一方で、「そういう境遇にいなければ罪を犯さなかっただろう人」もいるわけで、私はそんな、映画『プリズン・サークル』や映画『前科者』で描かれるような犯罪者に言及しているのだと理解してほしい。
犯罪に手を染めてしまう人の中には、児童養護施設でいじめられていたとか、親から虐待を受けていたみたいなキツい環境の中で、さらに「誰にも助けを求められなかった」というタイプの人が多いように思う。もちろん、そういう境遇に生まれ育ってもら犯罪に走らない人だっているわけで、「100%境遇のせい」なんて主張は成り立つはずがない。ただ、「そういう境遇にいなければ罪を犯さなかっただろう」ぐらいのことは言ってもいいんじゃないかと思っている。

さて問題は、「根本的な原因を解消しないまま、すべての責任を『犯罪者』に押し付けたところで何も解決しない」ということではないだろうか。「罪を犯した」ことは確かなので、法に則って彼らを刑務所に隔離するのは当然である。しかし、塀の外にいる我々が、「罪を犯した奴が悪いんだから刑務所に入って反省しろ」みたいなスタンスのままでいたら、状況は何も改善されないだろう。なにせ、彼らが犯罪に走ってしまった根本的な原因は放置されたままなのだから。
あわせて読みたい
【奇跡】信念を貫いた男が国の制度を変えた。特別養子縁組を実現させた石巻の産婦人科医の執念:『赤ち…
遊郭で生まれ育った石巻の医師が声を上げ、あらゆる障害をなぎ倒して前進したお陰で「特別養子縁組」の制度が実現した。そんな産婦人科医・菊田昇の生涯を描き出す小説『赤ちゃんをわが子として育てる方を求む』には、法を犯してでも信念を貫いた男の衝撃の人生が描かれている
本作でも、まさにそのような状況が描かれる。具体的には触れないが、本作で描かれる「犯罪」は、「塀の中よりも、外の方にこそ『問題』がある」ことを如実に示すものと言っていいと思う。だから私は、映画『プリズン・サークル』で取り上げられた受刑者が口にした「被害者と認めてもらえなかったら、加害者の自覚が持てない」という言葉に、共感させられてしまったのだ。
誤解されないように書いておくが、私は決して「犯罪者を無罪放免にすべき」などと主張しているのではない。法治国家に生きている以上、どんな理由があろうとも、「罪を犯した」という事実に対しては法が定める罰が与えられるべきだと思っている。しかしそれは、「事件をどう終結させるか」という話でしかない。個々の事件には被害者がいて、物理的・金銭的・精神的な被害が発生してしまう。そして「それらに対し法が裁定を下し、表面的に『事件は終わった』とみなす」というのが「罰則」の意味合いだと私は捉えているのだ。
となればやはり、「社会全体をどう導くか」という観点は薄いと考えるしかないだろう。
あわせて読みたい
【絶望】子供を犯罪者にしないために。「異常者」で片付けられない、希望を見いだせない若者の現実:『…
2人を殺し、7人に重傷を負わせた金川真大に同情の余地はない。しかし、この事件を取材した記者も、私も、彼が殺人に至った背景・動機については理解できてしまう部分がある。『死刑のための殺人』をベースに、「どうしようもないつまらなさ」と共に生きる現代を知る
個々の事件ではなく、社会全体に焦点を当てるのなら、やはり「犯罪をいかに減らすか」が最大の課題になるはずだ。そして、そのためには「根本的な原因」を解消する他ないのだが、それは「犯罪者に罰を与える」というやり方では実現しない。場合によっては「逆効果」ですらあると言えるだろうい。そのことについて、私たちは深く考えなければならないはずだ。
直接的な被害者は、加害者を感情的に恨んで当然だと思うが、そうではない人は「処罰感情」に囚われすぎず、「どうしたら社会全体において犯罪を減らせるか」という方向に思考を切り替えるべきだと思う。もちろん、その方向性に沿った存在として「保護司」がいるのだとは思うが、誰もが保護司のように生きられるわけではない。しかしだとしても、出来ることが無いなんてことはないはずだ。
というか、「罪を犯してしまうような環境を”維持している”」という意味で、我々は間接的に「犯罪者を生み出す社会」に加担していると理解すべきだろう。犯罪の少ない安全な社会を希求するのであれば、私たちはまず、「『犯罪に走ってしまうような環境』をいかにして減らせるか」という観点から犯罪者との関わりを考えるべきだと思う。これこそ”真っ当な人間”のやるべきことではないだろうか。
あわせて読みたい
【性加害】映画『SHE SAID その名を暴け』を観てくれ。#MeToo運動を生んだ報道の舞台裏(出演:キャリ…
「#MeToo」運動のきっかけとなった、ハリウッドの絶対権力者ハーヴェイ・ワインスタインを告発するニューヨーク・タイムズの記事。その取材を担った2人の女性記者の奮闘を描く映画『SHE SAID その名を暴け』は、ジャニー喜多川の性加害問題で揺れる今、絶対に観るべき映画だと思う
映画『前科者』の内容紹介
阿川佳代は、コンビニでのアルバイトの傍ら、犯罪者の更生を支援する保護司としても活動している。保護司は「非常勤の国家公務員」という扱いだが無報酬であり、完全なボランティアだ。出所した元受刑者と定期的に面談を行うのが主な役割で、その過程で大変な状況に巻き込まれることもある。彼女が自らそんな保護司になろうと決めたのには、今も引きずっている過去があるからだ。
さて、佳代は半年前から、仮釈放中の工藤誠という殺人犯を担当している。仮釈放期間中は月に2度の定期報告が義務付けられており、佳代は彼との面談を自宅で行っていた。期間は6ヶ月。その間何も問題がなければ晴れて出所できるという仕組みである。
あわせて読みたい
【あらすじ】死刑囚を救い出す実話を基にした映画『黒い司法』が指摘する、死刑制度の問題と黒人差別の現実
アメリカで死刑囚の支援を行う団体を立ち上げた若者の実話を基にした映画『黒い司法 0%からの奇跡』は、「死刑制度」の存在価値について考えさせる。上映後のトークイベントで、アメリカにおける「死刑制度」と「黒人差別」の結びつきを知り、一層驚かされた
工藤は自動車修理工場で働いていた。彼を雇い入れた社長もその腕前と人柄を買っていて、「仮釈放が終われば社員として迎え入れる」と言ってくれている。とても順調だ。そして工藤は、あと1回定期報告を済ませれば仮釈放が終わるというところまで来ている。本当に、もう少しなのだ。

一方、彼女が住んでいる地域で凶悪事件が発生した。交番勤務の警察官が襲われ、奪われた銃で撃たれてしまったのだ。幸い一命はとりとめたものの、銃は行方不明のまま。そしてその後、犯人が持ち去ったのだろう銃による犯罪が続いていた。
警視庁の刑事である鈴木と滝本は、現場を回って情報を掴もうと奔走するのだが、そもそも被害者同士の繋がりがまったく見えず、捜査は難航する。しかし同一犯のものと目される事件の1つで、ついに物的証拠が取れた。そしてそこから、仮釈放中の工藤誠が捜査線上に浮かぶのだが……。
あわせて読みたい
【感想】殺人事件が決定打となった「GUCCI家の崩壊」の実話を描く映画『ハウス・オブ・グッチ』の衝撃
GUCCI創業家一族の1人が射殺された衝撃の実話を基にした映画『ハウス・オブ・グッチ』。既に創業家一族は誰一人関わっていないという世界的ブランドGUCCIに一体何が起こったのか? アダム・ドライバー、レディー・ガガの演技も見事なリドリー・スコット監督作
映画『前科者』の感想
もしも罪を犯してしまったとしたら、彼女のような保護司と関わりたい
本作『前科者』は、様々な形で「善悪」について考えさせる作品だ。「保護司」というのは決して馴染み深い存在ではなく、恐らくその存在自体を知らない人もいるのではないかと思う。本作はそんな「保護司」を中心にして、「正しい」と「間違い」の境界を絶妙に衝いてくるのである。
あわせて読みたい
【実話】正論を振りかざす人が”強い”社会は窮屈だ。映画『すばらしき世界』が描く「正解の曖昧さ」
「SNSなどでの炎上を回避する」という気持ちから「正論を言うに留めよう」という態度がナチュラルになりつつある社会には、全員が全員の首を締め付け合っているような窮屈さを感じてしまう。西川美和『すばらしき世界』から、善悪の境界の曖昧さを体感する
先述した通り、「法治国家に生きている限り『社会的な正しさ』は法が決する」と言っていいだろう。というか私たちは、「法が決めたことを『正しい』と受け入れて生きていかなければならない」のである。法そのものが誤っていることもあるが、それを是正する仕組みも存在はするし、だから私たちは、「とりあえずは『法の裁定に従って生きること』が求められている」と考えるべきなのだと思う。
しかし、「社会的な正しさ」だけがすべてではない。日常生活においては、そうではない「正しさ」の方が重要な場面も多いだろう。そして本作では、そんな様々な「正しさ」を複層的に描き出すことで、「何が正しいのか分からない」という困惑が積み上がっていくことになる。この点に関しては本作でも、何か分かりやすい結論が提示されるわけではない。観る者に委ねられているというわけだ。
しかしそれはそれとして、佳代の振る舞いや決断からは、「これは正解の1つである」と感じさせるだけの力強さがあるようにも思う。彼女は、自身のある過去をきっかけとして保護司になった。そして、そんな個人的な起点を持つ彼女の生き方は、「これが私なりの正解だ」と突きつけるだけのパワー無しには成立し得ないということなのかもしれない。
あわせて読みたい
【脅迫】原発という巨大権力と闘ったモーリーン・カーニーをイザベル・ユペールが熱演する映画『私はモ…
実話を基にした映画『私はモーリーン・カーニー』は、前半の流れからはちょっと想像もつかないような展開を見せる物語だ。原発企業で従業員の雇用を守る労働組合の代表を務める主人公が、巨大権力に立ち向かった挙げ句に自宅で襲撃されてしまうという物語から、「良き被害者」という捉え方の”狂気”が浮かび上がる
保護司としての彼女のスタンスは、とても気持ちの良いものだ。
本作は、冒頭からなかなか荒々しく始まっていく。担当する元受刑者が仕事に行っていないと判明するのだ。佳代はすぐに元受刑者の家に向かうが、「あの職場は私に合っていない」と言い訳を口にするばかり。そこで彼女はある強硬手段を取り、元受刑者を説得する。
その時に発した言葉がとても良かった。
あなたは今崖っぷちなんです! このままだと、奈落の底に真っ逆さまです。そうなったらもう、助けてあげられなくなってしまいます。
あわせて読みたい
【誠実】戸田真琴は「言葉の人」だ。コンプレックスだらけの人生を「思考」と「行動」で突き進んだ記録…
戸田真琴のエッセイ第2弾『人を心から愛したことがないのだと気づいてしまっても』は、デビュー作以上に「誰かのために言葉を紡ぐ」という決意が溢れた1冊だ。AV女優という自身のあり方を客観的に踏まえた上で、「届くべき言葉がきちんと届く」ために、彼女は身を削ってでも生きる
保護司という役割に真摯に向き合っているからこそ、そんな言葉が口をついて出てきたのだろうなと思う。
あるいは、初めて工藤誠に会った時にも、こんな風に言っていた。
頑張りすぎないで下さいね。大切なのは、「普通」だと思うんです。頑張りすぎてしまったら、それは「普通」ではありません。
あわせて読みたい
【感想】世の中と足並みがそろわないのは「正常が異常」だから?自分の「正常」を守るために:『コンビ…
30代になっても未婚でコンビニアルバイトの古倉さんは、普通から外れたおかしな人、と見られてしまいます。しかし、本当でしょうか?『コンビニ人間』をベースに、多数派の人たちの方が人生を自ら選択していないのではないかと指摘する。
保護司に直接会ったこともなければ、その仕事ぶりを目にする機会もないのであくまでも想像でしかないのだが、佳代が口にする言葉は「元受刑者と向き合う人のもの」っぽくない気がする。「罪を犯してから出会うのは“真っ当な人間”ばかりだった」という元受刑者の言葉を踏まえると、「一般的な保護司」もやはり、「現実は厳しいんだから、ガムシャラに頑張っていきましょう」みたいなことを言うんじゃないだろうか。

そして、それはとてもしんどいだろうと思う。何故なら、「これまで頑張って来なかった」みたいに言われている気がするからだ。頑張って来たのにダメだった人もいるはずだし、色んな事情から頑張りたくても頑張れなかった人だってもいるだろう。だから、「普通でいい」と言ってもらえるのは、ホッとする。私も、万が一犯罪者になるようなことがあれば、阿川佳代のような保護司に出会いたいものだと思う。
阿川佳代にも幸せになってほしい
あわせて読みたい
【苦しい】「恋愛したくないし、興味ない」と気づいた女性が抉る、想像力が足りない社会の「暴力性」:…
「実は私は、恋愛的な関係を求めているわけじゃないかもしれない」と気づいた著者ムラタエリコが、自身の日常や専門学校でも学んだ写真との関わりを基に、「自分に相応しい関係性」や「社会の暴力性」について思考するエッセイ。久々に心にズバズバ刺さった、私にはとても刺激的な1冊だった。
佳代はある場面でこんな風に口にする。
法律や福祉だけではあなたを助けられない。それが現実です。
元受刑者の更生の現実を知らなくても、この点については容易に想像出来るだろう。しかし、「その最大のハードルが『犯罪者になったことのない私たち』にある」という事実は、あまり意識されないんじゃないかと思う。
あわせて読みたい
【葛藤】正論を振りかざしても、「正しさとは何か」に辿り着けない。「絶対的な正しさ」など存在しない…
「『正しさ』は人によって違う」というのは、私には「当たり前の考え」に感じられるが、この前提さえ共有できない社会に私たちは生きている。映画『由宇子の天秤』は、「誤りが含まれるならすべて間違い」という判断が当たり前になされる社会の「不寛容さ」を切り取っていく
本作には、ある人物が「殺人犯は人じゃないよ」と口にする場面がある。どうだろうか、口には出さないにしても、そんな風に感じている人は世の中に結構いるんじゃないだろうか。だからこれは、「世間の声」と言ってもいいのではないかと思う。そして、社会制度は「世間の声」が作ると言っても過言ではないのだから、当然、法律や福祉が「元犯罪者に優しいもの」になったりもしない。そのことに対しては「仕方ない」と思いつつも、同時に、「それで良いはずがない」とも感じる。
佳代が先のセリフに続けて発する言葉からは、とても強い信念が感じられるんじゃないかと思う。また、実際の保護司が何にやりがいを感じているのか知らないが、佳代が別の場面で口にした「人が”生き返る”瞬間に立ち会えるのって凄い」という言葉は、彼女が「自分のため」に保護司を続けていると感じさせるものだった。そのようなことをすべてひっくるめると、「保護司としての彼女の存在」は社会にとって必要不可欠だと言えるだろう。
そしてだからこそ私は、「阿川佳代には『一般的な幸せ』もちゃんと目指してほしい」と感じた。もちろんこれは、単なるおせっかいである。彼女が「保護司としてのやりがい」によって十分な「幸せ」を感じているというのであれば、他人がとやかく言うようなことではないだろう。ただ、ある人物が「恋してる? セックスしてるか?」とぶっ込んでいて、そんな風に言いたくなる感じも分かる。彼女がどんな過去を抱えているにせよ、自分のことを蔑ろにしてまで保護司としての役割を続けるべきではないと私は思う。
彼女のお陰で救われる人は間違いなくいるはずだし、その事実は佳代にとっても非常に重要だろう。しかしそれ以上に、「佳代が救われること」の方が大事だし、そのためにもちゃんと自分の時間を使ってほしいと願わずにはいられなかった。
あわせて読みたい
【壮絶】本当に「美人は得」か?「美しさ」という土俵を意識せざるを得ない少女・女性たちの現実:『自…
美醜で判断されがちな”ルッキズム”の世の中に刃を突きつける小説『自画像』。私自身は、「キレイな人もキレイな人なりの大変さを抱えている」と感じながら生きているつもりだが、やはりその辛さは理解されにくい。私も男性であり、ルッキズムに加担してないとはとても言えない
監督:岸善幸, Writer:岸善幸, 出演:有村架純, 出演:森田剛, 出演:磯村勇斗, 出演:若葉竜也, 出演:マキタスポーツ, 出演:石橋静河, 出演:北村有起哉, 出演:宇野祥平, 出演:リリー・フランキー, 出演:木村多江
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品視聴済】私が観てきた映画(フィクション)を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が観てきた映画(フィクション)を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。
最後に
最後に「どうでもいいこと」に触れてこの記事を終えよう。
私は、特に日本の作品であればエンドロールはちゃんと見る派なのだが(さすがに外国語のエンドロールは辛いが)、本作のエンドロールに「石橋静河」の名前があって驚いた。というのも私には、本作に石橋静河が出てきた記憶がなかったからだ。いや、実は彼女は割と重要な役で出ており、単に私が気づかなかっただけである。しかし本当に、映画の最後まであの人物を演じていたのが石橋静河だとは気づかなかったので、本当に驚かされてしまった。
あわせて読みたい
【信念】9.11後、「命の値段」を計算した男がいた。映画『WORTH』が描く、その凄絶な2年間(主演:マイ…
9.11テロの後、「被害者の『命の値段』を算出した男」がいたことをご存知だろうか?映画『WORTH』では、「被害者遺族のために貢献したい」と無償で難題と向き合うも、その信念が正しく理解されずに反発や対立を招いてしまった現実が描かれる。実話を基にしているとは思えない、凄まじい物語だ
まあそれは本当にどうでもいい話なのだが、本作はとにかく、「元受刑者」と「保護司」との関係を丁寧に描き出すことによって、「社会にとっては何が正しいのか?」「個人にとっては何が正しいのか?」とを突きつける作品である。色々と考えさせられてしまった。
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!「それってホントに『コミュ力』が高いって言えるの?」と疑問を感じている方に…
私は、「コミュ力が高い人」に関するよくある主張に、どうも違和感を覚えてしまうことが多くあります。そしてその一番大きな理由が、「『コミュ力が高い人』って、ただ『想像力がない』だけではないか?」と感じてしまう点にあると言っていいでしょう。出版したKindle本は、「ネガティブには見えないネガティブな人」(隠れネガティブ)を取り上げながら、「『コミュ力』って何だっけ?」と考え直してもらえる内容に仕上げたつもりです。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【壮絶】映画『フロントライン』は「コロナパンデミックの発端」におけるDMATの奮闘をリアルに描く(監…
映画『フロントライン』は、ド級の役者が集ったド級のエンタメ作品でありながら、「フィクションっぽさ」が非常に薄い映画でもあり、「起こった出来事をリアルに描く」という制作陣の覚悟が感じられた。マスコミ報道を通じて知ったつもりになっている「事実」が覆される内容で、あの時の混乱を知るすべての人が観るべき映画だと思う
あわせて読みたい
【狂気】映画『ミッシング』(吉田恵輔監督)は「我が子の失踪」を起点に様々な「嫌な世界」を描く(主…
映画『ミッシング』は、「娘の失踪を機に壊れてしまった母親」を石原さとみが熱演する絶望的な物語である。事件を取材する地元局の記者の葛藤を通じて「『事実』とは何か」「『事実を報じる』ことの難しさ」が突きつけられ、さらに、マスコミを頼るしかない母親の苦悩と相まって状況が混沌とする。ホントに「嫌な世界」だなと思う
あわせて読みたい
【信念】アフガニスタンに中村哲あり。映画『荒野に希望の灯をともす』が描く規格外の功績、生き方
映画『荒野に希望の灯をともす』は、アフガニスタンの支援に生涯を捧げ、個人で実現するなど不可能だと思われた用水路建設によって砂漠を緑地化してしまった中村哲を追うドキュメンタリー映画だ。2019年に凶弾に倒れるまで最前線で人々を先導し続けてきたその圧倒的な存在感に、「彼なき世界で何をすべきか」と考えさせられる
あわせて読みたい
【人生】映画『雪子 a.k.a.』は、言葉は出ないが嘘もないラップ好きの小学校教師の悩みや葛藤を描き出す
「小学校教師」と「ラップ」というなかなか異色の組み合わせの映画『雪子 a.k.a.』は、「ここが凄く良かった」と言えるようなはっきりしたポイントはないのに、ちょっと泣いてしまうぐらい良い映画だった。「口下手だけど嘘はない」という主人公・雪子の日常的な葛藤には、多くの人が共感させられるのではないかと思う
あわせて読みたい
【日々】映画『なみのおと』は、東日本大震災を語る人々の対話を”あり得ない”アングルから撮る(監督:…
映画『なみのおと』は、「東日本大震災の被災者が当時を振り返って対話をする」という内容そのものももちろん興味深いのだが、カメラをどう配置しているのかが分からない、ドキュメンタリー映画としては”あり得ない”映像であることにも驚かされた。また、悲惨な経験を軽妙に語る者たちの雰囲気も印象的な作品である
あわせて読みたい
【正義】名張毒ぶどう酒事件の真相解明の鍵を握る、唯一の再審請求人である妹・岡美代子を追う映画:『…
冤罪と目されている「名張毒ぶどう酒事件」を扱ったドキュメンタリー映画『いもうとの時間』は、逮捕され死刑囚として病死した奥西勝の妹・岡美代子に焦点を当てている。というのも彼女は、「再審請求権」を持つ唯一の人物なのだ。このままでは、事件の真相は闇の中だろう。まずは再審の扉が開かれるべきだと私は思う
あわせて読みたい
【拒絶】映画『ブルータリスト』は、ホロコーストを生き延びた建築家の数奇な人生を描く壮大な物語(監…
映画『ブルータリスト』は、ホロコーストを生き延びたユダヤ人建築家の、アメリカに移り住んで以降の人生を丁寧に追いながら、「ユダヤ人を受け入れないアメリカ」を静かに描き出す物語である。離れ離れにならざるを得なかった妻とのすれ違いにも焦点を当てつつ、時代に翻弄された者たちの悲哀が浮き彫りにされていく
あわせて読みたい
【実話】最低の環境で異次元の結果を出した最高の教師を描く映画『型破りな教室』は超クールだ
映画『型破りな教室』は、メキシコでの実話を基にした信じがたい物語だ。治安最悪な町にある最底辺の小学校に赴任した教師が、他の教師の反対を押し切って独自の授業を行い、結果として、全国テストで1位を取る児童を出すまでになったのである。「考える力」を徹底的に養おうとした主人公の孤軍奮闘がとにかく素晴らしい
あわせて読みたい
【尊厳】映画『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』は、安楽死をテーマに興味深い問いを突きつける(監督:ペ…
全然期待せずに観た映画『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』は、思いがけず面白い作品だった。「安楽死」をテーマにした、ティルダ・スウィントンとジュリアン・ムーアのほぼ2人芝居といったシンプルな作品だが、そこに通底する「死生観」や、「死生観」の違いによるすれ違いなどが実に見事に描かれていて、強く惹きつけられた
あわせて読みたい
【発見】映画『小学校~それは小さな社会~』(山崎エマ)が映し出すのは、我々には日常すぎる日常だ
映画『小学校~それは小さな社会~』は、ごく一般的な公立小学校に密着し、日本で生まれ育った人間には「当たり前」にしか思えない日常を切り取った作品なのだが、そんな映画が諸外国で大いに評価されているという。「TOKKATSU」という「日本式教育」が注目されているらしく、私たちの「当たり前」が違和感だらけに見えているのだそうだ
あわせて読みたい
【変異】映画『動物界』は斬新で刺激的な作品だった。我々はまさにこんな”分断社会”に生きている
映画『動物界』では、「奇病によって人間が動物化してしまう」という世界における複雑な人間模様が描き出される。パンデミックを経験した我々には、本作の設定は「単なるSF」には感じられないはずだ。そしてその上で、「『動物化してしまった妻を今も愛している主人公』が見せる実にややこしい感情」が複層的に描かれていて実に興味深い
あわせて読みたい
【奇妙】映画『画家と泥棒』は、非日常的なきっかけで始まったあり得ないほど奇跡的な関係を描く
映画『画家と泥棒』は、「自身の絵を盗まれた画家が、盗んだ泥棒と親しくなる」という奇妙奇天烈なきっかけから関係性が始まる物語であり、現実に起きたこととは思えないほど不可思議なドキュメンタリーである。アートを通じて奇妙に通じ合う2人の関係性は、ある種の美しささえ感じさせる、とても素晴らしいものに見えた
あわせて読みたい
【絶望】映画『若き見知らぬ者たち』が描くのは”不正解”だが、「じゃあ”正解”って何?」ってなる(監督…
映画『若き見知らぬ者たち』は、「まともな生活が送れなくなった母親の介護」を筆頭に、かなり絶望的な状況に置かれている若者たちを描き出す作品だ。あまりにも不毛で、あまりにも救いがなく、あまりにも辛すぎるその日々は、ついに限界を迎える。そしてその絶望を、磯村勇斗がその凄まじい存在感によって体現していく
あわせて読みたい
【異様】映画『大いなる不在』(近浦啓)は、認知症の父を中心に「記憶」と「存在」の複雑さを描く(主…
「父親が逮捕され、どうやら認知症のようだ」という一報を受けた息子が、30年間ほぼやり取りのなかった父親と再会するところから始まる映画『大いなる不在』は、なんとも言えない「不穏さ」に満ちた物語だった。「記憶」と「存在」のややこしさを問う本作は、「物語」としては成立していないが、圧倒的な“リアリティ”に満ちている
あわせて読みたい
【面白い】映画『ラストマイル』は、物流問題をベースに「起こり得るリアル」をポップに突きつける(監…
映画『ラストマイル』は、「物流」という「ネット社会では誰にでも関係し得る社会問題」に斬り込みながら、実に軽妙でポップな雰囲気で展開されるエンタメ作品である。『アンナチュラル』『MIU404』と同じ世界で展開される「シェアード・ユニバース」も話題で、様々な人の関心を広く喚起する作品と言えるだろう
あわせて読みたい
【実話】株仲買人が「イギリスのシンドラー」に。映画『ONE LIFE』が描くユダヤ難民救出(主演:アンソ…
実話を基にした映画『ONE LIFE 奇跡が繋いだ6000の命』は、「イギリスに住むニコラス・ウィントンがチェコのユダヤ人難民を救う」という話であり、仲間と共に669名も救助した知られざる偉業が扱われている。多くの人に知られるべき歴史だと思うし、また、主演を務めたアンソニー・ホプキンスの演技にも圧倒されてしまった
あわせて読みたい
【あらすじ】杉咲花と安田顕が圧巻!映画『朽ちないサクラ』(原廣利)は「正義の難しさ」を描く(原作…
柚月裕子の同名小説を原作とした映画『朽ちないサクラ』は、とにかく杉咲花と安田顕の演技に圧倒されてしまった作品だ。「トロッコ問題」を連想させる非常に難しい状況を提示することで「正義の難しさ」を描き出す展開も素晴らしいし、主人公・森口泉を演じた杉咲花の「絶望を静かに体現する演技」も見事だった
あわせて読みたい
【絶望】知られざる「国による嘘」!映画『蟻の兵隊』(池谷薫)が映し出す終戦直後の日本の欺瞞
映画『蟻の兵隊』は、「1945年8月15日の終戦以降も上官の命令で中国に残らされ、中国の内戦を闘った残留日本軍部隊」の1人である奥村和一を追うドキュメンタリー映画だ。「自らの意思で残った」と判断された彼らは、国からの戦後補償を受けられていない。そんな凄まじい現実と、奥村和一の驚くべき「誠実さ」が描かれる作品である
あわせて読みたい
【現在】ウーマンラッシュアワー村本大輔がテレビから消えた理由と彼の”優しさ”を描く映画:『アイアム…
「テレビから消えた」と言われるウーマンラッシュアワー・村本大輔に密着する映画『アイアム・ア・コメディアン』は、彼に対してさほど関心を抱いていない人でも面白く観られるドキュメンタリー映画だと思う。自身の存在意義を「拡声器」のように捉え、様々な社会問題を「お笑い」で発信し続ける姿には、静かな感動さえ抱かされるだろう
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『52ヘルツのクジラたち』の「無音で叫ぶ人」と「耳を澄ます人」の絶妙な響鳴(原作:…
映画『52ヘルツのクジラたち』は、「現代的な問題のごった煮」と感じられてしまうような”過剰さ”に溢れてはいますが、タイトルが作品全体を絶妙に上手くまとめていて良かったなと思います。主演の杉咲花がやはり見事で、身体の内側から「不幸」が滲み出ているような演技には圧倒されてしまいました
あわせて読みたい
【幻惑】映画『落下の解剖学』は、「真実は誰かが”決める”しかない」という現実の不安定さを抉る
「ある死」を巡って混沌とする状況をリアルに描き出す映画『落下の解剖学』は、「客観的な真実にはたどり着けない」という困難さを炙り出す作品に感じられた。事故なのか殺人なのか自殺なのか、明確な証拠が存在しない状況下で、憶測を繋ぎ合わせるようにして進行する「裁判」の様子から、「『真実性』の捉えがたさ」がよく理解できる
あわせて読みたい
【赦し】映画『過去負う者』が描く「元犯罪者の更生」から、社会による排除が再犯を生む現実を知る
映画『過去負う者』は、冒頭で「フィクション」だと明示されるにも拘らず、観ながら何度も「ドキュメンタリーだっけ?」と感じさせられるという、実に特異な体験をさせられた作品である。実在する「元犯罪者の更生を支援する団体」を舞台にした物語で、当然それは、私たち一般市民にも無関係ではない話なのだ
あわせて読みたい
【挑戦】映画『燃えあがる女性記者たち』が描く、インドカースト最下位・ダリットの女性による報道
映画『燃えあがる女性記者たち』は、インドで「カースト外の不可触民」として扱われるダリットの女性たちが立ち上げた新聞社「カバル・ラハリヤ」を取り上げる。自身の境遇に抗って、辛い状況にいる人の声を届けたり権力者を糾弾したりする彼女たちの奮闘ぶりが、インドの民主主義を変革させるかもしれない
あわせて読みたい
【狂気】ISISから孫を取り戻せ!映画『”敵”の子どもたち』が描くシリアの凄絶な現実
映画『”敵”の子どもたち』では、私がまったく知らなかった凄まじい現実が描かれる。イスラム過激派「ISIS」に望んで参加した女性の子ども7人を、シリアから救出するために奮闘する祖父パトリシオの物語であり、その最大の障壁がなんと自国のスウェーデン政府なのだる。目眩がするような、イカれた現実がここにある
あわせて読みたい
【斬新】フィクション?ドキュメンタリー?驚きの手法で撮られた、現実と虚構が入り混じる映画:『最悪…
映画『最悪な子どもたち』は、最後まで観てもフィクションなのかドキュメンタリーなのか確信が持てなかった、普段なかなか抱くことのない感覚がもたらされる作品だった。「演技未経験」の少年少女を集めての撮影はかなり実験的に感じられたし、「分からないこと」に惹かれる作品と言えるいだろうと思う
あわせて読みたい
【脅迫】原発という巨大権力と闘ったモーリーン・カーニーをイザベル・ユペールが熱演する映画『私はモ…
実話を基にした映画『私はモーリーン・カーニー』は、前半の流れからはちょっと想像もつかないような展開を見せる物語だ。原発企業で従業員の雇用を守る労働組合の代表を務める主人公が、巨大権力に立ち向かった挙げ句に自宅で襲撃されてしまうという物語から、「良き被害者」という捉え方の”狂気”が浮かび上がる
あわせて読みたい
【絶望】杉咲花主演映画『市子』の衝撃。毎日がしんどい「どん底の人生」を生き延びるための壮絶な決断…
映画『市子』はまず何よりも主演を務めた杉咲花に圧倒させられる作品だ。そしてその上で、主人公・川辺市子を巡る物語にあれこれと考えさせられてしまった。「川辺市子」は決してフィクショナルな存在ではなく、現実に存在し得る。本作は、そのような存在をリアルに想像するきっかけにもなるだろう
あわせて読みたい
【実話】映画『月』(石井裕也)は、障害者施設での虐待事件から「見て見ぬふりする社会」を抉る(出演…
実際に起こった障害者施設殺傷事件を基にした映画『月』(石井裕也)は、観客を作中世界に引きずり込み、「これはお前たちの物語だぞ」と刃を突きつける圧巻の作品だ。「意思疎通が不可能なら殺していい」という主張には誰もが反対するはずだが、しかしその態度は、ブーメランのように私たちに戻ってくることになる
あわせて読みたい
【感想】映画『キリエのうた』(岩井俊二)はアイナ・ジ・エンドに圧倒されっ放しの3時間だった(出演:…
映画『キリエのうた』(岩井俊二監督)では、とにかくアイナ・ジ・エンドに圧倒されてしまった。歌声はもちろんのことながら、ただそこにいるだけで場を支配するような存在感も凄まじい。全編に渡り「『仕方ないこと』はどうしようもなく起こるんだ」というメッセージに溢れた、とても力強い作品だ
あわせて読みたい
【嫌悪】映画『ドライビング・バニー』が描く、人生やり直したい主人公(母親)のウザさと絶望
映画『ドライビング・バニー』は、主人公であるバニーのことが最後まで嫌いだったにも拘わらず、全体的にはとても素敵に感じられた珍しいタイプの作品だ。私は、「バニーのような人間が世の中に存在する」という事実に嫌悪感を抱いてしまうのだが、それでも、狂気的でぶっ飛んだラストシーンによって、作品全体の印象が大きく変わったと言える
あわせて読みたい
【実話】アメリカの有名なシリアルキラーを基にした映画『グッド・ナース』の理解を拒む凄まじさ(主演…
実際に起こった連続殺人事件を基にした映画『グッド・ナース』は、「何が描かれているのか分からない」という不穏さがずっと付きまとう異様な作品だった。「事件そのもの」ではなく、ある2人の人物に焦点が当てられる展開から、人間のあまりに深淵な狂気と葛藤が抉り出されている
あわせて読みたい
【信念】凄いな久遠チョコレート!映画『チョコレートな人々』が映す、障害者雇用に挑む社長の奮闘
重度の人たちも含め、障害者を最低賃金保証で雇用するというかなり無謀な挑戦を続ける夏目浩次を追う映画『チョコレートな人々』には衝撃を受けた。キレイゴトではなく、「障害者を真っ当に雇用したい」と考えて「久遠チョコレート」を軌道に乗せたとんでもない改革者の軌跡を追うドキュメンタリー
あわせて読みたい
【天才】映画『Winny』(松本優作監督)で知った、金子勇の凄さと著作権法侵害事件の真相(ビットコイン…
稀代の天才プログラマー・金子勇が著作権法違反で逮捕・起訴された実話を描き出す映画『Winny』は、「警察の凄まじい横暴」「不用意な天才と、テック系知識に明るい弁護士のタッグ」「Winnyが明らかにしたとんでもない真実」など、見どころは多い。「金子勇=サトシ・ナカモト」説についても触れる
あわせて読みたい
【狂気?】オウム真理教を内部から映す映画『A』(森達也監督)は、ドキュメンタリー映画史に残る衝撃作だ
ドキュメンタリー映画の傑作『A』(森達也)をようやく観られた。「オウム真理教は絶対悪だ」というメディアの報道が凄まじい中、オウム真理教をその内部からフラットに映し出した特異な作品は、公開当時は特に凄まじい衝撃をもたらしただろう。私たちの「当たり前」が解体されていく斬新な一作
あわせて読みたい
【実話】映画『グリーンブック』は我々に問う。当たり前の行動に「差別意識」が含まれていないか、と
黒人差別が遥かに苛烈だった時代のアメリカにおいて、黒人ピアニストと彼に雇われた白人ドライバーを描く映画『グリーンブック』は、観客に「あなたも同じような振る舞いをしていないか?」と突きつける作品だ。「差別」に限らず、「同時代の『当たり前』に従った行動」について考え直させる1作
あわせて読みたい
【居場所】菊地凛子主演映画『658km、陽子の旅』(熊切和嘉)は、引きこもりロードムービーの傑作
映画『658km、陽子の旅』は、主演の菊地凛子の存在感が圧倒的だった。夢破れて長年引きこもり続けている女性が、否応なしにヒッチハイクで弘前を目指さなければならなくなるロードムービーであり、他人や社会と関わることへの葛藤に塗れた主人公の変化が、とても「勇敢」なものに映る
あわせて読みたい
【純真】ゲイが犯罪だった時代が舞台の映画『大いなる自由』は、刑務所内での極深な人間ドラマを描く
男性同士の恋愛が犯罪であり、ゲイの男性が刑法175条を理由に逮捕されてしまう時代のドイツを描いた映画『大いなる自由』は、確かに同性愛の物語なのだが、実はそこに本質はない。物語の本質は、まさにタイトルにある通り「自由」であり、ラストシーンで突きつけられるその深い問いかけには衝撃を受けるだろう
あわせて読みたい
【傑物】フランスに最も愛された政治家シモーヌ・ヴェイユの、強制収容所から国連までの凄絶な歩み:映…
「フランスに最も愛された政治家」と評されるシモーヌ・ヴェイユ。映画『シモーヌ』は、そんな彼女が強制収容所を生き延び、後に旧弊な社会を変革したその凄まじい功績を描き出す作品だ。「強制収容所からの生還が失敗に思える」とさえ感じたという戦後のフランスの中で、彼女はいかに革新的な歩みを続けたのか
あわせて読みたい
【おすすめ】柚月裕子『慈雨』は、「守るべきもの」と「過去の過ち」の狭間の葛藤から「正義」を考える小説
柚月裕子の小説『慈雨』は、「文庫X」として知られる『殺人犯はそこにいる』で扱われている事件を下敷きにしていると思われる。主人公の元刑事が「16年前に犯してしまったかもしれない過ち」について抱き続けている葛藤にいかに向き合い、どう決断し行動に移すのかの物語
あわせて読みたい
【実話】ポートアーサー銃乱射事件を扱う映画『ニトラム』が示す、犯罪への傾倒に抗えない人生の不条理
オーストラリアで実際に起こった銃乱射事件の犯人の生い立ちを描く映画『ニトラム/NITRAM』は、「頼むから何も起こらないでくれ」と願ってしまうほどの異様な不穏さに満ちている。「社会に順応できない人間」を社会がどう受け入れるべきかについて改めて考えさせる作品だ
あわせて読みたい
【解説】実話を基にした映画『シカゴ7裁判』で知る、「権力の暴走」と、それに正面から立ち向かう爽快さ
ベトナム戦争に反対する若者たちによるデモと、その後開かれた裁判の実話を描く『シカゴ7裁判』はメチャクチャ面白い映画だった。無理筋の起訴を押し付けられる主席検事、常軌を逸した言動を繰り返す不適格な判事、そして一枚岩にはなれない被告人たち。魅力満載の1本だ
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』で描かれる、グアンタナモ”刑務所”の衝撃の実話は必見
ベネディクト・カンバーバッチが制作を熱望した衝撃の映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』は、アメリカの信じがたい実話を基にしている。「9.11の首謀者」として不当に拘束され続けた男を「救おうとする者」と「追い詰めようとする者」の奮闘が、「アメリカの闇」を暴き出す
あわせて読みたい
【執念】「桶川ストーカー事件」で警察とマスコミの怠慢を暴き、社会を動かした清水潔の凄まじい取材:…
『殺人犯はそこにいる』(文庫X)で凄まじい巨悪を暴いた清水潔は、それよりずっと以前、週刊誌記者時代にも「桶川ストーカー殺人事件」で壮絶な取材を行っていた。著者の奮闘を契機に「ストーカー規制法」が制定されたほどの事件は、何故起こり、どんな問題を喚起したのか
あわせて読みたい
【あらすじ】ムロツヨシ主演映画『神は見返りを求める』の、”善意”が”悪意”に豹変するリアルが凄まじい
ムロツヨシ演じる田母神が「お人好し」から「復讐の権化」に豹変する映画『神は見返りを求める』。「こういう状況は、実際に世界中で起こっているだろう」と感じさせるリアリティが見事な作品だった。「善意」があっさりと踏みにじられる世界を、私たちは受け容れるべきだろうか?
あわせて読みたい
【感想】阿部サダヲが狂気を怪演。映画『死刑にいたる病』が突きつける「生きるのに必要なもの」の違い
サイコパスの連続殺人鬼・榛村大和を阿部サダヲが演じる映画『死刑にいたる病』は、「生きていくのに必要なもの」について考えさせる映画でもある。目に光を感じさせない阿部サダヲの演技が、リアリティを感じにくい「榛村大和」という人物を見事に屹立させる素晴らしい映画
あわせて読みたい
【魅惑】バーバラ・ローデン監督・脚本・主演の映画『WANDA』の、70年代の作品とは思えない今感
映画館で観た予告が気になって、それ以外の情報を知らずに観に行った映画『WANDA』なんと70年代の映画だと知って驚かされた。まったく「古さ」を感じなかったからだ。主演だけでなく、監督・脚本も務めたバーバラ・ローデンが遺した、死後評価が高まった歴史的一作
あわせて読みたい
【奇跡】信念を貫いた男が国の制度を変えた。特別養子縁組を実現させた石巻の産婦人科医の執念:『赤ち…
遊郭で生まれ育った石巻の医師が声を上げ、あらゆる障害をなぎ倒して前進したお陰で「特別養子縁組」の制度が実現した。そんな産婦人科医・菊田昇の生涯を描き出す小説『赤ちゃんをわが子として育てる方を求む』には、法を犯してでも信念を貫いた男の衝撃の人生が描かれている
あわせて読みたい
【差別】映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』の衝撃。プーチンが支持する国の蛮行・LGBT狩り
プーチン大統領の後ろ盾を得て独裁を維持しているチェチェン共和国。その国で「ゲイ狩り」と呼ぶしかない異常事態が継続している。映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』は、そんな現実を命がけで映し出し、「現代版ホロコースト」に立ち向かう支援団体の奮闘も描く作品
あわせて読みたい
【あらすじ】死刑囚を救い出す実話を基にした映画『黒い司法』が指摘する、死刑制度の問題と黒人差別の現実
アメリカで死刑囚の支援を行う団体を立ち上げた若者の実話を基にした映画『黒い司法 0%からの奇跡』は、「死刑制度」の存在価値について考えさせる。上映後のトークイベントで、アメリカにおける「死刑制度」と「黒人差別」の結びつきを知り、一層驚かされた
あわせて読みたい
【悲劇】アメリカの暗黒の歴史である奴隷制度の現実を、元奴隷の黒人女性自ら赤裸々に語る衝撃:『ある…
生まれながらに「奴隷」だった黒人女性が、多くの人の協力を得て自由を手にし、後に「奴隷制度」について書いたのが『ある奴隷少女に起こった出来事』。長らく「白人が書いた小説」と思われていたが、事実だと証明され、欧米で大ベストセラーとなった古典作品が示す「奴隷制度の残酷さ」
あわせて読みたい
【選択】特異な疑似家族を描く韓国映画『声もなく』の、「家族とは?」の本質を考えさせる深淵さ
喋れない男が、誘拐した女の子をしばらく匿い、疑似家族のような関係を築く韓国映画『声もなく』は、「映画の中で描かれていない部分」が最も印象に残る作品だ。「誘拐犯」と「被害者」のあり得ない関係性に、不自然さをまったく抱かせない設定・展開の妙が見事な映画
あわせて読みたい
【実話】台湾のろう学校のいじめ・性的虐待事件を描く映画『無聲』が問う、あまりに悲しい現実
台湾のろう学校で実際に起こったいじめ・性的虐待事件を基に作られた映画『無聲』は、健常者の世界に刃を突きつける物語だ。これが実話だという事実に驚かされる。いじめ・性的虐待が物語の「大前提」でしかないという衝撃と、「性的虐待の方がマシ」という選択を躊躇せず行う少女のあまりの絶望を描き出す
あわせて読みたい
【事件】デュポン社のテフロン加工が有害だと示した男の執念の実話を描く映画『ダーク・ウォーターズ』
世界的大企業デュポン社が、自社製品「テフロン」の危険性を40年以上前に把握しながら公表せず、莫大な利益を上げてきた事件の真相を暴き出した1人の弁護士がいる。映画『ダーク・ウォーターズ』は、大企業相手に闘いを挑み、住民と正義のために走り続けた実在の人物の勇敢さを描き出す
あわせて読みたい
【衝撃】映画『ダンサー・イン・ザ・ダーク』凄い。ラストの衝撃、ビョークの演技、”愛”とは呼びたくな…
言わずとしれた名作映画『ダンサー・イン・ザ・ダーク』を、ほぼ予備知識ゼロのまま劇場で観た。とんでもない映画だった。苦手なミュージカルシーンが効果的だと感じられたこと、「最低最悪のラストは回避できたはずだ」という想い、そして「セルマのような人こそ報われてほしい」という祈り
あわせて読みたい
【衝撃】洗脳を自ら脱した著者の『カルト脱出記』から、「社会・集団の洗脳」を避ける生き方を知る
「聖書研究に熱心な日本人証人」として「エホバの証人」で活動しながら、その聖書研究をきっかけに自ら「洗脳」を脱した著者の体験を著した『カルト脱出記』。広い意味での「洗脳」は社会のそこかしこに蔓延っているからこそ、著者の体験を「他人事」だと無視することはできない
あわせて読みたい
【不安】環境活動家グレタを追う映画。「たったひとりのストライキ」から国連スピーチまでの奮闘と激変…
環境活動家であるグレタのことを、私はずっと「怒りの人」「正義の人」だとばかり思っていた。しかしそうではない。彼女は「不安」から、いても立ってもいられずに行動を起こしただけなのだ。映画『グレタ ひとりぼっちの挑戦』から、グレタの実像とその強い想いを知る
あわせて読みたい
【理解】小野田寛郎を描く映画。「戦争終結という現実を受け入れない(=認知的不協和)」は他人事じゃ…
映画『ONODA 一万夜を越えて』を観るまで、小野田寛郎という人間に対して違和感を覚えていた。「戦争は終わっていない」という現実を生き続けたことが不自然に思えたのだ。しかし映画を観て、彼の生き方・決断は、私たちと大きく変わりはしないと実感できた
あわせて読みたい
【選択】映画『サウンド・オブ・メタル』で難聴に陥るバンドマンは、「障害」と「健常」の境界で揺れる
ドラムを叩くバンドマンが聴力を失ってしまう――そんな厳しい現実に直面する主人公を描く映画『サウンド・オブ・メタル』では、「『健常者との生活』を選ぶか否か」という選択が突きつけられる。ある意味では健常者にも向けられているこの問いに、どう答えるべきだろうか
あわせて読みたい
【信念】水俣病の真実を世界に伝えた写真家ユージン・スミスを描く映画。真実とは「痛みへの共感」だ:…
私はその存在をまったく知らなかったが、「水俣病」を「世界中が知る公害」にした報道写真家がいる。映画『MINAMATA―ミナマタ―』は、水俣病の真実を世界に伝えたユージン・スミスの知られざる生涯と、理不尽に立ち向かう多くの人々の奮闘を描き出す
あわせて読みたい
【葛藤】正論を振りかざしても、「正しさとは何か」に辿り着けない。「絶対的な正しさ」など存在しない…
「『正しさ』は人によって違う」というのは、私には「当たり前の考え」に感じられるが、この前提さえ共有できない社会に私たちは生きている。映画『由宇子の天秤』は、「誤りが含まれるならすべて間違い」という判断が当たり前になされる社会の「不寛容さ」を切り取っていく
あわせて読みたい
【喪失】家族とうまくいかない人、そして、家族に幻想を抱いてしまう人。家族ってなんてめんどくさいの…
「福島中央テレビ開局50周年記念作品」である映画『浜の朝日の嘘つきどもと』は、福島県に実在した映画館「朝日座」を舞台に、住民が抱く「希望(幻想)」が描かれる。震災・コロナによってありとあらゆるものが失われていく世の中で、私たちはどう生きるべきか
あわせて読みたい
【衝撃】『殺人犯はそこにいる』が実話だとは。真犯人・ルパンを野放しにした警察・司法を信じられるか?
タイトルを伏せられた覆面本「文庫X」としても話題になった『殺人犯はそこにいる』。「北関東で起こったある事件の取材」が、「私たちが生きる社会の根底を揺るがす信じがたい事実」を焙り出すことになった衝撃の展開。まさか「司法が真犯人を野放しにする」なんてことが実際に起こるとは。大げさではなく、全国民必読の1冊だと思う
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『流浪の月』を観て感じた、「『見て分かること』にしか反応できない世界」への気持ち悪さ
私は「見て分かること」に”しか”反応できない世界に日々苛立ちを覚えている。そういう社会だからこそ、映画『流浪の月』で描かれる文と更紗の関係も「気持ち悪い」と断罪されるのだ。私はむしろ、どうしようもなく文と更紗の関係を「羨ましい」と感じてしまう。
あわせて読みたい
【矛盾】法律の”抜け穴”を衝く驚愕の小説。「ルールを通り抜けたものは善」という発想に潜む罠:『法廷…
完璧なルールは存在し得ない。だからこそ私たちは、矛盾を内包していると理解しながらルールを遵守する必要がある。「ルールを通り抜けたものは善」という”とりあえずの最善解”で社会を回している私たちに、『法廷遊戯』は「世界を支える土台の脆さ」を突きつける
あわせて読みたい
【感想】映画『竜とそばかすの姫』が描く「あまりに批判が容易な世界」と「誰かを助けることの難しさ」
SNSの登場によって「批判が容易な社会」になったことで、批判を恐れてポジティブな言葉を口にしにくくなってしまった。そんな世の中で私は、「理想論だ」と言われても「誰かを助けたい」と発信する側の人間でいたいと、『竜とそばかすの姫』を観て改めて感じさせられた
あわせて読みたい
【正義】復讐なんかに意味はない。それでも「この復讐は正しいかもしれない」と思わされる映画:『プロ…
私は基本的に「復讐」を許容できないが、『プロミシング・ヤング・ウーマン』の主人公キャシーの行動は正当化したい。法を犯す明らかにイカれた言動なのだが、その動機は一考の余地がある。何も考えずキャシーを非難していると、矢が自分の方に飛んでくる、恐ろしい作品
あわせて読みたい
【勇敢】ユダヤ人を救った杉原千畝を描く映画。日本政府の方針に反しながら信念を貫いた男の生き様
日本政府の方針に逆らってまでユダヤ人のためにビザを発給し続けた外交官を描く映画『杉原千畝』。日本を良くしたいと考えてモスクワを夢見た青年は、何故キャリアを捨てる覚悟で「命のビザ」を発給したのか。困難な状況を前に、いかに決断するかを考えさせられる
あわせて読みたい
【生きる】しんどい人生を宿命付けられた子どもはどう生きるべき?格差社会・いじめ・恋愛を詰め込んだ…
厳しい受験戦争、壮絶な格差社会、残忍ないじめ……中国の社会問題をこれでもかと詰め込み、重苦しさもありながら「ボーイ・ミーツ・ガール」の爽やかさも融合されている映画『少年の君』。辛い境遇の中で、「すべてが最悪な選択肢」と向き合う少年少女の姿に心打たれる
あわせて読みたい
【驚愕】これ以上の”サバイバル映画”は存在するか?火星にたった一人残された男の生存術と救出劇:『オ…
1人で火星に取り残された男のサバイバルと救出劇を、現実的な科学技術の範囲で描き出す驚異の映画『オデッセイ』。不可能を可能にするアイデアと勇気、自分や他人を信じ抜く気持ち、そして極限の状況でより困難な道を進む決断をする者たちの、想像を絶するドラマに胸打たれる
あわせて読みたい
【実話】映画『ハドソン川の奇跡』の”糾弾された英雄”から、「正しさ」をどう「信じる」かを考える
制御不能の飛行機をハドソン川に不時着させ、乗員乗客155名全員の命を救った英雄はその後、「わざと機体を沈め損害を与えたのではないか」と疑われてしまう。映画『ハドソン川の奇跡』から、「正しさ」の難しさと、「『正しさ』の枠組み」の重要性を知る
あわせて読みたい
【死】映画『湯を沸かすほどの熱い愛』に号泣。「家族とは?」を問う物語と、タイトル通りのラストが見事
「死は特別なもの」と捉えてしまうが故に「日常感」が失われ、普段の生活から「排除」されているように感じてしまうのは私だけではないはずだ。『湯を沸かすほどの熱い愛』は、「死を日常に組み込む」ことを当たり前に許容する「家族」が、「家族」の枠組みを問い直す映画である
あわせて読みたい
【驚愕】あるジャーナリストの衝撃の実話を描く映画『凶悪』。「死刑囚の告発」から「正義」を考える物語
獄中の死刑囚が警察に明かしていない事件を雑誌記者に告発し、「先生」と呼ばれる人物を追い詰めた実際の出来事を描くノンフィクションを原作にして、「ジャーナリズムとは?」「家族とは?」を問う映画『凶悪』は、原作とセットでとにかく凄まじい作品だ
あわせて読みたい
【驚異】信念を貫く勇敢さを、「銃を持たずに戦場に立つ」という形で示した実在の兵士の凄まじさ:映画…
第二次世界大戦で最も過酷な戦場の1つと言われた「前田高地(ハクソー・リッジ)」を、銃を持たずに駆け回り信じがたい功績を残した衛生兵がいた。実在の人物をモデルにした映画『ハクソー・リッジ』から、「戦争の悲惨さ」だけでなく、「信念を貫くことの大事さ」を学ぶ
あわせて読みたい
【実話】権力の濫用を監視するマスコミが「教会の暗部」を暴く映画『スポットライト』が現代社会を斬る
地方紙である「ボストン・グローブ紙」は、数多くの神父が長年に渡り子どもに対して性的虐待を行い、その事実を教会全体で隠蔽していたという衝撃の事実を明らかにした。彼らの奮闘の実話を映画化した『スポットライト』から、「権力の監視」の重要性を改めて理解する
あわせて読みたい
【実話】映画『イミテーションゲーム』が描くエニグマ解読のドラマと悲劇、天才チューリングの不遇の死
映画『イミテーションゲーム』が描く衝撃の実話。「解読不可能」とまで言われた最強の暗号機エニグマを打ち破ったのはなんと、コンピューターの基本原理を生み出した天才数学者アラン・チューリングだった。暗号解読を実現させた驚きのプロセスと、1400万人以上を救ったとされながら偏見により自殺した不遇の人生を知る
あわせて読みたい
【正義】「正しさとは何か」を考えさせる映画『スリー・ビルボード』は、正しさの対立を絶妙に描く
「正しい」と主張するためには「正しさの基準」が必要だが、それでも「規制されていないことなら何でもしていいのか」は問題になる。3枚の立て看板というアナログなツールを使って現代のネット社会の現実をあぶり出す映画『スリー・ビルボード』から、「『正しさ』の難しさ」を考える
あわせて読みたい
【想像力】「知らなかったから仕方ない」で済ませていいのか?第二の「光州事件」は今もどこかで起きて…
「心地いい情報」だけに浸り、「知るべきことを知らなくても恥ずかしくない世の中」を生きてしまっている私たちは、世界で何が起こっているのかあまりに知らない。「光州事件」を描く映画『タクシー運転手 約束は海を越えて』から、世界の見方を考える
あわせて読みたい
【矛盾】その”誹謗中傷”は真っ当か?映画『万引き家族』から、日本社会の「善悪の判断基準」を考える
どんな理由があれ、法を犯した者は罰せられるべきだと思っている。しかしそれは、善悪の判断とは関係ない。映画『万引き家族』(是枝裕和監督)から、「国民の気分」によって「善悪」が決まる社会の是非と、「善悪の判断を保留する勇気」を持つ生き方について考える
あわせて読みたい
【矛盾】死刑囚を「教誨師」視点で描く映画。理解が及ばない”死刑という現実”が突きつけられる
先進国では数少なくなった「死刑存置国」である日本。社会が人間の命を奪うことを許容する制度は、果たして矛盾なく存在し得るのだろうか?死刑確定囚と対話する教誨師を主人公に、死刑制度の実状をあぶり出す映画『教誨師』から、死刑という現実を理解する
あわせて読みたい
【実話】障害者との接し方を考えさせる映画『こんな夜更けにバナナかよ』から”対等な関係”の大事さを知る
「障害者だから◯◯だ」という決まりきった捉え方をどうしてもしてしまいがちですが、『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』の主人公・鹿野靖明の生き様を知れば、少しは考え方が変わるかもしれません。筋ジストロフィーのまま病院・家族から離れて“自活”する決断をした驚異の人生
あわせて読みたい
【興奮】飲茶氏の超面白い哲学小説。「正義とは?」の意味を問う”3人の女子高生”の主張とは?:『正義の…
なんて面白いんだろうか。哲学・科学を初心者にも分かりやすく伝える飲茶氏による『正義の教室』は、哲学書でありながら、3人の女子高生が登場する小説でもある。「直観主義」「功利主義」「自由主義」という「正義論」の主張を、「高校の問題について議論する生徒会の話し合い」から学ぶ
あわせて読みたい
【レッテル】コミュニケーションで大事なのは、肩書や立場を外して、相手を”その人”として見ることだ:…
私は、それがポジティブなものであれ、「レッテル」で見られることは嫌いです。主人公の1人、障害を持つ大富豪もまたそんなタイプ。傍若無人な元犯罪者デルとの出会いでフィリップが変わっていく『THE UPSIDE 最強のふたり』からコミュニケーションを学ぶ
あわせて読みたい
【勇敢】”報道”は被害者を生む。私たちも同罪だ。”批判”による”正義の実現”は正義だろうか?:『リチャ…
「爆弾事件の被害を最小限に食い止めた英雄」が、メディアの勇み足のせいで「爆弾事件の犯人」と報じられてしまった実話を元にした映画『リチャード・ジュエル』から、「他人を公然と批判する行為」の是非と、「再発防止という名の正義」のあり方について考える
あわせて読みたい
【権利】衝撃のドキュメンタリー映画『ヤクザと憲法』は、「異質さを排除する社会」と「生きる権利」を問う
「ヤクザ」が排除された現在でも、「ヤクザが担ってきた機能」が不要になるわけじゃない。ではそれを、公権力が代替するのだろうか?実際の組事務所(東組清勇会)にカメラを持ち込むドキュメンタリー映画『ヤクザと憲法』が映し出す川口和秀・松山尚人・河野裕之の姿から、「基本的人権」のあり方について考えさせられた
あわせて読みたい
【人生】どう生きるべきかは、どう死にたいかから考える。死ぬ直前まで役割がある「理想郷」を描く:『…
「近隣の村から『姥捨て』と非難される理想郷」を描き出す『でんでら国』は、「死ぬ直前まで、コミュニティの中で役割が存在する」という世界で展開される物語。「お金があっても決して豊かとは言えない」という感覚が少しずつ広まる中で、「本当の豊かさ」とは何かを考える
あわせて読みたい
【真実?】佐村河内守のゴーストライター騒動に森達也が斬り込んだ『FAKE』は我々に何を問うか?
一時期メディアを騒がせた、佐村河内守の「ゴースト問題」に、森達也が斬り込む。「耳は聴こえないのか?」「作曲はできるのか?」という疑惑を様々な角度から追及しつつ、森達也らしく「事実とは何か?」を問いかける『FAKE』から、「事実の捉え方」について考える
あわせて読みたい
【告発】アメリカに”監視”される社会を暴露したスノーデンの苦悩と決断を映し出す映画:『スノーデン』…
NSA(アメリカ国家安全保障局)の最高機密にまでアクセスできたエドワード・スノーデンは、その機密情報を持ち出し内部告発を行った。「アメリカは世界中の通信を傍受している」と。『シチズンフォー』と『スノーデン』の2作品から、彼の告発内容とその葛藤を知る
あわせて読みたい
【多様性】神童から引きこもりになり、なんとか脱出したお笑い芸人が望む、誰も責められない社会:『ヒ…
お笑い芸人・髭男爵の山田ルイ53世は、“神童”と呼ばれるほど優秀だったが、“うんこ”をきっかけに6年間引きこもった。『ヒキコモリ漂流記』で彼は、ひきこもりに至ったきっかけ、ひきこもり中の心情、そしてそこからいかに脱出したのかを赤裸々に綴り、「誰にも優しい世界」を望む
あわせて読みたい
【危機】教員のセクハラは何故無くならない?資質だけではない、学校の構造的な問題も指摘する:『スク…
『スクールセクハラ なぜ教師のわいせつ犯罪は繰り返されるのか』では、自分が生徒に対して「権力」を持っているとは想像していなかったという教師が登場する。そしてこの「無自覚」は、学校以外の場でも起こりうる。特に男性は、読んで自分の振る舞いを見直すべきだ
あわせて読みたい
【感心】悩み相談とは、相手の問いに答える”だけ”じゃない。哲学者が相談者の「真意」に迫る:『哲学の…
「相談に乗る」とは、「自分の意見を言う行為」ではない。相談者が”本当に悩んでいること”を的確に捉えて、「回答を与えるべき問いは何か?」を見抜くことが本質だ。『哲学の先生と人生の話をしよう』から、「相談をすること/受けること」について考える
あわせて読みたい
【絶望】「人生上手くいかない」と感じる時、彼を思い出してほしい。壮絶な過去を背負って生きる彼を:…
「北九州連続監禁殺人事件」という、マスコミも報道規制するほどの残虐事件。その「主犯の息子」として生きざるを得なかった男の壮絶な人生。「ザ・ノンフィクション」のプロデューサーが『人殺しの息子と呼ばれて』で改めて取り上げた「真摯な男」の生き様と覚悟
あわせて読みたい
【あらすじ】子どもは大人よりずっと大人だ。「子ども扱い」するから、「子どもの枠」から抜け出せない…
宮部みゆき『ソロモンの偽証』は、その分厚さ故になかなか手が伸びない作品だろうが、「長い」というだけの理由で手を出さないのはあまりにももったいない傑作だ。「中学生が自前で裁判を行う」という非現実的設定をリアルに描き出すものすごい作品
あわせて読みたい
【助けて】息苦しい世の中に生きていて、人知れず「傷」を抱えていることを誰か知ってほしいのです:『…
元気で明るくて楽しそうな人ほど「傷」を抱えている。そんな人をたくさん見てきた。様々な理由から「傷」を表に出せない人がいる世の中で、『包帯クラブ』が提示する「見えない傷に包帯を巻く」という具体的な行動は、気休め以上の効果をもたらすかもしれない
あわせて読みたい
【理解】東田直樹の本は「自閉症の見方」を一変させた。自身も自閉症児を育てるプロデューサーが映画化…
東田直樹の著作を英訳し世界に広めた人物(自閉症児を育てている)も登場する映画『僕が跳びはねる理由』には、「東田直樹が語る自閉症の世界」を知ることで接し方や考え方が変わったという家族が登場する。「自閉症は知恵遅れではない」と示した東田直樹の多大な功績を実感できる
あわせて読みたい
【あらすじ】人生行き詰まってなお「生きたい」と思えるか?環境の激変を受け入れる難しさと生きる悲し…
勤務していた会社の都合で、町が1つ丸々無くなるという経験をし、住居を持たないノマド生活へと舵を切った女性を描く映画『ノマドランド』を通じて、人生の大きな変化に立ち向かう気力を持てるのか、我々はどう生きていくべきか、などについて考える
あわせて読みたい
【現実】生きる気力が持てない世の中で”働く”だけが人生か?「踊るホームレスたち」の物語:映画『ダン…
「ホームレスは怠けている」という見方は誤りだと思うし、「働かないことが悪」だとも私には思えない。振付師・アオキ裕キ主催のホームレスのダンスチームを追う映画『ダンシングホームレス』から、社会のレールを外れても許容される社会の在り方を希求する
あわせて読みたい
【逃避】つまらない世の中で生きる毎日を押し流す”何か”を求める気持ちに強烈に共感する:映画『サクリ…
子どもの頃「台風」にワクワクしたように、未だに、「自分のつまらない日常を押し流してくれる『何か』」の存在を待ちわびてしまう。立教大学の学生が撮った映画『サクリファイス』は、そんな「何か」として「東日本大震災」を描き出す、チャレンジングな作品だ
あわせて読みたい
【称賛】生き様がかっこいい。ムンバイのホテルのテロ事件で宿泊客を守り抜いたスタッフたち:映画『ホ…
インドの高級ホテルで実際に起こったテロ事件を元にした映画『ホテル・ムンバイ』。恐ろしいほどの臨場感で、当時の恐怖を観客に体感させる映画であり、だからこそ余計に、「逃げる選択」もできたホテルスタッフたちが自らの意思で残り、宿泊を助けた事実に感銘を受ける
あわせて読みたい
【リアル】社会の分断の仕組みを”ゾンビ”で学ぶ。「社会派ゾンビ映画」が対立の根源を抉り出す:映画『C…
まさか「ゾンビ映画」が、私たちが生きている現実をここまで活写するとは驚きだった。映画『CURED キュアード』をベースに、「見えない事実」がもたらす恐怖と、立場ごとに正しい主張をしながらも否応なしに「分断」が生まれてしまう状況について知る
あわせて読みたい
【改心】人生のリセットは困難だが不可能ではない。過去をやり直す強い意思をいかにして持つか:映画『S…
私は、「自分の正しさを疑わない人」が嫌いだ。そして、「正しさを他人に押し付ける人」が嫌いだ。「変わりたいと望む者の足を引っ張る人」が嫌いだ。全身刺青だらけのレイシストが人生をやり直す、実話を元にした映画『SKIN/スキン』から、再生について考える
あわせて読みたい
【実話】「家族とうまくいかない現実」に正解はあるか?選択肢が無いと感じる時、何を”選ぶ”べきか?:…
「自分の子どもなんだから、どんな風に育てたって勝手でしょ」という親の意見が正しいはずはないが、この言葉に反論することは難しい。虐待しようが生活能力が無かろうが、親は親だからだ。映画『MOTHER マザー』から、不正解しかない人生を考える
あわせて読みたい
【正義】マイノリティはどう生き、どう扱われるべきかを描く映画。「ルールを守る」だけが正解か?:映…
社会的弱者が闘争の末に権利を勝ち取ってきた歴史を知った上で私は、闘わずとも権利が認められるべきだと思っている。そして、そういう社会でない以上、「正義のためにルールを破るしかない」状況もある。映画『パブリック』から、ルールと正義のバランスを考える
あわせて読みたい
【勇敢】後悔しない生き方のために”間違い”を犯せるか?法に背いてでも正義を貫いた女性の生き様:映画…
国の諜報機関の職員でありながら、「イラク戦争を正当化する」という巨大な策略を知り、守秘義務違反をおかしてまで真実を明らかにしようとした実在の女性を描く映画『オフィシャル・シークレット』から、「法を守る」こと以上に重要な生き方の指針を学ぶ
あわせて読みたい
【情熱】「ルール」は守るため”だけ”に存在するのか?正義を実現するための「ルール」のあり方は?:映…
「ルールは守らなければならない」というのは大前提だが、常に例外は存在する。どれほど重度の自閉症患者でも断らない無許可の施設で、情熱を持って問題に対処する主人公を描く映画『スペシャルズ!』から、「ルールのあるべき姿」を考える
あわせて読みたい
【葛藤】「多様性を受け入れること」は難しい。映画『アイヌモシリ』で知る、アイデンティティの実際
「アイヌの町」として知られるアイヌコタンの住人は、「アイヌ語を勉強している」という。観光客のイメージに合わせるためだ。映画『アイヌモシリ』から、「伝統」や「文化」の継承者として生きるべきか、自らのアイデンティティを意識せず生きるべきかの葛藤を知る
あわせて読みたい
【実話】人質はなぜ犯人に好意を抱くか?「ストックホルム症候群」の由来である銀行強盗を描く映画:『…
「強盗や立てこもり事件などにおいて、人質が犯人に好意・共感を抱いてしまう状態」を「ストックホルム症候群」と呼ぶのだが、実はそう名付けられる由来となった実際の事件が存在する。実話を基にした映画『ストックホルムケース』から、犯人に協力してしまう人間の不可思議な心理について知る
あわせて読みたい
【排除】「分かり合えない相手」だけが「間違い」か?想像力の欠如が生む「無理解」と「対立」:映画『…
「共感」が強すぎる世の中では、自然と「想像力」が失われてしまう。そうならないようにと意識して踏ん張らなければ、他人の価値観を正しく認めることができない人間になってしまうだろう。映画『ミセス・ノイズィ』から、多様な価値観を排除しない生き方を考える
あわせて読みたい
【実話】正論を振りかざす人が”強い”社会は窮屈だ。映画『すばらしき世界』が描く「正解の曖昧さ」
「SNSなどでの炎上を回避する」という気持ちから「正論を言うに留めよう」という態度がナチュラルになりつつある社会には、全員が全員の首を締め付け合っているような窮屈さを感じてしまう。西川美和『すばらしき世界』から、善悪の境界の曖昧さを体感する
あわせて読みたい
【誠実】地下鉄サリン事件の被害者が荒木浩に密着。「贖罪」とは何かを考えさせる衝撃の映画:『AGANAI…
私には、「謝罪すること」が「誠実」だという感覚がない。むしろ映画『AGANAI 地下鉄サリン事件と私』では、「謝罪しない誠実さ」が描かれる。被害者側と加害者側の対話から、「謝罪」「贖罪」の意味と、信じているものを諦めさせることの難しさについて書く
あわせて読みたい
【再生】ヤクザの現実を切り取る映画『ヤクザと家族』から、我々が生きる社会の”今”を知る
「ヤクザ」を排除するだけでは「アンダーグラウンドの世界」は無くならないし、恐らく状況はより悪化しただけのはずだ。映画『ヤクザと家族』から、「悪は徹底的に叩きのめす」「悪じゃなければ何をしてもいい」という社会の風潮について考える。
あわせて読みたい
【狂気】アメリカの衝撃の実態。民営刑務所に刑務官として潜入した著者のレポートは国をも動かした:『…
アメリカには「民営刑務所」が存在する。取材のためにその1つに刑務官として潜入した著者が記した『アメリカン・プリズン』は信じがたい描写に溢れた1冊だ。あまりに非人道的な行いがまかり通る狂気の世界と、「民営刑務所」が誕生した歴史的背景を描き出すノンフィクション
あわせて読みたい
【救い】耐えられない辛さの中でどう生きるか。短歌で弱者の味方を志すホームレス少女の生き様:『セー…
死にゆく母を眺め、施設で暴力を振るわれ、拾った新聞で文字を覚えたという壮絶な過去を持つ鳥居。『セーラー服の歌人 鳥居』は、そんな辛い境遇を背景に、辛さに震えているだろう誰かを救うために短歌を生み出し続ける生き方を描き出す。凄い人がいるものだ
あわせて読みたい
【絶望】子供を犯罪者にしないために。「異常者」で片付けられない、希望を見いだせない若者の現実:『…
2人を殺し、7人に重傷を負わせた金川真大に同情の余地はない。しかし、この事件を取材した記者も、私も、彼が殺人に至った背景・動機については理解できてしまう部分がある。『死刑のための殺人』をベースに、「どうしようもないつまらなさ」と共に生きる現代を知る
あわせて読みたい
【余命】癌は治らないと”諦める”べき?治療しない方が長生きする現実を現役医師が小説で描く:『悪医』…
ガンを患い、余命宣告され、もう治療の手がないと言われれば絶望を抱くだろう。しかし医師は、治療しない方が長生きできることを知って提案しているという。現役医師・久坂部羊の小説『悪医』をベースに、ガン治療ですれ違う医師と患者の想いを知る
あわせて読みたい
【異端】子育てがうまくいかないと悩む方へ。9歳で大学入学の天才児に学ぶ「すべきでないこと」:『ぼく…
12歳で数学の未解決問題を解いた天才児は、3歳の時に「16歳で靴紐が結べるようになったらラッキー」と宣告されていた。専門家の意見に逆らって、重度の自閉症児の才能をどう開花させたのかを、『ぼくは数式で宇宙の美しさを伝えたい』から学ぶ
あわせて読みたい
【恐怖】SNSの危険性と子供の守り方を、ドキュメンタリー映画『SNS 少女たちの10日間』で学ぶ
実際にチェコの警察を動かした衝撃のドキュメンタリー映画『SNS 少女たちの10日間』は、少女の「寂しさ」に付け込むおっさんどもの醜悪さに満ちあふれている。「WEBの利用制限」だけでは子どもを守りきれない現実を、リアルなものとして実感すべき
あわせて読みたい
【衝撃】壮絶な戦争映画。最愛の娘を「産んで後悔している」と呟く母らは、正義のために戦場に留まる:…
こんな映画、二度と存在し得ないのではないかと感じるほど衝撃を受けた『娘は戦場で生まれた』。母であり革命家でもあるジャーナリストは、爆撃の続くシリアの街を記録し続け、同じ街で娘を産み育てた。「知らなかった」で済ませていい現実じゃない。
あわせて読みたい
【考察】世の中は理不尽だ。平凡な奴らがのさばる中で、”特別な私の美しい世界”を守る生き方:『オーダ…
自分以外は凡人、と考える主人公の少女はとてもイタい。しかし、世間の価値観と折り合わないなら、自分の美しい世界を守るために闘うしかない。中二病の少女が奮闘する『オーダーメイド殺人クラブ』をベースに、理解されない世界をどう生きるかについて考察する
あわせて読みたい
【異常】「助けて」と言えない。自己責任社会のしんどさと、我が子がホームレスである可能性:『助けて…
39歳で餓死した男性は、何故誰にも助けを求めなかったのか?異常な視聴率を叩き出した、NHK「クローズアップ現代」の特集を元に書かれた『助けてと言えない』をベースに、「自己責任社会」の厳しさと、若者が置かれている現実について書く。
あわせて読みたい
【呪縛】「良い子」に囚われ人生苦しい。どう見られるかを抜け出し、なりたい自分を生きるために:『わ…
「良い子でいなきゃいけない」と感じ、本来の自分を押し隠したまま生きているという方、いるんじゃないかと思います。私も昔はそうでした。「良い子」の呪縛から逃れることは難しいですが、「なりたい自分」をどう生きればいいかを、『わたしを見つけて』をベースに書いていきます
あわせて読みたい
【救い】自殺を否定しない「笑える自殺本」。「自殺したい」ってもっと気軽に言える社会がいい:『自殺…
生きることがしんどくて、自殺してしまいたくなる気持ちを、私はとても理解できます。しかし世の中的には、「死にたい」と口にすることはなかなか憚られるでしょう。「自殺を決して悪いと思わない」という著者が、「死」をもっと気楽に話せるようにと贈る、「笑える自殺本」
あわせて読みたい
【感想】人間関係って難しい。友達・恋人・家族になるよりも「あなた」のまま関わることに価値がある:…
誰かとの関係性には大抵、「友達」「恋人」「家族」のような名前がついてしまうし、そうなればその名前に縛られてしまいます。「名前がつかない関係性の奇跡」と「誰かを想う強い気持ちの表し方」について、『君の膵臓をたべたい』をベースに書いていきます
あわせて読みたい
【勇敢】日本を救った吉田昌郎と、福島第一原発事故に死を賭して立ち向かった者たちの極限を知る:『死…
日本は、死を覚悟して福島第一原発に残った「Fukushima50」に救われた。東京を含めた東日本が壊滅してもおかしくなかった大災害において、現場の人間が何を考えどう行動したのかを、『死の淵を見た男』をベースに書く。全日本人必読の書
あわせて読みたい
【あらすじ】家族ってめんどくさい……。それでも、あとから後悔せずに生きるために、今どう生きるか:小…
人が死んでも「悲しい」と感じられない男に共感できるか?(私はメチャクチャ共感してしまう) 西川美和の『永い言い訳』をベースに、「喪失の大きさを理解できない理由」と、「誰かに必要とされる生き方」について語る
あわせて読みたい
【議論】安楽死のできない日本は「死ぬ権利」を奪っていると思う(合法化を希望している):『安楽死を…
私は、安楽死が合法化されてほしいと思っている。そのためには、人間には「死ぬ権利」があると合意されなければならないだろう。安楽死は時折話題になるが、なかなか議論が深まらない。『安楽死を遂げた日本人』をベースに、安楽死の現状を理解する
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
どう生きるべきか・どうしたらいい【本・映画の感想】 | ルシルナ
どんな人生を歩みたいか、多くの人が考えながら生きていると思います。私は自分自身も穏やかに、そして周囲の人や社会にとっても何か貢献できたらいいなと、思っています。…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…












































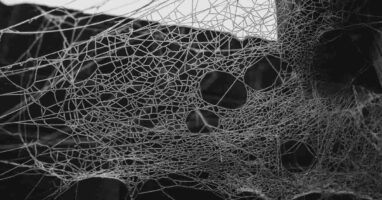











































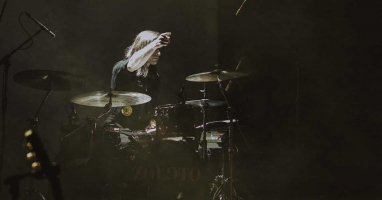
























































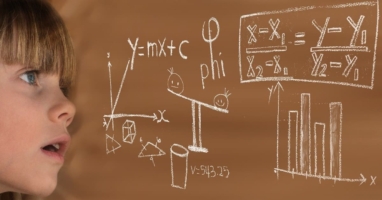



















コメント