目次
はじめに
著:西川美和
¥713 (2024/07/03 14:44時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
この記事で伝えたいこと
あなたは、「誰かに必要とされる生き方」ができていますか?
私は上手くできていません。だから、この作品の主人公に超共感してしまいます
この記事の3つの要点
- 親しい人が亡くなっても「悲しい」と思えなかった理由
- 「必要とする/される関係」には責任感が伴う
- 「自分が失ったものの大きさ」が分からないことの悲哀
小説とはいえ、こんな主人公が受け入れられているというのは、少しホッとする事実ではあります
この記事で取り上げる本
「永い言い訳」(西川美和/文藝春秋)
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!「それってホントに『コミュ力』が高いって言えるの?」と疑問を感じている方に…
私は、「コミュ力が高い人」に関するよくある主張に、どうも違和感を覚えてしまうことが多くあります。そしてその一番大きな理由が、「『コミュ力が高い人』って、ただ『想像力がない』だけではないか?」と感じてしまう点にあると言っていいでしょう。出版したKindle本は、「ネガティブには見えないネガティブな人」(隠れネガティブ)を取り上げながら、「『コミュ力』って何だっけ?」と考え直してもらえる内容に仕上げたつもりです。
西川美和『永い言い訳』を読んで考えさせられた「誰かに必要とされる生き方」
家族に対するめんどくささと、死を悲しめない私
あわせて読みたい
【感想】映画『窓辺にて』(今泉力哉監督)の稲垣吾郎の役に超共感。「好きとは何か」が分からない人へ
映画『窓辺にて』(今泉力哉監督)は、稲垣吾郎演じる主人公・市川茂巳が素晴らしかった。一般的には、彼の葛藤はまったく共感されないし、私もそのことは理解している。ただ私は、とにかく市川茂巳にもの凄く共感してしまった。「誰かを好きになること」に迷うすべての人に観てほしい
今はさほどでもありませんが、人生の長い期間にわたって、家族に対するめんどくささを感じていました。特に、実家に暮らしていた18年間はかなりしんどかったです。物心ついた頃から、「この人たちとは、合わないなー」という感覚をずっと抱いていましたし、「どうしてこの人たちと一緒にいなきゃいけないんだろう」と感じていたと思います。
今では、「家族だから嫌」っていうよりは、「誰かと一緒に暮らすことが嫌」っていう感覚が強かったんだろうって思うけどね
割と最近、父親が亡くなりました。62歳だったので、若くして死んだと言えるでしょう。ただその時でさえ私は、「悲しい」という感情を抱くことができませんでした。
あわせて読みたい
【諦め】母親の存在にモヤモヤを抱えた人生から、「生きてさえいればいい」への違和感を考える:『晴天…
生まれ育つ環境を選ぶことはできません。そして、家族との関わりや家庭環境は、その後の人生に大きな影響を及ぼします。努力するスタートラインにも立てないと感じる時、それでも前進することを諦めてはいけないのかを、『晴天の迷いクジラ』をベースに書く
昔からずっと同じです。これまでも、祖父母や大学時代の先輩など、それなりに身近な人の死に触れています。しかしその度に私は、「自分の内側から『悲しい』という感情が湧き上がってこないなぁ」と感じてきました。
この作品の主人公のように。
私はこの作品の主人公に恐ろしいほど共感してしまうのですが、「被害者になるのは怖い」というこんな感覚も非常に強く理解できるものでした。
理不尽な殺人などが起こるたびに、それまで他者に殺意など抱いたためしもなさそうな可憐な主婦が、テレビカメラの前で「極刑以外望みません」と強い口調で語ったりするのを見るにつけ、巨大な喪失がもたらす激しい動力を見たような気がして幸夫は圧倒され、被害そのものを恐れる以上に、被害者になるのは怖いと感じてきた。何かひどい目に遭った時、自分は彼らをはるかにしのぐ、桁違いの憎悪に狂う可能性を秘めているし、あるいは全くその逆もあるかもしれない。もし彼らのように迷いなく、真っ直ぐに怒りや悲しみの情動に浸れなかった場合、その先には何があるのだろうと考えると、それもまた恐ろしかった。
あわせて読みたい
【葛藤】子どもが抱く「家族を捨てたい気持ち」は、母親の「家族を守りたい気持ち」の終着点かもしれな…
家族のややこしさは、家族の数だけ存在する。そのややこしさを、「子どもを守るために母親が父親を殺す」という極限状況を設定することで包括的に描き出そうとする映画『ひとよ』。「暴力」と「殺人犯の子どもというレッテル」のどちらの方が耐え難いと感じるだろうか?
確かに私も、「真っ直ぐに怒りや悲しみの情動に浸れなかった場合」のことを考えてしまいます。それなりに親しい人が亡くなった時でさえ、私はあまり感情的になれません。しかし同時に私は、「そういう時には悲しむのが当然」という無言の圧力みたいなものを感じてしまいます。
まあ、「誰か死んだら悲しい」と感じるのが普通だろうから、これを「圧力」だなんて捉える人は少ないだろうけどね
直接被害を受けるのではなく、「被害者家族」のような立場に立たされた時に、自分が、よくニュース映像で見るような打ちひしがれた状態になれる気がしません。
あわせて読みたい
【感想】世の中と足並みがそろわないのは「正常が異常」だから?自分の「正常」を守るために:『コンビ…
30代になっても未婚でコンビニアルバイトの古倉さんは、普通から外れたおかしな人、と見られてしまいます。しかし、本当でしょうか?『コンビニ人間』をベースに、多数派の人たちの方が人生を自ら選択していないのではないかと指摘する。
こんな感覚は、きっと誰にも理解されないだろうと思っていたので、本書を読んだ時には本当に驚きました。こんな、世間からまったく共感されないような主人公を据えて、それで作品として成立させているのは凄まじいな、と感じたのです。
私は、以前こそ家族に対するめんどくささを感じていたとはいえ、今は大分薄れています。しかしその今の状態でさえ、家族の死(しかも父親の死)に対して、あまり心が動きません。そんな自分を理解しているので、「こういう時、人は感情的になるはずだ」と多くの人が感じる状況に陥りたくないなぁ、といつも考えています。
なぜ悲しいと思えないのか
私は、誰かの死に接した際に、「どうして悲しいと感じられないのか」と折に触れて考えてきました。
あわせて読みたい
【絶望】子供を犯罪者にしないために。「異常者」で片付けられない、希望を見いだせない若者の現実:『…
2人を殺し、7人に重傷を負わせた金川真大に同情の余地はない。しかし、この事件を取材した記者も、私も、彼が殺人に至った背景・動機については理解できてしまう部分がある。『死刑のための殺人』をベースに、「どうしようもないつまらなさ」と共に生きる現代を知る
今のところの私の結論は、「自分が必要とされているかどうか」に関係している、というものです。
年を重ねるごとに、そして自分の状況がいろいろと変化するたびに感じることですが、生きていく上で「自分が誰かに必要とされている感覚」は非常に重要だと感じるようになりました。若い頃は正直、この重要さにそこまで気づいていなかったと思います。他人と関わることがめんどくさいと感じていたし、一人でいることに苦痛を覚える人間ではないとも思っていたからです。
しかしそれは、仕事でのちょっとした関わりや、プライベートでそれなりに人と会うことで、「自分は必要とされている」という感覚を多少なりとも無意識に受け取っていたということなのだろうと思います。
年齢を重ねたことやコロナ禍であることなどによって、状況は少しずつ変わり、私は今、「自分が必要とされている感覚」をあまり実感できません。そしてそのことによって、自分が少し不安定になっていると感じています。
あわせて読みたい
【感想】人間関係って難しい。友達・恋人・家族になるよりも「あなた」のまま関わることに価値がある:…
誰かとの関係性には大抵、「友達」「恋人」「家族」のような名前がついてしまうし、そうなればその名前に縛られてしまいます。「名前がつかない関係性の奇跡」と「誰かを想う強い気持ちの表し方」について、『君の膵臓をたべたい』をベースに書いていきます
そういう思考を経て、「この人は私を必要としてくれているだろう」と感じられる相手が死んでしまったら、恐らく私は大きな喪失感を抱くのではないかと考えるようになりました。そしてそれこそが「悲しい」という感情なのでしょう。結局のところ、今まで私の周りで亡くなった人に対しては、そういう感覚を抱けなかったということなのだと思います。
「必要とされる」ためには「必要とする」ことが不可欠
あわせて読みたい
【居場所】菊地凛子主演映画『658km、陽子の旅』(熊切和嘉)は、引きこもりロードムービーの傑作
映画『658km、陽子の旅』は、主演の菊地凛子の存在感が圧倒的だった。夢破れて長年引きこもり続けている女性が、否応なしにヒッチハイクで弘前を目指さなければならなくなるロードムービーであり、他人や社会と関わることへの葛藤に塗れた主人公の変化が、とても「勇敢」なものに映る
そしてさらに感じることは、「誰かに必要とされること」は、「誰かを必要とすること」と表裏一体だ、ということです。確かに、そのバランスが崩れている、つまり、「必要としていない相手から必要とされる」や「必要とされていない相手を必要とする」という状況も考えられますが、大体の場合、お互いがお互いを必要とし合う、という関係性に落ち着くことが多いのではないかと思います。

この小説では、対照的な二家族が描かれます。どちらもバス事故によって妻を亡くした夫が中心となりますが、一方は妻を失って悲しみに暮れ、一方は妻を失っても動揺さえしません。
一方は、突然妻を奪われた悲しみを全身から発し、言葉でも悲しみを表現します。そして周囲も、そんな反応になるのは当然だと受け取り、理解を示します。
あわせて読みたい
【あらすじ】「愛されたい」「必要とされたい」はこんなに難しい。藤崎彩織が描く「ままならない関係性…
好きな人の隣にいたい。そんなシンプルな願いこそ、一番難しい。誰かの特別になるために「異性」であることを諦め、でも「異性」として見られないことに苦しさを覚えてしまう。藤崎彩織『ふたご』が描き出す、名前がつかない切実な関係性
もう一方は、妻が死んでも涙を流さず、しかし世間体があるので悲しんでいるフリはします。そして、自分が「不幸な事故によって妻を失った可哀相な人」という役割を”演じなければならない”という感覚にうんざりしているのです。
そして、あまりに対照的なこの二人の一番大きな違いは、「必要とする/される」という点なのです。
「自分が何を失ったのか」を理解できるか?
あわせて読みたい
【死】映画『湯を沸かすほどの熱い愛』に号泣。「家族とは?」を問う物語と、タイトル通りのラストが見事
「死は特別なもの」と捉えてしまうが故に「日常感」が失われ、普段の生活から「排除」されているように感じてしまうのは私だけではないはずだ。『湯を沸かすほどの熱い愛』は、「死を日常に組み込む」ことを当たり前に許容する「家族」が、「家族」の枠組みを問い直す映画である
私がこの物語を読みながら感じていたことは、何か喪失を経験した時に、自分が失ったものの大きさを理解できるのか? ということです。
妻を失って泣き崩れる男は、「その大きさを理解している側の人物」として物語に登場します。もちろん、「思っていた以上に大きな喪失だった」ということをさらに後から理解することはあるかもしれません。ただいずれにせよこの男は、妻を失ったその瞬間に、自分がどれほど大きなものを失ったのかを理解します。
しかしもう一方の男は、それが理解できません。
実際に彼も、妻の死によって大きなものを失いました。しかし、妻が亡くなった時点では、それに気づくことができていません。それは、男が妻から「必要とされず」、男も妻を「必要としていなかった」からです。
あわせて読みたい
【助けて】息苦しい世の中に生きていて、人知れず「傷」を抱えていることを誰か知ってほしいのです:『…
元気で明るくて楽しそうな人ほど「傷」を抱えている。そんな人をたくさん見てきた。様々な理由から「傷」を表に出せない人がいる世の中で、『包帯クラブ』が提示する「見えない傷に包帯を巻く」という具体的な行動は、気休め以上の効果をもたらすかもしれない
結婚当初は違いました。男は作家であり、デビュー前は全然食えなかったので、美容師として働く妻に10年以上も養ってもらっていました。しかしデビューして一気に人気作家になったことで、この関係は変わってしまいます。
男は、自分の才覚で稼げるようになったことで、妻を必要としなくなりました。それは、妻のことを「自分の生活を金銭面で支えてくれる人」としか見ていなかったということです。
あわせて読みたい
【家族】映画『そして父になる』が問う「子どもの親である」、そして「親の子どもである」の意味とは?
「血の繋がり」だけが家族なのか?「将来の幸せ」を与えることが子育てなのか?実際に起こった「赤ちゃんの取り違え事件」に着想を得て、苦悩する家族を是枝裕和が描く映画『そして父になる』から、「家族とは何か?」「子育てや幸せとどう向き合うべきか?」を考える
妻は、男の変化を理解し、自分が必要とされていないと受け取ったことでしょう。彼女は「悲しい」と感じますが、しかしそれは、「夫の変化によって自分が何を失ったのか理解できている」ということでもあります。そしてその現実を受け入れ、妻は妻なりにその喪失を織り込んだ上で、自分の人生を歩んでいきます。
しかし男の方はそうではありません。男は、人気作家になり妻を必要としなくなった時点で、自分が何を失ったのか理解できていませんでした。であれば当然、妻が死んだ時にもその喪失が理解できるはずがありません。
男は妻の死によって何を失ったか?
では、男が失ったものとは一体なんだったのでしょうか? まさにこの物語は、「自分は一体何を失ったのかを理解する」というこの男の旅路を描く作品なのです。
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『夕方のおともだち』は、「私はこう」という宣言からしか始まらない関係性の”純度”を描く
「こんな田舎にはもったいないほどのドM」と評された男が主人公の映画『夕方のおともだち』は、SM嬢と真性ドMの関わりを通じて、「宣言から始まる関係」の難しさを描き出す。「普通の世界」に息苦しさを感じ、どうしても馴染めないと思っている人に刺さるだろう作品

男は遺族会で、妻の死に対して悲しみを爆発させる長距離トラックのドライバーと出会い、関わりを持つようになります。そして、仕事で長く家を空けなければならないドライバーに代わって、妻を失い子供もいない男が子供の面倒を見る、という関わりが生まれるのです。
その過程で男に変化が現れることになります。
陽一にとってそうである以上に、この小さな友人たちにとっても自分の存在が命綱であるということが、何よりも幸夫を勇気づけた。他人からの毀誉褒貶ばかりを気にかけてきたこの十数年には手にしたことのない感覚だった。
あわせて読みたい
【認識】「固定観念」「思い込み」の外側に出るのは難しい。自分はどんな「へや」に囚われているのか:…
実際に起こった衝撃的な事件に着想を得て作られた映画『ルーム』は、フィクションだが、観客に「あなたも同じ状況にいるのではないか?」と突きつける力強さを持っている。「普通」「当たり前」という感覚に囚われて苦しむすべての人に、「何に気づけばいいか」を気づかせてくれる作品
男は、人気作家として世間と対峙し続けてきた時期には感じられずにいた「誰かに必要とされている感覚」を、子供たちとの関わりの中で実感できるようになります。そしてその感覚は、感情が揺れ動くことのなかった「妻の死」に対しての感覚も変えていくことになるのです。
もしも彼女が生きている間に、「夏子の人生にとって自分は不可欠だ」と盲目的にであれ幸夫自身が信じていたならば、そこには子供らに対して今抱いているのと同じ、甘美な充足があったのだろうか――。
つまり彼が失ったものは、「あり得たかもしれない未来」だと言えるでしょう。
確かに、”今”自分の手元にあるわけじゃないものを失っているんだとしたら、実感は難しいかもね
そういう感覚を、物語を通じてじわーっと感じさせるのがとても上手い
あわせて読みたい
【多様性】神童から引きこもりになり、なんとか脱出したお笑い芸人が望む、誰も責められない社会:『ヒ…
お笑い芸人・髭男爵の山田ルイ53世は、“神童”と呼ばれるほど優秀だったが、“うんこ”をきっかけに6年間引きこもった。『ヒキコモリ漂流記』で彼は、ひきこもりに至ったきっかけ、ひきこもり中の心情、そしてそこからいかに脱出したのかを赤裸々に綴り、「誰にも優しい世界」を望む
男が得た実感は、結局「擬似的」なもの
ドライバー一家と関わることで、男は少しずつ変わっていきます。子供たちから命綱のような形で「必要とされる」状況には、男自身さえも戸惑うような甘美な感覚があったからです。そして、その感覚を通じて、「もし妻が生きていれば……」と、過去の自分の振る舞いや妻との関わりを思い返す構成は見事だと感じます。
しかし一方で、子供たちと関わることで男が抱く「必要とされている」という感覚は、ある種の虚構でもあります。
というのも、男にとってドライバー一家の子供たちは、「最終的に自分の責任の対象ではない存在」だからです。自分の子供には厳しく接した祖父母が、孫には甘くなってしまうのと理屈は同じでしょう。責任がない立場だからこそできること、得られることがあるのです。
あわせて読みたい
【美麗】映画『CLOSE/クロース』はあまりにも切ない。「誰かの当たり前」に飲み込まれてしまう悲劇
子どもの頃から兄弟のように育った幼馴染のレオとレミの関係の変化を丁寧に描き出す映画『CLOSE/クロース』は、「自分自身で『美しい世界』を毀損しているのかもしれない」という話でもある。”些細な”言動によって、確かに存在したあまりに「美しい世界」があっさりと壊されてしまう悲哀が描かれる
だから、妻の死から時間が経った後で、男が「自分はこれほど大きなものを失ったのではないか」と感じる実感も、実際のところは誤りだと言えます。なぜなら男は、「必要とする/される関係」に付随する責任感を理解していないからです。「必要とする/される関係」から「責任感」を取り除けるなら、それは「甘美」にもなるでしょう。
しかしそんなの通用しない。子供は母親のアイデンティティや、順調だった人生や、正当性なんて、ハリケーンのように横暴になぎ倒す。子供のいる生活に対して抱いていた明るい夢もろともに。
男ではない別の人物が、こんな実感を吐露する場面があります。私は結婚していないし子供もいないのでちゃんとは分かりませんが、そりゃあ大変だろうと思います。
あわせて読みたい
【違和感】平田オリザ『わかりあえないことから』は「コミュニケーション苦手」問題を新たな視点で捉え…
「コミュニケーションが苦手」なのは、テクニックの問題ではない!?『わかりあえないことから』は、学校でのコミュニケーション教育に携わる演劇人・平田オリザが抱いた違和感を起点に、「コミュニケーション教育」が抱える問題と、私たち日本人が進むべき道を示す1冊
男は、自分が何を失ったのか理解したつもりになれます。しかしそれは、「擬似的」な感覚から得られた「虚構」でしかありません。

だから、すべての土台が崩れ去るような瞬間を迎えてしまうことになります。
大宮一家には気の毒だが、幸夫にとって、この二日の灯や真平や陽一との久々の邂逅は、振り返るのも怖いほど甘いひとときだった。しかし甘い時間の過剰摂取は、人生を蝕んでいく。甘いものなど、食べなければ良かったと思うようになる。
あわせて読みたい
【呪縛】「良い子」に囚われ人生苦しい。どう見られるかを抜け出し、なりたい自分を生きるために:『わ…
「良い子でいなきゃいけない」と感じ、本来の自分を押し隠したまま生きているという方、いるんじゃないかと思います。私も昔はそうでした。「良い子」の呪縛から逃れることは難しいですが、「なりたい自分」をどう生きればいいかを、『わたしを見つけて』をベースに書いていきます
この物語を読んで、改めて自分の感覚が整理できたように感じられました。自分が喪失感を抱けないのは、「必要とする/される関係」を上手く作ってこれなかったからでしょう。しかしそういう関係性には当然「責任感」も発生します。そこからは逃げたい。
そんな感覚を共有しているだろう、本書の主人公の「弱さ」や「卑怯さ」みたいなものは、私自身に突きつけられているようにも感じられました。
西川美和『永い言い訳』の内容紹介
ここで改めて本の内容を紹介します。
著:西川美和
¥713 (2021/05/22 07:51時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
出演:本木雅弘, 出演:竹原ピストル, 出演:藤田健心, 出演:白鳥玉季, 出演:堀内敬子, 出演:池松壮亮, 出演:黒木華, 出演:山田真歩, 出演:深津絵里, 監督:西川美和, Writer:西川美和, プロデュース:西川朝子, プロデュース:代情明彦, クリエイター:川城和実, クリエイター:中江康人, クリエイター:太田哲夫, クリエイター:長澤修一, クリエイター:松井清人, クリエイター:岩村卓
¥2,037 (2021/05/25 07:02時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
衣笠幸夫は、有名な野球選手と名前の響きが同じであり、子供の頃から自分の名前を嫌悪してきた。だから、作家としてデビューしてからは「津村啓」という名前で通し、本名はごく親しい人にしか伝えていない。
あわせて読みたい
【考察】ヨネダコウ『囀る鳥は羽ばたかない』は、BLの枠組みの中で「歪んだ人間」をリアルに描き出す
2巻までしか読んでいないが、ヨネダコウのマンガ『囀る鳥は羽ばたかない』は、「ヤクザ」「BL」という使い古されたフォーマットを使って、異次元の物語を紡ぎ出す作品だ。BLだが、BLという外枠を脇役にしてしまう矢代という歪んだ男の存在感が凄まじい。
美容師として働く妻は、出版社を辞めて作家を目指すという夫の突然の決断を快く受け入れ、家計を支えていく。しかし、夫が作家としてどんどん有名になっていき、夫と一緒にいても自分の存在意義を感じられなくなる。津村も、人気作家となったことで妻の存在を必要としなくなり、一緒に暮らしてはいるものの、夫婦の生活は見えないところで着実に破綻していく。
そんなある日。友人とスキー旅行に向かった妻は、その途中でバス事故に遭い、命を落とす。妻の死に感情が動かない津村。そんな折、遺族会で大宮陽一という男と出会う。妻と一緒にスキー旅行へ行き亡くなった友人の夫である。大宮は妻から”幸夫ちゃん”の話をよく聞いていたらしく、そんな縁で津村は、大宮と関わることとなる。
大宮などから、亡き妻に関する話を様々に聞き、一緒に暮らしていたにも拘わらずまったく知らずにいた妻の姿を知るようになっていく。しかしだからと言って、津村は妻に強い感情を持てるようになったわけではない。「人気作家が妻を事故で失ったこと」は報じられており、津村は「可哀相な被害者」として振る舞わなければならない現実にうんざりしているほどだった。
あわせて読みたい
【共感】「恋愛したくない」という社会をリアルに描く売野機子の漫画『ルポルタージュ』が示す未来像
売野機子のマンガ『ルポルタージュ』は、「恋愛を飛ばして結婚すること」が当たり前の世界が描かれる。私はこの感覚に凄く共感できてしまった。「恋愛」「結婚」に対して、「世間の『当たり前』に馴染めない感覚」を持つ私が考える、「恋愛」「結婚」が有する可能性
状況が変わるのは、大宮から頼まれて子供たちの面倒を見るようになってからだ。そこで津村は久々に、「誰かに必要とされる感覚」を味わうことになる。妻が亡くなったことで、自分が一体何を失ったのか、少しずつ掴み取れるようになっていき……。
西川美和『永い言い訳』の感想
もの凄く良い物語でした。何度か書いていますが、私は津村の感覚にメチャクチャ共感できてしまいます。その辺りの話は後で触れますが、私が不思議なのは、多くの人は一体何に共感しているのか、ということです。
この作品はどこが評価されているのか?
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『アンダーカレント』(今泉力哉)は、失踪をテーマに「分かり合えなさ」を描く
映画『アンダーカレント』において私は、恐らく多くの人が「受け入れがたい」と感じるだろう人物に共感させられてしまった。また本作は、「他者を理解すること」についての葛藤が深掘りされる作品でもある。そのため、私が普段から抱いている「『他者のホントウ』を知りたい」という感覚も強く刺激された
この作品は、本屋大賞候補となり、本屋大賞でも4位になっています。一般的にかなり高く評価されていると言えるでしょう。ただ、この津村という男は、とても共感されるタイプの主人公ではないと思うんですよね。
かなり酷い人間だと思うし、感情が欠けています。確かに、後半に行くにつれて津村も変化していくし、「最終的に良い感じになったから途中も許す」みたいなことなのかもしれないけれど、そうだとしても私には、この作品が高く評価されている理由が謎です。
あわせて読みたい
【あらすじ】趣味も仕事もない定年後の「退屈地獄」をリアルに描く内館牧子『終わった人』から人生を考える
映画化もされた『終わった人』(内館牧子)は、「定年後の人生の退屈さ」を真正面から描く小説。仕事一筋で生きてきた主人公が、定年を迎えたことで無為な日々を過ごすことになるのですが、今の時代、このような感覚はもしかしたら、若い世代にも無縁とは言えないかもしれないとさえ感じました
私が津村に共感したのと同じように、世間の多くの人も実は津村的な部分を抱えていて、だから津村のあり方に心の底から共感しているのだ、ということなら凄くいいなぁと思います。
もしそうなら、私が抱いている、到底大多数の人には受け入れられないだろうと考えていた価値観が、実は許容される、どころか多くの人が同じ感覚を抱いているということになるからです。
ただまあ、そんなことはないでしょう。そしてそういう期待をしないとすれば、この作品を読んだ人が何をどう評価しているのか、不思議だとずっと感じています。
私は津村にメチャクチャ共感する
あわせて読みたい
【家族】映画『女優は泣かない』は、蓮佛美沙子が「再起を賭ける女優」を演じる笑い泣き満載の作品(出…
蓮佛美沙子が、スキャンダルで落ちぶれ再起を賭ける女優を演じる映画『女優は泣かない』は、ミニマムかつシンプルな構成ながら、笑いあり涙ありのハートフルコメディだった。「やりたくはないが、やらねばならぬ」とお互いが感じているドキュメンタリー撮影を軸に、家族の物語を織り込む展開が素敵
津村は折に触れて、様々な思考を展開していきます。その多くが私の琴線に触れますし、「うわぁ、メッチャ分かる!」と感じてしまうのですが、なかでも、「まったく同じ思考だ」と驚いたのがこれです。
ぼくは人の親になれるような人間じゃない。「なんとかなるものさ」という他人の言葉は信用ならない。なんとかならなかったやつらがこんなにぞろぞろ居る世の中で、ぼくが「なんとかなる組」に入れる保証はどこにある? なんともならなかった時、「なんとかなるさ」と言った連中は、何をしてくれる? ぼくは子供が嫌いなんじゃない。そう信じている。ただ、「不幸な子供」の親にだけはなりたくなかったんだ

私は本当に昔から、このことを口にしていました。友人などとの会話でたまに、「結婚ぐらいしてみればいい」という話になります。私が、結婚願望がまったくない、みたいなことを言うからです。で、「結婚ぐらいしてみればいい」というのは私も同感ではあります。ただその流れで、「子供だって育ててみたらいいのに」みたいに言われることもあります。そう言われる度に私は、それは無理あるだろー、と感じてしまいます。
あわせて読みたい
【見方】日本の子どもの貧困は深刻だ。努力ではどうにもならない「見えない貧困」の現実と対策:『増補…
具体的には知らなくても、「日本の子どもの貧困の現状は厳しい」というイメージを持っている人は多いだろう。だからこそこの記事では、朝日新聞の記事を再編集した『増補版 子どもと貧困』をベースに、「『貧困問題』とどう向き合うべきか」に焦点を当てた
その理由は、先程引用した津村の思考とまったく同じです。私はよく、「自分の子供が将来藤井聡太になるなら、そりゃあ育ててみたい。でも、どんな子供か分かんないし」という話をします。
「藤井聡太になるなら」というのは別に、「大金を稼ぐ子供」とか「有名になる子供」という意味ではありません。私は天才が好きなので、自分の子供が何らかの意味で「天才」だったらいいな、と思ってよく藤井聡太の名前を出します。
「子供だって育ててみたらいいのに」と言う人が何を考えてそういう発言をするのかよく分かりませんが、私がいつも思うことは、世の中には児童虐待とか育児放棄とかメッチャ起こっているじゃないか、ということです。
そういう人の中には、様々な事情で子供を産むことを望んでいなかった人ももちろんいるでしょう。しかしその多くはやはり、「子供が欲しいし、自分には子育てができると思っている人たち」のはずだと私は考えています。そして、産んで育て始めるまではそう考えていた人たちが、虐待や放棄をしてしまうというわけです。
あわせて読みたい
【救い】耐えられない辛さの中でどう生きるか。短歌で弱者の味方を志すホームレス少女の生き様:『セー…
死にゆく母を眺め、施設で暴力を振るわれ、拾った新聞で文字を覚えたという壮絶な過去を持つ鳥居。『セーラー服の歌人 鳥居』は、そんな辛い境遇を背景に、辛さに震えているだろう誰かを救うために短歌を生み出し続ける生き方を描き出す。凄い人がいるものだ
「自分は大丈夫」って思ってる人が上手くいかないんだから…
もし世の中に虐待や放棄が一例も、あるいはほとんど存在しないのであれば、私も子育てできると思えるかもしれません。しかし世の中には、子育てに上手くいかなかった人たちの事例がたくさんあります。であれば、私が「なんとかなる組」に入れる保証などない、ってかきっと入れないだろうと考えてしまいます。まさに津村と同じです。
私も、別に殊更に子供が嫌いなわけではないし、案外良い親になれるんじゃないかと思えたりする瞬間もあります。でも、やっぱり、「不幸な子供」の親にはなりたくない、と考えてしまうんですよね。津村が言っている通りです。
私はこの物語が存在することで、なんとなくほんの少しだけですが、「自分のような考えも、世の中のどこかにはちゃんと存在しているんだな」と思えて、気持ちが軽くなった気がします。
あわせて読みたい
【嫌悪】映画『ドライビング・バニー』が描く、人生やり直したい主人公(母親)のウザさと絶望
映画『ドライビング・バニー』は、主人公であるバニーのことが最後まで嫌いだったにも拘わらず、全体的にはとても素敵に感じられた珍しいタイプの作品だ。私は、「バニーのような人間が世の中に存在する」という事実に嫌悪感を抱いてしまうのだが、それでも、狂気的でぶっ飛んだラストシーンによって、作品全体の印象が大きく変わったと言える
著:西川美和
¥713 (2022/02/03 23:27時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品読了済】私が読んできた小説を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が読んできた小説を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本選びの参考にして下さい。
最後に
あわせて読みたい
【絶望】人生どん底から生き方を変える。映画『シスター 夏のわかれ道』が描く中国人女性の葛藤と諦念
両親の死をきっかけに、「見知らぬ弟」を引き取らなければならなくなった女性を描く映画『シスター 夏のわかれ道』は、中国の特異な状況を背景にしつつ、誰もが抱き得る普遍的な葛藤が切り取られていく。現状を打破するために北京の大学院を目指す主人公は、一体どんな決断を下すのか。
「必要とする/される関係」を築けなければ喪失感を上手く捉えることはできません。しかし「必要とする/される関係」には、それ相応の責任も付随してきます。私は、その責任を果たす勇気がなくてどうしても遠ざかってしまい、そのせいで、誰かの死に対して感情が動かない人間になってしまいました。
津村のように、失ってからその大事さに気づいたとしても、できることは多くはありません。自戒を込めてですが、失う前にその大事さを捉えられるような関係性を築くことが重要だと改めて考えさせられました。
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!「それってホントに『コミュ力』が高いって言えるの?」と疑問を感じている方に…
私は、「コミュ力が高い人」に関するよくある主張に、どうも違和感を覚えてしまうことが多くあります。そしてその一番大きな理由が、「『コミュ力が高い人』って、ただ『想像力がない』だけではないか?」と感じてしまう点にあると言っていいでしょう。出版したKindle本は、「ネガティブには見えないネガティブな人」(隠れネガティブ)を取り上げながら、「『コミュ力』って何だっけ?」と考え直してもらえる内容に仕上げたつもりです。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【奇妙】映画『画家と泥棒』は、非日常的なきっかけで始まったあり得ないほど奇跡的な関係を描く
映画『画家と泥棒』は、「自身の絵を盗まれた画家が、盗んだ泥棒と親しくなる」という奇妙奇天烈なきっかけから関係性が始まる物語であり、現実に起きたこととは思えないほど不可思議なドキュメンタリーである。アートを通じて奇妙に通じ合う2人の関係性は、ある種の美しささえ感じさせる、とても素晴らしいものに見えた
あわせて読みたい
【日常】映画『大きな家』(竹林亮)は、児童養護施設で「家族」と「血縁」の違いや難しさに直面する
児童養護施設に長期密着した映画『大きな家』は、映画『14歳の栞』で中学2年生をフラットに撮り切った竹林亮が監督を務めたドキュメンタリーである。子どもたちの過去に焦点を当てるのではなく、「児童養護施設の日常風景」として彼らを捉えるスタンスで、その上でさらに「家族のあり方」に対する子どもたちの認識が掘り下げられる
あわせて読みたい
【絶望】満員続出の映画『どうすればよかったか?』が描き出す、娘の統合失調症を認めない両親の不条理
たった4館から100館以上にまで上映館が拡大した話題の映画『どうすればよかったか?』を公開2日目に観に行った私は、「ドキュメンタリー映画がどうしてこれほど注目されているのだろうか?」と不思議に感じた。統合失調症を発症した姉を中心に家族を切り取る本作は、観る者に「自分だったらどうするか?」という問いを突きつける
あわせて読みたい
【異様】映画『大いなる不在』(近浦啓)は、認知症の父を中心に「記憶」と「存在」の複雑さを描く(主…
「父親が逮捕され、どうやら認知症のようだ」という一報を受けた息子が、30年間ほぼやり取りのなかった父親と再会するところから始まる映画『大いなる不在』は、なんとも言えない「不穏さ」に満ちた物語だった。「記憶」と「存在」のややこしさを問う本作は、「物語」としては成立していないが、圧倒的な“リアリティ”に満ちている
あわせて読みたい
【あらすじ】有村架純が保護司を演じた映画『前科者』が抉る、罪を犯した者を待つ「更生」という現実
映画『前科者』は、仮釈放中の元受刑者の更生を手助けするボランティアである「保護司」を中心に据えることで、「元犯罪者をどう受け入れるべきか」「保護司としての葛藤」などを絶妙に描き出す作品。個別の事件への処罰感情はともかく、「社会全体としていかに犯罪を減らしていくか」という観点を忘れるべきではないと私は思っている
あわせて読みたい
【感想】映画『夜明けのすべて』は、「ままならなさ」を抱えて生きるすべての人に優しく寄り添う(監督…
映画『夜明けのすべて』は、「PMS」や「パニック障害」を通じて、「自分のものなのに、心・身体が思い通りにならない」という「ままならなさ」を描き出していく。決して他人事ではないし、「私たちもいつそのような状況に置かれるか分からない」という気持ちで観るのがいいでしょう。物語の起伏がないのに惹きつけられる素敵な作品です
あわせて読みたい
【常識】群青いろ制作『彼女はなぜ、猿を逃したか?』は、凄まじく奇妙で、実に魅力的な映画だった(主…
映画『彼女はなぜ、猿を逃したか?』(群青いろ制作)は、「絶妙に奇妙な展開」と「爽快感のあるラスト」の対比が魅力的な作品。主なテーマとして扱われている「週刊誌報道からのネットの炎上」よりも、私は「週刊誌記者が無意識に抱いている思い込み」の方に興味があったし、それを受け流す女子高生の受け答えがとても素敵だった
あわせて読みたい
【狂気】群青いろ制作『雨降って、ジ・エンド。』は、主演の古川琴音が成立させている映画だ
映画『雨降って、ジ・エンド。』は、冒頭からしばらくの間「若い女性とオジサンのちょっと変わった関係」を描く物語なのですが、後半のある時点から「共感を一切排除する」かのごとき展開になる物語です。色んな意味で「普通なら成立し得ない物語」だと思うのですが、古川琴音の演技などのお陰で、絶妙な形で素敵な作品に仕上がっています
あわせて読みたい
【狂気】異質なホラー映画『みなに幸あれ』(古川琴音主演)は古い因習に似せた「社会の異様さ」を描く
古川琴音主演映画『みなに幸あれ』は、”シュールさ”さえ感じさせる「異質なホラー映画」だ。「村の因習」というよくあるパターンをベースに据えつつ、そこで展開される異様な状況が、実は「私たちが生きる世界」に対応しているという構成になっている。「お前の物語だからな」と終始突きつけられ続ける作品だ
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『アンダーカレント』(今泉力哉)は、失踪をテーマに「分かり合えなさ」を描く
映画『アンダーカレント』において私は、恐らく多くの人が「受け入れがたい」と感じるだろう人物に共感させられてしまった。また本作は、「他者を理解すること」についての葛藤が深掘りされる作品でもある。そのため、私が普段から抱いている「『他者のホントウ』を知りたい」という感覚も強く刺激された
あわせて読みたい
【家族】映画『女優は泣かない』は、蓮佛美沙子が「再起を賭ける女優」を演じる笑い泣き満載の作品(出…
蓮佛美沙子が、スキャンダルで落ちぶれ再起を賭ける女優を演じる映画『女優は泣かない』は、ミニマムかつシンプルな構成ながら、笑いあり涙ありのハートフルコメディだった。「やりたくはないが、やらねばならぬ」とお互いが感じているドキュメンタリー撮影を軸に、家族の物語を織り込む展開が素敵
あわせて読みたい
【嫌悪】映画『ドライビング・バニー』が描く、人生やり直したい主人公(母親)のウザさと絶望
映画『ドライビング・バニー』は、主人公であるバニーのことが最後まで嫌いだったにも拘わらず、全体的にはとても素敵に感じられた珍しいタイプの作品だ。私は、「バニーのような人間が世の中に存在する」という事実に嫌悪感を抱いてしまうのだが、それでも、狂気的でぶっ飛んだラストシーンによって、作品全体の印象が大きく変わったと言える
あわせて読みたい
【絶望】人生どん底から生き方を変える。映画『シスター 夏のわかれ道』が描く中国人女性の葛藤と諦念
両親の死をきっかけに、「見知らぬ弟」を引き取らなければならなくなった女性を描く映画『シスター 夏のわかれ道』は、中国の特異な状況を背景にしつつ、誰もが抱き得る普遍的な葛藤が切り取られていく。現状を打破するために北京の大学院を目指す主人公は、一体どんな決断を下すのか。
あわせて読みたい
【美麗】映画『CLOSE/クロース』はあまりにも切ない。「誰かの当たり前」に飲み込まれてしまう悲劇
子どもの頃から兄弟のように育った幼馴染のレオとレミの関係の変化を丁寧に描き出す映画『CLOSE/クロース』は、「自分自身で『美しい世界』を毀損しているのかもしれない」という話でもある。”些細な”言動によって、確かに存在したあまりに「美しい世界」があっさりと壊されてしまう悲哀が描かれる
あわせて読みたい
【居場所】菊地凛子主演映画『658km、陽子の旅』(熊切和嘉)は、引きこもりロードムービーの傑作
映画『658km、陽子の旅』は、主演の菊地凛子の存在感が圧倒的だった。夢破れて長年引きこもり続けている女性が、否応なしにヒッチハイクで弘前を目指さなければならなくなるロードムービーであり、他人や社会と関わることへの葛藤に塗れた主人公の変化が、とても「勇敢」なものに映る
あわせて読みたい
【あらすじ】趣味も仕事もない定年後の「退屈地獄」をリアルに描く内館牧子『終わった人』から人生を考える
映画化もされた『終わった人』(内館牧子)は、「定年後の人生の退屈さ」を真正面から描く小説。仕事一筋で生きてきた主人公が、定年を迎えたことで無為な日々を過ごすことになるのですが、今の時代、このような感覚はもしかしたら、若い世代にも無縁とは言えないかもしれないとさえ感じました
あわせて読みたい
【共感】「恋愛したくない」という社会をリアルに描く売野機子の漫画『ルポルタージュ』が示す未来像
売野機子のマンガ『ルポルタージュ』は、「恋愛を飛ばして結婚すること」が当たり前の世界が描かれる。私はこの感覚に凄く共感できてしまった。「恋愛」「結婚」に対して、「世間の『当たり前』に馴染めない感覚」を持つ私が考える、「恋愛」「結婚」が有する可能性
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『夕方のおともだち』は、「私はこう」という宣言からしか始まらない関係性の”純度”を描く
「こんな田舎にはもったいないほどのドM」と評された男が主人公の映画『夕方のおともだち』は、SM嬢と真性ドMの関わりを通じて、「宣言から始まる関係」の難しさを描き出す。「普通の世界」に息苦しさを感じ、どうしても馴染めないと思っている人に刺さるだろう作品
あわせて読みたい
【考察】ヨネダコウ『囀る鳥は羽ばたかない』は、BLの枠組みの中で「歪んだ人間」をリアルに描き出す
2巻までしか読んでいないが、ヨネダコウのマンガ『囀る鳥は羽ばたかない』は、「ヤクザ」「BL」という使い古されたフォーマットを使って、異次元の物語を紡ぎ出す作品だ。BLだが、BLという外枠を脇役にしてしまう矢代という歪んだ男の存在感が凄まじい。
あわせて読みたい
【感想】おげれつたなか『エスケープジャーニー』は、BLでしか描けない”行き止まりの関係”が絶妙
おげれつたなか『エスケープジャーニー』のあらすじ紹介とレビュー。とにかく、「BLでしか描けない関係性」が素晴らしかった。友達なら完璧だったのに、「恋人」ではまったく上手く行かなくなってしまった直人と太一の葛藤を通じて、「進んでも行き止まり」である関係にどう向き合うか考えさせられる
あわせて読みたい
【違和感】平田オリザ『わかりあえないことから』は「コミュニケーション苦手」問題を新たな視点で捉え…
「コミュニケーションが苦手」なのは、テクニックの問題ではない!?『わかりあえないことから』は、学校でのコミュニケーション教育に携わる演劇人・平田オリザが抱いた違和感を起点に、「コミュニケーション教育」が抱える問題と、私たち日本人が進むべき道を示す1冊
あわせて読みたい
【感想】映画『窓辺にて』(今泉力哉監督)の稲垣吾郎の役に超共感。「好きとは何か」が分からない人へ
映画『窓辺にて』(今泉力哉監督)は、稲垣吾郎演じる主人公・市川茂巳が素晴らしかった。一般的には、彼の葛藤はまったく共感されないし、私もそのことは理解している。ただ私は、とにかく市川茂巳にもの凄く共感してしまった。「誰かを好きになること」に迷うすべての人に観てほしい
あわせて読みたい
【恋愛】モテない男は何がダメ?AV監督が男女共に贈る「コミュニケーション」と「居場所」の話:『すべ…
二村ヒトシ『すべてはモテるためである』は、タイトルも装丁も、どう見ても「モテ本」にしか感じられないだろうが、よくある「モテるためのマニュアル」が書かれた本ではまったくない。「行動」を促すのではなく「思考」が刺激される、「コミュニケーション」と「居場所」について語る1冊
あわせて読みたい
【感涙】映画『彼女が好きなものは』の衝撃。偏見・無関心・他人事の世界から”脱する勇気”をどう持つか
涙腺がぶっ壊れたのかと思ったほど泣かされた映画『彼女が好きなものは』について、作品の核となる「ある事実」に一切触れずに書いた「ネタバレなし」の感想です。「ただし摩擦はゼロとする」の世界で息苦しさを感じているすべての人に届く「普遍性」を体感してください
あわせて読みたい
【衝撃】卯月妙子『人間仮免中』、とんでもないコミックエッセイだわ。統合失調症との壮絶な闘いの日々
小学5年生から統合失調症を患い、社会の中でもがき苦しみながら生きる卯月妙子のコミックエッセイ『人間仮免中』はとんでもない衝撃作。周りにいる人とのぶっ飛んだ人間関係や、歩道橋から飛び降り自殺未遂を図り顔面がぐちゃぐちゃになって以降の壮絶な日々も赤裸々に描く
あわせて読みたい
【日常】「何もかも虚しい」という心のスキマを「異性」や「お金」で安易に埋めてしまうのは危険だ:映…
「どこにでもいる普通の女性」が「横領」に手を染める映画『紙の月』は、「日常の積み重ねが非日常に接続している」ことを否応なしに実感させる。「主人公の女性は自分とは違う」と考えたい観客の「祈り」は通じない。「梅澤梨花の物語」は「私たちの物語」でもあるのだ
あわせて読みたい
【生きる】しんどい人生を宿命付けられた子どもはどう生きるべき?格差社会・いじめ・恋愛を詰め込んだ…
厳しい受験戦争、壮絶な格差社会、残忍ないじめ……中国の社会問題をこれでもかと詰め込み、重苦しさもありながら「ボーイ・ミーツ・ガール」の爽やかさも融合されている映画『少年の君』。辛い境遇の中で、「すべてが最悪な選択肢」と向き合う少年少女の姿に心打たれる
あわせて読みたい
【認識】「固定観念」「思い込み」の外側に出るのは難しい。自分はどんな「へや」に囚われているのか:…
実際に起こった衝撃的な事件に着想を得て作られた映画『ルーム』は、フィクションだが、観客に「あなたも同じ状況にいるのではないか?」と突きつける力強さを持っている。「普通」「当たり前」という感覚に囚われて苦しむすべての人に、「何に気づけばいいか」を気づかせてくれる作品
あわせて読みたい
【死】映画『湯を沸かすほどの熱い愛』に号泣。「家族とは?」を問う物語と、タイトル通りのラストが見事
「死は特別なもの」と捉えてしまうが故に「日常感」が失われ、普段の生活から「排除」されているように感じてしまうのは私だけではないはずだ。『湯を沸かすほどの熱い愛』は、「死を日常に組み込む」ことを当たり前に許容する「家族」が、「家族」の枠組みを問い直す映画である
あわせて読みたい
【生き方】人生が虚しいなら映画『人生フルーツ』を見ると良い。素敵な老夫婦の尖った人生がここにある
社会派のドキュメンタリー映画に定評のある東海テレビが、「なんでもない老夫婦の日常」を映画にした『人生フルーツ』には、特に何が起こるわけでもないのに「観て良かった」と感じさせる強さがある。見た目は「お年寄り」だが中身はまったく古臭くない”穏やかに尖った夫婦”の人生とは?
あわせて読みたい
【家族】映画『そして父になる』が問う「子どもの親である」、そして「親の子どもである」の意味とは?
「血の繋がり」だけが家族なのか?「将来の幸せ」を与えることが子育てなのか?実際に起こった「赤ちゃんの取り違え事件」に着想を得て、苦悩する家族を是枝裕和が描く映画『そして父になる』から、「家族とは何か?」「子育てや幸せとどう向き合うべきか?」を考える
あわせて読みたい
【考察】生きづらい性格は変わらないから仮面を被るしかないし、仮面を被るとリア充だと思われる:『勝…
「リア充感」が滲み出ているのに「生きづらさ」を感じてしまう人に、私はこれまでたくさん会ってきた。見た目では「生きづらさ」は伝わらない。24年間「リアル彼氏」なし、「脳内彼氏」との妄想の中に生き続ける主人公を描く映画『勝手にふるえてろ』から「こじらせ」を知る
あわせて読みたい
【傑作】濱口竜介監督の映画『ドライブ・マイ・カー』(原作:村上春樹)は「自然な不自然さ」が見事な作品
村上春樹の短編小説を原作にした映画『ドライブ・マイ・カー』(濱口竜介監督)は、村上春樹の小説の雰囲気に似た「自然な不自然さ」を醸し出す。「不自然」でしかない世界をいかにして「自然」に見せているのか、そして「自然な不自然さ」は作品全体にどんな影響を与えているのか
あわせて読みたい
【考察】映画『ジョーカー』で知る。孤立無援の環境にこそ”悪”は偏在すると。個人の問題ではない
「バットマン」シリーズを観たことがない人間が、予備知識ゼロで映画『ジョーカー』を鑑賞。「悪」は「環境」に偏在し、誰もが「悪」に足を踏み入れ得ると改めて実感させられた。「個人」を断罪するだけでは社会から「悪」を減らせない現実について改めて考える
あわせて読みたい
【葛藤】子どもが抱く「家族を捨てたい気持ち」は、母親の「家族を守りたい気持ち」の終着点かもしれな…
家族のややこしさは、家族の数だけ存在する。そのややこしさを、「子どもを守るために母親が父親を殺す」という極限状況を設定することで包括的に描き出そうとする映画『ひとよ』。「暴力」と「殺人犯の子どもというレッテル」のどちらの方が耐え難いと感じるだろうか?
あわせて読みたい
【漫画原作】映画『殺さない彼と死なない彼女』は「ステレオタイプな人物像」の化学反応が最高に面白い
パッと見の印象は「よくある学園モノ」でしかなかったので、『殺さない彼と死なない彼女』を観て驚かされた。ステレオタイプで記号的なキャラクターが、感情が無いとしか思えないロボット的な言動をする物語なのに、メチャクチャ面白かった。設定も展開も斬新で面白い
あわせて読みたい
【狂気】「当たり前の日常」は全然当たり前じゃない。記憶が喪われる中で”日常”を生きることのリアル:…
私たちは普段、「記憶が当たり前に継続していること」に疑問も驚きも感じないが、「短期記憶を継続できない」という記憶障害を抱える登場人物の日常を描き出す『静かな雨』は、「記憶こそが日常を生み出している」と突きつけ、「当たり前の日常は当たり前じゃない」と示唆する
あわせて読みたい
【人生】どう生きるべきかは、どう死にたいかから考える。死ぬ直前まで役割がある「理想郷」を描く:『…
「近隣の村から『姥捨て』と非難される理想郷」を描き出す『でんでら国』は、「死ぬ直前まで、コミュニティの中で役割が存在する」という世界で展開される物語。「お金があっても決して豊かとは言えない」という感覚が少しずつ広まる中で、「本当の豊かさ」とは何かを考える
あわせて読みたい
【実像】ベートーヴェンの「有名なエピソード」をほぼ一人で捏造・創作した天才プロデューサーの実像:…
ベートーヴェンと言えば、誰もが知っている「運命」を始め、天才音楽家として音楽史に名を刻む人物だが、彼について良く知られたエピソードのほとんどは実は捏造かもしれない。『ベートーヴェン捏造 名プロデューサーは嘘をつく』が描く、シンドラーという”天才”の実像
あわせて読みたい
【鋭い】「俳優・堺雅人」のエピソードを綴るエッセイ。考える俳優の視点と言葉はとても面白い:『文・…
ドラマ『半沢直樹』で一躍脚光を浴びた堺雅人のエッセイ『文・堺雅人』は、「ファン向けの作品」に留まらない。言語化する力が高く、日常の中の些細な事柄を丁寧に掬い上げ、言葉との格闘を繰り広げる俳優の文章は、力強く自立しながらもゆるりと入り込んでくる
あわせて読みたい
【実話】「家族とうまくいかない現実」に正解はあるか?選択肢が無いと感じる時、何を”選ぶ”べきか?:…
「自分の子どもなんだから、どんな風に育てたって勝手でしょ」という親の意見が正しいはずはないが、この言葉に反論することは難しい。虐待しようが生活能力が無かろうが、親は親だからだ。映画『MOTHER マザー』から、不正解しかない人生を考える
あわせて読みたい
【実話】正論を振りかざす人が”強い”社会は窮屈だ。映画『すばらしき世界』が描く「正解の曖昧さ」
「SNSなどでの炎上を回避する」という気持ちから「正論を言うに留めよう」という態度がナチュラルになりつつある社会には、全員が全員の首を締め付け合っているような窮屈さを感じてしまう。西川美和『すばらしき世界』から、善悪の境界の曖昧さを体感する
あわせて読みたい
【感想】世の中と足並みがそろわないのは「正常が異常」だから?自分の「正常」を守るために:『コンビ…
30代になっても未婚でコンビニアルバイトの古倉さんは、普通から外れたおかしな人、と見られてしまいます。しかし、本当でしょうか?『コンビニ人間』をベースに、多数派の人たちの方が人生を自ら選択していないのではないかと指摘する。
あわせて読みたい
【あらすじ】「愛されたい」「必要とされたい」はこんなに難しい。藤崎彩織が描く「ままならない関係性…
好きな人の隣にいたい。そんなシンプルな願いこそ、一番難しい。誰かの特別になるために「異性」であることを諦め、でも「異性」として見られないことに苦しさを覚えてしまう。藤崎彩織『ふたご』が描き出す、名前がつかない切実な関係性
ルシルナ
家族・夫婦【本・映画の感想】 | ルシルナ
子どもの頃から、家族との関わりには色々と苦労してきました。別に辛い扱いを受けていたわけではありませんが、「家族だから」という理由で様々な「当たり前」がまかり通っ…
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…
 犀川後藤
犀川後藤
































































































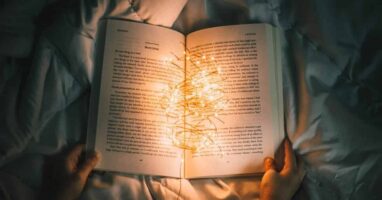
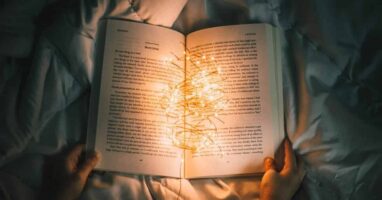














































































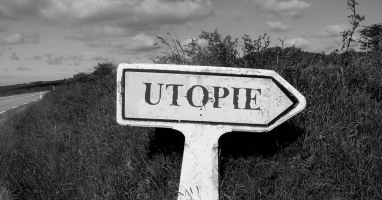
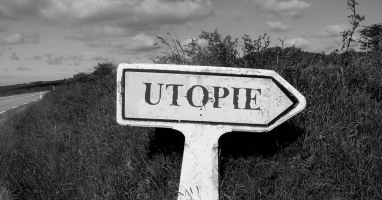


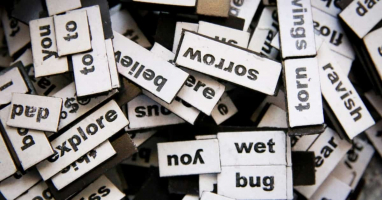
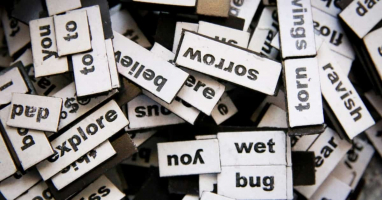























コメント