目次
はじめに
この記事で取り上げる映画
出演:山田孝之, 出演:ピエール瀧, 出演:リリー・フランキー, 出演:池脇千鶴, 出演:白川和子, Writer:高橋泉, Writer:白石和彌, 監督:白石和彌
¥300 (2022/04/08 05:46時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
編集:「新潮45」編集部
¥604 (2022/04/08 05:46時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
この映画をガイドにしながら記事を書いていきます
この記事の3つの要点
- 「記者側の話をノンフィクションで描く原作」と「犯罪者側の話をフィクションで描く映画」で1セット
- 実話とは思えない、あまりに「異例づくめ」の出来事
- 映画では、主人公・藤井修一(山田孝之)の存在が「正義」について問いかける
死刑囚と雑誌記者の執念が、娑婆にのさばる極悪人を追い詰める緊迫感が凄まじい
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
記事中の引用は、映画館で取ったメモを参考にしているので、正確なものではありません
ノンフィクションを映画化した『凶悪』は、死刑囚が雑誌記者に獄中から信じがたい「告発」を行った実話を基にした衝撃作だ
映画と原作で「ワンセット」と捉えると良い
あわせて読みたい
【執念】「桶川ストーカー事件」で警察とマスコミの怠慢を暴き、社会を動かした清水潔の凄まじい取材:…
『殺人犯はそこにいる』(文庫X)で凄まじい巨悪を暴いた清水潔は、それよりずっと以前、週刊誌記者時代にも「桶川ストーカー殺人事件」で壮絶な取材を行っていた。著者の奮闘を契機に「ストーカー規制法」が制定されたほどの事件は、何故起こり、どんな問題を喚起したのか
私は、先に原作を読んでおり、後から映画を観た。どちらも、凄まじい作品だった。
内容についてはこれから触れるが、この作品で描かれるのは、原作の解説を担当した佐藤優が、
少なくとも過去十年に私が読んだ殺人事件を扱ったノンフィクションのなかで最大の衝撃を受けた作品である
「凶悪」(「新潮45」編集部/新潮社)

というコメントを帯に寄せるほど凄まじい現実だ。死刑囚が雑誌記者に、「自分より悪いやつが娑婆にいる」と訴え、その記者が死刑囚の言葉を受けて捜査まがいのことを行って、事件の真相究明に関わっていくのである。ドラマや映画で採用したら「嘘くさい」と受け取られるだろう。とても現実に起こった出来事とは思えない状況だ。
あわせて読みたい
【衝撃】壮絶な戦争映画。最愛の娘を「産んで後悔している」と呟く母らは、正義のために戦場に留まる:…
こんな映画、二度と存在し得ないのではないかと感じるほど衝撃を受けた『娘は戦場で生まれた』。母であり革命家でもあるジャーナリストは、爆撃の続くシリアの街を記録し続け、同じ街で娘を産み育てた。「知らなかった」で済ませていい現実じゃない。
原作と映画、共に触れた私の意見としては、この『凶悪』という作品は、2つ併せて1作品、というような印象が強い。原作と映画で、焦点が当てられる部分が違うからだ。
原作は「ノンフィクション」であり、そう打ち出す以上は、「記者側の話」がメインになるのは当然だろう。犯罪者側の話は、どうしたって「憶測」が混じることになる。だから、ノンフィクションである原作は、この件を追いかけた雑誌記者側の話が中心になるわけだ。
一方、映画でももちろん「記者側の話」は描かれるわけだが、それ以上に「犯罪者側の話」に焦点が当てられる印象が強い。映画の冒頭で、「この映画は事実を基にしたフィクションです」という表示が出た。犯罪者側の描写は、本人の証言や物的証拠などから「想像」するしかないわけで、映画ではフィクションとしての要素も強いというわけだ。
このように、「記者側の話をノンフィクションで描く原作」と「犯罪者側の話をフィクションで描く映画」の組み合わせによって、合わせて1つの作品という印象が強くなる。どちらかだけに触れるのでも充分だが、原作と映画、どちらの視点からも捉えると、より深く作品に触れられるだろう。
あわせて読みたい
【実話】「家族とうまくいかない現実」に正解はあるか?選択肢が無いと感じる時、何を”選ぶ”べきか?:…
「自分の子どもなんだから、どんな風に育てたって勝手でしょ」という親の意見が正しいはずはないが、この言葉に反論することは難しい。虐待しようが生活能力が無かろうが、親は親だからだ。映画『MOTHER マザー』から、不正解しかない人生を考える
この実話のあまりの「異常さ」
少し設定に触れながら、この物語がどれほど「異常」なのかをまずは説明していこうと思う。

まず何よりも、「死刑囚からの告発」によってすべてが始まったという点があまりにも異例だと言える。後藤という死刑囚は、死刑判決は受けていたが、当時はまだ最高裁に上告中であり、いわゆる「死刑確定囚」ではなかった。しかし細かな呼び方はともかく、「死刑判決を受けている人物からの告発」という時点で既に普通ではないと言っていいだろう。
さらに、死刑囚が秘密を告発する相手として雑誌記者を選んだことも異例だ。何をもって「普通」と呼べばいいか悩む状況ではあるが、しかし普通はまず弁護人に相談するのではないだろうか。後藤死刑囚は、囚人仲間の伝手をたどる形で雑誌記者にアプローチしている。かなりまどろっこしいやり方だと言っていいだろう。警察さえまだ把握していない事件について、まずマスコミに話をしようと考えたこともなかなか異例ではないかと思う。
あわせて読みたい
【感想】阿部サダヲが狂気を怪演。映画『死刑にいたる病』が突きつける「生きるのに必要なもの」の違い
サイコパスの連続殺人鬼・榛村大和を阿部サダヲが演じる映画『死刑にいたる病』は、「生きていくのに必要なもの」について考えさせる映画でもある。目に光を感じさせない阿部サダヲの演技が、リアリティを感じにくい「榛村大和」という人物を見事に屹立させる素晴らしい映画
しかも、単なる偶然ではあるが、後藤死刑囚が「雑誌記者」を選んだことは正解だった。この点については、後藤死刑囚から直接話を聞いた『新潮45』の記者・宮本太一が原作の巻末で説明している。雑誌記者以外に話をしていたら、その後の展開はなかったのではないかと。
テレビや新聞は、警察発表のない事件については扱わないという。警察が事件を認知し、立件するか立件が確実になるかしない限り報道としては扱えないそうだ。その背景には「記者クラブ」の存在がある。警察に限る話ではないが、公的機関には取材全体を取りまとめる「記者クラブ制度」が存在し、公的機関は「記者クラブ」に一括で情報を流すのが慣例だ。「記者クラブ」から外されてしまえば情報が得られないし、だから公的機関の意に沿わない報道には慎重になる。
つまり、もし仮に、テレビや新聞が宮本氏と同等の情報を得ていたとしても、「警察が認知していない事件」という時点でその後の取材等には繋がらなかった可能性があるのだ。そして、ほとんどの雑誌(週刊誌)が記者クラブに加盟していない。雑誌ジャーナリズムだからこそ起こり得た展開だったというわけだ。
あわせて読みたい
【デマ】情報を”選ぶ”時代に、メディアの情報の”正しさ”はどのように判断されるのか?:『ニューヨーク…
一昔前、我々は「正しい情報を欲していた」はずだ。しかしいつの間にか世の中は変わった。「欲しい情報を正しいと思う」ようになったのだ。この激変は、トランプ元大統領の台頭で一層明確になった。『ニューヨーク・タイムズを守った男』から、情報の受け取り方を問う

また、死刑囚の告発をとりあえず信じて雑誌記者が取材に動いた、というのもまた異例だと思う。もちろん宮本氏も、「所詮死刑囚の話だ」と眉唾に感じていた。「どうせ嘘だろう」と放置されてもおかしくはなかったはずだ。しかし宮本氏は、嘘かもしれないと思いながらも、死刑囚の話に乗ってみることにした。だからこそ、「異例の展開」が導かれることになったのである。
最終的にどのような展開を迎えたのか。後藤死刑囚は、警察が把握していない3件の殺人事件を告発したが、その内の1件が実際に立件され、裁判にまでこぎつけたのだ。彼が告発したのは大分昔の事件であり、最後まで死体は発見されないままだった。物証もほとんど存在せず、立件など不可能に思える事件だったのだ。にも関わらず、記者の執念と奇策、そして偶然も味方し、最終的に裁判にまで至る奇跡的な展開が生まれたのである。
そしてすべてにおいて恐らく最も「異例」だったのが、「死刑確定囚を改めて裁判にかけたこと」だろう。後藤は、雑誌記者に告発した時点では上告中だったが、その後死刑判決が確定している。そしてそんな後藤を、再び裁判の場に立たせたのだ。もちろん、「死刑が確定した者を改めて裁判にかけることに意味はあるのか」という議論が出たそうだが、最終的には「真相解明が何より優先される」という理由で裁判が行われた。法務省でも、このような事態は少なくとも戦後では初だろうという見解を示しているそうだ。
あわせて読みたい
【誠実】地下鉄サリン事件の被害者が荒木浩に密着。「贖罪」とは何かを考えさせる衝撃の映画:『AGANAI…
私には、「謝罪すること」が「誠実」だという感覚がない。むしろ映画『AGANAI 地下鉄サリン事件と私』では、「謝罪しない誠実さ」が描かれる。被害者側と加害者側の対話から、「謝罪」「贖罪」の意味と、信じているものを諦めさせることの難しさについて書く
もしもフィクションだったら、「そんな偶然や奇跡が何度も起こるはずがない」と受け取られ、リアリティに欠けると判断されてしまうだろう。それぐらい、後藤死刑囚の告発から事件の立件まで、薄氷を踏むようなギリギリの道筋を辿っていく。普通ならまず結実しなかっただろう展開には実話とは思えないスリリングさがあり、結末が分かっていてもその緊張感に圧倒されてしまうだろう。
『凶悪』の内容紹介
ノンフィクションとフィクションという違いはあれど、描かれている内容は原作と映画で大差ないと思うので、ここでは原作の内容を中心に触れていくことにしよう。
宮本氏が囚人からある話を聞いたことを発端に物語は始まる。
あわせて読みたい
【衝撃】映画『JFK/新証言』(オリヴァー・ストーン)が描く、ケネディ暗殺の”知られざる陰謀”
映画『JFK/新証言』は、「非公開とされてきた『ケネディ暗殺に関する資料』が公開されたことで明らかになった様々な事実を基に、ケネディ暗殺事件の違和感を積み上げていく作品だ。「明確な証拠によって仮説を検証していく」というスタイルが明快であり、信頼度の高い調査と言えるのではないかと思う
彼は以前「FOCUS」という雑誌の編集部におり、取材対象として高橋という男と知り合っていた。取材終了後も個人的に関わりを続けていたのだが、その高橋が「後藤という死刑囚からとんでもない話を聞いた」と言ってきたのだ。
後藤は元暴力団組長。起訴された事件について一審・二審ともに死刑判決を受け、当時は最高裁に上告中の身だった。高橋を通じて後藤を紹介してもらった宮本氏は、直接面会に向かう。

そこで驚くべき話を耳にすることになった。なんと、彼が起訴された犯罪は、ある人物と一緒になって行ったものだというのだ。後藤はその人物を「先生」と呼んだ。そしてこれまで何度も金に困った人間を探し出して誑かし殺害してきたというのだ。高橋から聞いた通り、後藤はこの話をまだ警察には言ってないと主張していた。
あわせて読みたい
【告発】アメリカに”監視”される社会を暴露したスノーデンの苦悩と決断を映し出す映画:『スノーデン』…
NSA(アメリカ国家安全保障局)の最高機密にまでアクセスできたエドワード・スノーデンは、その機密情報を持ち出し内部告発を行った。「アメリカは世界中の通信を傍受している」と。『シチズンフォー』と『スノーデン』の2作品から、彼の告発内容とその葛藤を知る
宮本は当然、彼の話を疑う。死刑を遅らせる作戦かもしれないと考えたのだ。死刑が確定したとしても、未解決の事件の解明のために後藤の存在が必要だとなれば刑の執行が先送りになる可能性はある。そんな狙いがあるのではないかと突きつけた。
後藤は、確かにそういう考えがないとは言わないが、別に理由があるのだと口にする。後藤は捕まる際に、可愛がっていた舎弟を「先生」に託したのだが、「先生」はその舎弟をすぐに自殺に追い込んだという。そのことがどうしても許せない、だから「先生」を追い詰めたいのだと力説する。
とりあえず宮本氏は、後藤の話を聞くことにした。後藤は、「先生」が関与した3件の事件について告発する。
1つ目は、後藤が「先生」と知り合ったばかりの頃のこと。「先生」から、「金の返済の話で揉めて人を殺してしまった」と連絡があり、後藤はその死体の始末の手助けをした。
あわせて読みたい
【天才】映画『Winny』(松本優作監督)で知った、金子勇の凄さと著作権法侵害事件の真相(ビットコイン…
稀代の天才プログラマー・金子勇が著作権法違反で逮捕・起訴された実話を描き出す映画『Winny』は、「警察の凄まじい横暴」「不用意な天才と、テック系知識に明るい弁護士のタッグ」「Winnyが明らかにしたとんでもない真実」など、見どころは多い。「金子勇=サトシ・ナカモト」説についても触れる
2つ目は、土地の所有者を殺し転売した件。2人は、20年間失踪中の身で親兄弟がいないという土地所有者と知り合い、彼を殺して土地を奪っただ。
3つ目は、保険金殺人だ。バブルのあおりを受けて会社が倒産、多額の借金を背負ってしまった内装業者社長。「カーテン屋」と呼ばれたその社長の家族が、保険を掛けた上で彼を殺し、その保険金で借金を整理しようと考える。その計画を「先生」にも持ちかけて協力を仰ぎ、手数料を受け取った。
3つの告発を聞いた宮本氏は、半信半疑のまま裏付け取材を始めることにする。しかし、取材を進める中で、後藤の証言が事実だと確認できるような話が複数耳に入ってきた。もしかしたら後藤は本当に事実を話しているのかもしれない。
ある程度の確信を持てるようになった宮本氏は、後藤と協力しながら、実際に警察を動かして「先生」を立件するための闘いに挑むことになる……。
あわせて読みたい
【知的】「BLって何?」という初心者に魅力を伝える「腐男子」の「BLの想像力と創造力」講座:『ボクた…
「BLは知的遊戯である」という主張には「は?」と感じてしまうでしょうが、本書『ボクたちのBL論』を読めばその印象は変わるかもしれません。「余白の発見と補完」を通じて、「ありとあらゆる2者の間の関係性を解釈する」という創造性は、現実世界にどのような影響を与えているのか
『凶悪』の感想
原作は、「後藤との出会いから、『先生』をいかに追い詰めるかに至る事実を描く」という点がメインになり、やはりその「事実の強度」には圧倒される。印象的だったのは、2つ目の事件の被害者を埋めた場所を後藤が思い出す場面。最初から後藤は宮本氏に、「たぶん思い出せません」と言っていたのだが、宮本氏が拡大した住宅地図を見せたところ一気に記憶が蘇っていくのだ。

このシーンに限らず、宮本氏と後藤の執念が噴出する場面が多々ある。2人の執念が、「獄中からの告発」という”あり得ない状況”を、ピリオドを打てる地点まで前進させた推力になっていると感じた。
映画の方は「フィクション」と謳っていることもあり、恐らく事実ではないだろう脚色が含まれている。そしてその脚色によって、「ジャーナリズムとは?」「家族とは?」という問いが浮き上がるのだ。
あわせて読みたい
【異様】ジャーナリズムの役割って何だ?日本ではまだきちんと機能しているか?報道機関自らが問う映画…
ドキュメンタリーで定評のある東海テレビが、「東海テレビ」を被写体として撮ったドキュメンタリー映画『さよならテレビ』は、「メディアはどうあるべきか?」を問いかける。2011年の信じがたいミスを遠景にしつつ、メディア内部から「メディアの存在意義」を投げかける
そしてその問いの中心に、主人公である雑誌記者・藤井修一(山田孝之)がいる。ちなみに、映画では関係者の名前が変更されており、そのような言及はないが、基本的には「宮本太一=藤井修一」と考えればいいだろう。死刑囚の後藤も、映画では「須藤」である。
藤井は、須藤が告発した事件の取材にのめり込む。もちろんそこには、ジャーナリストとしての使命感や興味もあった。埋もれたままではいけないと感じる現実が目の前にある。そしてそれを暴くことこそがジャーナリストとしてやるべき仕事だ、という思いももちろん彼の中にはあるというわけだ。
しかし一方、映画の中では、「ジャーナリスト」は「印象の良くない存在」として扱われる。一昔前と比べれば今の時代は大分マシだと思うが、昔は「報道被害」という言葉ができるぐらい、加害者側のみならず、被害者側も報道によって傷つけられていた。被害者家族には、「良いジャーナリストと悪いジャーナリストを見分けること」などなかなかできない。藤井が「良いジャーナリスト」なのかはともかくとして、彼が取材先で「敵」のような扱いを受けることもある程度仕方ないことではある。
藤井は、「ジャーナリスト」としての使命感で真相究明を目指す。しかし一方で、そんな「ジャーナリスト」を許容できないと感じる人も描かれる。相手の傷口に土足で入り込むような状況をゼロにはできないのがジャーナリズムの現場だとは思うし、恐らく藤井自身矛盾を抱えながら突っ走る日々だろう。ジャーナリストとして取材に打ち込む藤井の姿から、「ジャーナリズムとは?」という問いが浮かび上がるというわけだ。
あわせて読みたい
【真実?】佐村河内守のゴーストライター騒動に森達也が斬り込んだ『FAKE』は我々に何を問うか?
一時期メディアを騒がせた、佐村河内守の「ゴースト問題」に、森達也が斬り込む。「耳は聴こえないのか?」「作曲はできるのか?」という疑惑を様々な角度から追及しつつ、森達也らしく「事実とは何か?」を問いかける『FAKE』から、「事実の捉え方」について考える
さらにこの映画では、「家族とは?」という問いも突きつけられる。具体的には触れないが、取材に没頭する藤井は、実は「ある家族の問題」を抱えているのだ。しかし彼は、須藤の事件の取材に忙しいことを理由に、その「問題」と向き合うことを避ける。というかむしろ、その「問題」と向き合わずに済むように須藤の事件の取材にのめり込んでいる、と表現してもいいかもしれない。

藤井はその「問題」から逃げ、すべてを妻に押し付ける。完全に、「家族」としては破綻してしまっているのだ。彼は「ジャーナリズム」を理由に家族の問題を後回しにするのだが、果たしてこのスタンスは「正義」と言えるだろうか? 観る人次第で様々な感想になるだろうが、いずれにしても「藤井を100%善」と捉えるのはなかなか無理があると感じる。確かに、藤井がこの事件に執念を燃やさなければ真相は明らかにならなかったわけだが、しかしそのために足元の「家族」を置き去りにしていいのだろうか?
私は生きてるんだよ。
「凶悪」(監督:白石和彌、主演:山田孝之)
そう藤井に零す妻の言葉が非常に印象的だった。
また、須藤や「先生」が関わった事件の描写でも「家族とは?」という問いが突きつけられていく。須藤らが絡む犯罪には、何かしら「家族の問題」が関係するからだ。
あわせて読みたい
【家族】映画『そして父になる』が問う「子どもの親である」、そして「親の子どもである」の意味とは?
「血の繋がり」だけが家族なのか?「将来の幸せ」を与えることが子育てなのか?実際に起こった「赤ちゃんの取り違え事件」に着想を得て、苦悩する家族を是枝裕和が描く映画『そして父になる』から、「家族とは何か?」「子育てや幸せとどう向き合うべきか?」を考える
当然だが、悪いのは事件を起こす須藤や「先生」である。しかし、仮に須藤らを排除したところで問題は解決しない。根本の問題が「家族」にある以上、別の「先生」が現れて事件が起きるだけだ。「凶悪な事件」を映し出すだけではなく、その背景に何があるのかを描くことで、「家族の問題」にも焦点を当てようとする作品だと感じた。
誰がどんな場面で言うセリフかには触れないが、
自分だけはそんな人間じゃないと思ってたんだけどね。
「凶悪」(監督:白石和彌、主演:山田孝之)
という一言は、「家族とは何か?」という問いを強烈に浮かび上がらせるものだと思う。
表面的には「藤井が須藤らの事件の真相を暴こうとする物語」だが、そこに「ジャーナリズムとは?」「家族とは?」という問いが付随することで、「誰が正しくて誰が間違っているのか」「誰が一番『凶悪』なのか」などについて様々な判断が可能になると思う。実際にあった出来事をベースにしながら、そこに脚色を加えることで、「正しさとは?」「正義とは?」と観客に突きつける作品にもなっているのである。
あわせて読みたい
【矛盾】その”誹謗中傷”は真っ当か?映画『万引き家族』から、日本社会の「善悪の判断基準」を考える
どんな理由があれ、法を犯した者は罰せられるべきだと思っている。しかしそれは、善悪の判断とは関係ない。映画『万引き家族』(是枝裕和監督)から、「国民の気分」によって「善悪」が決まる社会の是非と、「善悪の判断を保留する勇気」を持つ生き方について考える
出演:山田孝之, 出演:ピエール瀧, 出演:リリー・フランキー, 出演:池脇千鶴, 出演:白川和子, Writer:高橋泉, Writer:白石和彌, 監督:白石和彌
¥300 (2022/04/08 05:49時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
編集:「新潮45」編集部
¥604 (2022/04/08 05:49時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品視聴済】私が観てきた映画(フィクション)を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が観てきた映画(フィクション)を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。
最後に
あわせて読みたい
【天才】映画『笑いのカイブツ』のモデル「伝説のハガキ職人ツチヤタカユキ」の狂気に共感させられた
『「伝説のハガキ職人」として知られるツチヤタカユキの自伝的小説を基にした映画『笑いのカイブツ』は、凄まじい狂気に彩られた作品だった。「お笑い」にすべてを捧げ、「お笑い」以外はどうでもいいと考えているツチヤタカユキが、「コミュ力」や「人間関係」で躓かされる”理不尽”な世の中に、色々と考えさせられる
原作を読んで「事実の強度」に驚くもよし、映画を観て「様々な問い」を突きつけられるもよし。冒頭で書いた通り、合わせて1作品と捉えると分かりやすい作品だ。また、この記事ではあまり触れなかったが、扱われる事件そのものはあまりにも胸くそ悪いもので、「こんなことができてしまう人間がいるのか」と衝撃を受けるだろうと思う。
現実の「複雑さ」と「恐ろしさ」を是非体感してほしいと思う。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【捏造】袴田事件はついに再審での無罪が決定!冤罪の元死刑囚・袴田巌の現在と姉・秀子の奮闘:映画『…
映画『拳と祈り』は、2024年に再審無罪が確定した「袴田事件」の元死刑囚・袴田巌と、そんな弟を献身的にサポートする姉・秀子の日常を中心に、事件や裁判の凄まじい遍歴を追うドキュメンタリーである。日本の司法史上恐らく初めてだろう「前代未聞の状況」にマスコミで唯一関わることになった監督が使命感を持って追い続けた姉弟の記録
あわせて読みたい
【奇妙】映画『画家と泥棒』は、非日常的なきっかけで始まったあり得ないほど奇跡的な関係を描く
映画『画家と泥棒』は、「自身の絵を盗まれた画家が、盗んだ泥棒と親しくなる」という奇妙奇天烈なきっかけから関係性が始まる物語であり、現実に起きたこととは思えないほど不可思議なドキュメンタリーである。アートを通じて奇妙に通じ合う2人の関係性は、ある種の美しささえ感じさせる、とても素晴らしいものに見えた
あわせて読みたい
【異様】映画『大いなる不在』(近浦啓)は、認知症の父を中心に「記憶」と「存在」の複雑さを描く(主…
「父親が逮捕され、どうやら認知症のようだ」という一報を受けた息子が、30年間ほぼやり取りのなかった父親と再会するところから始まる映画『大いなる不在』は、なんとも言えない「不穏さ」に満ちた物語だった。「記憶」と「存在」のややこしさを問う本作は、「物語」としては成立していないが、圧倒的な“リアリティ”に満ちている
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『憐れみの3章』(ヨルゴス・ランティモス)は意味不明なのに何故か超絶面白かった(主…
映画『憐れみの3章』(ヨルゴス・ランティモス監督)は、最初から最後まで「意味不明」と言っていいレベルで理解できなかったが、しかし「実に良い映画を観たなぁ」という感覚にさせてもくれる、とても素敵な作品だった。さらに、「3つの異なる物語を同じ役者の組み合わせで撮る」という斬新な構成が上手くハマっていたようにも思う
あわせて読みたい
【狂気】「こんな作品を作ろうと考えて実際世に出した川上さわ、ヤベェな」って感じた映画『地獄のSE』…
私が観た時はポレポレ東中野のみで公開されていた映画『地獄のSE』は、最初から最後までイカれ狂ったゲロヤバな作品だった。久しぶりに出会ったな、こんな狂気的な映画。面白かったけど!「こんなヤバい作品を、多くの人の協力を得て作り公開した監督」に対する興味を強く抱かされた作品で、とにかく「凄いモノを観たな」という感じだった
あわせて読みたい
【真相?】映画『マミー』が描く和歌山毒物カレー事件・林眞須美の冤罪の可能性。超面白い!
世間を大騒ぎさせた「和歌山毒物カレー事件」の犯人とされた林眞須美死刑囚は無実かもしれない。映画『マミー』は、そんな可能性を示唆する作品だ。「目撃証言」と「ヒ素の鑑定」が詳細に検証し直され、さらに「保険金詐欺をやっていた」という夫の証言も相まって、証拠的にも感情的にも支持したくなるような驚きの仮説である
あわせて読みたい
【あらすじ】有村架純が保護司を演じた映画『前科者』が抉る、罪を犯した者を待つ「更生」という現実
映画『前科者』は、仮釈放中の元受刑者の更生を手助けするボランティアである「保護司」を中心に据えることで、「元犯罪者をどう受け入れるべきか」「保護司としての葛藤」などを絶妙に描き出す作品。個別の事件への処罰感情はともかく、「社会全体としていかに犯罪を減らしていくか」という観点を忘れるべきではないと私は思っている
あわせて読みたい
【常識】群青いろ制作『彼女はなぜ、猿を逃したか?』は、凄まじく奇妙で、実に魅力的な映画だった(主…
映画『彼女はなぜ、猿を逃したか?』(群青いろ制作)は、「絶妙に奇妙な展開」と「爽快感のあるラスト」の対比が魅力的な作品。主なテーマとして扱われている「週刊誌報道からのネットの炎上」よりも、私は「週刊誌記者が無意識に抱いている思い込み」の方に興味があったし、それを受け流す女子高生の受け答えがとても素敵だった
あわせて読みたい
【狂気】群青いろ制作『雨降って、ジ・エンド。』は、主演の古川琴音が成立させている映画だ
映画『雨降って、ジ・エンド。』は、冒頭からしばらくの間「若い女性とオジサンのちょっと変わった関係」を描く物語なのですが、後半のある時点から「共感を一切排除する」かのごとき展開になる物語です。色んな意味で「普通なら成立し得ない物語」だと思うのですが、古川琴音の演技などのお陰で、絶妙な形で素敵な作品に仕上がっています
あわせて読みたい
【幻惑】映画『落下の解剖学』は、「真実は誰かが”決める”しかない」という現実の不安定さを抉る
「ある死」を巡って混沌とする状況をリアルに描き出す映画『落下の解剖学』は、「客観的な真実にはたどり着けない」という困難さを炙り出す作品に感じられた。事故なのか殺人なのか自殺なのか、明確な証拠が存在しない状況下で、憶測を繋ぎ合わせるようにして進行する「裁判」の様子から、「『真実性』の捉えがたさ」がよく理解できる
あわせて読みたい
【衝撃】EUの難民問題の狂気的縮図!ポーランド・ベラルーシ国境での、国による非人道的対応:映画『人…
上映に際し政府から妨害を受けたという映画『人間の境界』は、ポーランド・ベラルーシ国境で起こっていた凄まじい現実が描かれている。「両国間で中東からの難民を押し付け合う」という醜悪さは見るに絶えないが、そのような状況下でも「可能な範囲でどうにか人助けをしたい」と考える者たちの奮闘には救われる思いがした
あわせて読みたい
【現在】猟師になった東出昌大を追う映画『WILL』は予想外に良かった。山小屋での生活は衝撃だ(監督:…
猟師・東出昌大に密着した映画『WILL』は、思いがけず面白い作品だった。正直、東出昌大にはまったく興味がなく、本作も期待せず観たのだが、異常なほどフラットなスタンス故に周囲にいる人間を否応なく惹きつける「人間力」や、狩猟の世界が突きつける「生と死」というテーマなど実に興味深い。本当に観て良かったなと思う
あわせて読みたい
【真相】飯塚事件は冤罪で死刑執行されたのか?西日本新聞・警察・弁護士が語る葛藤と贖罪:映画『正義…
映画『正義の行方』では、冤罪のまま死刑が執行されたかもしれない「飯塚事件」が扱われる。「久間三千年が犯行を行ったのか」という議論とは別に、「当時の捜査・司法手続きは正しかったのか?」という観点からも捉え直されるべきだし、それを自発的に行った西日本新聞の「再検証連載」はとても素晴らしかったと思う
あわせて読みたい
【赦し】映画『過去負う者』が描く「元犯罪者の更生」から、社会による排除が再犯を生む現実を知る
映画『過去負う者』は、冒頭で「フィクション」だと明示されるにも拘らず、観ながら何度も「ドキュメンタリーだっけ?」と感じさせられるという、実に特異な体験をさせられた作品である。実在する「元犯罪者の更生を支援する団体」を舞台にした物語で、当然それは、私たち一般市民にも無関係ではない話なのだ
あわせて読みたい
【実話】映画『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』が描く、白人警官による黒人射殺事件
映画『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』は、2011年に起こった実際の事件を元にした作品である。何の罪もない黒人男性が、白人警官に射殺されてしまったのだ。5時22分から始まる状況をほぼリアルタイムで描き切る83分間の物語には、役者の凄まじい演技も含め、圧倒されてしまった
あわせて読みたい
【挑戦】映画『燃えあがる女性記者たち』が描く、インドカースト最下位・ダリットの女性による報道
映画『燃えあがる女性記者たち』は、インドで「カースト外の不可触民」として扱われるダリットの女性たちが立ち上げた新聞社「カバル・ラハリヤ」を取り上げる。自身の境遇に抗って、辛い状況にいる人の声を届けたり権力者を糾弾したりする彼女たちの奮闘ぶりが、インドの民主主義を変革させるかもしれない
あわせて読みたい
【歴史】映画『シン・ちむどんどん』は、普天間基地移設問題に絡む辺野古埋め立てを”陽気に”追及する(…
映画『シン・ちむどんどん』は、映画『センキョナンデス』に続く「ダースレイダー・プチ鹿島による選挙戦リポート」第2弾である。今回のターゲットは沖縄知事選。そして本作においては、選挙戦の模様以上に、後半で取り上げられる「普天間基地の辺野古移設問題の掘り下げ」の方がより興味深かった
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『戦場のピアニスト』(ロマン・ポランスキー)が描く、ユダヤ人迫害の衝撃の実話
映画『戦場のピアニスト』の4Kリマスター版を観に行ったところ、上映後のトークイベントに主人公の息子が登壇したので驚いた。何せ私は、本作が「実話を基にしている」ことさえ知らなかったのである。だからその驚きもひとしおだった。ホロコーストの生存者である主人公の壮絶な人生を描き出す、不朽の名作だ
あわせて読みたい
【評価】映画『ゴジラ-1.0』(山崎貴監督)は面白い!迫力満点の映像と絶妙な人間ドラマ(米アカデミー…
米アカデミー賞で視覚効果賞を受賞した映画『ゴジラ-1.0』(山崎貴監督)は、もちろんそのVFXに圧倒される物語なのだが、「人間ドラマ」をきちんと描いていることも印象的だった。「終戦直後を舞台にする」という、ゴジラを描くには様々な意味でハードルのある設定を見事に活かした、とても見事な作品だ
あわせて読みたい
【あらすじ】原爆を作った人の後悔・葛藤を描く映画『オッペンハイマー』のための予習と評価(クリスト…
クリストファー・ノーラン監督作品『オッペンハイマー』は、原爆開発を主導した人物の葛藤・苦悩を複雑に描き出す作品だ。人間が持つ「多面性」を様々な方向から捉えようとする作品であり、受け取り方は人それぞれ異なるだろう。鑑賞前に知っておいた方がいい知識についてまとめたので、参考にしてほしい
あわせて読みたい
【驚愕】映画『リアリティ』の衝撃。FBIによる、機密情報をリークした女性の尋問音源を完全再現(リアリ…
映画『リアリティ』は、恐らく過去類を見ないだろう構成の作品だ。なんと、「FBI捜査官が録音していた実際の音声データのやり取りを一言一句完全に再現した映画」なのである。「第2のスノーデン」とも評される”普通の女性”は、一体何故、国家に反旗を翻す”反逆者”になったのだろうか?
あわせて読みたい
【無謀】映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、脱北ルートに撮影隊が同行する衝撃のドキュメンタリー
北朝鮮からの脱北者に同行し撮影を行う衝撃のドキュメンタリー映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、再現映像を一切使用していない衝撃的な作品だ。危険と隣り合わせの脱北の道程にカメラもついて回り、北朝鮮の厳しい現状と共に、脱北者が置かれた凄まじい状況を映し出す内容に驚かされてしまった
あわせて読みたい
【衝撃】映画『JFK/新証言』(オリヴァー・ストーン)が描く、ケネディ暗殺の”知られざる陰謀”
映画『JFK/新証言』は、「非公開とされてきた『ケネディ暗殺に関する資料』が公開されたことで明らかになった様々な事実を基に、ケネディ暗殺事件の違和感を積み上げていく作品だ。「明確な証拠によって仮説を検証していく」というスタイルが明快であり、信頼度の高い調査と言えるのではないかと思う
あわせて読みたい
【倫理】アート体験の行き着く未来は?映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』が描く狂気の世界(…
「『痛み』を失った世界」で「自然発生的に生まれる新たな『臓器』を除去するライブパフォーマンス」を行うソール・テンサーを主人公にした映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』は、すぐには答えの見出しにくい「境界線上にある事柄」を挑発的に描き出す、実に興味深い物語だ
あわせて読みたい
【天才】映画『Winny』(松本優作監督)で知った、金子勇の凄さと著作権法侵害事件の真相(ビットコイン…
稀代の天才プログラマー・金子勇が著作権法違反で逮捕・起訴された実話を描き出す映画『Winny』は、「警察の凄まじい横暴」「不用意な天才と、テック系知識に明るい弁護士のタッグ」「Winnyが明らかにしたとんでもない真実」など、見どころは多い。「金子勇=サトシ・ナカモト」説についても触れる
あわせて読みたい
【驚嘆】映画『TAR/ター』のリディア・ターと、彼女を演じたケイト・ブランシェットの凄まじさ
天才女性指揮者リディア・ターを強烈に描き出す映画『TAR/ター』は、とんでもない作品だ。「縦軸」としてのターの存在感があまりにも強すぎるため「横軸」を上手く捉えきれず、結果「よく分からなかった」という感想で終わったが、それでも「観て良かった」と感じるほど、揺さぶられる作品だった
あわせて読みたい
【知的】「BLって何?」という初心者に魅力を伝える「腐男子」の「BLの想像力と創造力」講座:『ボクた…
「BLは知的遊戯である」という主張には「は?」と感じてしまうでしょうが、本書『ボクたちのBL論』を読めばその印象は変わるかもしれません。「余白の発見と補完」を通じて、「ありとあらゆる2者の間の関係性を解釈する」という創造性は、現実世界にどのような影響を与えているのか
あわせて読みたい
【感想】これはドキュメンタリー(実話)なのか?映画『女神の継承』が突きつける土着的恐怖
ナ・ホンジンがプロデューサーを務めた映画『女神の継承』は、フィクションなのかドキュメンタリーなのか混乱させる異様な作品だった。タイ東北部で強く信じられている「精霊(ピー)」の信仰をベースに、圧倒的なリアリティで土着的恐怖を描き出す、強烈な作品
あわせて読みたい
【あらすじ】塩田武士『罪の声』が放つ、戦後最大の未解決事件「グリコ・森永事件」の圧倒的”リアル感”
戦後最大の未解決事件である「グリコ・森永事件」では、脅迫に子どもの声が使われていた。私はその事実を、塩田武士『罪の声』という小説を読むまで知らなかった。では、続く疑問はこうだろう。その子どもたちは、今どこでどんな風に生きているのか?その疑問に答える、凄まじい小説だ。
あわせて読みたい
【実話】ポートアーサー銃乱射事件を扱う映画『ニトラム』が示す、犯罪への傾倒に抗えない人生の不条理
オーストラリアで実際に起こった銃乱射事件の犯人の生い立ちを描く映画『ニトラム/NITRAM』は、「頼むから何も起こらないでくれ」と願ってしまうほどの異様な不穏さに満ちている。「社会に順応できない人間」を社会がどう受け入れるべきかについて改めて考えさせる作品だ
あわせて読みたい
【実話】ソ連の衝撃の事実を隠蔽する記者と暴く記者。映画『赤い闇』が描くジャーナリズムの役割と実態
ソ連の「闇」を暴いた名もなき記者の実話を描いた映画『赤い闇』は、「メディアの存在意義」と「メディアとの接し方」を問いかける作品だ。「真実」を届ける「社会の公器」であるべきメディアは、容易に腐敗し得る。情報の受け手である私たちの意識も改めなければならない
あわせて読みたい
【解説】実話を基にした映画『シカゴ7裁判』で知る、「権力の暴走」と、それに正面から立ち向かう爽快さ
ベトナム戦争に反対する若者たちによるデモと、その後開かれた裁判の実話を描く『シカゴ7裁判』はメチャクチャ面白い映画だった。無理筋の起訴を押し付けられる主席検事、常軌を逸した言動を繰り返す不適格な判事、そして一枚岩にはなれない被告人たち。魅力満載の1本だ
あわせて読みたい
【異様】西成のあいりん地区を舞台にした映画『解放区』は、リアルとフェイクの境界が歪んでいる
ドキュメンタリー映画だと思って観に行った『解放区』は、実際にはフィクションだったが、大阪市・西成区を舞台にしていることも相まって、ドキュメンタリー感がとても強い。作品から放たれる「異様さ」が凄まじく、「自分は何を観せられているんだろう」という感覚に襲われた
あわせて読みたい
【執念】「桶川ストーカー事件」で警察とマスコミの怠慢を暴き、社会を動かした清水潔の凄まじい取材:…
『殺人犯はそこにいる』(文庫X)で凄まじい巨悪を暴いた清水潔は、それよりずっと以前、週刊誌記者時代にも「桶川ストーカー殺人事件」で壮絶な取材を行っていた。著者の奮闘を契機に「ストーカー規制法」が制定されたほどの事件は、何故起こり、どんな問題を喚起したのか
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『1917』は、ワンカット風の凄まじい撮影手法が「戦場の壮絶な重圧」を見事に体感させる
映画『1917 命をかけた伝令』は、「全編ワンカット風」という凄まじい撮影手法で注目されたが、私は、その撮影手法が「戦場における緊迫感」を見事に増幅させているという点に驚かされた。「物語の中身」と「撮影手法」が素晴らしく合致したとんでもない作品だ
あわせて読みたい
【考察】ヨネダコウ『囀る鳥は羽ばたかない』は、BLの枠組みの中で「歪んだ人間」をリアルに描き出す
2巻までしか読んでいないが、ヨネダコウのマンガ『囀る鳥は羽ばたかない』は、「ヤクザ」「BL」という使い古されたフォーマットを使って、異次元の物語を紡ぎ出す作品だ。BLだが、BLという外枠を脇役にしてしまう矢代という歪んだ男の存在感が凄まじい。
あわせて読みたい
【感想】阿部サダヲが狂気を怪演。映画『死刑にいたる病』が突きつける「生きるのに必要なもの」の違い
サイコパスの連続殺人鬼・榛村大和を阿部サダヲが演じる映画『死刑にいたる病』は、「生きていくのに必要なもの」について考えさせる映画でもある。目に光を感じさせない阿部サダヲの演技が、リアリティを感じにくい「榛村大和」という人物を見事に屹立させる素晴らしい映画
あわせて読みたい
【あらすじ】嵐莉菜主演映画『マイスモールランド』は、日本の難民問題とクルド人の現状、入管の酷さを描く
映画『マイスモールランド』はフィクションではあるが、「日本に住む難民の厳しい現実」をリアルに描き出す作品だ。『東京クルド』『牛久』などのドキュメンタリー映画を観て「知識」としては知っていた「現実」が、当事者にどれほどの苦しみを与えるのか想像させられた
あわせて読みたい
【事件】デュポン社のテフロン加工が有害だと示した男の執念の実話を描く映画『ダーク・ウォーターズ』
世界的大企業デュポン社が、自社製品「テフロン」の危険性を40年以上前に把握しながら公表せず、莫大な利益を上げてきた事件の真相を暴き出した1人の弁護士がいる。映画『ダーク・ウォーターズ』は、大企業相手に闘いを挑み、住民と正義のために走り続けた実在の人物の勇敢さを描き出す
あわせて読みたい
【病理】本田靖春が「吉展ちゃん事件」を追う。誘拐を捜査する警察のお粗末さと時代を反映する犯罪:『…
「戦後最大の誘拐事件」と言われ、警察の初歩的なミスなどにより事件解決に膨大な月日を要した「吉展ちゃん誘拐殺人事件」。その発端から捜査体制、顛末までをジャーナリスト・本田靖春が徹底した取材で描き出す『誘拐』は、「『犯罪』とは『社会の病理』である」と明確に示している
あわせて読みたい
【誇り】福島民友新聞の記者は、東日本大震災直後海に向かった。門田隆将が「新聞人の使命」を描く本:…
自身も東日本大震災の被災者でありながら、「紙齢をつなぐ」ために取材に奔走した福島民友新聞の記者の面々。『記者たちは海に向かった』では、取材中に命を落とした若手記者を中心に据え、葛藤・後悔・使命感などを描き出す。「新聞」という”モノ”に乗っかっている重みを実感できる1冊
あわせて読みたい
【衝撃】『ゆきゆきて、神軍』はとんでもないドキュメンタリー映画だ。虚実が果てしなく入り混じる傑作
奥崎謙三という元兵士のアナーキストに密着する『ゆきゆきて、神軍』。ドキュメンタリー映画の名作として名前だけは知っていたが、まさかこんなとんでもない映画だったとはと驚かされた。トークショーで監督が「自分の意向を無視した編集だった」と語っていたのも印象的
あわせて読みたい
【評価】元総理大臣・菅義偉の来歴・政治手腕・疑惑を炙り出す映画。権力を得た「令和おじさん」の素顔…
「地盤・看板・カバン」を持たずに、総理大臣にまで上り詰めた菅義偉を追うドキュメンタリー映画『パンケーキを毒見する』では、その来歴や政治手腕、疑惑などが描かれる。学生団体「ivote」に所属する現役大学生による「若者から政治はどう見えるか」も興味深い
あわせて読みたい
【驚異】信念を貫く勇敢さを、「銃を持たずに戦場に立つ」という形で示した実在の兵士の凄まじさ:映画…
第二次世界大戦で最も過酷な戦場の1つと言われた「前田高地(ハクソー・リッジ)」を、銃を持たずに駆け回り信じがたい功績を残した衛生兵がいた。実在の人物をモデルにした映画『ハクソー・リッジ』から、「戦争の悲惨さ」だけでなく、「信念を貫くことの大事さ」を学ぶ
あわせて読みたい
【実話】権力の濫用を監視するマスコミが「教会の暗部」を暴く映画『スポットライト』が現代社会を斬る
地方紙である「ボストン・グローブ紙」は、数多くの神父が長年に渡り子どもに対して性的虐待を行い、その事実を教会全体で隠蔽していたという衝撃の事実を明らかにした。彼らの奮闘の実話を映画化した『スポットライト』から、「権力の監視」の重要性を改めて理解する
あわせて読みたい
【不正義】正しく行使されない権力こそ真の”悪”である。我々はその現実にどう立ち向かうべきだろうか:…
権力を持つ者のタガが外れてしまえば、市民は為す術がない。そんな状況に置かれた時、私たちにはどんな選択肢があるだろうか?白人警官が黒人を脅して殺害した、50年前の実際の事件をモチーフにした映画『デトロイト』から、「権力による不正義」の恐ろしさを知る
あわせて読みたい
【想像力】「知らなかったから仕方ない」で済ませていいのか?第二の「光州事件」は今もどこかで起きて…
「心地いい情報」だけに浸り、「知るべきことを知らなくても恥ずかしくない世の中」を生きてしまっている私たちは、世界で何が起こっているのかあまりに知らない。「光州事件」を描く映画『タクシー運転手 約束は海を越えて』から、世界の見方を考える
あわせて読みたい
【驚愕】正義は、人間の尊厳を奪わずに貫かれるべきだ。独裁政権を打倒した韓国の民衆の奮闘を描く映画…
たった30年前の韓国で、これほど恐ろしい出来事が起こっていたとは。「正義の実現」のために苛烈な「スパイ狩り」を行う秘密警察の横暴をきっかけに民主化運動が激化し、独裁政権が打倒された史実を描く『1987、ある闘いの真実』から、「正義」について考える
あわせて読みたい
【勇敢】”報道”は被害者を生む。私たちも同罪だ。”批判”による”正義の実現”は正義だろうか?:『リチャ…
「爆弾事件の被害を最小限に食い止めた英雄」が、メディアの勇み足のせいで「爆弾事件の犯人」と報じられてしまった実話を元にした映画『リチャード・ジュエル』から、「他人を公然と批判する行為」の是非と、「再発防止という名の正義」のあり方について考える
あわせて読みたい
【権利】衝撃のドキュメンタリー映画『ヤクザと憲法』は、「異質さを排除する社会」と「生きる権利」を問う
「ヤクザ」が排除された現在でも、「ヤクザが担ってきた機能」が不要になるわけじゃない。ではそれを、公権力が代替するのだろうか?実際の組事務所(東組清勇会)にカメラを持ち込むドキュメンタリー映画『ヤクザと憲法』が映し出す川口和秀・松山尚人・河野裕之の姿から、「基本的人権」のあり方について考えさせられた
あわせて読みたい
【告発】アメリカに”監視”される社会を暴露したスノーデンの苦悩と決断を映し出す映画:『スノーデン』…
NSA(アメリカ国家安全保障局)の最高機密にまでアクセスできたエドワード・スノーデンは、その機密情報を持ち出し内部告発を行った。「アメリカは世界中の通信を傍受している」と。『シチズンフォー』と『スノーデン』の2作品から、彼の告発内容とその葛藤を知る
あわせて読みたい
【絶望】「人生上手くいかない」と感じる時、彼を思い出してほしい。壮絶な過去を背負って生きる彼を:…
「北九州連続監禁殺人事件」という、マスコミも報道規制するほどの残虐事件。その「主犯の息子」として生きざるを得なかった男の壮絶な人生。「ザ・ノンフィクション」のプロデューサーが『人殺しの息子と呼ばれて』で改めて取り上げた「真摯な男」の生き様と覚悟
あわせて読みたい
【称賛】生き様がかっこいい。ムンバイのホテルのテロ事件で宿泊客を守り抜いたスタッフたち:映画『ホ…
インドの高級ホテルで実際に起こったテロ事件を元にした映画『ホテル・ムンバイ』。恐ろしいほどの臨場感で、当時の恐怖を観客に体感させる映画であり、だからこそ余計に、「逃げる選択」もできたホテルスタッフたちが自らの意思で残り、宿泊を助けた事実に感銘を受ける
あわせて読みたい
【絶望】権力の濫用を止めるのは我々だ。映画『新聞記者』から「ソフトな独裁国家・日本」の今を知る
私個人は、「ビジョンの達成」のためなら「ソフトな独裁」を許容する。しかし今の日本は、そもそも「ビジョン」などなく、「ソフトな独裁状態」だけが続いていると感じた。映画『新聞記者』をベースに、私たちがどれだけ絶望的な国に生きているのかを理解する
あわせて読みたい
【実話】「家族とうまくいかない現実」に正解はあるか?選択肢が無いと感じる時、何を”選ぶ”べきか?:…
「自分の子どもなんだから、どんな風に育てたって勝手でしょ」という親の意見が正しいはずはないが、この言葉に反論することは難しい。虐待しようが生活能力が無かろうが、親は親だからだ。映画『MOTHER マザー』から、不正解しかない人生を考える
あわせて読みたい
【正義】マイノリティはどう生き、どう扱われるべきかを描く映画。「ルールを守る」だけが正解か?:映…
社会的弱者が闘争の末に権利を勝ち取ってきた歴史を知った上で私は、闘わずとも権利が認められるべきだと思っている。そして、そういう社会でない以上、「正義のためにルールを破るしかない」状況もある。映画『パブリック』から、ルールと正義のバランスを考える
あわせて読みたい
【勇敢】後悔しない生き方のために”間違い”を犯せるか?法に背いてでも正義を貫いた女性の生き様:映画…
国の諜報機関の職員でありながら、「イラク戦争を正当化する」という巨大な策略を知り、守秘義務違反をおかしてまで真実を明らかにしようとした実在の女性を描く映画『オフィシャル・シークレット』から、「法を守る」こと以上に重要な生き方の指針を学ぶ
あわせて読みたい
【驚愕】「金正男の殺人犯」は”あなた”だったかも。「人気者になりたい女性」が陥った巧妙な罠:映画『…
金正男が暗殺された事件は、世界中で驚きをもって報じられた。その実行犯である2人の女性は、「有名にならないか?」と声を掛けられて暗殺者に仕立て上げられてしまった普通の人だ。映画『わたしは金正男を殺していない』から、危険と隣り合わせの現状を知る
あわせて読みたい
【誠実】地下鉄サリン事件の被害者が荒木浩に密着。「贖罪」とは何かを考えさせる衝撃の映画:『AGANAI…
私には、「謝罪すること」が「誠実」だという感覚がない。むしろ映画『AGANAI 地下鉄サリン事件と私』では、「謝罪しない誠実さ」が描かれる。被害者側と加害者側の対話から、「謝罪」「贖罪」の意味と、信じているものを諦めさせることの難しさについて書く
あわせて読みたい
【衝撃】森達也『A3』が指摘。地下鉄サリン事件を起こしたオウム真理教は社会を激変させた
「オウム真理教は特別だ、という理由で作られた”例外”が、いつの間にか社会の”前提”になっている」これが、森達也『A3』の主張の要点だ。異常な状態で続けられた麻原彰晃の裁判を傍聴したことをきっかけに、社会の”異様な”変質の正体を理解する。
あわせて読みたい
【加虐】メディアの役割とは?森達也『A』が提示した「事実を報じる限界」と「思考停止社会」
オウム真理教の内部に潜入した、森達也のドキュメンタリー映画『A』は衝撃を与えた。しかしそれは、宗教団体ではなく、社会の方を切り取った作品だった。思考することを止めた社会の加虐性と、客観的な事実など切り取れないという現実について書く
あわせて読みたい
【恐怖】SNSの危険性と子供の守り方を、ドキュメンタリー映画『SNS 少女たちの10日間』で学ぶ
実際にチェコの警察を動かした衝撃のドキュメンタリー映画『SNS 少女たちの10日間』は、少女の「寂しさ」に付け込むおっさんどもの醜悪さに満ちあふれている。「WEBの利用制限」だけでは子どもを守りきれない現実を、リアルなものとして実感すべき
あわせて読みたい
【衝撃】壮絶な戦争映画。最愛の娘を「産んで後悔している」と呟く母らは、正義のために戦場に留まる:…
こんな映画、二度と存在し得ないのではないかと感じるほど衝撃を受けた『娘は戦場で生まれた』。母であり革命家でもあるジャーナリストは、爆撃の続くシリアの街を記録し続け、同じ街で娘を産み育てた。「知らなかった」で済ませていい現実じゃない。
あわせて読みたい
【勇敢】日本を救った吉田昌郎と、福島第一原発事故に死を賭して立ち向かった者たちの極限を知る:『死…
日本は、死を覚悟して福島第一原発に残った「Fukushima50」に救われた。東京を含めた東日本が壊滅してもおかしくなかった大災害において、現場の人間が何を考えどう行動したのかを、『死の淵を見た男』をベースに書く。全日本人必読の書
あわせて読みたい
【驚愕】日本の司法は終わってる。「中世レベル」で「無罪判決が多いと出世に不利」な腐った現実:『裁…
三権分立の一翼を担う裁判所のことを、私たちはよく知らない。元エリート裁判官・瀬木比呂志と事件記者・清水潔の対談本『裁判所の正体』をベースに、「裁判所による統制」と「権力との癒着」について書く。「中世レベル」とさえ言われる日本の司法制度の現実は、「裁判になんか関わることない」という人も無視できないはずだ
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
メディア・マスコミ・表現の自由【本・映画の感想】 | ルシルナ
様々な現実を理解する上で、マスコミや出版などメディアの役割は非常に大きいでしょう。情報を受け取る我々が正しいリテラシーを持っていなければ、誤った情報を発信する側…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…


























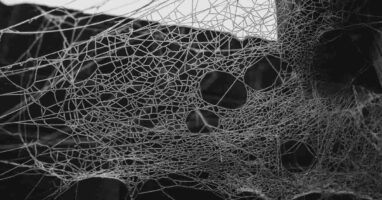

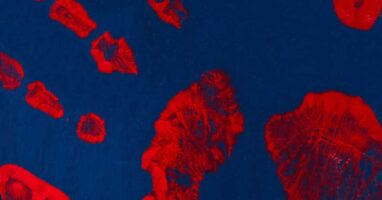






































































コメント