目次
はじめに
この記事で取り上げる映画

「オッペンハイマー」公式HP
この映画をガイドにしながら記事を書いていきます
今どこで観れるのか?
公式HPの劇場情報をご覧ください
この記事の3つの要点
- 決して難解な作品ではないが、まったくの知識ゼロで観ると混乱するかもしれないので、事前にある程度予習しておくことをオススメする
- 「『原爆開発』は避けがたかったが、『日本への投下』は許容できない」という私の感覚について
- 「共産主義との関わり」を丁寧に深く掘り下げることで、オッペンハイマーという人物の複雑さを明らかにしようとする物語
これまでのクリストファー・ノーラン作品とは大分趣の異なる作品だが、やはり観て良かったと感じさせられた
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
記事中の引用は、映画館で取ったメモを参考にしているので、正確なものではありません
映画『オッペンハイマー』(クリストファー・ノーラン監督)は知識無しではちょっと難しい映画だ。予習をしてから観た方がいい

なかなか難しい映画だった。これは決して「難解」という意味ではない。物語の構造としては「1人の人間の苦悩を描き出す」という作品であり、そういう意味ではシンプルな映画である。ただ、「きちんと鑑賞するには知識が要る」という意味で、ハードルがあるように感じられた。
あわせて読みたい
【考察】映画『テネット』の回転ドアの正体をネタバレ解説。「時間反転」ではなく「物質・反物質反転」…
クリストファー・ノーラン監督の「TENET テネット」は、「陽電子」「反物質」など量子力学の知見が満載です。この記事では、映画の内容そのものではなく、時間反転装置として登場する「回転ドア」の仕組みを端緒に、映画全体の設定を科学的に説明します
というわけでこの記事ではまず、「鑑賞前に知っておいても良いだろう知識」についてまとめておくことにする。
ちなみに、私自身のことについて少し触れておこう。私は元々科学(特に物理学)が好きで、原子爆弾の技術の根幹を成す「量子力学」についても、一般書に書かれているレベルの知識程度ではあるがそれなりに知ってはいる。また科学の知識だけではなく、科学史に関する本も好きなので、科学史を彩った科学者についてもそれなりには詳しい。特にアインシュタインが絡むものについてはよく読んでおり、そのため「マンハッタン計画」周辺の話は結構知っていると思う(アインシュタインは「マンハッタン計画」そのものには関わらなかったが、より重要な形で関係している)。その辺りの知識をまとめたkindle本も出版しているので、以下にリンクした記事を見て興味があれば是非読んでみてほしい。
著:犀川後藤
¥700 (2024/05/25 23:15時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を…
Kindleで本を出版しました。タイトルは、『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を分かりやすく書いた本:相対性理論も宇宙論も量子論も』です。科学や科学者に関する、文系の人でも読んでもらえる作品に仕上げました。そんな自著について紹介をしています。
そして本作『オッペンハイマー』は、「オッペンハイマーの人物像」「マンハッタン計画」などに関する知識があまりない人には、ついていくのがちょっと難しい作品かもしれない。そういう意味で、あらかじめ知識を入れておくことは重要だと思う。
鑑賞前に知っておいても良いだろう知識について
本作では主に2人の人物に焦点が当てられる。1人はもちろんオッペンハイマーだが、もう1人はストローズという人物だ。私は本作鑑賞時点で、このストローズという人物のことを知らなかった。確かに、「オッペンハイマー」の物語を描き出す上で対比的な存在だとは思ったが、科学史においてはさほど重要な人物ではないはずだ。
あわせて読みたい
【生涯】天才数学者ガロアが20歳で決闘で命を落とすまで。時代を先駆けた男の不幸な生い立ち:『ガロア…
現代数学に不可欠な「群論」をたった1人で生み出し、20歳という若さで決闘で亡くなったガロアは、どう生きたのか?『ガロア 天才数学者の生涯』から、数学に関心を抱くようになったきっかけや、信じられないほどの不運が彼の人生をどう変えてしまったのかを知る
ストローズについては後で紹介するとして、本作はこの2人の人物の物語が並行して描かれる構成になっている。オッペンハイマーは「保安聴聞会で尋問を受けている様子」が、そしてストローズは「閣僚として招聘するかを決める公聴会に出席している様子」が映し出されるのだ。オッペンハイマーの保安聴聞会の様子はカラーで、そしてストローズの公聴会の様子はモノクロで描かれるということを理解しておけば、混乱することはないだろう。
また、保安聴聞会・公聴会の様子に加えて、保安聴聞会・公聴会中に彼らが過去のことを回想するシーンも挟み込まれる。そしてその中で、「アメリカでは数少ない量子力学の理論物理学者だったオッペンハイマーが、マンハッタン計画のリーダーに就いてから戦後の混乱に巻き込まれるまでの物語」を描き出していくというわけだ。
では、ストローズとは一体何者なのか。彼は原子力委員会の委員長を務めた人物であり、また、戦後にオッペンハイマーをプリンストン高等研究所(アインシュタインの晩年の所属先としても知られる)の所長として迎え入れた人物でもある。そしてオッペンハイマーは戦後、原子力委員会の諮問委員会議長を務めており、原子力委員会に意見する立場にいた。もちろん、その時の委員長はストローズである。ここを直接の接点に、両者の対立が描かれるというわけだ。
あわせて読みたい
【勇敢】日本を救った吉田昌郎と、福島第一原発事故に死を賭して立ち向かった者たちの極限を知る:『死…
日本は、死を覚悟して福島第一原発に残った「Fukushima50」に救われた。東京を含めた東日本が壊滅してもおかしくなかった大災害において、現場の人間が何を考えどう行動したのかを、『死の淵を見た男』をベースに書く。全日本人必読の書
では、オッペンハイマーとストローズは一体何で対立していたのだろうか。それは「水爆の開発」である。私は本作を観る前の時点で、「オッペンハイマーは戦後、水爆の開発に反対した」という事実だけは知っていたのだが、詳しい事情は理解していなかった。本作ではオッペンハイマーとストローズがある会議の場で直接的に対立する場面が描かれている。そしてその描写によれば、「水爆開発を推進すべきと考えるストローズ」に対し、オッペンハイマーは「アメリカが開発に着手したらソ連も追随せざるを得なくなる」という理由で反対していたようだ。
そしてそのような背景もあり、聴聞会・公聴会が開かれているのである。「聴聞会・公聴会が何故開かれたのか」については、映画の後半で詳しく明らかにされる部分もあるため、この記事ではこれ以上触れないことにするが、映画を観る上ではとりあえず、「オッペンハイマーとストローズの対立のせいで聴聞会・公聴会が開かれた」ぐらいに捉えておけば十分だろう。
では、それぞれの会において、一体何が議題とされているのだろうか?
あわせて読みたい
【衝撃】映画『JFK/新証言』(オリヴァー・ストーン)が描く、ケネディ暗殺の”知られざる陰謀”
映画『JFK/新証言』は、「非公開とされてきた『ケネディ暗殺に関する資料』が公開されたことで明らかになった様々な事実を基に、ケネディ暗殺事件の違和感を積み上げていく作品だ。「明確な証拠によって仮説を検証していく」というスタイルが明快であり、信頼度の高い調査と言えるのではないかと思う
まず、ストローズの公聴会の方から説明していこう。この公聴会は基本的に、「閣僚を任命するための形式的なもの」でしかない。映画の早い段階で、そのことは示唆される。「ちゃんとした形式を踏んで任命した」という事実を作るための会であり、普通は荒れるようなことはない。側近がストローズにそのように伝えているのだ。しかし実際には、ストローズは公聴会でオッペンハイマーとの関わりについてかなり突っ込んだ質問を受ける。「形式的」とはちょっと言えないような展開になっていくというわけだ。

そこには1つ大きな理由があった。「戦後、オッペンハイマーに『共産主義者』というレッテルが貼られたこと」だ。「マンハッタン計画」に関する本を読むと、このような「赤狩り」の話が出てくる。本作で描かれるのも、登場人物の1人が「”ちょっと赤い”だけでも、すぐに大学を追われた」と語っていたぐらい、「共産主義者」との関わりが厳しく指摘される時代だったのだ。そして、オッペンハイマーに「共産主義者」の疑いが掛けられたため、プリンストン高等研究所の所長に彼を任命したストローズにも、同じような疑いが向けられたのである。
それでは、もう一方のオッペンハイマーの聴聞会では何が問われているのだろうか。もちろんそれは、「『共産主義者』か否か」である。しかし、この聴聞会には一応表向きの目的が用意されていた。それは「アクセス権の更新の可否」である。機密情報へのアクセス権の更新を審議するという名目であり、「共産主義者」であれば当然更新は出来ない。そのため「『共産主義者』か否か」が執拗に問われているというわけだ。そしてこの聴聞会にはオッペンハイマーだけではなく、彼の周辺にいる人物も多数呼ばれている。そして彼らからも話を聞くことで、オッペンハイマーの疑惑について判定しようというわけだ。
あわせて読みたい
【衝撃】匿名監督によるドキュメンタリー映画『理大囲城』は、香港デモ最大の衝撃である籠城戦の内部を映す
香港民主化デモにおける最大の衝撃を内側から描く映画『理大囲城』は、とんでもないドキュメンタリー映画だった。香港理工大学での13日間に渡る籠城戦のリアルを、デモ隊と共に残って撮影し続けた匿名監督たちによる映像は、ギリギリの判断を迫られる若者たちの壮絶な現実を映し出す
鑑賞前にこの辺りの情報を知っておけば、あまり混乱することなく作品を観られるのではないかと思う。逆に言えば、このようなことを知らずに観に行くと、「聴聞会・公聴会で何が行われているのか」を理解することはかなり難しくなるだろう。
一方、「回想シーン」を観るにあたって、難しいことは特に何もないはずだ。確かに、時折「物理学の専門用語」が出てくるが、それらについて知っている必要はない。物語を把握する上であらかじめ知っておくべき科学知識は、私が観る限り無かったように思う。なので、理解できない単語が出てきたとしても、「物理学者のリアルな日常を描いているシーンなのだろう」ぐらいに捉えておけば十分である。科学知識で言えばやはり、圧倒的に映画『TENET』の方がハードルが高かった。あの作品こそ、「量子力学」の知識無しにはまったく理解不能だと思う。
あわせて読みたい
【バトル】量子力学の歴史はこの1冊で。先駆者プランクから批判者アインシュタインまですべて描く:『量…
20世紀に生まれた量子論は、時代を彩る天才科学者たちの侃々諤々の議論から生み出された。アインシュタインは生涯量子論に反対し続けたことで知られているが、しかし彼の批判によって新たな知見も生まれた。『量子革命』から、量子論誕生の歴史を知る
「原爆開発に着手したことは仕方なかった」と私は考えている
本作は、「オッペンハイマーとストローズの対立」や「オッペンハイマーの原爆開発との関わり方」などを描き出すことによって、「世界を一変させる兵器を作り出してしまった男の苦悩」を描き出す物語である。本作はまず、そのような「個人史」として受け取られるべき作品だと思う。しかし「唯一の被爆国」である日本に生まれ育った人間としてはやはり、「原子爆弾の開発・投下に関する是非」について考えないわけにはいかないだろう。そこでしばらく、この点に関する私自身の考え方について触れておこうと思う。
まず大前提として、「“現代”を生きる“日本人”の私」の観点からすれば、当然「原爆投下は誤りだった」という思考になる。“現代”“日本人”を強調したが、まずは“日本人”の方から説明しよう。詳しくは知らないが、アメリカでは日本への原爆投下について、「戦争終結が早まり、余計な犠牲者を出さずに済んだ」という解釈が存在するようだ。この解釈を支持する人がどれぐらいの割合なのか分からないが、アメリカの視点に立てばそのように見えるということなのだろう。しかしやはり“日本人”としては、そのような理屈をどれだけ示されたところで「なるほど、だったら原爆投下は妥当でしたよね」とはならないはずだ。このような点を“日本人”として強調したつもりである。
あわせて読みたい
【アメリカ】長崎の「原爆ドーム」はなぜ残らなかった?爆心地にあった「浦上天主堂」の数奇な歴史:『…
原爆投下で半壊し、廃墟と化したキリスト教の大聖堂「浦上天主堂」。しかし何故か、「長崎の原爆ドーム」としては残されず、解体されてしまった。『ナガサキ 消えたもう一つの「原爆ドーム」』は、「浦上天主堂」を巡る知られざる歴史を掘り下げ、アメリカの強かさを描き出す

それでは、もう一方の”現代”の方に移ろう。この話は原爆投下に限るものではないのだが、私はその対象が何であれ、「”同時代”にその是非を判断すること」は難しいと考えている。作中では何度か、「歴史に裁かれるぞ」という主旨のセリフが出てくるのだが、まさにその通りだろう。中曽根康弘元総理が「政治家とは歴史という名の法廷で裁かれる被告である」という言葉を残したそうだが、まさに「政治家の判断によって決する事象」は概ね、「それを行った時点では是非の判断が不可能」であると考えるべきではないかと私は思っている。
「原爆投下」から見て「未来」を生きる私からすれば明確に「誤り」であると言えるが、しかし”同時代”の人にとっても同じ判断になるとは限らない。私は常に、そのような意識を持って物事の是非を捉えようと意識しているのだ。
そのためまずは、「”同時代”の人にとって『原爆開発』とはどのような意味を持っていたのか」について説明することにしよう。本作でもその点については多少触れられており、さらに私がこれまで読んできた本の知識を加える形で状況を整理したいと思う。
あわせて読みたい
【天才】『ご冗談でしょう、ファインマンさん』は、科学者のイメージが変わる逸話満載の非・科学エッセイ
「天才科学者」と言えばアインシュタインやニュートン、ホーキングが思い浮かぶだろうが、「科学者らしくないエピソード満載の天才科学者」という意味ではファインマンがずば抜けている。世界的大ベストセラー『ご冗談でしょう、ファインマンさん』は、「科学」をほぼ扱わないエッセイです
オッペンハイマーがマンハッタン計画のリーダーに就いたばかりの頃、物理学者で友人のラビから、「私はここには来ない」と告げられる場面がある。「ここ」とは、マンハッタン計画を遂行する場所として選ばれたロスアラモスのことだ。そして、ラビはさらに続けて、「物理学300年の歴史が爆弾なのか」と、原爆開発のリーダーを引き受けたオッペンハイマーを止めようとするような発言をする。
それに対してオッペンハイマーは次のように返したのだ。
分からない。そんな兵器を私たちが預かってよいかなど。
でも、ナチスではいけない。
あわせて読みたい
【実話】「アウシュビッツ・レポート」に記載された「収容所の記録」を持ち出した驚愕の史実を描く映画
アウシュビッツ強制収容所から抜け出し、詳細な記録と共にホロコーストの実態を世界に明らかにした人物がいる。そんな史実を私はまったく知らなかった。世界がホロコーストを知るきっかけとなった2人の奮闘を描く映画『アウシュヴィッツ・レポート』の凄まじい衝撃
そう、アメリカの原爆開発は、この点を抜きに考えることは出来ない。後で触れるが、アインシュタインもまさにこの点を懸念して、原爆開発を大統領に進言する手紙を書いたのだ(ここにも色々な歴史があるのだが、本筋とは関係ないので省略する。興味がある方は、冒頭で紹介した私のkindle本を読んでほしい)。
当時は「ナチスドイツ」こそが世界の脅威だった。ヒトラーを筆頭にした「何をするか分からない狂気的な集団」と目されていたのである。では、そんなナチスドイツが世界で初めて原子爆弾を開発してしまったらどうなるのだろうか? 当時この問題に懸念を抱いていたすべての人間は、「ナチスドイツなら、原子爆弾を使って世界を終焉に叩き込むだろう」と考えていたはずだ。オッペンハイマーの「ナチスではいけない」という発言には、このような背景があったのである。
また、「ナチスドイツが原子爆弾を先に開発するかもしれない」という懸念は、かなり現実的なものでもあった。というのも、先述した通り原子爆弾の根幹を成すのは「量子力学」なのだが、量子力学はまさにドイツで花開いた学術分野なのである。当時のドイツにはハイゼンベルグ、プランク、ボルン、ゾンマーフェルトなど、量子力学の創設・発展に重要な寄与を果たした理論物理学者がたくさんいた。まさにドイツこそ、量子力学の最先端の地だったのである。
あわせて読みたい
【敗北】「もつれ」から量子論の基礎を学ぶ。それまでの科学では説明不能な「異次元の現象」とは?:『…
アインシュタインは量子力学を生涯受け入れなかったのだが、アインシュタインが批判し続けたことによって明らかになったこともある。「もつれ」の重要性もその一つだ。『宇宙は「もつれ」でできている』から量子力学の基礎を成す現象を知る。
かたやアメリカには、量子力学を研究する理論物理学者はほとんど存在しなかった。そして「そのような状況を、オッペンハイマーが変えた」と言えるだろう。彼が大学内で量子力学の講座を立ち上げた際、生徒はたった1人という状態だった。そこから少しずつ勢力を拡大していき、アメリカでも量子力学の研究が盛んになっていったというわけだ。
しかしそんな状態であれば、ドイツとの差は歴然としていたはずである。ある場面でオッペンハイマーは、「ドイツは2年先を進んでいる」と語っていた。それが事実だったかどうかはともかく、アメリカ(あるいはオッペンハイマー)がそのように捉えていたのだとすれば、当然「ナチスドイツが先に原子爆弾を開発してもおかしくない」と思うだろう。そしてだからこそアメリカの科学者たちは、「原子爆弾を”作らなければならない”」と考えていたのである。これが”同時代”の認識というわけだ。
ちなみに余談だが、戦後明らかになったところによると、ドイツの原爆開発はまったく進んでいなかったという。ヒトラーが「半年で成果の出る研究」しか認めなかったからである。つまり、「ナチスドイツが先に原子爆弾を開発するかもしれない」というのは単なる幻想でしかなかったというわけだ。しかしそうだとしても、アメリカの科学者を責めるのは酷というものだろう。当時の彼らにとっては、間違いなく「現実的な脅威」だったのだから。
あわせて読みたい
【狂気】ホロコーストはなぜ起きた?映画『ヒトラーのための虐殺会議』が描くヴァンゼー会議の真実
映画『ヒトラーのための虐殺会議』は、ホロコーストの計画について話し合われた「ヴァンゼー会議」を描き出す作品だ。唯一1部だけ残った議事録を基に作られた本作は、「ユダヤ人虐殺」をイベントの準備でもしているかのように「理性的」に計画する様を映し出す。その「狂気」に驚かされてしまった。
またそもそもだが、マンハッタン計画が始動したきっかけは、「アインシュタインがルーズベルト大統領に宛てて書いた手紙」である。そしてそこにも、「ナチスドイツよりも先に原子爆弾を開発すべき」と書かれていた。そのため、オッペンハイマーが「原爆の父」と呼ばれるのに対して、アインシュタインは「原爆の祖父」と称されている。ただしアインシュタインは、ドイツから亡命した科学者だったため、マンハッタン計画そのものには呼ばれなかった。

ちなみに、アインシュタインの名誉のために付け加えておくと、彼は戦後「ラッセル=アインシュタイン宣言」を取りまとめている。これは「原爆開発には参加しない」という考えに賛同した科学者たちによる宣言だ。アインシュタインは、日本へ原爆が投下されたことを知り、間接的にとはいえ重大な形で原爆開発に関わってしまったことを生涯後悔したと言われている。
さて話を戻そう。アメリカによる原爆開発は「ナチスドイツへの恐怖」に追い立てられたものだった。ここで、少し「歴史のif」を想像してみたいと思う。仮にたったの1年で原子爆弾の開発が出来たのだとしよう。この時点ではまだ、ナチスドイツは世界の脅威だった。となれば、アメリカは恐らく、完成させた原子爆弾をドイツに投下したのではないだろうか。そうすれば、「ナチスドイツによる原爆開発の阻止」と「戦争の終結」を同時に実現できる。そして恐らく、日本には原子爆弾は投下されなかったはずだ。“日本人”の視点からすれば、このように歴史が進行していたらとても良かったと言えるだろう(ドイツが犠牲になることを良しとしているわけでは決してないのだが)。
あわせて読みたい
【考察】アニメ映画『虐殺器官』は、「便利さが無関心を生む現実」をリアルに描く”無関心ではいられない…
便利すぎる世の中に生きていると、「この便利さはどのように生み出されているのか」を想像しなくなる。そしてその「無関心」は、世界を確実に悪化させてしまう。伊藤計劃の小説を原作とするアニメ映画『虐殺器官』から、「無関心という残虐さ」と「想像することの大事さ」を知る
しかし実際にはそのようにはならなかった。
「日本への原爆投下」については、正しかったとは思えない
原爆開発には、莫大なコストが費やされている。20億ドル以上の資金と3年の歳月、そして4000人もの科学者の協力が必要だったのだ。そして、「開発に3年も掛かった」という点が、日本の命運を決したと言えるだろう。何故なら、アメリカが原子爆弾を開発した時点で既に、ヒトラーは自殺していたからだ。開発に着手した時とは異なり、ナチスドイツは現実的な脅威ではなくなっていたのである。
あわせて読みたい
【実話】暗号機エニグマ解読のドラマと悲劇を映画化。天才チューリングはなぜ不遇の死を遂げたのか:『…
「解読不可能」とまで言われた最強の暗号機エニグマを打ち破ったのは、コンピューターの基本原理を生み出した天才数学者アラン・チューリングだった。映画『イミテーションゲーム』から、1400万人以上を救ったとされながら、偏見により自殺した不遇の人生を知る
さて、これも仮定の話でしかないが、もしも、ヒトラーが自殺した時点で原爆開発にまったく見通しが立っていなかったとしたら、恐らくその時点で開発は中止されていたはずだ。ナチスドイツが自滅したのであれば、大金を費やしてまで開発する必要性がないからである。しかし実に不幸なことに、その時点で原子爆弾はほぼ完成していた。
となれば、「作ってしまった原子爆弾をどうするか」が議論されるのは当然と言えるだろう。作中でも、この点について描かれている。マンハッタン計画に関わる科学者たちはヒトラーの死を受けて話し合いを行い、その中である人物が、「今や、人類最大の脅威は敵ではなく私たちになった」との認識を示していた。人類史上類を見ない兵器を開発した自分たちこそが、世界における最大の脅威になってしまったというわけだ。これ以上の言及はなかったが、もちろんそのような発言をした科学者は、「マンハッタン計画の凍結」を考えていただろう。これ以上、どこにも進みようがないからだ。
しかし、その議論を聞いていたオッペンハイマーは、「確かにヒトラーは死んだ。でも日本がいる」と発言した。現代を生きる私たちにはなかなか想像が及ばないところではあるが、当時の日本は、さすがにナチスドイツ並とはいかないはずだが、比肩するぐらいの脅威として見られていたというわけだ。だからオッペンハイマーは、原子爆弾を日本に投下すべきだという考えを示すのである。
あわせて読みたい
【史実】太平洋戦争末期に原爆を落としたアメリカは、なぜ終戦後比較的穏やかな占領政策を取ったか?:…
『八月十五日に吹く風』は小説だが、史実を基にした作品だ。本作では、「終戦直前に原爆を落としながら、なぜ比較的平穏な占領政策を行ったか?」の疑問が解き明かされる。『源氏物語』との出会いで日本を愛するようになった「ロナルド・リーン(仮名)」の知られざる奮闘を知る
しかし当然、「投下をどう正当化する?」と疑問が呈された。それに対してオッペンハイマーは、次のように答えている。
我々は未来のことを想像し、脅威を感じれば行動を変える。
しかし、実際に使いその威力を理解するまでは、人々は恐れないだろう。
そのために投下する。
人類の平和を確実なものにするのだ。
この発言をより理解しやすくするために、オッペンハイマーが別の場面でした発言にも触れておこう。聴聞会において、「原爆投下の是非を決する会議でどのような助言を行ったのか」と問われ、次のように答えたのだ。
あわせて読みたい
【驚愕】本屋大賞受賞作『同志少女よ、敵を撃て』(逢坂冬馬)は凄まじい。戦場は人間を”怪物”にする
デビュー作で本屋大賞を受賞した『同志少女よ、敵を撃て』(逢坂冬馬)は、デビュー作であることを抜きにしても凄まじすぎる、規格外の小説だった。ソ連に実在した「女性狙撃兵」の視点から「独ソ戦」を描く物語は、生死の境でギリギリの葛藤や決断に直面する女性たちのとんでもない生き様を活写する
一度使えば、核戦争、いや、恐らくすべての戦争のことを考えもしなくなるだろう。
なんとなく発言の趣旨は理解できるだろうが、私なりにまとめておこう。オッペンハイマーは、「原子爆弾はそのあまりの威力ゆえ、『原子爆弾が存在する世の中では二度と戦争など起こせない』と感じさせるだけの力がある」と認識していた。しかし同時に、「一度も使わなければ、原子爆弾にそのような力があることを知り得ないだろう」とも考えていたのである。だから、「『恒久的な平和』を実現するためには、一度は原子爆弾を使わなければならない」というわけだ。これが、当時オッペンハイマーが考えていたことである。
ではこのような観点から、「日本への原爆投下」に関する是非について改めて考えてみたいと思う。
あわせて読みたい
【意外】東京裁判の真実を記録した映画。敗戦国での裁判が実に”フェア”に行われたことに驚いた:『東京…
歴史に詳しくない私は、「東京裁判では、戦勝国が理不尽な裁きを行ったのだろう」という漠然としたイメージを抱いていた。しかし、その印象はまったくの誤りだった。映画『東京裁判 4Kリマスター版』から東京裁判が、いかに公正に行われたのかを知る

まず先程同様、”現代”の視点で考えてみよう。残念なことに私たちは、「戦争が放棄された、『恒久的な平和』が実現された世の中」には生きていない。内戦だけではなく、ロシアによるウクライナ侵攻やパレスチナ・イスラエルの軍事衝突などの国家間の戦争も絶えないし、北朝鮮がミサイル技術を進化させて世界を挑発してもいる。オッペンハイマーが理想としていたような「誰も戦争のことを考えなくなる世界」は結局のところ実現しなかったのだ。そのような意味で、”現代”の視点からは「日本への原爆投下」は誤りだったと判断できる。
では”同時代”の視点ではどのように判断されるだろうか。ここからはあくまでも私の個人的な感覚になるが、”同時代”の視点からも「日本への原爆投下」は踏みとどまるべきだったと考えている。この点について理解してもらうために、有名な「トロッコ問題」を例に挙げよう。
知っている人も多いと思うが、「トロッコ問題」とは哲学の世界でよく引き合いに出される話である。詳しくはネットで調べてほしいが、要するに「5人を助けるために、1人を殺すことは許されるのか?」という倫理の問題だ。この「トロッコ問題」においては状況的に、「5人死ぬ」か「1人死ぬ」のどちらかしか選択肢がないため、「その2択しかないなら『1人死ぬ』を選ぶしかない」みたいな思考になってしまう。個人的には、その2択しかないなら、「1人死ぬ」を選ばざるを得ないと感じる。
あわせて読みたい
【感想】池田晶子『14歳からの哲学』で思考・自由・孤独の大事さを知る。孤独を感じることって大事だ
「元々持ってた価値観とは違う考えに触れ、それを理解したいと思う場面」でしか「考える」という行為は発動しないと著者は言う。つまり我々は普段、まったく考えていないのだ。『14歳からの哲学』をベースに、「考えること」と自由・孤独・人生との関係を知る
そこで問題となるのは、「『日本への原爆投下』は『トロッコ問題』と同じ状況だったのか」という点だ。オッペンハイマーはきっと、次のような2択を考えていたはずだ。「日本に投下し短期的には多くの犠牲を出すが、長期的には犠牲を少なく出来る」か、「日本に投下しないことで短期的には犠牲を出さずに済むが、長期的には犠牲が多くなる」かである。本当にこの2択しか存在しなかったのであれば、「日本への原爆投下」もやむを得ないと考えられるかもしれない。しかし私には、選択肢がこの2つしか存在しなかったとは思えないのである。「恒久的な平和」を獲得する方法は他にもあったはずだ。「日本に投下せず、さらに長期的にも犠牲を少なくする」道だってあっただろうし、やはりその可能性を探るべきだったのではないかと考えてしまうのだ。
しかし一方で、作中では「恒久的な平和を目指す」とは別の話も指摘されていた。原爆投下の直前の会議の中である人物が、「諜報員によると、日本はいかなる状況でも降伏しない」と発言するのだ。日本は「ハラキリ」「バンザイアタック」と、他の国の人には(というか、現代を生きる我々にも)理解しがたい国民性で戦争を戦っていたのであり、ナチスドイツとはまた違った形で「狂気的」と考えられていたのだろう。日本という国についてあまり知られていなかったわけで、「まともな話が通じる相手ではない」という前提で日本が捉えられていたのではないかと思う。
そして、当時のアメリカにとって日本が「狂気」に満ちた国に見えていたのだとすれば、”アメリカ人”の理屈では「日本への原爆投下」は正しかったと言えるのかもしれない。もちろん、”日本人”の私はその判断を許容しないが、私もやはり「ハラキリ」「バンザイアタック」は「狂気的」だと感じるし、私が当時を生きるアメリカ人だったとしたら、「日本への原爆投下」も仕方ないと感じていた可能性もあるのではないかと思う。
あわせて読みたい
【理解】小野田寛郎を描く映画。「戦争終結という現実を受け入れない(=認知的不協和)」は他人事じゃ…
映画『ONODA 一万夜を越えて』を観るまで、小野田寛郎という人間に対して違和感を覚えていた。「戦争は終わっていない」という現実を生き続けたことが不自然に思えたのだ。しかし映画を観て、彼の生き方・決断は、私たちと大きく変わりはしないと実感できた
長くなったが、これが原爆開発・投下に関する「基本的な知識」と「私の感覚」である。もちろんこの辺りの捉え方は人によって異なるだろう。いずれにせよ、立場の違いによって見ているものが変わるため、理解し合うことは相当難しいのだと思う。
オッペンハイマーが抱く様々な葛藤が描かれていく
さて、ここからはまた作品の話に戻すことにしよう。
あわせて読みたい
【狂気】”友好”のために北朝鮮入りした監督が撮った映画『ザ・レッド・チャペル』が映す平壌の衝撃
倫理的な葛藤を物ともせず、好奇心だけで突き進んでいくドキュメンタリー監督マッツ・ブリュガーが北朝鮮から「出禁」を食らう結果となった『ザ・レッド・チャペル』は、「友好」を表看板に北朝鮮に潜入し、その「日常」と「非日常」を映し出した衝撃作
前半では主に、「オッペンハイマーはどのような形で共産主義と関わっていたのか」が丁寧に描かれていく。戦後はアメリカだけではなく、日本を含め世界中で「共産主義」が問題視され、それが冷戦や全共闘に繋がっていったわけだが、正直なところ私にはその辺りの感覚はピンとこない。なので、本作で描かれる「共産主義への嫌悪感」についても共感しにくいわけだが、この点については生きてきた時代が違うのだから仕方ないだろう。とにかく、聴聞会に出席しているオッペンハイマーは、そんな「共産主義への苛烈な嫌悪感」がむき出しになった時代を生きていたのである。
さて、本作を観る限りにおいては、オッペンハイマーは共産党に入党したこともないし、自身のことを共産主義者だと認識したこともないようだ。本作では少なくとも、そのように描かれている。しかし彼の周囲には共産主義に関わる人物が結構いた。そのせいで、戦後に共産主義者だと疑われることになったのである。弟は共産党に入っていたことがあるし、かつての恋人で結婚後も不倫関係にあった人物もまた共産党員だったのだ。
あわせて読みたい
【情熱】選挙のおもしろ候補者含め”全員取材”をマイルールにする畠山理仁の異常な日常を描く映画:『NO …
選挙に取り憑かれた男・畠山理仁を追うドキュメンタリー映画『NO 選挙, NO LIFE』は、「平均睡眠時間2時間」の生活を長年続ける”イカれた”ライターの「選挙愛」が滲み出る作品だ。「候補者全員を取材しなければ記事にはしない」という厳しすぎるマイルールと、彼が惹かれる「泡沫候補」たちが実に興味深い

では、何故オッペンハイマーの周囲には共産主義者がたくさんいたのだろうか。その理由は、オッペンハイマーが「学内に労働組合を作ろう」と動き始めたことと関係があるようだ。正直私には「労働組合を作ること」と「共産主義」の関係が上手く理解できないのだが、恐らく当時はその2つが密接に結びついていたのだろう。オッペンハイマーは共産主義とは関係なく、単に「大学にも労働組合が必要だ」と考えて活動していたに過ぎないのだが、共産主義との関係を懸念する人物からその動きを度々封じられてしまう。ある時など、「国家プロジェクトに参加できなくなるぞ」と忠告を受けさえしたのだ。
あわせて読みたい
【実話】ソ連の衝撃の事実を隠蔽する記者と暴く記者。映画『赤い闇』が描くジャーナリズムの役割と実態
ソ連の「闇」を暴いた名もなき記者の実話を描いた映画『赤い闇』は、「メディアの存在意義」と「メディアとの接し方」を問いかける作品だ。「真実」を届ける「社会の公器」であるべきメディアは、容易に腐敗し得る。情報の受け手である私たちの意識も改めなければならない
そのようなことがあり、オッペンハイマーは学内での活動は避けるようになった。そしてその後、「FAECT」という集会と関わりを持つようになっていったようだ。シェル社という企業の労働組合のような集会として描かれていたと思う。そして恐らくだが、この「FAECT」が共産主義と何らかの関わりを持っていたのだろう。そのため「FAECT」には共産主義者が多く関わっていたというわけだ。オッペンハイマーは労働組合に関心があったわけだが、そのような事情から、彼は共産主義者と関わりを持つようになっていったのである。
さて、これもやはりその時代を知らない私にはなかなか上手く理解できなかったポイントなのだが、戦前・戦中と戦後では「共産主義者との関わり」に対する反応も大きく違っていたようだ。確かにオッペンハイマーは、「学内での労働組合の設立」に妨害を受けていたが、一方で、マンハッタン計画のリーダーに選出されてもいる。作中ではオッペンハイマーが、「『左翼との関係が核計画への参加を妨げることはない』と告げられた」と語る場面もあった。「オッペンハイマーは共産主義者と関わっている」という事実は恐らく知られていたことだったのだろうが、それでも、その事実が「マンハッタン計画のリーダー選び」には影響を与えなかったというわけだ。もちろんこれは、「共産主義者との関わりを知ってもなお、オッペンハイマーの力量の方を買った」と見ることも出来るわけだが。いずれにせよ、戦後と比べれば、戦前・戦中における「共産主義者との関わり」はさほど問題視されなかったということなのだろう。
あわせて読みたい
【告発】アメリカに”監視”される社会を暴露したスノーデンの苦悩と決断を映し出す映画:『スノーデン』…
NSA(アメリカ国家安全保障局)の最高機密にまでアクセスできたエドワード・スノーデンは、その機密情報を持ち出し内部告発を行った。「アメリカは世界中の通信を傍受している」と。『シチズンフォー』と『スノーデン』の2作品から、彼の告発内容とその葛藤を知る
しかし戦後、「赤狩り」の嵐が吹き荒れ、オッペンハイマーは改めて共産主義者との関わりについて追及を受けることになった。ここには、作中でも少しだけ言及されるが、「マンハッタン計画に関わった科学者の中に、ソ連のスパイがいた」という事実も関係していただろう。つまり、もしもオッペンハイマーが共産主義者だとしたら、「ソ連のスパイを意図的にメンバーに加えたのではないか?」とも疑えるのである。このような観点からもオッペンハイマーは追及されていたというわけだ。
このように本作では、「原子爆弾を生み出した人物」を「共産主義との関わり」という観点からも描き出し、より多面的に捉えようとするのである。
あわせて読みたい
【狂気】ISISから孫を取り戻せ!映画『”敵”の子どもたち』が描くシリアの凄絶な現実
映画『”敵”の子どもたち』では、私がまったく知らなかった凄まじい現実が描かれる。イスラム過激派「ISIS」に望んで参加した女性の子ども7人を、シリアから救出するために奮闘する祖父パトリシオの物語であり、その最大の障壁がなんと自国のスウェーデン政府なのだる。目眩がするような、イカれた現実がここにある
さて、本作の監督であるクリストファー・ノーランは、インタビューなどで作品について聞かれても、「鑑賞の可能性を狭めたくない」という理由であまり答えない。そして、そのようなスタンスの人物らしく、オッペンハイマーのことも「分かりやすい人物」とは描かないのである。本作を観ても、「オッペンハイマーがどのような人物だったのか」、あるいは「クリストファー・ノーランがオッペンハイマーをどのような人物として描こうとしたのか」についてはよく分からないんじゃないかと思う。少なくとも、シンプルに要約出来るような形では捉えられないだろう。そして、それでいいのだと私は思う。本作の良さは、「複雑な人間を、『複雑な人間である』という形で提示していること」にあると感じるからだ。そして、本作においてその「複雑さ」は「共産主義との関わり」によって描かれているというわけだ。
さてそういう意味で言えば、「原爆開発における葛藤」は、本作において最も理解しやすい部分と言えるだろう。特に物語の後半、実際日本に原子爆弾が投下されたことを知った後のオッペンハイマーの葛藤は、想像しやすいだろうと思う。もちろん、この点に関しても決して安易な描かれ方がなされているわけではないのだが、「凄まじいものを生み出してしまった」と考えているオッペンハイマーの内心については、我々一般人でも理解しやすいのではないだろうか。
あわせて読みたい
【誠実】地下鉄サリン事件の被害者が荒木浩に密着。「贖罪」とは何かを考えさせる衝撃の映画:『AGANAI…
私には、「謝罪すること」が「誠実」だという感覚がない。むしろ映画『AGANAI 地下鉄サリン事件と私』では、「謝罪しない誠実さ」が描かれる。被害者側と加害者側の対話から、「謝罪」「贖罪」の意味と、信じているものを諦めさせることの難しさについて書く
また原爆開発に関して言えば、トルーマン大統領との面会シーンも印象的だった。オッペンハイマーは大統領に「私の手は血塗られたように感じます」と口にするのだが、それに対して大統領が凄まじい返答をするのだ。この記事では、その返答には具体的には触れないことにするが、なかなか凄いことを言うものだなと感じさせられた。この描写もまた、違った形からオッペンハイマーの苦悩を描き出すものと言えるだろう。
「世界を破壊する」という言葉に込められた意外な背景
あわせて読みたい
【使命】「CRISPR-Cas9」を分かりやすく説明。ノーベル賞受賞の著者による発見物語とその使命:『CRISPR…
生物学の研究を一変させることになった遺伝子編集技術「CRISPR-Cas9」の開発者は、そんな発明をするつもりなどまったくなかった。ノーベル化学賞を受賞した著者による『CRISPR (クリスパー) 究極の遺伝子編集技術の発見』をベースに、その発見物語を知る
さて記事の最後に、作中の随所で登場する「世界を破壊する」という言葉について言及しておくことにしよう。

あわせて読みたい
【ル・マン】ゲーマーが本物のカーレース出場!映画『グランツーリスモ』が描く衝撃的すぎる軌跡(ヤン…
映画『グランツーリスモ』は、「ゲーマーをレーサーにする」という、実際に行われた無謀すぎるプロジェクトを基にした作品だ。登場人物は全員イカれていると感じたが、物語としてはシンプルかつ王道で、誰もが先の展開を予想出来るだろう。しかしそれでも、圧倒的に面白かった、ちょっと凄まじすぎる映画だった
もちろんこの言葉の表向きの意味は、本作を観ていなくたって想像できるはずだ。原子爆弾は、まさに世界を一変させるような破壊力を持つ兵器なのである。そのため、個人で成し遂げた偉業ではないとはいえ、その計画を主導したオッペンハイマーが「世界を破壊した」と捉えられることは理解できるだろうと思う。
しかし、この「世界を破壊する」という言葉には実は、もっと実際的な意味があったのである。本作を観て、その事実を初めて知った。
あわせて読みたい
【快挙】「チバニアン」は何が凄い?「地球の磁場が逆転する」驚異の現象がこの地層を有名にした:『地…
一躍その名が知れ渡ることになった「チバニアン」だが、なぜ話題になり、どう重要なのかを知っている人は多くないだろう。「チバニアン」の申請に深く関わった著者の『地磁気逆転と「チバニアン」』から、地球で起こった過去の不可思議な現象の正体を理解する
最初にその言及がなされるのは、マンハッタン計画始動直後のことである。テラーという物理学者が話し合いの場で、「ヤバい計算結果が出た」と口にする場面があるのだ。計算によって、「原子爆弾を爆発させることで、大気に引火する」という可能性が導き出されたというのである。つまり、「原子爆弾をどこに投下するにせよ、爆発と同時に大気が燃え、それによって世界が一斉に火に包まれるかもしれない」というわけだ。
この計算は後に、「テラーの仮定に重大な誤りがあった」と判明し撤回される。しかしその撤回は「ほぼ」だった。「ほぼ可能性はゼロ」、つまり「まったく可能性が無いわけではない」という状態だったのだ。
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『戦場のピアニスト』(ロマン・ポランスキー)が描く、ユダヤ人迫害の衝撃の実話
映画『戦場のピアニスト』の4Kリマスター版を観に行ったところ、上映後のトークイベントに主人公の息子が登壇したので驚いた。何せ私は、本作が「実話を基にしている」ことさえ知らなかったのである。だからその驚きもひとしおだった。ホロコーストの生存者である主人公の壮絶な人生を描き出す、不朽の名作だ
そしてこの「大気に引火する」という話は、原子爆弾を試験的に爆発させる「トリニティ実験」の直前に再び登場する。ある科学者が、「『大気に引火する』かどうかの賭け」を行っていたのだ。その様子を観ていた軍人が「あれは何をしているんだ?」とオッペンハイマーに聞き、彼は軍人に「当初そのような計算結果が存在したのだ」という話をするのである。
その話を聞いた軍人は、「だったらどうしてあんな賭けをしているんだ?」と問い返す。オッペンハイマーは「その計算は撤回された」と説明したため、軍人は「それだと賭けは成り立たないじゃないか」と考えたのだ。それに対してオッペンハイマーは「ブラックジョークだよ」と返すのだが、さらに軍人から「可能性は?」と聞かれたため、彼は「ほぼゼロだ」と答えるのである。
あわせて読みたい
【限界】「科学とは何か?」を知るためのおすすめ本。科学が苦手な人こそ読んでほしい易しい1冊:『哲学…
「科学的に正しい」という言葉は、一体何を意味しているのだろう?科学者が「絶対に正しい」とか「100%間違っている」という言い方をしないのは何故だろう?飲茶『哲学的な何か、あと科学とか』から、「科学とはどんな営みなのか?」について考える
これに対して軍人が「ほぼ?」と問うと、オッペンハイマーは「理論に何を求める?」と聞き返した。それに対して軍人が「ゼロがいい」と答えるのである。このやり取りは「科学に関わる者」と「そうではない者」の間にある深い溝を描写しているように私には感じられた。未知のものについて、「可能性は絶対に無い」などと答えることは、科学的に正しい態度とは言えない。しかし、「科学」の何たるかをあまり知らない人には、そのような態度は好ましくないものに見えてしまうというわけだ。このような溝については、コロナワクチンを始め、今も世界中の様々な場面で散見される。
さて話を戻すと、このようなやり取りを受けてのことだろう、原子爆弾に引火する直前、軍人がオッペンハイマーに「世界を壊すな」と口にする場面があるのだ。「ほぼゼロ」だとはいえ、「大気に引火して世界が破壊される可能性」も存在していたという話は初めて知ったし、個人的にはとても興味深い話に感じられた。人類はこのようにして、未知のものを乗り越えてきたというわけだ。
あわせて読みたい
【挑戦】相対性理論の光速度不変の原理を無視した主張『光速より速い光』は、青木薫訳だから安心だぞ
『光速より速い光』というタイトルを見て「トンデモ本」だと感じた方、安心してほしい。「光速変動理論(VSL理論)」が正しいかどうかはともかくとして、本書は実に真っ当な作品だ。「ビッグバン理論」の欠陥を「インフレーション理論」以外の理屈で補う挑戦的な仮説とは?
あわせて読みたい
【全作品視聴済】私が観てきた映画(フィクション)を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が観てきた映画(フィクション)を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。
最後に
あわせて読みたい
【感想】映画『レオン』は、殺し屋マチルダを演じたナタリー・ポートマンがとにかく素晴らしい(監督:…
映画『レオン』は、その性質ゆえに物議を醸す作品であることも理解できるが、私はやはりナタリー・ポートマンに圧倒されてしまった。絶望的な事態に巻き込まれたマチルダの葛藤と、そんな少女と共に生きることになった中年男性レオンとの関係性がとても見事に映し出されている。実に素敵な作品だった
ストローズに関してはほとんど言及しなかったが、全体的に「小物感」が漂うような描写になっていたと思う。少なくとも、ストローズは「分かりやすい人物」と言っていいだろう。しかし先程も触れた通りだが、オッペンハイマーはとにかくなかなか理解しがたいし、そのような感覚は映画の最後まで続く。人間を単純に捉えようとはしないクリストファー・ノーランらしさが貫かれていると言えるだろう。本作で示される「オッペンハイマーの複雑さ」は、観る度に受け取り方が変わるかもしれないとさえ感じた。
クリストファー・ノーラン作品としては珍しく「個人史」を扱った映画であり、これまでの作品とは大分趣きが異なる。さらに、なかなかとっつきにくい題材・人物が扱われているわけで、さらっと観られる映画でもないのだが、とにかく「観て良かった」と感じられる作品だった。改めてクリストファー・ノーランの凄さが感じられた1作だ。
あわせて読みたい
【感想】是枝裕和監督映画『怪物』(坂元裕二脚本)が抉る、「『何もしないこと』が生む加害性」
坂元裕二脚本、是枝裕和監督の映画『怪物』は、3つの視点を通して描かれる「日常の何気ない光景」に、思いがけない「加害性」が潜んでいることを炙り出す物語だ。これは間違いなく、私たち自身に関わる話であり、むしろ「自分には関係ない」と考えている人こそが自覚すべき問題だと思う
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を…
Kindleで本を出版しました。タイトルは、『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を分かりやすく書いた本:相対性理論も宇宙論も量子論も』です。科学や科学者に関する、文系の人でも読んでもらえる作品に仕上げました。そんな自著について紹介をしています。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【奇妙】大栗博司『重力とはなにか』は、相対性理論や量子力学の説明も秀逸だが、超弦理論の話が一番面白い
『重力とはなにか』(大栗博司)は、科学に馴染みの薄い人でもチャレンジできる易しい入門書だ。相対性理論や量子力学、あるいは超弦理論など、非常に難解な分野を基本的なところから平易に説明してくれるので、「科学に興味はあるけど難しいのはちょっと……」という方にこそ読んでほしい1冊
あわせて読みたい
【狂気】ISISから孫を取り戻せ!映画『”敵”の子どもたち』が描くシリアの凄絶な現実
映画『”敵”の子どもたち』では、私がまったく知らなかった凄まじい現実が描かれる。イスラム過激派「ISIS」に望んで参加した女性の子ども7人を、シリアから救出するために奮闘する祖父パトリシオの物語であり、その最大の障壁がなんと自国のスウェーデン政府なのだる。目眩がするような、イカれた現実がここにある
あわせて読みたい
【情熱】選挙のおもしろ候補者含め”全員取材”をマイルールにする畠山理仁の異常な日常を描く映画:『NO …
選挙に取り憑かれた男・畠山理仁を追うドキュメンタリー映画『NO 選挙, NO LIFE』は、「平均睡眠時間2時間」の生活を長年続ける”イカれた”ライターの「選挙愛」が滲み出る作品だ。「候補者全員を取材しなければ記事にはしない」という厳しすぎるマイルールと、彼が惹かれる「泡沫候補」たちが実に興味深い
あわせて読みたい
【感想】映画『レオン』は、殺し屋マチルダを演じたナタリー・ポートマンがとにかく素晴らしい(監督:…
映画『レオン』は、その性質ゆえに物議を醸す作品であることも理解できるが、私はやはりナタリー・ポートマンに圧倒されてしまった。絶望的な事態に巻き込まれたマチルダの葛藤と、そんな少女と共に生きることになった中年男性レオンとの関係性がとても見事に映し出されている。実に素敵な作品だった
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『戦場のピアニスト』(ロマン・ポランスキー)が描く、ユダヤ人迫害の衝撃の実話
映画『戦場のピアニスト』の4Kリマスター版を観に行ったところ、上映後のトークイベントに主人公の息子が登壇したので驚いた。何せ私は、本作が「実話を基にしている」ことさえ知らなかったのである。だからその驚きもひとしおだった。ホロコーストの生存者である主人公の壮絶な人生を描き出す、不朽の名作だ
あわせて読みたい
【ル・マン】ゲーマーが本物のカーレース出場!映画『グランツーリスモ』が描く衝撃的すぎる軌跡(ヤン…
映画『グランツーリスモ』は、「ゲーマーをレーサーにする」という、実際に行われた無謀すぎるプロジェクトを基にした作品だ。登場人物は全員イカれていると感じたが、物語としてはシンプルかつ王道で、誰もが先の展開を予想出来るだろう。しかしそれでも、圧倒的に面白かった、ちょっと凄まじすぎる映画だった
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『レザボア・ドッグス』(タランティーノ監督)はとにかく驚異的に脚本が面白い!
クエンティン・タランティーノ初の長編監督作『レザボア・ドッグス』は、のけぞるほど面白い映画だった。低予算という制約を逆手に取った「会話劇」の構成・展開があまりにも絶妙で、舞台がほぼ固定されているにも拘らずストーリーが面白すぎる。天才はやはり、デビュー作から天才だったのだなと実感させられた
あわせて読みたい
【感想】関東大震災前後を描く映画『福田村事件』(森達也)は、社会が孕む「思考停止」と「差別問題」…
森達也監督初の劇映画である『福田村事件』は、100年前の関東大震災直後に起こった「デマを起点とする悲劇」が扱われる作品だ。しかし、そんな作品全体が伝えるメッセージは、「100年前よりも現代の方がよりヤバい」だと私は感じた。SNS時代だからこそ意識すべき問題の詰まった、挑発的な作品である
あわせて読みたい
【おすすめ】カンヌ映画『PERFECT DAYS』は、ほぼ喋らない役所広司の沈黙が心地よい(ヴィム・ヴェンダ…
役所広司主演映画『PERFECT DAYS』(ヴィム・ヴェンダース監督)は、主人公・平山の「沈黙」がとにかく雄弁な物語である。渋谷区のトイレの清掃員である無口な平山の、世間とほとんど繋がりを持たない隔絶した日常が、色んなものを抱えた者たちを引き寄せ、穏やかさで満たしていく様が素晴らしい
あわせて読みたい
【絶望】杉咲花主演映画『市子』の衝撃。毎日がしんどい「どん底の人生」を生き延びるための壮絶な決断…
映画『市子』はまず何よりも主演を務めた杉咲花に圧倒させられる作品だ。そしてその上で、主人公・川辺市子を巡る物語にあれこれと考えさせられてしまった。「川辺市子」は決してフィクショナルな存在ではなく、現実に存在し得る。本作は、そのような存在をリアルに想像するきっかけにもなるだろう
あわせて読みたい
【感想】映画『キリエのうた』(岩井俊二)はアイナ・ジ・エンドに圧倒されっ放しの3時間だった(出演:…
映画『キリエのうた』(岩井俊二監督)では、とにかくアイナ・ジ・エンドに圧倒されてしまった。歌声はもちろんのことながら、ただそこにいるだけで場を支配するような存在感も凄まじい。全編に渡り「『仕方ないこと』はどうしようもなく起こるんだ」というメッセージに溢れた、とても力強い作品だ
あわせて読みたい
【考察】映画『街の上で』(今泉力哉)が描く「男女の友情は成立する」的会話が超絶妙で素晴らしい(出…
映画『街の上で』(今泉力哉監督)は、「映画・ドラマ的会話」ではない「自然な会話」を可能な限り目指すスタンスが見事だった。「会話の無駄」がとにかく随所に散りばめられていて、そのことが作品のリアリティを圧倒的に押し上げていると言える。ある男女の”恋愛未満”の会話もとても素晴らしかった
あわせて読みたい
【感想】映画『正欲』に超共感。多様性の時代でさえどこに行っても馴染めない者たちの業苦を抉る(出演…
映画『正欲』は、私には共感しかない作品だ。特に、新垣結衣演じる桐生夏月と磯村勇斗演じる佐々木佳道が抱える葛藤や息苦しさは私の内側にあるものと同じで、その描かれ方に圧倒されてしまった。「『多様性』には『理解』も『受け入れ』も不要で、単に否定しなければ十分」なのだと改めて思う
あわせて読みたい
【狂気】ホロコーストはなぜ起きた?映画『ヒトラーのための虐殺会議』が描くヴァンゼー会議の真実
映画『ヒトラーのための虐殺会議』は、ホロコーストの計画について話し合われた「ヴァンゼー会議」を描き出す作品だ。唯一1部だけ残った議事録を基に作られた本作は、「ユダヤ人虐殺」をイベントの準備でもしているかのように「理性的」に計画する様を映し出す。その「狂気」に驚かされてしまった。
あわせて読みたい
【驚愕】本屋大賞受賞作『同志少女よ、敵を撃て』(逢坂冬馬)は凄まじい。戦場は人間を”怪物”にする
デビュー作で本屋大賞を受賞した『同志少女よ、敵を撃て』(逢坂冬馬)は、デビュー作であることを抜きにしても凄まじすぎる、規格外の小説だった。ソ連に実在した「女性狙撃兵」の視点から「独ソ戦」を描く物語は、生死の境でギリギリの葛藤や決断に直面する女性たちのとんでもない生き様を活写する
あわせて読みたい
【映画】『別れる決心』(パク・チャヌク)は、「倫理的な葛藤」が描かれない、不穏で魅惑的な物語
巨匠パク・チャヌク監督が狂気的な関係性を描き出す映画『別れる決心』には、「倫理的な葛藤が描かれない」という特異さがあると感じた。「様々な要素が描かれるものの、それらが『主人公2人の関係性』に影響しないこと」や、「『理解は出来ないが、成立はしている』という不思議な感覚」について触れる
あわせて読みたい
【天才】タランティーノ作品ほぼ未見で観た面白ドキュメンタリー。映画に愛された映画オタクのリアル
『パルプ・フィクション』しか監督作品を観たことがないまま、本作『クエンティン・タランティーノ 映画に愛された男』を観たが、とても面白いドキュメンタリー映画だった。とにかく「撮影現場に笑いが絶えない」ようで、そんな魅力的なモノづくりに関わる者たちの証言から、天才の姿が浮かび上がる
あわせて読みたい
【天才】映画『Winny』(松本優作監督)で知った、金子勇の凄さと著作権法侵害事件の真相(ビットコイン…
稀代の天才プログラマー・金子勇が著作権法違反で逮捕・起訴された実話を描き出す映画『Winny』は、「警察の凄まじい横暴」「不用意な天才と、テック系知識に明るい弁護士のタッグ」「Winnyが明らかにしたとんでもない真実」など、見どころは多い。「金子勇=サトシ・ナカモト」説についても触れる
あわせて読みたい
【歴史】NIKEのエアジョーダン誕生秘話!映画『AIR/エア』が描くソニー・ヴァッカロの凄さ
ナイキがマイケル・ジョーダンと契約した時、ナイキは「バッシュ業界3位」であり、マイケル・ジョーダンも「ドラフト3位選手」だった。今からは信じられないだろう。映画『AIR/エア』は、「劣勢だったナイキが、いかにエアジョーダンを生み出したか」を描く、実話を基にした凄まじい物語だ
あわせて読みたい
【感想】是枝裕和監督映画『怪物』(坂元裕二脚本)が抉る、「『何もしないこと』が生む加害性」
坂元裕二脚本、是枝裕和監督の映画『怪物』は、3つの視点を通して描かれる「日常の何気ない光景」に、思いがけない「加害性」が潜んでいることを炙り出す物語だ。これは間違いなく、私たち自身に関わる話であり、むしろ「自分には関係ない」と考えている人こそが自覚すべき問題だと思う
あわせて読みたい
【狂気?】オウム真理教を内部から映す映画『A』(森達也監督)は、ドキュメンタリー映画史に残る衝撃作だ
ドキュメンタリー映画の傑作『A』(森達也)をようやく観られた。「オウム真理教は絶対悪だ」というメディアの報道が凄まじい中、オウム真理教をその内部からフラットに映し出した特異な作品は、公開当時は特に凄まじい衝撃をもたらしただろう。私たちの「当たり前」が解体されていく斬新な一作
あわせて読みたい
【驚嘆】映画『TAR/ター』のリディア・ターと、彼女を演じたケイト・ブランシェットの凄まじさ
天才女性指揮者リディア・ターを強烈に描き出す映画『TAR/ター』は、とんでもない作品だ。「縦軸」としてのターの存在感があまりにも強すぎるため「横軸」を上手く捉えきれず、結果「よく分からなかった」という感想で終わったが、それでも「観て良かった」と感じるほど、揺さぶられる作品だった
あわせて読みたい
【実話】映画『グリーンブック』は我々に問う。当たり前の行動に「差別意識」が含まれていないか、と
黒人差別が遥かに苛烈だった時代のアメリカにおいて、黒人ピアニストと彼に雇われた白人ドライバーを描く映画『グリーンブック』は、観客に「あなたも同じような振る舞いをしていないか?」と突きつける作品だ。「差別」に限らず、「同時代の『当たり前』に従った行動」について考え直させる1作
あわせて読みたい
【性加害】映画『SHE SAID その名を暴け』を観てくれ。#MeToo運動を生んだ報道の舞台裏(出演:キャリ…
「#MeToo」運動のきっかけとなった、ハリウッドの絶対権力者ハーヴェイ・ワインスタインを告発するニューヨーク・タイムズの記事。その取材を担った2人の女性記者の奮闘を描く映画『SHE SAID その名を暴け』は、ジャニー喜多川の性加害問題で揺れる今、絶対に観るべき映画だと思う
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『四畳半タイムマシンブルース』超面白い!森見登美彦も上田誠も超天才だな!
ヨーロッパ企画の演劇『サマータイムマシン・ブルース』の物語を、森見登美彦の『四畳半神話大系』の世界観で描いたアニメ映画『四畳半タイムマシンブルース』は、控えめに言って最高だった。ミニマム過ぎる設定・物語を突き詰め、さらにキャラクターが魅力的だと、これほど面白くなるのかというお手本のような傑作
あわせて読みたい
【感想】どんな話かわからない?難しい?ジブリ映画『君たちはどう生きるか』の考察・解説は必要?(監…
宮崎駿最新作であるジブリ映画『君たちはどう生きるか』は、宮崎アニメらしいファンタジックな要素を全開に詰め込みつつ、「生と死」「創造」についても考えさせる作品だ。さらに、「自分の頭の中から生み出されたものこそ『正解』」という、創造物と向き合う際の姿勢についても問うているように思う
あわせて読みたい
【感想】映画『すずめの戸締まり』(新海誠)は、東日本大震災後を生きる私達に「逃げ道」をくれる(松…
新海誠監督の『すずめの戸締まり』は、古代神話的な設定を現代のラブコメに組み込みながら、あまりに辛い現実を生きる人々に微かな「逃げ道」を指し示してくれる作品だと思う。テーマ自体は重いが、恋愛やコメディ要素とのバランスがとても良く、ロードムービー的な展開もとても魅力的
あわせて読みたい
【映画】今泉力哉監督『ちひろさん』(有村架純)が描く、「濃い寂しさ」が溶け合う素敵な関係性
今泉力哉監督、有村架純主演の映画『ちひろさん』は、その圧倒的な「寂しさの共有」がとても心地よい作品です。色んな「寂しさ」を抱えた様々な人と関わる、「元風俗嬢」であることを公言し海辺の町の弁当屋で働く「ちひろさん」からは、同じような「寂しさ」を抱える人を惹き付ける力強さが感じられるでしょう
あわせて読みたい
【あらすじ】アリ・アスター監督映画『ミッドサマー』は、気持ち悪さと怖さが詰まった超狂ホラーだった
「夏至の日に映画館で上映する」という企画でようやく観ることが叶った映画『ミッドサマー』は、「私がなんとなく想像していたのとはまるで異なる『ヤバさ』」に溢れる作品だった。いい知れぬ「狂気」が随所で描かれるが、同時に、「ある意味で合理的と言えなくもない」と感じさせられる怖さもある
あわせて読みたい
【あらすじ】塩田武士『罪の声』が放つ、戦後最大の未解決事件「グリコ・森永事件」の圧倒的”リアル感”
戦後最大の未解決事件である「グリコ・森永事件」では、脅迫に子どもの声が使われていた。私はその事実を、塩田武士『罪の声』という小説を読むまで知らなかった。では、続く疑問はこうだろう。その子どもたちは、今どこでどんな風に生きているのか?その疑問に答える、凄まじい小説だ。
あわせて読みたい
【驚異】映画『RRR』『バーフバリ』は「観るエナジードリンク」だ!これ程の作品にはなかなか出会えないぞ
2022年に劇場公開されるや、そのあまりの面白さから爆発的人気を博し、現在に至るまでロングラン上映が続いている『RRR』と、同監督作の『バーフバリ』は、大げさではなく「全人類にオススメ」と言える超絶的な傑作だ。まだ観ていない人がいるなら、是非観てほしい!
あわせて読みたい
【実話】ソ連の衝撃の事実を隠蔽する記者と暴く記者。映画『赤い闇』が描くジャーナリズムの役割と実態
ソ連の「闇」を暴いた名もなき記者の実話を描いた映画『赤い闇』は、「メディアの存在意義」と「メディアとの接し方」を問いかける作品だ。「真実」を届ける「社会の公器」であるべきメディアは、容易に腐敗し得る。情報の受け手である私たちの意識も改めなければならない
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』で描かれる、グアンタナモ”刑務所”の衝撃の実話は必見
ベネディクト・カンバーバッチが制作を熱望した衝撃の映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』は、アメリカの信じがたい実話を基にしている。「9.11の首謀者」として不当に拘束され続けた男を「救おうとする者」と「追い詰めようとする者」の奮闘が、「アメリカの闇」を暴き出す
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『1917』は、ワンカット風の凄まじい撮影手法が「戦場の壮絶な重圧」を見事に体感させる
映画『1917 命をかけた伝令』は、「全編ワンカット風」という凄まじい撮影手法で注目されたが、私は、その撮影手法が「戦場における緊迫感」を見事に増幅させているという点に驚かされた。「物語の中身」と「撮影手法」が素晴らしく合致したとんでもない作品だ
あわせて読みたい
【感想】映画『窓辺にて』(今泉力哉監督)の稲垣吾郎の役に超共感。「好きとは何か」が分からない人へ
映画『窓辺にて』(今泉力哉監督)は、稲垣吾郎演じる主人公・市川茂巳が素晴らしかった。一般的には、彼の葛藤はまったく共感されないし、私もそのことは理解している。ただ私は、とにかく市川茂巳にもの凄く共感してしまった。「誰かを好きになること」に迷うすべての人に観てほしい
あわせて読みたい
【感想】是枝裕和映画『ベイビー・ブローカー』は、「赤ちゃんポスト」を起点に「正義とは何か」を描く
韓国に多数存在するという「赤ちゃんポスト」を題材にした是枝裕和監督映画『ベイビー・ブローカー』は、「正義とは何か」を問いかける。「中絶はOKで、捨てるのはNG」という判断は不合理だし、「最も弱い関係者が救われる」ことが「正義」だと私は思う
あわせて読みたい
【欠落】映画『オードリー・ヘプバーン』が映し出す大スターの生き方。晩年に至るまで生涯抱いた悲しみ…
映画『オードリー・ヘプバーン』は、世界的大スターの知られざる素顔を切り取るドキュメンタリーだ。戦争による壮絶な飢え、父親の失踪、消えぬ孤独感、偶然がもたらした映画『ローマの休日』のオーディション、ユニセフでの活動など、様々な証言を元に稀代の天才を描き出す
あわせて読みたい
【純愛】映画『ぼくのエリ』の衝撃。「生き延びるために必要なもの」を貪欲に求める狂気と悲哀、そして恋
名作と名高い映画『ぼくのエリ』は、「生き延びるために必要なもの」が「他者を滅ぼしてしまうこと」であるという絶望を抱えながら、それでも生きることを選ぶ者たちの葛藤が描かれる。「純愛」と呼んでいいのか悩んでしまう2人の関係性と、予想もつかない展開に、感動させられる
あわせて読みたい
【感想】湯浅政明監督アニメ映画『犬王』は、実在した能楽師を”異形”として描くスペクタクル平家物語
観るつもりなし、期待値ゼロ、事前情報ほぼ皆無の状態で観た映画『犬王』(湯浅政明監督)はあまりにも凄まじく、私はこんなとんでもない傑作を見逃すところだったのかと驚愕させられた。原作の古川日出男が紡ぐ狂気の世界観に、リアルな「ライブ感」が加わった、素晴らしすぎる「音楽映画」
あわせて読みたい
【感想】殺人事件が決定打となった「GUCCI家の崩壊」の実話を描く映画『ハウス・オブ・グッチ』の衝撃
GUCCI創業家一族の1人が射殺された衝撃の実話を基にした映画『ハウス・オブ・グッチ』。既に創業家一族は誰一人関わっていないという世界的ブランドGUCCIに一体何が起こったのか? アダム・ドライバー、レディー・ガガの演技も見事なリドリー・スコット監督作
あわせて読みたい
【衝撃】映画『ダンサー・イン・ザ・ダーク』凄い。ラストの衝撃、ビョークの演技、”愛”とは呼びたくな…
言わずとしれた名作映画『ダンサー・イン・ザ・ダーク』を、ほぼ予備知識ゼロのまま劇場で観た。とんでもない映画だった。苦手なミュージカルシーンが効果的だと感じられたこと、「最低最悪のラストは回避できたはずだ」という想い、そして「セルマのような人こそ報われてほしい」という祈り
あわせて読みたい
【憤り】世界最強米海軍4人VS数百人のタリバン兵。死線を脱しただ1人生還を果たした奇跡の実話:『アフ…
アフガニスタンの山中で遭遇した羊飼いを見逃したことで、数百人のタリバン兵と死闘を繰り広げる羽目に陥った米軍最強部隊に所属する4人。奇跡的に生き残り生還を果たした著者が記す『アフガン、たった一人の生還』は、とても実話とは信じられない凄まじさに満ちている
あわせて読みたい
【感想】リドリー・スコット監督の映画『最後の決闘裁判』から、社会が”幻想”を共有する背景とその悲劇…
例えば、「1万円札」というただの紙切れに「価値を感じる」のは、社会の構成員が同じ「共同幻想」の中に生きているからだ。リドリー・スコット監督の映画『最後の決闘裁判』は、「強姦では妊娠しない」「裁判の勝者を決闘で決する」という社会通念と、現代にも通じる「共同幻想」の強さを描き出す
あわせて読みたい
【信念】水俣病の真実を世界に伝えた写真家ユージン・スミスを描く映画。真実とは「痛みへの共感」だ:…
私はその存在をまったく知らなかったが、「水俣病」を「世界中が知る公害」にした報道写真家がいる。映画『MINAMATA―ミナマタ―』は、水俣病の真実を世界に伝えたユージン・スミスの知られざる生涯と、理不尽に立ち向かう多くの人々の奮闘を描き出す
あわせて読みたい
【驚愕】キューバ危機の裏側を描くスパイ映画『クーリエ』。核戦争を回避させた民間人の衝撃の実話:『…
核戦争ギリギリまで進んだ「キューバ危機」。その陰で、世界を救った民間人がいたことをご存知だろうか?実話を元にした映画『クーリエ:最高機密の運び屋』は、ごく普通のセールスマンでありながら、ソ連の膨大な機密情報を盗み出した男の信じがたい奮闘を描き出す
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『流浪の月』を観て感じた、「『見て分かること』にしか反応できない世界」への気持ち悪さ
私は「見て分かること」に”しか”反応できない世界に日々苛立ちを覚えている。そういう社会だからこそ、映画『流浪の月』で描かれる文と更紗の関係も「気持ち悪い」と断罪されるのだ。私はむしろ、どうしようもなく文と更紗の関係を「羨ましい」と感じてしまう。
あわせて読みたい
【矛盾】法律の”抜け穴”を衝く驚愕の小説。「ルールを通り抜けたものは善」という発想に潜む罠:『法廷…
完璧なルールは存在し得ない。だからこそ私たちは、矛盾を内包していると理解しながらルールを遵守する必要がある。「ルールを通り抜けたものは善」という”とりあえずの最善解”で社会を回している私たちに、『法廷遊戯』は「世界を支える土台の脆さ」を突きつける
あわせて読みたい
【感想】映画『竜とそばかすの姫』が描く「あまりに批判が容易な世界」と「誰かを助けることの難しさ」
SNSの登場によって「批判が容易な社会」になったことで、批判を恐れてポジティブな言葉を口にしにくくなってしまった。そんな世の中で私は、「理想論だ」と言われても「誰かを助けたい」と発信する側の人間でいたいと、『竜とそばかすの姫』を観て改めて感じさせられた
あわせて読みたい
【正義】復讐なんかに意味はない。それでも「この復讐は正しいかもしれない」と思わされる映画:『プロ…
私は基本的に「復讐」を許容できないが、『プロミシング・ヤング・ウーマン』の主人公キャシーの行動は正当化したい。法を犯す明らかにイカれた言動なのだが、その動機は一考の余地がある。何も考えずキャシーを非難していると、矢が自分の方に飛んでくる、恐ろしい作品
あわせて読みたい
【衝撃】『ゆきゆきて、神軍』はとんでもないドキュメンタリー映画だ。虚実が果てしなく入り混じる傑作
奥崎謙三という元兵士のアナーキストに密着する『ゆきゆきて、神軍』。ドキュメンタリー映画の名作として名前だけは知っていたが、まさかこんなとんでもない映画だったとはと驚かされた。トークショーで監督が「自分の意向を無視した編集だった」と語っていたのも印象的
あわせて読みたい
【実話】「アウシュビッツ・レポート」に記載された「収容所の記録」を持ち出した驚愕の史実を描く映画
アウシュビッツ強制収容所から抜け出し、詳細な記録と共にホロコーストの実態を世界に明らかにした人物がいる。そんな史実を私はまったく知らなかった。世界がホロコーストを知るきっかけとなった2人の奮闘を描く映画『アウシュヴィッツ・レポート』の凄まじい衝撃
あわせて読みたい
【凄絶】北朝鮮の”真実”を描くアニメ映画。強制収容所から決死の脱出を試みた者が語る驚愕の実態:『ト…
在日コリアン4世の監督が、北朝鮮脱北者への取材を元に作り上げた壮絶なアニメ映画『トゥルーノース』は、私たちがあまりに恐ろしい世界と地続きに生きていることを思い知らせてくれる。最低最悪の絶望を前に、人間はどれだけ悪虐になれてしまうのか、そしていかに優しさを発揮できるのか。
あわせて読みたい
【日常】「何もかも虚しい」という心のスキマを「異性」や「お金」で安易に埋めてしまうのは危険だ:映…
「どこにでもいる普通の女性」が「横領」に手を染める映画『紙の月』は、「日常の積み重ねが非日常に接続している」ことを否応なしに実感させる。「主人公の女性は自分とは違う」と考えたい観客の「祈り」は通じない。「梅澤梨花の物語」は「私たちの物語」でもあるのだ
あわせて読みたい
【驚愕】これ以上の”サバイバル映画”は存在するか?火星にたった一人残された男の生存術と救出劇:『オ…
1人で火星に取り残された男のサバイバルと救出劇を、現実的な科学技術の範囲で描き出す驚異の映画『オデッセイ』。不可能を可能にするアイデアと勇気、自分や他人を信じ抜く気持ち、そして極限の状況でより困難な道を進む決断をする者たちの、想像を絶するドラマに胸打たれる
あわせて読みたい
【感想】才能の開花には”極限の環境”が必要か?映画『セッション』が描く世界を私は否定したい
「追い込む指導者」が作り出す”極限の環境”だからこそ、才能が開花する可能性もあるとは思う。しかし、そのような環境はどうしても必要だろうか?最高峰の音楽院での壮絶な”指導”を描く映画『セッション』から、私たちの生活を豊かにしてくれるものの背後にある「死者」を想像する
あわせて読みたい
【認識】「固定観念」「思い込み」の外側に出るのは難しい。自分はどんな「へや」に囚われているのか:…
実際に起こった衝撃的な事件に着想を得て作られた映画『ルーム』は、フィクションだが、観客に「あなたも同じ状況にいるのではないか?」と突きつける力強さを持っている。「普通」「当たり前」という感覚に囚われて苦しむすべての人に、「何に気づけばいいか」を気づかせてくれる作品
あわせて読みたい
【評価】映画『シン・ゴジラ』は、「もしゴジラが実際に現れたら」という”if”を徹底的にリアルに描く
ゴジラ作品にも特撮映画にもほとんど触れてこなかったが、庵野秀明作品というだけで観に行った『シン・ゴジラ』はとんでもなく面白かった。「ゴジラ」の存在以外のありとあらゆるものを圧倒的なリアリティで描き出す。「本当にゴジラが現れたらどうなるのか?」の現実感が凄まじい
あわせて読みたい
【実話】映画『ハドソン川の奇跡』の”糾弾された英雄”から、「正しさ」をどう「信じる」かを考える
制御不能の飛行機をハドソン川に不時着させ、乗員乗客155名全員の命を救った英雄はその後、「わざと機体を沈め損害を与えたのではないか」と疑われてしまう。映画『ハドソン川の奇跡』から、「正しさ」の難しさと、「『正しさ』の枠組み」の重要性を知る
あわせて読みたい
【死】映画『湯を沸かすほどの熱い愛』に号泣。「家族とは?」を問う物語と、タイトル通りのラストが見事
「死は特別なもの」と捉えてしまうが故に「日常感」が失われ、普段の生活から「排除」されているように感じてしまうのは私だけではないはずだ。『湯を沸かすほどの熱い愛』は、「死を日常に組み込む」ことを当たり前に許容する「家族」が、「家族」の枠組みを問い直す映画である
あわせて読みたい
【驚愕】あるジャーナリストの衝撃の実話を描く映画『凶悪』。「死刑囚の告発」から「正義」を考える物語
獄中の死刑囚が警察に明かしていない事件を雑誌記者に告発し、「先生」と呼ばれる人物を追い詰めた実際の出来事を描くノンフィクションを原作にして、「ジャーナリズムとは?」「家族とは?」を問う映画『凶悪』は、原作とセットでとにかく凄まじい作品だ
あわせて読みたい
【葛藤】正義とは何かを突きつける戦争映画。80人を救うために1人の少女を殺すボタンを押せるか?:『ア…
「80人の命を救うために、1人の少女の命を奪わなければならない」としたら、あなたはその決断を下せるだろうか?会議室で展開される現代の戦争を描く映画『アイ・イン・ザ・スカイ』から、「誤った問い」に答えを出さなければならない極限状況での葛藤を理解する
あわせて読みたい
【家族】映画『そして父になる』が問う「子どもの親である」、そして「親の子どもである」の意味とは?
「血の繋がり」だけが家族なのか?「将来の幸せ」を与えることが子育てなのか?実際に起こった「赤ちゃんの取り違え事件」に着想を得て、苦悩する家族を是枝裕和が描く映画『そして父になる』から、「家族とは何か?」「子育てや幸せとどう向き合うべきか?」を考える
あわせて読みたい
【実話】権力の濫用を監視するマスコミが「教会の暗部」を暴く映画『スポットライト』が現代社会を斬る
地方紙である「ボストン・グローブ紙」は、数多くの神父が長年に渡り子どもに対して性的虐待を行い、その事実を教会全体で隠蔽していたという衝撃の事実を明らかにした。彼らの奮闘の実話を映画化した『スポットライト』から、「権力の監視」の重要性を改めて理解する
あわせて読みたい
【実話】暗号機エニグマ解読のドラマと悲劇を映画化。天才チューリングはなぜ不遇の死を遂げたのか:『…
「解読不可能」とまで言われた最強の暗号機エニグマを打ち破ったのは、コンピューターの基本原理を生み出した天才数学者アラン・チューリングだった。映画『イミテーションゲーム』から、1400万人以上を救ったとされながら、偏見により自殺した不遇の人生を知る
あわせて読みたい
【真実】ホロコーストが裁判で争われた衝撃の実話が映画化。”明らかな虚偽”にどう立ち向かうべきか:『…
「ホロコーストが起こったか否か」が、なんとイギリスの裁判で争われたことがある。その衝撃の実話を元にした『否定と肯定』では、「真実とは何か?」「情報をどう信じるべきか?」が問われる。「フェイクニュース」という言葉が当たり前に使われる世界に生きているからこそ知っておくべき事実
あわせて読みたい
【想像力】「知らなかったから仕方ない」で済ませていいのか?第二の「光州事件」は今もどこかで起きて…
「心地いい情報」だけに浸り、「知るべきことを知らなくても恥ずかしくない世の中」を生きてしまっている私たちは、世界で何が起こっているのかあまりに知らない。「光州事件」を描く映画『タクシー運転手 約束は海を越えて』から、世界の見方を考える
あわせて読みたい
【傑作】濱口竜介監督の映画『ドライブ・マイ・カー』(原作:村上春樹)は「自然な不自然さ」が見事な作品
村上春樹の短編小説を原作にした映画『ドライブ・マイ・カー』(濱口竜介監督)は、村上春樹の小説の雰囲気に似た「自然な不自然さ」を醸し出す。「不自然」でしかない世界をいかにして「自然」に見せているのか、そして「自然な不自然さ」は作品全体にどんな影響を与えているのか
あわせて読みたい
【矛盾】その”誹謗中傷”は真っ当か?映画『万引き家族』から、日本社会の「善悪の判断基準」を考える
どんな理由があれ、法を犯した者は罰せられるべきだと思っている。しかしそれは、善悪の判断とは関係ない。映画『万引き家族』(是枝裕和監督)から、「国民の気分」によって「善悪」が決まる社会の是非と、「善悪の判断を保留する勇気」を持つ生き方について考える
あわせて読みたい
【考察】映画『ジョーカー』で知る。孤立無援の環境にこそ”悪”は偏在すると。個人の問題ではない
「バットマン」シリーズを観たことがない人間が、予備知識ゼロで映画『ジョーカー』を鑑賞。「悪」は「環境」に偏在し、誰もが「悪」に足を踏み入れ得ると改めて実感させられた。「個人」を断罪するだけでは社会から「悪」を減らせない現実について改めて考える
あわせて読みたい
【権利】衝撃のドキュメンタリー映画『ヤクザと憲法』は、「異質さを排除する社会」と「生きる権利」を問う
仮に「ヤクザ」を排除したところで、「ヤクザが担ってきた機能」が不要になるわけじゃない。ではそれを、公権力が代替するのだろうか?実際の組事務所にカメラを持ち込むドキュメンタリー映画『ヤクザと憲法』が、「基本的人権」のあり方について考えさせる
あわせて読みたい
【告発】アメリカに”監視”される社会を暴露したスノーデンの苦悩と決断を映し出す映画:『スノーデン』…
NSA(アメリカ国家安全保障局)の最高機密にまでアクセスできたエドワード・スノーデンは、その機密情報を持ち出し内部告発を行った。「アメリカは世界中の通信を傍受している」と。『シチズンフォー』と『スノーデン』の2作品から、彼の告発内容とその葛藤を知る
あわせて読みたい
【史実】太平洋戦争末期に原爆を落としたアメリカは、なぜ終戦後比較的穏やかな占領政策を取ったか?:…
『八月十五日に吹く風』は小説だが、史実を基にした作品だ。本作では、「終戦直前に原爆を落としながら、なぜ比較的平穏な占領政策を行ったか?」の疑問が解き明かされる。『源氏物語』との出会いで日本を愛するようになった「ロナルド・リーン(仮名)」の知られざる奮闘を知る
あわせて読みたい
【あらすじ】人生行き詰まってなお「生きたい」と思えるか?環境の激変を受け入れる難しさと生きる悲し…
勤務していた会社の都合で、町が1つ丸々無くなるという経験をし、住居を持たないノマド生活へと舵を切った女性を描く映画『ノマドランド』を通じて、人生の大きな変化に立ち向かう気力を持てるのか、我々はどう生きていくべきか、などについて考える
あわせて読みたい
【バトル】量子力学の歴史はこの1冊で。先駆者プランクから批判者アインシュタインまですべて描く:『量…
20世紀に生まれた量子論は、時代を彩る天才科学者たちの侃々諤々の議論から生み出された。アインシュタインは生涯量子論に反対し続けたことで知られているが、しかし彼の批判によって新たな知見も生まれた。『量子革命』から、量子論誕生の歴史を知る
あわせて読みたい
【絶望】権力の濫用を止めるのは我々だ。映画『新聞記者』から「ソフトな独裁国家・日本」の今を知る
私個人は、「ビジョンの達成」のためなら「ソフトな独裁」を許容する。しかし今の日本は、そもそも「ビジョン」などなく、「ソフトな独裁状態」だけが続いていると感じた。映画『新聞記者』をベースに、私たちがどれだけ絶望的な国に生きているのかを理解する
あわせて読みたい
【感想】「献身」こそがしんどくてつらい。映画『劇場』(又吉直樹原作)が抉る「信頼されること」の甘…
自信が持てない時、たった1人でも自分を肯定してくれる人がいてくれるだけで前に進めることがある。しかしその一方で、揺るぎない信頼に追い詰められてしまうこともある。映画『劇場』から、信じてくれる人に辛く当たってしまう歪んだ心の動きを知る
あわせて読みたい
【正義】マイノリティはどう生き、どう扱われるべきかを描く映画。「ルールを守る」だけが正解か?:『…
社会的弱者が闘争の末に権利を勝ち取ってきた歴史を知った上で私は、闘わずとも権利が認められるべきだと思っている。そして、そういう社会でない以上、「正義のためにルールを破るしかない」状況もある。映画『パブリック』から、ルールと正義のバランスを考える
あわせて読みたい
【映画】『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』で号泣し続けた私はTVアニメを観ていない
TVアニメは観ていない、というかその存在さえ知らず、物語や登場人物の設定も何も知らないまま観に行った映画『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』に、私は大号泣した。「悪意のない物語」は基本的に好きではないが、この作品は驚くほど私に突き刺さった
あわせて読みたい
【意外】東京裁判の真実を記録した映画。敗戦国での裁判が実に”フェア”に行われたことに驚いた:『東京…
歴史に詳しくない私は、「東京裁判では、戦勝国が理不尽な裁きを行ったのだろう」という漠然としたイメージを抱いていた。しかし、その印象はまったくの誤りだった。映画『東京裁判 4Kリマスター版』から東京裁判が、いかに公正に行われたのかを知る
あわせて読みたい
【解説】映画『鳩の撃退法』ネタバレ考察。津田伸一の小説は何が真実で、実際は何が起こっていたのか?
映画『鳩の撃退法』の考察をまとめていたら、かなり想像が膨らんでしまった。「東京編で起こったことはすべて事実」「富山編はすべてフィクションかもしれない」という前提に立ち、「津田伸一がこの小説を書いた動機」まで掘り下げて、実際に何が起こっていたのかを考察する
あわせて読みたい
【情熱】常識を疑え。人間の”狂気”こそが、想像し得ない偉業を成し遂げるための原動力だ:『博士と狂人』
世界最高峰の辞書である『オックスフォード英語大辞典』は、「学位を持たない独学者」と「殺人犯」のタッグが生みだした。出会うはずのない2人の「狂人」が邂逅したことで成し遂げられた偉業と、「狂気」からしか「偉業」が生まれない現実を、映画『博士と狂人』から学ぶ
あわせて読みたい
【天才】科学者とは思えないほど面白い逸話ばかりのファインマンは、一体どんな業績を残したのか?:『…
数々の面白エピソードで知られるファインマンの「科学者としての業績」を初めて網羅したと言われる一般書『ファインマンさんの流儀』をベースに、その独特の研究手法がもたらした様々な分野への間接的な貢献と、「ファインマン・ダイアグラム」の衝撃を理解する
あわせて読みたい
【研究】光の量子コンピュータの最前線。量子テレポーテーションを実現させた科学者の最先端の挑戦:『…
世界中がその開発にしのぎを削る「量子コンピューター」は、技術的制約がかなり高い。世界で初めて「量子テレポーテーション」の実験を成功させた研究者の著書『光の量子コンピューター』をベースに、量子コンピューター開発の現状を知る
あわせて読みたい
【知】宇宙は”無”からいかに誕生したのか?量子力学が解き明かす”ビッグバン”以前の謎:『宇宙が始まる…
宇宙は「ビッグバン」から始まったことは知っているだろう。しかし「どのようにビッグバンが起こったのか」を知っているだろうか。『宇宙が始まる前には何があったのか?』をベースに、「空間も時間も物理法則も存在しない無」からいかに宇宙が誕生したのかを学ぶ
あわせて読みたい
【究極】リサ・ランドールが「重力が超弱い理由」を解説する、超刺激的なひも理論の仮説:『ワープする…
現役の研究者であるリサ・ランドールが、自身の仮説を一般向けに分かりやすく説明する『ワープする宇宙』。一般相対性理論・量子力学の知識を深く記述しつつ「重力が超弱い理由」を説明する、ひも理論から導かれる「ワープする余剰次元」について解説する
あわせて読みたい
【実話】正論を振りかざす人が”強い”社会は窮屈だ。『すばらしき世界』が描く「正解の曖昧さ」
「SNSなどでの炎上を回避する」という気持ちから「正論を言うに留めよう」という態度がナチュラルになりつつある社会には、全員が全員の首を締め付け合っているような窮屈さを感じてしまう。西川美和『すばらしき世界』から、善悪の境界の曖昧さを体感する
あわせて読みたい
【考察】映画『テネット』の回転ドアの正体をネタバレ解説。「時間反転」ではなく「物質・反物質反転」…
クリストファー・ノーラン監督の「TENET テネット」は、「陽電子」「反物質」など量子力学の知見が満載です。この記事では、映画の内容そのものではなく、時間反転装置として登場する「回転ドア」の仕組みを端緒に、映画全体の設定を科学的に説明します
あわせて読みたい
【衝撃】森達也『A3』が指摘。地下鉄サリン事件を起こしたオウム真理教は社会を激変させた
「オウム真理教は特別だ、という理由で作られた”例外”が、いつの間にか社会の”前提”になっている」これが、森達也『A3』の主張の要点だ。異常な状態で続けられた麻原彰晃の裁判を傍聴したことをきっかけに、社会の”異様な”変質の正体を理解する。
あわせて読みたい
【現代】これが今の若者の特徴?衝撃のドキュメンタリー映画『14歳の栞』から中学生の今を知る
埼玉県春日部市に実在する中学校の2年6組の生徒35人。14歳の彼らに50日間密着した『14歳の栞』が凄かった。カメラが存在しないかのように自然に振る舞い、内心をさらけ出す彼らの姿から、「中学生の今」を知る
あわせて読みたい
【中二病】世の中は理不尽だ。平凡な奴らがのさばる中で、”特別な私の美しい世界”を守る生き方:『オー…
自分以外は凡人、と考える主人公の少女はとてもイタい。しかし、世間の価値観と折り合わないなら、自分の美しい世界を守るために闘うしかない。中二病の少女が奮闘する『オーダーメイド殺人クラブ』をベースに、理解されない世界をどう生きるかを知る
あわせて読みたい
【救い】自殺を否定しない「笑える自殺本」。「自殺したい」ってもっと気軽に言える社会がいい:『自殺…
生きることがしんどくて、自殺してしまいたくなる気持ちを、私はとても理解できます。しかし世の中的には、「死にたい」と口にすることはなかなか憚られるでしょう。「自殺を決して悪いと思わない」という著者が、「死」をもっと気楽に話せるようにと贈る、「笑える自殺本」
あわせて読みたい
【不満】この閉塞感は打破すべきか?自由意志が駆逐された社会と、不幸になる自由について:『巡査長 真…
自由に選択し、自由に行動し、自由に生きているつもりでも、現代社会においては既に「自由意志」は失われてしまっている。しかし、そんな世の中を生きることは果たして不幸だろうか?異色警察小説『巡査長 真行寺弘道』をベースに「不幸になる自由」について語る
あわせて読みたい
【議論】安楽死のできない日本は「死ぬ権利」を奪っていると思う(合法化を希望している):『安楽死を…
私は、安楽死が合法化されてほしいと思っている。そのためには、人間には「死ぬ権利」があると合意されなければならないだろう。安楽死は時折話題になるが、なかなか議論が深まらない。『安楽死を遂げた日本人』をベースに、安楽死の現状を理解する
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
孤独・寂しい・友達【本・映画の感想】 | ルシルナ
孤独と向き合うのは難しいものです。友達がいないから学校に行きたくない、社会人になって出会いがない、世の中的に他人と会いにくい。そんな風に居場所がないと思わされて…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…















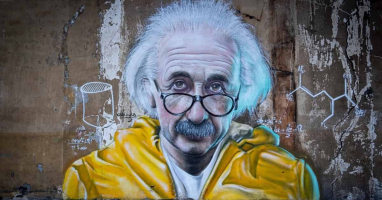

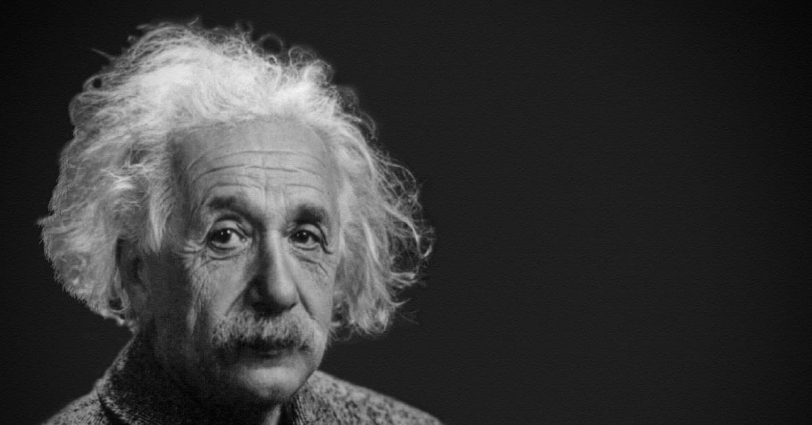












































































































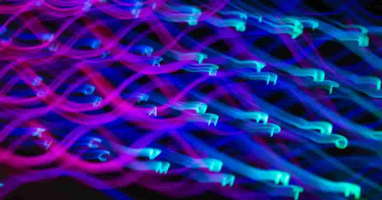




















コメント