目次
はじめに
この記事で取り上げる本
著:逢坂 冬馬
¥1,881 (2024/02/04 19:14時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
この本をガイドにしながら記事を書いていきます
この記事の3つの要点
- 「戦場」が人間を「怪物」に変えてしまう現実と、「戦場」を離れてもなお「人間」に戻れるわけではないという不条理
- 「生きるにせよ死ぬにせよ、そこに『明確な理由』が存在する」という事実に、ある種の羨ましさを感じてしまう
- 「『すべての選択肢が不正解』である理不尽な世界で何を選び取るのか」という決断に、個々の人間性が浮き彫りにされる
ジェンダーの問題も絶妙に入れ込みながら、異次元の世界における葛藤をリアルに描く、若き俊英による傑作
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
『同志少女よ、敵を撃て』(逢坂冬馬)は、新人のデビュー作だとはとても信じられない、あまりにも衝撃的な本屋大賞受賞作
あわせて読みたい
【矛盾】法律の”抜け穴”を衝く驚愕の小説。「ルールを通り抜けたものは善」という発想に潜む罠:『法廷…
完璧なルールは存在し得ない。だからこそ私たちは、矛盾を内包していると理解しながらルールを遵守する必要がある。「ルールを通り抜けたものは善」という”とりあえずの最善解”で社会を回している私たちに、『法廷遊戯』は「世界を支える土台の脆さ」を突きつける
とんでもない作品だった。「デビュー作の時点で、小説家としてあまりにも凄まじい」と感じさせる作家は、私が読んできた中でも何人かいるが、本書『同志少女よ、敵を撃て』もそんな1作である。「デビュー作にしては凄い」のではなく、「既にデビュー作の時点で、小説家として凄まじい」のだ。4000冊近くの本を読んできた私も、久々に度肝を抜かれてしまった。
そもそも扱われているテーマが「独ソ戦」である。著者の逢坂冬馬は1985年生まれで、私の2歳年下だ。当然、1941年から1945年に掛けての独ソ戦の記憶があるはずもない。そんな若手作家が、「戦争の緊迫感」「不可能とも思える作戦・戦術の遂行」「狙撃手としての心得」などについて、「とんでもなくリアリティがある」と感じさせる作品を紡ぎ出しているのだ。正直、ベテランの作家でも、ここまでの世界観を作り出すのは相当難しいのではないかと思う。

また本作では、実際に当時ソ連に存在したらしい「女性狙撃兵」が描かれる。登場人物の1人で、確認戦果309人という他の追随を許さない戦績を持つリュドミラ・パヴリチェンコは、巻末の参考文献の書名等から判断するに、実在した人物であるようだ。また作中には、「ソ連には女性狙撃兵が存在した」という事実を示す、様々な書籍からの引用が時折挿入されている。
あわせて読みたい
【衝撃】壮絶な戦争映画。最愛の娘を「産んで後悔している」と呟く母らは、正義のために戦場に留まる:…
こんな映画、二度と存在し得ないのではないかと感じるほど衝撃を受けた『娘は戦場で生まれた』。母であり革命家でもあるジャーナリストは、爆撃の続くシリアの街を記録し続け、同じ街で娘を産み育てた。「知らなかった」で済ませていい現実じゃない。
戦時中のことなのだから機密事項も多かっただろうし、「女性狙撃兵の育成」について現時点でどこまで明らかになっているのかは分からない。恐らく、まったく資料が存在しないなんてことは無いだろう。ただそうだとしても、女性狙撃兵たちの「訓練の日々や訓練外の日常」「抱き続ける葛藤や苦労」などをリアルに描き出すことはかなり困難ではないかと思う。
そのような凄まじく難しいテーマを扱いながら「とんでもなくリアルだ」とも感じさせる物語をデビュー作で書き上げた著者には、やはり喝采の気持ちしかないし、これからもその圧倒的な才能を駆使して面白い物語を紡いでいってほしいと思う。
「戦場」は、人間を「怪物」に変えてしまう
物語は、「否応なしに人生を破壊尽くされたセラフィマが、土壇場で女性狙撃兵を育成する訓練校の教官イリーナに命だけは救われ、そのまま強制的に女性狙撃兵としての人生を歩まされる」という形で進んでいく。当然と言えば当然だろうが、自ら望んで女性狙撃兵になろうと考えた者などいない。
あわせて読みたい
【弾圧】香港デモの象徴的存在デニス・ホーの奮闘の歴史。注目の女性活動家は周庭だけじゃない:映画『…
日本で香港民主化運動が報じられる際は周庭さんが取り上げられることが多いが、香港には彼女よりも前に民主化運動の象徴的存在として認められた人物がいる。映画『デニス・ホー ビカミング・ザ・ソング』の主人公であるスター歌手の激動の人生を知る
戦場は、過酷だ。
忘れるな。お前たちが泣くことが出来るのは、今日だけだ。
仲間の死を経験した者たちに、上官がこのように告げる場面がある。セラフィマはこの言葉を耳にした時、その正確な意味を理解できていなかった。単に、「次からは、甘えが許されなくなる」というぐらいの意味に受け取っていたのだ。
しかし、狙撃兵として実績を積み上げ、その圧倒的な実力から小隊が「魔女」と呼ばれるようになって初めて、彼女はようやく正しい意味を理解出来るようになった。
しかし実際は違った。今日を最後に、泣けないようになる。
要するに、「自分は『怪物』になってしまった」と自覚させられたのである。
あわせて読みたい
【感想】是枝裕和監督映画『怪物』(坂元裕二脚本)が抉る、「『何もしないこと』が生む加害性」
坂元裕二脚本、是枝裕和監督の映画『怪物』は、3つの視点を通して描かれる「日常の何気ない光景」に、思いがけない「加害性」が潜んでいることを炙り出す物語だ。これは間違いなく、私たち自身に関わる話であり、むしろ「自分には関係ない」と考えている人こそが自覚すべき問題だと思う
自分が怪物に近づいてゆくという実感が確かにあった。
しかし、怪物でなければこの戦いを生き延びることは出来ないのだ。
楽しむな、とイリーナは言った。自分は人殺しを楽しんでいた。

女性たちだけではなく、戦場に立つ男たちもまた、次のように考える。
イワン(※ロシア兵を意味するドイツ側の俗語)という怪物と戦うには、自らも怪物にならねばならない。
それって、指揮官が悪魔だったからじゃない……この戦争には、人間を悪魔にしてしまうような性質があるんだ。
あわせて読みたい
【実話】ソ連の衝撃の事実を隠蔽する記者と暴く記者。映画『赤い闇』が描くジャーナリズムの役割と実態
ソ連の「闇」を暴いた名もなき記者の実話を描いた映画『赤い闇』は、「メディアの存在意義」と「メディアとの接し方」を問いかける作品だ。「真実」を届ける「社会の公器」であるべきメディアは、容易に腐敗し得る。情報の受け手である私たちの意識も改めなければならない
多くの者たちが、「戦場にいる自分は『怪物』になってしまっている」という自覚を持ちながら闘いを続けているのだ。
一方で、当然だろうが、それを否定したい気持ちを強く抱く者もいる。
つまり、誰かがそれを殺す。殺す必要がある。誰が、いつ、どうやって殺したかなんて、誰も気にしない。……だから、私たちが殺したことにはならない。
自分たちが銃における引き金であって射手ではないことを教え、彼が敵はもちろん、NKVDやパルチザンを迷いなく撃てるように指南してやった。
あわせて読みたい
【感想】映画『野火』は、戦争の”虚しさ”をリアルに映し出す、後世に受け継がれるべき作品だ
「戦争の悲惨さ」は様々な形で描かれ、受け継がれてきたが、「戦争の虚しさ」を知る機会はなかなかない。映画『野火』は、第二次世界大戦中のフィリピンを舞台に、「敵が存在しない戦場で”人間の形”を保つ困難さ」を描き出す、「虚しさ」だけで構成された作品だ
自分は重要な任務を担っている。誰かがやらなければならないことだ。それをたまたま自分がやっているだけ。だから自分は決して「怪物」などではない。多くがそのように考えるのだが、しかし、「そんな風に言い聞かせなければ自分自身を保てない」という自覚こそが、既に「怪物」の証拠であるようにも感じられる。何とも凄まじい環境だ。
そして、そんな風に「怪物ではない」と思い込みたがっている者たちさえも、思いがけない瞬間に自身の「怪物」を自覚させられてしまう。それは、セラフィマが記者からインタビューを受けるシーンにも現れる。
「ああ、最後に一つだけ聞かせて下さい」
振り向いて首を傾げる。
「撃った敵の顔を、夢に見ることがありますか?」
それは、国内の記者の問いとしては異質なものだった。
職責から離れた問い、個人に属する質問のようでもあった。
英雄にまとわりついた虚構の皮膜をめくり、皮膚に触れようとするような問い。
「一度もありませんね」
セラフィマが直截に答えると、記者は挨拶とともに落胆の顔を浮かべた。
真の姿に迫ることはできなかった、と考えたようだった。
ちがうんだよ、とセラフィマは思う。
私は本当に一度も、そんなことで苦しんではいないんだ。
「他人の死」に鈍感だという事実を、「戦場に立たない者」に自覚させられた瞬間だ。このように彼女たちは、「『怪物』である自分」に葛藤しながら戦場を、そして日常を生きていくことになる。
あわせて読みたい
【妄執】チェス史上における天才ボビー・フィッシャーを描く映画。冷戦下の米ソ対立が盤上でも:映画『…
「500年に一度の天才」などと評され、一介のチェスプレーヤーでありながら世界的な名声を獲得するに至ったアメリカ人のボビー・フィッシャー。彼の生涯を描く映画『完全なるチェックメイト』から、今でも「伝説」と語り継がれる対局と、冷戦下ゆえの激動を知る
狙撃兵は、「『戦場』を離れれば『人間』に戻れる」わけではない

「怪物」になるのを避けたいのであれば、「戦場」から離れるしかない。しかし難しいのは、「『戦場』から離れれば『怪物』にならずに済むが、決して『人間』に戻れるわけではない」ということだろう。この点にこそ、狙撃兵の特異さが存在すると言える。「狙撃兵が『戦場』を離脱した」という事実は、また違った意味を持つのだ。
例えば、凄腕の女性狙撃兵2人の会話が、それを示唆している。
共通することに気付いた。
彼女ら二人はともに死ぬことなく狙撃兵という立場から降りた。
二人は生きながらえたまま、撃ちあい、殺し合う戦場の一線から退いたことを運が悪かったと形容し、それを前提として会話していた。
背筋が凍る思いがしたとき、リュドミラが微笑んだ。
「ま、これが狙撃兵の、言ってみれば生き方だ」
あるいは、ある者がイリーナに、こんな問いを投げかける場面もある。
イリーナ、戦場で死ぬつもりがないのなら、君の戦争はいつ終わる。
あわせて読みたい
【現実】戦争のリアルを”閉じ込めた”映画。第一次世界大戦の英軍を収めたフィルムが描く衝撃:映画『彼…
第一次世界大戦でのイギリス兵を映した膨大な白黒フィルムをカラー化して編集した『彼らは生きていた』は、白黒の映像では実感しにくい「リアルさ」を強く感じられる。そして、「戦争は思ったよりも安易に起こる」「戦争はやはりどこまでも虚しい」と実感できる
これらはすべて、「狙撃兵は戦場で死ぬものだ」という認識が前提になっていると言えるだろう。少なくとも、歴戦の強者と言っていい狙撃兵はそのように考えているのである。
狙撃兵というのは、ほとんど戦場でしか役に立たない能力を研ぎ澄ましていくのだから、次第に「戦場にいること」そのものが「生きる理由」になっていく。しかしそれは、とても脆い理由でもあると言える。がん細胞が自身の宿主の命を奪うことで自らの居場所を失ってしまうように、狙撃兵も「戦場」を失えばそのまま「生きる理由」を失ってしまうことになるからだ。そしてだからこそ、狙撃兵にとって「戦場」は「死を迎える場所」という認識になるのだろう。「『戦場』が無くなってしまう前に死ななければならない」というような、実に歪んだ思考に支配されていくのだと思う。
あまりにも異常で狂気的であり、理解の及ばない世界と言えるだろう。
あわせて読みたい
【凄絶】北朝鮮の”真実”を描くアニメ映画。強制収容所から決死の脱出を試みた者が語る驚愕の実態:『ト…
在日コリアン4世の監督が、北朝鮮脱北者への取材を元に作り上げた壮絶なアニメ映画『トゥルーノース』は、私たちがあまりに恐ろしい世界と地続きに生きていることを思い知らせてくれる。最低最悪の絶望を前に、人間はどれだけ悪虐になれてしまうのか、そしていかに優しさを発揮できるのか。
そして、そんな矛盾だらけの世界を生きざるを得ないからこそ、セラフィマたち個々の生き様が印象的な形で描かれることにもなる。黒一色の世界に微かな灯りが転々としているような、そんな仄かな希望が感じられるのだ。「『地獄』みたいな、誰もが『怪物』にならざるを得ないような世界の中でも、人間は『人間らしさ』を手放さずに生きていけるのかもしれない」と思わせる、「希望」と呼んでいいのか悩むほどの微かな光が映し出されていくのである。
セラフィマが戦争から学び取ったことは、八百メートル向こうの敵を撃つ技術でも、戦場であらわになる究極の心理でも、拷問の耐え方でも、敵との駆け引きでもない。
命の意味だった。
失った命は元に戻ることはなく、代わりになる命もまた存在しない。
学んだことがあるならば、ただこの率直な事実、それだけを学んだ。

そしてこのような彼女の感覚には、「狙撃兵になる以前の世界の酷さ」も含まれていると考えていいだろうと思う。というのも、「そんな過酷な環境に身を置かなければ『命の意味』を理解できないほど、人間があっさりと死んでいく日常を生きていた」と言えるからだ。
あわせて読みたい
【驚愕】一般人スパイが北朝鮮に潜入する映画『THE MOLE』はとてつもないドキュメンタリー映画
映画『THE MOLE』は、「ホントにドキュメンタリーなのか?」と疑いたくなるような衝撃映像満載の作品だ。「『元料理人のデンマーク人』が勝手に北朝鮮に潜入する」というスタートも謎なら、諜報経験も軍属経験もない男が北朝鮮の秘密をバンバン解き明かす展開も謎すぎる。ヤバい
あらゆる意味で「異常」でしかない世界なのである。
誤った考えだろうが、「生きるにせよ死ぬにせよ、そこに『理由』が存在するなら素敵」だと感じてしまう
さて、狙撃兵たちには「生きる理由」も「死ぬ理由」もある。もちろんそれは、「戦場」という圧倒的な不条理を大前提とした、あまりに仮初なものでしかない。しかしそれでも彼女たちには、生きるにせよ死ぬにせよ、そこには「理由」があると言っていいだろう。
そしてそれは、ある意味で悪くないと私には感じられてしまう。少なくとも、「生きる理由」も「死ぬ理由」も大して持たずに生きている私にはそう映るのだ。このような考えはもしかしたら、不謹慎と受け取られるかもしれないが。
少女たちは、「戦いたいか、死にたいか」という凄まじい2択を突きつけられ集められた。どちらもまったく選びたくない選択肢だが、そこで「戦うこと」を選択した者たちが、新たに「狙撃兵」としての人生をスタートさせていくことになる。
あわせて読みたい
【実話】映画『アウシュビッツ・レポート』が描き出す驚愕の史実。世界はいかにホロコーストを知ったのか?
映画『アウシュヴィッツ・レポート』は、アウシュビッツ強制収容所から抜け出し、詳細な記録と共にホロコーストの実態を世界に明らかにした実話を基にした作品。2人が持ち出した「アウシュビッツ・レポート」こそが、ホロコーストについて世界が知るきっかけだったのであり、そんな史実をまったく知らなかったことにも驚かされた
そんな彼女たちが「死ぬ理由」はとても明白だ。
現代の戦争では、機銃兵も砲兵も爆撃手も軍艦乗りも、あらゆる兵科は集団性とそれによる匿名性の陰に隠れることができる。しかし、お前たち狙撃兵にそれはできない。常に自分は何のために敵を撃つのかを見失うな。それは根本の目標を見失うことだ。そこで死を迎える。
彼女たちは、訓練校を卒業する際に改めて「何のために戦うか、答えろ」と上官から問われる。この問いに明確な答えを持っているかどうかが、ある意味では「最終試験」というわけだ。戦争に従事する他の者たちと比較して、「狙撃兵」は圧倒的に「個」として戦場に立たざるを得ない。だからこそ、「戦場に立つ理由」を明確に抱いていなければ、そこに居続けられないのである。
「居続けられない」というのは要するに、「死」を意味するというわけだ。
あわせて読みたい
【憤り】世界最強米海軍4人VS数百人のタリバン兵。死線を脱しただ1人生還を果たした奇跡の実話:『アフ…
アフガニスタンの山中で遭遇した羊飼いを見逃したことで、数百人のタリバン兵と死闘を繰り広げる羽目に陥った米軍最強部隊に所属する4人。奇跡的に生き残り生還を果たした著者が記す『アフガン、たった一人の生還』は、とても実話とは信じられない凄まじさに満ちている
また、容赦なくこんな言葉を突きつけられもする。
同志リュドミラは偉大な狙撃兵であるが故に生還した。お前たちは誰一人として、リュドミラ・パヴリチェンコではない。敗北は死だ。お前たちは、負けたときは死ぬ。
あるいは、狙撃兵であるが故の特殊性が指摘される場面もある。
通常の技術者は失敗を繰り返して熟練に近づく。だが我々の世界に試行錯誤は許されない。
つまり、「失敗は即、『死』を意味する」というわけだ。

作中では当然、狙撃兵たちの「死」も描かれる。仲間が命を落とす度に、「狙撃兵として生きることの難しさ」、そして「狙撃兵として死ぬことの容易さ」が突きつけられると言っていいだろう。
あわせて読みたい
【実話】「ホロコーストの映画」を観て改めて、「有事だから仕方ない」と言い訳しない人間でありたいと…
ノルウェーの警察が、自国在住のユダヤ人をまとめて船に乗せアウシュビッツへと送った衝撃の実話を元にした映画『ホロコーストの罪人』では、「自分はそんな愚かではない」と楽観してはいられない現実が映し出される。このような悲劇は、現在に至るまで幾度も起こっているのだ
しかし見方を変えれば、「彼女たちが死に至った理由は明白だ」とも捉えられる。そしてそのことは、私には悪くないことのように思えてしまう。特に理由も無く何となく死を迎えるよりは、「生を全うしている」という感じがするからだ。
一方、彼女たちは戦場で「生きる理由」も見出す。まあそれは、「撃つ理由」とでも言うべきものだが。
ドイツ軍も、あんたも殺す! 敵を皆殺しにして、敵を討つ!
あわせて読みたい
【史実】太平洋戦争末期に原爆を落としたアメリカは、なぜ終戦後比較的穏やかな占領政策を取ったか?:…
『八月十五日に吹く風』は小説だが、史実を基にした作品だ。本作では、「終戦直前に原爆を落としながら、なぜ比較的平穏な占領政策を行ったか?」の疑問が解き明かされる。『源氏物語』との出会いで日本を愛するようになった「ロナルド・リーン(仮名)」の知られざる奮闘を知る
凄いよね、復讐の力って。生きる希望を与えてくれる。
「復讐」という感情が褒められたものではないことは十分理解している。しかし彼女たちは「戦場」で生きていくために、「復讐」にその理由を見出すのだ。そして、あまりに特殊な状況ではあるものの、こんな風にはっきりと「生きる理由」を抱けることもまた、私には悪くないように感じられてしまった。
「戦争」というのは圧倒的に「悲惨さ」を纏った状況であり、その点を抜きにして何かを考えることにほとんど意味など無いと理解している。しかし、ある種の思考実験としてその「悲惨さ」を脇に置いてみた時、「『死ぬ理由』も『生きる理由』も明確に抱くことが出来る」という状況は、私には決して悪くないことのように感じられるのだ。
当然、そんな判断は間違っているのだが。
あわせて読みたい
【議論】安楽死のできない日本は「死ぬ権利」を奪っていると思う(合法化を希望している):『安楽死を…
私は、安楽死が合法化されてほしいと思っている。そのためには、人間には「死ぬ権利」があると合意されなければならないだろう。安楽死は時折話題になるが、なかなか議論が深まらない。『安楽死を遂げた日本人』をベースに、安楽死の現状を理解する
逢坂冬馬『同志少女よ、敵を撃て』の内容紹介
ソ連のイワノフスカヤ村で猟師の母親と2人で暮らしているセラフィマは、母親から教わりながら食害をもたらす野生動物を撃つ日々を送っていたのだが、一方で、村で初めて大学に進学することも決まっていた。熱心にドイツ語を学んでいるのは、外交官となり、戦争終結後にドイツとソ連の仲を取り持ちたいと考えているからだ。
しかし18歳のある日、抱いていた夢がすべて打ち砕かれる出来事が起こる。母娘が狩りをしている最中に、ドイツ軍が村を襲ったのだ。彼らが村人を殺し始めたため、母親は猟銃をドイツ兵に向けた。しかし人を撃ったことがない母親は結局引き金が引けず、逆にドイツ兵に撃ち殺されてしまう。その後セラフィマもドイツ兵に捕まった。そしてまさに蹂躙されそうになる直前に、赤軍の兵士が助けに来てくれたのである。
その中に、細身で黒髪のイリーナがいた。
あわせて読みたい
【絶望】子供を犯罪者にしないために。「異常者」で片付けられない、希望を見いだせない若者の現実:『…
2人を殺し、7人に重傷を負わせた金川真大に同情の余地はない。しかし、この事件を取材した記者も、私も、彼が殺人に至った背景・動機については理解できてしまう部分がある。『死刑のための殺人』をベースに、「どうしようもないつまらなさ」と共に生きる現代を知る
彼女はセラフィマに、「戦いたいか、死にたいか」と問う。セラフィマは「死にたい」と答えたのだが、母親の遺体を尊厳なく焼き捨てる様に怒りを覚え、イリーナに向かって「ドイツ軍も、あんたも殺す!」と啖呵を切ってみせた。

そんな風にしてセラフィマは、イリーナによってある施設へと連れていかれることになる。そこは女性狙撃兵を育成する訓練校であり、イリーナはその教官だったのだ。集められたのはセラフィマ同様、家族を殺された者たちで、イリーナはそんな彼女たちを一人前の狙撃兵に育て上げようと奮闘する。あまりにも壮絶な指導に脱落者を出しながらも、その圧倒的な育成力によって、短期間で彼女たちを戦場に出せる一流の狙撃兵へと育て上げていく。
その後、セラフィマ、シャルロッタ、アヤ、ヤーナ、オリガにイリーナを加えた6人が、最高司令部直属の第三九独立小隊として編成された。そして彼女たちは、「狙撃兵にとっての天国……すなわちこの世の地獄」と称される市街戦へと投入されることになり……。
あわせて読みたい
【感想】才能の開花には”極限の環境”が必要か?映画『セッション』が描く世界を私は否定したい
「追い込む指導者」が作り出す”極限の環境”だからこそ、才能が開花する可能性もあるとは思う。しかし、そのような環境はどうしても必要だろうか?最高峰の音楽院での壮絶な”指導”を描く映画『セッション』から、私たちの生活を豊かにしてくれるものの背後にある「死者」を想像する
逢坂冬馬『同志少女よ、敵を撃て』の感想
戦場における女性たちの濃密な関わり、そして「すべての選択肢が不正解」の中で何を選ぶべきかという葛藤
物語は主に、同じ訓練校の同期たちの訓練の奮闘と、後にイリーナを加えて編成される小隊での闘いの姿が描かれ、1人ひとりの個性がきちんと際立つように構成されている。個々の考え方を背景にした対立や協力、そしてそのような関わりを経た上での変化や成長が濃密に描かれているというわけだ。
まずは何よりも、そんな彼女たちの関わり方がとても素晴らしいと感じた。
戦争とは直接関わりのなかったセラフィマたちは、訓練や戦闘の過程で怒り、悲しみ、諦めなどを経験し、呆然とすることもあれば我を忘れることもある。さらにその中で、自身のエゴや怪物性が自覚させられることになるというわけだ。一方で、同期たちとの関わり方も大きく変化していく。戦時下であるが故に、「最悪」としか言いようのない関わり方からスタートした彼らの関係性は、時間の経過と共に少しずつ変質していき、出会った頃には想像も出来なかったようなある種の「親密さ」を帯びるまでになる。しかし、特殊な環境で生きざるを得ないが故に、それは決して「仲良し」という状態になることはない。そんな「異質で複雑で濃密な関係性」を実に見事に描写していると感じた。
あわせて読みたい
【あらすじ】原爆を作った人の後悔・葛藤を描く映画『オッペンハイマー』のための予習と評価(クリスト…
クリストファー・ノーラン監督作品『オッペンハイマー』は、原爆開発を主導した人物の葛藤・苦悩を複雑に描き出す作品だ。人間が持つ「多面性」を様々な方向から捉えようとする作品であり、受け取り方は人それぞれ異なるだろう。鑑賞前に知っておいた方がいい知識についてまとめたので、参考にしてほしい
私が特に感心したのは、途中から小隊に帯同することになった看護師のターニャである。もちろん、様々な場面におけるターニャ自身の立ち居振る舞いも素晴らしい。しかし最も印象的だったのは、物語のラストである。セラフィマが「狙撃兵」としての人生を歩まざるを得なくなった発端の出来事に繋がるやり取りをターニャとする場面が圧巻だと感じたのだ。
具体的には触れないが、セラフィマはターニャの話を聞くことで、「『選べなかった』という怒りが、『自ら選んだ』という納得へと変わる」という経験をすることになる。彼女は様々な状況で多くの人物と関わりを持つことで、その度ごとに自身の考えや価値観を変化させていくわけだが、その中でもこのラストのやり取りは、とても印象的なものに感じられた。
さらにこのやり取りは、セラフィマが「戦後をどう生きるか」を考える際にも影響したはずだ。もちろん、ターニャとの話だけで決断に至ったわけではないだろうが、「『戦場』を離脱した後どのように生きていくべきか」についての1つの大きな指針となったことは確かだと思う。
さて、個人の決断の話で言うなら、「『すべての選択肢が不正解』である理不尽な世界において、『どの不正解を選ぶのか』という決断に個々の生き様が反映される」という点もまた、とても印象的だった。
あわせて読みたい
【狂気】アメリカの衝撃の実態。民営刑務所に刑務官として潜入した著者のレポートは国をも動かした:『…
アメリカには「民営刑務所」が存在する。取材のためにその1つに刑務官として潜入した著者が記した『アメリカン・プリズン』は信じがたい描写に溢れた1冊だ。あまりに非人道的な行いがまかり通る狂気の世界と、「民営刑務所」が誕生した歴史的背景を描き出すノンフィクション
彼女たちの目の前に存在する選択肢は、結局のところ「すべてが不正解」なのだから、当然、他人の決断に対して「どうしてそんなことを?」という批判が常に成立し得る。実際、本書の登場人物たちも様々な場面で、「その決断が正しいとは思えない」と相手を説得しようとするのだ。

もちろんそれは、相手のことを思っての説得であり、ある意味で「友情」を抱いているからこその行動なのだが、同時に、「どうせすべてが不正解なのだから、何を選んでも変わらないだろう」という感覚にもなった。例えば、具体的な状況には触れないが、
最後までこの家と運命を共にする。
と主張した人物の決断もまた、そんな「不正解」を選んだものと言っていいだろう。明らかに「狂気」でしかない選択ではあるのだが、どうせ「正解」など存在しないのだから、どんな選択もほとんど等価だと考えていい。だったら、個人の価値観を最大限に反映させた選択をすればいいし、まさにそれが如実に現れたシーンだったと感じた。
あわせて読みたい
【思考】戸田真琴、経験も文章もとんでもない。「人生どうしたらいい?」と悩む時に読みたい救いの1冊:…
「AV女優のエッセイ」と聞くと、なかなか手が伸びにくいかもしれないが、戸田真琴『あなたの孤独は美しい』の、あらゆる先入観を吹っ飛ばすほどの文章力には圧倒されるだろう。凄まじい経験と、普通ではない思考を経てAV女優に至った彼女の「生きる指針」は、多くの人の支えになるはずだ
このような世界を描き出すことによって、「戦争の悲惨さ、虚しさ」を直接的にではなく切り取っていく手腕もまた、とても見事だと思う。
「ジェンダー問題」も描かれる
さて本作には、「性差別」もテーマとして内包されている。具体的には触れないが、タイトルになっている「同志少女よ、敵を撃て」という想いもまた、ジェンダー的なテーマを背景にしたものなのだ。
戦争をテーマにした作品である以上、ある意味で”当然”と言えるかもしれないが、本作では「戦場で女性が犯される」「売春宿で軍人相手に奉仕させられる」といった「性差別」も描かれる。これを「当然」と捉えていてはいけないが、しかし、一昔前の戦争で事実そのようなことがあったのだから、「戦争」をテーマにする以上、このような「性差別」が扱われることは避けられない。
あわせて読みたい
【脅迫】原発という巨大権力と闘ったモーリーン・カーニーをイザベル・ユペールが熱演する映画『私はモ…
実話を基にした映画『私はモーリーン・カーニー』は、前半の流れからはちょっと想像もつかないような展開を見せる物語だ。原発企業で従業員の雇用を守る労働組合の代表を務める主人公が、巨大権力に立ち向かった挙げ句に自宅で襲撃されてしまうという物語から、「良き被害者」という捉え方の”狂気”が浮かび上がる
しかし本書で扱われているのは、そのような「分かりやすい性差別」だけではない。作中では、「男性が抱く、無自覚の『女性差別』」もそこかしこに描かれるのだ。
例えばこんな場面がある。スターリングラードにたどり着いたセラフィマたちは、そこで徹底抗戦を続けている大隊(とは言うものの、既に4人しか残っていない)と合流した。彼らは大隊の本拠地で監視を続けるのだが、ある時彼らの視界に、大隊が「サンドラ」と呼ぶ女性が姿を現す。大隊の面々は彼女について、「ドイツ軍の被占領地から赤軍の陣地まで来て水を汲んでいるだけであり、怪しい人物ではないから注意する必要はない」と説明した。
それを聞いたセラフィマは、次のように感じる。
マクシム隊長はそれを当然と受け止めているが、それは彼女が女だからだろう。同じ女として、かすかな苛立ちを覚えていることに、遅れて気付いた。
あわせて読みたい
【抵抗】西加奈子のおすすめ小説『円卓』。「当たり前」と折り合いをつけられない生きづらさに超共感
小学3年生のこっこは、「孤独」と「人と違うこと」を愛するちょっと変わった女の子。三つ子の美人な姉を「平凡」と呼んで馬鹿にし、「眼帯」や「クラス会の途中、不整脈で倒れること」に憧れる。西加奈子『円卓』は、そんなこっこの振る舞いを通して「当たり前」について考えさせる
大隊が「危険人物かどうか」を客観的に判断しているのではなく、「女だから安全だ」という短絡的な見方をしているに過ぎないと見抜いたのだ。
また、大隊と今後の作戦について打ち合わせをしている場面でも似たような状況が描かれる。当然のことだが、狙撃兵はより危険な地点へと進んでいって敵を撃つ。それが狙撃兵の役割であり、だからこそ彼女たちは大隊にそのように説明する。しかしそれを聞いた隊長が複雑な表情を滲ませたことをセラフィマは見逃さなかった。そして、同じことを感じ取ったイリーナがこう問いただすのである。

自らが下がって我々のような女を前線に出させるのは恥かね? 上級曹長。
あわせて読みたい
【違和感】三浦透子主演映画『そばかす』はアセクシャルの生きづらさを描く。セクシャリティ理解の入り口に
「他者に対して恋愛感情・性的欲求を抱かないセクシャリティ」である「アセクシャル」をテーマにした映画『そばかす』は、「マイノリティのリアル」をかなり解像度高く映し出す作品だと思う。また、主人公・蘇畑佳純に共感できてしまう私には、「普通の人の怖さ」が描かれている映画にも感じられた
戦時下であること、さらに「女性狙撃兵」が非常に特殊な存在であることを踏まえると、イリーナからの指摘がより一層厳しいものに感じられたかもしれない。そして彼女たちは、「男性が女性のことを無意識レベルで下に見ており、そういう自覚が無いまま女性差別的な言動をしてしまう」という状況に、非常に敏感なのである。
このような「ジェンダー問題」に、当時の一般的な女性がどのような問題意識を抱いていたのか、あるいは抱いていなかったのか、その辺りのことは私には分からない。しかし本書で描かれる女性たちの場合は、「能力的には男性よりも遥かに上である」という自負があり、そう考えて当然なほどの実績も持ち合わせている。そしてそれ故に、「男性からの蔑視感情」にも気づきやすかったと言えるだろう。そういう感覚を物語の中に組み込む感じがとても上手いとも感じた。
特にセラフィマは、訓練校の卒業試験で「なぜ戦うのか」と問われた際に「女性を守るため」と返したこともあり、他の同期と比べても一層、「このような環境下で女性がきちんと守られているか」に敏感になっていると言っていいだろう。
しかしそんなセラフィマも、戦闘を重ねることによって葛藤を抱かされてしまう。
あわせて読みたい
【傑物】フランスに最も愛された政治家シモーヌ・ヴェイユの、強制収容所から国連までの凄絶な歩み:映…
「フランスに最も愛された政治家」と評されるシモーヌ・ヴェイユ。映画『シモーヌ』は、そんな彼女が強制収容所を生き延び、後に旧弊な社会を変革したその凄まじい功績を描き出す作品だ。「強制収容所からの生還が失敗に思える」とさえ感じたという戦後のフランスの中で、彼女はいかに革新的な歩みを続けたのか
女性を助ける。そのためにフリッツ(※作中では「ドイツ兵」を指す言葉)を殺す。自分の中で確定した原理が、どことなく胡乱に感じられた。
このような感覚になったのは、セラフィマが抱いていた「女性」という存在があまりにも漠然としすぎていたからだろう。
セラフィマが「女性を守るため」と答えた時には、その「女性」には具体的なイメージが付随していなかったのだと思う。というかそもそも、「女性を守るため」というのは、「復讐を果たすため」という本当の理由を伏せておくための都合の良い言葉でしかなかったのだろう。
しかしセラフィマは事ある毎に、自身が発した「女性を守るため」という言葉を思い返すことになる。そして少しずつ、自分が「守るべき」と考えたその「女性」という概念が、「様々な価値観を含む集合体」なのだと理解していくのだ。
あわせて読みたい
【感想】映画『キリエのうた』(岩井俊二)はアイナ・ジ・エンドに圧倒されっ放しの3時間だった(出演:…
映画『キリエのうた』(岩井俊二監督)では、とにかくアイナ・ジ・エンドに圧倒されてしまった。歌声はもちろんのことながら、ただそこにいるだけで場を支配するような存在感も凄まじい。全編に渡り「『仕方ないこと』はどうしようもなく起こるんだ」というメッセージに溢れた、とても力強い作品だ
このような視点はまさに、現代においてもとても有効だろう。「ジェンダー問題」と一括りにして捉えたところで、何も見えてこないし解決するはずもない。しかし実際は、そういう捉え方をベースに、「見た目や体裁だけをとにかく綺麗に整える」みたいな提言ばかりがなされている印象がある。正直、そんなことでは何も変わるはずがない。
本作は戦時下を舞台にした物語であり、もう少し抽象的に捉えるなら、「『あらゆる異常性が許容され得る』という共同幻想を抱く者たちの現実を描く作品」だと言えるだろう。そしてそれは、「綺麗に整える」みたいなこととはまったく無縁の世界でもあるのだ。そのような極端な世界で発露される「あらゆる虚飾を剥ぎ取った振る舞い」にこそ「ジェンダー問題」の本質があるように私は感じるし、そういう意味でもこの物語は読むべき価値があると言えるのではないかと思う。
またこのような考え方は、「ジェンダー問題」だけではなく「戦争」そのものに対しても適用出来るだろう。私たちはどうしても、「戦争」を漠然とした具体性の無いものとして捉えてしまいがちだが、それではそこに内包される「悲惨さ」を想像することは難しくなる。本作はそんな「戦争」を「女性狙撃兵」というかなり特殊な視点から描き出す作品であり、その特異な視点が「戦争の異常さ」をまた違った形で浮かび上がらせていると思う。そういう作品としても受け取られるべきだろうと感じた。

あわせて読みたい
【衝撃】ウクライナでのホロコーストを描く映画『バビ・ヤール』は、集めた素材映像が凄まじすぎる
ソ連生まれウクライナ育ちの映画監督セルゲイ・ロズニツァが、「過去映像」を繋ぎ合わせる形で作り上げた映画『バビ・ヤール』は、「単一のホロコーストで最大の犠牲者を出した」として知られる「バビ・ヤール大虐殺」を描き出す。ウクライナ市民も加担した、そのあまりに悲惨な歴史の真実とは?
「理性的な思考」が「最適解としての戦争」を導き出すことの怖さ
さて最後に、作品の本筋とはあまり関係ないが、私にとってとても印象的だった場面があるので、それに触れて終わろうと思う。
セラフィマはある事情から、ジューコフ上級大将と会うことになる。これはある意味で、とても危険な行為だった。ジューコフ上級大将とのやり取りが終わって部屋を出たセラフィマに、上官であるイリーナが「自分から死にに行くな」と叱責するほどの行為なのである。
ではセラフィマは、そんなジューコフ上級大将と一体どんな話をしたのだろうか。
あわせて読みたい
【証言】ナチスドイツでヒトラーに次ぐナンバー2だったゲッベルス。その秘書だった女性が歴史を語る映画…
ナチスドイツナンバー2だった宣伝大臣ゲッベルス。その秘書だったブルンヒルデ・ポムゼルが103歳の時にカメラの前で当時を語った映画『ゲッベルスと私』には、「愚かなことをしたが、避け難かった」という彼女の悔恨と教訓が含まれている。私たちは彼女の言葉を真摯に受け止めなければならない
彼がセラフィマに、「ナチはソ連を絶滅させようとしているし、だからこそ我々は奴らを徹底的に攻め落とさなければならないのだ」と話した上で、さらに次のように言う場面がある。
「レニングラードに転戦した時期、(中略)そして士気阻喪に陥った将校どもを処刑した。勝手に逃亡を試みたり、あるいは投降しようとした奴らだ」
ジューコフは振り向いた。
温和な教師ではない。冷徹な高級将校の顔がそこにあった。
「それがレニングラードの人民を守るために必要だからだ。それは他の戦線でも変わりはしない。ナチに交渉は通じない。これは通常の戦争ではない。軍隊が瓦解すればすべての人民は虐殺され、奴隷化させられる。故に、組織的焦土作戦を用いて撤退する局面を除いては、踏みとどまって防戦することが、唯一ソ連人民が生き残る術なのだ。逃亡する兵士は、もはや敵であり、ファシストの手先なのだ」
この主張内容が正しいのかどうか、私には判断できない。しかし先に引用したものも含め、ジューコフ上級大将の話しぶりを読んで理解できたことがある。
それは、「彼はとても真っ当で冷静な判断によって『戦争』という解を導き出している」ということだ。この事実は、「戦争」の恐ろしさをより強く実感させるものだと感じた。
あわせて読みたい
【アメリカ】長崎の「原爆ドーム」はなぜ残らなかった?爆心地にあった「浦上天主堂」の数奇な歴史:『…
原爆投下で半壊し、廃墟と化したキリスト教の大聖堂「浦上天主堂」。しかし何故か、「長崎の原爆ドーム」としては残されず、解体されてしまった。そのため長崎には原爆ドームがないのである。『ナガサキ 消えたもう一つの「原爆ドーム」』は、「浦上天主堂」を巡る知られざる歴史を掘り下げ、アメリカの強かさを描き出す
私たちは、ロシアのウクライナ侵攻や、イスラエルとパレスチナの戦争などと同じ時代に生きている。そしてやはり、私たちはこれらの状況を、「まともな理屈から生まれたものではない」と信じたいはずだ。「プーチン大統領がイカれている」とか、「長年に渡る宗教のいがみあいがこじれている」など、「理性的な判断がなされていればそうはなっていないはずだ」という風に捉えたいと、少なくとも私は考えてしまう。
しかしジューコフ上級大将の話しぶりからは、そうではないことが伝わってきた。彼は、その時点で手に入るすべての情報を精査し、「国家人民を守る」という自らのスタンスも考慮した上で、「弱気になった将校は処刑すべきだ」という結論を導き出し、実行しているのだ。「我を忘れて」とか「怒りに震えて」みたいなことではないのである。そのことが、とても恐ろしく感じられた。

作中で描かれる人物の多くは非常に理性的で、人間味も持ち合わせている者ばかりである。しかしそんな人でさえ、「『戦争』という『異常な最適解』」に行き着いてしまうというわけだ。
あわせて読みたい
【真実?】佐村河内守のゴーストライター騒動に森達也が斬り込んだ『FAKE』は我々に何を問うか?
一時期メディアを騒がせた、佐村河内守の「ゴースト問題」に、森達也が斬り込む。「耳は聴こえないのか?」「作曲はできるのか?」という疑惑を様々な角度から追及しつつ、森達也らしく「事実とは何か?」を問いかける『FAKE』から、「事実の捉え方」について考える
そのような怖さも実感させる作品だった。
著:逢坂 冬馬
¥1,881 (2024/02/04 19:18時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品読了済】私が読んできた小説を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が読んできた小説を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本選びの参考にして下さい。
最後に
あわせて読みたい
【狂気】ホロコーストはなぜ起きた?映画『ヒトラーのための虐殺会議』が描くヴァンゼー会議の真実
映画『ヒトラーのための虐殺会議』は、ホロコーストの計画について話し合われた「ヴァンゼー会議」を描き出す作品だ。唯一1部だけ残った議事録を基に作られた本作は、「ユダヤ人虐殺」をイベントの準備でもしているかのように「理性的」に計画する様を映し出す。その「狂気」に驚かされてしまった。
本作には、「戦時下だから」という理由で終わらせていいはずのない圧倒的な悲惨さが随所で描かれていく。そしてそのような作品だからこそ、「葛藤の末に、『人間』として踏み留まる」という決断に至る者たちの姿が読者の胸を打つのだと思う。
本当に、「凄まじい」としか言いようのない、あらゆるスケールが規格外の作品だった。どうかこの物語には触れてほしいと切実に思う。
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を…
Kindleで本を出版しました。タイトルは、『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を分かりやすく書いた本:相対性理論も宇宙論も量子論も』です。科学や科学者に関する、文系の人でも読んでもらえる作品に仕上げました。そんな自著について紹介をしています。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【解説】映画『シビル・ウォー アメリカ最後の日』は、凄まじい臨場感で内戦を描き、我々を警告する(…
映画『シビル・ウォー』は、「アメリカで勃発した内戦が長期化し、既に日常になってしまっている」という現実を圧倒的な臨場感で描き出す作品だ。戦争を伝える報道カメラマンを主人公に据え、「戦争そのもの」よりも「誰にどう戦争を伝えるか」に焦点を当てる本作は、様々な葛藤を抱きながら最前線を目指す者たちを切り取っていく
あわせて読みたい
【煌めき】映画『HAPPYEND』が描く、”監視への嫌悪”と”地震への恐怖”の中で躍動する若者の刹那(監督:…
映画『HAPPYEND』は、「監視システム」と「地震」という「外的な制約条件」を設定し、その窮屈な世界の中で屈せずに躍動しようとする若者たちをリアルに描き出す物語である。特に、幼稚園からの仲であるコウとユウタの関係性が絶妙で、演技未経験だという2人の存在感と映像の雰囲気が相まって、実に素敵に感じられた
あわせて読みたい
【孤独】映画『ナミビアの砂漠』は、自由だが居場所がない主人公を演じる河合優実の存在感が圧倒的(監…
映画『ナミビアの砂漠』は、とにかく「河合優実が凄まじい」のひと言に尽きる作品だ。彼女が演じたカナという主人公の「捉えどころの無さ」は絶妙で、一見すると凄まじく「自由」に羽ばたいている感じなのに、実際には全然「自由」には見えないというバランスが見事だった。特段の物語はないのに、137分間惹きつけられてしまうだろう
あわせて読みたい
【思想】川口大三郎は何故、早稲田を牛耳る革マル派に殺された?映画『ゲバルトの杜』が映す真実
映画『ゲバルトの杜』は、「『革マル派』という左翼の集団に牛耳られた早稲田大学内で、何の罪もない大学生・川口大三郎がリンチの末に殺された」という衝撃的な事件を、当時を知る様々な証言者の話と、鴻上尚史演出による劇映画パートによって炙り出すドキュメンタリー映画だ。同じ国で起こった出来事とは思えないほど狂気的で驚かされた
あわせて読みたい
【あらすじ】杉咲花と安田顕が圧巻!映画『朽ちないサクラ』(原廣利)は「正義の難しさ」を描く(原作…
柚月裕子の同名小説を原作とした映画『朽ちないサクラ』は、とにかく杉咲花と安田顕の演技に圧倒されてしまった作品だ。「トロッコ問題」を連想させる非常に難しい状況を提示することで「正義の難しさ」を描き出す展開も素晴らしいし、主人公・森口泉を演じた杉咲花の「絶望を静かに体現する演技」も見事だった
あわせて読みたい
【絶望】知られざる「国による嘘」!映画『蟻の兵隊』(池谷薫)が映し出す終戦直後の日本の欺瞞
映画『蟻の兵隊』は、「1945年8月15日の終戦以降も上官の命令で中国に残らされ、中国の内戦を闘った残留日本軍部隊」の1人である奥村和一を追うドキュメンタリー映画だ。「自らの意思で残った」と判断された彼らは、国からの戦後補償を受けられていない。そんな凄まじい現実と、奥村和一の驚くべき「誠実さ」が描かれる作品である
あわせて読みたい
【評価】高山一実の小説かつアニメ映画である『トラペジウム』は、アイドル作とは思えない傑作(声優:…
原作小説、そしてアニメ映画共に非常に面白かった『トラペジウム』は、高山一実が乃木坂46に在籍中、つまり「現役アイドル」として出版した作品であり、そのクオリティに驚かされました。「現役アイドル」が「アイドル」をテーマにするというド直球さを武器にしつつ、「アイドルらしからぬ感覚」をぶち込んでくる非常に面白い作品である
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『52ヘルツのクジラたち』の「無音で叫ぶ人」と「耳を澄ます人」の絶妙な響鳴(原作:…
映画『52ヘルツのクジラたち』は、「現代的な問題のごった煮」と感じられてしまうような”過剰さ”に溢れてはいますが、タイトルが作品全体を絶妙に上手くまとめていて良かったなと思います。主演の杉咲花がやはり見事で、身体の内側から「不幸」が滲み出ているような演技には圧倒されてしまいました
あわせて読みたい
【幻惑】映画『フォロウィング』の衝撃。初監督作から天才だよ、クリストファー・ノーラン
クリストファー・ノーランのデビュー作であり、多数の賞を受賞し世界に衝撃を与えた映画『フォロウィング』には、私も驚かされてしまった。冒頭からしばらくの間「何が描かれているのかさっぱり理解できない」という状態だったのに、ある瞬間一気に視界が晴れたように状況が理解できたのだ。脚本の力がとにかく圧倒的だった
あわせて読みたい
【現在】猟師になった東出昌大を追う映画『WILL』は予想外に良かった。山小屋での生活は衝撃だ(監督:…
猟師・東出昌大に密着した映画『WILL』は、思いがけず面白い作品だった。正直、東出昌大にはまったく興味がなく、本作も期待せず観たのだが、異常なほどフラットなスタンス故に周囲にいる人間を否応なく惹きつける「人間力」や、狩猟の世界が突きつける「生と死」というテーマなど実に興味深い。本当に観て良かったなと思う
あわせて読みたい
【衝撃】広末涼子映画デビュー作『20世紀ノスタルジア』は、「広末が異常にカワイイ」だけじゃない作品
広末涼子の映画デビュー・初主演作として知られる『20世紀ノスタルジア』は、まず何よりも「広末涼子の可愛さ」に圧倒される作品だ。しかし、決してそれだけではない。初めは「奇妙な設定」ぐらいにしか思っていなかった「宇宙人に憑依されている」という要素が、物語全体を実に上手くまとめている映画だと感じた
あわせて読みたい
【実話】映画『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』が描く、白人警官による黒人射殺事件
映画『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』は、2011年に起こった実際の事件を元にした作品である。何の罪もない黒人男性が、白人警官に射殺されてしまったのだ。5時22分から始まる状況をほぼリアルタイムで描き切る83分間の物語には、役者の凄まじい演技も含め、圧倒されてしまった
あわせて読みたい
【衝撃】ミキ・デザキが映画『主戦場』で示す「慰安婦問題」の実相。歴史修正主義者の発言がヤバすぎ
「慰安婦問題」に真正面から取り組んだ映画『主戦場』は、「『慰安婦問題』の根幹はどこにあるのか?」というその複雑さに焦点を当てていく。この記事では、本作で映し出された様々な情報を元に「慰安婦問題」について整理したものの、結局のところ「解決不可能な問題である」という結論に行き着いてしまった
あわせて読みたい
【問題】映画『国葬の日』が切り取る、安倍元首相の”独裁”が生んだ「政治への関心の無さ」(監督:大島新)
安倍元首相の国葬の1日を追ったドキュメンタリー映画『国葬の日』は、「国葬」をテーマにしながら、実は我々「国民」の方が深堀りされる作品だ。「安倍元首相の国葬」に対する、全国各地の様々な人たちの反応・価値観から、「『ソフトな独裁』を維持する”共犯者”なのではないか」という、我々自身の政治との向き合い方が問われているのである
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『戦場のピアニスト』(ロマン・ポランスキー)が描く、ユダヤ人迫害の衝撃の実話
映画『戦場のピアニスト』の4Kリマスター版を観に行ったところ、上映後のトークイベントに主人公の息子が登壇したので驚いた。何せ私は、本作が「実話を基にしている」ことさえ知らなかったのである。だからその驚きもひとしおだった。ホロコーストの生存者である主人公の壮絶な人生を描き出す、不朽の名作だ
あわせて読みたい
【あらすじ】原爆を作った人の後悔・葛藤を描く映画『オッペンハイマー』のための予習と評価(クリスト…
クリストファー・ノーラン監督作品『オッペンハイマー』は、原爆開発を主導した人物の葛藤・苦悩を複雑に描き出す作品だ。人間が持つ「多面性」を様々な方向から捉えようとする作品であり、受け取り方は人それぞれ異なるだろう。鑑賞前に知っておいた方がいい知識についてまとめたので、参考にしてほしい
あわせて読みたい
【狂気】異質なホラー映画『みなに幸あれ』(古川琴音主演)は古い因習に似せた「社会の異様さ」を描く
古川琴音主演映画『みなに幸あれ』は、”シュールさ”さえ感じさせる「異質なホラー映画」だ。「村の因習」というよくあるパターンをベースに据えつつ、そこで展開される異様な状況が、実は「私たちが生きる世界」に対応しているという構成になっている。「お前の物語だからな」と終始突きつけられ続ける作品だ
あわせて読みたい
【おすすめ】カンヌ映画『PERFECT DAYS』は、ほぼ喋らない役所広司の沈黙が心地よい(ヴィム・ヴェンダ…
役所広司主演映画『PERFECT DAYS』(ヴィム・ヴェンダース監督)は、主人公・平山の「沈黙」がとにかく雄弁な物語である。渋谷区のトイレの清掃員である無口な平山の、世間とほとんど繋がりを持たない隔絶した日常が、色んなものを抱えた者たちを引き寄せ、穏やかさで満たしていく様が素晴らしい
あわせて読みたい
【脅迫】原発という巨大権力と闘ったモーリーン・カーニーをイザベル・ユペールが熱演する映画『私はモ…
実話を基にした映画『私はモーリーン・カーニー』は、前半の流れからはちょっと想像もつかないような展開を見せる物語だ。原発企業で従業員の雇用を守る労働組合の代表を務める主人公が、巨大権力に立ち向かった挙げ句に自宅で襲撃されてしまうという物語から、「良き被害者」という捉え方の”狂気”が浮かび上がる
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『千年女優』(今敏)はシンプルな物語を驚愕の演出で味付けした天才的アニメ作品
今敏監督の映画『千年女優』は、ちょっとびっくりするほど凄まじく面白い作品だった。観ればスッと理解できるのに言葉で説明すると難解になってしまう「テクニカルな構成」に感心させられつつ、そんな構成に下支えされた「物語の感性的な部分」がストレートに胸を打つ、シンプルながら力強い作品だ
あわせて読みたい
【抵抗】映画『熊は、いない』は、映画製作を禁じられた映画監督ジャファル・パナヒの執念の結晶だ
映画『熊は、いない』は、「イラン当局から映画製作を20年間も禁じられながら、その後も作品を生み出し続けるジャファル・パナヒ監督」の手によるもので、彼は本作公開後に収監させられてしまった。パナヒ監督が「本人役」として出演する、「ドキュメンタリーとフィクションのあわい」を縫うような異様な作品だ
あわせて読みたい
【痛快】精神病院の隔離室から脱した、善悪の判断基準を持たない狂気の超能力者が大暴れする映画:『モ…
モナ・リザ アンド ザ ブラッドムーン』は、「10年以上拘束され続けた精神病院から脱走したアジア系女性が、特殊能力を使って大暴れする」というムチャクチャな設定の物語なのだが、全編に通底する「『善悪の判断基準』が歪んでいる」という要素がとても見事で、意味不明なのに最後まで惹きつけられてしまった
あわせて読みたい
【絶望】杉咲花主演映画『市子』の衝撃。毎日がしんどい「どん底の人生」を生き延びるための壮絶な決断…
映画『市子』はまず何よりも主演を務めた杉咲花に圧倒させられる作品だ。そしてその上で、主人公・川辺市子を巡る物語にあれこれと考えさせられてしまった。「川辺市子」は決してフィクショナルな存在ではなく、現実に存在し得る。本作は、そのような存在をリアルに想像するきっかけにもなるだろう
あわせて読みたい
【感想】映画『キリエのうた』(岩井俊二)はアイナ・ジ・エンドに圧倒されっ放しの3時間だった(出演:…
映画『キリエのうた』(岩井俊二監督)では、とにかくアイナ・ジ・エンドに圧倒されてしまった。歌声はもちろんのことながら、ただそこにいるだけで場を支配するような存在感も凄まじい。全編に渡り「『仕方ないこと』はどうしようもなく起こるんだ」というメッセージに溢れた、とても力強い作品だ
あわせて読みたい
【考察】映画『街の上で』(今泉力哉)が描く「男女の友情は成立する」的会話が超絶妙で素晴らしい(出…
映画『街の上で』(今泉力哉監督)は、「映画・ドラマ的会話」ではない「自然な会話」を可能な限り目指すスタンスが見事だった。「会話の無駄」がとにかく随所に散りばめられていて、そのことが作品のリアリティを圧倒的に押し上げていると言える。ある男女の”恋愛未満”の会話もとても素晴らしかった
あわせて読みたい
【衝撃】ウクライナでのホロコーストを描く映画『バビ・ヤール』は、集めた素材映像が凄まじすぎる
ソ連生まれウクライナ育ちの映画監督セルゲイ・ロズニツァが、「過去映像」を繋ぎ合わせる形で作り上げた映画『バビ・ヤール』は、「単一のホロコーストで最大の犠牲者を出した」として知られる「バビ・ヤール大虐殺」を描き出す。ウクライナ市民も加担した、そのあまりに悲惨な歴史の真実とは?
あわせて読みたい
【狂気】映画『ニューオーダー』の衝撃。法という秩序を混沌で駆逐する”悪”に圧倒されっ放しの86分
映画『ニューオーダー』は、理解不能でノンストップな展開に誘われる問題作だ。「貧富の差」や「法の支配」など「現実に存在する秩序」がひっくり返され、対極に振り切った「新秩序」に乗っ取られた世界をリアルに描き出すことで、私たちが今進んでいる道筋に警鐘を鳴らす作品になっている
あわせて読みたい
【絶望】人生どん底から生き方を変える。映画『シスター 夏のわかれ道』が描く中国人女性の葛藤と諦念
両親の死をきっかけに、「見知らぬ弟」を引き取らなければならなくなった女性を描く映画『シスター 夏のわかれ道』は、中国の特異な状況を背景にしつつ、誰もが抱き得る普遍的な葛藤が切り取られていく。現状を打破するために北京の大学院を目指す主人公は、一体どんな決断を下すのか。
あわせて読みたい
【現実】映画『私のはなし 部落のはなし』で初めて同和・部落問題を考えた。差別はいかに生まれ、続くのか
私はずっと、「部落差別なんてものが存在する意味が分からない」と感じてきたが、映画『私のはなし 部落のはなし』を観てようやく、「どうしてそんな差別が存在し得るのか」という歴史が何となく理解できた。非常に複雑で解決の難しい問題だが、まずは多くの人が正しく理解することが必要だと言えるだろう
あわせて読みたい
【狂気】ホロコーストはなぜ起きた?映画『ヒトラーのための虐殺会議』が描くヴァンゼー会議の真実
映画『ヒトラーのための虐殺会議』は、ホロコーストの計画について話し合われた「ヴァンゼー会議」を描き出す作品だ。唯一1部だけ残った議事録を基に作られた本作は、「ユダヤ人虐殺」をイベントの準備でもしているかのように「理性的」に計画する様を映し出す。その「狂気」に驚かされてしまった。
あわせて読みたい
【驚愕】ベリングキャットの調査報道がプーチンを追い詰める。映画『ナワリヌイ』が示す暗殺未遂の真実
弁護士であり、登録者数640万人を超えるYouTuberでもあるアレクセイ・ナワリヌイは、プーチンに対抗して大統領選挙に出馬しようとしたせいで暗殺されかかった。その実行犯を特定する調査をベリングキャットと共に行った記録映画『ナワリヌイ』は、現実とは思えないあまりの衝撃に満ちている
あわせて読みたい
【映画】『戦場記者』須賀川拓が、ニュースに乗らない中東・ウクライナの現実と報道の限界を切り取る
TBS所属の特派員・須賀川拓は、ロンドンを拠点に各国の取材を行っている。映画『戦場記者』は、そんな彼が中東を取材した映像をまとめたドキュメンタリーだ。ハマスを巡って食い違うガザ地区とイスラエル、ウクライナ侵攻直後に現地入りした際の様子、アフガニスタンの壮絶な薬物中毒の現実を映し出す
あわせて読みたい
【驚嘆】映画『TAR/ター』のリディア・ターと、彼女を演じたケイト・ブランシェットの凄まじさ
天才女性指揮者リディア・ターを強烈に描き出す映画『TAR/ター』は、とんでもない作品だ。「縦軸」としてのターの存在感があまりにも強すぎるため「横軸」を上手く捉えきれず、結果「よく分からなかった」という感想で終わったが、それでも「観て良かった」と感じるほど、揺さぶられる作品だった
あわせて読みたい
【衝撃】これが実話とは。映画『ウーマン・トーキング』が描く、性被害を受けた女性たちの凄まじい決断
映画『ウーマン・トーキング』の驚くべき点は、実話を基にしているという点だ。しかもその事件が起こったのは2000年代に入ってから。とある宗教コミュニティ内で起こった連続レイプ事件を機に村の女性たちがある決断を下す物語であり、そこに至るまでの「ある種異様な話し合い」が丁寧に描かれていく
あわせて読みたい
【苦悩】「やりがいのある仕事」だから見て見ぬふり?映画『アシスタント』が抉る搾取のリアル
とある映画会社で働く女性の「とある1日」を描く映画『アシスタント』は、「働くことの理不尽さ」が前面に描かれる作品だ。「雑用」に甘んじるしかない彼女の葛藤がリアルに描かれている。しかしそれだけではない。映画の「背景」にあるのは、あまりに悪逆な行為と、大勢による「見て見ぬふり」である
あわせて読みたい
【性加害】映画『SHE SAID その名を暴け』を観てくれ。#MeToo運動を生んだ報道の舞台裏(出演:キャリ…
「#MeToo」運動のきっかけとなった、ハリウッドの絶対権力者ハーヴェイ・ワインスタインを告発するニューヨーク・タイムズの記事。その取材を担った2人の女性記者の奮闘を描く映画『SHE SAID その名を暴け』は、ジャニー喜多川の性加害問題で揺れる今、絶対に観るべき映画だと思う
あわせて読みたい
【居場所】菊地凛子主演映画『658km、陽子の旅』(熊切和嘉)は、引きこもりロードムービーの傑作
映画『658km、陽子の旅』は、主演の菊地凛子の存在感が圧倒的だった。夢破れて長年引きこもり続けている女性が、否応なしにヒッチハイクで弘前を目指さなければならなくなるロードムービーであり、他人や社会と関わることへの葛藤に塗れた主人公の変化が、とても「勇敢」なものに映る
あわせて読みたい
【傑物】フランスに最も愛された政治家シモーヌ・ヴェイユの、強制収容所から国連までの凄絶な歩み:映…
「フランスに最も愛された政治家」と評されるシモーヌ・ヴェイユ。映画『シモーヌ』は、そんな彼女が強制収容所を生き延び、後に旧弊な社会を変革したその凄まじい功績を描き出す作品だ。「強制収容所からの生還が失敗に思える」とさえ感じたという戦後のフランスの中で、彼女はいかに革新的な歩みを続けたのか
あわせて読みたい
【驚異】映画『RRR』『バーフバリ』は「観るエナジードリンク」だ!これ程の作品にはなかなか出会えないぞ
2022年に劇場公開されるや、そのあまりの面白さから爆発的人気を博し、現在に至るまでロングラン上映が続いている『RRR』と、同監督作の『バーフバリ』は、大げさではなく「全人類にオススメ」と言える超絶的な傑作だ。まだ観ていない人がいるなら、是非観てほしい!
あわせて読みたい
【実話】ソ連の衝撃の事実を隠蔽する記者と暴く記者。映画『赤い闇』が描くジャーナリズムの役割と実態
ソ連の「闇」を暴いた名もなき記者の実話を描いた映画『赤い闇』は、「メディアの存在意義」と「メディアとの接し方」を問いかける作品だ。「真実」を届ける「社会の公器」であるべきメディアは、容易に腐敗し得る。情報の受け手である私たちの意識も改めなければならない
あわせて読みたい
【衝撃】匿名監督によるドキュメンタリー映画『理大囲城』は、香港デモ最大の衝撃である籠城戦の内部を映す
香港民主化デモにおける最大の衝撃を内側から描く映画『理大囲城』は、とんでもないドキュメンタリー映画だった。香港理工大学での13日間に渡る籠城戦のリアルを、デモ隊と共に残って撮影し続けた匿名監督たちによる映像は、ギリギリの判断を迫られる若者たちの壮絶な現実を映し出す
あわせて読みたい
【感想】映画『朝が来る』が描く、「我が子を返して欲しい気持ち」を消せない特別養子縁組のリアル
「特別養子縁組」を軸に人々の葛藤を描く映画『朝が来る』は、決して「特別養子縁組」の話ではない。「『起こるだろうが、起こるはずがない』と思っていた状況」に直面せざるを得ない人々が、「すべての選択肢が不正解」という中でどんな決断を下すのかが問われる、非常に示唆に富む作品だ
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『1917』は、ワンカット風の凄まじい撮影手法が「戦場の壮絶な重圧」を見事に体感させる
映画『1917 命をかけた伝令』は、「全編ワンカット風」という凄まじい撮影手法で注目されたが、私は、その撮影手法が「戦場における緊迫感」を見事に増幅させているという点に驚かされた。「物語の中身」と「撮影手法」が素晴らしく合致したとんでもない作品だ
あわせて読みたい
【あらすじ】蝦夷地の歴史と英雄・阿弖流為を描く高橋克彦の超大作小説『火怨』は全人類必読の超傑作
大げさではなく、「死ぬまでに絶対に読んでほしい1冊」としてお勧めしたい高橋克彦『火怨』は凄まじい小説だ。歴史が苦手で嫌いな私でも、上下1000ページの物語を一気読みだった。人間が人間として生きていく上で大事なものが詰まった、矜持と信念に溢れた物語に酔いしれてほしい
あわせて読みたい
【純愛】映画『ぼくのエリ』の衝撃。「生き延びるために必要なもの」を貪欲に求める狂気と悲哀、そして恋
名作と名高い映画『ぼくのエリ』は、「生き延びるために必要なもの」が「他者を滅ぼしてしまうこと」であるという絶望を抱えながら、それでも生きることを選ぶ者たちの葛藤が描かれる。「純愛」と呼んでいいのか悩んでしまう2人の関係性と、予想もつかない展開に、感動させられる
あわせて読みたい
【差別】映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』の衝撃。プーチンが支持する国の蛮行・LGBT狩り
プーチン大統領の後ろ盾を得て独裁を維持しているチェチェン共和国。その国で「ゲイ狩り」と呼ぶしかない異常事態が継続している。映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』は、そんな現実を命がけで映し出し、「現代版ホロコースト」に立ち向かう支援団体の奮闘も描く作品
あわせて読みたい
【悲劇】アメリカの暗黒の歴史である奴隷制度の現実を、元奴隷の黒人女性自ら赤裸々に語る衝撃:『ある…
生まれながらに「奴隷」だった黒人女性が、多くの人の協力を得て自由を手にし、後に「奴隷制度」について書いたのが『ある奴隷少女に起こった出来事』。長らく「白人が書いた小説」と思われていたが、事実だと証明され、欧米で大ベストセラーとなった古典作品が示す「奴隷制度の残酷さ」
あわせて読みたい
【対立】パレスチナとイスラエルの「音楽の架け橋」は実在する。映画『クレッシェンド』が描く奇跡の楽団
イスラエルとパレスチナの対立を背景に描く映画『クレッシェンド』は、ストーリーそのものは実話ではないものの、映画の中心となる「パレスチナ人・イスラエル人混合の管弦楽団」は実在する。私たちが生きる世界に残る様々な対立について、その「改善」の可能性を示唆する作品
あわせて読みたい
【現実】権力を乱用する中国ナチスへの抵抗の最前線・香港の民主化デモを映す衝撃の映画『時代革命』
2019年に起こった、逃亡犯条例改正案への反対運動として始まった香港の民主化デモ。その最初期からデモ参加者たちの姿をカメラに収め続けた。映画『時代革命』は、最初から最後まで「衝撃映像」しかない凄まじい作品だ。この現実は決して、「対岸の火事」ではない
あわせて読みたい
【愛】ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督の“衝撃の出世作”である映画『灼熱の魂』の凄さ。何も語りたくない
映画館で流れた予告映像だけで観ることを決め、他になんの情報も知らないまま鑑賞した映画『灼熱の魂』は、とんでもない映画だった。『DUNE/デューン 砂の惑星』『ブレードランナー 2049』など有名作を監督してきたドゥニ・ヴィルヌーヴの衝撃の出世作については、何も語りたくない
あわせて読みたい
【憤り】世界最強米海軍4人VS数百人のタリバン兵。死線を脱しただ1人生還を果たした奇跡の実話:『アフ…
アフガニスタンの山中で遭遇した羊飼いを見逃したことで、数百人のタリバン兵と死闘を繰り広げる羽目に陥った米軍最強部隊に所属する4人。奇跡的に生き残り生還を果たした著者が記す『アフガン、たった一人の生還』は、とても実話とは信じられない凄まじさに満ちている
あわせて読みたい
【歴史】『大地の子』を凌駕する中国残留孤児の現実。中国から奇跡的に”帰国”した父を城戸久枝が描く:…
文化大革命の最中、国交が成立していなかった中国から自力で帰国した中国残留孤児がいた。その娘である城戸久枝が著した『あの戦争から遠く離れて』は、父の特異な体験を起点に「中国残留孤児」の問題に分け入り、歴史の大きなうねりを個人史として体感させてくれる作品だ
あわせて読みたい
【アメリカ】長崎の「原爆ドーム」はなぜ残らなかった?爆心地にあった「浦上天主堂」の数奇な歴史:『…
原爆投下で半壊し、廃墟と化したキリスト教の大聖堂「浦上天主堂」。しかし何故か、「長崎の原爆ドーム」としては残されず、解体されてしまった。そのため長崎には原爆ドームがないのである。『ナガサキ 消えたもう一つの「原爆ドーム」』は、「浦上天主堂」を巡る知られざる歴史を掘り下げ、アメリカの強かさを描き出す
あわせて読みたい
【不安】環境活動家グレタを追う映画。「たったひとりのストライキ」から国連スピーチまでの奮闘と激変…
環境活動家であるグレタのことを、私はずっと「怒りの人」「正義の人」だとばかり思っていた。しかしそうではない。彼女は「不安」から、いても立ってもいられずに行動を起こしただけなのだ。映画『グレタ ひとりぼっちの挑戦』から、グレタの実像とその強い想いを知る
あわせて読みたい
【感想】リドリー・スコット監督の映画『最後の決闘裁判』から、社会が”幻想”を共有する背景とその悲劇…
例えば、「1万円札」というただの紙切れに「価値を感じる」のは、社会の構成員が同じ「共同幻想」の中に生きているからだ。リドリー・スコット監督の映画『最後の決闘裁判』は、「強姦では妊娠しない」「裁判の勝者を決闘で決する」という社会通念と、現代にも通じる「共同幻想」の強さを描き出す
あわせて読みたい
【理解】小野田寛郎を描く映画。「戦争終結という現実を受け入れない(=認知的不協和)」は他人事じゃ…
映画『ONODA 一万夜を越えて』を観るまで、小野田寛郎という人間に対して違和感を覚えていた。「戦争は終わっていない」という現実を生き続けたことが不自然に思えたのだ。しかし映画を観て、彼の生き方・決断は、私たちと大きく変わりはしないと実感できた
あわせて読みたい
【衝撃】権力の濫用、政治腐敗を描く映画『コレクティブ』は他人事じゃない。「国家の嘘」を監視せよ
火災で一命を取り留め入院していた患者が次々に死亡した原因が「表示の10倍に薄められた消毒液」だと暴き、国家の腐敗を追及した『ガゼタ』誌の奮闘を描く映画『コレクティブ 国家の嘘』は、「権力の監視」が機能しなくなった国家の成れの果てが映し出される衝撃作だ
あわせて読みたい
【驚愕】キューバ危機の裏側を描くスパイ映画『クーリエ』。核戦争を回避させた民間人の衝撃の実話:『…
核戦争ギリギリまで進んだ「キューバ危機」。その陰で、世界を救った民間人がいたことをご存知だろうか?実話を元にした映画『クーリエ:最高機密の運び屋』は、ごく普通のセールスマンでありながら、ソ連の膨大な機密情報を盗み出した男の信じがたい奮闘を描き出す
あわせて読みたい
【日常】難民問題の現状をスマホで撮る映画。タリバンから死刑宣告を受けた監督が家族と逃避行:『ミッ…
アフガニスタンを追われた家族4人が、ヨーロッパまで5600kmの逃避行を3台のスマホで撮影した映画『ミッドナイト・トラベラー』は、「『難民の厳しい現実』を切り取った作品」ではない。「家族アルバム」のような「笑顔溢れる日々」が難民にもあるのだと想像させてくれる
あわせて読みたい
【実話】「ホロコーストの映画」を観て改めて、「有事だから仕方ない」と言い訳しない人間でありたいと…
ノルウェーの警察が、自国在住のユダヤ人をまとめて船に乗せアウシュビッツへと送った衝撃の実話を元にした映画『ホロコーストの罪人』では、「自分はそんな愚かではない」と楽観してはいられない現実が映し出される。このような悲劇は、現在に至るまで幾度も起こっているのだ
あわせて読みたい
【正義】復讐なんかに意味はない。それでも「この復讐は正しいかもしれない」と思わされる映画:『プロ…
私は基本的に「復讐」を許容できないが、『プロミシング・ヤング・ウーマン』の主人公キャシーの行動は正当化したい。法を犯す明らかにイカれた言動なのだが、その動機は一考の余地がある。何も考えずキャシーを非難していると、矢が自分の方に飛んでくる、恐ろしい作品
あわせて読みたい
【凄絶】北朝鮮の”真実”を描くアニメ映画。強制収容所から決死の脱出を試みた者が語る驚愕の実態:『ト…
在日コリアン4世の監督が、北朝鮮脱北者への取材を元に作り上げた壮絶なアニメ映画『トゥルーノース』は、私たちがあまりに恐ろしい世界と地続きに生きていることを思い知らせてくれる。最低最悪の絶望を前に、人間はどれだけ悪虐になれてしまうのか、そしていかに優しさを発揮できるのか。
あわせて読みたい
【認識】「固定観念」「思い込み」の外側に出るのは難しい。自分はどんな「へや」に囚われているのか:…
実際に起こった衝撃的な事件に着想を得て作られた映画『ルーム』は、フィクションだが、観客に「あなたも同じ状況にいるのではないか?」と突きつける力強さを持っている。「普通」「当たり前」という感覚に囚われて苦しむすべての人に、「何に気づけばいいか」を気づかせてくれる作品
あわせて読みたい
【感想】映画『野火』は、戦争の”虚しさ”をリアルに映し出す、後世に受け継がれるべき作品だ
「戦争の悲惨さ」は様々な形で描かれ、受け継がれてきたが、「戦争の虚しさ」を知る機会はなかなかない。映画『野火』は、第二次世界大戦中のフィリピンを舞台に、「敵が存在しない戦場で”人間の形”を保つ困難さ」を描き出す、「虚しさ」だけで構成された作品だ
あわせて読みたい
【葛藤】正義とは何かを突きつける戦争映画。80人を救うために1人の少女を殺すボタンを押せるか?:『ア…
「80人の命を救うために、1人の少女の命を奪わなければならない」としたら、あなたはその決断を下せるだろうか?会議室で展開される現代の戦争を描く映画『アイ・イン・ザ・スカイ』から、「誤った問い」に答えを出さなければならない極限状況での葛藤を理解する
あわせて読みたい
【驚異】信念を貫く勇敢さを、「銃を持たずに戦場に立つ」という形で示した実在の兵士の凄まじさ:映画…
第二次世界大戦で最も過酷な戦場の1つと言われた「前田高地(ハクソー・リッジ)」を、銃を持たずに駆け回り信じがたい功績を残した衛生兵がいた。実在の人物をモデルにした映画『ハクソー・リッジ』から、「戦争の悲惨さ」だけでなく、「信念を貫くことの大事さ」を学ぶ
あわせて読みたい
【正義】「正しさとは何か」を考えさせる映画『スリー・ビルボード』は、正しさの対立を絶妙に描く
「正しい」と主張するためには「正しさの基準」が必要だが、それでも「規制されていないことなら何でもしていいのか」は問題になる。3枚の立て看板というアナログなツールを使って現代のネット社会の現実をあぶり出す映画『スリー・ビルボード』から、「『正しさ』の難しさ」を考える
あわせて読みたい
【史実】太平洋戦争末期に原爆を落としたアメリカは、なぜ終戦後比較的穏やかな占領政策を取ったか?:…
『八月十五日に吹く風』は小説だが、史実を基にした作品だ。本作では、「終戦直前に原爆を落としながら、なぜ比較的平穏な占領政策を行ったか?」の疑問が解き明かされる。『源氏物語』との出会いで日本を愛するようになった「ロナルド・リーン(仮名)」の知られざる奮闘を知る
あわせて読みたい
【称賛】生き様がかっこいい。ムンバイのホテルのテロ事件で宿泊客を守り抜いたスタッフたち:映画『ホ…
インドの高級ホテルで実際に起こったテロ事件を元にした映画『ホテル・ムンバイ』。恐ろしいほどの臨場感で、当時の恐怖を観客に体感させる映画であり、だからこそ余計に、「逃げる選択」もできたホテルスタッフたちが自らの意思で残り、宿泊を助けた事実に感銘を受ける
あわせて読みたい
【意外】東京裁判の真実を記録した映画。敗戦国での裁判が実に”フェア”に行われたことに驚いた:『東京…
歴史に詳しくない私は、「東京裁判では、戦勝国が理不尽な裁きを行ったのだろう」という漠然としたイメージを抱いていた。しかし、その印象はまったくの誤りだった。映画『東京裁判 4Kリマスター版』から東京裁判が、いかに公正に行われたのかを知る
あわせて読みたい
【差別】「女性の権利」とは闘争の歴史だ。ハリウッドを支えるスタントウーマンたちの苦悩と挑戦:『ス…
男性以上に危険で高度な技術を要するのに、男性優位な映画業界で低く評価されたままの女性スタントたちを描く映画『スタントウーマン ハリウッドの知られざるヒーローたち』。女性スタントの圧倒的な努力・技術と、その奮闘の歴史を知る。
あわせて読みたい
【現実】戦争のリアルを”閉じ込めた”映画。第一次世界大戦の英軍を収めたフィルムが描く衝撃:映画『彼…
第一次世界大戦でのイギリス兵を映した膨大な白黒フィルムをカラー化して編集した『彼らは生きていた』は、白黒の映像では実感しにくい「リアルさ」を強く感じられる。そして、「戦争は思ったよりも安易に起こる」「戦争はやはりどこまでも虚しい」と実感できる
あわせて読みたい
【恐怖】SNSの危険性と子供の守り方を、ドキュメンタリー映画『SNS 少女たちの10日間』で学ぶ
実際にチェコの警察を動かした衝撃のドキュメンタリー映画『SNS 少女たちの10日間』は、少女の「寂しさ」に付け込むおっさんどもの醜悪さに満ちあふれている。「WEBの利用制限」だけでは子どもを守りきれない現実を、リアルなものとして実感すべき
あわせて読みたい
【衝撃】壮絶な戦争映画。最愛の娘を「産んで後悔している」と呟く母らは、正義のために戦場に留まる:…
こんな映画、二度と存在し得ないのではないかと感じるほど衝撃を受けた『娘は戦場で生まれた』。母であり革命家でもあるジャーナリストは、爆撃の続くシリアの街を記録し続け、同じ街で娘を産み育てた。「知らなかった」で済ませていい現実じゃない。
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
戦争・世界情勢【本・映画の感想】 | ルシルナ
日本に生きているとなかなか実感できませんが、常に世界のどこかで戦争が起こっており、なくなることはありません。また、テロや独裁政権など、世界を取り巻く情勢は様々で…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…













































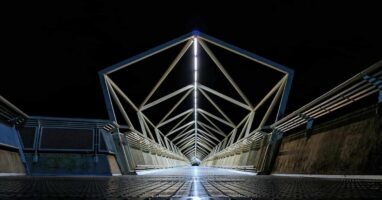

















































































コメント