目次
はじめに
この記事で取り上げる映画
出演:ケイト・ハレット, 出演:クレア・フォイ, 出演:シーラ・マッカーシー, 出演:キーラ・グロイオン, 出演:ベン・ウィッショ-, 出演:ジュディス・アイヴィー, 出演:ジェシー・バックリー, 出演:オーガスト・ウィンター, 出演:シャイラ・ブラウン, 出演:リブ マクニール, 出演:フランセシス・マクドーマンド, 出演:ルーニー・マーラ, 出演:ミッシェル・マクラウド, Writer:ミリアム・トーズ, Writer:サラ・ポーリー, 監督:サラ・ポーリー, プロデュース:ブラッド・ピット, プロデュース:デデ・ガードナー, プロデュース:リン・ルチベロ・ブランヴァテラ, プロデュース:フランシス・マクドーマンド, プロデュース:ジェレミー・クライナー, プロデュース:エミリー・ジェイド・フォーリー
 ポチップ
ポチップ
この映画をガイドにしながら記事を書いていきます
この記事の3つの要点
- 「宗教コミュニティ内で起こった出来事」という特殊さはあるものの、「尊厳を奪われ続けた者たちの闘いの物語」であり、あらゆる人に関わると言える
- 「実話である」と知らなければ、あまりにも非現実的過ぎて、フィクションとしてさえ受け入れがたいと感じさせられる物語
- 教育を与えられなかった女性たちが必死の議論によってたどり着いた決断とは?
男である私は、観ている間、喉元にずっとナイフを突きつけられているかのような感覚を抱かされた
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
2000年代に起こった実話を基にした映画『ウーマン・トーキング』は、現代の話とは信じがたい狂気に満ちている
実話を基にした、とある「宗教コミュニティ」での物語

あわせて読みたい
【苦悩】「やりがいのある仕事」だから見て見ぬふり?映画『アシスタント』が抉る搾取のリアル
とある映画会社で働く女性の「とある1日」を描く映画『アシスタント』は、「働くことの理不尽さ」が前面に描かれる作品だ。「雑用」に甘んじるしかない彼女の葛藤がリアルに描かれている。しかしそれだけではない。映画の「背景」にあるのは、あまりに悪逆な行為と、大勢による「見て見ぬふり」である
あまりに凄まじい物語だった。この作品をギリギリ成立させているのが、「実話を基にしている」という要素なのだと思う。正直なところ、「実話が基になっている」のでなければ、フィクションだとしてもあまりにもフィクショナル過ぎて、「受け入れがたい」という感覚の方が強くなってしまったかもしれない。フィクションだとしたらあまりにも現実離れしているため、「実話である」という要素が無ければ作品として成り立たないような印象さえある。
また、単に「実話を基にしている」という事実に驚かされたわけではない。それ以上に、「最近の出来事を扱っている」という点に凄まじさを感じた。
例えば、映画『ウーマン・トーキング』が「200年前の史実を基にしている作品」であるのなら、そこまで驚かなかったかもしれない。今以上に差別や偏見が酷かったわけで、「そういうことも起こり得たかもしれない」と思えた可能性もある。しかしこの映画の舞台は2010年なのだ。たかだか10年ちょっと前である。映画を観ながら、「さすがにその設定には無理があるだろう」と感じた。しかし、その印象は誤りだったようだ。本作には原作となる小説があるのだが、その小説で扱われている「実際の事件」は、2005年から2009年に掛けて起こったものなのである。映画を観れば私の感覚は理解してもらえると思うが、こんなことが「現代」に起こっているという事実には、きっと驚嘆せずにはいられないだろう。
あわせて読みたい
【悲劇】アメリカの暗黒の歴史である奴隷制度の現実を、元奴隷の黒人女性自ら赤裸々に語る衝撃:『ある…
生まれながらに「奴隷」だった黒人女性が、多くの人の協力を得て自由を手にし、後に「奴隷制度」について書いたのが『ある奴隷少女に起こった出来事』。長らく「白人が書いた小説」と思われていたが、事実だと証明され、欧米で大ベストセラーとなった古典作品が示す「奴隷制度の残酷さ」
さて、そんな「異常な出来事」が起こってしまった背景的な要素がある。正直なところ、私は映画を観ている時点では、その点についてほとんど認識できていなかった。劇中ではこの点についてほぼ説明されないので、映画を観る前に内容紹介など読んでいなければ知り得ない情報と言っていいだろう。
実は、主人公の女性たちが住んでいる村は「宗教コミュニティ」なのである。私も別に詳しいわけではないのだが、恐らく、「同じ宗教(映画を観る限り、キリスト教だと思う)を信仰する者たちが集まって共同生活しているコミュニティ」という感じなのだろう。「一緒にしないでくれ」と言われそうだが、日本人の私はやはり、「宗教コミュニティ」と言われると「オウム真理教の出家」を連想してしまう。オウム真理教の場合は都心のビル内にそのような施設を有していたために様々な軋轢を生んだわけだが、『ウーマン・トーキング』では、誰かの所有物なのか、広大な土地にコミュニティの生活が成り立っており、周囲との関わりもほとんどなさそうだった。そのような特殊な環境下で起こった出来事というわけだ。
先程も触れたが、この「宗教コミュニティ」という要素は、映画を観ているだけではなかなか理解できないだろうと思う。映画は基本的に、「女性たち(プラス男性1名)が真剣な話し合いをする」という、ほぼその状況のみで描かれる作品であり、女性たちは目の前にある喫緊の課題について激論を交わしているので、観客に向けて村の成り立ちなどについて説明する余裕はない。なので映画を観る前に、「宗教コミュニティ内で起こった出来事である」という点だけは押さえておくと、物語を理解しやすくなるだろう。
あわせて読みたい
【衝撃】洗脳を自ら脱した著者の『カルト脱出記』から、「社会・集団の洗脳」を避ける生き方を知る
「聖書研究に熱心な日本人証人」として「エホバの証人」で活動しながら、その聖書研究をきっかけに自ら「洗脳」を脱した著者の体験を著した『カルト脱出記』。広い意味での「洗脳」は社会のそこかしこに蔓延っているからこそ、著者の体験を「他人事」だと無視することはできない
普段から、映画の内容をほとんど調べずに観に行く私は、本作における「宗教コミュニティ」という設定を鑑賞時点で理解していなかった。そのため、話し合いの冒頭の方である女性が口にする、「男たちを許さないと、天国での居場所を失う」みたいな発言の「重み」を正しく捉えきれていなかったと言っていい。「宗教コミュニティ」であるという事実を知らなければ、「キリスト教の人もいるし、そうでない人もいる」と考える方が自然だろう。私は、「たまたまキリスト教の信者が多くいる村」ぐらいにしか捉えておらず、この点は、映画を理解する上でちょっと障害になったと言っていいと思う。

「宗教コミュニティ」という要素が加わることで、一気に「非日常感」が増す。それ故、「自分には関係のない話だ」と感じてしまう人もいるかもしれない。しかし、より広く捉えれば、映画『ウーマン・トーキング』は「尊厳のための闘い」が描かれる作品でもある。生きていれば、様々な場面で「尊厳が踏みにじられる状況」に出くわすことがあるだろう。そういう時にどう考え、どう決断するのか。それが問われている作品だと私は感じた。
話し合いを続ける女性たちは、一緒に住む男たちに対して「塩を取って」「辛い時に背中をさすって」程度の「頼み事」さえしたことがない。2000年代に生きているとは思えないほど、圧倒的な抑圧状態に置かれているのだ。そんな女性たちが、「生き延びる」ために真剣に話し合い、ギリギリの決断を迫られる。そんな2日間を描き出す物語は、私が「男である」という事実も相まって、喉元にナイフを突きつけられ続けているような緊迫感を感じさせられる鑑賞体験だった。
あわせて読みたい
【驚異】信念を貫く勇敢さを、「銃を持たずに戦場に立つ」という形で示した実在の兵士の凄まじさ:映画…
第二次世界大戦で最も過酷な戦場の1つと言われた「前田高地(ハクソー・リッジ)」を、銃を持たずに駆け回り信じがたい功績を残した衛生兵がいた。実在の人物をモデルにした映画『ハクソー・リッジ』から、「戦争の悲惨さ」だけでなく、「信念を貫くことの大事さ」を学ぶ
映画『ウーマン・トーキング』の内容紹介
自給自足によって生活を成り立たせているとある宗教コミュニティ内で事件が起こる。村に住む女性たちが、寝ている間に暴行されていくのだ。被害女性たちは、朝目が覚めた時に、自身の局部から血が流れていることに気づく。妊娠させられる者もいるし、自殺してしまう者もいた。
女性たちが被害を訴えても、村の男たちは「幽霊や悪魔の仕業だ」とまともに取り合わない。しかしある晩、被害女性が犯人の1人を目撃した。その男を捕まえた後、仲間の名前も自白させ、ようやく事件の全容が明るみになる。彼らは、寝ている女性たちに「馬用の鎮静剤」を打ち、犯行を続けていたのだそうだ。
犯行グループは街へと連れて行かれた。そしてその後、保釈金の支払いのために、村の男たちが街へと出払う。村から男がいなくなるまたとない機会だ。この機会に、女たちは今後の身の振り方を考えることにした。彼女たちの前にある選択肢は3つ。「何もしない」「残って闘う」「出ていく」である。文字を読むことが出来ない村の女性たちは、「投票」のやり方を即席で学び、村の全女性の投票によって今後の行動を決めることにした。
あわせて読みたい
【諦め】母親の存在にモヤモヤを抱えた人生から、「生きてさえいればいい」への違和感を考える:『晴天…
生まれ育つ環境を選ぶことはできません。そして、家族との関わりや家庭環境は、その後の人生に大きな影響を及ぼします。努力するスタートラインにも立てないと感じる時、それでも前進することを諦めてはいけないのかを、『晴天の迷いクジラ』をベースに書く
その結果、「残って闘う」と「出ていく」が同数という結果になる。村の女性の総意を取りまとめるために、代表として3家族計11人の女性が話し合いのために集まった。さらに「字が書けるから」という理由で、以前村から追放されたものの先ごろ戻ってきた男性教師も同席し、決断のための話し合いがスタートする。
期限は、男たちが村を出ている2日間だ。
女性たちの議論の行き着く先は?

あわせて読みたい
【壮絶】本当に「美人は得」か?「美しさ」という土俵を意識せざるを得ない少女・女性たちの現実:『自…
美醜で判断されがちな”ルッキズム”の世の中に刃を突きつける小説『自画像』。私自身は、「キレイな人もキレイな人なりの大変さを抱えている」と感じながら生きているつもりだが、やはりその辛さは理解されにくい。私も男性であり、ルッキズムに加担してないとはとても言えない
映画の基になった事件について少し調べてみると、その「宗教コミュニティ」には「『男尊女卑』を推奨する考え方」が存在していたそうだ。だから、村では男にしか教育を与えず、そのため女性は読み書きが出来ない。教育が与えられず、読み書きも出来ないとなると、「外の世界の知識」を手に入れることは不可能だ。だから、議論に挑む女性たちの中にも、「女は男に従属する存在だ」という考えが澱のように身体にこびついてしまっている者もいる。それ故に、女性同士でさえ意見がまとまらないのだ。
先に紹介した、「男たちを許さないと、天国での居場所を失う」という発言についても、男たちが「無知な女性を従属させるため」に、適当な考え方を植え付けて言いくるめようとしているだけだと考える方が自然だろう。この映画を観る上ではまず、このような背景が存在することを理解しておかなければならないのである。
「そんな状況はあまりに異常であり、文明化された国には存在しない」と感じる人もいるかもしれないが、恐らくそんなことはないはずだ。例えば日本には、未だに「部落差別」の問題がある。私は、部落差別の問題に触れる度に、「何がどうなってそんな差別が成立しているのか」という部分を含めてそのすべてが理解不能なのだが、現実に差別は頑然と存在するのだ。訳の分からない理屈によって「部落差別」という奇妙な状況が生み出されている現状は、映画『ウーマン・トーキング』で描かれる世界と決して遠いものではないと私は思う。
女性たちの議論は、当然のことながら紛糾する。「残って闘う」にせよ「出ていく」にせよ、彼女たちの生活環境が激変することは間違いないからだ。「塩を取って」という頼み事さえしたことがない女性たちが、「残って闘う」ことなど出来るのか。あるいは、「この宗教コミュニティ以外での生活」などまったく知らず、地図さえ見たことがない女性たちが「出ていく」ことなど可能なのか。また、「出ていく」場合は、「兄や弟、あるいは息子と離れ離れになる」と決断することにもなる。肉親との辛い別れを選んでまで、この村を離れるべきなのか。非常に難しい問題だ。
あわせて読みたい
【愛】ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督の“衝撃の出世作”である映画『灼熱の魂』の凄さ。何も語りたくない
映画館で流れた予告映像だけで観ることを決め、他になんの情報も知らないまま鑑賞した映画『灼熱の魂』は、とんでもない映画だった。『DUNE/デューン 砂の惑星』『ブレードランナー 2049』など有名作を監督してきたドゥニ・ヴィルヌーヴの衝撃の出世作については、何も語りたくない
映画では、村の代表としてどうしてこの3家族が選ばれたのか明確に説明されなかったと思うが、印象的だったのは、「同じ家族内でも決して意見が一致するわけではない」ということだ。話し合いはとにかく、「ホントにまとまるのか?」と感じさせるほど混沌としたまま進んでいく。「自分も被害者だ」という拭いきれない気持ち。「自分の子どもを絶対に被害者にはしたくない」という強い決意。そして、「どんな決断を下すにせよ、その後の生活が不安で仕方ない」という葛藤。話し合いに参加する者それぞれが、このような「相反する感覚」を抱えている。さらにその上で、議論とは直接関係のない個人的な恨みや、売り言葉に買い言葉といったやり取り、思わず口から出てしまうような吐露などがあり、女性たちの議論は混沌としていくというわけだ。
このような紆余曲折を経た上で、議論がどのような着地を迎えることになるのか。この点は非常に見応えがあると言っていいだろう。
このような状況下における「男」の存在がとても印象的
私が男だからということも関係しているだろうが、個人的には、書記を務めたオーガストの存在が非常に印象的だった。
あわせて読みたい
【あらすじ】「愛されたい」「必要とされたい」はこんなに難しい。藤崎彩織が描く「ままならない関係性…
好きな人の隣にいたい。そんなシンプルな願いこそ、一番難しい。誰かの特別になるために「異性」であることを諦め、でも「異性」として見られないことに苦しさを覚えてしまう。藤崎彩織『ふたご』が描き出す、名前がつかない切実な関係性
彼も元々はこの村に住んでいたのだが、彼の母親が村の方針に異を唱え始めたため、家族全員が村から追放されてしまったという過去を持つ。しかしその後、大学を出たオーガストは、村の少年を教育する教師として戻ってきた。外に世界を知っているからこそ余計に、「教育」の重要性を理解しているのである。
しかし一方で、恐らくかつての記憶がまだ村には残っているのだろう。男たち全員が街へと出払っているにも拘らず、オーガストだけが村に残されているのだ。詳しい事情は説明されないものの、やはり「仲間」扱いされていないと捉えるべきだろう。それで、彼に書記の役目が回ってきたのである。

オーガストの立ち位置はなかなかにややこしい。何故なら、女性たちは今まさに、「村の男たちに対してどのような態度を示すべきか」という話し合いをしているからだ。オーガスト自身は、「仲間」扱いされていないことからも明らかなように、レイプ事件とは何の関係もない。しかしどう振る舞おうが、「男である」という属性が消えるはずもないだろう。オーガストも、彼なりの意見を持って議論に加わろうとするのだが、「書記だけやってろ。口出すな」的な扱いを受けてしまう。女性たちとしても、オーガストに非がないことは十分理解しているのだが、どうしても気が立ってしまうのだ。
あわせて読みたい
【感涙】映画『彼女が好きなものは』の衝撃。偏見・無関心・他人事の世界から”脱する勇気”をどう持つか
涙腺がぶっ壊れたのかと思ったほど泣かされた映画『彼女が好きなものは』について、作品の核となる「ある事実」に一切触れずに書いた「ネタバレなし」の感想です。「ただし摩擦はゼロとする」の世界で息苦しさを感じているすべての人に届く「普遍性」を体感してください
興味深かったのは、オーガストが「女性からのそのような扱われ方を上手く吸収できるような存在感」を放っていることにある。女性から酷い扱いを受けるオーガストが、もしも「可哀想な人」に見えてしまったら、結果として女性たちが悪く映ってしまうことになるだろう。しかし、そうはならない。議論の場に「馴染めている」とは決して言えないもののが、さりとて「排除されている」という風にもならないというわけだ。オーガストが持つこのようなバランス感覚が、映画『ウーマン・トーキング』を絶妙に成立させているように私には感じられた。
「語るための言葉」が無ければ、何も語ることなど出来ない
さて、映画を観ながらもう1つ興味深いと感じたポイントは、「『こと』を語る言葉がない」という女性たちの認識だ。映画を観ている時には正直、何を言っているのか良く分からなかったのだが、「宗教コミュニティ」であることを知ってようやく理解できた。
恐らくこれは、「『レイプ』という言葉を知らない」という意味だと思う。教育を受けさせてもらえず、外部との接触がない村であれば、そういうこともあり得るだろう。
あわせて読みたい
【信念】凄いな久遠チョコレート!映画『チョコレートな人々』が映す、障害者雇用に挑む社長の奮闘
重度の人たちも含め、障害者を最低賃金保証で雇用するというかなり無謀な挑戦を続ける夏目浩次を追う映画『チョコレートな人々』には衝撃を受けた。キレイゴトではなく、「障害者を真っ当に雇用したい」と考えて「久遠チョコレート」を軌道に乗せたとんでもない改革者の軌跡を追うドキュメンタリー
私たちの場合、普通に生きていれば、どこかのタイミングで「レイプ」という言葉を知ることになるし、その意味だって理解する。だから、自身が被害に遭った時に、それが「レイプ」であると認識出来るというわけだ。しかし、被害者になった後でさえも「レイプ」という言葉を知らないままの彼女たちは、自分の身に起こったことが何であるのかをそもそも捉えることが出来ない。当然、それを訴えることも出来ないというわけだ。
また、「言葉が無い」というのはつまり「概念が存在しない」ということを意味するので、この点も女性たちが共闘しにくい理由の1つになっていたはずだと思う。映画を観ている時には、「さすがに『幽霊』『悪霊』の仕業という説明を信じるのは無理があるだろう」と感じていたのだが、「『こと』を語る言葉がない」という認識を知ったことで納得出来た。登場人物の1人が、「言葉が無いから、沈黙するしかない」みたいに口にするのだが、まさにその通りだろう。彼女たちは、このような点においても厳しい状況に置かれていたというわけだ。
話し合いの最中、「私たちには3つの権利がある」という話になった。そしてその内の1つとして「考える権利」が挙げられるのだ。当たり前過ぎてなかなかこのような思考をする機会はないが、「意図的に教育を与えられず、知識を得る機会もほとんどない女性たち」の議論を観ながら、当たり前のことがいかに当たり前ではないのかについても考えさせられた。

あわせて読みたい
【感想】是枝裕和監督映画『怪物』(坂元裕二脚本)が抉る、「『何もしないこと』が生む加害性」
坂元裕二脚本、是枝裕和監督の映画『怪物』は、3つの視点を通して描かれる「日常の何気ない光景」に、思いがけない「加害性」が潜んでいることを炙り出す物語だ。これは間違いなく、私たち自身に関わる話であり、むしろ「自分には関係ない」と考えている人こそが自覚すべき問題だと思う
映画『ウーマン・トーキング』で描かれる村では、男が女性を意図的に無学のままに留めているので、女性たちが無知であることは仕方ないと言えるだろう。しかし、私たちはそうではない。知る権利も学ぶ権利も考える権利も、基本的には保証されているのだ。だからこそ、知る・学ぶ・考えることから遠ざかってはいけないのである。
無知なままでは、闘えないのだ。
出演:ケイト・ハレット, 出演:クレア・フォイ, 出演:シーラ・マッカーシー, 出演:キーラ・グロイオン, 出演:ベン・ウィッショ-, 出演:ジュディス・アイヴィー, 出演:ジェシー・バックリー, 出演:オーガスト・ウィンター, 出演:シャイラ・ブラウン, 出演:リブ マクニール, 出演:フランセシス・マクドーマンド, 出演:ルーニー・マーラ, 出演:ミッシェル・マクラウド, Writer:ミリアム・トーズ, Writer:サラ・ポーリー, 監督:サラ・ポーリー, プロデュース:ブラッド・ピット, プロデュース:デデ・ガードナー, プロデュース:リン・ルチベロ・ブランヴァテラ, プロデュース:フランシス・マクドーマンド, プロデュース:ジェレミー・クライナー, プロデュース:エミリー・ジェイド・フォーリー
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品視聴済】私が観てきた映画(フィクション)を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が観てきた映画(フィクション)を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。
最後に
あわせて読みたい
【絶望】杉咲花主演映画『市子』の衝撃。毎日がしんどい「どん底の人生」を生き延びるための壮絶な決断…
映画『市子』はまず何よりも主演を務めた杉咲花に圧倒させられる作品だ。そしてその上で、主人公・川辺市子を巡る物語にあれこれと考えさせられてしまった。「川辺市子」は決してフィクショナルな存在ではなく、現実に存在し得る。本作は、そのような存在をリアルに想像するきっかけにもなるだろう
改めて書くが、映画『ウーマン・トーキング』は実話を基に描かれている。こうやって自分で記事を書いていても、その異常さに驚かされるくらいだ。
そして、本作を観た驚きは、自分の身近な世界にも向けるべきだと思う。2000年代に、このような異様さがまかり通る世界が存在していたのだ。となれば、そんな世界がすぐ近くに存在するとしても、決しておかしくはないと考えるべきだろう。
あわせて読みたい
【憤り】世界最強米海軍4人VS数百人のタリバン兵。死線を脱しただ1人生還を果たした奇跡の実話:『アフ…
アフガニスタンの山中で遭遇した羊飼いを見逃したことで、数百人のタリバン兵と死闘を繰り広げる羽目に陥った米軍最強部隊に所属する4人。奇跡的に生き残り生還を果たした著者が記す『アフガン、たった一人の生還』は、とても実話とは信じられない凄まじさに満ちている
人間は、いかようにでも「狂気」に染まることが出来る。そんなことを改めて実感させられる物語だった。
あわせて読みたい
【感想】映画『正欲』に超共感。多様性の時代でさえどこに行っても馴染めない者たちの業苦を抉る(出演…
映画『正欲』は、私には共感しかない作品だ。特に、新垣結衣演じる桐生夏月と磯村勇斗演じる佐々木佳道が抱える葛藤や息苦しさは私の内側にあるものと同じで、その描かれ方に圧倒されてしまった。「『多様性』には『理解』も『受け入れ』も不要で、単に否定しなければ十分」なのだと改めて思う
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!「それってホントに『コミュ力』が高いって言えるの?」と疑問を感じている方に…
私は、「コミュ力が高い人」に関するよくある主張に、どうも違和感を覚えてしまうことが多くあります。そしてその一番大きな理由が、「『コミュ力が高い人』って、ただ『想像力がない』だけではないか?」と感じてしまう点にあると言っていいでしょう。出版したKindle本は、「ネガティブには見えないネガティブな人」(隠れネガティブ)を取り上げながら、「『コミュ力』って何だっけ?」と考え直してもらえる内容に仕上げたつもりです。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【変異】映画『動物界』は斬新で刺激的な作品だった。我々はまさにこんな”分断社会”に生きている
映画『動物界』では、「奇病によって人間が動物化してしまう」という世界における複雑な人間模様が描き出される。パンデミックを経験した我々には、本作の設定は「単なるSF」には感じられないはずだ。そしてその上で、「『動物化してしまった妻を今も愛している主人公』が見せる実にややこしい感情」が複層的に描かれていて実に興味深い
あわせて読みたい
【孤独】映画『ナミビアの砂漠』は、自由だが居場所がない主人公を演じる河合優実の存在感が圧倒的(監…
映画『ナミビアの砂漠』は、とにかく「河合優実が凄まじい」のひと言に尽きる作品だ。彼女が演じたカナという主人公の「捉えどころの無さ」は絶妙で、一見すると凄まじく「自由」に羽ばたいている感じなのに、実際には全然「自由」には見えないというバランスが見事だった。特段の物語はないのに、137分間惹きつけられてしまうだろう
あわせて読みたい
【変態】映画『コンセント/同意』が描く50歳と14歳少女の”恋”は「キモっ!」では終われない
映画『コンセント/同意』は、50歳の著名小説家に恋をした14歳の少女が大人になってから出版した「告発本」をベースに作られた作品だ。もちろん実話を元にしており、その焦点はタイトルの通り「同意」にある。自ら望んで36歳年上の男性との恋に踏み出した少女は、いかにして「同意させられた」という状況に追い込まれたのか?
あわせて読みたい
【あらすじ】杉咲花と安田顕が圧巻!映画『朽ちないサクラ』(原廣利)は「正義の難しさ」を描く(原作…
柚月裕子の同名小説を原作とした映画『朽ちないサクラ』は、とにかく杉咲花と安田顕の演技に圧倒されてしまった作品だ。「トロッコ問題」を連想させる非常に難しい状況を提示することで「正義の難しさ」を描き出す展開も素晴らしいし、主人公・森口泉を演じた杉咲花の「絶望を静かに体現する演技」も見事だった
あわせて読みたい
【真相?】映画『マミー』が描く和歌山毒物カレー事件・林眞須美の冤罪の可能性。超面白い!
世間を大騒ぎさせた「和歌山毒物カレー事件」の犯人とされた林眞須美死刑囚は無実かもしれない。映画『マミー』は、そんな可能性を示唆する作品だ。「目撃証言」と「ヒ素の鑑定」が詳細に検証し直され、さらに「保険金詐欺をやっていた」という夫の証言も相まって、証拠的にも感情的にも支持したくなるような驚きの仮説である
あわせて読みたい
【?】現代思想「<友情>の現在」を読んで、友達・恋愛・好き・好意などへのモヤモヤを改めて考えた
「現代思想 <友情>の現在」では、「友情」をテーマにした様々な考察が掲載されているのだが、中でも、冒頭に載っていた対談が最も興味深く感じられた。「『友達』というのは、既存の概念からこぼれ落ちた関係性につけられる『残余カテゴリー』である」という中村香住の感覚を起点に、様々な人間関係について思考を巡らせてみる
あわせて読みたい
【実話】映画『ダム・マネー ウォール街を狙え!』は「株で大儲けした」だけじゃない痛快さが面白い
ダム・マネー ウォール街を狙え!』では、株取引で莫大な利益を得た実在の人物が取り上げられる。しかし驚くべきは「大金を得たこと」ではない。というのも彼はなんと、資産5万ドルの身にも拘らず、ウォール街の超巨大資本ファンドを脅かす存在になったのである! 実話とは思えない、あまりにも痛快な物語だった
あわせて読みたい
【あらすじ】有村架純が保護司を演じた映画『前科者』が抉る、罪を犯した者を待つ「更生」という現実
映画『前科者』は、仮釈放中の元受刑者の更生を手助けするボランティアである「保護司」を中心に据えることで、「元犯罪者をどう受け入れるべきか」「保護司としての葛藤」などを絶妙に描き出す作品。個別の事件への処罰感情はともかく、「社会全体としていかに犯罪を減らしていくか」という観点を忘れるべきではないと私は思っている
あわせて読みたい
【感想】映画『夜明けのすべて』は、「ままならなさ」を抱えて生きるすべての人に優しく寄り添う(監督…
映画『夜明けのすべて』は、「PMS」や「パニック障害」を通じて、「自分のものなのに、心・身体が思い通りにならない」という「ままならなさ」を描き出していく。決して他人事ではないし、「私たちもいつそのような状況に置かれるか分からない」という気持ちで観るのがいいでしょう。物語の起伏がないのに惹きつけられる素敵な作品です
あわせて読みたい
【狂気】群青いろ制作『雨降って、ジ・エンド。』は、主演の古川琴音が成立させている映画だ
映画『雨降って、ジ・エンド。』は、冒頭からしばらくの間「若い女性とオジサンのちょっと変わった関係」を描く物語なのですが、後半のある時点から「共感を一切排除する」かのごとき展開になる物語です。色んな意味で「普通なら成立し得ない物語」だと思うのですが、古川琴音の演技などのお陰で、絶妙な形で素敵な作品に仕上がっています
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『52ヘルツのクジラたち』の「無音で叫ぶ人」と「耳を澄ます人」の絶妙な響鳴(原作:…
映画『52ヘルツのクジラたち』は、「現代的な問題のごった煮」と感じられてしまうような”過剰さ”に溢れてはいますが、タイトルが作品全体を絶妙に上手くまとめていて良かったなと思います。主演の杉咲花がやはり見事で、身体の内側から「不幸」が滲み出ているような演技には圧倒されてしまいました
あわせて読みたい
【幻惑】映画『落下の解剖学』は、「真実は誰かが”決める”しかない」という現実の不安定さを抉る
「ある死」を巡って混沌とする状況をリアルに描き出す映画『落下の解剖学』は、「客観的な真実にはたどり着けない」という困難さを炙り出す作品に感じられた。事故なのか殺人なのか自殺なのか、明確な証拠が存在しない状況下で、憶測を繋ぎ合わせるようにして進行する「裁判」の様子から、「『真実性』の捉えがたさ」がよく理解できる
あわせて読みたい
【衝撃】EUの難民問題の狂気的縮図!ポーランド・ベラルーシ国境での、国による非人道的対応:映画『人…
上映に際し政府から妨害を受けたという映画『人間の境界』は、ポーランド・ベラルーシ国境で起こっていた凄まじい現実が描かれている。「両国間で中東からの難民を押し付け合う」という醜悪さは見るに絶えないが、そのような状況下でも「可能な範囲でどうにか人助けをしたい」と考える者たちの奮闘には救われる思いがした
あわせて読みたい
【真相】飯塚事件は冤罪で死刑執行されたのか?西日本新聞・警察・弁護士が語る葛藤と贖罪:映画『正義…
映画『正義の行方』では、冤罪のまま死刑が執行されたかもしれない「飯塚事件」が扱われる。「久間三千年が犯行を行ったのか」という議論とは別に、「当時の捜査・司法手続きは正しかったのか?」という観点からも捉え直されるべきだし、それを自発的に行った西日本新聞の「再検証連載」はとても素晴らしかったと思う
あわせて読みたい
【赦し】映画『過去負う者』が描く「元犯罪者の更生」から、社会による排除が再犯を生む現実を知る
映画『過去負う者』は、冒頭で「フィクション」だと明示されるにも拘らず、観ながら何度も「ドキュメンタリーだっけ?」と感じさせられるという、実に特異な体験をさせられた作品である。実在する「元犯罪者の更生を支援する団体」を舞台にした物語で、当然それは、私たち一般市民にも無関係ではない話なのだ
あわせて読みたい
【挑戦】映画『燃えあがる女性記者たち』が描く、インドカースト最下位・ダリットの女性による報道
映画『燃えあがる女性記者たち』は、インドで「カースト外の不可触民」として扱われるダリットの女性たちが立ち上げた新聞社「カバル・ラハリヤ」を取り上げる。自身の境遇に抗って、辛い状況にいる人の声を届けたり権力者を糾弾したりする彼女たちの奮闘ぶりが、インドの民主主義を変革させるかもしれない
あわせて読みたい
【問題】映画『国葬の日』が切り取る、安倍元首相の”独裁”が生んだ「政治への関心の無さ」(監督:大島新)
安倍元首相の国葬の1日を追ったドキュメンタリー映画『国葬の日』は、「国葬」をテーマにしながら、実は我々「国民」の方が深堀りされる作品だ。「安倍元首相の国葬」に対する、全国各地の様々な人たちの反応・価値観から、「『ソフトな独裁』を維持する”共犯者”なのではないか」という、我々自身の政治との向き合い方が問われているのである
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『戦場のピアニスト』(ロマン・ポランスキー)が描く、ユダヤ人迫害の衝撃の実話
映画『戦場のピアニスト』の4Kリマスター版を観に行ったところ、上映後のトークイベントに主人公の息子が登壇したので驚いた。何せ私は、本作が「実話を基にしている」ことさえ知らなかったのである。だからその驚きもひとしおだった。ホロコーストの生存者である主人公の壮絶な人生を描き出す、不朽の名作だ
あわせて読みたい
【無謀】映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、脱北ルートに撮影隊が同行する衝撃のドキュメンタリー
北朝鮮からの脱北者に同行し撮影を行う衝撃のドキュメンタリー映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、再現映像を一切使用していない衝撃的な作品だ。危険と隣り合わせの脱北の道程にカメラもついて回り、北朝鮮の厳しい現状と共に、脱北者が置かれた凄まじい状況を映し出す内容に驚かされてしまった
あわせて読みたい
【狂気】異質なホラー映画『みなに幸あれ』(古川琴音主演)は古い因習に似せた「社会の異様さ」を描く
古川琴音主演映画『みなに幸あれ』は、”シュールさ”さえ感じさせる「異質なホラー映画」だ。「村の因習」というよくあるパターンをベースに据えつつ、そこで展開される異様な状況が、実は「私たちが生きる世界」に対応しているという構成になっている。「お前の物語だからな」と終始突きつけられ続ける作品だ
あわせて読みたい
【斬新】映画『王国(あるいはその家について)』(草野なつか)を観よ。未経験の鑑賞体験を保証する
映画『王国(あるいはその家について)』は、まず経験できないだろう異様な鑑賞体験をもたらす特異な作品だった。「稽古場での台本読み」を映し出すパートが上映時間150分のほとんどを占め、同じやり取りをひたすら繰り返し見せ続ける本作は、「王国」をキーワードに様々な形の「狂気」を炙り出す異常な作品である
あわせて読みたい
【考察】A24のホラー映画『TALK TO ME』が描くのは、「薄く広がった人間関係」に悩む若者のリアルだ
「A24のホラー映画史上、北米最高興収」と謳われる『TALK TO ME トーク・トゥ・ミー』は、一見「とても分かりやすいホラー映画」である。しかし真のテーマは「SNS過剰社会における人間関係の困難さ」なのだと思う。結果としてSNSが人と人との距離を遠ざけてしまっている現実を、ホラー映画のスタイルに落とし込んだ怪作
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『千年女優』(今敏)はシンプルな物語を驚愕の演出で味付けした天才的アニメ作品
今敏監督の映画『千年女優』は、ちょっとびっくりするほど凄まじく面白い作品だった。観ればスッと理解できるのに言葉で説明すると難解になってしまう「テクニカルな構成」に感心させられつつ、そんな構成に下支えされた「物語の感性的な部分」がストレートに胸を打つ、シンプルながら力強い作品だ
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『アンダーカレント』(今泉力哉)は、失踪をテーマに「分かり合えなさ」を描く
映画『アンダーカレント』において私は、恐らく多くの人が「受け入れがたい」と感じるだろう人物に共感させられてしまった。また本作は、「他者を理解すること」についての葛藤が深掘りされる作品でもある。そのため、私が普段から抱いている「『他者のホントウ』を知りたい」という感覚も強く刺激された
あわせて読みたい
【絶望】杉咲花主演映画『市子』の衝撃。毎日がしんどい「どん底の人生」を生き延びるための壮絶な決断…
映画『市子』はまず何よりも主演を務めた杉咲花に圧倒させられる作品だ。そしてその上で、主人公・川辺市子を巡る物語にあれこれと考えさせられてしまった。「川辺市子」は決してフィクショナルな存在ではなく、現実に存在し得る。本作は、そのような存在をリアルに想像するきっかけにもなるだろう
あわせて読みたい
【感想】映画『キリエのうた』(岩井俊二)はアイナ・ジ・エンドに圧倒されっ放しの3時間だった(出演:…
映画『キリエのうた』(岩井俊二監督)では、とにかくアイナ・ジ・エンドに圧倒されてしまった。歌声はもちろんのことながら、ただそこにいるだけで場を支配するような存在感も凄まじい。全編に渡り「『仕方ないこと』はどうしようもなく起こるんだ」というメッセージに溢れた、とても力強い作品だ
あわせて読みたい
【感想】映画『正欲』に超共感。多様性の時代でさえどこに行っても馴染めない者たちの業苦を抉る(出演…
映画『正欲』は、私には共感しかない作品だ。特に、新垣結衣演じる桐生夏月と磯村勇斗演じる佐々木佳道が抱える葛藤や息苦しさは私の内側にあるものと同じで、その描かれ方に圧倒されてしまった。「『多様性』には『理解』も『受け入れ』も不要で、単に否定しなければ十分」なのだと改めて思う
あわせて読みたい
【衝撃】ウクライナでのホロコーストを描く映画『バビ・ヤール』は、集めた素材映像が凄まじすぎる
ソ連生まれウクライナ育ちの映画監督セルゲイ・ロズニツァが、「過去映像」を繋ぎ合わせる形で作り上げた映画『バビ・ヤール』は、「単一のホロコーストで最大の犠牲者を出した」として知られる「バビ・ヤール大虐殺」を描き出す。ウクライナ市民も加担した、そのあまりに悲惨な歴史の真実とは?
あわせて読みたい
【絶望】人生どん底から生き方を変える。映画『シスター 夏のわかれ道』が描く中国人女性の葛藤と諦念
両親の死をきっかけに、「見知らぬ弟」を引き取らなければならなくなった女性を描く映画『シスター 夏のわかれ道』は、中国の特異な状況を背景にしつつ、誰もが抱き得る普遍的な葛藤が切り取られていく。現状を打破するために北京の大学院を目指す主人公は、一体どんな決断を下すのか。
あわせて読みたい
【現実】映画『私のはなし 部落のはなし』で初めて同和・部落問題を考えた。差別はいかに生まれ、続くのか
私はずっと、「部落差別なんてものが存在する意味が分からない」と感じてきたが、映画『私のはなし 部落のはなし』を観てようやく、「どうしてそんな差別が存在し得るのか」という歴史が何となく理解できた。非常に複雑で解決の難しい問題だが、まずは多くの人が正しく理解することが必要だと言えるだろう
あわせて読みたい
【絶望】映画『少年たちの時代革命』が描く、香港デモの最中に自殺者を救おうとした若者たちの奮闘
香港の民主化運動の陰で、自殺者を救出しようと立ち上がったボランティア捜索隊が人知れず存在していた。映画『少年たちの時代革命』はそんな実話を基にしており、若者の自殺が急増した香港に様々な葛藤を抱えながら暮らし続ける若者たちのリアルが切り取られる作品だ
あわせて読みたい
【闘争】映画『あのこと』が描く、中絶が禁止だった時代と、望まぬ妊娠における圧倒的な「男の不在」
中絶が禁止されていた1960年代のフランスを舞台にした映画『あのこと』は、「望まぬ妊娠」をしてしまった秀才の大学生が、「未来を諦めない」ために中絶を目指す姿が描かれる。さらに、誰にも言えずに孤独に奮闘する彼女の姿が「男の不在」を強調する物語でもあり、まさに男が観るべき作品だ
あわせて読みたい
【驚愕】本屋大賞受賞作『同志少女よ、敵を撃て』(逢坂冬馬)は凄まじい。戦場は人間を”怪物”にする
デビュー作で本屋大賞を受賞した『同志少女よ、敵を撃て』(逢坂冬馬)は、デビュー作であることを抜きにしても凄まじすぎる、規格外の小説だった。ソ連に実在した「女性狙撃兵」の視点から「独ソ戦」を描く物語は、生死の境でギリギリの葛藤や決断に直面する女性たちのとんでもない生き様を活写する
あわせて読みたい
【信念】9.11後、「命の値段」を計算した男がいた。映画『WORTH』が描く、その凄絶な2年間(主演:マイ…
9.11テロの後、「被害者の『命の値段』を算出した男」がいたことをご存知だろうか?映画『WORTH』では、「被害者遺族のために貢献したい」と無償で難題と向き合うも、その信念が正しく理解されずに反発や対立を招いてしまった現実が描かれる。実話を基にしているとは思えない、凄まじい物語だ
あわせて読みたい
【デモ】クーデター後の軍事政権下のミャンマー。ドキュメンタリーさえ撮れない治安の中での映画制作:…
ベルリン国際映画祭でドキュメンタリー賞を受賞したミャンマー映画『ミャンマー・ダイアリーズ』はしかし、後半になればなるほどフィクショナルな映像が多くなる。クーデター後、映画制作が禁じられたミャンマーで、10人の”匿名”監督が死を賭して撮影した映像に込められた凄まじいリアルとは?
あわせて読みたい
【希望】誰も傷つけたくない。でも辛い。逃げたい。絶望しかない。それでも生きていく勇気がほしい時に…
2006年発売、2021年文庫化の『私を見て、ぎゅっと愛して』は、ブログ本のクオリティとは思えない凄まじい言語化力で、1人の女性の内面の葛藤を抉り、読者をグサグサと突き刺す。信じがたい展開が連続する苦しい状況の中で、著者は大事なものを見失わず手放さずに、勇敢に前へ進んでいく
あわせて読みたい
【信念】映画『ハマのドン』の主人公、横浜港の顔役・藤木幸夫は、91歳ながら「伝わる言葉」を操る
横浜港を取り仕切る藤木幸夫を追うドキュメンタリー映画『ハマのドン』は、盟友・菅義偉と対立してでもIR進出を防ごうとする91歳の決意が映し出される作品だ。高齢かつほとんど政治家のような立ち位置でありながら、「伝わる言葉」を発する非常に稀有な人物であり、とても興味深かった
あわせて読みたい
【悲劇】大川小学校はなぜ津波被害に遭ったのか?映画『生きる』が抉る現実と国家賠償請求の虚しさ
東日本大震災において、児童74人、教職員10人死亡という甚大な津波被害を生んだ大川小学校。その被害者遺族が真相究明のために奮闘する姿を追うドキュメンタリー映画『生きる』では、学校の酷い対応、出来れば避けたかった訴訟、下された画期的判決などが描かれ、様々な問題が提起される
あわせて読みたい
【理解】「多様性を受け入れる」とか言ってるヤツ、映画『炎上する君』でも観て「何も見てない」って知…
西加奈子の同名小説を原作とした映画『炎上する君』(ふくだももこ監督)は、「多様性」という言葉を安易に使いがちな世の中を挑発するような作品だ。「見えない存在」を「過剰に装飾」しなければならない現実と、マジョリティが無意識的にマイノリティを「削る」リアルを描き出していく
あわせて読みたい
【信念】凄いな久遠チョコレート!映画『チョコレートな人々』が映す、障害者雇用に挑む社長の奮闘
重度の人たちも含め、障害者を最低賃金保証で雇用するというかなり無謀な挑戦を続ける夏目浩次を追う映画『チョコレートな人々』には衝撃を受けた。キレイゴトではなく、「障害者を真っ当に雇用したい」と考えて「久遠チョコレート」を軌道に乗せたとんでもない改革者の軌跡を追うドキュメンタリー
あわせて読みたい
【家族】ゲイの男性が、拘置所を出所した20歳の男性と養子縁組し親子関係になるドキュメンタリー:映画…
「ゲイの男性が、拘置所から出所した20歳の男性と養子縁組し、親子関係になる」という現実を起点にしたドキュメンタリー映画『二十歳の息子』は、奇妙だが実に興味深い作品だ。しばらく何が描かれているのか分からない展開や、「ゲイであること」に焦点が当たらない構成など、随所で「不協和音」が鳴り響く1作
あわせて読みたい
【感想】是枝裕和監督映画『怪物』(坂元裕二脚本)が抉る、「『何もしないこと』が生む加害性」
坂元裕二脚本、是枝裕和監督の映画『怪物』は、3つの視点を通して描かれる「日常の何気ない光景」に、思いがけない「加害性」が潜んでいることを炙り出す物語だ。これは間違いなく、私たち自身に関わる話であり、むしろ「自分には関係ない」と考えている人こそが自覚すべき問題だと思う
あわせて読みたい
【高卒】就職できる気がしない。韓国のブラック企業の実態をペ・ドゥナ主演『あしたの少女』が抉る
韓国で実際に起こった「事件」を基に作られた映画『あしたの少女』は、公開後に世論が動き、法律の改正案が国会を通過するほどの影響力を及ぼした。学校から実習先をあてがわれた1人の女子高生の運命を軸に描かれる凄まじい現実を、ペ・ドゥナ演じる女刑事が調べ尽くす
あわせて読みたい
【苦悩】「やりがいのある仕事」だから見て見ぬふり?映画『アシスタント』が抉る搾取のリアル
とある映画会社で働く女性の「とある1日」を描く映画『アシスタント』は、「働くことの理不尽さ」が前面に描かれる作品だ。「雑用」に甘んじるしかない彼女の葛藤がリアルに描かれている。しかしそれだけではない。映画の「背景」にあるのは、あまりに悪逆な行為と、大勢による「見て見ぬふり」である
あわせて読みたい
【性加害】映画『SHE SAID その名を暴け』を観てくれ。#MeToo運動を生んだ報道の舞台裏(出演:キャリ…
「#MeToo」運動のきっかけとなった、ハリウッドの絶対権力者ハーヴェイ・ワインスタインを告発するニューヨーク・タイムズの記事。その取材を担った2人の女性記者の奮闘を描く映画『SHE SAID その名を暴け』は、ジャニー喜多川の性加害問題で揺れる今、絶対に観るべき映画だと思う
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』を観てくれ!現代の人間関係の教科書的作品を考…
映画『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』は、私にグサグサ突き刺さるとても素晴らしい映画だった。「ぬいぐるみに話しかける」という活動内容の大学サークルを舞台にした物語であり、「マイノリティ的マインド」を持つ人たちの辛さや葛藤を、「マジョリティ視点」を絶妙に織り交ぜて描き出す傑作について考察する
あわせて読みたい
【純真】ゲイが犯罪だった時代が舞台の映画『大いなる自由』は、刑務所内での極深な人間ドラマを描く
男性同士の恋愛が犯罪であり、ゲイの男性が刑法175条を理由に逮捕されてしまう時代のドイツを描いた映画『大いなる自由』は、確かに同性愛の物語なのだが、実はそこに本質はない。物語の本質は、まさにタイトルにある通り「自由」であり、ラストシーンで突きつけられるその深い問いかけには衝撃を受けるだろう
あわせて読みたい
【映画】今泉力哉監督『ちひろさん』(有村架純)が描く、「濃い寂しさ」が溶け合う素敵な関係性
今泉力哉監督、有村架純主演の映画『ちひろさん』は、その圧倒的な「寂しさの共有」がとても心地よい作品です。色んな「寂しさ」を抱えた様々な人と関わる、「元風俗嬢」であることを公言し海辺の町の弁当屋で働く「ちひろさん」からは、同じような「寂しさ」を抱える人を惹き付ける力強さが感じられるでしょう
あわせて読みたい
【あらすじ】塩田武士『罪の声』が放つ、戦後最大の未解決事件「グリコ・森永事件」の圧倒的”リアル感”
戦後最大の未解決事件である「グリコ・森永事件」では、脅迫に子どもの声が使われていた。私はその事実を、塩田武士『罪の声』という小説を読むまで知らなかった。では、続く疑問はこうだろう。その子どもたちは、今どこでどんな風に生きているのか?その疑問に答える、凄まじい小説だ。
あわせて読みたい
【生還】内戦下のシリアでISISに拘束された男の実話を基にした映画『ある人質』が描く壮絶すぎる現実
実話を基にした映画『ある人質 生還までの398日』は、内戦下のシリアでISISに拘束された男の壮絶な日々が描かれる。「テロリストとは交渉しない」という方針を徹底して貫くデンマーク政府のスタンスに翻弄されつつも、救出のために家族が懸命に奮闘する物語に圧倒される
あわせて読みたい
【感想】映画『朝が来る』が描く、「我が子を返して欲しい気持ち」を消せない特別養子縁組のリアル
「特別養子縁組」を軸に人々の葛藤を描く映画『朝が来る』は、決して「特別養子縁組」の話ではない。「『起こるだろうが、起こるはずがない』と思っていた状況」に直面せざるを得ない人々が、「すべての選択肢が不正解」という中でどんな決断を下すのかが問われる、非常に示唆に富む作品だ
あわせて読みたい
【執念】「桶川ストーカー事件」で警察とマスコミの怠慢を暴き、社会を動かした清水潔の凄まじい取材:…
『殺人犯はそこにいる』(文庫X)で凄まじい巨悪を暴いた清水潔は、それよりずっと以前、週刊誌記者時代にも「桶川ストーカー殺人事件」で壮絶な取材を行っていた。著者の奮闘を契機に「ストーカー規制法」が制定されたほどの事件は、何故起こり、どんな問題を喚起したのか
あわせて読みたい
【幸福】「死の克服」は「生の充実」となり得るか?映画『HUMAN LOST 人間失格』が描く超管理社会
アニメ映画『HUMAN LOST 人間失格』では、「死の克服」と「管理社会」が分かちがたく結びついた世界が描かれる。私たちは既に「緩やかな管理社会」を生きているが、この映画ほどの管理社会を果たして許容できるだろうか?そしてあなたは、「死」を克服したいと願うだろうか?
あわせて読みたい
【魅惑】バーバラ・ローデン監督・脚本・主演の映画『WANDA』の、70年代の作品とは思えない今感
映画館で観た予告が気になって、それ以外の情報を知らずに観に行った映画『WANDA』なんと70年代の映画だと知って驚かされた。まったく「古さ」を感じなかったからだ。主演だけでなく、監督・脚本も務めたバーバラ・ローデンが遺した、死後評価が高まった歴史的一作
あわせて読みたい
【あらすじ】ムロツヨシ主演映画『神は見返りを求める』の、”善意”が”悪意”に豹変するリアルが凄まじい
ムロツヨシ演じる田母神が「お人好し」から「復讐の権化」に豹変する映画『神は見返りを求める』。「こういう状況は、実際に世界中で起こっているだろう」と感じさせるリアリティが見事な作品だった。「善意」があっさりと踏みにじられる世界を、私たちは受け容れるべきだろうか?
あわせて読みたい
【感想】阿部サダヲが狂気を怪演。映画『死刑にいたる病』が突きつける「生きるのに必要なもの」の違い
サイコパスの連続殺人鬼・榛村大和を阿部サダヲが演じる映画『死刑にいたる病』は、「生きていくのに必要なもの」について考えさせる映画でもある。目に光を感じさせない阿部サダヲの演技が、リアリティを感じにくい「榛村大和」という人物を見事に屹立させる素晴らしい映画
あわせて読みたい
【感想】是枝裕和映画『ベイビー・ブローカー』は、「赤ちゃんポスト」を起点に「正義とは何か」を描く
韓国に多数存在するという「赤ちゃんポスト」を題材にした是枝裕和監督映画『ベイビー・ブローカー』は、「正義とは何か」を問いかける。「中絶はOKで、捨てるのはNG」という判断は不合理だし、「最も弱い関係者が救われる」ことが「正義」だと私は思う
あわせて読みたい
【あらすじ】嵐莉菜主演映画『マイスモールランド』は、日本の難民問題とクルド人の現状、入管の酷さを描く
映画『マイスモールランド』はフィクションではあるが、「日本に住む難民の厳しい現実」をリアルに描き出す作品だ。『東京クルド』『牛久』などのドキュメンタリー映画を観て「知識」としては知っていた「現実」が、当事者にどれほどの苦しみを与えるのか想像させられた
あわせて読みたい
【差別】映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』の衝撃。プーチンが支持する国の蛮行・LGBT狩り
プーチン大統領の後ろ盾を得て独裁を維持しているチェチェン共和国。その国で「ゲイ狩り」と呼ぶしかない異常事態が継続している。映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』は、そんな現実を命がけで映し出し、「現代版ホロコースト」に立ち向かう支援団体の奮闘も描く作品
あわせて読みたい
【悲劇】アメリカの暗黒の歴史である奴隷制度の現実を、元奴隷の黒人女性自ら赤裸々に語る衝撃:『ある…
生まれながらに「奴隷」だった黒人女性が、多くの人の協力を得て自由を手にし、後に「奴隷制度」について書いたのが『ある奴隷少女に起こった出来事』。長らく「白人が書いた小説」と思われていたが、事実だと証明され、欧米で大ベストセラーとなった古典作品が示す「奴隷制度の残酷さ」
あわせて読みたい
【対立】パレスチナとイスラエルの「音楽の架け橋」は実在する。映画『クレッシェンド』が描く奇跡の楽団
イスラエルとパレスチナの対立を背景に描く映画『クレッシェンド』は、ストーリーそのものは実話ではないものの、映画の中心となる「パレスチナ人・イスラエル人混合の管弦楽団」は実在する。私たちが生きる世界に残る様々な対立について、その「改善」の可能性を示唆する作品
あわせて読みたい
【実話】台湾のろう学校のいじめ・性的虐待事件を描く映画『無聲』が問う、あまりに悲しい現実
台湾のろう学校で実際に起こったいじめ・性的虐待事件を基に作られた映画『無聲』は、健常者の世界に刃を突きつける物語だ。これが実話だという事実に驚かされる。いじめ・性的虐待が物語の「大前提」でしかないという衝撃と、「性的虐待の方がマシ」という選択を躊躇せず行う少女のあまりの絶望を描き出す
あわせて読みたい
【事件】デュポン社のテフロン加工が有害だと示した男の執念の実話を描く映画『ダーク・ウォーターズ』
世界的大企業デュポン社が、自社製品「テフロン」の危険性を40年以上前に把握しながら公表せず、莫大な利益を上げてきた事件の真相を暴き出した1人の弁護士がいる。映画『ダーク・ウォーターズ』は、大企業相手に闘いを挑み、住民と正義のために走り続けた実在の人物の勇敢さを描き出す
あわせて読みたい
【LGBT】映画『リトル・ガール』で映し出される、性別違和を抱える8歳の”女の子”のリアルと苦悩
映画撮影時8歳だった、身体は男の子、心は女の子のサシャは、スカートを履いての登校が許されず、好きなバッグもペンケースも使わせてもらえない。映画『リトル・ガール』が描く、「性別違和」に対する社会の不寛容と、自分を責め続けてしまう母親の苦悩
あわせて読みたい
【愛】ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督の“衝撃の出世作”である映画『灼熱の魂』の凄さ。何も語りたくない
映画館で流れた予告映像だけで観ることを決め、他になんの情報も知らないまま鑑賞した映画『灼熱の魂』は、とんでもない映画だった。『DUNE/デューン 砂の惑星』『ブレードランナー 2049』など有名作を監督してきたドゥニ・ヴィルヌーヴの衝撃の出世作については、何も語りたくない
あわせて読みたい
【憤り】世界最強米海軍4人VS数百人のタリバン兵。死線を脱しただ1人生還を果たした奇跡の実話:『アフ…
アフガニスタンの山中で遭遇した羊飼いを見逃したことで、数百人のタリバン兵と死闘を繰り広げる羽目に陥った米軍最強部隊に所属する4人。奇跡的に生き残り生還を果たした著者が記す『アフガン、たった一人の生還』は、とても実話とは信じられない凄まじさに満ちている
あわせて読みたい
【病理】本田靖春が「吉展ちゃん事件」を追う。誘拐を捜査する警察のお粗末さと時代を反映する犯罪:『…
「戦後最大の誘拐事件」と言われ、警察の初歩的なミスなどにより事件解決に膨大な月日を要した「吉展ちゃん誘拐殺人事件」。その発端から捜査体制、顛末までをジャーナリスト・本田靖春が徹底した取材で描き出す『誘拐』は、「『犯罪』とは『社会の病理』である」と明確に示している
あわせて読みたい
【衝撃】洗脳を自ら脱した著者の『カルト脱出記』から、「社会・集団の洗脳」を避ける生き方を知る
「聖書研究に熱心な日本人証人」として「エホバの証人」で活動しながら、その聖書研究をきっかけに自ら「洗脳」を脱した著者の体験を著した『カルト脱出記』。広い意味での「洗脳」は社会のそこかしこに蔓延っているからこそ、著者の体験を「他人事」だと無視することはできない
あわせて読みたい
【感想】リドリー・スコット監督の映画『最後の決闘裁判』から、社会が”幻想”を共有する背景とその悲劇…
例えば、「1万円札」というただの紙切れに「価値を感じる」のは、社会の構成員が同じ「共同幻想」の中に生きているからだ。リドリー・スコット監督の映画『最後の決闘裁判』は、「強姦では妊娠しない」「裁判の勝者を決闘で決する」という社会通念と、現代にも通じる「共同幻想」の強さを描き出す
あわせて読みたい
【理解】小野田寛郎を描く映画。「戦争終結という現実を受け入れない(=認知的不協和)」は他人事じゃ…
映画『ONODA 一万夜を越えて』を観るまで、小野田寛郎という人間に対して違和感を覚えていた。「戦争は終わっていない」という現実を生き続けたことが不自然に思えたのだ。しかし映画を観て、彼の生き方・決断は、私たちと大きく変わりはしないと実感できた
あわせて読みたい
【衝撃】権力の濫用、政治腐敗を描く映画『コレクティブ』は他人事じゃない。「国家の嘘」を監視せよ
火災で一命を取り留め入院していた患者が次々に死亡した原因が「表示の10倍に薄められた消毒液」だと暴き、国家の腐敗を追及した『ガゼタ』誌の奮闘を描く映画『コレクティブ 国家の嘘』は、「権力の監視」が機能しなくなった国家の成れの果てが映し出される衝撃作だ
あわせて読みたい
【信念】水俣病の真実を世界に伝えた写真家ユージン・スミスを描く映画。真実とは「痛みへの共感」だ:…
私はその存在をまったく知らなかったが、「水俣病」を「世界中が知る公害」にした報道写真家がいる。映画『MINAMATA―ミナマタ―』は、水俣病の真実を世界に伝えたユージン・スミスの知られざる生涯と、理不尽に立ち向かう多くの人々の奮闘を描き出す
あわせて読みたい
【感想】映画『先生、私の隣に座っていただけませんか?』は、「リアル」と「漫画」の境界の消失が絶妙
映画『先生、私の隣に座っていただけませんか?』は、「マンガ家夫婦の不倫」という設定を非常に上手く活かしながら、「何がホントで何かウソなのかはっきりしないドキドキ感」を味わわせてくれる作品だ。黒木華・柄本佑の演技も絶妙で、良い映画を観たなぁと感じました
あわせて読みたい
【衝撃】『殺人犯はそこにいる』が実話だとは。真犯人・ルパンを野放しにした警察・司法を信じられるか?
タイトルを伏せられた覆面本「文庫X」としても話題になった『殺人犯はそこにいる』。「北関東で起こったある事件の取材」が、「私たちが生きる社会の根底を揺るがす信じがたい事実」を焙り出すことになった衝撃の展開。まさか「司法が真犯人を野放しにする」なんてことが実際に起こるとは。大げさではなく、全国民必読の1冊だと思う
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『流浪の月』を観て感じた、「『見て分かること』にしか反応できない世界」への気持ち悪さ
私は「見て分かること」に”しか”反応できない世界に日々苛立ちを覚えている。そういう社会だからこそ、映画『流浪の月』で描かれる文と更紗の関係も「気持ち悪い」と断罪されるのだ。私はむしろ、どうしようもなく文と更紗の関係を「羨ましい」と感じてしまう。
あわせて読みたい
【正義】復讐なんかに意味はない。それでも「この復讐は正しいかもしれない」と思わされる映画:『プロ…
私は基本的に「復讐」を許容できないが、『プロミシング・ヤング・ウーマン』の主人公キャシーの行動は正当化したい。法を犯す明らかにイカれた言動なのだが、その動機は一考の余地がある。何も考えずキャシーを非難していると、矢が自分の方に飛んでくる、恐ろしい作品
あわせて読みたい
【中絶】望まない妊娠をした若い女性が直面する現実をリアルに描く映画。誰もが現状を知るべきだ:『17…
他の様々な要素を一切排し、「望まぬ妊娠をした少女が中絶をする」というただ1点のみに全振りした映画『17歳の瞳に映る世界』は、説明もセリフも極端に削ぎ落としたチャレンジングな作品だ。主人公2人の沈黙が、彼女たちの置かれた現実を雄弁に物語っていく。
あわせて読みたい
【生きる】しんどい人生を宿命付けられた子どもはどう生きるべき?格差社会・いじめ・恋愛を詰め込んだ…
厳しい受験戦争、壮絶な格差社会、残忍ないじめ……中国の社会問題をこれでもかと詰め込み、重苦しさもありながら「ボーイ・ミーツ・ガール」の爽やかさも融合されている映画『少年の君』。辛い境遇の中で、「すべてが最悪な選択肢」と向き合う少年少女の姿に心打たれる
あわせて読みたい
【葛藤】正義とは何かを突きつける戦争映画。80人を救うために1人の少女を殺すボタンを押せるか?:『ア…
「80人の命を救うために、1人の少女の命を奪わなければならない」としたら、あなたはその決断を下せるだろうか?会議室で展開される現代の戦争を描く映画『アイ・イン・ザ・スカイ』から、「誤った問い」に答えを出さなければならない極限状況での葛藤を理解する
あわせて読みたい
【差別】才ある者の能力を正しく引き出す者こそ最も有能であり、偏見から能力を評価できない者は無能だ…
「偏見・差別ゆえに、他人の能力を活かせない人間」を、私は無能だと感じる。そういう人は、現代社会の中にも結構いるでしょう。ソ連との有人宇宙飛行競争中のNASAで働く黒人女性を描く映画『ドリーム』から、偏見・差別のない社会への道筋を考える
あわせて読みたい
【実話】権力の濫用を監視するマスコミが「教会の暗部」を暴く映画『スポットライト』が現代社会を斬る
地方紙である「ボストン・グローブ紙」は、数多くの神父が長年に渡り子どもに対して性的虐待を行い、その事実を教会全体で隠蔽していたという衝撃の事実を明らかにした。彼らの奮闘の実話を映画化した『スポットライト』から、「権力の監視」の重要性を改めて理解する
あわせて読みたい
【正義】「正しさとは何か」を考えさせる映画『スリー・ビルボード』は、正しさの対立を絶妙に描く
「正しい」と主張するためには「正しさの基準」が必要だが、それでも「規制されていないことなら何でもしていいのか」は問題になる。3枚の立て看板というアナログなツールを使って現代のネット社会の現実をあぶり出す映画『スリー・ビルボード』から、「『正しさ』の難しさ」を考える
あわせて読みたい
【葛藤】子どもが抱く「家族を捨てたい気持ち」は、母親の「家族を守りたい気持ち」の終着点かもしれな…
家族のややこしさは、家族の数だけ存在する。そのややこしさを、「子どもを守るために母親が父親を殺す」という極限状況を設定することで包括的に描き出そうとする映画『ひとよ』。「暴力」と「殺人犯の子どもというレッテル」のどちらの方が耐え難いと感じるだろうか?
あわせて読みたい
【壮絶】本当に「美人は得」か?「美しさ」という土俵を意識せざるを得ない少女・女性たちの現実:『自…
美醜で判断されがちな”ルッキズム”の世の中に刃を突きつける小説『自画像』。私自身は、「キレイな人もキレイな人なりの大変さを抱えている」と感じながら生きているつもりだが、やはりその辛さは理解されにくい。私も男性であり、ルッキズムに加担してないとはとても言えない
あわせて読みたい
【絶望】光過敏症の女性の、真っ暗な部屋で光という光をすべて遮断しなければ生きられない壮絶な日常:…
日光に限らず、ありとあらゆる「光」に肌が異常に反応してしまうため、ずっと真っ暗闇の中でしか生きられない女性が、その壮絶すぎる日常を綴った『まっくらやみで見えたもの 光アレルギーのわたしの奇妙な人生』から、それでも生きていく強さを感じ取る
あわせて読みたい
【危機】教員のセクハラは何故無くならない?資質だけではない、学校の構造的な問題も指摘する:『スク…
『スクールセクハラ なぜ教師のわいせつ犯罪は繰り返されるのか』では、自分が生徒に対して「権力」を持っているとは想像していなかったという教師が登場する。そしてこの「無自覚」は、学校以外の場でも起こりうる。特に男性は、読んで自分の振る舞いを見直すべきだ
あわせて読みたい
【絶望】「人生上手くいかない」と感じる時、彼を思い出してほしい。壮絶な過去を背負って生きる彼を:…
「北九州連続監禁殺人事件」という、マスコミも報道規制するほどの残虐事件。その「主犯の息子」として生きざるを得なかった男の壮絶な人生。「ザ・ノンフィクション」のプロデューサーが『人殺しの息子と呼ばれて』で改めて取り上げた「真摯な男」の生き様と覚悟
あわせて読みたい
【助けて】息苦しい世の中に生きていて、人知れず「傷」を抱えていることを誰か知ってほしいのです:『…
元気で明るくて楽しそうな人ほど「傷」を抱えている。そんな人をたくさん見てきた。様々な理由から「傷」を表に出せない人がいる世の中で、『包帯クラブ』が提示する「見えない傷に包帯を巻く」という具体的な行動は、気休め以上の効果をもたらすかもしれない
あわせて読みたい
【あらすじ】人生行き詰まってなお「生きたい」と思えるか?環境の激変を受け入れる難しさと生きる悲し…
勤務していた会社の都合で、町が1つ丸々無くなるという経験をし、住居を持たないノマド生活へと舵を切った女性を描く映画『ノマドランド』を通じて、人生の大きな変化に立ち向かう気力を持てるのか、我々はどう生きていくべきか、などについて考える
あわせて読みたい
【現実】生きる気力が持てない世の中で”働く”だけが人生か?「踊るホームレスたち」の物語:映画『ダン…
「ホームレスは怠けている」という見方は誤りだと思うし、「働かないことが悪」だとも私には思えない。振付師・アオキ裕キ主催のホームレスのダンスチームを追う映画『ダンシングホームレス』から、社会のレールを外れても許容される社会の在り方を希求する
あわせて読みたい
【称賛】生き様がかっこいい。ムンバイのホテルのテロ事件で宿泊客を守り抜いたスタッフたち:映画『ホ…
インドの高級ホテルで実際に起こったテロ事件を元にした映画『ホテル・ムンバイ』。恐ろしいほどの臨場感で、当時の恐怖を観客に体感させる映画であり、だからこそ余計に、「逃げる選択」もできたホテルスタッフたちが自らの意思で残り、宿泊を助けた事実に感銘を受ける
あわせて読みたい
【リアル】社会の分断の仕組みを”ゾンビ”で学ぶ。「社会派ゾンビ映画」が対立の根源を抉り出す:映画『C…
まさか「ゾンビ映画」が、私たちが生きている現実をここまで活写するとは驚きだった。映画『CURED キュアード』をベースに、「見えない事実」がもたらす恐怖と、立場ごとに正しい主張をしながらも否応なしに「分断」が生まれてしまう状況について知る
あわせて読みたい
【驚愕】「金正男の殺人犯」は”あなた”だったかも。「人気者になりたい女性」が陥った巧妙な罠:映画『…
金正男が暗殺された事件は、世界中で驚きをもって報じられた。その実行犯である2人の女性は、「有名にならないか?」と声を掛けられて暗殺者に仕立て上げられてしまった普通の人だ。映画『わたしは金正男を殺していない』から、危険と隣り合わせの現状を知る
あわせて読みたい
【排除】「分かり合えない相手」だけが「間違い」か?想像力の欠如が生む「無理解」と「対立」:映画『…
「共感」が強すぎる世の中では、自然と「想像力」が失われてしまう。そうならないようにと意識して踏ん張らなければ、他人の価値観を正しく認めることができない人間になってしまうだろう。映画『ミセス・ノイズィ』から、多様な価値観を排除しない生き方を考える
あわせて読みたい
【素顔】「ヨコハマメリー史」から「伊勢佐木町史」を知れる映画。謎の女性が町の歴史に刻んだものとは…
横浜で長らく目撃されていた白塗りの女性は、ある時から姿を消した。彼女の存在を欠いた伊勢佐木町という街は、大きく変わってしまったと語る者もいる。映画『ヨコハマメリー』から、ある種のアイコンとして存在した女性の生き様や彼女と関わった者たちの歴史、そして彼女の”素顔”を知る
あわせて読みたい
【差別】「女性の権利」とは闘争の歴史だ。ハリウッドを支えるスタントウーマンたちの苦悩と挑戦:『ス…
男性以上に危険で高度な技術を要するのに、男性優位な映画業界で低く評価されたままの女性スタントたちを描く映画『スタントウーマン ハリウッドの知られざるヒーローたち』。女性スタントの圧倒的な努力・技術と、その奮闘の歴史を知る。
あわせて読みたい
【幻想】心の傷を癒やすことの”難しさ”、寄り添い続けるために必要な”弱さ”と”冷たさ”:映画『心の傷を…
「優しいかどうか」が重要な要素として語られる場面が多いと感じるが、私は「優しさ」そのものにはさしたる意味はないと考えている。映画『心の傷を癒すということ 劇場版』から、「献身」と「優しさ」の違いと、誰かに寄り添うために必要な「弱さ」を理解する
あわせて読みたい
【救い】耐えられない辛さの中でどう生きるか。短歌で弱者の味方を志すホームレス少女の生き様:『セー…
死にゆく母を眺め、施設で暴力を振るわれ、拾った新聞で文字を覚えたという壮絶な過去を持つ鳥居。『セーラー服の歌人 鳥居』は、そんな辛い境遇を背景に、辛さに震えているだろう誰かを救うために短歌を生み出し続ける生き方を描き出す。凄い人がいるものだ
あわせて読みたい
【感想】世の中と足並みがそろわないのは「正常が異常」だから?自分の「正常」を守るために:『コンビ…
30代になっても未婚でコンビニアルバイトの古倉さんは、普通から外れたおかしな人、と見られてしまいます。しかし、本当でしょうか?『コンビニ人間』をベースに、多数派の人たちの方が人生を自ら選択していないのではないかと指摘する。
あわせて読みたい
【諦め】母親の存在にモヤモヤを抱えた人生から、「生きてさえいればいい」への違和感を考える:『晴天…
生まれ育つ環境を選ぶことはできません。そして、家族との関わりや家庭環境は、その後の人生に大きな影響を及ぼします。努力するスタートラインにも立てないと感じる時、それでも前進することを諦めてはいけないのかを、『晴天の迷いクジラ』をベースに書く
あわせて読みたい
【恐怖】SNSの危険性と子供の守り方を、ドキュメンタリー映画『SNS 少女たちの10日間』で学ぶ
実際にチェコの警察を動かした衝撃のドキュメンタリー映画『SNS 少女たちの10日間』は、少女の「寂しさ」に付け込むおっさんどもの醜悪さに満ちあふれている。「WEBの利用制限」だけでは子どもを守りきれない現実を、リアルなものとして実感すべき
あわせて読みたい
【異常】「助けて」と言えない。自己責任社会のしんどさと、我が子がホームレスである可能性:『助けて…
39歳で餓死した男性は、何故誰にも助けを求めなかったのか?異常な視聴率を叩き出した、NHK「クローズアップ現代」の特集を元に書かれた『助けてと言えない』をベースに、「自己責任社会」の厳しさと、若者が置かれている現実について書く。
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
どう生きるべきか・どうしたらいい【本・映画の感想】 | ルシルナ
どんな人生を歩みたいか、多くの人が考えながら生きていると思います。私は自分自身も穏やかに、そして周囲の人や社会にとっても何か貢献できたらいいなと、思っています。…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…













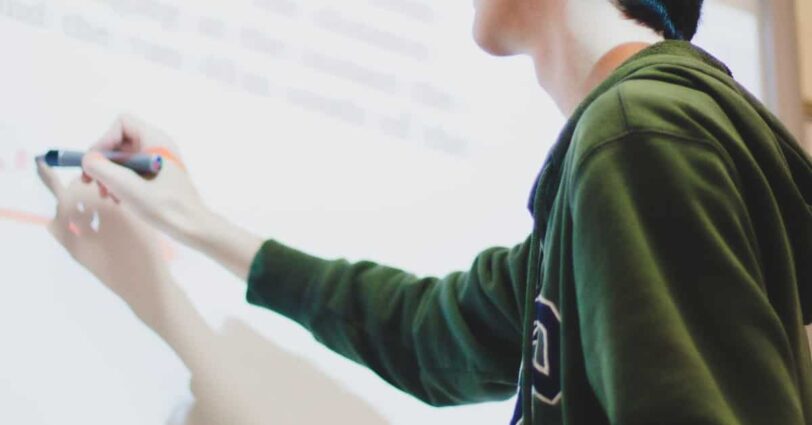
























































































































コメント