目次
はじめに
この記事で取り上げる映画
出演:ペ・ドゥナ, 出演:キム・シウン, 出演:チョン・フェリン, 出演:カン・ヒョンオ, 出演:パク・ウヨン, 監督:チョン・ジュリ, プロデュース:キム・ドンハ, プロデュース:キム・ジヨン, Writer:チョン・ジュリ
 ポチップ
ポチップ
この映画をガイドにしながら記事を書いていきます
この記事の3つの要点
- この映画は、単に「ブラック企業の酷さ」を描き出すだけの物語ではない
- 高校が「派遣会社」と化している現状と、その現実がもたらす悲惨な実態
- 韓国国内でもあまり知られていなかった事実を映画化した本作は、法改正を促すほどの影響力をもたらした
「調べても分からない空白部分を、敢えて創作によっては埋めない」という構成から、「真実を伝えたい」という制作側の強い想いを感じ取った
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
韓国で実際に起こった事件を基にした映画『あしたの少女』は、「教育現場がブラック企業を生み出す構造」を炙り出した凄まじい作品
少女を追い詰めたのは企業か? それとも学校か? 韓国に蔓延る信じがたい仕組み
衝撃的な作品だった。
あわせて読みたい
【実話】ポートアーサー銃乱射事件を扱う映画『ニトラム』が示す、犯罪への傾倒に抗えない人生の不条理
オーストラリアで実際に起こった銃乱射事件の犯人の生い立ちを描く映画『ニトラム/NITRAM』は、「頼むから何も起こらないでくれ」と願ってしまうほどの異様な不穏さに満ちている。「社会に順応できない人間」を社会がどう受け入れるべきかについて改めて考えさせる作品だ
映画には、「実話を基にした作品である」のような表記はなかったと思う。恐らく実話ベースだろうと思いつつ、映画を観ている時にはその確信が持てなかった。調べてみると、やはり実話がベースの作品であるようだ。それを知ったことで、映画を観て感じたことがより一層重さを増したようにも感じられた。
あまりにも酷い現実である。

最近の話で言えば、自動車修理・中古車販売業「ビッグモーター社」の問題を思い出した。映画で描かれるのはコールセンターであり、自動車修理業とはかけ離れているが、本質的な部分は変わらない。つまり、「顧客の利益を毀損してでも、自社の利益を”強奪する”」というスタンスで企業活動を行っているのである。
あわせて読みたい
【事件】デュポン社のテフロン加工が有害だと示した男の執念の実話を描く映画『ダーク・ウォーターズ』
世界的大企業デュポン社が、自社製品「テフロン」の危険性を40年以上前に把握しながら公表せず、莫大な利益を上げてきた事件の真相を暴き出した1人の弁護士がいる。映画『ダーク・ウォーターズ』は、大企業相手に闘いを挑み、住民と正義のために走り続けた実在の人物の勇敢さを描き出す
この「企業のスタンス」自体ももちろん大きな問題だ。もちろん、企業が存続するためには「キレイゴト」だけではどうにもならないと理解しているつもりだが、しかしやはり、「顧客の利益を毀損するやり方」は許されないだろう。
ただ重要なのは、「映画『あしたの少女』で描かれる現実は、単に一企業の問題に留まるものではない」という点だ。「何故そんな酷い経営が可能だったのか」という「構造的な問題」が指摘されているのである。そしてそこに、「いくらでも使い捨てが出来る」という「教育現場を含めた信じがたい仕組み」が見え隠れするというわけだ。
その仕組みを理解するために、まずは主人公キム・ソヒが何故コールセンターで働くことになったのか、その理由を見ていこう。
あわせて読みたい
【葛藤】部活で後悔しないために。今やりたいことをやりきって、過去を振り返らないための全力:『風に…
勉強の方が、部活動より重要な理由なんて無い。どれだけ止められても「全力で打ち込みたい」という気持ちを抑えきれないものに出会える人生の方が、これからの激動の未来を生き延びられるはずと信じて突き進んでほしい。部活小説『風に恋う』をベースに書いていく
愛玩動物管理科に通う高校生のソヒは、担任から実習先が指定された。それがコールセンターである。大手企業の下請けであるヒューマン&ネットでの仕事であり、教師は大いに喜んでいた。当校の実習先としては、これまでで最も大手の企業だからだ。ソヒは「やっとウチからも大手企業に人を送れる」「お前には期待してる」と言われ、ソヒ自身も「OLになるんだ」という期待で胸が膨らんでいた。
そして勤務初日を迎える。チーム長であるイ・ジュノはとても丁寧に仕事を教えてくれたのだが、渡されたマニュアルがとにかく酷かった。このコールセンターでは、サービスの解約を希望する客からの電話が掛かってくるのだが、マニュアルには、「様々な理由をつけて、いかに解約させずに電話を終わらせるか」についての手法が書かれていたのである。ソヒは、自分のやっている仕事に疑問を抱く。しかし、自分がここで頑張らなければ、学校に迷惑が掛かってしまう。自分は期待されている。とにかく頑張るしかないと、ソヒは目の前の仕事に必死に食らいついていく。
しかし、給料日になるとソヒは再び愕然とさせられる。教師からあらかじめ渡されていた「現場実習契約書」に記載されている金額通りには支払われなかったのだ。そのことを指摘すると、チーム長は「現場実習契約書」とは別の勤労契約書を提示し、そこに「状況によって賃金は変わる」と書かれていると説明した。それを聞いてソヒは引き下がる。しかし彼女の知るところではなかったが、「現場実習契約書」とは異なる契約を交わすことはもちろん法律違反だ。
あわせて読みたい
【感想】才能の開花には”極限の環境”が必要か?映画『セッション』が描く世界を私は否定したい
「追い込む指導者」が作り出す”極限の環境”だからこそ、才能が開花する可能性もあるとは思う。しかし、そのような環境はどうしても必要だろうか?最高峰の音楽院での壮絶な”指導”を描く映画『セッション』から、私たちの生活を豊かにしてくれるものの背後にある「死者」を想像する
また、「解約阻止率などの実績を考慮し、インセンティブが支払われる」とも聞いていたソヒは、成績を上げているにも拘らずインセンティブがもらえない状況についても指摘した。すると、「すぐ辞められては困るので、実習生には1~2ヶ月先に支払うことにしている」とあしらわれてしまう。映画での描かれ方からするに、「本当はインセンティブなど支払うつもりなどなく、適当にごまかしているだけ」という感じがした。
そんなわけでソヒは、「実習」とは名ばかりの、社内の大人たちとまったく同じ仕事をさせられながら、高校生だという理由で低賃金で働かされている。高校生なのに、仕事が終わらないせいで20時前に帰れたことなどほとんどないのだが、その状況について後に指摘されると、会社は「インセンティブ目当てに自発的に残業する者がいる」などと実態とは異なる説明をしたりするのだ。
キム・ソヒは、このような状況にあった。これは決して、彼女に特有の事情ではない。韓国の高校生は皆、ほぼ同じような状況下に置かれているのだ。映画は、2016年から2017年に掛けてを舞台にしている。たかだか5年前の話なのだ。
あわせて読みたい
【驚異】甲子園「2.9連覇」を成し遂げた駒大苫小牧野球部監督・香田誉士史の破天荒で規格外の人生:『勝…
「田中将大と斎藤佑樹の死闘」「37年ぶりの決勝戦再試合」「驚異の2.9連覇」など話題に事欠かなかった駒大苫小牧野球部。その伝説のチームを率いた名将・香田誉士史の評伝『勝ちすぎた監督』は、体罰が問題になった男の毀誉褒貶を余すところなく描き出す。しかしとんでもない男だ
韓国の若者が置かれている状況について、なんとなく理解していただけただろうか?
「高校が企業に『実習』という名目で働き手を送り出す」という異様な構図
映画は冒頭からしばらくの間、「コールセンターで働くキム・ソヒ」を中心に展開する。そして後半から、「ペ・ドゥナ演じる女刑事が状況を捜査する」という物語が始まっていくのだが、そこで「韓国の教育現場の実情」が明らかになっていくのだ。

韓国の高校は実質的に、「安い労働力を企業に送り込む派遣会社」のような存在に成り下がっている。そう捉えると、キム・ソヒの状況を理解しやすいだろう。彼女は、自ら望んでコールセンターで働いているわけではない。「お前はここに行け」と、学校から「実習先」としてあてがわれているだけなのだ。
あわせて読みたい
【権利】衝撃のドキュメンタリー映画『ヤクザと憲法』は、「異質さを排除する社会」と「生きる権利」を問う
「ヤクザ」が排除された現在でも、「ヤクザが担ってきた機能」が不要になるわけじゃない。ではそれを、公権力が代替するのだろうか?実際の組事務所(東組清勇会)にカメラを持ち込むドキュメンタリー映画『ヤクザと憲法』が映し出す川口和秀・松山尚人・河野裕之の姿から、「基本的人権」のあり方について考えさせられた
この状況の困難さは、「『自分の意思で辞める』という選択肢がほぼ存在しない」という点にあると言っていいだろう。実習生は「学校の代表」であり、理由はどうあれ、「実習生が実習先の企業を辞めた」となれば、それは「学校のマイナス」と扱われてしまうのだ。生徒たちは、「期待している」などの言葉を教師から掛けられることで、そのような事情を理解する。だからこそ、送り込まれた先がどれほど酷かろうと、辞めずに頑張るしかなくなってしまうのだ。
映画の中である人物が、「実習先を辞めたいと学校に頼んだけど辞めさせてもらえなかったから、学校を辞めるしかなかった」みたいなことを口にする場面がある。あまりに酷すぎる状況だろう。しかし、映画の中ではさらっと描かれる場面でしかなく、だからこそ私は、「彼女のような状況は決してレアケースではないのだ」と受け取った。
これは相当に尋常ではない状況と考えていいのではないかと思う。
あわせて読みたい
【現実】戦争のリアルを”閉じ込めた”映画。第一次世界大戦の英軍を収めたフィルムが描く衝撃:映画『彼…
第一次世界大戦でのイギリス兵を映した膨大な白黒フィルムをカラー化して編集した『彼らは生きていた』は、白黒の映像では実感しにくい「リアルさ」を強く感じられる。そして、「戦争は思ったよりも安易に起こる」「戦争はやはりどこまでも虚しい」と実感できる
さてそもそもだが、「愛玩動物管理科」に通っていたキム・ソヒが「コールセンター」で「実習」を行うというのはなかなかに意味不明だろう。せめて、動物と関わる実習先が用意されるべきではないのか。どうしてそのような状況になっているのか、その背景を知ろうと調べを進めた女刑事は、学校教育が置かれている状況を知ることになる。どの高校も、「生き残るのに必死」というわけだ。
映画で描かれているところによると、韓国の高校は、「新入生の入学率」と「実習生の就職率」の2点”のみ”で評価されるのだという。しかしそれは誰からの「評価」なのか。もちろん、「我が子をどの高校に入学させようかと考えている親」の目も意識しているとは思う。しかしそれだけではない。そもそも教育庁からの補助金が、「入学率」「就職率」の2点をベースに決められているのである。
だから、高校が生き残るためには、その2つの数字を高く維持し続けるしかない。そして、「就職率が下がるから」という理由で、高校は専攻に合った実習先を用意しないのだという。
あわせて読みたい
【日常】「何もかも虚しい」という心のスキマを「異性」や「お金」で安易に埋めてしまうのは危険だ:映…
「どこにでもいる普通の女性」が「横領」に手を染める映画『紙の月』は、「日常の積み重ねが非日常に接続している」ことを否応なしに実感させる。「主人公の女性は自分とは違う」と考えたい観客の「祈り」は通じない。「梅澤梨花の物語」は「私たちの物語」でもあるのだ
どういうことか。
生徒たちの専攻は、100%彼らの希望で決まるわけではない。というか、生徒が望むのとは異なる専攻になることが多いのだという。だから、専攻に合った実習先を選んでも、実習生が実習先でそのまま就職する可能性は低い。確かにキム・ソヒも、コールセンターでの実習が決まった時点では、「OLになれる」と喜んでいた。動物に関わる仕事に就きたかったわけでは恐らくないのだろう。
学校としては、「実習生の就職率」が下がるので、実習生が実習先でそのまま就職してくれないと困る。そこで、就職先として「生徒たちが希望しそうな一般企業」に頼んで実習生を受け入れてもらい、さらに生徒には「絶対に辞めるなよ」という”圧力”を掛けて送り出すというわけだ。
あわせて読みたい
【驚愕】「金正男の殺人犯」は”あなた”だったかも。「人気者になりたい女性」が陥った巧妙な罠:映画『…
金正男が暗殺された事件は、世界中で驚きをもって報じられた。その実行犯である2人の女性は、「有名にならないか?」と声を掛けられて暗殺者に仕立て上げられてしまった普通の人だ。映画『わたしは金正男を殺していない』から、危険と隣り合わせの現状を知る
そして当然のことながら企業側は、このような学校の事情をきちんと理解している。
状況を理解した上での「搾取」状態は、少しずつ変わり始めている
この状況を企業側から見れば、次のようになるだろう。高校の方から、「是非実習生を預かってほしい」とお願いに来るのだから、否もない。実習生の契約条件はあらかじめ決められるとはいえ、そんなものはどうとでもなる。安くこき使おうじゃないか。優秀な人間ならそのまま残ってもらえばいいし、無能なら使えるだけ使い倒して辞めてもらえばいい。「実習生の就職率」なんて知るか。都合の良い部分だけ利用させてもらおう。

あわせて読みたい
【あらすじ】人生行き詰まってなお「生きたい」と思えるか?環境の激変を受け入れる難しさと生きる悲し…
勤務していた会社の都合で、町が1つ丸々無くなるという経験をし、住居を持たないノマド生活へと舵を切った女性を描く映画『ノマドランド』を通じて、人生の大きな変化に立ち向かう気力を持てるのか、我々はどう生きていくべきか、などについて考える
映画の中で、企業側のこのような思惑がはっきりと描かれるわけではなく、あくまでも私の勝手な想像に過ぎないが、しかし、映画で描かれるコールセンターの状況を見れば、大きくは捉え間違っていないはずだ。
なにせ、キム・ソヒが働いていたコールセンターの実態が凄まじい。なんと「全員が実習生」、つまり「リーダー以外全員が高校生」なのである。この企業はコールセンターのチームを5つ持っており、その内の1つが「実習生しかいないチーム」というわけだ。そして、他の4つのチーム(当然、社会人が働いている)と競わせ、成績が悪いと「他のチームと比べて劣っている」とボロクソに言われるのである。
なかなかにイカれた環境と言っていいだろう。
そもそもこのコールセンター、後に女刑事が調べたところによると、全社員650名程度の会社なのだが、その内の629名が昨年退職し、617名を新たに採用したことが分かっている。つまり、従業員のほとんどが入れ替わっているというわけだ。そんな会社がまともなはずがない。
あわせて読みたい
【狂気】アメリカの衝撃の実態。民営刑務所に刑務官として潜入した著者のレポートは国をも動かした:『…
アメリカには「民営刑務所」が存在する。取材のためにその1つに刑務官として潜入した著者が記した『アメリカン・プリズン』は信じがたい描写に溢れた1冊だ。あまりに非人道的な行いがまかり通る狂気の世界と、「民営刑務所」が誕生した歴史的背景を描き出すノンフィクション
本来であれば教師は、生徒を送り込む企業について調べ、実際に訪問し、労働環境などをチェックしなければならないと定められている。しかし学校としては、「大手企業(実際にはその下請けだが)に実習生を送った」という実績が欲しい。だから、「禄な調査もしないまま、実習先として選定している」というのが実状なのだ。
本当に、知れば知るほど信じがたい状況である。あまりにも酷い世界だと思う。
先程も触れた通り、映画で描かれているのは2017年頃の話である。しかしその当時、このような状況は韓国国内でもほとんど知られていなかった。本当であれば、その当時起こったある「事件」をきっかけにこのような実態が明るみになり、社会問題化してもおかしくなかったはずだ。しかし残念ながらそうはならなかった。「事件」そのものは報じられたが、その背景についてはほとんど深入りされなかったからだ。高校も企業も教育庁も、「臭いものに蓋をしたい」という動機で一致していたのだろう。公式HPによると、ある人権活動家の働きかけによって多少は報道されたそうだが、大きな問題としては扱われなかったという。
しかし、まさにこの『あしたの少女』という映画が公開されたことをきっかけにして、韓国国内で「現場実習生の保護」を求める声が高まっていったのだそうだ。これは私にはかなり凄まじい話に思える。そしてなんと、通称「次のソヒ防止法」と呼ばれる改正案が国会を通過したというのだ。この映画の原題を直訳すると「次のソヒ」となる。つまり、まさにこの映画が、社会を動かす大きなきっかけを作ったというわけだ。いち映画が与えた影響としてはかなり大きなものと言えると思う。
あわせて読みたい
【実話】田舎暮らし失敗。映画『理想郷』が描く、めんどくさい人間関係が嫌がらせに発展した事件
実話を基にした映画『理想郷』は、「理想の田舎暮らし」が粉微塵に粉砕されていく過程を描く物語である。第一義的には当然、夫妻に嫌がらせを続ける兄弟が悪いのだが、しかしそのように捉えるだけでは何も変わらないだろう。双方の譲れない「価値観」が否応なしに正面衝突する状況で、一体何が「正解」となり得るだろうか?

さて、実話を基にした映画が作られる場合、一般的には状況が一通り落ち着いてからになることが多いだろう。「事件が解決した」とか「被害者への補償が決まった」などの状況を経ないと、「物語」としてのまとまりを保つのが難しくなるからだ。
そしてそういう意味で、この『あしたの少女』という映画は、非常にまとまりのない形で終わる。当然だろう。この映画を制作している時には、「現場実習生を保護する改正案」の話など、まったく存在していなかったのだから。そのため、物語としての「不完全燃焼感」は強いのだが、それはある意味では、「まさにこの映画が現実に影響を及ぼした証」とも捉えられるだろう。
別に私は、「映画」というメディアに対して常にそのような影響力を求めているつもりはない。しかし、「自分が作りたいと思う作品を完成させた」その結果として社会が正しい方向に動いてくれるというのは、とても素晴らしいことだろうと思う。
あわせて読みたい
【狂気】異質なホラー映画『みなに幸あれ』(古川琴音主演)は古い因習に似せた「社会の異様さ」を描く
古川琴音主演映画『みなに幸あれ』は、”シュールさ”さえ感じさせる「異質なホラー映画」だ。「村の因習」というよくあるパターンをベースに据えつつ、そこで展開される異様な状況が、実は「私たちが生きる世界」に対応しているという構成になっている。「お前の物語だからな」と終始突きつけられ続ける作品だ
ちなみに、「韓国は酷いことをしているなー」と対岸の火事のように感じている人は、少し足元を見たほうがいいかもしれない。日本も同じようなことをしているからだ。高校生にではなく、外国人労働者に対してだが。
映画の内容からは少しズレるので詳しくは触れないが、日本には「外国人技能実習制度」と呼ばれる仕組みがある。国が行っている、「表向き」の理由がちゃんと存在する制度なのだが、現実には「移民を受け入れずに外国人の労働力を確保するための仕組み」でしかない。そしてこの「外国人技能実習制度」について知れば知るほど、韓国の高校生が置かれているのと大差ない現実に驚かされることになるだろうと思う。
以前読んだ、『人生格差はこれで決まる 働き方の損益分岐点』(木暮太一)という本に、こんな文章がある。
しかし本来、資本主義経済のなかで働くということは、(法律の範囲内で)ギリギリまで働かされることを意味します。
程度の差はあれ、資本主義経済のなかで生きる企業は、みな元来「ブラック」なのです。
あわせて読みたい
【絶望】杉咲花主演映画『市子』の衝撃。毎日がしんどい「どん底の人生」を生き延びるための壮絶な決断…
映画『市子』はまず何よりも主演を務めた杉咲花に圧倒させられる作品だ。そしてその上で、主人公・川辺市子を巡る物語にあれこれと考えさせられてしまった。「川辺市子」は決してフィクショナルな存在ではなく、現実に存在し得る。本作は、そのような存在をリアルに想像するきっかけにもなるだろう
「マルクスの『資本論』をベースに考えれば、企業はすべて『ブラック』になって当然だ」と主張しているのだ。だからこそ、企業を適正に縛り付ける「法律」が必要とされるのであり、その「法律」を正しく守らせなければならないのである。
そうでなければ、「企業」はいつでも「化け物」に変貌出来てしまうというわけだ。
映画『あしたの少女』の内容紹介
キム・ソヒは、通っている近所のダンスクラブで「一番上手い」と褒められるのだが、それでも夜、誰もいなくなった練習場で、スマホで自撮りしながら延々とダンスの練習を続けるような女の子だ。映画の冒頭は、このダンスのシーンから始まる。
あわせて読みたい
【表現】映画『名付けようのない踊り』で初めて見た田中泯のダンス。「芸術以前」を志向する圧倒的パワー
映画『名付けようのない踊り』の中で田中泯は言う。「私」や「個性」を表現することには違和感がある、と。「踊りのために身体を作る」のではなく、「野良仕事で出来た身体で踊る」のだ、と。芸術になる前の踊りを探したい、と。「唯一無二の表現者」の生涯と現在地を映し出すドキュメンタリー
そんなソヒは高校の実習先が決まり、大手企業の下請けであるコールセンターで働くことになった。1つ上の先輩で、実習先が工場であるテジュンの元へ向かった彼女は、「明日からOLになる」と彼に伝える。同じダンスクラブに通っていた仲間であり、その嬉しさを伝えたかったのだ。彼女は期待を胸に、実習先であるコールセンターへと向かう。

しかし、その業務はかなり辛いものだった。解約を希望して電話をしてくる客を無理やりにでも引き留めることが求められていたからだ。「解約阻止率」が「成績」とみなされ、チーム内の成績が日々壁に張り出されていく。また、5つあるチーム同士でも競わされており、チーム全体の成績が下がっても上司からどやされてしまうのだ。ソヒは「今ならこんなキャンペーンをやっています」と望んでもないキャンペーンを勧めたり、「高額な違約金が掛かります」と脅したりするような仕事にどうにも馴染めず、チーム長から発破をかけられることも多かった。
仕事の辛さから「辞めたい」と感じることも増えてきたが、担任からは「絶対に辞めるなよ」と言われるし、良い会社で働いていると考えている両親にも話せないままだ。仕事の忙しさの合間を縫うようにして仲の良い友人と会う機会もあるのだが、仕事の疲れやイライラから些細なことで言い争い、険悪な雰囲気になってしまうこともあった。
あわせて読みたい
【驚愕】あるジャーナリストの衝撃の実話を描く映画『凶悪』。「死刑囚の告発」から「正義」を考える物語
獄中の死刑囚が警察に明かしていない事件を雑誌記者に告発し、「先生」と呼ばれる人物を追い詰めた実際の出来事を描くノンフィクションを原作にして、「ジャーナリズムとは?」「家族とは?」を問う映画『凶悪』は、原作とセットでとにかく凄まじい作品だ
そんなある日、ソヒは信じがたい光景を目撃し、想像もしなかった状況に動揺する。そしてこの出来事をきっかけに、人間としての感情が欠落してしまったのか、それ以降彼女はチーム内でも抜群の成績を残すようになっていく。
しかし給料の支払いに関してチーム長と揉めてしまい……。
その後、女刑事が「事件」の捜査に乗り出していく。
映画『あしたの少女』の感想
あわせて読みたい
【感想】是枝裕和映画『ベイビー・ブローカー』は、「赤ちゃんポスト」を起点に「正義とは何か」を描く
韓国に多数存在するという「赤ちゃんポスト」を題材にした是枝裕和監督映画『ベイビー・ブローカー』は、「正義とは何か」を問いかける。「中絶はOKで、捨てるのはNG」という判断は不合理だし、「最も弱い関係者が救われる」ことが「正義」だと私は思う
映画『あしたの少女』の主演は、是枝裕和監督作『ベイビー・ブローカー』にも出演していたペ・ドゥナである。しかし冒頭からしばらくの間、ペ・ドゥナはほとんどと言っていいくらい出てこない。一般的な映画とは違って、この映画は前後半でかなりくっきりと物語が分かれる作品だと言える。主演が後半になってからでないと出てこないというのは、なかなか珍しい構成ではないかと思う。
また、先程も少し触れたが、他の作品と異なる特徴として、「様々な事柄が投げっぱなしのまま終わる」という点が挙げられる。というか、「分からない部分を想像では埋めなかった」と言った方が正確かもしれない。
一般的に「実話を基にした作品」を作る場合、普通はそこに「創作」が入り込むことになる。「物語的に改変した方が面白くなるから」という理由ももちろんあるだろうが、他にも「『調べても絶対に分からないこと』は創作によって埋めるしかない」という事情もあるだろう。例えば、その実話に関わる人物が既に亡くなっている場合、その人物が当時どのように感じていたのかや、記録が存在しない場所でどんな行動を取っていたのかなどは、やはりどれだけ調べようが空白として残ってしまう。そして、そういう部分を創作で埋めているからこそ、「実話を”基に”している」という表記になるわけだ。
しかし映画『あしたの少女』では、「分からない部分を『創作』で埋める」ことをせずに制作しようと努力したのではないかと感じた。公式HPによると、映画後半の女刑事視点の物語は監督による創作らしいが、わざわざそう記載するということは、前半のキム・ソヒの物語はかなり事実に忠実だと捉えてもいいのではないかと思う。確かに観ている限り、「客観的な事実の積み重ねで描写できそうなシーン」がほとんどであるように感じられた。
あわせて読みたい
【真実】田原総一朗✕小泉純一郎!福島原発事故後を生きる我々が知るべき自然エネルギーの可能性:映画『…
田原総一朗が元総理・小泉純一郎にタブー無しで斬り込む映画『放送不可能。「原発、全部ウソだった」』は、「原発推進派だった自分は間違っていたし、騙されていた」と語る小泉純一郎の姿勢が印象的だった。脱原発に舵を切った小泉純一郎が、原発政策のウソに斬り込み、再生可能エネルギーの未来を語る
そしてだからこそ、「『想像で埋めなければならないはずの空白』がそのまま残っている」という事実に、違和感を覚えたのかもしれない。というか、そういう構成だったからこそ、「実話を基にした物語」のような表記が映画冒頭になかったにも拘らず、「きっとこれは実話を基にしているのだろう」と感じられたのだと思う。

恐らくこのようなスタンスになったのも、「事件」が一段落ついたという状態に達していなかったが故だろう。一定の評価なり捉えられ方なりが定まった状況に対してであれば、改変や創作の余地もあるだろうと思う。しかしこの映画を制作した時点では、そもそも問題そのものが広く知られてさえいない状態だった。だから、「フィクション」という形を取りながら、出来るだけ「ドキュメンタリー」に近いような作品を目指し、「まずは事実を届かせる」という点に注力しようとしたのではないだろうか。
そのような思惑で映画を作ったのだとしたら、まさにそれは見事な形で実を結んだと言っていいと思う。また、なかなか感じられないような「不穏さ」を残した造りにしたことで、なんとも言い難い強い印象を残す作品に仕上がったと言ってもいいだろう。さらに、ペ・ドゥナが登場する後半は、「真相の解明」よりも「無力感の共有」に焦点が当てられているように思えるし、そこには「どうかこの事実が多くの人の目に触れてほしい」という監督の強い想いが込められているようにも感じられた。
あわせて読みたい
【絶望】映画『少年たちの時代革命』が描く、香港デモの最中に自殺者を救おうとした若者たちの奮闘
香港の民主化運動の陰で、自殺者を救出しようと立ち上がったボランティア捜索隊が人知れず存在していた。映画『少年たちの時代革命』はそんな実話を基にしており、若者の自殺が急増した香港に様々な葛藤を抱えながら暮らし続ける若者たちのリアルが切り取られる作品だ
さて、1つだけ不満を挙げるとするなら、ペ・ドゥナ演じる女刑事の背景がもう少し伝わる何かがあればよかったと思う。今触れた通り、女刑事のパートは「無力感の共有」こそが目的だと思うので、だからこそ「何故彼女はこの『事件』に執着したのか」という描写がある方が良かった気がする。少なくとも私が観た限りにおいては、彼女がそのような強い動機を抱く背景を理解することは出来なかった。
作中では、「元々事務職として勤務していたが、最近異動で刑事課に移ってきた」「休暇が明けてすぐに担当した『事件』である」「休暇の理由には恐らく、彼女の母親が何らかの形で関係している」みたいなことは示唆される。しかしそれ以上には、彼女自身の背景は描かれない。それでいて彼女は、刑事課に移ってきたばかりにも拘らず、上司の反対を押し切ってまでこの「事件」の捜査にこだわるのだ。
138分というなかなかの長尺の作品であり、女刑事の背景を描く余裕はなかったのかもしれないが、気になる要素をいくつか置き去りにしたまま物語が閉じてしまったので、そこは少し気になった。キム・ソヒについては「空白を想像で埋める」ことを避ける意図があったと理解できるが、女刑事のパートはそもそもが創作なのだから、もう少し突っ込んだ描写があっても良かったように思う。
いくつかどうでもいい話を
あわせて読みたい
【感想】是枝裕和監督映画『怪物』(坂元裕二脚本)が抉る、「『何もしないこと』が生む加害性」
坂元裕二脚本、是枝裕和監督の映画『怪物』は、3つの視点を通して描かれる「日常の何気ない光景」に、思いがけない「加害性」が潜んでいることを炙り出す物語だ。これは間違いなく、私たち自身に関わる話であり、むしろ「自分には関係ない」と考えている人こそが自覚すべき問題だと思う
さて最後に、本筋とはまったく関係のない、どうでもいい話をして終わりにしよう。
まず、私としては大変珍しいことなのだが、ペ・ドゥナの顔がとても好みだなと感じる。普段私は、異性かどうかに限らず、「顔が好みかどうか」みたいな判断をあまりしない。もちろん、「綺麗だ」「可愛い」みたいに思うことはいくらでもあるのだけれど、「顔が好みだ」と感じることはほとんどないのだ。私が今思い出せる範囲では、「顔が好み」と感じる相手は、ペ・ドゥナ、サリー・ホーキンス、そして古川琴音だけである。
ペ・ドゥナのことは、『ベイビー・ブローカー』で初めてちゃんとその存在を認識したように思う。そして、『ベイビー・ブローカー』でも本作『あしたの少女』でも同様なのだが、私はどうも「一切笑わない、疲れ切ったようなペ・ドゥナの顔」がとても好きみたいだ。ネットでペ・ドゥナが笑っている写真を調べたりもしたが、どうもピンと来ない。無表情で生気が無いみたいに思える彼女の顔がとても良いなと思う。まあ、実にどうでもいい話だが。
さてもう1つ気になったのは、「高校生なのに、キム・ソヒたちが普通に酒を飲んでいること」である。調べてみると、韓国では19歳から酒を飲んでいいそうだが、それだと計算が合わないように思う。高校3年生だとしても、18歳が普通だろう。
あわせて読みたい
【衝撃】これが実話とは。映画『ウーマン・トーキング』が描く、性被害を受けた女性たちの凄まじい決断
映画『ウーマン・トーキング』の驚くべき点は、実話を基にしているという点だ。しかもその事件が起こったのは2000年代に入ってから。とある宗教コミュニティ内で起こった連続レイプ事件を機に村の女性たちがある決断を下す物語であり、そこに至るまでの「ある種異様な話し合い」が丁寧に描かれていく

しかしそう考えて、少し前に見たニュースのことを思い出した。韓国で、「年齢の数え方が変更された」というものだ。この映画は、年齢の数え方が変わる前の時代のことを描いているので、そう考えると辻褄が合う。
韓国での以前の年齢の数え方は、「生まれた年を1歳とし、1月1日になったら1歳年を取る」というものだった。例えば極端な話、12月31日に生まれた場合、生まれた瞬間に1歳、さらに翌日の1月1日に2歳になるという計算になる。生まれてからたった2日で2歳になってしまうのである。この場合、高校生で19歳になるという状況は自然なので、飲酒も可能なのだろう。
しかし最近韓国は、「現在の年度から出生年度を引いた数字を年齢とする」という、要するに日本と同じ年齢の数え方を採用した。私が見たニュースでは、「K-POPアイドルが2歳ぐらい若返る」みたいな話題として取り上げられていたはずだ。しかし、「酒が飲めるのは19歳から」というルールは変わらないらしいので、今後高校生の飲酒は認められなくなるのだろう。
あわせて読みたい
【絶望】人生どん底から生き方を変える。映画『シスター 夏のわかれ道』が描く中国人女性の葛藤と諦念
両親の死をきっかけに、「見知らぬ弟」を引き取らなければならなくなった女性を描く映画『シスター 夏のわかれ道』は、中国の特異な状況を背景にしつつ、誰もが抱き得る普遍的な葛藤が切り取られていく。現状を打破するために北京の大学院を目指す主人公は、一体どんな決断を下すのか。
あわせて読みたい
【全作品視聴済】私が観てきた映画(フィクション)を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が観てきた映画(フィクション)を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。
最後に
あわせて読みたい
【信念】9.11後、「命の値段」を計算した男がいた。映画『WORTH』が描く、その凄絶な2年間(主演:マイ…
9.11テロの後、「被害者の『命の値段』を算出した男」がいたことをご存知だろうか?映画『WORTH』では、「被害者遺族のために貢献したい」と無償で難題と向き合うも、その信念が正しく理解されずに反発や対立を招いてしまった現実が描かれる。実話を基にしているとは思えない、凄まじい物語だ
「新卒で一括採用し、社員のクビを簡単には切れず、終身雇用が当たり前」みたいな日本の雇用形態が「世界と比べておかしい」と批判されることがある。まあ、私もその捉え方に意義を唱えるつもりはない。しかし一方で、映画『あしたの少女』が示すように、雇用に関する制約を緩めれば緩めるほど、企業は法律の裏を掻い潜って自社の利益のために人間を酷使しようとすることもまた事実である。「競争原理を導入することで、優秀な人間が適切な労働環境で働けるようにする」という方向はもちろん間違っていないと思うが、やはり一定の制約は残しておかなければ、企業が「怪物」になるのを手助けするだけになってしまうだろう。
韓国の話ではないが、中国では若者の失業率がかなり高くなっており、先日見たテレビ番組では、16歳から24歳の失業率が50%に達しているのではないか、とも指摘されていた。「達しているのではないか」と何故断定できないのかと言えば、中国が失業率の公表を止めたからだ。都合の悪いことは隠したいのだろう。中国では「専業子ども」といって、「家事手伝いなどをすることで親から給料をもらう」みたいな形で「就職」する若者が増加しているという。中国に関しては「雇用の制約」ではなく「景気の問題」だと思うのでまた状況は異なるが、いずれにしても「失業率が高いこと」が国にとって喜ばしいことではないのは間違いないだろう。
あわせて読みたい
【衝撃】自ら立ち上げた「大分トリニータ」を放漫経営で潰したとされる溝畑宏の「真の実像」に迫る本:…
まったく何もないところからサッカーのクラブチーム「大分トリニータ」を立ち上げ、「県リーグから出発してチャンピオンになる」というJリーグ史上初の快挙を成し遂げた天才・溝畑宏を描く『爆走社長の天国と地獄』から、「正しく評価することの難しさ」について考える
企業の成長も大事だが、私は個人的に、「国民全員にそれなりに働き場所がある」ということも大事だと思っているし、やはりそのことが一定程度実現されるように雇用のルールが定められているべきだとも考えている。今後日本は、人口減少に伴って働き手が減る一方で、AIの導入によって不要とされる仕事も増えていくという、なかなか舵取りの難しい時代に入っていくはずだ。そういう中で、企業の自主性だけに任せるような仕組みにしてしまえば、また別の形で『あしたの少女』で描かれるような問題が生まれ得るだろう。
そうならないためにも、「雇用に関する制約をどのように設けるか」については慎重に制度設計される必要があると改めて感じさせられた。
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!「文章の書き方が分からない」「文章力がないから鍛えたい」という方にオススメ…
「文章の書き方」についてのKindle本を出版しました。「文章が書けない」「どう書いたらいいか分からない」「文章力を向上させたい」という方の悩みを解消できるような本に仕上げたつもりです。数多くの文章を書き、さらに頼まれて文章を推敲してきた経験を踏まえ、「文章を書けるようになるにはどうしたらいいか」についての私なりの考えをまとめました。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【絶望】映画『若き見知らぬ者たち』が描くのは”不正解”だが、「じゃあ”正解”って何?」ってなる(監督…
映画『若き見知らぬ者たち』は、「まともな生活が送れなくなった母親の介護」を筆頭に、かなり絶望的な状況に置かれている若者たちを描き出す作品だ。あまりにも不毛で、あまりにも救いがなく、あまりにも辛すぎるその日々は、ついに限界を迎える。そしてその絶望を、磯村勇斗がその凄まじい存在感によって体現していく
あわせて読みたい
【葛藤】映画『きみの色』(山田尚子)は、感受性が強すぎる若者のリアルをバンドを通じて描き出す(主…
山田尚子監督作『きみの色』は、これといった起伏のないストーリー展開でありながら、「若い世代の繊細さに満ちた人間関係」をとてもリアルに描き出す雰囲気が素敵な作品。「悩み・葛藤を抱えている状態が日常である」という雰囲気をベースにしつつ、「音楽」を起点に偶然繋がった3人の緩やかな日々を描き出す物語に惹きつけられた
あわせて読みたい
【面白い】映画『ラストマイル』は、物流問題をベースに「起こり得るリアル」をポップに突きつける(監…
映画『ラストマイル』は、「物流」という「ネット社会では誰にでも関係し得る社会問題」に斬り込みながら、実に軽妙でポップな雰囲気で展開されるエンタメ作品である。『アンナチュラル』『MIU404』と同じ世界で展開される「シェアード・ユニバース」も話題で、様々な人の関心を広く喚起する作品と言えるだろう
あわせて読みたい
【孤独】映画『ナミビアの砂漠』は、自由だが居場所がない主人公を演じる河合優実の存在感が圧倒的(監…
映画『ナミビアの砂漠』は、とにかく「河合優実が凄まじい」のひと言に尽きる作品だ。彼女が演じたカナという主人公の「捉えどころの無さ」は絶妙で、一見すると凄まじく「自由」に羽ばたいている感じなのに、実際には全然「自由」には見えないというバランスが見事だった。特段の物語はないのに、137分間惹きつけられてしまうだろう
あわせて読みたい
【あらすじ】老夫婦の”穏やかな日常”から核戦争の恐怖を描くアニメ映画『風が吹くとき』の衝撃
一軒家の中だけで展開される老夫婦の日常から「核戦争」の危機をリアルに描き出す映画『風が吹くとき』は、日本では1987年に公開された作品なのだが、今まさに観るべき作品ではないかと。世界的に「核戦争」の可能性が高まっているし、また「いつ起こるか分からない巨大地震」と読み替えても成立する作品で、実に興味深かった
あわせて読みたい
【感想】映画『夜明けのすべて』は、「ままならなさ」を抱えて生きるすべての人に優しく寄り添う(監督…
映画『夜明けのすべて』は、「PMS」や「パニック障害」を通じて、「自分のものなのに、心・身体が思い通りにならない」という「ままならなさ」を描き出していく。決して他人事ではないし、「私たちもいつそのような状況に置かれるか分からない」という気持ちで観るのがいいでしょう。物語の起伏がないのに惹きつけられる素敵な作品です
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『52ヘルツのクジラたち』の「無音で叫ぶ人」と「耳を澄ます人」の絶妙な響鳴(原作:…
映画『52ヘルツのクジラたち』は、「現代的な問題のごった煮」と感じられてしまうような”過剰さ”に溢れてはいますが、タイトルが作品全体を絶妙に上手くまとめていて良かったなと思います。主演の杉咲花がやはり見事で、身体の内側から「不幸」が滲み出ているような演技には圧倒されてしまいました
あわせて読みたい
【赦し】映画『過去負う者』が描く「元犯罪者の更生」から、社会による排除が再犯を生む現実を知る
映画『過去負う者』は、冒頭で「フィクション」だと明示されるにも拘らず、観ながら何度も「ドキュメンタリーだっけ?」と感じさせられるという、実に特異な体験をさせられた作品である。実在する「元犯罪者の更生を支援する団体」を舞台にした物語で、当然それは、私たち一般市民にも無関係ではない話なのだ
あわせて読みたい
【挑戦】映画『燃えあがる女性記者たち』が描く、インドカースト最下位・ダリットの女性による報道
映画『燃えあがる女性記者たち』は、インドで「カースト外の不可触民」として扱われるダリットの女性たちが立ち上げた新聞社「カバル・ラハリヤ」を取り上げる。自身の境遇に抗って、辛い状況にいる人の声を届けたり権力者を糾弾したりする彼女たちの奮闘ぶりが、インドの民主主義を変革させるかもしれない
あわせて読みたい
【実話】田舎暮らし失敗。映画『理想郷』が描く、めんどくさい人間関係が嫌がらせに発展した事件
実話を基にした映画『理想郷』は、「理想の田舎暮らし」が粉微塵に粉砕されていく過程を描く物語である。第一義的には当然、夫妻に嫌がらせを続ける兄弟が悪いのだが、しかしそのように捉えるだけでは何も変わらないだろう。双方の譲れない「価値観」が否応なしに正面衝突する状況で、一体何が「正解」となり得るだろうか?
あわせて読みたい
【驚愕】映画『リアリティ』の衝撃。FBIによる、機密情報をリークした女性の尋問音源を完全再現(リアリ…
映画『リアリティ』は、恐らく過去類を見ないだろう構成の作品だ。なんと、「FBI捜査官が録音していた実際の音声データのやり取りを一言一句完全に再現した映画」なのである。「第2のスノーデン」とも評される”普通の女性”は、一体何故、国家に反旗を翻す”反逆者”になったのだろうか?
あわせて読みたい
【狂気】異質なホラー映画『みなに幸あれ』(古川琴音主演)は古い因習に似せた「社会の異様さ」を描く
古川琴音主演映画『みなに幸あれ』は、”シュールさ”さえ感じさせる「異質なホラー映画」だ。「村の因習」というよくあるパターンをベースに据えつつ、そこで展開される異様な状況が、実は「私たちが生きる世界」に対応しているという構成になっている。「お前の物語だからな」と終始突きつけられ続ける作品だ
あわせて読みたい
【実話】英国王室衝撃!映画『ロスト・キング』が描く、一般人がリチャード3世の遺骨を発見した話(主演…
500年前に亡くなった王・リチャード3世の遺骨を、一介の会社員女性が発見した。映画『ロスト・キング』は、そんな実話を基にした凄まじい物語である。「リチャード3世の悪評を覆したい!」という動機だけで遺骨探しに邁進する「最強の推し活」は、最終的に英国王室までをも動かした!
あわせて読みたい
【絶望】杉咲花主演映画『市子』の衝撃。毎日がしんどい「どん底の人生」を生き延びるための壮絶な決断…
映画『市子』はまず何よりも主演を務めた杉咲花に圧倒させられる作品だ。そしてその上で、主人公・川辺市子を巡る物語にあれこれと考えさせられてしまった。「川辺市子」は決してフィクショナルな存在ではなく、現実に存在し得る。本作は、そのような存在をリアルに想像するきっかけにもなるだろう
あわせて読みたい
【感想】映画『キリエのうた』(岩井俊二)はアイナ・ジ・エンドに圧倒されっ放しの3時間だった(出演:…
映画『キリエのうた』(岩井俊二監督)では、とにかくアイナ・ジ・エンドに圧倒されてしまった。歌声はもちろんのことながら、ただそこにいるだけで場を支配するような存在感も凄まじい。全編に渡り「『仕方ないこと』はどうしようもなく起こるんだ」というメッセージに溢れた、とても力強い作品だ
あわせて読みたい
【現実】我々が食べてる魚は奴隷船が獲ったもの?映画『ゴースト・フリート』が描く驚くべき漁業の問題
私たちは、「奴隷」が獲った魚を食べているのかもしれない。映画『ゴースト・フリート』が描くのは、「拉致され、数十年も遠洋船上に隔離されながら漁をさせられている奴隷」の存在だ。本作は、その信じがたい現実に挑む女性活動家を追うドキュメンタリー映画であり、まさに世界が関心を持つべき問題だと思う
あわせて読みたい
【絶望】人生どん底から生き方を変える。映画『シスター 夏のわかれ道』が描く中国人女性の葛藤と諦念
両親の死をきっかけに、「見知らぬ弟」を引き取らなければならなくなった女性を描く映画『シスター 夏のわかれ道』は、中国の特異な状況を背景にしつつ、誰もが抱き得る普遍的な葛藤が切り取られていく。現状を打破するために北京の大学院を目指す主人公は、一体どんな決断を下すのか。
あわせて読みたい
【絶望】映画『少年たちの時代革命』が描く、香港デモの最中に自殺者を救おうとした若者たちの奮闘
香港の民主化運動の陰で、自殺者を救出しようと立ち上がったボランティア捜索隊が人知れず存在していた。映画『少年たちの時代革命』はそんな実話を基にしており、若者の自殺が急増した香港に様々な葛藤を抱えながら暮らし続ける若者たちのリアルが切り取られる作品だ
あわせて読みたい
【闘争】映画『あのこと』が描く、中絶が禁止だった時代と、望まぬ妊娠における圧倒的な「男の不在」
中絶が禁止されていた1960年代のフランスを舞台にした映画『あのこと』は、「望まぬ妊娠」をしてしまった秀才の大学生が、「未来を諦めない」ために中絶を目指す姿が描かれる。さらに、誰にも言えずに孤独に奮闘する彼女の姿が「男の不在」を強調する物語でもあり、まさに男が観るべき作品だ
あわせて読みたい
【衝撃】「きのくに子どもの村学園」に密着する映画『夢見る小学校』は、「義務教育」の概念を破壊する…
驚きの教育方針を有する私立小学校「きのくに子どもの村学園」に密着する映画『夢見る小学校』と、「日本の教育にはほとんどルールが無い」ことを示す特徴的な公立校を取り上げる映画『夢見る公立校長先生』を観ると、教育に対する印象が変わる。「改革を妨げる保護者」にならないためにも観るべき作品だ
あわせて読みたい
【信念】9.11後、「命の値段」を計算した男がいた。映画『WORTH』が描く、その凄絶な2年間(主演:マイ…
9.11テロの後、「被害者の『命の値段』を算出した男」がいたことをご存知だろうか?映画『WORTH』では、「被害者遺族のために貢献したい」と無償で難題と向き合うも、その信念が正しく理解されずに反発や対立を招いてしまった現実が描かれる。実話を基にしているとは思えない、凄まじい物語だ
あわせて読みたい
【デモ】クーデター後の軍事政権下のミャンマー。ドキュメンタリーさえ撮れない治安の中での映画制作:…
ベルリン国際映画祭でドキュメンタリー賞を受賞したミャンマー映画『ミャンマー・ダイアリーズ』はしかし、後半になればなるほどフィクショナルな映像が多くなる。クーデター後、映画制作が禁じられたミャンマーで、10人の”匿名”監督が死を賭して撮影した映像に込められた凄まじいリアルとは?
あわせて読みたい
【真実】田原総一朗✕小泉純一郎!福島原発事故後を生きる我々が知るべき自然エネルギーの可能性:映画『…
田原総一朗が元総理・小泉純一郎にタブー無しで斬り込む映画『放送不可能。「原発、全部ウソだった」』は、「原発推進派だった自分は間違っていたし、騙されていた」と語る小泉純一郎の姿勢が印象的だった。脱原発に舵を切った小泉純一郎が、原発政策のウソに斬り込み、再生可能エネルギーの未来を語る
あわせて読みたい
【悲劇】大川小学校はなぜ津波被害に遭ったのか?映画『生きる』が抉る現実と国家賠償請求の虚しさ
東日本大震災において、児童74人、教職員10人死亡という甚大な津波被害を生んだ大川小学校。その被害者遺族が真相究明のために奮闘する姿を追うドキュメンタリー映画『生きる』では、学校の酷い対応、出来れば避けたかった訴訟、下された画期的判決などが描かれ、様々な問題が提起される
あわせて読みたい
【理解】「多様性を受け入れる」とか言ってるヤツ、映画『炎上する君』でも観て「何も見てない」って知…
西加奈子の同名小説を原作とした映画『炎上する君』(ふくだももこ監督)は、「多様性」という言葉を安易に使いがちな世の中を挑発するような作品だ。「見えない存在」を「過剰に装飾」しなければならない現実と、マジョリティが無意識的にマイノリティを「削る」リアルを描き出していく
あわせて読みたい
【映画】『戦場記者』須賀川拓が、ニュースに乗らない中東・ウクライナの現実と報道の限界を切り取る
TBS所属の特派員・須賀川拓は、ロンドンを拠点に各国の取材を行っている。映画『戦場記者』は、そんな彼が中東を取材した映像をまとめたドキュメンタリーだ。ハマスを巡って食い違うガザ地区とイスラエル、ウクライナ侵攻直後に現地入りした際の様子、アフガニスタンの壮絶な薬物中毒の現実を映し出す
あわせて読みたい
【歴史】NIKEのエアジョーダン誕生秘話!映画『AIR/エア』が描くソニー・ヴァッカロの凄さ
ナイキがマイケル・ジョーダンと契約した時、ナイキは「バッシュ業界3位」であり、マイケル・ジョーダンも「ドラフト3位選手」だった。今からは信じられないだろう。映画『AIR/エア』は、「劣勢だったナイキが、いかにエアジョーダンを生み出したか」を描く、実話を基にした凄まじい物語だ
あわせて読みたい
【感想】是枝裕和監督映画『怪物』(坂元裕二脚本)が抉る、「『何もしないこと』が生む加害性」
坂元裕二脚本、是枝裕和監督の映画『怪物』は、3つの視点を通して描かれる「日常の何気ない光景」に、思いがけない「加害性」が潜んでいることを炙り出す物語だ。これは間違いなく、私たち自身に関わる話であり、むしろ「自分には関係ない」と考えている人こそが自覚すべき問題だと思う
あわせて読みたい
【衝撃】これが実話とは。映画『ウーマン・トーキング』が描く、性被害を受けた女性たちの凄まじい決断
映画『ウーマン・トーキング』の驚くべき点は、実話を基にしているという点だ。しかもその事件が起こったのは2000年代に入ってから。とある宗教コミュニティ内で起こった連続レイプ事件を機に村の女性たちがある決断を下す物語であり、そこに至るまでの「ある種異様な話し合い」が丁寧に描かれていく
あわせて読みたい
【異常】韓国衝撃の実話を映画化。『空気殺人』が描く、加湿器の恐怖と解決に至るまでの超ウルトラC
2011年に韓国で実際に起こった「加湿器殺菌剤による殺人事件」をモデルにした映画『空気殺人』は、金儲け主義の醜悪さが詰まった作品だ。国がその安全を保証し、17年間も販売され続けた国民的ブランドは、「水俣病」にも匹敵する凄まじい健康被害をもたらした
あわせて読みたい
【性加害】映画『SHE SAID その名を暴け』を観てくれ。#MeToo運動を生んだ報道の舞台裏(出演:キャリ…
「#MeToo」運動のきっかけとなった、ハリウッドの絶対権力者ハーヴェイ・ワインスタインを告発するニューヨーク・タイムズの記事。その取材を担った2人の女性記者の奮闘を描く映画『SHE SAID その名を暴け』は、ジャニー喜多川の性加害問題で揺れる今、絶対に観るべき映画だと思う
あわせて読みたい
【あらすじ】塩田武士『罪の声』が放つ、戦後最大の未解決事件「グリコ・森永事件」の圧倒的”リアル感”
戦後最大の未解決事件である「グリコ・森永事件」では、脅迫に子どもの声が使われていた。私はその事実を、塩田武士『罪の声』という小説を読むまで知らなかった。では、続く疑問はこうだろう。その子どもたちは、今どこでどんな風に生きているのか?その疑問に答える、凄まじい小説だ。
あわせて読みたい
【生還】内戦下のシリアでISISに拘束された男の実話を基にした映画『ある人質』が描く壮絶すぎる現実
実話を基にした映画『ある人質 生還までの398日』は、内戦下のシリアでISISに拘束された男の壮絶な日々が描かれる。「テロリストとは交渉しない」という方針を徹底して貫くデンマーク政府のスタンスに翻弄されつつも、救出のために家族が懸命に奮闘する物語に圧倒される
あわせて読みたい
【おすすめ】柚月裕子『慈雨』は、「守るべきもの」と「過去の過ち」の狭間の葛藤から「正義」を考える小説
柚月裕子の小説『慈雨』は、「文庫X」として知られる『殺人犯はそこにいる』で扱われている事件を下敷きにしていると思われる。主人公の元刑事が「16年前に犯してしまったかもしれない過ち」について抱き続けている葛藤にいかに向き合い、どう決断し行動に移すのかの物語
あわせて読みたい
【実話】ポートアーサー銃乱射事件を扱う映画『ニトラム』が示す、犯罪への傾倒に抗えない人生の不条理
オーストラリアで実際に起こった銃乱射事件の犯人の生い立ちを描く映画『ニトラム/NITRAM』は、「頼むから何も起こらないでくれ」と願ってしまうほどの異様な不穏さに満ちている。「社会に順応できない人間」を社会がどう受け入れるべきかについて改めて考えさせる作品だ
あわせて読みたい
【衝撃】匿名監督によるドキュメンタリー映画『理大囲城』は、香港デモ最大の衝撃である籠城戦の内部を映す
香港民主化デモにおける最大の衝撃を内側から描く映画『理大囲城』は、とんでもないドキュメンタリー映画だった。香港理工大学での13日間に渡る籠城戦のリアルを、デモ隊と共に残って撮影し続けた匿名監督たちによる映像は、ギリギリの判断を迫られる若者たちの壮絶な現実を映し出す
あわせて読みたい
【解説】実話を基にした映画『シカゴ7裁判』で知る、「権力の暴走」と、それに正面から立ち向かう爽快さ
ベトナム戦争に反対する若者たちによるデモと、その後開かれた裁判の実話を描く『シカゴ7裁判』はメチャクチャ面白い映画だった。無理筋の起訴を押し付けられる主席検事、常軌を逸した言動を繰り返す不適格な判事、そして一枚岩にはなれない被告人たち。魅力満載の1本だ
あわせて読みたい
【執念】「桶川ストーカー事件」で警察とマスコミの怠慢を暴き、社会を動かした清水潔の凄まじい取材:…
『殺人犯はそこにいる』(文庫X)で凄まじい巨悪を暴いた清水潔は、それよりずっと以前、週刊誌記者時代にも「桶川ストーカー殺人事件」で壮絶な取材を行っていた。著者の奮闘を契機に「ストーカー規制法」が制定されたほどの事件は、何故起こり、どんな問題を喚起したのか
あわせて読みたい
【狂気】アメリカの衝撃の実態。民営刑務所に刑務官として潜入した著者のレポートは国をも動かした:『…
アメリカには「民営刑務所」が存在する。取材のためにその1つに刑務官として潜入した著者が記した『アメリカン・プリズン』は信じがたい描写に溢れた1冊だ。あまりに非人道的な行いがまかり通る狂気の世界と、「民営刑務所」が誕生した歴史的背景を描き出すノンフィクション
あわせて読みたい
【驚愕】一般人スパイが北朝鮮に潜入する映画『THE MOLE』はとてつもないドキュメンタリー映画
映画『THE MOLE』は、「ホントにドキュメンタリーなのか?」と疑いたくなるような衝撃映像満載の作品だ。「『元料理人のデンマーク人』が勝手に北朝鮮に潜入する」というスタートも謎なら、諜報経験も軍属経験もない男が北朝鮮の秘密をバンバン解き明かす展開も謎すぎる。ヤバい
あわせて読みたい
【奇跡】信念を貫いた男が国の制度を変えた。特別養子縁組を実現させた石巻の産婦人科医の執念:『赤ち…
遊郭で生まれ育った石巻の医師が声を上げ、あらゆる障害をなぎ倒して前進したお陰で「特別養子縁組」の制度が実現した。そんな産婦人科医・菊田昇の生涯を描き出す小説『赤ちゃんをわが子として育てる方を求む』には、法を犯してでも信念を貫いた男の衝撃の人生が描かれている
あわせて読みたい
【差別】映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』の衝撃。プーチンが支持する国の蛮行・LGBT狩り
プーチン大統領の後ろ盾を得て独裁を維持しているチェチェン共和国。その国で「ゲイ狩り」と呼ぶしかない異常事態が継続している。映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』は、そんな現実を命がけで映し出し、「現代版ホロコースト」に立ち向かう支援団体の奮闘も描く作品
あわせて読みたい
【異次元】『ハイパーハードボイルドグルメリポート』は本も読め。衝撃すぎるドキュメンタリーだぞ
テレビ東京の上出遼平が作る、“異次元のグルメ番組”である「ハイパーハードボイルドグルメリポート」の書籍化。映像からも異様さが伝わる「激ヤバ地」に赴き、そこに住む者と同じモノを食べるという狂気が凄まじい。私がテレビで見た「ケニアのゴミ山の少年」の話は衝撃的だった
あわせて読みたい
【あらすじ】死刑囚を救い出す実話を基にした映画『黒い司法』が指摘する、死刑制度の問題と黒人差別の現実
アメリカで死刑囚の支援を行う団体を立ち上げた若者の実話を基にした映画『黒い司法 0%からの奇跡』は、「死刑制度」の存在価値について考えさせる。上映後のトークイベントで、アメリカにおける「死刑制度」と「黒人差別」の結びつきを知り、一層驚かされた
あわせて読みたい
【実話】台湾のろう学校のいじめ・性的虐待事件を描く映画『無聲』が問う、あまりに悲しい現実
台湾のろう学校で実際に起こったいじめ・性的虐待事件を基に作られた映画『無聲』は、健常者の世界に刃を突きつける物語だ。これが実話だという事実に驚かされる。いじめ・性的虐待が物語の「大前提」でしかないという衝撃と、「性的虐待の方がマシ」という選択を躊躇せず行う少女のあまりの絶望を描き出す
あわせて読みたい
【証言】ナチスドイツでヒトラーに次ぐナンバー2だったゲッベルス。その秘書だった女性が歴史を語る映画…
ナチスドイツナンバー2だった宣伝大臣ゲッベルス。その秘書だったブルンヒルデ・ポムゼルが103歳の時にカメラの前で当時を語った映画『ゲッベルスと私』には、「愚かなことをしたが、避け難かった」という彼女の悔恨と教訓が含まれている。私たちは彼女の言葉を真摯に受け止めなければならない
あわせて読みたい
【事件】デュポン社のテフロン加工が有害だと示した男の執念の実話を描く映画『ダーク・ウォーターズ』
世界的大企業デュポン社が、自社製品「テフロン」の危険性を40年以上前に把握しながら公表せず、莫大な利益を上げてきた事件の真相を暴き出した1人の弁護士がいる。映画『ダーク・ウォーターズ』は、大企業相手に闘いを挑み、住民と正義のために走り続けた実在の人物の勇敢さを描き出す
あわせて読みたい
【現実】権力を乱用する中国ナチスへの抵抗の最前線・香港の民主化デモを映す衝撃の映画『時代革命』
2019年に起こった、逃亡犯条例改正案への反対運動として始まった香港の民主化デモ。その最初期からデモ参加者たちの姿をカメラに収め続けた。映画『時代革命』は、最初から最後まで「衝撃映像」しかない凄まじい作品だ。この現実は決して、「対岸の火事」ではない
あわせて読みたい
【危機】災害時、「普通の人々」は冷静に、「エリート」はパニックになる。イメージを覆す災害学の知見…
地震やテロなどの大災害において、人々がどう行動するのかを研究する「災害学」。その知見が詰まった『災害ユートピア』は、ステレオタイプなイメージを一変させてくれる。有事の際には市民ではなくエリートこそが暴走する。そしてさらに、災害は様々な社会的な変化も促しもする
あわせて読みたい
【憤り】世界最強米海軍4人VS数百人のタリバン兵。死線を脱しただ1人生還を果たした奇跡の実話:『アフ…
アフガニスタンの山中で遭遇した羊飼いを見逃したことで、数百人のタリバン兵と死闘を繰り広げる羽目に陥った米軍最強部隊に所属する4人。奇跡的に生き残り生還を果たした著者が記す『アフガン、たった一人の生還』は、とても実話とは信じられない凄まじさに満ちている
あわせて読みたい
【病理】本田靖春が「吉展ちゃん事件」を追う。誘拐を捜査する警察のお粗末さと時代を反映する犯罪:『…
「戦後最大の誘拐事件」と言われ、警察の初歩的なミスなどにより事件解決に膨大な月日を要した「吉展ちゃん誘拐殺人事件」。その発端から捜査体制、顛末までをジャーナリスト・本田靖春が徹底した取材で描き出す『誘拐』は、「『犯罪』とは『社会の病理』である」と明確に示している
あわせて読みたい
【誇り】福島民友新聞の記者は、東日本大震災直後海に向かった。門田隆将が「新聞人の使命」を描く本:…
自身も東日本大震災の被災者でありながら、「紙齢をつなぐ」ために取材に奔走した福島民友新聞の記者の面々。『記者たちは海に向かった』では、取材中に命を落とした若手記者を中心に据え、葛藤・後悔・使命感などを描き出す。「新聞」という”モノ”に乗っかっている重みを実感できる1冊
あわせて読みたい
【衝撃】洗脳を自ら脱した著者の『カルト脱出記』から、「社会・集団の洗脳」を避ける生き方を知る
「聖書研究に熱心な日本人証人」として「エホバの証人」で活動しながら、その聖書研究をきっかけに自ら「洗脳」を脱した著者の体験を著した『カルト脱出記』。広い意味での「洗脳」は社会のそこかしこに蔓延っているからこそ、著者の体験を「他人事」だと無視することはできない
あわせて読みたい
【衝撃】権力の濫用、政治腐敗を描く映画『コレクティブ』は他人事じゃない。「国家の嘘」を監視せよ
火災で一命を取り留め入院していた患者が次々に死亡した原因が「表示の10倍に薄められた消毒液」だと暴き、国家の腐敗を追及した『ガゼタ』誌の奮闘を描く映画『コレクティブ 国家の嘘』は、「権力の監視」が機能しなくなった国家の成れの果てが映し出される衝撃作だ
あわせて読みたい
【信念】水俣病の真実を世界に伝えた写真家ユージン・スミスを描く映画。真実とは「痛みへの共感」だ:…
私はその存在をまったく知らなかったが、「水俣病」を「世界中が知る公害」にした報道写真家がいる。映画『MINAMATA―ミナマタ―』は、水俣病の真実を世界に伝えたユージン・スミスの知られざる生涯と、理不尽に立ち向かう多くの人々の奮闘を描き出す
あわせて読みたい
【日常】難民問題の現状をスマホで撮る映画。タリバンから死刑宣告を受けた監督が家族と逃避行:『ミッ…
アフガニスタンを追われた家族4人が、ヨーロッパまで5600kmの逃避行を3台のスマホで撮影した映画『ミッドナイト・トラベラー』は、「『難民の厳しい現実』を切り取った作品」ではない。「家族アルバム」のような「笑顔溢れる日々」が難民にもあるのだと想像させてくれる
あわせて読みたい
【衝撃】『殺人犯はそこにいる』が実話だとは。真犯人・ルパンを野放しにした警察・司法を信じられるか?
タイトルを伏せられた覆面本「文庫X」としても話題になった『殺人犯はそこにいる』。「北関東で起こったある事件の取材」が、「私たちが生きる社会の根底を揺るがす信じがたい事実」を焙り出すことになった衝撃の展開。まさか「司法が真犯人を野放しにする」なんてことが実際に起こるとは。大げさではなく、全国民必読の1冊だと思う
あわせて読みたい
【実話】「ホロコーストの映画」を観て改めて、「有事だから仕方ない」と言い訳しない人間でありたいと…
ノルウェーの警察が、自国在住のユダヤ人をまとめて船に乗せアウシュビッツへと送った衝撃の実話を元にした映画『ホロコーストの罪人』では、「自分はそんな愚かではない」と楽観してはいられない現実が映し出される。このような悲劇は、現在に至るまで幾度も起こっているのだ
あわせて読みたい
【実話】映画『アウシュビッツ・レポート』が描き出す驚愕の史実。世界はいかにホロコーストを知ったのか?
映画『アウシュヴィッツ・レポート』は、アウシュビッツ強制収容所から抜け出し、詳細な記録と共にホロコーストの実態を世界に明らかにした実話を基にした作品。2人が持ち出した「アウシュビッツ・レポート」こそが、ホロコーストについて世界が知るきっかけだったのであり、そんな史実をまったく知らなかったことにも驚かされた
あわせて読みたい
【悲哀】2度の東京オリンピックに翻弄された都営アパートから「公共の利益」と「個人の権利」を考える:…
1964年の東京オリンピックを機に建設された「都営霞ケ丘アパート」は、東京オリンピック2020を理由に解体が決まり、長年住み続けた高齢の住民に退去が告げられた。「公共の利益」と「個人の権利」の狭間で翻弄される人々の姿を淡々と映し出し、静かに「社会の在り方」を問う映画
あわせて読みたい
【凄絶】北朝鮮の”真実”を描くアニメ映画。強制収容所から決死の脱出を試みた者が語る驚愕の実態:『ト…
在日コリアン4世の監督が、北朝鮮脱北者への取材を元に作り上げた壮絶なアニメ映画『トゥルーノース』は、私たちがあまりに恐ろしい世界と地続きに生きていることを思い知らせてくれる。最低最悪の絶望を前に、人間はどれだけ悪虐になれてしまうのか、そしていかに優しさを発揮できるのか。
あわせて読みたい
【弾圧】香港デモの象徴的存在デニス・ホーの奮闘の歴史。注目の女性活動家は周庭だけじゃない:映画『…
日本で香港民主化運動が報じられる際は周庭さんが取り上げられることが多いが、香港には彼女よりも前に民主化運動の象徴的存在として認められた人物がいる。映画『デニス・ホー ビカミング・ザ・ソング』の主人公であるスター歌手の激動の人生を知る
あわせて読みたい
【認識】「固定観念」「思い込み」の外側に出るのは難しい。自分はどんな「へや」に囚われているのか:…
実際に起こった衝撃的な事件に着想を得て作られた映画『ルーム』は、フィクションだが、観客に「あなたも同じ状況にいるのではないか?」と突きつける力強さを持っている。「普通」「当たり前」という感覚に囚われて苦しむすべての人に、「何に気づけばいいか」を気づかせてくれる作品
あわせて読みたい
【感想】映画『野火』は、戦争の”虚しさ”をリアルに映し出す、後世に受け継がれるべき作品だ
「戦争の悲惨さ」は様々な形で描かれ、受け継がれてきたが、「戦争の虚しさ」を知る機会はなかなかない。映画『野火』は、第二次世界大戦中のフィリピンを舞台に、「敵が存在しない戦場で”人間の形”を保つ困難さ」を描き出す、「虚しさ」だけで構成された作品だ
あわせて読みたい
【残念】日本の「難民受け入れ」の現実に衝撃。こんな「恥ずべき国」に生きているのだと絶望させられる…
日本の「難民認定率」が他の先進国と比べて異常に低いことは知っていた。しかし、日本の「難民」を取り巻く実状がこれほど酷いものだとはまったく知らなかった。日本で育った2人のクルド人難民に焦点を当てる映画『東京クルド』から、日本に住む「難民」の現実を知る
あわせて読みたい
【実話】権力の濫用を監視するマスコミが「教会の暗部」を暴く映画『スポットライト』が現代社会を斬る
地方紙である「ボストン・グローブ紙」は、数多くの神父が長年に渡り子どもに対して性的虐待を行い、その事実を教会全体で隠蔽していたという衝撃の事実を明らかにした。彼らの奮闘の実話を映画化した『スポットライト』から、「権力の監視」の重要性を改めて理解する
あわせて読みたい
【不正義】正しく行使されない権力こそ真の”悪”である。我々はその現実にどう立ち向かうべきだろうか:…
権力を持つ者のタガが外れてしまえば、市民は為す術がない。そんな状況に置かれた時、私たちにはどんな選択肢があるだろうか?白人警官が黒人を脅して殺害した、50年前の実際の事件をモチーフにした映画『デトロイト』から、「権力による不正義」の恐ろしさを知る
あわせて読みたい
【驚愕】正義は、人間の尊厳を奪わずに貫かれるべきだ。独裁政権を打倒した韓国の民衆の奮闘を描く映画…
たった30年前の韓国で、これほど恐ろしい出来事が起こっていたとは。「正義の実現」のために苛烈な「スパイ狩り」を行う秘密警察の横暴をきっかけに民主化運動が激化し、独裁政権が打倒された史実を描く『1987、ある闘いの真実』から、「正義」について考える
あわせて読みたい
【葛藤】子どもが抱く「家族を捨てたい気持ち」は、母親の「家族を守りたい気持ち」の終着点かもしれな…
家族のややこしさは、家族の数だけ存在する。そのややこしさを、「子どもを守るために母親が父親を殺す」という極限状況を設定することで包括的に描き出そうとする映画『ひとよ』。「暴力」と「殺人犯の子どもというレッテル」のどちらの方が耐え難いと感じるだろうか?
あわせて読みたい
【勇敢】”報道”は被害者を生む。私たちも同罪だ。”批判”による”正義の実現”は正義だろうか?:『リチャ…
「爆弾事件の被害を最小限に食い止めた英雄」が、メディアの勇み足のせいで「爆弾事件の犯人」と報じられてしまった実話を元にした映画『リチャード・ジュエル』から、「他人を公然と批判する行為」の是非と、「再発防止という名の正義」のあり方について考える
あわせて読みたい
【真実?】佐村河内守のゴーストライター騒動に森達也が斬り込んだ『FAKE』は我々に何を問うか?
一時期メディアを騒がせた、佐村河内守の「ゴースト問題」に、森達也が斬り込む。「耳は聴こえないのか?」「作曲はできるのか?」という疑惑を様々な角度から追及しつつ、森達也らしく「事実とは何か?」を問いかける『FAKE』から、「事実の捉え方」について考える
あわせて読みたい
【告発】アメリカに”監視”される社会を暴露したスノーデンの苦悩と決断を映し出す映画:『スノーデン』…
NSA(アメリカ国家安全保障局)の最高機密にまでアクセスできたエドワード・スノーデンは、その機密情報を持ち出し内部告発を行った。「アメリカは世界中の通信を傍受している」と。『シチズンフォー』と『スノーデン』の2作品から、彼の告発内容とその葛藤を知る
あわせて読みたい
【危機】教員のセクハラは何故無くならない?資質だけではない、学校の構造的な問題も指摘する:『スク…
『スクールセクハラ なぜ教師のわいせつ犯罪は繰り返されるのか』では、自分が生徒に対して「権力」を持っているとは想像していなかったという教師が登場する。そしてこの「無自覚」は、学校以外の場でも起こりうる。特に男性は、読んで自分の振る舞いを見直すべきだ
あわせて読みたい
【絶望】「人生上手くいかない」と感じる時、彼を思い出してほしい。壮絶な過去を背負って生きる彼を:…
「北九州連続監禁殺人事件」という、マスコミも報道規制するほどの残虐事件。その「主犯の息子」として生きざるを得なかった男の壮絶な人生。「ザ・ノンフィクション」のプロデューサーが『人殺しの息子と呼ばれて』で改めて取り上げた「真摯な男」の生き様と覚悟
あわせて読みたい
【現実】東日本大震災発生時からの被災地の映像には、ニュースで見る「分かりやすさ」は微塵もない:『…
東日本大震災発生直後からカメラを回し、被災地の現実を切り取ってきたテレビ岩手。「分かりやすさ」が優先されるテレビではなかなか放送できないだろう映像を含め、「分かりにくい現実」を切り取った映像で構成する映画『たゆたえども沈まず』は静かな衝撃をもたらす作品
あわせて読みたい
【誠実】想像を超える辛い経験を言葉にするのは不可能だ。それを分かってなお筆を執った作家の震災記:…
旅行者として東日本大震災で被災した小説家・彩瀬まるは、『暗い夜、星を数えて 3.11被災鉄道からの脱出』でその体験を語る。「そんなこと、言わなければ分からない」と感じるような感情も包み隠さず記し、「絶望的な伝わらなさ」を感じながらも伝えようと奮闘する1冊
あわせて読みたい
【称賛】生き様がかっこいい。ムンバイのホテルのテロ事件で宿泊客を守り抜いたスタッフたち:映画『ホ…
インドの高級ホテルで実際に起こったテロ事件を元にした映画『ホテル・ムンバイ』。恐ろしいほどの臨場感で、当時の恐怖を観客に体感させる映画であり、だからこそ余計に、「逃げる選択」もできたホテルスタッフたちが自らの意思で残り、宿泊を助けた事実に感銘を受ける
あわせて読みたい
【権利】「難民だから支援すべき」じゃない。誰でも最低限の安全が確保できる世界であるべきだ:映画『…
難民申請中の少年が、国籍だけを理由にチェスの大会への出場でが危ぶまれる。そんな実際に起こった出来事を基にした『ファヒム パリが見た奇跡』は実に素晴らしい映画だが、賞賛すべきではない。「才能が無くても安全は担保されるべき」と考えるきっかけになる映画
あわせて読みたい
【驚愕】「金正男の殺人犯」は”あなた”だったかも。「人気者になりたい女性」が陥った巧妙な罠:映画『…
金正男が暗殺された事件は、世界中で驚きをもって報じられた。その実行犯である2人の女性は、「有名にならないか?」と声を掛けられて暗殺者に仕立て上げられてしまった普通の人だ。映画『わたしは金正男を殺していない』から、危険と隣り合わせの現状を知る
あわせて読みたい
【誤り】「信じたいものを信じる」のは正しい?映画『星の子』から「信じること」の難しさを考える
どんな病気も治す「奇跡の水」の存在を私は信じないが、しかし何故「信じない」と言えるのか?「奇跡の水を信じる人」を軽々に非難すべきではないと私は考えているが、それは何故か?映画『星の子』から、「何かを信じること」の難しさについて知る
あわせて読みたい
【排除】「分かり合えない相手」だけが「間違い」か?想像力の欠如が生む「無理解」と「対立」:映画『…
「共感」が強すぎる世の中では、自然と「想像力」が失われてしまう。そうならないようにと意識して踏ん張らなければ、他人の価値観を正しく認めることができない人間になってしまうだろう。映画『ミセス・ノイズィ』から、多様な価値観を排除しない生き方を考える
あわせて読みたい
【危機】遺伝子組み換え作物の危険性を指摘。バイオ企業「モンサント社」の実態を暴く衝撃の映画:映画…
「遺伝子組み換え作物が危険かどうか」以上に注目すべきは、「モンサント社の除草剤を摂取して大丈夫か」である。種子を独占的に販売し、農家を借金まみれにし、世界中の作物の多様性を失わせようとしている現状を、映画「モンサントの不自然な食べもの」から知る
あわせて読みたい
【衝撃】森達也『A3』が指摘。地下鉄サリン事件を起こしたオウム真理教は社会を激変させた
「オウム真理教は特別だ、という理由で作られた”例外”が、いつの間にか社会の”前提”になっている」これが、森達也『A3』の主張の要点だ。異常な状態で続けられた麻原彰晃の裁判を傍聴したことをきっかけに、社会の”異様な”変質の正体を理解する。
あわせて読みたい
【加虐】メディアの役割とは?森達也『A』が提示した「事実を報じる限界」と「思考停止社会」
オウム真理教の内部に潜入した、森達也のドキュメンタリー映画『A』は衝撃を与えた。しかしそれは、宗教団体ではなく、社会の方を切り取った作品だった。思考することを止めた社会の加虐性と、客観的な事実など切り取れないという現実について書く
あわせて読みたい
【衝撃】壮絶な戦争映画。最愛の娘を「産んで後悔している」と呟く母らは、正義のために戦場に留まる:…
こんな映画、二度と存在し得ないのではないかと感じるほど衝撃を受けた『娘は戦場で生まれた』。母であり革命家でもあるジャーナリストは、爆撃の続くシリアの街を記録し続け、同じ街で娘を産み育てた。「知らなかった」で済ませていい現実じゃない。
あわせて読みたい
【勇敢】日本を救った吉田昌郎と、福島第一原発事故に死を賭して立ち向かった者たちの極限を知る:『死…
日本は、死を覚悟して福島第一原発に残った「Fukushima50」に救われた。東京を含めた東日本が壊滅してもおかしくなかった大災害において、現場の人間が何を考えどう行動したのかを、『死の淵を見た男』をベースに書く。全日本人必読の書
あわせて読みたい
【驚愕】日本の司法は終わってる。「中世レベル」で「無罪判決が多いと出世に不利」な腐った現実:『裁…
三権分立の一翼を担う裁判所のことを、私たちはよく知らない。元エリート裁判官・瀬木比呂志と事件記者・清水潔の対談本『裁判所の正体』をベースに、「裁判所による統制」と「権力との癒着」について書く。「中世レベル」とさえ言われる日本の司法制度の現実は、「裁判になんか関わることない」という人も無視できないはずだ
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
理不尽・ストレス・イライラする【本・映画の感想】 | ルシルナ
「理不尽だなー」と感じてしまうことはよくあります。クレームや怒りなど、悪意や無理解から責められることもあるでしょうし、多数派や常識的な考え方に合わせられないとい…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…








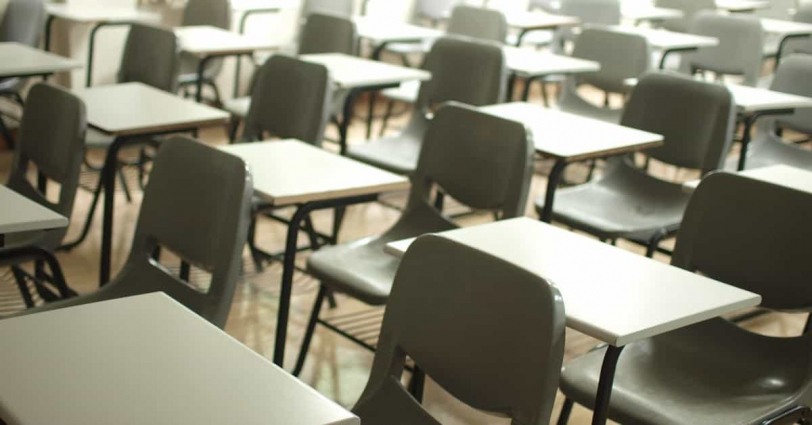












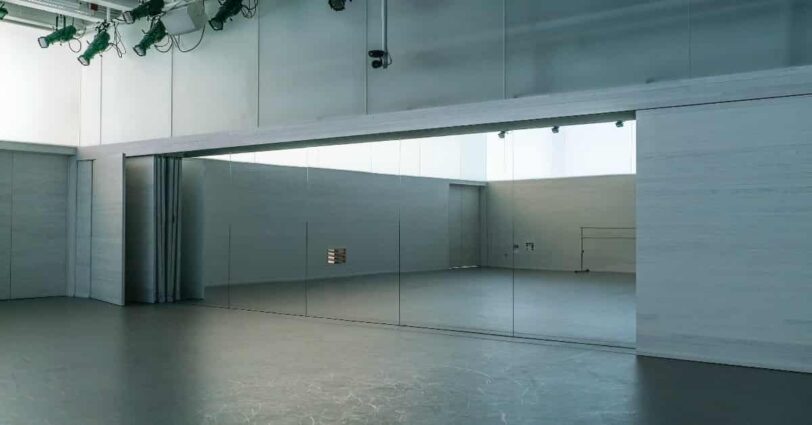
















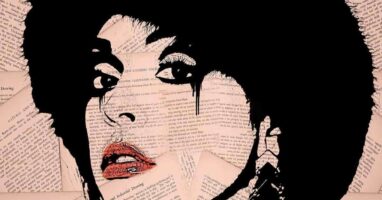




























































































コメント