目次
はじめに
この記事で取り上げる映画
出演:田中泯, 出演:石原淋, 出演:中村達也, 出演:大友良英, 出演:ライコー・フェリックス, Writer:犬童一心, 監督:犬童一心
¥550 (2022/09/15 20:28時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
この映画をガイドにしながら記事を書いていきます
この記事の3つの要点
- モダンバレエの稽古場で感じた「鏡に映る自分」への違和感
- どこまで深く掘ったところで、田中泯の「踊り」には正解も不正解も存在しない
- 世界的数学者・岡潔との共通項、そして哲学者ロジェ・カイヨワとの邂逅
他に類を見ない、唯一無二の存在感を放つ74歳の田中泯に圧倒された
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
記事中の引用は、映画館で取ったメモを参考にしているので、正確なものではありません
唯一無二の”踊り”を追求する「田中泯」に肉薄するドキュメンタリー映画『名付けようのない踊り』
あわせて読みたい
【革新】映画音楽における唯一のルールは「ルールなど無い」だ。”異次元の音”を生み出す天才を追う:映…
「無声映画」から始まった映画業界で、音楽の重要性はいかに認識されたのか?『JAWS』の印象的な音楽を生み出した天才は、映画音楽に何をもたらしたのか?様々な映画の実際の映像を組み込みながら、「映画音楽」の世界を深堀りする映画『すばらしき映画音楽たち』で、異才たちの「創作」に触れる
私は「田中泯」というダンサーの存在をは、この映画で初めて知った。それまでにももしかしたら何かで目にしたことがあるのかもしれないが、少なくともその人物を「田中泯」だと認識してはいない。

最近、学校の授業でも取り入れられるくらい「ダンス」は当たり前の存在になっているし、多くの若者がその世界に飛び込んでいると思う。ただ、田中泯の「踊り」は「ダンス」とはまた少し違うものがある。その点については後で触れるつもりだが、田中泯は他に類を見ない、唯一無二の存在感だと感じさせられた。
「表現」とは「私を表現すること」こそが最上と言えるのだろうか?
あわせて読みたい
【感想】努力では才能に勝てないのか?どうしても辿り着きたい地点まで迷いながらも突き進むために:『…
どうしても辿り着きたい場所があっても、そのあまりの遠さに目が眩んでしまうこともあるでしょう。そんな人に向けて、「才能がない」という言葉に逃げずに前進する勇気と、「仕事をする上で大事なスタンス」について『羊と鋼の森』をベースに書いていきます
映画の中で田中泯が、モダンバレエの教室に通っていた時のエピソードを話していた。フランスで大ブレイクを果たす以前のことだ。彼は、「稽古場の鏡」が嫌だったと言っていた。
向こうに映っている自分に支配され、囚われているように感じてしまった。
「名付けようのない踊り」(監督:犬童一心、主演:田中泯)
彼のこの発言を聞いて、ふと思い出したことがある。少し前にテレビで見たバラエティ番組での一コマだ。
世界中で撮影された動画を見てスタジオゲストがコメントを入れる番組を観ていた時のこと。水没した道路で立ち往生している車を見つけたトラクターの運転手が、子どもを含む4人を助けるという外国の動画が流れる。その動画を撮影しているのは、トラクターの運転手自身。その場には、トラクターの運転手以外にも何人かの人がいたため、彼はスマホで撮影しながらでも救助活動が出来たのである。
あわせて読みたい
【恐怖】SNSの危険性と子供の守り方を、ドキュメンタリー映画『SNS 少女たちの10日間』で学ぶ
実際にチェコの警察を動かした衝撃のドキュメンタリー映画『SNS 少女たちの10日間』は、少女の「寂しさ」に付け込むおっさんどもの醜悪さに満ちあふれている。「WEBの利用制限」だけでは子どもを守りきれない現実を、リアルなものとして実感すべき
この映像を見たスタジオゲストの1人が、「救助の様子を自撮りしてるってのが、なんかちょっと嫌だよね」と発言した。これに私はとても共感したことを覚えている。
田中泯の話と比較するようなエピソードではまったくないのだが、しかし、カメラも鏡も、「他者目線の自分」を映し出すものだと言っていいだろう。そして、それに対する感覚がまったく違う形で表出していることが印象的だった。トラクターの運転手は「他者目線の自分」を自ら発信し、一方で田中泯は、鏡に映る「他者目線の自分」が自分を支配する感覚に嫌なものを感じ取っていたのである。

鏡を嫌悪していた頃、彼は「”私”を表現しろ」「個性を出せ」とも言われていたという。しかし彼は、その「当たり前の思考」を前に立ち止まる。
あわせて読みたい
【欠落】映画『オードリー・ヘプバーン』が映し出す大スターの生き方。晩年に至るまで生涯抱いた悲しみ…
映画『オードリー・ヘプバーン』は、世界的大スターの知られざる素顔を切り取るドキュメンタリーだ。戦争による壮絶な飢え、父親の失踪、消えぬ孤独感、偶然がもたらした映画『ローマの休日』のオーディション、ユニセフでの活動など、様々な証言を元に稀代の天才を描き出す
「私を表現する」ということに、どうにもピンとこなかった。
「名付けようのない踊り」(監督:犬童一心、主演:田中泯)
この言葉は、「田中泯」という存在を捉える上で、非常に重要なものと言っていいだろう。
ダンスでも踊りでも呼び方はなんでもいいが、それらは一般的に「自己表現の手段」と捉えられているはずだ。それはつまり、「私」や「個性」が出ていれば出ているほど、世間的に評価されるということでもある。しかし田中泯はそうは考えない。そしてかつて抱いたその違和感を、決して捨てずにずっと持ち続けるのである。
その後、土方巽という人物と出会い、彼はこんな風に言われたそうだ。
あわせて読みたい
【継続】「言語化できない」を乗り越えろ。「読者としての文章術」で、自分の思考をクリアにする:『読…
ブログやSNSなどが登場したことで、文章を書く機会は増えていると言える。しかし同時に、「他人に評価されるために書く」という意識も強くなっているだろう。『読みたいことを書けばいい』から、「楽しく書き”続ける”」ための心得を学ぶ
これまで数多くの人間が生きてきた。『私』や『個性』なんてものは、過去のどこかに必ず存在する。
「名付けようのない踊り」(監督:犬童一心、主演:田中泯)
この言葉で気が楽になった、と彼は語っていた。
そうして彼は、40歳で農業を始める決断をする。ここにも、彼なりの信念があった。「野良仕事で身体を作り、その身体で踊る」と決めたのである。
ダンサーは、ダンスを目的に身体を作ってしまう。私は、その身体で踊ることは違うと思った。
「名付けようのない踊り」(監督:犬童一心、主演:田中泯)
あわせて読みたい
【挑戦】手足の指を失いながら、今なお挑戦し続ける世界的クライマー山野井泰史の”現在”を描く映画:『…
世界的クライマーとして知られる山野井泰史。手足の指を10本も失いながら、未だに世界のトップをひた走る男の「伝説的偉業」と「現在」を映し出すドキュメンタリー映画『人生クライマー』には、小学生の頃から山のことしか考えてこなかった男のヤバい人生が凝縮されている
彼のこの考えはとても素晴らしいものだと感じられた。田中泯にとって「踊り」は、「身体を動かすこと」ではなく「身体が動いてしまうようなもの」として捉えられているというわけだ。彼は、「ダンスのために腹筋を鍛える」という発想をしない。そうではなく、「今の自分のあるべき身体が自ずと動いてしまうことで成立する」という状態を目指しているのだ。

そのことを彼は、
芸術になる以前の踊りを探したかった。
「名付けようのない踊り」(監督:犬童一心、主演:田中泯)
と表現している。田中泯がこのように自身の「踊り」について言語化してくれた辺りから、彼の「踊り」の本質が少しずつ捉え易くなったように感じられた。
あわせて読みたい
【諦め】「人間が創作すること」に意味はあるか?AI社会で問われる、「創作の悩み」以前の問題:『電気…
AIが個人の好みに合わせて作曲してくれる世界に、「作曲家」の存在価値はあるだろうか?我々がもうすぐ経験するだろう近未来を描く『電気じかけのクジラは歌う』をベースに、「創作の世界に足を踏み入れるべきか」という問いに直面せざるを得ない現実を考える
田中泯の踊りには「正解」が存在しない
映画を観て、私がなんとなく掴んだ「田中泯にとっての『踊り』」について、少し言語化してみたいと思う。その説明のために、ここからは「ダンス」と「踊り」を明確に区別しよう。ここでは、
- バレエやヒップホップなど何らかのジャンルに分類可能なものを「ダンス」
- 「その他」としてしか括れないようなジャンルレスのものを「踊り」
と呼ぶことにしたいと思う。当然、田中泯は後者に当てはまる。
あわせて読みたい
【改革】改修期間中の国立西洋美術館の裏側と日本の美術展の現実を映すドキュメンタリー映画:『わたし…
「コロナ禍」という絶妙すぎるタイミングで改修工事を行った国立西洋美術館の、普段見ることが出来ない「裏側」が映し出される映画『わたしたちの国立西洋美術館』は、「日本の美術展」の問題点を炙り出しつつ、「『好き』を仕事にした者たち」の楽しそうな雰囲気がとても魅力的に映るドキュメンタリー
さて、私は別に、「ダンスには正解がある」と主張したいわけではない。ダンスにしても踊りにしても、「身体を動かす前」の時点では正解など存在しないだろう。しかし、「身体を動かした後」はそうではない。
「ダンス」の場合、発表会やコンクールなどではもちろん「評価」がなされ、優劣がつけられる。この状況は「分かりやすく正解が存在する」と言えるだろう。しかし発表会やコンクールでなくても、「ダンス」の場合は、「カッコいい」「真似したい」「決まってる」といった感想を見ている者に抱かせる。すべての「ダンス」がそんな感覚を与えるわけではないのだから、「カッコいい」「真似したい」「決まってる」という評価を便宜上「正解」と呼んでも不自然ではないはずだ。
そういう意味で「ダンス」には「正解」があると言っていいだろう。

あわせて読みたい
【感想】湯浅政明監督アニメ映画『犬王』は、実在した能楽師を”異形”として描くスペクタクル平家物語
観るつもりなし、期待値ゼロ、事前情報ほぼ皆無の状態で観た映画『犬王』(湯浅政明監督)はあまりにも凄まじく、私はこんなとんでもない傑作を見逃すところだったのかと驚愕させられた。原作の古川日出男が紡ぐ狂気の世界観に、リアルな「ライブ感」が加わった、素晴らしすぎる「音楽映画」
一方、「踊り」は違う。そもそも、どんなジャンルにも分類されず、比較対象が存在しないのだから、発表会やコンクールのような分かりやすい評価は不可能だ。また、田中泯の「踊り」を見て、「カッコいい」「真似したい」「決まってる」という感覚にもならないだろう。「カッコいい」「真似したい」「決まってる」という感覚の背後にはやはり、「私はこういうものを『良い』と感じる」という自分なりの評価基準があるはずだが、田中泯の「踊り」は、何らかの基準に照らして評価するような類のものではないからだ。彼のどんな動きに対しても、「あそこが違う」「あれは間違いだ」などと指摘できるような枠組みは存在しないだろう。
もちろん、田中泯の「踊り」を見て、「イケてない」という感覚を抱く者もいると思う。しかしそれは、「評価」ではなく「感想」でしかない。正解・不正解の基準が存在するとは思えない彼の「踊り」を見てどう感じようが、結局それは「個人の感想」の域を出られないのだ。
そして、非常に逆説的ではあるが、だからこそ私には、田中泯の「踊り」は安心して見ることができると感じられた。「正解」が存在する場合、「『評価する側』もまた評価される」というジレンマを回避することは難しい。だから、初心者であればあるほど、目にしたものを「良い」と評価することも怖くなってしまうだろう。しかし田中泯の「踊り」には、正解も不正解もない。どんな感じ方をしようが、それはすべて「個人の感想」にしかならないのだ。そのことが、「『分からない』『知識がない』という劣等感」を抱かせずに「踊り」に触れさせるポイントとなっているように私には感じられた。
ここで書いた「ダンス」と「踊り」の差は、結局のところ、「何のために?」という目的の違いから生まれているように思う。
あわせて読みたい
【おすすめ】「天才」を描くのは難しい。そんな無謀な挑戦を成し遂げた天才・野崎まどの『know』はヤバい
「物語で『天才』を描くこと」は非常に難しい。「理解できない」と「理解できる」を絶妙なバランスで成り立たせる必要があるからだ。そんな難題を高いレベルでクリアしている野崎まど『know』は、異次元の小説である。世界を一変させた天才を描き、「天才が見ている世界」を垣間見せてくれる
以前観た映画『蜜蜂と遠雷』の中に、こんな感じのセリフがあった。
野原にピアノが置いてあれば、世界中に僕一人しかいなくたって、僕はきっとピアノを弾くよ。
「蜜蜂と遠雷」(監督:石川慶、主演:松岡茉優、松坂桃李)
あわせて読みたい
【あらすじ】天才とは「分かりやすい才能」ではない。前進するのに躊躇する暗闇で直進できる勇気のこと…
ピアノのコンクールを舞台に描く『蜜蜂と遠雷』は、「天才とは何か?」と問いかける。既存の「枠組み」をいとも簡単に越えていく者こそが「天才」だと私は思うが、「枠組み」を安易に設定することの是非についても刃を突きつける作品だ。小説と映画の感想を一緒に書く
こう発した人物は、「観客がいるとか、コンクールに出場するみたいな理由がなくたって、ただ自分が弾きたいと思うからピアノを弾いているんだ」という感覚を明確に持っていると言える。そして、田中泯にも同じようなことを感じた。もし世界中から人類が消え、田中泯ひとりになったとしても、彼はその世界で踊るのではないか。私にはそんな風に感じられたのだ。
「ダンス」の場合はどうだろう? もちろん世の中には、自分ひとりしかいなくなってもダンスを続けるという人もいるとは思う。しかし多くの人はやはり、「誰かに認められたい」「誰かに見てもらいたい」という気持ちで「ダンス」をしているのではないだろうか。そしてそれは結局、「鏡に映る自分を見る」「自分の姿を自撮りする」などと近い行為であり、恐らく田中泯が求めているものからは遠ざかるのだ。

私がこうして書いているブログ記事を含め、あらゆる「表現」「創作」は基本的に「他人の存在」を当然のように前提としている。それはあまりに当たり前なことであり、それゆえ、自分の行動に違和感を覚えることがない。しかしこの映画を通じて、「他人の存在」を前提としない田中泯の生き様を知ることで、「他人の存在を前提とする表現」についての思考が促される。この映画には、そんな視点も込められているように感じられた。
あわせて読みたい
【革命】電子音楽誕生の陰に女性あり。楽器ではなく機械での作曲に挑んだ者たちを描く映画:『ショック…
現代では当たり前の「電子音楽」。その黎明期には、既存の音楽界から排除されていた女性が多く活躍した。1978年、パリに住む1人の女性が「電子音楽」の革命の扉をまさに開こうとしている、その1日を追う映画『ショック・ド・フューチャー』が描き出す「創作の熱狂」
田中泯と、世界的数学者・岡潔の共通点
映画を観ながら、世界的数学者の岡潔を連想した。まずは少し、岡潔についての紹介をしたいと思う。
彼は、「多変数函数論」という分野に存在した3つの超難問をたった1人で解決した、偉大な功績を持つことで知られる数学者だ。研究成果を発表した時、彼は世界でも国内でもまったく無名の存在だった。それまで存在さえ知られていなかった人物が、多くの数学者を困惑させ続けてきた超難問を次々に解決したという状況があまりに信じ難かったため、ヨーロッパでは「岡潔」という数学者集団が存在すると考えられていたほどである。とても1人で成し遂げたと信じるには無理がある業績だったのだ。
岡潔はまた、「数学研究」と「畑仕事」以外のことは一切しなかったことでも知られている。彼は30代後半から、故郷である和歌山県紀見村に籠もり、畑仕事の合間に数学研究を行うという生活を続けていたのだ。道理で国内でも名前が知られていないわけである。そしてこの紀見村隠遁中の研究が世界に紹介され、彼は一躍世界的数学者として認識されるようになったのだ。
あわせて読みたい
【奇人】天才数学者で、自宅を持たずに世界中を放浪した変人エルデシュは、迷惑な存在でも愛され続けた…
数学史上ガウスに次いで生涯発表論文数が多い天才エルデシュをご存知だろうか?数学者としてずば抜けた才能を発揮したが、それ以上に「奇人変人」としても知られる人物だ。『放浪の天才数学者エルデシュ』で、世界中の数学者の家を泊まり歩いた異端数学者の生涯を描き出す
なんとなく、田中泯に通ずる部分があると感じないだろうか? 「踊り」と「数学」という、対極ですらないまったく無関係の分野でトップランナーとなった2人は共に、「本質を突き詰めるためにどう生きるべきだろうか?」という思考を常に内包していたと言っていいだろう。
田中泯は映画の中で、
私がやっていることが、一応「踊り」だということになっています。ただ私は、見ている人と私との間に「踊り」が生まれることが理想です。
「名付けようのない踊り」(監督:犬童一心、主演:田中泯)
と語っている。ある意味でこの言葉は、彼の「踊り」の本質を凝縮したものだと言っていいだろう。彼は、「『田中泯』と『観客』という風に存在が分離されている」のではなく、「『田中泯及び観客』という関係性の中にこそ『踊り』が存在する」と解釈しているのである。
あわせて読みたい
【アート】「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」(森美術館)と「美術手帖 Chim↑Pom特集」の衝撃から「…
Chim↑Pomというアーティストについてさして詳しいことを知らずに観に行った、森美術館の「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」に、思考をドバドバと刺激されまくったので、Chim↑Pomが特集された「美術手帖」も慌てて買い、Chim↑Pomについてメッチャ考えてみた
一方、岡潔のものとして知られるこんな言葉も紹介しておこう。
数学の本質は、「計算」や「論理」ではなく「情緒の働き」だ。
「情緒」とは「何らかの対象に向けられる感情」ぐらいに捉えておけばいいだろう。つまり田中泯も岡潔も、それぞれの分野において、「『周辺のものとの関係性』を通じて物事の本質を突き詰めようとしていた」というわけだ。

そして、その実現のために彼らは「畑仕事」を行う。この共通項もまた非常に興味深いポイントだろう。恐らくだが、「人知を超えた何かを自然から感じ取る」という意識を強く持っていたのだろう。結果として彼らは、それぞれの分野で多大な功績を成しているのであり、その振る舞いには考えるべきポイントがあるのではないかと感じさせられた。
あわせて読みたい
【驚異】ガイア理論の提唱者が未来の地球を語る。100歳の主張とは思えない超絶刺激に満ちた内容:『ノヴ…
「地球は一種の生命体だ」という主張はかなり胡散臭い。しかし、そんな「ガイア理論」を提唱する著者は、数々の賞や学位を授与される、非常に良く知られた科学者だ。『ノヴァセン <超知能>が地球を更新する』から、AIと人類の共存に関する斬新な知見を知る
ロジェ・カイヨワにだけは「踊り」を見てほしいと切望した
この映画のタイトルである「名付けようのない踊り」というフレーズは、哲学者ロジェ・カイヨワが口にしたものだそうだ。
田中泯はまずフランスで評価された。1978年にパリで「踊り」を披露したことで、一躍有名になったのである。それ以降、彼の元には、様々な「甘い誘惑」が舞い込んできたという。「完成品としての『踊り』を持てば、20年はこの世界で生きられる」「パリに学校を作れば新たな流派を生み出せる」などである。それらの誘いを、田中泯は「嫌悪の極み」と一蹴していた。彼の「踊り」に対するスタンスを踏まえれば、当然の感覚だと思う。
そんな田中泯が、「この人にだけは自分の『踊り』を見てもらいたい」と切望した人物がいる。それがロジェ・カイヨワだ。田中泯は、ロジェ・カイヨワの『遊びと人間』という著作に惚れ込んだという。
著:ロジェ・カイヨワ, 翻訳:多田道太郎, 翻訳:塚崎幹夫
¥1,485 (2022/09/15 20:49時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【感想】池田晶子『14歳からの哲学』で思考・自由・孤独の大事さを知る。孤独を感じることって大事だ
「元々持ってた価値観とは違う考えに触れ、それを理解したいと思う場面」でしか「考える」という行為は発動しないと著者は言う。つまり我々は普段、まったく考えていないのだ。『14歳からの哲学』をベースに、「考えること」と自由・孤独・人生との関係を知る

田中泯はロジェ・カイヨワと連絡を取り、「窓からエッフェル塔が突っ込んでくるような部屋」で「踊り」を披露した。そして、それを見たロジェ・カイヨワが、
永遠に、名付けようのない踊りを続けて下さい。
「名付けようのない踊り」(監督:犬童一心、主演:田中泯)
と評したというのだ。「名付けようのない踊り」とはまさに、田中泯の元に集まった「甘い誘惑」とは対極に存在するものだと言える。この言葉に触れた田中泯がどんな感想を抱いたのかには触れられなかったが、恐らく、ロジェ・カイヨワのこの言葉が、現在に至るまで田中泯を突き動かしている原動力なのではないかと私は感じた。
あわせて読みたい
【奇跡】鈴木敏夫が2人の天才、高畑勲と宮崎駿を語る。ジブリの誕生から驚きの創作秘話まで:『天才の思…
徳間書店から成り行きでジブリ入りすることになったプロデューサー・鈴木敏夫が、宮崎駿・高畑勲という2人の天才と共に作り上げたジブリ作品とその背景を語り尽くす『天才の思考 高畑勲と宮崎駿』。日本のアニメ界のトップランナーたちの軌跡の奇跡を知る
出演:田中泯, 出演:石原淋, 出演:中村達也, 出演:大友良英, 出演:ライコー・フェリックス, Writer:犬童一心, 監督:犬童一心
¥550 (2022/09/15 20:32時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品視聴済】私が観てきたドキュメンタリー映画を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が観てきたドキュメンタリー映画を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。
最後に
あわせて読みたい
【圧巻】150年前に気球で科学と天気予報の歴史を変えた挑戦者を描く映画『イントゥ・ザ・スカイ』
「天気予報」が「占い」と同等に扱われていた1860年代に、気球を使って気象の歴史を切り開いた者たちがいた。映画『イントゥ・ザ・スカイ』は、酸素ボンベ無しで高度1万1000m以上まで辿り着いた科学者と気球操縦士の物語であり、「常識を乗り越える冒険」の素晴らしさを教えてくれる
田中泯は、屋外で即興で踊ることを「場踊り」と呼んでいる。映画の中でも、都会の広場や神社へと続くのだろう階段など様々な場所で「場踊り」を行う姿が映し出されていた。
世界にあるたくさんの速度が、一斉に押し寄せてくる。
「名付けようのない踊り」(監督:犬童一心、主演:田中泯)
あわせて読みたい
【人類学】少数民族・ムラブリ族に潜入した映画『森のムラブリ』は、私たちの「当たり前」を鮮やかに壊す
タイとラオスにまたがって存在する少数民族・ムラブリ族に密着したドキュメンタリー映画『森のムラブリ』。「ムラブリ族の居住地でたまたま出会った日本人人類学者」と意気投合し生まれたこの映画は、私たちがいかに「常識」「当たり前」という感覚に囚われているのかを炙り出してくれる
彼には、その場その場に宿る、私たちには見えない「何か」が見えているのかもしれない。そして、その彼にしか見えない「何か」が、彼の身体を自在に操っているのかもしれない。そんな風にさえ感じさせられる光景だった。
田中泯の「踊り」に限らないが、「この人には、この人にしか見えていないのだろう『何か』がある」と感じさせる人に、私はうらやましさを覚える。芸術家や小説家など、創作・表現を行う人の中にもそういうタイプの人がいるが、そういう「才能」に触れる度、自分がそちら側にいられないことの無念さみたいなものを痛感させられてしまう。
あわせて読みたい
【情報】日本の社会問題を”祈り”で捉える。市場原理の外にあるべき”歩哨”たる裁き・教育・医療:『日本…
「霊性」というテーマは馴染みが薄いし、胡散臭ささえある。しかし『日本霊性論』では、「霊性とは、人間社会が集団を存続させるために生み出した機能」であると主張する。裁き・教育・医療の変化が鈍い真っ当な理由と、情報感度の薄れた現代人が引き起こす問題を語る
脳みそが深海に沈んでいきそうな感じ……幸せだ。
「名付けようのない踊り」(監督:犬童一心、主演:田中泯)
74歳になってなお、ポルトガル・サンタクルスの街角でそんな風に呟ける田中泯に、曰く言い難い「憧れ」を抱かされてしまった。
あわせて読みたい
【食&芸術】死んでも車を運転したくない人間の香川うどん巡り& 豊島アート巡りの旅ルート(山越うどん…
仕事終わりの木曜日夜から日曜日に掛けて、「香川のうどん巡り」と「豊島のアート巡り」をしてきました。うどんだけでも7580円分食べたので、かなりの軒数を回ったことになります。しかも「死んでも車を運転したくない」ため、可能な限り公共交通機関のみで移動しました。私と同じように「車を運転したくない人」には、かなり参考になる記事と言えるのではないかと思います
次におすすめの記事
あわせて読みたい
金沢&富山のアート旅!「21世紀美術館」だけじゃない激アツなおすすめ美術館巡りをご提案
金沢・富山を巡るアート旅に出かけてきました!メインの目的は「21世紀美術館」でしたが、それ以上に「ASTER Curator Museum」「LIP BAR」「KAMU kanazawa」などがとにかく素晴らしかったです。アートや美術のことはド素人ですが、超個人的主観で「金沢・富山で触れられるアートの良さ」について書いた旅行記となります
あわせて読みたい
【異様】映画『大いなる不在』(近浦啓)は、認知症の父を中心に「記憶」と「存在」の複雑さを描く(主…
「父親が逮捕され、どうやら認知症のようだ」という一報を受けた息子が、30年間ほぼやり取りのなかった父親と再会するところから始まる映画『大いなる不在』は、なんとも言えない「不穏さ」に満ちた物語だった。「記憶」と「存在」のややこしさを問う本作は、「物語」としては成立していないが、圧倒的な“リアリティ”に満ちている
あわせて読みたい
【面白い】映画『ラストマイル』は、物流問題をベースに「起こり得るリアル」をポップに突きつける(監…
映画『ラストマイル』は、「物流」という「ネット社会では誰にでも関係し得る社会問題」に斬り込みながら、実に軽妙でポップな雰囲気で展開されるエンタメ作品である。『アンナチュラル』『MIU404』と同じ世界で展開される「シェアード・ユニバース」も話題で、様々な人の関心を広く喚起する作品と言えるだろう
あわせて読みたい
【実話】映画『ディア・ファミリー』は超良い話だし、大泉洋が演じた人物のモデル・筒井宣政は凄すぎる…
実話を基にした映画『ディア・ファミリー』では、個人が成したとは信じがたい偉業が描き出される。大泉洋が演じたのは、娘の病を治そうと全力で突き進んだ人物であり、そのモデルとなった筒井宣政は、17万人以上を救ったとされるIABPバルーンカテーテルの開発者なのだ。まったくホントに、凄まじい人物がいたものだと思う
あわせて読みたい
【現在】ウーマンラッシュアワー村本大輔がテレビから消えた理由と彼の”優しさ”を描く映画:『アイアム…
「テレビから消えた」と言われるウーマンラッシュアワー・村本大輔に密着する映画『アイアム・ア・コメディアン』は、彼に対してさほど関心を抱いていない人でも面白く観られるドキュメンタリー映画だと思う。自身の存在意義を「拡声器」のように捉え、様々な社会問題を「お笑い」で発信し続ける姿には、静かな感動さえ抱かされるだろう
あわせて読みたい
【感想】映画『ルックバック』の衝撃。創作における衝動・葛藤・苦悩が鮮やかに詰め込まれた傑作(原作…
アニメ映画『ルックバック』は、たった58分の、しかもセリフも動きも相当に抑制された「静」の映画とは思えない深い感動をもたらす作品だった。漫画を描くことに情熱を燃やす2人の小学生が出会ったことで駆動する物語は、「『創作』に限らず、何かに全力で立ち向かったことがあるすべての人」の心を突き刺していくはずだ
あわせて読みたい
【悲劇】映画『プリンセス・ダイアナ』『スペンサー』で知る、その凄まじい存在感と王室の窮屈さ
ドキュメンタリー映画『プリンセス・ダイアナ』と映画『スペンサー』は、衝撃的な死を遂げたダイアナ妃の生涯を対照的な形で描き出す作品だ。「過去映像のみ」で構成される非常に挑戦的な『プリンセス・ダイアナ』と、「王室との不和」を正面から描き出す『スペンサー』の2作によって、彼女が歩んだ壮絶な人生が浮き彫りにされる
あわせて読みたい
【常識】群青いろ制作『彼女はなぜ、猿を逃したか?』は、凄まじく奇妙で、実に魅力的な映画だった(主…
映画『彼女はなぜ、猿を逃したか?』(群青いろ制作)は、「絶妙に奇妙な展開」と「爽快感のあるラスト」の対比が魅力的な作品。主なテーマとして扱われている「週刊誌報道からのネットの炎上」よりも、私は「週刊誌記者が無意識に抱いている思い込み」の方に興味があったし、それを受け流す女子高生の受け答えがとても素敵だった
あわせて読みたい
【正義】ナン・ゴールディンの”覚悟”を映し出す映画『美と殺戮のすべて』が描く衝撃の薬害事件
映画『美と殺戮のすべて』は、写真家ナン・ゴールディンの凄まじい闘いが映し出されるドキュメンタリー映画である。ターゲットとなるのは、美術界にその名を轟かすサックラー家。なんと、彼らが創業した製薬会社で製造された処方薬によって、アメリカでは既に50万人が死亡しているのだ。そんな異次元の薬害事件が扱われる驚くべき作品
あわせて読みたい
【実話】さかなクンの若い頃を描く映画『さかなのこ』(沖田修一)は子育ての悩みを吹き飛ばす快作(主…
映画『さかなのこ』は、兎にも角にものん(能年玲奈)を主演に据えたことが圧倒的に正解すぎる作品でした。性別が違うのに、「さかなクンを演じられるのはのんしかいない!」と感じさせるほどのハマり役で、この配役を考えた人は天才だと思います。「母親からの全肯定」を濃密に描き出す、子どもと関わるすべての人に観てほしい作品です
あわせて読みたい
【現在】猟師になった東出昌大を追う映画『WILL』は予想外に良かった。山小屋での生活は衝撃だ(監督:…
猟師・東出昌大に密着した映画『WILL』は、思いがけず面白い作品だった。正直、東出昌大にはまったく興味がなく、本作も期待せず観たのだが、異常なほどフラットなスタンス故に周囲にいる人間を否応なく惹きつける「人間力」や、狩猟の世界が突きつける「生と死」というテーマなど実に興味深い。本当に観て良かったなと思う
あわせて読みたい
【憧憬】「フランク・ザッパ」を知らずに映画『ZAPPA』を観て、「この生き様は最高」だと感じた
「フランク・ザッパ」がミュージシャンであることさえ禄に知らない状態で私が映画『ZAPPA』を観た私は、そのあまりに特異なスタンス・生き様にある種の憧憬を抱かされた。貫きたいと思う強い欲求を真っ直ぐ突き進んだそのシンプルな人生に、とにかくグッときたのだ。さらに、こんな凄い人物を知らなかった自分にも驚かされてしまった
あわせて読みたい
【価値】レコードなどの「フィジカルメディア」が復権する今、映画『アザー・ミュージック』は必見だ
2016年に閉店した伝説のレコード店に密着するドキュメンタリー映画『アザー・ミュージック』は、「フィジカルメディアの衰退」を象徴的に映し出す。ただ私は、「デジタル的なもの」に駆逐されていく世の中において、「『制約』にこそ価値がある」と考えているのだが、若者の意識も実は「制約」に向き始めているのではないかとも思っている
あわせて読みたい
【問題】映画『国葬の日』が切り取る、安倍元首相の”独裁”が生んだ「政治への関心の無さ」(監督:大島新)
安倍元首相の国葬の1日を追ったドキュメンタリー映画『国葬の日』は、「国葬」をテーマにしながら、実は我々「国民」の方が深堀りされる作品だ。「安倍元首相の国葬」に対する、全国各地の様々な人たちの反応・価値観から、「『ソフトな独裁』を維持する”共犯者”なのではないか」という、我々自身の政治との向き合い方が問われているのである
あわせて読みたい
【ル・マン】ゲーマーが本物のカーレース出場!映画『グランツーリスモ』が描く衝撃的すぎる軌跡(ヤン…
映画『グランツーリスモ』は、「ゲーマーをレーサーにする」という、実際に行われた無謀すぎるプロジェクトを基にした作品だ。登場人物は全員イカれていると感じたが、物語としてはシンプルかつ王道で、誰もが先の展開を予想出来るだろう。しかしそれでも、圧倒的に面白かった、ちょっと凄まじすぎる映画だった
あわせて読みたい
【食&芸術】死んでも車を運転したくない人間の香川うどん巡り& 豊島アート巡りの旅ルート(山越うどん…
仕事終わりの木曜日夜から日曜日に掛けて、「香川のうどん巡り」と「豊島のアート巡り」をしてきました。うどんだけでも7580円分食べたので、かなりの軒数を回ったことになります。しかも「死んでも車を運転したくない」ため、可能な限り公共交通機関のみで移動しました。私と同じように「車を運転したくない人」には、かなり参考になる記事と言えるのではないかと思います
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『悪は存在しない』(濱口竜介)の衝撃のラストの解釈と、タイトルが示唆する現実(主…
映画『悪は存在しない』(濱口竜介監督)は、観る者すべてを困惑に叩き落とす衝撃のラストに、鑑賞直後は迷子のような状態になってしまうだろう。しかし、作中で提示される様々な要素を紐解き、私なりの解釈に辿り着いた。全編に渡り『悪は存在しない』というタイトルを強く意識させられる、脚本・映像も見事な作品だ
あわせて読みたい
【天才】映画『笑いのカイブツ』のモデル「伝説のハガキ職人ツチヤタカユキ」の狂気に共感させられた
『「伝説のハガキ職人」として知られるツチヤタカユキの自伝的小説を基にした映画『笑いのカイブツ』は、凄まじい狂気に彩られた作品だった。「お笑い」にすべてを捧げ、「お笑い」以外はどうでもいいと考えているツチヤタカユキが、「コミュ力」や「人間関係」で躓かされる”理不尽”な世の中に、色々と考えさせられる
あわせて読みたい
【斬新】映画『王国(あるいはその家について)』(草野なつか)を観よ。未経験の鑑賞体験を保証する
映画『王国(あるいはその家について)』は、まず経験できないだろう異様な鑑賞体験をもたらす特異な作品だった。「稽古場での台本読み」を映し出すパートが上映時間150分のほとんどを占め、同じやり取りをひたすら繰り返し見せ続ける本作は、「王国」をキーワードに様々な形の「狂気」を炙り出す異常な作品である
あわせて読みたい
【抵抗】映画『熊は、いない』は、映画製作を禁じられた映画監督ジャファル・パナヒの執念の結晶だ
映画『熊は、いない』は、「イラン当局から映画製作を20年間も禁じられながら、その後も作品を生み出し続けるジャファル・パナヒ監督」の手によるもので、彼は本作公開後に収監させられてしまった。パナヒ監督が「本人役」として出演する、「ドキュメンタリーとフィクションのあわい」を縫うような異様な作品だ
あわせて読みたい
【実話】英国王室衝撃!映画『ロスト・キング』が描く、一般人がリチャード3世の遺骨を発見した話(主演…
500年前に亡くなった王・リチャード3世の遺骨を、一介の会社員女性が発見した。映画『ロスト・キング』は、そんな実話を基にした凄まじい物語である。「リチャード3世の悪評を覆したい!」という動機だけで遺骨探しに邁進する「最強の推し活」は、最終的に英国王室までをも動かした!
あわせて読みたい
【感想】映画『キリエのうた』(岩井俊二)はアイナ・ジ・エンドに圧倒されっ放しの3時間だった(出演:…
映画『キリエのうた』(岩井俊二監督)では、とにかくアイナ・ジ・エンドに圧倒されてしまった。歌声はもちろんのことながら、ただそこにいるだけで場を支配するような存在感も凄まじい。全編に渡り「『仕方ないこと』はどうしようもなく起こるんだ」というメッセージに溢れた、とても力強い作品だ
あわせて読みたい
【映画】『キャスティング・ディレクター』の歴史を作り、ハリウッド映画俳優の運命を変えた女性の奮闘
映画『キャスティング・ディレクター』は、ハリウッドで伝説とされるマリオン・ドハティを描き出すドキュメンタリー。「神業」「芸術」とも評される配役を行ってきたにも拘わらず、長く評価されずにいた彼女の不遇の歴史や、再び「キャスティングの暗黒期」に入ってしまった現在のハリウッドなどを切り取っていく
あわせて読みたい
【未知】コーダに密着した映画『私だけ聴こえる』は、ろう者と聴者の狭間で居場所がない苦悩を映し出す
あなたは「コーダ」と呼ばれる存在を知っているだろうか?「耳の聴こえない親を持つ、耳が聴こえる子ども」のことであり、映画『私だけ聴こえる』は、まさにそんなコーダが置かれた状況を描くドキュメンタリー映画だ。自身は障害者ではないのに大変な苦労を強いられている現状が理解できる作品
あわせて読みたい
【改革】改修期間中の国立西洋美術館の裏側と日本の美術展の現実を映すドキュメンタリー映画:『わたし…
「コロナ禍」という絶妙すぎるタイミングで改修工事を行った国立西洋美術館の、普段見ることが出来ない「裏側」が映し出される映画『わたしたちの国立西洋美術館』は、「日本の美術展」の問題点を炙り出しつつ、「『好き』を仕事にした者たち」の楽しそうな雰囲気がとても魅力的に映るドキュメンタリー
あわせて読みたい
【天才】映画音楽の発明家『モリコーネ』の生涯。「映画が恋した音楽家」はいかに名曲を生んだか
「映画音楽のフォーマットを生み出した」とも評される天才作曲家エンリオ・モリコーネを扱った映画『モリコーネ 映画が恋した音楽家』では、生涯で500曲以上も生み出し、「映画音楽」というジャンルを比べ物にならないほどの高みにまで押し上げた人物の知られざる生涯が描かれる
あわせて読みたい
【伝説】映画『ミスター・ムーンライト』が描くビートルズ武道館公演までの軌跡と日本音楽への影響
ザ・ビートルズの武道館公演が行われるまでの軌跡を描き出したドキュメンタリー映画『ミスター・ムーンライト』は、その登場の衝撃について語る多数の著名人が登場する豪華な作品だ。ザ・ビートルズがまったく知られていなかった頃から、伝説の武道館公演に至るまでの驚くべきエピソードが詰まった1作
あわせて読みたい
【驚嘆】映画『TAR/ター』のリディア・ターと、彼女を演じたケイト・ブランシェットの凄まじさ
天才女性指揮者リディア・ターを強烈に描き出す映画『TAR/ター』は、とんでもない作品だ。「縦軸」としてのターの存在感があまりにも強すぎるため「横軸」を上手く捉えきれず、結果「よく分からなかった」という感想で終わったが、それでも「観て良かった」と感じるほど、揺さぶられる作品だった
あわせて読みたい
【実話】映画『グッドバイ、バッドマガジンズ』(杏花主演)が描く、もの作りの絶望(と楽しさ)
実在したエロ雑誌編集部を舞台に、タブーも忖度もなく業界の内実を描き切る映画『グッドバイ、バッドマガジンズ』は、「エロ雑誌」をテーマにしながら、「もの作りに懸ける想い」や「仕事への向き合い方」などがリアルに描かれる素敵な映画だった。とにかく、主役を演じた杏花が良い
あわせて読みたい
【勝負】実話を基にコンピューター将棋を描く映画『AWAKE』が人間同士の対局の面白さを再認識させる
実際に行われた将棋の対局をベースにして描かれる映画『AWAKE』は、プロ棋士と将棋ソフトの闘いを「人間ドラマ」として描き出す物語だ。年に4人しかプロ棋士になれない厳しい世界においては、「夢破れた者たち」もまた魅力的な物語を有している。光と影を対比的に描き出す、見事な作品
あわせて読みたい
【衝撃】自ら立ち上げた「大分トリニータ」を放漫経営で潰したとされる溝畑宏の「真の実像」に迫る本:…
まったく何もないところからサッカーのクラブチーム「大分トリニータ」を立ち上げ、「県リーグから出発してチャンピオンになる」というJリーグ史上初の快挙を成し遂げた天才・溝畑宏を描く『爆走社長の天国と地獄』から、「正しく評価することの難しさ」について考える
あわせて読みたい
【実話】ポートアーサー銃乱射事件を扱う映画『ニトラム』が示す、犯罪への傾倒に抗えない人生の不条理
オーストラリアで実際に起こった銃乱射事件の犯人の生い立ちを描く映画『ニトラム/NITRAM』は、「頼むから何も起こらないでくれ」と願ってしまうほどの異様な不穏さに満ちている。「社会に順応できない人間」を社会がどう受け入れるべきかについて改めて考えさせる作品だ
あわせて読みたい
【偉業】「卓球王国・中国」実現のため、周恩来が頭を下げて請うた天才・荻村伊智朗の信じがたい努力と…
「20世紀を代表するスポーツ選手」というアンケートで、その当時大活躍していた中田英寿よりも高順位だった荻村伊智朗を知っているだろうか?選手としてだけでなく、指導者としてもとんでもない功績を残した彼の生涯を描く『ピンポンさん』から、ノーベル平和賞級の活躍を知る
あわせて読みたい
【挑戦】手足の指を失いながら、今なお挑戦し続ける世界的クライマー山野井泰史の”現在”を描く映画:『…
世界的クライマーとして知られる山野井泰史。手足の指を10本も失いながら、未だに世界のトップをひた走る男の「伝説的偉業」と「現在」を映し出すドキュメンタリー映画『人生クライマー』には、小学生の頃から山のことしか考えてこなかった男のヤバい人生が凝縮されている
あわせて読みたい
【人類学】少数民族・ムラブリ族に潜入した映画『森のムラブリ』は、私たちの「当たり前」を鮮やかに壊す
タイとラオスにまたがって存在する少数民族・ムラブリ族に密着したドキュメンタリー映画『森のムラブリ』。「ムラブリ族の居住地でたまたま出会った日本人人類学者」と意気投合し生まれたこの映画は、私たちがいかに「常識」「当たり前」という感覚に囚われているのかを炙り出してくれる
あわせて読みたい
【伝説】やり投げ選手・溝口和洋は「思考力」が凄まじかった!「幻の世界記録」など数々の逸話を残した…
世界レベルのやり投げ選手だった溝口和洋を知っているだろうか? 私は本書『一投に賭ける』で初めてその存在を知った。他の追随を許さないほどの圧倒的なトレーニングと、常識を疑い続けるずば抜けた思考力を武器に、体格で劣る日本人ながら「幻の世界記録」を叩き出した天才の伝説と実像
あわせて読みたい
【驚嘆】「現在は森でキノコ狩り」と噂の天才”変人”数学者グリゴリー・ペレルマンの「ポアンカレ予想証…
数学界の超難問ポアンカレ予想を解決したが、100万ドルの賞金を断り、フィールズ賞(ノーベル賞級の栄誉)も辞退、現在は「森できのこ採取」と噂の天才数学者グリゴリー・ペレルマンの生涯を描く評伝『完全なる証明』。数学に関する記述はほぼなく、ソ連で生まれ育った1人の「ギフテッド」の苦悩に満ちた人生を丁寧に描き出す1冊
あわせて読みたい
【あらすじ】蝦夷地の歴史と英雄・阿弖流為を描く高橋克彦の超大作小説『火怨』は全人類必読の超傑作
大げさではなく、「死ぬまでに絶対に読んでほしい1冊」としてお勧めしたい高橋克彦『火怨』は凄まじい小説だ。歴史が苦手で嫌いな私でも、上下1000ページの物語を一気読みだった。人間が人間として生きていく上で大事なものが詰まった、矜持と信念に溢れた物語に酔いしれてほしい
あわせて読みたい
【革命】観る将必読。「将棋を観ること」の本質、より面白くなる見方、そして羽生善治の凄さが満載:『…
野球なら「なんで今振らないんだ!」みたいな素人の野次が成立するのに、将棋は「指せなきゃ観てもつまらない」と思われるのは何故か。この疑問を起点に、「将棋を観ること」と「羽生善治の凄さ」に肉薄する『羽生善治と現代』は、「将棋鑑賞」をより面白くしてくれる話が満載
あわせて読みたい
【驚異】甲子園「2.9連覇」を成し遂げた駒大苫小牧野球部監督・香田誉士史の破天荒で規格外の人生:『勝…
「田中将大と斎藤佑樹の死闘」「37年ぶりの決勝戦再試合」「驚異の2.9連覇」など話題に事欠かなかった駒大苫小牧野球部。その伝説のチームを率いた名将・香田誉士史の評伝『勝ちすぎた監督』は、体罰が問題になった男の毀誉褒貶を余すところなく描き出す。しかしとんでもない男だ
あわせて読みたい
【圧巻】150年前に気球で科学と天気予報の歴史を変えた挑戦者を描く映画『イントゥ・ザ・スカイ』
「天気予報」が「占い」と同等に扱われていた1860年代に、気球を使って気象の歴史を切り開いた者たちがいた。映画『イントゥ・ザ・スカイ』は、酸素ボンベ無しで高度1万1000m以上まで辿り着いた科学者と気球操縦士の物語であり、「常識を乗り越える冒険」の素晴らしさを教えてくれる
あわせて読みたい
【感想】阿部サダヲが狂気を怪演。映画『死刑にいたる病』が突きつける「生きるのに必要なもの」の違い
サイコパスの連続殺人鬼・榛村大和を阿部サダヲが演じる映画『死刑にいたる病』は、「生きていくのに必要なもの」について考えさせる映画でもある。目に光を感じさせない阿部サダヲの演技が、リアリティを感じにくい「榛村大和」という人物を見事に屹立させる素晴らしい映画
あわせて読みたい
【欠落】映画『オードリー・ヘプバーン』が映し出す大スターの生き方。晩年に至るまで生涯抱いた悲しみ…
映画『オードリー・ヘプバーン』は、世界的大スターの知られざる素顔を切り取るドキュメンタリーだ。戦争による壮絶な飢え、父親の失踪、消えぬ孤独感、偶然がもたらした映画『ローマの休日』のオーディション、ユニセフでの活動など、様々な証言を元に稀代の天才を描き出す
あわせて読みたい
【感想】湯浅政明監督アニメ映画『犬王』は、実在した能楽師を”異形”として描くスペクタクル平家物語
観るつもりなし、期待値ゼロ、事前情報ほぼ皆無の状態で観た映画『犬王』(湯浅政明監督)はあまりにも凄まじく、私はこんなとんでもない傑作を見逃すところだったのかと驚愕させられた。原作の古川日出男が紡ぐ狂気の世界観に、リアルな「ライブ感」が加わった、素晴らしすぎる「音楽映画」
あわせて読みたい
【あらすじ】映画化の小説『僕は、線を描く』。才能・センスではない「芸術の本質」に砥上裕將が迫る
「水墨画」という、多くの人にとって馴染みが無いだろう芸術を題材に据えた小説『線は、僕を描く』は、青春の葛藤と創作の苦悩を描き出す作品だ。「未経験のど素人である主人公が、巨匠の孫娘と勝負する」という、普通ならあり得ない展開をリアルに感じさせる設定が見事
あわせて読みたい
【特異】「カメラの存在」というドキュメンタリーの大前提を覆す映画『GUNDA/グンダ』の斬新さ
映画『GUNDA/グンダ』は、「カメラの存在」「撮影者の意図」を介在させずにドキュメンタリーとして成立させた、非常に異端的な作品だと私は感じた。ドキュメンタリーの「デュシャンの『泉』」と呼んでもいいのではないか。「家畜」を被写体に据えたという点も非常に絶妙
あわせて読みたい
【アート】映画『ダ・ヴィンチは誰に微笑む』が描く「美術界の闇」と「芸術作品の真正性」の奥深さ
美術界史上最高額510億円で落札された通称「救世主」は、発見される以前から「レオナルド・ダ・ヴィンチの失われた作品」として知られる有名な絵だった。映画『ダ・ヴィンチは誰に微笑む』は、「芸術作品の真正性の問題」に斬り込み、魑魅魍魎渦巻く美術界を魅力的に描き出す
あわせて読みたい
【信念】水俣病の真実を世界に伝えた写真家ユージン・スミスを描く映画。真実とは「痛みへの共感」だ:…
私はその存在をまったく知らなかったが、「水俣病」を「世界中が知る公害」にした報道写真家がいる。映画『MINAMATA―ミナマタ―』は、水俣病の真実を世界に伝えたユージン・スミスの知られざる生涯と、理不尽に立ち向かう多くの人々の奮闘を描き出す
あわせて読みたい
【革命】電子音楽誕生の陰に女性あり。楽器ではなく機械での作曲に挑んだ者たちを描く映画:『ショック…
現代では当たり前の「電子音楽」。その黎明期には、既存の音楽界から排除されていた女性が多く活躍した。1978年、パリに住む1人の女性が「電子音楽」の革命の扉をまさに開こうとしている、その1日を追う映画『ショック・ド・フューチャー』が描き出す「創作の熱狂」
あわせて読みたい
【感想】才能の開花には”極限の環境”が必要か?映画『セッション』が描く世界を私は否定したい
「追い込む指導者」が作り出す”極限の環境”だからこそ、才能が開花する可能性もあるとは思う。しかし、そのような環境はどうしても必要だろうか?最高峰の音楽院での壮絶な”指導”を描く映画『セッション』から、私たちの生活を豊かにしてくれるものの背後にある「死者」を想像する
あわせて読みたい
【革新】映画音楽における唯一のルールは「ルールなど無い」だ。”異次元の音”を生み出す天才を追う:映…
「無声映画」から始まった映画業界で、音楽の重要性はいかに認識されたのか?『JAWS』の印象的な音楽を生み出した天才は、映画音楽に何をもたらしたのか?様々な映画の実際の映像を組み込みながら、「映画音楽」の世界を深堀りする映画『すばらしき映画音楽たち』で、異才たちの「創作」に触れる
あわせて読みたい
【アート】「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」(森美術館)と「美術手帖 Chim↑Pom特集」の衝撃から「…
Chim↑Pomというアーティストについてさして詳しいことを知らずに観に行った、森美術館の「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」に、思考をドバドバと刺激されまくったので、Chim↑Pomが特集された「美術手帖」も慌てて買い、Chim↑Pomについてメッチャ考えてみた
あわせて読みたい
【本質】子どもの頃には読めない哲学書。「他人の哲学はつまらない」と語る著者が説く「問うこと」の大…
『<子ども>のための哲学』は決して、「子どもでも易しく理解できる哲学の入門書」ではない。むしろかなり難易度が高いと言っていい。著者の永井均が、子どもの頃から囚われ続けている2つの大きな疑問をベースに、「『哲学する』とはどういうことか?」を深堀りする作品
あわせて読みたい
【解釈】詩人が語る詩の読み方。意味や読み方や良さが分からなくて全然気にしなくていい:『今を生きる…
私は学生時代ずっと国語の授業が嫌いでしたが、それは「作品の解釈には正解がある」という決めつけが受け入れ難かったからです。しかし、詩人・渡邊十絲子の『今を生きるための現代詩』を読んで、詩に限らずどんな作品も、「解釈など不要」「理解できなければ分からないままでいい」と思えるようになりました
あわせて読みたい
【博覧強記】「紙の本はなくなる」説に「文化は忘却されるからこそ価値がある」と反論する世界的文学者…
世界的文学者であり、「紙の本」を偏愛するウンベルト・エーコが語る、「忘却という機能があるから書物に価値がある」という主張は実にスリリングだ。『もうすぐ絶滅するという紙の書物について』での対談から、「忘却しない電子データ」のデメリットと「本」の可能性を知る
あわせて読みたい
【感想】池田晶子『14歳からの哲学』で思考・自由・孤独の大事さを知る。孤独を感じることって大事だ
「元々持ってた価値観とは違う考えに触れ、それを理解したいと思う場面」でしか「考える」という行為は発動しないと著者は言う。つまり我々は普段、まったく考えていないのだ。『14歳からの哲学』をベースに、「考えること」と自由・孤独・人生との関係を知る
あわせて読みたい
【飛躍】有名哲学者は”中二病”だった?飲茶氏が易しく語る「古い常識を乗り越えるための哲学の力」:『1…
『14歳からの哲学入門』というタイトルは、「14歳向けの本」という意味ではなく、「14歳は哲学することに向いている」という示唆である。飲茶氏は「偉大な哲学者は皆”中二病”だ」と説き、特に若い人に向けて、「新しい価値観を生み出すためには哲学が重要だ」と語る
あわせて読みたい
【創作】クリエイターになりたい人は必読。ジブリに見習い入社した川上量生が語るコンテンツの本質:『…
ドワンゴの会長職に就きながら、ジブリに「見習い」として入社した川上量生が、様々なクリエイターの仕事に触れ、色んな質問をぶつけることで、「コンテンツとは何か」を考える『コンテンツの秘密』から、「創作」という営みの本質や、「クリエイター」の理屈を学ぶ
あわせて読みたい
【奇跡】鈴木敏夫が2人の天才、高畑勲と宮崎駿を語る。ジブリの誕生から驚きの創作秘話まで:『天才の思…
徳間書店から成り行きでジブリ入りすることになったプロデューサー・鈴木敏夫が、宮崎駿・高畑勲という2人の天才と共に作り上げたジブリ作品とその背景を語り尽くす『天才の思考 高畑勲と宮崎駿』。日本のアニメ界のトップランナーたちの軌跡の奇跡を知る
あわせて読みたい
【実像】ベートーヴェンの「有名なエピソード」をほぼ一人で捏造・創作した天才プロデューサーの実像:…
ベートーヴェンと言えば、誰もが知っている「運命」を始め、天才音楽家として音楽史に名を刻む人物だが、彼について良く知られたエピソードのほとんどは実は捏造かもしれない。『ベートーヴェン捏造 名プロデューサーは嘘をつく』が描く、シンドラーという”天才”の実像
あわせて読みたい
【教養】美術を「感じたまま鑑賞する」のは難しい。必要な予備知識をインストールするための1冊:『武器…
芸術を「感性の赴くまま見る」のは、日本特有だそうだ。欧米では美術は「勉強するもの」と認識されており、本書ではアートを理解しようとするスタンスがビジネスにも役立つと示唆される。美術館館長を務める著者の『武器になる知的教養 西洋美術鑑賞』から基礎の基礎を学ぶ
あわせて読みたい
【鋭い】「俳優・堺雅人」のエピソードを綴るエッセイ。考える俳優の視点と言葉はとても面白い:『文・…
ドラマ『半沢直樹』で一躍脚光を浴びた堺雅人のエッセイ『文・堺雅人』は、「ファン向けの作品」に留まらない。言語化する力が高く、日常の中の些細な事柄を丁寧に掬い上げ、言葉との格闘を繰り広げる俳優の文章は、力強く自立しながらもゆるりと入り込んでくる
あわせて読みたい
【天才】写真家・森山大道に密着する映画。菅田将暉の声でカッコよく始まる「撮り続ける男」の生き様:…
映画『あゝ荒野』のスチール撮影の際に憧れの森山大道に初めて会ったという菅田将暉の声で始まる映画『過去はいつも新しく、未来はつねに懐かしい』は、ちゃちなデジカメ1つでひたすら撮り続ける異端児の姿と、50年前の処女作復活物語が見事に交錯する
あわせて読みたい
【狂気】稀少本を収集・売買する「愛すべき変人コレクター」の世界と、インターネットによる激変:映画…
広大な本の世界を狩人のように渉猟し、お気に入りの本を異常なまでに偏愛する者たちを描き出す映画『ブックセラーズ』。実在の稀少本コレクターたちが、本への愛を語り、新たな価値を見出し、次世代を教育し、インターネットの脅威にどう立ち向かっているのかを知る
あわせて読みたい
【感想】「献身」こそがしんどくてつらい。映画『劇場』(又吉直樹原作)が抉る「信頼されること」の甘…
自信が持てない時、たった1人でも自分を肯定してくれる人がいてくれるだけで前に進めることがある。しかしその一方で、揺るぎない信頼に追い詰められてしまうこともある。映画『劇場』から、信じてくれる人に辛く当たってしまう歪んだ心の動きを知る
あわせて読みたい
【映画】『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』で号泣し続けた私はTVアニメを観ていない
TVアニメは観ていない、というかその存在さえ知らず、物語や登場人物の設定も何も知らないまま観に行った映画『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』に、私は大号泣した。「悪意のない物語」は基本的に好きではないが、この作品は驚くほど私に突き刺さった
あわせて読みたい
【差別】「女性の権利」とは闘争の歴史だ。ハリウッドを支えるスタントウーマンたちの苦悩と挑戦:『ス…
男性以上に危険で高度な技術を要するのに、男性優位な映画業界で低く評価されたままの女性スタントたちを描く映画『スタントウーマン ハリウッドの知られざるヒーローたち』。女性スタントの圧倒的な努力・技術と、その奮闘の歴史を知る。
あわせて読みたい
【救い】耐えられない辛さの中でどう生きるか。短歌で弱者の味方を志すホームレス少女の生き様:『セー…
死にゆく母を眺め、施設で暴力を振るわれ、拾った新聞で文字を覚えたという壮絶な過去を持つ鳥居。『セーラー服の歌人 鳥居』は、そんな辛い境遇を背景に、辛さに震えているだろう誰かを救うために短歌を生み出し続ける生き方を描き出す。凄い人がいるものだ
あわせて読みたい
【諦め】「人間が創作すること」に意味はあるか?AI社会で問われる、「創作の悩み」以前の問題:『電気…
AIが個人の好みに合わせて作曲してくれる世界に、「作曲家」の存在価値はあるだろうか?我々がもうすぐ経験するだろう近未来を描く『電気じかけのクジラは歌う』をベースに、「創作の世界に足を踏み入れるべきか」という問いに直面せざるを得ない現実を考える
あわせて読みたい
【継続】「言語化できない」を乗り越えろ。「読者としての文章術」で、自分の思考をクリアにする:『読…
ブログやSNSなどが登場したことで、文章を書く機会は増えていると言える。しかし同時に、「他人に評価されるために書く」という意識も強くなっているだろう。『読みたいことを書けばいい』から、「楽しく書き”続ける”」ための心得を学ぶ
あわせて読みたい
【表現者】「センスが良い」という言葉に逃げない。自分の内側から何かを表現することの本質:『作詞少…
大前提として、表現には「技術」が必要だ。しかし、「技術」だけでは乗り越えられない部分も当然ある。それを「あいつはセンスが良いから」という言葉に逃げずに、向き合ってぶつかっていくための心得とは何か。『作詞少女』をベースに「表現することの本質」を探る
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
才能・センスがない【本・映画の感想】 | ルシルナ
子どもの頃は、自分が何かの才能やセンスに恵まれていることを期待していましたが、残念ながら天才ではありませんでした。昔はやはり、凄い人に嫉妬したり、誰かと比べて苦…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…






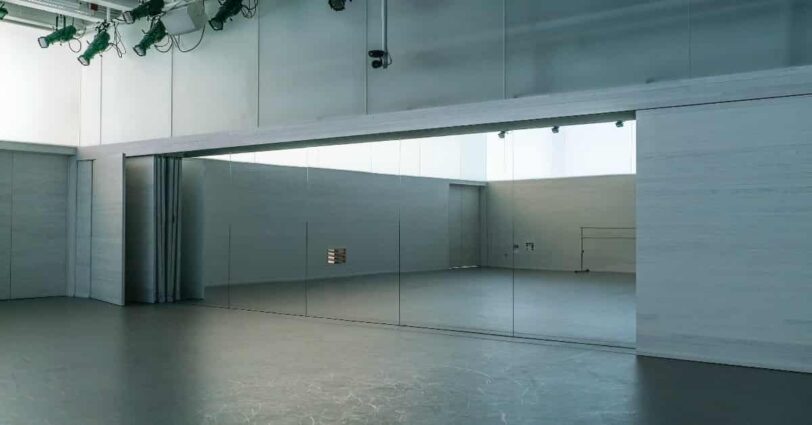














































































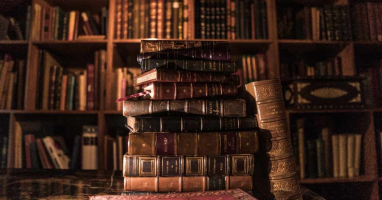






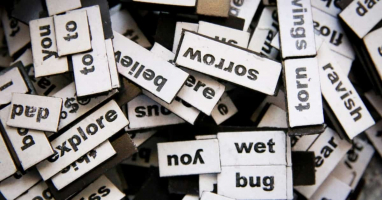

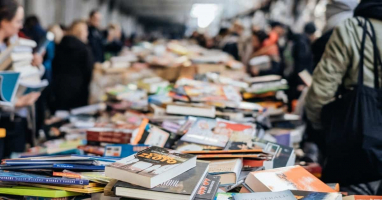

















コメント