目次
はじめに
この記事で取り上げる本
著:梅田望夫
¥836 (2022/11/27 18:44時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
この本をガイドにしながら記事を書いていきます
この記事の3つの要点
- 絵が描けなくても絵画を見て「感動した」と思うのは自然だが、将棋を指せない人が対局を見て「感動した」と口にするのは憚れる現実
- 「伝統」に凝り固まっていた将棋界の因習を打破し、「純粋な勝負」としての将棋をスタートさせた羽生善治の功績
- 「指さない将棋ファン」をいかに増やすかという渡辺明の問題意識と、凄まじい研究の先にたどり着けるかもしれない「真理」
これまで考えたことのない「問い」を軸に、現代将棋の様々な話題を盛り込む作品であり、非常に面白い
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!「文章の書き方が分からない」「文章力がないから鍛えたい」という方にオススメ…
「文章の書き方」についてのKindle本を出版しました。「文章が書けない」「どう書いたらいいか分からない」「文章力を向上させたい」という方の悩みを解消できるような本に仕上げたつもりです。数多くの文章を書き、さらに頼まれて文章を推敲してきた経験を踏まえ、「文章を書けるようになるにはどうしたらいいか」についての私なりの考えをまとめました。
将棋は何故「指せないと面白さが分からない」と思われがちなのか?将棋の新たな見方と、羽生善治の凄さが分かる1冊
あわせて読みたい
【特異】「カメラの存在」というドキュメンタリーの大前提を覆す映画『GUNDA/グンダ』の斬新さ
映画『GUNDA/グンダ』は、「カメラの存在」「撮影者の意図」を介在させずにドキュメンタリーとして成立させた、非常に異端的な作品だと私は感じた。ドキュメンタリーの「デュシャンの『泉』」と呼んでもいいのではないか。「家畜」を被写体に据えたという点も非常に絶妙
本書の中心となる問いは、「将棋の対局が『ルールを理解して指せる人間が観ないと面白くない』と受け取られてしまうのは何故か?」である。最近は「観る将」という、「ルールを理解しないまま将棋を観て楽しむ人」が増えており、この問いの意味を理解できない者もいるかもしれない。しかし本書が出版された時点では、ネット配信などの将棋を気軽に観られる環境はなかったはずで、「将棋」は今ほど身近に接することが出来るエンタメではなかったのだ。どちらかと言えば「自分でも指した経験のある将棋好きが熱心に観るもの」として受け取られていたはずだし、私もそんな印象を抱いていた。
そして、そんな将棋の捉えられ方に疑問を呈するのが本書なのである。

著者はシリコンバレー在住で、『ウェブ進化論』という新書が大ベストセラーとなった。著者自身、将棋を指しはするもののそこまで強くはなく、どちらかと言えば「将棋を観ること」を趣味にしているという。
著:梅田 望夫
¥880 (2022/11/27 18:48時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
そんな著者が、「将棋を観ること」を起点に、将棋の楽しみ方や羽生善治の凄さについて語る作品というわけだ。私も、将棋のルールは分かるが全然強くない人間で、いわゆる「下手の横好き」という感じである。そんな人間でもメチャクチャ楽しめる1冊で、物凄く面白かった。
あわせて読みたい
【教育】映画化に『3月のライオン』のモデルと話題の村山聖。その師匠である森信雄が語る「育て方」論:…
自身は決して強い棋士ではないが、棋界で最も多くの弟子を育てた森信雄。「村山聖の師匠」として有名な彼の「師匠としてのあり方」を描く『一門 ”冴えん師匠”がなぜ強い棋士を育てられたのか?』から、教育することの難しさと、その秘訣を学ぶ
本書は、著者が過去に出版した2冊の本、『シリコンバレーから将棋を観る 羽生善治と現代』『どうして羽生さんだけが、そんなに強いんですか?――現代将棋と進化の物語』を合本し、さらに羽生善治との対談や対局のリアルタイム観戦記などを新たに収録した作品になっている。将棋に詳しくなくても、「ちょっとは興味がある」程度の関心があれば十分楽しめる作品だと思うので、是非手に取ってみてほしい。
「将棋を観ること」に対して、どうして私たちは高いハードルを感じてしまうのか?
先程も触れたが、本書の中心的なテーマに改めて触れておこう。この点については本書にも、
『シリコンバレーから将棋を観る』と『どうして羽生さんだけが、そんなに強いんですか?』の二冊を貫く主テーマとは「将棋を観る」という行為についてである。
という形で明確に記されている。もう少し具体的に触れている箇所も引用しておこう。
将棋と言えばあくまでも「指す」もの、将棋とは二人で盤をはさんで戦うもの、というのが常識である。「趣味が将棋」といえば、ふつうは「将棋を指す」ことを意味する。そして将棋を指さない人、将棋が弱い人は、将棋を観てもきっとわからないだろう、と思われている。

あわせて読みたい
【妄執】チェス史上における天才ボビー・フィッシャーを描く映画。冷戦下の米ソ対立が盤上でも:映画『…
「500年に一度の天才」などと評され、一介のチェスプレーヤーでありながら世界的な名声を獲得するに至ったアメリカ人のボビー・フィッシャー。彼の生涯を描く映画『完全なるチェックメイト』から、今でも「伝説」と語り継がれる対局と、冷戦下ゆえの激動を知る
最近では、「藤井聡太がおやつに何を食べるのか」「対局中の棋士がどんな仕草をしているのか」など、将棋そのものに注目するわけではない「観る将」も増えてきているので、このような感覚は薄れているのかもしれない。一方で、「理解できる」という方もいるだろう。私も、元々はそう感じる側だった。自分は将棋が弱い、だからプロの対局を観たって分かるはずがない、と当然のように考えていたのだ。
しかし、本書のこんな記述を読んで、「なるほど、将棋に対してそのような感覚は確かにおかしい」と感じさせられた。
しかし考えてみれば、それも不思議な話なのである。
「小説を書く」人がいて「小説を読む」人がいる。「音楽を演奏する」人がいて「音楽を聴く」人がいる。「野球をやる」人がいて「野球を見る」人がいる。「小説を読む」「音楽を聴く」「野球を見る」のが趣味だという人に、「小説を書けないのに読んで面白いわけがないだろう」とか「演奏もできないのに聴いて楽しいはずがないよね」とか「野球をやらない人が見ても仕方がないでしょう」などと、誰も言わない。しかし将棋については「将棋を指さない人は、観ても面白くないでしょ、わからないでしょ」と言われてしまいがちだ。
あわせて読みたい
【奇跡】ビッグデータに”直感”を組み込んで活用。メジャーリーグを変えたデータ分析家の奮闘:『アスト…
「半世紀で最悪の野球チーム」と呼ばれたアストロズは、ビッグデータの分析によって優勝を果たす。その偉業は、野球のド素人によって行われた。『アストロボール』をベースに、「ビッグデータ」に「人間の直感」を組み込むという革命について学ぶ
いかがだろうか? 私はこの文章を読んで、「確かにその通りだ」と感じた。同じような捉えられ方になるものは他にも世の中に存在するかもしれないが、少なくとも「将棋」の場合は、「やらない人間が観ても面白くないはず」という感覚が当たり前のように存在しているというわけだ。
ちなみにだが、私は将棋に限らず、「リアルタイムで行われていることを鑑賞する」という行為がそもそも得意ではない。将棋、スポーツ、F1、競馬などを鑑賞する趣味がまったくないのだ。好き嫌いというよりは、得意不得意の問題だと自分では思っている。何を観ても、「結果だけ教えてくれ」というような身も蓋もない感覚になってしまうのだ。だから、スポーツ鑑賞と将棋鑑賞における私自身の実感を比べているわけではない。なんとなく感覚的に、「スポーツと将棋では確かに受け取り方が異なる」と理解できるというわけだ。
あわせて読みたい
【改革】AIは将棋をどう変えた?羽生善治・渡辺明ら11人の現役棋士が語る将棋の未来:『不屈の棋士』(…
既に将棋AIの実力はプロ棋士を越えたとも言われる。しかし、「棋力が強いかどうか」だけでは将棋AIの良し悪しは判断できない。11人の現役棋士が登場する『不屈の棋士』をベースに、「AIは将棋界をどう変えたのか?」について語る
では、このような違いは一体どこから生まれるのだろうか? その点について著者は、イチローに言及した後で、こんな風にまとめている。
イチローのいる野球の世界は、テレビ画面を通すとあまりにもやさしく見えてしまう。だからファンが映像で「わかった気になって楽しむ」ことができる。それゆえに野球は、膨大なファン層を抱える人気スポーツたり得るのである。

どんなスポーツ競技も、また頭脳スポーツである将棋も、その奥の深さを、観ている者が完全に理解したり、感じとったりすることはできない。しかし野球が「テレビ画面を通すとやさしく見えてしまう」から「わかった気になって楽しめる」のに対し、放っておくと将棋は「あまりにも高度でわからない」という感覚を、観る側に呼び起こさせてしまう。
あわせて読みたい
【狂気】バケモン・鶴瓶を映し出す映画。「おもしろいオッチャン」に潜む「異常さ」と「芸への情熱」:…
「俺が死ぬまで公開するな」という条件で撮影が許可された映画『バケモン』。コロナ禍で映画館が苦境に立たされなければ、公開はずっと先だっただろう。テレビで見るのとは違う「芸人・笑福亭鶴瓶」の凄みを、古典落語の名作と名高い「らくだ」の変遷と共に切り取る
確かにその通りだ。「野球を観ているおじさん」のステレオタイプなイメージを思い浮かべてみれば、「なんでそこで振らないんだよ!」「そんなボールも取れないのかよ!」と野次を飛ばす姿が出てくるだろう。もちろん野球経験者もいるとは思うが、少なくとも世の中の「野球を観ているおじさん」のほとんどが、プロよりも野球が下手なはずだ。それなのに、さも自分の方が巧手であるかのような視点で試合を観ることが出来る。著者が言う、「テレビ画面を通すとあまりにもやさしく見えてしまう」という感覚は、私の中にはないが、現にそういうおじさんが存在する以上、そのような「魔法」は存在するのだろう。そしてその「魔法」こそが、膨大な「野球ファン」を生み出しているというわけだ。
しかし将棋の場合はそうはならない。将棋の対局を鑑賞している者が、「どうしてそんなところに打つんだよ!」と怒っている姿はなかなかイメージできないだろう。それよりも、「えっ? どうしてそんなところに打ったんだ?」という困惑が先に来るのではないかと思う。これはつまり、「棋士が打った手はきっと正解なのだろうが、何故それが正解なのか自分には分からない」という表明だ。この感覚は、野球を観る人とはまったく異なるものだと思う。
あわせて読みたい
【驚嘆】この物語は「AIの危険性」を指摘しているのか?「完璧な予知能力」を手にした人類の過ち:『預…
完璧な未来予知を行えるロボットを開発し、地震予知のため”だけ”に使おうとしている科学者の自制を無視して、その能力が解放されてしまう世界を描くコミック『預言者ピッピ』から、「未来が分からないからこそ今を生きる価値が生まれるのではないか」などについて考える
また、対談の中で羽生善治が口にするこんな言葉も印象的だった。
たとえば絵画なら、自分で絵が描けなくても「感動した」と言う自由が許されているわけです。システィーナ礼拝堂の「最後の審判」を見て感動した、と言って「おまえ、描けないだろう」とは言われないですよね。将棋を観て感動したと言うと「え、君どのくらい指せるの」となる(笑)。プロのように美しい将棋を自分で指せるようになるには、それこそ一生を費やさねばならない。そんな根性はないから観るだけのファンになるのだけれど、棋力が伴っていないと、発言は控えなくてはいけない。将棋の世界には、そんな暗黙の了解があったと思います。
確かに、絵なら「おまえ、描けないだろう」とは言われないが、将棋だと「え、君どのくらい指せるの」という反応になってしまう感じは理解できる。本書の面白さは、何よりもまずこの点に気づかせてくれたことだと言っていいだろう。私自身、「将棋はそういうものだ」と当たり前のように考えており、他の何かと比較するとこれほど変なのだということに気づかなかった。それが何であれ、「当たり前」だと思いこんでいる対象には、なかなか疑問を抱くことができない。本書で示される「将棋だけは何故『指せないと面白くない』と思われるのか」という問いは、そういう意味で非常に新鮮に感じられた。
あわせて読みたい
【非努力】頑張らない働き方・生き方のための考え方。「◯◯しなきゃ」のほとんどは諦めても問題ない:『…
ブロガーであるちきりんが、ブログに書いた記事を取捨選択し加筆修正した『ゆるく考えよう』は、「頑張ってしまう理由」や「欲望の正体」などを深堀りしながら、「世の中の当たり前から意識的に外れること」を指南する。思考を深め、自力で本質に行き着くための参考にも
むしろ将棋の方が「観る面白さ」が高いのではないかという指摘
このように将棋はハードルの高さを感じさせてしまうわけだが、羽生善治は、「テレビやネットを通じて観る」という点において、将棋は他のどんなものよりも面白みがあるはずだ、という発言をしている。

ところがテレビで見ているときは、そんなことは見えないわけですよ。投げる瞬間、捕る瞬間だけ。球場にある、そのスポーツの全情報量と、テレビが切り取って見せている情報量とに、差がありますよね。非対称というか、全然違うわけです。ところがね、将棋というのはそこが同じなんです。だからそこは、すごく可能性を感じるんです。全員が同じ局面で同じことを観ていられる、共有できる。
これも「なるほど」と感じさせる指摘だと思う。
あわせて読みたい
【実話】暗号機エニグマ解読のドラマと悲劇を映画化。天才チューリングはなぜ不遇の死を遂げたのか:『…
「解読不可能」とまで言われた最強の暗号機エニグマを打ち破ったのは、コンピューターの基本原理を生み出した天才数学者アラン・チューリングだった。映画『イミテーションゲーム』から、1400万人以上を救ったとされながら、偏見により自殺した不遇の人生を知る
最近では、VRなどの技術を使い、まるで球場にいるかのような視点で野球観戦が可能なシステムも存在するようだが、普通はテレビやスマホなどで観るだろう。その場合、当然のことながら「カメラが切り取る光景」しか観れないことになる。ピッチャーとバッターを映している時には、センターにいる選手が何をしているのかは分からないし、ボールが外野に飛んだ場合に、内野手がどんな動きをしているのかもなかなか知ることができない。
野球に限らずだと思うが、このように一般的なエンタメの場合、「現場の全情報」が「画面」を通すことによって激減してしまうことになる。
しかし将棋はそうではない。もちろん、実際に対局場にいるからこそ感じられる「独特の緊張感」みたいなものまではなかなか伝わらないかもしれないが、それでも、将棋の場合は、「現場の全情報」が「画面」を通してすべて伝わる。プレイヤーと観客が、同じ情報を共有できるというわけだ。
あわせて読みたい
【考察】アニメ映画『虐殺器官』は、「便利さが無関心を生む現実」をリアルに描く”無関心ではいられない…
便利すぎる世の中に生きていると、「この便利さはどのように生み出されているのか」を想像しなくなる。そしてその「無関心」は、世界を確実に悪化させてしまう。伊藤計劃の小説を原作とするアニメ映画『虐殺器官』から、「無関心という残虐さ」と「想像することの大事さ」を知る
そしてだからこそ、羽生善治はこんな風にも言う。
極端な話をすれば、ルールがわからなくたって、観ていればそれなりに面白いと思うんです。もちろんルールを知っていたら尚更、将棋の多面的な面白さに行き着くってことがあるんですけど、たとえ基本的なことを知らなくても、ただ観るものとしても、まあ、何かしらの価値はあるのではないかと思っています。
この点について羽生善治が具体的なことに言及しているわけではないが、私なりに勝手に解釈して説明を加えてみたいと思う。
例えば野球の場合、「現場の全情報」の内の一部を切り取ってカメラに収めなければならない。そして当然のことながら、「野球ファンが観たいと感じるもの」が優先して映し出されることになるだろう。つまり逆に言えば、野球のルールをまったく知らない者がテレビで野球観戦をする場合、「何故この場面をカメラが映しているのか」を理解できない状況もあるのではないかと思う。「ルールを理解している野球ファン」の目線で情報が切り取られているのだから、その映像は、ルールを知らない者には意味不明に映る可能性は十分にあるだろう。
あわせて読みたい
【感想】リドリー・スコット監督の映画『最後の決闘裁判』から、社会が”幻想”を共有する背景とその悲劇…
例えば、「1万円札」というただの紙切れに「価値を感じる」のは、社会の構成員が同じ「共同幻想」の中に生きているからだ。リドリー・スコット監督の映画『最後の決闘裁判』は、「強姦では妊娠しない」「裁判の勝者を決闘で決する」という社会通念と、現代にも通じる「共同幻想」の強さを描き出す
野球でイメージできなければ、まったくルールを知らないどこか外国のスポーツをテレビで観ていることを想像してみてほしい。それが球技だとして、例えばボールの行方をカメラが追わない場面があった場合、観ている側は「???」となるだろう。恐らく何らかのルールが存在し、ボールの行方以上に注目すべきポイントがあるからこそそのような映像になっていると推定はできるが、ルールを知らなければ詳しい状況は理解できない。このように、情報が「非対称」であることは、「観る」という行為に直接的に影響を与えるのだ。

あわせて読みたい
【ル・マン】ゲーマーが本物のカーレース出場!映画『グランツーリスモ』が描く衝撃的すぎる軌跡(ヤン…
映画『グランツーリスモ』は、「ゲーマーをレーサーにする」という、実際に行われた無謀すぎるプロジェクトを基にした作品だ。登場人物は全員イカれていると感じたが、物語としてはシンプルかつ王道で、誰もが先の展開を予想出来るだろう。しかしそれでも、圧倒的に面白かった、ちょっと凄まじすぎる映画だった
しかし先述した通り、将棋の場合は「現場の全情報」が映し出される。「ルールを理解している将棋ファン」の目線で情報が取捨選択されるのではなく、プレイヤーと同等の情報を観客も得られるのだ。ということは、「どの情報に注目するか」は観る側の選択次第ということになるだろう。
こう考えると、「ルールを知らなくても『ただ観るもの』として価値がある」という感覚も理解しやすくなるだろうと思う。非常に面白い指摘だと感じた。
あわせて読みたい
【表現】映画『名付けようのない踊り』で初めて見た田中泯のダンス。「芸術以前」を志向する圧倒的パワー
映画『名付けようのない踊り』の中で田中泯は言う。「私」や「個性」を表現することには違和感がある、と。「踊りのために身体を作る」のではなく、「野良仕事で出来た身体で踊る」のだ、と。芸術になる前の踊りを探したい、と。「唯一無二の表現者」の生涯と現在地を映し出すドキュメンタリー
また本書には、トッププロ棋士の1人である渡辺明についても取り上げられている。将棋界には、中学卒業前にプロ棋士になった超天才が5人おり、彼もその内の1人だ。他の4人は、加藤一二三、谷川浩司、羽生善治、藤井聡太である。錚々たるメンツと言っていいだろう。
そんな渡辺明は、『頭脳勝負』という新書を出版しており、その中で早くも、「指さない将棋ファン」「将棋が弱くても観ることを楽しむファン」を増やさなければならないと問題意識を示していたという。
著:渡辺明
¥770 (2022/11/27 18:59時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
そんな意識を持っているからこそ、彼自身も様々な取り組みを行っている。例えば、自身のブログを開設し、棋士の日常を綴るなど対局場以外の姿も見せるようにした。また、「対局翌日に本音で解説する」という画期的な取り組みも始めている。勝った対局だけではなく、負けた対局であっても、何を考えどのような意図で指していったのかを自らの言葉で語るのだ。観客は「現場の全情報」を知ることが出来るわけだが、当然、「棋士の頭の中」まで覗くことはできない。だからこそ、彼の行動は、「将棋を観ること」を補完する非常に重要な要素だと言っていいだろう。
あわせて読みたい
【奇跡】鈴木敏夫が2人の天才、高畑勲と宮崎駿を語る。ジブリの誕生から驚きの創作秘話まで:『天才の思…
徳間書店から成り行きでジブリ入りすることになったプロデューサー・鈴木敏夫が、宮崎駿・高畑勲という2人の天才と共に作り上げたジブリ作品とその背景を語り尽くす『天才の思考 高畑勲と宮崎駿』。日本のアニメ界のトップランナーたちの軌跡の奇跡を知る
棋士は日々の研究に時間を割く必要があり、とにかく時間がない。そんな中で、トッププロである渡辺明が、「観るだけの将棋ファンを増やさなければならない」という問題意識を持って様々な取り組みを行っていることが、将棋界に大きな変化をもたらしているのではないかと本書では指摘されていた。実際に「観る将」と呼ばれる人が増えているわけで、彼の努力は身を結んだと言っていいのではないかと思う。

羽生善治が将棋界にもたらした「革命」
あわせて読みたい
【天才】映画『笑いのカイブツ』のモデル「伝説のハガキ職人ツチヤタカユキ」の狂気に共感させられた
『「伝説のハガキ職人」として知られるツチヤタカユキの自伝的小説を基にした映画『笑いのカイブツ』は、凄まじい狂気に彩られた作品だった。「お笑い」にすべてを捧げ、「お笑い」以外はどうでもいいと考えているツチヤタカユキが、「コミュ力」や「人間関係」で躓かされる”理不尽”な世の中に、色々と考えさせられる
本書のもう1つのテーマは、「羽生善治はどれほど凄い棋士なのか」である。もちろん、前人未到の記録を次々と成し遂げているという知識は、将棋にさほど詳しくない人でもニュースなどで見知っているだろうし、「凄いことは十分分かっている」と感じる人も多いかもしれない。しかし本書には、「なるほど、そんな『革命』も起こしていたのか」と感じさせるような驚きのエピソードも紹介されていた。
それが「序盤の進め方」である。
あわせて読みたい
【感想】湯浅政明監督アニメ映画『犬王』は、実在した能楽師を”異形”として描くスペクタクル平家物語
観るつもりなし、期待値ゼロ、事前情報ほぼ皆無の状態で観た映画『犬王』(湯浅政明監督)はあまりにも凄まじく、私はこんなとんでもない傑作を見逃すところだったのかと驚愕させられた。原作の古川日出男が紡ぐ狂気の世界観に、リアルな「ライブ感」が加わった、素晴らしすぎる「音楽映画」
その説明の前に、羽生善治が現状を打破する以前の将棋界について書かれた記述をまずは引用してみよう。
羽生さんが初めて七冠になったとき(著者注:1996年)は、将棋界全体の戦法の幅が狭く、どんな戦型でも中盤は指定局面になることが多かった。プロが序盤で個性を発揮できない時代だったわけです。
あわせて読みたい
【抵抗】映画『熊は、いない』は、映画製作を禁じられた映画監督ジャファル・パナヒの執念の結晶だ
映画『熊は、いない』は、「イラン当局から映画製作を20年間も禁じられながら、その後も作品を生み出し続けるジャファル・パナヒ監督」の手によるもので、彼は本作公開後に収監させられてしまった。パナヒ監督が「本人役」として出演する、「ドキュメンタリーとフィクションのあわい」を縫うような異様な作品だ
羽生に現代将棋の本質について尋ねるとき、決まって彼が語るのは、つい最近まで「盤上に自由がなかった」ということである。(中略)羽生が問題視していたのは、将棋界に存在していた、日本の村社会にも共通する、独特の年功を重んずる伝統や暗黙のルールが、盤上の自由を妨げていたことだった。
将棋に詳しい人なら知っていると思うが、そうではない方には少し説明が必要だろう。
あわせて読みたい
【青春】二宮和也で映画化もされた『赤めだか』。天才・立川談志を弟子・談春が描く衝撃爆笑自伝エッセイ
「落語協会」を飛び出し、新たに「落語立川流」を創設した立川談志と、そんな立川談志に弟子入りした立川談春。「師匠」と「弟子」という関係で過ごした”ぶっ飛んだ日々”を描く立川談春のエッセイ『赤めだか』は、立川談志の異端さに振り回された立川談春の成長譚が面白い
日本の将棋文化は、非常に長い伝統を持っており、現在のようなルールが確立したのは室町時代とされている。そしてそれが何であれ、長く続けば続くほど、「暗黙のルール」みたいなものが生まれてしまいがちだ。将棋の場合、「序盤における駒の進め方」もその1つである。将棋は長らく、「終盤戦でのぶつかり合いで勝負が決する」と考えられており、それ故、序盤は「こういう駒の動かし方が普通だよね」という、いわゆる「定跡形」と呼ばれる形になることが多かった。というか、「そのように指すべきだ」という圧力みたいなものさえあったという。現在のような「純粋な勝負」というよりも、空手や茶道など「型」「礼儀」が重んじられる世界だったのだろう。そんなわけで、「序盤はこんな風に展開させるのが当然である」という「暗黙のルール」が、羽生善治がプロ棋士になった頃まで連綿と続いていたというわけだ。
しかし彼は、その風潮に毅然として異を唱えた。羽生善治は1994年に初めて名人位に挑戦したのだが、その際なんと、「普通の定跡形は指さない」と宣言し、その通りに将棋を指したのである。
あわせて読みたい
【革新】天才マルタン・マルジェラの現在。顔出しNGでデザイナーの頂点に立った男の”素声”:映画『マル…
「マルタン・マルジェラ」というデザイナーもそのブランドのことも私は知らなかったが、そんなファッション音痴でも興味深く観ることができた映画『マルジェラが語る”マルタン・マルジェラ”』は、生涯顔出しせずにトップに上り詰めた天才の来歴と現在地が語られる
しかしそんな振る舞いに対して、将棋界の重鎮達は荒れ狂ったという。本書に書かれている「批判」を抜き出してみよう。
- 将棋界の第一人者たるもの、少なくとも若いときには居飛車党の正統派でなければならない。歴代の名人は皆そうだった
- 名人戦のような大舞台では、将棋の純文学たる矢倉を指すべきだ
- 大舞台で先手を持って大先輩を相手に飛車を振るなんて
あわせて読みたい
【天才】映画音楽の発明家『モリコーネ』の生涯。「映画が恋した音楽家」はいかに名曲を生んだか
「映画音楽のフォーマットを生み出した」とも評される天才作曲家エンリオ・モリコーネを扱った映画『モリコーネ 映画が恋した音楽家』では、生涯で500曲以上も生み出し、「映画音楽」というジャンルを比べ物にならないほどの高みにまで押し上げた人物の知られざる生涯が描かれる

将棋に詳しくない人には初見の単語も出てくると思うので、イメージを掴むには難しいかもしれない。例えば野球で例えるなら、「先頭打者の初球は真っ直ぐのストレートを投げるべきだ」「ピッチャー初年度からスプリットを投げるのは邪道だ」「大先輩に対して外角ギリギリの球を投げるなんて失礼だ」みたいな感じの反応と言えるのではないかと思う(私が野球に詳しくないので自信はないが)。
あわせて読みたい
【革新】映画音楽における唯一のルールは「ルールなど無い」だ。”異次元の音”を生み出す天才を追う:映…
「無声映画」から始まった映画業界で、音楽の重要性はいかに認識されたのか?『JAWS』の印象的な音楽を生み出した天才は、映画音楽に何をもたらしたのか?様々な映画の実際の映像を組み込みながら、「映画音楽」の世界を深堀りする映画『すばらしき映画音楽たち』で、異才たちの「創作」に触れる
多少将棋に詳しい、比較的新参の(古参ではない)将棋ファンであれば、これらの主張を「は?」と感じるだろう。私も、そう感じる。それはやはり、私たちが「将棋」を「純粋な勝負」だと考えているからだと思う。そして、「将棋は『純粋な勝負』である」という”当たり前”の感覚を将棋界にもたらした人物こそ、羽生善治なのである。
後手が想定局面まで安易に先手に追随するという怠惰を廃しさえすれば、その先に将棋の未来が広がっているに違いない。そう、羽生は問題提起したのだった。
あわせて読みたい
【伝説】映画『ミスター・ムーンライト』が描くビートルズ武道館公演までの軌跡と日本音楽への影響
ザ・ビートルズの武道館公演が行われるまでの軌跡を描き出したドキュメンタリー映画『ミスター・ムーンライト』は、その登場の衝撃について語る多数の著名人が登場する豪華な作品だ。ザ・ビートルズがまったく知られていなかった頃から、伝説の武道館公演に至るまでの驚くべきエピソードが詰まった1作
既に現代の将棋しか知らない私たちにはなかなかイメージしにくいが、30年ほど前までの将棋界では「伝統」の方が重んじられており、「棋士が自由に駒を動かすこと」が制約されていたというわけだ。そして、そんな「伝統」をその圧倒的な実力で打ち破り、それによって「現代将棋」への道筋を生み出したことこそが、彼の非常に大きな功績だというのである。実際に、
1994年には「邪道」だった「先手7六歩 後手3二金」は、盤上の自由が行き渡った現在では、当たり前の展開の一つになり、不確かな価値観に基づいた「邪道」などという曖昧な言葉は、将棋界から消え去った。
というような具体的な変化についても本書には記されている。現代将棋においては、「AIソフトを使った研究」との兼ね合いで「邪道」という言葉が出てくる可能性はあると思うが、「将棋の伝統」に照らして「邪道」と判断されるようなことは恐らくもうないだろう。
あわせて読みたい
【天才】写真家・森山大道に密着する映画。菅田将暉の声でカッコよく始まる「撮り続ける男」の生き様:…
映画『あゝ荒野』のスチール撮影の際に憧れの森山大道に初めて会ったという菅田将暉の声で始まる映画『過去はいつも新しく、未来はつねに懐かしい』は、ちゃちなデジカメ1つでひたすら撮り続ける異端児の姿と、50年前の処女作復活物語が見事に交錯する
羽生善治のそのようなスタンスは、彼自身の将棋に対する向き合い方にも滲み出ている。
いちばんの違いは時代における戦い方で、大山先生は人と戦っていたけれど、羽生さんは将棋そのものと戦っている。たとえば、羽生さんは相手のミスを期待するのではなく、できるだけ長く均衡が保たれた局面が続いて、将棋の真理に近づければいいと思っている。
どうやら羽生は、一局の将棋の勝ち負けや、ある局面での真理とかそういう個別のことではなく、現代将棋の進化のプロセスをすべて正確に記録しないともったいない、それが「いちばんの問題」だ、と言っているのである。どうも彼は、一人だけ別のことを考えているようなのだ。
あわせて読みたい
【天才】映画『Winny』(松本優作監督)で知った、金子勇の凄さと著作権法侵害事件の真相(ビットコイン…
稀代の天才プログラマー・金子勇が著作権法違反で逮捕・起訴された実話を描き出す映画『Winny』は、「警察の凄まじい横暴」「不用意な天才と、テック系知識に明るい弁護士のタッグ」「Winnyが明らかにしたとんでもない真実」など、見どころは多い。「金子勇=サトシ・ナカモト」説についても触れる

ここにはある種の捻れがあるように感じられる。当然のことながら、「伝統」を重んじていた者たちにしたところで、最終的には「相手との対局に勝つ」ことが目的だったはずだ。だからこそ、相手のミスを期待するような心理戦を仕掛けたりもしていたのである。しかし、将棋を「純粋な勝負」へと転換させた当の本人は、勝ち負けよりも「将棋の可能性」の方に関心を持っているというのだ。
あわせて読みたい
【不謹慎】コンプライアンス無視の『テレビで会えない芸人』松元ヒロを追う映画から芸と憲法を考える
かつてテレビの世界で大ブレイクを果たしながら、現在はテレビから完全に離れ、年間120もの公演を行う芸人・松元ヒロ。そんな知る人ぞ知る芸人を追った映画『テレビで会えない芸人』は、コンプライアンスに厳しく、少数派が蔑ろにされる社会へ一石を投じる、爆笑社会風刺である
だからこそ、普通では考えられない行動も取る。
何人かの棋士が口を揃えて言うのは「最近の羽生は、番勝負(真剣勝負)でリードすると実験をする」ということである。その時点で羽生が抱いている「将棋の真理を巡る仮説」を検証する場としてタイトル戦の大舞台が使われるという意味だ。
あわせて読みたい
【衝撃】自ら立ち上げた「大分トリニータ」を放漫経営で潰したとされる溝畑宏の「真の実像」に迫る本:…
まったく何もないところからサッカーのクラブチーム「大分トリニータ」を立ち上げ、「県リーグから出発してチャンピオンになる」というJリーグ史上初の快挙を成し遂げた天才・溝畑宏を描く『爆走社長の天国と地獄』から、「正しく評価することの難しさ」について考える
普通の棋士であれば、そのような大舞台では「どうやって相手に勝つか」しか考えられないだろう。しかし羽生善治は、「将棋の真理にたどり着くための実験を行っているように思える」というのだ。まさに異次元の闘い方をしていると言っていいだろう。
羽生は、きっと若き日に七冠を制覇する過程で、一人で勝ち続けるだけではその先にあるのは「砂漠の世界」に過ぎず、二人で作る芸術、二人で真理を追究する将棋において、「もっとすごいもの」は一人では絶対に作れないと悟ったのだ。そして「もっとすごいもの」を作るには、現代将棋を究める同志(むろんライバルでもある)が何よりも重要だと確信した。「周りに誰もいなければ(進むべき)方向性を定めるのがとても難し」いからである。そして、同志を増やすという目標を達成するための「知のオープン化」思想が、そのとき羽生の中で芽生えたのだと考えられる。
あわせて読みたい
【アート】「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」(森美術館)と「美術手帖 Chim↑Pom特集」の衝撃から「…
Chim↑Pomというアーティストについてさして詳しいことを知らずに観に行った、森美術館の「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」に、思考をドバドバと刺激されまくったので、Chim↑Pomが特集された「美術手帖」も慌てて買い、Chim↑Pomについてメッチャ考えてみた
将棋を「純粋な勝負」に転換させたのは、そうしなけば「真理」に到達できないと考えていたからというわけだ。だから羽生善治は時に、自身が勝利した対局において相手に怒ることさえあるという。「どうしてそこで止めてしまうんだ」という怒りである。確かに勝敗は決しているのかもしれない。しかし、この将棋はまだ先があるはずだ。そこまで行けば、何か見えてくるものもあるかもしれない。しかしあなたが投了してしまえば、その深淵に到達できないではないか。だからこんな形で投げ出すな。そんな怒りを抱いているのではないかと著者は想像するのである。
このような視点で捉えると、羽生善治という棋士がいかに異端的な存在であるかが理解できるだろうと思う。
あわせて読みたい
【伝説】「幻の世界新」などやり投げ界に数々の伝説を残した溝口和洋は「思考力」が凄まじかった:『一…
世界レベルのやり投げ選手だった溝口和洋を知っているだろうか? 私は本書『一投に賭ける』で初めてその存在を知った。他の追随を許さないほどの圧倒的な練習量と、常識を疑い続けるずば抜けた思考力を武器に、体格で劣る日本人ながら「幻の世界新」を叩き出した天才の実像
現代将棋における急速な変化と、それに対する危機感
「AIが将棋界をいかに激変させているか」については、『天才の考え方』の記事で詳しく触れている。「現代将棋の変化」という意味では、AIがもたらした影響力はとてつもなく大きなものなのだ。
あわせて読みたい
【激変】天才・藤井聡太と将棋界について加藤一二三、渡辺明が語る。AIがもたらした変化の是非は?:『…
『天才の考え方 藤井聡太とは何者か?』は、加藤一二三・渡辺明という棋界トップランナー2人が「将棋」をテーマに縦横無尽に語り合う対談本。この記事では、「AIがもたらした変化」について触れる。「答えを教えてくれるAI」は、将棋を、そして棋士をどう変えたのか?
一方、『羽生善治と現代』では、「AIソフトを使わない研究」に焦点が当てられている。「伝統」の軛が取り払われたことで、それまであまり研究されてこなかった序盤・中盤にも次々とメスが入り、プロ棋士たちの手で新たな知見・発想がどんどんと生み出されていった。2008年、羽生善治が「永世名人」の有資格者となった時、彼は「ここ10年は今までの将棋の歴史のなかで一番変化が大きい時代」と語ったという。羽生善治が切り開いた「将棋の『真理』を探究する道」に多くの者が続いたことで、将棋界は「日進月歩の研究が古い定跡を駆逐する世界」へと変貌したというわけだ。

あわせて読みたい
【知的】「BLって何?」という初心者に魅力を伝える「腐男子」の「BLの想像力と創造力」講座:『ボクた…
「BLは知的遊戯である」という主張には「は?」と感じてしまうでしょうが、本書『ボクたちのBL論』を読めばその印象は変わるかもしれません。「余白の発見と補完」を通じて、「ありとあらゆる2者の間の関係性を解釈する」という創造性は、現実世界にどのような影響を与えているのか
そのような変化についての様々な記述が本書にはある。
序盤の最新研究における知識の差が勝負に直結してしまう、その比率が上がっている、ということなのだと思います。
あわせて読みたい
【偉業】「卓球王国・中国」実現のため、周恩来が頭を下げて請うた天才・荻村伊智朗の信じがたい努力と…
「20世紀を代表するスポーツ選手」というアンケートで、その当時大活躍していた中田英寿よりも高順位だった荻村伊智朗を知っているだろうか?選手としてだけでなく、指導者としてもとんでもない功績を残した彼の生涯を描く『ピンポンさん』から、ノーベル平和賞級の活躍を知る
しかし2手目でこんなことになるとは……。こういう時代になるとは、思いもしませんでした。
以前、羽生が私に「最近は、公式戦の結果だけを見ていっても、将棋の真価を追うことができなくなってしまった」と話していたことがある。
あわせて読みたい
【能力】激変する未来で「必要とされる人」になるためのスキルや考え方を落合陽一に学ぶ:『働き方5.0』
AIが台頭する未来で生き残るのは難しい……。落合陽一『働き方5.0~これからの世界をつくる仲間たちへ~』はそう思わされる一冊で、本書は正直、未来を前向きに諦めるために読んでもいい。未来を担う若者に何を教え、どう教育すべきかの参考にもなる一冊。
そして、そのような変化を生み出す「棋士」という存在について、その異質さを表現するこんな文章も印象的だった。
ふつうは、技術が進歩する速度に合わせて人間がどう変わるべきかを必死で考えて追いつこうとするものなのに、将棋の世界では、棋士という人間そのものが技術を体現した存在であり、人間が進歩する力、推進力にこそすべてがある。そう考えるとあらためて、棋士たちの頭脳のすさまじさ、他の世界との異質さを感じざるを得ない。
先程も触れた通り、現在では「AI」の影響力が凄まじく、「棋士という人間そのものが技術を体現した存在」という記述にも修正の余地はあるだろうと思う。しかしどれだけAIが台頭したところで、それを理解し使いこなせる者がいなければ「真理」にはたどり着けないはずだ。「理屈は分からないが、AIが導き出したこの手は強い」という状況はいくらでも生まれ得るだろうが、それは単に「勝負に勝てる」というだけであり、「真理への到達」ではない。「真理」へ到達するためには、プロ棋士たちの高度な頭脳が必要になるというわけだ。
あわせて読みたい
【衝撃】「仕事の意味」とは?天才・野崎まどが『タイタン』で描く「仕事をしなくていい世界」の危機
「仕事が存在しない世界」は果たして人間にとって楽園なのか?万能のAIが人間の仕事をすべて肩代わりしてくれる世界を野崎まどが描く『タイタン』。その壮大な世界観を通じて、現代を照射する「仕事に関する思索」が多数登場する、エンタメ作品としてもド級に面白い傑作SF小説
羽生善治は、
つまり、誰か優れた人が出てきてその人だけがイノベーションを起こすというのじゃなくて、イノベーションを生み出しやすい土壌をこそ作らなければならない。逆に、そうした土壌がなくなってしまうと、どんなにいいアイデアを持った人がいても、そこからは花が咲かない、誰も咲かすことができない。
と言い、さらに「創造性以外のものは簡単に手に入る時代になった」とも語っている。
あわせて読みたい
【驚嘆】映画『TAR/ター』のリディア・ターと、彼女を演じたケイト・ブランシェットの凄まじさ
天才女性指揮者リディア・ターを強烈に描き出す映画『TAR/ター』は、とんでもない作品だ。「縦軸」としてのターの存在感があまりにも強すぎるため「横軸」を上手く捉えきれず、結果「よく分からなかった」という感想で終わったが、それでも「観て良かった」と感じるほど、揺さぶられる作品だった
そして、
何かを作り出すのは無駄な作業に見えるけど、一番大事なことなんじゃないか。
と主張するのである。このような彼のスタンスこそが、羽生善治という人間をトップランナー足らしめているのだと感じさせられた。
あわせて読みたい
【創作】クリエイターになりたい人は必読。ジブリに見習い入社した川上量生が語るコンテンツの本質:『…
ドワンゴの会長職に就きながら、ジブリに「見習い」として入社した川上量生が、様々なクリエイターの仕事に触れ、色んな質問をぶつけることで、「コンテンツとは何か」を考える『コンテンツの秘密』から、「創作」という営みの本質や、「クリエイター」の理屈を学ぶ
著:梅田望夫
¥836 (2022/11/27 18:48時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品読了済】私が読んできたノンフィクション・教養書を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が読んできたノンフィクションを様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本選びの参考にして下さい。
最後に
あわせて読みたい
【勝負】実話を基にコンピューター将棋を描く映画『AWAKE』が人間同士の対局の面白さを再認識させる
実際に行われた将棋の対局をベースにして描かれる映画『AWAKE』は、プロ棋士と将棋ソフトの闘いを「人間ドラマ」として描き出す物語だ。年に4人しかプロ棋士になれない厳しい世界においては、「夢破れた者たち」もまた魅力的な物語を有している。光と影を対比的に描き出す、見事な作品
この記事では、私が興味を持った部分について重点的に紹介したが、「将棋の新たな見方」を提示してくれる記述も多く、「将棋を観る」ということの可能性を広げてくれる作品だと感じた。「打ち方で分かる棋士の性格」「封じ手の心理戦」「1分将棋のプレッシャー」などなど、「説明してもらうことで見え方が変わる要素」が様々に描かれているのだ。「観る将」が読めば新たな視点に気づくだろうし、「将棋の対局を観たことがない」という人にはそのきっかけになる作品ではないかとも思う。
というわけで、少しでも将棋に関心があるという人なら面白く読める作品と言っていいだろう。「将棋を観戦すること」という、非常に狭い話題を起点としながら、現代将棋に関する様々な知識をちりばめる作品だ。また、羽生善治の凄さを改めて実感できたという点でも読んで良かった。
あわせて読みたい
【狂気】日本一将棋に金を使った将棋ファン・団鬼六の生涯を、『将棋世界』の元編集長・大崎善生が描く…
SM小説の大家として一時代を築きつつ、将棋に金を注ぎ込みすぎて2億円の借金を抱えた団鬼六の生涯を、『将棋世界』の元編集長・大崎善生が描くノンフィクション『赦す人』。虚実が判然としない、嘘だろうと感じてしまうトンデモエピソード満載の異端児が辿った凄まじい生涯
さて、将棋に詳しい人に聞いてみたいのだが、本書のP87には、2008年6月11日に行われた、「第79期棋聖戦第一局 羽生善治対佐藤康光」の対局の投了図が載っている。ネットで出て来ないかと探したが見つからなかったので本書を開いてもらうしかないが、この投了図が私にはまったく理解できなかった。羽生善治の負けで終わったらしいのだが、何故なのだろうか? 羽生善治の玉の周りに敵の駒は全然ないし、使える手駒もまだまだあるのだ。これで投了となった理由が、私にはまったく理解できなかった。誰か教えてくれると大変ありがたい。
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!「文章の書き方が分からない」「文章力がないから鍛えたい」という方にオススメ…
「文章の書き方」についてのKindle本を出版しました。「文章が書けない」「どう書いたらいいか分からない」「文章力を向上させたい」という方の悩みを解消できるような本に仕上げたつもりです。数多くの文章を書き、さらに頼まれて文章を推敲してきた経験を踏まえ、「文章を書けるようになるにはどうしたらいいか」についての私なりの考えをまとめました。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【魅惑】マツコも絶賛の“日本人初のパリコレトップモデル”山口小夜子のメイクの凄さや素顔を描く映画:…
日本人初のパリコレトップモデルである山口小夜子と親交があった監督が紡ぐ映画『氷の花火 山口小夜子』は、未だ謎に包まれているその人生の一端を垣間見せてくれる作品だ。彼女を知る様々な人の記憶と、彼女を敬愛する多くの人の想いがより合って、一時代を築いた凄まじい女性の姿が浮かび上がってくる
あわせて読みたい
【ル・マン】ゲーマーが本物のカーレース出場!映画『グランツーリスモ』が描く衝撃的すぎる軌跡(ヤン…
映画『グランツーリスモ』は、「ゲーマーをレーサーにする」という、実際に行われた無謀すぎるプロジェクトを基にした作品だ。登場人物は全員イカれていると感じたが、物語としてはシンプルかつ王道で、誰もが先の展開を予想出来るだろう。しかしそれでも、圧倒的に面白かった、ちょっと凄まじすぎる映画だった
あわせて読みたい
【天才】映画『笑いのカイブツ』のモデル「伝説のハガキ職人ツチヤタカユキ」の狂気に共感させられた
『「伝説のハガキ職人」として知られるツチヤタカユキの自伝的小説を基にした映画『笑いのカイブツ』は、凄まじい狂気に彩られた作品だった。「お笑い」にすべてを捧げ、「お笑い」以外はどうでもいいと考えているツチヤタカユキが、「コミュ力」や「人間関係」で躓かされる”理不尽”な世の中に、色々と考えさせられる
あわせて読みたい
【抵抗】映画『熊は、いない』は、映画製作を禁じられた映画監督ジャファル・パナヒの執念の結晶だ
映画『熊は、いない』は、「イラン当局から映画製作を20年間も禁じられながら、その後も作品を生み出し続けるジャファル・パナヒ監督」の手によるもので、彼は本作公開後に収監させられてしまった。パナヒ監督が「本人役」として出演する、「ドキュメンタリーとフィクションのあわい」を縫うような異様な作品だ
あわせて読みたい
【映画】『キャスティング・ディレクター』の歴史を作り、ハリウッド映画俳優の運命を変えた女性の奮闘
映画『キャスティング・ディレクター』は、ハリウッドで伝説とされるマリオン・ドハティを描き出すドキュメンタリー。「神業」「芸術」とも評される配役を行ってきたにも拘わらず、長く評価されずにいた彼女の不遇の歴史や、再び「キャスティングの暗黒期」に入ってしまった現在のハリウッドなどを切り取っていく
あわせて読みたい
【改革】改修期間中の国立西洋美術館の裏側と日本の美術展の現実を映すドキュメンタリー映画:『わたし…
「コロナ禍」という絶妙すぎるタイミングで改修工事を行った国立西洋美術館の、普段見ることが出来ない「裏側」が映し出される映画『わたしたちの国立西洋美術館』は、「日本の美術展」の問題点を炙り出しつつ、「『好き』を仕事にした者たち」の楽しそうな雰囲気がとても魅力的に映るドキュメンタリー
あわせて読みたい
【天才】映画音楽の発明家『モリコーネ』の生涯。「映画が恋した音楽家」はいかに名曲を生んだか
「映画音楽のフォーマットを生み出した」とも評される天才作曲家エンリオ・モリコーネを扱った映画『モリコーネ 映画が恋した音楽家』では、生涯で500曲以上も生み出し、「映画音楽」というジャンルを比べ物にならないほどの高みにまで押し上げた人物の知られざる生涯が描かれる
あわせて読みたい
【伝説】映画『ミスター・ムーンライト』が描くビートルズ武道館公演までの軌跡と日本音楽への影響
ザ・ビートルズの武道館公演が行われるまでの軌跡を描き出したドキュメンタリー映画『ミスター・ムーンライト』は、その登場の衝撃について語る多数の著名人が登場する豪華な作品だ。ザ・ビートルズがまったく知られていなかった頃から、伝説の武道館公演に至るまでの驚くべきエピソードが詰まった1作
あわせて読みたい
【天才】映画『Winny』(松本優作監督)で知った、金子勇の凄さと著作権法侵害事件の真相(ビットコイン…
稀代の天才プログラマー・金子勇が著作権法違反で逮捕・起訴された実話を描き出す映画『Winny』は、「警察の凄まじい横暴」「不用意な天才と、テック系知識に明るい弁護士のタッグ」「Winnyが明らかにしたとんでもない真実」など、見どころは多い。「金子勇=サトシ・ナカモト」説についても触れる
あわせて読みたい
【驚嘆】映画『TAR/ター』のリディア・ターと、彼女を演じたケイト・ブランシェットの凄まじさ
天才女性指揮者リディア・ターを強烈に描き出す映画『TAR/ター』は、とんでもない作品だ。「縦軸」としてのターの存在感があまりにも強すぎるため「横軸」を上手く捉えきれず、結果「よく分からなかった」という感想で終わったが、それでも「観て良かった」と感じるほど、揺さぶられる作品だった
あわせて読みたい
【知的】「BLって何?」という初心者に魅力を伝える「腐男子」の「BLの想像力と創造力」講座:『ボクた…
「BLは知的遊戯である」という主張には「は?」と感じてしまうでしょうが、本書『ボクたちのBL論』を読めばその印象は変わるかもしれません。「余白の発見と補完」を通じて、「ありとあらゆる2者の間の関係性を解釈する」という創造性は、現実世界にどのような影響を与えているのか
あわせて読みたい
【実話】福島智とその家族を描く映画『桜色の風が咲く』から、指点字誕生秘話と全盲ろうの絶望を知る
「目が見えず、耳も聞こえないのに大学に進学し、後に東京大学の教授になった」という、世界レベルの偉業を成し遂げた福島智。そんな彼の試練に満ちた生い立ちを描く映画『桜色の風が咲く』は、本人の葛藤や努力もさることながら、母親の凄まじい献身の物語でもある
あわせて読みたい
【傑物】フランスに最も愛された政治家シモーヌ・ヴェイユの、強制収容所から国連までの凄絶な歩み:映…
「フランスに最も愛された政治家」と評されるシモーヌ・ヴェイユ。映画『シモーヌ』は、そんな彼女が強制収容所を生き延び、後に旧弊な社会を変革したその凄まじい功績を描き出す作品だ。「強制収容所からの生還が失敗に思える」とさえ感じたという戦後のフランスの中で、彼女はいかに革新的な歩みを続けたのか
あわせて読みたい
【実話】映画『グッドバイ、バッドマガジンズ』(杏花主演)が描く、もの作りの絶望(と楽しさ)
実在したエロ雑誌編集部を舞台に、タブーも忖度もなく業界の内実を描き切る映画『グッドバイ、バッドマガジンズ』は、「エロ雑誌」をテーマにしながら、「もの作りに懸ける想い」や「仕事への向き合い方」などがリアルに描かれる素敵な映画だった。とにかく、主役を演じた杏花が良い
あわせて読みたい
【勝負】実話を基にコンピューター将棋を描く映画『AWAKE』が人間同士の対局の面白さを再認識させる
実際に行われた将棋の対局をベースにして描かれる映画『AWAKE』は、プロ棋士と将棋ソフトの闘いを「人間ドラマ」として描き出す物語だ。年に4人しかプロ棋士になれない厳しい世界においては、「夢破れた者たち」もまた魅力的な物語を有している。光と影を対比的に描き出す、見事な作品
あわせて読みたい
【衝撃】自ら立ち上げた「大分トリニータ」を放漫経営で潰したとされる溝畑宏の「真の実像」に迫る本:…
まったく何もないところからサッカーのクラブチーム「大分トリニータ」を立ち上げ、「県リーグから出発してチャンピオンになる」というJリーグ史上初の快挙を成し遂げた天才・溝畑宏を描く『爆走社長の天国と地獄』から、「正しく評価することの難しさ」について考える
あわせて読みたい
【偉業】「卓球王国・中国」実現のため、周恩来が頭を下げて請うた天才・荻村伊智朗の信じがたい努力と…
「20世紀を代表するスポーツ選手」というアンケートで、その当時大活躍していた中田英寿よりも高順位だった荻村伊智朗を知っているだろうか?選手としてだけでなく、指導者としてもとんでもない功績を残した彼の生涯を描く『ピンポンさん』から、ノーベル平和賞級の活躍を知る
あわせて読みたい
【挑戦】手足の指を失いながら、今なお挑戦し続ける世界的クライマー山野井泰史の”現在”を描く映画:『…
世界的クライマーとして知られる山野井泰史。手足の指を10本も失いながら、未だに世界のトップをひた走る男の「伝説的偉業」と「現在」を映し出すドキュメンタリー映画『人生クライマー』には、小学生の頃から山のことしか考えてこなかった男のヤバい人生が凝縮されている
あわせて読みたい
【伝説】「幻の世界新」などやり投げ界に数々の伝説を残した溝口和洋は「思考力」が凄まじかった:『一…
世界レベルのやり投げ選手だった溝口和洋を知っているだろうか? 私は本書『一投に賭ける』で初めてその存在を知った。他の追随を許さないほどの圧倒的な練習量と、常識を疑い続けるずば抜けた思考力を武器に、体格で劣る日本人ながら「幻の世界新」を叩き出した天才の実像
あわせて読みたい
【思考】文章の書き方が分かんない、トレーニングしたいって人はまず、古賀史健の文章講義の本を読め:…
古賀史健『20歳の自分に受けさせたい文章講義』は、「具体的なテクニック」ではない記述も非常に興味深い1冊だ。「なぜ文章を書く必要があるのか」という根本的な部分から丁寧に掘り下げる本書は、「書くからこそ考えられる」という、一般的なイメージとは逆だろう発想が提示される
あわせて読みたい
【挑戦】相対性理論の光速度不変の原理を無視した主張『光速より速い光』は、青木薫訳だから安心だぞ
『光速より速い光』というタイトルを見て「トンデモ本」だと感じた方、安心してほしい。「光速変動理論(VSL理論)」が正しいかどうかはともかくとして、本書は実に真っ当な作品だ。「ビッグバン理論」の欠陥を「インフレーション理論」以外の理屈で補う挑戦的な仮説とは?
あわせて読みたい
【驚愕】一般人スパイが北朝鮮に潜入する映画『THE MOLE』はとてつもないドキュメンタリー映画
映画『THE MOLE』は、「ホントにドキュメンタリーなのか?」と疑いたくなるような衝撃映像満載の作品だ。「『元料理人のデンマーク人』が勝手に北朝鮮に潜入する」というスタートも謎なら、諜報経験も軍属経験もない男が北朝鮮の秘密をバンバン解き明かす展開も謎すぎる。ヤバい
あわせて読みたい
【圧巻】150年前に気球で科学と天気予報の歴史を変えた挑戦者を描く映画『イントゥ・ザ・スカイ』
「天気予報」が「占い」と同等に扱われていた1860年代に、気球を使って気象の歴史を切り開いた者たちがいた。映画『イントゥ・ザ・スカイ』は、酸素ボンベ無しで高度1万1000m以上まで辿り着いた科学者と気球操縦士の物語であり、「常識を乗り越える冒険」の素晴らしさを教えてくれる
あわせて読みたい
【扇動】人生うまくいかないと感じる時に読みたい瀧本哲史の本。「未来をどう生きる?」と問われる1冊:…
瀧本哲史は非常に優れたアジテーターであり、『2020年6月30日にまたここで会おう』もまさにそんな1冊。「少数のカリスマ」ではなく「多数の『小さなリーダー』」によって社会が変革されるべきだ、誰にだってやれることはある、と若者を焚きつける、熱量満載の作品
あわせて読みたい
【欠落】映画『オードリー・ヘプバーン』が映し出す大スターの生き方。晩年に至るまで生涯抱いた悲しみ…
映画『オードリー・ヘプバーン』は、世界的大スターの知られざる素顔を切り取るドキュメンタリーだ。戦争による壮絶な飢え、父親の失踪、消えぬ孤独感、偶然がもたらした映画『ローマの休日』のオーディション、ユニセフでの活動など、様々な証言を元に稀代の天才を描き出す
あわせて読みたい
【奇跡】信念を貫いた男が国の制度を変えた。特別養子縁組を実現させた石巻の産婦人科医の執念:『赤ち…
遊郭で生まれ育った石巻の医師が声を上げ、あらゆる障害をなぎ倒して前進したお陰で「特別養子縁組」の制度が実現した。そんな産婦人科医・菊田昇の生涯を描き出す小説『赤ちゃんをわが子として育てる方を求む』には、法を犯してでも信念を貫いた男の衝撃の人生が描かれている
あわせて読みたい
【感想】湯浅政明監督アニメ映画『犬王』は、実在した能楽師を”異形”として描くスペクタクル平家物語
観るつもりなし、期待値ゼロ、事前情報ほぼ皆無の状態で観た映画『犬王』(湯浅政明監督)はあまりにも凄まじく、私はこんなとんでもない傑作を見逃すところだったのかと驚愕させられた。原作の古川日出男が紡ぐ狂気の世界観に、リアルな「ライブ感」が加わった、素晴らしすぎる「音楽映画」
あわせて読みたい
【異次元】『ハイパーハードボイルドグルメリポート』は本も読め。衝撃すぎるドキュメンタリーだぞ
テレビ東京の上出遼平が作る、“異次元のグルメ番組”である「ハイパーハードボイルドグルメリポート」の書籍化。映像からも異様さが伝わる「激ヤバ地」に赴き、そこに住む者と同じモノを食べるという狂気が凄まじい。私がテレビで見た「ケニアのゴミ山の少年」の話は衝撃的だった
あわせて読みたい
【評価】のん(能年玲奈)の映画『Ribbon』が描く、コロナ禍において「生きる糧」が芸術であることの葛藤
のん(能年玲奈)脚本・監督・主演の映画『Ribbon』。とても好きな作品だった。単に女優・のんが素晴らしいというだけではなく、コロナ禍によって炙り出された「生きていくのに必要なもの」の違いに焦点を当て、「魂を生き延びさせる行為」が制約される現実を切り取る感じが見事
あわせて読みたい
【あらすじ】死刑囚を救い出す実話を基にした映画『黒い司法』が指摘する、死刑制度の問題と黒人差別の現実
アメリカで死刑囚の支援を行う団体を立ち上げた若者の実話を基にした映画『黒い司法 0%からの奇跡』は、「死刑制度」の存在価値について考えさせる。上映後のトークイベントで、アメリカにおける「死刑制度」と「黒人差別」の結びつきを知り、一層驚かされた
あわせて読みたい
【表現】映画『名付けようのない踊り』で初めて見た田中泯のダンス。「芸術以前」を志向する圧倒的パワー
映画『名付けようのない踊り』の中で田中泯は言う。「私」や「個性」を表現することには違和感がある、と。「踊りのために身体を作る」のではなく、「野良仕事で出来た身体で踊る」のだ、と。芸術になる前の踊りを探したい、と。「唯一無二の表現者」の生涯と現在地を映し出すドキュメンタリー
あわせて読みたい
【不謹慎】コンプライアンス無視の『テレビで会えない芸人』松元ヒロを追う映画から芸と憲法を考える
かつてテレビの世界で大ブレイクを果たしながら、現在はテレビから完全に離れ、年間120もの公演を行う芸人・松元ヒロ。そんな知る人ぞ知る芸人を追った映画『テレビで会えない芸人』は、コンプライアンスに厳しく、少数派が蔑ろにされる社会へ一石を投じる、爆笑社会風刺である
あわせて読みたい
【激変】天才・藤井聡太と将棋界について加藤一二三、渡辺明が語る。AIがもたらした変化の是非は?:『…
『天才の考え方 藤井聡太とは何者か?』は、加藤一二三・渡辺明という棋界トップランナー2人が「将棋」をテーマに縦横無尽に語り合う対談本。この記事では、「AIがもたらした変化」について触れる。「答えを教えてくれるAI」は、将棋を、そして棋士をどう変えたのか?
あわせて読みたい
【現実】権力を乱用する中国ナチスへの抵抗の最前線・香港の民主化デモを映す衝撃の映画『時代革命』
2019年に起こった、逃亡犯条例改正案への反対運動として始まった香港の民主化デモ。その最初期からデモ参加者たちの姿をカメラに収め続けた。映画『時代革命』は、最初から最後まで「衝撃映像」しかない凄まじい作品だ。この現実は決して、「対岸の火事」ではない
あわせて読みたい
【LGBT】映画『リトル・ガール』で映し出される、性別違和を抱える8歳の”女の子”のリアルと苦悩
映画撮影時8歳だった、身体は男の子、心は女の子のサシャは、スカートを履いての登校が許されず、好きなバッグもペンケースも使わせてもらえない。映画『リトル・ガール』が描く、「性別違和」に対する社会の不寛容と、自分を責め続けてしまう母親の苦悩
あわせて読みたい
【貢献】社会問題を解決する2人の「社会起業家」の生き方。「豊かさ」「生きがい」に必要なものは?:『…
「ヤクの毛」を使ったファッションブランド「SHOKAY」を立ち上げ、チベットの遊牧民と中国・崇明島に住む女性の貧困問題を解決した2人の若き社会起業家の奮闘を描く『世界を変えるオシゴト』は、「仕事の意義」や「『お金』だけではない人生の豊かさ」について考えさせてくれる
あわせて読みたい
【超人】NHKによる「JAXAの宇宙飛行士選抜試験」のドキュメント。門外不出の「最強の就活」
難攻不落のJAXAと粘り強い交渉を重ね、門外不出の「最強の就活」を捉えたドキュメンタリーを書籍化した『ドキュメント宇宙飛行士選抜試験』。2021年の13年ぶりの募集も話題になったが、「欠点があってはいけない」という視点で厳しく問われる試験・面接の実情を描き出す
あわせて読みたい
【挑戦】深海に棲む”聖杯”ダイオウイカをNHKが世界初撮影。関わった者が語る奇跡のプロジェクト:『ドキ…
NHK主導で進められた、深海に棲む”聖杯”ダイオウイカの撮影プロジェクト。10年にも及ぶ過酷な挑戦を描いた『ドキュメント 深海の超巨大イカを追え!』は、ほぼ不可能と思われていたプロジェクトをスタートさせ、艱難辛苦の末に見事撮影に成功した者たちの軌跡を描き出す
あわせて読みたい
【変】「家を建てるより、モバイルハウスを自作する方がいいのでは?」坂口恭平の疑問は「常識」を壊す…
誰もが大体「家」に住んでいるでしょうが、そもそも「家」とは何なのか考える機会はありません。『モバイルハウス 三万円で家をつくる』の著者・坂口恭平は、「人間は土地を所有すべきなのか?」という疑問からスタートし、「家」の不可思議さを突き詰めることで新たな世界を垣間見せる
あわせて読みたい
【衝撃】NHKがアマゾン奥地の先住民ヤノマミ族に長期密着。剥き出しの生と死、文明との共存の難しさ
NHKのディレクターでありノンフィクション作家でもある国分拓が、アマゾン奥地に住む先住民ヤノマミ族の集落で150日間の長期密着を行った。1万年の歴史を持つ彼らの生活を描き出す『ヤノマミ』は、「生と死の価値観の差異」や「先住民と文明との関係の難しさ」を突きつける
あわせて読みたい
【狂気】日本一将棋に金を使った将棋ファン・団鬼六の生涯を、『将棋世界』の元編集長・大崎善生が描く…
SM小説の大家として一時代を築きつつ、将棋に金を注ぎ込みすぎて2億円の借金を抱えた団鬼六の生涯を、『将棋世界』の元編集長・大崎善生が描くノンフィクション『赦す人』。虚実が判然としない、嘘だろうと感じてしまうトンデモエピソード満載の異端児が辿った凄まじい生涯
あわせて読みたい
【斬新】ホームレスの家を「0円ハウス」と捉える坂口恭平の発想と視点に衝撃。日常の見え方が一変する:…
早稲田大学建築学科在籍中から「建築物の設計」に興味を持てなかった坂口恭平が、「ホームレスの家」に着目した『TOKYO 0円ハウス0円生活』には、「家」に対する考え方を一変させる視点が満載。「家に生活を合わせる」ではなく、「生活に家を合わせる」という発想の転換が見事
あわせて読みたい
【驚異】『グレイトフル・デッドにマーケティングを学ぶ』って書名通りの本。異端ロックバンドの”稼ぎ方”
日本ではあまり知られていないが、熱狂的なファンを持つロックバンド「グレイトフル・デッド」。彼らは50年も前から、現代では当たり前となった手法を続け、今でも年間5000万ドルを稼いでいる。『グレイトフル・デッドにマーケティングを学ぶ』で「ファンからの愛され方」を学ぶ
あわせて読みたい
【不安】環境活動家グレタを追う映画。「たったひとりのストライキ」から国連スピーチまでの奮闘と激変…
環境活動家であるグレタのことを、私はずっと「怒りの人」「正義の人」だとばかり思っていた。しかしそうではない。彼女は「不安」から、いても立ってもいられずに行動を起こしただけなのだ。映画『グレタ ひとりぼっちの挑戦』から、グレタの実像とその強い想いを知る
あわせて読みたい
【教育】映画化に『3月のライオン』のモデルと話題の村山聖。その師匠である森信雄が語る「育て方」論:…
自身は決して強い棋士ではないが、棋界で最も多くの弟子を育てた森信雄。「村山聖の師匠」として有名な彼の「師匠としてのあり方」を描く『一門 ”冴えん師匠”がなぜ強い棋士を育てられたのか?』から、教育することの難しさと、その秘訣を学ぶ
あわせて読みたい
【信念】水俣病の真実を世界に伝えた写真家ユージン・スミスを描く映画。真実とは「痛みへの共感」だ:…
私はその存在をまったく知らなかったが、「水俣病」を「世界中が知る公害」にした報道写真家がいる。映画『MINAMATA―ミナマタ―』は、水俣病の真実を世界に伝えたユージン・スミスの知られざる生涯と、理不尽に立ち向かう多くの人々の奮闘を描き出す
あわせて読みたい
【驚愕】キューバ危機の裏側を描くスパイ映画『クーリエ』。核戦争を回避させた民間人の衝撃の実話:『…
核戦争ギリギリまで進んだ「キューバ危機」。その陰で、世界を救った民間人がいたことをご存知だろうか?実話を元にした映画『クーリエ:最高機密の運び屋』は、ごく普通のセールスマンでありながら、ソ連の膨大な機密情報を盗み出した男の信じがたい奮闘を描き出す
あわせて読みたい
【衝撃】「文庫X」の正体『殺人犯はそこにいる』は必読。日本の警察・裁判・司法は信じていいか?
タイトルを伏せられた覆面本「文庫X」としても話題になった『殺人犯はそこにいる』。「北関東で起こったある事件の取材」が、「私たちが生きる社会の根底を揺るがす信じがたい事実」を焙り出すことになった衝撃の展開。大げさではなく、全国民必読の1冊だと思う
あわせて読みたい
【弾圧】香港デモの象徴的存在デニス・ホーの奮闘の歴史。注目の女性活動家は周庭だけじゃない:映画『…
日本で香港民主化運動が報じられる際は周庭さんが取り上げられることが多いが、香港には彼女よりも前に民主化運動の象徴的存在として認められた人物がいる。映画『デニス・ホー ビカミング・ザ・ソング』の主人公であるスター歌手の激動の人生を知る
あわせて読みたい
【狂気】バケモン・鶴瓶を映し出す映画。「おもしろいオッチャン」に潜む「異常さ」と「芸への情熱」:…
「俺が死ぬまで公開するな」という条件で撮影が許可された映画『バケモン』。コロナ禍で映画館が苦境に立たされなければ、公開はずっと先だっただろう。テレビで見るのとは違う「芸人・笑福亭鶴瓶」の凄みを、古典落語の名作と名高い「らくだ」の変遷と共に切り取る
あわせて読みたい
【危機】シードバンクを設立し世界の農業を変革した伝説の植物学者・スコウマンの生涯と作物の多様性:…
グローバル化した世界で「農業」がどんなリスクを負うのかを正しく予測し、その対策として「ジーンバンク」を設立した伝説の植物学者スコウマンの生涯を描く『地球最後の日のための種子』から、我々がいかに脆弱な世界に生きているのか、そして「世界の食」がどう守られているのかを知る
あわせて読みたい
【アート】「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」(森美術館)と「美術手帖 Chim↑Pom特集」の衝撃から「…
Chim↑Pomというアーティストについてさして詳しいことを知らずに観に行った、森美術館の「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」に、思考をドバドバと刺激されまくったので、Chim↑Pomが特集された「美術手帖」も慌てて買い、Chim↑Pomについてメッチャ考えてみた
あわせて読みたい
【実話】暗号機エニグマ解読のドラマと悲劇を映画化。天才チューリングはなぜ不遇の死を遂げたのか:『…
「解読不可能」とまで言われた最強の暗号機エニグマを打ち破ったのは、コンピューターの基本原理を生み出した天才数学者アラン・チューリングだった。映画『イミテーションゲーム』から、1400万人以上を救ったとされながら、偏見により自殺した不遇の人生を知る
あわせて読みたい
【考察】アニメ映画『虐殺器官』は、「便利さが無関心を生む現実」をリアルに描く”無関心ではいられない…
便利すぎる世の中に生きていると、「この便利さはどのように生み出されているのか」を想像しなくなる。そしてその「無関心」は、世界を確実に悪化させてしまう。伊藤計劃の小説を原作とするアニメ映画『虐殺器官』から、「無関心という残虐さ」と「想像することの大事さ」を知る
あわせて読みたい
【本質】子どもの頃には読めない哲学書。「他人の哲学はつまらない」と語る著者が説く「問うこと」の大…
『<子ども>のための哲学』は決して、「子どもでも易しく理解できる哲学の入門書」ではない。むしろかなり難易度が高いと言っていい。著者の永井均が、子どもの頃から囚われ続けている2つの大きな疑問をベースに、「『哲学する』とはどういうことか?」を深堀りする作品
あわせて読みたい
【自由】詩人が語る詩の読み方。「作者の言いたいこと」は無視。「分からないけど格好いい」で十分:『…
私は学生時代ずっと国語の授業が嫌いでしたが、それは「作品の解釈には正解がある」という決めつけが受け入れ難かったからです。詩人・渡邊十絲子の『今を生きるための現代詩』を読むと、詩に限らずどんな作品も、「解釈など不要」「分からなければ分からないままでいい」と思えるようになる
あわせて読みたい
【博覧強記】「紙の本はなくなる」説に「文化は忘却されるからこそ価値がある」と反論する世界的文学者…
世界的文学者であり、「紙の本」を偏愛するウンベルト・エーコが語る、「忘却という機能があるから書物に価値がある」という主張は実にスリリングだ。『もうすぐ絶滅するという紙の書物について』での対談から、「忘却しない電子データ」のデメリットと「本」の可能性を知る
あわせて読みたい
【異端】「仏教とは?」を簡単に知りたい方へ。ブッダは「異性と目も合わせないニートになれ」と主張し…
我々が馴染み深い「仏教」は「大乗仏教」であり、創始者ゴータマ・ブッダの主張が詰まった「小乗仏教」とは似て非なるものだそうだ。『講義ライブ だから仏教は面白い!』では、そんな「小乗仏教」の主張を「異性と目も合わせないニートになれ」とシンプルに要約して説明する
あわせて読みたい
【感想】池田晶子『14歳からの哲学』で思考・自由・孤独の大事さを知る。孤独を感じることって大事だ
「元々持ってた価値観とは違う考えに触れ、それを理解したいと思う場面」でしか「考える」という行為は発動しないと著者は言う。つまり我々は普段、まったく考えていないのだ。『14歳からの哲学』をベースに、「考えること」と自由・孤独・人生との関係を知る
あわせて読みたい
【飛躍】有名哲学者は”中二病”だった?飲茶氏が易しく語る「古い常識を乗り越えるための哲学の力」:『1…
『14歳からの哲学入門』というタイトルは、「14歳向けの本」という意味ではなく、「14歳は哲学することに向いている」という示唆である。飲茶氏は「偉大な哲学者は皆”中二病”だ」と説き、特に若い人に向けて、「新しい価値観を生み出すためには哲学が重要だ」と語る
あわせて読みたい
【歴史】ベイズ推定は現代社会を豊かにするのに必須だが、実は誕生から200年間嫌われ続けた:『異端の統…
現在では、人工知能を始め、我々の生活を便利にする様々なものに使われている「ベイズ推定」だが、その基本となるアイデアが生まれてから200年近く、科学の世界では毛嫌いされてきた。『異端の統計学ベイズ』は、そんな「ベイズ推定」の歴史を紐解く大興奮の1冊だ
あわせて読みたい
【興奮】世界的大ベストセラー『サピエンス全史』要約。人類が文明を築き上げるに至った3つの革命とは?
言わずと知れた大ベストセラー『サピエンス全史』は、「何故サピエンスだけが人類の中で生き残り、他の生物が成し得なかった歴史を歩んだのか」を、「認知革命」「農業革命」「科学革命」の3つを主軸としながら解き明かす、知的興奮に満ち溢れた1冊
あわせて読みたい
【誤解】世界的大ベストセラー『ファクトフルネス』の要約。我々はデータも世界も正しく捉えられない
世界の現状に関する13の質問に対して、ほとんどの人が同じ解答をする。最初の12問は不正解で、最後の1問だけ正答するのだ。世界的大ベストセラー『ファクトフルネス』から、「誤った世界の捉え方」を認識し、情報を受け取る際の「思い込み」を払拭する
あわせて読みたい
【知的】文系にオススメの、科学・数学・哲学の入門書。高橋昌一郎の「限界シリーズ」は超絶面白い:『…
例えば「科学」だけに限ってみても、「なんでもできる」わけでは決してない。「科学」に限らず、私たちが対峙する様々な事柄には「これ以上は不可能・無理」という「限界」が必ず存在する。高橋昌一郎の「限界シリーズ」から、我々が認識しておくべき「限界」を易しく学ぶ
あわせて読みたい
【感想】飲茶氏の東洋哲学入門書要約。「本書を読んでも東洋哲学は分からない」と言う著者は何を語る?…
東洋哲学というのは、「最終回しか存在しない連続ドラマ」のようなものだそうだ。西洋哲学と比較にならないほど異質さと、インド哲学・中国哲学など個別の思想を恐ろしく分かりやすく描く『史上最強の哲学入門 東洋の哲人たち』は、史上最強レベルに面白い
あわせて読みたい
【興奮】飲茶氏の超面白い哲学小説。「正義とは?」の意味を問う”3人の女子高生”の主張とは?:『正義の…
なんて面白いんだろうか。哲学・科学を初心者にも分かりやすく伝える飲茶氏による『正義の教室』は、哲学書でありながら、3人の女子高生が登場する小説でもある。「直観主義」「功利主義」「自由主義」という「正義論」の主張を、「高校の問題について議論する生徒会の話し合い」から学ぶ
あわせて読みたい
【貢献】飛行機を「安全な乗り物」に決定づけたMr.トルネードこと天才気象学者・藤田哲也の生涯:『Mr….
つい数十年前まで、飛行機は「死の乗り物」だったが、天才気象学者・藤田哲也のお陰で世界の空は安全になった。今では、自動車よりも飛行機の方が死亡事故の少ない乗り物なのだ。『Mr.トルネード 藤田哲也 世界の空を救った男』から、その激動の研究人生を知る
あわせて読みたい
【天才】読書猿のおすすめ本。「いかにアイデアを生むか」の発想法を人文書に昇華させた斬新な1冊:『ア…
「独学の達人」「博覧強記の読書家」などと評される読書猿氏が、古今東西さまざまな「発想法」を1冊にまとめた『アイデア大全』は、ただのHow To本ではない。「発想法」を学問として捉え、誕生した経緯やその背景なども深堀りする、「人文書」としての一面も持つ作品だ
あわせて読みたい
【驚異】ガイア理論の提唱者が未来の地球を語る。100歳の主張とは思えない超絶刺激に満ちた内容:『ノヴ…
「地球は一種の生命体だ」という主張はかなり胡散臭い。しかし、そんな「ガイア理論」を提唱する著者は、数々の賞や学位を授与される、非常に良く知られた科学者だ。『ノヴァセン <超知能>が地球を更新する』から、AIと人類の共存に関する斬新な知見を知る
あわせて読みたい
【興奮】飲茶氏が西洋哲学を語る。難解な思想が「グラップラー刃牙成分」の追加で驚異的な面白さに:『…
名前は聞いたことはあるがカントやニーチェがどんな主張をしたのかは分からないという方は多いだろう。私も無知なまったくの初心者だが、そんな人でも超絶分かりやすく超絶面白く西洋哲学を”分かった気になれる”飲茶『史上最強の哲学入門』は、入門書として最強
あわせて読みたい
【思考】「”考える”とはどういうことか」を”考える”のは難しい。だからこの1冊をガイドに”考えて”みよう…
私たちは普段、当たり前のように「考える」ことをしている。しかし、それがどんな行為で、どのように行っているのかを、きちんと捉えて説明することは難しい。「はじめて考えるときのように」は、横書き・イラスト付きの平易な文章で、「考えるという行為」の本質に迫り、上達のために必要な要素を伝える
あわせて読みたい
【実像】ベートーヴェンの「有名なエピソード」をほぼ一人で捏造・創作した天才プロデューサーの実像:…
ベートーヴェンと言えば、誰もが知っている「運命」を始め、天才音楽家として音楽史に名を刻む人物だが、彼について良く知られたエピソードのほとんどは実は捏造かもしれない。『ベートーヴェン捏造 名プロデューサーは嘘をつく』が描く、シンドラーという”天才”の実像
あわせて読みたい
【教養】美術を「感じたまま鑑賞する」のは難しい。必要な予備知識をインストールするための1冊:『武器…
芸術を「感性の赴くまま見る」のは、日本特有だそうだ。欧米では美術は「勉強するもの」と認識されており、本書ではアートを理解しようとするスタンスがビジネスにも役立つと示唆される。美術館館長を務める著者の『武器になる知的教養 西洋美術鑑賞』から基礎の基礎を学ぶ
あわせて読みたい
【逸脱】「人生良いことない」と感じるのは、「どう生きたら幸せか」を考えていないからでは?:『独立…
「常識的な捉え方」から逸脱し、世の中をまったく異なる視点から見る坂口恭平は、「より生きやすい社会にしたい」という強い思いから走り続ける。「どう生きたいか」から人生を考え直すスタンスと、「やりたいことをやるべきじゃない理由」を『独立国家のつくりかた』から学ぶ
あわせて読みたい
【使命】「CRISPR-Cas9」を分かりやすく説明。ノーベル賞受賞の著者による発見物語とその使命:『CRISPR…
生物学の研究を一変させることになった遺伝子編集技術「CRISPR-Cas9」の開発者は、そんな発明をするつもりなどまったくなかった。ノーベル化学賞を受賞した著者による『CRISPR (クリスパー) 究極の遺伝子編集技術の発見』をベースに、その発見物語を知る
あわせて読みたい
【未知】タコに「高度な脳」があるなんて初耳だ。人類とは違う進化を遂げた頭足類の「意識」とは?:『…
タコなどの頭足類は、無脊椎動物で唯一「脳」を進化させた。まったく違う進化を辿りながら「タコに心を感じる」という著者は、「タコは地球外生命体に最も近い存在」と書く。『タコの心身問題』から、腕にも脳があるタコの進化の歴史と、「意識のあり方」を知る。
あわせて読みたい
【変人】学校教育が担うべき役割は?子供の才能を伸ばすために「異質な人」とどう出会うべきか?:『飛…
高校の美術教師からアーティストとして活動するようになった著者は、教育の現場に「余白(スキマ)」が減っていると指摘する。『飛び立つスキマの設計学』をベースに、子どもたちが置かれている現状と、教育が成すべき役割について確認する。
あわせて読みたい
【能力】激変する未来で「必要とされる人」になるためのスキルや考え方を落合陽一に学ぶ:『働き方5.0』
AIが台頭する未来で生き残るのは難しい……。落合陽一『働き方5.0~これからの世界をつくる仲間たちへ~』はそう思わされる一冊で、本書は正直、未来を前向きに諦めるために読んでもいい。未来を担う若者に何を教え、どう教育すべきかの参考にもなる一冊。
あわせて読みたい
【デマ】情報を”選ぶ”時代に、メディアの情報の”正しさ”はどのように判断されるのか?:『ニューヨーク…
一昔前、我々は「正しい情報を欲していた」はずだ。しかしいつの間にか世の中は変わった。「欲しい情報を正しいと思う」ようになったのだ。この激変は、トランプ元大統領の台頭で一層明確になった。『ニューヨーク・タイムズを守った男』から、情報の受け取り方を問う
あわせて読みたい
【改革】AIは将棋をどう変えた?羽生善治・渡辺明ら11人の現役棋士が語る将棋の未来:『不屈の棋士』(…
既に将棋AIの実力はプロ棋士を越えたとも言われる。しかし、「棋力が強いかどうか」だけでは将棋AIの良し悪しは判断できない。11人の現役棋士が登場する『不屈の棋士』をベースに、「AIは将棋界をどう変えたのか?」について語る
あわせて読みたい
【無知】メディアの問題の本質は?「報道の限界」と「情報の受け取り方」を独裁政治の現実から知る:『…
メディアは確かに「事実」を報じている。しかし、報道に乗らない情報まで含めなければ、本当の意味で世の中を理解することは難しいと、『こうして世界は誤解する』は教えてくれる。アラブ諸国での取材の現実から、報道の「限界」と「受け取り方」を学ぶ
あわせて読みたい
【異端】子育ては「期待しない」「普通から外れさせる」が大事。”劇薬”のような父親の教育論:『オーマ…
どんな親でも、子どもを幸せにしてあげたい、と考えるでしょう。しかしそのために、過保護になりすぎてしまっている、ということもあるかもしれません。『オーマイ・ゴッドファーザー』をベースに、子どもを豊かに、力強く生きさせるための”劇薬”を学ぶ
あわせて読みたい
【発想力】「集中力が続かない」と悩むことはない。「集中しない思考」こそAI時代に必要だ:『集中力は…
『「集中力がない」と悩んでいる人は多いかもしれません。しかし本書では、「集中力は、思ってるほど素晴らしいものじゃない」と主張します。『集中力はいらない』をベースに、「分散思考」の重要性と、「発想」を得るための「情報の加工」を学ぶ
あわせて読みたい
【天職】頑張っても報われない方へ。「自分で選び取る」のとは違う、正しい未来の進み方:『そのうちな…
一般的に自己啓発本は、「今、そしてこれからどうしたらいいか」が具体的に語られるでしょう。しかし『そのうちなんとかなるだろう』では、決断・選択をするべきではないと主張されます。「選ばない」ことで相応しい未来を進む生き方について学ぶ
あわせて読みたい
【肯定】社会不適合者こそ非凡。学校・世の中に馴染めなかった異才たちの過去から”才能”の本質を知る:…
「みんなと同じ」に馴染めないと「社会不適合」と判断され、排除されてしまうことが多いでしょう。しかし『非属の才能』では、「どこにも属せない感覚」にこそ才能の源泉があると主張します。常識に違和感を覚えてしまう人を救う本から、同調圧力に屈しない生き方を学ぶ
あわせて読みたい
【呪縛】生きづらさの正体とそこからどう抜けるかを、「支配される安心」「自由の不自由」から考える:…
自由に生きられず、どうしたらいいのか悩む人も多くいるでしょう。『自由をつくる 自在に生きる』では、「自由」のためには「支配に気づくこと」が何より大事であり、さらに「自由」とは「不自由なもの」だと説きます。どう生きるかを考える指針となる一冊。
あわせて読みたい
【救い】自殺を否定しない「笑える自殺本」。「自殺したい」ってもっと気軽に言える社会がいい:『自殺…
生きることがしんどくて、自殺してしまいたくなる気持ちを、私はとても理解できます。しかし世の中的には、「死にたい」と口にすることはなかなか憚られるでしょう。「自殺を決して悪いと思わない」という著者が、「死」をもっと気楽に話せるようにと贈る、「笑える自殺本」
あわせて読みたい
【実話】仕事のやりがいは、「頑張るスタッフ」「人を大切にする経営者」「健全な商売」が生んでいる:…
メガネファストファッションブランド「オンデーズ」の社長・田中修治が経験した、波乱万丈な経営再生物語『破天荒フェニックス』をベースに、「仕事の目的」を見失わず、関わるすべての人に存在価値を感じさせる「働く現場」の作り方
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
文化・芸術・将棋・スポーツ【本・映画の感想】 | ルシルナ
知識や教養は、社会や学問について知ることだけではありません。文化的なものもリベラルアーツです。私自身は、創作的なことをしたり、勝負事に関わることはありませんが、…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…




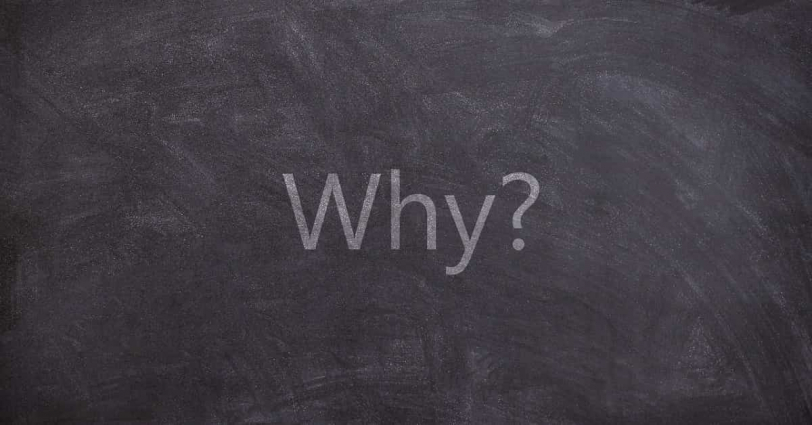







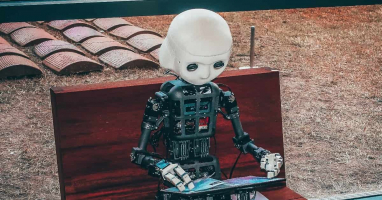









































































































































コメント