目次
はじめに
著:立川 談春
¥1,024 (2024/07/03 16:55時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
この記事で伝えたいこと
両親から勘当されながら落語立川流の門を叩いた立川談春の壮絶・爆笑の修行時代
落語界の本流を外れた世界だからこその”異常な日々”がメチャクチャ面白い
この記事の3つの要点
- 「落語協会」を抜けた立川談志が創設した「落語立川流」だからこその2つの大きな特徴
- 「前座はアルバイト禁止」が不文律の落語界で堂々と働いていた立川談春
- 立川談志の異端児っぷり満載の、弟子にとっては壮絶な日々
破天荒でありながら、非常に理知的でもある「立川談志」の姿を、本書で初めて知りました
この記事で取り上げる本
著:立川 談春
¥679 (2022/07/10 19:01時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
立川談志に弟子入りし、「天才落語家」と呼ばれるまでになった立川談春の、修行時代を描いた名エッセイ『赤めだか』

あわせて読みたい
【教育】映画化に『3月のライオン』のモデルと話題の村山聖。その師匠である森信雄が語る「育て方」論:…
自身は決して強い棋士ではないが、棋界で最も多くの弟子を育てた森信雄。「村山聖の師匠」として有名な彼の「師匠としてのあり方」を描く『一門 ”冴えん師匠”がなぜ強い棋士を育てられたのか?』から、教育することの難しさと、その秘訣を学ぶ
私は以前、立川談春の落語を聞いたことがあります。というか、初めて聞いた落語が立川談春でした。既に『赤めだか』を読んでいましたが、落語に関する素養はまったくなく、立川談春の落語についても「凄かった」という記憶はあるものの、具体的にはほとんど覚えていません。
せっかく聞く機会があったのだから、ちゃんと面白さが分かるぐらいにもう少し知識を持っていればよかったと後悔しています。自分が生きている間に、また聞く機会があるでしょうか。
どうせ取れないんだろうなぁとか思って試しもしてないんだけど
本書は、「天才」と呼ばれる落語家・立川談春が、さらなる天才・立川談志に弟子入りし、真打ちに駆け上がるまでのドタバタの日常を描いたエッセイです。二宮和也主演で映画化もされたのでご覧になった方もいるかもしれません。
あわせて読みたい
【狂気】バケモン・鶴瓶を映し出す映画。「おもしろいオッチャン」に潜む「異常さ」と「芸への情熱」:…
「俺が死ぬまで公開するな」という条件で撮影が許可された映画『バケモン』。コロナ禍で映画館が苦境に立たされなければ、公開はずっと先だっただろう。テレビで見るのとは違う「芸人・笑福亭鶴瓶」の凄みを、古典落語の名作と名高い「らくだ」の変遷と共に切り取る
本書の内容に触れる前に、立川談春役を演じた二宮和也について少し書きたいと思います。この話は、「日曜日の初耳学」(TBS系)での林修との対談に立川談春が登場した際に語られていたものです。
映画を観た誰か(誰か忘れた)が、「立川談春を演じる二宮和也の落語」に驚いてしまいます。あまりに、昔の立川談春にそっくりだったからです。そこでその人物は立川談春に、「お前が稽古つけたの?」と聞きました。そうでもなければ理解できないと考えたのでしょう。
しかし立川談春は二宮和也に稽古などつけていません。映画のプロデューサーから、「談春さんの落語のテープを渡してください」とだけ言われたと語っており、彼が二宮和也に対して行ったのはたったそれだけのことでした。つまり二宮和也は、落語など経験したことがないはずなのに、立川談春が落語をやっているテープの音声だけを聞いて、「立川談春としか思えない」と言わしめるだけの完成度まで持っていってしまった、というわけです。

あわせて読みたい
【感想】湯浅政明監督アニメ映画『犬王』は、実在した能楽師を”異形”として描くスペクタクル平家物語
観るつもりなし、期待値ゼロ、事前情報ほぼ皆無の状態で観た映画『犬王』(湯浅政明監督)はあまりにも凄まじく、私はこんなとんでもない傑作を見逃すところだったのかと驚愕させられた。原作の古川日出男が紡ぐ狂気の世界観に、リアルな「ライブ感」が加わった、素晴らしすぎる「音楽映画」
凄まじいエピソードだなと感じました。
二宮和也は、演技の直前までゲームしてるとかで、それなのに演技になるとすぐに役に入れるって中島健人が驚いてた
この話、もちろん一番凄いのは二宮和也ですが、私はプロデューサーも凄いなと感じました。プロデューサーは、二宮和也から「テープがあれば大丈夫」と言われていたわけではないと思います。プロデューサー自身の判断で、「テープがあれば、彼は大丈夫だろう」と判断したはずです。その絶大な信頼感と、それに応える二宮和也の才能にちょっと驚かされました。
記事の冒頭から関係ない話で申し訳ありません。それでは『赤めだか』の内容の紹介に入ろうと思います。
あわせて読みたい
【難しい】映画『鳩の撃退法』をネタバレ全開で考察。よくわからない物語を超詳細に徹底解説していく
とても難しくわかりにくい映画『鳩の撃退法』についての考察をまとめていたら、1万7000字を超えてしまった。「東京編で起こったことはすべて事実」「富山編はすべてフィクションかもしれない」という前提に立ち、「津田伸一がこの小説を書いた動機」まで掘り下げて、実際に何が起こっていたのかを解説する(ちなみに、「実話」ではないよ)
立川談志のあまりの異端さ
私は本書を読むまで、落語界の仕組みをほとんど理解していませんでした。その仕組みを知ると、なおさら「立川談志」という人物の異端さが理解できるようになるでしょう。
落語の世界には「落語協会」が存在し、落語家になりたい人は基本的にここに所属する形になります。落語協会に所属する落語家の中から師匠になってくれる人を探して弟子入りし、その後は「前座」として寄席に出て経験を積むわけです。それから、「二ツ目」「真打ち」と昇進していくのですが、その昇進を決めるのは落語協会ということになります。
これが一般的な落語の世界です。
あわせて読みたい
【改革】AIは将棋をどう変えた?羽生善治・渡辺明ら11人の現役棋士が語る将棋の未来:『不屈の棋士』(…
既に将棋AIの実力はプロ棋士を越えたとも言われる。しかし、「棋力が強いかどうか」だけでは将棋AIの良し悪しは判断できない。11人の現役棋士が登場する『不屈の棋士』をベースに、「AIは将棋界をどう変えたのか?」について語る
これはまあ、なんとなくイメージした通りではあったかな
もちろん、立川談志も元々は落語協会に所属していました。しかし彼は、色々あって落語協会を飛び出してしまうのです。そして、自ら「落語立川流」という新たな団体を作り、「落語協会」とは関係のない落語界を作り上げていくことになります。

立川談志がどんな落語をやっているのか知らなくても、この事実だけでいかに異端児であるかが理解できるでしょう。
あわせて読みたい
【天才】映画『笑いのカイブツ』のモデル「伝説のハガキ職人ツチヤタカユキ」の狂気に共感させられた
『「伝説のハガキ職人」として知られるツチヤタカユキの自伝的小説を基にした映画『笑いのカイブツ』は、凄まじい狂気に彩られた作品だった。「お笑い」にすべてを捧げ、「お笑い」以外はどうでもいいと考えているツチヤタカユキが、「コミュ力」や「人間関係」で躓かされる”理不尽”な世の中に、色々と考えさせられる
さて、落語協会を飛び出したことにより、落語立川流の弟子は落語協会に属する落語家と比べて大きく2つの点で違いが生まれることになりました。
1つは、弟子にとってはプラスの変化です。「二ツ目」への昇進基準が明確になりました。
落語協会に所属している場合、「どういう条件なら『二ツ目』や『真打ち』に昇進できるのか」が分からないそうです。これは、努力する側としてはなかなか難しい環境と言えるでしょう。しかし落語立川流の場合は昇進基準がとにかく明確にされています。それは、
古典落語を50席覚えること
だけです。これさえクリアできれば、弟子入りした順番も年齢も経験も一切関係なく、「二ツ目」に昇進できます。
あわせて読みたい
【抵抗】映画『熊は、いない』は、映画製作を禁じられた映画監督ジャファル・パナヒの執念の結晶だ
映画『熊は、いない』は、「イラン当局から映画製作を20年間も禁じられながら、その後も作品を生み出し続けるジャファル・パナヒ監督」の手によるもので、彼は本作公開後に収監させられてしまった。パナヒ監督が「本人役」として出演する、「ドキュメンタリーとフィクションのあわい」を縫うような異様な作品だ
こんな風にしてくれると、「何を頑張ればいいか」がはっきりするからやりやすいよね
伝統芸能だからといって別に、お客さんから見えない部分まで古いままでいる必要はないしね
さてもう1つの変化の方は、弟子たちにとってはかなり大変なものでした。「寄席がない」のです。例えば東京には、浅草・上野・池袋などに「寄席」がありますが、これらは当然のことながら「落語協会に所属している落語家が出る場」です。落語協会を飛び出してしまった落語立川流には当然「寄席」に出る機会がありません。
落語家の弟子というのは普通、「前座」として様々な「寄席」に出ながら実力をつけていくものです。しかし落語立川流に試す場はありません。しかしそれ以上に、「やることがない」というのが大変です。もちろん、師匠である立川談志のお世話はするわけですが、それ以外に「やらなければならないこと」はありません。落語協会の弟子はとにかく時間がないものですが、落語立川流の弟子はとにかく時間が有り余っています。つまり、自ら生活を律し、自分の頭ですべきことを考えて落語家としての研鑽を積んでいかなければならないのです。

あわせて読みたい
【あらすじ】映画化の小説『僕は、線を描く』。才能・センスではない「芸術の本質」に砥上裕將が迫る
「水墨画」という、多くの人にとって馴染みが無いだろう芸術を題材に据えた小説『線は、僕を描く』は、青春の葛藤と創作の苦悩を描き出す作品だ。「未経験のど素人である主人公が、巨匠の孫娘と勝負する」という、普通ならあり得ない展開をリアルに感じさせる設定が見事
立川談春は、そんな異端児・立川談志の元に弟子入りしたもんだから相当苦労することになります。そんな日々を描いたのがこのエッセイです。
できたばっかりの落語立川流に入ったから、大変さが分かってなかっただろうなぁ
ネットで調べると、落語立川流の設立が1983年、そして翌1984年に立川談春が弟子入りしてるね
立川談春の苦労
立川談春は、通っていた高校を中退し、17歳で立川談志に弟子入りします。両親からは勘当同然で追い出されたそうです。まあ、「落語家になる」と言って高校を中退するのは相当ヤンチャだと思うので、そのような厳しい扱いを受けても仕方ないかもしれません。
あわせて読みたい
【狂気】稀少本を収集・売買する「愛すべき変人コレクター」の世界と、インターネットによる激変:映画…
広大な本の世界を狩人のように渉猟し、お気に入りの本を異常なまでに偏愛する者たちを描き出す映画『ブックセラーズ』。実在の稀少本コレクターたちが、本への愛を語り、新たな価値を見出し、次世代を教育し、インターネットの脅威にどう立ち向かっているのかを知る
ただ、「両親に勘当された」という事実は、立川談春にとって大きな苦労の元となってしまいました。
立川談志はそもそも「内弟子」を取りたがらなかったといいます。落語家の師弟関係というのは、「師匠の家に住み込んで家事など手伝いながら修行する」という内弟子スタイルが普通だそうですが、他人が生活に関わってくることを嫌った談志は、内弟子を取らなかったのです。
また立川談志はさらに、「弟子入りには親の承諾が必要」という条件もつけていました。未成年であれば当然の扱いでしょう。しかし立川談春は、勘当同然で飛び出してきてしまっています。それでもどうにか弟子入りの許可だけはもらえたものの、「内弟子を取らない」という立川談志のスタンスがさらに困難さに拍車をかけることになります。
というのも落語の世界には、「前座の身分ではアルバイト禁止」という、凄まじい不文律が存在するからです。師匠の家に住み込みできるならまだ生活も成り立つでしょうが、「内弟子」を嫌う立川談志の場合はそうもいきません。勘当されているので親元から通うわけにもいかず、立川談春には「働きながら落語家の修行をする」という選択肢しかなかったのです。
あわせて読みたい
【感想】映画『若おかみは小学生!』は「子どもの感情」を「大人の世界」で素直に出す構成に号泣させられる
ネット記事を読まなければ絶対に観なかっただろう映画『若おかみは小学生!』は、基本的に子ども向け作品だと思うが、大人が観てもハマる。「大人の世界」でストレートに感情を表に出す主人公の小学生の振る舞いと成長に、否応なしに感動させられる
そもそもアルバイトなんかしてる余裕がないぐらい忙しいってのもあるだろうけどね
本書を読んでると、「前座は人間じゃない」みたいな扱いをされてる印象があるんだよなぁ……
立川談春は、新聞配達の住み込みのアルバイトを見つけ、特例として働くことが認められます。しかし、なんだかんだすぐに辞めてしまいました。その後なぜか、「修行」と称して立川談志から築地で働けと命じられるなど、落語立川流の弟子の中でもなかなか経験がないだろう弟子時代を過ごしているのです。

ちなみに、立川談志の一番弟子として知られる立川志の輔は、脱サラして落語家を目指しました。当然、前座の間は無収入です。既に結婚していたというのですから、凄まじい決断だと言えるでしょう。立川志の輔は、2年という驚異的なスピードで「古典落語を50席覚える」という条件をクリアし、二ツ目に昇進しました。彼もまた、凄まじい落語家だと言っていいでしょう。
さて、立川談志は「内弟子」を取りませんでしたが、弟子はやはり師匠のお世話をします。にしても立川談志という男は、落語以外の部分でも常軌を逸していると言わざるを得ません。例えば本書には、立川談志が弟子に命じた指示の例が載っています。
あわせて読みたい
【伝説】映画『ミスター・ムーンライト』が描くビートルズ武道館公演までの軌跡と日本音楽への影響
ザ・ビートルズの武道館公演が行われるまでの軌跡を描き出したドキュメンタリー映画『ミスター・ムーンライト』は、その登場の衝撃について語る多数の著名人が登場する豪華な作品だ。ザ・ビートルズがまったく知られていなかった頃から、伝説の武道館公演に至るまでの驚くべきエピソードが詰まった1作
二階のベランダ側の窓の桟が汚れている、きれいにしろ。葉書出しとけ。スーパーで牛乳買って来い。庭のつつじの花がしぼんで汚ぇ、むしっちまえ。留守の間に隣の家に宅配便が届いてる、もらってこい。枕カバー替えとけ。事務所に電話して、この間の仕事のギャラ確認しとけ。シャワーの出が良くない上にお湯がぬるい。原因を調べて直せ。どうしてもお前達で直せないなら職人を呼ぶことを許すが、金は使うな。物置に写真が大量にある。外枠の白い部分が俺は嫌いだ、キレイにカットしろ。豚のコマ切れ百グラム買ってこい。スリッパの裏が汚ぇ、きれいにふいとけ。家の塀を偉そうな顔して猫が歩きやがる。不愉快だ、空気銃で撃て。ただし殺すな。重傷でいい。庭の八重桜に毛虫がたかると嫌だから、薬まいとけ。何か探せばそれらしきものがあるだろう。なきゃ作れ。オリジナリティとはそうやって発揮してゆくもんだ。
立川談志は、これをバーっと一息で言い切るんだそうです。しかも自分が言ったことを正確に覚えていて、後ですべてチェックするのだとか。いかに弟子たちが振り回されたのか、想像できるだろうと思います。
親元を飛び出して落語家を目指したこと、そしてあまりに異端すぎる師匠の存在、そういったことに翻弄されながらも、立川談春は落語修行に邁進していくことになるわけです。
あわせて読みたい
【権利】衝撃のドキュメンタリー映画『ヤクザと憲法』は、「異質さを排除する社会」と「生きる権利」を問う
「ヤクザ」が排除された現在でも、「ヤクザが担ってきた機能」が不要になるわけじゃない。ではそれを、公権力が代替するのだろうか?実際の組事務所(東組清勇会)にカメラを持ち込むドキュメンタリー映画『ヤクザと憲法』が映し出す川口和秀・松山尚人・河野裕之の姿から、「基本的人権」のあり方について考えさせられた
立川談志の凄まじさ
立川談春がどのようなドタバタ修行時代を過ごしたのかは、是非本書を読んでください。ホントにこんなこと起こったのだろうかと感じてしまうようなムチャクチャな世界が描かれており、落語のことを詳しく知らなくても楽しめると思います。

この記事では最後に、落語家としての立川談志の凄まじさに少し触れて終わろうと思います。
あわせて読みたい
【無謀】園子温が役者のワークショップと同時並行で撮影した映画『エッシャー通りの赤いポスト』の”狂気”
「園子温の最新作」としか知らずに観に行った映画『エッシャー通りの赤いポスト』は、「ワークショップ参加者」を「役者」に仕立て、ワークショップと同時並行で撮影されたという異次元の作品だった。なかなか経験できないだろう、「0が1になる瞬間」を味わえる“狂気”の映画
まず、立川談春が師匠から落語の稽古をつけてもらった際のこんな言葉を紹介しましょう。
ま、こんなもんだ。今演ったものは覚えんでもいい。テープも録ってないしな。今度は、きちんと一席教えてやる。プロとはこういうものだということがわかればそれでいい。よく芸は盗むものだと云うがあれは嘘だ。盗む方にもキャリアが必要なんだ。最初は俺が教えたとおり覚えればいい。盗めるようになりゃ一人前だ。時間がかかるんだ。教える方に論理がないからそういういいかげんなことを云うんだ。いいか、落語を語るのに必要なのはリズムとメロディだ。それが基本だ。ま、それをクリアする自信があるなら今でも盗んでかまわんが、自信あるか?
このエピソードを読んで、立川談志というのは「教育者」としても非常に優れていたのだと実感させられました。「長嶋茂雄は選手としては天才だったけれど、指導者としては優秀ではなかった」みたいな話がありますが、これはまさに、「教える側に論理があるか否か」の違いなのでしょう。自身がプレイヤーであれば、その論理を掴めていなくてもセンスや感覚で出来てしまうことでも、「教える」となるとそうもいきません。立川談志は、「論理」をきちんと掴んだ上で落語をやっているからこそ、教育者としても優秀だったのだろうと感じました。
何かを教わるんであれば、こういう人に教えてもらいたいもんだね
世の中には、「◯◯コンサルタント」とか「〇〇コーディネーター」みたいな「自称」的な人が多いからなぁ
あわせて読みたい
【衝撃】自ら立ち上げた「大分トリニータ」を放漫経営で潰したとされる溝畑宏の「真の実像」に迫る本:…
まったく何もないところからサッカーのクラブチーム「大分トリニータ」を立ち上げ、「県リーグから出発してチャンピオンになる」というJリーグ史上初の快挙を成し遂げた天才・溝畑宏を描く『爆走社長の天国と地獄』から、「正しく評価することの難しさ」について考える
また、「嫉妬とは何か?」に対する立川談志の考え方も非常に印象的でした。
己が努力、行動を起こさずに対象となる人間の弱みを口であげつらって、自分のレベルまで下げる行為、これを嫉妬と云うんです。一緒になって同意してくれる仲間がいればさらに自分は安定する。本来なら相手に並び、抜くための行動、生活を送ればそれで解決するんだ。しかし人間はなかなかそれができない。嫉妬している方が楽だからな。芸人なんぞそういう輩のかたまりみたいなもんだ。だがそんなことで状況は何も変わらない。よく覚えとけ。現実は正解なんだ。時代が悪いの、世の中がおかしいと云ったところで仕方ない。現実は事実だ。そして現状を理解、分析してみろ。そこにはきっと、何故そうなったかという原因があるんだ。現状を認識して把握したら処理すりゃいいんだ。その行動を起こせない奴を俺の基準で馬鹿と云う。
私は本書を読んでから、「現実は正解なんだ」という彼の言葉をよく思い出すようになりました。非常に真理を衝く、良い言葉だと感じます。確かに、ウダウダ文句を言ったところで何かが変わるわけではありません。「目の前の現実を『起こるべきではなかった不正解』」と捉えていても何も変わらないのですから、「目の前の現実は『起こるべくして起こった正解』」なんだと受け取って物事を考える方が健全でしょう。

あわせて読みたい
【偉業】「卓球王国・中国」実現のため、周恩来が頭を下げて請うた天才・荻村伊智朗の信じがたい努力と…
「20世紀を代表するスポーツ選手」というアンケートで、その当時大活躍していた中田英寿よりも高順位だった荻村伊智朗を知っているだろうか?選手としてだけでなく、指導者としてもとんでもない功績を残した彼の生涯を描く『ピンポンさん』から、ノーベル平和賞級の活躍を知る
私はそもそも、「過去を振り返って後悔する」ってことがほとんどないんだよなぁ
後悔したところで意味がないって分かってるから、ほとんど振り返りもしないよね
立川談志は、非常に破天荒でハチャメチャに見えるのですが、本書を読んで、芯の部分は非常に真っ当な論理で組み上げられているという印象を強く抱きました。芸事の天才には、「論理などない、無鉄砲な破天荒さ」を発揮する人もいるでしょうし、そういう人はそういう人で興味深いと感じることもあります。ただ私は、「実はメチャクチャ考えている」というタイプの破天荒さの方が好きなので、立川談志に対してのプラスイメージが増しました。
あわせて読みたい
【考察】映画『ジョーカー』で知る。孤立無援の環境にこそ”悪”は偏在すると。個人の問題ではない
「バットマン」シリーズを観たことがない人間が、予備知識ゼロで映画『ジョーカー』を鑑賞。「悪」は「環境」に偏在し、誰もが「悪」に足を踏み入れ得ると改めて実感させられた。「個人」を断罪するだけでは社会から「悪」を減らせない現実について改めて考える
著:立川 談春
¥679 (2022/07/10 19:01時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品読了済】私が読んできたエッセイ・コミック・自己啓発本を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が読んできたエッセイ・コミックを様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本選びの参考にして下さい。
最後に
あわせて読みたい
【衝撃】卯月妙子『人間仮免中』、とんでもないコミックエッセイだわ。統合失調症との壮絶な闘いの日々
小学5年生から統合失調症を患い、社会の中でもがき苦しみながら生きる卯月妙子のコミックエッセイ『人間仮免中』はとんでもない衝撃作。周りにいる人とのぶっ飛んだ人間関係や、歩道橋から飛び降り自殺未遂を図り顔面がぐちゃぐちゃになって以降の壮絶な日々も赤裸々に描く
本書で描かれているのは、落語立川流が創設されたばかりの時代の話で、当然立川談志は存命でした。立川談志が亡くなった後、落語立川流がどんな風に変わったのか私は知りませんが、当然『赤めだか』で描かれているような世界ではないことだけは確かでしょう。その時その瞬間にしか成立し得なかった、いい意味でも悪い意味でも「奇跡」みたいな世界だったのだと思います。
そんな「特異な青春」を過ごした立川談春の凄まじいエピソードを是非読んでみてください。
あわせて読みたい
【価値】レコードなどの「フィジカルメディア」が復権する今、映画『アザー・ミュージック』は必見だ
2016年に閉店した伝説のレコード店に密着するドキュメンタリー映画『アザー・ミュージック』は、「フィジカルメディアの衰退」を象徴的に映し出す。ただ私は、「デジタル的なもの」に駆逐されていく世の中において、「『制約』にこそ価値がある」と考えているのだが、若者の意識も実は「制約」に向き始めているのではないかとも思っている
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【宣伝】アポロ計画での月面着陸映像は本当か?映画『フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン』のリアル
「月面着陸映像はニセモノだ」という陰謀論を逆手にとってリアリティのある物語を生み出した映画『フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン』は、「ベトナム戦争で疲弊し、事故続きのNASAが不人気だった」という現実を背景に「歴史のif」を描き出す。「確かにそれぐらいのことはするかもしれない」というリアリティをコメディタッチで展開させる
あわせて読みたい
【才能】映画『トノバン』が描く、「日本の音楽史を変えた先駆者・加藤和彦」のセンス良すぎる人生(「♪…
「♪おらは死んじまっただ~」が印象的な『帰って来たヨッパライ』で知られる加藤和彦の才能と魅力を余す所なく映し出すドキュメンタリー映画『トノバン』を観て、まったく知らなかった人物の凄まじい存在感に圧倒されてしまった。50年以上も前の人だが、音楽性や佇まいなどを含め、現代でも通用するだろうと思わせる雰囲気が凄まじい
あわせて読みたい
【記憶】映画『退屈な日々にさようならを』は「今泉力哉っぽさ」とは異なる魅力に溢れた初期作品だ(主…
今泉力哉作品のオールナイト上映に初めて参加し、『退屈な日々にさようならを』『街の上で』『サッドティー』を観ました。本作『退屈な日々にさようならを』は、時系列が複雑に入れ替わった群像劇で、私が思う「今泉力哉っぽさ」は薄い作品でしたが、構成も展開も会話も絶妙で、さすが今泉力哉という感じです
あわせて読みたい
【悲劇】映画『プリンセス・ダイアナ』『スペンサー』で知る、その凄まじい存在感と王室の窮屈さ
ドキュメンタリー映画『プリンセス・ダイアナ』と映画『スペンサー』は、衝撃的な死を遂げたダイアナ妃の生涯を対照的な形で描き出す作品だ。「過去映像のみ」で構成される非常に挑戦的な『プリンセス・ダイアナ』と、「王室との不和」を正面から描き出す『スペンサー』の2作によって、彼女が歩んだ壮絶な人生が浮き彫りにされる
あわせて読みたい
【実話】さかなクンの若い頃を描く映画『さかなのこ』(沖田修一)は子育ての悩みを吹き飛ばす快作(主…
映画『さかなのこ』は、兎にも角にものん(能年玲奈)を主演に据えたことが圧倒的に正解すぎる作品でした。性別が違うのに、「さかなクンを演じられるのはのんしかいない!」と感じさせるほどのハマり役で、この配役を考えた人は天才だと思います。「母親からの全肯定」を濃密に描き出す、子どもと関わるすべての人に観てほしい作品です
あわせて読みたい
【価値】レコードなどの「フィジカルメディア」が復権する今、映画『アザー・ミュージック』は必見だ
2016年に閉店した伝説のレコード店に密着するドキュメンタリー映画『アザー・ミュージック』は、「フィジカルメディアの衰退」を象徴的に映し出す。ただ私は、「デジタル的なもの」に駆逐されていく世の中において、「『制約』にこそ価値がある」と考えているのだが、若者の意識も実は「制約」に向き始めているのではないかとも思っている
あわせて読みたい
【奇妙】映画『鯨の骨』は、主演のあのちゃんが絶妙な存在感を醸し出す、斬新な設定の「推し活」物語
映画『鯨の骨』は、主演を務めたあのちゃんの存在感がとても魅力的な作品でした。「AR動画のカリスマ的存在」である主人公を演じたあのちゃんは、役の設定が絶妙だったこともありますが、演技がとても上手く見え、また作品全体の、「『推し活』をある意味で振り切って描き出す感じ」もとても皮肉的で良かったです
あわせて読みたい
【実話】田舎暮らし失敗。映画『理想郷』が描く、めんどくさい人間関係が嫌がらせに発展した事件
実話を基にした映画『理想郷』は、「理想の田舎暮らし」が粉微塵に粉砕されていく過程を描く物語である。第一義的には当然、夫妻に嫌がらせを続ける兄弟が悪いのだが、しかしそのように捉えるだけでは何も変わらないだろう。双方の譲れない「価値観」が否応なしに正面衝突する状況で、一体何が「正解」となり得るだろうか?
あわせて読みたい
【情熱】選挙のおもしろ候補者含め”全員取材”をマイルールにする畠山理仁の異常な日常を描く映画:『NO …
選挙に取り憑かれた男・畠山理仁を追うドキュメンタリー映画『NO 選挙, NO LIFE』は、「平均睡眠時間2時間」の生活を長年続ける”イカれた”ライターの「選挙愛」が滲み出る作品だ。「候補者全員を取材しなければ記事にはしない」という厳しすぎるマイルールと、彼が惹かれる「泡沫候補」たちが実に興味深い
あわせて読みたい
【食&芸術】死んでも車を運転したくない人間の香川うどん巡り& 豊島アート巡りの旅ルート(山越うどん…
仕事終わりの木曜日夜から日曜日に掛けて、「香川のうどん巡り」と「豊島のアート巡り」をしてきました。うどんだけでも7580円分食べたので、かなりの軒数を回ったことになります。しかも「死んでも車を運転したくない」ため、可能な限り公共交通機関のみで移動しました。私と同じように「車を運転したくない人」には、かなり参考になる記事と言えるのではないかと思います
あわせて読みたい
【天才】映画『笑いのカイブツ』のモデル「伝説のハガキ職人ツチヤタカユキ」の狂気に共感させられた
『「伝説のハガキ職人」として知られるツチヤタカユキの自伝的小説を基にした映画『笑いのカイブツ』は、凄まじい狂気に彩られた作品だった。「お笑い」にすべてを捧げ、「お笑い」以外はどうでもいいと考えているツチヤタカユキが、「コミュ力」や「人間関係」で躓かされる”理不尽”な世の中に、色々と考えさせられる
あわせて読みたい
【抵抗】映画『熊は、いない』は、映画製作を禁じられた映画監督ジャファル・パナヒの執念の結晶だ
映画『熊は、いない』は、「イラン当局から映画製作を20年間も禁じられながら、その後も作品を生み出し続けるジャファル・パナヒ監督」の手によるもので、彼は本作公開後に収監させられてしまった。パナヒ監督が「本人役」として出演する、「ドキュメンタリーとフィクションのあわい」を縫うような異様な作品だ
あわせて読みたい
【実話】英国王室衝撃!映画『ロスト・キング』が描く、一般人がリチャード3世の遺骨を発見した話(主演…
500年前に亡くなった王・リチャード3世の遺骨を、一介の会社員女性が発見した。映画『ロスト・キング』は、そんな実話を基にした凄まじい物語である。「リチャード3世の悪評を覆したい!」という動機だけで遺骨探しに邁進する「最強の推し活」は、最終的に英国王室までをも動かした!
あわせて読みたい
【改革】改修期間中の国立西洋美術館の裏側と日本の美術展の現実を映すドキュメンタリー映画:『わたし…
「コロナ禍」という絶妙すぎるタイミングで改修工事を行った国立西洋美術館の、普段見ることが出来ない「裏側」が映し出される映画『わたしたちの国立西洋美術館』は、「日本の美術展」の問題点を炙り出しつつ、「『好き』を仕事にした者たち」の楽しそうな雰囲気がとても魅力的に映るドキュメンタリー
あわせて読みたい
【天才】映画音楽の発明家『モリコーネ』の生涯。「映画が恋した音楽家」はいかに名曲を生んだか
「映画音楽のフォーマットを生み出した」とも評される天才作曲家エンリオ・モリコーネを扱った映画『モリコーネ 映画が恋した音楽家』では、生涯で500曲以上も生み出し、「映画音楽」というジャンルを比べ物にならないほどの高みにまで押し上げた人物の知られざる生涯が描かれる
あわせて読みたい
【伝説】映画『ミスター・ムーンライト』が描くビートルズ武道館公演までの軌跡と日本音楽への影響
ザ・ビートルズの武道館公演が行われるまでの軌跡を描き出したドキュメンタリー映画『ミスター・ムーンライト』は、その登場の衝撃について語る多数の著名人が登場する豪華な作品だ。ザ・ビートルズがまったく知られていなかった頃から、伝説の武道館公演に至るまでの驚くべきエピソードが詰まった1作
あわせて読みたい
【爆笑】ダースレイダー✕プチ鹿島が大暴れ!映画『センキョナンデス』流、選挙の楽しみ方と選び方
東大中退ラッパー・ダースレイダーと新聞14紙購読の時事芸人・プチ鹿島が、選挙戦を縦横無尽に駆け回る様を映し出す映画『劇場版 センキョナンデス』は、なかなか関わろうとは思えない「選挙」の捉え方が変わる作品だ。「フェスのように選挙を楽しめばいい」というスタンスが明快な爆笑作
あわせて読みたい
【驚嘆】映画『TAR/ター』のリディア・ターと、彼女を演じたケイト・ブランシェットの凄まじさ
天才女性指揮者リディア・ターを強烈に描き出す映画『TAR/ター』は、とんでもない作品だ。「縦軸」としてのターの存在感があまりにも強すぎるため「横軸」を上手く捉えきれず、結果「よく分からなかった」という感想で終わったが、それでも「観て良かった」と感じるほど、揺さぶられる作品だった
あわせて読みたい
【傑物】フランスに最も愛された政治家シモーヌ・ヴェイユの、強制収容所から国連までの凄絶な歩み:映…
「フランスに最も愛された政治家」と評されるシモーヌ・ヴェイユ。映画『シモーヌ』は、そんな彼女が強制収容所を生き延び、後に旧弊な社会を変革したその凄まじい功績を描き出す作品だ。「強制収容所からの生還が失敗に思える」とさえ感じたという戦後のフランスの中で、彼女はいかに革新的な歩みを続けたのか
あわせて読みたい
【あらすじ】アリ・アスター監督映画『ミッドサマー』は、気持ち悪さと怖さが詰まった超狂ホラーだった
「夏至の日に映画館で上映する」という企画でようやく観ることが叶った映画『ミッドサマー』は、「私がなんとなく想像していたのとはまるで異なる『ヤバさ』」に溢れる作品だった。いい知れぬ「狂気」が随所で描かれるが、同時に、「ある意味で合理的と言えなくもない」と感じさせられる怖さもある
あわせて読みたい
【実話】映画『グッドバイ、バッドマガジンズ』(杏花主演)が描く、もの作りの絶望(と楽しさ)
実在したエロ雑誌編集部を舞台に、タブーも忖度もなく業界の内実を描き切る映画『グッドバイ、バッドマガジンズ』は、「エロ雑誌」をテーマにしながら、「もの作りに懸ける想い」や「仕事への向き合い方」などがリアルに描かれる素敵な映画だった。とにかく、主役を演じた杏花が良い
あわせて読みたい
【あらすじ】大泉洋主演映画『月の満ち欠け』は「生まれ変わり」の可能性をリアルに描く超面白い作品
あなたは「生まれ変わり」を信じるだろうか? 私はまったく信じないが、その可能性を魅力的な要素を様々に散りばめて仄めかす映画『月の満ち欠け』を観れば、「生まれ変わり」の存在を信じていようがいまいが、「相手を想う気持ち」を強く抱く者たちの人間模様が素敵だと感じるだろう
あわせて読みたい
【衝撃】自ら立ち上げた「大分トリニータ」を放漫経営で潰したとされる溝畑宏の「真の実像」に迫る本:…
まったく何もないところからサッカーのクラブチーム「大分トリニータ」を立ち上げ、「県リーグから出発してチャンピオンになる」というJリーグ史上初の快挙を成し遂げた天才・溝畑宏を描く『爆走社長の天国と地獄』から、「正しく評価することの難しさ」について考える
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『夕方のおともだち』は、「私はこう」という宣言からしか始まらない関係性の”純度”を描く
「こんな田舎にはもったいないほどのドM」と評された男が主人公の映画『夕方のおともだち』は、SM嬢と真性ドMの関わりを通じて、「宣言から始まる関係」の難しさを描き出す。「普通の世界」に息苦しさを感じ、どうしても馴染めないと思っている人に刺さるだろう作品
あわせて読みたい
【偉業】「卓球王国・中国」実現のため、周恩来が頭を下げて請うた天才・荻村伊智朗の信じがたい努力と…
「20世紀を代表するスポーツ選手」というアンケートで、その当時大活躍していた中田英寿よりも高順位だった荻村伊智朗を知っているだろうか?選手としてだけでなく、指導者としてもとんでもない功績を残した彼の生涯を描く『ピンポンさん』から、ノーベル平和賞級の活躍を知る
あわせて読みたい
【伝説】やり投げ選手・溝口和洋は「思考力」が凄まじかった!「幻の世界記録」など数々の逸話を残した…
世界レベルのやり投げ選手だった溝口和洋を知っているだろうか? 私は本書『一投に賭ける』で初めてその存在を知った。他の追随を許さないほどの圧倒的なトレーニングと、常識を疑い続けるずば抜けた思考力を武器に、体格で劣る日本人ながら「幻の世界記録」を叩き出した天才の伝説と実像
あわせて読みたい
【驚嘆】「現在は森でキノコ狩り」と噂の天才”変人”数学者グリゴリー・ペレルマンの「ポアンカレ予想証…
数学界の超難問ポアンカレ予想を解決したが、100万ドルの賞金を断り、フィールズ賞(ノーベル賞級の栄誉)も辞退、現在は「森できのこ採取」と噂の天才数学者グリゴリー・ペレルマンの生涯を描く評伝『完全なる証明』。数学に関する記述はほぼなく、ソ連で生まれ育った1人の「ギフテッド」の苦悩に満ちた人生を丁寧に描き出す1冊
あわせて読みたい
【感想】湯浅政明監督アニメ映画『犬王』は、実在した能楽師を”異形”として描くスペクタクル平家物語
観るつもりなし、期待値ゼロ、事前情報ほぼ皆無の状態で観た映画『犬王』(湯浅政明監督)はあまりにも凄まじく、私はこんなとんでもない傑作を見逃すところだったのかと驚愕させられた。原作の古川日出男が紡ぐ狂気の世界観に、リアルな「ライブ感」が加わった、素晴らしすぎる「音楽映画」
あわせて読みたい
【あらすじ】映画化の小説『僕は、線を描く』。才能・センスではない「芸術の本質」に砥上裕將が迫る
「水墨画」という、多くの人にとって馴染みが無いだろう芸術を題材に据えた小説『線は、僕を描く』は、青春の葛藤と創作の苦悩を描き出す作品だ。「未経験のど素人である主人公が、巨匠の孫娘と勝負する」という、普通ならあり得ない展開をリアルに感じさせる設定が見事
あわせて読みたい
【不謹慎】コンプライアンス無視の『テレビで会えない芸人』松元ヒロを追う映画から芸と憲法を考える
かつてテレビの世界で大ブレイクを果たしながら、現在はテレビから完全に離れ、年間120もの公演を行う芸人・松元ヒロ。そんな知る人ぞ知る芸人を追った映画『テレビで会えない芸人』は、コンプライアンスに厳しく、少数派が蔑ろにされる社会へ一石を投じる、爆笑社会風刺である
あわせて読みたい
【無謀】園子温が役者のワークショップと同時並行で撮影した映画『エッシャー通りの赤いポスト』の”狂気”
「園子温の最新作」としか知らずに観に行った映画『エッシャー通りの赤いポスト』は、「ワークショップ参加者」を「役者」に仕立て、ワークショップと同時並行で撮影されたという異次元の作品だった。なかなか経験できないだろう、「0が1になる瞬間」を味わえる“狂気”の映画
あわせて読みたい
【特異】「カメラの存在」というドキュメンタリーの大前提を覆す映画『GUNDA/グンダ』の斬新さ
映画『GUNDA/グンダ』は、「カメラの存在」「撮影者の意図」を介在させずにドキュメンタリーとして成立させた、非常に異端的な作品だと私は感じた。ドキュメンタリーの「デュシャンの『泉』」と呼んでもいいのではないか。「家畜」を被写体に据えたという点も非常に絶妙
あわせて読みたい
【超人】NHKによる「JAXAの宇宙飛行士選抜試験」のドキュメント。門外不出の「最強の就活」:『ドキュメ…
難攻不落のJAXAと粘り強い交渉を重ね、門外不出の「最強の就活」を捉えたドキュメンタリーを書籍化した『ドキュメント宇宙飛行士選抜試験』。2021年の13年ぶりの募集も話題になったが、「欠点があってはいけない」という視点で厳しく問われる試験・面接の実情を描き出す
あわせて読みたい
【衝撃】卯月妙子『人間仮免中』、とんでもないコミックエッセイだわ。統合失調症との壮絶な闘いの日々
小学5年生から統合失調症を患い、社会の中でもがき苦しみながら生きる卯月妙子のコミックエッセイ『人間仮免中』はとんでもない衝撃作。周りにいる人とのぶっ飛んだ人間関係や、歩道橋から飛び降り自殺未遂を図り顔面がぐちゃぐちゃになって以降の壮絶な日々も赤裸々に描く
あわせて読みたい
【生き方】改めて『いま、地方で生きるということ』を考える。「どこで生きる」は「どう生きる」に直結する
東日本大震災やコロナ禍などの”激変”を経る度に、「どう生きるべきか」と考える機会が増えるのではないだろうか。『いま、地方で生きるということ』は、「どこででも生きていける」というスタンスを軸に、「地方」での著者自身の生活を踏まえつつ、「人生」や「生活」への思考を促す
あわせて読みたい
【衝撃】NHKがアマゾン奥地の先住民ヤノマミ族に長期密着。剥き出しの生と死、文明との共存の難しさ
NHKのディレクターでありノンフィクション作家でもある国分拓が、アマゾン奥地に住む先住民ヤノマミ族の集落で150日間の長期密着を行った。1万年の歴史を持つ彼らの生活を描き出す『ヤノマミ』は、「生と死の価値観の差異」や「先住民と文明との関係の難しさ」を突きつける
あわせて読みたい
【おすすめ】「天才」を描くのは難しい。そんな無謀な挑戦を成し遂げた天才・野崎まどの『know』はヤバい
「物語で『天才』を描くこと」は非常に難しい。「理解できない」と「理解できる」を絶妙なバランスで成り立たせる必要があるからだ。そんな難題を高いレベルでクリアしている野崎まど『know』は、異次元の小説である。世界を一変させた天才を描き、「天才が見ている世界」を垣間見せてくれる
あわせて読みたい
【狂気】日本一将棋に金を使った将棋ファン・団鬼六の生涯を、『将棋世界』の元編集長・大崎善生が描く…
SM小説の大家として一時代を築きつつ、将棋に金を注ぎ込みすぎて2億円の借金を抱えた団鬼六の生涯を、『将棋世界』の元編集長・大崎善生が描くノンフィクション『赦す人』。虚実が判然としない、嘘だろうと感じてしまうトンデモエピソード満載の異端児が辿った凄まじい生涯
あわせて読みたい
【斬新】ホームレスの家を「0円ハウス」と捉える坂口恭平の発想と視点に衝撃。日常の見え方が一変する:…
早稲田大学建築学科在籍中から「建築物の設計」に興味を持てなかった坂口恭平が、「ホームレスの家」に着目した『TOKYO 0円ハウス0円生活』には、「家」に対する考え方を一変させる視点が満載。「家に生活を合わせる」ではなく、「生活に家を合わせる」という発想の転換が見事
あわせて読みたい
【教育】映画化に『3月のライオン』のモデルと話題の村山聖。その師匠である森信雄が語る「育て方」論:…
自身は決して強い棋士ではないが、棋界で最も多くの弟子を育てた森信雄。「村山聖の師匠」として有名な彼の「師匠としてのあり方」を描く『一門 ”冴えん師匠”がなぜ強い棋士を育てられたのか?』から、教育することの難しさと、その秘訣を学ぶ
あわせて読みたい
【驚異】「持続可能な社会」での「豊かな生活」とは?「くじら漁の村」で生きる人々を描く映画:『くじ…
手作りの舟に乗り、銛1本で巨大なクジラを仕留める生活を続けるインドネシアのラマレラ村。そこに住む人々を映し出した映画『くじらびと LAMAFA』は、私たちが普段感じられない種類の「豊かさ」を描き出す。「どう生きるか」を改めて考えさせられる作品だ
あわせて読みたい
【感想】才能の開花には”極限の環境”が必要か?映画『セッション』が描く世界を私は否定したい
「追い込む指導者」が作り出す”極限の環境”だからこそ、才能が開花する可能性もあるとは思う。しかし、そのような環境はどうしても必要だろうか?最高峰の音楽院での壮絶な”指導”を描く映画『セッション』から、私たちの生活を豊かにしてくれるものの背後にある「死者」を想像する
あわせて読みたい
【狂気】バケモン・鶴瓶を映し出す映画。「おもしろいオッチャン」に潜む「異常さ」と「芸への情熱」:…
「俺が死ぬまで公開するな」という条件で撮影が許可された映画『バケモン』。コロナ禍で映画館が苦境に立たされなければ、公開はずっと先だっただろう。テレビで見るのとは違う「芸人・笑福亭鶴瓶」の凄みを、古典落語の名作と名高い「らくだ」の変遷と共に切り取る
あわせて読みたい
【革新】映画音楽における唯一のルールは「ルールなど無い」だ。”異次元の音”を生み出す天才を追う:映…
「無声映画」から始まった映画業界で、音楽の重要性はいかに認識されたのか?『JAWS』の印象的な音楽を生み出した天才は、映画音楽に何をもたらしたのか?様々な映画の実際の映像を組み込みながら、「映画音楽」の世界を深堀りする映画『すばらしき映画音楽たち』で、異才たちの「創作」に触れる
あわせて読みたい
【感想】映画『若おかみは小学生!』は「子どもの感情」を「大人の世界」で素直に出す構成に号泣させられる
ネット記事を読まなければ絶対に観なかっただろう映画『若おかみは小学生!』は、基本的に子ども向け作品だと思うが、大人が観てもハマる。「大人の世界」でストレートに感情を表に出す主人公の小学生の振る舞いと成長に、否応なしに感動させられる
あわせて読みたい
【個性】統合失調症との関わり方を芸人・松本ハウスから学ぶ。本人と周囲の人間はどう対処すべきか:『…
「統合失調症だからといって病気だとは捉えず、ただの個性だと思う」と話す松本キックは、相方・ハウス加賀谷とどう接したか。そしてハウス加賀谷は、いかにして病気と向き合ったか。『統合失調症がやってきた』『相方は、統合失調症』から、普遍的な「人間関係の極意」を学ぶ
あわせて読みたい
【権利】衝撃のドキュメンタリー映画『ヤクザと憲法』は、「異質さを排除する社会」と「生きる権利」を問う
「ヤクザ」が排除された現在でも、「ヤクザが担ってきた機能」が不要になるわけじゃない。ではそれを、公権力が代替するのだろうか?実際の組事務所(東組清勇会)にカメラを持ち込むドキュメンタリー映画『ヤクザと憲法』が映し出す川口和秀・松山尚人・河野裕之の姿から、「基本的人権」のあり方について考えさせられた
あわせて読みたい
【創作】クリエイターになりたい人は必読。ジブリに見習い入社した川上量生が語るコンテンツの本質:『…
ドワンゴの会長職に就きながら、ジブリに「見習い」として入社した川上量生が、様々なクリエイターの仕事に触れ、色んな質問をぶつけることで、「コンテンツとは何か」を考える『コンテンツの秘密』から、「創作」という営みの本質や、「クリエイター」の理屈を学ぶ
あわせて読みたい
【あらすじ】天才とは「分かりやすい才能」ではない。前進するのに躊躇する暗闇で直進できる勇気のこと…
ピアノのコンクールを舞台に描く『蜜蜂と遠雷』は、「天才とは何か?」と問いかける。既存の「枠組み」をいとも簡単に越えていく者こそが「天才」だと私は思うが、「枠組み」を安易に設定することの是非についても刃を突きつける作品だ。小説と映画の感想を一緒に書く
あわせて読みたい
【奇跡】鈴木敏夫が2人の天才、高畑勲と宮崎駿を語る。ジブリの誕生から驚きの創作秘話まで:『天才の思…
徳間書店から成り行きでジブリ入りすることになったプロデューサー・鈴木敏夫が、宮崎駿・高畑勲という2人の天才と共に作り上げたジブリ作品とその背景を語り尽くす『天才の思考 高畑勲と宮崎駿』。日本のアニメ界のトップランナーたちの軌跡の奇跡を知る
あわせて読みたい
【実像】ベートーヴェンの「有名なエピソード」をほぼ一人で捏造・創作した天才プロデューサーの実像:…
ベートーヴェンと言えば、誰もが知っている「運命」を始め、天才音楽家として音楽史に名を刻む人物だが、彼について良く知られたエピソードのほとんどは実は捏造かもしれない。『ベートーヴェン捏造 名プロデューサーは嘘をつく』が描く、シンドラーという”天才”の実像
あわせて読みたい
【天才】写真家・森山大道に密着する映画。菅田将暉の声でカッコよく始まる「撮り続ける男」の生き様:…
映画『あゝ荒野』のスチール撮影の際に憧れの森山大道に初めて会ったという菅田将暉の声で始まる映画『過去はいつも新しく、未来はつねに懐かしい』は、ちゃちなデジカメ1つでひたすら撮り続ける異端児の姿と、50年前の処女作復活物語が見事に交錯する
あわせて読みたい
【映画】『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』で号泣し続けた私はTVアニメを観ていない
TVアニメは観ていない、というかその存在さえ知らず、物語や登場人物の設定も何も知らないまま観に行った映画『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』に、私は大号泣した。「悪意のない物語」は基本的に好きではないが、この作品は驚くほど私に突き刺さった
あわせて読みたい
【天才】諦めない人は何が違う?「努力を努力だと思わない」という才能こそが、未来への道を開く:映画…
どれだけ「天賦の才能」に恵まれていても「努力できる才能」が無ければどこにも辿り着けない。そして「努力できる才能」さえあれば、仮に絶望の淵に立たされることになっても、立ち上がる勇気に変えられる。映画『マイ・バッハ』で知る衝撃の実話
あわせて読みたい
【差別】「女性の権利」とは闘争の歴史だ。ハリウッドを支えるスタントウーマンたちの苦悩と挑戦:『ス…
男性以上に危険で高度な技術を要するのに、男性優位な映画業界で低く評価されたままの女性スタントたちを描く映画『スタントウーマン ハリウッドの知られざるヒーローたち』。女性スタントの圧倒的な努力・技術と、その奮闘の歴史を知る。
あわせて読みたい
【再生】ヤクザの現実を切り取る映画『ヤクザと家族』から、我々が生きる社会の”今”を知る
「ヤクザ」を排除するだけでは「アンダーグラウンドの世界」は無くならないし、恐らく状況はより悪化しただけのはずだ。映画『ヤクザと家族』から、「悪は徹底的に叩きのめす」「悪じゃなければ何をしてもいい」という社会の風潮について考える。
あわせて読みたい
【救い】耐えられない辛さの中でどう生きるか。短歌で弱者の味方を志すホームレス少女の生き様:『セー…
死にゆく母を眺め、施設で暴力を振るわれ、拾った新聞で文字を覚えたという壮絶な過去を持つ鳥居。『セーラー服の歌人 鳥居』は、そんな辛い境遇を背景に、辛さに震えているだろう誰かを救うために短歌を生み出し続ける生き方を描き出す。凄い人がいるものだ
あわせて読みたい
【改革】AIは将棋をどう変えた?羽生善治・渡辺明ら11人の現役棋士が語る将棋の未来:『不屈の棋士』(…
既に将棋AIの実力はプロ棋士を越えたとも言われる。しかし、「棋力が強いかどうか」だけでは将棋AIの良し悪しは判断できない。11人の現役棋士が登場する『不屈の棋士』をベースに、「AIは将棋界をどう変えたのか?」について語る
あわせて読みたい
【葛藤】部活で後悔しないために。今やりたいことをやりきって、過去を振り返らないための全力:『風に…
勉強の方が、部活動より重要な理由なんて無い。どれだけ止められても「全力で打ち込みたい」という気持ちを抑えきれないものに出会える人生の方が、これからの激動の未来を生き延びられるはずと信じて突き進んでほしい。部活小説『風に恋う』をベースに書いていく
あわせて読みたい
【表現者】「センスが良い」という言葉に逃げない。自分の内側から何かを表現することの本質:『作詞少…
大前提として、表現には「技術」が必要だ。しかし、「技術」だけでは乗り越えられない部分も当然ある。それを「あいつはセンスが良いから」という言葉に逃げずに、向き合ってぶつかっていくための心得とは何か。『作詞少女』をベースに「表現することの本質」を探る
ルシルナ
文化・芸術・将棋・スポーツ【本・映画の感想】 | ルシルナ
知識や教養は、社会や学問について知ることだけではありません。文化的なものもリベラルアーツです。私自身は、創作的なことをしたり、勝負事に関わることはありませんが、…
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…
 犀川後藤
犀川後藤


















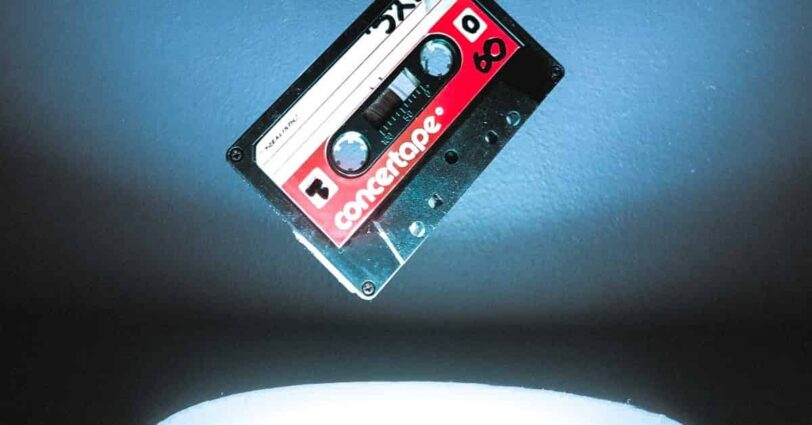
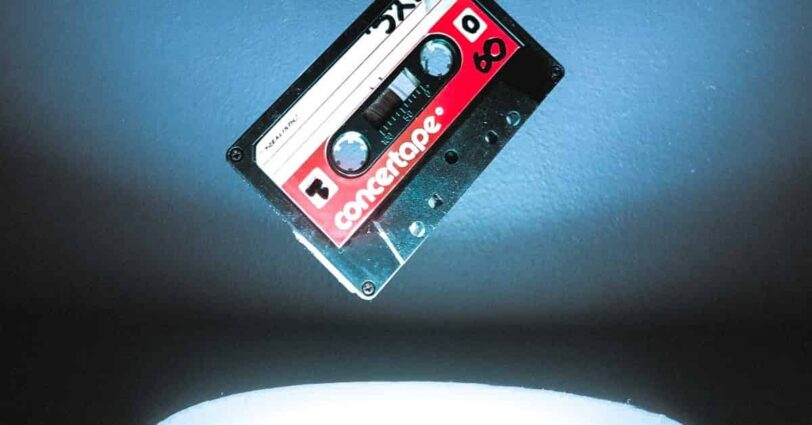





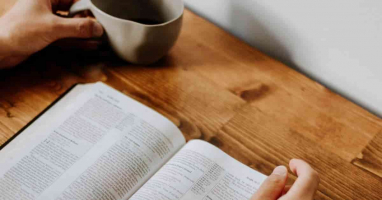
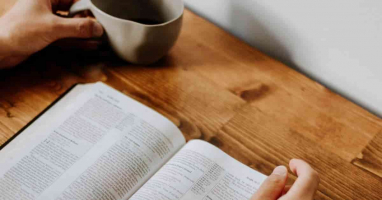





















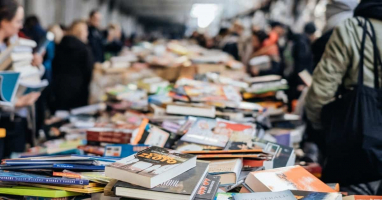
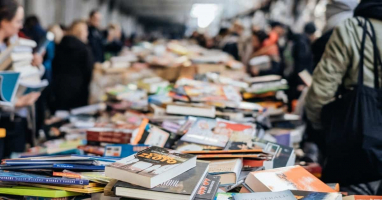
































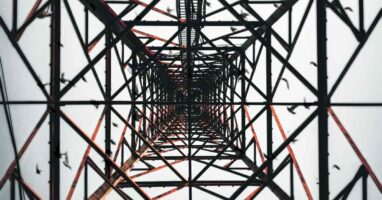
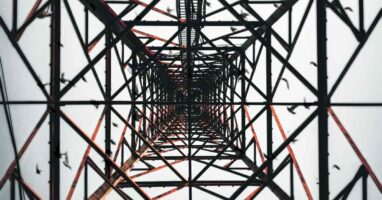














































































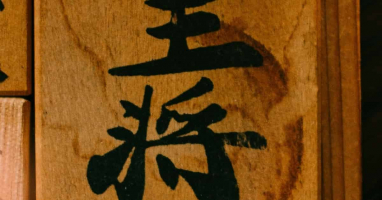
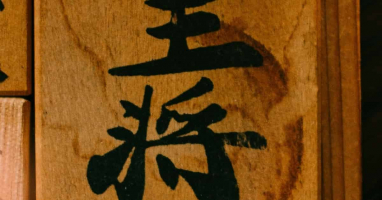














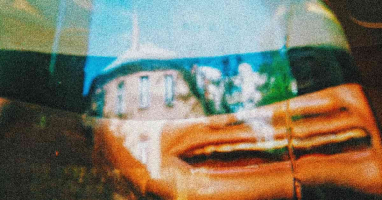
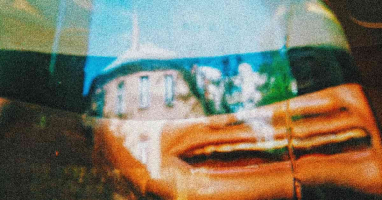














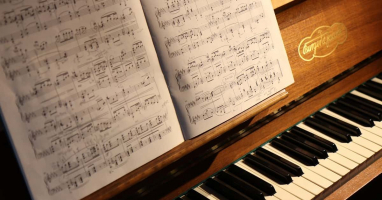
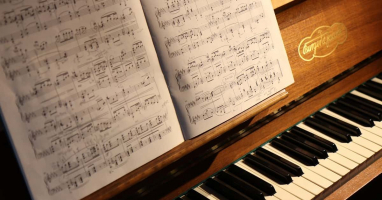


























コメント