目次
はじめに
この記事で取り上げる本
著:国分 拓
¥781 (2022/07/23 18:31時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
この本をガイドにしながら記事を書いていきます
この記事の3つの要点
- 1970年代に文明社会と接点を持ったばかりのヤノマミ族が送る、悠久の時間の堆積を感じさせる生活
- 「生まれたばかりの赤ちゃんは『人間』ではなく『精霊』」という価値観の衝撃
- 私たち文明社会とは大きく異なる「死」の捉え方
「映像で観たかった」と感じたほど、想像を遥かに超える「生活」に驚愕させられる
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
1万年以上独自の文化を保ってきたアマゾン先住民ヤノマミ族にNHK取材班が長期密着した記録

あわせて読みたい
【驚異】「持続可能な社会」での「豊かな生活」とは?「くじら漁の村」で生きる人々を描く映画:『くじ…
手作りの舟に乗り、銛1本で巨大なクジラを仕留める生活を続けるインドネシアのラマレラ村。そこに住む人々を映し出した映画『くじらびと LAMAFA』は、私たちが普段感じられない種類の「豊かさ」を描き出す。「どう生きるか」を改めて考えさせられる作品だ
本書は、NHKのドキュメンタリーとして放送された「ヤノマミ族の長期密着」に携わった、NHKのディレクターでありノンフィクション作家でもある国分拓が執筆した作品だ。取材班は、2007年11月から2008年12月に掛けて計4回、150日間に渡ってヤノマミ族と共に暮らした、その記録である。
ヤノマミ族についての説明と、「先住民と文明の関係の難しさ」
緊張を強いる「文明」社会から見ると、原初の森での暮らしは、時に理想郷に見える。だが、ワトリキは甘いユートピアではなかった。文明社会によって理想化された原始協賛的な共同体でもなかった。ワトリキには、ただ「生と死」だけがあった。「善悪」や「倫理」や「文明」や「法律」や「掟」を越えた、剥き出しの生と死だけがあった。一万年にわたった営々と続いてきた、生と死だけがあった。
あわせて読みたい
【人類学】少数民族・ムラブリ族に潜入した映画『森のムラブリ』は、私たちの「当たり前」を鮮やかに壊す
タイとラオスにまたがって存在する少数民族・ムラブリ族に密着したドキュメンタリー映画『森のムラブリ』。「ムラブリ族の居住地でたまたま出会った日本人人類学者」と意気投合し生まれたこの映画は、私たちがいかに「常識」「当たり前」という感覚に囚われているのかを炙り出してくれる
取材班が住まわせてもらった集落が「ワトリキ」である。「ただ『生と死』だけがあった」というのは、なんともインパクトの強い言葉だろう。そしてその指摘は、私たちが普段いかに”余計なもの”をまとって生活しているかという証なのかもしれないとも思う。「善悪」「倫理」「文明」「法律」「掟」が存在しない社会の方が良いなどと言いたいわけではない。しかし、まさにプリミティブであり、私たちの祖先も彼らのような生活を通ってきているはずだ。いかに私たちが”余計なもの”を抱えながら社会生活を行っているのかが実感できるだろうと思う。
ワトリキに住むヤノマミ族は、1970年代に初めて文明社会と接点を持ったという。1万年以上にも渡る長い歴史の中で、文明と関わった期間はごく僅かに過ぎない。また、ヤノマミの長老たちは、「文明社会と接触した少数民族が疫病などによって駆逐された」という歴史を知っている。少数民族は伝染病などに対する抵抗力を持たないため、私たちにとっては特に害を及ぼさないようなウイルス・細菌などによっても、命を落としてしまうのだ。コロンブス以降、アメリカ大陸に上陸したヨーロッパ人が簡単に先住民を制圧できたのも、そのような背景があったからだと考えられている。
あわせて読みたい
【最新】「コロンブス到達以前のアメリカ大陸」をリアルに描く歴史書。我々も米国人も大いに誤解してい…
サイエンスライターである著者は、「コロンブス到着以前のアメリカはどんな世界だったか?」という問いに触れ、その答えが書かれた本がいつまで経っても出版されないので自分で執筆した。『1491 先コロンブス期アメリカ大陸をめぐる新発見』には、アメリカ人も知らない歴史が満載だ
だから、ヤノマミ族にとって、文明側の人間と接触することは、ただそれだけで「命の危険」になり得るのだ。

さらに、先住民と文明の関係については、次のような問題もある。
ヤノマミの居住区が保護区に指定された時、FUNAIの総裁として陣頭に立ったシドニー・ポスエロ氏は、先住民と「文明」との難しい関係について、こう語っている。
「原初の世界に生きる先住民にとって最も不幸なことは、私たちと接触してしまうことなのかもしれない。彼らは私たちと接触することで笑顔を失う。モノを得る代わりに笑顔を失う。彼らの集落はどんなに小さくても一つの国なのだ。独自の言語、風習、文化を持つ一つの国なのだ。そうした国が滅んだり、なくなったり、変わってしまうということは、私たちが持つ豊かさを失うことなのだ」
本来は、お互いがまったく関わりを持たないことこそが最も理想的だと言えるだろう。しかし、そう簡単な話ではない。何もしなければ、彼らが住む土地を開発してリゾートやゴルフ場が建設されてしまうかもしれない。そのような状況を防ぐためにも、文明側のルールで「ここは保護されている」と区分するしかないのだ。
あわせて読みたい
【意外】思わぬ資源が枯渇。文明を支えてきた”砂”の減少と、今後我々が変えねばならぬこと:『砂と人類』
「砂が枯渇している」と聞いて信じられるだろうか?そこら中にありそうな砂だが、産業用途で使えるものは限られている。そしてそのために、砂浜の砂が世界中で盗掘されているのだ。『砂と人類』から、石油やプラスチックごみ以上に重要な環境問題を学ぶ
しかしそうだとしても、先住民にとってはやはり「関わりを持ってしまったこと」が何よりの悪手となる。このジレンマの解消はなかなか難しい。
そのようなことをすべて承知した上で、ヤノマミ族は取材班を受け入れてくれる。しかしだからと言って、常に友好的な関係だったのかというと、そうではない。
ナプの一語は、彼らと僕たちを一瞬のうちに隔て分ける魔法のコトバだった。誰かがナプと言った瞬間に彼らは一つにまとまり、僕たちは他者となった。ついさっきまで楽しげに話したり歌ったりしていたとしても、関係はなかった。ナプの一語は万能の神がかける呪いの言葉のように、瞬時に僕たちを遠くへと追いやり、懸命に積み上げようとしてきた関係が一気に崩壊する合図となった。
当然だが、取材班は「受け入れてもらっている側」であり、どんな状況であれ、彼らが我慢するしかないと思う。何度も繰り返すが、ヤノマミ族には取材班を受け入れるメリットなど1つとしてないからだ。そういう中で著者らも、可能な限りコミュニケーションを取ろうと努力する。しかし、言葉も歴史も価値観も何もかもが異なる相手と、”たった150日間”で気持ちを通じ合わせようと考える方にやはり無理があるだろう。
あわせて読みたい
【書評】奇跡の”国家”「ソマリランド」に高野秀行が潜入。崩壊国家・ソマリア内で唯一平和を保つ衝撃の”…
日本の「戦国時代」さながらの内戦状態にあるソマリア共和国内部に、十数年に渡り奇跡のように平和を維持している”未承認国家”が存在する。辺境作家・高野秀行の『謎の独立国家ソマリランド』から、「ソマリランド」の理解が難しい理由と、「奇跡のような民主主義」を知る
とはいえ、本書を読むと、取材班の苦労もしのばれる。
だから帰国してからも考え続けた。番組を作りながら考え、番組が終わったあとも考えた。なのに、やはり、分からない。考えれば考えるほど何かが壊れていくような感覚も変わらない。心身は不健全なままで、求める答えも見つかりそうになかった。
取材班は、ワトリキでの生活の様々な点に追い詰められていく。それは、食事の合わなさだったり、虫にたかられることだったり、何もすることがない退屈な時間だったりと様々だ。しかし、その中でも最も衝撃的で、取材班もどう受け取ればいいのか分からなかっただろうヤノマミ族の”ある風習”を取り上げようと思う。
あわせて読みたい
【異次元】『ハイパーハードボイルドグルメリポート』は本も読め。衝撃すぎるドキュメンタリーだぞ
テレビ東京の上出遼平が作る、“異次元のグルメ番組”である「ハイパーハードボイルドグルメリポート」の書籍化。映像からも異様さが伝わる「激ヤバ地」に赴き、そこに住む者と同じモノを食べるという狂気が凄まじい。私がテレビで見た「ケニアのゴミ山の少年」の話は衝撃的だった
生まれたばかりの赤ちゃんは「人間」ではなく「精霊」
取材班は、赤ちゃんを産んだ少女の衝撃的な行動を目撃する。

45時間後に無事出産した時、不覚にも涙が出そうになった。おめでとう、と声をかけたくもなった。だが、そうしようと思った矢先、少女は僕たちの目の前で嬰児を天に送った。自分の手と足を使って、表情を変えずに子どもを殺めた。動けなかった。心臓がバクバクした。それは思いもよらないことだったから、身体が硬直し、思考が停止した。
ここには、「生まれたばかりの子どもは『人間』ではなく『精霊』だ」という考えがある。「赤ちゃんは、母親に抱き上げられることで初めて『人間』になる」と考えられているのだ。
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『悪は存在しない』(濱口竜介)の衝撃のラストの解釈と、タイトルが示唆する現実(主…
映画『悪は存在しない』(濱口竜介監督)は、観る者すべてを困惑に叩き落とす衝撃のラストに、鑑賞直後は迷子のような状態になってしまうだろう。しかし、作中で提示される様々な要素を紐解き、私なりの解釈に辿り着いた。全編に渡り『悪は存在しない』というタイトルを強く意識させられる、脚本・映像も見事な作品だ
だから、子どもを産む女性は、毎回決断を迫られる。「精霊」として生まれた赤ちゃんを「人間」として迎え入れるか、あるいは「精霊」のまま天に還すのか、と。
子どもは死んだのではない。精霊となってホトカラに行っただけなのだ。自分も死ねば精霊となってホトカラに行く。ホトカラに行けば精霊となった子どもとまた会える。女はそう信じていた。ホトカラとは、女たちにとって再会の場でもあった。
このような死生観がどのようにして生まれたのか、正確には分からない。しかしかつて日本でも、貧しさ故に赤ちゃんを川に流したり山に捨てたりするのが当たり前だった時代がある。彼らを一方的に”野蛮”と判断することは難しい。
文明は「避妊」のための様々なツールを発明してきたが、そのような手段のない先住民の場合、私たちが生きる社会と比べ物にならないほど「予期せぬ妊娠」が多いのではないかと思う。様々な事情から、生まれてくる子どもをすべて育てることはできない。だからこそ、「精霊」という考え方によって、特に母親の負担を取り除こうとしたのではないだろうか。
あわせて読みたい
【中絶】望まない妊娠をした若い女性が直面する現実をリアルに描く映画。誰もが現状を知るべきだ:『17…
他の様々な要素を一切排し、「望まぬ妊娠をした少女が中絶をする」というただ1点のみに全振りした映画『17歳の瞳に映る世界』は、説明もセリフも極端に削ぎ落としたチャレンジングな作品だ。主人公2人の沈黙が、彼女たちの置かれた現実を雄弁に物語っていく。
精霊のまま我が子を送る母親の胸中を女たちはけっして語らない。ナプに対しても、身内に対しても語らない。ワトリキでは、「命」を巡る決断は女が下し理由は一切問われない。母親以外の者は何も言わず、ただ従うだけだ。
考えてみれば我々の社会でも、同じようなことが行われている。日本では、妊娠21週までは中絶が可能だ。これは極端に言えば、「妊娠21週までは、胎児は人間ではないから殺してもいい」と表現してもいいだろう。手法が違うだけで、ほとんど同じようなことをしていると言っていい。
しかし、ヤノマミ族の「死生観」に対しては、私たちの社会のものと大きな違いを感じるかもしれない。

あわせて読みたい
【異端】「仏教とは?」を簡単に知りたい方へ。ブッダは「異性と目も合わせないニートになれ」と主張し…
我々が馴染み深い「仏教」は「大乗仏教」であり、創始者ゴータマ・ブッダの主張が詰まった「小乗仏教」とは似て非なるものだそうだ。『講義ライブ だから仏教は面白い!』では、そんな「小乗仏教」の主張を「異性と目も合わせないニートになれ」とシンプルに要約して説明する
だが、ヤノマミには墓がない。遺骸は焼いて、埋めて、掘り起こして食べるだけだ。彼らにとって死とは、いたずらに悲しみ、悼み、神格化し、儀式化するものではない。僕たちには見えない大きな空間の中で、生とともに、ただそこに在るものなのだ。
人類が生み出してきたどんな文明も、大抵「死者を埋葬する」といった文化を有する印象を持っていたが、ヤノマミ族はそうではないようだ。私たちが生きる社会では、「死」を過度に特別視することによって、日常から「死」を排除しているようなイメージを私は持っている。しかしヤノマミ族にとっては、「生」も「死」も渾然一体となったものとして捉えられているというわけだ。
ただ決して、日常の中に「死」が組み込まれているというわけではない。
ヤノマミのしきたりでは、死者に縁のあるものは死者とともに燃やさねばならない。そして、死者にまつわるすべてを燃やしたのち、死者に関する全てを忘れる。名前も、顔も、そんな人間がいたことも忘れる。彼らは死者の名前をけっして口にしない。
「私たちが死者の名前を口にしないのは、思い出すと泣いてしまうからだ。その人がいなくなった淋しさに胸が壊れてしまうからだ。ヤノマミは言葉にはせず、心の奥底で想い、悲しみに暮れ、涙を流す。遠い昔、私たちを作った<オマム(ヤノマミの創造主)>はヤノマミに泣くことを教えた。死者の名前を忘れても、ヤノマミは泣くことを忘れない」
あわせて読みたい
【思考】『翔太と猫のインサイトの夏休み』は、中学生と猫の対話から「自分の頭で考える」を学べる良書
「中学生の翔太」と「猫のインサイト」が「答えの出ない問い」について対話する『翔太と猫のインサイトの夏休み』は、「哲学」の違う側面を見せてくれる。過去の哲学者・思想家の考えを知ることが「哲学」なのではなく、「自分の頭で考えること」こそ「哲学」の本質だと理解する
「死」は誰もが避けられないものだ。そんな「死」に際して文明社会は、「死者を埋葬し、折に触れて思い出す」という習慣を持つようになった。しかしヤノマミ族は、「悲しくなるから思い出さない」というやり方で「死」と向き合う文化を作り上げたのだ。これもまた「野蛮」という印象から遠ざかる捉え方だろう。否応なしに「日常」に侵食してくる「死」にどのように向き合い、どう対処していったのか。彼らの奮闘の歴史が僅かながらでも垣間見えるように感じられた。
ワトリキでの生活
著者は本書で、「できるだけ事実を淡々と記述する」ことに徹しているように思う。もちろん、子どもを殺した少女を目撃した場面など、著者の想いが溢れ出てしまう箇所もあるが、全体としてはかなり抑えられているといえる。またそもそも、言語の違いにより、完璧なコミュニケーションが取れるわけではない。ゆえに推測や想像でしか判断できない部分もあり、彼らが「事実」として書いていることが勘違いである可能性もゼロではないだろう。
いずれにせよ著者は、可能な限り「文明側」の論理を排して目の前の現実を捉えようとし、ヤノマミ側の視点で状況を描き出そうと努力している。
あわせて読みたい
【生き方】改めて『いま、地方で生きるということ』を考える。「どこで生きる」は「どう生きる」に直結する
東日本大震災やコロナ禍などの”激変”を経る度に、「どう生きるべきか」と考える機会が増えるのではないだろうか。『いま、地方で生きるということ』は、「どこででも生きていける」というスタンスを軸に、「地方」での著者自身の生活を踏まえつつ、「人生」や「生活」への思考を促す

「ヤノマミ族がどのような生活をしているのか」を短くまとめることは難しい。是非本書を読んでほしいと思う。ざっくり書くとこんな感じになるだろう。彼らは<シャボノ>と呼ばれるとてつもなく大きな家に住んでいる。ワトリキという集落に1つの家というイメージでいいだろう。間仕切りのないその<シャボノ>に、160名以上が共に生活をしている。男は狩りに出かけ、女は畑仕事だ。時折開かれる祭りを楽しみにし、夫婦の境を越えて男女は比較的自由に交わる。
ワトリキには、僕たちの社会にはない時間が流れているようだった。
と著者は書いているが、まさにそれは「1万年もの時間の堆積」なのだと思う。私たちは、あまりに早すぎる時間の中で生きているため、日常生活の中で「時間の堆積」を感じる機会などほとんどない。神社仏閣でなどその僅かな雰囲気を感じ取れるぐらいだろうか。著者が「異なる時間の流れ」を感じたのも当然と言えるだろう。
あわせて読みたい
【感想】どんな話かわからない?難しい?ジブリ映画『君たちはどう生きるか』の考察・解説は必要?(監…
宮崎駿最新作であるジブリ映画『君たちはどう生きるか』は、宮崎アニメらしいファンタジックな要素を全開に詰め込みつつ、「生と死」「創造」についても考えさせる作品だ。さらに、「自分の頭の中から生み出されたものこそ『正解』」という、創造物と向き合う際の姿勢についても問うているように思う
その一方で、ヤノマミ族の中でも文明化が急速に進んでいるらしく、若い世代と年配の世代とで対立が起き始めているとも書かれていた。これもまた、文明と接したことによるマイナスと言えるだろう。
ヤノマミの生活や価値観を知ることは、「文明の功罪」について考える機会にもなるというわけだ。
あわせて読みたい
【狂気】異質なホラー映画『みなに幸あれ』(古川琴音主演)は古い因習に似せた「社会の異様さ」を描く
古川琴音主演映画『みなに幸あれ』は、”シュールさ”さえ感じさせる「異質なホラー映画」だ。「村の因習」というよくあるパターンをベースに据えつつ、そこで展開される異様な状況が、実は「私たちが生きる世界」に対応しているという構成になっている。「お前の物語だからな」と終始突きつけられ続ける作品だ
著:国分 拓
¥781 (2022/07/23 18:33時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品読了済】私が読んできたノンフィクション・教養書を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が読んできたノンフィクションを様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本選びの参考にして下さい。
最後に
あわせて読みたい
【挑戦】深海に棲む”聖杯”ダイオウイカをNHKが世界初撮影。関わった者が語る奇跡のプロジェクト:『ドキ…
NHK主導で進められた、深海に棲む”聖杯”ダイオウイカの撮影プロジェクト。10年にも及ぶ過酷な挑戦を描いた『ドキュメント 深海の超巨大イカを追え!』は、ほぼ不可能と思われていたプロジェクトをスタートさせ、艱難辛苦の末に見事撮影に成功した者たちの軌跡を描き出す
本書を読んで、「やはり映像で観たかった」と感じた。調べると、NHKオンデマンドで観られるようだが、基本的に「サブスクには加入しない」と決めているので、私には観る機会はない(ただどうやら、サブスクに入らなくても番組を単品で観ることもできるようだ。いずれ観るかもしれない)
NHKオンデマンド
NHKスペシャル ヤノマミ 奥アマゾン 原初の森に生きる −NHKオンデマンド
月額990円(税込)でNHKの名作見放題!奥アマゾンの密林で1万年以上、独自の文化・風習を守り続けているヤノマミ族。“最後の石器人”と呼ばれる彼らの原初の生き方を通して…
解説を担当した俵万智は、「ドキュメンタリーを観た人たちの間でしばらく大きな話題となった」と書いている。そんな風に言われたら、やはり気になってしまう。
文明に触れたヤノマミ族のところにも、コロナウイルスは届いてしまっているのだろうか。彼らが彼らなりの幸せを維持できるような環境がどうにか残っていることを祈るばかりである。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【食&芸術】死んでも車を運転したくない人間の香川うどん巡り& 豊島アート巡りの旅ルート(山越うどん…
仕事終わりの木曜日夜から日曜日に掛けて、「香川のうどん巡り」と「豊島のアート巡り」をしてきました。うどんだけでも7580円分食べたので、かなりの軒数を回ったことになります。しかも「死んでも車を運転したくない」ため、可能な限り公共交通機関のみで移動しました。私と同じように「車を運転したくない人」には、かなり参考になる記事と言えるのではないかと思います
あわせて読みたい
【斬新】フィクション?ドキュメンタリー?驚きの手法で撮られた、現実と虚構が入り混じる映画:『最悪…
映画『最悪な子どもたち』は、最後まで観てもフィクションなのかドキュメンタリーなのか確信が持てなかった、普段なかなか抱くことのない感覚がもたらされる作品だった。「演技未経験」の少年少女を集めての撮影はかなり実験的に感じられたし、「分からないこと」に惹かれる作品と言えるいだろうと思う
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『悪は存在しない』(濱口竜介)の衝撃のラストの解釈と、タイトルが示唆する現実(主…
映画『悪は存在しない』(濱口竜介監督)は、観る者すべてを困惑に叩き落とす衝撃のラストに、鑑賞直後は迷子のような状態になってしまうだろう。しかし、作中で提示される様々な要素を紐解き、私なりの解釈に辿り着いた。全編に渡り『悪は存在しない』というタイトルを強く意識させられる、脚本・映像も見事な作品だ
あわせて読みたい
【狂気】異質なホラー映画『みなに幸あれ』(古川琴音主演)は古い因習に似せた「社会の異様さ」を描く
古川琴音主演映画『みなに幸あれ』は、”シュールさ”さえ感じさせる「異質なホラー映画」だ。「村の因習」というよくあるパターンをベースに据えつつ、そこで展開される異様な状況が、実は「私たちが生きる世界」に対応しているという構成になっている。「お前の物語だからな」と終始突きつけられ続ける作品だ
あわせて読みたい
【感想】映画『正欲』に超共感。多様性の時代でさえどこに行っても馴染めない者たちの業苦を抉る(出演…
映画『正欲』は、私には共感しかない作品だ。特に、新垣結衣演じる桐生夏月と磯村勇斗演じる佐々木佳道が抱える葛藤や息苦しさは私の内側にあるものと同じで、その描かれ方に圧倒されてしまった。「『多様性』には『理解』も『受け入れ』も不要で、単に否定しなければ十分」なのだと改めて思う
あわせて読みたい
【不穏】大友克洋の漫画『童夢』をモデルにした映画『イノセンツ』は、「無邪気な残酷さ」が恐ろしい
映画『イノセンツ』は、何がどう展開するのかまるで分からないまま進んでいく実に奇妙な物語だった。非現実的な設定で描かれるのだが、そのことによって子どもたちの「無邪気な残酷さ」が一層リアルに浮き彫りにされる物語であり、「意図的に大人が排除された構成」もその一助となっている
あわせて読みたい
【感想】これはドキュメンタリー(実話)なのか?映画『女神の継承』が突きつける土着的恐怖
ナ・ホンジンがプロデューサーを務めた映画『女神の継承』は、フィクションなのかドキュメンタリーなのか混乱させる異様な作品だった。タイ東北部で強く信じられている「精霊(ピー)」の信仰をベースに、圧倒的なリアリティで土着的恐怖を描き出す、強烈な作品
あわせて読みたい
【感想】どんな話かわからない?難しい?ジブリ映画『君たちはどう生きるか』の考察・解説は必要?(監…
宮崎駿最新作であるジブリ映画『君たちはどう生きるか』は、宮崎アニメらしいファンタジックな要素を全開に詰め込みつつ、「生と死」「創造」についても考えさせる作品だ。さらに、「自分の頭の中から生み出されたものこそ『正解』」という、創造物と向き合う際の姿勢についても問うているように思う
あわせて読みたい
【人類学】少数民族・ムラブリ族に潜入した映画『森のムラブリ』は、私たちの「当たり前」を鮮やかに壊す
タイとラオスにまたがって存在する少数民族・ムラブリ族に密着したドキュメンタリー映画『森のムラブリ』。「ムラブリ族の居住地でたまたま出会った日本人人類学者」と意気投合し生まれたこの映画は、私たちがいかに「常識」「当たり前」という感覚に囚われているのかを炙り出してくれる
あわせて読みたい
【感想】映画『朝が来る』が描く、「我が子を返して欲しい気持ち」を消せない特別養子縁組のリアル
「特別養子縁組」を軸に人々の葛藤を描く映画『朝が来る』は、決して「特別養子縁組」の話ではない。「『起こるだろうが、起こるはずがない』と思っていた状況」に直面せざるを得ない人々が、「すべての選択肢が不正解」という中でどんな決断を下すのかが問われる、非常に示唆に富む作品だ
あわせて読みたい
【異様】西成のあいりん地区を舞台にした映画『解放区』は、リアルとフェイクの境界が歪んでいる
ドキュメンタリー映画だと思って観に行った『解放区』は、実際にはフィクションだったが、大阪市・西成区を舞台にしていることも相まって、ドキュメンタリー感がとても強い。作品から放たれる「異様さ」が凄まじく、「自分は何を観せられているんだろう」という感覚に襲われた
あわせて読みたい
【考察】映画『哀愁しんでれら』から、「正しい」より「間違ってはいない」を選んでしまう人生を考える
「シンデレラストーリー」の「その後」を残酷に描き出す映画『哀愁しんでれら』は、「幸せになりたい」という気持ちが結果として「幸せ」を遠ざけてしまう現実を描き出す。「正しい/間違ってはいない」「幸せ/不幸せではない」を区別せずに行動した結果としての悲惨な結末
あわせて読みたい
【革命】観る将必読。「将棋を観ること」の本質、より面白くなる見方、そして羽生善治の凄さが満載:『…
野球なら「なんで今振らないんだ!」みたいな素人の野次が成立するのに、将棋は「指せなきゃ観てもつまらない」と思われるのは何故か。この疑問を起点に、「将棋を観ること」と「羽生善治の凄さ」に肉薄する『羽生善治と現代』は、「将棋鑑賞」をより面白くしてくれる話が満載
あわせて読みたい
【未知】「占い」が占い以外の効果を有するように、UFOなど「信じたいものを信じる」行為の機能を知れる…
「占い」に「見透かされたから仕方なく話す」という効用があるように、「『未知のもの』を信じる行為」には「『否定されたという状態』に絶対に達しない」という利点が存在する。映画『虚空門GATE』は、UFOを入り口に「『未知のもの』を信じる行為」そのものを切り取る
あわせて読みたい
【幸福】「死の克服」は「生の充実」となり得るか?映画『HUMAN LOST 人間失格』が描く超管理社会
アニメ映画『HUMAN LOST 人間失格』では、「死の克服」と「管理社会」が分かちがたく結びついた世界が描かれる。私たちは既に「緩やかな管理社会」を生きているが、この映画ほどの管理社会を果たして許容できるだろうか?そしてあなたは、「死」を克服したいと願うだろうか?
あわせて読みたい
【異次元】『ハイパーハードボイルドグルメリポート』は本も読め。衝撃すぎるドキュメンタリーだぞ
テレビ東京の上出遼平が作る、“異次元のグルメ番組”である「ハイパーハードボイルドグルメリポート」の書籍化。映像からも異様さが伝わる「激ヤバ地」に赴き、そこに住む者と同じモノを食べるという狂気が凄まじい。私がテレビで見た「ケニアのゴミ山の少年」の話は衝撃的だった
あわせて読みたい
【狂気】”友好”のために北朝鮮入りした監督が撮った映画『ザ・レッド・チャペル』が映す平壌の衝撃
倫理的な葛藤を物ともせず、好奇心だけで突き進んでいくドキュメンタリー監督マッツ・ブリュガーが北朝鮮から「出禁」を食らう結果となった『ザ・レッド・チャペル』は、「友好」を表看板に北朝鮮に潜入し、その「日常」と「非日常」を映し出した衝撃作
あわせて読みたい
【挑戦】深海に棲む”聖杯”ダイオウイカをNHKが世界初撮影。関わった者が語る奇跡のプロジェクト:『ドキ…
NHK主導で進められた、深海に棲む”聖杯”ダイオウイカの撮影プロジェクト。10年にも及ぶ過酷な挑戦を描いた『ドキュメント 深海の超巨大イカを追え!』は、ほぼ不可能と思われていたプロジェクトをスタートさせ、艱難辛苦の末に見事撮影に成功した者たちの軌跡を描き出す
あわせて読みたい
【生き方】改めて『いま、地方で生きるということ』を考える。「どこで生きる」は「どう生きる」に直結する
東日本大震災やコロナ禍などの”激変”を経る度に、「どう生きるべきか」と考える機会が増えるのではないだろうか。『いま、地方で生きるということ』は、「どこででも生きていける」というスタンスを軸に、「地方」での著者自身の生活を踏まえつつ、「人生」や「生活」への思考を促す
あわせて読みたい
【憤り】世界最強米海軍4人VS数百人のタリバン兵。死線を脱しただ1人生還を果たした奇跡の実話:『アフ…
アフガニスタンの山中で遭遇した羊飼いを見逃したことで、数百人のタリバン兵と死闘を繰り広げる羽目に陥った米軍最強部隊に所属する4人。奇跡的に生き残り生還を果たした著者が記す『アフガン、たった一人の生還』は、とても実話とは信じられない凄まじさに満ちている
あわせて読みたい
【おすすめ】「天才」を描くのは難しい。そんな無謀な挑戦を成し遂げた天才・野崎まどの『know』はヤバい
「物語で『天才』を描くこと」は非常に難しい。「理解できない」と「理解できる」を絶妙なバランスで成り立たせる必要があるからだ。そんな難題を高いレベルでクリアしている野崎まど『know』は、異次元の小説である。世界を一変させた天才を描き、「天才が見ている世界」を垣間見せてくれる
あわせて読みたい
【青春】二宮和也で映画化もされた『赤めだか』。天才・立川談志を弟子・談春が描く衝撃爆笑自伝エッセイ
「落語協会」を飛び出し、新たに「落語立川流」を創設した立川談志と、そんな立川談志に弟子入りした立川談春。「師匠」と「弟子」という関係で過ごした”ぶっ飛んだ日々”を描く立川談春のエッセイ『赤めだか』は、立川談志の異端さに振り回された立川談春の成長譚が面白い
あわせて読みたい
【衝撃】洗脳を自ら脱した著者の『カルト脱出記』から、「社会・集団の洗脳」を避ける生き方を知る
「聖書研究に熱心な日本人証人」として「エホバの証人」で活動しながら、その聖書研究をきっかけに自ら「洗脳」を脱した著者の体験を著した『カルト脱出記』。広い意味での「洗脳」は社会のそこかしこに蔓延っているからこそ、著者の体験を「他人事」だと無視することはできない
あわせて読みたい
【感想】リドリー・スコット監督の映画『最後の決闘裁判』から、社会が”幻想”を共有する背景とその悲劇…
例えば、「1万円札」というただの紙切れに「価値を感じる」のは、社会の構成員が同じ「共同幻想」の中に生きているからだ。リドリー・スコット監督の映画『最後の決闘裁判』は、「強姦では妊娠しない」「裁判の勝者を決闘で決する」という社会通念と、現代にも通じる「共同幻想」の強さを描き出す
あわせて読みたい
【理解】小野田寛郎を描く映画。「戦争終結という現実を受け入れない(=認知的不協和)」は他人事じゃ…
映画『ONODA 一万夜を越えて』を観るまで、小野田寛郎という人間に対して違和感を覚えていた。「戦争は終わっていない」という現実を生き続けたことが不自然に思えたのだ。しかし映画を観て、彼の生き方・決断は、私たちと大きく変わりはしないと実感できた
あわせて読みたい
【選択】映画『サウンド・オブ・メタル』で難聴に陥るバンドマンは、「障害」と「健常」の境界で揺れる
ドラムを叩くバンドマンが聴力を失ってしまう――そんな厳しい現実に直面する主人公を描く映画『サウンド・オブ・メタル』では、「『健常者との生活』を選ぶか否か」という選択が突きつけられる。ある意味では健常者にも向けられているこの問いに、どう答えるべきだろうか
あわせて読みたい
【驚異】「持続可能な社会」での「豊かな生活」とは?「くじら漁の村」で生きる人々を描く映画:『くじ…
手作りの舟に乗り、銛1本で巨大なクジラを仕留める生活を続けるインドネシアのラマレラ村。そこに住む人々を映し出した映画『くじらびと LAMAFA』は、私たちが普段感じられない種類の「豊かさ」を描き出す。「どう生きるか」を改めて考えさせられる作品だ
あわせて読みたい
【生と死】不老不死をリアルに描く映画。「若い肉体のまま死なずに生き続けること」は本当に幸せか?:…
あなたは「不老不死」を望むだろうか?私には、「不老不死」が魅力的には感じられない。科学技術によって「不老不死」が実現するとしても、私はそこに足を踏み入れないだろう。「不老不死」が実現する世界をリアルに描く映画『Arc アーク』から、「生と死」を考える
あわせて読みたい
【凄絶】北朝鮮の”真実”を描くアニメ映画。強制収容所から決死の脱出を試みた者が語る驚愕の実態:『ト…
在日コリアン4世の監督が、北朝鮮脱北者への取材を元に作り上げた壮絶なアニメ映画『トゥルーノース』は、私たちがあまりに恐ろしい世界と地続きに生きていることを思い知らせてくれる。最低最悪の絶望を前に、人間はどれだけ悪虐になれてしまうのか、そしていかに優しさを発揮できるのか。
あわせて読みたい
【驚愕】これ以上の”サバイバル映画”は存在するか?火星にたった一人残された男の生存術と救出劇:『オ…
1人で火星に取り残された男のサバイバルと救出劇を、現実的な科学技術の範囲で描き出す驚異の映画『オデッセイ』。不可能を可能にするアイデアと勇気、自分や他人を信じ抜く気持ち、そして極限の状況でより困難な道を進む決断をする者たちの、想像を絶するドラマに胸打たれる
あわせて読みたい
【認識】「固定観念」「思い込み」の外側に出るのは難しい。自分はどんな「へや」に囚われているのか:…
実際に起こった衝撃的な事件に着想を得て作られた映画『ルーム』は、フィクションだが、観客に「あなたも同じ状況にいるのではないか?」と突きつける力強さを持っている。「普通」「当たり前」という感覚に囚われて苦しむすべての人に、「何に気づけばいいか」を気づかせてくれる作品
あわせて読みたい
【感想】映画『野火』は、戦争の”虚しさ”をリアルに映し出す、後世に受け継がれるべき作品だ
「戦争の悲惨さ」は様々な形で描かれ、受け継がれてきたが、「戦争の虚しさ」を知る機会はなかなかない。映画『野火』は、第二次世界大戦中のフィリピンを舞台に、「敵が存在しない戦場で”人間の形”を保つ困難さ」を描き出す、「虚しさ」だけで構成された作品だ
あわせて読みたい
【考察】アニメ映画『虐殺器官』は、「便利さが無関心を生む現実」をリアルに描く”無関心ではいられない…
便利すぎる世の中に生きていると、「この便利さはどのように生み出されているのか」を想像しなくなる。そしてその「無関心」は、世界を確実に悪化させてしまう。伊藤計劃の小説を原作とするアニメ映画『虐殺器官』から、「無関心という残虐さ」と「想像することの大事さ」を知る
あわせて読みたい
【書評】奇跡の”国家”「ソマリランド」に高野秀行が潜入。崩壊国家・ソマリア内で唯一平和を保つ衝撃の”…
日本の「戦国時代」さながらの内戦状態にあるソマリア共和国内部に、十数年に渡り奇跡のように平和を維持している”未承認国家”が存在する。辺境作家・高野秀行の『謎の独立国家ソマリランド』から、「ソマリランド」の理解が難しい理由と、「奇跡のような民主主義」を知る
あわせて読みたい
【矛盾】その”誹謗中傷”は真っ当か?映画『万引き家族』から、日本社会の「善悪の判断基準」を考える
どんな理由があれ、法を犯した者は罰せられるべきだと思っている。しかしそれは、善悪の判断とは関係ない。映画『万引き家族』(是枝裕和監督)から、「国民の気分」によって「善悪」が決まる社会の是非と、「善悪の判断を保留する勇気」を持つ生き方について考える
あわせて読みたい
【絶望】光過敏症の女性の、真っ暗な部屋で光という光をすべて遮断しなければ生きられない壮絶な日常:…
日光に限らず、ありとあらゆる「光」に肌が異常に反応してしまうため、ずっと真っ暗闇の中でしか生きられない女性が、その壮絶すぎる日常を綴った『まっくらやみで見えたもの 光アレルギーのわたしの奇妙な人生』から、それでも生きていく強さを感じ取る
あわせて読みたい
【理解】東田直樹の本は「自閉症の見方」を一変させた。自身も自閉症児を育てるプロデューサーが映画化…
東田直樹の著作を英訳し世界に広めた人物(自閉症児を育てている)も登場する映画『僕が跳びはねる理由』には、「東田直樹が語る自閉症の世界」を知ることで接し方や考え方が変わったという家族が登場する。「自閉症は知恵遅れではない」と示した東田直樹の多大な功績を実感できる
あわせて読みたい
【リアル】社会の分断の仕組みを”ゾンビ”で学ぶ。「社会派ゾンビ映画」が対立の根源を抉り出す:映画『C…
まさか「ゾンビ映画」が、私たちが生きている現実をここまで活写するとは驚きだった。映画『CURED キュアード』をベースに、「見えない事実」がもたらす恐怖と、立場ごとに正しい主張をしながらも否応なしに「分断」が生まれてしまう状況について知る
あわせて読みたい
【誤り】「信じたいものを信じる」のは正しい?映画『星の子』から「信じること」の難しさを考える
どんな病気も治す「奇跡の水」の存在を私は信じないが、しかし何故「信じない」と言えるのか?「奇跡の水を信じる人」を軽々に非難すべきではないと私は考えているが、それは何故か?映画『星の子』から、「何かを信じること」の難しさについて知る
あわせて読みたい
【情熱】常識を疑え。人間の”狂気”こそが、想像し得ない偉業を成し遂げるための原動力だ:映画『博士と…
世界最高峰の辞書である『オックスフォード英語大辞典』は、「学位を持たない独学者」と「殺人犯」のタッグが生みだした。出会うはずのない2人の「狂人」が邂逅したことで成し遂げられた偉業と、「狂気」からしか「偉業」が生まれない現実を、映画『博士と狂人』から学ぶ
あわせて読みたい
【未知】タコに「高度な脳」があるなんて初耳だ。人類とは違う進化を遂げた頭足類の「意識」とは?:『…
タコなどの頭足類は、無脊椎動物で唯一「脳」を進化させた。まったく違う進化を辿りながら「タコに心を感じる」という著者は、「タコは地球外生命体に最も近い存在」と書く。『タコの心身問題』から、腕にも脳があるタコの進化の歴史と、「意識のあり方」を知る。
あわせて読みたい
【葛藤】「多様性を受け入れること」は難しい。映画『アイヌモシリ』で知る、アイデンティティの実際
「アイヌの町」として知られるアイヌコタンの住人は、「アイヌ語を勉強している」という。観光客のイメージに合わせるためだ。映画『アイヌモシリ』から、「伝統」や「文化」の継承者として生きるべきか、自らのアイデンティティを意識せず生きるべきかの葛藤を知る
あわせて読みたい
【絶望】子供を犯罪者にしないために。「異常者」で片付けられない、希望を見いだせない若者の現実:『…
2人を殺し、7人に重傷を負わせた金川真大に同情の余地はない。しかし、この事件を取材した記者も、私も、彼が殺人に至った背景・動機については理解できてしまう部分がある。『死刑のための殺人』をベースに、「どうしようもないつまらなさ」と共に生きる現代を知る
あわせて読みたい
【称賛?】日本社会は終わっているのか?日本在住20年以上のフランス人が本国との比較で日本を評価:『…
日本に住んでいると、日本の社会や政治に不満を抱くことも多い。しかし、日本在住20年以上の『理不尽な国ニッポン』のフランス人著者は、フランスと比べて日本は上手くやっていると語る。宗教や個人ではなく、唯一「社会」だけが善悪を決められる日本の特異性について書く
あわせて読みたい
【驚嘆】人類はいかにして言語を獲得したか?この未解明の謎に真正面から挑む異色小説:『Ank: a mirror…
小説家の想像力は無限だ。まさか、「人類はいかに言語を獲得したか?」という仮説を小説で読めるとは。『Ank: a mirroring ape』をベースに、コミュニケーションに拠らない言語獲得の過程と、「ヒト」が「ホモ・サピエンス」しか存在しない理由を知る
あわせて読みたい
【希望】貧困の解決は我々を豊かにする。「朝ベッドから起きたい」と思えない社会を変える課題解決:『…
現代は、過去どの時代と比べても安全で清潔で、豊かである。しかしそんな時代に、我々は「幸せ」を実感することができない。『隷属なき道』をベースに、その理由は一体なんなのか何故そうなってしまうのかを明らかにし、さらに、より良い暮らしを思い描くための社会課題の解決に触れる
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
旅・冒険・自然【本・映画の感想】 | ルシルナ
私自身は冒険家ではありませんし、旅行にもほとんど行かず、普段自然に触れることもありません。なのでここで書くことは、私の実体験ではなく、本や映画を通じて知った現実…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…
















































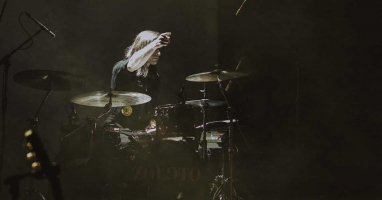





























コメント