目次
はじめに
この記事で取り上げる本
著:永井均
¥825 (2022/03/22 06:12時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
この本をガイドにしながら記事を書いていきます
この記事の3つの要点
- 本当の「哲学」は、子どもの頃にしかできない
- 「答えの出ない問いについて考え続けること」こそが「哲学」である
- 「今が夢じゃないって証拠はあるか」など、具体的な4つの問いについて対話する
決して易しくはないが、中高生でもチャレンジできる、というか、中高生にこそオススメの1冊
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!「文章の書き方が分からない」「文章力がないから鍛えたい」という方にオススメ…
「文章の書き方」についてのKindle本を出版しました。「文章が書けない」「どう書いたらいいか分からない」「文章力を向上させたい」という方の悩みを解消できるような本に仕上げたつもりです。数多くの文章を書き、さらに頼まれて文章を推敲してきた経験を踏まえ、「文章を書けるようになるにはどうしたらいいか」についての私なりの考えをまとめました。
永井均『翔太と猫のインサイトの夏休み』は、「哲学する」とはどういうことかを説く、中高生から読める「哲学入門」だ
本書と同じ永井均の著書に、『<子ども>のための哲学』がある。タイトルから、「子ども向けの哲学入門書」だと感じるかもしれないが、まったくそんなことはない。もの凄く難しく、大人でも簡単には読み進められない作品だ。
あわせて読みたい
【本質】子どもの頃には読めない哲学書。「他人の哲学はつまらない」と語る著者が説く「問うこと」の大…
『<子ども>のための哲学』は決して、「子どもでも易しく理解できる哲学の入門書」ではない。むしろかなり難易度が高いと言っていい。著者の永井均が、子どもの頃から囚われ続けている2つの大きな疑問をベースに、「『哲学する』とはどういうことか?」を深堀りする作品
一方、『翔太と猫のインサイトの夏休み』は、子どもでも読める作品である。「読んで理解できるか」は読む人次第だが、少なくとも、子どもでも読めるような体裁で書かれている作品であることは間違いない。「中学生の翔太」と「猫のインサイト」が対話する、という形で進んでいくので、非常に読みやすいだろう。内容は決して易しいとは言えないが、扱われるテーマは「生きている中でふと頭に浮かんでしまうかもしれないもの」であり、とっつきやすさもあると思う。

『<子ども>のための哲学』でも本書でも、著者は一貫して、「本当の哲学は、子どもの頃にしかできない」と書いている。だからこそ、幸運にも子ども時代にこの本に巡り合う機会を持てた人は、是非手にとって読んでみてほしい。
あわせて読みたい
【感想】池田晶子『14歳からの哲学』で思考・自由・孤独の大事さを知る。孤独を感じることって大事だ
「元々持ってた価値観とは違う考えに触れ、それを理解したいと思う場面」でしか「考える」という行為は発動しないと著者は言う。つまり我々は普段、まったく考えていないのだ。『14歳からの哲学』をベースに、「考えること」と自由・孤独・人生との関係を知る
読んですぐ理解できる必要はない。大人になっても理解できないかもしれない。しかし、「理解できるかどうか」が重要なのではない。「スタートラインに立てたことを確かめる」、あるいは「既にスタートを切っていたことを理解する」という点にこそ価値があるのだ。
「哲学」と聞くとカント・ニーチェ・孔子などが頭に浮かぶかもしれない。しかし、そういうものとはまったく異なる「哲学」が本書では展開される。
読み終わった時、中には「自分はごく自然に『哲学』をやっていた」と感じる人も出てくるかもしれない。そういう意味でも興味深い作品だと言える。
あわせて読みたい
【飛躍】有名哲学者は”中二病”だった?飲茶氏が易しく語る「古い常識を乗り越えるための哲学の力」:『1…
『14歳からの哲学入門』というタイトルは、「14歳向けの本」という意味ではなく、「14歳は哲学することに向いている」という示唆である。飲茶氏は「偉大な哲学者は皆”中二病”だ」と説き、特に若い人に向けて、「新しい価値観を生み出すためには哲学が重要だ」と語る
「答えのない問いについて考え続けること」こそ「哲学」だ
先ほど書いた通り本書は、翔太とインサイトが対話する形で進んでいく。中学生と猫の会話なので、難しい言葉もさほど出てこない。また彼らは、ある具体的な「問い」を前にして「どのように考えるべきか」を話している。そしてその対話の端々に「哲学とは何か」みたいな話題が組み込まれる構成も分かりやすいと思う。
あわせて読みたい
【抽象】「思考力がない」と嘆く人に。研究者で小説家の森博嗣が語る「客観的に考える」ために大事なこ…
世の中にはあまりに「具体的な情報」が溢れているために、「客観的、抽象的な思考」をする機会が少ない。そんな時代に、いかに思考力を育てていくべきか。森博嗣が『人間はいろいろな問題についてどう考えていけば良いのか』を通じて伝える「情報との接し方」「頭の使い方」

そしてそのような記述を読み解くことで、「考え続けることが哲学なのだ」という本書の主張を理解できることだろう。
「哲学」というとどうしても、「カントは何を考えたのか?」「ニーチェはなぜこんなことを言ったのか?」など、過去の哲学者・思想家たちの考えについてあーだこーだ思考する、というイメージになってしまう。一般的に「哲学」とはそのような意味で理解されているはずだ。
しかし著者は、本書の中で繰り返し、「哲学とは思想ではない」と書いている。「哲学」というのは「主張の内容」を指すのではなく、「その主張をする際にどうしてもついて回ってしまう枠組みそのもの」のことだと言うのだ。
あわせて読みたい
【興奮】飲茶氏が西洋哲学を語る。難解な思想が「グラップラー刃牙成分」の追加で驚異的な面白さに:『…
名前は聞いたことはあるがカントやニーチェがどんな主張をしたのかは分からないという方は多いだろう。私も無知なまったくの初心者だが、そんな人でも超絶分かりやすく超絶面白く西洋哲学を”分かった気になれる”飲茶『史上最強の哲学入門』は、入門書として最強
この説明のために、以前読んだ『こうして世界は誤解する』に書かれていたことを紹介しよう。
『こうして世界は誤解する』の中で著者は、「独裁政権下で起こっている出来事を報道することは難しい。何故なら『独裁政権下である』という事実こそが最も報じられるべきことだからだ」と主張していた。そしてその説明のために、「檻に入れられたホッキョクグマ」を引き合いに出す。
檻の中に閉じ込められたホッキョクグマは、恐らく、野生にいる時とはまったく違う振る舞いを見せるだろう。イライラしているように見えたり、落ち着きなく歩き回ったりするかもしれない。
さてここで、檻を映さずにホッキョクグマだけカメラに収めることを考えよう。その映像を見た人は、「イライラした、落ち着きのないホッキョクグマなんだな」と受け取るに違いない。そういう性質のホッキョクグマなのだろう、と。「檻」が映されないのだから当然だ。しかし実際には、檻の中に閉じ込められているからこそそんな振る舞いをしてしまうのである。

あわせて読みたい
【解釈】詩人が語る詩の読み方。意味や読み方や良さが分からなくて全然気にしなくていい:『今を生きる…
私は学生時代ずっと国語の授業が嫌いでしたが、それは「作品の解釈には正解がある」という決めつけが受け入れ難かったからです。しかし、詩人・渡邊十絲子の『今を生きるための現代詩』を読んで、詩に限らずどんな作品も、「解釈など不要」「理解できなければ分からないままでいい」と思えるようになりました
「独裁政権下に生きる人々」を「ホッキョクグマ」、「独裁政権下という状況」を「檻」に置き換えれば、状況は理解しやすくなるだろう。報道では「独裁政権下に生きる人々」を映し出すが、それは「檻を映さずにホッキョクグマを撮影するようなもの」だ。本当に報じなければならないのは「独裁政権下という状況」の方なのだが、それはなかなか難しい、ということが書かれている(なぜ難しいのかは、上の記事を読んでほしい)。
話を戻そう。永井均が言う「その主張をする際にどうしてもついて回ってしまう枠組みそのもの」も同じようなものだと考えればいいだろう。哲学者や思想家の本を読めば、そこには「主張の内容」が書かれている。しかしそれは、「檻に入れられたホッキョクグマ」のようなものだ。実際には、「その『主張の内容』がどんな『檻』の中にあるか」が重要なのであり、それこそが「哲学」だと著者は主張する。
そんなわけで著者は、「哲学するのに本を読んではいけない」と断言するのだ。
ではどうすればいいのか。著者は、「とにかく自分の頭で考えろ」と言う。さらに、「何について考えるか」も大事になってくる。その「問い」には「答え」が存在していてはいけない。少なくとも、「これ以外に正解は存在しない」というような、何か定まった「答え」が既に存在するものではダメなのだ。著者は、「その問いの前に立って呆然とする」ような「問い」でなければいけない、と書いている。
あわせて読みたい
【思考】「”考える”とはどういうことか」を”考える”のは難しい。だからこの1冊をガイドに”考えて”みよう…
私たちは普段、当たり前のように「考える」ことをしている。しかし、それがどんな行為で、どのように行っているのかを、きちんと捉えて説明することは難しい。「はじめて考えるときのように」は、横書き・イラスト付きの平易な文章で、「考えるという行為」の本質に迫り、上達のために必要な要素を伝える
なかなかそんな問いに出会うことは難しい。特に大人になってからは。だからこそ、「本当の哲学は、子どもの頃にしかできない」のだ。大人になってしまえば疑問に感じなくなるような、大人をハッとさせるような疑問を、子どもはなんでもないことのように口にすることがある。まさにそのようなものこそ、「哲学のための問い」に相応しい。
その「問い」について考え続けたところで何も良いことは起こらないだろうし、世界はきっと何も変わらない。しかしそれでも、なぜだか分からないけれどもどうしても囚われてしまう「問い」。大人に聞いても答えが分からないし、考えても考えてもどこにも行き着かないように思えるが、それでもどうしても手放すことができない「問い」がある。
あなたがもしそういう人なら、あなたはもうだいぶ前から「哲学」をやっていると言えるだろう。
本書『翔太と猫のインサイトの夏休み』で扱われる4つの「問い」
本書では、中学生と猫が対話をするにあたり、4つの「問い」が設定される。そしてその「問い」について、夏休みに入ってから眠りにつくと毎晩夢を見るようになった翔太が、その夢の中でインサイトと哲学談義をするのだ。
あわせて読みたい
【思考】文章の書き方が分かんない、トレーニングしたいって人はまず、古賀史健の文章講義の本を読め:…
古賀史健『20歳の自分に受けさせたい文章講義』は、「具体的なテクニック」ではない記述も非常に興味深い1冊だ。「なぜ文章を書く必要があるのか」という根本的な部分から丁寧に掘り下げる本書は、「書くからこそ考えられる」という、一般的なイメージとは逆だろう発想が提示される

ここからその4つの「問い」について書くことにしよう。しかし、前述した通り、「哲学」は「自分の頭で考えること」が何よりも大事だ。だからこそ、本書で展開される議論についてはほぼ触れない。『翔太と猫のインサイトの夏休み』を未読のままこの記事を読んでくれているなら、以下の4つの「問い」に自分なりに考えを深めてから本を読むのもアリだ。もちろん、いきなり本を読んでも構わないが、どうせなら「自分の頭で考えること」を実践した上で本書に臨んでみるのも面白いだろう。
それでは、4つの「問い」を紹介していく。
1つ目は、「今が夢じゃないって証拠はあるか」だ。観たことがある人は、映画『マトリックス』の設定をイメージすればいいだろう。自分たちももしかしたら、「本当の現実」では機械に繋がれてただ寝ているだけなのかもしれない。あるいは、「培養液に浸かった脳に刺激が与えられている」だけかもしれない。そうではないことを、私たちは何らかの手段で確かめることができるだろうか?
あわせて読みたい
【戸惑】人間の脳は摩訶不思議。意識ではコントロールできない「無意識の領域」に支配されている:『あ…
我々は決断や選択を「自分の意思」で行っていると感じるが、脳科学の研究はそれを否定している。我々に「自由意志」などない。「脳」の大部分は「意識以外のもの」に支配され、そこに「意識」はアクセスできないという驚愕の実態を『あなたの知らない脳』から学ぶ
2つ目は、「たくさんの人間の中に自分という特別なものがいるとは」だ。これはちょっと難しい問いかもしれない。
例えば、「自分が『心』を持っていることは自分が一番よく知っている。じゃあ、他人にも自分と同じように『心』があるとどうして信じていられるのか」という「問い」にあなたはどう答えるだろうか。あるいは、「自分が見ていない時には他人は存在していないのではないか」と考えたことはないだろうか。このような事柄について、「ロボットに心はあるのか」や「本当に脳がすべての感覚を支配しているのか」など、自他の存在から様々な思考が展開されていく。
3つ目は「さまざまな可能性の中でこれが正しいと言える根拠はあるか」だ。「問い」だけ読むと難しいが、要するに「『正しさ』はどのように決まるのか?」という思考である。
「ナチス」や「オウム真理教」は「間違っていた」と判断されるだろうが、それらが「正しい」と判断され得る可能性はあるだろうか? 何かを「正しい」と捉える時、その確信はどのようにしてやってくるのか? これは、私たちの実生活にも直結する「問い」だと言っていいだろう。
最後は「自分がいまここに存在していることに意味はあるか」だ。「ぼく」という存在は、どんな要素で明確化されるのか? 何がどうなっていれば「ぼく」は「存在している」と言えるのか? 「存在すること」を起点に、様々な思考が展開されていく。
あわせて読みたい
【正義】「正しさとは何か」を考えさせる映画『スリー・ビルボード』は、正しさの対立を絶妙に描く
「正しい」と主張するためには「正しさの基準」が必要だが、それでも「規制されていないことなら何でもしていいのか」は問題になる。3枚の立て看板というアナログなツールを使って現代のネット社会の現実をあぶり出す映画『スリー・ビルボード』から、「『正しさ』の難しさ」を考える
著:永井均
¥825 (2022/03/22 06:14時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品読了済】私が読んできたノンフィクション・教養書を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が読んできたノンフィクションを様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本選びの参考にして下さい。
最後に
あわせて読みたい
【驚異】数学の「無限」は面白い。アキレスと亀の矛盾、実無限と可能無限の違い、カントールの対角線論…
日常の中で「無限」について考える機会などなかなか無いだろうが、野矢茂樹『無限論の教室』は、「無限には種類がある」と示すメチャクチャ興味深い作品だった。「実無限」と「可能無限」の違い、「可能無限」派が「カントールの対角線論法」を拒絶する理由など、面白い話題が満載の1冊
考えるための「問い」は、本書で紹介されているものである必要はない。本書は、思考の「視点」や「深さ」の指標と捉えればいいと思う。そんな見方をしたことがなかった、そんな深くまで考えたことがなかった、という実感を得られれば、自分なりに「問い」を深堀りする際の役に立つことだろう。

もちろん、大人が読んでもいい。著者は「大人になってしまえばもう『哲学』はできない」と主張するが、著者の考えるレベルに到達できなかったとしても、その過程に十分価値を見出すことができるはずだ。
あわせて読みたい
【博覧強記】「紙の本はなくなる」説に「文化は忘却されるからこそ価値がある」と反論する世界的文学者…
世界的文学者であり、「紙の本」を偏愛するウンベルト・エーコが語る、「忘却という機能があるから書物に価値がある」という主張は実にスリリングだ。『もうすぐ絶滅するという紙の書物について』での対談から、「忘却しない電子データ」のデメリットと「本」の可能性を知る
世の中にはあまりにも情報が多いので、「いかに効率良く検索し、コスパ良く情報にたどり着いて吸収するか」ばかりが求められがちになってしまっている。しかしそんな時代だからこそ、「検索しても答えの出てこない問いを、自分が納得いくまで考え続ける」という時間の使い方に大きな価値が生まれるのではないかとも思う。
その際の伴走者として、本書は非常に頼もしい。
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!「文章の書き方が分からない」「文章力がないから鍛えたい」という方にオススメ…
「文章の書き方」についてのKindle本を出版しました。「文章が書けない」「どう書いたらいいか分からない」「文章力を向上させたい」という方の悩みを解消できるような本に仕上げたつもりです。数多くの文章を書き、さらに頼まれて文章を推敲してきた経験を踏まえ、「文章を書けるようになるにはどうしたらいいか」についての私なりの考えをまとめました。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【奇妙】大栗博司『重力とはなにか』は、相対性理論や量子力学の説明も秀逸だが、超弦理論の話が一番面白い
『重力とはなにか』(大栗博司)は、科学に馴染みの薄い人でもチャレンジできる易しい入門書だ。相対性理論や量子力学、あるいは超弦理論など、非常に難解な分野を基本的なところから平易に説明してくれるので、「科学に興味はあるけど難しいのはちょっと……」という方にこそ読んでほしい1冊
あわせて読みたい
【倫理】アート体験の行き着く未来は?映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』が描く狂気の世界(…
「『痛み』を失った世界」で「自然発生的に生まれる新たな『臓器』を除去するライブパフォーマンス」を行うソール・テンサーを主人公にした映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』は、すぐには答えの見出しにくい「境界線上にある事柄」を挑発的に描き出す、実に興味深い物語だ
あわせて読みたい
【知的】「BLって何?」という初心者に魅力を伝える「腐男子」の「BLの想像力と創造力」講座:『ボクた…
「BLは知的遊戯である」という主張には「は?」と感じてしまうでしょうが、本書『ボクたちのBL論』を読めばその印象は変わるかもしれません。「余白の発見と補完」を通じて、「ありとあらゆる2者の間の関係性を解釈する」という創造性は、現実世界にどのような影響を与えているのか
あわせて読みたい
【思考】文章の書き方が分かんない、トレーニングしたいって人はまず、古賀史健の文章講義の本を読め:…
古賀史健『20歳の自分に受けさせたい文章講義』は、「具体的なテクニック」ではない記述も非常に興味深い1冊だ。「なぜ文章を書く必要があるのか」という根本的な部分から丁寧に掘り下げる本書は、「書くからこそ考えられる」という、一般的なイメージとは逆だろう発想が提示される
あわせて読みたい
【驚異】数学の「無限」は面白い。アキレスと亀の矛盾、実無限と可能無限の違い、カントールの対角線論…
日常の中で「無限」について考える機会などなかなか無いだろうが、野矢茂樹『無限論の教室』は、「無限には種類がある」と示すメチャクチャ興味深い作品だった。「実無限」と「可能無限」の違い、「可能無限」派が「カントールの対角線論法」を拒絶する理由など、面白い話題が満載の1冊
あわせて読みたい
【幸福】「死の克服」は「生の充実」となり得るか?映画『HUMAN LOST 人間失格』が描く超管理社会
アニメ映画『HUMAN LOST 人間失格』では、「死の克服」と「管理社会」が分かちがたく結びついた世界が描かれる。私たちは既に「緩やかな管理社会」を生きているが、この映画ほどの管理社会を果たして許容できるだろうか?そしてあなたは、「死」を克服したいと願うだろうか?
あわせて読みたい
【おすすめ】江戸川乱歩賞受賞作、佐藤究『QJKJQ』は、新人のデビュー作とは思えない超ド級の小説だ
江戸川乱歩賞を受賞した佐藤究デビュー作『QJKJQ』はとんでもない衝撃作だ。とても新人作家の作品とは思えない超ド級の物語に、とにかく圧倒されてしまう。「社会は『幻想』を共有することで成り立っている」という、普段なかなか意識しない事実を巧みにちらつかせた、魔術のような作品
あわせて読みたい
【人生】日本人有名プロゲーマー・梅原大吾の名言満載の本。「努力そのものを楽しむ」ための生き方とは…
「eスポーツ」という呼び名が世の中に定着する遥か以前から活躍する日本人初のプロゲーマー・梅原大吾。17歳で世界一となり、今も一線を走り続けているが、そんな彼が『勝ち続ける意志力』で語る、「『努力している状態』こそを楽しむ」という考え方は、誰の人生にも参考になるはずだ
あわせて読みたい
【変革】「ビジネスより自由のために交渉力を」と語る瀧本哲史の”自己啓発”本に「交渉のコツ」を学ぶ:…
急逝してしまった瀧本哲史は、「交渉力」を伝授する『武器としての交渉思考』を通じて、「若者よ、立ち上がれ!」と促している。「同質性のタコツボ」から抜け出し、「異質な人」と「秘密結社」を作り、世の中に対する「不満」を「変革」へと向かわせる、その勇気と力を本書から感じてほしい
あわせて読みたい
【抽象】「思考力がない」と嘆く人に。研究者で小説家の森博嗣が語る「客観的に考える」ために大事なこ…
世の中にはあまりに「具体的な情報」が溢れているために、「客観的、抽象的な思考」をする機会が少ない。そんな時代に、いかに思考力を育てていくべきか。森博嗣が『人間はいろいろな問題についてどう考えていけば良いのか』を通じて伝える「情報との接し方」「頭の使い方」
あわせて読みたい
【考察】アニメ映画『虐殺器官』は、「便利さが無関心を生む現実」をリアルに描く”無関心ではいられない…
便利すぎる世の中に生きていると、「この便利さはどのように生み出されているのか」を想像しなくなる。そしてその「無関心」は、世界を確実に悪化させてしまう。伊藤計劃の小説を原作とするアニメ映画『虐殺器官』から、「無関心という残虐さ」と「想像することの大事さ」を知る
あわせて読みたい
【本質】子どもの頃には読めない哲学書。「他人の哲学はつまらない」と語る著者が説く「問うこと」の大…
『<子ども>のための哲学』は決して、「子どもでも易しく理解できる哲学の入門書」ではない。むしろかなり難易度が高いと言っていい。著者の永井均が、子どもの頃から囚われ続けている2つの大きな疑問をベースに、「『哲学する』とはどういうことか?」を深堀りする作品
あわせて読みたい
【解釈】詩人が語る詩の読み方。意味や読み方や良さが分からなくて全然気にしなくていい:『今を生きる…
私は学生時代ずっと国語の授業が嫌いでしたが、それは「作品の解釈には正解がある」という決めつけが受け入れ難かったからです。しかし、詩人・渡邊十絲子の『今を生きるための現代詩』を読んで、詩に限らずどんな作品も、「解釈など不要」「理解できなければ分からないままでいい」と思えるようになりました
あわせて読みたい
【異端】「仏教とは?」を簡単に知りたい方へ。ブッダは「異性と目も合わせないニートになれ」と主張し…
我々が馴染み深い「仏教」は「大乗仏教」であり、創始者ゴータマ・ブッダの主張が詰まった「小乗仏教」とは似て非なるものだそうだ。『講義ライブ だから仏教は面白い!』では、そんな「小乗仏教」の主張を「異性と目も合わせないニートになれ」とシンプルに要約して説明する
あわせて読みたい
【感想】池田晶子『14歳からの哲学』で思考・自由・孤独の大事さを知る。孤独を感じることって大事だ
「元々持ってた価値観とは違う考えに触れ、それを理解したいと思う場面」でしか「考える」という行為は発動しないと著者は言う。つまり我々は普段、まったく考えていないのだ。『14歳からの哲学』をベースに、「考えること」と自由・孤独・人生との関係を知る
あわせて読みたい
【飛躍】有名哲学者は”中二病”だった?飲茶氏が易しく語る「古い常識を乗り越えるための哲学の力」:『1…
『14歳からの哲学入門』というタイトルは、「14歳向けの本」という意味ではなく、「14歳は哲学することに向いている」という示唆である。飲茶氏は「偉大な哲学者は皆”中二病”だ」と説き、特に若い人に向けて、「新しい価値観を生み出すためには哲学が重要だ」と語る
あわせて読みたい
【感想】飲茶の超面白い東洋哲学入門書。「本書を読んでも東洋哲学は分からない」と言う著者は何を語る…
東洋哲学というのは、「最終回しか存在しない連続ドラマ」のようなものだそうだ。西洋哲学と比較にならないほど異質さと、インド哲学・中国哲学など個別の思想を恐ろしく分かりやすく描く『史上最強の哲学入門 東洋の哲人たち』は、ページをめくる手が止まらないくらい、史上最強レベルに面白かった
あわせて読みたい
【興奮】飲茶氏の超面白い哲学小説。「正義とは?」の意味を問う”3人の女子高生”の主張とは?:『正義の…
なんて面白いんだろうか。哲学・科学を初心者にも分かりやすく伝える飲茶氏による『正義の教室』は、哲学書でありながら、3人の女子高生が登場する小説でもある。「直観主義」「功利主義」「自由主義」という「正義論」の主張を、「高校の問題について議論する生徒会の話し合い」から学ぶ
あわせて読みたい
【知】内田樹が教育・政治を語る。「未来の自分」を「別人」と捉える「サル化した思考」が生む現実:『…
「朝三暮四」の故事成語を意識した「サル化」というキーワードは、現代性を映し出す「愚かさ」を象徴していると思う。内田樹『サル化する世界』から、日本の教育・政治の現状及び問題点をシンプルに把握し、現代社会を捉えるための新しい視点や価値観を学ぶ
あわせて読みたい
【人生】「資本主義の限界を埋める存在としての『贈与論』」から「不合理」に気づくための生き方を知る…
「贈与論」は簡単には理解できないが、一方で、「何かを受け取ったら、与えてくれた人に返す」という「交換」の論理では対処できない現実に対峙する力ともなる。『世界は贈与でできている』から「贈与」的な見方を理解し、「受取人の想像力」を立ち上げる
あわせて読みたい
【興奮】飲茶氏が西洋哲学を語る。難解な思想が「グラップラー刃牙成分」の追加で驚異的な面白さに:『…
名前は聞いたことはあるがカントやニーチェがどんな主張をしたのかは分からないという方は多いだろう。私も無知なまったくの初心者だが、そんな人でも超絶分かりやすく超絶面白く西洋哲学を”分かった気になれる”飲茶『史上最強の哲学入門』は、入門書として最強
あわせて読みたい
【思考】「”考える”とはどういうことか」を”考える”のは難しい。だからこの1冊をガイドに”考えて”みよう…
私たちは普段、当たり前のように「考える」ことをしている。しかし、それがどんな行為で、どのように行っているのかを、きちんと捉えて説明することは難しい。「はじめて考えるときのように」は、横書き・イラスト付きの平易な文章で、「考えるという行為」の本質に迫り、上達のために必要な要素を伝える
あわせて読みたい
【驚嘆】この物語は「AIの危険性」を指摘しているのか?「完璧な予知能力」を手にした人類の過ち:『預…
完璧な未来予知を行えるロボットを開発し、地震予知のため”だけ”に使おうとしている科学者の自制を無視して、その能力が解放されてしまう世界を描くコミック『預言者ピッピ』から、「未来が分からないからこそ今を生きる価値が生まれるのではないか」などについて考える
あわせて読みたい
【戸惑】人間の脳は摩訶不思議。意識ではコントロールできない「無意識の領域」に支配されている:『あ…
我々は決断や選択を「自分の意思」で行っていると感じるが、脳科学の研究はそれを否定している。我々に「自由意志」などない。「脳」の大部分は「意識以外のもの」に支配され、そこに「意識」はアクセスできないという驚愕の実態を『あなたの知らない脳』から学ぶ
あわせて読みたい
【衝撃】ABC予想の証明のために生まれたIUT理論を、提唱者・望月新一の盟友が分かりやすく語る:『宇宙…
8年のチェック期間を経て雑誌に掲載された「IUT理論(宇宙際タイヒミュラー理論)」は、数学の最重要未解決問題である「ABC予想」を証明するものとして大いに話題になった。『宇宙と宇宙をつなぐ数学』『abc予想入門』をベースに、「IUT理論」「ABC予想」について学ぶ
あわせて読みたい
【異端】数学の”証明”はなぜ生まれたのか?「無理数」と「無限」に恐怖した古代ギリシャ人の奮闘:『数…
学校で数学を習うと、当然のように「証明」が登場する。しかしこの「証明」、実は古代ギリシャでしか発展しなかった、数学史においては非常に”異端”の考え方なのだ。『数学の想像力 正しさの深層に何があるのか』をベースに、ギリシャ人が恐れたものの正体を知る
あわせて読みたい
【対立】数学はなぜ”美しい”のか?数学は「発見」か「発明」かの議論から、その奥深さを知る:『神は数…
数学界には、「数学は神が作った派」と「数学は人間が作った派」が存在する。『神は数学者か?』をベースに、「数学は発見か、発明か」という議論を理解し、数学史においてそれぞれの認識がどのような転換点によって変わっていったのかを学ぶ
あわせて読みたい
【始まり】宇宙ができる前が「無」なら何故「世界」が生まれた?「ビッグバンの前」は何が有った?:『…
「宇宙がビッグバンから生まれた」ことはよく知られているだろうが、では、「宇宙ができる前はどうなっていたのか」を知っているだろうか? 実は「宇宙は”無”から誕生した」と考えられているのだ。『宇宙が始まる前には何があったのか?』をベースに、ビッグバンが起こる前の「空間も時間も物理法則も存在しない無」について学ぶ
あわせて読みたい
【未知】タコに「高度な脳」があるなんて初耳だ。人類とは違う進化を遂げた頭足類の「意識」とは?:『…
タコなどの頭足類は、無脊椎動物で唯一「脳」を進化させた。まったく違う進化を辿りながら「タコに心を感じる」という著者は、「タコは地球外生命体に最も近い存在」と書く。『タコの心身問題』から、腕にも脳があるタコの進化の歴史と、「意識のあり方」を知る。
あわせて読みたい
【天才】『三島由紀夫vs東大全共闘』後に「伝説の討論」と呼ばれる天才のバトルを記録した驚異の映像
1969年5月13日、三島由紀夫と1000人の東大全共闘の討論が行われた。TBSだけが撮影していたフィルムを元に構成された映画「三島由紀夫vs東大全共闘」は、知的興奮に満ち溢れている。切腹の一年半前の討論から、三島由紀夫が考えていたことと、そのスタンスを学ぶ
あわせて読みたい
【感想】世の中と足並みがそろわないのは「正常が異常」だから?自分の「正常」を守るために:『コンビ…
30代になっても未婚でコンビニアルバイトの古倉さんは、普通から外れたおかしな人、と見られてしまいます。しかし、本当でしょうか?『コンビニ人間』をベースに、多数派の人たちの方が人生を自ら選択していないのではないかと指摘する。
あわせて読みたい
【天職】頑張っても報われない方へ。「自分で選び取る」のとは違う、正しい未来の進み方:『そのうちな…
一般的に自己啓発本は、「今、そしてこれからどうしたらいいか」が具体的に語られるでしょう。しかし『そのうちなんとかなるだろう』では、決断・選択をするべきではないと主張されます。「選ばない」ことで相応しい未来を進む生き方について学ぶ
あわせて読みたい
【肯定】社会不適合者こそ非凡。学校・世の中に馴染めなかった異才たちの過去から”才能”の本質を知る:…
「みんなと同じ」に馴染めないと「社会不適合」と判断され、排除されてしまうことが多いでしょう。しかし『非属の才能』では、「どこにも属せない感覚」にこそ才能の源泉があると主張します。常識に違和感を覚えてしまう人を救う本から、同調圧力に屈しない生き方を学ぶ
あわせて読みたい
【情報】日本の社会問題を”祈り”で捉える。市場原理の外にあるべき”歩哨”たる裁き・教育・医療:『日本…
「霊性」というテーマは馴染みが薄いし、胡散臭ささえある。しかし『日本霊性論』では、「霊性とは、人間社会が集団を存続させるために生み出した機能」であると主張する。裁き・教育・医療の変化が鈍い真っ当な理由と、情報感度の薄れた現代人が引き起こす問題を語る
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
哲学・思想【本・映画の感想】 | ルシルナ
私の知識欲は多方面に渡りますが、その中でも哲学や思想は知的好奇心を強く刺激してくれます。ニーチェやカントなどの西洋哲学も、禅や仏教などの東洋哲学もとても奥深いも…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…












































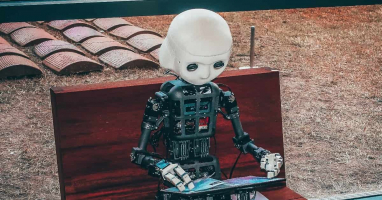


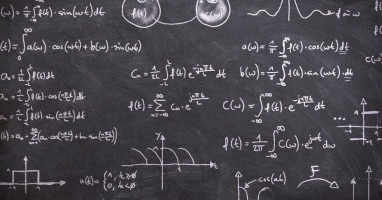

















コメント