目次
はじめに
あわせて読みたい
パンサー尾形が解説!NHKの超面白い数学番組『笑わない数学』の話題をさらに深掘りする記事
お笑い芸人・パンサー尾形が、笑い一切無しで、難解だが魅力的な数学世界を大真面目に解説するNHKの数学番組『笑わない数学』。同番組で紹介された様々な話題について、当ブログでも記事を書いているので、それらをまとめて紹介していきます。番組を観て興味を持った方、さらに深掘りするのにご参考下さい。
この記事で取り上げる本
著:マリオ リヴィオ, 翻訳:千葉 敏生
¥861 (2021/08/31 06:17時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
この本をガイドにしながら記事を書いていきます
この記事の3つの要点
- 元々数学は、探検家のように「発見」するものと考えられていた
- 「非ユークリッド幾何学」の発見が数学者に大きな衝撃を与えた
- 数学を完璧に体系付けようとしたヒルベルトの野望を、若き天才・ゲーデルが打ち砕いた
物理学の方程式が金融の世界で応用されるなど、数学にはまったく異なる領域を繋ぐ不思議さが溢れている
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
『神は数学者か?』が突きつける、「数学は『発見』か『発明』」かという刺激的な問い
まずは、何を問われているのか整理しよう
あわせて読みたい
【天才】数学の捉え方を一変させた「シンメトリー(対称性)」と、その発見から発展に至る歴史:『シン…
「5次方程式の解の公式は存在しない」というアーベルの証明や、天才・ガロアが発展させた「群論」は、「シンメトリー(対称性)」という領域に新たな光を当てた。『シンメトリーの地図帳』をベースに、「シンメトリー」の発展と「モンスター」の発見の物語を知る
本書は、「数学は人間が発見したものなのか、人間が発明したものなのか」について考える作品である。

数学は人間の心とはまったく独立して存在するのか? つまり、天文学者が未知の銀河を発見するのと同じように、われわれは単に数学的な真理を発見しているのか? あるいは、数学は人間の発明にすぎないのか?
まず、この問いの意味が分からない、という方も多いだろうと思う。そこで、もう少し具体的な例で、この「発見」と「発明」について考えてみよう。
あわせて読みたい
【興奮】世界的大ベストセラー『サピエンス全史』要約。人類が文明を築き上げるに至った3つの革命とは?
言わずと知れた大ベストセラー『サピエンス全史』は、「何故サピエンスだけが人類の中で生き残り、他の生物が成し得なかった歴史を歩んだのか」を、「認知革命」「農業革命」「科学革命」の3つを主軸としながら解き明かす、知的興奮に満ち溢れた1冊
まずは「発見」から。プロでもアマチュアでも、夜空に望遠鏡を向けて天体を観測することができる。そして、それまで誰にも知られていなかった天体を発見すると、自分で好きな名前を付けられるようだ。
さて、あなたが新しい天体を見つけたとして、これを「発明」と主張する人はいないだろう。天体というのは、我々人間が観測するかどうかに関係なく「そこにあるもの」だ。望遠鏡を向けたから天体が生まれた、なんてアホな話はない。だから、星を見つけるプロセスは明らかに「発見」である。
では、言語はどうだろうか? 世界中には、日本語・英語・フランス語など様々な言語が存在する。これらについて「発見した」と主張する人は恐らくいないだろう。
あわせて読みたい
【驚嘆】「現在は森でキノコ狩り」と噂の天才”変人”数学者グリゴリー・ペレルマンの「ポアンカレ予想証…
数学界の超難問ポアンカレ予想を解決したが、100万ドルの賞金を断り、フィールズ賞(ノーベル賞級の栄誉)も辞退、現在は「森できのこ採取」と噂の天才数学者グリゴリー・ペレルマンの生涯を描く評伝『完全なる証明』。数学に関する記述はほぼなく、ソ連で生まれ育った1人の「ギフテッド」の苦悩に満ちた人生を丁寧に描き出す1冊
例えば、「日本語」が「日本語を話す者」が現れる以前から存在していたとするなら、「発見」と呼んでもいいだろう。しかし、そんなわけがない。言語が生まれるプロセスは、明らかに「発明」である。
このように、「発見」なのか「発明」なのかは、それがどんな対象であるかによってかなり明らかに判断できるだろう。
では「数学」はどうだろうか? というのが、本書の問いである。
「発見派」と「発明派」のそれぞれの主張の骨子
あわせて読みたい
【興奮】素数の謎に迫った天才数学者たちの奮闘と、数学の”聖杯”である「リーマン予想」について:『素…
古今東西の数学者を惹きつけて止まない「素数」。その規則性を見つけ出すことは非常に困難だったが、「リーマン予想」として初めてそれが示された。『素数の音楽』『リーマン博士の大予想』から、天才数学者たちが挑んできた「リーマン予想」をざっくり理解する
数学の世界において、「発見派」と「発明派」の2つの立場に分かれている、というのが本書の前提となるスタンスだ。そして、それぞれの派閥の主張が、時代と共にどのように変化していったのかを追うのが、本書の構成である。
ここで余談だが、私は以前、日本の数学者にインタビューする機会があった。その際、「数学には、発見派と発明派がいるんですよね?」と問うと、「そんな議論は存在しない」と一蹴されたことがある。少なくともその数学者の周りは「発明派」しかいないという。
ただこれは、日本人であることが関係しているのかもしれない、とも思う。というのも、「発見派」の発想は、どうしても「神」に行き着くからだ。まさに本書のタイトルの通りである。
あわせて読みたい
【感想】飲茶の超面白い東洋哲学入門書。「本書を読んでも東洋哲学は分からない」と言う著者は何を語る…
東洋哲学というのは、「最終回しか存在しない連続ドラマ」のようなものだそうだ。西洋哲学と比較にならないほど異質さと、インド哲学・中国哲学など個別の思想を恐ろしく分かりやすく描く『史上最強の哲学入門 東洋の哲人たち』は、ページをめくる手が止まらないくらい、史上最強レベルに面白かった
「神が数学者だった」のであり、神が作り上げた数学を人間が「発見」している、というのが「発見派」の大雑把なイメージだと言っていい。だからこそ、欧米の数学者であればあるほど「発見派」が出てくる可能性があるのではないかと思う。
さてでは、それぞれの派閥がどんな主張をしているのかざっと見ていこう。
「発見派」は、数学という学問があまりにも様々な領域に関わっていることを指摘する。本書ではそのことが「数学の偏在性と全能性」という言葉で表現されている。

あわせて読みたい
【興奮】結城浩「数学ガール」で、決闘で命を落とした若き天才数学者・ガロアの理論を学ぶ
高校生を中心に、数学を通じて関わり合う者たちを描く「数学ガール」シリーズ第5弾のテーマは「ガロア理論」。独力で「群論」という新たな領域を切り開きながら、先駆的すぎて同時代の数学者には理解されず、その後決闘で死亡した天才の遺した思考を追う
例えば金融の世界には、オプション価格を決定する理論で用いられる「ブラック・ショールズ方程式」と呼ばれるものがある。これは実は、物理学の「ブラウン運動」という現象を記述する方程式がベースになっている。金融と物理というまったく異なる領域の事柄が、同じ発想の方程式で記述できてしまうということだ。
このような驚異的な応用力を目の当たりにすると、「神が数学を生み出し、この世界を構築したのだ」と考えたくもなるだろう。
「発見派」は、「『数学』というものが実在する」と考えているようで(この主張はなかなかイメージできないだろうが)、このスタンスを「プラトン主義」と呼ぶ。異なる領域によって数学で繋がる実例には確かに驚かされるが、しかし「『数学』が実在する」という考え方にも問題がある。
あわせて読みたい
【逸話】天才数学者ガロアが20歳で決闘で命を落とすまでの波乱万丈。時代を先駆けた男がもし生きていた…
現代数学に不可欠な「群論」をたった1人で生み出し、20歳という若さで決闘で亡くなったガロアは、その短い生涯をどう生きたのか?『ガロア 天才数学者の生涯』から、数学に関心を抱くようになったきっかけや信じられないほどの不運が彼の人生をどう変えてしまったのか、そして「もし生きていたらどうなっていたのか」を知る
一方、「発明派」の主張は要するに、「数学は人間が作ったものだ」ということになる。数学においては「無矛盾性」という概念が重要なのだが、相互に矛盾しないような規則を定めた上で人間が数学を作り出しているだけだ、というのが「発明派」の主張であり、この立場を「形式主義」と呼ぶ。
「形式主義」では、「『数学』は実在する」という「プラトン主義」とは対極に、「実在するものとの関連など不要だ」と考える。数学というのはあくまでもゲームのルールのようなものでしかなく、現実の何かと対応するかどうかなど関係ないのだ、と。
しかしこの「発明派」の主張ではやはり、どうして数学が異なる領域をまたぐ記述できてしまうのかを説明することは難しくなる。
あわせて読みたい
【衝撃】ABC予想の証明のために生まれたIUT理論を、提唱者・望月新一の盟友が分かりやすく語る:『宇宙…
8年のチェック期間を経て雑誌に掲載された「IUT理論(宇宙際タイヒミュラー理論)」は、数学の最重要未解決問題である「ABC予想」を証明するものとして大いに話題になった。『宇宙と宇宙をつなぐ数学』『abc予想入門』をベースに、「IUT理論」「ABC予想」について学ぶ
本書では、このような「思考の対立」が存在することを前提にした上で、数学史において「数学の捉えられ方」がどう変化していったのかを描き出していく。
ピタゴラス・デカルト・ニュートンら「発見派」の歴史
元々数学は「発見するもの」と考えられていた。この主張を明確な形で行ったのが「ピタゴラス学派」である。「ピタゴラスの定理」で有名なピタゴラスだが、これは彼一人の功績ではなく、「ピタゴラス学派」という数学を研究する集団の成果だと考えられており、ここが当時の数学研究を先導していたのだ。この学派は、
数とは、天界から人間の道徳まで、万物に宿る生きた実体であり、普遍的な原理であった
と捉えていた。数が実在するという、まさに「発見派」の立場である。「ピタゴラス学派」は、現代では「ある種の宗教的な存在」だったと捉えられているようだ。
あわせて読みたい
【興奮】飲茶氏が西洋哲学を語る。難解な思想が「グラップラー刃牙成分」の追加で驚異的な面白さに:『…
名前は聞いたことはあるがカントやニーチェがどんな主張をしたのかは分からないという方は多いだろう。私も無知なまったくの初心者だが、そんな人でも超絶分かりやすく超絶面白く西洋哲学を”分かった気になれる”飲茶『史上最強の哲学入門』は、入門書として最強
こんな有名な逸話がある。「ピタゴラス学派」は、「すべての数は、整数の比(分数)で表すことができる」と考えており(これは一種の教義のようなものだった)、「分数では表現できない数(無理数)は存在しない」と主張していた。しかし、まさに「ピタゴラスの定理」を使って、ピタゴラスの弟子が「√2」という無理数を発見してしまったのだ。ピタゴラスは驚き、この発見を封印するためにその弟子を殺した、と伝えられている。

ともかく、「ピタゴラス学派」は、探検家のように真理や定理を「発見」するのだと考えており、このような思想はその後、プラトンやアルキメデスらによってさらに高められていく。
さてその後、数学は科学と結び付けられる。
あわせて読みたい
【異端】数学の”証明”はなぜ生まれたのか?「無理数」と「無限」に恐怖した古代ギリシャ人の奮闘:『数…
学校で数学を習うと、当然のように「証明」が登場する。しかしこの「証明」、実は古代ギリシャでしか発展しなかった、数学史においては非常に”異端”の考え方なのだ。『数学の想像力 正しさの深層に何があるのか』をベースに、ギリシャ人が恐れたものの正体を知る
科学哲学者のアレクサンドル・コイレ(1892~1964)はかつて、ガリレオが科学的思考にもたらした革命は一点に集約されると指摘した。それは、数学が科学の文法だという発見である
ガリレオが、数学は科学を記述するためのものだと考え、さらにその後、デカルトが革命的な発想を持ち込む。数学の授業で必ず出てくる、x軸、y軸で表す「デカルト座標系」を生み出したのである。このように数学の捉え方や記述法が整えられることで科学と協力に結びついていくのだが、さらにそれを強く推し進めたのがニュートンだ。
ニュートンは4%程度もばらつきのある観測や実験から、100万分の1の精度を上回る重力法則を築き上げた。彼は史上初めて、自然現象の説明と観測結果の持つ予測能力を統合したのである。物理学と数学は永久に結び付き、科学と哲学の分離は避けられなくなった
こうして数学は、世界を正しく理解するための手段としての地位を確立していくことになる。
あわせて読みたい
【天才】『ご冗談でしょう、ファインマンさん』は、科学者のイメージが変わる逸話満載の非・科学エッセイ
「天才科学者」と言えばアインシュタインやニュートン、ホーキングが思い浮かぶだろうが、「科学者らしくないエピソード満載の天才科学者」という意味ではファインマンがずば抜けている。世界的大ベストセラー『ご冗談でしょう、ファインマンさん』は、「科学」をほぼ扱わないエッセイです
そんなニュートンは、デカルトが記した『幾何学』という書物に強く影響を受けた。そして当時の数学では、「幾何学」という分野(算数や数学でいう図形問題のようなイメージ)こそが最も有用性が高く、世界を記述するための法則であり、神が創造した永久不変の真理だとされていたのだ。
また、「確率・統計」の分野においても、「神の真理」を感じさせるものが現れる。それが「正規分布」だ。
「正規分布」は、ネットで調べればすぐ出てくるが、お寺の鐘のような形のグラフである。そして、「体重」「IQ」「株式指数の年間利益率」「メジャーリーグの平均打率」など、まったく無関係の様々なデータが、この「正規分布」に従うことが知られている。
自然界の現象だけではなく、人間の特徴や活動に関するデータであっても「正規分布」が関係するというのは、やはり「神が数学を創造した」ということではないのかと受け取られた。この頃までは、「数学は発見するもの」という考えが常識だったと言っていいだろう。
あわせて読みたい
【始まり】宇宙ができる前が「無」なら何故「世界」が生まれた?「ビッグバンの前」は何が有った?:『…
「宇宙がビッグバンから生まれた」ことはよく知られているだろうが、では、「宇宙ができる前はどうなっていたのか」を知っているだろうか? 実は「宇宙は”無”から誕生した」と考えられているのだ。『宇宙が始まる前には何があったのか?』をベースに、ビッグバンが起こる前の「空間も時間も物理法則も存在しない無」について学ぶ
「非ユークリッド幾何学」という衝撃
しかし、19世紀に衝撃的な事実が判明する。それが「非ユークリッド幾何学」の発見だ。「非ユークリッド幾何学」の存在が知られるようになったことで、それまで単に「幾何学」と呼ばれていたものが「ユークリッド幾何学」と名前が変わった。そして、この「非ユークリッド幾何学」の発見こそが、「神が数学を創造した」という根拠を揺るがすことになるのだが、その流れを見ていこう。
「幾何学」という分野は、紀元前300年頃のギリシャの数学者・ユークリッドが生み出した。彼は、「証明する必要のない5つの明白な前提」を組み合わせることで様々な定理を導き出していく。5つの前提というのは、「すべての直角は等しい」や「ある点から等距離の点を繋ぐと円になる」など、誰でも「まあその通りだろう」と考えるものである。
その中の1つに、後に「平行線公準」と呼ばれるようになる前提がある。これは、大雑把に説明すると「平行な2直線は交わらない」となる。これも当たり前だと思うだろう。
あわせて読みたい
【バトル】量子力学の歴史はこの1冊で。先駆者プランクから批判者アインシュタインまですべて描く:『量…
20世紀に生まれた量子論は、時代を彩る天才科学者たちの侃々諤々の議論から生み出された。アインシュタインは生涯量子論に反対し続けたことで知られているが、しかし彼の批判によって新たな知見も生まれた。『量子革命』から、量子論誕生の歴史を知る

しかし19世紀になるまでずっと、数学者はこの「平行線公準」に不満を抱いていた。他の4つの前提と比べると、説明が長くなるからだ。この「平行線公準」は、正確に表現するとこうなる。
2直線に他の1直線が交わってできる同じ側の内角の和が2直角より小さいなら、この2直線を延長すると、2直角より小さい側で交わる。
京都産業大学
確かに長い。そして数学者はシンプルを好む。
あわせて読みたい
【快挙】「チバニアン」は何が凄い?「地球の磁場が逆転する」驚異の現象がこの地層を有名にした:『地…
一躍その名が知れ渡ることになった「チバニアン」だが、なぜ話題になり、どう重要なのかを知っている人は多くないだろう。「チバニアン」の申請に深く関わった著者の『地磁気逆転と「チバニアン」』から、地球で起こった過去の不可思議な現象の正体を理解する
彼らはこう考えた。この「平行線公準」はどこか不自然だ、だから他の4つの前提を上手く組み合わせることで、この「平行線公準」を組み込む必要はないのではないか、と。ただ、数学者がどれだけ奮闘しても、「平行線公準は不要」と証明することはできなかった。
しかしその後、まったく新しい考え方をする数学者が登場する。それは、「平行線公準が成り立たない幾何学も存在するのではないか」という発想だ。つまり、「平行な2直線が交わる幾何学」も作れるのではないか、と考えたのである。
そしてなんと、実際にそれが可能であることが判明した。「平行線公準」が不要な幾何学が存在するということである。そこで、「平行な2直線が交わる」ような幾何学を、それまでの幾何学と区別するために「非ユークリッド幾何学」と呼ぶことになったのだ。
あわせて読みたい
【未知】タコに「高度な脳」があるなんて初耳だ。人類とは違う進化を遂げた頭足類の「意識」とは?:『…
タコなどの頭足類は、無脊椎動物で唯一「脳」を進化させた。まったく違う進化を辿りながら「タコに心を感じる」という著者は、「タコは地球外生命体に最も近い存在」と書く。『タコの心身問題』から、腕にも脳があるタコの進化の歴史と、「意識のあり方」を知る。
この事実は当時の数学者に衝撃を与えることになった。何故なら先述した通り、「幾何学(ユークリッド幾何学)こそが真理」と考えられていたからだ。「幾何学」こそが真理だと思っていたら、幾何学に複数の種類が存在すると判明してしまう。複数の種類が存在するものを「真理」と表現するには無理があるだろう。
また、「『数学』は実在する」と考えている「発明派」(プラトン主義)の数学者からすれば、「平行な2直線が交わる」なんていう、現実と対応しそうにない「非ユークリッド幾何学」の存在など許しがたかったはずである。
そして、この「非ユークリッド幾何学」の発見をきっかけに、「数学は人間が作ったものなのではないか」という考えが広がっていくことになる。
あわせて読みたい
【新視点】世界の歴史を「化学」で語る?デンプン・砂糖・ニコチンなどの「炭素化合物」が人類を動かし…
デンプン・砂糖・ニコチンなどは、地球上で非常に稀少な元素である「炭素」から作られる「炭素化合物」だ。そんな「炭素化合物」がどんな影響を与えたかという観点から世界の歴史を描く『「元素の王者」が歴史を動かす』は、学校の授業とはまったく違う視点で「歴史」を捉える
さらに「発見派」に大打撃がもたらされる
一方、「発明派」(形式主義)の数学者からすれば、「非ユークリッド幾何学」の発見など問題にならない。彼らにとっては「無矛盾性」こそが重要なのであり、幾何学が複数存在しようが相互に矛盾さえしなければいいのだ。
そして、数学の本質は自由だと考える形式主義の数学者たちは、やがて数学に論理学を組み込もうとする。
本書を読んで初めて知ったが、数学に論理学が組み込まれたのは実は最近のことなのだそうだ。学校で学ぶ数学は、明らかに論理学の形式で整えられているので、そういう記述が当然だと考えていた。しかし実際には、様々な分野で別々の形で生まれた数学を、「ごく僅かな前提から導こう」という形でまとめる過程で論理学が組み込まれていった、ということのようである。
あわせて読みたい
【不可思議】心理学の有名な実験から、人間の”欠陥”がどう明らかになっていったかを知る:『心は実験で…
『心は実験できるか 20世紀心理学実験物語』では、20世紀に行われた心理学実験からインパクトのある10の実験を選び紹介している。心理学者でもある著者が「科学であって科学ではない」と主張する心理学という学問で、人間のどんな不可思議さがあぶり出されてきたのかを知る

さて、数学に論理学を組み込む過程で、さらに「発見派」は大打撃を受けることになる。この話は非常にややこしいので、あまり具体的には書かないが、結論だけざっと書くと、
ツェルメロ=フレンケル公理系においては、『選択公理』も『連続体仮説』も共に、肯定も否定もできないことが判明した
ということになる。
あわせて読みたい
【究極】リサ・ランドールが「重力が超弱い理由」を解説する、超刺激的なひも理論の仮説:『ワープする…
現役の研究者であるリサ・ランドールが、自身の仮説を一般向けに分かりやすく説明する『ワープする宇宙』。一般相対性理論・量子力学の知識を深く記述しつつ「重力が超弱い理由」を説明する、ひも理論から導かれる「ワープする余剰次元」について解説する
つまりどういうことかというと、ツェルメロ=フレンケル公理系においては、
- 「選択公理」も「連続体仮説」も共に採用する
- 「選択公理」は採用するが「連続体仮説」は採用しない
- 「選択公理」は採用しないが「連続体仮説」は採用する
- 「選択公理」も「連続体仮説」も採用しない
という4パターンが存在しうる、ということだ。
あわせて読みたい
【敗北】「もつれ」から量子論の基礎を学ぶ。それまでの科学では説明不能な「異次元の現象」とは?:『…
アインシュタインは量子力学を生涯受け入れなかったのだが、アインシュタインが批判し続けたことによって明らかになったこともある。「もつれ」の重要性もその一つだ。『宇宙は「もつれ」でできている』から量子力学の基礎を成す現象を知る。
これも幾何学の時と同様、一つの分野に複数の選択肢が存在することになる。どれを選ぶかは、その時々の人間の判断次第だ。こうなると余計に、「数学は人間が作ったものだ」とという発想が自然ではないかと考える機運が高まることになるだろう。
ヒルベルトの計画を粉砕したゲーデル
しかし話はそう簡単ではない。今度は「発明派」が大打撃を受ける番である。
ヒルベルトという20世紀を代表する偉大な数学者が、ある計画をぶち上げた。それは「ヒルベルト・プログラム」と呼ばれ、多くの数学者がその完成のために動いていた。
あわせて読みたい
【驚嘆】「現在は森でキノコ狩り」と噂の天才”変人”数学者グリゴリー・ペレルマンの「ポアンカレ予想証…
数学界の超難問ポアンカレ予想を解決したが、100万ドルの賞金を断り、フィールズ賞(ノーベル賞級の栄誉)も辞退、現在は「森できのこ採取」と噂の天才数学者グリゴリー・ペレルマンの生涯を描く評伝『完全なる証明』。数学に関する記述はほぼなく、ソ連で生まれ育った1人の「ギフテッド」の苦悩に満ちた人生を丁寧に描き出す1冊
「ヒルベルト・プログラム」とは、大雑把に書けば、「数学のあらゆる分野を、僅かな前提と推論規則で記述し、それが無矛盾であることを示そうとする計画」だ。要するにヒルベルトは、「数学というのは形式主義そのものであり、それを完膚なきまでに示してみせよう」と考えてこのプロジェクトを始動させたのだろう。同時代の数学者を焚き付けて、「形式主義の勝利宣言」をしようとした、といったところではないか。
しかしこのプロジェクトは、完成を見ずに頓挫する。何故なら、天才数学者ゲーデルが25歳という若さで発表した「不完全性定理」が、彼の目論見に終止符を打ったからだ。この「不完全性定理」も非常に説明が難しく、この記事では具体的には記述しないが、要するにゲーデルは、「ヒルベルトがやろうとしているプロジェクトは、絶対に不可能だ」ということを証明したのだ。

もう少し詳しく書こう。ヒルベルトは、「数学のあらゆる分野を、僅かな前提と推論規則によって記述し、それが無矛盾だと示す」ことを目指した。しかしゲーデルは、「どんな風に数学を記述しても、その数学体系内部の理屈では、その数学体系が無矛盾だとは示せない」ということを証明したのだ。
あわせて読みたい
【刺激】結城浩「数学ガール」で、ゲーデルの不完全性定理(不可能性の証明として有名)を学ぶ
『結城浩「数学ガール」シリーズは、数学の面白さを伝えながら、かなり高難度の話題へと展開していく一般向けの数学書です。その第3弾のテーマは、「ゲーデルの不完全性定理」。ヒルベルトという数学者の野望を打ち砕いた若き天才の理論を学びます
「不完全性定理」によってヒルベルトの野望は潰えたのだが、しかし決して「数学は人間が作ったものだ」ということが完全に否定されたわけではない。「形式主義者」は、「人間が数学を作ったのなら、形式主義的に完璧に記述できるはずだ」と考えていたのだが、その目論見が無理だと証明されたにすぎない。
いずれにしてもゲーデルによって、「形式主義的な視点で捉えたとしても、数学は不完全なゲームでしかない」と示されてしまい、「形式主義」の勝利宣言とはならなかった。
現時点で議論は、ここで止まっているのだろう。今後数学でまた新たな展開が生まれれば、「発見派」と「発明派」の主張に変化が出るかもしれない。
このように「数学」という学問を「神が作ったのか、人間が作ったのか」という視点で捉えるのも面白いだろう。
あわせて読みたい
【驚異】数学の「無限」は面白い。アキレスと亀の矛盾、実無限と可能無限の違い、カントールの対角線論…
日常の中で「無限」について考える機会などなかなか無いだろうが、野矢茂樹『無限論の教室』は、「無限には種類がある」と示すメチャクチャ興味深い作品だった。「実無限」と「可能無限」の違い、「可能無限」派が「カントールの対角線論法」を拒絶する理由など、面白い話題が満載の1冊
「数学の偏在性と全能性」を示す実例
発見か発明かという議論はここまでで終了だが、本書では最後に、「結び目理論」と呼ばれるものが紹介される。数学が思いがけない領域と結びつくという実例だ。この記事では簡単に触れていこう。
元々「結び目理論」というのは、原子モデルを説明するために生み出された。しかし早々にこの考えは誤りだと分かり、原子モデルとしては廃れてしまう。
ただこの「結び目理論」、数学的にはなかなか興味をそそるものだったようで、物理学者が考え出したこの理論は、純粋な研究対象として数学者たちによって発展されていく。数学者たちは当然、それが何かの役に立つと考えていたわけではなく、突き詰めていったら面白そうだという興味だけで研究を続けていたわけだが、ある時、この「結び目理論」が、生命の根幹を成すDNAと関係していることが判明するのだ。これだけでもなかなか興味深いだろう。
あわせて読みたい
【幻想】超ひも理論って何?一般相対性理論と量子力学を繋ぐかもしれないぶっ飛んだ仮説:『大栗先生の…
『大栗先生の超弦理論入門』は最先端科学である「超弦理論」を説明する1冊だが、この記事では著者の主張の1つである「空間は幻想かもしれない」という発想を主に取り上げる。「人類史上初の『適用する次元が限定される理論』」が描像する不可思議な世界とは?
しかしそれだけではない。現在科学においては、「一般相対性理論」と「量子力学」を融合するために新しい重力理論が待望されているのだが、その候補の1つと考えられている「ひも理論」にも「結び目理論」の考え方が重要だということが分かってきているのだ。
当初は物理学の領域で生まれ、すぐに間違っていることが判明しながら、純粋に数学的興味で研究が続けられ、それが別の領域に関係していくというのは、やはり非常に不思議な感覚を抱かせるだろう。本書では、なぜこのようなことが起こるのだろうかと問題提起がなされる。やはり数学は、神が作ったのだろうか?
いずれにしても、数学の奥深さを強く感じることができる作品だ。
あわせて読みたい
【解説】テネットの回転ドアの正体を分かりやすく考察。「時間逆行」ではなく「物質・反物質反転」装置…
クリストファー・ノーラン監督の映画『TENET/テネット』は、「陽電子」「反物質」など量子力学の知見が満載です。この記事では、映画の内容そのものではなく、時間反転装置として登場する「回転ドア」をメインにしつつ、時間逆行の仕組みなど映画全体の設定について科学的にわかりやすく解説していきます
著:マリオ リヴィオ, 翻訳:千葉 敏生
¥861 (2022/01/29 21:47時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品読了済】私が読んできたノンフィクション・教養書を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が読んできたノンフィクションを様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本選びの参考にして下さい。
最後に

私は、個人的には「発見だったらいいな」と考えている。その方がロマンがあるし、「人間が作ったもの」と考えるのはやはり味気ない。別に「神」や「創造主」を信じているわけではないが、いつかそういう存在が「実は俺が作ったんだよねぇ~」と言って手書きのノートを見せてくれたりすると嬉しい。
あわせて読みたい
【ドラマ】「フェルマーの最終定理」のドラマティックな証明物語を、飲茶氏が平易に描き出す:『哲学的…
「フェルマーの最終定理」は、問題の提示から350年以上経ってようやく証明された超難問であり、その証明の過程では様々な人間ドラマが知られている。『哲学的な何か、あと数学とか』をベースに、数学的な記述を一切せず、ドラマティックなエピソードだけに触れる
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【奇妙】大栗博司『重力とはなにか』は、相対性理論や量子力学の説明も秀逸だが、超弦理論の話が一番面白い
『重力とはなにか』(大栗博司)は、科学に馴染みの薄い人でもチャレンジできる易しい入門書だ。相対性理論や量子力学、あるいは超弦理論など、非常に難解な分野を基本的なところから平易に説明してくれるので、「科学に興味はあるけど難しいのはちょっと……」という方にこそ読んでほしい1冊
あわせて読みたい
【倫理】アート体験の行き着く未来は?映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』が描く狂気の世界(…
「『痛み』を失った世界」で「自然発生的に生まれる新たな『臓器』を除去するライブパフォーマンス」を行うソール・テンサーを主人公にした映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』は、すぐには答えの見出しにくい「境界線上にある事柄」を挑発的に描き出す、実に興味深い物語だ
あわせて読みたい
【驚嘆】「現在は森でキノコ狩り」と噂の天才”変人”数学者グリゴリー・ペレルマンの「ポアンカレ予想証…
数学界の超難問ポアンカレ予想を解決したが、100万ドルの賞金を断り、フィールズ賞(ノーベル賞級の栄誉)も辞退、現在は「森できのこ採取」と噂の天才数学者グリゴリー・ペレルマンの生涯を描く評伝『完全なる証明』。数学に関する記述はほぼなく、ソ連で生まれ育った1人の「ギフテッド」の苦悩に満ちた人生を丁寧に描き出す1冊
あわせて読みたい
【驚異】数学の「無限」は面白い。アキレスと亀の矛盾、実無限と可能無限の違い、カントールの対角線論…
日常の中で「無限」について考える機会などなかなか無いだろうが、野矢茂樹『無限論の教室』は、「無限には種類がある」と示すメチャクチャ興味深い作品だった。「実無限」と「可能無限」の違い、「可能無限」派が「カントールの対角線論法」を拒絶する理由など、面白い話題が満載の1冊
あわせて読みたい
【特異】「カメラの存在」というドキュメンタリーの大前提を覆す映画『GUNDA/グンダ』の斬新さ
映画『GUNDA/グンダ』は、「カメラの存在」「撮影者の意図」を介在させずにドキュメンタリーとして成立させた、非常に異端的な作品だと私は感じた。ドキュメンタリーの「デュシャンの『泉』」と呼んでもいいのではないか。「家畜」を被写体に据えたという点も非常に絶妙
あわせて読みたい
【奇人】天才数学者で、自宅を持たずに世界中を放浪した変人エルデシュは、迷惑な存在でも愛され続けた…
数学史上ガウスに次いで生涯発表論文数が多い天才エルデシュをご存知だろうか?数学者としてずば抜けた才能を発揮したが、それ以上に「奇人変人」としても知られる人物だ。『放浪の天才数学者エルデシュ』で、世界中の数学者の家を泊まり歩いた異端数学者の生涯を描き出す
あわせて読みたい
【新視点】世界の歴史を「化学」で語る?デンプン・砂糖・ニコチンなどの「炭素化合物」が人類を動かし…
デンプン・砂糖・ニコチンなどは、地球上で非常に稀少な元素である「炭素」から作られる「炭素化合物」だ。そんな「炭素化合物」がどんな影響を与えたかという観点から世界の歴史を描く『「元素の王者」が歴史を動かす』は、学校の授業とはまったく違う視点で「歴史」を捉える
あわせて読みたい
【思考】『翔太と猫のインサイトの夏休み』は、中学生と猫の対話から「自分の頭で考える」を学べる良書
「中学生の翔太」と「猫のインサイト」が「答えの出ない問い」について対話する『翔太と猫のインサイトの夏休み』は、「哲学」の違う側面を見せてくれる。過去の哲学者・思想家の考えを知ることが「哲学」なのではなく、「自分の頭で考えること」こそ「哲学」の本質だと理解する
あわせて読みたい
【実話】映画『イミテーションゲーム』が描くエニグマ解読のドラマと悲劇、天才チューリングの不遇の死
映画『イミテーションゲーム』が描く衝撃の実話。「解読不可能」とまで言われた最強の暗号機エニグマを打ち破ったのはなんと、コンピューターの基本原理を生み出した天才数学者アラン・チューリングだった。暗号解読を実現させた驚きのプロセスと、1400万人以上を救ったとされながら偏見により自殺した不遇の人生を知る
あわせて読みたい
【本質】子どもの頃には読めない哲学書。「他人の哲学はつまらない」と語る著者が説く「問うこと」の大…
『<子ども>のための哲学』は決して、「子どもでも易しく理解できる哲学の入門書」ではない。むしろかなり難易度が高いと言っていい。著者の永井均が、子どもの頃から囚われ続けている2つの大きな疑問をベースに、「『哲学する』とはどういうことか?」を深堀りする作品
あわせて読みたい
【最新】「コロンブス到達以前のアメリカ大陸」をリアルに描く歴史書。我々も米国人も大いに誤解してい…
サイエンスライターである著者は、「コロンブス到着以前のアメリカはどんな世界だったか?」という問いに触れ、その答えが書かれた本がいつまで経っても出版されないので自分で執筆した。『1491 先コロンブス期アメリカ大陸をめぐる新発見』には、アメリカ人も知らない歴史が満載だ
あわせて読みたい
【異端】「仏教とは?」を簡単に知りたい方へ。ブッダは「異性と目も合わせないニートになれ」と主張し…
我々が馴染み深い「仏教」は「大乗仏教」であり、創始者ゴータマ・ブッダの主張が詰まった「小乗仏教」とは似て非なるものだそうだ。『講義ライブ だから仏教は面白い!』では、そんな「小乗仏教」の主張を「異性と目も合わせないニートになれ」とシンプルに要約して説明する
あわせて読みたい
【感想】池田晶子『14歳からの哲学』で思考・自由・孤独の大事さを知る。孤独を感じることって大事だ
「元々持ってた価値観とは違う考えに触れ、それを理解したいと思う場面」でしか「考える」という行為は発動しないと著者は言う。つまり我々は普段、まったく考えていないのだ。『14歳からの哲学』をベースに、「考えること」と自由・孤独・人生との関係を知る
あわせて読みたい
【興奮】世界的大ベストセラー『サピエンス全史』要約。人類が文明を築き上げるに至った3つの革命とは?
言わずと知れた大ベストセラー『サピエンス全史』は、「何故サピエンスだけが人類の中で生き残り、他の生物が成し得なかった歴史を歩んだのか」を、「認知革命」「農業革命」「科学革命」の3つを主軸としながら解き明かす、知的興奮に満ち溢れた1冊
あわせて読みたい
【知的】文系にオススメの、科学・数学・哲学の入門書。高橋昌一郎の「限界シリーズ」は超絶面白い:『…
例えば「科学」だけに限ってみても、「なんでもできる」わけでは決してない。「科学」に限らず、私たちが対峙する様々な事柄には「これ以上は不可能・無理」という「限界」が必ず存在する。高橋昌一郎の「限界シリーズ」から、我々が認識しておくべき「限界」を易しく学ぶ
あわせて読みたい
【感想】飲茶の超面白い東洋哲学入門書。「本書を読んでも東洋哲学は分からない」と言う著者は何を語る…
東洋哲学というのは、「最終回しか存在しない連続ドラマ」のようなものだそうだ。西洋哲学と比較にならないほど異質さと、インド哲学・中国哲学など個別の思想を恐ろしく分かりやすく描く『史上最強の哲学入門 東洋の哲人たち』は、ページをめくる手が止まらないくらい、史上最強レベルに面白かった
あわせて読みたい
【興奮】飲茶氏の超面白い哲学小説。「正義とは?」の意味を問う”3人の女子高生”の主張とは?:『正義の…
なんて面白いんだろうか。哲学・科学を初心者にも分かりやすく伝える飲茶氏による『正義の教室』は、哲学書でありながら、3人の女子高生が登場する小説でもある。「直観主義」「功利主義」「自由主義」という「正義論」の主張を、「高校の問題について議論する生徒会の話し合い」から学ぶ
あわせて読みたい
【驚異】ガイア理論の提唱者が未来の地球を語る。100歳の主張とは思えない超絶刺激に満ちた内容:『ノヴ…
「地球は一種の生命体だ」という主張はかなり胡散臭い。しかし、そんな「ガイア理論」を提唱する著者は、数々の賞や学位を授与される、非常に良く知られた科学者だ。『ノヴァセン <超知能>が地球を更新する』から、AIと人類の共存に関する斬新な知見を知る
あわせて読みたい
【人生】「資本主義の限界を埋める存在としての『贈与論』」から「不合理」に気づくための生き方を知る…
「贈与論」は簡単には理解できないが、一方で、「何かを受け取ったら、与えてくれた人に返す」という「交換」の論理では対処できない現実に対峙する力ともなる。『世界は贈与でできている』から「贈与」的な見方を理解し、「受取人の想像力」を立ち上げる
あわせて読みたい
【興奮】飲茶氏が西洋哲学を語る。難解な思想が「グラップラー刃牙成分」の追加で驚異的な面白さに:『…
名前は聞いたことはあるがカントやニーチェがどんな主張をしたのかは分からないという方は多いだろう。私も無知なまったくの初心者だが、そんな人でも超絶分かりやすく超絶面白く西洋哲学を”分かった気になれる”飲茶『史上最強の哲学入門』は、入門書として最強
あわせて読みたい
【あらすじ】天才とは「分かりやすい才能」ではない。前進するのに躊躇する暗闇で直進できる勇気のこと…
ピアノのコンクールを舞台に描く『蜜蜂と遠雷』は、「天才とは何か?」と問いかける。既存の「枠組み」をいとも簡単に越えていく者こそが「天才」だと私は思うが、「枠組み」を安易に設定することの是非についても刃を突きつける作品だ。小説と映画の感想を一緒に書く
あわせて読みたい
【驚愕】ロバート・キャパの「崩れ落ちる兵士」はどう解釈すべきか?沢木耕太郎が真相に迫る:『キャパ…
戦争写真として最も有名なロバート・キャパの「崩れ落ちる兵士」には、「本当に銃撃された瞬間を撮影したものか?」という真贋問題が長く議論されてきた。『キャパの十字架』は、そんな有名な謎に沢木耕太郎が挑み、予想だにしなかった結論を導き出すノンフィクション。「思いがけない解釈」に驚かされるだろう
あわせて読みたい
【限界】「科学とは何か?」を知るためのおすすめ本。科学が苦手な人こそ読んでほしい易しい1冊:『哲学…
「科学的に正しい」という言葉は、一体何を意味しているのだろう?科学者が「絶対に正しい」とか「100%間違っている」という言い方をしないのは何故だろう?飲茶『哲学的な何か、あと科学とか』から、「科学とはどんな営みなのか?」について考える
あわせて読みたい
【逸話】天才数学者ガロアが20歳で決闘で命を落とすまでの波乱万丈。時代を先駆けた男がもし生きていた…
現代数学に不可欠な「群論」をたった1人で生み出し、20歳という若さで決闘で亡くなったガロアは、その短い生涯をどう生きたのか?『ガロア 天才数学者の生涯』から、数学に関心を抱くようになったきっかけや信じられないほどの不運が彼の人生をどう変えてしまったのか、そして「もし生きていたらどうなっていたのか」を知る
あわせて読みたい
【証明】結城浩「数学ガール」とサイモン・シンから「フェルマーの最終定理」とそのドラマを学ぶ
350年以上前に一人の数学者が遺した予想であり「フェルマーの最終定理」には、1995年にワイルズによって証明されるまでの間に、これでもかというほどのドラマが詰め込まれている。サイモン・シンの著作と「数学ガール」シリーズから、その人間ドラマと数学的側面を知る
あわせて読みたい
【刺激】結城浩「数学ガール」で、ゲーデルの不完全性定理(不可能性の証明として有名)を学ぶ
『結城浩「数学ガール」シリーズは、数学の面白さを伝えながら、かなり高難度の話題へと展開していく一般向けの数学書です。その第3弾のテーマは、「ゲーデルの不完全性定理」。ヒルベルトという数学者の野望を打ち砕いた若き天才の理論を学びます
あわせて読みたい
【興奮】結城浩「数学ガール」で、決闘で命を落とした若き天才数学者・ガロアの理論を学ぶ
高校生を中心に、数学を通じて関わり合う者たちを描く「数学ガール」シリーズ第5弾のテーマは「ガロア理論」。独力で「群論」という新たな領域を切り開きながら、先駆的すぎて同時代の数学者には理解されず、その後決闘で死亡した天才の遺した思考を追う
あわせて読みたい
【異端】数学の”証明”はなぜ生まれたのか?「無理数」と「無限」に恐怖した古代ギリシャ人の奮闘:『数…
学校で数学を習うと、当然のように「証明」が登場する。しかしこの「証明」、実は古代ギリシャでしか発展しなかった、数学史においては非常に”異端”の考え方なのだ。『数学の想像力 正しさの深層に何があるのか』をベースに、ギリシャ人が恐れたものの正体を知る
あわせて読みたい
【天才】数学の捉え方を一変させた「シンメトリー(対称性)」と、その発見から発展に至る歴史:『シン…
「5次方程式の解の公式は存在しない」というアーベルの証明や、天才・ガロアが発展させた「群論」は、「シンメトリー(対称性)」という領域に新たな光を当てた。『シンメトリーの地図帳』をベースに、「シンメトリー」の発展と「モンスター」の発見の物語を知る
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
科学・数学の知識を身につける【本・映画の感想】 | ルシルナ
中退していますが、理系の大学に通っていました。学校の勉強で一番好きだったのは数学・物理ですし、大人になってからも科学や数学の本を数多く読んできました。偉人たちの…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…







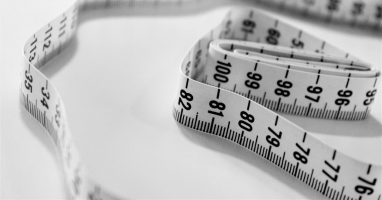







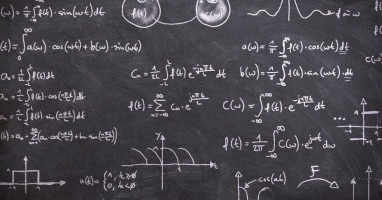










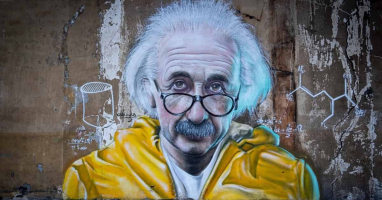




































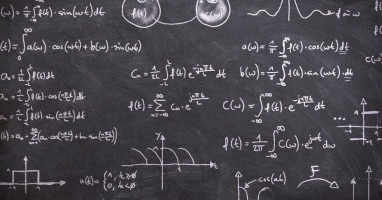










コメント