目次
はじめに
あわせて読みたい
パンサー尾形が解説!NHKの超面白い数学番組『笑わない数学』の話題をさらに深掘りする記事
お笑い芸人・パンサー尾形が、笑い一切無しで、難解だが魅力的な数学世界を大真面目に解説するNHKの数学番組『笑わない数学』。同番組で紹介された様々な話題について、当ブログでも記事を書いているので、それらをまとめて紹介していきます。番組を観て興味を持った方、さらに深掘りするのにご参考下さい。
この記事で取り上げる本
著:加藤 文元
¥1,870 (2021/09/01 06:09時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
この本をガイドにしながら記事を書いていきます
この記事の3つの要点
- 「証明」というプロセスは、古代ギリシャ人だけが発展させた
- 「無理数」の発見に恐怖し「証明」が生まれた
- 「無限」を回避するために「背理法」という特異な証明が誕生した
「証明」がなぜ・どのように生み出され、それが「数学の『正しさ』」とどう関係するのかが語られる
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
「数学はなぜ『正しい』と言えるのか?」について考えたことがあるだろうか?加藤文元『数学の想像力』から「数学の本質」について理解する
「数学の『正しさ』とは何か」というテーマについて
あわせて読みたい
【天才】数学の捉え方を一変させた「シンメトリー(対称性)」と、その発見から発展に至る歴史:『シン…
「5次方程式の解の公式は存在しない」というアーベルの証明や、天才・ガロアが発展させた「群論」は、「シンメトリー(対称性)」という領域に新たな光を当てた。『シンメトリーの地図帳』をベースに、「シンメトリー」の発展と「モンスター」の発見の物語を知る
本書のテーマについて、著者はこんな風に書いている。
「数学をカチコチの論理という臆見から解放する」こと。一般の人々が数学に対しているような「頭の硬い人々が理屈をこね回してでっちあげる机上の空論」という印象をぬぐい去ること。これらもまた、この本の基層に流れる主要テーマの一つである

つまり、「数学という学問の捉えられ方」を変えたい、というのが著者の大きな動機だというわけである。そして、それを実現するために著者が選んだ本書の”核”というのが、「数学の『正しさ』とは何か」である。
あわせて読みたい
【変人】結城浩「数学ガール」から、1億円も名誉ある賞も断った天才が証明したポアンカレ予想を学ぶ
1億円の賞金が懸けられた「ポアンカレ予想」は、ペレルマンという天才数学者が解き明かしたが、1億円もフィールズ賞も断った。そんな逸話のある「ポアンカレ予想」とは一体どんな主張であり、どのように証明されたのかを結城浩『数学ガール』から学ぶ
この問いについては、数学への関心度によって印象が変わるだろう。数学に興味がない人は、「そもそも何を言っているのか分からない」となるだろうし、数学に興味がある人は、「数学って正しいんじゃないの?」と感じることだろう。
さて、より具体的に書けば、本書のテーマは「証明」である。数学における「証明」という技法が、「なぜ」「どのように」生まれたのかを、数学史を紐解きながら追っていく作品だ。
あわせて読みたい
【対立】数学はなぜ”美しい”のか?数学は「発見」か「発明」かの議論から、その奥深さを知る:『神は数…
数学界には、「数学は神が作った派」と「数学は人間が作った派」が存在する。『神は数学者か?』をベースに、「数学は発見か、発明か」という議論を理解し、数学史においてそれぞれの認識がどのような転換点によって変わっていったのかを学ぶ
学生時代、数学の試験で「証明問題」に苦しんだという方も多いだろう。私も、理系の人間だが、やはり計算問題より証明問題の方が苦手だった。
好き嫌いはともかく、数学と言えば「証明」、みたいな印象はきっと誰もが持っているだろうし、数学が好きな人なら、「数学は、正しいと証明されなければほとんど意味がない」と理解しているだろう。数学の中には、「まだ正しいとは証明されていないが、非常に重要とされている予想」というものもあり、証明されていないから無意味というわけでは決してない。ただやはり、「証明されているかどうか」は、数学において非常に重要な要素だ。
しかしこの「証明」という手法、長い長い数学の歴史においては、非常に特異で異端な存在なのである。
「証明」は、古代ギリシャでしか発展しなかった
あわせて読みたい
【逸話】天才数学者ガロアが20歳で決闘で命を落とすまでの波乱万丈。時代を先駆けた男がもし生きていた…
現代数学に不可欠な「群論」をたった1人で生み出し、20歳という若さで決闘で亡くなったガロアは、その短い生涯をどう生きたのか?『ガロア 天才数学者の生涯』から、数学に関心を抱くようになったきっかけや信じられないほどの不運が彼の人生をどう変えてしまったのか、そして「もし生きていたらどうなっていたのか」を知る
本書に、こんな記述がある。
実際、我々が後に第8章で行うように、時代性・地域性という観点から「証明」という行いを見たとき、数や図形を論じる際に<正しさ>を確信させる方法として演繹的証明を採用するという流儀は、むしろ極めて特異なものに見える。それは古代ギリシャで生まれたものであるが、むしろ古代ギリシャでしか生まれなかったということの方が重大だ
まずこの意味を説明していこう。
あわせて読みたい
【衝撃】ABC予想の証明のために生まれたIUT理論を、提唱者・望月新一の盟友が分かりやすく語る:『宇宙…
8年のチェック期間を経て雑誌に掲載された「IUT理論(宇宙際タイヒミュラー理論)」は、数学の最重要未解決問題である「ABC予想」を証明するものとして大いに話題になった。『宇宙と宇宙をつなぐ数学』『abc予想入門』をベースに、「IUT理論」「ABC予想」について学ぶ
「数学」という学問は、世界中の様々な地域で独自に発展していった。有名なところだけ挙げても、「中国」「インド」「アラビア」「ギリシャ」「エジプト」「日本」と地域は多様だ。次第に1つの学問として統一されていくことになるが、それまでは、数学の研究には地域差があったのである。
たとえば有名な話でいえば、「0」という数字を発見したのはインドである。また、「位取り記数法」という手法を生み出したのはアラビアだ。他の地域にそれらの発見が伝わるまでは当然、「0」や「位取り記数法」を使わずに数学が行われていたのである。
そして同じように、「証明」というスタイルはギリシャでしか発展しなかった。
あわせて読みたい
【証明】結城浩「数学ガール」とサイモン・シンから「フェルマーの最終定理」とそのドラマを学ぶ
350年以上前に一人の数学者が遺した予想であり「フェルマーの最終定理」には、1995年にワイルズによって証明されるまでの間に、これでもかというほどのドラマが詰め込まれている。サイモン・シンの著作と「数学ガール」シリーズから、その人間ドラマと数学的側面を知る
ギリシャ以外の地域では主に、「計算」が重視されていたという。例えば円周率の計算などは有名だろう。手計算で力づくで計算する者もいれば、観察によって法則性を見抜き計算を進めた者もいる。いずれにせよ、ギリシャ以外では「いかに計算するか」こそが重要であり、「証明」などという論証スタイルが生まれることはなかった。

それではなぜギリシャは、「証明」を発明できたのだろうか?
「見る」からの脱却のきっかけとなった「通約不可能性の発見」の衝撃
まず、「証明」が発明される以前の状況を見ていこう。
あわせて読みたい
【興奮】結城浩「数学ガール」で、決闘で命を落とした若き天才数学者・ガロアの理論を学ぶ
高校生を中心に、数学を通じて関わり合う者たちを描く「数学ガール」シリーズ第5弾のテーマは「ガロア理論」。独力で「群論」という新たな領域を切り開きながら、先駆的すぎて同時代の数学者には理解されず、その後決闘で死亡した天才の遺した思考を追う
古代ギリシャにおいて「何かが正しい」という主張は、当初は「見ること」によって行われていた。どういうことか。
たとえば、目の前に同じ大きさの三角形が2つあるとする。これらが「同じ」であることを示すためには、「辺の長さ」や「角度の大きさ」などを比べればいい。このように最初は、「見ること」によって「正しさ」を示していたということだ。ざっくばらんに言えば、「見たら分かるでしょ」という主張によって「正しさ」を示すことができる、という共通理解が存在したのである。
この「見る」ことで「正しさ」を示すというやり方が、「通約不可能性の発見」によって打撃を受けるのだが、その説明の前にまず「ピタゴラス教団」の話をしよう。
あわせて読みたい
【ドラマ】「フェルマーの最終定理」のドラマティックな証明物語を、飲茶氏が平易に描き出す:『哲学的…
「フェルマーの最終定理」は、問題の提示から350年以上経ってようやく証明された超難問であり、その証明の過程では様々な人間ドラマが知られている。『哲学的な何か、あと数学とか』をベースに、数学的な記述を一切せず、ドラマティックなエピソードだけに触れる
古代ギリシャの数学研究において重要な存在だった「ピタゴラス教団」は、その名の通り「ピタゴラスの定理」でお馴染みのピタゴラスが率いた集団だが、これは「学問の研究機関」というよりむしろ「宗教的な集団」だったようだ。彼らは、「万物は数である」という思想を持っており、この考えを突き詰めた結果、他の地域では生まれなかった「数」に対するある幻想を抱くことになる。
それが、「この世には有理数しか存在しない」というものだ。「有理数」というのは要するに、「分数で表すことができる数」のことである。「ピタゴラス教団」は何故か、このような思想を抱くようになったのだ。
しかしやがて、なんと彼ら自身が有理数ではない数を発見してしまう。有名な「ピタゴラスの定理」は、ピタゴラスではなくピタゴラス教団の誰かが発見したものと考えられているが、まさにその「ピタゴラスの定理」を使うことで「無理数」が導き出されるのだ。

あわせて読みたい
【究極】リサ・ランドールが「重力が超弱い理由」を解説する、超刺激的なひも理論の仮説:『ワープする…
現役の研究者であるリサ・ランドールが、自身の仮説を一般向けに分かりやすく説明する『ワープする宇宙』。一般相対性理論・量子力学の知識を深く記述しつつ「重力が超弱い理由」を説明する、ひも理論から導かれる「ワープする余剰次元」について解説する
一辺の長さが1の正方形の対角線の長さは、「ピタゴラスの定理」から√2と分かる。そしてこの「√2」が「有理数ではない」ことを彼らは証明してしまうのだ(一説によれば、「√2」を発見した人物は殺されてしまったと言われている。教団の思想に反する発見をしてしまったからだ)。
この「無理数の発見」は「通約不可能性の発見」とも呼ばれており、「万物は数である」という思想の下に数学の研究を行っていた当時の数学者に衝撃を与えた。そしてそのことが、「証明」の誕生のきっかけの1つとなる。
なぜ「通約不可能性の発見」が「証明」を生み出すことになるのか。それは、「見る」ことで「正しさ」を示すやり方に不備があると気づいたからだ。彼らがどのように「見る」ことの限界に気づいたのか説明していこう。
あわせて読みたい
【解説】テネットの回転ドアの正体を分かりやすく考察。「時間逆行」ではなく「物質・反物質反転」装置…
クリストファー・ノーラン監督の映画『TENET/テネット』は、「陽電子」「反物質」など量子力学の知見が満載です。この記事では、映画の内容そのものではなく、時間反転装置として登場する「回転ドア」をメインにしつつ、時間逆行の仕組みなど映画全体の設定について科学的にわかりやすく解説していきます
算数や数学の授業で、「数直線」というのを習っただろう。真っ直ぐな線に「……-2,-1,0,1,2……」のようなメモリがついたものだ。
そして、「有理数しか存在しない」と考えていた「ピタゴラス教団」は要するに、「この数直線上にある数はすべて有理数だ」と考えていたということになる。
確かに、なんとなくのイメージでは、それもあり得るような気がしてくる。たとえば「0」と「1」の間について考えよう。この場合、「1」という数字を「2」「3」「4」……と様々な数字で割っていけば、それらはすべて「0と1の間にある有理数」となる。割る数は整数である必要はなく、「5.1」や「2.023689574」なんていう数字でもいい。
あわせて読みたい
【奇人】天才数学者で、自宅を持たずに世界中を放浪した変人エルデシュは、迷惑な存在でも愛され続けた…
数学史上ガウスに次いで生涯発表論文数が多い天才エルデシュをご存知だろうか?数学者としてずば抜けた才能を発揮したが、それ以上に「奇人変人」としても知られる人物だ。『放浪の天才数学者エルデシュ』で、世界中の数学者の家を泊まり歩いた異端数学者の生涯を描き出す
そうやってイメージしていけば、「0」と「1」の間はすべて「有理数」だけで埋まっている、となんとなく考えてしまうだろう。「無理数」の存在が知られる前ならなおさらだ。
しかし「無理数」が発見されたことで、「数直線上には有理数だけではなく、無理数も存在する」ということが明らかになった。
古代ギリシャ人が危惧したのは、「数直線上に無理数が存在すること」は「見る」ことによっては確かめられない、ということだ。つまり彼らはこの時、「見る」ことの限界を感じ取ったと推定できる。
あわせて読みたい
【始まり】宇宙ができる前が「無」なら何故「世界」が生まれた?「ビッグバンの前」は何が有った?:『…
「宇宙がビッグバンから生まれた」ことはよく知られているだろうが、では、「宇宙ができる前はどうなっていたのか」を知っているだろうか? 実は「宇宙は”無”から誕生した」と考えられているのだ。『宇宙が始まる前には何があったのか?』をベースに、ビッグバンが起こる前の「空間も時間も物理法則も存在しない無」について学ぶ
無理数という、彼らのそもそもの数認識では到達不可能な数の世界が現実に広がっている以上、数のとりあつかいには極めて慎重にならざるを得なかった。いい加減なことをやっていると間違いをしでかすことになりかねない。このような心理的警戒感が、恐らく紀元前五世紀頃からのギリシャ数学には蔓延し始めていたのではないだろうか。そしてそのために、彼らは「見る」ことによる直感的な議論で物事を考えるよりも、ピタゴラス学派がやったように「見る」ことをできるだけ排除して演繹的に、そして儀式的に議論を進めるほうが<正しさ>を留保するためのより確実な方法と感じたのだ、と推察されるのである
このようにして、「通約不可能性の発見」は、古代ギリシャにおいて「目に見えるものはまやかしだ」という感覚をもたらすことになった。そして「見る以外の方法で正しさを示すこと(=証明)」を模索するようになり、やがてそれは「天上世界とアクセスするための儀式」と捉えられるようになっていく(いずれにせよ、宗教的な感覚は抜けなかったようだ)。
これが、ギリシャ人が「証明」へと向かっていった最初の動機である。ここから古代ギリシャの数学は、他の地域では生まれなかった「証明」という手法を用いて、「計算」を重視しない特異な方向に発展していくことになる。
あわせて読みたい
【未知】タコに「高度な脳」があるなんて初耳だ。人類とは違う進化を遂げた頭足類の「意識」とは?:『…
タコなどの頭足類は、無脊椎動物で唯一「脳」を進化させた。まったく違う進化を辿りながら「タコに心を感じる」という著者は、「タコは地球外生命体に最も近い存在」と書く。『タコの心身問題』から、腕にも脳があるタコの進化の歴史と、「意識のあり方」を知る。
「背理法」という”おかしな”証明方法
その後ギリシャ人は、「背理法」という証明を生み出すことになる。
文系の人はあまり触れるきっかけがなかったかもしれないが、理系の人間であれば間違いなく学生時代に多用した証明法だろう。しかしこの背理法、「よくもまあこんなやり方を思いついたものだ」と感じるほど、物凄く”おかしな”証明なのだ。

あわせて読みたい
【興奮】素数の謎に迫った天才数学者たちの奮闘と、数学の”聖杯”である「リーマン予想」について:『素…
古今東西の数学者を惹きつけて止まない「素数」。その規則性を見つけ出すことは非常に困難だったが、「リーマン予想」として初めてそれが示された。『素数の音楽』『リーマン博士の大予想』から、天才数学者たちが挑んできた「リーマン予想」をざっくり理解する
例えばどんな風に使われるのか。「背理法」の証明として非常に有名な、「最大の素数は存在しない」という命題で説明しよう。
今あなたが、「最大の素数は存在しない」、つまり、「『これが最も大きな素数だ』と言える素数は存在しない」ということを示さなければならないとしたら、どうすればいいだろうか? これはなかなか難しいだろう。何から手をつけたらいいかよく分からないはずだ。
そこで「背理法」の出番である。「背理法」ではまず、「最大の素数は存在しない」という命題の「逆」(正確な表現は「対偶」)を考える。つまり、「最大の素数は存在する」と仮定するのだ。そして、
「最大の素数は存在する」と仮定して議論を進めることで、議論に矛盾が生じること
を示す。これによって、
あわせて読みたい
【使命】「CRISPR-Cas9」を分かりやすく説明。ノーベル賞受賞の著者による発見物語とその使命:『CRISPR…
生物学の研究を一変させることになった遺伝子編集技術「CRISPR-Cas9」の開発者は、そんな発明をするつもりなどまったくなかった。ノーベル化学賞を受賞した著者による『CRISPR (クリスパー) 究極の遺伝子編集技術の発見』をベースに、その発見物語を知る
矛盾が生じたのは、最初の仮定が誤っていたからだ。つまり、「最大の素数は存在する」という仮定が間違っているということであり、これによって「最大の素数は存在しない」という結論に達する
と主張する。
これが「背理法」の仕組みである。
この「背理法」は非常に便利であり、「背理法」を使わなければ証明できない命題も多い。しかしよくよく考えてみると、なぜこんな奇妙な証明を思いついたのだろう、とも感じる。
あわせて読みたい
【要約】福岡伸一『生物と無生物のあいだ』は、「生命とは何か」を「動的平衡」によって定義する入門書…
「生命とは何か?」という、あまりに基本的だと感じられる問いは、実はなかなか難しい。20世紀生物学は「DNAの自己複製」が本質と考えたが、「ウイルス」の発見により再考を迫られた。福岡伸一の『生物と無生物のあいだ』『動的平衡』の2著作から、「生命の本質」を知る
実はこの「背理法」誕生の背景には、「通約不可能性」と並んで古代ギリシャ人を怯えさせた「無限」の存在があるのだ。
古代ギリシャ人は「無限」を回避したかった
「ゼノンのパラドックス」という名前を耳にしたことはあるだろう。いくつか種類があり、一番有名なのが「カメとアルキメデスの競争」だが、「矢の逆理」と呼ばれるものもある。まずこれについて説明していこう。

ゼノンは「矢の逆理」というパラドックスにおいて、「飛んでいる矢は止まっている」ということを示した。ゼノンの主張はこうだ。飛んでいる矢は、瞬間瞬間で切り取れば静止している。飛んでいる矢を写真に撮れば、すべての矢は止まっているだろう。どの瞬間で切り取っても矢は止まっているのだから、つまり「飛んでいる矢は止まっている」ということになる。
あわせて読みたい
【新視点】世界の歴史を「化学」で語る?デンプン・砂糖・ニコチンなどの「炭素化合物」が人類を動かし…
デンプン・砂糖・ニコチンなどは、地球上で非常に稀少な元素である「炭素」から作られる「炭素化合物」だ。そんな「炭素化合物」がどんな影響を与えたかという観点から世界の歴史を描く『「元素の王者」が歴史を動かす』は、学校の授業とはまったく違う視点で「歴史」を捉える
これはとてもおかしな結論だ。しかし上述の結論は実は、「空間と時間は無限に分割できる」ことを前提にしている。もしかしたら、この前提がおかしいのかもしれない。
それでは、「空間と時間は無限には分割できない(それ以上分割することはできない<単位>から成り立っている)」と考えた場合はどうなるだろうか?
ゼノンはこの点に関して「競技場の逆理」というパラドックスで示している。説明が煩雑になるのでここでは省略するが、「空間と時間は無限には分割できない」ことを前提にしても、やはりおかしな状況に陥ってしまうのである。
あわせて読みたい
【論争】サイモン・シンが宇宙を語る。古代ギリシャからビッグバンモデルの誕生までの歴史を網羅:『宇…
古代から現代に至るまで、「宇宙」は様々な捉えられ方をしてきた。そして、新たな発見がなされる度に、「宇宙」は常識から外れた不可思議な姿を垣間見せることになる。サイモン・シン『宇宙創成』をベースに、「ビッグバンモデル」に至るまでの「宇宙観」の変遷を知る
つまりこういうことだ。「空間と時間は無限に分割できる」ことを前提にした「矢の逆理」も、「空間と時間は無限には分割できない」ことを前提にした「競技場の逆理」も、共にパラドキシカルな状況に陥ってしまう。「矢の逆理」も「競技場の逆理」も共に「運動」に関する話であり、つまり、「空間と時間を無限に分割できるとしても、無限には分割できないとしても、運動は不可能である」という結論になってしまう。
しかし我々は、「運動」がきちんと行われていることを知っている。であれば、議論の中におかしな点がある、ということになる。
そして古代ギリシャ人は、「『無限』なんてものについて考えるからおかしなことになるのだ」と結論するようになったのだという。
このようにして彼らは、パラドックスに陥らないために、「無限」をいかに回避するかという発想をするようになっていく。
あわせて読みたい
【挑戦】社会に欠かせない「暗号」はどう発展してきたか?サイモン・シンが、古代から量子暗号まで語る…
「暗号」は、ミステリやスパイの世界だけの話ではなく、インターネットなどのセキュリティで大活躍している、我々の生活に欠かせない存在だ。サイモン・シン『暗号解読』から、言語学から数学へとシフトした暗号の変遷と、「鍵配送問題」を解決した「公開鍵暗号」の仕組みを理解する
「無限の回避」から生まれた「取り尽くし法」
さてここで、有名なアルキメデスが登場する。彼は、「円の面積」を求める公式を導き出したのだが、その公式を考える過程で「取り尽くし法」というアイデアを生み出した。
「円の面積」については、普通は、「無限に分割したものを足し合わせる」という考えをするしかない。しかし「無限」を回避したかったギリシャ人は、「無限に分割する」というステップをどうにかして行わずに「円の面積」を計算したかった。そこでアルキメデスが生み出したのが「取り尽くし法」なのである。
「取り尽くし法」そのものの説明はここではしないが、「取り尽くし法」の非常に重要なポイントには触れておこう。それは、「与えられたどんな量よりも小さくできる」という考え方だ。
あわせて読みたい
【驚嘆】「現在は森でキノコ狩り」と噂の天才”変人”数学者グリゴリー・ペレルマンの「ポアンカレ予想証…
数学界の超難問ポアンカレ予想を解決したが、100万ドルの賞金を断り、フィールズ賞(ノーベル賞級の栄誉)も辞退、現在は「森できのこ採取」と噂の天才数学者グリゴリー・ペレルマンの生涯を描く評伝『完全なる証明』。数学に関する記述はほぼなく、ソ連で生まれ育った1人の「ギフテッド」の苦悩に満ちた人生を丁寧に描き出す1冊
何かを分割することを考えよう。「分割を繰り返す」と1つの領域はだんだん小さくなっていく。そして、「1つの領域の大きさが0になるまで分割する」のが「無限回の分割」である。しかしアルキメデスはこの「無限回の分割」を回避したい。さて、どうすればいいだろうか?
「無限回の分割」は「1つの領域の大きさを0」にするのだから、「1つの領域は限りなく小さいが0ではない」とすれば無限を扱わずに済みそうだ。そうやって、「与えられたどんな量よりも小さくできる」という発想に行き着くのである。
これをもう少し具体的に説明してみよう。

あわせて読みたい
【研究】光の量子コンピュータの最前線。量子テレポーテーションを実現させた科学者の最先端の挑戦:『…
世界中がその開発にしのぎを削る「量子コンピューター」は、技術的制約がかなり高い。世界で初めて「量子テレポーテーション」の実験を成功させた研究者の著書『光の量子コンピューター』をベースに、量子コンピューター開発の現状を知る
今1kgの砂があるとする。そしてこの砂を半分ずつ取り除いていくことを考えよう。取る量は、500g、250g、125g……と半分ずつになっていくというわけだ。この作業をしばらく繰り返していけば、いずれ取る量が「1g」を下回るだろう。
そしてここで重要なことは、「1g」を下回るまでに砂を取り去る回数は「有限回」だということだ。これは「1g」でなくても同じだ。「0.01g」でも「0.00000000000001g」でもいい、「与えられた量」がどんな数であっても、必ず「有限回の操作」でその量を下回ることができる。
これが「取り尽くし法」の肝となる考え方であり、「無限」を回避するためにアルキメデスが編み出した手法である。
あわせて読みたい
【バトル】量子力学の歴史はこの1冊で。先駆者プランクから批判者アインシュタインまですべて描く:『量…
20世紀に生まれた量子論は、時代を彩る天才科学者たちの侃々諤々の議論から生み出された。アインシュタインは生涯量子論に反対し続けたことで知られているが、しかし彼の批判によって新たな知見も生まれた。『量子革命』から、量子論誕生の歴史を知る
そしてこの「取り尽くし法」において重要な要素として使われているのが「背理法」なのである。つまり、「無限」を回避するために「背理法」が生まれた、と言っていいだろう。
このように古代ギリシャでは、「通約不可能性」と「無限」に恐怖したが故に「証明」やその一種である「背理法」が生まれたのである。
「微分積分」は「取り尽くし法」と発想は同じ
ここまでで、「証明」というプロセスがいかに生まれたのかを概観してきたが、ここからは「数学の『正しさ』」の話に移ろう。
あわせて読みたい
【平易】一般相対性理論を簡単に知りたい方へ。ブラックホール・膨張宇宙・重力波と盛りだくさんの1冊:…
現役の研究者が執筆した『ブラックホール・膨張宇宙・重力波』は、アインシュタインが導き出した一般相対性理論が関わる3つのテーマについて、初心者にも分かりやすく伝える内容になっている。歴史的背景も含めて科学的知見を知りたい方にオススメの1冊
まずは、17世紀に誕生した「微分積分」の話からだ。学生時代、苦労したという方も多いだろう。「微分積分」というのはは、ざっくり説明すると「無限に分割したものを足し合わせる」という手法のことである。
微分積分は、「正しさを示す」という意味で革命的な発明だ。ここまでの説明で触れたように、古代ギリシャでは「計算よりも証明が重視され、証明しなければ正しさが保証できない」と考えられていた。しかし微分積分は「計算」の手法であり、「計算」によって「正しさ」を示すことが可能なアプローチとして受け入れられていく。。
しかし一方で、やはり「無限」の問題は残る。古代ギリシャ人が嫌った「無限」は、17世紀においても同様の受け取られ方をされており、「微分積分で正しい計算ができる。しかし『無限に分割したものを足し合わせる』などはオカルトのようなものだ」と捉えられていたというのだ。微分積分は確かに正しい結果を導くが、論理的な基盤が脆弱であり、完全にはしきれなかったのである。
あわせて読みたい
【天才】科学者とは思えないほど面白い逸話ばかりのファインマンは、一体どんな業績を残したのか?:『…
数々の面白エピソードで知られるファインマンの「科学者としての業績」を初めて網羅したと言われる一般書『ファインマンさんの流儀』をベースに、その独特の研究手法がもたらした様々な分野への間接的な貢献と、「ファインマン・ダイアグラム」の衝撃を理解する

そこで微分積分にきちんとした土台を与えようと動きが出てくるようになり、やがて「イプシロン―デルタ法」と呼ばれる考え方によってきちんとした基盤が作られることになる。
さてこれで一安心、と考えるのはまだ早い。というのは、この「イプシロン―デルタ法」は、アルキメデスが考えた「取り尽くし法」と、基本的に同じ内容だからだ。
つまりこういうことである。アルキメデスは「無限を回避するため」に「取り尽くし法」を生み出した。しかし後の数学者は、「無限を扱う微分積分に論理的な基盤を与えるため」に「イプシロン―デルタ法」を使っているのだ。無限を回避するための手法と無限を扱うための手法が同じ、というのは、何かおかしいと感じられる。
あわせて読みたい
【到達】「ヒッグス粒子の発見」はなぜ大ニュースなのか?素粒子物理学の「標準模型」を易しく説明する…
「ヒッグス粒子の発見」はメディアでも大きく取り上げられたが、これが何故重要なのかを説明できる人はそう多くはないだろう。『強い力と弱い力 ヒッグス粒子が宇宙にかけた魔法を解く』をベースに、謎めいた「弱い力」を説明する「自発的対称性の破れ」を学ぶ
このような問題を提示した上で、著者は「数学における『正しさ』」の話を展開していく。
数学において「正しい」とはどういうことか?
著者はここから、「正しい」という意味の捉えられ方の変化について触れていくことになる。
まず、古代ギリシャにおける「正しさ」について触れていこう。「万物は数である」という思想からも分かるように、この当時の「正しさ」というのは「絶対的な正しさ」のことだった。これは要するに、私たちが「正しい」という言葉を思い浮かべる時にパッとイメージするものだと考えていい。「いつどんな場合でも間違いなく正しい」という意味で「正しい」という言葉を使っている。
あわせて読みたい
【奇妙】大栗博司『重力とはなにか』は、相対性理論や量子力学の説明も秀逸だが、超弦理論の話が一番面白い
『重力とはなにか』(大栗博司)は、科学に馴染みの薄い人でもチャレンジできる易しい入門書だ。相対性理論や量子力学、あるいは超弦理論など、非常に難解な分野を基本的なところから平易に説明してくれるので、「科学に興味はあるけど難しいのはちょっと……」という方にこそ読んでほしい1冊
そして「絶対的な正しさ」を追い求めていたからこそ、彼らにとって「無限」は非常に厄介な存在だった。「絶対的に正しい」と主張する際、「無限」のような、自分たちで上手く処理できないものを扱わなければならないのはマズい。だからこそ「無限」を回避し、「絶対的な正しさ」を追い求められるようにした。
しかし現代数学における「正しさ」は少し異なる。それは、「ある条件の下では正しい」という「科学的精神」と関係している。
科学には、「一般相対性理論」と「量子力学」という非常に重要な2つの理論が存在し、使われる領域が明確に異なっている。「一般相対性理論」は天体など非常に大きなものに、そして「量子力学」は原子など非常に小さなものに適用されるのだ。「一般相対性理論」を原子に当てはめても上手くいかないし、逆も同じだ。
あわせて読みたい
【未知】「占い」が占い以外の効果を有するように、UFOなど「信じたいものを信じる」行為の機能を知れる…
「占い」に「見透かされたから仕方なく話す」という効用があるように、「『未知のもの』を信じる行為」には「『否定されたという状態』に絶対に達しない」という利点が存在する。映画『虚空門GATE』は、UFOを入り口に「『未知のもの』を信じる行為」そのものを切り取る
科学の究極の目標は、唯一の理論ですべての現象を説明することである。しかしそこに到達するまでは、「あるモデルを想定し、そのモデルの範囲内で正しいかどうかを判定する」という手法を取っているというわけだ。
そして、現代数学も同じだと著者は言う。「微分積分」はどんな場合でも絶対的に正しいのではなく、「イプシロン―デルタ法」という枠組みの中では正しいと言える、という主張である。

このように本書では、「数学」は「絶対的な正しさ」を追い求めることから、「決まった範囲内で正しさ」を追究する学問へと変化していった、ということが示されるのだ。
あわせて読みたい
【興奮】世界的大ベストセラー『サピエンス全史』要約。人類が文明を築き上げるに至った3つの革命とは?
言わずと知れた大ベストセラー『サピエンス全史』は、「何故サピエンスだけが人類の中で生き残り、他の生物が成し得なかった歴史を歩んだのか」を、「認知革命」「農業革命」「科学革命」の3つを主軸としながら解き明かす、知的興奮に満ち溢れた1冊
著:加藤 文元
¥1,870 (2022/01/29 21:47時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品読了済】私が読んできたノンフィクション・教養書を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が読んできたノンフィクションを様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本選びの参考にして下さい。
最後に
あわせて読みたい
【驚異】数学の「無限」は面白い。アキレスと亀の矛盾、実無限と可能無限の違い、カントールの対角線論…
日常の中で「無限」について考える機会などなかなか無いだろうが、野矢茂樹『無限論の教室』は、「無限には種類がある」と示すメチャクチャ興味深い作品だった。「実無限」と「可能無限」の違い、「可能無限」派が「カントールの対角線論法」を拒絶する理由など、面白い話題が満載の1冊
数学は好きだが決して詳しいわけではない私は、「数学はどんな場合でも正しい」という「絶対的な正しさ」で捉えていた。しかし本書を読んで、決してそういうわけではないということが理解できた。
数学が「モデルによる正しさ」を目指しているということは、数学という学問には、「設定されたモデルを信じるかどうか」という人間の判断が入り込む余地がある、ということになる。
あわせて読みたい
【感想】飲茶の超面白い東洋哲学入門書。「本書を読んでも東洋哲学は分からない」と言う著者は何を語る…
東洋哲学というのは、「最終回しか存在しない連続ドラマ」のようなものだそうだ。西洋哲学と比較にならないほど異質さと、インド哲学・中国哲学など個別の思想を恐ろしく分かりやすく描く『史上最強の哲学入門 東洋の哲人たち』は、ページをめくる手が止まらないくらい、史上最強レベルに面白かった
実際、本書で書かれている例ではないが、「カントールの対角線論法を信じない」と記述されている本を読んで驚いたことがある。「実無限」と「可能無限」という、「無限」をどう捉えるかの異なる「モデル」が存在し、どちらを信じるかによって「正しさ」が変化してしまう、というわけなのだ。
数学の見方が変わる一冊だと言える。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【奇妙】大栗博司『重力とはなにか』は、相対性理論や量子力学の説明も秀逸だが、超弦理論の話が一番面白い
『重力とはなにか』(大栗博司)は、科学に馴染みの薄い人でもチャレンジできる易しい入門書だ。相対性理論や量子力学、あるいは超弦理論など、非常に難解な分野を基本的なところから平易に説明してくれるので、「科学に興味はあるけど難しいのはちょっと……」という方にこそ読んでほしい1冊
あわせて読みたい
【驚嘆】「現在は森でキノコ狩り」と噂の天才”変人”数学者グリゴリー・ペレルマンの「ポアンカレ予想証…
数学界の超難問ポアンカレ予想を解決したが、100万ドルの賞金を断り、フィールズ賞(ノーベル賞級の栄誉)も辞退、現在は「森できのこ採取」と噂の天才数学者グリゴリー・ペレルマンの生涯を描く評伝『完全なる証明』。数学に関する記述はほぼなく、ソ連で生まれ育った1人の「ギフテッド」の苦悩に満ちた人生を丁寧に描き出す1冊
あわせて読みたい
【驚異】数学の「無限」は面白い。アキレスと亀の矛盾、実無限と可能無限の違い、カントールの対角線論…
日常の中で「無限」について考える機会などなかなか無いだろうが、野矢茂樹『無限論の教室』は、「無限には種類がある」と示すメチャクチャ興味深い作品だった。「実無限」と「可能無限」の違い、「可能無限」派が「カントールの対角線論法」を拒絶する理由など、面白い話題が満載の1冊
あわせて読みたい
【挑戦】相対性理論の光速度不変の原理を無視した主張『光速より速い光』は、青木薫訳だから安心だぞ
『光速より速い光』というタイトルを見て「トンデモ本」だと感じた方、安心してほしい。「光速変動理論(VSL理論)」が正しいかどうかはともかくとして、本書は実に真っ当な作品だ。「ビッグバン理論」の欠陥を「インフレーション理論」以外の理屈で補う挑戦的な仮説とは?
あわせて読みたい
【未知】「占い」が占い以外の効果を有するように、UFOなど「信じたいものを信じる」行為の機能を知れる…
「占い」に「見透かされたから仕方なく話す」という効用があるように、「『未知のもの』を信じる行為」には「『否定されたという状態』に絶対に達しない」という利点が存在する。映画『虚空門GATE』は、UFOを入り口に「『未知のもの』を信じる行為」そのものを切り取る
あわせて読みたい
【奇人】天才数学者で、自宅を持たずに世界中を放浪した変人エルデシュは、迷惑な存在でも愛され続けた…
数学史上ガウスに次いで生涯発表論文数が多い天才エルデシュをご存知だろうか?数学者としてずば抜けた才能を発揮したが、それ以上に「奇人変人」としても知られる人物だ。『放浪の天才数学者エルデシュ』で、世界中の数学者の家を泊まり歩いた異端数学者の生涯を描き出す
あわせて読みたい
【新視点】世界の歴史を「化学」で語る?デンプン・砂糖・ニコチンなどの「炭素化合物」が人類を動かし…
デンプン・砂糖・ニコチンなどは、地球上で非常に稀少な元素である「炭素」から作られる「炭素化合物」だ。そんな「炭素化合物」がどんな影響を与えたかという観点から世界の歴史を描く『「元素の王者」が歴史を動かす』は、学校の授業とはまったく違う視点で「歴史」を捉える
あわせて読みたい
【思考】『翔太と猫のインサイトの夏休み』は、中学生と猫の対話から「自分の頭で考える」を学べる良書
「中学生の翔太」と「猫のインサイト」が「答えの出ない問い」について対話する『翔太と猫のインサイトの夏休み』は、「哲学」の違う側面を見せてくれる。過去の哲学者・思想家の考えを知ることが「哲学」なのではなく、「自分の頭で考えること」こそ「哲学」の本質だと理解する
あわせて読みたい
【実話】映画『イミテーションゲーム』が描くエニグマ解読のドラマと悲劇、天才チューリングの不遇の死
映画『イミテーションゲーム』が描く衝撃の実話。「解読不可能」とまで言われた最強の暗号機エニグマを打ち破ったのはなんと、コンピューターの基本原理を生み出した天才数学者アラン・チューリングだった。暗号解読を実現させた驚きのプロセスと、1400万人以上を救ったとされながら偏見により自殺した不遇の人生を知る
あわせて読みたい
【本質】子どもの頃には読めない哲学書。「他人の哲学はつまらない」と語る著者が説く「問うこと」の大…
『<子ども>のための哲学』は決して、「子どもでも易しく理解できる哲学の入門書」ではない。むしろかなり難易度が高いと言っていい。著者の永井均が、子どもの頃から囚われ続けている2つの大きな疑問をベースに、「『哲学する』とはどういうことか?」を深堀りする作品
あわせて読みたい
【最新】「コロンブス到達以前のアメリカ大陸」をリアルに描く歴史書。我々も米国人も大いに誤解してい…
サイエンスライターである著者は、「コロンブス到着以前のアメリカはどんな世界だったか?」という問いに触れ、その答えが書かれた本がいつまで経っても出版されないので自分で執筆した。『1491 先コロンブス期アメリカ大陸をめぐる新発見』には、アメリカ人も知らない歴史が満載だ
あわせて読みたい
【異端】「仏教とは?」を簡単に知りたい方へ。ブッダは「異性と目も合わせないニートになれ」と主張し…
我々が馴染み深い「仏教」は「大乗仏教」であり、創始者ゴータマ・ブッダの主張が詰まった「小乗仏教」とは似て非なるものだそうだ。『講義ライブ だから仏教は面白い!』では、そんな「小乗仏教」の主張を「異性と目も合わせないニートになれ」とシンプルに要約して説明する
あわせて読みたい
【感想】池田晶子『14歳からの哲学』で思考・自由・孤独の大事さを知る。孤独を感じることって大事だ
「元々持ってた価値観とは違う考えに触れ、それを理解したいと思う場面」でしか「考える」という行為は発動しないと著者は言う。つまり我々は普段、まったく考えていないのだ。『14歳からの哲学』をベースに、「考えること」と自由・孤独・人生との関係を知る
あわせて読みたい
【興奮】世界的大ベストセラー『サピエンス全史』要約。人類が文明を築き上げるに至った3つの革命とは?
言わずと知れた大ベストセラー『サピエンス全史』は、「何故サピエンスだけが人類の中で生き残り、他の生物が成し得なかった歴史を歩んだのか」を、「認知革命」「農業革命」「科学革命」の3つを主軸としながら解き明かす、知的興奮に満ち溢れた1冊
あわせて読みたい
【知的】文系にオススメの、科学・数学・哲学の入門書。高橋昌一郎の「限界シリーズ」は超絶面白い:『…
例えば「科学」だけに限ってみても、「なんでもできる」わけでは決してない。「科学」に限らず、私たちが対峙する様々な事柄には「これ以上は不可能・無理」という「限界」が必ず存在する。高橋昌一郎の「限界シリーズ」から、我々が認識しておくべき「限界」を易しく学ぶ
あわせて読みたい
【感想】飲茶の超面白い東洋哲学入門書。「本書を読んでも東洋哲学は分からない」と言う著者は何を語る…
東洋哲学というのは、「最終回しか存在しない連続ドラマ」のようなものだそうだ。西洋哲学と比較にならないほど異質さと、インド哲学・中国哲学など個別の思想を恐ろしく分かりやすく描く『史上最強の哲学入門 東洋の哲人たち』は、ページをめくる手が止まらないくらい、史上最強レベルに面白かった
あわせて読みたい
【興奮】飲茶氏の超面白い哲学小説。「正義とは?」の意味を問う”3人の女子高生”の主張とは?:『正義の…
なんて面白いんだろうか。哲学・科学を初心者にも分かりやすく伝える飲茶氏による『正義の教室』は、哲学書でありながら、3人の女子高生が登場する小説でもある。「直観主義」「功利主義」「自由主義」という「正義論」の主張を、「高校の問題について議論する生徒会の話し合い」から学ぶ
あわせて読みたい
【興奮】飲茶氏が西洋哲学を語る。難解な思想が「グラップラー刃牙成分」の追加で驚異的な面白さに:『…
名前は聞いたことはあるがカントやニーチェがどんな主張をしたのかは分からないという方は多いだろう。私も無知なまったくの初心者だが、そんな人でも超絶分かりやすく超絶面白く西洋哲学を”分かった気になれる”飲茶『史上最強の哲学入門』は、入門書として最強
あわせて読みたい
【驚愕】ロバート・キャパの「崩れ落ちる兵士」はどう解釈すべきか?沢木耕太郎が真相に迫る:『キャパ…
戦争写真として最も有名なロバート・キャパの「崩れ落ちる兵士」には、「本当に銃撃された瞬間を撮影したものか?」という真贋問題が長く議論されてきた。『キャパの十字架』は、そんな有名な謎に沢木耕太郎が挑み、予想だにしなかった結論を導き出すノンフィクション。「思いがけない解釈」に驚かされるだろう
あわせて読みたい
【限界】「科学とは何か?」を知るためのおすすめ本。科学が苦手な人こそ読んでほしい易しい1冊:『哲学…
「科学的に正しい」という言葉は、一体何を意味しているのだろう?科学者が「絶対に正しい」とか「100%間違っている」という言い方をしないのは何故だろう?飲茶『哲学的な何か、あと科学とか』から、「科学とはどんな営みなのか?」について考える
あわせて読みたい
【逸話】天才数学者ガロアが20歳で決闘で命を落とすまでの波乱万丈。時代を先駆けた男がもし生きていた…
現代数学に不可欠な「群論」をたった1人で生み出し、20歳という若さで決闘で亡くなったガロアは、その短い生涯をどう生きたのか?『ガロア 天才数学者の生涯』から、数学に関心を抱くようになったきっかけや信じられないほどの不運が彼の人生をどう変えてしまったのか、そして「もし生きていたらどうなっていたのか」を知る
あわせて読みたい
【証明】結城浩「数学ガール」とサイモン・シンから「フェルマーの最終定理」とそのドラマを学ぶ
350年以上前に一人の数学者が遺した予想であり「フェルマーの最終定理」には、1995年にワイルズによって証明されるまでの間に、これでもかというほどのドラマが詰め込まれている。サイモン・シンの著作と「数学ガール」シリーズから、その人間ドラマと数学的側面を知る
あわせて読みたい
【衝撃】ABC予想の証明のために生まれたIUT理論を、提唱者・望月新一の盟友が分かりやすく語る:『宇宙…
8年のチェック期間を経て雑誌に掲載された「IUT理論(宇宙際タイヒミュラー理論)」は、数学の最重要未解決問題である「ABC予想」を証明するものとして大いに話題になった。『宇宙と宇宙をつなぐ数学』『abc予想入門』をベースに、「IUT理論」「ABC予想」について学ぶ
あわせて読みたい
【刺激】結城浩「数学ガール」で、ゲーデルの不完全性定理(不可能性の証明として有名)を学ぶ
『結城浩「数学ガール」シリーズは、数学の面白さを伝えながら、かなり高難度の話題へと展開していく一般向けの数学書です。その第3弾のテーマは、「ゲーデルの不完全性定理」。ヒルベルトという数学者の野望を打ち砕いた若き天才の理論を学びます
あわせて読みたい
【興奮】結城浩「数学ガール」で、決闘で命を落とした若き天才数学者・ガロアの理論を学ぶ
高校生を中心に、数学を通じて関わり合う者たちを描く「数学ガール」シリーズ第5弾のテーマは「ガロア理論」。独力で「群論」という新たな領域を切り開きながら、先駆的すぎて同時代の数学者には理解されず、その後決闘で死亡した天才の遺した思考を追う
あわせて読みたい
【対立】数学はなぜ”美しい”のか?数学は「発見」か「発明」かの議論から、その奥深さを知る:『神は数…
数学界には、「数学は神が作った派」と「数学は人間が作った派」が存在する。『神は数学者か?』をベースに、「数学は発見か、発明か」という議論を理解し、数学史においてそれぞれの認識がどのような転換点によって変わっていったのかを学ぶ
あわせて読みたい
【興奮】素数の謎に迫った天才数学者たちの奮闘と、数学の”聖杯”である「リーマン予想」について:『素…
古今東西の数学者を惹きつけて止まない「素数」。その規則性を見つけ出すことは非常に困難だったが、「リーマン予想」として初めてそれが示された。『素数の音楽』『リーマン博士の大予想』から、天才数学者たちが挑んできた「リーマン予想」をざっくり理解する
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
科学・数学の知識を身につける【本・映画の感想】 | ルシルナ
中退していますが、理系の大学に通っていました。学校の勉強で一番好きだったのは数学・物理ですし、大人になってからも科学や数学の本を数多く読んできました。偉人たちの…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…




















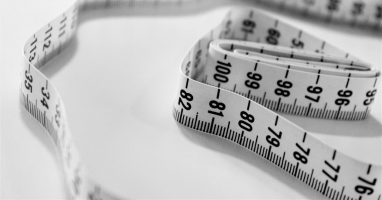








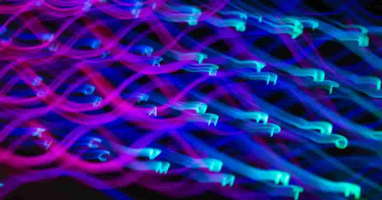




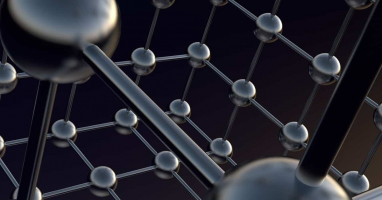


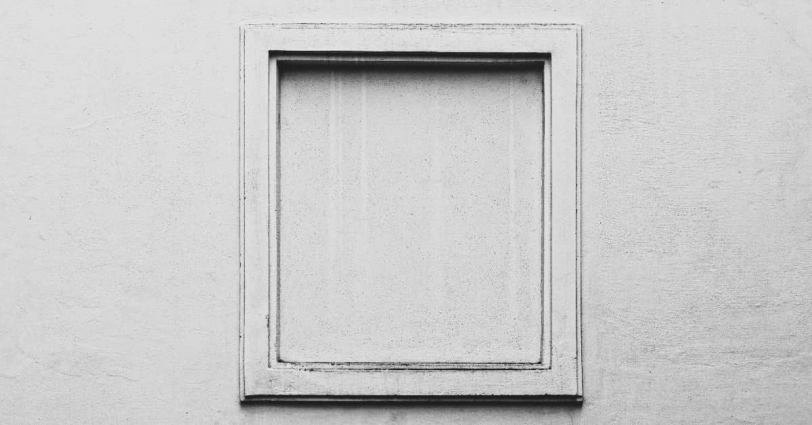






























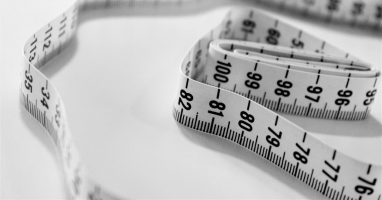



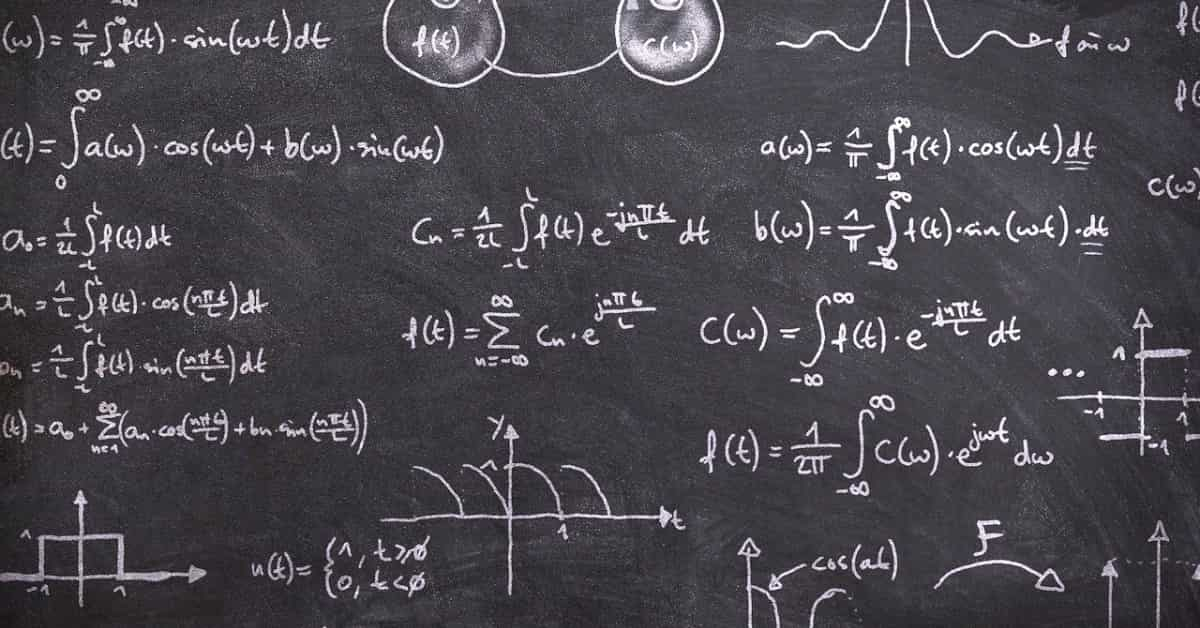





コメント