目次
はじめに
この記事で取り上げる本
著:大栗 博司
¥968 (2024/07/13 18:42時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
この本をガイドにしながら記事を書いていきます
この記事の3つの要点
- 科学に関する本を結構読んでいる私は、本書の記述の大半を元々知っていた。つまり「その分野の基本情報を的確に押さえている」と言えるだろうと思う
- 量子力学も超弦理論もとても難しいのだが、現役の研究者が「高校時代の同級生に説明する」ことを想定して書いているので、とても分かりやすい
- 「机上の空論」と批判されることもある「超弦理論」の来歴と、著者が関わったブラックホールに関する難問について
最先端の学問分野は大体難しいものだが、本書のような入門書がその理解のハードルを少しは下げてくれていると思う
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
大栗博司『重力とはなにか』は、相対性理論・量子力学の説明も分かりやすいが、やはり専門である超弦理論の話が抜群に面白い1冊
本作『重力とはなにか』の著者である大栗博司の著作については、当ブログ内にも『大栗先生の超弦理論入門』の記事がある。科学の話が好きな私にはとても面白い作品だったが、一般書としてはかなり難しい部類に入るだろう。タイトルにもある「超弦理論」は、大栗博司の専門分野であるかなり最先端の理論物理学であり、スパッと理解できるような話ではない。
あわせて読みたい
【幻想】超ひも理論って何?一般相対性理論と量子力学を繋ぐかもしれないぶっ飛んだ仮説:『大栗先生の…
『大栗先生の超弦理論入門』は最先端科学である「超弦理論」を説明する1冊だが、この記事では著者の主張の1つである「空間は幻想かもしれない」という発想を主に取り上げる。「人類史上初の『適用する次元が限定される理論』」が描像する不可思議な世界とは?
そういう意味で言えば、本作『重力とはなにか』の方がかなり易しいと言えるだろう。「重力とはなにか」という問いは実はなかなか難しく、その説明のために相対性理論や量子力学の知識が必要になるのだが、著者はそれらについてもかなり平易な説明を行いながら、さらに自身の専門分野である超弦理論にも話を広げていくのである。相対性理論も量子力学も一筋縄ではいかない理論なのでもちろん簡単なわけではないが、科学に多少なりとも関心を持つ人であれば読み通せる本ではないかと思う。

さて、本書はかなり「基本的」な記述が多いため、正直なところ私は、内容の大半を知っていた。しかし、だからといって「つまらなかった」などと言いたいわけではない。「知っていること」と「理解していること」にはやはり大きな差があるからだ。大学では理系学部に所属してはいたものの、専門課程に進む前に中退したので、科学についてきちんと学んだことはない。あくまでも、一般書を読んで分かった気になっているだけだ。だから何度でも同じ内容を頭に入れ、どんどんと「理解」に近づきたいと思っている。
じゃあ何が言いたいのかというと、「私が元々知っていたことが多い」ということは、「各分野の『押さえておくべき基礎知識』がまとまっている」と考えていいのではないかということだ。「科学の興味深い話の入口」みたいな作品と言えると思うので、本作を読んだ上で、惹かれた分野についてさらに掘り下げていくみたいな感じもオススメである。
あわせて読みたい
【究極】リサ・ランドールが「重力が超弱い理由」を解説する、超刺激的なひも理論の仮説:『ワープする…
現役の研究者であるリサ・ランドールが、自身の仮説を一般向けに分かりやすく説明する『ワープする宇宙』。一般相対性理論・量子力学の知識を深く記述しつつ「重力が超弱い理由」を説明する、ひも理論から導かれる「ワープする余剰次元」について解説する
それでは内容に触れていくことにしよう。
量子力学は大変難しい
本作では、物理学における様々なジャンルの話が触れられているわけだが、その中でもやはり「量子力学」は群を抜いて難しいと私は思う。科学の話とは思えないようなインパクトのある主張が非常に多く、雑学として頭に取り込む分にはとても楽しい分野だと思うが、いざ真剣に理解しようとすると「マジで何言ってるわけ?」と混乱してしまうだろう。
当ブログでも、量子力学を扱った本をいくつか紹介している。とりあえず、2つだけリンクを貼っておこう。
あわせて読みたい
【バトル】量子力学の歴史はこの1冊で。先駆者プランクから批判者アインシュタインまですべて描く:『量…
20世紀に生まれた量子論は、時代を彩る天才科学者たちの侃々諤々の議論から生み出された。アインシュタインは生涯量子論に反対し続けたことで知られているが、しかし彼の批判によって新たな知見も生まれた。『量子革命』から、量子論誕生の歴史を知る
あわせて読みたい
【敗北】「もつれ」から量子論の基礎を学ぶ。それまでの科学では説明不能な「異次元の現象」とは?:『…
アインシュタインは量子力学を生涯受け入れなかったのだが、アインシュタインが批判し続けたことによって明らかになったこともある。「もつれ」の重要性もその一つだ。『宇宙は「もつれ」でできている』から量子力学の基礎を成す現象を知る。
この記事では量子力学そのものの説明はしないので、興味がある方は先の記事を読んでみてほしい。
さてしかし、「量子力学がいかに難しいのか」については触れておこうと思う。
まずは、ファインマンという物理学者の言葉から。彼については以下の記事で紹介しているが、様々な逸話を持つ天才物理学者で、一般的な知名度で言っても、アインシュタイン、ホーキング博士に次ぐぐらいの知名度があるように思う。また、量子力学に関する功績でノーベル賞も受賞しており、量子力学についてもかなり詳しい人物である。というか、あまりにも天才すぎて「専門分野が無い」と言われたぐらい、様々な領域で活躍した物理学者なのだ。
あわせて読みたい
【天才】科学者とは思えないほど面白い逸話ばかりのファインマンは、一体どんな業績を残したのか?:『…
数々の面白エピソードで知られるファインマンの「科学者としての業績」を初めて網羅したと言われる一般書『ファインマンさんの流儀』をベースに、その独特の研究手法がもたらした様々な分野への間接的な貢献と、「ファインマン・ダイアグラム」の衝撃を理解する
あわせて読みたい
【天才】『ご冗談でしょう、ファインマンさん』は、科学者のイメージが変わる逸話満載の非・科学エッセイ
「天才科学者」と言えばアインシュタインやニュートン、ホーキングが思い浮かぶだろうが、「科学者らしくないエピソード満載の天才科学者」という意味ではファインマンがずば抜けている。世界的大ベストセラー『ご冗談でしょう、ファインマンさん』は、「科学」をほぼ扱わないエッセイです
そんなファインマンは量子力学について、「『量子力学のことが分かっている』なんて奴に会ったら、そいつは嘘をついている」みたいなことを言ったそうである。つまり、「量子力学に関して誰もが認めるだけの素晴らしい功績がある人物」でさえ、「量子力学のことなんか分からない」と口にしているのだ。となれば、凡人に理解できるはずもないだろう。

さて、このような主張は本書『重力とはなにか』にも書かれている。作中に「反粒子」について説明する箇所があるのだが、その記述に先立って著者は、別の本から引用をしつつ次のように書いているのだ。
これは、カブリIPMUの村山斉機構長の著書『宇宙は何でできているか』(幻冬舎新書)に、
あまりまじめに考えると頭が混乱して気持ち悪くなるので(笑)、「そういうものか」とファジーに受け止めたほうがいいでしょう。私もあまりまじめに考えないことにしています。
と書いてある話です。
著:村山斉
¥418 (2024/07/15 18:59時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【論争】サイモン・シンが宇宙を語る。古代ギリシャからビッグバンモデルの誕生までの歴史を網羅:『宇…
古代から現代に至るまで、「宇宙」は様々な捉えられ方をしてきた。そして、新たな発見がなされる度に、「宇宙」は常識から外れた不可思議な姿を垣間見せることになる。サイモン・シン『宇宙創成』をベースに、「ビッグバンモデル」に至るまでの「宇宙観」の変遷を知る
「カブリIPMU」というのは大栗博司が所属する研究機関である。そしてそのトップである村山斉もまた、「まじめに考えると混乱する」と言っているのだ。
なので、本書に限る話ではないが、量子力学の知識に触れる際には、「天才だって全然分かってないんだから、自分ごときが理解できるはずがない」と思っておくぐらいでちょうどいいだろう。理解しようとさえしなければ、そのあまりに奇妙な世界に惹きつけられてしまうはずだ。是非入門書などに触れてみてほしいと思う。
著者の説明の分かりやすさと、科学啓蒙書の宿命について
あわせて読みたい
【限界】「科学とは何か?」を知るためのおすすめ本。科学が苦手な人こそ読んでほしい易しい1冊:『哲学…
「科学的に正しい」という言葉は、一体何を意味しているのだろう?科学者が「絶対に正しい」とか「100%間違っている」という言い方をしないのは何故だろう?飲茶『哲学的な何か、あと科学とか』から、「科学とはどんな営みなのか?」について考える
さて、量子力学は大変難しいわけだが、本書『重力とはなにか』の記述は、量子力学の説明に限らずとても易しいと感じた。その理由の一端については、あとがきで次のように触れられている。
本書を書くときに思い浮かべたのは、卒業以来会っていない高校の同級生でした。(中略)
久しぶりに会ったので、一緒に勉強をした高校の理科から話を初めます。しかし、説明を簡単にするためにごまかしをしてはいけない。大切だと思うことはきちんとわかってもらえるように、少しぐらい話が長くなっても丁寧に説明しました。
「もし高校の同級生に再会したら、自分の研究分野についてどう説明するか?」を頭に思い浮かべながら書いたというわけだ。もちろん、学問分野そのものがかなり難解なので、易しく説明するにも限界があるわけだが、その中でも著者は、相当に努力して理解しやすい説明をしてくれていると思う。サイエンスライターではなく現役の研究者が書いているのだから、内容もお墨付きと言っていいだろう。「重力」というテーマも非常に身近なものなので、「最先端の理論物理学」に触れるのに本書はかなり最適と言えるのではないかと思う。
あわせて読みたい
【神秘】脳研究者・池谷裕二が中高生向けに行った講義の書籍化。とても分かりやすく面白い:『進化しす…
「宇宙」「深海」「脳」が、人類最後のフロンティアと呼ばれている。それほど「脳」というのは、未だに分からないことだらけの不思議な器官だ。池谷裕二による中高生向けの講義を元にした『進化しすぎた脳』『単純な脳、複雑な「私」』をベースに、脳の謎を知る
また本書の場合、例を使った説明もとても上手い。例えば、「光電効果」。この現象は発見された当初、「どうしてこのようなことが起こるのか誰も説明できない」というほど奇妙なものだった。その後、この奇妙な現象の理屈を、かのアインシュタインが「光量子仮説」によって説明し解決に導いたのだが、その「光電効果」についての説明がとても上手いのだ。「囚人」と「100円玉」という身近なものを使って、かなり直感的に説明してくれるのである。私は「光電効果」についても色んな本で読んだことがあるのだが、本書のような説明を目にしたことはないので、恐らく著者のオリジナルではないかと思う。

このように、「馴染みのない人にもいかに分かりやすく説明するか」という点をかなり突き詰めていると感じるので、「科学に興味はあるけど、難しいのはちょっと……」という方にこそ手にとってもらいたいと思う。
さて、科学の一般書の宿命ではあるのだが、科学の世界では常に「新たな発見」や「理論の更新」が続くので、どうしても本の内容は古びていく。本書は著者初の一般向けの科学解説書であり、2012年に発売された。そして2012年以降も当然、新たな発見が相次いでいる。例えば本書では、「重力波」も「ヒッグス粒子」も共に未発見となっているのだが、本書発売後にどちらも発見された。このように、どうしても記述に「意図せぬ誤り」が混じることはある。
あわせて読みたい
【嫉妬?】ヒッグス粒子はいかに発見されたか?そして科学の”発見”はどう評価されるべきか?:『ヒッグ…
科学研究はもはや個人単位では行えず、大規模な「ビッグサイエンス」としてしか成立しなくなっている。そんな中で、科学研究の成果がどう評価されるべきかなどについて、「ヒッグス粒子」発見の舞台裏を追った『ヒッグス 宇宙の最果ての粒子』をベースに書く
ただ、「相対性理論や量子力学の理論自体に大きな変更が加えられた」みたいなことは今のところないはずなので、そういう理論についての説明はそのまま受け取っても大丈夫だろう。その辺りのことを意識しつつ読んでいただければと思う。
「超弦理論」とは何か、そしてその研究が進展してきた過程について
それではまず、「超弦理論」についてざっくりと説明しておこう。
あわせて読みたい
【謎】恐竜を絶滅させた隕石はどこから来た?暗黒物質が絡む、リサ・ランドールの驚愕の仮説:『ダーク…
「生物の絶滅」には、以前から知られていたある謎があった。そしてその謎を、未だに観測されておらず、「科学者の妄想の産物」でしかない「ダークマター(暗黒物質)」が解決するかもしれない。現役の科学者が『ダークマターと恐竜絶滅』で語る驚きの仮説。
そもそもだが、科学の世界には「弦理論」と呼ばれるものが存在していた。この理論を生み出したのが、天才として名高い南部陽一郎である。彼の基本的な発想は、シンプルではあるが異端的なものだった。素粒子を「点」ではなく「弦(ひも)」として捉えようというのである。
素粒子というのは、とりあえず「原子」のことだと思ってもらえればいい(実際は違うのだが、その方が分かりやすいだろう)。つまり「物質の最小単位」のことだ。また、「原子」については「球体みたいなもの」と教わったはずだし、それはつまり「『小さな点』みたいに扱える」ことを意味する。これが従来的な発想だ。
しかし「弦理論」では、物質の最小単位は「点」ではなく「輪ゴムのようなひも状のもの」と捉える。そして、「その『ひも状のもの』の振動の仕方によって様々な異なる性質が現れる」と考えるのだ。これが「弦理論」である。
あわせて読みたい
【挑戦】相対性理論の光速度不変の原理を無視した主張『光速より速い光』は、青木薫訳だから安心だぞ
『光速より速い光』というタイトルを見て「トンデモ本」だと感じた方、安心してほしい。「光速変動理論(VSL理論)」が正しいかどうかはともかくとして、本書は実に真っ当な作品だ。「ビッグバン理論」の欠陥を「インフレーション理論」以外の理屈で補う挑戦的な仮説とは?
さて、素粒子(実際には「原子」ではなく「クォーク」と呼ばれるもの)には「ボソン」と「フェルミオン」という2種類が存在するのだが、南部陽一郎が生み出した「弦理論」では、実は「ボソン」しか扱うことが出来なかった。しかしその後、「超対称性」と呼ばれるものを「弦理論」に組み込むことで、「フェルミオン」も扱えることが判明したのである。そのため、「超対称性」から「超」を取り、「超弦理論」と呼ばれるようになったというわけだ。
では南部陽一郎はそもそも、何故「弦理論」などというものを生み出したのだろうか。そこには当時の科学界の混乱が関係している。当時実験室では、毎週のように「新しい素粒子」が発見されていた。いや、この表現は適切ではない。実際には「素粒子」ではなかったのだが、当時は「素粒子」だと思われていたというわけだ。ともかく、実験室では日々「未発見の素粒子みたいなもの」が見つかっていた。そのため当時の理論家には、「それら『素粒子みたいなもの』をどうまとめるのか」の理論構築が求められていたのである。そしてその過程で南部陽一郎が辿り着いた可能性が「弦理論」だったというわけだ。
しかし実はその後、それら「素粒子みたいなもの」の存在は別の理論で説明がつくことが判明し、「弦理論」「超弦理論」は用済みになってしまった。この時点で「弦理論」は科学の歴史から消え去ってもおかしくなかっただろう。しかし、シュワルツという物理学者だけが超弦理論にこだわり続けた。その理由が「重力子の予言」である。シュワルツは、超弦理論が予言する「謎の粒子」が、「重力波の粒子(重力子)」の性質を持つことに気づいたのだ。これはつまり、「超弦理論には、理論内部に『重力』が含まれている」ことを意味する。そして科学界にとって、この事実は非常に重要だったのだ。
あわせて読みたい
【到達】「ヒッグス粒子の発見」はなぜ大ニュースなのか?素粒子物理学の「標準模型」を易しく説明する…
「ヒッグス粒子の発見」はメディアでも大きく取り上げられたが、これが何故重要なのかを説明できる人はそう多くはないだろう。『強い力と弱い力 ヒッグス粒子が宇宙にかけた魔法を解く』をベースに、謎めいた「弱い力」を説明する「自発的対称性の破れ」を学ぶ
当時の理論物理学者にとっての最大の課題は、「一般相対性理論と量子力学の融合」だった。アインシュタインが生み出した「相対性理論」には、重力を含まない「特殊相対性理論」と、重力を含む「一般相対性理論」が存在する。そして、「特殊相対性理論」と「量子力学」は早い段階で融合されていたのだが、「一般相対性理論」と「量子力学」はとにかく相性が悪かったのだ。「量子力学に重力を組み込む」というのがあまりに難題で、その解決が強く望まれていたのである。

そういう状況にあって、「理論内部に初めから重力が含まれている超弦理論」は、「一般相対性理論と量子力学の融合」にとって有用ではないかとシュワルツは考えたのだ。そのような理由から「研究を続ける価値がある」と判断、彼はほぼたった1人で超弦理論の研究を続ける決断をし、その後次々に画期的な発見を成し遂げていったのである。
さて、超弦理論には色々と難点が存在したのだが、その1つに「次元の問題」があった。我々が生きる世界は、空間と時間を合わせて「4次元」だが、超弦理論はなんと「10次元」でしか成り立たないのだ。「そんな理論に何か意味があるのだろうか」と感じてしまうだろう。
その一方で、以前から行われていた「量子力学を4次元以上の高次元空間で解く」というアプローチがなかなか上手くいかないという問題も存在した。「量子力学」と「高次元」はとにかく相性が悪かったのだ。しかし研究によって、超弦理論を考慮することで、高次元空間内でも量子力学を扱いやすくなることが分かってきた。その理由が、超弦理論の本質である「弦」にある。
あわせて読みたい
【証明】結城浩「数学ガール」とサイモン・シンから「フェルマーの最終定理」とそのドラマを学ぶ
350年以上前に一人の数学者が遺した予想であり「フェルマーの最終定理」には、1995年にワイルズによって証明されるまでの間に、これでもかというほどのドラマが詰め込まれている。サイモン・シンの著作と「数学ガール」シリーズから、その人間ドラマと数学的側面を知る
素粒子を「点」と捉える場合、「素粒子同士がくっついている(距離がゼロになる)」という状態が想定される。ブレイクショットをする前のビリヤードの球のようにピッタリとくっついている状態を想像してもらえばいいだろう。そして、「重力」は2者の距離(の2乗)に反比例するため、「距離ゼロ」の場合、重力が無限大になってしまうのだ。とにかく物理学においては「無限大」ほど厄介なものはなく、「無限大」が出てきてしまったらそれ以上議論が進まないのである。このため、「量子力学」と「重力」はすこぶる相性が悪いのだ。しかし素粒子を「弦」と捉えれば、「距離ゼロ」になることはない。そのため、無限大を回避できるのである。これは超弦理論の有用性を感じさせるポイントの1つとなった。
またシュワルツは、「パリティの破れ」を超弦理論に組み込むことにも成功している。「パリティの破れ」が何なのかは説明しないが、「『標準模型』に必要な要素の1つ」ぐらいに認識してほしい。「標準模型」というのは「素粒子を分類するための理論」であり、量子力学はこの「標準模型」を基礎としている。また、この理論によって南部陽一郎の「弦理論」が不要になった。さて、一般相対性理論と量子力学を融合させるにあたって、「『標準模型』に必要な要素を揃えきれない」という問題も存在していた。そしてシュワルツは、その要素の1つである「パリティの破れ」を超弦理論に組み込むことに成功したのである。これによって、超弦理論が「一般相対性理論と量子力学を融合させるための理論」である可能性が一層高まったというわけだ。
このような発見が続いたことで超弦理論は注目を集めるようになり、たった1人で研究していたシュワルツに続く者が多く現れるようになった。そしてその1人が、大学院生だった著者というわけだ。このように超弦理論は「奇跡の復活」とでも言うべき変遷を辿りながら、今も熱く研究が進められているのである。
あわせて読みたい
【要約】福岡伸一『生物と無生物のあいだ』は、「生命とは何か」を「動的平衡」によって定義する入門書…
「生命とは何か?」という、あまりに基本的だと感じられる問いは、実はなかなか難しい。20世紀生物学は「DNAの自己複製」が本質と考えたが、「ウイルス」の発見により再考を迫られた。福岡伸一の『生物と無生物のあいだ』『動的平衡』の2著作から、「生命の本質」を知る
ブラックホールの話、そして「超弦理論研究の難しさ」について
さて、著者は研究によって、「トポロジカルな弦理論」という「超弦理論における計算法則」のようなものを共同で発見したそうだ。それ自体はちゃんとは理解できなかったが、この話は本書の最後で触れられる「ブラックホールの情報問題」に繋がっていく。
「ブラックホールの情報問題」は、車椅子の天才物理学者ホーキング博士が提唱したものである。これも難しい話で、こちらについてもちゃんとは理解できていないのだが、要するに「ブラックホールは情報を保存出来るのか?」という問いであるようだ。
あわせて読みたい
【快挙】「暗黒の天体」ブラックホールはなぜ直接観測できたのか?国際プロジェクトの舞台裏:『アイン…
「世界中に存在する電波望遠鏡を同期させてブラックホールを撮影する」という壮大なEHTプロジェクトの裏側を記した『アインシュタインの影』から、ブラックホール撮影の困難さや、「ノーベル賞」が絡む巨大プロジェクトにおける泥臭い人間ドラマを知る
例えば、「本に火をつけて燃やす」ことを考えてみよう。この場合、「本に書かれた情報を復元する」ことは可能だろうか? もちろん、”現実的”には不可能だ。燃えたら灰になるだけで、それをどうこねくり回したところで、「本に書かれた情報」が読み取れるはずもない。

ただ、ここで問うているのは「”原理的”に不可能なのかどうか」だ。そして”原理的”には可能である。というのも、すべての物理法則は「時間の流れに拘束されない」ことが分かっているからだ。どういうことか。例えば「燃焼」というのは、私たちにとっては「物質が燃えて灰になる」という現象である。しかし”原理的”にはその逆、つまり「灰が物質に戻る」という現象が制約されているわけではない。私たちの世界では”何故か”そのような現象が起こらないだけで、”原理的”には「燃えカスの灰が本に戻る」という現象が起こってもおかしくないのだ。そのため、「”原理的”には燃えた本の情報を復元することは可能」ということになる。
では、これと同じことをブラックホールでも考えてみよう。つまり、「ブラックホールに本を投げ込んだ場合、“原理的”に本の情報を復元できるか」というわけだ。そしてホーキング博士は、「ブラックホールに吸い込まれた情報は消える」という「ブラックホールの情報問題」を提唱したのである。量子力学では「すべての情報は保存される」と考えられているので、この「ブラックホールの情報問題」は科学にとっての大問題とみなされているのだそうだ。
あわせて読みたい
【平易】ブラックホールを分かりやすく知りたい。難しいことは抜きにふわっと理解するための1冊:『ブラ…
2019年に初めて直接観測されるも、未だに謎多き天体である「ブラックホール」について現役研究者が分かりやすく語る『ブラックホールをのぞいてみたら』をベースに、科学者がその存在を認めてこなかった歴史や、どんな性質を持つ天体なのかを理解する
そして、説明は難しくてよく分からなかったが、「著者らが生み出した『トポロジカルな弦理論』という計算法則がこの問題に上手く適用出来た」ということのようである。このように超弦理論は、様々に応用されるようにもなっているのだ。
しかし一方で、超弦理論には批判もある。著者は超弦理論の専門家なので、もちろん批判的なことを書いたりはしない。しかし私は、他の本も読んでいるので、「超弦理論には悪い評判もある」ということを知っている。専門外の人からは、「超弦理論は、実験で確かめることが不可能な机上の空論でしかない」と批判されることもあるのだそうだ。
というか、本作の中で著者がこのように書いていたりもする。
あわせて読みたい
【衝撃】ABC予想の証明のために生まれたIUT理論を、提唱者・望月新一の盟友が分かりやすく語る:『宇宙…
8年のチェック期間を経て雑誌に掲載された「IUT理論(宇宙際タイヒミュラー理論)」は、数学の最重要未解決問題である「ABC予想」を証明するものとして大いに話題になった。『宇宙と宇宙をつなぐ数学』『abc予想入門』をベースに、「IUT理論」「ABC予想」について学ぶ
いまのところ、この分野は理論が先行しており、それを検証する作業が追いついていません。そのため、「超弦理論は検証不能なのではないか」という疑問の声も聞かれます。
「素粒子が弦である」という主張を確かめるには、現存する素粒子加速器よりも遥かに高エネルギーな状態を作り出せる環境が必要だという話を聞いたことがある。そのため「検証不可能」と言われてしまうのだろう。
ただ、著者はそのような声を気にしていないようだ。その理由は、科学の歴史を振り返ってみれば理解できるだろう。例えば、「原子」はその存在が予測されてから直接の証拠が見つかるまでかなりの時間を要した。あるいは「ブラックホール」も、その実在が疑問視されていた頃から既に、理論面での研究がかなり進んでいたことで知られている。このように、科学研究は一筋縄ではいかないのだ。
あわせて読みたい
【誤解】「意味のない科学研究」にはこんな価値がある。高校生向けの講演から”科学の本質”を知る:『す…
科学研究に対して、「それは何の役に立つんですか?」と問うことは根本的に間違っている。そのことを、「携帯電話」と「東急ハンズの棚」の例を使って著者は力説する。『すごい実験』は素粒子物理学を超易しく解説する本だが、科学への関心を抱かせてもくれる
また著者は、次のようにも指摘している。
初期宇宙からの重力波を観測できるようになれば、超弦理論を使った宇宙論が直接検証されるようになるでしょう。

著者が本書を書いた時点ではまだ「重力波」そのものさえ発見されていなかったのだが、今ではもう「重力波」の観測自体は可能だ。となれば、「初期宇宙からの重力波」が捉えられる可能性も十分あると考えていいだろう。また、超弦理論から派生した「ホログラフィー原理」と呼ばれるものがあるのだが、そこから生まれたある予測が「クォーク・グルーオン・プラズマ」の実験によって実証されたとも書かれている。このような間接的な証拠からも、「超弦理論の正しさが検証される可能性」を実感出来るのではないかと思う。
あわせて読みたい
【快挙】「チバニアン」は何が凄い?「地球の磁場が逆転する」驚異の現象がこの地層を有名にした:『地…
一躍その名が知れ渡ることになった「チバニアン」だが、なぜ話題になり、どう重要なのかを知っている人は多くないだろう。「チバニアン」の申請に深く関わった著者の『地磁気逆転と「チバニアン」』から、地球で起こった過去の不可思議な現象の正体を理解する
超弦理論が科学の世界でどのような存在になっていくのかはまだまだ未知数だ。しかし外野にいる人間としてはやはり、「華麗なる復活からの大ホームラン」みたいな展開を望んでしまうし、超弦理論がそのような存在になってくれたらいいなと思っている。
本書を読んで初めて知ったこと
さて、私はこの記事の冒頭で、「本書の内容については大体知っていた」と書いたが、もちろん知らないこともあった。最後に、いくつかそれらに触れて終わろうと思う。
あわせて読みたい
【貢献】有名な科学者は、どんな派手な失敗をしてきたか?失敗が失敗でなかったアインシュタインも登場…
どれほど偉大な科学者であっても失敗を避けることはできないが、「単なる失敗」で終わることはない。誤った考え方や主張が、プラスの効果をもたらすこともあるのだ。『偉大なる失敗』から、天才科学者の「失敗」と、その意外な「貢献」を知る
まずは「ハイゼンベルグの不確定性原理」について。これは量子力学を学ぶ上で避けては通れない基本中の基本みたいな話であり、当然その存在は知っていた。しかし、私が知らなかったのは、この「ハイゼンベルグの不確定性原理」とは別に、単に「不確定性原理」と呼ばれているものが別に存在するという事実である。これまで色んな本を読んできたが、この2者の区別はまったく付いておらず、まずそのことに驚かされてしまった。ちなみに、よく分かってはいないものの、本書を読む限り、「不確定性原理」は「現象そのものに関する原理」、そして「ハイゼンベルグの不確定性原理」は「観測に関する原理」であるようだ。
さらに、量子力学において絶対的なルールだとばかり思っていた「ハイゼンベルグの不確定性原理」に疑義が生じているとも書かれており、そのことにも驚かされた。「ハイゼンベルグの不確定性原理」は、「測定精度の限界」に関する制約だ。つまり、「『ハイゼンベルグの不確定性原理』が示す測定精度以上の観測は不可能」という主張である。しかし既に、「ハイゼンベルグの不確定性原理」の測定精度を超えるような観測が存在しているのだそうだ。そのため今では、小澤正直という物理学者による「『ハイゼンベルグの不確定性原理』を拡張した新たな不等式」が知られているという。この話もまったく知らなかった。
あわせて読みたい
【知的】文系にオススメの、科学・数学・哲学の入門書。高橋昌一郎の「限界シリーズ」は超絶面白い:『…
例えば「科学」だけに限ってみても、「なんでもできる」わけでは決してない。「科学」に限らず、私たちが対峙する様々な事柄には「これ以上は不可能・無理」という「限界」が必ず存在する。高橋昌一郎の「限界シリーズ」から、我々が認識しておくべき「限界」を易しく学ぶ
他にも、雑学ネタ的な話で初耳だったこともある。例えば、「科学史上最も美しい実験」の話。量子力学の世界には、「二重スリット実験」と呼ばれる凄まじく有名な実験がある。そして「その中でも、日立製作所の外村彰のグループが行った実験が最も有名で、『科学史上最も美しい実験』の1位に選ばれたこともある」という事実は元々知っていた。しかし、そのランキングの2位に選ばれたのが、ガリレオが行ったとされる「ピサの斜塔の実験」だというのは本書で初めて知った事実である。これは一般的にもよく知られているだろう有名な実験だが、実際に行われたかどうかの真偽は不明なのだそうだ。そのような実験がランキングの2位に位置しているというのもなかなか興味深い話だと思う。
また、「特殊相対性理論を生み出したアインシュタインは、『時間の同時性』について考えを巡らし理論に行き着いた」みたいな話はなんとなく知っていたのだが、「時間の同時性」について考えを巡らすきっかけについては本書で初めて知った。アインシュタインは実は、特許局という役所で仕事をしながら科学研究を行っていたのだが、「特許局に『時計の時刻を合わせる技術に関する特許』の申請書が山のように届いていたことが『時間の同時性』について考えるきっかけになったかもしれない」という説があるのだそうだ。このような話も、とても興味深いものに感じられた。
こんな風に、様々な本を読みながら少しずつ「知らなかった」を減らしていくのが楽しいのである。
あわせて読みたい
【書評】奇跡の”国家”「ソマリランド」に高野秀行が潜入。崩壊国家・ソマリア内で唯一平和を保つ衝撃の”…
日本の「戦国時代」さながらの内戦状態にあるソマリア共和国内部に、十数年に渡り奇跡のように平和を維持している”未承認国家”が存在する。辺境作家・高野秀行の『謎の独立国家ソマリランド』から、「ソマリランド」の理解が難しい理由と、「奇跡のような民主主義」を知る
著:大栗 博司
¥968 (2024/07/13 18:43時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品読了済】私が読んできたノンフィクション・教養書を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が読んできたノンフィクションを様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本選びの参考にして下さい。
最後に
あわせて読みたい
【逸話】天才数学者ガロアが20歳で決闘で命を落とすまでの波乱万丈。時代を先駆けた男がもし生きていた…
現代数学に不可欠な「群論」をたった1人で生み出し、20歳という若さで決闘で亡くなったガロアは、その短い生涯をどう生きたのか?『ガロア 天才数学者の生涯』から、数学に関心を抱くようになったきっかけや信じられないほどの不運が彼の人生をどう変えてしまったのか、そして「もし生きていたらどうなっていたのか」を知る
さて最後に、本書冒頭で紹介されているこんなエピソードに触れて終わりにしよう。超弦理論や相対性理論・量子力学とは全然関係ないのだが、エピソードとしてはとても興味深いはずだ。
1969年、フェルミ国立加速器研究所の初代所長であるロバート・ウィルソンが米国議会に呼ばれた。呼ばれた理由は「加速器の建設計画」にある。これはアメリカ原子力委員会による事業の一環として検討されていたものなのだが、この委員会は原爆を生み出したマンハッタン計画にルーツがあった。そのため、加速器そのものは素粒子物理学の研究で使われるのだが、建前上「国防」に関係する目的が求められたのである。
そのような理由からウィルソンは、議会の場で「加速器の建設は、わが国の防衛にどのように役に立つか」と問われた。そしてこの時のことについて、本書には次のように書かれているのである。
あわせて読みたい
【驚異】ガイア理論の提唱者が未来の地球を語る。100歳の主張とは思えない超絶刺激に満ちた内容:『ノヴ…
「地球は一種の生命体だ」という主張はかなり胡散臭い。しかし、そんな「ガイア理論」を提唱する著者は、数々の賞や学位を授与される、非常に良く知られた科学者だ。『ノヴァセン <超知能>が地球を更新する』から、AIと人類の共存に関する斬新な知見を知る
「この加速器は、直接には国防の役には立ちません。しかし、わが国を守るに足る国にすることに役立ちます」
ウィルソンの答え方も立派なら、これで納得して計画を通した議会も立派だと思います。
つまり、「加速器の建設によって素粒子物理学の研究が盛んになれば、アメリカという国家がより一層『守るに値する国』になる」と主張したわけだ。なんというのか、プレゼンの上手さみたいなものも滲み出るやり取りだなと感じた。
こういうエピソードも散りばめられた、非常に読みやすい「科学の入門書」である。
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を…
Kindleで本を出版しました。タイトルは、『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を分かりやすく書いた本:相対性理論も宇宙論も量子論も』です。科学や科学者に関する、文系の人でも読んでもらえる作品に仕上げました。そんな自著について紹介をしています。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【憧憬】「フランク・ザッパ」を知らずに映画『ZAPPA』を観て、「この生き様は最高」だと感じた
「フランク・ザッパ」がミュージシャンであることさえ禄に知らない状態で私が映画『ZAPPA』を観た私は、そのあまりに特異なスタンス・生き様にある種の憧憬を抱かされた。貫きたいと思う強い欲求を真っ直ぐ突き進んだそのシンプルな人生に、とにかくグッときたのだ。さらに、こんな凄い人物を知らなかった自分にも驚かされてしまった
あわせて読みたい
【実話】映画『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』が描く、白人警官による黒人射殺事件
映画『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』は、2011年に起こった実際の事件を元にした作品である。何の罪もない黒人男性が、白人警官に射殺されてしまったのだ。5時22分から始まる状況をほぼリアルタイムで描き切る83分間の物語には、役者の凄まじい演技も含め、圧倒されてしまった
あわせて読みたい
【あらすじ】原爆を作った人の後悔・葛藤を描く映画『オッペンハイマー』のための予習と評価(クリスト…
クリストファー・ノーラン監督作品『オッペンハイマー』は、原爆開発を主導した人物の葛藤・苦悩を複雑に描き出す作品だ。人間が持つ「多面性」を様々な方向から捉えようとする作品であり、受け取り方は人それぞれ異なるだろう。鑑賞前に知っておいた方がいい知識についてまとめたので、参考にしてほしい
あわせて読みたい
【真実】田原総一朗✕小泉純一郎!福島原発事故後を生きる我々が知るべき自然エネルギーの可能性:映画『…
田原総一朗が元総理・小泉純一郎にタブー無しで斬り込む映画『放送不可能。「原発、全部ウソだった」』は、「原発推進派だった自分は間違っていたし、騙されていた」と語る小泉純一郎の姿勢が印象的だった。脱原発に舵を切った小泉純一郎が、原発政策のウソに斬り込み、再生可能エネルギーの未来を語る
あわせて読みたい
【挑発】「TBS史上最大の問題作」と評されるドキュメンタリー『日の丸』(構成:寺山修司)のリメイク映画
1967年に放送された、寺山修司が構成に関わったドキュメンタリー『日の丸』は、「TBS史上最大の問題作」と評されている。そのスタイルを踏襲して作られた映画『日の丸~それは今なのかもしれない~』は、予想以上に面白い作品だった。常軌を逸した街頭インタビューを起点に様々な思考に触れられる作品
あわせて読みたい
【驚嘆】「現在は森でキノコ狩り」と噂の天才”変人”数学者グリゴリー・ペレルマンの「ポアンカレ予想証…
数学界の超難問ポアンカレ予想を解決したが、100万ドルの賞金を断り、フィールズ賞(ノーベル賞級の栄誉)も辞退、現在は「森できのこ採取」と噂の天才数学者グリゴリー・ペレルマンの生涯を描く評伝『完全なる証明』。数学に関する記述はほぼなく、ソ連で生まれ育った1人の「ギフテッド」の苦悩に満ちた人生を丁寧に描き出す1冊
あわせて読みたい
【挑戦】相対性理論の光速度不変の原理を無視した主張『光速より速い光』は、青木薫訳だから安心だぞ
『光速より速い光』というタイトルを見て「トンデモ本」だと感じた方、安心してほしい。「光速変動理論(VSL理論)」が正しいかどうかはともかくとして、本書は実に真っ当な作品だ。「ビッグバン理論」の欠陥を「インフレーション理論」以外の理屈で補う挑戦的な仮説とは?
あわせて読みたい
【組織】意思決定もクリエイティブも「問う力」が不可欠だ。MIT教授がCEOから学んだ秘訣とは?:『問い…
組織マネジメントにおいては「問うこと」が最も重要だと、『問いこそが答えだ!』は主張する。MIT教授が多くのCEOから直接話を聞いて学んだ、「『問う環境』を実現するための『心理的安全性の確保』の重要性」とその実践の手法について、実例満載で説明する1冊
あわせて読みたい
【挑戦】深海に棲む”聖杯”ダイオウイカをNHKが世界初撮影。関わった者が語る奇跡のプロジェクト:『ドキ…
NHK主導で進められた、深海に棲む”聖杯”ダイオウイカの撮影プロジェクト。10年にも及ぶ過酷な挑戦を描いた『ドキュメント 深海の超巨大イカを追え!』は、ほぼ不可能と思われていたプロジェクトをスタートさせ、艱難辛苦の末に見事撮影に成功した者たちの軌跡を描き出す
あわせて読みたい
【化石】聞き馴染みのない「分子生物学」を通じて、科学という学問の本質を更科功が分かりやすく伝える…
映画『ジュラシック・パーク』を観たことがある方なら、「コハクの化石に閉じ込められた蚊の血液から恐竜の遺伝子を取り出す」という設定にワクワクしたことだろう。『化石の分子生物学』とは、まさにそのような研究を指す。科学以外の分野にも威力を発揮する知見に溢れた1冊
あわせて読みたい
【無謀】映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、脱北ルートに撮影隊が同行する衝撃のドキュメンタリー
北朝鮮からの脱北者に同行し撮影を行う衝撃のドキュメンタリー映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、再現映像を一切使用していない衝撃的な作品だ。危険と隣り合わせの脱北の道程にカメラもついて回り、北朝鮮の厳しい現状と共に、脱北者が置かれた凄まじい状況を映し出す内容に驚かされてしまった
あわせて読みたい
【不思議】森達也が「オカルト」に挑む本。「科学では説明できない現象はある」と否定も肯定もしない姿…
肯定派でも否定派でもない森達也が、「オカルト的なもの」に挑むノンフィクション『オカルト』。「現象を解釈する」ことよりも、「現象を記録する」こと点に注力し、「そのほとんどは勘違いや見間違いだが、本当に説明のつかない現象も存在する」というスタンスで追いかける姿勢が良い
あわせて読みたい
【奇人】天才数学者で、自宅を持たずに世界中を放浪した変人エルデシュは、迷惑な存在でも愛され続けた…
数学史上ガウスに次いで生涯発表論文数が多い天才エルデシュをご存知だろうか?数学者としてずば抜けた才能を発揮したが、それ以上に「奇人変人」としても知られる人物だ。『放浪の天才数学者エルデシュ』で、世界中の数学者の家を泊まり歩いた異端数学者の生涯を描き出す
あわせて読みたい
【天才】『ご冗談でしょう、ファインマンさん』は、科学者のイメージが変わる逸話満載の非・科学エッセイ
「天才科学者」と言えばアインシュタインやニュートン、ホーキングが思い浮かぶだろうが、「科学者らしくないエピソード満載の天才科学者」という意味ではファインマンがずば抜けている。世界的大ベストセラー『ご冗談でしょう、ファインマンさん』は、「科学」をほぼ扱わないエッセイです
あわせて読みたい
【抽象】「思考力がない」と嘆く人に。研究者で小説家の森博嗣が語る「客観的に考える」ために大事なこ…
世の中にはあまりに「具体的な情報」が溢れているために、「客観的、抽象的な思考」をする機会が少ない。そんな時代に、いかに思考力を育てていくべきか。森博嗣が『人間はいろいろな問題についてどう考えていけば良いのか』を通じて伝える「情報との接し方」「頭の使い方」
あわせて読みたい
【要約】福岡伸一『生物と無生物のあいだ』は、「生命とは何か」を「動的平衡」によって定義する入門書…
「生命とは何か?」という、あまりに基本的だと感じられる問いは、実はなかなか難しい。20世紀生物学は「DNAの自己複製」が本質と考えたが、「ウイルス」の発見により再考を迫られた。福岡伸一の『生物と無生物のあいだ』『動的平衡』の2著作から、「生命の本質」を知る
あわせて読みたい
【新視点】世界の歴史を「化学」で語る?デンプン・砂糖・ニコチンなどの「炭素化合物」が人類を動かし…
デンプン・砂糖・ニコチンなどは、地球上で非常に稀少な元素である「炭素」から作られる「炭素化合物」だ。そんな「炭素化合物」がどんな影響を与えたかという観点から世界の歴史を描く『「元素の王者」が歴史を動かす』は、学校の授業とはまったく違う視点で「歴史」を捉える
あわせて読みたい
【思考】『翔太と猫のインサイトの夏休み』は、中学生と猫の対話から「自分の頭で考える」を学べる良書
「中学生の翔太」と「猫のインサイト」が「答えの出ない問い」について対話する『翔太と猫のインサイトの夏休み』は、「哲学」の違う側面を見せてくれる。過去の哲学者・思想家の考えを知ることが「哲学」なのではなく、「自分の頭で考えること」こそ「哲学」の本質だと理解する
あわせて読みたい
【本質】子どもの頃には読めない哲学書。「他人の哲学はつまらない」と語る著者が説く「問うこと」の大…
『<子ども>のための哲学』は決して、「子どもでも易しく理解できる哲学の入門書」ではない。むしろかなり難易度が高いと言っていい。著者の永井均が、子どもの頃から囚われ続けている2つの大きな疑問をベースに、「『哲学する』とはどういうことか?」を深堀りする作品
あわせて読みたい
【歴史】ベイズ推定は現代社会を豊かにするのに必須だが、実は誕生から200年間嫌われ続けた:『異端の統…
現在では、人工知能を始め、我々の生活を便利にする様々なものに使われている「ベイズ推定」だが、その基本となるアイデアが生まれてから200年近く、科学の世界では毛嫌いされてきた。『異端の統計学ベイズ』は、そんな「ベイズ推定」の歴史を紐解く大興奮の1冊だ
あわせて読みたい
【興奮】世界的大ベストセラー『サピエンス全史』要約。人類が文明を築き上げるに至った3つの革命とは?
言わずと知れた大ベストセラー『サピエンス全史』は、「何故サピエンスだけが人類の中で生き残り、他の生物が成し得なかった歴史を歩んだのか」を、「認知革命」「農業革命」「科学革命」の3つを主軸としながら解き明かす、知的興奮に満ち溢れた1冊
あわせて読みたい
【知的】文系にオススメの、科学・数学・哲学の入門書。高橋昌一郎の「限界シリーズ」は超絶面白い:『…
例えば「科学」だけに限ってみても、「なんでもできる」わけでは決してない。「科学」に限らず、私たちが対峙する様々な事柄には「これ以上は不可能・無理」という「限界」が必ず存在する。高橋昌一郎の「限界シリーズ」から、我々が認識しておくべき「限界」を易しく学ぶ
あわせて読みたい
【興奮】飲茶氏が西洋哲学を語る。難解な思想が「グラップラー刃牙成分」の追加で驚異的な面白さに:『…
名前は聞いたことはあるがカントやニーチェがどんな主張をしたのかは分からないという方は多いだろう。私も無知なまったくの初心者だが、そんな人でも超絶分かりやすく超絶面白く西洋哲学を”分かった気になれる”飲茶『史上最強の哲学入門』は、入門書として最強
あわせて読みたい
【貢献】飛行機を「安全な乗り物」に決定づけたMr.トルネードこと天才気象学者・藤田哲也の生涯:『Mr….
つい数十年前まで、飛行機は「死の乗り物」だったが、天才気象学者・藤田哲也のお陰で世界の空は安全になった。今では、自動車よりも飛行機の方が死亡事故の少ない乗り物なのだ。『Mr.トルネード 藤田哲也 世界の空を救った男』から、その激動の研究人生を知る
あわせて読みたい
【驚異】ガイア理論の提唱者が未来の地球を語る。100歳の主張とは思えない超絶刺激に満ちた内容:『ノヴ…
「地球は一種の生命体だ」という主張はかなり胡散臭い。しかし、そんな「ガイア理論」を提唱する著者は、数々の賞や学位を授与される、非常に良く知られた科学者だ。『ノヴァセン <超知能>が地球を更新する』から、AIと人類の共存に関する斬新な知見を知る
あわせて読みたい
【人生】「資本主義の限界を埋める存在としての『贈与論』」から「不合理」に気づくための生き方を知る…
「贈与論」は簡単には理解できないが、一方で、「何かを受け取ったら、与えてくれた人に返す」という「交換」の論理では対処できない現実に対峙する力ともなる。『世界は贈与でできている』から「贈与」的な見方を理解し、「受取人の想像力」を立ち上げる
あわせて読みたい
【感想】飲茶の超面白い東洋哲学入門書。「本書を読んでも東洋哲学は分からない」と言う著者は何を語る…
東洋哲学というのは、「最終回しか存在しない連続ドラマ」のようなものだそうだ。西洋哲学と比較にならないほど異質さと、インド哲学・中国哲学など個別の思想を恐ろしく分かりやすく描く『史上最強の哲学入門 東洋の哲人たち』は、ページをめくる手が止まらないくらい、史上最強レベルに面白かった
あわせて読みたい
【幻想】超ひも理論って何?一般相対性理論と量子力学を繋ぐかもしれないぶっ飛んだ仮説:『大栗先生の…
『大栗先生の超弦理論入門』は最先端科学である「超弦理論」を説明する1冊だが、この記事では著者の主張の1つである「空間は幻想かもしれない」という発想を主に取り上げる。「人類史上初の『適用する次元が限定される理論』」が描像する不可思議な世界とは?
あわせて読みたい
【限界】「科学とは何か?」を知るためのおすすめ本。科学が苦手な人こそ読んでほしい易しい1冊:『哲学…
「科学的に正しい」という言葉は、一体何を意味しているのだろう?科学者が「絶対に正しい」とか「100%間違っている」という言い方をしないのは何故だろう?飲茶『哲学的な何か、あと科学とか』から、「科学とはどんな営みなのか?」について考える
あわせて読みたい
【戸惑】人間の脳は摩訶不思議。意識ではコントロールできない「無意識の領域」に支配されている:『あ…
我々は決断や選択を「自分の意思」で行っていると感じるが、脳科学の研究はそれを否定している。我々に「自由意志」などない。「脳」の大部分は「意識以外のもの」に支配され、そこに「意識」はアクセスできないという驚愕の実態を『あなたの知らない脳』から学ぶ
あわせて読みたい
【快挙】「暗黒の天体」ブラックホールはなぜ直接観測できたのか?国際プロジェクトの舞台裏:『アイン…
「世界中に存在する電波望遠鏡を同期させてブラックホールを撮影する」という壮大なEHTプロジェクトの裏側を記した『アインシュタインの影』から、ブラックホール撮影の困難さや、「ノーベル賞」が絡む巨大プロジェクトにおける泥臭い人間ドラマを知る
あわせて読みたい
【快挙】「チバニアン」は何が凄い?「地球の磁場が逆転する」驚異の現象がこの地層を有名にした:『地…
一躍その名が知れ渡ることになった「チバニアン」だが、なぜ話題になり、どう重要なのかを知っている人は多くないだろう。「チバニアン」の申請に深く関わった著者の『地磁気逆転と「チバニアン」』から、地球で起こった過去の不可思議な現象の正体を理解する
あわせて読みたい
【貢献】有名な科学者は、どんな派手な失敗をしてきたか?失敗が失敗でなかったアインシュタインも登場…
どれほど偉大な科学者であっても失敗を避けることはできないが、「単なる失敗」で終わることはない。誤った考え方や主張が、プラスの効果をもたらすこともあるのだ。『偉大なる失敗』から、天才科学者の「失敗」と、その意外な「貢献」を知る
あわせて読みたい
【平易】一般相対性理論を簡単に知りたい方へ。ブラックホール・膨張宇宙・重力波と盛りだくさんの1冊:…
現役の研究者が執筆した『ブラックホール・膨張宇宙・重力波』は、アインシュタインが導き出した一般相対性理論が関わる3つのテーマについて、初心者にも分かりやすく伝える内容になっている。歴史的背景も含めて科学的知見を知りたい方にオススメの1冊
あわせて読みたい
【逸話】天才数学者ガロアが20歳で決闘で命を落とすまでの波乱万丈。時代を先駆けた男がもし生きていた…
現代数学に不可欠な「群論」をたった1人で生み出し、20歳という若さで決闘で亡くなったガロアは、その短い生涯をどう生きたのか?『ガロア 天才数学者の生涯』から、数学に関心を抱くようになったきっかけや信じられないほどの不運が彼の人生をどう変えてしまったのか、そして「もし生きていたらどうなっていたのか」を知る
あわせて読みたい
【誤解】「意味のない科学研究」にはこんな価値がある。高校生向けの講演から”科学の本質”を知る:『す…
科学研究に対して、「それは何の役に立つんですか?」と問うことは根本的に間違っている。そのことを、「携帯電話」と「東急ハンズの棚」の例を使って著者は力説する。『すごい実験』は素粒子物理学を超易しく解説する本だが、科学への関心を抱かせてもくれる
あわせて読みたい
【バトル】量子力学の歴史はこの1冊で。先駆者プランクから批判者アインシュタインまですべて描く:『量…
20世紀に生まれた量子論は、時代を彩る天才科学者たちの侃々諤々の議論から生み出された。アインシュタインは生涯量子論に反対し続けたことで知られているが、しかし彼の批判によって新たな知見も生まれた。『量子革命』から、量子論誕生の歴史を知る
あわせて読みたい
【ドラマ】「フェルマーの最終定理」のドラマティックな証明物語を、飲茶氏が平易に描き出す:『哲学的…
「フェルマーの最終定理」は、問題の提示から350年以上経ってようやく証明された超難問であり、その証明の過程では様々な人間ドラマが知られている。『哲学的な何か、あと数学とか』をベースに、数学的な記述を一切せず、ドラマティックなエピソードだけに触れる
あわせて読みたい
【不可思議】心理学の有名な実験から、人間の”欠陥”がどう明らかになっていったかを知る:『心は実験で…
『心は実験できるか 20世紀心理学実験物語』では、20世紀に行われた心理学実験からインパクトのある10の実験を選び紹介している。心理学者でもある著者が「科学であって科学ではない」と主張する心理学という学問で、人間のどんな不可思議さがあぶり出されてきたのかを知る
あわせて読みたい
【神秘】脳研究者・池谷裕二が中高生向けに行った講義の書籍化。とても分かりやすく面白い:『進化しす…
「宇宙」「深海」「脳」が、人類最後のフロンティアと呼ばれている。それほど「脳」というのは、未だに分からないことだらけの不思議な器官だ。池谷裕二による中高生向けの講義を元にした『進化しすぎた脳』『単純な脳、複雑な「私」』をベースに、脳の謎を知る
あわせて読みたい
【論争】サイモン・シンが宇宙を語る。古代ギリシャからビッグバンモデルの誕生までの歴史を網羅:『宇…
古代から現代に至るまで、「宇宙」は様々な捉えられ方をしてきた。そして、新たな発見がなされる度に、「宇宙」は常識から外れた不可思議な姿を垣間見せることになる。サイモン・シン『宇宙創成』をベースに、「ビッグバンモデル」に至るまでの「宇宙観」の変遷を知る
あわせて読みたい
【証明】結城浩「数学ガール」とサイモン・シンから「フェルマーの最終定理」とそのドラマを学ぶ
350年以上前に一人の数学者が遺した予想であり「フェルマーの最終定理」には、1995年にワイルズによって証明されるまでの間に、これでもかというほどのドラマが詰め込まれている。サイモン・シンの著作と「数学ガール」シリーズから、その人間ドラマと数学的側面を知る
あわせて読みたい
【衝撃】ABC予想の証明のために生まれたIUT理論を、提唱者・望月新一の盟友が分かりやすく語る:『宇宙…
8年のチェック期間を経て雑誌に掲載された「IUT理論(宇宙際タイヒミュラー理論)」は、数学の最重要未解決問題である「ABC予想」を証明するものとして大いに話題になった。『宇宙と宇宙をつなぐ数学』『abc予想入門』をベースに、「IUT理論」「ABC予想」について学ぶ
あわせて読みたい
【限界】有名な「錯覚映像」で心理学界をザワつかせた著者らが語る「人間はいかに間違えるか」:『錯覚…
私たちは、知覚や記憶を頼りに社会を生きている。しかしその「知覚」「記憶」は、本当に信頼できるのだろうか?心理学の世界に衝撃を与えた実験を考案した著者らの『錯覚の科学』から、「避けられない失敗のクセ」を理解する
あわせて読みたい
【驚嘆】「現在は森でキノコ狩り」と噂の天才”変人”数学者グリゴリー・ペレルマンの「ポアンカレ予想証…
数学界の超難問ポアンカレ予想を解決したが、100万ドルの賞金を断り、フィールズ賞(ノーベル賞級の栄誉)も辞退、現在は「森できのこ採取」と噂の天才数学者グリゴリー・ペレルマンの生涯を描く評伝『完全なる証明』。数学に関する記述はほぼなく、ソ連で生まれ育った1人の「ギフテッド」の苦悩に満ちた人生を丁寧に描き出す1冊
あわせて読みたい
【興奮】結城浩「数学ガール」で、決闘で命を落とした若き天才数学者・ガロアの理論を学ぶ
高校生を中心に、数学を通じて関わり合う者たちを描く「数学ガール」シリーズ第5弾のテーマは「ガロア理論」。独力で「群論」という新たな領域を切り開きながら、先駆的すぎて同時代の数学者には理解されず、その後決闘で死亡した天才の遺した思考を追う
あわせて読みたい
【天才】科学者とは思えないほど面白い逸話ばかりのファインマンは、一体どんな業績を残したのか?:『…
数々の面白エピソードで知られるファインマンの「科学者としての業績」を初めて網羅したと言われる一般書『ファインマンさんの流儀』をベースに、その独特の研究手法がもたらした様々な分野への間接的な貢献と、「ファインマン・ダイアグラム」の衝撃を理解する
あわせて読みたい
【使命】「CRISPR-Cas9」を分かりやすく説明。ノーベル賞受賞の著者による発見物語とその使命:『CRISPR…
生物学の研究を一変させることになった遺伝子編集技術「CRISPR-Cas9」の開発者は、そんな発明をするつもりなどまったくなかった。ノーベル化学賞を受賞した著者による『CRISPR (クリスパー) 究極の遺伝子編集技術の発見』をベースに、その発見物語を知る
あわせて読みたい
【研究】光の量子コンピュータの最前線。量子テレポーテーションを実現させた科学者の最先端の挑戦:『…
世界中がその開発にしのぎを削る「量子コンピューター」は、技術的制約がかなり高い。世界で初めて「量子テレポーテーション」の実験を成功させた研究者の著書『光の量子コンピューター』をベースに、量子コンピューター開発の現状を知る
あわせて読みたい
【異端】数学の”証明”はなぜ生まれたのか?「無理数」と「無限」に恐怖した古代ギリシャ人の奮闘:『数…
学校で数学を習うと、当然のように「証明」が登場する。しかしこの「証明」、実は古代ギリシャでしか発展しなかった、数学史においては非常に”異端”の考え方なのだ。『数学の想像力 正しさの深層に何があるのか』をベースに、ギリシャ人が恐れたものの正体を知る
あわせて読みたい
【対立】数学はなぜ”美しい”のか?数学は「発見」か「発明」かの議論から、その奥深さを知る:『神は数…
数学界には、「数学は神が作った派」と「数学は人間が作った派」が存在する。『神は数学者か?』をベースに、「数学は発見か、発明か」という議論を理解し、数学史においてそれぞれの認識がどのような転換点によって変わっていったのかを学ぶ
あわせて読みたい
【始まり】宇宙ができる前が「無」なら何故「世界」が生まれた?「ビッグバンの前」は何が有った?:『…
「宇宙がビッグバンから生まれた」ことはよく知られているだろうが、では、「宇宙ができる前はどうなっていたのか」を知っているだろうか? 実は「宇宙は”無”から誕生した」と考えられているのだ。『宇宙が始まる前には何があったのか?』をベースに、ビッグバンが起こる前の「空間も時間も物理法則も存在しない無」について学ぶ
あわせて読みたい
【謎】恐竜を絶滅させた隕石はどこから来た?暗黒物質が絡む、リサ・ランドールの驚愕の仮説:『ダーク…
「生物の絶滅」には、以前から知られていたある謎があった。そしてその謎を、未だに観測されておらず、「科学者の妄想の産物」でしかない「ダークマター(暗黒物質)」が解決するかもしれない。現役の科学者が『ダークマターと恐竜絶滅』で語る驚きの仮説。
あわせて読みたい
【天才】数学の捉え方を一変させた「シンメトリー(対称性)」と、その発見から発展に至る歴史:『シン…
「5次方程式の解の公式は存在しない」というアーベルの証明や、天才・ガロアが発展させた「群論」は、「シンメトリー(対称性)」という領域に新たな光を当てた。『シンメトリーの地図帳』をベースに、「シンメトリー」の発展と「モンスター」の発見の物語を知る
あわせて読みたい
【敗北】「もつれ」から量子論の基礎を学ぶ。それまでの科学では説明不能な「異次元の現象」とは?:『…
アインシュタインは量子力学を生涯受け入れなかったのだが、アインシュタインが批判し続けたことによって明らかになったこともある。「もつれ」の重要性もその一つだ。『宇宙は「もつれ」でできている』から量子力学の基礎を成す現象を知る。
あわせて読みたい
【嫉妬?】ヒッグス粒子はいかに発見されたか?そして科学の”発見”はどう評価されるべきか?:『ヒッグ…
科学研究はもはや個人単位では行えず、大規模な「ビッグサイエンス」としてしか成立しなくなっている。そんな中で、科学研究の成果がどう評価されるべきかなどについて、「ヒッグス粒子」発見の舞台裏を追った『ヒッグス 宇宙の最果ての粒子』をベースに書く
あわせて読みたい
【興奮】素数の謎に迫った天才数学者たちの奮闘と、数学の”聖杯”である「リーマン予想」について:『素…
古今東西の数学者を惹きつけて止まない「素数」。その規則性を見つけ出すことは非常に困難だったが、「リーマン予想」として初めてそれが示された。『素数の音楽』『リーマン博士の大予想』から、天才数学者たちが挑んできた「リーマン予想」をざっくり理解する
あわせて読みたい
【究極】リサ・ランドールが「重力が超弱い理由」を解説する、超刺激的なひも理論の仮説:『ワープする…
現役の研究者であるリサ・ランドールが、自身の仮説を一般向けに分かりやすく説明する『ワープする宇宙』。一般相対性理論・量子力学の知識を深く記述しつつ「重力が超弱い理由」を説明する、ひも理論から導かれる「ワープする余剰次元」について解説する
あわせて読みたい
【解説】テネットの回転ドアの正体を分かりやすく考察。「時間逆行」ではなく「物質・反物質反転」装置…
クリストファー・ノーラン監督の映画『TENET/テネット』は、「陽電子」「反物質」など量子力学の知見が満載です。この記事では、映画の内容そのものではなく、時間反転装置として登場する「回転ドア」をメインにしつつ、時間逆行の仕組みなど映画全体の設定について科学的にわかりやすく解説していきます
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
宇宙・ビッグバン・ブラック ホール・相対性理論【本・映画の感想】 | ルシルナ
科学全般に関心を持っていますが、その中でも宇宙に関する本はたくさん読んできました。ビッグバンがいかに起こったか、ブラックホールはどうやって直接観測されたか、宇宙…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…






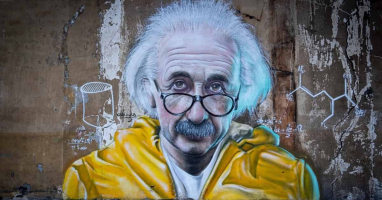


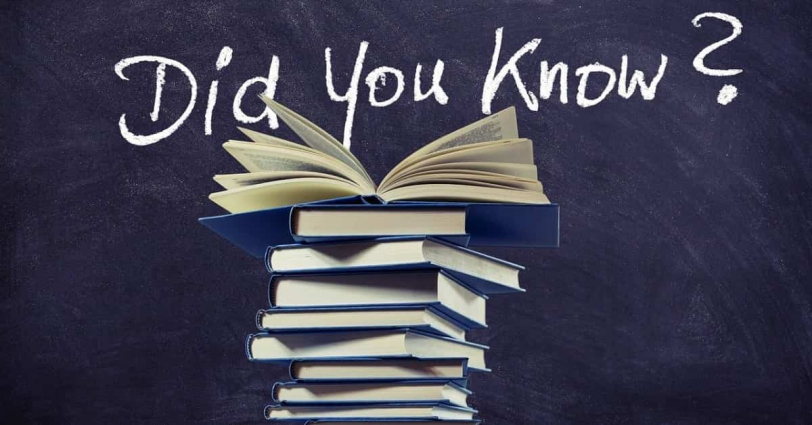





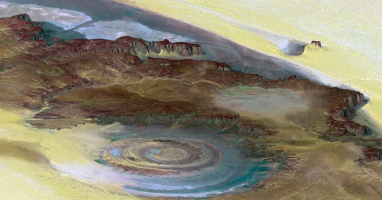

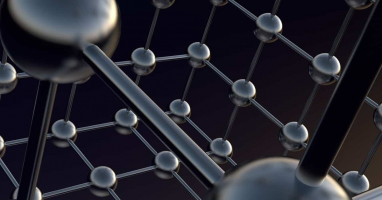
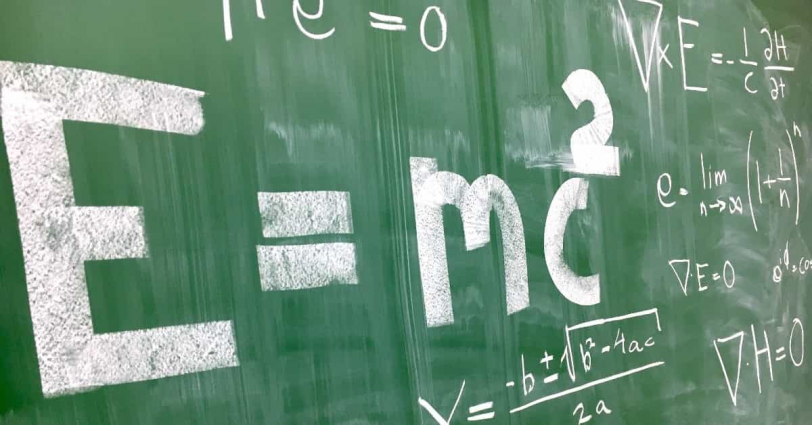




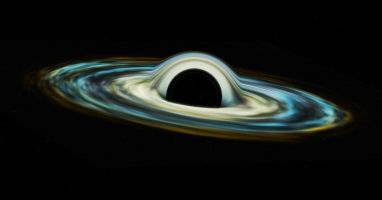



























































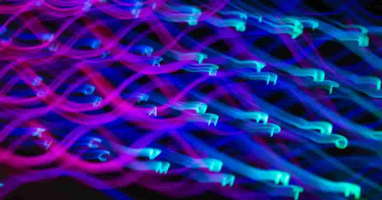
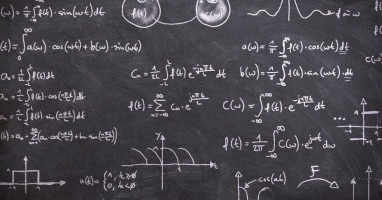


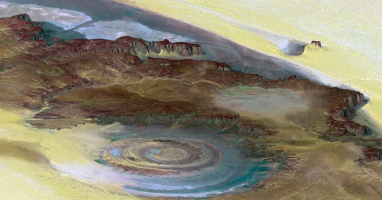

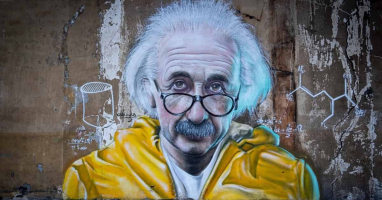

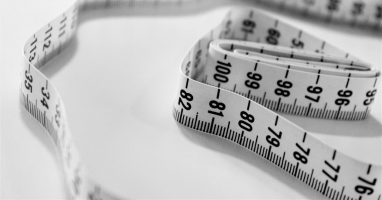












コメント