目次
はじめに
この記事で取り上げる本
著:森 達也
¥792 (2022/07/14 20:30時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
この本をガイドにしながら記事を書いていきます
この記事の3つの要点
- 「現象が観察者を迎合する、あるいは観察者から隠れたがる」という性質を持つものとして「オカルト」を捉える
- 私は「オカルト」に限らず、「不思議な出来事」をすべて「不思議なもの箱」に分類する
- 「『オカルト』が科学に馴染まない」としたら「科学的な検証が出来ないからインチキだ」という主張には難がある
読者がどのようなスタンスで本書を読むかによって作品の存在理由が変わる1冊だと言っていい
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
あわせて読みたい
【全作品視聴済】おすすめの森達也の本・映画、そしてオウム真理教を扱った本・映画【随時更新】
今まで私が触れてきた4000冊の本と1000本の映画の中から、森達也の作品、そしてオウム真理教を扱った作品をオススメします。特異な存在感を放つ映画監督・森達也と、日本近現代史における異質な存在であるオウム真理教に関する作品を併せてセレクトしてみました。是非本・映画選びの参考にして下さい。
「オカルト」に真面目に向き合い、「解釈」を交えずにその正体を突き詰めようとする森達也の眼差し
あわせて読みたい
【真実?】佐村河内守のゴーストライター騒動に森達也が斬り込んだ『FAKE』は我々に何を問うか?
一時期メディアを騒がせた、佐村河内守の「ゴースト問題」に、森達也が斬り込む。「耳は聴こえないのか?」「作曲はできるのか?」という疑惑を様々な角度から追及しつつ、森達也らしく「事実とは何か?」を問いかける『FAKE』から、「事実の捉え方」について考える
ドキュメンタリー作家でもある森達也は、かつて『職業欄はエスパー』という映像作品を発表し、同名の著書も執筆している。『職業欄はエスパー』は、「超能力者」と呼ばれる人たちに焦点を当てた作品だが、さらに広く「オカルト」と呼ばれるものを多数取材したのがこのノンフィクションだ。森達也はシンプルに現象を追いかけることに注力しており、議論を呼びそうな「解釈」には可能な限り足を踏み入れない。そのようなスタンスが非常に興味深いと感じる。
著:森 達也
¥772 (2022/07/14 20:36時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
扱われる対象と著者のスタンス

著者が「オカルト」という括りで取り上げる対象はとても広い。本書は全20章から成り、概ね章ごとに対象が変わると考えていいだろう。扱う対象をざっくり挙げると次のようになる。
- スプーン曲げの第一人者と呼ばれる男
- 恐山のイタコ
- オカルトハンター
- 占い師
- 幽霊が出没すると言われる寿司屋
- 永田町の陰陽師
- UFO観測会
- ダウジング
- 臨死体験者
- メンタリスト
確かに、「オカルト」という括りを提示されればなんとなく納得できそうなものばかりではあるが、しかしシンプルに捉えると、あまりにまとまりのない雑多な印象を受けもするだろう。
あわせて読みたい
【生きる】志尊淳・有村架純が聞き手の映画『人と仕事』から考える「生き延びるために必要なもの」の違い
撮影予定の映画が急遽中止になったことを受けて制作されたドキュメンタリー映画『人と仕事』は、コロナ禍でもリモートワークができない職種の人たちを取り上げ、その厳しい現状を映し出す。その過程で「生き延びるために必要なもの」の違いについて考えさせられた
本書で著者は、「オカルト」についての明確な定義を行わない。しかし、森達也が繰り返し主張する事柄から、そのエッセンスを拾い上げることはできるだろう。森達也が繰り返し行う主張というのは、ざっくり要約すると以下のようになる。
「現象そのもの」が観察者を迎合しようとする。あるいは、「現象」が観察者から隠れたがる
森達也はこのような主張を何度も口にするのだ。
何を言っているのかは、なんとなくイメージできるだろう。例えばオカルト的な現象は、「見たいと思う人間には見えるが、否定したいと思う人間には見えない」という場合が多い。これは、オカルト的な現象に対する胡散臭さを助長するような性質ではあるのだが、森達也はそのような「解釈」をしない。状況をとりあえずそのまま受け入れた上で、「『見たいと思う人間には見えるが、否定したいと思う人間には見えない』という性質を持っているのではないか」と考えるのだ。これが、「迎合しようとする」の意味である。
あわせて読みたい
【限界】有名な「錯覚映像」で心理学界をザワつかせた著者らが語る「人間はいかに間違えるか」:『錯覚…
私たちは、知覚や記憶を頼りに社会を生きている。しかしその「知覚」「記憶」は、本当に信頼できるのだろうか?心理学の世界に衝撃を与えた実験を考案した著者らの『錯覚の科学』から、「避けられない失敗のクセ」を理解する
あるいはオカルト的な現象の場合、写真に撮ったはずなのに何も写っていなかったり、カメラを取りに戻ろうとしたら既に消えていたり、間違いなく録音したテープを紛失したりといった話も多い。これらについても森達也は、「そのような『隠れたがる性質』を持っているのではないか」と考えるようにしているのである。

このスタンスはとても興味深いと思う。「オカルト」に対する私の考え方については後で触れるが、「『上手く捉えられない』という性質をそもそも有しているのだ」と考えることは、オカルト的な現象に本気で向き合おうとする場合には非常に有効な姿勢であるように感じられた。
それではまず、「オカルト」に対する森達也のスタンスから触れていこうと思う。
彼は「オカルト」に対して、否定も肯定もしない。ただその一方で、「『オカルト』と呼ばれるものの大部分が勘違いや気の所為」だとも主張している。この主張は、本書に登場するほとんどの人物に共通する見解だ。玉石混交でしかない「オカルト」のほとんどが「石」、つまり「本来的には『オカルト』と呼ばれるべきではない何か」である。しかし中には、どう説明しようとしても上手くいかない、なんだか全然理解できない、「宝石」かもしれないものが、ごく稀に存在する。これが基本的なスタンスだ。
あわせて読みたい
【限界】「科学とは何か?」を知るためのおすすめ本。科学が苦手な人こそ読んでほしい易しい1冊:『哲学…
「科学的に正しい」という言葉は、一体何を意味しているのだろう?科学者が「絶対に正しい」とか「100%間違っている」という言い方をしないのは何故だろう?飲茶『哲学的な何か、あと科学とか』から、「科学とはどんな営みなのか?」について考える
森達也は、「物理法則に反しているからおかしい」とも、「目の前で起こっているのを見たのだから真実だ」とも主張しない。彼自身は、「どちらかに自分の意見を振り切れる方が楽だ」というような言い方をしている。極端な肯定派、あるいは極端な否定派になれるならその方がいい、というわけだ。しかし、どうしてもそうはなれない。そのどっちつかずなスタンスが本書の特徴だと感じるし、面白さに繋がっていると思う。
「オカルト」に対する私のスタンス
それでは、私のスタンスについても書いておこうと思う。
私は理系の人間で、基本的に「科学」を信頼している。人類が生み出した「科学」という手法は、世界の現象の真偽を正しく判定してくれる見事なツールだと考えているし、「科学」というプロセスを経た結論は受け入れるというのが私の基本的なスタンスだ。
あわせて読みたい
【誤解】「意味のない科学研究」にはこんな価値がある。高校生向けの講演から”科学の本質”を知る:『す…
科学研究に対して、「それは何の役に立つんですか?」と問うことは根本的に間違っている。そのことを、「携帯電話」と「東急ハンズの棚」の例を使って著者は力説する。『すごい実験』は素粒子物理学を超易しく解説する本だが、科学への関心を抱かせてもくれる
しかし同時に、すべてを「科学」で捉えられるわけではないことも理解している。
例えば、少し専門的な話になるが、量子力学の世界に「ハイゼンベルグの不確定性原理」と呼ばれるものがある。これは、「極小の物質の場合、『位置』と『速度』を同時に正確に測定することは”原理的に”不可能」という主張だ。私たちは、例えば「100m走の選手がゴールラインを割った瞬間の速度は時速◯km」など、「位置」と「速度」を同時に正確に測定する手段を持っている。しかしこれは、「大きな物質」にしか当てはまらないルールだということが、物理学の研究から明らかになった。分子や原子などの非常に小さな物質の場合、「位置」と「速度」を同時に正確に測定することは不可能なのだ。これは、「測定技術に限界があるから不可能」という意味ではない。世界のルールがそれを許容していないのである。
つまりこれは、「科学の限界」だと言える。「科学」によっては立ち入れない領域なのだ。

あるいは、現在の「科学」では、「ビッグバン以前」について知ることは”原理的に”不可能だと考えられている。「ビッグバン」が時間も空間も生み出した。つまり「ビッグバン以前」は、時間も空間も何もないという意味での完全な「無」なのだ。そんな「ビッグバン以前」について考えることは、「科学」の領域ではない可能性が高いと考えられているのである。これもまた「科学の限界」だと言っていいだろう。
あわせて読みたい
【始まり】宇宙ができる前が「無」なら何故「世界」が生まれた?「ビッグバンの前」は何が有った?:『…
「宇宙がビッグバンから生まれた」ことはよく知られているだろうが、では、「宇宙ができる前はどうなっていたのか」を知っているだろうか? 実は「宇宙は”無”から誕生した」と考えられているのだ。『宇宙が始まる前には何があったのか?』をベースに、ビッグバンが起こる前の「空間も時間も物理法則も存在しない無」について学ぶ
つまり、「『科学』で捉えることができるもの」については科学的知見こそが真実だと言えるが、「『科学』で捉えることができないもの」については「科学」は無力だ、というわけだ。
そして私は、「オカルト」と呼ばれるものの中にも、「『科学』で捉えることができないもの」が含まれていてもおかしくはない、と考えている。「『科学』という箱」にそもそも入らないと考えられているものが実際に存在しているのだから、「オカルト」と呼ばれるものの中にも「『科学』という箱」に入らないものがあっても不思議ではないだろう。
さて、一方で、当たり前の話だが、「『科学』で捉えることができないもの」が存在するとして、それを即座に「『オカルト』という箱」に入れるわけではない。というか私の場合は、「不思議なもの箱」という分類がある。
この「不思議なもの箱」は決して、「『科学』で捉えることができないもの」だけを入れるのではない。科学的に解明されているだろう事柄でも、私が「不思議だ」と感じたものはすべて「不思議なもの箱」に分類されるというわけだ。
分かりやすい話で言えば、マジック全般はすべて「不思議なもの箱」に入る。そこに「トリック」があることは理解しているが、「不思議だ」と感じるから「不思議なもの箱」行きなのだ。また、「体重計に乗るだけで筋肉量や基礎代謝量が測定できる」というのも、私には不思議に感じられる。もちろんそこには何らかの仕組みが存在するのだろうが、私はそれを知らないので「不思議なもの箱」に分類されるというわけだ。
あわせて読みたい
【不穏】大友克洋の漫画『童夢』をモデルにした映画『イノセンツ』は、「無邪気な残酷さ」が恐ろしい
映画『イノセンツ』は、何がどう展開するのかまるで分からないまま進んでいく実に奇妙な物語だった。非現実的な設定で描かれるのだが、そのことによって子どもたちの「無邪気な残酷さ」が一層リアルに浮き彫りにされる物語であり、「意図的に大人が排除された構成」もその一助となっている
このように、科学的に解明されているかどうかに関係なく、私にとって「不思議だ」と感じられる物事は世の中にたくさんある。そして、「そういうものの一種として『オカルト』も存在する」というのが私の捉え方だ。「オカルト」は私にとって、「不思議なもの箱」の中にある「『科学』で捉えることができないもの」の一部ぐらいの扱いである。僕にとって、そこに「特別さ」はない。他の「不思議なもの」たちと同レベルに存在するものでしかないからだ。
だから私としては、「オカルトだけが特別なものとして注目されること」の方に疑問を抱いてしまう。
その理由については、森達也がこんな風に指摘していた。
オカルト的な現象には、人間的なものが、つまり擬人化したくなるようなものが付随するからだ。
あわせて読みたい
【狂気?】オウム真理教を内部から映す映画『A』(森達也監督)は、ドキュメンタリー映画史に残る衝撃作だ
ドキュメンタリー映画の傑作『A』(森達也)をようやく観られた。「オウム真理教は絶対悪だ」というメディアの報道が凄まじい中、オウム真理教をその内部からフラットに映し出した特異な作品は、公開当時は特に凄まじい衝撃をもたらしただろう。私たちの「当たり前」が解体されていく斬新な一作

なるほど、という感じではないだろうか。例えば「原子の振る舞い」や「体重計の計測」などには、「擬人化したくなるような何か」はあまりイメージされない。しかし、いわゆる「オカルト」と呼ばれるものは、そこに「擬人化したくなるような何か」が思い浮かんでしまう、というわけだ。UFOは地球外知的生命体を、臨死体験や心霊現象は死者の存在をイメージさせるし、曲がるスプーンやダウジングの棒などについては「物自体に意志が宿っている」ような捉え方もできる。「『擬人化したくなるような何か』がイメージしやすいと『オカルト』と呼ばれやすくなる」というのは一理あると感じた。
「心の動きの影響を受ける」ために、「再現性」を求める科学とは相性が悪い
先程、本書における「オカルト」の捉え方として、「『現象そのもの』が観察者を迎合しようとする。あるいは、『現象』が観察者から隠れたがる」という点に触れた。また、本書で森達也は、
オカルト的な能力は「心の動き」に強く影響を受けるのだから、再現性を強く求める科学とは相性が悪い。
という主旨の記述を何度も繰り返す。この辺りの話をもう少し深めてみたいと思う。
「科学」では基本的に、「反証可能性」と「再現性」の2つが常に求められる。「反証可能性」については下の記事を読んでほしいが、「再現性」は言葉通りの意味で、「同じ状況を再現できるか否か」という指標である。
あわせて読みたい
【誤り】「信じたいものを信じる」のは正しい?映画『星の子』から「信じること」の難しさを考える
どんな病気も治す「奇跡の水」の存在を私は信じないが、しかし何故「信じない」と言えるのか?「奇跡の水を信じる人」を軽々に非難すべきではないと私は考えているが、それは何故か?映画『星の子』から、「何かを信じること」の難しさについて知る
基本的には、この「反証可能性」と「再現性」の2つが揃っていなければ「科学」とは認められない。というか、この2つを大前提として科学は発達してきたと言った方がいいだろう。つまり、「再現性の低いもの」はそもそも「科学」の枠組みに入りようがないというわけだ。
分野によって異なる考え方も存在するが、基本的に「科学」は、「同じ条件であれば、同じ結果が導かれるはず」と考える学問であり、そのような「再現性を持つ現象」に対しては威力を発揮すると言っていい。
しかし、それがトリックの入り込む余地のないものなのだとして、「スプーン曲げ」や「透視」、「ダウジング」などは、「常に成功するとは限らない」という点に難しさがある。「同じような腕の振り方でボールを投げれば、同じような球速・曲がり具合のボールが投げられる」からこそピッチャーの育成は成り立つわけだが、「オカルト的な能力」は決してそうではない。その能力を持つと主張する者であっても、100%は成功しないことが多いはずだ。

あわせて読みたい
【神秘】脳研究者・池谷裕二が中高生向けに行った講義の書籍化。とても分かりやすく面白い:『進化しす…
「宇宙」「深海」「脳」が、人類最後のフロンティアと呼ばれている。それほど「脳」というのは、未だに分からないことだらけの不思議な器官だ。池谷裕二による中高生向けの講義を元にした『進化しすぎた脳』『単純な脳、複雑な「私」』をベースに、脳の謎を知る
著者はこれについて、「オカルト的な能力は『心の動き』に強く影響を受けるのではないか」と考える。もし本当にそうだとするなら、「科学的検証」には馴染まないということになるだろう。
一方、本書ではなく別の本で知った知識だが、かつてアメリカで、超能力などを研究するいわゆる「超心理学」の研究を衰退させた「プロジェクト・アルファ」と呼ばれる出来事が起こった。簡単に説明すると、「超心理学の研究所に『超能力者』だと偽ってマジシャンを送り込み、様々なマジックを駆使して研究員を欺き、超能力者であることを認めさせた後で、マジックだったと明かした」というなかなか壮大なものである。
私たちは、マジシャンのマジックを見てもそのネタを見破ることができない。であれば、「オカルト」と呼ばれる現象にも、私たちが真相に辿り着けないだけで、簡単に説明がつく何かがあるのかもしれない。そのような疑惑も常に残り続けてしまう難しさがあるというわけだ。
このように「オカルト」は、どうしても様々な要素が入り混じるため、取り上げるのが難しくなってしまうが、森達也の冷静で客観的でどちらの立場にも肩入れしない姿勢は、「現象そのもの」に着目しやすくなると感じられた。「オカルト」に対して馴染みのない人ほど読みやすく感じる作品だと思う。
あわせて読みたい
【衝撃】森達也『A3』が指摘。地下鉄サリン事件を起こしたオウム真理教は社会を激変させた
「オウム真理教は特別だ、という理由で作られた”例外”が、いつの間にか社会の”前提”になっている」これが、森達也『A3』の主張の要点だ。異常な状態で続けられた麻原彰晃の裁判を傍聴したことをきっかけに、社会の”異様な”変質の正体を理解する。
著:森 達也
¥792 (2022/07/14 20:34時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品読了済】私が読んできたノンフィクション・教養書を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が読んできたノンフィクションを様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本選びの参考にして下さい。
最後に
本書は、「読者がどのようなスタンスを取るかで、作品そのものが変わる」と言っていい作品だ。
あわせて読みたい
【感想】これはドキュメンタリー(実話)なのか?映画『女神の継承』が突きつける土着的恐怖
ナ・ホンジンがプロデューサーを務めた映画『女神の継承』は、フィクションなのかドキュメンタリーなのか混乱させる異様な作品だった。タイ東北部で強く信じられている「精霊(ピー)」の信仰をベースに、圧倒的なリアリティで土着的恐怖を描き出す、強烈な作品
例えば、誰もいないグラウンドでたった1人でボールを投げている人物がいるとしよう。あなたがそれを遠巻きに見ているだけなら「知らない人がボールを投げている」というだけのことだ。しかし、あなたがバットを持ってそのボールを打ち返せば「バッティング」になるし、大勢の人が集まって守備につく者が出てくればそれは「野球」になるだろう。「黙々とボールを投げ続ける森達也」に対して、読者がどんなアクションを起こす(どんな読み方をする)かで、作品そのものの存在理由が変わる作品に感じられたというわけだ。
賛成にせよ反対にせよ、「オカルト」に対する態度を既に決めている人にはあまり向かない作品かもしれない。しかし、オカルト的なものをどう捉えるべきか考えあぐねているという人には、最良の1冊と言っていいのではないかと思う。
あわせて読みたい
【未知】タコに「高度な脳」があるなんて初耳だ。人類とは違う進化を遂げた頭足類の「意識」とは?:『…
タコなどの頭足類は、無脊椎動物で唯一「脳」を進化させた。まったく違う進化を辿りながら「タコに心を感じる」という著者は、「タコは地球外生命体に最も近い存在」と書く。『タコの心身問題』から、腕にも脳があるタコの進化の歴史と、「意識のあり方」を知る。
私は、世の中に「不思議なもの」がたくさんある方が面白いと感じるタイプだ。もちろん、何かが科学的に解明されるのであればそれも素晴らしいのだが、「分からないまま」のものがあってもいいように思う。「この世の中のすべてを理解する」という姿勢は傲慢に感じられてしまう。「理解できない」という謙虚さで踏みとどまる領域があってもいいのではないだろうか。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【奇妙】大栗博司『重力とはなにか』は、相対性理論や量子力学の説明も秀逸だが、超弦理論の話が一番面白い
『重力とはなにか』(大栗博司)は、科学に馴染みの薄い人でもチャレンジできる易しい入門書だ。相対性理論や量子力学、あるいは超弦理論など、非常に難解な分野を基本的なところから平易に説明してくれるので、「科学に興味はあるけど難しいのはちょっと……」という方にこそ読んでほしい1冊
あわせて読みたい
【抵抗】映画『熊は、いない』は、映画製作を禁じられた映画監督ジャファル・パナヒの執念の結晶だ
映画『熊は、いない』は、「イラン当局から映画製作を20年間も禁じられながら、その後も作品を生み出し続けるジャファル・パナヒ監督」の手によるもので、彼は本作公開後に収監させられてしまった。パナヒ監督が「本人役」として出演する、「ドキュメンタリーとフィクションのあわい」を縫うような異様な作品だ
あわせて読みたい
【不穏】大友克洋の漫画『童夢』をモデルにした映画『イノセンツ』は、「無邪気な残酷さ」が恐ろしい
映画『イノセンツ』は、何がどう展開するのかまるで分からないまま進んでいく実に奇妙な物語だった。非現実的な設定で描かれるのだが、そのことによって子どもたちの「無邪気な残酷さ」が一層リアルに浮き彫りにされる物語であり、「意図的に大人が排除された構成」もその一助となっている
あわせて読みたい
【倫理】アート体験の行き着く未来は?映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』が描く狂気の世界(…
「『痛み』を失った世界」で「自然発生的に生まれる新たな『臓器』を除去するライブパフォーマンス」を行うソール・テンサーを主人公にした映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』は、すぐには答えの見出しにくい「境界線上にある事柄」を挑発的に描き出す、実に興味深い物語だ
あわせて読みたい
【狂気?】オウム真理教を内部から映す映画『A』(森達也監督)は、ドキュメンタリー映画史に残る衝撃作だ
ドキュメンタリー映画の傑作『A』(森達也)をようやく観られた。「オウム真理教は絶対悪だ」というメディアの報道が凄まじい中、オウム真理教をその内部からフラットに映し出した特異な作品は、公開当時は特に凄まじい衝撃をもたらしただろう。私たちの「当たり前」が解体されていく斬新な一作
あわせて読みたい
【驚嘆】映画『TAR/ター』のリディア・ターと、彼女を演じたケイト・ブランシェットの凄まじさ
天才女性指揮者リディア・ターを強烈に描き出す映画『TAR/ター』は、とんでもない作品だ。「縦軸」としてのターの存在感があまりにも強すぎるため「横軸」を上手く捉えきれず、結果「よく分からなかった」という感想で終わったが、それでも「観て良かった」と感じるほど、揺さぶられる作品だった
あわせて読みたい
【感想】これはドキュメンタリー(実話)なのか?映画『女神の継承』が突きつける土着的恐怖
ナ・ホンジンがプロデューサーを務めた映画『女神の継承』は、フィクションなのかドキュメンタリーなのか混乱させる異様な作品だった。タイ東北部で強く信じられている「精霊(ピー)」の信仰をベースに、圧倒的なリアリティで土着的恐怖を描き出す、強烈な作品
あわせて読みたい
【違和感】映画『コントラ』は、「よく分かんない」が「よく分かんないけど面白い」に変わる不思議な作品
ほぼ内容を知らないまま観に行った映画『コントラ』は、最後の最後まで結局何も理解できなかったが、それでもとても面白い作品だった。「後ろ向きに歩く男」が放つ違和感を主人公・ソラの存在感が中和させており、奇妙なのに可能な限り「日常感」を失わせずに展開させる構成が見事だと思う
あわせて読みたい
【異様】西成のあいりん地区を舞台にした映画『解放区』は、リアルとフェイクの境界が歪んでいる
ドキュメンタリー映画だと思って観に行った『解放区』は、実際にはフィクションだったが、大阪市・西成区を舞台にしていることも相まって、ドキュメンタリー感がとても強い。作品から放たれる「異様さ」が凄まじく、「自分は何を観せられているんだろう」という感覚に襲われた
あわせて読みたい
【驚異】甲子園「2.9連覇」を成し遂げた駒大苫小牧野球部監督・香田誉士史の破天荒で規格外の人生:『勝…
「田中将大と斎藤佑樹の死闘」「37年ぶりの決勝戦再試合」「驚異の2.9連覇」など話題に事欠かなかった駒大苫小牧野球部。その伝説のチームを率いた名将・香田誉士史の評伝『勝ちすぎた監督』は、体罰が問題になった男の毀誉褒貶を余すところなく描き出す。しかしとんでもない男だ
あわせて読みたい
【未知】「占い」が占い以外の効果を有するように、UFOなど「信じたいものを信じる」行為の機能を知れる…
「占い」に「見透かされたから仕方なく話す」という効用があるように、「『未知のもの』を信じる行為」には「『否定されたという状態』に絶対に達しない」という利点が存在する。映画『虚空門GATE』は、UFOを入り口に「『未知のもの』を信じる行為」そのものを切り取る
あわせて読みたい
【感想】阿部サダヲが狂気を怪演。映画『死刑にいたる病』が突きつける「生きるのに必要なもの」の違い
サイコパスの連続殺人鬼・榛村大和を阿部サダヲが演じる映画『死刑にいたる病』は、「生きていくのに必要なもの」について考えさせる映画でもある。目に光を感じさせない阿部サダヲの演技が、リアリティを感じにくい「榛村大和」という人物を見事に屹立させる素晴らしい映画
あわせて読みたい
【衝撃】洗脳を自ら脱した著者の『カルト脱出記』から、「社会・集団の洗脳」を避ける生き方を知る
「聖書研究に熱心な日本人証人」として「エホバの証人」で活動しながら、その聖書研究をきっかけに自ら「洗脳」を脱した著者の体験を著した『カルト脱出記』。広い意味での「洗脳」は社会のそこかしこに蔓延っているからこそ、著者の体験を「他人事」だと無視することはできない
あわせて読みたい
【要約】福岡伸一『生物と無生物のあいだ』は、「生命とは何か」を「動的平衡」によって定義する入門書…
「生命とは何か?」という、あまりに基本的だと感じられる問いは、実はなかなか難しい。20世紀生物学は「DNAの自己複製」が本質と考えたが、「ウイルス」の発見により再考を迫られた。福岡伸一の『生物と無生物のあいだ』『動的平衡』の2著作から、「生命の本質」を知る
あわせて読みたい
【生と死】不老不死をリアルに描く映画。「若い肉体のまま死なずに生き続けること」は本当に幸せか?:…
あなたは「不老不死」を望むだろうか?私には、「不老不死」が魅力的には感じられない。科学技術によって「不老不死」が実現するとしても、私はそこに足を踏み入れないだろう。「不老不死」が実現する世界をリアルに描く映画『Arc アーク』から、「生と死」を考える
あわせて読みたい
【感想】映画『若おかみは小学生!』は「子どもの感情」を「大人の世界」で素直に出す構成に号泣させられる
ネット記事を読まなければ絶対に観なかっただろう映画『若おかみは小学生!』は、基本的に子ども向け作品だと思うが、大人が観てもハマる。「大人の世界」でストレートに感情を表に出す主人公の小学生の振る舞いと成長に、否応なしに感動させられる
あわせて読みたい
【歴史】ベイズ推定は現代社会を豊かにするのに必須だが、実は誕生から200年間嫌われ続けた:『異端の統…
現在では、人工知能を始め、我々の生活を便利にする様々なものに使われている「ベイズ推定」だが、その基本となるアイデアが生まれてから200年近く、科学の世界では毛嫌いされてきた。『異端の統計学ベイズ』は、そんな「ベイズ推定」の歴史を紐解く大興奮の1冊だ
あわせて読みたい
【知的】文系にオススメの、科学・数学・哲学の入門書。高橋昌一郎の「限界シリーズ」は超絶面白い:『…
例えば「科学」だけに限ってみても、「なんでもできる」わけでは決してない。「科学」に限らず、私たちが対峙する様々な事柄には「これ以上は不可能・無理」という「限界」が必ず存在する。高橋昌一郎の「限界シリーズ」から、我々が認識しておくべき「限界」を易しく学ぶ
あわせて読みたい
【驚異】ガイア理論の提唱者が未来の地球を語る。100歳の主張とは思えない超絶刺激に満ちた内容:『ノヴ…
「地球は一種の生命体だ」という主張はかなり胡散臭い。しかし、そんな「ガイア理論」を提唱する著者は、数々の賞や学位を授与される、非常に良く知られた科学者だ。『ノヴァセン <超知能>が地球を更新する』から、AIと人類の共存に関する斬新な知見を知る
あわせて読みたい
【真実?】佐村河内守のゴーストライター騒動に森達也が斬り込んだ『FAKE』は我々に何を問うか?
一時期メディアを騒がせた、佐村河内守の「ゴースト問題」に、森達也が斬り込む。「耳は聴こえないのか?」「作曲はできるのか?」という疑惑を様々な角度から追及しつつ、森達也らしく「事実とは何か?」を問いかける『FAKE』から、「事実の捉え方」について考える
あわせて読みたい
【驚嘆】この物語は「AIの危険性」を指摘しているのか?「完璧な予知能力」を手にした人類の過ち:『預…
完璧な未来予知を行えるロボットを開発し、地震予知のため”だけ”に使おうとしている科学者の自制を無視して、その能力が解放されてしまう世界を描くコミック『預言者ピッピ』から、「未来が分からないからこそ今を生きる価値が生まれるのではないか」などについて考える
あわせて読みたい
【戸惑】人間の脳は摩訶不思議。意識ではコントロールできない「無意識の領域」に支配されている:『あ…
我々は決断や選択を「自分の意思」で行っていると感じるが、脳科学の研究はそれを否定している。我々に「自由意志」などない。「脳」の大部分は「意識以外のもの」に支配され、そこに「意識」はアクセスできないという驚愕の実態を『あなたの知らない脳』から学ぶ
あわせて読みたい
【バトル】量子力学の歴史はこの1冊で。先駆者プランクから批判者アインシュタインまですべて描く:『量…
20世紀に生まれた量子論は、時代を彩る天才科学者たちの侃々諤々の議論から生み出された。アインシュタインは生涯量子論に反対し続けたことで知られているが、しかし彼の批判によって新たな知見も生まれた。『量子革命』から、量子論誕生の歴史を知る
あわせて読みたい
【不可思議】心理学の有名な実験から、人間の”欠陥”がどう明らかになっていったかを知る:『心は実験で…
『心は実験できるか 20世紀心理学実験物語』では、20世紀に行われた心理学実験からインパクトのある10の実験を選び紹介している。心理学者でもある著者が「科学であって科学ではない」と主張する心理学という学問で、人間のどんな不可思議さがあぶり出されてきたのかを知る
あわせて読みたい
【限界】有名な「錯覚映像」で心理学界をザワつかせた著者らが語る「人間はいかに間違えるか」:『錯覚…
私たちは、知覚や記憶を頼りに社会を生きている。しかしその「知覚」「記憶」は、本当に信頼できるのだろうか?心理学の世界に衝撃を与えた実験を考案した著者らの『錯覚の科学』から、「避けられない失敗のクセ」を理解する
あわせて読みたい
【誤り】「信じたいものを信じる」のは正しい?映画『星の子』から「信じること」の難しさを考える
どんな病気も治す「奇跡の水」の存在を私は信じないが、しかし何故「信じない」と言えるのか?「奇跡の水を信じる人」を軽々に非難すべきではないと私は考えているが、それは何故か?映画『星の子』から、「何かを信じること」の難しさについて知る
あわせて読みたい
【未知】タコに「高度な脳」があるなんて初耳だ。人類とは違う進化を遂げた頭足類の「意識」とは?:『…
タコなどの頭足類は、無脊椎動物で唯一「脳」を進化させた。まったく違う進化を辿りながら「タコに心を感じる」という著者は、「タコは地球外生命体に最も近い存在」と書く。『タコの心身問題』から、腕にも脳があるタコの進化の歴史と、「意識のあり方」を知る。
あわせて読みたい
【到達】「ヒッグス粒子の発見」はなぜ大ニュースなのか?素粒子物理学の「標準模型」を易しく説明する…
「ヒッグス粒子の発見」はメディアでも大きく取り上げられたが、これが何故重要なのかを説明できる人はそう多くはないだろう。『強い力と弱い力 ヒッグス粒子が宇宙にかけた魔法を解く』をベースに、謎めいた「弱い力」を説明する「自発的対称性の破れ」を学ぶ
あわせて読みたい
【衝撃】森達也『A3』が指摘。地下鉄サリン事件を起こしたオウム真理教は社会を激変させた
「オウム真理教は特別だ、という理由で作られた”例外”が、いつの間にか社会の”前提”になっている」これが、森達也『A3』の主張の要点だ。異常な状態で続けられた麻原彰晃の裁判を傍聴したことをきっかけに、社会の”異様な”変質の正体を理解する。
あわせて読みたい
【驚嘆】人類はいかにして言語を獲得したか?この未解明の謎に真正面から挑む異色小説:『Ank: a mirror…
小説家の想像力は無限だ。まさか、「人類はいかに言語を獲得したか?」という仮説を小説で読めるとは。『Ank: a mirroring ape』をベースに、コミュニケーションに拠らない言語獲得の過程と、「ヒト」が「ホモ・サピエンス」しか存在しない理由を知る
あわせて読みたい
【加虐】メディアの役割とは?森達也『A』が提示した「事実を報じる限界」と「思考停止社会」
オウム真理教の内部に潜入した、森達也のドキュメンタリー映画『A』は衝撃を与えた。しかしそれは、宗教団体ではなく、社会の方を切り取った作品だった。思考することを止めた社会の加虐性と、客観的な事実など切り取れないという現実について書く
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
文化・芸術・将棋・スポーツ【本・映画の感想】 | ルシルナ
知識や教養は、社会や学問について知ることだけではありません。文化的なものもリベラルアーツです。私自身は、創作的なことをしたり、勝負事に関わることはありませんが、…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…


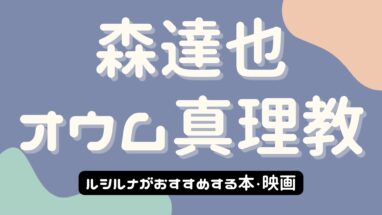


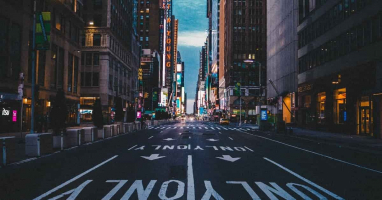


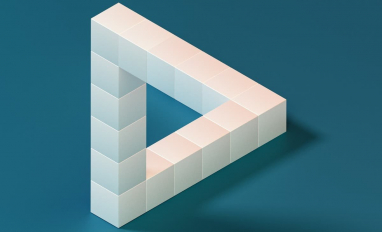
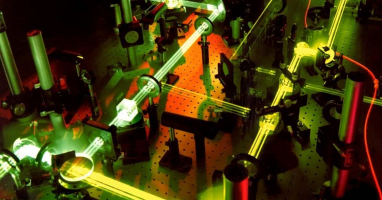




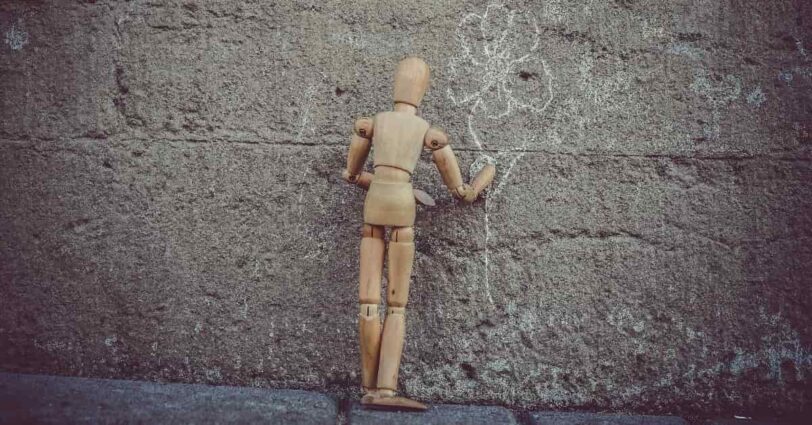


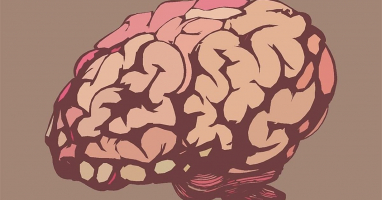
























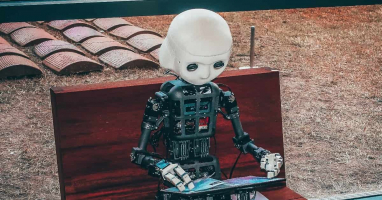

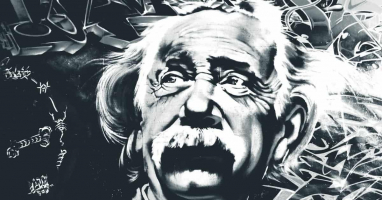




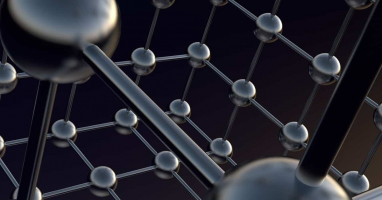













コメント