目次
はじめに
この記事で取り上げる本
著:チャブリス,クリストファー, 著:シモンズ,ダニエル, 原著:Chabris,Christopher, 原著:Simons,Daniel, 翻訳:博江, 木村
¥968 (2021/09/15 05:59時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
この本をガイドにしながら記事を書いていきます
この記事の3つの要点
- 著者らが考案した「衝撃の実験」をYoutubeで体感する
- 全人類に配布すべき、生きる上での教科書
- 人間の知覚や記憶は容易にミス・エラーを起こす
「努力で避けられない人間の欠陥」を知っておくことで、致命的なトラブルを回避できるようになるはずだ
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を…
Kindleで本を出版しました。タイトルは、『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を分かりやすく書いた本:相対性理論も宇宙論も量子論も』です。科学や科学者に関する、文系の人でも読んでもらえる作品に仕上げました。そんな自著について紹介をしています。
致命的なミスをしないために知っておくべき「人間が避けられない失敗のクセ」が記された『錯覚の科学』
心理学の世界に衝撃を与えた実験を、Youtubeで体感する
あわせて読みたい
【知的】「BLって何?」という初心者に魅力を伝える「腐男子」の「BLの想像力と創造力」講座:『ボクた…
「BLは知的遊戯である」という主張には「は?」と感じてしまうでしょうが、本書『ボクたちのBL論』を読めばその印象は変わるかもしれません。「余白の発見と補完」を通じて、「ありとあらゆる2者の間の関係性を解釈する」という創造性は、現実世界にどのような影響を与えているのか
本書の著者2人は、後に教科書にも載ることになったある実験を行い、心理学の世界に衝撃を与えた。本書ではそんな著者らが、心理学的な知見を紹介し、人間がどのようなエラーを起こしやすいか、どんなミスをしてしまい得るかについて、様々な実例を挙げながら紹介していく。

まずは、著者らが行い、心理学界をザワつかせた実験をYoutubeの動画を使って体感してみよう。
以下のYoutubeのリンクをクリックすると、ある動画が流れる。英語で指示が表記されるので、まずその指示を以下に日本語で書いておこう。
あわせて読みたい
【狂気?】オウム真理教を内部から映す映画『A』(森達也監督)は、ドキュメンタリー映画史に残る衝撃作だ
ドキュメンタリー映画の傑作『A』(森達也)をようやく観られた。「オウム真理教は絶対悪だ」というメディアの報道が凄まじい中、オウム真理教をその内部からフラットに映し出した特異な作品は、公開当時は特に凄まじい衝撃をもたらしただろう。私たちの「当たり前」が解体されていく斬新な一作
動画には6人の女性が登場する。3人が白いTシャツを、3人が黒いTシャツを着ている。彼女たちが、2つのバスケットボールのパス回しをするので、「白いTシャツを着た3人のパス回しの回数」を正確にカウントしてほしい。
やることはそれだけだ。では、以下の映像を見てみよう。
結果についてはここでは触れないが、著者らの実験でも、その後別のグループが行った追試でも、被験者の半分は「衝撃を受ける」そうだ。かくいう私も、「衝撃を受けた側」である。
あわせて読みたい
【戸惑】人間の脳は摩訶不思議。意識ではコントロールできない「無意識の領域」に支配されている:『あ…
我々は決断や選択を「自分の意思」で行っていると感じるが、脳科学の研究はそれを否定している。我々に「自由意志」などない。「脳」の大部分は「意識以外のもの」に支配され、そこに「意識」はアクセスできないという驚愕の実態を『あなたの知らない脳』から学ぶ
被験者の半分は「衝撃を受けない」そうなので、もしかしたらあなたも「衝撃を受けなかった側」かもしれないが、だからといって他の「エラー」や「ミス」も回避しやすい、というわけでは決してない。本書で指摘されていることはきちんと理解しておこう。
全人類が読むべき「人生の教科書」
大げさかもしれないが、本書は、世界中の人々に配られるべきではないかと思う。本書そのものでなくとも、その要約を図示したようなものでもいい。
本書は、日常の様々な場面で、「人間はこんなエラーを犯しがち」とあらかじめ警告してくれる。先程の動画で「衝撃を受けた側」の人であれば、この意味がより強く理解できるだろう。ちゃんと見ていると思っても見えていないし、ちゃんと覚えていると思っても覚えていない。人間には残念ながら、そのような欠陥がもともと備わっているのだ。
あわせて読みたい
【未知】タコに「高度な脳」があるなんて初耳だ。人類とは違う進化を遂げた頭足類の「意識」とは?:『…
タコなどの頭足類は、無脊椎動物で唯一「脳」を進化させた。まったく違う進化を辿りながら「タコに心を感じる」という著者は、「タコは地球外生命体に最も近い存在」と書く。『タコの心身問題』から、腕にも脳があるタコの進化の歴史と、「意識のあり方」を知る。
本書を読めば読むほど、自分の知覚や記憶への信頼感を失っていくだろう。そして、「知覚や記憶は信頼が置けないものだ」という事実は、社会の共通認識であるべきだとも感じた。だからこそ、社会に生きるすべての人が読むべき本だと思うのだ。
あとで紹介するが、「自分が明確に記憶していること」が、有無を言わさず誤りだったと判明する事例がある。つまり人間は、「自分の都合の良いように記憶を書き換えてしまう生き物」というわけだ。そして、このことが共通認識として存在しなければ、「私の記憶ではそうなっている」という誰かの主張をどうやっても突き崩せないことになってしまう。
私たちはもちろん、知覚や記憶を通じて他人や社会と関わっている。そして自分が感じたこと、覚えていることを、疑う機会はなかなかない。しかし、自分が「正しい」と信じていることが、実はまったくの間違いでしかない可能性もあるということなのだ。
日常の中でこのことを実感する機会があるとすれば、既に何か大きなトラブルが引き起こされてしまっている可能性が高いだろう。そうならないためにも、あらかじめ私たちは、「人間が避けられない失敗のクセ」を知り、ゼロにはできないにせよ、事前に注意を向けておくという姿勢が重要ではないかと思うのだ。
あわせて読みたい
【要約】福岡伸一『生物と無生物のあいだ』は、「生命とは何か」を「動的平衡」によって定義する入門書…
「生命とは何か?」という、あまりに基本的だと感じられる問いは、実はなかなか難しい。20世紀生物学は「DNAの自己複製」が本質と考えたが、「ウイルス」の発見により再考を迫られた。福岡伸一の『生物と無生物のあいだ』『動的平衡』の2著作から、「生命の本質」を知る
それでは以下では、各章の章題を見出しにしながら、どのような事例が紹介されるのかに触れていこうと思う。
えひめ丸はなぜ沈没したのか? 注意の錯覚
この章で扱われるのは、「視界に入っているのに『見えていない』」という事例である。章題にある「えひめ丸」はアメリカ海軍の原子力潜水艦に衝突されて沈没したのだが、潜水艦の艦長は明らかに視界の先に存在したはずの「えひめ丸」を「見えなかった」と証言したのだ。

別の事例として、偽証罪で起訴されたアメリカの警官が取り上げられる。その警官は、逃走中の被疑者を追跡中だったのが、同じ頃、別の警官がある行き違いからその被疑者と誤認され、警官仲間にボコボコにされていた。起訴された警官はその現場を目撃したはずなのに、「自分は見なかった」と証言し、偽証罪に問われた。
このように、「視界に入っていること」と「見えていること」は決してイコールではないことが、様々な事例を通じて示されるのだ。
あわせて読みたい
【ドラマ】「フェルマーの最終定理」のドラマティックな証明物語を、飲茶氏が平易に描き出す:『哲学的…
「フェルマーの最終定理」は、問題の提示から350年以上経ってようやく証明された超難問であり、その証明の過程では様々な人間ドラマが知られている。『哲学的な何か、あと数学とか』をベースに、数学的な記述を一切せず、ドラマティックなエピソードだけに触れる
他にも、我々の生活にもっと身近な話題も取り上げられる。
私は車を運転しないのでほとんど経験はないが、車を日常的に運転する人であれば、「バイクが突然飛び出してくる」という状況に遭遇することがあるだろう。これはもちろん、ドライバーの確認不足というケースもある。しかし、「視界には入っているが『見えていない』」場合もある。
なぜそうなってしまうのか。それは「バイクが自動車の形に似ていないから」だという。ドライバーにとって「車」は馴染みの存在だが、「バイク」はそうではない。人間というのは、「そこにあると予期できるもの」は見落とさないが、「そこにあると予期しにくいもの」は、視界に入っていても見落としてしまうということのようだ。
あわせて読みたい
【驚異】数学の「無限」は面白い。アキレスと亀の矛盾、実無限と可能無限の違い、カントールの対角線論…
日常の中で「無限」について考える機会などなかなか無いだろうが、野矢茂樹『無限論の教室』は、「無限には種類がある」と示すメチャクチャ興味深い作品だった。「実無限」と「可能無限」の違い、「可能無限」派が「カントールの対角線論法」を拒絶する理由など、面白い話題が満載の1冊
これは、歩行者と自転車に関しても同じことが言える。都市部ほど自転車での移動が頻繁なので、事故も多くなると予想するかもしれない。しかし実はアメリカでは、歩行者と自転車の事故は、都市部で最も少ないという結果が出ている。これについては、歩行者が自転車の存在を見慣れているために、視界に入った自転車をすぐに「認識する」ことができるからだろうと考えられているようだ。
しかし不思議に思わないだろうか? こんな「注意の錯覚」を抱えながら、人類はどうしてここまで生き残ってこられたのか、と。
実は、この「注意の錯覚」が現れるようになったのは最近のことだという。つまり、現代社会の生活があまりに複雑であり、「人間の注意の限界」まで達してしまっている、ということなのだ。
あわせて読みたい
【新視点】世界の歴史を「化学」で語る?デンプン・砂糖・ニコチンなどの「炭素化合物」が人類を動かし…
デンプン・砂糖・ニコチンなどは、地球上で非常に稀少な元素である「炭素」から作られる「炭素化合物」だ。そんな「炭素化合物」がどんな影響を与えたかという観点から世界の歴史を描く『「元素の王者」が歴史を動かす』は、学校の授業とはまったく違う視点で「歴史」を捉える
人類が進化してきた過程では、人類の生活環境は今ほど複雑ではなかった。船に乗っていたら潜水艦が下から突き上げてくることも、車に乗っていたら横からバイクが突然飛び出してきたりすることなど起こらなかったのである。だから「注意力」をそこまで酷使せずに済んだ。
しかし現代社会は、人類が進化の過程で手に入れたものを遥かに超える注意力が要求される環境であるが故に、「エラー」がて現れてしまっているのだと指摘されている。
捏造されたヒラリーの戦場体験 記憶の錯覚
この章では、「人間の記憶はいかに曖昧か」の実例が紹介される。ヒラリー・クリントンが繰り返し語っていた「戦場体験」は真っ赤な嘘だったと判明したのが、本人にとっては「正しい記憶」だった可能性があるというわけだ。
あわせて読みたい
【快挙】「チバニアン」は何が凄い?「地球の磁場が逆転する」驚異の現象がこの地層を有名にした:『地…
一躍その名が知れ渡ることになった「チバニアン」だが、なぜ話題になり、どう重要なのかを知っている人は多くないだろう。「チバニアン」の申請に深く関わった著者の『地磁気逆転と「チバニアン」』から、地球で起こった過去の不可思議な現象の正体を理解する
この章で非常に印象的な話は、バスケットボールのコーチに関するエピソードである。

バスケットボール選手の1人がある時、「コーチに首を締められた」と訴え、その時の状況を事細かに語った。しかし、その場にいた他の選手は、コーチが首を締めたなどという事実はなかった、と証言する。
決定的な証拠がなく、両者の言い分は平行線のままだったが、その数年後、その時の状況を映したビデオが偶然発見された。そして、首を締められたという選手の証言は誤りだと判明したのだ。しかしその後もその選手は、「自分の記憶では、コーチに首を締められたことに間違いない」と主張し続けたという。
あわせて読みたい
【天才】『ご冗談でしょう、ファインマンさん』は、科学者のイメージが変わる逸話満載の非・科学エッセイ
「天才科学者」と言えばアインシュタインやニュートン、ホーキングが思い浮かぶだろうが、「科学者らしくないエピソード満載の天才科学者」という意味ではファインマンがずば抜けている。世界的大ベストセラー『ご冗談でしょう、ファインマンさん』は、「科学」をほぼ扱わないエッセイです
もちろん、この選手が嘘をついている可能性はゼロではないが、この章では他にも、人間の記憶がいかに曖昧なものであるかを示す実験が紹介されている。
例えばこんな実験がある。ごく一般的な「研究室」に案内された被験者に、30秒間その部屋に留まってもらう。そして別室に移動した後で、唐突に「研究室には何がありましたか?」と質問される。被験者は、「本」「ファイルキャビネット」などがあったと答えるのだが、それらは実際には「研究室」には存在しなかった。これはどう説明されるだろうか?
人間は、「予期できるものを記憶することが多い」という。つまり、「研究室だったらこんなものがあるだろうと予期できるもの」を「思い出す」ということだ。思い込みによって、記憶が書き換わったしまうというわけである。
あわせて読みたい
【貢献】有名な科学者は、どんな派手な失敗をしてきたか?失敗が失敗でなかったアインシュタインも登場…
どれほど偉大な科学者であっても失敗を避けることはできないが、「単なる失敗」で終わることはない。誤った考え方や主張が、プラスの効果をもたらすこともあるのだ。『偉大なる失敗』から、天才科学者の「失敗」と、その意外な「貢献」を知る
また、こんな長期に渡る実験も行われている。「フラッシュバブル記憶」とは、物凄く印象的な出来事が起きた日のことは他の日よりも鮮明に記憶していることを指すのだが、その「フラッシュバブル記憶」さえ改ざんされてしまうことを示す実験だ。
アメリカで、9.11のテロ直後に、「9.11の時、あなたはどこで何をしていましたか?」と様々な人に質問をし、その答えを記録した。そして数年後、同じ人に再び同じ質問をし、その答えを記録する。
なんと、時間をおいた2つの回答が食い違う被験者が多かったという。さらに被験者に、「数年前、9.11直後のあなたはこう答えていますよ」と記録した答えを見せても、被験者の多くは、「今の自分の記憶の方が正しい」と感じるのだという。どう考えても9.11直後に答えた方が正しい可能性が高いはずだが、昔の記憶よりも上書きされてしまった今の記憶の方を正しいと感じるというのは、印象的だった。
あわせて読みたい
【逸話】天才数学者ガロアが20歳で決闘で命を落とすまでの波乱万丈。時代を先駆けた男がもし生きていた…
現代数学に不可欠な「群論」をたった1人で生み出し、20歳という若さで決闘で亡くなったガロアは、その短い生涯をどう生きたのか?『ガロア 天才数学者の生涯』から、数学に関心を抱くようになったきっかけや信じられないほどの不運が彼の人生をどう変えてしまったのか、そして「もし生きていたらどうなっていたのか」を知る
また、実験の話ではないが、映画の話題も取り上げられる。映画ではよく、単なるミスによって前後の繋がりがおかしな場面がある。例えば、『プリティ・ウーマン』で有名なのは、ジュリア・ロバーツがクロワッサンをつまんだ直後、口にパンケーキを入れる場面に変わるミスだという。
しかし人間は、このような映像を見てもあまり違和感を覚えない。それは「変化の見落とし」と呼ばれている。予期していない変化には気づけないことの方が多いし、また、「自分が見落としをするはずがない」という思い込みもその見落としを助長するのだという。
私にも、こんな話がある。私は子どもの頃、足の骨を3度ほど折り、松葉杖をついて学校に通った記憶がある。しかし両親とも、「そんな事実はない」というのである。1度もない、というのだ。両親いわく、「足を折ったら、学校に送り迎えをしなければならないが、そんなことをした記憶はない。だからお前は足を折っていない」ということのようだ。
あわせて読みたい
【神秘】脳研究者・池谷裕二が中高生向けに行った講義の書籍化。とても分かりやすく面白い:『進化しす…
「宇宙」「深海」「脳」が、人類最後のフロンティアと呼ばれている。それほど「脳」というのは、未だに分からないことだらけの不思議な器官だ。池谷裕二による中高生向けの講義を元にした『進化しすぎた脳』『単純な脳、複雑な「私」』をベースに、脳の謎を知る
この記憶の食い違いは、未だに決着がついていない。どちらかが間違っている(あるいは両方間違っている)のだが、真相が判明する機会は果たして来るだろうか。
冤罪証言はこうして作られた 自信の錯覚
この章では、自信と能力と信頼の関係性が描かれる。
こんな状況について考えてみてほしい。これは著者の1人の実体験だそうだ。
病院に行き医師の診察を受ける時、その医師があなたを診断しながら参考書も見ているとしよう。あなたはきっとこう感じるに違いない。参考書を見ながら診断するような医師を信頼して大丈夫だろうか? と。
あわせて読みたい
【バトル】量子力学の歴史はこの1冊で。先駆者プランクから批判者アインシュタインまですべて描く:『量…
20世紀に生まれた量子論は、時代を彩る天才科学者たちの侃々諤々の議論から生み出された。アインシュタインは生涯量子論に反対し続けたことで知られているが、しかし彼の批判によって新たな知見も生まれた。『量子革命』から、量子論誕生の歴史を知る

確かに想像してみると、私も著者と同じように不安を抱くかもしれない。一方で、自信満々な態度で診断をする医師に当たれば、信頼感を抱くだろうと思う。
しかし当たり前だが、自信と能力に関係はない。しかも心理学的には、「能力が低い者ほど自信過剰になる」という実験結果が複数存在するのだという。
確かに考えてみればそのことは理解できるだろう。
あわせて読みたい
【歴史】ベイズ推定は現代社会を豊かにするのに必須だが、実は誕生から200年間嫌われ続けた:『異端の統…
現在では、人工知能を始め、我々の生活を便利にする様々なものに使われている「ベイズ推定」だが、その基本となるアイデアが生まれてから200年近く、科学の世界では毛嫌いされてきた。『異端の統計学ベイズ』は、そんな「ベイズ推定」の歴史を紐解く大興奮の1冊だ
知識や経験があればあるほど、様々なケースを知ることになるし、やるべきこと・対処しなければならないことが膨大だと理解していることになる。知識や経験があればあるほど能力も高いと言っていいだろうが、一方で、直面する状況の難しさを知っているが故に自信は低くなっていくかもしれない。
一方、知識や経験が無ければ無いほど、知らないことが多い。そして性格にもよるだろうが、「知らないからこそ臆することなく自信を持って臨める」というタイプの人も存在するだろう。だからこそ、「能力が低い者ほど自信過剰になる」という状況が生まれてしまう。
ここまで考えれば、先ほどの「参考書を見ながら診断する医師」は、むしろ信頼できると考えていいはずだ。しかし直感的には、我々はなかなかそう考えることができない。
あわせて読みたい
【理解】小野田寛郎を描く映画。「戦争終結という現実を受け入れない(=認知的不協和)」は他人事じゃ…
映画『ONODA 一万夜を越えて』を観るまで、小野田寛郎という人間に対して違和感を覚えていた。「戦争は終わっていない」という現実を生き続けたことが不自然に思えたのだ。しかし映画を観て、彼の生き方・決断は、私たちと大きく変わりはしないと実感できた
また、自信を放つ人に信頼が集まる、という実験結果も多数存在する。確かにイメージできる話である。そしてその実例としてこの章では、章題にもなっている「レイプの冤罪事件」が取り上げられる。
被害女性はレイプされている間、犯人の顔を長時間見つめ完璧に記憶することに努めたという。そしてその後、レイプ犯と思われる容疑者が割り出され、その女性は法廷に証言者として立った。彼女は自信満々に堂々と、被告が自分をレイプした犯人だと証言したため、他の証拠は一切存在しなかったが、その被告の有罪が確定した。しかし10年以上も経ってから、冤罪であることが判明したのだという。
被害女性があまりにも堂々としていたからこそ、誰もがその証言を信頼したわけだが、それは誤りだと分かった。つまり、「自信があること」を能力や信頼の根拠として捉えるのは危険だということだ。
あわせて読みたい
【研究】光の量子コンピュータの最前線。量子テレポーテーションを実現させた科学者の最先端の挑戦:『…
世界中がその開発にしのぎを削る「量子コンピューター」は、技術的制約がかなり高い。世界で初めて「量子テレポーテーション」の実験を成功させた研究者の著書『光の量子コンピューター』をベースに、量子コンピューター開発の現状を知る
リーマン・ショックを招いた投資家の誤算 知識の錯覚
この章では、「人間は自分の能力を過大に評価しがちだ」ということが指摘される。
冒頭で、ヒトゲノム(人間の遺伝子)研究に関するエピソードが取り上げられる。人間は他の生物と比べて知能が高いので、遺伝子も多いと考えられていた。「ヒトゲノム計画」と呼ばれる、人間の遺伝子をすべて明らかにするプロジェクトが始まった当初は、人間の遺伝子は10万個以上あると思われていたが、実際には2万5000個以下だと判明する。これは、イネ科の植物の遺伝子数より少ないし、ウニの遺伝子とほぼ同じらしい。
章題となっている投資家に関しては、このような実験結果が知られている。株取引を模した実験によって、「与えられた情報が少ないほど儲けが多い」という結果が出たのだ。一般的には、情報が多ければ多いほど正しい判断ができると考えられているだろうが、この思い込みは間違っていると言えそうだ。
あわせて読みたい
【具体例】行動経済学のおすすめ本。経済も世界も”感情”で動くと実感できる「人間の不合理さ」:『経済…
普段どれだけ「合理的」に物事を判断しているつもりでも、私たちは非常に「不合理的」な行動を取ってしまっている。それを明らかにするのが「行動経済学」だ。『経済は感情で動く』『世界は感情で動く』の2冊をベースにして、様々な具体例と共に「人間の不思議さ」を理解する
そして投資家の、「自分は多くの情報を有しているから正しい判断ができる」という思い込みが、結果としてリーマンショックを引き起こすことになったのだと指摘される。
このような「知識の錯覚」が無くならない要因の一つは、社会が専門家をもてはやすからだと著者は言う。専門家というのは「実際以上に知識があると思い込んでいる人物」であり、そういう人物が必要とされるからこそ、「知識の錯覚」が延々と再生産されてしまうことになるのだと。
専門家の意見を”安易に”求める風潮は改めるべきだと言えそうだ。
俗説、デマゴーグ、そして陰謀論 原因の錯覚
この章では、「人間はいかにデマに騙されやすいか」が描かれる。コロナワクチンに関するデマが出回っている(らしい)現代においては、まさに無視できない章と言えるだろう。
あわせて読みたい
【危険】遺伝子組換え作物の問題点と、「食の安全」を守るために我々ができることを正しく理解しよう:…
映画『食の安全を守る人々』では、世界的バイオ企業「モンサント社」が作る除草剤「ラウンドアップ」の問題を中心に、「食の安全」の現状が映し出される。遺伝子組み換え作物や輸入作物の残留農薬など、我々が口にしているものの「実態」を理解しよう
冒頭では、「アメリカにおけるはしかの流行」が扱われる。これがどのように「デマ」と関係するのかは長い説明を要するので省略するが、要するに、「デマのせいではしかのワクチンを子どもに打たせない親が多いから」ということなのだ。アメリカでは、「はしかのワクチンを打つと自閉症になる」というデマが根強く存在するのだという。
デマに騙されてしまうのは、「相関関係」と「因果関係」を捉え間違えるからだ。人間は、前後に起こった出来事を「原因と結果」だと捉えてしまいがちだ。本書に載っている例ではないが、以前こんな話を読んだことがある。

どこかの団体が、「朝ごはんを食べれば子どもの成績が上がります。だから朝ごはんを食べましょう」というキャンペーンを行った。実際に、「朝ごはんを食べる子どもは、学校の成績がいい」という科学的なデータが存在する。しかしこのキャンペーンは誤りだ。何故だか分かるだろうか?
実際はこうだ。成績の良い子どもは、家庭学習もきちんとしていることが多い。そして、家庭学習がちゃんと行われている家では、当たり前のように朝ごはんが出てくる(家庭環境がきちんとしている、という意味だ)。
あわせて読みたい
【証明】結城浩「数学ガール」とサイモン・シンから「フェルマーの最終定理」とそのドラマを学ぶ
350年以上前に一人の数学者が遺した予想であり「フェルマーの最終定理」には、1995年にワイルズによって証明されるまでの間に、これでもかというほどのドラマが詰め込まれている。サイモン・シンの著作と「数学ガール」シリーズから、その人間ドラマと数学的側面を知る
つまり、「朝ごはんを食べるから成績が良い」のではなく、「成績が良い子の家では朝ごはんが出てくる」というわけなのである。因果関係を逆に捉えてしまっているというわけだ。
本書では、こんな例が紹介される。「アイスクリームの売上」が多い日は、「海難事故」が増えるのだが、「アイスクリーム」と「海難事故」に直接の関係がないことは誰でも分かるだろう。あなたはこれを説明できるだろうか?
要点は、「夏の暑さ」である。暑い日には「アイスクリーム」もたくさん売れるし、海に行く人が増えるから「海難事故」も多くなる。「アイスクリーム」と「海難事故」に関係があるのではなく、「夏の暑さ」と「アイスクリーム・海難事故」に関係がある、というわけだ。
気をつけていないと、原因と結果と捉え間違えたり、因果関係と相関関係を混同したりしてしまう。データや知識が正しくても、それを正しく解釈する方法を知らなければ、デマに騙されてしまうのである。この事実は、どれだけ気をつけても気をつけすぎということはないので注意しよう。
あわせて読みたい
【衝撃】ABC予想の証明のために生まれたIUT理論を、提唱者・望月新一の盟友が分かりやすく語る:『宇宙…
8年のチェック期間を経て雑誌に掲載された「IUT理論(宇宙際タイヒミュラー理論)」は、数学の最重要未解決問題である「ABC予想」を証明するものとして大いに話題になった。『宇宙と宇宙をつなぐ数学』『abc予想入門』をベースに、「IUT理論」「ABC予想」について学ぶ
自己啓発、サブリミナル効果のウソ 可能性の錯覚
この章では、「『人間の能力にはさらなる可能性がある』という主張を受け入れてしまう」という状況が描かかれる。
冒頭では、「モーツアルトを聞くと頭が良くなる」という俗説が取り上げられる。人間は、「自分にはまだ可能性がある」と信じていたいし、そして「その可能性が何か簡単な方法で開花したらいい」という淡い希望を持っている。だからこそ、「モーツアルトを聞けば頭が良くなる」という、まさにこの条件をピッタリ満たすような俗説が根強く残ってしまう、というわけだ。

あわせて読みたい
【究極】リサ・ランドールが「重力が超弱い理由」を解説する、超刺激的なひも理論の仮説:『ワープする…
現役の研究者であるリサ・ランドールが、自身の仮説を一般向けに分かりやすく説明する『ワープする宇宙』。一般相対性理論・量子力学の知識を深く記述しつつ「重力が超弱い理由」を説明する、ひも理論から導かれる「ワープする余剰次元」について解説する
また本書では、心理学の実験として非常に有名な「サブリミナル効果」も取り上げられる。映画上映中に、人間には意識できない短いカットを差し込むことで、鑑賞後にコーラを飲みたい気分にさせることができる、というものだ。
しかしこの実験はなんと、いんちきだということが判明しているのだ。というか、実験を行ったという人物が、「仕事がうまくいかずにむしゃくしゃしていたから、実験をでっちあげた」と証言しているのだという。
しかし、「人間の可能性」に対する盲信が強いが故に、この「サブリミナル効果」も未だに広く信じられている(私も本書を読むまで信じていた)。
自分にとって都合の良い情報ほど、疑って掛かった方が良さそうだ。
あわせて読みたい
【解説】テネットの回転ドアの正体を分かりやすく考察。「時間逆行」ではなく「物質・反物質反転」装置…
クリストファー・ノーラン監督の映画『TENET/テネット』は、「陽電子」「反物質」など量子力学の知見が満載です。この記事では、映画の内容そのものではなく、時間反転装置として登場する「回転ドア」をメインにしつつ、時間逆行の仕組みなど映画全体の設定について科学的にわかりやすく解説していきます
著:チャブリス,クリストファー, 著:シモンズ,ダニエル, 原著:Chabris,Christopher, 原著:Simons,Daniel, 翻訳:博江, 木村
¥968 (2022/01/29 21:39時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品読了済】私が読んできたノンフィクション・教養書を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が読んできたノンフィクションを様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本選びの参考にして下さい。
最後に
あわせて読みたい
【誤解】「意味のない科学研究」にはこんな価値がある。高校生向けの講演から”科学の本質”を知る:『す…
科学研究に対して、「それは何の役に立つんですか?」と問うことは根本的に間違っている。そのことを、「携帯電話」と「東急ハンズの棚」の例を使って著者は力説する。『すごい実験』は素粒子物理学を超易しく解説する本だが、科学への関心を抱かせてもくれる
ここまでで、様々な事例を紹介してきたが、最後に、「人間には何故このような『錯覚』が存在するのか」に軽く触れて終わろうと思う。
本書には、こんな風に書かれている。
あわせて読みたい
【奇妙】大栗博司『重力とはなにか』は、相対性理論や量子力学の説明も秀逸だが、超弦理論の話が一番面白い
『重力とはなにか』(大栗博司)は、科学に馴染みの薄い人でもチャレンジできる易しい入門書だ。相対性理論や量子力学、あるいは超弦理論など、非常に難解な分野を基本的なところから平易に説明してくれるので、「科学に興味はあるけど難しいのはちょっと……」という方にこそ読んでほしい1冊
錯覚は私たちの能力の限界から生じるものだが、この限界にはたいてい対価としてのメリットがある。
瞬間的な認識をつかさどる私たちの脳は、進化のもとになった問題の解決には力を発揮するが、現在の私たちの文化も社会もテクノロジーも、先祖の時代よりはるかに複雑化している。多くの場合、直感は現代社会の問題解決に十分適応できない
あわせて読みたい
【幸福】「死の克服」は「生の充実」となり得るか?映画『HUMAN LOST 人間失格』が描く超管理社会
アニメ映画『HUMAN LOST 人間失格』では、「死の克服」と「管理社会」が分かちがたく結びついた世界が描かれる。私たちは既に「緩やかな管理社会」を生きているが、この映画ほどの管理社会を果たして許容できるだろうか?そしてあなたは、「死」を克服したいと願うだろうか?
つまりこういうことだ。
「何かが出来ないこと」で「錯覚」が生み出されることになるわけだが、その「出来ないこと」は別の場面において人間にとってメリットとなる。だから、メリットをもたらす「何かが出来ないこと」の副作用としての「錯覚」は、許容するしかないというわけだ。
あわせて読みたい
【未知】「占い」が占い以外の効果を有するように、UFOなど「信じたいものを信じる」行為の機能を知れる…
「占い」に「見透かされたから仕方なく話す」という効用があるように、「『未知のもの』を信じる行為」には「『否定されたという状態』に絶対に達しない」という利点が存在する。映画『虚空門GATE』は、UFOを入り口に「『未知のもの』を信じる行為」そのものを切り取る
また、人類は進化の過程で、目の前の問題に対処するための様々な解決策を生み出してきた。それらの解決策は、該当する問題を処理するのには実に上手く働く。しかし同じ解決策が別の場面に適用されてしまうと、それがエラーとして表に出てしまう。先祖にとっては「便利な解決法」だったものが、複雑な現代社会に生きる我々にとっては「厄介なエラー」になってしまう、というわけだ。
人間社会は急激に進化したが、その変化に人類の遺伝子はまだ追いつけていない。我々は、このようなエラーを抱えたまま生きていくしかないだろう。
あわせて読みたい
【驚異】数学の「無限」は面白い。アキレスと亀の矛盾、実無限と可能無限の違い、カントールの対角線論…
日常の中で「無限」について考える機会などなかなか無いだろうが、野矢茂樹『無限論の教室』は、「無限には種類がある」と示すメチャクチャ興味深い作品だった。「実無限」と「可能無限」の違い、「可能無限」派が「カントールの対角線論法」を拒絶する理由など、面白い話題が満載の1冊
だからこそ、どのような場面でどんなエラーが発動しやすいのかを知っておくことは重要だ。それによって、トラブルや人命の喪失を回避できる可能性があるのだから。
大げさではなく、全人類が読むべき一冊だと思う。
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を…
Kindleで本を出版しました。タイトルは、『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を分かりやすく書いた本:相対性理論も宇宙論も量子論も』です。科学や科学者に関する、文系の人でも読んでもらえる作品に仕上げました。そんな自著について紹介をしています。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【奇妙】大栗博司『重力とはなにか』は、相対性理論や量子力学の説明も秀逸だが、超弦理論の話が一番面白い
『重力とはなにか』(大栗博司)は、科学に馴染みの薄い人でもチャレンジできる易しい入門書だ。相対性理論や量子力学、あるいは超弦理論など、非常に難解な分野を基本的なところから平易に説明してくれるので、「科学に興味はあるけど難しいのはちょっと……」という方にこそ読んでほしい1冊
あわせて読みたい
【狂気?】オウム真理教を内部から映す映画『A』(森達也監督)は、ドキュメンタリー映画史に残る衝撃作だ
ドキュメンタリー映画の傑作『A』(森達也)をようやく観られた。「オウム真理教は絶対悪だ」というメディアの報道が凄まじい中、オウム真理教をその内部からフラットに映し出した特異な作品は、公開当時は特に凄まじい衝撃をもたらしただろう。私たちの「当たり前」が解体されていく斬新な一作
あわせて読みたい
【知的】「BLって何?」という初心者に魅力を伝える「腐男子」の「BLの想像力と創造力」講座:『ボクた…
「BLは知的遊戯である」という主張には「は?」と感じてしまうでしょうが、本書『ボクたちのBL論』を読めばその印象は変わるかもしれません。「余白の発見と補完」を通じて、「ありとあらゆる2者の間の関係性を解釈する」という創造性は、現実世界にどのような影響を与えているのか
あわせて読みたい
【実話】実在の人物(?)をモデルに、あの世界的超巨大自動車企業の”内実”を暴く超絶面白い小説:『小…
誰もが知るあの世界的大企業をモデルに据えた『小説・巨大自動車企業トヨトミの野望』は、マンガみたいなキャラクターたちが繰り広げるマンガみたいな物語だが、実話をベースにしているという。実在の人物がモデルとされる武田剛平のあり得ない下剋上と、社長就任後の世界戦略にはとにかく驚かされる
あわせて読みたい
【驚異】数学の「無限」は面白い。アキレスと亀の矛盾、実無限と可能無限の違い、カントールの対角線論…
日常の中で「無限」について考える機会などなかなか無いだろうが、野矢茂樹『無限論の教室』は、「無限には種類がある」と示すメチャクチャ興味深い作品だった。「実無限」と「可能無限」の違い、「可能無限」派が「カントールの対角線論法」を拒絶する理由など、面白い話題が満載の1冊
あわせて読みたい
【挑戦】相対性理論の光速度不変の原理を無視した主張『光速より速い光』は、青木薫訳だから安心だぞ
『光速より速い光』というタイトルを見て「トンデモ本」だと感じた方、安心してほしい。「光速変動理論(VSL理論)」が正しいかどうかはともかくとして、本書は実に真っ当な作品だ。「ビッグバン理論」の欠陥を「インフレーション理論」以外の理屈で補う挑戦的な仮説とは?
あわせて読みたい
【未知】「占い」が占い以外の効果を有するように、UFOなど「信じたいものを信じる」行為の機能を知れる…
「占い」に「見透かされたから仕方なく話す」という効用があるように、「『未知のもの』を信じる行為」には「『否定されたという状態』に絶対に達しない」という利点が存在する。映画『虚空門GATE』は、UFOを入り口に「『未知のもの』を信じる行為」そのものを切り取る
あわせて読みたい
【幸福】「死の克服」は「生の充実」となり得るか?映画『HUMAN LOST 人間失格』が描く超管理社会
アニメ映画『HUMAN LOST 人間失格』では、「死の克服」と「管理社会」が分かちがたく結びついた世界が描かれる。私たちは既に「緩やかな管理社会」を生きているが、この映画ほどの管理社会を果たして許容できるだろうか?そしてあなたは、「死」を克服したいと願うだろうか?
あわせて読みたい
【特異】「カメラの存在」というドキュメンタリーの大前提を覆す映画『GUNDA/グンダ』の斬新さ
映画『GUNDA/グンダ』は、「カメラの存在」「撮影者の意図」を介在させずにドキュメンタリーとして成立させた、非常に異端的な作品だと私は感じた。ドキュメンタリーの「デュシャンの『泉』」と呼んでもいいのではないか。「家畜」を被写体に据えたという点も非常に絶妙
あわせて読みたい
【化石】聞き馴染みのない「分子生物学」を通じて、科学という学問の本質を更科功が分かりやすく伝える…
映画『ジュラシック・パーク』を観たことがある方なら、「コハクの化石に閉じ込められた蚊の血液から恐竜の遺伝子を取り出す」という設定にワクワクしたことだろう。『化石の分子生物学』とは、まさにそのような研究を指す。科学以外の分野にも威力を発揮する知見に溢れた1冊
あわせて読みたい
【不思議】森達也が「オカルト」に挑む本。「科学では説明できない現象はある」と否定も肯定もしない姿…
肯定派でも否定派でもない森達也が、「オカルト的なもの」に挑むノンフィクション『オカルト』。「現象を解釈する」ことよりも、「現象を記録する」こと点に注力し、「そのほとんどは勘違いや見間違いだが、本当に説明のつかない現象も存在する」というスタンスで追いかける姿勢が良い
あわせて読みたい
【理解】小野田寛郎を描く映画。「戦争終結という現実を受け入れない(=認知的不協和)」は他人事じゃ…
映画『ONODA 一万夜を越えて』を観るまで、小野田寛郎という人間に対して違和感を覚えていた。「戦争は終わっていない」という現実を生き続けたことが不自然に思えたのだ。しかし映画を観て、彼の生き方・決断は、私たちと大きく変わりはしないと実感できた
あわせて読みたい
【具体例】行動経済学のおすすめ本。経済も世界も”感情”で動くと実感できる「人間の不合理さ」:『経済…
普段どれだけ「合理的」に物事を判断しているつもりでも、私たちは非常に「不合理的」な行動を取ってしまっている。それを明らかにするのが「行動経済学」だ。『経済は感情で動く』『世界は感情で動く』の2冊をベースにして、様々な具体例と共に「人間の不思議さ」を理解する
あわせて読みたい
【要約】福岡伸一『生物と無生物のあいだ』は、「生命とは何か」を「動的平衡」によって定義する入門書…
「生命とは何か?」という、あまりに基本的だと感じられる問いは、実はなかなか難しい。20世紀生物学は「DNAの自己複製」が本質と考えたが、「ウイルス」の発見により再考を迫られた。福岡伸一の『生物と無生物のあいだ』『動的平衡』の2著作から、「生命の本質」を知る
あわせて読みたい
【認識】「固定観念」「思い込み」の外側に出るのは難しい。自分はどんな「へや」に囚われているのか:…
実際に起こった衝撃的な事件に着想を得て作られた映画『ルーム』は、フィクションだが、観客に「あなたも同じ状況にいるのではないか?」と突きつける力強さを持っている。「普通」「当たり前」という感覚に囚われて苦しむすべての人に、「何に気づけばいいか」を気づかせてくれる作品
あわせて読みたい
【新視点】世界の歴史を「化学」で語る?デンプン・砂糖・ニコチンなどの「炭素化合物」が人類を動かし…
デンプン・砂糖・ニコチンなどは、地球上で非常に稀少な元素である「炭素」から作られる「炭素化合物」だ。そんな「炭素化合物」がどんな影響を与えたかという観点から世界の歴史を描く『「元素の王者」が歴史を動かす』は、学校の授業とはまったく違う視点で「歴史」を捉える
あわせて読みたい
【本質】子どもの頃には読めない哲学書。「他人の哲学はつまらない」と語る著者が説く「問うこと」の大…
『<子ども>のための哲学』は決して、「子どもでも易しく理解できる哲学の入門書」ではない。むしろかなり難易度が高いと言っていい。著者の永井均が、子どもの頃から囚われ続けている2つの大きな疑問をベースに、「『哲学する』とはどういうことか?」を深堀りする作品
あわせて読みたい
【解釈】詩人が語る詩の読み方。意味や読み方や良さが分からなくて全然気にしなくていい:『今を生きる…
私は学生時代ずっと国語の授業が嫌いでしたが、それは「作品の解釈には正解がある」という決めつけが受け入れ難かったからです。しかし、詩人・渡邊十絲子の『今を生きるための現代詩』を読んで、詩に限らずどんな作品も、「解釈など不要」「理解できなければ分からないままでいい」と思えるようになりました
あわせて読みたい
【傑作】濱口竜介監督の映画『ドライブ・マイ・カー』(原作:村上春樹)は「自然な不自然さ」が見事な作品
村上春樹の短編小説を原作にした映画『ドライブ・マイ・カー』(濱口竜介監督)は、村上春樹の小説の雰囲気に似た「自然な不自然さ」を醸し出す。「不自然」でしかない世界をいかにして「自然」に見せているのか、そして「自然な不自然さ」は作品全体にどんな影響を与えているのか
あわせて読みたい
【矛盾】その”誹謗中傷”は真っ当か?映画『万引き家族』から、日本社会の「善悪の判断基準」を考える
どんな理由があれ、法を犯した者は罰せられるべきだと思っている。しかしそれは、善悪の判断とは関係ない。映画『万引き家族』(是枝裕和監督)から、「国民の気分」によって「善悪」が決まる社会の是非と、「善悪の判断を保留する勇気」を持つ生き方について考える
あわせて読みたい
【誤解】世界的大ベストセラー『ファクトフルネス』の要約。我々は「嘘の情報」を信じ込みやすい
世界の現状に関する13の質問に対して、ほとんどの人が同じ解答をする。最初の12問は不正解で、最後の1問だけ正答するのだ。世界的大ベストセラー『ファクトフルネス』から、「誤った世界の捉え方」を認識し、情報を受け取る際の「思い込み」を払拭する。「嘘の情報」に踊らされないために読んでおくべき1冊だ
あわせて読みたい
【知的】文系にオススメの、科学・数学・哲学の入門書。高橋昌一郎の「限界シリーズ」は超絶面白い:『…
例えば「科学」だけに限ってみても、「なんでもできる」わけでは決してない。「科学」に限らず、私たちが対峙する様々な事柄には「これ以上は不可能・無理」という「限界」が必ず存在する。高橋昌一郎の「限界シリーズ」から、我々が認識しておくべき「限界」を易しく学ぶ
あわせて読みたい
【感想】飲茶の超面白い東洋哲学入門書。「本書を読んでも東洋哲学は分からない」と言う著者は何を語る…
東洋哲学というのは、「最終回しか存在しない連続ドラマ」のようなものだそうだ。西洋哲学と比較にならないほど異質さと、インド哲学・中国哲学など個別の思想を恐ろしく分かりやすく描く『史上最強の哲学入門 東洋の哲人たち』は、ページをめくる手が止まらないくらい、史上最強レベルに面白かった
あわせて読みたい
【興奮】飲茶氏の超面白い哲学小説。「正義とは?」の意味を問う”3人の女子高生”の主張とは?:『正義の…
なんて面白いんだろうか。哲学・科学を初心者にも分かりやすく伝える飲茶氏による『正義の教室』は、哲学書でありながら、3人の女子高生が登場する小説でもある。「直観主義」「功利主義」「自由主義」という「正義論」の主張を、「高校の問題について議論する生徒会の話し合い」から学ぶ
あわせて読みたい
【貢献】飛行機を「安全な乗り物」に決定づけたMr.トルネードこと天才気象学者・藤田哲也の生涯:『Mr….
つい数十年前まで、飛行機は「死の乗り物」だったが、天才気象学者・藤田哲也のお陰で世界の空は安全になった。今では、自動車よりも飛行機の方が死亡事故の少ない乗り物なのだ。『Mr.トルネード 藤田哲也 世界の空を救った男』から、その激動の研究人生を知る
あわせて読みたい
【興奮】飲茶氏が西洋哲学を語る。難解な思想が「グラップラー刃牙成分」の追加で驚異的な面白さに:『…
名前は聞いたことはあるがカントやニーチェがどんな主張をしたのかは分からないという方は多いだろう。私も無知なまったくの初心者だが、そんな人でも超絶分かりやすく超絶面白く西洋哲学を”分かった気になれる”飲茶『史上最強の哲学入門』は、入門書として最強
あわせて読みたい
【狂気】「当たり前の日常」は全然当たり前じゃない。記憶が喪われる中で”日常”を生きることのリアル:…
私たちは普段、「記憶が当たり前に継続していること」に疑問も驚きも感じないが、「短期記憶を継続できない」という記憶障害を抱える登場人物の日常を描き出す『静かな雨』は、「記憶こそが日常を生み出している」と突きつけ、「当たり前の日常は当たり前じゃない」と示唆する
あわせて読みたい
【権威】心理学の衝撃実験をテレビ番組の収録で実践。「自分は残虐ではない」と思う人ほど知るべき:『…
フランスのテレビ局が行った「現代版ミルグラム実験」の詳細が語られる『死のテレビ実験 人はそこまで服従するのか』は、「権威」を感じる対象から命じられれば誰もが残虐な行為をしてしまい得ることを示す。全人類必読の「過ちを事前に回避する」ための知見を学ぶ
あわせて読みたい
【驚愕】ロバート・キャパの「崩れ落ちる兵士」はどう解釈すべきか?沢木耕太郎が真相に迫る:『キャパ…
戦争写真として最も有名なロバート・キャパの「崩れ落ちる兵士」には、「本当に銃撃された瞬間を撮影したものか?」という真贋問題が長く議論されてきた。『キャパの十字架』は、そんな有名な謎に沢木耕太郎が挑み、予想だにしなかった結論を導き出すノンフィクション。「思いがけない解釈」に驚かされるだろう
あわせて読みたい
【平易】ブラックホールを分かりやすく知りたい。難しいことは抜きにふわっと理解するための1冊:『ブラ…
2019年に初めて直接観測されるも、未だに謎多き天体である「ブラックホール」について現役研究者が分かりやすく語る『ブラックホールをのぞいてみたら』をベースに、科学者がその存在を認めてこなかった歴史や、どんな性質を持つ天体なのかを理解する
あわせて読みたい
【限界】「科学とは何か?」を知るためのおすすめ本。科学が苦手な人こそ読んでほしい易しい1冊:『哲学…
「科学的に正しい」という言葉は、一体何を意味しているのだろう?科学者が「絶対に正しい」とか「100%間違っている」という言い方をしないのは何故だろう?飲茶『哲学的な何か、あと科学とか』から、「科学とはどんな営みなのか?」について考える
あわせて読みたい
【戸惑】人間の脳は摩訶不思議。意識ではコントロールできない「無意識の領域」に支配されている:『あ…
我々は決断や選択を「自分の意思」で行っていると感じるが、脳科学の研究はそれを否定している。我々に「自由意志」などない。「脳」の大部分は「意識以外のもの」に支配され、そこに「意識」はアクセスできないという驚愕の実態を『あなたの知らない脳』から学ぶ
あわせて読みたい
【不可思議】心理学の有名な実験から、人間の”欠陥”がどう明らかになっていったかを知る:『心は実験で…
『心は実験できるか 20世紀心理学実験物語』では、20世紀に行われた心理学実験からインパクトのある10の実験を選び紹介している。心理学者でもある著者が「科学であって科学ではない」と主張する心理学という学問で、人間のどんな不可思議さがあぶり出されてきたのかを知る
あわせて読みたい
【誤り】「信じたいものを信じる」のは正しい?映画『星の子』から「信じること」の難しさを考える
どんな病気も治す「奇跡の水」の存在を私は信じないが、しかし何故「信じない」と言えるのか?「奇跡の水を信じる人」を軽々に非難すべきではないと私は考えているが、それは何故か?映画『星の子』から、「何かを信じること」の難しさについて知る
あわせて読みたい
【実話】人質はなぜ犯人に好意を抱くか?「ストックホルム症候群」の由来である銀行強盗を描く映画:『…
「強盗や立てこもり事件などにおいて、人質が犯人に好意・共感を抱いてしまう状態」を「ストックホルム症候群」と呼ぶのだが、実はそう名付けられる由来となった実際の事件が存在する。実話を基にした映画『ストックホルムケース』から、犯人に協力してしまう人間の不可思議な心理について知る
あわせて読みたい
【排除】「分かり合えない相手」だけが「間違い」か?想像力の欠如が生む「無理解」と「対立」:映画『…
「共感」が強すぎる世の中では、自然と「想像力」が失われてしまう。そうならないようにと意識して踏ん張らなければ、他人の価値観を正しく認めることができない人間になってしまうだろう。映画『ミセス・ノイズィ』から、多様な価値観を排除しない生き方を考える
あわせて読みたい
【意外】自己免疫疾患の原因は”清潔さ”?腸内フローラの多様性の欠如があらゆる病気を引き起こす:『寄…
人類は、コレラの蔓延を機に公衆衛生に力を入れ、寄生虫を排除した。しかし、感染症が減るにつれ、免疫関連疾患が増大していく。『寄生虫なき病』では、腸内細菌の多様性が失われたことが様々な疾患の原因になっていると指摘、「現代病」の蔓延に警鐘を鳴らす
あわせて読みたい
【余命】癌は治らないと”諦める”べき?治療しない方が長生きする現実を現役医師が小説で描く:『悪医』…
ガンを患い、余命宣告され、もう治療の手がないと言われれば絶望を抱くだろう。しかし医師は、治療しない方が長生きできることを知って提案しているという。現役医師・久坂部羊の小説『悪医』をベースに、ガン治療ですれ違う医師と患者の想いを知る
あわせて読みたい
【無知】メディアの問題の本質は?「報道の限界」と「情報の受け取り方」を独裁政治の現実から知る:『…
メディアは確かに「事実」を報じている。しかし、報道に乗らない情報まで含めなければ、本当の意味で世の中を理解することは難しいと、『こうして世界は誤解する』は教えてくれる。アラブ諸国での取材の現実から、報道の「限界」と「受け取り方」を学ぶ
あわせて読みたい
【加虐】メディアの役割とは?森達也『A』が提示した「事実を報じる限界」と「思考停止社会」
オウム真理教の内部に潜入した、森達也のドキュメンタリー映画『A』は衝撃を与えた。しかしそれは、宗教団体ではなく、社会の方を切り取った作品だった。思考することを止めた社会の加虐性と、客観的な事実など切り取れないという現実について書く
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
進化・生命・脳【本・映画の感想】 | ルシルナ
人類は、我々自身を理解するための知見を積み重ねてきました。生物の進化の過程、生命を司るDNAの働きや突然変異、高い知能を持つ人間の脳の仕組みや不思議など、面白い話…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…




















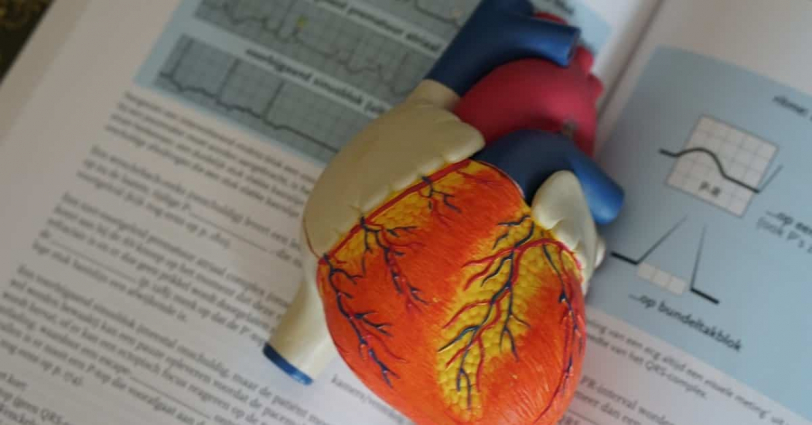


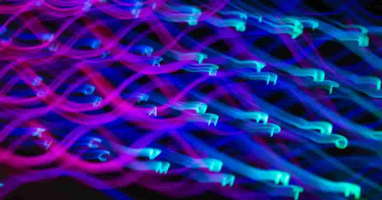












































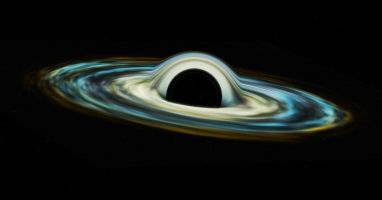



















コメント