目次
はじめに
この記事で取り上げる本
著:飲茶
¥911 (2022/02/07 23:34時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
この本をガイドにしながら記事を書いていきます
この記事の3つの要点
- 「本書を読んでも東洋哲学を理解できない」というほど、西洋哲学とはあまりに異質な特徴
- 釈迦は何故出家し、いかなる境地にたどり着き、死後何が起こったのか
- 中国で孔子・老子などの思想家が誕生した理由は「春秋戦国時代」にある
「東洋では、知識を理解したり他人に説明できても『知った』という状態にならない」という説明も興味深かった
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
あわせて読みたい
【全作品読了済】おすすめの飲茶の哲学本【随時更新】
今まで私が読んできた4000冊の本の中から、飲茶の哲学本をオススメします。哲学を中心に様々な知見を読みやすく解説してくれる飲茶の作品に、思考がギンギンに刺激されることでしょう。是非本選びの参考にして下さい。
飲茶『史上最強の哲学入門 東洋の哲人たち』は、「『東洋哲学』」は『西洋哲学』とはまったく異質」だと理解できる、超絶面白い入門書
飲茶氏は、数学・科学・哲学について、基礎知識のない人間にも分かりやすく面白く説明してくれる天才だ。このブログでも何冊か感想を書いており、哲学の本に絞っても、「正義」をテーマにした『正義の教室』や、「西洋哲学」を扱った『史上最強の哲学入門』がある。
あわせて読みたい
【興奮】飲茶氏の超面白い哲学小説。「正義とは?」の意味を問う”3人の女子高生”の主張とは?:『正義の…
なんて面白いんだろうか。哲学・科学を初心者にも分かりやすく伝える飲茶氏による『正義の教室』は、哲学書でありながら、3人の女子高生が登場する小説でもある。「直観主義」「功利主義」「自由主義」という「正義論」の主張を、「高校の問題について議論する生徒会の話し合い」から学ぶ
あわせて読みたい
【興奮】飲茶氏が西洋哲学を語る。難解な思想が「グラップラー刃牙成分」の追加で驚異的な面白さに:『…
名前は聞いたことはあるがカントやニーチェがどんな主張をしたのかは分からないという方は多いだろう。私も無知なまったくの初心者だが、そんな人でも超絶分かりやすく超絶面白く西洋哲学を”分かった気になれる”飲茶『史上最強の哲学入門』は、入門書として最強
本書『史上最強の哲学入門 東洋の哲人たち』は、『史上最強の哲学入門』の続編だ。前作が「西洋哲学」だったのに対し、本作は「東洋哲学」が扱われる。順番通りに読まなければならないわけではないのでどちらから読んでもいいが、このシリーズの場合むしろ本書から読んだ方がいいかもしれない。
というのも本書の冒頭には、「東洋哲学」と「西洋哲学」の違いが詳しく語られているからだ。この記事でもまず、この両者の違いについて触れてから、個々の東洋哲学の思想の紹介に移りたいと思う。

あわせて読みたい
【知的】「BLって何?」という初心者に魅力を伝える「腐男子」の「BLの想像力と創造力」講座:『ボクた…
「BLは知的遊戯である」という主張には「は?」と感じてしまうでしょうが、本書『ボクたちのBL論』を読めばその印象は変わるかもしれません。「余白の発見と補完」を通じて、「ありとあらゆる2者の間の関係性を解釈する」という創造性は、現実世界にどのような影響を与えているのか
相変わらず、知的好奇心をバシバシと刺激される、べらぼうに面白い作品だ。
「東洋哲学」は「最終回しか存在しない連続ドラマ」
本書の冒頭に、こんな文章がある。
まず最初にはっきりと断っておくが、本書を読んで東洋哲学を理解することは不可能である。
あわせて読みたい
【知的】文系にオススメの、科学・数学・哲学の入門書。高橋昌一郎の「限界シリーズ」は超絶面白い:『…
例えば「科学」だけに限ってみても、「なんでもできる」わけでは決してない。「科学」に限らず、私たちが対峙する様々な事柄には「これ以上は不可能・無理」という「限界」が必ず存在する。高橋昌一郎の「限界シリーズ」から、我々が認識しておくべき「限界」を易しく学ぶ
いきなりの試合放棄だ。「そんなこと言っちゃっていいのか?」と感じるが、続く説明を読むと納得できるだろう。「東洋哲学」が「西洋哲学」とはまったく異なる理屈で成り立っているが故に、どの東洋哲学入門書を選ぼうとも「読むだけでは理解できない」のである。
ではまず、「西洋哲学」について説明しよう。西洋哲学は基本的に「無知」を前提とする。つまり、「私はまだ何も知らない」というのが出発点なわけだ。そこから、様々な人間が協力し、階段を一段一段上るようにして知見を積み上げていく、というのが西洋哲学のスタンスである。これは西洋哲学に限らず、歴史や科学など、一般的に「知」と呼ばれるものの順当な発展形式だと言えるし、誰もがイメージしやすいと思う。
しかし「東洋哲学」はまったく違うと著者は語る。東洋哲学では「無知」が前提になることはなく、それどころか、「私は全部理解した!」と主張する人物が現れるところからすべてが始まるというのだ。著者は東洋哲学をこんな風に簡潔に説明している。
あわせて読みたい
【教養】美術を「感じたまま鑑賞する」のは難しい。必要な予備知識をインストールするための1冊:『武器…
芸術を「感性の赴くまま見る」のは、日本特有だそうだ。欧米では美術は「勉強するもの」と認識されており、本書ではアートを理解しようとするスタンスがビジネスにも役立つと示唆される。美術館館長を務める著者の『武器になる知的教養 西洋美術鑑賞』から基礎の基礎を学ぶ
ある日突然、「真理に到達した」と言い放つ不遜な人間が現れ、その人の言葉や考え方を後世の人たちが学問としてまとめ上げたものであると言える。
確かに禅でも仏教でも、「『悟った!』みたいな状態」が存在する印象はあるだろうし、それは「私はすべてを理解した」みたいなものと捉えていると思う。しかしやはり、分かったような分からないようなイメージになってしまうだろう。

あわせて読みたい
【本質】子どもの頃には読めない哲学書。「他人の哲学はつまらない」と語る著者が説く「問うこと」の大…
『<子ども>のための哲学』は決して、「子どもでも易しく理解できる哲学の入門書」ではない。むしろかなり難易度が高いと言っていい。著者の永井均が、子どもの頃から囚われ続けている2つの大きな疑問をベースに、「『哲学する』とはどういうことか?」を深堀りする作品
そこで著者は、この両者の違いを連続ドラマに喩える。
「西洋哲学」は、「現時点の知見」を最終回とする全13話の連続ドラマだと思えばいいと著者は言う。第1話にアリストテレスなど古代の哲学者が登場し、そこから順を追って話が進んで最終回に辿り着くという、我々が連想する「連ドラ」のイメージでいいというわけだ。
こう捉えた場合、「西洋哲学の難しさ」についての理解の仕方が変わるだろう。「西洋哲学が難しい」と感じられる理由は概ね、「全13話の連続ドラマの第5話しか見ていない」のと同じと考えていいからだ。5話ぐらいまでドラマが進めば、大体の主要登場人物は出きっていて既に紹介もされないし、舞台や世界観の設定も既に終わっているので、5話だけ見ても話の筋は理解できないだろう。
あわせて読みたい
【博覧強記】「紙の本はなくなる」説に「文化は忘却されるからこそ価値がある」と反論する世界的文学者…
世界的文学者であり、「紙の本」を偏愛するウンベルト・エーコが語る、「忘却という機能があるから書物に価値がある」という主張は実にスリリングだ。『もうすぐ絶滅するという紙の書物について』での対談から、「忘却しない電子データ」のデメリットと「本」の可能性を知る
西洋哲学の場合もこれと同じで、連綿と続く「知」の一部しか切り取っていないから、「なんだかよく分からない」という感覚に陥りがちだと著者は指摘する。
さて、同じく連続ドラマで喩えた場合、「東洋哲学」はどう理解されるのか。それは、「最終回しか存在しない、全何話かさえ不明な連続ドラマ」のようなものだという。
「連続ドラマの最終回を、最終回だと知らずに見る」という状況について少し想像してみてほしい。初めて見る登場人物たちが、それまでのやり取りを踏まえているのだろう会話をし、とりあえず何か解決に向かったのだ、ということぐらいは理解できるだろう。つまり、「ドラマの内容はよく分からないが、それはここに至るまでの様々なやり取りが抜け落ちているからであり、きっとこれは連続ドラマの最終回なのだろう」と推定できるはずだ。
あわせて読みたい
【飛躍】有名哲学者は”中二病”だった?飲茶氏が易しく語る「古い常識を乗り越えるための哲学の力」:『1…
『14歳からの哲学入門』というタイトルは、「14歳向けの本」という意味ではなく、「14歳は哲学することに向いている」という示唆である。飲茶氏は「偉大な哲学者は皆”中二病”だ」と説き、特に若い人に向けて、「新しい価値観を生み出すためには哲学が重要だ」と語る
そして「東洋哲学に触れる」ことは、「連続ドラマの最終回を、最終回だと知らずに見る」ことと同じだ、というわけである。何だかよく分からないが、とりあえず自分たちは「最終回」に触れているのだということは理解できるはずだ。そして、そんな「最終回」を色んな人が見て、そこに至るまでの過程についてあれこれ想像したものが「東洋哲学」なのである。
実際のドラマの最終回の場合は、「この2人は兄弟なのではないか」「このようなラストの展開を迎えたということは、恐らく主人公はかつていじめに遭っていたのだろう」のように想像することになるだろう。同じく東洋哲学の場合も、様々な人が「『悟った!』と主張する人物の思想(=最終回)」に触れ、あーでもないこーでもないとやり取りをしているというわけなのだ。

この説明で、「西洋哲学が理解できない理由」と「東洋哲学が理解できない理由」の違いがはっきり分かるだろう。「西洋哲学が理解できない理由」は連続ドラマの途中の回だけ見ているからであり、1話から見れば理解できる可能性がある。しかし、「東洋哲学が理解できない理由」は最終回しか存在しないからであり、そもそも「理解が及ぶものではない」というわけである。
あわせて読みたい
【誤解】世界的大ベストセラー『ファクトフルネス』の要約。我々は「嘘の情報」を信じ込みやすい
世界の現状に関する13の質問に対して、ほとんどの人が同じ解答をする。最初の12問は不正解で、最後の1問だけ正答するのだ。世界的大ベストセラー『ファクトフルネス』から、「誤った世界の捉え方」を認識し、情報を受け取る際の「思い込み」を払拭する。「嘘の情報」に踊らされないために読んでおくべき1冊だ
このように説明してもらえると、「東洋哲学」を学ぶ際の心構えが出来て良いのではないかと感じた。
西洋と東洋では、「『知った』とみなされる状態」が異なる
さらに西洋と東洋では、「何かを知っている」という状態に関する理解が異なる。意味が分からないと思うので、まずは本書から該当する箇所を引用してみよう。
西洋であれば、「知識」として得たことは素直に「知った」とみなされる。(中略)
しかし、東洋では、知識を持っていることも明晰に説明できることも、「知っている」ことの条件には含まれない。なぜなら、東洋では「わかった!」「ああ、そうか!」といった体験を伴っていないかぎり、「知った」とは認められないからだ。
あわせて読みたい
【興奮】世界的大ベストセラー『サピエンス全史』要約。人類が文明を築き上げるに至った3つの革命とは?
言わずと知れた大ベストセラー『サピエンス全史』は、「何故サピエンスだけが人類の中で生き残り、他の生物が成し得なかった歴史を歩んだのか」を、「認知革命」「農業革命」「科学革命」の3つを主軸としながら解き明かす、知的興奮に満ち溢れた1冊
西洋では、知識を頭の中で理解する、あるいはそれを他人に説明できる、という状態に達すれば「知った」とみなされる。しかし東洋ではそうはならない。東洋では、「分かった!」という感覚こそが重要だからだ。そしてこれは、東洋哲学が目指す「『悟った!』という状態」の話にも繋がっていく。
本書ではこの点について、「『白』と『黒』しかない部屋にずっと生きてきた人に、『赤』をどのように説明するか」という問題を取り上げながら説明していく。
西洋的な基準で言えば、「波長が◯◯の光は赤色に見える」という知識を理解していれば「知った」とみなされる。しかし東洋では、言葉での説明をいくら理解しようが意味はない。実際に「赤いもの」を目にして「これが『赤』なのか!」という実感が伴わなければ、「知った」とは見なされないのである。
このように東洋では、「真理はそもそも言語化できないものであり、言語で捉えようとする試みは誤りでしかない」という考えが主流なのだ。
あわせて読みたい
【知】内田樹が教育・政治を語る。「未来の自分」を「別人」と捉える「サル化した思考」が生む現実:『…
「朝三暮四」の故事成語を意識した「サル化」というキーワードは、現代性を映し出す「愚かさ」を象徴していると思う。内田樹『サル化する世界』から、日本の教育・政治の現状及び問題点をシンプルに把握し、現代社会を捉えるための新しい視点や価値観を学ぶ
このような東洋のスタンスを知ることで、禅の「公案」も理解しやすくなる。「公案」とは、言ってしまえば「意味不明ななぞなぞ」のことであり、一番有名だろう「公案」は以下のようなものだ。
両手で拍手するとパチパチと音がするけど、では片手でやるとどんな音がする?

禅の世界には、このような「なぞなぞ(公案)」を提示し、弟子がそれについて一生懸命考えるというプロセスが存在するのだ。そして本書では、禅におけるこの「公案」という仕組みが、一体どんな意味を持つのかが解説される。その緻密な説明はここでは触れないが、重要なポイントは、「公案の答えを、西洋哲学的な意味で『知る』ことには何の意味もない」ということだ。
あわせて読みたい
【人生】「資本主義の限界を埋める存在としての『贈与論』」から「不合理」に気づくための生き方を知る…
「贈与論」は簡単には理解できないが、一方で、「何かを受け取ったら、与えてくれた人に返す」という「交換」の論理では対処できない現実に対峙する力ともなる。『世界は贈与でできている』から「贈与」的な見方を理解し、「受取人の想像力」を立ち上げる
「公案」で重要なのは、「意味不明な問いについて、自力で超真剣に考え続ける」という点にある。答えを知っているかどうかはもちろん、答えに辿り着くかどうかも重要ではない。大事なポイントは、「考え続けるという過程」そのものにあるのだ。そして、考えて考えて考え続けた結果として「悟り」に達する可能性が生まれるのであり、このプロセスは西洋的なスタンスでは捉えがたいのである。
つまり「公案」は、意味不明だからこそ意味があるのであり、その根本となる仕組みを理解してしまえば、「公案」が持っている本来的な役割は発揮されなくなってしまうのだ。著者も巻末で、自著を皮肉るような形でこんな風に書いている。
そう、だから、ネット検索による知識の公開、そして本書のようなお手軽な入門書といったものは、本当は伝統的な東洋哲学を破壊してしまう存在なのだ。
東洋哲学は「知識を得ること」を重視しない、それどころか、知識を得ることでマイナスの効果さえ生まれる可能性がある。だからこそ「本書のようなお手軽な入門書」を読むべきではないのだ。
あわせて読みたい
【希望】貧困の解決は我々を豊かにする。「朝ベッドから起きたい」と思えない社会を変える課題解決:『…
現代は、過去どの時代と比べても安全で清潔で、豊かである。しかしそんな時代に、我々は「幸せ」を実感することができない。『隷属なき道』をベースに、その理由は一体なんなのか何故そうなってしまうのかを明らかにし、さらに、より良い暮らしを思い描くための社会課題の解決に触れる
東洋哲学がいかにややこしい存在なのかがなんとなく理解できるだろう。
「『悟る』ためなら嘘も方便」と考える
さらに東洋哲学には、「嘘も方便」という考え方が根底にある。本書には、
東洋哲学はあらゆる「理屈」に先立ち、まず「結果」を優先する。
と書かれているが、これは要するに、「『悟る』という結果を得るためなら手段を選ばない」という宣言なのだ。
あわせて読みたい
【限界】「科学とは何か?」を知るためのおすすめ本。科学が苦手な人こそ読んでほしい易しい1冊:『哲学…
「科学的に正しい」という言葉は、一体何を意味しているのだろう?科学者が「絶対に正しい」とか「100%間違っている」という言い方をしないのは何故だろう?飲茶『哲学的な何か、あと科学とか』から、「科学とはどんな営みなのか?」について考える
このように東洋哲学は「とにかく釈迦と同じ体験をすること」を目的とし、「その体験が起きるなら、理屈や根拠なんかどうだっていい! ウソだろうとなんだろうと使ってやる!」という気概でやってきた。なぜなら、彼らは「不可能を可能にする(伝達できないものを伝達する)」という絶望的な戦いに挑んでいるからだ。そういう「気概」でもなければ、とてもじゃないがやってられない!
そして、事実、東洋哲学者たちは、そのウソ(方便)を何千年もかけて根気強く練り続けてきた。
「悟ること」が何よりも重視されるのだが、それは大変難しい。そしてそんな難しいことをどうにか成し遂げようと、様々な天才たちがあらゆる手法を開発してきた歴史こそが東洋哲学なのである。
あわせて読みたい
【倫理】アート体験の行き着く未来は?映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』が描く狂気の世界(…
「『痛み』を失った世界」で「自然発生的に生まれる新たな『臓器』を除去するライブパフォーマンス」を行うソール・テンサーを主人公にした映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』は、すぐには答えの見出しにくい「境界線上にある事柄」を挑発的に描き出す、実に興味深い物語だ
東洋哲学における「嘘も方便」を理解するために、本書では、「法華経」に載っているあるエピソードが紹介される。それは次のような話だ。

父親が帰宅すると家が家事になっていたのだが、その燃え盛る家の中で子どもたちが遊んでいる。子どもは「火事」を知らず、その危険性に気付いていないのだ。さて、この状況であなたなら子どもたちになんと声を掛けるだろうか?
父親はこう考えた。子どもたちに「火事の危険性」を伝えられるならそれが一番良い。しかし、もう火の手はすぐそこまで迫っている。子どもたちに、「火事というのはこういう恐ろしいものだから早くそこから離れなさい」と言っても理解できない可能性もあるし、遊びに夢中で父親の話など聞かないかもしれない。
あわせて読みたい
【人生】どう生きるべきかは、どう死にたいかから考える。死ぬ直前まで役割がある「理想郷」を描く:『…
「近隣の村から『姥捨て』と非難される理想郷」を描き出す『でんでら国』は、「死ぬ直前まで、コミュニティの中で役割が存在する」という世界で展開される物語。「お金があっても決して豊かとは言えない」という感覚が少しずつ広まる中で、「本当の豊かさ」とは何かを考える
そこで父親は、悩んだ末こう叫んだ。「おーい! こっちに凄く楽しいおもちゃがたくさんあるぞ!」と。子どもたちは、火事の危険性を理解できたわけではないが、楽しいおもちゃがあると聞いて結果的に火事から離れ、命を落とさずに済んだ。まさに「嘘も方便」だろう。
そして東洋哲学も、まさにこれと同じことをしているのだ、と著者は語る。師匠は弟子に、嘘かどうかに関係なく様々なことを言う。それが「悟り」に繋がる手段だと考えるなら、東洋哲学においてはすべて許容されるのだ。
そんなわけで東洋哲学では、宗派によって言うことが違うし、師匠は弟子に何も教えないし、修行中に理解不能な状況に置かれることもある。そそこに一貫性を見出すのは難しいかもしれない。しかし、東洋哲学は「悟りに達すること」を究極の目標に据えているのであり、その点で共通しているのだ、と著者は主張している。
さてここまでで、「西洋哲学」と「東洋哲学」の違いについて触れてきたが、両者がまったく異なるものだと理解できただろうと思う。まずこのような理解に立ってそれぞれの哲学に挑むと、学びが進みやすいはずだ。本書の冒頭で詳しく説明されるこれらの差異を理解するだけでも、本書を読む価値があると言っていい。
あわせて読みたい
【誤解】「意味のない科学研究」にはこんな価値がある。高校生向けの講演から”科学の本質”を知る:『す…
科学研究に対して、「それは何の役に立つんですか?」と問うことは根本的に間違っている。そのことを、「携帯電話」と「東急ハンズの棚」の例を使って著者は力説する。『すごい実験』は素粒子物理学を超易しく解説する本だが、科学への関心を抱かせてもくれる
インド哲学はいかにして始まったのか?
それではここから、東洋哲学の個別の思想に触れていくことにしよう。
まずはインド哲学である。ここでは、釈迦や仏教について語ることになるが、まずはインド哲学の生みの親であるヤージュニャヴァルキヤの話から始めよう。
彼は「梵我一如」として知られる考え方を打ち出した。これについてはざっと書くに留めよう。この記事の説明ではきっと意味不明だと思うが、本書の記述以上に短く説明することは恐らく不可能なので、ここでは深入りしない。是非本書を読んでほしい。
あわせて読みたい
【天才】『三島由紀夫vs東大全共闘』後に「伝説の討論」と呼ばれる天才のバトルを記録した驚異の映像
1969年5月13日、三島由紀夫と1000人の東大全共闘の討論が行われた。TBSだけが撮影していたフィルムを元に構成された映画「三島由紀夫vs東大全共闘」は、知的興奮に満ち溢れている。切腹の一年半前の討論から、三島由紀夫が考えていたことと、そのスタンスを学ぶ
「私(=アートマン)と世界(=ブラフマン)は同一である」という考え方を「梵我一如」と呼ぶ。そしてヤージュニャヴァルキヤは「アートマンを捉えることはできない」と主張した。説明は以上である。しかしこれではなんのこっちゃ分からないだろうと思うので、本書に登場する映画館の例を紹介しておこう。

映画館で映画を観ているとしよう。暗闇で映画の世界に没入していると、「自分が映画の世界の中にいる」ような錯覚を覚えることもあるだろう。実際にはただの観客に過ぎないが、映画の世界にあなたが入り込み、登場人物たちと共にその映画世界を体感しているかのように感じられる。そして、映画の中の出来事が自分自身に起こったことのように思えてしまうというわけだ。
しかし、映画が終わり電気がつく(あるいはエンドロールが流れる)ことで、あなたは「映画を観ていただけだ」と、その錯覚から醒めることができる。
あわせて読みたい
【幻想】心の傷を癒やすことの”難しさ”、寄り添い続けるために必要な”弱さ”と”冷たさ”:映画『心の傷を…
「優しいかどうか」が重要な要素として語られる場面が多いと感じるが、私は「優しさ」そのものにはさしたる意味はないと考えている。映画『心の傷を癒すということ 劇場版』から、「献身」と「優しさ」の違いと、誰かに寄り添うために必要な「弱さ」を理解する
ヤージュニャヴァルキヤは、我々の人生における「悩み」も同じようなものだ、と説いた。つまり、「不幸だ」「辛い」と感じることがあっても、それは映画の中の出来事でしかない、というわけだ。映画の中で何が起ころうとも、観客である自分が傷ついたり壊れたりしないように、あらゆる悩みも、自分とは異なる世界の話でしかない。そんな境地に達することができさえすれば、あらゆる不安は消えてなくなる、というのがヤージュニャヴァルキヤの主張である。
さてこのような「梵我一如」という考え方の中で、当時のインドで特に受け入れられたのが、「アートマンを捉えることはできない」という部分だ。ヤージュニャヴァルキヤは「アートマン」を、「~ではない」という形式でしか捉えることができない、と主張した。つまり、「アートマン」が何かは分からないが、「Aではない」し「Bではない」し「Cではない」……ということは理解できる、というわけだ。
そしてこの考え方から、「身分制度の存在はおかしい」とヤージュニャヴァルキヤは主張した。「アートマン」が「~ではない」という形式でしか捉えられないということは、「アートマンは特権階級ではない」し、「アートマンは奴隷ではない」となるからだ。ヤージュニャヴァルキヤによる「アートマン」の捉え方を敷衍することで、「身分制度の矛盾」があぶり出されたのである。
この主張は、バラモン(特権階級)から奴隷まで様々な身分格差が存在した当時のインドにおいては画期的なものだった。そして彼の哲学は、身分制度に抑圧されていた特権階級以外の人たちを勇気づけ、支持を集めていくのである。
あわせて読みたい
【情熱】映画『パッドマン』から、女性への偏見が色濃く残る現実と、それを打ち破ったパワーを知る
「生理は語ることすらタブー」という、21世紀とは思えない偏見が残るインドで、灰や汚れた布を使って経血を処理する妻のために「安価な生理用ナプキン」の開発に挑んだ実在の人物をモデルにした映画『パッドマン 5億人の女性を救った男』から、「どう生きたいか」を考える
釈迦による方針転換
そしてそんなヤージュニャヴァルキヤの哲学に勇気づけられた者の中に釈迦がいた。ヤージュニャヴァルキヤに後押しされるようにして彼は出家し、当時のブームだった「『老病死の苦しみを克服する境地』を目指すために苦行」に励んでいたのだ。
そう、当時のインドでは「苦行を行うこと」が流行していた。そこには、こんな納得の理由がある。「悟った人物を見分けるのは難しい」のだ。

あわせて読みたい
【社会】学生が勉強しないのは、若者が働かないのは何故か?教育現場からの悲鳴と知見を内田樹が解説:…
教育現場では、「子どもたちが学びから逃走する」「学ばないことを誇らしく思う」という、それまでには考えられなかった振る舞いが目立っている。内田樹は『下流志向』の中で、その原因を「等価交換」だと指摘。「学ばないための努力をする」という発想の根幹にある理屈を解き明かす
悟っていようがいまいが言動に差はなく、見た目ではその区別をつけられない。だったらどうすればいいかが問題になっていたのだ。
そこで、こんな風に考えられるようになった。「悟った人」はあらゆる苦痛から解放されているとされる。つまり、ボコボコに殴られたとしても苦痛を感じないはずだ。だったら、「痛くて苦しい状況に耐えられる人物」ほど「悟っている」と判断できるのではないか。
そんな理屈を背景に、当時のインドでは、「俺は悟っているぞ」と示すための”ガマン大会”が行われていたのである。
あわせて読みたい
【異端】「仏教とは?」を簡単に知りたい方へ。ブッダは「異性と目も合わせないニートになれ」と主張し…
我々が馴染み深い「仏教」は「大乗仏教」であり、創始者ゴータマ・ブッダの主張が詰まった「小乗仏教」とは似て非なるものだそうだ。『講義ライブ だから仏教は面白い!』では、そんな「小乗仏教」の主張を「異性と目も合わせないニートになれ」とシンプルに要約して説明する
もちろん釈迦も、最初はこの”ガマン大会”に参加した。しかし、苦行に耐えども耐えども一向に悟る気配がない。というかそもそも、「悟っているかを判断するために苦行を行う」のであり、「苦行を行うことで悟ることができる」わけではないのだ。しばらくして釈迦は、自分が身を置いている状況のおかしさにようやく気づいた。
そして、「苦行こそ悟りの邪魔である」という「中道」の考え方に行き着いたのだ。非常に真っ当な判断だと言っていいだろう。
さて、釈迦の「中道」という考え方で最も重要な点は、「アートマンは存在しない」という主張だ。この考え方は当時のインドに衝撃を与えた。何故なら、「アートマンは『~ではない』という形式でしか捉えられない」というヤージュニャヴァルキヤの主張と真っ向から対立するからである。
あわせて読みたい
【情報】日本の社会問題を”祈り”で捉える。市場原理の外にあるべき”歩哨”たる裁き・教育・医療:『日本…
「霊性」というテーマは馴染みが薄いし、胡散臭ささえある。しかし『日本霊性論』では、「霊性とは、人間社会が集団を存続させるために生み出した機能」であると主張する。裁き・教育・医療の変化が鈍い真っ当な理由と、情報感度の薄れた現代人が引き起こす問題を語る
実は釈迦は、ヤージュニャヴァルキヤの主張に反対していたわけではない。というか、「中道」という考えを打ち出してからもヤージュニャヴァルキヤの主張に賛成していた。では何故、ヤージュニャヴァルキヤと対立するような主張をしたのだろうか?
それは、ヤージュニャヴァルキヤが見落としていた「大衆は誤解する」という事実を、釈迦が正しく理解していたからだ。
ヤージュニャヴァルキヤの言うように、「アートマンは『~ではない』という形式でしか捉えられない」のだが、正直、この主張はスパッとは理解しにくい。だから大衆は、この考えを理解するために、「アートマンは『~ではない』という形式でしか捉えられないものである」のように、「である」という形で概念化して理解するようになってしまった。しかし、そう捉えることは、ヤージュニャヴァルキヤの主張から遠ざかることになってしまう。本末転倒なのだ。
あわせて読みたい
【勇敢】”報道”は被害者を生む。私たちも同罪だ。”批判”による”正義の実現”は正義だろうか?:『リチャ…
「爆弾事件の被害を最小限に食い止めた英雄」が、メディアの勇み足のせいで「爆弾事件の犯人」と報じられてしまった実話を元にした映画『リチャード・ジュエル』から、「他人を公然と批判する行為」の是非と、「再発防止という名の正義」のあり方について考える
そこで釈迦は、大衆の勘違いを正すために、「アートマンは存在しない」と敢えて強烈な主張をすることにしたのである。

釈迦の理屈をまとめよう。ヤージュニャヴァルキヤの「アートマン」に関する主張は正しいのだが、その主張を正しく理解することは難しい。それゆえ大衆は誤った解釈をしてしまい、結果としてヤージュニャヴァルキヤが言いたかったことから遠ざかってしまった。そこで釈迦は、大衆の考えをヤージュニャヴァルキヤの主張に近づけるために、実際には正しくない「アートマンは存在しない」という主張をしたのである。
まさに釈迦も「嘘も方便」を上手く利用したというわけだ。
あわせて読みたい
【最新】「コロンブス到達以前のアメリカ大陸」をリアルに描く歴史書。我々も米国人も大いに誤解してい…
サイエンスライターである著者は、「コロンブス到着以前のアメリカはどんな世界だったか?」という問いに触れ、その答えが書かれた本がいつまで経っても出版されないので自分で執筆した。『1491 先コロンブス期アメリカ大陸をめぐる新発見』には、アメリカ人も知らない歴史が満載だ
釈迦の死後の混乱と、天才の登場
釈迦は生身の人間なので、当然いつかは死ぬ。「食あたりで死んだ」というのが通説だそうだ。
いつの時代も変わらず、トップがいなくなると組織は混乱する。仏教でも同じである。
そもそも釈迦は、自らの教えを言葉として残すことを好まなかったらしい。さらに東洋哲学は「悟るためなら何でもアリ」だ。釈迦も弟子ごとに全然違うことを言っていたという。
あわせて読みたい
【感想】池田晶子『14歳からの哲学』で思考・自由・孤独の大事さを知る。孤独を感じることって大事だ
「元々持ってた価値観とは違う考えに触れ、それを理解したいと思う場面」でしか「考える」という行為は発動しないと著者は言う。つまり我々は普段、まったく考えていないのだ。『14歳からの哲学』をベースに、「考えること」と自由・孤独・人生との関係を知る
だから釈迦の死後、弟子たちが釈迦の考えをまとめようと話し合っても折り合いがつかなかったのは当然だ。そして仏教は分裂した。元々の釈迦の思想をなるべく継承する形で存続した小規模な集団と、より大衆向けにアレンジした大規模な集団に分かれたのだ。そして後者の集団が「大乗仏教」と名乗り、小規模な集団の方を「小乗仏教」と下に見るようになっていったのである。
現在我々が知っている「仏教」は、いわゆる「大乗仏教」だ。当たり前と言えば当たり前だが、大衆向けにアレンジされたものが残るのは当然と言えるだろう。「小乗仏教」はよほどの覚悟がなければ続けられない厳しいものだそうで、所帯としても規模の大きかった「大乗仏教」の方がその後主流になっていった。
問題は、そんな「大乗仏教」を先導する人物がいるかどうかだ。そして運良く、龍樹という天才がいたのである。龍樹は「空の哲学」と呼ばれるものを完成させた。現在「般若心経」として知られているものだ。
あわせて読みたい
【考察】アニメ映画『虐殺器官』は、「便利さが無関心を生む現実」をリアルに描く”無関心ではいられない…
便利すぎる世の中に生きていると、「この便利さはどのように生み出されているのか」を想像しなくなる。そしてその「無関心」は、世界を確実に悪化させてしまう。伊藤計劃の小説を原作とするアニメ映画『虐殺器官』から、「無関心という残虐さ」と「想像することの大事さ」を知る

本書ではこの「般若心経」についても詳しく説明されるが、先程同様、本の内容よりも短く易しく説明することなど不可能なので、是非本書を読んでほしい。
ざっくり書けば、「すべてのものは実体としてそこに存在するのではなく、人間が言葉で区別を生み出しているにすぎない」となる。
あわせて読みたい
【おすすめ】江戸川乱歩賞受賞作、佐藤究『QJKJQ』は、新人のデビュー作とは思えない超ド級の小説だ
江戸川乱歩賞を受賞した佐藤究デビュー作『QJKJQ』はとんでもない衝撃作だ。とても新人作家の作品とは思えない超ド級の物語に、とにかく圧倒されてしまう。「社会は『幻想』を共有することで成り立っている」という、普段なかなか意識しない事実を巧みにちらつかせた、魔術のような作品
この世には実体など存在しないのだが、言葉で世界を捉えていると、どうしても実体が存在するような気がしてしまう。だからこそ、言葉ではない形で物事を捉える「無分別智」が「空の哲学」では推奨されるのだ。
しかし「無分別智」で物事を捉えようとしても、どうしても残ってしまう「違い」がある。それが「私と他者の区別」だ。「無分別智」を駆使して、世の中の様々なものの「違い」を「ない、ない、ない!」と言って否定し続けたところで、「そんな風に『ない!』と否定している私」のことはどうしても、他者とは違う存在として区別されてしまうのである。
「般若心経」ではその最後に残った「区別」をいかにして乗り越えるのだろうか? 本書によると、なんと「呪文」だそうだ。「呪文」によってその「違い」を突破しろ、という超展開について説明がなされたところで、インド哲学の説明は終わりということになる。
あわせて読みたい
【奇妙】大栗博司『重力とはなにか』は、相対性理論や量子力学の説明も秀逸だが、超弦理論の話が一番面白い
『重力とはなにか』(大栗博司)は、科学に馴染みの薄い人でもチャレンジできる易しい入門書だ。相対性理論や量子力学、あるいは超弦理論など、非常に難解な分野を基本的なところから平易に説明してくれるので、「科学に興味はあるけど難しいのはちょっと……」という方にこそ読んでほしい1冊
中国哲学を大雑把に捉えつつ、「孔子」「老子」の凄さに触れる
中国哲学については、孔子・莊子・韓非子・荀子・老子など、私でも名前を聞いたことがあるような人物の哲学が様々に紹介される。しかしこの記事では、それら個別の話には触れない。ここでは、中国哲学のパートで私が面白いと感じた、「彼らのような哲学者が中国で現れるようになった理由」についての説明に触れようと思う。
古代の中国には、「堯」「舜」「禹」という3人の英雄がいた。彼らは、生活に欠かせない存在でありながら、氾濫によって大きな被害をもたらす存在でもある「大河」に立ち向かった者たちだ。ドデカイ河が洪水を起こさないように治水工事を行うという、絶望的とも言える難事業に手を出したのである。
あわせて読みたい
【悲哀】2度の東京オリンピックに翻弄された都営アパートから「公共の利益」と「個人の権利」を考える:…
1964年の東京オリンピックを機に建設された「都営霞ケ丘アパート」は、東京オリンピック2020を理由に解体が決まり、長年住み続けた高齢の住民に退去が告げられた。「公共の利益」と「個人の権利」の狭間で翻弄される人々の姿を淡々と映し出し、静かに「社会の在り方」を問う映画

あまりにも壮大な計画であるがゆえに、国のトップは血縁ではなく優秀さで選ばれていた。優秀な人物が率いなければ実現不可能な事業だからだ。しかしその伝統は「禹」を最後に途切れてしまう。その後は世襲によって後継者が決まるようになってしまったのだ。
そうなると誰もが想像できるように、アホみたいな王も出てくる。そして、そんなアホみたいな王に耐えられないと革命が起こってしまう。「世襲制のせいでアホが王になり、革命が引き起こされる」という流れが幾度も繰り返されることになったのだ。
しかし、そんな愚かなやり方をいつまでも続けるわけにはいかない。そこで「周」という国が方針を転換する。「ちょっとぐらい王がアホでも崩れないような強固な政治体系を作る」ことに決めたのだ。それが「封建制度」である。国を分割し、それぞれの土地を有力な貴族に統治させたのだ。
あわせて読みたい
【幸福】「死の克服」は「生の充実」となり得るか?映画『HUMAN LOST 人間失格』が描く超管理社会
アニメ映画『HUMAN LOST 人間失格』では、「死の克服」と「管理社会」が分かちがたく結びついた世界が描かれる。私たちは既に「緩やかな管理社会」を生きているが、この映画ほどの管理社会を果たして許容できるだろうか?そしてあなたは、「死」を克服したいと願うだろうか?
もちろん、ただ国を分割して貴族に任せたところで上手く行くはずもない。必ず不届き者は出てくるからだ。そんな不届き者は中央の力で蹴散らしたいところだが、そうもいかない。なぜなら、中国は国土が広いこともあり、地方の貴族が武力を結集させることで、中央が太刀打ちできない勢力を獲得できてしまうのだ。
そこで上手い方法が考えられた。
当時の中国では、「天」という神様的な存在が素直に信じられていた。「天」というのは、「人間の頭上にいて、世界のすべての現象を司っている神秘的な存在」である。そして周王は、「自分は『天』の使いであり、『天』から命を受けて地上を支配している」と宣言した。さらに「周王は地方貴族の『本家』であり、地方貴族の先祖を祀る儀式は周王にしか行えない」とも主張したのだ。
つまり地方貴族に、「周王に逆らうことは『天』に逆らう行為だ」「周王に逆らえば先祖を祀る儀式は行われず、先祖の霊を怒らせることになる」と理解させたのである。
あわせて読みたい
【誤り】「信じたいものを信じる」のは正しい?映画『星の子』から「信じること」の難しさを考える
どんな病気も治す「奇跡の水」の存在を私は信じないが、しかし何故「信じない」と言えるのか?「奇跡の水を信じる人」を軽々に非難すべきではないと私は考えているが、それは何故か?映画『星の子』から、「何かを信じること」の難しさについて知る
このやり方は実に上手く行き、周王は安泰を得た。しかしこの仕組みによって新たな問題も生まれてしまう。
各地方を統治する貴族は、その地方における「王」なのだから、やはり好き放題やりたいと考える。しかし周王の宣言により、中央に逆らうことなど考えられない。だったら他の地方から奪えばいい、と考える地方貴族が現れる。周王には刃向かえないが、他の地方にだったら何をしても問題ないからだ。
このような流れで、地方貴族同士が争う「春秋戦国時代」が幕を開けることになる。そしてそんな時代の変化こそが、平民にとってのチャンスを生むことになったのだ。
どの国も、自国を強くしてどこかをやっつけたいと考えている。となれば、「国を強くする能力を持つ者」を探し出して登用することが急務となるだろう。これにより、貴族でない者でも、学問を身につけその実力を示しさえすれば、大出世が見込めることになったのである。
あわせて読みたい
【興奮】素数の謎に迫った天才数学者たちの奮闘と、数学の”聖杯”である「リーマン予想」について:『素…
古今東西の数学者を惹きつけて止まない「素数」。その規則性を見つけ出すことは非常に困難だったが、「リーマン予想」として初めてそれが示された。『素数の音楽』『リーマン博士の大予想』から、天才数学者たちが挑んできた「リーマン予想」をざっくり理解する
このような背景があったからこそ、孔子などの天才が活躍できる余地が生まれたのだ。
さてそんな孔子だが、何故ここまで高く評価されているのかという説明が興味深かった。というのも孔子は、ざっくり要約すれば、「思いやりの気持ちを大切にして礼儀正しく生きましょう」程度のことしか主張していないからだ。それなのに、世界4大聖人の1人に数えられている。ありきたりな主張をしていただけの孔子は、一体何故これほどの評価を得ているのだろうか?

その理由は、孔子が「空気を読まなかった」ことにあるという。
あわせて読みたい
【窮屈】日本の生きづらさの元凶は「失敗にツッコむ笑い」。「良し悪し」より「好き嫌い」を語ろう:『…
お笑い芸人・マキタスポーツが、一般社会にも「笑いの作法」が染み出すことで息苦しさが生み出されてしまうと分析する『一億総ツッコミ時代』を元に、「ツッコむ」という振る舞いを止め、「ツッコまれしろ」を持ち、「好き/嫌い」で物事を語るスタンスについて考える
孔子の主張は、当時の支配者たちの流行の考え方とはかけ離れたものだった。しかし孔子は、正しいと思う政治の実現のために、王に嫌われても自らの考えを変えずに主張し続けたのである。孔子ほど能力のある人物であれば、王に気に入られるようなことを言いさえすればすぐにでも出世が叶ったことだろう。しかし孔子はそれを良しとせず、だからこそ孔子自身は不遇な人生を送ることになってしまった。
しかし、後に弟子たちが孔子の考えをまとめ、それを広めたことで、時流に流されずに自らの主張を続けた孔子の心意気が理解され、後世に残る哲学者として評価されるに至った、ということのようだ。
また、老子の話も興味深かった。老子は、インドから伝わった仏教を中国に根付かせた人物だそうだ。そんな老子は、周の国の衰えを感じ取り、国を去ろうとしていた。しかし国境で弟子に捕まってしまう。そしてこの弟子が、「あなたの教えを書き残してください」と詰め寄るファインプレーを成し遂げたのだ。
何故これがファインプレーなのか。それは、この弟子が引き止めて詰め寄らなければ、恐らく老子の考えが後世に残ることはなかったからだ。老子も釈迦と同じく、自分の哲学思想を言葉で残していなかったのである。
あわせて読みたい
【不可思議】心理学の有名な実験から、人間の”欠陥”がどう明らかになっていったかを知る:『心は実験で…
『心は実験できるか 20世紀心理学実験物語』では、20世紀に行われた心理学実験からインパクトのある10の実験を選び紹介している。心理学者でもある著者が「科学であって科学ではない」と主張する心理学という学問で、人間のどんな不可思議さがあぶり出されてきたのかを知る
このように、哲学の中身そのものだけではなく、多彩なエピソードに触れることで、難しい印象のある哲学をとっつきやすくしてくれているのだ。
「禅」に関する驚愕の話
本書には当然、日本の哲学の話も紹介される。しかしこの記事では、「禅」だけに絞ろう。禅は元々、中国に伝わったインド仏教が老荘思想と融合して生まれたものだが、成熟したのは日本だとされている。世界でも「禅」は「ZEN」という日本語の音で知られているそうだ。
そんな禅に関する、一番面白かった話を紹介してこの記事を終わろう。
あわせて読みたい
【神秘】脳研究者・池谷裕二が中高生向けに行った講義の書籍化。とても分かりやすく面白い:『進化しす…
「宇宙」「深海」「脳」が、人類最後のフロンティアと呼ばれている。それほど「脳」というのは、未だに分からないことだらけの不思議な器官だ。池谷裕二による中高生向けの講義を元にした『進化しすぎた脳』『単純な脳、複雑な「私」』をベースに、脳の謎を知る
禅では伝統的に、「悟った者」が後継者になると決まっているそうだ。禅を生み出したのは達磨という人物で、そこから数えて5代目に弘忍がいる。そしてその弘忍に続く6代目の選定でドラマが生まれたのだ。
弘忍には何人か弟子がおり、その中でも最も優秀とされ、6代目の後継者に選ばれるだろうと目されていたのが神秀である。一方、弘忍のいる寺には、慧能という雑用係もいた。彼は極貧の木こりであり、読み書きは一切できない。後継者候補とはとても考えられない人物だった。

しかし弘忍の後継者として選ばれたのは、慧能の方である。一体何があったのか?
あわせて読みたい
【救い】耐えられない辛さの中でどう生きるか。短歌で弱者の味方を志すホームレス少女の生き様:『セー…
死にゆく母を眺め、施設で暴力を振るわれ、拾った新聞で文字を覚えたという壮絶な過去を持つ鳥居。『セーラー服の歌人 鳥居』は、そんな辛い境遇を背景に、辛さに震えているだろう誰かを救うために短歌を生み出し続ける生き方を描き出す。凄い人がいるものだ
ある時弘忍は弟子たちに、「自分がたどり着いた境地を詩にしろ。悟った者がいれば後継者にする」と告げた。弟子たちは頭を振り絞り詩を考え発表するが、やはり神秀のものが素晴らしい。
さてそこに慧能が通りかかる。字が読めない慧能だが、神秀の詩の内容を口頭で教えてもらうとなんと、「この詩を書いた人物はまだ悟っていないみたいですね」と口にしたのである。弟子たちは当然爆笑した。読み書きもできない雑用係に何が分かる、という態度だ。そして弟子たちは、だったらお前も詩を書いてみろよと挑発する。慧能は口頭で詩作し、字は書けないので弟子たちに文字にしてもらった。
さて、ちょうどそこに弘忍が通りかかる。そして慧能の詩を見るや、「こんなくだらない詩を書いたのは誰だ。全然悟ってない。消せ」と命じたのである。
その夜のこと。弘忍は慧能の寝室にやってきて、自分が着ている袈裟を渡した。この袈裟を受け継いだ人物こそが、後継者とみなされるのだ。そして弘忍は、「弟子たちの中で悟っているのはお前だけだ。だからお前を後継者にするが、そのことを知れば他の弟子は怒り狂い、お前はきっと殺されるだろう。だからこの袈裟を着てすぐに逃げろ」と告げたのである。
あわせて読みたい
【共感】斎藤工主演映画『零落』(浅野いにお原作)が、「創作の評価」を抉る。あと、趣里が良い!
かつてヒット作を生み出しながらも、今では「オワコン」みたいな扱いをされている漫画家を中心に描く映画『零落』は、「バズったものは正義」という世の中に斬り込んでいく。私自身は創作者ではないが、「売れる」「売れない」に支配されてしまう主人公の葛藤はよく理解できるつもりだ
翌朝、弟子たちは弘忍が袈裟を着ていないことに気づいた。そして慧能の不在を知り、慧能が後継者に選ばれたのだと理解するに至る。やはり彼らは怒り狂い、慧能を探し出そうと必死になるが、その頃には慧能は無事南に逃げ延びていた。
そしてそのお陰で、現在に至るまで禅が継承されている、という話である。
なんとも壮大で、イカれた話だ。そんなイカれた話が満載の本書は、とにかくメチャクチャ面白い。
あわせて読みたい
【驚異】数学の「無限」は面白い。アキレスと亀の矛盾、実無限と可能無限の違い、カントールの対角線論…
日常の中で「無限」について考える機会などなかなか無いだろうが、野矢茂樹『無限論の教室』は、「無限には種類がある」と示すメチャクチャ興味深い作品だった。「実無限」と「可能無限」の違い、「可能無限」派が「カントールの対角線論法」を拒絶する理由など、面白い話題が満載の1冊
著:飲茶
¥911 (2022/02/07 23:35時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品読了済】私が読んできたノンフィクション・教養書を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が読んできたノンフィクションを様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本選びの参考にして下さい。
最後に
あわせて読みたい
【証明】結城浩「数学ガール」とサイモン・シンから「フェルマーの最終定理」とそのドラマを学ぶ
350年以上前に一人の数学者が遺した予想であり「フェルマーの最終定理」には、1995年にワイルズによって証明されるまでの間に、これでもかというほどのドラマが詰め込まれている。サイモン・シンの著作と「数学ガール」シリーズから、その人間ドラマと数学的側面を知る
著者自身が書いている通り、東洋哲学というのは、入門書を読んで知識を得ることがマイナスに働いてしまう非常にややこしい学問である。東洋哲学を突き詰めたければ、知識を積み上げるのではなく、「悟った!」という状態にどうやったら到達できるかを真剣に考えなければならないというわけだ。
しかし、単純に東洋哲学を知識として知っておきたいという動機であれば、本書ほど面白い入門書はなかなか存在しないだろう。かなり分厚い本だが、非常に読みやすく書かれているので、臆することなく手に取ってほしい。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
金沢&富山のアート旅!「21世紀美術館」だけじゃない激アツなおすすめ美術館巡りをご提案
金沢・富山を巡るアート旅に出かけてきました!メインの目的は「21世紀美術館」でしたが、それ以上に「ASTER Curator Museum」「LIP BAR」「KAMU kanazawa」などがとにかく素晴らしかったです。アートや美術のことはド素人ですが、超個人的主観で「金沢・富山で触れられるアートの良さ」について書いた旅行記となります
あわせて読みたい
【奇妙】大栗博司『重力とはなにか』は、相対性理論や量子力学の説明も秀逸だが、超弦理論の話が一番面白い
『重力とはなにか』(大栗博司)は、科学に馴染みの薄い人でもチャレンジできる易しい入門書だ。相対性理論や量子力学、あるいは超弦理論など、非常に難解な分野を基本的なところから平易に説明してくれるので、「科学に興味はあるけど難しいのはちょっと……」という方にこそ読んでほしい1冊
あわせて読みたい
【映画】『街は誰のもの?』という問いは奥深い。「公共」の意味を考えさせる問題提起に満ちた作品
映画『街は誰のもの?』は、タイトルの通り「街(公共)は誰のものなのか?」を問う作品だ。そしてそのテーマの1つが、無許可で街中に絵を描く「グラフィティ」であることもまた面白い。想像もしなかった問いや価値観に直面させられる、とても興味深い作品である
あわせて読みたい
【共感】斎藤工主演映画『零落』(浅野いにお原作)が、「創作の評価」を抉る。あと、趣里が良い!
かつてヒット作を生み出しながらも、今では「オワコン」みたいな扱いをされている漫画家を中心に描く映画『零落』は、「バズったものは正義」という世の中に斬り込んでいく。私自身は創作者ではないが、「売れる」「売れない」に支配されてしまう主人公の葛藤はよく理解できるつもりだ
あわせて読みたい
【倫理】アート体験の行き着く未来は?映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』が描く狂気の世界(…
「『痛み』を失った世界」で「自然発生的に生まれる新たな『臓器』を除去するライブパフォーマンス」を行うソール・テンサーを主人公にした映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』は、すぐには答えの見出しにくい「境界線上にある事柄」を挑発的に描き出す、実に興味深い物語だ
あわせて読みたい
【知的】「BLって何?」という初心者に魅力を伝える「腐男子」の「BLの想像力と創造力」講座:『ボクた…
「BLは知的遊戯である」という主張には「は?」と感じてしまうでしょうが、本書『ボクたちのBL論』を読めばその印象は変わるかもしれません。「余白の発見と補完」を通じて、「ありとあらゆる2者の間の関係性を解釈する」という創造性は、現実世界にどのような影響を与えているのか
あわせて読みたい
【挑発】「TBS史上最大の問題作」と評されるドキュメンタリー『日の丸』(構成:寺山修司)のリメイク映画
1967年に放送された、寺山修司が構成に関わったドキュメンタリー『日の丸』は、「TBS史上最大の問題作」と評されている。そのスタイルを踏襲して作られた映画『日の丸~それは今なのかもしれない~』は、予想以上に面白い作品だった。常軌を逸した街頭インタビューを起点に様々な思考に触れられる作品
あわせて読みたい
【人類学】少数民族・ムラブリ族に潜入した映画『森のムラブリ』は、私たちの「当たり前」を鮮やかに壊す
タイとラオスにまたがって存在する少数民族・ムラブリ族に密着したドキュメンタリー映画『森のムラブリ』。「ムラブリ族の居住地でたまたま出会った日本人人類学者」と意気投合し生まれたこの映画は、私たちがいかに「常識」「当たり前」という感覚に囚われているのかを炙り出してくれる
あわせて読みたい
【思考】文章の書き方が分かんない、トレーニングしたいって人はまず、古賀史健の文章講義の本を読め:…
古賀史健『20歳の自分に受けさせたい文章講義』は、「具体的なテクニック」ではない記述も非常に興味深い1冊だ。「なぜ文章を書く必要があるのか」という根本的な部分から丁寧に掘り下げる本書は、「書くからこそ考えられる」という、一般的なイメージとは逆だろう発想が提示される
あわせて読みたい
【革命】観る将必読。「将棋を観ること」の本質、より面白くなる見方、そして羽生善治の凄さが満載:『…
野球なら「なんで今振らないんだ!」みたいな素人の野次が成立するのに、将棋は「指せなきゃ観てもつまらない」と思われるのは何故か。この疑問を起点に、「将棋を観ること」と「羽生善治の凄さ」に肉薄する『羽生善治と現代』は、「将棋鑑賞」をより面白くしてくれる話が満載
あわせて読みたい
【驚異】数学の「無限」は面白い。アキレスと亀の矛盾、実無限と可能無限の違い、カントールの対角線論…
日常の中で「無限」について考える機会などなかなか無いだろうが、野矢茂樹『無限論の教室』は、「無限には種類がある」と示すメチャクチャ興味深い作品だった。「実無限」と「可能無限」の違い、「可能無限」派が「カントールの対角線論法」を拒絶する理由など、面白い話題が満載の1冊
あわせて読みたい
【幸福】「死の克服」は「生の充実」となり得るか?映画『HUMAN LOST 人間失格』が描く超管理社会
アニメ映画『HUMAN LOST 人間失格』では、「死の克服」と「管理社会」が分かちがたく結びついた世界が描かれる。私たちは既に「緩やかな管理社会」を生きているが、この映画ほどの管理社会を果たして許容できるだろうか?そしてあなたは、「死」を克服したいと願うだろうか?
あわせて読みたい
【おすすめ】江戸川乱歩賞受賞作、佐藤究『QJKJQ』は、新人のデビュー作とは思えない超ド級の小説だ
江戸川乱歩賞を受賞した佐藤究デビュー作『QJKJQ』はとんでもない衝撃作だ。とても新人作家の作品とは思えない超ド級の物語に、とにかく圧倒されてしまう。「社会は『幻想』を共有することで成り立っている」という、普段なかなか意識しない事実を巧みにちらつかせた、魔術のような作品
あわせて読みたい
【特異】「カメラの存在」というドキュメンタリーの大前提を覆す映画『GUNDA/グンダ』の斬新さ
映画『GUNDA/グンダ』は、「カメラの存在」「撮影者の意図」を介在させずにドキュメンタリーとして成立させた、非常に異端的な作品だと私は感じた。ドキュメンタリーの「デュシャンの『泉』」と呼んでもいいのではないか。「家畜」を被写体に据えたという点も非常に絶妙
あわせて読みたい
【おすすめ】「天才」を描くのは難しい。そんな無謀な挑戦を成し遂げた天才・野崎まどの『know』はヤバい
「物語で『天才』を描くこと」は非常に難しい。「理解できない」と「理解できる」を絶妙なバランスで成り立たせる必要があるからだ。そんな難題を高いレベルでクリアしている野崎まど『know』は、異次元の小説である。世界を一変させた天才を描き、「天才が見ている世界」を垣間見せてくれる
あわせて読みたい
【妄執】チェス史上における天才ボビー・フィッシャーを描く映画。冷戦下の米ソ対立が盤上でも:映画『…
「500年に一度の天才」などと評され、一介のチェスプレーヤーでありながら世界的な名声を獲得するに至ったアメリカ人のボビー・フィッシャー。彼の生涯を描く映画『完全なるチェックメイト』から、今でも「伝説」と語り継がれる対局と、冷戦下ゆえの激動を知る
あわせて読みたい
【新視点】世界の歴史を「化学」で語る?デンプン・砂糖・ニコチンなどの「炭素化合物」が人類を動かし…
デンプン・砂糖・ニコチンなどは、地球上で非常に稀少な元素である「炭素」から作られる「炭素化合物」だ。そんな「炭素化合物」がどんな影響を与えたかという観点から世界の歴史を描く『「元素の王者」が歴史を動かす』は、学校の授業とはまったく違う視点で「歴史」を捉える
あわせて読みたい
【思考】『翔太と猫のインサイトの夏休み』は、中学生と猫の対話から「自分の頭で考える」を学べる良書
「中学生の翔太」と「猫のインサイト」が「答えの出ない問い」について対話する『翔太と猫のインサイトの夏休み』は、「哲学」の違う側面を見せてくれる。過去の哲学者・思想家の考えを知ることが「哲学」なのではなく、「自分の頭で考えること」こそ「哲学」の本質だと理解する
あわせて読みたい
【実話】映画『イミテーションゲーム』が描くエニグマ解読のドラマと悲劇、天才チューリングの不遇の死
映画『イミテーションゲーム』が描く衝撃の実話。「解読不可能」とまで言われた最強の暗号機エニグマを打ち破ったのはなんと、コンピューターの基本原理を生み出した天才数学者アラン・チューリングだった。暗号解読を実現させた驚きのプロセスと、1400万人以上を救ったとされながら偏見により自殺した不遇の人生を知る
あわせて読みたい
【本質】子どもの頃には読めない哲学書。「他人の哲学はつまらない」と語る著者が説く「問うこと」の大…
『<子ども>のための哲学』は決して、「子どもでも易しく理解できる哲学の入門書」ではない。むしろかなり難易度が高いと言っていい。著者の永井均が、子どもの頃から囚われ続けている2つの大きな疑問をベースに、「『哲学する』とはどういうことか?」を深堀りする作品
あわせて読みたい
【最新】「コロンブス到達以前のアメリカ大陸」をリアルに描く歴史書。我々も米国人も大いに誤解してい…
サイエンスライターである著者は、「コロンブス到着以前のアメリカはどんな世界だったか?」という問いに触れ、その答えが書かれた本がいつまで経っても出版されないので自分で執筆した。『1491 先コロンブス期アメリカ大陸をめぐる新発見』には、アメリカ人も知らない歴史が満載だ
あわせて読みたい
【博覧強記】「紙の本はなくなる」説に「文化は忘却されるからこそ価値がある」と反論する世界的文学者…
世界的文学者であり、「紙の本」を偏愛するウンベルト・エーコが語る、「忘却という機能があるから書物に価値がある」という主張は実にスリリングだ。『もうすぐ絶滅するという紙の書物について』での対談から、「忘却しない電子データ」のデメリットと「本」の可能性を知る
あわせて読みたい
【異端】「仏教とは?」を簡単に知りたい方へ。ブッダは「異性と目も合わせないニートになれ」と主張し…
我々が馴染み深い「仏教」は「大乗仏教」であり、創始者ゴータマ・ブッダの主張が詰まった「小乗仏教」とは似て非なるものだそうだ。『講義ライブ だから仏教は面白い!』では、そんな「小乗仏教」の主張を「異性と目も合わせないニートになれ」とシンプルに要約して説明する
あわせて読みたい
【感想】池田晶子『14歳からの哲学』で思考・自由・孤独の大事さを知る。孤独を感じることって大事だ
「元々持ってた価値観とは違う考えに触れ、それを理解したいと思う場面」でしか「考える」という行為は発動しないと著者は言う。つまり我々は普段、まったく考えていないのだ。『14歳からの哲学』をベースに、「考えること」と自由・孤独・人生との関係を知る
あわせて読みたい
【飛躍】有名哲学者は”中二病”だった?飲茶氏が易しく語る「古い常識を乗り越えるための哲学の力」:『1…
『14歳からの哲学入門』というタイトルは、「14歳向けの本」という意味ではなく、「14歳は哲学することに向いている」という示唆である。飲茶氏は「偉大な哲学者は皆”中二病”だ」と説き、特に若い人に向けて、「新しい価値観を生み出すためには哲学が重要だ」と語る
あわせて読みたい
【おすすめ】濱口竜介監督の映画『親密さ』は、「映像」よりも「言葉」が前面に来る衝撃の4時間だった
専門学校の卒業制作として濱口竜介が撮った映画『親密さ』は、2時間10分の劇中劇を組み込んだ意欲作。「映像」でありながら「言葉の力」が前面に押し出される作品で、映画や劇中劇の随所で放たれる「言葉」に圧倒される。4時間と非常に長いが、観て良かった
あわせて読みたい
【歴史】ベイズ推定は現代社会を豊かにするのに必須だが、実は誕生から200年間嫌われ続けた:『異端の統…
現在では、人工知能を始め、我々の生活を便利にする様々なものに使われている「ベイズ推定」だが、その基本となるアイデアが生まれてから200年近く、科学の世界では毛嫌いされてきた。『異端の統計学ベイズ』は、そんな「ベイズ推定」の歴史を紐解く大興奮の1冊だ
あわせて読みたい
【興奮】世界的大ベストセラー『サピエンス全史』要約。人類が文明を築き上げるに至った3つの革命とは?
言わずと知れた大ベストセラー『サピエンス全史』は、「何故サピエンスだけが人類の中で生き残り、他の生物が成し得なかった歴史を歩んだのか」を、「認知革命」「農業革命」「科学革命」の3つを主軸としながら解き明かす、知的興奮に満ち溢れた1冊
あわせて読みたい
【知的】文系にオススメの、科学・数学・哲学の入門書。高橋昌一郎の「限界シリーズ」は超絶面白い:『…
例えば「科学」だけに限ってみても、「なんでもできる」わけでは決してない。「科学」に限らず、私たちが対峙する様々な事柄には「これ以上は不可能・無理」という「限界」が必ず存在する。高橋昌一郎の「限界シリーズ」から、我々が認識しておくべき「限界」を易しく学ぶ
あわせて読みたい
【興奮】飲茶氏の超面白い哲学小説。「正義とは?」の意味を問う”3人の女子高生”の主張とは?:『正義の…
なんて面白いんだろうか。哲学・科学を初心者にも分かりやすく伝える飲茶氏による『正義の教室』は、哲学書でありながら、3人の女子高生が登場する小説でもある。「直観主義」「功利主義」「自由主義」という「正義論」の主張を、「高校の問題について議論する生徒会の話し合い」から学ぶ
あわせて読みたい
【知】内田樹が教育・政治を語る。「未来の自分」を「別人」と捉える「サル化した思考」が生む現実:『…
「朝三暮四」の故事成語を意識した「サル化」というキーワードは、現代性を映し出す「愚かさ」を象徴していると思う。内田樹『サル化する世界』から、日本の教育・政治の現状及び問題点をシンプルに把握し、現代社会を捉えるための新しい視点や価値観を学ぶ
あわせて読みたい
【驚異】ガイア理論の提唱者が未来の地球を語る。100歳の主張とは思えない超絶刺激に満ちた内容:『ノヴ…
「地球は一種の生命体だ」という主張はかなり胡散臭い。しかし、そんな「ガイア理論」を提唱する著者は、数々の賞や学位を授与される、非常に良く知られた科学者だ。『ノヴァセン <超知能>が地球を更新する』から、AIと人類の共存に関する斬新な知見を知る
あわせて読みたい
【興奮】飲茶氏が西洋哲学を語る。難解な思想が「グラップラー刃牙成分」の追加で驚異的な面白さに:『…
名前は聞いたことはあるがカントやニーチェがどんな主張をしたのかは分からないという方は多いだろう。私も無知なまったくの初心者だが、そんな人でも超絶分かりやすく超絶面白く西洋哲学を”分かった気になれる”飲茶『史上最強の哲学入門』は、入門書として最強
あわせて読みたい
【思考】「”考える”とはどういうことか」を”考える”のは難しい。だからこの1冊をガイドに”考えて”みよう…
私たちは普段、当たり前のように「考える」ことをしている。しかし、それがどんな行為で、どのように行っているのかを、きちんと捉えて説明することは難しい。「はじめて考えるときのように」は、横書き・イラスト付きの平易な文章で、「考えるという行為」の本質に迫り、上達のために必要な要素を伝える
あわせて読みたい
【権威】心理学の衝撃実験をテレビ番組の収録で実践。「自分は残虐ではない」と思う人ほど知るべき:『…
フランスのテレビ局が行った「現代版ミルグラム実験」の詳細が語られる『死のテレビ実験 人はそこまで服従するのか』は、「権威」を感じる対象から命じられれば誰もが残虐な行為をしてしまい得ることを示す。全人類必読の「過ちを事前に回避する」ための知見を学ぶ
あわせて読みたい
【教養】美術を「感じたまま鑑賞する」のは難しい。必要な予備知識をインストールするための1冊:『武器…
芸術を「感性の赴くまま見る」のは、日本特有だそうだ。欧米では美術は「勉強するもの」と認識されており、本書ではアートを理解しようとするスタンスがビジネスにも役立つと示唆される。美術館館長を務める著者の『武器になる知的教養 西洋美術鑑賞』から基礎の基礎を学ぶ
あわせて読みたい
【感心】悩み相談とは、相手の問いに答える”だけ”じゃない。哲学者が相談者の「真意」に迫る:『哲学の…
「相談に乗る」とは、「自分の意見を言う行為」ではない。相談者が”本当に悩んでいること”を的確に捉えて、「回答を与えるべき問いは何か?」を見抜くことが本質だ。『哲学の先生と人生の話をしよう』から、「相談をすること/受けること」について考える
あわせて読みたい
【幻想】超ひも理論って何?一般相対性理論と量子力学を繋ぐかもしれないぶっ飛んだ仮説:『大栗先生の…
『大栗先生の超弦理論入門』は最先端科学である「超弦理論」を説明する1冊だが、この記事では著者の主張の1つである「空間は幻想かもしれない」という発想を主に取り上げる。「人類史上初の『適用する次元が限定される理論』」が描像する不可思議な世界とは?
あわせて読みたい
【限界】「科学とは何か?」を知るためのおすすめ本。科学が苦手な人こそ読んでほしい易しい1冊:『哲学…
「科学的に正しい」という言葉は、一体何を意味しているのだろう?科学者が「絶対に正しい」とか「100%間違っている」という言い方をしないのは何故だろう?飲茶『哲学的な何か、あと科学とか』から、「科学とはどんな営みなのか?」について考える
あわせて読みたい
【戸惑】人間の脳は摩訶不思議。意識ではコントロールできない「無意識の領域」に支配されている:『あ…
我々は決断や選択を「自分の意思」で行っていると感じるが、脳科学の研究はそれを否定している。我々に「自由意志」などない。「脳」の大部分は「意識以外のもの」に支配され、そこに「意識」はアクセスできないという驚愕の実態を『あなたの知らない脳』から学ぶ
あわせて読みたい
【逸話】天才数学者ガロアが20歳で決闘で命を落とすまでの波乱万丈。時代を先駆けた男がもし生きていた…
現代数学に不可欠な「群論」をたった1人で生み出し、20歳という若さで決闘で亡くなったガロアは、その短い生涯をどう生きたのか?『ガロア 天才数学者の生涯』から、数学に関心を抱くようになったきっかけや信じられないほどの不運が彼の人生をどう変えてしまったのか、そして「もし生きていたらどうなっていたのか」を知る
あわせて読みたい
【バトル】量子力学の歴史はこの1冊で。先駆者プランクから批判者アインシュタインまですべて描く:『量…
20世紀に生まれた量子論は、時代を彩る天才科学者たちの侃々諤々の議論から生み出された。アインシュタインは生涯量子論に反対し続けたことで知られているが、しかし彼の批判によって新たな知見も生まれた。『量子革命』から、量子論誕生の歴史を知る
あわせて読みたい
【ドラマ】「フェルマーの最終定理」のドラマティックな証明物語を、飲茶氏が平易に描き出す:『哲学的…
「フェルマーの最終定理」は、問題の提示から350年以上経ってようやく証明された超難問であり、その証明の過程では様々な人間ドラマが知られている。『哲学的な何か、あと数学とか』をベースに、数学的な記述を一切せず、ドラマティックなエピソードだけに触れる
あわせて読みたい
【不可思議】心理学の有名な実験から、人間の”欠陥”がどう明らかになっていったかを知る:『心は実験で…
『心は実験できるか 20世紀心理学実験物語』では、20世紀に行われた心理学実験からインパクトのある10の実験を選び紹介している。心理学者でもある著者が「科学であって科学ではない」と主張する心理学という学問で、人間のどんな不可思議さがあぶり出されてきたのかを知る
あわせて読みたい
【神秘】脳研究者・池谷裕二が中高生向けに行った講義の書籍化。とても分かりやすく面白い:『進化しす…
「宇宙」「深海」「脳」が、人類最後のフロンティアと呼ばれている。それほど「脳」というのは、未だに分からないことだらけの不思議な器官だ。池谷裕二による中高生向けの講義を元にした『進化しすぎた脳』『単純な脳、複雑な「私」』をベースに、脳の謎を知る
あわせて読みたい
【論争】サイモン・シンが宇宙を語る。古代ギリシャからビッグバンモデルの誕生までの歴史を網羅:『宇…
古代から現代に至るまで、「宇宙」は様々な捉えられ方をしてきた。そして、新たな発見がなされる度に、「宇宙」は常識から外れた不可思議な姿を垣間見せることになる。サイモン・シン『宇宙創成』をベースに、「ビッグバンモデル」に至るまでの「宇宙観」の変遷を知る
あわせて読みたい
【衝撃】ABC予想の証明のために生まれたIUT理論を、提唱者・望月新一の盟友が分かりやすく語る:『宇宙…
8年のチェック期間を経て雑誌に掲載された「IUT理論(宇宙際タイヒミュラー理論)」は、数学の最重要未解決問題である「ABC予想」を証明するものとして大いに話題になった。『宇宙と宇宙をつなぐ数学』『abc予想入門』をベースに、「IUT理論」「ABC予想」について学ぶ
あわせて読みたい
【限界】有名な「錯覚映像」で心理学界をザワつかせた著者らが語る「人間はいかに間違えるか」:『錯覚…
私たちは、知覚や記憶を頼りに社会を生きている。しかしその「知覚」「記憶」は、本当に信頼できるのだろうか?心理学の世界に衝撃を与えた実験を考案した著者らの『錯覚の科学』から、「避けられない失敗のクセ」を理解する
あわせて読みたい
【興奮】結城浩「数学ガール」で、決闘で命を落とした若き天才数学者・ガロアの理論を学ぶ
高校生を中心に、数学を通じて関わり合う者たちを描く「数学ガール」シリーズ第5弾のテーマは「ガロア理論」。独力で「群論」という新たな領域を切り開きながら、先駆的すぎて同時代の数学者には理解されず、その後決闘で死亡した天才の遺した思考を追う
あわせて読みたい
【誤り】「信じたいものを信じる」のは正しい?映画『星の子』から「信じること」の難しさを考える
どんな病気も治す「奇跡の水」の存在を私は信じないが、しかし何故「信じない」と言えるのか?「奇跡の水を信じる人」を軽々に非難すべきではないと私は考えているが、それは何故か?映画『星の子』から、「何かを信じること」の難しさについて知る
あわせて読みたい
【刺激】結城浩「数学ガール」で、ゲーデルの不完全性定理(不可能性の証明として有名)を学ぶ
『結城浩「数学ガール」シリーズは、数学の面白さを伝えながら、かなり高難度の話題へと展開していく一般向けの数学書です。その第3弾のテーマは、「ゲーデルの不完全性定理」。ヒルベルトという数学者の野望を打ち砕いた若き天才の理論を学びます
あわせて読みたい
【異端】数学の”証明”はなぜ生まれたのか?「無理数」と「無限」に恐怖した古代ギリシャ人の奮闘:『数…
学校で数学を習うと、当然のように「証明」が登場する。しかしこの「証明」、実は古代ギリシャでしか発展しなかった、数学史においては非常に”異端”の考え方なのだ。『数学の想像力 正しさの深層に何があるのか』をベースに、ギリシャ人が恐れたものの正体を知る
あわせて読みたい
【対立】数学はなぜ”美しい”のか?数学は「発見」か「発明」かの議論から、その奥深さを知る:『神は数…
数学界には、「数学は神が作った派」と「数学は人間が作った派」が存在する。『神は数学者か?』をベースに、「数学は発見か、発明か」という議論を理解し、数学史においてそれぞれの認識がどのような転換点によって変わっていったのかを学ぶ
あわせて読みたい
【始まり】宇宙ができる前が「無」なら何故「世界」が生まれた?「ビッグバンの前」は何が有った?:『…
「宇宙がビッグバンから生まれた」ことはよく知られているだろうが、では、「宇宙ができる前はどうなっていたのか」を知っているだろうか? 実は「宇宙は”無”から誕生した」と考えられているのだ。『宇宙が始まる前には何があったのか?』をベースに、ビッグバンが起こる前の「空間も時間も物理法則も存在しない無」について学ぶ
あわせて読みたい
【未知】タコに「高度な脳」があるなんて初耳だ。人類とは違う進化を遂げた頭足類の「意識」とは?:『…
タコなどの頭足類は、無脊椎動物で唯一「脳」を進化させた。まったく違う進化を辿りながら「タコに心を感じる」という著者は、「タコは地球外生命体に最も近い存在」と書く。『タコの心身問題』から、腕にも脳があるタコの進化の歴史と、「意識のあり方」を知る。
あわせて読みたい
【驚嘆】人類はいかにして言語を獲得したか?この未解明の謎に真正面から挑む異色小説:『Ank: a mirror…
小説家の想像力は無限だ。まさか、「人類はいかに言語を獲得したか?」という仮説を小説で読めるとは。『Ank: a mirroring ape』をベースに、コミュニケーションに拠らない言語獲得の過程と、「ヒト」が「ホモ・サピエンス」しか存在しない理由を知る
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
哲学・思想【本・映画の感想】 | ルシルナ
私の知識欲は多方面に渡りますが、その中でも哲学や思想は知的好奇心を強く刺激してくれます。ニーチェやカントなどの西洋哲学も、禅や仏教などの東洋哲学もとても奥深いも…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…













































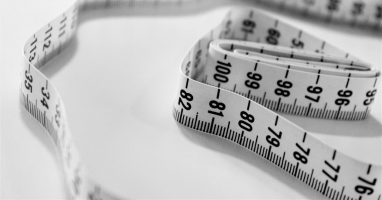





























































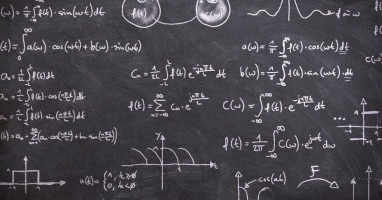













コメント