目次
はじめに
この記事で取り上げる本
著:秋元 雄史
¥1,760 (2021/12/08 06:17時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
この本をガイドにしながら記事を書いていきます
この記事の3つの要点
- なぜ日本人だけが「美術は感性のまま観るもの」と捉えるようになってしまったのか?
- 「現代アート」は本書の著者でさえ「よくわからない」と感じることがある
- 「ルネサンス」から「ポップアート」までの西洋美術の流れをざっと追う
本書を読んでから美術展に行けば、それまでとは全然違う美術鑑賞ができるのではないかと思います
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
「感性」では美術を鑑賞できない、知識がなければいくら見たって分からないのだと、秋元雄史『西洋美術鑑賞』を読んで理解できた
美術の鑑賞に、何故「知識」が必要なのか
あわせて読みたい
【アート】「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」(森美術館)と「美術手帖 Chim↑Pom特集」の衝撃から「…
Chim↑Pomというアーティストについてさして詳しいことを知らずに観に行った、森美術館の「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」に、思考をドバドバと刺激されまくったので、Chim↑Pomが特集された「美術手帖」も慌てて買い、Chim↑Pomについてメッチャ考えてみた
私は意識的に、時々美術館に行くようにしている。せっかく東京に住んでいるのだし、やはり「教養」として、美術を知っておくことはなんとなく大事だと思っているからだ。

しかし、観ても大体よく分からない。
もちろん、見て「あぁこれは好きだなぁ」と感じるような美術作品に出会うこともある。私にとって非常に印象的だったのは、白髪一雄というアーティストの作品だ。正直、何に凄いと感じたのかまったく説明できないのだが、これまで美術展で観たどの作品よりも衝撃的で、「凄いものを観た」という印象だった。
あわせて読みたい
【解釈】詩人が語る詩の読み方。意味や読み方や良さが分からなくて全然気にしなくていい:『今を生きる…
私は学生時代ずっと国語の授業が嫌いでしたが、それは「作品の解釈には正解がある」という決めつけが受け入れ難かったからです。しかし、詩人・渡邊十絲子の『今を生きるための現代詩』を読んで、詩に限らずどんな作品も、「解釈など不要」「理解できなければ分からないままでいい」と思えるようになりました
確かに、そういうことは時々ある。しかしだからと言って、そういう「感性に任せた鑑賞」が正しいというわけではない。著者はこんな風に書いている。
絵画の鑑賞法として、よく「感じたままに感性で観ればいい」という人がいます。もちろん、何の予備知識もなく偶然出合った絵に、心を打たれるような体験をする人もいるでしょうが、多くの場合、何の予備知識もなければ「何を感じて良いかもわからない」状態になるはずです。
そのような事態を避けるためにも予備知識は必須なのです。
こういうことをちゃんと教えてくれる大人にもっと早く出会いたかったものだ。
あわせて読みたい
【問い】「学ぶとはどういうことか」が学べる1冊。勉強や研究の指針に悩む人を導いてくれる物語:『喜嶋…
学校の勉強では常に「課題」が与えられていたが、「学び」というのは本来的に「問題を見つけること」にこそ価値がある。研究者の日常を描く小説『喜嶋先生の静かな世界』から、「学びの本質」と、我々はどんな風に生きていくべきかについて考える
私が面白いと感じたのは、「なぜ日本では、『感性のまま観る』という鑑賞法が定着したのか」の説明である。
「感性のおもむくまま観る」といった鑑賞の仕方は日本特有のもので、日本美術の歴史とも深く関わっています。一般の日本人が西洋美術に触れたのは、明治の文明開化以降のことでした。その頃の西洋美術は、「印象派」全盛の時代でした。印象派の作品は、理屈抜きで純粋に目の娯楽として楽しめます。
神話や古典を基盤とした従来のアカデミスム絵画は、鑑賞するにあたって高度な教養が求められていましたが、印象派の絵を見る際に、専門的な知識・教養はさほど必要ではありません。
多くの人は幸か不幸か、印象派の作品が西洋絵画を代表するものとすり込まれてしまいました。以来「アートは感じたままに観ればいい」となってしまい、本来知識や教養が必要とされるはずの西洋美術に馴染めなくなってしまったようです
なるほど、私たち日本人は、「西洋美術」との出会い方が、少しばかりまずかったようだ。著者の説明は非常に分かりやすいと感じるし、「やはり美術の鑑賞には知識が必要なのだ」という理解にも繋がるだろう。
あわせて読みたい
【アート】映画『ダ・ヴィンチは誰に微笑む』が描く「美術界の闇」と「芸術作品の真正性」の奥深さ
美術界史上最高額510億円で落札された通称「救世主」は、発見される以前から「レオナルド・ダ・ヴィンチの失われた作品」として知られる有名な絵だった。映画『ダ・ヴィンチは誰に微笑む』は、「芸術作品の真正性の問題」に斬り込み、魑魅魍魎渦巻く美術界を魅力的に描き出す
アメリカでは、「美術は勉強するもの」というのが常識だそうだ。
ニューヨークの社交界では、ニューヨーク近代美術館(以下MoMA)のボードメンバーかどうかが非常に重要視されます。どんなにお金を持っていようが、芸術の話題を出せないようでは、まったくもって話になりません。
つまり、美術鑑賞という行為は、品格のある者に求められる教養である、という共通認識があるのです。
そのため、地位も名誉も資産も勝ち取った初老のセレブリティや富豪たちが、こぞってMoMAの主宰する講習会に参加し、ボードメンバーになるべく勉強するのです
本書に書かれているわけではないが、欧米ではお金持ちになったら寄付をするのが当たり前だ、という話を聞いたことがある。正確には覚えていないが、キリスト教圏では「富を持つことは罪だ」というような発想があるようで、だから寄付文化が根づいているという説明だったと思う。

日本では、「お金を持っていること=偉い・羨ましい」という発想に陥りがちだが、欧米では、美術の教養や寄付行為などがなければ、いくらお金があっても認められないというわけだ。このような「社会的豊かさ」があるのとないのとでは、国全体の文化的資本も大きく変わってくるだろうと感じる。日本でも、教養のない金持ちは評価されない、という風になってほしいものだと思う。
あわせて読みたい
【表現】映画『名付けようのない踊り』で初めて見た田中泯のダンス。「芸術以前」を志向する圧倒的パワー
映画『名付けようのない踊り』の中で田中泯は言う。「私」や「個性」を表現することには違和感がある、と。「踊りのために身体を作る」のではなく、「野良仕事で出来た身体で踊る」のだ、と。芸術になる前の踊りを探したい、と。「唯一無二の表現者」の生涯と現在地を映し出すドキュメンタリー
さてで西洋美術館鑑賞のためには、どんなことを学ぶべきなのだろうか。具体的には是非本書を読んでほしいが、著者が挙げているものの1つに「人間の描き方」がある。
西洋において、人間は全知全能の神が自らに似せて創ったものとされます。ですから、人間を徹底的に観察することで、神や宇宙を知ろうと考えました。
(中略)
そのため、キリスト教絵画では、自然を描く風景画は、格が低いものとみなされ、産業革命を経て写実派が登場する以前、西洋では風景画はほとんど描かれてきませんでした。
やはり美術の鑑賞には、キリスト教の素養は不可欠だと言っていいだろう。それもまた、我々日本人が西洋美術を学ぶ上でのハードルだと言える。しかしこの違いは反対に、驚きを与えることにもなったという。
一方、日本では太陽や月、風や雨、動植物も人間もみんな神様です。人間もあくまで自然の一部でした。そうした視点で自然を描いた日本の浮世絵などに19世紀のヨーロッパの画家たちが衝撃を受けたことも、日本と西洋の文化的な違いを知っていれば、理解できることでしょう
東洋人が西洋の美術に触れることは、文化や価値観のギャップを知る機会でもあるし、逆もまた然りというわけである。だからこそ、美術の理解のためには、その前提となる文化や価値観を知っておく必要があるのだ。
あわせて読みたい
【称賛?】日本社会は終わっているのか?日本在住20年以上のフランス人が本国との比較で日本を評価:『…
日本に住んでいると、日本の社会や政治に不満を抱くことも多い。しかし、日本在住20年以上の『理不尽な国ニッポン』のフランス人著者は、フランスと比べて日本は上手くやっていると語る。宗教や個人ではなく、唯一「社会」だけが善悪を決められる日本の特異性について書く
「現代アートは分からない」のが当たり前
本書の著者は、東京芸術大学美術館と練馬区立美術館の館長を務める人物だが、そんな人がこんなことを言っている。
よく現代アートを「わからない」という人がいますが、マネやマティス、ピカソやゴッホも当時からすれば今でいう現代アートの扱いでした。彼らも当時は「よくわからない」と批評されたのです。正直にいうと、専門家でも「よくわからない」という状況はよくありますし、それは今も昔も変わりません
まず、こんな風に言ってもらえると、芸術のド素人としては安心できる。専門家でさえ「よくわからない」なら、我々に分かるはずがない。
あわせて読みたい
【革新】天才マルタン・マルジェラの現在。顔出しNGでデザイナーの頂点に立った男の”素声”:映画『マル…
「マルタン・マルジェラ」というデザイナーもそのブランドのことも私は知らなかったが、そんなファッション音痴でも興味深く観ることができた映画『マルジェラが語る”マルタン・マルジェラ”』は、生涯顔出しせずにトップに上り詰めた天才の来歴と現在地が語られる
例えば、ピカソは現在でこそ誰もが知るほど有名で高く評価された芸術家だが、
しかし、この時代にピカソと交流していたモンマルトルの仲間たちですら、この作品を初めて観たときは「ピカソは気が狂ったのではないか」と本気で心配したといいます。それほどこの作品は当時の常識からかけ離れていたのです
と本書には書かれている。どの時代でもアートの最先端というのは、最前線を突き抜けた者にしか理解できないということだろう。

あわせて読みたい
【あらすじ】天才とは「分かりやすい才能」ではない。前進するのに躊躇する暗闇で直進できる勇気のこと…
ピアノのコンクールを舞台に描く『蜜蜂と遠雷』は、「天才とは何か?」と問いかける。既存の「枠組み」をいとも簡単に越えていく者こそが「天才」だと私は思うが、「枠組み」を安易に設定することの是非についても刃を突きつける作品だ。小説と映画の感想を一緒に書く
また本書には、デュシャンの「泉」という作品についての言及がある。私は、この作品の存在とその評価について知った時は驚愕した。
まず、この「泉」という作品の評価について触れておこう。
2004年に、世界の芸術をリードする500人に「最もインパクトのある現代美術の作品」を5点選んでもらったアンケート調査でも、あのピカソの<アヴィニョンの娘たち>を抑えて1位となりました。多くの人が現代アートの出発点と考えているのが、デュシャンの<泉>なのです
この記述で、どれほど高く評価されているか理解できるだろう。しかしこの「泉」、「美術作品」と言われてピンと来るものでは到底ない。是非ネットで画像検索でもしてみてほしいが、「男性用小便器に偽名でサインを書いたもの」なのだ。
なんだってこんなものが評価されているのだろうか?
あわせて読みたい
【博覧強記】「紙の本はなくなる」説に「文化は忘却されるからこそ価値がある」と反論する世界的文学者…
世界的文学者であり、「紙の本」を偏愛するウンベルト・エーコが語る、「忘却という機能があるから書物に価値がある」という主張は実にスリリングだ。『もうすぐ絶滅するという紙の書物について』での対談から、「忘却しない電子データ」のデメリットと「本」の可能性を知る
当然と言えば当然だが、この「泉」にしても最初から評価されていたわけでは決してない。
アンデパンダン展でも実行委員から「こんなものはアートではない」と展示を拒否されています
まあそうだろう。その存在はシンプルに意味が分からない。展示拒否という扱いも仕方ないだろう。
では現在は何故評価されているのか。その理由は、
「ただ一つだけのハンドメイドにこそ価値があり、美こそ善である」といった、美術界の既成概念を打ち破るためでした
という点にある。
あわせて読みたい
【芸術】実話を下敷きに描く映画『皮膚を売った男』は、「アートによる鮮やかな社会問題風刺」が見事
「シリア難民の背中にタトゥーを彫り芸術作品として展示する」と聞くと非常に不謹慎に感じられるだろうが、彫ったのが国家間の移動を自由にする「シェンゲンビザ」だという点が絶妙な皮肉。実話をベースにした映画『皮膚を売った男』の、アートによる社会問題提起の見事な鮮やかさ
そして、何故「泉」が評価されているのかというその理由は、現代アートを捉える際の1つの軸足となる。つまり、「既成概念を打ち破ること」に価値がある、というわけだ。
「泉」の登場以前は、「芸術家が自ら作り上げた美しい一点物」ばかりが評価されていた。「美しい」の価値基準は人それぞれとはいえ、やはり総じて「美しい」と評したくなるようなものが芸術として残ってきたのだろう。

しかしデュシャンの「泉」は、「既製品の男性用小便器」を使うことで「美しいこと」も「一点物であること」も否定した。つまり、美術の価値判断において誰も疑問に思わなかった当然の事柄に、「泉」が疑問を投げかけたというわけだ。
あわせて読みたい
【創作】クリエイターになりたい人は必読。ジブリに見習い入社した川上量生が語るコンテンツの本質:『…
ドワンゴの会長職に就きながら、ジブリに「見習い」として入社した川上量生が、様々なクリエイターの仕事に触れ、色んな質問をぶつけることで、「コンテンツとは何か」を考える『コンテンツの秘密』から、「創作」という営みの本質や、「クリエイター」の理屈を学ぶ
「泉」の価値はこの点にある。
<泉>を見た人は「芸術とは何か」を自らに問わざるを得なくなりました
この作品によって、これ以降の芸術家は「デュシャン以降、何が芸術なのか」という問いに応えるような、新たな発想で作品をつくるようになりました。それこそ、デュシャンが現代アートの生みの親とされ、高く評価される理由なのです
まさにこの「泉」も、芸術の理解に知識が必要だと認識させてくれる実例だろう。何も知らなければ、ただの便器でしかない。しかしそこに上述のような知識が加わることで、「現代美術の1位作品」としての価値が立ち上がってくる、というわけだ。
あわせて読みたい
【奇跡】鈴木敏夫が2人の天才、高畑勲と宮崎駿を語る。ジブリの誕生から驚きの創作秘話まで:『天才の思…
徳間書店から成り行きでジブリ入りすることになったプロデューサー・鈴木敏夫が、宮崎駿・高畑勲という2人の天才と共に作り上げたジブリ作品とその背景を語り尽くす『天才の思考 高畑勲と宮崎駿』。日本のアニメ界のトップランナーたちの軌跡の奇跡を知る
そもそも「現代アート」に触れるべき理由は何か?
しかしそもそも、わざわざ勉強してまで西洋美術や現代アートを理解する必要はあるのだろうか? その理由を本書ではこう書いている。
あわせて読みたい
【改革】改修期間中の国立西洋美術館の裏側と日本の美術展の現実を映すドキュメンタリー映画:『わたし…
「コロナ禍」という絶妙すぎるタイミングで改修工事を行った国立西洋美術館の、普段見ることが出来ない「裏側」が映し出される映画『わたしたちの国立西洋美術館』は、「日本の美術展」の問題点を炙り出しつつ、「『好き』を仕事にした者たち」の楽しそうな雰囲気がとても魅力的に映るドキュメンタリー
あなたも今はまだ、これまでに見たこともない現代アートに遭遇したら、違和感を覚えるかもしれません。
しかし、その違和感こそが新たな目が開かれるチャンスでもあるのです。美術鑑賞は、自分がそれまでに知らなかった価値観があることに気づいたり、「むむっ、私はこういうものに対して、こんなふうに考えていたのか」といったことに気づいたりできる絶好の機会なのです。
現代アートを楽しむことは、知的なゲームのようなもの。あふれかえる情報で凝り固まった頭のストレッチにもなります。文脈を把握してみると、自分が今、どういう時代に生きているのかもわかります。
つまり時代が読めるようになるのです。そこにビジネスのヒントも隠されているかもしれません

あわせて読みたい
【思考】文章の書き方が分かんない、トレーニングしたいって人はまず、古賀史健の文章講義の本を読め:…
古賀史健『20歳の自分に受けさせたい文章講義』は、「具体的なテクニック」ではない記述も非常に興味深い1冊だ。「なぜ文章を書く必要があるのか」という根本的な部分から丁寧に掘り下げる本書は、「書くからこそ考えられる」という、一般的なイメージとは逆だろう発想が提示される
この記事の流れでは少し唐突かもしれないが、上の引用中に「ビジネスのヒント」などという単語が出てくるのは、本書の冒頭で、
欧米では今、ビジネスシーンでアートが注目されています
と書かれていることにも関係する。本書は、単なる美術鑑賞指南本ではなく、「ビジネスに活かすための教養」という観点からも読める作品に仕上がっているのだ。
あわせて読みたい
【能力】激変する未来で「必要とされる人」になるためのスキルや考え方を落合陽一に学ぶ:『働き方5.0』
AIが台頭する未来で生き残るのは難しい……。落合陽一『働き方5.0~これからの世界をつくる仲間たちへ~』はそう思わされる一冊で、本書は正直、未来を前向きに諦めるために読んでもいい。未来を担う若者に何を教え、どう教育すべきかの参考にもなる一冊。
アートとビジネスの関係性については、「Soup Stock Tokyo」で知られる「スマイルズ」の遠山正道氏や「ZOZOTOWN」の前澤友作氏の話を引き合いに出しながらこんな風に書かれている。
まだ世の中にないもの、自分自身でも何かわからないものを徐々に言語化して表現していくことが、遠山氏にとってのビジネスだといいます。
実際、テクノロジーの急激な変化で、さまざまな分野がボーダレスとなっている時代に、遠山氏や前澤氏らは、異質なものを結びつけながら新たな価値観を創造して、社会的な成功を収めました。それが創造プロセスとそっくりだというのです
確かにこのように考えれば、「アートを理解すること」と「新たなビジネスを生み出すこと」は表裏一体だと言えるだろう。資産運用的な意味合いもあるだろうが、経営者などは美術作品にお金を使っている印象がある。趣味と実益を兼ねている、ということかもしれない。
あわせて読みたい
【継続】「言語化できない」を乗り越えろ。「読者としての文章術」で、自分の思考をクリアにする:『読…
ブログやSNSなどが登場したことで、文章を書く機会は増えていると言える。しかし同時に、「他人に評価されるために書く」という意識も強くなっているだろう。『読みたいことを書けばいい』から、「楽しく書き”続ける”」ための心得を学ぶ
本書では、ビジネスとの関わりについての記述はそこまで多くないが、「西洋美術」や「現代アート」を理解することがビジネスに繋がるというスタンスは貫かれている。日本国内に留まり続けるのであればともかく、欧米と何らかの形で関わるのであれば、最低限必要となる知識が詰まっていると言えると思うので、入門書として手にとってみるのがいいだろう。
西洋美術のざっとした流れ
それでは最後に、本書で触れられている「西洋美術の流れ」について、ざっと紹介していこうと思う。
まず、名前はよく知られているだろう「ルネサンス」から変化が始まる。それまで絵画と言えば「宗教画」のことを指していた。しかし、教会の権威が揺らぎ始めたことで、「見る聖書」としての役割を担っていた宗教画に代わって、人間を描く絵画が生まれるようになる。
あわせて読みたい
【興奮】飲茶氏が西洋哲学を語る。難解な思想が「グラップラー刃牙成分」の追加で驚異的な面白さに:『…
名前は聞いたことはあるがカントやニーチェがどんな主張をしたのかは分からないという方は多いだろう。私も無知なまったくの初心者だが、そんな人でも超絶分かりやすく超絶面白く西洋哲学を”分かった気になれる”飲茶『史上最強の哲学入門』は、入門書として最強
それから「バロック」が生まれた。この背景には、「宗教画の禁止」がある。教会の権威が失墜しプロテスタントが誕生するのだが、旧約聖書では偶像崇拝が禁じられていることもあり、プロテスタントでは「宗教画」が認められなくなっていくのだ。それによって、フェルメールのような「日常を描く絵」が裕福な市民の邸宅を飾るという変化が起こる。
しかし、急速な近代化によって様々な「陰」が生まれるようにもなっていった。そしてそんな社会変化や人間の戸惑いを描き出すために、より客観的な絵画が誕生する。「写実主義」だ。しかしその「目に見えるものしか描かない」というスタンスがあまりにも強かったため、反動として「印象派」が生まれることになる。

「印象派」は、当時の美術界を牛耳っていた「サロン」に背を向け、独自の表現を目指すようになる。その最大の特徴は「色はモノに固定されているのではなく、光の加減で変わる。だからこそ、光による一瞬の変化を切り取る」というスタンスだ。
このような表現が実現した背景には、「チューブ入りの絵の具」と「写真」という2つの発明が関係している。光の変化を描くためには外で絵を描く必要があり、「チューブ入りの絵の具」はそれを可能にした。また「写真」が登場したことで、それまで勢力を誇っていた「写実的に描く肖像画家」が仕事を失い、衰退していったことも影響している。
あわせて読みたい
【革命】観る将必読。「将棋を観ること」の本質、より面白くなる見方、そして羽生善治の凄さが満載:『…
野球なら「なんで今振らないんだ!」みたいな素人の野次が成立するのに、将棋は「指せなきゃ観てもつまらない」と思われるのは何故か。この疑問を起点に、「将棋を観ること」と「羽生善治の凄さ」に肉薄する『羽生善治と現代』は、「将棋鑑賞」をより面白くしてくれる話が満載
「印象派」と言えばセザンヌだが、セザンヌの存在は後の美術界に大きな影響を及ぼした。
まずセザンヌは「現代アートの父」と呼ばれているという。それは、
絵画は、現実に存在している物体の模倣ではなく、それ自体で本物の価値に匹敵する一つの創造物
絵画は堅固で自立的な再構築物であるべきだ
という彼の考え方が、その後のアートの主流として受け入れられるようになっていったからだ。
あわせて読みたい
【無謀】園子温が役者のワークショップと同時並行で撮影した映画『エッシャー通りの赤いポスト』の”狂気”
「園子温の最新作」としか知らずに観に行った映画『エッシャー通りの赤いポスト』は、「ワークショップ参加者」を「役者」に仕立て、ワークショップと同時並行で撮影されたという異次元の作品だった。なかなか経験できないだろう、「0が1になる瞬間」を味わえる“狂気”の映画
またセザンヌは、ピカソのものとして有名な「キュビズム」に繋がる手法を試みてもいる。既に「多視点で捉えた構図を画面内で再構築する」という、まさに「キュビズム」として花開くことになる手法を実践しているのだそうだ。なかなか凄い人物である。
さてその後「フォービズム」という時代がやってくるが、ここにもセザンヌの影がある。「フォービズム」とは「色」の革命なのだが、そもそも彼が
絵画とは「色と形」の芸術である
という新解釈を探求し続けたことで、20世紀の画家たちは「色」と「形」の表現を突き詰めることになったのだ。
あわせて読みたい
【倫理】アート体験の行き着く未来は?映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』が描く狂気の世界(…
「『痛み』を失った世界」で「自然発生的に生まれる新たな『臓器』を除去するライブパフォーマンス」を行うソール・テンサーを主人公にした映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』は、すぐには答えの見出しにくい「境界線上にある事柄」を挑発的に描き出す、実に興味深い物語だ
「フォービズム」という、現実の色を描くのではなく色によって感情を描き出すという手法を取り入れたことで、
「どんな色で対象物を描いても構わない」という自由を与えたことは、20世紀の絵画史で最大の革命といえます
と著者が評価するほどの進化をもたらすこととなった。
さて、もう一方の「形」の革命はと言うと、前述した「キュビズム」である。セザンヌが試した「多視点」をさらに突き詰めることで、ピカソが新たな領域を切り開くことになったというわけだ。
あわせて読みたい
【特異】「カメラの存在」というドキュメンタリーの大前提を覆す映画『GUNDA/グンダ』の斬新さ
映画『GUNDA/グンダ』は、「カメラの存在」「撮影者の意図」を介在させずにドキュメンタリーとして成立させた、非常に異端的な作品だと私は感じた。ドキュメンタリーの「デュシャンの『泉』」と呼んでもいいのではないか。「家畜」を被写体に据えたという点も非常に絶妙
さて「フォービズム」と「キュビズム」によって、「色」と「形」の革命は起こった。次はどのような展開を見せるのだろうか?
すでにフォービスムにおいてはリアルな感情を反映した絵画になり、キュビズムにおいては絵画を見る視点も自由になりました。また、ともに対象物をリアルに表現することをすでに放棄しています。それを突き詰めていった先にあるのが抽象画です
「フォービズム」「キュビズム」という、元の対象物を「再現」しないスタンスが探求されたことで、さらにそれを推し進めた「抽象画」が現れることになったというわけだ。そしてその究極として、デュシャンの「泉」に代表される「ダダイズム」が登場する。先ほど説明した通り、既成概念を打ち破る、という思想を強く持った芸術活動だ。

あわせて読みたい
【魅惑】マツコも絶賛の“日本人初のパリコレトップモデル”山口小夜子のメイクの凄さや素顔を描く映画:…
日本人初のパリコレトップモデルである山口小夜子と親交があった監督が紡ぐ映画『氷の花火 山口小夜子』は、未だ謎に包まれているその人生の一端を垣間見せてくれる作品だ。彼女を知る様々な人の記憶と、彼女を敬愛する多くの人の想いがより合って、一時代を築いた凄まじい女性の姿が浮かび上がってくる
そして本書で最後に辿りつくのは「ポップアート」である。ポップアートを代表するアンディ・ウォーホルについて著者はこんな風に書いている。
そうした批判の声にウォーホルは、こう反論しました。
「人が美術作品として買うなら、それは美術作品だ」
つまり芸術かどうかは、鑑賞する側が決めることだと彼は言うのです。デュシャンは既存の芸術を否定しましたが、ウォーホルは、芸術品とそうでないものの境界を破壊してしまいました。そもそもアートとは何なのか、ウォーホルはこの作品でデュシャン同様、私たちに問いを投げかけたのです
このような流れを知ることで、捉えがたい「芸術作品」を理解する手助けになるだろう。
あわせて読みたい
【天才】写真家・森山大道に密着する映画。菅田将暉の声でカッコよく始まる「撮り続ける男」の生き様:…
映画『あゝ荒野』のスチール撮影の際に憧れの森山大道に初めて会ったという菅田将暉の声で始まる映画『過去はいつも新しく、未来はつねに懐かしい』は、ちゃちなデジカメ1つでひたすら撮り続ける異端児の姿と、50年前の処女作復活物語が見事に交錯する
著:秋元 雄史
¥1,760 (2022/01/29 20:50時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品読了済】私が読んできたノンフィクション・教養書を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が読んできたノンフィクションを様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本選びの参考にして下さい。
最後に
どんなものにも、それが生まれた背景や経緯がある。どれほど「意味不明」「理解不能」に思える現代アートであっても、正しい知識と豊富な経験によって、その作品が何故創作されるに至ったのか理解できるようになるだろう。
それこそが「美術の鑑賞」の本質なのだろうし、そのためにはどうしても「知識」が必要になる、というわけだ。
感覚的に捉えて衝撃を受ける、という体験ももちろん良いが、それでは読み解けない作品もたくさんある。本書を入門書として、正しい知識を持って美術の鑑賞をしてみてはいかがだろうか?
あわせて読みたい
【食&芸術】死んでも車を運転したくない人間の香川うどん巡り& 豊島アート巡りの旅ルート(山越うどん…
仕事終わりの木曜日夜から日曜日に掛けて、「香川のうどん巡り」と「豊島のアート巡り」をしてきました。うどんだけでも7580円分食べたので、かなりの軒数を回ったことになります。しかも「死んでも車を運転したくない」ため、可能な限り公共交通機関のみで移動しました。私と同じように「車を運転したくない人」には、かなり参考になる記事と言えるのではないかと思います
次にオススメの記事
あわせて読みたい
金沢&富山のアート旅!「21世紀美術館」だけじゃない激アツなおすすめ美術館巡りをご提案
金沢・富山を巡るアート旅に出かけてきました!メインの目的は「21世紀美術館」でしたが、それ以上に「ASTER Curator Museum」「LIP BAR」「KAMU kanazawa」などがとにかく素晴らしかったです。アートや美術のことはド素人ですが、超個人的主観で「金沢・富山で触れられるアートの良さ」について書いた旅行記となります
あわせて読みたい
【映画】ディオールのデザイナーだった天才ジョン・ガリアーノが差別発言で破滅した人生を語る:映画『…
何者なのかまったく知らない状態で観たドキュメンタリー映画『ジョン・ガリアーノ 世界一愚かな天才デザイナー』は、差別発言によって失墜しすべてを失った天才デザイナーの凄まじい来歴が描かれる作品だ。実に複雑で興味深い存在だったし、その波乱の人生は、私のようなファッションに疎い人間でも面白く感じられると思う
あわせて読みたい
【魅惑】マツコも絶賛の“日本人初のパリコレトップモデル”山口小夜子のメイクの凄さや素顔を描く映画:…
日本人初のパリコレトップモデルである山口小夜子と親交があった監督が紡ぐ映画『氷の花火 山口小夜子』は、未だ謎に包まれているその人生の一端を垣間見せてくれる作品だ。彼女を知る様々な人の記憶と、彼女を敬愛する多くの人の想いがより合って、一時代を築いた凄まじい女性の姿が浮かび上がってくる
あわせて読みたい
【食&芸術】死んでも車を運転したくない人間の香川うどん巡り& 豊島アート巡りの旅ルート(山越うどん…
仕事終わりの木曜日夜から日曜日に掛けて、「香川のうどん巡り」と「豊島のアート巡り」をしてきました。うどんだけでも7580円分食べたので、かなりの軒数を回ったことになります。しかも「死んでも車を運転したくない」ため、可能な限り公共交通機関のみで移動しました。私と同じように「車を運転したくない人」には、かなり参考になる記事と言えるのではないかと思います
あわせて読みたい
【映画】『キャスティング・ディレクター』の歴史を作り、ハリウッド映画俳優の運命を変えた女性の奮闘
映画『キャスティング・ディレクター』は、ハリウッドで伝説とされるマリオン・ドハティを描き出すドキュメンタリー。「神業」「芸術」とも評される配役を行ってきたにも拘わらず、長く評価されずにいた彼女の不遇の歴史や、再び「キャスティングの暗黒期」に入ってしまった現在のハリウッドなどを切り取っていく
あわせて読みたい
【改革】改修期間中の国立西洋美術館の裏側と日本の美術展の現実を映すドキュメンタリー映画:『わたし…
「コロナ禍」という絶妙すぎるタイミングで改修工事を行った国立西洋美術館の、普段見ることが出来ない「裏側」が映し出される映画『わたしたちの国立西洋美術館』は、「日本の美術展」の問題点を炙り出しつつ、「『好き』を仕事にした者たち」の楽しそうな雰囲気がとても魅力的に映るドキュメンタリー
あわせて読みたい
【共感】斎藤工主演映画『零落』(浅野いにお原作)が、「創作の評価」を抉る。あと、趣里が良い!
かつてヒット作を生み出しながらも、今では「オワコン」みたいな扱いをされている漫画家を中心に描く映画『零落』は、「バズったものは正義」という世の中に斬り込んでいく。私自身は創作者ではないが、「売れる」「売れない」に支配されてしまう主人公の葛藤はよく理解できるつもりだ
あわせて読みたい
【倫理】アート体験の行き着く未来は?映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』が描く狂気の世界(…
「『痛み』を失った世界」で「自然発生的に生まれる新たな『臓器』を除去するライブパフォーマンス」を行うソール・テンサーを主人公にした映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』は、すぐには答えの見出しにくい「境界線上にある事柄」を挑発的に描き出す、実に興味深い物語だ
あわせて読みたい
【知的】「BLって何?」という初心者に魅力を伝える「腐男子」の「BLの想像力と創造力」講座:『ボクた…
「BLは知的遊戯である」という主張には「は?」と感じてしまうでしょうが、本書『ボクたちのBL論』を読めばその印象は変わるかもしれません。「余白の発見と補完」を通じて、「ありとあらゆる2者の間の関係性を解釈する」という創造性は、現実世界にどのような影響を与えているのか
あわせて読みたい
【働く】給料が上がらない、上げる方法を知りたい人は木暮太一のこの本を。『資本論』が意外と役に立つ…
「仕事で成果を出しても給料が上がるわけではない」と聞いて、あなたはどう感じるだろうか?これは、マルクスの『資本論』における「使用価値」と「価値」の違いを踏まえた主張である。木暮太一『人生格差はこれで決まる 働き方の損益分岐点』から「目指すべき働き方」を学ぶ
あわせて読みたい
【思考】文章の書き方が分かんない、トレーニングしたいって人はまず、古賀史健の文章講義の本を読め:…
古賀史健『20歳の自分に受けさせたい文章講義』は、「具体的なテクニック」ではない記述も非常に興味深い1冊だ。「なぜ文章を書く必要があるのか」という根本的な部分から丁寧に掘り下げる本書は、「書くからこそ考えられる」という、一般的なイメージとは逆だろう発想が提示される
あわせて読みたい
【革命】観る将必読。「将棋を観ること」の本質、より面白くなる見方、そして羽生善治の凄さが満載:『…
野球なら「なんで今振らないんだ!」みたいな素人の野次が成立するのに、将棋は「指せなきゃ観てもつまらない」と思われるのは何故か。この疑問を起点に、「将棋を観ること」と「羽生善治の凄さ」に肉薄する『羽生善治と現代』は、「将棋鑑賞」をより面白くしてくれる話が満載
あわせて読みたい
【感想】湯浅政明監督アニメ映画『犬王』は、実在した能楽師を”異形”として描くスペクタクル平家物語
観るつもりなし、期待値ゼロ、事前情報ほぼ皆無の状態で観た映画『犬王』(湯浅政明監督)はあまりにも凄まじく、私はこんなとんでもない傑作を見逃すところだったのかと驚愕させられた。原作の古川日出男が紡ぐ狂気の世界観に、リアルな「ライブ感」が加わった、素晴らしすぎる「音楽映画」
あわせて読みたい
【あらすじ】映画化の小説『僕は、線を描く』。才能・センスではない「芸術の本質」に砥上裕將が迫る
「水墨画」という、多くの人にとって馴染みが無いだろう芸術を題材に据えた小説『線は、僕を描く』は、青春の葛藤と創作の苦悩を描き出す作品だ。「未経験のど素人である主人公が、巨匠の孫娘と勝負する」という、普通ならあり得ない展開をリアルに感じさせる設定が見事
あわせて読みたい
【表現】映画『名付けようのない踊り』で初めて見た田中泯のダンス。「芸術以前」を志向する圧倒的パワー
映画『名付けようのない踊り』の中で田中泯は言う。「私」や「個性」を表現することには違和感がある、と。「踊りのために身体を作る」のではなく、「野良仕事で出来た身体で踊る」のだ、と。芸術になる前の踊りを探したい、と。「唯一無二の表現者」の生涯と現在地を映し出すドキュメンタリー
あわせて読みたい
【無謀】園子温が役者のワークショップと同時並行で撮影した映画『エッシャー通りの赤いポスト』の”狂気”
「園子温の最新作」としか知らずに観に行った映画『エッシャー通りの赤いポスト』は、「ワークショップ参加者」を「役者」に仕立て、ワークショップと同時並行で撮影されたという異次元の作品だった。なかなか経験できないだろう、「0が1になる瞬間」を味わえる“狂気”の映画
あわせて読みたい
【特異】「カメラの存在」というドキュメンタリーの大前提を覆す映画『GUNDA/グンダ』の斬新さ
映画『GUNDA/グンダ』は、「カメラの存在」「撮影者の意図」を介在させずにドキュメンタリーとして成立させた、非常に異端的な作品だと私は感じた。ドキュメンタリーの「デュシャンの『泉』」と呼んでもいいのではないか。「家畜」を被写体に据えたという点も非常に絶妙
あわせて読みたい
【芸術】実話を下敷きに描く映画『皮膚を売った男』は、「アートによる鮮やかな社会問題風刺」が見事
「シリア難民の背中にタトゥーを彫り芸術作品として展示する」と聞くと非常に不謹慎に感じられるだろうが、彫ったのが国家間の移動を自由にする「シェンゲンビザ」だという点が絶妙な皮肉。実話をベースにした映画『皮膚を売った男』の、アートによる社会問題提起の見事な鮮やかさ
あわせて読みたい
【人生】日本人有名プロゲーマー・梅原大吾の名言満載の本。「努力そのものを楽しむ」ための生き方とは…
「eスポーツ」という呼び名が世の中に定着する遥か以前から活躍する日本人初のプロゲーマー・梅原大吾。17歳で世界一となり、今も一線を走り続けているが、そんな彼が『勝ち続ける意志力』で語る、「『努力している状態』こそを楽しむ」という考え方は、誰の人生にも参考になるはずだ
あわせて読みたい
【斬新】ホームレスの家を「0円ハウス」と捉える坂口恭平の発想と視点に衝撃。日常の見え方が一変する:…
早稲田大学建築学科在籍中から「建築物の設計」に興味を持てなかった坂口恭平が、「ホームレスの家」に着目した『TOKYO 0円ハウス0円生活』には、「家」に対する考え方を一変させる視点が満載。「家に生活を合わせる」ではなく、「生活に家を合わせる」という発想の転換が見事
あわせて読みたい
【変革】「ビジネスより自由のために交渉力を」と語る瀧本哲史の”自己啓発”本に「交渉のコツ」を学ぶ:…
急逝してしまった瀧本哲史は、「交渉力」を伝授する『武器としての交渉思考』を通じて、「若者よ、立ち上がれ!」と促している。「同質性のタコツボ」から抜け出し、「異質な人」と「秘密結社」を作り、世の中に対する「不満」を「変革」へと向かわせる、その勇気と力を本書から感じてほしい
あわせて読みたい
【革新】天才マルタン・マルジェラの現在。顔出しNGでデザイナーの頂点に立った男の”素声”:映画『マル…
「マルタン・マルジェラ」というデザイナーもそのブランドのことも私は知らなかったが、そんなファッション音痴でも興味深く観ることができた映画『マルジェラが語る”マルタン・マルジェラ”』は、生涯顔出しせずにトップに上り詰めた天才の来歴と現在地が語られる
あわせて読みたい
【驚異】「持続可能な社会」での「豊かな生活」とは?「くじら漁の村」で生きる人々を描く映画:『くじ…
手作りの舟に乗り、銛1本で巨大なクジラを仕留める生活を続けるインドネシアのラマレラ村。そこに住む人々を映し出した映画『くじらびと LAMAFA』は、私たちが普段感じられない種類の「豊かさ」を描き出す。「どう生きるか」を改めて考えさせられる作品だ
あわせて読みたい
【アート】「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」(森美術館)と「美術手帖 Chim↑Pom特集」の衝撃から「…
Chim↑Pomというアーティストについてさして詳しいことを知らずに観に行った、森美術館の「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」に、思考をドバドバと刺激されまくったので、Chim↑Pomが特集された「美術手帖」も慌てて買い、Chim↑Pomについてメッチャ考えてみた
あわせて読みたい
【新視点】世界の歴史を「化学」で語る?デンプン・砂糖・ニコチンなどの「炭素化合物」が人類を動かし…
デンプン・砂糖・ニコチンなどは、地球上で非常に稀少な元素である「炭素」から作られる「炭素化合物」だ。そんな「炭素化合物」がどんな影響を与えたかという観点から世界の歴史を描く『「元素の王者」が歴史を動かす』は、学校の授業とはまったく違う視点で「歴史」を捉える
あわせて読みたい
【最新】「コロンブス到達以前のアメリカ大陸」をリアルに描く歴史書。我々も米国人も大いに誤解してい…
サイエンスライターである著者は、「コロンブス到着以前のアメリカはどんな世界だったか?」という問いに触れ、その答えが書かれた本がいつまで経っても出版されないので自分で執筆した。『1491 先コロンブス期アメリカ大陸をめぐる新発見』には、アメリカ人も知らない歴史が満載だ
あわせて読みたい
【解釈】詩人が語る詩の読み方。意味や読み方や良さが分からなくて全然気にしなくていい:『今を生きる…
私は学生時代ずっと国語の授業が嫌いでしたが、それは「作品の解釈には正解がある」という決めつけが受け入れ難かったからです。しかし、詩人・渡邊十絲子の『今を生きるための現代詩』を読んで、詩に限らずどんな作品も、「解釈など不要」「理解できなければ分からないままでいい」と思えるようになりました
あわせて読みたい
【博覧強記】「紙の本はなくなる」説に「文化は忘却されるからこそ価値がある」と反論する世界的文学者…
世界的文学者であり、「紙の本」を偏愛するウンベルト・エーコが語る、「忘却という機能があるから書物に価値がある」という主張は実にスリリングだ。『もうすぐ絶滅するという紙の書物について』での対談から、「忘却しない電子データ」のデメリットと「本」の可能性を知る
あわせて読みたい
【興奮】世界的大ベストセラー『サピエンス全史』要約。人類が文明を築き上げるに至った3つの革命とは?
言わずと知れた大ベストセラー『サピエンス全史』は、「何故サピエンスだけが人類の中で生き残り、他の生物が成し得なかった歴史を歩んだのか」を、「認知革命」「農業革命」「科学革命」の3つを主軸としながら解き明かす、知的興奮に満ち溢れた1冊
あわせて読みたい
【知的】文系にオススメの、科学・数学・哲学の入門書。高橋昌一郎の「限界シリーズ」は超絶面白い:『…
例えば「科学」だけに限ってみても、「なんでもできる」わけでは決してない。「科学」に限らず、私たちが対峙する様々な事柄には「これ以上は不可能・無理」という「限界」が必ず存在する。高橋昌一郎の「限界シリーズ」から、我々が認識しておくべき「限界」を易しく学ぶ
あわせて読みたい
【感想】飲茶の超面白い東洋哲学入門書。「本書を読んでも東洋哲学は分からない」と言う著者は何を語る…
東洋哲学というのは、「最終回しか存在しない連続ドラマ」のようなものだそうだ。西洋哲学と比較にならないほど異質さと、インド哲学・中国哲学など個別の思想を恐ろしく分かりやすく描く『史上最強の哲学入門 東洋の哲人たち』は、ページをめくる手が止まらないくらい、史上最強レベルに面白かった
あわせて読みたい
【興奮】飲茶氏の超面白い哲学小説。「正義とは?」の意味を問う”3人の女子高生”の主張とは?:『正義の…
なんて面白いんだろうか。哲学・科学を初心者にも分かりやすく伝える飲茶氏による『正義の教室』は、哲学書でありながら、3人の女子高生が登場する小説でもある。「直観主義」「功利主義」「自由主義」という「正義論」の主張を、「高校の問題について議論する生徒会の話し合い」から学ぶ
あわせて読みたい
【天才】読書猿のおすすめ本。「いかにアイデアを生むか」の発想法を人文書に昇華させた斬新な1冊:『ア…
「独学の達人」「博覧強記の読書家」などと評される読書猿氏が、古今東西さまざまな「発想法」を1冊にまとめた『アイデア大全』は、ただのHow To本ではない。「発想法」を学問として捉え、誕生した経緯やその背景なども深堀りする、「人文書」としての一面も持つ作品だ
あわせて読みたい
【興奮】飲茶氏が西洋哲学を語る。難解な思想が「グラップラー刃牙成分」の追加で驚異的な面白さに:『…
名前は聞いたことはあるがカントやニーチェがどんな主張をしたのかは分からないという方は多いだろう。私も無知なまったくの初心者だが、そんな人でも超絶分かりやすく超絶面白く西洋哲学を”分かった気になれる”飲茶『史上最強の哲学入門』は、入門書として最強
あわせて読みたい
【創作】クリエイターになりたい人は必読。ジブリに見習い入社した川上量生が語るコンテンツの本質:『…
ドワンゴの会長職に就きながら、ジブリに「見習い」として入社した川上量生が、様々なクリエイターの仕事に触れ、色んな質問をぶつけることで、「コンテンツとは何か」を考える『コンテンツの秘密』から、「創作」という営みの本質や、「クリエイター」の理屈を学ぶ
あわせて読みたい
【奇跡】鈴木敏夫が2人の天才、高畑勲と宮崎駿を語る。ジブリの誕生から驚きの創作秘話まで:『天才の思…
徳間書店から成り行きでジブリ入りすることになったプロデューサー・鈴木敏夫が、宮崎駿・高畑勲という2人の天才と共に作り上げたジブリ作品とその背景を語り尽くす『天才の思考 高畑勲と宮崎駿』。日本のアニメ界のトップランナーたちの軌跡の奇跡を知る
あわせて読みたい
【天才】写真家・森山大道に密着する映画。菅田将暉の声でカッコよく始まる「撮り続ける男」の生き様:…
映画『あゝ荒野』のスチール撮影の際に憧れの森山大道に初めて会ったという菅田将暉の声で始まる映画『過去はいつも新しく、未来はつねに懐かしい』は、ちゃちなデジカメ1つでひたすら撮り続ける異端児の姿と、50年前の処女作復活物語が見事に交錯する
あわせて読みたい
【狂気】稀少本を収集・売買する「愛すべき変人コレクター」の世界と、インターネットによる激変:映画…
広大な本の世界を狩人のように渉猟し、お気に入りの本を異常なまでに偏愛する者たちを描き出す映画『ブックセラーズ』。実在の稀少本コレクターたちが、本への愛を語り、新たな価値を見出し、次世代を教育し、インターネットの脅威にどう立ち向かっているのかを知る
あわせて読みたい
【現実】生きる気力が持てない世の中で”働く”だけが人生か?「踊るホームレスたち」の物語:映画『ダン…
「ホームレスは怠けている」という見方は誤りだと思うし、「働かないことが悪」だとも私には思えない。振付師・アオキ裕キ主催のホームレスのダンスチームを追う映画『ダンシングホームレス』から、社会のレールを外れても許容される社会の在り方を希求する
あわせて読みたい
【映画】『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』で号泣し続けた私はTVアニメを観ていない
TVアニメは観ていない、というかその存在さえ知らず、物語や登場人物の設定も何も知らないまま観に行った映画『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』に、私は大号泣した。「悪意のない物語」は基本的に好きではないが、この作品は驚くほど私に突き刺さった
あわせて読みたい
【天才】諦めない人は何が違う?「努力を努力だと思わない」という才能こそが、未来への道を開く:映画…
どれだけ「天賦の才能」に恵まれていても「努力できる才能」が無ければどこにも辿り着けない。そして「努力できる才能」さえあれば、仮に絶望の淵に立たされることになっても、立ち上がる勇気に変えられる。映画『マイ・バッハ』で知る衝撃の実話
あわせて読みたい
【情熱】常識を疑え。人間の”狂気”こそが、想像し得ない偉業を成し遂げるための原動力だ:映画『博士と…
世界最高峰の辞書である『オックスフォード英語大辞典』は、「学位を持たない独学者」と「殺人犯」のタッグが生みだした。出会うはずのない2人の「狂人」が邂逅したことで成し遂げられた偉業と、「狂気」からしか「偉業」が生まれない現実を、映画『博士と狂人』から学ぶ
あわせて読みたい
【感想】映画『窮鼠はチーズの夢を見る』を異性愛者の男性(私)はこう観た。原作も読んだ上での考察
私は「腐男子」というわけでは決してないのですが、周りにいる腐女子の方に教えを請いながら、多少BL作品に触れたことがあります。その中でもダントツに素晴らしかったのが、水城せとな『窮鼠はチーズの夢を見る』です。その映画と原作の感想、そして私なりの考察について書いていきます
あわせて読みたい
【救い】耐えられない辛さの中でどう生きるか。短歌で弱者の味方を志すホームレス少女の生き様:『セー…
死にゆく母を眺め、施設で暴力を振るわれ、拾った新聞で文字を覚えたという壮絶な過去を持つ鳥居。『セーラー服の歌人 鳥居』は、そんな辛い境遇を背景に、辛さに震えているだろう誰かを救うために短歌を生み出し続ける生き方を描き出す。凄い人がいるものだ
あわせて読みたい
【改革】AIは将棋をどう変えた?羽生善治・渡辺明ら11人の現役棋士が語る将棋の未来:『不屈の棋士』(…
既に将棋AIの実力はプロ棋士を越えたとも言われる。しかし、「棋力が強いかどうか」だけでは将棋AIの良し悪しは判断できない。11人の現役棋士が登場する『不屈の棋士』をベースに、「AIは将棋界をどう変えたのか?」について語る
あわせて読みたい
【終焉】資本主義はもう限界だ。インターネットがもたらした「限界費用ゼロ社会」とその激変
資本主義は、これまで上手くやってきた。しかし、技術革新やインターネットの登場により、製造コストは限りなくゼロに近づき、そのことによって、資本主義の命脈が断たれつつある。『限界費用ゼロ社会』をベースに、これからの社会変化を捉える
あわせて読みたい
【諦め】「人間が創作すること」に意味はあるか?AI社会で問われる、「創作の悩み」以前の問題:『電気…
AIが個人の好みに合わせて作曲してくれる世界に、「作曲家」の存在価値はあるだろうか?我々がもうすぐ経験するだろう近未来を描く『電気じかけのクジラは歌う』をベースに、「創作の世界に足を踏み入れるべきか」という問いに直面せざるを得ない現実を考える
あわせて読みたい
【継続】「言語化できない」を乗り越えろ。「読者としての文章術」で、自分の思考をクリアにする:『読…
ブログやSNSなどが登場したことで、文章を書く機会は増えていると言える。しかし同時に、「他人に評価されるために書く」という意識も強くなっているだろう。『読みたいことを書けばいい』から、「楽しく書き”続ける”」ための心得を学ぶ
あわせて読みたい
【感想】努力では才能に勝てないのか?どうしても辿り着きたい地点まで迷いながらも突き進むために:『…
どうしても辿り着きたい場所があっても、そのあまりの遠さに目が眩んでしまうこともあるでしょう。そんな人に向けて、「才能がない」という言葉に逃げずに前進する勇気と、「仕事をする上で大事なスタンス」について『羊と鋼の森』をベースに書いていきます
あわせて読みたい
【葛藤】部活で後悔しないために。今やりたいことをやりきって、過去を振り返らないための全力:『風に…
勉強の方が、部活動より重要な理由なんて無い。どれだけ止められても「全力で打ち込みたい」という気持ちを抑えきれないものに出会える人生の方が、これからの激動の未来を生き延びられるはずと信じて突き進んでほしい。部活小説『風に恋う』をベースに書いていく
あわせて読みたい
【表現者】「センスが良い」という言葉に逃げない。自分の内側から何かを表現することの本質:『作詞少…
大前提として、表現には「技術」が必要だ。しかし、「技術」だけでは乗り越えられない部分も当然ある。それを「あいつはセンスが良いから」という言葉に逃げずに、向き合ってぶつかっていくための心得とは何か。『作詞少女』をベースに「表現することの本質」を探る
あわせて読みたい
【前進】誰とも価値観が合わない…。「普通」「当たり前」の中で生きることの難しさと踏み出し方:『出会…
生きていると、「常識的な考え方」に囚われたり、「普通」「当たり前」を無自覚で強要してくる人に出会ったりします。そういう価値観に合わせられない時、自分が間違っている、劣っていると感じがちですが、そういう中で一歩踏み出す勇気を得るための考え方です
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
文化・芸術・将棋・スポーツ【本・映画の感想】 | ルシルナ
知識や教養は、社会や学問について知ることだけではありません。文化的なものもリベラルアーツです。私自身は、創作的なことをしたり、勝負事に関わることはありませんが、…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…















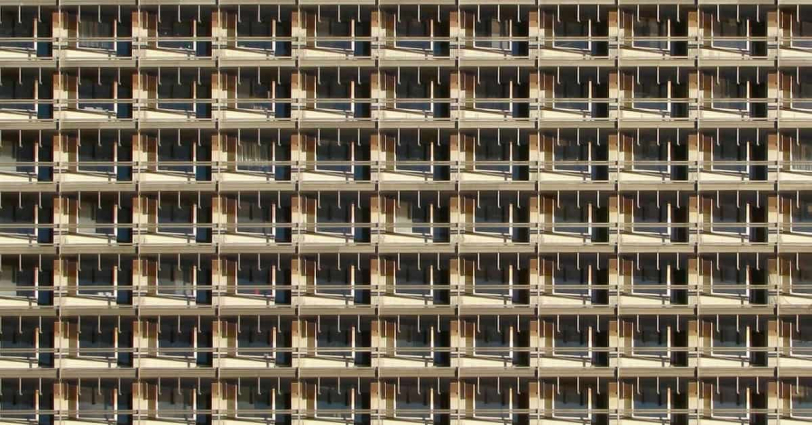















































































コメント