目次
はじめに
著:田中 泰延
¥1,336 (2024/07/03 14:52時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
この記事で伝えたいこと
文章は他人のためではなく、自分のために書け
「どう評価されるか」なんてことを考えて文章を書いたらつまらなくなります
この記事の3つの要点
- 「読んでもらいたい文章」は「読んでもらえない文章」
- 評価されることより、書き続けることの方が大事
- 文章を書く前に、徹底的に調べろ
一般的な文章術ではあまり語られない視点が満載の作品です
著:田中 泰延
¥1,336 (2021/06/10 06:57時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
この記事で取り上げる本
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!「文章の書き方が分からない」「文章力がないから鍛えたい」という方にオススメ…
「文章の書き方」についてのKindle本を出版しました。「文章が書けない」「どう書いたらいいか分からない」「文章力を向上させたい」という方の悩みを解消できるような本に仕上げたつもりです。数多くの文章を書き、さらに頼まれて文章を推敲してきた経験を踏まえ、「文章を書けるようになるにはどうしたらいいか」についての私なりの考えをまとめました。
田中泰延『読みたいことを書けばいい』は、「文章の書き方」だけではなく「文章を書く目的」についても再確認させてくれる
「読者としての文章術」を提示する、あまり見かけない主張
あわせて読みたい
【思考】文章の書き方が分かんない、トレーニングしたいって人はまず、古賀史健の文章講義の本を読め:…
古賀史健『20歳の自分に受けさせたい文章講義』は、「具体的なテクニック」ではない記述も非常に興味深い1冊だ。「なぜ文章を書く必要があるのか」という根本的な部分から丁寧に掘り下げる本書は、「書くからこそ考えられる」という、一般的なイメージとは逆だろう発想が提示される
本書で著者が主張することは、ほぼこの一点に集約されると言っていいでしょう。
それが「読者としての文章術」です。
(本書は)同時に、なによりわたし自身に向けて書かれるものである。
すべての文章は、自分のために書かれるものだからだ。
つまり、「文章は、自分のために書けよ」ということです。
あわせて読みたい
【組織】新入社員・就活生必読。「社内コミュニケーション」でやるべきことを山田ズーニーが語る:『半…
組織内のコミュニケーションが上手くできないと悩んでいる方、多いのではないだろうか。山田ズーニー『半年で職場の星になる!働くためのコミュニケーション力』は、組織に属するあらゆる人に向けて、「コミュニケーションで重視すべき本質」をテクニックと共に伝授する

もちろん世の中には、論文や報告書など、「自分以外のために書く文章」も存在します。しかし、本書では、そういう文章のことは念頭に置かれていません。自分以外のための文章をどう書くかという本は世の中にたくさんあるので、是非そちらを読んでください、ということでしょう。
本書で著者が書くのは、ブログやSNSなど、「そもそも書くことを求められているわけではない文章」についてです。そして、そういう文章なら、「自分のために書けよ」と主張します。
そうなんだけど、実際、自分以外のために書いてる人、多いからね
あわせて読みたい
【価値】どうせ世の中つまらない。「レンタルなんもしない人」の本でお金・仕事・人間関係でも考えよう…
「0円で何もしない」をコンセプトに始まった「レンタルなんもしない人」という活動は、それまで見えにくかった様々な価値観を炙り出した見事な社会実験だと思う。『<レンタルなんもしない人>というサービスをはじめます。』で本人が語る、お金・仕事・人間関係の新たな捉え方
「評価のために書く」なんてしてはいけない
ブログでもSNSでも、それが個人のものであれば、基本的にそこに書く文章というのは「書きたいから書いている」はずです。本来的にはそうなるでしょう。
しかし一方で、多くの人が、「評価」のために文章を書いてしまっていると思います。「いいね」やリツイートの数で「自分は評価されている」と感じたいために文章を書いている、みたいな人もたくさんいるでしょう。
章に限らず、何をするにしたって今は、そういう「評価」が丸見えだからなぁ
あわせて読みたい
【扇動】人生うまくいかないと感じる時に読みたい瀧本哲史の本。「未来をどう生きる?」と問われる1冊:…
瀧本哲史は非常に優れたアジテーターであり、『2020年6月30日にまたここで会おう』もまさにそんな1冊。「少数のカリスマ」ではなく「多数の『小さなリーダー』」によって社会が変革されるべきだ、誰にだってやれることはある、と若者を焚きつける、熱量満載の作品
しかし著者は、
だが、ほとんどの人はスタートのところで考え方がつまづいている。最初の放心が間違っている。その前にまず方針という漢字が間違っている。出発点からおかしいのだ。偉いと思われたい。おかねが欲しい。成功したい。目的意識があることは結構だが、その考え方で書くと、結局、人に読んでもらえない文章ができあがってしまう
と書いています。「読んでもらおう」と思って書くことで「読んでもらえない」文章になってしまう、というのです。
確かにその感覚は分かるような気がします。もちろん、緻密に設計された文章も面白いですが、それはほとんどプロの技です。我々のような素人にはなかなか真似できないでしょう。そういうプロやセミプロみたいな人を除けば、面白いと感じる文章というのは、「これ、誰かに読まれるなんてこと想定して書いてるんだろうか?」と感じてしまうようなものだったりします。
あわせて読みたい
【人生】日本人有名プロゲーマー・梅原大吾の名言満載の本。「努力そのものを楽しむ」ための生き方とは…
「eスポーツ」という呼び名が世の中に定着する遥か以前から活躍する日本人初のプロゲーマー・梅原大吾。17歳で世界一となり、今も一線を走り続けているが、そんな彼が『勝ち続ける意志力』で語る、「『努力している状態』こそを楽しむ」という考え方は、誰の人生にも参考になるはずだ
だから、読まれることを想定して、ちゃんと面白く文章が書ける人は凄いと改めて思います
さらに、
いずれにせよ、評価の奴隷になった時点で、書くことがいやになってしまう
とも書いています。確かにこれもその通りだなと実感します。
あわせて読みたい
【解釈】詩人が語る詩の読み方。意味や読み方や良さが分からなくて全然気にしなくていい:『今を生きる…
私は学生時代ずっと国語の授業が嫌いでしたが、それは「作品の解釈には正解がある」という決めつけが受け入れ難かったからです。しかし、詩人・渡邊十絲子の『今を生きるための現代詩』を読んで、詩に限らずどんな作品も、「解釈など不要」「理解できなければ分からないままでいい」と思えるようになりました
私は、本を読んで感想を書くことを、もう15年以上ひたすら続けています。本1冊読む度に、3,000字~5,000字の文章を書くわけです。それは、映画を観るようになってからも同じで、映画館にメモ帳を持ち込んで、毎回長々と感想を書いています。
自分がやってきたことを振り返った時、これが「誰かから頼まれた仕事」だったとしたら絶対続いてないよな、と思います。私はとにかく、自分が書きたいと思うことをただひたすら好きなように書き続けてきました。そこに「評価」という視点が入ると、途端にやる気がなくなってしまうだろうと思います。
「何をどう書くか」以上に、「書き続けること」の方が圧倒的に大事
恐らく私はこれまでに、かなり少なく見積もっても1,000万字ぐらい文章を書いています。ざっと新書100冊分ぐらいでしょうか。これだけ文章を書き続けることができたのは、「文章を書くこと」が「自分のため」だったからです。
あわせて読みたい
【諦め】「人間が創作すること」に意味はあるか?AI社会で問われる、「創作の悩み」以前の問題:『電気…
AIが個人の好みに合わせて作曲してくれる世界に、「作曲家」の存在価値はあるだろうか?我々がもうすぐ経験するだろう近未来を描く『電気じかけのクジラは歌う』をベースに、「創作の世界に足を踏み入れるべきか」という問いに直面せざるを得ない現実を考える
もちろん、「運良く誰かに読んでもらえたらいい」と思ってはいました。でも、読んでもらうことを期待して文章を書くことはしていません。この「ルシルナ」というブログは、私が人生で初めて、ちゃんと他人に読んでもらうために立ち上げたものですが、それまでは、そんな意識をまったく持たずに文章を書いていました。
「ルシルナ」は、ちゃんと文章を推敲してますが、それまではずっと推敲もせずアップしてたからなぁ
あわせて読みたい
【変革】「ビジネスより自由のために交渉力を」と語る瀧本哲史の”自己啓発”本に「交渉のコツ」を学ぶ:…
急逝してしまった瀧本哲史は、「交渉力」を伝授する『武器としての交渉思考』を通じて、「若者よ、立ち上がれ!」と促している。「同質性のタコツボ」から抜け出し、「異質な人」と「秘密結社」を作り、世の中に対する「不満」を「変革」へと向かわせる、その勇気と力を本書から感じてほしい
著者もこう書いています。
読み手など想定して書かなくていい。その文章を最初に読むのは、間違いなく自分だ。自分で読んでおもしろくなければ、書くこと自体が無駄になる
そんな風に、自分が「書きたい」と思うことだけをひたすら書いていたお陰で、文章を書くことに対する苦手意識はまったくなくなりました。私はもともと理系の人間なので、本の感想のブログを始めるまで、まともに文章を書いたこともありませんでした。しかしそんな人間でも、ひたすら続けていればそれなりに上達します。
まさに、「続けること」が大事だ、ということです。
あわせて読みたい
【変人】学校教育が担うべき役割は?子供の才能を伸ばすために「異質な人」とどう出会うべきか?:『飛…
高校の美術教師からアーティストとして活動するようになった著者は、教育の現場に「余白(スキマ)」が減っていると指摘する。『飛び立つスキマの設計学』をベースに、子どもたちが置かれている現状と、教育が成すべき役割について確認する。
さらに文章を書き続けて良かったことは、「考えたことを書く」というステップをすっ飛ばせるようになったことです。
どういうことでしょうか。
文章を書く場合、「どんな文章を書くか頭にざっと思い浮かべてから出力する」のが普通でしょう。しかし私は、毎日毎日大量の文章を書くために、そんなまどろっこしいことをしていられませんでした。

あわせて読みたい
【組織】意思決定もクリエイティブも「問う力」が不可欠だ。MIT教授がCEOから学んだ秘訣とは?:『問い…
組織マネジメントにおいては「問うこと」が最も重要だと、『問いこそが答えだ!』は主張する。MIT教授が多くのCEOから直接話を聞いて学んだ、「『問う環境』を実現するための『心理的安全性の確保』の重要性」とその実践の手法について、実例満載で説明する1冊
そこで、「どんな文章を書くか思い浮かんでいなくても、とりあえずキーボードを叩く。書きながら考える。で、文章が出てこなくなったら終了」というやり方を続けることにしました。こんなことをずっとやっていたお陰で、今では、5,000字程度の文章であれば、全体の構成などまったく考えずに、一気に書けます。
また、そんな文章の書き方をしていたからでしょう、文章をキーボードで打ち込みながら、「自分はこんなことを考えていたのか」と気づく瞬間さえあります。「指が思考してる」みたいなことが時々あって、自分の指が打ち込んでいる文章をモニターで見ながら、「ほぉ、こんな思考をしてたのか」と感じる、みたいなことがあります。これが、文章を書いてて一番面白い瞬間です。
あわせて読みたい
【天才】読書猿のおすすめ本。「いかにアイデアを生むか」の発想法を人文書に昇華させた斬新な1冊:『ア…
「独学の達人」「博覧強記の読書家」などと評される読書猿氏が、古今東西さまざまな「発想法」を1冊にまとめた『アイデア大全』は、ただのHow To本ではない。「発想法」を学問として捉え、誕生した経緯やその背景なども深堀りする、「人文書」としての一面も持つ作品だ
もし、「誰かに読んでもらおう」とか「文章がうまくなりたい」などの目的を持っていたら、15年以上も文章を書き続けられなかったでしょう。目的が、「自分が書きたいと思うことを書く」しかなかったお陰で、ただひたすらに文章を書き続けることができ、そのお陰で、様々なおまけが付随した、という印象です。
どれだけキーボード打っても、肩こりになったりしないのも、自分では凄いと思う
酷い時は、1日10時間以上文章書いてたりするのにね
「評価」について考えるのは、出力した後にすべき
そんなわけで、「文章を書くこと」に対しては、これといった目的意識を持たないほうがいいでしょう。どんな文章であれ、それが何らかの「評価」を受ける可能性があるのは「出力した後」です。文章に限りませんが、出力しないことには何も始まりません。
あわせて読みたい
【具体例】行動経済学のおすすめ本。経済も世界も”感情”で動くと実感できる「人間の不合理さ」:『経済…
普段どれだけ「合理的」に物事を判断しているつもりでも、私たちは非常に「不合理的」な行動を取ってしまっている。それを明らかにするのが「行動経済学」だ。『経済は感情で動く』『世界は感情で動く』の2冊をベースにして、様々な具体例と共に「人間の不思議さ」を理解する

だから、「出力するまでのこと」と「出力した後のこと」は切り離して考えましょう。「出力した後」は「評価」と無縁でいられないとしても、「出力するまで」は「評価」のことなど考えていてもまったく意味はない、ということです。
著者も、こんな風に書いています。
ライターになりたい人は、もっと起業家の話を聞いたほうがいい。彼らのように成功した人でも、十個目の商売でやっと成功したとか、成功するまで五つ会社をつぶしたとか、勝負をかけたはずの商品が全然売れなかったとかを経て、いまの商売があたったという人が多い。ライターも同じように、書いてみても、ほぼ駄目なことだらけだ。
自分がまずおもしろがれるものであること。これは、ビジネスアイデアでも文章を書くことでも全く同じだ。それが世の中に公開された時点で、あくまでも結果として、社会の役に立つか、いままでになかったものかがジャッジされる。
あわせて読みたい
【非努力】頑張らない働き方・生き方のための考え方。「◯◯しなきゃ」のほとんどは諦めても問題ない:『…
ブロガーであるちきりんが、ブログに書いた記事を取捨選択し加筆修正した『ゆるく考えよう』は、「頑張ってしまう理由」や「欲望の正体」などを深堀りしながら、「世の中の当たり前から意識的に外れること」を指南する。思考を深め、自力で本質に行き着くための参考にも
だからとにかく、ひたすら出力し続けるしかない、ということです。そして、出力し続けられるかどうかで、評価されるかどうかも決まる、と考えていいでしょう。
出力し続けるためには、自分が面白いと感じられる方がいい。そういう意味で本書では、「読者としての文章術」が提唱されるのです。
飽きっぽい私が、文章を書くことだけは続いてるんで、相性がいいんだろうと思います
「事実だけを書け」「内面を語る人間はつまらない」という主張
あわせて読みたい
【能力】激変する未来で「必要とされる人」になるためのスキルや考え方を落合陽一に学ぶ:『働き方5.0』
AIが台頭する未来で生き残るのは難しい……。落合陽一『働き方5.0~これからの世界をつくる仲間たちへ~』はそう思わされる一冊で、本書は正直、未来を前向きに諦めるために読んでもいい。未来を担う若者に何を教え、どう教育すべきかの参考にもなる一冊。
本書のもう一つの大きな主張は、「文章には事実だけを書け」というものです。正確には、こう表現されています。
物書きは「調べる」が九割九分五厘六毛
つまり、ライターの考えなど全体の一%以下でよいし、その一%以下を伝えるためにあとの九十九%以上が要る。
私は、この意見には少し反論したいのです。というか、著者の真意が適切に伝わっていないのではないか、と思っています。
あわせて読みたい
【発想力】「集中力が続かない」と悩むことはない。「集中しない思考」こそAI時代に必要だ:『集中力は…
『「集中力がない」と悩んでいる人は多いかもしれません。しかし本書では、「集中力は、思ってるほど素晴らしいものじゃない」と主張します。『集中力はいらない』をベースに、「分散思考」の重要性と、「発想」を得るための「情報の加工」を学ぶ
上記の引用を普通に受け取れば、「調べた事実だけを書け」ということになるでしょう。確かに著者の、
心象を語るためには事象の強度が不可欠
という言葉はとてもよく理解できます。「心象」だけ語っていてもダメで、その「心象」を下支えする「事象」と、その事象自体の「強度」が欠かせないというのは、その通りでしょう。
あわせて読みたい
【創作】クリエイターになりたい人は必読。ジブリに見習い入社した川上量生が語るコンテンツの本質:『…
ドワンゴの会長職に就きながら、ジブリに「見習い」として入社した川上量生が、様々なクリエイターの仕事に触れ、色んな質問をぶつけることで、「コンテンツとは何か」を考える『コンテンツの秘密』から、「創作」という営みの本質や、「クリエイター」の理屈を学ぶ
ただ、だからと言って、「調べた事実だけを書け」は言い切りすぎている、と感じます。これは恐らく、著者がコピーライター出身だからではないでしょうか。
あんたは「心象」ばっかりの文章を書いてるから、著者の主張を受け入れたくないんだろ?
「九割九分五厘六毛」に対する私の捉え方
著者の主張は一見、「出力された文章全体を『十割』とし、その内の『九割九分五厘六毛』は調べたことであるべき」という風に思えます。しかし私は、「調べたことだけ書け」という主張にはちょっと違和感を覚えてしまうのです。
あわせて読みたい
【実話】映画『グッドバイ、バッドマガジンズ』(杏花主演)が描く、もの作りの絶望(と楽しさ)
実在したエロ雑誌編集部を舞台に、タブーも忖度もなく業界の内実を描き切る映画『グッドバイ、バッドマガジンズ』は、「エロ雑誌」をテーマにしながら、「もの作りに懸ける想い」や「仕事への向き合い方」などがリアルに描かれる素敵な映画だった。とにかく、主役を演じた杏花が良い
ヒントは、著者の、
前の項で述べた「図書館」で「一次資料」に当たれという話は、ひとえに「巨人の肩に乗る」ためである。
巨人の肩に乗る、というのは「ここまでは議論の余地がありませんね。ここから先の話をしますけど」という姿勢なのだ
という発言にあるでしょう。これは、「先人の誰かが既にどこかに書いているようなことを、自分が思いついたことであるかのようにグダグダ書くなよ」という話の最後に書かれています。
あわせて読みたい
【天職】頑張っても報われない方へ。「自分で選び取る」のとは違う、正しい未来の進み方:『そのうちな…
一般的に自己啓発本は、「今、そしてこれからどうしたらいいか」が具体的に語られるでしょう。しかし『そのうちなんとかなるだろう』では、決断・選択をするべきではないと主張されます。「選ばない」ことで相応しい未来を進む生き方について学ぶ
つまり、「それが本当にお前のオリジナルな意見だって言えるのかどうかちゃんと調べろよ」ということです。
これを踏まえると、何を「十割」とするかには別の解釈が生まれます。それは、「書くという行為自体を『十割』とし、調べるという行為がその内の『九割九分五厘六毛』だ」です。これなら私もすんなり理解できます。「とにかくめちゃくちゃ調べて、書こうとしている『内面』や『心象』がオリジナルなものだって確認しろよ」という意味なら納得です。
まあ私は、『心象』や『内面』がオリジナルかどうかは調べてないけど
その辺も「出力するまで」のことだから、自分のやりたいスタイルでやってこう
「知っているからこそ調べられる」のであり、知識を頭の中に入れておくことは大事
あわせて読みたい
【貢献】働く上で大切にしたいことは結局「人」。海士町(離島)で持続可能な社会を目指す若者の挑戦:…
過疎地域を「日本の未来の課題の最前線」と捉え、島根県の離島である「海士町」に移住した2人の若者の『僕たちは島で、未来を見ることにした』から、「これからの未来をどう生きたいか」で仕事を捉える思考と、「持続可能な社会」の実現のためのチャレンジを知る
また、本書では詳しく触れられていないが、「調べる」に関して著者には重要な要素があります。
著者略歴に、
学生時代に6,000冊の本を乱読
と書かれているのです。
「調べる」と聞くと、「知らないことを調べる」と考えがちですが、実際には、「まったく知らないこと」については調べようがありません。ある事柄について「少しは知っている」からこそ、そこをスタート地点として「調べる」ことができるわけです。

あわせて読みたい
【思考】「働くとは?」と悩んだら読みたい本。安易な結論を提示しないからこそちゃんと向き合える:『…
「これが答えだ」と安易に結論を出す自己啓発本が多い中で、山田ズーニー『おとなの進路教室』は「著者が寄り添って共に悩んでくれる」という稀有な本だ。決して分かりやすいわけではないからこそ読む価値があると言える、「これからの人生」を考えるための1冊
本書では、「いかに調べるか」についても詳しく書かれていて、「一次資料にあたること」や「図書館を活用すること」など具体的なやり方にも触れられています。ただ、そういうことができるのは、ある程度以上著者の頭の中に知識があるからです。
例えば私はもともと理系の人間なので、数学や物理への関心を強く持っているし、それなりに知識もあります。だから、科学の本を読んでいても、「あれ、この記述、前に読んだ本と矛盾してないか?」とか、「ここで使われているこの単語、もしかしたら別のあの単語とほぼ同じ意味だったりするのか?」など、様々な知識を結びつけられるのです。
一方私には、歴史の知識がまったくありません。だから、歴史に関する本を読んでいても、自分の脳内にあまりにも知識がなさすぎて、何も引っかからずに終わってしまうと思います。
例えば、「勝海舟が何をしたか?」とか「石田三成って誰の部下?」みたいな質問にも答えられないよね
大人になって、もうちょっと真面目に歴史の勉強しとけばよかったって、よく思う
あわせて読みたい
【思考】「”考える”とはどういうことか」を”考える”のは難しい。だからこの1冊をガイドに”考えて”みよう…
私たちは普段、当たり前のように「考える」ことをしている。しかし、それがどんな行為で、どのように行っているのかを、きちんと捉えて説明することは難しい。「はじめて考えるときのように」は、横書き・イラスト付きの平易な文章で、「考えるという行為」の本質に迫り、上達のために必要な要素を伝える
「調べること」の重要さを強調するのであれば、「あらかじめ知識を持っていること」の重要さにも同時に触れてほしかったと思います。
まったく書かれていないわけではありません。
本を読むことを、すぐ使える実用的な知識を得るという意味に矮小化してはいけない。本を読むことを、その文章や文体を学ぶということに限定してはいけない。本という高密度な情報の集積こそ、あなたが人生で出会う事象の最たるものであり、あなたが心象をいだくべき対象である
ただこれは、「本を読むことの重要性」について触れている箇所の記述です。「調べる」ためにも知識が要るよ、という形でも書いてほしかった気がします。
あわせて読みたい
【映画】『キャスティング・ディレクター』の歴史を作り、ハリウッド映画俳優の運命を変えた女性の奮闘
映画『キャスティング・ディレクター』は、ハリウッドで伝説とされるマリオン・ドハティを描き出すドキュメンタリー。「神業」「芸術」とも評される配役を行ってきたにも拘わらず、長く評価されずにいた彼女の不遇の歴史や、再び「キャスティングの暗黒期」に入ってしまった現在のハリウッドなどを切り取っていく
著:田中 泰延
¥1,336 (2022/02/03 23:16時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品読了済】私が読んできたエッセイ・コミック・自己啓発本を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が読んできたエッセイ・コミックを様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本選びの参考にして下さい。
最後に
あわせて読みたい
【感想】どんな話かわからない?難しい?ジブリ映画『君たちはどう生きるか』の考察・解説は必要?(監…
宮崎駿最新作であるジブリ映画『君たちはどう生きるか』は、宮崎アニメらしいファンタジックな要素を全開に詰め込みつつ、「生と死」「創造」についても考えさせる作品だ。さらに、「自分の頭の中から生み出されたものこそ『正解』」という、創造物と向き合う際の姿勢についても問うているように思う
本書では徹底的に、「文章は自分のために書くものだ」と主張されます。ただもちろん、そうやって出力された文章が、運良く誰かのためになることはあるかもしれません。
この本で繰り返し述べている「事象に触れて生まれる心象」。それを書くことは、まず自分と、もしかして、誰かの心を救う。人間は書くことで、わたしとあなたの間にある風景を発見するのである
あわせて読みたい
【共感】斎藤工主演映画『零落』(浅野いにお原作)が、「創作の評価」を抉る。あと、趣里が良い!
かつてヒット作を生み出しながらも、今では「オワコン」みたいな扱いをされている漫画家を中心に描く映画『零落』は、「バズったものは正義」という世の中に斬り込んでいく。私自身は創作者ではないが、「売れる」「売れない」に支配されてしまう主人公の葛藤はよく理解できるつもりだ
自分のために書いたものが、だれかの目に触れて、その人とつながる。孤独な人生の中で、誰かとめぐりあうこと以上の奇跡なんてないとわたしは思う。
書くことは、生き方の問題である。
自分のために、書けばいい。読みたいことを、書けばいい。
出力する前から「誰かのために」みたいなことを考えていても上手くいきませんが、自分の文章が結果として誰かを救う可能性みたいなものを想像するのは自由でしょう。
あわせて読みたい
【肯定】社会不適合者こそ非凡。学校・世の中に馴染めなかった異才たちの過去から”才能”の本質を知る:…
「みんなと同じ」に馴染めないと「社会不適合」と判断され、排除されてしまうことが多いでしょう。しかし『非属の才能』では、「どこにも属せない感覚」にこそ才能の源泉があると主張します。常識に違和感を覚えてしまう人を救う本から、同調圧力に屈しない生き方を学ぶ
私にも、そんな経験がほんの僅かですが何度かあります。そういう時は本当に、文章を書き続けてきて良かったな、と心の底から思えます。
あわせて読みたい
【食&芸術】死んでも車を運転したくない人間の香川うどん巡り& 豊島アート巡りの旅ルート(山越うどん…
仕事終わりの木曜日夜から日曜日に掛けて、「香川のうどん巡り」と「豊島のアート巡り」をしてきました。うどんだけでも7580円分食べたので、かなりの軒数を回ったことになります。しかも「死んでも車を運転したくない」ため、可能な限り公共交通機関のみで移動しました。私と同じように「車を運転したくない人」には、かなり参考になる記事と言えるのではないかと思います
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!「文章の書き方が分からない」「文章力がないから鍛えたい」という方にオススメ…
「文章の書き方」についてのKindle本を出版しました。「文章が書けない」「どう書いたらいいか分からない」「文章力を向上させたい」という方の悩みを解消できるような本に仕上げたつもりです。数多くの文章を書き、さらに頼まれて文章を推敲してきた経験を踏まえ、「文章を書けるようになるにはどうしたらいいか」についての私なりの考えをまとめました。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【価値】レコードなどの「フィジカルメディア」が復権する今、映画『アザー・ミュージック』は必見だ
2016年に閉店した伝説のレコード店に密着するドキュメンタリー映画『アザー・ミュージック』は、「フィジカルメディアの衰退」を象徴的に映し出す。ただ私は、「デジタル的なもの」に駆逐されていく世の中において、「『制約』にこそ価値がある」と考えているのだが、若者の意識も実は「制約」に向き始めているのではないかとも思っている
あわせて読みたい
【魅惑】マツコも絶賛の“日本人初のパリコレトップモデル”山口小夜子のメイクの凄さや素顔を描く映画:…
日本人初のパリコレトップモデルである山口小夜子と親交があった監督が紡ぐ映画『氷の花火 山口小夜子』は、未だ謎に包まれているその人生の一端を垣間見せてくれる作品だ。彼女を知る様々な人の記憶と、彼女を敬愛する多くの人の想いがより合って、一時代を築いた凄まじい女性の姿が浮かび上がってくる
あわせて読みたい
【食&芸術】死んでも車を運転したくない人間の香川うどん巡り& 豊島アート巡りの旅ルート(山越うどん…
仕事終わりの木曜日夜から日曜日に掛けて、「香川のうどん巡り」と「豊島のアート巡り」をしてきました。うどんだけでも7580円分食べたので、かなりの軒数を回ったことになります。しかも「死んでも車を運転したくない」ため、可能な限り公共交通機関のみで移動しました。私と同じように「車を運転したくない人」には、かなり参考になる記事と言えるのではないかと思います
あわせて読みたい
【映画】『キャスティング・ディレクター』の歴史を作り、ハリウッド映画俳優の運命を変えた女性の奮闘
映画『キャスティング・ディレクター』は、ハリウッドで伝説とされるマリオン・ドハティを描き出すドキュメンタリー。「神業」「芸術」とも評される配役を行ってきたにも拘わらず、長く評価されずにいた彼女の不遇の歴史や、再び「キャスティングの暗黒期」に入ってしまった現在のハリウッドなどを切り取っていく
あわせて読みたい
【衝撃】「きのくに子どもの村学園」に密着する映画『夢見る小学校』は、「義務教育」の概念を破壊する…
驚きの教育方針を有する私立小学校「きのくに子どもの村学園」に密着する映画『夢見る小学校』と、「日本の教育にはほとんどルールが無い」ことを示す特徴的な公立校を取り上げる映画『夢見る公立校長先生』を観ると、教育に対する印象が変わる。「改革を妨げる保護者」にならないためにも観るべき作品だ
あわせて読みたい
【共感】斎藤工主演映画『零落』(浅野いにお原作)が、「創作の評価」を抉る。あと、趣里が良い!
かつてヒット作を生み出しながらも、今では「オワコン」みたいな扱いをされている漫画家を中心に描く映画『零落』は、「バズったものは正義」という世の中に斬り込んでいく。私自身は創作者ではないが、「売れる」「売れない」に支配されてしまう主人公の葛藤はよく理解できるつもりだ
あわせて読みたい
【感想】どんな話かわからない?難しい?ジブリ映画『君たちはどう生きるか』の考察・解説は必要?(監…
宮崎駿最新作であるジブリ映画『君たちはどう生きるか』は、宮崎アニメらしいファンタジックな要素を全開に詰め込みつつ、「生と死」「創造」についても考えさせる作品だ。さらに、「自分の頭の中から生み出されたものこそ『正解』」という、創造物と向き合う際の姿勢についても問うているように思う
あわせて読みたい
【実話】映画『グッドバイ、バッドマガジンズ』(杏花主演)が描く、もの作りの絶望(と楽しさ)
実在したエロ雑誌編集部を舞台に、タブーも忖度もなく業界の内実を描き切る映画『グッドバイ、バッドマガジンズ』は、「エロ雑誌」をテーマにしながら、「もの作りに懸ける想い」や「仕事への向き合い方」などがリアルに描かれる素敵な映画だった。とにかく、主役を演じた杏花が良い
あわせて読みたい
【思考】文章の書き方が分かんない、トレーニングしたいって人はまず、古賀史健の文章講義の本を読め:…
古賀史健『20歳の自分に受けさせたい文章講義』は、「具体的なテクニック」ではない記述も非常に興味深い1冊だ。「なぜ文章を書く必要があるのか」という根本的な部分から丁寧に掘り下げる本書は、「書くからこそ考えられる」という、一般的なイメージとは逆だろう発想が提示される
あわせて読みたい
【価値】どうせ世の中つまらない。「レンタルなんもしない人」の本でお金・仕事・人間関係でも考えよう…
「0円で何もしない」をコンセプトに始まった「レンタルなんもしない人」という活動は、それまで見えにくかった様々な価値観を炙り出した見事な社会実験だと思う。『<レンタルなんもしない人>というサービスをはじめます。』で本人が語る、お金・仕事・人間関係の新たな捉え方
あわせて読みたい
【表現】映画『名付けようのない踊り』で初めて見た田中泯のダンス。「芸術以前」を志向する圧倒的パワー
映画『名付けようのない踊り』の中で田中泯は言う。「私」や「個性」を表現することには違和感がある、と。「踊りのために身体を作る」のではなく、「野良仕事で出来た身体で踊る」のだ、と。芸術になる前の踊りを探したい、と。「唯一無二の表現者」の生涯と現在地を映し出すドキュメンタリー
あわせて読みたい
【組織】新入社員・就活生必読。「社内コミュニケーション」でやるべきことを山田ズーニーが語る:『半…
組織内のコミュニケーションが上手くできないと悩んでいる方、多いのではないだろうか。山田ズーニー『半年で職場の星になる!働くためのコミュニケーション力』は、組織に属するあらゆる人に向けて、「コミュニケーションで重視すべき本質」をテクニックと共に伝授する
あわせて読みたい
【変革】「ビジネスより自由のために交渉力を」と語る瀧本哲史の”自己啓発”本に「交渉のコツ」を学ぶ:…
急逝してしまった瀧本哲史は、「交渉力」を伝授する『武器としての交渉思考』を通じて、「若者よ、立ち上がれ!」と促している。「同質性のタコツボ」から抜け出し、「異質な人」と「秘密結社」を作り、世の中に対する「不満」を「変革」へと向かわせる、その勇気と力を本書から感じてほしい
あわせて読みたい
【革新】天才マルタン・マルジェラの現在。顔出しNGでデザイナーの頂点に立った男の”素声”:映画『マル…
「マルタン・マルジェラ」というデザイナーもそのブランドのことも私は知らなかったが、そんなファッション音痴でも興味深く観ることができた映画『マルジェラが語る”マルタン・マルジェラ”』は、生涯顔出しせずにトップに上り詰めた天才の来歴と現在地が語られる
あわせて読みたい
【革命】電子音楽誕生の陰に女性あり。楽器ではなく機械での作曲に挑んだ者たちを描く映画:『ショック…
現代では当たり前の「電子音楽」。その黎明期には、既存の音楽界から排除されていた女性が多く活躍した。1978年、パリに住む1人の女性が「電子音楽」の革命の扉をまさに開こうとしている、その1日を追う映画『ショック・ド・フューチャー』が描き出す「創作の熱狂」
あわせて読みたい
【狂気】バケモン・鶴瓶を映し出す映画。「おもしろいオッチャン」に潜む「異常さ」と「芸への情熱」:…
「俺が死ぬまで公開するな」という条件で撮影が許可された映画『バケモン』。コロナ禍で映画館が苦境に立たされなければ、公開はずっと先だっただろう。テレビで見るのとは違う「芸人・笑福亭鶴瓶」の凄みを、古典落語の名作と名高い「らくだ」の変遷と共に切り取る
あわせて読みたい
【革新】映画音楽における唯一のルールは「ルールなど無い」だ。”異次元の音”を生み出す天才を追う:映…
「無声映画」から始まった映画業界で、音楽の重要性はいかに認識されたのか?『JAWS』の印象的な音楽を生み出した天才は、映画音楽に何をもたらしたのか?様々な映画の実際の映像を組み込みながら、「映画音楽」の世界を深堀りする映画『すばらしき映画音楽たち』で、異才たちの「創作」に触れる
あわせて読みたい
【解釈】詩人が語る詩の読み方。意味や読み方や良さが分からなくて全然気にしなくていい:『今を生きる…
私は学生時代ずっと国語の授業が嫌いでしたが、それは「作品の解釈には正解がある」という決めつけが受け入れ難かったからです。しかし、詩人・渡邊十絲子の『今を生きるための現代詩』を読んで、詩に限らずどんな作品も、「解釈など不要」「理解できなければ分からないままでいい」と思えるようになりました
あわせて読みたい
【博覧強記】「紙の本はなくなる」説に「文化は忘却されるからこそ価値がある」と反論する世界的文学者…
世界的文学者であり、「紙の本」を偏愛するウンベルト・エーコが語る、「忘却という機能があるから書物に価値がある」という主張は実にスリリングだ。『もうすぐ絶滅するという紙の書物について』での対談から、「忘却しない電子データ」のデメリットと「本」の可能性を知る
あわせて読みたい
【おすすめ】濱口竜介監督の映画『親密さ』は、「映像」よりも「言葉」が前面に来る衝撃の4時間だった
専門学校の卒業制作として濱口竜介が撮った映画『親密さ』は、2時間10分の劇中劇を組み込んだ意欲作。「映像」でありながら「言葉の力」が前面に押し出される作品で、映画や劇中劇の随所で放たれる「言葉」に圧倒される。4時間と非常に長いが、観て良かった
あわせて読みたい
【天才】読書猿のおすすめ本。「いかにアイデアを生むか」の発想法を人文書に昇華させた斬新な1冊:『ア…
「独学の達人」「博覧強記の読書家」などと評される読書猿氏が、古今東西さまざまな「発想法」を1冊にまとめた『アイデア大全』は、ただのHow To本ではない。「発想法」を学問として捉え、誕生した経緯やその背景なども深堀りする、「人文書」としての一面も持つ作品だ
あわせて読みたい
【真実?】佐村河内守のゴーストライター騒動に森達也が斬り込んだ『FAKE』は我々に何を問うか?
一時期メディアを騒がせた、佐村河内守の「ゴースト問題」に、森達也が斬り込む。「耳は聴こえないのか?」「作曲はできるのか?」という疑惑を様々な角度から追及しつつ、森達也らしく「事実とは何か?」を問いかける『FAKE』から、「事実の捉え方」について考える
あわせて読みたい
【多様性】神童から引きこもりになり、なんとか脱出したお笑い芸人が望む、誰も責められない社会:『ヒ…
お笑い芸人・髭男爵の山田ルイ53世は、“神童”と呼ばれるほど優秀だったが、“うんこ”をきっかけに6年間引きこもった。『ヒキコモリ漂流記』で彼は、ひきこもりに至ったきっかけ、ひきこもり中の心情、そしてそこからいかに脱出したのかを赤裸々に綴り、「誰にも優しい世界」を望む
あわせて読みたい
【奇跡】鈴木敏夫が2人の天才、高畑勲と宮崎駿を語る。ジブリの誕生から驚きの創作秘話まで:『天才の思…
徳間書店から成り行きでジブリ入りすることになったプロデューサー・鈴木敏夫が、宮崎駿・高畑勲という2人の天才と共に作り上げたジブリ作品とその背景を語り尽くす『天才の思考 高畑勲と宮崎駿』。日本のアニメ界のトップランナーたちの軌跡の奇跡を知る
あわせて読みたい
【教養】美術を「感じたまま鑑賞する」のは難しい。必要な予備知識をインストールするための1冊:『武器…
芸術を「感性の赴くまま見る」のは、日本特有だそうだ。欧米では美術は「勉強するもの」と認識されており、本書ではアートを理解しようとするスタンスがビジネスにも役立つと示唆される。美術館館長を務める著者の『武器になる知的教養 西洋美術鑑賞』から基礎の基礎を学ぶ
あわせて読みたい
【問い】「学ぶとはどういうことか」が学べる1冊。勉強や研究の指針に悩む人を導いてくれる物語:『喜嶋…
学校の勉強では常に「課題」が与えられていたが、「学び」というのは本来的に「問題を見つけること」にこそ価値がある。研究者の日常を描く小説『喜嶋先生の静かな世界』から、「学びの本質」と、我々はどんな風に生きていくべきかについて考える
あわせて読みたい
【天才】写真家・森山大道に密着する映画。菅田将暉の声でカッコよく始まる「撮り続ける男」の生き様:…
映画『あゝ荒野』のスチール撮影の際に憧れの森山大道に初めて会ったという菅田将暉の声で始まる映画『過去はいつも新しく、未来はつねに懐かしい』は、ちゃちなデジカメ1つでひたすら撮り続ける異端児の姿と、50年前の処女作復活物語が見事に交錯する
あわせて読みたい
【狂気】稀少本を収集・売買する「愛すべき変人コレクター」の世界と、インターネットによる激変:映画…
広大な本の世界を狩人のように渉猟し、お気に入りの本を異常なまでに偏愛する者たちを描き出す映画『ブックセラーズ』。実在の稀少本コレクターたちが、本への愛を語り、新たな価値を見出し、次世代を教育し、インターネットの脅威にどう立ち向かっているのかを知る
あわせて読みたい
【表現者】「センスが良い」という言葉に逃げない。自分の内側から何かを表現することの本質:『作詞少…
大前提として、表現には「技術」が必要だ。しかし、「技術」だけでは乗り越えられない部分も当然ある。それを「あいつはセンスが良いから」という言葉に逃げずに、向き合ってぶつかっていくための心得とは何か。『作詞少女』をベースに「表現することの本質」を探る
あわせて読みたい
【感想】努力では才能に勝てないのか?どうしても辿り着きたい地点まで迷いながらも突き進むために:『…
どうしても辿り着きたい場所があっても、そのあまりの遠さに目が眩んでしまうこともあるでしょう。そんな人に向けて、「才能がない」という言葉に逃げずに前進する勇気と、「仕事をする上で大事なスタンス」について『羊と鋼の森』をベースに書いていきます
あわせて読みたい
【発想力】「集中力が続かない」と悩むことはない。「集中しない思考」こそAI時代に必要だ:『集中力は…
『「集中力がない」と悩んでいる人は多いかもしれません。しかし本書では、「集中力は、思ってるほど素晴らしいものじゃない」と主張します。『集中力はいらない』をベースに、「分散思考」の重要性と、「発想」を得るための「情報の加工」を学ぶ
ルシルナ
才能・センスがない【本・映画の感想】 | ルシルナ
子どもの頃は、自分が何かの才能やセンスに恵まれていることを期待していましたが、残念ながら天才ではありませんでした。昔はやはり、凄い人に嫉妬したり、誰かと比べて苦…
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…
 犀川後藤
犀川後藤









































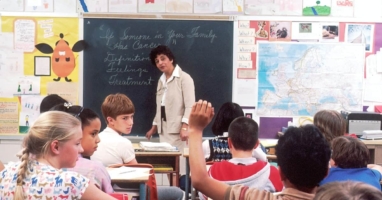
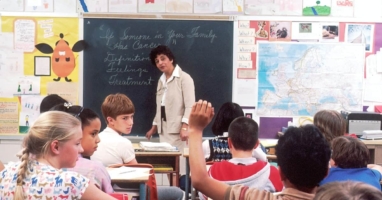























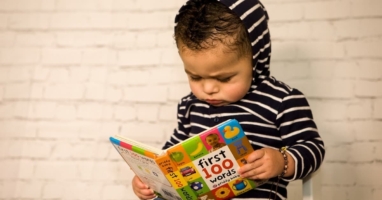
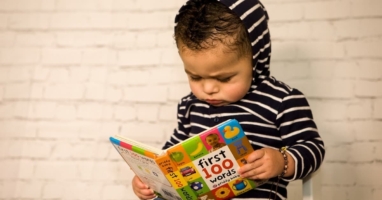





















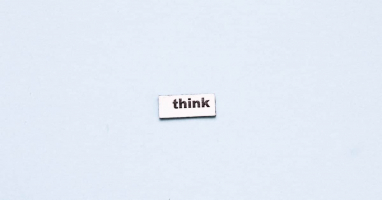
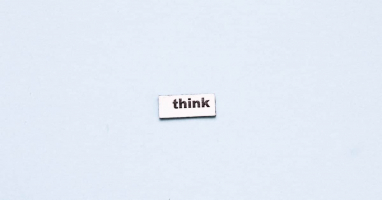


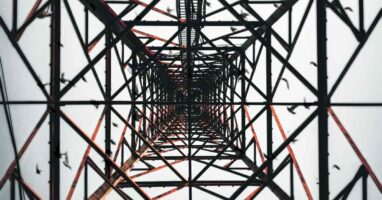
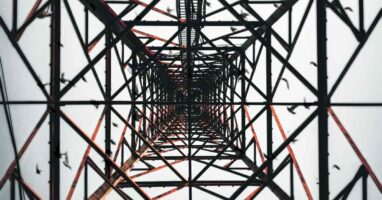














































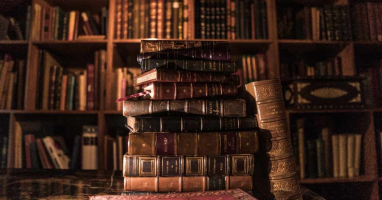
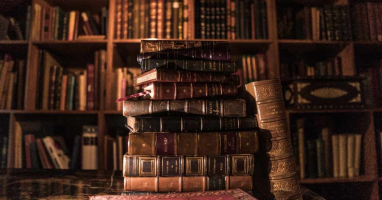
















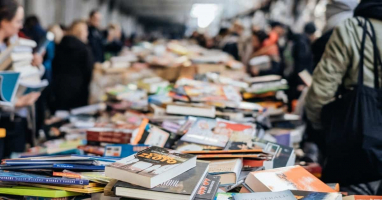
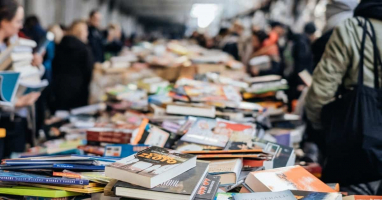




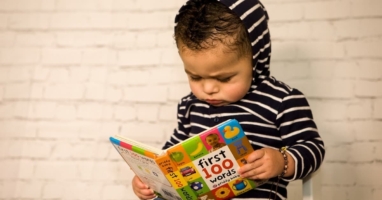
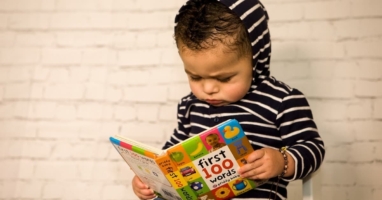








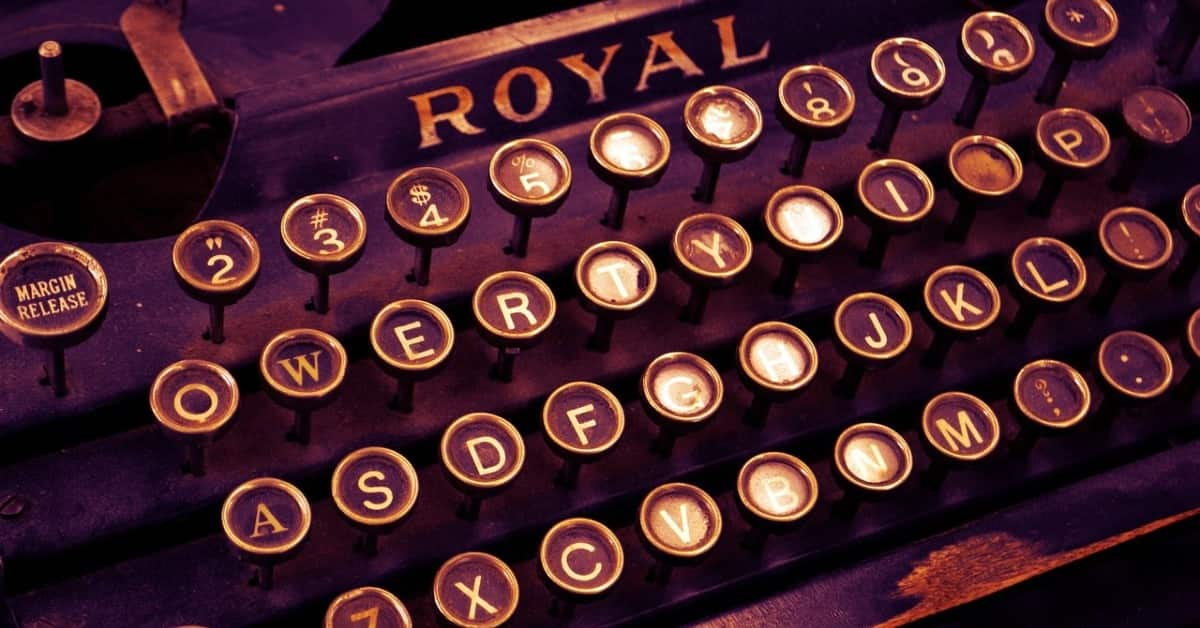





コメント