目次
はじめに
この記事で取り上げる本
著:ハル・グレガーセン, 翻訳:黒輪 篤嗣
¥1,760 (2022/09/27 20:19時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
この本をガイドにしながら記事を書いていきます
この記事の3つの要点
- 経営学の最終試験で評点Aを逃すことになった「衝撃的な問い」とは?
- 「心理的安全性」が確保されていない組織では「問う力」を伸ばすことはできない
- 「理想の従業員像」の認識を変えなければ、「判断のための正しい情報」は手に入らない
「答えを導くこと」よりも「正しい問いを見つけること」の方が遥かに重要だと理解できる1冊
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!「文章の書き方が分からない」「文章力がないから鍛えたい」という方にオススメ…
「文章の書き方」についてのKindle本を出版しました。「文章が書けない」「どう書いたらいいか分からない」「文章力を向上させたい」という方の悩みを解消できるような本に仕上げたつもりです。数多くの文章を書き、さらに頼まれて文章を推敲してきた経験を踏まえ、「文章を書けるようになるにはどうしたらいいか」についての私なりの考えをまとめました。
ビジネスやクリエイティブにおける「問う力」と、それを実現するための「心理的安全性の確保」の重要性を語る『問いこそが答えだ!』
本書で最も印象的なエピソードの紹介と、本書全体の構成について

あわせて読みたい
【変革】「ビジネスより自由のために交渉力を」と語る瀧本哲史の”自己啓発”本に「交渉のコツ」を学ぶ:…
急逝してしまった瀧本哲史は、「交渉力」を伝授する『武器としての交渉思考』を通じて、「若者よ、立ち上がれ!」と促している。「同質性のタコツボ」から抜け出し、「異質な人」と「秘密結社」を作り、世の中に対する「不満」を「変革」へと向かわせる、その勇気と力を本書から感じてほしい
まずは、本書で最もインパクトの大きかったエピソードから紹介しようと思う。エピローグに載っているもので、証券会社チャールズ・シュワブのCEOウォルト・ベッティンガーが学生時代に経験した話だ。この出来事をきっかけに、彼は「自分がそれまで指針にしてきた問いが間違っていたことに気づいた」という。
大学で経営学を専攻していたウォルトは、猛烈に勉強し、常にトップクラスの成績を取り続けた。3年生の時には、卒業を早めるために取得単位を倍に増やしたが、そのすべてで評価Aを維持したという。
しかし最後の最後、経営戦略コースの授業でオールAが阻まれてしまった。経営学部の別館で週2回、18時から22時まで、10週に渡って行われた授業の最後に行われた試験で、彼は白紙回答せざるを得なかったのだ。
最後のテストで教授が配ったのは、何も書かれていない真っ白な紙1枚。そして生徒にこう告げた。
あわせて読みたい
【知的】「BLって何?」という初心者に魅力を伝える「腐男子」の「BLの想像力と創造力」講座:『ボクた…
「BLは知的遊戯である」という主張には「は?」と感じてしまうでしょうが、本書『ボクたちのBL論』を読めばその印象は変わるかもしれません。「余白の発見と補完」を通じて、「ありとあらゆる2者の間の関係性を解釈する」という創造性は、現実世界にどのような影響を与えているのか
「もうみなさんは実際のビジネスの世界で仕事を始められるだけの知識を持っています。ですが、そこで成功するためにはもっと別のことも必要になります」。教授は学生たちに氏名を記入するよう指示してから、最後のテスト問題を発表した。それは次の一問のみだった。「この建物の清掃を担当しているのは誰か。彼女は何という名前か」
彼はこのテストで正解を書くことができず、オールAを逃した。そしてこのことをきっかけに彼は、その後の人生で最も役立つ教訓を得たと語っている。
どうすれば優秀な戦略家として頭角を現せるかと問うのではなく、この会社の成功は誰の働きにかかっているか、それらの社員全員に卓越した働きをしてもらうには何が必要か、問うべきだと。
なかなか興味深い話だろう。
あわせて読みたい
【扇動】人生うまくいかないと感じる時に読みたい瀧本哲史の本。「未来をどう生きる?」と問われる1冊:…
瀧本哲史は非常に優れたアジテーターであり、『2020年6月30日にまたここで会おう』もまさにそんな1冊。「少数のカリスマ」ではなく「多数の『小さなリーダー』」によって社会が変革されるべきだ、誰にだってやれることはある、と若者を焚きつける、熱量満載の作品
このエピソードをまず紹介したのは、本書の印象をざっくりとでも捉えてもらうためだ。「問う力」と聞いて、「議論で相手を打ち負かすような質問をする」みたいなイメージを持った方もいるかもしれないが、そうではない。もう少しきちんと説明するなら、「『問い』を適切に思い浮かべる力」となるだろうか。

本書の著者は、マサチューセッツ工科大(MIT)のリーダーシップセンター所長ハル・グレガーセンである。彼はこれまでに様々な企業のCEOから話を聞き、多くの企業で講演を重ねてきた。そしてその経験から、「『問うこと』の重要性」が語られる機会が多いことに気づき、その事実をより広く伝えようと本書を執筆したのだそうだ。
本書の重要な主張の1つは、「『問う力』は個人の資質だけの問題ではない」というものだ。著者はこう書いている。
あわせて読みたい
【思考】「”考える”とはどういうことか」を”考える”のは難しい。だからこの1冊をガイドに”考えて”みよう…
私たちは普段、当たり前のように「考える」ことをしている。しかし、それがどんな行為で、どのように行っているのかを、きちんと捉えて説明することは難しい。「はじめて考えるときのように」は、横書き・イラスト付きの平易な文章で、「考えるという行為」の本質に迫り、上達のために必要な要素を伝える
本書の核をなしているのは、よりよい問いが生まれるかどうかは――仕事でも私生活でも――環境に左右されるという主張だ。
つまり、「どんな環境にいるかによって『問う力』に差が生まれる」というわけだ。この理解は、「家庭」を含めたあらゆる組織運営に有効な視点と言えるだろう。元々の資質がまったく無関係とは言わないが、本書を読めば、環境が重要なファクターであることが理解できると思う。つまり、「問う力」は「組織のあり方」を変えることによって後天的に伸ばせる力と言えるはずだ。
本書は、著者が様々なCEOから直接聞いたエピソードで占められている。とにかく、徹底的に「実例」を提示しているというわけだ。「どのように『問いやすい環境』を作っているか」という手法はそれぞれ違うが、全体を通じて「環境を変えることで『問うこと』を活性化させられる」と実感できる内容になっている。非常に実践的な作品なのだ。
あわせて読みたい
【人生】仕事がつまらない人へ、自由な働き方・生き方のための「月3万円しか稼げないビジネス」指南:『…
SDGsが広がる世界で、「生活スタイルを変えなければならない」と理解していても、それをどう実践すべきかはなかなか難しいところでしょう。『月3万円ビジネス』で、「『仕事』と『生活』を密着させ、『お金・エネルギーの消費を抑える過程を楽しむ』」生き方を知る
私の場合、「問う段階」のことはかなり実践出来ていると感じた。つまり「問うこと」の重要性も理解していたし、「問いやすい環境」を作るという意識も昔から持っていたのである。また、多様な価値観が存在しなければ「問い」は生まれないので、「私自身の存在によって、その場の多様性が増すような言動」も割と意識しているつもりだ。
ただ、私にはその先が難しい。本書には「問いの資本」という表現が出てくるのだが、これは、「『問うこと』によって生まれた何かを実行する力」とでも言えばいいだろうか。残念ながら私には、この「問いの資本」が圧倒的に不足している。私にもしも「問いの資本」が十分あれば、起業なり組織運営なりに携わっていたかもしれないなぁ、と考えてしまった。
逆に、「問いの資本」はあるが、その前段階が不得手だという人には、本書は非常に役立つだろうと思う。
「未加工の情報」を手に入れるためには、「心理的安全性」が欠かせない
あわせて読みたい
【実話】仕事のやりがいは、「頑張るスタッフ」「人を大切にする経営者」「健全な商売」が生んでいる:…
メガネファストファッションブランド「オンデーズ」の社長・田中修治が経験した、波乱万丈な経営再生物語『破天荒フェニックス』をベースに、「仕事の目的」を見失わず、関わるすべての人に存在価値を感じさせる「働く現場」の作り方
まずはこんな文章を引用しよう。
つい最近も、革新的な企業の労働者の研究が注目を集めた。グーグル社の数百の作業チームを対象に、数年を費やして実施された「アリストテレス計画」だ。この調査では、成績の優秀なチームとそうではないチームとでは何がちがうのかが具体的に探られた。ニューヨーク・タイムズ・マガジン誌の記事によると、その結果は研究者たちを驚かせるものだった。IQの高さも勤勉さも関係なかったからだ。チームの成功といちばん強い相関が見られたのは、先に紹介した心理的安全性だった。

「心理的安全性」とは、「組織において、自分の考え・感情を誰に対しても不安を抱かずに発言できる状態」のことを言う。要するに、「こんな質問したらバカだと思われるかな」「こんなアホみたいなアイデアを口にしたらボロクソに批判されるかな」みたいな躊躇を一切感じずに、思ったことを思ったように口にできる状態を「心理的安全性」と呼ぶのである。「チームの成功といちばん強い相関が見られたのが心理的安全性だった」という事実は、人によっては意外に感じられるかもしれないが、私は当然そうだろうと感じてしまう。そして、昔何かで知った病院のエピソードを思い出した。
あわせて読みたい
【組織】新入社員・就活生必読。「社内コミュニケーション」でやるべきことを山田ズーニーが語る:『半…
組織内のコミュニケーションが上手くできないと悩んでいる方、多いのではないだろうか。山田ズーニー『半年で職場の星になる!働くためのコミュニケーション力』は、組織に属するあらゆる人に向けて、「コミュニケーションで重視すべき本質」をテクニックと共に伝授する
ある病院には、外科手術のチームが2つある。どちらも年間の手術件数やチームの人数など様々な条件が同じだとしよう。しかし1点だけ違いがある。「手術ミスの報告件数」だ。Aチームは、年間100件の手術をこなし、手術ミスの報告は2件だが、一方のBチームは、手術ミス0件である。
さて、もしあなたが、この情報を知った上で「どちらのチームに手術をお願いしたいか」と問われたら、どちらを選ぶだろうか?
シンプルに、「手術ミスのないBチームの方がいい」と感じるかもしれない。しかしその判断は早計と言える。というのもBチームでは、「手術ミス隠し」が行われている可能性があるからだ。仮にBチームに「心理的安全性」が存在しないとしよう。この場合、Bチームのスタッフはチーム長から叱責されることを恐れ、ギリギリ隠せてしまう程度の手術ミスは報告しないかもしれないし、だからこそ「手術ミスゼロ」という報告になっている可能性があるというわけだ。
あわせて読みたい
【実話】人質はなぜ犯人に好意を抱くか?「ストックホルム症候群」の由来である銀行強盗を描く映画:『…
「強盗や立てこもり事件などにおいて、人質が犯人に好意・共感を抱いてしまう状態」を「ストックホルム症候群」と呼ぶのだが、実はそう名付けられる由来となった実際の事件が存在する。実話を基にした映画『ストックホルムケース』から、犯人に協力してしまう人間の不可思議な心理について知る
一方Aチームでは、手術ミスが報告されている。もちろんミスは無いに越したことはないが、人間がすることだからゼロにはできない。ただ、Aチームでは恐らく「心理的安全性」が確保されているのだろう、スタッフが臆することなく自身のミスを報告できる雰囲気が存在していると推定できる。
となれば、「心理的安全性」が確保された、たぶん風通しが良いだろうAチームに手術をお願いする方が安全かもしれない、という思考も成立するだろう。こういう例を知ると、「心理的安全性」が組織において非常に重要だということが実感しやすくなるだろうと思う。
本書において「心理的安全性」は、「『未加工の情報』を手に入れること」と絡めた話として登場する。次のような理由から、上の立場にいればいるほど「生の情報」を手に入れるのは難しい。
あわせて読みたい
【不可思議】心理学の有名な実験から、人間の”欠陥”がどう明らかになっていったかを知る:『心は実験で…
『心は実験できるか 20世紀心理学実験物語』では、20世紀に行われた心理学実験からインパクトのある10の実験を選び紹介している。心理学者でもある著者が「科学であって科学ではない」と主張する心理学という学問で、人間のどんな不可思議さがあぶり出されてきたのかを知る
わたしの研究で最も深刻な隔絶が見られるのは、大企業のCEOや幹部という地位においてだ。その理由は、部下に情報の収集と取捨選択を任せてしまうことにある。それらのリーダーたちがほかの一般の人に比べて、心地よさを求める傾向が強いわけではないはずだが、日々、極度の重圧にさらされる中で、自分は有能だという自信を揺るがされたくないという心理が働く。しかも周りには、上司を不快な情報から守ることを自分たちの仕事と心得ている部下がいる。

思い当たる節があるという方、いるのではないだろうか。そして、このような環境に身を置いていると、当然のことながら、「未加工の情報」「生の情報」を手に入れにくくなってしまうというわけだ。
ビジネスであろうがなかろうか、物事を正しく判断するためには「情報」が欠かせない。しかし、最前線の現場が持っている「生の情報」が、組織の上層部に報告される過程でどんどん改変されてしまうことは想像に難くないだろう。これはまさに、「心理的安全性」が確保されているかどうかによって変わる問題だ。「こんな情報を上げたらマズいかもしれない」という心理が働けば、その情報に手を入れられてしまうかもしれない。それでは、適切な判断を下すために不可欠な「正しい情報」が手に入らなくなってしまう。
あわせて読みたい
【実話】実在の人物(?)をモデルに、あの世界的超巨大自動車企業の”内実”を暴く超絶面白い小説:『小…
誰もが知るあの世界的大企業をモデルに据えた『小説・巨大自動車企業トヨトミの野望』は、マンガみたいなキャラクターたちが繰り広げるマンガみたいな物語だが、実話をベースにしているという。実在の人物がモデルとされる武田剛平のあり得ない下剋上と、社長就任後の世界戦略にはとにかく驚かされる
私は別に組織を運営する立場にも、マネジメントするような地位にもいない。どちらかと言えば現場に近い場所をうろうろすることが多い人生であり、アイデア・不備・不満などが現場に多く転がっている印象を強く持っている。そしてそれらが、上の立場の人に届かず、ただ滞留しているだけの状態もよく目にしてきた。
私は、「心理的安全性」という概念を認識する以前からその重要性をなんとなく理解していたので、これまで属していた組織の中で、「問いやすい環境」を作ろうと奮闘したこともあるのだが、なかなか上手くいかなかった。特に私よりも上の世代の人たちには、「『心理的安全性』が重要である」ということがどうにも理解できないようだ。というか、「心理的安全性」そのものも何なのか分からないのだろう。そういう人たちがマネジメントをする組織では、残念ながら「未加工の情報」を手に入れることは難しい。
「心理的安全性」をいかに確保すべきか
「心理的安全性」の確保が難しい要因について、冒頭で紹介したウォルト・ベッティンガーはこんな風に語っている。
重役として成功を収められるかどうかは、意思決定の優劣で決まるのではありません。どんな重役も優れた判断を下せる率はだいたい同じで、60パーセントか、55パーセントぐらいです。ではどこがちがうかといえば、成功する重役は40パーセントないし45パーセントのまちがった判断にすばやく気づいて、それを修正できるのに対し、失敗する重役はしばしば事態をこじらせ、自分がまちがっていても、自分は正しいと部下を説き伏せようとします。

あわせて読みたい
【衝撃】権力の濫用、政治腐敗を描く映画『コレクティブ』は他人事じゃない。「国家の嘘」を監視せよ
火災で一命を取り留め入院していた患者が次々に死亡した原因が「表示の10倍に薄められた消毒液」だと暴き、国家の腐敗を追及した『ガゼタ』誌の奮闘を描く映画『コレクティブ 国家の嘘』は、「権力の監視」が機能しなくなった国家の成れの果てが映し出される衝撃作だ
重役が自らの間違いに気づかず(あるいは気づいていたとしても)、「自分は正しい」と部下を説き伏せるとすれば、とても「心理的安全性」の確保など望めないだろう。「こんな重役に何を言っても無駄だ」と思われてしまうだけだ。
あるいは、政治家が口にする「問い」を起点に著者がこのような指摘をしていたりもする。
(政治家たちが問いを使うのは)相手に立場をわきまえさせるためか、相手の無知を暴いて、面目を失わせるためか、あるいは相手に今していることをやめて、こちらに応じるべきであることを思い出させるためだ。権力に飢えた者は、相手より優位に立つことを求め、真実を求めようとはしない。
このことからは、なぜふつうの人があまり問いを発しようとしないのかが見えてくる。問いが権力の追求者たちによってそのように使われているのを目にしているせいで、問うことが攻撃的な行為だという印象を植えつけられてしまっているからだ。
似たような話として、「論破」という言葉を取り上げよう。2ちゃんねるの創始者ひろゆきの議論が「論破」と評され、若い世代を中心にウケている。「論破」という言葉は、「相手の意見をボコボコに粉砕する」みたいな意味で捉えられているだろう。そしてこの言葉もまた、「問うこと」のイメージを悪く見せている要因ではないかと思う。「問うこと」と「論破」が同一視されているとすれば、「問うこと」が攻撃的な行為であるように捉えられてしまうだろう。
あわせて読みたい
【天才】『三島由紀夫vs東大全共闘』後に「伝説の討論」と呼ばれる天才のバトルを記録した驚異の映像
1969年5月13日、三島由紀夫と1000人の東大全共闘の討論が行われた。TBSだけが撮影していたフィルムを元に構成された映画「三島由紀夫vs東大全共闘」は、知的興奮に満ち溢れている。切腹の一年半前の討論から、三島由紀夫が考えていたことと、そのスタンスを学ぶ
そのような状況を正しく理解している組織のトップは、「『問うこと』の『心理的安全性』をいかに確保するか」という課題に常に取り組んでおり、本書ではその実例が様々に紹介されている。
アニメーション・スタジオのピクサーには、制作中の映画を担当する監督に対して容赦ない意見を浴びせる「ブレイン・トラスト」というミーティングが存在するという。このミーティングは監督にとって相当過酷なのだそうだ。「ブレイン・トラスト」を終えた監督は家に帰されることが決まっていることからもその過酷さが伝わるだろう。その日はとても仕事にならないのだ。
「ブレイン・トラスト」の役割については、
制作初期の映画は、みんなゴミだからです。もちろん、そんないい方は身も蓋もないわけですが、あえてそういういい方をするのは、オブラートに包んだいい方をしていては、最初のバージョンがどうよくないかが伝わらないからです。わたしは遠回りに言ったり、控えめに言ったりはしません。ピクサーの映画は初めから傑作というわけではありません。それを磨いて傑作に仕上げることがわたしたちの仕事です。つまり”ゴミだったものをゴミではないものに”変えることです。
あわせて読みたい
【奇跡】鈴木敏夫が2人の天才、高畑勲と宮崎駿を語る。ジブリの誕生から驚きの創作秘話まで:『天才の思…
徳間書店から成り行きでジブリ入りすることになったプロデューサー・鈴木敏夫が、宮崎駿・高畑勲という2人の天才と共に作り上げたジブリ作品とその背景を語り尽くす『天才の思考 高畑勲と宮崎駿』。日本のアニメ界のトップランナーたちの軌跡の奇跡を知る
と説明されている。確かに、良い映画を作るには不可欠なのだろう。一方で、「容赦のない意見を浴びせる」ためには、「心理的安全性」の確保が欠かせない。「その作品を良くしたいという気持ち」で「作品を批判している」ということが、監督を含めたその場にいる全員が共有できていなければ成り立たないからだ。

わたしが提唱しているのは、自分の考えを覆される情報にもあえて耳を傾けられる場、その結果ひらめいた問い――ひねくれているとか、腹立たしいとか、的外れだとか思われそうな問いでも――を口にしたり、聞いたりできる場としてのセーフ・スペースだ。
このように、企業のトップが意識的に「心理的安全性」の確保に取り組むことで、類まれな創造性が維持されているというわけだ。
あわせて読みたい
【秘話】15年で世界を変えたグーグルの”異常な”創業エピソード。収益化無視の無料ビジネスはなぜ成功し…
スマホやネットを使う人で、グーグルのお世話になっていない人はまずいないだろう。もはや「インフラ」と呼んでいいレベルになったサービスを生み出した企業の創業からの歴史を描く『グーグル秘録』は、その歩みが「無邪気さ」と「偶然」の産物であることを示している。凄まじいエピソード満載の信じがたい企業秘話
私は、組織ではなく個人として、このような「心理的安全性」の確保を意識的にやっている。「相手との関係性を踏まえた上で、私がどのような振る舞いをしたら、相手が『話しやすい』と感じてくれるか」を常に考えているのだ。本書には、「触媒としての問い」という言葉が何度か登場する。これは「相手の発言を促すための問い」というような意味なのだが、私の場合は「私自身の存在全体」を「触媒」として機能させようという意識を持っているというわけだ。だからだろう、周りにいる人から、普通他人には話さないだろう話を聞く機会も結構ある。
また、普通の従業員の立場としても、私は悪くない振る舞いが出来ていると、本書を読んで感じた。ここからは、本書に出てくる「確信犯的エラーメーカー」についての話をしていこう。
本書では、「『問うこと』の重要性」が浸透しない理由の1つとして、「組織が理想とする従業員像」の設定に誤りがあると指摘している。企業は、「どんな問題でも、手早く処理し、上司や同僚を煩わせない従業員」こそ理想だと考えていることが多いそうだが、そもそもその設定が間違っているという指摘だ。
あわせて読みたい
【思考】文章の書き方が分かんない、トレーニングしたいって人はまず、古賀史健の文章講義の本を読め:…
古賀史健『20歳の自分に受けさせたい文章講義』は、「具体的なテクニック」ではない記述も非常に興味深い1冊だ。「なぜ文章を書く必要があるのか」という根本的な部分から丁寧に掘り下げる本書は、「書くからこそ考えられる」という、一般的なイメージとは逆だろう発想が提示される
同僚のミスをかばって、和を保つ者ではなく、めざとくミスを見つけてはいい立てる「うるさいトラブルメーカー」こそ、理想の従業員だという。この章の話に合わせるなら、それは「確信犯的エラーメーカー」といえる。完璧に業務が遂行されているというイメージを築こうとするより、公然とミスを認める従業員だ。そういう従業員は、ものごとをそっとしておくことのない「破壊的な質問者」でもある。「従来のやり方を受け入れたり、守ろうとしたりする前に、まずはそれでいいのかどうか、たえず問う」者たちだ。

若い頃、私はこの「確信犯的エラーメーカー」のような振る舞いをしていたと思う。まあ、その理由の大半は「苛立ち」によるものだったが、私の中には一応、「現場で応急処置をしたところで、根本が変わらなければまた同じことが起こり得る」という感覚もあったはずだ。これまで色んな組織でこの「確信犯的エラーメーカー」のような振る舞いをしてきたつもりだが、良い結果に結びつくことが少なく、今ではそのような言動はしていない。しかし、もし自分が何かマネジメントする側に立つのであれば、このような「確信犯的エラーメーカー」こそを重宝したいと改めて感じさせられた。
あわせて読みたい
【協働】日本の未来は福井から。地方だからこその「問題意識の共有」が、社会変革を成し遂げる強み:『…
コンパクトシティの先進地域・富山市や、起業家精神が醸成される鯖江市など、富山・福井の「変革」から日本の未来を照射する『福井モデル 未来は地方から始まる』は、決して「地方改革」だけの内容ではない。「危機意識の共有」があらゆる問題解決に重要だと認識できる1冊
著:ハル・グレガーセン, 翻訳:黒輪 篤嗣
¥1,760 (2022/09/27 20:22時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品読了済】私が読んできたエッセイ・コミック・自己啓発本を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が読んできたエッセイ・コミックを様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本選びの参考にして下さい。
最後に
記事の冒頭で書いた通り、本書には実例が満載であり、興味深いと感じる話を紹介しようと思えばいくらでも出来てしまう。しかしそれでは、本書の内容を延々とネタバレするだけの記事になってしまうので意識的に抑え気味にした。実例を知りたいという方は是非本書を読んでほしい。
この記事のまとめとして改めて触れておきたいことは、「何よりも『問うこと』が重要」という点である。
あわせて読みたい
【誤解】世界的大ベストセラー『ファクトフルネス』の要約。我々は「嘘の情報」を信じ込みやすい
世界の現状に関する13の質問に対して、ほとんどの人が同じ解答をする。最初の12問は不正解で、最後の1問だけ正答するのだ。世界的大ベストセラー『ファクトフルネス』から、「誤った世界の捉え方」を認識し、情報を受け取る際の「思い込み」を払拭する。「嘘の情報」に踊らされないために読んでおくべき1冊だ
いちばん重要で、なおかつむずかしいのは、正しい答えを見つけることではない。正しい問いを見つけることだ。誤った問いへの正しい答えほど、むだなもの――危険ではないにしても――はない。(ピーター・ドラッカー)
シーリグはアインシュタインのよく知られた逸話を紹介して、そのときにいわれた言葉を引用している。「もし問題を解決する時間が一時間あり、自分の人生がその問題の解決にかかっているなら、わたしは適切な問いを導き出すことに最初の五五分間を費やすでしょう。適切な問いがわかれば、問題は五分で解けるからです」
あわせて読みたい
【衝撃】「きのくに子どもの村学園」に密着する映画『夢見る小学校』は、「義務教育」の概念を破壊する…
驚きの教育方針を有する私立小学校「きのくに子どもの村学園」に密着する映画『夢見る小学校』と、「日本の教育にはほとんどルールが無い」ことを示す特徴的な公立校を取り上げる映画『夢見る公立校長先生』を観ると、教育に対する印象が変わる。「改革を妨げる保護者」にならないためにも観るべき作品だ
学校では主に、「答えを導き出すこと」に重点が置かれる。しかし本質的に最も重要なのは、「正しく問うこと」の方なのだ。学校でも会社でも、なかなかこのことは教わらないだろう。自分で気づくしかない。
本書では、大量の実例を通じて、「『問うこと』の重要性」や「『心理的安全性』をいかに確保すべきか」について語られる。本書を読んでまずは、「正しく問うこと」こそが何よりも大事なのだと実感し、自身の行動を変えてみてほしいと思う。
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!「文章の書き方が分からない」「文章力がないから鍛えたい」という方にオススメ…
「文章の書き方」についてのKindle本を出版しました。「文章が書けない」「どう書いたらいいか分からない」「文章力を向上させたい」という方の悩みを解消できるような本に仕上げたつもりです。数多くの文章を書き、さらに頼まれて文章を推敲してきた経験を踏まえ、「文章を書けるようになるにはどうしたらいいか」についての私なりの考えをまとめました。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【奇妙】大栗博司『重力とはなにか』は、相対性理論や量子力学の説明も秀逸だが、超弦理論の話が一番面白い
『重力とはなにか』(大栗博司)は、科学に馴染みの薄い人でもチャレンジできる易しい入門書だ。相対性理論や量子力学、あるいは超弦理論など、非常に難解な分野を基本的なところから平易に説明してくれるので、「科学に興味はあるけど難しいのはちょっと……」という方にこそ読んでほしい1冊
あわせて読みたい
【映画】『街は誰のもの?』という問いは奥深い。「公共」の意味を考えさせる問題提起に満ちた作品
映画『街は誰のもの?』は、タイトルの通り「街(公共)は誰のものなのか?」を問う作品だ。そしてそのテーマの1つが、無許可で街中に絵を描く「グラフィティ」であることもまた面白い。想像もしなかった問いや価値観に直面させられる、とても興味深い作品である
あわせて読みたい
【衝撃】「きのくに子どもの村学園」に密着する映画『夢見る小学校』は、「義務教育」の概念を破壊する…
驚きの教育方針を有する私立小学校「きのくに子どもの村学園」に密着する映画『夢見る小学校』と、「日本の教育にはほとんどルールが無い」ことを示す特徴的な公立校を取り上げる映画『夢見る公立校長先生』を観ると、教育に対する印象が変わる。「改革を妨げる保護者」にならないためにも観るべき作品だ
あわせて読みたい
【信念】映画『ハマのドン』の主人公、横浜港の顔役・藤木幸夫は、91歳ながら「伝わる言葉」を操る
横浜港を取り仕切る藤木幸夫を追うドキュメンタリー映画『ハマのドン』は、盟友・菅義偉と対立してでもIR進出を防ごうとする91歳の決意が映し出される作品だ。高齢かつほとんど政治家のような立ち位置でありながら、「伝わる言葉」を発する非常に稀有な人物であり、とても興味深かった
あわせて読みたい
【知的】「BLって何?」という初心者に魅力を伝える「腐男子」の「BLの想像力と創造力」講座:『ボクた…
「BLは知的遊戯である」という主張には「は?」と感じてしまうでしょうが、本書『ボクたちのBL論』を読めばその印象は変わるかもしれません。「余白の発見と補完」を通じて、「ありとあらゆる2者の間の関係性を解釈する」という創造性は、現実世界にどのような影響を与えているのか
あわせて読みたい
【実話】映画『グッドバイ、バッドマガジンズ』(杏花主演)が描く、もの作りの絶望(と楽しさ)
実在したエロ雑誌編集部を舞台に、タブーも忖度もなく業界の内実を描き切る映画『グッドバイ、バッドマガジンズ』は、「エロ雑誌」をテーマにしながら、「もの作りに懸ける想い」や「仕事への向き合い方」などがリアルに描かれる素敵な映画だった。とにかく、主役を演じた杏花が良い
あわせて読みたい
【実話】実在の人物(?)をモデルに、あの世界的超巨大自動車企業の”内実”を暴く超絶面白い小説:『小…
誰もが知るあの世界的大企業をモデルに据えた『小説・巨大自動車企業トヨトミの野望』は、マンガみたいなキャラクターたちが繰り広げるマンガみたいな物語だが、実話をベースにしているという。実在の人物がモデルとされる武田剛平のあり得ない下剋上と、社長就任後の世界戦略にはとにかく驚かされる
あわせて読みたい
【挑発】「TBS史上最大の問題作」と評されるドキュメンタリー『日の丸』(構成:寺山修司)のリメイク映画
1967年に放送された、寺山修司が構成に関わったドキュメンタリー『日の丸』は、「TBS史上最大の問題作」と評されている。そのスタイルを踏襲して作られた映画『日の丸~それは今なのかもしれない~』は、予想以上に面白い作品だった。常軌を逸した街頭インタビューを起点に様々な思考に触れられる作品
あわせて読みたい
【働く】給料が上がらない、上げる方法を知りたい人は木暮太一のこの本を。『資本論』が意外と役に立つ…
「仕事で成果を出しても給料が上がるわけではない」と聞いて、あなたはどう感じるだろうか?これは、マルクスの『資本論』における「使用価値」と「価値」の違いを踏まえた主張である。木暮太一『人生格差はこれで決まる 働き方の損益分岐点』から「目指すべき働き方」を学ぶ
あわせて読みたい
【思考】文章の書き方が分かんない、トレーニングしたいって人はまず、古賀史健の文章講義の本を読め:…
古賀史健『20歳の自分に受けさせたい文章講義』は、「具体的なテクニック」ではない記述も非常に興味深い1冊だ。「なぜ文章を書く必要があるのか」という根本的な部分から丁寧に掘り下げる本書は、「書くからこそ考えられる」という、一般的なイメージとは逆だろう発想が提示される
あわせて読みたい
【扇動】人生うまくいかないと感じる時に読みたい瀧本哲史の本。「未来をどう生きる?」と問われる1冊:…
瀧本哲史は非常に優れたアジテーターであり、『2020年6月30日にまたここで会おう』もまさにそんな1冊。「少数のカリスマ」ではなく「多数の『小さなリーダー』」によって社会が変革されるべきだ、誰にだってやれることはある、と若者を焚きつける、熱量満載の作品
あわせて読みたい
【対立】パレスチナとイスラエルの「音楽の架け橋」は実在する。映画『クレッシェンド』が描く奇跡の楽団
イスラエルとパレスチナの対立を背景に描く映画『クレッシェンド』は、ストーリーそのものは実話ではないものの、映画の中心となる「パレスチナ人・イスラエル人混合の管弦楽団」は実在する。私たちが生きる世界に残る様々な対立について、その「改善」の可能性を示唆する作品
あわせて読みたい
【実話】台湾のろう学校のいじめ・性的虐待事件を描く映画『無聲』が問う、あまりに悲しい現実
台湾のろう学校で実際に起こったいじめ・性的虐待事件を基に作られた映画『無聲』は、健常者の世界に刃を突きつける物語だ。これが実話だという事実に驚かされる。いじめ・性的虐待が物語の「大前提」でしかないという衝撃と、「性的虐待の方がマシ」という選択を躊躇せず行う少女のあまりの絶望を描き出す
あわせて読みたい
【狂気】”友好”のために北朝鮮入りした監督が撮った映画『ザ・レッド・チャペル』が映す平壌の衝撃
倫理的な葛藤を物ともせず、好奇心だけで突き進んでいくドキュメンタリー監督マッツ・ブリュガーが北朝鮮から「出禁」を食らう結果となった『ザ・レッド・チャペル』は、「友好」を表看板に北朝鮮に潜入し、その「日常」と「非日常」を映し出した衝撃作
あわせて読みたい
【継続】自己啓発本があまり好きじゃない私がおすすめする1冊。水野敬也『夢をかなえるゾウ』は面白い
世に数多ある「自己啓発本」の多くは、「いかに実践するか」という観点があまり重視されていないという印象がある。水野敬也『夢をかなえるゾウ』は、「僕」と「ガネーシャ」による小説形式で展開されることで、「とりあえずやってみよう」と思わせる力がとても強い、珍しい自己啓発本。
あわせて読みたい
【貢献】社会問題を解決する2人の「社会起業家」の生き方。「豊かさ」「生きがい」に必要なものは?:『…
「ヤクの毛」を使ったファッションブランド「SHOKAY」を立ち上げ、チベットの遊牧民と中国・崇明島に住む女性の貧困問題を解決した2人の若き社会起業家の奮闘を描く『世界を変えるオシゴト』は、「仕事の意義」や「『お金』だけではない人生の豊かさ」について考えさせてくれる
あわせて読みたい
【組織】新入社員・就活生必読。「社内コミュニケーション」でやるべきことを山田ズーニーが語る:『半…
組織内のコミュニケーションが上手くできないと悩んでいる方、多いのではないだろうか。山田ズーニー『半年で職場の星になる!働くためのコミュニケーション力』は、組織に属するあらゆる人に向けて、「コミュニケーションで重視すべき本質」をテクニックと共に伝授する
あわせて読みたい
【変】「家を建てるより、モバイルハウスを自作する方がいいのでは?」坂口恭平の疑問は「常識」を壊す…
誰もが大体「家」に住んでいるでしょうが、そもそも「家」とは何なのか考える機会はありません。『モバイルハウス 三万円で家をつくる』の著者・坂口恭平は、「人間は土地を所有すべきなのか?」という疑問からスタートし、「家」の不可思議さを突き詰めることで新たな世界を垣間見せる
あわせて読みたい
【秘話】15年で世界を変えたグーグルの”異常な”創業エピソード。収益化無視の無料ビジネスはなぜ成功し…
スマホやネットを使う人で、グーグルのお世話になっていない人はまずいないだろう。もはや「インフラ」と呼んでいいレベルになったサービスを生み出した企業の創業からの歴史を描く『グーグル秘録』は、その歩みが「無邪気さ」と「偶然」の産物であることを示している。凄まじいエピソード満載の信じがたい企業秘話
あわせて読みたい
【人生】日本人有名プロゲーマー・梅原大吾の名言満載の本。「努力そのものを楽しむ」ための生き方とは…
「eスポーツ」という呼び名が世の中に定着する遥か以前から活躍する日本人初のプロゲーマー・梅原大吾。17歳で世界一となり、今も一線を走り続けているが、そんな彼が『勝ち続ける意志力』で語る、「『努力している状態』こそを楽しむ」という考え方は、誰の人生にも参考になるはずだ
あわせて読みたい
【人生】仕事がつまらない人へ、自由な働き方・生き方のための「月3万円しか稼げないビジネス」指南:『…
SDGsが広がる世界で、「生活スタイルを変えなければならない」と理解していても、それをどう実践すべきかはなかなか難しいところでしょう。『月3万円ビジネス』で、「『仕事』と『生活』を密着させ、『お金・エネルギーの消費を抑える過程を楽しむ』」生き方を知る
あわせて読みたい
【斬新】ホームレスの家を「0円ハウス」と捉える坂口恭平の発想と視点に衝撃。日常の見え方が一変する:…
早稲田大学建築学科在籍中から「建築物の設計」に興味を持てなかった坂口恭平が、「ホームレスの家」に着目した『TOKYO 0円ハウス0円生活』には、「家」に対する考え方を一変させる視点が満載。「家に生活を合わせる」ではなく、「生活に家を合わせる」という発想の転換が見事
あわせて読みたい
【変革】「ビジネスより自由のために交渉力を」と語る瀧本哲史の”自己啓発”本に「交渉のコツ」を学ぶ:…
急逝してしまった瀧本哲史は、「交渉力」を伝授する『武器としての交渉思考』を通じて、「若者よ、立ち上がれ!」と促している。「同質性のタコツボ」から抜け出し、「異質な人」と「秘密結社」を作り、世の中に対する「不満」を「変革」へと向かわせる、その勇気と力を本書から感じてほしい
あわせて読みたい
【驚異】『グレイトフル・デッドにマーケティングを学ぶ』って書名通りの本。異端ロックバンドの”稼ぎ方”
日本ではあまり知られていないが、熱狂的なファンを持つロックバンド「グレイトフル・デッド」。彼らは50年も前から、現代では当たり前となった手法を続け、今でも年間5000万ドルを稼いでいる。『グレイトフル・デッドにマーケティングを学ぶ』で「ファンからの愛され方」を学ぶ
あわせて読みたい
【選択】映画『サウンド・オブ・メタル』で難聴に陥るバンドマンは、「障害」と「健常」の境界で揺れる
ドラムを叩くバンドマンが聴力を失ってしまう――そんな厳しい現実に直面する主人公を描く映画『サウンド・オブ・メタル』では、「『健常者との生活』を選ぶか否か」という選択が突きつけられる。ある意味では健常者にも向けられているこの問いに、どう答えるべきだろうか
あわせて読みたい
【抽象】「思考力がない」と嘆く人に。研究者で小説家の森博嗣が語る「客観的に考える」ために大事なこ…
世の中にはあまりに「具体的な情報」が溢れているために、「客観的、抽象的な思考」をする機会が少ない。そんな時代に、いかに思考力を育てていくべきか。森博嗣が『人間はいろいろな問題についてどう考えていけば良いのか』を通じて伝える「情報との接し方」「頭の使い方」
あわせて読みたい
【具体例】行動経済学のおすすめ本。経済も世界も”感情”で動くと実感できる「人間の不合理さ」:『経済…
普段どれだけ「合理的」に物事を判断しているつもりでも、私たちは非常に「不合理的」な行動を取ってしまっている。それを明らかにするのが「行動経済学」だ。『経済は感情で動く』『世界は感情で動く』の2冊をベースにして、様々な具体例と共に「人間の不思議さ」を理解する
あわせて読みたい
【狂気】バケモン・鶴瓶を映し出す映画。「おもしろいオッチャン」に潜む「異常さ」と「芸への情熱」:…
「俺が死ぬまで公開するな」という条件で撮影が許可された映画『バケモン』。コロナ禍で映画館が苦境に立たされなければ、公開はずっと先だっただろう。テレビで見るのとは違う「芸人・笑福亭鶴瓶」の凄みを、古典落語の名作と名高い「らくだ」の変遷と共に切り取る
あわせて読みたい
【差別】才ある者の能力を正しく引き出す者こそ最も有能であり、偏見から能力を評価できない者は無能だ…
「偏見・差別ゆえに、他人の能力を活かせない人間」を、私は無能だと感じる。そういう人は、現代社会の中にも結構いるでしょう。ソ連との有人宇宙飛行競争中のNASAで働く黒人女性を描く映画『ドリーム』から、偏見・差別のない社会への道筋を考える
あわせて読みたい
【矛盾】その”誹謗中傷”は真っ当か?映画『万引き家族』から、日本社会の「善悪の判断基準」を考える
どんな理由があれ、法を犯した者は罰せられるべきだと思っている。しかしそれは、善悪の判断とは関係ない。映画『万引き家族』(是枝裕和監督)から、「国民の気分」によって「善悪」が決まる社会の是非と、「善悪の判断を保留する勇気」を持つ生き方について考える
あわせて読みたい
【実話】障害者との接し方を考えさせる映画『こんな夜更けにバナナかよ』から”対等な関係”の大事さを知る
「障害者だから◯◯だ」という決まりきった捉え方をどうしてもしてしまいがちですが、『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』の主人公・鹿野靖明の生き様を知れば、少しは考え方が変わるかもしれません。筋ジストロフィーのまま病院・家族から離れて“自活”する決断をした驚異の人生
あわせて読みたい
【貢献】飛行機を「安全な乗り物」に決定づけたMr.トルネードこと天才気象学者・藤田哲也の生涯:『Mr….
つい数十年前まで、飛行機は「死の乗り物」だったが、天才気象学者・藤田哲也のお陰で世界の空は安全になった。今では、自動車よりも飛行機の方が死亡事故の少ない乗り物なのだ。『Mr.トルネード 藤田哲也 世界の空を救った男』から、その激動の研究人生を知る
あわせて読みたい
【天才】読書猿のおすすめ本。「いかにアイデアを生むか」の発想法を人文書に昇華させた斬新な1冊:『ア…
「独学の達人」「博覧強記の読書家」などと評される読書猿氏が、古今東西さまざまな「発想法」を1冊にまとめた『アイデア大全』は、ただのHow To本ではない。「発想法」を学問として捉え、誕生した経緯やその背景なども深堀りする、「人文書」としての一面も持つ作品だ
あわせて読みたい
【人生】「資本主義の限界を埋める存在としての『贈与論』」から「不合理」に気づくための生き方を知る…
「贈与論」は簡単には理解できないが、一方で、「何かを受け取ったら、与えてくれた人に返す」という「交換」の論理では対処できない現実に対峙する力ともなる。『世界は贈与でできている』から「贈与」的な見方を理解し、「受取人の想像力」を立ち上げる
あわせて読みたい
【人生】どう生きるべきかは、どう死にたいかから考える。死ぬ直前まで役割がある「理想郷」を描く:『…
「近隣の村から『姥捨て』と非難される理想郷」を描き出す『でんでら国』は、「死ぬ直前まで、コミュニティの中で役割が存在する」という世界で展開される物語。「お金があっても決して豊かとは言えない」という感覚が少しずつ広まる中で、「本当の豊かさ」とは何かを考える
あわせて読みたい
【奇跡】ホンダジェット驚愕の開発秘話。航空機未経験のホンダが革命的なアイデアで常識を打ち破る:『…
自動車メーカーの本田技研工業が開発した「ホンダジェット」は、航空機への夢を抱いていた創業者・本田宗一郎のスピリットを持ち続ける会社だからこそ実現できた。『ホンダジェット 開発リーダーが語る30年の全軌跡』からその革命的な技術開発と運用までのドラマを知る
あわせて読みたい
【多様性】神童から引きこもりになり、なんとか脱出したお笑い芸人が望む、誰も責められない社会:『ヒ…
お笑い芸人・髭男爵の山田ルイ53世は、“神童”と呼ばれるほど優秀だったが、“うんこ”をきっかけに6年間引きこもった。『ヒキコモリ漂流記』で彼は、ひきこもりに至ったきっかけ、ひきこもり中の心情、そしてそこからいかに脱出したのかを赤裸々に綴り、「誰にも優しい世界」を望む
あわせて読みたい
【権威】心理学の衝撃実験をテレビ番組の収録で実践。「自分は残虐ではない」と思う人ほど知るべき:『…
フランスのテレビ局が行った「現代版ミルグラム実験」の詳細が語られる『死のテレビ実験 人はそこまで服従するのか』は、「権威」を感じる対象から命じられれば誰もが残虐な行為をしてしまい得ることを示す。全人類必読の「過ちを事前に回避する」ための知見を学ぶ
あわせて読みたい
【感心】悩み相談とは、相手の問いに答える”だけ”じゃない。哲学者が相談者の「真意」に迫る:『哲学の…
「相談に乗る」とは、「自分の意見を言う行為」ではない。相談者が”本当に悩んでいること”を的確に捉えて、「回答を与えるべき問いは何か?」を見抜くことが本質だ。『哲学の先生と人生の話をしよう』から、「相談をすること/受けること」について考える
あわせて読みたい
【貢献】有名な科学者は、どんな派手な失敗をしてきたか?失敗が失敗でなかったアインシュタインも登場…
どれほど偉大な科学者であっても失敗を避けることはできないが、「単なる失敗」で終わることはない。誤った考え方や主張が、プラスの効果をもたらすこともあるのだ。『偉大なる失敗』から、天才科学者の「失敗」と、その意外な「貢献」を知る
あわせて読みたい
【助けて】息苦しい世の中に生きていて、人知れず「傷」を抱えていることを誰か知ってほしいのです:『…
元気で明るくて楽しそうな人ほど「傷」を抱えている。そんな人をたくさん見てきた。様々な理由から「傷」を表に出せない人がいる世の中で、『包帯クラブ』が提示する「見えない傷に包帯を巻く」という具体的な行動は、気休め以上の効果をもたらすかもしれない
あわせて読みたい
【不可思議】心理学の有名な実験から、人間の”欠陥”がどう明らかになっていったかを知る:『心は実験で…
『心は実験できるか 20世紀心理学実験物語』では、20世紀に行われた心理学実験からインパクトのある10の実験を選び紹介している。心理学者でもある著者が「科学であって科学ではない」と主張する心理学という学問で、人間のどんな不可思議さがあぶり出されてきたのかを知る
あわせて読みたい
【勇敢】後悔しない生き方のために”間違い”を犯せるか?法に背いてでも正義を貫いた女性の生き様:映画…
国の諜報機関の職員でありながら、「イラク戦争を正当化する」という巨大な策略を知り、守秘義務違反をおかしてまで真実を明らかにしようとした実在の女性を描く映画『オフィシャル・シークレット』から、「法を守る」こと以上に重要な生き方の指針を学ぶ
あわせて読みたい
【実話】人質はなぜ犯人に好意を抱くか?「ストックホルム症候群」の由来である銀行強盗を描く映画:『…
「強盗や立てこもり事件などにおいて、人質が犯人に好意・共感を抱いてしまう状態」を「ストックホルム症候群」と呼ぶのだが、実はそう名付けられる由来となった実際の事件が存在する。実話を基にした映画『ストックホルムケース』から、犯人に協力してしまう人間の不可思議な心理について知る
あわせて読みたい
【驚異】プロジェクトマネジメントの奇跡。ハリウッドの制作費以下で火星に到達したインドの偉業:映画…
実は、「一発で火星に探査機を送り込んだ国」はインドだけだ。アメリカもロシアも何度も失敗している。しかもインドの宇宙開発予算は大国と比べて圧倒的に低い。なぜインドは偉業を成し遂げられたのか?映画『ミッション・マンガル』からプロジェクトマネジメントを学ぶ
あわせて読みたい
【対話】刑務所内を撮影した衝撃の映画。「罰則」ではなく「更生」を目指す環境から罪と罰を学ぶ:映画…
2008年に開設された新たな刑務所「島根あさひ社会復帰促進センター」で行われる「TC」というプログラム。「罰則」ではなく「対話」によって「加害者であることを受け入れる」過程を、刑務所内にカメラを入れて撮影した『プリズン・サークル』で知る。
あわせて読みたい
【変人】学校教育が担うべき役割は?子供の才能を伸ばすために「異質な人」とどう出会うべきか?:『飛…
高校の美術教師からアーティストとして活動するようになった著者は、教育の現場に「余白(スキマ)」が減っていると指摘する。『飛び立つスキマの設計学』をベースに、子どもたちが置かれている現状と、教育が成すべき役割について確認する。
あわせて読みたい
【能力】激変する未来で「必要とされる人」になるためのスキルや考え方を落合陽一に学ぶ:『働き方5.0』
AIが台頭する未来で生き残るのは難しい……。落合陽一『働き方5.0~これからの世界をつくる仲間たちへ~』はそう思わされる一冊で、本書は正直、未来を前向きに諦めるために読んでもいい。未来を担う若者に何を教え、どう教育すべきかの参考にもなる一冊。
あわせて読みたい
【デマ】情報を”選ぶ”時代に、メディアの情報の”正しさ”はどのように判断されるのか?:『ニューヨーク…
一昔前、我々は「正しい情報を欲していた」はずだ。しかしいつの間にか世の中は変わった。「欲しい情報を正しいと思う」ようになったのだ。この激変は、トランプ元大統領の台頭で一層明確になった。『ニューヨーク・タイムズを守った男』から、情報の受け取り方を問う
あわせて読みたい
【感想】世の中と足並みがそろわないのは「正常が異常」だから?自分の「正常」を守るために:『コンビ…
30代になっても未婚でコンビニアルバイトの古倉さんは、普通から外れたおかしな人、と見られてしまいます。しかし、本当でしょうか?『コンビニ人間』をベースに、多数派の人たちの方が人生を自ら選択していないのではないかと指摘する。
あわせて読みたい
【発想力】「集中力が続かない」と悩むことはない。「集中しない思考」こそAI時代に必要だ:『集中力は…
『「集中力がない」と悩んでいる人は多いかもしれません。しかし本書では、「集中力は、思ってるほど素晴らしいものじゃない」と主張します。『集中力はいらない』をベースに、「分散思考」の重要性と、「発想」を得るための「情報の加工」を学ぶ
あわせて読みたい
【終焉】資本主義はもう限界だ。インターネットがもたらした「限界費用ゼロ社会」とその激変
資本主義は、これまで上手くやってきた。しかし、技術革新やインターネットの登場により、製造コストは限りなくゼロに近づき、そのことによって、資本主義の命脈が断たれつつある。『限界費用ゼロ社会』をベースに、これからの社会変化を捉える
あわせて読みたい
【奇跡】ビッグデータに”直感”を組み込んで活用。メジャーリーグを変えたデータ分析家の奮闘:『アスト…
「半世紀で最悪の野球チーム」と呼ばれたアストロズは、ビッグデータの分析によって優勝を果たす。その偉業は、野球のド素人によって行われた。『アストロボール』をベースに、「ビッグデータ」に「人間の直感」を組み込むという革命について学ぶ
あわせて読みたい
【肯定】社会不適合者こそ非凡。学校・世の中に馴染めなかった異才たちの過去から”才能”の本質を知る:…
「みんなと同じ」に馴染めないと「社会不適合」と判断され、排除されてしまうことが多いでしょう。しかし『非属の才能』では、「どこにも属せない感覚」にこそ才能の源泉があると主張します。常識に違和感を覚えてしまう人を救う本から、同調圧力に屈しない生き方を学ぶ
あわせて読みたい
【実話】仕事のやりがいは、「頑張るスタッフ」「人を大切にする経営者」「健全な商売」が生んでいる:…
メガネファストファッションブランド「オンデーズ」の社長・田中修治が経験した、波乱万丈な経営再生物語『破天荒フェニックス』をベースに、「仕事の目的」を見失わず、関わるすべての人に存在価値を感じさせる「働く現場」の作り方
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
自己啓発・努力・思考【本・映画の感想】 | ルシルナ
私自身は、仕事や社会貢献などにおいて自分の将来をもう諦めていますが、心の底では、自分の知識・スキルが他人や社会の役に立ったらいいな、と思っています。だから、自分…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…


























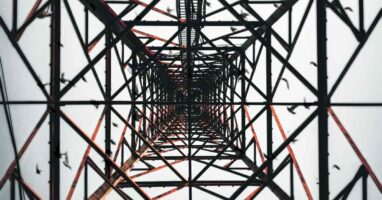



























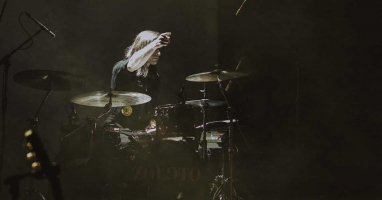



















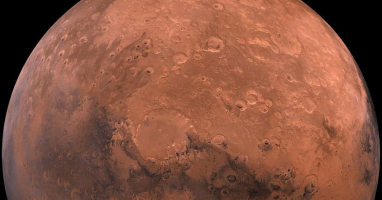



















コメント