目次
はじめに
この記事で取り上げる本
著:ローレン スレイター, 原著:Slater,Lauren, 翻訳:彰, 岩坂
¥2,699 (2021/09/30 06:13時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
この本をガイドにしながら記事を書いていきます
この記事の3つの要点
- 「普遍的な法則を追い求める」という意味で、心理学は科学にはなりきれない
- 「なぜそんな実験を行おうと思ったのか?」という意味での人間の複雑さも垣間見れる
- 日常生活の中でも注意すべき知見が多数描かれている
「傍観者効果」や「認知的不協和」などは、致命的な失敗を犯さないために知っておくべき知識と言えるだろう
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
『心は実験できるか』で扱われる有名な心理学の実験は、どう行われ、何を示してきたのか
著者は心理学という学問をどう捉えているか
あわせて読みたい
【知的】「BLって何?」という初心者に魅力を伝える「腐男子」の「BLの想像力と創造力」講座:『ボクた…
「BLは知的遊戯である」という主張には「は?」と感じてしまうでしょうが、本書『ボクたちのBL論』を読めばその印象は変わるかもしれません。「余白の発見と補完」を通じて、「ありとあらゆる2者の間の関係性を解釈する」という創造性は、現実世界にどのような影響を与えているのか
本書の著者はノンフィクションライターだが、心理学者でもある。自身も心理学という世界に身を置く彼女は、「心理学という学問」についてこんな風に書いている。

19世紀末、心理学の祖と考えられているヴィルヘルム・ヴントが世界初の道具的な心理学実験室、つまり計測を専門とする実験室を開設した。こうして科学としての心理学が誕生した。しかし、本書の実験が示すように、心理学は逆子の奇形児として生まれた。それは科学であるとも、ないともつかない怪物だった
著者は「心理学」を、科学であり科学ではない、と捉えているのだ。
あわせて読みたい
【不思議】森達也が「オカルト」に挑む本。「科学では説明できない現象はある」と否定も肯定もしない姿…
肯定派でも否定派でもない森達也が、「オカルト的なもの」に挑むノンフィクション『オカルト』。「現象を解釈する」ことよりも、「現象を記録する」こと点に注力し、「そのほとんどは勘違いや見間違いだが、本当に説明のつかない現象も存在する」というスタンスで追いかける姿勢が良い
心理学と科学とが結びついたこの学問は、誕生のときから先天異常があった。自力で呼吸できなかったのである。科学を、問題を体系的に追究して普遍的な法則に相当するものを生み出すものと定義するならば、心理学はその条件を満たすことに失敗し続けてきた。科学は現象を命名し、分離し、時間関係の中に位置づける。けれど、どうやって思考者から思考を、流れる思いの中から観念を分離できるというのだろう。身体ならば掴んでおくことができる。けれどもその行動は? この分野の本来的な性質が、科学的探求や科学的実験の成功を許さないのである
つまりこういうことだ。「科学」とは「普遍的な法則」、つまり「どんな場合でも成り立つ法則」を追い求める。しかし、「人間の心理」が対象となる「心理学」においては、そこから「普遍的な法則」を取り出すことは難しい。その「難しさ」の本質はいくつかあるが、その「難しさ」ゆえに、「心理学」というのは「実験が上手くいったかどうか判断することが困難」になるというわけだ。
本書は有名な10の心理学実験を取り上げる作品だが、そこで描かれているのは「実験手法」や「実験結果」だけではない。「心理学という”科学の逆子”に関わる者たちが、どのような軋轢・逸脱を生み出してきたか」という歴史を描き出す作品でもある。
あわせて読みたい
【限界】有名な「錯覚映像」で心理学界をザワつかせた著者らが語る「人間はいかに間違えるか」:『錯覚…
私たちは、知覚や記憶を頼りに社会を生きている。しかしその「知覚」「記憶」は、本当に信頼できるのだろうか?心理学の世界に衝撃を与えた実験を考案した著者らの『錯覚の科学』から、「避けられない失敗のクセ」を理解する
「心理学の実験」には常に、倫理・道徳の問題がつきまとう。「特殊な状況に置かれた人間がどう振る舞うか」を知るためには、「被験者を特殊な状況に置く」必要があるが、そのこと自体が倫理的・道徳的に認めがたい、というケースもある。現代ではとても許容されない実験もあるだろう。
「心理学」とはそのような歴史の堆積の上に成り立っているのだ、ということをまず理解しておこう。
本書『心は実験できるか』で紹介される10の実験について
先程も触れた通り本書では、20世紀に行われた様々な心理学実験の中から10個選び、それらについて「何故実験が行われたのか」「どんな影響を与えることになったのか」「どんな課題が残ったのか」などについて詳しく触れていく作品だ。
あわせて読みたい
【具体例】行動経済学のおすすめ本。経済も世界も”感情”で動くと実感できる「人間の不合理さ」:『経済…
普段どれだけ「合理的」に物事を判断しているつもりでも、私たちは非常に「不合理的」な行動を取ってしまっている。それを明らかにするのが「行動経済学」だ。『経済は感情で動く』『世界は感情で動く』の2冊をベースにして、様々な具体例と共に「人間の不思議さ」を理解する

選んだ基準について著者はこう書いている。
私はここに10の実験を選んだ。選択の基準は、同僚や私自身の物語的好みに基づくもので、私たちの目から見てきわめて大胆な疑問を大胆なしかたで提起している実験、というものだ。私たちは何者か。何が私たちを人間たらしめているか。私たちは本当に自分の人生を自分で決めているか。道徳的であるとはどういうことか。自由であるとは。
一言で言えば、「インパクトがある」ということだろうか。確かに、インパクトの強い実験が多い。
あわせて読みたい
【特異】「カメラの存在」というドキュメンタリーの大前提を覆す映画『GUNDA/グンダ』の斬新さ
映画『GUNDA/グンダ』は、「カメラの存在」「撮影者の意図」を介在させずにドキュメンタリーとして成立させた、非常に異端的な作品だと私は感じた。ドキュメンタリーの「デュシャンの『泉』」と呼んでもいいのではないか。「家畜」を被写体に据えたという点も非常に絶妙
それでは本書で紹介される10の実験の名称を以下に挙げよう。
- スキナー箱を開けて(スキナーのオペランド条件づけ実験)
- 権威への服従(ミルグラムの電気ショック実験)
- 患者のふりして病院へ(ローゼンハンの精神医学診断実験)
- 冷淡な傍観者(ダーリーとラタネの緊急事態介入実験)
- 理由を求める心(フェスティンガーの認知的不協和実験)
- 針金の母親を愛せるか(ハーローのサルの愛情実験)
- ネズミの楽園(アレグサンダーの依存症実験)
- 思い出された嘘(ロフタスの偽記憶実験)
- 記憶を保持する脳神経(カンデルの神経強化実験)
- 脳にメスを入れる(モニスの実験的ロボトミー)
この中で、本書を読む前に「ざっくりとでも実験に関する知識を持っていたもの」は大体半分と言ったところ。特別心理学に詳しいわけではない私が半分知っているということは、やはりメジャーな実験が扱われているということだろう。
この記事では、私が気になった5つの実験について紹介しようと思う。
あわせて読みたい
【要約】福岡伸一『生物と無生物のあいだ』は、「生命とは何か」を「動的平衡」によって定義する入門書…
「生命とは何か?」という、あまりに基本的だと感じられる問いは、実はなかなか難しい。20世紀生物学は「DNAの自己複製」が本質と考えたが、「ウイルス」の発見により再考を迫られた。福岡伸一の『生物と無生物のあいだ』『動的平衡』の2著作から、「生命の本質」を知る
ミルグラムの電気ショック実験
「心理学の実験」の中でも特に有名で、心理学についてまったく詳しくない人でも、何かしらで見聞きする機会が多いだろう実験だ。
この実験は「アイヒマン実験」とも呼ばれている。ホロコーストの責任者の一人であり、数百万人のユダヤ人を強制収容所に送ったアイヒマンは、当然「極悪非道」と捉えられたが、ミルグラムは、「アイヒマンの冷酷非情さは、本当にアイヒマンの個人の性格によるものなのか」を検証しようと考えて実験を行った。
実験の主たる目的は、「権威ある存在から強制された場合、他人を殺すような行動さえとってしまうのか」を調べることだった。ミルグラムが行った実験は以下のようなものである。
あわせて読みたい
【奇妙】大栗博司『重力とはなにか』は、相対性理論や量子力学の説明も秀逸だが、超弦理論の話が一番面白い
『重力とはなにか』(大栗博司)は、科学に馴染みの薄い人でもチャレンジできる易しい入門書だ。相対性理論や量子力学、あるいは超弦理論など、非常に難解な分野を基本的なところから平易に説明してくれるので、「科学に興味はあるけど難しいのはちょっと……」という方にこそ読んでほしい1冊

被験者は、目の前のボタンについて説明される。向かいに解答者(実験側の人間だが、被験者には、解答者も同じく被験者だと思い込ませる)が座っており、出された問題に解答者が正解できなければ、そのボタンを押すように命じられる。そのボタンは、解答者に電気ショックを与えるためのスイッチであり(実際に電気は流れず、解答者が電気ショックを受けている演技をする)、1問間違えるごとに電圧は上がっていく。電圧を上げる度に解答者に悲鳴は酷くなり、死んでしまうのではと想定されるような状況になるが、白衣を着た実験者から、解答者がどういう状態になろうがボタンを押すように指示される。
この状態で、被験者は苦しむ解答者にどれだけ電圧を高めた電気ショックを与えてしまうかを検証するという実験だ。
あわせて読みたい
【組織】意思決定もクリエイティブも「問う力」が不可欠だ。MIT教授がCEOから学んだ秘訣とは?:『問い…
組織マネジメントにおいては「問うこと」が最も重要だと、『問いこそが答えだ!』は主張する。MIT教授が多くのCEOから直接話を聞いて学んだ、「『問う環境』を実現するための『心理的安全性の確保』の重要性」とその実践の手法について、実例満載で説明する1冊
結果はなかなか驚くべきもので、65%もの人が最大電圧の電気ショックを与えたという。
この実験は、「権威ある存在から強制されれば、人は他人を殺すような行為をしてしまい得る」ことを示した実験として非常に有名だが、「実験室で作られた状況が現実的ではなく、信憑性がない」と批判を浴びる実験でもあるようだ。
しかし私は、この「ミルグラム実験」を「テレビ番組の収録」という現代的な設定に置き換えて行ったフランスでの実験に関する『死のテレビ実験』という本を読んだことがある。こちらでも同様の結果(実に80%以上)が出ているのだ。「現実的ではない」という批判は当てはまらないのではないかと私は感じている。
あわせて読みたい
【権威】心理学の衝撃実験をテレビ番組の収録で実践。「自分は残虐ではない」と思う人ほど知るべき:『…
フランスのテレビ局が行った「現代版ミルグラム実験」の詳細が語られる『死のテレビ実験 人はそこまで服従するのか』は、「権威」を感じる対象から命じられれば誰もが残虐な行為をしてしまい得ることを示す。全人類必読の「過ちを事前に回避する」ための知見を学ぶ
「何を『権威』と感じるか」は時代や国によって変わるだろうが、「『権威』に命じられたら酷い振る舞いもしてしまう」という人間の本質は変わらないと思う。「自分はそんなことしない」と楽観視してしまうのは怖いと感じさせる実験だ。
本書には驚くべきことに、実際にミルグラムの実験の被験者だった2人の人物が登場する。論文では全員仮名だったが、著者が苦労の末探しだしたのだ。一方は途中で電気ショックを中断でき、もう一方は中断できず最後まで与え続けてしまった。
彼らの話はとても興味深いし、ミルグラムの実験に参加したことが人生にどう影響したのかという話も載っていて考えさせられる。
ダーリーとラタネの緊急事態介入実験
この実験の説明には、必ずある殺人事件がセットになる。1964年にニューヨークで起こった「キティ・ジェノヴィーズ事件」である。ダーリーとラタネの2人はこの事件に触発されて実験を構築したので、まずは事件の説明からしていこう。

被害者であるキティ・ジェノヴィーズは、自宅のアパート前で暴漢に襲われ殺害されてしまう。彼女は叫び声を上げ、その声は、周辺に住む38人の住民が聞いていたことが後の捜査で明らかになった。
しかしその38人の誰一人として、彼女を助けに行かなかったどころか、警察にも通報しなかった。この事件は「都会の人間の冷淡さ」を示す事件として、当時大々的に報道されたという。
さて、ダーリーとラタネの2人はこの事件を、「都会の人間の冷淡さ」とは違う捉え方をした。彼らは、「自分以外にも事件に気づいた人がいることを知っていたからこそ、誰も行動を起こさなかったのではないか」という仮説を立てた。現在では「傍観者効果」として広く知られているものである。
そして彼らは、「傍観者効果」を実証するための実験を構築し、「人数が多くなるほど、トラブルが起きた際に行動を起こさない者が増える」ことを立証したのだ。
殺人事件に遭遇する機会などほとんどないだろうが、この「傍観者効果」を自分でも行ってしまっているケースはきっと多々あるだろう。私自身も、「誰かがなんとかするでしょう」とスルーしてしまったことはきっとあったと思う。人数が多ければ多いほど、自分1人の責任は薄まると考えてしまうこの心理効果は、日常の中でも気をつけた方がいいだろう。
あわせて読みたい
【称賛】生き様がかっこいい。ムンバイのホテルのテロ事件で宿泊客を守り抜いたスタッフたち:映画『ホ…
インドの高級ホテルで実際に起こったテロ事件を元にした映画『ホテル・ムンバイ』。恐ろしいほどの臨場感で、当時の恐怖を観客に体感させる映画であり、だからこそ余計に、「逃げる選択」もできたホテルスタッフたちが自らの意思で残り、宿泊を助けた事実に感銘を受ける
フェスティンガーの認知的不協和実験
そして、「傍観者効果」以上に私たちの生活で無視できない心理効果だと考えられるのが、この「フェスティンガーの認知的不協和実験」で明らかになった事実である。
まず実験内容に触れよう。
被験者を2つのグループに分け、一方には「1ドル渡す代わり嘘をついてもらう」、そしてもう一方は「20ドル渡す代わりに嘘をついてもらう」とする。もちろん被験者は、それが「嘘」だとちゃんと分かっている。
そして実験の最後にアンケートを取ると、1ドルもらったグループの方が、「自分がついた嘘を信じている」と語る者が多かったというのだ。
あわせて読みたい
【認識】「固定観念」「思い込み」の外側に出るのは難しい。自分はどんな「へや」に囚われているのか:…
実際に起こった衝撃的な事件に着想を得て作られた映画『ルーム』は、フィクションだが、観客に「あなたも同じ状況にいるのではないか?」と突きつける力強さを持っている。「普通」「当たり前」という感覚に囚われて苦しむすべての人に、「何に気づけばいいか」を気づかせてくれる作品
さて、これはどういうことだろうか? 本書ではこう説明される。
1ドルという金額は、「嘘をつく」という行為を正当化するには不十分であると被験者は感じている(認知A)。一方で、善良で賢明な人間は、理由もなく嘘をついたりはしない(認知B)。このように被験者の中には、「認知A」と「認知B」が存在し、これが「不協和」を起こしている。つまり、「自分は善良な人間なのに、たった1ドルで嘘をつかなければならない」という状態にあるのだ。

人間はこの「不協和」の状態を許容できない。だからこそ、その「不協和」を低減させるように認知を変えるのだ。この場合、「自分が口にすることが『嘘ではない』」という状況だとすれば、「不協和」は無くなる。だから「不協和」を無くすために、「自分は嘘をついているわけではない=自分が口にしたことを信じている」という認知に変わる、というのだ。
これは、「喫煙」や「馬券の購入」など様々な場面で現れる。「タバコが身体に悪いことは知っているが吸いたい」と思う人が自分の都合の良いように認知を変えたり、「馬券購入の締め切りが過ぎてもう変更できなくなることで、自分が買った馬に自信を深める」という心理を抱いたりするというわけだ。
日常生活の中でこの「認知的不協和」に直面することは多いだろう。そのような状況に置かれた時、人間が本能的にどのような対応を取ってしまうのか、理解しておくことは重要だと思う。
あわせて読みたい
【観察者】劣等感や嫉妬は簡単に振り払えない。就活に苦しむ若者の姿から学ぶ、他人と比べない覚悟:『…
朝井リョウの小説で、映画化もされた『何者』は、「就活」をテーマにしながら、生き方やSNSとの関わり方などについても考えさせる作品だ。拓人の、「全力でやって失敗したら恥ずかしい」という感覚から生まれる言動に、共感してしまう人も多いはず
アレグサンダーの依存症実験
この実験は、発表された際にはある意味で注目を集めたが、実際にはほとんど評価されていないそうだ。追試が何度も行われたが、アレグサンダーの実験結果を再現できなかった、という話もある。しかし、主張自体はなかなか興味深いので紹介しよう。
この実験は、「薬物依存症」に関するものだ。麻薬などの薬物は、脳の報酬系に作用することで依存性を引き起こすと考えられるようになり、それに関連する実験も行われている。現在でも、「薬物には、薬物そのものに依存を引き起こす要因が存在する」というのが一般的な認識だろうと思う。
しかしアレグサンダーは、それとは異なる主張をした。「薬物そのものに依存性はなく、服用する人間を取り巻くすべての環境が影響している」というのだ。つまりもっと言えば、「理想的な環境にいさえすれば、たとえどれだけ薬物を摂取しようが依存症になることはない」と考えたのである。
あわせて読みたい
【倫理】アート体験の行き着く未来は?映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』が描く狂気の世界(…
「『痛み』を失った世界」で「自然発生的に生まれる新たな『臓器』を除去するライブパフォーマンス」を行うソール・テンサーを主人公にした映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』は、すぐには答えの見出しにくい「境界線上にある事柄」を挑発的に描き出す、実に興味深い物語だ
これを立証するためにアレグサンダーは、実験用ラットが一切のストレスを感じずに済むよう、遊び場や食料を充実させた「ラットパーク」という空間を作り上げた。そしてこの「ラットパーク」に、「普通の水」と「モルヒネ入りの水」を用意し、実験を行った(モルヒネ入りの水は苦いので、砂糖が混ぜられたという)。
アレグサンダーが行った実験によれば、「一般的な実験用ケージのラットはモルヒネ入りの水を好んで飲んだが、ラットパークのラットはどれだけ砂糖を入れて甘くしてもモルヒネ入りの水を飲まなかった」「実験用ケージでモルヒネ入りの水を好んで飲んだラットをラットパークに移すと普通の水を飲むようになった」という。
さて先述した通り、様々な人間によって追試が行われたが、アレグサンダーが出したものと同じ結果を再現することは難しかったようだ。そもそも「薬物の依存性を否定する研究」というのは、科学的探究心としては良いが、倫理的にはグレーと言えるだろう。そういう意味で、賛否ある実験と受け取られているようだ。
またそもそも、「ラットパーク」による実験結果が正しいとしても、「人間がそれだけの理想的な環境にいられるか」という別の問題は出てくる。学問的には興味深い問いだが、この実験をどれだけ行いその信憑性を高めたところで、「社会で薬物使用が認められる」という方向には進んでいかないだろう。
あわせて読みたい
【誤り】「信じたいものを信じる」のは正しい?映画『星の子』から「信じること」の難しさを考える
どんな病気も治す「奇跡の水」の存在を私は信じないが、しかし何故「信じない」と言えるのか?「奇跡の水を信じる人」を軽々に非難すべきではないと私は考えているが、それは何故か?映画『星の子』から、「何かを信じること」の難しさについて知る
ロフタスの偽記憶実験
この実験が行われたのには、「催眠療法によって、過去の性的虐待の記憶を思い出す事例」が多数報告されるようになったという背景がある。「父親にレイプされた」という記憶を思い出す者も多く、それらに関する裁判も行われていった。

そんな中でロフタスが、「被験者に、偽の記憶を埋め込む実験に成功した」と発表する。「ショッピングモールで迷子になった」という偽りの記憶を、被験者の一部に「思い出させる」ことに成功したというのだ。
この実験によって、「人間の記憶はあやふやであり、被害者が『思い出した』と主張する記憶に誤りがある可能性がある」と判断されるようになり、裁判の結果にも影響を与えたそうだ。
あわせて読みたい
【感想】これはドキュメンタリー(実話)なのか?映画『女神の継承』が突きつける土着的恐怖
ナ・ホンジンがプロデューサーを務めた映画『女神の継承』は、フィクションなのかドキュメンタリーなのか混乱させる異様な作品だった。タイ東北部で強く信じられている「精霊(ピー)」の信仰をベースに、圧倒的なリアリティで土着的恐怖を描き出す、強烈な作品
しかしこの実験に関しても様々に批判があるという。確かに裁判の話だけに限ってみても、「人間には偽りの記憶が存在する可能性がある」と証明したところで、「目の前の被害女性の記憶が偽りである」ことの証明にはならない。しかし、他に物的証拠がなければ、裁判という仕組みの中で敗北してしまうのも仕方ない側面もあるかもしれないとも思う。
実は私にも、偽りかどうかは不明だが、両親と記憶が一致しない過去の出来事が2つある。その内の1つは、「足の骨折」に関するものだ。私は子どもの頃、足を3度骨折し、松葉杖をついて学校に通った記憶がある。しかし両親とも、「そんなことはなかった」と主張する。父親曰く、「もし足を骨折したら学校まで車で送り迎えしなければならないが、そんなことしたことはない」という。確かに私も、車で送り迎えをしてもらったのかどうか記憶はない。
いずれにせよ、私か両親のどちらか一方の記憶は確実に誤りであり、両親が揃って「無い」と言っているのであれば、僕の記憶が間違いである可能性の方が高いのだろう。しかしなぁ、松葉杖、ついてたんだけどなぁ……。
あわせて読みたい
【神秘】脳研究者・池谷裕二が中高生向けに行った講義の書籍化。とても分かりやすく面白い:『進化しす…
「宇宙」「深海」「脳」が、人類最後のフロンティアと呼ばれている。それほど「脳」というのは、未だに分からないことだらけの不思議な器官だ。池谷裕二による中高生向けの講義を元にした『進化しすぎた脳』『単純な脳、複雑な「私」』をベースに、脳の謎を知る
著:ローレン スレイター, 原著:Slater,Lauren, 翻訳:彰, 岩坂
¥603 (2022/01/29 21:28時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品読了済】私が読んできたノンフィクション・教養書を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が読んできたノンフィクションを様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本選びの参考にして下さい。
最後に
心理学の実験は様々に行われており、その中で、人間の不思議さが色々と明らかになっていった。一方で本書はさらに、「なぜそんな実験を行おうと思ったのか」という意味での人間の複雑さも明らかにしているとも言えるだろう。
科学であって科学ではない「心理学」という学問の一端を垣間見れる作品だ。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【奇妙】大栗博司『重力とはなにか』は、相対性理論や量子力学の説明も秀逸だが、超弦理論の話が一番面白い
『重力とはなにか』(大栗博司)は、科学に馴染みの薄い人でもチャレンジできる易しい入門書だ。相対性理論や量子力学、あるいは超弦理論など、非常に難解な分野を基本的なところから平易に説明してくれるので、「科学に興味はあるけど難しいのはちょっと……」という方にこそ読んでほしい1冊
あわせて読みたい
【倫理】アート体験の行き着く未来は?映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』が描く狂気の世界(…
「『痛み』を失った世界」で「自然発生的に生まれる新たな『臓器』を除去するライブパフォーマンス」を行うソール・テンサーを主人公にした映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』は、すぐには答えの見出しにくい「境界線上にある事柄」を挑発的に描き出す、実に興味深い物語だ
あわせて読みたい
【知的】「BLって何?」という初心者に魅力を伝える「腐男子」の「BLの想像力と創造力」講座:『ボクた…
「BLは知的遊戯である」という主張には「は?」と感じてしまうでしょうが、本書『ボクたちのBL論』を読めばその印象は変わるかもしれません。「余白の発見と補完」を通じて、「ありとあらゆる2者の間の関係性を解釈する」という創造性は、現実世界にどのような影響を与えているのか
あわせて読みたい
【感想】これはドキュメンタリー(実話)なのか?映画『女神の継承』が突きつける土着的恐怖
ナ・ホンジンがプロデューサーを務めた映画『女神の継承』は、フィクションなのかドキュメンタリーなのか混乱させる異様な作品だった。タイ東北部で強く信じられている「精霊(ピー)」の信仰をベースに、圧倒的なリアリティで土着的恐怖を描き出す、強烈な作品
あわせて読みたい
【感想】どんな話かわからない?難しい?ジブリ映画『君たちはどう生きるか』の考察・解説は必要?(監…
宮崎駿最新作であるジブリ映画『君たちはどう生きるか』は、宮崎アニメらしいファンタジックな要素を全開に詰め込みつつ、「生と死」「創造」についても考えさせる作品だ。さらに、「自分の頭の中から生み出されたものこそ『正解』」という、創造物と向き合う際の姿勢についても問うているように思う
あわせて読みたい
【組織】意思決定もクリエイティブも「問う力」が不可欠だ。MIT教授がCEOから学んだ秘訣とは?:『問い…
組織マネジメントにおいては「問うこと」が最も重要だと、『問いこそが答えだ!』は主張する。MIT教授が多くのCEOから直接話を聞いて学んだ、「『問う環境』を実現するための『心理的安全性の確保』の重要性」とその実践の手法について、実例満載で説明する1冊
あわせて読みたい
【特異】「カメラの存在」というドキュメンタリーの大前提を覆す映画『GUNDA/グンダ』の斬新さ
映画『GUNDA/グンダ』は、「カメラの存在」「撮影者の意図」を介在させずにドキュメンタリーとして成立させた、非常に異端的な作品だと私は感じた。ドキュメンタリーの「デュシャンの『泉』」と呼んでもいいのではないか。「家畜」を被写体に据えたという点も非常に絶妙
あわせて読みたい
【不思議】森達也が「オカルト」に挑む本。「科学では説明できない現象はある」と否定も肯定もしない姿…
肯定派でも否定派でもない森達也が、「オカルト的なもの」に挑むノンフィクション『オカルト』。「現象を解釈する」ことよりも、「現象を記録する」こと点に注力し、「そのほとんどは勘違いや見間違いだが、本当に説明のつかない現象も存在する」というスタンスで追いかける姿勢が良い
あわせて読みたい
【具体例】行動経済学のおすすめ本。経済も世界も”感情”で動くと実感できる「人間の不合理さ」:『経済…
普段どれだけ「合理的」に物事を判断しているつもりでも、私たちは非常に「不合理的」な行動を取ってしまっている。それを明らかにするのが「行動経済学」だ。『経済は感情で動く』『世界は感情で動く』の2冊をベースにして、様々な具体例と共に「人間の不思議さ」を理解する
あわせて読みたい
【要約】福岡伸一『生物と無生物のあいだ』は、「生命とは何か」を「動的平衡」によって定義する入門書…
「生命とは何か?」という、あまりに基本的だと感じられる問いは、実はなかなか難しい。20世紀生物学は「DNAの自己複製」が本質と考えたが、「ウイルス」の発見により再考を迫られた。福岡伸一の『生物と無生物のあいだ』『動的平衡』の2著作から、「生命の本質」を知る
あわせて読みたい
【認識】「固定観念」「思い込み」の外側に出るのは難しい。自分はどんな「へや」に囚われているのか:…
実際に起こった衝撃的な事件に着想を得て作られた映画『ルーム』は、フィクションだが、観客に「あなたも同じ状況にいるのではないか?」と突きつける力強さを持っている。「普通」「当たり前」という感覚に囚われて苦しむすべての人に、「何に気づけばいいか」を気づかせてくれる作品
あわせて読みたい
【本質】子どもの頃には読めない哲学書。「他人の哲学はつまらない」と語る著者が説く「問うこと」の大…
『<子ども>のための哲学』は決して、「子どもでも易しく理解できる哲学の入門書」ではない。むしろかなり難易度が高いと言っていい。著者の永井均が、子どもの頃から囚われ続けている2つの大きな疑問をベースに、「『哲学する』とはどういうことか?」を深堀りする作品
あわせて読みたい
【異端】「仏教とは?」を簡単に知りたい方へ。ブッダは「異性と目も合わせないニートになれ」と主張し…
我々が馴染み深い「仏教」は「大乗仏教」であり、創始者ゴータマ・ブッダの主張が詰まった「小乗仏教」とは似て非なるものだそうだ。『講義ライブ だから仏教は面白い!』では、そんな「小乗仏教」の主張を「異性と目も合わせないニートになれ」とシンプルに要約して説明する
あわせて読みたい
【飛躍】有名哲学者は”中二病”だった?飲茶氏が易しく語る「古い常識を乗り越えるための哲学の力」:『1…
『14歳からの哲学入門』というタイトルは、「14歳向けの本」という意味ではなく、「14歳は哲学することに向いている」という示唆である。飲茶氏は「偉大な哲学者は皆”中二病”だ」と説き、特に若い人に向けて、「新しい価値観を生み出すためには哲学が重要だ」と語る
あわせて読みたい
【矛盾】その”誹謗中傷”は真っ当か?映画『万引き家族』から、日本社会の「善悪の判断基準」を考える
どんな理由があれ、法を犯した者は罰せられるべきだと思っている。しかしそれは、善悪の判断とは関係ない。映画『万引き家族』(是枝裕和監督)から、「国民の気分」によって「善悪」が決まる社会の是非と、「善悪の判断を保留する勇気」を持つ生き方について考える
あわせて読みたい
【誤解】世界的大ベストセラー『ファクトフルネス』の要約。我々は「嘘の情報」を信じ込みやすい
世界の現状に関する13の質問に対して、ほとんどの人が同じ解答をする。最初の12問は不正解で、最後の1問だけ正答するのだ。世界的大ベストセラー『ファクトフルネス』から、「誤った世界の捉え方」を認識し、情報を受け取る際の「思い込み」を払拭する。「嘘の情報」に踊らされないために読んでおくべき1冊だ
あわせて読みたい
【知的】文系にオススメの、科学・数学・哲学の入門書。高橋昌一郎の「限界シリーズ」は超絶面白い:『…
例えば「科学」だけに限ってみても、「なんでもできる」わけでは決してない。「科学」に限らず、私たちが対峙する様々な事柄には「これ以上は不可能・無理」という「限界」が必ず存在する。高橋昌一郎の「限界シリーズ」から、我々が認識しておくべき「限界」を易しく学ぶ
あわせて読みたい
【感想】飲茶の超面白い東洋哲学入門書。「本書を読んでも東洋哲学は分からない」と言う著者は何を語る…
東洋哲学というのは、「最終回しか存在しない連続ドラマ」のようなものだそうだ。西洋哲学と比較にならないほど異質さと、インド哲学・中国哲学など個別の思想を恐ろしく分かりやすく描く『史上最強の哲学入門 東洋の哲人たち』は、ページをめくる手が止まらないくらい、史上最強レベルに面白かった
あわせて読みたい
【興奮】飲茶氏の超面白い哲学小説。「正義とは?」の意味を問う”3人の女子高生”の主張とは?:『正義の…
なんて面白いんだろうか。哲学・科学を初心者にも分かりやすく伝える飲茶氏による『正義の教室』は、哲学書でありながら、3人の女子高生が登場する小説でもある。「直観主義」「功利主義」「自由主義」という「正義論」の主張を、「高校の問題について議論する生徒会の話し合い」から学ぶ
あわせて読みたい
【天才】読書猿のおすすめ本。「いかにアイデアを生むか」の発想法を人文書に昇華させた斬新な1冊:『ア…
「独学の達人」「博覧強記の読書家」などと評される読書猿氏が、古今東西さまざまな「発想法」を1冊にまとめた『アイデア大全』は、ただのHow To本ではない。「発想法」を学問として捉え、誕生した経緯やその背景なども深堀りする、「人文書」としての一面も持つ作品だ
あわせて読みたい
【人生】「資本主義の限界を埋める存在としての『贈与論』」から「不合理」に気づくための生き方を知る…
「贈与論」は簡単には理解できないが、一方で、「何かを受け取ったら、与えてくれた人に返す」という「交換」の論理では対処できない現実に対峙する力ともなる。『世界は贈与でできている』から「贈与」的な見方を理解し、「受取人の想像力」を立ち上げる
あわせて読みたい
【興奮】飲茶氏が西洋哲学を語る。難解な思想が「グラップラー刃牙成分」の追加で驚異的な面白さに:『…
名前は聞いたことはあるがカントやニーチェがどんな主張をしたのかは分からないという方は多いだろう。私も無知なまったくの初心者だが、そんな人でも超絶分かりやすく超絶面白く西洋哲学を”分かった気になれる”飲茶『史上最強の哲学入門』は、入門書として最強
あわせて読みたい
【狂気】「当たり前の日常」は全然当たり前じゃない。記憶が喪われる中で”日常”を生きることのリアル:…
私たちは普段、「記憶が当たり前に継続していること」に疑問も驚きも感じないが、「短期記憶を継続できない」という記憶障害を抱える登場人物の日常を描き出す『静かな雨』は、「記憶こそが日常を生み出している」と突きつけ、「当たり前の日常は当たり前じゃない」と示唆する
あわせて読みたい
【実像】ベートーヴェンの「有名なエピソード」をほぼ一人で捏造・創作した天才プロデューサーの実像:…
ベートーヴェンと言えば、誰もが知っている「運命」を始め、天才音楽家として音楽史に名を刻む人物だが、彼について良く知られたエピソードのほとんどは実は捏造かもしれない。『ベートーヴェン捏造 名プロデューサーは嘘をつく』が描く、シンドラーという”天才”の実像
あわせて読みたい
【権威】心理学の衝撃実験をテレビ番組の収録で実践。「自分は残虐ではない」と思う人ほど知るべき:『…
フランスのテレビ局が行った「現代版ミルグラム実験」の詳細が語られる『死のテレビ実験 人はそこまで服従するのか』は、「権威」を感じる対象から命じられれば誰もが残虐な行為をしてしまい得ることを示す。全人類必読の「過ちを事前に回避する」ための知見を学ぶ
あわせて読みたい
【平易】ブラックホールを分かりやすく知りたい。難しいことは抜きにふわっと理解するための1冊:『ブラ…
2019年に初めて直接観測されるも、未だに謎多き天体である「ブラックホール」について現役研究者が分かりやすく語る『ブラックホールをのぞいてみたら』をベースに、科学者がその存在を認めてこなかった歴史や、どんな性質を持つ天体なのかを理解する
あわせて読みたい
【限界】「科学とは何か?」を知るためのおすすめ本。科学が苦手な人こそ読んでほしい易しい1冊:『哲学…
「科学的に正しい」という言葉は、一体何を意味しているのだろう?科学者が「絶対に正しい」とか「100%間違っている」という言い方をしないのは何故だろう?飲茶『哲学的な何か、あと科学とか』から、「科学とはどんな営みなのか?」について考える
あわせて読みたい
【戸惑】人間の脳は摩訶不思議。意識ではコントロールできない「無意識の領域」に支配されている:『あ…
我々は決断や選択を「自分の意思」で行っていると感じるが、脳科学の研究はそれを否定している。我々に「自由意志」などない。「脳」の大部分は「意識以外のもの」に支配され、そこに「意識」はアクセスできないという驚愕の実態を『あなたの知らない脳』から学ぶ
あわせて読みたい
【貢献】有名な科学者は、どんな派手な失敗をしてきたか?失敗が失敗でなかったアインシュタインも登場…
どれほど偉大な科学者であっても失敗を避けることはできないが、「単なる失敗」で終わることはない。誤った考え方や主張が、プラスの効果をもたらすこともあるのだ。『偉大なる失敗』から、天才科学者の「失敗」と、その意外な「貢献」を知る
あわせて読みたい
【限界】有名な「錯覚映像」で心理学界をザワつかせた著者らが語る「人間はいかに間違えるか」:『錯覚…
私たちは、知覚や記憶を頼りに社会を生きている。しかしその「知覚」「記憶」は、本当に信頼できるのだろうか?心理学の世界に衝撃を与えた実験を考案した著者らの『錯覚の科学』から、「避けられない失敗のクセ」を理解する
あわせて読みたい
【誤り】「信じたいものを信じる」のは正しい?映画『星の子』から「信じること」の難しさを考える
どんな病気も治す「奇跡の水」の存在を私は信じないが、しかし何故「信じない」と言えるのか?「奇跡の水を信じる人」を軽々に非難すべきではないと私は考えているが、それは何故か?映画『星の子』から、「何かを信じること」の難しさについて知る
あわせて読みたい
【幻想】心の傷を癒やすことの”難しさ”、寄り添い続けるために必要な”弱さ”と”冷たさ”:映画『心の傷を…
「優しいかどうか」が重要な要素として語られる場面が多いと感じるが、私は「優しさ」そのものにはさしたる意味はないと考えている。映画『心の傷を癒すということ 劇場版』から、「献身」と「優しさ」の違いと、誰かに寄り添うために必要な「弱さ」を理解する
あわせて読みたい
【衝撃】壮絶な戦争映画。最愛の娘を「産んで後悔している」と呟く母らは、正義のために戦場に留まる:…
こんな映画、二度と存在し得ないのではないかと感じるほど衝撃を受けた『娘は戦場で生まれた』。母であり革命家でもあるジャーナリストは、爆撃の続くシリアの街を記録し続け、同じ街で娘を産み育てた。「知らなかった」で済ませていい現実じゃない。
あわせて読みたい
【感想】世の中と足並みがそろわないのは「正常が異常」だから?自分の「正常」を守るために:『コンビ…
30代になっても未婚でコンビニアルバイトの古倉さんは、普通から外れたおかしな人、と見られてしまいます。しかし、本当でしょうか?『コンビニ人間』をベースに、多数派の人たちの方が人生を自ら選択していないのではないかと指摘する。
あわせて読みたい
【葛藤】部活で後悔しないために。今やりたいことをやりきって、過去を振り返らないための全力:『風に…
勉強の方が、部活動より重要な理由なんて無い。どれだけ止められても「全力で打ち込みたい」という気持ちを抑えきれないものに出会える人生の方が、これからの激動の未来を生き延びられるはずと信じて突き進んでほしい。部活小説『風に恋う』をベースに書いていく
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
進化・生命・脳【本・映画の感想】 | ルシルナ
人類は、我々自身を理解するための知見を積み重ねてきました。生物の進化の過程、生命を司るDNAの働きや突然変異、高い知能を持つ人間の脳の仕組みや不思議など、面白い話…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…


















































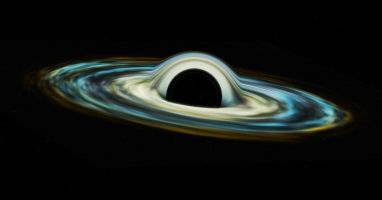


















コメント