目次
はじめに
この記事で取り上げる本
楽天ブックス
¥759 (2021/11/30 06:18時点 | 楽天市場調べ)
 ポチップ
ポチップ
この本をガイドにしながら記事を書いていきます
この記事の3つの要点
- 子どもの頃、私は勉強するのは好きだったが、決して純粋な動機からではなかった
- 大人になるほど、「学び」からますます遠ざかってしまう
- 問題さえ見つければ、解くことなど誰にだってできる
子どもの頃に、この小説で描かれるような発想を少しでも教えてほしかったなと感じました
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!「文章の書き方が分からない」「文章力がないから鍛えたい」という方にオススメ…
「文章の書き方」についてのKindle本を出版しました。「文章が書けない」「どう書いたらいいか分からない」「文章力を向上させたい」という方の悩みを解消できるような本に仕上げたつもりです。数多くの文章を書き、さらに頼まれて文章を推敲してきた経験を踏まえ、「文章を書けるようになるにはどうしたらいいか」についての私なりの考えをまとめました。
あわせて読みたい
【私が読了済のもののみ】森博嗣のおすすめ小説・エッセイ【随時更新】
この記事では、森博嗣のおすすめ小説をまとめました。私の一推しは『すべてがFになる』です。是非本選びの参考にして下さい。
学生時代には理解できていなかった「学ぶことの本質」と「学ぶ」ためにすべきこと」を、森博嗣『喜嶋先生の静かな世界』から知る
大人になると「学ぶ」ことから一層遠ざかってしまう
この記事では、「学びとは何か?」という本質的な部分の話を展開していくのだが、しばらくの間、「学び」=「お勉強」のようなイメージで受け取ってほしい。つまり、「知識を得る行為」というわけだ。実際には、「学びとはお勉強のことではない」と示すのがこの記事の本来の目的なのだが、当面は一般的なイメージで「学び」という言葉を使う。

大人になるとそもそも、「学ぶという行為」をしなくなってしまう。仕事に必要な資格の勉強をしたり、スキルアップや転職のためにTOEIC・プログラミングを学んだりすることはあるかもしれない。しかしそれらは、「働く上で必要だから」という理由であって、「何かを知る・理解する」という目的ではないことの方がほとんどだろう。
大人になるほど、「学び」から遠ざかってしまうというわけだ。
確かに、様々な理由から「仕事」に軸足を置くことになっていくので、「学び」のための時間を確保するのが難しくなるだろう。しかしそれだけではなく、「学び」のための「好奇心」が無いということも大きいと思う。
あわせて読みたい
【情熱】常識を疑え。人間の”狂気”こそが、想像し得ない偉業を成し遂げるための原動力だ:映画『博士と…
世界最高峰の辞書である『オックスフォード英語大辞典』は、「学位を持たない独学者」と「殺人犯」のタッグが生みだした。出会うはずのない2人の「狂人」が邂逅したことで成し遂げられた偉業と、「狂気」からしか「偉業」が生まれない現実を、映画『博士と狂人』から学ぶ
では、学生時代はどうだったか。
もちろん、勉強が嫌いだったという人もたくさんいるだろうし、そういう人からすれば、学生時代からずっと「学び」の動機なんかなかった、という感じだろうと思う。しかし中には、勉強するのが好きだった人、あるいは好きとまではいかないけど決して嫌いではなかった人もいるはずだ。
私も、割とそっちのタイプである。勉強するのが、結構好きだった。
「夏休みの宿題を夏休み前に終わらせ、夏休み中ずっと勉強している」ような子どもだったと書けば、どのぐらい好きだったのか伝わるだろうか。子どもの頃は自分の部屋がなく、「『勉強する人だけが使える部屋』にずっといたかった」という環境的な要因もあったのだが、勉強するのが好きだったことも確かである。
ただ、子どもの頃のことを振り返ると、もう少しちゃんとした動機で勉強していれば良かったと後悔してしまう。
あわせて読みたい
【社会】学生が勉強しないのは、若者が働かないのは何故か?教育現場からの悲鳴と知見を内田樹が解説:…
教育現場では、「子どもたちが学びから逃走する」「学ばないことを誇らしく思う」という、それまでには考えられなかった振る舞いが目立っている。内田樹は『下流志向』の中で、その原因を「等価交換」だと指摘。「学ばないための努力をする」という発想の根幹にある理屈を解き明かす
「知らなかったことを知れる」とか「難しい計算が解ける」など、勉強そのものに対する楽しさも確かに感じていた。しかしその一方で、「友達を作ること」も私が勉強を熱心にしていた大きな理由の1つだったのだ。
私は、今でもそうなのだが、自分から話しかけて他人とコミュニケーションを始めるのが得意ではない。話しかけられれば誰とでも話せるし仲良くなれる自信は割とあるのだが、自分から関わるのが苦手なのだ。
だから学生時代はずっと、「勉強を教える人」というキャラクターのみで乗り切っていたと言っていい。
私がそこそこ以上に勉強ができることは知られており、また結果的に誰かに何かを教えることも得意だったので、「勉強を教えてほしいと思っている人」が話しかけてくれた。大学に入るまでの私は、すべての人間関係をそれ一本で乗り切っていた記憶がある。そして、いつ「勉強を教えてほしい」と言われても正しく対応できるように常に勉強を欠かさない、というのが、私が勉強に勤しんでいた大きな理由の1つだったと言っていい。
あわせて読みたい
【誤解】「意味のない科学研究」にはこんな価値がある。高校生向けの講演から”科学の本質”を知る:『す…
科学研究に対して、「それは何の役に立つんですか?」と問うことは根本的に間違っている。そのことを、「携帯電話」と「東急ハンズの棚」の例を使って著者は力説する。『すごい実験』は素粒子物理学を超易しく解説する本だが、科学への関心を抱かせてもくれる
だからこそ大学入学以降は、それまで持っていたような熱心さでは勉強ができなくなってしまった。大学ではどうも、「勉強を教えること」がコミュニケーション上の利点にはならないと気づいたからだ。もちろん、自分の成績を維持する程度の勉強はしていたが、ずっと勉強し続けていた高校時代までの熱量みたいなものは、大学に入ってから消えてしまった。
もう少し「学び」のための動機を探し求めておくべきだったと思う。
今でも、ノンフィクション本を読んだり、ドキュメンタリー映画を観たりして、自分が知らない世界や知識について知りたいと思っているし、そういう事柄への関心は強く持っている。「学び」と言えば学びかもしれない。
しかし、この小説を読んで、「既存の知識を知ることは『学び』ではない」と理解した。「学び」の本質はそこにはない。だから結局、ノンフィクション本を読んでいようが、ドキュメンタリー映画を観ていようが、私がしていることは「学び」ではないということになる。
あわせて読みたい
【感想】世の中と足並みがそろわないのは「正常が異常」だから?自分の「正常」を守るために:『コンビ…
30代になっても未婚でコンビニアルバイトの古倉さんは、普通から外れたおかしな人、と見られてしまいます。しかし、本当でしょうか?『コンビニ人間』をベースに、多数派の人たちの方が人生を自ら選択していないのではないかと指摘する。
では、「学び」とは一体なんだろうか?
「問題を解くこと」は「学び」ではない
この小説は、普通にエンターテインメントとして楽しめる作品なのだが、一方で、「学び」とは何なのかを理解させてくれる作品でもある。

既にあるものを知ることも、理解することも、研究ではない。研究とは、今はないものを知ること、理解することだ。それを実現するための手がかりは、自分の発想しかない
あわせて読みたい
【無謀】園子温が役者のワークショップと同時並行で撮影した映画『エッシャー通りの赤いポスト』の”狂気”
「園子温の最新作」としか知らずに観に行った映画『エッシャー通りの赤いポスト』は、「ワークショップ参加者」を「役者」に仕立て、ワークショップと同時並行で撮影されたという異次元の作品だった。なかなか経験できないだろう、「0が1になる瞬間」を味わえる“狂気”の映画
この作品では研究者が主人公であり、その視点で物語が展開するので、「研究とは何か」がテーマとなる。しかしこれは決して研究者だけに関わる話ではない。「何かを学ぼうとするすべての人」に対して、「学びとは何か」を示唆する発想とも言える。
そしてその要点こそが、「今はないものを知ること」というわけだ。
そういう意味では、数学の問題を解くことは、極めて昆虫的だった。あれは考えているというよりは、おびき寄せられていただけなのだ。
問題を解くことも、既存の知識を知ることも、「学び」の本質ではないのだ。
あわせて読みたい
【奇跡】ホンダジェット驚愕の開発秘話。航空機未経験のホンダが革命的なアイデアで常識を打ち破る:『…
自動車メーカーの本田技研工業が開発した「ホンダジェット」は、航空機への夢を抱いていた創業者・本田宗一郎のスピリットを持ち続ける会社だからこそ実現できた。『ホンダジェット 開発リーダーが語る30年の全軌跡』からその革命的な技術開発と運用までのドラマを知る
そういう意味で、学校の勉強というのはすべて「学び」ではないと言える。
これは、すべてのことにいえると思う。小学校から高校、そして大学の三年生まで、とにかく、課題というのは常に与えられた。僕たちは目の前にあるものに取り組めば良かった。そのときには、気づかなかったけれど、それは本当に簡単なことなのだ。テーブルに並んだ料理を食べるくらい簡単だ。
もちろん、学校の勉強が無駄というわけでは決してない。それは、「スタートラインに立つ」という行為なのである。「今はないものを知る」ためには、「今どこまで分かっているのか」を知らなければならない。学校の勉強では、その作業をしていると言っていい。

そうやって調べることで、何を研究すれば良いのか、ということがわかるだけだ。本や資料に書かれていることは、誰かが考えたことで、それを知ることで、人間の知恵が及んだ限界点が見える。そこが、つまり研究のスタートラインだ。文献を調べ尽くすことで、やっとスタートラインに立てる。問題は、そこから自分の力で、どこへ進むのかだ。
あわせて読みたい
【貢献】飛行機を「安全な乗り物」に決定づけたMr.トルネードこと天才気象学者・藤田哲也の生涯:『Mr….
つい数十年前まで、飛行機は「死の乗り物」だったが、天才気象学者・藤田哲也のお陰で世界の空は安全になった。今では、自動車よりも飛行機の方が死亡事故の少ない乗り物なのだ。『Mr.トルネード 藤田哲也 世界の空を救った男』から、その激動の研究人生を知る
教師なり親なりがどこかの時点でこの事実を教えてくれたら良かったのに、と大人になった今振り返ってみて感じる。もちろん、そう言われたところで理解できたかどうかは分からないが、少なくとも、自分の内側からは出てこないだろう発想に触れることはできたはずだ。
もしそういう考えに触れて「学ぶこと」の捉え方が変わっていたら、今とは少し違う人生を歩んでいた、かもしれない。
もちろん「何かを学ぶ」という意味では、今からだって全然遅くはない。自由に学びたいことを学べばいいだけだ。しかし、「学び」の本質をもし学生時代に理解できていたら、仕事や生き方にも影響があったかもしれないと思うと、やはりその点は少し悔やまれる。
あわせて読みたい
【異端】子育ては「期待しない」「普通から外れさせる」が大事。”劇薬”のような父親の教育論:『オーマ…
どんな親でも、子どもを幸せにしてあげたい、と考えるでしょう。しかしそのために、過保護になりすぎてしまっている、ということもあるかもしれません。『オーマイ・ゴッドファーザー』をベースに、子どもを豊かに、力強く生きさせるための”劇薬”を学ぶ
最も重要なことは、「問題を見つけること」
最近、「今日は答えがほしくて」「答えを持ったらそこで終わり。問いを持ったらそこが始まり」と尾野真千子が言っているCMを見かける。そしてそのCMを見る度に、あぁそうだよなぁと思う。
本書にも、こんなセリフがある。
問題さえ見つければ、もうあとは解決するだけだ。そんなことは誰にだってできる
学生時代は問題を解くことが楽しかったのでそればかりに目がいってしまっていた。しかし学校で出される問題には必ず「答え」があるわけで、つまり「既に誰かがたどり着いている知見」でしかない、ということになる。それを理解することももちろん大事だが、しかし「問題を解く」という行為は結局、誰かが歩いた道を後追いしているだけに過ぎない。
あわせて読みたい
【限界】「科学とは何か?」を知るためのおすすめ本。科学が苦手な人こそ読んでほしい易しい1冊:『哲学…
「科学的に正しい」という言葉は、一体何を意味しているのだろう?科学者が「絶対に正しい」とか「100%間違っている」という言い方をしないのは何故だろう?飲茶『哲学的な何か、あと科学とか』から、「科学とはどんな営みなのか?」について考える
より重要なことは、「問題を見つけること」だ。
研究者が一番頭を使って考えるのは、自分に相応しい問題だ。自分にしか解けないような素敵な問題をいつも探している。不思議なことはないか、解決すべき問題はないか、という研究テーマを決めるまでが、最も大変な作業で、ここまでが山でいったら、上り坂になる。結局のところこれは、山を登りながら山を作っているようなもの。滑り台の階段を駆け上がるときのように、そのあとに待っている爽快感のために、とにかく高く登りたい、長く速く滑りたい、そんな夢を抱いて、どんどん山を高く作って、そこへ登っていくのだ。
少し「学び」そのものから外れた話をするが、私は20代の頃、パズルを作るのにハマっていたことがある。イメージとしては「ナンプレ(数独)」のようなものだ。自分でオリジナルのルールを設定し、それを元にしたパズルをいくつも作っていた。
あわせて読みたい
【生きろ】「どう生き延びるか」と覚悟を決める考え方。西原理恵子が語る「カネ」だけじゃない人生訓:…
西原理恵子『この世でいちばん大事な「カネ」の話』は、決して「お金」の話だけではありません。「自分が望む生き方」を実現するための「闘い方」を伝授してくれると同時に、「しなくていい失敗を回避する考え方」も提示してくれます。学校や家庭ではなかなか学べない人生訓

オリジナルのルールを自分で決めているので、そもそも「そのパズルを完成させられるかどうか」から分からない。自分が設定したルールでパズルを作り出せる保証などないということだ。さらに先例がないので、「このようなルールのパズルがあったら、どんな風に解いていくだろう」と解く人の思考を想像し、それを踏まえながらヒントを配置しなければならない。
そしてこれは、パズルを解くことよりも圧倒的に面白い、と感じた。
パズルを解くのは、「誰かの思考をトレースしていく」ようなものだ。もちろんそれも面白い。とんでもない発想の展開に驚かされることもあるし、解き終わった後に「なるほど。ここでこうなるから、あそこであのヒントが必要だったのか」とカタルシスを得られたりもする。
しかしやはり、自分が作る側の方がより楽しい。まったく何もないキャンバスに自分で足跡をつけていくこと、誰の何の思考も存在しないステージに自分の発想力だけで何かの形を生み出していくことには、解くのとは全然違う快感がある。
あわせて読みたい
【感想】映画『君が世界のはじまり』は、「伝わらない」「分かったフリをしたくない」の感情が濃密
「キラキラした青春学園モノ」かと思っていた映画『君が世界のはじまり』は、「そこはかとない鬱屈」に覆われた、とても私好みの映画だった。自分の決断だけではどうにもならない「現実」を前に、様々な葛藤渦巻く若者たちの「諦念」を丁寧に描き出す素晴らしい物語
学問もそれと同じなのだろうなと思う。いかにして問題を見つけるかが「学び」の本質であり、それこそが最も難しいことなのだ。
また、「問題を解くこと」は、「別の問題を発見するためのステップ」でしかない。
「この問題が解決したら、どうなるんですか?」
「もう少しむずかしい問題が把握できる」
こんなことは、研究者であれば当たり前のように理解しているのだろうが、「学び」に足を踏み入れる小中高時代に、その一端でも感じさせてほしかったとも思う。
あわせて読みたい
【奇跡】鈴木敏夫が2人の天才、高畑勲と宮崎駿を語る。ジブリの誕生から驚きの創作秘話まで:『天才の思…
徳間書店から成り行きでジブリ入りすることになったプロデューサー・鈴木敏夫が、宮崎駿・高畑勲という2人の天才と共に作り上げたジブリ作品とその背景を語り尽くす『天才の思考 高畑勲と宮崎駿』。日本のアニメ界のトップランナーたちの軌跡の奇跡を知る
主人公は「学びの本質」を早々と理解していた
本書の主人公である橋場は、子どもの頃からこの「学びの本質」を鋭く理解していた。
小さかった僕は、それを神様のご褒美だと考えた。つまり、考えて考えて考え抜いたことに対して、神様が褒めてくれる、そのプレゼントが「閃き」というものなのだと信じた。
あわせて読みたい
【おすすめ】「天才」を描くのは難しい。そんな無謀な挑戦を成し遂げた天才・野崎まどの『know』はヤバい
「物語で『天才』を描くこと」は非常に難しい。「理解できない」と「理解できる」を絶妙なバランスで成り立たせる必要があるからだ。そんな難題を高いレベルでクリアしている野崎まど『know』は、異次元の小説である。世界を一変させた天才を描き、「天才が見ている世界」を垣間見せてくれる
幼い頃から図書館で様々な本を読み、本を通じて知らなかった世界と出会い、子どもながらに思索に耽っていた橋場にとっては、「学ぶこと」はファンタスティックな経験だった。

しかし学校では、そんな感動を得られない。自分で考えて何かを見出すのではなく、既に知られていることをただ理解するだけの行為でしかないからだ。
学校で学ぶのは、本を読めば誰だって知ることができることばかり。大学に入りさえすればと期待したが、大学にしたところで専門課程に進むまでは似たようなものだ。
そんな橋場はようやく、奇跡的な出会いを果たすことになる。大学に、喜嶋先生がいたのだ。この出会いがなければ橋場は、その能力を持て余したまま絶望し、研究者としての道を進むこともなかっただろう。
あわせて読みたい
【教育】映画化に『3月のライオン』のモデルと話題の村山聖。その師匠である森信雄が語る「育て方」論:…
自身は決して強い棋士ではないが、棋界で最も多くの弟子を育てた森信雄。「村山聖の師匠」として有名な彼の「師匠としてのあり方」を描く『一門 ”冴えん師匠”がなぜ強い棋士を育てられたのか?』から、教育することの難しさと、その秘訣を学ぶ
喜嶋先生は、教授でも准教授でもなく助手という立場に過ぎなかったが、世界的な研究者として学内でも一目置かれる存在だった。助手であるが故に、正式な研究室は持てない身分ではあるのだが、橋場は実質的に「喜嶋研」と呼んでいい環境の中で、充実した研究生活を過ごすことになる。
本書は、そんな橋場を描く物語だ。橋場の葛藤や熱意を通じて、研究者ではない人間にも「学びの本質」を体感させてくれる作品である。
そして橋場の人生を通じて読者は、「自分はどんな方程式の解なのか」という問いについても考えさせられることだろう。
例えば棋士の藤井聡太は「将棋」という方程式を見つけた。つまり、「『藤井聡太の人生』は『将棋という方程式』の解なのだ」と自ら見出したということだ。
あわせて読みたい
【改革】AIは将棋をどう変えた?羽生善治・渡辺明ら11人の現役棋士が語る将棋の未来:『不屈の棋士』(…
既に将棋AIの実力はプロ棋士を越えたとも言われる。しかし、「棋力が強いかどうか」だけでは将棋AIの良し悪しは判断できない。11人の現役棋士が登場する『不屈の棋士』をベースに、「AIは将棋界をどう変えたのか?」について語る
このように、「自分の人生は、一体どんな方程式の解なのだろうか」という問いに答えを出せる人生は素敵だ。しかし、すべての人がそんな風に生きられるわけではない。
この小説には、「大学院生の自殺率が高い」という記述が出てくる。実際のところどうなのか、具体的な事実は知らないが、恐らくその通りなのだろうと思う。そしてそれは、「研究者の道こそ自分が属すべき方程式だ」と思い定めて飛び込んだものの、正しい理解ではなかったということかもしれない。
「学び」において「問題を見つけること」は大事だが、それは人生においても同じと言っていいだろう。自分がどんな方程式の解として生まれたのかを見定められれば、良い人生を歩める可能性は高い。しかしそれが分からない、あるいは見誤ってしまい、適切ではない人生を歩まざるを得ない人もいるだろう。
あわせて読みたい
【おすすめ】カンヌ映画『PERFECT DAYS』は、ほぼ喋らない役所広司の沈黙が心地よい(ヴィム・ヴェンダ…
役所広司主演映画『PERFECT DAYS』(ヴィム・ヴェンダース監督)は、主人公・平山の「沈黙」がとにかく雄弁な物語である。渋谷区のトイレの清掃員である無口な平山の、世間とほとんど繋がりを持たない隔絶した日常が、色んなものを抱えた者たちを引き寄せ、穏やかさで満たしていく様が素晴らしい
別に「人にはそれぞれ定められた方程式があり、そこから外れた生き方は不正解だ」などと言いたいわけではない。どんな人生を歩んだって自由だ。しかし、「この人は神から祝福されているのか」と感じるほど何かの才能に恵まれる人もいる一方で、中には何をやっても上手くいかないという実感しか残らないという人もいるだろう。そういう時にこの、「自分はどんな方程式の解なのか」という考え方は有効だと思うし、人生をまた違った形で捉えるきっかけにもなるとも思う。
つまり、学問も人生そのものも、「問題を解く」という発想から一度抜け出した方がいい、ということだろう。
ハッとさせられる思考の数々
この記事では、この小説で描かれる「学びの本質」に焦点を当てたが、本書にはそれに留まらず、多様な事柄に関する思いがけない思考が様々に繰り広げられるのでその点も興味深い。

あわせて読みたい
【感想】映画『正欲』に超共感。多様性の時代でさえどこに行っても馴染めない者たちの業苦を抉る(出演…
映画『正欲』は、私には共感しかない作品だ。特に、新垣結衣演じる桐生夏月と磯村勇斗演じる佐々木佳道が抱える葛藤や息苦しさは私の内側にあるものと同じで、その描かれ方に圧倒されてしまった。「『多様性』には『理解』も『受け入れ』も不要で、単に否定しなければ十分」なのだと改めて思う
たとえば、こんな言葉はどうだろう。
良い経験になった、という言葉で、人はなんでも肯定してしまうけれど、人間って、経験するために生きているのだろうか。今、僕がやっていることは、ただ経験すれば良いだけのものなんだろうか。
森博嗣の作品はどれもそういう傾向があるが、私たちが当たり前のように考えあまり疑問を抱かない事柄について、ハッとさせられる考えが提示される。私たちが触れている「社会」や「人間関係」が、実に曖昧模糊としたもので出来上がっているのだということを実感させてくれる思索が多い。
普通の人間は、言葉の内容なんかそっちのけで、言葉に現れる感情を読み取ろうとする。社会ではそれが常識みたいだ。そうそう、犬がそうだよ。犬は、人の言葉の意味を理解しているんじゃない。その人が好意を持っているか敵意を持っているかを読み取る。それと同じだね。特に日本の社会は、言葉よりも態度を重んじる傾向が強い。心が籠っていない、なんて言うだろう? 何だろうね、心の籠った言葉っていうのは
あわせて読みたい
【実話】「更生」とは何かを考えさせられる、演劇『ゴドーを待ちながら』を組み込んだ映画『アプローズ…
売れない舞台役者が、刑務所内で囚人に戯曲『ゴドーを待ちながら』の演技指導を行う映画『アプローズ、アプローズ!』は、その衝撃的なラストが実に印象的だ。しかもこのラストの展開は、実話を基にしている。喝采(アプローズ)を浴びる囚人たちの姿から、「更生」についても考えさせられる作品
私もどちらかと言えば、「態度」より「言葉」の方を重視する傾向があるので、この意見には賛同できてしまう。出来れば発した「言葉」で判断してほしいのだけど、どうもそうではない要素が重視され、「言葉」の通りには主張が通らないことも多い。もちろん私は、そんな社会にもそれなりに溶け込んでいると思うし、そこまでの不都合を感じるわけではないが、本質的には喜嶋先生の感覚に近い。
そしてそのような、人間社会の不可思議さについて、総じてこんな言い方をしている。
なにかの本で読んで、人間ならばそうするべきだ、というルールを学んだのかもしれないけれど、残念ながら、物理法則のように普遍的なものではない。同様のことは、宗教や哲学や、とにかく人間が作ったこの世の大多数のものにいえる。ようするに、ここから世界が築かれるという根拠に位置する基本法則がないのだ。ただなんとなく、そっちの方が良いかな、という程度の判断の積み重ねだけで、この世のすべてのルールが出来上がっているように思える
最近ではあまり無くなったが、子どもの頃や若い頃は特に、「今この場におけるルールがイマイチ理解できない」と感じることはよくあった。それでいて、その場にいる他の人には、その場を支配するルールが理解できているようなのだ。すごく不思議な感覚だった。みんなは一体いつ、この場のルールについての認識を統一したのだろうか? と思わされてしまう。
あわせて読みたい
【驚嘆】「現在は森でキノコ狩り」と噂の天才”変人”数学者グリゴリー・ペレルマンの「ポアンカレ予想証…
数学界の超難問ポアンカレ予想を解決したが、100万ドルの賞金を断り、フィールズ賞(ノーベル賞級の栄誉)も辞退、現在は「森できのこ採取」と噂の天才数学者グリゴリー・ペレルマンの生涯を描く評伝『完全なる証明』。数学に関する記述はほぼなく、ソ連で生まれ育った1人の「ギフテッド」の苦悩に満ちた人生を丁寧に描き出す1冊
「暗黙の了解」「阿吽の呼吸」など、明文化されないルールをみんなが瞬時に読み取って自分の言動に反映させるのだろうが、そういう現実への納得のいかなさとか不合理さみたいなものを感じてしまうことは結構あるし、同感だという方もいるだろう。
読む人によって引っかかるポイントは様々に違うだろうが、そんな風に「普段あまり意識は向かないが、言われてみれば確かにそうだと感じるような思考」が詰まっている。当たり前だと感じていた前提がスルッと覆るような感覚になるという点でも楽しめる作品だ。

そういう意味で、本書で展開される「清水スピカと橋場との会話」は非常に面白い。お互いが寄って立つ前提条件が違いすぎるが故に会話がまったく噛み合わず、相手に届けようと思ってお互いに真剣に投げているボールが、まったく明後日の方向に飛んでいくのだ。この会話はまさに、私たちが「曖昧な前提」をいかに「共有した気になっている」かを自覚させてくれるものであり、面白おかしくそのことを実感させてくれる。
あわせて読みたい
【前進】誰とも価値観が合わない…。「普通」「当たり前」の中で生きることの難しさと踏み出し方:『出会…
生きていると、「常識的な考え方」に囚われたり、「普通」「当たり前」を無自覚で強要してくる人に出会ったりします。そういう価値観に合わせられない時、自分が間違っている、劣っていると感じがちですが、そういう中で一歩踏み出す勇気を得るための考え方です
著:森博嗣
¥759 (2022/01/29 20:55時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品読了済】私が読んできた小説を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が読んできた小説を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本選びの参考にして下さい。
最後に
森博嗣の作品は、それが小説であってもエッセイであっても、「当たり前」とか「普通」みたいなものを軽々と飛び越える思索が展開されることが多く、いつも大いに刺激を受ける。様々な作品があり、好みは分かれると思うが、是非いくつか手にとってみて、「普段考えないような思考領域」へ連れ去られる感覚を楽しんでみてほしいと思う。
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!「文章の書き方が分からない」「文章力がないから鍛えたい」という方にオススメ…
「文章の書き方」についてのKindle本を出版しました。「文章が書けない」「どう書いたらいいか分からない」「文章力を向上させたい」という方の悩みを解消できるような本に仕上げたつもりです。数多くの文章を書き、さらに頼まれて文章を推敲してきた経験を踏まえ、「文章を書けるようになるにはどうしたらいいか」についての私なりの考えをまとめました。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【実話】さかなクンの若い頃を描く映画『さかなのこ』(沖田修一)は子育ての悩みを吹き飛ばす快作(主…
映画『さかなのこ』は、兎にも角にものん(能年玲奈)を主演に据えたことが圧倒的に正解すぎる作品でした。性別が違うのに、「さかなクンを演じられるのはのんしかいない!」と感じさせるほどのハマり役で、この配役を考えた人は天才だと思います。「母親からの全肯定」を濃密に描き出す、子どもと関わるすべての人に観てほしい作品です
あわせて読みたい
【おすすめ】カンヌ映画『PERFECT DAYS』は、ほぼ喋らない役所広司の沈黙が心地よい(ヴィム・ヴェンダ…
役所広司主演映画『PERFECT DAYS』(ヴィム・ヴェンダース監督)は、主人公・平山の「沈黙」がとにかく雄弁な物語である。渋谷区のトイレの清掃員である無口な平山の、世間とほとんど繋がりを持たない隔絶した日常が、色んなものを抱えた者たちを引き寄せ、穏やかさで満たしていく様が素晴らしい
あわせて読みたい
【感想】映画『正欲』に超共感。多様性の時代でさえどこに行っても馴染めない者たちの業苦を抉る(出演…
映画『正欲』は、私には共感しかない作品だ。特に、新垣結衣演じる桐生夏月と磯村勇斗演じる佐々木佳道が抱える葛藤や息苦しさは私の内側にあるものと同じで、その描かれ方に圧倒されてしまった。「『多様性』には『理解』も『受け入れ』も不要で、単に否定しなければ十分」なのだと改めて思う
あわせて読みたい
【映画】『キャスティング・ディレクター』の歴史を作り、ハリウッド映画俳優の運命を変えた女性の奮闘
映画『キャスティング・ディレクター』は、ハリウッドで伝説とされるマリオン・ドハティを描き出すドキュメンタリー。「神業」「芸術」とも評される配役を行ってきたにも拘わらず、長く評価されずにいた彼女の不遇の歴史や、再び「キャスティングの暗黒期」に入ってしまった現在のハリウッドなどを切り取っていく
あわせて読みたい
【実話】「更生」とは何かを考えさせられる、演劇『ゴドーを待ちながら』を組み込んだ映画『アプローズ…
売れない舞台役者が、刑務所内で囚人に戯曲『ゴドーを待ちながら』の演技指導を行う映画『アプローズ、アプローズ!』は、その衝撃的なラストが実に印象的だ。しかもこのラストの展開は、実話を基にしている。喝采(アプローズ)を浴びる囚人たちの姿から、「更生」についても考えさせられる作品
あわせて読みたい
【性加害】映画『SHE SAID その名を暴け』を観てくれ。#MeToo運動を生んだ報道の舞台裏(出演:キャリ…
「#MeToo」運動のきっかけとなった、ハリウッドの絶対権力者ハーヴェイ・ワインスタインを告発するニューヨーク・タイムズの記事。その取材を担った2人の女性記者の奮闘を描く映画『SHE SAID その名を暴け』は、ジャニー喜多川の性加害問題で揺れる今、絶対に観るべき映画だと思う
あわせて読みたい
【偉業】「卓球王国・中国」実現のため、周恩来が頭を下げて請うた天才・荻村伊智朗の信じがたい努力と…
「20世紀を代表するスポーツ選手」というアンケートで、その当時大活躍していた中田英寿よりも高順位だった荻村伊智朗を知っているだろうか?選手としてだけでなく、指導者としてもとんでもない功績を残した彼の生涯を描く『ピンポンさん』から、ノーベル平和賞級の活躍を知る
あわせて読みたい
【働く】給料が上がらない、上げる方法を知りたい人は木暮太一のこの本を。『資本論』が意外と役に立つ…
「仕事で成果を出しても給料が上がるわけではない」と聞いて、あなたはどう感じるだろうか?これは、マルクスの『資本論』における「使用価値」と「価値」の違いを踏まえた主張である。木暮太一『人生格差はこれで決まる 働き方の損益分岐点』から「目指すべき働き方」を学ぶ
あわせて読みたい
【感想】映画『君が世界のはじまり』は、「伝わらない」「分かったフリをしたくない」の感情が濃密
「キラキラした青春学園モノ」かと思っていた映画『君が世界のはじまり』は、「そこはかとない鬱屈」に覆われた、とても私好みの映画だった。自分の決断だけではどうにもならない「現実」を前に、様々な葛藤渦巻く若者たちの「諦念」を丁寧に描き出す素晴らしい物語
あわせて読みたい
【驚嘆】「現在は森でキノコ狩り」と噂の天才”変人”数学者グリゴリー・ペレルマンの「ポアンカレ予想証…
数学界の超難問ポアンカレ予想を解決したが、100万ドルの賞金を断り、フィールズ賞(ノーベル賞級の栄誉)も辞退、現在は「森できのこ採取」と噂の天才数学者グリゴリー・ペレルマンの生涯を描く評伝『完全なる証明』。数学に関する記述はほぼなく、ソ連で生まれ育った1人の「ギフテッド」の苦悩に満ちた人生を丁寧に描き出す1冊
あわせて読みたい
【無謀】園子温が役者のワークショップと同時並行で撮影した映画『エッシャー通りの赤いポスト』の”狂気”
「園子温の最新作」としか知らずに観に行った映画『エッシャー通りの赤いポスト』は、「ワークショップ参加者」を「役者」に仕立て、ワークショップと同時並行で撮影されたという異次元の作品だった。なかなか経験できないだろう、「0が1になる瞬間」を味わえる“狂気”の映画
あわせて読みたい
【おすすめ】「天才」を描くのは難しい。そんな無謀な挑戦を成し遂げた天才・野崎まどの『know』はヤバい
「物語で『天才』を描くこと」は非常に難しい。「理解できない」と「理解できる」を絶妙なバランスで成り立たせる必要があるからだ。そんな難題を高いレベルでクリアしている野崎まど『know』は、異次元の小説である。世界を一変させた天才を描き、「天才が見ている世界」を垣間見せてくれる
あわせて読みたい
【教育】映画化に『3月のライオン』のモデルと話題の村山聖。その師匠である森信雄が語る「育て方」論:…
自身は決して強い棋士ではないが、棋界で最も多くの弟子を育てた森信雄。「村山聖の師匠」として有名な彼の「師匠としてのあり方」を描く『一門 ”冴えん師匠”がなぜ強い棋士を育てられたのか?』から、教育することの難しさと、その秘訣を学ぶ
あわせて読みたい
【狂気】バケモン・鶴瓶を映し出す映画。「おもしろいオッチャン」に潜む「異常さ」と「芸への情熱」:…
「俺が死ぬまで公開するな」という条件で撮影が許可された映画『バケモン』。コロナ禍で映画館が苦境に立たされなければ、公開はずっと先だっただろう。テレビで見るのとは違う「芸人・笑福亭鶴瓶」の凄みを、古典落語の名作と名高い「らくだ」の変遷と共に切り取る
あわせて読みたい
【生き方】人生が虚しいなら映画『人生フルーツ』を見ると良い。素敵な老夫婦の尖った人生がここにある
社会派のドキュメンタリー映画に定評のある東海テレビが、「なんでもない老夫婦の日常」を映画にした『人生フルーツ』には、特に何が起こるわけでもないのに「観て良かった」と感じさせる強さがある。見た目は「お年寄り」だが中身はまったく古臭くない”穏やかに尖った夫婦”の人生とは?
あわせて読みたい
【博覧強記】「紙の本はなくなる」説に「文化は忘却されるからこそ価値がある」と反論する世界的文学者…
世界的文学者であり、「紙の本」を偏愛するウンベルト・エーコが語る、「忘却という機能があるから書物に価値がある」という主張は実にスリリングだ。『もうすぐ絶滅するという紙の書物について』での対談から、「忘却しない電子データ」のデメリットと「本」の可能性を知る
あわせて読みたい
【感想】池田晶子『14歳からの哲学』で思考・自由・孤独の大事さを知る。孤独を感じることって大事だ
「元々持ってた価値観とは違う考えに触れ、それを理解したいと思う場面」でしか「考える」という行為は発動しないと著者は言う。つまり我々は普段、まったく考えていないのだ。『14歳からの哲学』をベースに、「考えること」と自由・孤独・人生との関係を知る
あわせて読みたい
【貢献】飛行機を「安全な乗り物」に決定づけたMr.トルネードこと天才気象学者・藤田哲也の生涯:『Mr….
つい数十年前まで、飛行機は「死の乗り物」だったが、天才気象学者・藤田哲也のお陰で世界の空は安全になった。今では、自動車よりも飛行機の方が死亡事故の少ない乗り物なのだ。『Mr.トルネード 藤田哲也 世界の空を救った男』から、その激動の研究人生を知る
あわせて読みたい
【多様性】神童から引きこもりになり、なんとか脱出したお笑い芸人が望む、誰も責められない社会:『ヒ…
お笑い芸人・髭男爵の山田ルイ53世は、“神童”と呼ばれるほど優秀だったが、“うんこ”をきっかけに6年間引きこもった。『ヒキコモリ漂流記』で彼は、ひきこもりに至ったきっかけ、ひきこもり中の心情、そしてそこからいかに脱出したのかを赤裸々に綴り、「誰にも優しい世界」を望む
あわせて読みたい
【奇跡】鈴木敏夫が2人の天才、高畑勲と宮崎駿を語る。ジブリの誕生から驚きの創作秘話まで:『天才の思…
徳間書店から成り行きでジブリ入りすることになったプロデューサー・鈴木敏夫が、宮崎駿・高畑勲という2人の天才と共に作り上げたジブリ作品とその背景を語り尽くす『天才の思考 高畑勲と宮崎駿』。日本のアニメ界のトップランナーたちの軌跡の奇跡を知る
あわせて読みたい
【社会】学生が勉強しないのは、若者が働かないのは何故か?教育現場からの悲鳴と知見を内田樹が解説:…
教育現場では、「子どもたちが学びから逃走する」「学ばないことを誇らしく思う」という、それまでには考えられなかった振る舞いが目立っている。内田樹は『下流志向』の中で、その原因を「等価交換」だと指摘。「学ばないための努力をする」という発想の根幹にある理屈を解き明かす
あわせて読みたい
【限界】「科学とは何か?」を知るためのおすすめ本。科学が苦手な人こそ読んでほしい易しい1冊:『哲学…
「科学的に正しい」という言葉は、一体何を意味しているのだろう?科学者が「絶対に正しい」とか「100%間違っている」という言い方をしないのは何故だろう?飲茶『哲学的な何か、あと科学とか』から、「科学とはどんな営みなのか?」について考える
あわせて読みたい
【快挙】「暗黒の天体」ブラックホールはなぜ直接観測できたのか?国際プロジェクトの舞台裏:『アイン…
「世界中に存在する電波望遠鏡を同期させてブラックホールを撮影する」という壮大なEHTプロジェクトの裏側を記した『アインシュタインの影』から、ブラックホール撮影の困難さや、「ノーベル賞」が絡む巨大プロジェクトにおける泥臭い人間ドラマを知る
あわせて読みたい
【貢献】有名な科学者は、どんな派手な失敗をしてきたか?失敗が失敗でなかったアインシュタインも登場…
どれほど偉大な科学者であっても失敗を避けることはできないが、「単なる失敗」で終わることはない。誤った考え方や主張が、プラスの効果をもたらすこともあるのだ。『偉大なる失敗』から、天才科学者の「失敗」と、その意外な「貢献」を知る
あわせて読みたい
【天才】写真家・森山大道に密着する映画。菅田将暉の声でカッコよく始まる「撮り続ける男」の生き様:…
映画『あゝ荒野』のスチール撮影の際に憧れの森山大道に初めて会ったという菅田将暉の声で始まる映画『過去はいつも新しく、未来はつねに懐かしい』は、ちゃちなデジカメ1つでひたすら撮り続ける異端児の姿と、50年前の処女作復活物語が見事に交錯する
あわせて読みたい
【貢献】働く上で大切にしたいことは結局「人」。海士町(離島)で持続可能な社会を目指す若者の挑戦:…
過疎地域を「日本の未来の課題の最前線」と捉え、島根県の離島である「海士町」に移住した2人の若者の『僕たちは島で、未来を見ることにした』から、「これからの未来をどう生きたいか」で仕事を捉える思考と、「持続可能な社会」の実現のためのチャレンジを知る
あわせて読みたい
【逸話】天才数学者ガロアが20歳で決闘で命を落とすまでの波乱万丈。時代を先駆けた男がもし生きていた…
現代数学に不可欠な「群論」をたった1人で生み出し、20歳という若さで決闘で亡くなったガロアは、その短い生涯をどう生きたのか?『ガロア 天才数学者の生涯』から、数学に関心を抱くようになったきっかけや信じられないほどの不運が彼の人生をどう変えてしまったのか、そして「もし生きていたらどうなっていたのか」を知る
あわせて読みたい
【誤解】「意味のない科学研究」にはこんな価値がある。高校生向けの講演から”科学の本質”を知る:『す…
科学研究に対して、「それは何の役に立つんですか?」と問うことは根本的に間違っている。そのことを、「携帯電話」と「東急ハンズの棚」の例を使って著者は力説する。『すごい実験』は素粒子物理学を超易しく解説する本だが、科学への関心を抱かせてもくれる
あわせて読みたい
【バトル】量子力学の歴史はこの1冊で。先駆者プランクから批判者アインシュタインまですべて描く:『量…
20世紀に生まれた量子論は、時代を彩る天才科学者たちの侃々諤々の議論から生み出された。アインシュタインは生涯量子論に反対し続けたことで知られているが、しかし彼の批判によって新たな知見も生まれた。『量子革命』から、量子論誕生の歴史を知る
あわせて読みたい
【ドラマ】「フェルマーの最終定理」のドラマティックな証明物語を、飲茶氏が平易に描き出す:『哲学的…
「フェルマーの最終定理」は、問題の提示から350年以上経ってようやく証明された超難問であり、その証明の過程では様々な人間ドラマが知られている。『哲学的な何か、あと数学とか』をベースに、数学的な記述を一切せず、ドラマティックなエピソードだけに触れる
あわせて読みたい
【神秘】脳研究者・池谷裕二が中高生向けに行った講義の書籍化。とても分かりやすく面白い:『進化しす…
「宇宙」「深海」「脳」が、人類最後のフロンティアと呼ばれている。それほど「脳」というのは、未だに分からないことだらけの不思議な器官だ。池谷裕二による中高生向けの講義を元にした『進化しすぎた脳』『単純な脳、複雑な「私」』をベースに、脳の謎を知る
あわせて読みたい
【論争】サイモン・シンが宇宙を語る。古代ギリシャからビッグバンモデルの誕生までの歴史を網羅:『宇…
古代から現代に至るまで、「宇宙」は様々な捉えられ方をしてきた。そして、新たな発見がなされる度に、「宇宙」は常識から外れた不可思議な姿を垣間見せることになる。サイモン・シン『宇宙創成』をベースに、「ビッグバンモデル」に至るまでの「宇宙観」の変遷を知る
あわせて読みたい
【挑戦】社会に欠かせない「暗号」はどう発展してきたか?サイモン・シンが、古代から量子暗号まで語る…
「暗号」は、ミステリやスパイの世界だけの話ではなく、インターネットなどのセキュリティで大活躍している、我々の生活に欠かせない存在だ。サイモン・シン『暗号解読』から、言語学から数学へとシフトした暗号の変遷と、「鍵配送問題」を解決した「公開鍵暗号」の仕組みを理解する
あわせて読みたい
【証明】結城浩「数学ガール」とサイモン・シンから「フェルマーの最終定理」とそのドラマを学ぶ
350年以上前に一人の数学者が遺した予想であり「フェルマーの最終定理」には、1995年にワイルズによって証明されるまでの間に、これでもかというほどのドラマが詰め込まれている。サイモン・シンの著作と「数学ガール」シリーズから、その人間ドラマと数学的側面を知る
あわせて読みたい
【情熱】常識を疑え。人間の”狂気”こそが、想像し得ない偉業を成し遂げるための原動力だ:映画『博士と…
世界最高峰の辞書である『オックスフォード英語大辞典』は、「学位を持たない独学者」と「殺人犯」のタッグが生みだした。出会うはずのない2人の「狂人」が邂逅したことで成し遂げられた偉業と、「狂気」からしか「偉業」が生まれない現実を、映画『博士と狂人』から学ぶ
あわせて読みたい
【天才】科学者とは思えないほど面白い逸話ばかりのファインマンは、一体どんな業績を残したのか?:『…
数々の面白エピソードで知られるファインマンの「科学者としての業績」を初めて網羅したと言われる一般書『ファインマンさんの流儀』をベースに、その独特の研究手法がもたらした様々な分野への間接的な貢献と、「ファインマン・ダイアグラム」の衝撃を理解する
あわせて読みたい
【使命】「CRISPR-Cas9」を分かりやすく説明。ノーベル賞受賞の著者による発見物語とその使命:『CRISPR…
生物学の研究を一変させることになった遺伝子編集技術「CRISPR-Cas9」の開発者は、そんな発明をするつもりなどまったくなかった。ノーベル化学賞を受賞した著者による『CRISPR (クリスパー) 究極の遺伝子編集技術の発見』をベースに、その発見物語を知る
あわせて読みたい
【始まり】宇宙ができる前が「無」なら何故「世界」が生まれた?「ビッグバンの前」は何が有った?:『…
「宇宙がビッグバンから生まれた」ことはよく知られているだろうが、では、「宇宙ができる前はどうなっていたのか」を知っているだろうか? 実は「宇宙は”無”から誕生した」と考えられているのだ。『宇宙が始まる前には何があったのか?』をベースに、ビッグバンが起こる前の「空間も時間も物理法則も存在しない無」について学ぶ
あわせて読みたい
【未知】タコに「高度な脳」があるなんて初耳だ。人類とは違う進化を遂げた頭足類の「意識」とは?:『…
タコなどの頭足類は、無脊椎動物で唯一「脳」を進化させた。まったく違う進化を辿りながら「タコに心を感じる」という著者は、「タコは地球外生命体に最も近い存在」と書く。『タコの心身問題』から、腕にも脳があるタコの進化の歴史と、「意識のあり方」を知る。
あわせて読みたい
【危機】遺伝子組み換え作物の危険性を指摘。バイオ企業「モンサント社」の実態を暴く衝撃の映画:映画…
「遺伝子組み換え作物が危険かどうか」以上に注目すべきは、「モンサント社の除草剤を摂取して大丈夫か」である。種子を独占的に販売し、農家を借金まみれにし、世界中の作物の多様性を失わせようとしている現状を、映画「モンサントの不自然な食べもの」から知る
あわせて読みたい
【変人】学校教育が担うべき役割は?子供の才能を伸ばすために「異質な人」とどう出会うべきか?:『飛…
高校の美術教師からアーティストとして活動するようになった著者は、教育の現場に「余白(スキマ)」が減っていると指摘する。『飛び立つスキマの設計学』をベースに、子どもたちが置かれている現状と、教育が成すべき役割について確認する。
あわせて読みたい
【意外】自己免疫疾患の原因は”清潔さ”?腸内フローラの多様性の欠如があらゆる病気を引き起こす:『寄…
人類は、コレラの蔓延を機に公衆衛生に力を入れ、寄生虫を排除した。しかし、感染症が減るにつれ、免疫関連疾患が増大していく。『寄生虫なき病』では、腸内細菌の多様性が失われたことが様々な疾患の原因になっていると指摘、「現代病」の蔓延に警鐘を鳴らす
あわせて読みたい
【無知】メディアの問題の本質は?「報道の限界」と「情報の受け取り方」を独裁政治の現実から知る:『…
メディアは確かに「事実」を報じている。しかし、報道に乗らない情報まで含めなければ、本当の意味で世の中を理解することは難しいと、『こうして世界は誤解する』は教えてくれる。アラブ諸国での取材の現実から、報道の「限界」と「受け取り方」を学ぶ
あわせて読みたい
【驚嘆】人類はいかにして言語を獲得したか?この未解明の謎に真正面から挑む異色小説:『Ank: a mirror…
小説家の想像力は無限だ。まさか、「人類はいかに言語を獲得したか?」という仮説を小説で読めるとは。『Ank: a mirroring ape』をベースに、コミュニケーションに拠らない言語獲得の過程と、「ヒト」が「ホモ・サピエンス」しか存在しない理由を知る
あわせて読みたい
【奇跡】ビッグデータに”直感”を組み込んで活用。メジャーリーグを変えたデータ分析家の奮闘:『アスト…
「半世紀で最悪の野球チーム」と呼ばれたアストロズは、ビッグデータの分析によって優勝を果たす。その偉業は、野球のド素人によって行われた。『アストロボール』をベースに、「ビッグデータ」に「人間の直感」を組み込むという革命について学ぶ
あわせて読みたい
【継続】「言語化できない」を乗り越えろ。「読者としての文章術」で、自分の思考をクリアにする:『読…
ブログやSNSなどが登場したことで、文章を書く機会は増えていると言える。しかし同時に、「他人に評価されるために書く」という意識も強くなっているだろう。『読みたいことを書けばいい』から、「楽しく書き”続ける”」ための心得を学ぶ
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
自己啓発・努力・思考【本・映画の感想】 | ルシルナ
私自身は、仕事や社会貢献などにおいて自分の将来をもう諦めていますが、心の底では、自分の知識・スキルが他人や社会の役に立ったらいいな、と思っています。だから、自分…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…









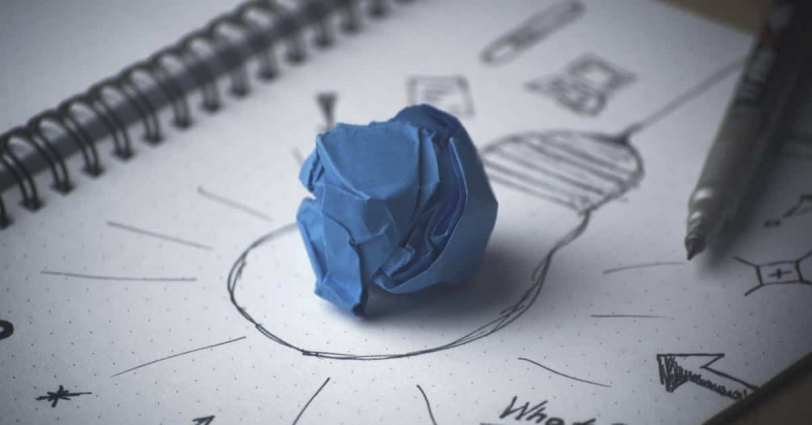















































































コメント