目次
はじめに
この記事で取り上げる本
著:ウンベルト・ エーコ, 著:ジャン=クロード・ カリエール, 翻訳:工藤 妙子
¥2,218 (2022/03/01 22:30時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
この本をガイドにしながら記事を書いていきます
この記事の3つの要点
- 「忘却によって選別されないものは文化ではない」とはどういう意味なのか?
- 対話や創造の共通基盤を持つためには、「忘却されること」は必須だ
- 残ったものが素晴らしいわけでも、忘れられたものがダメなわけでもない
「紙の本」を偏愛しつつ、「本は読まなくてもいい」「どうせすべての本は読めない」とも主張するスタンスが良い
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!「文章の書き方が分からない」「文章力がないから鍛えたい」という方にオススメ…
「文章の書き方」についてのKindle本を出版しました。「文章が書けない」「どう書いたらいいか分からない」「文章力を向上させたい」という方の悩みを解消できるような本に仕上げたつもりです。数多くの文章を書き、さらに頼まれて文章を推敲してきた経験を踏まえ、「文章を書けるようになるにはどうしたらいいか」についての私なりの考えをまとめました。
『もうすぐ絶滅するという紙の書物について』は、電子データは「『忘却されない』というデメリット」があると主張し、文化が持つ「フィルタリング」という本質を説く
あわせて読みたい
【知的】「BLって何?」という初心者に魅力を伝える「腐男子」の「BLの想像力と創造力」講座:『ボクた…
「BLは知的遊戯である」という主張には「は?」と感じてしまうでしょうが、本書『ボクたちのBL論』を読めばその印象は変わるかもしれません。「余白の発見と補完」を通じて、「ありとあらゆる2者の間の関係性を解釈する」という創造性は、現実世界にどのような影響を与えているのか
本書は、2人の書物愛好家が「紙の本」の価値について語り合う作品だ。

ただ、よくあるような「紙の本って素晴らしいよね」という単純な礼賛の本ではない。本書では、
世界規模で進められている文書のデジタル化と新しい読書ツールの導入という試練に直面している今
において、「電子データ」と比較して「紙の本」には「忘却される」という価値があるのだと指摘する。これはなかなか理解しにくい主張だと思うが、本書を読むと「なるほど」と感じさせられるし、「文化」というものの本質にも触れられるだろうと思う。
あわせて読みたい
【感想】湯浅政明監督アニメ映画『犬王』は、実在した能楽師を”異形”として描くスペクタクル平家物語
観るつもりなし、期待値ゼロ、事前情報ほぼ皆無の状態で観た映画『犬王』(湯浅政明監督)はあまりにも凄まじく、私はこんなとんでもない傑作を見逃すところだったのかと驚愕させられた。原作の古川日出男が紡ぐ狂気の世界観に、リアルな「ライブ感」が加わった、素晴らしすぎる「音楽映画」
本書には、
書物がフィルタリングという災難にもめげず、結局は張られた網をすべてかいくぐり、幸運にも、また時には不運にも、生きのびてきた。
というような形で「フィルタリング」という単語が登場する。そして、まさにこれが、「忘却という価値」の本質なのだ。
あわせて読みたい
【人生】「資本主義の限界を埋める存在としての『贈与論』」から「不合理」に気づくための生き方を知る…
「贈与論」は簡単には理解できないが、一方で、「何かを受け取ったら、与えてくれた人に返す」という「交換」の論理では対処できない現実に対峙する力ともなる。『世界は贈与でできている』から「贈与」的な見方を理解し、「受取人の想像力」を立ち上げる
この指摘は、決して「本」に限らない。ありとあらゆる「文化」が「電子化」される世の中では、文化の本質的な価値が失われ兼ねないと本書は警鐘を鳴らしているのだ。

そんな彼らの、危機を共有しながらもやはりどこか愉しそうな、「紙の本」にまつわる主張を見ていこう。
「忘却」という文化の価値について
まずは次の文章を読んでもらおう。
あわせて読みたい
【興奮】世界的大ベストセラー『サピエンス全史』要約。人類が文明を築き上げるに至った3つの革命とは?
言わずと知れた大ベストセラー『サピエンス全史』は、「何故サピエンスだけが人類の中で生き残り、他の生物が成し得なかった歴史を歩んだのか」を、「認知革命」「農業革命」「科学革命」の3つを主軸としながら解き明かす、知的興奮に満ち溢れた1冊
カエサルの最後の妻カルプルニアのことは、カエサルが暗殺された三月十五日までは、何でもわかっています。三月十五日、カルプルニアは不吉な夢を見て、夫カエサルに元老院に行かないでくれと頼みました。
カエサルの死後のカルプルニアについては、いっさい情報がありません。彼女は我々の記憶から姿を消したのです。なぜでしょう。これはなにも、彼女が女性だったからというわけではありません。(中略)文化とは、つまり、このような選別を行うことなのです。現代の文化は逆に、インターネット経由で、世界じゅうのあらゆるカルプルニアたちについて、毎日毎秒、詳細な情報をまき散らしているので、子供が学校の宿題で調べ物をしたら、カルプルニアのことを、カエサルと同じくらい重要な人物だと思うかもしれないほどです。(ウンベルト・エーコ)
カエサルの妻については、カエサルの死後以降のことについてはまったく知られていない。それは、「彼女について何も語られていない」ことを意味するわけではない。恐らく、何かは語られていただろうし、それを記録した文書も何かしらは存在したことだろう。しかしそれは、現在まで残らなかったのだ。
このように、記録されていた(かもしれない)情報が失われることを、本書では「忘れる」と表記している。「忘れる」の主語は、「文化」だと考えればいいだろう。引用中の「文化とは、つまり、このような選別を行うことなのです」という一文からもそうだと判断できる。
あわせて読みたい
【映画】『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』で号泣し続けた私はTVアニメを観ていない
TVアニメは観ていない、というかその存在さえ知らず、物語や登場人物の設定も何も知らないまま観に行った映画『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』に、私は大号泣した。「悪意のない物語」は基本的に好きではないが、この作品は驚くほど私に突き刺さった
つまり、ここで主張されているのは、「文化は忘れることで選別を行っている」ということだ。もっと言えば、「選別されないものは、文化ではない」となるだろう。
もしこの主張を受け入れるならば、「電子データは『文化』ではない」ということになる。何故なら「電子データ」は「基本的には情報が失われない」からだ。
電子データの情報が失われる可能性ももちろんあるが、重要なのは「『電子データ』は失われないと私たちが考えている」という点だろう。恐らく人類の歴史上、そんな環境が実現したことなどなかったのではないか。そしてそのことが、「文化である」という重要な本質を結果的に失わせているのではないか、と指摘しているのだ。
あわせて読みたい
【秘話】15年で世界を変えたグーグルの”異常な”創業エピソード。収益化無視の無料ビジネスはなぜ成功し…
スマホやネットを使う人で、グーグルのお世話になっていない人はまずいないだろう。もはや「インフラ」と呼んでいいレベルになったサービスを生み出した企業の創業からの歴史を描く『グーグル秘録』は、その歩みが「無邪気さ」と「偶然」の産物であることを示している。凄まじいエピソード満載の信じがたい企業秘話
この「文化が選別を行う」という主張は少し分かりにくいかもしれない。ここでは、「紙の本」と「ネット上の文章」を比較することで、もう少し分かりやすい形で「選別」の意味について考えてみることにしよう。
「紙の本」が出版されることは、まさに「選別」の果てにあると言える。出版社が「売れる」と見込んだもの、あるいは「売れるかどうか分からないが後世に残す価値がある」と判断したものしか書籍化されない。さらに「紙の本」には、ページ数という物理的な制約も存在する。製本の限界を超えて、ページ数を増やすことはできないのだ。つまり、「何を書くか」も絞らなければならないのである。

一方、電子書籍やネット上の記事には、「紙の本」のような「選別」は存在しないだろう。売れるかどうか分からなくてもとりあえずアップしておけるし、分量の制約もない。「選別」という関門をくぐらずとも、あらゆるものが同じ土俵に乗れるのである。
あわせて読みたい
【創作】クリエイターになりたい人は必読。ジブリに見習い入社した川上量生が語るコンテンツの本質:『…
ドワンゴの会長職に就きながら、ジブリに「見習い」として入社した川上量生が、様々なクリエイターの仕事に触れ、色んな質問をぶつけることで、「コンテンツとは何か」を考える『コンテンツの秘密』から、「創作」という営みの本質や、「クリエイター」の理屈を学ぶ
こう考えた時、とりあえず「電子データ」については、「選別されないものは、文化ではない」という主張に一理あると感じるのではないだろうか。
また「電子データ」には、「ひとりでに記録する」という性質もある。防犯カメラの映像、GPSによる経路記録、ネットショッピングの注文履歴など、「記録しよう」と考える主体が存在しなくても記録されていく情報はとても増えただろう。これもまた「選別」という過程を経ないものだ。
「勝手に記録される」という点もまた、電子データが文化の基盤にはなり得ないと思わせる要素の1つではないかと思う。
あわせて読みたい
【無謀】園子温が役者のワークショップと同時並行で撮影した映画『エッシャー通りの赤いポスト』の”狂気”
「園子温の最新作」としか知らずに観に行った映画『エッシャー通りの赤いポスト』は、「ワークショップ参加者」を「役者」に仕立て、ワークショップと同時並行で撮影されたという異次元の作品だった。なかなか経験できないだろう、「0が1になる瞬間」を味わえる“狂気”の映画
「フィルタリングを経た文化」が我々に共通基盤を与える
本書では、「フィルタリングがなされることで、共通の『百科事典』を手にすることができる」という内容のこんな文章がある。
諸文化は、保存すべきものと忘れるべきものを示すことで、フィルタリングを行います。その意味で、文化は我々に、暗黙裡の共通基盤を提供しています。間違いに関してもそうです。ガリレイが導いた革命を理解するには、どうしてもプトレマイオスの学説を出発点にしなければなりません。ガリレイの段階までたどり着くには、プトレマイオスの段階を共有しなければいけないし、プトレマイオスが間違っているということをわかっていなければいけない。何の議論をするにしても、共通の百科事典を基盤にしていなければいけません。ナポレオンなどという人物はじつは存在しなかった、ということを立証することだってできなくはない――でもそれは、我々が三人とも、ナポレオンという人物がいたということを知識として学んで知っているからです。対話の継続を保証するのはまさにそれなんです。こういった群居性によってこそ、対話や創造や自由が可能になってくるんです。
インターネットはすべてを与えてくれますが、それによって我々は、すでにご指摘なさったとおり、もはや文化という仲介によらず、自分自身の頭でフィルタリングを行うことを余儀なくされ、結果的にいまや、世の中に六〇億冊の百科事典があるのと同じようなことになりかねないのです。これはあらゆる相互理解の妨げになるでしょう。(ウンベルト・エーコ)
あわせて読みたい
【想像力】「知らなかったから仕方ない」で済ませていいのか?第二の「光州事件」は今もどこかで起きて…
「心地いい情報」だけに浸り、「知るべきことを知らなくても恥ずかしくない世の中」を生きてしまっている私たちは、世界で何が起こっているのかあまりに知らない。「光州事件」を描く映画『タクシー運転手 約束は海を越えて』から、世界の見方を考える
私はこの中の、「六〇億冊の百科事典があるのと同じようなこと」という指摘に特に納得させられた。確かに、今私たちが直面している問題は、「皆が共通の基盤持っておらず、個々人がてんでバラバラの百科事典を元にコミュニケーションをしていること」によって生まれると考えると理解しやすい。

上記の引用の主張を、私なりにもう少し分かりやすく説明してみたいと思う。
電子データが存在しない世界でも、情報はもちろん常に増え続けるわけだが、同時に忘却されフィルタリングされることで減りもする。この、増えもするし減りもする情報の総量を「1,000」としてみよう。増える量と減る量が同じで、常に送料は一定になっていると仮定するのである。そしてこの「1,000」が、人類にとっての共通基盤となる百科事典というわけだ。さらに、人間が認識できる情報の上限を「100」だとしよう。
私たちはもちろん、「1,000」すべてを認識することなどできないわけだが、「1,000」から各々が「100」取り出すことを考えた時、そこまで大きな齟齬は存在しないと想定できる。もちろん「1,000」からどのように「100」を取り出すかによってコミュニケーションや理解に齟齬は生まれるのだが、それでも上限が「1,000」なのだから、そこまで大きな差は生まれはしないという意味だ。
あわせて読みたい
【誤解】世界的大ベストセラー『ファクトフルネス』の要約。我々は「嘘の情報」を信じ込みやすい
世界の現状に関する13の質問に対して、ほとんどの人が同じ解答をする。最初の12問は不正解で、最後の1問だけ正答するのだ。世界的大ベストセラー『ファクトフルネス』から、「誤った世界の捉え方」を認識し、情報を受け取る際の「思い込み」を払拭する。「嘘の情報」に踊らされないために読んでおくべき1冊だ
一方で、電子データが存在する世界では、忘却というフィルタリングは行われない。つまり、情報は増え続ける一方というわけだ。その総量は「10,000」「100,000」「1,000,000」「10,000,000」「100,000,000」……といくらでも増えていく。
仮に、今私たちの世界にある情報の総量が「100,000,000」だとしてみよう。私たちはここから「100」を取ることになるが、その取り方は「1,000」から「100」を取る場合と比べて膨大な可能性が存在する。これが、引用中にある「自分自身の頭でフィルタリングを行うことを余儀なくされ」という状況だ。「文化」がフィルタリングを行わないのだから、各自でやるしかない。そしてそれゆえに、私たちは共通基盤を持てなくなってしまうというわけだ。
情報は失われることで「共通基盤としての文化」となり、対話や創造が可能となる。しかし電子データは忘却されないが故に「共通基盤としての文化」にはなりえず、対話や創造が阻害されてしまうことになるのだ。
あわせて読みたい
【告発】アメリカに”監視”される社会を暴露したスノーデンの苦悩と決断を映し出す映画:『スノーデン』…
NSA(アメリカ国家安全保障局)の最高機密にまでアクセスできたエドワード・スノーデンは、その機密情報を持ち出し内部告発を行った。「アメリカは世界中の通信を傍受している」と。『シチズンフォー』と『スノーデン』の2作品から、彼の告発内容とその葛藤を知る
このような指摘は、割と理解しやすいのではないかと思う。
「情報がたくさん存在する」という状況は、もちろんメリットにもなり得る。しかしそのメリットは、人類全体で考えた時には重要とは言えないかもしれないのだ。たった1人で生み出せるものは決して大きくはないし、だから創造のためには対話が必要になる。しかし共通基盤が存在しなければ対話は成り立たず、創造にも活かせないという事態に陥ってしまうのだ。

「忘却されなかったものこそが素晴らしい」というわけでもない
あわせて読みたい
【驚愕】ロバート・キャパの「崩れ落ちる兵士」はどう解釈すべきか?沢木耕太郎が真相に迫る:『キャパ…
戦争写真として最も有名なロバート・キャパの「崩れ落ちる兵士」には、「本当に銃撃された瞬間を撮影したものか?」という真贋問題が長く議論されてきた。『キャパの十字架』は、そんな有名な謎に沢木耕太郎が挑み、予想だにしなかった結論を導き出すノンフィクション。「思いがけない解釈」に驚かされるだろう
ここまで「文化による選別」に触れてきたが、誤解してはいけないのは、「残ったものだからと言って、それが素晴らしいものとは限らない」ということだ。もっと言えば、「より素晴らしいものが失われてしまっている可能性がある」のである。
それを示唆するこんな文章がある。
我々は今日なお、エウリピデス、ソフォクレス、アイスキュロスを読みますし、彼らをギリシャ三大悲劇詩人と見なしています。しかしアリストテレスは、悲劇について論じた「詩学」のなかで、当時の代表的な悲劇詩人たちの名前を列挙しながら、我らが三大悲劇詩人の誰についてもまったく触れていません。我々がうしなったものは、今日まで残ったものに比べて、より優れた、ギリシャ演劇を代表するものとしてよりふさわしいものだったのでしょうか。この先誰がこの疑念を晴らしてくれるのでしょう。(ジャン=フィリップ・ド・トナック)
良いものであれば残りやすいのは確かだが、だからと言って、残ったものが最上だとは言い切れない、とこの文章は示している。
あわせて読みたい
【改革】改修期間中の国立西洋美術館の裏側と日本の美術展の現実を映すドキュメンタリー映画:『わたし…
「コロナ禍」という絶妙すぎるタイミングで改修工事を行った国立西洋美術館の、普段見ることが出来ない「裏側」が映し出される映画『わたしたちの国立西洋美術館』は、「日本の美術展」の問題点を炙り出しつつ、「『好き』を仕事にした者たち」の楽しそうな雰囲気がとても魅力的に映るドキュメンタリー
また、「良い」の基準が時代や国よって変わる点も見過ごせない。
例えば私は、浮世絵が海外で評価されるようになったきっかけについて、「日本から海外に陶磁器を送る際の包み紙として使われたものを外国人が見て驚いた」という話を聞いたことがある。真偽のほどは分からないが、これはつまり、「日本では包み紙に使われるほど芸術としては大した評価を受けていなかったが、外国人には新鮮で評価のきっかけになった」ということになる。もしこのエピソードが本当だとすれば、「浮世絵が包み紙に使われること」がなければ、浮世絵は現在まで残っていなかったかもしれないのだ。
また本書には、こんな文章もある。
ストア派の哲学というのは、我々がその重要性を十分評価しきれていない知的達成の一つと言えそうですが、そのストア派について我々が知っていることの大部分は、ストア派の思想に反駁したセクストゥス・エンピリクスの文章がなければ、知りえなかったことです。(ウンベルト・エーコ)

補足しよう。「ストア派」と呼ばれる哲学の一派が存在するのだが、その「ストア派」に属した人たちの文書は一切残っていない。にもかかわらず現在「ストア派」の哲学が知られているのは、「ストア派に反論した人物の文書」が残っているからだというのだ。
あわせて読みたい
【感想】飲茶の超面白い東洋哲学入門書。「本書を読んでも東洋哲学は分からない」と言う著者は何を語る…
東洋哲学というのは、「最終回しか存在しない連続ドラマ」のようなものだそうだ。西洋哲学と比較にならないほど異質さと、インド哲学・中国哲学など個別の思想を恐ろしく分かりやすく描く『史上最強の哲学入門 東洋の哲人たち』は、ページをめくる手が止まらないくらい、史上最強レベルに面白かった
本書で「知的達成の一つ」と書かれているように、現在「ストア派」の哲学は高く評価されているのだろう。しかし「ストア派」の思想が書かれたものは現存していない。これが、「当時ストア派の哲学は重視されていなかったこと」を示すのか、あるいは「重視されていたが何らかの理由で失われたこと」を示すのかは分からないが、いずれにせよ、価値があるから残るわけでも、価値がないから忘却されるわけでもないということだ。
そんな「選別」に価値などあるのかと感じるかもしれない。確かに私も、価値のないものが残っていても別にいいが、価値のあるものが失われてしまうのは残念に思うし、それを回避できる電子データの存在にはメリットがあると感じる。どんなものでも、良い悪いの評価は様々な理由によって変動するのだから、あらゆるものが電子データとして保存され、いつの日か正しく評価されるかもしれないと期待できる点はプラスな気はする。
しかしやはり、本書で指摘されているような、「フィルタリングによって情報の総量が減り、そのことによって共通基盤としての価値を持つ」という文化の性質もまた非常に重要だと思う。また、本書に書かれているわけではないが、「忘却の可能性」があるからこそ「なんとか広めたい、残したい」という気持ちが強くなる面もあるだろうし、そのことが「良いものとは何か?」という指標にも一定の影響を与えもするのではないだろうか。
あわせて読みたい
【最新】「コロンブス到達以前のアメリカ大陸」をリアルに描く歴史書。我々も米国人も大いに誤解してい…
サイエンスライターである著者は、「コロンブス到着以前のアメリカはどんな世界だったか?」という問いに触れ、その答えが書かれた本がいつまで経っても出版されないので自分で執筆した。『1491 先コロンブス期アメリカ大陸をめぐる新発見』には、アメリカ人も知らない歴史が満載だ
さて、「忘却」という点に関して、「文化」の文脈とはまた異なる、非常に面白い話が載っていたので紹介したいと思う。
二十年前、NASAかどこかの米国政府機関が、核廃棄物を埋める場所について具体的に話し合いました。核廃棄物の放射能は一万年――とにかく天文学的な数字です――持続することが知られています。問題になったのは、土地がどこに見つかったとしても、そこへの侵入を防ぐために、どのような標識でまわりを取り囲めばいいのか、わからないということでした。
二、三千年たったら、読み解く鍵の失われた言語というのが出てくるのではないでしょうか。五千年後に人類が姿を消し、遠い宇宙からの来訪者たちが地球に降り立った場合、問題の土地に近づいてはいけないということをどうやって説明すればよいでしょう。(ウンベルト・エーコ)

あわせて読みたい
【課題】原子力発電の廃棄物はどこに捨てる?世界各国、全人類が直面する「核のゴミ」の現状:映画『地…
我々の日常生活は、原発が生み出す電気によって成り立っているが、核廃棄物の最終処分場は世界中で未だにどの国も決められていないのが現状だ。映画『地球で最も安全な場所を探して』をベースに、「核のゴミ」の問題の歴史と、それに立ち向かう人々の奮闘を知る
核廃棄物の処分問題そのものについては以前から認識していたが、「注意を促す標識」について考えたことがなかったので、非常に面白いと感じた。
確かに我々は、ピラミッドなどの遺跡に書かれている文字を読めない。専門家なら読めるだろうが、普通の市民には解読不可能だろう。そして、そこで生活する市民に解読不可能な言語で注意が促されたところでなんの効力も発揮しない。
これは、インターネットや電子データで解決できるような問題ではないだろう。まさに「忘却」という性質が直接的に生み出すものであり、「核廃棄物の処分」という課題に絡んでまさか人類がこのような問題に直面するなどとは想像もしていなかった。
情報には「忘却」という性質が付きものであることを如実に示す事例だと言っていいだろう。
あわせて読みたい
【実像】ベートーヴェンの「有名なエピソード」をほぼ一人で捏造・創作した天才プロデューサーの実像:…
ベートーヴェンと言えば、誰もが知っている「運命」を始め、天才音楽家として音楽史に名を刻む人物だが、彼について良く知られたエピソードのほとんどは実は捏造かもしれない。『ベートーヴェン捏造 名プロデューサーは嘘をつく』が描く、シンドラーという”天才”の実像
「紙の本」に絶対的な価値があるわけではない
本書は、「紙の本」を熱狂的に愛する2人による対談であるのだが、2人とも決してそれを他人に押し付けるような主張はしない。それどころか、「書物という存在」や「読書という行為」をそこまで重視していないような発言さえする。
我々は、書物というものを非常に高く評価しており、えてして神聖視しがちです。しかしよく見れば、我々の蔵書の圧倒的多数が、無能ないしは間抜けな人間、あるいは偏執狂によって書かれた本なんです。(ジャン=クロード・カリエール)
くどいようですが、べつに本を買わなくたっていいし、読まなくたっていいんですよ。ただぱらぱらめくってみて、背表紙に何が書いてあるか見てみるだけでいいんです。(ウンベルト・エーコ)
あわせて読みたい
【前進】誰とも価値観が合わない…。「普通」「当たり前」の中で生きることの難しさと踏み出し方:『出会…
生きていると、「常識的な考え方」に囚われたり、「普通」「当たり前」を無自覚で強要してくる人に出会ったりします。そういう価値観に合わせられない時、自分が間違っている、劣っていると感じがちですが、そういう中で一歩踏み出す勇気を得るための考え方です

書物が好きな人であればあるほど、「読まなきゃ損」「本になってこそ価値がある」みたいなことを言いがちだと感じるが、この2人はそのようなスタンスを取らない。この点が、本書全体を貫く非常に優れた点だと私は思う。書物への偏愛を自覚しながらも、その気持ちは自分の内側に留めておき、「紙の本」が持つ機能が「文化」にどのような影響を与えているのかについて純粋に論じているのだ。
こんな風にも語っている。
世界には書物があふれていて、我々にはその一冊一冊を知悉する時間がありません。出版されたすべての書物を読むことはおろか、ある特定の文化を代表するような最重要書だけでも、全部読むことは不可能です。ですから我々は、読んでいない書物、時間がなくて読めなかった書物から、深い影響を受けています。(ウンベルト・エーコ)
あわせて読みたい
【天才】『三島由紀夫vs東大全共闘』後に「伝説の討論」と呼ばれる天才のバトルを記録した驚異の映像
1969年5月13日、三島由紀夫と1000人の東大全共闘の討論が行われた。TBSだけが撮影していたフィルムを元に構成された映画「三島由紀夫vs東大全共闘」は、知的興奮に満ち溢れている。切腹の一年半前の討論から、三島由紀夫が考えていたことと、そのスタンスを学ぶ
ここまでの議論を振り返れば、この主張も納得しやすいだろう。文化にはフィルタリングという機能があり、「紙の本」はまさにその「忘却」という点で大きな”貢献”を成しているのだ。本を読むかどうかに関係なく「紙の本」は我々に影響を与えているのであり、このことは「紙の本」が持つメリットとしてより広く認識されるべきではないかと私は感じた。
現在、「紙の本」を取り巻く状況はなかなか厳しい。私も、長く書店員を経験してきたので、肌感覚としてそれが分かっているつもりだ。書店はどんどん減っているし、「紙の本」はなかなか読まれなくなっている。一部のベストセラー作家を除けば、書籍の出版だけで生計を立てるのはかなり困難だろう。
一方で、本書にはこんな文章もある。
ところで、楽観的になれる理由の一つは、最近は、大量の本を目にすることのできるチャンスが増えてきているからです。私がまだ子供だったころ、書店というのはひどく暗い所で、敷居が高かったんです。中に入ると、黒っぽい服を着た店員が、何かお探しですかと訊いてきます。それがあんまり恐ろしいので、長居しようという気にはとてもなれませんでした。時に、文明の歴史のなかで、今日ほど書店がたくさんあって、綺麗で、明るかったことはありません。(ウンベルト・エーコ)

あわせて読みたい
【正義】マイノリティはどう生き、どう扱われるべきかを描く映画。「ルールを守る」だけが正解か?:映…
社会的弱者が闘争の末に権利を勝ち取ってきた歴史を知った上で私は、闘わずとも権利が認められるべきだと思っている。そして、そういう社会でない以上、「正義のためにルールを破るしかない」状況もある。映画『パブリック』から、ルールと正義のバランスを考える
確かに、近視眼的な観点からすれば書店は減少している。しかし、より広い範囲で歴史を見渡してみれば、「本が置かれている書店という環境」を取り巻く状況は非常に良くなっているというのだ。なるほど、そんな風に考えたことはなかったので、斬新な主張に感じられた。
本書には、現在では「名作」と評されている作品が、出版当時どのような評価を受けていたのかに関する記述もある。
「もしかしたら私の能力が少し足りないのかもしれないが、誰かが眠れなくて輾転反側する様子を語るのに、どうして三〇ページも費やす必要があるのか私には理解できない」。これはプルーストの『失われた時を求めて』について最初に書かれた書評です。(ウンベルト・エーコ)
さらに続けて、『白鯨』『ボヴァリー夫人』『動物農場』『アンネの日記』など、現在では古典的名作として不動の地位を築いていると言っていい作品が、出版時には現在のような評価を受けていなかったという事実が語られていく。
あわせて読みたい
【衝撃】ABC予想の証明のために生まれたIUT理論を、提唱者・望月新一の盟友が分かりやすく語る:『宇宙…
8年のチェック期間を経て雑誌に掲載された「IUT理論(宇宙際タイヒミュラー理論)」は、数学の最重要未解決問題である「ABC予想」を証明するものとして大いに話題になった。『宇宙と宇宙をつなぐ数学』『abc予想入門』をベースに、「IUT理論」「ABC予想」について学ぶ
そしてこの点について本書では、「作品が評価されるためには『解釈』が必要なのだ」と指摘するのだ。
傑作が傑作であるためには、知られるということが大事です。つまり、作品がみずから喚起した解釈を吸収することで、その個性をより強く発揮していれば、傑作は傑作として認知されます。知られざる傑作には読者が足りなかったんです。充分に読まれなかったし、充分に解釈されなかった。(ウンベルト・エーコ)
当たり前と言えば当たり前の話ではあるが、作品はそれ単体では「傑作」には成れず、「読者の存在」と「読者による解釈」によって「傑作へと変わっていく」というわけである。
これは、作品に対する「評価」が変わる、というだけの話ではない。
おっしゃいましたね、今日我々が読んでいるシェイクスピアの戯曲は、書かれた当初よりきっと豊かになっている、なぜなら、それらの戯曲は、シェイクスピアが紙にペンを走らせて以来、積み重ねられた偉大な読みと解釈をすべて吸収してきたからだ、と。私もそう思います。シェイクスピアはたえず豊かになり、丈夫になりつづけているんです。(ジャン=クロード・カリエール)
あわせて読みたい
【思考】文章の書き方が分かんない、トレーニングしたいって人はまず、古賀史健の文章講義の本を読め:…
古賀史健『20歳の自分に受けさせたい文章講義』は、「具体的なテクニック」ではない記述も非常に興味深い1冊だ。「なぜ文章を書く必要があるのか」という根本的な部分から丁寧に掘り下げる本書は、「書くからこそ考えられる」という、一般的なイメージとは逆だろう発想が提示される
これは、「解釈」を吸収することで、「評価」だけではなく「作品そのもの」が変わっていく、という指摘だ。もちろんこの指摘は、「演じる者が存在する戯曲」だからこそ成立し得る可能性もある。紙に書かれたものが完成作ではない戯曲の場合、それを演じる者がいるお陰で、「解釈を吸収すること」が実際的に可能だからだ。

しかしより広義に捉えれば、紙に定着した作品も「解釈」を取り入れることで変わっていくと受け取ることも可能だろうと思う。様々な解釈が「作品の捉え方」を変え得るし、「捉えられ方の変化」は「作品そのものの変化」と考えていいのではないかとも感じる。
本の評価も、書物の存在価値も、どんどんと変遷していく。だからこそ、そこに絶対的な価値を見い出すのではなく、「『フィルタリングという機能』を優れて発揮するもの」と大枠で捉えておくのがいいのではないか。そんな風に思わされる作品だった。
あわせて読みたい
【魅惑】マツコも絶賛の“日本人初のパリコレトップモデル”山口小夜子のメイクの凄さや素顔を描く映画:…
日本人初のパリコレトップモデルである山口小夜子と親交があった監督が紡ぐ映画『氷の花火 山口小夜子』は、未だ謎に包まれているその人生の一端を垣間見せてくれる作品だ。彼女を知る様々な人の記憶と、彼女を敬愛する多くの人の想いがより合って、一時代を築いた凄まじい女性の姿が浮かび上がってくる
著:ウンベルト・ エーコ, 著:ジャン=クロード・ カリエール, 翻訳:工藤 妙子
¥2,218 (2022/03/01 22:31時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品読了済】私が読んできたノンフィクション・教養書を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が読んできたノンフィクションを様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本選びの参考にして下さい。
最後に
この記事で触れた話題はごく僅かであり、本書は実に様々な話題へとその触手を伸ばしていく。博覧強記としか言いようがないその知識量と、あらゆる領域へと話を展開させる縦横無尽の話術には非常に驚かされる。
「本」「インターネット」「電子データ」のような矮小的な領域の話に留まらず、広く「文化」をテーマにしている作品であり、知的好奇心を大いに刺激させられる一冊だ。
あわせて読みたい
【天才】読書猿のおすすめ本。「いかにアイデアを生むか」の発想法を人文書に昇華させた斬新な1冊:『ア…
「独学の達人」「博覧強記の読書家」などと評される読書猿氏が、古今東西さまざまな「発想法」を1冊にまとめた『アイデア大全』は、ただのHow To本ではない。「発想法」を学問として捉え、誕生した経緯やその背景なども深堀りする、「人文書」としての一面も持つ作品だ
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!「文章の書き方が分からない」「文章力がないから鍛えたい」という方にオススメ…
「文章の書き方」についてのKindle本を出版しました。「文章が書けない」「どう書いたらいいか分からない」「文章力を向上させたい」という方の悩みを解消できるような本に仕上げたつもりです。数多くの文章を書き、さらに頼まれて文章を推敲してきた経験を踏まえ、「文章を書けるようになるにはどうしたらいいか」についての私なりの考えをまとめました。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【魅惑】マツコも絶賛の“日本人初のパリコレトップモデル”山口小夜子のメイクの凄さや素顔を描く映画:…
日本人初のパリコレトップモデルである山口小夜子と親交があった監督が紡ぐ映画『氷の花火 山口小夜子』は、未だ謎に包まれているその人生の一端を垣間見せてくれる作品だ。彼女を知る様々な人の記憶と、彼女を敬愛する多くの人の想いがより合って、一時代を築いた凄まじい女性の姿が浮かび上がってくる
あわせて読みたい
【映画】『キャスティング・ディレクター』の歴史を作り、ハリウッド映画俳優の運命を変えた女性の奮闘
映画『キャスティング・ディレクター』は、ハリウッドで伝説とされるマリオン・ドハティを描き出すドキュメンタリー。「神業」「芸術」とも評される配役を行ってきたにも拘わらず、長く評価されずにいた彼女の不遇の歴史や、再び「キャスティングの暗黒期」に入ってしまった現在のハリウッドなどを切り取っていく
あわせて読みたい
【映画】『街は誰のもの?』という問いは奥深い。「公共」の意味を考えさせる問題提起に満ちた作品
映画『街は誰のもの?』は、タイトルの通り「街(公共)は誰のものなのか?」を問う作品だ。そしてそのテーマの1つが、無許可で街中に絵を描く「グラフィティ」であることもまた面白い。想像もしなかった問いや価値観に直面させられる、とても興味深い作品である
あわせて読みたい
【衝撃】「きのくに子どもの村学園」に密着する映画『夢見る小学校』は、「義務教育」の概念を破壊する…
驚きの教育方針を有する私立小学校「きのくに子どもの村学園」に密着する映画『夢見る小学校』と、「日本の教育にはほとんどルールが無い」ことを示す特徴的な公立校を取り上げる映画『夢見る公立校長先生』を観ると、教育に対する印象が変わる。「改革を妨げる保護者」にならないためにも観るべき作品だ
あわせて読みたい
【改革】改修期間中の国立西洋美術館の裏側と日本の美術展の現実を映すドキュメンタリー映画:『わたし…
「コロナ禍」という絶妙すぎるタイミングで改修工事を行った国立西洋美術館の、普段見ることが出来ない「裏側」が映し出される映画『わたしたちの国立西洋美術館』は、「日本の美術展」の問題点を炙り出しつつ、「『好き』を仕事にした者たち」の楽しそうな雰囲気がとても魅力的に映るドキュメンタリー
あわせて読みたい
【共感】斎藤工主演映画『零落』(浅野いにお原作)が、「創作の評価」を抉る。あと、趣里が良い!
かつてヒット作を生み出しながらも、今では「オワコン」みたいな扱いをされている漫画家を中心に描く映画『零落』は、「バズったものは正義」という世の中に斬り込んでいく。私自身は創作者ではないが、「売れる」「売れない」に支配されてしまう主人公の葛藤はよく理解できるつもりだ
あわせて読みたい
【倫理】アート体験の行き着く未来は?映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』が描く狂気の世界(…
「『痛み』を失った世界」で「自然発生的に生まれる新たな『臓器』を除去するライブパフォーマンス」を行うソール・テンサーを主人公にした映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』は、すぐには答えの見出しにくい「境界線上にある事柄」を挑発的に描き出す、実に興味深い物語だ
あわせて読みたい
【知的】「BLって何?」という初心者に魅力を伝える「腐男子」の「BLの想像力と創造力」講座:『ボクた…
「BLは知的遊戯である」という主張には「は?」と感じてしまうでしょうが、本書『ボクたちのBL論』を読めばその印象は変わるかもしれません。「余白の発見と補完」を通じて、「ありとあらゆる2者の間の関係性を解釈する」という創造性は、現実世界にどのような影響を与えているのか
あわせて読みたい
【感想】どんな話かわからない?難しい?ジブリ映画『君たちはどう生きるか』の考察・解説は必要?(監…
宮崎駿最新作であるジブリ映画『君たちはどう生きるか』は、宮崎アニメらしいファンタジックな要素を全開に詰め込みつつ、「生と死」「創造」についても考えさせる作品だ。さらに、「自分の頭の中から生み出されたものこそ『正解』」という、創造物と向き合う際の姿勢についても問うているように思う
あわせて読みたい
【実話】映画『グッドバイ、バッドマガジンズ』(杏花主演)が描く、もの作りの絶望(と楽しさ)
実在したエロ雑誌編集部を舞台に、タブーも忖度もなく業界の内実を描き切る映画『グッドバイ、バッドマガジンズ』は、「エロ雑誌」をテーマにしながら、「もの作りに懸ける想い」や「仕事への向き合い方」などがリアルに描かれる素敵な映画だった。とにかく、主役を演じた杏花が良い
あわせて読みたい
【人類学】少数民族・ムラブリ族に潜入した映画『森のムラブリ』は、私たちの「当たり前」を鮮やかに壊す
タイとラオスにまたがって存在する少数民族・ムラブリ族に密着したドキュメンタリー映画『森のムラブリ』。「ムラブリ族の居住地でたまたま出会った日本人人類学者」と意気投合し生まれたこの映画は、私たちがいかに「常識」「当たり前」という感覚に囚われているのかを炙り出してくれる
あわせて読みたい
【思考】文章の書き方が分かんない、トレーニングしたいって人はまず、古賀史健の文章講義の本を読め:…
古賀史健『20歳の自分に受けさせたい文章講義』は、「具体的なテクニック」ではない記述も非常に興味深い1冊だ。「なぜ文章を書く必要があるのか」という根本的な部分から丁寧に掘り下げる本書は、「書くからこそ考えられる」という、一般的なイメージとは逆だろう発想が提示される
あわせて読みたい
【革命】観る将必読。「将棋を観ること」の本質、より面白くなる見方、そして羽生善治の凄さが満載:『…
野球なら「なんで今振らないんだ!」みたいな素人の野次が成立するのに、将棋は「指せなきゃ観てもつまらない」と思われるのは何故か。この疑問を起点に、「将棋を観ること」と「羽生善治の凄さ」に肉薄する『羽生善治と現代』は、「将棋鑑賞」をより面白くしてくれる話が満載
あわせて読みたい
【驚異】数学の「無限」は面白い。アキレスと亀の矛盾、実無限と可能無限の違い、カントールの対角線論…
日常の中で「無限」について考える機会などなかなか無いだろうが、野矢茂樹『無限論の教室』は、「無限には種類がある」と示すメチャクチャ興味深い作品だった。「実無限」と「可能無限」の違い、「可能無限」派が「カントールの対角線論法」を拒絶する理由など、面白い話題が満載の1冊
あわせて読みたい
【幸福】「死の克服」は「生の充実」となり得るか?映画『HUMAN LOST 人間失格』が描く超管理社会
アニメ映画『HUMAN LOST 人間失格』では、「死の克服」と「管理社会」が分かちがたく結びついた世界が描かれる。私たちは既に「緩やかな管理社会」を生きているが、この映画ほどの管理社会を果たして許容できるだろうか?そしてあなたは、「死」を克服したいと願うだろうか?
あわせて読みたい
【感想】湯浅政明監督アニメ映画『犬王』は、実在した能楽師を”異形”として描くスペクタクル平家物語
観るつもりなし、期待値ゼロ、事前情報ほぼ皆無の状態で観た映画『犬王』(湯浅政明監督)はあまりにも凄まじく、私はこんなとんでもない傑作を見逃すところだったのかと驚愕させられた。原作の古川日出男が紡ぐ狂気の世界観に、リアルな「ライブ感」が加わった、素晴らしすぎる「音楽映画」
あわせて読みたい
【評価】のん(能年玲奈)の映画『Ribbon』が描く、コロナ禍において「生きる糧」が芸術であることの葛藤
のん(能年玲奈)脚本・監督・主演の映画『Ribbon』。とても好きな作品だった。単に女優・のんが素晴らしいというだけではなく、コロナ禍によって炙り出された「生きていくのに必要なもの」の違いに焦点を当て、「魂を生き延びさせる行為」が制約される現実を切り取る感じが見事
あわせて読みたい
【表現】映画『名付けようのない踊り』で初めて見た田中泯のダンス。「芸術以前」を志向する圧倒的パワー
映画『名付けようのない踊り』の中で田中泯は言う。「私」や「個性」を表現することには違和感がある、と。「踊りのために身体を作る」のではなく、「野良仕事で出来た身体で踊る」のだ、と。芸術になる前の踊りを探したい、と。「唯一無二の表現者」の生涯と現在地を映し出すドキュメンタリー
あわせて読みたい
【無謀】園子温が役者のワークショップと同時並行で撮影した映画『エッシャー通りの赤いポスト』の”狂気”
「園子温の最新作」としか知らずに観に行った映画『エッシャー通りの赤いポスト』は、「ワークショップ参加者」を「役者」に仕立て、ワークショップと同時並行で撮影されたという異次元の作品だった。なかなか経験できないだろう、「0が1になる瞬間」を味わえる“狂気”の映画
あわせて読みたい
【秘話】15年で世界を変えたグーグルの”異常な”創業エピソード。収益化無視の無料ビジネスはなぜ成功し…
スマホやネットを使う人で、グーグルのお世話になっていない人はまずいないだろう。もはや「インフラ」と呼んでいいレベルになったサービスを生み出した企業の創業からの歴史を描く『グーグル秘録』は、その歩みが「無邪気さ」と「偶然」の産物であることを示している。凄まじいエピソード満載の信じがたい企業秘話
あわせて読みたい
【天才】『ご冗談でしょう、ファインマンさん』は、科学者のイメージが変わる逸話満載の非・科学エッセイ
「天才科学者」と言えばアインシュタインやニュートン、ホーキングが思い浮かぶだろうが、「科学者らしくないエピソード満載の天才科学者」という意味ではファインマンがずば抜けている。世界的大ベストセラー『ご冗談でしょう、ファインマンさん』は、「科学」をほぼ扱わないエッセイです
あわせて読みたい
【狂気】日本一将棋に金を使った将棋ファン・団鬼六の生涯を、『将棋世界』の元編集長・大崎善生が描く…
SM小説の大家として一時代を築きつつ、将棋に金を注ぎ込みすぎて2億円の借金を抱えた団鬼六の生涯を、『将棋世界』の元編集長・大崎善生が描くノンフィクション『赦す人』。虚実が判然としない、嘘だろうと感じてしまうトンデモエピソード満載の異端児が辿った凄まじい生涯
あわせて読みたい
【斬新】ホームレスの家を「0円ハウス」と捉える坂口恭平の発想と視点に衝撃。日常の見え方が一変する:…
早稲田大学建築学科在籍中から「建築物の設計」に興味を持てなかった坂口恭平が、「ホームレスの家」に着目した『TOKYO 0円ハウス0円生活』には、「家」に対する考え方を一変させる視点が満載。「家に生活を合わせる」ではなく、「生活に家を合わせる」という発想の転換が見事
あわせて読みたい
【驚異】『グレイトフル・デッドにマーケティングを学ぶ』って書名通りの本。異端ロックバンドの”稼ぎ方”
日本ではあまり知られていないが、熱狂的なファンを持つロックバンド「グレイトフル・デッド」。彼らは50年も前から、現代では当たり前となった手法を続け、今でも年間5000万ドルを稼いでいる。『グレイトフル・デッドにマーケティングを学ぶ』で「ファンからの愛され方」を学ぶ
あわせて読みたい
【驚異】「持続可能な社会」での「豊かな生活」とは?「くじら漁の村」で生きる人々を描く映画:『くじ…
手作りの舟に乗り、銛1本で巨大なクジラを仕留める生活を続けるインドネシアのラマレラ村。そこに住む人々を映し出した映画『くじらびと LAMAFA』は、私たちが普段感じられない種類の「豊かさ」を描き出す。「どう生きるか」を改めて考えさせられる作品だ
あわせて読みたい
【抽象】「思考力がない」と嘆く人に。研究者で小説家の森博嗣が語る「客観的に考える」ために大事なこ…
世の中にはあまりに「具体的な情報」が溢れているために、「客観的、抽象的な思考」をする機会が少ない。そんな時代に、いかに思考力を育てていくべきか。森博嗣が『人間はいろいろな問題についてどう考えていけば良いのか』を通じて伝える「情報との接し方」「頭の使い方」
あわせて読みたい
【狂気】バケモン・鶴瓶を映し出す映画。「おもしろいオッチャン」に潜む「異常さ」と「芸への情熱」:…
「俺が死ぬまで公開するな」という条件で撮影が許可された映画『バケモン』。コロナ禍で映画館が苦境に立たされなければ、公開はずっと先だっただろう。テレビで見るのとは違う「芸人・笑福亭鶴瓶」の凄みを、古典落語の名作と名高い「らくだ」の変遷と共に切り取る
あわせて読みたい
【危機】シードバンクを設立し世界の農業を変革した伝説の植物学者・スコウマンの生涯と作物の多様性:…
グローバル化した世界で「農業」がどんなリスクを負うのかを正しく予測し、その対策として「ジーンバンク」を設立した伝説の植物学者スコウマンの生涯を描く『地球最後の日のための種子』から、我々がいかに脆弱な世界に生きているのか、そして「世界の食」がどう守られているのかを知る
あわせて読みたい
【新視点】世界の歴史を「化学」で語る?デンプン・砂糖・ニコチンなどの「炭素化合物」が人類を動かし…
デンプン・砂糖・ニコチンなどは、地球上で非常に稀少な元素である「炭素」から作られる「炭素化合物」だ。そんな「炭素化合物」がどんな影響を与えたかという観点から世界の歴史を描く『「元素の王者」が歴史を動かす』は、学校の授業とはまったく違う視点で「歴史」を捉える
あわせて読みたい
【最新】「コロンブス到達以前のアメリカ大陸」をリアルに描く歴史書。我々も米国人も大いに誤解してい…
サイエンスライターである著者は、「コロンブス到着以前のアメリカはどんな世界だったか?」という問いに触れ、その答えが書かれた本がいつまで経っても出版されないので自分で執筆した。『1491 先コロンブス期アメリカ大陸をめぐる新発見』には、アメリカ人も知らない歴史が満載だ
あわせて読みたい
【解釈】詩人が語る詩の読み方。意味や読み方や良さが分からなくて全然気にしなくていい:『今を生きる…
私は学生時代ずっと国語の授業が嫌いでしたが、それは「作品の解釈には正解がある」という決めつけが受け入れ難かったからです。しかし、詩人・渡邊十絲子の『今を生きるための現代詩』を読んで、詩に限らずどんな作品も、「解釈など不要」「理解できなければ分からないままでいい」と思えるようになりました
あわせて読みたい
【おすすめ】濱口竜介監督の映画『親密さ』は、「映像」よりも「言葉」が前面に来る衝撃の4時間だった
専門学校の卒業制作として濱口竜介が撮った映画『親密さ』は、2時間10分の劇中劇を組み込んだ意欲作。「映像」でありながら「言葉の力」が前面に押し出される作品で、映画や劇中劇の随所で放たれる「言葉」に圧倒される。4時間と非常に長いが、観て良かった
あわせて読みたい
【あらすじ】濱口竜介監督『偶然と想像』は、「脚本」と「役者」のみで成り立つ凄まじい映画。天才だと思う
「映画」というメディアを構成する要素は多々あるはずだが、濱口竜介監督作『偶然と想像』は、「脚本」と「役者」だけで狂気・感動・爆笑を生み出してしまう驚異の作品だ。まったく異なる3話オムニバス作品で、どの話も「ずっと観ていられる」と感じるほど素敵だった
あわせて読みたい
【傑作】濱口竜介監督の映画『ドライブ・マイ・カー』(原作:村上春樹)は「自然な不自然さ」が見事な作品
村上春樹の短編小説を原作にした映画『ドライブ・マイ・カー』(濱口竜介監督)は、村上春樹の小説の雰囲気に似た「自然な不自然さ」を醸し出す。「不自然」でしかない世界をいかにして「自然」に見せているのか、そして「自然な不自然さ」は作品全体にどんな影響を与えているのか
あわせて読みたい
【興奮】世界的大ベストセラー『サピエンス全史』要約。人類が文明を築き上げるに至った3つの革命とは?
言わずと知れた大ベストセラー『サピエンス全史』は、「何故サピエンスだけが人類の中で生き残り、他の生物が成し得なかった歴史を歩んだのか」を、「認知革命」「農業革命」「科学革命」の3つを主軸としながら解き明かす、知的興奮に満ち溢れた1冊
あわせて読みたい
【知的】文系にオススメの、科学・数学・哲学の入門書。高橋昌一郎の「限界シリーズ」は超絶面白い:『…
例えば「科学」だけに限ってみても、「なんでもできる」わけでは決してない。「科学」に限らず、私たちが対峙する様々な事柄には「これ以上は不可能・無理」という「限界」が必ず存在する。高橋昌一郎の「限界シリーズ」から、我々が認識しておくべき「限界」を易しく学ぶ
あわせて読みたい
【感想】飲茶の超面白い東洋哲学入門書。「本書を読んでも東洋哲学は分からない」と言う著者は何を語る…
東洋哲学というのは、「最終回しか存在しない連続ドラマ」のようなものだそうだ。西洋哲学と比較にならないほど異質さと、インド哲学・中国哲学など個別の思想を恐ろしく分かりやすく描く『史上最強の哲学入門 東洋の哲人たち』は、ページをめくる手が止まらないくらい、史上最強レベルに面白かった
あわせて読みたい
【考察】映画『ジョーカー』で知る。孤立無援の環境にこそ”悪”は偏在すると。個人の問題ではない
「バットマン」シリーズを観たことがない人間が、予備知識ゼロで映画『ジョーカー』を鑑賞。「悪」は「環境」に偏在し、誰もが「悪」に足を踏み入れ得ると改めて実感させられた。「個人」を断罪するだけでは社会から「悪」を減らせない現実について改めて考える
あわせて読みたい
【興奮】飲茶氏の超面白い哲学小説。「正義とは?」の意味を問う”3人の女子高生”の主張とは?:『正義の…
なんて面白いんだろうか。哲学・科学を初心者にも分かりやすく伝える飲茶氏による『正義の教室』は、哲学書でありながら、3人の女子高生が登場する小説でもある。「直観主義」「功利主義」「自由主義」という「正義論」の主張を、「高校の問題について議論する生徒会の話し合い」から学ぶ
あわせて読みたい
【漫画原作】映画『殺さない彼と死なない彼女』は「ステレオタイプな人物像」の化学反応が最高に面白い
パッと見の印象は「よくある学園モノ」でしかなかったので、『殺さない彼と死なない彼女』を観て驚かされた。ステレオタイプで記号的なキャラクターが、感情が無いとしか思えないロボット的な言動をする物語なのに、メチャクチャ面白かった。設定も展開も斬新で面白い
あわせて読みたい
【無知】映画『生理ちゃん』で理解した気になってはいけないが、男(私)にも苦労が伝わるコメディだ
男である私にはどうしても理解が及ばない領域ではあるが、女友達から「生理」の話を聞く機会があったり、映画『生理ちゃん』で視覚的に「生理」の辛さが示されることで、ちょっとは分かったつもりになっている。しかし男が「生理」を理解するのはやっぱり難しい
あわせて読みたい
【興奮】飲茶氏が西洋哲学を語る。難解な思想が「グラップラー刃牙成分」の追加で驚異的な面白さに:『…
名前は聞いたことはあるがカントやニーチェがどんな主張をしたのかは分からないという方は多いだろう。私も無知なまったくの初心者だが、そんな人でも超絶分かりやすく超絶面白く西洋哲学を”分かった気になれる”飲茶『史上最強の哲学入門』は、入門書として最強
あわせて読みたい
【創作】クリエイターになりたい人は必読。ジブリに見習い入社した川上量生が語るコンテンツの本質:『…
ドワンゴの会長職に就きながら、ジブリに「見習い」として入社した川上量生が、様々なクリエイターの仕事に触れ、色んな質問をぶつけることで、「コンテンツとは何か」を考える『コンテンツの秘密』から、「創作」という営みの本質や、「クリエイター」の理屈を学ぶ
あわせて読みたい
【あらすじ】天才とは「分かりやすい才能」ではない。前進するのに躊躇する暗闇で直進できる勇気のこと…
ピアノのコンクールを舞台に描く『蜜蜂と遠雷』は、「天才とは何か?」と問いかける。既存の「枠組み」をいとも簡単に越えていく者こそが「天才」だと私は思うが、「枠組み」を安易に設定することの是非についても刃を突きつける作品だ。小説と映画の感想を一緒に書く
あわせて読みたい
【奇跡】鈴木敏夫が2人の天才、高畑勲と宮崎駿を語る。ジブリの誕生から驚きの創作秘話まで:『天才の思…
徳間書店から成り行きでジブリ入りすることになったプロデューサー・鈴木敏夫が、宮崎駿・高畑勲という2人の天才と共に作り上げたジブリ作品とその背景を語り尽くす『天才の思考 高畑勲と宮崎駿』。日本のアニメ界のトップランナーたちの軌跡の奇跡を知る
あわせて読みたい
【実像】ベートーヴェンの「有名なエピソード」をほぼ一人で捏造・創作した天才プロデューサーの実像:…
ベートーヴェンと言えば、誰もが知っている「運命」を始め、天才音楽家として音楽史に名を刻む人物だが、彼について良く知られたエピソードのほとんどは実は捏造かもしれない。『ベートーヴェン捏造 名プロデューサーは嘘をつく』が描く、シンドラーという”天才”の実像
あわせて読みたい
【教養】美術を「感じたまま鑑賞する」のは難しい。必要な予備知識をインストールするための1冊:『武器…
芸術を「感性の赴くまま見る」のは、日本特有だそうだ。欧米では美術は「勉強するもの」と認識されており、本書ではアートを理解しようとするスタンスがビジネスにも役立つと示唆される。美術館館長を務める著者の『武器になる知的教養 西洋美術鑑賞』から基礎の基礎を学ぶ
あわせて読みたい
【問い】「学ぶとはどういうことか」が学べる1冊。勉強や研究の指針に悩む人を導いてくれる物語:『喜嶋…
学校の勉強では常に「課題」が与えられていたが、「学び」というのは本来的に「問題を見つけること」にこそ価値がある。研究者の日常を描く小説『喜嶋先生の静かな世界』から、「学びの本質」と、我々はどんな風に生きていくべきかについて考える
あわせて読みたい
【驚愕】ロバート・キャパの「崩れ落ちる兵士」はどう解釈すべきか?沢木耕太郎が真相に迫る:『キャパ…
戦争写真として最も有名なロバート・キャパの「崩れ落ちる兵士」には、「本当に銃撃された瞬間を撮影したものか?」という真贋問題が長く議論されてきた。『キャパの十字架』は、そんな有名な謎に沢木耕太郎が挑み、予想だにしなかった結論を導き出すノンフィクション。「思いがけない解釈」に驚かされるだろう
あわせて読みたい
【天才】写真家・森山大道に密着する映画。菅田将暉の声でカッコよく始まる「撮り続ける男」の生き様:…
映画『あゝ荒野』のスチール撮影の際に憧れの森山大道に初めて会ったという菅田将暉の声で始まる映画『過去はいつも新しく、未来はつねに懐かしい』は、ちゃちなデジカメ1つでひたすら撮り続ける異端児の姿と、50年前の処女作復活物語が見事に交錯する
あわせて読みたい
【狂気】稀少本を収集・売買する「愛すべき変人コレクター」の世界と、インターネットによる激変:映画…
広大な本の世界を狩人のように渉猟し、お気に入りの本を異常なまでに偏愛する者たちを描き出す映画『ブックセラーズ』。実在の稀少本コレクターたちが、本への愛を語り、新たな価値を見出し、次世代を教育し、インターネットの脅威にどう立ち向かっているのかを知る
あわせて読みたい
【映画】『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』で号泣し続けた私はTVアニメを観ていない
TVアニメは観ていない、というかその存在さえ知らず、物語や登場人物の設定も何も知らないまま観に行った映画『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』に、私は大号泣した。「悪意のない物語」は基本的に好きではないが、この作品は驚くほど私に突き刺さった
あわせて読みたい
【難しい】映画『鳩の撃退法』をネタバレ全開で考察。よくわからない物語を超詳細に徹底解説していく
とても難しくわかりにくい映画『鳩の撃退法』についての考察をまとめていたら、1万7000字を超えてしまった。「東京編で起こったことはすべて事実」「富山編はすべてフィクションかもしれない」という前提に立ち、「津田伸一がこの小説を書いた動機」まで掘り下げて、実際に何が起こっていたのかを解説する(ちなみに、「実話」ではないよ)
あわせて読みたい
【情熱】常識を疑え。人間の”狂気”こそが、想像し得ない偉業を成し遂げるための原動力だ:映画『博士と…
世界最高峰の辞書である『オックスフォード英語大辞典』は、「学位を持たない独学者」と「殺人犯」のタッグが生みだした。出会うはずのない2人の「狂人」が邂逅したことで成し遂げられた偉業と、「狂気」からしか「偉業」が生まれない現実を、映画『博士と狂人』から学ぶ
あわせて読みたい
【実話】正論を振りかざす人が”強い”社会は窮屈だ。映画『すばらしき世界』が描く「正解の曖昧さ」
「SNSなどでの炎上を回避する」という気持ちから「正論を言うに留めよう」という態度がナチュラルになりつつある社会には、全員が全員の首を締め付け合っているような窮屈さを感じてしまう。西川美和『すばらしき世界』から、善悪の境界の曖昧さを体感する
あわせて読みたい
【感想】映画『窮鼠はチーズの夢を見る』を異性愛者の男性(私)はこう観た。原作も読んだ上での考察
私は「腐男子」というわけでは決してないのですが、周りにいる腐女子の方に教えを請いながら、多少BL作品に触れたことがあります。その中でもダントツに素晴らしかったのが、水城せとな『窮鼠はチーズの夢を見る』です。その映画と原作の感想、そして私なりの考察について書いていきます
あわせて読みたい
【解説】テネットの回転ドアの正体を分かりやすく考察。「時間逆行」ではなく「物質・反物質反転」装置…
クリストファー・ノーラン監督の映画『TENET/テネット』は、「陽電子」「反物質」など量子力学の知見が満載です。この記事では、映画の内容そのものではなく、時間反転装置として登場する「回転ドア」をメインにしつつ、時間逆行の仕組みなど映画全体の設定について科学的にわかりやすく解説していきます
あわせて読みたい
【救い】耐えられない辛さの中でどう生きるか。短歌で弱者の味方を志すホームレス少女の生き様:『セー…
死にゆく母を眺め、施設で暴力を振るわれ、拾った新聞で文字を覚えたという壮絶な過去を持つ鳥居。『セーラー服の歌人 鳥居』は、そんな辛い境遇を背景に、辛さに震えているだろう誰かを救うために短歌を生み出し続ける生き方を描き出す。凄い人がいるものだ
あわせて読みたい
【改革】AIは将棋をどう変えた?羽生善治・渡辺明ら11人の現役棋士が語る将棋の未来:『不屈の棋士』(…
既に将棋AIの実力はプロ棋士を越えたとも言われる。しかし、「棋力が強いかどうか」だけでは将棋AIの良し悪しは判断できない。11人の現役棋士が登場する『不屈の棋士』をベースに、「AIは将棋界をどう変えたのか?」について語る
あわせて読みたい
【天職】頑張っても報われない方へ。「自分で選び取る」のとは違う、正しい未来の進み方:『そのうちな…
一般的に自己啓発本は、「今、そしてこれからどうしたらいいか」が具体的に語られるでしょう。しかし『そのうちなんとかなるだろう』では、決断・選択をするべきではないと主張されます。「選ばない」ことで相応しい未来を進む生き方について学ぶ
あわせて読みたい
【諦め】「人間が創作すること」に意味はあるか?AI社会で問われる、「創作の悩み」以前の問題:『電気…
AIが個人の好みに合わせて作曲してくれる世界に、「作曲家」の存在価値はあるだろうか?我々がもうすぐ経験するだろう近未来を描く『電気じかけのクジラは歌う』をベースに、「創作の世界に足を踏み入れるべきか」という問いに直面せざるを得ない現実を考える
あわせて読みたい
【継続】「言語化できない」を乗り越えろ。「読者としての文章術」で、自分の思考をクリアにする:『読…
ブログやSNSなどが登場したことで、文章を書く機会は増えていると言える。しかし同時に、「他人に評価されるために書く」という意識も強くなっているだろう。『読みたいことを書けばいい』から、「楽しく書き”続ける”」ための心得を学ぶ
あわせて読みたい
【感想】人間関係って難しい。友達・恋人・家族になるよりも「あなた」のまま関わることに価値がある:…
誰かとの関係性には大抵、「友達」「恋人」「家族」のような名前がついてしまうし、そうなればその名前に縛られてしまいます。「名前がつかない関係性の奇跡」と「誰かを想う強い気持ちの表し方」について、『君の膵臓をたべたい』をベースに書いていきます
あわせて読みたい
【感想】努力では才能に勝てないのか?どうしても辿り着きたい地点まで迷いながらも突き進むために:『…
どうしても辿り着きたい場所があっても、そのあまりの遠さに目が眩んでしまうこともあるでしょう。そんな人に向けて、「才能がない」という言葉に逃げずに前進する勇気と、「仕事をする上で大事なスタンス」について『羊と鋼の森』をベースに書いていきます
あわせて読みたい
【表現者】「センスが良い」という言葉に逃げない。自分の内側から何かを表現することの本質:『作詞少…
大前提として、表現には「技術」が必要だ。しかし、「技術」だけでは乗り越えられない部分も当然ある。それを「あいつはセンスが良いから」という言葉に逃げずに、向き合ってぶつかっていくための心得とは何か。『作詞少女』をベースに「表現することの本質」を探る
あわせて読みたい
【前進】誰とも価値観が合わない…。「普通」「当たり前」の中で生きることの難しさと踏み出し方:『出会…
生きていると、「常識的な考え方」に囚われたり、「普通」「当たり前」を無自覚で強要してくる人に出会ったりします。そういう価値観に合わせられない時、自分が間違っている、劣っていると感じがちですが、そういう中で一歩踏み出す勇気を得るための考え方です
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
読書・本屋・図書館【本・映画の感想】 | ルシルナ
子どもの頃から現在までで4000冊以上の本を読んできましたが、本格的に読書を始めたのは20代前半からです。読む習慣をつけたり、どう本を選んでどう感想を文章にするのかに…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…















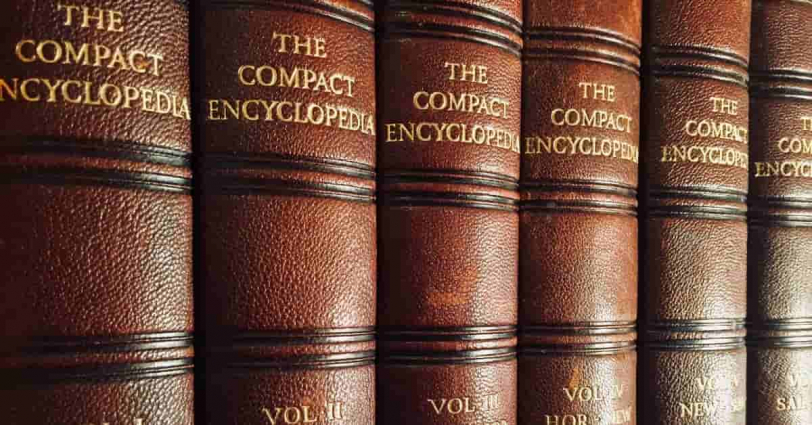


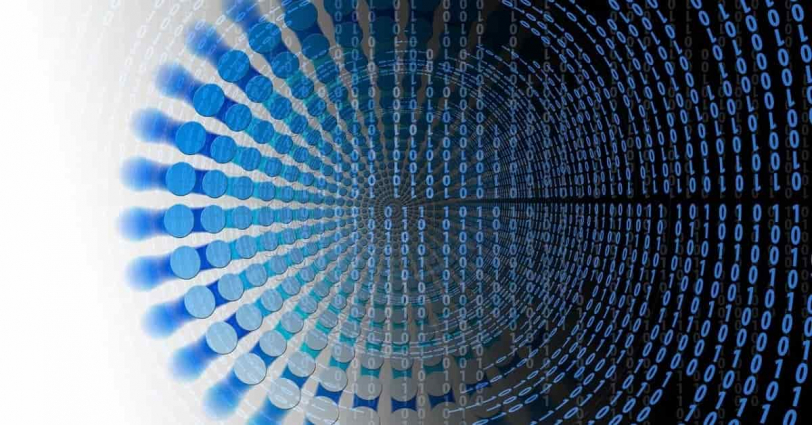




























































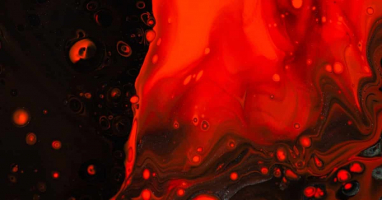


































コメント