目次
はじめに
この記事で取り上げる本
著:チャールズ・C. マン, 原著:Mann,Charles C., 翻訳:由紀子, 布施
¥4,250 (2022/03/09 20:49時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
この本をガイドにしながら記事を書いていきます
この記事の3つの要点
- アメリカの授業では、コロンブスが到着してからの歴史しか習わない
- 先住民を征服した過去を持つせいで、偏見の目で過去を捉えてしまう
- 「人口」「起源」「生態系との関わり」の3つの観点から主に記述する
歴史に興味がない、というかむしろ嫌いな私でも一気読みさせられた、知的興奮に満ちた1冊
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
『1491 先コロンブス期アメリカ大陸をめぐる新発見』を読んで知った「コロンブスが到着した頃のアメリカ」については、アメリカ人でさえ正しく理解できているわけではない
著者は本書のテーマとどう出会い、どう掘り下げていったのか
あわせて読みたい
【知的】「BLって何?」という初心者に魅力を伝える「腐男子」の「BLの想像力と創造力」講座:『ボクた…
「BLは知的遊戯である」という主張には「は?」と感じてしまうでしょうが、本書『ボクたちのBL論』を読めばその印象は変わるかもしれません。「余白の発見と補完」を通じて、「ありとあらゆる2者の間の関係性を解釈する」という創造性は、現実世界にどのような影響を与えているのか
本書のテーマは、この一文を抜き出すだけで理解できる。
コロンブスが到着したころの新世界はどんなところだったのだろう?

著者がこの「問い」に出会ったのは、コロンブスによる大陸到着500周年にあたる1992年のことだったそうだ。
著者はこの「問い」に触れ、学生時代の歴史の授業を思い返してみた。基本的に南北アメリカの歴史は、コロンブスがやってきてからのものしか語られない。そして、著者自身もそうだと言っているが、アメリカ人の多くは、「コロンブスが到着する以前のアメリカなんかには大した文明も存在せず、少数の人々が原始的な生活をしていただけだろう」と考えていた。
あわせて読みたい
【新視点】世界の歴史を「化学」で語る?デンプン・砂糖・ニコチンなどの「炭素化合物」が人類を動かし…
デンプン・砂糖・ニコチンなどは、地球上で非常に稀少な元素である「炭素」から作られる「炭素化合物」だ。そんな「炭素化合物」がどんな影響を与えたかという観点から世界の歴史を描く『「元素の王者」が歴史を動かす』は、学校の授業とはまったく違う視点で「歴史」を捉える
しかし著者は、そうではないことを知る。
そのときは知らなかったが、多くの研究者が生涯をかけてこれらの疑問に答えを出そうとしていたのだった。彼らが明らかにした当時の大陸のようすは、たいがいの欧米人が持っているイメージとはまったく異なっている。だがそれは、いまだに学会の外の人々にはほとんど知られていない。
「文明など存在しない原始的な生活」というよくあるイメージとはかけ離れた世界が既に明らかになっている。しかしそれらは研究の世界の外にはまったく知られていないと著者は気付いたのだ。
あわせて読みたい
【興奮】世界的大ベストセラー『サピエンス全史』要約。人類が文明を築き上げるに至った3つの革命とは?
言わずと知れた大ベストセラー『サピエンス全史』は、「何故サピエンスだけが人類の中で生き残り、他の生物が成し得なかった歴史を歩んだのか」を、「認知革命」「農業革命」「科学革命」の3つを主軸としながら解き明かす、知的興奮に満ち溢れた1冊
しかしその時点ではまだ、著者は本書の執筆など考えてもいなかった。それはある意味で当然だろう。というのも、著者は考古学者でも人類学者でも歴史学者でもなく、世界各国の一流誌に寄稿実績を持つサイエンスライターだからだ。歴史はまったくの門外漢であり、自分が手を出す領域ではないと考えていた。
しかし、やがて著者は、「コロンブス到着以前のアメリカの歴史」を著す決意をする。そのきっかけについてこんな風に書いている。
これはすごい、とわたしは思った。だれかが書くべきだ。きっと魅力的な本になるぞ、と。
わたしはそうした本が出版されるのをずっと待っていた。だが待っているうちに息子が学齢に達して、わたしが子供の頃に習ったとおりのことを――もうかなり前から疑問視されていた内容を――また学校で習いはじめ、いてもたってもいられない気持ちになってきた。そこでついに、だれも書いていないようだから自分で書いてみようと思い立ったのだ。

あわせて読みたい
【狂気?】オウム真理教を内部から映す映画『A』(森達也監督)は、ドキュメンタリー映画史に残る衝撃作だ
ドキュメンタリー映画の傑作『A』(森達也)をようやく観られた。「オウム真理教は絶対悪だ」というメディアの報道が凄まじい中、オウム真理教をその内部からフラットに映し出した特異な作品は、公開当時は特に凄まじい衝撃をもたらしただろう。私たちの「当たり前」が解体されていく斬新な一作
このようにして、畑違いの歴史分野に足を踏み入れることになったのである。
確かに専門外ではあるのだが、著者はサイエンスライターとして様々な専門家に話を聞き、実際に現場を見てきた経験があり、それを今回の取材にも活かすことができた。また、歴史は科学とは大きく異なり、発表された学説が「個人攻撃」「派閥争い」に発展することが多い。それ故、まったく畑違いの人物だからこそ様々な学説にアプローチでき、さらにそれらを公平に扱うことも可能だったと言っていいと思う。
また詳しくは後述するが、私は「歴史」という学問に対していささか嫌悪感を持ってしまうきらいがある。しかし、著者が科学者のようなスタンスで著してくれたお陰で、普段なら感じてしまうことが多い嫌悪感を抱かずに済んだ。そういう意味でも、サイエンスライターによる歴史書という本書の造りは、とても好ましいものに感じられる。
いずれにせよ本書は、「コロンブス到着以前のアメリカの歴史」というテーマが非常に秀逸であり、基本的に歴史にはまったく興味が持てない私のような人間にも非常に面白く読めてしまう見事な作品だと感じた。
あわせて読みたい
【驚嘆】人類はいかにして言語を獲得したか?この未解明の謎に真正面から挑む異色小説:『Ank: a mirror…
小説家の想像力は無限だ。まさか、「人類はいかに言語を獲得したか?」という仮説を小説で読めるとは。『Ank: a mirroring ape』をベースに、コミュニケーションに拠らない言語獲得の過程と、「ヒト」が「ホモ・サピエンス」しか存在しない理由を知る
私が抱いてしまう「歴史」という学問への「嫌悪感」について
まず、私が何故「歴史」という学問を好きになれないのかについて触れておきたいと思う。その説明をした上で、「本書の何が面白く感じられたのか」について触れていくつもりだ。基本的には本書の内容とはまったく関係がないので、特に興味がないという方は飛ばしていただいて構わない。
私は小学生の頃には既に、歴史の授業に対して違和感を覚えていた。その最大の理由は、「これこれこうでした」と断言するような形で説明されることだ。私はそれに対して、「断言するほど確実なことなのか?」と常に疑問に感じていた。

あわせて読みたい
【誤解】世界的大ベストセラー『ファクトフルネス』の要約。我々は「嘘の情報」を信じ込みやすい
世界の現状に関する13の質問に対して、ほとんどの人が同じ解答をする。最初の12問は不正解で、最後の1問だけ正答するのだ。世界的大ベストセラー『ファクトフルネス』から、「誤った世界の捉え方」を認識し、情報を受け取る際の「思い込み」を払拭する。「嘘の情報」に踊らされないために読んでおくべき1冊だ
例えば、私が学生だった頃は、鎌倉幕府の成立年は1192年だった。「いい国作ろう鎌倉幕府」というのは恐らく、語呂合わせの暗記法として一番有名だろう。しかし現在多くの教科書では1185年に変わっているそうだ。どのような背景からそうなったのかは知らないが、私たちが覚えた1192年は一体なんだったんだ、と感じる。
あるいは、歴史の教科書から「聖徳太子」という表記が消えるらしい。この話はややこしいので詳しくは触れないが、要するに、「『聖徳太子』のものとされる功績を1人で行ったと考えるのは無理がある」ということのようだ。「聖徳太子」のモデルとされる「厩戸皇子」は実在の人物だが、「聖徳太子」と呼ばれるべき個人は実在しなかったのではないか、というのが現在の通説らしい。
このように、教科書の記述が変わることもある。であれば、「これこれこうだった”可能性がある”」という風に教えてほしかったと私は感じてしまう。
もちろん、科学だって教科書の記述は変わる。例えば、恐らく教科書には未だに「物質を構成する最も小さなものは原子」と載っているだろう。しかし既に、原子よりも小さな存在として「クォーク」が知られている。
あわせて読みたい
【限界】「科学とは何か?」を知るためのおすすめ本。科学が苦手な人こそ読んでほしい易しい1冊:『哲学…
「科学的に正しい」という言葉は、一体何を意味しているのだろう?科学者が「絶対に正しい」とか「100%間違っている」という言い方をしないのは何故だろう?飲茶『哲学的な何か、あと科学とか』から、「科学とはどんな営みなのか?」について考える
しかし、歴史と科学では大きな違いがあると私は思う。それは、「明確な証拠の存在」だ。
科学では、「誰が実験を行っても同じ現象が再現される」と確認されて初めて、「これが現時点では最も正しい」と認められる。未発見の現象・効果が新たに見つかることで、それまでの理論が覆される可能性は常にあるが、科学の場合は、「その時点での正しさを確定させる証拠」が存在すると言っていいだろう。
しかし歴史の場合、それがどんな「証拠」であれ「確実」と呼べるものなど存在しないのではないか、というのが私の基本的な考えだ。科学の場合、「覆る可能性は常にあるが、その時点では絶対的な証拠が存在する」と言える。しかし歴史の場合、「絶対的と呼べる証拠」などほとんど存在し得ないと思っている。
もちろん、考古学の分野であれば、骨や土器などを科学的に分析することで、かなり客観性の高い証拠が得られると思う。しかし、書物や手紙など「人間が記したもの」を証拠にする場合、どうしても「曖昧さ」「不確実さ」が混じることになるはずだ。
例えばこんな風に考えてみよう。今から1000年後の未来に、2022年に使用されたスマートフォンが発見された。そしてその内部の情報を解析し、残された写真やSNSの記述、GPSで記録された経路などが判明したとする。では1000年後の歴史学者が、そのスマートフォンを元に「2022年はこのような時代だった」と判断するのは、歴史を正しく捉えていると言えるだろうか?

あわせて読みたい
【始まり】宇宙ができる前が「無」なら何故「世界」が生まれた?「ビッグバンの前」は何が有った?:『…
「宇宙がビッグバンから生まれた」ことはよく知られているだろうが、では、「宇宙ができる前はどうなっていたのか」を知っているだろうか? 実は「宇宙は”無”から誕生した」と考えられているのだ。『宇宙が始まる前には何があったのか?』をベースに、ビッグバンが起こる前の「空間も時間も物理法則も存在しない無」について学ぶ
2022年を生きた1人の人間のスマートフォンから得られる情報が、その時代を明確に反映していると考えるのは難しい。そして似たようなことを、私は歴史という学問に対して感じてしまうのだ。
歴史研究ではもう少しちゃんとした公的な文書を元に判断している、という反論もあると思う。しかし、仮にそれが公文書だとしても、都合よく改ざんされている可能性は常にある。我々だって、森友学園問題でその事実を改めて認識したはずだ。あるいは、改ざんされていないとしても、公文書が現実をきちんと反映しているかはまた別問題だ。「統計によれば、経済成長率が上がっている」などのニュースを耳にしても、それは私たち全体の実感とはかけ離れているかもしれない。
つまり、それが「人間による記録」である以上、「確実な証拠」にはなり得ない。そして歴史を教える際には、このことも一緒に伝えるべきだと私は思っているのだ。
しかし歴史の授業では、「このようなことがかつてあった」と、まるで断定するかのように教わる。そのことに、私は子どもの頃から苛立ちを覚えていた。大人になってからも、歴史の記述を読むと、なんだかイライラしてしまうことがある。
しかし本書は、サイエンスライターが書いていることもあり、断定するような押し付けを感じずに済んだ。様々な専門家の多様な意見が同時に提示された上で、門外漢である著者が最も可能性が高いと思うシナリオを物語的に提示する、というスタンスが明確なので、普段どうしても感じてしまう違和感を抱かずに読める。
そういう意味でも本書は、私と同じような「歴史が好きではなく馴染みもあまりない人」でも楽しめる作品だと言えると思う。
あわせて読みたい
【悲劇】アメリカの暗黒の歴史である奴隷制度の現実を、元奴隷の黒人女性自ら赤裸々に語る衝撃:『ある…
生まれながらに「奴隷」だった黒人女性が、多くの人の協力を得て自由を手にし、後に「奴隷制度」について書いたのが『ある奴隷少女に起こった出来事』。長らく「白人が書いた小説」と思われていたが、事実だと証明され、欧米で大ベストセラーとなった古典作品が示す「奴隷制度の残酷さ」
本書の3つのキーワードと、歴史を語る上で注意すべき「ホームバーグの誤り」について
わたしはまず、1492年当時の先住民人口の推計値が引き上げられたことを、また、その理由について書いた。それから、先住民が従来の説より古くからこの大陸に住んでいたと考えられるようになった理由、彼らが従来の説よりも複雑な社会を築き、高度なテクノロジーを持っていたと考えられる理由を書いた。この章では、ホームバーグの誤りのバリエーションをもう一つ、取りあげたい。それは、先住民が環境をコントロールしなかった、あるいはできなかったという思い込みである。
本書で著者はこのように書き、「人口」「起源」「生態系との関わり」という3つの切り口を提示する。話題は決してそれだけに留まらないが、主にこれら3つの観点から、アメリカ人が思い込んでいる「『コロンブス到着以前のアメリカ』のイメージ」を覆す主張を様々に紹介していく作品だ。しかしそれらに触れる前にまず、アメリカ人がどのようなイメージを抱いているのか抜き出しておこう。

あわせて読みたい
【人類学】少数民族・ムラブリ族に潜入した映画『森のムラブリ』は、私たちの「当たり前」を鮮やかに壊す
タイとラオスにまたがって存在する少数民族・ムラブリ族に密着したドキュメンタリー映画『森のムラブリ』。「ムラブリ族の居住地でたまたま出会った日本人人類学者」と意気投合し生まれたこの映画は、私たちがいかに「常識」「当たり前」という感覚に囚われているのかを炙り出してくれる
アメリカの先住民は、一万三千年ほどまえにベーリング海峡に出来た無氷回廊を通ってアメリカ大陸にやってきた。それからは、複雑な文明を築くことなく、槍などの原始的な道具で狩りをし、そこまで大規模な社会は存在せず、つまり人口も多くなく、自然の景観を損なうことなく自然に手を加えることなく、コロンブスがやってくるまでずっと生きてきた。
具体的に考えたことはないとしても、私たちも基本的に同じようなイメージを持っていると言っていいと思う。そしてこのイメージが本書によってどんどん覆されていくのだ。
さて、前述した引用中に「ホームバーグの誤り」という言葉が出てくるが、これについても説明しておこう。この用語自体は、著者の造語であるようだ。
ホームバーグというのは人名で、1940年から42年にかけてボリビア・ベニ地方に住む先住民シリオノ族と共に生活しながら彼らを研究した博士課程の若者である。そして彼がしてしまった「勘違い」を「ホームバーグの誤り」と名付けているわけだ。
あわせて読みたい
【驚愕】ロバート・キャパの「崩れ落ちる兵士」はどう解釈すべきか?沢木耕太郎が真相に迫る:『キャパ…
戦争写真として最も有名なロバート・キャパの「崩れ落ちる兵士」には、「本当に銃撃された瞬間を撮影したものか?」という真贋問題が長く議論されてきた。『キャパの十字架』は、そんな有名な謎に沢木耕太郎が挑み、予想だにしなかった結論を導き出すノンフィクション。「思いがけない解釈」に驚かされるだろう
ホームバーグはシリオノ族について、「世界で最も文化的に遅れた人々」と紹介している。その生活は、私たちがなんとなくイメージする「山奥で暮らす原住民」のものと同じと言っていいだろう。服を着ることはなく、飢えと貧困にさらされており、家畜を飼う余裕もなく、楽器や宗教らしきものも有していない、そんな生活だ。そしてホームバーグは、「彼らは太古の昔からこのような生活を続けてきた」と結論した。
しかしこれは「勘違い」であることが判明している。シリオノ族は、大昔からそのような貧しい生活をしていたわけではないのだ。ではなぜ彼らは、1940年の時点でそのような厳しい状況に置かれてしまっていたのか。

それは、1920年代にシリオノ族が暮らす地域でインフルエンザが大流行したからだ。ホームバーグがやってくるまでに、それまでの人口の95%以上が喪われたと後の調査で判明したのである。またシリオノ族は、彼らの土地を狙う白人の牧場経営者とも争いを続けており、その闘いに疲弊してもいた。様々な理由で、満身創痍だったのだ。
著者は、ホームバーグが置かれた状況をこのように表現している。
つまり、ナチの強制収容所から脱走してきた難民を見て、つねに裸足で腹を空かせている民族だと思いこんだようなものだった。
あわせて読みたい
【真実】ホロコーストが裁判で争われた衝撃の実話が映画化。”明らかな虚偽”にどう立ち向かうべきか:『…
「ホロコーストが起こったか否か」が、なんとイギリスの裁判で争われたことがある。その衝撃の実話を元にした『否定と肯定』では、「真実とは何か?」「情報をどう信じるべきか?」が問われる。「フェイクニュース」という言葉が当たり前に使われる世界に生きているからこそ知っておくべき事実
なるほどという感じではないだろうか。
では著者はなぜこの「ホームバーグの誤り」に言及しているのだろうか。それは、先コロンブス期におけるアメリカの歴史解釈においても、同じような「勘違い」が様々な場面で散見されるからだ。
私たちが、「コロンブス到着以前のアメリカ」を「大した文明を持たない世界」と捉えてしまうのは、コロンブスらヨーロッパの人々がアメリカ大陸にやってきた時にまさにそのような状態にあったからだ。しかし実は、ヨーロッパ人がやってくる以前に、疫病の蔓延によって人口が激減し、文明も崩壊してしまっていた。そして、その成れの果てだけを見ているからこそ、「アメリカ大陸には大した文明はなかった」と思い込んでしまっているのである。
あわせて読みたい
【無知】メディアの問題の本質は?「報道の限界」と「情報の受け取り方」を独裁政治の現実から知る:『…
メディアは確かに「事実」を報じている。しかし、報道に乗らない情報まで含めなければ、本当の意味で世の中を理解することは難しいと、『こうして世界は誤解する』は教えてくれる。アラブ諸国での取材の現実から、報道の「限界」と「受け取り方」を学ぶ
つまり本書は、「ホームバーグの誤り」を乗り越えて歴史を捉える視点も与えてくれる作品だと言える。
興味深いのは、「アメリカには『ホームバーグの誤り』を推進させる力が存在する」という点だろう。つまり、「先コロンブス期のアメリカ大陸は大した文明を持たない世界だった」と考えたい人が多いようなのだ。
その理由について、本書に登場するある先住民がこんな風に語っている。
考古学の主たる使命は、白人の罪悪感をやわらげることだという。
この視点は、非常に面白いと感じた。
アメリカという国家は基本的に、コロンブスに始まった「ヨーロッパ人による征服」によって出来上がった国である。だからこそ、その「征服以前の世界」が大したものではない方が、征服した側の罪悪感が薄まる、というわけだ。「アメリカ建国の祖たちは間違ったことをしたわけではないのだ」と考えたい気持ちが、「先コロンブス期のアメリカはどのような世界だったのか?」という問いを歪め、結果として「誤った歴史」が広まってしまった、と著者は指摘している。
あわせて読みたい
【意外】東京裁判の真実を記録した映画。敗戦国での裁判が実に”フェア”に行われたことに驚いた:『東京…
歴史に詳しくない私は、「東京裁判では、戦勝国が理不尽な裁きを行ったのだろう」という漠然としたイメージを抱いていた。しかし、その印象はまったくの誤りだった。映画『東京裁判 4Kリマスター版』から東京裁判が、いかに公正に行われたのかを知る

なるほどこれは、日本人が日本の歴史を学ぶ際には持つことがない視点だと思うし、「歴史認識」の難しさみたいなものを改めて感じさせられるエピソードだと感じた。
先コロンブス期の「人口」について
人口に関しては、「ホームバーグの誤り」の説明の中で触れた通り、コロンブス到着に直前に疫病が蔓延するまでは、アメリカ大陸の人口はかなりのものだったようだ。本書の中からそれが分かる文章をいくつか抜き出してみよう。
やがてドビンズは、1491年当時のアメリカ大陸の人口は9000万人から1億1200万人であったとする見解を発表した。べつの言い方をすれば、コロンブスが大西洋をわたったとき、アメリカ大陸には、ヨーロッパ全土を合わせたよりも多くの人々が暮らしていたというのである。
彼らは、コロンブス到着当時のメキシコには、中央高地だけでも2520万人の先住民が暮らしていたという結論を出したのだ。ちなみに、この時代のスペイン、ポルトガルは、両国の人口を合わせても1000万人に満たなかった。当時のメキシコ中央部は地球上でもっとも人口の多い地域であったとし、人口密度も中国やインドの二倍だったと推定した。
彼は紀元1000年にはこの都市(※ティワナク)が11万5000人もの人口を擁し、周辺地域にも25万人が暮らしていたと書いている。フランスのパリでさえ、人口が25万人に達したのは500年もあとのことだった。
研究者によって出てくる数値に多少の違いはあるようだが、どのデータからも言えることは、「先コロンブス期のアメリカ大陸には、地球上のどの地域よりも多くの人が住んでいた」ということだ。この点だけは間違いないと言えるだろう。

にもかかわらず、ヨーロッパ人にあっけなく侵略されてしまった。そして先述した通り、それは伝染病のせいなのだ。
国連の1999年の推計では、16世紀はじめごろの地球人口は約5億人とされている。もしドビンズの推計が正しいとすれば、伝染病によって、17世紀の前半までに8000万人から1億人の先住民が命を奪われたことになる。地球上に住む人の5人にひとりが伝染病で亡くなったということだ。
伝染病は決してアメリカ大陸だけを襲ったわけではないが、もし伝染病がなければヨーロッパ人の侵略を許すこともなかっただろう。アメリカ大陸では、伝染病の蔓延により、人口が90%以上減ったと推計されているそうだ。
あわせて読みたい
【デマ】情報を”選ぶ”時代に、メディアの情報の”正しさ”はどのように判断されるのか?:『ニューヨーク…
一昔前、我々は「正しい情報を欲していた」はずだ。しかしいつの間にか世の中は変わった。「欲しい情報を正しいと思う」ようになったのだ。この激変は、トランプ元大統領の台頭で一層明確になった。『ニューヨーク・タイムズを守った男』から、情報の受け取り方を問う
当時のヨーロッパ人も、
伝染病という神のご加護のお陰で、この土地を自由に平和に所有できる
というような記述をしているらしい。準備不足で少人数だったヨーロッパ人がアメリカ大陸を侵略できたのは、まさに伝染病のお陰なのである。
私たちはなんとなく、「勇猛果敢なヨーロッパ人が、非力で教養のない先住民を簡単に制圧した」と考えがちだが、最新の研究結果からはまったく違う姿が浮かんでいるというわけだ。アメリカ人としては認めたくない事実かもしれないし、そう考えると、これらの歴史が「アメリカの歴史」として広まることがない背景も理解できるように思う。
アメリカ先住民の「起源」と、文明の発展について
コロンブスが「新大陸」にやってきて以来、アメリカ先住民の「起源」はずっと謎のままだったそうだ。
あわせて読みたい
【驚嘆】人類はいかにして言語を獲得したか?この未解明の謎に真正面から挑む異色小説:『Ank: a mirror…
小説家の想像力は無限だ。まさか、「人類はいかに言語を獲得したか?」という仮説を小説で読めるとは。『Ank: a mirroring ape』をベースに、コミュニケーションに拠らない言語獲得の過程と、「ヒト」が「ホモ・サピエンス」しか存在しない理由を知る
先述した通り、元々は「1万3000年前にベーリング海峡の無氷回廊を通ってアメリカ大陸にやってきた」というのが通説だった。「無氷回廊」とは、氷に覆われた「氷床」と呼ばれる場所の一部にあったとされる、氷で覆われていない場所のことだ。アメリカ大陸へヒトが移動するための唯一の経路だと長年考えられていたものである。

しかし研究者が様々な証拠を突き合わせた結果、現在では、
彼らはほぼ間違いなく、無氷回廊が開けた時期より以前にそこに到達していたはずだった。
と考えられるようになっているという。「無氷回廊」が開けたのは今から1万4000年~1万5000年前とされているのだが、
アメリカ先住民が二万年前、三万年前から大陸に住んでいたかもしれない。
という説も存在するそうだ。結局現在も、アメリカ先住民がどこから大陸にやってきたのか、その移動経路は明らかになっていない。しかし少なくとも、それまで通説とされていた考えを否定する証拠がかなり積み上がっている、という状況ではあるようだ。
さて、この「アメリカ先住民の起源」だが、これが問題として持ち上がった理由が興味深い。なんとそこには「創世記」が関係しているのである。
有名な話だろうが、元々コロンブスは「インド」にたどり着いたと考えていた。だから、アメリカ先住民は「インディアン」と呼ばれているのだ。しかしコロンブスの後継者によって、コロンブスがたどり着いたのは、「インド」どころか「アジアの一部」ですらないことが明らかになる。そしてこれによって、キリスト教の世界に大問題が引き起こされたのだ。
あわせて読みたい
【教養】美術を「感じたまま鑑賞する」のは難しい。必要な予備知識をインストールするための1冊:『武器…
芸術を「感性の赴くまま見る」のは、日本特有だそうだ。欧米では美術は「勉強するもの」と認識されており、本書ではアートを理解しようとするスタンスがビジネスにも役立つと示唆される。美術館館長を務める著者の『武器になる知的教養 西洋美術鑑賞』から基礎の基礎を学ぶ
その問題とは、以下のようなものである。
創世記には、ありとあらゆる人間と動物はノアの洪水で死んでしまい、方舟に乗ってトルコ東部にあったと思われるアララト山の頂に降り立ったものだけが生き残ったと書いてある。ではなぜ、人間や動物があの広大な太平洋を渡ることができたのだろうか。インディオ/インディアンの存在は、聖書とキリスト教を否定するのだろうか。

キリスト教の世界では、ノアの洪水の後、地球上すべての生物は、今の地名で言うと「トルコ」にいたと考えられている。しかし、アメリカ大陸に人間が住んでいるということは、「ユーラシア大陸から海を越えてアメリカ大陸まで渡った」ということになるはずだ。しかし、コロンブスらはアメリカ大陸への渡航を相当な苦労を経て成し遂げた。ノアの洪水を生き延びて「トルコ」にいたはずの人間は、アメリカ大陸まで渡ることなど可能だっただろうか? もしそれが不可能だったなら、創世記の記述を疑わざるを得なくなってしまう。
このような観点から「アメリカ先住民の起源」が問題視されるようになった、というわけだ。考古学的な見地から生まれた問いではなく、キリスト教を揺るがす問題として認識されていた、という点が非常に興味深いと感じた。
さて、そんな起源不明のアメリカ先住民だが、現在までの研究によれば、世界有数の文明を持っていたとも考えられているようだ。歴史の授業では、インダス文明、メソポタミア文明などが「栄えた文明」だったと教わるが、古代からアメリカ大陸で文明が盛んだったと教わることなどない。
それには理由がある。考古学の常識では、「農耕に適した場所でしか文明は発展できない」と考えられており、アメリカ大陸がそれに当てはまるとは認識されていなかったのだ。
あわせて読みたい
【危機】シードバンクを設立し世界の農業を変革した伝説の植物学者・スコウマンの生涯と作物の多様性:…
グローバル化した世界で「農業」がどんなリスクを負うのかを正しく予測し、その対策として「ジーンバンク」を設立した伝説の植物学者スコウマンの生涯を描く『地球最後の日のための種子』から、我々がいかに脆弱な世界に生きているのか、そして「世界の食」がどう守られているのかを知る
しかし例えば、痩せた土地で地震が起きやすかったペルー中部のノルテ・チコという地域では、紀元前3500年前に文明が興ったと考えられている。他にも様々に研究がなされており、アメリカ大陸にはそれまで知られていなかった様々な文明が存在したという証拠が見つかっているそうだ。
彼らの推測通り、アスペロ遺跡が現在考えられているよりもずっと古いとなれば、世界最古の都市――人類の文明発祥地――を名乗る資格を獲得できる可能性もある。
もしいまマクニールが「世界史」を執筆するとしたら、新たに二つの地域を書き加えることになるだろう。二つのうち、より広く知られているのは、紀元前にオルメカなどの文明がいくつも栄えたメソアメリカ。もう一つは、メソアメリカよりもずっと古い文明の発祥地でありながら、二十一世紀になったようやく光があたったペルーの海岸地方だ。

研究が進めば、教科書の記述が書き換わるかもしれない。
さらに本書には、アメリカの文明が生み出したかもしれない様々な「発明」についても触れている。
考古学上の記録から判断すると、驚くほど短期間で文字がつくられ、発展したことになる。シュメールでは6000年かかったが、メソアメリカでは1000年もかからなかったのだ。しかもその短いあいだに、メソアメリカ社会全体で十種類以上の文字体系が生まれているのである。
あわせて読みたい
【人類学】少数民族・ムラブリ族に潜入した映画『森のムラブリ』は、私たちの「当たり前」を鮮やかに壊す
タイとラオスにまたがって存在する少数民族・ムラブリ族に密着したドキュメンタリー映画『森のムラブリ』。「ムラブリ族の居住地でたまたま出会った日本人人類学者」と意気投合し生まれたこの映画は、私たちがいかに「常識」「当たり前」という感覚に囚われているのかを炙り出してくれる
(ゼロは)ヨーロッパには十二世紀になってから、今日使われているアラビア数字ととともに伝わった。しかしアメリカ大陸で最古のゼロの記録は、357年ごろのものと思われるマヤ遺跡から見つかっている。これは恐らくサンスクリットよりも古い。
オルメカ人やマヤ人など、メソアメリカに文明を興した人々は、世界的に見ても数学と天文学のパイオニアだったのだが、なぜか車輪を実用的な道具として使わなかったのだ。驚いたことに、彼らは車輪を発明しながら、子供のおもちゃにしか使わなかった。
「ホームバーグの誤り」の方を信じておきたい人からすれば「不都合な真実」でしかないかもしれないが、アメリカ大陸でも高度な文明が発展していたのだという事実はとても興味深い。
先コロンブス期の「生態系との関わり」について
アマゾンの森林を見ると、「人の手が加わっていない、太古の昔からそのまま残っている自然だ」と感じるだろう。
メガーズという考古学者も、同じように考えた。彼は、
環境としての熱帯雨林は、焼き畑耕作に代表されるレベルまでしか文化の発達を許さない。

という説を唱え、環境団体などに支持された。そしてこの説を元に、「アマゾンの森林は、人間の干渉を受けたことがない土地だ」と考えられるようになり、「人の手が加わっていないありのままの自然をそのまま残そう」という機運が高まっていく。
あわせて読みたい
【ゴミ】プラスチックによる環境問題の実態を描く衝撃の映画。我々は現実をあまりに知らない:映画『プ…
プラスチックごみによる海洋汚染は、我々の想像を遥かに超えている。そしてその現実は、「我々は日常的にマイクロプラスチックを摂取している」という問題にも繋がっている。映画『プラスチックの海』から、現代文明が引き起こしている環境破壊の現実を知る
また1930年代には、「マヤ文明が崩壊したのは、環境容量の限界を超えたからだ」という仮説も出てきた。これは要するに、「人類よりも環境の方が強く、人類は環境の制約の中でしか生活できない」ということだ。
このような考え方を背景にしながら、「人跡未踏の自然を守る」という大義名分が広まっていった。
しかし近年、このような見方が疑問視され始めている。というのも、先住民たちが実は自然環境に積極的に関与しており、努力して改良を加えた結果として現在のような姿になっている、という考えが出てきたからだ。

近年、アマゾン先住民が環境に大きな影響を及ぼしたと考える研究者が増えてきた。人類学者のあいだでは、広大なアマゾンの森林もまた、カホキアやマヤ中部地域と同様、文化の所産――つまり人工物――だという意見が出てきているのだ。
ニューヨーク州立大学ビンガムトン校の人類学者、ピーター・スタールも、「環境保護論者は人跡未踏の原始の世界と思いたがっているが、多くの研究者は、じつは何千年もの昔から人の手によって管理されてきたと考えている」と報告している。エリクソンは「つくられた環境」という表現は、「すべてとは言わないまでも、新熱帯区(北回帰線の北米、中南米、西インド諸島をふくむ生物地理区)の景観のほとんどにあてはまる」とする見解を述べている。
あわせて読みたい
【意外】思わぬ資源が枯渇。文明を支えてきた”砂”の減少と、今後我々が変えねばならぬこと:『砂と人類』
「砂が枯渇している」と聞いて信じられるだろうか?そこら中にありそうな砂だが、産業用途で使えるものは限られている。そしてそのために、砂浜の砂が世界中で盗掘されているのだ。『砂と人類』から、石油やプラスチックごみ以上に重要な環境問題を学ぶ
現代では、海を埋め立てて土地にしたり、森林を切り開いてゴルフ場にするなど、「自然環境に大きく手を加えること」が可能だが、しかしそれらは、かなり大規模な工事を要するものだと認識されているだろう。だからこそ、重機などなかった先住民には、自然環境に手を加えられたはずがない、という発想も当然だと思う。
しかし、現在私たちが「手を加えられていない」と考えている様々な自然が、実は先住民の手によって改良された、いわば「人工物」なのではないかというのだ。しかもそれは、非常に高度に行われたと考えられている。

現代の観点から見れば、こうした移行を成功させたことはみごととしか言いようがない。徹底的に、しかも広範囲にわたっておこなわれたので、コロンブス以後、ここを訪れたヨーロッパ人は、果樹の数が多いことと、開けた広大な土地が多いことに驚いた。だが自分たちと同じ人間がそれをつくったのだとは夢にも思わなかった。バートラムも自分が目にした景観が人工のものであることを見抜けなかったが、それは一つに、森の外科手術がまったく痕跡を残さずにおこなわれてからである。
つまり、「人の手で行ったとは思えない規模のことを、人の手が行ったとまったく悟らせない形で実現した」というわけだ。当時のヨーロッパ人が「自分たちと同じ人間がやったと思わなかった」のは当然だろうし、我々もまたそんな風には考えられないだろう。
あわせて読みたい
【映画】『街は誰のもの?』という問いは奥深い。「公共」の意味を考えさせる問題提起に満ちた作品
映画『街は誰のもの?』は、タイトルの通り「街(公共)は誰のものなのか?」を問う作品だ。そしてそのテーマの1つが、無許可で街中に絵を描く「グラフィティ」であることもまた面白い。想像もしなかった問いや価値観に直面させられる、とても興味深い作品である
またアマゾンの森林地帯には、テラ・プレータという名前で知られる非常に肥沃な大地が存在するのだが、この土地は研究者をもの凄く驚かせたという。何故なら、
教科書どおりに考えれば、そんなところに、そんな土壌があるはずがない。
からだ。常識では考えられない土地だという。
もしこの土壌の秘密を解明できれば、アフリカの農業を危機に追い込んでいる劣悪な土地を改良することができるかもしれない。
とも考えられているのである。現代の知見でもその手法が解明できていない土地改良を、先住民がやってのけたというわけだ。
これもまた、イメージで歴史を捉えることの危険性を伝えてくれる話だろう。
あわせて読みたい
【危機】遺伝子組み換え作物の危険性を指摘。バイオ企業「モンサント社」の実態を暴く衝撃の映画:映画…
「遺伝子組み換え作物が危険かどうか」以上に注目すべきは、「モンサント社の除草剤を摂取して大丈夫か」である。種子を独占的に販売し、農家を借金まみれにし、世界中の作物の多様性を失わせようとしている現状を、映画「モンサントの不自然な食べもの」から知る
著:チャールズ・C. マン, 原著:Mann,Charles C., 翻訳:由紀子, 布施
¥4,250 (2022/03/09 20:51時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品読了済】私が読んできたノンフィクション・教養書を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が読んできたノンフィクションを様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本選びの参考にして下さい。
最後に
本書は、日本語版の発売が2007年であり、既に15年ほど経過している。本書出版後、アメリカの歴史教科書が変わったのか、あるいはそのままなのか分からないが、15年も経っていれば何か進展はありそうだと思う。
700ページを超える非常に分厚い本だが、歴史に興味のない私でも一気読みさせられてしまう作品だった。まさに「アメリカ人も知らない歴史」であり、教科書では知ることが出来ない知見が満載の1冊だ。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【衝撃】ウクライナでのホロコーストを描く映画『バビ・ヤール』は、集めた素材映像が凄まじすぎる
ソ連生まれウクライナ育ちの映画監督セルゲイ・ロズニツァが、「過去映像」を繋ぎ合わせる形で作り上げた映画『バビ・ヤール』は、「単一のホロコーストで最大の犠牲者を出した」として知られる「バビ・ヤール大虐殺」を描き出す。ウクライナ市民も加担した、そのあまりに悲惨な歴史の真実とは?
あわせて読みたい
【現実】映画『私のはなし 部落のはなし』で初めて同和・部落問題を考えた。差別はいかに生まれ、続くのか
私はずっと、「部落差別なんてものが存在する意味が分からない」と感じてきたが、映画『私のはなし 部落のはなし』を観てようやく、「どうしてそんな差別が存在し得るのか」という歴史が何となく理解できた。非常に複雑で解決の難しい問題だが、まずは多くの人が正しく理解することが必要だと言えるだろう
あわせて読みたい
【映画】『街は誰のもの?』という問いは奥深い。「公共」の意味を考えさせる問題提起に満ちた作品
映画『街は誰のもの?』は、タイトルの通り「街(公共)は誰のものなのか?」を問う作品だ。そしてそのテーマの1つが、無許可で街中に絵を描く「グラフィティ」であることもまた面白い。想像もしなかった問いや価値観に直面させられる、とても興味深い作品である
あわせて読みたい
【衝撃】「きのくに子どもの村学園」に密着する映画『夢見る小学校』は、「義務教育」の概念を破壊する…
驚きの教育方針を有する私立小学校「きのくに子どもの村学園」に密着する映画『夢見る小学校』と、「日本の教育にはほとんどルールが無い」ことを示す特徴的な公立校を取り上げる映画『夢見る公立校長先生』を観ると、教育に対する印象が変わる。「改革を妨げる保護者」にならないためにも観るべき作品だ
あわせて読みたい
【狂気?】オウム真理教を内部から映す映画『A』(森達也監督)は、ドキュメンタリー映画史に残る衝撃作だ
ドキュメンタリー映画の傑作『A』(森達也)をようやく観られた。「オウム真理教は絶対悪だ」というメディアの報道が凄まじい中、オウム真理教をその内部からフラットに映し出した特異な作品は、公開当時は特に凄まじい衝撃をもたらしただろう。私たちの「当たり前」が解体されていく斬新な一作
あわせて読みたい
【知的】「BLって何?」という初心者に魅力を伝える「腐男子」の「BLの想像力と創造力」講座:『ボクた…
「BLは知的遊戯である」という主張には「は?」と感じてしまうでしょうが、本書『ボクたちのBL論』を読めばその印象は変わるかもしれません。「余白の発見と補完」を通じて、「ありとあらゆる2者の間の関係性を解釈する」という創造性は、現実世界にどのような影響を与えているのか
あわせて読みたい
【挑発】「TBS史上最大の問題作」と評されるドキュメンタリー『日の丸』(構成:寺山修司)のリメイク映画
1967年に放送された、寺山修司が構成に関わったドキュメンタリー『日の丸』は、「TBS史上最大の問題作」と評されている。そのスタイルを踏襲して作られた映画『日の丸~それは今なのかもしれない~』は、予想以上に面白い作品だった。常軌を逸した街頭インタビューを起点に様々な思考に触れられる作品
あわせて読みたい
【人類学】少数民族・ムラブリ族に潜入した映画『森のムラブリ』は、私たちの「当たり前」を鮮やかに壊す
タイとラオスにまたがって存在する少数民族・ムラブリ族に密着したドキュメンタリー映画『森のムラブリ』。「ムラブリ族の居住地でたまたま出会った日本人人類学者」と意気投合し生まれたこの映画は、私たちがいかに「常識」「当たり前」という感覚に囚われているのかを炙り出してくれる
あわせて読みたい
【挑戦】相対性理論の光速度不変の原理を無視した主張『光速より速い光』は、青木薫訳だから安心だぞ
『光速より速い光』というタイトルを見て「トンデモ本」だと感じた方、安心してほしい。「光速変動理論(VSL理論)」が正しいかどうかはともかくとして、本書は実に真っ当な作品だ。「ビッグバン理論」の欠陥を「インフレーション理論」以外の理屈で補う挑戦的な仮説とは?
あわせて読みたい
【悲劇】アメリカの暗黒の歴史である奴隷制度の現実を、元奴隷の黒人女性自ら赤裸々に語る衝撃:『ある…
生まれながらに「奴隷」だった黒人女性が、多くの人の協力を得て自由を手にし、後に「奴隷制度」について書いたのが『ある奴隷少女に起こった出来事』。長らく「白人が書いた小説」と思われていたが、事実だと証明され、欧米で大ベストセラーとなった古典作品が示す「奴隷制度の残酷さ」
あわせて読みたい
【危機】シードバンクを設立し世界の農業を変革した伝説の植物学者・スコウマンの生涯と作物の多様性:…
グローバル化した世界で「農業」がどんなリスクを負うのかを正しく予測し、その対策として「ジーンバンク」を設立した伝説の植物学者スコウマンの生涯を描く『地球最後の日のための種子』から、我々がいかに脆弱な世界に生きているのか、そして「世界の食」がどう守られているのかを知る
あわせて読みたい
【新視点】世界の歴史を「化学」で語る?デンプン・砂糖・ニコチンなどの「炭素化合物」が人類を動かし…
デンプン・砂糖・ニコチンなどは、地球上で非常に稀少な元素である「炭素」から作られる「炭素化合物」だ。そんな「炭素化合物」がどんな影響を与えたかという観点から世界の歴史を描く『「元素の王者」が歴史を動かす』は、学校の授業とはまったく違う視点で「歴史」を捉える
あわせて読みたい
【真実】ホロコーストが裁判で争われた衝撃の実話が映画化。”明らかな虚偽”にどう立ち向かうべきか:『…
「ホロコーストが起こったか否か」が、なんとイギリスの裁判で争われたことがある。その衝撃の実話を元にした『否定と肯定』では、「真実とは何か?」「情報をどう信じるべきか?」が問われる。「フェイクニュース」という言葉が当たり前に使われる世界に生きているからこそ知っておくべき事実
あわせて読みたい
【異端】「仏教とは?」を簡単に知りたい方へ。ブッダは「異性と目も合わせないニートになれ」と主張し…
我々が馴染み深い「仏教」は「大乗仏教」であり、創始者ゴータマ・ブッダの主張が詰まった「小乗仏教」とは似て非なるものだそうだ。『講義ライブ だから仏教は面白い!』では、そんな「小乗仏教」の主張を「異性と目も合わせないニートになれ」とシンプルに要約して説明する
あわせて読みたい
【博覧強記】「紙の本はなくなる」説に「文化は忘却されるからこそ価値がある」と反論する世界的文学者…
世界的文学者であり、「紙の本」を偏愛するウンベルト・エーコが語る、「忘却という機能があるから書物に価値がある」という主張は実にスリリングだ。『もうすぐ絶滅するという紙の書物について』での対談から、「忘却しない電子データ」のデメリットと「本」の可能性を知る
あわせて読みたい
【興奮】世界的大ベストセラー『サピエンス全史』要約。人類が文明を築き上げるに至った3つの革命とは?
言わずと知れた大ベストセラー『サピエンス全史』は、「何故サピエンスだけが人類の中で生き残り、他の生物が成し得なかった歴史を歩んだのか」を、「認知革命」「農業革命」「科学革命」の3つを主軸としながら解き明かす、知的興奮に満ち溢れた1冊
あわせて読みたい
【知的】文系にオススメの、科学・数学・哲学の入門書。高橋昌一郎の「限界シリーズ」は超絶面白い:『…
例えば「科学」だけに限ってみても、「なんでもできる」わけでは決してない。「科学」に限らず、私たちが対峙する様々な事柄には「これ以上は不可能・無理」という「限界」が必ず存在する。高橋昌一郎の「限界シリーズ」から、我々が認識しておくべき「限界」を易しく学ぶ
あわせて読みたい
【感想】飲茶の超面白い東洋哲学入門書。「本書を読んでも東洋哲学は分からない」と言う著者は何を語る…
東洋哲学というのは、「最終回しか存在しない連続ドラマ」のようなものだそうだ。西洋哲学と比較にならないほど異質さと、インド哲学・中国哲学など個別の思想を恐ろしく分かりやすく描く『史上最強の哲学入門 東洋の哲人たち』は、ページをめくる手が止まらないくらい、史上最強レベルに面白かった
あわせて読みたい
【人生】「資本主義の限界を埋める存在としての『贈与論』」から「不合理」に気づくための生き方を知る…
「贈与論」は簡単には理解できないが、一方で、「何かを受け取ったら、与えてくれた人に返す」という「交換」の論理では対処できない現実に対峙する力ともなる。『世界は贈与でできている』から「贈与」的な見方を理解し、「受取人の想像力」を立ち上げる
あわせて読みたい
【興奮】飲茶氏が西洋哲学を語る。難解な思想が「グラップラー刃牙成分」の追加で驚異的な面白さに:『…
名前は聞いたことはあるがカントやニーチェがどんな主張をしたのかは分からないという方は多いだろう。私も無知なまったくの初心者だが、そんな人でも超絶分かりやすく超絶面白く西洋哲学を”分かった気になれる”飲茶『史上最強の哲学入門』は、入門書として最強
あわせて読みたい
【教養】美術を「感じたまま鑑賞する」のは難しい。必要な予備知識をインストールするための1冊:『武器…
芸術を「感性の赴くまま見る」のは、日本特有だそうだ。欧米では美術は「勉強するもの」と認識されており、本書ではアートを理解しようとするスタンスがビジネスにも役立つと示唆される。美術館館長を務める著者の『武器になる知的教養 西洋美術鑑賞』から基礎の基礎を学ぶ
あわせて読みたい
【史実】太平洋戦争末期に原爆を落としたアメリカは、なぜ終戦後比較的穏やかな占領政策を取ったか?:…
『八月十五日に吹く風』は小説だが、史実を基にした作品だ。本作では、「終戦直前に原爆を落としながら、なぜ比較的平穏な占領政策を行ったか?」の疑問が解き明かされる。『源氏物語』との出会いで日本を愛するようになった「ロナルド・リーン(仮名)」の知られざる奮闘を知る
あわせて読みたい
【限界】「科学とは何か?」を知るためのおすすめ本。科学が苦手な人こそ読んでほしい易しい1冊:『哲学…
「科学的に正しい」という言葉は、一体何を意味しているのだろう?科学者が「絶対に正しい」とか「100%間違っている」という言い方をしないのは何故だろう?飲茶『哲学的な何か、あと科学とか』から、「科学とはどんな営みなのか?」について考える
あわせて読みたい
【快挙】「チバニアン」は何が凄い?「地球の磁場が逆転する」驚異の現象がこの地層を有名にした:『地…
一躍その名が知れ渡ることになった「チバニアン」だが、なぜ話題になり、どう重要なのかを知っている人は多くないだろう。「チバニアン」の申請に深く関わった著者の『地磁気逆転と「チバニアン」』から、地球で起こった過去の不可思議な現象の正体を理解する
あわせて読みたい
【逸話】天才数学者ガロアが20歳で決闘で命を落とすまでの波乱万丈。時代を先駆けた男がもし生きていた…
現代数学に不可欠な「群論」をたった1人で生み出し、20歳という若さで決闘で亡くなったガロアは、その短い生涯をどう生きたのか?『ガロア 天才数学者の生涯』から、数学に関心を抱くようになったきっかけや信じられないほどの不運が彼の人生をどう変えてしまったのか、そして「もし生きていたらどうなっていたのか」を知る
あわせて読みたい
【バトル】量子力学の歴史はこの1冊で。先駆者プランクから批判者アインシュタインまですべて描く:『量…
20世紀に生まれた量子論は、時代を彩る天才科学者たちの侃々諤々の議論から生み出された。アインシュタインは生涯量子論に反対し続けたことで知られているが、しかし彼の批判によって新たな知見も生まれた。『量子革命』から、量子論誕生の歴史を知る
あわせて読みたい
【ドラマ】「フェルマーの最終定理」のドラマティックな証明物語を、飲茶氏が平易に描き出す:『哲学的…
「フェルマーの最終定理」は、問題の提示から350年以上経ってようやく証明された超難問であり、その証明の過程では様々な人間ドラマが知られている。『哲学的な何か、あと数学とか』をベースに、数学的な記述を一切せず、ドラマティックなエピソードだけに触れる
あわせて読みたい
【意外】東京裁判の真実を記録した映画。敗戦国での裁判が実に”フェア”に行われたことに驚いた:『東京…
歴史に詳しくない私は、「東京裁判では、戦勝国が理不尽な裁きを行ったのだろう」という漠然としたイメージを抱いていた。しかし、その印象はまったくの誤りだった。映画『東京裁判 4Kリマスター版』から東京裁判が、いかに公正に行われたのかを知る
あわせて読みたい
【論争】サイモン・シンが宇宙を語る。古代ギリシャからビッグバンモデルの誕生までの歴史を網羅:『宇…
古代から現代に至るまで、「宇宙」は様々な捉えられ方をしてきた。そして、新たな発見がなされる度に、「宇宙」は常識から外れた不可思議な姿を垣間見せることになる。サイモン・シン『宇宙創成』をベースに、「ビッグバンモデル」に至るまでの「宇宙観」の変遷を知る
あわせて読みたい
【証明】結城浩「数学ガール」とサイモン・シンから「フェルマーの最終定理」とそのドラマを学ぶ
350年以上前に一人の数学者が遺した予想であり「フェルマーの最終定理」には、1995年にワイルズによって証明されるまでの間に、これでもかというほどのドラマが詰め込まれている。サイモン・シンの著作と「数学ガール」シリーズから、その人間ドラマと数学的側面を知る
あわせて読みたい
【衝撃】ABC予想の証明のために生まれたIUT理論を、提唱者・望月新一の盟友が分かりやすく語る:『宇宙…
8年のチェック期間を経て雑誌に掲載された「IUT理論(宇宙際タイヒミュラー理論)」は、数学の最重要未解決問題である「ABC予想」を証明するものとして大いに話題になった。『宇宙と宇宙をつなぐ数学』『abc予想入門』をベースに、「IUT理論」「ABC予想」について学ぶ
あわせて読みたい
【変人】結城浩「数学ガール」から、1億円も名誉ある賞も断った天才が証明したポアンカレ予想を学ぶ
1億円の賞金が懸けられた「ポアンカレ予想」は、ペレルマンという天才数学者が解き明かしたが、1億円もフィールズ賞も断った。そんな逸話のある「ポアンカレ予想」とは一体どんな主張であり、どのように証明されたのかを結城浩『数学ガール』から学ぶ
あわせて読みたい
【興奮】結城浩「数学ガール」で、決闘で命を落とした若き天才数学者・ガロアの理論を学ぶ
高校生を中心に、数学を通じて関わり合う者たちを描く「数学ガール」シリーズ第5弾のテーマは「ガロア理論」。独力で「群論」という新たな領域を切り開きながら、先駆的すぎて同時代の数学者には理解されず、その後決闘で死亡した天才の遺した思考を追う
あわせて読みたい
【刺激】結城浩「数学ガール」で、ゲーデルの不完全性定理(不可能性の証明として有名)を学ぶ
『結城浩「数学ガール」シリーズは、数学の面白さを伝えながら、かなり高難度の話題へと展開していく一般向けの数学書です。その第3弾のテーマは、「ゲーデルの不完全性定理」。ヒルベルトという数学者の野望を打ち砕いた若き天才の理論を学びます
あわせて読みたい
【異端】数学の”証明”はなぜ生まれたのか?「無理数」と「無限」に恐怖した古代ギリシャ人の奮闘:『数…
学校で数学を習うと、当然のように「証明」が登場する。しかしこの「証明」、実は古代ギリシャでしか発展しなかった、数学史においては非常に”異端”の考え方なのだ。『数学の想像力 正しさの深層に何があるのか』をベースに、ギリシャ人が恐れたものの正体を知る
あわせて読みたい
【対立】数学はなぜ”美しい”のか?数学は「発見」か「発明」かの議論から、その奥深さを知る:『神は数…
数学界には、「数学は神が作った派」と「数学は人間が作った派」が存在する。『神は数学者か?』をベースに、「数学は発見か、発明か」という議論を理解し、数学史においてそれぞれの認識がどのような転換点によって変わっていったのかを学ぶ
あわせて読みたい
【謎】恐竜を絶滅させた隕石はどこから来た?暗黒物質が絡む、リサ・ランドールの驚愕の仮説:『ダーク…
「生物の絶滅」には、以前から知られていたある謎があった。そしてその謎を、未だに観測されておらず、「科学者の妄想の産物」でしかない「ダークマター(暗黒物質)」が解決するかもしれない。現役の科学者が『ダークマターと恐竜絶滅』で語る驚きの仮説。
あわせて読みたい
【未知】タコに「高度な脳」があるなんて初耳だ。人類とは違う進化を遂げた頭足類の「意識」とは?:『…
タコなどの頭足類は、無脊椎動物で唯一「脳」を進化させた。まったく違う進化を辿りながら「タコに心を感じる」という著者は、「タコは地球外生命体に最も近い存在」と書く。『タコの心身問題』から、腕にも脳があるタコの進化の歴史と、「意識のあり方」を知る。
あわせて読みたい
【興奮】素数の謎に迫った天才数学者たちの奮闘と、数学の”聖杯”である「リーマン予想」について:『素…
古今東西の数学者を惹きつけて止まない「素数」。その規則性を見つけ出すことは非常に困難だったが、「リーマン予想」として初めてそれが示された。『素数の音楽』『リーマン博士の大予想』から、天才数学者たちが挑んできた「リーマン予想」をざっくり理解する
あわせて読みたい
【究極】リサ・ランドールが「重力が超弱い理由」を解説する、超刺激的なひも理論の仮説:『ワープする…
現役の研究者であるリサ・ランドールが、自身の仮説を一般向けに分かりやすく説明する『ワープする宇宙』。一般相対性理論・量子力学の知識を深く記述しつつ「重力が超弱い理由」を説明する、ひも理論から導かれる「ワープする余剰次元」について解説する
あわせて読みたい
【意外】自己免疫疾患の原因は”清潔さ”?腸内フローラの多様性の欠如があらゆる病気を引き起こす:『寄…
人類は、コレラの蔓延を機に公衆衛生に力を入れ、寄生虫を排除した。しかし、感染症が減るにつれ、免疫関連疾患が増大していく。『寄生虫なき病』では、腸内細菌の多様性が失われたことが様々な疾患の原因になっていると指摘、「現代病」の蔓延に警鐘を鳴らす
あわせて読みたい
【驚嘆】人類はいかにして言語を獲得したか?この未解明の謎に真正面から挑む異色小説:『Ank: a mirror…
小説家の想像力は無限だ。まさか、「人類はいかに言語を獲得したか?」という仮説を小説で読めるとは。『Ank: a mirroring ape』をベースに、コミュニケーションに拠らない言語獲得の過程と、「ヒト」が「ホモ・サピエンス」しか存在しない理由を知る
あわせて読みたい
【意外】思わぬ資源が枯渇。文明を支えてきた”砂”の減少と、今後我々が変えねばならぬこと:『砂と人類』
「砂が枯渇している」と聞いて信じられるだろうか?そこら中にありそうな砂だが、産業用途で使えるものは限られている。そしてそのために、砂浜の砂が世界中で盗掘されているのだ。『砂と人類』から、石油やプラスチックごみ以上に重要な環境問題を学ぶ
あわせて読みたい
【希望】貧困の解決は我々を豊かにする。「朝ベッドから起きたい」と思えない社会を変える課題解決:『…
現代は、過去どの時代と比べても安全で清潔で、豊かである。しかしそんな時代に、我々は「幸せ」を実感することができない。『隷属なき道』をベースに、その理由は一体なんなのか何故そうなってしまうのかを明らかにし、さらに、より良い暮らしを思い描くための社会課題の解決に触れる
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
歴史・文明・人類【本・映画の感想】 | ルシルナ
現在、そして未来の社会について考える場合に、人類のこれまでの歴史を無視することは難しいでしょう。知的好奇心としても、人類がいかに誕生し、祖先がどのような文明を作…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…










































































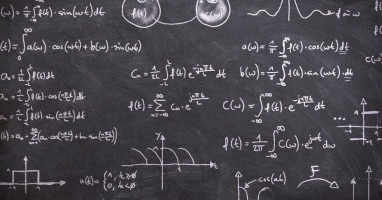

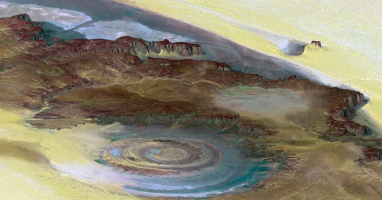

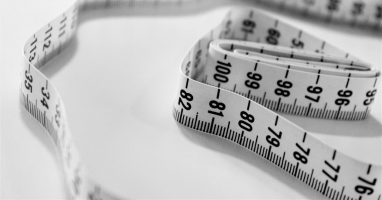














コメント