目次
はじめに
この記事で取り上げる映画

「私のはなし 部落のはなし」公式HP
この映画をガイドにしながら記事を書いていきます
今どこで観れるのか?
公式HPの劇場情報をご覧ください
この記事の3つの要点
- 見た目では判断できない「部落出身」という性質が何故差別を生むのか、私にはまったく理解できなかった
- 「部落解放運動」と「同和対策事業特別措置法」が、「部落差別」を別のステージへと引き上げることになった
- 映画に登場する、「『部落』に住む様々な人たち」の体験談がとても興味深い
いずれにせよ、「自分も差別感情を抱いている」と自覚することが、すべての「差別」に向き合う第一歩なのだと思う
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
記事中の引用は、映画館で取ったメモを参考にしているので、正確なものではありません
私にはどうしても、同和・部落問題が理解出来ない。映画『私のはなし 部落のはなし』から、長く続く差別の実態を知る
「面白かった」という表現が適切ではないタイプの作品だと理解しているが、「興味深かった」という意味でとても面白い作品だった。上映時間は205分とかなり長く、観るのに少し躊躇したが、観て良かったと感じられた作品だ。
あわせて読みたい
【倫理】報道の自由度に関わる「放送法の解釈変更」問題をわかりやすく説明(撤回の真相についても):…
安倍政権下で突然発表された「放送法の解釈変更」が、2023年3月17日に正式に”撤回された”という事実をご存知だろうか?映画『テレビ、沈黙。 放送不可能。Ⅱ』は、その「撤回」に尽力した小西洋之議員に田原総一朗がインタビューする作品だ。多くの人が知るべき事実である
「私には理解不能としか言いようがない部落差別」とは、一体何なのだろうか?
「部落差別」や「被差別部落」という言葉を初めて知ったのがいつだったのか、正確には覚えていないが、恐らく最初は学校の授業だったんじゃないかと思う。そしてその時はたぶん、何も考えていなかった。というのも、私が知らないだけかもしれないが、私が生まれ育った地域には恐らく、そういう問題が存在しないはずだからだ。だからそもそも、問題そのものが上手くイメージ出来なかったのだと思う。その後現在に至るまで、どういう形で「部落差別」「被差別部落」という言葉に触れてきたのかも覚えていないのだが、断片的に何か新たな知識を得る度に、「意味不明な問題だな」と感じてきたのである。

映画を観る前の時点で私が知っていたのは、通り一遍の知識でしかない。江戸時代に「穢多非人」の身分だった人たちの子孫が今でも差別を受けていること。そういう方々がまとまって住む「部落」と呼ばれる地域があり、昔から屠殺や皮革業など、一般的に「誰もやりたくないと感じる仕事」を引き受けていた(押し付けられていた)こと。私が知っていたのはこの程度のことだ。
あわせて読みたい
【悲劇】アメリカの暗黒の歴史である奴隷制度の現実を、元奴隷の黒人女性自ら赤裸々に語る衝撃:『ある…
生まれながらに「奴隷」だった黒人女性が、多くの人の協力を得て自由を手にし、後に「奴隷制度」について書いたのが『ある奴隷少女に起こった出来事』。長らく「白人が書いた小説」と思われていたが、事実だと証明され、欧米で大ベストセラーとなった古典作品が示す「奴隷制度の残酷さ」
穢多非人の身分は、1871年(明治4年)に“表向き”廃止された。250年以上も前のことである。もちろん、今まさに争いが激化しているイスラエルとパレスチナのように、どれだけ時間が経とうとも解決されない問題はあるわけで、経過した時間の長さなど関係ないと言えば関係ない。しかし正直なところ、私は部落差別に対して、「祖先が穢多非人だったから何なの?」みたいにしか感じられないため、そんな「差別」が現代に至るまで250年間も続いているという事実に、ちょっと驚愕させられてしまうのである。本当に、まったく意味が分からない。
さて、私はそのような状態で本作『私のはなし 部落のはなし』を観た。そして、「納得」などという状態に達したわけではもちろんないものの、少なくとも「今まで理解できなかったこと」が少しは解消されたと言えるだろうと思う。私のような素人でも十分理解できるくらい、その背景的な部分がかなりきちんと描かれている作品だと感じた。
しかし、この記事を読んでいただく上で注意してもらいたいことが1つある。それは、「これから私が書く文章はあくまでも、『映画を観て私が解釈したこと』に過ぎない」ということだ。非常にセンシティブな問題であるし、また、「部落差別が未だに続いている」という事実を踏まえれば、「『そういう差別を良しとしている人』が世の中にはたくさんいる」と考えるのが妥当だろう。となれば、私とはまるで異なるものの見方をしているはずだ。そういう人には恐らく、この記事は馴染まないと思う。タイトルにある通り、この記事はあくまでも「私のはなし」でしかないのである。なので、「私が書いた文章」だけから映画『私のはなし 部落のはなし』の内容を判断することだけは止めてほしいと思う。
あわせて読みたい
【狂気?】オウム真理教を内部から映す映画『A』(森達也監督)は、ドキュメンタリー映画史に残る衝撃作だ
ドキュメンタリー映画の傑作『A』(森達也)をようやく観られた。「オウム真理教は絶対悪だ」というメディアの報道が凄まじい中、オウム真理教をその内部からフラットに映し出した特異な作品は、公開当時は特に凄まじい衝撃をもたらしただろう。私たちの「当たり前」が解体されていく斬新な一作
さて、映画の内容に触れる前に、私自身の「部落差別」に対するスタンスについてもう少し触れておくことにしよう。
まず私は、「目の前にいる人が『被差別部落出身』だと知ったとして、それだけを理由に差別感情を抱くことはない」と考えている。ただ、あくまでもこれは「予想」でしかない。というのも私はこれまで、「あの人は被差別部落出身だ」と誰かに言われたことも、「私は被差別部落出身です」と自ら口にする人と出会ったこともないからだ。それどころか、生まれ育った場所やその後住んだいくつかの地域を含め、誰かから「あの辺りは部落だ」みたいに聞かされたことさえない。だから、「実際にそういう人に出会った時にどういう反応になるかは正直分からない」というのが正直なところだ。ただ一方で、「何の知識も思い込みも先入観も無いのだから、差別感情を抱きようがない」とも考えているのである。
さてもう1つ。部落差別に限らない「差別」全般に関しての話にも触れておこう。

私は基本的に、「どういう人に対しても、特段『差別感情』を抱いていない」という自覚でいる。LGBTQや障害者など、一般的に「差別感情を向けられやすい人たち」に対しても、単に「LGBTQ/障害者だから」という理由で差別意識を持つことはないと考えているのだ。もちろん、個別に誰かを嫌いになったり疎ましく感じたりすることはあるが、それは別に「LGBTQだから」「障害者だから」というわけではない、という意味である。
あわせて読みたい
【選択】映画『サウンド・オブ・メタル』で難聴に陥るバンドマンは、「障害」と「健常」の境界で揺れる
ドラムを叩くバンドマンが聴力を失ってしまう――そんな厳しい現実に直面する主人公を描く映画『サウンド・オブ・メタル』では、「『健常者との生活』を選ぶか否か」という選択が突きつけられる。ある意味では健常者にも向けられているこの問いに、どう答えるべきだろうか
ただ一方で、「『差別感情を抱いていない』という自覚」の恐ろしさについても認識しているつもりだ。「差別感情」は「本人が自覚できるもの」ではなく、「それを向けられた人が感じ取るもの」だと私は理解している。なので、私が「差別感情など抱いていない」と「自覚」していても、そんな私に対して「差別感情を抱いている」と感じる人がいてもおかしくはないと考えているのだ。
作中には、兵庫県の食肉センター長が、
差別意識を持っているという自覚を持つことが大事なんや。
と口にする場面があるのだが、まさにその通りだと思う。
あわせて読みたい
【差別】才ある者の能力を正しく引き出す者こそ最も有能であり、偏見から能力を評価できない者は無能だ…
「偏見・差別ゆえに、他人の能力を活かせない人間」を、私は無能だと感じる。そういう人は、現代社会の中にも結構いるでしょう。ソ連との有人宇宙飛行競争中のNASAで働く黒人女性を描く映画『ドリーム』から、偏見・差別のない社会への道筋を考える
そんなわけで私は、「差別感情を持ってはいないはず」と思いつつ、同時に、「必ずしも、他者からもそう見られているとは限らない」とも考えているというわけだ。これが、この記事を書いている私の「現在地」であり「大前提」である。この辺りのことを理解しつつ、この記事を読んでいただけるとありがたいと思う。
まずは問題を「差別する側の人間」の性質で分類する
さてまずは、「差別する側」の分類から始めたいと思う。これは、私が抱く「部落差別ってマジで意味が分からない」という感覚をより適切に理解してもらうために行うものだ。「差別する側」を分類することで、状況が少し見えやすくなるだろう。
あわせて読みたい
【情熱】常識を疑え。人間の”狂気”こそが、想像し得ない偉業を成し遂げるための原動力だ:映画『博士と…
世界最高峰の辞書である『オックスフォード英語大辞典』は、「学位を持たない独学者」と「殺人犯」のタッグが生みだした。出会うはずのない2人の「狂人」が邂逅したことで成し遂げられた偉業と、「狂気」からしか「偉業」が生まれない現実を、映画『博士と狂人』から学ぶ
「部落差別」に関して、「差別する側」が持ち得るだろう性質を、私は以下の3つに分類したいと思う。
- そもそもあらゆることに対して「差別感情」を抱いている人(対象は「部落差別」に限らない)
- 「人間という存在」に関して、「血の繋がり」を特段に重視している人
- その他の人(①でも②でもない人)
そして私はこの記事において、①と②の人を除外して考えようと思う。ではこの辺りの話から始めていこう。
あわせて読みたい
【理解】東田直樹の本は「自閉症の見方」を一変させた。自身も自閉症児を育てるプロデューサーが映画化…
東田直樹の著作を英訳し世界に広めた人物(自閉症児を育てている)も登場する映画『僕が跳びはねる理由』には、「東田直樹が語る自閉症の世界」を知ることで接し方や考え方が変わったという家族が登場する。「自閉症は知恵遅れではない」と示した東田直樹の多大な功績を実感できる
まず①の人について。彼らはとにかく、「理由に拘わらず、他人を差別したい」というマインドの人である。動機は様々だろう。「誰かを貶めること」によって「自身の全能感」みたいなものを感じたいのかもしれないし、あるいは、「誰かを貶めること」でしか自分を上手く肯定できないのかもしれない。こういう人にとっては、何か「それなりの人数が共感してくれるだろう理由」があれば、差別感情を向ける対象は誰だっていいのだろう。そして、こういう人のことを「部落差別」の問題と併せて議論するのは無駄なので、この記事では除外したいと思う。
②の人を除外する理由は、「時間の問題」だと考えているからだ。洋の東西を問わず、「血縁」は常に重視されてきたと思うが、昔と比べれば、今の日本ではそのような感覚はかなり薄れていると言えるのではないかと思う。もちろん、都市部と地方とではまだ大きな差はあるだろうし、あるいは、いわゆる「上流階級」みたいな世界ではまだまだ血縁が重視されている印象もある。ただやはり、「血の繋がりが云々」みたいに言っているのは主に年配の人だと思うし、若い世代になればなるほどそういう感覚を持つ人は少なくなるはずだと思う。

作中では、「結婚差別」について触れられる場面がある。本作には、実際に部落出身だという若者が顔出しで登場し様々な話をするのだが、彼らはやはり、恋愛や結婚に際して「部落出身」であることが障害になる経験を有している。ただその話をよく聞いてみると、「相手の親から反対された」という話ばかりで、「部落出身であることを理由に、付き合っている本人から拒絶された」という話はほとんどなかった。作中では1人だけ、撮影時50代だった女性が、自身が若い頃に付き合っていた人に「部落出身」だと告げたら、それを理由に恋愛を解消されたという話をしていたのだが、語られていたのはそれぐらいだったように思う。
あわせて読みたい
【魅惑】バーバラ・ローデン監督・脚本・主演の映画『WANDA』の、70年代の作品とは思えない今感
映画館で観た予告が気になって、それ以外の情報を知らずに観に行った映画『WANDA』なんと70年代の映画だと知って驚かされた。まったく「古さ」を感じなかったからだ。主演だけでなく、監督・脚本も務めたバーバラ・ローデンが遺した、死後評価が高まった歴史的一作
結婚の際に「部落出身」かどうか気にするというのはやはり、「一族に部落の血が混ざること」を嫌悪していると考えていいだろう。そして、「相手の親が反対するだけで、付き合っている本人は部落出身であるかどうかなど気にしない」という状況の方が多いとすれば、時間経過と共に「結婚差別」は少なくなっていくはずだ。であれば、「血の繋がりが云々」みたいなことを言っている人たちについても、あまり深く考える必要はないだろうと私は判断した。
このように①②の人たちについては、「確かに問題ではあるが、考えても仕方がない」という意味で、議論の対象から外している。そして私がこの記事の中で議論したいのが、③の「その他の人」である。①②を除外しているのだから、この③の人たちというのは、「差別感情を基本的には抱くことがないし、『血の繋がり』を特に重視しているわけでもないが、『部落』だけは許容できない」タイプというわけだ。そして私には、こういう人たちが「部落」の一体何を忌避しているのか、どうしても理解できなかったのである。
私が抱く「理解できなさ」を、もう少し具体的に説明する
あわせて読みたい
【実話】ポートアーサー銃乱射事件を扱う映画『ニトラム』が示す、犯罪への傾倒に抗えない人生の不条理
オーストラリアで実際に起こった銃乱射事件の犯人の生い立ちを描く映画『ニトラム/NITRAM』は、「頼むから何も起こらないでくれ」と願ってしまうほどの異様な不穏さに満ちている。「社会に順応できない人間」を社会がどう受け入れるべきかについて改めて考えさせる作品だ
さて、この③の人に対する「理解できなさ」を、もう少し具体的に書いていくことにしよう。
本作に登場する80代ぐらいの男性が、かつて近隣の住民に次のような話をしたことがあると口にする場面がある。
俺の背中に「部落出身」って書いてあるか? ないじゃろ。だったらわからんじゃろ。
本当にその通りだと思う。私が抱く疑問は、主にこの点に集約されていると言っていい。
さて、この点を深堀りする前に、まずは映画を観る前の時点での私の認識に触れておこう。私は「『部落出身と見做されるか否か』は、『両親(のどちらか)が部落出身であるかどうか』で判断される」のだと思っていた。つまり「『血の繋がり』こそが『差別の対象か否か』を判断する要因」だと考えていたのである。
あわせて読みたい
【居場所】菊地凛子主演映画『658km、陽子の旅』(熊切和嘉)は、引きこもりロードムービーの傑作
映画『658km、陽子の旅』は、主演の菊地凛子の存在感が圧倒的だった。夢破れて長年引きこもり続けている女性が、否応なしにヒッチハイクで弘前を目指さなければならなくなるロードムービーであり、他人や社会と関わることへの葛藤に塗れた主人公の変化が、とても「勇敢」なものに映る
しかし映画を観ていて、どうもそうではなさそうだと感じる場面があった。大阪府箕面市には北芝という地域があり、そこはどうやら「部落」なのだそうだが、作中にはその北芝出身の若者3人が話す場面がある。そしてその内の1人が、
生まれたのは箕面市だけど、その後北芝に引っ越してきた。北芝に住んでいたことがあるから、自分も差別されるのかな、と。

みたいな発言をしていたのだ。彼は母親に「何故北芝に引っ越すことにしたのか」と聞いたことがあるそうだが、母親は「なんか便利だから」程度の返答だったという。それ以上詳しくは触れられなかったが、恐らく、「親族の誰かが北芝出身だったから」みたいなことではないのだと思う。しかしそれでも、「部落とされる場所に住んでいたことがある」という事実が「差別の対象になるかもしれない」という恐れを引き起こしているというわけだ。
あわせて読みたい
【不正義】正しく行使されない権力こそ真の”悪”である。我々はその現実にどう立ち向かうべきだろうか:…
権力を持つ者のタガが外れてしまえば、市民は為す術がない。そんな状況に置かれた時、私たちにはどんな選択肢があるだろうか?白人警官が黒人を脅して殺害した、50年前の実際の事件をモチーフにした映画『デトロイト』から、「権力による不正義」の恐ろしさを知る
さてそうだとすれば、「血の繋がり」の問題ではないことは明らかだろう。まあそれは、ちょっと考えてみれば当然の話ではある。「血の繋がり」など、外見から判断できるはずがないからだ。そしてだからこそ、「部落地域に住んでいるか(住んでいたか)」という、外から見て判断できる要素が「差別」の基準になっているということなのだと思う。
この辺りの話は、京都市の元職員の話からも理解できるだろう。
後で詳しく触れる話だが、「部落差別」の問題に対処するために政府は、1969年に「同和対策事業特別措置法」を制定した。政府は「部落」を「同和地区」と言い換えたのだが、この法律は要するに「部落出身の人たちの生活改善の手助けをしよう」という目的で制定されたものである。制定後の33年間で、16兆円の公金が使われたそうだ。
あわせて読みたい
【感想】リドリー・スコット監督の映画『最後の決闘裁判』から、社会が”幻想”を共有する背景とその悲劇…
例えば、「1万円札」というただの紙切れに「価値を感じる」のは、社会の構成員が同じ「共同幻想」の中に生きているからだ。リドリー・スコット監督の映画『最後の決闘裁判』は、「強姦では妊娠しない」「裁判の勝者を決闘で決する」という社会通念と、現代にも通じる「共同幻想」の強さを描き出す
さて、この事業において一番問題となったのは、「この法律が適用される『部落出身者』は、一体誰のことを指すのか?」である。作中では元職員が京都市の例を挙げていたのだが、同市では「属地属人」を基本方針としていたという。これは要するに、「同和地区に住んでいる(住んでいた)人」を「部落出身者」と認定したという意味である。より具体的には、
- 世帯主の本籍が同和地区にある
- 親戚の本籍が同和地区にある
- 戦争以前から同和地区に住んでいる
のような条件で判断されたのだそうだ。
あわせて読みたい
【最新】「コロンブス到達以前のアメリカ大陸」をリアルに描く歴史書。我々も米国人も大いに誤解してい…
サイエンスライターである著者は、「コロンブス到着以前のアメリカはどんな世界だったか?」という問いに触れ、その答えが書かれた本がいつまで経っても出版されないので自分で執筆した。『1491 先コロンブス期アメリカ大陸をめぐる新発見』には、アメリカ人も知らない歴史が満載だ
作中で語られていたのはあくまでも京都市の事例だけであり、全国の他の地域も同様だったのかについては映画の内容からは判断できない。ただネットで調べてみると、「部落解放同盟は、『属地属人』主義に反対していた」みたいな記述が出てくるので、恐らく全国的に採られたスタンスだったのではないかという気がする。要するに、「そういうやり方でしか『部落出身』かどうかを判定できなかった」ということなのだと思う。
その元職員は、
どこまでいったら部落民なのか分からない。だから逆に言ったら、差別される印も根拠も何も無いんですよね。
という言い方をしていた。本当にその通りだろう。「『住んでいる地域』でしか判別出来ないような理由で差別が起こっている状況」こそが最もおかしなことだと私には感じられてしまうのだ。
あわせて読みたい
【驚異】「持続可能な社会」での「豊かな生活」とは?「くじら漁の村」で生きる人々を描く映画:『くじ…
手作りの舟に乗り、銛1本で巨大なクジラを仕留める生活を続けるインドネシアのラマレラ村。そこに住む人々を映し出した映画『くじらびと LAMAFA』は、私たちが普段感じられない種類の「豊かさ」を描き出す。「どう生きるか」を改めて考えさせられる作品だ
私が感じる「理解できなさ」は、まさにこの点にある。外見からは「部落民(ここでは「穢多非人の子孫」という意味)」かどうかを判断する方法は無い。だから最初は、「部落に住んでいる人は部落民である可能性が高いから遠ざけておこう」という程度の判断だったのだと思う。というか、そうとしか考えられない。そして、「その程度」でしかない差別が250年間も続いているのだ。これは本当に、私にはあまりにも理解不能な意味不明すぎる状況なのである。

「『部落差別』が問題になっていく過程」は、大きく2つの段階に分かれているのではないか
映画を観て私なりに、「『部落差別』の問題は、大きく2つの段階に分かれているのだろう」と理解した。
あわせて読みたい
【衝撃】NHKがアマゾン奥地の先住民ヤノマミ族に長期密着。剥き出しの生と死、文明との共存の難しさ
NHKのディレクターでありノンフィクション作家でもある国分拓が、アマゾン奥地に住む先住民ヤノマミ族の集落で150日間の長期密着を行った。1万年の歴史を持つ彼らの生活を描き出す『ヤノマミ』は、「生と死の価値観の差異」や「先住民と文明との関係の難しさ」を突きつける
最初の段階は、鑑賞以前から理解していた通りの「穢多非人の流れ」である。恐らく当時は、特に「血の繋がり」が忌避されていたのだと思う。もちろん今でもそのような忌避感は残っているわけだが、本記事ではその点について取り上げないと決めたので触れはしない。
さて、この最初の段階における「部落民の扱い」については、ちょっと意外な話もあった。その話が出てくるのは、京都の六条河原について郷土史家が語る場面である。六条河原というのはかつて処刑場だった場所であり、穢多非人がその処刑を担当させられていたそうだ。そしてその話に続く形で、「彼らはきちんと社会参加をしていたし、発言権もあった」と説明されるのである。もちろん「部落民である」という「区別」はあったわけだが、「その実態はもしかしたら、『差別』というほどのものではなかったかもしれない」と示唆されるのだ。
あるいは、同じく京都の崇仁という部落の話も出てくる。戦後かなり厳しい生活環境に置かれていた地域だそうだが、商売をやっている者も多く、経済活動には関わっていたというのだ。私は何となく「村八分」的なイメージを持っていたこともあり、少し意外に感じた。もちろん、部落民に対して苛烈な差別を行う地域もあったとは思う。ただ、映画を観ながら私は、「完全に排除されていたわけでもないようだ」という印象を受けた。
あわせて読みたい
【レッテル】コミュニケーションで大事なのは、肩書や立場を外して、相手を”その人”として見ることだ:…
私は、それがポジティブなものであれ、「レッテル」で見られることは嫌いです。主人公の1人、障害を持つ大富豪もまたそんなタイプ。傍若無人な元犯罪者デルとの出会いでフィリップが変わっていく『THE UPSIDE 最強のふたり』からコミュニケーションを学ぶ
歴史に「if」は無いと分かっているが、ただもしその状態が続いていれば、いつか「部落差別」は自然消滅していたかもしれない。そんな風にも思わされた。
ではその後、一体何が起こったのか。1つのきっかけとなったと思われるのが、1922年の水平社宣言である。これによって「部落解放運動」が活発になった。部落解放運動というのは、「部落出身の人たちが、差別の撤廃を目指して行った様々な活動」のことを指す。そしてここから第2のフェーズに入っていったのではないかと私は感じた。
この点について明確に語っていたのが、示現舎という出版社の代表・宮部龍彦である。彼については後で詳しく触れるが、「部落」に関する、裁判にまで発展した本を出版した人物だ。後で触れるその本の内容を知ると、「部落に対して、かなり差別的な意識を持っている人物なのだろう」と感じるのではないかと思う。ただ、映画には彼に直接話を聞く場面もあるのだが、そこまでで提示される「宮部龍彦」に関する情報からすると、「思ったほど『話が通じない人間』なわけではない」とも感じた。
あわせて読みたい
【権利】衝撃のドキュメンタリー映画『ヤクザと憲法』は、「異質さを排除する社会」と「生きる権利」を問う
「ヤクザ」が排除された現在でも、「ヤクザが担ってきた機能」が不要になるわけじゃない。ではそれを、公権力が代替するのだろうか?実際の組事務所(東組清勇会)にカメラを持ち込むドキュメンタリー映画『ヤクザと憲法』が映し出す川口和秀・松山尚人・河野裕之の姿から、「基本的人権」のあり方について考えさせられた
例えば、監督(なのか、撮影スタッフなのか)が彼に、「もし娘が、結婚相手として部落出身の人を連れてきたらどうしますか?」と質問する場面がある。これに対して宮部龍彦は、
どうもしませんよ。反対も賛成もしないと思います。
みたいな返答をしていた。かなりヤバい発言も躊躇せず口にする人物に見えたので、これも恐らく本心なのだろう。私には、「部落に対して強く思うところはあるが、それは決して感情的なものではない」みたいなスタンスを持っているように感じられた。彼の場合、「やっていることがかなりヤバい」のは間違いない。しかし、「考え方まで常軌を逸している」かと言えばそんなことはなさそうだったし、少なくとも「話は通じる人物」に思えた。
あわせて読みたい
【絶望】子供を犯罪者にしないために。「異常者」で片付けられない、希望を見いだせない若者の現実:『…
2人を殺し、7人に重傷を負わせた金川真大に同情の余地はない。しかし、この事件を取材した記者も、私も、彼が殺人に至った背景・動機については理解できてしまう部分がある。『死刑のための殺人』をベースに、「どうしようもないつまらなさ」と共に生きる現代を知る
そんな宮部龍彦が、「部落差別って結局、貧困問題だと思うんです」と語る場面がある。その上で彼は次のようにも語っていた。
差別が無くなったって貧乏な人は貧乏だと思いますよ。貧困の原因は階層化だから、差別が無くなっても、貧困は無くならない。

この指摘はその通りだと感じた。当然のことながら、「差別をいかに無くすか」という観点は忘れてはいけない。しかしそれ以上に、「貧困をどう脱するか」の方がより解決すべき問題であるように思う。そして宮部龍彦は、「『差別』に注目が集まることで、そのような視点が覆い隠されているのではないか」と指摘しているというわけだ。
あわせて読みたい
【見方】日本の子どもの貧困は深刻だ。努力ではどうにもならない「見えない貧困」の現実と対策:『増補…
具体的には知らなくても、「日本の子どもの貧困の現状は厳しい」というイメージを持っている人は多いだろう。だからこそこの記事では、朝日新聞の記事を再編集した『増補版 子どもと貧困』をベースに、「『貧困問題』とどう向き合うべきか」に焦点を当てた
さて、このようなスタンスの人物が、「部落差別」についてこんなことを言っている。
部落差別の問題は、昭和に行政が作ったんだ。
要するに、「1969年に制定された同和対策事業特別措置法に問題がある」という主張なわけだ。さらに、「それはつまり、部落解放運動に対する忌避感ですか?」と問われた彼は、「そうだ」と返答している。
映画を観ながら私も、「部落差別」の問題の根底には、まさにこの点が関係しているのだろうと感じた。というわけで、この辺りの話を少し掘り下げていこうと思う。
「部落に関わるとヤバい」という感覚こそが、問題に拍車をかけたのではないか
あわせて読みたい
【実話】正論を振りかざす人が”強い”社会は窮屈だ。映画『すばらしき世界』が描く「正解の曖昧さ」
「SNSなどでの炎上を回避する」という気持ちから「正論を言うに留めよう」という態度がナチュラルになりつつある社会には、全員が全員の首を締め付け合っているような窮屈さを感じてしまう。西川美和『すばらしき世界』から、善悪の境界の曖昧さを体感する
さて、先程の話には「部落解放運動」と「同和対策事業特別措置法」の2つが関係してくるわけだが、まずは「部落解放運動」の話から始めることにしよう。
先述した通り、1922年に水平社宣言が出された。これは「全国の部落出身者に対して共闘を呼びかける趣旨のもの」であり、この宣言をきっかけに「部落解放運動」が始まっていくことになる。
そしてどうやら、「部落解放同盟」の一部が、「部落解放運動」と称してかなり過激なことをやっていたようなのだ。例えば、少しでも「部落差別」を感じさせる言動をした者に対して、「徒党を組んで押しかける」「大勢で吊るし上げる」みたいな振る舞いをしていたのだという。
そうなれば当然、「部落民は怖い」という印象になるのも仕方ないだろう。本当は一部の者だけが過激なことをしているのだが、それが「部落出身者」全体に対するイメージになってしまうのだ。そうなれば当然、親だって子どもに、「部落の近くを通る時には気をつけなさい」と教えるしかなくなる。そしてこのような印象が蓄積されることで、「部落」が次第に「現実的な脅威」としての存在感を持ち始めたのではないかと私は感じた。
あわせて読みたい
【特異】「カメラの存在」というドキュメンタリーの大前提を覆す映画『GUNDA/グンダ』の斬新さ
映画『GUNDA/グンダ』は、「カメラの存在」「撮影者の意図」を介在させずにドキュメンタリーとして成立させた、非常に異端的な作品だと私は感じた。ドキュメンタリーの「デュシャンの『泉』」と呼んでもいいのではないか。「家畜」を被写体に据えたという点も非常に絶妙
作中では、「過去に出版された様々な書籍の中の文章が朗読される場面」が度々挿入されるのだが、部落解放運動について書かれた本の中に、次のような記述がある。

部落解放同盟が語る要求は、誰も否定できない命題として機能する。それはトランプのジョーカーのようなもので、要求を受け入れざるを得ないのだ。
これこそが、問題の本質をシンプルに衝く指摘なのだろうと感じた。
あわせて読みたい
【信念】9.11後、「命の値段」を計算した男がいた。映画『WORTH』が描く、その凄絶な2年間(主演:マイ…
9.11テロの後、「被害者の『命の値段』を算出した男」がいたことをご存知だろうか?映画『WORTH』では、「被害者遺族のために貢献したい」と無償で難題と向き合うも、その信念が正しく理解されずに反発や対立を招いてしまった現実が描かれる。実話を基にしているとは思えない、凄まじい物語だ
部落出身の人からすれば、「自分たちはこれまで散々苦労してきた」という想いがあるだろう。だからその気持ちが、共に立ち上がった全国の仲間による「部落解放運動」で一気に解放されていったわけだ。もちろんそれは、致し方ないことだと感じる。
また、「部落解放運動」を眺める、あるいはその煽りを食った人たちにしたって、その多くは恐らく、「『差別を無くすべきだ』という部落解放同盟の主張は当然だ」と感じていただろうと思う。それにそもそも、先述した通り、「水平社宣言以前は、部落出身者に対する扱いにはかなりグラデーションがあった」という話もある。あくまで想像でしかないが、「部落出身だからといって別に気にしない」みたいな人だって結構な割合でいたのではないかと思う。だから、理想的すぎる捉え方かもしれないが、そのまま何もしなければ、部落差別は自然消滅したのではないかとさえ考えてしまう。
しかし「部落解放運動」が起こったことで、フラットな感覚を持っていただろう人たちに対してもマイナスな印象が植え付けられたのではないだろうか。つまり、「部落解放同盟の人たちには何を言ってもメチャクチャに反論されるから、彼らの主張はすべて受け入れざるを得ない」みたいな感覚に陥ったのかもしれないというわけだ。彼らの主張が正しいのは当然だと感じつつ、一方で「出来れば関わりたくない」という認識になってしまったのではないか。そして結果として、「差別」が助長されるという状況が生まれたように私には感じられた。
あわせて読みたい
【勇敢】”報道”は被害者を生む。私たちも同罪だ。”批判”による”正義の実現”は正義だろうか?:『リチャ…
「爆弾事件の被害を最小限に食い止めた英雄」が、メディアの勇み足のせいで「爆弾事件の犯人」と報じられてしまった実話を元にした映画『リチャード・ジュエル』から、「他人を公然と批判する行為」の是非と、「再発防止という名の正義」のあり方について考える
「一部の過激な者たちの行動がきっかけでもたらされた状況」という私の捉え方が正しいとして、このような展開は双方にとって不幸でしかないだろうと思う。
「同和対策事業」が抱えていた問題点
さて、そのような流れがあって、1969年に同和対策事業特別措置法が制定されたのである。この法律については、映画に登場するある人物が、
世界に冠たる福祉事業で、恩恵を受けた人はたくさんいる。
という言い方で評価していた(ただ、ちょっと記憶が曖昧なのだが、その人物にしても、「恩恵を受けた人はたくさんいるんだけどね」みたいな、含みのあるニュアンスだったような気もする)。もちろん、33年間で16兆円というなかなかの金額が使われたのだから、そりゃあ”恩恵”はあっただろう。
あわせて読みたい
【情熱】「ルール」は守るため”だけ”に存在するのか?正義を実現するための「ルール」のあり方は?:映…
「ルールは守らなければならない」というのは大前提だが、常に例外は存在する。どれほど重度の自閉症患者でも断らない無許可の施設で、情熱を持って問題に対処する主人公を描く映画『スペシャルズ!』から、「ルールのあるべき姿」を考える
しかし、前述した宮部龍彦は、この同和対策事業について「公金を掠め取る」みたいな表現をしていた。そして確かに、そう受け取られても仕方ないような事件が起こっている。部落解放同盟が、同和対策事業を悪用して大金を得ていたと新聞で報じられたのだ。これについても、悪用した一部の人間のせいだとはいえ、やはり「部落出身者」全体のイメージ悪化に繋がったに違いないと思う。

また、この同和対策事業は別の問題も引き起こしている。ある部落出身者が、かつて次のように言われたことがあると語っていたのだ。
部落の人はいいね。土地をもろて、家も建ててもろて。
あわせて読みたい
【絶望】「人生上手くいかない」と感じる時、彼を思い出してほしい。壮絶な過去を背負って生きる彼を:…
「北九州連続監禁殺人事件」という、マスコミも報道規制するほどの残虐事件。その「主犯の息子」として生きざるを得なかった男の壮絶な人生。「ザ・ノンフィクション」のプロデューサーが『人殺しの息子と呼ばれて』で改めて取り上げた「真摯な男」の生き様と覚悟
これは要するに、「同和対策事業のお陰で、土地も家もタダだったんでしょう?」という妬みから来る発言である。しかし、それは間違った認識なのだそうだ。少なくともその人物の場合は、二重にも三重にも抵当を入れ、自身の金で土地と家を手に入れたのだという。しかし、同和対策事業に公金が流れたことで、「すべての部落出身者が、土地も家もタダで手に入れた」という風に見られ、「部落だけが良くなっている」と妬みの視線が向けられるようになったのだそうだ。
また宮部龍彦は、
同和事業では住宅改善が多く行われたが、住宅については同和事業でやらなくても何とかなったはず。
と語っていた。彼の主張は、「住宅改善などむしろやらない方が良かった」とまとめられる。「同和対策事業による住宅改善のせいで、一層の問題が引き起こされている」というのだ。その理由については、彼が「ライフワーク」にしている活動から理解できるだろう。
あわせて読みたい
【あらすじ】人生行き詰まってなお「生きたい」と思えるか?環境の激変を受け入れる難しさと生きる悲し…
勤務していた会社の都合で、町が1つ丸々無くなるという経験をし、住居を持たないノマド生活へと舵を切った女性を描く映画『ノマドランド』を通じて、人生の大きな変化に立ち向かう気力を持てるのか、我々はどう生きていくべきか、などについて考える
宮部龍彦は自身が代表を務める示現舎のHP上で、「部落探訪」という連載を続けている。名前から想像できる通り、様々な部落を巡っては写真を撮り、その様子をネット上にアップしているのだ。作中ではその取材の様子も映し出されるのだが、その中で、彼が部落に建つ建物を「ニコイチ」と呼ぶ場面がある。詳しい説明は無かったものの、恐らく「1軒の家を2家族が使えるように設計している」という意味なのだと思う。実際に、外側からもそんな風に見える画一的な住宅がたくさん並ぶ光景がカメラに映し出された。
「同和対策事業において、どうして『ニコイチ』の建物がたくさん建てられたのか」についての説明はなかったが、普通に考えて、「狭い地域に出来るだけ多くの戸数を確保するための工夫」なのだと思う。しかし結果としてそのせいで、「ニコイチの建物がある地域は部落である」のだと容易に判断可能な状況が生まれてしまったのだ。真意こそ不明ながら、宮部龍彦はどうも「ニコイチのような”カッコいい”風景に興味がある」のだそうで、別に「部落を晒そう」という意図で「部落探訪」を連載しているわけではないようである。まあ、その動機はともかく、「結果として、見れば『部落であること』が分かってしまう状況」はやはり大きな問題だと感じられた。
さらに、同和対策事業がもたらした問題としては、次のような点も挙げられるだろう。
あわせて読みたい
【違和感】平田オリザ『わかりあえないことから』は「コミュニケーション苦手」問題を新たな視点で捉え…
「コミュニケーションが苦手」なのは、テクニックの問題ではない!?『わかりあえないことから』は、学校でのコミュニケーション教育に携わる演劇人・平田オリザが抱いた違和感を起点に、「コミュニケーション教育」が抱える問題と、私たち日本人が進むべき道を示す1冊
この地域の市営住宅は、「部落にルーツがある人」の入居に限っている。
ある人物がこのように語っているのだが、何が問題なのか分かるだろうか? ここで言及されている「市営住宅」は「同和対策事業で建てられた建物」であり、だとすれば「部落出身者に限る」という制約はあって当然だと感じるかもしれない。しかし一方で、そのような制約があるせいで「同地域に部落出身者ではない人が入って来にくくなる」という問題も生まれているのである。

部落差別は当然、「部落に住んでいるかどうか」なんてことを人々が気にしなくなればなるほど薄れるのだから、部落に外から新しい人が入ってくる方が問題の改善に進展がもたらされるはずだ。しかし、「部落出身者に限る」という制約があるため、たとえ部屋に空きがあっても、外部の人は入居出来ない。となれば結局、「部落出身者ばかりが住む地域」という状況は変わらないし、問題は何も解消されないことになる。このように、「部落出身者のために行っているはずの事業」が、問題の抜本的な解決の障害にもなってしまっているというわけだ。
あわせて読みたい
【扇動】人生うまくいかないと感じる時に読みたい瀧本哲史の本。「未来をどう生きる?」と問われる1冊:…
瀧本哲史は非常に優れたアジテーターであり、『2020年6月30日にまたここで会おう』もまさにそんな1冊。「少数のカリスマ」ではなく「多数の『小さなリーダー』」によって社会が変革されるべきだ、誰にだってやれることはある、と若者を焚きつける、熱量満載の作品
同和対策事業に関してはこのように、特に住宅事業が問題視されていることもあり、「法律の制定によって一層差別が助長されたのではないか」と捉える人もいるのである。
「同和」という”言い換え”がもたらした問題と、国が「部落差別」を利用してきた歴史
「入居が部落出身者に限定されている」という問題を指摘した人物は、「そもそも『同和』という言葉に問題がある」という話もしていた。「同和」というのは、単に「部落」を言い換えた言葉に過ぎない。そしてこの話に触れた人物は、
「『同和地区』という言い方をすれば差別にならない」ってことになっている。
みたいな雰囲気を社会全体から感じるのだそうだ。その感覚は私も理解できる。「部落」という言葉からは、「部落差別」や「被差別部落」という単語がすぐに連想されることもあり、差別的な響きを免れない。しかし「同和」という言葉にはそういう響きを感じないだろう。そしてそれ故に、まったく同じことを表現しているにも拘わらず、「『同和』と表現すれば許される」みたいな感覚が生まれてしまうことになるのだ。「『そのような感覚が存在すること』こそが一番の『ガン』だ」とさえ言っていた。この点については、私自身も強く意識する必要があるだろうし、なるほどと感じさせられる指摘だったなと思う。
あわせて読みたい
【アメリカ】長崎の「原爆ドーム」はなぜ残らなかった?爆心地にあった「浦上天主堂」の数奇な歴史:『…
原爆投下で半壊し、廃墟と化したキリスト教の大聖堂「浦上天主堂」。しかし何故か、「長崎の原爆ドーム」としては残されず、解体されてしまった。そのため長崎には原爆ドームがないのである。『ナガサキ 消えたもう一つの「原爆ドーム」』は、「浦上天主堂」を巡る知られざる歴史を掘り下げ、アメリカの強かさを描き出す
このような「国の責任」については、別の形でも指摘される。「国家の危機を乗り越えるために、国は度々部落差別を利用してきた」という話を部落差別の研究者がしていたのだ。その研究者は、1918年に富山で起こった米騒動の例を挙げている。
前年の1917年にロシア革命が起こったこともあり、政府は富山の米騒動に対して、ロシアの二の舞いになることを強く恐れていたのだそうだ。だから、「どうしてもこの大衆運動を抑えなければならない」と考えていたのである。しかし、米騒動には中心人物はおらず、自然発生的に起こった運動であるため、普通には沈静化させることが難しい。そこで政府は、「米騒動に参加しているのは部落出身の野蛮な連中であり、部落外の者は関わってはいけない」というような発言を公の場でしたそうだ。このように実態とは異なる説明をすることで問題を矮小化し、沈静化を図ったのである。
さらに政府は、米騒動に関わった者たちを処罰する際にも部落差別を利用した。実際には部落・部落外関係なく共闘していたのだが、政府は部落出身の者だけを断罪し、「部落外の人たちはお咎め無し」という采配をしたのだ。このときも、「部落出身者がいかに暴力的であるか」という見せしめを行うことで、危機を乗り越えようとしたのである。
その後、水平社宣言をきっかけとした「部落解放運動」によって、「部落の人は怖い」という印象が強まっていったわけだが、そもそもそのような印象操作を国が率先して行っていたというわけだ。というかむしろ、国家の都合で度々「部落差別」が利用されてきたことが「水平社宣言」へと繋がったとさえ言えるだろう。そして結果として、巡り巡って「部落出身者」のマイナスイメージが一層強化されることになったのだと思う。何とも不幸な歴史である。
あわせて読みたい
【民主主義】占領下の沖縄での衝撃の実話「サンマ裁判」で、魚売りのおばぁの訴えがアメリカをひっかき…
戦後の沖縄で、魚売りのおばぁが起こした「サンマ裁判」は、様々な人が絡む大きな流れを生み出し、最終的に沖縄返還のきっかけともなった。そんな「サンマ裁判」を描く映画『サンマデモクラシー』から、民主主義のあり方と、今も沖縄に残り続ける問題について考える

さて、ここまでの話をまとめよう。
私はそもそも、「部落差別が存在すること自体が理解できない」と感じていた。「部落出身であるか否か」を外見から判断する方法など存在しないからである。そのため、「部落に住んでいるかどうか」で差別されることになるだが、そんな程度の差別が250年間も続いていること自体に違和感を覚えていたというわけだ。
この点に関しては、「部落差別には2つの段階が存在する」という可能性を知り、ようやく状況が把握できたように思う。最初は、「穢多非人」の流れから来る「血の繋がり」がベースの忌避感だったはずだ。その後、その差別感情を国家が便利に利用したことも要因の1つなのだろう、1922年に水平社宣言が出された。そして、これをきっかけにして巻き起こった「部落解放運動」が、「部落差別」を悪化させることに繋がったのだ。一部の者が過激な振る舞いをしたせいで、「部落民は怖い」というマイナスイメージが強化され、「部落には近づくな」と親から子へと伝えられるようになったのである。
あわせて読みたい
【壮絶】アウシュヴィッツで”人体実験の神メンゲレ”から生き残り、ホロコーストから生還した男の人生:…
映画『メンゲレと私』は、タイトルと内容がそぐわないものの、とても興味深い作品だった。44ヶ月間の収容所生活を生き延び、ホロコーストから生還したダニエル・ハノッホが、少年とは思えない「思考力」を武器に、最低最悪な状況を生き延びた経験をカメラの前で語る。あまりにも壮絶な、信じがたい現実である
そして、そのような状況を改善しようとして制定された「同和対策事業特別措置法」が、一層状況を悪化させていく。公金が流れたことで「部落出身者はお金がもらえて羨ましい」と妬まれるし、また、安易な住宅事業を行ったせいで、「見れば部落だと分かる」という状況も生まれてしまったのである。加えて、「部落」を「同和」と言い換えたことによって、「『同和』と表現すれば差別ではない」という正しくない風潮が定着することにもなったというわけだ。
「このような流れで『部落差別』という謎の現象が固定化されてしまった」というのが現時点での私の理解である。このような理解で正しいのか自信があるわけではないし、そもそも「部落差別」を一括りにして語るのも正しくないだろうとは思う。しかし少なくとも、本作を観てこのような理解に達したことで、「まったくの理解不能状態からは脱した」という感覚にはなれた。この点だけでも、本作を観た価値は十分にあるなと思う。
部落に住む者による様々な対話について
さてここまでは、「部落差別」の概略や歴史について触れてきたわけだが、ここからはもっと個別具体的な話について書いていきたいと思う。
あわせて読みたい
【信念】凄いな久遠チョコレート!映画『チョコレートな人々』が映す、障害者雇用に挑む社長の奮闘
重度の人たちも含め、障害者を最低賃金保証で雇用するというかなり無謀な挑戦を続ける夏目浩次を追う映画『チョコレートな人々』には衝撃を受けた。キレイゴトではなく、「障害者を真っ当に雇用したい」と考えて「久遠チョコレート」を軌道に乗せたとんでもない改革者の軌跡を追うドキュメンタリー
先に少し触れたが、本作では、部落に住む様々な人たちが自身の経験について対話するシーンが映し出される。前述した北芝の若者たちや京都の部落に住むお婆さん、あるいは部落に住んではいるが部落出身というわけではない主婦など、様々な人たちが作中に登場し、自身の経験を語っていく。
その中でもやはり、若い人たちの話が最も興味深かった。というのも、少し変な表現かもしれないが、「若者も『部落差別』の問題に直面せざるを得ないのだ」という事実を改めて理解出来たからである。
もちろん、映画を観る前の時点で、「部落出身者には『結婚差別』がつきまとうし、それは若い世代でも変わりないだろう」と思っていた。しかしそういうこととは関係ない部分でも、「『部落』に生まれ、今も住んでいるという事実」に対してあれこれ考えを巡らせなければならないのだと、本作を観て理解できたのである。
さてこれから、北芝の若者3人の話に触れるが、その前にまず、「北芝」という地域の特殊さについて触れておこう。北芝は90年代から、「同和対策事業に依存しないまちづくり」を積極的に行っており、今では「開かれた部落」とも呼ばれているのだそうだ。つまり、他と比べて「部落差別への意識が低い地域」だと言えるだろう。そのため、彼らの話を敷衍することはもしかしたら適切ではないかもしれない。この点は注意力が必要だろう。ただ、そういうことを抜きにしても、なかなか興味深い対話だったと思う。
あわせて読みたい
【幻想】日本での子育ては無理ゲーだ。現実解としての「夜間保育園」の実状と親の想いを描く映画:『夜…
映画『夜間もやってる保育園』によると、夜間保育も行う無認可の「ベビーホテル」は全国に1749ヶ所あるのに対し、「認可夜間保育園」は全国にたった80ヶ所しかないそうだ。また「保育園に預けるなんて可哀想」という「家族幻想」も、子育てする親を苦しめている現実を描く
北芝の若者3人の対話で特に印象的だったのは、「もしも差別的な言動に直面したらどうすべきか」に関する議論だった。
まずそもそもだが、彼ら3人は一様に、「日常生活の中で、部落であることを理由に差別的な扱いを受けることはない」と言っていたと思う。しかしその一方で、「そういう可能性は常に存在し得るのだから、そうなった場合の対処についてはあらかじめ考えておく必要がある」という感覚も持っているのだ。私にはまず、このような認識をしていること自体が印象的だった。

というのも、「具体的な差別感情に直面しての思考というわけではない」からだ。彼らがそれぞれ、何か差別的な言動に直接接したことがあるというなら、「そういう状況でどう振る舞うべきか」について思考を巡らしておくことは自然に思える。しかし実際にはそうではなく、「まだそのような状況になったことはないが、起こる可能性があるから先回りで考えておく」と彼らは言っているのだ。これは恐らく、「『部落に住んでいる』という事実が、何らかの形で彼らに影響を及ぼしている」という事実の表れなのだろう。そのような示唆がとても印象的だったのだ。
あわせて読みたい
【加虐】メディアの役割とは?森達也『A』が提示した「事実を報じる限界」と「思考停止社会」
オウム真理教の内部に潜入した、森達也のドキュメンタリー映画『A』は衝撃を与えた。しかしそれは、宗教団体ではなく、社会の方を切り取った作品だった。思考することを止めた社会の加虐性と、客観的な事実など切り取れないという現実について書く
さて、3人の内の1人は、「どう対処すべきか」について、
相手を変えることは大事だけど、それよりも自分が変わった方が楽。
何か言われてもスルーできるような体力をつけておくことは大事。
みたいに言っていた。これはこれで真っ当な意見だろう。しかし別の考えを持つ者もいる。
あわせて読みたい
【感想】阿部サダヲが狂気を怪演。映画『死刑にいたる病』が突きつける「生きるのに必要なもの」の違い
サイコパスの連続殺人鬼・榛村大和を阿部サダヲが演じる映画『死刑にいたる病』は、「生きていくのに必要なもの」について考えさせる映画でもある。目に光を感じさせない阿部サダヲの演技が、リアリティを感じにくい「榛村大和」という人物を見事に屹立させる素晴らしい映画
流すんじゃなくて、相手に理解してほしいし、そのために闘いたい。
こう主張した人物は、次のような経験について語っていた。彼は「同窓会を開こう」というやり取りの中で偶然、「部落に対して差別意識を持っているかもしれない同級生」の存在を認識してしまったという。そして「その時に、理解してもらうための行動が取れなかったこと」を、今でも悔しいと感じているのだそうだ。
この点に関しては、北芝とは別の部落に住む主婦(嫁いできたので、彼女は部落出身ではない)が似たような話をしていた場面がある。彼女は思いがけず、「大親友が部落出身だと知る」という経験をした。そして、「『そんなことを知らずに、まったく悪意なく発した言葉』で、もしかしたら相手を傷つけてしまっていたかもしれない」と葛藤しているのだそうだ。部落差別の問題はこのような形で、部落出身ではない者にも影響を及ぼし得るのだと実感出来たのである。
また、京都の部落に住むお婆さんの話もとても興味深かった。彼女はそもそも、「自分が部落に住んでいる」という事実を、長い間知らなかったそうだ。実際のところ、道を挟んで反対側の住民との交流はまったくなかったのは確かだという。それを聞いた監督が「交流したいとは思わなかったんですか?」と聞くと、「どうしたらいいか分からん」みたいに答えていた。まあそれはそうだろう。相手が全然近づいて来ないのだから、「どう接していいのか分からなかった」という感覚になるのは自然だろうし、何も知らなければ、その状態に対して「部落だから」などと考えることも不可能だろうと思う。
あわせて読みたい
【抵抗】映画『熊は、いない』は、映画製作を禁じられた映画監督ジャファル・パナヒの執念の結晶だ
映画『熊は、いない』は、「イラン当局から映画製作を20年間も禁じられながら、その後も作品を生み出し続けるジャファル・パナヒ監督」の手によるもので、彼は本作公開後に収監させられてしまった。パナヒ監督が「本人役」として出演する、「ドキュメンタリーとフィクションのあわい」を縫うような異様な作品だ
外から人がまったくやって来なかったこともあり、その地域の住民は皆、パンツ一丁の裸同然で外を歩いていたという。また、当時住んでいた家には水道さえ引かれていないぐらい生活には苦労したようだが、それでも「楽しかった」という感覚の方が強いそうだ。市営住宅に住んでいる今も、「長屋時代の方が大変だったけど、楽しかった」みたいに語っていた。「部落」での生活の捉え方も、人それぞれである。

そんな彼女が「部落に住んでいる」という事実を理解したエピソードがとても興味深かった。1951年に起こった「オールロマンス事件」がきっかけだというのだ。「オールロマンス」という雑誌に当時、『特殊部落』という暴露小説が掲載されたのだが、なんとそれが、まさに彼女が住む地域を舞台にしていたのである。これをきっかけに彼女は「部落」というものを理解し、さらに、男性に混じって部落解放運動に参加するようになったのだそうだ。夫から苦言を呈されても彼女は活動を止めなかった。そして活動をしながら様々なことを理解していき、市役所に乗り込むなど積極的に「生活環境の改善」を訴えることで、少しずつ権利を勝ち取っていったという。
「部落差別」という大きな捉え方とはまた別に、このような個々の体験談みたいなものもとても印象的だった。やはり人それぞれ捉え方は異なるものだし、「部落差別」という大きな括りの中で理解しようとすることの限界を感じさせてくれる要素だと言えるだろう。
あわせて読みたい
【衝撃】これが実話とは。映画『ウーマン・トーキング』が描く、性被害を受けた女性たちの凄まじい決断
映画『ウーマン・トーキング』の驚くべき点は、実話を基にしているという点だ。しかもその事件が起こったのは2000年代に入ってから。とある宗教コミュニティ内で起こった連続レイプ事件を機に村の女性たちがある決断を下す物語であり、そこに至るまでの「ある種異様な話し合い」が丁寧に描かれていく
宮部龍彦が訴えられた裁判と、その驚きの顛末
さて最後に、「部落差別」そのものとはあまり関係ないのだが、先述の宮部龍彦が関わった裁判の話に触れてこの記事を終えようと思う。取り上げるのは、「『全国部落地名総鑑』復刻版出版事件」と呼ばれている問題である。
そもそもの発端は、1936年に発行された「全国部落地名総鑑」の復刻版を、宮部龍彦が代表を務める示現舎が出版したことだ。「全国部落地名総鑑」というのは、全国36都道府県の5367箇所に及ぶ部落について、地名・住所・人口などを網羅した本であり、出版される度に社会問題になっていた。一方で、かつてはなんと、一流企業が購入し、採用面接などの際に活用していたこともあるほど影響力を持つ本でもあったのだ。
そして、そのような本の復刻版を出版した宮部龍彦が、部落解放同盟と原告245名から訴えを起こされ、「出版の停止」「ウェブサイトの削除」「1人あたり100万円の賠償金」を求められたのがこの裁判というわけだ。
あわせて読みたい
【驚愕】あるジャーナリストの衝撃の実話を描く映画『凶悪』。「死刑囚の告発」から「正義」を考える物語
獄中の死刑囚が警察に明かしていない事件を雑誌記者に告発し、「先生」と呼ばれる人物を追い詰めた実際の出来事を描くノンフィクションを原作にして、「ジャーナリズムとは?」「家族とは?」を問う映画『凶悪』は、原作とセットでとにかく凄まじい作品だ
本作には、「全国部落地名総鑑」の出版について、宮部龍彦がどのような認識を抱いているのかが理解できる場面がある。映画に登場するある人物が宮部龍彦に、「この名簿で結婚が破談になる人がいたとして、あなたその責任が取れるんですか?」と問い詰めるのだが、これに対して宮部龍彦は、
それは差別した本人が悪いのであって、情報を載せた私が悪いわけではない。
と返すのだ。まあ、理屈としてはそうかもしれないが、納得し難い主張だとも思う。私としては個人的に、「全国部落地名総鑑」の出版には賛成し難い感覚がある。
では、この裁判はどのような展開を迎えたのか。どうやら今もまだ上告中のようなのだが、少なくとも一審判決は既に出ているのだと思う。結果は、原告側(部落解放同盟側)の勝訴となった。まあ、それ自体は喜ばしいことだと思う。しかし私は、この判決の内容にちょっと驚かされてしまった。作中ではあまり深掘りされなかったのだが、私にはどうにも信じがたい判断に感じられたのだ。

あわせて読みたい
【感想】映画『正欲』に超共感。多様性の時代でさえどこに行っても馴染めない者たちの業苦を抉る(出演…
映画『正欲』は、私には共感しかない作品だ。特に、新垣結衣演じる桐生夏月と磯村勇斗演じる佐々木佳道が抱える葛藤や息苦しさは私の内側にあるものと同じで、その描かれ方に圧倒されてしまった。「『多様性』には『理解』も『受け入れ』も不要で、単に否定しなければ十分」なのだと改めて思う
私が驚いたのは、「『原告となった者が属する6県』に関しては差し止めの判断が下らなかった」ことである。どうしてそんなことになったのか、理解できるだろうか?
作中には説明がなかったので、あくまでも私の想像に過ぎないが、恐らくこのような理屈なのだと思う。原告が属する6県については、「原告が裁判を起こしたこと」によって、「そこが部落であることが公の事実になった」と判断された。だから、「示現舎による復刻版の出版」によって害を被ったとは認定できない。一方で、原告が存在しない他の都道府県については、差し止めの判断を下すことで部落であることが公の事実にならずに済む。そのため差し止めが認められたということなのだろう。
確かに理屈はその通りかもしれない。しかしこれでは、「勇気を出して原告になった者がただ損をしただけ」みたいなことになってしまうだろう。作中では、彼らの弁護を担当している弁護士が、「原告になって訴えを起こしたかったが、子どものことを考えて泣く泣く諦めた人もいる」みたいな話をしていた。つまり、原告になった245名は相当に勇気を振り絞って提訴に踏み切ったというわけだ。しかし、先のような判断が下されるとすれば、今後同じような状況が繰り返された場合、「訴えを起こそうという気持ちになれない」という感覚になってしまうだろうと思う。そしてそれは、特に弱者の権利を守るべきルールの運用において誤りだと私には感じられる。
ネットでざっくり調べてみたのだが、この裁判がどのように決着したのかよく分からなかった。しかしとにかく、「立ち上がろうとする者の意気をくじくような風潮」だけは生まれてほしくないと願っている。
あわせて読みたい
【驚愕】日本の司法は終わってる。「中世レベル」で「無罪判決が多いと出世に不利」な腐った現実:『裁…
三権分立の一翼を担う裁判所のことを、私たちはよく知らない。元エリート裁判官・瀬木比呂志と事件記者・清水潔の対談本『裁判所の正体』をベースに、「裁判所による統制」と「権力との癒着」について書く。「中世レベル」とさえ言われる日本の司法制度の現実は、「裁判になんか関わることない」という人も無視できないはずだ
あわせて読みたい
【全作品視聴済】私が観てきたドキュメンタリー映画を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が観てきたドキュメンタリー映画を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。
最後に
あわせて読みたい
【実話】映画『月』(石井裕也)は、障害者施設での虐待事件から「見て見ぬふりする社会」を抉る(出演…
実際に起こった障害者施設殺傷事件を基にした映画『月』(石井裕也)は、観客を作中世界に引きずり込み、「これはお前たちの物語だぞ」と刃を突きつける圧巻の作品だ。「意思疎通が不可能なら殺していい」という主張には誰もが反対するはずだが、しかしその態度は、ブーメランのように私たちに戻ってくることになる
映画の冒頭で、現在でも「総人口の1.5%程度が部落出身者」だというデータが示された。ざっくり150万人ぐらいはいるということだろう。今もまだ、かなり多くの人たちにとっての「現実的な問題」として「部落差別」が存在するというわけだ。
部落問題には、「寝た子を起こすな」のような考え方もあるという。つまり、「問題として取り上げるよりも、注目を集めずに風化を待つ方が、結果的には早く問題が解決するのではないか」という発想だ。「部落解放運動」とは真逆の考え方と言っていいだろう。このように部落出身者の間でも考え方が異なっているため、なかなか共闘が難しいのだろうと感じた。
とても残念なことであるが、部落問題がどのような進展を見せたところで、「①そもそもあらゆることに対して『差別感情』を抱いている人」がいなくなることはまずないので、部落出身者が苦労せざるを得ない状況は続いてしまうだろうと思う。ただ一方で、部落問題が正しく認識されれば、逆に①の人たちが非難されるような状況に転じる可能性だってあるのではないかとも考えている。私としては、どうにかそういう方向に進んでほしいものだと思う。

あわせて読みたい
【衝撃】ウクライナでのホロコーストを描く映画『バビ・ヤール』は、集めた素材映像が凄まじすぎる
ソ連生まれウクライナ育ちの映画監督セルゲイ・ロズニツァが、「過去映像」を繋ぎ合わせる形で作り上げた映画『バビ・ヤール』は、「単一のホロコーストで最大の犠牲者を出した」として知られる「バビ・ヤール大虐殺」を描き出す。ウクライナ市民も加担した、そのあまりに悲惨な歴史の真実とは?
ただ一方で、「関西在住60代女性」と表示される、顔出しせずにインタビューを受けていた女性は、
日本人がいる限り(部落差別が無くなることを期待するのは)難しいと思う。
と言っていた。この女性は、「普段は差別的な振る舞いはしていないんですよ」と口にしていたが、私には「差別意識を自覚できないタイプの典型」にしか思えなかったし、特に年配の人にはこういう感覚の人が多いんだろうなと思っている。であれば、一昔前の世代が一掃されないと、状況に劇的な変化は起こらないのかもしれない。
あわせて読みたい
【食&芸術】死んでも車を運転したくない人間の香川うどん巡り& 豊島アート巡りの旅ルート(山越うどん…
仕事終わりの木曜日夜から日曜日に掛けて、「香川のうどん巡り」と「豊島のアート巡り」をしてきました。うどんだけでも7580円分食べたので、かなりの軒数を回ったことになります。しかも「死んでも車を運転したくない」ため、可能な限り公共交通機関のみで移動しました。私と同じように「車を運転したくない人」には、かなり参考になる記事と言えるのではないかと思います
非常に難しい問題ではあるが、とにかく私は本作『私のはなし 部落のはなし』を観て、ようやく「部落差別の現在地」を理解できたように思う。そういう意味で、とても観て良かったと感じられる作品だった。
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を…
Kindleで本を出版しました。タイトルは、『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を分かりやすく書いた本:相対性理論も宇宙論も量子論も』です。科学や科学者に関する、文系の人でも読んでもらえる作品に仕上げました。そんな自著について紹介をしています。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【発見】映画『小学校~それは小さな社会~』(山崎エマ)が映し出すのは、我々には日常すぎる日常だ
映画『小学校~それは小さな社会~』は、ごく一般的な公立小学校に密着し、日本で生まれ育った人間には「当たり前」にしか思えない日常を切り取った作品なのだが、そんな映画が諸外国で大いに評価されているという。「TOKKATSU」という「日本式教育」が注目されているらしく、私たちの「当たり前」が違和感だらけに見えているのだそうだ
あわせて読みたい
【感動】映画『ぼくとパパ、約束の週末』は「自閉症への理解が深まる」という点で実に興味深かった
映画『ぼくとパパ、約束の週末』は「心温まる物語」であり、一般的にはそういう作品として評価されているはずだが、個人的には「『自閉症』への解像度が高まる」という意味でも興味深かった。「ルールは厳密に守るが、ルール同士が矛盾していて袋小路に陥ってしまう」という困難さが実に分かりやすく描かれている
あわせて読みたい
【変異】映画『動物界』は斬新で刺激的な作品だった。我々はまさにこんな”分断社会”に生きている
映画『動物界』では、「奇病によって人間が動物化してしまう」という世界における複雑な人間模様が描き出される。パンデミックを経験した我々には、本作の設定は「単なるSF」には感じられないはずだ。そしてその上で、「『動物化してしまった妻を今も愛している主人公』が見せる実にややこしい感情」が複層的に描かれていて実に興味深い
あわせて読みたい
【絶望】映画『若き見知らぬ者たち』が描くのは”不正解”だが、「じゃあ”正解”って何?」ってなる(監督…
映画『若き見知らぬ者たち』は、「まともな生活が送れなくなった母親の介護」を筆頭に、かなり絶望的な状況に置かれている若者たちを描き出す作品だ。あまりにも不毛で、あまりにも救いがなく、あまりにも辛すぎるその日々は、ついに限界を迎える。そしてその絶望を、磯村勇斗がその凄まじい存在感によって体現していく
あわせて読みたい
【絶望】満員続出の映画『どうすればよかったか?』が描き出す、娘の統合失調症を認めない両親の不条理
たった4館から100館以上にまで上映館が拡大した話題の映画『どうすればよかったか?』を公開2日目に観に行った私は、「ドキュメンタリー映画がどうしてこれほど注目されているのだろうか?」と不思議に感じた。統合失調症を発症した姉を中心に家族を切り取る本作は、観る者に「自分だったらどうするか?」という問いを突きつける
あわせて読みたい
【面白い】映画『ラストマイル』は、物流問題をベースに「起こり得るリアル」をポップに突きつける(監…
映画『ラストマイル』は、「物流」という「ネット社会では誰にでも関係し得る社会問題」に斬り込みながら、実に軽妙でポップな雰囲気で展開されるエンタメ作品である。『アンナチュラル』『MIU404』と同じ世界で展開される「シェアード・ユニバース」も話題で、様々な人の関心を広く喚起する作品と言えるだろう
あわせて読みたい
【思想】川口大三郎は何故、早稲田を牛耳る革マル派に殺された?映画『ゲバルトの杜』が映す真実
映画『ゲバルトの杜』は、「『革マル派』という左翼の集団に牛耳られた早稲田大学内で、何の罪もない大学生・川口大三郎がリンチの末に殺された」という衝撃的な事件を、当時を知る様々な証言者の話と、鴻上尚史演出による劇映画パートによって炙り出すドキュメンタリー映画だ。同じ国で起こった出来事とは思えないほど狂気的で驚かされた
あわせて読みたい
【あらすじ】老夫婦の”穏やかな日常”から核戦争の恐怖を描くアニメ映画『風が吹くとき』の衝撃
一軒家の中だけで展開される老夫婦の日常から「核戦争」の危機をリアルに描き出す映画『風が吹くとき』は、日本では1987年に公開された作品なのだが、今まさに観るべき作品ではないかと。世界的に「核戦争」の可能性が高まっているし、また「いつ起こるか分からない巨大地震」と読み替えても成立する作品で、実に興味深かった
あわせて読みたい
【現在】ウーマンラッシュアワー村本大輔がテレビから消えた理由と彼の”優しさ”を描く映画:『アイアム…
「テレビから消えた」と言われるウーマンラッシュアワー・村本大輔に密着する映画『アイアム・ア・コメディアン』は、彼に対してさほど関心を抱いていない人でも面白く観られるドキュメンタリー映画だと思う。自身の存在意義を「拡声器」のように捉え、様々な社会問題を「お笑い」で発信し続ける姿には、静かな感動さえ抱かされるだろう
あわせて読みたい
【感想】映画『夜明けのすべて』は、「ままならなさ」を抱えて生きるすべての人に優しく寄り添う(監督…
映画『夜明けのすべて』は、「PMS」や「パニック障害」を通じて、「自分のものなのに、心・身体が思い通りにならない」という「ままならなさ」を描き出していく。決して他人事ではないし、「私たちもいつそのような状況に置かれるか分からない」という気持ちで観るのがいいでしょう。物語の起伏がないのに惹きつけられる素敵な作品です
あわせて読みたい
【衝撃】EUの難民問題の狂気的縮図!ポーランド・ベラルーシ国境での、国による非人道的対応:映画『人…
上映に際し政府から妨害を受けたという映画『人間の境界』は、ポーランド・ベラルーシ国境で起こっていた凄まじい現実が描かれている。「両国間で中東からの難民を押し付け合う」という醜悪さは見るに絶えないが、そのような状況下でも「可能な範囲でどうにか人助けをしたい」と考える者たちの奮闘には救われる思いがした
あわせて読みたい
【挑戦】映画『燃えあがる女性記者たち』が描く、インドカースト最下位・ダリットの女性による報道
映画『燃えあがる女性記者たち』は、インドで「カースト外の不可触民」として扱われるダリットの女性たちが立ち上げた新聞社「カバル・ラハリヤ」を取り上げる。自身の境遇に抗って、辛い状況にいる人の声を届けたり権力者を糾弾したりする彼女たちの奮闘ぶりが、インドの民主主義を変革させるかもしれない
あわせて読みたい
【日本】原発再稼働が進むが、その安全性は?樋口英明の画期的判決とソーラーシェアリングを知る:映画…
映画『原発をとめた裁判長 そして原発をとめる農家たち』では、大飯原発の運転差し止め判決を下した裁判長による画期的な「樋口理論」の説明に重点が置かれる。「原発の耐震性」に関して知らないことが満載で、実に興味深かった。また、農家が発案した「ソーラーシェアリング」という新たな発電方法も注目である
あわせて読みたい
【歴史】映画『シン・ちむどんどん』は、普天間基地移設問題に絡む辺野古埋め立てを”陽気に”追及する(…
映画『シン・ちむどんどん』は、映画『センキョナンデス』に続く「ダースレイダー・プチ鹿島による選挙戦リポート」第2弾である。今回のターゲットは沖縄知事選。そして本作においては、選挙戦の模様以上に、後半で取り上げられる「普天間基地の辺野古移設問題の掘り下げ」の方がより興味深かった
あわせて読みたい
【食&芸術】死んでも車を運転したくない人間の香川うどん巡り& 豊島アート巡りの旅ルート(山越うどん…
仕事終わりの木曜日夜から日曜日に掛けて、「香川のうどん巡り」と「豊島のアート巡り」をしてきました。うどんだけでも7580円分食べたので、かなりの軒数を回ったことになります。しかも「死んでも車を運転したくない」ため、可能な限り公共交通機関のみで移動しました。私と同じように「車を運転したくない人」には、かなり参考になる記事と言えるのではないかと思います
あわせて読みたい
【斬新】フィクション?ドキュメンタリー?驚きの手法で撮られた、現実と虚構が入り混じる映画:『最悪…
映画『最悪な子どもたち』は、最後まで観てもフィクションなのかドキュメンタリーなのか確信が持てなかった、普段なかなか抱くことのない感覚がもたらされる作品だった。「演技未経験」の少年少女を集めての撮影はかなり実験的に感じられたし、「分からないこと」に惹かれる作品と言えるいだろうと思う
あわせて読みたい
【壮絶】アウシュヴィッツで”人体実験の神メンゲレ”から生き残り、ホロコーストから生還した男の人生:…
映画『メンゲレと私』は、タイトルと内容がそぐわないものの、とても興味深い作品だった。44ヶ月間の収容所生活を生き延び、ホロコーストから生還したダニエル・ハノッホが、少年とは思えない「思考力」を武器に、最低最悪な状況を生き延びた経験をカメラの前で語る。あまりにも壮絶な、信じがたい現実である
あわせて読みたい
【無謀】映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、脱北ルートに撮影隊が同行する衝撃のドキュメンタリー
北朝鮮からの脱北者に同行し撮影を行う衝撃のドキュメンタリー映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、再現映像を一切使用していない衝撃的な作品だ。危険と隣り合わせの脱北の道程にカメラもついて回り、北朝鮮の厳しい現状と共に、脱北者が置かれた凄まじい状況を映し出す内容に驚かされてしまった
あわせて読みたい
【挑戦】杉並区長・岸本聡子を誕生させた市民運動・選挙戦と、ミュニシパリズムの可能性を描く:『映画…
映画『映画 ◯月◯日、区長になる女。』は、杉並区初の女性区長・岸本聡子を誕生させた選挙戦の裏側を中心に、日本の民主主義を問う作品だ。劇場公開されるや、チケットを取るのが困難なほど観客が殺到した作品であり、観れば日本の政治の「変化」を感じられるのではないかと思う
あわせて読みたい
【感想】関東大震災前後を描く映画『福田村事件』(森達也)は、社会が孕む「思考停止」と「差別問題」…
森達也監督初の劇映画である『福田村事件』は、100年前の関東大震災直後に起こった「デマを起点とする悲劇」が扱われる作品だ。しかし、そんな作品全体が伝えるメッセージは、「100年前よりも現代の方がよりヤバい」だと私は感じた。SNS時代だからこそ意識すべき問題の詰まった、挑発的な作品である
あわせて読みたい
【抵抗】映画『熊は、いない』は、映画製作を禁じられた映画監督ジャファル・パナヒの執念の結晶だ
映画『熊は、いない』は、「イラン当局から映画製作を20年間も禁じられながら、その後も作品を生み出し続けるジャファル・パナヒ監督」の手によるもので、彼は本作公開後に収監させられてしまった。パナヒ監督が「本人役」として出演する、「ドキュメンタリーとフィクションのあわい」を縫うような異様な作品だ
あわせて読みたい
【絶望】安倍首相へのヤジが”排除”された衝撃の事件から、日本の民主主義の危機を考える:映画『ヤジと…
映画『ヤジと民主主義 劇場拡大版』が映し出すのは、「政治家にヤジを飛ばしただけで国家権力に制止させられた個人」を巡る凄まじい現実だ。「表現の自由」を威圧的に抑えつけようとする国家の横暴は、まさに「民主主義」の危機を象徴していると言えるだろう。全国民が知るべき、とんでもない事件である
あわせて読みたい
【実話】映画『月』(石井裕也)は、障害者施設での虐待事件から「見て見ぬふりする社会」を抉る(出演…
実際に起こった障害者施設殺傷事件を基にした映画『月』(石井裕也)は、観客を作中世界に引きずり込み、「これはお前たちの物語だぞ」と刃を突きつける圧巻の作品だ。「意思疎通が不可能なら殺していい」という主張には誰もが反対するはずだが、しかしその態度は、ブーメランのように私たちに戻ってくることになる
あわせて読みたい
【感想】映画『正欲』に超共感。多様性の時代でさえどこに行っても馴染めない者たちの業苦を抉る(出演…
映画『正欲』は、私には共感しかない作品だ。特に、新垣結衣演じる桐生夏月と磯村勇斗演じる佐々木佳道が抱える葛藤や息苦しさは私の内側にあるものと同じで、その描かれ方に圧倒されてしまった。「『多様性』には『理解』も『受け入れ』も不要で、単に否定しなければ十分」なのだと改めて思う
あわせて読みたい
【現実】我々が食べてる魚は奴隷船が獲ったもの?映画『ゴースト・フリート』が描く驚くべき漁業の問題
私たちは、「奴隷」が獲った魚を食べているのかもしれない。映画『ゴースト・フリート』が描くのは、「拉致され、数十年も遠洋船上に隔離されながら漁をさせられている奴隷」の存在だ。本作は、その信じがたい現実に挑む女性活動家を追うドキュメンタリー映画であり、まさに世界が関心を持つべき問題だと思う
あわせて読みたい
【衝撃】ウクライナでのホロコーストを描く映画『バビ・ヤール』は、集めた素材映像が凄まじすぎる
ソ連生まれウクライナ育ちの映画監督セルゲイ・ロズニツァが、「過去映像」を繋ぎ合わせる形で作り上げた映画『バビ・ヤール』は、「単一のホロコーストで最大の犠牲者を出した」として知られる「バビ・ヤール大虐殺」を描き出す。ウクライナ市民も加担した、そのあまりに悲惨な歴史の真実とは?
あわせて読みたい
【狂気】ホロコーストはなぜ起きた?映画『ヒトラーのための虐殺会議』が描くヴァンゼー会議の真実
映画『ヒトラーのための虐殺会議』は、ホロコーストの計画について話し合われた「ヴァンゼー会議」を描き出す作品だ。唯一1部だけ残った議事録を基に作られた本作は、「ユダヤ人虐殺」をイベントの準備でもしているかのように「理性的」に計画する様を映し出す。その「狂気」に驚かされてしまった。
あわせて読みたい
【映画】『街は誰のもの?』という問いは奥深い。「公共」の意味を考えさせる問題提起に満ちた作品
映画『街は誰のもの?』は、タイトルの通り「街(公共)は誰のものなのか?」を問う作品だ。そしてそのテーマの1つが、無許可で街中に絵を描く「グラフィティ」であることもまた面白い。想像もしなかった問いや価値観に直面させられる、とても興味深い作品である
あわせて読みたい
【驚愕】本屋大賞受賞作『同志少女よ、敵を撃て』(逢坂冬馬)は凄まじい。戦場は人間を”怪物”にする
デビュー作で本屋大賞を受賞した『同志少女よ、敵を撃て』(逢坂冬馬)は、デビュー作であることを抜きにしても凄まじすぎる、規格外の小説だった。ソ連に実在した「女性狙撃兵」の視点から「独ソ戦」を描く物語は、生死の境でギリギリの葛藤や決断に直面する女性たちのとんでもない生き様を活写する
あわせて読みたい
【信念】凄いな久遠チョコレート!映画『チョコレートな人々』が映す、障害者雇用に挑む社長の奮闘
重度の人たちも含め、障害者を最低賃金保証で雇用するというかなり無謀な挑戦を続ける夏目浩次を追う映画『チョコレートな人々』には衝撃を受けた。キレイゴトではなく、「障害者を真っ当に雇用したい」と考えて「久遠チョコレート」を軌道に乗せたとんでもない改革者の軌跡を追うドキュメンタリー
あわせて読みたい
【狂気?】オウム真理教を内部から映す映画『A』(森達也監督)は、ドキュメンタリー映画史に残る衝撃作だ
ドキュメンタリー映画の傑作『A』(森達也)をようやく観られた。「オウム真理教は絶対悪だ」というメディアの報道が凄まじい中、オウム真理教をその内部からフラットに映し出した特異な作品は、公開当時は特に凄まじい衝撃をもたらしただろう。私たちの「当たり前」が解体されていく斬新な一作
あわせて読みたい
【衝撃】これが実話とは。映画『ウーマン・トーキング』が描く、性被害を受けた女性たちの凄まじい決断
映画『ウーマン・トーキング』の驚くべき点は、実話を基にしているという点だ。しかもその事件が起こったのは2000年代に入ってから。とある宗教コミュニティ内で起こった連続レイプ事件を機に村の女性たちがある決断を下す物語であり、そこに至るまでの「ある種異様な話し合い」が丁寧に描かれていく
あわせて読みたい
【実話】映画『グリーンブック』は我々に問う。当たり前の行動に「差別意識」が含まれていないか、と
黒人差別が遥かに苛烈だった時代のアメリカにおいて、黒人ピアニストと彼に雇われた白人ドライバーを描く映画『グリーンブック』は、観客に「あなたも同じような振る舞いをしていないか?」と突きつける作品だ。「差別」に限らず、「同時代の『当たり前』に従った行動」について考え直させる1作
あわせて読みたい
【性加害】映画『SHE SAID その名を暴け』を観てくれ。#MeToo運動を生んだ報道の舞台裏(出演:キャリ…
「#MeToo」運動のきっかけとなった、ハリウッドの絶対権力者ハーヴェイ・ワインスタインを告発するニューヨーク・タイムズの記事。その取材を担った2人の女性記者の奮闘を描く映画『SHE SAID その名を暴け』は、ジャニー喜多川の性加害問題で揺れる今、絶対に観るべき映画だと思う
あわせて読みたい
【純真】ゲイが犯罪だった時代が舞台の映画『大いなる自由』は、刑務所内での極深な人間ドラマを描く
男性同士の恋愛が犯罪であり、ゲイの男性が刑法175条を理由に逮捕されてしまう時代のドイツを描いた映画『大いなる自由』は、確かに同性愛の物語なのだが、実はそこに本質はない。物語の本質は、まさにタイトルにある通り「自由」であり、ラストシーンで突きつけられるその深い問いかけには衝撃を受けるだろう
あわせて読みたい
【傑物】フランスに最も愛された政治家シモーヌ・ヴェイユの、強制収容所から国連までの凄絶な歩み:映…
「フランスに最も愛された政治家」と評されるシモーヌ・ヴェイユ。映画『シモーヌ』は、そんな彼女が強制収容所を生き延び、後に旧弊な社会を変革したその凄まじい功績を描き出す作品だ。「強制収容所からの生還が失敗に思える」とさえ感じたという戦後のフランスの中で、彼女はいかに革新的な歩みを続けたのか
あわせて読みたい
【実話】ポートアーサー銃乱射事件を扱う映画『ニトラム』が示す、犯罪への傾倒に抗えない人生の不条理
オーストラリアで実際に起こった銃乱射事件の犯人の生い立ちを描く映画『ニトラム/NITRAM』は、「頼むから何も起こらないでくれ」と願ってしまうほどの異様な不穏さに満ちている。「社会に順応できない人間」を社会がどう受け入れるべきかについて改めて考えさせる作品だ
あわせて読みたい
【実話】ソ連の衝撃の事実を隠蔽する記者と暴く記者。映画『赤い闇』が描くジャーナリズムの役割と実態
ソ連の「闇」を暴いた名もなき記者の実話を描いた映画『赤い闇』は、「メディアの存在意義」と「メディアとの接し方」を問いかける作品だ。「真実」を届ける「社会の公器」であるべきメディアは、容易に腐敗し得る。情報の受け手である私たちの意識も改めなければならない
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』で描かれる、グアンタナモ”刑務所”の衝撃の実話は必見
ベネディクト・カンバーバッチが制作を熱望した衝撃の映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』は、アメリカの信じがたい実話を基にしている。「9.11の首謀者」として不当に拘束され続けた男を「救おうとする者」と「追い詰めようとする者」の奮闘が、「アメリカの闇」を暴き出す
あわせて読みたい
【あらすじ】蝦夷地の歴史と英雄・阿弖流為を描く高橋克彦の超大作小説『火怨』は全人類必読の超傑作
大げさではなく、「死ぬまでに絶対に読んでほしい1冊」としてお勧めしたい高橋克彦『火怨』は凄まじい小説だ。歴史が苦手で嫌いな私でも、上下1000ページの物語を一気読みだった。人間が人間として生きていく上で大事なものが詰まった、矜持と信念に溢れた物語に酔いしれてほしい
あわせて読みたい
【狂気】アメリカの衝撃の実態。民営刑務所に刑務官として潜入した著者のレポートは国をも動かした:『…
アメリカには「民営刑務所」が存在する。取材のためにその1つに刑務官として潜入した著者が記した『アメリカン・プリズン』は信じがたい描写に溢れた1冊だ。あまりに非人道的な行いがまかり通る狂気の世界と、「民営刑務所」が誕生した歴史的背景を描き出すノンフィクション
あわせて読みたい
【あらすじ】死刑囚を救い出す実話を基にした映画『黒い司法』が指摘する、死刑制度の問題と黒人差別の現実
アメリカで死刑囚の支援を行う団体を立ち上げた若者の実話を基にした映画『黒い司法 0%からの奇跡』は、「死刑制度」の存在価値について考えさせる。上映後のトークイベントで、アメリカにおける「死刑制度」と「黒人差別」の結びつきを知り、一層驚かされた
あわせて読みたい
【不謹慎】コンプライアンス無視の『テレビで会えない芸人』松元ヒロを追う映画から芸と憲法を考える
かつてテレビの世界で大ブレイクを果たしながら、現在はテレビから完全に離れ、年間120もの公演を行う芸人・松元ヒロ。そんな知る人ぞ知る芸人を追った映画『テレビで会えない芸人』は、コンプライアンスに厳しく、少数派が蔑ろにされる社会へ一石を投じる、爆笑社会風刺である
あわせて読みたい
【悲劇】アメリカの暗黒の歴史である奴隷制度の現実を、元奴隷の黒人女性自ら赤裸々に語る衝撃:『ある…
生まれながらに「奴隷」だった黒人女性が、多くの人の協力を得て自由を手にし、後に「奴隷制度」について書いたのが『ある奴隷少女に起こった出来事』。長らく「白人が書いた小説」と思われていたが、事実だと証明され、欧米で大ベストセラーとなった古典作品が示す「奴隷制度の残酷さ」
あわせて読みたい
【対立】パレスチナとイスラエルの「音楽の架け橋」は実在する。映画『クレッシェンド』が描く奇跡の楽団
イスラエルとパレスチナの対立を背景に描く映画『クレッシェンド』は、ストーリーそのものは実話ではないものの、映画の中心となる「パレスチナ人・イスラエル人混合の管弦楽団」は実在する。私たちが生きる世界に残る様々な対立について、その「改善」の可能性を示唆する作品
あわせて読みたい
【実話】台湾のろう学校のいじめ・性的虐待事件を描く映画『無聲』が問う、あまりに悲しい現実
台湾のろう学校で実際に起こったいじめ・性的虐待事件を基に作られた映画『無聲』は、健常者の世界に刃を突きつける物語だ。これが実話だという事実に驚かされる。いじめ・性的虐待が物語の「大前提」でしかないという衝撃と、「性的虐待の方がマシ」という選択を躊躇せず行う少女のあまりの絶望を描き出す
あわせて読みたい
【証言】ナチスドイツでヒトラーに次ぐナンバー2だったゲッベルス。その秘書だった女性が歴史を語る映画…
ナチスドイツナンバー2だった宣伝大臣ゲッベルス。その秘書だったブルンヒルデ・ポムゼルが103歳の時にカメラの前で当時を語った映画『ゲッベルスと私』には、「愚かなことをしたが、避け難かった」という彼女の悔恨と教訓が含まれている。私たちは彼女の言葉を真摯に受け止めなければならない
あわせて読みたい
【衝撃】映画『ダンサー・イン・ザ・ダーク』凄い。ラストの衝撃、ビョークの演技、”愛”とは呼びたくな…
言わずとしれた名作映画『ダンサー・イン・ザ・ダーク』を、ほぼ予備知識ゼロのまま劇場で観た。とんでもない映画だった。苦手なミュージカルシーンが効果的だと感じられたこと、「最低最悪のラストは回避できたはずだ」という想い、そして「セルマのような人こそ報われてほしい」という祈り
あわせて読みたい
【理解】小野田寛郎を描く映画。「戦争終結という現実を受け入れない(=認知的不協和)」は他人事じゃ…
映画『ONODA 一万夜を越えて』を観るまで、小野田寛郎という人間に対して違和感を覚えていた。「戦争は終わっていない」という現実を生き続けたことが不自然に思えたのだ。しかし映画を観て、彼の生き方・決断は、私たちと大きく変わりはしないと実感できた
あわせて読みたい
【信念】水俣病の真実を世界に伝えた写真家ユージン・スミスを描く映画。真実とは「痛みへの共感」だ:…
私はその存在をまったく知らなかったが、「水俣病」を「世界中が知る公害」にした報道写真家がいる。映画『MINAMATA―ミナマタ―』は、水俣病の真実を世界に伝えたユージン・スミスの知られざる生涯と、理不尽に立ち向かう多くの人々の奮闘を描き出す
あわせて読みたい
【狂気】ホロコーストはなぜ起きた?映画『ヒトラーのための虐殺会議』が描くヴァンゼー会議の真実
映画『ヒトラーのための虐殺会議』は、ホロコーストの計画について話し合われた「ヴァンゼー会議」を描き出す作品だ。唯一1部だけ残った議事録を基に作られた本作は、「ユダヤ人虐殺」をイベントの準備でもしているかのように「理性的」に計画する様を映し出す。その「狂気」に驚かされてしまった。
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『流浪の月』を観て感じた、「『見て分かること』にしか反応できない世界」への気持ち悪さ
私は「見て分かること」に”しか”反応できない世界に日々苛立ちを覚えている。そういう社会だからこそ、映画『流浪の月』で描かれる文と更紗の関係も「気持ち悪い」と断罪されるのだ。私はむしろ、どうしようもなく文と更紗の関係を「羨ましい」と感じてしまう。
あわせて読みたい
【実話】映画『アウシュビッツ・レポート』が描き出す驚愕の史実。世界はいかにホロコーストを知ったのか?
映画『アウシュヴィッツ・レポート』は、アウシュビッツ強制収容所から抜け出し、詳細な記録と共にホロコーストの実態を世界に明らかにした実話を基にした作品。2人が持ち出した「アウシュビッツ・レポート」こそが、ホロコーストについて世界が知るきっかけだったのであり、そんな史実をまったく知らなかったことにも驚かされた
あわせて読みたい
【凄絶】北朝鮮の”真実”を描くアニメ映画。強制収容所から決死の脱出を試みた者が語る驚愕の実態:『ト…
在日コリアン4世の監督が、北朝鮮脱北者への取材を元に作り上げた壮絶なアニメ映画『トゥルーノース』は、私たちがあまりに恐ろしい世界と地続きに生きていることを思い知らせてくれる。最低最悪の絶望を前に、人間はどれだけ悪虐になれてしまうのか、そしていかに優しさを発揮できるのか。
あわせて読みたい
【勇敢】ユダヤ人を救った杉原千畝を描く映画。日本政府の方針に反しながら信念を貫いた男の生き様
日本政府の方針に逆らってまでユダヤ人のためにビザを発給し続けた外交官を描く映画『杉原千畝』。日本を良くしたいと考えてモスクワを夢見た青年は、何故キャリアを捨てる覚悟で「命のビザ」を発給したのか。困難な状況を前に、いかに決断するかを考えさせられる
あわせて読みたい
【残念】日本の「難民受け入れ」の現実に衝撃。こんな「恥ずべき国」に生きているのだと絶望させられる…
日本の「難民認定率」が他の先進国と比べて異常に低いことは知っていた。しかし、日本の「難民」を取り巻く実状がこれほど酷いものだとはまったく知らなかった。日本で育った2人のクルド人難民に焦点を当てる映画『東京クルド』から、日本に住む「難民」の現実を知る
あわせて読みたい
【実話】権力の濫用を監視するマスコミが「教会の暗部」を暴く映画『スポットライト』が現代社会を斬る
地方紙である「ボストン・グローブ紙」は、数多くの神父が長年に渡り子どもに対して性的虐待を行い、その事実を教会全体で隠蔽していたという衝撃の事実を明らかにした。彼らの奮闘の実話を映画化した『スポットライト』から、「権力の監視」の重要性を改めて理解する
あわせて読みたい
【最新】「コロンブス到達以前のアメリカ大陸」をリアルに描く歴史書。我々も米国人も大いに誤解してい…
サイエンスライターである著者は、「コロンブス到着以前のアメリカはどんな世界だったか?」という問いに触れ、その答えが書かれた本がいつまで経っても出版されないので自分で執筆した。『1491 先コロンブス期アメリカ大陸をめぐる新発見』には、アメリカ人も知らない歴史が満載だ
あわせて読みたい
【真実】ホロコーストが裁判で争われた衝撃の実話が映画化。”明らかな虚偽”にどう立ち向かうべきか:『…
「ホロコーストが起こったか否か」が、なんとイギリスの裁判で争われたことがある。その衝撃の実話を元にした『否定と肯定』では、「真実とは何か?」「情報をどう信じるべきか?」が問われる。「フェイクニュース」という言葉が当たり前に使われる世界に生きているからこそ知っておくべき事実
あわせて読みたい
【興奮】世界的大ベストセラー『サピエンス全史』要約。人類が文明を築き上げるに至った3つの革命とは?
言わずと知れた大ベストセラー『サピエンス全史』は、「何故サピエンスだけが人類の中で生き残り、他の生物が成し得なかった歴史を歩んだのか」を、「認知革命」「農業革命」「科学革命」の3つを主軸としながら解き明かす、知的興奮に満ち溢れた1冊
あわせて読みたい
【矛盾】死刑囚を「教誨師」視点で描く映画。理解が及ばない”死刑という現実”が突きつけられる
先進国では数少なくなった「死刑存置国」である日本。社会が人間の命を奪うことを許容する制度は、果たして矛盾なく存在し得るのだろうか?死刑確定囚と対話する教誨師を主人公に、死刑制度の実状をあぶり出す映画『教誨師』から、死刑という現実を理解する
あわせて読みたい
【人生】「資本主義の限界を埋める存在としての『贈与論』」から「不合理」に気づくための生き方を知る…
「贈与論」は簡単には理解できないが、一方で、「何かを受け取ったら、与えてくれた人に返す」という「交換」の論理では対処できない現実に対峙する力ともなる。『世界は贈与でできている』から「贈与」的な見方を理解し、「受取人の想像力」を立ち上げる
あわせて読みたい
【レッテル】コミュニケーションで大事なのは、肩書や立場を外して、相手を”その人”として見ることだ:…
私は、それがポジティブなものであれ、「レッテル」で見られることは嫌いです。主人公の1人、障害を持つ大富豪もまたそんなタイプ。傍若無人な元犯罪者デルとの出会いでフィリップが変わっていく『THE UPSIDE 最強のふたり』からコミュニケーションを学ぶ
あわせて読みたい
【勇敢】”報道”は被害者を生む。私たちも同罪だ。”批判”による”正義の実現”は正義だろうか?:『リチャ…
「爆弾事件の被害を最小限に食い止めた英雄」が、メディアの勇み足のせいで「爆弾事件の犯人」と報じられてしまった実話を元にした映画『リチャード・ジュエル』から、「他人を公然と批判する行為」の是非と、「再発防止という名の正義」のあり方について考える
あわせて読みたい
【興奮】飲茶氏が西洋哲学を語る。難解な思想が「グラップラー刃牙成分」の追加で驚異的な面白さに:『…
名前は聞いたことはあるがカントやニーチェがどんな主張をしたのかは分からないという方は多いだろう。私も無知なまったくの初心者だが、そんな人でも超絶分かりやすく超絶面白く西洋哲学を”分かった気になれる”飲茶『史上最強の哲学入門』は、入門書として最強
あわせて読みたい
【思考】「”考える”とはどういうことか」を”考える”のは難しい。だからこの1冊をガイドに”考えて”みよう…
私たちは普段、当たり前のように「考える」ことをしている。しかし、それがどんな行為で、どのように行っているのかを、きちんと捉えて説明することは難しい。「はじめて考えるときのように」は、横書き・イラスト付きの平易な文章で、「考えるという行為」の本質に迫り、上達のために必要な要素を伝える
あわせて読みたい
【真実?】佐村河内守のゴーストライター騒動に森達也が斬り込んだ『FAKE』は我々に何を問うか?
一時期メディアを騒がせた、佐村河内守の「ゴースト問題」に、森達也が斬り込む。「耳は聴こえないのか?」「作曲はできるのか?」という疑惑を様々な角度から追及しつつ、森達也らしく「事実とは何か?」を問いかける『FAKE』から、「事実の捉え方」について考える
あわせて読みたい
【絶望】「人生上手くいかない」と感じる時、彼を思い出してほしい。壮絶な過去を背負って生きる彼を:…
「北九州連続監禁殺人事件」という、マスコミも報道規制するほどの残虐事件。その「主犯の息子」として生きざるを得なかった男の壮絶な人生。「ザ・ノンフィクション」のプロデューサーが『人殺しの息子と呼ばれて』で改めて取り上げた「真摯な男」の生き様と覚悟
あわせて読みたい
【誠実】想像を超える辛い経験を言葉にするのは不可能だ。それを分かってなお筆を執った作家の震災記:…
旅行者として東日本大震災で被災した小説家・彩瀬まるは、『暗い夜、星を数えて 3.11被災鉄道からの脱出』でその体験を語る。「そんなこと、言わなければ分からない」と感じるような感情も包み隠さず記し、「絶望的な伝わらなさ」を感じながらも伝えようと奮闘する1冊
あわせて読みたい
【理解】東田直樹の本は「自閉症の見方」を一変させた。自身も自閉症児を育てるプロデューサーが映画化…
東田直樹の著作を英訳し世界に広めた人物(自閉症児を育てている)も登場する映画『僕が跳びはねる理由』には、「東田直樹が語る自閉症の世界」を知ることで接し方や考え方が変わったという家族が登場する。「自閉症は知恵遅れではない」と示した東田直樹の多大な功績を実感できる
あわせて読みたい
【現実】生きる気力が持てない世の中で”働く”だけが人生か?「踊るホームレスたち」の物語:映画『ダン…
「ホームレスは怠けている」という見方は誤りだと思うし、「働かないことが悪」だとも私には思えない。振付師・アオキ裕キ主催のホームレスのダンスチームを追う映画『ダンシングホームレス』から、社会のレールを外れても許容される社会の在り方を希求する
あわせて読みたい
【リアル】社会の分断の仕組みを”ゾンビ”で学ぶ。「社会派ゾンビ映画」が対立の根源を抉り出す:映画『C…
まさか「ゾンビ映画」が、私たちが生きている現実をここまで活写するとは驚きだった。映画『CURED キュアード』をベースに、「見えない事実」がもたらす恐怖と、立場ごとに正しい主張をしながらも否応なしに「分断」が生まれてしまう状況について知る
あわせて読みたい
【改心】人生のリセットは困難だが不可能ではない。過去をやり直す強い意思をいかにして持つか:映画『S…
私は、「自分の正しさを疑わない人」が嫌いだ。そして、「正しさを他人に押し付ける人」が嫌いだ。「変わりたいと望む者の足を引っ張る人」が嫌いだ。全身刺青だらけのレイシストが人生をやり直す、実話を元にした映画『SKIN/スキン』から、再生について考える
あわせて読みたい
【意外】東京裁判の真実を記録した映画。敗戦国での裁判が実に”フェア”に行われたことに驚いた:『東京…
歴史に詳しくない私は、「東京裁判では、戦勝国が理不尽な裁きを行ったのだろう」という漠然としたイメージを抱いていた。しかし、その印象はまったくの誤りだった。映画『東京裁判 4Kリマスター版』から東京裁判が、いかに公正に行われたのかを知る
あわせて読みたい
【情熱】「ルール」は守るため”だけ”に存在するのか?正義を実現するための「ルール」のあり方は?:映…
「ルールは守らなければならない」というのは大前提だが、常に例外は存在する。どれほど重度の自閉症患者でも断らない無許可の施設で、情熱を持って問題に対処する主人公を描く映画『スペシャルズ!』から、「ルールのあるべき姿」を考える
あわせて読みたい
【情熱】常識を疑え。人間の”狂気”こそが、想像し得ない偉業を成し遂げるための原動力だ:映画『博士と…
世界最高峰の辞書である『オックスフォード英語大辞典』は、「学位を持たない独学者」と「殺人犯」のタッグが生みだした。出会うはずのない2人の「狂人」が邂逅したことで成し遂げられた偉業と、「狂気」からしか「偉業」が生まれない現実を、映画『博士と狂人』から学ぶ
あわせて読みたい
【排除】「分かり合えない相手」だけが「間違い」か?想像力の欠如が生む「無理解」と「対立」:映画『…
「共感」が強すぎる世の中では、自然と「想像力」が失われてしまう。そうならないようにと意識して踏ん張らなければ、他人の価値観を正しく認めることができない人間になってしまうだろう。映画『ミセス・ノイズィ』から、多様な価値観を排除しない生き方を考える
あわせて読みたい
【素顔】「ヨコハマメリー史」から「伊勢佐木町史」を知れる映画。謎の女性が町の歴史に刻んだものとは…
横浜で長らく目撃されていた白塗りの女性は、ある時から姿を消した。彼女の存在を欠いた伊勢佐木町という街は、大きく変わってしまったと語る者もいる。映画『ヨコハマメリー』から、ある種のアイコンとして存在した女性の生き様や彼女と関わった者たちの歴史、そして彼女の”素顔”を知る
あわせて読みたい
【実話】正論を振りかざす人が”強い”社会は窮屈だ。映画『すばらしき世界』が描く「正解の曖昧さ」
「SNSなどでの炎上を回避する」という気持ちから「正論を言うに留めよう」という態度がナチュラルになりつつある社会には、全員が全員の首を締め付け合っているような窮屈さを感じてしまう。西川美和『すばらしき世界』から、善悪の境界の曖昧さを体感する
あわせて読みたい
【誠実】地下鉄サリン事件の被害者が荒木浩に密着。「贖罪」とは何かを考えさせる衝撃の映画:『AGANAI…
私には、「謝罪すること」が「誠実」だという感覚がない。むしろ映画『AGANAI 地下鉄サリン事件と私』では、「謝罪しない誠実さ」が描かれる。被害者側と加害者側の対話から、「謝罪」「贖罪」の意味と、信じているものを諦めさせることの難しさについて書く
あわせて読みたい
【再生】ヤクザの現実を切り取る映画『ヤクザと家族』から、我々が生きる社会の”今”を知る
「ヤクザ」を排除するだけでは「アンダーグラウンドの世界」は無くならないし、恐らく状況はより悪化しただけのはずだ。映画『ヤクザと家族』から、「悪は徹底的に叩きのめす」「悪じゃなければ何をしてもいい」という社会の風潮について考える。
あわせて読みたい
【現実】戦争のリアルを”閉じ込めた”映画。第一次世界大戦の英軍を収めたフィルムが描く衝撃:映画『彼…
第一次世界大戦でのイギリス兵を映した膨大な白黒フィルムをカラー化して編集した『彼らは生きていた』は、白黒の映像では実感しにくい「リアルさ」を強く感じられる。そして、「戦争は思ったよりも安易に起こる」「戦争はやはりどこまでも虚しい」と実感できる
あわせて読みたい
【対話】刑務所内を撮影した衝撃の映画。「罰則」ではなく「更生」を目指す環境から罪と罰を学ぶ:映画…
2008年に開設された新たな刑務所「島根あさひ社会復帰促進センター」で行われる「TC」というプログラム。「罰則」ではなく「対話」によって「加害者であることを受け入れる」過程を、刑務所内にカメラを入れて撮影した『プリズン・サークル』で知る。
あわせて読みたい
【救い】耐えられない辛さの中でどう生きるか。短歌で弱者の味方を志すホームレス少女の生き様:『セー…
死にゆく母を眺め、施設で暴力を振るわれ、拾った新聞で文字を覚えたという壮絶な過去を持つ鳥居。『セーラー服の歌人 鳥居』は、そんな辛い境遇を背景に、辛さに震えているだろう誰かを救うために短歌を生み出し続ける生き方を描き出す。凄い人がいるものだ
あわせて読みたい
【挑戦】自閉症のイメージを変えるおすすめ本。知的障害と”思い込む”専門家に挑む母子の闘い:『自閉症…
専門家の思い込みを覆し、自閉症のイメージを激変させた少年・イド。知的障害だと思われていた少年は、母親を通じコミュニケーションが取れるようになり、その知性を証明した。『自閉症の僕が「ありがとう」を言えるまで』が突きつける驚きの真実
あわせて読みたい
【衝撃】森達也『A3』が指摘。地下鉄サリン事件を起こしたオウム真理教は社会を激変させた
「オウム真理教は特別だ、という理由で作られた”例外”が、いつの間にか社会の”前提”になっている」これが、森達也『A3』の主張の要点だ。異常な状態で続けられた麻原彰晃の裁判を傍聴したことをきっかけに、社会の”異様な”変質の正体を理解する。
あわせて読みたい
【意外】思わぬ資源が枯渇。文明を支えてきた”砂”の減少と、今後我々が変えねばならぬこと:『砂と人類』
「砂が枯渇している」と聞いて信じられるだろうか?そこら中にありそうな砂だが、産業用途で使えるものは限られている。そしてそのために、砂浜の砂が世界中で盗掘されているのだ。『砂と人類』から、石油やプラスチックごみ以上に重要な環境問題を学ぶ
あわせて読みたい
【加虐】メディアの役割とは?森達也『A』が提示した「事実を報じる限界」と「思考停止社会」
オウム真理教の内部に潜入した、森達也のドキュメンタリー映画『A』は衝撃を与えた。しかしそれは、宗教団体ではなく、社会の方を切り取った作品だった。思考することを止めた社会の加虐性と、客観的な事実など切り取れないという現実について書く
あわせて読みたい
【呪縛】「良い子」に囚われ人生苦しい。どう見られるかを抜け出し、なりたい自分を生きるために:『わ…
「良い子でいなきゃいけない」と感じ、本来の自分を押し隠したまま生きているという方、いるんじゃないかと思います。私も昔はそうでした。「良い子」の呪縛から逃れることは難しいですが、「なりたい自分」をどう生きればいいかを、『わたしを見つけて』をベースに書いていきます
あわせて読みたい
【救い】自殺を否定しない「笑える自殺本」。「自殺したい」ってもっと気軽に言える社会がいい:『自殺…
生きることがしんどくて、自殺してしまいたくなる気持ちを、私はとても理解できます。しかし世の中的には、「死にたい」と口にすることはなかなか憚られるでしょう。「自殺を決して悪いと思わない」という著者が、「死」をもっと気楽に話せるようにと贈る、「笑える自殺本」
あわせて読みたい
【肯定】価値観の違いは受け入れられなくていい。「普通」に馴染めないからこそ見える世界:『君はレフ…
子どもの頃、周りと馴染めない感覚がとても強くて苦労しました。ただし、「普通」から意識的に外れる決断をしたことで、自分が持っている価値観を言葉で下支えすることができたとも感じています。「普通」に馴染めず、自分がダメだと感じてしまう人へ。
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
孤独・寂しい・友達【本・映画の感想】 | ルシルナ
孤独と向き合うのは難しいものです。友達がいないから学校に行きたくない、社会人になって出会いがない、世の中的に他人と会いにくい。そんな風に居場所がないと思わされて…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…







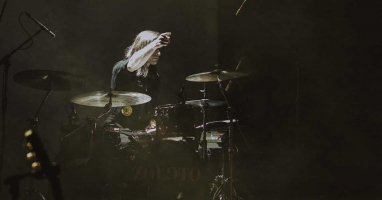





















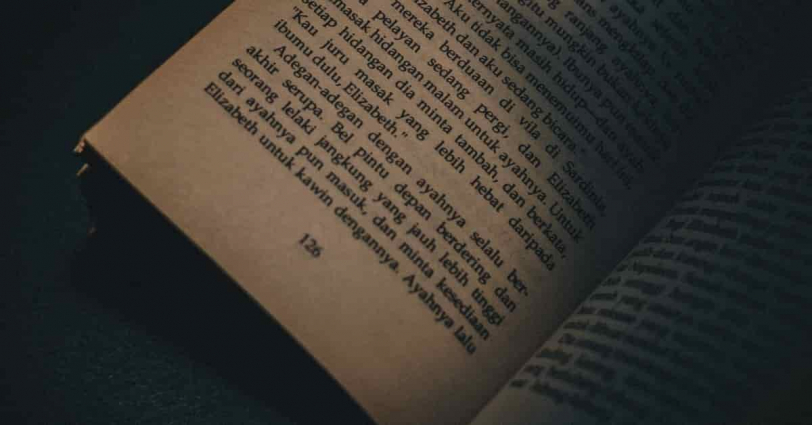



































































































































コメント