目次
はじめに
この記事で取り上げる映画
監督:セルゲイ・ロズニツァ
¥600 (2024/03/03 20:05時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
この映画をガイドにしながら記事を書いていきます
この記事の3つの要点
- 図書館等のアーカイブのみならず、個人収蔵の映像も自らの足で探し出して使用したという、凄まじい映像満載の映画
- 「バビ・ヤール大虐殺に至るまでの過程」と、「『バビ・ヤール大虐殺にウクライナ市民も加担していた』という事実」を、過去映像のみによって再構築していく
- 最も驚かされたのは、自身の衝撃的な経験について裁判で淡々と証言する女性の話である
使われている映像を観るだけでも価値があると感じるぐらい、驚愕のシーンが満載のドキュメンタリー映画
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
記事中の引用は、映画館で取ったメモを参考にしているので、正確なものではありません
ウクライナで起こったホロコースト(大虐殺)を、当時の映像を再構成することで浮かび上がらせる映画『バビ・ヤール』の衝撃
使われている映像素材がとにかく凄まじい
あわせて読みたい
【実話】映画『アウシュビッツ・レポート』が描き出す驚愕の史実。世界はいかにホロコーストを知ったのか?
映画『アウシュヴィッツ・レポート』は、アウシュビッツ強制収容所から抜け出し、詳細な記録と共にホロコーストの実態を世界に明らかにした実話を基にした作品。2人が持ち出した「アウシュビッツ・レポート」こそが、ホロコーストについて世界が知るきっかけだったのであり、そんな史実をまったく知らなかったことにも驚かされた
本作で扱われているのは、第二次世界大戦中にウクライナで起こったホロコーストとして知られる「バビ・ヤール大虐殺」だ。ユダヤ人が無惨に殺された痛ましい事件であり、本作を観るまでその存在さえ知らなかった私のような人が観るべき映画だと思う。
しかし、「バビ・ヤール大虐殺」そのものに触れる前にまず、本作の構成とその特異さに触れておくことにしよう。

本作『バビ・ヤール』は、「かつて撮影された白黒の映像を繋ぎ合わせて作られた映画」である。現代を生きる誰かにインタビューするシーンなどは一切含まれず、最初から最後まで「戦中戦後に撮られた映像」のみで構成されているというわけだ。
私はこれまでにもそのような構成の作品に触れてきたし、全編過去映像ではないが作中に古い映像が混じる構成のドキュメンタリー作品も結構観たことがある。しかし、本作で使われている映像はちょっと別格だった。「こんな映像が存在するのか!」と驚かされるようなものばかりだったのだ。
あわせて読みたい
【現実】戦争のリアルを”閉じ込めた”映画。第一次世界大戦の英軍を収めたフィルムが描く衝撃:映画『彼…
第一次世界大戦でのイギリス兵を映した膨大な白黒フィルムをカラー化して編集した『彼らは生きていた』は、白黒の映像では実感しにくい「リアルさ」を強く感じられる。そして、「戦争は思ったよりも安易に起こる」「戦争はやはりどこまでも虚しい」と実感できる
シンプルに驚愕させられたのは、公開処刑で一斉に首吊りが行われるシーンである。凄まじい映像が残っているものだなと感じた。また作中には随所で、「ハエがたかる死体」や「死体をモノのように扱って死体置き場へ放り投げる様子」のような映像が使われている。何とも凄まじいインパクトを与える映像ばかりだ。当然、それらにも驚かされたのだが、実はそれだけではない。
例えば、説明がほぼ無い作品なのでその行為の目的は不明なのだが、「人々がスコップで地面を掘り返している映像」なども印象的だった。何故なら、「わざわざこんなシーンを撮っておこうと考えた人がいたのだ」と感じさせられたからだ。水路でも作っているのか、地面を細長く掘り返している。スコップを持つ人の中には男性だけではなく女性もいて、しかも下着姿に見えるような半裸の女性もいたりするのだ。そんな映像を何故撮影していたのか不明だし、それを残しておこうと考えたのも不思議だと感じた。
また、映画の後半には裁判を映した映像も出てくるのだが、これもまあよく残っていたものだと思う。もちろん、有名な人物が被告となる裁判の映像が残っていることは何の不思議もないが、本作で映し出される裁判は、著名な人物のものではないのだ。この裁判は、「バビ・ヤール大虐殺」から5年後ぐらいに行われた。その時点ではまだ、「バビ・ヤール大虐殺」が後世どのような評価をされるのかまったく不透明だったはずだ。そのような時代に、「この裁判は記録に残しておくべきだ」と考えた人物がいたわけで、そういう背景を踏まえると、現代まで残っていることが驚きである。
あわせて読みたい
【意外】東京裁判の真実を記録した映画。敗戦国での裁判が実に”フェア”に行われたことに驚いた:『東京…
歴史に詳しくない私は、「東京裁判では、戦勝国が理不尽な裁きを行ったのだろう」という漠然としたイメージを抱いていた。しかし、その印象はまったくの誤りだった。映画『東京裁判 4Kリマスター版』から東京裁判が、いかに公正に行われたのかを知る
さらに、撮影手法にも驚かされた。作中には、「低空で飛ぶ飛行機の中から撮影されたのだろう映像」や「壊滅状態の街をまるでドローンで撮影しているかのような映像」もある。それらは、白黒であることを除けば、とても現代的な映像に見えた。このように本作ではとにかく、使われている素材そのものに対して、「よくこんな映像が残っていたものだ」と感じさせられたのだ。
映画を観ながら私はそう思っていたのだが、上映後に行われた、東京大学大学院教授によるアフタートークの中でも、登壇したソ連研究者・池田嘉郎氏が同じように語っていたので、学者の視点からも衝撃的な映像なのだと理解できた。池田氏によると、本作『バビ・ヤール』の監督セルゲイ・ロズニツァは、図書館等にあるアーカイブだけではなく、個人収蔵の映像も自らの足で探し出して本作を完成させたのだそうだ。個人収蔵のものも多くあるのなら、「こんな映像が存在するのか!」と感じるのも当然と言えるかもしれない。
そんなわけで、とにかく「素材の映像」が凄まじい作品だった。
あわせて読みたい
【書評】奇跡の”国家”「ソマリランド」に高野秀行が潜入。崩壊国家・ソマリア内で唯一平和を保つ衝撃の”…
日本の「戦国時代」さながらの内戦状態にあるソマリア共和国内部に、十数年に渡り奇跡のように平和を維持している”未承認国家”が存在する。辺境作家・高野秀行の『謎の独立国家ソマリランド』から、「ソマリランド」の理解が難しい理由と、「奇跡のような民主主義」を知る
さて、先ほども少し触れたが、本作は映像についての説明がほぼない。そのため、戦時中のヨーロッパやユダヤ人を取り巻く状況などについてかなり知識を有していなければ、映像だけ観ていても、「今何が行われているのか」「1つ前の映像とはどう繋がるのか」などを理解することは難しいように思う。少なくとも、私は把握できなかった。しかし、これは決して非難ではない。良い捉え方をするのなら、「説明が少ないお陰で、映像そのものが持つインパクトがストレートに伝わった」とも考えられるからだ。とはいえ、「内容の理解」という点で言えばやはり「説明不足」であると指摘せざるを得ない。私は正直、上映後のアフタートークを聞いてようやく、映画全体で一体何を描こうとしていたのかが理解できたような状態だった。

本作を観る場合、「映像だけ観ても意味が分からないかもしれない」という覚悟を持っておくことは必要かもしれない。
「バビ・ヤール大虐殺」だけではなく、そこに至るまでの過程を描き出す作品
あわせて読みたい
【実話】権力の濫用を監視するマスコミが「教会の暗部」を暴く映画『スポットライト』が現代社会を斬る
地方紙である「ボストン・グローブ紙」は、数多くの神父が長年に渡り子どもに対して性的虐待を行い、その事実を教会全体で隠蔽していたという衝撃の事実を明らかにした。彼らの奮闘の実話を映画化した『スポットライト』から、「権力の監視」の重要性を改めて理解する
本作の焦点が「バビ・ヤール大虐殺」にあるのは確かだが、この事件だけを描き出す作品なのではない。映画では、「バビ・ヤール大虐殺」に至るまでの長い長い過程が描写されるのである。正直、この点には驚かされた。なにせ先述した通り、本作は「過去映像を繋ぎ合わせただけの構成」なのだ。どう考えても映像資料が乏しいはずの時代に起こった出来事を、集めた映像だけを使って再構成するのはかなり困難だったのではないかと思う。
さて、ロシアによるウクライナ侵攻に関する報道でよく耳にした話なので知っている人も多いとは思うが、ウクライナという国は元々ソ連の一部だった。ソ連崩壊と共に独立を成し遂げたわけだが、映画で映し出される時代はまだソ連のままである。作中では、「ウクライナ・ソビエト社会主義共和国」という表記がなされていた。
映画は1941年6月から始まる。しばらくするとナチスドイツに占領されてしまうのだが、首都キエフ(今は「キーウ」と呼ばれている)では「解放者ヒトラー」として歓迎されていた。詳しい状況は不明だが、もしもウクライナが既にこの時点で「ソ連からの独立」を望んでいたのなら、「『ヒトラーがソ連からの独立を実現させてくれる』ことを期待し歓迎していた」という解釈も出来るかもしれない。その辺りのことは詳しくないので何とも言えないのだが。
あわせて読みたい
【実話】「ホロコーストの映画」を観て改めて、「有事だから仕方ない」と言い訳しない人間でありたいと…
ノルウェーの警察が、自国在住のユダヤ人をまとめて船に乗せアウシュビッツへと送った衝撃の実話を元にした映画『ホロコーストの罪人』では、「自分はそんな愚かではない」と楽観してはいられない現実が映し出される。このような悲劇は、現在に至るまで幾度も起こっているのだ
そして、1941年の9月29日・30日に、後に「バビ・ヤール大虐殺」と呼ばれることになる「ユダヤ人の大虐殺」が起こる。実はこの直前、ナチスドイツが占領していたキエフ市街が大規模な爆発に見舞われるという事件が起きていた。驚くべきことに、この爆発によって建物が崩壊する様子を映した映像も残っている。この爆発は、後にソ連の仕業だと判明するのだが、ナチスドイツは「キエフに住むユダヤ人の犯行」と断定した。そしてキエフに住むユダヤ人に、「貴重品を持って、バビ・ヤール渓谷まで来るように」と命令を出す。彼らはそのまま殺害され、2日間で33,771名が犠牲になったのだそうだ。この「バビ・ヤール大虐殺」は、「単一のホロコーストで最大の犠牲者を出した事件」として知られている。
その後、1943年11月にソ連がキエフを占領し、それから「バビ・ヤール大虐殺」に関する裁判が開かれた。本作ではそのような流れが、過去映像を繋ぎ合わせることで描かれていくというわけだ。
「ウクライナ市民がホロコーストに加担していた」という、本作が示す最も重要なテーマについて
あわせて読みたい
【証言】ナチスドイツでヒトラーに次ぐナンバー2だったゲッベルス。その秘書だった女性が歴史を語る映画…
ナチスドイツナンバー2だった宣伝大臣ゲッベルス。その秘書だったブルンヒルデ・ポムゼルが103歳の時にカメラの前で当時を語った映画『ゲッベルスと私』には、「愚かなことをしたが、避け難かった」という彼女の悔恨と教訓が含まれている。私たちは彼女の言葉を真摯に受け止めなければならない
さて、ここまで説明してきたような事実関係については、映画を観ていれば大雑把には理解できるだろう。しかし、本作が真に切り取ろうとしている事実については、私は自力では理解できなかった。それは、「ウクライナ市民がホロコーストに加担していた」という過去の汚点である。
アフタートークでそのように指摘された後、映画を観ながら取った自分のメモを見返し、作中には確かにそのことを示唆する要素がたくさんあることに気付かされた。例えば、ある場面では次のような字幕が表記される。
ユダヤ人の大虐殺について、キエフ市民からの抵抗も反対もなかった。
あわせて読みたい
【日常】難民問題の現状をスマホで撮る映画。タリバンから死刑宣告を受けた監督が家族と逃避行:『ミッ…
アフガニスタンを追われた家族4人が、ヨーロッパまで5600kmの逃避行を3台のスマホで撮影した映画『ミッドナイト・トラベラー』は、「『難民の厳しい現実』を切り取った作品」ではない。「家族アルバム」のような「笑顔溢れる日々」が難民にもあるのだと想像させてくれる

「間接的な加担」を示唆する言葉と言えるだろう。あるいはもっと直接的に示す場面もあった。戦後、欧米の記者がバビ・ヤール渓谷にやってきた際、ある人物がカメラの前で次のように語った映像が使われているのである。
キエフ市民がユダヤ人の死体の処理をさせられた。ナチスドイツは処理に加担した市民を殺そうとしたが、300人の内12名が脱走した。だからこうして世界にこの事実を発信する。
この人物は、「ナチスドイツがかつて行った恐ろしいホロコースト」についてカメラの前で訴えようとしているのだが、しかし彼の発言によって同時に、「キエフ市民がそのホロコーストに加担していた」という事実が図らずも明らかになってしまったというわけだ。
あわせて読みたい
【矛盾】死刑囚を「教誨師」視点で描く映画。理解が及ばない”死刑という現実”が突きつけられる
先進国では数少なくなった「死刑存置国」である日本。社会が人間の命を奪うことを許容する制度は、果たして矛盾なく存在し得るのだろうか?死刑確定囚と対話する教誨師を主人公に、死刑制度の実状をあぶり出す映画『教誨師』から、死刑という現実を理解する
このように本作では、「ウクライナがかつてホロコーストに加担していた」という事実が示されており、さらにその上で「その歴史を隠蔽しようとした」ことにも触れられている。というのも、本作は1952年12月2日の映像で終わるのだが、この映像には次のような字幕が付いていたのだ。
キエフ市はバビ・ヤール渓谷に産業廃棄物を埋め立てる決定をした。
私は当初この文章の意味が分からず、アフタートークを聞いてようやく理解できた。要するにこれは、「ウクライナが『バビ・ヤール大虐殺』という過去を隠蔽しようとしていた」という事実を示唆しているというわけだ。
そのような「指摘」を含む作品だったからだろう、本作はウクライナにおいてはかなり批判的に受け止められたという。まあ、このような作品の性質を理解すれば、それも当然と言えるだろう。
あわせて読みたい
【アメリカ】長崎の「原爆ドーム」はなぜ残らなかった?爆心地にあった「浦上天主堂」の数奇な歴史:『…
原爆投下で半壊し、廃墟と化したキリスト教の大聖堂「浦上天主堂」。しかし何故か、「長崎の原爆ドーム」としては残されず、解体されてしまった。そのため長崎には原爆ドームがないのである。『ナガサキ 消えたもう一つの「原爆ドーム」』は、「浦上天主堂」を巡る知られざる歴史を掘り下げ、アメリカの強かさを描き出す
さて、本作を観てその意図を正しく理解したことで、私はようやくあることに合点がいった。それは、ロシアがウクライナ侵攻を正当化する理由の1つとしてよく挙げられる「ウクライナの非ナチ化」についてである。私は報道などでこの言葉に触れる度に、「何故ウクライナが『ナチス』と見做されているのか」が分からなかった。正直なところ、「どうせプーチンが適当な言いがかりをつけているんだろう」ぐらいに考えていたのである。しかし本作を観て、「バビ・ヤール大虐殺にウクライナが加担していた」という事実を知ったことでようやく、「恐らくこの点を指してウクライナを非難しているのだろう」と理解できたというわけだ。

しかし、アフタートークの中で、この点に触れた池田氏は、観客に注意を促してもいた。本作は実際、ロシアが主張する「ウクライナの非ナチ化」を裏付ける「証拠」のようなものとしてプロパガンダ的に悪用されることが多いらしいのだが、「そのような分かりやすい捉え方はしない方がいい」と言っていたのである。彼は、監督セルゲイ・ロズニツァが本作に込めた意図について、「『ウクライナの個人』がナチスに加担した」という捉え方をしているという。「ウクライナが」ではなく「ウクライナの個人が」という点が重要なのであり、「あくまでも個人の問題だ」というスタンスをとっているようだ。
そのことが分かりやすく伝わるエピソードとして池田氏は、セルゲイ・ロズニツァがウクライナ映画人協会を除名された出来事について語っていた。除名の理由は、「ウクライナ映画人協会が『ロシアの映画を排除しろ』と主張していたことに彼が反対したから」である。これだけ聞くと、セルゲイ・ロズニツァがさもロシアの肩を持っているかのような印象になるだろう。
あわせて読みたい
【狂気】ISISから孫を取り戻せ!映画『”敵”の子どもたち』が描くシリアの凄絶な現実
映画『”敵”の子どもたち』では、私がまったく知らなかった凄まじい現実が描かれる。イスラム過激派「ISIS」に望んで参加した女性の子ども7人を、シリアから救出するために奮闘する祖父パトリシオの物語であり、その最大の障壁がなんと自国のスウェーデン政府なのだる。目眩がするような、イカれた現実がここにある
しかし実際にはそうではないという。彼は明確に、「ウクライナ映画人協会のトップが偏狭な人間であることが問題だ」と主張しており、あくまでも「個人の問題」だと認識しているというのだ。彼のそれまでの様々な言動からもそのようなスタンスは明快なのだそうで、「だからこそ、セルゲイ・ロズニツァが『ウクライナを非難するため』に本作を作ったはずがない」と池田氏は主張していたのである。
さらに池田氏は、セルゲイ・ロズニツァがかつてNHKのインタビューを受けた際の発言についても触れていた。インタビューの中で彼は、「過去の暗部を見つめることこそが、抵抗のための一番の手段ではないか」みたいなことを言っていたというのだ。池田氏はその発言に、「まさにその通りだ」と賛同していた。つまり、客観的な見え方はどうあれ、セルゲイ・ロズニツァのスタンスはむしろ「ウクライナ擁護」と捉えるべきなのだと思う。
「安易な解釈は禁物」というわけである。
セルゲイ・ロズニツァと「バビ・ヤール大虐殺」の関係について
あわせて読みたい
【壮絶】アウシュヴィッツで”人体実験の神メンゲレ”から生き残り、ホロコーストから生還した男の人生:…
映画『メンゲレと私』は、タイトルと内容がそぐわないものの、とても興味深い作品だった。44ヶ月間の収容所生活を生き延び、ホロコーストから生還したダニエル・ハノッホが、少年とは思えない「思考力」を武器に、最低最悪な状況を生き延びた経験をカメラの前で語る。あまりにも壮絶な、信じがたい現実である
アフタートークでは、監督セルゲイ・ロズニツァと「バビ・ヤール大虐殺」の関係についても触れられており、その話も非常に興味深かった。
セルゲイ・ロズニツァはウクライナで育ったのだが、そもそもの生まれはソ連である。子ども時代をキエフで過ごした後、映画を学ぶためにモスクワへと戻ったという。その後1980年代に、彼は「バビ・ヤール大虐殺」の存在を初めて知り、衝撃を受ける。そしてその時点で、「いつかこの出来事を映画にする」と決意したのだそうだ。
さて、「バビ・ヤール大虐殺」の存在を知った際、彼の脳裏にはある光景が過ぎったという。実は子どもの頃に、彼はそうとは知らず「バビ・ヤール大虐殺」の一端に触れていたというのだ。

あわせて読みたい
【驚愕】正義は、人間の尊厳を奪わずに貫かれるべきだ。独裁政権を打倒した韓国の民衆の奮闘を描く映画…
たった30年前の韓国で、これほど恐ろしい出来事が起こっていたとは。「正義の実現」のために苛烈な「スパイ狩り」を行う秘密警察の横暴をきっかけに民主化運動が激化し、独裁政権が打倒された史実を描く『1987、ある闘いの真実』から、「正義」について考える
子どもの頃、セルゲイ・ロズニツァはスイミングプールに通っていたのだが、そこが実は、「バビ・ヤール渓谷の埋め立てを起点とした大規模な建設計画において、実際に作られたいくつかの施設の内の1つ」だったのである。彼は巨大な埋立地の横を通ってプールへ行き来しており、そこに点在する墓も目にしていた。墓標は異国の言葉(恐らくドイツ語だろう)で書かれていたため読むことが出来ず、その墓が何だったのか当時は分からなかったそうだ。しかし、後に「バビ・ヤール大虐殺」の存在を知ったことで、その時に見た墓の記憶と繋がったのである。
そんなセルゲイ・ロズニツァについて池田氏は、「ソ連の素晴らしいインテリの末裔たる存在」と評していた。ソ連のインテリは昔から、ここぞという時には国家を批判する側にも回るし、芸術分野においても文句をつけられないぐらい完成度の高いものを作るなど、かなり高尚な気位を持っていたのだそうだ。そして彼の目からは、セルゲイ・ロズニツァもまた、「古き良きソ連のインテリ」の気質をかなり受け継いだ人であるように見えているのだという。「バビ・ヤール大虐殺」との偶然の繋がり、そしてソ連の伝統的なインテリの気質。それらが上手く入り混じることで、本作のような「特異」な作品が生まれたと言っていいのだろう。
アフタートークの最後で池田氏は、
セルゲイ・ロズニツァの映画は、『バビ・ヤール』も含めてすべてウクライナ侵攻以前に作られているのに、制作から数年が経った今、不思議なほど呼応するものがある。
と感慨深げに語っていた。「ウクライナ侵攻以前に作られた」という事実にはきっと、多くの人が驚かされるのではないかと思う。まさに「時代に呼ばれている」と言える創作者なのではないだろうか。
あわせて読みたい
【あらすじ】塩田武士『罪の声』が放つ、戦後最大の未解決事件「グリコ・森永事件」の圧倒的”リアル感”
戦後最大の未解決事件である「グリコ・森永事件」では、脅迫に子どもの声が使われていた。私はその事実を、塩田武士『罪の声』という小説を読むまで知らなかった。では、続く疑問はこうだろう。その子どもたちは、今どこでどんな風に生きているのか?その疑問に答える、凄まじい小説だ。
「凄まじい証言を淡々と行う裁判シーン」に衝撃を受けた
映画で使われた映像の中で、個人的に最も印象的だったのは裁判のシーンである。複数の裁判映像が使われているのだが、別々の裁判で証言する2人の女性の話には驚かされてしまった。
先に登場した女性については、「凄かった」という印象が残っているだけで詳しいことは忘れてしまったので、ここでは後に出てきた女性の証言について詳しく触れていこうと思う。
彼女は、運悪く「ユダヤ人の虐殺が行われている現場」に足を踏み入れてしまった。そこでナチスドイツの軍人に呼び止められ、彼女は「ウクライナ人だ」と答えたそうだ。その際のやり取りについて、「相手は信じたようだ」と女性が言っていたと思うので、私は「彼女は実際にはユダヤ人であり、『ウクライナ人だ』と答えることで難を逃れようとした」という風に受け取った。しかし、別の可能性もあるだろう。実際にウクライナ人だったとしても、それを証明する手段を持っていなかったため、「ユダヤ人だと疑われてもおかしくはない」という状況だったのかもしれない。だから、「本当にウクライナ人なのであり、そのことを相手がちゃんと信じてくれて良かった」という安堵を込めた言葉だった可能性もある。冒頭で書いた通り、映像に対する説明はほぼないので、正解がどちらなのかは分からない。
とにかくその女性は、虐殺の現場に居合わせてしまった。そして「ウクライナ人」であることを理由に軍人から、「その辺りに座ってろ。終わったら帰れ」みたいなことを言われたという。彼女は素直にそのまま待っていたのだが、恐らく上官なのだろう、しばらくして別の軍人が現れ、先程とは異なる指示が出された。「この状況を目撃した者が街に戻って話をすれば、明日からユダヤ人はここに来なくなるだろう。だからこいつも殺せ」という話に変わったのだ。この女性は一転して、殺される立場に立たされてしまったのである。
あわせて読みたい
【感想】関東大震災前後を描く映画『福田村事件』(森達也)は、社会が孕む「思考停止」と「差別問題」…
森達也監督初の劇映画である『福田村事件』は、100年前の関東大震災直後に起こった「デマを起点とする悲劇」が扱われる作品だ。しかし、そんな作品全体が伝えるメッセージは、「100年前よりも現代の方がよりヤバい」だと私は感じた。SNS時代だからこそ意識すべき問題の詰まった、挑発的な作品である

こうして、彼女を含む何人かの者たちが穴の縁に立たされた。そのまま銃撃が始まったのだが、彼女は撃たれたフリをして穴の中に倒れ込んだのだという。既に穴の下に積み上がっていた遺体の上に落ちたことで、死なずに済んだ。しかししばらくして、ナチスドイツの軍人が、うめき声を上げている者にナイフでとどめを刺しているのが視界に入る。彼女は微動だにしなかったが、しばらくしてある軍人が彼女の足を掴んで仰向けにひっくり返した。そして、血がついていないことを不審に思ったのか、軍人はスパイクのついた靴で彼女の胸と腕に乗り、そのまま腕をひねり上げたのである。彼女は「ここまでか」と思ったが、しかし声を上げずに黙っていたという。するとしばらくして、穴を砂で埋めようとしているのが伝わってきた。どうにか生き残ったようだ。
しかし、徐々に彼女の身体にも砂が積もり始め、窒息しそうになった。それまでまったく動かずにいたのだが、「生き埋めになるぐらいなら撃たれた方がマシだ」と考え、彼女は身体を動かすことに決める。どうにか気づかれずに穴から抜け出すことが出来たが、ナチスドイツは、サーチライトで足元を照らし呻く人々を撃っていたので、まだ危険は続いている状態だった。どうにか見つからないように這い進み、岩壁の上までたどり着いたところ、そこに少年がいたのだそうだ。父親が撃たれた際に一緒に穴に落ち、どうにか命が助かったのだという。その少年と2人で草原を這い、その後身を隠せる場所を見つけてしばらくそこに潜んでいた……。
あわせて読みたい
【実話】人質はなぜ犯人に好意を抱くか?「ストックホルム症候群」の由来である銀行強盗を描く映画:『…
「強盗や立てこもり事件などにおいて、人質が犯人に好意・共感を抱いてしまう状態」を「ストックホルム症候群」と呼ぶのだが、実はそう名付けられる由来となった実際の事件が存在する。実話を基にした映画『ストックホルムケース』から、犯人に協力してしまう人間の不可思議な心理について知る
みたいな壮絶な話を、教科書でも朗読しているかのように淡々とした口調で証言していたのだ。語られるエピソードは、あまりにも凄まじすぎるように思う。しかし一方で、彼女のその淡々とした口調からは、「これぐらいの経験をした人はそこら中にいる」というような雰囲気も感じさせられた。
平和な日本に住んでいると、彼女の証言は「とてつもない経験」に感じられるはずだが、彼女の主観では恐らく「よくある出来事の1つ」ぐらいの認識だったのだと思う。このような捉え方の差にこそ、当時の状況の凄まじさが滲み出ているように思えてしまった。裁判シーンは決して、「視覚的に衝撃を与える」ような類のものではないのだが、また違った意味で驚愕させられてしまったというわけだ。
本当に、随所で信じがたい衝撃を味わわされる作品だった。
あわせて読みたい
【凄絶】北朝鮮の”真実”を描くアニメ映画。強制収容所から決死の脱出を試みた者が語る驚愕の実態:『ト…
在日コリアン4世の監督が、北朝鮮脱北者への取材を元に作り上げた壮絶なアニメ映画『トゥルーノース』は、私たちがあまりに恐ろしい世界と地続きに生きていることを思い知らせてくれる。最低最悪の絶望を前に、人間はどれだけ悪虐になれてしまうのか、そしていかに優しさを発揮できるのか。
監督:セルゲイ・ロズニツァ
¥600 (2024/03/03 20:11時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品視聴済】私が観てきたドキュメンタリー映画を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が観てきたドキュメンタリー映画を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。
最後に
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『戦場のピアニスト』(ロマン・ポランスキー)が描く、ユダヤ人迫害の衝撃の実話
映画『戦場のピアニスト』の4Kリマスター版を観に行ったところ、上映後のトークイベントに主人公の息子が登壇したので驚いた。何せ私は、本作が「実話を基にしている」ことさえ知らなかったのである。だからその驚きもひとしおだった。ホロコーストの生存者である主人公の壮絶な人生を描き出す、不朽の名作だ
説明があまりにも少ない作品なので理解が難しい感じる部分はあるかもしれないが、正直なところ、素材として使われている映像を観るという目的でも十分に価値を感じられるのではないかと思う。「こんな映像が存在するのか!」という衝撃を是非体感してほしい。
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を…
Kindleで本を出版しました。タイトルは、『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を分かりやすく書いた本:相対性理論も宇宙論も量子論も』です。科学や科学者に関する、文系の人でも読んでもらえる作品に仕上げました。そんな自著について紹介をしています。
次におすすめの記事
あわせて読みたい
【解説】映画『シビル・ウォー アメリカ最後の日』は、凄まじい臨場感で内戦を描き、我々を警告する(…
映画『シビル・ウォー』は、「アメリカで勃発した内戦が長期化し、既に日常になってしまっている」という現実を圧倒的な臨場感で描き出す作品だ。戦争を伝える報道カメラマンを主人公に据え、「戦争そのもの」よりも「誰にどう戦争を伝えるか」に焦点を当てる本作は、様々な葛藤を抱きながら最前線を目指す者たちを切り取っていく
あわせて読みたい
【変異】映画『動物界』は斬新で刺激的な作品だった。我々はまさにこんな”分断社会”に生きている
映画『動物界』では、「奇病によって人間が動物化してしまう」という世界における複雑な人間模様が描き出される。パンデミックを経験した我々には、本作の設定は「単なるSF」には感じられないはずだ。そしてその上で、「『動物化してしまった妻を今も愛している主人公』が見せる実にややこしい感情」が複層的に描かれていて実に興味深い
あわせて読みたい
【正義】ナン・ゴールディンの”覚悟”を映し出す映画『美と殺戮のすべて』が描く衝撃の薬害事件
映画『美と殺戮のすべて』は、写真家ナン・ゴールディンの凄まじい闘いが映し出されるドキュメンタリー映画である。ターゲットとなるのは、美術界にその名を轟かすサックラー家。なんと、彼らが創業した製薬会社で製造された処方薬によって、アメリカでは既に50万人が死亡しているのだ。そんな異次元の薬害事件が扱われる驚くべき作品
あわせて読みたい
【衝撃】EUの難民問題の狂気的縮図!ポーランド・ベラルーシ国境での、国による非人道的対応:映画『人…
上映に際し政府から妨害を受けたという映画『人間の境界』は、ポーランド・ベラルーシ国境で起こっていた凄まじい現実が描かれている。「両国間で中東からの難民を押し付け合う」という醜悪さは見るに絶えないが、そのような状況下でも「可能な範囲でどうにか人助けをしたい」と考える者たちの奮闘には救われる思いがした
あわせて読みたい
【真相】飯塚事件は冤罪で死刑執行されたのか?西日本新聞・警察・弁護士が語る葛藤と贖罪:映画『正義…
映画『正義の行方』では、冤罪のまま死刑が執行されたかもしれない「飯塚事件」が扱われる。「久間三千年が犯行を行ったのか」という議論とは別に、「当時の捜査・司法手続きは正しかったのか?」という観点からも捉え直されるべきだし、それを自発的に行った西日本新聞の「再検証連載」はとても素晴らしかったと思う
あわせて読みたい
【赦し】映画『過去負う者』が描く「元犯罪者の更生」から、社会による排除が再犯を生む現実を知る
映画『過去負う者』は、冒頭で「フィクション」だと明示されるにも拘らず、観ながら何度も「ドキュメンタリーだっけ?」と感じさせられるという、実に特異な体験をさせられた作品である。実在する「元犯罪者の更生を支援する団体」を舞台にした物語で、当然それは、私たち一般市民にも無関係ではない話なのだ
あわせて読みたい
【日本】原発再稼働が進むが、その安全性は?樋口英明の画期的判決とソーラーシェアリングを知る:映画…
映画『原発をとめた裁判長 そして原発をとめる農家たち』では、大飯原発の運転差し止め判決を下した裁判長による画期的な「樋口理論」の説明に重点が置かれる。「原発の耐震性」に関して知らないことが満載で、実に興味深かった。また、農家が発案した「ソーラーシェアリング」という新たな発電方法も注目である
あわせて読みたい
【衝撃】ミキ・デザキが映画『主戦場』で示す「慰安婦問題」の実相。歴史修正主義者の発言がヤバすぎ
「慰安婦問題」に真正面から取り組んだ映画『主戦場』は、「『慰安婦問題』の根幹はどこにあるのか?」というその複雑さに焦点を当てていく。この記事では、本作で映し出された様々な情報を元に「慰安婦問題」について整理したものの、結局のところ「解決不可能な問題である」という結論に行き着いてしまった
あわせて読みたい
【狂気】ISISから孫を取り戻せ!映画『”敵”の子どもたち』が描くシリアの凄絶な現実
映画『”敵”の子どもたち』では、私がまったく知らなかった凄まじい現実が描かれる。イスラム過激派「ISIS」に望んで参加した女性の子ども7人を、シリアから救出するために奮闘する祖父パトリシオの物語であり、その最大の障壁がなんと自国のスウェーデン政府なのだる。目眩がするような、イカれた現実がここにある
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『戦場のピアニスト』(ロマン・ポランスキー)が描く、ユダヤ人迫害の衝撃の実話
映画『戦場のピアニスト』の4Kリマスター版を観に行ったところ、上映後のトークイベントに主人公の息子が登壇したので驚いた。何せ私は、本作が「実話を基にしている」ことさえ知らなかったのである。だからその驚きもひとしおだった。ホロコーストの生存者である主人公の壮絶な人生を描き出す、不朽の名作だ
あわせて読みたい
【壮絶】アウシュヴィッツで”人体実験の神メンゲレ”から生き残り、ホロコーストから生還した男の人生:…
映画『メンゲレと私』は、タイトルと内容がそぐわないものの、とても興味深い作品だった。44ヶ月間の収容所生活を生き延び、ホロコーストから生還したダニエル・ハノッホが、少年とは思えない「思考力」を武器に、最低最悪な状況を生き延びた経験をカメラの前で語る。あまりにも壮絶な、信じがたい現実である
あわせて読みたい
【驚愕】映画『リアリティ』の衝撃。FBIによる、機密情報をリークした女性の尋問音源を完全再現(リアリ…
映画『リアリティ』は、恐らく過去類を見ないだろう構成の作品だ。なんと、「FBI捜査官が録音していた実際の音声データのやり取りを一言一句完全に再現した映画」なのである。「第2のスノーデン」とも評される”普通の女性”は、一体何故、国家に反旗を翻す”反逆者”になったのだろうか?
あわせて読みたい
【無謀】映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、脱北ルートに撮影隊が同行する衝撃のドキュメンタリー
北朝鮮からの脱北者に同行し撮影を行う衝撃のドキュメンタリー映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、再現映像を一切使用していない衝撃的な作品だ。危険と隣り合わせの脱北の道程にカメラもついて回り、北朝鮮の厳しい現状と共に、脱北者が置かれた凄まじい状況を映し出す内容に驚かされてしまった
あわせて読みたい
【衝撃】映画『JFK/新証言』(オリヴァー・ストーン)が描く、ケネディ暗殺の”知られざる陰謀”
映画『JFK/新証言』は、「非公開とされてきた『ケネディ暗殺に関する資料』が公開されたことで明らかになった様々な事実を基に、ケネディ暗殺事件の違和感を積み上げていく作品だ。「明確な証拠によって仮説を検証していく」というスタイルが明快であり、信頼度の高い調査と言えるのではないかと思う
あわせて読みたい
【狂気】異質なホラー映画『みなに幸あれ』(古川琴音主演)は古い因習に似せた「社会の異様さ」を描く
古川琴音主演映画『みなに幸あれ』は、”シュールさ”さえ感じさせる「異質なホラー映画」だ。「村の因習」というよくあるパターンをベースに据えつつ、そこで展開される異様な状況が、実は「私たちが生きる世界」に対応しているという構成になっている。「お前の物語だからな」と終始突きつけられ続ける作品だ
あわせて読みたい
【感想】関東大震災前後を描く映画『福田村事件』(森達也)は、社会が孕む「思考停止」と「差別問題」…
森達也監督初の劇映画である『福田村事件』は、100年前の関東大震災直後に起こった「デマを起点とする悲劇」が扱われる作品だ。しかし、そんな作品全体が伝えるメッセージは、「100年前よりも現代の方がよりヤバい」だと私は感じた。SNS時代だからこそ意識すべき問題の詰まった、挑発的な作品である
あわせて読みたい
【脅迫】原発という巨大権力と闘ったモーリーン・カーニーをイザベル・ユペールが熱演する映画『私はモ…
実話を基にした映画『私はモーリーン・カーニー』は、前半の流れからはちょっと想像もつかないような展開を見せる物語だ。原発企業で従業員の雇用を守る労働組合の代表を務める主人公が、巨大権力に立ち向かった挙げ句に自宅で襲撃されてしまうという物語から、「良き被害者」という捉え方の”狂気”が浮かび上がる
あわせて読みたい
【実話】映画『月』(石井裕也)は、障害者施設での虐待事件から「見て見ぬふりする社会」を抉る(出演…
実際に起こった障害者施設殺傷事件を基にした映画『月』(石井裕也)は、観客を作中世界に引きずり込み、「これはお前たちの物語だぞ」と刃を突きつける圧巻の作品だ。「意思疎通が不可能なら殺していい」という主張には誰もが反対するはずだが、しかしその態度は、ブーメランのように私たちに戻ってくることになる
あわせて読みたい
【現実】映画『私のはなし 部落のはなし』で初めて同和・部落問題を考えた。差別はいかに生まれ、続くのか
私はずっと、「部落差別なんてものが存在する意味が分からない」と感じてきたが、映画『私のはなし 部落のはなし』を観てようやく、「どうしてそんな差別が存在し得るのか」という歴史が何となく理解できた。非常に複雑で解決の難しい問題だが、まずは多くの人が正しく理解することが必要だと言えるだろう
あわせて読みたい
【狂気】ホロコーストはなぜ起きた?映画『ヒトラーのための虐殺会議』が描くヴァンゼー会議の真実
映画『ヒトラーのための虐殺会議』は、ホロコーストの計画について話し合われた「ヴァンゼー会議」を描き出す作品だ。唯一1部だけ残った議事録を基に作られた本作は、「ユダヤ人虐殺」をイベントの準備でもしているかのように「理性的」に計画する様を映し出す。その「狂気」に驚かされてしまった。
あわせて読みたい
【驚愕】ベリングキャットの調査報道がプーチンを追い詰める。映画『ナワリヌイ』が示す暗殺未遂の真実
弁護士であり、登録者数640万人を超えるYouTuberでもあるアレクセイ・ナワリヌイは、プーチンに対抗して大統領選挙に出馬しようとしたせいで暗殺されかかった。その実行犯を特定する調査をベリングキャットと共に行った記録映画『ナワリヌイ』は、現実とは思えないあまりの衝撃に満ちている
あわせて読みたい
【抵抗】若者よ、映画『これは君の闘争だ』を見ろ!学校閉鎖に反対する学生運動がブラジルの闇を照らす
映画『これは君の闘争だ』で描かれるのは、厳しい状況に置かれた貧困層の学生たちによる公権力との闘いだ。「貧困層ばかりが通う」とされる公立校が大幅に再編されることを知った学生が高校を占拠して立て籠もる決断に至った背景を、ドキュメンタリー映画とは思えないナレーションで描く異色作
あわせて読みたい
【驚愕】本屋大賞受賞作『同志少女よ、敵を撃て』(逢坂冬馬)は凄まじい。戦場は人間を”怪物”にする
デビュー作で本屋大賞を受賞した『同志少女よ、敵を撃て』(逢坂冬馬)は、デビュー作であることを抜きにしても凄まじすぎる、規格外の小説だった。ソ連に実在した「女性狙撃兵」の視点から「独ソ戦」を描く物語は、生死の境でギリギリの葛藤や決断に直面する女性たちのとんでもない生き様を活写する
あわせて読みたい
【デモ】クーデター後の軍事政権下のミャンマー。ドキュメンタリーさえ撮れない治安の中での映画制作:…
ベルリン国際映画祭でドキュメンタリー賞を受賞したミャンマー映画『ミャンマー・ダイアリーズ』はしかし、後半になればなるほどフィクショナルな映像が多くなる。クーデター後、映画制作が禁じられたミャンマーで、10人の”匿名”監督が死を賭して撮影した映像に込められた凄まじいリアルとは?
あわせて読みたい
【悲劇】大川小学校はなぜ津波被害に遭ったのか?映画『生きる』が抉る現実と国家賠償請求の虚しさ
東日本大震災において、児童74人、教職員10人死亡という甚大な津波被害を生んだ大川小学校。その被害者遺族が真相究明のために奮闘する姿を追うドキュメンタリー映画『生きる』では、学校の酷い対応、出来れば避けたかった訴訟、下された画期的判決などが描かれ、様々な問題が提起される
あわせて読みたい
【狂気?】オウム真理教を内部から映す映画『A』(森達也監督)は、ドキュメンタリー映画史に残る衝撃作だ
ドキュメンタリー映画の傑作『A』(森達也)をようやく観られた。「オウム真理教は絶対悪だ」というメディアの報道が凄まじい中、オウム真理教をその内部からフラットに映し出した特異な作品は、公開当時は特に凄まじい衝撃をもたらしただろう。私たちの「当たり前」が解体されていく斬新な一作
あわせて読みたい
【衝撃】これが実話とは。映画『ウーマン・トーキング』が描く、性被害を受けた女性たちの凄まじい決断
映画『ウーマン・トーキング』の驚くべき点は、実話を基にしているという点だ。しかもその事件が起こったのは2000年代に入ってから。とある宗教コミュニティ内で起こった連続レイプ事件を機に村の女性たちがある決断を下す物語であり、そこに至るまでの「ある種異様な話し合い」が丁寧に描かれていく
あわせて読みたい
【異常】韓国衝撃の実話を映画化。『空気殺人』が描く、加湿器の恐怖と解決に至るまでの超ウルトラC
2011年に韓国で実際に起こった「加湿器殺菌剤による殺人事件」をモデルにした映画『空気殺人』は、金儲け主義の醜悪さが詰まった作品だ。国がその安全を保証し、17年間も販売され続けた国民的ブランドは、「水俣病」にも匹敵する凄まじい健康被害をもたらした
あわせて読みたい
【驚異】映画『RRR』『バーフバリ』は「観るエナジードリンク」だ!これ程の作品にはなかなか出会えないぞ
2022年に劇場公開されるや、そのあまりの面白さから爆発的人気を博し、現在に至るまでロングラン上映が続いている『RRR』と、同監督作の『バーフバリ』は、大げさではなく「全人類にオススメ」と言える超絶的な傑作だ。まだ観ていない人がいるなら、是非観てほしい!
あわせて読みたい
【生還】内戦下のシリアでISISに拘束された男の実話を基にした映画『ある人質』が描く壮絶すぎる現実
実話を基にした映画『ある人質 生還までの398日』は、内戦下のシリアでISISに拘束された男の壮絶な日々が描かれる。「テロリストとは交渉しない」という方針を徹底して貫くデンマーク政府のスタンスに翻弄されつつも、救出のために家族が懸命に奮闘する物語に圧倒される
あわせて読みたい
【実話】ソ連の衝撃の事実を隠蔽する記者と暴く記者。映画『赤い闇』が描くジャーナリズムの役割と実態
ソ連の「闇」を暴いた名もなき記者の実話を描いた映画『赤い闇』は、「メディアの存在意義」と「メディアとの接し方」を問いかける作品だ。「真実」を届ける「社会の公器」であるべきメディアは、容易に腐敗し得る。情報の受け手である私たちの意識も改めなければならない
あわせて読みたい
【衝撃】匿名監督によるドキュメンタリー映画『理大囲城』は、香港デモ最大の衝撃である籠城戦の内部を映す
香港民主化デモにおける最大の衝撃を内側から描く映画『理大囲城』は、とんでもないドキュメンタリー映画だった。香港理工大学での13日間に渡る籠城戦のリアルを、デモ隊と共に残って撮影し続けた匿名監督たちによる映像は、ギリギリの判断を迫られる若者たちの壮絶な現実を映し出す
あわせて読みたい
【解説】実話を基にした映画『シカゴ7裁判』で知る、「権力の暴走」と、それに正面から立ち向かう爽快さ
ベトナム戦争に反対する若者たちによるデモと、その後開かれた裁判の実話を描く『シカゴ7裁判』はメチャクチャ面白い映画だった。無理筋の起訴を押し付けられる主席検事、常軌を逸した言動を繰り返す不適格な判事、そして一枚岩にはなれない被告人たち。魅力満載の1本だ
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『1917』は、ワンカット風の凄まじい撮影手法が「戦場の壮絶な重圧」を見事に体感させる
映画『1917 命をかけた伝令』は、「全編ワンカット風」という凄まじい撮影手法で注目されたが、私は、その撮影手法が「戦場における緊迫感」を見事に増幅させているという点に驚かされた。「物語の中身」と「撮影手法」が素晴らしく合致したとんでもない作品だ
あわせて読みたい
【あらすじ】蝦夷地の歴史と英雄・阿弖流為を描く高橋克彦の超大作小説『火怨』は全人類必読の超傑作
大げさではなく、「死ぬまでに絶対に読んでほしい1冊」としてお勧めしたい高橋克彦『火怨』は凄まじい小説だ。歴史が苦手で嫌いな私でも、上下1000ページの物語を一気読みだった。人間が人間として生きていく上で大事なものが詰まった、矜持と信念に溢れた物語に酔いしれてほしい
あわせて読みたい
【奇跡】信念を貫いた男が国の制度を変えた。特別養子縁組を実現させた石巻の産婦人科医の執念:『赤ち…
遊郭で生まれ育った石巻の医師が声を上げ、あらゆる障害をなぎ倒して前進したお陰で「特別養子縁組」の制度が実現した。そんな産婦人科医・菊田昇の生涯を描き出す小説『赤ちゃんをわが子として育てる方を求む』には、法を犯してでも信念を貫いた男の衝撃の人生が描かれている
あわせて読みたい
【感想】湯浅政明監督アニメ映画『犬王』は、実在した能楽師を”異形”として描くスペクタクル平家物語
観るつもりなし、期待値ゼロ、事前情報ほぼ皆無の状態で観た映画『犬王』(湯浅政明監督)はあまりにも凄まじく、私はこんなとんでもない傑作を見逃すところだったのかと驚愕させられた。原作の古川日出男が紡ぐ狂気の世界観に、リアルな「ライブ感」が加わった、素晴らしすぎる「音楽映画」
あわせて読みたい
【差別】映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』の衝撃。プーチンが支持する国の蛮行・LGBT狩り
プーチン大統領の後ろ盾を得て独裁を維持しているチェチェン共和国。その国で「ゲイ狩り」と呼ぶしかない異常事態が継続している。映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』は、そんな現実を命がけで映し出し、「現代版ホロコースト」に立ち向かう支援団体の奮闘も描く作品
あわせて読みたい
【あらすじ】死刑囚を救い出す実話を基にした映画『黒い司法』が指摘する、死刑制度の問題と黒人差別の現実
アメリカで死刑囚の支援を行う団体を立ち上げた若者の実話を基にした映画『黒い司法 0%からの奇跡』は、「死刑制度」の存在価値について考えさせる。上映後のトークイベントで、アメリカにおける「死刑制度」と「黒人差別」の結びつきを知り、一層驚かされた
あわせて読みたい
【悲劇】アメリカの暗黒の歴史である奴隷制度の現実を、元奴隷の黒人女性自ら赤裸々に語る衝撃:『ある…
生まれながらに「奴隷」だった黒人女性が、多くの人の協力を得て自由を手にし、後に「奴隷制度」について書いたのが『ある奴隷少女に起こった出来事』。長らく「白人が書いた小説」と思われていたが、事実だと証明され、欧米で大ベストセラーとなった古典作品が示す「奴隷制度の残酷さ」
あわせて読みたい
【証言】ナチスドイツでヒトラーに次ぐナンバー2だったゲッベルス。その秘書だった女性が歴史を語る映画…
ナチスドイツナンバー2だった宣伝大臣ゲッベルス。その秘書だったブルンヒルデ・ポムゼルが103歳の時にカメラの前で当時を語った映画『ゲッベルスと私』には、「愚かなことをしたが、避け難かった」という彼女の悔恨と教訓が含まれている。私たちは彼女の言葉を真摯に受け止めなければならない
あわせて読みたい
【狂気】”友好”のために北朝鮮入りした監督が撮った映画『ザ・レッド・チャペル』が映す平壌の衝撃
倫理的な葛藤を物ともせず、好奇心だけで突き進んでいくドキュメンタリー監督マッツ・ブリュガーが北朝鮮から「出禁」を食らう結果となった『ザ・レッド・チャペル』は、「友好」を表看板に北朝鮮に潜入し、その「日常」と「非日常」を映し出した衝撃作
あわせて読みたい
【絶望】映画『少年たちの時代革命』が描く、香港デモの最中に自殺者を救おうとした若者たちの奮闘
香港の民主化運動の陰で、自殺者を救出しようと立ち上がったボランティア捜索隊が人知れず存在していた。映画『少年たちの時代革命』はそんな実話を基にしており、若者の自殺が急増した香港に様々な葛藤を抱えながら暮らし続ける若者たちのリアルが切り取られる作品だ
あわせて読みたい
【歴史】『大地の子』を凌駕する中国残留孤児の現実。中国から奇跡的に”帰国”した父を城戸久枝が描く:…
文化大革命の最中、国交が成立していなかった中国から自力で帰国した中国残留孤児がいた。その娘である城戸久枝が著した『あの戦争から遠く離れて』は、父の特異な体験を起点に「中国残留孤児」の問題に分け入り、歴史の大きなうねりを個人史として体感させてくれる作品だ
あわせて読みたい
【アメリカ】長崎の「原爆ドーム」はなぜ残らなかった?爆心地にあった「浦上天主堂」の数奇な歴史:『…
原爆投下で半壊し、廃墟と化したキリスト教の大聖堂「浦上天主堂」。しかし何故か、「長崎の原爆ドーム」としては残されず、解体されてしまった。そのため長崎には原爆ドームがないのである。『ナガサキ 消えたもう一つの「原爆ドーム」』は、「浦上天主堂」を巡る知られざる歴史を掘り下げ、アメリカの強かさを描き出す
あわせて読みたい
【感想】リドリー・スコット監督の映画『最後の決闘裁判』から、社会が”幻想”を共有する背景とその悲劇…
例えば、「1万円札」というただの紙切れに「価値を感じる」のは、社会の構成員が同じ「共同幻想」の中に生きているからだ。リドリー・スコット監督の映画『最後の決闘裁判』は、「強姦では妊娠しない」「裁判の勝者を決闘で決する」という社会通念と、現代にも通じる「共同幻想」の強さを描き出す
あわせて読みたい
【理解】小野田寛郎を描く映画。「戦争終結という現実を受け入れない(=認知的不協和)」は他人事じゃ…
映画『ONODA 一万夜を越えて』を観るまで、小野田寛郎という人間に対して違和感を覚えていた。「戦争は終わっていない」という現実を生き続けたことが不自然に思えたのだ。しかし映画を観て、彼の生き方・決断は、私たちと大きく変わりはしないと実感できた
あわせて読みたい
【信念】水俣病の真実を世界に伝えた写真家ユージン・スミスを描く映画。真実とは「痛みへの共感」だ:…
私はその存在をまったく知らなかったが、「水俣病」を「世界中が知る公害」にした報道写真家がいる。映画『MINAMATA―ミナマタ―』は、水俣病の真実を世界に伝えたユージン・スミスの知られざる生涯と、理不尽に立ち向かう多くの人々の奮闘を描き出す
あわせて読みたい
【驚愕】キューバ危機の裏側を描くスパイ映画『クーリエ』。核戦争を回避させた民間人の衝撃の実話:『…
核戦争ギリギリまで進んだ「キューバ危機」。その陰で、世界を救った民間人がいたことをご存知だろうか?実話を元にした映画『クーリエ:最高機密の運び屋』は、ごく普通のセールスマンでありながら、ソ連の膨大な機密情報を盗み出した男の信じがたい奮闘を描き出す
あわせて読みたい
【衝撃】ウクライナでのホロコーストを描く映画『バビ・ヤール』は、集めた素材映像が凄まじすぎる
ソ連生まれウクライナ育ちの映画監督セルゲイ・ロズニツァが、「過去映像」を繋ぎ合わせる形で作り上げた映画『バビ・ヤール』は、「単一のホロコーストで最大の犠牲者を出した」として知られる「バビ・ヤール大虐殺」を描き出す。ウクライナ市民も加担した、そのあまりに悲惨な歴史の真実とは?
あわせて読みたい
【衝撃】『ゆきゆきて、神軍』はとんでもないドキュメンタリー映画だ。虚実が果てしなく入り混じる傑作
奥崎謙三という元兵士のアナーキストに密着する『ゆきゆきて、神軍』。ドキュメンタリー映画の名作として名前だけは知っていたが、まさかこんなとんでもない映画だったとはと驚かされた。トークショーで監督が「自分の意向を無視した編集だった」と語っていたのも印象的
あわせて読みたい
【実話】映画『アウシュビッツ・レポート』が描き出す驚愕の史実。世界はいかにホロコーストを知ったのか?
映画『アウシュヴィッツ・レポート』は、アウシュビッツ強制収容所から抜け出し、詳細な記録と共にホロコーストの実態を世界に明らかにした実話を基にした作品。2人が持ち出した「アウシュビッツ・レポート」こそが、ホロコーストについて世界が知るきっかけだったのであり、そんな史実をまったく知らなかったことにも驚かされた
あわせて読みたい
【凄絶】北朝鮮の”真実”を描くアニメ映画。強制収容所から決死の脱出を試みた者が語る驚愕の実態:『ト…
在日コリアン4世の監督が、北朝鮮脱北者への取材を元に作り上げた壮絶なアニメ映画『トゥルーノース』は、私たちがあまりに恐ろしい世界と地続きに生きていることを思い知らせてくれる。最低最悪の絶望を前に、人間はどれだけ悪虐になれてしまうのか、そしていかに優しさを発揮できるのか。
あわせて読みたい
【悲哀】2度の東京オリンピックに翻弄された都営アパートから「公共の利益」と「個人の権利」を考える:…
1964年の東京オリンピックを機に建設された「都営霞ケ丘アパート」は、東京オリンピック2020を理由に解体が決まり、長年住み続けた高齢の住民に退去が告げられた。「公共の利益」と「個人の権利」の狭間で翻弄される人々の姿を淡々と映し出し、静かに「社会の在り方」を問う映画
あわせて読みたい
【民主主義】占領下の沖縄での衝撃の実話「サンマ裁判」で、魚売りのおばぁの訴えがアメリカをひっかき…
戦後の沖縄で、魚売りのおばぁが起こした「サンマ裁判」は、様々な人が絡む大きな流れを生み出し、最終的に沖縄返還のきっかけともなった。そんな「サンマ裁判」を描く映画『サンマデモクラシー』から、民主主義のあり方と、今も沖縄に残り続ける問題について考える
あわせて読みたい
【感想】映画『野火』は、戦争の”虚しさ”をリアルに映し出す、後世に受け継がれるべき作品だ
「戦争の悲惨さ」は様々な形で描かれ、受け継がれてきたが、「戦争の虚しさ」を知る機会はなかなかない。映画『野火』は、第二次世界大戦中のフィリピンを舞台に、「敵が存在しない戦場で”人間の形”を保つ困難さ」を描き出す、「虚しさ」だけで構成された作品だ
あわせて読みたい
【驚異】信念を貫く勇敢さを、「銃を持たずに戦場に立つ」という形で示した実在の兵士の凄まじさ:映画…
第二次世界大戦で最も過酷な戦場の1つと言われた「前田高地(ハクソー・リッジ)」を、銃を持たずに駆け回り信じがたい功績を残した衛生兵がいた。実在の人物をモデルにした映画『ハクソー・リッジ』から、「戦争の悲惨さ」だけでなく、「信念を貫くことの大事さ」を学ぶ
あわせて読みたい
【実話】権力の濫用を監視するマスコミが「教会の暗部」を暴く映画『スポットライト』が現代社会を斬る
地方紙である「ボストン・グローブ紙」は、数多くの神父が長年に渡り子どもに対して性的虐待を行い、その事実を教会全体で隠蔽していたという衝撃の事実を明らかにした。彼らの奮闘の実話を映画化した『スポットライト』から、「権力の監視」の重要性を改めて理解する
あわせて読みたい
【実話】映画『イミテーションゲーム』が描くエニグマ解読のドラマと悲劇、天才チューリングの不遇の死
映画『イミテーションゲーム』が描く衝撃の実話。「解読不可能」とまで言われた最強の暗号機エニグマを打ち破ったのはなんと、コンピューターの基本原理を生み出した天才数学者アラン・チューリングだった。暗号解読を実現させた驚きのプロセスと、1400万人以上を救ったとされながら偏見により自殺した不遇の人生を知る
あわせて読みたい
【最新】「コロンブス到達以前のアメリカ大陸」をリアルに描く歴史書。我々も米国人も大いに誤解してい…
サイエンスライターである著者は、「コロンブス到着以前のアメリカはどんな世界だったか?」という問いに触れ、その答えが書かれた本がいつまで経っても出版されないので自分で執筆した。『1491 先コロンブス期アメリカ大陸をめぐる新発見』には、アメリカ人も知らない歴史が満載だ
あわせて読みたい
【想像力】「知らなかったから仕方ない」で済ませていいのか?第二の「光州事件」は今もどこかで起きて…
「心地いい情報」だけに浸り、「知るべきことを知らなくても恥ずかしくない世の中」を生きてしまっている私たちは、世界で何が起こっているのかあまりに知らない。「光州事件」を描く映画『タクシー運転手 約束は海を越えて』から、世界の見方を考える
あわせて読みたい
【興奮】世界的大ベストセラー『サピエンス全史』要約。人類が文明を築き上げるに至った3つの革命とは?
言わずと知れた大ベストセラー『サピエンス全史』は、「何故サピエンスだけが人類の中で生き残り、他の生物が成し得なかった歴史を歩んだのか」を、「認知革命」「農業革命」「科学革命」の3つを主軸としながら解き明かす、知的興奮に満ち溢れた1冊
あわせて読みたい
【驚愕】正義は、人間の尊厳を奪わずに貫かれるべきだ。独裁政権を打倒した韓国の民衆の奮闘を描く映画…
たった30年前の韓国で、これほど恐ろしい出来事が起こっていたとは。「正義の実現」のために苛烈な「スパイ狩り」を行う秘密警察の横暴をきっかけに民主化運動が激化し、独裁政権が打倒された史実を描く『1987、ある闘いの真実』から、「正義」について考える
あわせて読みたい
【権利】衝撃のドキュメンタリー映画『ヤクザと憲法』は、「異質さを排除する社会」と「生きる権利」を問う
「ヤクザ」が排除された現在でも、「ヤクザが担ってきた機能」が不要になるわけじゃない。ではそれを、公権力が代替するのだろうか?実際の組事務所(東組清勇会)にカメラを持ち込むドキュメンタリー映画『ヤクザと憲法』が映し出す川口和秀・松山尚人・河野裕之の姿から、「基本的人権」のあり方について考えさせられた
あわせて読みたい
【史実】太平洋戦争末期に原爆を落としたアメリカは、なぜ終戦後比較的穏やかな占領政策を取ったか?:…
『八月十五日に吹く風』は小説だが、史実を基にした作品だ。本作では、「終戦直前に原爆を落としながら、なぜ比較的平穏な占領政策を行ったか?」の疑問が解き明かされる。『源氏物語』との出会いで日本を愛するようになった「ロナルド・リーン(仮名)」の知られざる奮闘を知る
あわせて読みたい
【現実】東日本大震災発生時からの被災地の映像には、ニュースで見る「分かりやすさ」は微塵もない:『…
東日本大震災発生直後からカメラを回し、被災地の現実を切り取ってきたテレビ岩手。「分かりやすさ」が優先されるテレビではなかなか放送できないだろう映像を含め、「分かりにくい現実」を切り取った映像で構成する映画『たゆたえども沈まず』は静かな衝撃をもたらす作品
あわせて読みたい
【称賛】生き様がかっこいい。ムンバイのホテルのテロ事件で宿泊客を守り抜いたスタッフたち:映画『ホ…
インドの高級ホテルで実際に起こったテロ事件を元にした映画『ホテル・ムンバイ』。恐ろしいほどの臨場感で、当時の恐怖を観客に体感させる映画であり、だからこそ余計に、「逃げる選択」もできたホテルスタッフたちが自らの意思で残り、宿泊を助けた事実に感銘を受ける
あわせて読みたい
【意外】東京裁判の真実を記録した映画。敗戦国での裁判が実に”フェア”に行われたことに驚いた:『東京…
歴史に詳しくない私は、「東京裁判では、戦勝国が理不尽な裁きを行ったのだろう」という漠然としたイメージを抱いていた。しかし、その印象はまったくの誤りだった。映画『東京裁判 4Kリマスター版』から東京裁判が、いかに公正に行われたのかを知る
あわせて読みたい
【驚愕】「金正男の殺人犯」は”あなた”だったかも。「人気者になりたい女性」が陥った巧妙な罠:映画『…
金正男が暗殺された事件は、世界中で驚きをもって報じられた。その実行犯である2人の女性は、「有名にならないか?」と声を掛けられて暗殺者に仕立て上げられてしまった普通の人だ。映画『わたしは金正男を殺していない』から、危険と隣り合わせの現状を知る
あわせて読みたい
【実話】人質はなぜ犯人に好意を抱くか?「ストックホルム症候群」の由来である銀行強盗を描く映画:『…
「強盗や立てこもり事件などにおいて、人質が犯人に好意・共感を抱いてしまう状態」を「ストックホルム症候群」と呼ぶのだが、実はそう名付けられる由来となった実際の事件が存在する。実話を基にした映画『ストックホルムケース』から、犯人に協力してしまう人間の不可思議な心理について知る
あわせて読みたい
【危機】遺伝子組み換え作物の危険性を指摘。バイオ企業「モンサント社」の実態を暴く衝撃の映画:映画…
「遺伝子組み換え作物が危険かどうか」以上に注目すべきは、「モンサント社の除草剤を摂取して大丈夫か」である。種子を独占的に販売し、農家を借金まみれにし、世界中の作物の多様性を失わせようとしている現状を、映画「モンサントの不自然な食べもの」から知る
あわせて読みたい
【衝撃】森達也『A3』が指摘。地下鉄サリン事件を起こしたオウム真理教は社会を激変させた
「オウム真理教は特別だ、という理由で作られた”例外”が、いつの間にか社会の”前提”になっている」これが、森達也『A3』の主張の要点だ。異常な状態で続けられた麻原彰晃の裁判を傍聴したことをきっかけに、社会の”異様な”変質の正体を理解する。
あわせて読みたい
【衝撃】壮絶な戦争映画。最愛の娘を「産んで後悔している」と呟く母らは、正義のために戦場に留まる:…
こんな映画、二度と存在し得ないのではないかと感じるほど衝撃を受けた『娘は戦場で生まれた』。母であり革命家でもあるジャーナリストは、爆撃の続くシリアの街を記録し続け、同じ街で娘を産み育てた。「知らなかった」で済ませていい現実じゃない。
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
歴史・文明・人類【本・映画の感想】 | ルシルナ
現在、そして未来の社会について考える場合に、人類のこれまでの歴史を無視することは難しいでしょう。知的好奇心としても、人類がいかに誕生し、祖先がどのような文明を作…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…















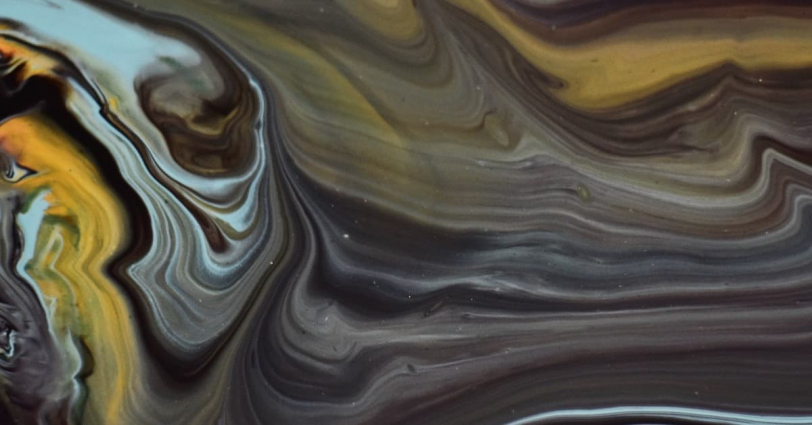






























































































コメント