目次
はじめに
この記事で取り上げる本
著:久枝, 城戸
¥979 (2022/07/12 14:33時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
この本をガイドにしながら記事を書いていきます
この記事の3つの要点
- 「日本生まれの中国残留孤児二世」という著者の類まれな特殊性
- 「中国残留孤児」という言葉が世に知られる10年以上も前に独力で日本への帰国を果たした城戸幹の壮絶な経験
- 特異な出生ゆえに困難を避けていられた著者が、「個人の物語」として「中国残留孤児」の問題に足を踏み入れていった経緯
「中国残留孤児」という大きな括りで捉えると切り捨てられてしまうだろう細部こそ大事にする著者のスタンスが素敵な作品
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
言葉だけは知っていた「中国残留孤児」の現実を本書『あの戦争から遠く離れて』で初めて知った。著者のあまりの特殊性にも驚かされる

あわせて読みたい
【知的】「BLって何?」という初心者に魅力を伝える「腐男子」の「BLの想像力と創造力」講座:『ボクた…
「BLは知的遊戯である」という主張には「は?」と感じてしまうでしょうが、本書『ボクたちのBL論』を読めばその印象は変わるかもしれません。「余白の発見と補完」を通じて、「ありとあらゆる2者の間の関係性を解釈する」という創造性は、現実世界にどのような影響を与えているのか
私は、「中国残留孤児」という言葉自体は知っていたが、それがどんなものであり、どのように大変な状況なのかについて考えたことがなかった。きっと多くの日本人が同じような感じではないかと思う。
さらに本書の著者は、「日本生まれの中国残留孤児二世」という”特殊な出生”なのだという。正直、この言葉の意味も、その特殊さも、本書を読み始めた時点ではまったく理解していなかった。本書をしばらく読み進めてもまだ、上手く捉えられずにいたのだ。
しかし本書の後半、中国残留孤児やその二世と著者が関わっていく辺りから、ようやくその意味が理解できるようになってきた。そして、そんな非常に特殊な出生を持つ著者だからこそ、「中国残留孤児」の問題を深く、そして新しい視点から捉えることが出来たのだ。
そんな著者の物語は、父親の激動の人生を追うところから始まる。
あわせて読みたい
【狂気】”友好”のために北朝鮮入りした監督が撮った映画『ザ・レッド・チャペル』が映す平壌の衝撃
倫理的な葛藤を物ともせず、好奇心だけで突き進んでいくドキュメンタリー監督マッツ・ブリュガーが北朝鮮から「出禁」を食らう結果となった『ザ・レッド・チャペル』は、「友好」を表看板に北朝鮮に潜入し、その「日常」と「非日常」を映し出した衝撃作
著者の父親は、「中国残留孤児」という言葉が世に知られる以前に自力で日本へと帰国を果たした
本書の凄まじさは、著者の父親の来歴とその壮絶な帰国劇にあると言っていい。「孫玉福」という中国名で生活していた城戸幹が中国から帰国したのは1970年のこと。中国との国交が正常化される2年も前のことであり、さらに「中国残留孤児」という言葉がメディアで盛んに取り上げられるようになる10年も前のことだった。もっと言えば、1970年というのは、中国で文化大革命の嵐が吹き荒れている最中でもあったのだ。
そんな時代に、著者・城戸久枝の父親は、自力での帰国を成し遂げたのである。まさにそれは「奇跡」としか言いようがないものだった。
それではまず、孫玉福こと城戸幹が、日本への帰国を果たすまでどんな生活を送っていたのかに触れていこうと思う。
あわせて読みたい
【驚愕】「金正男の殺人犯」は”あなた”だったかも。「人気者になりたい女性」が陥った巧妙な罠:映画『…
金正男が暗殺された事件は、世界中で驚きをもって報じられた。その実行犯である2人の女性は、「有名にならないか?」と声を掛けられて暗殺者に仕立て上げられてしまった普通の人だ。映画『わたしは金正男を殺していない』から、危険と隣り合わせの現状を知る
城戸幹は、満州国軍の軍人の子として生まれ、終戦時に様々な混乱と不運が重なったことで、そのまま中国に取り残されてしまう。城戸幹は多くの人の助けを得て、牡丹江のほとりにある頭道河子村へと連れてこられた。5歳の頃のことである。

育ての親はなかなか見つからなかった。「日本人の子を育てていると知られたら、ロシア人に何をされるか分からない」という恐怖があったからだ。しかしやがて、自警団長の義理の娘である付淑琴が名乗りを上げる。彼女は2度の流産を経験したことで子どもを産めない身体になっており、引き取りを強く希望したのだ。
そんな風にして城戸幹は、日本人であることを隠すために「孫玉福」という名前を与えられ、中国人として育てられることとなったのである。
あわせて読みたい
【家族】映画『そして父になる』が問う「子どもの親である」、そして「親の子どもである」の意味とは?
「血の繋がり」だけが家族なのか?「将来の幸せ」を与えることが子育てなのか?実際に起こった「赤ちゃんの取り違え事件」に着想を得て、苦悩する家族を是枝裕和が描く映画『そして父になる』から、「家族とは何か?」「子育てや幸せとどう向き合うべきか?」を考える
孫玉福は非常に優秀だった。当然のことながら中国語は苦手だったが、一念発起して克服する。他の教科の成績は元々良かったこともあり、小学校時代に飛び級を果たしたほどだ。その後、彼自身の努力と育ての母の必死の金策のお陰で高校まで通うことができ、そのままであれば名門・北京大学も狙えるほどの成績を維持していた。
しかしここで悲劇が起こる。孫玉福は、ちょっとしたすれ違いから、自らの戸籍の記載を「日本民族」と変更してしまったのだ。当時中国では文化大革命の嵐が吹き荒れていた。そんな時代にあって「日本民族」であることを明かしてしまった彼には、中国国内での真っ当な道は閉ざされてしまったと言っていい。
時を同じくして、孫玉福の中にアイデンティティに対する葛藤が生まれてくる。「中国人として育てられたこと」と「日本人であること」のギャップを無視できなくなっていったのだ。そして彼は、「生みの親をなんとしてでも探し出したい」という思いに駆られ、そこから猛烈に行動を起こすことになる……。
城戸久枝の父親の「奇跡の帰国」は、こんな風にして始まっていくのである。
あわせて読みたい
【憤り】世界最強米海軍4人VS数百人のタリバン兵。死線を脱しただ1人生還を果たした奇跡の実話:『アフ…
アフガニスタンの山中で遭遇した羊飼いを見逃したことで、数百人のタリバン兵と死闘を繰り広げる羽目に陥った米軍最強部隊に所属する4人。奇跡的に生き残り生還を果たした著者が記す『アフガン、たった一人の生還』は、とても実話とは信じられない凄まじさに満ちている
帰国に至るまでの奮闘と、帰国してからの苦労
孫玉福(城戸幹)の物語の凄まじさは、「彼が元々『帰国』を意識していたわけではない」という点にあると思う。日本で「中国残留孤児」という言葉が使われるようになってから、「そういう境遇の人たちを日本へと帰国させよう」という機運が生まれることになるわけだが、城戸幹が帰国したのはそうなる10年も前のことだった。「中国残留孤児」という言葉も恐らく存在せず、彼らが日本へと帰国するルートも当然存在していなかったのだから、そもそも「帰国する」という発想を持ちようがなかったというのが正しいだろう。

彼は純粋に、「生みの親について知りたい」と考えて行動を起こす。自分がどこの誰で、どんな経緯で育ての親の元へとやってきたのかという来歴を明らかにしようとしたのだ。しかし、どれだけ調べても何も分からなかった。彼は、話を聞ける限りすべての関係者に当たったと言っていいぐらいの調査を行うのだが、それでも自分の出生などについてほとんど情報を得ることができない。
あわせて読みたい
【矛盾】その”誹謗中傷”は真っ当か?映画『万引き家族』から、日本社会の「善悪の判断基準」を考える
どんな理由があれ、法を犯した者は罰せられるべきだと思っている。しかしそれは、善悪の判断とは関係ない。映画『万引き家族』(是枝裕和監督)から、「国民の気分」によって「善悪」が決まる社会の是非と、「善悪の判断を保留する勇気」を持つ生き方について考える
その一方で孫玉福は、日本赤十字に宛てて「自分の両親を探してほしい」という手紙を送り続けた。その数なんと数百通に及ぶという。どれだけ手紙を出しても音沙汰がなかったが、それでも諦めずに送り続けたことでようやく反応が返ってくる。しかしそこに書かれていたのは、「もっと情報がなければ両親を探せない」という主旨の文章だった。自身でこれでもかと調べた上で何も分からなかったのに、これ以上どうすればいいのかと彼は頭を抱えてしまう。
しかしその後、奇跡的な展開の末、ようやく自身の「城戸幹」としての身元にたどり着くことが出来た。その素晴らしい経緯については、是非本書を読んでほしい。
しかし、身元が分かったところで問題が解決するわけではない。何せ当時はまだ、日本と中国の間で国交が回復していなかったのだ。さらに、中国ではまさに文化大革命の真っ最中だった。つまり、「日本人」という身分がバレたら殺されてしまうかもしれないという恐怖を抱えながら、彼は「日本人」として帰国するための方策を探り続けなければならなかったというわけだ。その大変さは、想像に余りあるだろう。
あわせて読みたい
【凄絶】北朝鮮の”真実”を描くアニメ映画。強制収容所から決死の脱出を試みた者が語る驚愕の実態:『ト…
在日コリアン4世の監督が、北朝鮮脱北者への取材を元に作り上げた壮絶なアニメ映画『トゥルーノース』は、私たちがあまりに恐ろしい世界と地続きに生きていることを思い知らせてくれる。最低最悪の絶望を前に、人間はどれだけ悪虐になれてしまうのか、そしていかに優しさを発揮できるのか。
後年、日本への帰国を果たした城戸幹が、NHKドラマ『大地の子』の再放送を見る機会があったという。山崎豊子原作のこのドラマは中国残留孤児をテーマにしており、それを観て城戸幹はこんな風に口にしたそうだ。
なあ、久枝。父ちゃんがいた頃は、あんな甘いものじゃなかったよ。

私は、小説でもドラマでも『大地の子』に触れていないが、もしその内容をご存知の方がいれば、「『大地の子』で描かれているよりも壮絶だった」とイメージすればいいことになる。小説で描かれているよりも厳しかったというのだから、どれだけ辛い状況だったのか想像できるだろう。
著:山崎 豊子
¥652 (2022/07/12 14:39時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『流浪の月』を観て感じた、「『見て分かること』にしか反応できない世界」への気持ち悪さ
私は「見て分かること」に”しか”反応できない世界に日々苛立ちを覚えている。そういう社会だからこそ、映画『流浪の月』で描かれる文と更紗の関係も「気持ち悪い」と断罪されるのだ。私はむしろ、どうしようもなく文と更紗の関係を「羨ましい」と感じてしまう。
さて、そんな風にして無事に帰国を果たした城戸幹だが、ここで苦労が終わったわけではない。日本に戻ってからも大変なことの連続だった。そもそも、中国人として育てられたわけで、日本人なのに日本語を喋ることができない。これは社会生活を送る上で相当な障害となるだろう。また、「血の繋がった家族」との生活が始まっても、長い間関わりがなかったこともあり、自身が「厄介者」扱いされているような気がしてしまうのだ。
さらに、「中国での進学を諦めざるを得なかったこと」が日本帰国のモチベーションの1つだったにも拘わらず、結果として、日本での大学進学も難しいと判明する。「日本に帰国できたから万々歳」というわけにはいかなかったのだ。
しかしそれでも城戸幹は、社会の中で奮闘し、結婚し子どもをもうけた。だからこそ「城戸久枝」がこの世に生を享け、本書『あの戦争から遠く離れて』を執筆するに至ったのである。著者は、それまでまったく知らなかった、自身の背後に横たわる「歴史の大きな流れ」を実感し、「中国残留孤児」の世界へと足を踏み入れていく。
「日本生まれの中国残留孤児二世」という特殊さと、城戸久枝が「中国残留孤児」の問題に足を踏み入れていった経緯
あわせて読みたい
【衝撃】ミキ・デザキが映画『主戦場』で示す「慰安婦問題」の実相。歴史修正主義者の発言がヤバすぎ
「慰安婦問題」に真正面から取り組んだ映画『主戦場』は、「『慰安婦問題』の根幹はどこにあるのか?」というその複雑さに焦点を当てていく。この記事では、本作で映し出された様々な情報を元に「慰安婦問題」について整理したものの、結局のところ「解決不可能な問題である」という結論に行き着いてしまった
本書の前半は、父・城戸幹の来歴を追う構成だが、後半は、著者である城戸久枝がどのようにして「中国残留孤児」の問題に関わるようになっていったのかが描かれていく。
著者は、最初から「中国残留孤児」に関心を持っていたわけではない。自身が「日本生まれの中国残留孤児二世」という特殊な立場にあることは理解していたが、だからと言ってその背景を知るために行動を起こすほどのものではない、と感じていたのだ。そんな著者は、どのようにして「中国残留孤児」の世界に足を踏み入れることになったのか。
その話の前にまず、「日本生まれの中国残留孤児二世」という立場の特殊さについて整理しておくことにしよう。
ここまでの話で、父・城戸幹がいかに特異な形で日本への帰国を果たしたのかが理解してもらえたと思う。城戸幹が辿った経緯は、非常に特殊なものだった。
あわせて読みたい
【日本】原発再稼働が進むが、その安全性は?樋口英明の画期的判決とソーラーシェアリングを知る:映画…
映画『原発をとめた裁判長 そして原発をとめる農家たち』では、大飯原発の運転差し止め判決を下した裁判長による画期的な「樋口理論」の説明に重点が置かれる。「原発の耐震性」に関して知らないことが満載で、実に興味深かった。また、農家が発案した「ソーラーシェアリング」という新たな発電方法も注目である

一般的に、「中国残留孤児二世」は中国で生まれている。それはそうだろう。「中国残留孤児」の日本帰国をサポートする支援が始まったのは、城戸幹の帰国から10年以上も後のことだ。だから、中国国内に取り残されていた中国残留孤児たちは、中国国内で結婚し、子どもをもうけた。当然、「中国残留孤児二世」も中国で生活することになり、中国語しか喋れない両親の元で中国語話者として育っていくというわけだ
だからこそ、「中国残留孤児」やその二世の帰国事業が始まった際、その多くが言葉の問題で苦労することになった。
一方城戸久枝の場合、父親が結婚前に自力で日本帰国を果たしたこともあり、「日本生まれの中国残留孤児二世」という、普通にはあり得ない出生となった。この点こそが、城戸久枝が有する「中国残留孤児二世としての特殊性」というわけだ。彼女は日本生まれなので、「中国残留孤児二世」でありながら、もちろん言葉の問題で苦労したこともないし、父・城戸幹が中国に対して抱いている感情も理解できずにいたのである。
あわせて読みたい
【挑戦】映画『燃えあがる女性記者たち』が描く、インドカースト最下位・ダリットの女性による報道
映画『燃えあがる女性記者たち』は、インドで「カースト外の不可触民」として扱われるダリットの女性たちが立ち上げた新聞社「カバル・ラハリヤ」を取り上げる。自身の境遇に抗って、辛い状況にいる人の声を届けたり権力者を糾弾したりする彼女たちの奮闘ぶりが、インドの民主主義を変革させるかもしれない
城戸久枝にとっては、「中国残留孤児」は正直「遠い存在」でしかなかった、というわけだ。
しかしあることをきっかけに運命が変わった。育ての親である付淑琴が亡くなる9ヶ月ほど前に、突然父から中国行きを誘われたのだ。父の友人の家にホームステイしてみないかというのである。そしてこのことをきっかけに著者は、「中国という国家」に対する不思議さを抱くようになり、結果として父が辿った足跡を辿っていくことになった。
こうして城戸久枝は、「中国残留孤児」の問題に対する一歩を踏み出していくのである。
「個人の物語」として「中国残留孤児」の問題に関わっていく
あわせて読みたい
【歴史】映画『シン・ちむどんどん』は、普天間基地移設問題に絡む辺野古埋め立てを”陽気に”追及する(…
映画『シン・ちむどんどん』は、映画『センキョナンデス』に続く「ダースレイダー・プチ鹿島による選挙戦リポート」第2弾である。今回のターゲットは沖縄知事選。そして本作においては、選挙戦の模様以上に、後半で取り上げられる「普天間基地の辺野古移設問題の掘り下げ」の方がより興味深かった
本書は基本的に、「城戸久枝という個人の物語」として語られていく。「中国残留孤児」の問題について客観的に考えを深めていくような内容ではなく、個人史として「中国残留孤児」を追っていくのだ。
ある時、父・城戸幹が突然、県や厚生省を訴え始めた。中国残留孤児として帰国したのにまったく補償がなかったことに対してである。当初著者は、父のこの行動が理解できなかった。その時点で、父が生活に困窮していたり何か大きな支障を感じていたわけではない。だから著者は、今更そんな訴えを起こすことにどんな意味があるのか理解できずにいたのだ。
しかしその後、日本国内にいる他の中国残留孤児二世と関わりを深めていく中で、自分には見えていなかった世界を知ることになる。日本で生まれ育った彼女と異なり、中国で生まれ育った二世は、想像もできないような苦労を強いられていた。国に対して裁判を起こした他の中国残留孤児と関わる機会もあり、その中で彼女は、父の行動を少しは理解できたような気分になる。そしてその過程で、「中国残留孤児」という問題の根深さを一層深く知ることにもなったというわけだ。
さらに彼女は、自身のアイデンティティに対する葛藤も抱くようになっていく。彼女は「中国残留孤児」のことを知るにつれて、「『日本人』に対する強烈な悪感情」を自覚するようになる。しかしその一方で、当然のことではあるが、「『城戸久枝』という個人に対する親愛の情」を捨てられるわけではない。つまり、自身も日本人であるのだが、「中国残留孤児」の問題を通じて知った日本人の酷さに対して苛立ちを覚えてしまうというわけだ。そんな経験を何度も重ねることで彼女は、文化大革命真っ最中の中国という、彼女が生きる世界とまったく異なる環境で父が経験しただろう過酷さに思いを馳せることになる。
あわせて読みたい
【実話】障害者との接し方を考えさせる映画『こんな夜更けにバナナかよ』から”対等な関係”の大事さを知る
「障害者だから◯◯だ」という決まりきった捉え方をどうしてもしてしまいがちですが、『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』の主人公・鹿野靖明の生き様を知れば、少しは考え方が変わるかもしれません。筋ジストロフィーのまま病院・家族から離れて“自活”する決断をした驚異の人生

こんな風に彼女は、「城戸久枝という個人の物語」として「中国残留孤児」の問題を捉えていったのだ。
私が感じ、いまも思うことはたった一つだけだ――私と彼らの間には、わかりあえることもあれば、わかりあえないこともある。彼らが私を変えることはできないし、私が彼らを変えることもできない――特別なやり方など、どこにもありはしない。それでも、彼らとの関係は続いていく
「中国残留孤児」「日本」「中国」のような大きな枠組みで捉えてしまうと、様々な細部が顧みられることなく切り捨てられてしまうこともあるだろう。著者はそうではなく、切り捨てられてしまいがちな細部をきちんと手放さないように意識した上で、自分事として「中国残留孤児」の問題に接していく。その姿勢こそが、この作品が持つ力強さであるように私には感じられた。
あわせて読みたい
【信念】水俣病の真実を世界に伝えた写真家ユージン・スミスを描く映画。真実とは「痛みへの共感」だ:…
私はその存在をまったく知らなかったが、「水俣病」を「世界中が知る公害」にした報道写真家がいる。映画『MINAMATA―ミナマタ―』は、水俣病の真実を世界に伝えたユージン・スミスの知られざる生涯と、理不尽に立ち向かう多くの人々の奮闘を描き出す
また著者は、「城戸幹の娘」という立場だけではなく、「軍人だった祖父の孫」という立場も直視しようとする。中国留学時代、彼女は何度も日本への非難を耳にしたのだが、その多くは「日本の軍人」に対するものだった。「自身が軍人の孫である」という事実から逃げてはいけないと感じるようになった彼女は、僅かな資料を手がかりに祖父の面影も追おうとする。
このように彼女は、まさに「個人史」として大きな歴史を捉えようとしていくのである。
あわせて読みたい
【感想】関東大震災前後を描く映画『福田村事件』(森達也)は、社会が孕む「思考停止」と「差別問題」…
森達也監督初の劇映画である『福田村事件』は、100年前の関東大震災直後に起こった「デマを起点とする悲劇」が扱われる作品だ。しかし、そんな作品全体が伝えるメッセージは、「100年前よりも現代の方がよりヤバい」だと私は感じた。SNS時代だからこそ意識すべき問題の詰まった、挑発的な作品である
著:久枝, 城戸
¥979 (2022/07/12 14:35時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品読了済】私が読んできたノンフィクション・教養書を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が読んできたノンフィクションを様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本選びの参考にして下さい。
最後に
あわせて読みたい
【衝撃】ウクライナでのホロコーストを描く映画『バビ・ヤール』は、集めた素材映像が凄まじすぎる
ソ連生まれウクライナ育ちの映画監督セルゲイ・ロズニツァが、「過去映像」を繋ぎ合わせる形で作り上げた映画『バビ・ヤール』は、「単一のホロコーストで最大の犠牲者を出した」として知られる「バビ・ヤール大虐殺」を描き出す。ウクライナ市民も加担した、そのあまりに悲惨な歴史の真実とは?
本書で語られる、育ての親である付淑琴との関係も素晴らしい。血の繋がりや国籍の違いなど関係なく、彼女は孫玉福に惜しみない愛情を注ぐ。そしてその愛情を一身に受け止めた孫玉福も、大人になってからその恩に報いようとする。そしてこれもまた非常に奇跡的な話だと感じるのだが、孫玉福が付淑琴に最大限の感謝を以って恩返ししようとした行動が、結果として彼の帰国に繋がっていくのである。
最終的には帰国を決断する孫玉福だが、その別れは、双方にとって引きちぎられるような苦しみを伴うものだった。そのような「親子関係」にたどり着いた2人の人生もまた素晴らしいと思う。
あわせて読みたい
【映画】『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』で号泣し続けた私はTVアニメを観ていない
TVアニメは観ていない、というかその存在さえ知らず、物語や登場人物の設定も何も知らないまま観に行った映画『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』に、私は大号泣した。「悪意のない物語」は基本的に好きではないが、この作品は驚くほど私に突き刺さった
孫玉福がもし、戸籍を「日本民族」と書き換えなければ、2人はそのまま中国で暮らしていたことだろう。しかしそうだとすると、「城戸久枝」は生まれていないことになる。現代史の大きなうねりが、個人史として立ち現れるという経験をする機会はなかなかないが、城戸久枝の物語は、そんな疑似体験をさせてくれるのである。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【絶望】知られざる「国による嘘」!映画『蟻の兵隊』(池谷薫)が映し出す終戦直後の日本の欺瞞
映画『蟻の兵隊』は、「1945年8月15日の終戦以降も上官の命令で中国に残らされ、中国の内戦を闘った残留日本軍部隊」の1人である奥村和一を追うドキュメンタリー映画だ。「自らの意思で残った」と判断された彼らは、国からの戦後補償を受けられていない。そんな凄まじい現実と、奥村和一の驚くべき「誠実さ」が描かれる作品である
あわせて読みたい
【SDGs】パリコレデザイナー中里唯馬がファッション界の大量生産・大量消費マインド脱却に挑む映画:『…
映画『燃えるドレスを紡いで』は、世界的ファッションデザイナーである中里唯馬が、「服の墓場」と言うべきナイロビの現状を踏まえ、「もう服を作るのは止めましょう」というメッセージをパリコレの場から発信するまでを映し出すドキュメンタリー映画である。個人レベルで社会を変革しようとする凄まじい行動力と才能に圧倒させられた
あわせて読みたい
【正義】ナン・ゴールディンの”覚悟”を映し出す映画『美と殺戮のすべて』が描く衝撃の薬害事件
映画『美と殺戮のすべて』は、写真家ナン・ゴールディンの凄まじい闘いが映し出されるドキュメンタリー映画である。ターゲットとなるのは、美術界にその名を轟かすサックラー家。なんと、彼らが創業した製薬会社で製造された処方薬によって、アメリカでは既に50万人が死亡しているのだ。そんな異次元の薬害事件が扱われる驚くべき作品
あわせて読みたい
【衝撃】EUの難民問題の狂気的縮図!ポーランド・ベラルーシ国境での、国による非人道的対応:映画『人…
上映に際し政府から妨害を受けたという映画『人間の境界』は、ポーランド・ベラルーシ国境で起こっていた凄まじい現実が描かれている。「両国間で中東からの難民を押し付け合う」という醜悪さは見るに絶えないが、そのような状況下でも「可能な範囲でどうにか人助けをしたい」と考える者たちの奮闘には救われる思いがした
あわせて読みたい
【実話】映画『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』が描く、白人警官による黒人射殺事件
映画『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』は、2011年に起こった実際の事件を元にした作品である。何の罪もない黒人男性が、白人警官に射殺されてしまったのだ。5時22分から始まる状況をほぼリアルタイムで描き切る83分間の物語には、役者の凄まじい演技も含め、圧倒されてしまった
あわせて読みたい
【挑戦】映画『燃えあがる女性記者たち』が描く、インドカースト最下位・ダリットの女性による報道
映画『燃えあがる女性記者たち』は、インドで「カースト外の不可触民」として扱われるダリットの女性たちが立ち上げた新聞社「カバル・ラハリヤ」を取り上げる。自身の境遇に抗って、辛い状況にいる人の声を届けたり権力者を糾弾したりする彼女たちの奮闘ぶりが、インドの民主主義を変革させるかもしれない
あわせて読みたい
【日本】原発再稼働が進むが、その安全性は?樋口英明の画期的判決とソーラーシェアリングを知る:映画…
映画『原発をとめた裁判長 そして原発をとめる農家たち』では、大飯原発の運転差し止め判決を下した裁判長による画期的な「樋口理論」の説明に重点が置かれる。「原発の耐震性」に関して知らないことが満載で、実に興味深かった。また、農家が発案した「ソーラーシェアリング」という新たな発電方法も注目である
あわせて読みたい
【衝撃】ミキ・デザキが映画『主戦場』で示す「慰安婦問題」の実相。歴史修正主義者の発言がヤバすぎ
「慰安婦問題」に真正面から取り組んだ映画『主戦場』は、「『慰安婦問題』の根幹はどこにあるのか?」というその複雑さに焦点を当てていく。この記事では、本作で映し出された様々な情報を元に「慰安婦問題」について整理したものの、結局のところ「解決不可能な問題である」という結論に行き着いてしまった
あわせて読みたい
【歴史】映画『シン・ちむどんどん』は、普天間基地移設問題に絡む辺野古埋め立てを”陽気に”追及する(…
映画『シン・ちむどんどん』は、映画『センキョナンデス』に続く「ダースレイダー・プチ鹿島による選挙戦リポート」第2弾である。今回のターゲットは沖縄知事選。そして本作においては、選挙戦の模様以上に、後半で取り上げられる「普天間基地の辺野古移設問題の掘り下げ」の方がより興味深かった
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『戦場のピアニスト』(ロマン・ポランスキー)が描く、ユダヤ人迫害の衝撃の実話
映画『戦場のピアニスト』の4Kリマスター版を観に行ったところ、上映後のトークイベントに主人公の息子が登壇したので驚いた。何せ私は、本作が「実話を基にしている」ことさえ知らなかったのである。だからその驚きもひとしおだった。ホロコーストの生存者である主人公の壮絶な人生を描き出す、不朽の名作だ
あわせて読みたい
【評価】映画『ゴジラ-1.0』(山崎貴監督)は面白い!迫力満点の映像と絶妙な人間ドラマ(米アカデミー…
米アカデミー賞で視覚効果賞を受賞した映画『ゴジラ-1.0』(山崎貴監督)は、もちろんそのVFXに圧倒される物語なのだが、「人間ドラマ」をきちんと描いていることも印象的だった。「終戦直後を舞台にする」という、ゴジラを描くには様々な意味でハードルのある設定を見事に活かした、とても見事な作品だ
あわせて読みたい
【感想】関東大震災前後を描く映画『福田村事件』(森達也)は、社会が孕む「思考停止」と「差別問題」…
森達也監督初の劇映画である『福田村事件』は、100年前の関東大震災直後に起こった「デマを起点とする悲劇」が扱われる作品だ。しかし、そんな作品全体が伝えるメッセージは、「100年前よりも現代の方がよりヤバい」だと私は感じた。SNS時代だからこそ意識すべき問題の詰まった、挑発的な作品である
あわせて読みたい
【衝撃】ウクライナでのホロコーストを描く映画『バビ・ヤール』は、集めた素材映像が凄まじすぎる
ソ連生まれウクライナ育ちの映画監督セルゲイ・ロズニツァが、「過去映像」を繋ぎ合わせる形で作り上げた映画『バビ・ヤール』は、「単一のホロコーストで最大の犠牲者を出した」として知られる「バビ・ヤール大虐殺」を描き出す。ウクライナ市民も加担した、そのあまりに悲惨な歴史の真実とは?
あわせて読みたい
【驚愕】ベリングキャットの調査報道がプーチンを追い詰める。映画『ナワリヌイ』が示す暗殺未遂の真実
弁護士であり、登録者数640万人を超えるYouTuberでもあるアレクセイ・ナワリヌイは、プーチンに対抗して大統領選挙に出馬しようとしたせいで暗殺されかかった。その実行犯を特定する調査をベリングキャットと共に行った記録映画『ナワリヌイ』は、現実とは思えないあまりの衝撃に満ちている
あわせて読みたい
【驚愕】本屋大賞受賞作『同志少女よ、敵を撃て』(逢坂冬馬)は凄まじい。戦場は人間を”怪物”にする
デビュー作で本屋大賞を受賞した『同志少女よ、敵を撃て』(逢坂冬馬)は、デビュー作であることを抜きにしても凄まじすぎる、規格外の小説だった。ソ連に実在した「女性狙撃兵」の視点から「独ソ戦」を描く物語は、生死の境でギリギリの葛藤や決断に直面する女性たちのとんでもない生き様を活写する
あわせて読みたい
【映画】『戦場記者』須賀川拓が、ニュースに乗らない中東・ウクライナの現実と報道の限界を切り取る
TBS所属の特派員・須賀川拓は、ロンドンを拠点に各国の取材を行っている。映画『戦場記者』は、そんな彼が中東を取材した映像をまとめたドキュメンタリーだ。ハマスを巡って食い違うガザ地区とイスラエル、ウクライナ侵攻直後に現地入りした際の様子、アフガニスタンの壮絶な薬物中毒の現実を映し出す
あわせて読みたい
【知的】「BLって何?」という初心者に魅力を伝える「腐男子」の「BLの想像力と創造力」講座:『ボクた…
「BLは知的遊戯である」という主張には「は?」と感じてしまうでしょうが、本書『ボクたちのBL論』を読めばその印象は変わるかもしれません。「余白の発見と補完」を通じて、「ありとあらゆる2者の間の関係性を解釈する」という創造性は、現実世界にどのような影響を与えているのか
あわせて読みたい
【性加害】映画『SHE SAID その名を暴け』を観てくれ。#MeToo運動を生んだ報道の舞台裏(出演:キャリ…
「#MeToo」運動のきっかけとなった、ハリウッドの絶対権力者ハーヴェイ・ワインスタインを告発するニューヨーク・タイムズの記事。その取材を担った2人の女性記者の奮闘を描く映画『SHE SAID その名を暴け』は、ジャニー喜多川の性加害問題で揺れる今、絶対に観るべき映画だと思う
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』で描かれる、グアンタナモ”刑務所”の衝撃の実話は必見
ベネディクト・カンバーバッチが制作を熱望した衝撃の映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』は、アメリカの信じがたい実話を基にしている。「9.11の首謀者」として不当に拘束され続けた男を「救おうとする者」と「追い詰めようとする者」の奮闘が、「アメリカの闇」を暴き出す
あわせて読みたい
【悲劇】アメリカの暗黒の歴史である奴隷制度の現実を、元奴隷の黒人女性自ら赤裸々に語る衝撃:『ある…
生まれながらに「奴隷」だった黒人女性が、多くの人の協力を得て自由を手にし、後に「奴隷制度」について書いたのが『ある奴隷少女に起こった出来事』。長らく「白人が書いた小説」と思われていたが、事実だと証明され、欧米で大ベストセラーとなった古典作品が示す「奴隷制度の残酷さ」
あわせて読みたい
【選択】特異な疑似家族を描く韓国映画『声もなく』の、「家族とは?」の本質を考えさせる深淵さ
喋れない男が、誘拐した女の子をしばらく匿い、疑似家族のような関係を築く韓国映画『声もなく』は、「映画の中で描かれていない部分」が最も印象に残る作品だ。「誘拐犯」と「被害者」のあり得ない関係性に、不自然さをまったく抱かせない設定・展開の妙が見事な映画
あわせて読みたい
【感涙】映画『彼女が好きなものは』の衝撃。偏見・無関心・他人事の世界から”脱する勇気”をどう持つか
涙腺がぶっ壊れたのかと思ったほど泣かされた映画『彼女が好きなものは』について、作品の核となる「ある事実」に一切触れずに書いた「ネタバレなし」の感想です。「ただし摩擦はゼロとする」の世界で息苦しさを感じているすべての人に届く「普遍性」を体感してください
あわせて読みたい
【証言】ナチスドイツでヒトラーに次ぐナンバー2だったゲッベルス。その秘書だった女性が歴史を語る映画…
ナチスドイツナンバー2だった宣伝大臣ゲッベルス。その秘書だったブルンヒルデ・ポムゼルが103歳の時にカメラの前で当時を語った映画『ゲッベルスと私』には、「愚かなことをしたが、避け難かった」という彼女の悔恨と教訓が含まれている。私たちは彼女の言葉を真摯に受け止めなければならない
あわせて読みたい
【狂気】”友好”のために北朝鮮入りした監督が撮った映画『ザ・レッド・チャペル』が映す平壌の衝撃
倫理的な葛藤を物ともせず、好奇心だけで突き進んでいくドキュメンタリー監督マッツ・ブリュガーが北朝鮮から「出禁」を食らう結果となった『ザ・レッド・チャペル』は、「友好」を表看板に北朝鮮に潜入し、その「日常」と「非日常」を映し出した衝撃作
あわせて読みたい
【憤り】世界最強米海軍4人VS数百人のタリバン兵。死線を脱しただ1人生還を果たした奇跡の実話:『アフ…
アフガニスタンの山中で遭遇した羊飼いを見逃したことで、数百人のタリバン兵と死闘を繰り広げる羽目に陥った米軍最強部隊に所属する4人。奇跡的に生き残り生還を果たした著者が記す『アフガン、たった一人の生還』は、とても実話とは信じられない凄まじさに満ちている
あわせて読みたい
【アメリカ】長崎の「原爆ドーム」はなぜ残らなかった?爆心地にあった「浦上天主堂」の数奇な歴史:『…
原爆投下で半壊し、廃墟と化したキリスト教の大聖堂「浦上天主堂」。しかし何故か、「長崎の原爆ドーム」としては残されず、解体されてしまった。そのため長崎には原爆ドームがないのである。『ナガサキ 消えたもう一つの「原爆ドーム」』は、「浦上天主堂」を巡る知られざる歴史を掘り下げ、アメリカの強かさを描き出す
あわせて読みたい
【理解】小野田寛郎を描く映画。「戦争終結という現実を受け入れない(=認知的不協和)」は他人事じゃ…
映画『ONODA 一万夜を越えて』を観るまで、小野田寛郎という人間に対して違和感を覚えていた。「戦争は終わっていない」という現実を生き続けたことが不自然に思えたのだ。しかし映画を観て、彼の生き方・決断は、私たちと大きく変わりはしないと実感できた
あわせて読みたい
【衝撃】『ゆきゆきて、神軍』はとんでもないドキュメンタリー映画だ。虚実が果てしなく入り混じる傑作
奥崎謙三という元兵士のアナーキストに密着する『ゆきゆきて、神軍』。ドキュメンタリー映画の名作として名前だけは知っていたが、まさかこんなとんでもない映画だったとはと驚かされた。トークショーで監督が「自分の意向を無視した編集だった」と語っていたのも印象的
あわせて読みたい
【弾圧】香港デモの象徴的存在デニス・ホーの奮闘の歴史。注目の女性活動家は周庭だけじゃない:映画『…
日本で香港民主化運動が報じられる際は周庭さんが取り上げられることが多いが、香港には彼女よりも前に民主化運動の象徴的存在として認められた人物がいる。映画『デニス・ホー ビカミング・ザ・ソング』の主人公であるスター歌手の激動の人生を知る
あわせて読みたい
【感想】映画『野火』は、戦争の”虚しさ”をリアルに映し出す、後世に受け継がれるべき作品だ
「戦争の悲惨さ」は様々な形で描かれ、受け継がれてきたが、「戦争の虚しさ」を知る機会はなかなかない。映画『野火』は、第二次世界大戦中のフィリピンを舞台に、「敵が存在しない戦場で”人間の形”を保つ困難さ」を描き出す、「虚しさ」だけで構成された作品だ
あわせて読みたい
【実話】映画『イミテーションゲーム』が描くエニグマ解読のドラマと悲劇、天才チューリングの不遇の死
映画『イミテーションゲーム』が描く衝撃の実話。「解読不可能」とまで言われた最強の暗号機エニグマを打ち破ったのはなんと、コンピューターの基本原理を生み出した天才数学者アラン・チューリングだった。暗号解読を実現させた驚きのプロセスと、1400万人以上を救ったとされながら偏見により自殺した不遇の人生を知る
あわせて読みたい
【史実】太平洋戦争末期に原爆を落としたアメリカは、なぜ終戦後比較的穏やかな占領政策を取ったか?:…
『八月十五日に吹く風』は小説だが、史実を基にした作品だ。本作では、「終戦直前に原爆を落としながら、なぜ比較的平穏な占領政策を行ったか?」の疑問が解き明かされる。『源氏物語』との出会いで日本を愛するようになった「ロナルド・リーン(仮名)」の知られざる奮闘を知る
あわせて読みたい
【リアル】社会の分断の仕組みを”ゾンビ”で学ぶ。「社会派ゾンビ映画」が対立の根源を抉り出す:映画『C…
まさか「ゾンビ映画」が、私たちが生きている現実をここまで活写するとは驚きだった。映画『CURED キュアード』をベースに、「見えない事実」がもたらす恐怖と、立場ごとに正しい主張をしながらも否応なしに「分断」が生まれてしまう状況について知る
あわせて読みたい
【映画】『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』で号泣し続けた私はTVアニメを観ていない
TVアニメは観ていない、というかその存在さえ知らず、物語や登場人物の設定も何も知らないまま観に行った映画『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』に、私は大号泣した。「悪意のない物語」は基本的に好きではないが、この作品は驚くほど私に突き刺さった
あわせて読みたい
【現実】戦争のリアルを”閉じ込めた”映画。第一次世界大戦の英軍を収めたフィルムが描く衝撃:映画『彼…
第一次世界大戦でのイギリス兵を映した膨大な白黒フィルムをカラー化して編集した『彼らは生きていた』は、白黒の映像では実感しにくい「リアルさ」を強く感じられる。そして、「戦争は思ったよりも安易に起こる」「戦争はやはりどこまでも虚しい」と実感できる
あわせて読みたい
【無知】メディアの問題の本質は?「報道の限界」と「情報の受け取り方」を独裁政治の現実から知る:『…
メディアは確かに「事実」を報じている。しかし、報道に乗らない情報まで含めなければ、本当の意味で世の中を理解することは難しいと、『こうして世界は誤解する』は教えてくれる。アラブ諸国での取材の現実から、報道の「限界」と「受け取り方」を学ぶ
あわせて読みたい
【衝撃】壮絶な戦争映画。最愛の娘を「産んで後悔している」と呟く母らは、正義のために戦場に留まる:…
こんな映画、二度と存在し得ないのではないかと感じるほど衝撃を受けた『娘は戦場で生まれた』。母であり革命家でもあるジャーナリストは、爆撃の続くシリアの街を記録し続け、同じ街で娘を産み育てた。「知らなかった」で済ませていい現実じゃない。
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
国家・政治・制度・地方【本・映画の感想】 | ルシルナ
私たちがどのような社会で生きているのか理解することは重要でしょう。ニュースやネット記事などを総合して現実を理解することはなかなか難しいですが、政治や社会制度など…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…





















































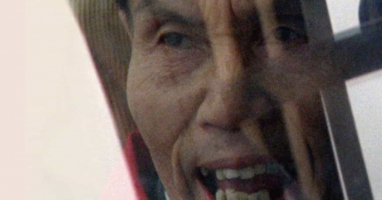



















コメント