目次
はじめに
この記事で取り上げる映画
監督:森達也, プロデュース:安岡卓治
¥400 (2023/12/10 23:28時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
この映画をガイドにしながら記事を書いていきます
この記事の3つの要点
- 私は当時の凄まじい過熱報道を知っているが、それを知らないだろう若者は、映画『A』を一体どのように受け取るのだろうか?
- 信者をフラットに映し出すからこそ、「カルト宗教」という印象が少しずつ薄れていく
- 信者が様々に語る、「自身の信仰心」と、「オウム真理教に留まることの葛藤」
ある意味で「時代が生み出したドキュメンタリー映画」とも言えるわけで、同じような衝撃をもたらす作品はもう作れないかもしれない
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
記事中の引用は、映画館で取ったメモを参考にしているので、正確なものではありません
あわせて読みたい
【全作品視聴済】おすすめの森達也の本・映画、そしてオウム真理教を扱った本・映画【随時更新】
今まで私が触れてきた4000冊の本と1000本の映画の中から、森達也の作品、そしてオウム真理教を扱った作品をオススメします。特異な存在感を放つ映画監督・森達也と、日本近現代史における異質な存在であるオウム真理教に関する作品を併せてセレクトしてみました。是非本・映画選びの参考にして下さい。
ドキュメンタリー映画の傑作として知られる『A』(森達也)は、「当たり前」を疑わせ、あっさりと反転させるような凄まじい力を持っている
あわせて読みたい
【あらすじ】原爆を作った人の後悔・葛藤を描く映画『オッペンハイマー』のための予習と評価(クリスト…
クリストファー・ノーラン監督作品『オッペンハイマー』は、原爆開発を主導した人物の葛藤・苦悩を複雑に描き出す作品だ。人間が持つ「多面性」を様々な方向から捉えようとする作品であり、受け取り方は人それぞれ異なるだろう。鑑賞前に知っておいた方がいい知識についてまとめたので、参考にしてほしい
まさか、森達也の『A』を観られる機会がくるとは思わなかった。もちろん、何かサブスクを登録すればいいのだろうが、「映画館で上映している作品しか観ない」というルールを課している私には、その機会があるとは思えなかったのだ。そして、やはり観て良かったと思う。

ちなみに私は、森達也が映画『A』を撮っていた時のことを自身でまとめた『A』という本を読んだことがある。そちらの記事は別途書いているので、合わせて読んでいただくといいだろう。
あわせて読みたい
【加虐】メディアの役割とは?森達也『A』が提示した「事実を報じる限界」と「思考停止社会」
オウム真理教の内部に潜入した、森達也のドキュメンタリー映画『A』は衝撃を与えた。しかしそれは、宗教団体ではなく、社会の方を切り取った作品だった。思考することを止めた社会の加虐性と、客観的な事実など切り取れないという現実について書く
さていきなりだが、M-1グランプリの話をしようと思う。普通に考えて、ドキュメンタリー映画『A』の話と繋がるとは到底思えないだろう。しかし、『A』を観たのが2022年のM-1グランプリの翌日だったこともあり、映画を観ながら、お笑いコンビ・さや香が決勝で披露したネタのことが頭に浮かんだのである。
そのネタは、「男女の友情は成立するか」がテーマだった。一方が「男女の友情は成立する」と主張し、「長年友人関係にある女性がいる」と口にするところから始まっていく。その後もう一方が、「大人の関係はないんだな」とツッコむと、それに対して「一度だけ」と答えるのだ。そして、「一度でもあったらもはや友情ではないだろう」と指摘しながら、「『男女の友情は成立する』と主張する男」のおかしさを追及する展開が続いていくという流れになる。
しかし面白いことに、後半になると逆に、それまで糾弾する立場だった側が、いつの間にか糾弾されているという展開になっていく。そのスライドのさせ方がとても見事だった。錯視画像として有名な「ルビンの壺」でも見ているかのように、白黒が逆転していく様が短い漫才の中に凝縮されていたと言える。
そして私は『A』を観て、さや香のこの漫才を観た時のような感覚になったのだ。ほんの僅かな「見方の違い」によって、物事の捉え方がまったく変わっていくからである。
あわせて読みたい
【不謹慎】コンプライアンス無視の『テレビで会えない芸人』松元ヒロを追う映画から芸と憲法を考える
かつてテレビの世界で大ブレイクを果たしながら、現在はテレビから完全に離れ、年間120もの公演を行う芸人・松元ヒロ。そんな知る人ぞ知る芸人を追った映画『テレビで会えない芸人』は、コンプライアンスに厳しく、少数派が蔑ろにされる社会へ一石を投じる、爆笑社会風刺である
「『オウム真理教』の凄まじい報道合戦」を知らない世代は、『A』をどう観るのか
私はポレポレ東中野という映画館で『A』を観たのだが、その上映は、大島新というドキュメンタリー映画監督が、自著の出版に合わせてドキュメンタリー映画の名作の再上映を企画したものだった。上映前に25分程度、森達也と大島新のトークショーが行われるという趣向である。そしてその中で大島新は、『A』を異なるタイミングで観たことによる「印象の違い」について語っていた。
あわせて読みたい
【感涙】衆議院議員・小川淳也の選挙戦に密着する映画から、「誠実さ」と「民主主義のあり方」を考える…
『衆議院議員・小川淳也が小選挙区で平井卓也と争う選挙戦を捉えた映画『香川1区』は、政治家とは思えない「誠実さ」を放つ”異端の議員”が、理想とする民主主義の実現のために徒手空拳で闘う様を描く。選挙のドキュメンタリー映画でこれほど号泣するとは自分でも信じられない
最初に観たのは、まだポレポレ東中野という名前になる前の「BOX東中野」という映画館でのことだったという。大島新は、
大げさではなく、椅子から立ち上がれないほどのショックを受けた。
と語っていた。この時は恐らく、オウム真理教がまだメディアで大きく取り上げられていた時期だったのではないかと思う。また、詳しい事情には触れなかったが、彼は「『A』を観たことがフジテレビを辞めるきっかけになった」とも言っていた。それほどまでに衝撃を受けたというわけだ。
その後大島新はドキュメンタリー作家となり、そして改めて『A』を観る機会を得た。そしてその際の感想として彼は、「実にオーソドックスな取材をされていますよね」と森達也に語るのである。上映前にトークショーが行われたこともあり、この時点では私には分からなかったわけだが、その後映画本編を観たことで、私も同様に「確かにオーソドックスな取材をしている」と感じた。
あわせて読みたい
【誠実】映画『なぜ君は総理大臣になれないのか』で長期密着した政治家・小川淳也の情熱と信念が凄まじい
政治家・小川淳也に17年間も長期密着した映画『なぜ君は総理大臣になれないのか』は、誠実であるが故に大成できない1人の悩める政治家のありのままが描かれる。サラリーマン家庭から政治家を目指し、未来の日本を健全にするために奮闘する男の信念と情熱が詰まった1本
さてここでの疑問は、同じ映画を観たにも拘らず、「椅子から立ち上がれないほどのショック」を受けたこともあれば、「オーソドックスな取材をしている」と感じたこともあるという点だ。もちろん、「初見のインパクト」は関係していると思う。しかし決してそれだけではないはずだ。というのも、トークイベントの中で2人とも語っていたことだが、とにかく「オウム真理教のメディアでの取り上げられ方」が凄まじかったのである。特に地下鉄サリン事件の時などは、「オウム真理教は問答無用で絶対悪」という感じだったし、朝から晩までありとあらゆるメディアがオウム真理教のことを流し続けていたのだ。そのような状態が、半年から1年ぐらい続いていたように思う。

想像してみてほしい。メディアでは、「オウム真理教は極悪非道だ」というニュースが連日連夜報じられている。オウム真理教の信者と見れば「犯罪者だ」とでも言わんばかりの扱いを、メディアがしていたのだ。そういう状況下で、「オーソドックスな取材」をしている『A』を観たらどう感じるだろうか。やはり、「椅子から立ち上がれないほどのショックを受ける」のではないかと思う。
映画『A』にはそもそも、このような特異性があったと言っていいだろう。そしてそう考えると、「オウム真理教を巡る凄まじい報道合戦を知らないはずの若い世代は、『A』を一体どのように捉えるのだろうか?」という点がとても疑問に感じられる。
あわせて読みたい
【衝撃】森達也『A3』が指摘。地下鉄サリン事件を起こしたオウム真理教は社会を激変させた
「オウム真理教は特別だ、という理由で作られた”例外”が、いつの間にか社会の”前提”になっている」これが、森達也『A3』の主張の要点だ。異常な状態で続けられた麻原彰晃の裁判を傍聴したことをきっかけに、社会の”異様な”変質の正体を理解する。
トークショーの中で2人は観客に向かって、「『A』を初めて観る方はどれぐらいいますか?」と質問していた。壇上からは若い人が多いように見えたらしく、初見なのかどうか確認したくなったのだろう。そして私を含め、観客の多くが手を挙げていた。
40歳を超えている私は、オウム真理教に関する凄まじい報道をリアルタイムで経験している。私の場合は特に、出身が静岡県なので、余計に苛烈な報道に接していたはずだと思う。教団施設があった上九一色村や富士宮市は、私の地元からかなり近いのだ。他の地域のことは知らないが、たぶん静岡県では他の地域にも増してオウム真理教が大きく取り上げられていたのではないかと思う。
また、これは個人的な関わりでしかないのだが、オウム真理教は私のライフイベントとも絡んでさらに強く記憶に残っている。私は自分の過去の記憶をスパスパ忘れてしまうので、正直子どもの頃のことなどほとんど覚えていない。しかし、「地下鉄サリン事件が起こった日に小学校の卒業式だったこと」、そして、「麻原彰晃が逮捕された日に中学校の遠足があったこと」は何故か覚えているのだ。
あわせて読みたい
【誠実】地下鉄サリン事件の被害者が荒木浩に密着。「贖罪」とは何かを考えさせる衝撃の映画:『AGANAI…
私には、「謝罪すること」が「誠実」だという感覚がない。むしろ映画『AGANAI 地下鉄サリン事件と私』では、「謝罪しない誠実さ」が描かれる。被害者側と加害者側の対話から、「謝罪」「贖罪」の意味と、信じているものを諦めさせることの難しさについて書く
その後も、「9.11」や「東日本大震災」など、世界の歴史に刻まれるだろう様々な出来事が起こり、メディアで報じられたわけだが、やはり私の中では「地下鉄サリン事件」「オウム真理教」は非常に強烈な記憶として残っている。事件に優劣もないのだが、オウム真理教はやはり別格の存在なのだ。
その背景には間違いなく、「テレビ」の存在が大きく関係していると思う。私が子どもの頃は、今とは比べ物にならないほどテレビの力が強かったはずだからだ。というか、テレビしかなかったのである。
現代は、YouTubeや各種SNSなど、メディアと呼ばれる存在が山ほど氾濫している時代だ。それはつまり、「『みんなが同じものを見ている』という状態がほとんど存在しなくなった」ことを意味するだろう。確かに、情報の収集という意味ではとても良い変化だと言える。もちろん、デマも増えたわけで、これまで以上にリテラシーが求められる時代にもなっただろう。しかし、きちんとしたリテラシーさえ持てるのであれば、多種多様な情報に触れられる環境はとても良いと感じている。
あわせて読みたい
【異様】ジャーナリズムの役割って何だ?日本ではまだきちんと機能しているか?報道機関自らが問う映画…
ドキュメンタリーで定評のある東海テレビが、「東海テレビ」を被写体として撮ったドキュメンタリー映画『さよならテレビ』は、「メディアはどうあるべきか?」を問いかける。2011年の信じがたいミスを遠景にしつつ、メディア内部から「メディアの存在意義」を投げかける
しかし、一昔前は違った。メディアと言えばテレビか新聞か雑誌ぐらいしかなかったわけだし、やはり私が子どもの頃には、その中でも圧倒的にテレビが強かったはずだ。だから、社会で何か起これば、みんなテレビを観た。そして他に情報を得るツールなど存在しないのだから、当然、「テレビでどう報じられたか(あるいは報じられなかったか)」こそが世論の形成に最も大きな影響を与えたはずだと思う。
当時のテレビは、オウム真理教を「絶対悪」として映し出し続けた。それは当然の判断だっただろうとは思う。しかし、『A』はまったく異なる手法を取った。森達也は、「オーソドックスな取材」を通じて、善悪の判断を入れ込まない視点でオウム真理教を捉えたのだ。大島新が感じた「椅子から立ち上がれないほどのショック」は、「オウム真理教を『絶対悪』として描かないスタイル」や「オウム真理教を『絶対悪』だと思い込んでいた自身のあり方」に対してのものだろう。オウム真理教の凄まじい報道をリアルタイムで体感した私にも、彼のその「ショック」はとてもよく理解できた。

あわせて読みたい
【感想】関東大震災前後を描く映画『福田村事件』(森達也)は、社会が孕む「思考停止」と「差別問題」…
森達也監督初の劇映画である『福田村事件』は、100年前の関東大震災直後に起こった「デマを起点とする悲劇」が扱われる作品だ。しかし、そんな作品全体が伝えるメッセージは、「100年前よりも現代の方がよりヤバい」だと私は感じた。SNS時代だからこそ意識すべき問題の詰まった、挑発的な作品である
そしてだからこそ私は、当時のすさまじい報道を知らない若い世代が、映画『A』を観てどう感じるのかにとても興味がある。「何が凄いのか分からない」という感覚になるのではないかという気がするからだ。
それは、私が黒澤明監督作の映画『七人の侍』を観た時の感想に近いと思う。「不朽の名作」と言われるような作品だということぐらいは知っていたので、以前映画館で観たことがある。4時間もある映画だということさえ知らなかったのでその点には驚かされたが、映画を観終えた私は、「この映画の何が凄いのか、さっぱり理解できない」と感じたのだ。
その後『七人の侍』について調べ、ようやく状況が理解できた。『七人の侍』はなんと、「私たちが今当たり前のように触れている物語の『フォーマット』を生み出した作品」らしいのだ。つまり『七人の侍』が上映された時には、そんな「物語のフォーマット」など存在しなかったのである。そりゃあ驚くのも当然だろう。しかし私たちは既に、黒澤明が生み出した「物語のフォーマット」を当たり前のものとして受け取っている。だから私には、『七人の侍』の凄さが分からなかったというわけだ。
あわせて読みたい
【無知】メディアの問題の本質は?「報道の限界」と「情報の受け取り方」を独裁政治の現実から知る:『…
メディアは確かに「事実」を報じている。しかし、報道に乗らない情報まで含めなければ、本当の意味で世の中を理解することは難しいと、『こうして世界は誤解する』は教えてくれる。アラブ諸国での取材の現実から、報道の「限界」と「受け取り方」を学ぶ
同じことが、「オウム真理教の凄まじい報じられ方を知らない若者」にも起こり得るのではないかと、私は『A』を観ながら感じたのである。
「切り取り方」によって印象はこれほどまでに変わる
冒頭で私は、さや香の漫才のネタの話をした。ざっくり要約すれば、「『明らかに間違っている』と思われていた側が実は正しく、『明らかに正しい』と思われていた側が実は間違っていた」という状況を実に上手く描き出し、漫才のネタに昇華していた、という内容である。
そしてまさに同じような感覚を、映画『A』を観ながらも実感出来るはずだ。
あわせて読みたい
【衝撃】洗脳を自ら脱した著者の『カルト脱出記』から、「社会・集団の洗脳」を避ける生き方を知る
「聖書研究に熱心な日本人証人」として「エホバの証人」で活動しながら、その聖書研究をきっかけに自ら「洗脳」を脱した著者の体験を著した『カルト脱出記』。広い意味での「洗脳」は社会のそこかしこに蔓延っているからこそ、著者の体験を「他人事」だと無視することはできない
先ほどから書いている通り、地下鉄サリン事件を起こしたオウム真理教は、メディアを通じて「絶対悪」のような描かれ方をしていた。もちろん、実行犯に非があることは当然なのだが、当時は「オウム真理教に関するすべて」が「極悪非道」であるかのように受け取られていたのだ。
一方、観れば分かるが、映画『A』において森達也は、実にフラットにオウム真理教信者と関わっている。まさに「オーソドックスな取材」というわけだ。信者を良く捉えることもない代わりに、悪く捉えることもない。世間が「オウム真理教」のことで大騒ぎしている時に、信者たちがどのように生活しているのかをそのまま映し出しているのだ。これだけで、当時の報道を知る人間からすれば「驚愕のドキュメンタリー」という捉え方になる。
さて、ここで少し、映画『A』の誕生の経緯に触れておこう。
元々は、フジテレビの番組の企画として始まったのだそうだ。そして、共同テレビジョンという制作会社に勤務する一介のサラリーマンだった森達也は、この企画に関わることになった。しかし撮影が始まって2日後、フジテレビと共同テレビジョンは議論を行ったという。何についてか。それは、森達也が撮ってくる映像についてである。
あわせて読みたい
【デマ】情報を”選ぶ”時代に、メディアの情報の”正しさ”はどのように判断されるのか?:『ニューヨーク…
一昔前、我々は「正しい情報を欲していた」はずだ。しかしいつの間にか世の中は変わった。「欲しい情報を正しいと思う」ようになったのだ。この激変は、トランプ元大統領の台頭で一層明確になった。『ニューヨーク・タイムズを守った男』から、情報の受け取り方を問う
「オウム真理教が悪く描かれていないじゃないか」と問題視されたのだ。
当時の報道を記憶している身からすれば、その感覚も分からないではない。当時はどのテレビ番組を観ても、「オウム真理教は絶対悪だ」と声高に訴える内容のものばかりであり、「良く描く報道」どころか「悪く描かない報道」さえ一切なかった。現代であれば、テレビが行き過ぎた報道をした場合、ネット上で「あれはおかしい」「やり過ぎだ」などと言った声が上がったりもするだろう。様々なメディアの報道を総合的に判断するなら、昔よりは「一面的な捉え方」は減ったと言えるかもしれない。しかし、テレビが強い影響力を持っていた時代には、「テレビが描いた姿こそが真実である」みたいな雰囲気がどこか社会にあったと思う。そして、当時のテレビは揃いも揃って「オウム真理教は極悪非道だ」とやっていたのだから、そんなオウム真理教を「悪く描いていない」というだけでも、十分「問題視」される理由になるというわけだ。

議論の末、森達也が関わっていた企画の中止が決まった。しかし森達也はなんと、休日を使って独自に撮影を継続したのだ。そして、そのことが会社にバレてクビになったため、どうにか「自主制作のドキュメンタリー映画」として完成させたのが『A』なのである。ある意味で、「『当時のマスコミの風潮』が生んだ作品」と言っていいだろうと思う。
あわせて読みたい
【実話】ソ連の衝撃の事実を隠蔽する記者と暴く記者。映画『赤い闇』が描くジャーナリズムの役割と実態
ソ連の「闇」を暴いた名もなき記者の実話を描いた映画『赤い闇』は、「メディアの存在意義」と「メディアとの接し方」を問いかける作品だ。「真実」を届ける「社会の公器」であるべきメディアは、容易に腐敗し得る。情報の受け手である私たちの意識も改めなければならない
さて、ここで少し、映画『A』の中身について触れておこう。『A』はとにかく、オウム真理教をその内部から映し出したドキュメンタリーである。森達也は、逮捕された上祐史浩に代わって広報の責任者の立場にいた荒木浩という信者と連絡を取り、彼に密着していた。そしてその過程で教団施設の内部にも入り込み、そこで生活する信者の普段の様子もカメラに収めていくのである。基本的にはそのような内容の作品だ。
これだけでも十分凄いのだが、より特徴的だったのは、「オウム真理教の内部から、『マスコミ』や『世間』を切り取ったこと」だろう。当時マスコミの人間で、オウム真理教の教団施設への出入りが許されていたのは森達也だけだったはずだ。というか、書籍の方の『A』には、「教団内部を撮らせて欲しいと荒木浩に願い出たのが森達也だけだった」みたいに書かれていた。まあ確かに普通の人間なら、「教団内部に入り込むことなど無理だろう」と考えて、依頼さえしないとは思う。
さて当然のことながら、「荒木浩に密着する」のであれば必然的に、「荒木浩が対応しているマスコミも撮る」ことになってしまうだろう。そして、森達也がトークショーの中で、
マスコミの醜悪さを殊更に暴き立てるつもりなどなかった。
と語っているのが皮肉に感じられるくらい、映画はまさに「マスコミの醜悪さ」が如実に浮かび上がるような作品に仕上がっていると言える。少し前に行われた、ジャニー喜多川の性加害を認めた旧ジャニーズ事務所の記者会見においても「マスコミの醜悪さ」が露呈したが、もしもその様子を旧ジャニーズ事務所側から撮影するカメラがあったとしたら、それこそが森達也の視点だったと考えればいいだろう。相当特異な状況でカメラを回していたと言っていいと思う。
あわせて読みたい
【真実?】佐村河内守のゴーストライター騒動に森達也が斬り込んだ『FAKE』は我々に何を問うか?
一時期メディアを騒がせた、佐村河内守の「ゴースト問題」に、森達也が斬り込む。「耳は聴こえないのか?」「作曲はできるのか?」という疑惑を様々な角度から追及しつつ、森達也らしく「事実とは何か?」を問いかける『FAKE』から、「事実の捉え方」について考える
オウム真理教に関する当時の報道に触れていた私は、当然、「オウム真理教は絶対悪だ」と考える側の人間だ。今でも、基本的にはそう考えている。しかし、映画『A』を観て改めて、「私は漠然と、『オウム真理教』を広く捉えすぎていた」と思い知らされた。確かに、地下鉄サリン事件などの犯罪事件を計画・実行した者たちは「絶対悪」であり、その判断に躊躇はない。しかし一方で、「上層部の計画など何も知らずに、ただオウム真理教に所属していた信者」までもが「絶対悪」なのかについては、判断を保留する必要があるだろう。そして私は、あまりに苛烈な報道に触れていたためにその両者を混同してしまい、「どちらも絶対悪だ」と捉えていたことに気付かされたのだ。
そしてそのように感じさせられたことで、「もしかしたら『悪』なのはマスコミの方なのではないか?」という視点さえ生まれた。まさにさや香のネタのような状況である。森達也はその後も、「マスコミが描き出す『正義』は本当に正しいのか?」という視点からドキュメンタリーを多く制作しているが、映画『A』はまさにそのことを痛烈に突きつける1作だったと思う。
さて、書籍の『A』に書かれていたが、森達也は荒木浩との撮影交渉において、「モザイクは一切つけない」という条件を強固に押し通したそうだ。その理由については『A』の記事を読んでほしいが、そういうスタンスで制作した映画だからこそ、当然、森達也のカメラに映るマスコミ人にもモザイクは掛けられていない。この点について、トークショーの中で面白いやり取りがあった。
発端は、大島新が「映画の中に映っているマスコミ関係者から文句を言われたことはないんですか?」と質問したことだ。森達也はそれに対して「直接的にはない」とまずは返答した。しかし、文句というわけではない「言及」は色々とあったそうだ。例えば初対面の相手と雑談をしている時に、「私、実は『A』に少しだけ出ているんですよね」と言われたり、あるいは飲みの席で「身内(マスコミ)に刃物を突きつけやがって」と笑いながら突っかかられたりしたことはあるという。森達也の関心は「オウム真理教」にあったわけだが、結果として作品のメイン級のテーマになってしまった「マスコミ」の存在が、映画『A』においていかに大きいのかを実感させるエピソードと言えるだろう。
あわせて読みたい
【絶望】権力の濫用を止めるのは我々だ。映画『新聞記者』から「ソフトな独裁国家・日本」の今を知る
私個人は、「ビジョンの達成」のためなら「ソフトな独裁」を許容する。しかし今の日本は、そもそも「ビジョン」などなく、「ソフトな独裁状態」だけが続いていると感じた。映画『新聞記者』をベースに、私たちがどれだけ絶望的な国に生きているのかを理解する

信者たちのフラットなスタンス
さて、誤解されないように先に書いておくが、私は「日本犯罪史に残る凶悪事件を起こしたこと」に対するオウム真理教という組織の責任は、どんな弁解をしようが免れようがないと考えている。まあ当然だろう。また、麻原彰晃が裁判で何も語らなかったため結果的には何も明らかにはならなかったものの、「地下鉄サリン事件を始めとする凶悪事件が、麻原彰晃の指示の元で行われたこと」もまた間違いないだろうと考えている。つまり、「オウム真理教という組織だけではなく、麻原彰晃の近くにいて、計画の片棒を担いだり、あるいは実行犯にはなっていないが計画を知っていた者たちも、責任を回避することなど出来るはずがない」というのが私の考えだ。
あわせて読みたい
【称賛】生き様がかっこいい。ムンバイのホテルのテロ事件で宿泊客を守り抜いたスタッフたち:映画『ホ…
インドの高級ホテルで実際に起こったテロ事件を元にした映画『ホテル・ムンバイ』。恐ろしいほどの臨場感で、当時の恐怖を観客に体感させる映画であり、だからこそ余計に、「逃げる選択」もできたホテルスタッフたちが自らの意思で残り、宿泊を助けた事実に感銘を受ける
しかし一方で、「ただオウム真理教に属していただけの人」を同罪と捉えるのは無理があるとも考えている。いや、やはり、「オウム真理教が凶悪事件を起こしたことを知った上で入信した人」のことは、ちょっと好意的には受け取れないかもしれない。しかし、「凶悪事件を起こす前の時点で既に入信していた人」は、どちらかと言えば「被害者」ではないかと思う。まあ、凶悪事件を起こそうが起こすまいが、私は「宗教」全般に対する嫌悪感を強く抱いてしまうタイプなので、どんな宗教であれ「熱心な信者」みたいな人はあまり好きになれない。ただその話は一旦脇に置いて、「『凶悪事件を起こしたオウム真理教』と『オウム真理教の信者』は基本的に切り離して考えているつもりだ」という主張である。
この考えに賛同できない人もいるだろうが、とりあえずこの記事は、私のそのようなスタンスを前提に書かれたものとして読んでほしい。
「映画『A』では、信者たちの普段の生活がそのまま映し出されている」と書いたが、それらを見て感じた印象は「真面目な努力家」である。森達也は一般信者にインタビューも行っており、彼らがどのような価値観の中で生きているのかについても質問していた。多くの信者が、「修行によってあらゆる欲を手放し、カルマの解放を目指す」みたいなことを口にするのだが、その意味は私には良く分からない。ただ、「自身が目指すべきと考える目標が明確に存在している」「その目標に向かって努力を惜しむつもりがない」という意味で、非常に真面目で誠実な人たちであるように私の目には映った。
特に印象的に感じられたのは、「『してはいけないこと』が非常に少ないように見えた」ことだ。以前、カズレーザーが司会を務める教養番組『カズレーザーと学ぶ。』で「マインドコントロール」が扱われていたのだが、その中で、「一般的な宗教」と「カルト宗教」の違いについて触れられていた。カルト宗教の特徴は「社会と無理やり断絶させる」ことだそうで、「様々な『制約』を与えることによって家族や社会との繋がりを絶たせ、孤立状態にさせることで、思考を硬直させる」というのがよくあるやり方なのだそうだ。
あわせて読みたい
【感想】才能の開花には”極限の環境”が必要か?映画『セッション』が描く世界を私は否定したい
「追い込む指導者」が作り出す”極限の環境”だからこそ、才能が開花する可能性もあるとは思う。しかし、そのような環境はどうしても必要だろうか?最高峰の音楽院での壮絶な”指導”を描く映画『セッション』から、私たちの生活を豊かにしてくれるものの背後にある「死者」を想像する
そういう観点で捉えた場合、オウム真理教には「制約」はかなり少ないように思えた。もちろん、「殺生はしてはいけない」など、教義によって定められた大枠の「制約」は存在するはずだ。しかし、それさえ守っていれば、信者たちの行動や思考を縛り付けるものはほとんど無いように見えた。本当に「自由意志でそこにいる」という印象を与える人物がとても多かったことが印象的だったと言える。
「してはいけないこと」に関しては、次のシーンが一番興味深かった。森達也がある信者に向かって、こんな質問をする場面でのことだ。
仮の話ですけど、(逮捕された)麻原彰晃が土下座して「自分だけは助けてくれ」と命乞いをしたって情報が入ってきたとしたらどうですか?
この質問に対して信者は、森達也と以下のようなやり取りをする。
あわせて読みたい
【狂気】入管の収容所を隠し撮りした映画『牛久』は、日本の難民受け入れ問題を抉るドキュメンタリー
映画『牛久』は、記録装置の持ち込みが一切禁じられている入管の収容施設に無許可でカメラを持ち込み、そこに収容されている難民申請者の声を隠し撮りした映像で構成された作品だ。日本という国家が、国際標準と照らしていかに酷い振る舞いをしているのかが理解できる衝撃作である
それでも、全然大丈夫ですね。
――それは、そういう情報を信じないということ? それとも、信じた上でも大丈夫ということ?
もし自分の目の前で土下座したとしても、僕の考えは変わらないです。最終的な解脱に導いてくれるのは、尊師しかいないと確信しているので。
さて、この信者の発言・考え方そのものはかなり「狂信的」に思えるし、ちょっと受け入れがたいと感じた。ただ私が気になったのは、「もし自分の目の前で土下座したとしても」という発言だ。私がなんとなくイメージする「カルト宗教」では、このような発言をすること自体が許容されないような印象がある。つまり、「誰かから『教祖が土下座して助けを乞うたとしたら?』と問われた場合には、『教祖は土下座などするはずがない』と強く否定しなければならない」みたいな雰囲気があるのではないかと思っているのだ。そんな風に「思考を限定させる環境」の中に信者を置くことによって、「カルト宗教」は成り立っているのだと私はイメージしているのである。

しかし、映画『A』で映し出される信者からは、そのような雰囲気をまったく感じなかったのだ。
あわせて読みたい
【おすすめ】江戸川乱歩賞受賞作、佐藤究『QJKJQ』は、新人のデビュー作とは思えない超ド級の小説だ
江戸川乱歩賞を受賞した佐藤究デビュー作『QJKJQ』はとんでもない衝撃作だ。とても新人作家の作品とは思えない超ド級の物語に、とにかく圧倒されてしまう。「社会は『幻想』を共有することで成り立っている」という、普段なかなか意識しない事実を巧みにちらつかせた、魔術のような作品
他にもこんな場面があった。映画では森達也が、麻原彰晃が逮捕された後に代表代行を務めた村岡達子に、
(地下鉄サリン事件などの)事件に(教団の)関与があったんだって思いますか?
と質問している。
それに対して彼女は、
今は「あったかもしれない」ぐらいにしか言えない。ただ、林さんの証言なんかを聞いているとかなり具体的で、だから林さんはきっとそういう行為を実際に行ったんだろうなと。
と答えていたのだ。
あわせて読みたい
【葛藤】正義とは何かを突きつける戦争映画。80人を救うために1人の少女を殺すボタンを押せるか?:『ア…
「80人の命を救うために、1人の少女の命を奪わなければならない」としたら、あなたはその決断を下せるだろうか?会議室で展開される現代の戦争を描く映画『アイ・イン・ザ・スカイ』から、「誤った問い」に答えを出さなければならない極限状況での葛藤を理解する
これもまた、普通にはなかなか出来ない発言であるように思う。もちろん、彼女は一般信者とは立場が違うので、自身の責任の範囲でより踏み込んだことを言いやすい立場にあったとも言えるかもしれない。しかしそれにしても、問われている内容は「教祖の責任」についてなのである。「制約」に塗れた組織であれば、おいそれと答えられる質問ではないだろう。
あるいは、村岡達子にしても先の信者にしても、「『森達也のカメラの向こう側にいるだろう一般大衆』を意識して、『オウム真理教の印象を間接的に高める』ための発言をしている」という可能性もあるかもしれない。そうだとしたら、それを見抜けなかった私が愚かだということになるのだが、しかし本当にそうだろうか? 先の信者の方が顕著だろうが、発言全体を捉えれば、決して「オウム真理教の印象を高める」ような内容のものではないと思う。主張内容としてはやはり「狂信的」という印象の方が強くなるはずだからだ。
印象を良くしたいということであれば、もう少し言いようがあるんじゃないかと思う。だから逆説的に、「彼らは特に取り繕うことなく本心を口にしているのではないか」と私は感じたのだ。このような信者たちの「フラットさ」が、全体を通じてとても印象的だった。
事件後もオウム真理教に留まり続ける信者たちの「信仰心」について
村岡達子が、自身の信仰心についてこんな風に語る場面がある。
あわせて読みたい
【天才】映画『Winny』(松本優作監督)で知った、金子勇の凄さと著作権法侵害事件の真相(ビットコイン…
稀代の天才プログラマー・金子勇が著作権法違反で逮捕・起訴された実話を描き出す映画『Winny』は、「警察の凄まじい横暴」「不用意な天才と、テック系知識に明るい弁護士のタッグ」「Winnyが明らかにしたとんでもない真実」など、見どころは多い。「金子勇=サトシ・ナカモト」説についても触れる

人間の社会っていうのは矛盾があるわけじゃないですか。(※その後で、「戦争に勝てば人を殺しても裁かれない」など、人間社会が持つ矛盾に対する違和感を具体的に口にする。)そういうことに、子どもの頃から疑問を抱き続けてきたんですけど、それに納得の行く答えをくれたのは、これまで尊師しかいないんです。
まあ、こういうことを言うと「マインドコントロールされてる」』なんて言われちゃうんですけどね(笑)
ただ、(尊師が逮捕されたからと言って)自分の体験・経験として体得してきたことがあるから、そういう信仰が揺らぐことはないですね。
ここでも、信者の側から「マインドコントロール」という言葉が出てくるわけで、映画『A』に映る信者だけ見ていると、あまり「カルト宗教」には見えない。
さて、記憶に新しいと思うが、少し前に旧統一教会に関する報道が加熱した。そしてその中で、「マインドコントロールを規制する法律を作る」みたいな話が出たことがあるのだが、「マインドコントロールを定義することはとても難しい」という指摘がなされていた記憶がある。確かにその通りだし、オウム真理教の信者が「マインドコントロール下に置かれていた」のかどうか、素人の私には判断のしようがない。
あわせて読みたい
【未知】「占い」が占い以外の効果を有するように、UFOなど「信じたいものを信じる」行為の機能を知れる…
「占い」に「見透かされたから仕方なく話す」という効用があるように、「『未知のもの』を信じる行為」には「『否定されたという状態』に絶対に達しない」という利点が存在する。映画『虚空門GATE』は、UFOを入り口に「『未知のもの』を信じる行為」そのものを切り取る
ただ映画の中で、何人かの信者が村岡達子と似たようなことを言っており、なんとなく私は「マインドコントロール下にはない」ような印象を受けた。ある信者など、「グルがどんな人物であっても構わない」と断言していたほどだ。これは、「麻原彰晃がどんな人物でもついていく」という狂信さではなく、むしろ「依って立つものは既に自身の内部にあるのだから、麻原彰晃の存在に頼る必要はない」という宣言であるように私には感じられた。
もちろん、すべての信者がそうなわけではない。中には「狂信的」と感じさせられる意見もあった。最もインパクトがあったのは、森達也が「麻原彰晃が逮捕されたことについてどう捉えているのか?」と質問した時の返答だ。ある信者は、なかなか驚くべき解釈をしていた。
弟子たちがあまりに修行しないから、修行を促すために演技をしているのだ。
意味が分かるだろうか? つまり麻原彰晃は、自ら逮捕され、オウム真理教が世間から猛烈に批判されるような状況を意図的に作り出すことで、「『その程度のことで諦めてしまう人間』を炙り出そうとしている」というのである。さすがにそれは、無理がありすぎる解釈だろう。
あわせて読みたい
【告発】アメリカに”監視”される社会を暴露したスノーデンの苦悩と決断を映し出す映画:『スノーデン』…
NSA(アメリカ国家安全保障局)の最高機密にまでアクセスできたエドワード・スノーデンは、その機密情報を持ち出し内部告発を行った。「アメリカは世界中の通信を傍受している」と。『シチズンフォー』と『スノーデン』の2作品から、彼の告発内容とその葛藤を知る
また他にも、
世間から批判されているこの状況は、自分がオウム真理教の教えをどれだけ体得しているか、どれだけ体得し得るかの実地訓練のようで、良かった。
と、非常に楽観的な意見を口にする信者もいた。そしてこれもまた、「『教祖が逮捕されたという事実』に対して、『特に何も感じていない』ことを示唆する発言」であり、「こういう発言をしても問題視されない心理的安全性のある環境」なのだと思わされたのである。
さて、森達也は基本的に荒木浩に密着しているわけで、彼に対してももちろん厳しい問いをぶつけていた。例えば、森達也がある場面でした質問は、大雑把にまとめると以下のようになる。

あわせて読みたい
【デモ】クーデター後の軍事政権下のミャンマー。ドキュメンタリーさえ撮れない治安の中での映画制作:…
ベルリン国際映画祭でドキュメンタリー賞を受賞したミャンマー映画『ミャンマー・ダイアリーズ』はしかし、後半になればなるほどフィクショナルな映像が多くなる。クーデター後、映画制作が禁じられたミャンマーで、10人の”匿名”監督が死を賭して撮影した映像に込められた凄まじいリアルとは?
確定こそしてはいないものの、事件にオウム真理教が関わっていることはほぼ間違いない。そして、どんな形であれ社会の中で生きているのだから、社会の規範は守るべきだ。だから、「社会の規律を蔑ろにした」という点で、社会は君たちに謝罪を求めているというのが現状だと思うが、その点についてどう感じるか?
こう聞かれた荒木浩は、長い沈黙を経て次のように答える。
1つ受け入れると、オウム真理教に対する世間のイメージすべてを受け入れることになりませんか?
「色々あったけど云々」みたいな中途半端な対応は私には出来ませんよ。「じゃあなんでまだ教団に留まってるんだ」って聞かれたら、答えられなくなるじゃないですか。
私は以前、地下鉄サリン事件の被害者である監督が荒木浩に密着した『AGANAI』(2021年公開)というドキュメンタリー映画を観たことがある。もちろん、映画『A』よりも先に観ているので、私の中の「荒木浩」のイメージは、『AGANAI』によるところが大きい。彼はとても誠実に自身や社会と向き合おうとしているように私には見えたし、それは先の返答からも感じ取れるのではないかと思う。かなり困難な状況に置かれ葛藤しつつも、「自身が信じて飛び込んだ世界を無下にしたくない」という想いに彩られた苦しさがその返答には込められていたように感じられた。
あわせて読みたい
【誠実】地下鉄サリン事件の被害者が荒木浩に密着。「贖罪」とは何かを考えさせる衝撃の映画:『AGANAI…
私には、「謝罪すること」が「誠実」だという感覚がない。むしろ映画『AGANAI 地下鉄サリン事件と私』では、「謝罪しない誠実さ」が描かれる。被害者側と加害者側の対話から、「謝罪」「贖罪」の意味と、信じているものを諦めさせることの難しさについて書く
荒木浩はまた、映画『A』の中でこんな風にも語っている。
オウム真理教に出家する前より「社会」に深く関わっているから、今からさらに出家したい。
これは要するに、「そうしたいけれど、広報副部長という立場ではそれが出来ない」という意味だろうし、であるならば、まさに荒木浩の責任感を表す言葉だとも受け取れるだろう。そもそも普通なら、森達也のような「マスコミの人間」を内部に招き入れる判断をしたりするはずがないわけで、そういう意味でも、荒木浩という人間の誠実さみたいなものが強く感じられる作品だった。
あわせて読みたい
【衝撃】権力の濫用、政治腐敗を描く映画『コレクティブ』は他人事じゃない。「国家の嘘」を監視せよ
火災で一命を取り留め入院していた患者が次々に死亡した原因が「表示の10倍に薄められた消毒液」だと暴き、国家の腐敗を追及した『ガゼタ』誌の奮闘を描く映画『コレクティブ 国家の嘘』は、「権力の監視」が機能しなくなった国家の成れの果てが映し出される衝撃作だ
監督:森達也, プロデュース:安岡卓治
¥400 (2023/12/10 23:28時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品視聴済】私が観てきたドキュメンタリー映画を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が観てきたドキュメンタリー映画を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。
最後に
あわせて読みたい
【絶望】杉咲花主演映画『市子』の衝撃。毎日がしんどい「どん底の人生」を生き延びるための壮絶な決断…
映画『市子』はまず何よりも主演を務めた杉咲花に圧倒させられる作品だ。そしてその上で、主人公・川辺市子を巡る物語にあれこれと考えさせられてしまった。「川辺市子」は決してフィクショナルな存在ではなく、現実に存在し得る。本作は、そのような存在をリアルに想像するきっかけにもなるだろう
この記事では、主に「マスコミの描かれ方」と「信者の生活」に触れたが、それ以外にも興味深い場面は多々ある。例えば、本で読んで存在自体は知っていた「転び公妨」がカメラの前で行われ、実際に逮捕に至る場面が映し出されたのには驚かされた。「転び公妨」とは、警察(特に公安警察だろうか)の常套手段で、「逮捕したい相手の前で勝手に転び、『お前が転ばせたんだ』と言って公務執行妨害で逮捕する」という凄まじいやり方である。こんな自作自演みたいなやり方で実際に逮捕に至るケースが存在するという知識はあったが、まさにそれがカメラの前で行われていたことにビックリしてしまった。
あわせて読みたい
【驚愕】キューバ危機の裏側を描くスパイ映画『クーリエ』。核戦争を回避させた民間人の衝撃の実話:『…
核戦争ギリギリまで進んだ「キューバ危機」。その陰で、世界を救った民間人がいたことをご存知だろうか?実話を元にした映画『クーリエ:最高機密の運び屋』は、ごく普通のセールスマンでありながら、ソ連の膨大な機密情報を盗み出した男の信じがたい奮闘を描き出す
一方で、別の意味でリアリティを感じた場面もある。服装に頓着しない荒木浩が、ある公の場に立つという機会に、スーツはちゃんと着ているものの、サンダル履きで来てしまったことがあったのだ。困った彼は、隣にいた人から直前に革靴を借りてどうにか難を逃れたのだが、そういう実に人間的な姿も収められている。普通なら何でもない場面だと思うが、「オウム真理教は絶対悪だ」という頭でこの映像を観ると、とても奇妙なものに映るだろう。そのような「視点の転換」を体感させられるという意味でも興味深い映画だった。
本当に、観られて良かったなと思う。
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!「文章の書き方が分からない」「文章力がないから鍛えたい」という方にオススメ…
「文章の書き方」についてのKindle本を出版しました。「文章が書けない」「どう書いたらいいか分からない」「文章力を向上させたい」という方の悩みを解消できるような本に仕上げたつもりです。数多くの文章を書き、さらに頼まれて文章を推敲してきた経験を踏まえ、「文章を書けるようになるにはどうしたらいいか」についての私なりの考えをまとめました。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【奇妙】映画『画家と泥棒』は、非日常的なきっかけで始まったあり得ないほど奇跡的な関係を描く
映画『画家と泥棒』は、「自身の絵を盗まれた画家が、盗んだ泥棒と親しくなる」という奇妙奇天烈なきっかけから関係性が始まる物語であり、現実に起きたこととは思えないほど不可思議なドキュメンタリーである。アートを通じて奇妙に通じ合う2人の関係性は、ある種の美しささえ感じさせる、とても素晴らしいものに見えた
あわせて読みたい
【捏造】袴田事件はついに再審での無罪が決定!冤罪の元死刑囚・袴田巌の現在と姉・秀子の奮闘:映画『…
映画『拳と祈り』は、2024年に再審無罪が確定した「袴田事件」の元死刑囚・袴田巌と、そんな弟を献身的にサポートする姉・秀子の日常を中心に、事件や裁判の凄まじい遍歴を追うドキュメンタリーである。日本の司法史上恐らく初めてだろう「前代未聞の状況」にマスコミで唯一関わることになった監督が使命感を持って追い続けた姉弟の記録
あわせて読みたい
【あらすじ】老夫婦の”穏やかな日常”から核戦争の恐怖を描くアニメ映画『風が吹くとき』の衝撃
一軒家の中だけで展開される老夫婦の日常から「核戦争」の危機をリアルに描き出す映画『風が吹くとき』は、日本では1987年に公開された作品なのだが、今まさに観るべき作品ではないかと。世界的に「核戦争」の可能性が高まっているし、また「いつ起こるか分からない巨大地震」と読み替えても成立する作品で、実に興味深かった
あわせて読みたい
【あらすじ】有村架純が保護司を演じた映画『前科者』が抉る、罪を犯した者を待つ「更生」という現実
映画『前科者』は、仮釈放中の元受刑者の更生を手助けするボランティアである「保護司」を中心に据えることで、「元犯罪者をどう受け入れるべきか」「保護司としての葛藤」などを絶妙に描き出す作品。個別の事件への処罰感情はともかく、「社会全体としていかに犯罪を減らしていくか」という観点を忘れるべきではないと私は思っている
あわせて読みたい
【悲劇】映画『プリンセス・ダイアナ』『スペンサー』で知る、その凄まじい存在感と王室の窮屈さ
ドキュメンタリー映画『プリンセス・ダイアナ』と映画『スペンサー』は、衝撃的な死を遂げたダイアナ妃の生涯を対照的な形で描き出す作品だ。「過去映像のみ」で構成される非常に挑戦的な『プリンセス・ダイアナ』と、「王室との不和」を正面から描き出す『スペンサー』の2作によって、彼女が歩んだ壮絶な人生が浮き彫りにされる
あわせて読みたい
【常識】群青いろ制作『彼女はなぜ、猿を逃したか?』は、凄まじく奇妙で、実に魅力的な映画だった(主…
映画『彼女はなぜ、猿を逃したか?』(群青いろ制作)は、「絶妙に奇妙な展開」と「爽快感のあるラスト」の対比が魅力的な作品。主なテーマとして扱われている「週刊誌報道からのネットの炎上」よりも、私は「週刊誌記者が無意識に抱いている思い込み」の方に興味があったし、それを受け流す女子高生の受け答えがとても素敵だった
あわせて読みたい
【狂気】群青いろ制作『雨降って、ジ・エンド。』は、主演の古川琴音が成立させている映画だ
映画『雨降って、ジ・エンド。』は、冒頭からしばらくの間「若い女性とオジサンのちょっと変わった関係」を描く物語なのですが、後半のある時点から「共感を一切排除する」かのごとき展開になる物語です。色んな意味で「普通なら成立し得ない物語」だと思うのですが、古川琴音の演技などのお陰で、絶妙な形で素敵な作品に仕上がっています
あわせて読みたい
【幻惑】映画『落下の解剖学』は、「真実は誰かが”決める”しかない」という現実の不安定さを抉る
「ある死」を巡って混沌とする状況をリアルに描き出す映画『落下の解剖学』は、「客観的な真実にはたどり着けない」という困難さを炙り出す作品に感じられた。事故なのか殺人なのか自殺なのか、明確な証拠が存在しない状況下で、憶測を繋ぎ合わせるようにして進行する「裁判」の様子から、「『真実性』の捉えがたさ」がよく理解できる
あわせて読みたい
【衝撃】EUの難民問題の狂気的縮図!ポーランド・ベラルーシ国境での、国による非人道的対応:映画『人…
上映に際し政府から妨害を受けたという映画『人間の境界』は、ポーランド・ベラルーシ国境で起こっていた凄まじい現実が描かれている。「両国間で中東からの難民を押し付け合う」という醜悪さは見るに絶えないが、そのような状況下でも「可能な範囲でどうにか人助けをしたい」と考える者たちの奮闘には救われる思いがした
あわせて読みたい
【実話】さかなクンの若い頃を描く映画『さかなのこ』(沖田修一)は子育ての悩みを吹き飛ばす快作(主…
映画『さかなのこ』は、兎にも角にものん(能年玲奈)を主演に据えたことが圧倒的に正解すぎる作品でした。性別が違うのに、「さかなクンを演じられるのはのんしかいない!」と感じさせるほどのハマり役で、この配役を考えた人は天才だと思います。「母親からの全肯定」を濃密に描き出す、子どもと関わるすべての人に観てほしい作品です
あわせて読みたい
【真相】飯塚事件は冤罪で死刑執行されたのか?西日本新聞・警察・弁護士が語る葛藤と贖罪:映画『正義…
映画『正義の行方』では、冤罪のまま死刑が執行されたかもしれない「飯塚事件」が扱われる。「久間三千年が犯行を行ったのか」という議論とは別に、「当時の捜査・司法手続きは正しかったのか?」という観点からも捉え直されるべきだし、それを自発的に行った西日本新聞の「再検証連載」はとても素晴らしかったと思う
あわせて読みたい
【憧憬】「フランク・ザッパ」を知らずに映画『ZAPPA』を観て、「この生き様は最高」だと感じた
「フランク・ザッパ」がミュージシャンであることさえ禄に知らない状態で私が映画『ZAPPA』を観た私は、そのあまりに特異なスタンス・生き様にある種の憧憬を抱かされた。貫きたいと思う強い欲求を真っ直ぐ突き進んだそのシンプルな人生に、とにかくグッときたのだ。さらに、こんな凄い人物を知らなかった自分にも驚かされてしまった
あわせて読みたい
【挑戦】映画『燃えあがる女性記者たち』が描く、インドカースト最下位・ダリットの女性による報道
映画『燃えあがる女性記者たち』は、インドで「カースト外の不可触民」として扱われるダリットの女性たちが立ち上げた新聞社「カバル・ラハリヤ」を取り上げる。自身の境遇に抗って、辛い状況にいる人の声を届けたり権力者を糾弾したりする彼女たちの奮闘ぶりが、インドの民主主義を変革させるかもしれない
あわせて読みたい
【日本】原発再稼働が進むが、その安全性は?樋口英明の画期的判決とソーラーシェアリングを知る:映画…
映画『原発をとめた裁判長 そして原発をとめる農家たち』では、大飯原発の運転差し止め判決を下した裁判長による画期的な「樋口理論」の説明に重点が置かれる。「原発の耐震性」に関して知らないことが満載で、実に興味深かった。また、農家が発案した「ソーラーシェアリング」という新たな発電方法も注目である
あわせて読みたい
【歴史】映画『シン・ちむどんどん』は、普天間基地移設問題に絡む辺野古埋め立てを”陽気に”追及する(…
映画『シン・ちむどんどん』は、映画『センキョナンデス』に続く「ダースレイダー・プチ鹿島による選挙戦リポート」第2弾である。今回のターゲットは沖縄知事選。そして本作においては、選挙戦の模様以上に、後半で取り上げられる「普天間基地の辺野古移設問題の掘り下げ」の方がより興味深かった
あわせて読みたい
【評価】映画『ゴジラ-1.0』(山崎貴監督)は面白い!迫力満点の映像と絶妙な人間ドラマ(米アカデミー…
米アカデミー賞で視覚効果賞を受賞した映画『ゴジラ-1.0』(山崎貴監督)は、もちろんそのVFXに圧倒される物語なのだが、「人間ドラマ」をきちんと描いていることも印象的だった。「終戦直後を舞台にする」という、ゴジラを描くには様々な意味でハードルのある設定を見事に活かした、とても見事な作品だ
あわせて読みたい
【壮絶】アウシュヴィッツで”人体実験の神メンゲレ”から生き残り、ホロコーストから生還した男の人生:…
映画『メンゲレと私』は、タイトルと内容がそぐわないものの、とても興味深い作品だった。44ヶ月間の収容所生活を生き延び、ホロコーストから生還したダニエル・ハノッホが、少年とは思えない「思考力」を武器に、最低最悪な状況を生き延びた経験をカメラの前で語る。あまりにも壮絶な、信じがたい現実である
あわせて読みたい
【あらすじ】原爆を作った人の後悔・葛藤を描く映画『オッペンハイマー』のための予習と評価(クリスト…
クリストファー・ノーラン監督作品『オッペンハイマー』は、原爆開発を主導した人物の葛藤・苦悩を複雑に描き出す作品だ。人間が持つ「多面性」を様々な方向から捉えようとする作品であり、受け取り方は人それぞれ異なるだろう。鑑賞前に知っておいた方がいい知識についてまとめたので、参考にしてほしい
あわせて読みたい
【驚愕】映画『リアリティ』の衝撃。FBIによる、機密情報をリークした女性の尋問音源を完全再現(リアリ…
映画『リアリティ』は、恐らく過去類を見ないだろう構成の作品だ。なんと、「FBI捜査官が録音していた実際の音声データのやり取りを一言一句完全に再現した映画」なのである。「第2のスノーデン」とも評される”普通の女性”は、一体何故、国家に反旗を翻す”反逆者”になったのだろうか?
あわせて読みたい
【天才】映画『笑いのカイブツ』のモデル「伝説のハガキ職人ツチヤタカユキ」の狂気に共感させられた
『「伝説のハガキ職人」として知られるツチヤタカユキの自伝的小説を基にした映画『笑いのカイブツ』は、凄まじい狂気に彩られた作品だった。「お笑い」にすべてを捧げ、「お笑い」以外はどうでもいいと考えているツチヤタカユキが、「コミュ力」や「人間関係」で躓かされる”理不尽”な世の中に、色々と考えさせられる
あわせて読みたい
【無謀】映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、脱北ルートに撮影隊が同行する衝撃のドキュメンタリー
北朝鮮からの脱北者に同行し撮影を行う衝撃のドキュメンタリー映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、再現映像を一切使用していない衝撃的な作品だ。危険と隣り合わせの脱北の道程にカメラもついて回り、北朝鮮の厳しい現状と共に、脱北者が置かれた凄まじい状況を映し出す内容に驚かされてしまった
あわせて読みたい
【挑戦】杉並区長・岸本聡子を誕生させた市民運動・選挙戦と、ミュニシパリズムの可能性を描く:『映画…
映画『映画 ◯月◯日、区長になる女。』は、杉並区初の女性区長・岸本聡子を誕生させた選挙戦の裏側を中心に、日本の民主主義を問う作品だ。劇場公開されるや、チケットを取るのが困難なほど観客が殺到した作品であり、観れば日本の政治の「変化」を感じられるのではないかと思う
あわせて読みたい
【斬新】映画『王国(あるいはその家について)』(草野なつか)を観よ。未経験の鑑賞体験を保証する
映画『王国(あるいはその家について)』は、まず経験できないだろう異様な鑑賞体験をもたらす特異な作品だった。「稽古場での台本読み」を映し出すパートが上映時間150分のほとんどを占め、同じやり取りをひたすら繰り返し見せ続ける本作は、「王国」をキーワードに様々な形の「狂気」を炙り出す異常な作品である
あわせて読みたい
【感想】関東大震災前後を描く映画『福田村事件』(森達也)は、社会が孕む「思考停止」と「差別問題」…
森達也監督初の劇映画である『福田村事件』は、100年前の関東大震災直後に起こった「デマを起点とする悲劇」が扱われる作品だ。しかし、そんな作品全体が伝えるメッセージは、「100年前よりも現代の方がよりヤバい」だと私は感じた。SNS時代だからこそ意識すべき問題の詰まった、挑発的な作品である
あわせて読みたい
【脅迫】原発という巨大権力と闘ったモーリーン・カーニーをイザベル・ユペールが熱演する映画『私はモ…
実話を基にした映画『私はモーリーン・カーニー』は、前半の流れからはちょっと想像もつかないような展開を見せる物語だ。原発企業で従業員の雇用を守る労働組合の代表を務める主人公が、巨大権力に立ち向かった挙げ句に自宅で襲撃されてしまうという物語から、「良き被害者」という捉え方の”狂気”が浮かび上がる
あわせて読みたい
【抵抗】映画『熊は、いない』は、映画製作を禁じられた映画監督ジャファル・パナヒの執念の結晶だ
映画『熊は、いない』は、「イラン当局から映画製作を20年間も禁じられながら、その後も作品を生み出し続けるジャファル・パナヒ監督」の手によるもので、彼は本作公開後に収監させられてしまった。パナヒ監督が「本人役」として出演する、「ドキュメンタリーとフィクションのあわい」を縫うような異様な作品だ
あわせて読みたい
【痛快】精神病院の隔離室から脱した、善悪の判断基準を持たない狂気の超能力者が大暴れする映画:『モ…
モナ・リザ アンド ザ ブラッドムーン』は、「10年以上拘束され続けた精神病院から脱走したアジア系女性が、特殊能力を使って大暴れする」というムチャクチャな設定の物語なのだが、全編に通底する「『善悪の判断基準』が歪んでいる」という要素がとても見事で、意味不明なのに最後まで惹きつけられてしまった
あわせて読みたい
【絶望】杉咲花主演映画『市子』の衝撃。毎日がしんどい「どん底の人生」を生き延びるための壮絶な決断…
映画『市子』はまず何よりも主演を務めた杉咲花に圧倒させられる作品だ。そしてその上で、主人公・川辺市子を巡る物語にあれこれと考えさせられてしまった。「川辺市子」は決してフィクショナルな存在ではなく、現実に存在し得る。本作は、そのような存在をリアルに想像するきっかけにもなるだろう
あわせて読みたい
【実話】映画『月』(石井裕也)は、障害者施設での虐待事件から「見て見ぬふりする社会」を抉る(出演…
実際に起こった障害者施設殺傷事件を基にした映画『月』(石井裕也)は、観客を作中世界に引きずり込み、「これはお前たちの物語だぞ」と刃を突きつける圧巻の作品だ。「意思疎通が不可能なら殺していい」という主張には誰もが反対するはずだが、しかしその態度は、ブーメランのように私たちに戻ってくることになる
あわせて読みたい
【衝撃】ウクライナでのホロコーストを描く映画『バビ・ヤール』は、集めた素材映像が凄まじすぎる
ソ連生まれウクライナ育ちの映画監督セルゲイ・ロズニツァが、「過去映像」を繋ぎ合わせる形で作り上げた映画『バビ・ヤール』は、「単一のホロコーストで最大の犠牲者を出した」として知られる「バビ・ヤール大虐殺」を描き出す。ウクライナ市民も加担した、そのあまりに悲惨な歴史の真実とは?
あわせて読みたい
【衝撃】映画『誰がハマーショルドを殺したか』は、予想外すぎる着地を見せる普通じゃないドキュメンタリー
国連事務総長だったハマーショルドが乗ったチャーター機が不審な墜落を遂げた事件を、ドキュメンタリー映画監督マッツ・ブリュガーが追う映画『誰がハマーショルドを殺したか』は、予想もつかない衝撃の展開を見せる作品だ。全世界を揺るがしかねない驚きの”真実”とは?
あわせて読みたい
【狂気】入管の収容所を隠し撮りした映画『牛久』は、日本の難民受け入れ問題を抉るドキュメンタリー
映画『牛久』は、記録装置の持ち込みが一切禁じられている入管の収容施設に無許可でカメラを持ち込み、そこに収容されている難民申請者の声を隠し撮りした映像で構成された作品だ。日本という国家が、国際標準と照らしていかに酷い振る舞いをしているのかが理解できる衝撃作である
あわせて読みたい
【現実】映画『私のはなし 部落のはなし』で初めて同和・部落問題を考えた。差別はいかに生まれ、続くのか
私はずっと、「部落差別なんてものが存在する意味が分からない」と感じてきたが、映画『私のはなし 部落のはなし』を観てようやく、「どうしてそんな差別が存在し得るのか」という歴史が何となく理解できた。非常に複雑で解決の難しい問題だが、まずは多くの人が正しく理解することが必要だと言えるだろう
あわせて読みたい
【抵抗】若者よ、映画『これは君の闘争だ』を見ろ!学校閉鎖に反対する学生運動がブラジルの闇を照らす
映画『これは君の闘争だ』で描かれるのは、厳しい状況に置かれた貧困層の学生たちによる公権力との闘いだ。「貧困層ばかりが通う」とされる公立校が大幅に再編されることを知った学生が高校を占拠して立て籠もる決断に至った背景を、ドキュメンタリー映画とは思えないナレーションで描く異色作
あわせて読みたい
【信念】9.11後、「命の値段」を計算した男がいた。映画『WORTH』が描く、その凄絶な2年間(主演:マイ…
9.11テロの後、「被害者の『命の値段』を算出した男」がいたことをご存知だろうか?映画『WORTH』では、「被害者遺族のために貢献したい」と無償で難題と向き合うも、その信念が正しく理解されずに反発や対立を招いてしまった現実が描かれる。実話を基にしているとは思えない、凄まじい物語だ
あわせて読みたい
【倫理】報道の自由度に関わる「放送法の解釈変更」問題をわかりやすく説明(撤回の真相についても):…
安倍政権下で突然発表された「放送法の解釈変更」が、2023年3月17日に正式に”撤回された”という事実をご存知だろうか?映画『テレビ、沈黙。 放送不可能。Ⅱ』は、その「撤回」に尽力した小西洋之議員に田原総一朗がインタビューする作品だ。多くの人が知るべき事実である
あわせて読みたい
【共感】斎藤工主演映画『零落』(浅野いにお原作)が、「創作の評価」を抉る。あと、趣里が良い!
かつてヒット作を生み出しながらも、今では「オワコン」みたいな扱いをされている漫画家を中心に描く映画『零落』は、「バズったものは正義」という世の中に斬り込んでいく。私自身は創作者ではないが、「売れる」「売れない」に支配されてしまう主人公の葛藤はよく理解できるつもりだ
あわせて読みたい
【デモ】クーデター後の軍事政権下のミャンマー。ドキュメンタリーさえ撮れない治安の中での映画制作:…
ベルリン国際映画祭でドキュメンタリー賞を受賞したミャンマー映画『ミャンマー・ダイアリーズ』はしかし、後半になればなるほどフィクショナルな映像が多くなる。クーデター後、映画制作が禁じられたミャンマーで、10人の”匿名”監督が死を賭して撮影した映像に込められた凄まじいリアルとは?
あわせて読みたい
【信念】映画『ハマのドン』の主人公、横浜港の顔役・藤木幸夫は、91歳ながら「伝わる言葉」を操る
横浜港を取り仕切る藤木幸夫を追うドキュメンタリー映画『ハマのドン』は、盟友・菅義偉と対立してでもIR進出を防ごうとする91歳の決意が映し出される作品だ。高齢かつほとんど政治家のような立ち位置でありながら、「伝わる言葉」を発する非常に稀有な人物であり、とても興味深かった
あわせて読みたい
【映画】『戦場記者』須賀川拓が、ニュースに乗らない中東・ウクライナの現実と報道の限界を切り取る
TBS所属の特派員・須賀川拓は、ロンドンを拠点に各国の取材を行っている。映画『戦場記者』は、そんな彼が中東を取材した映像をまとめたドキュメンタリーだ。ハマスを巡って食い違うガザ地区とイスラエル、ウクライナ侵攻直後に現地入りした際の様子、アフガニスタンの壮絶な薬物中毒の現実を映し出す
あわせて読みたい
【天才】映画『Winny』(松本優作監督)で知った、金子勇の凄さと著作権法侵害事件の真相(ビットコイン…
稀代の天才プログラマー・金子勇が著作権法違反で逮捕・起訴された実話を描き出す映画『Winny』は、「警察の凄まじい横暴」「不用意な天才と、テック系知識に明るい弁護士のタッグ」「Winnyが明らかにしたとんでもない真実」など、見どころは多い。「金子勇=サトシ・ナカモト」説についても触れる
あわせて読みたい
【違和感】三浦透子主演映画『そばかす』はアセクシャルの生きづらさを描く。セクシャリティ理解の入り口に
「他者に対して恋愛感情・性的欲求を抱かないセクシャリティ」である「アセクシャル」をテーマにした映画『そばかす』は、「マイノリティのリアル」をかなり解像度高く映し出す作品だと思う。また、主人公・蘇畑佳純に共感できてしまう私には、「普通の人の怖さ」が描かれている映画にも感じられた
あわせて読みたい
【驚嘆】映画『TAR/ター』のリディア・ターと、彼女を演じたケイト・ブランシェットの凄まじさ
天才女性指揮者リディア・ターを強烈に描き出す映画『TAR/ター』は、とんでもない作品だ。「縦軸」としてのターの存在感があまりにも強すぎるため「横軸」を上手く捉えきれず、結果「よく分からなかった」という感想で終わったが、それでも「観て良かった」と感じるほど、揺さぶられる作品だった
あわせて読みたい
【実話】映画『グリーンブック』は我々に問う。当たり前の行動に「差別意識」が含まれていないか、と
黒人差別が遥かに苛烈だった時代のアメリカにおいて、黒人ピアニストと彼に雇われた白人ドライバーを描く映画『グリーンブック』は、観客に「あなたも同じような振る舞いをしていないか?」と突きつける作品だ。「差別」に限らず、「同時代の『当たり前』に従った行動」について考え直させる1作
あわせて読みたい
【美麗】映画『CLOSE/クロース』はあまりにも切ない。「誰かの当たり前」に飲み込まれてしまう悲劇
子どもの頃から兄弟のように育った幼馴染のレオとレミの関係の変化を丁寧に描き出す映画『CLOSE/クロース』は、「自分自身で『美しい世界』を毀損しているのかもしれない」という話でもある。”些細な”言動によって、確かに存在したあまりに「美しい世界」があっさりと壊されてしまう悲哀が描かれる
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』を観てくれ!現代の人間関係の教科書的作品を考…
映画『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』は、私にグサグサ突き刺さるとても素晴らしい映画だった。「ぬいぐるみに話しかける」という活動内容の大学サークルを舞台にした物語であり、「マイノリティ的マインド」を持つ人たちの辛さや葛藤を、「マジョリティ視点」を絶妙に織り交ぜて描き出す傑作について考察する
あわせて読みたい
【純真】ゲイが犯罪だった時代が舞台の映画『大いなる自由』は、刑務所内での極深な人間ドラマを描く
男性同士の恋愛が犯罪であり、ゲイの男性が刑法175条を理由に逮捕されてしまう時代のドイツを描いた映画『大いなる自由』は、確かに同性愛の物語なのだが、実はそこに本質はない。物語の本質は、まさにタイトルにある通り「自由」であり、ラストシーンで突きつけられるその深い問いかけには衝撃を受けるだろう
あわせて読みたい
【映画】今泉力哉監督『ちひろさん』(有村架純)が描く、「濃い寂しさ」が溶け合う素敵な関係性
今泉力哉監督、有村架純主演の映画『ちひろさん』は、その圧倒的な「寂しさの共有」がとても心地よい作品です。色んな「寂しさ」を抱えた様々な人と関わる、「元風俗嬢」であることを公言し海辺の町の弁当屋で働く「ちひろさん」からは、同じような「寂しさ」を抱える人を惹き付ける力強さが感じられるでしょう
あわせて読みたい
【実話】映画『グッドバイ、バッドマガジンズ』(杏花主演)が描く、もの作りの絶望(と楽しさ)
実在したエロ雑誌編集部を舞台に、タブーも忖度もなく業界の内実を描き切る映画『グッドバイ、バッドマガジンズ』は、「エロ雑誌」をテーマにしながら、「もの作りに懸ける想い」や「仕事への向き合い方」などがリアルに描かれる素敵な映画だった。とにかく、主役を演じた杏花が良い
あわせて読みたい
【挑発】「TBS史上最大の問題作」と評されるドキュメンタリー『日の丸』(構成:寺山修司)のリメイク映画
1967年に放送された、寺山修司が構成に関わったドキュメンタリー『日の丸』は、「TBS史上最大の問題作」と評されている。そのスタイルを踏襲して作られた映画『日の丸~それは今なのかもしれない~』は、予想以上に面白い作品だった。常軌を逸した街頭インタビューを起点に様々な思考に触れられる作品
あわせて読みたい
【人類学】少数民族・ムラブリ族に潜入した映画『森のムラブリ』は、私たちの「当たり前」を鮮やかに壊す
タイとラオスにまたがって存在する少数民族・ムラブリ族に密着したドキュメンタリー映画『森のムラブリ』。「ムラブリ族の居住地でたまたま出会った日本人人類学者」と意気投合し生まれたこの映画は、私たちがいかに「常識」「当たり前」という感覚に囚われているのかを炙り出してくれる
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』で描かれる、グアンタナモ”刑務所”の衝撃の実話は必見
ベネディクト・カンバーバッチが制作を熱望した衝撃の映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』は、アメリカの信じがたい実話を基にしている。「9.11の首謀者」として不当に拘束され続けた男を「救おうとする者」と「追い詰めようとする者」の奮闘が、「アメリカの闇」を暴き出す
あわせて読みたい
【差別】映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』の衝撃。プーチンが支持する国の蛮行・LGBT狩り
プーチン大統領の後ろ盾を得て独裁を維持しているチェチェン共和国。その国で「ゲイ狩り」と呼ぶしかない異常事態が継続している。映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』は、そんな現実を命がけで映し出し、「現代版ホロコースト」に立ち向かう支援団体の奮闘も描く作品
あわせて読みたい
【あらすじ】死刑囚を救い出す実話を基にした映画『黒い司法』が指摘する、死刑制度の問題と黒人差別の現実
アメリカで死刑囚の支援を行う団体を立ち上げた若者の実話を基にした映画『黒い司法 0%からの奇跡』は、「死刑制度」の存在価値について考えさせる。上映後のトークイベントで、アメリカにおける「死刑制度」と「黒人差別」の結びつきを知り、一層驚かされた
あわせて読みたい
【悲劇】アメリカの暗黒の歴史である奴隷制度の現実を、元奴隷の黒人女性自ら赤裸々に語る衝撃:『ある…
生まれながらに「奴隷」だった黒人女性が、多くの人の協力を得て自由を手にし、後に「奴隷制度」について書いたのが『ある奴隷少女に起こった出来事』。長らく「白人が書いた小説」と思われていたが、事実だと証明され、欧米で大ベストセラーとなった古典作品が示す「奴隷制度の残酷さ」
あわせて読みたい
【対立】パレスチナとイスラエルの「音楽の架け橋」は実在する。映画『クレッシェンド』が描く奇跡の楽団
イスラエルとパレスチナの対立を背景に描く映画『クレッシェンド』は、ストーリーそのものは実話ではないものの、映画の中心となる「パレスチナ人・イスラエル人混合の管弦楽団」は実在する。私たちが生きる世界に残る様々な対立について、その「改善」の可能性を示唆する作品
あわせて読みたい
【感涙】映画『彼女が好きなものは』の衝撃。偏見・無関心・他人事の世界から”脱する勇気”をどう持つか
涙腺がぶっ壊れたのかと思ったほど泣かされた映画『彼女が好きなものは』について、作品の核となる「ある事実」に一切触れずに書いた「ネタバレなし」の感想です。「ただし摩擦はゼロとする」の世界で息苦しさを感じているすべての人に届く「普遍性」を体感してください
あわせて読みたい
【特異】「カメラの存在」というドキュメンタリーの大前提を覆す映画『GUNDA/グンダ』の斬新さ
映画『GUNDA/グンダ』は、「カメラの存在」「撮影者の意図」を介在させずにドキュメンタリーとして成立させた、非常に異端的な作品だと私は感じた。ドキュメンタリーの「デュシャンの『泉』」と呼んでもいいのではないか。「家畜」を被写体に据えたという点も非常に絶妙
あわせて読みたい
【不思議】森達也が「オカルト」に挑む本。「科学では説明できない現象はある」と否定も肯定もしない姿…
肯定派でも否定派でもない森達也が、「オカルト的なもの」に挑むノンフィクション『オカルト』。「現象を解釈する」ことよりも、「現象を記録する」こと点に注力し、「そのほとんどは勘違いや見間違いだが、本当に説明のつかない現象も存在する」というスタンスで追いかける姿勢が良い
あわせて読みたい
【衝撃】洗脳を自ら脱した著者の『カルト脱出記』から、「社会・集団の洗脳」を避ける生き方を知る
「聖書研究に熱心な日本人証人」として「エホバの証人」で活動しながら、その聖書研究をきっかけに自ら「洗脳」を脱した著者の体験を著した『カルト脱出記』。広い意味での「洗脳」は社会のそこかしこに蔓延っているからこそ、著者の体験を「他人事」だと無視することはできない
あわせて読みたい
【感想】リドリー・スコット監督の映画『最後の決闘裁判』から、社会が”幻想”を共有する背景とその悲劇…
例えば、「1万円札」というただの紙切れに「価値を感じる」のは、社会の構成員が同じ「共同幻想」の中に生きているからだ。リドリー・スコット監督の映画『最後の決闘裁判』は、「強姦では妊娠しない」「裁判の勝者を決闘で決する」という社会通念と、現代にも通じる「共同幻想」の強さを描き出す
あわせて読みたい
【理解】小野田寛郎を描く映画。「戦争終結という現実を受け入れない(=認知的不協和)」は他人事じゃ…
映画『ONODA 一万夜を越えて』を観るまで、小野田寛郎という人間に対して違和感を覚えていた。「戦争は終わっていない」という現実を生き続けたことが不自然に思えたのだ。しかし映画を観て、彼の生き方・決断は、私たちと大きく変わりはしないと実感できた
あわせて読みたい
【選択】映画『サウンド・オブ・メタル』で難聴に陥るバンドマンは、「障害」と「健常」の境界で揺れる
ドラムを叩くバンドマンが聴力を失ってしまう――そんな厳しい現実に直面する主人公を描く映画『サウンド・オブ・メタル』では、「『健常者との生活』を選ぶか否か」という選択が突きつけられる。ある意味では健常者にも向けられているこの問いに、どう答えるべきだろうか
あわせて読みたい
【実話】「ホロコーストの映画」を観て改めて、「有事だから仕方ない」と言い訳しない人間でありたいと…
ノルウェーの警察が、自国在住のユダヤ人をまとめて船に乗せアウシュビッツへと送った衝撃の実話を元にした映画『ホロコーストの罪人』では、「自分はそんな愚かではない」と楽観してはいられない現実が映し出される。このような悲劇は、現在に至るまで幾度も起こっているのだ
あわせて読みたい
【凄絶】北朝鮮の”真実”を描くアニメ映画。強制収容所から決死の脱出を試みた者が語る驚愕の実態:『ト…
在日コリアン4世の監督が、北朝鮮脱北者への取材を元に作り上げた壮絶なアニメ映画『トゥルーノース』は、私たちがあまりに恐ろしい世界と地続きに生きていることを思い知らせてくれる。最低最悪の絶望を前に、人間はどれだけ悪虐になれてしまうのか、そしていかに優しさを発揮できるのか。
あわせて読みたい
【認識】「固定観念」「思い込み」の外側に出るのは難しい。自分はどんな「へや」に囚われているのか:…
実際に起こった衝撃的な事件に着想を得て作られた映画『ルーム』は、フィクションだが、観客に「あなたも同じ状況にいるのではないか?」と突きつける力強さを持っている。「普通」「当たり前」という感覚に囚われて苦しむすべての人に、「何に気づけばいいか」を気づかせてくれる作品
あわせて読みたい
【感想】映画『野火』は、戦争の”虚しさ”をリアルに映し出す、後世に受け継がれるべき作品だ
「戦争の悲惨さ」は様々な形で描かれ、受け継がれてきたが、「戦争の虚しさ」を知る機会はなかなかない。映画『野火』は、第二次世界大戦中のフィリピンを舞台に、「敵が存在しない戦場で”人間の形”を保つ困難さ」を描き出す、「虚しさ」だけで構成された作品だ
あわせて読みたい
【家族】映画『そして父になる』が問う「子どもの親である」、そして「親の子どもである」の意味とは?
「血の繋がり」だけが家族なのか?「将来の幸せ」を与えることが子育てなのか?実際に起こった「赤ちゃんの取り違え事件」に着想を得て、苦悩する家族を是枝裕和が描く映画『そして父になる』から、「家族とは何か?」「子育てや幸せとどう向き合うべきか?」を考える
あわせて読みたい
【最新】「コロンブス到達以前のアメリカ大陸」をリアルに描く歴史書。我々も米国人も大いに誤解してい…
サイエンスライターである著者は、「コロンブス到着以前のアメリカはどんな世界だったか?」という問いに触れ、その答えが書かれた本がいつまで経っても出版されないので自分で執筆した。『1491 先コロンブス期アメリカ大陸をめぐる新発見』には、アメリカ人も知らない歴史が満載だ
あわせて読みたい
【書評】奇跡の”国家”「ソマリランド」に高野秀行が潜入。崩壊国家・ソマリア内で唯一平和を保つ衝撃の”…
日本の「戦国時代」さながらの内戦状態にあるソマリア共和国内部に、十数年に渡り奇跡のように平和を維持している”未承認国家”が存在する。辺境作家・高野秀行の『謎の独立国家ソマリランド』から、「ソマリランド」の理解が難しい理由と、「奇跡のような民主主義」を知る
あわせて読みたい
【興奮】世界的大ベストセラー『サピエンス全史』要約。人類が文明を築き上げるに至った3つの革命とは?
言わずと知れた大ベストセラー『サピエンス全史』は、「何故サピエンスだけが人類の中で生き残り、他の生物が成し得なかった歴史を歩んだのか」を、「認知革命」「農業革命」「科学革命」の3つを主軸としながら解き明かす、知的興奮に満ち溢れた1冊
あわせて読みたい
【知的】文系にオススメの、科学・数学・哲学の入門書。高橋昌一郎の「限界シリーズ」は超絶面白い:『…
例えば「科学」だけに限ってみても、「なんでもできる」わけでは決してない。「科学」に限らず、私たちが対峙する様々な事柄には「これ以上は不可能・無理」という「限界」が必ず存在する。高橋昌一郎の「限界シリーズ」から、我々が認識しておくべき「限界」を易しく学ぶ
あわせて読みたい
【実話】障害者との接し方を考えさせる映画『こんな夜更けにバナナかよ』から”対等な関係”の大事さを知る
「障害者だから◯◯だ」という決まりきった捉え方をどうしてもしてしまいがちですが、『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』の主人公・鹿野靖明の生き様を知れば、少しは考え方が変わるかもしれません。筋ジストロフィーのまま病院・家族から離れて“自活”する決断をした驚異の人生
あわせて読みたい
【考察】映画『ジョーカー』で知る。孤立無援の環境にこそ”悪”は偏在すると。個人の問題ではない
「バットマン」シリーズを観たことがない人間が、予備知識ゼロで映画『ジョーカー』を鑑賞。「悪」は「環境」に偏在し、誰もが「悪」に足を踏み入れ得ると改めて実感させられた。「個人」を断罪するだけでは社会から「悪」を減らせない現実について改めて考える
あわせて読みたい
【個性】統合失調症との関わり方を芸人・松本ハウスから学ぶ。本人と周囲の人間はどう対処すべきか:『…
「統合失調症だからといって病気だとは捉えず、ただの個性だと思う」と話す松本キックは、相方・ハウス加賀谷とどう接したか。そしてハウス加賀谷は、いかにして病気と向き合ったか。『統合失調症がやってきた』『相方は、統合失調症』から、普遍的な「人間関係の極意」を学ぶ
あわせて読みたい
【レッテル】コミュニケーションで大事なのは、肩書や立場を外して、相手を”その人”として見ることだ:…
私は、それがポジティブなものであれ、「レッテル」で見られることは嫌いです。主人公の1人、障害を持つ大富豪もまたそんなタイプ。傍若無人な元犯罪者デルとの出会いでフィリップが変わっていく『THE UPSIDE 最強のふたり』からコミュニケーションを学ぶ
あわせて読みたい
【勇敢】”報道”は被害者を生む。私たちも同罪だ。”批判”による”正義の実現”は正義だろうか?:『リチャ…
「爆弾事件の被害を最小限に食い止めた英雄」が、メディアの勇み足のせいで「爆弾事件の犯人」と報じられてしまった実話を元にした映画『リチャード・ジュエル』から、「他人を公然と批判する行為」の是非と、「再発防止という名の正義」のあり方について考える
あわせて読みたい
【真実?】佐村河内守のゴーストライター騒動に森達也が斬り込んだ『FAKE』は我々に何を問うか?
一時期メディアを騒がせた、佐村河内守の「ゴースト問題」に、森達也が斬り込む。「耳は聴こえないのか?」「作曲はできるのか?」という疑惑を様々な角度から追及しつつ、森達也らしく「事実とは何か?」を問いかける『FAKE』から、「事実の捉え方」について考える
あわせて読みたい
【絶望】「人生上手くいかない」と感じる時、彼を思い出してほしい。壮絶な過去を背負って生きる彼を:…
「北九州連続監禁殺人事件」という、マスコミも報道規制するほどの残虐事件。その「主犯の息子」として生きざるを得なかった男の壮絶な人生。「ザ・ノンフィクション」のプロデューサーが『人殺しの息子と呼ばれて』で改めて取り上げた「真摯な男」の生き様と覚悟
あわせて読みたい
【誠実】想像を超える辛い経験を言葉にするのは不可能だ。それを分かってなお筆を執った作家の震災記:…
旅行者として東日本大震災で被災した小説家・彩瀬まるは、『暗い夜、星を数えて 3.11被災鉄道からの脱出』でその体験を語る。「そんなこと、言わなければ分からない」と感じるような感情も包み隠さず記し、「絶望的な伝わらなさ」を感じながらも伝えようと奮闘する1冊
あわせて読みたい
【神秘】脳研究者・池谷裕二が中高生向けに行った講義の書籍化。とても分かりやすく面白い:『進化しす…
「宇宙」「深海」「脳」が、人類最後のフロンティアと呼ばれている。それほど「脳」というのは、未だに分からないことだらけの不思議な器官だ。池谷裕二による中高生向けの講義を元にした『進化しすぎた脳』『単純な脳、複雑な「私」』をベースに、脳の謎を知る
あわせて読みたい
【情熱】「ルール」は守るため”だけ”に存在するのか?正義を実現するための「ルール」のあり方は?:映…
「ルールは守らなければならない」というのは大前提だが、常に例外は存在する。どれほど重度の自閉症患者でも断らない無許可の施設で、情熱を持って問題に対処する主人公を描く映画『スペシャルズ!』から、「ルールのあるべき姿」を考える
あわせて読みたい
【限界】有名な「錯覚映像」で心理学界をザワつかせた著者らが語る「人間はいかに間違えるか」:『錯覚…
私たちは、知覚や記憶を頼りに社会を生きている。しかしその「知覚」「記憶」は、本当に信頼できるのだろうか?心理学の世界に衝撃を与えた実験を考案した著者らの『錯覚の科学』から、「避けられない失敗のクセ」を理解する
あわせて読みたい
【驚愕】「金正男の殺人犯」は”あなた”だったかも。「人気者になりたい女性」が陥った巧妙な罠:映画『…
金正男が暗殺された事件は、世界中で驚きをもって報じられた。その実行犯である2人の女性は、「有名にならないか?」と声を掛けられて暗殺者に仕立て上げられてしまった普通の人だ。映画『わたしは金正男を殺していない』から、危険と隣り合わせの現状を知る
あわせて読みたい
【誤り】「信じたいものを信じる」のは正しい?映画『星の子』から「信じること」の難しさを考える
どんな病気も治す「奇跡の水」の存在を私は信じないが、しかし何故「信じない」と言えるのか?「奇跡の水を信じる人」を軽々に非難すべきではないと私は考えているが、それは何故か?映画『星の子』から、「何かを信じること」の難しさについて知る
あわせて読みたい
【排除】「分かり合えない相手」だけが「間違い」か?想像力の欠如が生む「無理解」と「対立」:映画『…
「共感」が強すぎる世の中では、自然と「想像力」が失われてしまう。そうならないようにと意識して踏ん張らなければ、他人の価値観を正しく認めることができない人間になってしまうだろう。映画『ミセス・ノイズィ』から、多様な価値観を排除しない生き方を考える
あわせて読みたい
【素顔】「ヨコハマメリー史」から「伊勢佐木町史」を知れる映画。謎の女性が町の歴史に刻んだものとは…
横浜で長らく目撃されていた白塗りの女性は、ある時から姿を消した。彼女の存在を欠いた伊勢佐木町という街は、大きく変わってしまったと語る者もいる。映画『ヨコハマメリー』から、ある種のアイコンとして存在した女性の生き様や彼女と関わった者たちの歴史、そして彼女の”素顔”を知る
あわせて読みたい
【異端】子育てがうまくいかないと悩む方へ。9歳で大学入学の天才児に学ぶ「すべきでないこと」:『ぼく…
12歳で数学の未解決問題を解いた天才児は、3歳の時に「16歳で靴紐が結べるようになったらラッキー」と宣告されていた。専門家の意見に逆らって、重度の自閉症児の才能をどう開花させたのかを、『ぼくは数式で宇宙の美しさを伝えたい』から学ぶ
あわせて読みたい
【衝撃】森達也『A3』が指摘。地下鉄サリン事件を起こしたオウム真理教は社会を激変させた
「オウム真理教は特別だ、という理由で作られた”例外”が、いつの間にか社会の”前提”になっている」これが、森達也『A3』の主張の要点だ。異常な状態で続けられた麻原彰晃の裁判を傍聴したことをきっかけに、社会の”異様な”変質の正体を理解する。
あわせて読みたい
【無知】メディアの問題の本質は?「報道の限界」と「情報の受け取り方」を独裁政治の現実から知る:『…
メディアは確かに「事実」を報じている。しかし、報道に乗らない情報まで含めなければ、本当の意味で世の中を理解することは難しいと、『こうして世界は誤解する』は教えてくれる。アラブ諸国での取材の現実から、報道の「限界」と「受け取り方」を学ぶ
あわせて読みたい
【感想】世の中と足並みがそろわないのは「正常が異常」だから?自分の「正常」を守るために:『コンビ…
30代になっても未婚でコンビニアルバイトの古倉さんは、普通から外れたおかしな人、と見られてしまいます。しかし、本当でしょうか?『コンビニ人間』をベースに、多数派の人たちの方が人生を自ら選択していないのではないかと指摘する。
あわせて読みたい
【加虐】メディアの役割とは?森達也『A』が提示した「事実を報じる限界」と「思考停止社会」
オウム真理教の内部に潜入した、森達也のドキュメンタリー映画『A』は衝撃を与えた。しかしそれは、宗教団体ではなく、社会の方を切り取った作品だった。思考することを止めた社会の加虐性と、客観的な事実など切り取れないという現実について書く
あわせて読みたい
【辛い】こじらせ女子必読!ややこしさと共に生きるしかない、自分のことで精一杯なすべての人に:『女…
「こじらせ」って感覚は、伝わらない人には全然伝わりません。だからこそ余計に、自分が感じている「生きづらさ」が理解されないことにもどかしさを覚えます。AVライターに行き着いた著者の『女子をこじらせて』をベースに、ややこしさを抱えた仲間の生き方を知る
あわせて読みたい
【考察】世の中は理不尽だ。平凡な奴らがのさばる中で、”特別な私の美しい世界”を守る生き方:『オーダ…
自分以外は凡人、と考える主人公の少女はとてもイタい。しかし、世間の価値観と折り合わないなら、自分の美しい世界を守るために闘うしかない。中二病の少女が奮闘する『オーダーメイド殺人クラブ』をベースに、理解されない世界をどう生きるかについて考察する
あわせて読みたい
【覚悟】人生しんどい。その場の”空気”から敢えて外れる3人の中学生の処世術から生き方を学ぶ:『私を知…
空気を読んで摩擦を減らす方が、集団の中では大体穏やかにいられます。この記事では、様々な理由からそんな選択をしない/できない、『私を知らないで』に登場する中学生の生き方から、厳しい現実といかにして向き合うかというスタンスを学びます
あわせて読みたい
【感想】人間関係って難しい。友達・恋人・家族になるよりも「あなた」のまま関わることに価値がある:…
誰かとの関係性には大抵、「友達」「恋人」「家族」のような名前がついてしまうし、そうなればその名前に縛られてしまいます。「名前がつかない関係性の奇跡」と「誰かを想う強い気持ちの表し方」について、『君の膵臓をたべたい』をベースに書いていきます
あわせて読みたい
【議論】安楽死のできない日本は「死ぬ権利」を奪っていると思う(合法化を希望している):『安楽死を…
私は、安楽死が合法化されてほしいと思っている。そのためには、人間には「死ぬ権利」があると合意されなければならないだろう。安楽死は時折話題になるが、なかなか議論が深まらない。『安楽死を遂げた日本人』をベースに、安楽死の現状を理解する
あわせて読みたい
【驚愕】日本の司法は終わってる。「中世レベル」で「無罪判決が多いと出世に不利」な腐った現実:『裁…
三権分立の一翼を担う裁判所のことを、私たちはよく知らない。元エリート裁判官・瀬木比呂志と事件記者・清水潔の対談本『裁判所の正体』をベースに、「裁判所による統制」と「権力との癒着」について書く。「中世レベル」とさえ言われる日本の司法制度の現実は、「裁判になんか関わることない」という人も無視できないはずだ
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
メディア・マスコミ・表現の自由【本・映画の感想】 | ルシルナ
様々な現実を理解する上で、マスコミや出版などメディアの役割は非常に大きいでしょう。情報を受け取る我々が正しいリテラシーを持っていなければ、誤った情報を発信する側…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…







































































































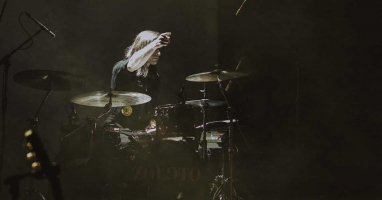
























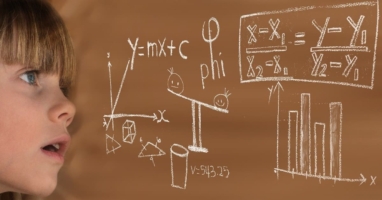



















コメント