目次
はじめに
あわせて読みたい
パンサー尾形が解説!NHKの超面白い数学番組『笑わない数学』の話題をさらに深掘りする記事
お笑い芸人・パンサー尾形が、笑い一切無しで、難解だが魅力的な数学世界を大真面目に解説するNHKの数学番組『笑わない数学』。同番組で紹介された様々な話題について、当ブログでも記事を書いているので、それらをまとめて紹介していきます。番組を観て興味を持った方、さらに深掘りするのにご参考下さい。
この記事で取り上げる本
著:結城 浩
¥1,782 (2021/09/07 06:23時点 | Amazon調べ)
ポチップ
この記事の3つの要点
「ペアノの公理」や「カントールの対角線論法」など、様々な話が展開される ヒルベルトが目指した「形式的体系」とは何か? ゲーデルはどのようにしてヒルベルトの大目標を粉砕する証明を行ったのか?
「ゲーデルの不完全性定理」の証明の中身が詳細に説明されている一般向けの数学書はほとんど無いと思うので、そういう意味でも貴重です
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
「数学ガール」では、どのようなステップを踏んで「ゲーデルの不完全性定理」にたどり着くのか?
「数学ガール」シリーズの設定
本書は、「数学ガール」シリーズの第3弾 です。どのシリーズから読んでも基本的には問題ありません が、数学の説明が小説仕立てで展開される作品で、登場人物の関係性や成長などは順番通りに読んだ方が良いと感じる人もいると思います
あわせて読みたい
【変人】結城浩「数学ガール」から、1億円も名誉ある賞も断った天才が証明したポアンカレ予想を学ぶ
1億円の賞金が懸けられた「ポアンカレ予想」は、ペレルマンという天才数学者が解き明かしたが、1億円もフィールズ賞も断った。そんな逸話のある「ポアンカレ予想」とは一体どんな主張であり、どのように証明されたのかを結城浩『数学ガール』から学ぶ
あわせて読みたい
【興奮】結城浩「数学ガール」で、決闘で命を落とした若き天才数学者・ガロアの理論を学ぶ
高校生を中心に、数学を通じて関わり合う者たちを描く「数学ガール」シリーズ第5弾のテーマは「ガロア理論」。独力で「群論」という新たな領域を切り開きながら、先駆的すぎて同時代の数学者には理解されず、その後決闘で死亡した天才の遺した思考を追う
違うタイプの女性がそれぞれの形で数学に取り組んでる感じがいいよね
というわけで、まずは登場人物の紹介 から。
主人公は「僕」 。高校2年生で、数学が趣味 。学校の勉強だけではなく、自分なりの興味に従って様々な数学の研究を自ら行っている。
あわせて読みたい
【天才】数学の捉え方を一変させた「シンメトリー(対称性)」と、その発見から発展に至る歴史:『シン…
「5次方程式の解の公式は存在しない」というアーベルの証明や、天才・ガロアが発展させた「群論」は、「シンメトリー(対称性)」という領域に新たな光を当てた。『シンメトリーの地図帳』をベースに、「シンメトリー」の発展と「モンスター」の発見の物語を知る
ミルカさん は、「僕」の同級生。数学の才媛 で、数学に関してずば抜けた能力を持つ。「僕」を中心に数学について語らう様々なメンバーを、予想もつかない高みへといつも連れて行ってくれる。ピアノの腕前もかなりのもの。常に冷静沈着でクールなのだが、高所恐怖症だと判明した。
一学年下のテトラちゃん 。英語は大得意だが、数学は大の苦手 で、それを克服するために、数学が得意だと噂されている先輩(「僕」のこと)に教わろうと決意。勇気を出して話しかけて以来、数学について語る間柄になっている。理解は決して早いとは言えないが、理解するまで決して諦めない粘り強さと、理解が追いついてからの定着度は素晴らしいものがある。そして時々「僕」をハッとさせるような質問をする。
従姉妹のユーリ 。「~にゃ」と猫っぽく喋る中学生で、よく「僕」の家に入り浸っている。お兄ちゃん(「僕」のこと)から数学を教わるのが好き。中学生なので数学そのものの知識はさほどない のだが、論理的な話になると滅法強い。
あわせて読みたい
【衝撃】ABC予想の証明のために生まれたIUT理論を、提唱者・望月新一の盟友が分かりやすく語る:『宇宙…
8年のチェック期間を経て雑誌に掲載された「IUT理論(宇宙際タイヒミュラー理論)」は、数学の最重要未解決問題である「ABC予想」を証明するものとして大いに話題になった。『宇宙と宇宙をつなぐ数学』『abc予想入門』をベースに、「IUT理論」「ABC予想」について学ぶ
この3人は、なんだかんだ「僕」のことが好きなんだよね
そういう恋愛っぽい設定も若干ありながら、数学の話が展開されていきます
小説仕立てということに加えてもう1つ、このシリーズの特徴 を挙げておきましょう。
シリーズ第1作を除いてすべて、このシリーズには副題がついており、本書では「ゲーデルの不完全性定理」です。そしてこの副題が、それぞれのシリーズの「最終到達地点」 ということになります。
あわせて読みたい
【ドラマ】「フェルマーの最終定理」のドラマティックな証明物語を、飲茶氏が平易に描き出す:『哲学的…
「フェルマーの最終定理」は、問題の提示から350年以上経ってようやく証明された超難問であり、その証明の過程では様々な人間ドラマが知られている。『哲学的な何か、あと数学とか』をベースに、数学的な記述を一切せず、ドラマティックなエピソードだけに触れる
冒頭からしばらくの間は、「これがどんな風に最終到達地点に関係するのだろうか?」と感じるような話が展開されます。しかし読んでいくと、「なるほど、最終到達地点にたどり着くためにこのような順番になっているのか」と理解できる 、という流れになるわけです。
どのシリーズにおいても、「最終到達地点」が近づくにつれて説明はかなり高度で難しくなり、相当の数学力を持つ人でなければ読み解けないだろうと思います(私も、「最終到達地点」については、何が書いてあるのかほとんど理解できないことが多いです)。ただし、「最終到達地点」に近づくまでは、数学初心者でも結構ついていける内容 ですし、説明の流れに乗って行けば、自力ではまず到達できない高みまでたどり着く ことは間違いないと思っています。
あわせて読みたい
【証明】結城浩「数学ガール」とサイモン・シンから「フェルマーの最終定理」とそのドラマを学ぶ
350年以上前に一人の数学者が遺した予想であり「フェルマーの最終定理」には、1995年にワイルズによって証明されるまでの間に、これでもかというほどのドラマが詰め込まれている。サイモン・シンの著作と「数学ガール」シリーズから、その人間ドラマと数学的側面を知る
この記事にしても、「最終到達地点」である「ゲーデルの不完全性定理」についてはほぼ説明しません 。私が他人に説明できるほど理解できていないからです。なのでこの記事では、「どのようなステップを踏んでゲーデルの不完全性定理に辿り着こうとしているのか」について触れていこうと思います。
一般向けの数学書で、難易度を安易に落とさずに、それでいてこれほど面白い作品ってなかなかないよね
「ペアノの公理」とは何か?
このシリーズには、メインキャラクターではありませんが、村木先生という数学教師 も登場します。主人公やテトラちゃんに、数学をより深く理解するための問題を出してくれる人物 です。
あわせて読みたい
【バトル】量子力学の歴史はこの1冊で。先駆者プランクから批判者アインシュタインまですべて描く:『量…
20世紀に生まれた量子論は、時代を彩る天才科学者たちの侃々諤々の議論から生み出された。アインシュタインは生涯量子論に反対し続けたことで知られているが、しかし彼の批判によって新たな知見も生まれた。『量子革命』から、量子論誕生の歴史を知る
本書では、細々した話が冒頭で展開された後、最初に出てくる大きな話が村木先生が出してくれた「ペアノの公理」になります。「ペアノの公理」とは一体なんでしょうか ? まずはその定義を書き出してみます。
① 1は自然数である
仰々しく書かれたこの「ペアノの公理」は、「自然数を定義する」ために必要なもの です。
あわせて読みたい
【歴史】ベイズ推定は現代社会を豊かにするのに必須だが、実は誕生から200年間嫌われ続けた:『異端の統…
現在では、人工知能を始め、我々の生活を便利にする様々なものに使われている「ベイズ推定」だが、その基本となるアイデアが生まれてから200年近く、科学の世界では毛嫌いされてきた。『異端の統計学ベイズ』は、そんな「ベイズ推定」の歴史を紐解く大興奮の1冊だ
「自然数」って、「1,2,3,4…」でしょ? 定義するも何も無くない?
大事なことは、「自然数がどういうものなのか『知らないフリ』をする 」ということです。私たちは「自然数」がどんなものなのか知っているので、それを「定義する」なんて意味があるように思えません。ただ、「知っているから定義しなくていい」というのも、数学的な態度ではないとも言えます。
だから、当たり前の存在でしかない「自然数」とは何なのかについてとりあえず一旦「知らないフリ」をして、「自然数」をどのようにきちんと定義した上で作り出すか、という話が展開されます 。
あわせて読みたい
【興奮】素数の謎に迫った天才数学者たちの奮闘と、数学の”聖杯”である「リーマン予想」について:『素…
古今東西の数学者を惹きつけて止まない「素数」。その規則性を見つけ出すことは非常に困難だったが、「リーマン予想」として初めてそれが示された。『素数の音楽』『リーマン博士の大予想』から、天才数学者たちが挑んできた「リーマン予想」をざっくり理解する
しかし、「1,2,3,4…」を定義するために、これだけ複雑そうに見えるルールが必要なんだなぁ 、と思うと、なんとなく不思議な感じがしてきます。
「0.999999…=1」について
それから話は「無限」に移っていきます 。「無限」の話は数学の世界の中でも結構ややこしく、不思議な話がたくさんあるのです。そんな「無限」の不思議について議論が展開される ことになります。
あわせて読みたい
【快挙】「チバニアン」は何が凄い?「地球の磁場が逆転する」驚異の現象がこの地層を有名にした:『地…
一躍その名が知れ渡ることになった「チバニアン」だが、なぜ話題になり、どう重要なのかを知っている人は多くないだろう。「チバニアン」の申請に深く関わった著者の『地磁気逆転と「チバニアン」』から、地球で起こった過去の不可思議な現象の正体を理解する
「無限」の話で興味深いと感じたのが、「0.999999…=1」です。「0.999999…」と「1」が同じ数 だ、ということは昔から知っていたのですが、その解釈について面白いことが書かれていました。
まず、私が元から知っていた話を書きましょう。なぜ「0.999999…=1」になるのかについての説明です 。
① x=0.999999…と置く
まあ、そう見えるかもしれないけど、別に騙してないし、数学的にはこれで合ってるのよ
あわせて読みたい
【貢献】有名な科学者は、どんな派手な失敗をしてきたか?失敗が失敗でなかったアインシュタインも登場…
どれほど偉大な科学者であっても失敗を避けることはできないが、「単なる失敗」で終わることはない。誤った考え方や主張が、プラスの効果をもたらすこともあるのだ。『偉大なる失敗』から、天才科学者の「失敗」と、その意外な「貢献」を知る
計算的な理解は元々していましたが、「0.999999…=1」というのが一体どういう意味なのか については、本書を読むまできちんと理解していませんでした。
その点に関しては、ユーリの発言を引用 することにしましょう。
この、「0.999…」という書き方が犯人だ。これ紛らわしいっ!
●0.9、0.99、0.999、…は、♡に限りなく近づく。
こんなふうに言ってくれれば、何も混乱しないのに
ここで重要なポイントは、「0.9、0.99、0.999の先に、0.999…は出てこない」という部分です。
あわせて読みたい
【敗北】「もつれ」から量子論の基礎を学ぶ。それまでの科学では説明不能な「異次元の現象」とは?:『…
アインシュタインは量子力学を生涯受け入れなかったのだが、アインシュタインが批判し続けたことによって明らかになったこともある。「もつれ」の重要性もその一つだ。『宇宙は「もつれ」でできている』から量子力学の基礎を成す現象を知る。
私もなんとなく、いつか「0.999…」が出てくるという風に思っていたんです。でもそうじゃないと。ユーリは「♡」と表記していますが、要するに数学では、
0.9、0.99、0.999と進んでいくと、その数字の列は『ある数♡』に近づく
とまず考え、その上で、
その『ある数♡』は、0.9、0.99、0.999と進んでいった先には出てこない。その出てこない『ある数♡』を、とりあえず0.999…と表記することに決めた
というわけです。
あわせて読みたい
【知的】文系にオススメの、科学・数学・哲学の入門書。高橋昌一郎の「限界シリーズ」は超絶面白い:『…
例えば「科学」だけに限ってみても、「なんでもできる」わけでは決してない。「科学」に限らず、私たちが対峙する様々な事柄には「これ以上は不可能・無理」という「限界」が必ず存在する。高橋昌一郎の「限界シリーズ」から、我々が認識しておくべき「限界」を易しく学ぶ
さらに、
0.9、0.99、0.999と進んでいくことでこの数字の列が近づいていく『ある数♡』とは1である
というのも当然の話です、だからこそ、
0.999999…=1という結論になる
ということになります。
あわせて読みたい
【天才】『ご冗談でしょう、ファインマンさん』は、科学者のイメージが変わる逸話満載の非・科学エッセイ
「天才科学者」と言えばアインシュタインやニュートン、ホーキングが思い浮かぶだろうが、「科学者らしくないエピソード満載の天才科学者」という意味ではファインマンがずば抜けている。世界的大ベストセラー『ご冗談でしょう、ファインマンさん』は、「科学」をほぼ扱わないエッセイです
でも、さっきの計算よりは、騙されてる感はないでしょ?
0.999999…は、見た目は「1よりちょっと小さい数」っぽいですが、そうではなく「1」と同じ数だ、ということが理解できるのではないでしょうか。
カントールの対角線論法と極限
「無限」の流れからさらに、「カントールの対角線論法 」の話が続きます。
あわせて読みたい
【使命】「CRISPR-Cas9」を分かりやすく説明。ノーベル賞受賞の著者による発見物語とその使命:『CRISPR…
生物学の研究を一変させることになった遺伝子編集技術「CRISPR-Cas9」の開発者は、そんな発明をするつもりなどまったくなかった。ノーベル化学賞を受賞した著者による『CRISPR (クリスパー) 究極の遺伝子編集技術の発見』をベースに、その発見物語を知る
私はこの「カントールの対角線論法」が、数学の証明の中で一番好き です。ちゃんと理屈を追っていけば文系の人でも全然理解できる証明 なのですが、「よくこんな手法思いついたな」と感じると共に、「そもそもよくこんなことを証明しようと考えたな」という驚き があります。
ただ、図を使わずに説明するのが困難なので、この記事では「カントールの対角線論法」そのものの説明はしません。本書を読むか、以下のリンク先に飛ぶかしてください(ネットで探して、分かりやすいと思った記事です)。
数学美術館
『無限について ~カントールの対角線論法~』
こんにちは。数学学芸員のようじです。無限の話もだんだんと終わりに近づいてきました。今日ご紹介するのは、無限の話で最も大切なカントールの対角線論法です。これを理…
「カントールの対角線論法」そのものの説明はしませんが、「カントールの対角線論法」によってカントールが何を証明したのか については触れておきましょう。
これは、「自然数と実数はどちらの方が多いか」という問題と関係します 。「多い」という表現は正確ではなくて、「濃度が高い」と表記すべきなのですが、ここでは「多い」と書きます。
あわせて読みたい
【謎】恐竜を絶滅させた隕石はどこから来た?暗黒物質が絡む、リサ・ランドールの驚愕の仮説:『ダーク…
「生物の絶滅」には、以前から知られていたある謎があった。そしてその謎を、未だに観測されておらず、「科学者の妄想の産物」でしかない「ダークマター(暗黒物質)」が解決するかもしれない。現役の科学者が『ダークマターと恐竜絶滅』で語る驚きの仮説。
「自然数と実数」の話の前に、まず「自然数」と「正の偶数」について考えましょう。つまり、「自然数と正の偶数はどっちの方が多いか 」という話です。
そもそも、何が問われているんだかよく分かんないよね
ホントそう。だから、「カントールはよくもまあこんなことを考えたもんだよなぁ」って思うんだよね
あわせて読みたい
【研究】光の量子コンピュータの最前線。量子テレポーテーションを実現させた科学者の最先端の挑戦:『…
世界中がその開発にしのぎを削る「量子コンピューター」は、技術的制約がかなり高い。世界で初めて「量子テレポーテーション」の実験を成功させた研究者の著書『光の量子コンピューター』をベースに、量子コンピューター開発の現状を知る
自然数というのは「1,2,3,4…」であり、正の偶数は「2,4,6,8…」となっていくのだから、なんとなくイメージとしては「自然数の方が正の偶数より多い」と考えてしまうかもしれません 。確かに、「100までの自然数」と「100までの正の偶数」なら、明らかに「100までの自然数」の方が多いと言えます。
しかしこの話のポイントは、どちらも無限について考えているという点です。「無限の自然数」と「無限の正の偶数」ならどちらが多いかという話になると、何をどう説明をすればいいか分からなくなるでしょう 。
そこでカントールは、「一対一の対応」という基準 を考えました。そして、「一対一の対応が付くものは同じだけ存在する(濃度が同じ) 」と考えたわけです。
具体的に見ていきましょう。
あわせて読みたい
【誤解】「意味のない科学研究」にはこんな価値がある。高校生向けの講演から”科学の本質”を知る:『す…
科学研究に対して、「それは何の役に立つんですか?」と問うことは根本的に間違っている。そのことを、「携帯電話」と「東急ハンズの棚」の例を使って著者は力説する。『すごい実験』は素粒子物理学を超易しく解説する本だが、科学への関心を抱かせてもくれる
自然数:1 2 3 4 5 6 …
上記のように、ある自然数を1つ選べば、それに対応する正の偶数を必ず1つ対応させることができます 。これは、自然数がどれほど大きくなっても変わりません。どんな自然数に対しても、それに対応する正の偶数を指定できると分かるでしょう。
このように、「一対一の対応が付くものは同じだけ存在する」と考えたわけです。
さて、その後カントールは、同じ議論を「自然数」と「実数」で行おうとします 。つまり、自然数と実数に一対一の対応が付くのか? ということです。
あわせて読みたい
【異端】数学の”証明”はなぜ生まれたのか?「無理数」と「無限」に恐怖した古代ギリシャ人の奮闘:『数…
学校で数学を習うと、当然のように「証明」が登場する。しかしこの「証明」、実は古代ギリシャでしか発展しなかった、数学史においては非常に”異端”の考え方なのだ。『数学の想像力 正しさの深層に何があるのか』をベースに、ギリシャ人が恐れたものの正体を知る
そして、この証明に使われたものこそ「カントールの対角線論法」 であり、カントールは、「自然数と実数に一対一の対応は付かない」と証明しました。
「実数」というのは、小数や無理数まで含めたありとあらゆる数のことです。もちろん、自然数も実数に含まれています。普通に考えれば当然、「自然数より実数の方が多い」となるでしょう。しかし先程「自然数と正の偶数」で考えた時も、イメージと異なる結果が出ました。数学においては、厳密な議論を行わずにイメージで捉えると間違えてしまう 状況は多々あります。
そこで厳密な議論をカントールが行い、そのハイパーテクニカルな手法によって、「一対一の対応は付かない」、つまり「自然数よりも実数の方が多い」と証明できた というわけです。
あわせて読みたい
【快挙】「暗黒の天体」ブラックホールはなぜ直接観測できたのか?国際プロジェクトの舞台裏:『アイン…
「世界中に存在する電波望遠鏡を同期させてブラックホールを撮影する」という壮大なEHTプロジェクトの裏側を記した『アインシュタインの影』から、ブラックホール撮影の困難さや、「ノーベル賞」が絡む巨大プロジェクトにおける泥臭い人間ドラマを知る
そしてこれは、「無限にも大きさがある」という事実を示してもいます 。自然数も無限に存在するのですが、「自然数の無限」よりも「実数の無限」の方が大きい、というわけです。同じ無限でも、「一方の無限の方がより大きい」と示した のですね。
ホント、よくもまあこんなことを考えたもんだと思います。
「無限に大きさがある」なんて、意味不明な話だもんなぁ
さらにそこから、極限の話 も展開されます。理系の人間なら必ず行う「lim」の計算ですね。
あわせて読みたい
【感想】飲茶の超面白い東洋哲学入門書。「本書を読んでも東洋哲学は分からない」と言う著者は何を語る…
東洋哲学というのは、「最終回しか存在しない連続ドラマ」のようなものだそうだ。西洋哲学と比較にならないほど異質さと、インド哲学・中国哲学など個別の思想を恐ろしく分かりやすく描く『史上最強の哲学入門 東洋の哲人たち』は、ページをめくる手が止まらないくらい、史上最強レベルに面白かった
私は学生時代、この極限の話をうまく理解できませんでした。計算のやり方は覚えればいいし、試験などでさほど困ることはありませんでしたが、「極限について考えることな何を意味しているのか?」という点が全然分からなかった のです。
本書ではそんな「極限」について、定義からきちんと捉えなおそう、という話が展開されます。やはり定義の話は理解にてこずるわけですが、しかし、「極限とは一体何なのか?」について、なんとなく分かったような気になれる説明 でした。
「形式的体系」について
さてそれから、「最終到達地点」である「ゲーデルの不完全性定理」に直接的に関係する話 が出てきます。それが「形式的体系 」です。
あわせて読みたい
【誤解】世界的大ベストセラー『ファクトフルネス』の要約。我々は「嘘の情報」を信じ込みやすい
世界の現状に関する13の質問に対して、ほとんどの人が同じ解答をする。最初の12問は不正解で、最後の1問だけ正答するのだ。世界的大ベストセラー『ファクトフルネス』から、「誤った世界の捉え方」を認識し、情報を受け取る際の「思い込み」を払拭する。「嘘の情報」に踊らされないために読んでおくべき1冊だ
これも非常に説明しにくいものですが、頑張ってみます。
まず大雑把に歴史の話 をしていきましょう。
「形式的体系」というのは、ヒルベルトという数学者が「数学を体系的に整理しよう」と考えたプロジェクトが関係しています 。ヒルベルトは、「シアン・マゼンタ・イエロー(色の3原色)の3色ですべての色を作り出せるのと同じように、「限られた公理と推論規則から数学のすべての定理を証明できるはずだ 」と考え、その大目標の実現のために動き出すのです。
しかし、そのヒルベルトプログラムを粉砕し、「あなたがやろうとしていることは不可能ですよ」と突きつけた人物 がいます。それがゲーデルという数学者であり、ヒルベルトの野望を砕いた理論が「ゲーデルの不完全性定理」 だというわけです。
あわせて読みたい
【興奮】飲茶氏が西洋哲学を語る。難解な思想が「グラップラー刃牙成分」の追加で驚異的な面白さに:『…
名前は聞いたことはあるがカントやニーチェがどんな主張をしたのかは分からないという方は多いだろう。私も無知なまったくの初心者だが、そんな人でも超絶分かりやすく超絶面白く西洋哲学を”分かった気になれる”飲茶『史上最強の哲学入門』は、入門書として最強
というわけでこの「形式的体系」は、「ゲーデルの不完全性定理」が生まれたきっかけとして重要 だということになります。
でも、「不可能だ」って早い段階で分かったことで、それ以上無駄な時間を過ごさずに済んだ、とも言えるかもよ
それでは、「形式的体系」について、私が理解した範囲のことに触れていきましょう。
そもそも「数学」という学問は、世界各地さまざまな時代の数学者による発見を組み合わせたもの です。それはつまり、「設計図が存在し、順番に組み上げている」わけではない 、ということを意味します。
あわせて読みたい
【興奮】飲茶氏の超面白い哲学小説。「正義とは?」の意味を問う”3人の女子高生”の主張とは?:『正義の…
なんて面白いんだろうか。哲学・科学を初心者にも分かりやすく伝える飲茶氏による『正義の教室』は、哲学書でありながら、3人の女子高生が登場する小説でもある。「直観主義」「功利主義」「自由主義」という「正義論」の主張を、「高校の問題について議論する生徒会の話し合い」から学ぶ
たとえば家を建てる時には、まず設計図を作り、必要な材料を揃え、作業員と打ち合わせをし、スケジュールを決める、というようなステップを踏むでしょう。しかし数学はそうではなく、家造りに喩えるなら、「誰かが浴室を作る」「別の人がリビングの床を敷く」「支える柱が足りないのに屋根が先に完成する」など、てんでばらばらの流れの中で作られていった というわけです。
当然、そんなやり方をしていたら、「謎の空間ができた」「何も支えていない柱がある」など、「家」を組み上げていくのに支障が出てくるでしょう。実際に数学においても、「あれ? なんかここでおかしなことが起こりそうだ 」「ここになんか矛盾が発生するぞ 」というような状況が出るようになってしまいました。
そこでヒルベルトが、「家を建てる時のように、正しい順番で『数学』を組み上げていこう」と考える わけです。
あわせて読みたい
【最新】「コロンブス到達以前のアメリカ大陸」をリアルに描く歴史書。我々も米国人も大いに誤解してい…
サイエンスライターである著者は、「コロンブス到着以前のアメリカはどんな世界だったか?」という問いに触れ、その答えが書かれた本がいつまで経っても出版されないので自分で執筆した。『1491 先コロンブス期アメリカ大陸をめぐる新発見』には、アメリカ人も知らない歴史が満載だ
このようにして、「限られた公理と推論規則から数学の定理を証明する」というヒルベルトプログラム がスタートします。
これはある意味で、「釘を使わない宮大工」のようなイメージでいいかもしれません。「木材と瓦という限られた材料」と「木を組み合わせる継手・仕口」だけで家を建てるように、「限られた公理」と「証明済みの定理を含む公理をどう組み合わせるかの推論規則」だけを使って、既に知られているすべての定理を証明しよう というのがヒルベルトプログラムの根幹であり、このようにして整えられた数学の体系を「形式的体系」と呼ぶ わけです。
壮大なプロジェクトで時間は掛かりそうだけど、確かに、やれそうな気はするよね
あわせて読みたい
【対立】数学はなぜ”美しい”のか?数学は「発見」か「発明」かの議論から、その奥深さを知る:『神は数…
数学界には、「数学は神が作った派」と「数学は人間が作った派」が存在する。『神は数学者か?』をベースに、「数学は発見か、発明か」という議論を理解し、数学史においてそれぞれの認識がどのような転換点によって変わっていったのかを学ぶ
しかしヒルベルトの野望はゲーデルによって打ち砕かれてしまう のでした。
「ゲーデルの不完全性定理」についてざっくりと
本書では、ラストに畳み掛けるようにして「ゲーデルの不完全性定理」の話が展開されますが、やはりこれは非常に難しいと感じました。もちろん、字面を追うことで、なんとなく分かったような気分にはなれるのですが、誰かに説明できるほど理解はできていません。
というわけでこの記事では、「ゲーデルの不完全性定理」についてはざっくりと書く に留めます。
さて、「ゲーデルの不完全性定理」はヒルベルトの計画を打ち砕いたわけですが、どのように打ち砕いたのでしょうか? その説明をするために、ヒルベルトが構築しようとしていた「形式的体系」についてもう少し説明をする 必要があります。
ヒルベルトは「形式的体系」において、数学の「完全性」と「無矛盾性」を示そうとしていました 。これは、より具体的には以下のようになります。
あわせて読みたい
【興奮】世界的大ベストセラー『サピエンス全史』要約。人類が文明を築き上げるに至った3つの革命とは?
言わずと知れた大ベストセラー『サピエンス全史』は、「何故サピエンスだけが人類の中で生き残り、他の生物が成し得なかった歴史を歩んだのか」を、「認知革命」「農業革命」「科学革命」の3つを主軸としながら解き明かす、知的興奮に満ち溢れた1冊
完全性:真である命題は必ず証明できる
「完全性」については何となく「当たり前だろう」と感じないでしょうか? これは「正しい主張は正しいと証明できる」ということで、数学はそういう学問だと思っている人も多いでしょう 。また、「矛盾が生じるような現状に対処したい」という動機からヒルベルトプログラムが生まれたのですから、「無矛盾性」を期待するのも当然 と言えます。
しかしゲーデルは「ゲーデルの不完全性定理」によって、ヒルベルトの期待を打ち砕く以下の2点を証明してしまいました 。
・形式的体系が無矛盾なら、それは完全ではない
あわせて読みたい
【知】内田樹が教育・政治を語る。「未来の自分」を「別人」と捉える「サル化した思考」が生む現実:『…
「朝三暮四」の故事成語を意識した「サル化」というキーワードは、現代性を映し出す「愚かさ」を象徴していると思う。内田樹『サル化する世界』から、日本の教育・政治の現状及び問題点をシンプルに把握し、現代社会を捉えるための新しい視点や価値観を学ぶ
つまりこういうことです。ヒルベルトは 、
数学は「完全」かつ「無矛盾」で、それを証明することができる
と考えていたのですが、ゲーデルは 、
数学がもし「無矛盾」なら「完全ではない」し、数学がもし「無矛盾」だとしても「その無矛盾性は証明できない」
と証明したわけです。
ゲーデルは、「我々が接している数学」が完全なのか、あるいは無矛盾なのかについては語っていない ことに注意しましょう。そして彼は、「数学が無矛盾なら完全ではない」と示すことで、ヒルベルトの「数学は完全かつ無矛盾だ」という考えを打ち砕くことになります。さらに、「無矛盾性」についても、「もし数学が無矛盾だとしても、そのことを証明することはできない」と証明してしまったわけです。
あわせて読みたい
【驚嘆】「現在は森でキノコ狩り」と噂の天才”変人”数学者グリゴリー・ペレルマンの「ポアンカレ予想証…
数学界の超難問ポアンカレ予想を解決したが、100万ドルの賞金を断り、フィールズ賞(ノーベル賞級の栄誉)も辞退、現在は「森できのこ採取」と噂の天才数学者グリゴリー・ペレルマンの生涯を描く評伝『完全なる証明』。数学に関する記述はほぼなく、ソ連で生まれ育った1人の「ギフテッド」の苦悩に満ちた人生を丁寧に描き出す1冊
ヒルベルトの大目標にとっては大きな打撃 だということが分かるでしょう。
しかし、「証明できないことを証明する」なんて出来るの?
うーん、私には「ゲーデルの不完全性定理」の証明は難しくて理解できなかったけれど、出来たってことなんだろうね
こんなアクロバティックな証明をゲーデルがいかに行ったのかという流れが、本書にはかなり詳細に記されています 。正直、一読しただけで理解できるような簡単なものではなく、私には難しすぎました。ただ、一般的な数学書では、「ゲーデルの不完全性定理はどういうものなのか」について語られることはあっても、その証明の詳細に触れられることはほぼないので、そういう意味ではかなり貴重な作品 だと言えると思います。
本書を読んでいて、ゲーデルの発想の凄さに驚かされたのが「ゲーデル数」 です。
あわせて読みたい
【驚異】数学の「無限」は面白い。アキレスと亀の矛盾、実無限と可能無限の違い、カントールの対角線論…
日常の中で「無限」について考える機会などなかなか無いだろうが、野矢茂樹『無限論の教室』は、「無限には種類がある」と示すメチャクチャ興味深い作品だった。「実無限」と「可能無限」の違い、「可能無限」派が「カントールの対角線論法」を拒絶する理由など、面白い話題が満載の1冊
ゲーデルは、「論理式」について深く考えることで「ゲーデルの不完全性定理」を導きました 。「論理式」というのは、「命題を記号で表したもの」で、例えば「1+1=2」も論理式です。論理式には、「+」「>」などのお馴染みのものから、「!%」「&&」のように見慣れない記号まで出てきますが、いずれにしても何らかの「記号」が関係しています。
そしてゲーデルは、それぞれの「記号」に特殊な方法で「固有の数字」を対応させました 。それが「ゲーデル数」です。
つまりゲーデルは、「論理式」を記号まで含めてすべて「数字」に変換することで議論を進めやすくし、それによって「ゲーデルの不完全性定理」を導いたわけです。
「記号を数字に変換する」という発想がまず凄いし、その実現のためにゲーデルが考えたことも見事だと感じます。「ゲーデルの不完全性定理」に関してはところどころしか理解できませんでしたが、この「ゲーデル数」にはとにかく驚かされました。
あわせて読みたい
【情報】日本の社会問題を”祈り”で捉える。市場原理の外にあるべき”歩哨”たる裁き・教育・医療:『日本…
「霊性」というテーマは馴染みが薄いし、胡散臭ささえある。しかし『日本霊性論』では、「霊性とは、人間社会が集団を存続させるために生み出した機能」であると主張する。裁き・教育・医療の変化が鈍い真っ当な理由と、情報感度の薄れた現代人が引き起こす問題を語る
Softbank Creative/Tsai Fong Books
¥1,980 (2022/01/29 21:42時点 | Amazon調べ)
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品読了済】私が読んできたノンフィクション・教養書を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が読んできたノンフィクションを様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本選びの参考にして下さい。
最後に
あわせて読みたい
【希望】貧困の解決は我々を豊かにする。「朝ベッドから起きたい」と思えない社会を変える課題解決:『…
現代は、過去どの時代と比べても安全で清潔で、豊かである。しかしそんな時代に、我々は「幸せ」を実感することができない。『隷属なき道』をベースに、その理由は一体なんなのか何故そうなってしまうのかを明らかにし、さらに、より良い暮らしを思い描くための社会課題の解決に触れる
本書の「最終到達地点」である「ゲーデルの不完全性定理」は確かに超絶難しいのですが、難しい話ばかり載っているわけではなく、「数学ってこんな見方も出来るんだ」と感じられるような作品 だと思います。数学が嫌いな人には勧めませんが、数学に興味はあるけれど難しいというイメージのせいでなかなか手を出せない、と感じている人には是非読んでほしい作品です。
また、数学部分だけではなく、登場人物たちのやり取りも魅力的 だと思います。中でも私はミルカさんが好きなんですが、とにかく数学が頭から離れない彼女が主人公を励ます場面も、非常に数学的で面白いです。
きみには――すべての次元が見えているのかな
あわせて読みたい
【天才】『三島由紀夫vs東大全共闘』後に「伝説の討論」と呼ばれる天才のバトルを記録した驚異の映像
1969年5月13日、三島由紀夫と1000人の東大全共闘の討論が行われた。TBSだけが撮影していたフィルムを元に構成された映画「三島由紀夫vs東大全共闘」は、知的興奮に満ち溢れている。切腹の一年半前の討論から、三島由紀夫が考えていたことと、そのスタンスを学ぶ
3次元空間で見れば「螺旋」と分かるけれど、2次元空間で見るとそれは単なる「円周を回る点」でしかない、という話をすることで、「落ち込んでいるようだが、それは、見るべきものがちゃんと見えていないだけではないか」と示唆しているというわけです。「数学」が共通言語である2人だからこそ成立する励ましの言葉 で、こういうやり取りもとてもいいなと感じます。
濃密な「数学体験」を是非。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【奇妙】大栗博司『重力とはなにか』は、相対性理論や量子力学の説明も秀逸だが、超弦理論の話が一番面白い
『重力とはなにか』(大栗博司)は、科学に馴染みの薄い人でもチャレンジできる易しい入門書だ。相対性理論や量子力学、あるいは超弦理論など、非常に難解な分野を基本的なところから平易に説明してくれるので、「科学に興味はあるけど難しいのはちょっと……」という方にこそ読んでほしい1冊
あわせて読みたい
【驚嘆】「現在は森でキノコ狩り」と噂の天才”変人”数学者グリゴリー・ペレルマンの「ポアンカレ予想証…
数学界の超難問ポアンカレ予想を解決したが、100万ドルの賞金を断り、フィールズ賞(ノーベル賞級の栄誉)も辞退、現在は「森できのこ採取」と噂の天才数学者グリゴリー・ペレルマンの生涯を描く評伝『完全なる証明』。数学に関する記述はほぼなく、ソ連で生まれ育った1人の「ギフテッド」の苦悩に満ちた人生を丁寧に描き出す1冊
あわせて読みたい
【驚異】数学の「無限」は面白い。アキレスと亀の矛盾、実無限と可能無限の違い、カントールの対角線論…
日常の中で「無限」について考える機会などなかなか無いだろうが、野矢茂樹『無限論の教室』は、「無限には種類がある」と示すメチャクチャ興味深い作品だった。「実無限」と「可能無限」の違い、「可能無限」派が「カントールの対角線論法」を拒絶する理由など、面白い話題が満載の1冊
あわせて読みたい
【挑戦】相対性理論の光速度不変の原理を無視した主張『光速より速い光』は、青木薫訳だから安心だぞ
『光速より速い光』というタイトルを見て「トンデモ本」だと感じた方、安心してほしい。「光速変動理論(VSL理論)」が正しいかどうかはともかくとして、本書は実に真っ当な作品だ。「ビッグバン理論」の欠陥を「インフレーション理論」以外の理屈で補う挑戦的な仮説とは?
あわせて読みたい
【おすすめ】「天才」を描くのは難しい。そんな無謀な挑戦を成し遂げた天才・野崎まどの『know』はヤバい
「物語で『天才』を描くこと」は非常に難しい。「理解できない」と「理解できる」を絶妙なバランスで成り立たせる必要があるからだ。そんな難題を高いレベルでクリアしている野崎まど『know』は、異次元の小説である。世界を一変させた天才を描き、「天才が見ている世界」を垣間見せてくれる
あわせて読みたい
【奇人】天才数学者で、自宅を持たずに世界中を放浪した変人エルデシュは、迷惑な存在でも愛され続けた…
数学史上ガウスに次いで生涯発表論文数が多い天才エルデシュをご存知だろうか?数学者としてずば抜けた才能を発揮したが、それ以上に「奇人変人」としても知られる人物だ。『放浪の天才数学者エルデシュ』で、世界中の数学者の家を泊まり歩いた異端数学者の生涯を描き出す
あわせて読みたい
【実話】映画『イミテーションゲーム』が描くエニグマ解読のドラマと悲劇、天才チューリングの不遇の死
映画『イミテーションゲーム』が描く衝撃の実話。「解読不可能」とまで言われた最強の暗号機エニグマを打ち破ったのはなんと、コンピューターの基本原理を生み出した天才数学者アラン・チューリングだった。暗号解読を実現させた驚きのプロセスと、1400万人以上を救ったとされながら偏見により自殺した不遇の人生を知る
あわせて読みたい
【本質】子どもの頃には読めない哲学書。「他人の哲学はつまらない」と語る著者が説く「問うこと」の大…
『<子ども>のための哲学』は決して、「子どもでも易しく理解できる哲学の入門書」ではない。むしろかなり難易度が高いと言っていい。著者の永井均が、子どもの頃から囚われ続けている2つの大きな疑問をベースに、「『哲学する』とはどういうことか?」を深堀りする作品
あわせて読みたい
【最新】「コロンブス到達以前のアメリカ大陸」をリアルに描く歴史書。我々も米国人も大いに誤解してい…
サイエンスライターである著者は、「コロンブス到着以前のアメリカはどんな世界だったか?」という問いに触れ、その答えが書かれた本がいつまで経っても出版されないので自分で執筆した。『1491 先コロンブス期アメリカ大陸をめぐる新発見』には、アメリカ人も知らない歴史が満載だ
あわせて読みたい
【異端】「仏教とは?」を簡単に知りたい方へ。ブッダは「異性と目も合わせないニートになれ」と主張し…
我々が馴染み深い「仏教」は「大乗仏教」であり、創始者ゴータマ・ブッダの主張が詰まった「小乗仏教」とは似て非なるものだそうだ。『講義ライブ だから仏教は面白い!』では、そんな「小乗仏教」の主張を「異性と目も合わせないニートになれ」とシンプルに要約して説明する
あわせて読みたい
【飛躍】有名哲学者は”中二病”だった?飲茶氏が易しく語る「古い常識を乗り越えるための哲学の力」:『1…
『14歳からの哲学入門』というタイトルは、「14歳向けの本」という意味ではなく、「14歳は哲学することに向いている」という示唆である。飲茶氏は「偉大な哲学者は皆”中二病”だ」と説き、特に若い人に向けて、「新しい価値観を生み出すためには哲学が重要だ」と語る
あわせて読みたい
【知的】文系にオススメの、科学・数学・哲学の入門書。高橋昌一郎の「限界シリーズ」は超絶面白い:『…
例えば「科学」だけに限ってみても、「なんでもできる」わけでは決してない。「科学」に限らず、私たちが対峙する様々な事柄には「これ以上は不可能・無理」という「限界」が必ず存在する。高橋昌一郎の「限界シリーズ」から、我々が認識しておくべき「限界」を易しく学ぶ
あわせて読みたい
【感想】飲茶の超面白い東洋哲学入門書。「本書を読んでも東洋哲学は分からない」と言う著者は何を語る…
東洋哲学というのは、「最終回しか存在しない連続ドラマ」のようなものだそうだ。西洋哲学と比較にならないほど異質さと、インド哲学・中国哲学など個別の思想を恐ろしく分かりやすく描く『史上最強の哲学入門 東洋の哲人たち』は、ページをめくる手が止まらないくらい、史上最強レベルに面白かった
あわせて読みたい
【興奮】飲茶氏の超面白い哲学小説。「正義とは?」の意味を問う”3人の女子高生”の主張とは?:『正義の…
なんて面白いんだろうか。哲学・科学を初心者にも分かりやすく伝える飲茶氏による『正義の教室』は、哲学書でありながら、3人の女子高生が登場する小説でもある。「直観主義」「功利主義」「自由主義」という「正義論」の主張を、「高校の問題について議論する生徒会の話し合い」から学ぶ
あわせて読みたい
【驚異】ガイア理論の提唱者が未来の地球を語る。100歳の主張とは思えない超絶刺激に満ちた内容:『ノヴ…
「地球は一種の生命体だ」という主張はかなり胡散臭い。しかし、そんな「ガイア理論」を提唱する著者は、数々の賞や学位を授与される、非常に良く知られた科学者だ。『ノヴァセン <超知能>が地球を更新する』から、AIと人類の共存に関する斬新な知見を知る
あわせて読みたい
【興奮】飲茶氏が西洋哲学を語る。難解な思想が「グラップラー刃牙成分」の追加で驚異的な面白さに:『…
名前は聞いたことはあるがカントやニーチェがどんな主張をしたのかは分からないという方は多いだろう。私も無知なまったくの初心者だが、そんな人でも超絶分かりやすく超絶面白く西洋哲学を”分かった気になれる”飲茶『史上最強の哲学入門』は、入門書として最強
あわせて読みたい
【逸話】天才数学者ガロアが20歳で決闘で命を落とすまでの波乱万丈。時代を先駆けた男がもし生きていた…
現代数学に不可欠な「群論」をたった1人で生み出し、20歳という若さで決闘で亡くなったガロアは、その短い生涯をどう生きたのか?『ガロア 天才数学者の生涯』から、数学に関心を抱くようになったきっかけや信じられないほどの不運が彼の人生をどう変えてしまったのか、そして「もし生きていたらどうなっていたのか」を知る
あわせて読みたい
【挑戦】社会に欠かせない「暗号」はどう発展してきたか?サイモン・シンが、古代から量子暗号まで語る…
「暗号」は、ミステリやスパイの世界だけの話ではなく、インターネットなどのセキュリティで大活躍している、我々の生活に欠かせない存在だ。サイモン・シン『暗号解読』から、言語学から数学へとシフトした暗号の変遷と、「鍵配送問題」を解決した「公開鍵暗号」の仕組みを理解する
あわせて読みたい
【証明】結城浩「数学ガール」とサイモン・シンから「フェルマーの最終定理」とそのドラマを学ぶ
350年以上前に一人の数学者が遺した予想であり「フェルマーの最終定理」には、1995年にワイルズによって証明されるまでの間に、これでもかというほどのドラマが詰め込まれている。サイモン・シンの著作と「数学ガール」シリーズから、その人間ドラマと数学的側面を知る
あわせて読みたい
【衝撃】ABC予想の証明のために生まれたIUT理論を、提唱者・望月新一の盟友が分かりやすく語る:『宇宙…
8年のチェック期間を経て雑誌に掲載された「IUT理論(宇宙際タイヒミュラー理論)」は、数学の最重要未解決問題である「ABC予想」を証明するものとして大いに話題になった。『宇宙と宇宙をつなぐ数学』『abc予想入門』をベースに、「IUT理論」「ABC予想」について学ぶ
あわせて読みたい
【興奮】結城浩「数学ガール」で、決闘で命を落とした若き天才数学者・ガロアの理論を学ぶ
高校生を中心に、数学を通じて関わり合う者たちを描く「数学ガール」シリーズ第5弾のテーマは「ガロア理論」。独力で「群論」という新たな領域を切り開きながら、先駆的すぎて同時代の数学者には理解されず、その後決闘で死亡した天才の遺した思考を追う
あわせて読みたい
【対立】数学はなぜ”美しい”のか?数学は「発見」か「発明」かの議論から、その奥深さを知る:『神は数…
数学界には、「数学は神が作った派」と「数学は人間が作った派」が存在する。『神は数学者か?』をベースに、「数学は発見か、発明か」という議論を理解し、数学史においてそれぞれの認識がどのような転換点によって変わっていったのかを学ぶ
あわせて読みたい
【異端】数学の”証明”はなぜ生まれたのか?「無理数」と「無限」に恐怖した古代ギリシャ人の奮闘:『数…
学校で数学を習うと、当然のように「証明」が登場する。しかしこの「証明」、実は古代ギリシャでしか発展しなかった、数学史においては非常に”異端”の考え方なのだ。『数学の想像力 正しさの深層に何があるのか』をベースに、ギリシャ人が恐れたものの正体を知る
あわせて読みたい
【興奮】素数の謎に迫った天才数学者たちの奮闘と、数学の”聖杯”である「リーマン予想」について:『素…
古今東西の数学者を惹きつけて止まない「素数」。その規則性を見つけ出すことは非常に困難だったが、「リーマン予想」として初めてそれが示された。『素数の音楽』『リーマン博士の大予想』から、天才数学者たちが挑んできた「リーマン予想」をざっくり理解する
ルシルナ
科学・数学の知識を身につける【本・映画の感想】 | ルシルナ
中退していますが、理系の大学に通っていました。学校の勉強で一番好きだったのは数学・物理ですし、大人になってからも科学や数学の本を数多く読んできました。偉人たちの…
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…











































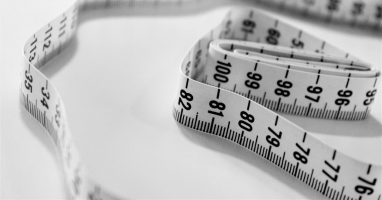
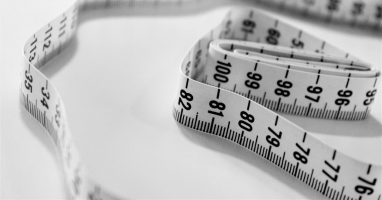
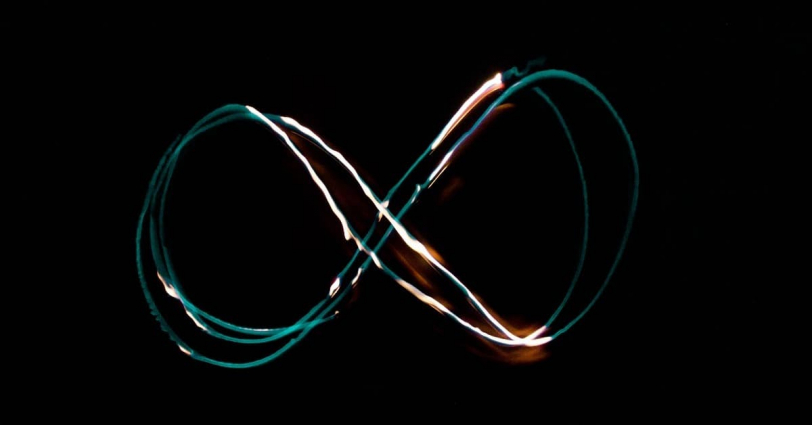
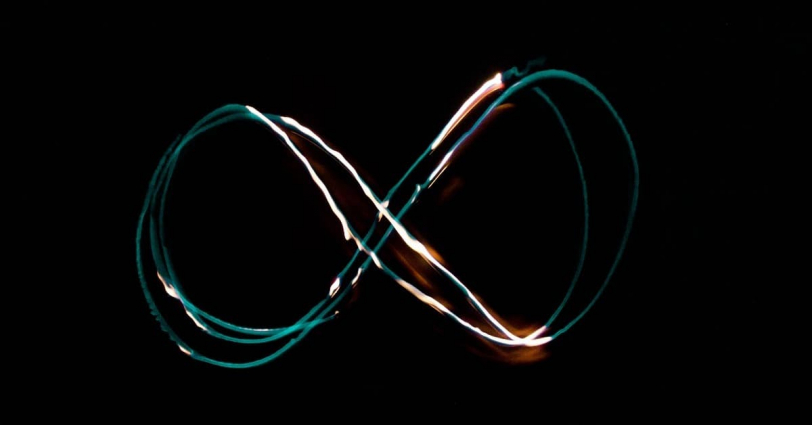







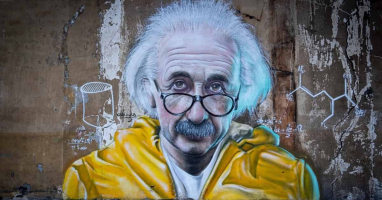
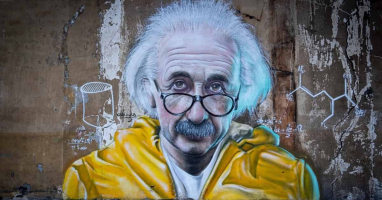













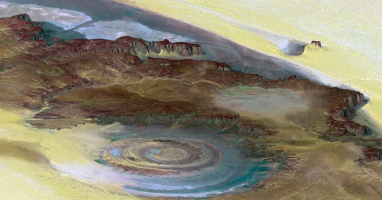
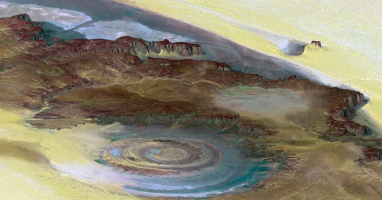



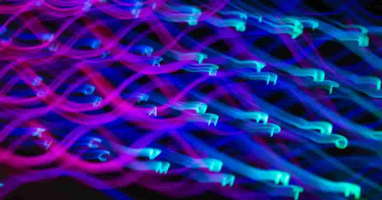
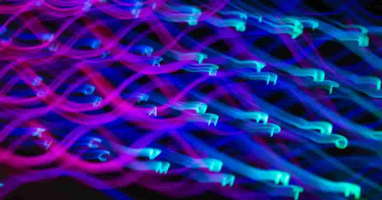


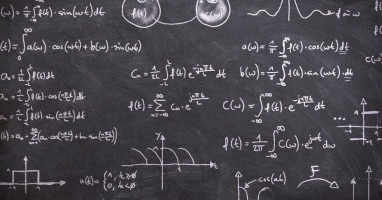
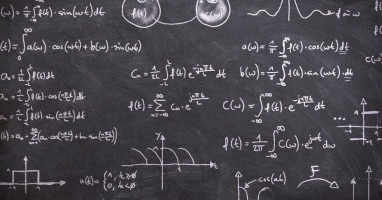
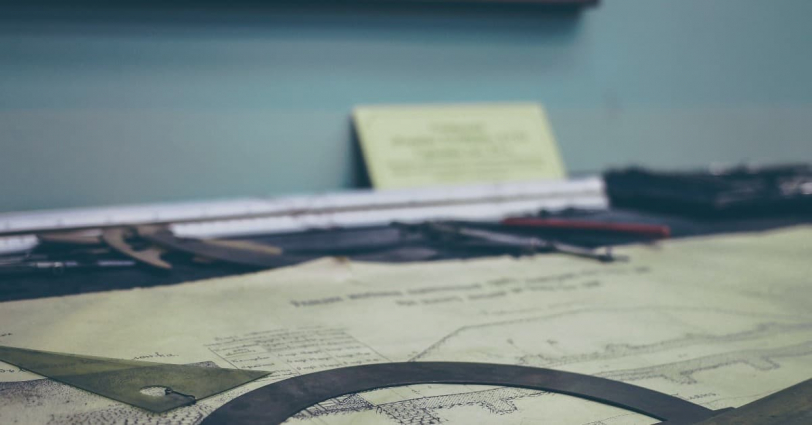
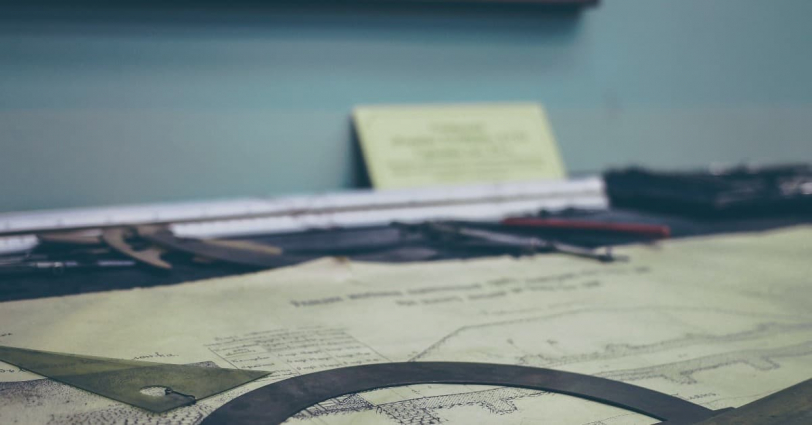




























































































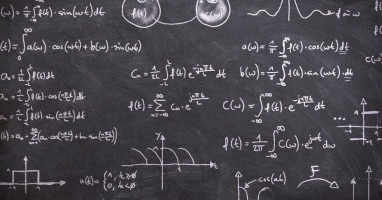
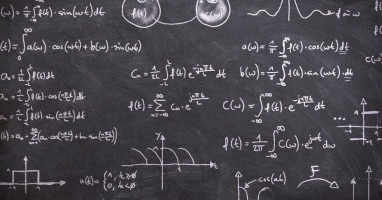
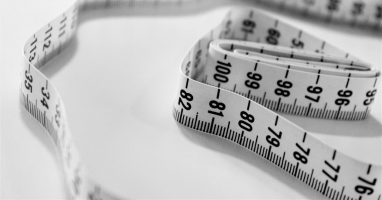
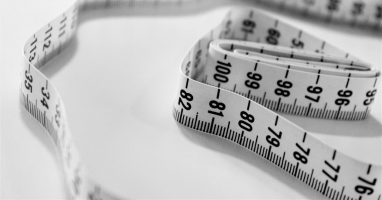















コメント