目次
はじめに
この記事で取り上げる本
著:クマール,マンジット, 翻訳:薫, 青木
¥1,155 (2021/10/20 07:31時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
この本をガイドにしながら記事を書いていきます
この記事の3つの要点
- 天才たちが嘆くほど、量子論は捉えにくく難しい
- 実は「アインシュタインの再評価」がなされている
- 量子論はどのように誕生し、アインシュタインはなぜ批判し続けたのか
量子論を先導するボーアと、不完全だと認めさせたいアインシュタインの攻防に興奮させられる
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を…
Kindleで本を出版しました。タイトルは、『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を分かりやすく書いた本:相対性理論も宇宙論も量子論も』です。科学や科学者に関する、文系の人でも読んでもらえる作品に仕上げました。そんな自著について紹介をしています。
「量子論」の歴史は本書『量子革命』ですべて知ることができる。天才たちの議論の応酬に大興奮
本書『量子革命』の構成
あわせて読みたい
【驚嘆】「現在は森でキノコ狩り」と噂の天才”変人”数学者グリゴリー・ペレルマンの「ポアンカレ予想証…
数学界の超難問ポアンカレ予想を解決したが、100万ドルの賞金を断り、フィールズ賞(ノーベル賞級の栄誉)も辞退、現在は「森できのこ採取」と噂の天才数学者グリゴリー・ペレルマンの生涯を描く評伝『完全なる証明』。数学に関する記述はほぼなく、ソ連で生まれ育った1人の「ギフテッド」の苦悩に満ちた人生を丁寧に描き出す1冊
本書は、物理学の「量子論」(「量子力学」とも表記する)という分野の誕生前夜から現在に至るまでの、その発展の歴史が描かれている作品だ。

科学に関する本には主に、「科学的な知識を紹介する本」と「科学の進展の歴史を伝える本」がある。そして作品によってどちらの比重がより大きいかは変わってくる。
本書は後者、つまり「科学の進展の歴史を伝える」という方に重点が置かれている。もちろんそれを描くためには、どの科学者がどんな主張をしたのかという科学的な説明にも触れる必要があるわけだが、本書で描こうとしているのは主に、「量子論はどのように発展したのか」という歴史の方である。
あわせて読みたい
【あらすじ】原爆を作った人の後悔・葛藤を描く映画『オッペンハイマー』のための予習と評価(クリスト…
クリストファー・ノーラン監督作品『オッペンハイマー』は、原爆開発を主導した人物の葛藤・苦悩を複雑に描き出す作品だ。人間が持つ「多面性」を様々な方向から捉えようとする作品であり、受け取り方は人それぞれ異なるだろう。鑑賞前に知っておいた方がいい知識についてまとめたので、参考にしてほしい
あとですぐ触れるが、量子論というのは常識に反する主張を様々に受け入れなければならない幾多の天才科学者たちを悩ませた分野であり、そのため膨大な議論が繰り広げられた。中でも、「量子論の重鎮たちのリーダー的存在であるボーア」と「科学界にその名を轟かせる孤高の天才アインシュタイン」は、量子論の解釈を巡って最後の最後まで対立したことで知られている。
アインシュタインのものとして知られる名言は数多く存在するが、その中の1つに「神はサイコロを振らない」がある。実はこれは、「私は量子論など受け入れない」という決意表明なのだ。アインシュタインは死ぬまで量子論に反対し続けたが、それはつまり、アインシュタインが生きている間には、ボーアとアインシュタインのバトルに明確な決着がつかなかった、ということでもある。
しかし実は、ボーアもアインシュタインも亡くなった後、その論争に終止符が打たれることになった。そしてそこで明らかになった結論が、現在世界中で開発競争が繰り広げられている「量子コンピューター」に繋がっていくのである。
あわせて読みたい
【研究】光の量子コンピュータの最前線。量子テレポーテーションを実現させた科学者の最先端の挑戦:『…
世界中がその開発にしのぎを削る「量子コンピューター」は、技術的制約がかなり高い。世界で初めて「量子テレポーテーション」の実験を成功させた研究者の著書『光の量子コンピューター』をベースに、量子コンピューター開発の現状を知る
この記事では、本書に書かれている流れすべてに触れるわけにはいかないが、「量子論」への関心を抱いてもらえるように解説していきたいと思う。
量子論はどれほど難しいのか
20世紀(1900年代)に、物理学は大きな躍進を遂げた。そして、その躍進を支えた2つの理論がある。
あわせて読みたい
【要約】福岡伸一『生物と無生物のあいだ』は、「生命とは何か」を「動的平衡」によって定義する入門書…
「生命とは何か?」という、あまりに基本的だと感じられる問いは、実はなかなか難しい。20世紀生物学は「DNAの自己複製」が本質と考えたが、「ウイルス」の発見により再考を迫られた。福岡伸一の『生物と無生物のあいだ』『動的平衡』の2著作から、「生命の本質」を知る
1つは、アインシュタインが独力で作り上げた「相対性理論」だ。そしてもう1つが、この記事のメインテーマ「量子論」である。1800年代終わりの科学界には、「既に人類はあらゆる知識に到達した」という雰囲気が支配的だったようだが、1900年に入ってすぐ「相対性理論」が生まれ、「量子論」誕生のきっかけとなる考え方が提示された。人類は世界について全然分かっていなかったのだ。
そんな量子論だが、これは「相対性理論」とは違い、同時代を生きる数々の天才科学者たちの侃々諤々の議論によって少しずつ形作られたものだ。量子論に関わった物理学者の名前をズラリと並べてみれば、これでもかと言うほど有名な人物ばかりだと分かるだろう。そして、そんな天才たちが少しずつアイデアを出し合い、別の誰かの発想を批判し、新たな見方を提示することによって、それまでの常識を覆す理論が生み出されたのである。

あわせて読みたい
【新視点】世界の歴史を「化学」で語る?デンプン・砂糖・ニコチンなどの「炭素化合物」が人類を動かし…
デンプン・砂糖・ニコチンなどは、地球上で非常に稀少な元素である「炭素」から作られる「炭素化合物」だ。そんな「炭素化合物」がどんな影響を与えたかという観点から世界の歴史を描く『「元素の王者」が歴史を動かす』は、学校の授業とはまったく違う視点で「歴史」を捉える
本書はそんな歴史を概観できる作品で、長い長い映画を観ているような印象を抱くのではないかと思う。
さて、天才が数多く関わった量子論だが、そんな天才たちの「嘆き」の言葉が、本書には多数収録されている。ちょっと多くなるが、量子論がどれほど彼らを苦しめたのか理解してもらうのに必要だと思うので挙げていこう。
アインシュタインは後年、次のように述べた。「この理論のことを考えていると、すばらしく頭の良い偏執症患者が、支離滅裂な考えを寄せ集めて作った妄想体型のように思われるのです」
あわせて読みたい
【驚異】ガイア理論の提唱者が未来の地球を語る。100歳の主張とは思えない超絶刺激に満ちた内容:『ノヴ…
「地球は一種の生命体だ」という主張はかなり胡散臭い。しかし、そんな「ガイア理論」を提唱する著者は、数々の賞や学位を授与される、非常に良く知られた科学者だ。『ノヴァセン <超知能>が地球を更新する』から、AIと人類の共存に関する斬新な知見を知る
量子論にはじめて出会った時にショックを受けない者に、量子論を理解できたはずがない(ニールス・ボーア)
ヴェルナー・ハイゼンベルグが不確定性原理を発見する。その原理はあまりにも常識に反していたため、ドイツの生んだ神童ハイゼンベルグでさえも、はじめはどう解釈したものかわからず頭を抱えたほどだった
現在、物理学はまたしても滅茶苦茶だ。ともかくわたしには難し過ぎて、自分が映画の喜劇役者かなにかで、物理学のことなど聞いたこともないというのならよかったのにと思う(ヴォルフガング・パウリ)
あわせて読みたい
【不思議】森達也が「オカルト」に挑む本。「科学では説明できない現象はある」と否定も肯定もしない姿…
肯定派でも否定派でもない森達也が、「オカルト的なもの」に挑むノンフィクション『オカルト』。「現象を解釈する」ことよりも、「現象を記録する」こと点に注力し、「そのほとんどは勘違いや見間違いだが、本当に説明のつかない現象も存在する」というスタンスで追いかける姿勢が良い
もしもこの忌まわしい量子飛躍が本当にこれからも居座るなら、わたしは量子論にかかわったことを後悔するだろう(エルヴィン・シュレディンガー)
エーレンフェストはそれに続けて、「目標に到達するためには、この道を取るしかないというなら、わたしは物理学をやめなければなりません」と述べた
アインシュタインは、黒体問題の解決案を提唱したプランクの論文が出るとすぐにそれを読み、のちにそのときの気持を次のように述べた。「まるで足もとの大地が下から引き抜かれてしまったかのように、確かな基礎はどこにも見えず、建設しようにも足場がなかった」
ノーベル賞を受賞したアメリカの物理学者、マレー・ゲルマンは、そんな状況を指して次のように述べた。量子力学は、「真に理解している者はひとりもいないにもかかわらず、使い方だけはわかっているという、謎めいて混乱した学問領域である」
あわせて読みたい
【平易】ブラックホールを分かりやすく知りたい。難しいことは抜きにふわっと理解するための1冊:『ブラ…
2019年に初めて直接観測されるも、未だに謎多き天体である「ブラックホール」について現役研究者が分かりやすく語る『ブラックホールをのぞいてみたら』をベースに、科学者がその存在を認めてこなかった歴史や、どんな性質を持つ天体なのかを理解する
どうだろうか? 繰り返すが、ここで名前が挙がっている人物は皆、科学の歴史に名を残す天才中の天才たちだ。そんな科学者たちが量子論についてこれほど嘆いている。それほどまでに既存の常識と相容れない考え方を要求されたということだ。
さて、このような認識は、かなり後まで続くことになる。本書にはこんな文章がある。
著名なアメリカの物理学者で、ノーベル賞受賞者でもあるリチャード・ファインマンは、アインシュタインの死後十年を経た1965年に、次のように述べた。「量子力学を理解している者は、ひとりもいないと言ってよいと思う」。コペンハーゲン解釈が、量子論の正統解釈として、あたかもローマ教皇から発布される教皇令のごとき権威を打ち立てると、ほとんどの物理学者は、ファインマンの次の忠告に素直に従った。「『こんなことがあっていいのか?』と考え続けるのはやめなさい――やめられるのならば。その問いへの答えは、誰も知らないのだから」
あわせて読みたい
【天才】科学者とは思えないほど面白い逸話ばかりのファインマンは、一体どんな業績を残したのか?:『…
数々の面白エピソードで知られるファインマンの「科学者としての業績」を初めて網羅したと言われる一般書『ファインマンさんの流儀』をベースに、その独特の研究手法がもたらした様々な分野への間接的な貢献と、「ファインマン・ダイアグラム」の衝撃を理解する
1965年の時点では、謎はまだまだ残ってはいたものの、量子論という分野の大きな枠組みはきちんと完成していたはずだ。アインシュタインやボーアら、まさに構築している最中の人たちが嘆くのとは状況が違い、ある程度輪郭が完成し、理論としての形が整っている段階でさえまだ、ファインマンのような捉え方が一般的だった、ということだ。

科学者というのは、「理論や実験を通じて、世界はどうなっているのかを探求する人々」である。そんな彼らが、「世界がどうなっているのか理解するのは諦めよう」と言っているのだから、あまりに異常だろう。
あわせて読みたい
【幻想】超ひも理論って何?一般相対性理論と量子力学を繋ぐかもしれないぶっ飛んだ仮説:『大栗先生の…
『大栗先生の超弦理論入門』は最先端科学である「超弦理論」を説明する1冊だが、この記事では著者の主張の1つである「空間は幻想かもしれない」という発想を主に取り上げる。「人類史上初の『適用する次元が限定される理論』」が描像する不可思議な世界とは?
この記事で紹介するのは、そんな白熱の議論と常識の転換によって生み出された量子論がどのように形作られていったのかという歴史である。
この記事は「アインシュタインの貢献」という観点で歴史を切り取る
本書は、量子論に関わる長い長い歴史の物語であり、そのすべてに触れることは困難だ(というか、すべて知りたければ是非本書を読んでほしい)。そこでこの記事では、「量子論の発展に、アインシュタインはいかに貢献することになったのか」という観点から書いていこうと思う。
これには明確な理由がある。
先ほどアインシュタインが量子論に対して反対したことを示す「神はサイコロを振らない」という言葉を紹介した。そして、具体的にはこれから触れるが、アインシュタインの反対にも関わず、量子論は世界を説明する法則として認められたわけであり、それはつまり「アインシュタインの敗北」を意味するだろう。
あわせて読みたい
【戸惑】人間の脳は摩訶不思議。意識ではコントロールできない「無意識の領域」に支配されている:『あ…
我々は決断や選択を「自分の意思」で行っていると感じるが、脳科学の研究はそれを否定している。我々に「自由意志」などない。「脳」の大部分は「意識以外のもの」に支配され、そこに「意識」はアクセスできないという驚愕の実態を『あなたの知らない脳』から学ぶ
実際に、本書の訳者である青木薫は、解説でこんな風に書いている。
さて、アインシュタインが最後まで量子力学を受け入れなかったことについては、ながらく次のような理解が広くゆきわたっていた。「かつては革命的な考えを次々と打ち出したアインシュタインも、年老いてひびの入った骨董品のようになり、新しい量子力学の考え方についてこられなくなった」と。わたしが大学に入った1970年代半ばにも、そんなアインシュタイン像が、いわば歴史の常識のようになっていた
アインシュタインは、「若い頃は煌めくような業績を連発したが、晩年はこれといった成果も出せず、さらに量子論のような新しい考えを受け入れられない古臭い人間だった」と思われていた、ということだ。しかしこの見方は徐々に変わっているのだという。同じく青木薫がこんな風に書いている。
あわせて読みたい
【快挙】「チバニアン」は何が凄い?「地球の磁場が逆転する」驚異の現象がこの地層を有名にした:『地…
一躍その名が知れ渡ることになった「チバニアン」だが、なぜ話題になり、どう重要なのかを知っている人は多くないだろう。「チバニアン」の申請に深く関わった著者の『地磁気逆転と「チバニアン」』から、地球で起こった過去の不可思議な現象の正体を理解する
今日では、コペンハーゲン解釈とはいったい何だったのか(コペンハーゲン解釈に関する解釈問題があると言われたりするほど、この解釈にはあいまいなところがあるのだ)、そしてアインシュタイン=ボーア論争とは何だったのかが、改めて問い直され、それにともなってアインシュタインの名誉回復が進んでいるのである
そして、青木薫が「名誉回復」と指摘しているのが、「アインシュタインの批判が量子論を発展させたのではないか」という捉え方なのだ。
本書の記述は決してその観点に留まるものではないが、この記事では「アインシュタインの貢献」という点を重視して書いていこうと思う。
量子論誕生前夜
あわせて読みたい
【論争】サイモン・シンが宇宙を語る。古代ギリシャからビッグバンモデルの誕生までの歴史を網羅:『宇…
古代から現代に至るまで、「宇宙」は様々な捉えられ方をしてきた。そして、新たな発見がなされる度に、「宇宙」は常識から外れた不可思議な姿を垣間見せることになる。サイモン・シン『宇宙創成』をベースに、「ビッグバンモデル」に至るまでの「宇宙観」の変遷を知る
アインシュタインの「相対性理論」は、突然生まれたものだ。どういうことかと言えば、「具体的な問題を解決するために生み出されたのではなく、純粋な思考のみから考え出された」ということである。アインシュタインが「相対性理論」を生み出した当時、相対性理論のような理論が望まれていたわけではなかった。科学者に立ちふさがる謎が存在し、その解決のために「相対性理論」が登場したというわけではないのだ。
一方の「量子論」は違う。ある具体的な問題を解決するために考え出された「量子」という発想がその根底に存在する。

「量子」というのは「不連続量」という意味だ。この説明のために、水道を思い浮かべてほしい。
あわせて読みたい
【貢献】有名な科学者は、どんな派手な失敗をしてきたか?失敗が失敗でなかったアインシュタインも登場…
どれほど偉大な科学者であっても失敗を避けることはできないが、「単なる失敗」で終わることはない。誤った考え方や主張が、プラスの効果をもたらすこともあるのだ。『偉大なる失敗』から、天才科学者の「失敗」と、その意外な「貢献」を知る
水道の蛇口を思い切りひねり、水をジャーっと出すとしよう。この状態の水は「1つ、2つ……」とは数えられないので「連続量」と言っていい。では、蛇口を絞って、水滴がぽつぽつと垂れる状態にしてみよう。この場合、その水滴を「1つ、2つ……」と数えることができるので「不連続量」だと言える。
このように、「1つ、2つ……」と数えられるもの(状態)を「量子」と呼ぶ。
そしてこの「不連続量」「連続量」は、物理学の世界における「波」「粒子」と対応していると考えればいい。海で発生する「波」も「1つ、2つ……」とは数えられないだろう。一方、原子などを「粒子」と呼ぶが、これらは「1つ、2つ……」と数えられる。そして「量子論」というのは、「今まで波だと考えていたものを、粒子としても捉えなければならなくなった」という発想の転換を強いられるという点で、科学者を大いに悩ませることになったのだ。
「波」と「粒子」については以下の記事により詳しくまとめているので参照してほしい。
あわせて読みたい
【敗北】「もつれ」から量子論の基礎を学ぶ。それまでの科学では説明不能な「異次元の現象」とは?:『…
アインシュタインは量子力学を生涯受け入れなかったのだが、アインシュタインが批判し続けたことによって明らかになったこともある。「もつれ」の重要性もその一つだ。『宇宙は「もつれ」でできている』から量子力学の基礎を成す現象を知る。
さて、「量子論」の誕生のきっかけとなった具体的な問題というのが「黒体放射」と呼ばれるものである。これについて具体的に説明はしないが、それまでの「波として捉える」という考え方ではどうにもうまく理解ができなかった。
そこでプランクという科学者が、本人さえ「破れかぶれ」と呼んだアイデアによってこれを解決する。それが、「波だと考えられていたものを粒子として捉えてみる」という発想だ。このように「量子」という概念を導入することで「黒体放射」の問題はあっさり解決する。
しかしこれによって、「波でもあり、粒子でもあるなどということがあり得るだろうか?」という新たな問題が生まれることにもなってしまった。アインシュタインも、先の引用の通り、「足もとの大地が下から引き抜かれてしまったかのよう」に感じたほど衝撃的な考え方だったのだ。
プランクが「黒体放射」の問題を解決するために「量子」という考えを導入したことが量子論の誕生のきっかけであり、プランクは「量子論の父」と呼ばれている。
あわせて読みたい
【平易】一般相対性理論を簡単に知りたい方へ。ブラックホール・膨張宇宙・重力波と盛りだくさんの1冊:…
現役の研究者が執筆した『ブラックホール・膨張宇宙・重力波』は、アインシュタインが導き出した一般相対性理論が関わる3つのテーマについて、初心者にも分かりやすく伝える内容になっている。歴史的背景も含めて科学的知見を知りたい方にオススメの1冊
今度はアインシュタインが「量子」という考え方を導入する
さて、アインシュタインは生涯「量子論」を批判し続けたし、プランクの「量子」という考え方にも衝撃を受けたわけだが、その後アインシュタイン自身が、「量子」という考え方を使い、別の難問を解き明かすことになる。
それが、アインシュタインのノーベル賞受賞理由にもなっている「光電効果」の説明だ。アインシュタインは実は、有名な「相対性理論」でノーベル賞を受賞しているわけではないのである。
あわせて読みたい
【逸話】天才数学者ガロアが20歳で決闘で命を落とすまでの波乱万丈。時代を先駆けた男がもし生きていた…
現代数学に不可欠な「群論」をたった1人で生み出し、20歳という若さで決闘で亡くなったガロアは、その短い生涯をどう生きたのか?『ガロア 天才数学者の生涯』から、数学に関心を抱くようになったきっかけや信じられないほどの不運が彼の人生をどう変えてしまったのか、そして「もし生きていたらどうなっていたのか」を知る
「光電効果」という名前で知られる現象が、理論家にとっては大きな謎だった。この現象についても詳しくは説明しないが、先ほどの「黒体放射」と同様、それまで常識だった「光は波である」という考え方ではまったく説明が不可能なのだ。

そこでアインシュタインは、「光を粒子(量子)と捉えれば、光電効果は問題なく説明できる」という考え方を提示した。しかし、この「光量子仮説」を提唱した当時、「光量子」(「光子」とも呼ばれる)の実在を信じていたのはアインシュタインただ一人であり、数多くの科学者が「光量子」に批判的だった。
何故なら科学の世界には、「光は波である」という実験結果が山のように存在するからだ(「波」と「粒子」の問題については、先にも紹介した以下の記事を)。
あわせて読みたい
【敗北】「もつれ」から量子論の基礎を学ぶ。それまでの科学では説明不能な「異次元の現象」とは?:『…
アインシュタインは量子力学を生涯受け入れなかったのだが、アインシュタインが批判し続けたことによって明らかになったこともある。「もつれ」の重要性もその一つだ。『宇宙は「もつれ」でできている』から量子力学の基礎を成す現象を知る。
確かにアインシュタインが言うように、光が量子だと仮定するなら光電効果は説明可能かもしれない。しかし、これまでの実験などから光は波に決まっているのだから、アインシュタインが言うような「光量子」など存在するはずがない。ほとんどの科学者がこのように考えていたのだ。
アインシュタインの光量子仮説を実証する光電効果の実験を行いノーベル賞を受賞したミリカンという科学者も、自分で行った実験にも関わらず、その実験結果を信じられなかった、と語っているほどである。それぐらい、光を粒子と捉えることに対する抵抗感が当時の科学者の間で強かったということだ。
「光量子仮説」でアインシュタインはノーベル賞を受賞したのだが、この時点でもまだ「光量子」の実在を信じる科学者はほとんどいなかった。そんな状況を踏まえノーベル賞委員会は「光電効果を説明する数式を発見したこと」に対してアインシュタインにノーベル賞を与えたのである。
あわせて読みたい
【快挙】「暗黒の天体」ブラックホールはなぜ直接観測できたのか?国際プロジェクトの舞台裏:『アイン…
「世界中に存在する電波望遠鏡を同期させてブラックホールを撮影する」という壮大なEHTプロジェクトの裏側を記した『アインシュタインの影』から、ブラックホール撮影の困難さや、「ノーベル賞」が絡む巨大プロジェクトにおける泥臭い人間ドラマを知る
つまりノーベル賞委員会は、「光量子」に関する評価を避けた、というわけだ。光量子はまだまだ科学者の間で議論が続いている。そんな状況でノーベル賞委員会が光量子の実在にお墨付きを与えるようなリスクを負うわけにはいかない(ノーベル賞を授与した後、それが誤りであると判明したら致命的だ)。そこで、光量子には触れず、「数式を発見した」という理由での受賞となったのである。
「光量子仮説」は、「波だと考えられていたものを粒子(量子)と捉える」という量子論的な考え方であるにも関わらず、量子論の研究を先導したボーアは、生涯「光量子」の存在を信じなかったという。「光量子」の実在については、「コンプトン効果」と呼ばれる現象が観測されたことで反論の余地なく証明されたのだが、「コンプトン効果」が発見されてからもボーアは「光量子」の実在を認めなかったというから、相当頑なだったと言っていいだろう。
このように、「量子」という考え方は、様々な形で議論を引き起こすことになったのである。
あわせて読みたい
【誤解】「意味のない科学研究」にはこんな価値がある。高校生向けの講演から”科学の本質”を知る:『す…
科学研究に対して、「それは何の役に立つんですか?」と問うことは根本的に間違っている。そのことを、「携帯電話」と「東急ハンズの棚」の例を使って著者は力説する。『すごい実験』は素粒子物理学を超易しく解説する本だが、科学への関心を抱かせてもくれる
さて、自らも「量子」という考え方を導入したアインシュタインだったが、その後、量子論を猛烈に反対する立場に回ることになる。しかし、アインシュタインが何故そう考えたのかを説明するためには、いくつか事前準備が必要となる。まずは、アインシュタインが忌み嫌った「コペンハーゲン解釈」がいかに生まれたのか、その流れを見ていこう。
量子論の方程式の解をどう捉えればいいのか分からない
プランクのアイデアによって生まれた量子論だが、理論が進展していくためには、その世界を記述する方程式が必要だ。そして、量子論の世界を記述する方程式は2つ存在する。
1つは、ハイゼンベルクという科学者が発見した。これは「行列」という、当時としてはあまり知られていなかった数学分野の知見が駆使された方程式で、その難解さに物理学者は困惑した。頑張れば方程式を解くことはできるが、あまりにも難しすぎて使い勝手が悪かったのだ。
あわせて読みたい
【到達】「ヒッグス粒子の発見」はなぜ大ニュースなのか?素粒子物理学の「標準模型」を易しく説明する…
「ヒッグス粒子の発見」はメディアでも大きく取り上げられたが、これが何故重要なのかを説明できる人はそう多くはないだろう。『強い力と弱い力 ヒッグス粒子が宇宙にかけた魔法を解く』をベースに、謎めいた「弱い力」を説明する「自発的対称性の破れ」を学ぶ
一方、シュレディンガーという科学者が、後に「波動方程式」と呼ばれる方程式を生み出した。こちらの方程式は非常に扱いやすく、量子論の方程式としてはこの「シュレディンガーの波動方程式」が人気を博すことになる。
方程式は2つ存在するが、どちらを解いても最終的には同じ答えにたどり着く。だったら計算が簡単な方に人気が集まるのは当然だ。
しかし波動方程式には1つだけ問題があった。それは、「波動方程式の解が何を示しているのか分からない」ということだ。「波動関数の解」は「波動関数」と呼ばれるが、これが現実の何と対応するのか分からなかったのである。「現実との対応」など考えず、単に計算を行うだけであれば波動方程式は非常に有用なのだが、「波動関数」が何を意味するのかは長らく謎だった。
あわせて読みたい
【ドラマ】「フェルマーの最終定理」のドラマティックな証明物語を、飲茶氏が平易に描き出す:『哲学的…
「フェルマーの最終定理」は、問題の提示から350年以上経ってようやく証明された超難問であり、その証明の過程では様々な人間ドラマが知られている。『哲学的な何か、あと数学とか』をベースに、数学的な記述を一切せず、ドラマティックなエピソードだけに触れる

その説明を与えたのが、ボルンという科学者である。彼は「波動関数は存在確率だ」という解釈を提示したのだ。
「波動方程式」というのは要するに、「原子がどのような運動をするのかを記述する式」である。これまでの科学の常識では、「運動の方程式を解けば、運動の状態が確定する」はずだ。つまり、与えられた条件における位置・速度・加速度などが、方程式を解けば確実に分かる、という意味である。
しかしボルンは、波動方程式を解いても確率しか分からない、と説明した。波動方程式を解いて分かるのは、「ある時刻・ある場所に原子が存在する確率だ」というわけである。
あわせて読みたい
【不可思議】心理学の有名な実験から、人間の”欠陥”がどう明らかになっていったかを知る:『心は実験で…
『心は実験できるか 20世紀心理学実験物語』では、20世紀に行われた心理学実験からインパクトのある10の実験を選び紹介している。心理学者でもある著者が「科学であって科学ではない」と主張する心理学という学問で、人間のどんな不可思議さがあぶり出されてきたのかを知る
この主張は、それまでの科学の常識に真っ向から歯向かう異端の考えだと言っていいだろう。
シュレディンガーは、ボルンの確率解釈に納得しなかったという。そして、「確率解釈には納得できない」という立場を示すために、後に非常に有名となる「シュレディンガーの猫」を生み出した(本書によると、この有名な猫の原型となるアイデアを考えたのは実はアインシュタインなのだそうだ)。
しかしこの「量子論の方程式を解いても確率しか分からない」という「確率解釈」は、量子論の主流派の間で受け入れられていくことになる。
あわせて読みたい
【神秘】脳研究者・池谷裕二が中高生向けに行った講義の書籍化。とても分かりやすく面白い:『進化しす…
「宇宙」「深海」「脳」が、人類最後のフロンティアと呼ばれている。それほど「脳」というのは、未だに分からないことだらけの不思議な器官だ。池谷裕二による中高生向けの講義を元にした『進化しすぎた脳』『単純な脳、複雑な「私」』をベースに、脳の謎を知る
「ハイゼンベルクの不確定性原理」が示す「実在」の考え方
さて、量子論の主流派が考えた、もう1つの重要な要素がある。それは、「人間が観測するまで、物理的な性質は実在しない」という発想だ。
これもまた意味不明な主張だろう。どうしてこのようなアイデアが生まれたのか見ていこう。
先ほど「行列」を使った方程式を作った人物として紹介したハイゼンベルクは、「不確定性原理」なるものを発表している。これは、量子論の世界を支配する大原則として知られるものだ。
あわせて読みたい
【証明】結城浩「数学ガール」とサイモン・シンから「フェルマーの最終定理」とそのドラマを学ぶ
350年以上前に一人の数学者が遺した予想であり「フェルマーの最終定理」には、1995年にワイルズによって証明されるまでの間に、これでもかというほどのドラマが詰め込まれている。サイモン・シンの著作と「数学ガール」シリーズから、その人間ドラマと数学的側面を知る
具体的には触れないが、当時、「霧箱内の原子の軌道」をどう説明すべきかという問題が存在していた。そしてこの大問題を解決するためにハイゼンベルクがたどり着いたのが「不確定性原理」なのである。
ここではざっくりした説明に留めるが、「不確定性原理」というのは、「共役変数という関係にある2つの物理量を同時には測定できない」というルールだ。例えば「位置」と「速度(運動量)」は「共役変数」の関係にあり、量子の世界ではこの2つを同時には測定できないことになる。
これは、私たちの日常生活と比較して考えてみると非常に奇妙なことになる。
例えば、「車が駐車場に停めてある」という状態は、物理的に厳密に表現すると、「車という物体が、速度ゼロで駐車場という位置に存在している」ということになる。これはつまり、位置と速度を同時に測定している、ということになるわけだ。このように私たちが生きている世界では、位置と速度が同時に測定できることなど当たり前だ。
あわせて読みたい
【衝撃】ABC予想の証明のために生まれたIUT理論を、提唱者・望月新一の盟友が分かりやすく語る:『宇宙…
8年のチェック期間を経て雑誌に掲載された「IUT理論(宇宙際タイヒミュラー理論)」は、数学の最重要未解決問題である「ABC予想」を証明するものとして大いに話題になった。『宇宙と宇宙をつなぐ数学』『abc予想入門』をベースに、「IUT理論」「ABC予想」について学ぶ
しかし量子の世界ではそうはいかない。位置を100%正確に測定しようとすれば速度は曖昧にしか測定できないし、逆もまた同じだ。量子の世界はこのような「不確定性原理」に支配されているというのが、量子論の主流派の考えなのである。
そして彼らは、さらにその発想を突き詰め、こう考えるようになる。
彼にとって、電子の位置や運動量を測定するための実験が行われなければ、はっきりした位置や、はっきりした運動量を持つ電子は、そもそも存在しないのだ。電子の位置を測定するという行為が、位置をもつ電子を生み出し、電子の運動量を測定するという行為が、運動量をもつ電子を生み出す。はっきりした「位置」や「運動量」をもつ電子という概念は、測定が行われるまでは意味をもたない、と彼は述べた
あわせて読みたい
【限界】有名な「錯覚映像」で心理学界をザワつかせた著者らが語る「人間はいかに間違えるか」:『錯覚…
私たちは、知覚や記憶を頼りに社会を生きている。しかしその「知覚」「記憶」は、本当に信頼できるのだろうか?心理学の世界に衝撃を与えた実験を考案した著者らの『錯覚の科学』から、「避けられない失敗のクセ」を理解する
どういうことか理解できるだろうか?
量子の世界では、「位置」と「速度」は同時には測定できない。つまり、「はっきりした位置を持ち、かつ、はっきりした速度を持つ原子」の存在を、我々人間は観測によって捉えることができない、ということだ。
となれば、「そんなものは存在しない」と考えてもいいだろう、と彼らは主張しているのである。

例えば私たちは、昼間に月が見えなくても「月は存在する」と思うし、何か計算など駆使すれば、直接的に見ることができなくても、月は今この位置にこれぐらいの速度の状態にある、ということが分かるだろう。観測するかどうかに関係なく「月は存在する」というのが当たり前の考え方だ。
あわせて読みたい
【興奮】結城浩「数学ガール」で、決闘で命を落とした若き天才数学者・ガロアの理論を学ぶ
高校生を中心に、数学を通じて関わり合う者たちを描く「数学ガール」シリーズ第5弾のテーマは「ガロア理論」。独力で「群論」という新たな領域を切り開きながら、先駆的すぎて同時代の数学者には理解されず、その後決闘で死亡した天才の遺した思考を追う
しかし量子論の主流派は、量子の世界ではそう考えることを諦めよう、と主張した。つまり、人間が観測しなければ原子がどうなっているか分からないし、観測することによって初めて「そこにある」と言える、ということだ。観測以前の「実在」について考えても仕方がないから、そこには触れないでおこう、という立場なのである。
さてこのように、「確率解釈」と「観測以前の実在を諦める」という考え方が、量子論の主流派の主張の根幹にあると言っていい。この考え方には、「コペンハーゲン解釈」と名前がついている。ボーアの研究所がコペンハーゲンにあったことから付けられた名前であり、ボーアが量子論の主流派を率いていたこともあり、「コペンハーゲン解釈」こそが量子論の正しい認識であると考えられていたわけだ。
そしてアインシュタインは、この「コペンハーゲン解釈」に猛然と立ち向かったのである。
アインシュタインの批判
あわせて読みたい
【刺激】結城浩「数学ガール」で、ゲーデルの不完全性定理(不可能性の証明として有名)を学ぶ
『結城浩「数学ガール」シリーズは、数学の面白さを伝えながら、かなり高難度の話題へと展開していく一般向けの数学書です。その第3弾のテーマは、「ゲーデルの不完全性定理」。ヒルベルトという数学者の野望を打ち砕いた若き天才の理論を学びます
アインシュタインは、「確率解釈」も「観測以前の実在を諦めること」もどちらも忌み嫌った。アインシュタインが「確率解釈」を批判した言葉として有名なのが、何度か触れた「神はサイコロを振らない」である。「確率しか分からないようなものを科学と呼んでいいのか。世界は確率ではない形で捉えられるはずだ」というアインシュタインの主張を端的に表わしている。
しかし、量子論の世界に「確率」という考え方を持ち込んだのは実はアインシュタインだった。先ほど「光電効果」の話に触れたが(「光量子仮説」で解決した)、アインシュタインは「光電効果」を説明するために、「光量子が放出される向きや時刻は運任せである」という確率的な考えを盛り込まざるを得なかったのだ。
しかしアインシュタインは、こうも考えていた。今はまだ、我々が世界を捉える能力が不十分なだけであり、理論には改善の余地がある。正しい理論を作り出せば、「確率」などという忌まわしいものは取り除けるはずだ、と。
あわせて読みたい
【使命】「CRISPR-Cas9」を分かりやすく説明。ノーベル賞受賞の著者による発見物語とその使命:『CRISPR…
生物学の研究を一変させることになった遺伝子編集技術「CRISPR-Cas9」の開発者は、そんな発明をするつもりなどまったくなかった。ノーベル化学賞を受賞した著者による『CRISPR (クリスパー) 究極の遺伝子編集技術の発見』をベースに、その発見物語を知る
だからこそ同じく、「確率」という考えが組み込まれた「コペンハーゲン解釈」にも異議を唱えたのだ。
また、「観測以前の実在を諦めること」への批判として有名なのが、「月」を使ったこの名言だ。
アインシュタインの物理学の核心にあったのは、観測されるかどうかによらず、「そこ」にある実在へのゆるぎない信念だった。「月は、きみが見上げたときだけ存在するとでも言うのかね?」と、彼はその考えの愚かしさを印象づけようとしてアブラハム・パイスに言った。
あわせて読みたい
【異端】数学の”証明”はなぜ生まれたのか?「無理数」と「無限」に恐怖した古代ギリシャ人の奮闘:『数…
学校で数学を習うと、当然のように「証明」が登場する。しかしこの「証明」、実は古代ギリシャでしか発展しなかった、数学史においては非常に”異端”の考え方なのだ。『数学の想像力 正しさの深層に何があるのか』をベースに、ギリシャ人が恐れたものの正体を知る
要するに、「見ている時にしかそこに存在していると言えない理論なんて、正しくないだろう」と批判しているのだ。アインシュタインは記憶に残る名フレーズを連発するコピーライターさながらで、問題点を端的に表現する力がずば抜けていると言える。

アインシュタインは、「実在に対する理解」を諦めたくなかった。「コペンハーゲン解釈」では、「観測以前の実在については分からないから諦めよう」とされているが、それは量子論への理解が不十分なだけではないか、とアインシュタインは考えていたのだ。「光電効果」に関する「確率」の問題がいずれ解消されるはずだと思っていたように、量子論の知見が深まれば、「観測以前の実在」についても正しい理解が得られるようになるに違いない、と考えていたのである。
あわせて読みたい
【対立】数学はなぜ”美しい”のか?数学は「発見」か「発明」かの議論から、その奥深さを知る:『神は数…
数学界には、「数学は神が作った派」と「数学は人間が作った派」が存在する。『神は数学者か?』をベースに、「数学は発見か、発明か」という議論を理解し、数学史においてそれぞれの認識がどのような転換点によって変わっていったのかを学ぶ
つまりアインシュタインは量子論を、「正しいが完全ではない」と捉えていたということだ。量子論は現象を正しく捉えるし、方程式を解くことで正確な予測も可能である。しかし、「確率」などという忌まわしいものが含まれているし、「実在」に関する記述も不十分だ。だから、量子論をさらにブラッシュアップさせることで、世界をより正しく理解するための理論が得られるはずである。
アインシュタインの批判の骨子はここにあったと言っていいだろう。
さて、「コペンハーゲン解釈」の説明とアインシュタインの批判を理解した上で、どちらの意見の方が真っ当だと感じるだろうか? 私はどう考えても、アインシュタインの言っていることの方がまともだと感じる。「位置が確率でしか分からない」とか「観測するまで実在について語るのは諦める」など、「ムチャクチャなこと言ってるなぁ」と思えてしまう。
あわせて読みたい
【始まり】宇宙ができる前が「無」なら何故「世界」が生まれた?「ビッグバンの前」は何が有った?:『…
「宇宙がビッグバンから生まれた」ことはよく知られているだろうが、では、「宇宙ができる前はどうなっていたのか」を知っているだろうか? 実は「宇宙は”無”から誕生した」と考えられているのだ。『宇宙が始まる前には何があったのか?』をベースに、ビッグバンが起こる前の「空間も時間も物理法則も存在しない無」について学ぶ
しかし当時の科学者の捉え方は違った。アインシュタインの批判を大して重要なものと捉えていなかったのだ。
ここにはいくつか理由がある。
例えば、量子論を主導していたのがボーアだったので、そのボーアの考え方が色濃く反映されるのは仕方ないと言える。ボーアはアインシュタインと違って多くの弟子を育てたことで知られており、その弟子たちが様々な発見をし、ボーアの考えを広め、量子論を作り上げていったのだから、ボーアの影響力が大きくなるのは当然だ。
また、「科学者にはやることが山ほどあった」という理由もある。量子論は当時まだ生まれたばかりの理論だ。研究すべきことは無限に存在する。そんな時に、「観測する以前の実在がどうのこうの」なんていう哲学的な話に興味を持つ余裕などなかった、というわけだ。ボーアの考えだろうがアインシュタインの考えだろうが、計算結果には影響しない。だったらそんなのどっちでもいいよ、というのが、特に若手の科学者たちの本音だったのである。
あわせて読みたい
【謎】恐竜を絶滅させた隕石はどこから来た?暗黒物質が絡む、リサ・ランドールの驚愕の仮説:『ダーク…
「生物の絶滅」には、以前から知られていたある謎があった。そしてその謎を、未だに観測されておらず、「科学者の妄想の産物」でしかない「ダークマター(暗黒物質)」が解決するかもしれない。現役の科学者が『ダークマターと恐竜絶滅』で語る驚きの仮説。
そして、ボーアもそのことを正しく理解しており、量子論の先導者として次のような立場を取った。
ニールス・ボーアが一世代の物理学者をまるごと洗脳して、問題はすでに解決したかのように思い込ませた
つまり、「若手は量子論の研究に勤しめ。アインシュタインの相手は俺がするし、アインシュタインが言っていることなんて全部俺が粉砕してやるから」という立場を取ることで、量子論研究の歩みを前進させようとした、というわけだ。
このような背景があり、アインシュタインの批判はあまりまともに受け取ってもらえなかったのである。しかしアインシュタインは、「コペンハーゲン解釈」への攻撃の手を緩めることはなかった。そして、アインシュタインが量子論に対して批判し続けたお陰で、大きな発見に繋がっていくことになる。
あわせて読みたい
【未知】タコに「高度な脳」があるなんて初耳だ。人類とは違う進化を遂げた頭足類の「意識」とは?:『…
タコなどの頭足類は、無脊椎動物で唯一「脳」を進化させた。まったく違う進化を辿りながら「タコに心を感じる」という著者は、「タコは地球外生命体に最も近い存在」と書く。『タコの心身問題』から、腕にも脳があるタコの進化の歴史と、「意識のあり方」を知る。
コペンハーゲン解釈を攻撃するアインシュタインの戦略
アインシュタインの攻撃は、実は2段階に分かれていた。
当初アインシュタインの標的は「ハイゼンベルクの不確定性原理」だった。「共役変数の関係にある2つの物理量を同時に測ることはできない」という主張だ。アインシュタインは、この「ハイゼンベルクの不確定性原理」に穴があるのではないかと考え、「不可能とされる測定が行える思考実験」を次々に生み出してはボーアに投げつけたのである。
しかしボーアは、アインシュタインが生み出す思考実験のすべてに反論することができた。アインシュタインの思考実験には、どこかしらに穴があり、どうしても「不確定性原理」を突き崩すことができなかったのだ。
あわせて読みたい
【奇妙】大栗博司『重力とはなにか』は、相対性理論や量子力学の説明も秀逸だが、超弦理論の話が一番面白い
『重力とはなにか』(大栗博司)は、科学に馴染みの薄い人でもチャレンジできる易しい入門書だ。相対性理論や量子力学、あるいは超弦理論など、非常に難解な分野を基本的なところから平易に説明してくれるので、「科学に興味はあるけど難しいのはちょっと……」という方にこそ読んでほしい1冊

そこで途中からアインシュタインは戦略を変える。「不確定性原理」を攻撃するのを止め、「コペンハーゲン解釈は不完全だ」と示そうとした。
アインシュタインの戦略をざっと説明するとこうなる。「コペンハーゲン解釈」の主張を突き詰めると「ある現象A」が起こると想定される。しかし、アインシュタインが生み出した「相対性理論」を踏まえて考えると、「ある現象A」は実際には起こるはずがない。「コペンハーゲン解釈」を信じることで、実際に起こるはずがない「ある現象A」を許容してしまうことになる。だからそんな解釈は認められない。
あわせて読みたい
【嫉妬?】ヒッグス粒子はいかに発見されたか?そして科学の”発見”はどう評価されるべきか?:『ヒッグ…
科学研究はもはや個人単位では行えず、大規模な「ビッグサイエンス」としてしか成立しなくなっている。そんな中で、科学研究の成果がどう評価されるべきかなどについて、「ヒッグス粒子」発見の舞台裏を追った『ヒッグス 宇宙の最果ての粒子』をベースに書く
これが、アインシュタインの主張の要点である。アインシュタインがボーアに突きつけた思考実験は「EPRパラドックス」という名前で有名だ。
さて、唐突だが、「EPRパラドックス」の説明も含め、以降の流れについては以下の記事にまとめてあるので、是非そちらを読んでほしい。アインシュタインの「EPRパラドックス」がどのような問題を提示し、ボーアがそれにどう対峙し、両者が共に亡くなった後でどのような展開を見せて決着がついたのかという流れについて触れてある。
読めば、「EPRパラドックスでのアインシュタインの敗北が、量子論を発展させた」という流れが理解できることだろう。
あわせて読みたい
【敗北】「もつれ」から量子論の基礎を学ぶ。それまでの科学では説明不能な「異次元の現象」とは?:『…
アインシュタインは量子力学を生涯受け入れなかったのだが、アインシュタインが批判し続けたことによって明らかになったこともある。「もつれ」の重要性もその一つだ。『宇宙は「もつれ」でできている』から量子力学の基礎を成す現象を知る。
著:クマール,マンジット, 翻訳:薫, 青木
¥1,155 (2022/01/29 21:19時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品読了済】私が読んできたノンフィクション・教養書を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が読んできたノンフィクションを様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本選びの参考にして下さい。
最後に
あわせて読みたい
【挑戦】相対性理論の光速度不変の原理を無視した主張『光速より速い光』は、青木薫訳だから安心だぞ
『光速より速い光』というタイトルを見て「トンデモ本」だと感じた方、安心してほしい。「光速変動理論(VSL理論)」が正しいかどうかはともかくとして、本書は実に真っ当な作品だ。「ビッグバン理論」の欠陥を「インフレーション理論」以外の理屈で補う挑戦的な仮説とは?
最終的に、「アインシュタインの批判」の方が間違っていると判定されることになったのだが、しかしこれは、「コペンハーゲン解釈」が正しいことを意味するわけではない。あくまでもアインシュタインが正しくなかったというだけのことであり、「コペンハーゲン解釈」が正しいことが示されたわけではない。
本書には、1997年7月にケンブリッジ大学で開かれた量子物理学の会議で行われた意見調査の結果が載っている。
新世代の物理学者たちが、量子力学の解釈問題という、頭の痛い問題をどのように見ているかが明らかになった。90人の物理学者が回答したなかで、コペンハーゲン解釈に票を投じたのはわずか4名にすぎず、30名はエヴェレットの多世界解釈の現代版を選んだのである。考えさせられるのは、「上の選択肢のどれでもない、あるいは決心がつかない」という選択肢を選んだ者が、50名もいたことだ
つまり現代の科学者たちは、「コペンハーゲン解釈ではない別の解釈が成り立つはずだ」と考えているということだろう。
あわせて読みたい
【解説】テネットの回転ドアの正体を分かりやすく考察。「時間逆行」ではなく「物質・反物質反転」装置…
クリストファー・ノーラン監督の映画『TENET/テネット』は、「陽電子」「反物質」など量子力学の知見が満載です。この記事では、映画の内容そのものではなく、時間反転装置として登場する「回転ドア」をメインにしつつ、時間逆行の仕組みなど映画全体の設定について科学的にわかりやすく解説していきます
「量子論をどう解釈するか」という問題は、未だに難しい問題として捉えられているのである。
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を…
Kindleで本を出版しました。タイトルは、『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を分かりやすく書いた本:相対性理論も宇宙論も量子論も』です。科学や科学者に関する、文系の人でも読んでもらえる作品に仕上げました。そんな自著について紹介をしています。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【奇妙】大栗博司『重力とはなにか』は、相対性理論や量子力学の説明も秀逸だが、超弦理論の話が一番面白い
『重力とはなにか』(大栗博司)は、科学に馴染みの薄い人でもチャレンジできる易しい入門書だ。相対性理論や量子力学、あるいは超弦理論など、非常に難解な分野を基本的なところから平易に説明してくれるので、「科学に興味はあるけど難しいのはちょっと……」という方にこそ読んでほしい1冊
あわせて読みたい
【あらすじ】原爆を作った人の後悔・葛藤を描く映画『オッペンハイマー』のための予習と評価(クリスト…
クリストファー・ノーラン監督作品『オッペンハイマー』は、原爆開発を主導した人物の葛藤・苦悩を複雑に描き出す作品だ。人間が持つ「多面性」を様々な方向から捉えようとする作品であり、受け取り方は人それぞれ異なるだろう。鑑賞前に知っておいた方がいい知識についてまとめたので、参考にしてほしい
あわせて読みたい
【挑戦】相対性理論の光速度不変の原理を無視した主張『光速より速い光』は、青木薫訳だから安心だぞ
『光速より速い光』というタイトルを見て「トンデモ本」だと感じた方、安心してほしい。「光速変動理論(VSL理論)」が正しいかどうかはともかくとして、本書は実に真っ当な作品だ。「ビッグバン理論」の欠陥を「インフレーション理論」以外の理屈で補う挑戦的な仮説とは?
あわせて読みたい
【秘話】15年で世界を変えたグーグルの”異常な”創業エピソード。収益化無視の無料ビジネスはなぜ成功し…
スマホやネットを使う人で、グーグルのお世話になっていない人はまずいないだろう。もはや「インフラ」と呼んでいいレベルになったサービスを生み出した企業の創業からの歴史を描く『グーグル秘録』は、その歩みが「無邪気さ」と「偶然」の産物であることを示している。凄まじいエピソード満載の信じがたい企業秘話
あわせて読みたい
【憤り】世界最強米海軍4人VS数百人のタリバン兵。死線を脱しただ1人生還を果たした奇跡の実話:『アフ…
アフガニスタンの山中で遭遇した羊飼いを見逃したことで、数百人のタリバン兵と死闘を繰り広げる羽目に陥った米軍最強部隊に所属する4人。奇跡的に生き残り生還を果たした著者が記す『アフガン、たった一人の生還』は、とても実話とは信じられない凄まじさに満ちている
あわせて読みたい
【おすすめ】「天才」を描くのは難しい。そんな無謀な挑戦を成し遂げた天才・野崎まどの『know』はヤバい
「物語で『天才』を描くこと」は非常に難しい。「理解できない」と「理解できる」を絶妙なバランスで成り立たせる必要があるからだ。そんな難題を高いレベルでクリアしている野崎まど『know』は、異次元の小説である。世界を一変させた天才を描き、「天才が見ている世界」を垣間見せてくれる
あわせて読みたい
【不思議】森達也が「オカルト」に挑む本。「科学では説明できない現象はある」と否定も肯定もしない姿…
肯定派でも否定派でもない森達也が、「オカルト的なもの」に挑むノンフィクション『オカルト』。「現象を解釈する」ことよりも、「現象を記録する」こと点に注力し、「そのほとんどは勘違いや見間違いだが、本当に説明のつかない現象も存在する」というスタンスで追いかける姿勢が良い
あわせて読みたい
【奇人】天才数学者で、自宅を持たずに世界中を放浪した変人エルデシュは、迷惑な存在でも愛され続けた…
数学史上ガウスに次いで生涯発表論文数が多い天才エルデシュをご存知だろうか?数学者としてずば抜けた才能を発揮したが、それ以上に「奇人変人」としても知られる人物だ。『放浪の天才数学者エルデシュ』で、世界中の数学者の家を泊まり歩いた異端数学者の生涯を描き出す
あわせて読みたい
【驚愕】これ以上の”サバイバル映画”は存在するか?火星にたった一人残された男の生存術と救出劇:『オ…
1人で火星に取り残された男のサバイバルと救出劇を、現実的な科学技術の範囲で描き出す驚異の映画『オデッセイ』。不可能を可能にするアイデアと勇気、自分や他人を信じ抜く気持ち、そして極限の状況でより困難な道を進む決断をする者たちの、想像を絶するドラマに胸打たれる
あわせて読みたい
【妄執】チェス史上における天才ボビー・フィッシャーを描く映画。冷戦下の米ソ対立が盤上でも:映画『…
「500年に一度の天才」などと評され、一介のチェスプレーヤーでありながら世界的な名声を獲得するに至ったアメリカ人のボビー・フィッシャー。彼の生涯を描く映画『完全なるチェックメイト』から、今でも「伝説」と語り継がれる対局と、冷戦下ゆえの激動を知る
あわせて読みたい
【危機】シードバンクを設立し世界の農業を変革した伝説の植物学者・スコウマンの生涯と作物の多様性:…
グローバル化した世界で「農業」がどんなリスクを負うのかを正しく予測し、その対策として「ジーンバンク」を設立した伝説の植物学者スコウマンの生涯を描く『地球最後の日のための種子』から、我々がいかに脆弱な世界に生きているのか、そして「世界の食」がどう守られているのかを知る
あわせて読みたい
【新視点】世界の歴史を「化学」で語る?デンプン・砂糖・ニコチンなどの「炭素化合物」が人類を動かし…
デンプン・砂糖・ニコチンなどは、地球上で非常に稀少な元素である「炭素」から作られる「炭素化合物」だ。そんな「炭素化合物」がどんな影響を与えたかという観点から世界の歴史を描く『「元素の王者」が歴史を動かす』は、学校の授業とはまったく違う視点で「歴史」を捉える
あわせて読みたい
【実話】映画『イミテーションゲーム』が描くエニグマ解読のドラマと悲劇、天才チューリングの不遇の死
映画『イミテーションゲーム』が描く衝撃の実話。「解読不可能」とまで言われた最強の暗号機エニグマを打ち破ったのはなんと、コンピューターの基本原理を生み出した天才数学者アラン・チューリングだった。暗号解読を実現させた驚きのプロセスと、1400万人以上を救ったとされながら偏見により自殺した不遇の人生を知る
あわせて読みたい
【最新】「コロンブス到達以前のアメリカ大陸」をリアルに描く歴史書。我々も米国人も大いに誤解してい…
サイエンスライターである著者は、「コロンブス到着以前のアメリカはどんな世界だったか?」という問いに触れ、その答えが書かれた本がいつまで経っても出版されないので自分で執筆した。『1491 先コロンブス期アメリカ大陸をめぐる新発見』には、アメリカ人も知らない歴史が満載だ
あわせて読みたい
【飛躍】有名哲学者は”中二病”だった?飲茶氏が易しく語る「古い常識を乗り越えるための哲学の力」:『1…
『14歳からの哲学入門』というタイトルは、「14歳向けの本」という意味ではなく、「14歳は哲学することに向いている」という示唆である。飲茶氏は「偉大な哲学者は皆”中二病”だ」と説き、特に若い人に向けて、「新しい価値観を生み出すためには哲学が重要だ」と語る
あわせて読みたい
【歴史】ベイズ推定は現代社会を豊かにするのに必須だが、実は誕生から200年間嫌われ続けた:『異端の統…
現在では、人工知能を始め、我々の生活を便利にする様々なものに使われている「ベイズ推定」だが、その基本となるアイデアが生まれてから200年近く、科学の世界では毛嫌いされてきた。『異端の統計学ベイズ』は、そんな「ベイズ推定」の歴史を紐解く大興奮の1冊だ
あわせて読みたい
【興奮】世界的大ベストセラー『サピエンス全史』要約。人類が文明を築き上げるに至った3つの革命とは?
言わずと知れた大ベストセラー『サピエンス全史』は、「何故サピエンスだけが人類の中で生き残り、他の生物が成し得なかった歴史を歩んだのか」を、「認知革命」「農業革命」「科学革命」の3つを主軸としながら解き明かす、知的興奮に満ち溢れた1冊
あわせて読みたい
【知的】文系にオススメの、科学・数学・哲学の入門書。高橋昌一郎の「限界シリーズ」は超絶面白い:『…
例えば「科学」だけに限ってみても、「なんでもできる」わけでは決してない。「科学」に限らず、私たちが対峙する様々な事柄には「これ以上は不可能・無理」という「限界」が必ず存在する。高橋昌一郎の「限界シリーズ」から、我々が認識しておくべき「限界」を易しく学ぶ
あわせて読みたい
【感想】飲茶の超面白い東洋哲学入門書。「本書を読んでも東洋哲学は分からない」と言う著者は何を語る…
東洋哲学というのは、「最終回しか存在しない連続ドラマ」のようなものだそうだ。西洋哲学と比較にならないほど異質さと、インド哲学・中国哲学など個別の思想を恐ろしく分かりやすく描く『史上最強の哲学入門 東洋の哲人たち』は、ページをめくる手が止まらないくらい、史上最強レベルに面白かった
あわせて読みたい
【興奮】飲茶氏の超面白い哲学小説。「正義とは?」の意味を問う”3人の女子高生”の主張とは?:『正義の…
なんて面白いんだろうか。哲学・科学を初心者にも分かりやすく伝える飲茶氏による『正義の教室』は、哲学書でありながら、3人の女子高生が登場する小説でもある。「直観主義」「功利主義」「自由主義」という「正義論」の主張を、「高校の問題について議論する生徒会の話し合い」から学ぶ
あわせて読みたい
【貢献】飛行機を「安全な乗り物」に決定づけたMr.トルネードこと天才気象学者・藤田哲也の生涯:『Mr….
つい数十年前まで、飛行機は「死の乗り物」だったが、天才気象学者・藤田哲也のお陰で世界の空は安全になった。今では、自動車よりも飛行機の方が死亡事故の少ない乗り物なのだ。『Mr.トルネード 藤田哲也 世界の空を救った男』から、その激動の研究人生を知る
あわせて読みたい
【驚異】ガイア理論の提唱者が未来の地球を語る。100歳の主張とは思えない超絶刺激に満ちた内容:『ノヴ…
「地球は一種の生命体だ」という主張はかなり胡散臭い。しかし、そんな「ガイア理論」を提唱する著者は、数々の賞や学位を授与される、非常に良く知られた科学者だ。『ノヴァセン <超知能>が地球を更新する』から、AIと人類の共存に関する斬新な知見を知る
あわせて読みたい
【人生】「資本主義の限界を埋める存在としての『贈与論』」から「不合理」に気づくための生き方を知る…
「贈与論」は簡単には理解できないが、一方で、「何かを受け取ったら、与えてくれた人に返す」という「交換」の論理では対処できない現実に対峙する力ともなる。『世界は贈与でできている』から「贈与」的な見方を理解し、「受取人の想像力」を立ち上げる
あわせて読みたい
【興奮】飲茶氏が西洋哲学を語る。難解な思想が「グラップラー刃牙成分」の追加で驚異的な面白さに:『…
名前は聞いたことはあるがカントやニーチェがどんな主張をしたのかは分からないという方は多いだろう。私も無知なまったくの初心者だが、そんな人でも超絶分かりやすく超絶面白く西洋哲学を”分かった気になれる”飲茶『史上最強の哲学入門』は、入門書として最強
あわせて読みたい
【あらすじ】天才とは「分かりやすい才能」ではない。前進するのに躊躇する暗闇で直進できる勇気のこと…
ピアノのコンクールを舞台に描く『蜜蜂と遠雷』は、「天才とは何か?」と問いかける。既存の「枠組み」をいとも簡単に越えていく者こそが「天才」だと私は思うが、「枠組み」を安易に設定することの是非についても刃を突きつける作品だ。小説と映画の感想を一緒に書く
あわせて読みたい
【奇跡】鈴木敏夫が2人の天才、高畑勲と宮崎駿を語る。ジブリの誕生から驚きの創作秘話まで:『天才の思…
徳間書店から成り行きでジブリ入りすることになったプロデューサー・鈴木敏夫が、宮崎駿・高畑勲という2人の天才と共に作り上げたジブリ作品とその背景を語り尽くす『天才の思考 高畑勲と宮崎駿』。日本のアニメ界のトップランナーたちの軌跡の奇跡を知る
あわせて読みたい
【問い】「学ぶとはどういうことか」が学べる1冊。勉強や研究の指針に悩む人を導いてくれる物語:『喜嶋…
学校の勉強では常に「課題」が与えられていたが、「学び」というのは本来的に「問題を見つけること」にこそ価値がある。研究者の日常を描く小説『喜嶋先生の静かな世界』から、「学びの本質」と、我々はどんな風に生きていくべきかについて考える
あわせて読みたい
【幻想】超ひも理論って何?一般相対性理論と量子力学を繋ぐかもしれないぶっ飛んだ仮説:『大栗先生の…
『大栗先生の超弦理論入門』は最先端科学である「超弦理論」を説明する1冊だが、この記事では著者の主張の1つである「空間は幻想かもしれない」という発想を主に取り上げる。「人類史上初の『適用する次元が限定される理論』」が描像する不可思議な世界とは?
あわせて読みたい
【限界】「科学とは何か?」を知るためのおすすめ本。科学が苦手な人こそ読んでほしい易しい1冊:『哲学…
「科学的に正しい」という言葉は、一体何を意味しているのだろう?科学者が「絶対に正しい」とか「100%間違っている」という言い方をしないのは何故だろう?飲茶『哲学的な何か、あと科学とか』から、「科学とはどんな営みなのか?」について考える
あわせて読みたい
【快挙】「暗黒の天体」ブラックホールはなぜ直接観測できたのか?国際プロジェクトの舞台裏:『アイン…
「世界中に存在する電波望遠鏡を同期させてブラックホールを撮影する」という壮大なEHTプロジェクトの裏側を記した『アインシュタインの影』から、ブラックホール撮影の困難さや、「ノーベル賞」が絡む巨大プロジェクトにおける泥臭い人間ドラマを知る
あわせて読みたい
【貢献】有名な科学者は、どんな派手な失敗をしてきたか?失敗が失敗でなかったアインシュタインも登場…
どれほど偉大な科学者であっても失敗を避けることはできないが、「単なる失敗」で終わることはない。誤った考え方や主張が、プラスの効果をもたらすこともあるのだ。『偉大なる失敗』から、天才科学者の「失敗」と、その意外な「貢献」を知る
あわせて読みたい
【平易】一般相対性理論を簡単に知りたい方へ。ブラックホール・膨張宇宙・重力波と盛りだくさんの1冊:…
現役の研究者が執筆した『ブラックホール・膨張宇宙・重力波』は、アインシュタインが導き出した一般相対性理論が関わる3つのテーマについて、初心者にも分かりやすく伝える内容になっている。歴史的背景も含めて科学的知見を知りたい方にオススメの1冊
あわせて読みたい
【誤解】「意味のない科学研究」にはこんな価値がある。高校生向けの講演から”科学の本質”を知る:『す…
科学研究に対して、「それは何の役に立つんですか?」と問うことは根本的に間違っている。そのことを、「携帯電話」と「東急ハンズの棚」の例を使って著者は力説する。『すごい実験』は素粒子物理学を超易しく解説する本だが、科学への関心を抱かせてもくれる
あわせて読みたい
【逸話】天才数学者ガロアが20歳で決闘で命を落とすまでの波乱万丈。時代を先駆けた男がもし生きていた…
現代数学に不可欠な「群論」をたった1人で生み出し、20歳という若さで決闘で亡くなったガロアは、その短い生涯をどう生きたのか?『ガロア 天才数学者の生涯』から、数学に関心を抱くようになったきっかけや信じられないほどの不運が彼の人生をどう変えてしまったのか、そして「もし生きていたらどうなっていたのか」を知る
あわせて読みたい
【解説】テネットの回転ドアの正体を分かりやすく考察。「時間逆行」ではなく「物質・反物質反転」装置…
クリストファー・ノーラン監督の映画『TENET/テネット』は、「陽電子」「反物質」など量子力学の知見が満載です。この記事では、映画の内容そのものではなく、時間反転装置として登場する「回転ドア」をメインにしつつ、時間逆行の仕組みなど映画全体の設定について科学的にわかりやすく解説していきます
あわせて読みたい
【始まり】宇宙ができる前が「無」なら何故「世界」が生まれた?「ビッグバンの前」は何が有った?:『…
「宇宙がビッグバンから生まれた」ことはよく知られているだろうが、では、「宇宙ができる前はどうなっていたのか」を知っているだろうか? 実は「宇宙は”無”から誕生した」と考えられているのだ。『宇宙が始まる前には何があったのか?』をベースに、ビッグバンが起こる前の「空間も時間も物理法則も存在しない無」について学ぶ
あわせて読みたい
【情熱】常識を疑え。人間の”狂気”こそが、想像し得ない偉業を成し遂げるための原動力だ:映画『博士と…
世界最高峰の辞書である『オックスフォード英語大辞典』は、「学位を持たない独学者」と「殺人犯」のタッグが生みだした。出会うはずのない2人の「狂人」が邂逅したことで成し遂げられた偉業と、「狂気」からしか「偉業」が生まれない現実を、映画『博士と狂人』から学ぶ
あわせて読みたい
【嫉妬?】ヒッグス粒子はいかに発見されたか?そして科学の”発見”はどう評価されるべきか?:『ヒッグ…
科学研究はもはや個人単位では行えず、大規模な「ビッグサイエンス」としてしか成立しなくなっている。そんな中で、科学研究の成果がどう評価されるべきかなどについて、「ヒッグス粒子」発見の舞台裏を追った『ヒッグス 宇宙の最果ての粒子』をベースに書く
あわせて読みたい
【到達】「ヒッグス粒子の発見」はなぜ大ニュースなのか?素粒子物理学の「標準模型」を易しく説明する…
「ヒッグス粒子の発見」はメディアでも大きく取り上げられたが、これが何故重要なのかを説明できる人はそう多くはないだろう。『強い力と弱い力 ヒッグス粒子が宇宙にかけた魔法を解く』をベースに、謎めいた「弱い力」を説明する「自発的対称性の破れ」を学ぶ
あわせて読みたい
【究極】リサ・ランドールが「重力が超弱い理由」を解説する、超刺激的なひも理論の仮説:『ワープする…
現役の研究者であるリサ・ランドールが、自身の仮説を一般向けに分かりやすく説明する『ワープする宇宙』。一般相対性理論・量子力学の知識を深く記述しつつ「重力が超弱い理由」を説明する、ひも理論から導かれる「ワープする余剰次元」について解説する
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
量子力学・量子コンピュータ【本・映画の感想】 | ルシルナ
量子コンピュータが注目されていますが、そのベースとなる量子力学は非常に奇妙で日常感覚では理解できない不思議なものです。「シュレディンガーの猫」が一番有名でしょう…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…






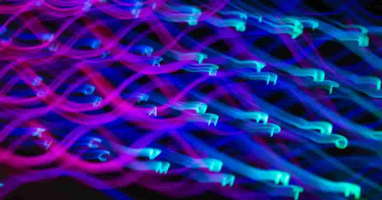





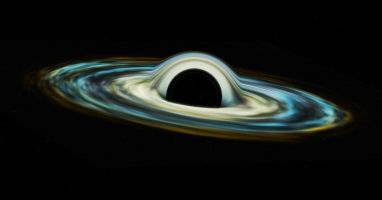








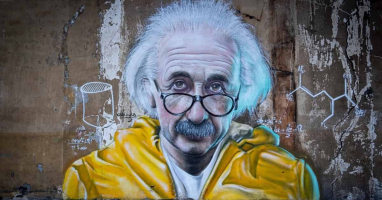



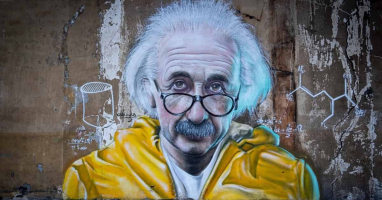


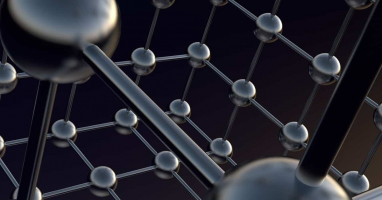











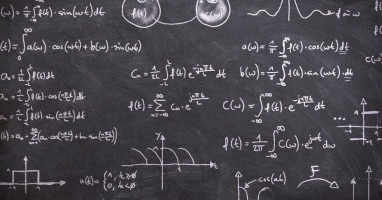



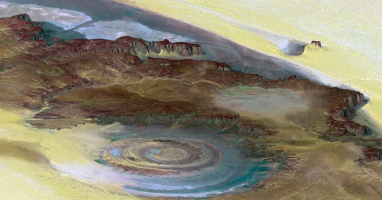


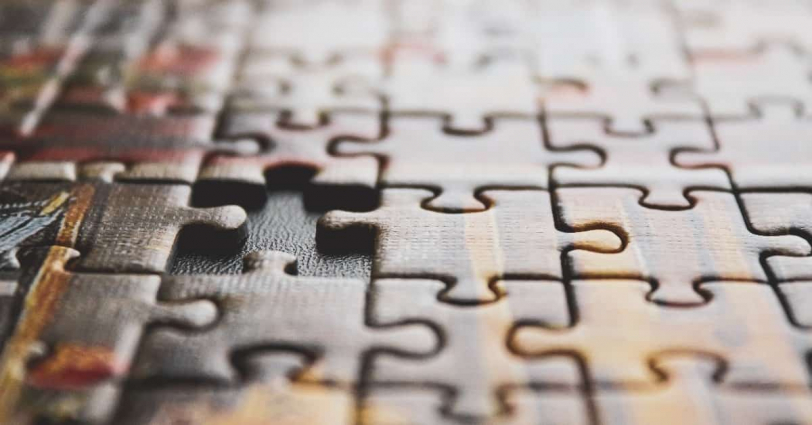

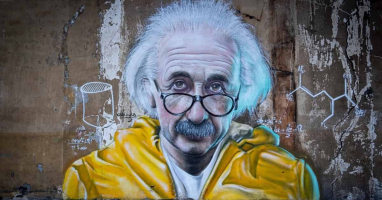










































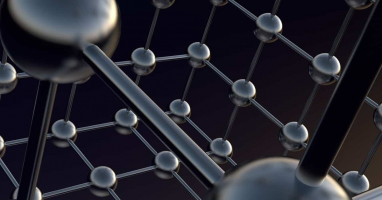

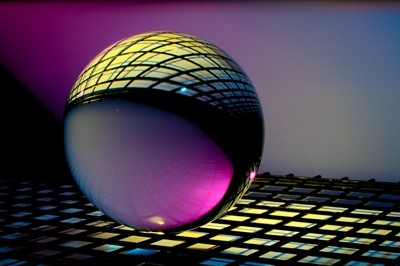


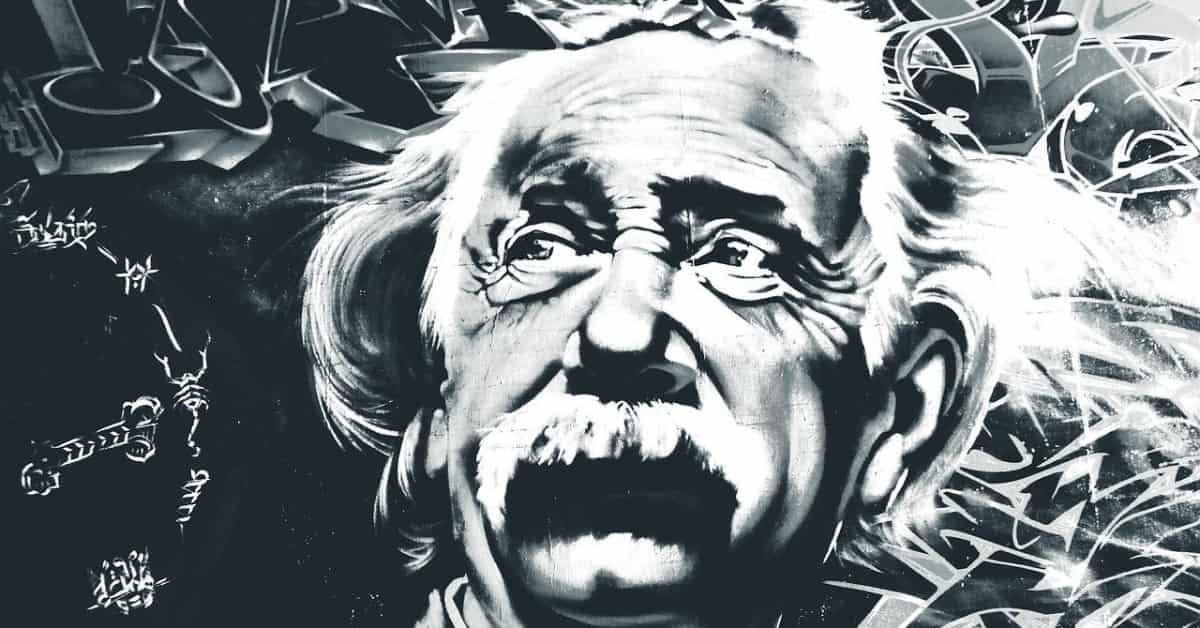





コメント