目次
はじめに
この記事で取り上げる本
講談社
¥549 (2021/08/10 06:09時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
この本をガイドにしながら記事を書いていきます
この記事の3つの要点
- 「ヒッグス粒子」の発見はなぜ大きな話題となったのか?
- 「ヒッグス粒子」の発見はどれほど難しいのか?
- 「ヒッグス粒子」の発見に貢献した研究者はなぜノーベル賞を受賞できなかったのか?
この記事では「ヒッグス粒子」そのものの説明はせず、その舞台裏にスポットライトを当てます
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を…
Kindleで本を出版しました。タイトルは、『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を分かりやすく書いた本:相対性理論も宇宙論も量子論も』です。科学や科学者に関する、文系の人でも読んでもらえる作品に仕上げました。そんな自著について紹介をしています。
『ヒッグス 宇宙の最果ての粒子』で扱われる「ヒッグス粒子」の発見から学ぶ、現代科学の規模の大きさと、「科学の評価」の難しさ
あわせて読みたい
【知的】文系にオススメの、科学・数学・哲学の入門書。高橋昌一郎の「限界シリーズ」は超絶面白い:『…
例えば「科学」だけに限ってみても、「なんでもできる」わけでは決してない。「科学」に限らず、私たちが対峙する様々な事柄には「これ以上は不可能・無理」という「限界」が必ず存在する。高橋昌一郎の「限界シリーズ」から、我々が認識しておくべき「限界」を易しく学ぶ
本書は、科学者が執筆する本としては珍しく、「科学的な記述」が少ない。もちろん、「ヒッグス粒子」という不可思議な存在について説明されているし、その説明のために科学的な記述は出てくる。しかし、本書のメインはそこにはない。

ヒッグス粒子の探索は単に、基本的粒子や難解な理論がどうのという話ではない。予算、政治、嫉妬の物語でもある。計画には非常に多くの人々、前例のない規模の国際協力、そして少なからぬ数の技術的ブレークスルーが関わっている。そんな途方も無い計画を実現させるには、ある程度、ずる賢さや取り引き、そしてときには、いんちきも必要となってくる
本書の内容は、「ヒッグス粒子をいかに発見したか」がメインであり、つまり「科学書」というより「ドキュメンタリー」に近いと言える。そこでこの記事でも、「ヒッグス粒子」そのものや、その説明のために必要な「標準模型」などについて詳しくは書かない。「ヒッグス粒子」の発見物語を通じて、現代科学の現状に触れていこうと思う。
あわせて読みたい
【論争】サイモン・シンが宇宙を語る。古代ギリシャからビッグバンモデルの誕生までの歴史を網羅:『宇…
古代から現代に至るまで、「宇宙」は様々な捉えられ方をしてきた。そして、新たな発見がなされる度に、「宇宙」は常識から外れた不可思議な姿を垣間見せることになる。サイモン・シン『宇宙創成』をベースに、「ビッグバンモデル」に至るまでの「宇宙観」の変遷を知る
ちなみに、本書の「科学的な記述」はかなり易しく書かれていると思うので、文系の方でもチャレンジできるだろう。
「ヒッグス粒子」の発見とその意味
これまでけわしい道のりを経ながらもなんとかLHCの完成まで関係者を導き、LHCの建設計画で他の誰よりも責任のあったウェールズの物理学者リン・エヴァンズは、これら二つの実験の申し分のない一致を目の当たりにして、「あっけにとられた」と告白している
あわせて読みたい
【始まり】宇宙ができる前が「無」なら何故「世界」が生まれた?「ビッグバンの前」は何が有った?:『…
「宇宙がビッグバンから生まれた」ことはよく知られているだろうが、では、「宇宙ができる前はどうなっていたのか」を知っているだろうか? 実は「宇宙は”無”から誕生した」と考えられているのだ。『宇宙が始まる前には何があったのか?』をベースに、ビッグバンが起こる前の「空間も時間も物理法則も存在しない無」について学ぶ
本書にはこんな風に書かれている。
この「あっけにとられた」には、「探すのが困難なものが本当に見つかった」という驚きもあるだろうが、別の感情も含まれているはずだ。それを的確に表現しているのが、科学者の大栗博司である。
ヒッグス粒子発見の宣言を聞いて、「自然界は本当に標準模型を採用していたのだ」という驚きと感動をかみ締めました
『強い力と弱い力 ヒッグス粒子が宇宙にかけた魔法を解く』(大栗博司/幻冬舎)
著:大栗博司
¥815 (2021/08/10 06:14時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【到達】「ヒッグス粒子の発見」はなぜ大ニュースなのか?素粒子物理学の「標準模型」を易しく説明する…
「ヒッグス粒子の発見」はメディアでも大きく取り上げられたが、これが何故重要なのかを説明できる人はそう多くはないだろう。『強い力と弱い力 ヒッグス粒子が宇宙にかけた魔法を解く』をベースに、謎めいた「弱い力」を説明する「自発的対称性の破れ」を学ぶ
人間がその思考力だけでたどり着いた「ヒッグス粒子」という「妄想の産物」が、この世界の仕組みとして本当に採用されているのだ、という驚きである。
本書の原書は、「ヒッグス粒子が発見された可能性が高いと考えられる」という時点で出版されている。本書の出版の後、「ヒッグス粒子の発見は間違いない」と確定され、その後「ヒッグス粒子の発見」はノーベル賞を受賞した。

「ヒッグス粒子」の発見は、科学の話題としては異例だと感じられるほどメディアでも大きく取り上げられた。
あわせて読みたい
【解説】テネットの回転ドアの正体を分かりやすく考察。「時間逆行」ではなく「物質・反物質反転」装置…
クリストファー・ノーラン監督の映画『TENET/テネット』は、「陽電子」「反物質」など量子力学の知見が満載です。この記事では、映画の内容そのものではなく、時間反転装置として登場する「回転ドア」をメインにしつつ、時間逆行の仕組みなど映画全体の設定について科学的にわかりやすく解説していきます
本書を読めば、「”科学者”がヒッグス粒子の発見に湧くのは理解できる」と感じるだろう。「標準模型」の最後のピースを埋める存在として予言され、その予言者の一人であるピーター・ヒッグスが、
セミナーを聴くために部屋にいた83歳のヒッグスは明らかに感動した様子で、「生きてるうちにこの瞬間が来るとは思わなかった」と語った
と言うほどに発見が難しいとされていたものをついに見つけたのだから、歓喜するのも当然だ。
あわせて読みたい
【挑戦】相対性理論の光速度不変の原理を無視した主張『光速より速い光』は、青木薫訳だから安心だぞ
『光速より速い光』というタイトルを見て「トンデモ本」だと感じた方、安心してほしい。「光速変動理論(VSL理論)」が正しいかどうかはともかくとして、本書は実に真っ当な作品だ。「ビッグバン理論」の欠陥を「インフレーション理論」以外の理屈で補う挑戦的な仮説とは?
科学者ではなく、世間が大きく騒いだのには、「ヒッグス粒子」の通称である「神の粒子」という呼び方にも関係するだろう。メディア的には、非常にキャッチーで、「何か重要な発見がなされたのだ」と伝えやすかったのだと思う。
また、当時メディアではよく、「ヒッグス粒子は質量の起源である」という”不正確な情報”が流れていた。このことも、「神の粒子」の重要性をなんとなく伝える役割を果たしただろう。実際には、「ヒッグス粒子」は物質の質量の1%程度は担っているが、99%以上は別の効果によるものであり、「ヒッグス粒子が質量の起源」という表現は正しくない。
さて、この「神の粒子」という表現だが、「質量の起源」という情報とも相まって、「ヒッグス粒子は非常に重要な存在=神」と名付けられたと考えるだろう。しかしそうではない。実際はこうだ。
あわせて読みたい
【平易】ブラックホールを分かりやすく知りたい。難しいことは抜きにふわっと理解するための1冊:『ブラ…
2019年に初めて直接観測されるも、未だに謎多き天体である「ブラックホール」について現役研究者が分かりやすく語る『ブラックホールをのぞいてみたら』をベースに、科学者がその存在を認めてこなかった歴史や、どんな性質を持つ天体なのかを理解する
ある科学者がヒッグス粒子に関する本を出版する際、「くそったれ(God damn)素粒子」というタイトルにしたかったそうだ(あまりに発見されないからイラついていたのかもしれない)。しかし出版社がこのタイトルを受け入れず、最終的に「神の(God)素粒子」に落ち着いたのだという。これが広まって「神の粒子」と呼ばれるようになった、とされている。
では、「ヒッグス粒子」の発見は、科学的にどんな意味を持つのだろうか?
ヒッグスの発見は素粒子物理学の終わりではない。ヒッグスは標準模型の最後のピースだが、標準模型の先にある物理を見せてくれる窓でもある。これから先、何年、何十年と、ヒッグスを使って様々な現象を探索し、その性質を探求することになる。それらの現象には、暗黒物質や超対称性、余剰次元が含まれる。その他にも、急速に増加しつつある新データと付き合わせて検証すべきあらゆる現象が含まれる。ヒッグスの発見は一つの時代の終わりであり、新しい時代の始まりなのだ
あわせて読みたい
【限界】「科学とは何か?」を知るためのおすすめ本。科学が苦手な人こそ読んでほしい易しい1冊:『哲学…
「科学的に正しい」という言葉は、一体何を意味しているのだろう?科学者が「絶対に正しい」とか「100%間違っている」という言い方をしないのは何故だろう?飲茶『哲学的な何か、あと科学とか』から、「科学とはどんな営みなのか?」について考える
科学にはまだまだ謎めいた領域が山ほどあるが、それらの研究に「ヒッグス粒子」が関わっていくことになるということだ。我々一般人が科学の成果を知る時は、「これは凄い発見だ」といううところで止まってしまうが、本当はそこからが新たな始まりとなのである。
「ヒッグス粒子」はどれほど探すのが困難なのか?
「ヒッグス粒子を発見」と聞くと、どんなイメージを抱くだろうか? 私もそうだが、普通は、「何を探せばいいか理解した上で、顕微鏡などのツールで目的となるものがないか探す」という感じだろう。
しかし実際は、そんな易しい話ではない。
あわせて読みたい
【幻想】超ひも理論って何?一般相対性理論と量子力学を繋ぐかもしれないぶっ飛んだ仮説:『大栗先生の…
『大栗先生の超弦理論入門』は最先端科学である「超弦理論」を説明する1冊だが、この記事では著者の主張の1つである「空間は幻想かもしれない」という発想を主に取り上げる。「人類史上初の『適用する次元が限定される理論』」が描像する不可思議な世界とは?
本書には、著者ではない別の科学者による、「ヒッグス粒子」探しの困難さを表現する喩えが載っている。

ヒッグス探索は干し草の山から少数の干し草を探すようなものだ。干し草の山から針を探すなら、見つければ、見つけたとすぐわかる。しかし、全部干し草だとそうはいかない。判別する唯一の方法は、干し草の山にある干し草を一本一本、全部調べるしかない。すると突然、ある長さの干し草だけが他の長さのものよりも多いことが分かる。ヒッグス探索でしていることは、まさにこういうことだ
あわせて読みたい
【逸話】天才数学者ガロアが20歳で決闘で命を落とすまでの波乱万丈。時代を先駆けた男がもし生きていた…
現代数学に不可欠な「群論」をたった1人で生み出し、20歳という若さで決闘で亡くなったガロアは、その短い生涯をどう生きたのか?『ガロア 天才数学者の生涯』から、数学に関心を抱くようになったきっかけや信じられないほどの不運が彼の人生をどう変えてしまったのか、そして「もし生きていたらどうなっていたのか」を知る
こう聞くと、なかなか絶望的な状況だと理解できるだろう。「干し草の中から干し草を探す」というのは、まさに気の遠くなるような話だ。見ていてもずっと「干し草」しかないのだから。しかも、「探しているのがどんな長さの干し草なのか」さえ分かっていない。「干し草」を全部チェックして、「この長さの干し草だけちょっと多いじゃん」となって初めて「発見」と言える、ということだ。
しかもこの「干し草」は、「10のマイナス21乗秒」で消えてしまう。まったくイメージできないが、「10のマイナス21乗」というのは「小数点の後に0が20個続いた後に1がくる」というメチャクチャ小さな数字である。とにかく瞬時に無くなってしまうということだ。
だから科学者は、「干し草」そのものをチェックできるわけではない。「干し草が存在した痕跡」を観察して「干し草」について推測しなければならないのだ。
あわせて読みたい
【異端】数学の”証明”はなぜ生まれたのか?「無理数」と「無限」に恐怖した古代ギリシャ人の奮闘:『数…
学校で数学を習うと、当然のように「証明」が登場する。しかしこの「証明」、実は古代ギリシャでしか発展しなかった、数学史においては非常に”異端”の考え方なのだ。『数学の想像力 正しさの深層に何があるのか』をベースに、ギリシャ人が恐れたものの正体を知る
本書では、そんな「ヒッグス粒子」探索の過程を、推理小説に喩えている。
素粒子物理学が推理小説だ。刑事はほとんどの場合、事件現場に到着しても、事件の一部始終を記録したテープや、疑う余地のない目撃証言、あるいは署名入りの自白書などが得られるわけではない。せいぜい、部分的な指紋や小さなDNA標本などからなるランダムな少数の手がかりが得られるだけだ。刑事は、それらの手がかりをつなぎ合わせて犯罪の一部始終を再構成しなければならない。それが刑事の仕事の最も要となる部分である。
実験素粒子物理学者の仕事もこれと似ている
「ヒッグス粒子」は、スイス・ジュネーブにあるCERNという研究所のLHCという実験施設で発見された。LHCである操作を行うことで「ヒッグス粒子が生成される”かもしれない”実験」を行えるが、毎回ヒッグス粒子が生成されるわけではない。実験家は、「犯行現場に残された、誰のものなのかも分からない踏み荒らされたたくさんの足跡から、犯人のものだけ探す」ようなことをし続けるのだ。
あわせて読みたい
【謎】恐竜を絶滅させた隕石はどこから来た?暗黒物質が絡む、リサ・ランドールの驚愕の仮説:『ダーク…
「生物の絶滅」には、以前から知られていたある謎があった。そしてその謎を、未だに観測されておらず、「科学者の妄想の産物」でしかない「ダークマター(暗黒物質)」が解決するかもしれない。現役の科学者が『ダークマターと恐竜絶滅』で語る驚きの仮説。
だからこそ、実験規模はとんでもないものとなる。そもそもCERNというのは、第二次世界大戦後の国際協調の機運を背景に生まれた研究所で、LHCだけでも90億ドルもの建造費が掛かっている。世界70ヶ国から研究者が集い、ヒッグス粒子の探索だけでも、1チーム3000人の研究チームが2つあるほどだ。

このような大規模な実験は「ビッグサイエンス」と呼ばれており、ここ最近の科学研究の主流になっている。というか、ならざるを得ない。
あわせて読みたい
【衝撃】ABC予想の証明のために生まれたIUT理論を、提唱者・望月新一の盟友が分かりやすく語る:『宇宙…
8年のチェック期間を経て雑誌に掲載された「IUT理論(宇宙際タイヒミュラー理論)」は、数学の最重要未解決問題である「ABC予想」を証明するものとして大いに話題になった。『宇宙と宇宙をつなぐ数学』『abc予想入門』をベースに、「IUT理論」「ABC予想」について学ぶ
本書に登場する科学者が、こんなことを言っている。
最近ではいかなる進歩も達成するのが非常に難しく、LHCはその象徴だ。この状況は65年前の、私が博士課程の学生だった時代と大きく異なる。当時、私は興味深い進展をもたらす実験を、一人で、しかも半年で行うことができた
私は科学のノンフィクションを結構読むが、例えばアインシュタインが生きていた時代には、実験家は個人レベルで重大な発見を成し遂げられた。物理や化学の教科書に登場するような偉人たちのほとんどは、その本人を中心とした何人かの小規模なチームでその偉業を成し遂げているものだ。
あわせて読みたい
【究極】リサ・ランドールが「重力が超弱い理由」を解説する、超刺激的なひも理論の仮説:『ワープする…
現役の研究者であるリサ・ランドールが、自身の仮説を一般向けに分かりやすく説明する『ワープする宇宙』。一般相対性理論・量子力学の知識を深く記述しつつ「重力が超弱い理由」を説明する、ひも理論から導かれる「ワープする余剰次元」について解説する
しかし現在は、後に教科書に載るようなレベルの発見をしようと思えば、個人では不可能だ(理論家は別だが)。莫大な費用を投じて作られた実験施設を使わなければ、最先端科学の研究は行えないからだ。そして、LHCもそうだが、そのような大規模な実験施設の建造は一大学や一研究機関で行えるものではなく、国家レベルで取り組まなければならなくなっている。
だからこそ、科学者にはこれまで以上に「政治力」や「資金集め」などが求められるようにもなっているのだ。冒頭で引用した「予算、政治、嫉妬の物語」という言葉は、まさに「ビッグサイエンス」ゆえである。
「ヒッグス粒子の発見」は誰が評価されるべきか?
あわせて読みたい
【快挙】「暗黒の天体」ブラックホールはなぜ直接観測できたのか?国際プロジェクトの舞台裏:『アイン…
「世界中に存在する電波望遠鏡を同期させてブラックホールを撮影する」という壮大なEHTプロジェクトの裏側を記した『アインシュタインの影』から、ブラックホール撮影の困難さや、「ノーベル賞」が絡む巨大プロジェクトにおける泥臭い人間ドラマを知る
また「ビッグサイエンス」は、「発見に対して誰が評価されるべきか?」という問題も引き起こすことになる。
実験が小規模だった時代は、評価されるべき人ははっきりしていた。実際に手を動かして実験をしたかどうかに関係なく(それは助手がやってもいい)、「こういう実験をしよう」と計画し実現に動いた人間が評価されてきたはずだ。
しかし現在ではそうはいかない。例えば「ヒッグス粒子」は、CERNの研究チームが発見したわけだが、2チームで6000人以上の研究者がいる。またそもそも、LHCという実験施設がなければ絶対に発見できなかったのだから、「LHCの建造に携わった人」や「CERNを運営してきた人」も評価されてもいいかもしれない。当然だが、「ヒッグス粒子を予言した人物」もいる。さて、誰が褒められるべきだろうか?

あわせて読みたい
【未知】タコに「高度な脳」があるなんて初耳だ。人類とは違う進化を遂げた頭足類の「意識」とは?:『…
タコなどの頭足類は、無脊椎動物で唯一「脳」を進化させた。まったく違う進化を辿りながら「タコに心を感じる」という著者は、「タコは地球外生命体に最も近い存在」と書く。『タコの心身問題』から、腕にも脳があるタコの進化の歴史と、「意識のあり方」を知る。
ここまで読んだ方は、「全員頑張った! でいいじゃないか」と感じるかもしれない。しかしそうもいかない。「ノーベル賞」の問題があるからだ。
著者も本書でこう書いている。
本当に残念なのは、実際にヒッグス粒子を発見した実験家が誰もノーベル賞をもらえそうにないことだ。問題は数で、あまりに多くの物理学者があまりに多くの仕方で実験に貢献しているため、誰か一人または二人または三人を、妥当な根拠に基づいて選び出すことなどできないのだ
ノーベル賞には明確な規定がある。「故人には与えられない」「組織ではなく個人に与える」「1年に3人までしか受賞できない」などである。
あわせて読みたい
【驚異】数学の「無限」は面白い。アキレスと亀の矛盾、実無限と可能無限の違い、カントールの対角線論…
日常の中で「無限」について考える機会などなかなか無いだろうが、野矢茂樹『無限論の教室』は、「無限には種類がある」と示すメチャクチャ興味深い作品だった。「実無限」と「可能無限」の違い、「可能無限」派が「カントールの対角線論法」を拒絶する理由など、面白い話題が満載の1冊
ヒッグス粒子の発見に関して、ノーベル賞の受賞規定を無視するならば、「予言したヒッグス氏」「CERNという組織」「ヒッグス粒子の研究チーム」となるだろう。しかし、組織には与えられないのだから、「CERN」と「研究チーム」は外すしかない。また、それら組織から特定の誰かを選ぶとしても不公平感は出てくるし、「1年に3人まで」という規定がかなり厳しい。
さらにヒッグス粒子にはこんな話もある。実は、「ヒッグス粒子」と同等の予測を同時期に行ったチームが、ヒッグス氏の他に2つ存在するという。科学の世界にはこういうことはよくあり、ほぼ同時期に同じようなことを考える人物が出てくる。しかしその場合でも、「1年に3人」という規定に阻まれ、本来的には認められるべき人が評価されない、ということが起こりうる。
本書の原書は「ヒッグス粒子」がノーベル賞受賞となる前に発売されているが、私が読んだ時点ではノーベル賞受賞者が決まっていた。ノーベル賞は、成果の発表から受賞まで数十年掛かることもざらであり、ヒッグス粒子の発見に対するノーベル賞の授与は異例のスピードで決まった。そして、本書の著者が危惧した通り、実験家は誰も受賞できず、「ピーター・ヒッグス氏」のみの受賞となった。
あわせて読みたい
【研究】光の量子コンピュータの最前線。量子テレポーテーションを実現させた科学者の最先端の挑戦:『…
世界中がその開発にしのぎを削る「量子コンピューター」は、技術的制約がかなり高い。世界で初めて「量子テレポーテーション」の実験を成功させた研究者の著書『光の量子コンピューター』をベースに、量子コンピューター開発の現状を知る
彼は、「ヒッグス粒子が発見されたかもしれない」と発表された際、記者からコメントを求められるが、短く発言するに留め、こう言った。

その後の記者室で、記者たちはヒッグスからもっと聞き出そうとしたが、ヒッグスは、今日みたいな日に注目されるべきなのは実験家たちだ、と言ってコメントを控えた
もちろん理論家も素晴らしい仕事をしているが、実験家だって同様に奮闘している。科学の評価は決してノーベル賞だけではないとはいえ、一般向けの知名度で言えばやはり段違いだ。ノーベル賞を受賞できるかどうかは、科学者にとっては非常に大きいだろう。ノーベル賞の規定が変わることはなかなか期待できないかもしれないが、努力した人間が正しく評価される世界であってほしいと感じる。
あわせて読みたい
【快挙】「チバニアン」は何が凄い?「地球の磁場が逆転する」驚異の現象がこの地層を有名にした:『地…
一躍その名が知れ渡ることになった「チバニアン」だが、なぜ話題になり、どう重要なのかを知っている人は多くないだろう。「チバニアン」の申請に深く関わった著者の『地磁気逆転と「チバニアン」』から、地球で起こった過去の不可思議な現象の正体を理解する
講談社
¥599 (2022/02/03 22:54時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品読了済】私が読んできたノンフィクション・教養書を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が読んできたノンフィクションを様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本選びの参考にして下さい。
最後に
本書では他にも、「LHCの建造物語」「膨大な実験データをいかに保存するか」「直接利益に結びつくわけではない基礎研究の重要性」など、「科学そのもの」ではなく「科学研究の周辺」について深く語られていく。「ヒッグス粒子」というヘンテコな存在も知的好奇心を刺激するが、科学者がどんな環境で研究を行っているのかという舞台裏を知ることができるのも興味深い。
あわせて読みたい
【誤解】「意味のない科学研究」にはこんな価値がある。高校生向けの講演から”科学の本質”を知る:『す…
科学研究に対して、「それは何の役に立つんですか?」と問うことは根本的に間違っている。そのことを、「携帯電話」と「東急ハンズの棚」の例を使って著者は力説する。『すごい実験』は素粒子物理学を超易しく解説する本だが、科学への関心を抱かせてもくれる
たった「10のマイナス21乗秒」しか存在できないものに対して、人類がどれだけの叡智と時間とエネルギーを費やしてきたかという奮闘は非常に面白いし、科学という営みが人類をどのように豊かにしていくのかも理解できる。本書を読むことで、なかなか馴染みの薄い「科学者」という存在を、少し身近に感じることができるかもしれない。
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を…
Kindleで本を出版しました。タイトルは、『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を分かりやすく書いた本:相対性理論も宇宙論も量子論も』です。科学や科学者に関する、文系の人でも読んでもらえる作品に仕上げました。そんな自著について紹介をしています。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【奇妙】大栗博司『重力とはなにか』は、相対性理論や量子力学の説明も秀逸だが、超弦理論の話が一番面白い
『重力とはなにか』(大栗博司)は、科学に馴染みの薄い人でもチャレンジできる易しい入門書だ。相対性理論や量子力学、あるいは超弦理論など、非常に難解な分野を基本的なところから平易に説明してくれるので、「科学に興味はあるけど難しいのはちょっと……」という方にこそ読んでほしい1冊
あわせて読みたい
【挑戦】相対性理論の光速度不変の原理を無視した主張『光速より速い光』は、青木薫訳だから安心だぞ
『光速より速い光』というタイトルを見て「トンデモ本」だと感じた方、安心してほしい。「光速変動理論(VSL理論)」が正しいかどうかはともかくとして、本書は実に真っ当な作品だ。「ビッグバン理論」の欠陥を「インフレーション理論」以外の理屈で補う挑戦的な仮説とは?
あわせて読みたい
【激変】天才・藤井聡太と将棋界について加藤一二三、渡辺明が語る。AIがもたらした変化の是非は?:『…
『天才の考え方 藤井聡太とは何者か?』は、加藤一二三・渡辺明という棋界トップランナー2人が「将棋」をテーマに縦横無尽に語り合う対談本。この記事では、「AIがもたらした変化」について触れる。「答えを教えてくれるAI」は、将棋を、そして棋士をどう変えたのか?
あわせて読みたい
【不思議】森達也が「オカルト」に挑む本。「科学では説明できない現象はある」と否定も肯定もしない姿…
肯定派でも否定派でもない森達也が、「オカルト的なもの」に挑むノンフィクション『オカルト』。「現象を解釈する」ことよりも、「現象を記録する」こと点に注力し、「そのほとんどは勘違いや見間違いだが、本当に説明のつかない現象も存在する」というスタンスで追いかける姿勢が良い
あわせて読みたい
【知的】文系にオススメの、科学・数学・哲学の入門書。高橋昌一郎の「限界シリーズ」は超絶面白い:『…
例えば「科学」だけに限ってみても、「なんでもできる」わけでは決してない。「科学」に限らず、私たちが対峙する様々な事柄には「これ以上は不可能・無理」という「限界」が必ず存在する。高橋昌一郎の「限界シリーズ」から、我々が認識しておくべき「限界」を易しく学ぶ
あわせて読みたい
【情熱】映画『パッドマン』から、女性への偏見が色濃く残る現実と、それを打ち破ったパワーを知る
「生理は語ることすらタブー」という、21世紀とは思えない偏見が残るインドで、灰や汚れた布を使って経血を処理する妻のために「安価な生理用ナプキン」の開発に挑んだ実在の人物をモデルにした映画『パッドマン 5億人の女性を救った男』から、「どう生きたいか」を考える
あわせて読みたい
【興奮】飲茶氏が西洋哲学を語る。難解な思想が「グラップラー刃牙成分」の追加で驚異的な面白さに:『…
名前は聞いたことはあるがカントやニーチェがどんな主張をしたのかは分からないという方は多いだろう。私も無知なまったくの初心者だが、そんな人でも超絶分かりやすく超絶面白く西洋哲学を”分かった気になれる”飲茶『史上最強の哲学入門』は、入門書として最強
あわせて読みたい
【奇跡】ホンダジェット驚愕の開発秘話。航空機未経験のホンダが革命的なアイデアで常識を打ち破る:『…
自動車メーカーの本田技研工業が開発した「ホンダジェット」は、航空機への夢を抱いていた創業者・本田宗一郎のスピリットを持ち続ける会社だからこそ実現できた。『ホンダジェット 開発リーダーが語る30年の全軌跡』からその革命的な技術開発と運用までのドラマを知る
あわせて読みたい
【幻想】超ひも理論って何?一般相対性理論と量子力学を繋ぐかもしれないぶっ飛んだ仮説:『大栗先生の…
『大栗先生の超弦理論入門』は最先端科学である「超弦理論」を説明する1冊だが、この記事では著者の主張の1つである「空間は幻想かもしれない」という発想を主に取り上げる。「人類史上初の『適用する次元が限定される理論』」が描像する不可思議な世界とは?
あわせて読みたい
【限界】「科学とは何か?」を知るためのおすすめ本。科学が苦手な人こそ読んでほしい易しい1冊:『哲学…
「科学的に正しい」という言葉は、一体何を意味しているのだろう?科学者が「絶対に正しい」とか「100%間違っている」という言い方をしないのは何故だろう?飲茶『哲学的な何か、あと科学とか』から、「科学とはどんな営みなのか?」について考える
あわせて読みたい
【快挙】「チバニアン」は何が凄い?「地球の磁場が逆転する」驚異の現象がこの地層を有名にした:『地…
一躍その名が知れ渡ることになった「チバニアン」だが、なぜ話題になり、どう重要なのかを知っている人は多くないだろう。「チバニアン」の申請に深く関わった著者の『地磁気逆転と「チバニアン」』から、地球で起こった過去の不可思議な現象の正体を理解する
あわせて読みたい
【貢献】有名な科学者は、どんな派手な失敗をしてきたか?失敗が失敗でなかったアインシュタインも登場…
どれほど偉大な科学者であっても失敗を避けることはできないが、「単なる失敗」で終わることはない。誤った考え方や主張が、プラスの効果をもたらすこともあるのだ。『偉大なる失敗』から、天才科学者の「失敗」と、その意外な「貢献」を知る
あわせて読みたい
【バトル】量子力学の歴史はこの1冊で。先駆者プランクから批判者アインシュタインまですべて描く:『量…
20世紀に生まれた量子論は、時代を彩る天才科学者たちの侃々諤々の議論から生み出された。アインシュタインは生涯量子論に反対し続けたことで知られているが、しかし彼の批判によって新たな知見も生まれた。『量子革命』から、量子論誕生の歴史を知る
あわせて読みたい
【到達】「ヒッグス粒子の発見」はなぜ大ニュースなのか?素粒子物理学の「標準模型」を易しく説明する…
「ヒッグス粒子の発見」はメディアでも大きく取り上げられたが、これが何故重要なのかを説明できる人はそう多くはないだろう。『強い力と弱い力 ヒッグス粒子が宇宙にかけた魔法を解く』をベースに、謎めいた「弱い力」を説明する「自発的対称性の破れ」を学ぶ
あわせて読みたい
【研究】光の量子コンピュータの最前線。量子テレポーテーションを実現させた科学者の最先端の挑戦:『…
世界中がその開発にしのぎを削る「量子コンピューター」は、技術的制約がかなり高い。世界で初めて「量子テレポーテーション」の実験を成功させた研究者の著書『光の量子コンピューター』をベースに、量子コンピューター開発の現状を知る
あわせて読みたい
【謎】恐竜を絶滅させた隕石はどこから来た?暗黒物質が絡む、リサ・ランドールの驚愕の仮説:『ダーク…
「生物の絶滅」には、以前から知られていたある謎があった。そしてその謎を、未だに観測されておらず、「科学者の妄想の産物」でしかない「ダークマター(暗黒物質)」が解決するかもしれない。現役の科学者が『ダークマターと恐竜絶滅』で語る驚きの仮説。
あわせて読みたい
【解説】テネットの回転ドアの正体を分かりやすく考察。「時間逆行」ではなく「物質・反物質反転」装置…
クリストファー・ノーラン監督の映画『TENET/テネット』は、「陽電子」「反物質」など量子力学の知見が満載です。この記事では、映画の内容そのものではなく、時間反転装置として登場する「回転ドア」をメインにしつつ、時間逆行の仕組みなど映画全体の設定について科学的にわかりやすく解説していきます
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
宇宙・ビッグバン・ブラック ホール・相対性理論【本・映画の感想】 | ルシルナ
科学全般に関心を持っていますが、その中でも宇宙に関する本はたくさん読んできました。ビッグバンがいかに起こったか、ブラックホールはどうやって直接観測されたか、宇宙…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…







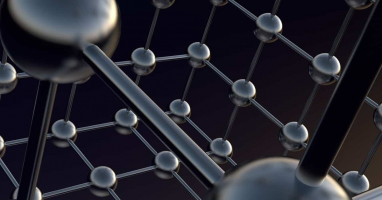



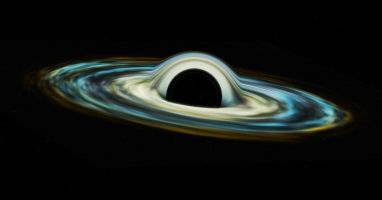




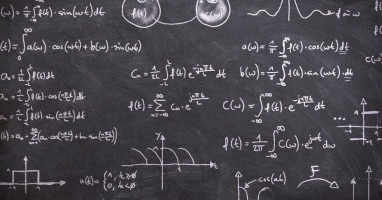
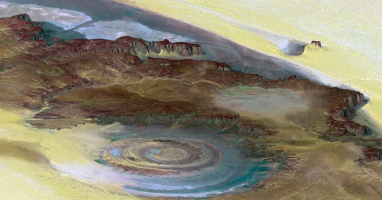







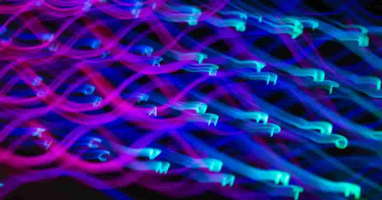


















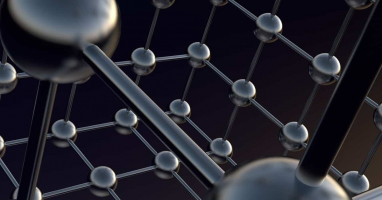
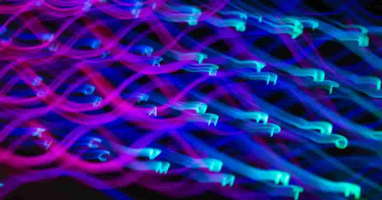
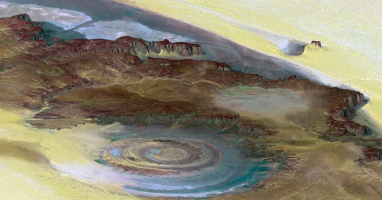











コメント