目次
はじめに
この記事で取り上げる映画
出演:ラーケル・レノーラ・フレットゥム, 出演:アルヴァ・ブリンスモ・ラームスタ, 出演:ミナ・ヤスミン・ブレムセット・アシェイム, 出演:サム・アシュラフ, 出演:エレン・ドリト・ピーターセン, 出演:モーテン・シュバラ, Writer:エスキル・フォクト, 監督:エスキル・フォクト
¥2,500 (2024/02/04 21:29時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
この映画をガイドにしながら記事を書いていきます
今どこで観れるのか?
公式HPの劇場情報をご覧ください
この記事の3つの要点
- 中盤に至るまで、何が描かれているのか、どう展開していくのかが全然想像がつかない物語にゾワゾワさせられた
- 「人間は空を飛ぶことが出来ない」のような「当たり前」を、私たちはいつどこでどのように学んだのだろうか?
- 「非現実的な設定」と「大人の不在」によって、「無邪気な残酷さ」がより強調される構成がとても見事
ラストシーンも含めてとても印象的な物語であり、同じ北欧映画である『ぼくのエリ』を彷彿とさせる不穏さにも満ちていた
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
子どもたちの「無邪気な残酷さ」に大人はどう向き合うべきか。そんな示唆にも富んだ映画『イノセンツ』の恐ろしさ
ストーリーがどう展開していくのかまったく想像できなかった、凄まじい作品

あわせて読みたい
【純愛】映画『ぼくのエリ』の衝撃。「生き延びるために必要なもの」を貪欲に求める狂気と悲哀、そして恋
名作と名高い映画『ぼくのエリ』は、「生き延びるために必要なもの」が「他者を滅ぼしてしまうこと」であるという絶望を抱えながら、それでも生きることを選ぶ者たちの葛藤が描かれる。「純愛」と呼んでいいのか悩んでしまう2人の関係性と、予想もつかない展開に、感動させられる
とんでもない作品だった。静かに淡々と展開されるのに狂気に満ちていること、子どもたちの物語であること、そして北欧の映画であることなど様々な点で、映画『ぼくのエリ』を彷彿とさせる雰囲気を持つ作品だと思う。
この映画については、公開直前まで私はその存在さえまったく知らなかった。映画館で予告を観たこともなければ、公開前に何かの評判が聞こえてくることもなかったのだ。そして公開直前になって、何がどう話題になっていたのか未だに知らないが、映画『イノセンツ』の名前をSNSでよく見かけることになった。そんなわけで、『イノセンツ』というタイトルと、少女が吊り下げられたようなメインビジュアルだけしか知らないまま、この映画を観に行こうと決めたのである。
もともと内容についてまったく何も知らなかったとはいえ、物語の中盤に差し掛かっても、どんな話なのか全然捉えきれなかったことには驚かされた。私は、内容や評判をまったく知らずに映画を観に行くのが好きなのだが、もし私と同じタイプの人がこの記事を読んでくれているとしたら、すぐに読むのを止めて映画を観た方がいい。何も知らずに観る方が、「物語に翻弄されていく感じ」が一層強く味わえるからだ。
あわせて読みたい
【実話】「更生」とは何かを考えさせられる、演劇『ゴドーを待ちながら』を組み込んだ映画『アプローズ…
売れない舞台役者が、刑務所内で囚人に戯曲『ゴドーを待ちながら』の演技指導を行う映画『アプローズ、アプローズ!』は、その衝撃的なラストが実に印象的だ。しかもこのラストの展開は、実話を基にしている。喝采(アプローズ)を浴びる囚人たちの姿から、「更生」についても考えさせられる作品
私にとって幸運だったのは、映画のタイトルが『イノセンツ』だということだろう。原題をそのまま邦訳(というか英訳)したもののようだが、もし別のタイトルだったら、映画を最後まで観ても、何を描きたかったのか捉えきれなかった可能性があるからだ。
この映画で描かれているのは、要するに「イノセンツ(無邪気さ)」、つまり「子どもは無邪気なほどに残酷だ」ということなのだと思う。そしてそれを描き出すために「超能力」というモチーフが登場するのである。「超能力」の存在をとてもリアルに描き出すことによって、「子どもの残酷なまでの無邪気さ」を丁寧に描き出しているというわけだ。
普通に考えれば、「超能力」が登場する時点で「非現実的な物語」に仕上がってしまうはずだが、映画『イノセンツ』は決してそうはなっていない。観れば観るほど「現実そのものを抉り取っている」と感じさせる作品であり、そのバランスの取り方がとても見事だったと思う。さらに、この記事の後半で触れるが、「『大人の存在』が完全に排除されている」という本作の特徴的な構成も、物語全体の主題を浮かび上がらせる要素の1つと言えるだろう。
あわせて読みたい
【感想】映画『若おかみは小学生!』は「子どもの感情」を「大人の世界」で素直に出す構成に号泣させられる
ネット記事を読まなければ絶対に観なかっただろう映画『若おかみは小学生!』は、基本的に子ども向け作品だと思うが、大人が観てもハマる。「大人の世界」でストレートに感情を表に出す主人公の小学生の振る舞いと成長に、否応なしに感動させられる
さて、私は鑑賞後に知ったのだが、映画『イノセンツ』は、大友克洋の『童夢』にインスパイアされて生まれた作品なのだそうだ。監督自身が、そのように公言しているのだという。私は『童夢』を読んだこともないので、その情報を事前に知っていたとしてもストーリーの展開を想像出来たとは思えないが、『童夢』を知っている人なら大体の想像がつくのかもしれない。しかし、『AKIRA』もそうだが、やはり大友克洋の影響力はとても強いんだなぁと改めて実感させられた。
著:大友 克洋
¥2,970 (2023/12/13 20:13時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
映画『イノセンツ』の内容紹介

あわせて読みたい
【天才】映画『ツィゴイネルワイゼン』(鈴木清順)は意味不明だが、大楠道代のトークが面白かった
鈴木清順監督作『ツィゴイネルワイゼン』は、最初から最後まで何を描いているのかさっぱり分からない映画だった。しかし、出演者の1人で、上映後のトークイベントにも登壇した大楠道代でさえ「よく分からない」と言っていたのだから、それでいいのだろう。意味不明なのに、どこか惹きつけられてしまう、実に変な映画だった
9歳のイーダは、郊外の団地へと引っ越してきた。両親と姉の4人家族である。姉のアナは重度の自閉症と診断されており、言葉を発することはおろか、自律的な運動も困難なほどだ。両親はそんなアナにも愛情を注いでいるのだが、当然イーダには不満がある。両親がアナにばかり構っていることや、時々アナのお守りをしなければならないことなど嫌なことばかりだ。しかし、彼女がその不満を表立って口にすることはない。
引っ越した時期は夏休み期間中であり、家族で旅行にでも出かけているのか、団地に残っている者は僅かだ。そんな中イーダは、同じ団地に住むベンという少年と仲良くなる。彼は不思議な力を持っていた。軽いものであれば、手を触れずにその落下軌道を変えることが出来るのだ。そんな普通じゃないところも、彼に惹かれた理由である。
その日イーダは、ベンと遊ぶために、アナをしばらくブランコに独りで座らせていた。しかしブランコに戻ってみると、そこにいるはずのアナがいなくなっている。彼女が自発的に動けるはずがない。近くを探してみると、アナはアイシャという女の子と一緒にいた。アナは喋れないはずなのだが、しかし2人を見ていると、どうもアナとアイシャの間で心が通じ合っているような感じがするのだ。実際アイシャは「アナの考えていることが分かる」と言うし、アナも普段と比べるとおとなしいように見える。
4人はこんな風にして出会った。ベンとアイシャは出会った当初から不思議な力を備えていたのだが、4人で遊ぶ内、なんとアナにも謎めいた力があることが判明し……。
あわせて読みたい
【異端】子育てがうまくいかないと悩む方へ。9歳で大学入学の天才児に学ぶ「すべきでないこと」:『ぼく…
12歳で数学の未解決問題を解いた天才児は、3歳の時に「16歳で靴紐が結べるようになったらラッキー」と宣告されていた。専門家の意見に逆らって、重度の自閉症児の才能をどう開花させたのかを、『ぼくは数式で宇宙の美しさを伝えたい』から学ぶ
私たちは「当たり前」をいつどのようにして学んだのか
冒頭でも触れた通り、映画『イノセンツ』は「無邪気な残酷さ」を描き出している。そしてその背景にあるのが、「何が『当たり前』なのかを知らない」という感覚なのだと私は感じた。
例えば、少し前にネットで見かけたこんな話はどうだろう。ママ友同士の会話の中で、ある親が「子どもがジブリ作品に興味を持ち始めた」と話したところ、先輩ママから「『人間は空を飛べない』って何度も教えた方がいいよ」とアドバイスされた、という話である。
私はこの話を読んだ時、「なるほど、確かにその通りだ」と感じた。人間が空を飛べないことなど「当たり前」なのだが、しかしその「当たり前」を私は一体いつどこで学んだのだろう? 「人間は空を飛べませんよ」と、誰かが教えてくれたような記憶はない。「空を飛ぼうとしてはダメですよ」なんて注意されたことだって恐らくないはずだ。しかしいつの間にか、「人間は空を飛ぶことが出来ない」という「当たり前」を理解している。
あわせて読みたい
【斬新】フィクション?ドキュメンタリー?驚きの手法で撮られた、現実と虚構が入り混じる映画:『最悪…
映画『最悪な子どもたち』は、最後まで観てもフィクションなのかドキュメンタリーなのか確信が持てなかった、普段なかなか抱くことのない感覚がもたらされる作品だった。「演技未経験」の少年少女を集めての撮影はかなり実験的に感じられたし、「分からないこと」に惹かれる作品と言えるいだろうと思う

さらに、先ほどのママ友の話を踏まえれば、「生まれた時からそのことを理解しているわけではない」とも判断できるだろう。「空は飛べないよ」と子どもに注意しておかなければ、「自分もジブリの登場人物みたいに空を飛べるかも」と試してしまうかもしれないのである。
こんな風に考えてみると、とても不思議ではないだろうか? 「赤信号では渡っちゃいけません」みたいなことはちゃんと教わったことがある。しかし、世の中のすべての「当たり前」をそんな風に誰かに教えてもらったわけではない。それなのに、世の中の大体の人が、そう大きくは異ならない「当たり前」をちゃんと身につけて大人になっていくのだ。
私たちは、そういう「当たり前」を、いつどのように学んだのだろう?
あわせて読みたい
【衝撃】洗脳を自ら脱した著者の『カルト脱出記』から、「社会・集団の洗脳」を避ける生き方を知る
「聖書研究に熱心な日本人証人」として「エホバの証人」で活動しながら、その聖書研究をきっかけに自ら「洗脳」を脱した著者の体験を著した『カルト脱出記』。広い意味での「洗脳」は社会のそこかしこに蔓延っているからこそ、著者の体験を「他人事」だと無視することはできない
何故こんな問いかけをしているのかと言えば、映画『イノセンツ』で描かれる主人公たちが、「『◯◯をしてはいけない』という『当たり前』」を全然理解していないように見えるからだ。「◯◯」には様々な動作が含まれるわけだが、とにかく彼らは、「しちゃいけないことを、あっさりと無邪気に飛び越えていく」のである。
これはまさに、「ジブリ作品を観て、空を飛べるか試してみたくなる」ようなことに近いだろう。「人間は空を飛べない」という「当たり前」を知らなければ、そりゃあジブリ作品を観て自分も飛べるか試してみたくなるはずだ。それと同じように、映画の登場人物たちは、「しちゃいけない」という「当たり前」を理解していないように見えるのだ。
そしてその様が、「無邪気な残酷さ」として映し出されていくのである。
「超能力者の物語」と聞くと現実離れしているように感じられるだろうが、実際には「『当たり前』を知らない子どもたち」が描かれているというわけだ。私たち自身にも「いつ理解したのか覚えていない『当たり前』がたくさんある」のだし、裏を返せば、「誰もが知っているべき『当たり前』を、実は自分だけが知らなかった」みたいなことだって十分あり得るはずだ。だからこそこの映画が示唆することは、決して他人事ではないと言えるのである。
あわせて読みたい
【感想】池田晶子『14歳からの哲学』で思考・自由・孤独の大事さを知る。孤独を感じることって大事だ
「元々持ってた価値観とは違う考えに触れ、それを理解したいと思う場面」でしか「考える」という行為は発動しないと著者は言う。つまり我々は普段、まったく考えていないのだ。『14歳からの哲学』をベースに、「考えること」と自由・孤独・人生との関係を知る
「超能力」を描くからこそ、「無邪気な残酷さ」をよりリアルに切り取ることが出来る
この映画の見事な点は、「超能力」が扱われていることだと私は思う。

例えば、少し卑近な例を出すが、私たちは未だに、「『回転寿司店で醤油差しを舐める』みたいな動画がネットで出回る世の中」に生きている。この「醤油差しを舐める」みたいな行為は、私には「無邪気な残酷さ」とは受け取れない。何故なら、「生きていればどこかのタイミングで理解すべき事柄」だからだ。「回転寿司店に行ったら醤油差しを舐めている人が多い」みたいな状況はまずあり得ない。また、「醤油差しを舐めるな」と直接的に指摘される経験は無いにしても、店の商品やサービスに対して何か注意されたみたいな経験は誰にでもあるはずだ。そういう中で、「醤油差しを舐めてはいけないとは知らなかった」という主張はまず通らないし、だからそれが「無邪気な残酷さ」だと受け取られるはずもないと思う。
あわせて読みたい
【不思議】森達也が「オカルト」に挑む本。「科学では説明できない現象はある」と否定も肯定もしない姿…
肯定派でも否定派でもない森達也が、「オカルト的なもの」に挑むノンフィクション『オカルト』。「現象を解釈する」ことよりも、「現象を記録する」こと点に注力し、「そのほとんどは勘違いや見間違いだが、本当に説明のつかない現象も存在する」というスタンスで追いかける姿勢が良い
しかし、「超能力」の場合は少し違う。私たちは普段、「超能力者」に出会うことはない。だから子どもに、「超能力者に出会ったらこうしなさい」「もし自分に超能力があると気づいても、こうしてはいけない」などと注意することはないはずだ。つまり、「『超能力を持っていることに気づいた子ども』が普通取るべき行動」などという規範は存在しないと言っていいだろう。
そしてそれ故に、彼らの「無邪気な残酷さ」が一層強調されているように感じられたのだ。
「醤油差しを舐める」みたいな「当然してはいけないこと」の場合、最終的には「個々人の倫理観」や「親からの教育」などの話に収斂していくだろう。しかし「超能力」というのは、「当たり前」からかけ離れた存在である。だからこそ、「個々人の倫理観」「親からの教育」などではない「何か」が浮き彫りにされるのだと感じるし、その「何か」というのは要するに「子どもが生来的に持ち得る性質」なのだろうと思う。そしてまさにそれが「無邪気な残酷さ」として現れているである。「超能力」という非現実的なものを突き詰めて描き出すからこそ、子どもが持つ普遍的な「残酷さ」が浮き彫りにされるというわけだ。
そう考えて物語全体を振り返ってみると、随所で「無邪気な残酷さ」が描かれていることに気付くだろう。例えば冒頭で、イーダが自閉症の姉の腕をきつく抓る場面がある。これは「姉に対する苛立ち」によるものとも捉えられるが、同時に、「自閉症なら痛みに鈍感だろう」という興味関心からの行動とも受け取れるだろう。あるいは、ベンが「ヤバ」と名付けた猫に関する描写も挙げられる。その行動自体はここでは触れないが、「当たり前」を理解した大人であればまずしないだろう振る舞いをしているのだ。
あわせて読みたい
【考察】映画『街の上で』(今泉力哉)が描く「男女の友情は成立する」的会話が超絶妙で素晴らしい(出…
映画『街の上で』(今泉力哉監督)は、「映画・ドラマ的会話」ではない「自然な会話」を可能な限り目指すスタンスが見事だった。「会話の無駄」がとにかく随所に散りばめられていて、そのことが作品のリアリティを圧倒的に押し上げていると言える。ある男女の”恋愛未満”の会話もとても素晴らしかった
繰り返すが、これらの背景には子どもの「無知」があり、そしてその「無知」は普通、個人の能力や家庭環境など様々な要因と結びつけられる。しかし「超能力」が扱われる場合は、すべての人間が「超能力」に対して「無知」だと言っていいはずだ。つまり、その「無知」の要因となる要素は存在しないわけで、すべての焦点が「子どもが生来的に持ち得る性質」に当たるのである。このような構成がとても見事だったと思う。
「大人の存在」が完全に排除されている物語
さて、物語の焦点が「子どもが生来的に持ち得る性質」に当たるためには、1つ重要な要素がある。それが「大人の不在」だ。映画『イノセンツ』ではとにかく、物語から「大人の存在」が完璧に、そして意図的に排除されているのである。
もちろん、映画には大人も登場するし、基本的には「4人の子どもの親」と考えていいだろう。そして彼らは物語の中で、子どもたちの日常にそれなりに関わっていく。
あわせて読みたい
【嫌悪】映画『ドライビング・バニー』が描く、人生やり直したい主人公(母親)のウザさと絶望
映画『ドライビング・バニー』は、主人公であるバニーのことが最後まで嫌いだったにも拘わらず、全体的にはとても素敵に感じられた珍しいタイプの作品だ。私は、「バニーのような人間が世の中に存在する」という事実に嫌悪感を抱いてしまうのだが、それでも、狂気的でぶっ飛んだラストシーンによって、作品全体の印象が大きく変わったと言える

しかし大人たちは、最後の最後まで「超能力」の存在について一切知らないままなのだ。だから当然、子どもたちの間で何が起こっているのかも理解できていない。もちろん、「何かおかしなことが進行している」という兆候を掴んではいるのだが、その背景にあるものが何なのかは、まったく想像が及んでいないのである。核となる物語から、「大人」が完全に排除されているというわけだ。
しかし映画『イノセンツ』においては、状況の凄まじい変化に伴って、「大人の存在」が求められることにもなる。ただ先述の通り、「大人」は完膚なきまでに排除されてしまっているのだ。となれば、誰かが「大人」になるしかないだろう。
その象徴とも言えるシーンが、とても印象的だった。映画全体の中でも、かなり胸に刺さるシーンだったと言っていいだろう。
あわせて読みたい
【美麗】映画『CLOSE/クロース』はあまりにも切ない。「誰かの当たり前」に飲み込まれてしまう悲劇
子どもの頃から兄弟のように育った幼馴染のレオとレミの関係の変化を丁寧に描き出す映画『CLOSE/クロース』は、「自分自身で『美しい世界』を毀損しているのかもしれない」という話でもある。”些細な”言動によって、確かに存在したあまりに「美しい世界」があっさりと壊されてしまう悲哀が描かれる
物語におけるかなり後半の展開なので、具体的には伝わらないように書くが、イーダがある場面で「もし大人だったら?」と口にするシーンがそれである。
イーダのその問いを耳にした者たちは、当然それを「仮定の話」として受け取った。イーダは9歳で、「大人ではない」ことは明らかだからだ。しかし、観客には明確に伝わるのだが、イーダははっきりと「大人である私はどう行動すべきか?」という意図を持って質問を繰り出している。そのことは、その後の彼女の行動からも明らかだろう。
映画『イノセンツ』の物語に、何らかの形できちんと「大人」が関わっているのであれば、「もし大人だったら?」などとイーダが口にする必要はなかったはずだ。しかしイーダは、大人たちが「超能力」なんてものを信じるはずがないと理解していた。イーダの両親は決して理解力に乏しい人たちではないと思うが、それでもやはり「超能力」の存在は受け入れないだろう。なにせイーダの母親は、「アナが喋った」というイーダの訴えさえ疑って掛かるのだ。「超能力」なんてもっての他だろう。
となれば、誰かが「大人」になるしかない。そして、「自分が『大人』になるしかない」というイーダの決意が観客に伝わるのが、先のシーンというわけだ。「大人の排除」については作中の様々な場面で示唆されるのだが、イーダの決意のシーンが最も象徴的な場面だと私には感じられた。
あわせて読みたい
【中絶】望まない妊娠をした若い女性が直面する現実をリアルに描く映画。誰もが現状を知るべきだ:『17…
他の様々な要素を一切排し、「望まぬ妊娠をした少女が中絶をする」というただ1点のみに全振りした映画『17歳の瞳に映る世界』は、説明もセリフも極端に削ぎ落としたチャレンジングな作品だ。主人公2人の沈黙が、彼女たちの置かれた現実を雄弁に物語っていく。
そして、このように徹底して「大人の存在」が排除され、そのせいでイーダが「大人になる決意」をせざるを得ならなかったという物語は、「子どもは、大人が思っている以上に物事を深く考えている」という示唆にも繋がっていくだろうと思う。
私には子どもはいないが、親子に関する様々な話を知るにつけ、「どうも子を持つ親は、『自分もかつては子どもだった』という事実を忘れているんじゃないか」と感じることが多い。「自分が子どもの頃、親に言われたら絶対に嫌だっただろう」と感じることを、自分の子どもに言ってしまっている親は、結構いるんじゃないかと思うのだ。「親の立場になったからこそ分かることがある」みたいに反論されるだろうし、それは確かに一側面だとも思うが、同時に「自分が子どもだったことを忘れている」という捉え方もあながち間違ってはいないはずだとも感じる。
そんなわけで、最初から最後まで「子ども視点」で物語を描き出す映画『イノセンツ』を観ることで、「子どもは子どもなりにきちんと考えて様々な判断をしている」と理解しやすいのではないかと思う。大人の視点では、「嘘をついている」「何か隠している」ように見える言動でも、そこには子どもなりの切実さや葛藤を経た決断があるのかもしれないのである。
あわせて読みたい
【あらすじ】子どもは大人よりずっと大人だ。「子ども扱い」するから、「子どもの枠」から抜け出せない…
宮部みゆき『ソロモンの偽証』は、その分厚さ故になかなか手が伸びない作品だろうが、「長い」というだけの理由で手を出さないのはあまりにももったいない傑作だ。「中学生が自前で裁判を行う」という非現実的設定をリアルに描き出すものすごい作品

もちろん、繰り返しになるが、本作で扱われているのは「超能力」であり、非現実的なものだ。その点だけを捉えるなら、映画で示唆される様々な事柄をリアルに捉えるのは正しくないと感じられるかもしれない。しかしやはり、「超能力」というモチーフは「無邪気な残酷さ」を強調する舞台装置だと感じられたし、描かれていることは私にはとても現実的なものに思えたのである。
実に興味深い物語だった。
あわせて読みたい
【痛快】精神病院の隔離室から脱した、善悪の判断基準を持たない狂気の超能力者が大暴れする映画:『モ…
モナ・リザ アンド ザ ブラッドムーン』は、「10年以上拘束され続けた精神病院から脱走したアジア系女性が、特殊能力を使って大暴れする」というムチャクチャな設定の物語なのだが、全編に通底する「『善悪の判断基準』が歪んでいる」という要素がとても見事で、意味不明なのに最後まで惹きつけられてしまった
出演:ラーケル・レノーラ・フレットゥム, 出演:アルヴァ・ブリンスモ・ラームスタ, 出演:ミナ・ヤスミン・ブレムセット・アシェイム, 出演:サム・アシュラフ, 出演:エレン・ドリト・ピーターセン, 出演:モーテン・シュバラ, Writer:エスキル・フォクト, 監督:エスキル・フォクト
¥2,500 (2024/02/04 21:30時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品視聴済】私が観てきた映画(フィクション)を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が観てきた映画(フィクション)を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。
最後に
あわせて読みたい
【あらすじ】アリ・アスター監督映画『ミッドサマー』は、気持ち悪さと怖さが詰まった超狂ホラーだった
「夏至の日に映画館で上映する」という企画でようやく観ることが叶った映画『ミッドサマー』は、「私がなんとなく想像していたのとはまるで異なる『ヤバさ』」に溢れる作品だった。いい知れぬ「狂気」が随所で描かれるが、同時に、「ある意味で合理的と言えなくもない」と感じさせられる怖さもある
ラストシーンには、色々と考えさせられてしまった。想像力を掻き立てさせる終わり方であり、観る人によって受け取り方は様々だと思う。グッドともバッドとも形容し難い、なんとも言えないラストなのだが、同時に「これしかないよな」という着地の仕方でもあり、物語は上手く閉じていると言えるだろう。
まったく想像もしていなかったような設定・展開の物語であり、その訳の分からなさも含めて全体としてとても良かった。「大人の存在」をナチュラルに排除しながら、子どもの無邪気さ、残酷さをリアルに描き出す物語は、圧巻の一言である。
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を…
Kindleで本を出版しました。タイトルは、『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を分かりやすく書いた本:相対性理論も宇宙論も量子論も』です。科学や科学者に関する、文系の人でも読んでもらえる作品に仕上げました。そんな自著について紹介をしています。
次におすすめの記事
あわせて読みたい
【奇妙】映画『画家と泥棒』は、非日常的なきっかけで始まったあり得ないほど奇跡的な関係を描く
映画『画家と泥棒』は、「自身の絵を盗まれた画家が、盗んだ泥棒と親しくなる」という奇妙奇天烈なきっかけから関係性が始まる物語であり、現実に起きたこととは思えないほど不可思議なドキュメンタリーである。アートを通じて奇妙に通じ合う2人の関係性は、ある種の美しささえ感じさせる、とても素晴らしいものに見えた
あわせて読みたい
【恐怖】「1970年代の生放送の怪しげなテレビ番組」を見事に再現したフェイクドキュメンタリー:映画『…
映画『悪魔と夜ふかし』は、「1970年代に放送されていた生放送番組のマスターテープが発見された」というテイで、ハロウィンの夜の放送回をそのまま流すという設定のモキュメンタリーである。番組の細部までリアルに作り込まれており、それ故に、「悪魔の召喚」という非現実的な状況もするっと受け入れられる感じがした
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『憐れみの3章』(ヨルゴス・ランティモス)は意味不明なのに何故か超絶面白かった(主…
映画『憐れみの3章』(ヨルゴス・ランティモス監督)は、最初から最後まで「意味不明」と言っていいレベルで理解できなかったが、しかし「実に良い映画を観たなぁ」という感覚にさせてもくれる、とても素敵な作品だった。さらに、「3つの異なる物語を同じ役者の組み合わせで撮る」という斬新な構成が上手くハマっていたようにも思う
あわせて読みたい
【狂気】「こんな作品を作ろうと考えて実際世に出した川上さわ、ヤベェな」って感じた映画『地獄のSE』…
私が観た時はポレポレ東中野のみで公開されていた映画『地獄のSE』は、最初から最後までイカれ狂ったゲロヤバな作品だった。久しぶりに出会ったな、こんな狂気的な映画。面白かったけど!「こんなヤバい作品を、多くの人の協力を得て作り公開した監督」に対する興味を強く抱かされた作品で、とにかく「凄いモノを観たな」という感じだった
あわせて読みたい
【葛藤】映画『きみの色』(山田尚子)は、感受性が強すぎる若者のリアルをバンドを通じて描き出す(主…
山田尚子監督作『きみの色』は、これといった起伏のないストーリー展開でありながら、「若い世代の繊細さに満ちた人間関係」をとてもリアルに描き出す雰囲気が素敵な作品。「悩み・葛藤を抱えている状態が日常である」という雰囲気をベースにしつつ、「音楽」を起点に偶然繋がった3人の緩やかな日々を描き出す物語に惹きつけられた
あわせて読みたい
【感想】B級サメ映画の傑作『温泉シャーク』は、『シン・ゴジラ』的壮大さをバカバカしく描き出す
「温泉に入っているとサメに襲われる」という荒唐無稽すぎる設定のサメ映画『温泉シャーク』は、確かにふざけ倒した作品ではあるものの、観てみる価値のある映画だと思います。サメの生態を上手く利用した設定や、「伏線回収」と表現していいだろう展開などが巧みで、細かなことを気にしなければ、そのバカバカしさを楽しめるはずです
あわせて読みたい
【感想】映画『夜明けのすべて』は、「ままならなさ」を抱えて生きるすべての人に優しく寄り添う(監督…
映画『夜明けのすべて』は、「PMS」や「パニック障害」を通じて、「自分のものなのに、心・身体が思い通りにならない」という「ままならなさ」を描き出していく。決して他人事ではないし、「私たちもいつそのような状況に置かれるか分からない」という気持ちで観るのがいいでしょう。物語の起伏がないのに惹きつけられる素敵な作品です
あわせて読みたい
【狂気】押見修造デザインの「ちーちゃん」(映画『毒娘』)は「『正しさ』によって歪む何か」の象徴だ…
映画『毒娘』は、押見修造デザインの「ちーちゃん」の存在感が圧倒的であることは確かなのだが、しかし観ていくと、「決して『ちーちゃん』がメインなわけではない」ということに気づくだろう。本作は、全体として「『正しさ』によって歪む何か」を描き出そうとする物語であり、私たちが生きる社会のリアルを抉り出す作品である
あわせて読みたい
【常識】群青いろ制作『彼女はなぜ、猿を逃したか?』は、凄まじく奇妙で、実に魅力的な映画だった(主…
映画『彼女はなぜ、猿を逃したか?』(群青いろ制作)は、「絶妙に奇妙な展開」と「爽快感のあるラスト」の対比が魅力的な作品。主なテーマとして扱われている「週刊誌報道からのネットの炎上」よりも、私は「週刊誌記者が無意識に抱いている思い込み」の方に興味があったし、それを受け流す女子高生の受け答えがとても素敵だった
あわせて読みたい
【狂気】群青いろ制作『雨降って、ジ・エンド。』は、主演の古川琴音が成立させている映画だ
映画『雨降って、ジ・エンド。』は、冒頭からしばらくの間「若い女性とオジサンのちょっと変わった関係」を描く物語なのですが、後半のある時点から「共感を一切排除する」かのごとき展開になる物語です。色んな意味で「普通なら成立し得ない物語」だと思うのですが、古川琴音の演技などのお陰で、絶妙な形で素敵な作品に仕上がっています
あわせて読みたい
【幻惑】映画『フォロウィング』の衝撃。初監督作から天才だよ、クリストファー・ノーラン
クリストファー・ノーランのデビュー作であり、多数の賞を受賞し世界に衝撃を与えた映画『フォロウィング』には、私も驚かされてしまった。冒頭からしばらくの間「何が描かれているのかさっぱり理解できない」という状態だったのに、ある瞬間一気に視界が晴れたように状況が理解できたのだ。脚本の力がとにかく圧倒的だった
あわせて読みたい
【天才】映画『ツィゴイネルワイゼン』(鈴木清順)は意味不明だが、大楠道代のトークが面白かった
鈴木清順監督作『ツィゴイネルワイゼン』は、最初から最後まで何を描いているのかさっぱり分からない映画だった。しかし、出演者の1人で、上映後のトークイベントにも登壇した大楠道代でさえ「よく分からない」と言っていたのだから、それでいいのだろう。意味不明なのに、どこか惹きつけられてしまう、実に変な映画だった
あわせて読みたい
【斬新】フィクション?ドキュメンタリー?驚きの手法で撮られた、現実と虚構が入り混じる映画:『最悪…
映画『最悪な子どもたち』は、最後まで観てもフィクションなのかドキュメンタリーなのか確信が持てなかった、普段なかなか抱くことのない感覚がもたらされる作品だった。「演技未経験」の少年少女を集めての撮影はかなり実験的に感じられたし、「分からないこと」に惹かれる作品と言えるいだろうと思う
あわせて読みたい
【天才】映画『笑いのカイブツ』のモデル「伝説のハガキ職人ツチヤタカユキ」の狂気に共感させられた
『「伝説のハガキ職人」として知られるツチヤタカユキの自伝的小説を基にした映画『笑いのカイブツ』は、凄まじい狂気に彩られた作品だった。「お笑い」にすべてを捧げ、「お笑い」以外はどうでもいいと考えているツチヤタカユキが、「コミュ力」や「人間関係」で躓かされる”理不尽”な世の中に、色々と考えさせられる
あわせて読みたい
【斬新】映画『王国(あるいはその家について)』(草野なつか)を観よ。未経験の鑑賞体験を保証する
映画『王国(あるいはその家について)』は、まず経験できないだろう異様な鑑賞体験をもたらす特異な作品だった。「稽古場での台本読み」を映し出すパートが上映時間150分のほとんどを占め、同じやり取りをひたすら繰り返し見せ続ける本作は、「王国」をキーワードに様々な形の「狂気」を炙り出す異常な作品である
あわせて読みたい
【考察】A24のホラー映画『TALK TO ME』が描くのは、「薄く広がった人間関係」に悩む若者のリアルだ
「A24のホラー映画史上、北米最高興収」と謳われる『TALK TO ME トーク・トゥ・ミー』は、一見「とても分かりやすいホラー映画」である。しかし真のテーマは「SNS過剰社会における人間関係の困難さ」なのだと思う。結果としてSNSが人と人との距離を遠ざけてしまっている現実を、ホラー映画のスタイルに落とし込んだ怪作
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『千年女優』(今敏)はシンプルな物語を驚愕の演出で味付けした天才的アニメ作品
今敏監督の映画『千年女優』は、ちょっとびっくりするほど凄まじく面白い作品だった。観ればスッと理解できるのに言葉で説明すると難解になってしまう「テクニカルな構成」に感心させられつつ、そんな構成に下支えされた「物語の感性的な部分」がストレートに胸を打つ、シンプルながら力強い作品だ
あわせて読みたい
【痛快】精神病院の隔離室から脱した、善悪の判断基準を持たない狂気の超能力者が大暴れする映画:『モ…
モナ・リザ アンド ザ ブラッドムーン』は、「10年以上拘束され続けた精神病院から脱走したアジア系女性が、特殊能力を使って大暴れする」というムチャクチャな設定の物語なのだが、全編に通底する「『善悪の判断基準』が歪んでいる」という要素がとても見事で、意味不明なのに最後まで惹きつけられてしまった
あわせて読みたい
【考察】映画『街の上で』(今泉力哉)が描く「男女の友情は成立する」的会話が超絶妙で素晴らしい(出…
映画『街の上で』(今泉力哉監督)は、「映画・ドラマ的会話」ではない「自然な会話」を可能な限り目指すスタンスが見事だった。「会話の無駄」がとにかく随所に散りばめられていて、そのことが作品のリアリティを圧倒的に押し上げていると言える。ある男女の”恋愛未満”の会話もとても素晴らしかった
あわせて読みたい
【嫌悪】映画『ドライビング・バニー』が描く、人生やり直したい主人公(母親)のウザさと絶望
映画『ドライビング・バニー』は、主人公であるバニーのことが最後まで嫌いだったにも拘わらず、全体的にはとても素敵に感じられた珍しいタイプの作品だ。私は、「バニーのような人間が世の中に存在する」という事実に嫌悪感を抱いてしまうのだが、それでも、狂気的でぶっ飛んだラストシーンによって、作品全体の印象が大きく変わったと言える
あわせて読みたい
【狂気】映画『ニューオーダー』の衝撃。法という秩序を混沌で駆逐する”悪”に圧倒されっ放しの86分
映画『ニューオーダー』は、理解不能でノンストップな展開に誘われる問題作だ。「貧富の差」や「法の支配」など「現実に存在する秩序」がひっくり返され、対極に振り切った「新秩序」に乗っ取られた世界をリアルに描き出すことで、私たちが今進んでいる道筋に警鐘を鳴らす作品になっている
あわせて読みたい
【実話】アメリカの有名なシリアルキラーを基にした映画『グッド・ナース』の理解を拒む凄まじさ(主演…
実際に起こった連続殺人事件を基にした映画『グッド・ナース』は、「何が描かれているのか分からない」という不穏さがずっと付きまとう異様な作品だった。「事件そのもの」ではなく、ある2人の人物に焦点が当てられる展開から、人間のあまりに深淵な狂気と葛藤が抉り出されている
あわせて読みたい
【映画】『別れる決心』(パク・チャヌク)は、「倫理的な葛藤」が描かれない、不穏で魅惑的な物語
巨匠パク・チャヌク監督が狂気的な関係性を描き出す映画『別れる決心』には、「倫理的な葛藤が描かれない」という特異さがあると感じた。「様々な要素が描かれるものの、それらが『主人公2人の関係性』に影響しないこと」や、「『理解は出来ないが、成立はしている』という不思議な感覚」について触れる
あわせて読みたい
【倫理】アート体験の行き着く未来は?映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』が描く狂気の世界(…
「『痛み』を失った世界」で「自然発生的に生まれる新たな『臓器』を除去するライブパフォーマンス」を行うソール・テンサーを主人公にした映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』は、すぐには答えの見出しにくい「境界線上にある事柄」を挑発的に描き出す、実に興味深い物語だ
あわせて読みたい
【映画】ストップモーションアニメ『マルセル 靴をはいた小さな貝』はシンプルでコミカルで面白い!
靴を履いた体長2.5センチの貝をコマ撮りで撮影したストップモーション映画『マルセル 靴をはいた小さな貝』は、フェイクドキュメンタリーの手法で描き出すリアリティ満載の作品だ。謎の生き物が人間用の住居で工夫を凝らしながら生活する日常を舞台にした、感情揺さぶる展開が素晴らしい
あわせて読みたい
【感想】是枝裕和監督映画『怪物』(坂元裕二脚本)が抉る、「『何もしないこと』が生む加害性」
坂元裕二脚本、是枝裕和監督の映画『怪物』は、3つの視点を通して描かれる「日常の何気ない光景」に、思いがけない「加害性」が潜んでいることを炙り出す物語だ。これは間違いなく、私たち自身に関わる話であり、むしろ「自分には関係ない」と考えている人こそが自覚すべき問題だと思う
あわせて読みたい
【驚嘆】映画『TAR/ター』のリディア・ターと、彼女を演じたケイト・ブランシェットの凄まじさ
天才女性指揮者リディア・ターを強烈に描き出す映画『TAR/ター』は、とんでもない作品だ。「縦軸」としてのターの存在感があまりにも強すぎるため「横軸」を上手く捉えきれず、結果「よく分からなかった」という感想で終わったが、それでも「観て良かった」と感じるほど、揺さぶられる作品だった
あわせて読みたい
【美麗】映画『CLOSE/クロース』はあまりにも切ない。「誰かの当たり前」に飲み込まれてしまう悲劇
子どもの頃から兄弟のように育った幼馴染のレオとレミの関係の変化を丁寧に描き出す映画『CLOSE/クロース』は、「自分自身で『美しい世界』を毀損しているのかもしれない」という話でもある。”些細な”言動によって、確かに存在したあまりに「美しい世界」があっさりと壊されてしまう悲哀が描かれる
あわせて読みたい
【感想】これはドキュメンタリー(実話)なのか?映画『女神の継承』が突きつける土着的恐怖
ナ・ホンジンがプロデューサーを務めた映画『女神の継承』は、フィクションなのかドキュメンタリーなのか混乱させる異様な作品だった。タイ東北部で強く信じられている「精霊(ピー)」の信仰をベースに、圧倒的なリアリティで土着的恐怖を描き出す、強烈な作品
あわせて読みたい
【あらすじ】アリ・アスター監督映画『ミッドサマー』は、気持ち悪さと怖さが詰まった超狂ホラーだった
「夏至の日に映画館で上映する」という企画でようやく観ることが叶った映画『ミッドサマー』は、「私がなんとなく想像していたのとはまるで異なる『ヤバさ』」に溢れる作品だった。いい知れぬ「狂気」が随所で描かれるが、同時に、「ある意味で合理的と言えなくもない」と感じさせられる怖さもある
あわせて読みたい
【あらすじ】塩田武士『罪の声』が放つ、戦後最大の未解決事件「グリコ・森永事件」の圧倒的”リアル感”
戦後最大の未解決事件である「グリコ・森永事件」では、脅迫に子どもの声が使われていた。私はその事実を、塩田武士『罪の声』という小説を読むまで知らなかった。では、続く疑問はこうだろう。その子どもたちは、今どこでどんな風に生きているのか?その疑問に答える、凄まじい小説だ。
あわせて読みたい
【違和感】映画『コントラ』は、「よく分かんない」が「よく分かんないけど面白い」に変わる不思議な作品
ほぼ内容を知らないまま観に行った映画『コントラ』は、最後の最後まで結局何も理解できなかったが、それでもとても面白い作品だった。「後ろ向きに歩く男」が放つ違和感を主人公・ソラの存在感が中和させており、奇妙なのに可能な限り「日常感」を失わせずに展開させる構成が見事だと思う
あわせて読みたい
【実話】ポートアーサー銃乱射事件を扱う映画『ニトラム』が示す、犯罪への傾倒に抗えない人生の不条理
オーストラリアで実際に起こった銃乱射事件の犯人の生い立ちを描く映画『ニトラム/NITRAM』は、「頼むから何も起こらないでくれ」と願ってしまうほどの異様な不穏さに満ちている。「社会に順応できない人間」を社会がどう受け入れるべきかについて改めて考えさせる作品だ
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『夕方のおともだち』は、「私はこう」という宣言からしか始まらない関係性の”純度”を描く
「こんな田舎にはもったいないほどのドM」と評された男が主人公の映画『夕方のおともだち』は、SM嬢と真性ドMの関わりを通じて、「宣言から始まる関係」の難しさを描き出す。「普通の世界」に息苦しさを感じ、どうしても馴染めないと思っている人に刺さるだろう作品
あわせて読みたい
【感想】映画『君が世界のはじまり』は、「伝わらない」「分かったフリをしたくない」の感情が濃密
「キラキラした青春学園モノ」かと思っていた映画『君が世界のはじまり』は、「そこはかとない鬱屈」に覆われた、とても私好みの映画だった。自分の決断だけではどうにもならない「現実」を前に、様々な葛藤渦巻く若者たちの「諦念」を丁寧に描き出す素晴らしい物語
あわせて読みたい
【感想】のん主演映画『私をくいとめて』から考える、「誰かと一緒にいられれば孤独じゃないのか」問題
のん(能年玲奈)が「おひとり様ライフ」を満喫する主人公を演じる映画『私をくいとめて』を観て、「孤独」について考えさせられた。「誰かと関わっていられれば孤独じゃない」という考えに私は賛同できないし、むしろ誰かと一緒にいる時の方がより強く孤独を感じることさえある
あわせて読みたい
【考察】映画『哀愁しんでれら』から、「正しい」より「間違ってはいない」を選んでしまう人生を考える
「シンデレラストーリー」の「その後」を残酷に描き出す映画『哀愁しんでれら』は、「幸せになりたい」という気持ちが結果として「幸せ」を遠ざけてしまう現実を描き出す。「正しい/間違ってはいない」「幸せ/不幸せではない」を区別せずに行動した結果としての悲惨な結末
あわせて読みたい
【考察】ヨネダコウ『囀る鳥は羽ばたかない』は、BLの枠組みの中で「歪んだ人間」をリアルに描き出す
2巻までしか読んでいないが、ヨネダコウのマンガ『囀る鳥は羽ばたかない』は、「ヤクザ」「BL」という使い古されたフォーマットを使って、異次元の物語を紡ぎ出す作品だ。BLだが、BLという外枠を脇役にしてしまう矢代という歪んだ男の存在感が凄まじい。
あわせて読みたい
【幸福】「死の克服」は「生の充実」となり得るか?映画『HUMAN LOST 人間失格』が描く超管理社会
アニメ映画『HUMAN LOST 人間失格』では、「死の克服」と「管理社会」が分かちがたく結びついた世界が描かれる。私たちは既に「緩やかな管理社会」を生きているが、この映画ほどの管理社会を果たして許容できるだろうか?そしてあなたは、「死」を克服したいと願うだろうか?
あわせて読みたい
【おすすめ】江戸川乱歩賞受賞作、佐藤究『QJKJQ』は、新人のデビュー作とは思えない超ド級の小説だ
江戸川乱歩賞を受賞した佐藤究デビュー作『QJKJQ』はとんでもない衝撃作だ。とても新人作家の作品とは思えない超ド級の物語に、とにかく圧倒されてしまう。「社会は『幻想』を共有することで成り立っている」という、普段なかなか意識しない事実を巧みにちらつかせた、魔術のような作品
あわせて読みたい
【感想】阿部サダヲが狂気を怪演。映画『死刑にいたる病』が突きつける「生きるのに必要なもの」の違い
サイコパスの連続殺人鬼・榛村大和を阿部サダヲが演じる映画『死刑にいたる病』は、「生きていくのに必要なもの」について考えさせる映画でもある。目に光を感じさせない阿部サダヲの演技が、リアリティを感じにくい「榛村大和」という人物を見事に屹立させる素晴らしい映画
あわせて読みたい
【純愛】映画『ぼくのエリ』の衝撃。「生き延びるために必要なもの」を貪欲に求める狂気と悲哀、そして恋
名作と名高い映画『ぼくのエリ』は、「生き延びるために必要なもの」が「他者を滅ぼしてしまうこと」であるという絶望を抱えながら、それでも生きることを選ぶ者たちの葛藤が描かれる。「純愛」と呼んでいいのか悩んでしまう2人の関係性と、予想もつかない展開に、感動させられる
あわせて読みたい
【悲劇】アメリカの暗黒の歴史である奴隷制度の現実を、元奴隷の黒人女性自ら赤裸々に語る衝撃:『ある…
生まれながらに「奴隷」だった黒人女性が、多くの人の協力を得て自由を手にし、後に「奴隷制度」について書いたのが『ある奴隷少女に起こった出来事』。長らく「白人が書いた小説」と思われていたが、事実だと証明され、欧米で大ベストセラーとなった古典作品が示す「奴隷制度の残酷さ」
あわせて読みたい
【無謀】園子温が役者のワークショップと同時並行で撮影した映画『エッシャー通りの赤いポスト』の”狂気”
「園子温の最新作」としか知らずに観に行った映画『エッシャー通りの赤いポスト』は、「ワークショップ参加者」を「役者」に仕立て、ワークショップと同時並行で撮影されたという異次元の作品だった。なかなか経験できないだろう、「0が1になる瞬間」を味わえる“狂気”の映画
あわせて読みたい
【衝撃】映画『ダンサー・イン・ザ・ダーク』凄い。ラストの衝撃、ビョークの演技、”愛”とは呼びたくな…
言わずとしれた名作映画『ダンサー・イン・ザ・ダーク』を、ほぼ予備知識ゼロのまま劇場で観た。とんでもない映画だった。苦手なミュージカルシーンが効果的だと感じられたこと、「最低最悪のラストは回避できたはずだ」という想い、そして「セルマのような人こそ報われてほしい」という祈り
あわせて読みたい
【LGBT】映画『リトル・ガール』で映し出される、性別違和を抱える8歳の”女の子”のリアルと苦悩
映画撮影時8歳だった、身体は男の子、心は女の子のサシャは、スカートを履いての登校が許されず、好きなバッグもペンケースも使わせてもらえない。映画『リトル・ガール』が描く、「性別違和」に対する社会の不寛容と、自分を責め続けてしまう母親の苦悩
あわせて読みたい
【衝撃】卯月妙子『人間仮免中』、とんでもないコミックエッセイだわ。統合失調症との壮絶な闘いの日々
小学5年生から統合失調症を患い、社会の中でもがき苦しみながら生きる卯月妙子のコミックエッセイ『人間仮免中』はとんでもない衝撃作。周りにいる人とのぶっ飛んだ人間関係や、歩道橋から飛び降り自殺未遂を図り顔面がぐちゃぐちゃになって以降の壮絶な日々も赤裸々に描く
あわせて読みたい
【抵抗】西加奈子のおすすめ小説『円卓』。「当たり前」と折り合いをつけられない生きづらさに超共感
小学3年生のこっこは、「孤独」と「人と違うこと」を愛するちょっと変わった女の子。三つ子の美人な姉を「平凡」と呼んで馬鹿にし、「眼帯」や「クラス会の途中、不整脈で倒れること」に憧れる。西加奈子『円卓』は、そんなこっこの振る舞いを通して「当たり前」について考えさせる
あわせて読みたい
【衝撃】NHKがアマゾン奥地の先住民ヤノマミ族に長期密着。剥き出しの生と死、文明との共存の難しさ
NHKのディレクターでありノンフィクション作家でもある国分拓が、アマゾン奥地に住む先住民ヤノマミ族の集落で150日間の長期密着を行った。1万年の歴史を持つ彼らの生活を描き出す『ヤノマミ』は、「生と死の価値観の差異」や「先住民と文明との関係の難しさ」を突きつける
あわせて読みたい
【不思議】森達也が「オカルト」に挑む本。「科学では説明できない現象はある」と否定も肯定もしない姿…
肯定派でも否定派でもない森達也が、「オカルト的なもの」に挑むノンフィクション『オカルト』。「現象を解釈する」ことよりも、「現象を記録する」こと点に注力し、「そのほとんどは勘違いや見間違いだが、本当に説明のつかない現象も存在する」というスタンスで追いかける姿勢が良い
あわせて読みたい
【衝撃】洗脳を自ら脱した著者の『カルト脱出記』から、「社会・集団の洗脳」を避ける生き方を知る
「聖書研究に熱心な日本人証人」として「エホバの証人」で活動しながら、その聖書研究をきっかけに自ら「洗脳」を脱した著者の体験を著した『カルト脱出記』。広い意味での「洗脳」は社会のそこかしこに蔓延っているからこそ、著者の体験を「他人事」だと無視することはできない
あわせて読みたい
【不安】環境活動家グレタを追う映画。「たったひとりのストライキ」から国連スピーチまでの奮闘と激変…
環境活動家であるグレタのことを、私はずっと「怒りの人」「正義の人」だとばかり思っていた。しかしそうではない。彼女は「不安」から、いても立ってもいられずに行動を起こしただけなのだ。映画『グレタ ひとりぼっちの挑戦』から、グレタの実像とその強い想いを知る
あわせて読みたい
【日常】難民問題の現状をスマホで撮る映画。タリバンから死刑宣告を受けた監督が家族と逃避行:『ミッ…
アフガニスタンを追われた家族4人が、ヨーロッパまで5600kmの逃避行を3台のスマホで撮影した映画『ミッドナイト・トラベラー』は、「『難民の厳しい現実』を切り取った作品」ではない。「家族アルバム」のような「笑顔溢れる日々」が難民にもあるのだと想像させてくれる
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『流浪の月』を観て感じた、「『見て分かること』にしか反応できない世界」への気持ち悪さ
私は「見て分かること」に”しか”反応できない世界に日々苛立ちを覚えている。そういう社会だからこそ、映画『流浪の月』で描かれる文と更紗の関係も「気持ち悪い」と断罪されるのだ。私はむしろ、どうしようもなく文と更紗の関係を「羨ましい」と感じてしまう。
あわせて読みたい
【矛盾】法律の”抜け穴”を衝く驚愕の小説。「ルールを通り抜けたものは善」という発想に潜む罠:『法廷…
完璧なルールは存在し得ない。だからこそ私たちは、矛盾を内包していると理解しながらルールを遵守する必要がある。「ルールを通り抜けたものは善」という”とりあえずの最善解”で社会を回している私たちに、『法廷遊戯』は「世界を支える土台の脆さ」を突きつける
あわせて読みたい
【感想】映画『竜とそばかすの姫』が描く「あまりに批判が容易な世界」と「誰かを助けることの難しさ」
SNSの登場によって「批判が容易な社会」になったことで、批判を恐れてポジティブな言葉を口にしにくくなってしまった。そんな世の中で私は、「理想論だ」と言われても「誰かを助けたい」と発信する側の人間でいたいと、『竜とそばかすの姫』を観て改めて感じさせられた
あわせて読みたい
【中絶】望まない妊娠をした若い女性が直面する現実をリアルに描く映画。誰もが現状を知るべきだ:『17…
他の様々な要素を一切排し、「望まぬ妊娠をした少女が中絶をする」というただ1点のみに全振りした映画『17歳の瞳に映る世界』は、説明もセリフも極端に削ぎ落としたチャレンジングな作品だ。主人公2人の沈黙が、彼女たちの置かれた現実を雄弁に物語っていく。
あわせて読みたい
【凄絶】北朝鮮の”真実”を描くアニメ映画。強制収容所から決死の脱出を試みた者が語る驚愕の実態:『ト…
在日コリアン4世の監督が、北朝鮮脱北者への取材を元に作り上げた壮絶なアニメ映画『トゥルーノース』は、私たちがあまりに恐ろしい世界と地続きに生きていることを思い知らせてくれる。最低最悪の絶望を前に、人間はどれだけ悪虐になれてしまうのか、そしていかに優しさを発揮できるのか。
あわせて読みたい
【生きる】しんどい人生を宿命付けられた子どもはどう生きるべき?格差社会・いじめ・恋愛を詰め込んだ…
厳しい受験戦争、壮絶な格差社会、残忍ないじめ……中国の社会問題をこれでもかと詰め込み、重苦しさもありながら「ボーイ・ミーツ・ガール」の爽やかさも融合されている映画『少年の君』。辛い境遇の中で、「すべてが最悪な選択肢」と向き合う少年少女の姿に心打たれる
あわせて読みたい
【認識】「固定観念」「思い込み」の外側に出るのは難しい。自分はどんな「へや」に囚われているのか:…
実際に起こった衝撃的な事件に着想を得て作られた映画『ルーム』は、フィクションだが、観客に「あなたも同じ状況にいるのではないか?」と突きつける力強さを持っている。「普通」「当たり前」という感覚に囚われて苦しむすべての人に、「何に気づけばいいか」を気づかせてくれる作品
あわせて読みたい
【本質】子どもの頃には読めない哲学書。「他人の哲学はつまらない」と語る著者が説く「問うこと」の大…
『<子ども>のための哲学』は決して、「子どもでも易しく理解できる哲学の入門書」ではない。むしろかなり難易度が高いと言っていい。著者の永井均が、子どもの頃から囚われ続けている2つの大きな疑問をベースに、「『哲学する』とはどういうことか?」を深堀りする作品
あわせて読みたい
【感想】映画『若おかみは小学生!』は「子どもの感情」を「大人の世界」で素直に出す構成に号泣させられる
ネット記事を読まなければ絶対に観なかっただろう映画『若おかみは小学生!』は、基本的に子ども向け作品だと思うが、大人が観てもハマる。「大人の世界」でストレートに感情を表に出す主人公の小学生の振る舞いと成長に、否応なしに感動させられる
あわせて読みたい
【矛盾】その”誹謗中傷”は真っ当か?映画『万引き家族』から、日本社会の「善悪の判断基準」を考える
どんな理由があれ、法を犯した者は罰せられるべきだと思っている。しかしそれは、善悪の判断とは関係ない。映画『万引き家族』(是枝裕和監督)から、「国民の気分」によって「善悪」が決まる社会の是非と、「善悪の判断を保留する勇気」を持つ生き方について考える
あわせて読みたい
【考察】映画『ジョーカー』で知る。孤立無援の環境にこそ”悪”は偏在すると。個人の問題ではない
「バットマン」シリーズを観たことがない人間が、予備知識ゼロで映画『ジョーカー』を鑑賞。「悪」は「環境」に偏在し、誰もが「悪」に足を踏み入れ得ると改めて実感させられた。「個人」を断罪するだけでは社会から「悪」を減らせない現実について改めて考える
あわせて読みたい
【葛藤】子どもが抱く「家族を捨てたい気持ち」は、母親の「家族を守りたい気持ち」の終着点かもしれな…
家族のややこしさは、家族の数だけ存在する。そのややこしさを、「子どもを守るために母親が父親を殺す」という極限状況を設定することで包括的に描き出そうとする映画『ひとよ』。「暴力」と「殺人犯の子どもというレッテル」のどちらの方が耐え難いと感じるだろうか?
あわせて読みたい
【個性】統合失調症との関わり方を芸人・松本ハウスから学ぶ。本人と周囲の人間はどう対処すべきか:『…
「統合失調症だからといって病気だとは捉えず、ただの個性だと思う」と話す松本キックは、相方・ハウス加賀谷とどう接したか。そしてハウス加賀谷は、いかにして病気と向き合ったか。『統合失調症がやってきた』『相方は、統合失調症』から、普遍的な「人間関係の極意」を学ぶ
あわせて読みたい
【見方】日本の子どもの貧困は深刻だ。努力ではどうにもならない「見えない貧困」の現実と対策:『増補…
具体的には知らなくても、「日本の子どもの貧困の現状は厳しい」というイメージを持っている人は多いだろう。だからこそこの記事では、朝日新聞の記事を再編集した『増補版 子どもと貧困』をベースに、「『貧困問題』とどう向き合うべきか」に焦点を当てた
あわせて読みたい
【生きろ】「どう生き延びるか」と覚悟を決める考え方。西原理恵子が語る「カネ」だけじゃない人生訓:…
西原理恵子『この世でいちばん大事な「カネ」の話』は、決して「お金」の話だけではありません。「自分が望む生き方」を実現するための「闘い方」を伝授してくれると同時に、「しなくていい失敗を回避する考え方」も提示してくれます。学校や家庭ではなかなか学べない人生訓
あわせて読みたい
【壮絶】本当に「美人は得」か?「美しさ」という土俵を意識せざるを得ない少女・女性たちの現実:『自…
美醜で判断されがちな”ルッキズム”の世の中に刃を突きつける小説『自画像』。私自身は、「キレイな人もキレイな人なりの大変さを抱えている」と感じながら生きているつもりだが、やはりその辛さは理解されにくい。私も男性であり、ルッキズムに加担してないとはとても言えない
あわせて読みたい
【危機】教員のセクハラは何故無くならない?資質だけではない、学校の構造的な問題も指摘する:『スク…
『スクールセクハラ なぜ教師のわいせつ犯罪は繰り返されるのか』では、自分が生徒に対して「権力」を持っているとは想像していなかったという教師が登場する。そしてこの「無自覚」は、学校以外の場でも起こりうる。特に男性は、読んで自分の振る舞いを見直すべきだ
あわせて読みたい
【絶望】「人生上手くいかない」と感じる時、彼を思い出してほしい。壮絶な過去を背負って生きる彼を:…
「北九州連続監禁殺人事件」という、マスコミも報道規制するほどの残虐事件。その「主犯の息子」として生きざるを得なかった男の壮絶な人生。「ザ・ノンフィクション」のプロデューサーが『人殺しの息子と呼ばれて』で改めて取り上げた「真摯な男」の生き様と覚悟
あわせて読みたい
【あらすじ】子どもは大人よりずっと大人だ。「子ども扱い」するから、「子どもの枠」から抜け出せない…
宮部みゆき『ソロモンの偽証』は、その分厚さ故になかなか手が伸びない作品だろうが、「長い」というだけの理由で手を出さないのはあまりにももったいない傑作だ。「中学生が自前で裁判を行う」という非現実的設定をリアルに描き出すものすごい作品
あわせて読みたい
【助けて】息苦しい世の中に生きていて、人知れず「傷」を抱えていることを誰か知ってほしいのです:『…
元気で明るくて楽しそうな人ほど「傷」を抱えている。そんな人をたくさん見てきた。様々な理由から「傷」を表に出せない人がいる世の中で、『包帯クラブ』が提示する「見えない傷に包帯を巻く」という具体的な行動は、気休め以上の効果をもたらすかもしれない
あわせて読みたい
【理解】東田直樹の本は「自閉症の見方」を一変させた。自身も自閉症児を育てるプロデューサーが映画化…
東田直樹の著作を英訳し世界に広めた人物(自閉症児を育てている)も登場する映画『僕が跳びはねる理由』には、「東田直樹が語る自閉症の世界」を知ることで接し方や考え方が変わったという家族が登場する。「自閉症は知恵遅れではない」と示した東田直樹の多大な功績を実感できる
あわせて読みたい
【逃避】つまらない世の中で生きる毎日を押し流す”何か”を求める気持ちに強烈に共感する:映画『サクリ…
子どもの頃「台風」にワクワクしたように、未だに、「自分のつまらない日常を押し流してくれる『何か』」の存在を待ちわびてしまう。立教大学の学生が撮った映画『サクリファイス』は、そんな「何か」として「東日本大震災」を描き出す、チャレンジングな作品だ
あわせて読みたい
【実話】「家族とうまくいかない現実」に正解はあるか?選択肢が無いと感じる時、何を”選ぶ”べきか?:…
「自分の子どもなんだから、どんな風に育てたって勝手でしょ」という親の意見が正しいはずはないが、この言葉に反論することは難しい。虐待しようが生活能力が無かろうが、親は親だからだ。映画『MOTHER マザー』から、不正解しかない人生を考える
あわせて読みたい
【権利】「難民だから支援すべき」じゃない。誰でも最低限の安全が確保できる世界であるべきだ:映画『…
難民申請中の少年が、国籍だけを理由にチェスの大会への出場でが危ぶまれる。そんな実際に起こった出来事を基にした『ファヒム パリが見た奇跡』は実に素晴らしい映画だが、賞賛すべきではない。「才能が無くても安全は担保されるべき」と考えるきっかけになる映画
あわせて読みたい
【誤り】「信じたいものを信じる」のは正しい?映画『星の子』から「信じること」の難しさを考える
どんな病気も治す「奇跡の水」の存在を私は信じないが、しかし何故「信じない」と言えるのか?「奇跡の水を信じる人」を軽々に非難すべきではないと私は考えているが、それは何故か?映画『星の子』から、「何かを信じること」の難しさについて知る
あわせて読みたい
【葛藤】「多様性を受け入れること」は難しい。映画『アイヌモシリ』で知る、アイデンティティの実際
「アイヌの町」として知られるアイヌコタンの住人は、「アイヌ語を勉強している」という。観光客のイメージに合わせるためだ。映画『アイヌモシリ』から、「伝統」や「文化」の継承者として生きるべきか、自らのアイデンティティを意識せず生きるべきかの葛藤を知る
あわせて読みたい
【排除】「分かり合えない相手」だけが「間違い」か?想像力の欠如が生む「無理解」と「対立」:映画『…
「共感」が強すぎる世の中では、自然と「想像力」が失われてしまう。そうならないようにと意識して踏ん張らなければ、他人の価値観を正しく認めることができない人間になってしまうだろう。映画『ミセス・ノイズィ』から、多様な価値観を排除しない生き方を考える
あわせて読みたい
【変人】学校教育が担うべき役割は?子供の才能を伸ばすために「異質な人」とどう出会うべきか?:『飛…
高校の美術教師からアーティストとして活動するようになった著者は、教育の現場に「余白(スキマ)」が減っていると指摘する。『飛び立つスキマの設計学』をベースに、子どもたちが置かれている現状と、教育が成すべき役割について確認する。
あわせて読みたい
【救い】耐えられない辛さの中でどう生きるか。短歌で弱者の味方を志すホームレス少女の生き様:『セー…
死にゆく母を眺め、施設で暴力を振るわれ、拾った新聞で文字を覚えたという壮絶な過去を持つ鳥居。『セーラー服の歌人 鳥居』は、そんな辛い境遇を背景に、辛さに震えているだろう誰かを救うために短歌を生み出し続ける生き方を描き出す。凄い人がいるものだ
あわせて読みたい
【挑戦】自閉症のイメージを変えるおすすめ本。知的障害と”思い込む”専門家に挑む母子の闘い:『自閉症…
専門家の思い込みを覆し、自閉症のイメージを激変させた少年・イド。知的障害だと思われていた少年は、母親を通じコミュニケーションが取れるようになり、その知性を証明した。『自閉症の僕が「ありがとう」を言えるまで』が突きつける驚きの真実
あわせて読みたい
【爆笑】「だるい」「何もしたくない」なら、「自分は負け組」と納得して穏やかに生きよう:『負ける技…
勝利は敗北の始まり」という感覚は、多くの人が理解できると思います。日本では特に、目立てば目立つほど足を引っ張られてしまいます。だったら、そもそも「勝つ」ことに意味などないのでは?『負ける技術』をベースに、ほどほどの生き方を学びます
あわせて読みたい
【異端】子育てがうまくいかないと悩む方へ。9歳で大学入学の天才児に学ぶ「すべきでないこと」:『ぼく…
12歳で数学の未解決問題を解いた天才児は、3歳の時に「16歳で靴紐が結べるようになったらラッキー」と宣告されていた。専門家の意見に逆らって、重度の自閉症児の才能をどう開花させたのかを、『ぼくは数式で宇宙の美しさを伝えたい』から学ぶ
あわせて読みたい
【異端】子育ては「期待しない」「普通から外れさせる」が大事。”劇薬”のような父親の教育論:『オーマ…
どんな親でも、子どもを幸せにしてあげたい、と考えるでしょう。しかしそのために、過保護になりすぎてしまっている、ということもあるかもしれません。『オーマイ・ゴッドファーザー』をベースに、子どもを豊かに、力強く生きさせるための”劇薬”を学ぶ
あわせて読みたい
【あらすじ】「愛されたい」「必要とされたい」はこんなに難しい。藤崎彩織が描く「ままならない関係性…
好きな人の隣にいたい。そんなシンプルな願いこそ、一番難しい。誰かの特別になるために「異性」であることを諦め、でも「異性」として見られないことに苦しさを覚えてしまう。藤崎彩織『ふたご』が描き出す、名前がつかない切実な関係性
あわせて読みたい
【恐怖】SNSの危険性と子供の守り方を、ドキュメンタリー映画『SNS 少女たちの10日間』で学ぶ
実際にチェコの警察を動かした衝撃のドキュメンタリー映画『SNS 少女たちの10日間』は、少女の「寂しさ」に付け込むおっさんどもの醜悪さに満ちあふれている。「WEBの利用制限」だけでは子どもを守りきれない現実を、リアルなものとして実感すべき
あわせて読みたい
【現代】これが今の若者の特徴?衝撃のドキュメンタリー映画『14歳の栞』から中学生の今を知る
埼玉県春日部市に実在する中学校の2年6組の生徒35人。14歳の彼らに50日間密着した『14歳の栞』が凄かった。カメラが存在しないかのように自然に振る舞い、内心をさらけ出す彼らの姿から、「中学生の今」を知る
あわせて読みたい
【肯定】社会不適合者こそ非凡。学校・世の中に馴染めなかった異才たちの過去から”才能”の本質を知る:…
「みんなと同じ」に馴染めないと「社会不適合」と判断され、排除されてしまうことが多いでしょう。しかし『非属の才能』では、「どこにも属せない感覚」にこそ才能の源泉があると主張します。常識に違和感を覚えてしまう人を救う本から、同調圧力に屈しない生き方を学ぶ
あわせて読みたい
【考察】世の中は理不尽だ。平凡な奴らがのさばる中で、”特別な私の美しい世界”を守る生き方:『オーダ…
自分以外は凡人、と考える主人公の少女はとてもイタい。しかし、世間の価値観と折り合わないなら、自分の美しい世界を守るために闘うしかない。中二病の少女が奮闘する『オーダーメイド殺人クラブ』をベースに、理解されない世界をどう生きるかについて考察する
あわせて読みたい
【覚悟】人生しんどい。その場の”空気”から敢えて外れる3人の中学生の処世術から生き方を学ぶ:『私を知…
空気を読んで摩擦を減らす方が、集団の中では大体穏やかにいられます。この記事では、様々な理由からそんな選択をしない/できない、『私を知らないで』に登場する中学生の生き方から、厳しい現実といかにして向き合うかというスタンスを学びます
あわせて読みたい
【呪縛】「良い子」に囚われ人生苦しい。どう見られるかを抜け出し、なりたい自分を生きるために:『わ…
「良い子でいなきゃいけない」と感じ、本来の自分を押し隠したまま生きているという方、いるんじゃないかと思います。私も昔はそうでした。「良い子」の呪縛から逃れることは難しいですが、「なりたい自分」をどう生きればいいかを、『わたしを見つけて』をベースに書いていきます
あわせて読みたい
【感想】人間関係って難しい。友達・恋人・家族になるよりも「あなた」のまま関わることに価値がある:…
誰かとの関係性には大抵、「友達」「恋人」「家族」のような名前がついてしまうし、そうなればその名前に縛られてしまいます。「名前がつかない関係性の奇跡」と「誰かを想う強い気持ちの表し方」について、『君の膵臓をたべたい』をベースに書いていきます
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
苦しい・しんどい【本・映画の感想】 | ルシルナ
生きていると、しんどい・悲しいと感じることも多いでしょう。私も、世の中の「当たり前」に馴染めなかったり、みんなが普通にできることが上手くやれずに苦しい思いをする…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…








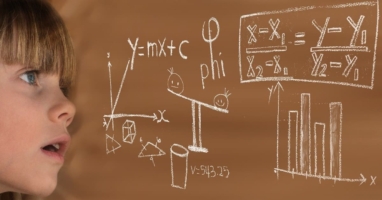




















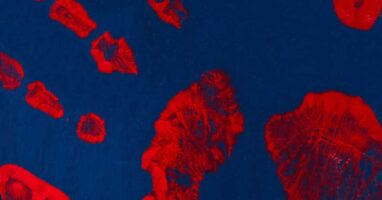



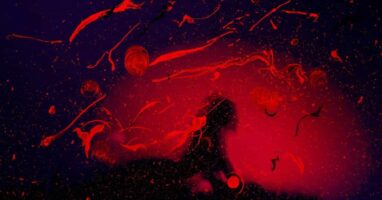












































































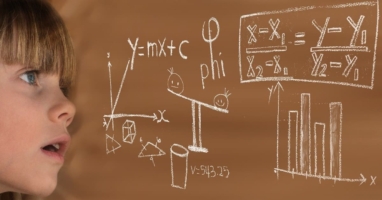



















コメント