目次
はじめに
この記事で取り上げる映画
出演:中村佳穂, 出演:成田凌, 出演:染谷将太, 出演:玉城ティナ, 出演:幾田りら, 出演:森山良子, 出演:清水ミチコ, 出演:坂本冬美, 出演:岩崎良美, 出演:中尾幸世, 出演:森川智之, 出演:宮野真守, 出演:津田健次郎, 出演:小山茉美, 出演:役所広司, 出演:佐藤健, Writer:細田守, 監督:細田守
¥2,500 (2022/05/25 22:21時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
この映画をガイドにしながら記事を書いていくようだよ
この記事で伝えたいこと
行動が伴っていなくても「誰かを助けたい」と言いやすい社会であってほしい
「誰かを助けること」が「カッコいい」と受け取られる世の中であることを願っている
この記事の3つの要点
- 私は、なかなか行動は伴わないが、「誰かを助けたい」という気持ちは持っている
- 「批判」することでマウントを取ろうとする行為はクソ喰らえだ
- 「誰かを助けたい」という気持ちが否定されない世界観だからこそ、『竜とそばかすの姫』は素敵に感じられる
ポジティブな言葉こそ”安易に”口にできるような社会に私は生きていたいと思います
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
記事中の引用は、映画館で取ったメモを参考にしているので、正確なものではありません
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!「それってホントに『コミュ力』が高いって言えるの?」と疑問を感じている方に…
私は、「コミュ力が高い人」に関するよくある主張に、どうも違和感を覚えてしまうことが多くあります。そしてその一番大きな理由が、「『コミュ力が高い人』って、ただ『想像力がない』だけではないか?」と感じてしまう点にあると言っていいでしょう。出版したKindle本は、「ネガティブには見えないネガティブな人」(隠れネガティブ)を取り上げながら、「『コミュ力』って何だっけ?」と考え直してもらえる内容に仕上げたつもりです。
映画『竜とそばかすの姫』を観て、改めて私は「それでも『誰かを助けたい』と言う側の人間でありたい」と思った
私はいつも、「誰かを助けたい」と思ってはいる
あわせて読みたい
【感想】映画『すずめの戸締まり』(新海誠)は、東日本大震災後を生きる私達に「逃げ道」をくれる(松…
新海誠監督の『すずめの戸締まり』は、古代神話的な設定を現代のラブコメに組み込みながら、あまりに辛い現実を生きる人々に微かな「逃げ道」を指し示してくれる作品だと思う。テーマ自体は重いが、恋愛やコメディ要素とのバランスがとても良く、ロードムービー的な展開もとても魅力的

『竜とそばかすの姫』は、難しいことを考えずに楽しんで観ればいい映画でしょう。ただ私は、映画のかなり後半で、ある人物が「助ける助ける助ける……」と口にする場面からの、物語がガラッと変わっていく展開がとても好きで、いろいろと考えさせられました。なので、この記事ではまず、「『助ける』ということの難しさ」に触れることにしましょう。
私はたぶん、世の中の平均的な人よりも「『誰かを助けたい』という気持ち」を持っていると思っています。別に証明はできませんが、「見返りなんかなくなって、それが相手のためになるなら全然やる」という気持ちでいるし、周りの人と話をしたりネットであれこれ読んだりしても、「平均よりは上なんじゃないか」と感じるのです。
ただ、ここが大きな問題なのですが、じゃあ実際に行動をしているのかと言われたら何もしていません。時々思いついたように寄付をしてみるぐらいで、ボランティアに従事するといったような積極的な行動を取れてはいないのです。
あわせて読みたい
【感想】のん主演映画『私をくいとめて』から考える、「誰かと一緒にいられれば孤独じゃないのか」問題
のん(能年玲奈)が「おひとり様ライフ」を満喫する主人公を演じる映画『私をくいとめて』を観て、「孤独」について考えさせられた。「誰かと関わっていられれば孤独じゃない」という考えに私は賛同できないし、むしろ誰かと一緒にいる時の方がより強く孤独を感じることさえある
ホントにいつも「まず自分を生き延びさせるので精一杯だ」って気持ちが強いんだよね
自分も助けられないような人間に、誰かを助けられる気はしないんだけど、言い訳だよなって自分でも思う
「気持ちはある」と言っても、行動に移していないなら、気持ちだって無いのと同じでしょう。そう判断されても仕方ないと私自身感じています。「高尚なことを言うならまず行動しろ」という批判はある意味で真っ当だと思うし、「同情するなら金をくれ」のように、実際に苦しんでいる人からすれば「気持ちなんか要らないよ」という感じでしょう。そういうことは、一通り理解しているつもりでいます。
あわせて読みたい
【恐怖】SNSの危険性と子供の守り方を、ドキュメンタリー映画『SNS 少女たちの10日間』で学ぶ
実際にチェコの警察を動かした衝撃のドキュメンタリー映画『SNS 少女たちの10日間』は、少女の「寂しさ」に付け込むおっさんどもの醜悪さに満ちあふれている。「WEBの利用制限」だけでは子どもを守りきれない現実を、リアルなものとして実感すべき
ただその上で敢えて言うと、「それでも『誰かを助けたい』って口にできる社会」であってほしいと願ってしまうのです。実際には行動に移せていない人でも、「誰かを助けたい」という気持ちを持っていると表明することを「良し」とする世の中であってほしいなと思ってしまいます。
何故なら私は、人間の行動の多くが「それって『カッコ良い/カッコ悪い』よね」みたいな理屈で決まると考えているからです。

「いじめの解決法」も、最終的には「いじめってカッコ悪いよね」っていう雰囲気を作る以外にないと思ってる
個別のいじめの事案はともかく、いじめ全体の話だとすれば、そんな感じするよね
実際に行動できているかどうかに関係なく、「誰かを助けたい」という気持ちの発信が多数存在すれば、それは「カッコ良いこと」と認められるのではないかと期待しています。逆にアメリカなどでは、「富裕層になったら寄付ぐらいしないのはカッコ悪い」という風潮があるから寄付文化が根付いていると聞いたことがあるほどです。人間の行動はそういう「全体の雰囲気」で大分変わるでしょう。だからその第一歩として、「行動が伴っていなくても、『誰かを助けたい』と口にすること」が当たり前の社会になればいい、と私は考えているのです。
あわせて読みたい
【勇敢】ユダヤ人を救った杉原千畝を描く映画。日本政府の方針に反しながら信念を貫いた男の生き様
日本政府の方針に逆らってまでユダヤ人のためにビザを発給し続けた外交官を描く映画『杉原千畝』。日本を良くしたいと考えてモスクワを夢見た青年は、何故キャリアを捨てる覚悟で「命のビザ」を発給したのか。困難な状況を前に、いかに決断するかを考えさせられる
そういう意味で、『竜とそばかすの姫』のようなアニメ・マンガの世界は素敵だと感じる点があります。「誰かを助けたい」という気持ちが上滑りすることなく当たり前のように存在し得る世界が多いからです。アニメ・マンガがこれだけ人気なのだから、多くの人が実は「そういう世界」を望んでいるのではないか、とさえ感じています。
まあ、アニメ・マンガの世界も、主人公周辺の人たちだけがそういう感じなのであって、世界全部がそうとは限らないのかもだけどね
ってかそもそも、アニメもマンガもほとんど見ないからよく分かってないでしょ
あわせて読みたい
【天才】映画音楽の発明家『モリコーネ』の生涯。「映画が恋した音楽家」はいかに名曲を生んだか
「映画音楽のフォーマットを生み出した」とも評される天才作曲家エンリオ・モリコーネを扱った映画『モリコーネ 映画が恋した音楽家』では、生涯で500曲以上も生み出し、「映画音楽」というジャンルを比べ物にならないほどの高みにまで押し上げた人物の知られざる生涯が描かれる
大体すべて、SNSが悪い
ただ現実には、私たちは「『誰かを助けたい』と口にしにくい世界」に生きています。そしてその理由の大半は「SNS」にあると私は考えているのです。

私は基本的に、「批判」という行為があまり好きではありません。自分がするのもされるのも、という意味です。そもそも「100%完璧な人間」などどこにもいないのですから、どんな人・どんな場合でも「批判すべき点」を見つけられるでしょう。そして批判する側は「絶対に反論されない正論」で自説を固めておけば安全圏にいられます。
つまり、「どれほど能力がない人間でも、簡単に『相手より優位に立っている』と”錯覚できる”行為」が、私にとっての「批判」です。
あわせて読みたい
【天才】『三島由紀夫vs東大全共闘』後に「伝説の討論」と呼ばれる天才のバトルを記録した驚異の映像
1969年5月13日、三島由紀夫と1000人の東大全共闘の討論が行われた。TBSだけが撮影していたフィルムを元に構成された映画「三島由紀夫vs東大全共闘」は、知的興奮に満ち溢れている。切腹の一年半前の討論から、三島由紀夫が考えていたことと、そのスタンスを学ぶ
たまにネットで炎上している状況をチラ見すると、あまりのアホさに驚かされる
「炎上させてる側」の主張には首を傾げちゃうことが多いよね
そして、この「批判」をあまりに容易に行えるようにしたのが「SNS」だと私は思っているのです。これまでは、「グリコ・森永事件」のような犯罪行為でもしない限り、一個人が社会に大きなインパクトを与えることなどできませんでしたが、SNSの登場で、個人の「批判」でも社会に一定の力を与えられるようになりました。これはもの凄く大きな変化だと思います。
「相手よりも優位に立てる手軽な手段」である「批判」を、それまでと比べ物にならないくらい容易に行えるようになってしまえば、「悪い批判」が増えていくのは当然と言えるでしょう。
もちろん世の中には、「状況を好転させる『良い批判』」も存在します。ただ、その違いが的確には理解されず、同じ「批判」と扱われてしまうことも多いでしょう。そしてそうなればなるほど「良い批判」を行おうとする人は減ってしまいます。だから結果として、ますます「悪い批判」ばかり増えていくという悪循環に陥ってしまうのです。
あわせて読みたい
【知】内田樹が教育・政治を語る。「未来の自分」を「別人」と捉える「サル化した思考」が生む現実:『…
「朝三暮四」の故事成語を意識した「サル化」というキーワードは、現代性を映し出す「愚かさ」を象徴していると思う。内田樹『サル化する世界』から、日本の教育・政治の現状及び問題点をシンプルに把握し、現代社会を捉えるための新しい視点や価値観を学ぶ
残念なことに、SNSのせいで「批判」が容易になってしまったことで、「誰かを助けたい」というポジティブな言葉を口にすることのハードルは上がってしまいます。恐らく、「口だけ」「偽善者」「やってから言え」みたいな批判が出るでしょうし、そうなることが容易に予想できてしまうからこそ、そういう発言をする人も減ってしまいます。
メンタルが強い人じゃないとポジティブな言葉が言えなくなる世の中はちょっと怖いよね
もちろん、今苦しい立場にいる人が、「『助けたい』なんてどうせ口だけだろう」と批判する行為は受け入れるべきでしょう。真に救援を求めている人からの厳しい視線は受け止めなければならないと考えているのです。ただ、「仮に口だけだとしても発した方がいい言葉」はあるはずだと私は信じていますし、そういう言葉を口にしやすい世の中であってほしいとも願っています。

あわせて読みたい
【アート】「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」(森美術館)と「美術手帖 Chim↑Pom特集」の衝撃から「…
Chim↑Pomというアーティストについてさして詳しいことを知らずに観に行った、森美術館の「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」に、思考をドバドバと刺激されまくったので、Chim↑Pomが特集された「美術手帖」も慌てて買い、Chim↑Pomについてメッチャ考えてみた
『竜とそばかすの姫』では、「批判」が優位になってしまうそんなクソみたいな風潮を、Belleの歌声が吹き飛ばしていく感じが爽快だと感じました。私の主張は「理想的だ」と感じられてしまうかもしれませんが、変わるために大金が必要なわけではないし、個人の努力の積み重ねで可能な範囲のはずです。それぐらいの「理想」は語ってもいいのではないかと思っています。
映画『竜とそばかすの姫』の内容紹介
自然豊かな田舎で、平凡な毎日を過ごしている女子高生のすずは、幼い頃に母親を事故で亡くしたことをきっかけに、大好きな歌を人前で歌えなくなってしまった。幼馴染で同級生のルカのように、明るくみんなに慕われる存在に憧れてはいるが、そうはなれないと諦めてひっそりと学生生活を過ごしている。同じく幼馴染のしのぶくんは、学校中の人気者で、いつの間にか遠い存在になってしまった。同級生のヒロちゃんだけが、唯一心を許せる親友だ。
事故以来、父親と2人暮らし。ほとんど会話らしい会話はない。学校生活もパッとせず、昨日と今日と明日の違いが分からないような日々である。
あわせて読みたい
【感想】どんな話かわからない?難しい?ジブリ映画『君たちはどう生きるか』の考察・解説は必要?(監…
宮崎駿最新作であるジブリ映画『君たちはどう生きるか』は、宮崎アニメらしいファンタジックな要素を全開に詰め込みつつ、「生と死」「創造」についても考えさせる作品だ。さらに、「自分の頭の中から生み出されたものこそ『正解』」という、創造物と向き合う際の姿勢についても問うているように思う
そんなある日、ヒロちゃんから「U」に誘われた。「U」は世界最大の仮想空間で、なんと50億ものアカウントが存在する。耳に装着したデバイスで生体情報を読み取り、その情報を元に「U」内での自分の分身「As(アズ)」が生成される。アカウントと生体情報が紐づいているので、1人1アカウントしか作ることができないのが特徴だ。
すずは「Belle」という名前で登録し、「U」の世界を試してみた。人前ではずっと歌えずにいたが、ここだったら歌えるかもしれない。そう思い立って試してみると、自分でもびっくりするぐらい気持ちよく声を出すことができた。すずは「歌えるじゃん」と満足し、「U」の世界から離脱して眠りにつく。
翌日。とんでもないことになっていた。「Belle」のフォロワーが急増しているのだ。登録初日に一度歌っただけなのに、その際の映像が拡散され、「Belle」は「U」内の超有名人になっていたのである。多くの人が「自分のために歌ってくれている気がする」と称賛、すずはすぐに「U」内で大規模なライブを開くまでになっていく。
あわせて読みたい
【感想】映画『君が世界のはじまり』は、「伝わらない」「分かったフリをしたくない」の感情が濃密
「キラキラした青春学園モノ」かと思っていた映画『君が世界のはじまり』は、「そこはかとない鬱屈」に覆われた、とても私好みの映画だった。自分の決断だけではどうにもならない「現実」を前に、様々な葛藤渦巻く若者たちの「諦念」を丁寧に描き出す素晴らしい物語
しかしすずは、有名人になった高揚感など得られない。それどころか、現実とのギャップに困惑する日々で……。
映画『竜とそばかすの姫』の感想

賛否あるようですが、私はすごく好きな映画でした。あまりSNSもやらないし、仮想空間やらメタバースやらにも特に興味はないので、「U」の世界そのものには特に惹かれませんでしたが、「現実のような虚構」を用意することによって「すず/Belle」を掘り下げていく展開はとても良かったと思います。
この記事の冒頭で書いたように、やっぱり私は、この映画の「誰かを助けたい」という場面にグッときました。「誰かを助けたい」という気持ちが頭ごなしに否定されない世界の良さみたいなものを存分に生かしている感じがします。また、「現実的じゃない」という見方があることも理解した上でですが、「やはりこういう世界であってほしい」という自分の内側の願望が確認できもしました。
あわせて読みたい
【感動】円井わん主演映画『MONDAYS』は、タイムループものの物語を革新する衝撃的に面白い作品だった
タイムループという古びた設定と、ほぼオフィスのみという舞台設定を駆使した、想像を遥かに超えて面白かった映画『MONDAYS』は、テンポよく進むドタバタコメディでありながら、同時に、思いがけず「感動」をも呼び起こす、竹林亮のフィクション初監督作品
「それは理想論だ」って批判、基本的に好きになれないんだよね
実現可能かどうかはともかく、「理想を語ること」はどんな場合でも受け入れられてほしいって思う
また、「誰かを助けたい」という気持ちに関連して、すず(Belle)がある決断を胸に大勢の前で歌うシーンは特に良かったと感じました。すず自身が重い決断を下したことも勇敢だったと感じますが、さらに「立場が変わることで理解できたこと」が描かれる展開も良かったと思います。すずは、ある理由から「母親の死」に対して納得できない思いを抱いていたわけですが、否応なしに自分の立ち位置が変化したことで「母親の気持ち」が理解できるようになり、それによって母親を受け入れられるようになるわけです。そんな展開になるとは思っていなかったので、これも素敵な場面だと感じました。
すずの父親の「存在感」
私は、出番こそ少ないものの、すずの父親はとても重要な役割を担っていると感じました。先述した「すずが決意を胸に歌うシーン」で彼女が大きく変化したことが示唆されるわけですが、そこではあくまでも予感を抱かせる程度でしかありません。すずはあまり感情を表に出す人物ではないので、その変化を正しく捉えるのは難しいと思います。しかし、父親との場面で明白な変化を見せるのです。

あわせて読みたい
【天才】映画『リバー、流れないでよ』は、ヨーロッパ企画・上田誠によるタイムループの新発明だ
ヨーロッパ企画の上田誠が生み出した、タイムループものの新機軸映画『リバー、流れないでよ』は、「同じ2分間が繰り返される」という斬新すぎる物語。その設定だけ聞くと、「どう物語を展開させるんだ?」と感じるかもしれないが、あらゆる「制約」を押しのけて、とんでもない傑作に仕上がっている
冒頭からずっと、すずは父親につれない振る舞いをし続けます。父親は娘とコミュニケーションを取ろうとしますが、すずの方が閉ざしてしまっているという印象です。すずと父親の描写はとても少ないのであくまで想像にすぎませんが、恐らく、母親の死から10年ぐらい、すずと父親の関係はずっとこんな状態だったのだろうと私は感じました。
そう感じた理由の1つは、父親がすずに毎日同じ質問をすることです。そしてすずは、その質問にまともに返答しません。そんなやり取りが当たり前に描かれるので、この状態がずっと続いているのだろうと私は判断したわけです。
父親としても、質問を止めたら「止めたことに理由がある」って受け取られかねないしね
あわせて読みたい
【死】映画『湯を沸かすほどの熱い愛』に号泣。「家族とは?」を問う物語と、タイトル通りのラストが見事
「死は特別なもの」と捉えてしまうが故に「日常感」が失われ、普段の生活から「排除」されているように感じてしまうのは私だけではないはずだ。『湯を沸かすほどの熱い愛』は、「死を日常に組み込む」ことを当たり前に許容する「家族」が、「家族」の枠組みを問い直す映画である
父親は恐らく、時間を掛けて解決するしかない、と覚悟していたのだと思います。すずが閉じてしまっている理由は「母親が死に至った際の行動」にあり、すずにはその行動がどうしても理解できません。その理解が伴わなければ何も変わらないだろうし、時間を掛けて付き合っていくしかないと父親は決めていたのでしょう。
その決意をなんとなく感じさせるのが、駅ですずと父親がやり取りをする場面です。ここで父親は、毎日すずにしている質問を投げかけますが、それに対してすずは、恐らく初めていつもとは異なる返答をします。しかし父親は、この時のすずの返答に驚く素振りを見せず、いつもと変わらない振る舞いをするのです。
私はここに父親の決意を感じました。
なんでもないっちゃなんでもない場面なんだけど、凄く良かったよね
出番の少ない父親との掛け合いだからこそ余計にグッと来る感じもあった
あわせて読みたい
【思考】戸田真琴、経験も文章もとんでもない。「人生どうしたらいい?」と悩む時に読みたい救いの1冊:…
「AV女優のエッセイ」と聞くと、なかなか手が伸びにくいかもしれないが、戸田真琴『あなたの孤独は美しい』の、あらゆる先入観を吹っ飛ばすほどの文章力には圧倒されるだろう。凄まじい経験と、普通ではない思考を経てAV女優に至った彼女の「生きる指針」は、多くの人の支えになるはずだ
普通なら、それまでの10年間と違う返答が返ってきたら、咄嗟にいつもと違う反応をしてしまうはずです。しかし、そうしなかったということは、父親が「いつもと違う返答が返ってきても驚かない」と決めていたと考えるしかないでしょう。いつその瞬間が訪れてもいいように、父親はきっと普段から意識していたはずです。特別そんな風に描かれるわけではありませんし、私の勝手な深読みにすぎませんが、そんな風に考えて私は、映画全体の中でも、出番の少ないこの父親が印象的でした。

ヒロちゃんと友だちになりたい
映画全体の話とは全然関係ありませんが、私はヒロちゃんみたいな人が凄く好きです。メチャクチャ友だちになりたい。
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『四畳半タイムマシンブルース』超面白い!森見登美彦も上田誠も超天才だな!
ヨーロッパ企画の演劇『サマータイムマシン・ブルース』の物語を、森見登美彦の『四畳半神話大系』の世界観で描いたアニメ映画『四畳半タイムマシンブルース』は、控えめに言って最高だった。ミニマム過ぎる設定・物語を突き詰め、さらにキャラクターが魅力的だと、これほど面白くなるのかというお手本のような傑作
ほどよく毒があって、ほどよく陰があって、考え方も行動もぶっ飛んでいて、でも人間としての節度はちゃんとある、みたいな感じにとても惹かれます。ヒロちゃんみたいな友だちができないかなぁ。
ヒロちゃんについては、エンドロールを見て驚きました。声優が、YOASOBIの幾田りらだったのです。
ただ、「幾田りらだったこと」に驚いたわけじゃないんだよね
あわせて読みたい
【幸福】「死の克服」は「生の充実」となり得るか?映画『HUMAN LOST 人間失格』が描く超管理社会
アニメ映画『HUMAN LOST 人間失格』では、「死の克服」と「管理社会」が分かちがたく結びついた世界が描かれる。私たちは既に「緩やかな管理社会」を生きているが、この映画ほどの管理社会を果たして許容できるだろうか?そしてあなたは、「死」を克服したいと願うだろうか?
映画を観る前に、テレビのワイドショー番組かなにかで、「幾田りらが『竜とそばかすの姫』で声優に初挑戦」みたいな特集がされていました。だから私は、情報として「ヒロちゃんの声は幾田りら」ということは知っていたはずなのです。ただ、映画を観る頃にはそのことを忘れており、いざ映画を観ても、エンドロールを目にするまでそのことに気づきませんでした。そのことに私はとても驚かされたというわけです。
こんな言い方をすると失礼かもしれませんが、「声優初挑戦」だったらもう少し「違和感がある」「上手くないな」という感想になってもおかしくない気がします。ヒロちゃんは映画で結構出てくる場面が多いので、その分ボロが出る可能性も高いはずです。それでも、違和感をまったく抱かずに最後まで観れてしまったことにも驚かされました。
なんというのか、出来る人は何でも出来るもんだなぁ、と思わされます。羨ましい。
あわせて読みたい
【狂気】バケモン・鶴瓶を映し出す映画。「おもしろいオッチャン」に潜む「異常さ」と「芸への情熱」:…
「俺が死ぬまで公開するな」という条件で撮影が許可された映画『バケモン』。コロナ禍で映画館が苦境に立たされなければ、公開はずっと先だっただろう。テレビで見るのとは違う「芸人・笑福亭鶴瓶」の凄みを、古典落語の名作と名高い「らくだ」の変遷と共に切り取る
出演:中村佳穂, 出演:成田凌, 出演:染谷将太, 出演:玉城ティナ, 出演:幾田りら, 出演:森山良子, 出演:清水ミチコ, 出演:坂本冬美, 出演:岩崎良美, 出演:中尾幸世, 出演:森川智之, 出演:宮野真守, 出演:津田健次郎, 出演:小山茉美, 出演:役所広司, 出演:佐藤健, Writer:細田守, 監督:細田守
¥2,500 (2022/05/25 22:23時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品視聴済】私が観てきた映画(フィクション)を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が観てきた映画(フィクション)を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。
最後に
全体的にはとても好きな映画でしたが、「竜」に関する描写はもう少し必要だった気もします。「竜」に付随する様々な情報がちょっと説明不足だった気がしていて、個人的にはそれが「しっくりこない感」に繋がっているような気もしました。
繰り返しますが、たとえ「理想論」だと言われようとも、私は、「『誰かを助けたい』と主張する側」でいたいと改めて感じましたし、実際に「誰かを助ける行動」が取れる人間になりたいとも思いました。
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!「それってホントに『コミュ力』が高いって言えるの?」と疑問を感じている方に…
私は、「コミュ力が高い人」に関するよくある主張に、どうも違和感を覚えてしまうことが多くあります。そしてその一番大きな理由が、「『コミュ力が高い人』って、ただ『想像力がない』だけではないか?」と感じてしまう点にあると言っていいでしょう。出版したKindle本は、「ネガティブには見えないネガティブな人」(隠れネガティブ)を取り上げながら、「『コミュ力』って何だっけ?」と考え直してもらえる内容に仕上げたつもりです。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【迷路】映画『国境ナイトクルージング』は、青春と呼ぶにはちょっと大人な3人の関係を丁寧に描く
映画『国境ナイトクルージング』は、男2人女1人の3人による、「青春」と呼ぶには少し年を取りすぎてしまったビターな関係を描き出す物語。説明が少なく、また、様々な示唆的な描写の意味するところを捉えきれなかったためり、「分からないこと」が多かったのだが、全体的な雰囲気が素敵で好きなタイプの作品だった
あわせて読みたい
【失恋】ひたすらカオスに展開する映画『エターナル・サンシャイン』は、最後まで観ると面白い!(主演…
映画『エターナル・サンシャイン』は、冒頭からしばらくの間、とにかくまったく意味不明で、「何がどうなっているのか全然分からない!」と思いながら観ていました。しかし、映像がカオスになるにつれて状況の理解は進み始め、最終的には「よくもまあこんな素っ頓狂なストーリーを理解できる物語に落とし込んだな」と感心させられました
あわせて読みたい
【父親】パキスタン本国では上映禁止の映画『ジョイランド』は、古い価値観に翻弄される家族を描く
映画『ジョイランド』は、本国パキスタンで一時上映禁止とされた作品だが、私たち日本人からすれば「どうして?」と感じるような内容だと思う。「(旧弊な)家族観を否定している」と受け取られたからだろうが、それにしたってやはり理不尽だ。そしてそんな「家族のややこしさ」には、現代日本を生きる我々も共感できるに違いない
あわせて読みたい
【友情】セリフの無い映画『ロボット・ドリームズ』は、そのシンプルさ故に深い感動へと連れて行く
映画『ロボット・ドリームズ』は、普通に考えれば「映画としては成立しない」と思えるほどシンプルすぎる「幼児向けの絵本」のような内容なのだが、「セリフが一切無い」という特殊な構成によって感動的な作品に仕上がっている。お互いを想い合う「ドッグ」と「ロボット」の関係性が胸に染み入る、とても素敵な作品だ
あわせて読みたい
【感動】映画『ぼくとパパ、約束の週末』は「自閉症への理解が深まる」という点で実に興味深かった
映画『ぼくとパパ、約束の週末』は「心温まる物語」であり、一般的にはそういう作品として評価されているはずだが、個人的には「『自閉症』への解像度が高まる」という意味でも興味深かった。「ルールは厳密に守るが、ルール同士が矛盾していて袋小路に陥ってしまう」という困難さが実に分かりやすく描かれている
あわせて読みたい
【奇妙】映画『画家と泥棒』は、非日常的なきっかけで始まったあり得ないほど奇跡的な関係を描く
映画『画家と泥棒』は、「自身の絵を盗まれた画家が、盗んだ泥棒と親しくなる」という奇妙奇天烈なきっかけから関係性が始まる物語であり、現実に起きたこととは思えないほど不可思議なドキュメンタリーである。アートを通じて奇妙に通じ合う2人の関係性は、ある種の美しささえ感じさせる、とても素晴らしいものに見えた
あわせて読みたい
【日常】映画『大きな家』(竹林亮)は、児童養護施設で「家族」と「血縁」の違いや難しさに直面する
児童養護施設に長期密着した映画『大きな家』は、映画『14歳の栞』で中学2年生をフラットに撮り切った竹林亮が監督を務めたドキュメンタリーである。子どもたちの過去に焦点を当てるのではなく、「児童養護施設の日常風景」として彼らを捉えるスタンスで、その上でさらに「家族のあり方」に対する子どもたちの認識が掘り下げられる
あわせて読みたい
【煌めき】映画『HAPPYEND』が描く、”監視への嫌悪”と”地震への恐怖”の中で躍動する若者の刹那(監督:…
映画『HAPPYEND』は、「監視システム」と「地震」という「外的な制約条件」を設定し、その窮屈な世界の中で屈せずに躍動しようとする若者たちをリアルに描き出す物語である。特に、幼稚園からの仲であるコウとユウタの関係性が絶妙で、演技未経験だという2人の存在感と映像の雰囲気が相まって、実に素敵に感じられた
あわせて読みたい
【豪快】これまで観た中でもトップクラスに衝撃的だった映画『ベイビーわるきゅーれ ナイスデイズ』(…
私は、シリーズ最新作『ベイビーわるきゅーれ ナイスデイズ』と、そのメイキングが中心のドキュメンタリー映画しか観ていませんが、あらゆる要素に圧倒される素晴らしい鑑賞体験でした。アクションシーンの凄まじさはもちろん、個人的には、杉本ちさとと深川まひろのダルダルな会話がとても好きで、混ざりたいなとさえ思います
あわせて読みたい
【葛藤】映画『きみの色』(山田尚子)は、感受性が強すぎる若者のリアルをバンドを通じて描き出す(主…
山田尚子監督作『きみの色』は、これといった起伏のないストーリー展開でありながら、「若い世代の繊細さに満ちた人間関係」をとてもリアルに描き出す雰囲気が素敵な作品。「悩み・葛藤を抱えている状態が日常である」という雰囲気をベースにしつつ、「音楽」を起点に偶然繋がった3人の緩やかな日々を描き出す物語に惹きつけられた
あわせて読みたい
【繊細】映画『ぼくのお日さま』(奥山大史)は、小さな世界での小さな恋を美しい映像で描く(主演:越…
映画『ぼくのお日さま』は、舞台設定も人間関係も実にミニマムでありながら、とても奥行きのある物語が展開される作品。予告編で「3つの恋」と言及されなければ、描かれるすべての「恋」には気付けなかっただろうと思うくらいの繊細な関係性と、映像・音楽を含めてすべてが美しい旋律として奏でられる物語がとても素敵でした
あわせて読みたい
【異例】東映京都撮影所が全面協力!自主制作の時代劇映画『侍タイムスリッパー』は第2の『カメ止め』だ…
映画『侍タイムスリッパー』は、「自主制作映画なのに時代劇」「撮影スタッフ10人なのに東映京都撮影所全面協力」「助監督役が実際の助監督も務めている」など、中身以外でも話題に事欠かない作品ですが、何もよりも物語が実に面白い!「幕末の侍が現代にタイムスリップ」というよくある設定からこれほど面白い物語が生まれるとは
あわせて読みたい
【宣伝】アポロ計画での月面着陸映像は本当か?映画『フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン』のリアル
「月面着陸映像はニセモノだ」という陰謀論を逆手にとってリアリティのある物語を生み出した映画『フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン』は、「ベトナム戦争で疲弊し、事故続きのNASAが不人気だった」という現実を背景に「歴史のif」を描き出す。「確かにそれぐらいのことはするかもしれない」というリアリティをコメディタッチで展開させる
あわせて読みたい
【感想】B級サメ映画の傑作『温泉シャーク』は、『シン・ゴジラ』的壮大さをバカバカしく描き出す
「温泉に入っているとサメに襲われる」という荒唐無稽すぎる設定のサメ映画『温泉シャーク』は、確かにふざけ倒した作品ではあるものの、観てみる価値のある映画だと思います。サメの生態を上手く利用した設定や、「伏線回収」と表現していいだろう展開などが巧みで、細かなことを気にしなければ、そのバカバカしさを楽しめるはずです
あわせて読みたい
【恋心】映画『サッドティー』は、「『好き』を巡ってウロウロする人々」を描く今泉力哉節全開の作品だった
映画『サッドティー』は、今泉力哉らしい「恋愛の周辺でグルグルする人たち」を描き出す物語。関係性が微妙に重なる複数の人間を映し出す群像劇の中で、「『好き』のややこしさ」に焦点を当てていく構成はさすがです。実に奇妙な展開で終わる物語ですが、それでもなお「リアルだ」と感じさせる雰囲気は、まるで魔法のようでした
あわせて読みたい
【あらすじ】有村架純が保護司を演じた映画『前科者』が抉る、罪を犯した者を待つ「更生」という現実
映画『前科者』は、仮釈放中の元受刑者の更生を手助けするボランティアである「保護司」を中心に据えることで、「元犯罪者をどう受け入れるべきか」「保護司としての葛藤」などを絶妙に描き出す作品。個別の事件への処罰感情はともかく、「社会全体としていかに犯罪を減らしていくか」という観点を忘れるべきではないと私は思っている
あわせて読みたい
【感想】映画『夜明けのすべて』は、「ままならなさ」を抱えて生きるすべての人に優しく寄り添う(監督…
映画『夜明けのすべて』は、「PMS」や「パニック障害」を通じて、「自分のものなのに、心・身体が思い通りにならない」という「ままならなさ」を描き出していく。決して他人事ではないし、「私たちもいつそのような状況に置かれるか分からない」という気持ちで観るのがいいでしょう。物語の起伏がないのに惹きつけられる素敵な作品です
あわせて読みたい
【狂気】押見修造デザインの「ちーちゃん」(映画『毒娘』)は「『正しさ』によって歪む何か」の象徴だ…
映画『毒娘』は、押見修造デザインの「ちーちゃん」の存在感が圧倒的であることは確かなのだが、しかし観ていくと、「決して『ちーちゃん』がメインなわけではない」ということに気づくだろう。本作は、全体として「『正しさ』によって歪む何か」を描き出そうとする物語であり、私たちが生きる社会のリアルを抉り出す作品である
あわせて読みたい
【狂気】群青いろ制作『雨降って、ジ・エンド。』は、主演の古川琴音が成立させている映画だ
映画『雨降って、ジ・エンド。』は、冒頭からしばらくの間「若い女性とオジサンのちょっと変わった関係」を描く物語なのですが、後半のある時点から「共感を一切排除する」かのごとき展開になる物語です。色んな意味で「普通なら成立し得ない物語」だと思うのですが、古川琴音の演技などのお陰で、絶妙な形で素敵な作品に仕上がっています
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『52ヘルツのクジラたち』の「無音で叫ぶ人」と「耳を澄ます人」の絶妙な響鳴(原作:…
映画『52ヘルツのクジラたち』は、「現代的な問題のごった煮」と感じられてしまうような”過剰さ”に溢れてはいますが、タイトルが作品全体を絶妙に上手くまとめていて良かったなと思います。主演の杉咲花がやはり見事で、身体の内側から「不幸」が滲み出ているような演技には圧倒されてしまいました
あわせて読みたい
【幻惑】映画『フォロウィング』の衝撃。初監督作から天才だよ、クリストファー・ノーラン
クリストファー・ノーランのデビュー作であり、多数の賞を受賞し世界に衝撃を与えた映画『フォロウィング』には、私も驚かされてしまった。冒頭からしばらくの間「何が描かれているのかさっぱり理解できない」という状態だったのに、ある瞬間一気に視界が晴れたように状況が理解できたのだ。脚本の力がとにかく圧倒的だった
あわせて読みたい
【現在】猟師になった東出昌大を追う映画『WILL』は予想外に良かった。山小屋での生活は衝撃だ(監督:…
猟師・東出昌大に密着した映画『WILL』は、思いがけず面白い作品だった。正直、東出昌大にはまったく興味がなく、本作も期待せず観たのだが、異常なほどフラットなスタンス故に周囲にいる人間を否応なく惹きつける「人間力」や、狩猟の世界が突きつける「生と死」というテーマなど実に興味深い。本当に観て良かったなと思う
あわせて読みたい
【衝撃】広末涼子映画デビュー作『20世紀ノスタルジア』は、「広末が異常にカワイイ」だけじゃない作品
広末涼子の映画デビュー・初主演作として知られる『20世紀ノスタルジア』は、まず何よりも「広末涼子の可愛さ」に圧倒される作品だ。しかし、決してそれだけではない。初めは「奇妙な設定」ぐらいにしか思っていなかった「宇宙人に憑依されている」という要素が、物語全体を実に上手くまとめている映画だと感じた
あわせて読みたい
【感想】アニメ映画『パーフェクトブルー』(今敏監督)は、現実と妄想が混在する構成が少し怖い
本作で監督デビューを果たした今敏のアニメ映画『パーフェクトブルー』は、とにかくメチャクチャ面白かった。現実と虚構の境界を絶妙に壊しつつ、最終的にはリアリティのある着地を見せる展開で、25年以上も前の作品だなんて信じられない。今でも十分通用するだろうし、81分とは思えない濃密さに溢れた見事な作品である
あわせて読みたい
【映画】ウォン・カーウァイ4Kレストア版の衝撃!『恋する惑星』『天使の涙』は特にオススメ!
『恋する惑星』『天使の涙』で一躍その名を世界に知らしめた巨匠ウォン・カーウァイ作品の4Kレストア版5作品を劇場で一気見した。そして、監督の存在さえまったく知らずに観た『恋する惑星』に圧倒され、『天使の涙』に惹きつけられ、その世界観に驚かされたのである。1990年代の映画だが、現在でも通用する凄まじい魅力を放つ作品だ
あわせて読みたい
【あらすじ】声優の幾田りらとあのちゃんが超絶良い!アニメ映画『デデデデ』はビビるほど面白い!:『…
幾田りらとあのちゃんが声優を務めた映画『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』は、とにかく最高の物語だった。浅野いにおらしいポップさと残酷さを兼ね備えつつ、「終わってしまった世界でそれでも生きていく」という王道的展開を背景に、門出・おんたんという女子高生のぶっ飛んだ関係性が描かれる物語が見事すぎる
あわせて読みたい
【感想】映画『レオン』は、殺し屋マチルダを演じたナタリー・ポートマンがとにかく素晴らしい(監督:…
映画『レオン』は、その性質ゆえに物議を醸す作品であることも理解できるが、私はやはりナタリー・ポートマンに圧倒されてしまった。絶望的な事態に巻き込まれたマチルダの葛藤と、そんな少女と共に生きることになった中年男性レオンとの関係性がとても見事に映し出されている。実に素敵な作品だった
あわせて読みたい
【評価】映画『ゴジラ-1.0』(山崎貴監督)は面白い!迫力満点の映像と絶妙な人間ドラマ(米アカデミー…
米アカデミー賞で視覚効果賞を受賞した映画『ゴジラ-1.0』(山崎貴監督)は、もちろんそのVFXに圧倒される物語なのだが、「人間ドラマ」をきちんと描いていることも印象的だった。「終戦直後を舞台にする」という、ゴジラを描くには様々な意味でハードルのある設定を見事に活かした、とても見事な作品だ
あわせて読みたい
【あらすじ】原爆を作った人の後悔・葛藤を描く映画『オッペンハイマー』のための予習と評価(クリスト…
クリストファー・ノーラン監督作品『オッペンハイマー』は、原爆開発を主導した人物の葛藤・苦悩を複雑に描き出す作品だ。人間が持つ「多面性」を様々な方向から捉えようとする作品であり、受け取り方は人それぞれ異なるだろう。鑑賞前に知っておいた方がいい知識についてまとめたので、参考にしてほしい
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『レザボア・ドッグス』(タランティーノ監督)はとにかく驚異的に脚本が面白い!
クエンティン・タランティーノ初の長編監督作『レザボア・ドッグス』は、のけぞるほど面白い映画だった。低予算という制約を逆手に取った「会話劇」の構成・展開があまりにも絶妙で、舞台がほぼ固定されているにも拘らずストーリーが面白すぎる。天才はやはり、デビュー作から天才だったのだなと実感させられた
あわせて読みたい
【感想】映画『ローマの休日』はアン王女を演じるオードリー・ヘプバーンの美しさが際立つ名作
オードリー・ヘプバーン主演映画『ローマの休日』には驚かされた。現代の視点で観ても十分に通用する作品だからだ。まさに「不朽の名作」と言っていいだろう。シンプルな設定と王道の展開、そしてオードリー・ヘプバーンの時代を超える美しさが相まって、普通ならまずあり得ない見事なコラボレーションが見事に実現している
あわせて読みたい
【考察】A24のホラー映画『TALK TO ME』が描くのは、「薄く広がった人間関係」に悩む若者のリアルだ
「A24のホラー映画史上、北米最高興収」と謳われる『TALK TO ME トーク・トゥ・ミー』は、一見「とても分かりやすいホラー映画」である。しかし真のテーマは「SNS過剰社会における人間関係の困難さ」なのだと思う。結果としてSNSが人と人との距離を遠ざけてしまっている現実を、ホラー映画のスタイルに落とし込んだ怪作
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『アンダーカレント』(今泉力哉)は、失踪をテーマに「分かり合えなさ」を描く
映画『アンダーカレント』において私は、恐らく多くの人が「受け入れがたい」と感じるだろう人物に共感させられてしまった。また本作は、「他者を理解すること」についての葛藤が深掘りされる作品でもある。そのため、私が普段から抱いている「『他者のホントウ』を知りたい」という感覚も強く刺激された
あわせて読みたい
【絶望】杉咲花主演映画『市子』の衝撃。毎日がしんどい「どん底の人生」を生き延びるための壮絶な決断…
映画『市子』はまず何よりも主演を務めた杉咲花に圧倒させられる作品だ。そしてその上で、主人公・川辺市子を巡る物語にあれこれと考えさせられてしまった。「川辺市子」は決してフィクショナルな存在ではなく、現実に存在し得る。本作は、そのような存在をリアルに想像するきっかけにもなるだろう
あわせて読みたい
【家族】映画『女優は泣かない』は、蓮佛美沙子が「再起を賭ける女優」を演じる笑い泣き満載の作品(出…
蓮佛美沙子が、スキャンダルで落ちぶれ再起を賭ける女優を演じる映画『女優は泣かない』は、ミニマムかつシンプルな構成ながら、笑いあり涙ありのハートフルコメディだった。「やりたくはないが、やらねばならぬ」とお互いが感じているドキュメンタリー撮影を軸に、家族の物語を織り込む展開が素敵
あわせて読みたい
【感想】映画『正欲』に超共感。多様性の時代でさえどこに行っても馴染めない者たちの業苦を抉る(出演…
映画『正欲』は、私には共感しかない作品だ。特に、新垣結衣演じる桐生夏月と磯村勇斗演じる佐々木佳道が抱える葛藤や息苦しさは私の内側にあるものと同じで、その描かれ方に圧倒されてしまった。「『多様性』には『理解』も『受け入れ』も不要で、単に否定しなければ十分」なのだと改めて思う
あわせて読みたい
【絶望】人生どん底から生き方を変える。映画『シスター 夏のわかれ道』が描く中国人女性の葛藤と諦念
両親の死をきっかけに、「見知らぬ弟」を引き取らなければならなくなった女性を描く映画『シスター 夏のわかれ道』は、中国の特異な状況を背景にしつつ、誰もが抱き得る普遍的な葛藤が切り取られていく。現状を打破するために北京の大学院を目指す主人公は、一体どんな決断を下すのか。
あわせて読みたい
【未知】コーダに密着した映画『私だけ聴こえる』は、ろう者と聴者の狭間で居場所がない苦悩を映し出す
あなたは「コーダ」と呼ばれる存在を知っているだろうか?「耳の聴こえない親を持つ、耳が聴こえる子ども」のことであり、映画『私だけ聴こえる』は、まさにそんなコーダが置かれた状況を描くドキュメンタリー映画だ。自身は障害者ではないのに大変な苦労を強いられている現状が理解できる作品
あわせて読みたい
【絶望】映画『少年たちの時代革命』が描く、香港デモの最中に自殺者を救おうとした若者たちの奮闘
香港の民主化運動の陰で、自殺者を救出しようと立ち上がったボランティア捜索隊が人知れず存在していた。映画『少年たちの時代革命』はそんな実話を基にしており、若者の自殺が急増した香港に様々な葛藤を抱えながら暮らし続ける若者たちのリアルが切り取られる作品だ
あわせて読みたい
【助けて】映画『生きててごめんなさい』は、「共依存カップル」視点で生きづらい世の中を抉る物語(主…
映画『生きててごめんなさい』は、「ちょっと歪な共依存関係」を描きながら、ある種現代的な「生きづらさ」を抉り出す作品。出版社の編集部で働きながら小説の新人賞を目指す園田修一は何故、バイトを9度もクビになり、一日中ベッドの上で何もせずに過ごす同棲相手・清川莉奈を”必要とする”のか?
あわせて読みたい
【天才】映画音楽の発明家『モリコーネ』の生涯。「映画が恋した音楽家」はいかに名曲を生んだか
「映画音楽のフォーマットを生み出した」とも評される天才作曲家エンリオ・モリコーネを扱った映画『モリコーネ 映画が恋した音楽家』では、生涯で500曲以上も生み出し、「映画音楽」というジャンルを比べ物にならないほどの高みにまで押し上げた人物の知られざる生涯が描かれる
あわせて読みたい
【不穏】大友克洋の漫画『童夢』をモデルにした映画『イノセンツ』は、「無邪気な残酷さ」が恐ろしい
映画『イノセンツ』は、何がどう展開するのかまるで分からないまま進んでいく実に奇妙な物語だった。非現実的な設定で描かれるのだが、そのことによって子どもたちの「無邪気な残酷さ」が一層リアルに浮き彫りにされる物語であり、「意図的に大人が排除された構成」もその一助となっている
あわせて読みたい
【伝説】映画『ミスター・ムーンライト』が描くビートルズ武道館公演までの軌跡と日本音楽への影響
ザ・ビートルズの武道館公演が行われるまでの軌跡を描き出したドキュメンタリー映画『ミスター・ムーンライト』は、その登場の衝撃について語る多数の著名人が登場する豪華な作品だ。ザ・ビートルズがまったく知られていなかった頃から、伝説の武道館公演に至るまでの驚くべきエピソードが詰まった1作
あわせて読みたい
【違和感】三浦透子主演映画『そばかす』はアセクシャルの生きづらさを描く。セクシャリティ理解の入り口に
「他者に対して恋愛感情・性的欲求を抱かないセクシャリティ」である「アセクシャル」をテーマにした映画『そばかす』は、「マイノリティのリアル」をかなり解像度高く映し出す作品だと思う。また、主人公・蘇畑佳純に共感できてしまう私には、「普通の人の怖さ」が描かれている映画にも感じられた
あわせて読みたい
【苦悩】「やりがいのある仕事」だから見て見ぬふり?映画『アシスタント』が抉る搾取のリアル
とある映画会社で働く女性の「とある1日」を描く映画『アシスタント』は、「働くことの理不尽さ」が前面に描かれる作品だ。「雑用」に甘んじるしかない彼女の葛藤がリアルに描かれている。しかしそれだけではない。映画の「背景」にあるのは、あまりに悪逆な行為と、大勢による「見て見ぬふり」である
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』を観てくれ!現代の人間関係の教科書的作品を考…
映画『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』は、私にグサグサ突き刺さるとても素晴らしい映画だった。「ぬいぐるみに話しかける」という活動内容の大学サークルを舞台にした物語であり、「マイノリティ的マインド」を持つ人たちの辛さや葛藤を、「マジョリティ視点」を絶妙に織り交ぜて描き出す傑作について考察する
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『四畳半タイムマシンブルース』超面白い!森見登美彦も上田誠も超天才だな!
ヨーロッパ企画の演劇『サマータイムマシン・ブルース』の物語を、森見登美彦の『四畳半神話大系』の世界観で描いたアニメ映画『四畳半タイムマシンブルース』は、控えめに言って最高だった。ミニマム過ぎる設定・物語を突き詰め、さらにキャラクターが魅力的だと、これほど面白くなるのかというお手本のような傑作
あわせて読みたい
【純真】ゲイが犯罪だった時代が舞台の映画『大いなる自由』は、刑務所内での極深な人間ドラマを描く
男性同士の恋愛が犯罪であり、ゲイの男性が刑法175条を理由に逮捕されてしまう時代のドイツを描いた映画『大いなる自由』は、確かに同性愛の物語なのだが、実はそこに本質はない。物語の本質は、まさにタイトルにある通り「自由」であり、ラストシーンで突きつけられるその深い問いかけには衝撃を受けるだろう
あわせて読みたい
【感想】どんな話かわからない?難しい?ジブリ映画『君たちはどう生きるか』の考察・解説は必要?(監…
宮崎駿最新作であるジブリ映画『君たちはどう生きるか』は、宮崎アニメらしいファンタジックな要素を全開に詰め込みつつ、「生と死」「創造」についても考えさせる作品だ。さらに、「自分の頭の中から生み出されたものこそ『正解』」という、創造物と向き合う際の姿勢についても問うているように思う
あわせて読みたい
【感想】映画『すずめの戸締まり』(新海誠)は、東日本大震災後を生きる私達に「逃げ道」をくれる(松…
新海誠監督の『すずめの戸締まり』は、古代神話的な設定を現代のラブコメに組み込みながら、あまりに辛い現実を生きる人々に微かな「逃げ道」を指し示してくれる作品だと思う。テーマ自体は重いが、恋愛やコメディ要素とのバランスがとても良く、ロードムービー的な展開もとても魅力的
あわせて読みたい
【天才】映画『リバー、流れないでよ』は、ヨーロッパ企画・上田誠によるタイムループの新発明だ
ヨーロッパ企画の上田誠が生み出した、タイムループものの新機軸映画『リバー、流れないでよ』は、「同じ2分間が繰り返される」という斬新すぎる物語。その設定だけ聞くと、「どう物語を展開させるんだ?」と感じるかもしれないが、あらゆる「制約」を押しのけて、とんでもない傑作に仕上がっている
あわせて読みたい
【感動】円井わん主演映画『MONDAYS』は、タイムループものの物語を革新する衝撃的に面白い作品だった
タイムループという古びた設定と、ほぼオフィスのみという舞台設定を駆使した、想像を遥かに超えて面白かった映画『MONDAYS』は、テンポよく進むドタバタコメディでありながら、同時に、思いがけず「感動」をも呼び起こす、竹林亮のフィクション初監督作品
あわせて読みたい
【あらすじ】大泉洋主演映画『月の満ち欠け』は「生まれ変わり」の可能性をリアルに描く超面白い作品
あなたは「生まれ変わり」を信じるだろうか? 私はまったく信じないが、その可能性を魅力的な要素を様々に散りばめて仄めかす映画『月の満ち欠け』を観れば、「生まれ変わり」の存在を信じていようがいまいが、「相手を想う気持ち」を強く抱く者たちの人間模様が素敵だと感じるだろう
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『夕方のおともだち』は、「私はこう」という宣言からしか始まらない関係性の”純度”を描く
「こんな田舎にはもったいないほどのドM」と評された男が主人公の映画『夕方のおともだち』は、SM嬢と真性ドMの関わりを通じて、「宣言から始まる関係」の難しさを描き出す。「普通の世界」に息苦しさを感じ、どうしても馴染めないと思っている人に刺さるだろう作品
あわせて読みたい
【苦しい】「恋愛したくないし、興味ない」と気づいた女性が抉る、想像力が足りない社会の「暴力性」:…
「実は私は、恋愛的な関係を求めているわけじゃないかもしれない」と気づいた著者ムラタエリコが、自身の日常や専門学校でも学んだ写真との関わりを基に、「自分に相応しい関係性」や「社会の暴力性」について思考するエッセイ。久々に心にズバズバ刺さった、私にはとても刺激的な1冊だった。
あわせて読みたい
【感想】映画『君が世界のはじまり』は、「伝わらない」「分かったフリをしたくない」の感情が濃密
「キラキラした青春学園モノ」かと思っていた映画『君が世界のはじまり』は、「そこはかとない鬱屈」に覆われた、とても私好みの映画だった。自分の決断だけではどうにもならない「現実」を前に、様々な葛藤渦巻く若者たちの「諦念」を丁寧に描き出す素晴らしい物語
あわせて読みたい
【感想】のん主演映画『私をくいとめて』から考える、「誰かと一緒にいられれば孤独じゃないのか」問題
のん(能年玲奈)が「おひとり様ライフ」を満喫する主人公を演じる映画『私をくいとめて』を観て、「孤独」について考えさせられた。「誰かと関わっていられれば孤独じゃない」という考えに私は賛同できないし、むしろ誰かと一緒にいる時の方がより強く孤独を感じることさえある
あわせて読みたい
【考察】ヨネダコウ『囀る鳥は羽ばたかない』は、BLの枠組みの中で「歪んだ人間」をリアルに描き出す
2巻までしか読んでいないが、ヨネダコウのマンガ『囀る鳥は羽ばたかない』は、「ヤクザ」「BL」という使い古されたフォーマットを使って、異次元の物語を紡ぎ出す作品だ。BLだが、BLという外枠を脇役にしてしまう矢代という歪んだ男の存在感が凄まじい。
あわせて読みたい
【感想】おげれつたなか『エスケープジャーニー』は、BLでしか描けない”行き止まりの関係”が絶妙
おげれつたなか『エスケープジャーニー』のあらすじ紹介とレビュー。とにかく、「BLでしか描けない関係性」が素晴らしかった。友達なら完璧だったのに、「恋人」ではまったく上手く行かなくなってしまった直人と太一の葛藤を通じて、「進んでも行き止まり」である関係にどう向き合うか考えさせられる
あわせて読みたい
【違和感】平田オリザ『わかりあえないことから』は「コミュニケーション苦手」問題を新たな視点で捉え…
「コミュニケーションが苦手」なのは、テクニックの問題ではない!?『わかりあえないことから』は、学校でのコミュニケーション教育に携わる演劇人・平田オリザが抱いた違和感を起点に、「コミュニケーション教育」が抱える問題と、私たち日本人が進むべき道を示す1冊
あわせて読みたい
【幸福】「死の克服」は「生の充実」となり得るか?映画『HUMAN LOST 人間失格』が描く超管理社会
アニメ映画『HUMAN LOST 人間失格』では、「死の克服」と「管理社会」が分かちがたく結びついた世界が描かれる。私たちは既に「緩やかな管理社会」を生きているが、この映画ほどの管理社会を果たして許容できるだろうか?そしてあなたは、「死」を克服したいと願うだろうか?
あわせて読みたい
【思考】森博嗣のおすすめエッセイ。「どう生きるかべきか」「生き方が分からない」と悩む人に勧めたい…
エッセイも多数出版している説家・森博嗣が、読者からの悩み相談を受けて執筆した『自分探しと楽しさについて』は、生きていく上で囚われてしまう漠然とした悩みを解消する力を持っている。どう生きるべきか悩んでしまう若者に特に読んでもらいたい1冊
あわせて読みたい
【あらすじ】ムロツヨシ主演映画『神は見返りを求める』の、”善意”が”悪意”に豹変するリアルが凄まじい
ムロツヨシ演じる田母神が「お人好し」から「復讐の権化」に豹変する映画『神は見返りを求める』。「こういう状況は、実際に世界中で起こっているだろう」と感じさせるリアリティが見事な作品だった。「善意」があっさりと踏みにじられる世界を、私たちは受け容れるべきだろうか?
あわせて読みたい
【思考】戸田真琴、経験も文章もとんでもない。「人生どうしたらいい?」と悩む時に読みたい救いの1冊:…
「AV女優のエッセイ」と聞くと、なかなか手が伸びにくいかもしれないが、戸田真琴『あなたの孤独は美しい』の、あらゆる先入観を吹っ飛ばすほどの文章力には圧倒されるだろう。凄まじい経験と、普通ではない思考を経てAV女優に至った彼女の「生きる指針」は、多くの人の支えになるはずだ
あわせて読みたい
【あらすじ】映画化の小説『僕は、線を描く』。才能・センスではない「芸術の本質」に砥上裕將が迫る
「水墨画」という、多くの人にとって馴染みが無いだろう芸術を題材に据えた小説『線は、僕を描く』は、青春の葛藤と創作の苦悩を描き出す作品だ。「未経験のど素人である主人公が、巨匠の孫娘と勝負する」という、普通ならあり得ない展開をリアルに感じさせる設定が見事
あわせて読みたい
【恋愛】モテない男は何がダメ?AV監督が男女共に贈る「コミュニケーション」と「居場所」の話:『すべ…
二村ヒトシ『すべてはモテるためである』は、タイトルも装丁も、どう見ても「モテ本」にしか感じられないだろうが、よくある「モテるためのマニュアル」が書かれた本ではまったくない。「行動」を促すのではなく「思考」が刺激される、「コミュニケーション」と「居場所」について語る1冊
あわせて読みたい
【激変】天才・藤井聡太と将棋界について加藤一二三、渡辺明が語る。AIがもたらした変化の是非は?:『…
『天才の考え方 藤井聡太とは何者か?』は、加藤一二三・渡辺明という棋界トップランナー2人が「将棋」をテーマに縦横無尽に語り合う対談本。この記事では、「AIがもたらした変化」について触れる。「答えを教えてくれるAI」は、将棋を、そして棋士をどう変えたのか?
あわせて読みたい
【実話】台湾のろう学校のいじめ・性的虐待事件を描く映画『無聲』が問う、あまりに悲しい現実
台湾のろう学校で実際に起こったいじめ・性的虐待事件を基に作られた映画『無聲』は、健常者の世界に刃を突きつける物語だ。これが実話だという事実に驚かされる。いじめ・性的虐待が物語の「大前提」でしかないという衝撃と、「性的虐待の方がマシ」という選択を躊躇せず行う少女のあまりの絶望を描き出す
あわせて読みたい
【芸術】実話を下敷きに描く映画『皮膚を売った男』は、「アートによる鮮やかな社会問題風刺」が見事
「シリア難民の背中にタトゥーを彫り芸術作品として展示する」と聞くと非常に不謹慎に感じられるだろうが、彫ったのが国家間の移動を自由にする「シェンゲンビザ」だという点が絶妙な皮肉。実話をベースにした映画『皮膚を売った男』の、アートによる社会問題提起の見事な鮮やかさ
あわせて読みたい
【衝撃】卯月妙子『人間仮免中』、とんでもないコミックエッセイだわ。統合失調症との壮絶な闘いの日々
小学5年生から統合失調症を患い、社会の中でもがき苦しみながら生きる卯月妙子のコミックエッセイ『人間仮免中』はとんでもない衝撃作。周りにいる人とのぶっ飛んだ人間関係や、歩道橋から飛び降り自殺未遂を図り顔面がぐちゃぐちゃになって以降の壮絶な日々も赤裸々に描く
あわせて読みたい
【驚異】『グレイトフル・デッドにマーケティングを学ぶ』って書名通りの本。異端ロックバンドの”稼ぎ方”
日本ではあまり知られていないが、熱狂的なファンを持つロックバンド「グレイトフル・デッド」。彼らは50年も前から、現代では当たり前となった手法を続け、今でも年間5000万ドルを稼いでいる。『グレイトフル・デッドにマーケティングを学ぶ』で「ファンからの愛され方」を学ぶ
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『流浪の月』を観て感じた、「『見て分かること』にしか反応できない世界」への気持ち悪さ
私は「見て分かること」に”しか”反応できない世界に日々苛立ちを覚えている。そういう社会だからこそ、映画『流浪の月』で描かれる文と更紗の関係も「気持ち悪い」と断罪されるのだ。私はむしろ、どうしようもなく文と更紗の関係を「羨ましい」と感じてしまう。
あわせて読みたい
【正義】復讐なんかに意味はない。それでも「この復讐は正しいかもしれない」と思わされる映画:『プロ…
私は基本的に「復讐」を許容できないが、『プロミシング・ヤング・ウーマン』の主人公キャシーの行動は正当化したい。法を犯す明らかにイカれた言動なのだが、その動機は一考の余地がある。何も考えずキャシーを非難していると、矢が自分の方に飛んでくる、恐ろしい作品
あわせて読みたい
【凄絶】北朝鮮の”真実”を描くアニメ映画。強制収容所から決死の脱出を試みた者が語る驚愕の実態:『ト…
在日コリアン4世の監督が、北朝鮮脱北者への取材を元に作り上げた壮絶なアニメ映画『トゥルーノース』は、私たちがあまりに恐ろしい世界と地続きに生きていることを思い知らせてくれる。最低最悪の絶望を前に、人間はどれだけ悪虐になれてしまうのか、そしていかに優しさを発揮できるのか。
あわせて読みたい
【勇敢】ユダヤ人を救った杉原千畝を描く映画。日本政府の方針に反しながら信念を貫いた男の生き様
日本政府の方針に逆らってまでユダヤ人のためにビザを発給し続けた外交官を描く映画『杉原千畝』。日本を良くしたいと考えてモスクワを夢見た青年は、何故キャリアを捨てる覚悟で「命のビザ」を発給したのか。困難な状況を前に、いかに決断するかを考えさせられる
あわせて読みたい
【生きる】しんどい人生を宿命付けられた子どもはどう生きるべき?格差社会・いじめ・恋愛を詰め込んだ…
厳しい受験戦争、壮絶な格差社会、残忍ないじめ……中国の社会問題をこれでもかと詰め込み、重苦しさもありながら「ボーイ・ミーツ・ガール」の爽やかさも融合されている映画『少年の君』。辛い境遇の中で、「すべてが最悪な選択肢」と向き合う少年少女の姿に心打たれる
あわせて読みたい
【驚異】信念を貫く勇敢さを、「銃を持たずに戦場に立つ」という形で示した実在の兵士の凄まじさ:映画…
第二次世界大戦で最も過酷な戦場の1つと言われた「前田高地(ハクソー・リッジ)」を、銃を持たずに駆け回り信じがたい功績を残した衛生兵がいた。実在の人物をモデルにした映画『ハクソー・リッジ』から、「戦争の悲惨さ」だけでなく、「信念を貫くことの大事さ」を学ぶ
あわせて読みたい
【実話】権力の濫用を監視するマスコミが「教会の暗部」を暴く映画『スポットライト』が現代社会を斬る
地方紙である「ボストン・グローブ紙」は、数多くの神父が長年に渡り子どもに対して性的虐待を行い、その事実を教会全体で隠蔽していたという衝撃の事実を明らかにした。彼らの奮闘の実話を映画化した『スポットライト』から、「権力の監視」の重要性を改めて理解する
あわせて読みたい
【実話】映画『イミテーションゲーム』が描くエニグマ解読のドラマと悲劇、天才チューリングの不遇の死
映画『イミテーションゲーム』が描く衝撃の実話。「解読不可能」とまで言われた最強の暗号機エニグマを打ち破ったのはなんと、コンピューターの基本原理を生み出した天才数学者アラン・チューリングだった。暗号解読を実現させた驚きのプロセスと、1400万人以上を救ったとされながら偏見により自殺した不遇の人生を知る
あわせて読みたい
【実話】障害者との接し方を考えさせる映画『こんな夜更けにバナナかよ』から”対等な関係”の大事さを知る
「障害者だから◯◯だ」という決まりきった捉え方をどうしてもしてしまいがちですが、『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』の主人公・鹿野靖明の生き様を知れば、少しは考え方が変わるかもしれません。筋ジストロフィーのまま病院・家族から離れて“自活”する決断をした驚異の人生
あわせて読みたい
【情熱】映画『パッドマン』から、女性への偏見が色濃く残る現実と、それを打ち破ったパワーを知る
「生理は語ることすらタブー」という、21世紀とは思えない偏見が残るインドで、灰や汚れた布を使って経血を処理する妻のために「安価な生理用ナプキン」の開発に挑んだ実在の人物をモデルにした映画『パッドマン 5億人の女性を救った男』から、「どう生きたいか」を考える
あわせて読みたい
【告発】アメリカに”監視”される社会を暴露したスノーデンの苦悩と決断を映し出す映画:『スノーデン』…
NSA(アメリカ国家安全保障局)の最高機密にまでアクセスできたエドワード・スノーデンは、その機密情報を持ち出し内部告発を行った。「アメリカは世界中の通信を傍受している」と。『シチズンフォー』と『スノーデン』の2作品から、彼の告発内容とその葛藤を知る
あわせて読みたい
【史実】太平洋戦争末期に原爆を落としたアメリカは、なぜ終戦後比較的穏やかな占領政策を取ったか?:…
『八月十五日に吹く風』は小説だが、史実を基にした作品だ。本作では、「終戦直前に原爆を落としながら、なぜ比較的平穏な占領政策を行ったか?」の疑問が解き明かされる。『源氏物語』との出会いで日本を愛するようになった「ロナルド・リーン(仮名)」の知られざる奮闘を知る
あわせて読みたい
【誠実】想像を超える辛い経験を言葉にするのは不可能だ。それを分かってなお筆を執った作家の震災記:…
旅行者として東日本大震災で被災した小説家・彩瀬まるは、『暗い夜、星を数えて 3.11被災鉄道からの脱出』でその体験を語る。「そんなこと、言わなければ分からない」と感じるような感情も包み隠さず記し、「絶望的な伝わらなさ」を感じながらも伝えようと奮闘する1冊
あわせて読みたい
【助けて】息苦しい世の中に生きていて、人知れず「傷」を抱えていることを誰か知ってほしいのです:『…
元気で明るくて楽しそうな人ほど「傷」を抱えている。そんな人をたくさん見てきた。様々な理由から「傷」を表に出せない人がいる世の中で、『包帯クラブ』が提示する「見えない傷に包帯を巻く」という具体的な行動は、気休め以上の効果をもたらすかもしれない
あわせて読みたい
【称賛】生き様がかっこいい。ムンバイのホテルのテロ事件で宿泊客を守り抜いたスタッフたち:映画『ホ…
インドの高級ホテルで実際に起こったテロ事件を元にした映画『ホテル・ムンバイ』。恐ろしいほどの臨場感で、当時の恐怖を観客に体感させる映画であり、だからこそ余計に、「逃げる選択」もできたホテルスタッフたちが自らの意思で残り、宿泊を助けた事実に感銘を受ける
あわせて読みたい
【情熱】「ルール」は守るため”だけ”に存在するのか?正義を実現するための「ルール」のあり方は?:映…
「ルールは守らなければならない」というのは大前提だが、常に例外は存在する。どれほど重度の自閉症患者でも断らない無許可の施設で、情熱を持って問題に対処する主人公を描く映画『スペシャルズ!』から、「ルールのあるべき姿」を考える
あわせて読みたい
【幻想】心の傷を癒やすことの”難しさ”、寄り添い続けるために必要な”弱さ”と”冷たさ”:映画『心の傷を…
「優しいかどうか」が重要な要素として語られる場面が多いと感じるが、私は「優しさ」そのものにはさしたる意味はないと考えている。映画『心の傷を癒すということ 劇場版』から、「献身」と「優しさ」の違いと、誰かに寄り添うために必要な「弱さ」を理解する
あわせて読みたい
【衝撃】壮絶な戦争映画。最愛の娘を「産んで後悔している」と呟く母らは、正義のために戦場に留まる:…
こんな映画、二度と存在し得ないのではないかと感じるほど衝撃を受けた『娘は戦場で生まれた』。母であり革命家でもあるジャーナリストは、爆撃の続くシリアの街を記録し続け、同じ街で娘を産み育てた。「知らなかった」で済ませていい現実じゃない。
あわせて読みたい
【異常】「助けて」と言えない。自己責任社会のしんどさと、我が子がホームレスである可能性:『助けて…
39歳で餓死した男性は、何故誰にも助けを求めなかったのか?異常な視聴率を叩き出した、NHK「クローズアップ現代」の特集を元に書かれた『助けてと言えない』をベースに、「自己責任社会」の厳しさと、若者が置かれている現実について書く。
ルシルナ
苦しい・しんどい【本・映画の感想】 | ルシルナ
生きていると、しんどい・悲しいと感じることも多いでしょう。私も、世の中の「当たり前」に馴染めなかったり、みんなが普通にできることが上手くやれずに苦しい思いをする…
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…

































































































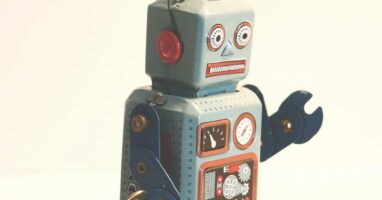
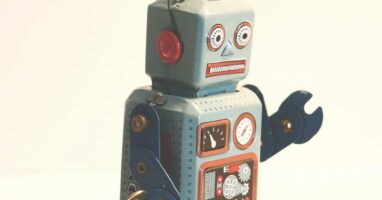






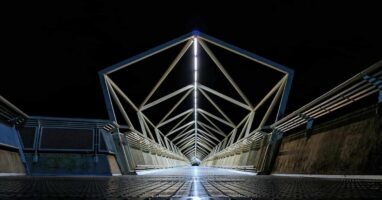
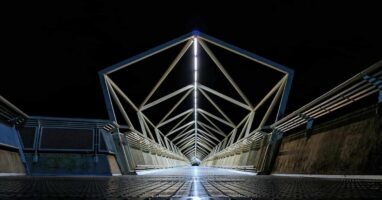


















































































































































































コメント