目次
はじめに
この記事で取り上げる映画
出演:エンニオ・モリコーネ, 出演:クエンティン・タランティーノ, 出演:クリント・イーストウッド, 出演:ウォン・カーウァイ, 出演:オリバー・ストーン, 出演:ハンス・ジマー, 出演:ジョン・ウィリアムズ, 出演:ブルース・スプリングスティーン, 出演:クインシー・ジョーンズ, 監督:ジュゼッペ・トルナトーレ
¥2,500 (2023/12/16 18:45時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
この映画をガイドにしながら記事を書いていきます
この記事の3つの要点
- 88歳でアカデミー賞作曲賞を受賞したほど、死の間際まで圧倒的な創造性を発揮し続けた天才
- 監督よりも作品に必要な曲を理解し、「まさにそれしかない」と感じさせる曲を生み出してしまう凄まじさ
- 楽器を一切使わず、紙とペンだけで作曲を行う独自のスタイルに驚かされた
エンリオ・モリコーネがいなかったら間違いなく、「映画音楽」の世界は今ほど芳醇なものにはなっていなかっただろう
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
記事中の引用は、映画館で取ったメモを参考にしているので、正確なものではありません
映画音楽に、そして音楽そのものに革新をもたらし続けた天才作曲家モリコーネの創造力に満ちた生涯を描く映画『モリコーネ』
エンリオ・モリコーネという稀代の映画音楽作曲家に対する凄まじい評価

映画『モリコーネ 映画が恋した音楽家』は、数多くの名作映画に「これしかない」という曲をあてがい続けた天才作曲家エンリオ・モリコーネについて、様々な角度から語るドキュメンタリー映画である。私は彼の存在についてこの映画を観て初めて知ったが、とにかく凄まじい人物だったようだ。作中では、数多くの人たちが彼のことを多様な表現で評価していた。
あわせて読みたい
【革新】映画音楽における唯一のルールは「ルールなど無い」だ。”異次元の音”を生み出す天才を追う:映…
「無声映画」から始まった映画業界で、音楽の重要性はいかに認識されたのか?『JAWS』の印象的な音楽を生み出した天才は、映画音楽に何をもたらしたのか?様々な映画の実際の映像を組み込みながら、「映画音楽」の世界を深堀りする映画『すばらしき映画音楽たち』で、異才たちの「創作」に触れる
あらゆるルールにおける偉大なる例外。
私にとっての羅針盤。
音楽の未来を決めた。
伝説の人。
彼との仕事は勲章だ。
あわせて読みたい
【天才】タランティーノ作品ほぼ未見で観た面白ドキュメンタリー。映画に愛された映画オタクのリアル
『パルプ・フィクション』しか監督作品を観たことがないまま、本作『クエンティン・タランティーノ 映画に愛された男』を観たが、とても面白いドキュメンタリー映画だった。とにかく「撮影現場に笑いが絶えない」ようで、そんな魅力的なモノづくりに関わる者たちの証言から、天才の姿が浮かび上がる
また、『殺人捜査』という映画について言及していた人物は、モリコーネのことをこんな風に語る。
「映画音楽」というフォーマットを生み出した。
「映画音楽」の発明者。
「『映画音楽』というフォーマットを生み出した」というのは、凄まじい功績だと感じられた。
さて、私は、映画音楽の世界についてほとんど何も知らないものの、映画音楽の制作で有名な「ハンス・ジマー」の名前ぐらいは知っている。そして彼も映画に登場し、
彼のことを知らない作曲家は存在しない。
と言っていた。彼のこの評価だけでも、モリコーネの凄さが実感できるだろう。
あわせて読みたい
【諦め】「人間が創作すること」に意味はあるか?AI社会で問われる、「創作の悩み」以前の問題:『電気…
AIが個人の好みに合わせて作曲してくれる世界に、「作曲家」の存在価値はあるだろうか?我々がもうすぐ経験するだろう近未来を描く『電気じかけのクジラは歌う』をベースに、「創作の世界に足を踏み入れるべきか」という問いに直面せざるを得ない現実を考える
驚異的なのは、モリコーネが「単に音楽を生み出す」だけではない才能を有していたことだ。映画に登場したある監督は、このように語っていた。
困ったことに、監督や編集者よりもずっと、その場面に相応しい音楽を直感的に理解してしまう。そして、音楽を聴くと、彼のものだと分かる。

映画については普通、監督がその全体像について最も把握しているはずだろう。しかしこと音楽に関して言えば、モリコーネは「そのシーンに必要な音楽を監督よりも深く理解し、それを的確に表現する音楽を生み出してしまう」のだ。単に「作るだけ」ではなく、「想像もしてみなかったけれど、嵌めてみると『それしかない!』と感じるような音楽を生み出し続けてきた」のである。
あわせて読みたい
【表現者】「センスが良い」という言葉に逃げない。自分の内側から何かを表現することの本質:『作詞少…
大前提として、表現には「技術」が必要だ。しかし、「技術」だけでは乗り越えられない部分も当然ある。それを「あいつはセンスが良いから」という言葉に逃げずに、向き合ってぶつかっていくための心得とは何か。『作詞少女』をベースに「表現することの本質」を探る
本作はそんな、とにかく「凄まじい」としか表現しようのない人物についてのドキュメンタリー映画というわけだ。
モリコーネが生み出した音楽のとてつもなさ
映画『モリコーネ』では、モリコーネが劇中音楽を担当した名作映画の実際の映像と共にその音楽が流れる。彼が生み出した曲は、ある意味で「現代映画のスタンダード」になっているわけで、その「新鮮さ」を感じ取るのは難しいかもしれないと想像していたのだが、まったくそんなことはなかった。例えば、映画『荒野の用心棒』の冒頭、それまでの西部劇の常識を覆した音楽などは、今聴いてもやはり「新しさ」と感じさせるものだったと思う。
あわせて読みたい
【奇跡】鈴木敏夫が2人の天才、高畑勲と宮崎駿を語る。ジブリの誕生から驚きの創作秘話まで:『天才の思…
徳間書店から成り行きでジブリ入りすることになったプロデューサー・鈴木敏夫が、宮崎駿・高畑勲という2人の天才と共に作り上げたジブリ作品とその背景を語り尽くす『天才の思考 高畑勲と宮崎駿』。日本のアニメ界のトップランナーたちの軌跡の奇跡を知る
その中でも、彼の凄まじさを最も感じさせられた場面がある。先ほど少し名前を出した、1970年公開の映画『殺人捜査』に関するものだ。映画で語られていた、『殺人捜査』の劇中音楽の作曲依頼に関する細かな状況はちょっと忘れてしまったのだが、この映画では監督は何故か、モリコーネに作曲を依頼しつつも、映画冒頭では既存の曲を使おうとしていたそうだ。しかし実際には、冒頭でもモリコーネ作曲のものが使われることになった。
というわけで映画『モリコーネ』では、当初の案だった既存曲バージョンと、モリコーネの作曲曲バージョンとで、同じ冒頭の場面を2パターン流すという演出がなされる。そして、まさにその差は「圧倒的」だったと言っていい。
音楽について言語化するのは得意ではないのだが、頑張ってみよう。既存曲バージョンの方からは、「単なる不穏さ」しか感じられなかった。一方、モリコーネ作曲曲の方は、「跳ねるような、どこか陽気さを感じさせるリズムの中に、どことなく不穏な空気が宿っている」みたいな雰囲気になる。これだけでも、これから映画が始まるという状況において、観客が抱く印象はまったく違ったものになるはずだと思う。
あわせて読みたい
【創作】クリエイターになりたい人は必読。ジブリに見習い入社した川上量生が語るコンテンツの本質:『…
ドワンゴの会長職に就きながら、ジブリに「見習い」として入社した川上量生が、様々なクリエイターの仕事に触れ、色んな質問をぶつけることで、「コンテンツとは何か」を考える『コンテンツの秘密』から、「創作」という営みの本質や、「クリエイター」の理屈を学ぶ
さらに凄かったのは、モリコーネの作曲曲の方がとにかく「キャッチー」なことだ。映画音楽なのだから、「あてがわれたシーンにピタッと嵌まっている」ことは当然だろうが、決してそれだけではなく、その曲単体で取り出してみても十分インパクトがあると感じたのである。もちろん、本来は「映画の効果を高めるための付属物」であり、それ自体が目立った存在感を持つべきものではない。実際、モリコーネの作曲曲は、冒頭のシーンと合わせた場合には、映像とバチッと合いながら決して主張しすぎないという絶妙な存在感を保っている。ただし、映像から切り離して曲だけを聴いた場合には圧倒的な存在感を放っており、曲単体でも十分に成立するだけの強さを有していたのだ。音楽についてはまったく詳しくないが、そんな私でも、これはかなり難易度の高いことではないかと感じさせられた。
さて、映画に登場する人物がこんなことを言う場面がある。
彼がいなかったら、21世紀の音楽はまったく違うものになっていたはずだ。

ここで注目すべきは「21世紀の音楽」という表現である。「21世紀の映画音楽」ではないことに注意してほしい。モリコーネは、ほぼ映画音楽の世界でそのキャリアを終えた人物であり、確かにそこで比類なき成果を残した。しかし彼は、映画音楽のみならず、音楽の世界にも多大なる影響を与えていたというのだ。映画の中では、「映画音楽」と対比させる形で「絶対音楽」という表現が使われていたが、そんな「絶対音楽」にも彼の功績が届いていたのである。
あわせて読みたい
【驚嘆】映画『TAR/ター』のリディア・ターと、彼女を演じたケイト・ブランシェットの凄まじさ
天才女性指揮者リディア・ターを強烈に描き出す映画『TAR/ター』は、とんでもない作品だ。「縦軸」としてのターの存在感があまりにも強すぎるため「横軸」を上手く捉えきれず、結果「よく分からなかった」という感想で終わったが、それでも「観て良かった」と感じるほど、揺さぶられる作品だった
「そんなバカな」と感じる人もいるかもしれないが、本作を観れば納得できるんじゃないかと思う。音楽に詳しいわけではない私には、作中での説明が完璧に理解できたとは言えないが、どうやらモリコーネは、「映画音楽」だけではなく「絶対音楽」の「先駆者」でもあったのだそうだ。だから、1928年に生まれ、2020年に亡くなり、その生涯に渡って常に名曲を生み出し続けてきたエンリオ・モリコーネは、今も若いクリエーターを刺激し続けているのだという。映画に登場したある若いクリエーターは、
20年前よりも今の方が影響力が大きい。
とさえ言っていた。本当に、凄まじい功績を遺した人物なのである。
あわせて読みたい
【感想】湯浅政明監督アニメ映画『犬王』は、実在した能楽師を”異形”として描くスペクタクル平家物語
観るつもりなし、期待値ゼロ、事前情報ほぼ皆無の状態で観た映画『犬王』(湯浅政明監督)はあまりにも凄まじく、私はこんなとんでもない傑作を見逃すところだったのかと驚愕させられた。原作の古川日出男が紡ぐ狂気の世界観に、リアルな「ライブ感」が加わった、素晴らしすぎる「音楽映画」
セルジオ・レオーネとの不可分のタッグ
確か、映画『ワンス・アポン・ア・タイムイン・アメリカ』についての話題だったと思うが、誰もが口を揃えて、「あの映画は、モリコーネの音楽が無ければ成立しない」と語っていたのが印象的だった。つまり、彼の音楽は単なる「サウンドトラック」ではなく、「映画表現の1つの要素」なのである。そして何にも増して重要なのは、「映画音楽にはそのような力があるのだ」と、そのキャリアにおいて証明し続けたことだろう。
そんな『ワンス・アポン・ア・タイムイン・アメリカ』を監督したセルジオ・レオーネは、生涯モリコーネと不可分のタッグを組んだのだそうだ。その出会いのエピソードがなかなかに興味深い。初めてレオーネがモリコーネに映画音楽制作を依頼した際、モリコーネは「どこかで見た顔だ」と感じたというのだ。そう、なんと彼らは、小学校時代の同級生だったのである。偶然にしては出来すぎと言えるだろう。そんな縁もあり、彼らは「映画監督」「映画音楽作曲家」として、その生涯を伴走するのである。映画に登場したレオーネの娘が、
父は彼の音楽に頼っていた。
とはっきり口にしていたのが印象的だった。
あわせて読みたい
【評価】のん(能年玲奈)の映画『Ribbon』が描く、コロナ禍において「生きる糧」が芸術であることの葛藤
のん(能年玲奈)脚本・監督・主演の映画『Ribbon』。とても好きな作品だった。単に女優・のんが素晴らしいというだけではなく、コロナ禍によって炙り出された「生きていくのに必要なもの」の違いに焦点を当て、「魂を生き延びさせる行為」が制約される現実を切り取る感じが見事
モリコーネはその生涯で様々な映画監督と仕事をしたのだが、やはりレオーネとのエピソードがとても興味深い。映画『ワンス・アポン・ア・タイムイン・アメリカ』の場合は、撮影が始まる何年も前から作曲を依頼されていたという。またレオーネはモリコーネに、「リジェクトされた曲も聴かせてくれ」とよく言っていたそうだ。いくらモリコーネといえども、常に1案のみで提案が通るわけではない。だから、他の映画用に作曲したものの、実際には使われなかった曲がたくさんあるのだ。そしてそれらが、レオーネの映画で復活することもあったという。

あるいは、レオーネは「映画の全編でパンフルートを使いたい」と相談したことがある。しかしモリコーネは、「適切な場面で使う」と、「全編で使いたい」というレオーネの提案を却下した。そして見事、パンフルートの存在感が際立つ印象的な場面を作り上げてみせたのだ。
そんなレオーネとのエピソードの中で一番印象的だったのが、「撮影現場でもモリコーネの曲を流す」という話。つまりこれは、「役者のセリフを現場では録らない」ことを意味する。今でこそこのようなやり方がされることも多いのかもしれないが、当時としては「クレイジー」な手法だったそうだ。しかし、現場にモリコーネの音楽を流すことで、「そこに既に『映画』が存在しているかのような雰囲気」が生み出され、それが映画制作に多大な影響を与えることになったという。ロバート・デ・ニーロは、現場での録音にこだわる役者として有名だそうだが、そんな彼でさえ、
モリコーネの音楽が演技の役に立った。
と、レオーネの手法を称賛していたというのだから凄い話である。
あわせて読みたい
【革新】天才マルタン・マルジェラの現在。顔出しNGでデザイナーの頂点に立った男の”素声”:映画『マル…
「マルタン・マルジェラ」というデザイナーもそのブランドのことも私は知らなかったが、そんなファッション音痴でも興味深く観ることができた映画『マルジェラが語る”マルタン・マルジェラ”』は、生涯顔出しせずにトップに上り詰めた天才の来歴と現在地が語られる
ただ、そんな盟友とえるレオーネとも、仕事をし始めた当初はなかなか上手くいかなかったそうだ。最初の何作かは思い通りに出来なかったと、その苦悩を語っていた。しかし最終的には強力なタッグになるわけで、それは音楽のセールスにも現れている。モリコーネは、レオーネの映画用に作曲した曲を収録したレコードで、2度もベストセールスを記録しているのだ。イタリアのレコード史において、これは異例の快挙であると紹介されていた。まさに完璧なコンビだったと言っていいと思う。
紙とペンだけで作曲するという異次元の作曲家
さて、少し突拍子もない話をしよう。私は映画を観ながら、インドの天才数学者ラマヌジャンのことを連想していた。
彼は、その常軌を逸した様々なエピソードで知られた人物であり、数学に詳しくない人でも、もしかしたらどこかで彼の名前を耳にしたことがあるかもしれない。ラマヌジャンは、高等教育を受けたことがなく、当然数学についてもほとんど学んだことがない。にも拘らず、あまりにも難解で複雑怪奇な数式を数多残しているのである。それらは「ラマヌジャン 数式」で検索すれば色々と出てくるので眺めてみてほしい。
あわせて読みたい
【奇人】天才数学者で、自宅を持たずに世界中を放浪した変人エルデシュは、迷惑な存在でも愛され続けた…
数学史上ガウスに次いで生涯発表論文数が多い天才エルデシュをご存知だろうか?数学者としてずば抜けた才能を発揮したが、それ以上に「奇人変人」としても知られる人物だ。『放浪の天才数学者エルデシュ』で、世界中の数学者の家を泊まり歩いた異端数学者の生涯を描き出す
しかし、「数学を学んだことがないのに、どうしてそのような数式を生み出せたのか」と疑問に感じないだろうか? その理由はなんと、「夢の中に神様が出てきて、数式を教えてくれるから」なのである。夢で見た数式をひたすら紙に書き続けただけというわけだ。だから彼自身は、自ら書き写した数式の正しさを証明することが出来なかった。しかし、別の数学者がそれらに挑み、そのほとんどが正しいと証明されている。
しかし何故ラマヌジャンを連想したのか。それはモリコーネの驚くべき作曲法にある。なんと彼は「五線譜」と「ペン」だけを使って作曲するというのだ。つまり、一切の楽器を使用しないのである。恐らく頭の中で音楽が鳴っており、それを書き写すようにして作曲しているのだと思う。

あわせて読みたい
【おすすめ】「天才」を描くのは難しい。そんな無謀な挑戦を成し遂げた天才・野崎まどの『know』はヤバい
「物語で『天才』を描くこと」は非常に難しい。「理解できない」と「理解できる」を絶妙なバランスで成り立たせる必要があるからだ。そんな難題を高いレベルでクリアしている野崎まど『know』は、異次元の小説である。世界を一変させた天才を描き、「天才が見ている世界」を垣間見せてくれる
このスタイルだけでも、多くの作曲家にとっては信じがたいものだろう。さらにその上で音楽家を驚かせるのは、モリコーネの楽譜があまりにも整然として見やすいことだそうだ。恐らくだが、そんな楽譜を書き直しなしの一発書きで生み出せてしまうのだと思う。そしてそれが、まさに映画の各シーンに絶妙に嵌まるものになっているというわけだ。
本当に、天才としか言いようがないだろう。
あわせて読みたい
【価値】レコードなどの「フィジカルメディア」が復権する今、映画『アザー・ミュージック』は必見だ
2016年に閉店した伝説のレコード店に密着するドキュメンタリー映画『アザー・ミュージック』は、「フィジカルメディアの衰退」を象徴的に映し出す。ただ私は、「デジタル的なもの」に駆逐されていく世の中において、「『制約』にこそ価値がある」と考えているのだが、若者の意識も実は「制約」に向き始めているのではないかとも思っている
しかしやはり、ラマヌジャンと同じというわけにはいかない。彼には、当然「夢で音楽を教えてくれるような神様」はいないからだ。映画のラストで、モリコーネは次のように語っていた。
音楽を書く前に、熟考しなくてはいけない。それが問題だ。
作曲家の前には、白紙の紙がある。何も考えずに書き始めれば行き詰まる。まず思考があり、それを展開させなければ。
では何を追求する? 分からない。
モリコーネは生涯に500曲以上も映画音楽を作曲した。そしてそれらはどれも、誰も考えつかなかったようなアイデアが盛り込まれ、聴く者を驚かせ、さらに聴けばモリコーネ作だと分かる曲なのだ。ウィキペディアによると、彼が最後に映画音楽を手掛けたのが2016年、88歳の時のことだ。さらにその前年には、映画『ヘイトフル・エイト』でアカデミー賞の作曲賞を受賞している。90歳近い年齢になっても、抜群のクリエイティビティを発揮したというわけだ。ちょっと想像を絶する凄まじさと言えるのではないだろうか。
映画音楽を作曲する上での様々な困難
あわせて読みたい
【魅惑】マツコも絶賛の“日本人初のパリコレトップモデル”山口小夜子のメイクの凄さや素顔を描く映画:…
日本人初のパリコレトップモデルである山口小夜子と親交があった監督が紡ぐ映画『氷の花火 山口小夜子』は、未だ謎に包まれているその人生の一端を垣間見せてくれる作品だ。彼女を知る様々な人の記憶と、彼女を敬愛する多くの人の想いがより合って、一時代を築いた凄まじい女性の姿が浮かび上がってくる
モリコーネは、映画音楽を作曲する上での様々な苦悩についても語っている。その1つがこれだ。
映画音楽には、答えがいくつもある。これが作曲家の苦悩だ。
複数送った中で、自身が「クズ曲」だと思っていたものが採用されるなど、「自分が生み出した音楽のどこが評価されたのか」を判断するのが難しかったと彼は語っている。そんなこともあり、彼は途中から、まず妻のマリアに聴かせ、彼女が良いと言ったものを監督に聴かせるというやり方に変えたと言っていた。
しかしそれでも、予想外のことは起こる。例えば、映画『ニュー・シネマ・パラダイス』のある場面のために9曲作曲した際、彼は「6番目だけは選ばないでくれ。一番気に入っていないから」と書いて送ったそうだ。しかし最終的にはなんと、その6番目が選ばれたのだという。まさに「創作の難しさ」を実感させるエピソードと言えるだろう。
あわせて読みたい
【感想】映画『レオン』は、殺し屋マチルダを演じたナタリー・ポートマンがとにかく素晴らしい(監督:…
映画『レオン』は、その性質ゆえに物議を醸す作品であることも理解できるが、私はやはりナタリー・ポートマンに圧倒されてしまった。絶望的な事態に巻き込まれたマチルダの葛藤と、そんな少女と共に生きることになった中年男性レオンとの関係性がとても見事に映し出されている。実に素敵な作品だった

彼はずっと、映画音楽の世界から離れようと考えていたと話していた。やはり、あまりにハードな仕事なのだろう。そんな彼が、映画の終わりの方でこんな言い方をしていたのが印象的だった。
1961年、初めて映画音楽に関わった際、妻には「1970年には辞める」と伝えていた。
1970年には、「1980年には辞める」と、1980年には「1990年には辞める」と、1990年には「2000年には辞める」と言った。
もう言わない。
そして結局、亡くなる直前まで映画音楽を作り続けたのである。
あわせて読みたい
【感想】是枝裕和監督映画『怪物』(坂元裕二脚本)が抉る、「『何もしないこと』が生む加害性」
坂元裕二脚本、是枝裕和監督の映画『怪物』は、3つの視点を通して描かれる「日常の何気ない光景」に、思いがけない「加害性」が潜んでいることを炙り出す物語だ。これは間違いなく、私たち自身に関わる話であり、むしろ「自分には関係ない」と考えている人こそが自覚すべき問題だと思う
さて先ほど、2015年にアカデミー賞の作曲賞を受賞したことに触れたが、実は6度目のノミネートでの受賞だった。受賞に至るまでには、こんなエピソードがある。彼は1986年に映画『ミッション』で2度目のノミネートとなったのだが、この時は誰もがモリコーネの受賞を疑わなかったため、別の人物の受賞が発表された際、なんと会場ではブーイングが起こったのだそうだ。3度目は映画『アンタッチャブル』でのノミネートだったが、この時受賞したのは坂本龍一だった。2006年には、それまでの映画音楽に対する功績に対して「名誉賞」が与えられたのだが、その後2015年に”改めて”作曲賞を受賞したというわけだ。
モリコーネの場合、権威ある賞を受賞したかどうかなど関係なく、多くの映画人から称賛を集めているわけで、その方が価値があると私は思う。しかし外野が、「モリコーネが正当に評価されないのはおかしい」という感覚を抱くのも理解できる。ただ恐らくモリコーネ自身は、賞などにはさほど関心はなかったのではないかと思う。とにかく、求められるままに創造性豊かな曲を作り続けただけというわけだ。
ちなみに映画では、スタンリー・キューブリックとのこんなエピソードにも触れられていた。モリコーネが、「逃して惜しいと感じたのはこの映画だけ」と語っていた話だ。
あわせて読みたい
【感想】リドリー・スコット監督の映画『最後の決闘裁判』から、社会が”幻想”を共有する背景とその悲劇…
例えば、「1万円札」というただの紙切れに「価値を感じる」のは、社会の構成員が同じ「共同幻想」の中に生きているからだ。リドリー・スコット監督の映画『最後の決闘裁判』は、「強姦では妊娠しない」「裁判の勝者を決闘で決する」という社会通念と、現代にも通じる「共同幻想」の強さを描き出す
モリコーネの映画音楽を聴いたキューブリックが、映画『時計じかけのオレンジ』のために曲を作ってほしいと考えたことがある。そこでキューブリックは、映画監督のレオーネに連絡をした。モリコーネの盟友であることを知ってのことである。するとレオーネは、「モリコーネは今、私の作品の作曲中だから受けられない」と断った。それでキューブリックは作曲依頼を諦めたという。しかし実際には、作曲自体は既に終わっており、ミキシングをしていただけだったそうだ。作曲の余裕は十分あったのである。キューブリックにしてもモリコーネにしても、不運だったとしか言いようのないピソードだろう。
モリコーネは、いかにして作曲家になったのか
映画『モリコーネ』は、全体的にはとても興味深く展開される作品なのだが、冒頭の構成だけはちょっといただけなかった。というのも、映画が始まってすぐ、幼少期からの生い立ちの話が描かれるからだ。時系列順にエピソードを紡いでいくのは確かに常道ではあるのだが、やはりまずは「エンリオ・モリコーネという人物についての興味深いエピソード」から始めるべきではないかと思う。確かに、本国イタリアにおいては広く知られた存在なのだろうし、その功績についても誰もが知っているみたいな人物なのかもしれない。しかしそれにしたってやはり、幼少期の話から始めるのが正解だとは思えなかったし、冒頭からしばらくの間は、少し退屈に感じられてしまった。

あわせて読みたい
【表現】映画『名付けようのない踊り』で初めて見た田中泯のダンス。「芸術以前」を志向する圧倒的パワー
映画『名付けようのない踊り』の中で田中泯は言う。「私」や「個性」を表現することには違和感がある、と。「踊りのために身体を作る」のではなく、「野良仕事で出来た身体で踊る」のだ、と。芸術になる前の踊りを探したい、と。「唯一無二の表現者」の生涯と現在地を映し出すドキュメンタリー
モリコーネは元々、医者になりたかったそうだ。しかし父親がトランペット奏者だったこともあり、「トランペットをやれ」と音楽院に入学させられてしまう。なかなか強引な父親である。初めは楽譜も読めず、成績も平凡だったそうだが、副科として専攻していた和声のクラスで才能の片鱗が現れた。既存のルールに囚われない作曲をしていたのだ。そこに目をつけた教師が、「作曲を学べ」とアドバイスした。このアドバイスが、その後のモリコーネの人生を決定づけるものとなったのである。
当時のイタリアには、ペトラッシという著名な作曲家がおり、モリコーネは彼を師と定めることに決めた。しかしそのペトラッシも、初めのうちはモリコーネを過小評価していたという。それほど、学生時代のモリコーネは目立たない存在だったというわけだ。しかしその後、RCAというレコード会社で編曲家として頭角を表すようになる。どう活躍したのかは分からないが、映画では「倒産寸前だったRCAを救った」みたいな説明がなされていたと思う。それまでまったく無名だったにも拘らず、その才能が一気に花開いたというわけだ。
編曲の仕事と言っても様々だと思うが、モリコーネに関して映画の中で紹介されていたのが、いわゆる「イントロ」である。とにかく、モリコーネが生み出すイントロは、どれも物凄くキャッチーで魅力的なのだ。現代では、サブスクが広まったことでイントロの無い曲が増えたが、だからこそなのだろう、若者の間では、昭和の曲のイントロに惹かれるという人が出てきているという。そういう人もきっと、モリコーネが作ったイントロを好きになるんじゃないかと思う。現代でも十分通用するようなものばかりだと私は感じた。
あわせて読みたい
【伝説】やり投げ選手・溝口和洋は「思考力」が凄まじかった!「幻の世界記録」など数々の逸話を残した…
世界レベルのやり投げ選手だった溝口和洋を知っているだろうか? 私は本書『一投に賭ける』で初めてその存在を知った。他の追随を許さないほどの圧倒的なトレーニングと、常識を疑い続けるずば抜けた思考力を武器に、体格で劣る日本人ながら「幻の世界記録」を叩き出した天才の伝説と実像
また、編曲家時代に彼は、「別の音楽を引用する」という、今では割とよく使われているだろう手法も編み出したのだそうだ。本人も「編曲家時代には様々なチャレンジをした」と語っていた。モリコーネは「映画音楽を発明した」ことで名を残したわけだが、それ以前に「編曲を発明する」という挑戦にも携わっていたのである。本当に、生涯を通じて常にチャレンジし続けた、前のめりの人生だったと言っていいだろう。
しかし、今でこそ「編曲家」の名前は必ず表に出るはずだが、当時はそうではなかった。だから、RCAを立て直すほどの貢献をしながら、モリコーネの名前は広く知られてはいなかったのだ。しかしその後、小学校の同級生だったレオーネから映画音楽の依頼が舞い込んだことで、彼の新たなキャリアが始まっていく。
稀代の映画音楽家は、このようにして生まれたのである。
あわせて読みたい
【感想】映画『ローマの休日』はアン王女を演じるオードリー・ヘプバーンの美しさが際立つ名作
オードリー・ヘプバーン主演映画『ローマの休日』には驚かされた。現代の視点で観ても十分に通用する作品だからだ。まさに「不朽の名作」と言っていいだろう。シンプルな設定と王道の展開、そしてオードリー・ヘプバーンの時代を超える美しさが相まって、普通ならまずあり得ない見事なコラボレーションが見事に実現している
出演:エンニオ・モリコーネ, 出演:クエンティン・タランティーノ, 出演:クリント・イーストウッド, 出演:ウォン・カーウァイ, 出演:オリバー・ストーン, 出演:ハンス・ジマー, 出演:ジョン・ウィリアムズ, 出演:ブルース・スプリングスティーン, 出演:クインシー・ジョーンズ, 監督:ジュゼッペ・トルナトーレ
¥2,500 (2023/12/16 18:48時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品視聴済】私が観てきたドキュメンタリー映画を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が観てきたドキュメンタリー映画を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。
最後に
あわせて読みたい
【アート】「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」(森美術館)と「美術手帖 Chim↑Pom特集」の衝撃から「…
Chim↑Pomというアーティストについてさして詳しいことを知らずに観に行った、森美術館の「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」に、思考をドバドバと刺激されまくったので、Chim↑Pomが特集された「美術手帖」も慌てて買い、Chim↑Pomについてメッチャ考えてみた
意外と言っていいと思うが、モリコーネは、
映画音楽を作ることを、当初は「屈辱」だと感じていた。
と語っている。
あわせて読みたい
【情熱】選挙のおもしろ候補者含め”全員取材”をマイルールにする畠山理仁の異常な日常を描く映画:『NO …
選挙に取り憑かれた男・畠山理仁を追うドキュメンタリー映画『NO 選挙, NO LIFE』は、「平均睡眠時間2時間」の生活を長年続ける”イカれた”ライターの「選挙愛」が滲み出る作品だ。「候補者全員を取材しなければ記事にはしない」という厳しすぎるマイルールと、彼が惹かれる「泡沫候補」たちが実に興味深い
とはいえ、この発言を「意外」に感じるということは、映画音楽の世界が今では高く評価されていることを意味するはずだ。そしてそれはつまるところ、モリコーネ自身の努力によるものと言えるだろう。「屈辱」と感じるほどに低い地位に甘んじていた映画音楽の世界を、たった1人で(とは言い過ぎかもしれないが)革新させ、その類まれな才能をフルに発揮してとんでもない高みにまで押し上げたのだ。モリコーネは今では、
映画音楽も本格的な音楽だと考え直すようになった。
と考えを改めている。
あわせて読みたい
【対立】パレスチナとイスラエルの「音楽の架け橋」は実在する。映画『クレッシェンド』が描く奇跡の楽団
イスラエルとパレスチナの対立を背景に描く映画『クレッシェンド』は、ストーリーそのものは実話ではないものの、映画の中心となる「パレスチナ人・イスラエル人混合の管弦楽団」は実在する。私たちが生きる世界に残る様々な対立について、その「改善」の可能性を示唆する作品

モリコーネのこの心境の変化は、同時代の他の作曲家の気持ちの変化とも比例していると言っていいだろう。というのも、前時代の作曲家たちは、「クラシックこそ偉大」という世界の中で生きてきたからだ。それ故にモリコーネは、「クラシック信者」とでも言うべき作曲家たちから、まったく才能が認められなかったという。
しかしモリコーネのあまりに創造的な仕事を長年目の当たりにして、彼らもついに頭を垂れた。モリコーネの作曲家としての才能を認めざるを得なくなったのである。
あわせて読みたい
【映画】『キャスティング・ディレクター』の歴史を作り、ハリウッド映画俳優の運命を変えた女性の奮闘
映画『キャスティング・ディレクター』は、ハリウッドで伝説とされるマリオン・ドハティを描き出すドキュメンタリー。「神業」「芸術」とも評される配役を行ってきたにも拘わらず、長く評価されずにいた彼女の不遇の歴史や、再び「キャスティングの暗黒期」に入ってしまった現在のハリウッドなどを切り取っていく
このようにモリコーネは、その凄まじい才能と努力によって、「映画音楽」というジャンルそのものを更新したと言っていいだろう。私たちが今、豊かな「映画音楽」の世界に触れられるのは、まさしく彼のお陰なのである。
ホントに、凄い人物がいたものだと思う。
あわせて読みたい
【食&芸術】死んでも車を運転したくない人間の香川うどん巡り& 豊島アート巡りの旅ルート(山越うどん…
仕事終わりの木曜日夜から日曜日に掛けて、「香川のうどん巡り」と「豊島のアート巡り」をしてきました。うどんだけでも7580円分食べたので、かなりの軒数を回ったことになります。しかも「死んでも車を運転したくない」ため、可能な限り公共交通機関のみで移動しました。私と同じように「車を運転したくない人」には、かなり参考になる記事と言えるのではないかと思います
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!「文章の書き方が分からない」「文章力がないから鍛えたい」という方にオススメ…
「文章の書き方」についてのKindle本を出版しました。「文章が書けない」「どう書いたらいいか分からない」「文章力を向上させたい」という方の悩みを解消できるような本に仕上げたつもりです。数多くの文章を書き、さらに頼まれて文章を推敲してきた経験を踏まえ、「文章を書けるようになるにはどうしたらいいか」についての私なりの考えをまとめました。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
金沢&富山のアート旅!「21世紀美術館」だけじゃない激アツなおすすめ美術館巡りをご提案
金沢・富山を巡るアート旅に出かけてきました!メインの目的は「21世紀美術館」でしたが、それ以上に「ASTER Curator Museum」「LIP BAR」「KAMU kanazawa」などがとにかく素晴らしかったです。アートや美術のことはド素人ですが、超個人的主観で「金沢・富山で触れられるアートの良さ」について書いた旅行記となります
あわせて読みたい
【感動】映画『ボストン1947』は、アメリカ駐留時代の朝鮮がマラソンで奇跡を起こした実話を描く
映画『ボストン1947』は、アメリカ軍駐留時代の朝鮮を舞台に、様々な困難を乗り越えながらボストンマラソン出場を目指す者たちの奮闘を描き出す物語。日本統治下で日本人としてメダルを授与された”国民の英雄”ソン・ギジョンを中心に、「東洋の小国の奇跡」と評された驚くべき成果を実現させた者たちの努力と葛藤の実話である
あわせて読みたい
【感想】高倍率のやばい藝大入試に挑む映画『ブルーピリオド』は「生きてる実感の無さ」をぶち壊す(監…
映画『ブルーピリオド』は、大学入試で最高倍率とも言われる200倍の試験に挑む高校生たちの物語。東京藝術大学絵画科という果てしない最難関に、高校2年生から突然挑戦すると決めた矢口八虎を中心に、「『好き』に囚われた者たち」の果てしない情熱と葛藤を描き出す。絵を描くシーンを吹き替えなしで行った役者の演技にも注目だ
あわせて読みたい
【映画】ディオールのデザイナーだった天才ジョン・ガリアーノが差別発言で破滅した人生を語る:映画『…
何者なのかまったく知らない状態で観たドキュメンタリー映画『ジョン・ガリアーノ 世界一愚かな天才デザイナー』は、差別発言によって失墜しすべてを失った天才デザイナーの凄まじい来歴が描かれる作品だ。実に複雑で興味深い存在だったし、その波乱の人生は、私のようなファッションに疎い人間でも面白く感じられると思う
あわせて読みたい
【才能】映画『トノバン』が描く、「日本の音楽史を変えた先駆者・加藤和彦」のセンス良すぎる人生(「♪…
「♪おらは死んじまっただ~」が印象的な『帰って来たヨッパライ』で知られる加藤和彦の才能と魅力を余す所なく映し出すドキュメンタリー映画『トノバン』を観て、まったく知らなかった人物の凄まじい存在感に圧倒されてしまった。50年以上も前の人だが、音楽性や佇まいなどを含め、現代でも通用するだろうと思わせる雰囲気が凄まじい
あわせて読みたい
【感想】映画『ルックバック』の衝撃。創作における衝動・葛藤・苦悩が鮮やかに詰め込まれた傑作(原作…
アニメ映画『ルックバック』は、たった58分の、しかもセリフも動きも相当に抑制された「静」の映画とは思えない深い感動をもたらす作品だった。漫画を描くことに情熱を燃やす2人の小学生が出会ったことで駆動する物語は、「『創作』に限らず、何かに全力で立ち向かったことがあるすべての人」の心を突き刺していくはずだ
あわせて読みたい
【悲劇】映画『プリンセス・ダイアナ』『スペンサー』で知る、その凄まじい存在感と王室の窮屈さ
ドキュメンタリー映画『プリンセス・ダイアナ』と映画『スペンサー』は、衝撃的な死を遂げたダイアナ妃の生涯を対照的な形で描き出す作品だ。「過去映像のみ」で構成される非常に挑戦的な『プリンセス・ダイアナ』と、「王室との不和」を正面から描き出す『スペンサー』の2作によって、彼女が歩んだ壮絶な人生が浮き彫りにされる
あわせて読みたい
【正義】ナン・ゴールディンの”覚悟”を映し出す映画『美と殺戮のすべて』が描く衝撃の薬害事件
映画『美と殺戮のすべて』は、写真家ナン・ゴールディンの凄まじい闘いが映し出されるドキュメンタリー映画である。ターゲットとなるのは、美術界にその名を轟かすサックラー家。なんと、彼らが創業した製薬会社で製造された処方薬によって、アメリカでは既に50万人が死亡しているのだ。そんな異次元の薬害事件が扱われる驚くべき作品
あわせて読みたい
【実話】さかなクンの若い頃を描く映画『さかなのこ』(沖田修一)は子育ての悩みを吹き飛ばす快作(主…
映画『さかなのこ』は、兎にも角にものん(能年玲奈)を主演に据えたことが圧倒的に正解すぎる作品でした。性別が違うのに、「さかなクンを演じられるのはのんしかいない!」と感じさせるほどのハマり役で、この配役を考えた人は天才だと思います。「母親からの全肯定」を濃密に描き出す、子どもと関わるすべての人に観てほしい作品です
あわせて読みたい
【現在】猟師になった東出昌大を追う映画『WILL』は予想外に良かった。山小屋での生活は衝撃だ(監督:…
猟師・東出昌大に密着した映画『WILL』は、思いがけず面白い作品だった。正直、東出昌大にはまったく興味がなく、本作も期待せず観たのだが、異常なほどフラットなスタンス故に周囲にいる人間を否応なく惹きつける「人間力」や、狩猟の世界が突きつける「生と死」というテーマなど実に興味深い。本当に観て良かったなと思う
あわせて読みたい
【憧憬】「フランク・ザッパ」を知らずに映画『ZAPPA』を観て、「この生き様は最高」だと感じた
「フランク・ザッパ」がミュージシャンであることさえ禄に知らない状態で私が映画『ZAPPA』を観た私は、そのあまりに特異なスタンス・生き様にある種の憧憬を抱かされた。貫きたいと思う強い欲求を真っ直ぐ突き進んだそのシンプルな人生に、とにかくグッときたのだ。さらに、こんな凄い人物を知らなかった自分にも驚かされてしまった
あわせて読みたい
【価値】レコードなどの「フィジカルメディア」が復権する今、映画『アザー・ミュージック』は必見だ
2016年に閉店した伝説のレコード店に密着するドキュメンタリー映画『アザー・ミュージック』は、「フィジカルメディアの衰退」を象徴的に映し出す。ただ私は、「デジタル的なもの」に駆逐されていく世の中において、「『制約』にこそ価値がある」と考えているのだが、若者の意識も実は「制約」に向き始めているのではないかとも思っている
あわせて読みたい
【情熱】選挙のおもしろ候補者含め”全員取材”をマイルールにする畠山理仁の異常な日常を描く映画:『NO …
選挙に取り憑かれた男・畠山理仁を追うドキュメンタリー映画『NO 選挙, NO LIFE』は、「平均睡眠時間2時間」の生活を長年続ける”イカれた”ライターの「選挙愛」が滲み出る作品だ。「候補者全員を取材しなければ記事にはしない」という厳しすぎるマイルールと、彼が惹かれる「泡沫候補」たちが実に興味深い
あわせて読みたい
【感想】映画『レオン』は、殺し屋マチルダを演じたナタリー・ポートマンがとにかく素晴らしい(監督:…
映画『レオン』は、その性質ゆえに物議を醸す作品であることも理解できるが、私はやはりナタリー・ポートマンに圧倒されてしまった。絶望的な事態に巻き込まれたマチルダの葛藤と、そんな少女と共に生きることになった中年男性レオンとの関係性がとても見事に映し出されている。実に素敵な作品だった
あわせて読みたい
【魅惑】マツコも絶賛の“日本人初のパリコレトップモデル”山口小夜子のメイクの凄さや素顔を描く映画:…
日本人初のパリコレトップモデルである山口小夜子と親交があった監督が紡ぐ映画『氷の花火 山口小夜子』は、未だ謎に包まれているその人生の一端を垣間見せてくれる作品だ。彼女を知る様々な人の記憶と、彼女を敬愛する多くの人の想いがより合って、一時代を築いた凄まじい女性の姿が浮かび上がってくる
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『戦場のピアニスト』(ロマン・ポランスキー)が描く、ユダヤ人迫害の衝撃の実話
映画『戦場のピアニスト』の4Kリマスター版を観に行ったところ、上映後のトークイベントに主人公の息子が登壇したので驚いた。何せ私は、本作が「実話を基にしている」ことさえ知らなかったのである。だからその驚きもひとしおだった。ホロコーストの生存者である主人公の壮絶な人生を描き出す、不朽の名作だ
あわせて読みたい
【ル・マン】ゲーマーが本物のカーレース出場!映画『グランツーリスモ』が描く衝撃的すぎる軌跡(ヤン…
映画『グランツーリスモ』は、「ゲーマーをレーサーにする」という、実際に行われた無謀すぎるプロジェクトを基にした作品だ。登場人物は全員イカれていると感じたが、物語としてはシンプルかつ王道で、誰もが先の展開を予想出来るだろう。しかしそれでも、圧倒的に面白かった、ちょっと凄まじすぎる映画だった
あわせて読みたい
【食&芸術】死んでも車を運転したくない人間の香川うどん巡り& 豊島アート巡りの旅ルート(山越うどん…
仕事終わりの木曜日夜から日曜日に掛けて、「香川のうどん巡り」と「豊島のアート巡り」をしてきました。うどんだけでも7580円分食べたので、かなりの軒数を回ったことになります。しかも「死んでも車を運転したくない」ため、可能な限り公共交通機関のみで移動しました。私と同じように「車を運転したくない人」には、かなり参考になる記事と言えるのではないかと思います
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『レザボア・ドッグス』(タランティーノ監督)はとにかく驚異的に脚本が面白い!
クエンティン・タランティーノ初の長編監督作『レザボア・ドッグス』は、のけぞるほど面白い映画だった。低予算という制約を逆手に取った「会話劇」の構成・展開があまりにも絶妙で、舞台がほぼ固定されているにも拘らずストーリーが面白すぎる。天才はやはり、デビュー作から天才だったのだなと実感させられた
あわせて読みたい
【感想】映画『ローマの休日』はアン王女を演じるオードリー・ヘプバーンの美しさが際立つ名作
オードリー・ヘプバーン主演映画『ローマの休日』には驚かされた。現代の視点で観ても十分に通用する作品だからだ。まさに「不朽の名作」と言っていいだろう。シンプルな設定と王道の展開、そしてオードリー・ヘプバーンの時代を超える美しさが相まって、普通ならまずあり得ない見事なコラボレーションが見事に実現している
あわせて読みたい
【抵抗】映画『熊は、いない』は、映画製作を禁じられた映画監督ジャファル・パナヒの執念の結晶だ
映画『熊は、いない』は、「イラン当局から映画製作を20年間も禁じられながら、その後も作品を生み出し続けるジャファル・パナヒ監督」の手によるもので、彼は本作公開後に収監させられてしまった。パナヒ監督が「本人役」として出演する、「ドキュメンタリーとフィクションのあわい」を縫うような異様な作品だ
あわせて読みたい
【感想】映画『キリエのうた』(岩井俊二)はアイナ・ジ・エンドに圧倒されっ放しの3時間だった(出演:…
映画『キリエのうた』(岩井俊二監督)では、とにかくアイナ・ジ・エンドに圧倒されてしまった。歌声はもちろんのことながら、ただそこにいるだけで場を支配するような存在感も凄まじい。全編に渡り「『仕方ないこと』はどうしようもなく起こるんだ」というメッセージに溢れた、とても力強い作品だ
あわせて読みたい
【映画】『キャスティング・ディレクター』の歴史を作り、ハリウッド映画俳優の運命を変えた女性の奮闘
映画『キャスティング・ディレクター』は、ハリウッドで伝説とされるマリオン・ドハティを描き出すドキュメンタリー。「神業」「芸術」とも評される配役を行ってきたにも拘わらず、長く評価されずにいた彼女の不遇の歴史や、再び「キャスティングの暗黒期」に入ってしまった現在のハリウッドなどを切り取っていく
あわせて読みたい
【伝説】映画『ミスター・ムーンライト』が描くビートルズ武道館公演までの軌跡と日本音楽への影響
ザ・ビートルズの武道館公演が行われるまでの軌跡を描き出したドキュメンタリー映画『ミスター・ムーンライト』は、その登場の衝撃について語る多数の著名人が登場する豪華な作品だ。ザ・ビートルズがまったく知られていなかった頃から、伝説の武道館公演に至るまでの驚くべきエピソードが詰まった1作
あわせて読みたい
【天才】タランティーノ作品ほぼ未見で観た面白ドキュメンタリー。映画に愛された映画オタクのリアル
『パルプ・フィクション』しか監督作品を観たことがないまま、本作『クエンティン・タランティーノ 映画に愛された男』を観たが、とても面白いドキュメンタリー映画だった。とにかく「撮影現場に笑いが絶えない」ようで、そんな魅力的なモノづくりに関わる者たちの証言から、天才の姿が浮かび上がる
あわせて読みたい
【感想】是枝裕和監督映画『怪物』(坂元裕二脚本)が抉る、「『何もしないこと』が生む加害性」
坂元裕二脚本、是枝裕和監督の映画『怪物』は、3つの視点を通して描かれる「日常の何気ない光景」に、思いがけない「加害性」が潜んでいることを炙り出す物語だ。これは間違いなく、私たち自身に関わる話であり、むしろ「自分には関係ない」と考えている人こそが自覚すべき問題だと思う
あわせて読みたい
【驚嘆】映画『TAR/ター』のリディア・ターと、彼女を演じたケイト・ブランシェットの凄まじさ
天才女性指揮者リディア・ターを強烈に描き出す映画『TAR/ター』は、とんでもない作品だ。「縦軸」としてのターの存在感があまりにも強すぎるため「横軸」を上手く捉えきれず、結果「よく分からなかった」という感想で終わったが、それでも「観て良かった」と感じるほど、揺さぶられる作品だった
あわせて読みたい
【あらすじ】アリ・アスター監督映画『ミッドサマー』は、気持ち悪さと怖さが詰まった超狂ホラーだった
「夏至の日に映画館で上映する」という企画でようやく観ることが叶った映画『ミッドサマー』は、「私がなんとなく想像していたのとはまるで異なる『ヤバさ』」に溢れる作品だった。いい知れぬ「狂気」が随所で描かれるが、同時に、「ある意味で合理的と言えなくもない」と感じさせられる怖さもある
あわせて読みたい
【天才】映画『リバー、流れないでよ』は、ヨーロッパ企画・上田誠によるタイムループの新発明だ
ヨーロッパ企画の上田誠が生み出した、タイムループものの新機軸映画『リバー、流れないでよ』は、「同じ2分間が繰り返される」という斬新すぎる物語。その設定だけ聞くと、「どう物語を展開させるんだ?」と感じるかもしれないが、あらゆる「制約」を押しのけて、とんでもない傑作に仕上がっている
あわせて読みたい
【感動】円井わん主演映画『MONDAYS』は、タイムループものの物語を革新する衝撃的に面白い作品だった
タイムループという古びた設定と、ほぼオフィスのみという舞台設定を駆使した、想像を遥かに超えて面白かった映画『MONDAYS』は、テンポよく進むドタバタコメディでありながら、同時に、思いがけず「感動」をも呼び起こす、竹林亮のフィクション初監督作品
あわせて読みたい
【驚異】映画『RRR』『バーフバリ』は「観るエナジードリンク」だ!これ程の作品にはなかなか出会えないぞ
2022年に劇場公開されるや、そのあまりの面白さから爆発的人気を博し、現在に至るまでロングラン上映が続いている『RRR』と、同監督作の『バーフバリ』は、大げさではなく「全人類にオススメ」と言える超絶的な傑作だ。まだ観ていない人がいるなら、是非観てほしい!
あわせて読みたい
【勝負】実話を基にコンピューター将棋を描く映画『AWAKE』が人間同士の対局の面白さを再認識させる
実際に行われた将棋の対局をベースにして描かれる映画『AWAKE』は、プロ棋士と将棋ソフトの闘いを「人間ドラマ」として描き出す物語だ。年に4人しかプロ棋士になれない厳しい世界においては、「夢破れた者たち」もまた魅力的な物語を有している。光と影を対比的に描き出す、見事な作品
あわせて読みたい
【偉業】「卓球王国・中国」実現のため、周恩来が頭を下げて請うた天才・荻村伊智朗の信じがたい努力と…
「20世紀を代表するスポーツ選手」というアンケートで、その当時大活躍していた中田英寿よりも高順位だった荻村伊智朗を知っているだろうか?選手としてだけでなく、指導者としてもとんでもない功績を残した彼の生涯を描く『ピンポンさん』から、ノーベル平和賞級の活躍を知る
あわせて読みたい
【挑戦】手足の指を失いながら、今なお挑戦し続ける世界的クライマー山野井泰史の”現在”を描く映画:『…
世界的クライマーとして知られる山野井泰史。手足の指を10本も失いながら、未だに世界のトップをひた走る男の「伝説的偉業」と「現在」を映し出すドキュメンタリー映画『人生クライマー』には、小学生の頃から山のことしか考えてこなかった男のヤバい人生が凝縮されている
あわせて読みたい
【伝説】やり投げ選手・溝口和洋は「思考力」が凄まじかった!「幻の世界記録」など数々の逸話を残した…
世界レベルのやり投げ選手だった溝口和洋を知っているだろうか? 私は本書『一投に賭ける』で初めてその存在を知った。他の追随を許さないほどの圧倒的なトレーニングと、常識を疑い続けるずば抜けた思考力を武器に、体格で劣る日本人ながら「幻の世界記録」を叩き出した天才の伝説と実像
あわせて読みたい
【革命】観る将必読。「将棋を観ること」の本質、より面白くなる見方、そして羽生善治の凄さが満載:『…
野球なら「なんで今振らないんだ!」みたいな素人の野次が成立するのに、将棋は「指せなきゃ観てもつまらない」と思われるのは何故か。この疑問を起点に、「将棋を観ること」と「羽生善治の凄さ」に肉薄する『羽生善治と現代』は、「将棋鑑賞」をより面白くしてくれる話が満載
あわせて読みたい
【感想】映画『窓辺にて』(今泉力哉監督)の稲垣吾郎の役に超共感。「好きとは何か」が分からない人へ
映画『窓辺にて』(今泉力哉監督)は、稲垣吾郎演じる主人公・市川茂巳が素晴らしかった。一般的には、彼の葛藤はまったく共感されないし、私もそのことは理解している。ただ私は、とにかく市川茂巳にもの凄く共感してしまった。「誰かを好きになること」に迷うすべての人に観てほしい
あわせて読みたい
【感想】是枝裕和映画『ベイビー・ブローカー』は、「赤ちゃんポスト」を起点に「正義とは何か」を描く
韓国に多数存在するという「赤ちゃんポスト」を題材にした是枝裕和監督映画『ベイビー・ブローカー』は、「正義とは何か」を問いかける。「中絶はOKで、捨てるのはNG」という判断は不合理だし、「最も弱い関係者が救われる」ことが「正義」だと私は思う
あわせて読みたい
【異端】子育ては「期待しない」「普通から外れさせる」が大事。”劇薬”のような父親の教育論:『オーマ…
どんな親でも、子どもを幸せにしてあげたい、と考えるでしょう。しかしそのために、過保護になりすぎてしまっている、ということもあるかもしれません。『オーマイ・ゴッドファーザー』をベースに、子どもを豊かに、力強く生きさせるための”劇薬”を学ぶ
あわせて読みたい
【純愛】映画『ぼくのエリ』の衝撃。「生き延びるために必要なもの」を貪欲に求める狂気と悲哀、そして恋
名作と名高い映画『ぼくのエリ』は、「生き延びるために必要なもの」が「他者を滅ぼしてしまうこと」であるという絶望を抱えながら、それでも生きることを選ぶ者たちの葛藤が描かれる。「純愛」と呼んでいいのか悩んでしまう2人の関係性と、予想もつかない展開に、感動させられる
あわせて読みたい
【感想】湯浅政明監督アニメ映画『犬王』は、実在した能楽師を”異形”として描くスペクタクル平家物語
観るつもりなし、期待値ゼロ、事前情報ほぼ皆無の状態で観た映画『犬王』(湯浅政明監督)はあまりにも凄まじく、私はこんなとんでもない傑作を見逃すところだったのかと驚愕させられた。原作の古川日出男が紡ぐ狂気の世界観に、リアルな「ライブ感」が加わった、素晴らしすぎる「音楽映画」
あわせて読みたい
【表現】映画『名付けようのない踊り』で初めて見た田中泯のダンス。「芸術以前」を志向する圧倒的パワー
映画『名付けようのない踊り』の中で田中泯は言う。「私」や「個性」を表現することには違和感がある、と。「踊りのために身体を作る」のではなく、「野良仕事で出来た身体で踊る」のだ、と。芸術になる前の踊りを探したい、と。「唯一無二の表現者」の生涯と現在地を映し出すドキュメンタリー
あわせて読みたい
【無謀】園子温が役者のワークショップと同時並行で撮影した映画『エッシャー通りの赤いポスト』の”狂気”
「園子温の最新作」としか知らずに観に行った映画『エッシャー通りの赤いポスト』は、「ワークショップ参加者」を「役者」に仕立て、ワークショップと同時並行で撮影されたという異次元の作品だった。なかなか経験できないだろう、「0が1になる瞬間」を味わえる“狂気”の映画
あわせて読みたい
【特異】「カメラの存在」というドキュメンタリーの大前提を覆す映画『GUNDA/グンダ』の斬新さ
映画『GUNDA/グンダ』は、「カメラの存在」「撮影者の意図」を介在させずにドキュメンタリーとして成立させた、非常に異端的な作品だと私は感じた。ドキュメンタリーの「デュシャンの『泉』」と呼んでもいいのではないか。「家畜」を被写体に据えたという点も非常に絶妙
あわせて読みたい
【愛】ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督の“衝撃の出世作”である映画『灼熱の魂』の凄さ。何も語りたくない
映画館で流れた予告映像だけで観ることを決め、他になんの情報も知らないまま鑑賞した映画『灼熱の魂』は、とんでもない映画だった。『DUNE/デューン 砂の惑星』『ブレードランナー 2049』など有名作を監督してきたドゥニ・ヴィルヌーヴの衝撃の出世作については、何も語りたくない
あわせて読みたい
【青春】二宮和也で映画化もされた『赤めだか』。天才・立川談志を弟子・談春が描く衝撃爆笑自伝エッセイ
「落語協会」を飛び出し、新たに「落語立川流」を創設した立川談志と、そんな立川談志に弟子入りした立川談春。「師匠」と「弟子」という関係で過ごした”ぶっ飛んだ日々”を描く立川談春のエッセイ『赤めだか』は、立川談志の異端さに振り回された立川談春の成長譚が面白い
あわせて読みたい
【狂気】日本一将棋に金を使った将棋ファン・団鬼六の生涯を、『将棋世界』の元編集長・大崎善生が描く…
SM小説の大家として一時代を築きつつ、将棋に金を注ぎ込みすぎて2億円の借金を抱えた団鬼六の生涯を、『将棋世界』の元編集長・大崎善生が描くノンフィクション『赦す人』。虚実が判然としない、嘘だろうと感じてしまうトンデモエピソード満載の異端児が辿った凄まじい生涯
あわせて読みたい
【教育】映画化に『3月のライオン』のモデルと話題の村山聖。その師匠である森信雄が語る「育て方」論:…
自身は決して強い棋士ではないが、棋界で最も多くの弟子を育てた森信雄。「村山聖の師匠」として有名な彼の「師匠としてのあり方」を描く『一門 ”冴えん師匠”がなぜ強い棋士を育てられたのか?』から、教育することの難しさと、その秘訣を学ぶ
あわせて読みたい
【革新】天才マルタン・マルジェラの現在。顔出しNGでデザイナーの頂点に立った男の”素声”:映画『マル…
「マルタン・マルジェラ」というデザイナーもそのブランドのことも私は知らなかったが、そんなファッション音痴でも興味深く観ることができた映画『マルジェラが語る”マルタン・マルジェラ”』は、生涯顔出しせずにトップに上り詰めた天才の来歴と現在地が語られる
あわせて読みたい
【革命】電子音楽誕生の陰に女性あり。楽器ではなく機械での作曲に挑んだ者たちを描く映画:『ショック…
現代では当たり前の「電子音楽」。その黎明期には、既存の音楽界から排除されていた女性が多く活躍した。1978年、パリに住む1人の女性が「電子音楽」の革命の扉をまさに開こうとしている、その1日を追う映画『ショック・ド・フューチャー』が描き出す「創作の熱狂」
あわせて読みたい
【抽象】「思考力がない」と嘆く人に。研究者で小説家の森博嗣が語る「客観的に考える」ために大事なこ…
世の中にはあまりに「具体的な情報」が溢れているために、「客観的、抽象的な思考」をする機会が少ない。そんな時代に、いかに思考力を育てていくべきか。森博嗣が『人間はいろいろな問題についてどう考えていけば良いのか』を通じて伝える「情報との接し方」「頭の使い方」
あわせて読みたい
【感想】映画『竜とそばかすの姫』が描く「あまりに批判が容易な世界」と「誰かを助けることの難しさ」
SNSの登場によって「批判が容易な社会」になったことで、批判を恐れてポジティブな言葉を口にしにくくなってしまった。そんな世の中で私は、「理想論だ」と言われても「誰かを助けたい」と発信する側の人間でいたいと、『竜とそばかすの姫』を観て改めて感じさせられた
あわせて読みたい
【驚愕】これ以上の”サバイバル映画”は存在するか?火星にたった一人残された男の生存術と救出劇:『オ…
1人で火星に取り残された男のサバイバルと救出劇を、現実的な科学技術の範囲で描き出す驚異の映画『オデッセイ』。不可能を可能にするアイデアと勇気、自分や他人を信じ抜く気持ち、そして極限の状況でより困難な道を進む決断をする者たちの、想像を絶するドラマに胸打たれる
あわせて読みたい
【評価】映画『シン・ゴジラ』は、「もしゴジラが実際に現れたら」という”現実”を徹底的にリアルに描く
ゴジラ作品にも特撮映画にもほとんど触れてこなかったが、庵野秀明作品というだけで観に行った『シン・ゴジラ』はとんでもなく面白かった。「ゴジラ」の存在以外のありとあらゆるものを圧倒的なリアリティで描き出す。「本当にゴジラがいたらどうなるのか?」という”現実”の描写がとにかく素晴らしかった
あわせて読みたい
【狂気】バケモン・鶴瓶を映し出す映画。「おもしろいオッチャン」に潜む「異常さ」と「芸への情熱」:…
「俺が死ぬまで公開するな」という条件で撮影が許可された映画『バケモン』。コロナ禍で映画館が苦境に立たされなければ、公開はずっと先だっただろう。テレビで見るのとは違う「芸人・笑福亭鶴瓶」の凄みを、古典落語の名作と名高い「らくだ」の変遷と共に切り取る
あわせて読みたい
【世界観】映画『夜は短し歩けよ乙女』の”黒髪の乙女”は素敵だなぁ。ニヤニヤが止まらない素晴らしいアニメ
森見登美彦の原作も大好きな映画『夜は短し歩けよ乙女』は、「リアル」と「ファンタジー」の境界を絶妙に漂う世界観がとても好き。「黒髪の乙女」は、こんな人がいたら好きになっちゃうよなぁ、と感じる存在です。ずっとニヤニヤしながら観ていた、とても大好きな映画
あわせて読みたい
【革新】映画音楽における唯一のルールは「ルールなど無い」だ。”異次元の音”を生み出す天才を追う:映…
「無声映画」から始まった映画業界で、音楽の重要性はいかに認識されたのか?『JAWS』の印象的な音楽を生み出した天才は、映画音楽に何をもたらしたのか?様々な映画の実際の映像を組み込みながら、「映画音楽」の世界を深堀りする映画『すばらしき映画音楽たち』で、異才たちの「創作」に触れる
あわせて読みたい
【実話】映画『イミテーションゲーム』が描くエニグマ解読のドラマと悲劇、天才チューリングの不遇の死
映画『イミテーションゲーム』が描く衝撃の実話。「解読不可能」とまで言われた最強の暗号機エニグマを打ち破ったのはなんと、コンピューターの基本原理を生み出した天才数学者アラン・チューリングだった。暗号解読を実現させた驚きのプロセスと、1400万人以上を救ったとされながら偏見により自殺した不遇の人生を知る
あわせて読みたい
【おすすめ】濱口竜介監督の映画『親密さ』は、「映像」よりも「言葉」が前面に来る衝撃の4時間だった
専門学校の卒業制作として濱口竜介が撮った映画『親密さ』は、2時間10分の劇中劇を組み込んだ意欲作。「映像」でありながら「言葉の力」が前面に押し出される作品で、映画や劇中劇の随所で放たれる「言葉」に圧倒される。4時間と非常に長いが、観て良かった
あわせて読みたい
【あらすじ】濱口竜介監督『偶然と想像』は、「脚本」と「役者」のみで成り立つ凄まじい映画。天才だと思う
「映画」というメディアを構成する要素は多々あるはずだが、濱口竜介監督作『偶然と想像』は、「脚本」と「役者」だけで狂気・感動・爆笑を生み出してしまう驚異の作品だ。まったく異なる3話オムニバス作品で、どの話も「ずっと観ていられる」と感じるほど素敵だった
あわせて読みたい
【傑作】濱口竜介監督の映画『ドライブ・マイ・カー』(原作:村上春樹)は「自然な不自然さ」が見事な作品
村上春樹の短編小説を原作にした映画『ドライブ・マイ・カー』(濱口竜介監督)は、村上春樹の小説の雰囲気に似た「自然な不自然さ」を醸し出す。「不自然」でしかない世界をいかにして「自然」に見せているのか、そして「自然な不自然さ」は作品全体にどんな影響を与えているのか
あわせて読みたい
【矛盾】その”誹謗中傷”は真っ当か?映画『万引き家族』から、日本社会の「善悪の判断基準」を考える
どんな理由があれ、法を犯した者は罰せられるべきだと思っている。しかしそれは、善悪の判断とは関係ない。映画『万引き家族』(是枝裕和監督)から、「国民の気分」によって「善悪」が決まる社会の是非と、「善悪の判断を保留する勇気」を持つ生き方について考える
あわせて読みたい
【貢献】飛行機を「安全な乗り物」に決定づけたMr.トルネードこと天才気象学者・藤田哲也の生涯:『Mr….
つい数十年前まで、飛行機は「死の乗り物」だったが、天才気象学者・藤田哲也のお陰で世界の空は安全になった。今では、自動車よりも飛行機の方が死亡事故の少ない乗り物なのだ。『Mr.トルネード 藤田哲也 世界の空を救った男』から、その激動の研究人生を知る
あわせて読みたい
【創作】クリエイターになりたい人は必読。ジブリに見習い入社した川上量生が語るコンテンツの本質:『…
ドワンゴの会長職に就きながら、ジブリに「見習い」として入社した川上量生が、様々なクリエイターの仕事に触れ、色んな質問をぶつけることで、「コンテンツとは何か」を考える『コンテンツの秘密』から、「創作」という営みの本質や、「クリエイター」の理屈を学ぶ
あわせて読みたい
【あらすじ】天才とは「分かりやすい才能」ではない。前進するのに躊躇する暗闇で直進できる勇気のこと…
ピアノのコンクールを舞台に描く『蜜蜂と遠雷』は、「天才とは何か?」と問いかける。既存の「枠組み」をいとも簡単に越えていく者こそが「天才」だと私は思うが、「枠組み」を安易に設定することの是非についても刃を突きつける作品だ。小説と映画の感想を一緒に書く
あわせて読みたい
【奇跡】鈴木敏夫が2人の天才、高畑勲と宮崎駿を語る。ジブリの誕生から驚きの創作秘話まで:『天才の思…
徳間書店から成り行きでジブリ入りすることになったプロデューサー・鈴木敏夫が、宮崎駿・高畑勲という2人の天才と共に作り上げたジブリ作品とその背景を語り尽くす『天才の思考 高畑勲と宮崎駿』。日本のアニメ界のトップランナーたちの軌跡の奇跡を知る
あわせて読みたい
【実像】ベートーヴェンの「有名なエピソード」をほぼ一人で捏造・創作した天才プロデューサーの実像:…
ベートーヴェンと言えば、誰もが知っている「運命」を始め、天才音楽家として音楽史に名を刻む人物だが、彼について良く知られたエピソードのほとんどは実は捏造かもしれない。『ベートーヴェン捏造 名プロデューサーは嘘をつく』が描く、シンドラーという”天才”の実像
あわせて読みたい
【天才】写真家・森山大道に密着する映画。菅田将暉の声でカッコよく始まる「撮り続ける男」の生き様:…
映画『あゝ荒野』のスチール撮影の際に憧れの森山大道に初めて会ったという菅田将暉の声で始まる映画『過去はいつも新しく、未来はつねに懐かしい』は、ちゃちなデジカメ1つでひたすら撮り続ける異端児の姿と、50年前の処女作復活物語が見事に交錯する
あわせて読みたい
【逸話】天才数学者ガロアが20歳で決闘で命を落とすまでの波乱万丈。時代を先駆けた男がもし生きていた…
現代数学に不可欠な「群論」をたった1人で生み出し、20歳という若さで決闘で亡くなったガロアは、その短い生涯をどう生きたのか?『ガロア 天才数学者の生涯』から、数学に関心を抱くようになったきっかけや信じられないほどの不運が彼の人生をどう変えてしまったのか、そして「もし生きていたらどうなっていたのか」を知る
あわせて読みたい
【証明】結城浩「数学ガール」とサイモン・シンから「フェルマーの最終定理」とそのドラマを学ぶ
350年以上前に一人の数学者が遺した予想であり「フェルマーの最終定理」には、1995年にワイルズによって証明されるまでの間に、これでもかというほどのドラマが詰め込まれている。サイモン・シンの著作と「数学ガール」シリーズから、その人間ドラマと数学的側面を知る
あわせて読みたい
【情熱】常識を疑え。人間の”狂気”こそが、想像し得ない偉業を成し遂げるための原動力だ:映画『博士と…
世界最高峰の辞書である『オックスフォード英語大辞典』は、「学位を持たない独学者」と「殺人犯」のタッグが生みだした。出会うはずのない2人の「狂人」が邂逅したことで成し遂げられた偉業と、「狂気」からしか「偉業」が生まれない現実を、映画『博士と狂人』から学ぶ
あわせて読みたい
【天才】科学者とは思えないほど面白い逸話ばかりのファインマンは、一体どんな業績を残したのか?:『…
数々の面白エピソードで知られるファインマンの「科学者としての業績」を初めて網羅したと言われる一般書『ファインマンさんの流儀』をベースに、その独特の研究手法がもたらした様々な分野への間接的な貢献と、「ファインマン・ダイアグラム」の衝撃を理解する
あわせて読みたい
【実話】正論を振りかざす人が”強い”社会は窮屈だ。映画『すばらしき世界』が描く「正解の曖昧さ」
「SNSなどでの炎上を回避する」という気持ちから「正論を言うに留めよう」という態度がナチュラルになりつつある社会には、全員が全員の首を締め付け合っているような窮屈さを感じてしまう。西川美和『すばらしき世界』から、善悪の境界の曖昧さを体感する
あわせて読みたい
【天才】『三島由紀夫vs東大全共闘』後に「伝説の討論」と呼ばれる天才のバトルを記録した驚異の映像
1969年5月13日、三島由紀夫と1000人の東大全共闘の討論が行われた。TBSだけが撮影していたフィルムを元に構成された映画「三島由紀夫vs東大全共闘」は、知的興奮に満ち溢れている。切腹の一年半前の討論から、三島由紀夫が考えていたことと、そのスタンスを学ぶ
あわせて読みたい
【解説】テネットの回転ドアの正体を分かりやすく考察。「時間逆行」ではなく「物質・反物質反転」装置…
クリストファー・ノーラン監督の映画『TENET/テネット』は、「陽電子」「反物質」など量子力学の知見が満載です。この記事では、映画の内容そのものではなく、時間反転装置として登場する「回転ドア」をメインにしつつ、時間逆行の仕組みなど映画全体の設定について科学的にわかりやすく解説していきます
あわせて読みたい
【異端】子育てがうまくいかないと悩む方へ。9歳で大学入学の天才児に学ぶ「すべきでないこと」:『ぼく…
12歳で数学の未解決問題を解いた天才児は、3歳の時に「16歳で靴紐が結べるようになったらラッキー」と宣告されていた。専門家の意見に逆らって、重度の自閉症児の才能をどう開花させたのかを、『ぼくは数式で宇宙の美しさを伝えたい』から学ぶ
あわせて読みたい
【驚嘆】人類はいかにして言語を獲得したか?この未解明の謎に真正面から挑む異色小説:『Ank: a mirror…
小説家の想像力は無限だ。まさか、「人類はいかに言語を獲得したか?」という仮説を小説で読めるとは。『Ank: a mirroring ape』をベースに、コミュニケーションに拠らない言語獲得の過程と、「ヒト」が「ホモ・サピエンス」しか存在しない理由を知る
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
文化・芸術・将棋・スポーツ【本・映画の感想】 | ルシルナ
知識や教養は、社会や学問について知ることだけではありません。文化的なものもリベラルアーツです。私自身は、創作的なことをしたり、勝負事に関わることはありませんが、…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…
















































































































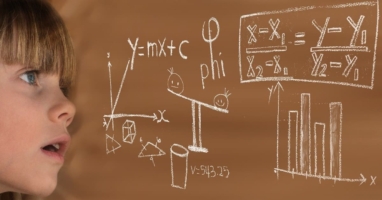










コメント