目次
はじめに
この記事で取り上げる本
KADOKAWA
¥968 (2022/07/17 18:33時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
この本をガイドにしながら記事を書いていきます
この記事の3つの要点
- 新聞人にとって「紙齢をつなぐ」ことは矜持であり、その使命感だけで動き続けた
- 誰からも愛された有能な記者の死と、その死に後悔や自責の念を抱く者たち
- 福島第一原発事故の取材の壮絶さと、記者以外の者たちの奮闘
「当たり前に存在する」という新聞の価値を、有事でも実現しようと奔走した者たちの葛藤の記録
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
「新聞記者としての矜持」が発揮された、東日本大震災での福島民友新聞の奮闘を描き出す『記者たちは海に向かった』
「紙齢をつなぐ」という耳馴染みの薄い言葉と、新聞人にとっての矜持
あわせて読みたい
【実話】ソ連の衝撃の事実を隠蔽する記者と暴く記者。映画『赤い闇』が描くジャーナリズムの役割と実態
ソ連の「闇」を暴いた名もなき記者の実話を描いた映画『赤い闇』は、「メディアの存在意義」と「メディアとの接し方」を問いかける作品だ。「真実」を届ける「社会の公器」であるべきメディアは、容易に腐敗し得る。情報の受け手である私たちの意識も改めなければならない
紙齢をつなぐ―― 一般には全く馴染みのないこの言葉の意味をご存知の方がいるだろうか?
私は本書で初めて「紙齢をつなぐ」という言葉を知った。恐らく、何らかの形で新聞に関わっている人でなければ触れる機会のない言葉ではないかと思う。

「紙齢」とは、新聞が創刊号以来、出しつづけている通算の号数を表すものである。「紙齢」は、毎日の新聞の題字の周辺に必ず出ている。
読者はほとんど目に留めていないが、これを「つなぐ」ことは、新聞人の使命とも言うべきものである。
あわせて読みたい
【デマ】情報を”選ぶ”時代に、メディアの情報の”正しさ”はどのように判断されるのか?:『ニューヨーク…
一昔前、我々は「正しい情報を欲していた」はずだ。しかしいつの間にか世の中は変わった。「欲しい情報を正しいと思う」ようになったのだ。この激変は、トランプ元大統領の台頭で一層明確になった。『ニューヨーク・タイムズを守った男』から、情報の受け取り方を問う
著者は冒頭でこのように書いている。私は正直、「大げさではないか」と感じてしまった。私が新聞に関わりがないからだろうか、「紙齢をつなぐ」ことがそこまで重要なことには感じられなかったのだ。
しかし読み進める中で、本書に登場する福島民友新聞の面々が、繰り返し「紙齢をつなぐ」ことに言及する。
「紙齢が途切れるというか、新聞を出さないということは読者の信頼を失うことですから、これが新聞社にとって一番あってはならないことなのです」
仮に明日、ライバル紙の福島民報は出たのに福島民友が出ないとすれば、「会社の存亡」にかかわる問題だった。当然、地元紙は、避難所にいる被災者にも新聞を届けるべきだろう。そんな時に新聞そのものが「発行できない」などという事態は、そのまま会社の「死」を意味するといっても過言ではなかった。
紙齢をつなぐというのが、われわれにとっての責務ですからね。これは、読者に対する責任です。大震災の状況を読者に届けるというのが新聞の使命だと思っていますので、なんとしても新聞を届けたいという思いがありました。当時、われわれには、二十万読者がいましたからね。その責任を果たせて、ほっとしました。
あわせて読みたい
【異様】ジャーナリズムの役割って何だ?日本ではまだきちんと機能しているか?報道機関自らが問う映画…
ドキュメンタリーで定評のある東海テレビが、「東海テレビ」を被写体として撮ったドキュメンタリー映画『さよならテレビ』は、「メディアはどうあるべきか?」を問いかける。2011年の信じがたいミスを遠景にしつつ、メディア内部から「メディアの存在意義」を投げかける
もちろん、平時であれば「紙齢が途切れる」のは大問題だと思う。新聞が当たり前に発行できる状況下で、何らかの理由によってそれが出来なくなってしまうのであれば、それを「会社の存亡」と捉えるのも分からなくはない。
しかしこのように口にしているのは、未曾有の災害だった東日本大震災でのことなのだ。にもかかわらず、

ああ、こんな大震災の時に新聞が出なかったら、会社自体が潰れるかもしれない、と思いました。
という感想を抱くのは、ちょっと凄まじいことのように思う。結局のところ、この「紙齢をつなぐ」という感覚については、本書を最後まで読んでも私には上手く捉えることができないものだった。
あわせて読みたい
【無知】メディアの問題の本質は?「報道の限界」と「情報の受け取り方」を独裁政治の現実から知る:『…
メディアは確かに「事実」を報じている。しかし、報道に乗らない情報まで含めなければ、本当の意味で世の中を理解することは難しいと、『こうして世界は誤解する』は教えてくれる。アラブ諸国での取材の現実から、報道の「限界」と「受け取り方」を学ぶ
新聞人としての想いが共通だからこその震災時の行動
ただ、その感覚そのものが理解できなかったとしても、「皆の想いが共通していること」による連帯感みたいなものは、本書から痛いほど伝わってきた。多くの人が、「1人の人間」としてどう振る舞うか以上に、「新聞人」としてこの震災を記録しなければならない、と思い立つのである。
それでも、請戸に行ったのは、たぶん“僕が撮らないと、誰も伝えられない”という想いがあったからだと思います。
あの三月十一日、十二日の二日間、僕は純粋に、新聞記者として動いたと思うんですよ。あの時、会社と連絡がとれなくなっていました。ということは、会社の仕事としてではなく、記録として、誰かが、この震災の被害を書き残さなければいけなかった。それは、会社に記事として送ることができるとか、できないとか、そんなことではなく、ただ純粋な気持ちだけでやったことを、思い出します。誌面に反映されるかどうかではなく、純粋に“記録者”として動いた二日間だったんじゃないか、と思うんです。会社というものも超えて、あの二日間、記録者として特化して、あそこにいたのではないか、と。そして、自分には、それしかできなかったのではないかと思います。
このように語る者たちは、当然、東日本大震災を生き延びたからこそ、当時のことについて語ることが出来ている。結果だけ見れば、彼らの行動は正しかったと言っていいだろう。
あわせて読みたい
【現実】東日本大震災発生時からの被災地の映像には、ニュースで見る「分かりやすさ」は微塵もない:『…
東日本大震災発生直後からカメラを回し、被災地の現実を切り取ってきたテレビ岩手。「分かりやすさ」が優先されるテレビではなかなか放送できないだろう映像を含め、「分かりにくい現実」を切り取った映像で構成する映画『たゆたえども沈まず』は静かな衝撃をもたらす作品
しかし全員がそうだったわけではない。震災の日に、1人の若い記者が命を落としている。
だが、この若者には、ほかの犠牲者とは異なる点がひとつだけあった。それは、彼の死が「取材中」にもたらされたということである。

彼の名は熊田由貴生。福島民友新聞の記者2年目、24歳の若者だ。
あの人が死んだのか。彼の記事は、切り抜いて今も手帳に挟んで持っている。温かい記事を書いてくれる記者だった。
読者の1人がそんな風に語る場面がある。誰からも愛され、記者としても頭角を現しつつあった最中の死。本書では、そんな若者の死を中心に据えながら、福島民友新聞の面々が東日本大震災の日以降に何を見て、どんな経験をしてきたのかが丹念に描き出されていく。
あわせて読みたい
【実話】権力の濫用を監視するマスコミが「教会の暗部」を暴く映画『スポットライト』が現代社会を斬る
地方紙である「ボストン・グローブ紙」は、数多くの神父が長年に渡り子どもに対して性的虐待を行い、その事実を教会全体で隠蔽していたという衝撃の事実を明らかにした。彼らの奮闘の実話を映画化した『スポットライト』から、「権力の監視」の重要性を改めて理解する
熊田の死に、誰もが後悔の念を抱いている
私が、この作品を書くために取材を始めた時、福島民友新聞は困惑し、ある意味、狼狽した。
取材に応じていいものかどうか、見方によっては、恥ともいうべき事柄も含め、世の中にそれが明らかにされて、果たしていいものかどうか。
おそらく、そんな迷いと逡巡があったからだろうと思う。
著者がこんな風に書くほど、福島民友新聞にとって熊田の死は大きなものだった。もちろん、東日本大震災によって多くの人が亡くなっている。福島民友新聞社員の家族・親類にも命を落としてしまった人はいただろう。しかし熊田の場合はやはり、「取材中に亡くなった」という特殊さがある。何かが違えば、死なずに済んだのではないか。誰もがそんな風に感じてしまうのだ。
あわせて読みたい
【思考】戸田真琴、経験も文章もとんでもない。「人生どうしたらいい?」と悩む時に読みたい救いの1冊:…
「AV女優のエッセイ」と聞くと、なかなか手が伸びにくいかもしれないが、戸田真琴『あなたの孤独は美しい』の、あらゆる先入観を吹っ飛ばすほどの文章力には圧倒されるだろう。凄まじい経験と、普通ではない思考を経てAV女優に至った彼女の「生きる指針」は、多くの人の支えになるはずだ
熊田の死は、浪江支局長である木口拓哉にも衝撃を与えた。
なぜカメラなんかに手を伸ばそうとしたんだ。おまえは、なんで助けなかったんだ……。
津波から逃げながら、木口の頭の中を、そんな言葉がぐるぐるとまわっていた。
おまえは何だ! おまえはなぜ人を助けないのか! おまえは記者である前に「人間」ではないのか!
死の恐怖にがたがた震えながら、木口はアクセルを踏みつづけた。助けられなかった命の重さが、運転席にいる木口の全身に覆いかぶさっていた。
熊田の遺体が見つかった後、「熊田は人助けをして逃げ遅れた」という話が漏れ聞こえてくる。そして、実際に熊田に助けられたという大工から、後に福島民友新聞に電話が掛かってきた。この事実は、「おまえは記者である前に『人間』ではないのか!」と、自身の行動を悔やむ葛藤へと繋がっていくことになる。
熊田は人を助けて、俺は助けられなかった――。

あわせて読みたい
【奇跡】信念を貫いた男が国の制度を変えた。特別養子縁組を実現させた石巻の産婦人科医の執念:『赤ち…
遊郭で生まれ育った石巻の医師が声を上げ、あらゆる障害をなぎ倒して前進したお陰で「特別養子縁組」の制度が実現した。そんな産婦人科医・菊田昇の生涯を描き出す小説『赤ちゃんをわが子として育てる方を求む』には、法を犯してでも信念を貫いた男の衝撃の人生が描かれている
僕は卑怯なんです。そこから、僕は逃げたんです。僕が逡巡していなければ、二人は助かったと思っています。僕は請戸漁港でも、警官に出るように言われて、命を拾っています。そして、ここでも、人を助けられずに生き残ったんです。一度ならず、二度も命を拾っている。僕は、卑怯な人間なんです。
あの大震災を福島や岩手など被害の酷かった土地で直接経験したわけではない私が何を言っても説得力などないが、誰もが生き延びるのに必死だった時の行動を、「卑怯だ」なんて責める人間はいないだろうと思う。しかしやはり、本人は否応なしに自責の念を抱えてしまう。そんなこと熊田は望んじゃいないと木口も恐らく頭では理解しているはずだ。それでも彼は、自分を責めずにはいられないのである。
また、相双支社長である菅野は、棺に入った熊田の胸に、3月12日の新聞を置きながらこう呟いた。
あわせて読みたい
【感想】映画『竜とそばかすの姫』が描く「あまりに批判が容易な世界」と「誰かを助けることの難しさ」
SNSの登場によって「批判が容易な社会」になったことで、批判を恐れてポジティブな言葉を口にしにくくなってしまった。そんな世の中で私は、「理想論だ」と言われても「誰かを助けたい」と発信する側の人間でいたいと、『竜とそばかすの姫』を観て改めて感じさせられた
熊ちゃん、こんな風になったんだよ。
それを近くで見ていた國分はこんな風に語っている。
熊田は、その新聞を見ることができなかったわけじゃないですか。しかし、まさにこの新聞のために、熊田は取材に行ったんです。こんな風になったんだよ、という菅野さんの言葉は、熊田にあの津波のことを伝えていたんだと思います。岩手、宮城、福島の浜通りと、あれほどの被害を出した津波のことを、熊田は知らないわけですから、菅野さんはそれを熊田に伝えようとしたんだと思います。本当にあの時は、つらかったです……。
誰もが熊田のように命を落としてもおかしくない。そう理解していた。というのも、地方紙であればこそ、記者はカメラマンとしての役割も求められるからだ。何かあれば皆、「とにかくまず写真を撮らねば」という思考になるのだという。
あわせて読みたい
【信念】水俣病の真実を世界に伝えた写真家ユージン・スミスを描く映画。真実とは「痛みへの共感」だ:…
私はその存在をまったく知らなかったが、「水俣病」を「世界中が知る公害」にした報道写真家がいる。映画『MINAMATA―ミナマタ―』は、水俣病の真実を世界に伝えたユージン・スミスの知られざる生涯と、理不尽に立ち向かう多くの人々の奮闘を描き出す
そうだ、津波だ、津波を撮らねば。
海に行かなければ……。
結果として命を落としたのは熊田だった。しかし、誰もが同じ条件にあったと言っていい。命を落とさずに生き残った記者は、ただ幸運だったに過ぎない。誰もがそう実感していたからこそ、こんな風に語る者もいた。
自分が生きていることが無性に申し訳なかった。

熊田の死は、様々な形で多くの者に影響を与えることになったのである。
壮絶だった取材現場と、「新聞を届ける者たち」の奮闘
あわせて読みたい
【挑戦】東日本大震災における奇跡。日本の出版を支える日本製紙石巻工場のありえない復活劇:『紙つな…
本を読む人も書く人も作る人も、出版で使われる紙がどこで作られているのか知らない。その多くは、東日本大震災で甚大な被害を受けた日本製紙石巻工場で作られていた。『紙つなげ』をベースに、誰もが不可能だと思った早期復旧の舞台裏を知る
福島民友新聞の記者は当然、福島第一原発の取材も日常的に行ってきた。そしてだからこそ、震災後の取材は驚きと苦労の連続だったという。
木口は、本社に戻ろうと車を運転していた。検問で警官に止められ、南相馬経由で福島市に戻るつもりだと伝えると、「あんた、原発が爆発したのを知らねえのか?」と言われてしまう。
木口には信じがたい話だった。
その時、警官は、こう言った。
「死にますよ、あんた」
「……」
木口は、警官の言っていることは本当なのか、と思った。まさか……と、それを打ち消しながら、そこを通してもらった。いくら警官に脅されても、心の中では、「原発が爆発した」などということを、信じようとしていなかったのである。
あわせて読みたい
【歴史】映画『シン・ちむどんどん』は、普天間基地移設問題に絡む辺野古埋め立てを”陽気に”追及する(…
映画『シン・ちむどんどん』は、映画『センキョナンデス』に続く「ダースレイダー・プチ鹿島による選挙戦リポート」第2弾である。今回のターゲットは沖縄知事選。そして本作においては、選挙戦の模様以上に、後半で取り上げられる「普天間基地の辺野古移設問題の掘り下げ」の方がより興味深かった
原発は安全なのだと彼は信じていた。原発取材を担当していた木口だからこそ、「そんなはずがない」という想いが強かったのだ。それぐらい、原発の安全神話は強かったということだろう。
またこんなこともあった。東京電力常務の小森明生が記者会見を開いた際の出来事だ。

小森は福島第一原発の元所長であり、浜通りに長く住んでいた。福島を第二の故郷だと考えていた人物である。その時の彼は、100を超す記者から「吊るし上げられ」、ようやく解放されてエレベーターの方向へ向かっているところだった。
あわせて読みたい
【絶望】映画『少年たちの時代革命』が描く、香港デモの最中に自殺者を救おうとした若者たちの奮闘
香港の民主化運動の陰で、自殺者を救出しようと立ち上がったボランティア捜索隊が人知れず存在していた。映画『少年たちの時代革命』はそんな実話を基にしており、若者の自殺が急増した香港に様々な葛藤を抱えながら暮らし続ける若者たちのリアルが切り取られる作品だ
そこで福島民友新聞の橋本から声を掛けられる。
「これから、地元はどうなるんでしょうか」
小森に、そう声をかけてきた記者がいた。
橋本だった。
(あっ、橋本さんだ)
小森は、声のする方に目を向けた瞬間、橋本だと気づいた。顔も知らない全国紙やテレビの記者たちと長時間のやりとりをしていた小森は、そこに知り合いの記者がいたことに驚いた。
そして、その瞬間に、涙が溢れ出してしまった。
橋本の方は、福島県庁の道を隔てた西側に建つ「福島県自治会館」内に置かれた災害対策本部の担当を命じられており、泊まり込みで取材を続けている最中だった。福島第一原発元所長の小森とは知った仲である。
橋本の方を向いた小森は、何も答えず、そのまま声を押し殺して泣き始めた。それを見た橋本の目からも涙が溢れ出てきた。
記者が取材対象者と一緒に「泣く」ことなど、あってはならない。そんなことはわかっている。だが、橋本も、涙を抑えられなかった。
あわせて読みたい
【執念】「桶川ストーカー事件」で警察とマスコミの怠慢を暴き、社会を動かした清水潔の凄まじい取材:…
『殺人犯はそこにいる』(文庫X)で凄まじい巨悪を暴いた清水潔は、それよりずっと以前、週刊誌記者時代にも「桶川ストーカー殺人事件」で壮絶な取材を行っていた。著者の奮闘を契機に「ストーカー規制法」が制定されたほどの事件は、何故起こり、どんな問題を喚起したのか
「あってはならない涙」が止めどもなく流れてしまうほどの地獄絵図。そんな渦中に否応なしに放り込まれた者たちの奮闘が、本書には詰め込まれている。自らも「被災者」でありながら、同時に「記録者」であろうと足掻き続けたその時間こそが、「新聞」という形あるものを生み出す原動力となり、また、全社的に「紙齢をつなぐ」という使命へと突き進む契機となっていったのだ。

奮闘したのは決して記者だけではない。印刷工場が被災したことで、3工場分の新聞を1つの印刷所で刷らなければならなくなった。また当然のことながら、配達をする者がいなければ、いくら新聞を作ったところで届かない。新聞を支える者たちの奮闘から、「新聞」という”モノ”にずっしりと乗っている、様々な人間の想いの重みを感じさせられた。
また本書には、こんな記述もある。
あわせて読みたい
【絶望】権力の濫用を止めるのは我々だ。映画『新聞記者』から「ソフトな独裁国家・日本」の今を知る
私個人は、「ビジョンの達成」のためなら「ソフトな独裁」を許容する。しかし今の日本は、そもそも「ビジョン」などなく、「ソフトな独裁状態」だけが続いていると感じた。映画『新聞記者』をベースに、私たちがどれだけ絶望的な国に生きているのかを理解する
あの大震災は、福島県内において、日本の新聞史上、これまで誰も経験したことがない大事態を惹起している。
それは、「新聞エリアの欠落」である。
(中略)
つまり、福島の浜通りの一部では、「読者」も、「新聞記者」も、「販売店」も、すべてが被災者となりそのエリアから「去らざるを得ない事態」に陥ったのだ。
福島第一原発から半径二十キロ以内の避難区域の中にあった福島民友新聞の「二つの支局」と「十二の販売店」は避難を余儀なくされ、完全なる「空白区域」となった。
だからこそ福島民友新聞の者たちにとって、震災翌日の3月12日に、「紙齢をつなぐ新聞」を発行できたことは誇りなのだ。
福島民友の読者の中には、放射能による避難から半年経って「一時帰宅」した際に、三月十二日付の福島民友新聞を新聞ポストに見つけて感動した人間が少なくなかった。読む人が避難した主なき家に、それでも新聞は「配られていた」のである。
新聞を購読していない私には、その「感動」をリアルに実感することはなかなか難しいが、「当たり前の存在」だからこそ、「当たり前ではない時にも存在することの凄まじさ」は理解できるつもりだ。
そんな彼らの奮闘が詰まった1冊である。
あわせて読みたい
【喪失】家族とうまくいかない人、そして、家族に幻想を抱いてしまう人。家族ってなんてめんどくさいの…
「福島中央テレビ開局50周年記念作品」である映画『浜の朝日の嘘つきどもと』は、福島県に実在した映画館「朝日座」を舞台に、住民が抱く「希望(幻想)」が描かれる。震災・コロナによってありとあらゆるものが失われていく世の中で、私たちはどう生きるべきか
KADOKAWA
¥968 (2022/07/17 18:35時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品読了済】私が読んできたノンフィクション・教養書を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が読んできたノンフィクションを様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本選びの参考にして下さい。
最後に
あわせて読みたい
【驚愕】映画『リアリティ』の衝撃。FBIによる、機密情報をリークした女性の尋問音源を完全再現(リアリ…
映画『リアリティ』は、恐らく過去類を見ないだろう構成の作品だ。なんと、「FBI捜査官が録音していた実際の音声データのやり取りを一言一句完全に再現した映画」なのである。「第2のスノーデン」とも評される”普通の女性”は、一体何故、国家に反旗を翻す”反逆者”になったのだろうか?
この記事の冒頭でも書いた通り、結局私には、自ら被災しながらも「紙齢をつなぐ」ことにこれほど人生をかける感覚は分からなかった。しかし、有事だからこそ、「『あって当たり前のもの』がある安心感」を強く感じるというのはなんとなく分かるような気がする。そして、新聞を購読している人にとってそれは、新聞こそが果たすことのできる役割だったというわけだ。
「誰かが記録しなければ」という使命感に突き動かされるようにして、あまりに悲惨な現実を取材し続けた新聞人の「誇り」を、是非本書で体感してほしい。
あわせて読みたい
【挑戦】映画『燃えあがる女性記者たち』が描く、インドカースト最下位・ダリットの女性による報道
映画『燃えあがる女性記者たち』は、インドで「カースト外の不可触民」として扱われるダリットの女性たちが立ち上げた新聞社「カバル・ラハリヤ」を取り上げる。自身の境遇に抗って、辛い状況にいる人の声を届けたり権力者を糾弾したりする彼女たちの奮闘ぶりが、インドの民主主義を変革させるかもしれない
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【発見】映画『小学校~それは小さな社会~』(山崎エマ)が映し出すのは、我々には日常すぎる日常だ
映画『小学校~それは小さな社会~』は、ごく一般的な公立小学校に密着し、日本で生まれ育った人間には「当たり前」にしか思えない日常を切り取った作品なのだが、そんな映画が諸外国で大いに評価されているという。「TOKKATSU」という「日本式教育」が注目されているらしく、私たちの「当たり前」が違和感だらけに見えているのだそうだ
あわせて読みたい
【絶望】知られざる「国による嘘」!映画『蟻の兵隊』(池谷薫)が映し出す終戦直後の日本の欺瞞
映画『蟻の兵隊』は、「1945年8月15日の終戦以降も上官の命令で中国に残らされ、中国の内戦を闘った残留日本軍部隊」の1人である奥村和一を追うドキュメンタリー映画だ。「自らの意思で残った」と判断された彼らは、国からの戦後補償を受けられていない。そんな凄まじい現実と、奥村和一の驚くべき「誠実さ」が描かれる作品である
あわせて読みたい
【あらすじ】老夫婦の”穏やかな日常”から核戦争の恐怖を描くアニメ映画『風が吹くとき』の衝撃
一軒家の中だけで展開される老夫婦の日常から「核戦争」の危機をリアルに描き出す映画『風が吹くとき』は、日本では1987年に公開された作品なのだが、今まさに観るべき作品ではないかと。世界的に「核戦争」の可能性が高まっているし、また「いつ起こるか分からない巨大地震」と読み替えても成立する作品で、実に興味深かった
あわせて読みたい
【真相?】映画『マミー』が描く和歌山毒物カレー事件・林眞須美の冤罪の可能性。超面白い!
世間を大騒ぎさせた「和歌山毒物カレー事件」の犯人とされた林眞須美死刑囚は無実かもしれない。映画『マミー』は、そんな可能性を示唆する作品だ。「目撃証言」と「ヒ素の鑑定」が詳細に検証し直され、さらに「保険金詐欺をやっていた」という夫の証言も相まって、証拠的にも感情的にも支持したくなるような驚きの仮説である
あわせて読みたい
【幻惑】映画『落下の解剖学』は、「真実は誰かが”決める”しかない」という現実の不安定さを抉る
「ある死」を巡って混沌とする状況をリアルに描き出す映画『落下の解剖学』は、「客観的な真実にはたどり着けない」という困難さを炙り出す作品に感じられた。事故なのか殺人なのか自殺なのか、明確な証拠が存在しない状況下で、憶測を繋ぎ合わせるようにして進行する「裁判」の様子から、「『真実性』の捉えがたさ」がよく理解できる
あわせて読みたい
【衝撃】EUの難民問題の狂気的縮図!ポーランド・ベラルーシ国境での、国による非人道的対応:映画『人…
上映に際し政府から妨害を受けたという映画『人間の境界』は、ポーランド・ベラルーシ国境で起こっていた凄まじい現実が描かれている。「両国間で中東からの難民を押し付け合う」という醜悪さは見るに絶えないが、そのような状況下でも「可能な範囲でどうにか人助けをしたい」と考える者たちの奮闘には救われる思いがした
あわせて読みたい
【真相】飯塚事件は冤罪で死刑執行されたのか?西日本新聞・警察・弁護士が語る葛藤と贖罪:映画『正義…
映画『正義の行方』では、冤罪のまま死刑が執行されたかもしれない「飯塚事件」が扱われる。「久間三千年が犯行を行ったのか」という議論とは別に、「当時の捜査・司法手続きは正しかったのか?」という観点からも捉え直されるべきだし、それを自発的に行った西日本新聞の「再検証連載」はとても素晴らしかったと思う
あわせて読みたい
【挑戦】映画『燃えあがる女性記者たち』が描く、インドカースト最下位・ダリットの女性による報道
映画『燃えあがる女性記者たち』は、インドで「カースト外の不可触民」として扱われるダリットの女性たちが立ち上げた新聞社「カバル・ラハリヤ」を取り上げる。自身の境遇に抗って、辛い状況にいる人の声を届けたり権力者を糾弾したりする彼女たちの奮闘ぶりが、インドの民主主義を変革させるかもしれない
あわせて読みたい
【日本】原発再稼働が進むが、その安全性は?樋口英明の画期的判決とソーラーシェアリングを知る:映画…
映画『原発をとめた裁判長 そして原発をとめる農家たち』では、大飯原発の運転差し止め判決を下した裁判長による画期的な「樋口理論」の説明に重点が置かれる。「原発の耐震性」に関して知らないことが満載で、実に興味深かった。また、農家が発案した「ソーラーシェアリング」という新たな発電方法も注目である
あわせて読みたい
【歴史】映画『シン・ちむどんどん』は、普天間基地移設問題に絡む辺野古埋め立てを”陽気に”追及する(…
映画『シン・ちむどんどん』は、映画『センキョナンデス』に続く「ダースレイダー・プチ鹿島による選挙戦リポート」第2弾である。今回のターゲットは沖縄知事選。そして本作においては、選挙戦の模様以上に、後半で取り上げられる「普天間基地の辺野古移設問題の掘り下げ」の方がより興味深かった
あわせて読みたい
【驚愕】映画『リアリティ』の衝撃。FBIによる、機密情報をリークした女性の尋問音源を完全再現(リアリ…
映画『リアリティ』は、恐らく過去類を見ないだろう構成の作品だ。なんと、「FBI捜査官が録音していた実際の音声データのやり取りを一言一句完全に再現した映画」なのである。「第2のスノーデン」とも評される”普通の女性”は、一体何故、国家に反旗を翻す”反逆者”になったのだろうか?
あわせて読みたい
【感想】関東大震災前後を描く映画『福田村事件』(森達也)は、社会が孕む「思考停止」と「差別問題」…
森達也監督初の劇映画である『福田村事件』は、100年前の関東大震災直後に起こった「デマを起点とする悲劇」が扱われる作品だ。しかし、そんな作品全体が伝えるメッセージは、「100年前よりも現代の方がよりヤバい」だと私は感じた。SNS時代だからこそ意識すべき問題の詰まった、挑発的な作品である
あわせて読みたい
【絶望】映画『少年たちの時代革命』が描く、香港デモの最中に自殺者を救おうとした若者たちの奮闘
香港の民主化運動の陰で、自殺者を救出しようと立ち上がったボランティア捜索隊が人知れず存在していた。映画『少年たちの時代革命』はそんな実話を基にしており、若者の自殺が急増した香港に様々な葛藤を抱えながら暮らし続ける若者たちのリアルが切り取られる作品だ
あわせて読みたい
【倫理】報道の自由度に関わる「放送法の解釈変更」問題をわかりやすく説明(撤回の真相についても):…
安倍政権下で突然発表された「放送法の解釈変更」が、2023年3月17日に正式に”撤回された”という事実をご存知だろうか?映画『テレビ、沈黙。 放送不可能。Ⅱ』は、その「撤回」に尽力した小西洋之議員に田原総一朗がインタビューする作品だ。多くの人が知るべき事実である
あわせて読みたい
【信念】映画『ハマのドン』の主人公、横浜港の顔役・藤木幸夫は、91歳ながら「伝わる言葉」を操る
横浜港を取り仕切る藤木幸夫を追うドキュメンタリー映画『ハマのドン』は、盟友・菅義偉と対立してでもIR進出を防ごうとする91歳の決意が映し出される作品だ。高齢かつほとんど政治家のような立ち位置でありながら、「伝わる言葉」を発する非常に稀有な人物であり、とても興味深かった
あわせて読みたい
【映画】『戦場記者』須賀川拓が、ニュースに乗らない中東・ウクライナの現実と報道の限界を切り取る
TBS所属の特派員・須賀川拓は、ロンドンを拠点に各国の取材を行っている。映画『戦場記者』は、そんな彼が中東を取材した映像をまとめたドキュメンタリーだ。ハマスを巡って食い違うガザ地区とイスラエル、ウクライナ侵攻直後に現地入りした際の様子、アフガニスタンの壮絶な薬物中毒の現実を映し出す
あわせて読みたい
【高卒】就職できる気がしない。韓国のブラック企業の実態をペ・ドゥナ主演『あしたの少女』が抉る
韓国で実際に起こった「事件」を基に作られた映画『あしたの少女』は、公開後に世論が動き、法律の改正案が国会を通過するほどの影響力を及ぼした。学校から実習先をあてがわれた1人の女子高生の運命を軸に描かれる凄まじい現実を、ペ・ドゥナ演じる女刑事が調べ尽くす
あわせて読みたい
【性加害】映画『SHE SAID その名を暴け』を観てくれ。#MeToo運動を生んだ報道の舞台裏(出演:キャリ…
「#MeToo」運動のきっかけとなった、ハリウッドの絶対権力者ハーヴェイ・ワインスタインを告発するニューヨーク・タイムズの記事。その取材を担った2人の女性記者の奮闘を描く映画『SHE SAID その名を暴け』は、ジャニー喜多川の性加害問題で揺れる今、絶対に観るべき映画だと思う
あわせて読みたい
【傑物】フランスに最も愛された政治家シモーヌ・ヴェイユの、強制収容所から国連までの凄絶な歩み:映…
「フランスに最も愛された政治家」と評されるシモーヌ・ヴェイユ。映画『シモーヌ』は、そんな彼女が強制収容所を生き延び、後に旧弊な社会を変革したその凄まじい功績を描き出す作品だ。「強制収容所からの生還が失敗に思える」とさえ感じたという戦後のフランスの中で、彼女はいかに革新的な歩みを続けたのか
あわせて読みたい
【感想】どんな話かわからない?難しい?ジブリ映画『君たちはどう生きるか』の考察・解説は必要?(監…
宮崎駿最新作であるジブリ映画『君たちはどう生きるか』は、宮崎アニメらしいファンタジックな要素を全開に詰め込みつつ、「生と死」「創造」についても考えさせる作品だ。さらに、「自分の頭の中から生み出されたものこそ『正解』」という、創造物と向き合う際の姿勢についても問うているように思う
あわせて読みたい
【生還】内戦下のシリアでISISに拘束された男の実話を基にした映画『ある人質』が描く壮絶すぎる現実
実話を基にした映画『ある人質 生還までの398日』は、内戦下のシリアでISISに拘束された男の壮絶な日々が描かれる。「テロリストとは交渉しない」という方針を徹底して貫くデンマーク政府のスタンスに翻弄されつつも、救出のために家族が懸命に奮闘する物語に圧倒される
あわせて読みたい
【実話】ソ連の衝撃の事実を隠蔽する記者と暴く記者。映画『赤い闇』が描くジャーナリズムの役割と実態
ソ連の「闇」を暴いた名もなき記者の実話を描いた映画『赤い闇』は、「メディアの存在意義」と「メディアとの接し方」を問いかける作品だ。「真実」を届ける「社会の公器」であるべきメディアは、容易に腐敗し得る。情報の受け手である私たちの意識も改めなければならない
あわせて読みたい
【執念】「桶川ストーカー事件」で警察とマスコミの怠慢を暴き、社会を動かした清水潔の凄まじい取材:…
『殺人犯はそこにいる』(文庫X)で凄まじい巨悪を暴いた清水潔は、それよりずっと以前、週刊誌記者時代にも「桶川ストーカー殺人事件」で壮絶な取材を行っていた。著者の奮闘を契機に「ストーカー規制法」が制定されたほどの事件は、何故起こり、どんな問題を喚起したのか
あわせて読みたい
【思考】戸田真琴、経験も文章もとんでもない。「人生どうしたらいい?」と悩む時に読みたい救いの1冊:…
「AV女優のエッセイ」と聞くと、なかなか手が伸びにくいかもしれないが、戸田真琴『あなたの孤独は美しい』の、あらゆる先入観を吹っ飛ばすほどの文章力には圧倒されるだろう。凄まじい経験と、普通ではない思考を経てAV女優に至った彼女の「生きる指針」は、多くの人の支えになるはずだ
あわせて読みたい
【欠落】映画『オードリー・ヘプバーン』が映し出す大スターの生き方。晩年に至るまで生涯抱いた悲しみ…
映画『オードリー・ヘプバーン』は、世界的大スターの知られざる素顔を切り取るドキュメンタリーだ。戦争による壮絶な飢え、父親の失踪、消えぬ孤独感、偶然がもたらした映画『ローマの休日』のオーディション、ユニセフでの活動など、様々な証言を元に稀代の天才を描き出す
あわせて読みたい
【奇跡】信念を貫いた男が国の制度を変えた。特別養子縁組を実現させた石巻の産婦人科医の執念:『赤ち…
遊郭で生まれ育った石巻の医師が声を上げ、あらゆる障害をなぎ倒して前進したお陰で「特別養子縁組」の制度が実現した。そんな産婦人科医・菊田昇の生涯を描き出す小説『赤ちゃんをわが子として育てる方を求む』には、法を犯してでも信念を貫いた男の衝撃の人生が描かれている
あわせて読みたい
【証言】ナチスドイツでヒトラーに次ぐナンバー2だったゲッベルス。その秘書だった女性が歴史を語る映画…
ナチスドイツナンバー2だった宣伝大臣ゲッベルス。その秘書だったブルンヒルデ・ポムゼルが103歳の時にカメラの前で当時を語った映画『ゲッベルスと私』には、「愚かなことをしたが、避け難かった」という彼女の悔恨と教訓が含まれている。私たちは彼女の言葉を真摯に受け止めなければならない
あわせて読みたい
【秘話】15年で世界を変えたグーグルの”異常な”創業エピソード。収益化無視の無料ビジネスはなぜ成功し…
スマホやネットを使う人で、グーグルのお世話になっていない人はまずいないだろう。もはや「インフラ」と呼んでいいレベルになったサービスを生み出した企業の創業からの歴史を描く『グーグル秘録』は、その歩みが「無邪気さ」と「偶然」の産物であることを示している。凄まじいエピソード満載の信じがたい企業秘話
あわせて読みたい
【信念】水俣病の真実を世界に伝えた写真家ユージン・スミスを描く映画。真実とは「痛みへの共感」だ:…
私はその存在をまったく知らなかったが、「水俣病」を「世界中が知る公害」にした報道写真家がいる。映画『MINAMATA―ミナマタ―』は、水俣病の真実を世界に伝えたユージン・スミスの知られざる生涯と、理不尽に立ち向かう多くの人々の奮闘を描き出す
あわせて読みたい
【葛藤】正論を振りかざしても、「正しさとは何か」に辿り着けない。「絶対的な正しさ」など存在しない…
「『正しさ』は人によって違う」というのは、私には「当たり前の考え」に感じられるが、この前提さえ共有できない社会に私たちは生きている。映画『由宇子の天秤』は、「誤りが含まれるならすべて間違い」という判断が当たり前になされる社会の「不寛容さ」を切り取っていく
あわせて読みたい
【喪失】家族とうまくいかない人、そして、家族に幻想を抱いてしまう人。家族ってなんてめんどくさいの…
「福島中央テレビ開局50周年記念作品」である映画『浜の朝日の嘘つきどもと』は、福島県に実在した映画館「朝日座」を舞台に、住民が抱く「希望(幻想)」が描かれる。震災・コロナによってありとあらゆるものが失われていく世の中で、私たちはどう生きるべきか
あわせて読みたい
【衝撃】『殺人犯はそこにいる』が実話だとは。真犯人・ルパンを野放しにした警察・司法を信じられるか?
タイトルを伏せられた覆面本「文庫X」としても話題になった『殺人犯はそこにいる』。「北関東で起こったある事件の取材」が、「私たちが生きる社会の根底を揺るがす信じがたい事実」を焙り出すことになった衝撃の展開。まさか「司法が真犯人を野放しにする」なんてことが実際に起こるとは。大げさではなく、全国民必読の1冊だと思う
あわせて読みたい
【驚愕】あるジャーナリストの衝撃の実話を描く映画『凶悪』。「死刑囚の告発」から「正義」を考える物語
獄中の死刑囚が警察に明かしていない事件を雑誌記者に告発し、「先生」と呼ばれる人物を追い詰めた実際の出来事を描くノンフィクションを原作にして、「ジャーナリズムとは?」「家族とは?」を問う映画『凶悪』は、原作とセットでとにかく凄まじい作品だ
あわせて読みたい
【実話】権力の濫用を監視するマスコミが「教会の暗部」を暴く映画『スポットライト』が現代社会を斬る
地方紙である「ボストン・グローブ紙」は、数多くの神父が長年に渡り子どもに対して性的虐待を行い、その事実を教会全体で隠蔽していたという衝撃の事実を明らかにした。彼らの奮闘の実話を映画化した『スポットライト』から、「権力の監視」の重要性を改めて理解する
あわせて読みたい
【驚愕】正義は、人間の尊厳を奪わずに貫かれるべきだ。独裁政権を打倒した韓国の民衆の奮闘を描く映画…
たった30年前の韓国で、これほど恐ろしい出来事が起こっていたとは。「正義の実現」のために苛烈な「スパイ狩り」を行う秘密警察の横暴をきっかけに民主化運動が激化し、独裁政権が打倒された史実を描く『1987、ある闘いの真実』から、「正義」について考える
あわせて読みたい
【異様】ジャーナリズムの役割って何だ?日本ではまだきちんと機能しているか?報道機関自らが問う映画…
ドキュメンタリーで定評のある東海テレビが、「東海テレビ」を被写体として撮ったドキュメンタリー映画『さよならテレビ』は、「メディアはどうあるべきか?」を問いかける。2011年の信じがたいミスを遠景にしつつ、メディア内部から「メディアの存在意義」を投げかける
あわせて読みたい
【権威】心理学の衝撃実験をテレビ番組の収録で実践。「自分は残虐ではない」と思う人ほど知るべき:『…
フランスのテレビ局が行った「現代版ミルグラム実験」の詳細が語られる『死のテレビ実験 人はそこまで服従するのか』は、「権威」を感じる対象から命じられれば誰もが残虐な行為をしてしまい得ることを示す。全人類必読の「過ちを事前に回避する」ための知見を学ぶ
あわせて読みたい
【現実】東日本大震災発生時からの被災地の映像には、ニュースで見る「分かりやすさ」は微塵もない:『…
東日本大震災発生直後からカメラを回し、被災地の現実を切り取ってきたテレビ岩手。「分かりやすさ」が優先されるテレビではなかなか放送できないだろう映像を含め、「分かりにくい現実」を切り取った映像で構成する映画『たゆたえども沈まず』は静かな衝撃をもたらす作品
あわせて読みたい
【誠実】想像を超える辛い経験を言葉にするのは不可能だ。それを分かってなお筆を執った作家の震災記:…
旅行者として東日本大震災で被災した小説家・彩瀬まるは、『暗い夜、星を数えて 3.11被災鉄道からの脱出』でその体験を語る。「そんなこと、言わなければ分からない」と感じるような感情も包み隠さず記し、「絶望的な伝わらなさ」を感じながらも伝えようと奮闘する1冊
あわせて読みたい
【絶望】権力の濫用を止めるのは我々だ。映画『新聞記者』から「ソフトな独裁国家・日本」の今を知る
私個人は、「ビジョンの達成」のためなら「ソフトな独裁」を許容する。しかし今の日本は、そもそも「ビジョン」などなく、「ソフトな独裁状態」だけが続いていると感じた。映画『新聞記者』をベースに、私たちがどれだけ絶望的な国に生きているのかを理解する
あわせて読みたい
【課題】原子力発電の廃棄物はどこに捨てる?世界各国、全人類が直面する「核のゴミ」の現状:映画『地…
我々の日常生活は、原発が生み出す電気によって成り立っているが、核廃棄物の最終処分場は世界中で未だにどの国も決められていないのが現状だ。映画『地球で最も安全な場所を探して』をベースに、「核のゴミ」の問題の歴史と、それに立ち向かう人々の奮闘を知る
あわせて読みたい
【挑戦】東日本大震災における奇跡。日本の出版を支える日本製紙石巻工場のありえない復活劇:『紙つな…
本を読む人も書く人も作る人も、出版で使われる紙がどこで作られているのか知らない。その多くは、東日本大震災で甚大な被害を受けた日本製紙石巻工場で作られていた。『紙つなげ』をベースに、誰もが不可能だと思った早期復旧の舞台裏を知る
あわせて読みたい
【デマ】情報を”選ぶ”時代に、メディアの情報の”正しさ”はどのように判断されるのか?:『ニューヨーク…
一昔前、我々は「正しい情報を欲していた」はずだ。しかしいつの間にか世の中は変わった。「欲しい情報を正しいと思う」ようになったのだ。この激変は、トランプ元大統領の台頭で一層明確になった。『ニューヨーク・タイムズを守った男』から、情報の受け取り方を問う
あわせて読みたい
【衝撃】森達也『A3』が指摘。地下鉄サリン事件を起こしたオウム真理教は社会を激変させた
「オウム真理教は特別だ、という理由で作られた”例外”が、いつの間にか社会の”前提”になっている」これが、森達也『A3』の主張の要点だ。異常な状態で続けられた麻原彰晃の裁判を傍聴したことをきっかけに、社会の”異様な”変質の正体を理解する。
あわせて読みたい
【無知】メディアの問題の本質は?「報道の限界」と「情報の受け取り方」を独裁政治の現実から知る:『…
メディアは確かに「事実」を報じている。しかし、報道に乗らない情報まで含めなければ、本当の意味で世の中を理解することは難しいと、『こうして世界は誤解する』は教えてくれる。アラブ諸国での取材の現実から、報道の「限界」と「受け取り方」を学ぶ
あわせて読みたい
【加虐】メディアの役割とは?森達也『A』が提示した「事実を報じる限界」と「思考停止社会」
オウム真理教の内部に潜入した、森達也のドキュメンタリー映画『A』は衝撃を与えた。しかしそれは、宗教団体ではなく、社会の方を切り取った作品だった。思考することを止めた社会の加虐性と、客観的な事実など切り取れないという現実について書く
あわせて読みたい
【勇敢】日本を救った吉田昌郎と、福島第一原発事故に死を賭して立ち向かった者たちの極限を知る:『死…
日本は、死を覚悟して福島第一原発に残った「Fukushima50」に救われた。東京を含めた東日本が壊滅してもおかしくなかった大災害において、現場の人間が何を考えどう行動したのかを、『死の淵を見た男』をベースに書く。全日本人必読の書
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
どう生きるべきか・どうしたらいい【本・映画の感想】 | ルシルナ
どんな人生を歩みたいか、多くの人が考えながら生きていると思います。私は自分自身も穏やかに、そして周囲の人や社会にとっても何か貢献できたらいいなと、思っています。…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…






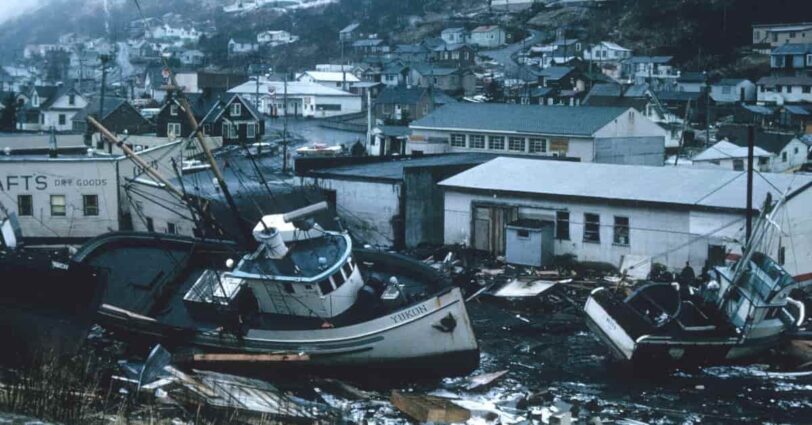













































































コメント