目次
はじめに
この記事で取り上げる映画
監督:ブラディ・コーベット, プロデュース:ブラディ・コーベット, プロデュース:トレヴァー・マシューズ, プロデュース:ニック・ゴードン, プロデュース:ブライアン・ヤング, プロデュース:アンドリュー・モリソン, プロデュース:アンドリュー・ローレン, プロデュース:D.J.グッゲンハイム, Writer:ブラディ・コーベット, Writer:モナ・ファストボールド, 出演:エイドリアン・ブロディ, 出演:フェリシティ・ジョーンズ, 出演:ガイ・ピアース, 出演:ジョー・アルウィン, 出演:ラフィー・キャシディ, 出演:ステイシー・マーティン, 出演:イザック・デ・バンコレ, 出演:アレッサンドロ・ニヴォラ
¥2,500 (2025/07/29 23:34時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
この映画をガイドにしながら記事を書いていきます
この記事の3つの要点
- 215分にも及ぶ本作では、表向き大した物語は描かれないのだが、底流ではずっと「不寛容」に焦点が当てられている
- 絶望と幸運の紆余曲折の果てに、主人公のラースローはある資産家のパトロンを得て飛躍し始める
- 5年以上も離れ離れで過ごしていた夫婦がついに再会を果たすも、2人は時代に引き裂かれてしまう
彼ほどの人物でもこれほど苦労させられたのだとすれば、同時代のユダヤ人はもっと大変だっただろうと想像させる物語でもある
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
記事中の引用は、映画館で取ったメモを参考にしているので、正確なものではありません
ある建築家の壮大な人生を描き出す映画『ブルータリスト』は、ホロコーストを生き延びたユダヤ人に対する“不寛容”を丁寧に描き出す
215分間淡々と展開し続けるだけの物語なのに、建築家のその壮大な人生に圧倒されてしまった

本作『ブルータリスト』は元々観ようと思っていた作品なのだが、公開直前に公開館などを調べていて驚いた。上映時間が215分となっていたからだ。ざっと3時間半である。配信で観るならともかく、劇場で観るにはなかなか気合が必要な映画と言えるだろう。
あわせて読みたい
【実話】映画『アウシュビッツ・レポート』が描き出す驚愕の史実。世界はいかにホロコーストを知ったのか?
映画『アウシュヴィッツ・レポート』は、アウシュビッツ強制収容所から抜け出し、詳細な記録と共にホロコーストの実態を世界に明らかにした実話を基にした作品。2人が持ち出した「アウシュビッツ・レポート」こそが、ホロコーストについて世界が知るきっかけだったのであり、そんな史実をまったく知らなかったことにも驚かされた
そしてもう1つ、私が鑑賞前の時点では理解していなかった点に触れておこうと思う。私は何となく、本作では「実在の人物が扱われている」のだと思い込んでいた。特に理由はない。そんなわけで、劇場で小冊子を受け取った時も特に疑問に思わなかったのだ。その小冊子は、本作の主人公である建築家ラースロー・トートの来歴をまとめたものだった。そして私は、「実在の人物なんだから、そりゃあこんな小冊子だって作れるよね」みたいに思いながら受け取ったのである。
ただ、その小冊子を読んでいる時、裏面の最後に小さく、「※本書の内容は一部を除きすべて架空の内容です。」と書かれていることに気づいた。そこで私はようやく、「そうか、ラースロー・トートは実在の人物じゃないんだな」と理解したのである。まあ、だからどうということもない話なのだが、個人的には「実話を基にした物語」である方が好みだったりもするので、「そうか違うのか」と感じたというわけだ。
さて私は本作を観て、215分もあるのに飽きさせない、実に壮大な物語だったことに驚かされた。
あわせて読みたい
【驚愕】これ以上の”サバイバル映画”は存在するか?火星にたった一人残された男の生存術と救出劇:『オ…
1人で火星に取り残された男のサバイバルと救出劇を、現実的な科学技術の範囲で描き出す驚異の映画『オデッセイ』。不可能を可能にするアイデアと勇気、自分や他人を信じ抜く気持ち、そして極限の状況でより困難な道を進む決断をする者たちの、想像を絶するドラマに胸打たれる
ただ、確かに「壮大」ではあるのだが、正直大した物語が描かれているわけではない。序盤こそ、「ホロコーストをギリギリ生き延びた主人公が、どうにかアメリカへと渡る」という歴史の重みを感じさせる展開だったが、それ以降は、「物語の規模」みたいな意味で言えばそこまでスケールは大きくないだろう。物語の骨子は、「ハンガリーでは新進気鋭だった建築家が、アメリカではしばらく不遇の時期を過ごすことになり、しかし様々な偶然と幸運によって、ある資産家の個人的なプロジェクトに関わるようになる」という感じで、別に凄まじくドラマチックなことが起こるわけでもない。
にも拘らず、本作にはかなり圧倒されてしまった。なかなか骨太の物語である。
「アメリカはホロコーストの生存者を”受け入れない”」という、主人公が感じ続けただろう視線について
「大した物語が描かれているわけではない」と書いた通り、主人公がアメリカの地を踏んでからの紆余曲折の人生は正直なところ、物語として描くほどの何かがあるようには見えないんじゃないかと思う。ただそれは、あくまでも「表の物語」の話である。
あわせて読みたい
【感動】映画『ボストン1947』は、アメリカ駐留時代の朝鮮がマラソンで奇跡を起こした実話を描く
映画『ボストン1947』は、アメリカ軍駐留時代の朝鮮を舞台に、様々な困難を乗り越えながらボストンマラソン出場を目指す者たちの奮闘を描き出す物語。日本統治下で日本人としてメダルを授与された”国民の英雄”ソン・ギジョンを中心に、「東洋の小国の奇跡」と評された驚くべき成果を実現させた者たちの努力と葛藤の実話である
本作ではその底流の部分に、ある感覚がずっと流れ続けているように私には感じられた。それが、「アメリカはホロコーストの生存者を”受け入れない”」である。そして、そんな物語を印象的に描き出そうとしたら、「こんな凄い人物でさえ受け入れられないのだ」と思わせる方が効果的だろう。だからこそ主人公は「ハンガリーで新進気鋭だった建築家」なのだろうし、そしてそんな人物の人生を215分も掛けて描き出したのだと思う。
ラースローが最初にそのことを強く実感したのは、早くにアメリカに移り住んでいたいとこのアティラとの関わりにおいてである。家具店を経営している彼はユダヤ人なのだが、妻に合わせる形でカトリックに改宗した。そして、命からがらアメリカに渡ったラースローは、まずは彼を頼ることにしたのである。建築家という経験を活かしながら家具店の仕事も手伝いつつ、店の一角に住まわせてもらって生活の基盤を作ろうと考えていたのだ。

しかし、そんな生活はある日突然終わってしまう。アティラから「もう協力出来ない」と突きつけられたからだ。表向きの理由は、「得意先の資産家を怒らせてしまったこと」である。ハリソンというその資産家の双子の息子・娘が、父親に内緒で書斎を作り変えるというサプライズを考えたのだが、結果としてこれがハリソンの逆鱗に触れてしまったのだ。そのためアティラは、その罪をラースローになすりつけるようにして彼を追い出したのである。
あわせて読みたい
【驚愕】映画『リアリティ』の衝撃。FBIによる、機密情報をリークした女性の尋問音源を完全再現(リアリ…
映画『リアリティ』は、恐らく過去類を見ないだろう構成の作品だ。なんと、「FBI捜査官が録音していた実際の音声データのやり取りを一言一句完全に再現した映画」なのである。「第2のスノーデン」とも評される”普通の女性”は、一体何故、国家に反旗を翻す”反逆者”になったのだろうか?
しかしより本質的な理由は、アティラの妻が関係している。ざっくり書くと、「彼女が『ラースローを受け入れたくない』と考えたために、彼は去らざるを得なくなった」のである。そしてそれは、妻の個人的な感覚というより、やはり「アメリカという国が、ユダヤ人の受け入れを拒んでいる」みたいに捉える方が自然だろうと思う。
ただ結果的には、ハリソンの書斎の仕事を請け負っていたことが、彼の人生を大きく変えることに繋がった。どんな経緯からそうなったのかは是非本編を観てほしいが、かなり不遇な生活を送っていたラースローに「蜘蛛の糸」が垂れてきたかのように、その境遇が一変するのである。
ハリソンは後々こんなことを語っていた。
多少なりとも権威を持つ者として、”時代の才能”を育てることは責務だと考えている。
あわせて読みたい
【驚愕】ベリングキャットの調査報道がプーチンを追い詰める。映画『ナワリヌイ』が示す暗殺未遂の真実
弁護士であり、登録者数640万人を超えるYouTuberでもあるアレクセイ・ナワリヌイは、プーチンに対抗して大統領選挙に出馬しようとしたせいで暗殺されかかった。その実行犯を特定する調査をベリングキャットと共に行った記録映画『ナワリヌイ』は、現実とは思えないあまりの衝撃に満ちている
「才能ある人物にチャンスを与え、飛躍のきっかけを与える」という役割にかなり自覚的だったというわけだ。そしてこのことからも分かるように、ハリソンはラースローのことをかなり高く評価しているのである。
また別の場面でのやり取りも興味深かったなと思う。ハリソンがラースローに「どうして建築をやる?」と質問した際に、彼は「何事もそれ自体は説明しない。立方体には本質的に、その構造以外の説明があるか?」と答えた後、さらに次のような話をしていた。
戦争は多くのものを破壊したが、私のプロジェクトの多くは残った。いずれ、戦争の惨禍が人々を辱めなくなった頃に、建築物が政治的刺激の代わりになってくれたら嬉しい。
なかなか含蓄のある言葉ではないだろうか。そしてこの返答に対してハリソンは、「実に詩的な回答だ」と感心していた。恐らく、本心だと思う。私の感触では、ハリソンの周囲にいる人間はハリソンほどラースローに関心を抱いていないようなのだが、ハリソンだけは「その才能に嫉妬する」と口に出すほど、ラースローという個人に強く興味を持っているのである。
あわせて読みたい
【狂気】バケモン・鶴瓶を映し出す映画。「おもしろいオッチャン」に潜む「異常さ」と「芸への情熱」:…
「俺が死ぬまで公開するな」という条件で撮影が許可された映画『バケモン』。コロナ禍で映画館が苦境に立たされなければ、公開はずっと先だっただろう。テレビで見るのとは違う「芸人・笑福亭鶴瓶」の凄みを、古典落語の名作と名高い「らくだ」の変遷と共に切り取る
そしてこの時彼は、「少なくともハリソンという人間には受け入れてもらえた」みたいな感覚になれたのではないかと思う。ハリソンの周りにいる者たちは、「どこの誰とも知れない人物が上流階級の世界に潜り込んでいること」に、何なら不快感すら抱いているように見えるのだが、ハリソンからの敬意・関心は本物である。そして、「こんな風に認めてもらえた」という事実は彼にとって、かなり誇らしいことだったに違いないと思う。

しかしそんな「蜜月」も、残念ながらずっと続くわけではなかった。しかも、かつて書斎の改装に関わった時と同じように、ラースロー自身にはまったく非の無い状況が、結果として彼を破滅に導くことになったのである。いや、「まったく非が無い」とも言えないか。ハリソンのプロジェクトは、個人発注のものとしてはなかなかの規模のものであり、だからこそ関わる人間も多い。そんな中でラースローは、自身の主張を押し通そうとかなり高圧的な振る舞いを続けていたのだ。それが災いした可能性も無くはない。とはいえ、仮にラースローがお行儀よくしていたところで、あんな「事故」が起こってしまえばどうにもならなかっただろうとは思うけれども。
そんなわけでラースローは、またしても「受け入れられた」という感覚を手放さなければならなくなってしまった。このように、「アメリカ」という分厚い壁に幾度も跳ね返される、そんな人生が描かれる作品なのだ。
あわせて読みたい
【妄執】チェス史上における天才ボビー・フィッシャーを描く映画。冷戦下の米ソ対立が盤上でも:映画『…
「500年に一度の天才」などと評され、一介のチェスプレーヤーでありながら世界的な名声を獲得するに至ったアメリカ人のボビー・フィッシャー。彼の生涯を描く映画『完全なるチェックメイト』から、今でも「伝説」と語り継がれる対局と、冷戦下ゆえの激動を知る
後に合流した妻エルジェーベトとの関係性の変化
また、「受け入れられたかどうか」みたいな描写は他にもあった。ラースローは、欧州に妻エルジェーベトを残したままアメリカにやってきたのだが、そんな彼女との関係性においてもこの話が絡んでくるのだ。
物語後半に、ラースローが欧州を脱出した時のことについて語る場面がある。彼が乗った船がアメリカに辿り着いたことはかなり幸運だったようで、そもそも出航さえ出来なかった船も多かったという。また、男女で収容所が別だったからだろう、ラースローは妻・姪と離れ離れにされており、同じタイミングで脱出することも叶わなかったのである。
さらに、戦後しばらくの間「アメリカを目指そうとするユダヤ人」がかなり多かったこと、そして姪には何らかの事情(結局詳しくは説明されなかった)があったことから、「姪を置いて妻だけがアメリカを目指す」みたいなことも出来なかった。2人でアメリカを目指すには2人の関係性を示すものを用意しなければならず、それもあってアメリカの地を踏むのにかなりの時間がかかってしまったのだ。
そしてその間に、2人の関係性は大きく変わってしまっていたのである。
あわせて読みたい
【助けて】映画『生きててごめんなさい』は、「共依存カップル」視点で生きづらい世の中を抉る物語(主…
映画『生きててごめんなさい』は、「ちょっと歪な共依存関係」を描きながら、ある種現代的な「生きづらさ」を抉り出す作品。出版社の編集部で働きながら小説の新人賞を目指す園田修一は何故、バイトを9度もクビになり、一日中ベッドの上で何もせずに過ごす同棲相手・清川莉奈を”必要とする”のか?
ラースローがハンガリーにいた頃の描写は本作中には存在しないので、2人が元々どんな夫婦だったのかは分からない。しかし、どうにかアメリカに辿り着いたラースローが、「エルジェーベトは生きてるぞ」とアティラから聞かされた時に大号泣していたことを考えると、お互いの存在を思いやる良い夫婦だったんじゃないかという気がする。しかし彼は、後に姪と共にアメリカにやってきた妻とどうにも上手く関われなくなっていくのだ。
さて、本作において観客はずっと「ラースローが辿ってきた苦労」を追うことになる。最初こそアティラのことを頼れはしたものの、その関係はすぐに破綻してしまい、ラースローは1人で生きていくしかなくなってしまう。そしてその後、紆余曲折あってようやく、建築家としての手腕を再び発揮できる状況にまで辿り着いていたのである。
そして妻と姪がやってきたのはそんな、「様々な苦労の末に、建築家としてのキャリアをどうにか再び重ねられそうだ」というタイミングだったのだ。ラースローの感覚で言えば恐らく、「相当しんどい思いをしてどうにかここまで来たのだから、なんとかやり遂げたい」みたいな感じだったんじゃないかと思う。
そしてそんなラースローにエルジェーベトは共感できなくなっていったのだと私は受け取った。
あわせて読みたい
【あらすじ】「愛されたい」「必要とされたい」はこんなに難しい。藤崎彩織が描く「ままならない関係性…
好きな人の隣にいたい。そんなシンプルな願いこそ、一番難しい。誰かの特別になるために「異性」であることを諦め、でも「異性」として見られないことに苦しさを覚えてしまう。藤崎彩織『ふたご』が描き出す、名前がつかない切実な関係性
私は別に、エルジェーベトを非難したいわけではない。このすれ違いは結局、「離れ離れになっていた間の『苦労』が違いすぎて、お互いの『苦労』が共有出来なくなってしまっただけ」だと思っているからだ。
ハンガリーにいた頃はたぶん、2人とも同じような苦労を重ねてきていて、だからこそ、どれだけ大変でも分かり合えたんじゃないかという気がする。しかし、慣れないアメリカの地で慣れない生き方をしてきたラースローと、事情を抱えた姪を守りつつ欧州をどうにか脱出しようと奮闘していたエルジェーベトとでは、「苦労」の性質があまりにも違いすぎた。そしてそんな異なる数年間を過ごしたが故に、2人の関係性は決定的に壊れてしまったのだろう。
言っても仕方ないことではあるが、もしラースローとエルジェーベトが同じタイミングでアメリカまで来られていれば、彼らは同じ苦労を重ねながら今も良い関係性のままでいられたのではないかと思う。しかし、結果として全然違う苦労を積み重ねてきたことで、「お互いがお互いを受け入れられない」という状態になってしまったんじゃないだろうか。
あわせて読みたい
【映画】『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』で号泣し続けた私はTVアニメを観ていない
TVアニメは観ていない、というかその存在さえ知らず、物語や登場人物の設定も何も知らないまま観に行った映画『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』に、私は大号泣した。「悪意のない物語」は基本的に好きではないが、この作品は驚くほど私に突き刺さった
そのことが、何だかとても淋しく感じられてしまったなと思う。
映画『ブルータリスト』のその他感想
ラースローは、アメリカでの辛い生活の苦痛から逃れるために、割と早い段階から薬物に手を出していた。そしてそのこともまた、彼の人生に暗い影を落としてしまう。しんどい日常をやり過ごすためには仕方ない選択だったのかもしれないが、「ハンガリーにずっといられればその才能を十全に発揮できただろう人物が薬物に冒されていく」というのは非常にもったいない気分にさせられた。

さらに、後半で描かれる姪のある決断は、ラースロー、エルジェーベトどちらにも大きな衝撃を与えるものであり、そのこともある種の「心労」に繋がっていったのだと思う。そしてそういう様々な状況がアメリカへと渡ったラースローの生活を蝕み、少しずつ土台を腐らせながら絶望が積み上がっていくみたいな人生だったのである。
あわせて読みたい
【勇敢】ユダヤ人を救った杉原千畝を描く映画。日本政府の方針に反しながら信念を貫いた男の生き様
日本政府の方針に逆らってまでユダヤ人のためにビザを発給し続けた外交官を描く映画『杉原千畝』。日本を良くしたいと考えてモスクワを夢見た青年は、何故キャリアを捨てる覚悟で「命のビザ」を発給したのか。困難な状況を前に、いかに決断するかを考えさせられる
物語の前半では特に、常にギリギリの状態に置かれながら、それでもどうにか人生を前進させようとして奮闘するラースローの姿にかなり惹きつけられるんじゃないかと思う。また、彼ほどの才能を持つ人物でもこれほどの苦労を経験したのだと理解できれば、同時代のユダヤ人たちがどれだけ苦労したのかも推し量れる気がする。表に見えている部分以外の様々な奥行きを感じさせる作品であり、そういう意味での重厚感みたいなものはかなり強く感じられた。
さて本作については、撮影に関して1点気になっていることがある。「あの建造物を実際に建てたのだろうか?」という点についてだ。ハリソンによる個人プロジェクトではなかなか壮大な建造物を造ることになっており、本作では後半、そんなメチャクチャデカい建造物を組み立てている様子がタイムラプス的な映像で挿入されるのである。まあ、普通に考えればCGだろう。しかし、特に予算の潤沢なアメリカの映画の場合、「CGかと思ったけど実は実写だった」みたいなことはよくあるし、だとすれば、実際に建てている可能性もゼロではないと思う。個人的には、「本当に建てていてほしいな」と願ってしまいたくもなる。
また、上映時間が3時間半もあるからだろう、途中休憩が設けられていた。映画館がそのように設定していたのではなく、本編中にちゃんと「休憩時間」が組み込まれているのだ。ラースローとエルジェーベトが結婚した際の記念写真をバックに「Intermission」と表示され、15分のカウントが始まるのである。休憩が用意されている映画は時々あるが、本編中に組み込まれているのはかなり珍しいように思う。ちなみに逆パターンだが、映画『RRR』では、本編中に「Intermission」の表示が出てくるにも拘らず、劇場側の判断だったのか、そのまま休憩なしで上映が続いたような記憶がある。色んなケースが存在するものだ。
あわせて読みたい
【驚異】映画『RRR』『バーフバリ』は「観るエナジードリンク」だ!これ程の作品にはなかなか出会えないぞ
2022年に劇場公開されるや、そのあまりの面白さから爆発的人気を博し、現在に至るまでロングラン上映が続いている『RRR』と、同監督作の『バーフバリ』は、大げさではなく「全人類にオススメ」と言える超絶的な傑作だ。まだ観ていない人がいるなら、是非観てほしい!
さらに、本作のエンドロールは斜めに移動していくスタイルであり、かなりインパクトがあったなと思う。少なくとも私は、そういうスタイルのエンドロールを初めて観た気がする。また、途中からまったく無音のまま文字がスクロールしていくのも凄く良かった。冒頭の自由の女神像の登場もインパクトが大きかったし、最初から最後まで印象的な映画だったなと思う。
監督:ブラディ・コーベット, プロデュース:ブラディ・コーベット, プロデュース:トレヴァー・マシューズ, プロデュース:ニック・ゴードン, プロデュース:ブライアン・ヤング, プロデュース:アンドリュー・モリソン, プロデュース:アンドリュー・ローレン, プロデュース:D.J.グッゲンハイム, Writer:ブラディ・コーベット, Writer:モナ・ファストボールド, 出演:エイドリアン・ブロディ, 出演:フェリシティ・ジョーンズ, 出演:ガイ・ピアース, 出演:ジョー・アルウィン, 出演:ラフィー・キャシディ, 出演:ステイシー・マーティン, 出演:イザック・デ・バンコレ, 出演:アレッサンドロ・ニヴォラ
¥2,500 (2025/07/29 23:36時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品視聴済】私が観てきた映画(フィクション)を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が観てきた映画(フィクション)を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。
最後に
本作は、米アカデミー賞で10部門にノミネートされ、3部門で受賞を果たしたそうだ。確かに、そういう評価を得るのも納得という感じの作品である。215分という長さはちょっとハードルの高さを感じさせるだろうが、是非挑戦してみてほしい。その壮大さに圧倒させられるだろう。
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を…
Kindleで本を出版しました。タイトルは、『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を分かりやすく書いた本:相対性理論も宇宙論も量子論も』です。科学や科学者に関する、文系の人でも読んでもらえる作品に仕上げました。そんな自著について紹介をしています。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【冷戦】”アメリカのビートルズ”と評された、「鉄のカーテンを超えた初のロックバンド」を襲った悲劇:…
映画『ブラッド・スウェット&ティアーズに何が起こったのか?』では、米ソ冷戦の最中に人気を博したロックバンド・BS&Tが辿った数奇な運命を描き出すドキュメンタリー映画である。当時は公表できなかった理由により「鉄のカーテン」の向こう側に行かざるを得なかった彼らは、何を見て、どんな不遇に直面させられたのか?
あわせて読みたい
【異様】映画『聖なるイチジクの種』は、イランで起こった実際の市民デモを背景にした驚愕の物語である
「家庭内で銃を紛失した」という設定しか知らずに観に行った映画『聖なるイチジクの種』は、「実際に起こった市民デモをベースに、イランという国家の狂気をあぶり出す作品」であり、思いがけず惹きつけられてしまった。「反政府的な作品」に関わった本作監督・役者・スタッフらが処罰されるなど、人生を賭けて生み出された映画でもある
あわせて読みたい
【父親】パキスタン本国では上映禁止の映画『ジョイランド』は、古い価値観に翻弄される家族を描く
映画『ジョイランド』は、本国パキスタンで一時上映禁止とされた作品だが、私たち日本人からすれば「どうして?」と感じるような内容だと思う。「(旧弊な)家族観を否定している」と受け取られたからだろうが、それにしたってやはり理不尽だ。そしてそんな「家族のややこしさ」には、現代日本を生きる我々も共感できるに違いない
あわせて読みたい
【解説】映画『シビル・ウォー アメリカ最後の日』は、凄まじい臨場感で内戦を描き、我々を警告する(…
映画『シビル・ウォー』は、「アメリカで勃発した内戦が長期化し、既に日常になってしまっている」という現実を圧倒的な臨場感で描き出す作品だ。戦争を伝える報道カメラマンを主人公に据え、「戦争そのもの」よりも「誰にどう戦争を伝えるか」に焦点を当てる本作は、様々な葛藤を抱きながら最前線を目指す者たちを切り取っていく
あわせて読みたい
【変異】映画『動物界』は斬新で刺激的な作品だった。我々はまさにこんな”分断社会”に生きている
映画『動物界』では、「奇病によって人間が動物化してしまう」という世界における複雑な人間模様が描き出される。パンデミックを経験した我々には、本作の設定は「単なるSF」には感じられないはずだ。そしてその上で、「『動物化してしまった妻を今も愛している主人公』が見せる実にややこしい感情」が複層的に描かれていて実に興味深い
あわせて読みたい
【絶望】映画『若き見知らぬ者たち』が描くのは”不正解”だが、「じゃあ”正解”って何?」ってなる(監督…
映画『若き見知らぬ者たち』は、「まともな生活が送れなくなった母親の介護」を筆頭に、かなり絶望的な状況に置かれている若者たちを描き出す作品だ。あまりにも不毛で、あまりにも救いがなく、あまりにも辛すぎるその日々は、ついに限界を迎える。そしてその絶望を、磯村勇斗がその凄まじい存在感によって体現していく
あわせて読みたい
【天才】映画『箱男』はやはり、安部公房がSNSの無い時代に見通した「匿名性」への洞察が驚異的(監督:…
映画『箱男』は、安部公房本人から映画化権を託されるも一度は企画が頓挫、しかしその後27年の月日を経て完成させた石井岳龍の執念が宿る作品だ。SNSなど無かった時代に生み出された「匿名性」に関する洞察と、「本物とは何か?」という深淵な問いが折り重なるようにして進む物語で、その魅惑的な雰囲気に観客は幻惑される
あわせて読みたい
【絶望】満員続出の映画『どうすればよかったか?』が描き出す、娘の統合失調症を認めない両親の不条理
たった4館から100館以上にまで上映館が拡大した話題の映画『どうすればよかったか?』を公開2日目に観に行った私は、「ドキュメンタリー映画がどうしてこれほど注目されているのだろうか?」と不思議に感じた。統合失調症を発症した姉を中心に家族を切り取る本作は、観る者に「自分だったらどうするか?」という問いを突きつける
あわせて読みたい
【異様】映画『大いなる不在』(近浦啓)は、認知症の父を中心に「記憶」と「存在」の複雑さを描く(主…
「父親が逮捕され、どうやら認知症のようだ」という一報を受けた息子が、30年間ほぼやり取りのなかった父親と再会するところから始まる映画『大いなる不在』は、なんとも言えない「不穏さ」に満ちた物語だった。「記憶」と「存在」のややこしさを問う本作は、「物語」としては成立していないが、圧倒的な“リアリティ”に満ちている
あわせて読みたい
【孤独】映画『ナミビアの砂漠』は、自由だが居場所がない主人公を演じる河合優実の存在感が圧倒的(監…
映画『ナミビアの砂漠』は、とにかく「河合優実が凄まじい」のひと言に尽きる作品だ。彼女が演じたカナという主人公の「捉えどころの無さ」は絶妙で、一見すると凄まじく「自由」に羽ばたいている感じなのに、実際には全然「自由」には見えないというバランスが見事だった。特段の物語はないのに、137分間惹きつけられてしまうだろう
あわせて読みたい
【現在】ウーマンラッシュアワー村本大輔がテレビから消えた理由と彼の”優しさ”を描く映画:『アイアム…
「テレビから消えた」と言われるウーマンラッシュアワー・村本大輔に密着する映画『アイアム・ア・コメディアン』は、彼に対してさほど関心を抱いていない人でも面白く観られるドキュメンタリー映画だと思う。自身の存在意義を「拡声器」のように捉え、様々な社会問題を「お笑い」で発信し続ける姿には、静かな感動さえ抱かされるだろう
あわせて読みたい
【真相?】映画『マミー』が描く和歌山毒物カレー事件・林眞須美の冤罪の可能性。超面白い!
世間を大騒ぎさせた「和歌山毒物カレー事件」の犯人とされた林眞須美死刑囚は無実かもしれない。映画『マミー』は、そんな可能性を示唆する作品だ。「目撃証言」と「ヒ素の鑑定」が詳細に検証し直され、さらに「保険金詐欺をやっていた」という夫の証言も相まって、証拠的にも感情的にも支持したくなるような驚きの仮説である
あわせて読みたい
【あらすじ】有村架純が保護司を演じた映画『前科者』が抉る、罪を犯した者を待つ「更生」という現実
映画『前科者』は、仮釈放中の元受刑者の更生を手助けするボランティアである「保護司」を中心に据えることで、「元犯罪者をどう受け入れるべきか」「保護司としての葛藤」などを絶妙に描き出す作品。個別の事件への処罰感情はともかく、「社会全体としていかに犯罪を減らしていくか」という観点を忘れるべきではないと私は思っている
あわせて読みたい
【狂気】群青いろ制作『雨降って、ジ・エンド。』は、主演の古川琴音が成立させている映画だ
映画『雨降って、ジ・エンド。』は、冒頭からしばらくの間「若い女性とオジサンのちょっと変わった関係」を描く物語なのですが、後半のある時点から「共感を一切排除する」かのごとき展開になる物語です。色んな意味で「普通なら成立し得ない物語」だと思うのですが、古川琴音の演技などのお陰で、絶妙な形で素敵な作品に仕上がっています
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『52ヘルツのクジラたち』の「無音で叫ぶ人」と「耳を澄ます人」の絶妙な響鳴(原作:…
映画『52ヘルツのクジラたち』は、「現代的な問題のごった煮」と感じられてしまうような”過剰さ”に溢れてはいますが、タイトルが作品全体を絶妙に上手くまとめていて良かったなと思います。主演の杉咲花がやはり見事で、身体の内側から「不幸」が滲み出ているような演技には圧倒されてしまいました
あわせて読みたい
【衝撃】EUの難民問題の狂気的縮図!ポーランド・ベラルーシ国境での、国による非人道的対応:映画『人…
上映に際し政府から妨害を受けたという映画『人間の境界』は、ポーランド・ベラルーシ国境で起こっていた凄まじい現実が描かれている。「両国間で中東からの難民を押し付け合う」という醜悪さは見るに絶えないが、そのような状況下でも「可能な範囲でどうにか人助けをしたい」と考える者たちの奮闘には救われる思いがした
あわせて読みたい
【赦し】映画『過去負う者』が描く「元犯罪者の更生」から、社会による排除が再犯を生む現実を知る
映画『過去負う者』は、冒頭で「フィクション」だと明示されるにも拘らず、観ながら何度も「ドキュメンタリーだっけ?」と感じさせられるという、実に特異な体験をさせられた作品である。実在する「元犯罪者の更生を支援する団体」を舞台にした物語で、当然それは、私たち一般市民にも無関係ではない話なのだ
あわせて読みたい
【実話】映画『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』が描く、白人警官による黒人射殺事件
映画『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』は、2011年に起こった実際の事件を元にした作品である。何の罪もない黒人男性が、白人警官に射殺されてしまったのだ。5時22分から始まる状況をほぼリアルタイムで描き切る83分間の物語には、役者の凄まじい演技も含め、圧倒されてしまった
あわせて読みたい
【挑戦】映画『燃えあがる女性記者たち』が描く、インドカースト最下位・ダリットの女性による報道
映画『燃えあがる女性記者たち』は、インドで「カースト外の不可触民」として扱われるダリットの女性たちが立ち上げた新聞社「カバル・ラハリヤ」を取り上げる。自身の境遇に抗って、辛い状況にいる人の声を届けたり権力者を糾弾したりする彼女たちの奮闘ぶりが、インドの民主主義を変革させるかもしれない
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『戦場のピアニスト』(ロマン・ポランスキー)が描く、ユダヤ人迫害の衝撃の実話
映画『戦場のピアニスト』の4Kリマスター版を観に行ったところ、上映後のトークイベントに主人公の息子が登壇したので驚いた。何せ私は、本作が「実話を基にしている」ことさえ知らなかったのである。だからその驚きもひとしおだった。ホロコーストの生存者である主人公の壮絶な人生を描き出す、不朽の名作だ
あわせて読みたい
【斬新】フィクション?ドキュメンタリー?驚きの手法で撮られた、現実と虚構が入り混じる映画:『最悪…
映画『最悪な子どもたち』は、最後まで観てもフィクションなのかドキュメンタリーなのか確信が持てなかった、普段なかなか抱くことのない感覚がもたらされる作品だった。「演技未経験」の少年少女を集めての撮影はかなり実験的に感じられたし、「分からないこと」に惹かれる作品と言えるいだろうと思う
あわせて読みたい
【天才】映画『笑いのカイブツ』のモデル「伝説のハガキ職人ツチヤタカユキ」の狂気に共感させられた
『「伝説のハガキ職人」として知られるツチヤタカユキの自伝的小説を基にした映画『笑いのカイブツ』は、凄まじい狂気に彩られた作品だった。「お笑い」にすべてを捧げ、「お笑い」以外はどうでもいいと考えているツチヤタカユキが、「コミュ力」や「人間関係」で躓かされる”理不尽”な世の中に、色々と考えさせられる
あわせて読みたい
【狂気】異質なホラー映画『みなに幸あれ』(古川琴音主演)は古い因習に似せた「社会の異様さ」を描く
古川琴音主演映画『みなに幸あれ』は、”シュールさ”さえ感じさせる「異質なホラー映画」だ。「村の因習」というよくあるパターンをベースに据えつつ、そこで展開される異様な状況が、実は「私たちが生きる世界」に対応しているという構成になっている。「お前の物語だからな」と終始突きつけられ続ける作品だ
あわせて読みたい
【感想】関東大震災前後を描く映画『福田村事件』(森達也)は、社会が孕む「思考停止」と「差別問題」…
森達也監督初の劇映画である『福田村事件』は、100年前の関東大震災直後に起こった「デマを起点とする悲劇」が扱われる作品だ。しかし、そんな作品全体が伝えるメッセージは、「100年前よりも現代の方がよりヤバい」だと私は感じた。SNS時代だからこそ意識すべき問題の詰まった、挑発的な作品である
あわせて読みたい
【抵抗】映画『熊は、いない』は、映画製作を禁じられた映画監督ジャファル・パナヒの執念の結晶だ
映画『熊は、いない』は、「イラン当局から映画製作を20年間も禁じられながら、その後も作品を生み出し続けるジャファル・パナヒ監督」の手によるもので、彼は本作公開後に収監させられてしまった。パナヒ監督が「本人役」として出演する、「ドキュメンタリーとフィクションのあわい」を縫うような異様な作品だ
あわせて読みたい
【実話】映画『月』(石井裕也)は、障害者施設での虐待事件から「見て見ぬふりする社会」を抉る(出演…
実際に起こった障害者施設殺傷事件を基にした映画『月』(石井裕也)は、観客を作中世界に引きずり込み、「これはお前たちの物語だぞ」と刃を突きつける圧巻の作品だ。「意思疎通が不可能なら殺していい」という主張には誰もが反対するはずだが、しかしその態度は、ブーメランのように私たちに戻ってくることになる
あわせて読みたい
【感想】映画『正欲』に超共感。多様性の時代でさえどこに行っても馴染めない者たちの業苦を抉る(出演…
映画『正欲』は、私には共感しかない作品だ。特に、新垣結衣演じる桐生夏月と磯村勇斗演じる佐々木佳道が抱える葛藤や息苦しさは私の内側にあるものと同じで、その描かれ方に圧倒されてしまった。「『多様性』には『理解』も『受け入れ』も不要で、単に否定しなければ十分」なのだと改めて思う
あわせて読みたい
【嫌悪】映画『ドライビング・バニー』が描く、人生やり直したい主人公(母親)のウザさと絶望
映画『ドライビング・バニー』は、主人公であるバニーのことが最後まで嫌いだったにも拘わらず、全体的にはとても素敵に感じられた珍しいタイプの作品だ。私は、「バニーのような人間が世の中に存在する」という事実に嫌悪感を抱いてしまうのだが、それでも、狂気的でぶっ飛んだラストシーンによって、作品全体の印象が大きく変わったと言える
あわせて読みたい
【絶望】人生どん底から生き方を変える。映画『シスター 夏のわかれ道』が描く中国人女性の葛藤と諦念
両親の死をきっかけに、「見知らぬ弟」を引き取らなければならなくなった女性を描く映画『シスター 夏のわかれ道』は、中国の特異な状況を背景にしつつ、誰もが抱き得る普遍的な葛藤が切り取られていく。現状を打破するために北京の大学院を目指す主人公は、一体どんな決断を下すのか。
あわせて読みたい
【未知】コーダに密着した映画『私だけ聴こえる』は、ろう者と聴者の狭間で居場所がない苦悩を映し出す
あなたは「コーダ」と呼ばれる存在を知っているだろうか?「耳の聴こえない親を持つ、耳が聴こえる子ども」のことであり、映画『私だけ聴こえる』は、まさにそんなコーダが置かれた状況を描くドキュメンタリー映画だ。自身は障害者ではないのに大変な苦労を強いられている現状が理解できる作品
あわせて読みたい
【現実】映画『私のはなし 部落のはなし』で初めて同和・部落問題を考えた。差別はいかに生まれ、続くのか
私はずっと、「部落差別なんてものが存在する意味が分からない」と感じてきたが、映画『私のはなし 部落のはなし』を観てようやく、「どうしてそんな差別が存在し得るのか」という歴史が何となく理解できた。非常に複雑で解決の難しい問題だが、まずは多くの人が正しく理解することが必要だと言えるだろう
あわせて読みたい
【助けて】映画『生きててごめんなさい』は、「共依存カップル」視点で生きづらい世の中を抉る物語(主…
映画『生きててごめんなさい』は、「ちょっと歪な共依存関係」を描きながら、ある種現代的な「生きづらさ」を抉り出す作品。出版社の編集部で働きながら小説の新人賞を目指す園田修一は何故、バイトを9度もクビになり、一日中ベッドの上で何もせずに過ごす同棲相手・清川莉奈を”必要とする”のか?
あわせて読みたい
【共感】斎藤工主演映画『零落』(浅野いにお原作)が、「創作の評価」を抉る。あと、趣里が良い!
かつてヒット作を生み出しながらも、今では「オワコン」みたいな扱いをされている漫画家を中心に描く映画『零落』は、「バズったものは正義」という世の中に斬り込んでいく。私自身は創作者ではないが、「売れる」「売れない」に支配されてしまう主人公の葛藤はよく理解できるつもりだ
あわせて読みたい
【希望】誰も傷つけたくない。でも辛い。逃げたい。絶望しかない。それでも生きていく勇気がほしい時に…
2006年発売、2021年文庫化の『私を見て、ぎゅっと愛して』は、ブログ本のクオリティとは思えない凄まじい言語化力で、1人の女性の内面の葛藤を抉り、読者をグサグサと突き刺す。信じがたい展開が連続する苦しい状況の中で、著者は大事なものを見失わず手放さずに、勇敢に前へ進んでいく
あわせて読みたい
【信念】凄いな久遠チョコレート!映画『チョコレートな人々』が映す、障害者雇用に挑む社長の奮闘
重度の人たちも含め、障害者を最低賃金保証で雇用するというかなり無謀な挑戦を続ける夏目浩次を追う映画『チョコレートな人々』には衝撃を受けた。キレイゴトではなく、「障害者を真っ当に雇用したい」と考えて「久遠チョコレート」を軌道に乗せたとんでもない改革者の軌跡を追うドキュメンタリー
あわせて読みたい
【家族】ゲイの男性が、拘置所を出所した20歳の男性と養子縁組し親子関係になるドキュメンタリー:映画…
「ゲイの男性が、拘置所から出所した20歳の男性と養子縁組し、親子関係になる」という現実を起点にしたドキュメンタリー映画『二十歳の息子』は、奇妙だが実に興味深い作品だ。しばらく何が描かれているのか分からない展開や、「ゲイであること」に焦点が当たらない構成など、随所で「不協和音」が鳴り響く1作
あわせて読みたい
【天才】映画『Winny』(松本優作監督)で知った、金子勇の凄さと著作権法侵害事件の真相(ビットコイン…
稀代の天才プログラマー・金子勇が著作権法違反で逮捕・起訴された実話を描き出す映画『Winny』は、「警察の凄まじい横暴」「不用意な天才と、テック系知識に明るい弁護士のタッグ」「Winnyが明らかにしたとんでもない真実」など、見どころは多い。「金子勇=サトシ・ナカモト」説についても触れる
あわせて読みたい
【衝撃】これが実話とは。映画『ウーマン・トーキング』が描く、性被害を受けた女性たちの凄まじい決断
映画『ウーマン・トーキング』の驚くべき点は、実話を基にしているという点だ。しかもその事件が起こったのは2000年代に入ってから。とある宗教コミュニティ内で起こった連続レイプ事件を機に村の女性たちがある決断を下す物語であり、そこに至るまでの「ある種異様な話し合い」が丁寧に描かれていく
あわせて読みたい
【高卒】就職できる気がしない。韓国のブラック企業の実態をペ・ドゥナ主演『あしたの少女』が抉る
韓国で実際に起こった「事件」を基に作られた映画『あしたの少女』は、公開後に世論が動き、法律の改正案が国会を通過するほどの影響力を及ぼした。学校から実習先をあてがわれた1人の女子高生の運命を軸に描かれる凄まじい現実を、ペ・ドゥナ演じる女刑事が調べ尽くす
あわせて読みたい
【実話】映画『グリーンブック』は我々に問う。当たり前の行動に「差別意識」が含まれていないか、と
黒人差別が遥かに苛烈だった時代のアメリカにおいて、黒人ピアニストと彼に雇われた白人ドライバーを描く映画『グリーンブック』は、観客に「あなたも同じような振る舞いをしていないか?」と突きつける作品だ。「差別」に限らず、「同時代の『当たり前』に従った行動」について考え直させる1作
あわせて読みたい
【苦悩】「やりがいのある仕事」だから見て見ぬふり?映画『アシスタント』が抉る搾取のリアル
とある映画会社で働く女性の「とある1日」を描く映画『アシスタント』は、「働くことの理不尽さ」が前面に描かれる作品だ。「雑用」に甘んじるしかない彼女の葛藤がリアルに描かれている。しかしそれだけではない。映画の「背景」にあるのは、あまりに悪逆な行為と、大勢による「見て見ぬふり」である
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』を観てくれ!現代の人間関係の教科書的作品を考…
映画『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』は、私にグサグサ突き刺さるとても素晴らしい映画だった。「ぬいぐるみに話しかける」という活動内容の大学サークルを舞台にした物語であり、「マイノリティ的マインド」を持つ人たちの辛さや葛藤を、「マジョリティ視点」を絶妙に織り交ぜて描き出す傑作について考察する
あわせて読みたい
【居場所】菊地凛子主演映画『658km、陽子の旅』(熊切和嘉)は、引きこもりロードムービーの傑作
映画『658km、陽子の旅』は、主演の菊地凛子の存在感が圧倒的だった。夢破れて長年引きこもり続けている女性が、否応なしにヒッチハイクで弘前を目指さなければならなくなるロードムービーであり、他人や社会と関わることへの葛藤に塗れた主人公の変化が、とても「勇敢」なものに映る
あわせて読みたい
【異様】映画『大いなる不在』(近浦啓)は、認知症の父を中心に「記憶」と「存在」の複雑さを描く(主…
「父親が逮捕され、どうやら認知症のようだ」という一報を受けた息子が、30年間ほぼやり取りのなかった父親と再会するところから始まる映画『大いなる不在』は、なんとも言えない「不穏さ」に満ちた物語だった。「記憶」と「存在」のややこしさを問う本作は、「物語」としては成立していないが、圧倒的な“リアリティ”に満ちている
あわせて読みたい
【映画】今泉力哉監督『ちひろさん』(有村架純)が描く、「濃い寂しさ」が溶け合う素敵な関係性
今泉力哉監督、有村架純主演の映画『ちひろさん』は、その圧倒的な「寂しさの共有」がとても心地よい作品です。色んな「寂しさ」を抱えた様々な人と関わる、「元風俗嬢」であることを公言し海辺の町の弁当屋で働く「ちひろさん」からは、同じような「寂しさ」を抱える人を惹き付ける力強さが感じられるでしょう
あわせて読みたい
【違和感】映画『コントラ』は、「よく分かんない」が「よく分かんないけど面白い」に変わる不思議な作品
ほぼ内容を知らないまま観に行った映画『コントラ』は、最後の最後まで結局何も理解できなかったが、それでもとても面白い作品だった。「後ろ向きに歩く男」が放つ違和感を主人公・ソラの存在感が中和させており、奇妙なのに可能な限り「日常感」を失わせずに展開させる構成が見事だと思う
あわせて読みたい
【実話】ポートアーサー銃乱射事件を扱う映画『ニトラム』が示す、犯罪への傾倒に抗えない人生の不条理
オーストラリアで実際に起こった銃乱射事件の犯人の生い立ちを描く映画『ニトラム/NITRAM』は、「頼むから何も起こらないでくれ」と願ってしまうほどの異様な不穏さに満ちている。「社会に順応できない人間」を社会がどう受け入れるべきかについて改めて考えさせる作品だ
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『夕方のおともだち』は、「私はこう」という宣言からしか始まらない関係性の”純度”を描く
「こんな田舎にはもったいないほどのドM」と評された男が主人公の映画『夕方のおともだち』は、SM嬢と真性ドMの関わりを通じて、「宣言から始まる関係」の難しさを描き出す。「普通の世界」に息苦しさを感じ、どうしても馴染めないと思っている人に刺さるだろう作品
あわせて読みたい
【誠実】戸田真琴は「言葉の人」だ。コンプレックスだらけの人生を「思考」と「行動」で突き進んだ記録…
戸田真琴のエッセイ第2弾『人を心から愛したことがないのだと気づいてしまっても』は、デビュー作以上に「誰かのために言葉を紡ぐ」という決意が溢れた1冊だ。AV女優という自身のあり方を客観的に踏まえた上で、「届くべき言葉がきちんと届く」ために、彼女は身を削ってでも生きる
あわせて読みたい
【苦しい】「恋愛したくないし、興味ない」と気づいた女性が抉る、想像力が足りない社会の「暴力性」:…
「実は私は、恋愛的な関係を求めているわけじゃないかもしれない」と気づいた著者ムラタエリコが、自身の日常や専門学校でも学んだ写真との関わりを基に、「自分に相応しい関係性」や「社会の暴力性」について思考するエッセイ。久々に心にズバズバ刺さった、私にはとても刺激的な1冊だった。
あわせて読みたい
【感想】映画『朝が来る』が描く、「我が子を返して欲しい気持ち」を消せない特別養子縁組のリアル
「特別養子縁組」を軸に人々の葛藤を描く映画『朝が来る』は、決して「特別養子縁組」の話ではない。「『起こるだろうが、起こるはずがない』と思っていた状況」に直面せざるを得ない人々が、「すべての選択肢が不正解」という中でどんな決断を下すのかが問われる、非常に示唆に富む作品だ
あわせて読みたい
【感想】のん主演映画『私をくいとめて』から考える、「誰かと一緒にいられれば孤独じゃないのか」問題
のん(能年玲奈)が「おひとり様ライフ」を満喫する主人公を演じる映画『私をくいとめて』を観て、「孤独」について考えさせられた。「誰かと関わっていられれば孤独じゃない」という考えに私は賛同できないし、むしろ誰かと一緒にいる時の方がより強く孤独を感じることさえある
あわせて読みたい
【考察】映画『哀愁しんでれら』から、「正しい」より「間違ってはいない」を選んでしまう人生を考える
「シンデレラストーリー」の「その後」を残酷に描き出す映画『哀愁しんでれら』は、「幸せになりたい」という気持ちが結果として「幸せ」を遠ざけてしまう現実を描き出す。「正しい/間違ってはいない」「幸せ/不幸せではない」を区別せずに行動した結果としての悲惨な結末
あわせて読みたい
【違和感】平田オリザ『わかりあえないことから』は「コミュニケーション苦手」問題を新たな視点で捉え…
「コミュニケーションが苦手」なのは、テクニックの問題ではない!?『わかりあえないことから』は、学校でのコミュニケーション教育に携わる演劇人・平田オリザが抱いた違和感を起点に、「コミュニケーション教育」が抱える問題と、私たち日本人が進むべき道を示す1冊
あわせて読みたい
【あらすじ】蝦夷地の歴史と英雄・阿弖流為を描く高橋克彦の超大作小説『火怨』は全人類必読の超傑作
大げさではなく、「死ぬまでに絶対に読んでほしい1冊」としてお勧めしたい高橋克彦『火怨』は凄まじい小説だ。歴史が苦手で嫌いな私でも、上下1000ページの物語を一気読みだった。人間が人間として生きていく上で大事なものが詰まった、矜持と信念に溢れた物語に酔いしれてほしい
あわせて読みたい
【魅惑】バーバラ・ローデン監督・脚本・主演の映画『WANDA』の、70年代の作品とは思えない今感
映画館で観た予告が気になって、それ以外の情報を知らずに観に行った映画『WANDA』なんと70年代の映画だと知って驚かされた。まったく「古さ」を感じなかったからだ。主演だけでなく、監督・脚本も務めたバーバラ・ローデンが遺した、死後評価が高まった歴史的一作
あわせて読みたい
【あらすじ】ムロツヨシ主演映画『神は見返りを求める』の、”善意”が”悪意”に豹変するリアルが凄まじい
ムロツヨシ演じる田母神が「お人好し」から「復讐の権化」に豹変する映画『神は見返りを求める』。「こういう状況は、実際に世界中で起こっているだろう」と感じさせるリアリティが見事な作品だった。「善意」があっさりと踏みにじられる世界を、私たちは受け容れるべきだろうか?
あわせて読みたい
【感想】湯浅政明監督アニメ映画『犬王』は、実在した能楽師を”異形”として描くスペクタクル平家物語
観るつもりなし、期待値ゼロ、事前情報ほぼ皆無の状態で観た映画『犬王』(湯浅政明監督)はあまりにも凄まじく、私はこんなとんでもない傑作を見逃すところだったのかと驚愕させられた。原作の古川日出男が紡ぐ狂気の世界観に、リアルな「ライブ感」が加わった、素晴らしすぎる「音楽映画」
あわせて読みたい
【差別】映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』の衝撃。プーチンが支持する国の蛮行・LGBT狩り
プーチン大統領の後ろ盾を得て独裁を維持しているチェチェン共和国。その国で「ゲイ狩り」と呼ぶしかない異常事態が継続している。映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』は、そんな現実を命がけで映し出し、「現代版ホロコースト」に立ち向かう支援団体の奮闘も描く作品
あわせて読みたい
【あらすじ】死刑囚を救い出す実話を基にした映画『黒い司法』が指摘する、死刑制度の問題と黒人差別の現実
アメリカで死刑囚の支援を行う団体を立ち上げた若者の実話を基にした映画『黒い司法 0%からの奇跡』は、「死刑制度」の存在価値について考えさせる。上映後のトークイベントで、アメリカにおける「死刑制度」と「黒人差別」の結びつきを知り、一層驚かされた
あわせて読みたい
【不謹慎】コンプライアンス無視の『テレビで会えない芸人』松元ヒロを追う映画から芸と憲法を考える
かつてテレビの世界で大ブレイクを果たしながら、現在はテレビから完全に離れ、年間120もの公演を行う芸人・松元ヒロ。そんな知る人ぞ知る芸人を追った映画『テレビで会えない芸人』は、コンプライアンスに厳しく、少数派が蔑ろにされる社会へ一石を投じる、爆笑社会風刺である
あわせて読みたい
【対立】パレスチナとイスラエルの「音楽の架け橋」は実在する。映画『クレッシェンド』が描く奇跡の楽団
イスラエルとパレスチナの対立を背景に描く映画『クレッシェンド』は、ストーリーそのものは実話ではないものの、映画の中心となる「パレスチナ人・イスラエル人混合の管弦楽団」は実在する。私たちが生きる世界に残る様々な対立について、その「改善」の可能性を示唆する作品
あわせて読みたい
【実話】台湾のろう学校のいじめ・性的虐待事件を描く映画『無聲』が問う、あまりに悲しい現実
台湾のろう学校で実際に起こったいじめ・性的虐待事件を基に作られた映画『無聲』は、健常者の世界に刃を突きつける物語だ。これが実話だという事実に驚かされる。いじめ・性的虐待が物語の「大前提」でしかないという衝撃と、「性的虐待の方がマシ」という選択を躊躇せず行う少女のあまりの絶望を描き出す
あわせて読みたい
【衝撃】映画『ダンサー・イン・ザ・ダーク』凄い。ラストの衝撃、ビョークの演技、”愛”とは呼びたくな…
言わずとしれた名作映画『ダンサー・イン・ザ・ダーク』を、ほぼ予備知識ゼロのまま劇場で観た。とんでもない映画だった。苦手なミュージカルシーンが効果的だと感じられたこと、「最低最悪のラストは回避できたはずだ」という想い、そして「セルマのような人こそ報われてほしい」という祈り
あわせて読みたい
【芸術】実話を下敷きに描く映画『皮膚を売った男』は、「アートによる鮮やかな社会問題風刺」が見事
「シリア難民の背中にタトゥーを彫り芸術作品として展示する」と聞くと非常に不謹慎に感じられるだろうが、彫ったのが国家間の移動を自由にする「シェンゲンビザ」だという点が絶妙な皮肉。実話をベースにした映画『皮膚を売った男』の、アートによる社会問題提起の見事な鮮やかさ
あわせて読みたい
【抵抗】西加奈子のおすすめ小説『円卓』。「当たり前」と折り合いをつけられない生きづらさに超共感
小学3年生のこっこは、「孤独」と「人と違うこと」を愛するちょっと変わった女の子。三つ子の美人な姉を「平凡」と呼んで馬鹿にし、「眼帯」や「クラス会の途中、不整脈で倒れること」に憧れる。西加奈子『円卓』は、そんなこっこの振る舞いを通して「当たり前」について考えさせる
あわせて読みたい
【不安】環境活動家グレタを追う映画。「たったひとりのストライキ」から国連スピーチまでの奮闘と激変…
環境活動家であるグレタのことを、私はずっと「怒りの人」「正義の人」だとばかり思っていた。しかしそうではない。彼女は「不安」から、いても立ってもいられずに行動を起こしただけなのだ。映画『グレタ ひとりぼっちの挑戦』から、グレタの実像とその強い想いを知る
あわせて読みたい
【選択】映画『サウンド・オブ・メタル』で難聴に陥るバンドマンは、「障害」と「健常」の境界で揺れる
ドラムを叩くバンドマンが聴力を失ってしまう――そんな厳しい現実に直面する主人公を描く映画『サウンド・オブ・メタル』では、「『健常者との生活』を選ぶか否か」という選択が突きつけられる。ある意味では健常者にも向けられているこの問いに、どう答えるべきだろうか
あわせて読みたい
【苦しい】恋愛で寂しさは埋まらない。恋に悩む女性に「心の穴」を自覚させ、自己肯定感を高めるための…
「どうして恋愛が上手くいかないのか?」を起点にして、「女性として生きることの苦しさ」の正体を「心の穴」という言葉で説明する『なぜあなたは「愛してくれない人」を好きになるのか』はオススメ。「著者がAV監督」という情報に臆せず是非手を伸ばしてほしい
あわせて読みたい
【実話】「ホロコーストの映画」を観て改めて、「有事だから仕方ない」と言い訳しない人間でありたいと…
ノルウェーの警察が、自国在住のユダヤ人をまとめて船に乗せアウシュビッツへと送った衝撃の実話を元にした映画『ホロコーストの罪人』では、「自分はそんな愚かではない」と楽観してはいられない現実が映し出される。このような悲劇は、現在に至るまで幾度も起こっているのだ
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『流浪の月』を観て感じた、「『見て分かること』にしか反応できない世界」への気持ち悪さ
私は「見て分かること」に”しか”反応できない世界に日々苛立ちを覚えている。そういう社会だからこそ、映画『流浪の月』で描かれる文と更紗の関係も「気持ち悪い」と断罪されるのだ。私はむしろ、どうしようもなく文と更紗の関係を「羨ましい」と感じてしまう。
あわせて読みたい
【正義】復讐なんかに意味はない。それでも「この復讐は正しいかもしれない」と思わされる映画:『プロ…
私は基本的に「復讐」を許容できないが、『プロミシング・ヤング・ウーマン』の主人公キャシーの行動は正当化したい。法を犯す明らかにイカれた言動なのだが、その動機は一考の余地がある。何も考えずキャシーを非難していると、矢が自分の方に飛んでくる、恐ろしい作品
あわせて読みたい
【生きる】しんどい人生を宿命付けられた子どもはどう生きるべき?格差社会・いじめ・恋愛を詰め込んだ…
厳しい受験戦争、壮絶な格差社会、残忍ないじめ……中国の社会問題をこれでもかと詰め込み、重苦しさもありながら「ボーイ・ミーツ・ガール」の爽やかさも融合されている映画『少年の君』。辛い境遇の中で、「すべてが最悪な選択肢」と向き合う少年少女の姿に心打たれる
あわせて読みたい
【残念】日本の「難民受け入れ」の現実に衝撃。こんな「恥ずべき国」に生きているのだと絶望させられる…
日本の「難民認定率」が他の先進国と比べて異常に低いことは知っていた。しかし、日本の「難民」を取り巻く実状がこれほど酷いものだとはまったく知らなかった。日本で育った2人のクルド人難民に焦点を当てる映画『東京クルド』から、日本に住む「難民」の現実を知る
あわせて読みたい
【家族】映画『そして父になる』が問う「子どもの親である」、そして「親の子どもである」の意味とは?
「血の繋がり」だけが家族なのか?「将来の幸せ」を与えることが子育てなのか?実際に起こった「赤ちゃんの取り違え事件」に着想を得て、苦悩する家族を是枝裕和が描く映画『そして父になる』から、「家族とは何か?」「子育てや幸せとどう向き合うべきか?」を考える
あわせて読みたい
【正義】「正しさとは何か」を考えさせる映画『スリー・ビルボード』は、正しさの対立を絶妙に描く
「正しい」と主張するためには「正しさの基準」が必要だが、それでも「規制されていないことなら何でもしていいのか」は問題になる。3枚の立て看板というアナログなツールを使って現代のネット社会の現実をあぶり出す映画『スリー・ビルボード』から、「『正しさ』の難しさ」を考える
あわせて読みたい
【不正義】正しく行使されない権力こそ真の”悪”である。我々はその現実にどう立ち向かうべきだろうか:…
権力を持つ者のタガが外れてしまえば、市民は為す術がない。そんな状況に置かれた時、私たちにはどんな選択肢があるだろうか?白人警官が黒人を脅して殺害した、50年前の実際の事件をモチーフにした映画『デトロイト』から、「権力による不正義」の恐ろしさを知る
あわせて読みたい
【矛盾】その”誹謗中傷”は真っ当か?映画『万引き家族』から、日本社会の「善悪の判断基準」を考える
どんな理由があれ、法を犯した者は罰せられるべきだと思っている。しかしそれは、善悪の判断とは関係ない。映画『万引き家族』(是枝裕和監督)から、「国民の気分」によって「善悪」が決まる社会の是非と、「善悪の判断を保留する勇気」を持つ生き方について考える
あわせて読みたい
【実話】障害者との接し方を考えさせる映画『こんな夜更けにバナナかよ』から”対等な関係”の大事さを知る
「障害者だから◯◯だ」という決まりきった捉え方をどうしてもしてしまいがちですが、『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』の主人公・鹿野靖明の生き様を知れば、少しは考え方が変わるかもしれません。筋ジストロフィーのまま病院・家族から離れて“自活”する決断をした驚異の人生
あわせて読みたい
【考察】映画『ジョーカー』で知る。孤立無援の環境にこそ”悪”は偏在すると。個人の問題ではない
「バットマン」シリーズを観たことがない人間が、予備知識ゼロで映画『ジョーカー』を鑑賞。「悪」は「環境」に偏在し、誰もが「悪」に足を踏み入れ得ると改めて実感させられた。「個人」を断罪するだけでは社会から「悪」を減らせない現実について改めて考える
あわせて読みたい
【勇敢】”報道”は被害者を生む。私たちも同罪だ。”批判”による”正義の実現”は正義だろうか?:『リチャ…
「爆弾事件の被害を最小限に食い止めた英雄」が、メディアの勇み足のせいで「爆弾事件の犯人」と報じられてしまった実話を元にした映画『リチャード・ジュエル』から、「他人を公然と批判する行為」の是非と、「再発防止という名の正義」のあり方について考える
あわせて読みたい
【権利】衝撃のドキュメンタリー映画『ヤクザと憲法』は、「異質さを排除する社会」と「生きる権利」を問う
「ヤクザ」が排除された現在でも、「ヤクザが担ってきた機能」が不要になるわけじゃない。ではそれを、公権力が代替するのだろうか?実際の組事務所(東組清勇会)にカメラを持ち込むドキュメンタリー映画『ヤクザと憲法』が映し出す川口和秀・松山尚人・河野裕之の姿から、「基本的人権」のあり方について考えさせられた
あわせて読みたい
【告発】アメリカに”監視”される社会を暴露したスノーデンの苦悩と決断を映し出す映画:『スノーデン』…
NSA(アメリカ国家安全保障局)の最高機密にまでアクセスできたエドワード・スノーデンは、その機密情報を持ち出し内部告発を行った。「アメリカは世界中の通信を傍受している」と。『シチズンフォー』と『スノーデン』の2作品から、彼の告発内容とその葛藤を知る
あわせて読みたい
【絶望】光過敏症の女性の、真っ暗な部屋で光という光をすべて遮断しなければ生きられない壮絶な日常:…
日光に限らず、ありとあらゆる「光」に肌が異常に反応してしまうため、ずっと真っ暗闇の中でしか生きられない女性が、その壮絶すぎる日常を綴った『まっくらやみで見えたもの 光アレルギーのわたしの奇妙な人生』から、それでも生きていく強さを感じ取る
あわせて読みたい
【絶望】「人生上手くいかない」と感じる時、彼を思い出してほしい。壮絶な過去を背負って生きる彼を:…
「北九州連続監禁殺人事件」という、マスコミも報道規制するほどの残虐事件。その「主犯の息子」として生きざるを得なかった男の壮絶な人生。「ザ・ノンフィクション」のプロデューサーが『人殺しの息子と呼ばれて』で改めて取り上げた「真摯な男」の生き様と覚悟
あわせて読みたい
【現実】生きる気力が持てない世の中で”働く”だけが人生か?「踊るホームレスたち」の物語:映画『ダン…
「ホームレスは怠けている」という見方は誤りだと思うし、「働かないことが悪」だとも私には思えない。振付師・アオキ裕キ主催のホームレスのダンスチームを追う映画『ダンシングホームレス』から、社会のレールを外れても許容される社会の在り方を希求する
あわせて読みたい
【逃避】つまらない世の中で生きる毎日を押し流す”何か”を求める気持ちに強烈に共感する:映画『サクリ…
子どもの頃「台風」にワクワクしたように、未だに、「自分のつまらない日常を押し流してくれる『何か』」の存在を待ちわびてしまう。立教大学の学生が撮った映画『サクリファイス』は、そんな「何か」として「東日本大震災」を描き出す、チャレンジングな作品だ
あわせて読みたい
【リアル】社会の分断の仕組みを”ゾンビ”で学ぶ。「社会派ゾンビ映画」が対立の根源を抉り出す:映画『C…
まさか「ゾンビ映画」が、私たちが生きている現実をここまで活写するとは驚きだった。映画『CURED キュアード』をベースに、「見えない事実」がもたらす恐怖と、立場ごとに正しい主張をしながらも否応なしに「分断」が生まれてしまう状況について知る
あわせて読みたい
【実話】「家族とうまくいかない現実」に正解はあるか?選択肢が無いと感じる時、何を”選ぶ”べきか?:…
「自分の子どもなんだから、どんな風に育てたって勝手でしょ」という親の意見が正しいはずはないが、この言葉に反論することは難しい。虐待しようが生活能力が無かろうが、親は親だからだ。映画『MOTHER マザー』から、不正解しかない人生を考える
あわせて読みたい
【正義】マイノリティはどう生き、どう扱われるべきかを描く映画。「ルールを守る」だけが正解か?:映…
社会的弱者が闘争の末に権利を勝ち取ってきた歴史を知った上で私は、闘わずとも権利が認められるべきだと思っている。そして、そういう社会でない以上、「正義のためにルールを破るしかない」状況もある。映画『パブリック』から、ルールと正義のバランスを考える
あわせて読みたい
【権利】「難民だから支援すべき」じゃない。誰でも最低限の安全が確保できる世界であるべきだ:映画『…
難民申請中の少年が、国籍だけを理由にチェスの大会への出場でが危ぶまれる。そんな実際に起こった出来事を基にした『ファヒム パリが見た奇跡』は実に素晴らしい映画だが、賞賛すべきではない。「才能が無くても安全は担保されるべき」と考えるきっかけになる映画
あわせて読みたい
【情熱】「ルール」は守るため”だけ”に存在するのか?正義を実現するための「ルール」のあり方は?:映…
「ルールは守らなければならない」というのは大前提だが、常に例外は存在する。どれほど重度の自閉症患者でも断らない無許可の施設で、情熱を持って問題に対処する主人公を描く映画『スペシャルズ!』から、「ルールのあるべき姿」を考える
あわせて読みたい
【排除】「分かり合えない相手」だけが「間違い」か?想像力の欠如が生む「無理解」と「対立」:映画『…
「共感」が強すぎる世の中では、自然と「想像力」が失われてしまう。そうならないようにと意識して踏ん張らなければ、他人の価値観を正しく認めることができない人間になってしまうだろう。映画『ミセス・ノイズィ』から、多様な価値観を排除しない生き方を考える
あわせて読みたい
【実話】正論を振りかざす人が”強い”社会は窮屈だ。映画『すばらしき世界』が描く「正解の曖昧さ」
「SNSなどでの炎上を回避する」という気持ちから「正論を言うに留めよう」という態度がナチュラルになりつつある社会には、全員が全員の首を締め付け合っているような窮屈さを感じてしまう。西川美和『すばらしき世界』から、善悪の境界の曖昧さを体感する
あわせて読みたい
【再生】ヤクザの現実を切り取る映画『ヤクザと家族』から、我々が生きる社会の”今”を知る
「ヤクザ」を排除するだけでは「アンダーグラウンドの世界」は無くならないし、恐らく状況はより悪化しただけのはずだ。映画『ヤクザと家族』から、「悪は徹底的に叩きのめす」「悪じゃなければ何をしてもいい」という社会の風潮について考える。
あわせて読みたい
【救い】耐えられない辛さの中でどう生きるか。短歌で弱者の味方を志すホームレス少女の生き様:『セー…
死にゆく母を眺め、施設で暴力を振るわれ、拾った新聞で文字を覚えたという壮絶な過去を持つ鳥居。『セーラー服の歌人 鳥居』は、そんな辛い境遇を背景に、辛さに震えているだろう誰かを救うために短歌を生み出し続ける生き方を描き出す。凄い人がいるものだ
あわせて読みたい
【挑戦】自閉症のイメージを変えるおすすめ本。知的障害と”思い込む”専門家に挑む母子の闘い:『自閉症…
専門家の思い込みを覆し、自閉症のイメージを激変させた少年・イド。知的障害だと思われていた少年は、母親を通じコミュニケーションが取れるようになり、その知性を証明した。『自閉症の僕が「ありがとう」を言えるまで』が突きつける驚きの真実
あわせて読みたい
【加虐】メディアの役割とは?森達也『A』が提示した「事実を報じる限界」と「思考停止社会」
オウム真理教の内部に潜入した、森達也のドキュメンタリー映画『A』は衝撃を与えた。しかしそれは、宗教団体ではなく、社会の方を切り取った作品だった。思考することを止めた社会の加虐性と、客観的な事実など切り取れないという現実について書く
あわせて読みたい
【覚悟】人生しんどい。その場の”空気”から敢えて外れる3人の中学生の処世術から生き方を学ぶ:『私を知…
空気を読んで摩擦を減らす方が、集団の中では大体穏やかにいられます。この記事では、様々な理由からそんな選択をしない/できない、『私を知らないで』に登場する中学生の生き方から、厳しい現実といかにして向き合うかというスタンスを学びます
あわせて読みたい
【異常】「助けて」と言えない。自己責任社会のしんどさと、我が子がホームレスである可能性:『助けて…
39歳で餓死した男性は、何故誰にも助けを求めなかったのか?異常な視聴率を叩き出した、NHK「クローズアップ現代」の特集を元に書かれた『助けてと言えない』をベースに、「自己責任社会」の厳しさと、若者が置かれている現実について書く。
あわせて読みたい
【感想】人間関係って難しい。友達・恋人・家族になるよりも「あなた」のまま関わることに価値がある:…
誰かとの関係性には大抵、「友達」「恋人」「家族」のような名前がついてしまうし、そうなればその名前に縛られてしまいます。「名前がつかない関係性の奇跡」と「誰かを想う強い気持ちの表し方」について、『君の膵臓をたべたい』をベースに書いていきます
あわせて読みたい
【肯定】価値観の違いは受け入れられなくていい。「普通」に馴染めないからこそ見える世界:『君はレフ…
子どもの頃、周りと馴染めない感覚がとても強くて苦労しました。ただし、「普通」から意識的に外れる決断をしたことで、自分が持っている価値観を言葉で下支えすることができたとも感じています。「普通」に馴染めず、自分がダメだと感じてしまう人へ。
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
理不尽・ストレス・イライラする【本・映画の感想】 | ルシルナ
「理不尽だなー」と感じてしまうことはよくあります。クレームや怒りなど、悪意や無理解から責められることもあるでしょうし、多数派や常識的な考え方に合わせられないとい…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…



















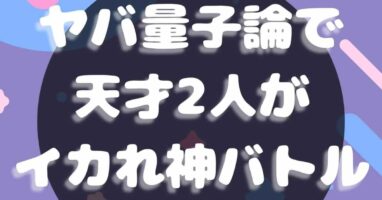









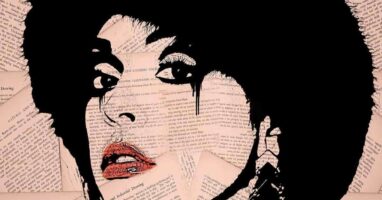

























































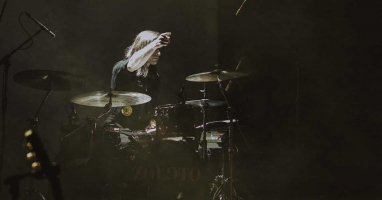











































コメント