目次
はじめに
この記事で取り上げる映画
監督:ロバート・ケナー, 監督:メリッサ・ロブレド, クリエイター:パーティパント&リバーロード, 出演:マイケル・ポーラン, 出演:ゲラルド・レイエス・チャベス, 出演:エリック・シュローサー, 出演:トニー・トンプソン, 出演:サラ・ロイド
¥440 (2025/06/23 06:25時点 | Amazon調べ)
ポチップ
VIDEO
この映画をガイドにしながら記事を書いていきます
この記事の3つの要点
「『超加工食品』は、『摂取カロリー』が低くても『代謝されないカロリー』が多いかもしれない」ことを示す興味深い研究結果 「独占禁止法(反トラスト法)」をベースに語られる寡占企業誕生の歴史と、顕在化してきた弊害 「寡占」によって競争原理が適切に働かないことによる「労働者の使い捨て」の現実はあまりにも酷すぎる これから生きていく上で知っておくべき「健康」や「食」に関する知見が満載の1作である
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
私たちを取り巻く「食」の環境は安全なのか?映画『フード・インク ポスト・コロナ』が描き出す、「世界的大企業による『食の支配』」の現実
あわせて読みたい
【危機】遺伝子組み換え作物の危険性を指摘。バイオ企業「モンサント社」の実態を暴く衝撃の映画:映画…
「遺伝子組み換え作物が危険かどうか」以上に注目すべきは、「モンサント社の除草剤を摂取して大丈夫か」である。種子を独占的に販売し、農家を借金まみれにし、世界中の作物の多様性を失わせようとしている現状を、映画「モンサントの不自然な食べもの」から知る
実に興味深い作品 だった。本作には、第1弾となる映画『フード・インク』 が存在するが、私はそちらを観てはいない。2011年公開の作品のようで、ポスタービジュアルには「ごはんがあぶない。 」と書かれている。そしてそれと同じスタイルで、コロナ後の世界の現状を描き出しているのが本作『フード・インク』 なのだろう。ちなみに、本作のポスタービジュアルには「あなたのごはん、大丈夫!? 」と書かれている。
監督:ロバート・ケナー, 出演:エリック・シュローサー, 出演:マイケル・ポーラン
ポチップ
本作でなされている警告 をひと言で表現するなら、「世界の『食』が危険な状態にある 」となるだろう。そしてその具体的な指摘が、実に興味深かった 。「代替肉」など鑑賞前の時点で知っていた話題もあるが、扱われる内容のほとんどが「こんなことになってるのか!」と感じるようなもの だったのだ。
確かに、本作で描かれているのは主にアメリカの現実 であり、世界中がグローバルに繋がっているとはいえ、今の日本に直接的に関係するものは正直なところそう多くはない かもしれない。ただもちろん無関係なはずがない し、また「世界的大企業の動向」は今後我々が生きていく未来の世界にも大きな影響を与え得る だろう。本作を観て日常の行動を大きく変えるなんて必要はないかもしれないが、少なくとも「知っておくべき現実」が扱われていることだけは確か だと思う。
本作『フード・インク ポスト・コロナ』の中で最も興味深く感じられた「超加工食品」の話
本作では実に様々な内容が扱われる のだが、その中でも、私が最も興味深いと感じた話題 から触れていくことにしよう。本作では全体的に「多国籍企業がヤバいことをしている」という現実が炙り出される のだが、今から説明するのはそれとは少し違った話 である。「ダイエット」なんかにも関係する話題 であり、本作の中で恐らく最も一般的な関心を喚起できる内容 ではないかと思う。
話の中心は「超加工食品 」である。正確な定義はともかく、概ね「糖分、塩分、脂肪をたんまり含んだ加工済みの食品 」のことを指す。ざっくり、「アメリカ人が食べている、添加物や着色料が山ほど入っていそうな身体に悪そうな食べ物 」をイメージすればいいだろう。本作では、「アメリカ人が摂取するカロリーの58%は超加工食品によるもの 」と表示されていたので、このイメージはほぼ間違っていないと思う。
あわせて読みたい
【危険】遺伝子組換え作物の問題点と、「食の安全」を守るために我々ができることを正しく理解しよう:…
映画『食の安全を守る人々』では、世界的バイオ企業「モンサント社」が作る除草剤「ラウンドアップ」の問題を中心に、「食の安全」の現状が映し出される。遺伝子組み換え作物や輸入作物の残留農薬など、我々が口にしているものの「実態」を理解しよう
正直なところ、日本にはこういう「超加工食品」はあまり無い ような気がする。しかし、だからと言って知らなくていいなんてことはない 。というのも、「超加工食品」に関する研究の過程で、実に興味深いことが判明した からだ。そしてその知見は、ダイエットにも活かせる はずである。
さて、作中で取り上げられる研究者は元々、「脳の報酬系」と「食品」の関係性を調べていた 。具体的には、「チョコレートを摂取した際の脳の活動の変化」の研究 である。チョコレートが脳のどの部位を刺激するか に関心を持っていたのだそうだ。
そんな研究を続けていたところ、ペプシ社から連絡がきた という。彼女の研究に興味を持ったようで、「資金を出すからさらなる研究をしてほしい 」とのことだった。ペプシ社が調べてほしいと考えていたのは、「もしも『甘みを変えずにカロリーだけを抑えた飲料』を作ったら、脳はどう反応するのか? 」だったそうだ。その研究者は、「ペプシ社は恐らく、より健康的な商品を作りたいと考えていたのでしょう」と、資金提供の理由を推測していた 。
あわせて読みたい
【使命】「CRISPR-Cas9」を分かりやすく説明。ノーベル賞受賞の著者による発見物語とその使命:『CRISPR…
生物学の研究を一変させることになった遺伝子編集技術「CRISPR-Cas9」の開発者は、そんな発明をするつもりなどまったくなかった。ノーベル化学賞を受賞した著者による『CRISPR (クリスパー) 究極の遺伝子編集技術の発見』をベースに、その発見物語を知る
さて、彼女が行った実験内容について説明する前に、後の説明で必要になるある事実 に触れておこう。「自然界における『甘さ』と『カロリー』の関係 」である。実はこの両者には相関関係が認められている のだという。例えば、「甘さ100」(単位は気にしないでほしい)の食べ物なら「カロリー100」という感じ である。「甘さ100」なのに「カロリー70」みたいな食べ物は、少なくとも自然界には存在しない そうなのだ。この事実は重要なので頭に入れておいてほしい。
それでは、彼女が実際に行った実験 について説明していこう。まず、「甘さは一定だが、カロリーだけを変えた飲料」を5種類用意した 。つまり、「甘さ100」に対して「カロリー30・70・100・150・200」といったような、カロリーだけが異なる飲料が5種類ある というわけだ(甘さやカロリーの数値は実際のものとは違い、説明を分かりやすくするために私が勝手に設定した)。そしてこれらを被験者に飲んでもらい、「脳が最も反応する飲料はどれか」を調べよう というのである。
彼女は当初、「『カロリー200の飲料』に最も強く脳が反応する」と考えていた そうだ。恐らくだが、彼女はこれまでの研究から「高カロリーのものほど脳が強く反応する」と理解していたのだろう し、だとすれば、「甘さが同じなら最もカロリーの高い飲料に脳が反応する」という発想は実に自然 だと言えるだろう。
あわせて読みたい
【興奮】世界的大ベストセラー『サピエンス全史』要約。人類が文明を築き上げるに至った3つの革命とは?
言わずと知れた大ベストセラー『サピエンス全史』は、「何故サピエンスだけが人類の中で生き残り、他の生物が成し得なかった歴史を歩んだのか」を、「認知革命」「農業革命」「科学革命」の3つを主軸としながら解き明かす、知的興奮に満ち溢れた1冊
しかし実際にはそうはならなかった 。実に興味深いことに、脳が最も反応したのは「甘さ」と「カロリー」が正しく対応したもの 、つまり「カロリー100の飲料」だった のだ。この点に関しては、この研究者とは別の学者が、「人類は長い年月をかけて、『甘さ(味)』から『カロリー』などを推定する能力を蓄積してきた 」みたいな話をしていた。これはもちろん現代ではなく、狩猟採集生活が行われていた時代の話 である。つまり、自然界にあるものは「甘さ」と「カロリー」が対応しており、さらに人類は「甘さ」から「カロリー」を推定する能力を高めてきたのだから、脳だって当然「甘さ」と「カロリー」が対応したものに反応するように進化していったと考えられる というわけだ。
さて、この事実だけでもなかなか興味深いだろうが、面白いのはここから である。さらに研究を行ったところ、「『甘さ』と『カロリー』が対応した飲料」の場合に最も代謝が高くなり、それ以外の飲料では代謝が落ちた というのだ。作中ではこれ以上詳しい説明はなされなかったので、推測も含めながらではあるが、この事実を私なりにもう少し解説してみたい と思う。
「代謝される 」というのは、「体内に取り込んだカロリーがエネルギーに変換され、体内には残らない 」という理解でいいだろう。そして、「『カロリー100の飲料』の場合に最も代謝が高まる 」というのは、「カロリーのエネルギー変換効率が最も高い 」と捉えればいいはずだ。というわけで、ここでは仮に「摂取したカロリー100の内、90が代謝され、10が体内に残る(脂肪に変換されるなど)」ということにしてみよう 。
あわせて読みたい
【新視点】世界の歴史を「化学」で語る?デンプン・砂糖・ニコチンなどの「炭素化合物」が人類を動かし…
デンプン・砂糖・ニコチンなどは、地球上で非常に稀少な元素である「炭素」から作られる「炭素化合物」だ。そんな「炭素化合物」がどんな影響を与えたかという観点から世界の歴史を描く『「元素の王者」が歴史を動かす』は、学校の授業とはまったく違う視点で「歴史」を捉える
一方、「カロリー100」以外の飲料では代謝が落ちる という。これは例えば、「カロリー70の飲料」を摂取した場合、「70の内40が代謝され、30が体内に残る」みたいに考えればいい ということだろう。まとめると、「カロリー100を摂取した時に体内に10残る 」「カロリー70を摂取した時に体内に30残る 」という話である。つまり、前者の方が摂取したカロリーは多いのに、後者の方が体内に残るカロリーが多い というわけだ。
実験によってこのように、「『自然界に存在する甘さに対応したカロリー』を摂取した方が、体内に残るカロリーを抑えられる」という結果が出た のである。これは要するに、ペプシ社の目論見が崩れたことを意味する だろう。彼らは「『甘さ』は変えずに『カロリー』を抑えた飲料を作れば、より健康的で訴求力のある商品が作れるのではないか」と考えていたのだが、「『甘さ』と『カロリー』が対応していないと、結果として体内に残るカロリーが増えてしまう」という可能性が示唆されてしまった というわけだ。
研究者は出た結果をペプシ社に送った そうだが、彼らは彼女に「この研究は意味不明だ」という主旨のメールを何通も送った挙げ句、資金提供も打ち切った という。研究者は本作中で、「後になって分かりましたが、ペプシ社は恐らく、私の研究の正しさを理解していたからこそそんな反応をしたのでしょう 」と当時のことについて語っていた。
あわせて読みたい
【要約】福岡伸一『生物と無生物のあいだ』は、「生命とは何か」を「動的平衡」によって定義する入門書…
「生命とは何か?」という、あまりに基本的だと感じられる問いは、実はなかなか難しい。20世紀生物学は「DNAの自己複製」が本質と考えたが、「ウイルス」の発見により再考を迫られた。福岡伸一の『生物と無生物のあいだ』『動的平衡』の2著作から、「生命の本質」を知る
さて、この研究結果は私たちの生活にも非常に重要になってくる と言えるだろう。例えば世の中には、「人工甘味料」と呼ばれる商品 が様々に存在する。その名の通り「人工的に作られた甘味料 」であり、「砂糖よりも甘く、一度に使う分量が減らせるので、摂取カロリーを抑えられる 」という理由で人気らしい。しかし先の研究を踏まえれば、確かに「摂取カロリー」は減るかもしれないが、「代謝されないカロリー(体内に残るカロリー)」はむしろ増える可能性がある のだ(「代謝されないカロリー」という表現は正しくないかもしれないが、まあ意味は通じるだろう)。
とはいえ、別に私は「自然由来のものがすべてにおいて勝る」みたいな主張をするつもりはない 。じゃがいもの芽の部分にあるらしい「ソラニン」や、あるいはフグ・キノコなど、いわゆる「自然毒」だってたくさん存在する からだ。とはいえ、この「超加工食品」の実験の話に絡めて言えば、「自然のもの、あるいは、『甘さ』と『カロリー』が自然のものと同等の関係性にあるもの」を摂取した方が健康にもダイエットにも良い ということは明白だろう。ダイエット中の人は特に、この点に気をつけた方がいい のではないかと思う。
ブラジルで行われた「超加工食品」に関する興味深い実験について
さて「超加工食品」については、もう1つ興味深い話 が出てきたので紹介しておこう。
あわせて読みたい
【生き方】人生が虚しいなら映画『人生フルーツ』を見ると良い。素敵な老夫婦の尖った人生がここにある
社会派のドキュメンタリー映画に定評のある東海テレビが、「なんでもない老夫婦の日常」を映画にした『人生フルーツ』には、特に何が起こるわけでもないのに「観て良かった」と感じさせる強さがある。見た目は「お年寄り」だが中身はまったく古臭くない”穏やかに尖った夫婦”の人生とは?
サンパウロの元小児科医が、「昔と比べて栄養失調の子どもが減り、肥満が増えている 」という事実に気がついた。これ自体は別に驚くようなことではないが、「一般消費者による『塩・砂糖・油の購入量』が減っている」というデータと併せると奇妙に思えてくる だろう。これらは肥満を誘発する食材 であり、「肥満が増えている」のならば、それらの購入量も増加していなければおかしい 。しかしデータでは、明らかに減少していた のだ。
そこで彼は「超加工食品」に目を付けた 。なんとブラジルでは既に、伝統的な食べ物・食事の多くが「超加工食品」に置き換わってしまっている という。となれば、これが原因の可能性もあるだろう。そこで彼は、この疑問を研究してくれる機関を探す ことにした。
そのような経緯で行われたのが次のような実験 だ。まず被験者を2つのグループに分け、別々の食事を提供した 。一方は「超加工食品をふんだんに使ったもの 」、そしてもう一方は「超加工食品をまったく使用しないもの 」である。両者はカロリーだけではなく、脂質や糖質などあらゆる要素が同じ になるように調整された。
あわせて読みたい
【化石】聞き馴染みのない「分子生物学」を通じて、科学という学問の本質を更科功が分かりやすく伝える…
映画『ジュラシック・パーク』を観たことがある方なら、「コハクの化石に閉じ込められた蚊の血液から恐竜の遺伝子を取り出す」という設定にワクワクしたことだろう。『化石の分子生物学』とは、まさにそのような研究を指す。科学以外の分野にも威力を発揮する知見に溢れた1冊
それぞれのグループにあてがわれた食事を食べてもらうのだが、重要なのは「食べる量は自分で決めていい」という指示 である。つまり、「満足いくまで食べて、もう十分だと思ったら残してもいい 」と伝えたのだ。
では、結果はどうなったのだろうか? 何となく想像出来るかもしれないが、「超加工食品をふんだんに使ったもの」の方がそうでない食事よりも500kcalも多く食べられた のだそうだ。食事における摂取カロリーの個人差は普通30~50kcalだそうで、500kcalもの違いが出るのは「異常」 と言っていいという。つまりこの研究によって、「超加工食品には、より多く食べさせる性質がある 」ことが判明したというわけだ。
これは、単に「摂取カロリーが増える」という話に留まらない 。先述のペプシ社が資金提供した研究の結果によると、「超加工食品は『甘さ』と『カロリー』が対応していない場合が多く、そのため『代謝されないカロリー』が多くなる 」のだから、「超加工食品を食べること」は、「摂取カロリー」も「代謝されないカロリー」もどちらも増やすことに繋がる のである。そりゃあ、「塩・砂糖・油の購入量」が減っていたってサンパウロの子どもは太る だろうし、「摂取カロリーの58%が超加工食品」であるアメリカ人も太る だろう。
あわせて読みたい
【事件】デュポン社のテフロン加工が有害だと示した男の執念の実話を描く映画『ダーク・ウォーターズ』
世界的大企業デュポン社が、自社製品「テフロン」の危険性を40年以上前に把握しながら公表せず、莫大な利益を上げてきた事件の真相を暴き出した1人の弁護士がいる。映画『ダーク・ウォーターズ』は、大企業相手に闘いを挑み、住民と正義のために走り続けた実在の人物の勇敢さを描き出す
色んな技術が進化したことで、私たちが食べるものは「甘さ」も「カロリー」も大きく調整されている可能性が高い はずだ。だからこそ「美味しい」と感じる のだろうし、結果として「たくさん食べてしまう」 のだと思う。しかし、そういう食品を摂取すればするほど、「代謝されないカロリー」が蓄積されていく だけというわけだ。コンビニや食品会社などが「カロリー控えめ」みたいな商品を色々と出していると思うが、もしかしたらそれらも、「自然界に存在する食べ物との相違が大きい」場合は、「代謝されないカロリー」ばかり摂り込んでいるにすぎないのかもしれない のである。
そんなわけでこの話は、健康に生きていく上で非常に重要な知見 と言えるのではないかと思う。
アメリカにおける「独占禁止法」の変遷と、近年浮き彫りになった弊害について
さて、本作『フード・インク ポスト・コロナ』で扱われる大きなテーマの中で、もう1つ興味深かったのが「独占禁止法」 である。
あわせて読みたい
【秘話】15年で世界を変えたグーグルの”異常な”創業エピソード。収益化無視の無料ビジネスはなぜ成功し…
スマホやネットを使う人で、グーグルのお世話になっていない人はまずいないだろう。もはや「インフラ」と呼んでいいレベルになったサービスを生み出した企業の創業からの歴史を描く『グーグル秘録』は、その歩みが「無邪気さ」と「偶然」の産物であることを示している。凄まじいエピソード満載の信じがたい企業秘話
本作を観る少し前、「『グーグルが反トラスト法に抵触している』ため、アメリカ司法省が事業の分割を要求するかもしれない」というニュース を見かけて驚かされたことを思い出す(「反トラスト法」は、日本でいう「独占禁止法」のこと) 。ただ私は正直、「何だかんだ、事業分割なんて話にはならないだろう」と思っていた 。グーグルは世界的に見ても超大企業であり、そんな強い企業を強いまま維持しておく方がアメリカ国家にとっても都合がいいはず だと考えていたからである。
しかし本作を観て、少し考えが変わった 。どうやらアメリカというのは、そもそも「『市場の独占を許さない』という方針を貫くことで発展してきた国」 らしいのである。「自由市場」を何よりも重視してきた国 であり、その分かりやすい例として「AT&T」という電話会社が紹介されていた 。
1940年代、AT&Tは市場の14%を占めており、当時のアメリカはこの数字を懸念していた という。私としては正直、「たった14%で『市場の独占』と判断されるのか? 」と感じたのだが、アメリカという国はそれぐらい「自由市場」を重視していた ということなのだろう。しかし結局当時は、「AT&Tを解体する」みたいな話にはならなかった。電話線の設置や管理などが急務であり、膨大な設備投資とその管理を行う会社は必要だと判断された からだ。
あわせて読みたい
【脅迫】原発という巨大権力と闘ったモーリーン・カーニーをイザベル・ユペールが熱演する映画『私はモ…
実話を基にした映画『私はモーリーン・カーニー』は、前半の流れからはちょっと想像もつかないような展開を見せる物語だ。原発企業で従業員の雇用を守る労働組合の代表を務める主人公が、巨大権力に立ち向かった挙げ句に自宅で襲撃されてしまうという物語から、「良き被害者」という捉え方の”狂気”が浮かび上がる
しかしその後、恐らく「市場の独占」が理由だったのだろう、AT&Tは解体された 。そしてそれにより、長距離電話の料金は劇的に下がり、そのお陰で、携帯電話やインターネットなどの技術革新が進んだ のだそうだ。作中では明確に、「『市場独占の解消』はイノベーションを生む 」を指摘されていた。
ただその後1980年代に入り、アメリカは少し方針を変えた という。「モノを安く提供するのであれば、1つの企業が業界を独占していても構わない」という判断 に変わっていったのだ。そしてそのようなタイミングを見計らって、企業は他社の買収を繰り返し巨大化していった 。こうして、決して食品業界に限る話ではないが、現在のような「ごく一握りの多国籍企業による市場独占」という状況が生まれることになった のである。
本作では、実際のデータ も示された。もちろんアメリカの数字だが、
食肉業界:大手4社で市場の85% シリアル業界:大手3社で市場の83% 炭酸飲料業界:大手2社で70% 乳児用ミルク業界:大手2社で80% というような凄まじい寡占状態 にあるという。
あわせて読みたい
【正義】ナン・ゴールディンの”覚悟”を映し出す映画『美と殺戮のすべて』が描く衝撃の薬害事件
映画『美と殺戮のすべて』は、写真家ナン・ゴールディンの凄まじい闘いが映し出されるドキュメンタリー映画である。ターゲットとなるのは、美術界にその名を轟かすサックラー家。なんと、彼らが創業した製薬会社で製造された処方薬によって、アメリカでは既に50万人が死亡しているのだ。そんな異次元の薬害事件が扱われる驚くべき作品
そしてこの寡占によって、現実に様々な弊害が生まれている 。
ある畜産業者は、買い取り金額の変化 の話をしていた。様々な加工業者が存在していた頃であれば、買い取り金額に納得いかなくても別の業者に売る選択肢があった が、今は加工業者が買収によって統廃合されたこともあり、相手の言い値で売らざるを得ない のだそうだ。まさしく、「競争原理がまともに働かなくなっている 」という状態だと言えるだろう。
また、寡占状態の脆弱性を示すこんなエピソード も紹介されている。ある時、乳児用ミルクを製造するアボット社が生産工場で問題を起こし、その工場の閉鎖を決めた 。すると、市場から43%もの乳児用ミルクが一気に消え、母親たちがミルク難民になってしまった というのだ。これもまた、とても健全な状態とは言えない だろう。
あわせて読みたい
【幻想】日本での子育ては無理ゲーだ。現実解としての「夜間保育園」の実状と親の想いを描く映画:『夜…
映画『夜間もやってる保育園』によると、夜間保育も行う無認可の「ベビーホテル」は全国に1749ヶ所あるのに対し、「認可夜間保育園」は全国にたった80ヶ所しかないそうだ。また「保育園に預けるなんて可哀想」という「家族幻想」も、子育てする親を苦しめている現実を描く
このように、「反トラスト法(独占禁止法)」をベースにして「企業の変遷」と「顕在化された弊害」が説明される 。アメリカがもう少し当初の方針、つまり「寡占状態を許さない」というスタンスを堅持していれば状況は違ったのかもしれない し、だとすれば、そんな反省を踏まえて「グーグルに対する事業分割」などに意欲を見せているのではないか とも思う。
「労働者の使い捨て」というあまりにも酷い現実
さらに、「企業による寡占状態」はより深刻な問題 を引き起こしていることが明らかにされる。それが「労働者の使い捨て 」だ。本作ではかなり冒頭で扱われるのだが、アイオワ州ウォータールーにある大手食肉会社「タイソン・フーズ」の工場の現状は、なかなか酷かった なと思う。
コロナウイルスが広がり始めた頃、この工場でも次々に陽性者が出始めた 。そのため、実際に保安官が工場へと足を運んだ そうだ。本作には、当時担当した保安官が出演しており、その時の驚きについて語っていた。タイソン・フーズの工場では多くの住民が働いており、街としても企業との関係を悪化させたくはない 。とはいえ、陽性者が続出している現状はどうにかする必要がある 。そこで工場内を見てみたのだが、そこはあまりにも酷い環境 だった。
あわせて読みたい
【信念】水俣病の真実を世界に伝えた写真家ユージン・スミスを描く映画。真実とは「痛みへの共感」だ:…
私はその存在をまったく知らなかったが、「水俣病」を「世界中が知る公害」にした報道写真家がいる。映画『MINAMATA―ミナマタ―』は、水俣病の真実を世界に伝えたユージン・スミスの知られざる生涯と、理不尽に立ち向かう多くの人々の奮闘を描き出す
本作では、コロナ禍前に撮影されたらしい工場内の様子 も映し出される。それを見ると、肘を突き合わせるようなかなり密集した環境 であることが分かるだろう。極限まで効率化されているのだと思う。そして保安官が工場内をチェックした際もその状態、つまり、感染対策など一切なされないまま作業員が働かされ、さらに、「従業員が床に吐いた後、何事もなかったかのようにそのまま作業に戻る」みたいな状況さえ目にした というのだ。
さすがにこれは問題だと考えたウォータールーは、タイソン・フーズ社に「10日~14日程度の操業停止」を申し入れた 。その頃には陽性者が爆発的に増え始め、死者も出るようになっていた からだ。しかし会社の反応は「あり得ない 」だった。それどころか同社は、当時の大統領であるドナルド・トランプに訴え出ることまでした のである。
さて、アメリカには「国防生産法」という法律が存在する のだそうだ。そしてタイソン・フーズ社はこの法律を盾に、「国民のための食肉生産を行っているのだから工場の操業を認めてほしい」と嘆願した 。そしてそれを受けて、トランプ大統領が工場の操業を許可する書類にサインした のである。
あわせて読みたい
【日本】原発再稼働が進むが、その安全性は?樋口英明の画期的判決とソーラーシェアリングを知る:映画…
映画『原発をとめた裁判長 そして原発をとめる農家たち』では、大飯原発の運転差し止め判決を下した裁判長による画期的な「樋口理論」の説明に重点が置かれる。「原発の耐震性」に関して知らないことが満載で、実に興味深かった。また、農家が発案した「ソーラーシェアリング」という新たな発電方法も注目である
しかし作中に登場した専門家は、「このような法律の運用はあり得ない 」と憤っていた。というのも「国防生産法」はそもそも「企業活動を抑止する」という目的で作られた法律 だからだ。それを逆手にとって、企業活動のために利用するなんてあり得ない というわけだ。しかし驚くべきはそれだけではない。「国防生産法」を盾にとって操業を続けた工場ではなんと、「海外輸出用の食肉」が多く加工されていた というのである。つまり、「国民のための食肉生産」というのは真っ赤な嘘だった というわけだ。「超大企業による寡占状態」が、このような「歪み」を引き起こしている と考えるべきだろう。
また本作は、フロリダ州イモカリーという地域での「労働者の使い捨て」の現実 を描くところから始まる。同地では南米やハイチなどの移民労働者が劣悪な環境下で働かされ、虐待・搾取が当たり前のように横行していた というのだ。競争原理が働かないからこそ、このような横暴が蔓延ってしまう のである。
しかしこの点に関しては映画の後半で、新たな取り組みによって改善した と紹介されていた。「フェアフードプログラム 」という仕組みが新たに生まれたのだ。これは、「『フェアフードプログラム』によって生産された農作物は、『フェアフードプログラム』と契約した企業しか購入できない 」という仕組みである。これによって、生産者の労働環境を守ろう というわけだ。
あわせて読みたい
【貢献】社会問題を解決する2人の「社会起業家」の生き方。「豊かさ」「生きがい」に必要なものは?:『…
「ヤクの毛」を使ったファッションブランド「SHOKAY」を立ち上げ、チベットの遊牧民と中国・崇明島に住む女性の貧困問題を解決した2人の若き社会起業家の奮闘を描く『世界を変えるオシゴト』は、「仕事の意義」や「『お金』だけではない人生の豊かさ」について考えさせてくれる
しかし、企業の中にはこの契約を受け入れないところも多い らしい。例えば作中では、ウェンディーズがこの取り組みを拒否し、トマトをフロリダ州ではなくブラジルから仕入れる形に変更した と紹介されていた。他にも多くの企業がこの仕組みを受け入れていない ようで、まだまだ十分に改善したとは言えない ようだ。とはいえ、フロリダ州では既に、生産されているトマトの9割が「フェアフードプログラム」によって作られている そうで、以前のような搾取・虐待は大幅に減っていると考えていいのではないか と思う。
このように、「寡占企業」の支配をかいくぐる取り組みがもっと広まればいい と思うし、そうやって「食の世界」が健全になっていくことで、巡り巡って日本に住む私たちの生活もより良くなっていくのだと信じたい 。
監督:ロバート・ケナー, 監督:メリッサ・ロブレド, クリエイター:パーティパント&リバーロード, 出演:マイケル・ポーラン, 出演:ゲラルド・レイエス・チャベス, 出演:エリック・シュローサー, 出演:トニー・トンプソン, 出演:サラ・ロイド
¥440 (2025/06/23 06:26時点 | Amazon調べ)
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品視聴済】私が観てきたドキュメンタリー映画を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が観てきたドキュメンタリー映画を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。
最後に
あわせて読みたい
【ゴミ】プラスチックによる環境問題の実態を描く衝撃の映画。我々は現実をあまりに知らない:映画『プ…
プラスチックごみによる海洋汚染は、我々の想像を遥かに超えている。そしてその現実は、「我々は日常的にマイクロプラスチックを摂取している」という問題にも繋がっている。映画『プラスチックの海』から、現代文明が引き起こしている環境破壊の現実を知る
本作では他にも、「政府が特定の農作物に補助金を出すせいで、豊かな土壌だったのに表土の半分が既に失われてしまった土地 」や「外科医やスタンフォード大学の教授の地位を捨ててまで代替肉の研究に没頭する者たち 」、あるいは「海洋資源を守るために昆布を育て始めた漁師 」など様々な人・状況が取り上げられている。また学校給食の話 もあり、「全体の3割は地元農家から仕入れることを定めたサンパウロ 」や、「流通業者からではなく農家からの直接仕入れに切り替えたニュージャージー州カムデン 」など、新しい取り組みも色々と紹介されていた。
本作では当然アメリカの事例ばかりが取り上げられている のだが、「食」には誰もが無関係ではいられないし、私たちも決して無視は出来ない と思う。恐らく、本作で描かれているのと比べれば、日本が置かれた状況は決して酷くないと思うが、これからどうなっていくのかは分からない 。また「食」に限る話ではないが、「購入する」というのはある種の「投票行動」 であり、私たちは普段の生活における「食の選択」によって、企業や社会に対して意思を示し続ける必要がある 。
本作は、そんな私たちの判断の参考になるような作品 とも言えるのではないかと思う。
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を…
Kindleで本を出版しました。タイトルは、『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を分かりやすく書いた本:相対性理論も宇宙論も量子論も』です。科学や科学者に関する、文系の人でも読んでもらえる作品に仕上げました。そんな自著について紹介をしています。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【悲劇】東京大空襲経験者の体験談。壊滅した浅草、隅田川の遺体、その後の人々の暮らし等の証言集:映…
映画『東京大空襲 CARPET BOMBING of Tokyo』は、2時間半で10万人の命が奪われたという「東京大空襲」を始め、「山手空襲」「八王子空襲」などを実際に経験した者たちの証言が収録された作品だ。そのあまりに悲惨な実態と、その記憶を具体的にはっきりと語る証言者の姿、そのどちらにも驚かされてしまった
あわせて読みたい
【異様】映画『聖なるイチジクの種』は、イランで起こった実際の市民デモを背景にした驚愕の物語である
「家庭内で銃を紛失した」という設定しか知らずに観に行った映画『聖なるイチジクの種』は、「実際に起こった市民デモをベースに、イランという国家の狂気をあぶり出す作品」であり、思いがけず惹きつけられてしまった。「反政府的な作品」に関わった本作監督・役者・スタッフらが処罰されるなど、人生を賭けて生み出された映画でもある
あわせて読みたい
【発見】映画『小学校~それは小さな社会~』(山崎エマ)が映し出すのは、我々には日常すぎる日常だ
映画『小学校~それは小さな社会~』は、ごく一般的な公立小学校に密着し、日本で生まれ育った人間には「当たり前」にしか思えない日常を切り取った作品なのだが、そんな映画が諸外国で大いに評価されているという。「TOKKATSU」という「日本式教育」が注目されているらしく、私たちの「当たり前」が違和感だらけに見えているのだそうだ
あわせて読みたい
金沢&富山のアート旅!「21世紀美術館」だけじゃない激アツなおすすめ美術館巡りをご提案
金沢・富山を巡るアート旅に出かけてきました!メインの目的は「21世紀美術館」でしたが、それ以上に「ASTER Curator Museum」「LIP BAR」「KAMU kanazawa」などがとにかく素晴らしかったです。アートや美術のことはド素人ですが、超個人的主観で「金沢・富山で触れられるアートの良さ」について書いた旅行記となります
あわせて読みたい
【日常】映画『大きな家』(竹林亮)は、児童養護施設で「家族」と「血縁」の違いや難しさに直面する
児童養護施設に長期密着した映画『大きな家』は、映画『14歳の栞』で中学2年生をフラットに撮り切った竹林亮が監督を務めたドキュメンタリーである。子どもたちの過去に焦点を当てるのではなく、「児童養護施設の日常風景」として彼らを捉えるスタンスで、その上でさらに「家族のあり方」に対する子どもたちの認識が掘り下げられる
あわせて読みたい
【映画】ディオールのデザイナーだった天才ジョン・ガリアーノが差別発言で破滅した人生を語る:映画『…
何者なのかまったく知らない状態で観たドキュメンタリー映画『ジョン・ガリアーノ 世界一愚かな天才デザイナー』は、差別発言によって失墜しすべてを失った天才デザイナーの凄まじい来歴が描かれる作品だ。実に複雑で興味深い存在だったし、その波乱の人生は、私のようなファッションに疎い人間でも面白く感じられると思う
あわせて読みたい
【変態】映画『コンセント/同意』が描く50歳と14歳少女の”恋”は「キモっ!」では終われない
映画『コンセント/同意』は、50歳の著名小説家に恋をした14歳の少女が大人になってから出版した「告発本」をベースに作られた作品だ。もちろん実話を元にしており、その焦点はタイトルの通り「同意」にある。自ら望んで36歳年上の男性との恋に踏み出した少女は、いかにして「同意させられた」という状況に追い込まれたのか?
あわせて読みたい
【正義?】FBIが警告した映画『HOW TO BLOW UP』は環境活動家の実力行使をリアルに描き出す
映画『HOW TO BLOW UP』は、「テロを助長する」としてFBIが警告を発したことでも話題になったが、最後まで観てみると、エンタメ作品として実に見事で、とにかく脚本が優れた作品だった。「環境アクティビストが、石油パイプラインを爆破する」というシンプルな物語が、見事な脚本・演出によって魅力的に仕上がっている
あわせて読みたい
【実話】映画『ダム・マネー ウォール街を狙え!』は「株で大儲けした」だけじゃない痛快さが面白い
ダム・マネー ウォール街を狙え!』では、株取引で莫大な利益を得た実在の人物が取り上げられる。しかし驚くべきは「大金を得たこと」ではない。というのも彼はなんと、資産5万ドルの身にも拘らず、ウォール街の超巨大資本ファンドを脅かす存在になったのである! 実話とは思えない、あまりにも痛快な物語だった
あわせて読みたい
【SDGs】パリコレデザイナー中里唯馬がファッション界の大量生産・大量消費マインド脱却に挑む映画:『…
映画『燃えるドレスを紡いで』は、世界的ファッションデザイナーである中里唯馬が、「服の墓場」と言うべきナイロビの現状を踏まえ、「もう服を作るのは止めましょう」というメッセージをパリコレの場から発信するまでを映し出すドキュメンタリー映画である。個人レベルで社会を変革しようとする凄まじい行動力と才能に圧倒させられた
あわせて読みたい
【幻惑】映画『落下の解剖学』は、「真実は誰かが”決める”しかない」という現実の不安定さを抉る
「ある死」を巡って混沌とする状況をリアルに描き出す映画『落下の解剖学』は、「客観的な真実にはたどり着けない」という困難さを炙り出す作品に感じられた。事故なのか殺人なのか自殺なのか、明確な証拠が存在しない状況下で、憶測を繋ぎ合わせるようにして進行する「裁判」の様子から、「『真実性』の捉えがたさ」がよく理解できる
あわせて読みたい
【正義】ナン・ゴールディンの”覚悟”を映し出す映画『美と殺戮のすべて』が描く衝撃の薬害事件
映画『美と殺戮のすべて』は、写真家ナン・ゴールディンの凄まじい闘いが映し出されるドキュメンタリー映画である。ターゲットとなるのは、美術界にその名を轟かすサックラー家。なんと、彼らが創業した製薬会社で製造された処方薬によって、アメリカでは既に50万人が死亡しているのだ。そんな異次元の薬害事件が扱われる驚くべき作品
あわせて読みたい
【衝撃】EUの難民問題の狂気的縮図!ポーランド・ベラルーシ国境での、国による非人道的対応:映画『人…
上映に際し政府から妨害を受けたという映画『人間の境界』は、ポーランド・ベラルーシ国境で起こっていた凄まじい現実が描かれている。「両国間で中東からの難民を押し付け合う」という醜悪さは見るに絶えないが、そのような状況下でも「可能な範囲でどうにか人助けをしたい」と考える者たちの奮闘には救われる思いがした
あわせて読みたい
【真相】飯塚事件は冤罪で死刑執行されたのか?西日本新聞・警察・弁護士が語る葛藤と贖罪:映画『正義…
映画『正義の行方』では、冤罪のまま死刑が執行されたかもしれない「飯塚事件」が扱われる。「久間三千年が犯行を行ったのか」という議論とは別に、「当時の捜査・司法手続きは正しかったのか?」という観点からも捉え直されるべきだし、それを自発的に行った西日本新聞の「再検証連載」はとても素晴らしかったと思う
あわせて読みたい
【実話】映画『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』が描く、白人警官による黒人射殺事件
映画『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』は、2011年に起こった実際の事件を元にした作品である。何の罪もない黒人男性が、白人警官に射殺されてしまったのだ。5時22分から始まる状況をほぼリアルタイムで描き切る83分間の物語には、役者の凄まじい演技も含め、圧倒されてしまった
あわせて読みたい
【挑戦】映画『燃えあがる女性記者たち』が描く、インドカースト最下位・ダリットの女性による報道
映画『燃えあがる女性記者たち』は、インドで「カースト外の不可触民」として扱われるダリットの女性たちが立ち上げた新聞社「カバル・ラハリヤ」を取り上げる。自身の境遇に抗って、辛い状況にいる人の声を届けたり権力者を糾弾したりする彼女たちの奮闘ぶりが、インドの民主主義を変革させるかもしれない
あわせて読みたい
【日本】原発再稼働が進むが、その安全性は?樋口英明の画期的判決とソーラーシェアリングを知る:映画…
映画『原発をとめた裁判長 そして原発をとめる農家たち』では、大飯原発の運転差し止め判決を下した裁判長による画期的な「樋口理論」の説明に重点が置かれる。「原発の耐震性」に関して知らないことが満載で、実に興味深かった。また、農家が発案した「ソーラーシェアリング」という新たな発電方法も注目である
あわせて読みたい
【あらすじ】原爆を作った人の後悔・葛藤を描く映画『オッペンハイマー』のための予習と評価(クリスト…
クリストファー・ノーラン監督作品『オッペンハイマー』は、原爆開発を主導した人物の葛藤・苦悩を複雑に描き出す作品だ。人間が持つ「多面性」を様々な方向から捉えようとする作品であり、受け取り方は人それぞれ異なるだろう。鑑賞前に知っておいた方がいい知識についてまとめたので、参考にしてほしい
あわせて読みたい
【驚愕】映画『リアリティ』の衝撃。FBIによる、機密情報をリークした女性の尋問音源を完全再現(リアリ…
映画『リアリティ』は、恐らく過去類を見ないだろう構成の作品だ。なんと、「FBI捜査官が録音していた実際の音声データのやり取りを一言一句完全に再現した映画」なのである。「第2のスノーデン」とも評される”普通の女性”は、一体何故、国家に反旗を翻す”反逆者”になったのだろうか?
あわせて読みたい
【無謀】映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、脱北ルートに撮影隊が同行する衝撃のドキュメンタリー
北朝鮮からの脱北者に同行し撮影を行う衝撃のドキュメンタリー映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、再現映像を一切使用していない衝撃的な作品だ。危険と隣り合わせの脱北の道程にカメラもついて回り、北朝鮮の厳しい現状と共に、脱北者が置かれた凄まじい状況を映し出す内容に驚かされてしまった
あわせて読みたい
【脅迫】原発という巨大権力と闘ったモーリーン・カーニーをイザベル・ユペールが熱演する映画『私はモ…
実話を基にした映画『私はモーリーン・カーニー』は、前半の流れからはちょっと想像もつかないような展開を見せる物語だ。原発企業で従業員の雇用を守る労働組合の代表を務める主人公が、巨大権力に立ち向かった挙げ句に自宅で襲撃されてしまうという物語から、「良き被害者」という捉え方の”狂気”が浮かび上がる
あわせて読みたい
【絶望】安倍首相へのヤジが”排除”された衝撃の事件から、日本の民主主義の危機を考える:映画『ヤジと…
映画『ヤジと民主主義 劇場拡大版』が映し出すのは、「政治家にヤジを飛ばしただけで国家権力に制止させられた個人」を巡る凄まじい現実だ。「表現の自由」を威圧的に抑えつけようとする国家の横暴は、まさに「民主主義」の危機を象徴していると言えるだろう。全国民が知るべき、とんでもない事件である
あわせて読みたい
【現実】我々が食べてる魚は奴隷船が獲ったもの?映画『ゴースト・フリート』が描く驚くべき漁業の問題
私たちは、「奴隷」が獲った魚を食べているのかもしれない。映画『ゴースト・フリート』が描くのは、「拉致され、数十年も遠洋船上に隔離されながら漁をさせられている奴隷」の存在だ。本作は、その信じがたい現実に挑む女性活動家を追うドキュメンタリー映画であり、まさに世界が関心を持つべき問題だと思う
あわせて読みたい
【衝撃】映画『誰がハマーショルドを殺したか』は、予想外すぎる着地を見せる普通じゃないドキュメンタリー
国連事務総長だったハマーショルドが乗ったチャーター機が不審な墜落を遂げた事件を、ドキュメンタリー映画監督マッツ・ブリュガーが追う映画『誰がハマーショルドを殺したか』は、予想もつかない衝撃の展開を見せる作品だ。全世界を揺るがしかねない驚きの”真実”とは?
あわせて読みたい
【狂気】入管の収容所を隠し撮りした映画『牛久』は、日本の難民受け入れ問題を抉るドキュメンタリー
映画『牛久』は、記録装置の持ち込みが一切禁じられている入管の収容施設に無許可でカメラを持ち込み、そこに収容されている難民申請者の声を隠し撮りした映像で構成された作品だ。日本という国家が、国際標準と照らしていかに酷い振る舞いをしているのかが理解できる衝撃作である
あわせて読みたい
【映画】『街は誰のもの?』という問いは奥深い。「公共」の意味を考えさせる問題提起に満ちた作品
映画『街は誰のもの?』は、タイトルの通り「街(公共)は誰のものなのか?」を問う作品だ。そしてそのテーマの1つが、無許可で街中に絵を描く「グラフィティ」であることもまた面白い。想像もしなかった問いや価値観に直面させられる、とても興味深い作品である
あわせて読みたい
【驚愕】ベリングキャットの調査報道がプーチンを追い詰める。映画『ナワリヌイ』が示す暗殺未遂の真実
弁護士であり、登録者数640万人を超えるYouTuberでもあるアレクセイ・ナワリヌイは、プーチンに対抗して大統領選挙に出馬しようとしたせいで暗殺されかかった。その実行犯を特定する調査をベリングキャットと共に行った記録映画『ナワリヌイ』は、現実とは思えないあまりの衝撃に満ちている
あわせて読みたい
【抵抗】若者よ、映画『これは君の闘争だ』を見ろ!学校閉鎖に反対する学生運動がブラジルの闇を照らす
映画『これは君の闘争だ』で描かれるのは、厳しい状況に置かれた貧困層の学生たちによる公権力との闘いだ。「貧困層ばかりが通う」とされる公立校が大幅に再編されることを知った学生が高校を占拠して立て籠もる決断に至った背景を、ドキュメンタリー映画とは思えないナレーションで描く異色作
あわせて読みたい
【信念】9.11後、「命の値段」を計算した男がいた。映画『WORTH』が描く、その凄絶な2年間(主演:マイ…
9.11テロの後、「被害者の『命の値段』を算出した男」がいたことをご存知だろうか?映画『WORTH』では、「被害者遺族のために貢献したい」と無償で難題と向き合うも、その信念が正しく理解されずに反発や対立を招いてしまった現実が描かれる。実話を基にしているとは思えない、凄まじい物語だ
あわせて読みたい
【真実】田原総一朗✕小泉純一郎!福島原発事故後を生きる我々が知るべき自然エネルギーの可能性:映画『…
田原総一朗が元総理・小泉純一郎にタブー無しで斬り込む映画『放送不可能。「原発、全部ウソだった」』は、「原発推進派だった自分は間違っていたし、騙されていた」と語る小泉純一郎の姿勢が印象的だった。脱原発に舵を切った小泉純一郎が、原発政策のウソに斬り込み、再生可能エネルギーの未来を語る
あわせて読みたい
【映画】『戦場記者』須賀川拓が、ニュースに乗らない中東・ウクライナの現実と報道の限界を切り取る
TBS所属の特派員・須賀川拓は、ロンドンを拠点に各国の取材を行っている。映画『戦場記者』は、そんな彼が中東を取材した映像をまとめたドキュメンタリーだ。ハマスを巡って食い違うガザ地区とイスラエル、ウクライナ侵攻直後に現地入りした際の様子、アフガニスタンの壮絶な薬物中毒の現実を映し出す
あわせて読みたい
【天才】映画『Winny』(松本優作監督)で知った、金子勇の凄さと著作権法侵害事件の真相(ビットコイン…
稀代の天才プログラマー・金子勇が著作権法違反で逮捕・起訴された実話を描き出す映画『Winny』は、「警察の凄まじい横暴」「不用意な天才と、テック系知識に明るい弁護士のタッグ」「Winnyが明らかにしたとんでもない真実」など、見どころは多い。「金子勇=サトシ・ナカモト」説についても触れる
あわせて読みたい
【狂気?】オウム真理教を内部から映す映画『A』(森達也監督)は、ドキュメンタリー映画史に残る衝撃作だ
ドキュメンタリー映画の傑作『A』(森達也)をようやく観られた。「オウム真理教は絶対悪だ」というメディアの報道が凄まじい中、オウム真理教をその内部からフラットに映し出した特異な作品は、公開当時は特に凄まじい衝撃をもたらしただろう。私たちの「当たり前」が解体されていく斬新な一作
あわせて読みたい
【実話】映画『グリーンブック』は我々に問う。当たり前の行動に「差別意識」が含まれていないか、と
黒人差別が遥かに苛烈だった時代のアメリカにおいて、黒人ピアニストと彼に雇われた白人ドライバーを描く映画『グリーンブック』は、観客に「あなたも同じような振る舞いをしていないか?」と突きつける作品だ。「差別」に限らず、「同時代の『当たり前』に従った行動」について考え直させる1作
あわせて読みたい
【性加害】映画『SHE SAID その名を暴け』を観てくれ。#MeToo運動を生んだ報道の舞台裏(出演:キャリ…
「#MeToo」運動のきっかけとなった、ハリウッドの絶対権力者ハーヴェイ・ワインスタインを告発するニューヨーク・タイムズの記事。その取材を担った2人の女性記者の奮闘を描く映画『SHE SAID その名を暴け』は、ジャニー喜多川の性加害問題で揺れる今、絶対に観るべき映画だと思う
あわせて読みたい
【異様】映画『大いなる不在』(近浦啓)は、認知症の父を中心に「記憶」と「存在」の複雑さを描く(主…
「父親が逮捕され、どうやら認知症のようだ」という一報を受けた息子が、30年間ほぼやり取りのなかった父親と再会するところから始まる映画『大いなる不在』は、なんとも言えない「不穏さ」に満ちた物語だった。「記憶」と「存在」のややこしさを問う本作は、「物語」としては成立していないが、圧倒的な“リアリティ”に満ちている
あわせて読みたい
【傑物】フランスに最も愛された政治家シモーヌ・ヴェイユの、強制収容所から国連までの凄絶な歩み:映…
「フランスに最も愛された政治家」と評されるシモーヌ・ヴェイユ。映画『シモーヌ』は、そんな彼女が強制収容所を生き延び、後に旧弊な社会を変革したその凄まじい功績を描き出す作品だ。「強制収容所からの生還が失敗に思える」とさえ感じたという戦後のフランスの中で、彼女はいかに革新的な歩みを続けたのか
あわせて読みたい
【生還】内戦下のシリアでISISに拘束された男の実話を基にした映画『ある人質』が描く壮絶すぎる現実
実話を基にした映画『ある人質 生還までの398日』は、内戦下のシリアでISISに拘束された男の壮絶な日々が描かれる。「テロリストとは交渉しない」という方針を徹底して貫くデンマーク政府のスタンスに翻弄されつつも、救出のために家族が懸命に奮闘する物語に圧倒される
あわせて読みたい
【衝撃】匿名監督によるドキュメンタリー映画『理大囲城』は、香港デモ最大の衝撃である籠城戦の内部を映す
香港民主化デモにおける最大の衝撃を内側から描く映画『理大囲城』は、とんでもないドキュメンタリー映画だった。香港理工大学での13日間に渡る籠城戦のリアルを、デモ隊と共に残って撮影し続けた匿名監督たちによる映像は、ギリギリの判断を迫られる若者たちの壮絶な現実を映し出す
あわせて読みたい
【解説】実話を基にした映画『シカゴ7裁判』で知る、「権力の暴走」と、それに正面から立ち向かう爽快さ
ベトナム戦争に反対する若者たちによるデモと、その後開かれた裁判の実話を描く『シカゴ7裁判』はメチャクチャ面白い映画だった。無理筋の起訴を押し付けられる主席検事、常軌を逸した言動を繰り返す不適格な判事、そして一枚岩にはなれない被告人たち。魅力満載の1本だ
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』で描かれる、グアンタナモ”刑務所”の衝撃の実話は必見
ベネディクト・カンバーバッチが制作を熱望した衝撃の映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』は、アメリカの信じがたい実話を基にしている。「9.11の首謀者」として不当に拘束され続けた男を「救おうとする者」と「追い詰めようとする者」の奮闘が、「アメリカの闇」を暴き出す
あわせて読みたい
【狂気】アメリカの衝撃の実態。民営刑務所に刑務官として潜入した著者のレポートは国をも動かした:『…
アメリカには「民営刑務所」が存在する。取材のためにその1つに刑務官として潜入した著者が記した『アメリカン・プリズン』は信じがたい描写に溢れた1冊だ。あまりに非人道的な行いがまかり通る狂気の世界と、「民営刑務所」が誕生した歴史的背景を描き出すノンフィクション
あわせて読みたい
【驚愕】一般人スパイが北朝鮮に潜入する映画『THE MOLE』はとてつもないドキュメンタリー映画
映画『THE MOLE』は、「ホントにドキュメンタリーなのか?」と疑いたくなるような衝撃映像満載の作品だ。「『元料理人のデンマーク人』が勝手に北朝鮮に潜入する」というスタートも謎なら、諜報経験も軍属経験もない男が北朝鮮の秘密をバンバン解き明かす展開も謎すぎる。ヤバい
あわせて読みたい
【あらすじ】嵐莉菜主演映画『マイスモールランド』は、日本の難民問題とクルド人の現状、入管の酷さを描く
映画『マイスモールランド』はフィクションではあるが、「日本に住む難民の厳しい現実」をリアルに描き出す作品だ。『東京クルド』『牛久』などのドキュメンタリー映画を観て「知識」としては知っていた「現実」が、当事者にどれほどの苦しみを与えるのか想像させられた
あわせて読みたい
【差別】映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』の衝撃。プーチンが支持する国の蛮行・LGBT狩り
プーチン大統領の後ろ盾を得て独裁を維持しているチェチェン共和国。その国で「ゲイ狩り」と呼ぶしかない異常事態が継続している。映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』は、そんな現実を命がけで映し出し、「現代版ホロコースト」に立ち向かう支援団体の奮闘も描く作品
あわせて読みたい
【異次元】『ハイパーハードボイルドグルメリポート』は本も読め。衝撃すぎるドキュメンタリーだぞ
テレビ東京の上出遼平が作る、“異次元のグルメ番組”である「ハイパーハードボイルドグルメリポート」の書籍化。映像からも異様さが伝わる「激ヤバ地」に赴き、そこに住む者と同じモノを食べるという狂気が凄まじい。私がテレビで見た「ケニアのゴミ山の少年」の話は衝撃的だった
あわせて読みたい
【あらすじ】死刑囚を救い出す実話を基にした映画『黒い司法』が指摘する、死刑制度の問題と黒人差別の現実
アメリカで死刑囚の支援を行う団体を立ち上げた若者の実話を基にした映画『黒い司法 0%からの奇跡』は、「死刑制度」の存在価値について考えさせる。上映後のトークイベントで、アメリカにおける「死刑制度」と「黒人差別」の結びつきを知り、一層驚かされた
あわせて読みたい
【対立】パレスチナとイスラエルの「音楽の架け橋」は実在する。映画『クレッシェンド』が描く奇跡の楽団
イスラエルとパレスチナの対立を背景に描く映画『クレッシェンド』は、ストーリーそのものは実話ではないものの、映画の中心となる「パレスチナ人・イスラエル人混合の管弦楽団」は実在する。私たちが生きる世界に残る様々な対立について、その「改善」の可能性を示唆する作品
あわせて読みたい
【実話】台湾のろう学校のいじめ・性的虐待事件を描く映画『無聲』が問う、あまりに悲しい現実
台湾のろう学校で実際に起こったいじめ・性的虐待事件を基に作られた映画『無聲』は、健常者の世界に刃を突きつける物語だ。これが実話だという事実に驚かされる。いじめ・性的虐待が物語の「大前提」でしかないという衝撃と、「性的虐待の方がマシ」という選択を躊躇せず行う少女のあまりの絶望を描き出す
あわせて読みたい
【事件】デュポン社のテフロン加工が有害だと示した男の執念の実話を描く映画『ダーク・ウォーターズ』
世界的大企業デュポン社が、自社製品「テフロン」の危険性を40年以上前に把握しながら公表せず、莫大な利益を上げてきた事件の真相を暴き出した1人の弁護士がいる。映画『ダーク・ウォーターズ』は、大企業相手に闘いを挑み、住民と正義のために走り続けた実在の人物の勇敢さを描き出す
あわせて読みたい
【現実】権力を乱用する中国ナチスへの抵抗の最前線・香港の民主化デモを映す衝撃の映画『時代革命』
2019年に起こった、逃亡犯条例改正案への反対運動として始まった香港の民主化デモ。その最初期からデモ参加者たちの姿をカメラに収め続けた。映画『時代革命』は、最初から最後まで「衝撃映像」しかない凄まじい作品だ。この現実は決して、「対岸の火事」ではない
あわせて読みたい
【貢献】社会問題を解決する2人の「社会起業家」の生き方。「豊かさ」「生きがい」に必要なものは?:『…
「ヤクの毛」を使ったファッションブランド「SHOKAY」を立ち上げ、チベットの遊牧民と中国・崇明島に住む女性の貧困問題を解決した2人の若き社会起業家の奮闘を描く『世界を変えるオシゴト』は、「仕事の意義」や「『お金』だけではない人生の豊かさ」について考えさせてくれる
あわせて読みたい
【秘話】15年で世界を変えたグーグルの”異常な”創業エピソード。収益化無視の無料ビジネスはなぜ成功し…
スマホやネットを使う人で、グーグルのお世話になっていない人はまずいないだろう。もはや「インフラ」と呼んでいいレベルになったサービスを生み出した企業の創業からの歴史を描く『グーグル秘録』は、その歩みが「無邪気さ」と「偶然」の産物であることを示している。凄まじいエピソード満載の信じがたい企業秘話
あわせて読みたい
【憤り】世界最強米海軍4人VS数百人のタリバン兵。死線を脱しただ1人生還を果たした奇跡の実話:『アフ…
アフガニスタンの山中で遭遇した羊飼いを見逃したことで、数百人のタリバン兵と死闘を繰り広げる羽目に陥った米軍最強部隊に所属する4人。奇跡的に生き残り生還を果たした著者が記す『アフガン、たった一人の生還』は、とても実話とは信じられない凄まじさに満ちている
あわせて読みたい
【アメリカ】長崎の「原爆ドーム」はなぜ残らなかった?爆心地にあった「浦上天主堂」の数奇な歴史:『…
原爆投下で半壊し、廃墟と化したキリスト教の大聖堂「浦上天主堂」。しかし何故か、「長崎の原爆ドーム」としては残されず、解体されてしまった。そのため長崎には原爆ドームがないのである。『ナガサキ 消えたもう一つの「原爆ドーム」』は、「浦上天主堂」を巡る知られざる歴史を掘り下げ、アメリカの強かさを描き出す
あわせて読みたい
【衝撃】洗脳を自ら脱した著者の『カルト脱出記』から、「社会・集団の洗脳」を避ける生き方を知る
「聖書研究に熱心な日本人証人」として「エホバの証人」で活動しながら、その聖書研究をきっかけに自ら「洗脳」を脱した著者の体験を著した『カルト脱出記』。広い意味での「洗脳」は社会のそこかしこに蔓延っているからこそ、著者の体験を「他人事」だと無視することはできない
あわせて読みたい
【不安】環境活動家グレタを追う映画。「たったひとりのストライキ」から国連スピーチまでの奮闘と激変…
環境活動家であるグレタのことを、私はずっと「怒りの人」「正義の人」だとばかり思っていた。しかしそうではない。彼女は「不安」から、いても立ってもいられずに行動を起こしただけなのだ。映画『グレタ ひとりぼっちの挑戦』から、グレタの実像とその強い想いを知る
あわせて読みたい
【衝撃】権力の濫用、政治腐敗を描く映画『コレクティブ』は他人事じゃない。「国家の嘘」を監視せよ
火災で一命を取り留め入院していた患者が次々に死亡した原因が「表示の10倍に薄められた消毒液」だと暴き、国家の腐敗を追及した『ガゼタ』誌の奮闘を描く映画『コレクティブ 国家の嘘』は、「権力の監視」が機能しなくなった国家の成れの果てが映し出される衝撃作だ
あわせて読みたい
【信念】水俣病の真実を世界に伝えた写真家ユージン・スミスを描く映画。真実とは「痛みへの共感」だ:…
私はその存在をまったく知らなかったが、「水俣病」を「世界中が知る公害」にした報道写真家がいる。映画『MINAMATA―ミナマタ―』は、水俣病の真実を世界に伝えたユージン・スミスの知られざる生涯と、理不尽に立ち向かう多くの人々の奮闘を描き出す
あわせて読みたい
【日常】難民問題の現状をスマホで撮る映画。タリバンから死刑宣告を受けた監督が家族と逃避行:『ミッ…
アフガニスタンを追われた家族4人が、ヨーロッパまで5600kmの逃避行を3台のスマホで撮影した映画『ミッドナイト・トラベラー』は、「『難民の厳しい現実』を切り取った作品」ではない。「家族アルバム」のような「笑顔溢れる日々」が難民にもあるのだと想像させてくれる
あわせて読みたい
【衝撃】『殺人犯はそこにいる』が実話だとは。真犯人・ルパンを野放しにした警察・司法を信じられるか?
タイトルを伏せられた覆面本「文庫X」としても話題になった『殺人犯はそこにいる』。「北関東で起こったある事件の取材」が、「私たちが生きる社会の根底を揺るがす信じがたい事実」を焙り出すことになった衝撃の展開。まさか「司法が真犯人を野放しにする」なんてことが実際に起こるとは。大げさではなく、全国民必読の1冊だと思う
あわせて読みたい
【実話】「ホロコーストの映画」を観て改めて、「有事だから仕方ない」と言い訳しない人間でありたいと…
ノルウェーの警察が、自国在住のユダヤ人をまとめて船に乗せアウシュビッツへと送った衝撃の実話を元にした映画『ホロコーストの罪人』では、「自分はそんな愚かではない」と楽観してはいられない現実が映し出される。このような悲劇は、現在に至るまで幾度も起こっているのだ
あわせて読みたい
【抽象】「思考力がない」と嘆く人に。研究者で小説家の森博嗣が語る「客観的に考える」ために大事なこ…
世の中にはあまりに「具体的な情報」が溢れているために、「客観的、抽象的な思考」をする機会が少ない。そんな時代に、いかに思考力を育てていくべきか。森博嗣が『人間はいろいろな問題についてどう考えていけば良いのか』を通じて伝える「情報との接し方」「頭の使い方」
あわせて読みたい
【実話】映画『アウシュビッツ・レポート』が描き出す驚愕の史実。世界はいかにホロコーストを知ったのか?
映画『アウシュヴィッツ・レポート』は、アウシュビッツ強制収容所から抜け出し、詳細な記録と共にホロコーストの実態を世界に明らかにした実話を基にした作品。2人が持ち出した「アウシュビッツ・レポート」こそが、ホロコーストについて世界が知るきっかけだったのであり、そんな史実をまったく知らなかったことにも驚かされた
あわせて読みたい
【凄絶】北朝鮮の”真実”を描くアニメ映画。強制収容所から決死の脱出を試みた者が語る驚愕の実態:『ト…
在日コリアン4世の監督が、北朝鮮脱北者への取材を元に作り上げた壮絶なアニメ映画『トゥルーノース』は、私たちがあまりに恐ろしい世界と地続きに生きていることを思い知らせてくれる。最低最悪の絶望を前に、人間はどれだけ悪虐になれてしまうのか、そしていかに優しさを発揮できるのか。
あわせて読みたい
【弾圧】香港デモの象徴的存在デニス・ホーの奮闘の歴史。注目の女性活動家は周庭だけじゃない:映画『…
日本で香港民主化運動が報じられる際は周庭さんが取り上げられることが多いが、香港には彼女よりも前に民主化運動の象徴的存在として認められた人物がいる。映画『デニス・ホー ビカミング・ザ・ソング』の主人公であるスター歌手の激動の人生を知る
あわせて読みたい
【葛藤】正義とは何かを突きつける戦争映画。80人を救うために1人の少女を殺すボタンを押せるか?:『ア…
「80人の命を救うために、1人の少女の命を奪わなければならない」としたら、あなたはその決断を下せるだろうか?会議室で展開される現代の戦争を描く映画『アイ・イン・ザ・スカイ』から、「誤った問い」に答えを出さなければならない極限状況での葛藤を理解する
あわせて読みたい
【危機】シードバンクを設立し世界の農業を変革した伝説の植物学者・スコウマンの生涯と作物の多様性:…
グローバル化した世界で「農業」がどんなリスクを負うのかを正しく予測し、その対策として「ジーンバンク」を設立した伝説の植物学者スコウマンの生涯を描く『地球最後の日のための種子』から、我々がいかに脆弱な世界に生きているのか、そして「世界の食」がどう守られているのかを知る
あわせて読みたい
【実話】権力の濫用を監視するマスコミが「教会の暗部」を暴く映画『スポットライト』が現代社会を斬る
地方紙である「ボストン・グローブ紙」は、数多くの神父が長年に渡り子どもに対して性的虐待を行い、その事実を教会全体で隠蔽していたという衝撃の事実を明らかにした。彼らの奮闘の実話を映画化した『スポットライト』から、「権力の監視」の重要性を改めて理解する
あわせて読みたい
【書評】奇跡の”国家”「ソマリランド」に高野秀行が潜入。崩壊国家・ソマリア内で唯一平和を保つ衝撃の”…
日本の「戦国時代」さながらの内戦状態にあるソマリア共和国内部に、十数年に渡り奇跡のように平和を維持している”未承認国家”が存在する。辺境作家・高野秀行の『謎の独立国家ソマリランド』から、「ソマリランド」の理解が難しい理由と、「奇跡のような民主主義」を知る
あわせて読みたい
【情熱】映画『パッドマン』から、女性への偏見が色濃く残る現実と、それを打ち破ったパワーを知る
「生理は語ることすらタブー」という、21世紀とは思えない偏見が残るインドで、灰や汚れた布を使って経血を処理する妻のために「安価な生理用ナプキン」の開発に挑んだ実在の人物をモデルにした映画『パッドマン 5億人の女性を救った男』から、「どう生きたいか」を考える
あわせて読みたい
【貢献】飛行機を「安全な乗り物」に決定づけたMr.トルネードこと天才気象学者・藤田哲也の生涯:『Mr….
つい数十年前まで、飛行機は「死の乗り物」だったが、天才気象学者・藤田哲也のお陰で世界の空は安全になった。今では、自動車よりも飛行機の方が死亡事故の少ない乗り物なのだ。『Mr.トルネード 藤田哲也 世界の空を救った男』から、その激動の研究人生を知る
あわせて読みたい
【驚異】ガイア理論の提唱者が未来の地球を語る。100歳の主張とは思えない超絶刺激に満ちた内容:『ノヴ…
「地球は一種の生命体だ」という主張はかなり胡散臭い。しかし、そんな「ガイア理論」を提唱する著者は、数々の賞や学位を授与される、非常に良く知られた科学者だ。『ノヴァセン <超知能>が地球を更新する』から、AIと人類の共存に関する斬新な知見を知る
あわせて読みたい
【告発】アメリカに”監視”される社会を暴露したスノーデンの苦悩と決断を映し出す映画:『スノーデン』…
NSA(アメリカ国家安全保障局)の最高機密にまでアクセスできたエドワード・スノーデンは、その機密情報を持ち出し内部告発を行った。「アメリカは世界中の通信を傍受している」と。『シチズンフォー』と『スノーデン』の2作品から、彼の告発内容とその葛藤を知る
あわせて読みたい
【権威】心理学の衝撃実験をテレビ番組の収録で実践。「自分は残虐ではない」と思う人ほど知るべき:『…
フランスのテレビ局が行った「現代版ミルグラム実験」の詳細が語られる『死のテレビ実験 人はそこまで服従するのか』は、「権威」を感じる対象から命じられれば誰もが残虐な行為をしてしまい得ることを示す。全人類必読の「過ちを事前に回避する」ための知見を学ぶ
あわせて読みたい
【危機】教員のセクハラは何故無くならない?資質だけではない、学校の構造的な問題も指摘する:『スク…
『スクールセクハラ なぜ教師のわいせつ犯罪は繰り返されるのか』では、自分が生徒に対して「権力」を持っているとは想像していなかったという教師が登場する。そしてこの「無自覚」は、学校以外の場でも起こりうる。特に男性は、読んで自分の振る舞いを見直すべきだ
あわせて読みたい
【快挙】「チバニアン」は何が凄い?「地球の磁場が逆転する」驚異の現象がこの地層を有名にした:『地…
一躍その名が知れ渡ることになった「チバニアン」だが、なぜ話題になり、どう重要なのかを知っている人は多くないだろう。「チバニアン」の申請に深く関わった著者の『地磁気逆転と「チバニアン」』から、地球で起こった過去の不可思議な現象の正体を理解する
あわせて読みたい
【理解】東田直樹の本は「自閉症の見方」を一変させた。自身も自閉症児を育てるプロデューサーが映画化…
東田直樹の著作を英訳し世界に広めた人物(自閉症児を育てている)も登場する映画『僕が跳びはねる理由』には、「東田直樹が語る自閉症の世界」を知ることで接し方や考え方が変わったという家族が登場する。「自閉症は知恵遅れではない」と示した東田直樹の多大な功績を実感できる
あわせて読みたい
【リアル】社会の分断の仕組みを”ゾンビ”で学ぶ。「社会派ゾンビ映画」が対立の根源を抉り出す:映画『C…
まさか「ゾンビ映画」が、私たちが生きている現実をここまで活写するとは驚きだった。映画『CURED キュアード』をベースに、「見えない事実」がもたらす恐怖と、立場ごとに正しい主張をしながらも否応なしに「分断」が生まれてしまう状況について知る
あわせて読みたい
【情熱】「ルール」は守るため”だけ”に存在するのか?正義を実現するための「ルール」のあり方は?:映…
「ルールは守らなければならない」というのは大前提だが、常に例外は存在する。どれほど重度の自閉症患者でも断らない無許可の施設で、情熱を持って問題に対処する主人公を描く映画『スペシャルズ!』から、「ルールのあるべき姿」を考える
あわせて読みたい
【驚愕】「金正男の殺人犯」は”あなた”だったかも。「人気者になりたい女性」が陥った巧妙な罠:映画『…
金正男が暗殺された事件は、世界中で驚きをもって報じられた。その実行犯である2人の女性は、「有名にならないか?」と声を掛けられて暗殺者に仕立て上げられてしまった普通の人だ。映画『わたしは金正男を殺していない』から、危険と隣り合わせの現状を知る
あわせて読みたい
【誤り】「信じたいものを信じる」のは正しい?映画『星の子』から「信じること」の難しさを考える
どんな病気も治す「奇跡の水」の存在を私は信じないが、しかし何故「信じない」と言えるのか?「奇跡の水を信じる人」を軽々に非難すべきではないと私は考えているが、それは何故か?映画『星の子』から、「何かを信じること」の難しさについて知る
あわせて読みたい
【ゴミ】プラスチックによる環境問題の実態を描く衝撃の映画。我々は現実をあまりに知らない:映画『プ…
プラスチックごみによる海洋汚染は、我々の想像を遥かに超えている。そしてその現実は、「我々は日常的にマイクロプラスチックを摂取している」という問題にも繋がっている。映画『プラスチックの海』から、現代文明が引き起こしている環境破壊の現実を知る
あわせて読みたい
【危機】遺伝子組み換え作物の危険性を指摘。バイオ企業「モンサント社」の実態を暴く衝撃の映画:映画…
「遺伝子組み換え作物が危険かどうか」以上に注目すべきは、「モンサント社の除草剤を摂取して大丈夫か」である。種子を独占的に販売し、農家を借金まみれにし、世界中の作物の多様性を失わせようとしている現状を、映画「モンサントの不自然な食べもの」から知る
あわせて読みたい
【意外】自己免疫疾患の原因は”清潔さ”?腸内フローラの多様性の欠如があらゆる病気を引き起こす:『寄…
人類は、コレラの蔓延を機に公衆衛生に力を入れ、寄生虫を排除した。しかし、感染症が減るにつれ、免疫関連疾患が増大していく。『寄生虫なき病』では、腸内細菌の多様性が失われたことが様々な疾患の原因になっていると指摘、「現代病」の蔓延に警鐘を鳴らす
あわせて読みたい
【デマ】情報を”選ぶ”時代に、メディアの情報の”正しさ”はどのように判断されるのか?:『ニューヨーク…
一昔前、我々は「正しい情報を欲していた」はずだ。しかしいつの間にか世の中は変わった。「欲しい情報を正しいと思う」ようになったのだ。この激変は、トランプ元大統領の台頭で一層明確になった。『ニューヨーク・タイムズを守った男』から、情報の受け取り方を問う
あわせて読みたい
【無知】メディアの問題の本質は?「報道の限界」と「情報の受け取り方」を独裁政治の現実から知る:『…
メディアは確かに「事実」を報じている。しかし、報道に乗らない情報まで含めなければ、本当の意味で世の中を理解することは難しいと、『こうして世界は誤解する』は教えてくれる。アラブ諸国での取材の現実から、報道の「限界」と「受け取り方」を学ぶ
あわせて読みたい
【意外】思わぬ資源が枯渇。文明を支えてきた”砂”の減少と、今後我々が変えねばならぬこと:『砂と人類』
「砂が枯渇している」と聞いて信じられるだろうか?そこら中にありそうな砂だが、産業用途で使えるものは限られている。そしてそのために、砂浜の砂が世界中で盗掘されているのだ。『砂と人類』から、石油やプラスチックごみ以上に重要な環境問題を学ぶ
あわせて読みたい
【加虐】メディアの役割とは?森達也『A』が提示した「事実を報じる限界」と「思考停止社会」
オウム真理教の内部に潜入した、森達也のドキュメンタリー映画『A』は衝撃を与えた。しかしそれは、宗教団体ではなく、社会の方を切り取った作品だった。思考することを止めた社会の加虐性と、客観的な事実など切り取れないという現実について書く
あわせて読みたい
【恐怖】SNSの危険性と子供の守り方を、ドキュメンタリー映画『SNS 少女たちの10日間』で学ぶ
実際にチェコの警察を動かした衝撃のドキュメンタリー映画『SNS 少女たちの10日間』は、少女の「寂しさ」に付け込むおっさんどもの醜悪さに満ちあふれている。「WEBの利用制限」だけでは子どもを守りきれない現実を、リアルなものとして実感すべき
あわせて読みたい
【衝撃】壮絶な戦争映画。最愛の娘を「産んで後悔している」と呟く母らは、正義のために戦場に留まる:…
こんな映画、二度と存在し得ないのではないかと感じるほど衝撃を受けた『娘は戦場で生まれた』。母であり革命家でもあるジャーナリストは、爆撃の続くシリアの街を記録し続け、同じ街で娘を産み育てた。「知らなかった」で済ませていい現実じゃない。
あわせて読みたい
【勇敢】日本を救った吉田昌郎と、福島第一原発事故に死を賭して立ち向かった者たちの極限を知る:『死…
日本は、死を覚悟して福島第一原発に残った「Fukushima50」に救われた。東京を含めた東日本が壊滅してもおかしくなかった大災害において、現場の人間が何を考えどう行動したのかを、『死の淵を見た男』をベースに書く。全日本人必読の書
あわせて読みたい
【議論】安楽死のできない日本は「死ぬ権利」を奪っていると思う(合法化を希望している):『安楽死を…
私は、安楽死が合法化されてほしいと思っている。そのためには、人間には「死ぬ権利」があると合意されなければならないだろう。安楽死は時折話題になるが、なかなか議論が深まらない。『安楽死を遂げた日本人』をベースに、安楽死の現状を理解する
あわせて読みたい
【驚愕】日本の司法は終わってる。「中世レベル」で「無罪判決が多いと出世に不利」な腐った現実:『裁…
三権分立の一翼を担う裁判所のことを、私たちはよく知らない。元エリート裁判官・瀬木比呂志と事件記者・清水潔の対談本『裁判所の正体』をベースに、「裁判所による統制」と「権力との癒着」について書く。「中世レベル」とさえ言われる日本の司法制度の現実は、「裁判になんか関わることない」という人も無視できないはずだ
あわせて読みたい
【希望】貧困の解決は我々を豊かにする。「朝ベッドから起きたい」と思えない社会を変える課題解決:『…
現代は、過去どの時代と比べても安全で清潔で、豊かである。しかしそんな時代に、我々は「幸せ」を実感することができない。『隷属なき道』をベースに、その理由は一体なんなのか何故そうなってしまうのかを明らかにし、さらに、より良い暮らしを思い描くための社会課題の解決に触れる
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
経済・企業・マーケティング【本・映画の感想】 | ルシルナ
私自身にはビジネスセンスや起業経験などはありませんが、興味があって、経済や企業の様々な事例についての本を読むようにしています。専門的な踏み込んだ描写ができるわけ…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…

























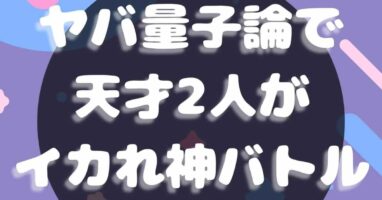









































































































コメント