目次
はじめに
この記事で取り上げる映画
監督:モハマド・ラスロフ, 出演:ソヘイラ・ゴレスターニ, 出演:ミシャク・ザラ, 出演:マフサ・ロスタミ, 出演:セターレ・マレキ, 出演:ミシャク・ザラ
¥550 (2025/07/06 23:04時点 | Amazon調べ)
ポチップ
VIDEO
この映画をガイドにしながら記事を書いていきます
この記事の3つの要点
「ヒジャブの付け方」を咎められ拘束された女性が死亡した実際の事件を背景に、市民デモが激しくなる中で混沌とする「家族」を描き出す物語 冒頭からしばらくは、「妻であり母であるナジメがおかしい」と思っていたのだが、次第にその印象は変わっていく 「ひと家族」という最小単位内での対立を描き出すことで、「イランという国家の縮図」をあぶり出す構成が見事 「パスポートを取り上げられていたモハマド・ラスロフ監督が徒歩でイランを脱出し、28日間掛けてカンヌ国際映画祭までたどり着いた」というエピソードも含め、とにかく衝撃的な内容である
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
記事中の引用は、映画館で取ったメモを参考にしているので、正確なものではありません
マフサ・アミニの死がきっかけとなった実際の市民デモを背景にイランの現状を描き出す映画『聖なるイチジクの種』は、監督・役者・スタッフが人生を賭して生み出した凄まじい作品だ
これはちょっと凄まじい物語 だった。正直なところ、観る前はそこまで大きく期待して はいなかったのだが、実際にはちょっとビックリするぐらいの作品 だったなと思う。予告編では「自宅にあった銃が無くなった」ぐらいの情報しか出ていなかった ため(監督がどういう人なのかは知らなかったし、調べもしなかった)、「まさかこんな話になるとは」という感覚 がかなり強かったのである。
あわせて読みたい
【現実】権力を乱用する中国ナチスへの抵抗の最前線・香港の民主化デモを映す衝撃の映画『時代革命』
2019年に起こった、逃亡犯条例改正案への反対運動として始まった香港の民主化デモ。その最初期からデモ参加者たちの姿をカメラに収め続けた。映画『時代革命』は、最初から最後まで「衝撃映像」しかない凄まじい作品だ。この現実は決して、「対岸の火事」ではない
実際に起こった市民デモを背景として組み込んだ物語
私はそもそも、「実際の出来事を扱っている」という事実さえも知らなかった 。本作で扱われている事件については、鑑賞中に何となく「そんなニュースを目にしたことがあるな」程度に思い出した のだが、「実際の出来事を扱っている」と判断できた理由は、「スマホで撮影したのだろう映像」が多数使われていた からである。もちろん、「そういう演出」という可能性もあるのだが、その後の展開なども踏まえつつ、「なるほど、あの事件が背景にあるのか」と認識した というわけだ。
それは、マフサ・アミニという女性が命を落とした事件 である。そして彼女の死に抗議する形で市民デモがあちこちで始まってい くことになったのだ。というわけで、まずはこの事件の背景 について説明しておこう。
本作『聖なるイチジクの種』の舞台は、イランの首都テヘラン である。イランはイスラム教の国 であり、作中で描かれている雰囲気からすると、イスラム教の中でも「コーランを厳守すべき」という圧力が強い国 なのだと思う。当然、「女性は外出時、ヒジャブを着用しなければならない」というルールについてもかなり厳格 で、不適切だと判断されると「道徳警察」に摘発 を受けてしまう。
あわせて読みたい
【衝撃】匿名監督によるドキュメンタリー映画『理大囲城』は、香港デモ最大の衝撃である籠城戦の内部を映す
香港民主化デモにおける最大の衝撃を内側から描く映画『理大囲城』は、とんでもないドキュメンタリー映画だった。香港理工大学での13日間に渡る籠城戦のリアルを、デモ隊と共に残って撮影し続けた匿名監督たちによる映像は、ギリギリの判断を迫られる若者たちの壮絶な現実を映し出す
そんなイランで事件は起こった。2022年9月16日、ヒジャブの付け方の不備で道徳警察に拘束されたマフサ・アミニが、その後死亡した のだ。国は「心臓発作だった」と発表した が、彼女が警察に襲われているような姿を捉えた防犯カメラの映像 がネットで拡散しており、「仮に心臓発作で亡くなったのだとしても、その原因は警察による暴行だったはずだ」と考える人が増えていった のである。
そして、普段から国に対する不満を溜め込んできた市民が、彼女の死をきっかけに連帯し立ち上がった 。SNSで繋がる若い世代が中心となって抗議デモ を行い、「独裁者を倒せ!」「女性、命、自由」といったスローガンを多くの人が叫び始めた のである。
本作は、このような市民デモが起こっている中で展開される物語 であり、そして、そんな暴動の様子が様々なスマホ映像によって映し出されていく というわけだ。
あわせて読みたい
【抵抗】若者よ、映画『これは君の闘争だ』を見ろ!学校閉鎖に反対する学生運動がブラジルの闇を照らす
映画『これは君の闘争だ』で描かれるのは、厳しい状況に置かれた貧困層の学生たちによる公権力との闘いだ。「貧困層ばかりが通う」とされる公立校が大幅に再編されることを知った学生が高校を占拠して立て籠もる決断に至った背景を、ドキュメンタリー映画とは思えないナレーションで描く異色作
イランをどうにか抜け出した監督、イランからの出国が許可されない主演の2人
作中では、国営放送を家族で見るシーン が何度か映し出されるのだが、国営放送は当然この市民デモを「市民側が悪い」という形で取り上げていた 。デモに関わったと判断された者たちは問答無用で逮捕 され、それによって主人公イマンの仕事は殺人的に忙しくなっていく わけだが、その辺りの話はまた後でしよう。国としてはとにかく、市民デモを徹底的に弾圧する構え である。
さて、そんなイランにおいて、本作『聖なるイチジクの種』のような映画を製作して無事なはずがない 。監督のモハマド・ラスロフは、本作の公開以前の時点で既に、「イラン政府を批判した」という罪で禁錮8年とむち打ちの有罪判決が下っていた ようだ。その判決が確定した時点で本作の撮影は終了していたそうで、そのため彼は徒歩で国外へと脱出(ずっと以前にパスポートを没収されていたのだ)、28日間かけてカンヌ国際映画祭の地へと辿り着き、そこで喝采を浴びた という。そして、そのままドイツへの亡命を果たす ことができたそうである。
本当に、身の危険を顧みずに映画を作り続けている というわけだ。
あわせて読みたい
【挑戦】映画『燃えあがる女性記者たち』が描く、インドカースト最下位・ダリットの女性による報道
映画『燃えあがる女性記者たち』は、インドで「カースト外の不可触民」として扱われるダリットの女性たちが立ち上げた新聞社「カバル・ラハリヤ」を取り上げる。自身の境遇に抗って、辛い状況にいる人の声を届けたり権力者を糾弾したりする彼女たちの奮闘ぶりが、インドの民主主義を変革させるかもしれない
さらに、公式HPには次のような文章が掲載されていた 。これを読んだ上で本作を観ると、見え方がまた少し変わってくる んじゃないかと思う。
イスラーム共和国の諜報機関が私の映画製作について情報を得る前に、なんとかイランを脱出することができた俳優も多数います。けれども、今もイランには俳優や映画のエージェントがたくさん残っていて、諜報機関から圧力がかかっています。長い取り調べを受けたり、家族が呼び出されて脅されたりした人もいます。この映画に出演したことで、彼らは起訴され、出国を禁じられました。カメラマンの事務所は強制捜査に遭い、機材はすべて押収されました。音響技師がカナダへ出国することも妨害されました。諜報機関は映画クルーの取り調べの際、私にカンヌ国際映画祭からの撤退を促すよう要求しました。クルーに対し、映画のストーリーを認識しないまま私に操られてプロジェクトに参加させられた、と丸めこもうとしていたのです。
公式HPには他にも色々と書かれており、例えば、イマンとナジメを演じた役者は共に、本作とは関係なく元々イランからの出国が禁じられていた そうだ。イマンを演じた役者の場合は恐らく、モハマド・ラスロフ監督の過去作への出演が原因 ではないかと思う。また、ナジメを演じた女優は元々活動家としての一面も持っており、実刑判決を受けたこともある そうだ。スタッフも含め、皆相当の覚悟を持ってこの撮影に臨んだ のだろうと思う。本当に凄まじい話である。
あわせて読みたい
【告発】アメリカに”監視”される社会を暴露したスノーデンの苦悩と決断を映し出す映画:『スノーデン』…
NSA(アメリカ国家安全保障局)の最高機密にまでアクセスできたエドワード・スノーデンは、その機密情報を持ち出し内部告発を行った。「アメリカは世界中の通信を傍受している」と。『シチズンフォー』と『スノーデン』の2作品から、彼の告発内容とその葛藤を知る
こういう事実を知った上で観ると、「本作のほとんどが、『室内』か『テヘランから離れた辺鄙な場所』で撮影されている」ことにも納得できる だろう。とてもじゃないが、「撮影許可」など得られるような状況ではなかったはず だからだ。市民デモの様子をスマホの映像で代用したのも、そうせざるを得なかったから だろう。
しかし本作は、そういう制約の存在を特に感じさせることのない構成 になっており、その辺りとても見事だっ たなと思う。そしてさらに、そんな厳しい状況に置かれてもなお「映画製作」を止めなかったその情熱や信念の強さみたいなものにも圧倒させられてしまった 。
映画『聖なるイチジクの種』の内容紹介
イマンは、20年間勤めた革命裁判所でようやく昇進の機会を得る 。それまではずっと、「被疑者を起訴するための証拠集め 」を行っており、「被疑者から恨みを買う可能性がある」ため、2人の娘にすら仕事内容を打ち明けられずにいた のだ。正直なところ、昇進後の調査官という立場も恨まれる存在であることに変わりはない のだが、調査官になれば3LDKの官舎に住める 。そこで妻ナジメの勧めもあり、このタイミングで大学生のレズワンと高校生のサナの2人に自身の仕事について話すことに決めた のだ。
あわせて読みたい
【衝撃】映画『JFK/新証言』(オリヴァー・ストーン)が描く、ケネディ暗殺の”知られざる陰謀”
映画『JFK/新証言』は、「非公開とされてきた『ケネディ暗殺に関する資料』が公開されたことで明らかになった様々な事実を基に、ケネディ暗殺事件の違和感を積み上げていく作品だ。「明確な証拠によって仮説を検証していく」というスタイルが明快であり、信頼度の高い調査と言えるのではないかと思う
しかし慎重な母ナジメは2人に、「SNSへの投稿は禁止」「付き合う友人は選びなさい」と厳しく諭す 。政府に対して批判的な意見の多いイランでは、革命裁判所は「体制側」の存在として嫌われる ことが多い。そのため、少しでも隙を見せたらすぐに糾弾されかねない のである。「もしもの時のことを考えて、常に”清廉潔白”でいなければならない 」と口にする母親に対して、娘たちは顔をしかめてみせた 。
さて、念願だったはずの昇進を果たした イマンだったが、しかし彼はすぐに厳しい現実に直面させられる 。というのも、調書が5巻もある事件の被疑者をすぐに死刑で起訴しろと命じられた のだ。彼は直属の上司であるカデリに、「そんなこと出来るわけがない 」「これまで20年間真面目に仕事をしてきた。なのに、調書を読む時間もないまま起訴だなんて 」と拒絶する。しかしカデリは手元のメモに「盗聴されている 」と書き、イマンを食事に誘った。
カデリの話によると、ボスはイマンを嫌っており、本当はボスの直属の部下を昇進させたがっていたのだが、色んな状況があり、最終的には自分が推したイマンが調査官のポストに就くことになった のだそうだ。だからこそ、イマンにはミスは許されない 。ボスは常に、イマンを失脚させるネタを探している からだ。つまり、起訴状へのサインを拒絶したら、イマンもカデリも失墜する のである。ようやく広い官舎に移れ、娘たちも喜んでいる中、今の立場を失うなんて想像も出来ない 。そのためイマンは、信念を曲げざるを得なかった のだ。
あわせて読みたい
【絶望】安倍首相へのヤジが”排除”された衝撃の事件から、日本の民主主義の危機を考える:映画『ヤジと…
映画『ヤジと民主主義 劇場拡大版』が映し出すのは、「政治家にヤジを飛ばしただけで国家権力に制止させられた個人」を巡る凄まじい現実だ。「表現の自由」を威圧的に抑えつけようとする国家の横暴は、まさに「民主主義」の危機を象徴していると言えるだろう。全国民が知るべき、とんでもない事件である
一方で、イマンの昇進と重なるようにして、テヘランでは市民デモが頻発していった 。テレビも盛んに、暴動の様子を伝えている。サナが通う高校は暴動のため休校 となり、そしてさらに、レズワンが通う大学では、構内で発生した暴動に巻き込まれる形で、レズワン唯一の親友であるサダフが顔に散弾銃を被弾、大怪我を負ってしまった のだ。
レズワンはサダフをとりあえず家に連れて帰ろうとした のだが(サダフが「病院に行ったら逮捕される 」と危惧していたため)、そこには1つ問題があった 。その少し前のこと、寮住まいのサダフを家に泊めた ことがある。翌日まで寮が閉鎖されるため行き場がなかったサダフの手助けになれば と思ったのだ。しかしそのことを、母ナジメは良く思わなかった 。夫がどんな反応をするのか分からなかった からだ。レズワンは「二度とこんなことはしない 」「父親が帰ってきたら寝室から出さない 」ことを約束することでどうにかサダフの宿泊を許可してもらった 。
そんなことがあったため、普通にはサダフを家に連れてはいけなかった のである。そのため、家にいたサナが機転を利かせて一旦母を家から遠ざけ、その隙にサダフを家に連れ込む ことが出来た。しかし、「親には連絡しないでほしい」と懇願するサダフ には、とりあえずの応急処置を施してあげるぐらいのこと しか出来ない。
あわせて読みたい
【絶望】映画『少年たちの時代革命』が描く、香港デモの最中に自殺者を救おうとした若者たちの奮闘
香港の民主化運動の陰で、自殺者を救出しようと立ち上がったボランティア捜索隊が人知れず存在していた。映画『少年たちの時代革命』はそんな実話を基にしており、若者の自殺が急増した香港に様々な葛藤を抱えながら暮らし続ける若者たちのリアルが切り取られる作品だ
市民デモは日々激しさを増し 、娘2人がチェックするSNSには警察による横暴を記録した映像が多数アップ されている。一方で、国営放送は国に都合の良い情報しか伝えようとしない 。こうして、SNSでの情報を元にしてデモ側にシンパシーを感じている姉妹 と、夫の仕事上の立ち位置を踏まえ、さらに「そもそも夫・父親には敬意を払うべき」という感覚を持っているナジメ との間に溝が生まれ始めていく 。
さて、一家の大黒柱であるイマンは、暴動を機に仕事が殺人的に忙しくなっていった 。1日の逮捕者が200~300人 、起訴するかどうかの判断を1件2~3分 でこなさなければならないという、もの凄くハードな環境 に置かれていたのだ。そのため、彼は家族を顧みる余裕をどんどんと失っていき 、そして、そんなイマンに対してナジメは憤りを感じ始める 。元々は「家族の幸せ」のためになるはずだった昇進が、「家族をバラバラにするもの」になり始めている からだ。
そしてまさにそのような状況で、重大な”事件”が起こる 。昇進に伴ってイマンに貸与されていた拳銃が紛失してしまった のだ。イマンの記憶では家に持ち帰ったことは確か なのだが、どう探しても見つからない 。拳銃の紛失はそもそも懲役6ヶ月から3年の実刑 なのだが、それ以上に、昇進からわずか2週間での失態は信用を失墜させてしまう 。上司の責任 も追及されるだろう。だから、何が何でも探し出さなければならない 。そのためイマンは、妻と娘たちを疑いとんでもない行動に出る のだが……。
あわせて読みたい
【絶望】知られざる「国による嘘」!映画『蟻の兵隊』(池谷薫)が映し出す終戦直後の日本の欺瞞
映画『蟻の兵隊』は、「1945年8月15日の終戦以降も上官の命令で中国に残らされ、中国の内戦を闘った残留日本軍部隊」の1人である奥村和一を追うドキュメンタリー映画だ。「自らの意思で残った」と判断された彼らは、国からの戦後補償を受けられていない。そんな凄まじい現実と、奥村和一の驚くべき「誠実さ」が描かれる作品である
初めは「ナジメがおかしい」のだとばかり思っていた
本作はもちろん、まず「現実の凄まじさ」みたいな部分に圧倒される物語 だと思う。市民デモの高まりや、イランという国家の運営のされ方など、様々な現実が入り交じることで混沌 としていく。一応、誰もが「正義」を実現しようと行動しているはず なのだが、その気持ちや行動が絶妙にすれ違っていくことでズレが積み重なり、最終的には巨大な溝になっていってしまうような恐ろしさ が、絶妙に描かれていたと思う。
しかし本作は決して、「圧倒的にヤバい現実を舞台にしている」という点だけに依存しているわけではない 。もしそうだとすれば、ドキュメンタリー映画の方がより一層観客を圧倒するはず だ(実際にはイランでは撮れないだろうが )。本作はむしろ「フィクションだからこその凄まじさ 」みたいなものに溢れていて、個人的にはそちらの方により強く惹きつけられた ように思う。
そしてその中心にいるのがナジメ である。
さて、映画が始まってからしばらくの間、私は「ナジメがちょっとおかしいんだ」と考えていた 。というわけで、しばらくその辺りの話をしていこうと思う。
あわせて読みたい
【実話】「家族とうまくいかない現実」に正解はあるか?選択肢が無いと感じる時、何を”選ぶ”べきか?:…
「自分の子どもなんだから、どんな風に育てたって勝手でしょ」という親の意見が正しいはずはないが、この言葉に反論することは難しい。虐待しようが生活能力が無かろうが、親は親だからだ。映画『MOTHER マザー』から、不正解しかない人生を考える
まずはやはり、レズワンの親友サダフに対する態度が気になった 。ナジメは、「寮が閉鎖しているからサダフには行き場がない」という事情を知った上でなお彼女を家から追い出そうと考える 。また、暴動後にサダフを匿っていることを知ったナジメは、自宅で出来る最低限の手当こそしてあげるものの、その後は彼女を自宅に留めず寮へと追い返してしまう 。
サダフが大学で被弾した際、レズワンもすぐ傍にいた 。だからレズワンは、「サダフは暴動に参加していたわけではなく、たまたま巻き込まれただけだ」ということを知っている 。しかし彼女がそう母親に訴えても、ナジメは「無実なら、大怪我を負わせるような捕まえ方はしないでしょ」と、まるで警察のやり方を擁護するかのような主張 をするのだ。
また、暴動の様子を伝えるテレビを観ている時にも価値観の違いが浮き彫りにされる 。SNSを見ている娘たちは、「テレビは警察の暴力を報じない」と国営放送による情報統制を訴える が、ナジメは「テレビが嘘をつくはずがない 」と言い返すのだ。日本でも、上の世代の人ほど「テレビ」を殊更に信じる傾向 があるように思うが、そういうのとは違う何かを感じ、少し違和感を覚えてしまった 。
あわせて読みたい
【倫理】報道の自由度に関わる「放送法の解釈変更」問題をわかりやすく説明(撤回の真相についても):…
安倍政権下で突然発表された「放送法の解釈変更」が、2023年3月17日に正式に”撤回された”という事実をご存知だろうか?映画『テレビ、沈黙。 放送不可能。Ⅱ』は、その「撤回」に尽力した小西洋之議員に田原総一朗がインタビューする作品だ。多くの人が知るべき事実である
そもそもナジメは、夫イマンの主張には基本的に逆らわない し、娘2人には「私の父親は飲んだくれのギャンブル中毒だった。それと比べたらパパは本当に頑張っているんだから、もっと敬意を払いなさい」と説教する ほどである。娘2人はSNSを通じてデモ側にシンパシーを感じているため、体制側の”犬”みたいに革命裁判所に忠誠を誓っているのだろう父親に嫌悪感を抱く ようになるのだが、ナジメは父親に対する娘たちのそんな態度を改めさせようとする のだ。
本作の物語は一応、「家の中で銃が紛失した」という要素がメインになると思う のだが、展開がそこに至るまでにはとにかく時間が掛かる 。本作は167分もある大作 なのだが、私の体感では、物語の中盤ぐらい、大体80分ぐらいが経過した辺りでようやく「銃の紛失」の話になる印象 だった。そこに至るまでの間はとにかく、「ナジメと娘たち」、そして「ナジメとイマン」の関係性について、様々な観点から掘り下げていく という感じである。
そして、「銃の紛失」に至るまでに描かれるナジメの印象は、とにかく「こいつ、ヤバっ」だった 。もっと具体的に書けば、「夫を盲信している妻が、世界標準で見たら平均的な感覚を持っているはずの娘2人を、旧弊な価値観へと押し留めようとしている」みたいに見えていた というわけだ。
あわせて読みたい
【絶望】人生どん底から生き方を変える。映画『シスター 夏のわかれ道』が描く中国人女性の葛藤と諦念
両親の死をきっかけに、「見知らぬ弟」を引き取らなければならなくなった女性を描く映画『シスター 夏のわかれ道』は、中国の特異な状況を背景にしつつ、誰もが抱き得る普遍的な葛藤が切り取られていく。現状を打破するために北京の大学院を目指す主人公は、一体どんな決断を下すのか。
しかし面白いことに、そんな印象は少しずつ変わっていく のである。
もしかしたら、ナジメこそが最も理性的だったと言えるかもしれない
さて、「ナジメはもしかしたらまともなのかもしれない」という感覚は、「銃の紛失」以前にも少しだけ感じていた 。それはこんな場面である。
ナジメが夫のイマンに、レズワンの親友サダフの話をしていた時 のこと。彼女は夫に、「サダフのことを助けてあげてほしい」と頼んでいた 。サダフは結局その後逮捕されてしまった ため、調査官である夫ならどうにか対処できるのではないか と考えての訴えである。まあ、やはりそれは難しそう だという話になるのだが、この時のナジメの言い方が印象的だった 。レズワンには「無実なら、大怪我を負わせるような捕まえ方はしないでしょ」と言っていた にも拘らず、夫に対しては「彼女は本当に無実なのよ」と主張していた のだ。
あわせて読みたい
【抵抗】映画『熊は、いない』は、映画製作を禁じられた映画監督ジャファル・パナヒの執念の結晶だ
映画『熊は、いない』は、「イラン当局から映画製作を20年間も禁じられながら、その後も作品を生み出し続けるジャファル・パナヒ監督」の手によるもので、彼は本作公開後に収監させられてしまった。パナヒ監督が「本人役」として出演する、「ドキュメンタリーとフィクションのあわい」を縫うような異様な作品だ
この時私は「正反対のこと言ってるじゃん 」と感じた。ただ、夫の協力を得ようとしたら「助けるべき人物が無実であること」は絶対条件 だとも思うので、「そういうことも踏まえて『無実』と断言したのかもしれない 」みたいに私は受け取ったのだろう。だからそれ以上深く考えはしなかった のだと思う。
ただ、「銃の紛失」騒ぎが起こり 、そのせいでイマンがメチャクチャ追い詰められていく過程で、少しずつナジメのスタンスが理解できる ようになっていく。彼女は実は、「イカれているようにしか見えない振る舞い」を率先して行っていただけ なのだ。ただ、その理由についてはここでは詳しく触れない ことにしよう。映画のラスト付近で、ナジメが娘2人に「◯◯だから」とその真意を説明する場面 があるのだが、私はそれを聞いてようやくナジメの行動の意味が理解できるようになった のである。
つまりナジメは、常に「最善」を目指して努力し続けていた というわけだ。言動は奇妙に思える かもしれないが、それはそうせざるを得なかっただけ であり、実際には誰よりもまともで、誰よりも頭を使い、常に「最善」を追い求め続けていた のである。
あわせて読みたい
【正義】復讐なんかに意味はない。それでも「この復讐は正しいかもしれない」と思わされる映画:『プロ…
私は基本的に「復讐」を許容できないが、『プロミシング・ヤング・ウーマン』の主人公キャシーの行動は正当化したい。法を犯す明らかにイカれた言動なのだが、その動機は一考の余地がある。何も考えずキャシーを非難していると、矢が自分の方に飛んでくる、恐ろしい作品
そしてそんな事実が明らかになることで、物語の全体像も少し違って見えてくる んじゃないかと思う。「誰がどのように『正義』を実現しようとしているのか? 」に関して、映画冒頭での印象と、映画後半に入ってからのそれとではかなり差が出てくる はずだ。
本作はそんな、ナジメを中心とした「家族の物語」がなかなかに狂気的 であり、そしてそれ故に興味深い作品に仕上がっている のではないかと感じさせられた。
私にはちょっと許容しがたかった、「神」と「法律」についての議論
さて、「正義」に関係する話 として本作では、「神」と「法律」に関する議論 が登場する。私はそもそも、イスラム教に限らず「宗教」全般を嫌悪しているため、イマンの主張にはまったく与することが出来ない が、議論としてはとても興味深かった 。
あわせて読みたい
【衝撃】洗脳を自ら脱した著者の『カルト脱出記』から、「社会・集団の洗脳」を避ける生き方を知る
「聖書研究に熱心な日本人証人」として「エホバの証人」で活動しながら、その聖書研究をきっかけに自ら「洗脳」を脱した著者の体験を著した『カルト脱出記』。広い意味での「洗脳」は社会のそこかしこに蔓延っているからこそ、著者の体験を「他人事」だと無視することはできない
私の理解では、イスラム教を国教に据えている国は、国家全体のルールも相当コーランに依存している印象 がある。例えば、イランの刑罰としてよく「むち打ち」が出てくる が、これも恐らく、コーランにそういう刑罰が記載されているから だと思う。となればコーランは、日本で言う「日本国憲法」に限らず「刑法・民法」にも強く影響する存在 と考えていいだろう。
つまりイランでは「コーラン」=「法律」 であり、だからこそ次のような会話も成立する のである。
娘たち「もし法律が間違っていたら?」
あわせて読みたい
【あらすじ】蝦夷地の歴史と英雄・阿弖流為を描く高橋克彦の超大作小説『火怨』は全人類必読の超傑作
大げさではなく、「死ぬまでに絶対に読んでほしい1冊」としてお勧めしたい高橋克彦『火怨』は凄まじい小説だ。歴史が苦手で嫌いな私でも、上下1000ページの物語を一気読みだった。人間が人間として生きていく上で大事なものが詰まった、矜持と信念に溢れた物語に酔いしれてほしい
確かこの後、ナジメが「パパに逆らうんじゃない」みたいなことを言ってこの会話は終わった 。では、このやり取りから何が理解できるだろうか。まず3人とも、「『コーラン』=『法律』である」という共通認識は持っている と思う(娘2人はそのことを許容してはいない と思うが)。ただ、イマンは「『コーラン』は『神の教え』である」と考えていて、娘たちはそれを疑っている 。イマンは、「『法律』とは『コーラン』のことであり、『コーラン』は『神の教え』なのだから疑う余地などない 」と思っているわけだが、娘たちは「『コーラン』が『法律』なのは一旦許容するとしても、『コーラン』が『神の教え』である保証などないのだから、『コーラン』(つまり『法律』)が間違っている可能性だってある 」と考えているというわけだ。
先述した通り、私は「宗教」全般に嫌悪感を抱いている ので、当然、娘たちの感覚に賛同してしまう 。イマンの主張は、私にはまったく意味不明 である。しかし一方で、「信仰」がイマンのようなスタンスによって今日までの長きに渡り継続されてきたことも理解している つもりだ。私はイマンの価値観には賛同できないが、イマンのような思考の方が長い歴史を有している わけで、それを「不合理だから」で一刀両断するのも正しくないかもしれない 。
さて、別の場面でもイマンは「神の教え」について言及 していた。色んな事情が重なったこともあり、イマンとナジメがサナに対して、「髪を青くしてもいいし、爪を塗っても良い」と歩み寄る場面 がある。しかしその後2人になると、イマンはナジメに「サナは髪を青くしたいのか」と嘆息する のだ。ナジメは「時代が変わったよね」と夫を諌めようとする のだが、それに対してイマンはこんなことを口にする のである。
あわせて読みたい
【差別】映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』の衝撃。プーチンが支持する国の蛮行・LGBT狩り
プーチン大統領の後ろ盾を得て独裁を維持しているチェチェン共和国。その国で「ゲイ狩り」と呼ぶしかない異常事態が継続している。映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』は、そんな現実を命がけで映し出し、「現代版ホロコースト」に立ち向かう支援団体の奮闘も描く作品
でも神は変わっていない。神の法もだ。
私としては本当に嫌悪するしかない感覚 なのだが、恐らくこれが、イランという国家を統治する者たちのベースとなる考え方なのだろう とも思う。作中では「神権政治打倒!」というデモ隊によるシュプレヒコールの声が響く場面 があるのだが、この「神権政治」を私は、「コーランの記載に準じて国家運営を行う」という意味だと理解している 。そしてイランの若者たちは、そんな国家のあり方に対して不満を募らせている というわけだ。他の国のことを知るのが容易ではなかった時代ならともかく、SNSで世界中の情報に触れられる時代においては、特に若者がそういう不満を溜め込んでいくのは当然 だろう。
結局のところ、イランが抱える本質的な問題はここにある のだし、本作『聖なるイチジクの種』は、「父娘の対立」に重ねる形でそんな問題を炙り出している のだと思う。そしてそう捉えるなら、この4人家族は「イラン」という国の現状を象徴している とも言えるだろう。父親が「体制側」、そして娘2人は「体制批判側」 であり、そして、初めはそんな風にはとても見えないだろうが、そんな両者のバランスを絶妙に取ろうとしている「中間層」みたいな存在をナジメが担っている と考えると分かりやすいだろう。
あわせて読みたい
【リアル】社会の分断の仕組みを”ゾンビ”で学ぶ。「社会派ゾンビ映画」が対立の根源を抉り出す:映画『C…
まさか「ゾンビ映画」が、私たちが生きている現実をここまで活写するとは驚きだった。映画『CURED キュアード』をベースに、「見えない事実」がもたらす恐怖と、立場ごとに正しい主張をしながらも否応なしに「分断」が生まれてしまう状況について知る
このように、4人家族というごく小さな単位における様々な対立が、「イランという国家が抱える混乱そのもの」を反映している 感じがあって、そのこともまた印象的な作品だった。「家族の物語」として捉えた場合、本作はあまりにも「狂気的」 なのだが、「実はイランという国家の現状を反映している」と捉えれば、その「狂気」の見え方も変わってくる というわけだ。
そんなわけで、現実をそのまま映し出すドキュメンタリー的な部分も興味深かったが、フィクション部分もとても面白い作品 だった。
映画『聖なるイチジクの種』のその他感想
最後まで観れば作品の構図が色々と分かるわけだが、リアルタイムに物語を追っている時には違和感を覚える部分が結構多かった ように思う。というか、本作のメインの描写であるはずの「銃の紛失」がなかなか描かれなかったり 、それ以降の展開も、「誰が銃を盗んだのか?」に焦点が当たるのかと思いきやそうではなかったり して、何となく予想を裏切る感じが面白い 。また、先程長々と書いた通り、「ナジメの印象がどんどん変わってく」みたいな部分も印象的 で、様々な要素が詰め込まれた魅力的な作品 だったなと思う。
あわせて読みたい
【正義?】FBIが警告した映画『HOW TO BLOW UP』は環境活動家の実力行使をリアルに描き出す
映画『HOW TO BLOW UP』は、「テロを助長する」としてFBIが警告を発したことでも話題になったが、最後まで観てみると、エンタメ作品として実に見事で、とにかく脚本が優れた作品だった。「環境アクティビストが、石油パイプラインを爆破する」というシンプルな物語が、見事な脚本・演出によって魅力的に仕上がっている
また本作では、ラストのラストで「ある人物が、銃を持ってある人物と対峙する」という展開 になる。このような場合、私は普段「撃つなよ!」と思いながら観ていることが多い ように思う。普通に考えれば、「撃たなければならないが撃ちたくはない」みたいな葛藤を描くことが物語的なセオリー だろうし、だとすれば、観ている側としてはやはり、「撃つなよ!」という感覚を抱くのが「製作側が望む正解」 であることが多いはずだ。
ただ本作の場合まったく逆で、私は「撃て!撃て!撃て!」と思いながら観ていた し、それは自分でもかなり意外だった 。とはいえ、本作のこのシーンにおいてはそういう見方が「正解」 であるように思うし、そうなるように上手く誘導されていたのだとしたら流石 だなとも思う。
さて最後に。本作のタイトルにもある「聖なるイチジク」について、本作冒頭でこんな説明が表示される (これは劇場でのメモが追いつかなかったので、ネットで調べて文面を拾った )。
あわせて読みたい
【幻惑】映画『落下の解剖学』は、「真実は誰かが”決める”しかない」という現実の不安定さを抉る
「ある死」を巡って混沌とする状況をリアルに描き出す映画『落下の解剖学』は、「客観的な真実にはたどり着けない」という困難さを炙り出す作品に感じられた。事故なのか殺人なのか自殺なのか、明確な証拠が存在しない状況下で、憶測を繋ぎ合わせるようにして進行する「裁判」の様子から、「『真実性』の捉えがたさ」がよく理解できる
聖なるイチジクの木の一生は独特だ。種子は鳥の糞に混ざり、他の木に落ち、発芽すると地面に向けて根を伸ばす。そして宿主の木に枝を巻き付け、締め上げ、最後には独り立ちするのである。
https://numero.jp/cinema-news-20250215/p6 そもそも「聖なるイチジク」という名前の植物が存在するのかどうかよく分からない のだが(「聖なるイチジク」で調べると検索結果には本作に関する情報がズラッと並んでしまうため)、「イチジク」で調べると、「仏教やヒンドゥー教では『聖なる木』とされる」「エデンの園にあった果物で『原罪』のシンボル」などの話 が出てきた。色んな宗教において特別な意味を持つ果物 であるようだ。しかしざっくり調べた限りにおいては、イスラム教においてどんな意味を持つのかはよく分からなかった 。
また本作を観ても結局、何が「聖なるイチジク」であり、何が「種」なのか、私は理解できていない 。ただ、何となく「目を引くタイトルだな 」とは思うし、さらに「宿主の木に枝を巻き付け、締め上げ、最後には独り立ちする」という説明も本作の雰囲気に合っている感じ がして、タイトルとして秀逸 だった。そういう外枠の部分も含めとても良く出来た作品だったなと思う。
あわせて読みたい
【傑物】フランスに最も愛された政治家シモーヌ・ヴェイユの、強制収容所から国連までの凄絶な歩み:映…
「フランスに最も愛された政治家」と評されるシモーヌ・ヴェイユ。映画『シモーヌ』は、そんな彼女が強制収容所を生き延び、後に旧弊な社会を変革したその凄まじい功績を描き出す作品だ。「強制収容所からの生還が失敗に思える」とさえ感じたという戦後のフランスの中で、彼女はいかに革新的な歩みを続けたのか
監督:モハマド・ラスロフ, 出演:ソヘイラ・ゴレスターニ, 出演:ミシャク・ザラ, 出演:マフサ・ロスタミ, 出演:セターレ・マレキ, 出演:ミシャク・ザラ
¥550 (2025/07/06 23:07時点 | Amazon調べ)
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品視聴済】私が観てきた映画(フィクション)を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が観てきた映画(フィクション)を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。
最後に
あまり期待せず観たからということもあるかもしれないが、思いがけず面白い作品で非常に満足だった 。「映画を撮影するだけで逮捕されてしまう国」というのはどう考えてもヤバい し、宗教の是非はともかく、人々が不当に「自由」を奪われずに済む世の中であってほしい なと思う。
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!「文章の書き方が分からない」「文章力がないから鍛えたい」という方にオススメ…
「文章の書き方」についてのKindle本を出版しました。「文章が書けない」「どう書いたらいいか分からない」「文章力を向上させたい」という方の悩みを解消できるような本に仕上げたつもりです。数多くの文章を書き、さらに頼まれて文章を推敲してきた経験を踏まえ、「文章を書けるようになるにはどうしたらいいか」についての私なりの考えをまとめました。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【不寛容】カルトと呼ばれた「イエスの方舟」の現在は?「理解できなければ排除する社会」を斬る映画:…
映画『方舟にのって』は、1980年に社会を騒がせ、「ハーレム教団」「セックスカルト教団」と呼ばれて大問題となった「イエスの方舟」の現在を追うドキュメンタリー映画だ。そして、そんな本作が本当に映し出してるのは「大衆」の方である。「『理解できないもの』は排除する」という社会に対する違和感を改めて浮き彫りにする1作
あわせて読みたい
【煽動】プロパガンダの天才ゲッベルスがいかにヒトラーやナチスを”演出”したのかを描く映画:『ゲッベ…
映画『ゲッベルス ヒトラーをプロデュースした男』では、ナチスドイツで宣伝大臣を担当したヨーゼフ・ゲッベルスに焦点が当てられる。「プロパガンダの天才」と呼ばれた彼は、いかにして国民の感情を操作したのか。「現代の扇動家」に騙されないためにも、そんな彼の数奇な人生や実像を理解しておいた方がいいのではないかと思う
あわせて読みたい
【評価】都知事選出馬、安芸高田市長時代の「恥を知れ」などで知られる石丸伸二を描く映画『掟』
石丸伸二をモデルに描くフィクション映画『掟』は、「地方政治に無関心な人」に現状の酷さを伝え、「自分ごと」として捉えてもらうきっかけとして機能し得る作品ではないかと感じた。首長がどれだけ変革しようと試みても、旧弊な理屈が邪魔をして何も決まらない。そんな「地方政治の絶望」が本作には詰め込まれているように思う
あわせて読みたい
【リアル】多様性を受け入れる気がない差別主義者のヘイトクライムを描く映画『ソフト/クワイエット』
映画『ソフト/クワイエット』は、「白人至上主義者の女性たちがムチャクチャする」という内容なのだが、実は「多様性」について再考を迫るようなストーリーでもあり、実に興味深かった。さらに「全編ワンカット」というスタイルで撮られており、緊張感や没入感も圧倒的なのだ。凄い映画を観たなと感じさせられた
あわせて読みたい
【悲劇】東京大空襲経験者の体験談。壊滅した浅草、隅田川の遺体、その後の人々の暮らし等の証言集:映…
映画『東京大空襲 CARPET BOMBING of Tokyo』は、2時間半で10万人の命が奪われたという「東京大空襲」を始め、「山手空襲」「八王子空襲」などを実際に経験した者たちの証言が収録された作品だ。そのあまりに悲惨な実態と、その記憶を具体的にはっきりと語る証言者の姿、そのどちらにも驚かされてしまった
あわせて読みたい
【信念】映画『太陽の運命』は、2人の知事、大田昌秀・翁長雄志から沖縄の基地問題の歴史を追う(監督:…
映画『太陽(ティダ)の運命』は、米軍基地問題に翻弄され続けた沖縄の歴史を、大田昌秀・翁長雄志という2人の知事に焦点を当てることで浮き彫りにしていくドキュメンタリー映画である。「日本一難しい問題を背負わされている」という沖縄県知事の苦悩と、「2人の間にあった様々な因縁」がないまぜになった数奇な“運命”の物語
あわせて読みたい
【人権】フランスの民主主義は死んではいないか?映画『暴力をめぐる対話』が問う「権力の行使」の是非
映画『暴力をめぐる対話』は、「『黄色いベスト運動』のデモの映像を観ながら『警察による暴力』について討論を行う者たちを映し出す映画」である。「デモの映像」と「討論の様子」だけというシンプル過ぎる作品で、その上内容はかなり高度でついていくのが難しいのだが、「民主主義とは何か?」について考えさせる、実に有意義なやり取りだなと思う
あわせて読みたい
【権力】コンクラーベをリアルに描く映画『教皇選挙』は、ミステリ的にも秀逸で面白い超社会派物語(監…
映画『教皇選挙』は、「カトリックの教皇を選ぶコンクラーベ」という、一般的な日本人にはまず馴染みのないテーマながら劇場が満員になるほどで、まずそのことに驚かされた。本質的には「権力争い」なのだが、そこに「神に仕える者」という宗教ならではの要素が組み込まれることによって特異で狂気的な状況が生み出されている
あわせて読みたい
【人権】チリ女性の怒り爆発!家父長制と腐敗政治への大規模な市民デモを映し出すドキュメンタリー:映…
「第2のチリ革命」とも呼ばれる2019年の市民デモを映し出すドキュメンタリー映画『私の想う国』は、家父長制と腐敗政治を背景にかなり厳しい状況に置かれている女性たちの怒りに焦点が当てられる。そのデモがきっかけとなったチリの変化も興味深いが、やはり「楽しそうにデモをやるなぁ」という部分にも惹きつけられた
あわせて読みたい
【実話】映画『あんのこと』(入江悠)は、最低の母親に人生を壊された少女の更生と絶望を描く(主演:…
映画『あんのこと』では、クソみたいな母親の元でクソみたいな人生を歩まされた主人公・杏の絶望を河合優実が絶妙に演じている。色んな意味で実に胸糞悪い作品で、こんな社会の歪さがどうしてずっとずっと放置され続けるのか理解できないなと思う。また、河合優実だけではなく、佐藤二朗の演技にも圧倒させられてしまった
あわせて読みたい
【冷戦】”アメリカのビートルズ”と評された、「鉄のカーテンを超えた初のロックバンド」を襲った悲劇:…
映画『ブラッド・スウェット&ティアーズに何が起こったのか?』では、米ソ冷戦の最中に人気を博したロックバンド・BS&Tが辿った数奇な運命を描き出すドキュメンタリー映画である。当時は公表できなかった理由により「鉄のカーテン」の向こう側に行かざるを得なかった彼らは、何を見て、どんな不遇に直面させられたのか?
あわせて読みたい
【洗脳】激しく挑発的だった映画『クラブゼロ』が描く、「食べないこと」を「健康」と言い張る狂気(主…
映画『クラブゼロ』は、「健康的な食事」として「まったく食べないこと」を推奨する女性教師と、彼女に賛同し実践する高校生を描き出す物語。実に狂気的な設定ではあるが、しかし同時に、本作で描かれているのは「日々SNS上で繰り広げられていること」でもある。そんな「現代性」をSNSを登場させずに描き出す、挑発的な作品だ
あわせて読みたい
【狂気】瀧内公美の一人語りのみで展開される映画『奇麗な、悪』の衝撃。凄まじいものを見た(監督:奥…
映画『奇麗な、悪』は、女優・瀧内公美が78分間一人語りするだけの作品で、彼女が放つ雰囲気・存在感に圧倒させられてしまった。誰もいない廃院で、目の前に医師がいるかのように話し続ける主人公の「狂気」が凄まじい。スクリーンの向こう側の出来事なのに、客席で何故か息苦しさを感じたほどの圧巻の演技に打ちのめされた
あわせて読みたい
【正義】名張毒ぶどう酒事件の真相解明の鍵を握る、唯一の再審請求人である妹・岡美代子を追う映画:『…
冤罪と目されている「名張毒ぶどう酒事件」を扱ったドキュメンタリー映画『いもうとの時間』は、逮捕され死刑囚として病死した奥西勝の妹・岡美代子に焦点を当てている。というのも彼女は、「再審請求権」を持つ唯一の人物なのだ。このままでは、事件の真相は闇の中だろう。まずは再審の扉が開かれるべきだと私は思う
あわせて読みたい
【拒絶】映画『ブルータリスト』は、ホロコーストを生き延びた建築家の数奇な人生を描く壮大な物語(監…
映画『ブルータリスト』は、ホロコーストを生き延びたユダヤ人建築家の、アメリカに移り住んで以降の人生を丁寧に追いながら、「ユダヤ人を受け入れないアメリカ」を静かに描き出す物語である。離れ離れにならざるを得なかった妻とのすれ違いにも焦点を当てつつ、時代に翻弄された者たちの悲哀が浮き彫りにされていく
あわせて読みたい
【友情】映画『ノー・アザー・ランド』が映し出す酷すぎる現実。イスラエル軍が住居を壊す様は衝撃だ
イスラエルのヨルダン川西岸地区内の集落マサーフェル・ヤッタを舞台にしたドキュメンタリー映画『ノー・アザー・ランド』では、「昔からその場所に住み続けているパレスチナ人の住居をイスラエル軍が強制的に破壊する」という信じがたい暴挙が映し出される。そんな酷い現状に、立場を越えた友情で立ち向かう様を捉えた作品だ
あわせて読みたい
【忌避】小児性愛者から子どもを救え!映画『サウンド・オブ・フリーダム』が描く衝撃の実話(主演:ジ…
映画『サウンド・オブ・フリーダム』は、世界的に大問題となっている「子どもの人身売買」を扱った、実話を基にした物語である。「フィクションとしか思えないようなおとり捜査」を実行に移した主人公の凄まじい奮闘と、「小児性愛者の変態的欲望」の餌食になる悲惨な子どもたちの現実をリアルに描き出していく
あわせて読みたい
【父親】パキスタン本国では上映禁止の映画『ジョイランド』は、古い価値観に翻弄される家族を描く
映画『ジョイランド』は、本国パキスタンで一時上映禁止とされた作品だが、私たち日本人からすれば「どうして?」と感じるような内容だと思う。「(旧弊な)家族観を否定している」と受け取られたからだろうが、それにしたってやはり理不尽だ。そしてそんな「家族のややこしさ」には、現代日本を生きる我々も共感できるに違いない
あわせて読みたい
【現実】「食」が危ない!映画『フード・インク ポスト・コロナ』が描く、大企業が操る食べ物の罠
映画『フード・インク ポスト・コロナ』は、主にアメリカの事例を取り上げながら、「私たちが直面している『食』はかなり危険な状態にある」と警告する作品だ。「アメリカ人の摂取カロリーの58%を占める」と言われる「超加工食品」の研究はダイエット的な意味でも興味深いし、寡占企業による様々な弊害は私たちにも関係してくるだろう
あわせて読みたい
【解説】映画『シビル・ウォー アメリカ最後の日』は、凄まじい臨場感で内戦を描き、我々を警告する(…
映画『シビル・ウォー』は、「アメリカで勃発した内戦が長期化し、既に日常になってしまっている」という現実を圧倒的な臨場感で描き出す作品だ。戦争を伝える報道カメラマンを主人公に据え、「戦争そのもの」よりも「誰にどう戦争を伝えるか」に焦点を当てる本作は、様々な葛藤を抱きながら最前線を目指す者たちを切り取っていく
あわせて読みたい
【変異】映画『動物界』は斬新で刺激的な作品だった。我々はまさにこんな”分断社会”に生きている
映画『動物界』では、「奇病によって人間が動物化してしまう」という世界における複雑な人間模様が描き出される。パンデミックを経験した我々には、本作の設定は「単なるSF」には感じられないはずだ。そしてその上で、「『動物化してしまった妻を今も愛している主人公』が見せる実にややこしい感情」が複層的に描かれていて実に興味深い
あわせて読みたい
【捏造】袴田事件はついに再審での無罪が決定!冤罪の元死刑囚・袴田巌の現在と姉・秀子の奮闘:映画『…
映画『拳と祈り』は、2024年に再審無罪が確定した「袴田事件」の元死刑囚・袴田巌と、そんな弟を献身的にサポートする姉・秀子の日常を中心に、事件や裁判の凄まじい遍歴を追うドキュメンタリーである。日本の司法史上恐らく初めてだろう「前代未聞の状況」にマスコミで唯一関わることになった監督が使命感を持って追い続けた姉弟の記録
あわせて読みたい
【絶望】満員続出の映画『どうすればよかったか?』が描き出す、娘の統合失調症を認めない両親の不条理
たった4館から100館以上にまで上映館が拡大した話題の映画『どうすればよかったか?』を公開2日目に観に行った私は、「ドキュメンタリー映画がどうしてこれほど注目されているのだろうか?」と不思議に感じた。統合失調症を発症した姉を中心に家族を切り取る本作は、観る者に「自分だったらどうするか?」という問いを突きつける
あわせて読みたい
【感動】映画『ボストン1947』は、アメリカ駐留時代の朝鮮がマラソンで奇跡を起こした実話を描く
映画『ボストン1947』は、アメリカ軍駐留時代の朝鮮を舞台に、様々な困難を乗り越えながらボストンマラソン出場を目指す者たちの奮闘を描き出す物語。日本統治下で日本人としてメダルを授与された”国民の英雄”ソン・ギジョンを中心に、「東洋の小国の奇跡」と評された驚くべき成果を実現させた者たちの努力と葛藤の実話である
あわせて読みたい
【思想】川口大三郎は何故、早稲田を牛耳る革マル派に殺された?映画『ゲバルトの杜』が映す真実
映画『ゲバルトの杜』は、「『革マル派』という左翼の集団に牛耳られた早稲田大学内で、何の罪もない大学生・川口大三郎がリンチの末に殺された」という衝撃的な事件を、当時を知る様々な証言者の話と、鴻上尚史演出による劇映画パートによって炙り出すドキュメンタリー映画だ。同じ国で起こった出来事とは思えないほど狂気的で驚かされた
あわせて読みたい
【実話】株仲買人が「イギリスのシンドラー」に。映画『ONE LIFE』が描くユダヤ難民救出(主演:アンソ…
実話を基にした映画『ONE LIFE 奇跡が繋いだ6000の命』は、「イギリスに住むニコラス・ウィントンがチェコのユダヤ人難民を救う」という話であり、仲間と共に669名も救助した知られざる偉業が扱われている。多くの人に知られるべき歴史だと思うし、また、主演を務めたアンソニー・ホプキンスの演技にも圧倒されてしまった
あわせて読みたい
【絶望】知られざる「国による嘘」!映画『蟻の兵隊』(池谷薫)が映し出す終戦直後の日本の欺瞞
映画『蟻の兵隊』は、「1945年8月15日の終戦以降も上官の命令で中国に残らされ、中国の内戦を闘った残留日本軍部隊」の1人である奥村和一を追うドキュメンタリー映画だ。「自らの意思で残った」と判断された彼らは、国からの戦後補償を受けられていない。そんな凄まじい現実と、奥村和一の驚くべき「誠実さ」が描かれる作品である
あわせて読みたい
【正義?】FBIが警告した映画『HOW TO BLOW UP』は環境活動家の実力行使をリアルに描き出す
映画『HOW TO BLOW UP』は、「テロを助長する」としてFBIが警告を発したことでも話題になったが、最後まで観てみると、エンタメ作品として実に見事で、とにかく脚本が優れた作品だった。「環境アクティビストが、石油パイプラインを爆破する」というシンプルな物語が、見事な脚本・演出によって魅力的に仕上がっている
あわせて読みたい
【実話】映画『ダム・マネー ウォール街を狙え!』は「株で大儲けした」だけじゃない痛快さが面白い
ダム・マネー ウォール街を狙え!』では、株取引で莫大な利益を得た実在の人物が取り上げられる。しかし驚くべきは「大金を得たこと」ではない。というのも彼はなんと、資産5万ドルの身にも拘らず、ウォール街の超巨大資本ファンドを脅かす存在になったのである! 実話とは思えない、あまりにも痛快な物語だった
あわせて読みたい
【SDGs】パリコレデザイナー中里唯馬がファッション界の大量生産・大量消費マインド脱却に挑む映画:『…
映画『燃えるドレスを紡いで』は、世界的ファッションデザイナーである中里唯馬が、「服の墓場」と言うべきナイロビの現状を踏まえ、「もう服を作るのは止めましょう」というメッセージをパリコレの場から発信するまでを映し出すドキュメンタリー映画である。個人レベルで社会を変革しようとする凄まじい行動力と才能に圧倒させられた
あわせて読みたい
【正義】ナン・ゴールディンの”覚悟”を映し出す映画『美と殺戮のすべて』が描く衝撃の薬害事件
映画『美と殺戮のすべて』は、写真家ナン・ゴールディンの凄まじい闘いが映し出されるドキュメンタリー映画である。ターゲットとなるのは、美術界にその名を轟かすサックラー家。なんと、彼らが創業した製薬会社で製造された処方薬によって、アメリカでは既に50万人が死亡しているのだ。そんな異次元の薬害事件が扱われる驚くべき作品
あわせて読みたい
【衝撃】EUの難民問題の狂気的縮図!ポーランド・ベラルーシ国境での、国による非人道的対応:映画『人…
上映に際し政府から妨害を受けたという映画『人間の境界』は、ポーランド・ベラルーシ国境で起こっていた凄まじい現実が描かれている。「両国間で中東からの難民を押し付け合う」という醜悪さは見るに絶えないが、そのような状況下でも「可能な範囲でどうにか人助けをしたい」と考える者たちの奮闘には救われる思いがした
あわせて読みたい
【実話】映画『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』が描く、白人警官による黒人射殺事件
映画『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』は、2011年に起こった実際の事件を元にした作品である。何の罪もない黒人男性が、白人警官に射殺されてしまったのだ。5時22分から始まる状況をほぼリアルタイムで描き切る83分間の物語には、役者の凄まじい演技も含め、圧倒されてしまった
あわせて読みたい
【挑戦】映画『燃えあがる女性記者たち』が描く、インドカースト最下位・ダリットの女性による報道
映画『燃えあがる女性記者たち』は、インドで「カースト外の不可触民」として扱われるダリットの女性たちが立ち上げた新聞社「カバル・ラハリヤ」を取り上げる。自身の境遇に抗って、辛い状況にいる人の声を届けたり権力者を糾弾したりする彼女たちの奮闘ぶりが、インドの民主主義を変革させるかもしれない
あわせて読みたい
【狂気】ISISから孫を取り戻せ!映画『”敵”の子どもたち』が描くシリアの凄絶な現実
映画『”敵”の子どもたち』では、私がまったく知らなかった凄まじい現実が描かれる。イスラム過激派「ISIS」に望んで参加した女性の子ども7人を、シリアから救出するために奮闘する祖父パトリシオの物語であり、その最大の障壁がなんと自国のスウェーデン政府なのだる。目眩がするような、イカれた現実がここにある
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『戦場のピアニスト』(ロマン・ポランスキー)が描く、ユダヤ人迫害の衝撃の実話
映画『戦場のピアニスト』の4Kリマスター版を観に行ったところ、上映後のトークイベントに主人公の息子が登壇したので驚いた。何せ私は、本作が「実話を基にしている」ことさえ知らなかったのである。だからその驚きもひとしおだった。ホロコーストの生存者である主人公の壮絶な人生を描き出す、不朽の名作だ
あわせて読みたい
【情熱】選挙のおもしろ候補者含め”全員取材”をマイルールにする畠山理仁の異常な日常を描く映画:『NO …
選挙に取り憑かれた男・畠山理仁を追うドキュメンタリー映画『NO 選挙, NO LIFE』は、「平均睡眠時間2時間」の生活を長年続ける”イカれた”ライターの「選挙愛」が滲み出る作品だ。「候補者全員を取材しなければ記事にはしない」という厳しすぎるマイルールと、彼が惹かれる「泡沫候補」たちが実に興味深い
あわせて読みたい
【問題】映画『国葬の日』が切り取る、安倍元首相の”独裁”が生んだ「政治への関心の無さ」(監督:大島新)
安倍元首相の国葬の1日を追ったドキュメンタリー映画『国葬の日』は、「国葬」をテーマにしながら、実は我々「国民」の方が深堀りされる作品だ。「安倍元首相の国葬」に対する、全国各地の様々な人たちの反応・価値観から、「『ソフトな独裁』を維持する”共犯者”なのではないか」という、我々自身の政治との向き合い方が問われているのである
あわせて読みたい
【壮絶】アウシュヴィッツで”人体実験の神メンゲレ”から生き残り、ホロコーストから生還した男の人生:…
映画『メンゲレと私』は、タイトルと内容がそぐわないものの、とても興味深い作品だった。44ヶ月間の収容所生活を生き延び、ホロコーストから生還したダニエル・ハノッホが、少年とは思えない「思考力」を武器に、最低最悪な状況を生き延びた経験をカメラの前で語る。あまりにも壮絶な、信じがたい現実である
あわせて読みたい
【無謀】映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、脱北ルートに撮影隊が同行する衝撃のドキュメンタリー
北朝鮮からの脱北者に同行し撮影を行う衝撃のドキュメンタリー映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、再現映像を一切使用していない衝撃的な作品だ。危険と隣り合わせの脱北の道程にカメラもついて回り、北朝鮮の厳しい現状と共に、脱北者が置かれた凄まじい状況を映し出す内容に驚かされてしまった
あわせて読みたい
【衝撃】映画『JFK/新証言』(オリヴァー・ストーン)が描く、ケネディ暗殺の”知られざる陰謀”
映画『JFK/新証言』は、「非公開とされてきた『ケネディ暗殺に関する資料』が公開されたことで明らかになった様々な事実を基に、ケネディ暗殺事件の違和感を積み上げていく作品だ。「明確な証拠によって仮説を検証していく」というスタイルが明快であり、信頼度の高い調査と言えるのではないかと思う
あわせて読みたい
【脅迫】原発という巨大権力と闘ったモーリーン・カーニーをイザベル・ユペールが熱演する映画『私はモ…
実話を基にした映画『私はモーリーン・カーニー』は、前半の流れからはちょっと想像もつかないような展開を見せる物語だ。原発企業で従業員の雇用を守る労働組合の代表を務める主人公が、巨大権力に立ち向かった挙げ句に自宅で襲撃されてしまうという物語から、「良き被害者」という捉え方の”狂気”が浮かび上がる
あわせて読みたい
【抵抗】映画『熊は、いない』は、映画製作を禁じられた映画監督ジャファル・パナヒの執念の結晶だ
映画『熊は、いない』は、「イラン当局から映画製作を20年間も禁じられながら、その後も作品を生み出し続けるジャファル・パナヒ監督」の手によるもので、彼は本作公開後に収監させられてしまった。パナヒ監督が「本人役」として出演する、「ドキュメンタリーとフィクションのあわい」を縫うような異様な作品だ
あわせて読みたい
【絶望】安倍首相へのヤジが”排除”された衝撃の事件から、日本の民主主義の危機を考える:映画『ヤジと…
映画『ヤジと民主主義 劇場拡大版』が映し出すのは、「政治家にヤジを飛ばしただけで国家権力に制止させられた個人」を巡る凄まじい現実だ。「表現の自由」を威圧的に抑えつけようとする国家の横暴は、まさに「民主主義」の危機を象徴していると言えるだろう。全国民が知るべき、とんでもない事件である
あわせて読みたい
【狂気】ホロコーストはなぜ起きた?映画『ヒトラーのための虐殺会議』が描くヴァンゼー会議の真実
映画『ヒトラーのための虐殺会議』は、ホロコーストの計画について話し合われた「ヴァンゼー会議」を描き出す作品だ。唯一1部だけ残った議事録を基に作られた本作は、「ユダヤ人虐殺」をイベントの準備でもしているかのように「理性的」に計画する様を映し出す。その「狂気」に驚かされてしまった。
あわせて読みたい
【抵抗】若者よ、映画『これは君の闘争だ』を見ろ!学校閉鎖に反対する学生運動がブラジルの闇を照らす
映画『これは君の闘争だ』で描かれるのは、厳しい状況に置かれた貧困層の学生たちによる公権力との闘いだ。「貧困層ばかりが通う」とされる公立校が大幅に再編されることを知った学生が高校を占拠して立て籠もる決断に至った背景を、ドキュメンタリー映画とは思えないナレーションで描く異色作
あわせて読みたい
【倫理】報道の自由度に関わる「放送法の解釈変更」問題をわかりやすく説明(撤回の真相についても):…
安倍政権下で突然発表された「放送法の解釈変更」が、2023年3月17日に正式に”撤回された”という事実をご存知だろうか?映画『テレビ、沈黙。 放送不可能。Ⅱ』は、その「撤回」に尽力した小西洋之議員に田原総一朗がインタビューする作品だ。多くの人が知るべき事実である
あわせて読みたい
【デモ】クーデター後の軍事政権下のミャンマー。ドキュメンタリーさえ撮れない治安の中での映画制作:…
ベルリン国際映画祭でドキュメンタリー賞を受賞したミャンマー映画『ミャンマー・ダイアリーズ』はしかし、後半になればなるほどフィクショナルな映像が多くなる。クーデター後、映画制作が禁じられたミャンマーで、10人の”匿名”監督が死を賭して撮影した映像に込められた凄まじいリアルとは?
あわせて読みたい
【天才】映画『Winny』(松本優作監督)で知った、金子勇の凄さと著作権法侵害事件の真相(ビットコイン…
稀代の天才プログラマー・金子勇が著作権法違反で逮捕・起訴された実話を描き出す映画『Winny』は、「警察の凄まじい横暴」「不用意な天才と、テック系知識に明るい弁護士のタッグ」「Winnyが明らかにしたとんでもない真実」など、見どころは多い。「金子勇=サトシ・ナカモト」説についても触れる
あわせて読みたい
【爆笑】ダースレイダー✕プチ鹿島が大暴れ!映画『センキョナンデス』流、選挙の楽しみ方と選び方
東大中退ラッパー・ダースレイダーと新聞14紙購読の時事芸人・プチ鹿島が、選挙戦を縦横無尽に駆け回る様を映し出す映画『劇場版 センキョナンデス』は、なかなか関わろうとは思えない「選挙」の捉え方が変わる作品だ。「フェスのように選挙を楽しめばいい」というスタンスが明快な爆笑作
あわせて読みたい
【狂気?】オウム真理教を内部から映す映画『A』(森達也監督)は、ドキュメンタリー映画史に残る衝撃作だ
ドキュメンタリー映画の傑作『A』(森達也)をようやく観られた。「オウム真理教は絶対悪だ」というメディアの報道が凄まじい中、オウム真理教をその内部からフラットに映し出した特異な作品は、公開当時は特に凄まじい衝撃をもたらしただろう。私たちの「当たり前」が解体されていく斬新な一作
あわせて読みたい
【生還】内戦下のシリアでISISに拘束された男の実話を基にした映画『ある人質』が描く壮絶すぎる現実
実話を基にした映画『ある人質 生還までの398日』は、内戦下のシリアでISISに拘束された男の壮絶な日々が描かれる。「テロリストとは交渉しない」という方針を徹底して貫くデンマーク政府のスタンスに翻弄されつつも、救出のために家族が懸命に奮闘する物語に圧倒される
あわせて読みたい
【誠実】映画『なぜ君は総理大臣になれないのか』で長期密着した政治家・小川淳也の情熱と信念が凄まじい
政治家・小川淳也に17年間も長期密着した映画『なぜ君は総理大臣になれないのか』は、誠実であるが故に大成できない1人の悩める政治家のありのままが描かれる。サラリーマン家庭から政治家を目指し、未来の日本を健全にするために奮闘する男の信念と情熱が詰まった1本
あわせて読みたい
【挑発】「TBS史上最大の問題作」と評されるドキュメンタリー『日の丸』(構成:寺山修司)のリメイク映画
1967年に放送された、寺山修司が構成に関わったドキュメンタリー『日の丸』は、「TBS史上最大の問題作」と評されている。そのスタイルを踏襲して作られた映画『日の丸~それは今なのかもしれない~』は、予想以上に面白い作品だった。常軌を逸した街頭インタビューを起点に様々な思考に触れられる作品
あわせて読みたい
【実話】ソ連の衝撃の事実を隠蔽する記者と暴く記者。映画『赤い闇』が描くジャーナリズムの役割と実態
ソ連の「闇」を暴いた名もなき記者の実話を描いた映画『赤い闇』は、「メディアの存在意義」と「メディアとの接し方」を問いかける作品だ。「真実」を届ける「社会の公器」であるべきメディアは、容易に腐敗し得る。情報の受け手である私たちの意識も改めなければならない
あわせて読みたい
【衝撃】匿名監督によるドキュメンタリー映画『理大囲城』は、香港デモ最大の衝撃である籠城戦の内部を映す
香港民主化デモにおける最大の衝撃を内側から描く映画『理大囲城』は、とんでもないドキュメンタリー映画だった。香港理工大学での13日間に渡る籠城戦のリアルを、デモ隊と共に残って撮影し続けた匿名監督たちによる映像は、ギリギリの判断を迫られる若者たちの壮絶な現実を映し出す
あわせて読みたい
【解説】実話を基にした映画『シカゴ7裁判』で知る、「権力の暴走」と、それに正面から立ち向かう爽快さ
ベトナム戦争に反対する若者たちによるデモと、その後開かれた裁判の実話を描く『シカゴ7裁判』はメチャクチャ面白い映画だった。無理筋の起訴を押し付けられる主席検事、常軌を逸した言動を繰り返す不適格な判事、そして一枚岩にはなれない被告人たち。魅力満載の1本だ
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』で描かれる、グアンタナモ”刑務所”の衝撃の実話は必見
ベネディクト・カンバーバッチが制作を熱望した衝撃の映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』は、アメリカの信じがたい実話を基にしている。「9.11の首謀者」として不当に拘束され続けた男を「救おうとする者」と「追い詰めようとする者」の奮闘が、「アメリカの闇」を暴き出す
あわせて読みたい
【執念】「桶川ストーカー事件」で警察とマスコミの怠慢を暴き、社会を動かした清水潔の凄まじい取材:…
『殺人犯はそこにいる』(文庫X)で凄まじい巨悪を暴いた清水潔は、それよりずっと以前、週刊誌記者時代にも「桶川ストーカー殺人事件」で壮絶な取材を行っていた。著者の奮闘を契機に「ストーカー規制法」が制定されたほどの事件は、何故起こり、どんな問題を喚起したのか
あわせて読みたい
【あらすじ】蝦夷地の歴史と英雄・阿弖流為を描く高橋克彦の超大作小説『火怨』は全人類必読の超傑作
大げさではなく、「死ぬまでに絶対に読んでほしい1冊」としてお勧めしたい高橋克彦『火怨』は凄まじい小説だ。歴史が苦手で嫌いな私でも、上下1000ページの物語を一気読みだった。人間が人間として生きていく上で大事なものが詰まった、矜持と信念に溢れた物語に酔いしれてほしい
あわせて読みたい
【狂気】アメリカの衝撃の実態。民営刑務所に刑務官として潜入した著者のレポートは国をも動かした:『…
アメリカには「民営刑務所」が存在する。取材のためにその1つに刑務官として潜入した著者が記した『アメリカン・プリズン』は信じがたい描写に溢れた1冊だ。あまりに非人道的な行いがまかり通る狂気の世界と、「民営刑務所」が誕生した歴史的背景を描き出すノンフィクション
あわせて読みたい
【あらすじ】嵐莉菜主演映画『マイスモールランド』は、日本の難民問題とクルド人の現状、入管の酷さを描く
映画『マイスモールランド』はフィクションではあるが、「日本に住む難民の厳しい現実」をリアルに描き出す作品だ。『東京クルド』『牛久』などのドキュメンタリー映画を観て「知識」としては知っていた「現実」が、当事者にどれほどの苦しみを与えるのか想像させられた
あわせて読みたい
【差別】映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』の衝撃。プーチンが支持する国の蛮行・LGBT狩り
プーチン大統領の後ろ盾を得て独裁を維持しているチェチェン共和国。その国で「ゲイ狩り」と呼ぶしかない異常事態が継続している。映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』は、そんな現実を命がけで映し出し、「現代版ホロコースト」に立ち向かう支援団体の奮闘も描く作品
あわせて読みたい
【あらすじ】死刑囚を救い出す実話を基にした映画『黒い司法』が指摘する、死刑制度の問題と黒人差別の現実
アメリカで死刑囚の支援を行う団体を立ち上げた若者の実話を基にした映画『黒い司法 0%からの奇跡』は、「死刑制度」の存在価値について考えさせる。上映後のトークイベントで、アメリカにおける「死刑制度」と「黒人差別」の結びつきを知り、一層驚かされた
あわせて読みたい
【悲劇】アメリカの暗黒の歴史である奴隷制度の現実を、元奴隷の黒人女性自ら赤裸々に語る衝撃:『ある…
生まれながらに「奴隷」だった黒人女性が、多くの人の協力を得て自由を手にし、後に「奴隷制度」について書いたのが『ある奴隷少女に起こった出来事』。長らく「白人が書いた小説」と思われていたが、事実だと証明され、欧米で大ベストセラーとなった古典作品が示す「奴隷制度の残酷さ」
あわせて読みたい
【対立】パレスチナとイスラエルの「音楽の架け橋」は実在する。映画『クレッシェンド』が描く奇跡の楽団
イスラエルとパレスチナの対立を背景に描く映画『クレッシェンド』は、ストーリーそのものは実話ではないものの、映画の中心となる「パレスチナ人・イスラエル人混合の管弦楽団」は実在する。私たちが生きる世界に残る様々な対立について、その「改善」の可能性を示唆する作品
あわせて読みたい
【証言】ナチスドイツでヒトラーに次ぐナンバー2だったゲッベルス。その秘書だった女性が歴史を語る映画…
ナチスドイツナンバー2だった宣伝大臣ゲッベルス。その秘書だったブルンヒルデ・ポムゼルが103歳の時にカメラの前で当時を語った映画『ゲッベルスと私』には、「愚かなことをしたが、避け難かった」という彼女の悔恨と教訓が含まれている。私たちは彼女の言葉を真摯に受け止めなければならない
あわせて読みたい
【事件】デュポン社のテフロン加工が有害だと示した男の執念の実話を描く映画『ダーク・ウォーターズ』
世界的大企業デュポン社が、自社製品「テフロン」の危険性を40年以上前に把握しながら公表せず、莫大な利益を上げてきた事件の真相を暴き出した1人の弁護士がいる。映画『ダーク・ウォーターズ』は、大企業相手に闘いを挑み、住民と正義のために走り続けた実在の人物の勇敢さを描き出す
あわせて読みたい
【狂気】”友好”のために北朝鮮入りした監督が撮った映画『ザ・レッド・チャペル』が映す平壌の衝撃
倫理的な葛藤を物ともせず、好奇心だけで突き進んでいくドキュメンタリー監督マッツ・ブリュガーが北朝鮮から「出禁」を食らう結果となった『ザ・レッド・チャペル』は、「友好」を表看板に北朝鮮に潜入し、その「日常」と「非日常」を映し出した衝撃作
あわせて読みたい
【現実】権力を乱用する中国ナチスへの抵抗の最前線・香港の民主化デモを映す衝撃の映画『時代革命』
2019年に起こった、逃亡犯条例改正案への反対運動として始まった香港の民主化デモ。その最初期からデモ参加者たちの姿をカメラに収め続けた。映画『時代革命』は、最初から最後まで「衝撃映像」しかない凄まじい作品だ。この現実は決して、「対岸の火事」ではない
あわせて読みたい
【アメリカ】長崎の「原爆ドーム」はなぜ残らなかった?爆心地にあった「浦上天主堂」の数奇な歴史:『…
原爆投下で半壊し、廃墟と化したキリスト教の大聖堂「浦上天主堂」。しかし何故か、「長崎の原爆ドーム」としては残されず、解体されてしまった。そのため長崎には原爆ドームがないのである。『ナガサキ 消えたもう一つの「原爆ドーム」』は、「浦上天主堂」を巡る知られざる歴史を掘り下げ、アメリカの強かさを描き出す
あわせて読みたい
【衝撃】権力の濫用、政治腐敗を描く映画『コレクティブ』は他人事じゃない。「国家の嘘」を監視せよ
火災で一命を取り留め入院していた患者が次々に死亡した原因が「表示の10倍に薄められた消毒液」だと暴き、国家の腐敗を追及した『ガゼタ』誌の奮闘を描く映画『コレクティブ 国家の嘘』は、「権力の監視」が機能しなくなった国家の成れの果てが映し出される衝撃作だ
あわせて読みたい
【驚愕】キューバ危機の裏側を描くスパイ映画『クーリエ』。核戦争を回避させた民間人の衝撃の実話:『…
核戦争ギリギリまで進んだ「キューバ危機」。その陰で、世界を救った民間人がいたことをご存知だろうか?実話を元にした映画『クーリエ:最高機密の運び屋』は、ごく普通のセールスマンでありながら、ソ連の膨大な機密情報を盗み出した男の信じがたい奮闘を描き出す
あわせて読みたい
【日常】難民問題の現状をスマホで撮る映画。タリバンから死刑宣告を受けた監督が家族と逃避行:『ミッ…
アフガニスタンを追われた家族4人が、ヨーロッパまで5600kmの逃避行を3台のスマホで撮影した映画『ミッドナイト・トラベラー』は、「『難民の厳しい現実』を切り取った作品」ではない。「家族アルバム」のような「笑顔溢れる日々」が難民にもあるのだと想像させてくれる
あわせて読みたい
【衝撃】『殺人犯はそこにいる』が実話だとは。真犯人・ルパンを野放しにした警察・司法を信じられるか?
タイトルを伏せられた覆面本「文庫X」としても話題になった『殺人犯はそこにいる』。「北関東で起こったある事件の取材」が、「私たちが生きる社会の根底を揺るがす信じがたい事実」を焙り出すことになった衝撃の展開。まさか「司法が真犯人を野放しにする」なんてことが実際に起こるとは。大げさではなく、全国民必読の1冊だと思う
あわせて読みたい
【実話】「ホロコーストの映画」を観て改めて、「有事だから仕方ない」と言い訳しない人間でありたいと…
ノルウェーの警察が、自国在住のユダヤ人をまとめて船に乗せアウシュビッツへと送った衝撃の実話を元にした映画『ホロコーストの罪人』では、「自分はそんな愚かではない」と楽観してはいられない現実が映し出される。このような悲劇は、現在に至るまで幾度も起こっているのだ
あわせて読みたい
【凄絶】北朝鮮の”真実”を描くアニメ映画。強制収容所から決死の脱出を試みた者が語る驚愕の実態:『ト…
在日コリアン4世の監督が、北朝鮮脱北者への取材を元に作り上げた壮絶なアニメ映画『トゥルーノース』は、私たちがあまりに恐ろしい世界と地続きに生きていることを思い知らせてくれる。最低最悪の絶望を前に、人間はどれだけ悪虐になれてしまうのか、そしていかに優しさを発揮できるのか。
あわせて読みたい
【弾圧】香港デモの象徴的存在デニス・ホーの奮闘の歴史。注目の女性活動家は周庭だけじゃない:映画『…
日本で香港民主化運動が報じられる際は周庭さんが取り上げられることが多いが、香港には彼女よりも前に民主化運動の象徴的存在として認められた人物がいる。映画『デニス・ホー ビカミング・ザ・ソング』の主人公であるスター歌手の激動の人生を知る
あわせて読みたい
【民主主義】占領下の沖縄での衝撃の実話「サンマ裁判」で、魚売りのおばぁの訴えがアメリカをひっかき…
戦後の沖縄で、魚売りのおばぁが起こした「サンマ裁判」は、様々な人が絡む大きな流れを生み出し、最終的に沖縄返還のきっかけともなった。そんな「サンマ裁判」を描く映画『サンマデモクラシー』から、民主主義のあり方と、今も沖縄に残り続ける問題について考える
あわせて読みたい
【感想】映画『野火』は、戦争の”虚しさ”をリアルに映し出す、後世に受け継がれるべき作品だ
「戦争の悲惨さ」は様々な形で描かれ、受け継がれてきたが、「戦争の虚しさ」を知る機会はなかなかない。映画『野火』は、第二次世界大戦中のフィリピンを舞台に、「敵が存在しない戦場で”人間の形”を保つ困難さ」を描き出す、「虚しさ」だけで構成された作品だ
あわせて読みたい
【残念】日本の「難民受け入れ」の現実に衝撃。こんな「恥ずべき国」に生きているのだと絶望させられる…
日本の「難民認定率」が他の先進国と比べて異常に低いことは知っていた。しかし、日本の「難民」を取り巻く実状がこれほど酷いものだとはまったく知らなかった。日本で育った2人のクルド人難民に焦点を当てる映画『東京クルド』から、日本に住む「難民」の現実を知る
あわせて読みたい
【矛盾】その”誹謗中傷”は真っ当か?映画『万引き家族』から、日本社会の「善悪の判断基準」を考える
どんな理由があれ、法を犯した者は罰せられるべきだと思っている。しかしそれは、善悪の判断とは関係ない。映画『万引き家族』(是枝裕和監督)から、「国民の気分」によって「善悪」が決まる社会の是非と、「善悪の判断を保留する勇気」を持つ生き方について考える
あわせて読みたい
【驚愕】正義は、人間の尊厳を奪わずに貫かれるべきだ。独裁政権を打倒した韓国の民衆の奮闘を描く映画…
たった30年前の韓国で、これほど恐ろしい出来事が起こっていたとは。「正義の実現」のために苛烈な「スパイ狩り」を行う秘密警察の横暴をきっかけに民主化運動が激化し、独裁政権が打倒された史実を描く『1987、ある闘いの真実』から、「正義」について考える
あわせて読みたい
【勇敢】”報道”は被害者を生む。私たちも同罪だ。”批判”による”正義の実現”は正義だろうか?:『リチャ…
「爆弾事件の被害を最小限に食い止めた英雄」が、メディアの勇み足のせいで「爆弾事件の犯人」と報じられてしまった実話を元にした映画『リチャード・ジュエル』から、「他人を公然と批判する行為」の是非と、「再発防止という名の正義」のあり方について考える
あわせて読みたい
【権利】衝撃のドキュメンタリー映画『ヤクザと憲法』は、「異質さを排除する社会」と「生きる権利」を問う
「ヤクザ」が排除された現在でも、「ヤクザが担ってきた機能」が不要になるわけじゃない。ではそれを、公権力が代替するのだろうか?実際の組事務所(東組清勇会)にカメラを持ち込むドキュメンタリー映画『ヤクザと憲法』が映し出す川口和秀・松山尚人・河野裕之の姿から、「基本的人権」のあり方について考えさせられた
あわせて読みたい
【真実?】佐村河内守のゴーストライター騒動に森達也が斬り込んだ『FAKE』は我々に何を問うか?
一時期メディアを騒がせた、佐村河内守の「ゴースト問題」に、森達也が斬り込む。「耳は聴こえないのか?」「作曲はできるのか?」という疑惑を様々な角度から追及しつつ、森達也らしく「事実とは何か?」を問いかける『FAKE』から、「事実の捉え方」について考える
あわせて読みたい
【告発】アメリカに”監視”される社会を暴露したスノーデンの苦悩と決断を映し出す映画:『スノーデン』…
NSA(アメリカ国家安全保障局)の最高機密にまでアクセスできたエドワード・スノーデンは、その機密情報を持ち出し内部告発を行った。「アメリカは世界中の通信を傍受している」と。『シチズンフォー』と『スノーデン』の2作品から、彼の告発内容とその葛藤を知る
あわせて読みたい
【絶望】権力の濫用を止めるのは我々だ。映画『新聞記者』から「ソフトな独裁国家・日本」の今を知る
私個人は、「ビジョンの達成」のためなら「ソフトな独裁」を許容する。しかし今の日本は、そもそも「ビジョン」などなく、「ソフトな独裁状態」だけが続いていると感じた。映画『新聞記者』をベースに、私たちがどれだけ絶望的な国に生きているのかを理解する
あわせて読みたい
【正義】マイノリティはどう生き、どう扱われるべきかを描く映画。「ルールを守る」だけが正解か?:映…
社会的弱者が闘争の末に権利を勝ち取ってきた歴史を知った上で私は、闘わずとも権利が認められるべきだと思っている。そして、そういう社会でない以上、「正義のためにルールを破るしかない」状況もある。映画『パブリック』から、ルールと正義のバランスを考える
あわせて読みたい
【意外】東京裁判の真実を記録した映画。敗戦国での裁判が実に”フェア”に行われたことに驚いた:『東京…
歴史に詳しくない私は、「東京裁判では、戦勝国が理不尽な裁きを行ったのだろう」という漠然としたイメージを抱いていた。しかし、その印象はまったくの誤りだった。映画『東京裁判 4Kリマスター版』から東京裁判が、いかに公正に行われたのかを知る
あわせて読みたい
【勇敢】後悔しない生き方のために”間違い”を犯せるか?法に背いてでも正義を貫いた女性の生き様:映画…
国の諜報機関の職員でありながら、「イラク戦争を正当化する」という巨大な策略を知り、守秘義務違反をおかしてまで真実を明らかにしようとした実在の女性を描く映画『オフィシャル・シークレット』から、「法を守る」こと以上に重要な生き方の指針を学ぶ
あわせて読みたい
【情熱】「ルール」は守るため”だけ”に存在するのか?正義を実現するための「ルール」のあり方は?:映…
「ルールは守らなければならない」というのは大前提だが、常に例外は存在する。どれほど重度の自閉症患者でも断らない無許可の施設で、情熱を持って問題に対処する主人公を描く映画『スペシャルズ!』から、「ルールのあるべき姿」を考える
あわせて読みたい
【驚愕】「金正男の殺人犯」は”あなた”だったかも。「人気者になりたい女性」が陥った巧妙な罠:映画『…
金正男が暗殺された事件は、世界中で驚きをもって報じられた。その実行犯である2人の女性は、「有名にならないか?」と声を掛けられて暗殺者に仕立て上げられてしまった普通の人だ。映画『わたしは金正男を殺していない』から、危険と隣り合わせの現状を知る
あわせて読みたい
【情熱】常識を疑え。人間の”狂気”こそが、想像し得ない偉業を成し遂げるための原動力だ:映画『博士と…
世界最高峰の辞書である『オックスフォード英語大辞典』は、「学位を持たない独学者」と「殺人犯」のタッグが生みだした。出会うはずのない2人の「狂人」が邂逅したことで成し遂げられた偉業と、「狂気」からしか「偉業」が生まれない現実を、映画『博士と狂人』から学ぶ
あわせて読みたい
【実話】正論を振りかざす人が”強い”社会は窮屈だ。映画『すばらしき世界』が描く「正解の曖昧さ」
「SNSなどでの炎上を回避する」という気持ちから「正論を言うに留めよう」という態度がナチュラルになりつつある社会には、全員が全員の首を締め付け合っているような窮屈さを感じてしまう。西川美和『すばらしき世界』から、善悪の境界の曖昧さを体感する
あわせて読みたい
【再生】ヤクザの現実を切り取る映画『ヤクザと家族』から、我々が生きる社会の”今”を知る
「ヤクザ」を排除するだけでは「アンダーグラウンドの世界」は無くならないし、恐らく状況はより悪化しただけのはずだ。映画『ヤクザと家族』から、「悪は徹底的に叩きのめす」「悪じゃなければ何をしてもいい」という社会の風潮について考える。
あわせて読みたい
【天才】『三島由紀夫vs東大全共闘』後に「伝説の討論」と呼ばれる天才のバトルを記録した驚異の映像
1969年5月13日、三島由紀夫と1000人の東大全共闘の討論が行われた。TBSだけが撮影していたフィルムを元に構成された映画「三島由紀夫vs東大全共闘」は、知的興奮に満ち溢れている。切腹の一年半前の討論から、三島由紀夫が考えていたことと、そのスタンスを学ぶ
あわせて読みたい
【絶望】子供を犯罪者にしないために。「異常者」で片付けられない、希望を見いだせない若者の現実:『…
2人を殺し、7人に重傷を負わせた金川真大に同情の余地はない。しかし、この事件を取材した記者も、私も、彼が殺人に至った背景・動機については理解できてしまう部分がある。『死刑のための殺人』をベースに、「どうしようもないつまらなさ」と共に生きる現代を知る
あわせて読みたい
【衝撃】森達也『A3』が指摘。地下鉄サリン事件を起こしたオウム真理教は社会を激変させた
「オウム真理教は特別だ、という理由で作られた”例外”が、いつの間にか社会の”前提”になっている」これが、森達也『A3』の主張の要点だ。異常な状態で続けられた麻原彰晃の裁判を傍聴したことをきっかけに、社会の”異様な”変質の正体を理解する。
あわせて読みたい
【加虐】メディアの役割とは?森達也『A』が提示した「事実を報じる限界」と「思考停止社会」
オウム真理教の内部に潜入した、森達也のドキュメンタリー映画『A』は衝撃を与えた。しかしそれは、宗教団体ではなく、社会の方を切り取った作品だった。思考することを止めた社会の加虐性と、客観的な事実など切り取れないという現実について書く
あわせて読みたい
【衝撃】壮絶な戦争映画。最愛の娘を「産んで後悔している」と呟く母らは、正義のために戦場に留まる:…
こんな映画、二度と存在し得ないのではないかと感じるほど衝撃を受けた『娘は戦場で生まれた』。母であり革命家でもあるジャーナリストは、爆撃の続くシリアの街を記録し続け、同じ街で娘を産み育てた。「知らなかった」で済ませていい現実じゃない。
あわせて読みたい
【驚愕】日本の司法は終わってる。「中世レベル」で「無罪判決が多いと出世に不利」な腐った現実:『裁…
三権分立の一翼を担う裁判所のことを、私たちはよく知らない。元エリート裁判官・瀬木比呂志と事件記者・清水潔の対談本『裁判所の正体』をベースに、「裁判所による統制」と「権力との癒着」について書く。「中世レベル」とさえ言われる日本の司法制度の現実は、「裁判になんか関わることない」という人も無視できないはずだ
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
国家・政治・制度・地方【本・映画の感想】 | ルシルナ
私たちがどのような社会で生きているのか理解することは重要でしょう。ニュースやネット記事などを総合して現実を理解することはなかなか難しいですが、政治や社会制度など…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…






















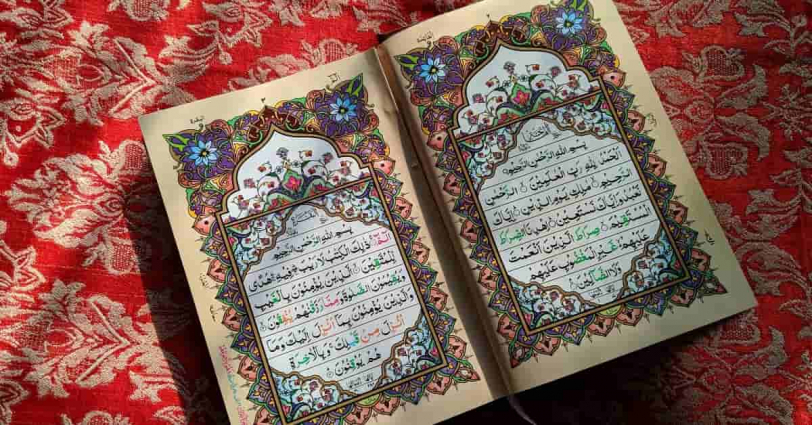





































































































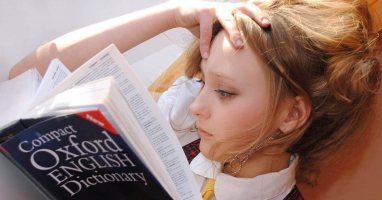

















コメント