目次
はじめに
この記事で取り上げる映画
出演:網谷勇気, 出演:渉, 監督:島田隆一
¥500 (2024/08/02 23:33時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
この映画をガイドにしながら記事を書いていきます
今どこで観れるのか?
公式HPの劇場情報を御覧ください
この記事の3つの要点
- ほぼ何の説明もされないまま展開される構成が、ドキュメンタリーなのにフィクションっぽくもあり、面白い
- カメラの存在がほぼ透明になっている点も、フィクションっぽさを感じさせる要素になっている
- マイノリティである主人公が突きつける「『無関心であること』に対する憤り」に共感させられた
なんとも説明が難しい”変な”映画なのだが、観て良かったと感じる、実に興味深い作品
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
記事中の引用は、映画館で取ったメモを参考にしているので、正確なものではありません
「ゲイの男性」を主人公にしながら、「LGBTQ」「マイノリティ」といった要素が前面に押し出されない、ちょっと変わったドキュメンタリー映画『二十歳の息子』
あわせて読みたい
【純真】ゲイが犯罪だった時代が舞台の映画『大いなる自由』は、刑務所内での極深な人間ドラマを描く
男性同士の恋愛が犯罪であり、ゲイの男性が刑法175条を理由に逮捕されてしまう時代のドイツを描いた映画『大いなる自由』は、確かに同性愛の物語なのだが、実はそこに本質はない。物語の本質は、まさにタイトルにある通り「自由」であり、ラストシーンで突きつけられるその深い問いかけには衝撃を受けるだろう
想像していたよりもずっと、好きなタイプの映画だった。しかし、かなり変わった作品である。
冒頭からしばらくの間、何が描かれようとしているのかさっぱり理解できなかった
私は普段から、これから観ようと思っている映画について情報も評価も特に調べないことにしている。なので、私がこの映画を観る前に知っていた情報は、『二十歳の息子』というタイトルと、ポスターなどに書かれていた「ゲイの私が、父親になった。」というフレーズだけ。そしてそれらから漠然と、「カミングアウト」が描かれる映画なのかなと想像していた。

その予想は、大外れだったと言っていいだろう。まさに『二十歳の息子』というタイトルそのままの映画だったのである。
あわせて読みたい
【差別】映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』の衝撃。プーチンが支持する国の蛮行・LGBT狩り
プーチン大統領の後ろ盾を得て独裁を維持しているチェチェン共和国。その国で「ゲイ狩り」と呼ぶしかない異常事態が継続している。映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』は、そんな現実を命がけで映し出し、「現代版ホロコースト」に立ち向かう支援団体の奮闘も描く作品
私は今回、記事タイトルで既にどんな内容なのかを書いてしまっているので、この記事を読んで観ようと思ってくれた人は無理だが、私と同じように、内容をまったく知らない状態で観に行くのも面白いだろう。とにかく冒頭から、ほぼなんの説明もないまま主人公となる男性が映し出され、そのまま展開していくのだ。その「分からなさ」を楽しんでみるのも、アリだと私は思う。
冒頭からしばらくは、中年男性が引っ越し作業をしている様子が淡々と映し出されていく。彼が引っ越しをするのには、当然、その後の展開に関係する理由があるのだが、冒頭の時点ではそれはまだ分からない。その中年男性が、この映画においてメインで映し出される人物の1人であり、しばらく観ていると、彼が「網谷勇気」という名前であることが分かってくる。
引っ越しの準備を終えた網谷勇気が向かったのは、なんと東京拘置所だった。年若い男性と一緒に出てくる。2人は、あるアパートの1室へと入っていった。そして、網谷勇気が引っ越し作業をしていたのは、東京拘置所へと迎えに行った男性と一緒に住むためだということが、ここで明らかになる。階段が急であることを除けば、2人で暮らすには十分な部屋だろう。
あわせて読みたい
【感想】おげれつたなか『エスケープジャーニー』は、BLでしか描けない”行き止まりの関係”が絶妙
おげれつたなか『エスケープジャーニー』のあらすじ紹介とレビュー。とにかく、「BLでしか描けない関係性」が素晴らしかった。友達なら完璧だったのに、「恋人」ではまったく上手く行かなくなってしまった直人と太一の葛藤を通じて、「進んでも行き止まり」である関係にどう向き合うか考えさせられる
しかしそもそも、彼らの関係性も分からないし、何故一緒に住むことになったのかも分からないままだ。いや、その説明は正しくはないか。この時点では「親子なのだろう」と考えるのが自然だし、私もそう認識していたと思う。年齢的にも、網谷勇気には、拘置所へ迎えに行った男性ぐらいの息子がいてもおかしくなさそうだ。「刑期を終えた息子を迎えに行った」と考えるのが、状況としては一番しっくり来るだろう。
しかし次に続くシーンで、そうではなさそうだということが明らかになった。
網谷勇気を含む何人かの男性が、車座になって雑談をしている。それが何の集まりなのかは説明されない。しばらくとりとめのない話をした後で、網谷勇気がおもむろに「養子縁組をした」と話し始める。さらに、それを受けての周囲の人々の反応から、網谷勇気が「ゲイ」であることが分かるのだ。ただし、何の集まりなのか不明なため、その場にいる全員がゲイなのかは分からない。
あわせて読みたい
【LGBT】映画『リトル・ガール』で映し出される、性別違和を抱える8歳の”女の子”のリアルと苦悩
映画撮影時8歳だった、身体は男の子、心は女の子のサシャは、スカートを履いての登校が許されず、好きなバッグもペンケースも使わせてもらえない。映画『リトル・ガール』が描く、「性別違和」に対する社会の不寛容と、自分を責め続けてしまう母親の苦悩
こうして観客は、網谷勇気が、「ゲイでありながら、拘置所から出所した男性と養子縁組して親子関係となり、一緒に暮らすことになった」と理解することになるのだ。まさに『二十歳の息子』というタイトルがピッタリだと言えるだろう。もう1人の主人公である若者の名は、「網谷渉」である。
そんな2人と、彼らを取り巻く様々な人たちを映し出すドキュメンタリー映画というわけだ。
「カメラの透明さ」、そして「『ゲイであること』に焦点が当たらない構成」
映画を観ながら印象的だったのは、「カメラの存在が透明だったこと」だ。
あわせて読みたい
【対話】刑務所内を撮影した衝撃の映画。「罰則」ではなく「更生」を目指す環境から罪と罰を学ぶ:映画…
2008年に開設された新たな刑務所「島根あさひ社会復帰促進センター」で行われる「TC」というプログラム。「罰則」ではなく「対話」によって「加害者であることを受け入れる」過程を、刑務所内にカメラを入れて撮影した『プリズン・サークル』で知る。

私は結構ドキュメンタリー映画を観ているが、普通は「そこにカメラがあること」は大前提の事実として存在しているように思う。特に、「状況」にではなく「人物」に焦点を当てて撮影を行うドキュメンタリーであればなおさらだ。「カメラがあるという事実」は通常、「出演者のカメラ目線」や「撮影者との会話」、あるいは「出演者がカメラを意識する素振り」などによって強調されることになるのだが、『二十歳の息子』ではとにかく、「カメラの存在の希薄さ」が目立つように感じられた。
網谷勇気と網谷渉がカメラに向かって話す場面はある。しかし私の記憶では、そのような場面は2回ずつの計4回、時間にして2分もなかったんじゃないかと思う。そしてそれ以外の時間はすべて、「そこにカメラなど存在しない」かのように撮影がなされていたのだ。
同じようなやり方をしていて驚かされた作品が、映画『14歳の栞』である。ある中学校に長期密着したそのドキュメンタリー映画でも、カメラの存在をまったく感じさせない演出に驚かされた。
あわせて読みたい
【現代】これが今の若者の特徴?衝撃のドキュメンタリー映画『14歳の栞』から中学生の今を知る
埼玉県春日部市に実在する中学校の2年6組の生徒35人。14歳の彼らに50日間密着した『14歳の栞』が凄かった。カメラが存在しないかのように自然に振る舞い、内心をさらけ出す彼らの姿から、「中学生の今」を知る
私は色々あって、テレビの取材を受ける経験を何度かしたことがあるのだが、やはり「カメラを向けられた状態」で「自然に振る舞う」ことは結構難しい。現代であれば、YouTuberや配信者みたいな人たちが増えているから、そういう状況に慣れている人も多いかもしれない。ただ映画『二十歳の息子』では、網谷勇気の両親や妹、あるいは彼が所属するある団体にもカメラが入り込む。そういう状況でも、常に「カメラの存在」が無いかのように撮り続けるのはかなり困難だろう。
『14歳の栞』をどんな風に撮影したのかは未だに謎だが、『二十歳の息子』の場合は、メインとなるのは網谷勇気と網谷渉だけなので、彼ら2人がカメラの存在に慣れてくれさえすればどうにかなりそうな気はする。他の場面については、「カメラに干渉したシーンはすべてカットした」と考えればいいからだ。
しかし、もしもこの想像が正しいなら、その演出は意図的なものと受け取るべきだろう。恐らくだが制作側はこの作品を、「ドキュメンタリーっぽく仕上げる」のではなく「フィクションっぽく仕上げる」ことを意図していたのではないかと思う。そう考えないと、「カメラの透明さ」の説明がつけられない気がするのだ。
冒頭で「変わった映画」と書いたが、それは、「ドキュメンタリー映画なのに、フィクションっぽい」という、この映画が有する特徴に依るところが大きかったのかもしれない。
あわせて読みたい
【特異】「カメラの存在」というドキュメンタリーの大前提を覆す映画『GUNDA/グンダ』の斬新さ
映画『GUNDA/グンダ』は、「カメラの存在」「撮影者の意図」を介在させずにドキュメンタリーとして成立させた、非常に異端的な作品だと私は感じた。ドキュメンタリーの「デュシャンの『泉』」と呼んでもいいのではないか。「家畜」を被写体に据えたという点も非常に絶妙
またもう1点、良い意味で奇妙さを感じさせられたポイントがある。それは、「『網谷勇気がゲイである』という事実に、作中ではほぼ焦点が当てられない」ということだ。どうしてこれを「良い」と感じたのかと言えば、1つには、現代の「ポリティカル・コレクトネス」への”過剰な”配慮が挙げられる。
「ポリティカル・コレクトネス」とは「差別的な意味や誤解が含まれてしまわないように配慮された態度・表現」ぐらいの意味で捉えておけばいいだろう。いつ頃からかは分からないが、映画に限らずあらゆる表現において、「ポリティカル・コレクトネスを念頭に置いているだろう描写」が出てくるようになった。それ自体は決して悪いことではないものの、「過剰」「あからさま」と感じさせるものもあり、正直、あまり気分が良いものではない。「我々は差別に配慮していますし、差別的な感情なんてまったく持っていませんよ」という「圧力」みたいなものが強すぎて、その表現が伝えるべき本来の意味を的確に受け取れなくなってしまうからだ。

しかしこの映画に、そのような雰囲気は一切ない。というか、「網谷勇気がゲイであろうがなかろうが、どっちでもいい」ぐらいのスタンスにさえ感じられた。もちろん、そんなわけはない。ゲイではない男性が養子縁組をしたところで、恐らく「映画にしよう」とは思わなかったはずだからだ。「ゲイの男性が養子縁組をする」からこそ、この映画の制作が決まったと考えていいはずである。しかし、制作側のそのようなスタンスは、少なくとも画面からは滲み出て来なかった。その点がとても良かったと私は思う。
あわせて読みたい
【感想】映画『朝が来る』が描く、「我が子を返して欲しい気持ち」を消せない特別養子縁組のリアル
「特別養子縁組」を軸に人々の葛藤を描く映画『朝が来る』は、決して「特別養子縁組」の話ではない。「『起こるだろうが、起こるはずがない』と思っていた状況」に直面せざるを得ない人々が、「すべての選択肢が不正解」という中でどんな決断を下すのかが問われる、非常に示唆に富む作品だ
そのような雰囲気の作品に仕上がったのは、もちろん、網谷勇気自身が「ゲイであること」を大したことだと捉えていないような振る舞いをしているからだろう。そしてさらにその背景には、彼の両親の存在が大きかったように思う。
網谷勇気には、ゲイである自身の様々な体験談を講演などで話す機会があるようだ。映画でも、そのいくつかが映し出されていた。その中で、彼が初めて両親にカミングアウトした際の話が出てくる。彼がゲイであることを自覚したのは14歳の頃だった。そしてその後様々に悩んだ末、「死にたい。でも、どうせ死ぬならカミングアウトしてダメだったら死のう」と考え、両親に打ち明けたのである。
その際の両親の反応が実に興味深かった。父親は、「ゲイ雑誌があるから知ってた」と、そして母親は「そんなことより学校の成績は大丈夫なの?」と言ったのそうだ。きっと本人も拍子抜けしたことだろう。そして恐らく、最初に打ち明けた両親がそんな感じだったから、彼も「ゲイである」という自身のアイデンティティについて「大したことじゃない」と思えるようになったのではないかと思う。
あわせて読みたい
【感想】映画『窮鼠はチーズの夢を見る』を異性愛者の男性(私)はこう観た。原作も読んだ上での考察
私は「腐男子」というわけでは決してないのですが、周りにいる腐女子の方に教えを請いながら、多少BL作品に触れたことがあります。その中でもダントツに素晴らしかったのが、水城せとな『窮鼠はチーズの夢を見る』です。その映画と原作の感想、そして私なりの考察について書いていきます
また作中では、網谷勇気が「息子」である網谷渉を連れて実家を訪れる場面も映し出されていた。みんなで鍋をつつき、途中から妹も加わり、妹から問われるような形で、網谷渉は「生まれた時から親がいなくて……」と自身の身の上を語っていく。恐らく網谷渉にとっては、「初めての家族団らん」だったのではないかと思う。
「ゲイの息子が、養子縁組した『孫』を連れてくる」という状況は、なかなか普通には起こり得ないと思うのだが、妹はともかく、網谷勇気の両親はさも当たり前かのように網谷渉を受け入れていた。また本作には、網谷渉と父親がベランダでタバコを吸うシーンもある。恐らくこの日が初対面のはずだが、とても普通に接していた。一般的には、年配の男性の方が「頭が固い」ような先入観を抱いてしまうだろうが、網谷勇気の父親には当てはまらないようだ。
網谷渉がなぜ網谷勇気と養子縁組をしたのかは分からない。単に、「拘置所から出るには身元引受人が必要だから」みたいなことだったのかもしれないが、私はなんとなく、「網谷勇気の人間としての凄さ」みたいなものをどこかで感じて惹きつけられたのではないかと勝手に想像している。そしてその根源はきっと、彼の両親にあるのだと思う。
あわせて読みたい
【不安】環境活動家グレタを追う映画。「たったひとりのストライキ」から国連スピーチまでの奮闘と激変…
環境活動家であるグレタのことを、私はずっと「怒りの人」「正義の人」だとばかり思っていた。しかしそうではない。彼女は「不安」から、いても立ってもいられずに行動を起こしただけなのだ。映画『グレタ ひとりぼっちの挑戦』から、グレタの実像とその強い想いを知る
父親はタバコを吸いながら、網谷渉にこんな風に言っていた。
母さんも俺も、子どもが大好きだから、子どもがこうしたいと言ったことはやらせてあげたいし、君のことも、「勇気が信じている渉」なら信じられる。

あわせて読みたい
【肯定】社会不適合者こそ非凡。学校・世の中に馴染めなかった異才たちの過去から”才能”の本質を知る:…
「みんなと同じ」に馴染めないと「社会不適合」と判断され、排除されてしまうことが多いでしょう。しかし『非属の才能』では、「どこにも属せない感覚」にこそ才能の源泉があると主張します。常識に違和感を覚えてしまう人を救う本から、同調圧力に屈しない生き方を学ぶ
そのシンプルな力強さに、私は少し圧倒されてしまった。
「マイノリティであること」に関する網谷勇気のとある主張について
そんなわけで、「網谷勇気がゲイであること」には特段焦点は当たらないのだが、「マイノリティであること」については映画全体のテーマとしても浮かび上がらせようとしている感じがした。「ゲイ」である網谷勇気も、「両親がおらず、拘置所から出てきた」網谷渉もマイノリティと言っていいだろうし、彼らの周りにいる人たちも実は「マイノリティと関わる当事者」なのだ。というのも、網谷勇気は「ブリッジフォースマイル」というNPOを立ち上げており、その活動内容が「児童養護施設から巣立つ子どもたちの自立支援」なのである。網谷渉とも、その活動を行う中で知り合ったのだろう。
このように、映画『二十歳の息子』は、「マイノリティであること」が「当たり前」と言える環境で展開される物語なのである。そしてそのような作品において、私が最もグッと来た場面を紹介したいと思う。
あわせて読みたい
【斬新】映画『王国(あるいはその家について)』(草野なつか)を観よ。未経験の鑑賞体験を保証する
映画『王国(あるいはその家について)』は、まず経験できないだろう異様な鑑賞体験をもたらす特異な作品だった。「稽古場での台本読み」を映し出すパートが上映時間150分のほとんどを占め、同じやり取りをひたすら繰り返し見せ続ける本作は、「王国」をキーワードに様々な形の「狂気」を炙り出す異常な作品である
先に書いておくが、このシーンは本作において、決して重要な場面というわけではない。そもそもが網谷渉が絡まないシーンであり、あくまでも「網谷勇気という人物」に関する描写でしかないのだ。ただ、「この感覚はとても良い」と感じたので、紹介したいと思う。
それは、「ブリッジフォースマイル」のメンバーが次回のイベントについての話し合いをしている場面でのことだ。彼らは、恐らく毎年アートイベントを行っているようで、今回のテーマは「グレー」らしい。そしてその「グレー」というテーマの切り口の1つとして「罪」が挙げられ、それをどう掘り下げていくのかが話し合われているという状況だ。
意見の1つとして、「実際の事件を取り上げる」という案が出る。そしてこれに対して、「実際の事件には被害者がいるのだから、それを素材のように取り上げるのはNPOとしていかがなものか」「単純に、『殺人事件を扱う』ことに『重い』って感じてしまった」みたいな、比較的否定的な意見がいくつか出た。その後、この点についてどう思うかと話を振られた網谷勇気が、こんなことを言うのである。
俺は「無関心」こそ「罪」だと思うのね。つまり、ここにいる全員、誰かの死に間接的に関わってるわけよ。そういう自覚がない奴とは、喋りたくないんだよね。そういうことを自覚できもしないのに泣くな、とか思っちゃう。
あわせて読みたい
【映画】今泉力哉監督『ちひろさん』(有村架純)が描く、「濃い寂しさ」が溶け合う素敵な関係性
今泉力哉監督、有村架純主演の映画『ちひろさん』は、その圧倒的な「寂しさの共有」がとても心地よい作品です。色んな「寂しさ」を抱えた様々な人と関わる、「元風俗嬢」であることを公言し海辺の町の弁当屋で働く「ちひろさん」からは、同じような「寂しさ」を抱える人を惹き付ける力強さが感じられるでしょう
このセリフはとても良かった。もちろんその「良さ」は、NPOのメンバーというある種の「仲間」に対しても厳しいことが言える網谷勇気という人物に対する評価でもあるのだが、やはり何よりも、その発言内容そのものにグッときたと言っていい。
言語学的な知識に明るいわけではないのだが、しかし普通に考えて、「言葉」や「概念」というのは「何かと何かを区別する」ために生まれるはずだろう。例えば、目の前に「犬」がいるとして、その隣に見慣れない動物がいる場合、「犬」と区別するために、例えば「猫」のような言葉を必要とする。このようにして、言葉や概念はどんどん生まれていったはずだ。

そして私は、言葉を”使う”際にもこのことを意識する必要があると思っている。つまり、「区別するために言葉を使っている」のだと自覚すべきということだ。そしてより重要なことは、「『何のために区別するか』をきちんと意識できているか」だと私は考えている。
あわせて読みたい
【驚嘆】人類はいかにして言語を獲得したか?この未解明の謎に真正面から挑む異色小説:『Ank: a mirror…
小説家の想像力は無限だ。まさか、「人類はいかに言語を獲得したか?」という仮説を小説で読めるとは。『Ank: a mirroring ape』をベースに、コミュニケーションに拠らない言語獲得の過程と、「ヒト」が「ホモ・サピエンス」しか存在しない理由を知る
例えば「マイノリティ」という言葉は、状況によっては「私には関係がない、理解できない存在」のように「区別する」ために使われるだろう。つまり、「『自分の領域から”切り離す”』ために、ある概念で括るような言葉を使う」ということだ。まさにこのような言動こそが「無関心」の正体だと私は考えている。世の中にはこのようなタイプの人間が多いようにも感じられるし、先ほどの「ポリティカル・コレクトネス」にしても、それを過剰に打ち出そうとする人に対しては同じような印象を抱いてしまう。
私はなるべく、言葉をそんな風に使わないように意識しているつもりだ。「自分の領域から切り離す」ためではなく、「可視化して他の人にも見えやすくする」ために言葉を使いたいと私は思っている。こんな風にブログで文章を書き続けているのには、そんな動機も少しはあったりするというわけだ。そして、似たような感覚を持っていると思える人とじゃないとなかなか話が合わないし、網谷勇気が言うように「喋りたくない」とさえ感じてしまうのである。
なかなかこういう感覚が“通じる”人に出会うのは難しいので、網谷勇気のこの発言は、私にはとても響いた。網谷勇気ほどの強さで同じことを考えているのかについてはなんとも言えないが、少なくとも同じライン上にいるだろうなとは思えたし、そういう人にはやはり興味が持てる。
このような感覚は、まさに「マイノリティ」に分類される人が斬り込んでいかなければなかなか可視化されないものであり、そういう意味でも彼には頑張って欲しいと感じさせられた。
あわせて読みたい
【思考】戸田真琴、経験も文章もとんでもない。「人生どうしたらいい?」と悩む時に読みたい救いの1冊:…
「AV女優のエッセイ」と聞くと、なかなか手が伸びにくいかもしれないが、戸田真琴『あなたの孤独は美しい』の、あらゆる先入観を吹っ飛ばすほどの文章力には圧倒されるだろう。凄まじい経験と、普通ではない思考を経てAV女優に至った彼女の「生きる指針」は、多くの人の支えになるはずだ
あわせて読みたい
【全作品視聴済】私が観てきたドキュメンタリー映画を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が観てきたドキュメンタリー映画を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。
最後に
あわせて読みたい
【未知】コーダに密着した映画『私だけ聴こえる』は、ろう者と聴者の狭間で居場所がない苦悩を映し出す
あなたは「コーダ」と呼ばれる存在を知っているだろうか?「耳の聴こえない親を持つ、耳が聴こえる子ども」のことであり、映画『私だけ聴こえる』は、まさにそんなコーダが置かれた状況を描くドキュメンタリー映画だ。自身は障害者ではないのに大変な苦労を強いられている現状が理解できる作品
映画全体に対する印象を一言でまとめるなら、「不協和音」という言葉がちょうどいいと思う。「なんとなく噛み合わない」みたいな感覚が、そこかしこに漂っていた気がするのだ。それは決して、網谷勇気と網谷渉の関係だけに限らない。先ほど触れた「無関心こそ罪」の話が出てくるシーンもまさに「不協和音」が鳴り響く場面だったし、そういう「なんとも言えない違和感」が散りばめられている作品だと感じた。

あわせて読みたい
【考察】アニメ映画『虐殺器官』は、「便利さが無関心を生む現実」をリアルに描く”無関心ではいられない…
便利すぎる世の中に生きていると、「この便利さはどのように生み出されているのか」を想像しなくなる。そしてその「無関心」は、世界を確実に悪化させてしまう。伊藤計劃の小説を原作とするアニメ映画『虐殺器官』から、「無関心という残虐さ」と「想像することの大事さ」を知る
そしてだからこそ「リアルさ」を感じさせられたとも言えるだろう。現実というのは物語のように綺麗にはまとまらないものだし、そりゃあ違和感が漂って当然だよなと、妙に納得させられもしたのだ。ドキュメンタリーでありながらフィクションっぽい映像であり、しかし作中に漂う「不協和音」が、やはりドキュメンタリーであることを思い起こさせてくれるような、そんなとても「変な」映画だった。
正直、さほど期待せずに観たのだが、思っていた以上に興味深い作品であり、観て良かったと思う。
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!「それってホントに『コミュ力』が高いって言えるの?」と疑問を感じている方に…
私は、「コミュ力が高い人」に関するよくある主張に、どうも違和感を覚えてしまうことが多くあります。そしてその一番大きな理由が、「『コミュ力が高い人』って、ただ『想像力がない』だけではないか?」と感じてしまう点にあると言っていいでしょう。出版したKindle本は、「ネガティブには見えないネガティブな人」(隠れネガティブ)を取り上げながら、「『コミュ力』って何だっけ?」と考え直してもらえる内容に仕上げたつもりです。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【狂気】映画『ミッシング』(吉田恵輔監督)は「我が子の失踪」を起点に様々な「嫌な世界」を描く(主…
映画『ミッシング』は、「娘の失踪を機に壊れてしまった母親」を石原さとみが熱演する絶望的な物語である。事件を取材する地元局の記者の葛藤を通じて「『事実』とは何か」「『事実を報じる』ことの難しさ」が突きつけられ、さらに、マスコミを頼るしかない母親の苦悩と相まって状況が混沌とする。ホントに「嫌な世界」だなと思う
あわせて読みたい
【信念】アフガニスタンに中村哲あり。映画『荒野に希望の灯をともす』が描く規格外の功績、生き方
映画『荒野に希望の灯をともす』は、アフガニスタンの支援に生涯を捧げ、個人で実現するなど不可能だと思われた用水路建設によって砂漠を緑地化してしまった中村哲を追うドキュメンタリー映画だ。2019年に凶弾に倒れるまで最前線で人々を先導し続けてきたその圧倒的な存在感に、「彼なき世界で何をすべきか」と考えさせられる
あわせて読みたい
【日々】映画『なみのおと』は、東日本大震災を語る人々の対話を”あり得ない”アングルから撮る(監督:…
映画『なみのおと』は、「東日本大震災の被災者が当時を振り返って対話をする」という内容そのものももちろん興味深いのだが、カメラをどう配置しているのかが分からない、ドキュメンタリー映画としては”あり得ない”映像であることにも驚かされた。また、悲惨な経験を軽妙に語る者たちの雰囲気も印象的な作品である
あわせて読みたい
【拒絶】映画『ブルータリスト』は、ホロコーストを生き延びた建築家の数奇な人生を描く壮大な物語(監…
映画『ブルータリスト』は、ホロコーストを生き延びたユダヤ人建築家の、アメリカに移り住んで以降の人生を丁寧に追いながら、「ユダヤ人を受け入れないアメリカ」を静かに描き出す物語である。離れ離れにならざるを得なかった妻とのすれ違いにも焦点を当てつつ、時代に翻弄された者たちの悲哀が浮き彫りにされていく
あわせて読みたい
【感動】映画『ぼくとパパ、約束の週末』は「自閉症への理解が深まる」という点で実に興味深かった
映画『ぼくとパパ、約束の週末』は「心温まる物語」であり、一般的にはそういう作品として評価されているはずだが、個人的には「『自閉症』への解像度が高まる」という意味でも興味深かった。「ルールは厳密に守るが、ルール同士が矛盾していて袋小路に陥ってしまう」という困難さが実に分かりやすく描かれている
あわせて読みたい
【奇妙】映画『画家と泥棒』は、非日常的なきっかけで始まったあり得ないほど奇跡的な関係を描く
映画『画家と泥棒』は、「自身の絵を盗まれた画家が、盗んだ泥棒と親しくなる」という奇妙奇天烈なきっかけから関係性が始まる物語であり、現実に起きたこととは思えないほど不可思議なドキュメンタリーである。アートを通じて奇妙に通じ合う2人の関係性は、ある種の美しささえ感じさせる、とても素晴らしいものに見えた
あわせて読みたい
【日常】映画『大きな家』(竹林亮)は、児童養護施設で「家族」と「血縁」の違いや難しさに直面する
児童養護施設に長期密着した映画『大きな家』は、映画『14歳の栞』で中学2年生をフラットに撮り切った竹林亮が監督を務めたドキュメンタリーである。子どもたちの過去に焦点を当てるのではなく、「児童養護施設の日常風景」として彼らを捉えるスタンスで、その上でさらに「家族のあり方」に対する子どもたちの認識が掘り下げられる
あわせて読みたい
【絶望】満員続出の映画『どうすればよかったか?』が描き出す、娘の統合失調症を認めない両親の不条理
たった4館から100館以上にまで上映館が拡大した話題の映画『どうすればよかったか?』を公開2日目に観に行った私は、「ドキュメンタリー映画がどうしてこれほど注目されているのだろうか?」と不思議に感じた。統合失調症を発症した姉を中心に家族を切り取る本作は、観る者に「自分だったらどうするか?」という問いを突きつける
あわせて読みたい
【異様】映画『大いなる不在』(近浦啓)は、認知症の父を中心に「記憶」と「存在」の複雑さを描く(主…
「父親が逮捕され、どうやら認知症のようだ」という一報を受けた息子が、30年間ほぼやり取りのなかった父親と再会するところから始まる映画『大いなる不在』は、なんとも言えない「不穏さ」に満ちた物語だった。「記憶」と「存在」のややこしさを問う本作は、「物語」としては成立していないが、圧倒的な“リアリティ”に満ちている
あわせて読みたい
【繊細】映画『ぼくのお日さま』(奥山大史)は、小さな世界での小さな恋を美しい映像で描く(主演:越…
映画『ぼくのお日さま』は、舞台設定も人間関係も実にミニマムでありながら、とても奥行きのある物語が展開される作品。予告編で「3つの恋」と言及されなければ、描かれるすべての「恋」には気付けなかっただろうと思うくらいの繊細な関係性と、映像・音楽を含めてすべてが美しい旋律として奏でられる物語がとても素敵でした
あわせて読みたい
【実話】映画『ディア・ファミリー』は超良い話だし、大泉洋が演じた人物のモデル・筒井宣政は凄すぎる…
実話を基にした映画『ディア・ファミリー』では、個人が成したとは信じがたい偉業が描き出される。大泉洋が演じたのは、娘の病を治そうと全力で突き進んだ人物であり、そのモデルとなった筒井宣政は、17万人以上を救ったとされるIABPバルーンカテーテルの開発者なのだ。まったくホントに、凄まじい人物がいたものだと思う
あわせて読みたい
【記憶】映画『退屈な日々にさようならを』は「今泉力哉っぽさ」とは異なる魅力に溢れた初期作品だ(主…
今泉力哉作品のオールナイト上映に初めて参加し、『退屈な日々にさようならを』『街の上で』『サッドティー』を観ました。本作『退屈な日々にさようならを』は、時系列が複雑に入れ替わった群像劇で、私が思う「今泉力哉っぽさ」は薄い作品でしたが、構成も展開も会話も絶妙で、さすが今泉力哉という感じです
あわせて読みたい
【?】現代思想「<友情>の現在」を読んで、友達・恋愛・好き・好意などへのモヤモヤを改めて考えた
「現代思想 <友情>の現在」では、「友情」をテーマにした様々な考察が掲載されているのだが、中でも、冒頭に載っていた対談が最も興味深く感じられた。「『友達』というのは、既存の概念からこぼれ落ちた関係性につけられる『残余カテゴリー』である」という中村香住の感覚を起点に、様々な人間関係について思考を巡らせてみる
あわせて読みたい
【感想】映画『夜明けのすべて』は、「ままならなさ」を抱えて生きるすべての人に優しく寄り添う(監督…
映画『夜明けのすべて』は、「PMS」や「パニック障害」を通じて、「自分のものなのに、心・身体が思い通りにならない」という「ままならなさ」を描き出していく。決して他人事ではないし、「私たちもいつそのような状況に置かれるか分からない」という気持ちで観るのがいいでしょう。物語の起伏がないのに惹きつけられる素敵な作品です
あわせて読みたい
【常識】群青いろ制作『彼女はなぜ、猿を逃したか?』は、凄まじく奇妙で、実に魅力的な映画だった(主…
映画『彼女はなぜ、猿を逃したか?』(群青いろ制作)は、「絶妙に奇妙な展開」と「爽快感のあるラスト」の対比が魅力的な作品。主なテーマとして扱われている「週刊誌報道からのネットの炎上」よりも、私は「週刊誌記者が無意識に抱いている思い込み」の方に興味があったし、それを受け流す女子高生の受け答えがとても素敵だった
あわせて読みたい
【狂気】群青いろ制作『雨降って、ジ・エンド。』は、主演の古川琴音が成立させている映画だ
映画『雨降って、ジ・エンド。』は、冒頭からしばらくの間「若い女性とオジサンのちょっと変わった関係」を描く物語なのですが、後半のある時点から「共感を一切排除する」かのごとき展開になる物語です。色んな意味で「普通なら成立し得ない物語」だと思うのですが、古川琴音の演技などのお陰で、絶妙な形で素敵な作品に仕上がっています
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『52ヘルツのクジラたち』の「無音で叫ぶ人」と「耳を澄ます人」の絶妙な響鳴(原作:…
映画『52ヘルツのクジラたち』は、「現代的な問題のごった煮」と感じられてしまうような”過剰さ”に溢れてはいますが、タイトルが作品全体を絶妙に上手くまとめていて良かったなと思います。主演の杉咲花がやはり見事で、身体の内側から「不幸」が滲み出ているような演技には圧倒されてしまいました
あわせて読みたい
【挑戦】映画『燃えあがる女性記者たち』が描く、インドカースト最下位・ダリットの女性による報道
映画『燃えあがる女性記者たち』は、インドで「カースト外の不可触民」として扱われるダリットの女性たちが立ち上げた新聞社「カバル・ラハリヤ」を取り上げる。自身の境遇に抗って、辛い状況にいる人の声を届けたり権力者を糾弾したりする彼女たちの奮闘ぶりが、インドの民主主義を変革させるかもしれない
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『悪は存在しない』(濱口竜介)の衝撃のラストの解釈と、タイトルが示唆する現実(主…
映画『悪は存在しない』(濱口竜介監督)は、観る者すべてを困惑に叩き落とす衝撃のラストに、鑑賞直後は迷子のような状態になってしまうだろう。しかし、作中で提示される様々な要素を紐解き、私なりの解釈に辿り着いた。全編に渡り『悪は存在しない』というタイトルを強く意識させられる、脚本・映像も見事な作品だ
あわせて読みたい
【狂気】異質なホラー映画『みなに幸あれ』(古川琴音主演)は古い因習に似せた「社会の異様さ」を描く
古川琴音主演映画『みなに幸あれ』は、”シュールさ”さえ感じさせる「異質なホラー映画」だ。「村の因習」というよくあるパターンをベースに据えつつ、そこで展開される異様な状況が、実は「私たちが生きる世界」に対応しているという構成になっている。「お前の物語だからな」と終始突きつけられ続ける作品だ
あわせて読みたい
【斬新】映画『王国(あるいはその家について)』(草野なつか)を観よ。未経験の鑑賞体験を保証する
映画『王国(あるいはその家について)』は、まず経験できないだろう異様な鑑賞体験をもたらす特異な作品だった。「稽古場での台本読み」を映し出すパートが上映時間150分のほとんどを占め、同じやり取りをひたすら繰り返し見せ続ける本作は、「王国」をキーワードに様々な形の「狂気」を炙り出す異常な作品である
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『アンダーカレント』(今泉力哉)は、失踪をテーマに「分かり合えなさ」を描く
映画『アンダーカレント』において私は、恐らく多くの人が「受け入れがたい」と感じるだろう人物に共感させられてしまった。また本作は、「他者を理解すること」についての葛藤が深掘りされる作品でもある。そのため、私が普段から抱いている「『他者のホントウ』を知りたい」という感覚も強く刺激された
あわせて読みたい
【実話】映画『月』(石井裕也)は、障害者施設での虐待事件から「見て見ぬふりする社会」を抉る(出演…
実際に起こった障害者施設殺傷事件を基にした映画『月』(石井裕也)は、観客を作中世界に引きずり込み、「これはお前たちの物語だぞ」と刃を突きつける圧巻の作品だ。「意思疎通が不可能なら殺していい」という主張には誰もが反対するはずだが、しかしその態度は、ブーメランのように私たちに戻ってくることになる
あわせて読みたい
【感想】映画『正欲』に超共感。多様性の時代でさえどこに行っても馴染めない者たちの業苦を抉る(出演…
映画『正欲』は、私には共感しかない作品だ。特に、新垣結衣演じる桐生夏月と磯村勇斗演じる佐々木佳道が抱える葛藤や息苦しさは私の内側にあるものと同じで、その描かれ方に圧倒されてしまった。「『多様性』には『理解』も『受け入れ』も不要で、単に否定しなければ十分」なのだと改めて思う
あわせて読みたい
【絶望】人生どん底から生き方を変える。映画『シスター 夏のわかれ道』が描く中国人女性の葛藤と諦念
両親の死をきっかけに、「見知らぬ弟」を引き取らなければならなくなった女性を描く映画『シスター 夏のわかれ道』は、中国の特異な状況を背景にしつつ、誰もが抱き得る普遍的な葛藤が切り取られていく。現状を打破するために北京の大学院を目指す主人公は、一体どんな決断を下すのか。
あわせて読みたい
【未知】コーダに密着した映画『私だけ聴こえる』は、ろう者と聴者の狭間で居場所がない苦悩を映し出す
あなたは「コーダ」と呼ばれる存在を知っているだろうか?「耳の聴こえない親を持つ、耳が聴こえる子ども」のことであり、映画『私だけ聴こえる』は、まさにそんなコーダが置かれた状況を描くドキュメンタリー映画だ。自身は障害者ではないのに大変な苦労を強いられている現状が理解できる作品
あわせて読みたい
【助けて】映画『生きててごめんなさい』は、「共依存カップル」視点で生きづらい世の中を抉る物語(主…
映画『生きててごめんなさい』は、「ちょっと歪な共依存関係」を描きながら、ある種現代的な「生きづらさ」を抉り出す作品。出版社の編集部で働きながら小説の新人賞を目指す園田修一は何故、バイトを9度もクビになり、一日中ベッドの上で何もせずに過ごす同棲相手・清川莉奈を”必要とする”のか?
あわせて読みたい
【映画】『別れる決心』(パク・チャヌク)は、「倫理的な葛藤」が描かれない、不穏で魅惑的な物語
巨匠パク・チャヌク監督が狂気的な関係性を描き出す映画『別れる決心』には、「倫理的な葛藤が描かれない」という特異さがあると感じた。「様々な要素が描かれるものの、それらが『主人公2人の関係性』に影響しないこと」や、「『理解は出来ないが、成立はしている』という不思議な感覚」について触れる
あわせて読みたい
【理解】「多様性を受け入れる」とか言ってるヤツ、映画『炎上する君』でも観て「何も見てない」って知…
西加奈子の同名小説を原作とした映画『炎上する君』(ふくだももこ監督)は、「多様性」という言葉を安易に使いがちな世の中を挑発するような作品だ。「見えない存在」を「過剰に装飾」しなければならない現実と、マジョリティが無意識的にマイノリティを「削る」リアルを描き出していく
あわせて読みたい
【違和感】三浦透子主演映画『そばかす』はアセクシャルの生きづらさを描く。セクシャリティ理解の入り口に
「他者に対して恋愛感情・性的欲求を抱かないセクシャリティ」である「アセクシャル」をテーマにした映画『そばかす』は、「マイノリティのリアル」をかなり解像度高く映し出す作品だと思う。また、主人公・蘇畑佳純に共感できてしまう私には、「普通の人の怖さ」が描かれている映画にも感じられた
あわせて読みたい
【衝撃】これが実話とは。映画『ウーマン・トーキング』が描く、性被害を受けた女性たちの凄まじい決断
映画『ウーマン・トーキング』の驚くべき点は、実話を基にしているという点だ。しかもその事件が起こったのは2000年代に入ってから。とある宗教コミュニティ内で起こった連続レイプ事件を機に村の女性たちがある決断を下す物語であり、そこに至るまでの「ある種異様な話し合い」が丁寧に描かれていく
あわせて読みたい
【実話】福島智とその家族を描く映画『桜色の風が咲く』から、指点字誕生秘話と全盲ろうの絶望を知る
「目が見えず、耳も聞こえないのに大学に進学し、後に東京大学の教授になった」という、世界レベルの偉業を成し遂げた福島智。そんな彼の試練に満ちた生い立ちを描く映画『桜色の風が咲く』は、本人の葛藤や努力もさることながら、母親の凄まじい献身の物語でもある
あわせて読みたい
【実話】映画『グリーンブック』は我々に問う。当たり前の行動に「差別意識」が含まれていないか、と
黒人差別が遥かに苛烈だった時代のアメリカにおいて、黒人ピアニストと彼に雇われた白人ドライバーを描く映画『グリーンブック』は、観客に「あなたも同じような振る舞いをしていないか?」と突きつける作品だ。「差別」に限らず、「同時代の『当たり前』に従った行動」について考え直させる1作
あわせて読みたい
【性加害】映画『SHE SAID その名を暴け』を観てくれ。#MeToo運動を生んだ報道の舞台裏(出演:キャリ…
「#MeToo」運動のきっかけとなった、ハリウッドの絶対権力者ハーヴェイ・ワインスタインを告発するニューヨーク・タイムズの記事。その取材を担った2人の女性記者の奮闘を描く映画『SHE SAID その名を暴け』は、ジャニー喜多川の性加害問題で揺れる今、絶対に観るべき映画だと思う
あわせて読みたい
【居場所】菊地凛子主演映画『658km、陽子の旅』(熊切和嘉)は、引きこもりロードムービーの傑作
映画『658km、陽子の旅』は、主演の菊地凛子の存在感が圧倒的だった。夢破れて長年引きこもり続けている女性が、否応なしにヒッチハイクで弘前を目指さなければならなくなるロードムービーであり、他人や社会と関わることへの葛藤に塗れた主人公の変化が、とても「勇敢」なものに映る
あわせて読みたい
【純真】ゲイが犯罪だった時代が舞台の映画『大いなる自由』は、刑務所内での極深な人間ドラマを描く
男性同士の恋愛が犯罪であり、ゲイの男性が刑法175条を理由に逮捕されてしまう時代のドイツを描いた映画『大いなる自由』は、確かに同性愛の物語なのだが、実はそこに本質はない。物語の本質は、まさにタイトルにある通り「自由」であり、ラストシーンで突きつけられるその深い問いかけには衝撃を受けるだろう
あわせて読みたい
【傑物】フランスに最も愛された政治家シモーヌ・ヴェイユの、強制収容所から国連までの凄絶な歩み:映…
「フランスに最も愛された政治家」と評されるシモーヌ・ヴェイユ。映画『シモーヌ』は、そんな彼女が強制収容所を生き延び、後に旧弊な社会を変革したその凄まじい功績を描き出す作品だ。「強制収容所からの生還が失敗に思える」とさえ感じたという戦後のフランスの中で、彼女はいかに革新的な歩みを続けたのか
あわせて読みたい
【映画】今泉力哉監督『ちひろさん』(有村架純)が描く、「濃い寂しさ」が溶け合う素敵な関係性
今泉力哉監督、有村架純主演の映画『ちひろさん』は、その圧倒的な「寂しさの共有」がとても心地よい作品です。色んな「寂しさ」を抱えた様々な人と関わる、「元風俗嬢」であることを公言し海辺の町の弁当屋で働く「ちひろさん」からは、同じような「寂しさ」を抱える人を惹き付ける力強さが感じられるでしょう
あわせて読みたい
【共感】「恋愛したくない」という社会をリアルに描く売野機子の漫画『ルポルタージュ』が示す未来像
売野機子のマンガ『ルポルタージュ』は、「恋愛を飛ばして結婚すること」が当たり前の世界が描かれる。私はこの感覚に凄く共感できてしまった。「恋愛」「結婚」に対して、「世間の『当たり前』に馴染めない感覚」を持つ私が考える、「恋愛」「結婚」が有する可能性
あわせて読みたい
【実話】ポートアーサー銃乱射事件を扱う映画『ニトラム』が示す、犯罪への傾倒に抗えない人生の不条理
オーストラリアで実際に起こった銃乱射事件の犯人の生い立ちを描く映画『ニトラム/NITRAM』は、「頼むから何も起こらないでくれ」と願ってしまうほどの異様な不穏さに満ちている。「社会に順応できない人間」を社会がどう受け入れるべきかについて改めて考えさせる作品だ
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『夕方のおともだち』は、「私はこう」という宣言からしか始まらない関係性の”純度”を描く
「こんな田舎にはもったいないほどのドM」と評された男が主人公の映画『夕方のおともだち』は、SM嬢と真性ドMの関わりを通じて、「宣言から始まる関係」の難しさを描き出す。「普通の世界」に息苦しさを感じ、どうしても馴染めないと思っている人に刺さるだろう作品
あわせて読みたい
【誠実】戸田真琴は「言葉の人」だ。コンプレックスだらけの人生を「思考」と「行動」で突き進んだ記録…
戸田真琴のエッセイ第2弾『人を心から愛したことがないのだと気づいてしまっても』は、デビュー作以上に「誰かのために言葉を紡ぐ」という決意が溢れた1冊だ。AV女優という自身のあり方を客観的に踏まえた上で、「届くべき言葉がきちんと届く」ために、彼女は身を削ってでも生きる
あわせて読みたい
【感想】映画『朝が来る』が描く、「我が子を返して欲しい気持ち」を消せない特別養子縁組のリアル
「特別養子縁組」を軸に人々の葛藤を描く映画『朝が来る』は、決して「特別養子縁組」の話ではない。「『起こるだろうが、起こるはずがない』と思っていた状況」に直面せざるを得ない人々が、「すべての選択肢が不正解」という中でどんな決断を下すのかが問われる、非常に示唆に富む作品だ
あわせて読みたい
【思考】戸田真琴、経験も文章もとんでもない。「人生どうしたらいい?」と悩む時に読みたい救いの1冊:…
「AV女優のエッセイ」と聞くと、なかなか手が伸びにくいかもしれないが、戸田真琴『あなたの孤独は美しい』の、あらゆる先入観を吹っ飛ばすほどの文章力には圧倒されるだろう。凄まじい経験と、普通ではない思考を経てAV女優に至った彼女の「生きる指針」は、多くの人の支えになるはずだ
あわせて読みたい
【純愛】映画『ぼくのエリ』の衝撃。「生き延びるために必要なもの」を貪欲に求める狂気と悲哀、そして恋
名作と名高い映画『ぼくのエリ』は、「生き延びるために必要なもの」が「他者を滅ぼしてしまうこと」であるという絶望を抱えながら、それでも生きることを選ぶ者たちの葛藤が描かれる。「純愛」と呼んでいいのか悩んでしまう2人の関係性と、予想もつかない展開に、感動させられる
あわせて読みたい
【奇跡】信念を貫いた男が国の制度を変えた。特別養子縁組を実現させた石巻の産婦人科医の執念:『赤ち…
遊郭で生まれ育った石巻の医師が声を上げ、あらゆる障害をなぎ倒して前進したお陰で「特別養子縁組」の制度が実現した。そんな産婦人科医・菊田昇の生涯を描き出す小説『赤ちゃんをわが子として育てる方を求む』には、法を犯してでも信念を貫いた男の衝撃の人生が描かれている
あわせて読みたい
【差別】映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』の衝撃。プーチンが支持する国の蛮行・LGBT狩り
プーチン大統領の後ろ盾を得て独裁を維持しているチェチェン共和国。その国で「ゲイ狩り」と呼ぶしかない異常事態が継続している。映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』は、そんな現実を命がけで映し出し、「現代版ホロコースト」に立ち向かう支援団体の奮闘も描く作品
あわせて読みたい
【あらすじ】死刑囚を救い出す実話を基にした映画『黒い司法』が指摘する、死刑制度の問題と黒人差別の現実
アメリカで死刑囚の支援を行う団体を立ち上げた若者の実話を基にした映画『黒い司法 0%からの奇跡』は、「死刑制度」の存在価値について考えさせる。上映後のトークイベントで、アメリカにおける「死刑制度」と「黒人差別」の結びつきを知り、一層驚かされた
あわせて読みたい
【悲劇】アメリカの暗黒の歴史である奴隷制度の現実を、元奴隷の黒人女性自ら赤裸々に語る衝撃:『ある…
生まれながらに「奴隷」だった黒人女性が、多くの人の協力を得て自由を手にし、後に「奴隷制度」について書いたのが『ある奴隷少女に起こった出来事』。長らく「白人が書いた小説」と思われていたが、事実だと証明され、欧米で大ベストセラーとなった古典作品が示す「奴隷制度の残酷さ」
あわせて読みたい
【実話】台湾のろう学校のいじめ・性的虐待事件を描く映画『無聲』が問う、あまりに悲しい現実
台湾のろう学校で実際に起こったいじめ・性的虐待事件を基に作られた映画『無聲』は、健常者の世界に刃を突きつける物語だ。これが実話だという事実に驚かされる。いじめ・性的虐待が物語の「大前提」でしかないという衝撃と、「性的虐待の方がマシ」という選択を躊躇せず行う少女のあまりの絶望を描き出す
あわせて読みたい
【LGBT】映画『リトル・ガール』で映し出される、性別違和を抱える8歳の”女の子”のリアルと苦悩
映画撮影時8歳だった、身体は男の子、心は女の子のサシャは、スカートを履いての登校が許されず、好きなバッグもペンケースも使わせてもらえない。映画『リトル・ガール』が描く、「性別違和」に対する社会の不寛容と、自分を責め続けてしまう母親の苦悩
あわせて読みたい
【衝撃】卯月妙子『人間仮免中』、とんでもないコミックエッセイだわ。統合失調症との壮絶な闘いの日々
小学5年生から統合失調症を患い、社会の中でもがき苦しみながら生きる卯月妙子のコミックエッセイ『人間仮免中』はとんでもない衝撃作。周りにいる人とのぶっ飛んだ人間関係や、歩道橋から飛び降り自殺未遂を図り顔面がぐちゃぐちゃになって以降の壮絶な日々も赤裸々に描く
あわせて読みたい
【不安】環境活動家グレタを追う映画。「たったひとりのストライキ」から国連スピーチまでの奮闘と激変…
環境活動家であるグレタのことを、私はずっと「怒りの人」「正義の人」だとばかり思っていた。しかしそうではない。彼女は「不安」から、いても立ってもいられずに行動を起こしただけなのだ。映画『グレタ ひとりぼっちの挑戦』から、グレタの実像とその強い想いを知る
あわせて読みたい
【選択】映画『サウンド・オブ・メタル』で難聴に陥るバンドマンは、「障害」と「健常」の境界で揺れる
ドラムを叩くバンドマンが聴力を失ってしまう――そんな厳しい現実に直面する主人公を描く映画『サウンド・オブ・メタル』では、「『健常者との生活』を選ぶか否か」という選択が突きつけられる。ある意味では健常者にも向けられているこの問いに、どう答えるべきだろうか
あわせて読みたい
【信念】水俣病の真実を世界に伝えた写真家ユージン・スミスを描く映画。真実とは「痛みへの共感」だ:…
私はその存在をまったく知らなかったが、「水俣病」を「世界中が知る公害」にした報道写真家がいる。映画『MINAMATA―ミナマタ―』は、水俣病の真実を世界に伝えたユージン・スミスの知られざる生涯と、理不尽に立ち向かう多くの人々の奮闘を描き出す
あわせて読みたい
【葛藤】正論を振りかざしても、「正しさとは何か」に辿り着けない。「絶対的な正しさ」など存在しない…
「『正しさ』は人によって違う」というのは、私には「当たり前の考え」に感じられるが、この前提さえ共有できない社会に私たちは生きている。映画『由宇子の天秤』は、「誤りが含まれるならすべて間違い」という判断が当たり前になされる社会の「不寛容さ」を切り取っていく
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『流浪の月』を観て感じた、「『見て分かること』にしか反応できない世界」への気持ち悪さ
私は「見て分かること」に”しか”反応できない世界に日々苛立ちを覚えている。そういう社会だからこそ、映画『流浪の月』で描かれる文と更紗の関係も「気持ち悪い」と断罪されるのだ。私はむしろ、どうしようもなく文と更紗の関係を「羨ましい」と感じてしまう。
あわせて読みたい
【正義】復讐なんかに意味はない。それでも「この復讐は正しいかもしれない」と思わされる映画:『プロ…
私は基本的に「復讐」を許容できないが、『プロミシング・ヤング・ウーマン』の主人公キャシーの行動は正当化したい。法を犯す明らかにイカれた言動なのだが、その動機は一考の余地がある。何も考えずキャシーを非難していると、矢が自分の方に飛んでくる、恐ろしい作品
あわせて読みたい
【弾圧】香港デモの象徴的存在デニス・ホーの奮闘の歴史。注目の女性活動家は周庭だけじゃない:映画『…
日本で香港民主化運動が報じられる際は周庭さんが取り上げられることが多いが、香港には彼女よりも前に民主化運動の象徴的存在として認められた人物がいる。映画『デニス・ホー ビカミング・ザ・ソング』の主人公であるスター歌手の激動の人生を知る
あわせて読みたい
【生きる】しんどい人生を宿命付けられた子どもはどう生きるべき?格差社会・いじめ・恋愛を詰め込んだ…
厳しい受験戦争、壮絶な格差社会、残忍ないじめ……中国の社会問題をこれでもかと詰め込み、重苦しさもありながら「ボーイ・ミーツ・ガール」の爽やかさも融合されている映画『少年の君』。辛い境遇の中で、「すべてが最悪な選択肢」と向き合う少年少女の姿に心打たれる
あわせて読みたい
【認識】「固定観念」「思い込み」の外側に出るのは難しい。自分はどんな「へや」に囚われているのか:…
実際に起こった衝撃的な事件に着想を得て作られた映画『ルーム』は、フィクションだが、観客に「あなたも同じ状況にいるのではないか?」と突きつける力強さを持っている。「普通」「当たり前」という感覚に囚われて苦しむすべての人に、「何に気づけばいいか」を気づかせてくれる作品
あわせて読みたい
【死】映画『湯を沸かすほどの熱い愛』に号泣。「家族とは?」を問う物語と、タイトル通りのラストが見事
「死は特別なもの」と捉えてしまうが故に「日常感」が失われ、普段の生活から「排除」されているように感じてしまうのは私だけではないはずだ。『湯を沸かすほどの熱い愛』は、「死を日常に組み込む」ことを当たり前に許容する「家族」が、「家族」の枠組みを問い直す映画である
あわせて読みたい
【家族】映画『そして父になる』が問う「子どもの親である」、そして「親の子どもである」の意味とは?
「血の繋がり」だけが家族なのか?「将来の幸せ」を与えることが子育てなのか?実際に起こった「赤ちゃんの取り違え事件」に着想を得て、苦悩する家族を是枝裕和が描く映画『そして父になる』から、「家族とは何か?」「子育てや幸せとどう向き合うべきか?」を考える
あわせて読みたい
【矛盾】その”誹謗中傷”は真っ当か?映画『万引き家族』から、日本社会の「善悪の判断基準」を考える
どんな理由があれ、法を犯した者は罰せられるべきだと思っている。しかしそれは、善悪の判断とは関係ない。映画『万引き家族』(是枝裕和監督)から、「国民の気分」によって「善悪」が決まる社会の是非と、「善悪の判断を保留する勇気」を持つ生き方について考える
あわせて読みたい
【実話】障害者との接し方を考えさせる映画『こんな夜更けにバナナかよ』から”対等な関係”の大事さを知る
「障害者だから◯◯だ」という決まりきった捉え方をどうしてもしてしまいがちですが、『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』の主人公・鹿野靖明の生き様を知れば、少しは考え方が変わるかもしれません。筋ジストロフィーのまま病院・家族から離れて“自活”する決断をした驚異の人生
あわせて読みたい
【葛藤】子どもが抱く「家族を捨てたい気持ち」は、母親の「家族を守りたい気持ち」の終着点かもしれな…
家族のややこしさは、家族の数だけ存在する。そのややこしさを、「子どもを守るために母親が父親を殺す」という極限状況を設定することで包括的に描き出そうとする映画『ひとよ』。「暴力」と「殺人犯の子どもというレッテル」のどちらの方が耐え難いと感じるだろうか?
あわせて読みたい
【多様性】神童から引きこもりになり、なんとか脱出したお笑い芸人が望む、誰も責められない社会:『ヒ…
お笑い芸人・髭男爵の山田ルイ53世は、“神童”と呼ばれるほど優秀だったが、“うんこ”をきっかけに6年間引きこもった。『ヒキコモリ漂流記』で彼は、ひきこもりに至ったきっかけ、ひきこもり中の心情、そしてそこからいかに脱出したのかを赤裸々に綴り、「誰にも優しい世界」を望む
あわせて読みたい
【絶望】光過敏症の女性の、真っ暗な部屋で光という光をすべて遮断しなければ生きられない壮絶な日常:…
日光に限らず、ありとあらゆる「光」に肌が異常に反応してしまうため、ずっと真っ暗闇の中でしか生きられない女性が、その壮絶すぎる日常を綴った『まっくらやみで見えたもの 光アレルギーのわたしの奇妙な人生』から、それでも生きていく強さを感じ取る
あわせて読みたい
【絶望】「人生上手くいかない」と感じる時、彼を思い出してほしい。壮絶な過去を背負って生きる彼を:…
「北九州連続監禁殺人事件」という、マスコミも報道規制するほどの残虐事件。その「主犯の息子」として生きざるを得なかった男の壮絶な人生。「ザ・ノンフィクション」のプロデューサーが『人殺しの息子と呼ばれて』で改めて取り上げた「真摯な男」の生き様と覚悟
あわせて読みたい
【助けて】息苦しい世の中に生きていて、人知れず「傷」を抱えていることを誰か知ってほしいのです:『…
元気で明るくて楽しそうな人ほど「傷」を抱えている。そんな人をたくさん見てきた。様々な理由から「傷」を表に出せない人がいる世の中で、『包帯クラブ』が提示する「見えない傷に包帯を巻く」という具体的な行動は、気休め以上の効果をもたらすかもしれない
あわせて読みたい
【理解】東田直樹の本は「自閉症の見方」を一変させた。自身も自閉症児を育てるプロデューサーが映画化…
東田直樹の著作を英訳し世界に広めた人物(自閉症児を育てている)も登場する映画『僕が跳びはねる理由』には、「東田直樹が語る自閉症の世界」を知ることで接し方や考え方が変わったという家族が登場する。「自閉症は知恵遅れではない」と示した東田直樹の多大な功績を実感できる
あわせて読みたい
【逸脱】「仕事を辞めたい」という気持ちは抑えちゃダメ。アウェイな土俵で闘っても負けるだけだ:『ニ…
京都大学卒「日本一有名なニート」であるpha氏の『ニートの歩き方 お金がなくても楽しくクラスためのインターネット活用法』は、常識や当たり前に囚われず、「無理なものは無理」という自分の肌感覚に沿って生きていくことの重要性と、そのための考え方が満載の1冊
あわせて読みたい
【あらすじ】人生行き詰まってなお「生きたい」と思えるか?環境の激変を受け入れる難しさと生きる悲し…
勤務していた会社の都合で、町が1つ丸々無くなるという経験をし、住居を持たないノマド生活へと舵を切った女性を描く映画『ノマドランド』を通じて、人生の大きな変化に立ち向かう気力を持てるのか、我々はどう生きていくべきか、などについて考える
あわせて読みたい
【現実】生きる気力が持てない世の中で”働く”だけが人生か?「踊るホームレスたち」の物語:映画『ダン…
「ホームレスは怠けている」という見方は誤りだと思うし、「働かないことが悪」だとも私には思えない。振付師・アオキ裕キ主催のホームレスのダンスチームを追う映画『ダンシングホームレス』から、社会のレールを外れても許容される社会の在り方を希求する
あわせて読みたい
【実話】「家族とうまくいかない現実」に正解はあるか?選択肢が無いと感じる時、何を”選ぶ”べきか?:…
「自分の子どもなんだから、どんな風に育てたって勝手でしょ」という親の意見が正しいはずはないが、この言葉に反論することは難しい。虐待しようが生活能力が無かろうが、親は親だからだ。映画『MOTHER マザー』から、不正解しかない人生を考える
あわせて読みたい
【正義】マイノリティはどう生き、どう扱われるべきかを描く映画。「ルールを守る」だけが正解か?:映…
社会的弱者が闘争の末に権利を勝ち取ってきた歴史を知った上で私は、闘わずとも権利が認められるべきだと思っている。そして、そういう社会でない以上、「正義のためにルールを破るしかない」状況もある。映画『パブリック』から、ルールと正義のバランスを考える
あわせて読みたい
【情熱】「ルール」は守るため”だけ”に存在するのか?正義を実現するための「ルール」のあり方は?:映…
「ルールは守らなければならない」というのは大前提だが、常に例外は存在する。どれほど重度の自閉症患者でも断らない無許可の施設で、情熱を持って問題に対処する主人公を描く映画『スペシャルズ!』から、「ルールのあるべき姿」を考える
あわせて読みたい
【誤り】「信じたいものを信じる」のは正しい?映画『星の子』から「信じること」の難しさを考える
どんな病気も治す「奇跡の水」の存在を私は信じないが、しかし何故「信じない」と言えるのか?「奇跡の水を信じる人」を軽々に非難すべきではないと私は考えているが、それは何故か?映画『星の子』から、「何かを信じること」の難しさについて知る
あわせて読みたい
【葛藤】「多様性を受け入れること」は難しい。映画『アイヌモシリ』で知る、アイデンティティの実際
「アイヌの町」として知られるアイヌコタンの住人は、「アイヌ語を勉強している」という。観光客のイメージに合わせるためだ。映画『アイヌモシリ』から、「伝統」や「文化」の継承者として生きるべきか、自らのアイデンティティを意識せず生きるべきかの葛藤を知る
あわせて読みたい
【再生】ヤクザの現実を切り取る映画『ヤクザと家族』から、我々が生きる社会の”今”を知る
「ヤクザ」を排除するだけでは「アンダーグラウンドの世界」は無くならないし、恐らく状況はより悪化しただけのはずだ。映画『ヤクザと家族』から、「悪は徹底的に叩きのめす」「悪じゃなければ何をしてもいい」という社会の風潮について考える。
あわせて読みたい
【救い】耐えられない辛さの中でどう生きるか。短歌で弱者の味方を志すホームレス少女の生き様:『セー…
死にゆく母を眺め、施設で暴力を振るわれ、拾った新聞で文字を覚えたという壮絶な過去を持つ鳥居。『セーラー服の歌人 鳥居』は、そんな辛い境遇を背景に、辛さに震えているだろう誰かを救うために短歌を生み出し続ける生き方を描き出す。凄い人がいるものだ
あわせて読みたい
【異端】子育てがうまくいかないと悩む方へ。9歳で大学入学の天才児に学ぶ「すべきでないこと」:『ぼく…
12歳で数学の未解決問題を解いた天才児は、3歳の時に「16歳で靴紐が結べるようになったらラッキー」と宣告されていた。専門家の意見に逆らって、重度の自閉症児の才能をどう開花させたのかを、『ぼくは数式で宇宙の美しさを伝えたい』から学ぶ
あわせて読みたい
【感想】世の中と足並みがそろわないのは「正常が異常」だから?自分の「正常」を守るために:『コンビ…
30代になっても未婚でコンビニアルバイトの古倉さんは、普通から外れたおかしな人、と見られてしまいます。しかし、本当でしょうか?『コンビニ人間』をベースに、多数派の人たちの方が人生を自ら選択していないのではないかと指摘する。
あわせて読みたい
【諦め】母親の存在にモヤモヤを抱えた人生から、「生きてさえいればいい」への違和感を考える:『晴天…
生まれ育つ環境を選ぶことはできません。そして、家族との関わりや家庭環境は、その後の人生に大きな影響を及ぼします。努力するスタートラインにも立てないと感じる時、それでも前進することを諦めてはいけないのかを、『晴天の迷いクジラ』をベースに書く
あわせて読みたい
【感想】人間関係って難しい。友達・恋人・家族になるよりも「あなた」のまま関わることに価値がある:…
誰かとの関係性には大抵、「友達」「恋人」「家族」のような名前がついてしまうし、そうなればその名前に縛られてしまいます。「名前がつかない関係性の奇跡」と「誰かを想う強い気持ちの表し方」について、『君の膵臓をたべたい』をベースに書いていきます
あわせて読みたい
【肯定】価値観の違いは受け入れられなくていい。「普通」に馴染めないからこそ見える世界:『君はレフ…
子どもの頃、周りと馴染めない感覚がとても強くて苦労しました。ただし、「普通」から意識的に外れる決断をしたことで、自分が持っている価値観を言葉で下支えすることができたとも感じています。「普通」に馴染めず、自分がダメだと感じてしまう人へ。
あわせて読みたい
【前進】誰とも価値観が合わない…。「普通」「当たり前」の中で生きることの難しさと踏み出し方:『出会…
生きていると、「常識的な考え方」に囚われたり、「普通」「当たり前」を無自覚で強要してくる人に出会ったりします。そういう価値観に合わせられない時、自分が間違っている、劣っていると感じがちですが、そういう中で一歩踏み出す勇気を得るための考え方です
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
ジェンダー・LGBT【本・映画の感想】 | ルシルナ
私はLGBTではありません。また、ジェンダーギャップは女性が辛さを感じることの方が多いでしょうが、私は男性です。なので、私自身がジェンダーやLGBTの問題を実感すること…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…



































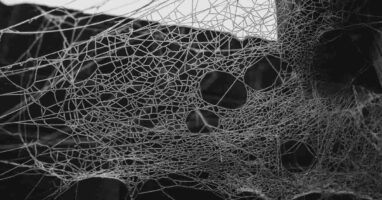












































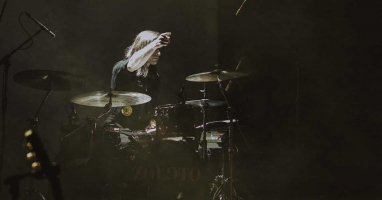



























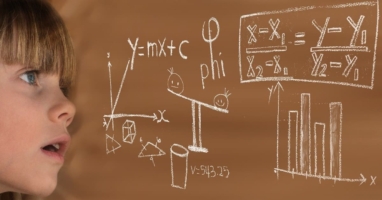














コメント