目次
はじめに
この記事で取り上げる映画
監督:ペドロ・アルモドバル, Writer:ペドロ・アルモドバル, 出演:ティルダ・スウィントン, 出演:ジュリアン・ムーア, 出演:ジョン・タトゥーロ, 出演:アレッサンドロ・ニボラ
 ポチップ
ポチップ
この映画をガイドにしながら記事を書いていきます
この記事の3つの要点
- 癌を患い、安楽死を決意した親友から、「死の間際まで近くにいてほしい」と頼まれた場合、あなたならどうするだろうか?
- 「病気に負けないで、尊厳ある死を迎えるためには『安楽死』しかない」という「死生観」を導く理屈はとても理路整然としており、私は強く共感させられた
- 「生きていることへの喜びがない」「ただ身体が生存しているだけ」という状態でも、果たして「生きること」を選び続けなければならないのだろうか?
普段考える機会のない思考を通じて、「どう生きるべきか」について考えを深められる作品だと思う
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
記事中の引用は、映画館で取ったメモを参考にしているので、正確なものではありません
「私が死ぬ時は隣の部屋にいてほしい」と、安楽死を望む親友から頼まれる映画『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』は、様々な問いを突きつける作品だ
実に興味深い作品だった。さらに、正直なところ全然観るつもりはなかったので、思いがけず良い映画に出会えたという感覚も強い。
あわせて読みたい
【実話】映画『ディア・ファミリー』は超良い話だし、大泉洋が演じた人物のモデル・筒井宣政は凄すぎる…
実話を基にした映画『ディア・ファミリー』では、個人が成したとは信じがたい偉業が描き出される。大泉洋が演じたのは、娘の病を治そうと全力で突き進んだ人物であり、そのモデルとなった筒井宣政は、17万人以上を救ったとされるIABPバルーンカテーテルの開発者なのだ。まったくホントに、凄まじい人物がいたものだと思う
本作の予告編は劇場で何度も目にしたが、まったく観ようという気にはなれなかった。そもそも「どんな話なのか」も予告編からはよく分からなかったが(「安楽死」というキーワードが出てきていたかも覚えていない)、もし仮に話の筋が理解できたとしても観ようとは思わなかった気がする。主演の2人、ティルダ・スウィントンとジュリアン・ムーアが(たぶん)有名な女優なので、「この2人が出演している」ということが伝わりさえすれば十分という判断だったのかもしれないが、少なくとも私にとっては、予告編としてまったく機能しなかった。ちょうど「観ようと思っている映画のストック」が切れ、それで、「じゃあこれでも観てみるか」みたいな消極的な感じで観ることにしただけである。

本作で描かれるのは、「ステージ3の子宮頸がんと診断された女性が、いかに『死』を迎えるかを考え実行に移す」という物語だ。ストーリー展開はほぼそれしか存在しないし、登場人物もほぼ2人だけ。これ以上ないというぐらいのシンプルな作品で、だからこそ魅力を伝えるのはなかなか難しい。本編を観て、「確かにこれは、予告編を作るのが難しい作品かもしれないな」と感じた。
さて、本作においてとにかくメチャクチャ良かったのが、がんと診断されたマーサを演じたティルダ・スウィントンである。凄まじく良くてびっくりした。正直私は、彼女のことをこれまでちゃんと認識したことがなかったのだけど、これからはちょっと注目してしまうと思う。本作はまさに彼女の存在感で成り立っていると言っていいように思うし、彼女が演じたマーサという役柄も実に興味深い存在だった。
あわせて読みたい
【正義】復讐なんかに意味はない。それでも「この復讐は正しいかもしれない」と思わされる映画:『プロ…
私は基本的に「復讐」を許容できないが、『プロミシング・ヤング・ウーマン』の主人公キャシーの行動は正当化したい。法を犯す明らかにイカれた言動なのだが、その動機は一考の余地がある。何も考えずキャシーを非難していると、矢が自分の方に飛んでくる、恐ろしい作品
それでは、まずは内容を紹介するところから始めることにしよう。
映画『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』の内容紹介
物語は、作家のイングリッドが書店でサイン会をしている場面から始まる。彼女は昔から「死」を恐れる気持ちを強く持っていたそうで、そんな自身の感覚をテーマにした小説を上梓したばかりなのだ。するとそのサインの列に、旧友のステラが並んでいることに気づいた。別件で近くまで来る用事があり、立ち寄ってみることにしたという。
そしてイングリッドはステラから、マーサが癌センターに入院していると聞かされた。イングリッドは旧友の現状に驚く。彼女は、マーサが入院していることも、癌を患っていることも知らなかった。長い間連絡を取らずにいたからだ。
あわせて読みたい
【余命】癌は治らないと”諦める”べき?治療しない方が長生きする現実を現役医師が小説で描く:『悪医』…
ガンを患い、余命宣告され、もう治療の手がないと言われれば絶望を抱くだろう。しかし医師は、治療しない方が長生きできることを知って提案しているという。現役医師・久坂部羊の小説『悪医』をベースに、ガン治療ですれ違う医師と患者の想いを知る
そこでイングリッドはすぐに、マーサが入院しているマンハッタン癌センターへと向かった。彼女はやせ細った状態で、ベッドの上に横たわっている。診断はステージ3の子宮頸がん。マーサは当初、治療を拒否するつもりだったそうだが、その後、「まだ人生のステージを下りるタイミングではないかもしれない」と思い直し、現在治療を受けている最中だ。
しかし一方でマーサは、「自身の癌が完治することは恐らくないだろう」とも理解していた。そしてだからだろう、彼女は「死を前にすると、生きていることが残酷に思える」と弱音とも取れることを口にする。親友の発言を受けて、どうにか勇気づけようと言葉を返すイングリッド。しかし彼女は解釈を間違えていた。マーサは「死を恐れて狼狽えている」のではなく、「どうせ回避できない死であるならば、身も心も平穏な状態で、少しは威厳を保った状態でこの世を去りたい」と考えていたのである。
こんな風に2人は、病気の話から会話を始め、そしてそれからは、会っていなかった時間を埋め合わせるかのようにお互いの話をし続けた。中でも2人は、マーサの娘ミシェルの話に時間を割く。NYタイムズの戦場記者として長く働いてきたマーサは、「母親としては失格だった」という自覚を持っている。一方ミシェルはというと、シングルマザーの母親(マーサ)が父親について何も教えてくれないことにずっと苛立ちを募らせてきたようだ。
あわせて読みたい
【母娘】よしながふみ『愛すべき娘たち』で描かれる「女であることの呪い」に男の私には圧倒されるばかりだ
「女であること」は、「男であること」と比べて遥かに「窮屈さ」に満ちている。母として、娘として、妻として、働く者として、彼女たちは社会の中で常に闘いを強いられてきた。よしながふみ『愛すべき娘たち』は、そんな女性の「ややこしさ」を繊細に描き出すコミック
そんな母娘のわだかまりは、マーサの癌が判明した時にも浮き彫りになった。マーサが家族に「治療を受けるつもりはない」と話をした際、ミシェルは「あなたの選択だから」と突き放すような言い方をしたというのである。マーサとミシェルの間には、今も距離があるそうだ。
しばらくしてマーサは、自ら「実験台」という表現を使いつつ、医師から勧められた新しい治療法を試したこと、そしてその結果があまり良くないことをイングリッドに話す。マーサは「少しでも希望を抱いてしまった自分がバカだった」と嘆き、そしてこの出来事が引き金となったのだろう、彼女はある大きな決断を下したのである。
イングリッドはその後、マーサから驚きの計画を聞かされた。マーサはなんと、闇サイトで安楽死用の薬を手に入れており、癌でやられる前に自ら始末をつけると決めたというのだ。ただその一方で、これまでに戦場で多くの死に触れてきた彼女は、「死にゆく者の傍には必ず誰かがいた」という記憶も強く持っていた。そんなこともあり彼女は、「自分が死を迎える時も、誰かが傍にいてくれたら嬉しい」と考えているのだ。
あわせて読みたい
【議論】安楽死のできない日本は「死ぬ権利」を奪っていると思う(合法化を希望している):『安楽死を…
私は、安楽死が合法化されてほしいと思っている。そのためには、人間には「死ぬ権利」があると合意されなければならないだろう。安楽死は時折話題になるが、なかなか議論が深まらない。『安楽死を遂げた日本人』をベースに、安楽死の現状を理解する
そしてその役回りをお願いしたいと、イングリッドは頼まれたのである。
決して、「安楽死の手伝いをしてほしい」なんて話ではない。薬は自分で飲むし、いつ安楽死するのかも教えない。警察から疑いを掛けられると思うが、罪に問われない最大限の配慮はする。「だから、隣の部屋にいてほしい」というお願いなのだ。

イングリッドは普通の人以上に「死」を恐れる気持ちを強く抱いている。そしてだからこそ、いくら親友の頼みだとはいえ、「死の直前まで一緒にいてほしい」なんて話をすぐに快諾することは出来なかった。しかし悩みに悩んだ末に、最終的にはその提案を受け入れる決断をし……。
あわせて読みたい
【絶望】杉咲花主演映画『市子』の衝撃。毎日がしんどい「どん底の人生」を生き延びるための壮絶な決断…
映画『市子』はまず何よりも主演を務めた杉咲花に圧倒させられる作品だ。そしてその上で、主人公・川辺市子を巡る物語にあれこれと考えさせられてしまった。「川辺市子」は決してフィクショナルな存在ではなく、現実に存在し得る。本作は、そのような存在をリアルに想像するきっかけにもなるだろう
ティルダ・スウィントンが演じたマーサの存在感が実に圧倒的で興味深かった
本作は、先述した内容紹介でほぼすべてを説明し切ったと言っていいぐらいの物語で、とにかくシンプルである。前半は「マーサと再会したイングリッドが、マーサの過去・現在・未来の話を色々と聞き、親友からの重い提案を受け入れる」という流れであり、そして後半は、「マーサが借りた森の中の家で2人が静かな日々を過ごす」だけなのだ。本当にそれ以上でもそれ以下でもなく、展開と言えるほどのストーリーがあるわけではない。
ただ何度も書いている通り、とにかくマーサが魅力的な人物であり、さらにそんなマーサをティルダ・スウィントンが素敵に演じていたので、素晴らしい作品に感じられたのだと思う。
私がマーサのどこに惹かれたのかというと、まずは「男っぽさ」みたいな部分な気がする。「男だから/女だから」みたいな話はあまりしたくないのだが、ただ本作においては、「子宮頸がんという女性特有の癌を患った女性が、見た目も振る舞いもどこまでも男性的である」という要素が、作品の魅力の1つとして機能していたように思う。
あわせて読みたい
【実話】さかなクンの若い頃を描く映画『さかなのこ』(沖田修一)は子育ての悩みを吹き飛ばす快作(主…
映画『さかなのこ』は、兎にも角にものん(能年玲奈)を主演に据えたことが圧倒的に正解すぎる作品でした。性別が違うのに、「さかなクンを演じられるのはのんしかいない!」と感じさせるほどのハマり役で、この配役を考えた人は天才だと思います。「母親からの全肯定」を濃密に描き出す、子どもと関わるすべての人に観てほしい作品です
彼女はある場面で、こんな話をしていた。
女性の戦場特派員はとにかく少ない。戦争は男のものだからね。ある意味では男として生きなければならなかったわけだけど、それは私にはとても簡単なことだった。
マーサは両サイドを刈り上げたような短髪で、また、表情や顔の雰囲気には「強さ」がにじみ出ている感じがあり、見た目的にとても男っぽい。そしてその風貌は、彼女にとっては「生きやすさ」みたいなものに繋がっていたようだ。女性の世界で生きていくよりも男社会の方が馴染みやすかったということなのだろう。とすれば勝手な想像でしかないが、彼女の中には「そんな自分が、まさか子宮頸がんとはね」みたいな感覚さえあったかもしれない。
さらにマーサは、「母親」という役割に上手く収まれずにいる。彼女はちょっと色々あって、20代の頃に望まぬ形で妊娠・出産を経験しシングルマザーになった。その後、「ペーパーマガジン」を皮切りに夜のNYで記者として奔走するようになり、「とても子育てなんかしていられない」という状態になっていく。「母親」よりも「仕事」を取ったというわけだ。現代では「仕事を優先しているから男っぽい」なんて発想はむしろ古いものと受け取られるだろうが、彼女が現役バリバリだった頃にはやはりまだ、「女性は家で子育て」みたいな価値観の方が支配的だったはずだ。そしてそういう時代においても彼女は、仕事に没頭する道を選んだのである。
あわせて読みたい
【革命】電子音楽誕生の陰に女性あり。楽器ではなく機械での作曲に挑んだ者たちを描く映画:『ショック…
現代では当たり前の「電子音楽」。その黎明期には、既存の音楽界から排除されていた女性が多く活躍した。1978年、パリに住む1人の女性が「電子音楽」の革命の扉をまさに開こうとしている、その1日を追う映画『ショック・ド・フューチャー』が描き出す「創作の熱狂」
さて、そんなマーサの思考は実に理屈っぽく、この点でも男性的だと感じさせられた。作中では「死生観」についての彼女の思考が強く表に出るのだが、イングリッドには許容できない彼女のその思考は、客観的にはとても理屈が通っているように感じられるんじゃないかと思う。もちろん、「男は理屈、女は感情」みたいな話もステレオタイプすぎるが、とはいえそういう傾向はそれなりにはあるはずだ。そして、マーサの価値観にはとにかく「感情」がまったく入りこまない。隙のない理屈で押し通そうとするところも、個人的には凄く好きだなと思う。

またマーサに対しては、まさにその「死生観」そのものにも興味を抱かされた。私自身が普段から考えていることと結構近いものがあり、とても共感させられたのだ。もちろん、「安楽死」という選択肢を過激だと感じる人は一定数いるとは思うが(ただ私は、「安楽死」が制度として存在してほしい派である)、それはともかく、「尊厳ある死を目指したい」という感覚については頷ける部分が大きいんじゃないかと考えている。
彼女が語るその「尊厳ある死」という感覚は恐らく、娘ミシェルの父親であるフレッドのその後の話を知ったこととも関係しているのだと思う。マーサは長くフレッドと連絡を取っていなかったのだが、ミシェルがあまりにも父親についてしつこく聞いてくるため、その後の消息を調べてみることにした。すると、フレッドが事故で亡くなっていることが判明したのである。
あわせて読みたい
【実話】映画『ハドソン川の奇跡』の”糾弾された英雄”から、「正しさ」をどう「信じる」かを考える
制御不能の飛行機をハドソン川に不時着させ、乗員乗客155名全員の命を救った英雄はその後、「わざと機体を沈め損害を与えたのではないか」と疑われてしまう。映画『ハドソン川の奇跡』から、「正しさ」の難しさと、「『正しさ』の枠組み」の重要性を知る
そしてその「死に方」は、マーサに強い印象をもたらしたはずだ。
その話は、フレッドが後に結婚した妻から聞いたものである。フレッドは妻を乗せてドライブしている最中、道路脇の家が燃えているのを見つけた。彼は車を停め、なんと燃え盛る家に飛び込んでいく。「中から声が聞こえる」と言って、妻の静止を振り切って炎の中へと入っていったのだ。そのままフレッドは出てこなかった。そして後にやってきた消防が中を確かめたところ、焼け落ちた家からは彼の遺体だけが見つかったという。
フレッドは、マーサと付き合い始めて数ヶ月でベトナム戦争に徴集され、1年後に戻ってきた時には別人のようになってしまっていた。そのこともあり、ミシェルを妊娠していたマーサは彼と別れることを選んだのだが、結局フレッドは、戦争による後遺症である「幻覚・幻聴」によって命を落としていたことになる。そしてその「死」に、マーサは「尊厳」を感じられなかったのだと思う。
さらに彼女は、戦争に”奪われた”フレッドのことも念頭にあって選択したのだろう「戦場特派員」という仕事においても、「尊厳の無い死」を数多く目にしてきた。そしてそういう経験を積み重ねてきたからこそ、自身が「死」に直面した際、何よりも「尊厳」にこだわったのではないかと思う。
あわせて読みたい
【映画】『戦場記者』須賀川拓が、ニュースに乗らない中東・ウクライナの現実と報道の限界を切り取る
TBS所属の特派員・須賀川拓は、ロンドンを拠点に各国の取材を行っている。映画『戦場記者』は、そんな彼が中東を取材した映像をまとめたドキュメンタリーだ。ハマスを巡って食い違うガザ地区とイスラエル、ウクライナ侵攻直後に現地入りした際の様子、アフガニスタンの壮絶な薬物中毒の現実を映し出す
そんなマーサの「様々な経験に裏打ちされたのだろう『死生観』」が実に興味深く、さらに本作においては、まさに彼女の「死生観」こそが作品の核になっていくわけで、だからこそ本作は観る人を惹きつける物語に仕上がっている気がする。
マーサが抱く、「『病気に”負けない”ための死』という感覚」と「『死ぬ時は隣にいてほしい』という希望」について
それでは、彼女が考える「尊厳のある死」についてもう少し深堀りしていくことにしよう。彼女の根底にはずっと「人間には『上質な死』を迎える権利があるはずだ」という考えがある。彼女の「死生観」は常にそういう思考に裏打ちされているわけだが、そんな話をしている中で彼女が口にした「『病気と闘うこと』についての感覚」が実に興味深かった。
癌患者となったマーサは、「周囲の人間は『私が病気と闘い続けること』を望んでいる」という認識を持っている。マーサは当初「治療しない」と考えていたわけで、その際の反応からそんな風に感じているのだろう。つまり、「治療を諦めるのではなく病気と闘うべきだ」という感覚を、癌を患った当人ではない周囲の人間が抱いているというわけだ。
あわせて読みたい
【死】映画『湯を沸かすほどの熱い愛』に号泣。「家族とは?」を問う物語と、タイトル通りのラストが見事
「死は特別なもの」と捉えてしまうが故に「日常感」が失われ、普段の生活から「排除」されているように感じてしまうのは私だけではないはずだ。『湯を沸かすほどの熱い愛』は、「死を日常に組み込む」ことを当たり前に許容する「家族」が、「家族」の枠組みを問い直す映画である
しかし、長いこと戦場記者として従事してきた彼女には、そのような感覚は「善と悪の闘い」に近いものがあると感じられたという。どういうことか理解できるだろうか?
病気でも戦争でも、勝てば「英雄」として扱われる。つまりこれは、「頑張って努力したから偉い」という評価だと考えていいだろう。では、負けたらどういう扱いになるのか。やはり「頑張り(努力)が足りなかった」という評価になるのだろう。彼女は多くの戦争を目にする中で、世間のそういう感覚を理解していった。しかしマーサ自身はそのようには考えていない。努力云々の問題なんかじゃなく、あるのはただ、「勝つ」か「負ける」かという結果だけでしかないというわけだ。

そして彼女は、明確に「負けたくない」と感じていた。彼女が言う「負け」というのは「死」を意味しているのではなく、「完治出来ないまま治療を止める」とか「治療の過程で耐え難いほどの苦痛に襲われる」といった状態を指していると考えればいいだろう。そして、「治療」を選択したところで必ずしも「勝てる」保証はない。だったら「勝つ」ためではなく「負けない」ための闘いをすべきなのではないか。そのような思考から彼女が導き出した結論が「安楽死」だったというわけだ。
あわせて読みたい
【救い】自殺を否定しない「笑える自殺本」。「自殺したい」ってもっと気軽に言える社会がいい:『自殺…
生きることがしんどくて、自殺してしまいたくなる気持ちを、私はとても理解できます。しかし世の中的には、「死にたい」と口にすることはなかなか憚られるでしょう。「自殺を決して悪いと思わない」という著者が、「死」をもっと気楽に話せるようにと贈る、「笑える自殺本」
この理屈はとても筋が通っていると思うし、私はものすごく共感させられた。彼女と同じ状況にいたら、私も同じ思考で同じ結論に達すると思う。まあ、「闇サイトで安楽死の薬を手に入れる」みたいな行動力が私にあるかは何とも言えないが、少なくとも理屈の部分はメチャクチャ理解できてしまったのである。もちろん、マーサのこの感覚に共感できない人も多いとは思うが、私は個人的にとても理に適った理屈だと思っているので、「こんな風に考える人もいる」という理解を元に、「安楽死」の議論をもう少し進めてほしいものだなと思う。
さて、そんな風にして「安楽死」という答えを導き出したマーサだったが、1つ大きな問題があった。それが「隣の部屋にいてほしい」という希望である。彼女が1人で死を迎えられるのであれば、何の問題も生じなかっただろう。自分が良いと思うタイミングで薬を飲めばそれで終わりである。しかし彼女は、「自分が死を迎える瞬間は、誰かに傍にいてほしい」という強い希望を持ってもいたのだ。
正直なところ、これはなかなか難しい問題である。というのも、マーサ自身も自覚していたが、一歩間違えれば「自殺幇助」の疑いをかけられてしまう可能性があるからだ。
あわせて読みたい
【異常】「助けて」と言えない。自己責任社会のしんどさと、我が子がホームレスである可能性:『助けて…
39歳で餓死した男性は、何故誰にも助けを求めなかったのか?異常な視聴率を叩き出した、NHK「クローズアップ現代」の特集を元に書かれた『助けてと言えない』をベースに、「自己責任社会」の厳しさと、若者が置かれている現実について書く。
そもそも私は「自殺幇助」という犯罪がどういう要件で成立するのか知らないし、日本とアメリカの間にも違いはあるかもしれないが、いずれにせよマーサは、イングリッドには容疑が向かないように万難を排して準備をしていた。遺書とは別に警察宛の手紙を残し、そこには薬の入手先なども含めすべての情報が記載してある。さらにイングリッドには「決行日」を教えず、また、その他の「知っておく必要のない情報」も伝えなかった。こうすることで、万が一警察の取り調べを受けても「私は何も知らなかった」と言い張れるように準備していたのだ。
つまり逆に考えれば、ここまでお膳立てしなければ「関わった者が『自殺幇助』の罪に問われる可能性」を排除できないとも言えるだろう。マーサは、そんな危ない橋をイングリッドに渡らせていることをちゃんと自覚した上で頼んでいるのである。
さらに、イングリッドの方にも大きな問題があった。こちらに関してはあまり強く焦点は当てられないのだが、イングリッドは「死」に対する恐怖心をとにかく強く持っている人物として描かれる。そのため、「親友がまさに死を迎える空間に一緒にいる」という行為が、普通の人以上に恐ろしく感じられてしまうのだ。イングリッドがマーサの頼みを受け入れたのは、まさに「戦友」と言ってもいいような濃密な時間を過ごした経験があったからだろう。そういう相手からの「最後の頼み」だからこそ、自身の苦痛を押しのけてでもどうにか受け入れることにしたのだと思う。
あわせて読みたい
【リアル】社会の分断の仕組みを”ゾンビ”で学ぶ。「社会派ゾンビ映画」が対立の根源を抉り出す:映画『C…
まさか「ゾンビ映画」が、私たちが生きている現実をここまで活写するとは驚きだった。映画『CURED キュアード』をベースに、「見えない事実」がもたらす恐怖と、立場ごとに正しい主張をしながらも否応なしに「分断」が生まれてしまう状況について知る
そんなわけで本作は、「安楽死」という決して目新しいわけではない要素、そして「主たる登場人物が2人」というあまりにシンプルな構成にも拘らず、観る者を惹きつける作品に仕上がっていると言えるだろう。マーサのキャラクターや警察沙汰になるかもしれない危うい計画、さらに「死」への恐怖を強く抱いてしまうイングリッドの心情などが絶妙に絡まり合い、とても見ごたえの作品になっていると思う。
「安楽死」はもっと議論されるべきだし、その過程で「死」そのものの議論も深めるべきだと思う
「安楽死」が話題に上る度に私は、社会全体で「安楽死」がもう少し積極的に議論されるべきだと感じる。キリスト教が自殺を「禁忌」としているはずなので、欧米ではそういう観点でも安楽死のハードルが高いことは理解できるのだが、日本の場合は別に宗教による制約はないはずだ。だから、個人的にはもう少し議論が進んでもいいと思っているのだが、何故ここまで停滞してしまうのかよく分からない。
例えばだが、マーサが口にするこんなセリフからも「安楽死についてもっと議論すべき」だと感じられるんじゃないかと思う。
あわせて読みたい
【爆笑】「だるい」「何もしたくない」なら、「自分は負け組」と納得して穏やかに生きよう:『負ける技…
勝利は敗北の始まり」という感覚は、多くの人が理解できると思います。日本では特に、目立てば目立つほど足を引っ張られてしまいます。だったら、そもそも「勝つ」ことに意味などないのでは?『負ける技術』をベースに、ほどほどの生き方を学びます
すべての喜びが消えてしまった。もう、何に気を向けたらいいのか分からない。
マーサは大の読書家であるようだが、癌を患った身体では集中して本を読むのがなかなか難しいようだ。さらに音楽は、「鳥のさえずり」以外聴きたいと思えなくなってしまったという。それまではたくさんあった「自分の心を震わせるもの」が、死を前にした今すべて無くなってしまい、「ただ人の形をしたまま存在しているだけ」みたいな状態にあるというわけだ。

私は、そんな状態ではとても「生きている」などとは感じられない。しかし、「身体が生命を維持できてさえいれば、それは喜ばしいことなんだ」とでも言わんばかりに、「生きることを諦めるべきではない」みたいに思われてしまう。さすがにそれは、ちょっとしんどすぎないだろうか。
イングリッドはマーサからこのような「死生観」を突きつけられ、度々言葉に詰まっていた。イングリッドもきっと、大した関係性ではない相手であれば、当たり障りないことを言ってその場を取り繕っただろう。しかし、目の前にいるのは親友である。そしてそんな親友が、「生きていることに喜びを感じられなくなってしまった」と吐露しているのだ。そんなことを言われて、掛けてあげられる言葉が何かあるだろうか?
あわせて読みたい
【絶望】子供を犯罪者にしないために。「異常者」で片付けられない、希望を見いだせない若者の現実:『…
2人を殺し、7人に重傷を負わせた金川真大に同情の余地はない。しかし、この事件を取材した記者も、私も、彼が殺人に至った背景・動機については理解できてしまう部分がある。『死刑のための殺人』をベースに、「どうしようもないつまらなさ」と共に生きる現代を知る
もちろんイングリッドは、「そうだとしても、マーサには生きていてほしい」と願っている。それはごく当たり前の感覚だろう。ただ残念ながら、そんな想いがマーサに届くことはない。また、マーサがイングリッドに対する”気遣い”を見せる場面も描かれるのだが、彼女が望むものとはズレすぎていて、イングリッドとしては素直に喜べないなんてこともある。
例えば、森の中の家で生活し始めてからの話だが、イングリッドとマーサはある日、「死生観」を巡って少し口論めいた感じになった。そしてその翌朝、マーサは「昨日の私は最悪だった」と謝るのだが、その上で、「ここに鎮静剤を入れておくから、もしも私のおかしさに耐えられなくなったら飲んで」みたいに言っていたのだ。もちろんこれは、マーサなりの最大限の配慮であり、そのこと自体はイングリッドも理解している。しかし彼女は同時に、「別にそういうことじゃないんだよ」みたいにも感じていたはずだ。本当に望んでいるのは、「マーサが安楽死を撤回して生き続けること」なのだから。しかし当然、この期に及んでもうそんなことは言えない。だからイングリッドの”不満”は溜まっていく一方というわけだ。
こんな風に、マーサとイングリッドの間では、些細と言えば些細だが、しかし「死」という巨大なものを間に挟んでいるが故に大きすぎるようにも感じられる「ズレ」が少しずつ浮き彫りになっていくのである。そういう描写もまた、実に興味深く感じさせられた。
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『悪は存在しない』(濱口竜介)の衝撃のラストの解釈と、タイトルが示唆する現実(主…
映画『悪は存在しない』(濱口竜介監督)は、観る者すべてを困惑に叩き落とす衝撃のラストに、鑑賞直後は迷子のような状態になってしまうだろう。しかし、作中で提示される様々な要素を紐解き、私なりの解釈に辿り着いた。全編に渡り『悪は存在しない』というタイトルを強く意識させられる、脚本・映像も見事な作品だ
実際には、本作で描かれる「死の間際まで隣の部屋にいてほしい」みたいな状況になることはまずないだろう。そういう意味でいうなら「非リアルな設定」だ。ただ、このような特異な状況を設定したことによって、それまであまり考えたことのなかった「死」に関する様々な問いが浮かび上がってくる。静かに淡々と展開される物語なのだが、ある意味で”挑発的”とも言える内容であり、そういう部分が個人的にはとても素敵に感じられた。
監督:ペドロ・アルモドバル, Writer:ペドロ・アルモドバル, 出演:ティルダ・スウィントン, 出演:ジュリアン・ムーア, 出演:ジョン・タトゥーロ, 出演:アレッサンドロ・ニボラ
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品視聴済】私が観てきた映画(フィクション)を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が観てきた映画(フィクション)を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。
最後に
最後にいくつか余談に触れてこの記事を終えることにしよう。
まず映画のラストで、それまで一度も姿を現さなかったマーサの娘ミシェルが登場する。しかしこのシーンにはとにかく驚かされた。マーサとそっくりだったからだ。私は、映画を観ている間はホントに、「よくもまあこんなに似ている人物を見つけてきたものだ」と思っていたのだが、そうではなかった。ティルダ・スウィントンによる1人2役なのだそうだ。
あわせて読みたい
【傑作】濱口竜介監督の映画『ドライブ・マイ・カー』(原作:村上春樹)は「自然な不自然さ」が見事な作品
村上春樹の短編小説を原作にした映画『ドライブ・マイ・カー』(濱口竜介監督)は、村上春樹の小説の雰囲気に似た「自然な不自然さ」を醸し出す。「不自然」でしかない世界をいかにして「自然」に見せているのか、そして「自然な不自然さ」は作品全体にどんな影響を与えているのか
であれば「似ていること」には納得だが、しかし「同じ人物が演じている」のならそれはそれで驚きである。調べてみると、ティルダ・スウィントンは64歳なのだそうだ。マーサの年齢は不明だが、恐らく大体同じようなものだろう。また、マーサは20歳ぐらいでミシェルを産んだのだから、ミシェルは40代半ばぐらいということになる。そしてミシェル役のティルダ・スウィントンは、それぐらいの年齢にしか見えなかったのだ。もちろん、CGなどで加工しているのかもしれないし、そうだとしたら別に驚くようなことではないのかもしれないが、もし生身の人間の存在だけであの若さを醸し出しているのであれば、ちょっと凄いなと思う。

また、本作を観ていて個人的に結構驚いたのが、マーサとイングリッドの英語がメチャクチャ聞き取りやすかったことである。普段私は、字幕を観ながらでさえ、役者が発する英語のセリフをあまり聞き取れない。しかし本作は、ティルダ・スウィントンもジュリアン・ムーアももの凄く聞き取りやすい英語を話していて、あくまでも字幕を観ながらではあるが、どんな英語を口にしていたのか大体理解できたと思う。私は別に外国人と話したいわけではないし、英語を習得したいなんて特に思ってもいないのだけど、本作を観て、「英語圏の人がみんなこれぐらいの発音で喋ってくれたら頑張ろうって思えるんだけどな」と感じたりした。
あと、これこそどうでもいいことだが、冷蔵庫の中に、日本語ラベルの「お~いお茶」があったと思う。確か大谷翔平がCMキャラクターを務めているはずで、だからもしかしたら、アメリカでも日本語ラベルのペットボトルが普通に流通しているのかもしれない。一瞬しか映らなかったが、日本人なら「ん?」ってなるシーンじゃないかと思う。
そんなわけで、個人的にはとても面白く感じられる作品だった。本作は「どう死にたいか」を考えるきっかけになるだろうし、また、そんな思考を通じて「どう生きたいか」についても考えさせられるのではないかと思う。
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!「それってホントに『コミュ力』が高いって言えるの?」と疑問を感じている方に…
私は、「コミュ力が高い人」に関するよくある主張に、どうも違和感を覚えてしまうことが多くあります。そしてその一番大きな理由が、「『コミュ力が高い人』って、ただ『想像力がない』だけではないか?」と感じてしまう点にあると言っていいでしょう。出版したKindle本は、「ネガティブには見えないネガティブな人」(隠れネガティブ)を取り上げながら、「『コミュ力』って何だっけ?」と考え直してもらえる内容に仕上げたつもりです。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【不寛容】カルトと呼ばれた「イエスの方舟」の現在は?「理解できなければ排除する社会」を斬る映画:…
映画『方舟にのって』は、1980年に社会を騒がせ、「ハーレム教団」「セックスカルト教団」と呼ばれて大問題となった「イエスの方舟」の現在を追うドキュメンタリー映画だ。そして、そんな本作が本当に映し出してるのは「大衆」の方である。「『理解できないもの』は排除する」という社会に対する違和感を改めて浮き彫りにする1作
あわせて読みたい
【レビュー】実写映画『秒速5センチメートル』が描く「魂が震える人と出会うこと」の煌めきと残酷さ(監…
実写映画『秒速5センチメートル』は、何よりもまず「雰囲気」が最高に素晴らしい作品でした。「人生の早い段階で『魂が震える人』と出会ってしまったこと」の煌めきと残酷さが深く描かれていて、観ている間じゅう色んなことを考えさせられたし、会話も役者の演技も主題歌もすべてが完璧で、とにかく観て良かったなと思います
あわせて読みたい
【日々】映画『なみのおと』は、東日本大震災を語る人々の対話を”あり得ない”アングルから撮る(監督:…
映画『なみのおと』は、「東日本大震災の被災者が当時を振り返って対話をする」という内容そのものももちろん興味深いのだが、カメラをどう配置しているのかが分からない、ドキュメンタリー映画としては”あり得ない”映像であることにも驚かされた。また、悲惨な経験を軽妙に語る者たちの雰囲気も印象的な作品である
あわせて読みたい
【人生】映画『雪子 a.k.a.』は、言葉は出ないが嘘もないラップ好きの小学校教師の悩みや葛藤を描き出す
「小学校教師」と「ラップ」というなかなか異色の組み合わせの映画『雪子 a.k.a.』は、「ここが凄く良かった」と言えるようなはっきりしたポイントはないのに、ちょっと泣いてしまうぐらい良い映画だった。「口下手だけど嘘はない」という主人公・雪子の日常的な葛藤には、多くの人が共感させられるのではないかと思う
あわせて読みたい
【包容】映画『違国日記』を観て思う。「他者との接し方」が皆こうだったらもっと平和なはずだって(主…
映画『違国日記』は、人見知りの小説家・高代槙生が両親を亡くした姪・朝を引き取り一緒に暮らすところから始まる物語で、槙生と朝を中心とした様々な人間関係が絶妙に描かれている作品でした。人付き合いが苦手ながら、15歳という繊細な存在を壊さないように、でも腫れ物みたいには扱わないように慎重になる槙生のスタンスが素敵です
あわせて読みたい
【秘密】映画『ドライブ・イン・マンハッタン』は、「タクシー内の会話のみ」だが絶妙に良かった(主演…
映画『ドライブ・イン・マンハッタン』は、「タクシー内」というワンシチュエーションで「会話のみ」によって展開されるミニマムな要素しかない物語なのに、とにかく面白くて驚かされてしまった。運転手による「ゲスい会話」や女性客が抱えているのだろう「謎の秘密」などについて、色々と考えたくなるような深みのある物語である
あわせて読みたい
【忌避】小児性愛者から子どもを救え!映画『サウンド・オブ・フリーダム』が描く衝撃の実話(主演:ジ…
映画『サウンド・オブ・フリーダム』は、世界的に大問題となっている「子どもの人身売買」を扱った、実話を基にした物語である。「フィクションとしか思えないようなおとり捜査」を実行に移した主人公の凄まじい奮闘と、「小児性愛者の変態的欲望」の餌食になる悲惨な子どもたちの現実をリアルに描き出していく
あわせて読みたい
【父親】パキスタン本国では上映禁止の映画『ジョイランド』は、古い価値観に翻弄される家族を描く
映画『ジョイランド』は、本国パキスタンで一時上映禁止とされた作品だが、私たち日本人からすれば「どうして?」と感じるような内容だと思う。「(旧弊な)家族観を否定している」と受け取られたからだろうが、それにしたってやはり理不尽だ。そしてそんな「家族のややこしさ」には、現代日本を生きる我々も共感できるに違いない
あわせて読みたい
【絶望】映画『若き見知らぬ者たち』が描くのは”不正解”だが、「じゃあ”正解”って何?」ってなる(監督…
映画『若き見知らぬ者たち』は、「まともな生活が送れなくなった母親の介護」を筆頭に、かなり絶望的な状況に置かれている若者たちを描き出す作品だ。あまりにも不毛で、あまりにも救いがなく、あまりにも辛すぎるその日々は、ついに限界を迎える。そしてその絶望を、磯村勇斗がその凄まじい存在感によって体現していく
あわせて読みたい
【捏造】袴田事件はついに再審での無罪が決定!冤罪の元死刑囚・袴田巌の現在と姉・秀子の奮闘:映画『…
映画『拳と祈り』は、2024年に再審無罪が確定した「袴田事件」の元死刑囚・袴田巌と、そんな弟を献身的にサポートする姉・秀子の日常を中心に、事件や裁判の凄まじい遍歴を追うドキュメンタリーである。日本の司法史上恐らく初めてだろう「前代未聞の状況」にマスコミで唯一関わることになった監督が使命感を持って追い続けた姉弟の記録
あわせて読みたい
【絶望】満員続出の映画『どうすればよかったか?』が描き出す、娘の統合失調症を認めない両親の不条理
たった4館から100館以上にまで上映館が拡大した話題の映画『どうすればよかったか?』を公開2日目に観に行った私は、「ドキュメンタリー映画がどうしてこれほど注目されているのだろうか?」と不思議に感じた。統合失調症を発症した姉を中心に家族を切り取る本作は、観る者に「自分だったらどうするか?」という問いを突きつける
あわせて読みたい
【異様】映画『大いなる不在』(近浦啓)は、認知症の父を中心に「記憶」と「存在」の複雑さを描く(主…
「父親が逮捕され、どうやら認知症のようだ」という一報を受けた息子が、30年間ほぼやり取りのなかった父親と再会するところから始まる映画『大いなる不在』は、なんとも言えない「不穏さ」に満ちた物語だった。「記憶」と「存在」のややこしさを問う本作は、「物語」としては成立していないが、圧倒的な“リアリティ”に満ちている
あわせて読みたい
【絶望】知られざる「国による嘘」!映画『蟻の兵隊』(池谷薫)が映し出す終戦直後の日本の欺瞞
映画『蟻の兵隊』は、「1945年8月15日の終戦以降も上官の命令で中国に残らされ、中国の内戦を闘った残留日本軍部隊」の1人である奥村和一を追うドキュメンタリー映画だ。「自らの意思で残った」と判断された彼らは、国からの戦後補償を受けられていない。そんな凄まじい現実と、奥村和一の驚くべき「誠実さ」が描かれる作品である
あわせて読みたい
【真相?】映画『マミー』が描く和歌山毒物カレー事件・林眞須美の冤罪の可能性。超面白い!
世間を大騒ぎさせた「和歌山毒物カレー事件」の犯人とされた林眞須美死刑囚は無実かもしれない。映画『マミー』は、そんな可能性を示唆する作品だ。「目撃証言」と「ヒ素の鑑定」が詳細に検証し直され、さらに「保険金詐欺をやっていた」という夫の証言も相まって、証拠的にも感情的にも支持したくなるような驚きの仮説である
あわせて読みたい
【あらすじ】有村架純が保護司を演じた映画『前科者』が抉る、罪を犯した者を待つ「更生」という現実
映画『前科者』は、仮釈放中の元受刑者の更生を手助けするボランティアである「保護司」を中心に据えることで、「元犯罪者をどう受け入れるべきか」「保護司としての葛藤」などを絶妙に描き出す作品。個別の事件への処罰感情はともかく、「社会全体としていかに犯罪を減らしていくか」という観点を忘れるべきではないと私は思っている
あわせて読みたい
【衝撃】EUの難民問題の狂気的縮図!ポーランド・ベラルーシ国境での、国による非人道的対応:映画『人…
上映に際し政府から妨害を受けたという映画『人間の境界』は、ポーランド・ベラルーシ国境で起こっていた凄まじい現実が描かれている。「両国間で中東からの難民を押し付け合う」という醜悪さは見るに絶えないが、そのような状況下でも「可能な範囲でどうにか人助けをしたい」と考える者たちの奮闘には救われる思いがした
あわせて読みたい
【現在】猟師になった東出昌大を追う映画『WILL』は予想外に良かった。山小屋での生活は衝撃だ(監督:…
猟師・東出昌大に密着した映画『WILL』は、思いがけず面白い作品だった。正直、東出昌大にはまったく興味がなく、本作も期待せず観たのだが、異常なほどフラットなスタンス故に周囲にいる人間を否応なく惹きつける「人間力」や、狩猟の世界が突きつける「生と死」というテーマなど実に興味深い。本当に観て良かったなと思う
あわせて読みたい
【赦し】映画『過去負う者』が描く「元犯罪者の更生」から、社会による排除が再犯を生む現実を知る
映画『過去負う者』は、冒頭で「フィクション」だと明示されるにも拘らず、観ながら何度も「ドキュメンタリーだっけ?」と感じさせられるという、実に特異な体験をさせられた作品である。実在する「元犯罪者の更生を支援する団体」を舞台にした物語で、当然それは、私たち一般市民にも無関係ではない話なのだ
あわせて読みたい
【実話】映画『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』が描く、白人警官による黒人射殺事件
映画『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』は、2011年に起こった実際の事件を元にした作品である。何の罪もない黒人男性が、白人警官に射殺されてしまったのだ。5時22分から始まる状況をほぼリアルタイムで描き切る83分間の物語には、役者の凄まじい演技も含め、圧倒されてしまった
あわせて読みたい
【実話】田舎暮らし失敗。映画『理想郷』が描く、めんどくさい人間関係が嫌がらせに発展した事件
実話を基にした映画『理想郷』は、「理想の田舎暮らし」が粉微塵に粉砕されていく過程を描く物語である。第一義的には当然、夫妻に嫌がらせを続ける兄弟が悪いのだが、しかしそのように捉えるだけでは何も変わらないだろう。双方の譲れない「価値観」が否応なしに正面衝突する状況で、一体何が「正解」となり得るだろうか?
あわせて読みたい
【無謀】映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、脱北ルートに撮影隊が同行する衝撃のドキュメンタリー
北朝鮮からの脱北者に同行し撮影を行う衝撃のドキュメンタリー映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、再現映像を一切使用していない衝撃的な作品だ。危険と隣り合わせの脱北の道程にカメラもついて回り、北朝鮮の厳しい現状と共に、脱北者が置かれた凄まじい状況を映し出す内容に驚かされてしまった
あわせて読みたい
【感想】関東大震災前後を描く映画『福田村事件』(森達也)は、社会が孕む「思考停止」と「差別問題」…
森達也監督初の劇映画である『福田村事件』は、100年前の関東大震災直後に起こった「デマを起点とする悲劇」が扱われる作品だ。しかし、そんな作品全体が伝えるメッセージは、「100年前よりも現代の方がよりヤバい」だと私は感じた。SNS時代だからこそ意識すべき問題の詰まった、挑発的な作品である
あわせて読みたい
【絶望】杉咲花主演映画『市子』の衝撃。毎日がしんどい「どん底の人生」を生き延びるための壮絶な決断…
映画『市子』はまず何よりも主演を務めた杉咲花に圧倒させられる作品だ。そしてその上で、主人公・川辺市子を巡る物語にあれこれと考えさせられてしまった。「川辺市子」は決してフィクショナルな存在ではなく、現実に存在し得る。本作は、そのような存在をリアルに想像するきっかけにもなるだろう
あわせて読みたい
【実話】映画『月』(石井裕也)は、障害者施設での虐待事件から「見て見ぬふりする社会」を抉る(出演…
実際に起こった障害者施設殺傷事件を基にした映画『月』(石井裕也)は、観客を作中世界に引きずり込み、「これはお前たちの物語だぞ」と刃を突きつける圧巻の作品だ。「意思疎通が不可能なら殺していい」という主張には誰もが反対するはずだが、しかしその態度は、ブーメランのように私たちに戻ってくることになる
あわせて読みたい
【現実】我々が食べてる魚は奴隷船が獲ったもの?映画『ゴースト・フリート』が描く驚くべき漁業の問題
私たちは、「奴隷」が獲った魚を食べているのかもしれない。映画『ゴースト・フリート』が描くのは、「拉致され、数十年も遠洋船上に隔離されながら漁をさせられている奴隷」の存在だ。本作は、その信じがたい現実に挑む女性活動家を追うドキュメンタリー映画であり、まさに世界が関心を持つべき問題だと思う
あわせて読みたい
【衝撃】ウクライナでのホロコーストを描く映画『バビ・ヤール』は、集めた素材映像が凄まじすぎる
ソ連生まれウクライナ育ちの映画監督セルゲイ・ロズニツァが、「過去映像」を繋ぎ合わせる形で作り上げた映画『バビ・ヤール』は、「単一のホロコーストで最大の犠牲者を出した」として知られる「バビ・ヤール大虐殺」を描き出す。ウクライナ市民も加担した、そのあまりに悲惨な歴史の真実とは?
あわせて読みたい
【衝撃】映画『誰がハマーショルドを殺したか』は、予想外すぎる着地を見せる普通じゃないドキュメンタリー
国連事務総長だったハマーショルドが乗ったチャーター機が不審な墜落を遂げた事件を、ドキュメンタリー映画監督マッツ・ブリュガーが追う映画『誰がハマーショルドを殺したか』は、予想もつかない衝撃の展開を見せる作品だ。全世界を揺るがしかねない驚きの”真実”とは?
あわせて読みたい
【狂気】映画『ニューオーダー』の衝撃。法という秩序を混沌で駆逐する”悪”に圧倒されっ放しの86分
映画『ニューオーダー』は、理解不能でノンストップな展開に誘われる問題作だ。「貧富の差」や「法の支配」など「現実に存在する秩序」がひっくり返され、対極に振り切った「新秩序」に乗っ取られた世界をリアルに描き出すことで、私たちが今進んでいる道筋に警鐘を鳴らす作品になっている
あわせて読みたい
【現実】映画『私のはなし 部落のはなし』で初めて同和・部落問題を考えた。差別はいかに生まれ、続くのか
私はずっと、「部落差別なんてものが存在する意味が分からない」と感じてきたが、映画『私のはなし 部落のはなし』を観てようやく、「どうしてそんな差別が存在し得るのか」という歴史が何となく理解できた。非常に複雑で解決の難しい問題だが、まずは多くの人が正しく理解することが必要だと言えるだろう
あわせて読みたい
【狂気】ホロコーストはなぜ起きた?映画『ヒトラーのための虐殺会議』が描くヴァンゼー会議の真実
映画『ヒトラーのための虐殺会議』は、ホロコーストの計画について話し合われた「ヴァンゼー会議」を描き出す作品だ。唯一1部だけ残った議事録を基に作られた本作は、「ユダヤ人虐殺」をイベントの準備でもしているかのように「理性的」に計画する様を映し出す。その「狂気」に驚かされてしまった。
あわせて読みたい
【驚愕】ベリングキャットの調査報道がプーチンを追い詰める。映画『ナワリヌイ』が示す暗殺未遂の真実
弁護士であり、登録者数640万人を超えるYouTuberでもあるアレクセイ・ナワリヌイは、プーチンに対抗して大統領選挙に出馬しようとしたせいで暗殺されかかった。その実行犯を特定する調査をベリングキャットと共に行った記録映画『ナワリヌイ』は、現実とは思えないあまりの衝撃に満ちている
あわせて読みたい
【驚愕】本屋大賞受賞作『同志少女よ、敵を撃て』(逢坂冬馬)は凄まじい。戦場は人間を”怪物”にする
デビュー作で本屋大賞を受賞した『同志少女よ、敵を撃て』(逢坂冬馬)は、デビュー作であることを抜きにしても凄まじすぎる、規格外の小説だった。ソ連に実在した「女性狙撃兵」の視点から「独ソ戦」を描く物語は、生死の境でギリギリの葛藤や決断に直面する女性たちのとんでもない生き様を活写する
あわせて読みたい
【信念】凄いな久遠チョコレート!映画『チョコレートな人々』が映す、障害者雇用に挑む社長の奮闘
重度の人たちも含め、障害者を最低賃金保証で雇用するというかなり無謀な挑戦を続ける夏目浩次を追う映画『チョコレートな人々』には衝撃を受けた。キレイゴトではなく、「障害者を真っ当に雇用したい」と考えて「久遠チョコレート」を軌道に乗せたとんでもない改革者の軌跡を追うドキュメンタリー
あわせて読みたい
【衝撃】これが実話とは。映画『ウーマン・トーキング』が描く、性被害を受けた女性たちの凄まじい決断
映画『ウーマン・トーキング』の驚くべき点は、実話を基にしているという点だ。しかもその事件が起こったのは2000年代に入ってから。とある宗教コミュニティ内で起こった連続レイプ事件を機に村の女性たちがある決断を下す物語であり、そこに至るまでの「ある種異様な話し合い」が丁寧に描かれていく
あわせて読みたい
【苦悩】「やりがいのある仕事」だから見て見ぬふり?映画『アシスタント』が抉る搾取のリアル
とある映画会社で働く女性の「とある1日」を描く映画『アシスタント』は、「働くことの理不尽さ」が前面に描かれる作品だ。「雑用」に甘んじるしかない彼女の葛藤がリアルに描かれている。しかしそれだけではない。映画の「背景」にあるのは、あまりに悪逆な行為と、大勢による「見て見ぬふり」である
あわせて読みたい
【性加害】映画『SHE SAID その名を暴け』を観てくれ。#MeToo運動を生んだ報道の舞台裏(出演:キャリ…
「#MeToo」運動のきっかけとなった、ハリウッドの絶対権力者ハーヴェイ・ワインスタインを告発するニューヨーク・タイムズの記事。その取材を担った2人の女性記者の奮闘を描く映画『SHE SAID その名を暴け』は、ジャニー喜多川の性加害問題で揺れる今、絶対に観るべき映画だと思う
あわせて読みたい
【純真】ゲイが犯罪だった時代が舞台の映画『大いなる自由』は、刑務所内での極深な人間ドラマを描く
男性同士の恋愛が犯罪であり、ゲイの男性が刑法175条を理由に逮捕されてしまう時代のドイツを描いた映画『大いなる自由』は、確かに同性愛の物語なのだが、実はそこに本質はない。物語の本質は、まさにタイトルにある通り「自由」であり、ラストシーンで突きつけられるその深い問いかけには衝撃を受けるだろう
あわせて読みたい
【生還】内戦下のシリアでISISに拘束された男の実話を基にした映画『ある人質』が描く壮絶すぎる現実
実話を基にした映画『ある人質 生還までの398日』は、内戦下のシリアでISISに拘束された男の壮絶な日々が描かれる。「テロリストとは交渉しない」という方針を徹底して貫くデンマーク政府のスタンスに翻弄されつつも、救出のために家族が懸命に奮闘する物語に圧倒される
あわせて読みたい
【衝撃】匿名監督によるドキュメンタリー映画『理大囲城』は、香港デモ最大の衝撃である籠城戦の内部を映す
香港民主化デモにおける最大の衝撃を内側から描く映画『理大囲城』は、とんでもないドキュメンタリー映画だった。香港理工大学での13日間に渡る籠城戦のリアルを、デモ隊と共に残って撮影し続けた匿名監督たちによる映像は、ギリギリの判断を迫られる若者たちの壮絶な現実を映し出す
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』で描かれる、グアンタナモ”刑務所”の衝撃の実話は必見
ベネディクト・カンバーバッチが制作を熱望した衝撃の映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』は、アメリカの信じがたい実話を基にしている。「9.11の首謀者」として不当に拘束され続けた男を「救おうとする者」と「追い詰めようとする者」の奮闘が、「アメリカの闇」を暴き出す
あわせて読みたい
【執念】「桶川ストーカー事件」で警察とマスコミの怠慢を暴き、社会を動かした清水潔の凄まじい取材:…
『殺人犯はそこにいる』(文庫X)で凄まじい巨悪を暴いた清水潔は、それよりずっと以前、週刊誌記者時代にも「桶川ストーカー殺人事件」で壮絶な取材を行っていた。著者の奮闘を契機に「ストーカー規制法」が制定されたほどの事件は、何故起こり、どんな問題を喚起したのか
あわせて読みたい
【解説】実話を基にした映画『シカゴ7裁判』で知る、「権力の暴走」と、それに正面から立ち向かう爽快さ
ベトナム戦争に反対する若者たちによるデモと、その後開かれた裁判の実話を描く『シカゴ7裁判』はメチャクチャ面白い映画だった。無理筋の起訴を押し付けられる主席検事、常軌を逸した言動を繰り返す不適格な判事、そして一枚岩にはなれない被告人たち。魅力満載の1本だ
あわせて読みたい
【あらすじ】蝦夷地の歴史と英雄・阿弖流為を描く高橋克彦の超大作小説『火怨』は全人類必読の超傑作
大げさではなく、「死ぬまでに絶対に読んでほしい1冊」としてお勧めしたい高橋克彦『火怨』は凄まじい小説だ。歴史が苦手で嫌いな私でも、上下1000ページの物語を一気読みだった。人間が人間として生きていく上で大事なものが詰まった、矜持と信念に溢れた物語に酔いしれてほしい
あわせて読みたい
【狂気】アメリカの衝撃の実態。民営刑務所に刑務官として潜入した著者のレポートは国をも動かした:『…
アメリカには「民営刑務所」が存在する。取材のためにその1つに刑務官として潜入した著者が記した『アメリカン・プリズン』は信じがたい描写に溢れた1冊だ。あまりに非人道的な行いがまかり通る狂気の世界と、「民営刑務所」が誕生した歴史的背景を描き出すノンフィクション
あわせて読みたい
【幸福】「死の克服」は「生の充実」となり得るか?映画『HUMAN LOST 人間失格』が描く超管理社会
アニメ映画『HUMAN LOST 人間失格』では、「死の克服」と「管理社会」が分かちがたく結びついた世界が描かれる。私たちは既に「緩やかな管理社会」を生きているが、この映画ほどの管理社会を果たして許容できるだろうか?そしてあなたは、「死」を克服したいと願うだろうか?
あわせて読みたい
【感想】阿部サダヲが狂気を怪演。映画『死刑にいたる病』が突きつける「生きるのに必要なもの」の違い
サイコパスの連続殺人鬼・榛村大和を阿部サダヲが演じる映画『死刑にいたる病』は、「生きていくのに必要なもの」について考えさせる映画でもある。目に光を感じさせない阿部サダヲの演技が、リアリティを感じにくい「榛村大和」という人物を見事に屹立させる素晴らしい映画
あわせて読みたい
【あらすじ】死刑囚を救い出す実話を基にした映画『黒い司法』が指摘する、死刑制度の問題と黒人差別の現実
アメリカで死刑囚の支援を行う団体を立ち上げた若者の実話を基にした映画『黒い司法 0%からの奇跡』は、「死刑制度」の存在価値について考えさせる。上映後のトークイベントで、アメリカにおける「死刑制度」と「黒人差別」の結びつきを知り、一層驚かされた
あわせて読みたい
【悲劇】アメリカの暗黒の歴史である奴隷制度の現実を、元奴隷の黒人女性自ら赤裸々に語る衝撃:『ある…
生まれながらに「奴隷」だった黒人女性が、多くの人の協力を得て自由を手にし、後に「奴隷制度」について書いたのが『ある奴隷少女に起こった出来事』。長らく「白人が書いた小説」と思われていたが、事実だと証明され、欧米で大ベストセラーとなった古典作品が示す「奴隷制度の残酷さ」
あわせて読みたい
【実話】台湾のろう学校のいじめ・性的虐待事件を描く映画『無聲』が問う、あまりに悲しい現実
台湾のろう学校で実際に起こったいじめ・性的虐待事件を基に作られた映画『無聲』は、健常者の世界に刃を突きつける物語だ。これが実話だという事実に驚かされる。いじめ・性的虐待が物語の「大前提」でしかないという衝撃と、「性的虐待の方がマシ」という選択を躊躇せず行う少女のあまりの絶望を描き出す
あわせて読みたい
【狂気】”友好”のために北朝鮮入りした監督が撮った映画『ザ・レッド・チャペル』が映す平壌の衝撃
倫理的な葛藤を物ともせず、好奇心だけで突き進んでいくドキュメンタリー監督マッツ・ブリュガーが北朝鮮から「出禁」を食らう結果となった『ザ・レッド・チャペル』は、「友好」を表看板に北朝鮮に潜入し、その「日常」と「非日常」を映し出した衝撃作
あわせて読みたい
【現実】権力を乱用する中国ナチスへの抵抗の最前線・香港の民主化デモを映す衝撃の映画『時代革命』
2019年に起こった、逃亡犯条例改正案への反対運動として始まった香港の民主化デモ。その最初期からデモ参加者たちの姿をカメラに収め続けた。映画『時代革命』は、最初から最後まで「衝撃映像」しかない凄まじい作品だ。この現実は決して、「対岸の火事」ではない
あわせて読みたい
【愛】ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督の“衝撃の出世作”である映画『灼熱の魂』の凄さ。何も語りたくない
映画館で流れた予告映像だけで観ることを決め、他になんの情報も知らないまま鑑賞した映画『灼熱の魂』は、とんでもない映画だった。『DUNE/デューン 砂の惑星』『ブレードランナー 2049』など有名作を監督してきたドゥニ・ヴィルヌーヴの衝撃の出世作については、何も語りたくない
あわせて読みたい
【歴史】『大地の子』を凌駕する中国残留孤児の現実。中国から奇跡的に”帰国”した父を城戸久枝が描く:…
文化大革命の最中、国交が成立していなかった中国から自力で帰国した中国残留孤児がいた。その娘である城戸久枝が著した『あの戦争から遠く離れて』は、父の特異な体験を起点に「中国残留孤児」の問題に分け入り、歴史の大きなうねりを個人史として体感させてくれる作品だ
あわせて読みたい
【衝撃】洗脳を自ら脱した著者の『カルト脱出記』から、「社会・集団の洗脳」を避ける生き方を知る
「聖書研究に熱心な日本人証人」として「エホバの証人」で活動しながら、その聖書研究をきっかけに自ら「洗脳」を脱した著者の体験を著した『カルト脱出記』。広い意味での「洗脳」は社会のそこかしこに蔓延っているからこそ、著者の体験を「他人事」だと無視することはできない
あわせて読みたい
【感想】リドリー・スコット監督の映画『最後の決闘裁判』から、社会が”幻想”を共有する背景とその悲劇…
例えば、「1万円札」というただの紙切れに「価値を感じる」のは、社会の構成員が同じ「共同幻想」の中に生きているからだ。リドリー・スコット監督の映画『最後の決闘裁判』は、「強姦では妊娠しない」「裁判の勝者を決闘で決する」という社会通念と、現代にも通じる「共同幻想」の強さを描き出す
あわせて読みたい
【衝撃】権力の濫用、政治腐敗を描く映画『コレクティブ』は他人事じゃない。「国家の嘘」を監視せよ
火災で一命を取り留め入院していた患者が次々に死亡した原因が「表示の10倍に薄められた消毒液」だと暴き、国家の腐敗を追及した『ガゼタ』誌の奮闘を描く映画『コレクティブ 国家の嘘』は、「権力の監視」が機能しなくなった国家の成れの果てが映し出される衝撃作だ
あわせて読みたい
【驚愕】キューバ危機の裏側を描くスパイ映画『クーリエ』。核戦争を回避させた民間人の衝撃の実話:『…
核戦争ギリギリまで進んだ「キューバ危機」。その陰で、世界を救った民間人がいたことをご存知だろうか?実話を元にした映画『クーリエ:最高機密の運び屋』は、ごく普通のセールスマンでありながら、ソ連の膨大な機密情報を盗み出した男の信じがたい奮闘を描き出す
あわせて読みたい
【日常】難民問題の現状をスマホで撮る映画。タリバンから死刑宣告を受けた監督が家族と逃避行:『ミッ…
アフガニスタンを追われた家族4人が、ヨーロッパまで5600kmの逃避行を3台のスマホで撮影した映画『ミッドナイト・トラベラー』は、「『難民の厳しい現実』を切り取った作品」ではない。「家族アルバム」のような「笑顔溢れる日々」が難民にもあるのだと想像させてくれる
あわせて読みたい
【衝撃】『殺人犯はそこにいる』が実話だとは。真犯人・ルパンを野放しにした警察・司法を信じられるか?
タイトルを伏せられた覆面本「文庫X」としても話題になった『殺人犯はそこにいる』。「北関東で起こったある事件の取材」が、「私たちが生きる社会の根底を揺るがす信じがたい事実」を焙り出すことになった衝撃の展開。まさか「司法が真犯人を野放しにする」なんてことが実際に起こるとは。大げさではなく、全国民必読の1冊だと思う
あわせて読みたい
【信念】水俣病の真実を世界に伝えた写真家ユージン・スミスを描く映画。真実とは「痛みへの共感」だ:…
私はその存在をまったく知らなかったが、「水俣病」を「世界中が知る公害」にした報道写真家がいる。映画『MINAMATA―ミナマタ―』は、水俣病の真実を世界に伝えたユージン・スミスの知られざる生涯と、理不尽に立ち向かう多くの人々の奮闘を描き出す
あわせて読みたい
【実話】映画『アウシュビッツ・レポート』が描き出す驚愕の史実。世界はいかにホロコーストを知ったのか?
映画『アウシュヴィッツ・レポート』は、アウシュビッツ強制収容所から抜け出し、詳細な記録と共にホロコーストの実態を世界に明らかにした実話を基にした作品。2人が持ち出した「アウシュビッツ・レポート」こそが、ホロコーストについて世界が知るきっかけだったのであり、そんな史実をまったく知らなかったことにも驚かされた
あわせて読みたい
【凄絶】北朝鮮の”真実”を描くアニメ映画。強制収容所から決死の脱出を試みた者が語る驚愕の実態:『ト…
在日コリアン4世の監督が、北朝鮮脱北者への取材を元に作り上げた壮絶なアニメ映画『トゥルーノース』は、私たちがあまりに恐ろしい世界と地続きに生きていることを思い知らせてくれる。最低最悪の絶望を前に、人間はどれだけ悪虐になれてしまうのか、そしていかに優しさを発揮できるのか。
あわせて読みたい
【弾圧】香港デモの象徴的存在デニス・ホーの奮闘の歴史。注目の女性活動家は周庭だけじゃない:映画『…
日本で香港民主化運動が報じられる際は周庭さんが取り上げられることが多いが、香港には彼女よりも前に民主化運動の象徴的存在として認められた人物がいる。映画『デニス・ホー ビカミング・ザ・ソング』の主人公であるスター歌手の激動の人生を知る
あわせて読みたい
【勇敢】ユダヤ人を救った杉原千畝を描く映画。日本政府の方針に反しながら信念を貫いた男の生き様
日本政府の方針に逆らってまでユダヤ人のためにビザを発給し続けた外交官を描く映画『杉原千畝』。日本を良くしたいと考えてモスクワを夢見た青年は、何故キャリアを捨てる覚悟で「命のビザ」を発給したのか。困難な状況を前に、いかに決断するかを考えさせられる
あわせて読みたい
【感想】映画『野火』は、戦争の”虚しさ”をリアルに映し出す、後世に受け継がれるべき作品だ
「戦争の悲惨さ」は様々な形で描かれ、受け継がれてきたが、「戦争の虚しさ」を知る機会はなかなかない。映画『野火』は、第二次世界大戦中のフィリピンを舞台に、「敵が存在しない戦場で”人間の形”を保つ困難さ」を描き出す、「虚しさ」だけで構成された作品だ
あわせて読みたい
【葛藤】正義とは何かを突きつける戦争映画。80人を救うために1人の少女を殺すボタンを押せるか?:『ア…
「80人の命を救うために、1人の少女の命を奪わなければならない」としたら、あなたはその決断を下せるだろうか?会議室で展開される現代の戦争を描く映画『アイ・イン・ザ・スカイ』から、「誤った問い」に答えを出さなければならない極限状況での葛藤を理解する
あわせて読みたい
【残念】日本の「難民受け入れ」の現実に衝撃。こんな「恥ずべき国」に生きているのだと絶望させられる…
日本の「難民認定率」が他の先進国と比べて異常に低いことは知っていた。しかし、日本の「難民」を取り巻く実状がこれほど酷いものだとはまったく知らなかった。日本で育った2人のクルド人難民に焦点を当てる映画『東京クルド』から、日本に住む「難民」の現実を知る
あわせて読みたい
【驚異】信念を貫く勇敢さを、「銃を持たずに戦場に立つ」という形で示した実在の兵士の凄まじさ:映画…
第二次世界大戦で最も過酷な戦場の1つと言われた「前田高地(ハクソー・リッジ)」を、銃を持たずに駆け回り信じがたい功績を残した衛生兵がいた。実在の人物をモデルにした映画『ハクソー・リッジ』から、「戦争の悲惨さ」だけでなく、「信念を貫くことの大事さ」を学ぶ
あわせて読みたい
【不正義】正しく行使されない権力こそ真の”悪”である。我々はその現実にどう立ち向かうべきだろうか:…
権力を持つ者のタガが外れてしまえば、市民は為す術がない。そんな状況に置かれた時、私たちにはどんな選択肢があるだろうか?白人警官が黒人を脅して殺害した、50年前の実際の事件をモチーフにした映画『デトロイト』から、「権力による不正義」の恐ろしさを知る
あわせて読みたい
【矛盾】死刑囚を「教誨師」視点で描く映画。理解が及ばない”死刑という現実”が突きつけられる
先進国では数少なくなった「死刑存置国」である日本。社会が人間の命を奪うことを許容する制度は、果たして矛盾なく存在し得るのだろうか?死刑確定囚と対話する教誨師を主人公に、死刑制度の実状をあぶり出す映画『教誨師』から、死刑という現実を理解する
あわせて読みたい
【実話】障害者との接し方を考えさせる映画『こんな夜更けにバナナかよ』から”対等な関係”の大事さを知る
「障害者だから◯◯だ」という決まりきった捉え方をどうしてもしてしまいがちですが、『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』の主人公・鹿野靖明の生き様を知れば、少しは考え方が変わるかもしれません。筋ジストロフィーのまま病院・家族から離れて“自活”する決断をした驚異の人生
あわせて読みたい
【勇敢】”報道”は被害者を生む。私たちも同罪だ。”批判”による”正義の実現”は正義だろうか?:『リチャ…
「爆弾事件の被害を最小限に食い止めた英雄」が、メディアの勇み足のせいで「爆弾事件の犯人」と報じられてしまった実話を元にした映画『リチャード・ジュエル』から、「他人を公然と批判する行為」の是非と、「再発防止という名の正義」のあり方について考える
あわせて読みたい
【人生】どう生きるべきかは、どう死にたいかから考える。死ぬ直前まで役割がある「理想郷」を描く:『…
「近隣の村から『姥捨て』と非難される理想郷」を描き出す『でんでら国』は、「死ぬ直前まで、コミュニティの中で役割が存在する」という世界で展開される物語。「お金があっても決して豊かとは言えない」という感覚が少しずつ広まる中で、「本当の豊かさ」とは何かを考える
あわせて読みたい
【告発】アメリカに”監視”される社会を暴露したスノーデンの苦悩と決断を映し出す映画:『スノーデン』…
NSA(アメリカ国家安全保障局)の最高機密にまでアクセスできたエドワード・スノーデンは、その機密情報を持ち出し内部告発を行った。「アメリカは世界中の通信を傍受している」と。『シチズンフォー』と『スノーデン』の2作品から、彼の告発内容とその葛藤を知る
あわせて読みたい
【史実】太平洋戦争末期に原爆を落としたアメリカは、なぜ終戦後比較的穏やかな占領政策を取ったか?:…
『八月十五日に吹く風』は小説だが、史実を基にした作品だ。本作では、「終戦直前に原爆を落としながら、なぜ比較的平穏な占領政策を行ったか?」の疑問が解き明かされる。『源氏物語』との出会いで日本を愛するようになった「ロナルド・リーン(仮名)」の知られざる奮闘を知る
あわせて読みたい
【絶望】「人生上手くいかない」と感じる時、彼を思い出してほしい。壮絶な過去を背負って生きる彼を:…
「北九州連続監禁殺人事件」という、マスコミも報道規制するほどの残虐事件。その「主犯の息子」として生きざるを得なかった男の壮絶な人生。「ザ・ノンフィクション」のプロデューサーが『人殺しの息子と呼ばれて』で改めて取り上げた「真摯な男」の生き様と覚悟
あわせて読みたい
【観察者】劣等感や嫉妬は簡単に振り払えない。就活に苦しむ若者の姿から学ぶ、他人と比べない覚悟:『…
朝井リョウの小説で、映画化もされた『何者』は、「就活」をテーマにしながら、生き方やSNSとの関わり方などについても考えさせる作品だ。拓人の、「全力でやって失敗したら恥ずかしい」という感覚から生まれる言動に、共感してしまう人も多いはず
あわせて読みたい
【あらすじ】子どもは大人よりずっと大人だ。「子ども扱い」するから、「子どもの枠」から抜け出せない…
宮部みゆき『ソロモンの偽証』は、その分厚さ故になかなか手が伸びない作品だろうが、「長い」というだけの理由で手を出さないのはあまりにももったいない傑作だ。「中学生が自前で裁判を行う」という非現実的設定をリアルに描き出すものすごい作品
あわせて読みたい
【逸話】天才数学者ガロアが20歳で決闘で命を落とすまでの波乱万丈。時代を先駆けた男がもし生きていた…
現代数学に不可欠な「群論」をたった1人で生み出し、20歳という若さで決闘で亡くなったガロアは、その短い生涯をどう生きたのか?『ガロア 天才数学者の生涯』から、数学に関心を抱くようになったきっかけや信じられないほどの不運が彼の人生をどう変えてしまったのか、そして「もし生きていたらどうなっていたのか」を知る
あわせて読みたい
【あらすじ】人生行き詰まってなお「生きたい」と思えるか?環境の激変を受け入れる難しさと生きる悲し…
勤務していた会社の都合で、町が1つ丸々無くなるという経験をし、住居を持たないノマド生活へと舵を切った女性を描く映画『ノマドランド』を通じて、人生の大きな変化に立ち向かう気力を持てるのか、我々はどう生きていくべきか、などについて考える
あわせて読みたい
【現実】生きる気力が持てない世の中で”働く”だけが人生か?「踊るホームレスたち」の物語:映画『ダン…
「ホームレスは怠けている」という見方は誤りだと思うし、「働かないことが悪」だとも私には思えない。振付師・アオキ裕キ主催のホームレスのダンスチームを追う映画『ダンシングホームレス』から、社会のレールを外れても許容される社会の在り方を希求する
あわせて読みたい
【驚愕】「金正男の殺人犯」は”あなた”だったかも。「人気者になりたい女性」が陥った巧妙な罠:映画『…
金正男が暗殺された事件は、世界中で驚きをもって報じられた。その実行犯である2人の女性は、「有名にならないか?」と声を掛けられて暗殺者に仕立て上げられてしまった普通の人だ。映画『わたしは金正男を殺していない』から、危険と隣り合わせの現状を知る
あわせて読みたい
【葛藤】「多様性を受け入れること」は難しい。映画『アイヌモシリ』で知る、アイデンティティの実際
「アイヌの町」として知られるアイヌコタンの住人は、「アイヌ語を勉強している」という。観光客のイメージに合わせるためだ。映画『アイヌモシリ』から、「伝統」や「文化」の継承者として生きるべきか、自らのアイデンティティを意識せず生きるべきかの葛藤を知る
あわせて読みたい
【排除】「分かり合えない相手」だけが「間違い」か?想像力の欠如が生む「無理解」と「対立」:映画『…
「共感」が強すぎる世の中では、自然と「想像力」が失われてしまう。そうならないようにと意識して踏ん張らなければ、他人の価値観を正しく認めることができない人間になってしまうだろう。映画『ミセス・ノイズィ』から、多様な価値観を排除しない生き方を考える
あわせて読みたい
【幻想】心の傷を癒やすことの”難しさ”、寄り添い続けるために必要な”弱さ”と”冷たさ”:映画『心の傷を…
「優しいかどうか」が重要な要素として語られる場面が多いと感じるが、私は「優しさ」そのものにはさしたる意味はないと考えている。映画『心の傷を癒すということ 劇場版』から、「献身」と「優しさ」の違いと、誰かに寄り添うために必要な「弱さ」を理解する
あわせて読みたい
【実話】正論を振りかざす人が”強い”社会は窮屈だ。映画『すばらしき世界』が描く「正解の曖昧さ」
「SNSなどでの炎上を回避する」という気持ちから「正論を言うに留めよう」という態度がナチュラルになりつつある社会には、全員が全員の首を締め付け合っているような窮屈さを感じてしまう。西川美和『すばらしき世界』から、善悪の境界の曖昧さを体感する
あわせて読みたい
【対話】刑務所内を撮影した衝撃の映画。「罰則」ではなく「更生」を目指す環境から罪と罰を学ぶ:映画…
2008年に開設された新たな刑務所「島根あさひ社会復帰促進センター」で行われる「TC」というプログラム。「罰則」ではなく「対話」によって「加害者であることを受け入れる」過程を、刑務所内にカメラを入れて撮影した『プリズン・サークル』で知る。
あわせて読みたい
【絶望】子供を犯罪者にしないために。「異常者」で片付けられない、希望を見いだせない若者の現実:『…
2人を殺し、7人に重傷を負わせた金川真大に同情の余地はない。しかし、この事件を取材した記者も、私も、彼が殺人に至った背景・動機については理解できてしまう部分がある。『死刑のための殺人』をベースに、「どうしようもないつまらなさ」と共に生きる現代を知る
あわせて読みたい
【称賛?】日本社会は終わっているのか?日本在住20年以上のフランス人が本国との比較で日本を評価:『…
日本に住んでいると、日本の社会や政治に不満を抱くことも多い。しかし、日本在住20年以上の『理不尽な国ニッポン』のフランス人著者は、フランスと比べて日本は上手くやっていると語る。宗教や個人ではなく、唯一「社会」だけが善悪を決められる日本の特異性について書く
あわせて読みたい
【衝撃】森達也『A3』が指摘。地下鉄サリン事件を起こしたオウム真理教は社会を激変させた
「オウム真理教は特別だ、という理由で作られた”例外”が、いつの間にか社会の”前提”になっている」これが、森達也『A3』の主張の要点だ。異常な状態で続けられた麻原彰晃の裁判を傍聴したことをきっかけに、社会の”異様な”変質の正体を理解する。
あわせて読みたい
【衝撃】壮絶な戦争映画。最愛の娘を「産んで後悔している」と呟く母らは、正義のために戦場に留まる:…
こんな映画、二度と存在し得ないのではないかと感じるほど衝撃を受けた『娘は戦場で生まれた』。母であり革命家でもあるジャーナリストは、爆撃の続くシリアの街を記録し続け、同じ街で娘を産み育てた。「知らなかった」で済ませていい現実じゃない。
あわせて読みたい
【考察】世の中は理不尽だ。平凡な奴らがのさばる中で、”特別な私の美しい世界”を守る生き方:『オーダ…
自分以外は凡人、と考える主人公の少女はとてもイタい。しかし、世間の価値観と折り合わないなら、自分の美しい世界を守るために闘うしかない。中二病の少女が奮闘する『オーダーメイド殺人クラブ』をベースに、理解されない世界をどう生きるかについて考察する
あわせて読みたい
【異常】「助けて」と言えない。自己責任社会のしんどさと、我が子がホームレスである可能性:『助けて…
39歳で餓死した男性は、何故誰にも助けを求めなかったのか?異常な視聴率を叩き出した、NHK「クローズアップ現代」の特集を元に書かれた『助けてと言えない』をベースに、「自己責任社会」の厳しさと、若者が置かれている現実について書く。
あわせて読みたい
【救い】自殺を否定しない「笑える自殺本」。「自殺したい」ってもっと気軽に言える社会がいい:『自殺…
生きることがしんどくて、自殺してしまいたくなる気持ちを、私はとても理解できます。しかし世の中的には、「死にたい」と口にすることはなかなか憚られるでしょう。「自殺を決して悪いと思わない」という著者が、「死」をもっと気楽に話せるようにと贈る、「笑える自殺本」
あわせて読みたい
【勇敢】日本を救った吉田昌郎と、福島第一原発事故に死を賭して立ち向かった者たちの極限を知る:『死…
日本は、死を覚悟して福島第一原発に残った「Fukushima50」に救われた。東京を含めた東日本が壊滅してもおかしくなかった大災害において、現場の人間が何を考えどう行動したのかを、『死の淵を見た男』をベースに書く。全日本人必読の書
あわせて読みたい
【議論】安楽死のできない日本は「死ぬ権利」を奪っていると思う(合法化を希望している):『安楽死を…
私は、安楽死が合法化されてほしいと思っている。そのためには、人間には「死ぬ権利」があると合意されなければならないだろう。安楽死は時折話題になるが、なかなか議論が深まらない。『安楽死を遂げた日本人』をベースに、安楽死の現状を理解する
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
普通って何?【本・映画の感想】 | ルシルナ
人生のほとんどの場面で、「普通」「常識」「当たり前」に対して違和感を覚え、生きづらさを感じてきました。周りから浮いてしまったり、みんなが当然のようにやっているこ…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…



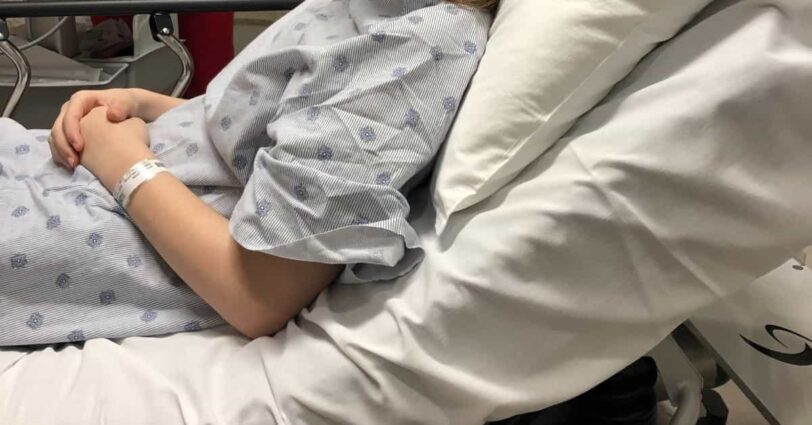
































































































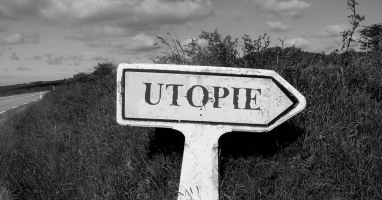



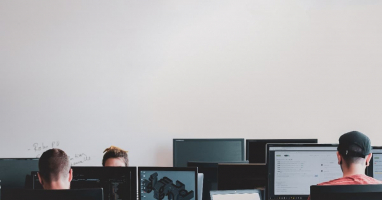











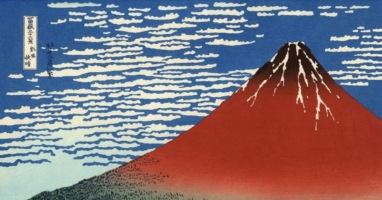










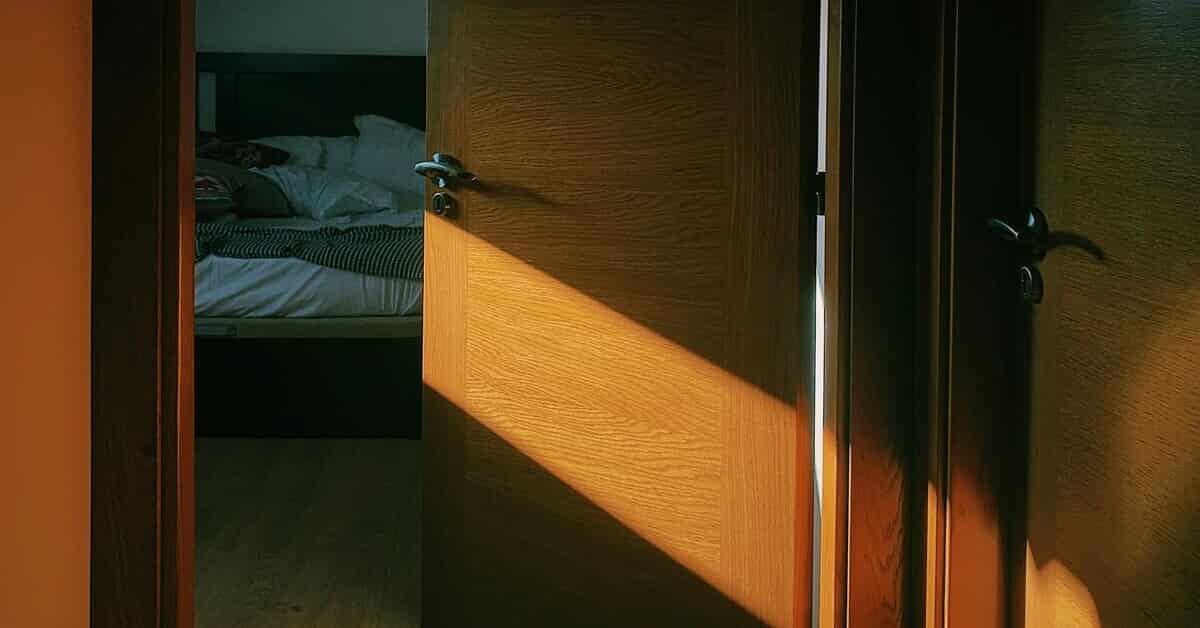





コメント