目次
はじめに
この記事で取り上げる映画
出演:細田佳央太, 出演:駒井蓮, 出演:新谷ゆづみ, 出演:真魚, 出演:細川岳, 出演:上大迫祐希, 出演:若杉凩, Writer:金子鈴幸, Writer:金子由里奈, 監督:金子由里奈, プロデュース:髭野純
 ポチップ
ポチップ
この映画をガイドにしながら記事を書いていくようだよ
今どこで観れるのか?
公式HPの劇場情報を御覧ください
この記事で伝えたいこと
「相手を辛い気持ちにさせたくないからぬいぐるみに話す」という設定がとにかく絶妙
私自身はぬいぐるみに話しかけたりしませんが、感覚的には凄く理解できると感じました
この記事の3つの要点
- 「マイノリティ」という言葉が使われる時のその「狭さ」に、私は違和感を覚えてしまうことが多い
- イベントサークルにも所属している登場人物が持ち込む「マジョリティ視点」こそが、この作品を成立させている
- 私が普段から強く意識している問題意識を含め、設定や導入からは想像できない展開に至る物語に驚かされた
「『優しさ』って何だっけ?」とも考えさせられる、他者との関係性を繊細に深掘りする見事な作品
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
記事中の引用は、映画館で取ったメモを参考にしているので、正確なものではありません
映画『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』はあまりに衝撃的だった。大げさではなく、現代を生きるあらゆる人に観てほしい教科書的作品
あわせて読みたい
【苦しい】「恋愛したくないし、興味ない」と気づいた女性が抉る、想像力が足りない社会の「暴力性」:…
「実は私は、恋愛的な関係を求めているわけじゃないかもしれない」と気づいた著者ムラタエリコが、自身の日常や専門学校でも学んだ写真との関わりを基に、「自分に相応しい関係性」や「社会の暴力性」について思考するエッセイ。久々に心にズバズバ刺さった、私にはとても刺激的な1冊だった。
メチャクチャ素晴らしい映画でした。ただ、友人からタイトルを聞くまで存在すら知らない作品だったし、そのままだったらまず観ることはなかっただろうと思います。また、普段から幅広く色んな映画に興味を示すようにしているつもりですが、それでも、『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』を観ようとは思わなかったかもしれません。なので教えてくれた友人に感謝しているし、こういう出会いがあるからこそ、「自分の興味関心だけで何かを選ぶのは良くない」と改めて実感させられた気もします。

まあその友人も、私に話をしてくれた時点ではまだ観てなかったんだけど
でも面白いことに、お互いに「これは観るべき映画だね」って感覚が共通したんだよね
ただ、冒頭からしばらくの間は正直、「一体ここから、どう物語が展開していくんだ?」みたいに感じていました。そのような状態が、体感では1時間ぐらい続いたように思います。「ぬいぐるみに話しかける」ことが活動内容の大学サークルを舞台にした物語であり、最初は「ちょっと変わった青春モノなのか?」ぐらいの印象でした。ただ中盤から後半に掛けて物語が大きく動き、「なるほど、そういう話なのか!」という展開になっていくのです。さらにその過程で、私の頭の中に普段からある問題意識に焦点が当てられることもあって、その刺さり具合はえげつないほどでした。
あわせて読みたい
【魅惑】バーバラ・ローデン監督・脚本・主演の映画『WANDA』の、70年代の作品とは思えない今感
映画館で観た予告が気になって、それ以外の情報を知らずに観に行った映画『WANDA』なんと70年代の映画だと知って驚かされた。まったく「古さ」を感じなかったからだ。主演だけでなく、監督・脚本も務めたバーバラ・ローデンが遺した、死後評価が高まった歴史的一作
とにかく、映画全体が描こうとしている「何か」にとても共感できてしまったのです。普段あまりこんな風には思わないのですが、「この映画の監督や脚本家とメチャクチャ喋りたい」という感じになりました。
あくまで予想だけど、こういう作品を作る人とは、永遠に喋っていられそうな気がする
日常生活の中で話しても通じないことの方が多い話題だったりするから、余計にね
映画『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』の内容紹介
七森剛志は京都の大学に入学した。彼は「男らしい振る舞い」みたいなものにどうしても違和感を覚えてしまうことが多く、そのせいで高校時代にも「不器用な瞬間」を経験している。自分自身の存在やアイデンティティがあやふやで、彼自身モヤモヤすることが多いのだが、かといって、自身のスタンスが「間違っている」と思っているわけでもない。
あわせて読みたい
【感想】おげれつたなか『エスケープジャーニー』は、BLでしか描けない”行き止まりの関係”が絶妙
おげれつたなか『エスケープジャーニー』のあらすじ紹介とレビュー。とにかく、「BLでしか描けない関係性」が素晴らしかった。友達なら完璧だったのに、「恋人」ではまったく上手く行かなくなってしまった直人と太一の葛藤を通じて、「進んでも行き止まり」である関係にどう向き合うか考えさせられる
そんな七森は、学科の懇親会でとある女性と意気投合した。麦戸と名乗ったその女性とは、空気感が似ている感じがする。「男らしさ」みたいなことを感じずに一緒にいられる心地良さがあり、すぐに仲良くなった。
2人は、学内に貼られたサークル募集のポスターを見ながら、「ぬいぐるみサークル(ぬいサー)」に目を留める。ぬいぐるみと喋るサークルらしいが、良く分からない。とりあえず見学に行くと、まさにそのままのサークルだった。部室には大量のぬいぐるみがあり、部員たちはそれぞれぬいぐるみに何か話しかけている。部室にいる時は、基本的にヘッドホンをするのがルール。他の部員がぬいぐるみに何を話しているのかを聞かないようにするためだ。
2人はぬいサーに入ることに決めた。そして、同じタイミングで入った白城ゆいも含め、ぬいサーのメンバーと仲良くなっていく。
ぬいサーの部員たちがそれぞれに秘めている秘密や葛藤、ぬいサーに所属しながらぬいぐるみには話しかけない白城、唐突に提示される「不在」、そして七森が抱えているどうにもしようがない「息苦しさ」。様々な要素を取り込みつつ、世間の「それって当たり前だよね」からするりと抜け落ちてしまう者たちが、「他者といかに関わるか」に悩む様が描き出されていく。
あわせて読みたい
【あらすじ】「愛されたい」「必要とされたい」はこんなに難しい。藤崎彩織が描く「ままならない関係性…
好きな人の隣にいたい。そんなシンプルな願いこそ、一番難しい。誰かの特別になるために「異性」であることを諦め、でも「異性」として見られないことに苦しさを覚えてしまう。藤崎彩織『ふたご』が描き出す、名前がつかない切実な関係性
「人と話すのが難しいからぬいぐるみに話す」という設定の絶妙さ
さて、いきなり本作とは関係のない話から始めましょう。

本作を観るちょうど前の日の夜、寝ようかなと思っていた直前に女友達からLINEが来ました。ざっくり要約すれば、「生きづらくてしんどい」という内容です。さらにそのLINEには、「こんなマイナスな話は人を不愉快にするだけですよねすいません」「休みの前の日なのにこんな話してごめんなさい」みたいなことも書かれていました。その子は時々メンタルが落ちたような状態になるので、「しんどい感情は、出せる時に出せるだけ出しておいた方がいいよ」みたいに言うようにしています。
あわせて読みたい
【考察】A24のホラー映画『TALK TO ME』が描くのは、「薄く広がった人間関係」に悩む若者のリアルだ
「A24のホラー映画史上、北米最高興収」と謳われる『TALK TO ME トーク・トゥ・ミー』は、一見「とても分かりやすいホラー映画」である。しかし真のテーマは「SNS過剰社会における人間関係の困難さ」なのだと思う。結果としてSNSが人と人との距離を遠ざけてしまっている現実を、ホラー映画のスタイルに落とし込んだ怪作
私は、割とこういう「辛いんです」「話を聞いて下さい」みたいな相談を聞く機会が結構ある
さて、彼女は本心から「こんな話してすいません」みたいに思っているわけですが、同時に、「誰かに話を聞いてもらわずにはいられない」という状態にもあるわけです。そしてそういう時、自分で言うのも何ですが、私は結構「喋りやすい相手」なのだと思います。というか昔から、「こいつには何でも話せる」みたいな雰囲気を醸し出せるように頑張ってきたつもりなので、そういう意識的な振る舞いがきっと上手くいっているのでしょう。
そして、これも「自分で言うのも何ですが」という話なのですが、私のように「何を話しても大丈夫」みたいな雰囲気の人は、なかなかいないと思います(本当に、こんなこと自分では言いたくないのですが)。私は色んな人から、「他人に相談して失敗した話」を聞く機会もあるのですが、やはり「誰かの相談事を、その人が望むようなスタンスで聞く」というのは、かなり難しいことみたいです。特に「マイノリティ的マインドを持つ人」の場合、マジョリティ側の人に話が通じないのは当然として、マイノリティ同士でも、問題や葛藤が重ならないと上手く話が通じなかったりもするでしょう。そんなわけで、「自分の話を良い感じに聞いてくれる人」を見つけるのはかなり難しいのだと思います。
私も、「この人になら話してもいいな」みたいに感じる人って、相当限られるからなぁ
大体の場合、「話してはみたものの、この人には何も伝わってないな」って感じちゃうよね
あわせて読みたい
【おすすめ】カンヌ映画『PERFECT DAYS』は、ほぼ喋らない役所広司の沈黙が心地よい(ヴィム・ヴェンダ…
役所広司主演映画『PERFECT DAYS』(ヴィム・ヴェンダース監督)は、主人公・平山の「沈黙」がとにかく雄弁な物語である。渋谷区のトイレの清掃員である無口な平山の、世間とほとんど繋がりを持たない隔絶した日常が、色んなものを抱えた者たちを引き寄せ、穏やかさで満たしていく様が素晴らしい
だからこそ、「ぬいぐるみに話す」という設定は非常に絶妙だと感じました。もちろん、「人と話すのが難しいからぬいぐるみに話す」というのは決してベストな方法ではないでしょうが、かなりベターなやり方だとは思います。
さらに、「ぬいぐるみに話すこと」の良さとしては「話す側の負担が減る」という点も挙げられるでしょう。というのも、私にLINEをくれた子のように、「こんな話をして申し訳ない」みたいに感じてしまう人は結構いるからです。あるいは、作中でぬいサーのメンバーが口にした、「誰かに辛い話を聞いてもらうと、その相手のことを辛い気持ちにさせてしまう。だからぬいぐるみに聞いてもらうんだ」というセリフも印象的でした。「『上手く話を聞いてくれる人』を探すのは難しいから、『誰にも負担をかけずに済む方法』を選択する」というのは、理にかなっていると言えるでしょう。
そんなわけで、「ぬいぐるみに話す」というこの設定はとても絶妙だと思うし、さらに私は本作の随所でそのような「絶妙さ」を感じました。設定も登場人物のキャラクターも物語の展開もすべて良いのですが、中でもやはり「会話」が素晴らしかったなと思います。「沈黙」や「間」も含めた彼らの会話がもう「絶妙」としか言えないもので、会話を聞いているだけでも心地よさを感じるような作品でした。是非観てほしいなと思います。
ストーリーがほとんどないような作品でも、会話が素敵だったら全然観れちゃう
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『アンダーカレント』(今泉力哉)は、失踪をテーマに「分かり合えなさ」を描く
映画『アンダーカレント』において私は、恐らく多くの人が「受け入れがたい」と感じるだろう人物に共感させられてしまった。また本作は、「他者を理解すること」についての葛藤が深掘りされる作品でもある。そのため、私が普段から抱いている「『他者のホントウ』を知りたい」という感覚も強く刺激された
「マイノリティ」という言葉の「狭さ」
本作を観ながら、普段から問題意識を抱いている様々な事柄について改めて考えさせられました。その1つが「『マイノリティ』という言葉の『狭さ』」です。私は「『マイノリティ』という言葉が使われる状況で、『なんか違うんだよなぁ』という違和感を抱いてしまう」ことが多く、その点についての思考が刺激されました。
「マイノリティ」という言葉は一般的に、「『分かりやすい何か』を持っている人」という意味で使われることが多いと思います。「分かりやすい何か」というのはつまり、「障害者」「LGBTQ」などのことです。大雑把に、「『名称が与えられている概念』のことを『分かりやすい何か』と呼んでいる」と考えてもらえばいいでしょう。

あわせて読みたい
【あらすじ】映画『夕方のおともだち』は、「私はこう」という宣言からしか始まらない関係性の”純度”を描く
「こんな田舎にはもったいないほどのドM」と評された男が主人公の映画『夕方のおともだち』は、SM嬢と真性ドMの関わりを通じて、「宣言から始まる関係」の難しさを描き出す。「普通の世界」に息苦しさを感じ、どうしても馴染めないと思っている人に刺さるだろう作品
誤解されたくないのであらかじめ書いておきますが、私は決して、「障害者やLGBTQは『分かりやすいマイノリティ』である」などと言っているのではありません。そうではなく、「いわゆる『マジョリティ』の人たちが『マイノリティ』という言葉を使う時には、『障害者』や『LGBTQ』のような『名称が与えられている概念』しか想定してないんじゃないだろうか」と疑問を呈したいのです。そしてそういう状況に出くわす度に、「それは何か違うんじゃないか」と感じてしまいます。
もっと酷い言い方をするなら、「自分には理解できないもの」って意味で「マイノリティ」って言葉を使ってる人もいるんじゃないかと思ってる
そういう「『分かりやすい何か』を持っている人」はもちろん「マイノリティ」に含めていいでしょう。「含めていいでしょう」と書いたのは、「『分かりやすい何か』を持っている人」の中にも「『マイノリティ』に分類されたくないと思っている人」が一定数いると考えているからです。私は基本的に、「マイノリティか否か」を決めるのは「その人の気分」だと思っているので、「分かりやすい何か」を持っていたとしても、マインドが「マイノリティ」でなければ、私の中でその人は「マイノリティ」ではありません。
さて一方で、「マイノリティだなぁ」と感じる人の中には、「分かりやすい何か」を持っていない人もいます。私の判断はやはり「気分(マインド)」基準なので、たとえ「容姿に恵まれ、大金持ちで、友人も多く、何不自由なく暮らしている人」であっても、その人のマインドが「マイノリティ」なら、私の中では「マイノリティ」です。実際私の友人にも、「どう考えても見た目や行動が『リア充』なのに、マインドは明らかに『マイノリティ』」という人がいて、私は彼女を「マイノリティ」に分類しています。
あわせて読みたい
【感想】映画『正欲』に超共感。多様性の時代でさえどこに行っても馴染めない者たちの業苦を抉る(出演…
映画『正欲』は、私には共感しかない作品だ。特に、新垣結衣演じる桐生夏月と磯村勇斗演じる佐々木佳道が抱える葛藤や息苦しさは私の内側にあるものと同じで、その描かれ方に圧倒されてしまった。「『多様性』には『理解』も『受け入れ』も不要で、単に否定しなければ十分」なのだと改めて思う
一応書いておくけど、今私が言っている「マイノリティか否か」って話は、法律が絡むような厳密な場面に当てはまることじゃない
そうじゃなくて、「どういう人のことを『マイノリティ』だと感じるか」っていう、個人の感覚の話だよね
そしてぬいサーの面々はまさに、そのような「分かりやすい何か」を持たない「マイノリティ」なのです。部員の中に1人だけ「分かりやすい何か」を持っていると言える人がいますが、他のメンバーは「名称が与えられている概念」とは接していないと言っていいでしょう。しかし間違いなくマインドは「マイノリティ」であり、だからこそ私の中では、彼らは皆「マイノリティ」なのです。
そして、いわゆる「マジョリティ」の人たちが「マイノリティ」という言葉を使う場合、ぬいサーの部員のような人たちのことはきっと頭に浮かんでいない気がします。特に、「マイノリティ」という言葉を「自分たちとは違う」という含みを持たせて使っているとしたら、違いが分かりやすい「名称が与えられている概念」しか捉えられないのも当然でしょう。ただ個人的には、「マイノリティ」という言葉のこの「狭さ」こそが色んな息苦しさや無理解を生み出す要因なのではないかと考えているし、本作を観て改めてそのように感じさせられました。
もちろん、「マジョリティ」側としてずっと生きてきたとしたら、同じ状況にいただろうけどね
「マイノリティが抱える問題」って結局、「マジョリティがどう振る舞うか」によってしか変わらない部分も結構あるから、難しいだろうけど、この「狭さ」が解消されてほしいなとは思う
あわせて読みたい
【感想】映画『キリエのうた』(岩井俊二)はアイナ・ジ・エンドに圧倒されっ放しの3時間だった(出演:…
映画『キリエのうた』(岩井俊二監督)では、とにかくアイナ・ジ・エンドに圧倒されてしまった。歌声はもちろんのことながら、ただそこにいるだけで場を支配するような存在感も凄まじい。全編に渡り「『仕方ないこと』はどうしようもなく起こるんだ」というメッセージに溢れた、とても力強い作品だ
「マジョリティ視点」こそが、この映画を成立させているポイントである
さて、本作『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』において実に興味深かった点は、作品の中にきちんと「マジョリティ視点」が含まれていたことです。ぬいサーという「マイノリティのための場所」と言ってもいい空間を舞台にしながら、そこに無理なく「マジョリティ視点」を入れ込む作りはとても見事だったなと思います。そして、その「マジョリティ視点」のキーパーソンこそが、ぬいサーのメンバーである白城ゆいであり、私には、「本作は白城ゆいの存在によって成立していると言っても過言ではない」と感じられました。

白城はぬいサーだけではなく、イベントサークルにも所属しています。そのイベントサークルについてはあまり詳しくは描かれませんが、彼女は「セクハラまがいのことも多い」と口にしていました。「『リア充の大学生』をステレオタイプ的にイメージする際、頭に思い浮かぶような人がたくさんいる集団」みたいに理解しておけばたぶん大きくは外れないでしょう。
あわせて読みたい
【嫌悪】映画『ドライビング・バニー』が描く、人生やり直したい主人公(母親)のウザさと絶望
映画『ドライビング・バニー』は、主人公であるバニーのことが最後まで嫌いだったにも拘わらず、全体的にはとても素敵に感じられた珍しいタイプの作品だ。私は、「バニーのような人間が世の中に存在する」という事実に嫌悪感を抱いてしまうのだが、それでも、狂気的でぶっ飛んだラストシーンによって、作品全体の印象が大きく変わったと言える
まあ、大体のマイノリティが、そういうタイプを苦手だって思うだろうね
白城は本作全体において「客観視」的な立ち位置を取ることが多いため、彼女自身はそこまで深くは描かれません。なので、七森や麦戸と比べるとどんな人物なのか分かりにくいのですが、確実に言えることは、「超マイノリティ側の『ぬいサー』にも、超マジョリティ側の『イベントサークル』にもそれなりに馴染める人物」だということです。作中においては、「両者の視点を持ち得る唯一のキャラクター」だと言えるでしょう。
そして、白城の感覚や価値観を通じて、本作には「マジョリティ視点」が入り込むのです。「マイノリティ視点」だけではどうしてもバランスが悪くなるでしょうが、そこに白城の「マジョリティ視点」が組み込まれることで、ぬいサーの面々が抱える葛藤の輪郭が分かりやすくなり、全体として伝わりやすさが増していると感じました。
七森も麦戸もとてもいいけど、やっぱりキャラクターとしては、白城が一番良かったよね
私自身が割と、白城のような「バランサー」タイプだってことも、彼女のことが気になったポイントだと思うけど
あわせて読みたい
【危機】教員のセクハラは何故無くならない?資質だけではない、学校の構造的な問題も指摘する:『スク…
『スクールセクハラ なぜ教師のわいせつ犯罪は繰り返されるのか』では、自分が生徒に対して「権力」を持っているとは想像していなかったという教師が登場する。そしてこの「無自覚」は、学校以外の場でも起こりうる。特に男性は、読んで自分の振る舞いを見直すべきだ
さて本作には、彼女が七森に「どうしてセクハラまがいのイベントサークルなんかに所属しているのか?」と聞かれる場面があります。そして彼女はその問いに、「世の中は安心できる場所の方が少ないんだから、ぬいサーみたいな環境だけにいたら、生き抜けないほど弱くなってしまう」みたいに返していたのです。
その上で私は、「『こんな風に認識せざるを得ない』という事実こそが、世の中のあらゆる場面における『問題』の根本にあるんじゃないか」と考えています。「安心できる場所の方が少ない」と感じるのは、「そのまま社会を渡り歩くのはしんどいぐらい自分もマイノリティ側の人間だ」と認識しているからでしょう。そしてそれ故に、「『マジョリティの世界に潜り込める自分』を保っておかなければならない」と考えているわけです。こんな思考に囚われてしまう人は結構いるんじゃないかと思っています。
結局大体の問題って、「マジョリティ」とか「強い側」に「どう取り入るのか」みたいな話に集約されちゃうからなぁ
マイノリティは、「マイノリティである」が故に、どうしたって「マジョリティの社会」で生きていくしかないんだよね
そして結局、マジョリティの世界との関わりはどうしたって避けがたいわけで、その接点で様々な摩擦が生まれてしまうというわけです。
あわせて読みたい
【助けて】映画『生きててごめんなさい』は、「共依存カップル」視点で生きづらい世の中を抉る物語(主…
映画『生きててごめんなさい』は、「ちょっと歪な共依存関係」を描きながら、ある種現代的な「生きづらさ」を抉り出す作品。出版社の編集部で働きながら小説の新人賞を目指す園田修一は何故、バイトを9度もクビになり、一日中ベッドの上で何もせずに過ごす同棲相手・清川莉奈を”必要とする”のか?
「マジョリティ」が無意識に作り出している「制約」
本作に、その「摩擦」がとても印象的に描かれているシーンがありました。ぬいサーのメンバーで唯一「分かりやすい何か」を持つ人が、その「何か」をさらっと告白した場面で、こんな風に語っていたのです。
その場の言葉遣いが制約されたような感じがあった。「私は尊重してますよ」みたいな空気を出すの。なんか「自分自身」として見られていないような感じだった。

あわせて読みたい
【闘争】映画『あのこと』が描く、中絶が禁止だった時代と、望まぬ妊娠における圧倒的な「男の不在」
中絶が禁止されていた1960年代のフランスを舞台にした映画『あのこと』は、「望まぬ妊娠」をしてしまった秀才の大学生が、「未来を諦めない」ために中絶を目指す姿が描かれる。さらに、誰にも言えずに孤独に奮闘する彼女の姿が「男の不在」を強調する物語でもあり、まさに男が観るべき作品だ
具体性を排して説明しているので上手くイメージ出来ないかもしれませんが、私はとても共感させられました。
ホントにこういう感覚、私も日常的に抱くことがあるからなぁ
相手は良かれと思ってそういう振る舞いをしているわけだから、余計に厄介だよね
つまり、こういうことです。その人物はある状況で「言葉遣いが制約されたような感じ」になったわけですが、それは「名称が与えられた概念」としてしか見てもらえなくなったからだと思います。その人物の名前を仮に「山田田中」とすると、その人物は「山田田中」という個人ではなく、「『名称が与えられた概念』の人」でしかなくなってしまったというわけです。そして、「マジョリティがイメージするその『名称が与えられた概念』の範囲内の会話しか許容されなくない雰囲気になってしまった」ということなのでしょう(分かりにくいですよね。すいません)。
私もこのような感覚を抱くことが結構あります。私は別に「分かりやすい何か」を持っている人間ではないのですが、会話の中で、相手の反応から「こういうことは言わない方がいいんだろうな」という雰囲気を感じることがあるのです。私はそれでも敢えて話し続けたりしますが、「言葉遣いが制約された」と感じて言いたいことが言えなくなる人もいるだろうと思います。
あわせて読みたい
【理解】「多様性を受け入れる」とか言ってるヤツ、映画『炎上する君』でも観て「何も見てない」って知…
西加奈子の同名小説を原作とした映画『炎上する君』(ふくだももこ監督)は、「多様性」という言葉を安易に使いがちな世の中を挑発するような作品だ。「見えない存在」を「過剰に装飾」しなければならない現実と、マジョリティが無意識的にマイノリティを「削る」リアルを描き出していく
気を遣っているつもりなんだろうけど、「真逆の結果になってるよ」っていつも思っちゃう
さて、「LGBTQ」が分かりやすいと思いますが、世の中的に今、「LGBTQの人に言ってはいけないこと、やってはいけないこと」がかなり“マニュアル化”されつつある気がしないでしょうか。「こういう状況ではこうしましょう」みたいな対応が整備されつつあるように思います。良い風潮だとは感じますが、とはいえ人それぞれ受け取り方は様々です。一律化された「配慮」に違和感を覚える人がいてもおかしくありません。
また、LGBTQとは違いますが、「テレビの世界では女芸人の“ブサイクいじり”が許容されなくなり、“笑い”に出来なくなっている」みたいな話を聞いたことがあります。関係性や状況次第では、「ブサイク」という言葉を使っても問題ないはずです。しかし、世の中の「マニュアル化」の流れの方が強いせいで「ブサイク」という表現が一律で制約されているような気がするし、そんな状況にはどうしても違和感を覚えてしまいます。
もちろん、昔ほどではないとはいえテレビはまだまだ影響力のあるメディアなので、「テレビの世界で当然のように”ブサイクいじり”をすると、観ている人に悪影響を与えかねない」という理屈は理解できるし、間違っているとも思いません。ただ、そういう「外部への影響力」など微塵も関係ない状況でも、同じような「マニュアル化」が進んでいるような気がしているのです。私には「言葉狩り」にしか感じられないのですが、マジョリティはそのような振る舞いを「配慮」と表現して推し進めている感じがします。しかし結局それは、「目の前の個人」を見ているのではなく、「『名称が与えられた概念』の人」という捉え方をしているだけのことです。そしてそのようなスタンスは、むしろ「配慮」から遠ざかっているように思えてしまいます。
ちょっと前に観た映画『炎上する君』でも、似たような場面が描かれてたよね
居酒屋で、「私女子校だったから、レズとかには全然理解あるよ」とか言ってた登場人物がいたなぁ
あわせて読みたい
【理解】「多様性を受け入れる」とか言ってるヤツ、映画『炎上する君』でも観て「何も見てない」って知…
西加奈子の同名小説を原作とした映画『炎上する君』(ふくだももこ監督)は、「多様性」という言葉を安易に使いがちな世の中を挑発するような作品だ。「見えない存在」を「過剰に装飾」しなければならない現実と、マジョリティが無意識的にマイノリティを「削る」リアルを描き出していく
あるいは別の人物が、マジョリティに対するまたちょっと違う種類の違和感を次のような言葉で表現していたのも印象的でした。
ヤなこと言うヤツは、もっとヤなヤツであってくれ。
これも、具体的な状況を排してセリフだけを抜き出しているので上手く伝わらないとは思うのですが、私にはとても共感できました。このセリフは「良い人っぽいのに配慮に欠けたことを言ってくる」ということであり、要するに「マジョリティであれば誰でも、『無理解』や『配慮の無さ』を有している」みたいに理解すればいいでしょう。「マジョリティの一部」に問題があるのではなく、「無理解」や「配慮の無さ」は「マジョリティ」全体に薄く広く蔓延っているというわけです。この状況を何とかしようとしたら、「ミルクティーからミルクだけを取り除く」ような難しさがあるのだろうし、これも「マジョリティ」が生んでいる「制約」という感じがしました。

あわせて読みたい
【絶望】人生どん底から生き方を変える。映画『シスター 夏のわかれ道』が描く中国人女性の葛藤と諦念
両親の死をきっかけに、「見知らぬ弟」を引き取らなければならなくなった女性を描く映画『シスター 夏のわかれ道』は、中国の特異な状況を背景にしつつ、誰もが抱き得る普遍的な葛藤が切り取られていく。現状を打破するために北京の大学院を目指す主人公は、一体どんな決断を下すのか。
私の中にもある「ズルさ」が引きずり出される
前半から中盤に掛けてはこのように、「マイノリティを描くことによって、マジョリティへの違和感を浮き彫りにする」みたいな受け取り方をしていたのですが、後半に進むにつれて、また少し違った部分に焦点が当たるようになります。これもまた、私が普段から意識している問題の1つです。しかもそれは私自身の「ズルさ」とも関係しているため、「積極的には直視したくない」と感じるものでもありました。
映画の冒頭からは想像できないような物語の展開だよね
ここでも具体的な状況の説明は省きますが、そのことが描かれるシーンでは次のようなセリフが出てきます。
あわせて読みたい
【感想】是枝裕和監督映画『怪物』(坂元裕二脚本)が抉る、「『何もしないこと』が生む加害性」
坂元裕二脚本、是枝裕和監督の映画『怪物』は、3つの視点を通して描かれる「日常の何気ない光景」に、思いがけない「加害性」が潜んでいることを炙り出す物語だ。これは間違いなく、私たち自身に関わる話であり、むしろ「自分には関係ない」と考えている人こそが自覚すべき問題だと思う
でも結局のところ、傷つきたくて傷ついてるだけなんじゃないかって思うんだ。傷ついている自分は、加害者じゃないって思い込みたいだけなんじゃないかって。
このセリフは、なるべく見ないようにしている自身の「ズルさ」をズバッと指摘するものだったので、ちょっとドキッとさせられました。私は前々からこの「ズルさ」に気づいてはいたのでそこまでのダメージではなかったのですが、今まで気づかなかった人からすれば、「痛いところを突かれた」みたいな感覚になるんじゃないかと思います。
そして、さらに具体性を排して書きますが、このセリフの後に続く「私は◯◯だから……」という認識は、私が昔から対人関係において最も気をつけていたことであり、そんな話が展開されることにも驚かされました。この話は正直、自分の周りの同性に話してもまず話自体が通じません(もちろん、異性には通じます)。なので、そんな話が物語後半の核として描かれる展開にかなりビックリさせられたのでした。
「◯◯であること」自体が持つ加害性みたいなものに自覚的でない人ってメチャクチャ多いからなぁ
若い世代は大分変わってる感じするけど、同年代とかは「なにそれ?」って言って話を終わらせそうな感じだよね
あわせて読みたい
【衝撃】これが実話とは。映画『ウーマン・トーキング』が描く、性被害を受けた女性たちの凄まじい決断
映画『ウーマン・トーキング』の驚くべき点は、実話を基にしているという点だ。しかもその事件が起こったのは2000年代に入ってから。とある宗教コミュニティ内で起こった連続レイプ事件を機に村の女性たちがある決断を下す物語であり、そこに至るまでの「ある種異様な話し合い」が丁寧に描かれていく

私が「◯◯であること」はもはやどうやっても避けられないことであり、この状況に対処するとしたら、先述の「ミルクティーからミルクだけを取り除く」以上の難しさがあるかもしれません。ただそもそも、「ここに問題が内在している」という事実に気づかない人が多すぎるので、それ故に「無理解」や「配慮の無さ」が生まれていることもまた確かでしょう。私は普段から、そのようなある種の「加害性」を自覚しつつ生きているつもりですが、同時に、私が「◯◯であること」はほぼ変えようがないので、「他者からの見られ方」において難しさを感じることも結構あります。
また、これも具体的な状況説明なしでは理解しにくいでしょうが、
みんな笑いながらそういう話をするんだよ。真剣に話せない空気があるっていうか。
というセリフもとても印象的でした。本作を観る直前に、友人から似たような状況について話を聞いていたこともあり、余計刺さったのかもしれません。これは広く捉えるなら、「被害者を『被害者』と認識せずに済むための雰囲気作り」みたいな話であり、「ジャニー喜多川の性加害問題」を例に挙げるまでもなく、このような状況は社会のあちこちに蔓延っているでしょう。私はそのような雰囲気作りに加担しないように意識しているつもりですが、だからと言って、既に存在している雰囲気を無くすような行動が出来ているかと言えば、もちろんそんなことはありません。
あわせて読みたい
【壮絶】本当に「美人は得」か?「美しさ」という土俵を意識せざるを得ない少女・女性たちの現実:『自…
美醜で判断されがちな”ルッキズム”の世の中に刃を突きつける小説『自画像』。私自身は、「キレイな人もキレイな人なりの大変さを抱えている」と感じながら生きているつもりだが、やはりその辛さは理解されにくい。私も男性であり、ルッキズムに加担してないとはとても言えない
昨日もテレビのニュースで、セクハラ的な行為を指摘されている人が「冗談のつもりだった」みたいに言ってる映像を見たなぁ
そういうのを見る度に、「お前の『つもり』なんかクソどうでもいいんだよ」って感じちゃうよね
私は「◯◯であること」から逃れられはしないので、「気をつけていないと『加害側』になってしまうかもしれない」という自覚を常に持つようにしています。そして、私のように考える人が社会に増えることで、みんなが生きやすい世の中になるはずだと信じたいところです。
「優しさ」とは一体何を指すのか?
多くの人にとって、ぬいサーの面々は恐らく「とても奇妙な人たち」に見えるだろうと思います。あるいは、「ぬいぐるみに話すなんて気持ち悪い」みたいに受け取る人もいるかもしれません。しかし私は、特に「優しさ」に関していえば、ぬいサーのメンバーの方が世の中の大多数の人よりも「真っ当」だと思っています。
あわせて読みたい
【美麗】映画『CLOSE/クロース』はあまりにも切ない。「誰かの当たり前」に飲み込まれてしまう悲劇
子どもの頃から兄弟のように育った幼馴染のレオとレミの関係の変化を丁寧に描き出す映画『CLOSE/クロース』は、「自分自身で『美しい世界』を毀損しているのかもしれない」という話でもある。”些細な”言動によって、確かに存在したあまりに「美しい世界」があっさりと壊されてしまう悲哀が描かれる
作中では、色んな人が様々な場面で「優しさ」について言及していました。それらをここで取り上げたりはしませんが、私なりの捉え方を1つ書くと、「『私には優しくしなくていい』と相手に感じてもらえるように振る舞うこと」が「優しさ」だったりします。そしてそのようなスタンスは、広く括れば、ぬいサーの部員たちのものと同じだと言えるかもしれません。
「分かりやすく優しい振る舞いをされる」のとかって、かなり嫌いだもんね
「相手の優しさに気づいてしまう」ってのが、思いのほかしんどく感じられるんだよなぁ

さて、「どうしたら相手が『私には優しくしなくていい』と感じてくれるのか」は、その時々でまったく違うでしょう。つまり、「どんな状況なのかによって『優しい振る舞い』は異なる」というわけです。しかし私には、多くの人が「優しい振る舞い」を固定的に捉えているように感じられます。要するに「こういう時にはこうすればいい」みたいな発想であり、その上で、「そんな風に振る舞っていれば優しい」みたいに考えているように思えてしまうのです。
あわせて読みたい
【違和感】三浦透子主演映画『そばかす』はアセクシャルの生きづらさを描く。セクシャリティ理解の入り口に
「他者に対して恋愛感情・性的欲求を抱かないセクシャリティ」である「アセクシャル」をテーマにした映画『そばかす』は、「マイノリティのリアル」をかなり解像度高く映し出す作品だと思う。また、主人公・蘇畑佳純に共感できてしまう私には、「普通の人の怖さ」が描かれている映画にも感じられた
確かに、そういう生き方はシンプルで分かりやすいでしょう。「誕生日にプレゼントをくれたから優しい」とか、「ダイエットを頑張ったのに褒めてくれなかったから優しくない」みたいに、相手の行動だけから「優しさ」を判定出来るようになるからです。しかし私は、そんな想像力の欠如した捉え方が好きではありません。同じ行為が、ある人には「優しさ」として受け取られ、別の人にはそう受け取られないなんてことは当然起こり得るはずです。しかし、どうもそんな風には考えない人が多いような気がしています。
「優しさ」が「固定的な振る舞い」でしか判断されないんだとしたら、むしろ「優しさ」を発揮したくないって感じちゃうんだよなぁ
そして、そういう世の中に生きざるを得ないと分かっているからこそ、ぬいサーの面々はぬいぐるみに話しかけるのです。それは、「優しさ」を大いに履き違えた世界における「真っ当な振る舞い」だと私には思えるのですが、皆さんはどう感じるでしょうか?
あわせて読みたい
【誠実】戸田真琴は「言葉の人」だ。コンプレックスだらけの人生を「思考」と「行動」で突き進んだ記録…
戸田真琴のエッセイ第2弾『人を心から愛したことがないのだと気づいてしまっても』は、デビュー作以上に「誰かのために言葉を紡ぐ」という決意が溢れた1冊だ。AV女優という自身のあり方を客観的に踏まえた上で、「届くべき言葉がきちんと届く」ために、彼女は身を削ってでも生きる
出演:細田佳央太, 出演:駒井蓮, 出演:新谷ゆづみ, 出演:真魚, 出演:細川岳, 出演:上大迫祐希, 出演:若杉凩, Writer:金子鈴幸, Writer:金子由里奈, 監督:金子由里奈, プロデュース:髭野純
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品視聴済】私が観てきた映画(フィクション)を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が観てきた映画(フィクション)を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。
最後に
あわせて読みたい
【無知】映画『生理ちゃん』で理解した気になってはいけないが、男(私)にも苦労が伝わるコメディだ
男である私にはどうしても理解が及ばない領域ではあるが、女友達から「生理」の話を聞く機会があったり、映画『生理ちゃん』で視覚的に「生理」の辛さが示されることで、ちょっとは分かったつもりになっている。しかし男が「生理」を理解するのはやっぱり難しい
あまりにも映画の中身について具体的に触れていないので、最後に少しだけ書いておきたいと思います。

あわせて読みたい
【痛快】精神病院の隔離室から脱した、善悪の判断基準を持たない狂気の超能力者が大暴れする映画:『モ…
モナ・リザ アンド ザ ブラッドムーン』は、「10年以上拘束され続けた精神病院から脱走したアジア系女性が、特殊能力を使って大暴れする」というムチャクチャな設定の物語なのだが、全編に通底する「『善悪の判断基準』が歪んでいる」という要素がとても見事で、意味不明なのに最後まで惹きつけられてしまった
まずとても印象的だったのが、「違和感を覚えるぐらい、物語がかなりスキップされていく」という構成です。観ている最中に、「あれ? ちょっと寝ちゃったんだっけ?」と感じたほど、「説明がなされないまま状況が唐突に変わっている」みたいになることが、特に前半は多かった気がします。もちろん、その欠落部分は後半できちんと説明されるわけですが、そういう「違和感」さえも、映画全体の雰囲気に合っていると感じさせるような物語でした。
「あれ? 麦戸ちゃん???」みたいな感じになるよなぁ
あわせて読みたい
【苦悩】「やりがいのある仕事」だから見て見ぬふり?映画『アシスタント』が抉る搾取のリアル
とある映画会社で働く女性の「とある1日」を描く映画『アシスタント』は、「働くことの理不尽さ」が前面に描かれる作品だ。「雑用」に甘んじるしかない彼女の葛藤がリアルに描かれている。しかしそれだけではない。映画の「背景」にあるのは、あまりに悪逆な行為と、大勢による「見て見ぬふり」である
あとは何にせよ、「双子みたい」と評される七森と麦戸の関係性がとにかく素敵だったなと思います。現時点において私が考える、異性と関わる際の理想的な関係性だと言っていいでしょう。さらに言えば、「こういう関係性が『なんかちょっと変なもの』みたいに受け取られないような世の中であってほしい」とも感じました。
そんなわけで、とにかくメチャクチャ素晴らしい映画です。是非観てみて下さい。
あわせて読みたい
【考察】映画『街の上で』(今泉力哉)が描く「男女の友情は成立する」的会話が超絶妙で素晴らしい(出…
映画『街の上で』(今泉力哉監督)は、「映画・ドラマ的会話」ではない「自然な会話」を可能な限り目指すスタンスが見事だった。「会話の無駄」がとにかく随所に散りばめられていて、そのことが作品のリアリティを圧倒的に押し上げていると言える。ある男女の”恋愛未満”の会話もとても素晴らしかった
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!「それってホントに『コミュ力』が高いって言えるの?」と疑問を感じている方に…
私は、「コミュ力が高い人」に関するよくある主張に、どうも違和感を覚えてしまうことが多くあります。そしてその一番大きな理由が、「『コミュ力が高い人』って、ただ『想像力がない』だけではないか?」と感じてしまう点にあると言っていいでしょう。出版したKindle本は、「ネガティブには見えないネガティブな人」(隠れネガティブ)を取り上げながら、「『コミュ力』って何だっけ?」と考え直してもらえる内容に仕上げたつもりです。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【レビュー】実写映画『秒速5センチメートル』が描く「魂が震える人と出会うこと」の煌めきと残酷さ(監…
実写映画『秒速5センチメートル』は、何よりもまず「雰囲気」が最高に素晴らしい作品でした。「人生の早い段階で『魂が震える人』と出会ってしまったこと」の煌めきと残酷さが深く描かれていて、観ている間じゅう色んなことを考えさせられたし、会話も役者の演技も主題歌もすべてが完璧で、とにかく観て良かったなと思います
あわせて読みたい
【相違】友人の友人が作ったZINE『our house』には様々な「恋愛に惑う気持ち」が詰まっている
ひょんなことから知り合った女性が制作したZINE『our house』は、「恋愛」や「友情」に対して私が以前から抱いていた感覚にかなり近い内容で、実に興味深い。特に「恋愛においても、自分のことを性別で捉えられたくない」という感覚は新鮮で、そこから「男性は『恋愛的に惹かれている』という感覚を持たないかも」とも考えた
あわせて読みたい
【あらすじ】驚きの設定で「死と生」、そして「未練」を描く映画『片思い世界』は実に素敵だった(監督…
広瀬すず・杉咲花・清原果耶という超豪華俳優が主演を務める映画『片思い世界』は、是非、何も知らないまま観て下さい。この記事ではネタバレをせずに作品について語っていますが、それすらも読まずにまっさらな状態で鑑賞することをオススメします。「そうであってほしい」と感じてしまうような世界が“リアル”に描かれていました
あわせて読みたい
【あらすじ】「夢を追い求めた先」を辛辣に描く映画『ネムルバカ』は「ダルっとした会話」が超良い(監…
映画『ネムルバカ』は、まず何よりも「ダルっとした会話・日常」が素晴らしい作品です。そしてその上で、「夢を追い求めること」についてのかなり現代的な感覚を描き出していて、非常に印象的でした。「コスパが悪い」という言い方で「努力」を否定したくなる気持ちも全然理解できるし、若い人たちは特に大変だろうなと思います
あわせて読みたい
【死】映画『ミッキー17』は、「何度でも生まれ変われる」ってありがち設定を魅力的な物語に変えた(監…
映画『ミッキー17』は、「ありきたりな設定」がベースにあるのに、エンタメとしても考えさせる物語としても非常に興味深く面白い作品だった。「1人の人間が複数の肉体を持つこと」を禁じた法律の存在により絶妙な面白さとなっていると言えるだろう。さらにイカれた夫婦の言動もぶっ飛んでいて、そういう意味でも興味深い作品だ
あわせて読みたい
【切実】映画『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』は河合優実目当てだったが伊東蒼が超最高!(…
映画『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』は、伊東蒼演じるさっちゃんがひたすらに独白し続けるシーンがとにかく圧巻で、恋しさとせつなさと心強さが無限に伝わる最高すぎるシーンだった!「想いを伝えたい気持ち」と「伝えることの暴力性」の間で葛藤しながら、それでも喋らずにはいられない想いの強さが素敵すぎる
あわせて読みたい
【日々】映画『なみのおと』は、東日本大震災を語る人々の対話を”あり得ない”アングルから撮る(監督:…
映画『なみのおと』は、「東日本大震災の被災者が当時を振り返って対話をする」という内容そのものももちろん興味深いのだが、カメラをどう配置しているのかが分からない、ドキュメンタリー映画としては”あり得ない”映像であることにも驚かされた。また、悲惨な経験を軽妙に語る者たちの雰囲気も印象的な作品である
あわせて読みたい
【人生】映画『雪子 a.k.a.』は、言葉は出ないが嘘もないラップ好きの小学校教師の悩みや葛藤を描き出す
「小学校教師」と「ラップ」というなかなか異色の組み合わせの映画『雪子 a.k.a.』は、「ここが凄く良かった」と言えるようなはっきりしたポイントはないのに、ちょっと泣いてしまうぐらい良い映画だった。「口下手だけど嘘はない」という主人公・雪子の日常的な葛藤には、多くの人が共感させられるのではないかと思う
あわせて読みたい
【包容】映画『違国日記』を観て思う。「他者との接し方」が皆こうだったらもっと平和なはずだって(主…
映画『違国日記』は、人見知りの小説家・高代槙生が両親を亡くした姪・朝を引き取り一緒に暮らすところから始まる物語で、槙生と朝を中心とした様々な人間関係が絶妙に描かれている作品でした。人付き合いが苦手ながら、15歳という繊細な存在を壊さないように、でも腫れ物みたいには扱わないように慎重になる槙生のスタンスが素敵です
あわせて読みたい
【秘密】映画『ドライブ・イン・マンハッタン』は、「タクシー内の会話のみ」だが絶妙に良かった(主演…
映画『ドライブ・イン・マンハッタン』は、「タクシー内」というワンシチュエーションで「会話のみ」によって展開されるミニマムな要素しかない物語なのに、とにかく面白くて驚かされてしまった。運転手による「ゲスい会話」や女性客が抱えているのだろう「謎の秘密」などについて、色々と考えたくなるような深みのある物語である
あわせて読みたい
【拒絶】映画『ブルータリスト』は、ホロコーストを生き延びた建築家の数奇な人生を描く壮大な物語(監…
映画『ブルータリスト』は、ホロコーストを生き延びたユダヤ人建築家の、アメリカに移り住んで以降の人生を丁寧に追いながら、「ユダヤ人を受け入れないアメリカ」を静かに描き出す物語である。離れ離れにならざるを得なかった妻とのすれ違いにも焦点を当てつつ、時代に翻弄された者たちの悲哀が浮き彫りにされていく
あわせて読みたい
【異常】オンラインゲーム『DayZ』内でドキュメンタリー映画を撮るという狂気的な実験が映す人間模様:…
映画『ニッツ・アイランド』は、「『DayZ(デイジー)』というサバイバル・ゲーム内で撮られたドキュメンタリー映画」という斬新すぎる作品だ。「生き物を殺さない集団」「人殺しを楽しんで行う集団」など、ゲーム内の様々なプレイヤーから話を聞きつつ、「ゲーム内の世界は『リアル』なのか?」という問いにも焦点が当てられる
あわせて読みたい
【迷路】映画『国境ナイトクルージング』は、青春と呼ぶにはちょっと大人な3人の関係を丁寧に描く
映画『国境ナイトクルージング』は、男2人女1人の3人による、「青春」と呼ぶには少し年を取りすぎてしまったビターな関係を描き出す物語。説明が少なく、また、様々な示唆的な描写の意味するところを捉えきれなかったためり、「分からないこと」が多かったのだが、全体的な雰囲気が素敵で好きなタイプの作品だった
あわせて読みたい
【失恋】ひたすらカオスに展開する映画『エターナル・サンシャイン』は、最後まで観ると面白い!(主演…
映画『エターナル・サンシャイン』は、冒頭からしばらくの間、とにかくまったく意味不明で、「何がどうなっているのか全然分からない!」と思いながら観ていました。しかし、映像がカオスになるにつれて状況の理解は進み始め、最終的には「よくもまあこんな素っ頓狂なストーリーを理解できる物語に落とし込んだな」と感心させられました
あわせて読みたい
【発見】映画『小学校~それは小さな社会~』(山崎エマ)が映し出すのは、我々には日常すぎる日常だ
映画『小学校~それは小さな社会~』は、ごく一般的な公立小学校に密着し、日本で生まれ育った人間には「当たり前」にしか思えない日常を切り取った作品なのだが、そんな映画が諸外国で大いに評価されているという。「TOKKATSU」という「日本式教育」が注目されているらしく、私たちの「当たり前」が違和感だらけに見えているのだそうだ
あわせて読みたい
【奇妙】映画『画家と泥棒』は、非日常的なきっかけで始まったあり得ないほど奇跡的な関係を描く
映画『画家と泥棒』は、「自身の絵を盗まれた画家が、盗んだ泥棒と親しくなる」という奇妙奇天烈なきっかけから関係性が始まる物語であり、現実に起きたこととは思えないほど不可思議なドキュメンタリーである。アートを通じて奇妙に通じ合う2人の関係性は、ある種の美しささえ感じさせる、とても素晴らしいものに見えた
あわせて読みたい
【天才】映画『アット・ザ・ベンチ』面白すぎる!蓮見翔の脚本に爆笑、生方美久の会話劇にうっとり(監…
役者も脚本家も監督も何も知らないまま、「有名な役者が出てこないマイナーな映画」だと思い込んで観に行った映画『アット・ザ・ベンチ』は、衝撃的に面白い作品だった。各話ごと脚本家が異なるのだが、何よりも、第2話「回らない」を担当したダウ90000・蓮見翔の脚本が超絶面白い。あまりの衝撃にぶっ飛ばされてしまった
あわせて読みたい
【葛藤】映画『きみの色』(山田尚子)は、感受性が強すぎる若者のリアルをバンドを通じて描き出す(主…
山田尚子監督作『きみの色』は、これといった起伏のないストーリー展開でありながら、「若い世代の繊細さに満ちた人間関係」をとてもリアルに描き出す雰囲気が素敵な作品。「悩み・葛藤を抱えている状態が日常である」という雰囲気をベースにしつつ、「音楽」を起点に偶然繋がった3人の緩やかな日々を描き出す物語に惹きつけられた
あわせて読みたい
【繊細】映画『ぼくのお日さま』(奥山大史)は、小さな世界での小さな恋を美しい映像で描く(主演:越…
映画『ぼくのお日さま』は、舞台設定も人間関係も実にミニマムでありながら、とても奥行きのある物語が展開される作品。予告編で「3つの恋」と言及されなければ、描かれるすべての「恋」には気付けなかっただろうと思うくらいの繊細な関係性と、映像・音楽を含めてすべてが美しい旋律として奏でられる物語がとても素敵でした
あわせて読みたい
【孤独】映画『ナミビアの砂漠』は、自由だが居場所がない主人公を演じる河合優実の存在感が圧倒的(監…
映画『ナミビアの砂漠』は、とにかく「河合優実が凄まじい」のひと言に尽きる作品だ。彼女が演じたカナという主人公の「捉えどころの無さ」は絶妙で、一見すると凄まじく「自由」に羽ばたいている感じなのに、実際には全然「自由」には見えないというバランスが見事だった。特段の物語はないのに、137分間惹きつけられてしまうだろう
あわせて読みたい
【変態】映画『コンセント/同意』が描く50歳と14歳少女の”恋”は「キモっ!」では終われない
映画『コンセント/同意』は、50歳の著名小説家に恋をした14歳の少女が大人になってから出版した「告発本」をベースに作られた作品だ。もちろん実話を元にしており、その焦点はタイトルの通り「同意」にある。自ら望んで36歳年上の男性との恋に踏み出した少女は、いかにして「同意させられた」という状況に追い込まれたのか?
あわせて読みたい
【評価】高山一実の小説かつアニメ映画である『トラペジウム』は、アイドル作とは思えない傑作(声優:…
原作小説、そしてアニメ映画共に非常に面白かった『トラペジウム』は、高山一実が乃木坂46に在籍中、つまり「現役アイドル」として出版した作品であり、そのクオリティに驚かされました。「現役アイドル」が「アイドル」をテーマにするというド直球さを武器にしつつ、「アイドルらしからぬ感覚」をぶち込んでくる非常に面白い作品である
あわせて読みたい
【恋心】映画『サッドティー』は、「『好き』を巡ってウロウロする人々」を描く今泉力哉節全開の作品だった
映画『サッドティー』は、今泉力哉らしい「恋愛の周辺でグルグルする人たち」を描き出す物語。関係性が微妙に重なる複数の人間を映し出す群像劇の中で、「『好き』のややこしさ」に焦点を当てていく構成はさすがです。実に奇妙な展開で終わる物語ですが、それでもなお「リアルだ」と感じさせる雰囲気は、まるで魔法のようでした
あわせて読みたい
【?】現代思想「<友情>の現在」を読んで、友達・恋愛・好き・好意などへのモヤモヤを改めて考えた
「現代思想 <友情>の現在」では、「友情」をテーマにした様々な考察が掲載されているのだが、中でも、冒頭に載っていた対談が最も興味深く感じられた。「『友達』というのは、既存の概念からこぼれ落ちた関係性につけられる『残余カテゴリー』である」という中村香住の感覚を起点に、様々な人間関係について思考を巡らせてみる
あわせて読みたい
【絶妙】映画『水深ゼロメートルから』(山下敦弘)は、何気ない会話から「女性性の葛藤」を描く(主演…
高校演劇を舞台化する企画第2弾に選ばれた映画『水深ゼロメートルから』は、「水のないプール」にほぼ舞台が固定された状態で、非常に秀逸な会話劇として展開される作品だ。退屈な時間を埋めるようにして始まった「ダルい会話」から思いがけない展開が生まれ、「女として生きること」についての様々な葛藤が描き出される点が面白い
あわせて読みたい
【感想】映画『夜明けのすべて』は、「ままならなさ」を抱えて生きるすべての人に優しく寄り添う(監督…
映画『夜明けのすべて』は、「PMS」や「パニック障害」を通じて、「自分のものなのに、心・身体が思い通りにならない」という「ままならなさ」を描き出していく。決して他人事ではないし、「私たちもいつそのような状況に置かれるか分からない」という気持ちで観るのがいいでしょう。物語の起伏がないのに惹きつけられる素敵な作品です
あわせて読みたい
【狂気】群青いろ制作『雨降って、ジ・エンド。』は、主演の古川琴音が成立させている映画だ
映画『雨降って、ジ・エンド。』は、冒頭からしばらくの間「若い女性とオジサンのちょっと変わった関係」を描く物語なのですが、後半のある時点から「共感を一切排除する」かのごとき展開になる物語です。色んな意味で「普通なら成立し得ない物語」だと思うのですが、古川琴音の演技などのお陰で、絶妙な形で素敵な作品に仕上がっています
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『52ヘルツのクジラたち』の「無音で叫ぶ人」と「耳を澄ます人」の絶妙な響鳴(原作:…
映画『52ヘルツのクジラたち』は、「現代的な問題のごった煮」と感じられてしまうような”過剰さ”に溢れてはいますが、タイトルが作品全体を絶妙に上手くまとめていて良かったなと思います。主演の杉咲花がやはり見事で、身体の内側から「不幸」が滲み出ているような演技には圧倒されてしまいました
あわせて読みたい
【幻惑】映画『フォロウィング』の衝撃。初監督作から天才だよ、クリストファー・ノーラン
クリストファー・ノーランのデビュー作であり、多数の賞を受賞し世界に衝撃を与えた映画『フォロウィング』には、私も驚かされてしまった。冒頭からしばらくの間「何が描かれているのかさっぱり理解できない」という状態だったのに、ある瞬間一気に視界が晴れたように状況が理解できたのだ。脚本の力がとにかく圧倒的だった
あわせて読みたい
【衝撃】広末涼子映画デビュー作『20世紀ノスタルジア』は、「広末が異常にカワイイ」だけじゃない作品
広末涼子の映画デビュー・初主演作として知られる『20世紀ノスタルジア』は、まず何よりも「広末涼子の可愛さ」に圧倒される作品だ。しかし、決してそれだけではない。初めは「奇妙な設定」ぐらいにしか思っていなかった「宇宙人に憑依されている」という要素が、物語全体を実に上手くまとめている映画だと感じた
あわせて読みたい
【感想】アニメ映画『パーフェクトブルー』(今敏監督)は、現実と妄想が混在する構成が少し怖い
本作で監督デビューを果たした今敏のアニメ映画『パーフェクトブルー』は、とにかくメチャクチャ面白かった。現実と虚構の境界を絶妙に壊しつつ、最終的にはリアリティのある着地を見せる展開で、25年以上も前の作品だなんて信じられない。今でも十分通用するだろうし、81分とは思えない濃密さに溢れた見事な作品である
あわせて読みたい
【奇妙】映画『鯨の骨』は、主演のあのちゃんが絶妙な存在感を醸し出す、斬新な設定の「推し活」物語
映画『鯨の骨』は、主演を務めたあのちゃんの存在感がとても魅力的な作品でした。「AR動画のカリスマ的存在」である主人公を演じたあのちゃんは、役の設定が絶妙だったこともありますが、演技がとても上手く見え、また作品全体の、「『推し活』をある意味で振り切って描き出す感じ」もとても皮肉的で良かったです
あわせて読みたい
【実話】田舎暮らし失敗。映画『理想郷』が描く、めんどくさい人間関係が嫌がらせに発展した事件
実話を基にした映画『理想郷』は、「理想の田舎暮らし」が粉微塵に粉砕されていく過程を描く物語である。第一義的には当然、夫妻に嫌がらせを続ける兄弟が悪いのだが、しかしそのように捉えるだけでは何も変わらないだろう。双方の譲れない「価値観」が否応なしに正面衝突する状況で、一体何が「正解」となり得るだろうか?
あわせて読みたい
【斬新】フィクション?ドキュメンタリー?驚きの手法で撮られた、現実と虚構が入り混じる映画:『最悪…
映画『最悪な子どもたち』は、最後まで観てもフィクションなのかドキュメンタリーなのか確信が持てなかった、普段なかなか抱くことのない感覚がもたらされる作品だった。「演技未経験」の少年少女を集めての撮影はかなり実験的に感じられたし、「分からないこと」に惹かれる作品と言えるいだろうと思う
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『レザボア・ドッグス』(タランティーノ監督)はとにかく驚異的に脚本が面白い!
クエンティン・タランティーノ初の長編監督作『レザボア・ドッグス』は、のけぞるほど面白い映画だった。低予算という制約を逆手に取った「会話劇」の構成・展開があまりにも絶妙で、舞台がほぼ固定されているにも拘らずストーリーが面白すぎる。天才はやはり、デビュー作から天才だったのだなと実感させられた
あわせて読みたい
【感想】映画『ローマの休日』はアン王女を演じるオードリー・ヘプバーンの美しさが際立つ名作
オードリー・ヘプバーン主演映画『ローマの休日』には驚かされた。現代の視点で観ても十分に通用する作品だからだ。まさに「不朽の名作」と言っていいだろう。シンプルな設定と王道の展開、そしてオードリー・ヘプバーンの時代を超える美しさが相まって、普通ならまずあり得ない見事なコラボレーションが見事に実現している
あわせて読みたい
【おすすめ】カンヌ映画『PERFECT DAYS』は、ほぼ喋らない役所広司の沈黙が心地よい(ヴィム・ヴェンダ…
役所広司主演映画『PERFECT DAYS』(ヴィム・ヴェンダース監督)は、主人公・平山の「沈黙」がとにかく雄弁な物語である。渋谷区のトイレの清掃員である無口な平山の、世間とほとんど繋がりを持たない隔絶した日常が、色んなものを抱えた者たちを引き寄せ、穏やかさで満たしていく様が素晴らしい
あわせて読みたい
【考察】A24のホラー映画『TALK TO ME』が描くのは、「薄く広がった人間関係」に悩む若者のリアルだ
「A24のホラー映画史上、北米最高興収」と謳われる『TALK TO ME トーク・トゥ・ミー』は、一見「とても分かりやすいホラー映画」である。しかし真のテーマは「SNS過剰社会における人間関係の困難さ」なのだと思う。結果としてSNSが人と人との距離を遠ざけてしまっている現実を、ホラー映画のスタイルに落とし込んだ怪作
あわせて読みたい
【痛快】精神病院の隔離室から脱した、善悪の判断基準を持たない狂気の超能力者が大暴れする映画:『モ…
モナ・リザ アンド ザ ブラッドムーン』は、「10年以上拘束され続けた精神病院から脱走したアジア系女性が、特殊能力を使って大暴れする」というムチャクチャな設定の物語なのだが、全編に通底する「『善悪の判断基準』が歪んでいる」という要素がとても見事で、意味不明なのに最後まで惹きつけられてしまった
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『アンダーカレント』(今泉力哉)は、失踪をテーマに「分かり合えなさ」を描く
映画『アンダーカレント』において私は、恐らく多くの人が「受け入れがたい」と感じるだろう人物に共感させられてしまった。また本作は、「他者を理解すること」についての葛藤が深掘りされる作品でもある。そのため、私が普段から抱いている「『他者のホントウ』を知りたい」という感覚も強く刺激された
あわせて読みたい
【絶望】杉咲花主演映画『市子』の衝撃。毎日がしんどい「どん底の人生」を生き延びるための壮絶な決断…
映画『市子』はまず何よりも主演を務めた杉咲花に圧倒させられる作品だ。そしてその上で、主人公・川辺市子を巡る物語にあれこれと考えさせられてしまった。「川辺市子」は決してフィクショナルな存在ではなく、現実に存在し得る。本作は、そのような存在をリアルに想像するきっかけにもなるだろう
あわせて読みたい
【感想】映画『キリエのうた』(岩井俊二)はアイナ・ジ・エンドに圧倒されっ放しの3時間だった(出演:…
映画『キリエのうた』(岩井俊二監督)では、とにかくアイナ・ジ・エンドに圧倒されてしまった。歌声はもちろんのことながら、ただそこにいるだけで場を支配するような存在感も凄まじい。全編に渡り「『仕方ないこと』はどうしようもなく起こるんだ」というメッセージに溢れた、とても力強い作品だ
あわせて読みたい
【考察】映画『街の上で』(今泉力哉)が描く「男女の友情は成立する」的会話が超絶妙で素晴らしい(出…
映画『街の上で』(今泉力哉監督)は、「映画・ドラマ的会話」ではない「自然な会話」を可能な限り目指すスタンスが見事だった。「会話の無駄」がとにかく随所に散りばめられていて、そのことが作品のリアリティを圧倒的に押し上げていると言える。ある男女の”恋愛未満”の会話もとても素晴らしかった
あわせて読みたい
【感想】映画『正欲』に超共感。多様性の時代でさえどこに行っても馴染めない者たちの業苦を抉る(出演…
映画『正欲』は、私には共感しかない作品だ。特に、新垣結衣演じる桐生夏月と磯村勇斗演じる佐々木佳道が抱える葛藤や息苦しさは私の内側にあるものと同じで、その描かれ方に圧倒されてしまった。「『多様性』には『理解』も『受け入れ』も不要で、単に否定しなければ十分」なのだと改めて思う
あわせて読みたい
【嫌悪】映画『ドライビング・バニー』が描く、人生やり直したい主人公(母親)のウザさと絶望
映画『ドライビング・バニー』は、主人公であるバニーのことが最後まで嫌いだったにも拘わらず、全体的にはとても素敵に感じられた珍しいタイプの作品だ。私は、「バニーのような人間が世の中に存在する」という事実に嫌悪感を抱いてしまうのだが、それでも、狂気的でぶっ飛んだラストシーンによって、作品全体の印象が大きく変わったと言える
あわせて読みたい
【絶望】人生どん底から生き方を変える。映画『シスター 夏のわかれ道』が描く中国人女性の葛藤と諦念
両親の死をきっかけに、「見知らぬ弟」を引き取らなければならなくなった女性を描く映画『シスター 夏のわかれ道』は、中国の特異な状況を背景にしつつ、誰もが抱き得る普遍的な葛藤が切り取られていく。現状を打破するために北京の大学院を目指す主人公は、一体どんな決断を下すのか。
あわせて読みたい
【未知】コーダに密着した映画『私だけ聴こえる』は、ろう者と聴者の狭間で居場所がない苦悩を映し出す
あなたは「コーダ」と呼ばれる存在を知っているだろうか?「耳の聴こえない親を持つ、耳が聴こえる子ども」のことであり、映画『私だけ聴こえる』は、まさにそんなコーダが置かれた状況を描くドキュメンタリー映画だ。自身は障害者ではないのに大変な苦労を強いられている現状が理解できる作品
あわせて読みたい
【闘争】映画『あのこと』が描く、中絶が禁止だった時代と、望まぬ妊娠における圧倒的な「男の不在」
中絶が禁止されていた1960年代のフランスを舞台にした映画『あのこと』は、「望まぬ妊娠」をしてしまった秀才の大学生が、「未来を諦めない」ために中絶を目指す姿が描かれる。さらに、誰にも言えずに孤独に奮闘する彼女の姿が「男の不在」を強調する物語でもあり、まさに男が観るべき作品だ
あわせて読みたい
【助けて】映画『生きててごめんなさい』は、「共依存カップル」視点で生きづらい世の中を抉る物語(主…
映画『生きててごめんなさい』は、「ちょっと歪な共依存関係」を描きながら、ある種現代的な「生きづらさ」を抉り出す作品。出版社の編集部で働きながら小説の新人賞を目指す園田修一は何故、バイトを9度もクビになり、一日中ベッドの上で何もせずに過ごす同棲相手・清川莉奈を”必要とする”のか?
あわせて読みたい
【映画】『別れる決心』(パク・チャヌク)は、「倫理的な葛藤」が描かれない、不穏で魅惑的な物語
巨匠パク・チャヌク監督が狂気的な関係性を描き出す映画『別れる決心』には、「倫理的な葛藤が描かれない」という特異さがあると感じた。「様々な要素が描かれるものの、それらが『主人公2人の関係性』に影響しないこと」や、「『理解は出来ないが、成立はしている』という不思議な感覚」について触れる
あわせて読みたい
【希望】誰も傷つけたくない。でも辛い。逃げたい。絶望しかない。それでも生きていく勇気がほしい時に…
2006年発売、2021年文庫化の『私を見て、ぎゅっと愛して』は、ブログ本のクオリティとは思えない凄まじい言語化力で、1人の女性の内面の葛藤を抉り、読者をグサグサと突き刺す。信じがたい展開が連続する苦しい状況の中で、著者は大事なものを見失わず手放さずに、勇敢に前へ進んでいく
あわせて読みたい
【理解】「多様性を受け入れる」とか言ってるヤツ、映画『炎上する君』でも観て「何も見てない」って知…
西加奈子の同名小説を原作とした映画『炎上する君』(ふくだももこ監督)は、「多様性」という言葉を安易に使いがちな世の中を挑発するような作品だ。「見えない存在」を「過剰に装飾」しなければならない現実と、マジョリティが無意識的にマイノリティを「削る」リアルを描き出していく
あわせて読みたい
【感想】是枝裕和監督映画『怪物』(坂元裕二脚本)が抉る、「『何もしないこと』が生む加害性」
坂元裕二脚本、是枝裕和監督の映画『怪物』は、3つの視点を通して描かれる「日常の何気ない光景」に、思いがけない「加害性」が潜んでいることを炙り出す物語だ。これは間違いなく、私たち自身に関わる話であり、むしろ「自分には関係ない」と考えている人こそが自覚すべき問題だと思う
あわせて読みたい
【狂気?】オウム真理教を内部から映す映画『A』(森達也監督)は、ドキュメンタリー映画史に残る衝撃作だ
ドキュメンタリー映画の傑作『A』(森達也)をようやく観られた。「オウム真理教は絶対悪だ」というメディアの報道が凄まじい中、オウム真理教をその内部からフラットに映し出した特異な作品は、公開当時は特に凄まじい衝撃をもたらしただろう。私たちの「当たり前」が解体されていく斬新な一作
あわせて読みたい
【違和感】三浦透子主演映画『そばかす』はアセクシャルの生きづらさを描く。セクシャリティ理解の入り口に
「他者に対して恋愛感情・性的欲求を抱かないセクシャリティ」である「アセクシャル」をテーマにした映画『そばかす』は、「マイノリティのリアル」をかなり解像度高く映し出す作品だと思う。また、主人公・蘇畑佳純に共感できてしまう私には、「普通の人の怖さ」が描かれている映画にも感じられた
あわせて読みたい
【衝撃】これが実話とは。映画『ウーマン・トーキング』が描く、性被害を受けた女性たちの凄まじい決断
映画『ウーマン・トーキング』の驚くべき点は、実話を基にしているという点だ。しかもその事件が起こったのは2000年代に入ってから。とある宗教コミュニティ内で起こった連続レイプ事件を機に村の女性たちがある決断を下す物語であり、そこに至るまでの「ある種異様な話し合い」が丁寧に描かれていく
あわせて読みたい
【美麗】映画『CLOSE/クロース』はあまりにも切ない。「誰かの当たり前」に飲み込まれてしまう悲劇
子どもの頃から兄弟のように育った幼馴染のレオとレミの関係の変化を丁寧に描き出す映画『CLOSE/クロース』は、「自分自身で『美しい世界』を毀損しているのかもしれない」という話でもある。”些細な”言動によって、確かに存在したあまりに「美しい世界」があっさりと壊されてしまう悲哀が描かれる
あわせて読みたい
【苦悩】「やりがいのある仕事」だから見て見ぬふり?映画『アシスタント』が抉る搾取のリアル
とある映画会社で働く女性の「とある1日」を描く映画『アシスタント』は、「働くことの理不尽さ」が前面に描かれる作品だ。「雑用」に甘んじるしかない彼女の葛藤がリアルに描かれている。しかしそれだけではない。映画の「背景」にあるのは、あまりに悪逆な行為と、大勢による「見て見ぬふり」である
あわせて読みたい
【居場所】菊地凛子主演映画『658km、陽子の旅』(熊切和嘉)は、引きこもりロードムービーの傑作
映画『658km、陽子の旅』は、主演の菊地凛子の存在感が圧倒的だった。夢破れて長年引きこもり続けている女性が、否応なしにヒッチハイクで弘前を目指さなければならなくなるロードムービーであり、他人や社会と関わることへの葛藤に塗れた主人公の変化が、とても「勇敢」なものに映る
あわせて読みたい
【純真】ゲイが犯罪だった時代が舞台の映画『大いなる自由』は、刑務所内での極深な人間ドラマを描く
男性同士の恋愛が犯罪であり、ゲイの男性が刑法175条を理由に逮捕されてしまう時代のドイツを描いた映画『大いなる自由』は、確かに同性愛の物語なのだが、実はそこに本質はない。物語の本質は、まさにタイトルにある通り「自由」であり、ラストシーンで突きつけられるその深い問いかけには衝撃を受けるだろう
あわせて読みたい
【あらすじ】趣味も仕事もない定年後の「退屈地獄」をリアルに描く内館牧子『終わった人』から人生を考える
映画化もされた『終わった人』(内館牧子)は、「定年後の人生の退屈さ」を真正面から描く小説。仕事一筋で生きてきた主人公が、定年を迎えたことで無為な日々を過ごすことになるのですが、今の時代、このような感覚はもしかしたら、若い世代にも無縁とは言えないかもしれないとさえ感じました
あわせて読みたい
【共感】「恋愛したくない」という社会をリアルに描く売野機子の漫画『ルポルタージュ』が示す未来像
売野機子のマンガ『ルポルタージュ』は、「恋愛を飛ばして結婚すること」が当たり前の世界が描かれる。私はこの感覚に凄く共感できてしまった。「恋愛」「結婚」に対して、「世間の『当たり前』に馴染めない感覚」を持つ私が考える、「恋愛」「結婚」が有する可能性
あわせて読みたい
【実話】ポートアーサー銃乱射事件を扱う映画『ニトラム』が示す、犯罪への傾倒に抗えない人生の不条理
オーストラリアで実際に起こった銃乱射事件の犯人の生い立ちを描く映画『ニトラム/NITRAM』は、「頼むから何も起こらないでくれ」と願ってしまうほどの異様な不穏さに満ちている。「社会に順応できない人間」を社会がどう受け入れるべきかについて改めて考えさせる作品だ
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『夕方のおともだち』は、「私はこう」という宣言からしか始まらない関係性の”純度”を描く
「こんな田舎にはもったいないほどのドM」と評された男が主人公の映画『夕方のおともだち』は、SM嬢と真性ドMの関わりを通じて、「宣言から始まる関係」の難しさを描き出す。「普通の世界」に息苦しさを感じ、どうしても馴染めないと思っている人に刺さるだろう作品
あわせて読みたい
【苦しい】「恋愛したくないし、興味ない」と気づいた女性が抉る、想像力が足りない社会の「暴力性」:…
「実は私は、恋愛的な関係を求めているわけじゃないかもしれない」と気づいた著者ムラタエリコが、自身の日常や専門学校でも学んだ写真との関わりを基に、「自分に相応しい関係性」や「社会の暴力性」について思考するエッセイ。久々に心にズバズバ刺さった、私にはとても刺激的な1冊だった。
あわせて読みたい
【感想】映画『君が世界のはじまり』は、「伝わらない」「分かったフリをしたくない」の感情が濃密
「キラキラした青春学園モノ」かと思っていた映画『君が世界のはじまり』は、「そこはかとない鬱屈」に覆われた、とても私好みの映画だった。自分の決断だけではどうにもならない「現実」を前に、様々な葛藤渦巻く若者たちの「諦念」を丁寧に描き出す素晴らしい物語
あわせて読みたい
【感想】のん主演映画『私をくいとめて』から考える、「誰かと一緒にいられれば孤独じゃないのか」問題
のん(能年玲奈)が「おひとり様ライフ」を満喫する主人公を演じる映画『私をくいとめて』を観て、「孤独」について考えさせられた。「誰かと関わっていられれば孤独じゃない」という考えに私は賛同できないし、むしろ誰かと一緒にいる時の方がより強く孤独を感じることさえある
あわせて読みたい
【考察】ヨネダコウ『囀る鳥は羽ばたかない』は、BLの枠組みの中で「歪んだ人間」をリアルに描き出す
2巻までしか読んでいないが、ヨネダコウのマンガ『囀る鳥は羽ばたかない』は、「ヤクザ」「BL」という使い古されたフォーマットを使って、異次元の物語を紡ぎ出す作品だ。BLだが、BLという外枠を脇役にしてしまう矢代という歪んだ男の存在感が凄まじい。
あわせて読みたい
【違和感】平田オリザ『わかりあえないことから』は「コミュニケーション苦手」問題を新たな視点で捉え…
「コミュニケーションが苦手」なのは、テクニックの問題ではない!?『わかりあえないことから』は、学校でのコミュニケーション教育に携わる演劇人・平田オリザが抱いた違和感を起点に、「コミュニケーション教育」が抱える問題と、私たち日本人が進むべき道を示す1冊
あわせて読みたい
【感想】映画『窓辺にて』(今泉力哉監督)の稲垣吾郎の役に超共感。「好きとは何か」が分からない人へ
映画『窓辺にて』(今泉力哉監督)は、稲垣吾郎演じる主人公・市川茂巳が素晴らしかった。一般的には、彼の葛藤はまったく共感されないし、私もそのことは理解している。ただ私は、とにかく市川茂巳にもの凄く共感してしまった。「誰かを好きになること」に迷うすべての人に観てほしい
あわせて読みたい
【魅惑】バーバラ・ローデン監督・脚本・主演の映画『WANDA』の、70年代の作品とは思えない今感
映画館で観た予告が気になって、それ以外の情報を知らずに観に行った映画『WANDA』なんと70年代の映画だと知って驚かされた。まったく「古さ」を感じなかったからだ。主演だけでなく、監督・脚本も務めたバーバラ・ローデンが遺した、死後評価が高まった歴史的一作
あわせて読みたい
【思考】戸田真琴、経験も文章もとんでもない。「人生どうしたらいい?」と悩む時に読みたい救いの1冊:…
「AV女優のエッセイ」と聞くと、なかなか手が伸びにくいかもしれないが、戸田真琴『あなたの孤独は美しい』の、あらゆる先入観を吹っ飛ばすほどの文章力には圧倒されるだろう。凄まじい経験と、普通ではない思考を経てAV女優に至った彼女の「生きる指針」は、多くの人の支えになるはずだ
あわせて読みたい
【欠落】映画『オードリー・ヘプバーン』が映し出す大スターの生き方。晩年に至るまで生涯抱いた悲しみ…
映画『オードリー・ヘプバーン』は、世界的大スターの知られざる素顔を切り取るドキュメンタリーだ。戦争による壮絶な飢え、父親の失踪、消えぬ孤独感、偶然がもたらした映画『ローマの休日』のオーディション、ユニセフでの活動など、様々な証言を元に稀代の天才を描き出す
あわせて読みたい
【純愛】映画『ぼくのエリ』の衝撃。「生き延びるために必要なもの」を貪欲に求める狂気と悲哀、そして恋
名作と名高い映画『ぼくのエリ』は、「生き延びるために必要なもの」が「他者を滅ぼしてしまうこと」であるという絶望を抱えながら、それでも生きることを選ぶ者たちの葛藤が描かれる。「純愛」と呼んでいいのか悩んでしまう2人の関係性と、予想もつかない展開に、感動させられる
あわせて読みたい
【選択】特異な疑似家族を描く韓国映画『声もなく』の、「家族とは?」の本質を考えさせる深淵さ
喋れない男が、誘拐した女の子をしばらく匿い、疑似家族のような関係を築く韓国映画『声もなく』は、「映画の中で描かれていない部分」が最も印象に残る作品だ。「誘拐犯」と「被害者」のあり得ない関係性に、不自然さをまったく抱かせない設定・展開の妙が見事な映画
あわせて読みたい
【感涙】映画『彼女が好きなものは』の衝撃。偏見・無関心・他人事の世界から”脱する勇気”をどう持つか
涙腺がぶっ壊れたのかと思ったほど泣かされた映画『彼女が好きなものは』について、作品の核となる「ある事実」に一切触れずに書いた「ネタバレなし」の感想です。「ただし摩擦はゼロとする」の世界で息苦しさを感じているすべての人に届く「普遍性」を体感してください
あわせて読みたい
【感想】綿矢りさ原作の映画『ひらいて』は、溢れる”狂気”を山田杏奈の”見た目”が絶妙に中和する
「片想いの相手には近づけないから、その恋人を”奪おう”」と考える主人公・木村愛の「狂気」を描く、綿矢りさ原作の映画『ひらいて』。木村愛を演じる山田杏奈の「顔」が、木村愛の狂気を絶妙に中和する見事な配役により、「狂気の境界線」をあっさり飛び越える木村愛がリアルに立ち上がる
あわせて読みたい
【衝撃】卯月妙子『人間仮免中』、とんでもないコミックエッセイだわ。統合失調症との壮絶な闘いの日々
小学5年生から統合失調症を患い、社会の中でもがき苦しみながら生きる卯月妙子のコミックエッセイ『人間仮免中』はとんでもない衝撃作。周りにいる人とのぶっ飛んだ人間関係や、歩道橋から飛び降り自殺未遂を図り顔面がぐちゃぐちゃになって以降の壮絶な日々も赤裸々に描く
あわせて読みたい
【母娘】よしながふみ『愛すべき娘たち』で描かれる「女であることの呪い」に男の私には圧倒されるばかりだ
「女であること」は、「男であること」と比べて遥かに「窮屈さ」に満ちている。母として、娘として、妻として、働く者として、彼女たちは社会の中で常に闘いを強いられてきた。よしながふみ『愛すべき娘たち』は、そんな女性の「ややこしさ」を繊細に描き出すコミック
あわせて読みたい
【抵抗】西加奈子のおすすめ小説『円卓』。「当たり前」と折り合いをつけられない生きづらさに超共感
小学3年生のこっこは、「孤独」と「人と違うこと」を愛するちょっと変わった女の子。三つ子の美人な姉を「平凡」と呼んで馬鹿にし、「眼帯」や「クラス会の途中、不整脈で倒れること」に憧れる。西加奈子『円卓』は、そんなこっこの振る舞いを通して「当たり前」について考えさせる
あわせて読みたい
【葛藤】正論を振りかざしても、「正しさとは何か」に辿り着けない。「絶対的な正しさ」など存在しない…
「『正しさ』は人によって違う」というのは、私には「当たり前の考え」に感じられるが、この前提さえ共有できない社会に私たちは生きている。映画『由宇子の天秤』は、「誤りが含まれるならすべて間違い」という判断が当たり前になされる社会の「不寛容さ」を切り取っていく
あわせて読みたい
【苦しい】恋愛で寂しさは埋まらない。恋に悩む女性に「心の穴」を自覚させ、自己肯定感を高めるための…
「どうして恋愛が上手くいかないのか?」を起点にして、「女性として生きることの苦しさ」の正体を「心の穴」という言葉で説明する『なぜあなたは「愛してくれない人」を好きになるのか』はオススメ。「著者がAV監督」という情報に臆せず是非手を伸ばしてほしい
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『流浪の月』を観て感じた、「『見て分かること』にしか反応できない世界」への気持ち悪さ
私は「見て分かること」に”しか”反応できない世界に日々苛立ちを覚えている。そういう社会だからこそ、映画『流浪の月』で描かれる文と更紗の関係も「気持ち悪い」と断罪されるのだ。私はむしろ、どうしようもなく文と更紗の関係を「羨ましい」と感じてしまう。
あわせて読みたい
【感想】映画『竜とそばかすの姫』が描く「あまりに批判が容易な世界」と「誰かを助けることの難しさ」
SNSの登場によって「批判が容易な社会」になったことで、批判を恐れてポジティブな言葉を口にしにくくなってしまった。そんな世の中で私は、「理想論だ」と言われても「誰かを助けたい」と発信する側の人間でいたいと、『竜とそばかすの姫』を観て改めて感じさせられた
あわせて読みたい
【考察】『うみべの女の子』が伝えたいことを全力で解説。「関係性の名前」を手放し、”裸”で対峙する勇敢さ
ともすれば「エロ本」としか思えない浅野いにおの原作マンガを、その空気感も含めて忠実に映像化した映画『うみべの女の子』。本作が一体何を伝えたかったのかを、必死に考察し全力で解説する。中学生がセックスから関係性をスタートさせることで、友達でも恋人でもない「名前の付かない関係性」となり、行き止まってしまう感じがリアル
あわせて読みたい
【生きる】しんどい人生を宿命付けられた子どもはどう生きるべき?格差社会・いじめ・恋愛を詰め込んだ…
厳しい受験戦争、壮絶な格差社会、残忍ないじめ……中国の社会問題をこれでもかと詰め込み、重苦しさもありながら「ボーイ・ミーツ・ガール」の爽やかさも融合されている映画『少年の君』。辛い境遇の中で、「すべてが最悪な選択肢」と向き合う少年少女の姿に心打たれる
あわせて読みたい
【考察】生きづらい性格は変わらないから仮面を被るしかないし、仮面を被るとリア充だと思われる:『勝…
「リア充感」が滲み出ているのに「生きづらさ」を感じてしまう人に、私はこれまでたくさん会ってきた。見た目では「生きづらさ」は伝わらない。24年間「リアル彼氏」なし、「脳内彼氏」との妄想の中に生き続ける主人公を描く映画『勝手にふるえてろ』から「こじらせ」を知る
あわせて読みたい
【おすすめ】濱口竜介監督の映画『親密さ』は、「映像」よりも「言葉」が前面に来る衝撃の4時間だった
専門学校の卒業制作として濱口竜介が撮った映画『親密さ』は、2時間10分の劇中劇を組み込んだ意欲作。「映像」でありながら「言葉の力」が前面に押し出される作品で、映画や劇中劇の随所で放たれる「言葉」に圧倒される。4時間と非常に長いが、観て良かった
あわせて読みたい
【実話】障害者との接し方を考えさせる映画『こんな夜更けにバナナかよ』から”対等な関係”の大事さを知る
「障害者だから◯◯だ」という決まりきった捉え方をどうしてもしてしまいがちですが、『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』の主人公・鹿野靖明の生き様を知れば、少しは考え方が変わるかもしれません。筋ジストロフィーのまま病院・家族から離れて“自活”する決断をした驚異の人生
あわせて読みたい
【葛藤】子どもが抱く「家族を捨てたい気持ち」は、母親の「家族を守りたい気持ち」の終着点かもしれな…
家族のややこしさは、家族の数だけ存在する。そのややこしさを、「子どもを守るために母親が父親を殺す」という極限状況を設定することで包括的に描き出そうとする映画『ひとよ』。「暴力」と「殺人犯の子どもというレッテル」のどちらの方が耐え難いと感じるだろうか?
あわせて読みたい
【壮絶】本当に「美人は得」か?「美しさ」という土俵を意識せざるを得ない少女・女性たちの現実:『自…
美醜で判断されがちな”ルッキズム”の世の中に刃を突きつける小説『自画像』。私自身は、「キレイな人もキレイな人なりの大変さを抱えている」と感じながら生きているつもりだが、やはりその辛さは理解されにくい。私も男性であり、ルッキズムに加担してないとはとても言えない
あわせて読みたい
【逃避】つまらない世の中で生きる毎日を押し流す”何か”を求める気持ちに強烈に共感する:映画『サクリ…
子どもの頃「台風」にワクワクしたように、未だに、「自分のつまらない日常を押し流してくれる『何か』」の存在を待ちわびてしまう。立教大学の学生が撮った映画『サクリファイス』は、そんな「何か」として「東日本大震災」を描き出す、チャレンジングな作品だ
あわせて読みたい
【映画】『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』で号泣し続けた私はTVアニメを観ていない
TVアニメは観ていない、というかその存在さえ知らず、物語や登場人物の設定も何も知らないまま観に行った映画『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』に、私は大号泣した。「悪意のない物語」は基本的に好きではないが、この作品は驚くほど私に突き刺さった
あわせて読みたい
【誤り】「信じたいものを信じる」のは正しい?映画『星の子』から「信じること」の難しさを考える
どんな病気も治す「奇跡の水」の存在を私は信じないが、しかし何故「信じない」と言えるのか?「奇跡の水を信じる人」を軽々に非難すべきではないと私は考えているが、それは何故か?映画『星の子』から、「何かを信じること」の難しさについて知る
あわせて読みたい
【排除】「分かり合えない相手」だけが「間違い」か?想像力の欠如が生む「無理解」と「対立」:映画『…
「共感」が強すぎる世の中では、自然と「想像力」が失われてしまう。そうならないようにと意識して踏ん張らなければ、他人の価値観を正しく認めることができない人間になってしまうだろう。映画『ミセス・ノイズィ』から、多様な価値観を排除しない生き方を考える
あわせて読みたい
【実話】正論を振りかざす人が”強い”社会は窮屈だ。映画『すばらしき世界』が描く「正解の曖昧さ」
「SNSなどでの炎上を回避する」という気持ちから「正論を言うに留めよう」という態度がナチュラルになりつつある社会には、全員が全員の首を締め付け合っているような窮屈さを感じてしまう。西川美和『すばらしき世界』から、善悪の境界の曖昧さを体感する
あわせて読みたい
【感想】映画『窮鼠はチーズの夢を見る』を異性愛者の男性(私)はこう観た。原作も読んだ上での考察
私は「腐男子」というわけでは決してないのですが、周りにいる腐女子の方に教えを請いながら、多少BL作品に触れたことがあります。その中でもダントツに素晴らしかったのが、水城せとな『窮鼠はチーズの夢を見る』です。その映画と原作の感想、そして私なりの考察について書いていきます
あわせて読みたい
【救い】耐えられない辛さの中でどう生きるか。短歌で弱者の味方を志すホームレス少女の生き様:『セー…
死にゆく母を眺め、施設で暴力を振るわれ、拾った新聞で文字を覚えたという壮絶な過去を持つ鳥居。『セーラー服の歌人 鳥居』は、そんな辛い境遇を背景に、辛さに震えているだろう誰かを救うために短歌を生み出し続ける生き方を描き出す。凄い人がいるものだ
あわせて読みたい
【あらすじ】「愛されたい」「必要とされたい」はこんなに難しい。藤崎彩織が描く「ままならない関係性…
好きな人の隣にいたい。そんなシンプルな願いこそ、一番難しい。誰かの特別になるために「異性」であることを諦め、でも「異性」として見られないことに苦しさを覚えてしまう。藤崎彩織『ふたご』が描き出す、名前がつかない切実な関係性
あわせて読みたい
【諦め】母親の存在にモヤモヤを抱えた人生から、「生きてさえいればいい」への違和感を考える:『晴天…
生まれ育つ環境を選ぶことはできません。そして、家族との関わりや家庭環境は、その後の人生に大きな影響を及ぼします。努力するスタートラインにも立てないと感じる時、それでも前進することを諦めてはいけないのかを、『晴天の迷いクジラ』をベースに書く
あわせて読みたい
【辛い】こじらせ女子必読!ややこしさと共に生きるしかない、自分のことで精一杯なすべての人に:『女…
「こじらせ」って感覚は、伝わらない人には全然伝わりません。だからこそ余計に、自分が感じている「生きづらさ」が理解されないことにもどかしさを覚えます。AVライターに行き着いた著者の『女子をこじらせて』をベースに、ややこしさを抱えた仲間の生き方を知る
あわせて読みたい
【考察】世の中は理不尽だ。平凡な奴らがのさばる中で、”特別な私の美しい世界”を守る生き方:『オーダ…
自分以外は凡人、と考える主人公の少女はとてもイタい。しかし、世間の価値観と折り合わないなら、自分の美しい世界を守るために闘うしかない。中二病の少女が奮闘する『オーダーメイド殺人クラブ』をベースに、理解されない世界をどう生きるかについて考察する
あわせて読みたい
【覚悟】人生しんどい。その場の”空気”から敢えて外れる3人の中学生の処世術から生き方を学ぶ:『私を知…
空気を読んで摩擦を減らす方が、集団の中では大体穏やかにいられます。この記事では、様々な理由からそんな選択をしない/できない、『私を知らないで』に登場する中学生の生き方から、厳しい現実といかにして向き合うかというスタンスを学びます
あわせて読みたい
【呪縛】「良い子」に囚われ人生苦しい。どう見られるかを抜け出し、なりたい自分を生きるために:『わ…
「良い子でいなきゃいけない」と感じ、本来の自分を押し隠したまま生きているという方、いるんじゃないかと思います。私も昔はそうでした。「良い子」の呪縛から逃れることは難しいですが、「なりたい自分」をどう生きればいいかを、『わたしを見つけて』をベースに書いていきます
あわせて読みたい
【肯定】価値観の違いは受け入れられなくていい。「普通」に馴染めないからこそ見える世界:『君はレフ…
子どもの頃、周りと馴染めない感覚がとても強くて苦労しました。ただし、「普通」から意識的に外れる決断をしたことで、自分が持っている価値観を言葉で下支えすることができたとも感じています。「普通」に馴染めず、自分がダメだと感じてしまう人へ。
ルシルナ
多様性・ダイバーシティ【本・映画の感想】 | ルシルナ
私は、子どもの頃から周囲と馴染めなかったり、当たり前の感覚に違和感を覚えることが多かったこともあり、ダイバーシティが社会環境に実装されることを常に望んでいます。…
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…


























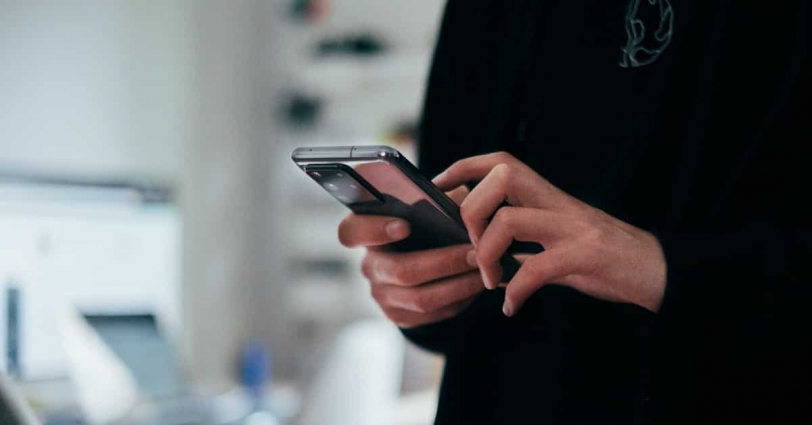
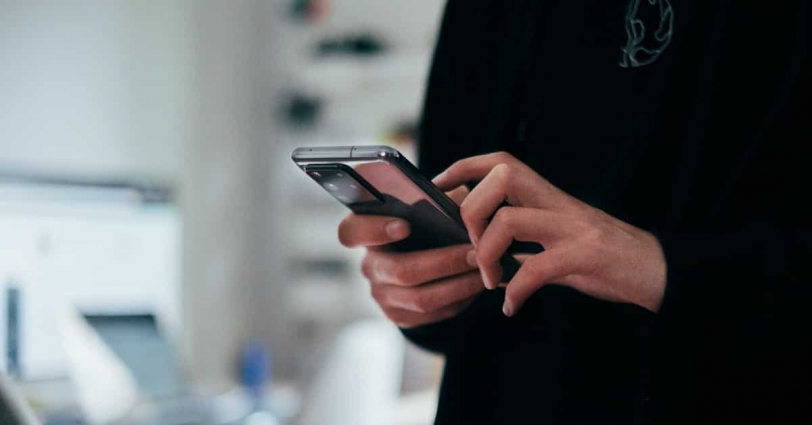
































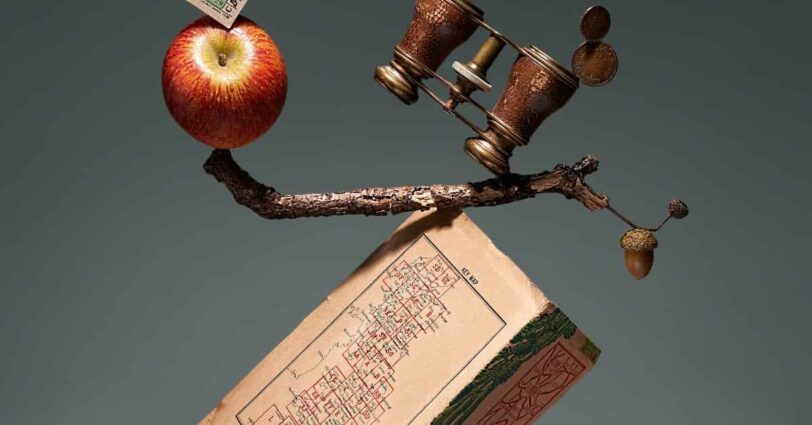
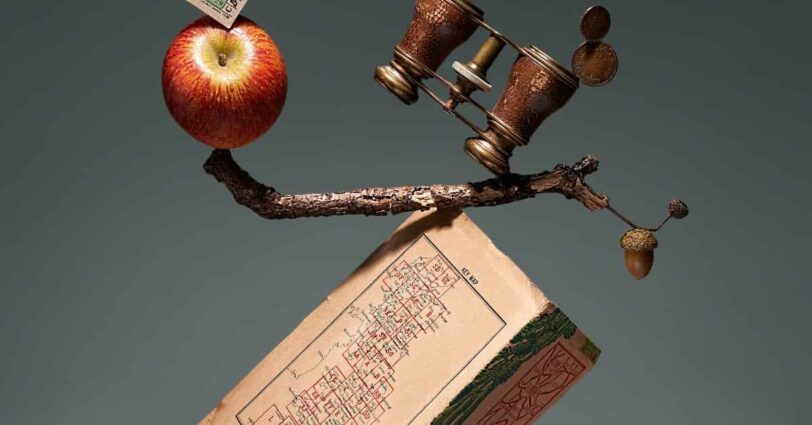


























































































































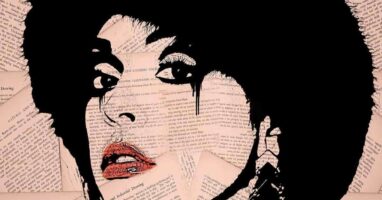
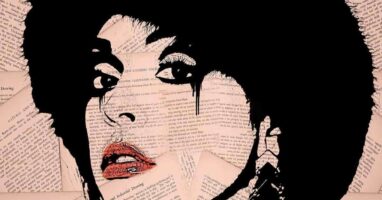
























































































































































































コメント