目次
はじめに
この記事で取り上げる映画
監督:バーセル・アドラー, Writer:バーセル・アドラー, 出演:バーセル・アドラー, 出演:ユヴァル・アブラハーム, 出演:ハムダーン・バラール
¥2,200 (2025/11/01 23:11時点 | Amazon調べ)
ポチップ
VIDEO
この映画をガイドにしながら記事を書いていきます
今どこで観れるのか?
公式HPの劇場方法 をご覧下さい
この記事の3つの要点
イスラエルの最高裁が許可を出しているとはいえ、19世紀からその地に住み続けている住民を強制的に立ち退かせるイスラエル軍の暴挙はあまりに酷い イスラエル人でありながら立ち退きの現状に憤り、パレスチナ人のバーセルに協力する形でイスラエル軍にも立ち向かうユヴァル あまりにも立場が異なるバーセルとユヴァルの関係性は、パレスチナとイスラエルの関係性そのものであり、実に残酷だなと思う お互いの間にある大きな壁を乗り越える形で横暴と立ち向かおうとする若者たちの奮闘に、「自分も出来ることをしなければ」という気分にさせられる
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
記事中の引用は、映画館で取ったメモを参考にしているので、正確なものではありません
イスラエル軍がパレスチナ人の住居をぶっ壊している衝撃の現実を映し出す映画『ノー・アザー・ランド』にはとにかく圧倒させられた。あまりにも酷すぎる世界である
本当にクソみたいな現実 だった。もちろん、イスラエルとパレスチナの間で起こっていることはすべて最低最悪 でしかないだろうし、その中で、本作で描かれている現実がどの程度のレベル感にあるのか、中東に詳しい知識を持っているわけではない私には何とも言えない 。ただ、そういうことは一旦置いておこう。本作を観れば、そのあまりの酷さに驚かされてしまう はずだ。
あわせて読みたい
【異様】映画『聖なるイチジクの種』は、イランで起こった実際の市民デモを背景にした驚愕の物語である
「家庭内で銃を紛失した」という設定しか知らずに観に行った映画『聖なるイチジクの種』は、「実際に起こった市民デモをベースに、イランという国家の狂気をあぶり出す作品」であり、思いがけず惹きつけられてしまった。「反政府的な作品」に関わった本作監督・役者・スタッフらが処罰されるなど、人生を賭けて生み出された映画でもある
本作『ノー・アザー・ランド』で映し出される、あまりにも酷すぎる現実
それではまず、本作で映し出される、そんなあまりにも最低最悪な現実 について説明しておこうと思う。焦点が当てられるのは、2019年から2023年に掛けての出来事 である。
舞台になるのは、イスラエルのヨルダン川西岸地区内にあるマサーフェル・ヤッタ という集落。ここには、作中人物が「19世紀の地図に載っている」と語るぐらいの歴史 があり、以前からパレスチナ人(アラブ人)が居住していた地域 である。
そしてそんな地域で、「イスラエル軍による住居の破壊 」が行われていたのだ。武装した軍人が大挙 してやってきて、住民に「家の中から家財道具などを全部出せ」と命令、そして空っぽになった家をそのままブルドーザーで破壊していく のである。
マジで意味が分からなかった 。イスラエル軍の理屈は後で説明するが、到底理解できるようなものではない 。
あわせて読みたい
【残念】日本の「難民受け入れ」の現実に衝撃。こんな「恥ずべき国」に生きているのだと絶望させられる…
日本の「難民認定率」が他の先進国と比べて異常に低いことは知っていた。しかし、日本の「難民」を取り巻く実状がこれほど酷いものだとはまったく知らなかった。日本で育った2人のクルド人難民に焦点を当てる映画『東京クルド』から、日本に住む「難民」の現実を知る
私はそもそも、「本作の舞台であるマサーフェル・ヤッタがヨルダン川西岸地区内にある」という事実を、鑑賞後に公式HPを見て初めて理解した (もちろん、作中での説明を私が見逃しただけかもしれないが)。そして私の理解では、「ガザ地区とヨルダン川西岸地区では、パレスチナ人の居住が認められている 」はずである。もちろん、ガザ地区がイスラエル軍から空爆を受けたりしているわけで、両地区が「パレスチナ人にとって安全な土地」なんてことはない だろう。しかしそれでも、法的には「パレスチナ人の居住が認められている土地」であるはず だ。
にも拘らず、マサーフェル・ヤッタにイスラエル軍が押し寄せ、住民がまさに今暮らしている家を壊しては彼らを強制的に追い出している のである。
では、どうしてそんなことになっているのだろうか? 本作ではその来歴について、マサーフェル・ヤッタ出身のパレスチナ人であるバーセル が説明している。彼は活動家の両親の元で育ち 、そして大人になった今、スマホを使って目の前の現実を撮影・発信することで何か事態が好転することを期待している のだ。
あわせて読みたい
【衝撃】壮絶な戦争映画。最愛の娘を「産んで後悔している」と呟く母らは、正義のために戦場に留まる:…
こんな映画、二度と存在し得ないのではないかと感じるほど衝撃を受けた『娘は戦場で生まれた』。母であり革命家でもあるジャーナリストは、爆撃の続くシリアの街を記録し続け、同じ街で娘を産み育てた。「知らなかった」で済ませていい現実じゃない。
彼は「僕がカメラを持つようになった頃から終わりが始まった 」と話していた。恐らくそれが2019年頃 であり、その頃からイスラエル軍による破壊が始まった のだと思う。彼がそう語るシーンの合間に挟み込まれたニュース映像では、「1967年の占領以来、最大規模の立ち退きの可能性 」「8つの村で1000人(別のニュースでは2500人と表示された)が危機に瀕している 」と報じられていた。
ではそのタイミングで一体何があったのか? 直接的なきっかけは恐らく、「イスラエルの最高裁がマサーフェル・ヤッタの住民を追い出す許可を出したこと 」のようである。実はこの問題は1990年代から顕在化 していた。どうやらイスラエル軍が、「マサーフェル・ヤッタは軍の訓練地である」として住民の排除を国(だと思う)に求めていた ようなのだ。それに対し住民は、裁判所に「立ち退きの取り消し」を求めて異議申し立て を行っていた。そして、裁判所は住民のこの訴えを22年掛けて退け、最高裁の決定として「マサーフェル・ヤッタの住民の立ち退き」が許可された のである。
イスラエル軍による「軍の訓練地だから」という主張が、「元々軍の訓練地だったから」なのか、あるいは「新たに軍の訓練地に指定されたから」なのかはよく分からなかった が、「マサーフェル・ヤッタが19世紀の地図に載っている」ことを踏まえると、前者の主張にはちょっと無理がある ように思う。となると後者だとしか考えられないが、しかし「新たに指定された」みたいなことはいくらでも言いようがあるし、好き放題出来てしまう だろう。そして、そんな薄弱な根拠を元に、「軍の訓練地に居住することは禁止されているし、家も水道も井戸もすべて違法なので取り壊す」などと言って実力行使を繰り出すのは、やはりちょっと異様 だと私には感じられる。
あわせて読みたい
【現実】戦争のリアルを”閉じ込めた”映画。第一次世界大戦の英軍を収めたフィルムが描く衝撃:映画『彼…
第一次世界大戦でのイギリス兵を映した膨大な白黒フィルムをカラー化して編集した『彼らは生きていた』は、白黒の映像では実感しにくい「リアルさ」を強く感じられる。そして、「戦争は思ったよりも安易に起こる」「戦争はやはりどこまでも虚しい」と実感できる
その「実力行使」は、本当に酷い の一言だ。パレスチナ人とイスラエル人ではそもそも言語が違う ようで(パレスチナ人がアラビア語で、イスラエル人の多くは英語 を話すようだ)、両者の会話はそのままでは成り立たない 。そしてイスラエル軍は、通訳など連れて来るでもなく、パレスチナ人には伝わらない言葉と身振り手振りで説明を繰り返しては家を破壊していく のだ。作中では言語の違いが字幕で区別され、「お互いが伝わらない言葉で怒鳴り合っている様子」が理解できる ようになっている。住民が何を言っても、そもそも言葉が聞き取れないイスラエル軍は全無視 、そして有無を言わさずに家をぶち壊していく というわけだ。
観ながらある種の「痛快さ」さえ感じさせられたぐらい本当にイカれた状況 だったなと思う。
イスラエル人の多くは自国の振る舞いを擁護するが、そんな中でもイスラエル人のユヴァルは現状に憤りを覚え取材を続ける
私はこういう時、「イスラエル軍の兵士たちは一体、何を考えながら家を壊しているのだろう? 」みたいなことを考えてしまう。彼らがもし、「本当は全然やりたくないが、軍の命令だから仕方ない」と思っているのであれば、まだ救いはある と言えるだろう。単に一部の権力者が暴走しているだけ であり、「上が変われば一気に状況が好転する可能性がある 」と信じていられるからだ。
あわせて読みたい
【現実】権力を乱用する中国ナチスへの抵抗の最前線・香港の民主化デモを映す衝撃の映画『時代革命』
2019年に起こった、逃亡犯条例改正案への反対運動として始まった香港の民主化デモ。その最初期からデモ参加者たちの姿をカメラに収め続けた。映画『時代革命』は、最初から最後まで「衝撃映像」しかない凄まじい作品だ。この現実は決して、「対岸の火事」ではない
ただ、あくまでも本作を観ている限りの判断にすぎないが、私の目にはとてもそんな風には見えなかった 。「通訳を連れて行かない」というのは上官の判断だろうから下の立場の人間にはどうにも出来なかったとは思うが、それにしたってイスラエルの兵士たちの言動からは、「お前たちの存在はすべて違法なんだ」という感覚のまますべてを押し切ろうという意図しか感じられなかった のだ。
とはいえ、もしも自分がイスラエルの兵士だったとしたら、「『他人の家を壊す』なんて行為はまともな神経では出来ないし、だから『自分は正しいことをしているんだ』とでも思い込まなければやっていられない」みたいにと考えるんじゃないか という気もする。本心としては「やりたくない」と思っていても、そういう気持ちを押し殺さなければ任務の遂行は不可能なわけで、だから「相手のことなど何も考えない振る舞い」になってしまっている可能性 もゼロではないだろう。まあその辺りのことは何とも判断できないものの、本作ではまた違った場面でイスラエル人の本音を知ることができる 。
本作では何度かテレビ番組の映像が挿入される のだが、その1つに「マサーフェル・ヤッタの立ち退きについて議論している番組 」のものがあった。そしてコメンテーターの1人(どんな立場の人間かは分からない)が、「軍の訓練地に居住しているのは違法なんだから、強制的に退去させられて然るべきだ」みたいな発言をしていた のである。こういう映像が差し込まれるということは、少なくとも本作の制作側は「イスラエルにはそう思っている人が多くいる」と伝えたい のだろうし、恐らくそれが実情なのだろうなとも思う。
あわせて読みたい
【デマ】情報を”選ぶ”時代に、メディアの情報の”正しさ”はどのように判断されるのか?:『ニューヨーク…
一昔前、我々は「正しい情報を欲していた」はずだ。しかしいつの間にか世の中は変わった。「欲しい情報を正しいと思う」ようになったのだ。この激変は、トランプ元大統領の台頭で一層明確になった。『ニューヨーク・タイムズを守った男』から、情報の受け取り方を問う
さて、本作のもう1人の主人公であるユヴァルはそういう多数派とは異なる感覚を持っている 。彼はイスラエル人の記者 であり、「マサーフェル・ヤッタの立ち退き問題」に憤りを覚えて取材を進めている人物 なのだ。実際に、立ち退きを迫るイスラエル兵に歯向かうような行動 を取ったりもしていた。パレスチナ人であるバーセルとイスラエル人であるユヴァルは、生まれも置かれている状況もまったく正反対 なのだが、立場を越えた関係性を築いた のである。本作は、そんな2人の”友情”をも描き出す作品 だ。
本作では何度か、バーセルとユヴァルが2人で語り合うシーン が映し出される。議論になったり、あるいは価値観を共有したりと色んなやり取りがあるのだが、いずれにせよ「2人の間にある見えない大きな壁」が浮き彫りにされることが多い 。そしてそれはそのまま、パレスチナ・イスラエルの問題の縮図(バーセルとユヴァルは別に争ってはいないが)にも感じられる だろう。
バーセルは「両親が活動家」という特殊な環境で育ったこともあり、当然のように活動家みたいな人生を歩む ことになった。さらに、勇敢だった父親は何度も逮捕されており 、そのため、今では家族を養うために給油所の仕事に専念 している。そのため、マサーフェル・ヤッタでは今、バーセルこそが抗議活動の中心 になっているのだ。彼自身も周囲からのそんな期待に自覚的であり、それに応えようと奮闘している ところである。
あわせて読みたい
【実話】映画『イミテーションゲーム』が描くエニグマ解読のドラマと悲劇、天才チューリングの不遇の死
映画『イミテーションゲーム』が描く衝撃の実話。「解読不可能」とまで言われた最強の暗号機エニグマを打ち破ったのはなんと、コンピューターの基本原理を生み出した天才数学者アラン・チューリングだった。暗号解読を実現させた驚きのプロセスと、1400万人以上を救ったとされながら偏見により自殺した不遇の人生を知る
そしてユヴァルは、そんなバーセルのことを「凄まじい」という風に見ている ようだ。「もし自分が同じ立場にいたとしても、同じようには振る舞えないだろう」と感じている のである。2人は同い年 のようで、そんなこともあってユヴァルは、バーセルが秘めている「強さ」に圧倒されている のだと思う。
そんなバーセルに触発されたユヴァルは、「マサーフェル・ヤッタが直面しているこの酷い現実を世界に伝えなければ」と強く考えている わけだが、その想いはちょっと空回ってしまってもいる 。そのことが伝わる印象的なシーン があった。車内で熱弁を振るうユヴァルにバーセルが「君は熱くなりすぎている」と諭すシーン である。こう言われたユヴァルが「ダメかな?」と返すと、バーセルは次のように冷静な主張を繰り広げていた のだ。
君は10日でこの地を離れるだろうけど、この問題は数十年も続いているんだ。すぐには解決しないし、負けたって続けていくしかないんだ。
あわせて読みたい
【危機】シードバンクを設立し世界の農業を変革した伝説の植物学者・スコウマンの生涯と作物の多様性:…
グローバル化した世界で「農業」がどんなリスクを負うのかを正しく予測し、その対策として「ジーンバンク」を設立した伝説の植物学者スコウマンの生涯を描く『地球最後の日のための種子』から、我々がいかに脆弱な世界に生きているのか、そして「世界の食」がどう守られているのかを知る
このやり取りがいつ行われたのかよく分からないが、恐らく、2人が出会ってまだそう月日が経っていない頃なんじゃないか と思う。「君は10日でこの地を離れるだろうけど」という言い方に、親しくなり切れていない微妙な距離感を感じた からだ。もちろんバーセルは別に嫌味を言ったわけではなく、単に事実を指摘したに過ぎない と思う。ユヴァルがどのくらいの期間ここにいられるにせよ、ずっとはいられないことは確か だからだ。数十年単位で継続している問題なわけで、ユヴァルがどれほどこの問題に強い想いを持っていようが、バーセルの視点からは「すぐに帰っていく」ように見えてしまうのも仕方ない と思う。
そして実際に、ユヴァルは「帰ることが出来る」 のである。
圧倒的に立場の異なるバーセルとユヴァルによる奮闘とその無力さ
「帰ることが出来る」という表現には、ざっくり2つの意味を込めた つもりである。1つは、本作のタイトルである「ノー・アザー・ランド」にも関係することではあるが、言葉通り「他に帰る場所がある」という意味 だ。彼は日々マサーフェル・ヤッタに通っているのだが、夜になるとヨルダン川西岸地区を出て、イスラエルにある自宅へと帰る 。別にそれは悪いことでも責められることでもないのだが、バーセルの立場からしたら「自分たちには他に行き場などないのに」という感覚になってしまう のも当然だろう。
あわせて読みたい
【無謀】映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、脱北ルートに撮影隊が同行する衝撃のドキュメンタリー
北朝鮮からの脱北者に同行し撮影を行う衝撃のドキュメンタリー映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、再現映像を一切使用していない衝撃的な作品だ。危険と隣り合わせの脱北の道程にカメラもついて回り、北朝鮮の厳しい現状と共に、脱北者が置かれた凄まじい状況を映し出す内容に驚かされてしまった
そしてもう1つは、「どこにでも行ける」という意味 だ。イスラエルを走る車のナンバープレートの色 には意味があり、イスラエル人は黄色、そしてパレスチナ人は緑 と決まっている。そしてイスラエル国内には、「黄色ナンバーの車でなければ通行できない道」がたくさん存在する のだ。ユヴァルの車は黄色ナンバーであり、だから彼は国内のどこへでも自由に行き来可能である。しかしバーセルの車は緑ナンバーであり、ヨルダン川西岸地区からは出られない のだ。
バーセルとユヴァルは、同じぐらい強い想いを抱いて目の前の現実に対処し、同じぐらい危険な状況に直面しながら日々の活動を続けている のだが、その両者の立場は圧倒的に異なっている 。どれだけユヴァルが熱心に取り組もうとも、彼が生まれながらにして持つ「恵まれた立場」がある意味では邪魔してしまっている というわけだ。本作では、バーセルとユヴァルが仲違いするようなシーンが映し出されたりはしない が(とはいえ、単に使われていないだけで、そういう状況がなかったとは言い切れない)、バーセルが生まれた村の住民とユヴァルが口論(当人たちは「ディベート」と言っていたが)をするような場面 はあった(ちゃんと覚えていないが、もしかしたらバーセルの父親だったかもしれない)。その住民はバーセルとユヴァルの関係に触れつつ、「こんな状況でずっと『友達』でいられると思うか? お前の親戚や友人が俺たちの家を壊している可能性だってあるんだぞ」みたいなことを言っていた のだ。
まあ、ユヴァルにそんなことを言いたくなる気持ちもよく理解できる 。なにせ前述した通り、マサーフェル・ヤッタにやってくるイスラエルの兵士とは言葉が通じない のだ。だから、アラビア語を流暢に話せるユヴァルに意見をぶつけ、「お前はどう思っているんだ?」と議論したくもなる のだろう。その気持ちはもちろん理解できるのだが、同時に「ユヴァルに文句を言ってもなぁ 」という気分になってしまうこともまた確かである。
あわせて読みたい
【あらすじ】嵐莉菜主演映画『マイスモールランド』は、日本の難民問題とクルド人の現状、入管の酷さを描く
映画『マイスモールランド』はフィクションではあるが、「日本に住む難民の厳しい現実」をリアルに描き出す作品だ。『東京クルド』『牛久』などのドキュメンタリー映画を観て「知識」としては知っていた「現実」が、当事者にどれほどの苦しみを与えるのか想像させられた
ちなみにユヴァルは、高校時代に友人と一緒にアラビア語を学んだ そうだが、そのお陰で(という表現で合っているか分からないが)、イスラエルの諜報部からスカウトが来た という。スパイ的な役割が期待されていたのだろう 。しかしユヴァルは、「アラビア語を学んだことで物事の見方が広がった 」と話しており、それ故、諜報部からのスカウトを断ることが出来た のだそうだ。以前何かの本で、「使う言語によって思考が制約される」という「サピア=ウォーフの仮説」の話を知ったが、彼も、違う言語を学んだことで世界の捉え方が変わった のだと思う。
さて、少し前に「立ち退き問題を議論するテレビ番組」の話に触れたが、その番組に、マサーフェル・ヤッタの現状を伝える側の人間として出演していたのがユヴァル である。そして彼はその中で、「パレスチナ人の自由無しには我々の安全は無い」と主張していた 。もちろん彼は本心からそう思っているはず だ。ただその一方で、「他人事だと思っていると、自分たちにも不利益がもたらされるぞ」という啓蒙的な意味も込めて、敢えてそういう強い言葉を使っている のだとも思う。
映画の後半、バーセルとユヴァルが2人で話しているシーンで、確かユヴァルだったと思うのだが、「世界が狂っていく」みたいなことを言っていた 。私も、そのことは強く感じている。私は別に、自分がまともで常識的な人間だなんてまったく思っていない。しかしそれにしたって、ムチャクチャな主張や価値観が当たり前のように蔓延する世の中になってしまったな という感覚を抱いている。そもそも、トランプ大統領を始めとする世界のリーダーがかなり極端な主張をして耳目を集めている し、PV数や再生数を稼ぎたいインフルエンサー的な人たちも「分かりやすいワンイシュー」ばかり強調するようになっている ように思う。もちろん、情報の受け手にも問題がある だろう。特に、若い世代に顕著らしいが、「情報の真偽」を「発信者のフォロワー数」や「その情報が閲覧された数」などで判断する人がいるみたい なのだ。正直私には「狂気の沙汰」としか思えない が、一方で、「そりゃあ、誤情報があっさり広まっていくわけだよな 」とも納得させられる。
あわせて読みたい
【考察】A24のホラー映画『TALK TO ME』が描くのは、「薄く広がった人間関係」に悩む若者のリアルだ
「A24のホラー映画史上、北米最高興収」と謳われる『TALK TO ME トーク・トゥ・ミー』は、一見「とても分かりやすいホラー映画」である。しかし真のテーマは「SNS過剰社会における人間関係の困難さ」なのだと思う。結果としてSNSが人と人との距離を遠ざけてしまっている現実を、ホラー映画のスタイルに落とし込んだ怪作
そりゃあ、世界も狂っていく だろうよ。
そして、パレスチナ・イスラエルの争いはまさに、そんな「狂気」が最大化されたもの であるようにも思う。さらにバーセルとユヴァルは、そんな「狂った世界」の中でどうにか「まとも側」に踏み留まろうと考え、「正しいことを正しいようにやる」という信念だけで行動し続けている ように私には見えた。
あまりにも難しすぎる問題ではあるが、我々にも何か出来ることはあるはずだ
さて、強制的に住居を奪われているマサーフェル・ヤッタの住民たちは、この現実にどう対処しているのだろうか? 実は彼らは「非暴力的な抵抗 」を続けている。イスラエル軍は、まさに暴力を詰め込んだようなムチャクチャなやり方で立ち退きを迫ってくる わけだが、住民たちは、家や水道管を壊されようが、井戸を埋められようが、長年暮らし続けた土地を離れずに留まっている のだ。何もかもが破壊された場所で生活を続けるのはあまりにも茨の道 だろうが、それでも身一つで立ち退きに抵抗し続けるのは、「暴力なんかに屈してたまるか」という強い想いの現れ なのだと思う。
あわせて読みたい
【思想】川口大三郎は何故、早稲田を牛耳る革マル派に殺された?映画『ゲバルトの杜』が映す真実
映画『ゲバルトの杜』は、「『革マル派』という左翼の集団に牛耳られた早稲田大学内で、何の罪もない大学生・川口大三郎がリンチの末に殺された」という衝撃的な事件を、当時を知る様々な証言者の話と、鴻上尚史演出による劇映画パートによって炙り出すドキュメンタリー映画だ。同じ国で起こった出来事とは思えないほど狂気的で驚かされた
だからこそ、バーセルが口にした次のような指摘は、私にはとても印象的 に感じられた。
確かに今彼らは、強い軍と技術力を持っている。
確かにその通りだなと思う。イスラエルは、たぶんアメリカの支援を受けて、昔と比べたら軍事力が強化されている のだろうが、建国当初はパレスチナと同じように「弱かった」 はずだ。そしてパレスチナとイスラエルは、その頃から(というか、それ以前から)ずっと争いを続けている のである。今は軍事力という意味でパワーバランスに圧倒的な差 が存在するが、そんな「暴力」では結局何も解決出来ない 。「北風と太陽」の「北風」みたいな発想では乗り越えられない状況なのである。
ただ一方で、「暴力」で押し切ろうとするイスラエルはそもそも、「『解決』なんて別に望んじゃいない」のだろう とも思う。「本質的に『解決』しなくても、何となく『終結』すれば十分 」みたいに考えているのだろう。イスラエル(ネタニヤフ首相)だけではなく、プーチンやトランプなども同じように考えている気がする し、そういう「暴力で圧倒して相手に有無を言わせない」みたいなやり方がデフォルトになりつつある ようにも思う。当事者の一方がそういう立場であれば当然、本質的な「解決」など到底望めるはずがない 。であれば、イスラエルに住むパレスチナ人はこれからもしんどい状況に置かれ続けてしまう のだろう。
あわせて読みたい
【実話】「ホロコーストの映画」を観て改めて、「有事だから仕方ない」と言い訳しない人間でありたいと…
ノルウェーの警察が、自国在住のユダヤ人をまとめて船に乗せアウシュビッツへと送った衝撃の実話を元にした映画『ホロコーストの罪人』では、「自分はそんな愚かではない」と楽観してはいられない現実が映し出される。このような悲劇は、現在に至るまで幾度も起こっているのだ
本当に狂っている なと感じるし、そんな世界に生きていると思うとうんざり させられてしまいもする。
ただ、諦めるのはまだ早い だろう。作中で誰かが、「水1滴じゃダメでも、滴が出続ければ何かが変わるはず 」みたいなことを言っていた。イスラエルが「住居を破壊する」なんて横暴を当たり前のように続けられるのも、そんな現状が世界にあまり知られていないから だろう。この現実を知る人が1人でも増えれば(「滴」が溜まっていけば)、大きなうねりとなって何かをぐわっと動かしていける かもしれない。
私たちはそういう希望を持ちながら世界の色んな現実を知るべき だし、「そのことが酷い現状を変えるきっかけになる」と信じたい なと改めて実感させられた。
あわせて読みたい
【SDGs】パリコレデザイナー中里唯馬がファッション界の大量生産・大量消費マインド脱却に挑む映画:『…
映画『燃えるドレスを紡いで』は、世界的ファッションデザイナーである中里唯馬が、「服の墓場」と言うべきナイロビの現状を踏まえ、「もう服を作るのは止めましょう」というメッセージをパリコレの場から発信するまでを映し出すドキュメンタリー映画である。個人レベルで社会を変革しようとする凄まじい行動力と才能に圧倒させられた
あわせて読みたい
【全作品視聴済】私が観てきたドキュメンタリー映画を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が観てきたドキュメンタリー映画を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。
最後に
パレスチナとイスラエルの争いは数世紀にも及ぶ ものであり、さらに宗教やら民族やら戦争やら大国の思惑やらが色々入り混じり、もう訳の分からない問題になってしまっている と思う。「世界一解決が難しい問題 」という表現も目にしたことがあるし、簡単には状況が変わったりしないだろう 。
しかしそれでも、「解決の道は存在するはず」と信じて前に進むしかない し、遠く離れた地のことではあるが、私たちも「何か出来ることはないだろうか?」という視点を持ち続けなければならない と思う。
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を…
Kindleで本を出版しました。タイトルは、『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を分かりやすく書いた本:相対性理論も宇宙論も量子論も』です。科学や科学者に関する、文系の人でも読んでもらえる作品に仕上げました。そんな自著について紹介をしています。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【壮絶】映画『フロントライン』は「コロナパンデミックの発端」におけるDMATの奮闘をリアルに描く(監…
映画『フロントライン』は、ド級の役者が集ったド級のエンタメ作品でありながら、「フィクションっぽさ」が非常に薄い映画でもあり、「起こった出来事をリアルに描く」という制作陣の覚悟が感じられた。マスコミ報道を通じて知ったつもりになっている「事実」が覆される内容で、あの時の混乱を知るすべての人が観るべき映画だと思う
あわせて読みたい
【未来】6度目の大量絶滅時代を生きる今、映画『アニマル』を観て気候変動の現状と対策を知るべき
映画『アニマル ぼくたちと動物のこと』は、環境問題や気候変動の現状・問題を改めて突きつけるドキュメンタリーだ。16歳の若き環境活動家2人が世界中を巡り、現状を確認したり専門家に話を聞いたりする構成で、彼らはその過程で「誰も『解決策』を持っていない」と知り驚かされる。これからどう生きるべきか考えさせられる作品だ
あわせて読みたい
【煽動】プロパガンダの天才ゲッベルスがいかにヒトラーやナチスを”演出”したのかを描く映画:『ゲッベ…
映画『ゲッベルス ヒトラーをプロデュースした男』では、ナチスドイツで宣伝大臣を担当したヨーゼフ・ゲッベルスに焦点が当てられる。「プロパガンダの天才」と呼ばれた彼は、いかにして国民の感情を操作したのか。「現代の扇動家」に騙されないためにも、そんな彼の数奇な人生や実像を理解しておいた方がいいのではないかと思う
あわせて読みたい
【評価】都知事選出馬、安芸高田市長時代の「恥を知れ」などで知られる石丸伸二を描く映画『掟』
石丸伸二をモデルに描くフィクション映画『掟』は、「地方政治に無関心な人」に現状の酷さを伝え、「自分ごと」として捉えてもらうきっかけとして機能し得る作品ではないかと感じた。首長がどれだけ変革しようと試みても、旧弊な理屈が邪魔をして何も決まらない。そんな「地方政治の絶望」が本作には詰め込まれているように思う
あわせて読みたい
【平和】巣鴨プリズン収監のBC級戦犯だった冬至堅太郎の貴重な記録から知られざる歴史を紐解く映画:『…
映画『巣鴨日記 あるBC級戦犯の生涯』は、一般的にはまったく詳しいことが知られていないという「BC級戦犯」に関するドキュメンタリー映画である。巣鴨プリズンに収監された冬至堅太郎がつけていた日記、そして横浜軍事法廷で行われた彼の裁判の記録。これらを基に知られざる戦後史が明らかにされていく
あわせて読みたい
【悲劇】東京大空襲経験者の体験談。壊滅した浅草、隅田川の遺体、その後の人々の暮らし等の証言集:映…
映画『東京大空襲 CARPET BOMBING of Tokyo』は、2時間半で10万人の命が奪われたという「東京大空襲」を始め、「山手空襲」「八王子空襲」などを実際に経験した者たちの証言が収録された作品だ。そのあまりに悲惨な実態と、その記憶を具体的にはっきりと語る証言者の姿、そのどちらにも驚かされてしまった
あわせて読みたい
【信念】映画『太陽の運命』は、2人の知事、大田昌秀・翁長雄志から沖縄の基地問題の歴史を追う(監督:…
映画『太陽(ティダ)の運命』は、米軍基地問題に翻弄され続けた沖縄の歴史を、大田昌秀・翁長雄志という2人の知事に焦点を当てることで浮き彫りにしていくドキュメンタリー映画である。「日本一難しい問題を背負わされている」という沖縄県知事の苦悩と、「2人の間にあった様々な因縁」がないまぜになった数奇な“運命”の物語
あわせて読みたい
【人権】フランスの民主主義は死んではいないか?映画『暴力をめぐる対話』が問う「権力の行使」の是非
映画『暴力をめぐる対話』は、「『黄色いベスト運動』のデモの映像を観ながら『警察による暴力』について討論を行う者たちを映し出す映画」である。「デモの映像」と「討論の様子」だけというシンプル過ぎる作品で、その上内容はかなり高度でついていくのが難しいのだが、「民主主義とは何か?」について考えさせる、実に有意義なやり取りだなと思う
あわせて読みたい
【権力】コンクラーベをリアルに描く映画『教皇選挙』は、ミステリ的にも秀逸で面白い超社会派物語(監…
映画『教皇選挙』は、「カトリックの教皇を選ぶコンクラーベ」という、一般的な日本人にはまず馴染みのないテーマながら劇場が満員になるほどで、まずそのことに驚かされた。本質的には「権力争い」なのだが、そこに「神に仕える者」という宗教ならではの要素が組み込まれることによって特異で狂気的な状況が生み出されている
あわせて読みたい
【人権】チリ女性の怒り爆発!家父長制と腐敗政治への大規模な市民デモを映し出すドキュメンタリー:映…
「第2のチリ革命」とも呼ばれる2019年の市民デモを映し出すドキュメンタリー映画『私の想う国』は、家父長制と腐敗政治を背景にかなり厳しい状況に置かれている女性たちの怒りに焦点が当てられる。そのデモがきっかけとなったチリの変化も興味深いが、やはり「楽しそうにデモをやるなぁ」という部分にも惹きつけられた
あわせて読みたい
【包容】映画『違国日記』を観て思う。「他者との接し方」が皆こうだったらもっと平和なはずだって(主…
映画『違国日記』は、人見知りの小説家・高代槙生が両親を亡くした姪・朝を引き取り一緒に暮らすところから始まる物語で、槙生と朝を中心とした様々な人間関係が絶妙に描かれている作品でした。人付き合いが苦手ながら、15歳という繊細な存在を壊さないように、でも腫れ物みたいには扱わないように慎重になる槙生のスタンスが素敵です
あわせて読みたい
【冷戦】”アメリカのビートルズ”と評された、「鉄のカーテンを超えた初のロックバンド」を襲った悲劇:…
映画『ブラッド・スウェット&ティアーズに何が起こったのか?』では、米ソ冷戦の最中に人気を博したロックバンド・BS&Tが辿った数奇な運命を描き出すドキュメンタリー映画である。当時は公表できなかった理由により「鉄のカーテン」の向こう側に行かざるを得なかった彼らは、何を見て、どんな不遇に直面させられたのか?
あわせて読みたい
【異様】映画『聖なるイチジクの種』は、イランで起こった実際の市民デモを背景にした驚愕の物語である
「家庭内で銃を紛失した」という設定しか知らずに観に行った映画『聖なるイチジクの種』は、「実際に起こった市民デモをベースに、イランという国家の狂気をあぶり出す作品」であり、思いがけず惹きつけられてしまった。「反政府的な作品」に関わった本作監督・役者・スタッフらが処罰されるなど、人生を賭けて生み出された映画でもある
あわせて読みたい
【忌避】小児性愛者から子どもを救え!映画『サウンド・オブ・フリーダム』が描く衝撃の実話(主演:ジ…
映画『サウンド・オブ・フリーダム』は、世界的に大問題となっている「子どもの人身売買」を扱った、実話を基にした物語である。「フィクションとしか思えないようなおとり捜査」を実行に移した主人公の凄まじい奮闘と、「小児性愛者の変態的欲望」の餌食になる悲惨な子どもたちの現実をリアルに描き出していく
あわせて読みたい
【父親】パキスタン本国では上映禁止の映画『ジョイランド』は、古い価値観に翻弄される家族を描く
映画『ジョイランド』は、本国パキスタンで一時上映禁止とされた作品だが、私たち日本人からすれば「どうして?」と感じるような内容だと思う。「(旧弊な)家族観を否定している」と受け取られたからだろうが、それにしたってやはり理不尽だ。そしてそんな「家族のややこしさ」には、現代日本を生きる我々も共感できるに違いない
あわせて読みたい
【解説】映画『シビル・ウォー アメリカ最後の日』は、凄まじい臨場感で内戦を描き、我々を警告する(…
映画『シビル・ウォー』は、「アメリカで勃発した内戦が長期化し、既に日常になってしまっている」という現実を圧倒的な臨場感で描き出す作品だ。戦争を伝える報道カメラマンを主人公に据え、「戦争そのもの」よりも「誰にどう戦争を伝えるか」に焦点を当てる本作は、様々な葛藤を抱きながら最前線を目指す者たちを切り取っていく
あわせて読みたい
【変異】映画『動物界』は斬新で刺激的な作品だった。我々はまさにこんな”分断社会”に生きている
映画『動物界』では、「奇病によって人間が動物化してしまう」という世界における複雑な人間模様が描き出される。パンデミックを経験した我々には、本作の設定は「単なるSF」には感じられないはずだ。そしてその上で、「『動物化してしまった妻を今も愛している主人公』が見せる実にややこしい感情」が複層的に描かれていて実に興味深い
あわせて読みたい
【感動】映画『ボストン1947』は、アメリカ駐留時代の朝鮮がマラソンで奇跡を起こした実話を描く
映画『ボストン1947』は、アメリカ軍駐留時代の朝鮮を舞台に、様々な困難を乗り越えながらボストンマラソン出場を目指す者たちの奮闘を描き出す物語。日本統治下で日本人としてメダルを授与された”国民の英雄”ソン・ギジョンを中心に、「東洋の小国の奇跡」と評された驚くべき成果を実現させた者たちの努力と葛藤の実話である
あわせて読みたい
【思想】川口大三郎は何故、早稲田を牛耳る革マル派に殺された?映画『ゲバルトの杜』が映す真実
映画『ゲバルトの杜』は、「『革マル派』という左翼の集団に牛耳られた早稲田大学内で、何の罪もない大学生・川口大三郎がリンチの末に殺された」という衝撃的な事件を、当時を知る様々な証言者の話と、鴻上尚史演出による劇映画パートによって炙り出すドキュメンタリー映画だ。同じ国で起こった出来事とは思えないほど狂気的で驚かされた
あわせて読みたい
【実話】株仲買人が「イギリスのシンドラー」に。映画『ONE LIFE』が描くユダヤ難民救出(主演:アンソ…
実話を基にした映画『ONE LIFE 奇跡が繋いだ6000の命』は、「イギリスに住むニコラス・ウィントンがチェコのユダヤ人難民を救う」という話であり、仲間と共に669名も救助した知られざる偉業が扱われている。多くの人に知られるべき歴史だと思うし、また、主演を務めたアンソニー・ホプキンスの演技にも圧倒されてしまった
あわせて読みたい
【絶望】知られざる「国による嘘」!映画『蟻の兵隊』(池谷薫)が映し出す終戦直後の日本の欺瞞
映画『蟻の兵隊』は、「1945年8月15日の終戦以降も上官の命令で中国に残らされ、中国の内戦を闘った残留日本軍部隊」の1人である奥村和一を追うドキュメンタリー映画だ。「自らの意思で残った」と判断された彼らは、国からの戦後補償を受けられていない。そんな凄まじい現実と、奥村和一の驚くべき「誠実さ」が描かれる作品である
あわせて読みたい
【SDGs】パリコレデザイナー中里唯馬がファッション界の大量生産・大量消費マインド脱却に挑む映画:『…
映画『燃えるドレスを紡いで』は、世界的ファッションデザイナーである中里唯馬が、「服の墓場」と言うべきナイロビの現状を踏まえ、「もう服を作るのは止めましょう」というメッセージをパリコレの場から発信するまでを映し出すドキュメンタリー映画である。個人レベルで社会を変革しようとする凄まじい行動力と才能に圧倒させられた
あわせて読みたい
【衝撃】EUの難民問題の狂気的縮図!ポーランド・ベラルーシ国境での、国による非人道的対応:映画『人…
上映に際し政府から妨害を受けたという映画『人間の境界』は、ポーランド・ベラルーシ国境で起こっていた凄まじい現実が描かれている。「両国間で中東からの難民を押し付け合う」という醜悪さは見るに絶えないが、そのような状況下でも「可能な範囲でどうにか人助けをしたい」と考える者たちの奮闘には救われる思いがした
あわせて読みたい
【正義】ナン・ゴールディンの”覚悟”を映し出す映画『美と殺戮のすべて』が描く衝撃の薬害事件
映画『美と殺戮のすべて』は、写真家ナン・ゴールディンの凄まじい闘いが映し出されるドキュメンタリー映画である。ターゲットとなるのは、美術界にその名を轟かすサックラー家。なんと、彼らが創業した製薬会社で製造された処方薬によって、アメリカでは既に50万人が死亡しているのだ。そんな異次元の薬害事件が扱われる驚くべき作品
あわせて読みたい
【真相】飯塚事件は冤罪で死刑執行されたのか?西日本新聞・警察・弁護士が語る葛藤と贖罪:映画『正義…
映画『正義の行方』では、冤罪のまま死刑が執行されたかもしれない「飯塚事件」が扱われる。「久間三千年が犯行を行ったのか」という議論とは別に、「当時の捜査・司法手続きは正しかったのか?」という観点からも捉え直されるべきだし、それを自発的に行った西日本新聞の「再検証連載」はとても素晴らしかったと思う
あわせて読みたい
【実話】映画『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』が描く、白人警官による黒人射殺事件
映画『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』は、2011年に起こった実際の事件を元にした作品である。何の罪もない黒人男性が、白人警官に射殺されてしまったのだ。5時22分から始まる状況をほぼリアルタイムで描き切る83分間の物語には、役者の凄まじい演技も含め、圧倒されてしまった
あわせて読みたい
【挑戦】映画『燃えあがる女性記者たち』が描く、インドカースト最下位・ダリットの女性による報道
映画『燃えあがる女性記者たち』は、インドで「カースト外の不可触民」として扱われるダリットの女性たちが立ち上げた新聞社「カバル・ラハリヤ」を取り上げる。自身の境遇に抗って、辛い状況にいる人の声を届けたり権力者を糾弾したりする彼女たちの奮闘ぶりが、インドの民主主義を変革させるかもしれない
あわせて読みたい
【日本】原発再稼働が進むが、その安全性は?樋口英明の画期的判決とソーラーシェアリングを知る:映画…
映画『原発をとめた裁判長 そして原発をとめる農家たち』では、大飯原発の運転差し止め判決を下した裁判長による画期的な「樋口理論」の説明に重点が置かれる。「原発の耐震性」に関して知らないことが満載で、実に興味深かった。また、農家が発案した「ソーラーシェアリング」という新たな発電方法も注目である
あわせて読みたい
【衝撃】ミキ・デザキが映画『主戦場』で示す「慰安婦問題」の実相。歴史修正主義者の発言がヤバすぎ
「慰安婦問題」に真正面から取り組んだ映画『主戦場』は、「『慰安婦問題』の根幹はどこにあるのか?」というその複雑さに焦点を当てていく。この記事では、本作で映し出された様々な情報を元に「慰安婦問題」について整理したものの、結局のところ「解決不可能な問題である」という結論に行き着いてしまった
あわせて読みたい
【実話】田舎暮らし失敗。映画『理想郷』が描く、めんどくさい人間関係が嫌がらせに発展した事件
実話を基にした映画『理想郷』は、「理想の田舎暮らし」が粉微塵に粉砕されていく過程を描く物語である。第一義的には当然、夫妻に嫌がらせを続ける兄弟が悪いのだが、しかしそのように捉えるだけでは何も変わらないだろう。双方の譲れない「価値観」が否応なしに正面衝突する状況で、一体何が「正解」となり得るだろうか?
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『戦場のピアニスト』(ロマン・ポランスキー)が描く、ユダヤ人迫害の衝撃の実話
映画『戦場のピアニスト』の4Kリマスター版を観に行ったところ、上映後のトークイベントに主人公の息子が登壇したので驚いた。何せ私は、本作が「実話を基にしている」ことさえ知らなかったのである。だからその驚きもひとしおだった。ホロコーストの生存者である主人公の壮絶な人生を描き出す、不朽の名作だ
あわせて読みたい
【あらすじ】原爆を作った人の後悔・葛藤を描く映画『オッペンハイマー』のための予習と評価(クリスト…
クリストファー・ノーラン監督作品『オッペンハイマー』は、原爆開発を主導した人物の葛藤・苦悩を複雑に描き出す作品だ。人間が持つ「多面性」を様々な方向から捉えようとする作品であり、受け取り方は人それぞれ異なるだろう。鑑賞前に知っておいた方がいい知識についてまとめたので、参考にしてほしい
あわせて読みたい
【挑戦】杉並区長・岸本聡子を誕生させた市民運動・選挙戦と、ミュニシパリズムの可能性を描く:『映画…
映画『映画 ◯月◯日、区長になる女。』は、杉並区初の女性区長・岸本聡子を誕生させた選挙戦の裏側を中心に、日本の民主主義を問う作品だ。劇場公開されるや、チケットを取るのが困難なほど観客が殺到した作品であり、観れば日本の政治の「変化」を感じられるのではないかと思う
あわせて読みたい
【感想】関東大震災前後を描く映画『福田村事件』(森達也)は、社会が孕む「思考停止」と「差別問題」…
森達也監督初の劇映画である『福田村事件』は、100年前の関東大震災直後に起こった「デマを起点とする悲劇」が扱われる作品だ。しかし、そんな作品全体が伝えるメッセージは、「100年前よりも現代の方がよりヤバい」だと私は感じた。SNS時代だからこそ意識すべき問題の詰まった、挑発的な作品である
あわせて読みたい
【脅迫】原発という巨大権力と闘ったモーリーン・カーニーをイザベル・ユペールが熱演する映画『私はモ…
実話を基にした映画『私はモーリーン・カーニー』は、前半の流れからはちょっと想像もつかないような展開を見せる物語だ。原発企業で従業員の雇用を守る労働組合の代表を務める主人公が、巨大権力に立ち向かった挙げ句に自宅で襲撃されてしまうという物語から、「良き被害者」という捉え方の”狂気”が浮かび上がる
あわせて読みたい
【絶望】安倍首相へのヤジが”排除”された衝撃の事件から、日本の民主主義の危機を考える:映画『ヤジと…
映画『ヤジと民主主義 劇場拡大版』が映し出すのは、「政治家にヤジを飛ばしただけで国家権力に制止させられた個人」を巡る凄まじい現実だ。「表現の自由」を威圧的に抑えつけようとする国家の横暴は、まさに「民主主義」の危機を象徴していると言えるだろう。全国民が知るべき、とんでもない事件である
あわせて読みたい
【実話】映画『月』(石井裕也)は、障害者施設での虐待事件から「見て見ぬふりする社会」を抉る(出演…
実際に起こった障害者施設殺傷事件を基にした映画『月』(石井裕也)は、観客を作中世界に引きずり込み、「これはお前たちの物語だぞ」と刃を突きつける圧巻の作品だ。「意思疎通が不可能なら殺していい」という主張には誰もが反対するはずだが、しかしその態度は、ブーメランのように私たちに戻ってくることになる
あわせて読みたい
【現実】我々が食べてる魚は奴隷船が獲ったもの?映画『ゴースト・フリート』が描く驚くべき漁業の問題
私たちは、「奴隷」が獲った魚を食べているのかもしれない。映画『ゴースト・フリート』が描くのは、「拉致され、数十年も遠洋船上に隔離されながら漁をさせられている奴隷」の存在だ。本作は、その信じがたい現実に挑む女性活動家を追うドキュメンタリー映画であり、まさに世界が関心を持つべき問題だと思う
あわせて読みたい
【衝撃】映画『誰がハマーショルドを殺したか』は、予想外すぎる着地を見せる普通じゃないドキュメンタリー
国連事務総長だったハマーショルドが乗ったチャーター機が不審な墜落を遂げた事件を、ドキュメンタリー映画監督マッツ・ブリュガーが追う映画『誰がハマーショルドを殺したか』は、予想もつかない衝撃の展開を見せる作品だ。全世界を揺るがしかねない驚きの”真実”とは?
あわせて読みたい
【狂気】映画『ニューオーダー』の衝撃。法という秩序を混沌で駆逐する”悪”に圧倒されっ放しの86分
映画『ニューオーダー』は、理解不能でノンストップな展開に誘われる問題作だ。「貧富の差」や「法の支配」など「現実に存在する秩序」がひっくり返され、対極に振り切った「新秩序」に乗っ取られた世界をリアルに描き出すことで、私たちが今進んでいる道筋に警鐘を鳴らす作品になっている
あわせて読みたい
【狂気】入管の収容所を隠し撮りした映画『牛久』は、日本の難民受け入れ問題を抉るドキュメンタリー
映画『牛久』は、記録装置の持ち込みが一切禁じられている入管の収容施設に無許可でカメラを持ち込み、そこに収容されている難民申請者の声を隠し撮りした映像で構成された作品だ。日本という国家が、国際標準と照らしていかに酷い振る舞いをしているのかが理解できる衝撃作である
あわせて読みたい
【現実】映画『私のはなし 部落のはなし』で初めて同和・部落問題を考えた。差別はいかに生まれ、続くのか
私はずっと、「部落差別なんてものが存在する意味が分からない」と感じてきたが、映画『私のはなし 部落のはなし』を観てようやく、「どうしてそんな差別が存在し得るのか」という歴史が何となく理解できた。非常に複雑で解決の難しい問題だが、まずは多くの人が正しく理解することが必要だと言えるだろう
あわせて読みたい
【驚愕】ベリングキャットの調査報道がプーチンを追い詰める。映画『ナワリヌイ』が示す暗殺未遂の真実
弁護士であり、登録者数640万人を超えるYouTuberでもあるアレクセイ・ナワリヌイは、プーチンに対抗して大統領選挙に出馬しようとしたせいで暗殺されかかった。その実行犯を特定する調査をベリングキャットと共に行った記録映画『ナワリヌイ』は、現実とは思えないあまりの衝撃に満ちている
あわせて読みたい
【抵抗】若者よ、映画『これは君の闘争だ』を見ろ!学校閉鎖に反対する学生運動がブラジルの闇を照らす
映画『これは君の闘争だ』で描かれるのは、厳しい状況に置かれた貧困層の学生たちによる公権力との闘いだ。「貧困層ばかりが通う」とされる公立校が大幅に再編されることを知った学生が高校を占拠して立て籠もる決断に至った背景を、ドキュメンタリー映画とは思えないナレーションで描く異色作
あわせて読みたい
【驚愕】本屋大賞受賞作『同志少女よ、敵を撃て』(逢坂冬馬)は凄まじい。戦場は人間を”怪物”にする
デビュー作で本屋大賞を受賞した『同志少女よ、敵を撃て』(逢坂冬馬)は、デビュー作であることを抜きにしても凄まじすぎる、規格外の小説だった。ソ連に実在した「女性狙撃兵」の視点から「独ソ戦」を描く物語は、生死の境でギリギリの葛藤や決断に直面する女性たちのとんでもない生き様を活写する
あわせて読みたい
【デモ】クーデター後の軍事政権下のミャンマー。ドキュメンタリーさえ撮れない治安の中での映画制作:…
ベルリン国際映画祭でドキュメンタリー賞を受賞したミャンマー映画『ミャンマー・ダイアリーズ』はしかし、後半になればなるほどフィクショナルな映像が多くなる。クーデター後、映画制作が禁じられたミャンマーで、10人の”匿名”監督が死を賭して撮影した映像に込められた凄まじいリアルとは?
あわせて読みたい
【映画】『戦場記者』須賀川拓が、ニュースに乗らない中東・ウクライナの現実と報道の限界を切り取る
TBS所属の特派員・須賀川拓は、ロンドンを拠点に各国の取材を行っている。映画『戦場記者』は、そんな彼が中東を取材した映像をまとめたドキュメンタリーだ。ハマスを巡って食い違うガザ地区とイスラエル、ウクライナ侵攻直後に現地入りした際の様子、アフガニスタンの壮絶な薬物中毒の現実を映し出す
あわせて読みたい
【傑物】フランスに最も愛された政治家シモーヌ・ヴェイユの、強制収容所から国連までの凄絶な歩み:映…
「フランスに最も愛された政治家」と評されるシモーヌ・ヴェイユ。映画『シモーヌ』は、そんな彼女が強制収容所を生き延び、後に旧弊な社会を変革したその凄まじい功績を描き出す作品だ。「強制収容所からの生還が失敗に思える」とさえ感じたという戦後のフランスの中で、彼女はいかに革新的な歩みを続けたのか
あわせて読みたい
【生還】内戦下のシリアでISISに拘束された男の実話を基にした映画『ある人質』が描く壮絶すぎる現実
実話を基にした映画『ある人質 生還までの398日』は、内戦下のシリアでISISに拘束された男の壮絶な日々が描かれる。「テロリストとは交渉しない」という方針を徹底して貫くデンマーク政府のスタンスに翻弄されつつも、救出のために家族が懸命に奮闘する物語に圧倒される
あわせて読みたい
【実話】ソ連の衝撃の事実を隠蔽する記者と暴く記者。映画『赤い闇』が描くジャーナリズムの役割と実態
ソ連の「闇」を暴いた名もなき記者の実話を描いた映画『赤い闇』は、「メディアの存在意義」と「メディアとの接し方」を問いかける作品だ。「真実」を届ける「社会の公器」であるべきメディアは、容易に腐敗し得る。情報の受け手である私たちの意識も改めなければならない
あわせて読みたい
【衝撃】匿名監督によるドキュメンタリー映画『理大囲城』は、香港デモ最大の衝撃である籠城戦の内部を映す
香港民主化デモにおける最大の衝撃を内側から描く映画『理大囲城』は、とんでもないドキュメンタリー映画だった。香港理工大学での13日間に渡る籠城戦のリアルを、デモ隊と共に残って撮影し続けた匿名監督たちによる映像は、ギリギリの判断を迫られる若者たちの壮絶な現実を映し出す
あわせて読みたい
【解説】実話を基にした映画『シカゴ7裁判』で知る、「権力の暴走」と、それに正面から立ち向かう爽快さ
ベトナム戦争に反対する若者たちによるデモと、その後開かれた裁判の実話を描く『シカゴ7裁判』はメチャクチャ面白い映画だった。無理筋の起訴を押し付けられる主席検事、常軌を逸した言動を繰り返す不適格な判事、そして一枚岩にはなれない被告人たち。魅力満載の1本だ
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』で描かれる、グアンタナモ”刑務所”の衝撃の実話は必見
ベネディクト・カンバーバッチが制作を熱望した衝撃の映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』は、アメリカの信じがたい実話を基にしている。「9.11の首謀者」として不当に拘束され続けた男を「救おうとする者」と「追い詰めようとする者」の奮闘が、「アメリカの闇」を暴き出す
あわせて読みたい
【執念】「桶川ストーカー事件」で警察とマスコミの怠慢を暴き、社会を動かした清水潔の凄まじい取材:…
『殺人犯はそこにいる』(文庫X)で凄まじい巨悪を暴いた清水潔は、それよりずっと以前、週刊誌記者時代にも「桶川ストーカー殺人事件」で壮絶な取材を行っていた。著者の奮闘を契機に「ストーカー規制法」が制定されたほどの事件は、何故起こり、どんな問題を喚起したのか
あわせて読みたい
【あらすじ】蝦夷地の歴史と英雄・阿弖流為を描く高橋克彦の超大作小説『火怨』は全人類必読の超傑作
大げさではなく、「死ぬまでに絶対に読んでほしい1冊」としてお勧めしたい高橋克彦『火怨』は凄まじい小説だ。歴史が苦手で嫌いな私でも、上下1000ページの物語を一気読みだった。人間が人間として生きていく上で大事なものが詰まった、矜持と信念に溢れた物語に酔いしれてほしい
あわせて読みたい
【幸福】「死の克服」は「生の充実」となり得るか?映画『HUMAN LOST 人間失格』が描く超管理社会
アニメ映画『HUMAN LOST 人間失格』では、「死の克服」と「管理社会」が分かちがたく結びついた世界が描かれる。私たちは既に「緩やかな管理社会」を生きているが、この映画ほどの管理社会を果たして許容できるだろうか?そしてあなたは、「死」を克服したいと願うだろうか?
あわせて読みたい
【奇跡】信念を貫いた男が国の制度を変えた。特別養子縁組を実現させた石巻の産婦人科医の執念:『赤ち…
遊郭で生まれ育った石巻の医師が声を上げ、あらゆる障害をなぎ倒して前進したお陰で「特別養子縁組」の制度が実現した。そんな産婦人科医・菊田昇の生涯を描き出す小説『赤ちゃんをわが子として育てる方を求む』には、法を犯してでも信念を貫いた男の衝撃の人生が描かれている
あわせて読みたい
【あらすじ】嵐莉菜主演映画『マイスモールランド』は、日本の難民問題とクルド人の現状、入管の酷さを描く
映画『マイスモールランド』はフィクションではあるが、「日本に住む難民の厳しい現実」をリアルに描き出す作品だ。『東京クルド』『牛久』などのドキュメンタリー映画を観て「知識」としては知っていた「現実」が、当事者にどれほどの苦しみを与えるのか想像させられた
あわせて読みたい
【差別】映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』の衝撃。プーチンが支持する国の蛮行・LGBT狩り
プーチン大統領の後ろ盾を得て独裁を維持しているチェチェン共和国。その国で「ゲイ狩り」と呼ぶしかない異常事態が継続している。映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』は、そんな現実を命がけで映し出し、「現代版ホロコースト」に立ち向かう支援団体の奮闘も描く作品
あわせて読みたい
【異次元】『ハイパーハードボイルドグルメリポート』は本も読め。衝撃すぎるドキュメンタリーだぞ
テレビ東京の上出遼平が作る、“異次元のグルメ番組”である「ハイパーハードボイルドグルメリポート」の書籍化。映像からも異様さが伝わる「激ヤバ地」に赴き、そこに住む者と同じモノを食べるという狂気が凄まじい。私がテレビで見た「ケニアのゴミ山の少年」の話は衝撃的だった
あわせて読みたい
【あらすじ】死刑囚を救い出す実話を基にした映画『黒い司法』が指摘する、死刑制度の問題と黒人差別の現実
アメリカで死刑囚の支援を行う団体を立ち上げた若者の実話を基にした映画『黒い司法 0%からの奇跡』は、「死刑制度」の存在価値について考えさせる。上映後のトークイベントで、アメリカにおける「死刑制度」と「黒人差別」の結びつきを知り、一層驚かされた
あわせて読みたい
【事件】デュポン社のテフロン加工が有害だと示した男の執念の実話を描く映画『ダーク・ウォーターズ』
世界的大企業デュポン社が、自社製品「テフロン」の危険性を40年以上前に把握しながら公表せず、莫大な利益を上げてきた事件の真相を暴き出した1人の弁護士がいる。映画『ダーク・ウォーターズ』は、大企業相手に闘いを挑み、住民と正義のために走り続けた実在の人物の勇敢さを描き出す
あわせて読みたい
【現実】権力を乱用する中国ナチスへの抵抗の最前線・香港の民主化デモを映す衝撃の映画『時代革命』
2019年に起こった、逃亡犯条例改正案への反対運動として始まった香港の民主化デモ。その最初期からデモ参加者たちの姿をカメラに収め続けた。映画『時代革命』は、最初から最後まで「衝撃映像」しかない凄まじい作品だ。この現実は決して、「対岸の火事」ではない
あわせて読みたい
【歴史】『大地の子』を凌駕する中国残留孤児の現実。中国から奇跡的に”帰国”した父を城戸久枝が描く:…
文化大革命の最中、国交が成立していなかった中国から自力で帰国した中国残留孤児がいた。その娘である城戸久枝が著した『あの戦争から遠く離れて』は、父の特異な体験を起点に「中国残留孤児」の問題に分け入り、歴史の大きなうねりを個人史として体感させてくれる作品だ
あわせて読みたい
【アメリカ】長崎の「原爆ドーム」はなぜ残らなかった?爆心地にあった「浦上天主堂」の数奇な歴史:『…
原爆投下で半壊し、廃墟と化したキリスト教の大聖堂「浦上天主堂」。しかし何故か、「長崎の原爆ドーム」としては残されず、解体されてしまった。そのため長崎には原爆ドームがないのである。『ナガサキ 消えたもう一つの「原爆ドーム」』は、「浦上天主堂」を巡る知られざる歴史を掘り下げ、アメリカの強かさを描き出す
あわせて読みたい
【衝撃】洗脳を自ら脱した著者の『カルト脱出記』から、「社会・集団の洗脳」を避ける生き方を知る
「聖書研究に熱心な日本人証人」として「エホバの証人」で活動しながら、その聖書研究をきっかけに自ら「洗脳」を脱した著者の体験を著した『カルト脱出記』。広い意味での「洗脳」は社会のそこかしこに蔓延っているからこそ、著者の体験を「他人事」だと無視することはできない
あわせて読みたい
【感想】リドリー・スコット監督の映画『最後の決闘裁判』から、社会が”幻想”を共有する背景とその悲劇…
例えば、「1万円札」というただの紙切れに「価値を感じる」のは、社会の構成員が同じ「共同幻想」の中に生きているからだ。リドリー・スコット監督の映画『最後の決闘裁判』は、「強姦では妊娠しない」「裁判の勝者を決闘で決する」という社会通念と、現代にも通じる「共同幻想」の強さを描き出す
あわせて読みたい
【衝撃】権力の濫用、政治腐敗を描く映画『コレクティブ』は他人事じゃない。「国家の嘘」を監視せよ
火災で一命を取り留め入院していた患者が次々に死亡した原因が「表示の10倍に薄められた消毒液」だと暴き、国家の腐敗を追及した『ガゼタ』誌の奮闘を描く映画『コレクティブ 国家の嘘』は、「権力の監視」が機能しなくなった国家の成れの果てが映し出される衝撃作だ
あわせて読みたい
【信念】水俣病の真実を世界に伝えた写真家ユージン・スミスを描く映画。真実とは「痛みへの共感」だ:…
私はその存在をまったく知らなかったが、「水俣病」を「世界中が知る公害」にした報道写真家がいる。映画『MINAMATA―ミナマタ―』は、水俣病の真実を世界に伝えたユージン・スミスの知られざる生涯と、理不尽に立ち向かう多くの人々の奮闘を描き出す
あわせて読みたい
【日常】難民問題の現状をスマホで撮る映画。タリバンから死刑宣告を受けた監督が家族と逃避行:『ミッ…
アフガニスタンを追われた家族4人が、ヨーロッパまで5600kmの逃避行を3台のスマホで撮影した映画『ミッドナイト・トラベラー』は、「『難民の厳しい現実』を切り取った作品」ではない。「家族アルバム」のような「笑顔溢れる日々」が難民にもあるのだと想像させてくれる
あわせて読みたい
【衝撃】『殺人犯はそこにいる』が実話だとは。真犯人・ルパンを野放しにした警察・司法を信じられるか?
タイトルを伏せられた覆面本「文庫X」としても話題になった『殺人犯はそこにいる』。「北関東で起こったある事件の取材」が、「私たちが生きる社会の根底を揺るがす信じがたい事実」を焙り出すことになった衝撃の展開。まさか「司法が真犯人を野放しにする」なんてことが実際に起こるとは。大げさではなく、全国民必読の1冊だと思う
あわせて読みたい
【実話】「ホロコーストの映画」を観て改めて、「有事だから仕方ない」と言い訳しない人間でありたいと…
ノルウェーの警察が、自国在住のユダヤ人をまとめて船に乗せアウシュビッツへと送った衝撃の実話を元にした映画『ホロコーストの罪人』では、「自分はそんな愚かではない」と楽観してはいられない現実が映し出される。このような悲劇は、現在に至るまで幾度も起こっているのだ
あわせて読みたい
【民主主義】占領下の沖縄での衝撃の実話「サンマ裁判」で、魚売りのおばぁの訴えがアメリカをひっかき…
戦後の沖縄で、魚売りのおばぁが起こした「サンマ裁判」は、様々な人が絡む大きな流れを生み出し、最終的に沖縄返還のきっかけともなった。そんな「サンマ裁判」を描く映画『サンマデモクラシー』から、民主主義のあり方と、今も沖縄に残り続ける問題について考える
あわせて読みたい
【葛藤】正義とは何かを突きつける戦争映画。80人を救うために1人の少女を殺すボタンを押せるか?:『ア…
「80人の命を救うために、1人の少女の命を奪わなければならない」としたら、あなたはその決断を下せるだろうか?会議室で展開される現代の戦争を描く映画『アイ・イン・ザ・スカイ』から、「誤った問い」に答えを出さなければならない極限状況での葛藤を理解する
あわせて読みたい
【残念】日本の「難民受け入れ」の現実に衝撃。こんな「恥ずべき国」に生きているのだと絶望させられる…
日本の「難民認定率」が他の先進国と比べて異常に低いことは知っていた。しかし、日本の「難民」を取り巻く実状がこれほど酷いものだとはまったく知らなかった。日本で育った2人のクルド人難民に焦点を当てる映画『東京クルド』から、日本に住む「難民」の現実を知る
あわせて読みたい
【実話】権力の濫用を監視するマスコミが「教会の暗部」を暴く映画『スポットライト』が現代社会を斬る
地方紙である「ボストン・グローブ紙」は、数多くの神父が長年に渡り子どもに対して性的虐待を行い、その事実を教会全体で隠蔽していたという衝撃の事実を明らかにした。彼らの奮闘の実話を映画化した『スポットライト』から、「権力の監視」の重要性を改めて理解する
あわせて読みたい
【考察】アニメ映画『虐殺器官』は、「便利さが無関心を生む現実」をリアルに描く”無関心ではいられない…
便利すぎる世の中に生きていると、「この便利さはどのように生み出されているのか」を想像しなくなる。そしてその「無関心」は、世界を確実に悪化させてしまう。伊藤計劃の小説を原作とするアニメ映画『虐殺器官』から、「無関心という残虐さ」と「想像することの大事さ」を知る
あわせて読みたい
【真実】ホロコーストが裁判で争われた衝撃の実話が映画化。”明らかな虚偽”にどう立ち向かうべきか:『…
「ホロコーストが起こったか否か」が、なんとイギリスの裁判で争われたことがある。その衝撃の実話を元にした『否定と肯定』では、「真実とは何か?」「情報をどう信じるべきか?」が問われる。「フェイクニュース」という言葉が当たり前に使われる世界に生きているからこそ知っておくべき事実
あわせて読みたい
【想像力】「知らなかったから仕方ない」で済ませていいのか?第二の「光州事件」は今もどこかで起きて…
「心地いい情報」だけに浸り、「知るべきことを知らなくても恥ずかしくない世の中」を生きてしまっている私たちは、世界で何が起こっているのかあまりに知らない。「光州事件」を描く映画『タクシー運転手 約束は海を越えて』から、世界の見方を考える
あわせて読みたい
【驚愕】正義は、人間の尊厳を奪わずに貫かれるべきだ。独裁政権を打倒した韓国の民衆の奮闘を描く映画…
たった30年前の韓国で、これほど恐ろしい出来事が起こっていたとは。「正義の実現」のために苛烈な「スパイ狩り」を行う秘密警察の横暴をきっかけに民主化運動が激化し、独裁政権が打倒された史実を描く『1987、ある闘いの真実』から、「正義」について考える
あわせて読みたい
【勇敢】”報道”は被害者を生む。私たちも同罪だ。”批判”による”正義の実現”は正義だろうか?:『リチャ…
「爆弾事件の被害を最小限に食い止めた英雄」が、メディアの勇み足のせいで「爆弾事件の犯人」と報じられてしまった実話を元にした映画『リチャード・ジュエル』から、「他人を公然と批判する行為」の是非と、「再発防止という名の正義」のあり方について考える
あわせて読みたい
【権利】衝撃のドキュメンタリー映画『ヤクザと憲法』は、「異質さを排除する社会」と「生きる権利」を問う
「ヤクザ」が排除された現在でも、「ヤクザが担ってきた機能」が不要になるわけじゃない。ではそれを、公権力が代替するのだろうか?実際の組事務所(東組清勇会)にカメラを持ち込むドキュメンタリー映画『ヤクザと憲法』が映し出す川口和秀・松山尚人・河野裕之の姿から、「基本的人権」のあり方について考えさせられた
あわせて読みたい
【告発】アメリカに”監視”される社会を暴露したスノーデンの苦悩と決断を映し出す映画:『スノーデン』…
NSA(アメリカ国家安全保障局)の最高機密にまでアクセスできたエドワード・スノーデンは、その機密情報を持ち出し内部告発を行った。「アメリカは世界中の通信を傍受している」と。『シチズンフォー』と『スノーデン』の2作品から、彼の告発内容とその葛藤を知る
あわせて読みたい
【史実】太平洋戦争末期に原爆を落としたアメリカは、なぜ終戦後比較的穏やかな占領政策を取ったか?:…
『八月十五日に吹く風』は小説だが、史実を基にした作品だ。本作では、「終戦直前に原爆を落としながら、なぜ比較的平穏な占領政策を行ったか?」の疑問が解き明かされる。『源氏物語』との出会いで日本を愛するようになった「ロナルド・リーン(仮名)」の知られざる奮闘を知る
あわせて読みたい
【絶望】権力の濫用を止めるのは我々だ。映画『新聞記者』から「ソフトな独裁国家・日本」の今を知る
私個人は、「ビジョンの達成」のためなら「ソフトな独裁」を許容する。しかし今の日本は、そもそも「ビジョン」などなく、「ソフトな独裁状態」だけが続いていると感じた。映画『新聞記者』をベースに、私たちがどれだけ絶望的な国に生きているのかを理解する
あわせて読みたい
【改心】人生のリセットは困難だが不可能ではない。過去をやり直す強い意思をいかにして持つか:映画『S…
私は、「自分の正しさを疑わない人」が嫌いだ。そして、「正しさを他人に押し付ける人」が嫌いだ。「変わりたいと望む者の足を引っ張る人」が嫌いだ。全身刺青だらけのレイシストが人生をやり直す、実話を元にした映画『SKIN/スキン』から、再生について考える
あわせて読みたい
【正義】マイノリティはどう生き、どう扱われるべきかを描く映画。「ルールを守る」だけが正解か?:映…
社会的弱者が闘争の末に権利を勝ち取ってきた歴史を知った上で私は、闘わずとも権利が認められるべきだと思っている。そして、そういう社会でない以上、「正義のためにルールを破るしかない」状況もある。映画『パブリック』から、ルールと正義のバランスを考える
あわせて読みたい
【勇敢】後悔しない生き方のために”間違い”を犯せるか?法に背いてでも正義を貫いた女性の生き様:映画…
国の諜報機関の職員でありながら、「イラク戦争を正当化する」という巨大な策略を知り、守秘義務違反をおかしてまで真実を明らかにしようとした実在の女性を描く映画『オフィシャル・シークレット』から、「法を守る」こと以上に重要な生き方の指針を学ぶ
あわせて読みたい
【情熱】「ルール」は守るため”だけ”に存在するのか?正義を実現するための「ルール」のあり方は?:映…
「ルールは守らなければならない」というのは大前提だが、常に例外は存在する。どれほど重度の自閉症患者でも断らない無許可の施設で、情熱を持って問題に対処する主人公を描く映画『スペシャルズ!』から、「ルールのあるべき姿」を考える
あわせて読みたい
【排除】「分かり合えない相手」だけが「間違い」か?想像力の欠如が生む「無理解」と「対立」:映画『…
「共感」が強すぎる世の中では、自然と「想像力」が失われてしまう。そうならないようにと意識して踏ん張らなければ、他人の価値観を正しく認めることができない人間になってしまうだろう。映画『ミセス・ノイズィ』から、多様な価値観を排除しない生き方を考える
あわせて読みたい
【天才】『三島由紀夫vs東大全共闘』後に「伝説の討論」と呼ばれる天才のバトルを記録した驚異の映像
1969年5月13日、三島由紀夫と1000人の東大全共闘の討論が行われた。TBSだけが撮影していたフィルムを元に構成された映画「三島由紀夫vs東大全共闘」は、知的興奮に満ち溢れている。切腹の一年半前の討論から、三島由紀夫が考えていたことと、そのスタンスを学ぶ
あわせて読みたい
【挑戦】自閉症のイメージを変えるおすすめ本。知的障害と”思い込む”専門家に挑む母子の闘い:『自閉症…
専門家の思い込みを覆し、自閉症のイメージを激変させた少年・イド。知的障害だと思われていた少年は、母親を通じコミュニケーションが取れるようになり、その知性を証明した。『自閉症の僕が「ありがとう」を言えるまで』が突きつける驚きの真実
あわせて読みたい
【デマ】情報を”選ぶ”時代に、メディアの情報の”正しさ”はどのように判断されるのか?:『ニューヨーク…
一昔前、我々は「正しい情報を欲していた」はずだ。しかしいつの間にか世の中は変わった。「欲しい情報を正しいと思う」ようになったのだ。この激変は、トランプ元大統領の台頭で一層明確になった。『ニューヨーク・タイムズを守った男』から、情報の受け取り方を問う
あわせて読みたい
【加虐】メディアの役割とは?森達也『A』が提示した「事実を報じる限界」と「思考停止社会」
オウム真理教の内部に潜入した、森達也のドキュメンタリー映画『A』は衝撃を与えた。しかしそれは、宗教団体ではなく、社会の方を切り取った作品だった。思考することを止めた社会の加虐性と、客観的な事実など切り取れないという現実について書く
あわせて読みたい
【衝撃】壮絶な戦争映画。最愛の娘を「産んで後悔している」と呟く母らは、正義のために戦場に留まる:…
こんな映画、二度と存在し得ないのではないかと感じるほど衝撃を受けた『娘は戦場で生まれた』。母であり革命家でもあるジャーナリストは、爆撃の続くシリアの街を記録し続け、同じ街で娘を産み育てた。「知らなかった」で済ませていい現実じゃない。
あわせて読みたい
【勇敢】日本を救った吉田昌郎と、福島第一原発事故に死を賭して立ち向かった者たちの極限を知る:『死…
日本は、死を覚悟して福島第一原発に残った「Fukushima50」に救われた。東京を含めた東日本が壊滅してもおかしくなかった大災害において、現場の人間が何を考えどう行動したのかを、『死の淵を見た男』をベースに書く。全日本人必読の書
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
理不尽・ストレス・イライラする【本・映画の感想】 | ルシルナ
「理不尽だなー」と感じてしまうことはよくあります。クレームや怒りなど、悪意や無理解から責められることもあるでしょうし、多数派や常識的な考え方に合わせられないとい…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…






















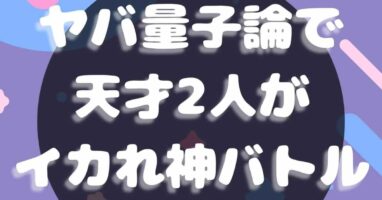









































































































コメント