目次
はじめに
あわせて読みたい
オススメ記事一覧(本・映画の感想・レビュー・解説)
本・映画の感想ブログ「ルシルナ」の中から、「読んでほしい記事」を一覧にしてまとめました。「ルシルナ」に初めて訪れてくれた方は、まずここから記事を選んでいただくのも良いでしょう。基本的には「オススメの本・映画」しか紹介していませんが、その中でも管理人が「記事内容もオススメ」と判断した記事をセレクトしています。
この記事で取り上げる映画
出演:平野鈴, 出演:佐藤亮, 出演:伊藤綾子, 出演:田山幹雄, 出演:手塚加奈子, Writer:濱口竜介, 監督:濱口竜介, クリエイター:—
 ポチップ
ポチップ
この映画をガイドにしながら記事を書いていくようだよ
この記事で伝えたいこと
「言葉が屹立する場面」が随所にあり、その「言葉の力」に何度も圧倒された
学生が制作する、どうしても制約の多い作品だからこそ、余計に「言葉」が持つ力が重要に感じられた
この記事の3つの要点
- 「暴力と選択」という詩の朗読や、ラブレターの音読の凄まじいインパクト
- 夜明け前の橋の上でカップルが語る場面と、あるカップルが別れた理由を示唆する場面での「すれ違い」の描写が見事
- 「未開の部族の成人の儀式」から語られる「勇気」の話はとても印象的
最初こそ面白い作品なのかと不安を抱きましたが、美しいラストに至る4時間、堪能させられました
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
記事中の引用は、映画館で取ったメモを参考にしているので、正確なものではありません
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!「それってホントに『コミュ力』が高いって言えるの?」と疑問を感じている方に…
私は、「コミュ力が高い人」に関するよくある主張に、どうも違和感を覚えてしまうことが多くあります。そしてその一番大きな理由が、「『コミュ力が高い人』って、ただ『想像力がない』だけではないか?」と感じてしまう点にあると言っていいでしょう。出版したKindle本は、「ネガティブには見えないネガティブな人」(隠れネガティブ)を取り上げながら、「『コミュ力』って何だっけ?」と考え直してもらえる内容に仕上げたつもりです。
映画『親密さ』は、「映像」よりも「言葉」のインパクトが強い作品だったことに驚かされっぱなしだった
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『悪は存在しない』(濱口竜介)の衝撃のラストの解釈と、タイトルが示唆する現実(主…
映画『悪は存在しない』(濱口竜介監督)は、観る者すべてを困惑に叩き落とす衝撃のラストに、鑑賞直後は迷子のような状態になってしまうだろう。しかし、作中で提示される様々な要素を紐解き、私なりの解釈に辿り着いた。全編に渡り『悪は存在しない』というタイトルを強く意識させられる、脚本・映像も見事な作品だ
内容に触れる前にまず、この映画を観るに至った流れに触れておきたいと思います。

まず、「絶対に観ない」と決めていた『ドライブ・マイ・カー』を2021年の年末に観ました。観ないと決めていた理由は、以下の記事を読んでください。
あわせて読みたい
【傑作】濱口竜介監督の映画『ドライブ・マイ・カー』(原作:村上春樹)は「自然な不自然さ」が見事な作品
村上春樹の短編小説を原作にした映画『ドライブ・マイ・カー』(濱口竜介監督)は、村上春樹の小説の雰囲気に似た「自然な不自然さ」を醸し出す。「不自然」でしかない世界をいかにして「自然」に見せているのか、そして「自然な不自然さ」は作品全体にどんな影響を与えているのか
それから、同じ監督の作品だと初めて知り、これまた「絶対に観ない」と決めていた『偶然と想像』を見に行くことにします。
あわせて読みたい
【あらすじ】濱口竜介監督『偶然と想像』は、「脚本」と「役者」のみで成り立つ凄まじい映画。天才だと思う
「映画」というメディアを構成する要素は多々あるはずだが、濱口竜介監督作『偶然と想像』は、「脚本」と「役者」だけで狂気・感動・爆笑を生み出してしまう驚異の作品だ。まったく異なる3話オムニバス作品で、どの話も「ずっと観ていられる」と感じるほど素敵だった
どちらもとにかく素晴らしい映画で、こんな映画が成立し得るのかと感じるほど見事な作品でした。
2021年の年末に『ドライブ・マイ・カー』、そして2022年の年始に『偶然と想像』だったからね
凄い作品で終わり、凄い作品で始まったなぁ、って感じだったよ
その後、映画の話もする友人と『ドライブ・マイ・カー』『偶然と想像』について語っていたのですが、その友人から「下北沢のK2という新しく出来た映画館で、濱口竜介監督の過去作品を上映している」という話を耳にします。調べてみると、「『偶然と想像』公開記念 濱口竜介監督特集上映<言葉との乗り物>」というイベントが、全国のいくつかの映画館で行われていることを知りました。
濱口竜介監督特集上映《言葉と乗り…
濱口竜介監督特集上映《言葉と乗り物》特設ページ|映画『偶然と想像』公式サイト
濱口竜介最新作『偶然と想像』までの濱口竜介の歩みをたどる監督作をセレクトし特集上映します。
その中から、自分のスケジュールを踏まえて観られる作品を選んだところ、この『親密さ』という映画に行き着いた、というわけです。
本当に、何かがちょっと違っていれば『ドライブ・マイ・カー』『偶然と想像』『親密さ』のどれもすべて観る機会はなかったと思うので、そういうタイミングの良さも含めて、濱口竜介監督作品との出会いは非常に印象的でした。
あわせて読みたい
【革新】映画音楽における唯一のルールは「ルールなど無い」だ。”異次元の音”を生み出す天才を追う:映…
「無声映画」から始まった映画業界で、音楽の重要性はいかに認識されたのか?『JAWS』の印象的な音楽を生み出した天才は、映画音楽に何をもたらしたのか?様々な映画の実際の映像を組み込みながら、「映画音楽」の世界を深堀りする映画『すばらしき映画音楽たち』で、異才たちの「創作」に触れる
さて、内容に触れる前に、先にこの映画の構成をざっと説明しておきましょう。映画はなんと4時間という長尺で、前後半に分かれます。前半は、「ある劇団が次回公演作を準備する」という物語であり、そして後半はなんと、前半で準備された演劇が丸々収録されるという斬新な構成です。映画も演劇も共に『親密さ』というタイトルであり、「『親密さ』という舞台演劇を準備する者たちを描く『親密さ』という映画の中で、実際に『親密さ』という舞台公演が行われる」という構成になります。

この映画の作りだけ見ても、非常に異端的な作品だと言えるでしょう。
「映像」がおまけに感じられる、「言葉」がメインになる作品
『ドライブ・マイ・カー』『偶然と想像』の記事の中で私は、濱口竜介作品の「動き」「感情」の希薄さについて触れました。「映像」を構成する要素として、役者の動きや感情の表出などは非常に重要なはずですが、濱口竜介作品ではそれらが徹底的に抑制されているのです。そのことがどのような効果を生んでいるのかについては、是非それぞれの記事を読んでください。
あわせて読みたい
【傑作】濱口竜介監督の映画『ドライブ・マイ・カー』(原作:村上春樹)は「自然な不自然さ」が見事な作品
村上春樹の短編小説を原作にした映画『ドライブ・マイ・カー』(濱口竜介監督)は、村上春樹の小説の雰囲気に似た「自然な不自然さ」を醸し出す。「不自然」でしかない世界をいかにして「自然」に見せているのか、そして「自然な不自然さ」は作品全体にどんな影響を与えているのか
あわせて読みたい
【あらすじ】濱口竜介監督『偶然と想像』は、「脚本」と「役者」のみで成り立つ凄まじい映画。天才だと思う
「映画」というメディアを構成する要素は多々あるはずだが、濱口竜介監督作『偶然と想像』は、「脚本」と「役者」だけで狂気・感動・爆笑を生み出してしまう驚異の作品だ。まったく異なる3話オムニバス作品で、どの話も「ずっと観ていられる」と感じるほど素敵だった
映画『親密さ』では、「動き」は一般的な映画とさほど変わらないと思いますが、やはり「感情」は抑え気味です。しかしこの点については正直、意図的なものなのかは判断が難しいと感じます。というのもこの映画は、「ENBUゼミナール」という専門学校の卒業制作として作成されたもので、役者はその専門学校の学生だからです。正直、お世辞にも「上手い」とは言い難い役者であり、「感情を表に出していない」のか「感情を表に出せていない」のかは判断に迷ってしまいます。
ただ「演技の良し悪し」は正直、「映画の良し悪し」にはさほど直結していないって感じはする
映画が始まってしばらくは「大丈夫だろうか」って思ってたけど、最終的には「メチャクチャ良い映画を観たな」って感じたしね
そういう意味で映画『親密さ』は、『ドライブ・マイ・カー』『偶然と想像』で感じたような「『動き』と『感情』を抑制することで成立させている映画」という印象にはなりませんでした。
『親密さ』を成立させているのは「言葉」の力だと感じます。

あわせて読みたい
【継続】「言語化できない」を乗り越えろ。「読者としての文章術」で、自分の思考をクリアにする:『読…
ブログやSNSなどが登場したことで、文章を書く機会は増えていると言える。しかし同時に、「他人に評価されるために書く」という意識も強くなっているだろう。『読みたいことを書けばいい』から、「楽しく書き”続ける”」ための心得を学ぶ
『偶然と想像』について私は、「脚本がこの作品を成立させている」と書きました。「脚本」も「言葉」ではありますが、『親密さ』では「脚本」というよりも「言葉」そのものの力が前面に出ているという印象です。『ドライブ・マイ・カー』や『偶然と想像』に既に触れている私としては、『親密さ』のストーリーそのものは、映画も劇中劇もそこまで大したものには感じられませんでした。ただ、随所で「言葉」が屹立し、その存在感をぎょっとさせるレベルで示すことで、撮影機材・撮影場所・役者・資金などにどうしても制約が出るだろう「専門学校の卒業制作」において、そのクオリティを高めることに成功しているのだと私は感じます。
なのでこの記事では、映画や劇中劇に登場する「言葉が屹立する場面」を取り上げる形で話を進めていくことにしましょう。
「暴力と選択」という詩の朗読
映画『親密さ』の主人公の1人である良平は、劇中劇『親密さ』の脚本を担当しており、さらに「衛」という役名で劇中劇にも登場します。衛は、自作の詩を朗読し合う会に参加しているという設定で、その中で朗読される詩の1つが「暴力と選択」です。
この詩が私にはとても響きました。劇中劇では計4作の詩が朗読されるのですが、他の詩は正直まったく覚えていません。この「暴力と選択」だけが、圧倒的な質量で私の内側にドンと届いたのです。私としては、映画『親密さ』全体の中で一番好きな場面と言っていいかもしれません。

「詩」というにはちょっと論理的すぎる文章かもしれないけど、私はすごく好きだった
世間の感覚とズレてるけど、言われてみれば確かにそうかもしれない、と思わせる内容が絶妙だよね
衛はもの凄い早口でこの詩を朗読するので、正直そのすべてを記憶・整理できたわけではありませんが、私が覚えている範囲の内容をなんとなく再現してみます。
あわせて読みたい
【表現者】「センスが良い」という言葉に逃げない。自分の内側から何かを表現することの本質:『作詞少…
大前提として、表現には「技術」が必要だ。しかし、「技術」だけでは乗り越えられない部分も当然ある。それを「あいつはセンスが良いから」という言葉に逃げずに、向き合ってぶつかっていくための心得とは何か。『作詞少女』をベースに「表現することの本質」を探る
暴力とは何か。それは、「相手から選択肢を奪うこと、もしくは『選択など不可能だ』と相手に信じ込ませること」だ。
たとえ身体を殴られたり傷を負わされたとしても、そこにまだ選択肢が残っているのならば、それは「暴力」と呼ばれないと考えていいのではないか。
そしてこのように定義することで、肉体的な暴力以外の暴力も定義することができる。
つまり、肉体的な苦痛を伴わなくても、そこに選択肢がなければそれは「暴力」だと言っていいということだ。
さて今ここに、暴力と呼びたいような状況に直面している者がいるとしよう。
しかしその者にはまだ選択肢が残っている。
それでもその者は、「自分は暴力を振るわれた」と主張するだろう。
そしてこの場合、選択肢が残っているのに「暴力を振るわれた」と叫ぶ者の存在こそが、むしろ「暴力」と呼ばれるべきなのではないだろうか。

正直、このように書いてみたところで、映画で聞いた時の感動をまったく再現できておらず歯がゆいです。内容的にはもっと様々な話に触れており、「私たちは『選べない』ということだけは選ぶことができない」という論理的帰結にも非常に共感したのですが、再現できるほどには記憶がありません。
劇中劇『親密さ』の脚本は、「良平」役の俳優・佐藤亮が実際に書いているらしいから、この詩も彼の手によるものかもね
そもそも「良平」も「衛」も、他人との共感性が非常に薄く、理屈っぽく人を丸め込むような話し方をする人物であり、そのような性質もまた、この「暴力と選択」という詩の内容にマッチしていたと思います。まくしたてるように一気に言葉を吐き出す衛の「狂気」は、ある種「暴力的」とも言えるものであり、そんな口調で「暴力とは選択肢を奪うことだ」という内容の詩を朗読しているという異様さにも惹かれてしまいました。
あわせて読みたい
【矛盾】死刑囚を「教誨師」視点で描く映画。理解が及ばない”死刑という現実”が突きつけられる
先進国では数少なくなった「死刑存置国」である日本。社会が人間の命を奪うことを許容する制度は、果たして矛盾なく存在し得るのだろうか?死刑確定囚と対話する教誨師を主人公に、死刑制度の実状をあぶり出す映画『教誨師』から、死刑という現実を理解する
詩そのものは、映画の内容とも劇中劇の内容ともそこまでリンクするわけではない、離れ小島のような要素ではあるのですが、とにかくガツンとやられたインパクト大の場面でした。
一気に書き上げたラブレターを電話越しに読み上げる
劇中劇には、ある女性が手紙の内容を親友女性に電話越しに聞かせる、という場面も出てきます。このシーンも非常に良かったです。まさにこれも、「言葉」だけで状況を支配していると感じる場面であり、惹き込まれてしまいました。
女性が書いたのはラブレターで、相手は、血の繋がらない兄のルームメイトである郵便局員です。彼女はその郵便局員と友人として仲が良く、あけすけに自分の色んな話をしてしまっています。実は彼女は誰とでもセックスをしてしまうところがあり、大学でも「サークルクラッシャー」と呼ばれる存在です。そしてそういう話も郵便局員に自分の口から伝えてしまっています。彼女は真剣に彼のことが好きなのですが、ただ普通に想いを伝えるだけでは自分の気持ちは絶対に伝わらないはず、とも考えているわけです。
あわせて読みたい
【感想】映画『窮鼠はチーズの夢を見る』を異性愛者の男性(私)はこう観た。原作も読んだ上での考察
私は「腐男子」というわけでは決してないのですが、周りにいる腐女子の方に教えを請いながら、多少BL作品に触れたことがあります。その中でもダントツに素晴らしかったのが、水城せとな『窮鼠はチーズの夢を見る』です。その映画と原作の感想、そして私なりの考察について書いていきます
これまでは、兄のルームメイトだということもあり、当たり前のように合える関係でした。とりあえずその状態に満足していたのですが、その郵便局員が突然引っ越しすると決まり、彼女は失意の底に沈んでしまいます。これはきちんと想いを伝えるしかないと決意した彼女は一気に手紙を書き上げますが、その内容に自信が持てず、親友に電話で聞いてもらっている、という場面です。
この手紙の内容も非常に素敵でした。

あわせて読みたい
【あらすじ】映画『レザボア・ドッグス』(タランティーノ監督)はとにかく驚異的に脚本が面白い!
クエンティン・タランティーノ初の長編監督作『レザボア・ドッグス』は、のけぞるほど面白い映画だった。低予算という制約を逆手に取った「会話劇」の構成・展開があまりにも絶妙で、舞台がほぼ固定されているにも拘らずストーリーが面白すぎる。天才はやはり、デビュー作から天才だったのだなと実感させられた
この手紙で、劇中劇でのその女性の印象が一気に変わるぐらいのインパクトがあった
内容に具体的には触れませんが、「あなたが私のことをどう見ているか理解しているつもりですが、私は真剣にあなたに想いを伝えたいと思っているし、これまであなたにしてきた言動のすべては『愛してほしい』の言い換えです」と必死で伝える内容に、心揺さぶられました。
橋の上で脚本家と演出家が話をする
映画の中で、映像的にとても美しいのが「橋の上での会話」の場面でしょう。劇中劇『親密さ』の脚本家の良平と演出家の令子が、夜明け前の歩道を歩き、そのまま橋を渡りながら、言葉を交換していくのです。
あわせて読みたい
【斬新】映画『王国(あるいはその家について)』(草野なつか)を観よ。未経験の鑑賞体験を保証する
映画『王国(あるいはその家について)』は、まず経験できないだろう異様な鑑賞体験をもたらす特異な作品だった。「稽古場での台本読み」を映し出すパートが上映時間150分のほとんどを占め、同じやり取りをひたすら繰り返し見せ続ける本作は、「王国」をキーワードに様々な形の「狂気」を炙り出す異常な作品である

良平と令子は、脚本家と演出家というだけでなく、同棲している恋人同士という関係でもあります。共に演劇に対して情熱を持っているがゆえに、どうしてもすれ違ってしまうこともあるわけです。劇中劇『親密さ』では、普段は役者としても出演している2人が今回は制作に専念する、という形を取ることに決めます。それは演出の令子の提案で、良平は正直そこまで納得しているわけではありません。また他にも、彼らは様々な場面で意見の対立に直面してしまうのです。
良平が「ぶっ殺すからな」って言ってる場面も出てきたよね
真剣さが伝わる場面でもあると思うけど、やっぱりあんなこと言われたら怖いよなー
あわせて読みたい
【あらすじ】「愛されたい」「必要とされたい」はこんなに難しい。藤崎彩織が描く「ままならない関係性…
好きな人の隣にいたい。そんなシンプルな願いこそ、一番難しい。誰かの特別になるために「異性」であることを諦め、でも「異性」として見られないことに苦しさを覚えてしまう。藤崎彩織『ふたご』が描き出す、名前がつかない切実な関係性
さて、そんな一連の流れがあった後で、この橋のシーンがやってきます。様々な出来事を経験した彼らは、演劇についてではなく、2人の関係性についてぽつりぽつりと会話を交わすのです。口火を切るのは令子で、「長く一緒に生活しているけれども、私は良平のことを知る手がかりがほとんどない」と言います。そして良平は、「『知ること』にどんな意味があるのか分からない」と返すのです。そんな風に「一緒にいること」「理解し合うこと」についての2人の応酬が展開されることになります。
この場面は、確かに映像的にもキレイでインパクトがあるのですが、一方で、映像的な要素は極力排除されているとも言えるでしょう。夜明け前の薄暗いシーンなので、喋っている2人の表情は見えません。というかそもそも、2人の後ろから撮影していることもあり、「2人が歩いていること」と「多くの車が走っていること」ぐらいしか映像から伝わる情報はないのです。
だからこそここでも「言葉」が前面に立ち現れることになります。
良平と令子は、演劇を創作する相手としてお互いに尊敬しているし、一緒にいたいという気持ちも共有しているのですが、それでも、お互いが考えていることがまったく噛み合いません。相手に何を求めるのか、そのためにどう変わらなければならないのか、変わりたくないという気持ちはどうすればいいのか。2人が、「これからも一緒に上手くやっていくためにどうあるべきか」を、恐らく初めて真剣に語り合っているのだろうこの場面には、特に令子の切実さみたいなものが滲み出ていて、とても印象的でした。良平の頑なさも、めんどくさいなと感じつつ、個人的には決して悪い印象はありません。
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『アンダーカレント』(今泉力哉)は、失踪をテーマに「分かり合えなさ」を描く
映画『アンダーカレント』において私は、恐らく多くの人が「受け入れがたい」と感じるだろう人物に共感させられてしまった。また本作は、「他者を理解すること」についての葛藤が深掘りされる作品でもある。そのため、私が普段から抱いている「『他者のホントウ』を知りたい」という感覚も強く刺激された
なぜカップルが別れたのかが分かる「水をぶっ掛ける」場面
「言葉」ですれ違いを描く場面としては他に、劇中劇『親密さ』の中の「水をぶっ掛ける」場面を挙げたいと思います。つい先日、年下の友人女性にこのシーンについて説明したところ、「それはホントに凄いね」という反応でした。私としても印象に残った場面です。「わかり味が深い」という、日本語として正しいのか悩む表現がありますが、まさにそんな「わかり味が深い」場面だと感じました。
まず劇中劇の最初の方で、あるカップルの別れの場面が描かれます。どうやら男性にとっては、あまりに唐突な別れの切り出しだったようです。女性もは、別れたいと思う明確な理由を伝えたりせず、あなたのことが嫌いになったわけでも、誰か好きな人ができたわけでもない、ぐらいのことしか言いません。「あなたは『唐突』だっていうけど、私なりにグラデーションはあったよ。でもそういうことを上手く言葉にできない」という女性の主張に対し、男性は深く追及することを諦め、納得はできないもののその別れを受け入れる、という展開になります。
その後この男女は、ある偶然から再会することとなり、喫茶店と思しき場所で話をすることにしました。そこで男性が女性に、「今何考えてる?」と唐突に聞きます。別れた相手と何を話そう、と思ってなんとなく頭に浮かんだぐらいの、男性としてはさほど意味を持たない質問だったのでしょう。しかしそこで女性が、「今この水をぶっ掛けたら何が起こるんだろう? って考えてるよ」と返すのです。
あわせて読みたい
【考察】映画『街の上で』(今泉力哉)が描く「男女の友情は成立する」的会話が超絶妙で素晴らしい(出…
映画『街の上で』(今泉力哉監督)は、「映画・ドラマ的会話」ではない「自然な会話」を可能な限り目指すスタンスが見事だった。「会話の無駄」がとにかく随所に散りばめられていて、そのことが作品のリアリティを圧倒的に押し上げていると言える。ある男女の”恋愛未満”の会話もとても素晴らしかった

この答えに男性はぎょっとし、「俺にってこと? なんか俺に恨みでもあるのかよ」と言うのですが、女性は「そうじゃないの、ただなんとなくそう考えてるってだけ」と返します。しかし男性は、そんな女性の言葉をまったく理解することができません。だから男性は、「水を掛けたいと思ってるってことは、何か恨みがあるはずだ」という思考から離れられないのです。女性は本当にただ、「水掛けたらどうなるんだろう?」という想像をしているだけなのですが、男性は「こいつは俺のことを恨んでいる」という理解で固定されてしまうことになります。
そしてまさにこのすれ違いこそが、女性が別れを決断した理由なのだろうと観客には伝わる、というわけです。
この話を、先に出した友人女性に話をした時、「男性側の気持ちで観ている人もいるだろうね」と言っていて、まさにそれはその通りだと思いました。この場面を観ても、「女性が別れを切り出した理由がさっぱり分からない」と感じる人はいるでしょう。というかもしかしたら、この男性の捉え方の方が一般的だという可能性もあるかもしれません。
あわせて読みたい
【映画】『キャスティング・ディレクター』の歴史を作り、ハリウッド映画俳優の運命を変えた女性の奮闘
映画『キャスティング・ディレクター』は、ハリウッドで伝説とされるマリオン・ドハティを描き出すドキュメンタリー。「神業」「芸術」とも評される配役を行ってきたにも拘わらず、長く評価されずにいた彼女の不遇の歴史や、再び「キャスティングの暗黒期」に入ってしまった現在のハリウッドなどを切り取っていく
その友人女性からは、「むしろ、よくそのシーンの意味が分かりましたね」って褒められたよ
男だと特に、「俺を恨んでるんだろ」って発想になりがちな気がするしね
私はよく、「言葉の解像度」という言い方をします。「解像度」というのは、カメラなどの性能を示す言葉としても使われるでしょう。例えば、肉眼で月を見る人と望遠鏡で月を見る人とでは、見えるものはまったく違うと思います。同じように、「言葉の解像度」が合わない人同士の会話は成立しない、というのが私の持論です。

この男女も、「言葉の解像度」が合わなかったのだろう、と想像できるでしょう。女性が「水を掛けたら」という想像を口にした時に、それを言葉通りに受け取れなかった男性は、女性から「言葉の解像度」が合わないと判定されているのだと思います。私は、もの凄く分かるなぁ、と感じました。私も普段からこの「言葉の解像度」の問題にはぶち当たっているので、女性の葛藤が理解できるつもりです。
あわせて読みたい
【天才】映画音楽の発明家『モリコーネ』の生涯。「映画が恋した音楽家」はいかに名曲を生んだか
「映画音楽のフォーマットを生み出した」とも評される天才作曲家エンリオ・モリコーネを扱った映画『モリコーネ 映画が恋した音楽家』では、生涯で500曲以上も生み出し、「映画音楽」というジャンルを比べ物にならないほどの高みにまで押し上げた人物の知られざる生涯が描かれる
その後、この「水をぶっ掛ける」場面を下敷きにしたのだろうと感じた、「言葉の解像度」を強く意識させるシーンが出てきます。
女性の両親は幼い頃に離婚しており、その際、兄と離れ離れになってしまいました。その兄こそが、詩の朗読をしていた「衛」なのです。女性と衛は手紙でのやり取りを続けており、女性の方から衛に「会いたい」と声を掛けたことで再開を果たしていました。
そんな2人が話をする場面が後半で出てきます。衛は、パン工場のアルバイトを続けている自身について、「お前が周りの人に自慢したくなるような兄だったら良かったんだけどな」と卑下するようなことを口にしますが、それに対して女性が、
お兄ちゃんは「世界は情報なんかじゃない」と理解している人だと分かった。だから会えて凄く嬉しかった。
と返すのです。
あわせて読みたい
【爆発】どうしても人目が気になる自意識過剰者2人、せきしろと又吉直樹のエッセイに爆笑&共感:『蕎麦…
「コンビニのコピー機で並べない」せきしろ氏と、「フラッシュモブでの告白に恐怖する」又吉直樹氏が、おのれの「自意識過剰さ」を「可笑しさ」に変えるエッセイ『蕎麦湯が来ない』は、同じように「考えすぎてしまう人」には共感の嵐だと思います
衛は確かに、ちょっと異端的な部分があるんだけど、この女性からは「話が通じる人」に見えているのは分かる感じする
女性は、世の中の多くの人が「世界を情報だと捉えている」と感じており、その振る舞いにどうしても違和感を覚えてしまいます。彼女が「言葉の通じなさ」を感じる原因もその点にあるのでしょうし、だから元カレとも別れることになってしまったわけです。一方で、色んな点で「ちょっと難アリ」に見えてしまう衛の方が、情報としてではない形で世界を捉えていて、女性はその点に惹かれます。どんな場にいてもなんとなく浮いてしまう衛の存在が、この女性の言葉で救われている感じもあって、とても良いシーンだと感じました。
「水をぶっ掛ける」場面も、生き別れた兄と話す場面も、どちらもやはり「言葉」で構成されています。加えて、「言葉の解像度」に焦点に当たることでさらに「言葉」の存在が前面に押し出される印象が強くなったとも感じました。
バンジージャンプの「勇気」の話
さて、「言葉が屹立する場面」の実例は、これで最後にしましょう。「成人の儀式としてバンジージャンプを行う部族」の話です。
あわせて読みたい
【感想】どんな話かわからない?難しい?ジブリ映画『君たちはどう生きるか』の考察・解説は必要?(監…
宮崎駿最新作であるジブリ映画『君たちはどう生きるか』は、宮崎アニメらしいファンタジックな要素を全開に詰め込みつつ、「生と死」「創造」についても考えさせる作品だ。さらに、「自分の頭の中から生み出されたものこそ『正解』」という、創造物と向き合う際の姿勢についても問うているように思う

劇中劇『親密さ』を自身の考えに沿って演出することに決めた令子は、演劇の練習を一切せずに、「ワークショップ」と称して様々なことを行うことにします。役者同士にインタビューをさせたり、「戦争に自衛隊を派遣すべきか」をテーマに議論を行うなど、これが演劇とどう関係するのだろうかと思わされる謎めいた行動を取っていくのです。そしてその1つとして、「勇気」についての講義が行われます。
「世界のどこかに、こんな未開の部族がいるとする」という語り口で始まる令子の話は、大雑把に以下のような話です。
どこかにいるその部族は、世界の広さを知ることはなく、「世界」と言えばこの村のことだと考えています。つまり、この村で起こることが世界のすべてだ、ということです。
そんな村では、成人になったらバンジージャンプを行うことが決まっています。このような儀式を行う部族は他にもあるでしょうが、特徴的なのは、「このバンジージャンプで最後まで飛べなかった者が、次の長に選ばれる」ということです。もちろん、若者たちはその事実を知らされません。
若者は当然、バンジージャンプを飛ぶことが「成人の証」なのだと理解していますし、だからこそ、恐怖を感じつつも皆つぎつぎに飛んでいきます。しかしここに、どうしても飛べないでいる者がいるとしましょう。彼は事前に説明を受け、安全対策がきちんと施されていることを理解しているのですが、それでも「万が一」を考えてしまいます。命を落とす可能性がゼロとは言えないのではないか、と。
他の者がどんどん飛ぶ姿を目にすることで、「飛ばなければ部族の一員として受け容れられないのではないか」という恐怖もせり上がってきます。しかしそこに部族の長がやってきて、「もし飛べなかったとしても、お前を受け容れないなんてことは絶対にない」と保証するのです。
彼は大いに悩みますが、その内にこんな思考が浮かんできます。今この瞬間にもバンジージャンプを飛べていない自分は、「世界で最も臆病な人間」なのは間違いない、しかしそんな自分が勇気を出して飛べるのなら、その「勇気」は世界中すべての人のためのものとなるだろう。彼はそんな風に考えて、ついにバンジージャンプを飛ぶことができるのです。
あわせて読みたい
【勇敢】日本を救った吉田昌郎と、福島第一原発事故に死を賭して立ち向かった者たちの極限を知る:『死…
日本は、死を覚悟して福島第一原発に残った「Fukushima50」に救われた。東京を含めた東日本が壊滅してもおかしくなかった大災害において、現場の人間が何を考えどう行動したのかを、『死の淵を見た男』をベースに書く。全日本人必読の書
面白い設定だし、「自分が飛ぶことが『世界中の勇気』になる」っていう帰結もすごく良かったと思う
「臆病者にも臆病者なりの価値がある」っていう示唆は、なんか素敵だよね
この場面も本当に、ただひたすら令子が喋るだけで、まさに「言葉」によって成り立っていると言っていいでしょう。ワンカット長回しというわけではありませんが、誰かが合いの手を入れたり質問したりすることもありません。そんな中、この「未開の部族」の話を語り続ける令子の姿は、一種異様でさえあります。これが演劇に繋がる何かであるならともかく、聞いている役者たちも、この講義にどんな意味があるのかイマイチ理解できていないからです。
私の解釈では、この「勇気」の話は、恋人である良平に向けられたものなのだと思っています。「ワークショップ」という形を通して、なかなか伝える機会のない想いを良平に回りくどく伝えているということなのでしょう。恐らく令子は良平に対して、「狭い世界から抜け出して外へと踏み出さない」と感じており、そんな良平に変革を促したくてこの「勇気」の話を読んでいるのではないかと思います。確かに、そこまでの描写で、この劇団の問題点の一端が良平にあると示唆されるので、この講義は、間接的には劇団全体の問題解消を狙ったものだと言えるのだろうとも思います。
あわせて読みたい
【違和感】平田オリザ『わかりあえないことから』は「コミュニケーション苦手」問題を新たな視点で捉え…
「コミュニケーションが苦手」なのは、テクニックの問題ではない!?『わかりあえないことから』は、学校でのコミュニケーション教育に携わる演劇人・平田オリザが抱いた違和感を起点に、「コミュニケーション教育」が抱える問題と、私たち日本人が進むべき道を示す1冊

令子の意図はともかくとして、この講義もまた、「言葉」で場を支配する印象深い場面でした。
「映像的なもの」ばかりが評価される世の中へ一石を投じる作品
私は、特にここ最近、「映像的なもの」ばかりにしか目が向けられない世の中に違和感を覚えてしまうことが多くあります。YoutubeやTik TokなどのSNSが情報収集において優位になったために、写真・デザイン・映像などの視覚情報ばかりが優先され、評価されているように感じているのです。
別に「映像的なもの」が悪いわけではありませんが、「映像的なもの」しか選ばれない状況はちょっとマズいのではないかと感じています。
だからこそ、「映像作品」でありながら、「言葉」を前面に押し出して作られた『親密さ』にはとても惹かれてしまいました。
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『夕方のおともだち』は、「私はこう」という宣言からしか始まらない関係性の”純度”を描く
「こんな田舎にはもったいないほどのドM」と評された男が主人公の映画『夕方のおともだち』は、SM嬢と真性ドMの関わりを通じて、「宣言から始まる関係」の難しさを描き出す。「普通の世界」に息苦しさを感じ、どうしても馴染めないと思っている人に刺さるだろう作品
私は「映像的なもの」よりも「言葉」が気になるタイプだから、なかなか馴染めない世界になりつつあると思ってる
まあ、しばらくはこういう世の中が続いていくだろうねぇ
濱口竜介作品は『ドライブ・マイ・カー』も『偶然と想像』も、「脚本」の力強さ、「会話」の魅力が印象的で、全体的に「言葉が重視されている」と感じます。特にこの『親密さ』は「言葉」が強く、「映像」を観ながら「言葉の力」を再確認させられるという稀有な体験になりました。

「言葉の力」で闘う場合、世界に打って出るのが難しくなりそうな印象もありますが、『ドライブ・マイ・カー』は日本映画史上初めて米アカデミー賞の作品賞にノミネートされるなど大いに評価されています。「映像的なもの」の方が海外展開も含めて有利であることは分かっていますが、そういう中でも「言葉」で闘いを挑む濱口竜介監督には、これからも是非頑張ってほしいです。
あわせて読みたい
【解説】テネットの回転ドアの正体を分かりやすく考察。「時間逆行」ではなく「物質・反物質反転」装置…
クリストファー・ノーラン監督の映画『TENET/テネット』は、「陽電子」「反物質」など量子力学の知見が満載です。この記事では、映画の内容そのものではなく、時間反転装置として登場する「回転ドア」をメインにしつつ、時間逆行の仕組みなど映画全体の設定について科学的にわかりやすく解説していきます
出演:平野鈴, 出演:佐藤亮, 出演:伊藤綾子, 出演:田山幹雄, 出演:手塚加奈子, Writer:濱口竜介, 監督:濱口竜介, クリエイター:—
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品視聴済】私が観てきた映画(フィクション)を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が観てきた映画(フィクション)を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。
最後に
映画のラストシーンは、非常に美しいものに仕上がっていると感じました。
あわせて読みたい
【救い】耐えられない辛さの中でどう生きるか。短歌で弱者の味方を志すホームレス少女の生き様:『セー…
死にゆく母を眺め、施設で暴力を振るわれ、拾った新聞で文字を覚えたという壮絶な過去を持つ鳥居。『セーラー服の歌人 鳥居』は、そんな辛い境遇を背景に、辛さに震えているだろう誰かを救うために短歌を生み出し続ける生き方を描き出す。凄い人がいるものだ
映画の中で、衛ではなく良平が書いた「言葉のダイアグラム」という詩が2度読み上げられます。これは、脚本家として、言葉と常に格闘している良平が、言葉をいかに紡いでいるのかを電車のダイアグラムになぞらえて表現したものです。電車がダイアグラムに沿ってその流れを作り出しているように、言葉も流れを無視した形では存在できないという内容で、この詩もまた、「言葉」が前面に出るというこの映画の特徴に合致するものと言えるでしょう。
その詩の中に、「言葉がぎゅうぎゅうに詰まった急行と空いている各停が、ほんの一瞬同じ速度になり並走する瞬間がある」というような文章が出てきます。映画のラストシーンが先にあったのか、この詩の一文が先にあったのかは分かりませんが、この両者が響き合って映画全体を美しく締めくくっているのです。
あわせて読みたい
【感想】映画『すずめの戸締まり』(新海誠)は、東日本大震災後を生きる私達に「逃げ道」をくれる(松…
新海誠監督の『すずめの戸締まり』は、古代神話的な設定を現代のラブコメに組み込みながら、あまりに辛い現実を生きる人々に微かな「逃げ道」を指し示してくれる作品だと思う。テーマ自体は重いが、恋愛やコメディ要素とのバランスがとても良く、ロードムービー的な展開もとても魅力的
電車は、定められたルートしか通れないけれども、必要な場所で分岐や合流をする乗り物でもあります。それが、色んなことがあった良平と令子のこれまでの人生を、そしてこれからの人生をも想像させる絶妙な要素として映し出されているのです。とても良いラストシーンだと感じました。
4時間という長さに怯む人も、専門学校の卒業制作という情報に迷う人もいるかもしれませんが、上映される機会を見かけたら是非観てほしい作品だと私は思います。
あわせて読みたい
【矛盾】その”誹謗中傷”は真っ当か?映画『万引き家族』から、日本社会の「善悪の判断基準」を考える
どんな理由があれ、法を犯した者は罰せられるべきだと思っている。しかしそれは、善悪の判断とは関係ない。映画『万引き家族』(是枝裕和監督)から、「国民の気分」によって「善悪」が決まる社会の是非と、「善悪の判断を保留する勇気」を持つ生き方について考える
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!「それってホントに『コミュ力』が高いって言えるの?」と疑問を感じている方に…
私は、「コミュ力が高い人」に関するよくある主張に、どうも違和感を覚えてしまうことが多くあります。そしてその一番大きな理由が、「『コミュ力が高い人』って、ただ『想像力がない』だけではないか?」と感じてしまう点にあると言っていいでしょう。出版したKindle本は、「ネガティブには見えないネガティブな人」(隠れネガティブ)を取り上げながら、「『コミュ力』って何だっけ?」と考え直してもらえる内容に仕上げたつもりです。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【相違】友人の友人が作ったZINE『our house』には様々な「恋愛に惑う気持ち」が詰まっている
ひょんなことから知り合った女性が制作したZINE『our house』は、「恋愛」や「友情」に対して私が以前から抱いていた感覚にかなり近い内容で、実に興味深い。特に「恋愛においても、自分のことを性別で捉えられたくない」という感覚は新鮮で、そこから「男性は『恋愛的に惹かれている』という感覚を持たないかも」とも考えた
あわせて読みたい
【日々】映画『なみのおと』は、東日本大震災を語る人々の対話を”あり得ない”アングルから撮る(監督:…
映画『なみのおと』は、「東日本大震災の被災者が当時を振り返って対話をする」という内容そのものももちろん興味深いのだが、カメラをどう配置しているのかが分からない、ドキュメンタリー映画としては”あり得ない”映像であることにも驚かされた。また、悲惨な経験を軽妙に語る者たちの雰囲気も印象的な作品である
あわせて読みたい
【包容】映画『違国日記』を観て思う。「他者との接し方」が皆こうだったらもっと平和なはずだって(主…
映画『違国日記』は、人見知りの小説家・高代槙生が両親を亡くした姪・朝を引き取り一緒に暮らすところから始まる物語で、槙生と朝を中心とした様々な人間関係が絶妙に描かれている作品でした。人付き合いが苦手ながら、15歳という繊細な存在を壊さないように、でも腫れ物みたいには扱わないように慎重になる槙生のスタンスが素敵です
あわせて読みたい
【煌めき】映画『HAPPYEND』が描く、”監視への嫌悪”と”地震への恐怖”の中で躍動する若者の刹那(監督:…
映画『HAPPYEND』は、「監視システム」と「地震」という「外的な制約条件」を設定し、その窮屈な世界の中で屈せずに躍動しようとする若者たちをリアルに描き出す物語である。特に、幼稚園からの仲であるコウとユウタの関係性が絶妙で、演技未経験だという2人の存在感と映像の雰囲気が相まって、実に素敵に感じられた
あわせて読みたい
【葛藤】映画『きみの色』(山田尚子)は、感受性が強すぎる若者のリアルをバンドを通じて描き出す(主…
山田尚子監督作『きみの色』は、これといった起伏のないストーリー展開でありながら、「若い世代の繊細さに満ちた人間関係」をとてもリアルに描き出す雰囲気が素敵な作品。「悩み・葛藤を抱えている状態が日常である」という雰囲気をベースにしつつ、「音楽」を起点に偶然繋がった3人の緩やかな日々を描き出す物語に惹きつけられた
あわせて読みたい
【繊細】映画『ぼくのお日さま』(奥山大史)は、小さな世界での小さな恋を美しい映像で描く(主演:越…
映画『ぼくのお日さま』は、舞台設定も人間関係も実にミニマムでありながら、とても奥行きのある物語が展開される作品。予告編で「3つの恋」と言及されなければ、描かれるすべての「恋」には気付けなかっただろうと思うくらいの繊細な関係性と、映像・音楽を含めてすべてが美しい旋律として奏でられる物語がとても素敵でした
あわせて読みたい
【恋心】映画『サッドティー』は、「『好き』を巡ってウロウロする人々」を描く今泉力哉節全開の作品だった
映画『サッドティー』は、今泉力哉らしい「恋愛の周辺でグルグルする人たち」を描き出す物語。関係性が微妙に重なる複数の人間を映し出す群像劇の中で、「『好き』のややこしさ」に焦点を当てていく構成はさすがです。実に奇妙な展開で終わる物語ですが、それでもなお「リアルだ」と感じさせる雰囲気は、まるで魔法のようでした
あわせて読みたい
【絶妙】映画『水深ゼロメートルから』(山下敦弘)は、何気ない会話から「女性性の葛藤」を描く(主演…
高校演劇を舞台化する企画第2弾に選ばれた映画『水深ゼロメートルから』は、「水のないプール」にほぼ舞台が固定された状態で、非常に秀逸な会話劇として展開される作品だ。退屈な時間を埋めるようにして始まった「ダルい会話」から思いがけない展開が生まれ、「女として生きること」についての様々な葛藤が描き出される点が面白い
あわせて読みたい
【感想】映画『夜明けのすべて』は、「ままならなさ」を抱えて生きるすべての人に優しく寄り添う(監督…
映画『夜明けのすべて』は、「PMS」や「パニック障害」を通じて、「自分のものなのに、心・身体が思い通りにならない」という「ままならなさ」を描き出していく。決して他人事ではないし、「私たちもいつそのような状況に置かれるか分からない」という気持ちで観るのがいいでしょう。物語の起伏がないのに惹きつけられる素敵な作品です
あわせて読みたい
【幻惑】映画『フォロウィング』の衝撃。初監督作から天才だよ、クリストファー・ノーラン
クリストファー・ノーランのデビュー作であり、多数の賞を受賞し世界に衝撃を与えた映画『フォロウィング』には、私も驚かされてしまった。冒頭からしばらくの間「何が描かれているのかさっぱり理解できない」という状態だったのに、ある瞬間一気に視界が晴れたように状況が理解できたのだ。脚本の力がとにかく圧倒的だった
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『悪は存在しない』(濱口竜介)の衝撃のラストの解釈と、タイトルが示唆する現実(主…
映画『悪は存在しない』(濱口竜介監督)は、観る者すべてを困惑に叩き落とす衝撃のラストに、鑑賞直後は迷子のような状態になってしまうだろう。しかし、作中で提示される様々な要素を紐解き、私なりの解釈に辿り着いた。全編に渡り『悪は存在しない』というタイトルを強く意識させられる、脚本・映像も見事な作品だ
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『レザボア・ドッグス』(タランティーノ監督)はとにかく驚異的に脚本が面白い!
クエンティン・タランティーノ初の長編監督作『レザボア・ドッグス』は、のけぞるほど面白い映画だった。低予算という制約を逆手に取った「会話劇」の構成・展開があまりにも絶妙で、舞台がほぼ固定されているにも拘らずストーリーが面白すぎる。天才はやはり、デビュー作から天才だったのだなと実感させられた
あわせて読みたい
【斬新】映画『王国(あるいはその家について)』(草野なつか)を観よ。未経験の鑑賞体験を保証する
映画『王国(あるいはその家について)』は、まず経験できないだろう異様な鑑賞体験をもたらす特異な作品だった。「稽古場での台本読み」を映し出すパートが上映時間150分のほとんどを占め、同じやり取りをひたすら繰り返し見せ続ける本作は、「王国」をキーワードに様々な形の「狂気」を炙り出す異常な作品である
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『アンダーカレント』(今泉力哉)は、失踪をテーマに「分かり合えなさ」を描く
映画『アンダーカレント』において私は、恐らく多くの人が「受け入れがたい」と感じるだろう人物に共感させられてしまった。また本作は、「他者を理解すること」についての葛藤が深掘りされる作品でもある。そのため、私が普段から抱いている「『他者のホントウ』を知りたい」という感覚も強く刺激された
あわせて読みたい
【考察】映画『街の上で』(今泉力哉)が描く「男女の友情は成立する」的会話が超絶妙で素晴らしい(出…
映画『街の上で』(今泉力哉監督)は、「映画・ドラマ的会話」ではない「自然な会話」を可能な限り目指すスタンスが見事だった。「会話の無駄」がとにかく随所に散りばめられていて、そのことが作品のリアリティを圧倒的に押し上げていると言える。ある男女の”恋愛未満”の会話もとても素晴らしかった
あわせて読みたい
【映画】『キャスティング・ディレクター』の歴史を作り、ハリウッド映画俳優の運命を変えた女性の奮闘
映画『キャスティング・ディレクター』は、ハリウッドで伝説とされるマリオン・ドハティを描き出すドキュメンタリー。「神業」「芸術」とも評される配役を行ってきたにも拘わらず、長く評価されずにいた彼女の不遇の歴史や、再び「キャスティングの暗黒期」に入ってしまった現在のハリウッドなどを切り取っていく
あわせて読みたい
【未知】コーダに密着した映画『私だけ聴こえる』は、ろう者と聴者の狭間で居場所がない苦悩を映し出す
あなたは「コーダ」と呼ばれる存在を知っているだろうか?「耳の聴こえない親を持つ、耳が聴こえる子ども」のことであり、映画『私だけ聴こえる』は、まさにそんなコーダが置かれた状況を描くドキュメンタリー映画だ。自身は障害者ではないのに大変な苦労を強いられている現状が理解できる作品
あわせて読みたい
【助けて】映画『生きててごめんなさい』は、「共依存カップル」視点で生きづらい世の中を抉る物語(主…
映画『生きててごめんなさい』は、「ちょっと歪な共依存関係」を描きながら、ある種現代的な「生きづらさ」を抉り出す作品。出版社の編集部で働きながら小説の新人賞を目指す園田修一は何故、バイトを9度もクビになり、一日中ベッドの上で何もせずに過ごす同棲相手・清川莉奈を”必要とする”のか?
あわせて読みたい
【天才】映画音楽の発明家『モリコーネ』の生涯。「映画が恋した音楽家」はいかに名曲を生んだか
「映画音楽のフォーマットを生み出した」とも評される天才作曲家エンリオ・モリコーネを扱った映画『モリコーネ 映画が恋した音楽家』では、生涯で500曲以上も生み出し、「映画音楽」というジャンルを比べ物にならないほどの高みにまで押し上げた人物の知られざる生涯が描かれる
あわせて読みたい
【伝説】映画『ミスター・ムーンライト』が描くビートルズ武道館公演までの軌跡と日本音楽への影響
ザ・ビートルズの武道館公演が行われるまでの軌跡を描き出したドキュメンタリー映画『ミスター・ムーンライト』は、その登場の衝撃について語る多数の著名人が登場する豪華な作品だ。ザ・ビートルズがまったく知られていなかった頃から、伝説の武道館公演に至るまでの驚くべきエピソードが詰まった1作
あわせて読みたい
【希望】誰も傷つけたくない。でも辛い。逃げたい。絶望しかない。それでも生きていく勇気がほしい時に…
2006年発売、2021年文庫化の『私を見て、ぎゅっと愛して』は、ブログ本のクオリティとは思えない凄まじい言語化力で、1人の女性の内面の葛藤を抉り、読者をグサグサと突き刺す。信じがたい展開が連続する苦しい状況の中で、著者は大事なものを見失わず手放さずに、勇敢に前へ進んでいく
あわせて読みたい
【天才】タランティーノ作品ほぼ未見で観た面白ドキュメンタリー。映画に愛された映画オタクのリアル
『パルプ・フィクション』しか監督作品を観たことがないまま、本作『クエンティン・タランティーノ 映画に愛された男』を観たが、とても面白いドキュメンタリー映画だった。とにかく「撮影現場に笑いが絶えない」ようで、そんな魅力的なモノづくりに関わる者たちの証言から、天才の姿が浮かび上がる
あわせて読みたい
【感想】是枝裕和監督映画『怪物』(坂元裕二脚本)が抉る、「『何もしないこと』が生む加害性」
坂元裕二脚本、是枝裕和監督の映画『怪物』は、3つの視点を通して描かれる「日常の何気ない光景」に、思いがけない「加害性」が潜んでいることを炙り出す物語だ。これは間違いなく、私たち自身に関わる話であり、むしろ「自分には関係ない」と考えている人こそが自覚すべき問題だと思う
あわせて読みたい
【違和感】三浦透子主演映画『そばかす』はアセクシャルの生きづらさを描く。セクシャリティ理解の入り口に
「他者に対して恋愛感情・性的欲求を抱かないセクシャリティ」である「アセクシャル」をテーマにした映画『そばかす』は、「マイノリティのリアル」をかなり解像度高く映し出す作品だと思う。また、主人公・蘇畑佳純に共感できてしまう私には、「普通の人の怖さ」が描かれている映画にも感じられた
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』を観てくれ!現代の人間関係の教科書的作品を考…
映画『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』は、私にグサグサ突き刺さるとても素晴らしい映画だった。「ぬいぐるみに話しかける」という活動内容の大学サークルを舞台にした物語であり、「マイノリティ的マインド」を持つ人たちの辛さや葛藤を、「マジョリティ視点」を絶妙に織り交ぜて描き出す傑作について考察する
あわせて読みたい
【純真】ゲイが犯罪だった時代が舞台の映画『大いなる自由』は、刑務所内での極深な人間ドラマを描く
男性同士の恋愛が犯罪であり、ゲイの男性が刑法175条を理由に逮捕されてしまう時代のドイツを描いた映画『大いなる自由』は、確かに同性愛の物語なのだが、実はそこに本質はない。物語の本質は、まさにタイトルにある通り「自由」であり、ラストシーンで突きつけられるその深い問いかけには衝撃を受けるだろう
あわせて読みたい
【感想】どんな話かわからない?難しい?ジブリ映画『君たちはどう生きるか』の考察・解説は必要?(監…
宮崎駿最新作であるジブリ映画『君たちはどう生きるか』は、宮崎アニメらしいファンタジックな要素を全開に詰め込みつつ、「生と死」「創造」についても考えさせる作品だ。さらに、「自分の頭の中から生み出されたものこそ『正解』」という、創造物と向き合う際の姿勢についても問うているように思う
あわせて読みたい
【感想】映画『すずめの戸締まり』(新海誠)は、東日本大震災後を生きる私達に「逃げ道」をくれる(松…
新海誠監督の『すずめの戸締まり』は、古代神話的な設定を現代のラブコメに組み込みながら、あまりに辛い現実を生きる人々に微かな「逃げ道」を指し示してくれる作品だと思う。テーマ自体は重いが、恋愛やコメディ要素とのバランスがとても良く、ロードムービー的な展開もとても魅力的
あわせて読みたい
【あらすじ】塩田武士『罪の声』が放つ、戦後最大の未解決事件「グリコ・森永事件」の圧倒的”リアル感”
戦後最大の未解決事件である「グリコ・森永事件」では、脅迫に子どもの声が使われていた。私はその事実を、塩田武士『罪の声』という小説を読むまで知らなかった。では、続く疑問はこうだろう。その子どもたちは、今どこでどんな風に生きているのか?その疑問に答える、凄まじい小説だ。
あわせて読みたい
【共感】「恋愛したくない」という社会をリアルに描く売野機子の漫画『ルポルタージュ』が示す未来像
売野機子のマンガ『ルポルタージュ』は、「恋愛を飛ばして結婚すること」が当たり前の世界が描かれる。私はこの感覚に凄く共感できてしまった。「恋愛」「結婚」に対して、「世間の『当たり前』に馴染めない感覚」を持つ私が考える、「恋愛」「結婚」が有する可能性
あわせて読みたい
【誠実】戸田真琴は「言葉の人」だ。コンプレックスだらけの人生を「思考」と「行動」で突き進んだ記録…
戸田真琴のエッセイ第2弾『人を心から愛したことがないのだと気づいてしまっても』は、デビュー作以上に「誰かのために言葉を紡ぐ」という決意が溢れた1冊だ。AV女優という自身のあり方を客観的に踏まえた上で、「届くべき言葉がきちんと届く」ために、彼女は身を削ってでも生きる
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『夕方のおともだち』は、「私はこう」という宣言からしか始まらない関係性の”純度”を描く
「こんな田舎にはもったいないほどのドM」と評された男が主人公の映画『夕方のおともだち』は、SM嬢と真性ドMの関わりを通じて、「宣言から始まる関係」の難しさを描き出す。「普通の世界」に息苦しさを感じ、どうしても馴染めないと思っている人に刺さるだろう作品
あわせて読みたい
【苦しい】「恋愛したくないし、興味ない」と気づいた女性が抉る、想像力が足りない社会の「暴力性」:…
「実は私は、恋愛的な関係を求めているわけじゃないかもしれない」と気づいた著者ムラタエリコが、自身の日常や専門学校でも学んだ写真との関わりを基に、「自分に相応しい関係性」や「社会の暴力性」について思考するエッセイ。久々に心にズバズバ刺さった、私にはとても刺激的な1冊だった。
あわせて読みたい
【感想】映画『君が世界のはじまり』は、「伝わらない」「分かったフリをしたくない」の感情が濃密
「キラキラした青春学園モノ」かと思っていた映画『君が世界のはじまり』は、「そこはかとない鬱屈」に覆われた、とても私好みの映画だった。自分の決断だけではどうにもならない「現実」を前に、様々な葛藤渦巻く若者たちの「諦念」を丁寧に描き出す素晴らしい物語
あわせて読みたい
【伝説】やり投げ選手・溝口和洋は「思考力」が凄まじかった!「幻の世界記録」など数々の逸話を残した…
世界レベルのやり投げ選手だった溝口和洋を知っているだろうか? 私は本書『一投に賭ける』で初めてその存在を知った。他の追随を許さないほどの圧倒的なトレーニングと、常識を疑い続けるずば抜けた思考力を武器に、体格で劣る日本人ながら「幻の世界記録」を叩き出した天才の伝説と実像
あわせて読みたい
【感想】のん主演映画『私をくいとめて』から考える、「誰かと一緒にいられれば孤独じゃないのか」問題
のん(能年玲奈)が「おひとり様ライフ」を満喫する主人公を演じる映画『私をくいとめて』を観て、「孤独」について考えさせられた。「誰かと関わっていられれば孤独じゃない」という考えに私は賛同できないし、むしろ誰かと一緒にいる時の方がより強く孤独を感じることさえある
あわせて読みたい
【感想】おげれつたなか『エスケープジャーニー』は、BLでしか描けない”行き止まりの関係”が絶妙
おげれつたなか『エスケープジャーニー』のあらすじ紹介とレビュー。とにかく、「BLでしか描けない関係性」が素晴らしかった。友達なら完璧だったのに、「恋人」ではまったく上手く行かなくなってしまった直人と太一の葛藤を通じて、「進んでも行き止まり」である関係にどう向き合うか考えさせられる
あわせて読みたい
【違和感】平田オリザ『わかりあえないことから』は「コミュニケーション苦手」問題を新たな視点で捉え…
「コミュニケーションが苦手」なのは、テクニックの問題ではない!?『わかりあえないことから』は、学校でのコミュニケーション教育に携わる演劇人・平田オリザが抱いた違和感を起点に、「コミュニケーション教育」が抱える問題と、私たち日本人が進むべき道を示す1冊
あわせて読みたい
【感想】映画『窓辺にて』(今泉力哉監督)の稲垣吾郎の役に超共感。「好きとは何か」が分からない人へ
映画『窓辺にて』(今泉力哉監督)は、稲垣吾郎演じる主人公・市川茂巳が素晴らしかった。一般的には、彼の葛藤はまったく共感されないし、私もそのことは理解している。ただ私は、とにかく市川茂巳にもの凄く共感してしまった。「誰かを好きになること」に迷うすべての人に観てほしい
あわせて読みたい
【言葉】「戸田真琴の生きづらさ」を起点に世の中を描く映画『永遠が通り過ぎていく』の”しんどい叫び”
『あなたの孤独は美しい』というエッセイでその存在を知ったAV女優・戸田真琴の初監督映画『永遠が通り過ぎていく』。トークショーで「自分が傷つけられた時の心象風景を映像にした」と語るのを聞いて、映画全体の捉え方が変わった。他者のために創作を続ける彼女からの「贈り物」
あわせて読みたい
【魅惑】バーバラ・ローデン監督・脚本・主演の映画『WANDA』の、70年代の作品とは思えない今感
映画館で観た予告が気になって、それ以外の情報を知らずに観に行った映画『WANDA』なんと70年代の映画だと知って驚かされた。まったく「古さ」を感じなかったからだ。主演だけでなく、監督・脚本も務めたバーバラ・ローデンが遺した、死後評価が高まった歴史的一作
あわせて読みたい
【価値】どうせ世の中つまらない。「レンタルなんもしない人」の本でお金・仕事・人間関係でも考えよう…
「0円で何もしない」をコンセプトに始まった「レンタルなんもしない人」という活動は、それまで見えにくかった様々な価値観を炙り出した見事な社会実験だと思う。『<レンタルなんもしない人>というサービスをはじめます。』で本人が語る、お金・仕事・人間関係の新たな捉え方
あわせて読みたい
【感想】湯浅政明監督アニメ映画『犬王』は、実在した能楽師を”異形”として描くスペクタクル平家物語
観るつもりなし、期待値ゼロ、事前情報ほぼ皆無の状態で観た映画『犬王』(湯浅政明監督)はあまりにも凄まじく、私はこんなとんでもない傑作を見逃すところだったのかと驚愕させられた。原作の古川日出男が紡ぐ狂気の世界観に、リアルな「ライブ感」が加わった、素晴らしすぎる「音楽映画」
あわせて読みたい
【あらすじ】映画化の小説『僕は、線を描く』。才能・センスではない「芸術の本質」に砥上裕將が迫る
「水墨画」という、多くの人にとって馴染みが無いだろう芸術を題材に据えた小説『線は、僕を描く』は、青春の葛藤と創作の苦悩を描き出す作品だ。「未経験のど素人である主人公が、巨匠の孫娘と勝負する」という、普通ならあり得ない展開をリアルに感じさせる設定が見事
あわせて読みたい
【恋愛】モテない男は何がダメ?AV監督が男女共に贈る「コミュニケーション」と「居場所」の話:『すべ…
二村ヒトシ『すべてはモテるためである』は、タイトルも装丁も、どう見ても「モテ本」にしか感じられないだろうが、よくある「モテるためのマニュアル」が書かれた本ではまったくない。「行動」を促すのではなく「思考」が刺激される、「コミュニケーション」と「居場所」について語る1冊
あわせて読みたい
【実話】台湾のろう学校のいじめ・性的虐待事件を描く映画『無聲』が問う、あまりに悲しい現実
台湾のろう学校で実際に起こったいじめ・性的虐待事件を基に作られた映画『無聲』は、健常者の世界に刃を突きつける物語だ。これが実話だという事実に驚かされる。いじめ・性的虐待が物語の「大前提」でしかないという衝撃と、「性的虐待の方がマシ」という選択を躊躇せず行う少女のあまりの絶望を描き出す
あわせて読みたい
【アート】映画『ダ・ヴィンチは誰に微笑む』が描く「美術界の闇」と「芸術作品の真正性」の奥深さ
美術界史上最高額510億円で落札された通称「救世主」は、発見される以前から「レオナルド・ダ・ヴィンチの失われた作品」として知られる有名な絵だった。映画『ダ・ヴィンチは誰に微笑む』は、「芸術作品の真正性の問題」に斬り込み、魑魅魍魎渦巻く美術界を魅力的に描き出す
あわせて読みたい
【斬新】ホームレスの家を「0円ハウス」と捉える坂口恭平の発想と視点に衝撃。日常の見え方が一変する:…
早稲田大学建築学科在籍中から「建築物の設計」に興味を持てなかった坂口恭平が、「ホームレスの家」に着目した『TOKYO 0円ハウス0円生活』には、「家」に対する考え方を一変させる視点が満載。「家に生活を合わせる」ではなく、「生活に家を合わせる」という発想の転換が見事
あわせて読みたい
【抽象】「思考力がない」と嘆く人に。研究者で小説家の森博嗣が語る「客観的に考える」ために大事なこ…
世の中にはあまりに「具体的な情報」が溢れているために、「客観的、抽象的な思考」をする機会が少ない。そんな時代に、いかに思考力を育てていくべきか。森博嗣が『人間はいろいろな問題についてどう考えていけば良いのか』を通じて伝える「情報との接し方」「頭の使い方」
あわせて読みたい
【考察】『うみべの女の子』が伝えたいことを全力で解説。「関係性の名前」を手放し、”裸”で対峙する勇敢さ
ともすれば「エロ本」としか思えない浅野いにおの原作マンガを、その空気感も含めて忠実に映像化した映画『うみべの女の子』。本作が一体何を伝えたかったのかを、必死に考察し全力で解説する。中学生がセックスから関係性をスタートさせることで、友達でも恋人でもない「名前の付かない関係性」となり、行き止まってしまう感じがリアル
あわせて読みたい
【感想】才能の開花には”極限の環境”が必要か?映画『セッション』が描く世界を私は否定したい
「追い込む指導者」が作り出す”極限の環境”だからこそ、才能が開花する可能性もあるとは思う。しかし、そのような環境はどうしても必要だろうか?最高峰の音楽院での壮絶な”指導”を描く映画『セッション』から、私たちの生活を豊かにしてくれるものの背後にある「死者」を想像する
あわせて読みたい
【妄執】チェス史上における天才ボビー・フィッシャーを描く映画。冷戦下の米ソ対立が盤上でも:映画『…
「500年に一度の天才」などと評され、一介のチェスプレーヤーでありながら世界的な名声を獲得するに至ったアメリカ人のボビー・フィッシャー。彼の生涯を描く映画『完全なるチェックメイト』から、今でも「伝説」と語り継がれる対局と、冷戦下ゆえの激動を知る
あわせて読みたい
【死】映画『湯を沸かすほどの熱い愛』に号泣。「家族とは?」を問う物語と、タイトル通りのラストが見事
「死は特別なもの」と捉えてしまうが故に「日常感」が失われ、普段の生活から「排除」されているように感じてしまうのは私だけではないはずだ。『湯を沸かすほどの熱い愛』は、「死を日常に組み込む」ことを当たり前に許容する「家族」が、「家族」の枠組みを問い直す映画である
あわせて読みたい
【狂気】バケモン・鶴瓶を映し出す映画。「おもしろいオッチャン」に潜む「異常さ」と「芸への情熱」:…
「俺が死ぬまで公開するな」という条件で撮影が許可された映画『バケモン』。コロナ禍で映画館が苦境に立たされなければ、公開はずっと先だっただろう。テレビで見るのとは違う「芸人・笑福亭鶴瓶」の凄みを、古典落語の名作と名高い「らくだ」の変遷と共に切り取る
あわせて読みたい
【世界観】映画『夜は短し歩けよ乙女』の”黒髪の乙女”は素敵だなぁ。ニヤニヤが止まらない素晴らしいアニメ
森見登美彦の原作も大好きな映画『夜は短し歩けよ乙女』は、「リアル」と「ファンタジー」の境界を絶妙に漂う世界観がとても好き。「黒髪の乙女」は、こんな人がいたら好きになっちゃうよなぁ、と感じる存在です。ずっとニヤニヤしながら観ていた、とても大好きな映画
あわせて読みたい
【生き方】人生が虚しいなら映画『人生フルーツ』を見ると良い。素敵な老夫婦の尖った人生がここにある
社会派のドキュメンタリー映画に定評のある東海テレビが、「なんでもない老夫婦の日常」を映画にした『人生フルーツ』には、特に何が起こるわけでもないのに「観て良かった」と感じさせる強さがある。見た目は「お年寄り」だが中身はまったく古臭くない”穏やかに尖った夫婦”の人生とは?
あわせて読みたい
【革新】映画音楽における唯一のルールは「ルールなど無い」だ。”異次元の音”を生み出す天才を追う:映…
「無声映画」から始まった映画業界で、音楽の重要性はいかに認識されたのか?『JAWS』の印象的な音楽を生み出した天才は、映画音楽に何をもたらしたのか?様々な映画の実際の映像を組み込みながら、「映画音楽」の世界を深堀りする映画『すばらしき映画音楽たち』で、異才たちの「創作」に触れる
あわせて読みたい
【考察】生きづらい性格は変わらないから仮面を被るしかないし、仮面を被るとリア充だと思われる:『勝…
「リア充感」が滲み出ているのに「生きづらさ」を感じてしまう人に、私はこれまでたくさん会ってきた。見た目では「生きづらさ」は伝わらない。24年間「リアル彼氏」なし、「脳内彼氏」との妄想の中に生き続ける主人公を描く映画『勝手にふるえてろ』から「こじらせ」を知る
あわせて読みたい
【博覧強記】「紙の本はなくなる」説に「文化は忘却されるからこそ価値がある」と反論する世界的文学者…
世界的文学者であり、「紙の本」を偏愛するウンベルト・エーコが語る、「忘却という機能があるから書物に価値がある」という主張は実にスリリングだ。『もうすぐ絶滅するという紙の書物について』での対談から、「忘却しない電子データ」のデメリットと「本」の可能性を知る
あわせて読みたい
【誤解】世界的大ベストセラー『ファクトフルネス』の要約。我々は「嘘の情報」を信じ込みやすい
世界の現状に関する13の質問に対して、ほとんどの人が同じ解答をする。最初の12問は不正解で、最後の1問だけ正答するのだ。世界的大ベストセラー『ファクトフルネス』から、「誤った世界の捉え方」を認識し、情報を受け取る際の「思い込み」を払拭する。「嘘の情報」に踊らされないために読んでおくべき1冊だ
あわせて読みたい
【知的】文系にオススメの、科学・数学・哲学の入門書。高橋昌一郎の「限界シリーズ」は超絶面白い:『…
例えば「科学」だけに限ってみても、「なんでもできる」わけでは決してない。「科学」に限らず、私たちが対峙する様々な事柄には「これ以上は不可能・無理」という「限界」が必ず存在する。高橋昌一郎の「限界シリーズ」から、我々が認識しておくべき「限界」を易しく学ぶ
あわせて読みたい
【感想】飲茶の超面白い東洋哲学入門書。「本書を読んでも東洋哲学は分からない」と言う著者は何を語る…
東洋哲学というのは、「最終回しか存在しない連続ドラマ」のようなものだそうだ。西洋哲学と比較にならないほど異質さと、インド哲学・中国哲学など個別の思想を恐ろしく分かりやすく描く『史上最強の哲学入門 東洋の哲人たち』は、ページをめくる手が止まらないくらい、史上最強レベルに面白かった
あわせて読みたい
【感涙】衆議院議員・小川淳也の選挙戦に密着する映画から、「誠実さ」と「民主主義のあり方」を考える…
『衆議院議員・小川淳也が小選挙区で平井卓也と争う選挙戦を捉えた映画『香川1区』は、政治家とは思えない「誠実さ」を放つ”異端の議員”が、理想とする民主主義の実現のために徒手空拳で闘う様を描く。選挙のドキュメンタリー映画でこれほど号泣するとは自分でも信じられない
あわせて読みたい
【人生】「資本主義の限界を埋める存在としての『贈与論』」から「不合理」に気づくための生き方を知る…
「贈与論」は簡単には理解できないが、一方で、「何かを受け取ったら、与えてくれた人に返す」という「交換」の論理では対処できない現実に対峙する力ともなる。『世界は贈与でできている』から「贈与」的な見方を理解し、「受取人の想像力」を立ち上げる
あわせて読みたい
【異様】ジャーナリズムの役割って何だ?日本ではまだきちんと機能しているか?報道機関自らが問う映画…
ドキュメンタリーで定評のある東海テレビが、「東海テレビ」を被写体として撮ったドキュメンタリー映画『さよならテレビ』は、「メディアはどうあるべきか?」を問いかける。2011年の信じがたいミスを遠景にしつつ、メディア内部から「メディアの存在意義」を投げかける
あわせて読みたい
【レッテル】コミュニケーションで大事なのは、肩書や立場を外して、相手を”その人”として見ることだ:…
私は、それがポジティブなものであれ、「レッテル」で見られることは嫌いです。主人公の1人、障害を持つ大富豪もまたそんなタイプ。傍若無人な元犯罪者デルとの出会いでフィリップが変わっていく『THE UPSIDE 最強のふたり』からコミュニケーションを学ぶ
あわせて読みたい
【興奮】飲茶氏が西洋哲学を語る。難解な思想が「グラップラー刃牙成分」の追加で驚異的な面白さに:『…
名前は聞いたことはあるがカントやニーチェがどんな主張をしたのかは分からないという方は多いだろう。私も無知なまったくの初心者だが、そんな人でも超絶分かりやすく超絶面白く西洋哲学を”分かった気になれる”飲茶『史上最強の哲学入門』は、入門書として最強
あわせて読みたい
【権利】衝撃のドキュメンタリー映画『ヤクザと憲法』は、「異質さを排除する社会」と「生きる権利」を問う
「ヤクザ」が排除された現在でも、「ヤクザが担ってきた機能」が不要になるわけじゃない。ではそれを、公権力が代替するのだろうか?実際の組事務所(東組清勇会)にカメラを持ち込むドキュメンタリー映画『ヤクザと憲法』が映し出す川口和秀・松山尚人・河野裕之の姿から、「基本的人権」のあり方について考えさせられた
あわせて読みたい
【狂気】「当たり前の日常」は全然当たり前じゃない。記憶が喪われる中で”日常”を生きることのリアル:…
私たちは普段、「記憶が当たり前に継続していること」に疑問も驚きも感じないが、「短期記憶を継続できない」という記憶障害を抱える登場人物の日常を描き出す『静かな雨』は、「記憶こそが日常を生み出している」と突きつけ、「当たり前の日常は当たり前じゃない」と示唆する
あわせて読みたい
【告発】アメリカに”監視”される社会を暴露したスノーデンの苦悩と決断を映し出す映画:『スノーデン』…
NSA(アメリカ国家安全保障局)の最高機密にまでアクセスできたエドワード・スノーデンは、その機密情報を持ち出し内部告発を行った。「アメリカは世界中の通信を傍受している」と。『シチズンフォー』と『スノーデン』の2作品から、彼の告発内容とその葛藤を知る
あわせて読みたい
【あらすじ】天才とは「分かりやすい才能」ではない。前進するのに躊躇する暗闇で直進できる勇気のこと…
ピアノのコンクールを舞台に描く『蜜蜂と遠雷』は、「天才とは何か?」と問いかける。既存の「枠組み」をいとも簡単に越えていく者こそが「天才」だと私は思うが、「枠組み」を安易に設定することの是非についても刃を突きつける作品だ。小説と映画の感想を一緒に書く
あわせて読みたい
【窮屈】日本の生きづらさの元凶は「失敗にツッコむ笑い」。「良し悪し」より「好き嫌い」を語ろう:『…
お笑い芸人・マキタスポーツが、一般社会にも「笑いの作法」が染み出すことで息苦しさが生み出されてしまうと分析する『一億総ツッコミ時代』を元に、「ツッコむ」という振る舞いを止め、「ツッコまれしろ」を持ち、「好き/嫌い」で物事を語るスタンスについて考える
あわせて読みたい
【奇跡】鈴木敏夫が2人の天才、高畑勲と宮崎駿を語る。ジブリの誕生から驚きの創作秘話まで:『天才の思…
徳間書店から成り行きでジブリ入りすることになったプロデューサー・鈴木敏夫が、宮崎駿・高畑勲という2人の天才と共に作り上げたジブリ作品とその背景を語り尽くす『天才の思考 高畑勲と宮崎駿』。日本のアニメ界のトップランナーたちの軌跡の奇跡を知る
あわせて読みたい
【感心】悩み相談とは、相手の問いに答える”だけ”じゃない。哲学者が相談者の「真意」に迫る:『哲学の…
「相談に乗る」とは、「自分の意見を言う行為」ではない。相談者が”本当に悩んでいること”を的確に捉えて、「回答を与えるべき問いは何か?」を見抜くことが本質だ。『哲学の先生と人生の話をしよう』から、「相談をすること/受けること」について考える
あわせて読みたい
【逸脱】「人生良いことない」と感じるのは、「どう生きたら幸せか」を考えていないからでは?:『独立…
「常識的な捉え方」から逸脱し、世の中をまったく異なる視点から見る坂口恭平は、「より生きやすい社会にしたい」という強い思いから走り続ける。「どう生きたいか」から人生を考え直すスタンスと、「やりたいことをやるべきじゃない理由」を『独立国家のつくりかた』から学ぶ
あわせて読みたい
【絶望】「人生上手くいかない」と感じる時、彼を思い出してほしい。壮絶な過去を背負って生きる彼を:…
「北九州連続監禁殺人事件」という、マスコミも報道規制するほどの残虐事件。その「主犯の息子」として生きざるを得なかった男の壮絶な人生。「ザ・ノンフィクション」のプロデューサーが『人殺しの息子と呼ばれて』で改めて取り上げた「真摯な男」の生き様と覚悟
あわせて読みたい
【現実】生きる気力が持てない世の中で”働く”だけが人生か?「踊るホームレスたち」の物語:映画『ダン…
「ホームレスは怠けている」という見方は誤りだと思うし、「働かないことが悪」だとも私には思えない。振付師・アオキ裕キ主催のホームレスのダンスチームを追う映画『ダンシングホームレス』から、社会のレールを外れても許容される社会の在り方を希求する
あわせて読みたい
【逃避】つまらない世の中で生きる毎日を押し流す”何か”を求める気持ちに強烈に共感する:映画『サクリ…
子どもの頃「台風」にワクワクしたように、未だに、「自分のつまらない日常を押し流してくれる『何か』」の存在を待ちわびてしまう。立教大学の学生が撮った映画『サクリファイス』は、そんな「何か」として「東日本大震災」を描き出す、チャレンジングな作品だ
あわせて読みたい
【実話】「家族とうまくいかない現実」に正解はあるか?選択肢が無いと感じる時、何を”選ぶ”べきか?:…
「自分の子どもなんだから、どんな風に育てたって勝手でしょ」という親の意見が正しいはずはないが、この言葉に反論することは難しい。虐待しようが生活能力が無かろうが、親は親だからだ。映画『MOTHER マザー』から、不正解しかない人生を考える
あわせて読みたい
【感想】「献身」こそがしんどくてつらい。映画『劇場』(又吉直樹原作)が抉る「信頼されること」の甘…
自信が持てない時、たった1人でも自分を肯定してくれる人がいてくれるだけで前に進めることがある。しかしその一方で、揺るぎない信頼に追い詰められてしまうこともある。映画『劇場』から、信じてくれる人に辛く当たってしまう歪んだ心の動きを知る
あわせて読みたい
【映画】『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』で号泣し続けた私はTVアニメを観ていない
TVアニメは観ていない、というかその存在さえ知らず、物語や登場人物の設定も何も知らないまま観に行った映画『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』に、私は大号泣した。「悪意のない物語」は基本的に好きではないが、この作品は驚くほど私に突き刺さった
あわせて読みたい
【情熱】「ルール」は守るため”だけ”に存在するのか?正義を実現するための「ルール」のあり方は?:映…
「ルールは守らなければならない」というのは大前提だが、常に例外は存在する。どれほど重度の自閉症患者でも断らない無許可の施設で、情熱を持って問題に対処する主人公を描く映画『スペシャルズ!』から、「ルールのあるべき姿」を考える
あわせて読みたい
【実話】正論を振りかざす人が”強い”社会は窮屈だ。映画『すばらしき世界』が描く「正解の曖昧さ」
「SNSなどでの炎上を回避する」という気持ちから「正論を言うに留めよう」という態度がナチュラルになりつつある社会には、全員が全員の首を締め付け合っているような窮屈さを感じてしまう。西川美和『すばらしき世界』から、善悪の境界の曖昧さを体感する
あわせて読みたい
【誠実】地下鉄サリン事件の被害者が荒木浩に密着。「贖罪」とは何かを考えさせる衝撃の映画:『AGANAI…
私には、「謝罪すること」が「誠実」だという感覚がない。むしろ映画『AGANAI 地下鉄サリン事件と私』では、「謝罪しない誠実さ」が描かれる。被害者側と加害者側の対話から、「謝罪」「贖罪」の意味と、信じているものを諦めさせることの難しさについて書く
あわせて読みたい
【権利】衝撃のドキュメンタリー映画『ヤクザと憲法』は、「異質さを排除する社会」と「生きる権利」を問う
「ヤクザ」が排除された現在でも、「ヤクザが担ってきた機能」が不要になるわけじゃない。ではそれを、公権力が代替するのだろうか?実際の組事務所(東組清勇会)にカメラを持ち込むドキュメンタリー映画『ヤクザと憲法』が映し出す川口和秀・松山尚人・河野裕之の姿から、「基本的人権」のあり方について考えさせられた
あわせて読みたい
【感想】映画『窮鼠はチーズの夢を見る』を異性愛者の男性(私)はこう観た。原作も読んだ上での考察
私は「腐男子」というわけでは決してないのですが、周りにいる腐女子の方に教えを請いながら、多少BL作品に触れたことがあります。その中でもダントツに素晴らしかったのが、水城せとな『窮鼠はチーズの夢を見る』です。その映画と原作の感想、そして私なりの考察について書いていきます
あわせて読みたい
【対話】刑務所内を撮影した衝撃の映画。「罰則」ではなく「更生」を目指す環境から罪と罰を学ぶ:映画…
2008年に開設された新たな刑務所「島根あさひ社会復帰促進センター」で行われる「TC」というプログラム。「罰則」ではなく「対話」によって「加害者であることを受け入れる」過程を、刑務所内にカメラを入れて撮影した『プリズン・サークル』で知る。
あわせて読みたい
【天才】『三島由紀夫vs東大全共闘』後に「伝説の討論」と呼ばれる天才のバトルを記録した驚異の映像
1969年5月13日、三島由紀夫と1000人の東大全共闘の討論が行われた。TBSだけが撮影していたフィルムを元に構成された映画「三島由紀夫vs東大全共闘」は、知的興奮に満ち溢れている。切腹の一年半前の討論から、三島由紀夫が考えていたことと、そのスタンスを学ぶ
あわせて読みたい
【救い】耐えられない辛さの中でどう生きるか。短歌で弱者の味方を志すホームレス少女の生き様:『セー…
死にゆく母を眺め、施設で暴力を振るわれ、拾った新聞で文字を覚えたという壮絶な過去を持つ鳥居。『セーラー服の歌人 鳥居』は、そんな辛い境遇を背景に、辛さに震えているだろう誰かを救うために短歌を生み出し続ける生き方を描き出す。凄い人がいるものだ
あわせて読みたい
【理解】東田直樹の本は「自閉症の見方」を一変させた。自身も自閉症児を育てるプロデューサーが映画化…
東田直樹の著作を英訳し世界に広めた人物(自閉症児を育てている)も登場する映画『僕が跳びはねる理由』には、「東田直樹が語る自閉症の世界」を知ることで接し方や考え方が変わったという家族が登場する。「自閉症は知恵遅れではない」と示した東田直樹の多大な功績を実感できる
あわせて読みたい
【無知】メディアの問題の本質は?「報道の限界」と「情報の受け取り方」を独裁政治の現実から知る:『…
メディアは確かに「事実」を報じている。しかし、報道に乗らない情報まで含めなければ、本当の意味で世の中を理解することは難しいと、『こうして世界は誤解する』は教えてくれる。アラブ諸国での取材の現実から、報道の「限界」と「受け取り方」を学ぶ
あわせて読みたい
【異端】子育ては「期待しない」「普通から外れさせる」が大事。”劇薬”のような父親の教育論:『オーマ…
どんな親でも、子どもを幸せにしてあげたい、と考えるでしょう。しかしそのために、過保護になりすぎてしまっている、ということもあるかもしれません。『オーマイ・ゴッドファーザー』をベースに、子どもを豊かに、力強く生きさせるための”劇薬”を学ぶ
あわせて読みたい
【あらすじ】「愛されたい」「必要とされたい」はこんなに難しい。藤崎彩織が描く「ままならない関係性…
好きな人の隣にいたい。そんなシンプルな願いこそ、一番難しい。誰かの特別になるために「異性」であることを諦め、でも「異性」として見られないことに苦しさを覚えてしまう。藤崎彩織『ふたご』が描き出す、名前がつかない切実な関係性
あわせて読みたい
【継続】「言語化できない」を乗り越えろ。「読者としての文章術」で、自分の思考をクリアにする:『読…
ブログやSNSなどが登場したことで、文章を書く機会は増えていると言える。しかし同時に、「他人に評価されるために書く」という意識も強くなっているだろう。『読みたいことを書けばいい』から、「楽しく書き”続ける”」ための心得を学ぶ
あわせて読みたい
【加虐】メディアの役割とは?森達也『A』が提示した「事実を報じる限界」と「思考停止社会」
オウム真理教の内部に潜入した、森達也のドキュメンタリー映画『A』は衝撃を与えた。しかしそれは、宗教団体ではなく、社会の方を切り取った作品だった。思考することを止めた社会の加虐性と、客観的な事実など切り取れないという現実について書く
あわせて読みたい
【議論】安楽死のできない日本は「死ぬ権利」を奪っていると思う(合法化を希望している):『安楽死を…
私は、安楽死が合法化されてほしいと思っている。そのためには、人間には「死ぬ権利」があると合意されなければならないだろう。安楽死は時折話題になるが、なかなか議論が深まらない。『安楽死を遂げた日本人』をベースに、安楽死の現状を理解する
ルシルナ
苦しい・しんどい【本・映画の感想】 | ルシルナ
生きていると、しんどい・悲しいと感じることも多いでしょう。私も、世の中の「当たり前」に馴染めなかったり、みんなが普通にできることが上手くやれずに苦しい思いをする…
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…
























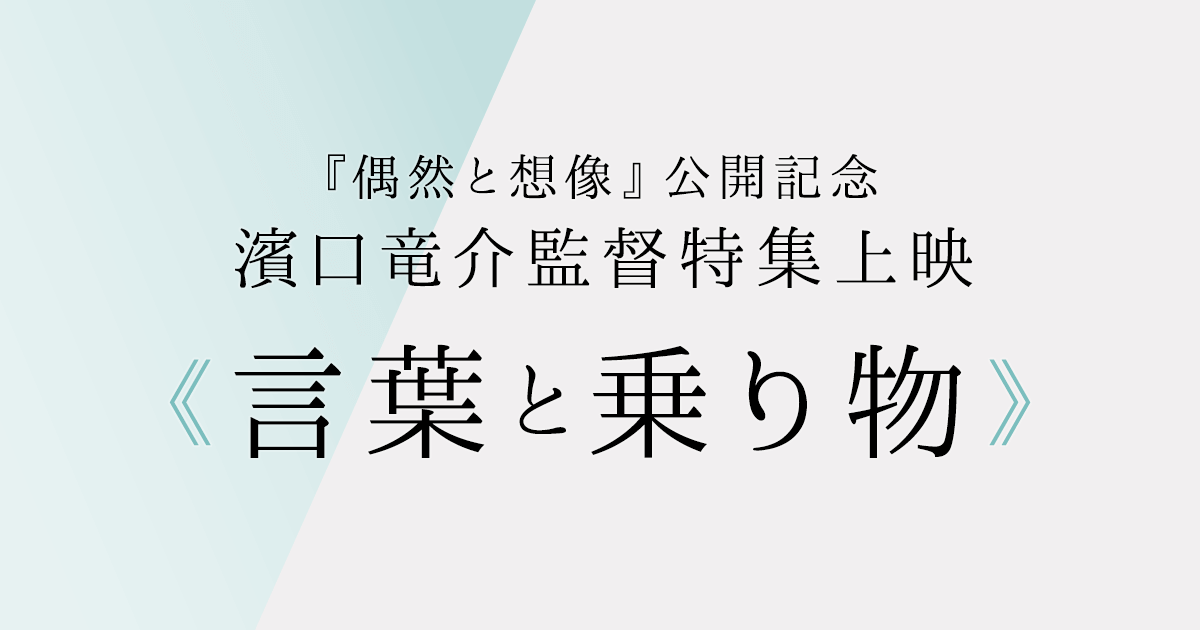
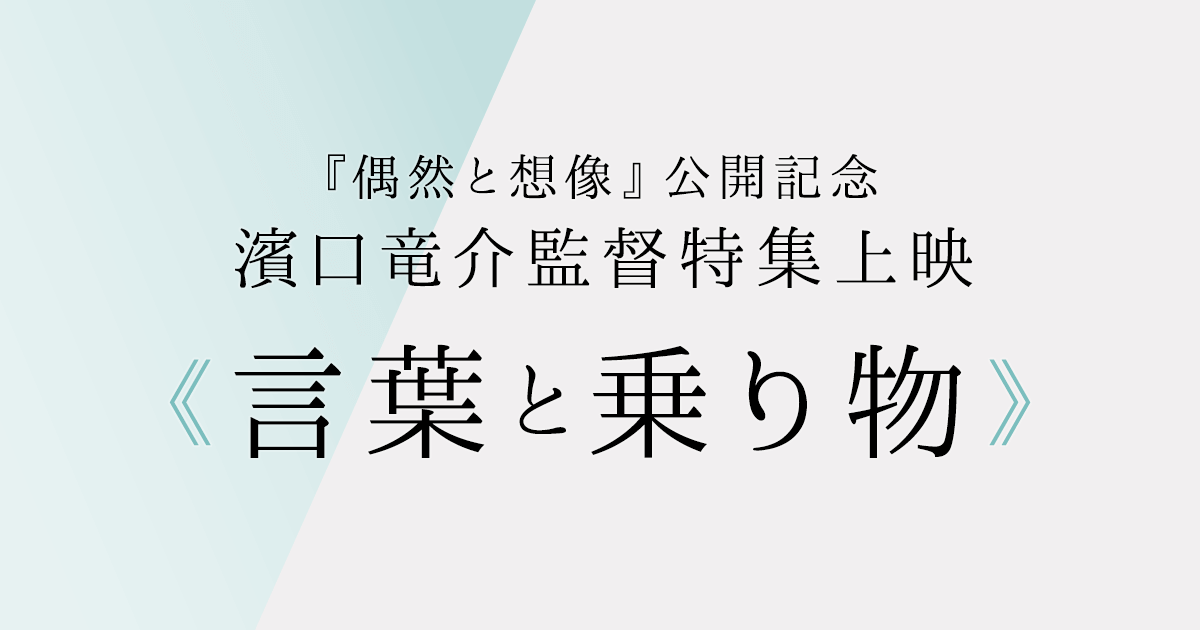









































































































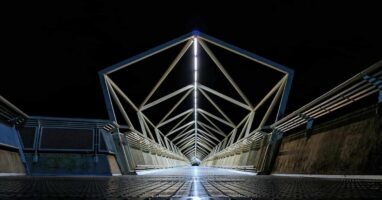
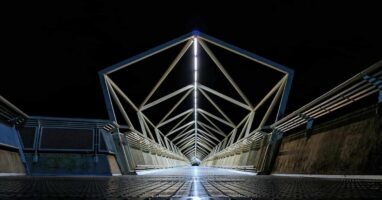






































































































































































































コメント