目次
はじめに
この記事で取り上げる映画

「夢見る小学校」公式HP
この映画をガイドにしながら記事を書いていきます
今どこで観れるのか?
特にありません
この記事の3つの要点
- 「英語」以外の授業が存在せず、「プロジェクト」と呼ばれる「体験学習」がメインの私立小学校「きのくに子どもの村学園」の衝撃
- 「私立校だから出来るんだ」という思い込みを覆す、全国様々な公立校の興味深い取り組み
- 「学校は”楽しい場所”であるべきだ」という信念と、基本的に制約を設けない方針の文科省
時間割も通知表も宿題も校則も、全部無くしたって問題ないくらい、日本の教育は「自由」なのだと、本作を観て初めて知ることが出来た
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
記事中の引用は、映画館で取ったメモを参考にしているので、正確なものではありません
衝撃的な教育を行う私立小学校「きのくに子どもの村学園」を描く映画『夢見る小学校』、そして様々な公立校の奮闘を描く映画『夢見る公立校長先生』
あわせて読みたい
【本質】子どもの頃には読めない哲学書。「他人の哲学はつまらない」と語る著者が説く「問うこと」の大…
『<子ども>のための哲学』は決して、「子どもでも易しく理解できる哲学の入門書」ではない。むしろかなり難易度が高いと言っていい。著者の永井均が、子どもの頃から囚われ続けている2つの大きな疑問をベースに、「『哲学する』とはどういうことか?」を深堀りする作品
この記事では、『夢見る小学校』『夢見る公立校長先生』という2作品を取り上げる。映画『夢見る公立校長先生』は映画『夢見る小学校』の続編的な作品ではあるが、どちらから先に観ても問題ないだろう。
どちらも物凄く興味深い作品だった。映画『夢見る小学校』では、先進的・革新的な教育を行う「きのくに子どもの村学園」という私立小学校に密着しているのだが、ここで行われている教育は非常に面白い。「教育というのは本来こうあるべきだよなぁ」と感じさせられたし、「もし子どもの頃の自分がここに通っていたらどうだっただろうか」とも考えさせられた。

さて恐らく、映画を観ながら多くの人が、「私立小学校だからこういう取り組みが出来るんだろう」と感じるのではないかと思う。だからだろう、映画『夢見る小学校』では後半に少し、「チャレンジングなことをしている公立校」も扱われている。そして、「そのような公立校の校長先生」をメインで取り上げたのが、続編の映画『夢見る公立校長先生』なのだ。
あわせて読みたい
【変人】学校教育が担うべき役割は?子供の才能を伸ばすために「異質な人」とどう出会うべきか?:『飛…
高校の美術教師からアーティストとして活動するようになった著者は、教育の現場に「余白(スキマ)」が減っていると指摘する。『飛び立つスキマの設計学』をベースに、子どもたちが置かれている現状と、教育が成すべき役割について確認する。
実は、「公教育の枠組み」の範囲内でも、かなり自由なことが出来る。例えば、この2作品を観て初めて知ったが、「通知表」「時間割」「宿題」などはすべて、「法律等で定められているもの」ではないそうだ。学校が「自主的」に行っているものであり、本来的には無くても問題ないのだ。そして本作では、そのような「公教育の枠組み」を正しく理解している校長先生が、ルールの範囲内で行っている革新的な取り組みを取り上げているというわけだだ。
だから本作は、「公立校に子どもを通わせている人」も含めた、「既に親である、あるいはこれから親になるつもりがあるすべての人」が観るべき作品だと思う。私は別に、親でもないし親になるつもりもないのだが、確かにそんな私にも「知識」としてとても興味深い作品だった。しかし、私が「親に観てほしい」と考えるのには、もっと実際的な理由がある。
というのも、「親が文句を言いさえしなければ、公立校は何だって出来る」からだ。この「文句を言う」というのは、実際に言うかどうかは関係ない。何故なら、学校側が「こんなことをしたら保護者から文句が出るかもしれない」と考えた時点で、先進的・革新的な取り組みは行われなくなってしまうからだ。
だから大事なのは、「文句を言うつもりはない」と明確な意思表示をすることだろう。映画を観れば、その必要性がとても強く理解できるはずだ。そんなわけで私は、「既に親である、あるいはこれから親になるつもりがある人」は全員観るべきだと思う。
あわせて読みたい
【感想】映画『朝が来る』が描く、「我が子を返して欲しい気持ち」を消せない特別養子縁組のリアル
「特別養子縁組」を軸に人々の葛藤を描く映画『朝が来る』は、決して「特別養子縁組」の話ではない。「『起こるだろうが、起こるはずがない』と思っていた状況」に直面せざるを得ない人々が、「すべての選択肢が不正解」という中でどんな決断を下すのかが問われる、非常に示唆に富む作品だ
それではまず、私が以前読んだ本の話をしながら、「環境の重要さ」について触れていくことにしよう。
「世界一の技術を持つ中小企業」と「東大生に勝った女子高生アイドル」はいかにして生まれたのか?
私は以前、『先着順採用、会議自由参加で「世界一の小企業」をつくった』(松浦元男/講談社)という本を読んだことがある。愛知県の樹研工業という中小企業を取り上げた作品だ。極小精密部品の製造では国内トップメーカーであり、世界的に見ても「この会社でしか作れないもの」があるくらい技術レベルの高さで知られているという。
著:松浦 元男
¥65 (2024/02/03 21:10時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
さて、そのような会社なのだから、「凄腕の技術者を中途で採用する」など、技術者の確保に力を入れていると考えるのが普通だろう。しかしなんとこの会社の採用は、「面接に来た順」だという。性別、学歴、年齢、能力、人種など一切関係なく、「応募があった順に人を採用していく」という、普通では考えられないようなやり方をしているのである。

あわせて読みたい
【働く】給料が上がらない、上げる方法を知りたい人は木暮太一のこの本を。『資本論』が意外と役に立つ…
「仕事で成果を出しても給料が上がるわけではない」と聞いて、あなたはどう感じるだろうか?これは、マルクスの『資本論』における「使用価値」と「価値」の違いを踏まえた主張である。木暮太一『人生格差はこれで決まる 働き方の損益分岐点』から「目指すべき働き方」を学ぶ
しかしそんなやり方だと、入社時の能力にはかなりバラツキがあるはずで、だとすれば、その後の業務に支障を来たしてもおかしくないと感じるだろう。しかしまったくそんなことはないそうだ。例えば、高校時代にまったく数学が出来なかった女性は、入社から数年後には独学で大学受験レベルの問題が解けるようになったという。中卒の工場長は「歯車理論」について独学し、海外の世界的権威から大学院卒だと思われていたというレベルにまでなった。入社時にまったく英語を喋れなかった者も、いつの間にか英語で外国人と交渉するようになっていたのだそうだ。
そんな凄まじい変化をもたらしている要因は、間違いなく社長のモットーにあるだろう。「チャンスとモチベーションを与えること」を明確に意識しているのだそうだ。それによって社員は独自に成長し、会社は結果として世界に類を見ない技術を持つ企業へと成長した。まさに「環境が人を成長させた事例」と言っていいと思う。
あわせて読みたい
【人生】日本人有名プロゲーマー・梅原大吾の名言満載の本。「努力そのものを楽しむ」ための生き方とは…
「eスポーツ」という呼び名が世の中に定着する遥か以前から活躍する日本人初のプロゲーマー・梅原大吾。17歳で世界一となり、今も一線を走り続けているが、そんな彼が『勝ち続ける意志力』で語る、「『努力している状態』こそを楽しむ」という考え方は、誰の人生にも参考になるはずだ
さて、もう1冊紹介しよう。『女子高生アイドルは、なぜ東大生に知力で勝てたのか?』という本で、私は観たことはないが、NHKの「すイエんサー」という番組のプロデューサーが書いている。タイトルから想像出来る通りの内容で、「女子高生アイドルが、東大生とガチの知力バトルをして勝ってしまった」というその凄まじい軌跡が描かれている作品だ。
著:村松秀, イラスト:五月女ケイ子
¥770 (2024/02/03 21:11時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
本書の冒頭には、実際に東大生と勝負をして勝利した対決の模様が描かれている。与えられたお題は「ペーパーブリッジ」。ルールは簡単で、「A4の紙15枚だけを使用して『橋状の構造物』を作成し、より強い荷重に耐えられた方が勝ち」というものだ。バリバリの知力バトルである。集められた「すイエんサーガールズ」は、お世辞にも勉強が出来るとは言えない女子高生アイドルであり、普通に考えて彼女たちに勝ち目があるとは思えない。
しかしなんと「すイエんサーガールズ」はこの勝負に圧勝したのである。東大生が作った構造物よりも3倍の荷重に耐えたのだ。この結果には番組スタッフも驚愕したという。そして、この勝利が「まぐれ」ではないことを確かめるべく、京都大学・東北大学・北海道大学など様々な大学生と対決を行い、最終的に5勝4敗と勝ち越す結果で終わった。ちょっと驚くべき結果と言えるだろう。
あわせて読みたい
【社会】学生が勉強しないのは、若者が働かないのは何故か?教育現場からの悲鳴と知見を内田樹が解説:…
教育現場では、「子どもたちが学びから逃走する」「学ばないことを誇らしく思う」という、それまでには考えられなかった振る舞いが目立っている。内田樹は『下流志向』の中で、その原因を「等価交換」だと指摘。「学ばないための努力をする」という発想の根幹にある理屈を解き明かす
しかし何故彼女たちは大学生に勝つことが出来たのか。その背景には、「すイエんサー」という番組内で行っていることが関係していると言えるだろう。彼女たちはいつも、何も知らされずに集められ、そして唐突に訳の分からないお題が与えられる。例えば、「パスタを食べるときにソースの飛び跳ねをなくしたい!」「バースデーケーキのロウソクの火を一息だけで消したい!」「スイカの種がまったく入らないようにカットしたい!」と言ったような感じだ。そして「正解に辿り着くまで収録が終わらない」という地獄のような状態に放り込まれるのである。

彼女たちには途中で、「意味不明」としか言いようがない「謎のヒント」が与えられる。そして、それ以外には何の情報もない。その状況下で、訳の分からないお題の「正解」を導き出さなければならないのだ。
そのためにはとにかく考えるしかない。番組プロデューサーはこれを「グルグル思考」と呼んでおり、「この『グルグル思考』を日頃からやり続けたお陰で、東大生に勝つような発想を身につけることが出来たのだろう」と書いていた。
あわせて読みたい
【貢献】有名な科学者は、どんな派手な失敗をしてきたか?失敗が失敗でなかったアインシュタインも登場…
どれほど偉大な科学者であっても失敗を避けることはできないが、「単なる失敗」で終わることはない。誤った考え方や主張が、プラスの効果をもたらすこともあるのだ。『偉大なる失敗』から、天才科学者の「失敗」と、その意外な「貢献」を知る
さて、この2つのエピソードから私が主張したいのは次のようなことだ。
大人でも、制約のない環境が与えられれば、その能力は飛躍的に開花する。であれば、子どもだったら余計そうなるはずだ。
そしてまさに、そのような考え方をベースに教育を行っているのが、映画『夢見る小学校』で扱われる「きのくに子どもの村学園」なのである。
「きのくに子どもの村学園」という凄まじい衝撃
「きのくに子どもの村学園」は全国に5校、山梨・福井・和歌山・福岡・長崎にあるのだが、映画の中で主に映し出されるのは山梨にある学校である。
本当に、凄まじく衝撃的だった。
あわせて読みたい
【異端】子育てがうまくいかないと悩む方へ。9歳で大学入学の天才児に学ぶ「すべきでないこと」:『ぼく…
12歳で数学の未解決問題を解いた天才児は、3歳の時に「16歳で靴紐が結べるようになったらラッキー」と宣告されていた。専門家の意見に逆らって、重度の自閉症児の才能をどう開花させたのかを、『ぼくは数式で宇宙の美しさを伝えたい』から学ぶ
壁に貼られている時間割を見る限り、この学校には「英語」以外の授業らしい授業は存在しない。国語・算数・理科・社会を教えるための時間など無いのだ。では児童たちは一日の大半を何に費やしているのか。それが「プロジェクト」と呼ばれるもので、いわゆる「体験学習」である。
児童たちは、「料理」「大工」「工作」「演劇」「伝統から学ぶ」の5つの中から、自らの意思で何か1つのクラスを選ぶ。この学校では、この「クラス」単位ですべての行動が決まるため、学年ごとに区分けされるのではなく、1年生から6年生までが「同じクラス」に所属するという構成になっている。
では、それぞれのクラスでどのようなことが行われているのだろうか。
あわせて読みたい
【呪縛】生きづらさの正体とそこからどう抜けるかを、「支配される安心」「自由の不自由」から考える:…
自由に生きられず、どうしたらいいのか悩む人も多くいるでしょう。『自由をつくる 自在に生きる』では、「自由」のためには「支配に気づくこと」が何より大事であり、さらに「自由」とは「不自由なもの」だと説きます。どう生きるかを考える指針となる一冊。
例えば「料理」なら、まず1年間のテーマを決めるところから始まる。もちろん決めるのは児童たちだ。大人(先生)は口を出さない。そして、そのテーマが「麺」に決まれば、「そばの実を育てる」ことからプロジェクトが始まるのである。もちろんその計画を主導するのも子どもたちだ。1週間の時間割の中で、どの時間に種まきし、どの時期に収穫するのかというスケジュールを決めるのである。決定はすべて投票によって行われ、大人にも投票権があるのだが、それは児童たちと同じ1票だ。完全に民主的なプロセスで決められるのである。その後子どもたちは、採取したそばの実を使って蕎麦づくりを始めるのだが、どうも上手くいかない。そこで子どもたちは、自ら県内の蕎麦店に連絡をし、蕎麦打ちやつゆの作り方などを取材に行くというわけだ。

「大工」の場合にはなんと、学校の渡り廊下の屋根やテラスなどを児童自ら作る。もちろん、「作るもの」や「設計」も子どもたちの主導であり、大人が口を出すことはない。作業ももちろん子どもたちが行い、のこぎりで木を切り、電動ドライバーでネジを入れ、高いところに登って屋根に板を貼っていくのである。
これを小学生がやっている光景は、本当にちょっと衝撃的だった。本作では、ナレーションを務めている吉岡秀隆が「日本一楽しい学校」と紹介している。確かにその通りだろう。こんな楽しい学校はなかなかないと思う。
あわせて読みたい
【思考】『翔太と猫のインサイトの夏休み』は、中学生と猫の対話から「自分の頭で考える」を学べる良書
「中学生の翔太」と「猫のインサイト」が「答えの出ない問い」について対話する『翔太と猫のインサイトの夏休み』は、「哲学」の違う側面を見せてくれる。過去の哲学者・思想家の考えを知ることが「哲学」なのではなく、「自分の頭で考えること」こそ「哲学」の本質だと理解する
例えばこの学校には、「椅子に座る」みたいな規則はない。だから子どもたちは、話し合いをしている時に思い思いの状態でいる。廊下に寝転んでいたり、机に突っ伏していたり、大人におんぶしてもらったりもするのだ。とにかくすべてが、本人の自主性に任されているのである。
また大きな特徴として、「『先生』という存在はいない」という方針が挙げられるだろう。だからここまで、「大人」という表記をしてきた。「先生」と「生徒」だと、そこに必然的に上下関係みたいなものが生まれてしまうが、この学校ではそれをかなり意識的に取り払おうとしている。だから基本的に、「大人」と「子ども」の垣根はない。もちろん、「大人だから意見が通りやすい」とか「大人の意見だから従わなければならない」みたいなことも一切ないのである。大人でさえ、自ら意見し、子どもたちから賛同を得なければ、その主張が通ることはないのだ。
とてもフェアだなぁと思う。私には、とても理想的な環境に映った。
あわせて読みたい
【驚異】甲子園「2.9連覇」を成し遂げた駒大苫小牧野球部監督・香田誉士史の破天荒で規格外の人生:『勝…
「田中将大と斎藤佑樹の死闘」「37年ぶりの決勝戦再試合」「驚異の2.9連覇」など話題に事欠かなかった駒大苫小牧野球部。その伝説のチームを率いた名将・香田誉士史の評伝『勝ちすぎた監督』は、体罰が問題になった男の毀誉褒貶を余すところなく描き出す。しかしとんでもない男だ
「君は何をしてもいいし、自由である」というメッセージこそが安心を生み、成長に繋がる
「きのくに子どもの村学園」の学園長であり、子どもたちから「ほりさん」と呼ばれている堀真一郎は、密着中に何度も印象的な言葉を口にする。その中でも一番響いたのは次のようなものだ。
(普通の学校や社会では)「自由には責任が伴う」と言ってしまう。でもここでは、「大人が責任を取るから思いっきりやってくれ」と伝えています。「児童に責任が伴う」というのは、この学校では”タブー”なんです。
『夢見る小学校』(監督:オオタヴィン)
あわせて読みたい
【生きろ】「どう生き延びるか」と覚悟を決める考え方。西原理恵子が語る「カネ」だけじゃない人生訓:…
西原理恵子『この世でいちばん大事な「カネ」の話』は、決して「お金」の話だけではありません。「自分が望む生き方」を実現するための「闘い方」を伝授してくれると同時に、「しなくていい失敗を回避する考え方」も提示してくれます。学校や家庭ではなかなか学べない人生訓
言うのは簡単だが、これほど難しいこともないだろうと思う。
心理学の世界に、「心理的安全性」という言葉がある。ざっくり説明すれば、「『どんな言動をしても批判されたり馬鹿にされたりしないだろう』と感じられている状態」となるだろう。この「心理的安全性」が低いと、例えば「不正の隠蔽」など様々な問題が起こることが知られている。また、何かで読んだのだが、チームマネジメントにおいて「成果」との相関関係が最も高かったのが「心理的安全性」だったと、グーグルが自社の調査で明らかにしたという話もあったはずだ。このように、どんな組織であれ「心理的安全性」は非常に重要なのだが、「きのくに子どもの村学園」では、この「心理的安全性」が極限まで高められていると言っていいのではないかと思う。
子どもたちは基本的に何をしてもいい。もちろん、他人を傷つけてはいけないし、そういう「大前提となる約束ごと」みたいなものはたぶんあるのだと思う。作中には、それがどのように子どもたちと共有されているのかについて触れられる場面はなかったが、さすがにそのような「絶対的な禁止事項」は用意されているはずだ。しかし、そこさえ守られていれば、あとは何をしてもいい。以前観た映画『すばらしき映画音楽たち』の中に、「映画音楽のルールは1つだけ。『ルールなどない』だ」という言葉が出てきたが、まさにそのような環境だと言っていいだろうと思う。
あわせて読みたい
【革新】映画音楽における唯一のルールは「ルールなど無い」だ。”異次元の音”を生み出す天才を追う:映…
「無声映画」から始まった映画業界で、音楽の重要性はいかに認識されたのか?『JAWS』の印象的な音楽を生み出した天才は、映画音楽に何をもたらしたのか?様々な映画の実際の映像を組み込みながら、「映画音楽」の世界を深堀りする映画『すばらしき映画音楽たち』で、異才たちの「創作」に触れる
映画に登場する、卒業式でコメントをする女の子の言葉がとても印象的だった。彼女はこの学校に来た時、最初は「何をしたらいいのか分からない」と感じ、周りの人に聞いてばかりだったそうだ。しかし誰に聞いても、「やりたいことをやればいいんだよ」という答えが返ってくるので、それで「本当に何をしてもいいんだ」と思えるようになったと話していた。

あるいは、学園長の堀真一郎が、昔この学校にいた女の子の話をしていた場面も印象深い。その子は初めホームシックが強かったのだが、慣れてくると次第に、「ほりさん、私はここにいると私でいられるの」と口にするようになったという。その時、女の子は小学4年生。そんな年頃の子が「私でいられる」という実感を得て、さらにそれを言語化できたことへの驚きを込めて学園長は回想していた。
「何をしてもいい」と口で言うのは簡単だが、相手にそう感じさせるのはとても難しい。さらにそれを、学校という組織の中で、幼い子どもたち相手に実行するのは相当のハードルだろう。しかし恐らく、学校全体でそのような考えがきちんと共有されているのだろうし、だからこそ、本当に「心理的安全性」が確保された環境が作れているのだと思う。
あわせて読みたい
【権威】心理学の衝撃実験をテレビ番組の収録で実践。「自分は残虐ではない」と思う人ほど知るべき:『…
フランスのテレビ局が行った「現代版ミルグラム実験」の詳細が語られる『死のテレビ実験 人はそこまで服従するのか』は、「権威」を感じる対象から命じられれば誰もが残虐な行為をしてしまい得ることを示す。全人類必読の「過ちを事前に回避する」ための知見を学ぶ
確か茂木健一郎だったと思うが、映画の中で、
夢中になれるもの、それを見つけることができれば、この世界にいていいんだと思える。
『夢見る小学校』(監督:オオタヴィン)
みたいなことを言っていた。
あるいは、映画のラストで、
子どもたちは、自由さえあれば幸せになれる力を持っているんです。
『夢見る小学校』(監督:オオタヴィン)
というナレーションが流れもする。まさにその通りだろうし、そのことを強く実感させてくれる作品だった。
あわせて読みたい
【飛躍】有名哲学者は”中二病”だった?飲茶氏が易しく語る「古い常識を乗り越えるための哲学の力」:『1…
『14歳からの哲学入門』というタイトルは、「14歳向けの本」という意味ではなく、「14歳は哲学することに向いている」という示唆である。飲茶氏は「偉大な哲学者は皆”中二病”だ」と説き、特に若い人に向けて、「新しい価値観を生み出すためには哲学が重要だ」と語る
「学力」に問題はないのだろうか?
さて、親の立場からすれば、「このような教育で、学力的に問題はないのか?」と心配になるところだろう。この点については作中で、「卒業生の、高校での成績の平均」みたいな図が表示された。詳しく説明できるほどその詳細について覚えてはいないが、卒業生の学力は「かなり上位」に位置するようだ。
また本作には、文化人類学者である辻信一が出演している。何故なら、彼のゼミに「きのくに子どもの村学園」の卒業生が何人か在籍していたことがあるからだ。その中でも辻氏の印象に強く残っているのは、ある年の卒業生のトップである「総代」だった女性だという。もちろん、彼女は例外的な存在と言っていいだろうが、しかし少なくとも、「このような教育方針だからと言って、学力が劣ることはない」という事実の証明にはなるだろう。
さて、辻氏が話していたことで興味深かったのは「質問力」に関する話だ。海外の学生と関わる機会もある彼は、日本人学生が圧倒的に質問しないことに言及していた。例えば、アメリカでは相手がまだ喋っていてもお構いなくどんどん質問を繰り出すのに対して、日本ではそもそも質問する人が少ないのだそうだ。しかし「きのくに子どもの村学園」は、逆に異常なほど質問するという。とにかく、「探究心」がずば抜けているそうだ。

そんな彼が、このようなことを言う場面がある。
あわせて読みたい
【協働】日本の未来は福井から。地方だからこその「問題意識の共有」が、社会変革を成し遂げる強み:『…
コンパクトシティの先進地域・富山市や、起業家精神が醸成される鯖江市など、富山・福井の「変革」から日本の未来を照射する『福井モデル 未来は地方から始まる』は、決して「地方改革」だけの内容ではない。「危機意識の共有」があらゆる問題解決に重要だと認識できる1冊
問いというのは教室から生まれるわけじゃない。暮らしの中から生まれるのではないか。だから、生活の中から問いを拾える環境にいる子たちは強い。
『夢見る小学校』(監督:オオタヴィン)
世の中のことにはほとんど答えなんかない。世界は問いに満ちている。だから僕たちは、死ぬまで「知りたい」という気持ちが消えない。
それなのに、問いを抑え込まれてしまったら、人生って一体何なんだろうって感じる。
『夢見る小学校』(監督:オオタヴィン)
このような感覚は、私もとても理解できる。近い話だと思うが、以前観た何かの番組でマツコ・デラックスが、「昨日より、ほんの少しでもいいから新しい何かを知って死にたい」と言っていた。同じように私も、日々、「何かを知りたい」と思って生きている。私が抱くこの「知りたい欲」がどのように醸成されたのかはよく分からないが、「きのくに子どもの村学園」ではそれが自発的に生み出されるような教育がなされていると言えるだろう。そしてこのことは、「学校の勉強が出来るかどうか」以上に、社会に出てから価値を持つと私は感じる。そういう意味でも、「体験学習」重視の教育にはとても大きな意味があると言えるだろう。
さて、学力の話に戻そう。冒頭で少し触れた通り、映画『夢見る小学校』には公立校の話も出てくる。その中から、学力に関して非常に興味深い取り組みを行っている事例を紹介しよう。
あわせて読みたい
【肯定】社会不適合者こそ非凡。学校・世の中に馴染めなかった異才たちの過去から”才能”の本質を知る:…
「みんなと同じ」に馴染めないと「社会不適合」と判断され、排除されてしまうことが多いでしょう。しかし『非属の才能』では、「どこにも属せない感覚」にこそ才能の源泉があると主張します。常識に違和感を覚えてしまう人を救う本から、同調圧力に屈しない生き方を学ぶ
その学校は、世田谷区にある桜ヶ丘中学校。同校で長年校長を務めた人物はかなりの改革者であり、公立校にも拘わらず、「校則はすべて廃止」「『遅刻』という概念を無くす」「通知表をつけない」など、様々な改革を推進していった。生徒がやりたいと言ったことは出来るだけ実現するように努め、「浴衣でもOKな日」を設けたり、ハロウィンでは仮装して登校しても良いことにしたりするなど興味深いことを次々に行ってきた人物である。
そしてそんな改革を少しずつ推し進めた校長は、最終的に、「全校集会で決まったことは可能な限り実現する」と生徒たちに約束した。それまでは、全校集会で何か決まっても、最終的に教師がNOと言えば提案が破棄されてしまう状況だったため、全校集会がまったく盛り上がらなかったという。しかし校長の宣言以降、状況は大きく変わり、活発に意見が出されるようになる。
そしてついに生徒から、「定期テストを無くしてほしい」という要望が出たそうだ。この時、校長は内心でガッツポーズしたと話していた。何故なら、彼も前々から定期テストを無くしたいと考えていたからだ。そして本当にそれを実現し、日々の小テストのみだけは残した上で、定期テストは無くしてしまったのである。
あわせて読みたい
【感想】池田晶子『14歳からの哲学』で思考・自由・孤独の大事さを知る。孤独を感じることって大事だ
「元々持ってた価値観とは違う考えに触れ、それを理解したいと思う場面」でしか「考える」という行為は発動しないと著者は言う。つまり我々は普段、まったく考えていないのだ。『14歳からの哲学』をベースに、「考えること」と自由・孤独・人生との関係を知る
その結果どうなったのか。定期テストを止めた後、同校は世田谷区で学力トップに躍り出たそうだ。もちろん、「定期テストを止めたこと」との因果関係が明確に示されているわけではないと思うが、まったく無関係とも思えないだろう。このような事例を考慮してみても、いわゆる「普通の授業」を行わない「きのくに子どもの村学園」で学力が劣るとは考えにくいのではないだろうか。

では、その背景に何があるのか、少し想像してみることにしよう。
私は学生時代、結構勉強が出来た方だ。ただ、「生まれながらの天才」なんてことはまったくなく、「自主的に勉強する努力を続けたことによる秀才」である。地方の進学校で常に学年5位以内ぐらいはキープ出来ていたような気がする(昔のことはあまり覚えていないので自信はないが)。
あわせて読みたい
【天才】『三島由紀夫vs東大全共闘』後に「伝説の討論」と呼ばれる天才のバトルを記録した驚異の映像
1969年5月13日、三島由紀夫と1000人の東大全共闘の討論が行われた。TBSだけが撮影していたフィルムを元に構成された映画「三島由紀夫vs東大全共闘」は、知的興奮に満ち溢れている。切腹の一年半前の討論から、三島由紀夫が考えていたことと、そのスタンスを学ぶ
さて、そんな私が学力を保てていたのは、「とにかく長時間ひたすら勉強していた」からだ。これは、「そうしなければ学力を維持出来なかっただろう」という意味を含んでいる。そして大人になり、「何かを学ぶのに膨大な時間を注ぎ込めなくなった」ことで浮き彫りになったのは、「興味・関心の無いことはなかなか覚えられない」という残念な事実だ。これは恐らく、一部の「超天才」を除くほとんどの人に共通することではないかと思う。
そしてだからこそ、「自分の興味・関心に自分のリソースのすべてを注ぎ込む」ことが大事になると私は考えている。特に今の時代、なかなか「ジェネラリスト」では生きていくのが難しいだろう。突出した何かを持つ「スペシャリスト」が求められているように感じるので、時代の変化を鑑みても一層その点が重視される世の中になっているのではないかと思う。
そしてだからこそ、「きのくに子どもの村学園」のような環境が重要だと言えるだろう。まさしく「興味・関心」以外のことをすべて無視できる環境なのだ。また同じことは、定期テストを無くした桜ヶ丘中学校にも言えると思う。定期テストは普通、「興味・関心」の外側にあるものだからだ。そういうものをなるべく無くし、「興味・関心」に集中できる環境を作ったことが、結果として「学力トップ」を実現する要因になったのだと私は考えている。
あわせて読みたい
【天才】映画『Winny』(松本優作監督)で知った、金子勇の凄さと著作権法侵害事件の真相(ビットコイン…
稀代の天才プログラマー・金子勇が著作権法違反で逮捕・起訴された実話を描き出す映画『Winny』は、「警察の凄まじい横暴」「不用意な天才と、テック系知識に明るい弁護士のタッグ」「Winnyが明らかにしたとんでもない真実」など、見どころは多い。「金子勇=サトシ・ナカモト」説についても触れる
また「きのくに子どもの村学園」の良さは、「探究心」が「行動」と結びついていることにあるとも感じた。
先ほども少し触れた通り、私は「探究心」が強い方だと思う。しかし残念ながら、私の「探究心」はなかなか「行動」に結びつかない。一人で本を読んだり映画を観たりすることは普段からしているのだが、誰かに話を聞きに行ったり、フィールドワークに飛び出していったりするのは苦手なのだ。性格的な問題もあるし、そういう経験が少ないからというのも大きいと思う。
「きのくに子どもの村学園」では、自分たちで考えて行動しなければ何も始まらないのだから、必然的に「探究心」が「行動」と結びつくことになる。この環境はなかなか得難いものだと感じるし、大人にとってはなおさらだろう。それを子どもの頃から体験でき、しかも「責任は大人が取るから自由にやれ」と言われるのだから、こんな素晴らしい環境はないと思う。本当に羨ましい教育である。
あわせて読みたい
【斬新】ホームレスの家を「0円ハウス」と捉える坂口恭平の発想と視点に衝撃。日常の見え方が一変する:…
早稲田大学建築学科在籍中から「建築物の設計」に興味を持てなかった坂口恭平が、「ホームレスの家」に着目した『TOKYO 0円ハウス0円生活』には、「家」に対する考え方を一変させる視点が満載。「家に生活を合わせる」ではなく、「生活に家を合わせる」という発想の転換が見事
日本の教育の「許容度」は、実はとても広い
さて、「きのくに子どもの村学園」の教育方針を知って、「私立なんだからそりゃあ何だって出来るよな」と感じる人もいるだろう。しかし、その印象は正しくない。何故なら、「きのくに子どもの村学園」のカリキュラムも、きちんと文科省から認定を受けているからだ。文科省から認定を受けているのだから、「きのくに子どもの村学園」とまったく同じことを公立校がやっても何の問題も無いことになる。実際、長野県にある伊那小学校は公立校だが、机に向かって受けるような授業ではなく「体験学習」メインの教育を60年以上も行っているのだ。通知表もずっと出していないという。

公立校だって、全然出来るのだ。
あわせて読みたい
【アート】「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」(森美術館)と「美術手帖 Chim↑Pom特集」の衝撃から「…
Chim↑Pomというアーティストについてさして詳しいことを知らずに観に行った、森美術館の「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」に、思考をドバドバと刺激されまくったので、Chim↑Pomが特集された「美術手帖」も慌てて買い、Chim↑Pomについてメッチャ考えてみた
文科省は確かに、学習指導要領という形で「こういうことを教えなさい」と規定してはいる。しかしそれを「どのように教えるべきか」までは定めていない。「国語」「算数」「理科」「社会」のような授業をしなければならないというルールは存在しないのである。伊那小学校に関しては確か、「『この体験学習では算数の知識が、この体験学習では理科の知識が身につきます』という説明を文科省に対して行うことで認定を得ている」みたいな説明がされていたように思う。
公立校はとにかく、「校長が運営に関するすべての権限を持つ」と定められているそうで、そのようなメッセージは特に続編である映画『夢見る公立校長先生』で強く主張されていた。校長の権限については「学校教育法 第37条 第4項」で定められており、「『学習指導要領』をきちんと満たしさえすれば、学校運営に関する制約はほとんど存在しない」と言っていいほどである。
この2作品を観て私は、この点に最も驚かされ、また最もためになる知識だと感じた。
あわせて読みたい
【悲劇】大川小学校はなぜ津波被害に遭ったのか?映画『生きる』が抉る現実と国家賠償請求の虚しさ
東日本大震災において、児童74人、教職員10人死亡という甚大な津波被害を生んだ大川小学校。その被害者遺族が真相究明のために奮闘する姿を追うドキュメンタリー映画『生きる』では、学校の酷い対応、出来れば避けたかった訴訟、下された画期的判決などが描かれ、様々な問題が提起される
冒頭でも書いた通り、文科省は「通知表」「時間割」「宿題」「校則」などについて何も規定していない。しかし、大抵の学校にはこれらが存在するし、だから多くの人が「無くてはならないもの」と考えているのではないかと思う。私もそんな1人だった。映画ではある校長が、「こんなことは、校長先生や校長先生になろうとしている人は大隊知っている」と言っていたが、裏を返せば、そういう立場にいる人以外はほとんど知らないのだと思う。
だからこそ、繰り返しになるが、「保護者のスタンス」がとても重要になってくるのだ。学校の改革の足を引っ張っているのは、実はあなたかもしれないのである。
公立校が行っている様々な挑戦
茅ヶ崎市立香川小学校は、2020年に通知表を廃止した。かなり最近の話である。前述した伊那小学校のように、昔から通知表が存在しなければ「そういうものなんだろう」と受け入れやすいと思うが、元々あったものを無くすとなると、やはり様々な反応が生まれ得るだろう。
あわせて読みたい
【不安】環境活動家グレタを追う映画。「たったひとりのストライキ」から国連スピーチまでの奮闘と激変…
環境活動家であるグレタのことを、私はずっと「怒りの人」「正義の人」だとばかり思っていた。しかしそうではない。彼女は「不安」から、いても立ってもいられずに行動を起こしただけなのだ。映画『グレタ ひとりぼっちの挑戦』から、グレタの実像とその強い想いを知る
茅ヶ崎市立香川小学校も当然、そのように考えた。そのため、児童数1000人を超えるマンモス校なのだが、通知表を廃止するにあたっては、すべての家庭に対してあらかじめ説明を行ったそうだ。校長はその時のことについて、「説明の後、記名ありで何らかの反応が返ってきたケースが100件ほどあった」と言っていた。それ以上の情報はなかったので、賛成・反対の割合などは不明だが、しかし「わざわざ学校に何か言おう」という人は反対意見を持つ可能性の方が高いように思う。校長は、反応をくれたすべての人にきちんと対応したと話していたが、この反応が「対応しきれないぐらいの量」だったら、「通知表を無くす」という改革は頓挫したかもしれない。やはり、「保護者」のスタンスがとても大事だと言えるだろう。
さて、先ほど「定期テストを無くした」と紹介した世田谷区立桜ヶ丘中学校は、学力以外でも凄まじく改革を行っている。なにせ、「法律を破らなければ何をしてもいい」というルール以外、何の制約もない学校なのだ。服装や髪型が自由なのは当然のこと、携帯電話やパソコンの持ち込みもOKだし、何ならハンモックを持ってくる者もいる。また、「登校しさえすれば、学校内のどこで何をしていても出席扱いにする」ということになっているので、授業に出ず、図書館や校長室にいてもOKだそうだ。

印象的だったのが、不登校になったことをきっかけに桜ヶ丘中学校に転校したという卒業生の話。転校してからは毎日学校が楽しくて、今は教師を目指して勉強している最中だという。彼女は、「桜ヶ丘中学校に転校しなかったら、今もまだ引きこもりだったかもしれないし、『学校なんか要らない』と思って教師を目指したりもしなかったかもしれない」と語っていた。この話だけでも、どれほど素晴らしい環境なのか理解できるだろう。
あわせて読みたい
【救い】自殺を否定しない「笑える自殺本」。「自殺したい」ってもっと気軽に言える社会がいい:『自殺…
生きることがしんどくて、自殺してしまいたくなる気持ちを、私はとても理解できます。しかし世の中的には、「死にたい」と口にすることはなかなか憚られるでしょう。「自殺を決して悪いと思わない」という著者が、「死」をもっと気楽に話せるようにと贈る、「笑える自殺本」
ある校長は、
何かやってもほとんど(文科省から)怒られはしないし、怒られたら止めればいい。
『夢見る公立校長先生』(監督:オオタヴィン)
と言っていた。学校の決まりごとのほとんどが、「なんとなく」あるいは「起こられないための予防策」程度のものでしかないということだろう。
あわせて読みたい
【矛盾】法律の”抜け穴”を衝く驚愕の小説。「ルールを通り抜けたものは善」という発想に潜む罠:『法廷…
完璧なルールは存在し得ない。だからこそ私たちは、矛盾を内包していると理解しながらルールを遵守する必要がある。「ルールを通り抜けたものは善」という”とりあえずの最善解”で社会を回している私たちに、『法廷遊戯』は「世界を支える土台の脆さ」を突きつける
映画を観ながら私は、「ルールがそんな感じなら、私が通っていた学校ももっと自由だったら良かったのに」と感じた。私は別に不登校になることはなかったし、勉強が出来る方だったので生き延びる方策はギリギリあったのだが、それでも「学生時代はキツかったなぁ」と今でも思っている。大人になった今の方が、全体的には息がしやすいと感じているのだ。私の場合、「時間割や通知表などの制約」による窮屈さだけではなかったと思うが、いずれにせよ、本作に登場するような「自由な学校」に通えていたら、当時懐いていた息苦しさを味わわずに済んだのではないかと感じてしまった。
さて、作中の話で最も感心したのが、栃木県の日光市立足尾中学校の事例である。この学校はなんと、コロナ禍にあった2020年と2021年に、修学旅行や運動会を含むすべての学校行事を中止せずに実施したというのだ。そんな学校があったなんてまったく知らなかったので、物凄く驚かされてしまった。この話、「興味深い取り組みをしている事例」として、マスコミが食いついてもおかしくないように思う。もちろん、学校側がマスコミからの取材を断っていた可能性もあるが、しかし映画には出ているわけで、その可能性も低いだろう。もし、この学校について取り上げなかったことが、マスコミ側の「なんらかの忖度」と関係しているとしたら、それはとても残念なことだなと感じる。
まだまだ記憶に新しいと思うが、コロナ禍においては、「休校」や「黙食」などが政府から指針として出されていた。多くの学校が、政府のその方針に従ったはずである。しかし足尾中学校の原口真一校長は、自ら科学論文を読み漁ったり、大学の教授に自らアポイントを取って話を聞いたりと、科学的に正しい知見を収集したという。そしてその上で、「保護者からの質問はすべて私が対応する」「何かマズいことが起こったら私がすべて責任を取る」と宣言し、「すべての学校行事を止めない」という決断に踏み切ったのだそうだ。本作で取り上げられる校長は色んな意味で「挑戦者」だと思うのだが、中でもこの原口氏は最もチャレンジングなことを行ったなと感じさせられた。
あわせて読みたい
【衝撃】自ら立ち上げた「大分トリニータ」を放漫経営で潰したとされる溝畑宏の「真の実像」に迫る本:…
まったく何もないところからサッカーのクラブチーム「大分トリニータ」を立ち上げ、「県リーグから出発してチャンピオンになる」というJリーグ史上初の快挙を成し遂げた天才・溝畑宏を描く『爆走社長の天国と地獄』から、「正しく評価することの難しさ」について考える
足尾中学校では結果として、恐らく教師を含めての話だと思うのだが、ずっと「感染者ゼロ」を実現し続けたそうだ。科学的な知見と、原口氏の勇敢さによる偉大な勝利と言っていいだろう。

さて、私はこの記事の中で何度か「保護者の理解こそが大事」という話をしているが、その点で最も恵まれていると言えるのが、先ほども少し紹介した伊那小学校だろう。公立校でありながら、60年以上も前から「体験学習」メインの教育を行ってきた学校である。決して「特別区」や「実験校」などではなく、全国どこにでもある普通の小学校と同じ立ち位置の学校だ。だから、「伊那小学校で出来ていることが、他の公立校で出来ない理由はどこにもない」と断言できるのである。
さて、そんな伊那小学校が「保護者からの理解」に恵まれている理由は明白だ。それは、「祖父母や両親の時代から、そのような教育スタイルが『当たり前』だったから」である。今まさに伊那小学校に子どもを通わせている親も、同じ教育で育ってきたのだ。当然、反対の声など出るはずもない。
あわせて読みたい
【現代】これが今の若者の特徴?衝撃のドキュメンタリー映画『14歳の栞』から中学生の今を知る
埼玉県春日部市に実在する中学校の2年6組の生徒35人。14歳の彼らに50日間密着した『14歳の栞』が凄かった。カメラが存在しないかのように自然に振る舞い、内心をさらけ出す彼らの姿から、「中学生の今」を知る
最近では、その名が全国的に知られるようになったこともあり、「伊那小学校に子どもを通わせたい」という動機で移住してくる人も増えてきているらしいが、基本的には地元の人が通う学校である。だから、移住者もその「カルチャーギャップ」みたいなものに驚かされるそうだ。映画に登場したある移住者は、
伊那小学校の教育が「普通」とみなされていることに、最初は驚いた。
『夢見る公立校長先生』(監督:オオタヴィン)
と語っていた。全国的にも、かなり珍しい地域だと言っていいかもしれない。
あわせて読みたい
【偉業】「卓球王国・中国」実現のため、周恩来が頭を下げて請うた天才・荻村伊智朗の信じがたい努力と…
「20世紀を代表するスポーツ選手」というアンケートで、その当時大活躍していた中田英寿よりも高順位だった荻村伊智朗を知っているだろうか?選手としてだけでなく、指導者としてもとんでもない功績を残した彼の生涯を描く『ピンポンさん』から、ノーベル平和賞級の活躍を知る
とにかく「子どもたちの『やりたい!』を起点に教育を考える」という方針が一貫している
本作では様々な学校が取り上げられ、そこでは様々な形の「総合学習」が行われているわけだが、そのすべてに共通していると言えるのは、「生徒が『やりたい』と言ったことをやる」というスタンスだろう。ある校長は、
生徒の「やりたい」が無いと、授業が始まらない。
『夢見る公立校長先生』(監督:オオタヴィン)
とさえ話していた。その学校でも、「和紙を作りたい」という声に応えるなど様々なことを行っているのだが、中でも面白いと感じたのが、生徒からの発案で企画された「学校に泊まる」という学習だ。普通にはなかなか認められないだろうこんな提案も、「どうすればそれが実現できるのか」を教師が考え、出来る限りの範囲内でその実現に向けて大枠を整えることで成り立たせてしまう。そして、その範囲内で生徒たちが自主的に行動していくのである。観ながらホント、「学校に泊まるとか楽しそうだよなぁ」と感じたし、私もそんなことしてみたかったと思わされてしまった。
あわせて読みたい
【評価】のん(能年玲奈)の映画『Ribbon』が描く、コロナ禍において「生きる糧」が芸術であることの葛藤
のん(能年玲奈)脚本・監督・主演の映画『Ribbon』。とても好きな作品だった。単に女優・のんが素晴らしいというだけではなく、コロナ禍によって炙り出された「生きていくのに必要なもの」の違いに焦点を当て、「魂を生き延びさせる行為」が制約される現実を切り取る感じが見事
しかし、このような「自主的な学習」がどうして成立するのか不思議に感じる人もいるだろう。私は子育ての経験はないし、教師だったこともないが、やはり「子どもは言うことを聞かない」という印象があるし、小中学生ぐらいだとなおさらではないかと思う。
ただ、映画を観て「そりゃそうだな」と納得できた。「生徒の『やりたい』から始めれば、生徒は自らルールを作るし、約束を守るようにもなる」と指摘されるからだ。確かにその通りだろう。子どもに限らないが、やはり「これをやれ」と言われたら反発したくもなるし、「どうしたらそうせずに済むのか」という方向に思考を働かせたくもなると思う。しかし、「自分から『やりたい』と言っていること」なら、そんな発想になるはずもない。だから、生徒の自主性に任せる授業が成立するというわけだ。

このような学校運営が成立するという事実を多くの教師や保護者が知れば、現場レベルでの変化は加速度的に起こるのではないかと思う。そういう意味でこの映画は、未来への希望を抱かせる作品だとも感じさせられた。
あわせて読みたい
【実話】仕事のやりがいは、「頑張るスタッフ」「人を大切にする経営者」「健全な商売」が生んでいる:…
メガネファストファッションブランド「オンデーズ」の社長・田中修治が経験した、波乱万丈な経営再生物語『破天荒フェニックス』をベースに、「仕事の目的」を見失わず、関わるすべての人に存在価値を感じさせる「働く現場」の作り方
さて、映画に登場する校長先生の中で、キャラクター的に最も面白いと感じたのは、横浜市立日枝小学校の住田昌治だ。彼が口にしていた、
校長の機嫌が悪いのは「犯罪」です。
『夢見る公立校長先生』(監督:オオタヴィン)
という言葉は絶妙だなと思う。
彼は他にも、
学校運営は「校長が機嫌良くしておく」だけでいい。

いつでも相談してもらえるように、暇そうにしておく。
あわせて読みたい
【挑戦】杉並区長・岸本聡子を誕生させた市民運動・選挙戦と、ミュニシパリズムの可能性を描く:『映画…
映画『映画 ◯月◯日、区長になる女。』は、杉並区初の女性区長・岸本聡子を誕生させた選挙戦の裏側を中心に、日本の民主主義を問う作品だ。劇場公開されるや、チケットを取るのが困難なほど観客が殺到した作品であり、観れば日本の政治の「変化」を感じられるのではないかと思う
校長になって私がしたことは、校長室の机を捨てたことだけ。あとは他の人がやった。
など、校長先生とは思えないかなり自由な発言をしている。こういう人がトップにいると、下の人もメチャクチャやりやすいだろうし、組織運営としてとても正しいことをしていると感じさせられた。
日本の教育の「可能性」について、強く希望を抱かせてくれる作品だと私は思う。
あわせて読みたい
【実話】実在の人物(?)をモデルに、あの世界的超巨大自動車企業の”内実”を暴く超絶面白い小説:『小…
誰もが知るあの世界的大企業をモデルに据えた『小説・巨大自動車企業トヨトミの野望』は、マンガみたいなキャラクターたちが繰り広げるマンガみたいな物語だが、実話をベースにしているという。実在の人物がモデルとされる武田剛平のあり得ない下剋上と、社長就任後の世界戦略にはとにかく驚かされる
あわせて読みたい
【全作品視聴済】私が観てきたドキュメンタリー映画を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が観てきたドキュメンタリー映画を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。
最後に
あわせて読みたい
【情熱】選挙のおもしろ候補者含め”全員取材”をマイルールにする畠山理仁の異常な日常を描く映画:『NO …
選挙に取り憑かれた男・畠山理仁を追うドキュメンタリー映画『NO 選挙, NO LIFE』は、「平均睡眠時間2時間」の生活を長年続ける”イカれた”ライターの「選挙愛」が滲み出る作品だ。「候補者全員を取材しなければ記事にはしない」という厳しすぎるマイルールと、彼が惹かれる「泡沫候補」たちが実に興味深い
コロナ禍において「きのくに子どもの村学園」は、保護者に向けて「学習の遅れを取り戻すという発想はしません」と宣言した上で、このような通達をしていた。
優先されるべきは、子どもたちがホッとできる時間です。取り戻すべきは、子どもの楽しい時間です。
『夢見る小学校』(監督:オオタヴィン)
あわせて読みたい
【生きる】しんどい人生を宿命付けられた子どもはどう生きるべき?格差社会・いじめ・恋愛を詰め込んだ…
厳しい受験戦争、壮絶な格差社会、残忍ないじめ……中国の社会問題をこれでもかと詰め込み、重苦しさもありながら「ボーイ・ミーツ・ガール」の爽やかさも融合されている映画『少年の君』。辛い境遇の中で、「すべてが最悪な選択肢」と向き合う少年少女の姿に心打たれる
また、別の場面ではこんな風にも言っている。
とにかく学校は「楽しいだけ」でいいんだという考えでやっています。世の中には「がんばれ、がんばれ」って言葉が溢れてしまうけど、ここでは「がんばらなくていいよ」ってメッセージを敢えて送るようにしています。
『夢見る小学校』(監督:オオタヴィン)
あわせて読みたい
【実話】英国王室衝撃!映画『ロスト・キング』が描く、一般人がリチャード3世の遺骨を発見した話(主演…
500年前に亡くなった王・リチャード3世の遺骨を、一介の会社員女性が発見した。映画『ロスト・キング』は、そんな実話を基にした凄まじい物語である。「リチャード3世の悪評を覆したい!」という動機だけで遺骨探しに邁進する「最強の推し活」は、最終的に英国王室までをも動かした!

こういうスタンスもとても素敵だと思う。
あわせて読みたい
【衝撃】卯月妙子『人間仮免中』、とんでもないコミックエッセイだわ。統合失調症との壮絶な闘いの日々
小学5年生から統合失調症を患い、社会の中でもがき苦しみながら生きる卯月妙子のコミックエッセイ『人間仮免中』はとんでもない衝撃作。周りにいる人とのぶっ飛んだ人間関係や、歩道橋から飛び降り自殺未遂を図り顔面がぐちゃぐちゃになって以降の壮絶な日々も赤裸々に描く
あるいは、映画『夢見る公立校長先生』には、元文科省の官僚だった前川喜平も登場するのだが、彼が文科省のスタンスについて、
現場の自由こそが教育にとって何よりも大事である。
『夢見る公立校長先生』(監督:オオタヴィン)
と表現していたのも印象的だった。映画を観る前は、「文科省が何か締め付けを行っているせいで日本の教育は窮屈になっているのだろう」と勝手に邪推していたのだが、彼の言葉を信じるならば、文科省としてはむしろ真逆の考えを持っているのだそうだ。
あわせて読みたい
【挑戦】自閉症のイメージを変えるおすすめ本。知的障害と”思い込む”専門家に挑む母子の闘い:『自閉症…
専門家の思い込みを覆し、自閉症のイメージを激変させた少年・イド。知的障害だと思われていた少年は、母親を通じコミュニケーションが取れるようになり、その知性を証明した。『自閉症の僕が「ありがとう」を言えるまで』が突きつける驚きの真実
だったらもっと自由にやろうよ。映画を観て私は、とにかく強くそんな風に感じさせられた。ルールの範囲内でもっとはっちゃけられることは明白だし、その方が絶対に学校は楽しくなるはずだ。そんな面白い教育者が出てくれることを私は期待している。
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!「文章の書き方が分からない」「文章力がないから鍛えたい」という方にオススメ…
「文章の書き方」についてのKindle本を出版しました。「文章が書けない」「どう書いたらいいか分からない」「文章力を向上させたい」という方の悩みを解消できるような本に仕上げたつもりです。数多くの文章を書き、さらに頼まれて文章を推敲してきた経験を踏まえ、「文章を書けるようになるにはどうしたらいいか」についての私なりの考えをまとめました。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【壮絶】映画『フロントライン』は「コロナパンデミックの発端」におけるDMATの奮闘をリアルに描く(監…
映画『フロントライン』は、ド級の役者が集ったド級のエンタメ作品でありながら、「フィクションっぽさ」が非常に薄い映画でもあり、「起こった出来事をリアルに描く」という制作陣の覚悟が感じられた。マスコミ報道を通じて知ったつもりになっている「事実」が覆される内容で、あの時の混乱を知るすべての人が観るべき映画だと思う
あわせて読みたい
【実話】最低の環境で異次元の結果を出した最高の教師を描く映画『型破りな教室』は超クールだ
映画『型破りな教室』は、メキシコでの実話を基にした信じがたい物語だ。治安最悪な町にある最底辺の小学校に赴任した教師が、他の教師の反対を押し切って独自の授業を行い、結果として、全国テストで1位を取る児童を出すまでになったのである。「考える力」を徹底的に養おうとした主人公の孤軍奮闘がとにかく素晴らしい
あわせて読みたい
【発見】映画『小学校~それは小さな社会~』(山崎エマ)が映し出すのは、我々には日常すぎる日常だ
映画『小学校~それは小さな社会~』は、ごく一般的な公立小学校に密着し、日本で生まれ育った人間には「当たり前」にしか思えない日常を切り取った作品なのだが、そんな映画が諸外国で大いに評価されているという。「TOKKATSU」という「日本式教育」が注目されているらしく、私たちの「当たり前」が違和感だらけに見えているのだそうだ
あわせて読みたい
【感動】映画『ボストン1947』は、アメリカ駐留時代の朝鮮がマラソンで奇跡を起こした実話を描く
映画『ボストン1947』は、アメリカ軍駐留時代の朝鮮を舞台に、様々な困難を乗り越えながらボストンマラソン出場を目指す者たちの奮闘を描き出す物語。日本統治下で日本人としてメダルを授与された”国民の英雄”ソン・ギジョンを中心に、「東洋の小国の奇跡」と評された驚くべき成果を実現させた者たちの努力と葛藤の実話である
あわせて読みたい
【SDGs】パリコレデザイナー中里唯馬がファッション界の大量生産・大量消費マインド脱却に挑む映画:『…
映画『燃えるドレスを紡いで』は、世界的ファッションデザイナーである中里唯馬が、「服の墓場」と言うべきナイロビの現状を踏まえ、「もう服を作るのは止めましょう」というメッセージをパリコレの場から発信するまでを映し出すドキュメンタリー映画である。個人レベルで社会を変革しようとする凄まじい行動力と才能に圧倒させられた
あわせて読みたい
【悲劇】映画『プリンセス・ダイアナ』『スペンサー』で知る、その凄まじい存在感と王室の窮屈さ
ドキュメンタリー映画『プリンセス・ダイアナ』と映画『スペンサー』は、衝撃的な死を遂げたダイアナ妃の生涯を対照的な形で描き出す作品だ。「過去映像のみ」で構成される非常に挑戦的な『プリンセス・ダイアナ』と、「王室との不和」を正面から描き出す『スペンサー』の2作によって、彼女が歩んだ壮絶な人生が浮き彫りにされる
あわせて読みたい
【情熱】選挙のおもしろ候補者含め”全員取材”をマイルールにする畠山理仁の異常な日常を描く映画:『NO …
選挙に取り憑かれた男・畠山理仁を追うドキュメンタリー映画『NO 選挙, NO LIFE』は、「平均睡眠時間2時間」の生活を長年続ける”イカれた”ライターの「選挙愛」が滲み出る作品だ。「候補者全員を取材しなければ記事にはしない」という厳しすぎるマイルールと、彼が惹かれる「泡沫候補」たちが実に興味深い
あわせて読みたい
【ル・マン】ゲーマーが本物のカーレース出場!映画『グランツーリスモ』が描く衝撃的すぎる軌跡(ヤン…
映画『グランツーリスモ』は、「ゲーマーをレーサーにする」という、実際に行われた無謀すぎるプロジェクトを基にした作品だ。登場人物は全員イカれていると感じたが、物語としてはシンプルかつ王道で、誰もが先の展開を予想出来るだろう。しかしそれでも、圧倒的に面白かった、ちょっと凄まじすぎる映画だった
あわせて読みたい
【挑戦】杉並区長・岸本聡子を誕生させた市民運動・選挙戦と、ミュニシパリズムの可能性を描く:『映画…
映画『映画 ◯月◯日、区長になる女。』は、杉並区初の女性区長・岸本聡子を誕生させた選挙戦の裏側を中心に、日本の民主主義を問う作品だ。劇場公開されるや、チケットを取るのが困難なほど観客が殺到した作品であり、観れば日本の政治の「変化」を感じられるのではないかと思う
あわせて読みたい
【実話】英国王室衝撃!映画『ロスト・キング』が描く、一般人がリチャード3世の遺骨を発見した話(主演…
500年前に亡くなった王・リチャード3世の遺骨を、一介の会社員女性が発見した。映画『ロスト・キング』は、そんな実話を基にした凄まじい物語である。「リチャード3世の悪評を覆したい!」という動機だけで遺骨探しに邁進する「最強の推し活」は、最終的に英国王室までをも動かした!
あわせて読みたい
【映画】『街は誰のもの?』という問いは奥深い。「公共」の意味を考えさせる問題提起に満ちた作品
映画『街は誰のもの?』は、タイトルの通り「街(公共)は誰のものなのか?」を問う作品だ。そしてそのテーマの1つが、無許可で街中に絵を描く「グラフィティ」であることもまた面白い。想像もしなかった問いや価値観に直面させられる、とても興味深い作品である
あわせて読みたい
【改革】改修期間中の国立西洋美術館の裏側と日本の美術展の現実を映すドキュメンタリー映画:『わたし…
「コロナ禍」という絶妙すぎるタイミングで改修工事を行った国立西洋美術館の、普段見ることが出来ない「裏側」が映し出される映画『わたしたちの国立西洋美術館』は、「日本の美術展」の問題点を炙り出しつつ、「『好き』を仕事にした者たち」の楽しそうな雰囲気がとても魅力的に映るドキュメンタリー
あわせて読みたい
【悲劇】大川小学校はなぜ津波被害に遭ったのか?映画『生きる』が抉る現実と国家賠償請求の虚しさ
東日本大震災において、児童74人、教職員10人死亡という甚大な津波被害を生んだ大川小学校。その被害者遺族が真相究明のために奮闘する姿を追うドキュメンタリー映画『生きる』では、学校の酷い対応、出来れば避けたかった訴訟、下された画期的判決などが描かれ、様々な問題が提起される
あわせて読みたい
【信念】凄いな久遠チョコレート!映画『チョコレートな人々』が映す、障害者雇用に挑む社長の奮闘
重度の人たちも含め、障害者を最低賃金保証で雇用するというかなり無謀な挑戦を続ける夏目浩次を追う映画『チョコレートな人々』には衝撃を受けた。キレイゴトではなく、「障害者を真っ当に雇用したい」と考えて「久遠チョコレート」を軌道に乗せたとんでもない改革者の軌跡を追うドキュメンタリー
あわせて読みたい
【高卒】就職できる気がしない。韓国のブラック企業の実態をペ・ドゥナ主演『あしたの少女』が抉る
韓国で実際に起こった「事件」を基に作られた映画『あしたの少女』は、公開後に世論が動き、法律の改正案が国会を通過するほどの影響力を及ぼした。学校から実習先をあてがわれた1人の女子高生の運命を軸に描かれる凄まじい現実を、ペ・ドゥナ演じる女刑事が調べ尽くす
あわせて読みたい
【実話】「更生」とは何かを考えさせられる、演劇『ゴドーを待ちながら』を組み込んだ映画『アプローズ…
売れない舞台役者が、刑務所内で囚人に戯曲『ゴドーを待ちながら』の演技指導を行う映画『アプローズ、アプローズ!』は、その衝撃的なラストが実に印象的だ。しかもこのラストの展開は、実話を基にしている。喝采(アプローズ)を浴びる囚人たちの姿から、「更生」についても考えさせられる作品
あわせて読みたい
【働く】給料が上がらない、上げる方法を知りたい人は木暮太一のこの本を。『資本論』が意外と役に立つ…
「仕事で成果を出しても給料が上がるわけではない」と聞いて、あなたはどう感じるだろうか?これは、マルクスの『資本論』における「使用価値」と「価値」の違いを踏まえた主張である。木暮太一『人生格差はこれで決まる 働き方の損益分岐点』から「目指すべき働き方」を学ぶ
あわせて読みたい
【感想】映画『朝が来る』が描く、「我が子を返して欲しい気持ち」を消せない特別養子縁組のリアル
「特別養子縁組」を軸に人々の葛藤を描く映画『朝が来る』は、決して「特別養子縁組」の話ではない。「『起こるだろうが、起こるはずがない』と思っていた状況」に直面せざるを得ない人々が、「すべての選択肢が不正解」という中でどんな決断を下すのかが問われる、非常に示唆に富む作品だ
あわせて読みたい
【思考】文章の書き方が分かんない、トレーニングしたいって人はまず、古賀史健の文章講義の本を読め:…
古賀史健『20歳の自分に受けさせたい文章講義』は、「具体的なテクニック」ではない記述も非常に興味深い1冊だ。「なぜ文章を書く必要があるのか」という根本的な部分から丁寧に掘り下げる本書は、「書くからこそ考えられる」という、一般的なイメージとは逆だろう発想が提示される
あわせて読みたい
【違和感】平田オリザ『わかりあえないことから』は「コミュニケーション苦手」問題を新たな視点で捉え…
「コミュニケーションが苦手」なのは、テクニックの問題ではない!?『わかりあえないことから』は、学校でのコミュニケーション教育に携わる演劇人・平田オリザが抱いた違和感を起点に、「コミュニケーション教育」が抱える問題と、私たち日本人が進むべき道を示す1冊
あわせて読みたい
【思考】森博嗣のおすすめエッセイ。「どう生きるかべきか」「生き方が分からない」と悩む人に勧めたい…
エッセイも多数出版している説家・森博嗣が、読者からの悩み相談を受けて執筆した『自分探しと楽しさについて』は、生きていく上で囚われてしまう漠然とした悩みを解消する力を持っている。どう生きるべきか悩んでしまう若者に特に読んでもらいたい1冊
あわせて読みたい
【扇動】人生うまくいかないと感じる時に読みたい瀧本哲史の本。「未来をどう生きる?」と問われる1冊:…
瀧本哲史は非常に優れたアジテーターであり、『2020年6月30日にまたここで会おう』もまさにそんな1冊。「少数のカリスマ」ではなく「多数の『小さなリーダー』」によって社会が変革されるべきだ、誰にだってやれることはある、と若者を焚きつける、熱量満載の作品
あわせて読みたい
【価値】どうせ世の中つまらない。「レンタルなんもしない人」の本でお金・仕事・人間関係でも考えよう…
「0円で何もしない」をコンセプトに始まった「レンタルなんもしない人」という活動は、それまで見えにくかった様々な価値観を炙り出した見事な社会実験だと思う。『<レンタルなんもしない人>というサービスをはじめます。』で本人が語る、お金・仕事・人間関係の新たな捉え方
あわせて読みたい
【組織】意思決定もクリエイティブも「問う力」が不可欠だ。MIT教授がCEOから学んだ秘訣とは?:『問い…
組織マネジメントにおいては「問うこと」が最も重要だと、『問いこそが答えだ!』は主張する。MIT教授が多くのCEOから直接話を聞いて学んだ、「『問う環境』を実現するための『心理的安全性の確保』の重要性」とその実践の手法について、実例満載で説明する1冊
あわせて読みたい
【貢献】社会問題を解決する2人の「社会起業家」の生き方。「豊かさ」「生きがい」に必要なものは?:『…
「ヤクの毛」を使ったファッションブランド「SHOKAY」を立ち上げ、チベットの遊牧民と中国・崇明島に住む女性の貧困問題を解決した2人の若き社会起業家の奮闘を描く『世界を変えるオシゴト』は、「仕事の意義」や「『お金』だけではない人生の豊かさ」について考えさせてくれる
あわせて読みたい
【超人】NHKによる「JAXAの宇宙飛行士選抜試験」のドキュメント。門外不出の「最強の就活」:『ドキュメ…
難攻不落のJAXAと粘り強い交渉を重ね、門外不出の「最強の就活」を捉えたドキュメンタリーを書籍化した『ドキュメント宇宙飛行士選抜試験』。2021年の13年ぶりの募集も話題になったが、「欠点があってはいけない」という視点で厳しく問われる試験・面接の実情を描き出す
あわせて読みたい
【抵抗】西加奈子のおすすめ小説『円卓』。「当たり前」と折り合いをつけられない生きづらさに超共感
小学3年生のこっこは、「孤独」と「人と違うこと」を愛するちょっと変わった女の子。三つ子の美人な姉を「平凡」と呼んで馬鹿にし、「眼帯」や「クラス会の途中、不整脈で倒れること」に憧れる。西加奈子『円卓』は、そんなこっこの振る舞いを通して「当たり前」について考えさせる
あわせて読みたい
【人生】日本人有名プロゲーマー・梅原大吾の名言満載の本。「努力そのものを楽しむ」ための生き方とは…
「eスポーツ」という呼び名が世の中に定着する遥か以前から活躍する日本人初のプロゲーマー・梅原大吾。17歳で世界一となり、今も一線を走り続けているが、そんな彼が『勝ち続ける意志力』で語る、「『努力している状態』こそを楽しむ」という考え方は、誰の人生にも参考になるはずだ
あわせて読みたい
【生きる】志尊淳・有村架純が聞き手の映画『人と仕事』から考える「生き延びるために必要なもの」の違い
撮影予定の映画が急遽中止になったことを受けて制作されたドキュメンタリー映画『人と仕事』は、コロナ禍でもリモートワークができない職種の人たちを取り上げ、その厳しい現状を映し出す。その過程で「生き延びるために必要なもの」の違いについて考えさせられた
あわせて読みたい
【抽象】「思考力がない」と嘆く人に。研究者で小説家の森博嗣が語る「客観的に考える」ために大事なこ…
世の中にはあまりに「具体的な情報」が溢れているために、「客観的、抽象的な思考」をする機会が少ない。そんな時代に、いかに思考力を育てていくべきか。森博嗣が『人間はいろいろな問題についてどう考えていけば良いのか』を通じて伝える「情報との接し方」「頭の使い方」
あわせて読みたい
【アート】「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」(森美術館)と「美術手帖 Chim↑Pom特集」の衝撃から「…
Chim↑Pomというアーティストについてさして詳しいことを知らずに観に行った、森美術館の「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」に、思考をドバドバと刺激されまくったので、Chim↑Pomが特集された「美術手帖」も慌てて買い、Chim↑Pomについてメッチャ考えてみた
あわせて読みたい
【本質】子どもの頃には読めない哲学書。「他人の哲学はつまらない」と語る著者が説く「問うこと」の大…
『<子ども>のための哲学』は決して、「子どもでも易しく理解できる哲学の入門書」ではない。むしろかなり難易度が高いと言っていい。著者の永井均が、子どもの頃から囚われ続けている2つの大きな疑問をベースに、「『哲学する』とはどういうことか?」を深堀りする作品
あわせて読みたい
【解釈】詩人が語る詩の読み方。意味や読み方や良さが分からなくて全然気にしなくていい:『今を生きる…
私は学生時代ずっと国語の授業が嫌いでしたが、それは「作品の解釈には正解がある」という決めつけが受け入れ難かったからです。しかし、詩人・渡邊十絲子の『今を生きるための現代詩』を読んで、詩に限らずどんな作品も、「解釈など不要」「理解できなければ分からないままでいい」と思えるようになりました
あわせて読みたい
【幻想】日本での子育ては無理ゲーだ。現実解としての「夜間保育園」の実状と親の想いを描く映画:『夜…
映画『夜間もやってる保育園』によると、夜間保育も行う無認可の「ベビーホテル」は全国に1749ヶ所あるのに対し、「認可夜間保育園」は全国にたった80ヶ所しかないそうだ。また「保育園に預けるなんて可哀想」という「家族幻想」も、子育てする親を苦しめている現実を描く
あわせて読みたい
【感想】池田晶子『14歳からの哲学』で思考・自由・孤独の大事さを知る。孤独を感じることって大事だ
「元々持ってた価値観とは違う考えに触れ、それを理解したいと思う場面」でしか「考える」という行為は発動しないと著者は言う。つまり我々は普段、まったく考えていないのだ。『14歳からの哲学』をベースに、「考えること」と自由・孤独・人生との関係を知る
あわせて読みたい
【飛躍】有名哲学者は”中二病”だった?飲茶氏が易しく語る「古い常識を乗り越えるための哲学の力」:『1…
『14歳からの哲学入門』というタイトルは、「14歳向けの本」という意味ではなく、「14歳は哲学することに向いている」という示唆である。飲茶氏は「偉大な哲学者は皆”中二病”だ」と説き、特に若い人に向けて、「新しい価値観を生み出すためには哲学が重要だ」と語る
あわせて読みたい
【感想】映画『若おかみは小学生!』は「子どもの感情」を「大人の世界」で素直に出す構成に号泣させられる
ネット記事を読まなければ絶対に観なかっただろう映画『若おかみは小学生!』は、基本的に子ども向け作品だと思うが、大人が観てもハマる。「大人の世界」でストレートに感情を表に出す主人公の小学生の振る舞いと成長に、否応なしに感動させられる
あわせて読みたい
【天才】読書猿のおすすめ本。「いかにアイデアを生むか」の発想法を人文書に昇華させた斬新な1冊:『ア…
「独学の達人」「博覧強記の読書家」などと評される読書猿氏が、古今東西さまざまな「発想法」を1冊にまとめた『アイデア大全』は、ただのHow To本ではない。「発想法」を学問として捉え、誕生した経緯やその背景なども深堀りする、「人文書」としての一面も持つ作品だ
あわせて読みたい
【協働】日本の未来は福井から。地方だからこその「問題意識の共有」が、社会変革を成し遂げる強み:『…
コンパクトシティの先進地域・富山市や、起業家精神が醸成される鯖江市など、富山・福井の「変革」から日本の未来を照射する『福井モデル 未来は地方から始まる』は、決して「地方改革」だけの内容ではない。「危機意識の共有」があらゆる問題解決に重要だと認識できる1冊
あわせて読みたい
【思考】「”考える”とはどういうことか」を”考える”のは難しい。だからこの1冊をガイドに”考えて”みよう…
私たちは普段、当たり前のように「考える」ことをしている。しかし、それがどんな行為で、どのように行っているのかを、きちんと捉えて説明することは難しい。「はじめて考えるときのように」は、横書き・イラスト付きの平易な文章で、「考えるという行為」の本質に迫り、上達のために必要な要素を伝える
あわせて読みたい
【見方】日本の子どもの貧困は深刻だ。努力ではどうにもならない「見えない貧困」の現実と対策:『増補…
具体的には知らなくても、「日本の子どもの貧困の現状は厳しい」というイメージを持っている人は多いだろう。だからこそこの記事では、朝日新聞の記事を再編集した『増補版 子どもと貧困』をベースに、「『貧困問題』とどう向き合うべきか」に焦点を当てた
あわせて読みたい
【生きろ】「どう生き延びるか」と覚悟を決める考え方。西原理恵子が語る「カネ」だけじゃない人生訓:…
西原理恵子『この世でいちばん大事な「カネ」の話』は、決して「お金」の話だけではありません。「自分が望む生き方」を実現するための「闘い方」を伝授してくれると同時に、「しなくていい失敗を回避する考え方」も提示してくれます。学校や家庭ではなかなか学べない人生訓
あわせて読みたい
【多様性】神童から引きこもりになり、なんとか脱出したお笑い芸人が望む、誰も責められない社会:『ヒ…
お笑い芸人・髭男爵の山田ルイ53世は、“神童”と呼ばれるほど優秀だったが、“うんこ”をきっかけに6年間引きこもった。『ヒキコモリ漂流記』で彼は、ひきこもりに至ったきっかけ、ひきこもり中の心情、そしてそこからいかに脱出したのかを赤裸々に綴り、「誰にも優しい世界」を望む
あわせて読みたい
【危機】教員のセクハラは何故無くならない?資質だけではない、学校の構造的な問題も指摘する:『スク…
『スクールセクハラ なぜ教師のわいせつ犯罪は繰り返されるのか』では、自分が生徒に対して「権力」を持っているとは想像していなかったという教師が登場する。そしてこの「無自覚」は、学校以外の場でも起こりうる。特に男性は、読んで自分の振る舞いを見直すべきだ
あわせて読みたい
【社会】学生が勉強しないのは、若者が働かないのは何故か?教育現場からの悲鳴と知見を内田樹が解説:…
教育現場では、「子どもたちが学びから逃走する」「学ばないことを誇らしく思う」という、それまでには考えられなかった振る舞いが目立っている。内田樹は『下流志向』の中で、その原因を「等価交換」だと指摘。「学ばないための努力をする」という発想の根幹にある理屈を解き明かす
あわせて読みたい
【感心】悩み相談とは、相手の問いに答える”だけ”じゃない。哲学者が相談者の「真意」に迫る:『哲学の…
「相談に乗る」とは、「自分の意見を言う行為」ではない。相談者が”本当に悩んでいること”を的確に捉えて、「回答を与えるべき問いは何か?」を見抜くことが本質だ。『哲学の先生と人生の話をしよう』から、「相談をすること/受けること」について考える
あわせて読みたい
【逸脱】「人生良いことない」と感じるのは、「どう生きたら幸せか」を考えていないからでは?:『独立…
「常識的な捉え方」から逸脱し、世の中をまったく異なる視点から見る坂口恭平は、「より生きやすい社会にしたい」という強い思いから走り続ける。「どう生きたいか」から人生を考え直すスタンスと、「やりたいことをやるべきじゃない理由」を『独立国家のつくりかた』から学ぶ
あわせて読みたい
【非努力】頑張らない働き方・生き方のための考え方。「◯◯しなきゃ」のほとんどは諦めても問題ない:『…
ブロガーであるちきりんが、ブログに書いた記事を取捨選択し加筆修正した『ゆるく考えよう』は、「頑張ってしまう理由」や「欲望の正体」などを深堀りしながら、「世の中の当たり前から意識的に外れること」を指南する。思考を深め、自力で本質に行き着くための参考にも
あわせて読みたい
【あらすじ】子どもは大人よりずっと大人だ。「子ども扱い」するから、「子どもの枠」から抜け出せない…
宮部みゆき『ソロモンの偽証』は、その分厚さ故になかなか手が伸びない作品だろうが、「長い」というだけの理由で手を出さないのはあまりにももったいない傑作だ。「中学生が自前で裁判を行う」という非現実的設定をリアルに描き出すものすごい作品
あわせて読みたい
【助けて】息苦しい世の中に生きていて、人知れず「傷」を抱えていることを誰か知ってほしいのです:『…
元気で明るくて楽しそうな人ほど「傷」を抱えている。そんな人をたくさん見てきた。様々な理由から「傷」を表に出せない人がいる世の中で、『包帯クラブ』が提示する「見えない傷に包帯を巻く」という具体的な行動は、気休め以上の効果をもたらすかもしれない
あわせて読みたい
【理解】東田直樹の本は「自閉症の見方」を一変させた。自身も自閉症児を育てるプロデューサーが映画化…
東田直樹の著作を英訳し世界に広めた人物(自閉症児を育てている)も登場する映画『僕が跳びはねる理由』には、「東田直樹が語る自閉症の世界」を知ることで接し方や考え方が変わったという家族が登場する。「自閉症は知恵遅れではない」と示した東田直樹の多大な功績を実感できる
あわせて読みたい
【逸脱】「仕事を辞めたい」という気持ちは抑えちゃダメ。アウェイな土俵で闘っても負けるだけだ:『ニ…
京都大学卒「日本一有名なニート」であるpha氏の『ニートの歩き方 お金がなくても楽しくクラスためのインターネット活用法』は、常識や当たり前に囚われず、「無理なものは無理」という自分の肌感覚に沿って生きていくことの重要性と、そのための考え方が満載の1冊
あわせて読みたい
【誤り】「信じたいものを信じる」のは正しい?映画『星の子』から「信じること」の難しさを考える
どんな病気も治す「奇跡の水」の存在を私は信じないが、しかし何故「信じない」と言えるのか?「奇跡の水を信じる人」を軽々に非難すべきではないと私は考えているが、それは何故か?映画『星の子』から、「何かを信じること」の難しさについて知る
あわせて読みたい
【葛藤】「多様性を受け入れること」は難しい。映画『アイヌモシリ』で知る、アイデンティティの実際
「アイヌの町」として知られるアイヌコタンの住人は、「アイヌ語を勉強している」という。観光客のイメージに合わせるためだ。映画『アイヌモシリ』から、「伝統」や「文化」の継承者として生きるべきか、自らのアイデンティティを意識せず生きるべきかの葛藤を知る
あわせて読みたい
【変人】学校教育が担うべき役割は?子供の才能を伸ばすために「異質な人」とどう出会うべきか?:『飛…
高校の美術教師からアーティストとして活動するようになった著者は、教育の現場に「余白(スキマ)」が減っていると指摘する。『飛び立つスキマの設計学』をベースに、子どもたちが置かれている現状と、教育が成すべき役割について確認する。
あわせて読みたい
【救い】耐えられない辛さの中でどう生きるか。短歌で弱者の味方を志すホームレス少女の生き様:『セー…
死にゆく母を眺め、施設で暴力を振るわれ、拾った新聞で文字を覚えたという壮絶な過去を持つ鳥居。『セーラー服の歌人 鳥居』は、そんな辛い境遇を背景に、辛さに震えているだろう誰かを救うために短歌を生み出し続ける生き方を描き出す。凄い人がいるものだ
あわせて読みたい
【挑戦】自閉症のイメージを変えるおすすめ本。知的障害と”思い込む”専門家に挑む母子の闘い:『自閉症…
専門家の思い込みを覆し、自閉症のイメージを激変させた少年・イド。知的障害だと思われていた少年は、母親を通じコミュニケーションが取れるようになり、その知性を証明した。『自閉症の僕が「ありがとう」を言えるまで』が突きつける驚きの真実
あわせて読みたい
【能力】激変する未来で「必要とされる人」になるためのスキルや考え方を落合陽一に学ぶ:『働き方5.0』
AIが台頭する未来で生き残るのは難しい……。落合陽一『働き方5.0~これからの世界をつくる仲間たちへ~』はそう思わされる一冊で、本書は正直、未来を前向きに諦めるために読んでもいい。未来を担う若者に何を教え、どう教育すべきかの参考にもなる一冊。
あわせて読みたい
【異端】子育てがうまくいかないと悩む方へ。9歳で大学入学の天才児に学ぶ「すべきでないこと」:『ぼく…
12歳で数学の未解決問題を解いた天才児は、3歳の時に「16歳で靴紐が結べるようになったらラッキー」と宣告されていた。専門家の意見に逆らって、重度の自閉症児の才能をどう開花させたのかを、『ぼくは数式で宇宙の美しさを伝えたい』から学ぶ
あわせて読みたい
【異端】子育ては「期待しない」「普通から外れさせる」が大事。”劇薬”のような父親の教育論:『オーマ…
どんな親でも、子どもを幸せにしてあげたい、と考えるでしょう。しかしそのために、過保護になりすぎてしまっている、ということもあるかもしれません。『オーマイ・ゴッドファーザー』をベースに、子どもを豊かに、力強く生きさせるための”劇薬”を学ぶ
あわせて読みたい
【発想力】「集中力が続かない」と悩むことはない。「集中しない思考」こそAI時代に必要だ:『集中力は…
『「集中力がない」と悩んでいる人は多いかもしれません。しかし本書では、「集中力は、思ってるほど素晴らしいものじゃない」と主張します。『集中力はいらない』をベースに、「分散思考」の重要性と、「発想」を得るための「情報の加工」を学ぶ
あわせて読みたい
【天職】頑張っても報われない方へ。「自分で選び取る」のとは違う、正しい未来の進み方:『そのうちな…
一般的に自己啓発本は、「今、そしてこれからどうしたらいいか」が具体的に語られるでしょう。しかし『そのうちなんとかなるだろう』では、決断・選択をするべきではないと主張されます。「選ばない」ことで相応しい未来を進む生き方について学ぶ
あわせて読みたい
【継続】「言語化できない」を乗り越えろ。「読者としての文章術」で、自分の思考をクリアにする:『読…
ブログやSNSなどが登場したことで、文章を書く機会は増えていると言える。しかし同時に、「他人に評価されるために書く」という意識も強くなっているだろう。『読みたいことを書けばいい』から、「楽しく書き”続ける”」ための心得を学ぶ
あわせて読みたい
【恐怖】SNSの危険性と子供の守り方を、ドキュメンタリー映画『SNS 少女たちの10日間』で学ぶ
実際にチェコの警察を動かした衝撃のドキュメンタリー映画『SNS 少女たちの10日間』は、少女の「寂しさ」に付け込むおっさんどもの醜悪さに満ちあふれている。「WEBの利用制限」だけでは子どもを守りきれない現実を、リアルなものとして実感すべき
あわせて読みたい
【現代】これが今の若者の特徴?衝撃のドキュメンタリー映画『14歳の栞』から中学生の今を知る
埼玉県春日部市に実在する中学校の2年6組の生徒35人。14歳の彼らに50日間密着した『14歳の栞』が凄かった。カメラが存在しないかのように自然に振る舞い、内心をさらけ出す彼らの姿から、「中学生の今」を知る
あわせて読みたい
【肯定】社会不適合者こそ非凡。学校・世の中に馴染めなかった異才たちの過去から”才能”の本質を知る:…
「みんなと同じ」に馴染めないと「社会不適合」と判断され、排除されてしまうことが多いでしょう。しかし『非属の才能』では、「どこにも属せない感覚」にこそ才能の源泉があると主張します。常識に違和感を覚えてしまう人を救う本から、同調圧力に屈しない生き方を学ぶ
あわせて読みたい
【考察】世の中は理不尽だ。平凡な奴らがのさばる中で、”特別な私の美しい世界”を守る生き方:『オーダ…
自分以外は凡人、と考える主人公の少女はとてもイタい。しかし、世間の価値観と折り合わないなら、自分の美しい世界を守るために闘うしかない。中二病の少女が奮闘する『オーダーメイド殺人クラブ』をベースに、理解されない世界をどう生きるかについて考察する
あわせて読みたい
【覚悟】人生しんどい。その場の”空気”から敢えて外れる3人の中学生の処世術から生き方を学ぶ:『私を知…
空気を読んで摩擦を減らす方が、集団の中では大体穏やかにいられます。この記事では、様々な理由からそんな選択をしない/できない、『私を知らないで』に登場する中学生の生き方から、厳しい現実といかにして向き合うかというスタンスを学びます
あわせて読みたい
【呪縛】生きづらさの正体とそこからどう抜けるかを、「支配される安心」「自由の不自由」から考える:…
自由に生きられず、どうしたらいいのか悩む人も多くいるでしょう。『自由をつくる 自在に生きる』では、「自由」のためには「支配に気づくこと」が何より大事であり、さらに「自由」とは「不自由なもの」だと説きます。どう生きるかを考える指針となる一冊。
あわせて読みたい
【異常】「助けて」と言えない。自己責任社会のしんどさと、我が子がホームレスである可能性:『助けて…
39歳で餓死した男性は、何故誰にも助けを求めなかったのか?異常な視聴率を叩き出した、NHK「クローズアップ現代」の特集を元に書かれた『助けてと言えない』をベースに、「自己責任社会」の厳しさと、若者が置かれている現実について書く。
あわせて読みたい
【呪縛】「良い子」に囚われ人生苦しい。どう見られるかを抜け出し、なりたい自分を生きるために:『わ…
「良い子でいなきゃいけない」と感じ、本来の自分を押し隠したまま生きているという方、いるんじゃないかと思います。私も昔はそうでした。「良い子」の呪縛から逃れることは難しいですが、「なりたい自分」をどう生きればいいかを、『わたしを見つけて』をベースに書いていきます
あわせて読みたい
【救い】自殺を否定しない「笑える自殺本」。「自殺したい」ってもっと気軽に言える社会がいい:『自殺…
生きることがしんどくて、自殺してしまいたくなる気持ちを、私はとても理解できます。しかし世の中的には、「死にたい」と口にすることはなかなか憚られるでしょう。「自殺を決して悪いと思わない」という著者が、「死」をもっと気楽に話せるようにと贈る、「笑える自殺本」
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
教育・学校【本・映画の感想】 | ルシルナ
大人になって様々な本を読んだことで、「子どもの頃にこういう考えを知れたらよかった」「学校でこういうことを教えてほしかった」とよく感じるようになりました。子どもの…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…












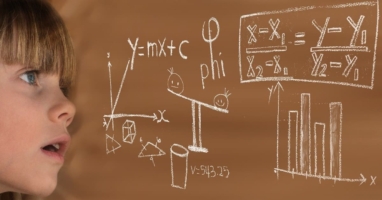




































































































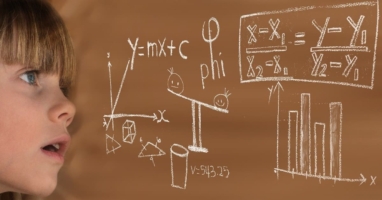
























コメント