目次
はじめに
この記事で取り上げる映画・本
出演:松岡茉優, 出演:松坂桃李, 出演:森崎ウィン, 出演:鈴鹿央士, 出演:臼田あさ美, 出演:鹿賀丈史, 監督:石川慶, Writer:石川慶
¥500 (2021/12/19 22:52時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
著:恩田陸
¥540 (2021/12/19 22:53時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
この映画・本をガイドにしながら記事を書いていくようだよ
この記事で伝えたいこと
「枠組み」の存在など気にせずやすやすと飛び越えていく者こそ「天才」と呼ばれるべき
「ランキング1位」は、「天才」の指標になどならないと私は思う
この記事の3つの要点
- 「天才」をどう評価すべきか
- 「天才」になれない者はどう生きるべきか
- 勝敗が決する「コンクール」を舞台にしながら、「仲間」「協調」なども描かれる
「天才」ではない私は未だに、「天才」が見ている世界を体感したい、という気持ちを捨てきれません
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
記事中の引用は、映画館で取ったメモを参考にしているので、正確なものではありません
「天才」というのは、どこまでいっても清々しいぐらいに「天才」なのだと、『蜜蜂と遠雷』の物語に触れて実感させられる
あわせて読みたい
【革新】天才マルタン・マルジェラの現在。顔出しNGでデザイナーの頂点に立った男の”素声”:映画『マル…
「マルタン・マルジェラ」というデザイナーもそのブランドのことも私は知らなかったが、そんなファッション音痴でも興味深く観ることができた映画『マルジェラが語る”マルタン・マルジェラ”』は、生涯顔出しせずにトップに上り詰めた天才の来歴と現在地が語られる
「天才」が見ている世界を体感してみたい、とずっと願ってきました。今でもそう思っています。私たちのような凡人とはまったく異なる世界で生きているだろう彼らの日常を、一瞬でもいいから知ってみたい。そのためなら、天才であることのデメリットをすべて引き受けてもいい、と思うことさえあります。

悔しいけど、俺にもわからないよ。あっち側の世界は
「蜜蜂と遠雷」(監督:石川慶、主演:松岡茉優、松坂桃李)
でも、「凄い人」と「天才」の差があまりにも大きなこと、そしてどれだけ「凄い人」であっても「天才」の世界は理解できないのだということを、この作品で理解しました。
あわせて読みたい
【おすすめ】「天才」を描くのは難しい。そんな無謀な挑戦を成し遂げた天才・野崎まどの『know』はヤバい
「物語で『天才』を描くこと」は非常に難しい。「理解できない」と「理解できる」を絶妙なバランスで成り立たせる必要があるからだ。そんな難題を高いレベルでクリアしている野崎まど『know』は、異次元の小説である。世界を一変させた天才を描き、「天才が見ている世界」を垣間見せてくれる
それでもやっぱり、「天才」の世界に足を踏み入れてみたいと考えてしまいます。
「既存の枠組み」を飛び越える者こそが「天才」
生きていると本当に、「凄い人」って世の中にはたくさんいるものだなぁ、と感じさせられます。どうやってそんなことやってるんだろう、なんでそんなこと知ってるんだろう、みたいな圧倒的な能力・知性を感じさせる人は、なんだかんだごろごろいるものです。そういう人の存在を知る度に、自分のちっぽけさを感じてしまうわけですが、まあそれは仕方ありません。
さて、そういう「凄い人」の存在を知る度、「うわぁ、天才!」というような表現をついしてしまいます。同じだという方は結構いるのではないでしょうか。でも一方で私の感触としては、そんなにごろごろ「天才」がいたら困ってしまいます。「天才」というのはもっと、ほとんど現れない稀少な存在だと私は考えているからです。
だとすれば、「凄い人」と「天才」を分けるものはなんでしょうか?
あわせて読みたい
【天才】科学者とは思えないほど面白い逸話ばかりのファインマンは、一体どんな業績を残したのか?:『…
数々の面白エピソードで知られるファインマンの「科学者としての業績」を初めて網羅したと言われる一般書『ファインマンさんの流儀』をベースに、その独特の研究手法がもたらした様々な分野への間接的な貢献と、「ファインマン・ダイアグラム」の衝撃を理解する
まあ、私からすれば、どっちも「自分には辿り着けない」って意味では遠い存在だけどね
才能に関して、私がよく考えることがあります。それは、「ランキングの1位は必ず存在する」という事実についてです。
何かの「ランキング」を決めるとすれば、そこには必ず「1位」が存在します。当たり前ですが、それが「ランキング」というものです。
あわせて読みたい
【あらすじ】映画化の小説『僕は、線を描く』。才能・センスではない「芸術の本質」に砥上裕將が迫る
「水墨画」という、多くの人にとって馴染みが無いだろう芸術を題材に据えた小説『線は、僕を描く』は、青春の葛藤と創作の苦悩を描き出す作品だ。「未経験のど素人である主人公が、巨匠の孫娘と勝負する」という、普通ならあり得ない展開をリアルに感じさせる設定が見事
それが何であれ、「ランキング1位」は凄いことだと扱われます。もちろん凄いことではあるんですが、しかし必ず誰かは「1位」に選ばれるという意味ではさほどの重要さはないとも言えるでしょう。例えばですが、メチャクチャ足の遅い人100人を走らせて「1位」を決めることもできます。しかしその「1位」に何か意味があるでしょうか?
このようにして私は、「ランキング1位だからと言って天才なわけではない」と考えます。そしてこの考えを押し広げることで、「既存の枠組みの範囲内にいる人は天才ではない」と言っていいのではないか、と考えています。
つまり、「既存の枠組みを飛び越える者こそ天才」というわけです。

あわせて読みたい
【改革】AIは将棋をどう変えた?羽生善治・渡辺明ら11人の現役棋士が語る将棋の未来:『不屈の棋士』(…
既に将棋AIの実力はプロ棋士を越えたとも言われる。しかし、「棋力が強いかどうか」だけでは将棋AIの良し悪しは判断できない。11人の現役棋士が登場する『不屈の棋士』をベースに、「AIは将棋界をどう変えたのか?」について語る
「枠組み」というのは、「理解のための補助」だと言えます。「テレビ」という枠組みがあるから「ドッキリ」が理解できるし、「一般相対性理論」という枠組みがあるから「重力」が理解できるわけです。「甲子園出場」や「東大合格」などの「枠組み」が存在することで、その内側では評価軸が定まり、だからこそそれに沿った努力ができることになります。「ランキング」が成立するのも「枠組みの内側にいる」からです。
しかし一方で、「枠組み」が存在することによって、その外側に出るのがとても危険なことだと感じられるでしょう。そこは、「理解の補助が存在しない領域」なわけですから。だから私たちはどうしても、「枠組み」の外側に出ないように意識しがちです。
しかし中にはその「枠組み」の境界線をあっさりと越えて、まったく別のステージに行き着く人もいます。
あわせて読みたい
【逸話】天才数学者ガロアが20歳で決闘で命を落とすまでの波乱万丈。時代を先駆けた男がもし生きていた…
現代数学に不可欠な「群論」をたった1人で生み出し、20歳という若さで決闘で亡くなったガロアは、その短い生涯をどう生きたのか?『ガロア 天才数学者の生涯』から、数学に関心を抱くようになったきっかけや信じられないほどの不運が彼の人生をどう変えてしまったのか、そして「もし生きていたらどうなっていたのか」を知る
越えようと思って越えるんじゃなくて、いつの間にか越えてる、みたいなのが天才って感じする
「あれ? 超えちゃダメなんでしたっけ?」みたいなね
最近では、大谷翔平の例を挙げるのが一番分かりやすいでしょう。大谷翔平は、野球界の「枠組み」を打ち破り、投手と打者という二刀流を実現させ、そのどちらでも驚異的な成績を残しました。投手あるいは打者のどちらか一方でとんでもない成績を出す人はそれなりにいるでしょうが、やはりそれは「凄い人」に留まってしまう印象があります。大谷翔平のように、既存の「枠組み」を当然のように突破していく者だけが「天才」と呼ばれるに相応しいのではないかと私は思うのです。
『蜜蜂と遠雷』にも、そんな「枠組み」をあっさり越えてしまう「天才」が登場します。
あわせて読みたい
【感想】湯浅政明監督アニメ映画『犬王』は、実在した能楽師を”異形”として描くスペクタクル平家物語
観るつもりなし、期待値ゼロ、事前情報ほぼ皆無の状態で観た映画『犬王』(湯浅政明監督)はあまりにも凄まじく、私はこんなとんでもない傑作を見逃すところだったのかと驚愕させられた。原作の古川日出男が紡ぐ狂気の世界観に、リアルな「ライブ感」が加わった、素晴らしすぎる「音楽映画」
野原にピアノが置いてあれば、世界中に僕一人しかいなくたって、僕はきっとピアノを弾くよ
「蜜蜂と遠雷」(監督:石川慶、主演:松岡茉優、松坂桃李)
彼は、「ピアノを弾く」という行為につきまとうありとあらゆるものをさらりと振り払って、「ただ弾きたいから弾くんだ」というスタンスを持ち続けます。子どもの頃にはきっと、誰もがそう思いながらピアノを弾いていたでしょうが、コンクールに出場するようなレベルともなればそうもいきません。しかしそういう「枠組み」を当たり前のように越えていくのです。
この作品では、そういう「枠組みを越える」という意味での「天才」を描き出し、その圧倒的な存在に直面する人々が様々な問いに向き合うことになります。
あわせて読みたい
【天才】諦めない人は何が違う?「努力を努力だと思わない」という才能こそが、未来への道を開く:映画…
どれだけ「天賦の才能」に恵まれていても「努力できる才能」が無ければどこにも辿り着けない。そして「努力できる才能」さえあれば、仮に絶望の淵に立たされることになっても、立ち上がる勇気に変えられる。映画『マイ・バッハ』で知る衝撃の実話
「天才」をどう評価するのか
その「問いに直面する人」の中には、コンクールの審査員も含まれます。つまり、「枠組みを飛び越えた『天才』をいかに評価すべきか」という、まさに「審査員が審査される状況」が生み出されているわけです。
よく言われることだが、審査員は審査するほうでありながら、審査されている。審査することによって、その人の音楽性や音楽に対する姿勢を露呈してしまうのだ
「蜜蜂と遠雷」(恩田陸/幻冬舎)
そして、審査員たちも薄々気付いている。
ホフマンの罠の狡猾さと恐ろしさに。
風間塵を本選に残せるか否かが、自分の音楽家としての立ち位置を示すことになるのだということを。
「蜜蜂と遠雷」(恩田陸/幻冬舎)
あわせて読みたい
【諦め】「人間が創作すること」に意味はあるか?AI社会で問われる、「創作の悩み」以前の問題:『電気…
AIが個人の好みに合わせて作曲してくれる世界に、「作曲家」の存在価値はあるだろうか?我々がもうすぐ経験するだろう近未来を描く『電気じかけのクジラは歌う』をベースに、「創作の世界に足を踏み入れるべきか」という問いに直面せざるを得ない現実を考える
風間塵というのがその「天才」の名前ですが、彼はホフマンという大御所の隠し玉としてコンクールに出場します。そしてホフマンは、「お前ら審査員に、風間塵を評価できるのか?」という問いを投げかけている、というわけなのです。
では、ピアノコンクールにおける「枠組み」とは一体なんでしょうか?

近年、演奏家は作曲者の思いをいかに正確に伝えるかということが至上命題になった感があり、いかに譜面を読みこみ作曲当時の時代や個人的背景をイメージするか、ということに重きが置かれるようになっている。演奏家の自由な解釈、自由な演奏はあまり歓迎されない風潮があるのだ
「蜜蜂と遠雷」(恩田陸/幻冬舎)
あわせて読みたい
【アート】映画『ダ・ヴィンチは誰に微笑む』が描く「美術界の闇」と「芸術作品の真正性」の奥深さ
美術界史上最高額510億円で落札された通称「救世主」は、発見される以前から「レオナルド・ダ・ヴィンチの失われた作品」として知られる有名な絵だった。映画『ダ・ヴィンチは誰に微笑む』は、「芸術作品の真正性の問題」に斬り込み、魑魅魍魎渦巻く美術界を魅力的に描き出す
それが「審査」である以上、何らかの「枠組み」を必要とするのは当然です。しかし一方で、ピアノコンクールに限る話ではありませんが、「『枠組み』から外れているからダメだ」というあまりにも短絡的な評価・批評が多いように、私個人としても感じています。
まあ、「枠組みの外側にあるからダメ」って言っておけば、自分は安全圏にいられるからね
そういう、批評する側がリスクを犯さない評価ってつまらんよね
本来的には、「枠組み」の内側にあるか否かは、指標の1つに過ぎないはずです。野球の場合は「ストライクゾーン」に入らないものはすべて「ボール」と判定されますが、普通は「ストライクゾーン」に入らなかったとしても、ただそれだけで「ダメなもの」という扱いをすべきではないでしょう。
あわせて読みたい
【奇跡】鈴木敏夫が2人の天才、高畑勲と宮崎駿を語る。ジブリの誕生から驚きの創作秘話まで:『天才の思…
徳間書店から成り行きでジブリ入りすることになったプロデューサー・鈴木敏夫が、宮崎駿・高畑勲という2人の天才と共に作り上げたジブリ作品とその背景を語り尽くす『天才の思考 高畑勲と宮崎駿』。日本のアニメ界のトップランナーたちの軌跡の奇跡を知る
もちろん、必要があって「枠組み」を設けているなら別です。例えば、「ミステリー小説」を公募する賞に「純文学作品」を送っても、正しく評価されないでしょう。それは良し悪しの問題ではなく、求められているものと違うからです。「私たちはこういうものを求めています」という「枠組み」から外れたものが、正しく評価されないのは当然と言えます。
しかし、そういう大前提をクリアしているのであれば、「枠組み」の存在は評価する際の指標の1つに過ぎないはずです。そこに固執するのは、批評する側の怠慢だと私は感じます。
私が特に嫌いなのは、「対象となる作品が『枠組み』の外側にくるように恣意的に『枠組み』を設定しているように感じられる批評」です。後出しジャンケンのように後から「枠組み」を提示し、「そこから外れているからこの作品はダメだ」と批判するような人が結構いるように感じています。はっきり言って私には、何がしたいのかよく分かりません。「自分は安全な場所にいながらその作品を徹底的に貶したい」というぐらいの理由しか思いつかないのです。
そこまでとは言わずとも、やはり「枠組み」に固執してしまう批評は多く存在するだろうし、だからこそ、ホフマンが風間塵という「天才」を送り込んで「審査とは何か?」を問いかけようとする気持ちも分かるような気がします。
あわせて読みたい
【創作】クリエイターになりたい人は必読。ジブリに見習い入社した川上量生が語るコンテンツの本質:『…
ドワンゴの会長職に就きながら、ジブリに「見習い」として入社した川上量生が、様々なクリエイターの仕事に触れ、色んな質問をぶつけることで、「コンテンツとは何か」を考える『コンテンツの秘密』から、「創作」という営みの本質や、「クリエイター」の理屈を学ぶ
よし、塵、おまえが連れ出してやれ。
少年はきょとんとした。
先生は、底の見えない淵のような、恐ろしい目で少年を見た。
ただし、とても難しいぞ。本当の意味で、音楽を外へ連れ出すのはとても難しい。私が言っていることは分かるな? 音楽を閉じこめているのは、ホールや教会じゃない。人々の意識だ。綺麗な景色の屋外に連れ出した程度では、「本当に」音を連れ出したことにはならない。解放したことにはならない。
「蜜蜂と遠雷」(恩田陸/幻冬舎)
「枠組み」の存在が、音楽に限らず、様々な作品を閉じ込めていると言えるかもしれません。
「天才」ではない人間はどう生きるべきか
ほとんどの人間が「天才」にはなれません。では、「天才」ではなかった者はどう生きていくべきなのでしょうか。
あわせて読みたい
【天才】写真家・森山大道に密着する映画。菅田将暉の声でカッコよく始まる「撮り続ける男」の生き様:…
映画『あゝ荒野』のスチール撮影の際に憧れの森山大道に初めて会ったという菅田将暉の声で始まる映画『過去はいつも新しく、未来はつねに懐かしい』は、ちゃちなデジカメ1つでひたすら撮り続ける異端児の姿と、50年前の処女作復活物語が見事に交錯する
私がよく考えるのは、「努力し続ければ、ステージには立ち続けられる」ということです。

「天才」のように世に衝撃を与えたり、新しい可能性を示したり、未知の世界に連れ出したりすることはできないかもしれません。ただ、自分が努力を止めずにいれば、「評価される場」に立ち続けることはできるでしょう。世の中には、「評価」というステージに辿り着くことができない人もたくさんいます。「評価される状況にいる」というのは、「天才」にはなれない我々の1つの目標になると言っていいでしょう。
また、こういう考え方もできるかもしれません。「天才」が生まれるための「枠組み」を保持する役割があるのだ、と。
あわせて読みたい
【感想】努力では才能に勝てないのか?どうしても辿り着きたい地点まで迷いながらも突き進むために:『…
どうしても辿り着きたい場所があっても、そのあまりの遠さに目が眩んでしまうこともあるでしょう。そんな人に向けて、「才能がない」という言葉に逃げずに前進する勇気と、「仕事をする上で大事なスタンス」について『羊と鋼の森』をベースに書いていきます
先ほど書いた通り、「天才」というのは「枠組み」を越えていく存在だと思っています。つまり、「天才」が生まれるためには「枠組み」が存在していなければならない、とも言えるでしょう。「こういうのが当たり前だ」という「枠組み」がきちんと存在するからこそ、それを超越する者が「天才」だと評価できるわけです。
であれば、その「枠組み」を保持し続けることもまた、「天才」の出現を間接的に助けていると言えるでしょう。「凄い人」を含めた様々な人たちが「枠組み」の内側で切磋琢磨することで、その「枠組み」が確固たるものになっていきます。そしてそんな確固たる「枠組み」が存在するからこそ、それを飛び越える者が目立つわけです。
「天才」の礎なんていう役割に甘んじたくないと感じもするでしょう。しかしどうやったって「天才」にはなれない以上、自分の存在に別の形でなんらかの意味を見出した方がいいと思います。自分が「枠組み」をの内側で奮闘しているからこそ「天才」が正しく評価されるのだと考えることは、個人の存在意義としてそう悪いものではないと思うのですが、いかがでしょうか?
もちろん、自分こそが注目される存在でありたい、と多くの人が望むだろうけどね
でも、そうなれないから自分の人生は不幸だ、と考えるようになったらしんどいよ
『蜜蜂と遠雷』の内容紹介
あわせて読みたい
【偉業】「卓球王国・中国」実現のため、周恩来が頭を下げて請うた天才・荻村伊智朗の信じがたい努力と…
「20世紀を代表するスポーツ選手」というアンケートで、その当時大活躍していた中田英寿よりも高順位だった荻村伊智朗を知っているだろうか?選手としてだけでなく、指導者としてもとんでもない功績を残した彼の生涯を描く『ピンポンさん』から、ノーベル平和賞級の活躍を知る
映画では、作品のメインであるコンクールでの描写が主となるが、小説ではそのコンクールのオーディションから描かれる。
3年ごとに開かれる「芳ヶ江国際ピアノコンクール」のオーディションが、日本を含む世界5都市で行われている。パリ会場で審査員を務める嵯峨三枝子、アラン・シモン、セルゲイ・スミノフの3人は、退屈な演奏が続く中で、その少年に出会う。
風間塵である。
風間は異例づくしの候補者だった。履歴書はほぼ真っ白、学歴もコンクールへの出場歴もなし。日本の小学校を卒業した後に渡仏した、という程度の情報しか分からない。オーディション開始ぎりぎりに会場へとたどり着いた風間の手は、なんと泥だらけだったという。後に彼の父親が養蜂家であると知る。

あわせて読みたい
【青春】二宮和也で映画化もされた『赤めだか』。天才・立川談志を弟子・談春が描く衝撃爆笑自伝エッセイ
「落語協会」を飛び出し、新たに「落語立川流」を創設した立川談志と、そんな立川談志に弟子入りした立川談春。「師匠」と「弟子」という関係で過ごした”ぶっ飛んだ日々”を描く立川談春のエッセイ『赤めだか』は、立川談志の異端さに振り回された立川談春の成長譚が面白い
しかし、それらの情報を遥かに上回る衝撃も持ち合わせていた。それは、風間がユウジ・フォン=ホフマンに5歳から師事しており、彼の推薦状を持って現れた、ということだ。
ホフマンは世界中の音楽家から愛された伝説的な人物で、今年亡くなった。弟子を取らないことでも有名だった彼の弟子であるというだけでも驚きだったのだが、ホフマンが死の間際に、
僕は爆弾をセットしておいたよ。僕がいなくなったら、ちゃんと爆発するはずさ。世にも美しい爆弾がね
「蜜蜂と遠雷」(恩田陸/幻冬舎)
と語っていたことが思い出され、風間塵こそがその「爆弾」なのかと直感したのだ。
果たしてその通りだった。風間の演奏は、常軌を逸していた。オーディションを通すかどうか侃々諤々の議論の末、風間塵を合格とする。
あわせて読みたい
【伝説】やり投げ選手・溝口和洋は「思考力」が凄まじかった!「幻の世界記録」など数々の逸話を残した…
世界レベルのやり投げ選手だった溝口和洋を知っているだろうか? 私は本書『一投に賭ける』で初めてその存在を知った。他の追随を許さないほどの圧倒的なトレーニングと、常識を疑い続けるずば抜けた思考力を武器に、体格で劣る日本人ながら「幻の世界記録」を叩き出した天才の伝説と実像
そんな風間塵も出場する、「芳ヶ江国際ピアノコンクール」の幕がいよいよ開く。ホフマンが亡くなった年に開かれるという意味でも、今回のコンクールは例年にも増して注目度が高く、それに呼応するように参加者のレベルも高くなった。前回の優勝者でも今年の最終審査には残れなかったのではないか、と言われるほどだ。
風間塵の他に、メインで描かれるのは3人。
栄伝亜夜は、幼い頃から「天才」と評され、中学生の頃には既に自身のコンサートを開くまでになっていたが、7年前に母親が亡くなったことでピアノが弾けなくなってしまう。予定されていたコンサートをドタキャンして以来、表舞台に出てくることはなかった。今回のコンクールを最後のチャンスと捉えており、優勝できなければピアノから離れる覚悟で挑んでいる。
あわせて読みたい
【実像】ベートーヴェンの「有名なエピソード」をほぼ一人で捏造・創作した天才プロデューサーの実像:…
ベートーヴェンと言えば、誰もが知っている「運命」を始め、天才音楽家として音楽史に名を刻む人物だが、彼について良く知られたエピソードのほとんどは実は捏造かもしれない。『ベートーヴェン捏造 名プロデューサーは嘘をつく』が描く、シンドラーという”天才”の実像
マサル・カルロス・レヴィ・アナトールは、長身に甘いマスクのお陰で舞台映えし、既にスターの予感を漂わせている、ジュリアード音楽院期待の星だ。実は子どもの頃に、亜夜の母親からピアノを教わっており、短期間に驚くべき飛躍を遂げた圧倒的な才能の持ち主だった。マサルは、亜夜との久々の再開を喜んでいる。
高島明石は、「楽器店で働くサラリーマン」という、コンクール出場者としては異色の経歴を持っている。仕事の合間を縫い、家族の協力も得ながら、睡眠時間を削ってコンクールのための調整を続けてきた彼には、「生活者の音楽」という持論がある。音楽だけを生業とする者だけのために音楽はあるのではない、という想いを伝えるべく、コンクール出場を決意したのだ。そんな彼の挑戦を、高校時代の同級生がカメラを回し、ドキュメンタリーとして記録している。
様々な形で音楽と向き合う者たちの人生が緩やかに折り重なりながら、コンクールという場を軸として様々な葛藤や苦悩が描かれていく。勝敗が明確に決する場を舞台にしながら、「仲間」「協調」と言った要素も描かれる熱い物語。
あわせて読みたい
【救い】耐えられない辛さの中でどう生きるか。短歌で弱者の味方を志すホームレス少女の生き様:『セー…
死にゆく母を眺め、施設で暴力を振るわれ、拾った新聞で文字を覚えたという壮絶な過去を持つ鳥居。『セーラー服の歌人 鳥居』は、そんな辛い境遇を背景に、辛さに震えているだろう誰かを救うために短歌を生み出し続ける生き方を描き出す。凄い人がいるものだ
『蜜蜂と遠雷』の感想
どうしてもこの作品を紹介する際には、「風間塵という天才」が中心になりがちですが、決してそれだけではなく、メインで描かれる他の3人にもそれぞれ物語があります。ピアノという、正直私にはあまり馴染みのない世界が描かれるのですが、誰もが抱いてしまうだろう悩みや葛藤が物語の中心にあるのです。
栄伝亜夜は「ピアノ」とどんな風に向き合うべきなのか分からないでいました。
しかし、意外にも、亜夜自身に挫折感はなかった。
彼女の中では、コンサートのドタキャンは筋が通っていたからである。
取り出すべき音楽がピアノの中に見つからないのに、なぜステージに立つ必要などあるだろうか。
「蜜蜂と遠雷」(恩田陸/幻冬舎)
あわせて読みたい
【天才】映画『笑いのカイブツ』のモデル「伝説のハガキ職人ツチヤタカユキ」の狂気に共感させられた
『「伝説のハガキ職人」として知られるツチヤタカユキの自伝的小説を基にした映画『笑いのカイブツ』は、凄まじい狂気に彩られた作品だった。「お笑い」にすべてを捧げ、「お笑い」以外はどうでもいいと考えているツチヤタカユキが、「コミュ力」や「人間関係」で躓かされる”理不尽”な世の中に、色々と考えさせられる

母親の死によって「取り出すべき音楽」が無くなってしまった、だからピアノを弾かない、というのは、彼女にとっては当たり前の選択だったわけです。そもそも彼女は、
彼女は、元々ピアノなど必要としていなかった。
子供の頃、トタン屋根の雨音に馬たちのギャロップを聴いていた時から、彼女はあらゆるものに音楽を聴き、それを楽しむことができたからである
「蜜蜂と遠雷」(恩田陸/幻冬舎)
というように、「音楽」と関わるのに「ピアノ」でなければならない理由はありませんでした。その上でいかにコンクールに挑むのか、また他の参加者と関わる中で気持ちがどう変化していくのかが描かれていきます。
あわせて読みたい
【価値】レコードなどの「フィジカルメディア」が復権する今、映画『アザー・ミュージック』は必見だ
2016年に閉店した伝説のレコード店に密着するドキュメンタリー映画『アザー・ミュージック』は、「フィジカルメディアの衰退」を象徴的に映し出す。ただ私は、「デジタル的なもの」に駆逐されていく世の中において、「『制約』にこそ価値がある」と考えているのだが、若者の意識も実は「制約」に向き始めているのではないかとも思っている
高島明石のスタンスは、音楽やピアノの世界とは関係ない場面でも身近な問いに落とし込むことができるような普遍的なものではないでしょうか。
俺はいつも不思議に思っていた――孤高の音楽家だけが正しいのか? 音楽のみに生きる者だけが尊敬に値するのか? と。
生活者の音楽は、音楽だけを生業とする者より劣るのだろうか、と。
「蜜蜂と遠雷」(恩田陸/幻冬舎)
音楽を生活の中で楽しめる、まっとうな耳を持っている人は、祖母のように、普通のところにいるのだ。演奏者もまた、普通のところにいてよいのではないだろうか
「蜜蜂と遠雷」(恩田陸/幻冬舎)
芸術であれなんであれ、自分が望む場所から楽しめばいいはずです。しかし、冒頭で触れた「枠組み」の話のように、「こうでなければダメだ」という批評が当たり前のように存在する世の中においては、その「好きなように楽しむ」という振る舞いが許されない雰囲気が生まれてしまいます。
あわせて読みたい
【実話】英国王室衝撃!映画『ロスト・キング』が描く、一般人がリチャード3世の遺骨を発見した話(主演…
500年前に亡くなった王・リチャード3世の遺骨を、一介の会社員女性が発見した。映画『ロスト・キング』は、そんな実話を基にした凄まじい物語である。「リチャード3世の悪評を覆したい!」という動機だけで遺骨探しに邁進する「最強の推し活」は、最終的に英国王室までをも動かした!
そういう世の中を打破したい、という彼のスタンスに共感できる人は多いのではないでしょうか。
にわかだろうが間違ってようが、好きなように好きなものと触れればいいはずなんだけどね
それを認めちゃうと、「自分の知識・経験に価値がなくなる」って怖くなっちゃう人がいるんだろうなぁ
一方で明石自身も、こんな風に考えています。
もし自分が抜きん出た才能を持っていたら迷わずプロの音楽家の道を選んだだろうし、それ以外の職に就くことなど考えもしなかっただろう。そして、そちら側にいたならば就職して所帯を持ち、「生活者の音楽」などと嘯いている者をきっと軽んじていたに違いないのだ
「蜜蜂と遠雷」(恩田陸/幻冬舎)
あわせて読みたい
【感想】どんな話かわからない?難しい?ジブリ映画『君たちはどう生きるか』の考察・解説は必要?(監…
宮崎駿最新作であるジブリ映画『君たちはどう生きるか』は、宮崎アニメらしいファンタジックな要素を全開に詰め込みつつ、「生と死」「創造」についても考えさせる作品だ。さらに、「自分の頭の中から生み出されたものこそ『正解』」という、創造物と向き合う際の姿勢についても問うているように思う
これもまた非常に素直な独白であり、そのスタンスに好感が持てます。
マサル・カルロス・レヴィ・アナトールについてはちょっと、具体的に言及するのは止めておきましょう。彼もまた、このコンクールに出場することで、「ただコンクールに出場する」以上のものを得ることになるのです。
映画における「鈴鹿央士」の存在と、「音楽の受け取り方」の難しさ
風間塵を演じた鈴鹿央士は、『ドラゴン桜』にも出演していました。そして、彼が映像作品に初めて出演したのがこの『蜜蜂と遠雷』なのです。
あわせて読みたい
【改革】改修期間中の国立西洋美術館の裏側と日本の美術展の現実を映すドキュメンタリー映画:『わたし…
「コロナ禍」という絶妙すぎるタイミングで改修工事を行った国立西洋美術館の、普段見ることが出来ない「裏側」が映し出される映画『わたしたちの国立西洋美術館』は、「日本の美術展」の問題点を炙り出しつつ、「『好き』を仕事にした者たち」の楽しそうな雰囲気がとても魅力的に映るドキュメンタリー
私は、「風間塵」と「鈴鹿央士」の存在がリンクするという点を、この映画の面白さの1つに挙げられると感じました。

風間塵は、それまでコンクールに出場したことも、人前でピアノの演奏を披露したこともなく、まったく謎めいた存在としてオーディション会場に現れます。そんな人物が、音楽界の巨匠であるホフマンの推薦状を持っていたことが衝撃だったわけです。
鈴鹿央士も、それまで映像作品に出演したことも、演技の経験もなく、誰だか分からない存在として映画の主演を務めることになります。さらになんと彼は、女優の広瀬アリスに見いだされて芸能界入りしているのです。
あわせて読みたい
【勝負】実話を基にコンピューター将棋を描く映画『AWAKE』が人間同士の対局の面白さを再認識させる
実際に行われた将棋の対局をベースにして描かれる映画『AWAKE』は、プロ棋士と将棋ソフトの闘いを「人間ドラマ」として描き出す物語だ。年に4人しかプロ棋士になれない厳しい世界においては、「夢破れた者たち」もまた魅力的な物語を有している。光と影を対比的に描き出す、見事な作品
テレビで見た記憶では、広瀬アリスが出演する映画だかドラマの撮影である学校を訪れ、そこの生徒がエキストラとして参加することになったのだけれど、その中に鈴鹿央士がおり、広瀬アリスがスタッフに「凄い子がいる」という話をして芸能界入りすることになった、とのことでした。
まさに「風間塵」役を演じるのにぴったりと言える存在だと感じました。そういう、役柄と役者のリンクが非常に印象的な作品でもあります。
さて、映画に関してもう1点書いておきたいことは、「音楽の受け取り方の難しさ」です。これは、映画『羊と鋼の森』でも感じたことで、この点に関しては私のような人間には小説の方がいいと感じました。
小説中の音楽の描写は、当然すべて言葉で説明されます。「凄い音楽だ」と書いてあればそうだと理解できますし、「誰々の演奏とはこれこれの点で違う」と書いてあればその違いを認識できるというわけです。
あわせて読みたい
【魅力】モンゴル映画『セールス・ガールの考現学』は、人生どうでもいい無気力女子の激変が面白い!
なかなか馴染みのないモンゴル映画ですが、『セールス・ガールの考現学』はメチャクチャ面白かったです!設定もキャラクターも物語の展開もとても変わっていて、日常を描き出す物語にも拘らず、「先の展開がまったく読めない」とも思わされました。主人公の「成長に至る過程」が見応えのある映画です
しかし映画では、音楽そのものを流せるので、評価や違いに関して観客自らが理解して受け取る部分が増えます。そして、音楽の素養がさほどない私には、それはとてもハードルが高いものに感じられてしまうのです。
原作では「風間塵の演奏は、それまでにはない斬新なものだ」と書いてくれますが、映画で聞く彼の演奏が、他の人のものと比べて凄まじいのかどうか、私にはなんとも言えないなぁ、と感じてしまいました。他の人も、みんな凄いからです。
音楽の素養がある人なら当然、映像の方がいいと思うけどね
私のような人間には、全部言葉で説明してくれる小説の方がありがたいね
音楽がテーマとなる映画では、いつもこの点が難しいと思っています。
あわせて読みたい
【衝撃】自ら立ち上げた「大分トリニータ」を放漫経営で潰したとされる溝畑宏の「真の実像」に迫る本:…
まったく何もないところからサッカーのクラブチーム「大分トリニータ」を立ち上げ、「県リーグから出発してチャンピオンになる」というJリーグ史上初の快挙を成し遂げた天才・溝畑宏を描く『爆走社長の天国と地獄』から、「正しく評価することの難しさ」について考える
著:恩田陸
¥687 (2022/01/29 20:41時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
出演:松岡茉優, 出演:松坂桃李, 出演:森崎ウィン, 出演:鈴鹿央士, 出演:臼田あさ美, 出演:鹿賀丈史, 監督:石川慶, Writer:石川慶
¥500 (2022/01/29 20:41時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品読了済】私が読んできた小説を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が読んできた小説を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本選びの参考にして下さい。
最後に
「才能とは何か」について考えさせつつ、様々な立場で表現と向き合う者たちを圧倒的に描き出す素晴らしい作品だと感じました。音など鳴らないはずの小説からも、音楽が漂ってくるような作品で、恩田陸という作家に圧倒されるでしょう。
あわせて読みたい
【食&芸術】死んでも車を運転したくない人間の香川うどん巡り& 豊島アート巡りの旅ルート(山越うどん…
仕事終わりの木曜日夜から日曜日に掛けて、「香川のうどん巡り」と「豊島のアート巡り」をしてきました。うどんだけでも7580円分食べたので、かなりの軒数を回ったことになります。しかも「死んでも車を運転したくない」ため、可能な限り公共交通機関のみで移動しました。私と同じように「車を運転したくない人」には、かなり参考になる記事と言えるのではないかと思います
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【あらすじ】驚きの設定で「死と生」、そして「未練」を描く映画『片思い世界』は実に素敵だった(監督…
広瀬すず・杉咲花・清原果耶という超豪華俳優が主演を務める映画『片思い世界』は、是非、何も知らないまま観て下さい。この記事ではネタバレをせずに作品について語っていますが、それすらも読まずにまっさらな状態で鑑賞することをオススメします。「そうであってほしい」と感じてしまうような世界が“リアル”に描かれていました
あわせて読みたい
【あらすじ】「夢を追い求めた先」を辛辣に描く映画『ネムルバカ』は「ダルっとした会話」が超良い(監…
映画『ネムルバカ』は、まず何よりも「ダルっとした会話・日常」が素晴らしい作品です。そしてその上で、「夢を追い求めること」についてのかなり現代的な感覚を描き出していて、非常に印象的でした。「コスパが悪い」という言い方で「努力」を否定したくなる気持ちも全然理解できるし、若い人たちは特に大変だろうなと思います
あわせて読みたい
【死】映画『ミッキー17』は、「何度でも生まれ変われる」ってありがち設定を魅力的な物語に変えた(監…
映画『ミッキー17』は、「ありきたりな設定」がベースにあるのに、エンタメとしても考えさせる物語としても非常に興味深く面白い作品だった。「1人の人間が複数の肉体を持つこと」を禁じた法律の存在により絶妙な面白さとなっていると言えるだろう。さらにイカれた夫婦の言動もぶっ飛んでいて、そういう意味でも興味深い作品だ
あわせて読みたい
【切実】映画『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』は河合優実目当てだったが伊東蒼が超最高!(…
映画『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』は、伊東蒼演じるさっちゃんがひたすらに独白し続けるシーンがとにかく圧巻で、恋しさとせつなさと心強さが無限に伝わる最高すぎるシーンだった!「想いを伝えたい気持ち」と「伝えることの暴力性」の間で葛藤しながら、それでも喋らずにはいられない想いの強さが素敵すぎる
あわせて読みたい
【虚構】映画『シアトリカル』が追う唐十郎と劇団唐組の狂気。芝居に生きる者たちの”リアル”とは?
映画『シアトリカル』は、異端児・唐十郎と、彼が主宰する「劇団唐組」に密着するドキュメンタリー映画である。「普段から唐十郎を演じている」らしい唐十郎は、「ややこしさ」と「分かりやすさ」をないまぜにした実に奇妙な存在だった。「演劇」や「演じること」に己を捧げた「狂気を孕む者たち」の生き様が切り取られた作品だ
あわせて読みたい
【あらすじ】のん(能年玲奈)が実に素敵な映画『私にふさわしいホテル』が描く文壇の変な世界(監督:…
「こんな奴いないだろ」というような人物を絶妙な雰囲気で演じるのん(能年玲奈)の存在感がとにかく素敵な映画『私にふさわしいホテル』では、小説家・編集者がワチャワチャする「文壇」の世界が描かれる。無名の新人と大御所がハチャメチャなバトルを繰り広げるストーリーに、様々な「皮肉」が散りばめられた、なかなか痛快な物語
あわせて読みたい
【アート】映画『ヒプノシス』は、レコードジャケットの天才創作集団の繁栄と衰退を掘り起こす
映画『ヒプノシス』は、レコードのジャケットデザインで一世を風靡した天才集団「ヒプノシス」の栄枯盛衰を描き出すドキュメンタリー映画である。ストームとポーの2人が中心となって作り上げた凄まじいクリエイティブはそのまま、レコードジャケットの歴史と言っていいほどだ。ぶっ飛んだ才能とその生き方を知れる映画である
あわせて読みたい
【全力】圧巻の演奏シーンに驚愕させられた映画『BLUE GIANT』。ライブ中の宮本はとにかく凄い(主演:…
映画『BLUE GIANT』は、「演奏シーン」がとにかく圧倒的すぎる作品でした。ストーリーは、これ以上シンプルには出来ないだろうというぐらいシンプルなのですが、「王道的物語」だからこその感動もあります。また、全体の1/4がライブシーンらしく、その視覚的な演出も含めて、まさに「音楽を体感する映画」だと言えるでしょう
あわせて読みたい
金沢&富山のアート旅!「21世紀美術館」だけじゃない激アツなおすすめ美術館巡りをご提案
金沢・富山を巡るアート旅に出かけてきました!メインの目的は「21世紀美術館」でしたが、それ以上に「ASTER Curator Museum」「LIP BAR」「KAMU kanazawa」などがとにかく素晴らしかったです。アートや美術のことはド素人ですが、超個人的主観で「金沢・富山で触れられるアートの良さ」について書いた旅行記となります
あわせて読みたい
【煌めき】映画『HAPPYEND』が描く、”監視への嫌悪”と”地震への恐怖”の中で躍動する若者の刹那(監督:…
映画『HAPPYEND』は、「監視システム」と「地震」という「外的な制約条件」を設定し、その窮屈な世界の中で屈せずに躍動しようとする若者たちをリアルに描き出す物語である。特に、幼稚園からの仲であるコウとユウタの関係性が絶妙で、演技未経験だという2人の存在感と映像の雰囲気が相まって、実に素敵に感じられた
あわせて読みたい
【感動】映画『ボストン1947』は、アメリカ駐留時代の朝鮮がマラソンで奇跡を起こした実話を描く
映画『ボストン1947』は、アメリカ軍駐留時代の朝鮮を舞台に、様々な困難を乗り越えながらボストンマラソン出場を目指す者たちの奮闘を描き出す物語。日本統治下で日本人としてメダルを授与された”国民の英雄”ソン・ギジョンを中心に、「東洋の小国の奇跡」と評された驚くべき成果を実現させた者たちの努力と葛藤の実話である
あわせて読みたい
【感想】高倍率のやばい藝大入試に挑む映画『ブルーピリオド』は「生きてる実感の無さ」をぶち壊す(監…
映画『ブルーピリオド』は、大学入試で最高倍率とも言われる200倍の試験に挑む高校生たちの物語。東京藝術大学絵画科という果てしない最難関に、高校2年生から突然挑戦すると決めた矢口八虎を中心に、「『好き』に囚われた者たち」の果てしない情熱と葛藤を描き出す。絵を描くシーンを吹き替えなしで行った役者の演技にも注目だ
あわせて読みたい
【異例】東映京都撮影所が全面協力!自主制作の時代劇映画『侍タイムスリッパー』は第2の『カメ止め』だ…
映画『侍タイムスリッパー』は、「自主制作映画なのに時代劇」「撮影スタッフ10人なのに東映京都撮影所全面協力」「助監督役が実際の助監督も務めている」など、中身以外でも話題に事欠かない作品ですが、何もよりも物語が実に面白い!「幕末の侍が現代にタイムスリップ」というよくある設定からこれほど面白い物語が生まれるとは
あわせて読みたい
【評価】高山一実の小説かつアニメ映画である『トラペジウム』は、アイドル作とは思えない傑作(声優:…
原作小説、そしてアニメ映画共に非常に面白かった『トラペジウム』は、高山一実が乃木坂46に在籍中、つまり「現役アイドル」として出版した作品であり、そのクオリティに驚かされました。「現役アイドル」が「アイドル」をテーマにするというド直球さを武器にしつつ、「アイドルらしからぬ感覚」をぶち込んでくる非常に面白い作品である
あわせて読みたい
【正義】ナン・ゴールディンの”覚悟”を映し出す映画『美と殺戮のすべて』が描く衝撃の薬害事件
映画『美と殺戮のすべて』は、写真家ナン・ゴールディンの凄まじい闘いが映し出されるドキュメンタリー映画である。ターゲットとなるのは、美術界にその名を轟かすサックラー家。なんと、彼らが創業した製薬会社で製造された処方薬によって、アメリカでは既に50万人が死亡しているのだ。そんな異次元の薬害事件が扱われる驚くべき作品
あわせて読みたい
【幻惑】映画『フォロウィング』の衝撃。初監督作から天才だよ、クリストファー・ノーラン
クリストファー・ノーランのデビュー作であり、多数の賞を受賞し世界に衝撃を与えた映画『フォロウィング』には、私も驚かされてしまった。冒頭からしばらくの間「何が描かれているのかさっぱり理解できない」という状態だったのに、ある瞬間一気に視界が晴れたように状況が理解できたのだ。脚本の力がとにかく圧倒的だった
あわせて読みたい
【価値】レコードなどの「フィジカルメディア」が復権する今、映画『アザー・ミュージック』は必見だ
2016年に閉店した伝説のレコード店に密着するドキュメンタリー映画『アザー・ミュージック』は、「フィジカルメディアの衰退」を象徴的に映し出す。ただ私は、「デジタル的なもの」に駆逐されていく世の中において、「『制約』にこそ価値がある」と考えているのだが、若者の意識も実は「制約」に向き始めているのではないかとも思っている
あわせて読みたい
【魅惑】マツコも絶賛の“日本人初のパリコレトップモデル”山口小夜子のメイクの凄さや素顔を描く映画:…
日本人初のパリコレトップモデルである山口小夜子と親交があった監督が紡ぐ映画『氷の花火 山口小夜子』は、未だ謎に包まれているその人生の一端を垣間見せてくれる作品だ。彼女を知る様々な人の記憶と、彼女を敬愛する多くの人の想いがより合って、一時代を築いた凄まじい女性の姿が浮かび上がってくる
あわせて読みたい
【食&芸術】死んでも車を運転したくない人間の香川うどん巡り& 豊島アート巡りの旅ルート(山越うどん…
仕事終わりの木曜日夜から日曜日に掛けて、「香川のうどん巡り」と「豊島のアート巡り」をしてきました。うどんだけでも7580円分食べたので、かなりの軒数を回ったことになります。しかも「死んでも車を運転したくない」ため、可能な限り公共交通機関のみで移動しました。私と同じように「車を運転したくない人」には、かなり参考になる記事と言えるのではないかと思います
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『レザボア・ドッグス』(タランティーノ監督)はとにかく驚異的に脚本が面白い!
クエンティン・タランティーノ初の長編監督作『レザボア・ドッグス』は、のけぞるほど面白い映画だった。低予算という制約を逆手に取った「会話劇」の構成・展開があまりにも絶妙で、舞台がほぼ固定されているにも拘らずストーリーが面白すぎる。天才はやはり、デビュー作から天才だったのだなと実感させられた
あわせて読みたい
【天才】映画『笑いのカイブツ』のモデル「伝説のハガキ職人ツチヤタカユキ」の狂気に共感させられた
『「伝説のハガキ職人」として知られるツチヤタカユキの自伝的小説を基にした映画『笑いのカイブツ』は、凄まじい狂気に彩られた作品だった。「お笑い」にすべてを捧げ、「お笑い」以外はどうでもいいと考えているツチヤタカユキが、「コミュ力」や「人間関係」で躓かされる”理不尽”な世の中に、色々と考えさせられる
あわせて読みたい
【実話】英国王室衝撃!映画『ロスト・キング』が描く、一般人がリチャード3世の遺骨を発見した話(主演…
500年前に亡くなった王・リチャード3世の遺骨を、一介の会社員女性が発見した。映画『ロスト・キング』は、そんな実話を基にした凄まじい物語である。「リチャード3世の悪評を覆したい!」という動機だけで遺骨探しに邁進する「最強の推し活」は、最終的に英国王室までをも動かした!
あわせて読みたい
【感想】映画『キリエのうた』(岩井俊二)はアイナ・ジ・エンドに圧倒されっ放しの3時間だった(出演:…
映画『キリエのうた』(岩井俊二監督)では、とにかくアイナ・ジ・エンドに圧倒されてしまった。歌声はもちろんのことながら、ただそこにいるだけで場を支配するような存在感も凄まじい。全編に渡り「『仕方ないこと』はどうしようもなく起こるんだ」というメッセージに溢れた、とても力強い作品だ
あわせて読みたい
【映画】『キャスティング・ディレクター』の歴史を作り、ハリウッド映画俳優の運命を変えた女性の奮闘
映画『キャスティング・ディレクター』は、ハリウッドで伝説とされるマリオン・ドハティを描き出すドキュメンタリー。「神業」「芸術」とも評される配役を行ってきたにも拘わらず、長く評価されずにいた彼女の不遇の歴史や、再び「キャスティングの暗黒期」に入ってしまった現在のハリウッドなどを切り取っていく
あわせて読みたい
【改革】改修期間中の国立西洋美術館の裏側と日本の美術展の現実を映すドキュメンタリー映画:『わたし…
「コロナ禍」という絶妙すぎるタイミングで改修工事を行った国立西洋美術館の、普段見ることが出来ない「裏側」が映し出される映画『わたしたちの国立西洋美術館』は、「日本の美術展」の問題点を炙り出しつつ、「『好き』を仕事にした者たち」の楽しそうな雰囲気がとても魅力的に映るドキュメンタリー
あわせて読みたい
【天才】映画音楽の発明家『モリコーネ』の生涯。「映画が恋した音楽家」はいかに名曲を生んだか
「映画音楽のフォーマットを生み出した」とも評される天才作曲家エンリオ・モリコーネを扱った映画『モリコーネ 映画が恋した音楽家』では、生涯で500曲以上も生み出し、「映画音楽」というジャンルを比べ物にならないほどの高みにまで押し上げた人物の知られざる生涯が描かれる
あわせて読みたい
【伝説】映画『ミスター・ムーンライト』が描くビートルズ武道館公演までの軌跡と日本音楽への影響
ザ・ビートルズの武道館公演が行われるまでの軌跡を描き出したドキュメンタリー映画『ミスター・ムーンライト』は、その登場の衝撃について語る多数の著名人が登場する豪華な作品だ。ザ・ビートルズがまったく知られていなかった頃から、伝説の武道館公演に至るまでの驚くべきエピソードが詰まった1作
あわせて読みたい
【天才】映画『Winny』(松本優作監督)で知った、金子勇の凄さと著作権法侵害事件の真相(ビットコイン…
稀代の天才プログラマー・金子勇が著作権法違反で逮捕・起訴された実話を描き出す映画『Winny』は、「警察の凄まじい横暴」「不用意な天才と、テック系知識に明るい弁護士のタッグ」「Winnyが明らかにしたとんでもない真実」など、見どころは多い。「金子勇=サトシ・ナカモト」説についても触れる
あわせて読みたい
【魅力】モンゴル映画『セールス・ガールの考現学』は、人生どうでもいい無気力女子の激変が面白い!
なかなか馴染みのないモンゴル映画ですが、『セールス・ガールの考現学』はメチャクチャ面白かったです!設定もキャラクターも物語の展開もとても変わっていて、日常を描き出す物語にも拘らず、「先の展開がまったく読めない」とも思わされました。主人公の「成長に至る過程」が見応えのある映画です
あわせて読みたい
【驚嘆】映画『TAR/ター』のリディア・ターと、彼女を演じたケイト・ブランシェットの凄まじさ
天才女性指揮者リディア・ターを強烈に描き出す映画『TAR/ター』は、とんでもない作品だ。「縦軸」としてのターの存在感があまりにも強すぎるため「横軸」を上手く捉えきれず、結果「よく分からなかった」という感想で終わったが、それでも「観て良かった」と感じるほど、揺さぶられる作品だった
あわせて読みたい
【感想】どんな話かわからない?難しい?ジブリ映画『君たちはどう生きるか』の考察・解説は必要?(監…
宮崎駿最新作であるジブリ映画『君たちはどう生きるか』は、宮崎アニメらしいファンタジックな要素を全開に詰め込みつつ、「生と死」「創造」についても考えさせる作品だ。さらに、「自分の頭の中から生み出されたものこそ『正解』」という、創造物と向き合う際の姿勢についても問うているように思う
あわせて読みたい
【驚異】映画『RRR』『バーフバリ』は「観るエナジードリンク」だ!これ程の作品にはなかなか出会えないぞ
2022年に劇場公開されるや、そのあまりの面白さから爆発的人気を博し、現在に至るまでロングラン上映が続いている『RRR』と、同監督作の『バーフバリ』は、大げさではなく「全人類にオススメ」と言える超絶的な傑作だ。まだ観ていない人がいるなら、是非観てほしい!
あわせて読みたい
【勝負】実話を基にコンピューター将棋を描く映画『AWAKE』が人間同士の対局の面白さを再認識させる
実際に行われた将棋の対局をベースにして描かれる映画『AWAKE』は、プロ棋士と将棋ソフトの闘いを「人間ドラマ」として描き出す物語だ。年に4人しかプロ棋士になれない厳しい世界においては、「夢破れた者たち」もまた魅力的な物語を有している。光と影を対比的に描き出す、見事な作品
あわせて読みたい
【衝撃】自ら立ち上げた「大分トリニータ」を放漫経営で潰したとされる溝畑宏の「真の実像」に迫る本:…
まったく何もないところからサッカーのクラブチーム「大分トリニータ」を立ち上げ、「県リーグから出発してチャンピオンになる」というJリーグ史上初の快挙を成し遂げた天才・溝畑宏を描く『爆走社長の天国と地獄』から、「正しく評価することの難しさ」について考える
あわせて読みたい
【偉業】「卓球王国・中国」実現のため、周恩来が頭を下げて請うた天才・荻村伊智朗の信じがたい努力と…
「20世紀を代表するスポーツ選手」というアンケートで、その当時大活躍していた中田英寿よりも高順位だった荻村伊智朗を知っているだろうか?選手としてだけでなく、指導者としてもとんでもない功績を残した彼の生涯を描く『ピンポンさん』から、ノーベル平和賞級の活躍を知る
あわせて読みたい
【感想】映画『君が世界のはじまり』は、「伝わらない」「分かったフリをしたくない」の感情が濃密
「キラキラした青春学園モノ」かと思っていた映画『君が世界のはじまり』は、「そこはかとない鬱屈」に覆われた、とても私好みの映画だった。自分の決断だけではどうにもならない「現実」を前に、様々な葛藤渦巻く若者たちの「諦念」を丁寧に描き出す素晴らしい物語
あわせて読みたい
【伝説】やり投げ選手・溝口和洋は「思考力」が凄まじかった!「幻の世界記録」など数々の逸話を残した…
世界レベルのやり投げ選手だった溝口和洋を知っているだろうか? 私は本書『一投に賭ける』で初めてその存在を知った。他の追随を許さないほどの圧倒的なトレーニングと、常識を疑い続けるずば抜けた思考力を武器に、体格で劣る日本人ながら「幻の世界記録」を叩き出した天才の伝説と実像
あわせて読みたい
【言葉】「戸田真琴の生きづらさ」を起点に世の中を描く映画『永遠が通り過ぎていく』の”しんどい叫び”
『あなたの孤独は美しい』というエッセイでその存在を知ったAV女優・戸田真琴の初監督映画『永遠が通り過ぎていく』。トークショーで「自分が傷つけられた時の心象風景を映像にした」と語るのを聞いて、映画全体の捉え方が変わった。他者のために創作を続ける彼女からの「贈り物」
あわせて読みたい
【感想】湯浅政明監督アニメ映画『犬王』は、実在した能楽師を”異形”として描くスペクタクル平家物語
観るつもりなし、期待値ゼロ、事前情報ほぼ皆無の状態で観た映画『犬王』(湯浅政明監督)はあまりにも凄まじく、私はこんなとんでもない傑作を見逃すところだったのかと驚愕させられた。原作の古川日出男が紡ぐ狂気の世界観に、リアルな「ライブ感」が加わった、素晴らしすぎる「音楽映画」
あわせて読みたい
【あらすじ】映画化の小説『僕は、線を描く』。才能・センスではない「芸術の本質」に砥上裕將が迫る
「水墨画」という、多くの人にとって馴染みが無いだろう芸術を題材に据えた小説『線は、僕を描く』は、青春の葛藤と創作の苦悩を描き出す作品だ。「未経験のど素人である主人公が、巨匠の孫娘と勝負する」という、普通ならあり得ない展開をリアルに感じさせる設定が見事
あわせて読みたい
【アート】映画『ダ・ヴィンチは誰に微笑む』が描く「美術界の闇」と「芸術作品の真正性」の奥深さ
美術界史上最高額510億円で落札された通称「救世主」は、発見される以前から「レオナルド・ダ・ヴィンチの失われた作品」として知られる有名な絵だった。映画『ダ・ヴィンチは誰に微笑む』は、「芸術作品の真正性の問題」に斬り込み、魑魅魍魎渦巻く美術界を魅力的に描き出す
あわせて読みたい
【おすすめ】「天才」を描くのは難しい。そんな無謀な挑戦を成し遂げた天才・野崎まどの『know』はヤバい
「物語で『天才』を描くこと」は非常に難しい。「理解できない」と「理解できる」を絶妙なバランスで成り立たせる必要があるからだ。そんな難題を高いレベルでクリアしている野崎まど『know』は、異次元の小説である。世界を一変させた天才を描き、「天才が見ている世界」を垣間見せてくれる
あわせて読みたい
【奇人】天才数学者で、自宅を持たずに世界中を放浪した変人エルデシュは、迷惑な存在でも愛され続けた…
数学史上ガウスに次いで生涯発表論文数が多い天才エルデシュをご存知だろうか?数学者としてずば抜けた才能を発揮したが、それ以上に「奇人変人」としても知られる人物だ。『放浪の天才数学者エルデシュ』で、世界中の数学者の家を泊まり歩いた異端数学者の生涯を描き出す
あわせて読みたい
【天才】『ご冗談でしょう、ファインマンさん』は、科学者のイメージが変わる逸話満載の非・科学エッセイ
「天才科学者」と言えばアインシュタインやニュートン、ホーキングが思い浮かぶだろうが、「科学者らしくないエピソード満載の天才科学者」という意味ではファインマンがずば抜けている。世界的大ベストセラー『ご冗談でしょう、ファインマンさん』は、「科学」をほぼ扱わないエッセイです
あわせて読みたい
【青春】二宮和也で映画化もされた『赤めだか』。天才・立川談志を弟子・談春が描く衝撃爆笑自伝エッセイ
「落語協会」を飛び出し、新たに「落語立川流」を創設した立川談志と、そんな立川談志に弟子入りした立川談春。「師匠」と「弟子」という関係で過ごした”ぶっ飛んだ日々”を描く立川談春のエッセイ『赤めだか』は、立川談志の異端さに振り回された立川談春の成長譚が面白い
あわせて読みたい
【革新】天才マルタン・マルジェラの現在。顔出しNGでデザイナーの頂点に立った男の”素声”:映画『マル…
「マルタン・マルジェラ」というデザイナーもそのブランドのことも私は知らなかったが、そんなファッション音痴でも興味深く観ることができた映画『マルジェラが語る”マルタン・マルジェラ”』は、生涯顔出しせずにトップに上り詰めた天才の来歴と現在地が語られる
あわせて読みたい
【感想】才能の開花には”極限の環境”が必要か?映画『セッション』が描く世界を私は否定したい
「追い込む指導者」が作り出す”極限の環境”だからこそ、才能が開花する可能性もあるとは思う。しかし、そのような環境はどうしても必要だろうか?最高峰の音楽院での壮絶な”指導”を描く映画『セッション』から、私たちの生活を豊かにしてくれるものの背後にある「死者」を想像する
あわせて読みたい
【解釈】詩人が語る詩の読み方。意味や読み方や良さが分からなくて全然気にしなくていい:『今を生きる…
私は学生時代ずっと国語の授業が嫌いでしたが、それは「作品の解釈には正解がある」という決めつけが受け入れ難かったからです。しかし、詩人・渡邊十絲子の『今を生きるための現代詩』を読んで、詩に限らずどんな作品も、「解釈など不要」「理解できなければ分からないままでいい」と思えるようになりました
あわせて読みたい
【博覧強記】「紙の本はなくなる」説に「文化は忘却されるからこそ価値がある」と反論する世界的文学者…
世界的文学者であり、「紙の本」を偏愛するウンベルト・エーコが語る、「忘却という機能があるから書物に価値がある」という主張は実にスリリングだ。『もうすぐ絶滅するという紙の書物について』での対談から、「忘却しない電子データ」のデメリットと「本」の可能性を知る
あわせて読みたい
【おすすめ】濱口竜介監督の映画『親密さ』は、「映像」よりも「言葉」が前面に来る衝撃の4時間だった
専門学校の卒業制作として濱口竜介が撮った映画『親密さ』は、2時間10分の劇中劇を組み込んだ意欲作。「映像」でありながら「言葉の力」が前面に押し出される作品で、映画や劇中劇の随所で放たれる「言葉」に圧倒される。4時間と非常に長いが、観て良かった
あわせて読みたい
【あらすじ】濱口竜介監督『偶然と想像』は、「脚本」と「役者」のみで成り立つ凄まじい映画。天才だと思う
「映画」というメディアを構成する要素は多々あるはずだが、濱口竜介監督作『偶然と想像』は、「脚本」と「役者」だけで狂気・感動・爆笑を生み出してしまう驚異の作品だ。まったく異なる3話オムニバス作品で、どの話も「ずっと観ていられる」と感じるほど素敵だった
あわせて読みたい
【傑作】濱口竜介監督の映画『ドライブ・マイ・カー』(原作:村上春樹)は「自然な不自然さ」が見事な作品
村上春樹の短編小説を原作にした映画『ドライブ・マイ・カー』(濱口竜介監督)は、村上春樹の小説の雰囲気に似た「自然な不自然さ」を醸し出す。「不自然」でしかない世界をいかにして「自然」に見せているのか、そして「自然な不自然さ」は作品全体にどんな影響を与えているのか
あわせて読みたい
【情熱】映画『パッドマン』から、女性への偏見が色濃く残る現実と、それを打ち破ったパワーを知る
「生理は語ることすらタブー」という、21世紀とは思えない偏見が残るインドで、灰や汚れた布を使って経血を処理する妻のために「安価な生理用ナプキン」の開発に挑んだ実在の人物をモデルにした映画『パッドマン 5億人の女性を救った男』から、「どう生きたいか」を考える
あわせて読みたい
【創作】クリエイターになりたい人は必読。ジブリに見習い入社した川上量生が語るコンテンツの本質:『…
ドワンゴの会長職に就きながら、ジブリに「見習い」として入社した川上量生が、様々なクリエイターの仕事に触れ、色んな質問をぶつけることで、「コンテンツとは何か」を考える『コンテンツの秘密』から、「創作」という営みの本質や、「クリエイター」の理屈を学ぶ
あわせて読みたい
【奇跡】鈴木敏夫が2人の天才、高畑勲と宮崎駿を語る。ジブリの誕生から驚きの創作秘話まで:『天才の思…
徳間書店から成り行きでジブリ入りすることになったプロデューサー・鈴木敏夫が、宮崎駿・高畑勲という2人の天才と共に作り上げたジブリ作品とその背景を語り尽くす『天才の思考 高畑勲と宮崎駿』。日本のアニメ界のトップランナーたちの軌跡の奇跡を知る
あわせて読みたい
【実像】ベートーヴェンの「有名なエピソード」をほぼ一人で捏造・創作した天才プロデューサーの実像:…
ベートーヴェンと言えば、誰もが知っている「運命」を始め、天才音楽家として音楽史に名を刻む人物だが、彼について良く知られたエピソードのほとんどは実は捏造かもしれない。『ベートーヴェン捏造 名プロデューサーは嘘をつく』が描く、シンドラーという”天才”の実像
あわせて読みたい
【問い】「学ぶとはどういうことか」が学べる1冊。勉強や研究の指針に悩む人を導いてくれる物語:『喜嶋…
学校の勉強では常に「課題」が与えられていたが、「学び」というのは本来的に「問題を見つけること」にこそ価値がある。研究者の日常を描く小説『喜嶋先生の静かな世界』から、「学びの本質」と、我々はどんな風に生きていくべきかについて考える
あわせて読みたい
【驚愕】ロバート・キャパの「崩れ落ちる兵士」はどう解釈すべきか?沢木耕太郎が真相に迫る:『キャパ…
戦争写真として最も有名なロバート・キャパの「崩れ落ちる兵士」には、「本当に銃撃された瞬間を撮影したものか?」という真贋問題が長く議論されてきた。『キャパの十字架』は、そんな有名な謎に沢木耕太郎が挑み、予想だにしなかった結論を導き出すノンフィクション。「思いがけない解釈」に驚かされるだろう
あわせて読みたい
【貢献】有名な科学者は、どんな派手な失敗をしてきたか?失敗が失敗でなかったアインシュタインも登場…
どれほど偉大な科学者であっても失敗を避けることはできないが、「単なる失敗」で終わることはない。誤った考え方や主張が、プラスの効果をもたらすこともあるのだ。『偉大なる失敗』から、天才科学者の「失敗」と、その意外な「貢献」を知る
あわせて読みたい
【天才】写真家・森山大道に密着する映画。菅田将暉の声でカッコよく始まる「撮り続ける男」の生き様:…
映画『あゝ荒野』のスチール撮影の際に憧れの森山大道に初めて会ったという菅田将暉の声で始まる映画『過去はいつも新しく、未来はつねに懐かしい』は、ちゃちなデジカメ1つでひたすら撮り続ける異端児の姿と、50年前の処女作復活物語が見事に交錯する
あわせて読みたい
【逸話】天才数学者ガロアが20歳で決闘で命を落とすまでの波乱万丈。時代を先駆けた男がもし生きていた…
現代数学に不可欠な「群論」をたった1人で生み出し、20歳という若さで決闘で亡くなったガロアは、その短い生涯をどう生きたのか?『ガロア 天才数学者の生涯』から、数学に関心を抱くようになったきっかけや信じられないほどの不運が彼の人生をどう変えてしまったのか、そして「もし生きていたらどうなっていたのか」を知る
あわせて読みたい
【狂気】稀少本を収集・売買する「愛すべき変人コレクター」の世界と、インターネットによる激変:映画…
広大な本の世界を狩人のように渉猟し、お気に入りの本を異常なまでに偏愛する者たちを描き出す映画『ブックセラーズ』。実在の稀少本コレクターたちが、本への愛を語り、新たな価値を見出し、次世代を教育し、インターネットの脅威にどう立ち向かっているのかを知る
あわせて読みたい
【誤解】「意味のない科学研究」にはこんな価値がある。高校生向けの講演から”科学の本質”を知る:『す…
科学研究に対して、「それは何の役に立つんですか?」と問うことは根本的に間違っている。そのことを、「携帯電話」と「東急ハンズの棚」の例を使って著者は力説する。『すごい実験』は素粒子物理学を超易しく解説する本だが、科学への関心を抱かせてもくれる
あわせて読みたい
【バトル】量子力学の歴史はこの1冊で。先駆者プランクから批判者アインシュタインまですべて描く:『量…
20世紀に生まれた量子論は、時代を彩る天才科学者たちの侃々諤々の議論から生み出された。アインシュタインは生涯量子論に反対し続けたことで知られているが、しかし彼の批判によって新たな知見も生まれた。『量子革命』から、量子論誕生の歴史を知る
あわせて読みたい
【証明】結城浩「数学ガール」とサイモン・シンから「フェルマーの最終定理」とそのドラマを学ぶ
350年以上前に一人の数学者が遺した予想であり「フェルマーの最終定理」には、1995年にワイルズによって証明されるまでの間に、これでもかというほどのドラマが詰め込まれている。サイモン・シンの著作と「数学ガール」シリーズから、その人間ドラマと数学的側面を知る
あわせて読みたい
【衝撃】ABC予想の証明のために生まれたIUT理論を、提唱者・望月新一の盟友が分かりやすく語る:『宇宙…
8年のチェック期間を経て雑誌に掲載された「IUT理論(宇宙際タイヒミュラー理論)」は、数学の最重要未解決問題である「ABC予想」を証明するものとして大いに話題になった。『宇宙と宇宙をつなぐ数学』『abc予想入門』をベースに、「IUT理論」「ABC予想」について学ぶ
あわせて読みたい
【天才】諦めない人は何が違う?「努力を努力だと思わない」という才能こそが、未来への道を開く:映画…
どれだけ「天賦の才能」に恵まれていても「努力できる才能」が無ければどこにも辿り着けない。そして「努力できる才能」さえあれば、仮に絶望の淵に立たされることになっても、立ち上がる勇気に変えられる。映画『マイ・バッハ』で知る衝撃の実話
あわせて読みたい
【変人】結城浩「数学ガール」から、1億円も名誉ある賞も断った天才が証明したポアンカレ予想を学ぶ
1億円の賞金が懸けられた「ポアンカレ予想」は、ペレルマンという天才数学者が解き明かしたが、1億円もフィールズ賞も断った。そんな逸話のある「ポアンカレ予想」とは一体どんな主張であり、どのように証明されたのかを結城浩『数学ガール』から学ぶ
あわせて読みたい
【興奮】結城浩「数学ガール」で、決闘で命を落とした若き天才数学者・ガロアの理論を学ぶ
高校生を中心に、数学を通じて関わり合う者たちを描く「数学ガール」シリーズ第5弾のテーマは「ガロア理論」。独力で「群論」という新たな領域を切り開きながら、先駆的すぎて同時代の数学者には理解されず、その後決闘で死亡した天才の遺した思考を追う
あわせて読みたい
【情熱】常識を疑え。人間の”狂気”こそが、想像し得ない偉業を成し遂げるための原動力だ:映画『博士と…
世界最高峰の辞書である『オックスフォード英語大辞典』は、「学位を持たない独学者」と「殺人犯」のタッグが生みだした。出会うはずのない2人の「狂人」が邂逅したことで成し遂げられた偉業と、「狂気」からしか「偉業」が生まれない現実を、映画『博士と狂人』から学ぶ
あわせて読みたい
【天才】科学者とは思えないほど面白い逸話ばかりのファインマンは、一体どんな業績を残したのか?:『…
数々の面白エピソードで知られるファインマンの「科学者としての業績」を初めて網羅したと言われる一般書『ファインマンさんの流儀』をベースに、その独特の研究手法がもたらした様々な分野への間接的な貢献と、「ファインマン・ダイアグラム」の衝撃を理解する
あわせて読みたい
【対立】数学はなぜ”美しい”のか?数学は「発見」か「発明」かの議論から、その奥深さを知る:『神は数…
数学界には、「数学は神が作った派」と「数学は人間が作った派」が存在する。『神は数学者か?』をベースに、「数学は発見か、発明か」という議論を理解し、数学史においてそれぞれの認識がどのような転換点によって変わっていったのかを学ぶ
あわせて読みたい
【驚異】プロジェクトマネジメントの奇跡。ハリウッドの制作費以下で火星に到達したインドの偉業:映画…
実は、「一発で火星に探査機を送り込んだ国」はインドだけだ。アメリカもロシアも何度も失敗している。しかもインドの宇宙開発予算は大国と比べて圧倒的に低い。なぜインドは偉業を成し遂げられたのか?映画『ミッション・マンガル』からプロジェクトマネジメントを学ぶ
あわせて読みたい
【究極】リサ・ランドールが「重力が超弱い理由」を解説する、超刺激的なひも理論の仮説:『ワープする…
現役の研究者であるリサ・ランドールが、自身の仮説を一般向けに分かりやすく説明する『ワープする宇宙』。一般相対性理論・量子力学の知識を深く記述しつつ「重力が超弱い理由」を説明する、ひも理論から導かれる「ワープする余剰次元」について解説する
あわせて読みたい
【能力】激変する未来で「必要とされる人」になるためのスキルや考え方を落合陽一に学ぶ:『働き方5.0』
AIが台頭する未来で生き残るのは難しい……。落合陽一『働き方5.0~これからの世界をつくる仲間たちへ~』はそう思わされる一冊で、本書は正直、未来を前向きに諦めるために読んでもいい。未来を担う若者に何を教え、どう教育すべきかの参考にもなる一冊。
あわせて読みたい
【改革】AIは将棋をどう変えた?羽生善治・渡辺明ら11人の現役棋士が語る将棋の未来:『不屈の棋士』(…
既に将棋AIの実力はプロ棋士を越えたとも言われる。しかし、「棋力が強いかどうか」だけでは将棋AIの良し悪しは判断できない。11人の現役棋士が登場する『不屈の棋士』をベースに、「AIは将棋界をどう変えたのか?」について語る
あわせて読みたい
【異端】子育ては「期待しない」「普通から外れさせる」が大事。”劇薬”のような父親の教育論:『オーマ…
どんな親でも、子どもを幸せにしてあげたい、と考えるでしょう。しかしそのために、過保護になりすぎてしまっている、ということもあるかもしれません。『オーマイ・ゴッドファーザー』をベースに、子どもを豊かに、力強く生きさせるための”劇薬”を学ぶ
あわせて読みたい
【奇跡】ビッグデータに”直感”を組み込んで活用。メジャーリーグを変えたデータ分析家の奮闘:『アスト…
「半世紀で最悪の野球チーム」と呼ばれたアストロズは、ビッグデータの分析によって優勝を果たす。その偉業は、野球のド素人によって行われた。『アストロボール』をベースに、「ビッグデータ」に「人間の直感」を組み込むという革命について学ぶ
あわせて読みたい
【諦め】「人間が創作すること」に意味はあるか?AI社会で問われる、「創作の悩み」以前の問題:『電気…
AIが個人の好みに合わせて作曲してくれる世界に、「作曲家」の存在価値はあるだろうか?我々がもうすぐ経験するだろう近未来を描く『電気じかけのクジラは歌う』をベースに、「創作の世界に足を踏み入れるべきか」という問いに直面せざるを得ない現実を考える
あわせて読みたい
【肯定】社会不適合者こそ非凡。学校・世の中に馴染めなかった異才たちの過去から”才能”の本質を知る:…
「みんなと同じ」に馴染めないと「社会不適合」と判断され、排除されてしまうことが多いでしょう。しかし『非属の才能』では、「どこにも属せない感覚」にこそ才能の源泉があると主張します。常識に違和感を覚えてしまう人を救う本から、同調圧力に屈しない生き方を学ぶ
あわせて読みたい
【感想】努力では才能に勝てないのか?どうしても辿り着きたい地点まで迷いながらも突き進むために:『…
どうしても辿り着きたい場所があっても、そのあまりの遠さに目が眩んでしまうこともあるでしょう。そんな人に向けて、「才能がない」という言葉に逃げずに前進する勇気と、「仕事をする上で大事なスタンス」について『羊と鋼の森』をベースに書いていきます
あわせて読みたい
【実話】仕事のやりがいは、「頑張るスタッフ」「人を大切にする経営者」「健全な商売」が生んでいる:…
メガネファストファッションブランド「オンデーズ」の社長・田中修治が経験した、波乱万丈な経営再生物語『破天荒フェニックス』をベースに、「仕事の目的」を見失わず、関わるすべての人に存在価値を感じさせる「働く現場」の作り方
あわせて読みたい
【表現者】「センスが良い」という言葉に逃げない。自分の内側から何かを表現することの本質:『作詞少…
大前提として、表現には「技術」が必要だ。しかし、「技術」だけでは乗り越えられない部分も当然ある。それを「あいつはセンスが良いから」という言葉に逃げずに、向き合ってぶつかっていくための心得とは何か。『作詞少女』をベースに「表現することの本質」を探る
ルシルナ
才能・センスがない【本・映画の感想】 | ルシルナ
子どもの頃は、自分が何かの才能やセンスに恵まれていることを期待していましたが、残念ながら天才ではありませんでした。昔はやはり、凄い人に嫉妬したり、誰かと比べて苦…
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…



















































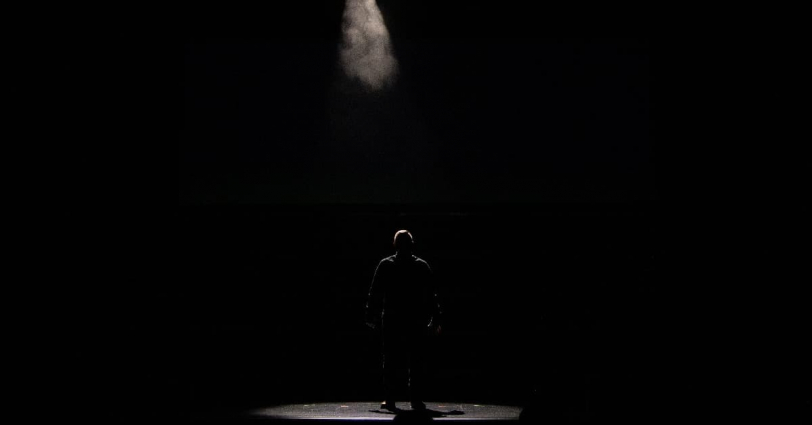
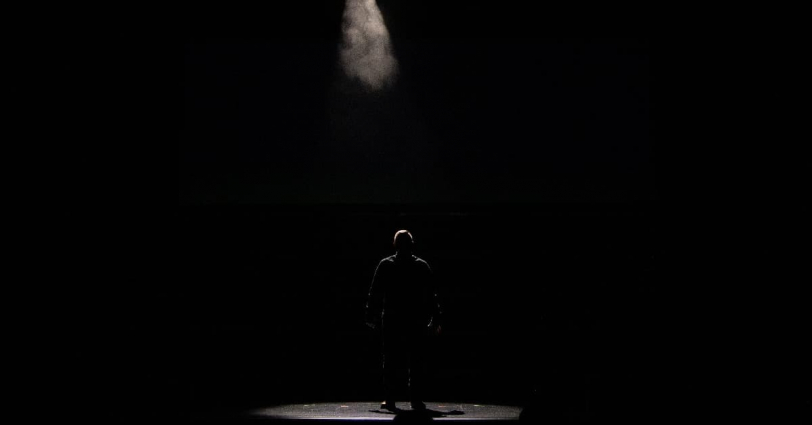

































































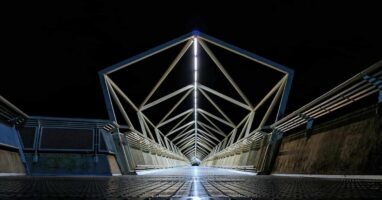
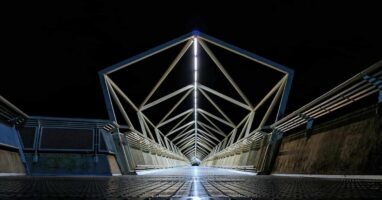




























































































































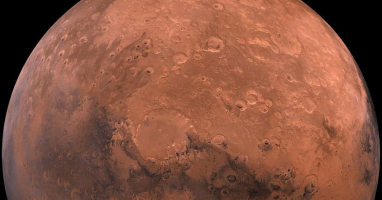
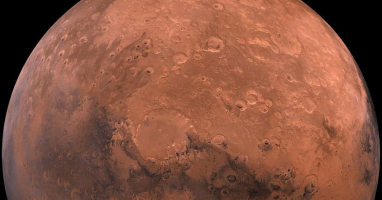



































コメント