目次
はじめに
この記事で取り上げる映画
監督:ヴァネッサ・フィロ, 出演:キム・イジュラン, 出演:ジャン=ポール・ルーヴ, 出演:レティシア・カスタ, 出演:エロディ・ブシェーズ
¥550 (2025/02/21 22:29時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
この映画をガイドにしながら記事を書いていきます
この記事の3つの要点
- 本作においては、「決して『個人の問題』などではなく『社会システムの問題』である」という認識が非常に重要だ
- 自ら最初の1歩を踏み出した少女を、老獪な小説家はいかにして言葉巧みに幻惑させていったのか?
- 母親の理解できなかった振る舞いと、「同意が存在した」と判断することの困難さ
確かに本作は「小児性愛者(ロリコン)」の話なのだが、物語の本質は決して他人事ではないと私には感じられた
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
記事中の引用は、映画館で取ったメモを参考にしているので、正確なものではありません
実際にあった「50歳男性と14歳少女の”恋”」を描く映画『コンセント/同意』は、「変態の話だから自分たちには関係ない」なんて考えで無視できるものではない
本作は冒頭で「実話を基にした物語」であることが記される。そしてそこから、監督(制作側)の強い想いが読み取れるはずだ。
あわせて読みたい
【性加害】映画『SHE SAID その名を暴け』を観てくれ。#MeToo運動を生んだ報道の舞台裏(出演:キャリ…
「#MeToo」運動のきっかけとなった、ハリウッドの絶対権力者ハーヴェイ・ワインスタインを告発するニューヨーク・タイムズの記事。その取材を担った2人の女性記者の奮闘を描く映画『SHE SAID その名を暴け』は、ジャニー喜多川の性加害問題で揺れる今、絶対に観るべき映画だと思う
本作は、ヴァネッサ・スプリンゴラの著書『同意』を基に、若干のフィクションを交えて映画化された。
著者の想いを届けたい。それだけを願って制作された。
本作のストーリーを知れば、監督がそんな風に考えた理由も理解できるだろう。あまりにも「醜悪」な物語だからだ。

「個人の問題」ではなく「システムの問題」だと受け取られるべき
本作で描かれるのは、50歳の男性小説家と14歳の少女の”恋”である。50歳の国民的小説家ガブリエル・マツネフのアプローチを”受け入れる”形で、14歳のヴァネッサとの恋が始まった。そう、『コンセント/同意』というタイトルの通り、少女が初老男性との”恋”に同意したことで、2人の関係性が始まっていくのである。
あわせて読みたい
【危機】教員のセクハラは何故無くならない?資質だけではない、学校の構造的な問題も指摘する:『スク…
『スクールセクハラ なぜ教師のわいせつ犯罪は繰り返されるのか』では、自分が生徒に対して「権力」を持っているとは想像していなかったという教師が登場する。そしてこの「無自覚」は、学校以外の場でも起こりうる。特に男性は、読んで自分の振る舞いを見直すべきだ
さて、「最初こそ、ヴァネッサも積極的にマツネフの求愛を受け入れていた」という事実こそあるものの、そもそも「50歳の男が14歳の少女に恋をする」という時点で醜悪であり気持ち悪い。ただ本作は、単にそんな感情を観客に抱かせるために存在しているのではないと思う。「キモっ!」と一刀両断してお終い、なんて風に片付けていい話ではないのである。
さて、「50歳の男と14歳の少女の恋愛」と聞いて、「どんな風にデートをしている」と想像するだろうか。普通に考えれば、「その関係性をなるべく秘密裏にしようとする」のではないかと思う。出来るだけ人目に付かないようにして会い、その関係性を大っぴらにしない方が安全だろう。いくら本人同士が「同意」しているとしても、社会的には普通、「50歳の男と14歳の少女の恋愛」など許されるはずがないからだ。
しかし本作ではそうではない。2人は人目を気にせずに大っぴらに会い、さらに、仕事仲間(編集者や評論家)にもヴァネッサのことを紹介している。もちろん、「親密な関係である」ことを匂わせた上でだ。もちろん、そんな状況が成立した背景には、「ガブリエル・マツネフが熱狂的なファンを持つ大作家だ」という要素は関係しているだろう。本人曰く、「ミッテラン大統領も私のファンだ」とのことだった。そしてそうだとすれば、「そんな偉大な作家だからこそ、『おかしい』と思っていても誰も指摘できなかった」みたいなことなのかもしれない。
あわせて読みたい
【驚嘆】映画『TAR/ター』のリディア・ターと、彼女を演じたケイト・ブランシェットの凄まじさ
天才女性指揮者リディア・ターを強烈に描き出す映画『TAR/ター』は、とんでもない作品だ。「縦軸」としてのターの存在感があまりにも強すぎるため「横軸」を上手く捉えきれず、結果「よく分からなかった」という感想で終わったが、それでも「観て良かった」と感じるほど、揺さぶられる作品だった
ただ本作には、そのようなシーンはほとんどない。まあ、ある意味でそれは当然だ。本作は、ヴァネッサが書いた著書を基に映画化されているのだから、「マツネフ周辺の話」は彼女が目にしたことぐらいしか書けない。マツネフの周囲の人間が実際には「ためらい」みたいなものを抱えていたとしてもヴァネッサには分からなかっただろうし、そういうスタンスを映画でも踏襲しているのであれば、「マツネフの周辺の人間が葛藤を抱きつつ何も出来なかった」みたいな描写が無いことも不思議ではない。
しかし、作中のあるシーンを踏まえると、「偉大な作家だから言えなかった」みたいな感じではないような気もする。私がそう感じたのは、ヴァネッサと母親がテレビに出演しているガブリエル・マツネフの様子を観ていた時のことだった。番組出演者の1人が次のような発言をしていたのだ。
この国は「文学」と名前が付けば、どんな悪徳でも許容される。
あわせて読みたい
【苦悩】「やりがいのある仕事」だから見て見ぬふり?映画『アシスタント』が抉る搾取のリアル
とある映画会社で働く女性の「とある1日」を描く映画『アシスタント』は、「働くことの理不尽さ」が前面に描かれる作品だ。「雑用」に甘んじるしかない彼女の葛藤がリアルに描かれている。しかしそれだけではない。映画の「背景」にあるのは、あまりに悪逆な行為と、大勢による「見て見ぬふり」である
そう、本作で最も重要なのはこの点だと私には感じられた。
「マツネフが生粋の小児性愛者である」という事実も、もちろん大問題である。しかしそれは「個人の問題」であり、他人が何らかの形で介入出来る余地は少ない。当然、マツネフが犯罪を起こせば警察が介入することになるわけだが(作中でも実は、そんな動きが描かれていた)、本作の場合、2人の関係は「同意」の下にある。もちろん、「同意」の中身こそ注目すべきであり、それについては後で触れるが、法律的な話をするのであれば、マツネフの行為は恐らく「犯罪」とは見なされないだろう。となれば、「マツネフが小児性愛者である」という事実に外部から対処することは困難である。だからこの問題を掘り下げても、広く益する知見が得られたりはしないと思う。

しかし、「『文学』なら何でも許される」というのはそれとは違う話である。「個人の問題」ではなく「システムの問題」だからだ。「ガブリエルが小児性愛者である」という事実には何も対処できないとしても、「そんな人間を社会でのさばらせないようにする」ことは出来るはずだろう。にも拘らず、「文学だから」という理由で、一般的な倫理観では許されないはずのことまでスルーされてしまう現状は異様だし、そのことこそが問題視されるべきだと私は思う。
あわせて読みたい
【正義】ナン・ゴールディンの”覚悟”を映し出す映画『美と殺戮のすべて』が描く衝撃の薬害事件
映画『美と殺戮のすべて』は、写真家ナン・ゴールディンの凄まじい闘いが映し出されるドキュメンタリー映画である。ターゲットとなるのは、美術界にその名を轟かすサックラー家。なんと、彼らが創業した製薬会社で製造された処方薬によって、アメリカでは既に50万人が死亡しているのだ。そんな異次元の薬害事件が扱われる驚くべき作品
公式HPには、「本国で異例の大ヒット。国家を動かした衝撃の告発。」と書かれている。「国家を動かした」というのが何を指すのかざっくり調べてみたのだが、どうやら、「国からガブリエル・マツネフに支払われていた『文学者手当』が打ち切られたこと」を指すようだ。また、彼の著作の多くが出版社の判断で販売中止にもなったという。本作を観る限りにおいては、少なくともマツネフの周囲の人間は彼の行いを知っていたはずなので「何を今さら」といったところだが、実話を基にしているとはいえ、フィクションの映画がこれほどの影響力をもたらしたことは素晴らしいなと思う。
そしてその原動力となったのが、フランスの若者の反応なのだという。公式HPには、「特に若者たちの反応は凄まじく」と書かれていた。「私たちはそんな社会を断固許さない」というスタンスを明確に示しているのだろう。私は、若い世代ほど色んな事柄に対する考えがまともだと思っているし、だから「上の世代(そうしたくはないが、ここには私自身も入れるしかないだろう)が退場すれば世の中は良くなる」とさえ考えている。なので若い世代には、社会の「醜悪さ」を排除していくような動きをどんどん見せてほしいものだと思う。
「同意した」のではなく「同意させられた」に過ぎない
ではここからしばらく、「同意」について考えていくことにしよう。そしてその説明に関係するため、ここでまず、「そもそも、ヴァネッサは何故36歳も年上の男性に惹かれたのか?」に注目しつつ、「ガブリエル・マツネフがどのように14歳の少女にアプローチしていったのか?」という本作の物語の展開に少し触れておきたいと思う。
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『夕方のおともだち』は、「私はこう」という宣言からしか始まらない関係性の”純度”を描く
「こんな田舎にはもったいないほどのドM」と評された男が主人公の映画『夕方のおともだち』は、SM嬢と真性ドMの関わりを通じて、「宣言から始まる関係」の難しさを描き出す。「普通の世界」に息苦しさを感じ、どうしても馴染めないと思っている人に刺さるだろう作品
重要なポイントは、ヴァネッサが大の読書家であり、作家志望でもあるという点だ。それは、編集者である母親も驚くほどだった。作中では、ヴァネッサ14歳の誕生日パーティーの様子が映し出されるのだが、そこで彼女はJ=D・ヴォルフロムという人物から声を掛けられる。どうやら文芸評論家として著名な人物のようだ。そして彼はヴァネッサに、「将来作家になる君へ」というメッセージを送っているのである。評論家からそう目されるほど作家としての才能が垣間見えていたのだろう。となれば、ごく一般的な中学生よりも「言葉」に対する感度は高かったはずだと思う。
そしてそれ故にヴァネッサは、「著名な作家」であり、かつ「巧みで熱烈なラブレター」を送ってくれるマツネフのことを好きになっていくのである。
さて、確かにアプローチを仕掛けたのはマツネフの方なのだが、彼はヴァネッサが自ら行動を始めるまで何もしなかった。そして、マツネフとしばらく手紙のやり取りをしたヴァネッサは、マツネフの求めに応じて彼と2人で会うことに決める。これは「最初の一歩を自らの意思で踏み出した」と言えるし、そういう意味で「36歳年上の男性との“恋”に『同意』していた」と見ることは可能だ。ただ恐らくだが、後の展開を考えて、「そうなるまで待っていた」と考えるのが妥当ではないかと思う。
あわせて読みたい
【闘争】映画『あのこと』が描く、中絶が禁止だった時代と、望まぬ妊娠における圧倒的な「男の不在」
中絶が禁止されていた1960年代のフランスを舞台にした映画『あのこと』は、「望まぬ妊娠」をしてしまった秀才の大学生が、「未来を諦めない」ために中絶を目指す姿が描かれる。さらに、誰にも言えずに孤独に奮闘する彼女の姿が「男の不在」を強調する物語でもあり、まさに男が観るべき作品だ
マツネフはヴァネッサをそのまま自宅へと連れて行く。何か嫌な予感がしたのだろう、この時点でヴァネッサは「帰った方がいいかも」と口にしている。それに対してマツネフは「君が嫌がることはしないから」と声を掛け彼女を引き止めるのだが、こういう「言葉のセレクト」が上手いなと随所で感じさせられた。マツネフはヴァネッサ以前にも同様のことを何度も経験してきたはずで、だから「どうすれば上手くコトが進むのか」を心得ていたのだと思う。
さて、マツネフはそれから、ヴァネッサにキスをしたり服を脱がせたりする。もちろんヴァネッサはそんなこと想定していなかっただろうし、そのことを言葉ではっきりと表明することこそなかった(出来なかった)ものの、当然「嫌だった」だろうと思う。ただ、ここで「ヴァネッサが自らの意思でやってきた」という事実が重要になってくる。「自ら望んだことなんだから」という理由で自分を納得させる力が働き得るからだ。また、将来小説家になりたいと思っているヴァネッサとしては、「大作家から嫌われる」ことを恐れる気持ちもあったはずだ。恐らくそのような複合的な理由から、ヴァネッサは「本当は嫌だったけど、マツネフの行為を受け入れる」という選択をした(せざるを得なかった)のだと思う。

さらに、これも実に巧妙なのだが、ここでマツネフがあらかじめ口にしていた「君が嫌がることはしないから」という言葉が効いてくることになる。先にそう言っておいたことで、「嫌だったら嫌って言ってね」みたいな表向きのニュアンスとは別に、「拒否しないってことは嫌じゃないんだよね」というメッセージとしても機能し得るからだ。こんな風にしてヴァネッサは、「マツネフと会う」と決めた時には想定していなかったはずの「身体の関係」まで「同意」した(させられた)格好になったのである。
あわせて読みたい
【違和感】平田オリザ『わかりあえないことから』は「コミュニケーション苦手」問題を新たな視点で捉え…
「コミュニケーションが苦手」なのは、テクニックの問題ではない!?『わかりあえないことから』は、学校でのコミュニケーション教育に携わる演劇人・平田オリザが抱いた違和感を起点に、「コミュニケーション教育」が抱える問題と、私たち日本人が進むべき道を示す1冊
このような「同意」の巧みさは別の場面でも発揮されていた。彼らは正式に付き合うようになってからもよく手紙のやり取りをしていたのだが、ある日ヴァネッサがSEXを拒むと、マツネフはかつて彼女が送ってきた手紙を読み上げて、「ここにはこう書いてあるが、これは嘘なのか? お前は嘘つきだ!」みたいな責め方をしてきたのである。つまりこういうことだ。最初は「拒否しないってことは(この行為は)嫌じゃないんだよね」という形での「同意」だったにも拘らず、次第に「拒否するってことは(私のことが)嫌いってことだ」というような「強制」に変わっていくのである。これは明確に「強制」だと私には思えるのだが、しかし、マツネフが示す理屈のスライドが割と上手いので、ヴァネッサにはこれも「同意」のいち形態であるように感じられたに違いない。
マツネフが巧みなのは、目の前の状況を常に「ヴァネッサ主体で物事が進んでいる」という形で把握させようとしていたことだと思う。「(君が)拒否したら~」という言い方もそうだし、別の場面でも、「君のせいで〇〇になった」「君のために△△をしたのに」みたいな表現を使っていた。マツネフはとにかく、「今のこの状況は、お前が引き起こしているんだぞ」と思わせるような言葉を繰り出すのである。小説家ゆえのこのような巧みさもまた絶妙という感じだった。
このようなやり取りを踏まえればで、「ヴァネッサがマツネフとの関係を『同意』したとは言えない」ことが理解できるだろう。単に「同意させられた」に過ぎないのだが、言葉巧みに「同意した」と思い込まされているだけなのだ。長々と書いたこんな話については「当然分かっている」みたいに感じる人も多いとは思うのだが、しかし、自分がそのような状況に置かれた時に客観的に状況を判断できるかはまた別の話だろう。「自分にも起こり得ること」と認識しておくべきだと私は思う。
あわせて読みたい
【あらすじ】「愛されたい」「必要とされたい」はこんなに難しい。藤崎彩織が描く「ままならない関係性…
好きな人の隣にいたい。そんなシンプルな願いこそ、一番難しい。誰かの特別になるために「異性」であることを諦め、でも「異性」として見られないことに苦しさを覚えてしまう。藤崎彩織『ふたご』が描き出す、名前がつかない切実な関係性
「同意」に対する認識と、「孤立」を促そうとする卑劣なやり方
日本でも最近、「性的同意」に関する議論が少しずつ進み始めた印象がある。その過程で世代間・異性間のギャップが可視化されつつあると思うが、その中でよく出てくるのが「NOじゃないならYES」という話だろう。特に私ぐらいの年齢(この文章を書いている時点で41歳である)やさらに上の世代であるほど、「拒否しない=OKサイン」みたいな発想が当たり前なんじゃないかと思う。
しかし昔はともかく、今ではそんな感覚通用しない。性的な行為に限らずだが、「同意」というのは「YESと言えばYES」「NOと言えばNO」が鉄則のはずだ。まあ、もちろんそこにはグラデーションがあって然るべきで、「ちょっと手を出してみて拒否されなかったらOK」みたいなコミュニケーションを完全にゼロにしてしまうのも窮屈過ぎるかもしれない。ただその場合、「相手はNOと言えないだけかもしれない」という可能性を常に頭の片隅に残しておくべきだと思う。
あわせて読みたい
【考察】『うみべの女の子』が伝えたいことを全力で解説。「関係性の名前」を手放し、”裸”で対峙する勇敢さ
ともすれば「エロ本」としか思えない浅野いにおの原作マンガを、その空気感も含めて忠実に映像化した映画『うみべの女の子』。本作が一体何を伝えたかったのかを、必死に考察し全力で解説する。中学生がセックスから関係性をスタートさせることで、友達でも恋人でもない「名前の付かない関係性」となり、行き止まってしまう感じがリアル
本作で描かれているのも、そのような「同意」である。「身体の関係」に関してヴァネッサは、様々な理由から「NO」とは言えなかった。また重要なのは、「『同意』は変化し得る」という点だろう。母親に対してマツネフへの愛を語っていたことからも分かるように、ヴァネッサは自ら”恋”にのめり込んでいった。そのため、初めの内は「彼女自身が積極的に同意した関係」と捉えていいと思う。しかし当たり前の話だが、「最初の同意」が未来永劫有効なはずもない。法律で規定されている状況ならそれに沿うしかないが、そうではないのであれば、「同意はいつだって不同意に変更できる」はずだ。しかしマツネフは、言葉巧みにそのような可能性を排除していく。

ヴァネッサが置かれたような状況は、ネット社会では特に頻繁に起こっているはずだ。ニュースでは時々、「若い女性が、関係性の分からない男に殺される」みたいな事件が報じられるが、それもネット上のやり取りで近寄っていたりすることが多いのだろう。本作で描かれているのはネットがない時代であり、だからこそ「ガブリエル・マツネフのような著名な人物」にしかこんな状況を生み出せなかったわけだが、現代では誰でも出来てしまう。私は以前、『SNS 少女たちの10日間』というドキュメンタリー映画を観たことがあるのだが、その中でも、醜悪な男たちが少女を狙うあまりにもイカれた世界が描かれていた。本当に危うい世の中になってしまったものだと思う
あわせて読みたい
【恐怖】SNSの危険性と子供の守り方を、ドキュメンタリー映画『SNS 少女たちの10日間』で学ぶ
実際にチェコの警察を動かした衝撃のドキュメンタリー映画『SNS 少女たちの10日間』は、少女の「寂しさ」に付け込むおっさんどもの醜悪さに満ちあふれている。「WEBの利用制限」だけでは子どもを守りきれない現実を、リアルなものとして実感すべき
さて、もう少しマツネフのやり方を詳しく見ていくことにしよう。彼は言葉巧みにヴァネッサの心を掌握した後で、さらに彼女を「孤立」させようとする。このやり方もとても上手かった。例えばマツネフは手紙の中で、「子どもの世界から離れることは辛いかもしれないが、勇気を出してほしい」みたいなことを書いている。これは要するに、「学校の友だちと遊ぶ時間があるなら、私と会う時間を増やしなさい」という意味だ。
あるいは、ヴァネッサが「マツネフとの交際の件で母親と喧嘩になった」という話をした際には、「君は私じゃなくて母親を取るのか?」みたいに詰め寄ったりもしていた。これも、ヴァネッサの周囲の人間関係から引き剥がそうとする振る舞いだろう。そしてそうすることで、ヴァネッサをどんどん「孤立」させ、ヴァネッサの世界におけるマツネフの割合を増そうとしているというわけだ。そうなればなるほどマツネフの要求を拒否しにくくなるし、「同意せざるを得ない」とより強く感じるようになっていくだろう。そしてそれ故に、ヴァネッサはますます「自らの意思で同意した」という感覚を強めていくことになるはずだ。
マツネフがヴァネッサに近づいていったやり方は「グルーミング」と呼ばれる手法だろうし、それに関する言及は世の中にたくさんあるはずなので、ここで詳しく触れたりはしない。ただ、1つはっきりと書いておきたいのは、「本作を観て、『マツネフの何が悪いのか分からない』みたいに感じた人は、自分のヤバさを自覚した方がいい」ということだ。恐らく世の中には、「マツネフはちゃんと相手の同意を得ているし、お互いが合意しているのだから、何が問題なのか分からない」みたいに感じる人もいるんじゃないかと思う。恐らくそういう人は、「最近の若い人には、何をしても『セクハラ』って言われちゃうから、どうしていいか分からない」みたいに言ってしまえる人なのだろう。「お前の自覚の無さを、他人のせいにするな」と私は感じるし、本当にそういう人は猛省してほしいと思う。
あわせて読みたい
【絶望】人生どん底から生き方を変える。映画『シスター 夏のわかれ道』が描く中国人女性の葛藤と諦念
両親の死をきっかけに、「見知らぬ弟」を引き取らなければならなくなった女性を描く映画『シスター 夏のわかれ道』は、中国の特異な状況を背景にしつつ、誰もが抱き得る普遍的な葛藤が切り取られていく。現状を打破するために北京の大学院を目指す主人公は、一体どんな決断を下すのか。
謎だった母親の振る舞いと、「同意が存在するかどうかの判断」の難しさ
さて、私が最も理解できなかったのがヴァネッサの母親である。当初はマツネフとの交際に反対しており、それは母親として当然の振る舞いだと思う。そりゃあ、14歳の娘が36歳も年上の男と付き合っていると知ったら止めさせようとするだろう。しかししばらくして母親は、2人の交際を受け入れたようなのだ。この流れが、私にはかなり不可解に感じられた。本作にはあまり母親は登場しないので断片的にしか分からないのだが、何なら2人の交際を応援しているような雰囲気を感じさせる場面さえある。どんな心境の変化なのかと、ちょっと驚かされてしまった。

確かに、フランスに限らず欧米諸国では「個人の人権」がかなり重視されるはずなので、「14歳ではあるが、娘の判断を尊重した」みたいなことなのかもしれない。日本的な感覚とはちょっと違うが、それはまあ国民性の違いなのでいいだろう。ただ、ヴァネッサが「私の勝手でしょ」みたいな発言をした際に、母親が「親の私には責任がある」みたいな反論をしていたのである。つまり母親は当初「子どもの判断に親が介入できる」と考えていたはずなのだ。だから、「娘の判断を尊重する」という思考に変わったのだとしたら、どのタイミングで切り替わったのかが私にはちょっとよく分からなかった。
あわせて読みたい
【実話】「家族とうまくいかない現実」に正解はあるか?選択肢が無いと感じる時、何を”選ぶ”べきか?:…
「自分の子どもなんだから、どんな風に育てたって勝手でしょ」という親の意見が正しいはずはないが、この言葉に反論することは難しい。虐待しようが生活能力が無かろうが、親は親だからだ。映画『MOTHER マザー』から、不正解しかない人生を考える
また先程少し触れた通り、本作には「ガブリエル・マツネフが警察から捜査される」というシーンがあるのだが、その事実を知った母親がヴァネッサに「親権を取り上げられるかもしれない」みたいに言う場面がある。外国の映画を観てよく感じることなのだが、欧米では恐らく「危険だと判断した場合に、公権力が親権を強制的に奪う仕組み」が備わっているのだと思う。日本の場合は「法的な親子関係」がとても強いのでそんな風にはできない。そしてそれ故に児童相談所が苦労することになるわけで、日本とは大違いである。母親の心配も要するに、「『ロリコン男との交際を止めなかった母親』という点が問題視され、親権を奪われるかもしれない」という話なのだろうと思う。そしてそういう状況に置かれていたにも拘らず、母親がマツネフとの交際を許容していたように見えたことが実に不思議だったのだ。
ただこの点については、「母親が編集者である」という要素も無視できないとは思う。そもそも、ヴァネッサがマツネフと初めて会ったのは、母親が編集者として出席していた出版業界のパーティーの席である。となれば、「母親は普段から仕事で小説家ガブリエル・マツネフと関わりがある」と考えるのが自然だろう。そしてマツネフは、フランスでは人気作家である。そうなると編集者としては、「マツネフとの関係を荒立てない方がいい」という発想になってもおかしくはない。
しかし仮にそうだとしても、ことは娘の話なのだ。母親は編集者としてガブリエル・マツネフと関わりがあるのだから、一般の人以上に「小児性愛者としてのマツネフ」の顔も知っていたはずである。そしてその上でマツネフとの交際を許容していたのだとすれば、やはり私には理解しきれないのだ。
あわせて読みたい
【母娘】よしながふみ『愛すべき娘たち』で描かれる「女であることの呪い」に男の私には圧倒されるばかりだ
「女であること」は、「男であること」と比べて遥かに「窮屈さ」に満ちている。母として、娘として、妻として、働く者として、彼女たちは社会の中で常に闘いを強いられてきた。よしながふみ『愛すべき娘たち』は、そんな女性の「ややこしさ」を繊細に描き出すコミック
さてそんなわけで、「50の男と14歳少女の“恋”」についてここまで色々と書いてきたわけだが、様々な物事に対する私のそもそもの基本的なスタンスは、「法律に触れておらず、他者に大きな迷惑をかけず、さらにお互いが同意しているなら何をしてもいい」である。フランスに「50歳男と14歳少女の“恋”」を禁ずる法律があるのかどうかは知らないが、もし無いのであれば、あとは「お互いの同意」次第だろう。そして「その同意が“ちゃんと”成立しているのであれば、『50歳男と14歳少女の“恋”』も許容しよう」と考えているのである。
その上で、この記事でとにかく私が主張したかったのは、「『同意が存在するかどうかの判断』はとても難しい」ということだ。本作で描かれるガブリエル・マツネフはクソ野郎なので、彼を擁護するつもりは一切無い。ただ、「50歳男と14歳少女の“恋”」が本当の意味で成立する可能性だって決してゼロではないと思っている。ただそこには「“ちゃんとした”同意」が必要であり、そしてその判断は非常に難しいので、「まず成立し得ない」と考えておくべきだろう。
特に本作は、ヴァネッサの「告発本」をベースにしている。つまり、「事後的に『同意は存在しなかった』と明らかにされた」という状況なのだ。もちろん先述した通り、「最初は『同意していた』が、次第に『不同意』に変わっていった」みたいなケースもあるだろう。本作で描かれているのも、そのようなパターンだと私は捉えている。そう考えるとやはり、よほどの状況でもない限り、「『一般的に成立しないと思われている同意』はやはり成立しない」と認識しておく必要があると私は思う。
あわせて読みたい
【正義】復讐なんかに意味はない。それでも「この復讐は正しいかもしれない」と思わされる映画:『プロ…
私は基本的に「復讐」を許容できないが、『プロミシング・ヤング・ウーマン』の主人公キャシーの行動は正当化したい。法を犯す明らかにイカれた言動なのだが、その動機は一考の余地がある。何も考えずキャシーを非難していると、矢が自分の方に飛んでくる、恐ろしい作品
監督:ヴァネッサ・フィロ, 出演:キム・イジュラン, 出演:ジャン=ポール・ルーヴ, 出演:レティシア・カスタ, 出演:エロディ・ブシェーズ
¥550 (2025/02/21 22:31時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品視聴済】私が観てきた映画(フィクション)を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が観てきた映画(フィクション)を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。
最後に
さて、「ガブリエル・マツネフがクズであること」に議論の余地は一切ないのだが、それとは別に、「小児性愛者はどう生きていくべきか?」という議論がもう少しあってもいいような気がする。「小児性愛者」の話となるとなかなかイメージしにくいが、例えば「『毒キノコ』以外のすべての食べ物が不味いと感じられる」みたいな状況を想定すると少しは考えやすくなるかもしれない。
あわせて読みたい
【愛】ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督の“衝撃の出世作”である映画『灼熱の魂』の凄さ。何も語りたくない
映画館で流れた予告映像だけで観ることを決め、他になんの情報も知らないまま鑑賞した映画『灼熱の魂』は、とんでもない映画だった。『DUNE/デューン 砂の惑星』『ブレードランナー 2049』など有名作を監督してきたドゥニ・ヴィルヌーヴの衝撃の出世作については、何も語りたくない
もしあなたがそのような状況に置かれたらどうするだろうか? 「毒キノコ」以外のものを食べても、美味しいと感じられないどころか、すべてが不味く感じられてしまう。しかし、唯一「美味しい」と感じられる「毒キノコ」を食べると、最悪死に至るぐらいの症状に襲われるのである。このような状況は絶望的だし、「どう生きたらいいんだろう?」と苦悩させられるはずだ。そして、状況はだいぶ違うかもしれないが、「小児性愛者」もこれとそう大きくは変わらない世界で生きていると言っていいのではないかと思う。だとすれば、それはあまりにもしんどいだろう。だからこそ、「小児性愛者はキモいし死ね」と排除するだけではなく、何らかの対策なり支援なりがあってもいいのかもしれないと思ったりもするのである(どんな可能性があり得るのかはちょっとよく分からないのだが)。
そんなことも考えさせられる物語だった。
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!「それってホントに『コミュ力』が高いって言えるの?」と疑問を感じている方に…
私は、「コミュ力が高い人」に関するよくある主張に、どうも違和感を覚えてしまうことが多くあります。そしてその一番大きな理由が、「『コミュ力が高い人』って、ただ『想像力がない』だけではないか?」と感じてしまう点にあると言っていいでしょう。出版したKindle本は、「ネガティブには見えないネガティブな人」(隠れネガティブ)を取り上げながら、「『コミュ力』って何だっけ?」と考え直してもらえる内容に仕上げたつもりです。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【不寛容】カルトと呼ばれた「イエスの方舟」の現在は?「理解できなければ排除する社会」を斬る映画:…
映画『方舟にのって』は、1980年に社会を騒がせ、「ハーレム教団」「セックスカルト教団」と呼ばれて大問題となった「イエスの方舟」の現在を追うドキュメンタリー映画だ。そして、そんな本作が本当に映し出してるのは「大衆」の方である。「『理解できないもの』は排除する」という社会に対する違和感を改めて浮き彫りにする1作
あわせて読みたい
【狂気】映画『ミッシング』(吉田恵輔監督)は「我が子の失踪」を起点に様々な「嫌な世界」を描く(主…
映画『ミッシング』は、「娘の失踪を機に壊れてしまった母親」を石原さとみが熱演する絶望的な物語である。事件を取材する地元局の記者の葛藤を通じて「『事実』とは何か」「『事実を報じる』ことの難しさ」が突きつけられ、さらに、マスコミを頼るしかない母親の苦悩と相まって状況が混沌とする。ホントに「嫌な世界」だなと思う
あわせて読みたい
【人生】映画『雪子 a.k.a.』は、言葉は出ないが嘘もないラップ好きの小学校教師の悩みや葛藤を描き出す
「小学校教師」と「ラップ」というなかなか異色の組み合わせの映画『雪子 a.k.a.』は、「ここが凄く良かった」と言えるようなはっきりしたポイントはないのに、ちょっと泣いてしまうぐらい良い映画だった。「口下手だけど嘘はない」という主人公・雪子の日常的な葛藤には、多くの人が共感させられるのではないかと思う
あわせて読みたい
【冷戦】”アメリカのビートルズ”と評された、「鉄のカーテンを超えた初のロックバンド」を襲った悲劇:…
映画『ブラッド・スウェット&ティアーズに何が起こったのか?』では、米ソ冷戦の最中に人気を博したロックバンド・BS&Tが辿った数奇な運命を描き出すドキュメンタリー映画である。当時は公表できなかった理由により「鉄のカーテン」の向こう側に行かざるを得なかった彼らは、何を見て、どんな不遇に直面させられたのか?
あわせて読みたい
【洗脳】激しく挑発的だった映画『クラブゼロ』が描く、「食べないこと」を「健康」と言い張る狂気(主…
映画『クラブゼロ』は、「健康的な食事」として「まったく食べないこと」を推奨する女性教師と、彼女に賛同し実践する高校生を描き出す物語。実に狂気的な設定ではあるが、しかし同時に、本作で描かれているのは「日々SNS上で繰り広げられていること」でもある。そんな「現代性」をSNSを登場させずに描き出す、挑発的な作品だ
あわせて読みたい
【狂気】瀧内公美の一人語りのみで展開される映画『奇麗な、悪』の衝撃。凄まじいものを見た(監督:奥…
映画『奇麗な、悪』は、女優・瀧内公美が78分間一人語りするだけの作品で、彼女が放つ雰囲気・存在感に圧倒させられてしまった。誰もいない廃院で、目の前に医師がいるかのように話し続ける主人公の「狂気」が凄まじい。スクリーンの向こう側の出来事なのに、客席で何故か息苦しさを感じたほどの圧巻の演技に打ちのめされた
あわせて読みたい
【正義】名張毒ぶどう酒事件の真相解明の鍵を握る、唯一の再審請求人である妹・岡美代子を追う映画:『…
冤罪と目されている「名張毒ぶどう酒事件」を扱ったドキュメンタリー映画『いもうとの時間』は、逮捕され死刑囚として病死した奥西勝の妹・岡美代子に焦点を当てている。というのも彼女は、「再審請求権」を持つ唯一の人物なのだ。このままでは、事件の真相は闇の中だろう。まずは再審の扉が開かれるべきだと私は思う
あわせて読みたい
【異常】オンラインゲーム『DayZ』内でドキュメンタリー映画を撮るという狂気的な実験が映す人間模様:…
映画『ニッツ・アイランド』は、「『DayZ(デイジー)』というサバイバル・ゲーム内で撮られたドキュメンタリー映画」という斬新すぎる作品だ。「生き物を殺さない集団」「人殺しを楽しんで行う集団」など、ゲーム内の様々なプレイヤーから話を聞きつつ、「ゲーム内の世界は『リアル』なのか?」という問いにも焦点が当てられる
あわせて読みたい
【現実】「食」が危ない!映画『フード・インク ポスト・コロナ』が描く、大企業が操る食べ物の罠
映画『フード・インク ポスト・コロナ』は、主にアメリカの事例を取り上げながら、「私たちが直面している『食』はかなり危険な状態にある」と警告する作品だ。「アメリカ人の摂取カロリーの58%を占める」と言われる「超加工食品」の研究はダイエット的な意味でも興味深いし、寡占企業による様々な弊害は私たちにも関係してくるだろう
あわせて読みたい
【奇妙】映画『画家と泥棒』は、非日常的なきっかけで始まったあり得ないほど奇跡的な関係を描く
映画『画家と泥棒』は、「自身の絵を盗まれた画家が、盗んだ泥棒と親しくなる」という奇妙奇天烈なきっかけから関係性が始まる物語であり、現実に起きたこととは思えないほど不可思議なドキュメンタリーである。アートを通じて奇妙に通じ合う2人の関係性は、ある種の美しささえ感じさせる、とても素晴らしいものに見えた
あわせて読みたい
【絶望】映画『若き見知らぬ者たち』が描くのは”不正解”だが、「じゃあ”正解”って何?」ってなる(監督…
映画『若き見知らぬ者たち』は、「まともな生活が送れなくなった母親の介護」を筆頭に、かなり絶望的な状況に置かれている若者たちを描き出す作品だ。あまりにも不毛で、あまりにも救いがなく、あまりにも辛すぎるその日々は、ついに限界を迎える。そしてその絶望を、磯村勇斗がその凄まじい存在感によって体現していく
あわせて読みたい
【異次元】リアリティ皆無の怪作映画『Cloud クラウド』は、役者の演技でギリ成立している(監督:黒沢…
映画『Cloud クラウド』(黒沢清監督)は、リアリティなどまったく感じさせないかなり異様な作品だった。登場人物のほとんどが「人間っぽくない」のだが、錚々たる役者陣による見事な演技によって、「リアリティ」も「っぽさ」も欠いたまま作品としては成立している。「共感は一切出来ない」と理解した上で観るなら面白いと思う
あわせて読みたい
【天才】映画『箱男』はやはり、安部公房がSNSの無い時代に見通した「匿名性」への洞察が驚異的(監督:…
映画『箱男』は、安部公房本人から映画化権を託されるも一度は企画が頓挫、しかしその後27年の月日を経て完成させた石井岳龍の執念が宿る作品だ。SNSなど無かった時代に生み出された「匿名性」に関する洞察と、「本物とは何か?」という深淵な問いが折り重なるようにして進む物語で、その魅惑的な雰囲気に観客は幻惑される
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『憐れみの3章』(ヨルゴス・ランティモス)は意味不明なのに何故か超絶面白かった(主…
映画『憐れみの3章』(ヨルゴス・ランティモス監督)は、最初から最後まで「意味不明」と言っていいレベルで理解できなかったが、しかし「実に良い映画を観たなぁ」という感覚にさせてもくれる、とても素敵な作品だった。さらに、「3つの異なる物語を同じ役者の組み合わせで撮る」という斬新な構成が上手くハマっていたようにも思う
あわせて読みたい
【狂気】「こんな作品を作ろうと考えて実際世に出した川上さわ、ヤベェな」って感じた映画『地獄のSE』…
私が観た時はポレポレ東中野のみで公開されていた映画『地獄のSE』は、最初から最後までイカれ狂ったゲロヤバな作品だった。久しぶりに出会ったな、こんな狂気的な映画。面白かったけど!「こんなヤバい作品を、多くの人の協力を得て作り公開した監督」に対する興味を強く抱かされた作品で、とにかく「凄いモノを観たな」という感じだった
あわせて読みたい
【宣伝】アポロ計画での月面着陸映像は本当か?映画『フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン』のリアル
「月面着陸映像はニセモノだ」という陰謀論を逆手にとってリアリティのある物語を生み出した映画『フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン』は、「ベトナム戦争で疲弊し、事故続きのNASAが不人気だった」という現実を背景に「歴史のif」を描き出す。「確かにそれぐらいのことはするかもしれない」というリアリティをコメディタッチで展開させる
あわせて読みたい
【評価】高山一実の小説かつアニメ映画である『トラペジウム』は、アイドル作とは思えない傑作(声優:…
原作小説、そしてアニメ映画共に非常に面白かった『トラペジウム』は、高山一実が乃木坂46に在籍中、つまり「現役アイドル」として出版した作品であり、そのクオリティに驚かされました。「現役アイドル」が「アイドル」をテーマにするというド直球さを武器にしつつ、「アイドルらしからぬ感覚」をぶち込んでくる非常に面白い作品である
あわせて読みたい
【感想】B級サメ映画の傑作『温泉シャーク』は、『シン・ゴジラ』的壮大さをバカバカしく描き出す
「温泉に入っているとサメに襲われる」という荒唐無稽すぎる設定のサメ映画『温泉シャーク』は、確かにふざけ倒した作品ではあるものの、観てみる価値のある映画だと思います。サメの生態を上手く利用した設定や、「伏線回収」と表現していいだろう展開などが巧みで、細かなことを気にしなければ、そのバカバカしさを楽しめるはずです
あわせて読みたい
【恋心】映画『サッドティー』は、「『好き』を巡ってウロウロする人々」を描く今泉力哉節全開の作品だった
映画『サッドティー』は、今泉力哉らしい「恋愛の周辺でグルグルする人たち」を描き出す物語。関係性が微妙に重なる複数の人間を映し出す群像劇の中で、「『好き』のややこしさ」に焦点を当てていく構成はさすがです。実に奇妙な展開で終わる物語ですが、それでもなお「リアルだ」と感じさせる雰囲気は、まるで魔法のようでした
あわせて読みたい
【感想】映画『ルックバック』の衝撃。創作における衝動・葛藤・苦悩が鮮やかに詰め込まれた傑作(原作…
アニメ映画『ルックバック』は、たった58分の、しかもセリフも動きも相当に抑制された「静」の映画とは思えない深い感動をもたらす作品だった。漫画を描くことに情熱を燃やす2人の小学生が出会ったことで駆動する物語は、「『創作』に限らず、何かに全力で立ち向かったことがあるすべての人」の心を突き刺していくはずだ
あわせて読みたい
【解説】映画『スターフィッシュ』をネタバレ全開で考察。主人公が直面する”奇妙な世界”の正体は?
映画『スターフィッシュ』は、「親友の葬儀」とそれに続く「不法侵入」の後、唐突に「意味不明な世界観」に突入していき、その状態のまま物語が終わってしまう。解釈が非常に難しい物語だが、しかし私なりの仮説には辿り着いた。そこでこの記事では、ネタバレを一切気にせずに「私が捉えた物語」について解説していくことにする
あわせて読みたい
【常識】群青いろ制作『彼女はなぜ、猿を逃したか?』は、凄まじく奇妙で、実に魅力的な映画だった(主…
映画『彼女はなぜ、猿を逃したか?』(群青いろ制作)は、「絶妙に奇妙な展開」と「爽快感のあるラスト」の対比が魅力的な作品。主なテーマとして扱われている「週刊誌報道からのネットの炎上」よりも、私は「週刊誌記者が無意識に抱いている思い込み」の方に興味があったし、それを受け流す女子高生の受け答えがとても素敵だった
あわせて読みたい
【幻惑】映画『フォロウィング』の衝撃。初監督作から天才だよ、クリストファー・ノーラン
クリストファー・ノーランのデビュー作であり、多数の賞を受賞し世界に衝撃を与えた映画『フォロウィング』には、私も驚かされてしまった。冒頭からしばらくの間「何が描かれているのかさっぱり理解できない」という状態だったのに、ある瞬間一気に視界が晴れたように状況が理解できたのだ。脚本の力がとにかく圧倒的だった
あわせて読みたい
【実話】さかなクンの若い頃を描く映画『さかなのこ』(沖田修一)は子育ての悩みを吹き飛ばす快作(主…
映画『さかなのこ』は、兎にも角にものん(能年玲奈)を主演に据えたことが圧倒的に正解すぎる作品でした。性別が違うのに、「さかなクンを演じられるのはのんしかいない!」と感じさせるほどのハマり役で、この配役を考えた人は天才だと思います。「母親からの全肯定」を濃密に描き出す、子どもと関わるすべての人に観てほしい作品です
あわせて読みたい
【衝撃】広末涼子映画デビュー作『20世紀ノスタルジア』は、「広末が異常にカワイイ」だけじゃない作品
広末涼子の映画デビュー・初主演作として知られる『20世紀ノスタルジア』は、まず何よりも「広末涼子の可愛さ」に圧倒される作品だ。しかし、決してそれだけではない。初めは「奇妙な設定」ぐらいにしか思っていなかった「宇宙人に憑依されている」という要素が、物語全体を実に上手くまとめている映画だと感じた
あわせて読みたい
【感想】アニメ映画『パーフェクトブルー』(今敏監督)は、現実と妄想が混在する構成が少し怖い
本作で監督デビューを果たした今敏のアニメ映画『パーフェクトブルー』は、とにかくメチャクチャ面白かった。現実と虚構の境界を絶妙に壊しつつ、最終的にはリアリティのある着地を見せる展開で、25年以上も前の作品だなんて信じられない。今でも十分通用するだろうし、81分とは思えない濃密さに溢れた見事な作品である
あわせて読みたい
【映画】ウォン・カーウァイ4Kレストア版の衝撃!『恋する惑星』『天使の涙』は特にオススメ!
『恋する惑星』『天使の涙』で一躍その名を世界に知らしめた巨匠ウォン・カーウァイ作品の4Kレストア版5作品を劇場で一気見した。そして、監督の存在さえまったく知らずに観た『恋する惑星』に圧倒され、『天使の涙』に惹きつけられ、その世界観に驚かされたのである。1990年代の映画だが、現在でも通用する凄まじい魅力を放つ作品だ
あわせて読みたい
【奇妙】映画『鯨の骨』は、主演のあのちゃんが絶妙な存在感を醸し出す、斬新な設定の「推し活」物語
映画『鯨の骨』は、主演を務めたあのちゃんの存在感がとても魅力的な作品でした。「AR動画のカリスマ的存在」である主人公を演じたあのちゃんは、役の設定が絶妙だったこともありますが、演技がとても上手く見え、また作品全体の、「『推し活』をある意味で振り切って描き出す感じ」もとても皮肉的で良かったです
あわせて読みたい
【あらすじ】声優の幾田りらとあのちゃんが超絶良い!アニメ映画『デデデデ』はビビるほど面白い!:『…
幾田りらとあのちゃんが声優を務めた映画『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』は、とにかく最高の物語だった。浅野いにおらしいポップさと残酷さを兼ね備えつつ、「終わってしまった世界でそれでも生きていく」という王道的展開を背景に、門出・おんたんという女子高生のぶっ飛んだ関係性が描かれる物語が見事すぎる
あわせて読みたい
【ル・マン】ゲーマーが本物のカーレース出場!映画『グランツーリスモ』が描く衝撃的すぎる軌跡(ヤン…
映画『グランツーリスモ』は、「ゲーマーをレーサーにする」という、実際に行われた無謀すぎるプロジェクトを基にした作品だ。登場人物は全員イカれていると感じたが、物語としてはシンプルかつ王道で、誰もが先の展開を予想出来るだろう。しかしそれでも、圧倒的に面白かった、ちょっと凄まじすぎる映画だった
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『レザボア・ドッグス』(タランティーノ監督)はとにかく驚異的に脚本が面白い!
クエンティン・タランティーノ初の長編監督作『レザボア・ドッグス』は、のけぞるほど面白い映画だった。低予算という制約を逆手に取った「会話劇」の構成・展開があまりにも絶妙で、舞台がほぼ固定されているにも拘らずストーリーが面白すぎる。天才はやはり、デビュー作から天才だったのだなと実感させられた
あわせて読みたい
【天才】映画『笑いのカイブツ』のモデル「伝説のハガキ職人ツチヤタカユキ」の狂気に共感させられた
『「伝説のハガキ職人」として知られるツチヤタカユキの自伝的小説を基にした映画『笑いのカイブツ』は、凄まじい狂気に彩られた作品だった。「お笑い」にすべてを捧げ、「お笑い」以外はどうでもいいと考えているツチヤタカユキが、「コミュ力」や「人間関係」で躓かされる”理不尽”な世の中に、色々と考えさせられる
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『千年女優』(今敏)はシンプルな物語を驚愕の演出で味付けした天才的アニメ作品
今敏監督の映画『千年女優』は、ちょっとびっくりするほど凄まじく面白い作品だった。観ればスッと理解できるのに言葉で説明すると難解になってしまう「テクニカルな構成」に感心させられつつ、そんな構成に下支えされた「物語の感性的な部分」がストレートに胸を打つ、シンプルながら力強い作品だ
あわせて読みたい
【痛快】精神病院の隔離室から脱した、善悪の判断基準を持たない狂気の超能力者が大暴れする映画:『モ…
モナ・リザ アンド ザ ブラッドムーン』は、「10年以上拘束され続けた精神病院から脱走したアジア系女性が、特殊能力を使って大暴れする」というムチャクチャな設定の物語なのだが、全編に通底する「『善悪の判断基準』が歪んでいる」という要素がとても見事で、意味不明なのに最後まで惹きつけられてしまった
あわせて読みたい
【理解】「多様性を受け入れる」とか言ってるヤツ、映画『炎上する君』でも観て「何も見てない」って知…
西加奈子の同名小説を原作とした映画『炎上する君』(ふくだももこ監督)は、「多様性」という言葉を安易に使いがちな世の中を挑発するような作品だ。「見えない存在」を「過剰に装飾」しなければならない現実と、マジョリティが無意識的にマイノリティを「削る」リアルを描き出していく
あわせて読みたい
【映画】ストップモーションアニメ『マルセル 靴をはいた小さな貝』はシンプルでコミカルで面白い!
靴を履いた体長2.5センチの貝をコマ撮りで撮影したストップモーション映画『マルセル 靴をはいた小さな貝』は、フェイクドキュメンタリーの手法で描き出すリアリティ満載の作品だ。謎の生き物が人間用の住居で工夫を凝らしながら生活する日常を舞台にした、感情揺さぶる展開が素晴らしい
あわせて読みたい
【歴史】NIKEのエアジョーダン誕生秘話!映画『AIR/エア』が描くソニー・ヴァッカロの凄さ
ナイキがマイケル・ジョーダンと契約した時、ナイキは「バッシュ業界3位」であり、マイケル・ジョーダンも「ドラフト3位選手」だった。今からは信じられないだろう。映画『AIR/エア』は、「劣勢だったナイキが、いかにエアジョーダンを生み出したか」を描く、実話を基にした凄まじい物語だ
あわせて読みたい
【実話】「更生」とは何かを考えさせられる、演劇『ゴドーを待ちながら』を組み込んだ映画『アプローズ…
売れない舞台役者が、刑務所内で囚人に戯曲『ゴドーを待ちながら』の演技指導を行う映画『アプローズ、アプローズ!』は、その衝撃的なラストが実に印象的だ。しかもこのラストの展開は、実話を基にしている。喝采(アプローズ)を浴びる囚人たちの姿から、「更生」についても考えさせられる作品
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『四畳半タイムマシンブルース』超面白い!森見登美彦も上田誠も超天才だな!
ヨーロッパ企画の演劇『サマータイムマシン・ブルース』の物語を、森見登美彦の『四畳半神話大系』の世界観で描いたアニメ映画『四畳半タイムマシンブルース』は、控えめに言って最高だった。ミニマム過ぎる設定・物語を突き詰め、さらにキャラクターが魅力的だと、これほど面白くなるのかというお手本のような傑作
あわせて読みたい
【感想】どんな話かわからない?難しい?ジブリ映画『君たちはどう生きるか』の考察・解説は必要?(監…
宮崎駿最新作であるジブリ映画『君たちはどう生きるか』は、宮崎アニメらしいファンタジックな要素を全開に詰め込みつつ、「生と死」「創造」についても考えさせる作品だ。さらに、「自分の頭の中から生み出されたものこそ『正解』」という、創造物と向き合う際の姿勢についても問うているように思う
あわせて読みたい
【感想】映画『すずめの戸締まり』(新海誠)は、東日本大震災後を生きる私達に「逃げ道」をくれる(松…
新海誠監督の『すずめの戸締まり』は、古代神話的な設定を現代のラブコメに組み込みながら、あまりに辛い現実を生きる人々に微かな「逃げ道」を指し示してくれる作品だと思う。テーマ自体は重いが、恋愛やコメディ要素とのバランスがとても良く、ロードムービー的な展開もとても魅力的
あわせて読みたい
【天才】映画『リバー、流れないでよ』は、ヨーロッパ企画・上田誠によるタイムループの新発明だ
ヨーロッパ企画の上田誠が生み出した、タイムループものの新機軸映画『リバー、流れないでよ』は、「同じ2分間が繰り返される」という斬新すぎる物語。その設定だけ聞くと、「どう物語を展開させるんだ?」と感じるかもしれないが、あらゆる「制約」を押しのけて、とんでもない傑作に仕上がっている
あわせて読みたい
【感動】円井わん主演映画『MONDAYS』は、タイムループものの物語を革新する衝撃的に面白い作品だった
タイムループという古びた設定と、ほぼオフィスのみという舞台設定を駆使した、想像を遥かに超えて面白かった映画『MONDAYS』は、テンポよく進むドタバタコメディでありながら、同時に、思いがけず「感動」をも呼び起こす、竹林亮のフィクション初監督作品
あわせて読みたい
【驚異】映画『RRR』『バーフバリ』は「観るエナジードリンク」だ!これ程の作品にはなかなか出会えないぞ
2022年に劇場公開されるや、そのあまりの面白さから爆発的人気を博し、現在に至るまでロングラン上映が続いている『RRR』と、同監督作の『バーフバリ』は、大げさではなく「全人類にオススメ」と言える超絶的な傑作だ。まだ観ていない人がいるなら、是非観てほしい!
あわせて読みたい
【感想】映画『君が世界のはじまり』は、「伝わらない」「分かったフリをしたくない」の感情が濃密
「キラキラした青春学園モノ」かと思っていた映画『君が世界のはじまり』は、「そこはかとない鬱屈」に覆われた、とても私好みの映画だった。自分の決断だけではどうにもならない「現実」を前に、様々な葛藤渦巻く若者たちの「諦念」を丁寧に描き出す素晴らしい物語
あわせて読みたい
【解説】実話を基にした映画『シカゴ7裁判』で知る、「権力の暴走」と、それに正面から立ち向かう爽快さ
ベトナム戦争に反対する若者たちによるデモと、その後開かれた裁判の実話を描く『シカゴ7裁判』はメチャクチャ面白い映画だった。無理筋の起訴を押し付けられる主席検事、常軌を逸した言動を繰り返す不適格な判事、そして一枚岩にはなれない被告人たち。魅力満載の1本だ
あわせて読みたい
【感想】のん主演映画『私をくいとめて』から考える、「誰かと一緒にいられれば孤独じゃないのか」問題
のん(能年玲奈)が「おひとり様ライフ」を満喫する主人公を演じる映画『私をくいとめて』を観て、「孤独」について考えさせられた。「誰かと関わっていられれば孤独じゃない」という考えに私は賛同できないし、むしろ誰かと一緒にいる時の方がより強く孤独を感じることさえある
あわせて読みたい
【考察】映画『哀愁しんでれら』から、「正しい」より「間違ってはいない」を選んでしまう人生を考える
「シンデレラストーリー」の「その後」を残酷に描き出す映画『哀愁しんでれら』は、「幸せになりたい」という気持ちが結果として「幸せ」を遠ざけてしまう現実を描き出す。「正しい/間違ってはいない」「幸せ/不幸せではない」を区別せずに行動した結果としての悲惨な結末
あわせて読みたい
【感想】湯浅政明監督アニメ映画『犬王』は、実在した能楽師を”異形”として描くスペクタクル平家物語
観るつもりなし、期待値ゼロ、事前情報ほぼ皆無の状態で観た映画『犬王』(湯浅政明監督)はあまりにも凄まじく、私はこんなとんでもない傑作を見逃すところだったのかと驚愕させられた。原作の古川日出男が紡ぐ狂気の世界観に、リアルな「ライブ感」が加わった、素晴らしすぎる「音楽映画」
あわせて読みたい
【衝撃】「仕事の意味」とは?天才・野崎まどが『タイタン』で描く「仕事をしなくていい世界」の危機
「仕事が存在しない世界」は果たして人間にとって楽園なのか?万能のAIが人間の仕事をすべて肩代わりしてくれる世界を野崎まどが描く『タイタン』。その壮大な世界観を通じて、現代を照射する「仕事に関する思索」が多数登場する、エンタメ作品としてもド級に面白い傑作SF小説
あわせて読みたい
【無謀】園子温が役者のワークショップと同時並行で撮影した映画『エッシャー通りの赤いポスト』の”狂気”
「園子温の最新作」としか知らずに観に行った映画『エッシャー通りの赤いポスト』は、「ワークショップ参加者」を「役者」に仕立て、ワークショップと同時並行で撮影されたという異次元の作品だった。なかなか経験できないだろう、「0が1になる瞬間」を味わえる“狂気”の映画
あわせて読みたい
【感想】映画『先生、私の隣に座っていただけませんか?』は、「リアル」と「漫画」の境界の消失が絶妙
映画『先生、私の隣に座っていただけませんか?』は、「マンガ家夫婦の不倫」という設定を非常に上手く活かしながら、「何がホントで何かウソなのかはっきりしないドキドキ感」を味わわせてくれる作品だ。黒木華・柄本佑の演技も絶妙で、良い映画を観たなぁと感じました
あわせて読みたい
【矛盾】法律の”抜け穴”を衝く驚愕の小説。「ルールを通り抜けたものは善」という発想に潜む罠:『法廷…
完璧なルールは存在し得ない。だからこそ私たちは、矛盾を内包していると理解しながらルールを遵守する必要がある。「ルールを通り抜けたものは善」という”とりあえずの最善解”で社会を回している私たちに、『法廷遊戯』は「世界を支える土台の脆さ」を突きつける
あわせて読みたい
【感想】映画『竜とそばかすの姫』が描く「あまりに批判が容易な世界」と「誰かを助けることの難しさ」
SNSの登場によって「批判が容易な社会」になったことで、批判を恐れてポジティブな言葉を口にしにくくなってしまった。そんな世の中で私は、「理想論だ」と言われても「誰かを助けたい」と発信する側の人間でいたいと、『竜とそばかすの姫』を観て改めて感じさせられた
あわせて読みたい
【正義】復讐なんかに意味はない。それでも「この復讐は正しいかもしれない」と思わされる映画:『プロ…
私は基本的に「復讐」を許容できないが、『プロミシング・ヤング・ウーマン』の主人公キャシーの行動は正当化したい。法を犯す明らかにイカれた言動なのだが、その動機は一考の余地がある。何も考えずキャシーを非難していると、矢が自分の方に飛んでくる、恐ろしい作品
あわせて読みたい
【驚愕】これ以上の”サバイバル映画”は存在するか?火星にたった一人残された男の生存術と救出劇:『オ…
1人で火星に取り残された男のサバイバルと救出劇を、現実的な科学技術の範囲で描き出す驚異の映画『オデッセイ』。不可能を可能にするアイデアと勇気、自分や他人を信じ抜く気持ち、そして極限の状況でより困難な道を進む決断をする者たちの、想像を絶するドラマに胸打たれる
あわせて読みたい
【感想】B級サメ映画の傑作『温泉シャーク』は、『シン・ゴジラ』的壮大さをバカバカしく描き出す
「温泉に入っているとサメに襲われる」という荒唐無稽すぎる設定のサメ映画『温泉シャーク』は、確かにふざけ倒した作品ではあるものの、観てみる価値のある映画だと思います。サメの生態を上手く利用した設定や、「伏線回収」と表現していいだろう展開などが巧みで、細かなことを気にしなければ、そのバカバカしさを楽しめるはずです
あわせて読みたい
【死】映画『湯を沸かすほどの熱い愛』に号泣。「家族とは?」を問う物語と、タイトル通りのラストが見事
「死は特別なもの」と捉えてしまうが故に「日常感」が失われ、普段の生活から「排除」されているように感じてしまうのは私だけではないはずだ。『湯を沸かすほどの熱い愛』は、「死を日常に組み込む」ことを当たり前に許容する「家族」が、「家族」の枠組みを問い直す映画である
あわせて読みたい
【世界観】映画『夜は短し歩けよ乙女』の”黒髪の乙女”は素敵だなぁ。ニヤニヤが止まらない素晴らしいアニメ
森見登美彦の原作も大好きな映画『夜は短し歩けよ乙女』は、「リアル」と「ファンタジー」の境界を絶妙に漂う世界観がとても好き。「黒髪の乙女」は、こんな人がいたら好きになっちゃうよなぁ、と感じる存在です。ずっとニヤニヤしながら観ていた、とても大好きな映画
あわせて読みたい
【差別】才ある者の能力を正しく引き出す者こそ最も有能であり、偏見から能力を評価できない者は無能だ…
「偏見・差別ゆえに、他人の能力を活かせない人間」を、私は無能だと感じる。そういう人は、現代社会の中にも結構いるでしょう。ソ連との有人宇宙飛行競争中のNASAで働く黒人女性を描く映画『ドリーム』から、偏見・差別のない社会への道筋を考える
あわせて読みたい
【考察】生きづらい性格は変わらないから仮面を被るしかないし、仮面を被るとリア充だと思われる:『勝…
「リア充感」が滲み出ているのに「生きづらさ」を感じてしまう人に、私はこれまでたくさん会ってきた。見た目では「生きづらさ」は伝わらない。24年間「リアル彼氏」なし、「脳内彼氏」との妄想の中に生き続ける主人公を描く映画『勝手にふるえてろ』から「こじらせ」を知る
あわせて読みたい
【あらすじ】濱口竜介監督『偶然と想像』は、「脚本」と「役者」のみで成り立つ凄まじい映画。天才だと思う
「映画」というメディアを構成する要素は多々あるはずだが、濱口竜介監督作『偶然と想像』は、「脚本」と「役者」だけで狂気・感動・爆笑を生み出してしまう驚異の作品だ。まったく異なる3話オムニバス作品で、どの話も「ずっと観ていられる」と感じるほど素敵だった
あわせて読みたい
【実話】障害者との接し方を考えさせる映画『こんな夜更けにバナナかよ』から”対等な関係”の大事さを知る
「障害者だから◯◯だ」という決まりきった捉え方をどうしてもしてしまいがちですが、『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』の主人公・鹿野靖明の生き様を知れば、少しは考え方が変わるかもしれません。筋ジストロフィーのまま病院・家族から離れて“自活”する決断をした驚異の人生
あわせて読みたい
【漫画原作】映画『殺さない彼と死なない彼女』は「ステレオタイプな人物像」の化学反応が最高に面白い
パッと見の印象は「よくある学園モノ」でしかなかったので、『殺さない彼と死なない彼女』を観て驚かされた。ステレオタイプで記号的なキャラクターが、感情が無いとしか思えないロボット的な言動をする物語なのに、メチャクチャ面白かった。設定も展開も斬新で面白い
あわせて読みたい
【人生】どう生きるべきかは、どう死にたいかから考える。死ぬ直前まで役割がある「理想郷」を描く:『…
「近隣の村から『姥捨て』と非難される理想郷」を描き出す『でんでら国』は、「死ぬ直前まで、コミュニティの中で役割が存在する」という世界で展開される物語。「お金があっても決して豊かとは言えない」という感覚が少しずつ広まる中で、「本当の豊かさ」とは何かを考える
あわせて読みたい
【あらすじ】天才とは「分かりやすい才能」ではない。前進するのに躊躇する暗闇で直進できる勇気のこと…
ピアノのコンクールを舞台に描く『蜜蜂と遠雷』は、「天才とは何か?」と問いかける。既存の「枠組み」をいとも簡単に越えていく者こそが「天才」だと私は思うが、「枠組み」を安易に設定することの是非についても刃を突きつける作品だ。小説と映画の感想を一緒に書く
あわせて読みたい
【正義】マイノリティはどう生き、どう扱われるべきかを描く映画。「ルールを守る」だけが正解か?:映…
社会的弱者が闘争の末に権利を勝ち取ってきた歴史を知った上で私は、闘わずとも権利が認められるべきだと思っている。そして、そういう社会でない以上、「正義のためにルールを破るしかない」状況もある。映画『パブリック』から、ルールと正義のバランスを考える
あわせて読みたい
【映画】『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』で号泣し続けた私はTVアニメを観ていない
TVアニメは観ていない、というかその存在さえ知らず、物語や登場人物の設定も何も知らないまま観に行った映画『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』に、私は大号泣した。「悪意のない物語」は基本的に好きではないが、この作品は驚くほど私に突き刺さった
あわせて読みたい
【天才】諦めない人は何が違う?「努力を努力だと思わない」という才能こそが、未来への道を開く:映画…
どれだけ「天賦の才能」に恵まれていても「努力できる才能」が無ければどこにも辿り着けない。そして「努力できる才能」さえあれば、仮に絶望の淵に立たされることになっても、立ち上がる勇気に変えられる。映画『マイ・バッハ』で知る衝撃の実話
あわせて読みたい
【難しい】映画『鳩の撃退法』をネタバレ全開で考察。よくわからない物語を超詳細に徹底解説していく
とても難しくわかりにくい映画『鳩の撃退法』についての考察をまとめていたら、1万7000字を超えてしまった。「東京編で起こったことはすべて事実」「富山編はすべてフィクションかもしれない」という前提に立ち、「津田伸一がこの小説を書いた動機」まで掘り下げて、実際に何が起こっていたのかを解説する(ちなみに、「実話」ではないよ)
あわせて読みたい
【解説】「小説のお約束」を悉く無視する『鳩の撃退法』を読む者は、「読者の椅子」を下りるしかない
佐藤正午『鳩の撃退法』は、小説家である主人公・津田が、”事実”をベースに、起こったかどうか分からない事柄を作家的想像力で埋める物語であり、「小説のお約束を逸脱しています」というアナウンスが作品内部から発せられるが故に、読者は「読者の椅子」を下りざるを得ない
あわせて読みたい
【排除】「分かり合えない相手」だけが「間違い」か?想像力の欠如が生む「無理解」と「対立」:映画『…
「共感」が強すぎる世の中では、自然と「想像力」が失われてしまう。そうならないようにと意識して踏ん張らなければ、他人の価値観を正しく認めることができない人間になってしまうだろう。映画『ミセス・ノイズィ』から、多様な価値観を排除しない生き方を考える
あわせて読みたい
【驚異】プロジェクトマネジメントの奇跡。ハリウッドの制作費以下で火星に到達したインドの偉業:映画…
実は、「一発で火星に探査機を送り込んだ国」はインドだけだ。アメリカもロシアも何度も失敗している。しかもインドの宇宙開発予算は大国と比べて圧倒的に低い。なぜインドは偉業を成し遂げられたのか?映画『ミッション・マンガル』からプロジェクトマネジメントを学ぶ
あわせて読みたい
【解説】テネットの回転ドアの正体を分かりやすく考察。「時間逆行」ではなく「物質・反物質反転」装置…
クリストファー・ノーラン監督の映画『TENET/テネット』は、「陽電子」「反物質」など量子力学の知見が満載です。この記事では、映画の内容そのものではなく、時間反転装置として登場する「回転ドア」をメインにしつつ、時間逆行の仕組みなど映画全体の設定について科学的にわかりやすく解説していきます
あわせて読みたい
【実話】仕事のやりがいは、「頑張るスタッフ」「人を大切にする経営者」「健全な商売」が生んでいる:…
メガネファストファッションブランド「オンデーズ」の社長・田中修治が経験した、波乱万丈な経営再生物語『破天荒フェニックス』をベースに、「仕事の目的」を見失わず、関わるすべての人に存在価値を感じさせる「働く現場」の作り方
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
あわせて読みたい
【前進】誰とも価値観が合わない…。「普通」「当たり前」の中で生きることの難しさと踏み出し方:『出会…
生きていると、「常識的な考え方」に囚われたり、「普通」「当たり前」を無自覚で強要してくる人に出会ったりします。そういう価値観に合わせられない時、自分が間違っている、劣っていると感じがちですが、そういう中で一歩踏み出す勇気を得るための考え方です
ルシルナ
苦しい・しんどい【本・映画の感想】 | ルシルナ
生きていると、しんどい・悲しいと感じることも多いでしょう。私も、世の中の「当たり前」に馴染めなかったり、みんなが普通にできることが上手くやれずに苦しい思いをする…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…







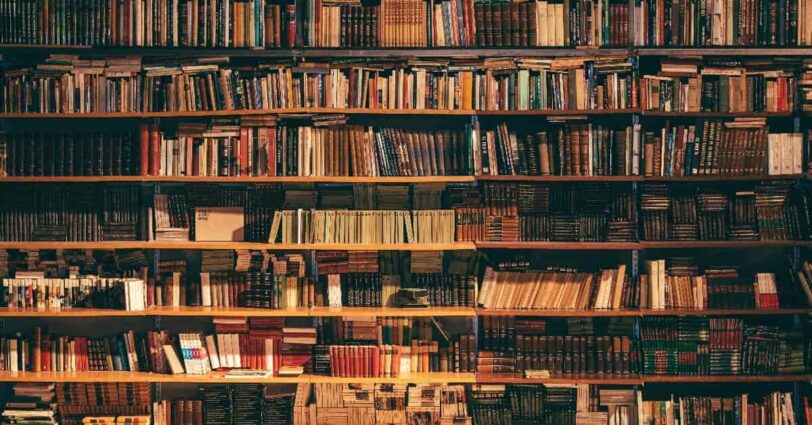










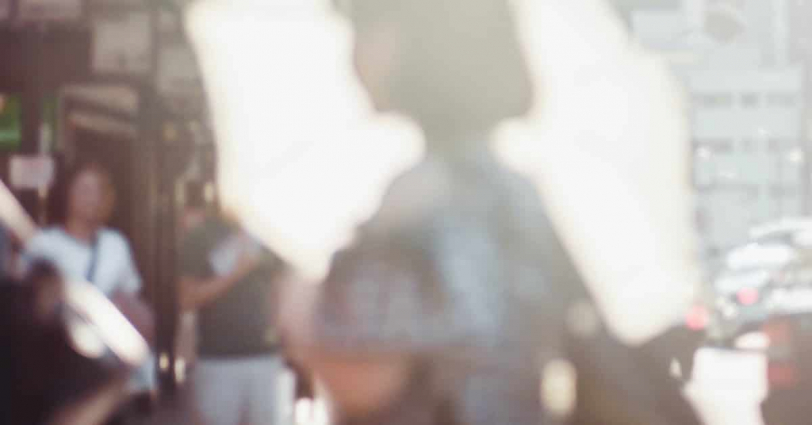

























































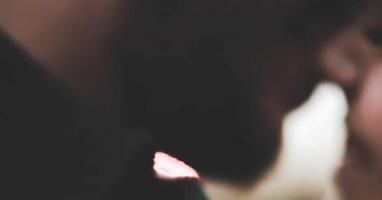












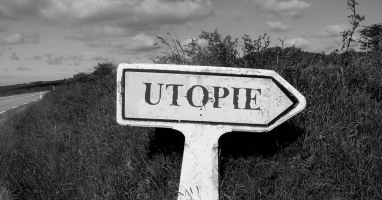



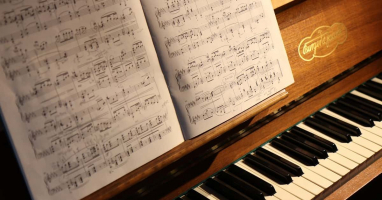
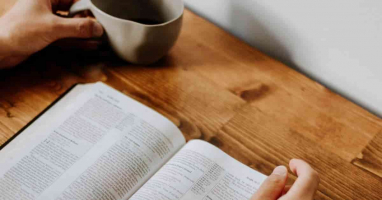


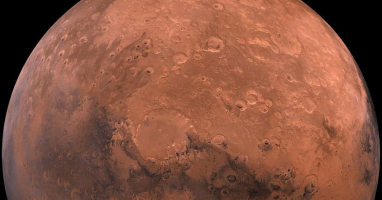












コメント