目次
はじめに
この記事で取り上げる本
著:高橋昌一郎
¥825 (2022/02/09 20:47時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
著:高橋昌一郎
¥715 (2022/02/09 20:48時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
講談社
¥1,100 (2022/02/09 20:48時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
この本をガイドにしながら記事を書いていきます
この記事の3つの要点
- 科学・哲学・経済・生命など様々な分野の話が展開される『理性の限界』『知性の限界』『感性の限界』の3作を一気に紹介する
- 「専門家と一般人が架空のシンポジウムで議論する」というスタイルがもの凄く読みやすい
- どの順番で読んでもいいので、気になった巻から手に取ってみてほしい
「存在さえ知らない事柄」を理解することはできない。本書は「未知の考え・議論の存在」を知るのに有効な1冊だ
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!「文章の書き方が分からない」「文章力がないから鍛えたい」という方にオススメ…
「文章の書き方」についてのKindle本を出版しました。「文章が書けない」「どう書いたらいいか分からない」「文章力を向上させたい」という方の悩みを解消できるような本に仕上げたつもりです。数多くの文章を書き、さらに頼まれて文章を推敲してきた経験を踏まえ、「文章を書けるようになるにはどうしたらいいか」についての私なりの考えをまとめました。
高橋昌一郎「限界シリーズ」3作『理性の限界』『知性の限界』『感性の限界』を一気に紹介。人間の「理性・知性・感性」の限界を認識しておこう
あわせて読みたい
【知的】「BLって何?」という初心者に魅力を伝える「腐男子」の「BLの想像力と創造力」講座:『ボクた…
「BLは知的遊戯である」という主張には「は?」と感じてしまうでしょうが、本書『ボクたちのBL論』を読めばその印象は変わるかもしれません。「余白の発見と補完」を通じて、「ありとあらゆる2者の間の関係性を解釈する」という創造性は、現実世界にどのような影響を与えているのか
この記事では、『理性の限界』『知性の限界』『感性の限界』という、いわゆる「限界シリーズ」3作を一気に紹介する。タイトルの字面も、「講談社現代新書」から出版されているという事実も、なんとなく「難しさ」を感じさせるかもしれないが、そんなことはない。後で詳しく触れるが、「会話形式」になっており、見た目の印象とは大きく違って非常に読みやすい作品だ。

テーマも多岐に渡り、「科学」「数学」のような理系分野から「言語」「思考」、あるいは「愛」「自由」など様々な領域の話題に触れられていく。特定の話に留まらず、複数の分野の話題をシンプルにまとめているので、「特定の知識について知りたい」という動機ではなく、「知的好奇心を味わいたい」という気分で読むことをオススメする。
あわせて読みたい
【興奮】飲茶氏が西洋哲学を語る。難解な思想が「グラップラー刃牙成分」の追加で驚異的な面白さに:『…
名前は聞いたことはあるがカントやニーチェがどんな主張をしたのかは分からないという方は多いだろう。私も無知なまったくの初心者だが、そんな人でも超絶分かりやすく超絶面白く西洋哲学を”分かった気になれる”飲茶『史上最強の哲学入門』は、入門書として最強
それまでの「限界シリーズ」と同じように、本書の最大の目標は、なによりも読者に知的刺激を味わっていただくことにある。
「感性の限界」(高橋昌一郎/講談社)
読む順番は、出版順である必要はない。興味のある巻から読んでもらって大丈夫だ。どれか1冊読み、その議論のスタイルが気に入れば、関心の持てないテーマだとしても別の作品も読んでみよう。テーマとして設定されている話題以外にも様々な話が盛りだくさんなので、メインテーマだけで判断するのはもったいないと思う。
「架空のシンポジウム」という設定
あわせて読みたい
【感想】飲茶の超面白い東洋哲学入門書。「本書を読んでも東洋哲学は分からない」と言う著者は何を語る…
東洋哲学というのは、「最終回しか存在しない連続ドラマ」のようなものだそうだ。西洋哲学と比較にならないほど異質さと、インド哲学・中国哲学など個別の思想を恐ろしく分かりやすく描く『史上最強の哲学入門 東洋の哲人たち』は、ページをめくる手が止まらないくらい、史上最強レベルに面白かった
本書の最大の特徴は、様々な人物が「架空のシンポジウム」で話しているという設定で議論が展開されることだ。これが、難しいテーマを扱いながら読みやすい作品に仕上がっている最大の要因と言えるだろう。

シンポジウムという設定なので、「論理学者」「数理経済学者」「科学主義者」「軍事評論家」「急進的フェミニスト」など、堅い肩書きを持つ人も当然出てくる。しかしそれだけではない。本書には、一般人代表として、「会社員」や「学生A」といった人物も出てくるのだ。
議論はこんな風に展開する。専門家がある話題を出し、それに別の専門家が批判を繰り出す。と同時に、「会社員」や「学生A」が、そもそもそれってどういうことなんですか? と素朴な疑問をぶつけていく。「司会者」がきちんと議論を采配しながら、参加者みんなであーでもないこーでもないと意見や疑問をぶつけ合うスタイルなのだ。
あわせて読みたい
【興奮】世界的大ベストセラー『サピエンス全史』要約。人類が文明を築き上げるに至った3つの革命とは?
言わずと知れた大ベストセラー『サピエンス全史』は、「何故サピエンスだけが人類の中で生き残り、他の生物が成し得なかった歴史を歩んだのか」を、「認知革命」「農業革命」「科学革命」の3つを主軸としながら解き明かす、知的興奮に満ち溢れた1冊
『理性の限界』で初めてこの構成に触れた時には衝撃を受けた。
私は、科学・数学・哲学などの分野が好きなのだが、決してそれらをするっと理解できるほど頭が良いわけではない。いわゆる「下手の横好き」であり、好きだが決して得意ではないのだ。
だから、「科学者や哲学者が一般向けに書いた本」でも難しく感じることが結構多い。
もちろん、そういう専門家の中にも、異常に読みやすい文章を書いてくれる人はいる。しかし、みんながみんなそうではない。どうしても、基本的な知識やある程度以上の理解力がないと読めない本もあって、なかなか苦労させられてしまう。
あわせて読みたい
【驚異】ガイア理論の提唱者が未来の地球を語る。100歳の主張とは思えない超絶刺激に満ちた内容:『ノヴ…
「地球は一種の生命体だ」という主張はかなり胡散臭い。しかし、そんな「ガイア理論」を提唱する著者は、数々の賞や学位を授与される、非常に良く知られた科学者だ。『ノヴァセン <超知能>が地球を更新する』から、AIと人類の共存に関する斬新な知見を知る
しかしこのシリーズのようなスタイルだと、扱われている内容が高度でも、議論の進め方が非常に秀逸なので、割とすんなり理解できる。特に、「会社員」や「学生A」が、読者が疑問に感じる部分を先回りで質問してくれるので、とてもありがたい。
本書は、このようなスタイルの本であるため、個々の話題についてそこまで深堀りはされない。しかし、本書を読んだ後でそれぞれの話題の入門書に進めば、理解度は格段にアップするだろうと思う。
「何かを知る」ためにはそもそも、「その『何か』が存在していること」を認識しなければならない。しかし本書で扱われるテーマの多くはそもそもその存在を知る機会が少ないものだと思う。また、「愛」「自由」といった普遍的なテーマも取り上げられるが、それらに対してどのような知見・議論が存在するのかを知らないことも多いだろう。
だからこそ、まずは「この世の中に何が存在するのか」を知ることが大事だ。深堀りするかどうかはそこから考えればいい。
あわせて読みたい
【人生】「資本主義の限界を埋める存在としての『贈与論』」から「不合理」に気づくための生き方を知る…
「贈与論」は簡単には理解できないが、一方で、「何かを受け取ったら、与えてくれた人に返す」という「交換」の論理では対処できない現実に対峙する力ともなる。『世界は贈与でできている』から「贈与」的な見方を理解し、「受取人の想像力」を立ち上げる
そういう、「存在を知る」という意味で、本書ほど秀逸な作品はなかなかないだろう。
それではここから、3作それぞれにおいてメインとなるテーマや、私が面白いと思った話題について個々に触れていくことにする。この記事では当然「架空のシンポジウム」のやり取りを真似ることは難しいので、紹介するテーマや議論を難しいと感じることもあるかもしれない。しかし、「架空のシンポジウム」という議論スタイルを通せば格段に分かりやすくなるので、この記事だけで難しさを判断しないでもらえるとありがたい。
アロウの不可能性定理:『理性の限界』
「アロウの不可能性定理」は、ざっくり言えば「投票」に関する話だ。その帰結を難しく書けば、「完全に民主的な社会的決定方式は存在しない」となる。分かりやすく書くと、「世の中に存在するすべての『投票形式』にはどれも欠陥がある」というイメージだ。
あわせて読みたい
【感涙】衆議院議員・小川淳也の選挙戦に密着する映画から、「誠実さ」と「民主主義のあり方」を考える…
『衆議院議員・小川淳也が小選挙区で平井卓也と争う選挙戦を捉えた映画『香川1区』は、政治家とは思えない「誠実さ」を放つ”異端の議員”が、理想とする民主主義の実現のために徒手空拳で闘う様を描く。選挙のドキュメンタリー映画でこれほど号泣するとは自分でも信じられない
「投票」の話は、国政選挙や人気投票など、日常の様々な場面で出てくるかなり身近な話題と言っていいだろう。そして研究によって、「どのような『投票形式』を採用するかで、同じ得票数でも結果が変わってしまう」ことが既に明らかになっている。投票形式の違いで、どんな人が1位になりやすいかが変わってくるのだ。そう言われると、ちょっと自分にも関係しそうな話だと感じられるだろう。

この「アロウの不可能性定理」は非常に難解なようで、自力で証明できる経済学者はほとんど存在しないと言われているらしい。しかしそんな難しいテーマを、なんとなく分かった気にさせてくれるのだ。
「アロウの不可能性定理」の説明のために、過去あった実際の選挙の話題が多数取り上げられる。ブッシュとゴアがアメリカ大統領選で争った際には、ゴアの方がブッシュよりも33万票も上回っていたのだが、実際に当選したのはブッシュだった。これは、「勝った方が、その州の票を総取りできる」という選挙の仕組みによるものだ。また、フランスで行われたある選挙では、上位2名による決選投票が行われるスタイルで争われたが、最有力とされていた候補が決選投票に進めないという波乱があった。これもまた、投票形式によるものなのだ。
あわせて読みたい
【幸福】「死の克服」は「生の充実」となり得るか?映画『HUMAN LOST 人間失格』が描く超管理社会
アニメ映画『HUMAN LOST 人間失格』では、「死の克服」と「管理社会」が分かちがたく結びついた世界が描かれる。私たちは既に「緩やかな管理社会」を生きているが、この映画ほどの管理社会を果たして許容できるだろうか?そしてあなたは、「死」を克服したいと願うだろうか?
実際、私たちの日常生活でも、状況に適した投票形式が採用されている。「単記投票方式」や「上位二者決選投票方式」では「強いリーダーシップを持つ者」が選ばれ、「順位評点方式」は様々な分野の専門家集団から代表者を選出する場合に使われ、「勝ち抜き決選投票方式」は企業の商品開発の現場でよく見られるという。
普段特に、「投票形式」のことなど意識せずに投票してしまうが、それぞれが持つ性質はかなり違うということだ。考えたことなどなかったので、「違いがある」ということに驚かされた。
また、「アロウの不可能性定理」と直接には関係ないのだが、「囚人のジレンマ」に関する話も出てきて興味深い。「囚人のジレンマ」についてはちょっと自分で調べてほしいが(「ゲーム理論」と呼ばれる分野で非常に有名だ)、この「囚人のジレンマ」をゲーム化しプログラム同士で闘わせた結果、「TFT」あるいは「しっぺ返し戦略」と呼ばれる、相手の打った手をそのままやり返す戦略が最も勝ちやすいと分かったそうだ。この話もとても面白かった。
ハイゼンベルグの不完全性原理:『理性の限界』
あわせて読みたい
【バトル】量子力学の歴史はこの1冊で。先駆者プランクから批判者アインシュタインまですべて描く:『量…
20世紀に生まれた量子論は、時代を彩る天才科学者たちの侃々諤々の議論から生み出された。アインシュタインは生涯量子論に反対し続けたことで知られているが、しかし彼の批判によって新たな知見も生まれた。『量子革命』から、量子論誕生の歴史を知る
「ハイゼンベルグの不完全性原理」は、科学の世界の「量子力学」という分野で登場する。その詳細については以下の記事に書いたので読んでほしい。
非常にざっくり説明すれば、「小さな物質の『位置』と『速度』を”同時に正確に”測定することはできない」という、「量子力学」の世界を制約する強いルールのことを指す。私たちの日常生活では、「位置」と「速度」を同時に正確に測定することは決して難しくないが、極小の世界になるとそれが「原理的に」不可能なのだ。「原理的に」というのは、測定機械の精度に制約があって調べられないのではなく、どれほど精密な測定機械を作ったとしても不可能という意味である。
この不確定性原理、あまりに私たちの日常感覚とかけ離れているためイメージするのは難しいが、本書の「バードウォッチング」を例にした説明が非常に分かりやすかったので紹介しよう。

あわせて読みたい
【快挙】「チバニアン」は何が凄い?「地球の磁場が逆転する」驚異の現象がこの地層を有名にした:『地…
一躍その名が知れ渡ることになった「チバニアン」だが、なぜ話題になり、どう重要なのかを知っている人は多くないだろう。「チバニアン」の申請に深く関わった著者の『地磁気逆転と「チバニアン」』から、地球で起こった過去の不可思議な現象の正体を理解する
いつか友人と一緒にバードウォッチングに行った時に、似たような経験をしました。バードウォッチングの醍醐味は、まったく自然のままの鳥の姿を見て、その鳴き声を楽しむことにあります。遠くから双眼鏡を使えば、いきいきとした鳥の姿を観察することはできますが、あまり鳴き声が聞こえません。ところが、鳴き声が聞こえるまで鳥に近づこうとすると、今度は鳥が人の気配を察して逃げてしまうのです。つまり、自然なままの「鳥の姿」と「鳴き声」を同時に味わうのは非常に難しいわけでして……
「理性の限界」(高橋昌一郎/講談社)
なるほど、上手い説明をするものだ。しかし、あくまで「例え」である。誤解してほしくないのは、この「バードウォッチング」の話なら、技術で解決できるということだ。たとえば、木に無人カメラを設置すれば、自然なままの「鳥の姿」と「鳴き声」は同時に味わえる(もちろん、それを「バードウォッチング」と呼んでいいのか、という問題は残るが)。しかし、「ハイゼンベルグの不完全性原理」の場合は、技術での解決は不可能なのだ。「生身の人間が宙に浮くことはできない」というのと同じような意味で、「位置」と「速度」を同時に測定することはできないのである。
この「ハイゼンベルグの不完全性原理」と併せてよく語られるのが、科学の世界を驚愕させ続けている「二重スリット実験」だ。これについては図を使わずに説明するのが困難なので、以下のリンク先の説明を読んでほしい。
ブルーバックス | 講談社
「世界一ふしぎな実験」を腹落ちさせる2つの方法
古典的な「ヤングの干渉実験」なら、「波の重ね合わせ」の図を描いて勉強した記憶があったらわかるのだけれど、水の波が量子の波になった瞬間、いきなりチンプンカンプンに…
この「二重スリット実験」については様々な亜種実験が存在し、世界の原理原則について驚くべき示唆を与えてくれている。本書でもその亜種実験がいくつか紹介されているが、中でも最も驚かされたのは、「世界各地で同時に『電子1個だけを発射』し、後にそのフィルムを重ね合わせたところ、干渉縞が現れた」という実験だ。「二重スリット実験」が何か分からない方にはどこが驚きポイントなのかも理解できないと思うが、とにかく、「我々が生きる世界の法則は常軌を逸している」と実感できる非常に興味深い実験なので、是非理解を試みてほしい。
あわせて読みたい
【限界】「科学とは何か?」を知るためのおすすめ本。科学が苦手な人こそ読んでほしい易しい1冊:『哲学…
「科学的に正しい」という言葉は、一体何を意味しているのだろう?科学者が「絶対に正しい」とか「100%間違っている」という言い方をしないのは何故だろう?飲茶『哲学的な何か、あと科学とか』から、「科学とはどんな営みなのか?」について考える
本書には、「結局『科学』とはどんな営みなのか?」という議論も展開される。
その議論の帰結の1つとして、「科学とは物語でしかない」という話が出てくるのも興味深い。私たちは、「科学的に証明された」と聞くと、「絶対に正しい」と思い込んでしまいがちだ。しかし、「科学って何?」を突き詰めて考えてみると、結局「信じるか信じないか」の話に行き着いてしまう。だからこそ「物語でしかない」という捉え方になるというわけだ。
しかしそれでも、人類が長年の叡智を結集させた「最も確からしい物語」こそが「科学」なのだから、私はそれを信じる。しかし同時に、「科学の限界」を理解しておくこともまた重要だと示唆するのだ。
あわせて読みたい
【誤解】「意味のない科学研究」にはこんな価値がある。高校生向けの講演から”科学の本質”を知る:『す…
科学研究に対して、「それは何の役に立つんですか?」と問うことは根本的に間違っている。そのことを、「携帯電話」と「東急ハンズの棚」の例を使って著者は力説する。『すごい実験』は素粒子物理学を超易しく解説する本だが、科学への関心を抱かせてもくれる
ゲーデルの不完全性定理:『理性の限界』
「ゲーデルの不完全性定理」は数学の世界では非常に有名な話である。これについても別に記事があるので、どんなものなのか詳しい話は以下の記事を読んでほしい。
あわせて読みたい
【刺激】結城浩「数学ガール」で、ゲーデルの不完全性定理(不可能性の証明として有名)を学ぶ
『結城浩「数学ガール」シリーズは、数学の面白さを伝えながら、かなり高難度の話題へと展開していく一般向けの数学書です。その第3弾のテーマは、「ゲーデルの不完全性定理」。ヒルベルトという数学者の野望を打ち砕いた若き天才の理論を学びます
ざっくり説明すると、「それがどんな枠組みであれ、『その枠組み中では正しいかどうかを判定できない問題』が存在する」という主張になる。この記事で初めて「ゲーデルの不完全性定理」という単語を目にした人には、何を言っているのかさっぱり理解できないと思うが、本書では「司法システムと犯罪者」を例にした説明がある。「司法システム」というのは、要するに憲法や刑法などを指していると考えてもらえばいいだろう。

例えば、ある人物Aがある行為Xを行ったとしよう。その行為Xは、誰がどう判断しても「犯罪」と感じられるようなものである。そして、その行為Xを行ったのが人物Aであることも間違いないとしよう。つまり、「人物Aが犯人」と確定しているというわけだ。
しかし、日本の法律を洗いざらいすべてひっくり返してみても、この行為Xを「犯罪」と規定する条文を見つけることができない。市民の気分としては行為Xは明らかに犯罪であり、すなわち「人物Aが犯人」であるにも関わらず、行為Xを犯罪と立証する「司法システム」が存在しないのだ。
あわせて読みたい
【天才】『ご冗談でしょう、ファインマンさん』は、科学者のイメージが変わる逸話満載の非・科学エッセイ
「天才科学者」と言えばアインシュタインやニュートン、ホーキングが思い浮かぶだろうが、「科学者らしくないエピソード満載の天才科学者」という意味ではファインマンがずば抜けている。世界的大ベストセラー『ご冗談でしょう、ファインマンさん』は、「科学」をほぼ扱わないエッセイです
より具体的な例を出した方がわかりやすければ、「盗聴」を挙げよう。「盗聴」は明らかに犯罪に思われるが、「盗聴器を設置して盗聴する行為」を犯罪と規定する法律は存在しない。「盗聴」で逮捕されるのは大体、「住居侵入罪」である。
ゲーデルが主張した「不完全性定理」もこれに近い。私たちが採用する「司法システム」では、「盗聴」という行為を「正しい」とも「間違っている」とも判定できないように、ゲーデルは、「どんな枠組みを設定しても、その枠組みの内側の理屈では正しいかどうかを判定できない命題が存在する」と示したのだ。
しかしそもそもだが、何故そんな証明が生まれたのだろうか。そこにはヒルベルトという数学者が関係している。数学という学問はそれまで、様々な数学者が色んな発見をバラバラに行うことで発展してきたが、それを体系的に整理して、ごく少数の前提からすべての命題を証明しよう、というプログラムをヒルベルトが立ち上げたのだ。しかし、「真偽を判定できない命題が存在する」とゲーデルが証明したことで、このプログラムが実現不可能であると判明してしまったのである。
ここまでくると、数学なのか哲学なのか分からなくなってくるが、数学・哲学どちらの世界にも衝撃を与えた定理として、非常によく知られている。
あわせて読みたい
【衝撃】ABC予想の証明のために生まれたIUT理論を、提唱者・望月新一の盟友が分かりやすく語る:『宇宙…
8年のチェック期間を経て雑誌に掲載された「IUT理論(宇宙際タイヒミュラー理論)」は、数学の最重要未解決問題である「ABC予想」を証明するものとして大いに話題になった。『宇宙と宇宙をつなぐ数学』『abc予想入門』をベースに、「IUT理論」「ABC予想」について学ぶ
言語の限界:『知性の限界』
メインで語られるのは、ウィトゲンシュタインだ。彼は前期と後期でその主張がまったく異なることでも知られており、本書ではその変遷にも触れられていた。
前期の哲学は、『論理哲学論考』という本にまとめられている。
著:ウィトゲンシュタイン, 著:野矢 茂樹
¥858 (2022/02/09 20:57時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
ウィトゲンシュタインは、「哲学的な問題などそもそも存在しない」という結論にたどり着いた。彼自身の言葉を引用するとこうなる。
語りうることは明らかに語りうるのであって、語りえないことについては沈黙しなければならない
あわせて読みたい
【平易】一般相対性理論を簡単に知りたい方へ。ブラックホール・膨張宇宙・重力波と盛りだくさんの1冊:…
現役の研究者が執筆した『ブラックホール・膨張宇宙・重力波』は、アインシュタインが導き出した一般相対性理論が関わる3つのテーマについて、初心者にも分かりやすく伝える内容になっている。歴史的背景も含めて科学的知見を知りたい方にオススメの1冊

語れる事柄は、「語れる」のだからそもそも問題ではない。そして語れない事柄は、ただ言葉の意味が不明瞭なだけであり、それは「問題として認識される以前の混沌」でしかないのである。「哲学的な問題が存在する」ように見える理由は、ただ言葉が不明瞭なだけに過ぎず、「哲学的な問題」はすべて「擬似問題」という主張をしているわけだ。
一方、後期のウィトゲンシュタインは「言語ゲーム」という概念を生み出し、ここから「すべての言語に共通する本質的なものなど存在しない」という結論に至る。
言語はそもそも、「社会集団におけるそれぞれの生活形式によってルール付けされるもの」だとウィトゲンシュタインは指摘した。そしてだからこそ、そんな言語によって行われる思考や身につく習慣も、自ずと文化によって違いが生じるというわけだ。
どちらの話も、短く紹介できるようなテーマではまったくないのでこれ以上の説明は諦めるが、ウィトゲンシュタインを中心軸に据えながら、「言語」がどのような限界を内包しているのかを明らかにする内容だ。またその過程で、思考は言語に依存してしまうという「サピアウォーフの仮説」や、観察は理論と切り離すことができないという「ハンソンの観測の理論負荷性」なども取り上げられる。
あわせて読みたい
【驚嘆】人類はいかにして言語を獲得したか?この未解明の謎に真正面から挑む異色小説:『Ank: a mirror…
小説家の想像力は無限だ。まさか、「人類はいかに言語を獲得したか?」という仮説を小説で読めるとは。『Ank: a mirroring ape』をベースに、コミュニケーションに拠らない言語獲得の過程と、「ヒト」が「ホモ・サピエンス」しか存在しない理由を知る
予測の限界:『知性の限界』
「予測の限界」では主に、「科学」に関する話題が扱われる。

「『科学である』とはどういうことか?」を定義するのは、実はなかなか難しかった。科学では基本的に、「帰納法」と呼ばれる、これまでに起こった様々な事象から本質を抽出する手法を用いて実験や観察の結果を分析し、理論を導いてきた。しかしポパーという人物が、この「帰納法」には根本的な問題が存在することを明らかにしてしまったのである。「帰納法」に基づいているからといって科学とは言い切れない、というわけだ。
そこでポパーが提唱したのが「反証可能性」という考え方である。これについては以下の記事で詳しく書いた。
あわせて読みたい
【誤り】「信じたいものを信じる」のは正しい?映画『星の子』から「信じること」の難しさを考える
どんな病気も治す「奇跡の水」の存在を私は信じないが、しかし何故「信じない」と言えるのか?「奇跡の水を信じる人」を軽々に非難すべきではないと私は考えているが、それは何故か?映画『星の子』から、「何かを信じること」の難しさについて知る
簡単に書くと、「『誤りだと指摘される可能性のある仮説』でなければ科学とは言えない」となる。なんとなく、「誤りだと指摘される可能性のある仮説」では不十分に思えるかもしれない。しかし、次の占い師の話で考えてみると、この「反証可能性」の威力を理解できるだろうと思う。
あなたは占い師から「今日の運勢はとても良いいです」と言われたとしよう。しかし同じ日に、車に轢かれて大怪我に遭ってしまう。普通に考えれば「運勢が良い」という「占い(仮説)」は間違いだったと思えるが、占い師は「運勢が良かったから、事故に遭っても死ななかったのだ」と主張するかもしれない。
つまりこの占い師の「占い(仮説)」は、どうやっても「間違い」だとは指摘できない「反証不可能な仮説」なのである。だから「科学的ではない」と判断できるのだ。
あわせて読みたい
【勝負】実話を基にコンピューター将棋を描く映画『AWAKE』が人間同士の対局の面白さを再認識させる
実際に行われた将棋の対局をベースにして描かれる映画『AWAKE』は、プロ棋士と将棋ソフトの闘いを「人間ドラマ」として描き出す物語だ。年に4人しかプロ棋士になれない厳しい世界においては、「夢破れた者たち」もまた魅力的な物語を有している。光と影を対比的に描き出す、見事な作品
このように、「反証可能性」こそが科学の指標であることが説明される。
また、「確証原理」の話も実に興味深い。本書では、カラスの例で説明される。

まずは「確証原理」そのものの説明をしよう。例えば、「すべてのカラスは黒い」という「仮説」を立てるとする。この場合、黒いカラスが1羽発見される度に、この「仮説」の確証度(正しさの度合い)は高まると考えていいだろう。このような判断を「確証原理」と呼ぶ。
あわせて読みたい
【狂気?】オウム真理教を内部から映す映画『A』(森達也監督)は、ドキュメンタリー映画史に残る衝撃作だ
ドキュメンタリー映画の傑作『A』(森達也)をようやく観られた。「オウム真理教は絶対悪だ」というメディアの報道が凄まじい中、オウム真理教をその内部からフラットに映し出した特異な作品は、公開当時は特に凄まじい衝撃をもたらしただろう。私たちの「当たり前」が解体されていく斬新な一作
さてここで、論理学の「対偶」という概念に触れよう。「AであればBである」という命題に対して、「BでなければAではない」を対偶と呼ぶ。先ほどのカラスの「仮説」の場合は、「すべての黒くないものはカラスではない」が待遇だ。論理学の世界では、「命題」と「対偶」の真偽は常に一致することが知られており、命題が真なら対偶も真、命題が偽なら対偶も偽である。
さて、この「対偶」の考え方から「確証度パラドックス」が生まれるのだが、その説明をしていこう。
先ほどと同様に考えれば、「すべての黒くないものはカラスではない」という主張は、「黒くないもの」、つまり「黄色いバナナ」や「赤いリンゴ」などが見つかれば見つかるほど確証度が高まる。一方で、「すべての黒くないものはカラスではない」は「すべてのカラスは黒い」と真偽が一致すると先述した。つまり、「黄色いバナナ」や「赤いリンゴ」は、「すべてのカラスは黒い」の確証度を高める存在でもあるわけだ。
あわせて読みたい
【対立】数学はなぜ”美しい”のか?数学は「発見」か「発明」かの議論から、その奥深さを知る:『神は数…
数学界には、「数学は神が作った派」と「数学は人間が作った派」が存在する。『神は数学者か?』をベースに、「数学は発見か、発明か」という議論を理解し、数学史においてそれぞれの認識がどのような転換点によって変わっていったのかを学ぶ
ではここで、「すべてのカラスは白い」という「仮説」について考えよう。先ほどと同じように考えて、「すべての白くないものはカラスではない」が待遇である。
ここで何かに気づかないだろうか? そう、「黄色いバナナ」や「赤いリンゴ」は黒色でもないが白色でもない。つまりそれらは、「すべての白くないものはカラスではない」の確証度を高める要素でもあるのだ。さらに先ほどと同様に考えることで、「すべてのカラスは白い」の確証度も高めることになる。
まとめるとこういうことだ。「黄色いバナナ」や「赤いリンゴ」の存在は、「すべてのカラスは黒い」という「仮説」だけではなく、「すべてのカラスは白い」という「仮説」の確証度をも高める。しかし、「すべてのカラスは白い」という主張は明らかに誤りだ。それなのに、「黄色いバナナ」や「赤いリンゴ」の存在はその主張を、「すべてのカラスは黒い」と同程度の確証度へと引き上げるのだ。
これを「確証度パラドックス」と呼んでいる。正しい論理を積み重ねたはずなのに矛盾が生じてしまう奇妙な理屈は非常に興味深い。
あわせて読みたい
【異端】数学の”証明”はなぜ生まれたのか?「無理数」と「無限」に恐怖した古代ギリシャ人の奮闘:『数…
学校で数学を習うと、当然のように「証明」が登場する。しかしこの「証明」、実は古代ギリシャでしか発展しなかった、数学史においては非常に”異端”の考え方なのだ。『数学の想像力 正しさの深層に何があるのか』をベースに、ギリシャ人が恐れたものの正体を知る
また未来予測に関するパラドックスも、考えれば考えるほど頭が混乱してくる面白い話だ。
宇宙人が地球にやってきたとしよう。この宇宙人は「脳検索装置」というテクノロジーを持っている。地球人の脳を一瞬でスキャンして思考を読み取り、そこから得られる情報によってその人間の未来の行動を正確に予測することができるのだ。あなたは地球へとやってきたその宇宙人の案内役を買って出る。そしてその期間中ずっと、宇宙人はあなたの未来の行動すべてを完璧に予測し続けていたとしよう。

さて、宇宙人が地球を去る日がきた。宇宙人はあなたにプレゼントを用意しており、目の前には2つの箱が置かれている。箱Aは透明で中に100万円が入っているのが見えるが、箱Bは不透明で中身が入っているかどうかも見えない状態だ。
あわせて読みたい
【要約】福岡伸一『生物と無生物のあいだ』は、「生命とは何か」を「動的平衡」によって定義する入門書…
「生命とは何か?」という、あまりに基本的だと感じられる問いは、実はなかなか難しい。20世紀生物学は「DNAの自己複製」が本質と考えたが、「ウイルス」の発見により再考を迫られた。福岡伸一の『生物と無生物のあいだ』『動的平衡』の2著作から、「生命の本質」を知る
さてこの2つの箱を前にして、宇宙人はあなたにこんなことを言う。
あなたは、①箱Bのみを取るか ②箱AとBを両方取るという二つの選択肢の内の一つを選べます。ただ、私があなたの脳をスキャンしてあなたの行動を予測していることに注意してください。もし脳検索装置が、①あなたが箱Bのみを取ると予測した場合、私は箱Bに1億円入れておくが、もし②あなたが箱Aと箱Bの両方を取ると予測した場合、箱Bは空にしておく。
「知性の限界」(高橋昌一郎/講談社)
このパラドックスで重要な点は、「1億100万円を手に入れられる可能性は存在するか」である。①箱Bのみを取ることにして1億円手にすれば十分かもしれないが、やはり可能性が存在するなら、最大利益である1億100万円を手に入れたいところだ。しかし、1億100万円を手にするためにはどうしたらいいだろうか?
考えれば考えるほど思考が迷宮入りしていくような話で、まさに「予測の限界」を実感させられるパラドックスだと言える。
あわせて読みたい
【化石】聞き馴染みのない「分子生物学」を通じて、科学という学問の本質を更科功が分かりやすく伝える…
映画『ジュラシック・パーク』を観たことがある方なら、「コハクの化石に閉じ込められた蚊の血液から恐竜の遺伝子を取り出す」という設定にワクワクしたことだろう。『化石の分子生物学』とは、まさにそのような研究を指す。科学以外の分野にも威力を発揮する知見に溢れた1冊
思考の限界:『知性の限界』
まず紹介されるのは、「人間原理」と呼ばれるものだ。科学の世界の話題なのだが、とても科学の話とは思えないぶっ飛んだ考えだと感じる人もいるだろう。詳しく説明すると色んな話に触れる必要があるのだが、ここではあまり深入りはしない。概要をざっと紹介するに留めよう。
「人間原理」の基本的な発想は、「この宇宙は、我々人間のような知的生命体が生まれる性質を備えた形で誕生した」となる。一気に胡散臭くなっただろう。何故なら、この考えを採用すれば自然と、「創造主がこの世界を作った」という結論に行き着いてしまうからだ。実は、創造主の存在を仮定せずとも成立する「人間原理」の解釈もあり、私はそちらの考えを気に入っているのだが、その説明はまた別の機会に回そう。
あわせて読みたい
【始まり】宇宙ができる前が「無」なら何故「世界」が生まれた?「ビッグバンの前」は何が有った?:『…
「宇宙がビッグバンから生まれた」ことはよく知られているだろうが、では、「宇宙ができる前はどうなっていたのか」を知っているだろうか? 実は「宇宙は”無”から誕生した」と考えられているのだ。『宇宙が始まる前には何があったのか?』をベースに、ビッグバンが起こる前の「空間も時間も物理法則も存在しない無」について学ぶ
「創造主」がいるかどうかは一旦脇に置くとして、科学の世界には「人間原理」という、「知的生命体が生まれるような形で宇宙が誕生した」とする考えが存在するわけだ。もちろん、すべての科学者が認めているわけではないし、というか、大半の科学者が眉唾ものだと捉えているようだが、しかし「人間原理」的な考え方を採用しなければ解釈が難しいものも存在する。
その一例として本書で紹介されるのが、「宇宙を支配する6つの定数」だ。「定数」というのは、「変動しない固定された数値」のことを指す。例えば、「光速」はどんな場合でも一定で、秒速約30万kmだ。つまり「光速」も「定数」である。

本書で紹介される「6つの定数」の中に、「ε(イプシロン)」と表記されるものがある。これが何を示す定数なのかイマイチ理解していない。しかし、我々が生きているこの宇宙の「ε」の値は「0.007」であり、もしこの数値が「0.008」や「0.006」だったら、我々人間は存在できないという事実が明らかになっているのだ。
あわせて読みたい
【未知】タコに「高度な脳」があるなんて初耳だ。人類とは違う進化を遂げた頭足類の「意識」とは?:『…
タコなどの頭足類は、無脊椎動物で唯一「脳」を進化させた。まったく違う進化を辿りながら「タコに心を感じる」という著者は、「タコは地球外生命体に最も近い存在」と書く。『タコの心身問題』から、腕にも脳があるタコの進化の歴史と、「意識のあり方」を知る。
この「ε」は、ある一定の範囲内という制約はあるかもしれないが、基本的にどんな値でも取りうる。つまり、「0.007」でなければならない必然性はないということだ。しかし、「0.007」からほんの僅かでもズレていれば、宇宙が誕生したとしても、その中で我々人類が生まれることはなかったのである。
また、この「6つの定数」の中には、「空間次元数」も含まれている。私たちが生きる宇宙はご存知の通り「3次元空間」(時間も含めれば「4次元時空」)だが、3次元空間でなければ生命は進化できないと分かっているそうだ。
私たちは3次元空間でしか生きたことがないからイメージしにくいが、宇宙の空間次元は別に「3」である必然性はない。2でも100億でもいいのだ。しかしその中で、「3」だけが生命の進化を可能にする空間次元なのである。
このような話を聞くとどうしても、「『ε』や『空間次元数』は、生命が誕生するように”調整”されているのではないか」と考えたくなるだろう。そのような発想の延長にあるのが「人間原理(の解釈の1つ)」というわけだ。本書ではこの「人間原理」を端緒にして、「神の存在証明」の話が展開されていく。
あわせて読みたい
【不思議】森達也が「オカルト」に挑む本。「科学では説明できない現象はある」と否定も肯定もしない姿…
肯定派でも否定派でもない森達也が、「オカルト的なもの」に挑むノンフィクション『オカルト』。「現象を解釈する」ことよりも、「現象を記録する」こと点に注力し、「そのほとんどは勘違いや見間違いだが、本当に説明のつかない現象も存在する」というスタンスで追いかける姿勢が良い
本書では様々な種類の「神の存在証明」が紹介されるが、個人的に面白いと感じた証明について触れよう。
証明したい命題を整理しておくと、「全能の神は存在する」となる。ここでは「全能」というのがポイントだ。「神」にどんなイメージを持つかは人それぞれだろうが、やはり「何でもできる存在」と考えたくなるだろう。
さてここで、誰かと「神は存在するか」という議論をしているとしよう。そしてそのやり取りの帰結として相手が、「神は存在しないだろうが、もし存在するのなら全能だろう」と主張したとする。
この場合、これを認めた人物は「全能の神は存在する」という命題も受け入れざるを得ないことになるのだ。何故だろうか。
あわせて読みたい
【天才】数学の捉え方を一変させた「シンメトリー(対称性)」と、その発見から発展に至る歴史:『シン…
「5次方程式の解の公式は存在しない」というアーベルの証明や、天才・ガロアが発展させた「群論」は、「シンメトリー(対称性)」という領域に新たな光を当てた。『シンメトリーの地図帳』をベースに、「シンメトリー」の発展と「モンスター」の発見の物語を知る
全能である神は何だってできる。そして当然、何だってできる神が、「存在する」なんて簡単なことができないはずがない。つまり、「存在するなら神は全能だ」と主張するなら、必然的に「全能の神が存在する」という命題も認めなければならないということになるのである。
なんともパラドキシカルな話に思えるが、なんとなく納得させられてしまう感じもある。面白い話だ。
行為の限界:『感性の限界』
ここでは、「知覚」を出発点として、「行動経済学」「動物行動学」「情報科学」「認知科学」など、かなり多様な分野に渡って話が展開される。人間や動物が、行動に際してどんな情報・認知に影響を受けてしまうのかについて様々な実例が紹介されていて面白い。
中でも最も興味深いのは、やはり「行動経済学」の話だろう。ここからは、本書で紹介されている「行動経済学」に関する様々な話を取り上げる。
あわせて読みたい
【具体例】行動経済学のおすすめ本。経済も世界も”感情”で動くと実感できる「人間の不合理さ」:『経済…
普段どれだけ「合理的」に物事を判断しているつもりでも、私たちは非常に「不合理的」な行動を取ってしまっている。それを明らかにするのが「行動経済学」だ。『経済は感情で動く』『世界は感情で動く』の2冊をベースにして、様々な具体例と共に「人間の不思議さ」を理解する
まずは「アンカリング」から。これは、ある数字が「アンカー(錨)」となり、その数字を基準に物事を判断してしまう人間の行動原理のことを指す。本書では、「アンカリング効果」を発見しノーベル経済学賞を受賞したカーネマンとトヴェルスキーによる「国連実験」が紹介されている。

2人は大学の教室に、1から100までの数字が書かれたルーレットを持ち込んだ。このルーレットは「10」か「65」のどちらかでしか止まらないように細工されていたのだが、被験者である学生にはそのことは知らされていない。
さて2人はルーレットを回し、「国連にアフリカ諸国が占める割合が、ルーレットで出た数字より高いか低いか」という質問をした。つまり学生は、「10が出ました。では国連にアフリカ諸国が占める割合は10%よりも高いか低いか?」「65が出ました。では国連にアフリカ諸国が占める割合は65%よりも高いか低いか?」のどちらかの質問に答えることが求められるというわけだ。
あわせて読みたい
【革命】観る将必読。「将棋を観ること」の本質、より面白くなる見方、そして羽生善治の凄さが満載:『…
野球なら「なんで今振らないんだ!」みたいな素人の野次が成立するのに、将棋は「指せなきゃ観てもつまらない」と思われるのは何故か。この疑問を起点に、「将棋を観ること」と「羽生善治の凄さ」に肉薄する『羽生善治と現代』は、「将棋鑑賞」をより面白くしてくれる話が満載
すると、前者の場合は「10%高い」と推定し、その平均は25%だったのに対し、後者の場合は「65%より低い」と推定し、その平均は45%だった。これは明らかに、質問内容とはまったく無関係であるルーレットの数字に引きずられて答えているということになる。
この「アンカリング効果」を実に効果的に使ったとされる「悪名高い裁判」がある。「マクドナルドのコーヒーを自らの過失でこぼして重度の火傷を負った老婦人が、『コーヒーの温度が高すぎたから』とマクドナルドを訴えた裁判」だ。老婦人に対してなんと286万ドル(およそ3億円)というとんでもない額の損害賠償の支払いが命じられた。この裁判で弁護士が巧みに「アンカリング」を行ったという。
日本の場合、「損害賠償」は「実際の損害を補填する金額」しか算出されないが、アメリカでは「懲罰的損害賠償」の請求が可能だ。そこで弁護士はその算出に際して、「マクドナルド全店のコーヒーの売上を基準にするのはどうか」と主張した。つまり弁護士の「アンカリング」によって陪審員は、「懲罰的な意味を込めて、マクドナルド全店のコーヒー売上の1日分ぐらいの損害賠償金を認定してもいいのではないか」と刷り込まれ、結果として約3億円という日本では考えられない額になったのである。
あわせて読みたい
【おすすめ】江戸川乱歩賞受賞作、佐藤究『QJKJQ』は、新人のデビュー作とは思えない超ド級の小説だ
江戸川乱歩賞を受賞した佐藤究デビュー作『QJKJQ』はとんでもない衝撃作だ。とても新人作家の作品とは思えない超ド級の物語に、とにかく圧倒されてしまう。「社会は『幻想』を共有することで成り立っている」という、普段なかなか意識しない事実を巧みにちらつかせた、魔術のような作品
また、「フレーミング効果」も有名だろう。本書には以下のような質問が載っている。あまり深く考えずに、すぐ答えを出してみてほしい。
二つのボウルがあって、「ボウルA」には白玉9個と赤玉1個、「ボウルB」には白玉92個と赤玉8個が入っているのが見えていて、各々の個数も被験者にハッキリと告げられているとしましょう。被験者はボウルに手を入れて、かき混ぜてから一つの玉を取り、それが赤玉だったら景品を獲得するというゲームです。さて、あなただったら、どちらのボウルから玉を取りますか?
「感性の限界」(高橋昌一郎/講談社)
これについては実際に実験が行われており、「ボウルB」から取る被験者が多かったという。冷静に確率を考えれば、明らかに「ボウルA」から取るのが正解だと分かるはずだ。しかし瞬時に答えなければならないとしたら、「ボウルAよりボウルBの方が赤玉がたくさん入っているから」と考えて「ボウルB」を選んでしまうかもしれない。
あわせて読みたい
【倫理】アート体験の行き着く未来は?映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』が描く狂気の世界(…
「『痛み』を失った世界」で「自然発生的に生まれる新たな『臓器』を除去するライブパフォーマンス」を行うソール・テンサーを主人公にした映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』は、すぐには答えの見出しにくい「境界線上にある事柄」を挑発的に描き出す、実に興味深い物語だ
このように、表現方法や伝え方によって、相手に与える印象が変わることを「フレーミング効果」と呼ぶ。
では次に、2つの問いを用意するので、それぞれ大臣の立場に立って答えを考えてみてほしい。
あなたは主要国の厚生大臣で、ある感染症の病気に対策を講じようとしているとします。この病気には、すでに600人が感染していて、このまま放っておけば死亡することが推定されています。この感染症に対して、二つの対策が提案されます。
「対策A」を採用すれば、200人が助かります。「対策B」を採用すれば、600人が助かる確率が1/3、一人も助からない確率が2/3です。
さて、あなたが大臣だったら、どちらの対策を採用しますか?
「感性の限界」(高橋昌一郎/講談社)
あなたは主要国の厚生大臣で、ある感染症の病気に対策を講じようとしているとします。この病気には、すでに600人が感染していて、このまま放っておけば死亡することが推定されています。この感染症に対して、二つの対策が提案されます。
「対策C」を採用すれば、400人が死亡します。「対策D」を採用すれば、一人も死亡しない確率が1/3、600人が死亡する確率が2/3です。
さて、あなたが大臣だったら、どちらの対策を採用しますか?
「感性の限界」(高橋昌一郎/講談社)
あわせて読みたい
【無知】メディアの問題の本質は?「報道の限界」と「情報の受け取り方」を独裁政治の現実から知る:『…
メディアは確かに「事実」を報じている。しかし、報道に乗らない情報まで含めなければ、本当の意味で世の中を理解することは難しいと、『こうして世界は誤解する』は教えてくれる。アラブ諸国での取材の現実から、報道の「限界」と「受け取り方」を学ぶ

いかがだろうか?
これも実験が行われており、前者では「対策A」が、後者では「対策D」が選ばれる傾向が強いそうだ。
しかし、文章をよく読めば理解できるが、この2つの問いは実は同じことを主張している。つまり、「対策A」と「対策C」はまったく同じものだし、同様に「対策B」と「対策D」もまったく同じだ。しかし、情報の出し方で、どちらが選ばれるのかが変わってしまうのである。
あわせて読みたい
【限界】有名な「錯覚映像」で心理学界をザワつかせた著者らが語る「人間はいかに間違えるか」:『錯覚…
私たちは、知覚や記憶を頼りに社会を生きている。しかしその「知覚」「記憶」は、本当に信頼できるのだろうか?心理学の世界に衝撃を与えた実験を考案した著者らの『錯覚の科学』から、「避けられない失敗のクセ」を理解する
人間の判断にはこのようなエラーが付きものであり、だからこそ事前に、どんな間違いを犯す可能性があるのか知っておくべきだと思う。
意思の限界:『感性の限界』
ここでの大きなテーマは、「人間に自由意志など存在するのか?」である。
そしてその議論のために、「ミルグラムのアイヒマン実験」を実例にした「服従」の話と、「ドーキンスの利己的遺伝子」を中心とした「遺伝子による支配」の話が展開されていく。
あわせて読みたい
【不満】この閉塞感は打破すべきか?自由意志が駆逐された社会と、不幸になる自由について:『巡査長 真…
自由に選択し、自由に行動し、自由に生きているつもりでも、現代社会においては既に「自由意志」は失われてしまっている。しかし、そんな世の中を生きることは果たして不幸だろうか?異色警察小説『巡査長 真行寺弘道』をベースに「不幸になる自由」について語る
「ミルグラムのアイヒマン実験」については、以下の記事に詳しく書いたのでそちらを読んでほしい。
様々な心理学の知見から、人間がいかに「服従」させられてしまうのかが分かっており、私たちの日常生活と無関係とは言えない話が様々に出てくる。
もう一方の、ドーキンスが主張した「利己的遺伝子」の考え方は次のようなものだ。

あわせて読みたい
【挑発】「TBS史上最大の問題作」と評されるドキュメンタリー『日の丸』(構成:寺山修司)のリメイク映画
1967年に放送された、寺山修司が構成に関わったドキュメンタリー『日の丸』は、「TBS史上最大の問題作」と評されている。そのスタイルを踏襲して作られた映画『日の丸~それは今なのかもしれない~』は、予想以上に面白い作品だった。常軌を逸した街頭インタビューを起点に様々な思考に触れられる作品
私たちは当たり前のように、「生命の基本は個体(肉体)だ」と考えてしまう。それぞれの個体が最小単位となって、生命の様々な行動が規定されているのだ、と。しかしドーキンスは、「生命の個体は単なる『遺伝子の乗り物』に過ぎず、生命の行動は、『種全体として遺伝子が最大利益を享受できるように規定されている』」と主張した。これが「利己的遺伝子」である。
例えばミツバチを思い浮かべると分かりやすいかもしれない。ミツバチは「女王蜂」や「働き蜂」などの役割に分かれており、それぞれの個体ではなく、「種(というか「巣」)全体」で最大の利益が得られるような行動をとっている。そして、ミツバチに限らずすべての生命にこの考えが当てはまるというのが「利己的遺伝子」の主張なのだ。
もし「利己的遺伝子」の考え方を採用するなら、我々には「自由意志」など存在しないということになるだろう。種全体として遺伝子が最大利益を得られるようにすべての行動が決まっているとするなら、各個体に自由意志があると考えるのは難しい。
しかし、決してそうとも限らないようだ。例えば本書には、「苦味物質を好んで摂取するのは地球上でヒトだけだ」という話が出てくる。そしてそれに続ける形で、心理学者スタノヴィッチの次のような考えが紹介される。
あわせて読みたい
【奇妙】大栗博司『重力とはなにか』は、相対性理論や量子力学の説明も秀逸だが、超弦理論の話が一番面白い
『重力とはなにか』(大栗博司)は、科学に馴染みの薄い人でもチャレンジできる易しい入門書だ。相対性理論や量子力学、あるいは超弦理論など、非常に難解な分野を基本的なところから平易に説明してくれるので、「科学に興味はあるけど難しいのはちょっと……」という方にこそ読んでほしい1冊
私たちはロボット――複製子の繁殖に利するように設計された乗り物――かもしれないが、自分たちが、複製子の利益とは異なる利益を持つということを発見した唯一のロボットでもある。
「感性の限界」(高橋昌一郎/講談社)
少なくとも我々ヒトは、完全なる「遺伝子の乗り物」というわけではなさそうだ。
また、『感性の限界』全体で言及される「二重過程理論」という理論があるのだが、これも「利己的遺伝子」の話と結びついていく。
あわせて読みたい
【使命】「CRISPR-Cas9」を分かりやすく説明。ノーベル賞受賞の著者による発見物語とその使命:『CRISPR…
生物学の研究を一変させることになった遺伝子編集技術「CRISPR-Cas9」の開発者は、そんな発明をするつもりなどまったくなかった。ノーベル化学賞を受賞した著者による『CRISPR (クリスパー) 究極の遺伝子編集技術の発見』をベースに、その発見物語を知る
「二重過程理論」とは、人間には異なる2種類の思考システムが存在する、という考え方だ。論理的・意識的な「分析的システム」と、直感的・無意識的な「自律的システム」の2つが存在し、この2つの思考システムの存在で人間の様々な行動が説明できる、というわけである。世界的ベストセラーである『ファスト&スロー』は、この2つのシステムを理解し、どのようにして意思決定するのかについて書かれた本だ(私は読んでいないが)。
¥1,848 (2022/02/09 21:06時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
そして、「自律的システム」を「遺伝子の利益を優先するもの」と解釈することで、「二重過程理論」の話は「利己的遺伝子」と結びつくというわけだ。
我々が意識的にコントロール可能なのは「分析的システム」だけであり、こちらが個体としての利益を優先する行動を生む。一方で、遺伝子の利益を優先する「自律的システム」も存在し、我々はこのシステムをコントロールする自由がない。個体の利益と遺伝子の利益が相反する場合、2つのシステムが矛盾した働きをしてしまい、その結果、人間の行動が不合理なものになってしまうという説明は、非常に分かりやすかった。

また、「意識」と「行動」に関する衝撃的な実験も紹介されている。この実験については以下の記事で触れた。
あわせて読みたい
【神秘】脳研究者・池谷裕二が中高生向けに行った講義の書籍化。とても分かりやすく面白い:『進化しす…
「宇宙」「深海」「脳」が、人類最後のフロンティアと呼ばれている。それほど「脳」というのは、未だに分からないことだらけの不思議な器官だ。池谷裕二による中高生向けの講義を元にした『進化しすぎた脳』『単純な脳、複雑な「私」』をベースに、脳の謎を知る
ざっくりと結論を書くと、「『行動しよう』と意識する前に、その行動を取るための司令が無意識的に出されている」となる。
例えば「ペンを取る」という行動で考えてみよう。この場合、「ペンを取ろう」と意識した後で手が動く、と考えるのが自然なはずだ。つまり、「意識することで行動の司令が発せられる」という認識である。
しかし実験から、「意識する前に行動の司令が発せられている」ことが判明したのだ。私たちが「ペンを取ろう」と意識するよりも前に、既に手を動かす指令が出ているのである。では一体「行動の司令」を発したのは誰なのか? 「自分が意識するよりも前」に行動の司令が出ているのだから、行動の司令を出しているのは自分ではないことになる。
このような実験からも、「人間には自由意思などない」と考えられるようになっていったのだ。
存在の限界:『感性の限界』
ここでは、「死」や「存在そのもの」などについて議論が展開される。紹介の仕方が難しいので詳しくは触れないが、「肉体の消滅という意味だけではない死」「カミュ作品を引き合いに出して行う『不条理』の議論」「『脳』と『意識』と『私の死』の関係性」など、「死」を中心軸としながら、様々に哲学的な思考が展開されていく。
あわせて読みたい
【戸惑】人間の脳は摩訶不思議。意識ではコントロールできない「無意識の領域」に支配されている:『あ…
我々は決断や選択を「自分の意思」で行っていると感じるが、脳科学の研究はそれを否定している。我々に「自由意志」などない。「脳」の大部分は「意識以外のもの」に支配され、そこに「意識」はアクセスできないという驚愕の実態を『あなたの知らない脳』から学ぶ
著:高橋昌一郎
¥825 (2022/02/09 20:50時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
著:高橋昌一郎
¥715 (2022/02/09 20:50時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
講談社
¥1,100 (2022/02/09 20:51時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品読了済】私が読んできたノンフィクション・教養書を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が読んできたノンフィクションを様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本選びの参考にして下さい。
最後に
あわせて読みたい
【未知】「占い」が占い以外の効果を有するように、UFOなど「信じたいものを信じる」行為の機能を知れる…
「占い」に「見透かされたから仕方なく話す」という効用があるように、「『未知のもの』を信じる行為」には「『否定されたという状態』に絶対に達しない」という利点が存在する。映画『虚空門GATE』は、UFOを入り口に「『未知のもの』を信じる行為」そのものを切り取る
『感性の限界』の巻末に、こんな文章がある。
「充分に進化した科学技術は、魔法と見分けがつかない」というアーサー・クラークの有名な言葉がある。それに付け加えたいのは、現代の科学者は「科学」を行なっているが、一般大衆は「科学」ではなく「魔法」を期待しているということである。
「感性の限界」(高橋昌一郎/講談社)

「限界シリーズ」で語られるのは決して「科学」の話に留まらないが、他の学問領域にも同じことが当てはまる。
「『魔法』を期待している」というのは、「どんなことも可能」と考えているということであり、それは即ち「限界を理解できていない」ことを意味する。「科学」に限らず、様々な物事の「限界」を知っておくことは、「どんなことも可能」という誤った捉え方を避けるために必要不可欠と言っていいだろう。
そしてまさにこのシリーズは、我々人間が直面する様々な事象の「限界」を分かりやすく提示してくれる作品なのだ。知的好奇心を満たすというだけではなく、そういう実用的な観点からも非常に有益な作品だと言っていいだろう。
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!「文章の書き方が分からない」「文章力がないから鍛えたい」という方にオススメ…
「文章の書き方」についてのKindle本を出版しました。「文章が書けない」「どう書いたらいいか分からない」「文章力を向上させたい」という方の悩みを解消できるような本に仕上げたつもりです。数多くの文章を書き、さらに頼まれて文章を推敲してきた経験を踏まえ、「文章を書けるようになるにはどうしたらいいか」についての私なりの考えをまとめました。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【日々】映画『なみのおと』は、東日本大震災を語る人々の対話を”あり得ない”アングルから撮る(監督:…
映画『なみのおと』は、「東日本大震災の被災者が当時を振り返って対話をする」という内容そのものももちろん興味深いのだが、カメラをどう配置しているのかが分からない、ドキュメンタリー映画としては”あり得ない”映像であることにも驚かされた。また、悲惨な経験を軽妙に語る者たちの雰囲気も印象的な作品である
あわせて読みたい
金沢&富山のアート旅!「21世紀美術館」だけじゃない激アツなおすすめ美術館巡りをご提案
金沢・富山を巡るアート旅に出かけてきました!メインの目的は「21世紀美術館」でしたが、それ以上に「ASTER Curator Museum」「LIP BAR」「KAMU kanazawa」などがとにかく素晴らしかったです。アートや美術のことはド素人ですが、超個人的主観で「金沢・富山で触れられるアートの良さ」について書いた旅行記となります
あわせて読みたい
【奇妙】大栗博司『重力とはなにか』は、相対性理論や量子力学の説明も秀逸だが、超弦理論の話が一番面白い
『重力とはなにか』(大栗博司)は、科学に馴染みの薄い人でもチャレンジできる易しい入門書だ。相対性理論や量子力学、あるいは超弦理論など、非常に難解な分野を基本的なところから平易に説明してくれるので、「科学に興味はあるけど難しいのはちょっと……」という方にこそ読んでほしい1冊
あわせて読みたい
【映画】『街は誰のもの?』という問いは奥深い。「公共」の意味を考えさせる問題提起に満ちた作品
映画『街は誰のもの?』は、タイトルの通り「街(公共)は誰のものなのか?」を問う作品だ。そしてそのテーマの1つが、無許可で街中に絵を描く「グラフィティ」であることもまた面白い。想像もしなかった問いや価値観に直面させられる、とても興味深い作品である
あわせて読みたい
【倫理】アート体験の行き着く未来は?映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』が描く狂気の世界(…
「『痛み』を失った世界」で「自然発生的に生まれる新たな『臓器』を除去するライブパフォーマンス」を行うソール・テンサーを主人公にした映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』は、すぐには答えの見出しにくい「境界線上にある事柄」を挑発的に描き出す、実に興味深い物語だ
あわせて読みたい
【狂気?】オウム真理教を内部から映す映画『A』(森達也監督)は、ドキュメンタリー映画史に残る衝撃作だ
ドキュメンタリー映画の傑作『A』(森達也)をようやく観られた。「オウム真理教は絶対悪だ」というメディアの報道が凄まじい中、オウム真理教をその内部からフラットに映し出した特異な作品は、公開当時は特に凄まじい衝撃をもたらしただろう。私たちの「当たり前」が解体されていく斬新な一作
あわせて読みたい
【知的】「BLって何?」という初心者に魅力を伝える「腐男子」の「BLの想像力と創造力」講座:『ボクた…
「BLは知的遊戯である」という主張には「は?」と感じてしまうでしょうが、本書『ボクたちのBL論』を読めばその印象は変わるかもしれません。「余白の発見と補完」を通じて、「ありとあらゆる2者の間の関係性を解釈する」という創造性は、現実世界にどのような影響を与えているのか
あわせて読みたい
【勝負】実話を基にコンピューター将棋を描く映画『AWAKE』が人間同士の対局の面白さを再認識させる
実際に行われた将棋の対局をベースにして描かれる映画『AWAKE』は、プロ棋士と将棋ソフトの闘いを「人間ドラマ」として描き出す物語だ。年に4人しかプロ棋士になれない厳しい世界においては、「夢破れた者たち」もまた魅力的な物語を有している。光と影を対比的に描き出す、見事な作品
あわせて読みたい
【挑発】「TBS史上最大の問題作」と評されるドキュメンタリー『日の丸』(構成:寺山修司)のリメイク映画
1967年に放送された、寺山修司が構成に関わったドキュメンタリー『日の丸』は、「TBS史上最大の問題作」と評されている。そのスタイルを踏襲して作られた映画『日の丸~それは今なのかもしれない~』は、予想以上に面白い作品だった。常軌を逸した街頭インタビューを起点に様々な思考に触れられる作品
あわせて読みたい
【思考】文章の書き方が分かんない、トレーニングしたいって人はまず、古賀史健の文章講義の本を読め:…
古賀史健『20歳の自分に受けさせたい文章講義』は、「具体的なテクニック」ではない記述も非常に興味深い1冊だ。「なぜ文章を書く必要があるのか」という根本的な部分から丁寧に掘り下げる本書は、「書くからこそ考えられる」という、一般的なイメージとは逆だろう発想が提示される
あわせて読みたい
【革命】観る将必読。「将棋を観ること」の本質、より面白くなる見方、そして羽生善治の凄さが満載:『…
野球なら「なんで今振らないんだ!」みたいな素人の野次が成立するのに、将棋は「指せなきゃ観てもつまらない」と思われるのは何故か。この疑問を起点に、「将棋を観ること」と「羽生善治の凄さ」に肉薄する『羽生善治と現代』は、「将棋鑑賞」をより面白くしてくれる話が満載
あわせて読みたい
【驚異】数学の「無限」は面白い。アキレスと亀の矛盾、実無限と可能無限の違い、カントールの対角線論…
日常の中で「無限」について考える機会などなかなか無いだろうが、野矢茂樹『無限論の教室』は、「無限には種類がある」と示すメチャクチャ興味深い作品だった。「実無限」と「可能無限」の違い、「可能無限」派が「カントールの対角線論法」を拒絶する理由など、面白い話題が満載の1冊
あわせて読みたい
【挑戦】相対性理論の光速度不変の原理を無視した主張『光速より速い光』は、青木薫訳だから安心だぞ
『光速より速い光』というタイトルを見て「トンデモ本」だと感じた方、安心してほしい。「光速変動理論(VSL理論)」が正しいかどうかはともかくとして、本書は実に真っ当な作品だ。「ビッグバン理論」の欠陥を「インフレーション理論」以外の理屈で補う挑戦的な仮説とは?
あわせて読みたい
【未知】「占い」が占い以外の効果を有するように、UFOなど「信じたいものを信じる」行為の機能を知れる…
「占い」に「見透かされたから仕方なく話す」という効用があるように、「『未知のもの』を信じる行為」には「『否定されたという状態』に絶対に達しない」という利点が存在する。映画『虚空門GATE』は、UFOを入り口に「『未知のもの』を信じる行為」そのものを切り取る
あわせて読みたい
【幸福】「死の克服」は「生の充実」となり得るか?映画『HUMAN LOST 人間失格』が描く超管理社会
アニメ映画『HUMAN LOST 人間失格』では、「死の克服」と「管理社会」が分かちがたく結びついた世界が描かれる。私たちは既に「緩やかな管理社会」を生きているが、この映画ほどの管理社会を果たして許容できるだろうか?そしてあなたは、「死」を克服したいと願うだろうか?
あわせて読みたい
【おすすめ】江戸川乱歩賞受賞作、佐藤究『QJKJQ』は、新人のデビュー作とは思えない超ド級の小説だ
江戸川乱歩賞を受賞した佐藤究デビュー作『QJKJQ』はとんでもない衝撃作だ。とても新人作家の作品とは思えない超ド級の物語に、とにかく圧倒されてしまう。「社会は『幻想』を共有することで成り立っている」という、普段なかなか意識しない事実を巧みにちらつかせた、魔術のような作品
あわせて読みたい
【特異】「カメラの存在」というドキュメンタリーの大前提を覆す映画『GUNDA/グンダ』の斬新さ
映画『GUNDA/グンダ』は、「カメラの存在」「撮影者の意図」を介在させずにドキュメンタリーとして成立させた、非常に異端的な作品だと私は感じた。ドキュメンタリーの「デュシャンの『泉』」と呼んでもいいのではないか。「家畜」を被写体に据えたという点も非常に絶妙
あわせて読みたい
【化石】聞き馴染みのない「分子生物学」を通じて、科学という学問の本質を更科功が分かりやすく伝える…
映画『ジュラシック・パーク』を観たことがある方なら、「コハクの化石に閉じ込められた蚊の血液から恐竜の遺伝子を取り出す」という設定にワクワクしたことだろう。『化石の分子生物学』とは、まさにそのような研究を指す。科学以外の分野にも威力を発揮する知見に溢れた1冊
あわせて読みたい
【不思議】森達也が「オカルト」に挑む本。「科学では説明できない現象はある」と否定も肯定もしない姿…
肯定派でも否定派でもない森達也が、「オカルト的なもの」に挑むノンフィクション『オカルト』。「現象を解釈する」ことよりも、「現象を記録する」こと点に注力し、「そのほとんどは勘違いや見間違いだが、本当に説明のつかない現象も存在する」というスタンスで追いかける姿勢が良い
あわせて読みたい
【感想】リドリー・スコット監督の映画『最後の決闘裁判』から、社会が”幻想”を共有する背景とその悲劇…
例えば、「1万円札」というただの紙切れに「価値を感じる」のは、社会の構成員が同じ「共同幻想」の中に生きているからだ。リドリー・スコット監督の映画『最後の決闘裁判』は、「強姦では妊娠しない」「裁判の勝者を決闘で決する」という社会通念と、現代にも通じる「共同幻想」の強さを描き出す
あわせて読みたい
【抽象】「思考力がない」と嘆く人に。研究者で小説家の森博嗣が語る「客観的に考える」ために大事なこ…
世の中にはあまりに「具体的な情報」が溢れているために、「客観的、抽象的な思考」をする機会が少ない。そんな時代に、いかに思考力を育てていくべきか。森博嗣が『人間はいろいろな問題についてどう考えていけば良いのか』を通じて伝える「情報との接し方」「頭の使い方」
あわせて読みたい
【感想】才能の開花には”極限の環境”が必要か?映画『セッション』が描く世界を私は否定したい
「追い込む指導者」が作り出す”極限の環境”だからこそ、才能が開花する可能性もあるとは思う。しかし、そのような環境はどうしても必要だろうか?最高峰の音楽院での壮絶な”指導”を描く映画『セッション』から、私たちの生活を豊かにしてくれるものの背後にある「死者」を想像する
あわせて読みたい
【認識】「固定観念」「思い込み」の外側に出るのは難しい。自分はどんな「へや」に囚われているのか:…
実際に起こった衝撃的な事件に着想を得て作られた映画『ルーム』は、フィクションだが、観客に「あなたも同じ状況にいるのではないか?」と突きつける力強さを持っている。「普通」「当たり前」という感覚に囚われて苦しむすべての人に、「何に気づけばいいか」を気づかせてくれる作品
あわせて読みたい
【本質】子どもの頃には読めない哲学書。「他人の哲学はつまらない」と語る著者が説く「問うこと」の大…
『<子ども>のための哲学』は決して、「子どもでも易しく理解できる哲学の入門書」ではない。むしろかなり難易度が高いと言っていい。著者の永井均が、子どもの頃から囚われ続けている2つの大きな疑問をベースに、「『哲学する』とはどういうことか?」を深堀りする作品
あわせて読みたい
【最新】「コロンブス到達以前のアメリカ大陸」をリアルに描く歴史書。我々も米国人も大いに誤解してい…
サイエンスライターである著者は、「コロンブス到着以前のアメリカはどんな世界だったか?」という問いに触れ、その答えが書かれた本がいつまで経っても出版されないので自分で執筆した。『1491 先コロンブス期アメリカ大陸をめぐる新発見』には、アメリカ人も知らない歴史が満載だ
あわせて読みたい
【博覧強記】「紙の本はなくなる」説に「文化は忘却されるからこそ価値がある」と反論する世界的文学者…
世界的文学者であり、「紙の本」を偏愛するウンベルト・エーコが語る、「忘却という機能があるから書物に価値がある」という主張は実にスリリングだ。『もうすぐ絶滅するという紙の書物について』での対談から、「忘却しない電子データ」のデメリットと「本」の可能性を知る
あわせて読みたい
【飛躍】有名哲学者は”中二病”だった?飲茶氏が易しく語る「古い常識を乗り越えるための哲学の力」:『1…
『14歳からの哲学入門』というタイトルは、「14歳向けの本」という意味ではなく、「14歳は哲学することに向いている」という示唆である。飲茶氏は「偉大な哲学者は皆”中二病”だ」と説き、特に若い人に向けて、「新しい価値観を生み出すためには哲学が重要だ」と語る
あわせて読みたい
【おすすめ】濱口竜介監督の映画『親密さ』は、「映像」よりも「言葉」が前面に来る衝撃の4時間だった
専門学校の卒業制作として濱口竜介が撮った映画『親密さ』は、2時間10分の劇中劇を組み込んだ意欲作。「映像」でありながら「言葉の力」が前面に押し出される作品で、映画や劇中劇の随所で放たれる「言葉」に圧倒される。4時間と非常に長いが、観て良かった
あわせて読みたい
【歴史】ベイズ推定は現代社会を豊かにするのに必須だが、実は誕生から200年間嫌われ続けた:『異端の統…
現在では、人工知能を始め、我々の生活を便利にする様々なものに使われている「ベイズ推定」だが、その基本となるアイデアが生まれてから200年近く、科学の世界では毛嫌いされてきた。『異端の統計学ベイズ』は、そんな「ベイズ推定」の歴史を紐解く大興奮の1冊だ
あわせて読みたい
【興奮】世界的大ベストセラー『サピエンス全史』要約。人類が文明を築き上げるに至った3つの革命とは?
言わずと知れた大ベストセラー『サピエンス全史』は、「何故サピエンスだけが人類の中で生き残り、他の生物が成し得なかった歴史を歩んだのか」を、「認知革命」「農業革命」「科学革命」の3つを主軸としながら解き明かす、知的興奮に満ち溢れた1冊
あわせて読みたい
【興奮】飲茶氏の超面白い哲学小説。「正義とは?」の意味を問う”3人の女子高生”の主張とは?:『正義の…
なんて面白いんだろうか。哲学・科学を初心者にも分かりやすく伝える飲茶氏による『正義の教室』は、哲学書でありながら、3人の女子高生が登場する小説でもある。「直観主義」「功利主義」「自由主義」という「正義論」の主張を、「高校の問題について議論する生徒会の話し合い」から学ぶ
あわせて読みたい
【天才】読書猿のおすすめ本。「いかにアイデアを生むか」の発想法を人文書に昇華させた斬新な1冊:『ア…
「独学の達人」「博覧強記の読書家」などと評される読書猿氏が、古今東西さまざまな「発想法」を1冊にまとめた『アイデア大全』は、ただのHow To本ではない。「発想法」を学問として捉え、誕生した経緯やその背景なども深堀りする、「人文書」としての一面も持つ作品だ
あわせて読みたい
【驚異】ガイア理論の提唱者が未来の地球を語る。100歳の主張とは思えない超絶刺激に満ちた内容:『ノヴ…
「地球は一種の生命体だ」という主張はかなり胡散臭い。しかし、そんな「ガイア理論」を提唱する著者は、数々の賞や学位を授与される、非常に良く知られた科学者だ。『ノヴァセン <超知能>が地球を更新する』から、AIと人類の共存に関する斬新な知見を知る
あわせて読みたい
【感想】飲茶の超面白い東洋哲学入門書。「本書を読んでも東洋哲学は分からない」と言う著者は何を語る…
東洋哲学というのは、「最終回しか存在しない連続ドラマ」のようなものだそうだ。西洋哲学と比較にならないほど異質さと、インド哲学・中国哲学など個別の思想を恐ろしく分かりやすく描く『史上最強の哲学入門 東洋の哲人たち』は、ページをめくる手が止まらないくらい、史上最強レベルに面白かった
あわせて読みたい
【興奮】飲茶氏が西洋哲学を語る。難解な思想が「グラップラー刃牙成分」の追加で驚異的な面白さに:『…
名前は聞いたことはあるがカントやニーチェがどんな主張をしたのかは分からないという方は多いだろう。私も無知なまったくの初心者だが、そんな人でも超絶分かりやすく超絶面白く西洋哲学を”分かった気になれる”飲茶『史上最強の哲学入門』は、入門書として最強
あわせて読みたい
【権威】心理学の衝撃実験をテレビ番組の収録で実践。「自分は残虐ではない」と思う人ほど知るべき:『…
フランスのテレビ局が行った「現代版ミルグラム実験」の詳細が語られる『死のテレビ実験 人はそこまで服従するのか』は、「権威」を感じる対象から命じられれば誰もが残虐な行為をしてしまい得ることを示す。全人類必読の「過ちを事前に回避する」ための知見を学ぶ
あわせて読みたい
【教養】美術を「感じたまま鑑賞する」のは難しい。必要な予備知識をインストールするための1冊:『武器…
芸術を「感性の赴くまま見る」のは、日本特有だそうだ。欧米では美術は「勉強するもの」と認識されており、本書ではアートを理解しようとするスタンスがビジネスにも役立つと示唆される。美術館館長を務める著者の『武器になる知的教養 西洋美術鑑賞』から基礎の基礎を学ぶ
あわせて読みたい
【驚嘆】この物語は「AIの危険性」を指摘しているのか?「完璧な予知能力」を手にした人類の過ち:『預…
完璧な未来予知を行えるロボットを開発し、地震予知のため”だけ”に使おうとしている科学者の自制を無視して、その能力が解放されてしまう世界を描くコミック『預言者ピッピ』から、「未来が分からないからこそ今を生きる価値が生まれるのではないか」などについて考える
あわせて読みたい
【平易】ブラックホールを分かりやすく知りたい。難しいことは抜きにふわっと理解するための1冊:『ブラ…
2019年に初めて直接観測されるも、未だに謎多き天体である「ブラックホール」について現役研究者が分かりやすく語る『ブラックホールをのぞいてみたら』をベースに、科学者がその存在を認めてこなかった歴史や、どんな性質を持つ天体なのかを理解する
あわせて読みたい
【幻想】超ひも理論って何?一般相対性理論と量子力学を繋ぐかもしれないぶっ飛んだ仮説:『大栗先生の…
『大栗先生の超弦理論入門』は最先端科学である「超弦理論」を説明する1冊だが、この記事では著者の主張の1つである「空間は幻想かもしれない」という発想を主に取り上げる。「人類史上初の『適用する次元が限定される理論』」が描像する不可思議な世界とは?
あわせて読みたい
【限界】「科学とは何か?」を知るためのおすすめ本。科学が苦手な人こそ読んでほしい易しい1冊:『哲学…
「科学的に正しい」という言葉は、一体何を意味しているのだろう?科学者が「絶対に正しい」とか「100%間違っている」という言い方をしないのは何故だろう?飲茶『哲学的な何か、あと科学とか』から、「科学とはどんな営みなのか?」について考える
あわせて読みたい
【戸惑】人間の脳は摩訶不思議。意識ではコントロールできない「無意識の領域」に支配されている:『あ…
我々は決断や選択を「自分の意思」で行っていると感じるが、脳科学の研究はそれを否定している。我々に「自由意志」などない。「脳」の大部分は「意識以外のもの」に支配され、そこに「意識」はアクセスできないという驚愕の実態を『あなたの知らない脳』から学ぶ
あわせて読みたい
【快挙】「暗黒の天体」ブラックホールはなぜ直接観測できたのか?国際プロジェクトの舞台裏:『アイン…
「世界中に存在する電波望遠鏡を同期させてブラックホールを撮影する」という壮大なEHTプロジェクトの裏側を記した『アインシュタインの影』から、ブラックホール撮影の困難さや、「ノーベル賞」が絡む巨大プロジェクトにおける泥臭い人間ドラマを知る
あわせて読みたい
【快挙】「チバニアン」は何が凄い?「地球の磁場が逆転する」驚異の現象がこの地層を有名にした:『地…
一躍その名が知れ渡ることになった「チバニアン」だが、なぜ話題になり、どう重要なのかを知っている人は多くないだろう。「チバニアン」の申請に深く関わった著者の『地磁気逆転と「チバニアン」』から、地球で起こった過去の不可思議な現象の正体を理解する
あわせて読みたい
【貢献】有名な科学者は、どんな派手な失敗をしてきたか?失敗が失敗でなかったアインシュタインも登場…
どれほど偉大な科学者であっても失敗を避けることはできないが、「単なる失敗」で終わることはない。誤った考え方や主張が、プラスの効果をもたらすこともあるのだ。『偉大なる失敗』から、天才科学者の「失敗」と、その意外な「貢献」を知る
あわせて読みたい
【平易】一般相対性理論を簡単に知りたい方へ。ブラックホール・膨張宇宙・重力波と盛りだくさんの1冊:…
現役の研究者が執筆した『ブラックホール・膨張宇宙・重力波』は、アインシュタインが導き出した一般相対性理論が関わる3つのテーマについて、初心者にも分かりやすく伝える内容になっている。歴史的背景も含めて科学的知見を知りたい方にオススメの1冊
あわせて読みたい
【逸話】天才数学者ガロアが20歳で決闘で命を落とすまでの波乱万丈。時代を先駆けた男がもし生きていた…
現代数学に不可欠な「群論」をたった1人で生み出し、20歳という若さで決闘で亡くなったガロアは、その短い生涯をどう生きたのか?『ガロア 天才数学者の生涯』から、数学に関心を抱くようになったきっかけや信じられないほどの不運が彼の人生をどう変えてしまったのか、そして「もし生きていたらどうなっていたのか」を知る
あわせて読みたい
【誤解】「意味のない科学研究」にはこんな価値がある。高校生向けの講演から”科学の本質”を知る:『す…
科学研究に対して、「それは何の役に立つんですか?」と問うことは根本的に間違っている。そのことを、「携帯電話」と「東急ハンズの棚」の例を使って著者は力説する。『すごい実験』は素粒子物理学を超易しく解説する本だが、科学への関心を抱かせてもくれる
あわせて読みたい
【バトル】量子力学の歴史はこの1冊で。先駆者プランクから批判者アインシュタインまですべて描く:『量…
20世紀に生まれた量子論は、時代を彩る天才科学者たちの侃々諤々の議論から生み出された。アインシュタインは生涯量子論に反対し続けたことで知られているが、しかし彼の批判によって新たな知見も生まれた。『量子革命』から、量子論誕生の歴史を知る
あわせて読みたい
【到達】「ヒッグス粒子の発見」はなぜ大ニュースなのか?素粒子物理学の「標準模型」を易しく説明する…
「ヒッグス粒子の発見」はメディアでも大きく取り上げられたが、これが何故重要なのかを説明できる人はそう多くはないだろう。『強い力と弱い力 ヒッグス粒子が宇宙にかけた魔法を解く』をベースに、謎めいた「弱い力」を説明する「自発的対称性の破れ」を学ぶ
あわせて読みたい
【ドラマ】「フェルマーの最終定理」のドラマティックな証明物語を、飲茶氏が平易に描き出す:『哲学的…
「フェルマーの最終定理」は、問題の提示から350年以上経ってようやく証明された超難問であり、その証明の過程では様々な人間ドラマが知られている。『哲学的な何か、あと数学とか』をベースに、数学的な記述を一切せず、ドラマティックなエピソードだけに触れる
あわせて読みたい
【不可思議】心理学の有名な実験から、人間の”欠陥”がどう明らかになっていったかを知る:『心は実験で…
『心は実験できるか 20世紀心理学実験物語』では、20世紀に行われた心理学実験からインパクトのある10の実験を選び紹介している。心理学者でもある著者が「科学であって科学ではない」と主張する心理学という学問で、人間のどんな不可思議さがあぶり出されてきたのかを知る
あわせて読みたい
【神秘】脳研究者・池谷裕二が中高生向けに行った講義の書籍化。とても分かりやすく面白い:『進化しす…
「宇宙」「深海」「脳」が、人類最後のフロンティアと呼ばれている。それほど「脳」というのは、未だに分からないことだらけの不思議な器官だ。池谷裕二による中高生向けの講義を元にした『進化しすぎた脳』『単純な脳、複雑な「私」』をベースに、脳の謎を知る
あわせて読みたい
【論争】サイモン・シンが宇宙を語る。古代ギリシャからビッグバンモデルの誕生までの歴史を網羅:『宇…
古代から現代に至るまで、「宇宙」は様々な捉えられ方をしてきた。そして、新たな発見がなされる度に、「宇宙」は常識から外れた不可思議な姿を垣間見せることになる。サイモン・シン『宇宙創成』をベースに、「ビッグバンモデル」に至るまでの「宇宙観」の変遷を知る
あわせて読みたい
【挑戦】社会に欠かせない「暗号」はどう発展してきたか?サイモン・シンが、古代から量子暗号まで語る…
「暗号」は、ミステリやスパイの世界だけの話ではなく、インターネットなどのセキュリティで大活躍している、我々の生活に欠かせない存在だ。サイモン・シン『暗号解読』から、言語学から数学へとシフトした暗号の変遷と、「鍵配送問題」を解決した「公開鍵暗号」の仕組みを理解する
あわせて読みたい
【衝撃】ABC予想の証明のために生まれたIUT理論を、提唱者・望月新一の盟友が分かりやすく語る:『宇宙…
8年のチェック期間を経て雑誌に掲載された「IUT理論(宇宙際タイヒミュラー理論)」は、数学の最重要未解決問題である「ABC予想」を証明するものとして大いに話題になった。『宇宙と宇宙をつなぐ数学』『abc予想入門』をベースに、「IUT理論」「ABC予想」について学ぶ
あわせて読みたい
【限界】有名な「錯覚映像」で心理学界をザワつかせた著者らが語る「人間はいかに間違えるか」:『錯覚…
私たちは、知覚や記憶を頼りに社会を生きている。しかしその「知覚」「記憶」は、本当に信頼できるのだろうか?心理学の世界に衝撃を与えた実験を考案した著者らの『錯覚の科学』から、「避けられない失敗のクセ」を理解する
あわせて読みたい
【変人】結城浩「数学ガール」から、1億円も名誉ある賞も断った天才が証明したポアンカレ予想を学ぶ
1億円の賞金が懸けられた「ポアンカレ予想」は、ペレルマンという天才数学者が解き明かしたが、1億円もフィールズ賞も断った。そんな逸話のある「ポアンカレ予想」とは一体どんな主張であり、どのように証明されたのかを結城浩『数学ガール』から学ぶ
あわせて読みたい
【興奮】結城浩「数学ガール」で、決闘で命を落とした若き天才数学者・ガロアの理論を学ぶ
高校生を中心に、数学を通じて関わり合う者たちを描く「数学ガール」シリーズ第5弾のテーマは「ガロア理論」。独力で「群論」という新たな領域を切り開きながら、先駆的すぎて同時代の数学者には理解されず、その後決闘で死亡した天才の遺した思考を追う
あわせて読みたい
【誤り】「信じたいものを信じる」のは正しい?映画『星の子』から「信じること」の難しさを考える
どんな病気も治す「奇跡の水」の存在を私は信じないが、しかし何故「信じない」と言えるのか?「奇跡の水を信じる人」を軽々に非難すべきではないと私は考えているが、それは何故か?映画『星の子』から、「何かを信じること」の難しさについて知る
あわせて読みたい
【刺激】結城浩「数学ガール」で、ゲーデルの不完全性定理(不可能性の証明として有名)を学ぶ
『結城浩「数学ガール」シリーズは、数学の面白さを伝えながら、かなり高難度の話題へと展開していく一般向けの数学書です。その第3弾のテーマは、「ゲーデルの不完全性定理」。ヒルベルトという数学者の野望を打ち砕いた若き天才の理論を学びます
あわせて読みたい
【天才】科学者とは思えないほど面白い逸話ばかりのファインマンは、一体どんな業績を残したのか?:『…
数々の面白エピソードで知られるファインマンの「科学者としての業績」を初めて網羅したと言われる一般書『ファインマンさんの流儀』をベースに、その独特の研究手法がもたらした様々な分野への間接的な貢献と、「ファインマン・ダイアグラム」の衝撃を理解する
あわせて読みたい
【使命】「CRISPR-Cas9」を分かりやすく説明。ノーベル賞受賞の著者による発見物語とその使命:『CRISPR…
生物学の研究を一変させることになった遺伝子編集技術「CRISPR-Cas9」の開発者は、そんな発明をするつもりなどまったくなかった。ノーベル化学賞を受賞した著者による『CRISPR (クリスパー) 究極の遺伝子編集技術の発見』をベースに、その発見物語を知る
あわせて読みたい
【研究】光の量子コンピュータの最前線。量子テレポーテーションを実現させた科学者の最先端の挑戦:『…
世界中がその開発にしのぎを削る「量子コンピューター」は、技術的制約がかなり高い。世界で初めて「量子テレポーテーション」の実験を成功させた研究者の著書『光の量子コンピューター』をベースに、量子コンピューター開発の現状を知る
あわせて読みたい
【異端】数学の”証明”はなぜ生まれたのか?「無理数」と「無限」に恐怖した古代ギリシャ人の奮闘:『数…
学校で数学を習うと、当然のように「証明」が登場する。しかしこの「証明」、実は古代ギリシャでしか発展しなかった、数学史においては非常に”異端”の考え方なのだ。『数学の想像力 正しさの深層に何があるのか』をベースに、ギリシャ人が恐れたものの正体を知る
あわせて読みたい
【対立】数学はなぜ”美しい”のか?数学は「発見」か「発明」かの議論から、その奥深さを知る:『神は数…
数学界には、「数学は神が作った派」と「数学は人間が作った派」が存在する。『神は数学者か?』をベースに、「数学は発見か、発明か」という議論を理解し、数学史においてそれぞれの認識がどのような転換点によって変わっていったのかを学ぶ
あわせて読みたい
【始まり】宇宙ができる前が「無」なら何故「世界」が生まれた?「ビッグバンの前」は何が有った?:『…
「宇宙がビッグバンから生まれた」ことはよく知られているだろうが、では、「宇宙ができる前はどうなっていたのか」を知っているだろうか? 実は「宇宙は”無”から誕生した」と考えられているのだ。『宇宙が始まる前には何があったのか?』をベースに、ビッグバンが起こる前の「空間も時間も物理法則も存在しない無」について学ぶ
あわせて読みたい
【謎】恐竜を絶滅させた隕石はどこから来た?暗黒物質が絡む、リサ・ランドールの驚愕の仮説:『ダーク…
「生物の絶滅」には、以前から知られていたある謎があった。そしてその謎を、未だに観測されておらず、「科学者の妄想の産物」でしかない「ダークマター(暗黒物質)」が解決するかもしれない。現役の科学者が『ダークマターと恐竜絶滅』で語る驚きの仮説。
あわせて読みたい
【未知】タコに「高度な脳」があるなんて初耳だ。人類とは違う進化を遂げた頭足類の「意識」とは?:『…
タコなどの頭足類は、無脊椎動物で唯一「脳」を進化させた。まったく違う進化を辿りながら「タコに心を感じる」という著者は、「タコは地球外生命体に最も近い存在」と書く。『タコの心身問題』から、腕にも脳があるタコの進化の歴史と、「意識のあり方」を知る。
あわせて読みたい
【天才】数学の捉え方を一変させた「シンメトリー(対称性)」と、その発見から発展に至る歴史:『シン…
「5次方程式の解の公式は存在しない」というアーベルの証明や、天才・ガロアが発展させた「群論」は、「シンメトリー(対称性)」という領域に新たな光を当てた。『シンメトリーの地図帳』をベースに、「シンメトリー」の発展と「モンスター」の発見の物語を知る
あわせて読みたい
【敗北】「もつれ」から量子論の基礎を学ぶ。それまでの科学では説明不能な「異次元の現象」とは?:『…
アインシュタインは量子力学を生涯受け入れなかったのだが、アインシュタインが批判し続けたことによって明らかになったこともある。「もつれ」の重要性もその一つだ。『宇宙は「もつれ」でできている』から量子力学の基礎を成す現象を知る。
あわせて読みたい
【嫉妬?】ヒッグス粒子はいかに発見されたか?そして科学の”発見”はどう評価されるべきか?:『ヒッグ…
科学研究はもはや個人単位では行えず、大規模な「ビッグサイエンス」としてしか成立しなくなっている。そんな中で、科学研究の成果がどう評価されるべきかなどについて、「ヒッグス粒子」発見の舞台裏を追った『ヒッグス 宇宙の最果ての粒子』をベースに書く
あわせて読みたい
【興奮】素数の謎に迫った天才数学者たちの奮闘と、数学の”聖杯”である「リーマン予想」について:『素…
古今東西の数学者を惹きつけて止まない「素数」。その規則性を見つけ出すことは非常に困難だったが、「リーマン予想」として初めてそれが示された。『素数の音楽』『リーマン博士の大予想』から、天才数学者たちが挑んできた「リーマン予想」をざっくり理解する
あわせて読みたい
【究極】リサ・ランドールが「重力が超弱い理由」を解説する、超刺激的なひも理論の仮説:『ワープする…
現役の研究者であるリサ・ランドールが、自身の仮説を一般向けに分かりやすく説明する『ワープする宇宙』。一般相対性理論・量子力学の知識を深く記述しつつ「重力が超弱い理由」を説明する、ひも理論から導かれる「ワープする余剰次元」について解説する
あわせて読みたい
【解説】テネットの回転ドアの正体を分かりやすく考察。「時間逆行」ではなく「物質・反物質反転」装置…
クリストファー・ノーラン監督の映画『TENET/テネット』は、「陽電子」「反物質」など量子力学の知見が満載です。この記事では、映画の内容そのものではなく、時間反転装置として登場する「回転ドア」をメインにしつつ、時間逆行の仕組みなど映画全体の設定について科学的にわかりやすく解説していきます
あわせて読みたい
【驚嘆】人類はいかにして言語を獲得したか?この未解明の謎に真正面から挑む異色小説:『Ank: a mirror…
小説家の想像力は無限だ。まさか、「人類はいかに言語を獲得したか?」という仮説を小説で読めるとは。『Ank: a mirroring ape』をベースに、コミュニケーションに拠らない言語獲得の過程と、「ヒト」が「ホモ・サピエンス」しか存在しない理由を知る
あわせて読みたい
【情報】日本の社会問題を”祈り”で捉える。市場原理の外にあるべき”歩哨”たる裁き・教育・医療:『日本…
「霊性」というテーマは馴染みが薄いし、胡散臭ささえある。しかし『日本霊性論』では、「霊性とは、人間社会が集団を存続させるために生み出した機能」であると主張する。裁き・教育・医療の変化が鈍い真っ当な理由と、情報感度の薄れた現代人が引き起こす問題を語る
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
哲学・思想【本・映画の感想】 | ルシルナ
私の知識欲は多方面に渡りますが、その中でも哲学や思想は知的好奇心を強く刺激してくれます。ニーチェやカントなどの西洋哲学も、禅や仏教などの東洋哲学もとても奥深いも…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…

































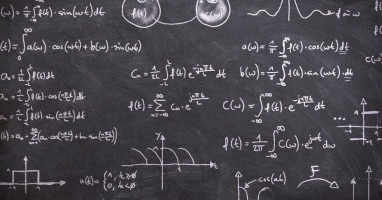

































































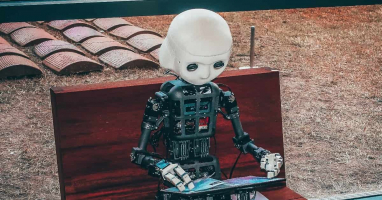
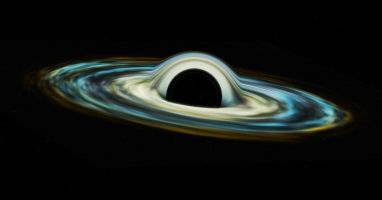










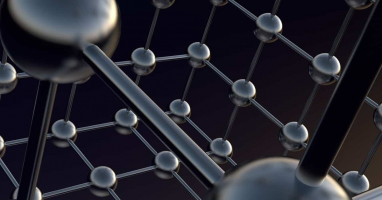













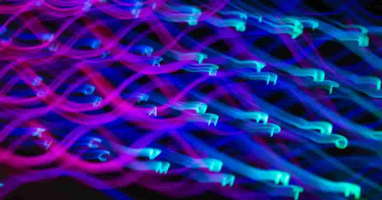
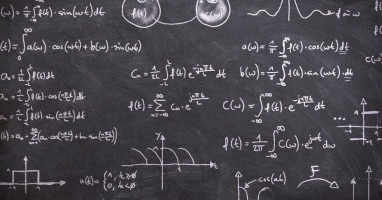


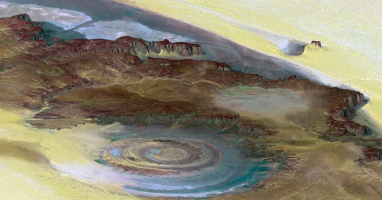


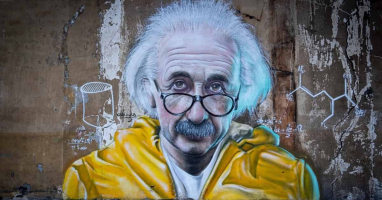

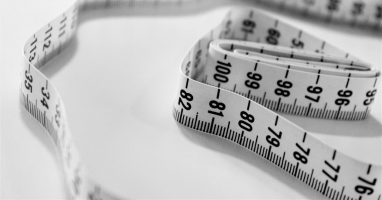

















コメント