目次
はじめに
この記事で取り上げる本
著:砥上裕將
¥858 (2022/10/02 19:10時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
この記事で伝えたいこと
「孤独」に囚われる主人公の葛藤が、「水墨画」の世界と見事に調和する物語
「水墨画は技術ではない」という要素が、主人公の挑戦にリアリティを与える
この記事の3つの要点
- 「言葉」でも「絵」でも、世界を”正確に”捉えることはほとんど不可能
- 「完成させた絵」以上に、「その絵をいかに描いたかという過程」にこそ水墨画の本質がある
- 『主人公の「孤独」が、あり得ないはずの奇跡をリアルに感じさせる
横浜流星主演で映画化もされる話題作であり、青春小説の中に哲学的な思考が詰まった見事な小説
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!「文章の書き方が分からない」「文章力がないから鍛えたい」という方にオススメ…
「文章の書き方」についてのKindle本を出版しました。「文章が書けない」「どう書いたらいいか分からない」「文章力を向上させたい」という方の悩みを解消できるような本に仕上げたつもりです。数多くの文章を書き、さらに頼まれて文章を推敲してきた経験を踏まえ、「文章を書けるようになるにはどうしたらいいか」についての私なりの考えをまとめました。
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!「それってホントに『コミュ力』が高いって言えるの?」と疑問を感じている方に…
私は、「コミュ力が高い人」に関するよくある主張に、どうも違和感を覚えてしまうことが多くあります。そしてその一番大きな理由が、「『コミュ力が高い人』って、ただ『想像力がない』だけではないか?」と感じてしまう点にあると言っていいでしょう。出版したKindle本は、「ネガティブには見えないネガティブな人」(隠れネガティブ)を取り上げながら、「『コミュ力』って何だっけ?」と考え直してもらえる内容に仕上げたつもりです。
砥上裕將『線は、僕を描く』は、「技術に本質はない」という知られざる「水墨画」の世界を描きながら、無気力な若者の成長を描き出す傑作小説だ
あわせて読みたい
【特異】「カメラの存在」というドキュメンタリーの大前提を覆す映画『GUNDA/グンダ』の斬新さ
映画『GUNDA/グンダ』は、「カメラの存在」「撮影者の意図」を介在させずにドキュメンタリーとして成立させた、非常に異端的な作品だと私は感じた。ドキュメンタリーの「デュシャンの『泉』」と呼んでもいいのではないか。「家畜」を被写体に据えたという点も非常に絶妙
『線は、僕を描く』の中心テーマは「水墨画」です。世に数多ある小説の中でも、「水墨画」がメインになる作品はそうないでしょう。著者の砥上裕將は、若手水墨画家としても活躍しており、だからこそ、なかなか馴染みのない「水墨画」の世界をリアルに描き出せるのです。
どうしても、掛け軸とかによく描いてある「中国の川と絶壁」みたいな絵しか思い浮かべられない

主人公の青山霜介は、両親の死をきっかけに自らの殻に閉じこもってしまうのですが、「水墨画」をきっかけに変わっていきます。「弱々しい」という印象の主人公が、あちこちを彷徨い歩くような物語でありながら、読み応えとしては非常に骨太で、そのギャップがとても面白い作品です。その「骨太さ」は実は、彼が元々内側に秘めていた「人間としての強さ」であり、それが「水墨画」を通して明らかになるという展開が、とても見事に描かれています。
しかしこの記事ではまず、そういう人間的な部分ではなく、「水墨画というテーマが突きつける、実に哲学的な問い」について考えてみることにしましょう。本書を読めば、「水墨画」が他の芸術ジャンルとはちょっと一線を画すような存在だと理解できるはずです。その本質は一体なんなのかなどについてまずは考えてみたいと思います。
あわせて読みたい
【狂気】バケモン・鶴瓶を映し出す映画。「おもしろいオッチャン」に潜む「異常さ」と「芸への情熱」:…
「俺が死ぬまで公開するな」という条件で撮影が許可された映画『バケモン』。コロナ禍で映画館が苦境に立たされなければ、公開はずっと先だっただろう。テレビで見るのとは違う「芸人・笑福亭鶴瓶」の凄みを、古典落語の名作と名高い「らくだ」の変遷と共に切り取る
「言語化すること」は「細部を切り落とすこと」である
まずは、本書とは全然関係のない「言語化」の話をしようと思います。
私は、本や映画の感想を長々と書いているこのブログのように、私はこれまでずっと「文章を書くこと」を通じて色んな世界と関わってきました。大げさですが、「言葉を武器に闘ってきた」と言ってもいいかもしれません。その闘いを通じて、お金を稼いだり社会に影響を与えたりすることができたとは言えませんが、私なりに「闘ってきたなぁ」という実感はあります。
色んなことを止めたり飽きたりしてきたけど、20代から「文章を書くこと」だけはずっと続けてるもんね
ホント、自分の関心って最終的には「頭の中を言語化すること」しかないんだろうなっていつも思う
あわせて読みたい
【継続】「言語化できない」を乗り越えろ。「読者としての文章術」で、自分の思考をクリアにする:『読…
ブログやSNSなどが登場したことで、文章を書く機会は増えていると言える。しかし同時に、「他人に評価されるために書く」という意識も強くなっているだろう。『読みたいことを書けばいい』から、「楽しく書き”続ける”」ための心得を学ぶ
本や映画の感想を書くことで「自分が今何を考えているのか」を明確にしたり、書店員時代には、POPのフレーズを考えることによって「どうしたら本の魅力が伝わり得るか」などについて考えてきたりしたつもりです。そしてそういう経験を通じて実感したことは、「言語化能力によって、『見える世界』そのものに違いが生じる」ということでした。
唐突ですが、マーケティングの世界で有名なエピソードだろう、誰もが裸足で生活するアフリカに送られた靴のセールスマン2人の話を紹介しましょう。1人は「誰も靴なんか履いてないから、この国で靴は売れない」と考えるのに対し、もう1人は「誰も靴なんか履いてないから、この国で靴はメチャクチャ売れるぞ」と考えるという話です。これは「言語化能力」とは関係ない話ではありますが、「同じものを見ていても、捉え方はまったく違う」という例としては分かりやすいでしょう。そして、同じことが、「言語化能力」の差によっても起こる、というわけです。この点については、『彼女が好きなものは』の記事で詳しく書いたので読んでみてください。
これはつまり、「言語化する力を磨けば磨くほど、世界をより高解像度で捉えることができる」という意味でもあります。なんとなく理解していただけるでしょうか?

あわせて読みたい
【奇妙】映画『鯨の骨』は、主演のあのちゃんが絶妙な存在感を醸し出す、斬新な設定の「推し活」物語
映画『鯨の骨』は、主演を務めたあのちゃんの存在感がとても魅力的な作品でした。「AR動画のカリスマ的存在」である主人公を演じたあのちゃんは、役の設定が絶妙だったこともありますが、演技がとても上手く見え、また作品全体の、「『推し活』をある意味で振り切って描き出す感じ」もとても皮肉的で良かったです
しかし同時に、言語化能力を高めれば高めるほど、こんな風にも感じるようになりました。それは、「『言葉』では捉えられないものも存在する」ということです。
描こうとすれば、遠ざかる。
『線は、僕を描く』には、「描こうとすれば、遠ざかる」みたいな哲学っぽいフレーズが結構出てくるのよね
読後感はまさに青春小説って感じなんだけど、こういう描写があるから、ただそれだけの作品じゃないって印象も残る
どうしてなのか考えてみて、こういう結論に至りました。「言語化する」というのは「細部を切り落とすこと」だからだ、と。
あわせて読みたい
【抽象】「思考力がない」と嘆く人に。研究者で小説家の森博嗣が語る「客観的に考える」ために大事なこ…
世の中にはあまりに「具体的な情報」が溢れているために、「客観的、抽象的な思考」をする機会が少ない。そんな時代に、いかに思考力を育てていくべきか。森博嗣が『人間はいろいろな問題についてどう考えていけば良いのか』を通じて伝える「情報との接し方」「頭の使い方」
私たちが「言葉」によって表現したいと考えるものは無数に存在します。物質の名称・風景・感情・価値観・固有名詞などなど様々に存在し、さらにそれらは刻一刻と変化していくのです。ネットミームと化している、アンミカの「白色って200色あんねん」のように、「白色」1つとってもいくらでも細分化できてしまうので、「現実を構成する差異」をすべて「違うもの」と扱うのなら、「言葉が割り当てられるべき対象」は無限大に存在すると言っていいでしょう。
しかし当然ですが、「言葉」は有限個しかありません。基本的には辞書に載っている程度ですし、「まだ辞書に載せるほどメジャーではない言葉」や「あまり使われなくなったため辞書から削除された言葉」などを含めたとしても、「現実を構成する差異」すべてを賄えるほどの数があるはずもないでしょう。
命としての花も極限のところでは、刻々と姿を変えているのだ。(中略)命とはつまるところ、変化し続けるこの瞬間のことなのだ。
このように考えることで、「言語化すること」が「細部を切り落とすこと」だと理解できるようになります。「現実を構成する差異」よりも「言葉」の方が圧倒的に少ないのですから、何かに「言葉」を当てはめる時、「そのものをピッタリ表す言葉ではない」という状況は当たり前に生まれるでしょう。そういう状況に接した時に、「若者言葉」や「ネットスラング」のような「新しい言葉」が生まれるのかもしれません。しかし、そうやって生まれた「新しい言葉」も、時間経過と共にすぐ「ピッタリの言葉」ではなくなってしまうでしょう。つまりほとんどの場合、「言葉」は「現実を構成する差異をピッタリ表現するもの」ではないということになるのです。
あわせて読みたい
【表現】映画『名付けようのない踊り』で初めて見た田中泯のダンス。「芸術以前」を志向する圧倒的パワー
映画『名付けようのない踊り』の中で田中泯は言う。「私」や「個性」を表現することには違和感がある、と。「踊りのために身体を作る」のではなく、「野良仕事で出来た身体で踊る」のだ、と。芸術になる前の踊りを探したい、と。「唯一無二の表現者」の生涯と現在地を映し出すドキュメンタリー
だからといって、なんでも「ヤバい」で済ませる会話も「ヤバい」と思うけどね
こう考えることで、「現実を言語化すること」は、「現実の細部を切り落とすこと」だと言うこともできるでしょう。理想的には、「言葉」を「現実」に合わせて変化させられればいいのですが、誰も知らない言葉を生み出したところでコミュニケーションには使えません。だからこそ私たちは、「『既存の言葉』に無理矢理当てはめるために、現実の細部を切り落とす」というやり方をするしかないのです。

株の根元も、絵では省略して描かれているが、しっかりとした存在感がある。見れば見るほど絵との違いは明らかだ。そして、どちらが間違っているのか、と考えれば、考えるまでもなく絵のほうが間違っているのだ。現物はこちらで、現実はここにある。
あわせて読みたい
【飛躍】有名哲学者は”中二病”だった?飲茶氏が易しく語る「古い常識を乗り越えるための哲学の力」:『1…
『14歳からの哲学入門』というタイトルは、「14歳向けの本」という意味ではなく、「14歳は哲学することに向いている」という示唆である。飲茶氏は「偉大な哲学者は皆”中二病”だ」と説き、特に若い人に向けて、「新しい価値観を生み出すためには哲学が重要だ」と語る
これが「言語化する」という行為の本質だと私は考えています。
さて、少し脱線しましょう。先程も触れた通り、『線は、僕を描く』という小説には、哲学的だと感じられるフレーズが多数出てきます。
まじめというのはね、悪くないけれど、少なくとも自然じゃない。
青春小説の場合、このようなセリフやフレーズは「浮いてしまう」ことが多い印象がありますが、『線は、僕を描く』では決してそうはなっていません。恐らくその理由は、彼らが対峙している「水墨画」が、まさに「言語化が困難な世界」だからでしょう。言葉にするのは難しいけれど、より深く伝えるためには言葉で表現しなければならない。そういう世界なのだと読者が諒解するからこそ、このような哲学っぽいフレーズが、作品を下支えする土台のような役割を果たし得るのだと感じました。
あわせて読みたい
【おすすめ】「天才」を描くのは難しい。そんな無謀な挑戦を成し遂げた天才・野崎まどの『know』はヤバい
「物語で『天才』を描くこと」は非常に難しい。「理解できない」と「理解できる」を絶妙なバランスで成り立たせる必要があるからだ。そんな難題を高いレベルでクリアしている野崎まど『know』は、異次元の小説である。世界を一変させた天才を描き、「天才が見ている世界」を垣間見せてくれる
こういう哲学っぽい雰囲気を出すのがメチャクチャ上手いのが、やっぱり森博嗣だよね
著:森博嗣
¥869 (2022/10/02 19:26時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
「水墨画」は、現実をどのように映し出すのか
さて話を戻しましょう。私は「言葉」に惹かれ、「言葉」を武器に現実を捉えようと闘ってきたつもりです。しかしもちろん、「言葉」だけが物事を捉える手段なわけではありません。音楽でも絵画でもダンスでも、「外的世界を、自分を通して発信し直すための手段」はいくらでもありますし、「言葉」はあくまでもその1つに過ぎません。
あわせて読みたい
【革新】天才マルタン・マルジェラの現在。顔出しNGでデザイナーの頂点に立った男の”素声”:映画『マル…
「マルタン・マルジェラ」というデザイナーもそのブランドのことも私は知らなかったが、そんなファッション音痴でも興味深く観ることができた映画『マルジェラが語る”マルタン・マルジェラ”』は、生涯顔出しせずにトップに上り詰めた天才の来歴と現在地が語られる
そして本書では、その手段として「水墨画」が描かれるというわけです。
著者はもちろん、読者が水墨画の世界に馴染みがないことを理解しており、様々な場面でその世界の一端について表現してくれています。
水墨画はほかの絵画とは少し違うところがあります。(中略)線の性質が絵の良否を決めることが多いということです。水墨画はほとんどの場合、瞬間的に表現される絵画です。その表現を支えているのは線です。そして線を支えているのは、絵師の身体です。水墨画にはほかの絵画よりも少しだけ多くアスリート的な要素が必要です。

あわせて読みたい
【映画】『キャスティング・ディレクター』の歴史を作り、ハリウッド映画俳優の運命を変えた女性の奮闘
映画『キャスティング・ディレクター』は、ハリウッドで伝説とされるマリオン・ドハティを描き出すドキュメンタリー。「神業」「芸術」とも評される配役を行ってきたにも拘わらず、長く評価されずにいた彼女の不遇の歴史や、再び「キャスティングの暗黒期」に入ってしまった現在のハリウッドなどを切り取っていく
正しい理解ではないかもしれませんが、本書を読んで私が感じたのは、「水墨画とは、結果よりも過程に価値がある」ということです。もちろん、水墨画ではない他の芸術においても同じようなことが言えるかもしれません。しかし、少なくとも「絵画」というジャンルに絞った場合、「水彩画」「油絵」「版画」などとは違って、「水墨画」は「過程」の方に価値があるのではないかと感じました。他の絵画では、どういう制作過程を経ようとも、最終的な成果物の良し悪しの方が重視される印象があります。しかし水墨画の場合は、最終的な成果物ももちろん重要ですが、それ以上に「描く瞬間の挙動」こそが重視されるのでしょう。確かにこの点は、ある意味で「なんでもアリ」の現代美術を除けば、非常に特殊な世界と言えるのではないかと感じました。
現代美術なら、「このような制作過程・背景を持つ作品だ」って部分が重要になることは多いよね
それにしても、「アスリート的要素」が必要とされるジャンルっていうのは凄く珍しいと思う
さて、そんな特殊な水墨画の世界では、「瞬間的な現実をいかに映し出すのか」という点に強く焦点が当たります。そしてそれ故に、水墨画という芸術は前述した「言語化」と比較が可能だと感じるのです。
我々の手は現象を追うには遅すぎるんだ。
あわせて読みたい
【天才】写真家・森山大道に密着する映画。菅田将暉の声でカッコよく始まる「撮り続ける男」の生き様:…
映画『あゝ荒野』のスチール撮影の際に憧れの森山大道に初めて会ったという菅田将暉の声で始まる映画『過去はいつも新しく、未来はつねに懐かしい』は、ちゃちなデジカメ1つでひたすら撮り続ける異端児の姿と、50年前の処女作復活物語が見事に交錯する
この言葉だけでも、水墨画が他の絵画と異なる地平を目指しているということが理解できるでしょう。他の絵画であれば、どれだけ時間を掛けてもいいですし、やり直すこともできます。しかし水墨画は、一筆置いた瞬間から一気呵成に描き上げ、やり直しはしません。そしてその手法はもちろん、「瞬間を捉える」ために発達したのです。
水墨画は確かに形を追うのではない、完成を目指すものでもない。
生きているその瞬間を描くことこそが、水墨画の本質なのだ。
自分がいまその場所に生きている瞬間の輝き、生命に対する深い共感、生きているその瞬間に感謝し賛美し、その喜びがある瞬間に筆致から伝わる。そのとき水墨画は完成する。
そして、このような感覚はまさに、私たちが何かを「言語化」する際に行っていることに近いのではないかと思うのです。私たちは日々、「現実」を切り取ろうとして「言語化」するわけですが、しかし「言葉」には限りがあるために、現実の細部を切り落とさなければなりません。同じように水墨画は、「瞬間を描く」という無謀な闘いに挑むことで、同じ困難さに直面することになるというわけです。
つまりこの小説は、「水墨画の”過程”において、現実がどう切り取られるか」を描いているって感じだよね
こういうテーマが、青春小説の中に組み込まれてるって部分が、この作品の奥深さに繋がってるんだと思う
あわせて読みたい
【現代】これが今の若者の特徴?衝撃のドキュメンタリー映画『14歳の栞』から中学生の今を知る
埼玉県春日部市に実在する中学校の2年6組の生徒35人。14歳の彼らに50日間密着した『14歳の栞』が凄かった。カメラが存在しないかのように自然に振る舞い、内心をさらけ出す彼らの姿から、「中学生の今」を知る
水墨画は「技術」ではない。だからこそ、素人の主人公が土俵に上がることもできる
当然の話ですが、どんなジャンルであれ、「技術」があれば成立するなんてことはないでしょう。「技術」があることは大前提で、さらにプラスアルファが求められるということの方が多いはずです。しかし、そのプラスアルファにしても、「技術を突き詰めること」による副産物ということもあるだろうし、全体的には、「技術こそが本質に繋がっている」ということは意外と多いのではないかと思っています。例えば料理であれば、「彩り」「器のセレクト」「季節感」など、「技術」以外の要素も重要でしょうが、それらも最終的には、「料理の『技術』とどう組み合わせるか」こそが何よりも大事なのであり、やはり「技術」に焦点が当たっていると言っていいでしょう。

あわせて読みたい
【現実】生きる気力が持てない世の中で”働く”だけが人生か?「踊るホームレスたち」の物語:映画『ダン…
「ホームレスは怠けている」という見方は誤りだと思うし、「働かないことが悪」だとも私には思えない。振付師・アオキ裕キ主催のホームレスのダンスチームを追う映画『ダンシングホームレス』から、社会のレールを外れても許容される社会の在り方を希求する
しかし本書を読む限り、水墨画はそうではなさそうです。もちろん水墨画にも「技術」は存在するわけですが、「技術こそが本質に繋がっている」という感覚は薄いと言えるかもしれません。
本書には、それを示唆するような言葉が様々に散りばめられています。
けれども『絵を描く』ことは、高度な技術や自分が習得した技術をちらつかせることだけではない。それは技術を伝えてくれた『誰か』との繋がりであって、自然との繋がりではない。
手先の技法など無意味に思えてしまうほど、その命の気配が画面の中で濃厚だった。
あわせて読みたい
【倫理】アート体験の行き着く未来は?映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』が描く狂気の世界(…
「『痛み』を失った世界」で「自然発生的に生まれる新たな『臓器』を除去するライブパフォーマンス」を行うソール・テンサーを主人公にした映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』は、すぐには答えの見出しにくい「境界線上にある事柄」を挑発的に描き出す、実に興味深い物語だ
才能やセンスなんて、絵を楽しんでいるかどうかに比べればどうということもない。
この辺りの描写は、この物語を成立させる上でかなり重要なポイントだよね
「まったくの素人が主人公」という点にリアリティを与えてる感じ
中でも、次のセリフが最もシンプルな表現で、私にはとても印象的でした。
拙さが巧みさに劣るわけではないんだよ。
あわせて読みたい
【感想】どんな話かわからない?難しい?ジブリ映画『君たちはどう生きるか』の考察・解説は必要?(監…
宮崎駿最新作であるジブリ映画『君たちはどう生きるか』は、宮崎アニメらしいファンタジックな要素を全開に詰め込みつつ、「生と死」「創造」についても考えさせる作品だ。さらに、「自分の頭の中から生み出されたものこそ『正解』」という、創造物と向き合う際の姿勢についても問うているように思う
私たちの日常においても、「ヘタウマなイラスト」に人気が集まったりすることはありますが、ここで言及されているのはそういうことではありません。技術以外の要素こそが、成果物としての水墨画に何よりも重要な影響を与えるという示唆なのです。
この人は、ただ単に技を突き詰めただけの絵師ではない。技を通じ、絵を描くことで生きようとしていた実直な人間なのだと、その瞬間に分かった。
本書を読めば読むほど、水墨画が「絵を描く」という行為そのものから遠ざかる芸術だと理解できるでしょう。まさにそれは、次のようなセリフからも読み取ることができます。

あわせて読みたい
【天才】タランティーノ作品ほぼ未見で観た面白ドキュメンタリー。映画に愛された映画オタクのリアル
『パルプ・フィクション』しか監督作品を観たことがないまま、本作『クエンティン・タランティーノ 映画に愛された男』を観たが、とても面白いドキュメンタリー映画だった。とにかく「撮影現場に笑いが絶えない」ようで、そんな魅力的なモノづくりに関わる者たちの証言から、天才の姿が浮かび上がる
減筆とは端的に言えば描かないことです。
これは、「水墨画の世界には『減筆』という技法があり、それは『描かないこと』だ」という意味です。意味が分からないでしょう。本書を読んでも、その真髄を正確に理解することは難しいかもしれません。
普通は言葉で表現できないだろう「水墨画の真髄」みたいなものを、著者はメチャクチャ言語化してくれてるって感じする
こういうのってマジで、誰かが説明してくれないと自力では絶対に辿り着けない知識って感じするもんね
しかし、「『減筆』こそが水墨画における『最高の技法』だ」というこの指摘は、ある意味で、主人公・青山霜介が水墨画の世界で闘える余地にもなっていると言えるでしょう。彼は、師匠となる人物に声を掛けてもらった時点では、水墨画には一切触れたことがありませんでした。そんな主人公が、水墨画の世界で一定以上の水準で闘うことができているのは、「技術ではない何か」こそが本質であり、さらに「『描かないこと』が最高の技術である」という、ちょっと普通ではない水墨画の世界だったからでしょう。
あわせて読みたい
【驚異】映画『RRR』『バーフバリ』は「観るエナジードリンク」だ!これ程の作品にはなかなか出会えないぞ
2022年に劇場公開されるや、そのあまりの面白さから爆発的人気を博し、現在に至るまでロングラン上映が続いている『RRR』と、同監督作の『バーフバリ』は、大げさではなく「全人類にオススメ」と言える超絶的な傑作だ。まだ観ていない人がいるなら、是非観てほしい!
本当はもっといろいろなものが美しいのではないかって思いました。いつも何気なく見ているものが実はとても美しいもので、僕らの意識がただ単にそれを捉えられないだけじゃないかって思って……。
作中にはもちろん、主人公と比べて圧倒的な技術を持つ人物が出てくるわけですが、しかし、「技量があるからと言って良い水墨画家だとは限らない」という示唆が繰り返しなされます。技術はもちろん良い水墨画を生み出すための手段の1つではありますが、技術が高いからといって水墨画の本質にたどり着けるのかと言えばそんなことはありません。だからこそこの小説は、リアリティを損なわずに「ど素人が、技術の高い者と競い合う」という展開を描くことができるのです。
喩えるなら、「スケボーに乗ったことさえない人間が、プロと勝負する」みたいな設定だからね
美しいものを創ろうとは思っていなかったから。
本書はまた、「水墨画の本質」に肉薄しようとする過程で、青山霜介という人間のある種の「異常さ」が炙り出され、そのことが結果として、彼を「水墨画の本質」へと連れて行くというような構成の物語であり、人間的な成長と芸術的な思索が見事にリンクして描かれる構成が素晴らしいと感じました。
あわせて読みたい
【映画】『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』で号泣し続けた私はTVアニメを観ていない
TVアニメは観ていない、というかその存在さえ知らず、物語や登場人物の設定も何も知らないまま観に行った映画『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』に、私は大号泣した。「悪意のない物語」は基本的に好きではないが、この作品は驚くほど私に突き刺さった
砥上裕將『線は、僕を描く』の内容紹介
青山霜介は、無気力な青年だ。高校時代に両親を交通事故で喪ったことがきっかけで、きちんと生きていくためのネジを無くしてしまう。彼はそのまま、「ガラス張りの空間」から外側をぼんやり眺めているような主体性のない日々を送っていた。その後、強制的に選択肢が提示され、彼は大学へ進学し、一人暮らしを始めることになる。

大学入学後も、他人や世界との関わり方に変わりはなかったのだが、古前という友人のお陰で少しだけ社交性が生まれた。古前は常にサングラスを掛け、恋にうつつを抜かしているばかりの男なのだが、そのシンプルすぎる行動原理には好感が持てたし、彼のお陰で他人との関わりも少しずつ増えていくことになる。
あわせて読みたい
【前進】誰とも価値観が合わない…。「普通」「当たり前」の中で生きることの難しさと踏み出し方:『出会…
生きていると、「常識的な考え方」に囚われたり、「普通」「当たり前」を無自覚で強要してくる人に出会ったりします。そういう価値観に合わせられない時、自分が間違っている、劣っていると感じがちですが、そういう中で一歩踏み出す勇気を得るための考え方です
そんなある日のこと。古前から手伝ってくれと頼まれたアルバイトで、彼は人生を変えるような出会いを経験することになった。
青山を含めた数名の文化系男子は、古前から「飾り付けのアルバイト」だと聞かされて現場へ向かう。しかし実際には、展覧会設営のために、自分の背丈よりも高いパネルを50枚以上、さらにパーティションを100枚近くも運ばなければならなかった。文化系には困難なアルバイトだ。他の者たちが次々と脱落していく中、青山は逃げ出すことなくアルバイトを続けた。設営現場にいたガテン系のお兄さんと仲良くなったこと、また、状況を理解した古前が再度人員を手配したことによって、展覧会の準備はどうにか終了する。
そして青山はその会場で、篠田湖山と出会った。日本を代表する水墨画家だ。彼は美術の教科書に載っており、CMに出演した経験もある。しかし青山は、湖山のことを知らず、単に通りすがりのおじいちゃんだと思い込んでいた。彼は、「一緒に弁当でも食べよう」と誘われたのを機に、話の流れで何故か彼の内弟子になることが決まってしまう。会場には、同じく水墨画家であり、湖山の孫娘である篠田千瑛もいたのだが、内弟子などほとんど取ったことがない祖父が、何故初対面の、水墨画の経験などまるでない男に声を掛けたのか、大いに訝っていた。
それは、青山にしても同感だ。彼は別に、湖山の前で絵を描いたわけではなく、ただ喋っていたに過ぎない。そんな自分の、一体何をどう判断して内弟子にしようと考えたのか。
あわせて読みたい
【感想】努力では才能に勝てないのか?どうしても辿り着きたい地点まで迷いながらも突き進むために:『…
どうしても辿り着きたい場所があっても、そのあまりの遠さに目が眩んでしまうこともあるでしょう。そんな人に向けて、「才能がない」という言葉に逃げずに前進する勇気と、「仕事をする上で大事なスタンス」について『羊と鋼の森』をベースに書いていきます
そして成り行き上、青山と千瑛はなんと、来年の湖山賞で勝負をすることが決まってしまった。青山が設営を手伝っていた展覧会こそ、まさにその湖山賞のものである。水墨画などまったく何の経験もないただの大学生と、巨匠の孫娘というプレッシャーの中で長年鍛錬を続けてきた若きエースの対決など、勝負をする前から結果など明らかに思える。しかし湖山はその勝負を面白がり、青山の戸惑いなど無視して勝手に受けてしまう。
そんなわけで彼は、湖山の家に通い、水墨画と向き合うことになった。自分が何をしているのかさえ理解できない中、彼は墨をすり、筆を持ち、とにかく手を動かす。しかしそんな生活が、彼を大きく変えていくことになり……。
砥上裕將『線は、僕を描く』の感想
とても面白い小説でした。水墨画に関する話はここまで散々書いてきたので、ここからは「孤独」の話をすることにしましょう。
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『流浪の月』を観て感じた、「『見て分かること』にしか反応できない世界」への気持ち悪さ
私は「見て分かること」に”しか”反応できない世界に日々苛立ちを覚えている。そういう社会だからこそ、映画『流浪の月』で描かれる文と更紗の関係も「気持ち悪い」と断罪されるのだ。私はむしろ、どうしようもなく文と更紗の関係を「羨ましい」と感じてしまう。
水墨画で重要なのは技術以外の何かだ、という話は既に触れた通りですが、この作品では、その1つとして「孤独」が描かれます。本書の中でそうと明確に記されているわけではありませんが、水墨画を描くにあたって「孤独であること」は非常に重要だと私は感じました。というのも、「あらゆる虚飾を剥ぎ取って、現実そのものを捉える必要がある」からです。

『だから仏教は面白い!』で出てくる、「欲望を剥ぎ取って世界を見る」って話みたいだね
「あらゆる虚飾を剥ぎ取って、現実そのものを捉える」ためには、言語・価値観・常識など、意識せずとも自身を構成してしまう様々な要素を「ないもの」として世界を見つめる必要があります。水墨画の技術があるからといってどうにかなるわけではありません。自分の中のあらゆる「当たり前」をフラットにして、「何でもない存在」として世界を捉えることでしか、水墨画で描くべき「現実」を捉えることはできないのです。
あわせて読みたい
【異端】「仏教とは?」を簡単に知りたい方へ。ブッダは「異性と目も合わせないニートになれ」と主張し…
我々が馴染み深い「仏教」は「大乗仏教」であり、創始者ゴータマ・ブッダの主張が詰まった「小乗仏教」とは似て非なるものだそうだ。『講義ライブ だから仏教は面白い!』では、そんな「小乗仏教」の主張を「異性と目も合わせないニートになれ」とシンプルに要約して説明する
そしてそれは、まさに「孤独」そのものだと言っていいでしょう。他人や世界との関わりだけでなく、自分が依って立つ土台からも遠ざかり、「誰でもない、何でもない自分」として存在することは、「孤独」と同義だと私は感じます。
そういう意味で青山霜介は、非常に「強い」と言っていいでしょう。
僕にも真っ白になってしまった経験があるからです。
偏見もあると思うけど、「創作者」って総じて「孤独」なイメージはある
孤独でなければ「創作」に向かおうと思わない、みたいな側面も関係しているんだろうけどね
あわせて読みたい
【考察】生きづらい性格は変わらないから仮面を被るしかないし、仮面を被るとリア充だと思われる:『勝…
「リア充感」が滲み出ているのに「生きづらさ」を感じてしまう人に、私はこれまでたくさん会ってきた。見た目では「生きづらさ」は伝わらない。24年間「リアル彼氏」なし、「脳内彼氏」との妄想の中に生き続ける主人公を描く映画『勝手にふるえてろ』から「こじらせ」を知る
彼は、両親の死を境に、長い間「孤独」の側にいました。望んでその状態にいたわけではありませんが、そうあり続けるしかないと感じるほどにあらゆる気力を奪われてしまっていたのです。そのことは彼を長く悩ませました。とても「良い状態」であるとは思えなかったのです。「孤独」な状態は彼にとってマイナスでしかなく、作中でも、そのようなスタンスで描かれています。
そんな彼が、「孤独であること」が強みになる「水墨画」の世界に足を踏み入れたことは、とても良かったと言えるでしょう。さらに面白いことに、彼は「孤独を志向する水墨画」の世界に深く関わることで、結果として少し「孤独」から抜け出せるようになっていくのです。
二年前、父と母がいなくなったあの夏の終わりから、今日までたくさんの独りぼっちを味わったけれど、気づかないうちにその空気を忘れていることに驚いていた。たぶん僕が、与えられた場所ではなく、歩き出した場所で立ち止まっているからだろう。

あわせて読みたい
【肯定】社会不適合者こそ非凡。学校・世の中に馴染めなかった異才たちの過去から”才能”の本質を知る:…
「みんなと同じ」に馴染めないと「社会不適合」と判断され、排除されてしまうことが多いでしょう。しかし『非属の才能』では、「どこにも属せない感覚」にこそ才能の源泉があると主張します。常識に違和感を覚えてしまう人を救う本から、同調圧力に屈しない生き方を学ぶ
彼が言うように、それまで青山霜介は「消極的に孤独を選んでいる」という状態にありました。そこにしか居場所がなかったのです。しかし水墨画と関わることで彼は、「積極的に孤独を選んでいる」という状態へと移っていきます。積極的な行動であるが故に、それまで感じていた強烈な「孤独感」は薄れただろうし、さらに、彼の振る舞いから「悲壮感」が消えたことで、周りも関わりやすくなったのでしょう。さらに、孤独な者が集う水墨画の世界には、感覚を共有できる「同志」もいるわけです。このような理由から彼は、「孤独を志向したことで孤独感を薄れさせる」という、それだけ聞くと奇妙な状況に辿り着いたのだろうと思います。
この作品は、主人公が「悪い孤独」から「良い孤独」へと移行できたっていう物語でもあるかなって思う
僕らはたぶんお互いが、自分の想いをそのままうまく口にすることができない人間同士なのだ。僕らはそれほど多くのことを語らないまま生きてきたのだろう。こんなときにお互いの距離を上手に埋める言葉を何一つ持っていないなんてカッコ悪すぎる。
この場面で青山霜介は、自身の言葉の稚拙さを自覚するわけですが、この気付きはある意味で、「『言葉ではない何か』で分かり合う世界に生きることで生きやすくなった」という変化を示唆するものでもあると思います。墨一色で描かれる水墨画の世界を舞台にしながら、随所に「鮮やかさ」を感じさせる物語であり、その「鮮やかさ」が、今まさに「孤独」の内側にいる人を仄かに照らしてくれるのではないかとも感じました。
あなたはもう独りじゃないわ。語らなくても、こうして描くものを通して、私はあなたを理解できる。私だけじゃなくて、私たち皆があなたのことを信じて、感じていられる。あなたはもう私たちの一員よ。
あわせて読みたい
【考察】『うみべの女の子』が伝えたいことを全力で解説。「関係性の名前」を手放し、”裸”で対峙する勇敢さ
ともすれば「エロ本」としか思えない浅野いにおの原作マンガを、その空気感も含めて忠実に映像化した映画『うみべの女の子』。本作が一体何を伝えたかったのかを、必死に考察し全力で解説する。中学生がセックスから関係性をスタートさせることで、友達でも恋人でもない「名前の付かない関係性」となり、行き止まってしまう感じがリアル
著:砥上裕將
¥858 (2022/10/02 19:14時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品読了済】私が読んできた小説を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が読んできた小説を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本選びの参考にして下さい。
最後に
決して身近とは言い難い水墨画の世界を描きながら、青春における葛藤や、創作と向き合う恐怖など、普遍的だと感じる描写の多い物語だと感じました。著者自身が水墨画家であり、普段は「言葉」ではないもので世界を捉えようとしているわけですが、そんな人間が「言葉」を武器に世界と対峙した際の破壊力をまざまざと見せつけられる作品だと言えるでしょう。
あわせて読みたい
【食&芸術】死んでも車を運転したくない人間の香川うどん巡り& 豊島アート巡りの旅ルート(山越うどん…
仕事終わりの木曜日夜から日曜日に掛けて、「香川のうどん巡り」と「豊島のアート巡り」をしてきました。うどんだけでも7580円分食べたので、かなりの軒数を回ったことになります。しかも「死んでも車を運転したくない」ため、可能な限り公共交通機関のみで移動しました。私と同じように「車を運転したくない人」には、かなり参考になる記事と言えるのではないかと思います
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!「文章の書き方が分からない」「文章力がないから鍛えたい」という方にオススメ…
「文章の書き方」についてのKindle本を出版しました。「文章が書けない」「どう書いたらいいか分からない」「文章力を向上させたい」という方の悩みを解消できるような本に仕上げたつもりです。数多くの文章を書き、さらに頼まれて文章を推敲してきた経験を踏まえ、「文章を書けるようになるにはどうしたらいいか」についての私なりの考えをまとめました。
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!「それってホントに『コミュ力』が高いって言えるの?」と疑問を感じている方に…
私は、「コミュ力が高い人」に関するよくある主張に、どうも違和感を覚えてしまうことが多くあります。そしてその一番大きな理由が、「『コミュ力が高い人』って、ただ『想像力がない』だけではないか?」と感じてしまう点にあると言っていいでしょう。出版したKindle本は、「ネガティブには見えないネガティブな人」(隠れネガティブ)を取り上げながら、「『コミュ力』って何だっけ?」と考え直してもらえる内容に仕上げたつもりです。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『国宝』は圧巻だった!吉沢亮の女形のリアル、圧倒的な映像美、歌舞伎の芸道の狂気(…
映画『国宝』は、ちょっと圧倒的すぎる作品だった。原作・監督・役者すべての布陣が最強で、「そりゃ良い作品になるよね」という感じではあったが、そんな期待をあっさりと超えていくえげつない完成度は圧巻だ。あらゆる意味で「血」に翻弄される主人公・喜久雄の「狂気の生涯」を、常軌を逸したレベルで描き出す快作である
あわせて読みたい
【虚構】映画『シアトリカル』が追う唐十郎と劇団唐組の狂気。芝居に生きる者たちの”リアル”とは?
映画『シアトリカル』は、異端児・唐十郎と、彼が主宰する「劇団唐組」に密着するドキュメンタリー映画である。「普段から唐十郎を演じている」らしい唐十郎は、「ややこしさ」と「分かりやすさ」をないまぜにした実に奇妙な存在だった。「演劇」や「演じること」に己を捧げた「狂気を孕む者たち」の生き様が切り取られた作品だ
あわせて読みたい
【アート】映画『ヒプノシス』は、レコードジャケットの天才創作集団の繁栄と衰退を掘り起こす
映画『ヒプノシス』は、レコードのジャケットデザインで一世を風靡した天才集団「ヒプノシス」の栄枯盛衰を描き出すドキュメンタリー映画である。ストームとポーの2人が中心となって作り上げた凄まじいクリエイティブはそのまま、レコードジャケットの歴史と言っていいほどだ。ぶっ飛んだ才能とその生き方を知れる映画である
あわせて読みたい
【全力】圧巻の演奏シーンに驚愕させられた映画『BLUE GIANT』。ライブ中の宮本はとにかく凄い(主演:…
映画『BLUE GIANT』は、「演奏シーン」がとにかく圧倒的すぎる作品でした。ストーリーは、これ以上シンプルには出来ないだろうというぐらいシンプルなのですが、「王道的物語」だからこその感動もあります。また、全体の1/4がライブシーンらしく、その視覚的な演出も含めて、まさに「音楽を体感する映画」だと言えるでしょう
あわせて読みたい
【迷路】映画『国境ナイトクルージング』は、青春と呼ぶにはちょっと大人な3人の関係を丁寧に描く
映画『国境ナイトクルージング』は、男2人女1人の3人による、「青春」と呼ぶには少し年を取りすぎてしまったビターな関係を描き出す物語。説明が少なく、また、様々な示唆的な描写の意味するところを捉えきれなかったためり、「分からないこと」が多かったのだが、全体的な雰囲気が素敵で好きなタイプの作品だった
あわせて読みたい
【失恋】ひたすらカオスに展開する映画『エターナル・サンシャイン』は、最後まで観ると面白い!(主演…
映画『エターナル・サンシャイン』は、冒頭からしばらくの間、とにかくまったく意味不明で、「何がどうなっているのか全然分からない!」と思いながら観ていました。しかし、映像がカオスになるにつれて状況の理解は進み始め、最終的には「よくもまあこんな素っ頓狂なストーリーを理解できる物語に落とし込んだな」と感心させられました
あわせて読みたい
金沢&富山のアート旅!「21世紀美術館」だけじゃない激アツなおすすめ美術館巡りをご提案
金沢・富山を巡るアート旅に出かけてきました!メインの目的は「21世紀美術館」でしたが、それ以上に「ASTER Curator Museum」「LIP BAR」「KAMU kanazawa」などがとにかく素晴らしかったです。アートや美術のことはド素人ですが、超個人的主観で「金沢・富山で触れられるアートの良さ」について書いた旅行記となります
あわせて読みたい
【煌めき】映画『HAPPYEND』が描く、”監視への嫌悪”と”地震への恐怖”の中で躍動する若者の刹那(監督:…
映画『HAPPYEND』は、「監視システム」と「地震」という「外的な制約条件」を設定し、その窮屈な世界の中で屈せずに躍動しようとする若者たちをリアルに描き出す物語である。特に、幼稚園からの仲であるコウとユウタの関係性が絶妙で、演技未経験だという2人の存在感と映像の雰囲気が相まって、実に素敵に感じられた
あわせて読みたい
【感想】高倍率のやばい藝大入試に挑む映画『ブルーピリオド』は「生きてる実感の無さ」をぶち壊す(監…
映画『ブルーピリオド』は、大学入試で最高倍率とも言われる200倍の試験に挑む高校生たちの物語。東京藝術大学絵画科という果てしない最難関に、高校2年生から突然挑戦すると決めた矢口八虎を中心に、「『好き』に囚われた者たち」の果てしない情熱と葛藤を描き出す。絵を描くシーンを吹き替えなしで行った役者の演技にも注目だ
あわせて読みたい
【映画】ディオールのデザイナーだった天才ジョン・ガリアーノが差別発言で破滅した人生を語る:映画『…
何者なのかまったく知らない状態で観たドキュメンタリー映画『ジョン・ガリアーノ 世界一愚かな天才デザイナー』は、差別発言によって失墜しすべてを失った天才デザイナーの凄まじい来歴が描かれる作品だ。実に複雑で興味深い存在だったし、その波乱の人生は、私のようなファッションに疎い人間でも面白く感じられると思う
あわせて読みたい
【才能】映画『トノバン』が描く、「日本の音楽史を変えた先駆者・加藤和彦」のセンス良すぎる人生(「♪…
「♪おらは死んじまっただ~」が印象的な『帰って来たヨッパライ』で知られる加藤和彦の才能と魅力を余す所なく映し出すドキュメンタリー映画『トノバン』を観て、まったく知らなかった人物の凄まじい存在感に圧倒されてしまった。50年以上も前の人だが、音楽性や佇まいなどを含め、現代でも通用するだろうと思わせる雰囲気が凄まじい
あわせて読みたい
【評価】高山一実の小説かつアニメ映画である『トラペジウム』は、アイドル作とは思えない傑作(声優:…
原作小説、そしてアニメ映画共に非常に面白かった『トラペジウム』は、高山一実が乃木坂46に在籍中、つまり「現役アイドル」として出版した作品であり、そのクオリティに驚かされました。「現役アイドル」が「アイドル」をテーマにするというド直球さを武器にしつつ、「アイドルらしからぬ感覚」をぶち込んでくる非常に面白い作品である
あわせて読みたい
【実話】映画『ダム・マネー ウォール街を狙え!』は「株で大儲けした」だけじゃない痛快さが面白い
ダム・マネー ウォール街を狙え!』では、株取引で莫大な利益を得た実在の人物が取り上げられる。しかし驚くべきは「大金を得たこと」ではない。というのも彼はなんと、資産5万ドルの身にも拘らず、ウォール街の超巨大資本ファンドを脅かす存在になったのである! 実話とは思えない、あまりにも痛快な物語だった
あわせて読みたい
【感想】映画『ルックバック』の衝撃。創作における衝動・葛藤・苦悩が鮮やかに詰め込まれた傑作(原作…
アニメ映画『ルックバック』は、たった58分の、しかもセリフも動きも相当に抑制された「静」の映画とは思えない深い感動をもたらす作品だった。漫画を描くことに情熱を燃やす2人の小学生が出会ったことで駆動する物語は、「『創作』に限らず、何かに全力で立ち向かったことがあるすべての人」の心を突き刺していくはずだ
あわせて読みたい
【正義】ナン・ゴールディンの”覚悟”を映し出す映画『美と殺戮のすべて』が描く衝撃の薬害事件
映画『美と殺戮のすべて』は、写真家ナン・ゴールディンの凄まじい闘いが映し出されるドキュメンタリー映画である。ターゲットとなるのは、美術界にその名を轟かすサックラー家。なんと、彼らが創業した製薬会社で製造された処方薬によって、アメリカでは既に50万人が死亡しているのだ。そんな異次元の薬害事件が扱われる驚くべき作品
あわせて読みたい
【幻惑】映画『フォロウィング』の衝撃。初監督作から天才だよ、クリストファー・ノーラン
クリストファー・ノーランのデビュー作であり、多数の賞を受賞し世界に衝撃を与えた映画『フォロウィング』には、私も驚かされてしまった。冒頭からしばらくの間「何が描かれているのかさっぱり理解できない」という状態だったのに、ある瞬間一気に視界が晴れたように状況が理解できたのだ。脚本の力がとにかく圧倒的だった
あわせて読みたい
【実話】さかなクンの若い頃を描く映画『さかなのこ』(沖田修一)は子育ての悩みを吹き飛ばす快作(主…
映画『さかなのこ』は、兎にも角にものん(能年玲奈)を主演に据えたことが圧倒的に正解すぎる作品でした。性別が違うのに、「さかなクンを演じられるのはのんしかいない!」と感じさせるほどのハマり役で、この配役を考えた人は天才だと思います。「母親からの全肯定」を濃密に描き出す、子どもと関わるすべての人に観てほしい作品です
あわせて読みたい
【憧憬】「フランク・ザッパ」を知らずに映画『ZAPPA』を観て、「この生き様は最高」だと感じた
「フランク・ザッパ」がミュージシャンであることさえ禄に知らない状態で私が映画『ZAPPA』を観た私は、そのあまりに特異なスタンス・生き様にある種の憧憬を抱かされた。貫きたいと思う強い欲求を真っ直ぐ突き進んだそのシンプルな人生に、とにかくグッときたのだ。さらに、こんな凄い人物を知らなかった自分にも驚かされてしまった
あわせて読みたい
【価値】レコードなどの「フィジカルメディア」が復権する今、映画『アザー・ミュージック』は必見だ
2016年に閉店した伝説のレコード店に密着するドキュメンタリー映画『アザー・ミュージック』は、「フィジカルメディアの衰退」を象徴的に映し出す。ただ私は、「デジタル的なもの」に駆逐されていく世の中において、「『制約』にこそ価値がある」と考えているのだが、若者の意識も実は「制約」に向き始めているのではないかとも思っている
あわせて読みたい
【奇妙】映画『鯨の骨』は、主演のあのちゃんが絶妙な存在感を醸し出す、斬新な設定の「推し活」物語
映画『鯨の骨』は、主演を務めたあのちゃんの存在感がとても魅力的な作品でした。「AR動画のカリスマ的存在」である主人公を演じたあのちゃんは、役の設定が絶妙だったこともありますが、演技がとても上手く見え、また作品全体の、「『推し活』をある意味で振り切って描き出す感じ」もとても皮肉的で良かったです
あわせて読みたい
【情熱】選挙のおもしろ候補者含め”全員取材”をマイルールにする畠山理仁の異常な日常を描く映画:『NO …
選挙に取り憑かれた男・畠山理仁を追うドキュメンタリー映画『NO 選挙, NO LIFE』は、「平均睡眠時間2時間」の生活を長年続ける”イカれた”ライターの「選挙愛」が滲み出る作品だ。「候補者全員を取材しなければ記事にはしない」という厳しすぎるマイルールと、彼が惹かれる「泡沫候補」たちが実に興味深い
あわせて読みたい
【魅惑】マツコも絶賛の“日本人初のパリコレトップモデル”山口小夜子のメイクの凄さや素顔を描く映画:…
日本人初のパリコレトップモデルである山口小夜子と親交があった監督が紡ぐ映画『氷の花火 山口小夜子』は、未だ謎に包まれているその人生の一端を垣間見せてくれる作品だ。彼女を知る様々な人の記憶と、彼女を敬愛する多くの人の想いがより合って、一時代を築いた凄まじい女性の姿が浮かび上がってくる
あわせて読みたい
【食&芸術】死んでも車を運転したくない人間の香川うどん巡り& 豊島アート巡りの旅ルート(山越うどん…
仕事終わりの木曜日夜から日曜日に掛けて、「香川のうどん巡り」と「豊島のアート巡り」をしてきました。うどんだけでも7580円分食べたので、かなりの軒数を回ったことになります。しかも「死んでも車を運転したくない」ため、可能な限り公共交通機関のみで移動しました。私と同じように「車を運転したくない人」には、かなり参考になる記事と言えるのではないかと思います
あわせて読みたい
【天才】映画『笑いのカイブツ』のモデル「伝説のハガキ職人ツチヤタカユキ」の狂気に共感させられた
『「伝説のハガキ職人」として知られるツチヤタカユキの自伝的小説を基にした映画『笑いのカイブツ』は、凄まじい狂気に彩られた作品だった。「お笑い」にすべてを捧げ、「お笑い」以外はどうでもいいと考えているツチヤタカユキが、「コミュ力」や「人間関係」で躓かされる”理不尽”な世の中に、色々と考えさせられる
あわせて読みたい
【感想】映画『ローマの休日』はアン王女を演じるオードリー・ヘプバーンの美しさが際立つ名作
オードリー・ヘプバーン主演映画『ローマの休日』には驚かされた。現代の視点で観ても十分に通用する作品だからだ。まさに「不朽の名作」と言っていいだろう。シンプルな設定と王道の展開、そしてオードリー・ヘプバーンの時代を超える美しさが相まって、普通ならまずあり得ない見事なコラボレーションが見事に実現している
あわせて読みたい
【考察】A24のホラー映画『TALK TO ME』が描くのは、「薄く広がった人間関係」に悩む若者のリアルだ
「A24のホラー映画史上、北米最高興収」と謳われる『TALK TO ME トーク・トゥ・ミー』は、一見「とても分かりやすいホラー映画」である。しかし真のテーマは「SNS過剰社会における人間関係の困難さ」なのだと思う。結果としてSNSが人と人との距離を遠ざけてしまっている現実を、ホラー映画のスタイルに落とし込んだ怪作
あわせて読みたい
【抵抗】映画『熊は、いない』は、映画製作を禁じられた映画監督ジャファル・パナヒの執念の結晶だ
映画『熊は、いない』は、「イラン当局から映画製作を20年間も禁じられながら、その後も作品を生み出し続けるジャファル・パナヒ監督」の手によるもので、彼は本作公開後に収監させられてしまった。パナヒ監督が「本人役」として出演する、「ドキュメンタリーとフィクションのあわい」を縫うような異様な作品だ
あわせて読みたい
【痛快】精神病院の隔離室から脱した、善悪の判断基準を持たない狂気の超能力者が大暴れする映画:『モ…
モナ・リザ アンド ザ ブラッドムーン』は、「10年以上拘束され続けた精神病院から脱走したアジア系女性が、特殊能力を使って大暴れする」というムチャクチャな設定の物語なのだが、全編に通底する「『善悪の判断基準』が歪んでいる」という要素がとても見事で、意味不明なのに最後まで惹きつけられてしまった
あわせて読みたい
【絶望】杉咲花主演映画『市子』の衝撃。毎日がしんどい「どん底の人生」を生き延びるための壮絶な決断…
映画『市子』はまず何よりも主演を務めた杉咲花に圧倒させられる作品だ。そしてその上で、主人公・川辺市子を巡る物語にあれこれと考えさせられてしまった。「川辺市子」は決してフィクショナルな存在ではなく、現実に存在し得る。本作は、そのような存在をリアルに想像するきっかけにもなるだろう
あわせて読みたい
【感想】映画『キリエのうた』(岩井俊二)はアイナ・ジ・エンドに圧倒されっ放しの3時間だった(出演:…
映画『キリエのうた』(岩井俊二監督)では、とにかくアイナ・ジ・エンドに圧倒されてしまった。歌声はもちろんのことながら、ただそこにいるだけで場を支配するような存在感も凄まじい。全編に渡り「『仕方ないこと』はどうしようもなく起こるんだ」というメッセージに溢れた、とても力強い作品だ
あわせて読みたい
【映画】『キャスティング・ディレクター』の歴史を作り、ハリウッド映画俳優の運命を変えた女性の奮闘
映画『キャスティング・ディレクター』は、ハリウッドで伝説とされるマリオン・ドハティを描き出すドキュメンタリー。「神業」「芸術」とも評される配役を行ってきたにも拘わらず、長く評価されずにいた彼女の不遇の歴史や、再び「キャスティングの暗黒期」に入ってしまった現在のハリウッドなどを切り取っていく
あわせて読みたい
【改革】改修期間中の国立西洋美術館の裏側と日本の美術展の現実を映すドキュメンタリー映画:『わたし…
「コロナ禍」という絶妙すぎるタイミングで改修工事を行った国立西洋美術館の、普段見ることが出来ない「裏側」が映し出される映画『わたしたちの国立西洋美術館』は、「日本の美術展」の問題点を炙り出しつつ、「『好き』を仕事にした者たち」の楽しそうな雰囲気がとても魅力的に映るドキュメンタリー
あわせて読みたい
【共感】斎藤工主演映画『零落』(浅野いにお原作)が、「創作の評価」を抉る。あと、趣里が良い!
かつてヒット作を生み出しながらも、今では「オワコン」みたいな扱いをされている漫画家を中心に描く映画『零落』は、「バズったものは正義」という世の中に斬り込んでいく。私自身は創作者ではないが、「売れる」「売れない」に支配されてしまう主人公の葛藤はよく理解できるつもりだ
あわせて読みたい
【伝説】映画『ミスター・ムーンライト』が描くビートルズ武道館公演までの軌跡と日本音楽への影響
ザ・ビートルズの武道館公演が行われるまでの軌跡を描き出したドキュメンタリー映画『ミスター・ムーンライト』は、その登場の衝撃について語る多数の著名人が登場する豪華な作品だ。ザ・ビートルズがまったく知られていなかった頃から、伝説の武道館公演に至るまでの驚くべきエピソードが詰まった1作
あわせて読みたい
【倫理】アート体験の行き着く未来は?映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』が描く狂気の世界(…
「『痛み』を失った世界」で「自然発生的に生まれる新たな『臓器』を除去するライブパフォーマンス」を行うソール・テンサーを主人公にした映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』は、すぐには答えの見出しにくい「境界線上にある事柄」を挑発的に描き出す、実に興味深い物語だ
あわせて読みたい
【天才】タランティーノ作品ほぼ未見で観た面白ドキュメンタリー。映画に愛された映画オタクのリアル
『パルプ・フィクション』しか監督作品を観たことがないまま、本作『クエンティン・タランティーノ 映画に愛された男』を観たが、とても面白いドキュメンタリー映画だった。とにかく「撮影現場に笑いが絶えない」ようで、そんな魅力的なモノづくりに関わる者たちの証言から、天才の姿が浮かび上がる
あわせて読みたい
【感想】どんな話かわからない?難しい?ジブリ映画『君たちはどう生きるか』の考察・解説は必要?(監…
宮崎駿最新作であるジブリ映画『君たちはどう生きるか』は、宮崎アニメらしいファンタジックな要素を全開に詰め込みつつ、「生と死」「創造」についても考えさせる作品だ。さらに、「自分の頭の中から生み出されたものこそ『正解』」という、創造物と向き合う際の姿勢についても問うているように思う
あわせて読みたい
【感想】映画『すずめの戸締まり』(新海誠)は、東日本大震災後を生きる私達に「逃げ道」をくれる(松…
新海誠監督の『すずめの戸締まり』は、古代神話的な設定を現代のラブコメに組み込みながら、あまりに辛い現実を生きる人々に微かな「逃げ道」を指し示してくれる作品だと思う。テーマ自体は重いが、恋愛やコメディ要素とのバランスがとても良く、ロードムービー的な展開もとても魅力的
あわせて読みたい
【実話】映画『グッドバイ、バッドマガジンズ』(杏花主演)が描く、もの作りの絶望(と楽しさ)
実在したエロ雑誌編集部を舞台に、タブーも忖度もなく業界の内実を描き切る映画『グッドバイ、バッドマガジンズ』は、「エロ雑誌」をテーマにしながら、「もの作りに懸ける想い」や「仕事への向き合い方」などがリアルに描かれる素敵な映画だった。とにかく、主役を演じた杏花が良い
あわせて読みたい
【驚異】映画『RRR』『バーフバリ』は「観るエナジードリンク」だ!これ程の作品にはなかなか出会えないぞ
2022年に劇場公開されるや、そのあまりの面白さから爆発的人気を博し、現在に至るまでロングラン上映が続いている『RRR』と、同監督作の『バーフバリ』は、大げさではなく「全人類にオススメ」と言える超絶的な傑作だ。まだ観ていない人がいるなら、是非観てほしい!
あわせて読みたい
【勝負】実話を基にコンピューター将棋を描く映画『AWAKE』が人間同士の対局の面白さを再認識させる
実際に行われた将棋の対局をベースにして描かれる映画『AWAKE』は、プロ棋士と将棋ソフトの闘いを「人間ドラマ」として描き出す物語だ。年に4人しかプロ棋士になれない厳しい世界においては、「夢破れた者たち」もまた魅力的な物語を有している。光と影を対比的に描き出す、見事な作品
あわせて読みたい
【偉業】「卓球王国・中国」実現のため、周恩来が頭を下げて請うた天才・荻村伊智朗の信じがたい努力と…
「20世紀を代表するスポーツ選手」というアンケートで、その当時大活躍していた中田英寿よりも高順位だった荻村伊智朗を知っているだろうか?選手としてだけでなく、指導者としてもとんでもない功績を残した彼の生涯を描く『ピンポンさん』から、ノーベル平和賞級の活躍を知る
あわせて読みたい
【感想】映画『君が世界のはじまり』は、「伝わらない」「分かったフリをしたくない」の感情が濃密
「キラキラした青春学園モノ」かと思っていた映画『君が世界のはじまり』は、「そこはかとない鬱屈」に覆われた、とても私好みの映画だった。自分の決断だけではどうにもならない「現実」を前に、様々な葛藤渦巻く若者たちの「諦念」を丁寧に描き出す素晴らしい物語
あわせて読みたい
【伝説】やり投げ選手・溝口和洋は「思考力」が凄まじかった!「幻の世界記録」など数々の逸話を残した…
世界レベルのやり投げ選手だった溝口和洋を知っているだろうか? 私は本書『一投に賭ける』で初めてその存在を知った。他の追随を許さないほどの圧倒的なトレーニングと、常識を疑い続けるずば抜けた思考力を武器に、体格で劣る日本人ながら「幻の世界記録」を叩き出した天才の伝説と実像
あわせて読みたい
【感想】のん主演映画『私をくいとめて』から考える、「誰かと一緒にいられれば孤独じゃないのか」問題
のん(能年玲奈)が「おひとり様ライフ」を満喫する主人公を演じる映画『私をくいとめて』を観て、「孤独」について考えさせられた。「誰かと関わっていられれば孤独じゃない」という考えに私は賛同できないし、むしろ誰かと一緒にいる時の方がより強く孤独を感じることさえある
あわせて読みたい
【あらすじ】蝦夷地の歴史と英雄・阿弖流為を描く高橋克彦の超大作小説『火怨』は全人類必読の超傑作
大げさではなく、「死ぬまでに絶対に読んでほしい1冊」としてお勧めしたい高橋克彦『火怨』は凄まじい小説だ。歴史が苦手で嫌いな私でも、上下1000ページの物語を一気読みだった。人間が人間として生きていく上で大事なものが詰まった、矜持と信念に溢れた物語に酔いしれてほしい
あわせて読みたい
【思考】森博嗣のおすすめエッセイ。「どう生きるかべきか」「生き方が分からない」と悩む人に勧めたい…
エッセイも多数出版している説家・森博嗣が、読者からの悩み相談を受けて執筆した『自分探しと楽しさについて』は、生きていく上で囚われてしまう漠然とした悩みを解消する力を持っている。どう生きるべきか悩んでしまう若者に特に読んでもらいたい1冊
あわせて読みたい
【言葉】「戸田真琴の生きづらさ」を起点に世の中を描く映画『永遠が通り過ぎていく』の”しんどい叫び”
『あなたの孤独は美しい』というエッセイでその存在を知ったAV女優・戸田真琴の初監督映画『永遠が通り過ぎていく』。トークショーで「自分が傷つけられた時の心象風景を映像にした」と語るのを聞いて、映画全体の捉え方が変わった。他者のために創作を続ける彼女からの「贈り物」
あわせて読みたい
【純愛】映画『ぼくのエリ』の衝撃。「生き延びるために必要なもの」を貪欲に求める狂気と悲哀、そして恋
名作と名高い映画『ぼくのエリ』は、「生き延びるために必要なもの」が「他者を滅ぼしてしまうこと」であるという絶望を抱えながら、それでも生きることを選ぶ者たちの葛藤が描かれる。「純愛」と呼んでいいのか悩んでしまう2人の関係性と、予想もつかない展開に、感動させられる
あわせて読みたい
【評価】のん(能年玲奈)の映画『Ribbon』が描く、コロナ禍において「生きる糧」が芸術であることの葛藤
のん(能年玲奈)脚本・監督・主演の映画『Ribbon』。とても好きな作品だった。単に女優・のんが素晴らしいというだけではなく、コロナ禍によって炙り出された「生きていくのに必要なもの」の違いに焦点を当て、「魂を生き延びさせる行為」が制約される現実を切り取る感じが見事
あわせて読みたい
【表現】映画『名付けようのない踊り』で初めて見た田中泯のダンス。「芸術以前」を志向する圧倒的パワー
映画『名付けようのない踊り』の中で田中泯は言う。「私」や「個性」を表現することには違和感がある、と。「踊りのために身体を作る」のではなく、「野良仕事で出来た身体で踊る」のだ、と。芸術になる前の踊りを探したい、と。「唯一無二の表現者」の生涯と現在地を映し出すドキュメンタリー
あわせて読みたい
【感涙】映画『彼女が好きなものは』の衝撃。偏見・無関心・他人事の世界から”脱する勇気”をどう持つか
涙腺がぶっ壊れたのかと思ったほど泣かされた映画『彼女が好きなものは』について、作品の核となる「ある事実」に一切触れずに書いた「ネタバレなし」の感想です。「ただし摩擦はゼロとする」の世界で息苦しさを感じているすべての人に届く「普遍性」を体感してください
あわせて読みたい
【アート】映画『ダ・ヴィンチは誰に微笑む』が描く「美術界の闇」と「芸術作品の真正性」の奥深さ
美術界史上最高額510億円で落札された通称「救世主」は、発見される以前から「レオナルド・ダ・ヴィンチの失われた作品」として知られる有名な絵だった。映画『ダ・ヴィンチは誰に微笑む』は、「芸術作品の真正性の問題」に斬り込み、魑魅魍魎渦巻く美術界を魅力的に描き出す
あわせて読みたい
【感想】綿矢りさ原作の映画『ひらいて』は、溢れる”狂気”を山田杏奈の”見た目”が絶妙に中和する
「片想いの相手には近づけないから、その恋人を”奪おう”」と考える主人公・木村愛の「狂気」を描く、綿矢りさ原作の映画『ひらいて』。木村愛を演じる山田杏奈の「顔」が、木村愛の狂気を絶妙に中和する見事な配役により、「狂気の境界線」をあっさり飛び越える木村愛がリアルに立ち上がる
あわせて読みたい
【貢献】社会問題を解決する2人の「社会起業家」の生き方。「豊かさ」「生きがい」に必要なものは?:『…
「ヤクの毛」を使ったファッションブランド「SHOKAY」を立ち上げ、チベットの遊牧民と中国・崇明島に住む女性の貧困問題を解決した2人の若き社会起業家の奮闘を描く『世界を変えるオシゴト』は、「仕事の意義」や「『お金』だけではない人生の豊かさ」について考えさせてくれる
あわせて読みたい
【青春】二宮和也で映画化もされた『赤めだか』。天才・立川談志を弟子・談春が描く衝撃爆笑自伝エッセイ
「落語協会」を飛び出し、新たに「落語立川流」を創設した立川談志と、そんな立川談志に弟子入りした立川談春。「師匠」と「弟子」という関係で過ごした”ぶっ飛んだ日々”を描く立川談春のエッセイ『赤めだか』は、立川談志の異端さに振り回された立川談春の成長譚が面白い
あわせて読みたい
【革新】天才マルタン・マルジェラの現在。顔出しNGでデザイナーの頂点に立った男の”素声”:映画『マル…
「マルタン・マルジェラ」というデザイナーもそのブランドのことも私は知らなかったが、そんなファッション音痴でも興味深く観ることができた映画『マルジェラが語る”マルタン・マルジェラ”』は、生涯顔出しせずにトップに上り詰めた天才の来歴と現在地が語られる
あわせて読みたい
【革命】電子音楽誕生の陰に女性あり。楽器ではなく機械での作曲に挑んだ者たちを描く映画:『ショック…
現代では当たり前の「電子音楽」。その黎明期には、既存の音楽界から排除されていた女性が多く活躍した。1978年、パリに住む1人の女性が「電子音楽」の革命の扉をまさに開こうとしている、その1日を追う映画『ショック・ド・フューチャー』が描き出す「創作の熱狂」
あわせて読みたい
【感想】映画『竜とそばかすの姫』が描く「あまりに批判が容易な世界」と「誰かを助けることの難しさ」
SNSの登場によって「批判が容易な社会」になったことで、批判を恐れてポジティブな言葉を口にしにくくなってしまった。そんな世の中で私は、「理想論だ」と言われても「誰かを助けたい」と発信する側の人間でいたいと、『竜とそばかすの姫』を観て改めて感じさせられた
あわせて読みたい
【考察】『うみべの女の子』が伝えたいことを全力で解説。「関係性の名前」を手放し、”裸”で対峙する勇敢さ
ともすれば「エロ本」としか思えない浅野いにおの原作マンガを、その空気感も含めて忠実に映像化した映画『うみべの女の子』。本作が一体何を伝えたかったのかを、必死に考察し全力で解説する。中学生がセックスから関係性をスタートさせることで、友達でも恋人でもない「名前の付かない関係性」となり、行き止まってしまう感じがリアル
あわせて読みたい
【狂気】バケモン・鶴瓶を映し出す映画。「おもしろいオッチャン」に潜む「異常さ」と「芸への情熱」:…
「俺が死ぬまで公開するな」という条件で撮影が許可された映画『バケモン』。コロナ禍で映画館が苦境に立たされなければ、公開はずっと先だっただろう。テレビで見るのとは違う「芸人・笑福亭鶴瓶」の凄みを、古典落語の名作と名高い「らくだ」の変遷と共に切り取る
あわせて読みたい
【世界観】映画『夜は短し歩けよ乙女』の”黒髪の乙女”は素敵だなぁ。ニヤニヤが止まらない素晴らしいアニメ
森見登美彦の原作も大好きな映画『夜は短し歩けよ乙女』は、「リアル」と「ファンタジー」の境界を絶妙に漂う世界観がとても好き。「黒髪の乙女」は、こんな人がいたら好きになっちゃうよなぁ、と感じる存在です。ずっとニヤニヤしながら観ていた、とても大好きな映画
あわせて読みたい
【革新】映画音楽における唯一のルールは「ルールなど無い」だ。”異次元の音”を生み出す天才を追う:映…
「無声映画」から始まった映画業界で、音楽の重要性はいかに認識されたのか?『JAWS』の印象的な音楽を生み出した天才は、映画音楽に何をもたらしたのか?様々な映画の実際の映像を組み込みながら、「映画音楽」の世界を深堀りする映画『すばらしき映画音楽たち』で、異才たちの「創作」に触れる
あわせて読みたい
【アート】「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」(森美術館)と「美術手帖 Chim↑Pom特集」の衝撃から「…
Chim↑Pomというアーティストについてさして詳しいことを知らずに観に行った、森美術館の「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」に、思考をドバドバと刺激されまくったので、Chim↑Pomが特集された「美術手帖」も慌てて買い、Chim↑Pomについてメッチャ考えてみた
あわせて読みたい
【考察】生きづらい性格は変わらないから仮面を被るしかないし、仮面を被るとリア充だと思われる:『勝…
「リア充感」が滲み出ているのに「生きづらさ」を感じてしまう人に、私はこれまでたくさん会ってきた。見た目では「生きづらさ」は伝わらない。24年間「リアル彼氏」なし、「脳内彼氏」との妄想の中に生き続ける主人公を描く映画『勝手にふるえてろ』から「こじらせ」を知る
あわせて読みたい
【おすすめ】濱口竜介監督の映画『親密さ』は、「映像」よりも「言葉」が前面に来る衝撃の4時間だった
専門学校の卒業制作として濱口竜介が撮った映画『親密さ』は、2時間10分の劇中劇を組み込んだ意欲作。「映像」でありながら「言葉の力」が前面に押し出される作品で、映画や劇中劇の随所で放たれる「言葉」に圧倒される。4時間と非常に長いが、観て良かった
あわせて読みたい
【無知】映画『生理ちゃん』で理解した気になってはいけないが、男(私)にも苦労が伝わるコメディだ
男である私にはどうしても理解が及ばない領域ではあるが、女友達から「生理」の話を聞く機会があったり、映画『生理ちゃん』で視覚的に「生理」の辛さが示されることで、ちょっとは分かったつもりになっている。しかし男が「生理」を理解するのはやっぱり難しい
あわせて読みたい
【人生】どう生きるべきかは、どう死にたいかから考える。死ぬ直前まで役割がある「理想郷」を描く:『…
「近隣の村から『姥捨て』と非難される理想郷」を描き出す『でんでら国』は、「死ぬ直前まで、コミュニティの中で役割が存在する」という世界で展開される物語。「お金があっても決して豊かとは言えない」という感覚が少しずつ広まる中で、「本当の豊かさ」とは何かを考える
あわせて読みたい
【あらすじ】天才とは「分かりやすい才能」ではない。前進するのに躊躇する暗闇で直進できる勇気のこと…
ピアノのコンクールを舞台に描く『蜜蜂と遠雷』は、「天才とは何か?」と問いかける。既存の「枠組み」をいとも簡単に越えていく者こそが「天才」だと私は思うが、「枠組み」を安易に設定することの是非についても刃を突きつける作品だ。小説と映画の感想を一緒に書く
あわせて読みたい
【壮絶】本当に「美人は得」か?「美しさ」という土俵を意識せざるを得ない少女・女性たちの現実:『自…
美醜で判断されがちな”ルッキズム”の世の中に刃を突きつける小説『自画像』。私自身は、「キレイな人もキレイな人なりの大変さを抱えている」と感じながら生きているつもりだが、やはりその辛さは理解されにくい。私も男性であり、ルッキズムに加担してないとはとても言えない
あわせて読みたい
【奇跡】鈴木敏夫が2人の天才、高畑勲と宮崎駿を語る。ジブリの誕生から驚きの創作秘話まで:『天才の思…
徳間書店から成り行きでジブリ入りすることになったプロデューサー・鈴木敏夫が、宮崎駿・高畑勲という2人の天才と共に作り上げたジブリ作品とその背景を語り尽くす『天才の思考 高畑勲と宮崎駿』。日本のアニメ界のトップランナーたちの軌跡の奇跡を知る
あわせて読みたい
【実像】ベートーヴェンの「有名なエピソード」をほぼ一人で捏造・創作した天才プロデューサーの実像:…
ベートーヴェンと言えば、誰もが知っている「運命」を始め、天才音楽家として音楽史に名を刻む人物だが、彼について良く知られたエピソードのほとんどは実は捏造かもしれない。『ベートーヴェン捏造 名プロデューサーは嘘をつく』が描く、シンドラーという”天才”の実像
あわせて読みたい
【教養】美術を「感じたまま鑑賞する」のは難しい。必要な予備知識をインストールするための1冊:『武器…
芸術を「感性の赴くまま見る」のは、日本特有だそうだ。欧米では美術は「勉強するもの」と認識されており、本書ではアートを理解しようとするスタンスがビジネスにも役立つと示唆される。美術館館長を務める著者の『武器になる知的教養 西洋美術鑑賞』から基礎の基礎を学ぶ
あわせて読みたい
【天才】写真家・森山大道に密着する映画。菅田将暉の声でカッコよく始まる「撮り続ける男」の生き様:…
映画『あゝ荒野』のスチール撮影の際に憧れの森山大道に初めて会ったという菅田将暉の声で始まる映画『過去はいつも新しく、未来はつねに懐かしい』は、ちゃちなデジカメ1つでひたすら撮り続ける異端児の姿と、50年前の処女作復活物語が見事に交錯する
あわせて読みたい
【あらすじ】子どもは大人よりずっと大人だ。「子ども扱い」するから、「子どもの枠」から抜け出せない…
宮部みゆき『ソロモンの偽証』は、その分厚さ故になかなか手が伸びない作品だろうが、「長い」というだけの理由で手を出さないのはあまりにももったいない傑作だ。「中学生が自前で裁判を行う」という非現実的設定をリアルに描き出すものすごい作品
あわせて読みたい
【助けて】息苦しい世の中に生きていて、人知れず「傷」を抱えていることを誰か知ってほしいのです:『…
元気で明るくて楽しそうな人ほど「傷」を抱えている。そんな人をたくさん見てきた。様々な理由から「傷」を表に出せない人がいる世の中で、『包帯クラブ』が提示する「見えない傷に包帯を巻く」という具体的な行動は、気休め以上の効果をもたらすかもしれない
あわせて読みたい
【映画】『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』で号泣し続けた私はTVアニメを観ていない
TVアニメは観ていない、というかその存在さえ知らず、物語や登場人物の設定も何も知らないまま観に行った映画『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』に、私は大号泣した。「悪意のない物語」は基本的に好きではないが、この作品は驚くほど私に突き刺さった
あわせて読みたい
【天才】諦めない人は何が違う?「努力を努力だと思わない」という才能こそが、未来への道を開く:映画…
どれだけ「天賦の才能」に恵まれていても「努力できる才能」が無ければどこにも辿り着けない。そして「努力できる才能」さえあれば、仮に絶望の淵に立たされることになっても、立ち上がる勇気に変えられる。映画『マイ・バッハ』で知る衝撃の実話
あわせて読みたい
【変人】学校教育が担うべき役割は?子供の才能を伸ばすために「異質な人」とどう出会うべきか?:『飛…
高校の美術教師からアーティストとして活動するようになった著者は、教育の現場に「余白(スキマ)」が減っていると指摘する。『飛び立つスキマの設計学』をベースに、子どもたちが置かれている現状と、教育が成すべき役割について確認する。
あわせて読みたい
【あらすじ】「愛されたい」「必要とされたい」はこんなに難しい。藤崎彩織が描く「ままならない関係性…
好きな人の隣にいたい。そんなシンプルな願いこそ、一番難しい。誰かの特別になるために「異性」であることを諦め、でも「異性」として見られないことに苦しさを覚えてしまう。藤崎彩織『ふたご』が描き出す、名前がつかない切実な関係性
あわせて読みたい
【肯定】社会不適合者こそ非凡。学校・世の中に馴染めなかった異才たちの過去から”才能”の本質を知る:…
「みんなと同じ」に馴染めないと「社会不適合」と判断され、排除されてしまうことが多いでしょう。しかし『非属の才能』では、「どこにも属せない感覚」にこそ才能の源泉があると主張します。常識に違和感を覚えてしまう人を救う本から、同調圧力に屈しない生き方を学ぶ
あわせて読みたい
【考察】世の中は理不尽だ。平凡な奴らがのさばる中で、”特別な私の美しい世界”を守る生き方:『オーダ…
自分以外は凡人、と考える主人公の少女はとてもイタい。しかし、世間の価値観と折り合わないなら、自分の美しい世界を守るために闘うしかない。中二病の少女が奮闘する『オーダーメイド殺人クラブ』をベースに、理解されない世界をどう生きるかについて考察する
あわせて読みたい
【感想】人間関係って難しい。友達・恋人・家族になるよりも「あなた」のまま関わることに価値がある:…
誰かとの関係性には大抵、「友達」「恋人」「家族」のような名前がついてしまうし、そうなればその名前に縛られてしまいます。「名前がつかない関係性の奇跡」と「誰かを想う強い気持ちの表し方」について、『君の膵臓をたべたい』をベースに書いていきます
あわせて読みたい
【感想】努力では才能に勝てないのか?どうしても辿り着きたい地点まで迷いながらも突き進むために:『…
どうしても辿り着きたい場所があっても、そのあまりの遠さに目が眩んでしまうこともあるでしょう。そんな人に向けて、「才能がない」という言葉に逃げずに前進する勇気と、「仕事をする上で大事なスタンス」について『羊と鋼の森』をベースに書いていきます
あわせて読みたい
【葛藤】部活で後悔しないために。今やりたいことをやりきって、過去を振り返らないための全力:『風に…
勉強の方が、部活動より重要な理由なんて無い。どれだけ止められても「全力で打ち込みたい」という気持ちを抑えきれないものに出会える人生の方が、これからの激動の未来を生き延びられるはずと信じて突き進んでほしい。部活小説『風に恋う』をベースに書いていく
あわせて読みたい
【肯定】価値観の違いは受け入れられなくていい。「普通」に馴染めないからこそ見える世界:『君はレフ…
子どもの頃、周りと馴染めない感覚がとても強くて苦労しました。ただし、「普通」から意識的に外れる決断をしたことで、自分が持っている価値観を言葉で下支えすることができたとも感じています。「普通」に馴染めず、自分がダメだと感じてしまう人へ。
ルシルナ
文化・芸術・将棋・スポーツ【本・映画の感想】 | ルシルナ
知識や教養は、社会や学問について知ることだけではありません。文化的なものもリベラルアーツです。私自身は、創作的なことをしたり、勝負事に関わることはありませんが、…
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…


















































































































































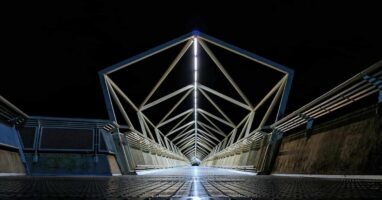
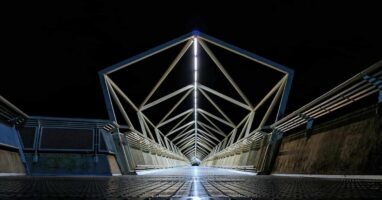




















































































































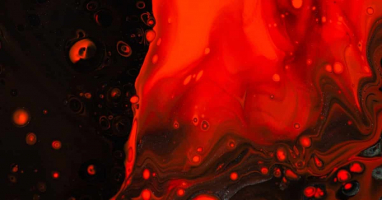
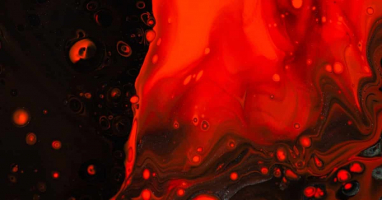














































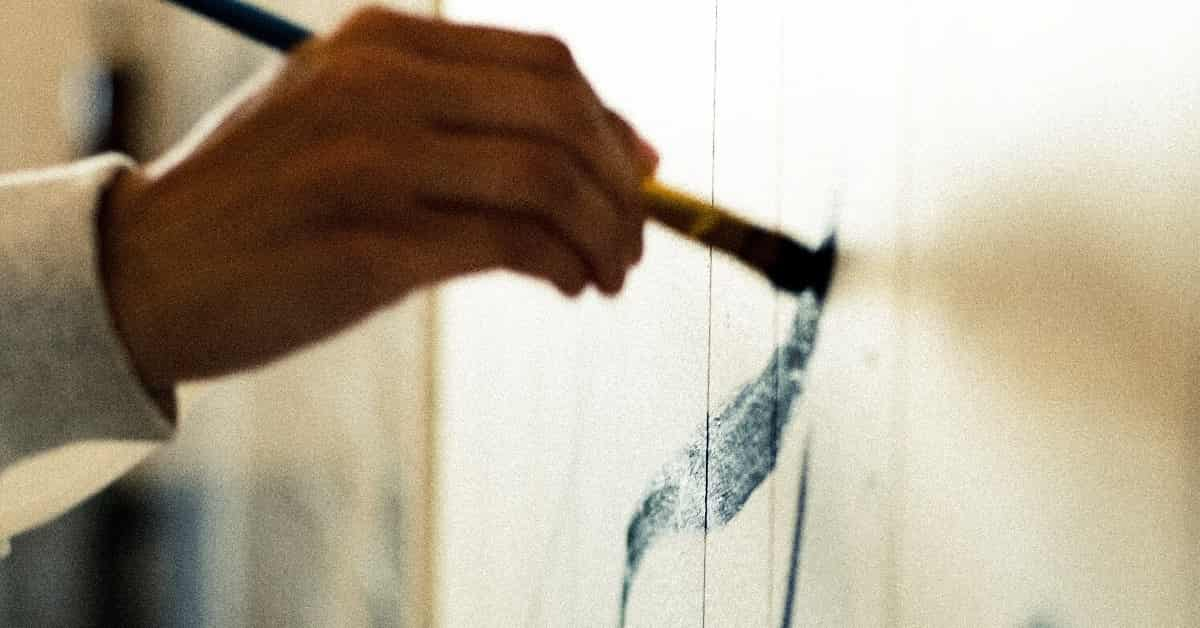






コメント