目次
はじめに
この記事で取り上げる映画
Writer:ヴィクトル・コサコフスキー, 監督:ヴィクトル・コサコフスキー
¥2,500 (2022/09/22 07:31時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
この映画をガイドにしながら記事を書いていきます
今どこで観れるのか?
「シネマ映画.com」で観られます
この記事の3つの要点
- 普通は、「カメラで撮られている」という事実が、どうしても「現実」に影響を与えてしまう
- 「どんな風に現実を切り取りたいか」という「撮影者の意図」も、「現実」の解釈を歪ませる可能性を持っている
- 「カメラの存在」「撮影者の意図」を排し、さらに「家畜」を被写体に据えたことで、ドキュメンタリーとして奇跡的に成立している
「面白かったか」と聞かれれば答えに窮するが、「斬新かどうか」で言えば間違いなく斬新な作品
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
「カメラの存在」や「撮影者の意図」を感じさせない、ドキュメンタリーとして”斬新さ”に満ちた映画『GUNDA』
あわせて読みたい
【悲哀】2度の東京オリンピックに翻弄された都営アパートから「公共の利益」と「個人の権利」を考える:…
1964年の東京オリンピックを機に建設された「都営霞ケ丘アパート」は、東京オリンピック2020を理由に解体が決まり、長年住み続けた高齢の住民に退去が告げられた。「公共の利益」と「個人の権利」の狭間で翻弄される人々の姿を淡々と映し出し、静かに「社会の在り方」を問う映画
基本的にこの「ルシルナ」というブログでは、「私が良いと感じた映画・本」に関する記事のみを書いている。そういう意味で、映画『GUNDA/グンダ』を取り上げることは、少しルールに反していると言えるかもしれない。正直、そこまで面白いと思えたわけではないからだ。

ただこの映画はドキュメンタリーとして、ある”特異さ”を有していると感じた。その点について、私は文章を書きたいと思ったのだ。面白いかどうかと聞かれれば、私は口を濁すが、ドキュメンタリーとして斬新かどうかと聞かれれば、「斬新だ」と即答するだろう。
この映画は、ドキュメンタリーにおける「デュシャンの『泉』」ではないかと思う。その意味は後で説明することにしよう。
ドキュメンタリーでは回避不可能な「そこにカメラがある問題」について
あわせて読みたい
【驚異】甲子園「2.9連覇」を成し遂げた駒大苫小牧野球部監督・香田誉士史の破天荒で規格外の人生:『勝…
「田中将大と斎藤佑樹の死闘」「37年ぶりの決勝戦再試合」「驚異の2.9連覇」など話題に事欠かなかった駒大苫小牧野球部。その伝説のチームを率いた名将・香田誉士史の評伝『勝ちすぎた監督』は、体罰が問題になった男の毀誉褒貶を余すところなく描き出す。しかしとんでもない男だ
私はドキュメンタリーが好きで、結構観ている方だと思う。今まで知らなかった、あるいは想像さえしたことがないような現実が様々に切り取られるドキュメンタリーには、これまで何度も衝撃を受けてきた。
しかし一方で、ドキュメンタリーはその性質上、「現実を完全に切る取る」ことができない。何故なら、「カメラを向けられている」という事実が、少なからず「現実」に影響を及ぼすはずだからだ。
普段立ちションをしているという人も、カメラの前ではまずしないだろう。信号無視やちょっとした暴言、放屁なども、「そこにカメラがある」という事実がブレーキを掛けるかもしれない。あるいは逆に、普段お年寄りに座席を譲る人が、「カメラの前でそんなことをするのは恥ずかしい」と考えて止める可能性だってあるだろう。
あわせて読みたい
【現代】これが今の若者の特徴?衝撃のドキュメンタリー映画『14歳の栞』から中学生の今を知る
埼玉県春日部市に実在する中学校の2年6組の生徒35人。14歳の彼らに50日間密着した『14歳の栞』が凄かった。カメラが存在しないかのように自然に振る舞い、内心をさらけ出す彼らの姿から、「中学生の今」を知る
長期に渡る密着取材であれば、次第に「カメラの存在」に意識が向かなくなるかもしれないし、あるいは、芸能人やYouTuberなど「普段から撮られている人」の場合は、普通の人よりもカメラの前で「素」でいられるのかもしれない。しかし問題は、「カメラの存在がどの程度影響を与えているのか」を判断する術が受け取り手にはないという点にある。
例えば、ドキュメンタリーで映し出されるのが自分の知り合いなら、「普段の振る舞い」と「カメラの前での振る舞い」を比較することで、「カメラの存在」の影響を推し量ることができるだろう。しかしほとんどの場合、ドキュメンタリーの被写体は、自分の知り合いではない。だから、「カメラがなかったら、その人はどんな風に振る舞うのか」を想像するきっかけを掴むことはなかなか難しいと思う。

もちろん、「どうせ、カメラを通じた姿しか自分は知り得ないのだから、『カメラがなかったら』なんて考えても仕方がない」みたいに思考する人もいるだろう。その考え方でまったく何の問題もないし、私にしても、この「カメラの存在」という要素で作品の捉え方が大きく変わるなどと考えているわけではない。しかしやはり、原理的には、「ドキュメンタリー映画から『カメラの存在』の影響を取り除くのは困難」と考えるべきだと思うし、撮影に当たって実際的な問題を引き起こすケースだってあるのではないだろうか。
あわせて読みたい
【衝撃】『ゆきゆきて、神軍』はとんでもないドキュメンタリー映画だ。虚実が果てしなく入り混じる傑作
奥崎謙三という元兵士のアナーキストに密着する『ゆきゆきて、神軍』。ドキュメンタリー映画の名作として名前だけは知っていたが、まさかこんなとんでもない映画だったとはと驚かされた。トークショーで監督が「自分の意向を無視した編集だった」と語っていたのも印象的
「撮影者の意図」さえも排除されていると感じられる
映画『GUNDA/グンダ』は、「カメラの存在」の問題をシンプルに解決する。被写体が人間ではないのだ。人間以外の生き物の場合も、カメラのあるなしで振る舞いが変わる可能性はゼロではないが、少なくとも観る側は、「カメラが無くてもきっと同じ振る舞いのはず」と思えるだろう。こうして、「そこにカメラがある問題」はシンプルに解決される。
しかしただこれだけの話であれば、「人間以外を撮影対象としたドキュメンタリー全般」に同じことが当てはまるだろう。この映画には実はもう1つ特長がある。それは「『撮影者の意図』が存在しないように見える」ということだ。
ドキュメンタリーは、「現実を切り取る」ものだが、目の前に存在する現実をむやみやたらに切り取ったところで作品として成立するわけではない。監督には普通「撮影意図」があるはずで、その「意図」こそが作品の肝だ。カメラマンはその意図を踏まえて、「こういう画がほしい」「こういう展開を望んでいる」というような思惑と共に撮影しているはずだ。
あわせて読みたい
【誠実】地下鉄サリン事件の被害者が荒木浩に密着。「贖罪」とは何かを考えさせる衝撃の映画:『AGANAI…
私には、「謝罪すること」が「誠実」だという感覚がない。むしろ映画『AGANAI 地下鉄サリン事件と私』では、「謝罪しない誠実さ」が描かれる。被害者側と加害者側の対話から、「謝罪」「贖罪」の意味と、信じているものを諦めさせることの難しさについて書く
この事実は、撮影対象が動物だろうと変わることはない。
例えば、アフリカのサバンナの映像を見ていて、そこに「ライオン」と「インパラ」が映ったとしよう。この時点で見ている者は、「インパラがライオンに襲われるのではないか」と想像するはずだ。もちろん、その予想を裏切って別の展開になる可能性もあるのだが、ライオンとインパラを目にした時点で私たちはそのように誘導される。

そしてその誘導は間違いなく、監督が意図したものだ。
あわせて読みたい
【天才】映画音楽の発明家『モリコーネ』の生涯。「映画が恋した音楽家」はいかに名曲を生んだか
「映画音楽のフォーマットを生み出した」とも評される天才作曲家エンリオ・モリコーネを扱った映画『モリコーネ 映画が恋した音楽家』では、生涯で500曲以上も生み出し、「映画音楽」というジャンルを比べ物にならないほどの高みにまで押し上げた人物の知られざる生涯が描かれる
「撮影者の意図」があろうがなかろうが、ライオン・インパラの行動に違いはない。しかしくその「意図」は、見ている者の意識をコントロールする。見る側としても、「撮影者の意図」は映像を見る上での指針となるのだから、あるのが当然だと考えるだろう。
つまり、監督が「こう撮りたい」と考えるだけではなく、見る側もそのような誘導を望むからこそ、ドキュメンタリーには「撮影者の意図」が組み込まれることになる。そしてそれは、逆に言えば、「『撮影者の意図』に沿った『現実』しか切り取れない」という状況にも繋がっていくはずだ。
例えば、公園に水道の蛇口をひねって水を飲む特技を持つカラスがいるとする。しかしその成功率は低く、100回チャレンジして1回成功するかどうかだとしよう。しかし、その1回をカメラに収めることで、あたかもこのカラスが常に蛇口をひねることに成功するかのように誤認させることができる。本当は「100回に1回しか成功しない」というのが「現実」なのに、「撮影者の意図」が存在することでその「現実」が勝手に歪曲されてしまうというわけだ。
この「撮影者の意図」も、「ドキュメンタリーが現実を正しく映し出しているか」に影響する要素だと私は考えている。
あわせて読みたい
【改革】改修期間中の国立西洋美術館の裏側と日本の美術展の現実を映すドキュメンタリー映画:『わたし…
「コロナ禍」という絶妙すぎるタイミングで改修工事を行った国立西洋美術館の、普段見ることが出来ない「裏側」が映し出される映画『わたしたちの国立西洋美術館』は、「日本の美術展」の問題点を炙り出しつつ、「『好き』を仕事にした者たち」の楽しそうな雰囲気がとても魅力的に映るドキュメンタリー
しかし映画『GUNDA/グンダ』には、そんな「意図」は一切感じられない。もちろん、私がそう感じただけで、監督は「意図」を持っていた可能性もある。しかし、「豚」「鶏」「牛」の、何が起こるわけでもない日常を、ただただ淡々と切り取っているようにしか見えない映像の連続から、「撮影者の意図」を読み取ることはなかなか難しいのではないかと思う。
ある意味では、「だからこそ私には退屈に感じられた」とも言える。しかしいずれにしても、「ドキュメンタリー」に必要不可欠に思われた「撮影者の意図」が感じられないという点は非常に斬新ではないかと感じた。
「ドキュメンタリーとして新たな価値を提示した」という点こそが評価されているのではないか
ここまで説明してきたように、この映画は、「カメラの存在」「撮影者の意図」を排した形で撮影されたドキュメンタリーだという点に特長があると私には感じられた。「カメラの存在」も「撮影者の意図」も、ドキュメンタリーから外すことが難しい要素に思えるのだが、この映画はその2つを存在させない形で成立していると私は思う。
そしてだからこそ、この映画を「デュシャンの『泉』」だと感じた。
「デュシャンの『泉』」の詳しい説明については、以下の記事を読んでほしい。
あわせて読みたい
【教養】美術を「感じたまま鑑賞する」のは難しい。必要な予備知識をインストールするための1冊:『武器…
芸術を「感性の赴くまま見る」のは、日本特有だそうだ。欧米では美術は「勉強するもの」と認識されており、本書ではアートを理解しようとするスタンスがビジネスにも役立つと示唆される。美術館館長を務める著者の『武器になる知的教養 西洋美術鑑賞』から基礎の基礎を学ぶ
ざっと説明すると、「既製品の男性用小便器に作家自身の署名をサインペンで書いただけのアート」である。しかしこれが、現代アートとしてものすごく高く評価されているのだ。例えば、世界中の美術関係者500人による2004年のアンケートでは、「最も影響力のある現代アート」の1位にこの「デュシャンの『泉』」が選ばれている。ピカソやアンディー・ウォーホルよりも評価が高いというのだから驚きだろう。
MUTERIUM
【美術解説】「現代アート」の父と呼ばれたマルセル・デュシャン | MUTERIUM
マルセル・デュシャンは「現代アートの父」と呼ばれ、今日においてもその影響は計り知れません。ここでは、そのデュシャンの代表作を紹介し、彼の謎めいた作品内部に秘めら…
何故ここまで評価が高いのか。それは「既存の常識を打ち壊した」からだ。それまでの美術界では「美しいモノ」「一点モノ」にこそ価値があると考えられてきた。しかし、「デュシャンの『泉』」はそのどちらの価値観も一撃で粉砕するような存在感を放っている。「既存の常識」を破壊することでその存在に気づかせる「デュシャンの『泉』の」ような作品は、歴史の中で高く評価され得るのだ。

あわせて読みたい
【狂気?】オウム真理教を内部から映す映画『A』(森達也監督)は、ドキュメンタリー映画史に残る衝撃作だ
ドキュメンタリー映画の傑作『A』(森達也)をようやく観られた。「オウム真理教は絶対悪だ」というメディアの報道が凄まじい中、オウム真理教をその内部からフラットに映し出した特異な作品は、公開当時は特に凄まじい衝撃をもたらしただろう。私たちの「当たり前」が解体されていく斬新な一作
そう考えた時、「カメラの存在」「撮影者の意図」という2つの「常識」を打ち壊しているように感じられる『GUNDA/グンダ』もまた、ドキュメンタリーの歴史の上で高く評価され得るのではないか、と感じた。
まあ、私がまったく的外れなことを書いている可能性も十分にあるので、話半分ぐらいに受け取ってもらえればいいだろう。
被写体が「家畜」であることの絶妙さと皮肉
さて、普通に考えて「カメラの存在」「撮影者の意図」の存在しないドキュメンタリーは、ドキュメンタリーとして成立しにくいだろう。しかし、その困難さを乗り越えるのに上手く利用しているのが被写体の選択だと私は感じた。
あわせて読みたい
【違和感】映画『コントラ』は、「よく分かんない」が「よく分かんないけど面白い」に変わる不思議な作品
ほぼ内容を知らないまま観に行った映画『コントラ』は、最後の最後まで結局何も理解できなかったが、それでもとても面白い作品だった。「後ろ向きに歩く男」が放つ違和感を主人公・ソラの存在感が中和させており、奇妙なのに可能な限り「日常感」を失わせずに展開させる構成が見事だと思う
映画で映し出されるのは「豚」「鶏」「牛」という、私たちが日常的に食している「家畜」なのだ。
「家畜」というのは私たちにとって、なかなかに微妙な存在だ。誰もがある程度「生き物を大切にする気持ち」を持っているだろう。また、豚・鶏・牛に「可愛い」という感覚を抱いたり、触れることで「親しみ」を感じることもあると思う。
しかし私たちは、同じ手でその「家畜」を食べている。この2つの事実は大いに矛盾するはずだが、私たちは普段その矛盾をあまり意識しない。それはつまり、「最終的には食肉になる」という事実と矛盾しないような形で、「家畜」をある意味で少し低く捉えているということだと思う。
そんな”撮るに足らない”存在でしかないはずの「家畜」を、この映画では非常に美しい映像でカッコよく描き出していく。私たちが「家畜」という言葉からイメージするものとは真逆の世界観だと言っていい。そしてだからこそ、観る者はざわついた気分にさせられてしまう。
あわせて読みたい
【異様】西成のあいりん地区を舞台にした映画『解放区』は、リアルとフェイクの境界が歪んでいる
ドキュメンタリー映画だと思って観に行った『解放区』は、実際にはフィクションだったが、大阪市・西成区を舞台にしていることも相まって、ドキュメンタリー感がとても強い。作品から放たれる「異様さ」が凄まじく、「自分は何を観せられているんだろう」という感覚に襲われた
私たちが犬や猫の肉を食べることに抵抗を感じるのは、犬や猫を「愛玩」という捉え方をしているからだ。「愛玩している存在」を「食べる」などあり得ない。そして同じ理屈を当てはめるなら、豚・鶏・牛は私たちの意識の中で「愛玩」には成り得ない、ということになるだろう。

しかしこの映画で描かれる豚・鶏・牛は、「美しい」「カッコいい」という感情を通じて「愛玩」を訴えかける。豚の親子は必死に生きているし、片足の鶏は勇敢に見えるし、ハエにたかられている牛たちの表情はなんだかカッコいい。そして、そんな印象が高まれば高まるほど、私たちの内側で「矛盾」が大きく募っていくことになる。
「美しい」「カッコいい」と感じる対象を、自分たちは「食べている」のか、という矛盾が。
あわせて読みたい
【称賛?】日本社会は終わっているのか?日本在住20年以上のフランス人が本国との比較で日本を評価:『…
日本に住んでいると、日本の社会や政治に不満を抱くことも多い。しかし、日本在住20年以上の『理不尽な国ニッポン』のフランス人著者は、フランスと比べて日本は上手くやっていると語る。宗教や個人ではなく、唯一「社会」だけが善悪を決められる日本の特異性について書く
もし、この映画の被写体が「家畜」でないとしたら、観客にこのような「矛盾した気分」を湧き上がらせることはできなかっただろう。この「『家畜』を撮影対象にしている」という点が、「カメラの存在」「撮影者の意図」なくしてドキュメンタリーを成立させた大きな要素だと私は感じた。
どこまでが監督の意図通りなのか私には判断できないが、あらゆる要素が絶妙に絡まり合って、「普通にはドキュメンタリーとして成立しない作品を、斬新な形でドキュメンタリーとして成立させた」という”特異さ”を生み出すことに成功していると思う。
あわせて読みたい
【表現】映画『名付けようのない踊り』で初めて見た田中泯のダンス。「芸術以前」を志向する圧倒的パワー
映画『名付けようのない踊り』の中で田中泯は言う。「私」や「個性」を表現することには違和感がある、と。「踊りのために身体を作る」のではなく、「野良仕事で出来た身体で踊る」のだ、と。芸術になる前の踊りを探したい、と。「唯一無二の表現者」の生涯と現在地を映し出すドキュメンタリー
Writer:ヴィクトル・コサコフスキー, 監督:ヴィクトル・コサコフスキー
¥2,500 (2023/09/23 20:01時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品視聴済】私が観てきたドキュメンタリー映画を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が観てきたドキュメンタリー映画を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。
最後に
あわせて読みたい
【映画】『キャスティング・ディレクター』の歴史を作り、ハリウッド映画俳優の運命を変えた女性の奮闘
映画『キャスティング・ディレクター』は、ハリウッドで伝説とされるマリオン・ドハティを描き出すドキュメンタリー。「神業」「芸術」とも評される配役を行ってきたにも拘わらず、長く評価されずにいた彼女の不遇の歴史や、再び「キャスティングの暗黒期」に入ってしまった現在のハリウッドなどを切り取っていく
正直に言えば、睡魔に耐えながら、時々ウトウトしてしまうような映画鑑賞だった。全体的に単調で、音楽もナレーションもないので、どうしても眠くなってしまう。
そういう意味で「面白い」とはなかなか言い難い作品だ。しかしその一方で、ドキュメンタリーの歴史の中で、エポックメイキングな出来事として記憶される作品になるのではないかとも感じさせられた。
あわせて読みたい
【魅惑】マツコも絶賛の“日本人初のパリコレトップモデル”山口小夜子のメイクの凄さや素顔を描く映画:…
日本人初のパリコレトップモデルである山口小夜子と親交があった監督が紡ぐ映画『氷の花火 山口小夜子』は、未だ謎に包まれているその人生の一端を垣間見せてくれる作品だ。彼女を知る様々な人の記憶と、彼女を敬愛する多くの人の想いがより合って、一時代を築いた凄まじい女性の姿が浮かび上がってくる
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【丁寧】筒井康隆『敵』を吉田大八が映画化!死を見定めた老紳士が囚われた狂気的日常を描く(主演:長…
映画『敵』(吉田大八監督)は、原作が筒井康隆だけのことはあり、物語はとにかく意味不明だった。しかしそれでも「面白い」と感じさせるのだから凄いものだと思う。前半では「イケオジのスローライフ」が丁寧に描かれ、そこから次第に、「元大学教授が狂気に飲み込まれていく様」が淡々と、しかし濃密に描かれていく
あわせて読みたい
【アート】映画『ヒプノシス』は、レコードジャケットの天才創作集団の繁栄と衰退を掘り起こす
映画『ヒプノシス』は、レコードのジャケットデザインで一世を風靡した天才集団「ヒプノシス」の栄枯盛衰を描き出すドキュメンタリー映画である。ストームとポーの2人が中心となって作り上げた凄まじいクリエイティブはそのまま、レコードジャケットの歴史と言っていいほどだ。ぶっ飛んだ才能とその生き方を知れる映画である
あわせて読みたい
金沢&富山のアート旅!「21世紀美術館」だけじゃない激アツなおすすめ美術館巡りをご提案
金沢・富山を巡るアート旅に出かけてきました!メインの目的は「21世紀美術館」でしたが、それ以上に「ASTER Curator Museum」「LIP BAR」「KAMU kanazawa」などがとにかく素晴らしかったです。アートや美術のことはド素人ですが、超個人的主観で「金沢・富山で触れられるアートの良さ」について書いた旅行記となります
あわせて読みたい
【解説】映画『スターフィッシュ』をネタバレ全開で考察。主人公が直面する”奇妙な世界”の正体は?
映画『スターフィッシュ』は、「親友の葬儀」とそれに続く「不法侵入」の後、唐突に「意味不明な世界観」に突入していき、その状態のまま物語が終わってしまう。解釈が非常に難しい物語だが、しかし私なりの仮説には辿り着いた。そこでこの記事では、ネタバレを一切気にせずに「私が捉えた物語」について解説していくことにする
あわせて読みたい
【常識】群青いろ制作『彼女はなぜ、猿を逃したか?』は、凄まじく奇妙で、実に魅力的な映画だった(主…
映画『彼女はなぜ、猿を逃したか?』(群青いろ制作)は、「絶妙に奇妙な展開」と「爽快感のあるラスト」の対比が魅力的な作品。主なテーマとして扱われている「週刊誌報道からのネットの炎上」よりも、私は「週刊誌記者が無意識に抱いている思い込み」の方に興味があったし、それを受け流す女子高生の受け答えがとても素敵だった
あわせて読みたい
【魅惑】マツコも絶賛の“日本人初のパリコレトップモデル”山口小夜子のメイクの凄さや素顔を描く映画:…
日本人初のパリコレトップモデルである山口小夜子と親交があった監督が紡ぐ映画『氷の花火 山口小夜子』は、未だ謎に包まれているその人生の一端を垣間見せてくれる作品だ。彼女を知る様々な人の記憶と、彼女を敬愛する多くの人の想いがより合って、一時代を築いた凄まじい女性の姿が浮かび上がってくる
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『悪は存在しない』(濱口竜介)の衝撃のラストの解釈と、タイトルが示唆する現実(主…
映画『悪は存在しない』(濱口竜介監督)は、観る者すべてを困惑に叩き落とす衝撃のラストに、鑑賞直後は迷子のような状態になってしまうだろう。しかし、作中で提示される様々な要素を紐解き、私なりの解釈に辿り着いた。全編に渡り『悪は存在しない』というタイトルを強く意識させられる、脚本・映像も見事な作品だ
あわせて読みたい
【斬新】映画『王国(あるいはその家について)』(草野なつか)を観よ。未経験の鑑賞体験を保証する
映画『王国(あるいはその家について)』は、まず経験できないだろう異様な鑑賞体験をもたらす特異な作品だった。「稽古場での台本読み」を映し出すパートが上映時間150分のほとんどを占め、同じやり取りをひたすら繰り返し見せ続ける本作は、「王国」をキーワードに様々な形の「狂気」を炙り出す異常な作品である
あわせて読みたい
【おすすめ】カンヌ映画『PERFECT DAYS』は、ほぼ喋らない役所広司の沈黙が心地よい(ヴィム・ヴェンダ…
役所広司主演映画『PERFECT DAYS』(ヴィム・ヴェンダース監督)は、主人公・平山の「沈黙」がとにかく雄弁な物語である。渋谷区のトイレの清掃員である無口な平山の、世間とほとんど繋がりを持たない隔絶した日常が、色んなものを抱えた者たちを引き寄せ、穏やかさで満たしていく様が素晴らしい
あわせて読みたい
【痛快】精神病院の隔離室から脱した、善悪の判断基準を持たない狂気の超能力者が大暴れする映画:『モ…
モナ・リザ アンド ザ ブラッドムーン』は、「10年以上拘束され続けた精神病院から脱走したアジア系女性が、特殊能力を使って大暴れする」というムチャクチャな設定の物語なのだが、全編に通底する「『善悪の判断基準』が歪んでいる」という要素がとても見事で、意味不明なのに最後まで惹きつけられてしまった
あわせて読みたい
【映画】『キャスティング・ディレクター』の歴史を作り、ハリウッド映画俳優の運命を変えた女性の奮闘
映画『キャスティング・ディレクター』は、ハリウッドで伝説とされるマリオン・ドハティを描き出すドキュメンタリー。「神業」「芸術」とも評される配役を行ってきたにも拘わらず、長く評価されずにいた彼女の不遇の歴史や、再び「キャスティングの暗黒期」に入ってしまった現在のハリウッドなどを切り取っていく
あわせて読みたい
【天才】映画音楽の発明家『モリコーネ』の生涯。「映画が恋した音楽家」はいかに名曲を生んだか
「映画音楽のフォーマットを生み出した」とも評される天才作曲家エンリオ・モリコーネを扱った映画『モリコーネ 映画が恋した音楽家』では、生涯で500曲以上も生み出し、「映画音楽」というジャンルを比べ物にならないほどの高みにまで押し上げた人物の知られざる生涯が描かれる
あわせて読みたい
【狂気?】オウム真理教を内部から映す映画『A』(森達也監督)は、ドキュメンタリー映画史に残る衝撃作だ
ドキュメンタリー映画の傑作『A』(森達也)をようやく観られた。「オウム真理教は絶対悪だ」というメディアの報道が凄まじい中、オウム真理教をその内部からフラットに映し出した特異な作品は、公開当時は特に凄まじい衝撃をもたらしただろう。私たちの「当たり前」が解体されていく斬新な一作
あわせて読みたい
【驚嘆】映画『TAR/ター』のリディア・ターと、彼女を演じたケイト・ブランシェットの凄まじさ
天才女性指揮者リディア・ターを強烈に描き出す映画『TAR/ター』は、とんでもない作品だ。「縦軸」としてのターの存在感があまりにも強すぎるため「横軸」を上手く捉えきれず、結果「よく分からなかった」という感想で終わったが、それでも「観て良かった」と感じるほど、揺さぶられる作品だった
あわせて読みたい
【感想】これはドキュメンタリー(実話)なのか?映画『女神の継承』が突きつける土着的恐怖
ナ・ホンジンがプロデューサーを務めた映画『女神の継承』は、フィクションなのかドキュメンタリーなのか混乱させる異様な作品だった。タイ東北部で強く信じられている「精霊(ピー)」の信仰をベースに、圧倒的なリアリティで土着的恐怖を描き出す、強烈な作品
あわせて読みたい
【違和感】映画『コントラ』は、「よく分かんない」が「よく分かんないけど面白い」に変わる不思議な作品
ほぼ内容を知らないまま観に行った映画『コントラ』は、最後の最後まで結局何も理解できなかったが、それでもとても面白い作品だった。「後ろ向きに歩く男」が放つ違和感を主人公・ソラの存在感が中和させており、奇妙なのに可能な限り「日常感」を失わせずに展開させる構成が見事だと思う
あわせて読みたい
【異様】西成のあいりん地区を舞台にした映画『解放区』は、リアルとフェイクの境界が歪んでいる
ドキュメンタリー映画だと思って観に行った『解放区』は、実際にはフィクションだったが、大阪市・西成区を舞台にしていることも相まって、ドキュメンタリー感がとても強い。作品から放たれる「異様さ」が凄まじく、「自分は何を観せられているんだろう」という感覚に襲われた
あわせて読みたい
【驚異】甲子園「2.9連覇」を成し遂げた駒大苫小牧野球部監督・香田誉士史の破天荒で規格外の人生:『勝…
「田中将大と斎藤佑樹の死闘」「37年ぶりの決勝戦再試合」「驚異の2.9連覇」など話題に事欠かなかった駒大苫小牧野球部。その伝説のチームを率いた名将・香田誉士史の評伝『勝ちすぎた監督』は、体罰が問題になった男の毀誉褒貶を余すところなく描き出す。しかしとんでもない男だ
あわせて読みたい
【表現】映画『名付けようのない踊り』で初めて見た田中泯のダンス。「芸術以前」を志向する圧倒的パワー
映画『名付けようのない踊り』の中で田中泯は言う。「私」や「個性」を表現することには違和感がある、と。「踊りのために身体を作る」のではなく、「野良仕事で出来た身体で踊る」のだ、と。芸術になる前の踊りを探したい、と。「唯一無二の表現者」の生涯と現在地を映し出すドキュメンタリー
あわせて読みたい
【衝撃】映画『ダンサー・イン・ザ・ダーク』凄い。ラストの衝撃、ビョークの演技、”愛”とは呼びたくな…
言わずとしれた名作映画『ダンサー・イン・ザ・ダーク』を、ほぼ予備知識ゼロのまま劇場で観た。とんでもない映画だった。苦手なミュージカルシーンが効果的だと感じられたこと、「最低最悪のラストは回避できたはずだ」という想い、そして「セルマのような人こそ報われてほしい」という祈り
あわせて読みたい
【現実】権力を乱用する中国ナチスへの抵抗の最前線・香港の民主化デモを映す衝撃の映画『時代革命』
2019年に起こった、逃亡犯条例改正案への反対運動として始まった香港の民主化デモ。その最初期からデモ参加者たちの姿をカメラに収め続けた。映画『時代革命』は、最初から最後まで「衝撃映像」しかない凄まじい作品だ。この現実は決して、「対岸の火事」ではない
あわせて読みたい
【芸術】実話を下敷きに描く映画『皮膚を売った男』は、「アートによる鮮やかな社会問題風刺」が見事
「シリア難民の背中にタトゥーを彫り芸術作品として展示する」と聞くと非常に不謹慎に感じられるだろうが、彫ったのが国家間の移動を自由にする「シェンゲンビザ」だという点が絶妙な皮肉。実話をベースにした映画『皮膚を売った男』の、アートによる社会問題提起の見事な鮮やかさ
あわせて読みたい
【貢献】社会問題を解決する2人の「社会起業家」の生き方。「豊かさ」「生きがい」に必要なものは?:『…
「ヤクの毛」を使ったファッションブランド「SHOKAY」を立ち上げ、チベットの遊牧民と中国・崇明島に住む女性の貧困問題を解決した2人の若き社会起業家の奮闘を描く『世界を変えるオシゴト』は、「仕事の意義」や「『お金』だけではない人生の豊かさ」について考えさせてくれる
あわせて読みたい
【変】「家を建てるより、モバイルハウスを自作する方がいいのでは?」坂口恭平の疑問は「常識」を壊す…
誰もが大体「家」に住んでいるでしょうが、そもそも「家」とは何なのか考える機会はありません。『モバイルハウス 三万円で家をつくる』の著者・坂口恭平は、「人間は土地を所有すべきなのか?」という疑問からスタートし、「家」の不可思議さを突き詰めることで新たな世界を垣間見せる
あわせて読みたい
【おすすめ】「天才」を描くのは難しい。そんな無謀な挑戦を成し遂げた天才・野崎まどの『know』はヤバい
「物語で『天才』を描くこと」は非常に難しい。「理解できない」と「理解できる」を絶妙なバランスで成り立たせる必要があるからだ。そんな難題を高いレベルでクリアしている野崎まど『know』は、異次元の小説である。世界を一変させた天才を描き、「天才が見ている世界」を垣間見せてくれる
あわせて読みたい
【青春】二宮和也で映画化もされた『赤めだか』。天才・立川談志を弟子・談春が描く衝撃爆笑自伝エッセイ
「落語協会」を飛び出し、新たに「落語立川流」を創設した立川談志と、そんな立川談志に弟子入りした立川談春。「師匠」と「弟子」という関係で過ごした”ぶっ飛んだ日々”を描く立川談春のエッセイ『赤めだか』は、立川談志の異端さに振り回された立川談春の成長譚が面白い
あわせて読みたい
【人生】仕事がつまらない人へ、自由な働き方・生き方のための「月3万円しか稼げないビジネス」指南:『…
SDGsが広がる世界で、「生活スタイルを変えなければならない」と理解していても、それをどう実践すべきかはなかなか難しいところでしょう。『月3万円ビジネス』で、「『仕事』と『生活』を密着させ、『お金・エネルギーの消費を抑える過程を楽しむ』」生き方を知る
あわせて読みたい
【斬新】ホームレスの家を「0円ハウス」と捉える坂口恭平の発想と視点に衝撃。日常の見え方が一変する:…
早稲田大学建築学科在籍中から「建築物の設計」に興味を持てなかった坂口恭平が、「ホームレスの家」に着目した『TOKYO 0円ハウス0円生活』には、「家」に対する考え方を一変させる視点が満載。「家に生活を合わせる」ではなく、「生活に家を合わせる」という発想の転換が見事
あわせて読みたい
【驚異】『グレイトフル・デッドにマーケティングを学ぶ』って書名通りの本。異端ロックバンドの”稼ぎ方”
日本ではあまり知られていないが、熱狂的なファンを持つロックバンド「グレイトフル・デッド」。彼らは50年も前から、現代では当たり前となった手法を続け、今でも年間5000万ドルを稼いでいる。『グレイトフル・デッドにマーケティングを学ぶ』で「ファンからの愛され方」を学ぶ
あわせて読みたい
【革新】天才マルタン・マルジェラの現在。顔出しNGでデザイナーの頂点に立った男の”素声”:映画『マル…
「マルタン・マルジェラ」というデザイナーもそのブランドのことも私は知らなかったが、そんなファッション音痴でも興味深く観ることができた映画『マルジェラが語る”マルタン・マルジェラ”』は、生涯顔出しせずにトップに上り詰めた天才の来歴と現在地が語られる
あわせて読みたい
【革命】電子音楽誕生の陰に女性あり。楽器ではなく機械での作曲に挑んだ者たちを描く映画:『ショック…
現代では当たり前の「電子音楽」。その黎明期には、既存の音楽界から排除されていた女性が多く活躍した。1978年、パリに住む1人の女性が「電子音楽」の革命の扉をまさに開こうとしている、その1日を追う映画『ショック・ド・フューチャー』が描き出す「創作の熱狂」
あわせて読みたい
【矛盾】法律の”抜け穴”を衝く驚愕の小説。「ルールを通り抜けたものは善」という発想に潜む罠:『法廷…
完璧なルールは存在し得ない。だからこそ私たちは、矛盾を内包していると理解しながらルールを遵守する必要がある。「ルールを通り抜けたものは善」という”とりあえずの最善解”で社会を回している私たちに、『法廷遊戯』は「世界を支える土台の脆さ」を突きつける
あわせて読みたい
【生と死】不老不死をリアルに描く映画。「若い肉体のまま死なずに生き続けること」は本当に幸せか?:…
あなたは「不老不死」を望むだろうか?私には、「不老不死」が魅力的には感じられない。科学技術によって「不老不死」が実現するとしても、私はそこに足を踏み入れないだろう。「不老不死」が実現する世界をリアルに描く映画『Arc アーク』から、「生と死」を考える
あわせて読みたい
【妄執】チェス史上における天才ボビー・フィッシャーを描く映画。冷戦下の米ソ対立が盤上でも:映画『…
「500年に一度の天才」などと評され、一介のチェスプレーヤーでありながら世界的な名声を獲得するに至ったアメリカ人のボビー・フィッシャー。彼の生涯を描く映画『完全なるチェックメイト』から、今でも「伝説」と語り継がれる対局と、冷戦下ゆえの激動を知る
あわせて読みたい
【革新】映画音楽における唯一のルールは「ルールなど無い」だ。”異次元の音”を生み出す天才を追う:映…
「無声映画」から始まった映画業界で、音楽の重要性はいかに認識されたのか?『JAWS』の印象的な音楽を生み出した天才は、映画音楽に何をもたらしたのか?様々な映画の実際の映像を組み込みながら、「映画音楽」の世界を深堀りする映画『すばらしき映画音楽たち』で、異才たちの「創作」に触れる
あわせて読みたい
【危機】シードバンクを設立し世界の農業を変革した伝説の植物学者・スコウマンの生涯と作物の多様性:…
グローバル化した世界で「農業」がどんなリスクを負うのかを正しく予測し、その対策として「ジーンバンク」を設立した伝説の植物学者スコウマンの生涯を描く『地球最後の日のための種子』から、我々がいかに脆弱な世界に生きているのか、そして「世界の食」がどう守られているのかを知る
あわせて読みたい
【アート】「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」(森美術館)と「美術手帖 Chim↑Pom特集」の衝撃から「…
Chim↑Pomというアーティストについてさして詳しいことを知らずに観に行った、森美術館の「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」に、思考をドバドバと刺激されまくったので、Chim↑Pomが特集された「美術手帖」も慌てて買い、Chim↑Pomについてメッチャ考えてみた
あわせて読みたい
【解釈】詩人が語る詩の読み方。意味や読み方や良さが分からなくて全然気にしなくていい:『今を生きる…
私は学生時代ずっと国語の授業が嫌いでしたが、それは「作品の解釈には正解がある」という決めつけが受け入れ難かったからです。しかし、詩人・渡邊十絲子の『今を生きるための現代詩』を読んで、詩に限らずどんな作品も、「解釈など不要」「理解できなければ分からないままでいい」と思えるようになりました
あわせて読みたい
【感想】池田晶子『14歳からの哲学』で思考・自由・孤独の大事さを知る。孤独を感じることって大事だ
「元々持ってた価値観とは違う考えに触れ、それを理解したいと思う場面」でしか「考える」という行為は発動しないと著者は言う。つまり我々は普段、まったく考えていないのだ。『14歳からの哲学』をベースに、「考えること」と自由・孤独・人生との関係を知る
あわせて読みたい
【飛躍】有名哲学者は”中二病”だった?飲茶氏が易しく語る「古い常識を乗り越えるための哲学の力」:『1…
『14歳からの哲学入門』というタイトルは、「14歳向けの本」という意味ではなく、「14歳は哲学することに向いている」という示唆である。飲茶氏は「偉大な哲学者は皆”中二病”だ」と説き、特に若い人に向けて、「新しい価値観を生み出すためには哲学が重要だ」と語る
あわせて読みたい
【あらすじ】濱口竜介監督『偶然と想像』は、「脚本」と「役者」のみで成り立つ凄まじい映画。天才だと思う
「映画」というメディアを構成する要素は多々あるはずだが、濱口竜介監督作『偶然と想像』は、「脚本」と「役者」だけで狂気・感動・爆笑を生み出してしまう驚異の作品だ。まったく異なる3話オムニバス作品で、どの話も「ずっと観ていられる」と感じるほど素敵だった
あわせて読みたい
【興奮】世界的大ベストセラー『サピエンス全史』要約。人類が文明を築き上げるに至った3つの革命とは?
言わずと知れた大ベストセラー『サピエンス全史』は、「何故サピエンスだけが人類の中で生き残り、他の生物が成し得なかった歴史を歩んだのか」を、「認知革命」「農業革命」「科学革命」の3つを主軸としながら解き明かす、知的興奮に満ち溢れた1冊
あわせて読みたい
【知的】文系にオススメの、科学・数学・哲学の入門書。高橋昌一郎の「限界シリーズ」は超絶面白い:『…
例えば「科学」だけに限ってみても、「なんでもできる」わけでは決してない。「科学」に限らず、私たちが対峙する様々な事柄には「これ以上は不可能・無理」という「限界」が必ず存在する。高橋昌一郎の「限界シリーズ」から、我々が認識しておくべき「限界」を易しく学ぶ
あわせて読みたい
【感想】飲茶の超面白い東洋哲学入門書。「本書を読んでも東洋哲学は分からない」と言う著者は何を語る…
東洋哲学というのは、「最終回しか存在しない連続ドラマ」のようなものだそうだ。西洋哲学と比較にならないほど異質さと、インド哲学・中国哲学など個別の思想を恐ろしく分かりやすく描く『史上最強の哲学入門 東洋の哲人たち』は、ページをめくる手が止まらないくらい、史上最強レベルに面白かった
あわせて読みたい
【貢献】飛行機を「安全な乗り物」に決定づけたMr.トルネードこと天才気象学者・藤田哲也の生涯:『Mr….
つい数十年前まで、飛行機は「死の乗り物」だったが、天才気象学者・藤田哲也のお陰で世界の空は安全になった。今では、自動車よりも飛行機の方が死亡事故の少ない乗り物なのだ。『Mr.トルネード 藤田哲也 世界の空を救った男』から、その激動の研究人生を知る
あわせて読みたい
【天才】読書猿のおすすめ本。「いかにアイデアを生むか」の発想法を人文書に昇華させた斬新な1冊:『ア…
「独学の達人」「博覧強記の読書家」などと評される読書猿氏が、古今東西さまざまな「発想法」を1冊にまとめた『アイデア大全』は、ただのHow To本ではない。「発想法」を学問として捉え、誕生した経緯やその背景なども深堀りする、「人文書」としての一面も持つ作品だ
あわせて読みたい
【協働】日本の未来は福井から。地方だからこその「問題意識の共有」が、社会変革を成し遂げる強み:『…
コンパクトシティの先進地域・富山市や、起業家精神が醸成される鯖江市など、富山・福井の「変革」から日本の未来を照射する『福井モデル 未来は地方から始まる』は、決して「地方改革」だけの内容ではない。「危機意識の共有」があらゆる問題解決に重要だと認識できる1冊
あわせて読みたい
【驚異】ガイア理論の提唱者が未来の地球を語る。100歳の主張とは思えない超絶刺激に満ちた内容:『ノヴ…
「地球は一種の生命体だ」という主張はかなり胡散臭い。しかし、そんな「ガイア理論」を提唱する著者は、数々の賞や学位を授与される、非常に良く知られた科学者だ。『ノヴァセン <超知能>が地球を更新する』から、AIと人類の共存に関する斬新な知見を知る
あわせて読みたい
【奇跡】ホンダジェット驚愕の開発秘話。航空機未経験のホンダが革命的なアイデアで常識を打ち破る:『…
自動車メーカーの本田技研工業が開発した「ホンダジェット」は、航空機への夢を抱いていた創業者・本田宗一郎のスピリットを持ち続ける会社だからこそ実現できた。『ホンダジェット 開発リーダーが語る30年の全軌跡』からその革命的な技術開発と運用までのドラマを知る
あわせて読みたい
【実像】ベートーヴェンの「有名なエピソード」をほぼ一人で捏造・創作した天才プロデューサーの実像:…
ベートーヴェンと言えば、誰もが知っている「運命」を始め、天才音楽家として音楽史に名を刻む人物だが、彼について良く知られたエピソードのほとんどは実は捏造かもしれない。『ベートーヴェン捏造 名プロデューサーは嘘をつく』が描く、シンドラーという”天才”の実像
あわせて読みたい
【教養】美術を「感じたまま鑑賞する」のは難しい。必要な予備知識をインストールするための1冊:『武器…
芸術を「感性の赴くまま見る」のは、日本特有だそうだ。欧米では美術は「勉強するもの」と認識されており、本書ではアートを理解しようとするスタンスがビジネスにも役立つと示唆される。美術館館長を務める著者の『武器になる知的教養 西洋美術鑑賞』から基礎の基礎を学ぶ
あわせて読みたい
【逸脱】「人生良いことない」と感じるのは、「どう生きたら幸せか」を考えていないからでは?:『独立…
「常識的な捉え方」から逸脱し、世の中をまったく異なる視点から見る坂口恭平は、「より生きやすい社会にしたい」という強い思いから走り続ける。「どう生きたいか」から人生を考え直すスタンスと、「やりたいことをやるべきじゃない理由」を『独立国家のつくりかた』から学ぶ
あわせて読みたい
【戸惑】人間の脳は摩訶不思議。意識ではコントロールできない「無意識の領域」に支配されている:『あ…
我々は決断や選択を「自分の意思」で行っていると感じるが、脳科学の研究はそれを否定している。我々に「自由意志」などない。「脳」の大部分は「意識以外のもの」に支配され、そこに「意識」はアクセスできないという驚愕の実態を『あなたの知らない脳』から学ぶ
あわせて読みたい
【貢献】働く上で大切にしたいことは結局「人」。海士町(離島)で持続可能な社会を目指す若者の挑戦:…
過疎地域を「日本の未来の課題の最前線」と捉え、島根県の離島である「海士町」に移住した2人の若者の『僕たちは島で、未来を見ることにした』から、「これからの未来をどう生きたいか」で仕事を捉える思考と、「持続可能な社会」の実現のためのチャレンジを知る
あわせて読みたい
【逸話】天才数学者ガロアが20歳で決闘で命を落とすまでの波乱万丈。時代を先駆けた男がもし生きていた…
現代数学に不可欠な「群論」をたった1人で生み出し、20歳という若さで決闘で亡くなったガロアは、その短い生涯をどう生きたのか?『ガロア 天才数学者の生涯』から、数学に関心を抱くようになったきっかけや信じられないほどの不運が彼の人生をどう変えてしまったのか、そして「もし生きていたらどうなっていたのか」を知る
あわせて読みたい
【不可思議】心理学の有名な実験から、人間の”欠陥”がどう明らかになっていったかを知る:『心は実験で…
『心は実験できるか 20世紀心理学実験物語』では、20世紀に行われた心理学実験からインパクトのある10の実験を選び紹介している。心理学者でもある著者が「科学であって科学ではない」と主張する心理学という学問で、人間のどんな不可思議さがあぶり出されてきたのかを知る
あわせて読みたい
【挑戦】社会に欠かせない「暗号」はどう発展してきたか?サイモン・シンが、古代から量子暗号まで語る…
「暗号」は、ミステリやスパイの世界だけの話ではなく、インターネットなどのセキュリティで大活躍している、我々の生活に欠かせない存在だ。サイモン・シン『暗号解読』から、言語学から数学へとシフトした暗号の変遷と、「鍵配送問題」を解決した「公開鍵暗号」の仕組みを理解する
あわせて読みたい
【限界】有名な「錯覚映像」で心理学界をザワつかせた著者らが語る「人間はいかに間違えるか」:『錯覚…
私たちは、知覚や記憶を頼りに社会を生きている。しかしその「知覚」「記憶」は、本当に信頼できるのだろうか?心理学の世界に衝撃を与えた実験を考案した著者らの『錯覚の科学』から、「避けられない失敗のクセ」を理解する
あわせて読みたい
【情熱】常識を疑え。人間の”狂気”こそが、想像し得ない偉業を成し遂げるための原動力だ:映画『博士と…
世界最高峰の辞書である『オックスフォード英語大辞典』は、「学位を持たない独学者」と「殺人犯」のタッグが生みだした。出会うはずのない2人の「狂人」が邂逅したことで成し遂げられた偉業と、「狂気」からしか「偉業」が生まれない現実を、映画『博士と狂人』から学ぶ
あわせて読みたい
【使命】「CRISPR-Cas9」を分かりやすく説明。ノーベル賞受賞の著者による発見物語とその使命:『CRISPR…
生物学の研究を一変させることになった遺伝子編集技術「CRISPR-Cas9」の開発者は、そんな発明をするつもりなどまったくなかった。ノーベル化学賞を受賞した著者による『CRISPR (クリスパー) 究極の遺伝子編集技術の発見』をベースに、その発見物語を知る
あわせて読みたい
【研究】光の量子コンピュータの最前線。量子テレポーテーションを実現させた科学者の最先端の挑戦:『…
世界中がその開発にしのぎを削る「量子コンピューター」は、技術的制約がかなり高い。世界で初めて「量子テレポーテーション」の実験を成功させた研究者の著書『光の量子コンピューター』をベースに、量子コンピューター開発の現状を知る
あわせて読みたい
【対立】数学はなぜ”美しい”のか?数学は「発見」か「発明」かの議論から、その奥深さを知る:『神は数…
数学界には、「数学は神が作った派」と「数学は人間が作った派」が存在する。『神は数学者か?』をベースに、「数学は発見か、発明か」という議論を理解し、数学史においてそれぞれの認識がどのような転換点によって変わっていったのかを学ぶ
あわせて読みたい
【未知】タコに「高度な脳」があるなんて初耳だ。人類とは違う進化を遂げた頭足類の「意識」とは?:『…
タコなどの頭足類は、無脊椎動物で唯一「脳」を進化させた。まったく違う進化を辿りながら「タコに心を感じる」という著者は、「タコは地球外生命体に最も近い存在」と書く。『タコの心身問題』から、腕にも脳があるタコの進化の歴史と、「意識のあり方」を知る。
あわせて読みたい
【究極】リサ・ランドールが「重力が超弱い理由」を解説する、超刺激的なひも理論の仮説:『ワープする…
現役の研究者であるリサ・ランドールが、自身の仮説を一般向けに分かりやすく説明する『ワープする宇宙』。一般相対性理論・量子力学の知識を深く記述しつつ「重力が超弱い理由」を説明する、ひも理論から導かれる「ワープする余剰次元」について解説する
あわせて読みたい
【解説】テネットの回転ドアの正体を分かりやすく考察。「時間逆行」ではなく「物質・反物質反転」装置…
クリストファー・ノーラン監督の映画『TENET/テネット』は、「陽電子」「反物質」など量子力学の知見が満載です。この記事では、映画の内容そのものではなく、時間反転装置として登場する「回転ドア」をメインにしつつ、時間逆行の仕組みなど映画全体の設定について科学的にわかりやすく解説していきます
あわせて読みたい
【挑戦】自閉症のイメージを変えるおすすめ本。知的障害と”思い込む”専門家に挑む母子の闘い:『自閉症…
専門家の思い込みを覆し、自閉症のイメージを激変させた少年・イド。知的障害だと思われていた少年は、母親を通じコミュニケーションが取れるようになり、その知性を証明した。『自閉症の僕が「ありがとう」を言えるまで』が突きつける驚きの真実
あわせて読みたい
【異端】子育てがうまくいかないと悩む方へ。9歳で大学入学の天才児に学ぶ「すべきでないこと」:『ぼく…
12歳で数学の未解決問題を解いた天才児は、3歳の時に「16歳で靴紐が結べるようになったらラッキー」と宣告されていた。専門家の意見に逆らって、重度の自閉症児の才能をどう開花させたのかを、『ぼくは数式で宇宙の美しさを伝えたい』から学ぶ
あわせて読みたい
【異端】子育ては「期待しない」「普通から外れさせる」が大事。”劇薬”のような父親の教育論:『オーマ…
どんな親でも、子どもを幸せにしてあげたい、と考えるでしょう。しかしそのために、過保護になりすぎてしまっている、ということもあるかもしれません。『オーマイ・ゴッドファーザー』をベースに、子どもを豊かに、力強く生きさせるための”劇薬”を学ぶ
あわせて読みたい
【驚嘆】人類はいかにして言語を獲得したか?この未解明の謎に真正面から挑む異色小説:『Ank: a mirror…
小説家の想像力は無限だ。まさか、「人類はいかに言語を獲得したか?」という仮説を小説で読めるとは。『Ank: a mirroring ape』をベースに、コミュニケーションに拠らない言語獲得の過程と、「ヒト」が「ホモ・サピエンス」しか存在しない理由を知る
あわせて読みたい
【感想】世の中と足並みがそろわないのは「正常が異常」だから?自分の「正常」を守るために:『コンビ…
30代になっても未婚でコンビニアルバイトの古倉さんは、普通から外れたおかしな人、と見られてしまいます。しかし、本当でしょうか?『コンビニ人間』をベースに、多数派の人たちの方が人生を自ら選択していないのではないかと指摘する。
あわせて読みたい
【奇跡】ビッグデータに”直感”を組み込んで活用。メジャーリーグを変えたデータ分析家の奮闘:『アスト…
「半世紀で最悪の野球チーム」と呼ばれたアストロズは、ビッグデータの分析によって優勝を果たす。その偉業は、野球のド素人によって行われた。『アストロボール』をベースに、「ビッグデータ」に「人間の直感」を組み込むという革命について学ぶ
あわせて読みたい
【天職】頑張っても報われない方へ。「自分で選び取る」のとは違う、正しい未来の進み方:『そのうちな…
一般的に自己啓発本は、「今、そしてこれからどうしたらいいか」が具体的に語られるでしょう。しかし『そのうちなんとかなるだろう』では、決断・選択をするべきではないと主張されます。「選ばない」ことで相応しい未来を進む生き方について学ぶ
あわせて読みたい
【現代】これが今の若者の特徴?衝撃のドキュメンタリー映画『14歳の栞』から中学生の今を知る
埼玉県春日部市に実在する中学校の2年6組の生徒35人。14歳の彼らに50日間密着した『14歳の栞』が凄かった。カメラが存在しないかのように自然に振る舞い、内心をさらけ出す彼らの姿から、「中学生の今」を知る
あわせて読みたい
【不満】この閉塞感は打破すべきか?自由意志が駆逐された社会と、不幸になる自由について:『巡査長 真…
自由に選択し、自由に行動し、自由に生きているつもりでも、現代社会においては既に「自由意志」は失われてしまっている。しかし、そんな世の中を生きることは果たして不幸だろうか?異色警察小説『巡査長 真行寺弘道』をベースに「不幸になる自由」について語る
あわせて読みたい
【実話】仕事のやりがいは、「頑張るスタッフ」「人を大切にする経営者」「健全な商売」が生んでいる:…
メガネファストファッションブランド「オンデーズ」の社長・田中修治が経験した、波乱万丈な経営再生物語『破天荒フェニックス』をベースに、「仕事の目的」を見失わず、関わるすべての人に存在価値を感じさせる「働く現場」の作り方
あわせて読みたい
【希望】貧困の解決は我々を豊かにする。「朝ベッドから起きたい」と思えない社会を変える課題解決:『…
現代は、過去どの時代と比べても安全で清潔で、豊かである。しかしそんな時代に、我々は「幸せ」を実感することができない。『隷属なき道』をベースに、その理由は一体なんなのか何故そうなってしまうのかを明らかにし、さらに、より良い暮らしを思い描くための社会課題の解決に触れる
あわせて読みたい
【表現者】「センスが良い」という言葉に逃げない。自分の内側から何かを表現することの本質:『作詞少…
大前提として、表現には「技術」が必要だ。しかし、「技術」だけでは乗り越えられない部分も当然ある。それを「あいつはセンスが良いから」という言葉に逃げずに、向き合ってぶつかっていくための心得とは何か。『作詞少女』をベースに「表現することの本質」を探る
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
おすすめのドキュメンタリー映画【映画の感想】 | ルシルナ
このブログは、本と映画をベースに考えたことを綴っていますが、このタグではブログで取り上げたドキュメンタリー映画をまとめています。観る映画の8割はドキュメンタリー…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…




















































































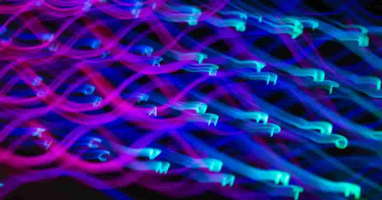





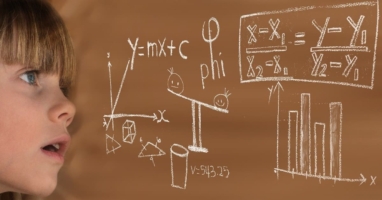



















コメント